【初心者向け】ガーデニング入門|何から始めれば良い?

家の中で始められる趣味としてすっかり定着したガーデニングですが、これから始めてみようかな?という方もいらっしゃるのではないでしょうか?
ガーデニングは手軽に始められるのが魅力である一方、お世話のしかたが間違っていると、せっかく咲いた花が枯れてしまったり虫が湧いたりといったことも。
また、ガーデニングを始めるにあたって、どんな道具を揃えれば良いかわからない方もいるでしょう。
本記事ではガーデニング初心者の方や、これから始めたいという方に向けて、注意すべきことや必要なアイテムなどについて詳しく解説します。
ガーデニングを始める前に確認しておくこと

ガーデニングの最初のステップとして、“場所”に関する確認をしておきましょう。
スペースの確認
- 室内
- ベランダ
- 庭
ガーデニングを行う場所として、マンションなどの集合住宅であれば室内やベランダ、一軒家や一部の集合住宅では、これらに加えて庭も選択肢となるでしょう。
植物を育てるためには十分なスペースが必要です。この後に解説しますが、ガーデニングの種類、あるいは育てる植物によって必要となるスペースの大きさは異なります。
そのため、育てたい植物がある場合は、そのために十分なスペースがあるか確認しましょう。
もし希望がないのであれば、確保できるスペースから逆算してガーデニングの規模を決めると良いでしょう。
日当たりや風通しの確認
ガーデニングには日当たりや風通しが重要です。
特に日光は光合成にとって不可欠です。しかし植物によっては強すぎる日差しが逆効果になることも。
例えば、部屋が西向きの場合は日照時間が長くなるため、鉢を簡単に日陰に移動させられるかどうかといったことも考慮する必要があるでしょう。
また、植物の成長を阻害する要素として蒸れや病害虫といったものがありますが、これらは風通しの良い環境に置くことである程度対策ができます。
関連記事:掃除がメンタルヘルスに与える影響とは?心も部屋もスッキリさせる方法
初心者におすすめのガーデニングの種類
ここでは、初心者の方におすすめのガーデニングの種類を紹介します。
コンテナガーデニング

コンテナガーデニングとは、鉢やプランターといった容器(コンテナ)を使って植物を育てるガーデニングのスタイルです。
庭がない場合でも、ベランダや玄関先などの小さなスペースで手軽に楽しめます。また、移動が簡単なので、日当たりや風通しの良い場所に簡単に移動できるのもメリット。
コンテナガーデニングは季節ごとに植物を入れ替えられるため、常に新しい景色を楽しむことができます。
デザインや規模を自由に自分で決められるので人気のスタイルとなっています。
家庭菜園

家庭菜園とは自宅の庭やベランダ、プランターなどを利用して、野菜やハーブ、果物を栽培することを指します。自宅に小さな畑を作るイメージでしょうか。
商業的な目的ではなく、楽しみながら育てて収穫したものを食べることが主な目的です。
普段何気なくスーパーなどで購入している野菜や果物を自分で栽培することで、出荷するまでの大変さやありがたみを理解できることが家庭菜園の魅力といえるでしょう。
道具と少しの知識があれば誰でも始められますが、植物の栽培自体が完全に初めてという方は、まずはミニトマトやラディッシュといった初心者向けの野菜からチャレンジしてみましょう。
花壇づくり

庭がある場合に限られますが、花壇づくりもおすすめです。
レンガやブロックなどで縁取りをつくり、園芸用の土を入れて、植物の種や苗を植えていきます。
ホームセンターや園芸専門店などではレンガに見立てた花壇用の囲いなども販売されており、持ち運びやすいように軽量化されたものもあります。
土の持ち運びだけは大変ですが、それ以外でいえばイメージほど大掛かりな作業を必要としないため、初心者の方でも十分にトライできるでしょう。
関連記事:ストレスを解消するにはどうすればいい?ハグがおすすめな理由も解説
ガーデニング初心者の方が気を付けるべきこと

ここでは、ガーデニングを始めるにあたって初心者の方が気を付けるべきことを見ていきましょう。
水やりの頻度
鉢植えの場合、鉢の底から水が流れ出るまでたっぷりと水を与え、根腐れしないように受け皿に溜まった水はすぐに捨てるようにしましょう。
推奨される水やりの頻度は植物の種類や季節、気象条件などで異なります。上記を踏まえた上で、基本となるポイントを解説します。
春
1〜2日に1回が目安です。気温が上がってきたら水やりの回数を徐々に増やします。午前中の気温が上がりきる前に水やりをするのが理想的です。
夏
気温が高く乾燥しやすいため、必ず1日に1〜2回は水やりを行います。早朝や夕方の涼しい時間帯に水を与え、日中の直射日光が強い時間帯は避けましょう。
秋
気温が20℃台前半くらいまで下がり始めたら、1〜3日に1回の頻度に減らしましょう。土が乾いているかどうかを確認し、乾燥している場合に水を与えます。
冬
週に1〜2回の水やりで十分です。午前中の暖かい時間に水を与え、夕方以降は避けましょう。特に、寒い地域では水をあげすぎると土が凍るため注意が必要です。
健康状態のチェックと日々のケア
植物がすくすく育つには、水やりと並行して適切に肥料を与えることが重要です。
肥料は多すぎも少なすぎも良くないので、植物ごとの目安をよく確認して与えるようにしましょう。
日々の状態チェックを行うことで、微妙な変化や病害虫の存在に気付くことも。
病害虫は植物の寿命を縮める厄介な存在です。見つけたら自然由来の防虫スプレーなどを使用して寄りつかないように対策することが大事です。
自然由来の成分でも植物によってはダメージとなってしまうことがあります。必ず植物ごとに使用できる防虫スプレーのタイプを確認しましょう。
ガーデニング初心者の方が揃えるべきアイテム

ここでは、ガーデニング初心者の方が揃えておくべきアイテムを紹介します。
スコップ
植物を植え替えたり土を掘る際に必須です。目盛り付きのスコップを選ぶと植える深さを正確に把握できるので便利です。
園芸用ハサミ
植物の成長を促進するためには栄養が分散しすぎないように“剪定”という作業が必要になります。
植物によっては枝が硬いため、専用のハサミがあると便利でしょう。
ジョウロ
室内やベランダでガーデニングを行う際の水やりに使用します。
コップや霧吹きを使う方法もありますが、ある程度の水の量を均等かつ広範囲に届けるためにはジョウロが最適です。
庭の場合はホースの先に散水ノズルを取り付けて使用するのが良いでしょう。
ガーデングローブ
特に土いじりやトゲのある植物の手入れをする際に手や爪を保護するために必須です。防水や耐久性が高いものを選ぶと良いでしょう。
熊手
雑草を抜いたり土を整えるために使用します。特に広いスペースでガーデニングを行う場合に重宝するでしょう。
プランター・鉢
植物を植えるのに必要です。ガーデニングに使えるスペースや植物の種類で購入すべきサイズが異なります。
プランターや鉢まで含めてひとつの作品となるので、素材やデザインにも気を配りましょう。
関連記事:エプソムソルトでバスタイムにスキンケア|おすすめの商品を紹介
ガーデニング初心者の方におすすめのアイテム5選
ここでは、ガーデニング初心者の方におすすめのアイテムを紹介します。
APRTAT 天然竹製フラワースタンド

天然竹製のフラワースタンドです。お花や観葉植物を飾れるだけではなく、家具などが鉢と接触するのを防ぐのにも役立ちます。
コンパクトなデザインなのでさまざまな植物によくマッチし、屋内屋外のどこでも洗練された雰囲気を演出できるのもポイント。
取り付けの手順書とネジが付いており、プラスドライバー一本で組み立てが完了します。
床との接触部には滑り止めカバーを取り付けるため安定性が高く、床を傷つけずに済みます。
SENUN ソーラーランタンガーデンライト

おしゃれなランタン風ガーデン用ライトです。日が落ちてくると光センサーが作動し、温かみのある光が庭先を照らします。
太陽光パネル充電であるため電池が不要で、自然環境に優しいのもポイント。
ロープは取り外し可能な設計で底は平らになっているので、枝やフックなどに引っ掛けたり玄関前に置いたりなど、さまざまな設置方法が楽しめ、庭先をおしゃれに彩ってくれるでしょう。
なないろ館 プラントホルダー 3個セット

おしゃれなプラントホルダーの3個セットです。フックが付いており、ベランダや柵など、さまざまな部分に引っ掛けられるように設計されています。
頑丈なアイアン製でリーフ型のモチーフがアクセントとなっています。色は黒で統一されていますが隙間の多いデザインなので、重たい印象は受けません。
上部の直径が約22cm、底部が16.5cmとなっているので、この規格に合う鉢植えを使用されている方は、ぜひ購入を検討してみてください。
T4U 植木鉢 プラスチックプランター 4点セット

「シンプル至上」のデザインコンセプトに基づき、余計な面倒な要素を取り除き、単一の線、クラシックな白、つや消しの質感を採用しています。
底に細かな排水孔が開いているため、余った水が流れ出し、植物の根腐れを防ぐことができます。
受け皿は簡単に取り外せるので、余った水はさっと捨てるだけで良いのもポイントです。
白を基調としたシンプルなガーデンを演出したい場合にマッチするでしょう。
SUN-E SE フクロウポット

まるっとしたフクロウのデザインが特徴的なセラミック製の小型植木鉢。小型のサボテンやアロエのような多肉植物を栽培するのにおすすめです。
鉢そのものが置物として可愛らしいため、窓際に飾っておくだけでもインテリアの一部として機能してくれるでしょう。
ガーデニング初心者の方におすすめの書籍2選
続いては、ガーデニング初心者の方におすすめの教科書となる書籍を紹介します。
ベランダ寄せ植え菜園:自然の力を借りるから失敗しない
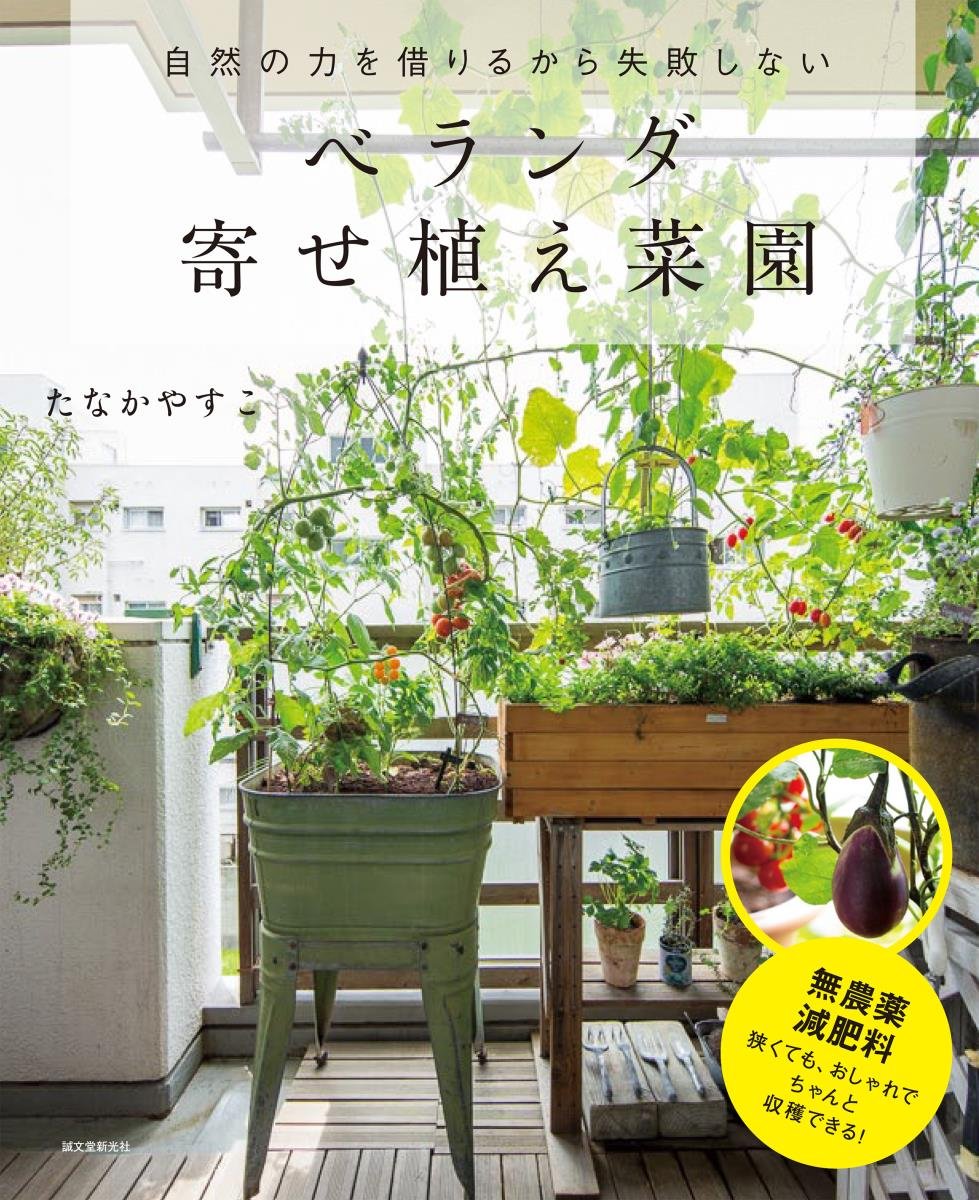
数々の家庭菜園本でおなじみのたなかやすこ氏監修の、シンプルかつオーガニックなコンテナ栽培のノウハウを一冊にまとめた本です。
自然の力を最大限に活かすたなか流のルールを活用することで、狭いベランダでもちゃんと収穫できることが具体例を交えて紹介されています。
今まで野菜のコンテナ栽培が上手くいかなかった人や、野菜づくり初心者の方でもすぐに真似できる一冊です。
NHK趣味の園芸 おぎはら流 がんばらなくても幸せな庭 宿根草のナチュラルガーデン(生活実用シリーズ)
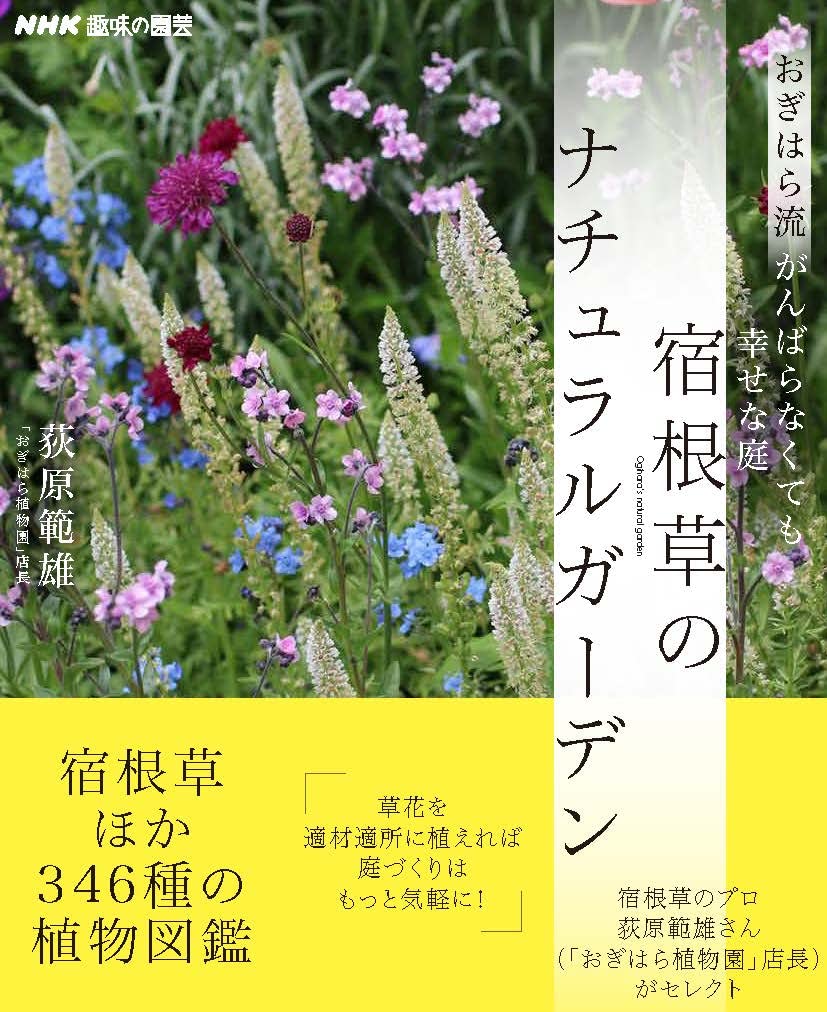
国内外で注目を集める「ナチュラルガーデン」。魅力は何といってもメンテナンスが簡単なことでしょう。
宿根草のスペシャリストである荻原範雄氏がナチュラルガーデンに適した346種の植物を紹介し、日陰・酷暑・狭いなど植える場所の悩みに応じた植物選びをレクチャーします。
負担を減らしたシンプルな栽培法がわかるほか、豊富な庭の写真も紹介されているので、ガーデニングのイメージを掴むのにもおすすめです。
まとめ
ガーデニングは自宅でできる、初心者の方にもおすすめの趣味です。
室内や庭先を植物で彩ることで気分も上がりますが、反対に栽培方法を間違えて枯れたり病気になると、寂れた暗い印象になってしまうでしょう。
そのため、初心者の方であっても基本的な知識を身につけた上でチャレンジしたいところです。
本記事で紹介した内容を参考に、ガーデニングデビューを果たしましょう。
ガスライティングとは?実例や被害者への影響について解説

私たちが他者と関わりを持つとき、その全てが対等であるとは限りません。
どちらかが目上でもう片方が目下の立場になることもありますが、そこには相手への思いやりや尊敬の意が必要となるでしょう。
今回ご紹介する「ガスライティング」は、一方がもう片方を一方的に支配し、感情や行動を抑制する問題行動の一種です。
自身や身の回りの人がガスライティングによる被害を受けないためにも、目的や実例・影響について知っておきましょう。
ガスライティングとは?

ガスライティングとは精神的な虐待の一種であり、相手に間違った情報を植え付け、正しい行動や認識ができないように誘導する問題行動です。
家族や友人関係など親しい間柄で起こる場合もあれば、クラスや職場内など複数人によって行われる場合もあり、被害者は重大なダメージを受けてしまいます。
暴力のように目に見える形で行われることが少ないため、周りはもちろん被害者自身がガスライティングに気が付かず、長年苦しい思いをさせられるケースも珍しくありません。
例えば、仕事でミスをしてしまった部下を上司が叱責するシーンで考えてみましょう。
ミスの原因を探りながら部下の失態を叱り、次のミスが起こらないように対策を考える場合、ガスライティングのような問題は起こりません。
必要な情報だけを伝えて改善策を講じることが重要であり、ミスをしたことだけを責めていても解決には至らないでしょう。
一方、ミスの根本的な原因を無視し、「お前の根性が悪いためだ」「高卒は何をやらせても使えない」などと部下の精神にダメージを与えるような叱責の方法はどうでしょうか。
今回のミスでは部下の性格に問題があったわけではないにもかかわらず、生まれ持った性格や育ちを責め、ミスの責任を押し付けようとしています。
この場合は間違った情報で相手を支配している上司が、部下に対しガスライティングを行っているといえます。
このように、ガスライティングでは「現実とは異なる情報」を相手に正しいと思いこませ、自分の思い通りに支配しようとするのが特徴です。
上記の例では部下が「自分は根性が悪く使えない人間だ」と思い込んでしまうことで、さらなるミスが増えたり、塞ぎ込みがちになったりと様々な影響が出るでしょう。
何をするにも上司の言いなりになり、結果として立派な支配関係が成り立ってしまいます。
こういった状態が続くと、被害者は何も悪いことをしていないにも関わらず、「自分は悪だ」などと正しい判断ができなくなってしまいます。
問題となった上司に対してだけでなく、周りに対してもネガティブな感情しか抱くことができず、人間関係の悪化を招いてしまう点にも注意が必要です。
ガスライティングを行う目的は?
加害者となる側が、被害者に向けてガスライティングを行う目的とは一体何なのでしょうか。
意識的に相手を支配しようとしている人もいれば、無意識のうちに自分を優位に立たせ、相手を破滅に追い込もうとしている加害者もいます。
いずれの場合も、ガスライティングの特徴にいち早く気づき、なるべく早い段階で身を守ることが重要です。
自主的な服従状態に追い込む
ガスライティングの加害者は、相手を服従させ、優越感に浸ることを目的としています。
無理やり自分の言うことを聞かせるのではなく、あくまでも被害者が自主的に服従するよう仕向けることで、より上の立場から相手を見下すことを目指しています。
自分の行いが間違っていると指摘されたり服従を拒否されたりすると逆行し、さらなる暴言を吐くようになるため、被害者は次第に抵抗することを諦めるようになるでしょう。
破滅へ誘導
ガスライティングは単純な支配とは異なり、相手が自立心を失い、自分なしでは何もできないといったレベルまで落ちてしまうことを目的としています。
言うことを聞かせたり思い通りに行動させたりといった序盤から、正しい判断ができず社会に適合できなくなる終わりまで、執拗に追い続けるのです。
特に身内や恋愛・友情関係においては執拗なガスライティングが行われることが多く、周りに打ち明けることもなく苦しんでいる被害者がたくさんいるといわれています。
ガスライティングとモラハラ・ストーカーとの違い

ガスライティングという言葉は未だ社会に浸透していないため、「モラハラ」や「ストーカー」と同義であると捉える方も少なくありません。
モラハラやストーカーとどのように違うのか、それぞれの定義を確認しておきましょう。
モラハラとの違い
モラハラとは「モラルハラスメント」の略称であり、主に言葉によって相手の尊厳を奪い、精神的に傷つける問題行動の一種です。
意見が食い違う相手に対して必要以上に声を荒げて怒鳴ったり、相手の人格を否定するような言葉を投げつけたりと、モラルが備わっている人であればしないであろう過激な言動が特徴です。
直接相手に暴力をふるうことはないものの、大きな音を立ててドアを閉める・物を壊すなどして相手へ恐怖を与える行動もモラハラの一種だといえます。
モラハラがガスライティングと異なるのは、モラハラの方が比較的問題が明るみに出やすいといった点です。
モラハラの被害者は被害を受けたことを実感しやすく、周りにも相談しやすいでしょう。
会社やクラスといった場所でのモラハラであれば、被害者よりも周囲が先に声を上げる場合も見られます。
一方のガスライティングは、被害者はもちろん周りも気が付かないようなスピードで徐々に精神を追い詰めていく点に注意が必要です。
被害者は知らず知らずのうちに加害者から離れられなくなり、気が付いたときには手遅れとなっていることも多いでしょう。
周りから見ると加害者と被害者の関係が非常に良好に見える場合もあり、なかなか問題が露呈しにくいといった危険性があります。
ストーカーとの違い
相手を自分の好きなように支配したい、といった感情は、ガスライティングだけでなくストーカーにも当てはまります。
相手が好きで仕方がない、または相手が自分のことを好いていると思い込んだ結果、行動を監視したり過度に連絡を取ったりしてしまうのがストーカーの特徴です。
中には相手が自分の恋人だと思い込んだ加害者が、被害者が異性といるのを発見し、勢い余って暴力に及ぶケースも珍しくありません。
ガスライティングもストーカー同様に相手へ強い執着を見せますが、その根底にあるのは「相手を服従させたい」といった思いであり、恋愛感情とは異なります。
ストーカーはあくまでも相手に振り向いてほしくて行うケースが多いのに対し、ガスライティングは相手の人生を破滅させ、とことん追い込むことを目的としています。
「相手に幸せになってほしい」といった思いは一切なく、嫌がらせの数々は全て自分の快楽のために行われているのが特徴です。
ガスライティングの実例
続いて、実際に起こったガスライティングの実例をご紹介します。
先程もご紹介したように、ガスライティングは被害者が自覚しにくいといった危険性があります。
これからご紹介する実例に当てはまるケースはないか、身の回りをイメージしながらご覧ください。
疑心暗鬼に陥らせる
ガスライティングで頻繁に見られるのが、何もしていない人に対して不安になるような言動を行うことで、「自分が悪いのではないか」と疑心暗鬼に陥らせる行動です。
例えばある日会社で重要な書類の紛失事件が起こったとします。
Aさんは何もしていないはずのBさんに対し、「そういえばこの前Bさんがその書類を持っていたよね」と話しかけます。
Bさんは身に覚えがないものの、Aさんがあまりにもハッキリと断言するため、「もしかしたら自分が書類をなくしたのではないか」と不安に感じてしまいます。
このように、Aさんにとって書類を紛失したのが誰であるかは関係なく、「Bさんをいじめてやろう」「困らせてやろう」といった考えだけで行動しているのが特徴です。
このような出来事が繰り返されると、Bさんは次第に自信を失い、何事にも挑戦できなくなってしまうでしょう。
わざと侵入した痕跡を残す
先程の例を引き続き見ていきましょう。
書類の紛失事件をBさんになすりつけて困らせようと考えたAさんは、事前にBさんが犯人であると疑われるように仕掛けます。
Cさんが出張に行った際に職場で配ったお土産をBさんが机に置いたのを見て、Aさんはこれをこっそりと隠してしまうのです。
Bさんはお土産がないことに気が付きますが、Cさんになくしたとはいえず、モヤモヤとした気持ちで過ごすこととなるでしょう。
そんな折に書類の紛失事件が明るみに出ます。Aさんは先程同様にBさんを疑い、同時に「前もCさんのお土産をなくしてたよね」と発言しました。
これによって職場のメンバーからは、「人からもらったものをなくすなんて、きっとBさんが書類をなくしたんだろう」といったイメージを持たれることとなるでしょう。
このように、被害者を疑心暗鬼に陥らせるため、わざと証拠を残すのもガスライティングのやり口です。
これにより、加害者から受けるガスライティングだけでなく、周りからも孤立しやすくなってしまうといった危険性があります。
偶然を装う
ガスライティングでは、被害者が加害者に精神的な依存を見せるのが特徴です。
そのためには被害者と加害者がより近しい関係になる必要があり、お互いの物理的な距離は縮まっていくでしょう。
AさんはさらにBさんを追い詰めるため、職場のメンバーと共謀してBさんの行動を監視します。
職場内だけでなく、外出先などでも偶然を装って姿を現し、Bさんのプライベートを侵食していきます。
Bさんは怪しんで職場のメンバーに相談しますが、Aさんと共謀しているメンバーが口を割ることはありません。
結果、BさんはいつもAさんに監視されていると思い込むようになり、外出自体を怖がり、ひきこもるようになってしまいました。
このとき、AさんはBさんに対し「いつも監視している」と伝えたわけではありません。あくまでもBさんが勝手な思い込みで苦しんでいる、といった状況を作り出すため、偶然を装って行動を監視しているのです。
嘘を吹き込む
AさんはBさんを孤立させ、さらに自身への依存を高めるために嘘を吹き込むようになります。
「〇〇さんがBさんのことを苦手だって言っていた」「Bさんは仕事ができないから重要な案件を任せられないと上司が言っていた」など、根も葉もない嘘を吹き込んでBさんの不安をあおります。
さらには「皆には内緒だけど、特別に教えてあげる」などと伝えることで、Bさんは周りのメンバーに相談ができなくなり、たった一人で悩むこととなってしまいました。
このような嘘はガスライティングにおいてよくあるケースであり、被害者は簡単にこの嘘を信じてしまいます。
加害者は最初から嘘を信じるような純粋な人や、周りになかなか相談できない内向的な人を狙ってガスライティングを行うのです。
行動の邪魔をする
ガスライティングの手口として最後にご紹介するのが「行動の邪魔をする」といった点です。
Bさんが職場でしようとすることを端からAさんが邪魔をしていくため、Bさんは思い通りに動くことができません。
それどころかAさんの指示通りに動くよう強制され、いつしかAさんがいなければ何もできないようになってしまうのです。
関連記事:マイノリティ・マジョリティとは? 多様な社会の理解を深めるために
ガスライティングの被害者への影響

ガスライティングでは、ときに被害者に対し社会復帰できないレベルの重大な影響が及ぶ可能性があります。
こういった最悪のケースを防ぐためにも、自身や周囲がガスライティングの可能性を疑い、日々確認しながら過ごすことが大切です。
精神的影響とトラウマ
ガスライティングの被害者は自身を信じることができなくなり、自分が何をすれば良いのか、どう生きていけば良いのか分からないといった不安に襲われることとなります。
自分で自分の意思を決められないため、職場や学校でのコミュニケーションがうまく取れなくなり、結果として外出できず引きこもりになってしまうケースも少なくありません。
こうしたガスライティングの被害者は、加害者による抑圧が終わった後も、しばしば被害についてフラッシュバックしてしまうことがあります。
嫌な思いをした場所に足を踏み入れることができなくなったり、パニック症状やうつ症状が現れたりと、精神的にも身体的にも弊害が起こってしまうでしょう。
長期的な健康への影響
ガスライティングの被害者は精神疾患を抱えやすいほか、不眠・イライラ・焦り・便秘や下痢といった症状が慢性的に現れるようになったり、思うように食事がとれなくなったりする場合があります。
こういった状況が続くと健康を害し、様々な病気にかかりやすくなってしまうでしょう。
外出の機会が減ると日光を浴びる回数が減り、骨や歯がもろくなったり、皮膚病にかかりやすくなったりする可能性が高まります。
一度でもガスライティングによる被害を受けてしまうと、被害者はこういった身体症状が現れていても、すぐに医療機関を受診できない場合があります。
一人暮らしなどで周りに頼れる人がいない場合や、周りに不調を隠してしまう場合などは特に、症状が長引く可能性が高いといえます。
社会的孤立
ガスライティングでは加害者が被害者を孤立させる目的で様々な行動を起こします。
辛いことがあっても頼る人がおらず、結果として加害者に依存するしかない状態を作り上げているのです。
周りがガスライティングに気が付かなければ、被害者は永遠と一人で苦しむことになるでしょう。
また、加害者の巧妙な手口によって孤立した被害者は、自分だけでなく周りも信用できなくなってしまいます。
うまくいって加害者とは別の環境に移動できたとしても、心から周りを信じることができず、結果として孤立してしまうケースが多々見られます。
ガスライティングに仕返しすることはできる?
ガスライティングを受けていることに気が付いたり、周りにいる人が被害者なのではないかと感じたりしたとき、誰でも一度は「仕返しをしたらいいのではないか」と考えることでしょう。
ガスライティングに対し仕返しをすることは可能なのか、リスクと共にご紹介します。
仕返しのリスク
ガスライティングの加害者に対し、同じような方法で仕返しをすることはおすすめできません。
何故なら加害者は既に被害者に対して優位に立っていると思い込んでおり、仕返しをするようなそぶりを見せると直ちに攻撃を開始してくると考えられるためです。
今までよりも強い言葉でなじったり、周りから孤立させたりするだけでなく、今度は暴力などを用いて支配しようとするかもしれません。
また、被害者が加害者に仕返しをしたことが原因で、「喧嘩両成敗」となってしまう可能性があります。
周りに相談しても「どっちも悪いね」と済まされてしまい、被害者の無念は晴れないでしょう。
仕返しを考える前にできること
ガスライティングに対しては、仕返しをする前にまず「周りに相談」することが大切です。
なるべく加害者から距離のある知人に、第三者目線で判断してもらうと良いでしょう。
時には精神科医や臨床心理士・カウンセラーなど、専門家に協力を求めるのも大切です。
加害者の言動が度を過ぎていると感じたり、距離を取ろうとしてもうまくいかなかったりする場合は、法的措置を検討するのも一つの手です。
辛い現状を変えるため、受けた被害は全て証拠を残しておきましょう。
チャットのトーク画面を保存したり、音声データを残したり、壊されたものをそのまま保管しておいたりするのも重要です。
ガスライティングから身を守るための対処法

ガスライティングを受けたと感じたときは、ただちに立ち向かうのではなく、まず自分の身を守る行動をとることが大切です。
これからご紹介する5つの対処法を頭に入れておき、万が一の際にしっかりと判断できるように心掛けておきましょう。
1.第三者に助けを求める
ガスライティングは加害者と被害者が一対一の関係になったり、複数人の加害者に対し少数の被害者が攻撃を受けたりすることが多いとされています。
ガスライティングに当てはまる行動を見たり、実際に受けたりした場合は、すぐに第三者の助けを借りましょう。
先程もご紹介したように、必ずしも加害者に近しい人を選ぶ必要はありません。
時には家族を、またある時には上司や先生など立場が上の人を巻き込んで、加害者の言動をチェックしてもらうことが大切です。
2.起きやすい場所を避ける
ガスライティングは個室などの閉鎖空間で起こることが多いため、加害者と二人きりになるような状況をできるだけ避けるのがおすすめです。
自分のいない間に何かされているのではないかと心配な方は、自分のデスクやロッカーにしっかりと鍵をかけるなどの対策を行うのも良いでしょう。
集団で行うガスライティングを避けるためには、一定期間その集団から離れてみても良いでしょう。
普段一緒にいるグループから少しの間離れたり、別の人と一緒にいるようにしたりするだけで、被害を抑えることに繋がります。
加害者が家族や友人内にいる場合は、プライベートの時間をしっかりと確保し、なるべく同じ空間で過ごさないよう工夫することをおすすめします。
3.加害者を無視する
ガスライティングの被害者になりやすいのは、相手の発言を無視できず、つい言うことを聞いてしまう心の優しい人です。
どんなにひどいことを言われていても強く反発できず、加害者に自信を与えてしまうでしょう。
嫌なことをされたとき、加害者を無視する強さを持つことも大切です。嫌なことをされてまで、相手に嫌われないようにと振舞うのは得策ではありません。
さりげなく相手から距離を取ったり、嫌な話題を変えたりするだけでも、ガスライティングの被害を最小限に抑えられるでしょう。
4.証拠を集める
最終手段として専門家に相談するため、ガスライティングで受けた被害は全て証拠を集めておくことが大切です。
メッセージや写真・録音など、様々な形で証拠を残しておくことで、被害の全貌を明らかにすることができます。
加害者が無意識で行っていたことも含めてしっかりと責任を負わせるためにも、辛い中ではあるものの、証拠を失ってしまわないように注意しましょう。
こういった精神的被害は、被害者の日記も証拠になる場合があります。
その日されたことや嫌だったことを時系列順に書き留め、風化させないように保管しておきましょう。
5.専門家・専門機関への相談
被害が甚大な場合や、加害者に更生の兆しが見られない場合は、専門家へ相談することをおすすめします。
既に被害者に身体的・精神的症状が出ている場合は、精神科や心療内科を受診しましょう。
医薬品の服用やカウンセリングなど、被害者一人ひとりに合った治療を選択できます。
また、社内でのトラブルは上司や人事へ、家庭内でのトラブルはDV支援施設など、それぞれ役割の異なる施設がたくさんあります。
どこに相談すべきか分からない方は、弁護士に話を聞いてもらうのもおすすめです。
関連記事:人間関係が「めんどくさい」「疲れた」と感じる心理や対処法を解説
まとめ
ガスライティングは一人の被害者の人生を狂わせてしまう悪質な行為です。
自身が被害を受けないように注意するだけでなく、周りに苦しんでいる人がいないかどうか確認しておくのも大切です。
ガスライティングの特徴や実例・困ったときの相談先などをイメージし、万が一の際に備えましょう。
日本におけるゴミ問題の現状は?環境への影響やわたしたちにもできることを紹介

私たちが地球上に暮らす上で見て見ぬふりはできない「ゴミ問題」
うずたかく積まれたゴミが問題となっている海外諸国の映像を見て、どこか他人事のように感じている方も多いのではないでしょうか。
私たち日本人もゴミ問題とは切っても切り離せない関係であり、一人ひとりが意識していかなければならない課題の一つです。
今回は日本におけるゴミ問題について、詳しい現状や原因・今後私たちが行わなければならない取り組みについてご紹介します。
近年世界各国で行われているゴミ問題への対策を参考に、自分にできることを模索していきましょう。
ゴミ問題とは?

一言で「ゴミ問題」といっても、その種類は様々です。ありとあらゆる問題を含め、一人ひとりにできることを検討していかなければなりません。
具体的には以下のような問題が挙げられますが、これらは氷山の一角であり、全ての問題点を網羅できているわけではないでしょう。
- ゴミの焼却時に出る温室効果ガスによる地球温暖化
- 自動車や船の排気ガスによる環境汚染
- 海洋ゴミの蓄積による生態系への悪影響
- ポイ捨てや不法投棄などによる公衆衛生の悪化
- ゴミの焼却に関する費用や設備の問題
- 燃やせないゴミの埋立地不足
例えばゴミの焼却場に関する費用や、燃やせないゴミの埋立地不足などの問題点を、私たち個人がすぐに解決するのは難しいことです。
これらの問題は社会全体で取り組むべきであり、これまでも長い年月をかけて各自治体が頭を悩ませています。
一方、海洋ゴミやポイ捨て・不法投棄などは、私たち一人ひとりの心掛けで確実にゴミの数を減らすことができます。
もちろんすぐに現状を変えることはできませんが、いくら社会全体で解決策を講じても、一人ひとりの意識が伴っていなければ解決には至らないでしょう。
関連記事:グレートリセットがもたらす変革とは?経済・環境・社会の未来
日本のゴミ問題の現状
そもそもかつての日本には、限られたものを修理しながら長く使う習慣がありました。
食材や日用品などの消耗品以外は頻繁に買い替えることはなく、専門の修理業者も今より多かったといわれています。
そんな日本が、今は大きなゴミ問題を抱えているのはなぜなのでしょうか。
2024年現在、日本では「電子廃棄物」によるゴミの量が増え続けています。
これは主にスマートフォンやタブレットによるものであり、国民一人ひとりがこのような電子機器を所有するようになったことから、必然的にゴミの量が増えたと考えられます。
電子廃棄物は一般の燃やせるゴミと同じように廃棄できないため、処理には多額の費用と人材・設備が必要となっています。
また、日常的に出るゴミの排出量も見て見ぬふりはできません。
特に顕著なのは食品ロスで、2024年に農林水産省から発表された2022年度の食品ロスは472万トンにも及ぶといわれています。
1人当たりに換算すると年で38kgもの食品を捨てていることになり、どれだけ多くの食材が無駄になっているかが分かるでしょう。
これらの多くは燃やせるゴミとして焼却されますが、最終的に残った灰は最終処分場へ送られ、今もその体積を圧迫し続けています。
焼却時には多くの温室効果ガスが発生するため、地球温暖化の加速に繋がっているのも大きな問題の一つです。
もちろん、燃やせないゴミの埋立地が不足している問題も見逃せません。日本は国土が狭いため、広大な埋立地を用意することができません。
現在使用している埋立地を含め、2040年にはゴミを処分する場所がなくなるといわれています。
埋立地を新たに作るには土地関係者の理解を得られなければならないため、気軽に別の場所へ移すこともできません。
今ある埋立地をできるだけ長く使うため、家庭や事業所から出るゴミを減らしたり、リサイクルに回したりといった工夫が必要といえます。
ゴミ問題の原因

様々な問題が絡み合い、世界全体の課題となっているゴミ問題。その中でも大きな割合を占めている原因についてご紹介します。
大量生産・大量消費
先程もご紹介したように、かつての日本は今あるものを大切に使う習慣が根付いており、職人によって作られたものを必要なときにだけ購入する、といった生活スタイルが主流でした。
ものが壊れてしまったときはまず「直す」ことを選び、すぐに捨てるようなものはほとんどありませんでした。
これに対し現在はというと、スーパーなどの店舗ではいつ訪れてもずらりと製品が並び、消費者がいつでも購入できるように準備されています。
中には購入されないまま消費期限を迎え、廃棄されてしまうものもあるでしょう。
こういった大量生産による過剰な供給が、ゴミ問題を引き起こす一つの要因といえます。
また、大量生産に伴い、消費者自身がものを大量に消費するようになったのも原因の一つです。
特に食品や日用品など安価に購入できるものは、必要以上に購入し、不要となったら気軽に廃棄を選ぶ人が増えています。
使いきれずにゴミとして捨ててしまう食材がある方や、ティッシュペーパーや割り箸など最終的にゴミとなるものを日常的に使っている方も多いのではないでしょうか。
こういった大量消費を控え、本当に必要なものだけを購入したり、繰り返し使えるものを選んだりといった工夫が大切だといえます。
自然災害の増加
日本は災害大国ともいわれており、地震や台風による豪雨災害などが多い国の一つです。
海に面した地域では津波による被害を受けたり、山や川の近くでは土砂災害や洪水が起こったりと、どこに住んでいても常に災害の危険が付きまとうでしょう。
こういった災害とゴミ問題は一見関係がないようにも見えるでしょう。
現実では災害によって家屋が倒壊したり道が崩れたりすることによって、多くの廃棄物が生まれます。
これらのほとんどは焼却できず、埋立地に運ばれて体積を圧迫するでしょう。
現在使用されている埋立地の残余年数は、あくまでも家庭や事業所から出たゴミを処分することを想定して計算されたものです。
これに加え大きな災害が起こってしまうと、埋立地の多くで残余年数が減り、さらなる問題が起こる可能性が高まります。
台風による豪雨災害などは、地球温暖化が加速することでも起こりやすくなるといわれています。
豪雨災害によりゴミが増えるだけでなく、最悪の場合は命を落とす危険性もあるため、こういった意味でも地球温暖化を軽く見てはなりません。
食品ロス
世界の中には今日食べるものすらない人々がいるのに対し、日本では多くの食品ロスが生まれています。
私たち個人が家庭で出すゴミのほか、店頭で売れ残り廃棄される製品や、飲食店で食べ残された食材の分も含まれています。
特に予約販売がメインとなるクリスマスケーキや恵方巻などの季節商品は、該当する日にちが1日過ぎるだけで売れなくなるため、食品ロスになりやすいことでも有名です。
こういった食品ロスがやがてゴミになり、地球温暖化や埋立地の不足問題となるのはご存じのとおりです。
また、このままの状態が続くと将来人口が急激に増加したり、大災害が起きてインフラが機能しなくなったりした場合、深刻な食糧不足になる可能性もあるでしょう。
食材は食べきれる分を選んで購入し、冷凍など食材を廃棄せずに済む工夫を心掛けながら、日々の食品ロスを少しでも減らすことが大切です。
ゴミ問題が及ぼす環境への影響
ゴミが多く出ると環境に悪い、というイメージがあっても、具体的にどのような影響を及ぼしているかまで詳細に想像するのは難しいものです。
私たちの知らないところでどのような悪影響が出ているのか、詳しく知っておきましょう。
地球温暖化
先程から度々触れているように、ゴミを燃やす際に出る温室効果ガスによって、地球温暖化が加速することは有名です。
温室効果ガスの主な成分は二酸化炭素であり、これが地球の大気を覆ってしまうと、地熱がこもって大気の温度が上がってしまいます。
南極など寒冷地の氷が解けて海面が上昇したり、植物の不足によって生態系に異常が生じたりと、様々な面で悪影響を及ぼしてしまうでしょう。
私たち人間にとっても、地球温暖化は切り離せない問題の一つです。
数十年前は夏であっても気温が30℃に満たない日が多かったにも関わらず、近年は40℃に達する日が出てくるなど、屋外での活動が難しい気温が続いています。
エアコンなどの機器を正しく使わずにいたり、水分や塩分が不足したりすることで、熱中症により命を落とす方も増加しています。
土壌汚染
ゴミを焼却した後に残る灰や燃やせないゴミなどは、圧縮されて埋め立てられるのが一般的です。
安全に配慮して埋め立てられているとはいえ、時間をかけて有害物質が土壌に染み込み、付近を汚染する可能性も高いといわれています。
土壌汚染は埋め立ててからすぐに影響が出るものではなく、日々少しずつ広がりを見せるため、私たちが気づいたときには既に手の施しようがない状態にまで進んでしまう点に注意しなければなりません。
汚染された土壌に雨が降って水が染み込むと、有害物質を含んだ水が低地へと流れ、やがて広範囲を汚染することとなります。
作物が育たなくなったり、付近の水質を汚染したりする可能性があり、私たちの健康にも悪影響となるでしょう。
海洋汚染
一見どこまでも綺麗に広がっているように見える海ですが、実は多くの海洋ゴミが漂い、生態系に影響を及ぼしています。
海の生き物がプラスチックなどの海洋ゴミを食べたり、ネットに絡まったりして命を落とすケースも珍しくありません。
こういった海洋ゴミの多くは、元々私たちの家庭から出たゴミが街に捨てられ、山から川へ、川から海へと流れ着いたものです。
周りに海がないからといって、海洋汚染と関係がないわけではないことを覚えておきましょう。
自然環境破壊
燃やせるゴミは温室効果ガスを放出して地球温暖化を加速し、燃やせないゴミは埋立地を圧迫したり土壌を汚染したりするなど、様々な場面で環境に悪影響を与えています。
ゴミ処理場や埋立地を開拓するために森林を伐採したり、有害物質の含まれた土壌を放置したりすると、そこに住んでいた生き物は住処を追われて路頭に彷徨うことになるでしょう。
食べ物が足りずに人里に下りてきたクマやサルなどが、人間を傷つけて殺処分されるケースも珍しいことではありません。
また、山間部や海沿いなどで問題となっているのが不法投棄です。冷蔵庫やテレビなどの大型家電を中心に、廃棄する際に必要な料金を出し渋り、目の付きにくいところへ捨てていく人が後を絶ちません。
中には自動車など、簡単に撤去できないものまで捨てられていることもあります。
不法投棄されたゴミが自然に還ることはないため、誰かが気づいて処分するまでは変わらずに放置されることとなるでしょう。
動物が触って怪我をしたり、土壌汚染や水質汚染に繋がったりする可能性も高く、自然環境を破壊する大きな一因となっています。
関連記事:リデュースとは?リユース・リサイクルとの違いやそれぞれができることを解説
ゴミ問題解決のためにできること

ゴミ問題を解決するためには、「5R」を生活に取り入れることが大切です。
かつてはリデュース・リユース・リサイクルを中心とした「3R」が推進されてきましたが、近年はリフューズ・リペアを加えた5Rとして生まれ変わっています。
それぞれの内容を詳しく知り、自分にできることを検討してみましょう。
リデュース(Reduce)
リデュースは「ゴミを発生させるのを防ぐ」ことです。
必要以上にものを購入してゴミにしてしまったり、食べきれない量のメニューを頼んだりせず、自分から出るゴミの量を減らすように努めましょう。
必要とする期間が限られているものは中古品やレンタル品で賄ったり、本体に詰替えられるタイプの洗剤やシャンプーを使ったりするのも良いでしょう。
リユース(Reuse)
リユースは「繰り返し使う」ことを指します。1回だけ使ってすぐに捨ててしまうのではなく、形を変えて利用できないか検討してみましょう。
たくさん使って古くなってしまった衣類を雑巾として再利用したり、子どもが成長して使わなくなってしまったおもちゃをリユースショップへ売却したりと、一つひとつのものを少しでも長く使ってあげることが大切です。
リサイクル(Recycle)
リサイクルは「再生して利用する」という意味を持ちます。
ペットボトルや古紙などが主な資源であり、同じペットボトルとして使われることもあれば、トイレットペーパーやスタッキングボックス・衣類などに生まれ変わることもあります。
こうしたリサイクル製品を生み出すためには、私たち消費者が資源ゴミをしっかりと分別し、清潔な状態で出すことが重要です。
リフューズ(Refuse)
リフューズは「不要なものをもらわない(断る)」という意味の言葉です。
つい食べきれない量の食材をもらってしまったり、無料だからと割り箸や試供品をたくさん持ってきてしまったりする方も多いのではないでしょうか。
こういった不用品によるゴミの発生を防ぐため、マイバッグを持参してビニール袋の購入を控えたり、最低限の包装で販売されているものを選んだりすると良いでしょう。
リペア(Repair)
リペアは「直しながら長く使う」ことを指します。安価なものであればあるほど、気軽に捨てて新しいものを購入したくなってしまう方が多いはず。
接着剤などを使って自力で直したり、修理業者に依頼したりしながら、一つのものに愛着をもって長く使ってみてはいかがでしょうか。
ものの寿命が長くなる分、普段使っているものよりも少しランクの高いリッチなものを選べるようにもなるはずです。
ゴミ問題に対する世界の取り組み

最後に、日本をはじめとする世界各国では、ゴミ問題に対してどのような取り組みが行われているのかを確認してみましょう。
未だ日本が取り入れていない対策を知っておくことで、個人でできる取り組みも増えるはずです。
日本
日本では先ほどご紹介した「5R運動」を中心として、個人はもちろん各企業がゴミの削減に向けて取り組んでいます。
現在問題視されているゴミの約半分は一般家庭から、そして約半分は企業から出ているため、各々が削減に向けて取り組む必要があります。
ビニール袋の有料化を始め、私たち一般市民の目にも分かりやすいところで対策が始まっているのもポイントです。
アメリカ
アメリカではリデュース・リユース・リサイクルの3Rに加え、「ロット」と呼ばれる行動を勧めています。
これは「腐る」という意味の単語であり、主に生ゴミを腐らせ、土壌に還すことでゴミを削減する目的で行われているものです。
生ゴミだけを腐らせることで土壌汚染を防ぐとともに、肥料として食物の育成に活用できるため、まさに一石二鳥の取り組みといえるでしょう。
スウェーデン
日本では多くのゴミが埋め立てられて問題となっていますが、スウェーデンでは家庭ゴミのうち埋め立てられるのはわずか1%程度であり、埋立地の圧迫などの問題も起こっていないといわれています。
これはほとんどのゴミがリサイクルに回っているためであり、さらにリサイクル時に出る熱などを利用した発電機能を使い、エネルギーの無駄遣いを減らしているのもポイントです。
空き缶やペットボトルなどはデポジット制を導入しており、製品を購入する際に一部の料金を負担し、飲み終わったボトルを返却する際に返金を受けることで、ゴミの発生を防いでいます。
シンガポール
世界一清潔な国としても知られるシンガポールでは、ゴミのポイ捨てや不法投棄に重い罰金刑があるなど、ゴミ問題に対し積極的に取り組んでいます。
民間のアパートなどには特殊なゴミ収集システムが備わっており、空気の力で捨てたゴミを処理場まで運ぶことができ、人件費や環境汚染を最低限に抑えられているのが特徴です。
中国
人口が多く、その分出るゴミの量が多いことで知られる中国。
これまでは埋め立てによるゴミ処理が一般的でしたが、近年は埋立地の不足などを背景に、焼却によるゴミ処理方法への移行が進められています。
これまで各地域でバラバラだった条例を一つにまとめ、リサイクルの方法などを統一したことで、ゴミの削減に向けて住民たちの意欲も高まりつつあります。
ベトナム
ベトナムでは、事業所から出たゴミは全て生産者が責任を負う形を取っており、産業廃棄物の削減を目指しています。
一方で一般家庭にゴミの分別方法が浸透しきっていないため、プラスチックなど再生可能な素材がゴミとして出されてしまい、深刻な問題となっています。
現時点ではプラスチックゴミのおよそ7割が埋め立て処理されているといわれており、今後の発展に期待が寄せられています。
まとめ
日本はもちろん世界各国で取り組むべきゴミ問題。さらにいえば、私たち一人ひとりがゴミを減らす工夫をすることで、地球を守ることに繋がるでしょう。
人間はもちろん動物や植物も含めたすべての命が過ごしやすい環境を作るため、5Rを中心に自分にできることを模索していきましょう。
リデュースとは?リユース・リサイクルとの違いやそれぞれができることを解説
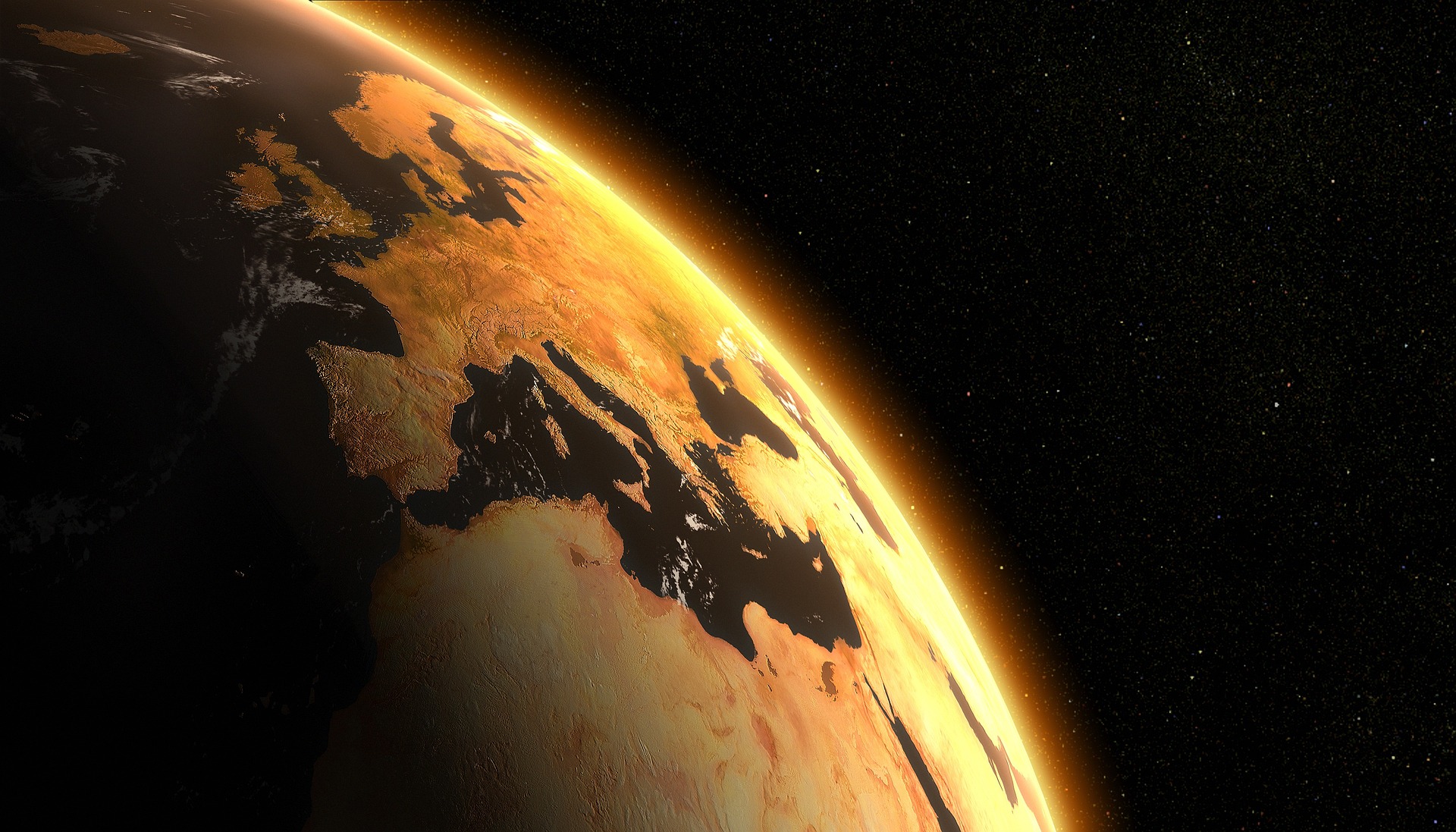
誰もが聞いたことがあるであろう「地球温暖化問題」ですが、誰もが日々の生活の中で地球温暖化対策ができているかといわれればそうではないでしょう。
地球全体という大きな問題であるのと同時に、私たち一人ひとりが意識を正し、環境のために行動しなければなりません。
今回は私たち個人が環境のために行える行動の一つ「リデュース」についてご紹介します。
具体的にどんな行動をとるべきなのか、また「3R」であるリユースやリサイクルとの違いにも触れていきましょう。
リデュース(Reduce)とは?

「Reduce(リデュース)」とは、直訳すると「減らす」という意味の単語です。
環境問題においては、ゴミの出る量を減らすといった意味を持ち、私たち一人ひとりが意識しなければならない行動の一つです。
そもそも地球温暖化は様々な要因が重なってできていますが、その内の一つが「ゴミを償却する際に出る温室効果ガス」であるといわれています。
ゴミを正しく分別したり、不要なものを購入しないよう工夫したりといった取り組みに加え、そもそもゴミになるものを持たないといったリデュースの考え方が重要となります。
日本ではほとんどの地域でゴミ袋の購入に別途費用がかかる仕組みとなっているため、ゴミの量を減らすことで、家計の助けにもなるでしょう。
リデュース・リユース・リサイクル(3R)の違いや意味は?
小中学生の頃に教科書で学んだことがあるであろう「3R」。ゴミによる環境問題に関する対策として重要な考え方であり、先ほどご紹介したリデュースに加えリユース・リサイクルが当てはまります。
近年はここに「リフューズ(不要なものをもらわない)」や「リペア(修理しながら長く使う)」といったRを加え、5Rとして考えられることも増えてきました。
今回はこの中から、ゴミ問題の中心となる「3R」に関して詳しく見ていきましょう。
それぞれの違いを知り、生活の中で無意識に実践できるように学んでおくことをおすすめします。
リユース(Reuse)とは?
「Reuse(リユース)」とは、直訳すると「再利用」といった意味の単語です。
使い終わったものをそのままゴミとして出してしまうのではなく、洗ったり形を変えたりして再び使えるように工夫するといった意味を持ちます。
上の子が着た衣類を下の子が使うことも、不要なチラシを折ってゴミ箱して活用することもリユースの一部といえるでしょう。
3Rのうち、最初に取り組むべきだといえるのが「リデュース」、そして次が「リユース」です。
まずは自分の元から出るゴミを減らす努力をし、続けてゴミとして出す前に再度利用できないかを検討しましょう。
ものがものとして使われた後、さらなる使い道を探すことで、今あるものを大切にできるのもメリットといえます。
愛着のあるものはもちろん、普段であればすぐに捨ててしまうようなものを再利用することで、新たな出費を減らせるのもポイントです。
リサイクル(Recycle)とは?
「Recycle(リサイクル)」とは、「再循環」といった意味を持ちます。
ペットボトルや新聞紙などは、リサイクルされて再び製品として生まれ変わることを知っている方も多いのではないでしょうか。
ペットボトルが再びペットボトルとして使われるだけでなく、細かく粉砕した後に文具や衣類に生まれ変わることも多く、リサイクルの可能性は日々広がりを見せています。
リサイクルをする際にもっとも重要なのは、私たち一人ひとりが正しくゴミを分別し、決まったタイミングで捨てることです。
ペットボトルの回収はラベルやキャップを外して中を綺麗に洗い、乾かした状態で回収に出すのがベストです。
そのほかにも、空き瓶を色ごとに分けたり、新聞紙と雑誌を細かく分別したりと、決められたルールをしっかりと守る必要があります。
回収に出した資源ゴミを、実際にリサイクルをするのは業者の方々です。
しかしリサイクルは私たちの生活からスタートしていることを念頭に置き、限られた資源を効率的に利用できるように工夫しましょう。
関連記事:自然と共存して生きること。ドキュメンタリー映画『ビッグ・リトル・ファーム』 レビュー
リデュースを行うメリット

「リデュースを行うと良い」と頭では分かっていても、実際にどんなメリットがあるのか意識して行動できる方はそれほど多くありません。
リデュースを行うことで環境にどんな影響を与えられるのか、その具体例を知っておきましょう。
エネルギーの使用を抑える
私たちが普段使っているものは、全て作る際にエネルギーを必要としています。
食べ物も、日用品も、娯楽品も全て、何らかのエネルギーを消費することで形づくられているといえるでしょう。
もちろん必要なものを必要なだけ作ることは重要ですが、過剰消費を抑えエネルギーを節約することで、ものづくりの観点からも地球環境へ貢献できます。
また、不要となったものをゴミとして出す際もエネルギーが消費されています。
燃やせるゴミはゴミ自身が燃料となって燃えることで効率的に焼却されていますが、温度が適温に達しないときなどは灯油や都市ガスといった補助燃料が使われています。
リデュースによってゴミが減ることで、こういった補助燃料の消費も減り、限りある資源を大切に使えるでしょう。
二酸化炭素排出を抑える
私たちが出したゴミが、一体どのように処理されているのかご存じでしょうか。
リサイクルされる資源ゴミは各工場でそれぞれの姿へと生まれ変わりますが、燃やせるゴミや燃やせないゴミはそのままゴミとして処理されることとなります。
燃やせるゴミはまとめて焼却され、燃やせないゴミは埋立地へと運ばれ、ものとしての生涯を終えるのです。
燃やして終わりであれば環境に影響を与えることもなく、誰もが好きなようにゴミを出すことでしょう。
しかしゴミを燃やす際には「二酸化炭素」を中心とする温室効果ガスが発生し、地熱が放出されるのを邪魔してしまいます。
結果地表は徐々に温められ、海面上昇や生態系の異常などさまざまなトラブルを引き起こすのです。
つまり、リデュースによってゴミの量が減ると、必要以上に二酸化炭素が増えるのを防ぎ、結果として地球温暖化を食い止める効果が期待できます。
森林を伐採して植物による二酸化炭素の使用が制限されたり、自動車や船などの乗り物から二酸化炭素を含む排気ガスが放出されていたりと、地球温暖化を加速させる要因には様々なものがあります。
とはいえ明日から急に森林伐採や自動車の利用をやめることはできないため、私たち個人でもできる方法を探すことが大切です。
リデュースによってゴミの量を減らすことは、一般人でも取り組みやすい地球温暖化対策といえるでしょう。
省資源化によるコスト削減
ゴミを減らすということは、すなわち「無駄なものを作らずに済む」ということでもあります。
私たちが使い捨ての割り箸やスプーン・フォークなどを使う機会が減ると、生産量が減り、資源を無駄に消費することがなくなります。
割り箸やスプーン・フォークを作るために使っていたコストを抑え、別の製品に回すことも可能となるでしょう。
また、私たち日本人には「おもてなしの心」が備わっているため、どうしても入念な梱包でお客様に安心してもらうよう努力したり、丁寧に書かれた取扱説明書を付けたりといった工夫をする企業が多く見られます。
ここにリデュースの考え方を取り入れることで、梱包は必要最低限になったり、取り扱い説明書が簡素で分かりやすいものになったりと、紙資源に関するコストの削減に繋がるはずです。
ごみ処理費用削減
私たちがゴミを出すときに使うゴミ袋は、製品本体の価格に加え、「ゴミ証紙代」として処理費用が上乗せされています。
各自治体はこの証紙代の中からゴミの処理にかかる費用を捻出し、私たちの出したゴミを適切な形で処理してくれています。
リデュースの考え方を多くの人が取り入れることで、ゴミの量が減り、処理場や自治体の負担軽減に繋がります。
結果としてゴミの処理にかかる費用が減り、私たちが負担する証紙代の軽減を目指せるでしょう。
わたしたちができるリデュースの取り組み

私たち一般人がすぐにでもできる取り組みがリデュースであり、3Rの中でも最初に取り組むべき課題だとされています。
生活の中でリデュースをどのように実現していくべきなのか、それぞれのシーンごとに具体例をご紹介します。
外出時にできるリデュース
外出時に意識したいリデュースは、まず「購入したものを無駄にしない」ことが大切です。
ランチやディナーで出た食事を残さずに食べきったり、目に付いたものを買うときは本当に必要かどうか一度検討したりと、後々ゴミに繋がる行動を減らすよう心掛けましょう。
ランチやディナーの量が多く残してしまいがちな方は、自宅からお弁当を持参するのもおすすめです。
また、外出時に出やすいゴミの例として挙げられるのが、ストローや紙ナプキン・使い捨ておしぼりなどです。
これらはマイストローやハンカチなどを持ち歩くことでゴミとして捨てられることを防げるでしょう。
買い物時にできるリデュース
買い物の際にどんなリデュースができるかというと、まずは普段から使っている日用品を「エコ」を謳った製品に変えてみるのがおすすめです。
詰替え用品などプラスチックを削減できるものや、リサイクル素材からできたもの、綺麗に洗うことで再びリサイクルできるものなど様々な製品が売られています。
こういった製品を積極的に選ぶことで、ゴミとして出るものを減らし、リデュースとしてのメリットが得られるでしょう。
また、近年急激に浸透しつつある「マイバッグ」も効果的です。
レジ袋の利用を極力抑え、何度も再利用できるマイバッグを使うことで、ゴミとして捨てられてしまうプラスチックの削減に繋がります。
気分の上がるようなデザインのエコバッグを一つ持っているだけで、普段のショッピングをさらに楽しめるのではないでしょうか。
自宅でできるリデュース
自宅で出るゴミを極力抑えるには、外出時にできるリデュースの中でもご紹介したように、食事をできるだけ残さず食べるといった取り組みが大切です。
出来上がった料理を完食するだけでなく、野菜を皮ごと使ったり、プラスチックのトレイを洗ってリサイクルに出したりと、1回の料理でも様々な場面でゴミを削減できます。
生ゴミは乾燥させて体積を減らしたり、畑にまいて堆肥として使ったりすることで、さらなるリデュースが期待できます。
加えて、整理整頓を心掛ける際に難しいのが「不用品の選別」です。
リデュースの観点においては、使えそうなものは直しながらなるべく長く使い、ものを大切に扱うことが大切です。
整理整頓を目指す際は「一年間使わないものは処分する」といわれることもありますが、やみくもに捨ててしまうのではなく、最後まで使い道を模索してみるのがおすすめです。
まとめ
私たち一人ひとりが心がけることで初めて意味を持つ「3R」。
その中でもっとも先に行うべきとされる「リデュース」は、今後の環境をより良くするために必要不可欠な考え方です。
意識しなくても生活に取り入れられるよう、具体例を元にリデュースのイメージを膨らませてみてはいかがでしょうか。
リフューズの意味は?具体例やメリットについて解説

地球温暖化など様々な環境破壊が進んでいる現代では、私たち一人ひとりが環境へ意識を向け、できることをしていかなければなりません。
中でも「3R」や「5R」などの考え方を抑えておくと、子どもから大人まで多くの方が分かりやすく環境問題に取り組めるでしょう。
今回はその中でも詳しく意味を知らない方も多い「Refuse(リフューズ)」について、意味や具体例を挙げながらご紹介します。
リフューズの考え方をスムーズに取り入れるために、自身の生活をイメージしながらチェックしていきましょう。
リフューズ(Refuse)とは?意味と基本的な考え方

「Refuse(リフューズ)」という単語は、直訳すると「拒否する」といった意味になります。
環境問題におけるリフューズは、そもそもゴミになるようなものを購入したり受け取ったりせず、家の中に不要なものを持ち込まないといった意味を持ちます。
捨てるかどうか悩むのではなく、そもそもゴミになるものが少ないため、家の中を綺麗に保ちやすいといったメリットがあります。
そもそもリフューズを含む「5R」と呼ばれる考え方は、それぞれの方法を用いてゴミを減らすためのものです。
燃やせるゴミは燃やす際に出る温室効果ガスが地球温暖化を促進してしまうことが問題視されており、燃やせないゴミは埋立地の不足や土壌の汚染などがリスクとして挙げられます。
リフューズの考え方を生活に取り入れることで、これらのゴミ問題を軽減し、長い目で見れば地球を守ることに繋がるでしょう。
リフューズ(Refuse)以外の5Rとは
最初はリデュース・リユース・リサイクルの頭文字をとって「3R」と呼ばれていた環境問題における行動指針ですが、近年は先ほど触れたリフューズに加え、リペアを追加した「5R」が最適だといわれています。
企業や団体が取り入れるのはもちろん、私たち個人が積極的に行動しなければ、地球全体の環境を変えることはできないでしょう。
5Rそれぞれの意味と行動を知り、意識せずともできるよう工夫してみてはいかがでしょうか。
リデュース(Reduce)
「Reduce(リデュース)」とは、ゴミの量を減らして地球環境を守るための考え方です。
ゴミになるものを買ったりもらったりしない、といった意味のリフューズと似ていますが、リデュースは無駄なものを買うのを控えるだけでなく、今あるものを限りあるまで使ったり、同じものを買う場合でもゴミが出ないように工夫したりといった考え方も含まれます。
例えば、新しいコスメが出るとついすぐに購入してしまい、まだ使えるはずだった古いコスメがゴミになってしまうこともあるのではないでしょうか。
流行に左右されず今あるものを使いきってから新しい製品を購入することも、立派なリデュースの取り組みです。
また、私たちの身の回りには常に食べ物が溢れているため、つい食べられる分以上の食材を購入して腐らせてしまったり、食べきれなかった分を生ゴミとして出してしまったりしがちです。
買い物の際は必要なものをメモに書いてから行ったり、食材を小分けにして冷凍することで作りすぎを防いだりと、リデュースの考え方を取り入れてみると良いでしょう。
リユース(Reuse)
「Reuse(リユース)」とは、今あるものを寿命が来るまで長く使うことで、結果としてゴミを減らすといった考え方です。
リデュースの際に触れた内容と一部重複する部分がありますが、不要になったものをすぐに捨てるのではなくフリマアプリに出品してみたり、汚れを拭き取るためにティッシュペーパーではなく布巾を使ったりする行動も当てはまります。
やむを得ずものを購入する際は、繰り返し使える寿命の長いものを選び、愛着が湧くまで大切に使いましょう。
近年はリユースショップも多数登場しており、不要なものを売るだけでなく、その中でまだ使えそうなものを購入しながら過ごすこともできます。
特に衣類や食器などは不用品として売られていることも多いため、新品を購入する前に一度チェックしてみてはいかがでしょうか。
リサイクル(Recycle)
5Rの中でもひときわ有名であり、子どもから大人まで多くの方が耳にしたことがあるであろう「Recycle(リサイクル」。
不要になったものを粉砕して別のものとして生まれ変わらせたり、ゴミを燃やす過程で出る熱を動力に発電したりといった行動が当てはまります。
ペットボトルや空き缶・空きビンなど、資源ゴミとして回収されるものはいずれも新たな姿に生まれ変わるために集められているのです。
私たちが出すゴミは燃えるゴミ・プラスチックゴミ・燃えないゴミ・資源ゴミなどに分けられていますが、これらは全て行き先が異なるため、しっかりと分別しなければなりません。
プラスチックゴミや資源ゴミに異なるものが含まれていると、正しくリサイクルができなくなるほか、機械の破損や事故に繋がる可能性もあります。
リペア(Repair)
5Rの最後として挙げられる「Repair(リペア)」は、壊れてしまったものや古くなったものを修繕しながら、なるべく長く使う行動を指します。
元々の価格が安価であればあるほど、私たちは修繕よりも買い直しを選んでしまいがちです。
新しいものが手軽に手に入る環境であれば、使用する上で問題がないものでも、ゴミ箱行きとなってしまうことが多いでしょう。
例えば、シミができてしまった洋服がある場合は、無事な部分を切り取って別の衣類へと生まれ変わらせてみるのはいかがでしょうか。
専門のリペア職人がいる製品であれば良いですが、接着剤などを使って自力で直せるものもたくさんあります。
自分で直しながら使うことで愛着が湧きやすくなり、長年一つのものを大切に使うことに繋がります。
関連記事:グレートリセットがもたらす変革とは?経済・環境・社会の未来
リフューズ(Refuse)は断ること!断るためにできること

環境を守るために必要となる5Rの活動指針の中で、もっともスタートに適しているのがリフューズです。
「ゴミを減らす」という目的において、ゴミとなる可能性の高いものを手に取らず、「捨てる」という行為を減らすことができるでしょう。
まずはリフューズについてなかなかイメージができない方のために、具体的にできる対策を3種類ピックアップしてご紹介します。
1.必要のないものをもらわない・買わない
リフューズの考え方を生活に活かす際は、第一に「ものを増やさない」ことが大切です。
家族や友人などから使わなくなったものをもらう機会の多い方や、つい不要なものまで衝動買いしてしまう方は特に注意しましょう。
家に持ち込むものの数を減らすことで、結果としてゴミの数を減らすことに繋がります。
2.マイボトルを持ち歩く
気温の上がりやすい夏場はもちろん、冬であっても水分補給は欠かせません。
中には毎日のように使い捨て容器の飲料を購入している方も多いのではないでしょうか。
1年間毎日購入すると単純計算で365杯分のゴミが出ることとなります。
たった1人分のゴミだとはいえ、365個もの容器が積み重なっているのを想像すると、思ったよりも多いと感じるはずです。
リフューズの考え方を取り入れる際は、日々の水分補給をマイボトルに変え、1日に出るゴミを減らすことも大切です。
家でお茶を入れていくのはもちろん、コーヒーショップでドリンクをオーダーしても良いでしょう。
中にはマイボトルを持参するとポイントが貯まったり、数%引きになるなどのキャンペーンをやっていたりするショップも見られます。
3.マイバッグの持参
普段スーパーなどで買い物をする際、レジ袋の購入を断ってマイバッグへ入れるようになったという方も多いのではないでしょうか。
日本では2020年7月よりレジ袋が有料化され、プラスチック製品の削減に向けて大きな一歩を踏み出しました。
1枚あたり数円の費用が加算されるため、マイバッグを使うことで単純な節約にもなるでしょう。
近年は優れたマイバッグが多数登場しており、ワンタッチで畳めるものや抗菌作用のあるもの・買い物カゴに装着できるものなど様々な製品が見られます。
コンビニ用・スーパー用など、用途によって複数のマイバッグを用意しておくのもおすすめです。
リフューズ(Refuse)のメリット

従来の3Rに追加される形となったリフューズですが、まだまだ広く知れ渡っているとはいえません。
リフューズの考えを生活に活かすとどんなメリットがあるのか、メインとなる2つの点に絞ってご紹介します。
1.ごみの削減
私たちの生活は常に新たなものを入手し、使用してからゴミに出すといった繰り返しで成り立っています。
ものの種類によって、長く使えたり一瞬でゴミになったりと様々な運命を辿りますが、行きつく先はほぼ全てがゴミとなるでしょう。
リフューズの考え方を取り入れることで、使用する→ゴミになるといった繰り返しに加わるものの数が減り、結果としてゴミの削減に繋がります。
家の中がものでいっぱいになることがなく、整理整頓がしやすいのもメリットといえるでしょう。
近年話題の「ミニマリスト」なども、生活に必要なものを見極め、最低限のもので暮らすというリフューズを実現しているといえます。
2.節約につながる
リフューズは「人から不要なものをもらわない」といった行動だけでなく、自分で不要なものを購入しないといった意味も含んでいます。
買い物に出かける際は購入品リストを作るなど、目についたものをカゴに入れてしまわないように注意すると良いでしょう。
不要なものを購入することが減れば、余計な出費を抑えられ、家計の助けになるのもメリットの一つです。
近年は物価の高騰が留まるところを知らず、一般家庭にも大きな打撃となっています。
特に家計の多くを占める食費や日用品費を少しでも節約すべく、家族みんなでリフューズの考えを心に留めてみてはいかがでしょうか。
関連記事:掃除がメンタルヘルスに与える影響とは?心も部屋もスッキリさせる方法
まとめ
地球全体のことだと広く考えるのではなく、私たち一人ひとりが意識をして変えていかなければならない環境問題。
近年5Rに加わった「リフューズ」もまた、私たちが長く地球で暮らすために必要な考え方だといえます。
無意識のうちに5Rの考えを生活に活かせるようになるためにも、まずはリフューズから意識していきましょう。
自然と共存して生きること。ドキュメンタリー映画『ビッグ・リトル・ファーム』 レビュー

Humming編集部からお届けする映画レビュー。今回ご紹介するのは、世界中の映画祭で観客賞を受賞したドキュメンタリー映画『ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方』。この映画から私が得た気づきや感動を共有します。
ジョンとモリーは、カリフォルニア州サンタモニカの小さなアパートに住む若い夫婦。彼らには、「伝統的な方法で作物を育てる農場を持ちたい」という大きな夢がありました。シェフであるモリーは、栄養豊富な食材を育てる鍵は土壌にあると気がついたからです。個人で農場を持つという夢は遠く感じられるものの、状況を一変させたのは、トッドという犬との出会いでした。
トッドはよく吠える犬で、ジョンとモリーは騒音による苦情を受け、アパートを退去せざるを得なくなりました。新たな住まいを探している中、彼らは荒れ果てた234エーカー(東京ドーム約17個分)の農場に出会います。ここから、彼らの新しい物語が始まるのです。
このドキュメンタリーを見て、私は地球の持つ驚異的な回復力と自然の仕組みの精巧さに圧倒されました。たとえば、鶏がコヨーテに襲われた際、農場の犬が自然と鶏を守るようになり、コヨーテはゴーファー(ジリス)という害獣を駆除する存在へと変わっていきます。また、果樹が豊かになると、大量のカタツムリの発生に悩まされましたが、調査を進めるうちに、鶏がカタツムリを好んで食べることを発見。作物が害虫の被害にあった際も、化学薬品に頼らず、テントウムシが害虫を食べてくれるのをじっと待つ。自然のプロセスに耳を傾けて尊重することで、すべての問題が解決されていったのです。
農業に関する知識がほとんどなかったジョンとモリーに「自然の調和を信じて、忍耐強く見守ること」を教えてくれたのは、アランという農夫です。彼は自然の美しさを詩的に語る人で、「自然の調和を信じ、忍耐強く見守ることで、『共存の繊細なダンス』が始まり、命が互いに支え合う網の目が形成される。この過程は10億年以上にわたって続いている」と教えてくれました。アランの話を最初は半信半疑で聞いていたジョンは、時が経つにつれ、アランが語った内容が現実となっていく様子を目の当たりにするのです。
アランが癌で亡くなったり、彼らが大切に育てていた鶏がコヨーテに食べられたり、この物語は「死」についても描かれています。死んだ鶏を手に取ったジョンは、悲しみと苛立ちの中で「意思だけでは(問題を)解決できない」と語ります。しかし、自然界は弱肉強食の世界。生き残るために命をかけて狩りをする姿を、責めることはできません。
「シンプルであることは、必ずしも簡単ではない」「失敗から得られる小さな気づきが、生態系を作り上げるエンジンになる」とジョンは言います。数々の困難に直面しながらも、彼らは自然の力を信じ続け、多様な生き物たちが共存できる自然の生態系を築き上げました。多様な生き物の中にはきっと私たち人間も含まれているでしょう。

ジョンとモリーが農場で仲間を増やしていったように、私たちも夢や目標に向かって一歩踏み出すことで、同じ志を持つ人々と出会い、互いに影響しながら成長していくのだと思います。自然界では生態系。人間界ではコミュニティ。それらを築いていくことは、世界をより良くするために必要不可欠だと強く感じました。このドキュメンタリーには、農場の外での出来事はあまり描かれていません。欲を言えば、予算が底をついた時にどのように資金を調達したのか、農場の卵が市場で大ヒットした時に彼らの想いがどのように広がっていったのか、人間が創りだすコミュニティについてももっと知りたかったです。
この映画を通して、地球がどのように機能しているのか、また調和と混沌が共存する自然の美しさを垣間見れた気がします。私たちは飽食の時代に生き、便利さを追い求めるあまり、ファストフードや加工食品に頼りがちです。しかし、これからは自然の中で育った食材を味わう喜びをもっと感じたいと思いました。また、失敗を繰り返しても諦めず、理想の農場を追い続けるジョンとモリーの姿勢に、深く心を打たれました。
現在、ジョンとモリーが作ったアプリコット・レーン・ファームは繁栄し、自然の生態系について学べるツアーも行っているとのことです。「自然と調和して生きるということは、自然の不快さとともに生きるということだ」とジョンが映画の終わりに語った言葉は、人生そのものを象徴するメッセージだと感じました。
映画を見たい方はこちら
掃除がメンタルヘルスに与える影響とは?心も部屋もスッキリさせる方法

なんか上手くいかない、何をやってもダメ。
悪いことが起こったというわけではないのに、どこか鬱々と気分が晴れない。
そう感じること、たまにありますよね。
そんなときは、一旦落ち着いて自分の周りを見渡してみましょう。
あなたの周り、ちょっと散らかっていたりしませんか?
実は身を置いている環境が片づいていないこと自体が、メンタルにも悪影響を及ぼすことがあるのです。
今回はそんな掃除とメンタルヘルスの関係、そして上手く習慣化させるコツについて紹介していきたいと思います。
掃除すると心も晴れる?
みなさんは、こんな経験ありませんか?
面倒だと思って嫌々はじめた掃除も、途中から楽しくなって「ここもあそこも!」と時間を忘れて没頭してしまうこと。
そして、ひと通り終えてピカピカになった部屋を見渡して、とても清々しく明るい気持ちになったこと。
理由を聞かれても上手く答えられないけど、掃除するととにかくスッキリ前向きな気持ちになる。
誰しも一度は、そんな経験をしたことがあると思います。
筆者もその一人です。
元々、細かいところまで考えすぎるタイプで、そのぶん落ち込みやすい性格なのですが、それを差し引いてもメンタルがずーんと沈みすぎていると感じることがありました。
どんよりした気分でうつむきながら歩く、仕事からの帰り道。
「なんで全部上手くいかないんだろう」
「あれもこれも気になるし、毎日ストレスだらけ」
「周りは十分やってるとか言ってくれるけど、何も出来てないのに…どこが?」
「絶対気を遣われてるだけじゃん…ああもうこの捻くれた性格も嫌になる!」
そんな独り言が頭を駆け巡り、メンタルはネガティブまっしぐら。
今にも泣きそうな顔で家に帰り、真っ暗な部屋の電気を点けたときのことです。
目に飛び込んできたのは、恐ろしく散らかった自分の部屋でした。
ベッドの上に勢いよく脱ぎ捨てられたパジャマ。
冷ます時間がなく、勢いよく床に投げ捨てられたヘアアイロン。
テーブルにはそのままの朝ごはんの食器と、飲みきれなかったコーヒーでくっきり茶渋がついたマグカップ。
当然、昨晩畳むのを後回しにした洗濯の山もそのままです。
仕事着を取り出すのに邪魔だったから、クローゼットの前からベッドの上に場所が変わっているだけ。
泥棒が入ったようなとまではいかないけれど、朝、ドタバタ身支度に走り回った自分がそこに蘇ってくる散らかりようでした。
そして思ったんです。
「分かった、まずこれだ」って。
ただでさえざわついてる心が、部屋を見た瞬間、さらにぞわっとしたから。
まずこのめちゃくちゃな空間を整えないことには、自分の心だってどうにもならないと悟ったのです。
そして地道に一つずつ片づけはじめると、このめちゃくちゃは朝だけのことじゃないとも気づくのです。
食器を下げにシンクに持っていくと、昨晩飲んだ水のグラスも洗っていなかったことに気づく。
ヘアアイロンを拾おうとすると、昨晩のドライヤーで抜けまくった髪の毛が床に散らばっていることに気づく。
洗濯物を畳んで片づけようとすれば、下着もパジャマもあと1セットしかない状態だったことに気づく。
アイロンをかけないといけない服が溜まっていることにも気づく。
だから仕事に着ていける服がなかったんだと気づく。
さらに部屋を見渡せば、あちこちに読みかけの本が置かれ、「何か」やった気になろうとノートやペンで作業した痕跡もそのままになっていることに気づく。
小さなことが全く整っていなかったことに、次々と気づいていったのです。
どちらかといえば綺麗好きなほうなのに、ここまでめちゃくちゃになっていることに気づいてすらいなかったことが衝撃すぎて、そこからは一心不乱に片づけに取り掛かりました。
片っ端から部屋を整える間、帰宅中に浮かんでいたような独り言は1ミリも顔をのぞかせませんでした。
代わりに、ようやく片づけ終わった瞬間には、清々しさと心地よい疲れに加え、ちょっぴり自信もこみあげてきました。
それ以来、メンタルが沈み、考え込んでしまいそうなときは、まず部屋の掃除をするように意識しはじめました。
目に見える汚れがなければ、普段はしない一歩踏み込んだ掃除をしてみる。
掃除中は余計な考えごとが浮かばないし、何より達成感があって終わると少し気分も上向く。
そんな経験を何度かしたことで、すっかり掃除が私のメンタル回復方法の一つになったのです。

掃除がメンタルにもたらす効果
私たちが経験則で感じているこの掃除とメンタルの関係、実は科学的にも証明されています。
では、具体的に掃除がメンタルにもたらす良い影響には、どんなものがあるのでしょうか?
ストレスが減る
先ほどの筆者の経験談のように、散らかっている部屋に心を乱されるというのは、実は科学的にも関連性が証明されています。
心理学の論文では、家が散らかっていると感じている人は、気分が落ち込みやすく、ストレスに応じて分泌される「コルチゾール」も増加すると発表されているんです。
逆に言えば、ただ片づける、掃除するというだけでもストレスは減らせるということですね。
幸せホルモンが分泌される
掃除の中でも特に、床を拭いたり、窓を磨いたりといった単純な反復作業で、幸せホルモンの「セロトニン」が分泌されることも分かっています。
セロトニンは脳の興奮を鎮静させ、気持ちをリラックスさせる効果があるので、淡々と掃除するうちに、イライラや不安感も落ち着いてくるわけです。
自己肯定感が上がる
整理整頓された部屋は、なんとなく明るくなった感じもして、気持ちも前向きになります。
そして何より、黙々と掃除を終えて、綺麗になった部屋を見渡すときって「よし、やりきったぞ!」という達成感も感じますよね。
こうした達成感は自己肯定感を高め、家族や友達など周囲との人間関係も上向いていきます。
実際、毎日の掃除の習慣は、精神療法としても効果が高いと言われています。
生産性や効率が上がる
周囲に物があふれていたり、雑多な環境に身を置くと、なんとなく日々の行動や意思決定も適当になっていくもの。
「ちょっとくらい」とか「明日でいいや」とか、小さな言い訳が増え、ついだらけてしまいます。
筆者の場合、ストレッチやトレーニングを習慣にしたくても、十分なスペースがないことを言い訳に先延ばししてしまうことがあります。
また、スペースがあったとしても、ヨガマットなど道具を探すのに時間がかかれば、その間にやる気は下がっていくもの。
仕事術なんかでも、よく、デスクを片付けるだけで生産性や効率がアップするなんて言われます。
それは片付いていれば、必要なものがすぐに取り出せ、やりたいことにすぐ取り掛かれるからですよね。
このように、掃除には私たちの心や行動にさまざまなメリットをもたらしてくれるのです。

機嫌を取り戻すお掃除のコツ
はじめてしまえば、芋づる式に良い効果がもたらされると分かっても、最初は掃除に取り掛かること自体面倒かもしれません。
そこで最後に、筆者が普段どのように「メンタルケアの一環としての掃除」を習慣化しているかをご紹介したいと思います。
大前提として、筆者は特別掃除が好きというわけではなく、基本は「掃除、面倒だな~」と取り掛かるまで時間がかかるタイプです。
なので、意識高く、頑張ってやるというようなものはないのでご安心ください。
毎日のちょっとした掃除
この掃除は「自己肯定感を下げない」ための習慣です。
筆者は、昔から髪の毛が良く抜けるタイプで、ドライヤー1回でもかなりの量が床に散らばります。
仕事から帰ってきて、部屋や脱衣所などあちこちに髪の毛が落ちていると、それだけでもげんなりしてしまいます。
なので、これだけはできるだけ毎日掃除するようにしています。
例えば、朝の身支度が終わったあと、ササッと掃除機かカーペットクリーナーをかける。
本当はドライヤーを済ませた後、つまり汚した直後にやるほうがスムーズだし時間にも余裕がありますが、やる気が出ないので朝に定着しました。
一人暮らしの狭い部屋なので、ものの3~5分程度で終わります。
なのに、それだけで帰ってきたときの気持ちが全然違うのです。
掃除したことでご機嫌になるというよりは、帰ってきたときにげんなりしないためなので「自己肯定感を下げない」ための掃除と位置付けています。
とはいえ、それでも時間の余裕がない日は、スパッと諦めます。
「帰ってきたときの自分のために!」とドタバタしてまでやったところで、結局心がざわざわしたまま家を出ることになり、一日の始まりのご機嫌を損ねるという逆効果になりかねません。
帰ってきて散らかっている髪の毛に一瞬げんなりはしますが、心の準備があるのでそこまでメンタルダウンすることはありません。
「まあそういう日もあるよね」と思いながら、簡単にそのまま掃除するか、潔く翌朝の自分に託しています。
週末のイッキ掃除
こちらは「自己肯定感上げるため」の掃除習慣です。
今さらなことを言いますが、家ってすぐ散らかるしすぐ汚れますよね。
埃はすぐ溜まるし、洗濯物もすぐ溜まるし、洗面台はすぐに水垢がつくし、トイレの便器はすぐ黒ずみます。
「え?こないだ掃除したのに?」と思うことが1週間に何度あることか。
でも筆者の場合、平日はなかなか時間が取れないので、見て見ぬふりをして、土日などに一気に家全体の掃除をするようにしています。
もしくは、平日でも少し余裕があれば1~2カ所だけでもまとめてガーッと掃除します。
ある程度の時間をとって、お気に入りの音楽やラジオをタイマー代わりにしながら、集中してピカピカに磨き上げる。
掃除がメンタルにもたらす効果のパートでもありましたが、確かに淡々と単純作業することで、気持ちもだんだん落ち着いてきますし、終わった後には心地よい疲れと達成感が味わえるんですよね。
たまに1日1ヵ所掃除すれば、無理なくずっとお家を綺麗に保てるという話もありますが、筆者の性格には合いませんでした。
例えば食器洗いにしても、コップ1個でも毎回洗って、常にシンクに何もない状態にするより、1日分溜めた食器を「よし!」と気合を入れ、片っ端から洗いあげるほうが好きです。
掃除や食器洗いがご褒美になるなんて、字面では考えづらいですが、日々の暮らしの中でそれを無意識に実感している人も多いのではないでしょうか。
掃除は「ルール」ではなくご機嫌を取るため
掃除タイプを2種類に分けて考えている筆者ですが、何よりもまず大事にしている考え方があります。
それは「ルール」にしないこと。
毎朝のササッと掃除も、週末のイッキ掃除も、あくまで自分の性格やライフスタイルには、そういう掃除の仕方が合っていると認識しているだけで「必須」とは思っていません。
忙しいとか気力がわかないとかで、1週間朝の掃除をさぼってしまうことも、週末に予定が続いて、気づいたら1ヶ月掃除できていないことだってあります。
それぞれの掃除を「ルール」にしていたら、今日も出来なかった、今週も出来なかったと自分を責めてしまいかねません。
そうではなく、掃除はあくまでご機嫌を取り戻すための手段。
そう考えておくと、日々汚れや散らかった部屋が目に飛び込んできても「そりゃメンタルも沈むよな…」と冷静に判断できますし、「忙しいけど、悪い流れを断ち切るために、この日だけは掃除デーにしよう」と戦略的にもなれます。
真面目な人ほど、ちゃんとしようと「ルール」にしてしまいがちです。
でもそのルールに縛られ、振り回されては本末転倒。
そうではなく、掃除の主導権はあなたが握ること。
ちなみに、そうは言っても汚れが気になるのに掃除ができなくて発狂しそうという人には、おすすめの回避法があります。
それは、視力が低い人限定になりますが、汚れが目立つところでは眼鏡やコンタクトを外してしまうこと。
当然ですが、そうすると髪の毛や部屋の隅の埃は一切見えなくなりますよね。
そもそも見えなければ、気にすることもなくなるという理論です。
実はこれ、昔どこかでたまたま聞いた年配の方のアドバイスの受け売りで、その方は「細かい汚れまで気にするほど残りの人生は長くない、だから掃除のときは眼鏡を外す」のだそう。
ふざけて聞こえるかもしれませんが、こういうクスッと笑える発想の転換で、普段頑張りすぎている自分を緩めるのは結構おすすめですよ。
まとめ
掃除というと面倒でやらなくていいに越したことはないことかもしれませんが、掃除で心もスッキリすると意識的に感じられるようになれば、少しずつ億劫な気持ちは小さくなっていくはずです。
じっとしたまま心のモヤモヤについて考えを巡らすと、それは不用意に膨らみかねません。
それよりも体を動かしながら、そのモヤモヤを目の前のゴミなどに投影して、物理的に掃除してしまえば、意外とすぐ心は晴れてくるかもしれませんよ。
無理のない範囲で、自分に合ったご機嫌お掃除方法を見つけてみてくださいね。
理想のひとり旅プラン。体も心も「私だけの時間」を求めて

家事や育児に仕事。目まぐるしい毎日。そんな私が夢見る、ちょっとわがままな2泊3日のひとり旅。
はたして理想のひとり旅は実現できるのか。そして、その先に待っているものとは……。日常から少し離れて、自分らしさを取り戻す旅の計画を一緒に想像してみませんか?
日常に埋もれる「私の時間」
結婚し、子どもを産み、育児に家事に仕事に、毎日が目まぐるしく過ぎていきます。
私にとってひとりの時間はとても大切。ひとりになれない日が続くと、心がざわついてイライラしがちになることも。
だからこそ、子どもたちがいない平日の昼間にジムに通ったり、単身赴任中の夫が帰国した際には夜の街に繰り出してバーでビールを飲んでみたり、定期的に自分だけの時間を作るように心がけています。
とはいえ、そんな「ひとり時間」にも、常に何かが付きまといます。ジムでトレーニング中も「もうすぐ子どもの帰宅時間だ」と時計を気にしたり、スマホの通知音に反応して「仕事の連絡かも」と慌てたり。頭の中には、やるべきことリストがテロップのように流れ続けているようです。
どれだけひとりの時間を確保しても、心はいつもソワソワ。果たして、これが本当の意味での「ひとりの時間」と言えるのでしょうか。
家族のこと、家のこと、仕事のこと、一旦全てを忘れて、完全に自分の世界に没頭できる時間を欲している自分に気がつきました。
そんな時、ふと頭をよぎったのが「ひとり旅」です。
2泊3日から挑戦したい、憧れのひとり旅
日々の喧騒から少し離れた場所で、ひたすら自分の好きなことに集中する時間を味わいたい。今の私が惹かれているのは、韓国への2泊3日のひとり旅です。
国内ではなく、飛行機に乗って異国の地に降り立つことで、物理的にも精神的にも日常から解放される気がします。また、休日+平日1日の日程なら、そこまで罪悪感を感じずに仕事を休めるし、子どもの学校のスケジュールを気にする必要もありません。
旅のプランは、あえてゆったりと。少しだけ奮発してちょっとおしゃれなホテルに宿泊。ホテルで朝食を堪能し、そのあとはゆっくりと部屋の湯船に浸かりながら、気になっていた本を誰にも邪魔されずに読み進める。お昼過ぎには街に繰り出し、垢すりで体を整えてから買い物を楽しむ。夜は地元の人たちが集う居酒屋でマッコリを味わって再びホテルへ。ホテルの部屋では、お酒を片手に読書したり、思いを文章にしてみたり。翌日は美容クリニックで気になっていた施術を受け、お土産を買って子どもたちの待つ家に帰る。
想像するだけで、思わず頬が緩みます。
ひとり旅、しかも海外。もちろん不安がないわけではありません。
いつも夫に頼りっぱなしの飛行機やホテルの予約。自分で問題なくできるだろうか?
街中で迷子になったらどうしよう?
言葉の壁は乗り越えられるだろうか?
ひとりになりたいと思いつつも、子どもたちに会えない寂しさや仕事をしないことへの不安が押し寄せてくるかもしれない。
もしかしたら、「家族や友達と一緒に行くべきだった」と後悔するかもしれない。
けれど、全てはやってみなければわからないこと。だからこそ、私は今、ひとり旅に挑戦してみたいと思っています。

ひとり旅で出会えるかもしれない新たな自分
ひとり旅には、日常を離れることで得られる大切な気づきがあるかもしれません。家族や仕事から少し距離を置いて、静かな場所で過ごしたり、知らない街を歩くことで、忙しい日々の喧騒から解放され、自分自身と向き合う時間が生まれるでしょう。
また、ひとり旅では、小さなことから大きなことまで、すべての決断を自分でしなければなりません。どこに行くか、何を食べるか……。その過程で、普段は見過ごしがちな自分の好みや価値観に気づくこともあるでしょう。
そして何より、不安や戸惑いを乗り越えて旅を終えた時には、「私にもできた」という達成感を味わえるのではないでしょうか。ひとり旅の経験は、日常に戻ってからも新たな挑戦への原動力となるかもしれません。
今、この瞬間を大切に
「子どもが大きくなったら、自分の時間はいくらでもできるじゃない」
確かに、そうかもしれません。しかし、今だからこそ感じられること、味わえることがきっとあるはずです。人生は思っているよりも短いかもしれないし、明日何が起こるかは誰にもわからない。だからこそ、やりたいことは先送りせず、近い未来に実現させたいなと。
「時間ができたら」
「お金がたまったら」
「自信が持てたら」
できない言い訳を繰り返していては、チャンスは永遠に訪れないかもしれません。
莫大な費用が必要だったり、誰かを傷つけたりすることでなければ、やりたいことは全てやりたい。最近そんな風に思います。なぜなら、経験したことは必ず自分の糧になると思うからです。
また、私が自分のやりたいことをやって楽しく過ごすことで、「人生は楽しいよ」「自分の好きなことをたくさんやって良いんだよ」、そんなことを子どもたちに伝えていけたら良いなとも思います。
夫の単身赴任が終わったら、私はひとり旅に挑戦する!「いつか」ではなく、2026年までに必ず実現させようと思います。無理やりスケジュールをこじ開けて、予約をしてしまえば、あとは行くしか選択肢はありません。
あなたは、どんな場所にひとりで旅してみたいですか?
瞑想はとっつきにくい?初心者の私が実感した無理なく始めて続けるコツ

いろんなことが目まぐるしく変わる時代。
心配ごとは次から次へ増えるし、とにかくストレスだらけの現代社会ですよね。
そんなときは「瞑想」が良いとは最近よく聞きますが、まったくの初心者だとちょっととっつきにくい部分があるのも本音ではないでしょうか。
今回はそんな初心者におすすめの「瞑想」のはじめ方、そして続け方のコツを筆者自身の体験を交えてご紹介します。
瞑想は正直ハードルが高い
瞑想には集中力を高めたり、ストレスを緩和したりと様々な効果があります。
これは決して精神論ではなく、実は瞑想は科学的根拠に基づいたものだということをご存知でしょうか?
実際、瞑想で勉強やスポーツの成績が向上したことを報告する研究もいくつかあるのです。
また、医療現場ではれっきとした治療法として活用されていたりと、海外では特に瞑想が身近で一般的な存在になっています。
最近は日本でも「瞑想」ということば自体はよく聞きますし、著名人やアスリートでも取り入れているという人は増えていますよね。
ただ、そうは言っても、まだまだ心理的ハードルが高いというのも、正直なところではないでしょうか?
まったく触れたことがない人にとっては、宗教っぽい、スピリチュアルっぽい、なんだか怪しいなど、とっつきにくさが拭えないかもしれません。
そもそも日本人にとっては宗教や信仰というもの自体、普段からあまり馴染みがないため、そういうを感じただけで反射的にブロックしてしまうのも無理もないことでしょう。
また、仮にそうした心理的ハードルを越えられたとしても、今度は意外と継続が難しいというケースもあるでしょう。
当サイト含め、ネットで検索すれば、瞑想のやり方を解説している記事はたくさんヒットします。
どの記事でも手順はおおむね同じ。
静かな場所であぐらをかいて目を瞑り、呼吸や自分の内側に集中するという、とてもシンプルなものです。
でもやってみると、シンプルなわりに継続は意外と難しいのです。
数回チャレンジしてみて少し良いかもと思ったものの、気づいたら習慣からフェードアウトしている。
筆者自身、そんな経験を何度もしてきました。
1,2回しただけでは効果を実感しないという意味では、瞑想は筋トレと似ています。
ただ筋トレと異なるのは、外見など何か目に見える変化が現れるのではなく、自分の感じ方や考え方といった内面が少しずつ変化していく点です。
瞑想がもたらしてくれる変化は、注意深く意識していないと見逃してしまうこともあります。
変化が感じられないことを、脳が意識の外に追い出してしまうのは自然なことですよね。
なんなら目に見えて変化が出る筋トレですら、それを感じる前に心が折れて辞めてしまう人も多いわけですから、目に見えた変化を感じにくい瞑想が続かないというのも、おかしなことではないでしょう。
とはいえ、メンタルが揺らぎやすい筆者は、この状況を変えるべく、どうにか瞑想を習慣にしようと何度もトライしつづけてきました。
辞めては再開してのサイクルを繰り返すなかで、だんだんと続けるコツや考え方が見えてきたので、同じような状況の方の参考になればと思いシェアしてみます。

☞メディテーションの意味とは?瞑想やマインドフルネスとの違いは?
瞑想へのハードルを下げるコツ
まず筆者は、一旦「瞑想」という概念そのものから離れてみました。
今から自分は「瞑想」をするのではなく「深呼吸の練習」をするのだと、ことばを変えてみたのです。
「瞑想」にハードルを感じるのであれば、そもそも「瞑想」だと思わなければハードルはグッと下がると思いませんか?
とんちのように聞こえるかもしれませんが、筆者の場合これが意外とハマりました。
呼吸については、瞑想に関する記事でもよく言及されるので、捉え方の違いが分からないと感じるかもしれません。
でもそういった記事の文脈では、あくまで「瞑想の中の呼吸」という位置づけですよね。
そうではなく、本当にただ純粋に「呼吸」だけにフォーカスする。
自分の行為が瞑想かどうかは一旦置いておいて、とにかく自分がどれだけ呼吸できているかに意識を向けるだけ。
「呼吸なんて無意識にしてるでしょ」と思うかもしれません。
ですが、実はしっかり呼吸できていないことって、結構あるのです。
特に現代人はストレスで呼吸が浅くなっていたり、強い緊張を感じたときは、無意識に数秒間息を止めていることすらあります。
でもご存じのとおり、呼吸は生きていくうえで無くてはならないものです。
浅い呼吸だと十分に酸素を体に取り込めず、いつまでも交感神経が優位になってリラックスできず、血圧も上がりやすくなってしまいます。
逆に言えば、しっかり深い呼吸ができれば、それだけで心や体の調子を少し上向けることができる。
たかが呼吸、されど呼吸なのです。
一度、仕事中など、普段の何気ない瞬間に自分の呼吸がどうなっているか意識してみてください。
「深呼吸の練習」の必要性を実感する場面が、きっとあると思います。
そして何より「瞑想」より、単なる「深呼吸の練習」のほうが、心理的ハードルも低く感じられませんか?
それは「深呼吸」であれば、私たちはすでに取り入れたことがあるからです。
人前で話すときの緊張をほぐす深呼吸、遅刻しないよう猛ダッシュしたあとに息を整える深呼吸、イラっとしたときに冷静さを取り戻す深呼吸。
誰しもどれか一つはやったことがありますよね。
ストレスを上手く解消する手段として、日々の呼吸に意識を向ける。
そう捉え方を変えただけでも、筆者の場合は何か小さなステップを乗り越えた感じがしました。
気持ちの問題といえばそれまでですが、習慣化のためにいかに脳を上手く騙すかも大事なコツの一つです。

「深呼吸の練習」を習慣にするコツ
心理的ハードルが下がったら、次の課題は「継続」でしたよね。
ここでは現時点での筆者の考えるベストアンサーを紹介します。
まずは就寝前から始めてみる
まず、深呼吸の練習を始めるのに一番おすすめのタイミングは夜、できれば就寝直前です。
朝の活動前や、仕事の休憩中などちょっとしたスキマ時間でももちろん出来ますが、慣れないうちはどうしても、その後にやらなければならないことなど、あれこれ考えごとが浮かんできます。
その点、就寝直前なら、あとはもう寝るだけ。
やることが残っていない状態のほうがスムーズなので、入浴や歯磨き、スキンケアやストレッチなど、寝る前のルーティーンを全て終え、布団に入ってしまってからが特におすすめです。
横になって全身リラックスして、頭の中で数を数えながら、ただただ深呼吸を繰り返す。
最初はアプリなどのガイドに合わせて行うと、より集中しやすいでしょう。
☞おすすめのアプリ
就寝直前に布団の中で行うことの、もう一つのメリットは考えごと防止です。
夜は何か一つ考えごとが浮かぶと、それがあっという間にネガティブな方向に膨らんでいくもの。
その最初の考えごとすら浮かぶ前に深呼吸に集中することで、不安の渦に飲み込まれて寝付けなくなることを防いでくれます。
自分に合ったスタイルを見つける
と言ったものの、ライフスタイルは人の数だけ存在するので、必ずしも全員にとって就寝直前がベストタイミングとは限りません。
朝、家族全員を送り出したあとのほうが頭も心もスッキリしている、あるいはお昼休みに使う公園のベンチが結構リラックススポットという人もいるかもしれません。
大切なのは自分にとって一番続けやすいタイミングや場所、シチュエーションを見つけることです。
ツールに関しても同じことが言えます。
「瞑想アプリ」をインストールすることで結局またハードルを感じてしまうなら、リラックスできるBGMを小さく流しておくのでもいいでしょう。
筆者も先ほど紹介したようなアプリのガイドを活用していますが、日によっては音声が少し邪魔だなと思ったり、なんとなくペースが合わないと感じられたりもします。
そんなときはガイド音声なしのBGMだけにしたり、お気に入りのプレイリストをタイマー付きで流したり、まったく何も流さず頭の中だけで深呼吸したりと、その日の自分に合わせてスタイルを変えています。
習慣=毎日という思い込みを捨てる
継続、習慣ということばからは、どうしても「毎日やること」をイメージしますよね。
でも例えば、週1回しかジムに行ってなくても、それを何年も続けているならそれは立派な「習慣」といえますよね?
深呼吸の練習も、瞑想も同じです。
まずは心からリラックスできる、金曜の夜から取り入れてみるでもいい。
不定期でも、とにかく気がついたら深呼吸するでもいい。
極端なことを言えば、筆者みたいに辞めては再開しての繰り返しでも、継続していると言えると思っています。
眠れない夜が続けば「そうだ、最近深呼吸の練習サボっていたからだ」と思い出せるくらいには、十分頭と体に染みついているからです。
もちろん、アプリやカレンダーでリマインダーを設定して、毎日継続できることに越したことはありません。
ただそれで苦しくなったり、ストレスを感じたりしては本末転倒ですよね。
どれだけ健康によいことでも、義務に感じた途端、やる気を失うのは当然のことです。
もっとやりたいと思ったら毎日やってみる、逆に何年やっても毎日は無理と思うならやらない。
それくらいで十分です。
まずは気づいたときだけでもOKと自分に許可を出してあげて、ゆるく取り入れるほうが、結局スムーズに習慣化できるものです。

「深呼吸」を意識してみて感じた変化
最後に、とにかくゆるく細長く「深呼吸」や「瞑想」を続けてきた筆者が、少しずつ感じている変化にも触れておきます。
考えごとに飲まれることが減った
筆者は常に考えごとが絶え間なく湧き上がってくるタイプ。
考えごとには最悪のタイミングだといわれる夜は、むしろ一番考えごとをしてしまう時間で、見事に不安の渦に飲まれて眠れなくなるというのがデフォルトでした。
でも、ベッドに入った瞬間に「深呼吸の練習」をするというのを何日か続けると、そのままスムーズに入眠できる日が増えてきました。
始めたばかりは特にやり方がまだ身についていないので、自然とアプリのガイド音声に集中し、その時点で考えごとは強制終了されていたのです。
何度かそういう経験をすると、体や脳も慣れるのか、アプリを使わなくても数回深呼吸しただけで、フッと寝落ちすることもありました。
もちろん、いつも完璧にできるわけではなく、ガイド音声に慣れるとそちらに意識が向きにくくなったり、ストレスが重なった日は考えごとが我慢できなかったりと、気づいたらガイドが終わっていたという日もあります。
それでも「呼吸で考えごとの沼から脱出できる」という成功体験は記憶に残っているので、日中イラっとしたときも、まずは深呼吸してみようという、ある種のお守りを手に入れた感覚があります。
瞑想へのハードルが低くなった
「瞑想」ではなく「深呼吸の練習」という、より身近でとっつきやすい形に変換した結果、習慣としても馴染みやすくなったというのは、ここまででなんとなくお分かりいただけたかと思います。
ただ、予想外だったのが「深呼吸の練習」を続けた結果、とっつきにくさを感じていたはずの「瞑想」にも興味が出てきたことです。
以前は、自分の内面に集中するというのも、考えごとをそのままにして受け入れるのも、なんだかピンときていませんでした。
ましてや数十分も瞑想するなんて絶対無理だし、別世界の話だと思っていました。
でも「深呼吸の練習」をしてみると、意外と時間はすぐに経つし、もしかしたら思っているほどは難しくないのではと思えてきたのです。
しかも今は「就寝前の深呼吸で、気持ちよく入眠できる」くらいの効果ですが、もしもっと踏み込んで「瞑想」ができれば、根本にあるメンタルの揺らぎやすさも、本当に改善できるのかもしれないと感じはじめています。
初めて「瞑想」ということばに出会ったときとはまったく違う感覚で、明らかに心理的ハードルが下がっているのです。
ただ、やはりまだ一歩踏みとどまっている部分があるので、その障壁が何なのかを見極めながら、スムーズに一歩踏み出せるやり方や考え方を模索しているところです。
何かいい方法が見つかったらまた皆さんにもシェアしたいと思います。
まとめ
みんな良いと言っているから、流行っているからというだけで、無理して取り入れても瞑想の効果は発揮されません。
大切なのは自分が納得して、習慣にしていけるかです。
「瞑想」と捉えるか「深呼吸の練習」と捉えるか、どちらが良いかという話ではなく、自分自身が心地よく始めるため、頭と心が拒否反応を起こさないためにはどうしたらいいのか。
今回の記事がそんな道を探すヒントになれば幸いです。
瞑想やマインドフルネスに関連した記事は、やり方の解説やインタビュー記事などたくさんあるので、ぜひ参考にしてみてください。
☞幸福度が上がる瞑想方法。楽に続けられる、続けてこそ実感する!
☞マインドフルネスと瞑想の違いや初心者におすすめのやり方を徹底解説!
アニミズムとはどんな意味か簡単に説明|日本における例とは

日本には古くから神や仏を信仰する文化が根付いており、無意識のうちに神仏へ祈りを捧げたり、季節ごとの行事に参加したりしている方も多いのではないでしょうか。
神仏はそれほど私たちの身近にある存在ですが、これらは決して日本だけでなく、世界各国で様々な神仏が信仰されています。
今回はこういった特別な神仏以外に、私たち人間や動物・植物などの全てに宿る霊魂を信じる考え方「アニミズム」についてご紹介します。
詳しい意味を探ると共に、日本におけるアニミズムの在り方についても見ていきましょう。
アニミズムとはどんな意味?簡単に説明

アニミズムとは、私たち人間や犬・猫などの動物、植物などの全てには霊魂(アニマ)が宿っているとする考え方のことです。
アニマが宿るのは生き物だけでなく、家や車・土地・おもちゃなど身近にあるもの全てが対象とされています。
アニマが宿ることによってこれらの無生物には心が宿り、時には所有者に向けて、またある時にはその場所そのものに影響を与えてきました。
私たち人間も、幼い頃に「おもちゃを大切にしないとおもちゃが悲しんでしまうよ」「物を投げたり壊したりするとバチが当たるよ」などと言われた経験があるのではないでしょうか。
これらは無意識で出たものだとはいえ立派なアニミズムの一種であり、私たちの心に深く根付いているといえます。
生き物はもちろん無生物にもアニマが宿ると考えるからこそ、私たち人間はむやみに物を破壊したり、無駄にしたりせず生きることができます。
「宗教の一種」として敬遠するのではなく、アニミズムの考えが世界中の様々な宗教に影響を与える存在であり、いわば私たちが正しく生きるための道標となることを覚えておきましょう。
アニミズムは日本にいつからある?神道との関係性とは
アニミズムの考え方は近年生まれたものではなく、古くから日本に根付いてきたものです。
その始まりを辿り、日本に伝わってきたルーツを知ることで、アニミズムを正しく理解できるでしょう。
19世紀にイギリスの文化人類学者によって提唱
「アニミズム」という言葉が誕生したのは、19世紀のイギリスだったといわれています。
文化人類学者として活動していたエドワード・B・タイラー氏が、世界各国で信仰されている宗教に通じるものとして提唱したのがアニミズムです。
この宇宙に存在する全てのものにはアニマが宿り、その結果私たちが自然の力を借りて生きられているとの考え方は、現在の社会においても大きな軸となっていることは間違いありません。
それぞれの物にはアニマが宿っており、相互に干渉はできなくても、それぞれの役割を全うしながら生きています。
寿命や生き方に違いはあれど、私たちはみな宇宙に生きる一つの生命であり、種類によって脅かされるべきではありません。
アニミズムの考えは物体そのものにアニマが宿るとされるため、私たち人間が死んだ後も、アニマそのものは体に残ると思われてきました。
そのため、土葬にする際は個人を偲ぶものを入れたり、「屈葬」と呼ばれる特殊な姿勢で魂が抜けるのを防いだりといった文化も生まれています。
日本では古代から神道に似た概念が存在
日本の宗教として特徴的なのは、キリスト教におけるイエス・キリスト、イスラム教におけるアッラーなどといった信仰の対象が限定されない「神道」ではないでしょうか。
神道は多神教であり、自然や土地など様々なものに神が宿ると考えるもの。
太陽には太陽の神が、風には風の神がいると考えられ、災害が起こると神の怒りを鎮めるための儀式が行われていました。
この考え方は古代から日本に浸透しており、その始まりは縄文時代に遡るといわれています。
その後こういった考えが正式に「神道」と呼ばれるまでには時間がかかりましたが、現代に至るまで大きく形を変えることなく語り継がれてきたのです。
関連記事:「本当の自分」が分からない?迷ったときに思い出したい考え方
日本におけるアニミズムの例

これまでご紹介したように、日本には様々な形でアニミズムの考え方が浸透しています。
さらにアニミズムを分かりやすくイメージするために、実際の例について見てみましょう。
八百万の神
日本の神道は種類が豊富なことでも知られており、身の回りに神のいないものはないといっても過言ではないほどです。
これらは総称で「八百万の神」と呼ばれており、どんなものにも神様が宿っているため、大切にしようといった考え方に繋がっています。
字で見ると「八百万」と書きますが、実際にピッタリ800万人の神様がいるわけではありません。八百万(やおよろず)とは、すなわち「数えきれないほどたくさん」という意味。
元々太陽や風などの自然現象を司るという神もいれば、長年大切に扱ってきた物に神が宿り、「付喪神」と呼ばれるようになったものまで様々な種類が該当します。
かつての日本は幾度となく飢饉に苦しめられ、多くの民が命を落としました。
「お米一粒にも神様が宿っている」ともいわれるように、食べ物を無駄にすることなく大切にいただくことも、アニミズムの考えに倣っているといえます。
お盆の送り火と迎え火
日本ではお盆になると亡くなった方の魂が帰ってくると信じられており、自宅に帰る先祖のために精霊馬を作ったり、お供え物をしたりしてお迎えします。
このとき先祖の魂が現世へ迷わずに帰ってこられるようにとの願いを込めて「迎え火」を、反対に帰るときも迷わずに行けるようにと「送り火」を焚くという伝統文化があります。
これもまた本質を紐解けば、既に亡くなっておりこの世に存在しないはずの先祖でも、魂だけは残っていていつまでも見守ってくれているといったアニミズムの考えに通じるものがあるでしょう。
古くからの慣習にも思える迎え火や送り火ですが、意外にもお盆の行事として広まったのは江戸時代頃だといわれています。
いつの時代も家族や友人など大切な人が亡くなったとき、その人の全てが失われてしまうとは考えたくないものです。
魂がいつまでも残っており、お盆のタイミングで帰ってきてくれると考えることで、親しい人の死を乗り越えてきたのではないでしょうか。
アイヌ民族の信仰
現代においても北海道の一部を中心に生活し、「アイヌ語」を使ってコミュニケーションをとるアイヌ民族。
数が減ってしまったとはいえ歴史ある民族の一つであり、日本語を話す人々とは異なる文化も多数築いてきました。
そんなアイヌ民族の間で信仰されている考えの一つに「精神文化」というものがあります。
これは八百万の神と同じく、身の回りにある全てのものに神が宿っているといった考え方です。
狩猟対象である動物や生活に使う道具・自然現象・人の病気に至るまで全てが神(カムイ)の意思で生まれたものであり、これらに尊敬の念を込めることで、これまで共存・繁栄をしてきました。
折り紙の鶴
親しい人が病気や怪我で入院したり、誰かの成功を祈ったりする際に、千羽鶴を作った経験のある方も多いのではないでしょうか。
折り紙の鶴が千羽集まることはもちろん、人々の祈りと願いが込められた鶴を使うことで、贈られた人の不幸を癒すとされています。
千羽鶴の始まりは、長年生きることでも知られる「鶴」が、神にとって良いものだと考えられていたためです。
絵馬やお守りなどに鶴の絵が描いてある神社も珍しくないでしょう。
神に願いを聞いてもらい、そのお礼として鶴の入った絵や折り紙などを奉納することが、今でいう千羽鶴に繋がったといわれています。
御神木や神聖視される岩など
日本には今でも至るところに「パワースポット」があり、旅行のついでに巡ってみた経験のある方も多いはずです。
その中でも古くから神が宿るといわれてきた御神木や御神岩などは、神社を参拝する際に訪れたいスポットとして紹介されているケースも珍しくありません。
こういった古くから信仰されてきたものには人々の思いが込められているため、神の力も強く、信仰には大きな意味があるといわれています。
何も知らない人から見ればただの木や岩であっても、そこに神が宿っていると考えれば途端に神聖なものに見えてくるでしょう。
始まりは「ひときわ大きかったから」「〇〇に形が似ていたから」といった理由でも、それが長年人々の心を繋ぎ、神がいると信じられてきたことが大切なのです。
アニミズムと汎神論の違いとは?
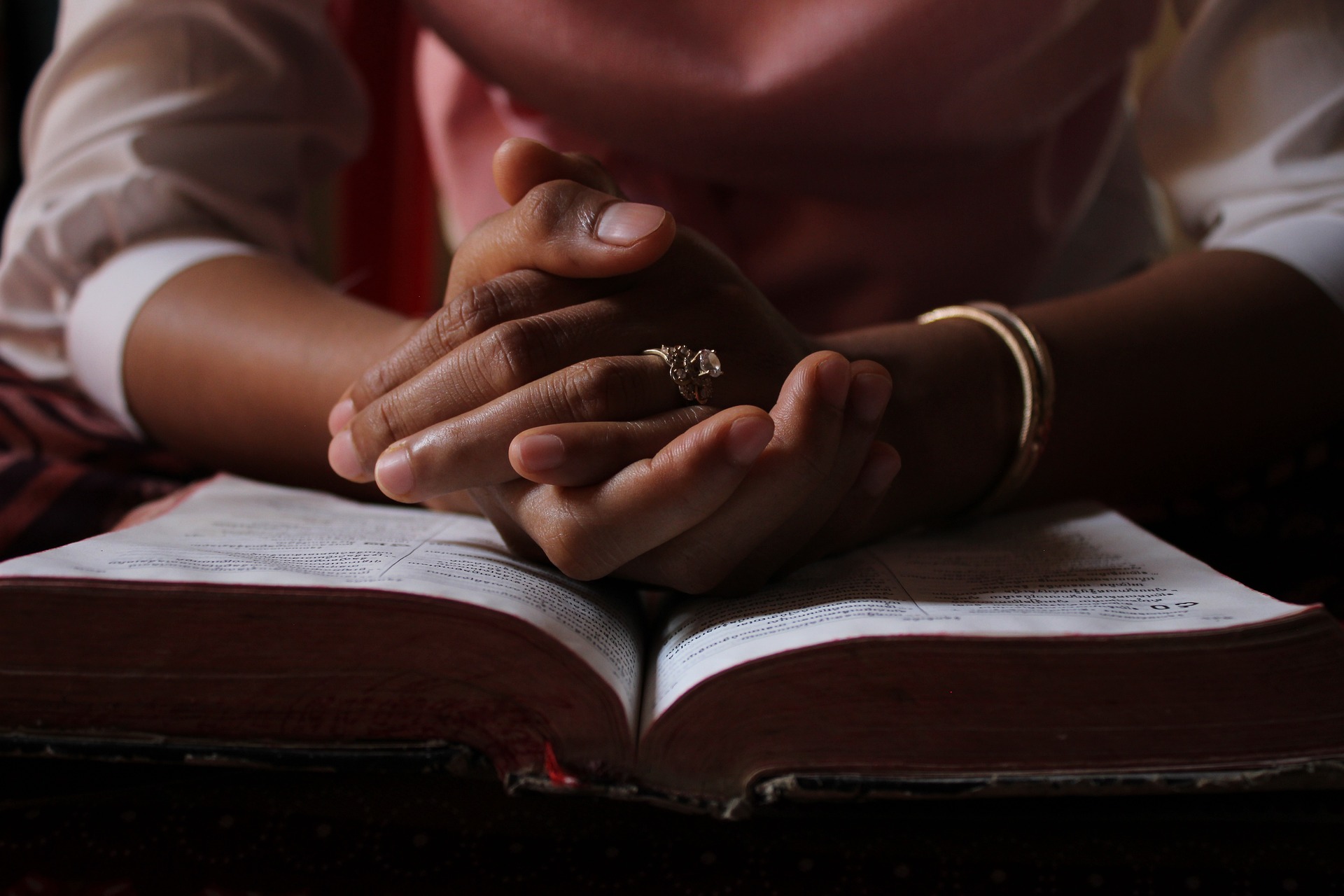
アニミズムと混同されやすい考え方の一つに、「汎神論」があります。
これは「この世における全てのものは神が作った」という考え方であり、神はこの社会そのもの、宇宙そのものであると捉えられます。
一つひとつの物に神が宿るのではなく、物も、人も、自然も全てが絶対神によって作られたものであり、その恩恵に感謝して生きていかなければなりません。
そして汎神論における神とは人の形をしておらず、いわば神という一種の概念でしかありません。
神があらゆるところに存在するといった点ではアニミズムと似ていますが、そもそも神は宿るものではなく、万物こそが神であるといった考え方が汎神論です。
まとめ
「アニミズム」というと耳なじみのない方も多いですが、その考え方自体は古くから私たちの中に強く根付いています。
今後も「宗教だから」と避けるのではなく、万物に神が宿るといった考えから、物や命を大切にすることを心掛けてみてはいかがでしょうか。
ポリアモリーは頭おかしい?浮気性との違いはなに?

近年は一言で「恋愛」といっても様々なタイプがあり、必ずしもたった一人の異性を愛することだけが恋愛とはいえない社会となってきました。
つい固定観念を元に自分とは違う存在を避けてしまいがちですが、その根底にあるのは相手のことをよく知らず、理解できていないのが原因です。
今回はそんな多様性の中で注目を浴びるようになった「ポリアモリー」という考え方についてご紹介します。
現代に至るまでポリアモリーがどのように生まれ、そして発展していったのかも併せて確認してみましょう。
ポリアモリーとはどんな意味?

ポリアモリーとは、合意の上で複数のパートナーとお付き合いをするといった考え方のことです。
この場合のパートナーとは必ずしも異性とは限らず、ゲイ・レズ・バイセクシュアルも含めて複数の人とお付き合いをしている場合はポリアモリーに当てはまります。
ポリアモリーは相手に黙って他の人とお付きあいをするのではなく、関係者全員が複数とお付き合いをすることに合意しているのが特徴です。
例えば、A子さんとB男さんがパートナーである場合を見てみましょう。
このうちA子さんがポリアモリーで新たにC太さんとお付き合いを始めるならば、A子さんとC太さんの関係をB男さんが知っていなければなりません。
さらにはC太さんも、A子さんには他にB男さんというパートナーがおり、これに合意しなければポリアモリーとはなりません。
一見嫉妬心が芽生えてしまいそうな関係性に見えますが、ポリアモリーの中では様々なシーンで交流が生まれ、大きな団体となっている場合も珍しくありません。
前述の例でいえば、A子さんをきっかけにB男さんとC太さんが仲良くなり、3人でデートをすることもあるでしょう。
さらにはB男さん・C太さんがお付き合いしている他のパートナーも含め、大人数が知り合いになることも多いのです。
また、ポリアモリーは身体の関係を結ぶことが必須ではなく、精神的な安定性を求めてお付き合いをしている方もたくさんいます。
身体関係がある場合・ない場合に関わらずこれらの関係は長期的に続くものであり、一夜の関係で終わるものではありません。
性欲を満たすために短期間の関わりを持ちたいと願う場合とは異なるため、ポリアモリーを実践している方と接するときは誤解しないよう注意が必要です。
もちろん、相手や自分に複数のパートナーがいるからといって、相手に「他の女性と会ってほしくない」「自分を優先してほしい」と願っても間違いではありません。
こういった嫉妬心を含めてパートナー同士で話し合い、納得した上で少しずつ関係性を深めていくのがポリアモリーの特徴といえるでしょう。
関連記事:ポリアモリーの特徴は?浮気と何が違うのか誤解されやすいポイントを解説
ポリアモリーという概念が生まれた原因・背景
私たち日本人からすると、ポリアモリーの考えはすぐに受け入れられるものではないかもしれません。
これは一重に国による文化の違いともいえますが、そもそもどうやってポリアモリーの概念が生まれたのでしょうか。
現在日本でポリアモリーが増えているのは果たして何故なのか、そのルーツを辿っていきましょう。
1990年代にアメリカで生まれた恋愛スタイル
ポリアモリーを実践し、多様な愛の形を追い求める人のことを「ポリアモリスト」と呼びます。
その始まりは1990年代のアメリカであり、この頃はフェミニズムの考えが広まりつつありました。
「家族は父親が絶対的な存在である」「異性同士のパートナーの場合は男性が優位に立つ」といった考え方に疑問を持ち、男性/女性とはこうあるべきだといった固定観念から脱却した人々が、それぞれ自由な恋愛観を持ち始めたのです。
こうした自由な恋愛観は、年代が進むにつれてアメリカ以外の国でも受け入れられるようになりました。
私たちの住む日本ではまだまだ浸透しているとはいえませんが、言葉の意味を知っている人が増えてきているのも事実です。
近年のアメリカではポリアモリストが増えた結果、お互いが合意の上で3人以上が家族として同じ家に住み、それぞれ異なる恋愛関係を紡いでいるのも珍しくありません。
ポリアモリストが集う「ポリーラウンジ」といった交流会が開かれるなど、誰しもが周りを気にすることなく恋愛を楽しめる社会に近づいているのです。
根底にあるのは「愛は無限である」という考え
ポリアモリーについての知識が少ない人にとって、彼らの生き方は不思議であり、想像できないものであるでしょう。
ポリアモリストであることを周りに公表できず苦しい思いをしている人や、後ろ指を指された経験のある人もゼロではないはずです。
しかしポリアモリーを紐解いてみると、根底にあるのは「愛は無限である」といったシンプルな考えであることが分かります。
たった一人のパートナーを大切にしたからといって、自分の中に眠る愛が全て失われてしまうわけではありません。
大切な人が複数いるのならば、それぞれに同じだけ愛を与え、大勢で生活することもできるでしょう。
「愛は一人に対して送るべきだ」という考えを持つ人にとって、ポリアモリーは不誠実に見えることもあるでしょう。
とはいえ愛は数値化できるものではないため、自分の愛を100%相手に与えているように見えても、実はそうではない場合も多いのです。
パートナーと子どもに平等な愛を与える人が多いように、ポリアモリーはパートナーが複数いて、それぞれに対し愛を投げかけているにすぎません。
ポリアモリーと浮気性の違い

ポリアモリーを語る上でもっとも誤解されてしまいやすいのが、浮気性との違いです。
「同時に複数の人を愛する」という意味を持つ両者ですが、大きく異なる点があるため、一括りにしてしまうのは間違いです。
ポリアモリーと浮気性の違いをしっかりと抑え、ポリアモリストに対して不要な誤解を抱かなくても済むようにしておきましょう。
合意と透明性があること
一般的に、パートナーに隠れて浮気をする場合、その事実がバレないように嘘や隠ぺいをしながらドキドキして過ごしているケースが多いのではないでしょうか。
万が一隠していた事実が明るみに出てしまえば、破局や離婚に繋がったり、慰謝料を請求されたりする可能性が高まります。
多くの人の間で「浮気は悪である」といった考えが広まっていることからも、浮気は不誠実でありすべきではない行動の一つといえるでしょう。
これに対しポリアモリーは、全てのパートナーが合意した上で関係が進んでいる状態をいいます。
A子さんにB男さんとC太さんというパートナーがいる場合、B男さんもC太さんもお互いの存在を理解していなければなりません。
ここには嘘や隠ぺいは一切なく、どこへ行っていたのか、この日は誰と会うのかなどの情報がしっかりと明かされており、透明性があるのもポイントです。
そのため、A子さんがB男さんと会っていても、C太さんが怒ったり悲しんだりすることは少ないでしょう。
時には3人が同じ場所に集い、コミュニケーションをとることで、浮気とは異なる関係性を築けるのです。
全ての相手に誠実であること
浮気や不倫でパートナーをだましている人は、少なからず嘘をつきながら、後ろめたい気持ちで生活をしていることでしょう。
通常、心が移ってしまったのならパートナーとの関係を清算してから次に進む必要がありますが、それをしないということは不誠実に他ありません。
しかしポリアモリーの場合、複数いるパートナーの全てに誠実であり、嘘や隠し事のない関係が築かれます。
「今日はB男さんと会うからC太さんとは会えない」「明日はC太さんの番」といったように、違うパートナーと会う際もしっかりと連絡しておく方が多いでしょう。
相手も順番でのデートに合意しており、揉め事が起こらないのも特徴といえます。
一次的な快楽が目的ではないこと
先ほども触れたように、ポリアモリーは長期的な関係を築くため、どのパートナーとも慎重なコミュニケーションが行われます。
これはたった一人のパートナーを愛する人も同じであり、真剣に交際したいと思えば思うほど、ゆっくりと時間をかけて関係を進展させていく人が多いのではないでしょうか。
こういったことから、ポリアモリーは恋愛感情を抱く相手が複数いるだけで、その他の部分は他の恋愛と変わらないことが分かります。
複数のパートナーを探しているからといって、身体だけの関係を望んだり、性行為をしたい・寂しさを埋めるために誰でもいいから話したいといった短期間の関係が目的ではないことを覚えておきましょう。
日本に根付いている「モノガミー」について
私たちの住んでいる日本でポリアモリーがなかなか浸透しないのは、古くから「モノガミー」の考えが広まっており、固定観念として根付いているためだと考えられます。
古い時代も今も男性と女性が一対一で婚姻を結ぶのが常識であり、男性同士・女性同士の婚姻や複数婚は事実上できないこととなっています。
こういった考えは当たり前のように思われていますが、これもポリアモリーと同じく一つの概念であり、たまたま現代の日本で多くの人が受け入れているだけにすぎません。
イスラム圏にある国々は古くから一夫多妻制を導入しており、現代も「当たり前」として受け入れられています。
このような古くからの慣習をそのままに、新たな考え方も否定せずに取り入れることで、大勢が生活しやすい社会が生まれるのではないでしょうか。
ポリアモリーは「頭おかしい?」「気持ち悪い?」

ポリアモリーについてネット上で調べてみると、時に「頭おかしい」「気持ち悪い」といったキーワードがヒットすることがあります。
これまでに述べたように日本では複数婚が承認されていないため、ポリアモリーについて否定的な考えが多く出てきても不思議ではありません。
今後どのようにポリアモリーが広まるかは分かりませんが、現時点ではまだまだマイノリティであり、カミングアウトしにくい社会が続いているといえます。
筆者はポリアモリーと現代社会について、今後人々がさらに寛容になり、自分の気持ちを大切にしてほしいと願います。
自分は異性が好き、自分は複数のパートナーを持ちたいといったそれぞれの願いを大切に、周りの人々を良い意味で「気にしない」状態になれたら良いのではないでしょうか。
自分と違う意見をすぐさま受け入れるのは難しいため、まずは人それぞれ異なる意見を否定せず、多様化する社会で自由に生きられるような変化が起こることを期待します。
上記はあくまでも筆者一個人の考えであるため、必ずしも同じ意見を持つ必要はありません。
さらに時代が進み、誰もが「私は〇〇だ」とカミングアウトできる社会になれば良いと考えます。
まとめ
性自認が多様化するにつれ、恋愛の仕方にも様々な方法が登場してきた現代。
ポリアモリーは決して浮気性のように不誠実なものではなく、多くの人と同じように愛し合うことで、モノガミーと同等もしくはそれ以上の経験ができるでしょう。
ポリアモリーをカミングアウトする著名人も多数いるため、まずはその人の生き方を見ながら、多様性を受け入れる準備を進めていくことが大切です。
アロマンティックとは?特徴やアセクシャルとの違いを解説

近年は男性・女性だけでなく、自身がそのどちらにも当てはまらないとする「性的マイノリティ」への理解が深まりつつあります。
とはいえ性的マイノリティはその特徴ごとに様々な種類に分けられており、一気にそのすべてを理解しようとするのは難しいでしょう。
まずは身近に感じやすい種類から言葉の意味を調べ、どのような方がいて、どのような悩みがあるのか学ぶことが大切です。
今回は数ある性的マイノリティの中から、日本に未だ浸透していないとされる「アロマンティック」についてご紹介します。
混同されやすいアセクシャルとの違いや、自身がアロマンティックであることはどう判断すべきなのかといった点にも触れていきましょう。
アロマンティックとは?

アロマンティックとは、端的にいえば「他人に恋愛感情を抱かない」人のことを指します。
恋愛感情を抱かないからといって周りに興味がないかといえばそうではなく、他の方々と同じように友人と楽しく過ごしたり、家族を大切にしたりといった愛情はあります。
あくまでも恋愛的な「好き」を感じないだけであって、「冷たい人だ」と誤解しないよう注意が必要です。
アロマンティックの方々は恋愛感情がどのようなものなのか分からなかったり、恋愛感情に嫌悪感を抱いたりする場合があります。
恋愛映画を見たがらなかったり、恋愛的な相談に乗るのを嫌がったりする方もいるため、無理に押し付けるのはやめましょう。
アロマンティックであると自認していなくても、恋愛関係の話が苦手な方もいるため、こういった相談をする相手はしっかりと見極めることが大切です。
また、恋愛ができない理由の中には、やむを得ないものもあるでしょう。
例えば「統一教会」や「エホバの証人」といった宗教団体は、一部で恋愛を禁止しています。
こういった理由があって恋愛をしないことを選んでいる場合は、アロマンティックには当てはまりません。
アロマンティックの特徴
アロマンティックの概要が分かったところで、実際の特徴について詳しくご紹介します。
まずはアロマンティックの方々について正しいイメージを持つために、その他の性的マイノリティとどう異なるのか見ていきましょう。
恋愛感情を抱かない
アロマンティックは周りに恋愛感情を抱かないため、その類の経験がほとんどない場合が多く、恋愛話に積極的な姿勢を見せません。
とはいえ恋愛感情を抱かないだけであり、性的欲求の有無は限定されません。
アロマンティックでありながら性的欲求もない場合は、性的欲求を抱かない「アセクシャル」と重ね合わせ、「アロマンティック・アセクシャル」などと呼ばれます。
恋愛作品や恋愛の話題に共感できない
アロマンティックは自身の判断で恋愛を行わない方々であるため、他人の恋愛を見たり聞いたりするのが苦手な方が多いといえます。
アロマンティックを公表している方に無理やり恋愛話を持ち掛けたり、「恋愛経験がないの?」と過去を探るような話題をしたりするのはやめましょう。
もちろん中には他人の恋愛話くらいなら聞ける、といったアロマンティックの方もいるため、その人に合わせた対応をすることが大切です。
社会的なプレッシャーを感じがち
アロマンティックは他人と恋愛関係に発展するのを避ける傾向にあるため、生涯結婚をせずに過ごしたいと願う方も少なくありません。
しかしこの場合、理解の及ばない周囲の人々によって、「もう〇歳なんだから結婚すべきだ」と言われてしまうことがあります。
女性であれば、早く子を産むべきだと批判されることもあるでしょう。
また、結婚適齢期を過ぎても結婚をしていないことで、何らかの問題があるのではないかと偏見の目で見られてしまう場合もあります。
自分の意思で結婚をしていないのだ、といっても信じてもらえず、周囲の人間に対し不信感を持ってしまう方もいます。
恋愛感情を抱かないだけで他の感情は持ち合わせている
アロマンティックだからといって、周りの人に興味がないとは限りません。
私たちが恋愛的に好きではない方でも話したり遊んだりできるように、アロマンティックの方にも家族や友人がおり、同じように娯楽を楽しんでいます。
自分以外の他者と親しくなるために必ずしも恋愛感情が必要とは限らないため、「1人が好きな人」「周りに関心のない冷たい人」といった誤解を抱かないよう正しく理解することが大切です。
また、先程もご紹介したように、アロマンティックの中には性欲のみ持っている方もいます。
相手の了承を得て性行為のみをするパートナーになってもらうなど、工夫しながら自身の性欲と付き合っている方もいます。
アロマンティックとアセクシャルの違いは?

アロマンティックと似たような意味を持つ言葉として「アセクシャル」があります。
両者には似ていながらも明確な違いがあるため、それぞれの特徴をしっかりと学んでおきましょう。
アロマンティックとは、すなわち「恋愛感情がない」人のこと。そしてアセクシャルとは、「恋愛感情も性的欲求もない」人を指します。
両者は似ているようで異なっており、恋愛感情がなくても性的欲求はある方、そのいずれもない方、性行為がなくても恋愛関係だけはある方など様々な性的マイノリティがあることを覚えておきましょう。
- アロマンティック:恋愛感情がない
- ノンセクシャル:性的欲求がない
- アセクシャル:恋愛感情・性的欲求の両方がない
→ロマンティック・アセクシャル:恋愛感情はあるが性的欲求がない
→アロマンティック・アセクシャル:恋愛感情と性的欲求の両方がない
- リスロマンティック:恋愛感情はあるが相手から恋愛感情を持たれたくない
- バイロマンティック:男性・女性のいずれに対しても恋愛感情を抱く
- クワロマンティック:恋愛感情と友情の違いが分からない
- パンロマンティック:性別(この場合は性的マイノリティも含む)に関わらず恋愛感情を抱く
アロマンティック診断をしてみよう
自身がアロマンティックであるかどうかは、他人に診断してもらうものではありません。
しかし何らかの目安があって初めて、自分の状態がアロマンティックであると実感できる方もいるでしょう。
続いては自身の状態を正しく把握するために、参考となるアロマンティック診断をご紹介します。
以下の中で当てはまる項目が多ければ多いほど、アロマンティックの要素が強いといえるでしょう。
- 異性に興味がない
- 他の人と同じように遊んだり話したりはできるがスキンシップが極端に苦手である
- 恋愛ドラマや恋愛映画のストーリーに共感できない
- これまでに恋愛的な意味で人を好きになったことがない
- 恋人になっても何をすれば良いか分からない
- 異性を自分だけのものにしたいという欲求がない
アロマンティックの人はモテる?

アロマンティックの方は、時折「モテる」と思われることがあります。アロマンティックとモテることがどうつながるのか、その理由を見てみましょう。
アロマンティックの方の中には、幼い頃から異性にモテることが多く、恋愛関係がこりごりだと感じてしまう方がいます。
モテるが故に同性から疎ましく思われたり、複数の異性とトラブルに発展してしまったりした経験があると、自分から積極的に恋愛するのを避けるようになるでしょう。
こういった場合、自分のことを好きだと言ってくれる人よりも、「興味がない」「友達としか思えない」といった人を選んで一緒にいるようになります。
また、男性の場合は特に、恋愛に対してガツガツしていない様子が異性にモテるといった風潮があります。
本人は恋愛に興味がなく、異性に対しガツガツとしていない様子が、逆に周りから見れば魅力的に映ってしまうのです。
こういった結果、アロマンティックであることでむしろ周囲から注目されやすくなり、恋愛関係に発展する可能性が高まるばあいがあります。
いずれにしても望まない関係はしっかりと断り、自分の気持ちを大切にすると良いでしょう。
関連記事:ボディポジティブとはどんな意味?日本や海外に与えた影響をご紹介
まとめ
未だ日本国内に浸透したとはいえないアロマンティックやアセクシャルの考え方。
公表している人はまだまだ少ないため、実は身の回りにもアロマンティックを自認している方がいるかもしれません。
今後さらに彼らのような性的マイノリティが生活しやすくなるために、今のうちから正しい理解を心掛けていきましょう。
Xジェンダーは思い込みなのか?恋愛対象や割合は?

近年は性について多様性を受け入れる動きが広まっており、様々な性の形が広く知られるようになってきました。
とはいえ未だ全てに広まったとはいえず、数の少ない性の種類について聞いたことがない方も多いのが現状です。
性差を受け入れるより前に、その特徴をしっかりと理解することが理解の始まりだといえるでしょう。
今回はその中から「Xジェンダー」について、特徴や恋愛対象なども併せてご紹介します。
身の回りにXジェンダーの方がどれほどいるのか、全体的な割合を元にイメージしてみましょう。
Xジェンダーとは?

「Xジェンダー」とは、すなわち「男性でも女性でもない性自認を持つ方々」のことを指します。
近年は様々なアンケートや問診などで、男性・女性・どちらでもないといった記載を見ることが増えてきました。
全ての人が必ずしも男性と女性に分けられるのではなく、どちらなのか自分でも分からない方、どちらの性も持ち合わせている方など、様々な方へ配慮した記載がなされています。
自らをXジェンダーだと認識していても、未だ周りに理解されず、公ではやむを得ず身体の性に合う方を選択している方も少なくありません。
男性・女性に当てはまる方がXジェンダーについてしっかりと理解し、自分たちと同じだと受け入れることで、Xジェンダーの方々が過ごしやすい社会になるはずです。
そしてXジェンダーの中にも様々なタイプがあり、単に一つの性と括られないことも重要なポイントとなります。
また、Xジェンダーと混同されがちな言葉として、以下のようなものが挙げられます。
- トランスジェンダー:身体の性と心の性が一致していない方
- クエスチョニング:自身の性がどれに当てはまるか分からない、もしくは意図的に決定していない方
- ノンバイナリー:性自認だけでなく、性的表現も男女の枠組みにとらわれない方
特にノンバイナリーは、Xジェンダーと似通っており、どちらに当てはまるのか分からない方が多いものです。
Xジェンダーはあくまでも「性自認」について述べたものであり、自分がどう思うかに関連しています。
ノンバイナリーは性自認に加え、「男性・女性どちらの性としてふるまうか」といった性表現においても、二分化されない方々を指します。
Xジェンダーよりも自由度が高く、タイミングによって表現の方法が異なるのもノンバイナリーならではといえるでしょう。
Xジェンダーの特徴
一言でXジェンダーといっても、その中には様々なタイプの方が存在します。
「Xジェンダー=〇〇」といった決めつけはできず、私たちの個性と同じように、様々な性自認・性的表現の方がいるのだと知っておきましょう。
続いてはXジェンダーの方々を大まかなタイプに分け、それぞれの特徴についてご紹介します。
中性
Xジェンダーの「中性」とは、自分が男性と女性のちょうど中間にいると感じる方を指します。
男性よりでも女性よりでもありませんが、「どちらでもない」というよりは、あくまでも「男女の中間」と感じているのが特徴です。
男性・女性・Xジェンダーと、第3の性として捉えると分かりやすいのではないでしょうか。
両性
Xジェンダーの「両性」とは、男性の要素と女性の要素をどちらも持ち合わせている方を指します。
どちらの要素も同じだけ持っている中間的な存在の方もいれば、男性より・女性よりと偏りのある方もいます。
性自認は男性よりでも、ファッションは女性よりのものを選ぶことが多いなど人によって特徴が異なるため、「Xジェンダーだからこうであるはず」といった固定的な観念は当てはまりません。
無性
Xジェンダーの「無性」とは、自分が男性でも女性でもなく、どちらの要素も持ち合わせていないと感じる方を指します。
中性や両性が男女いずれかの性を持っているのに対し、無性は男性・女性といった性別を一切持っていないため、第3の性として考えるのも良いでしょう。
不定性
Xジェンダーの「不定性」とは、時に男性よりの性になったり、またある時は女性よりの性になったりとタイミングによって性の状態が変わる方を指します。
これまでご紹介した中性・両性・無性の3種類を経験したことのある方や、1日ごとに性自認が異なる方もいます。
数ある性的マイノリティの中でも自由で、性別にとらわれない種類ともいえます。
Xジェンダーは思い込み?
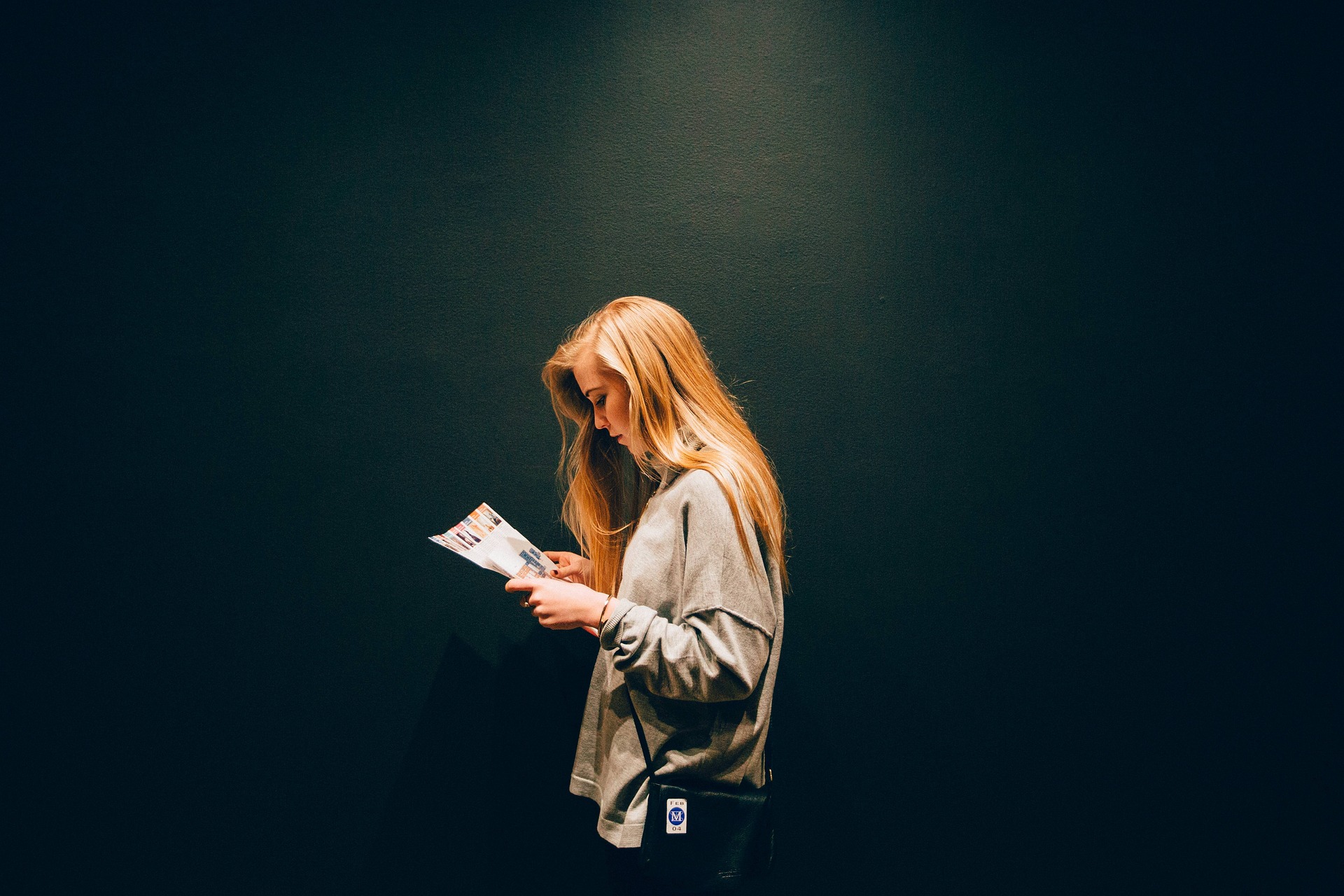
自分の性が男性・女性のいずれにも当てはまらないと感じ、悩んでいる方はたくさんいます。
その中でも自身がXジェンダーであると理解できれば良いですが、「思い込みなのではないか」「自分だけがおかしいのではないか」といった悩みを抱えている方もいるでしょう。
そもそもXジェンダーを始めとする性的マイノリティの数々は、誰かに認められて達成するものではありません。
自身が男性・女性のいずれにも当てはまらないと感じた場合、それはすなわち性的マイノリティであり、誰かに否定されるものではないのです。
同じ性自認をもつ方が見つからない場合は、無理に周りへ公表する必要もありません。
周りに受け入れられることは素晴らしいことですが、だからといって自分の全てを打ち明けなければならないわけではないでしょう。
もちろん、自身がXジェンダーだと強く信じていても、実際は別の性的マイノリティである可能性もゼロではありません。
一つの情報で自身の性自認を信じ込むのではなく、情報を広く求め、本来の自分と向き合ってみることが大切です。
ネット上に溢れている性的マイノリティの方々の意見を参考に、自分がもっとも当てはまる種類を探してみてはいかがでしょうか。
Xジェンダーを始めとする性的マイノリティはこの先さらに増え、男性・女性に限らず自由な性自認を持てる社会が来るはずです。
その時までに私たち一人ひとりが数ある性的マイノリティについて知り、彼らの意見に耳を傾けることで、深い理解につながるのではないでしょうか。
Xジェンダーの恋愛対象は?
Xジェンダーについて理解しようとする中で、多くの人が気になるのが「恋愛対象」ではないでしょうか。
男性は女性へ、女性は男性へ恋愛感情を抱くのが当たり前ではなくなった社会で、Xジェンダーはどのような恋愛をしているのか知っておきましょう。
パンセクシャル
パンセクシャルは「全体愛」という意味を持ち、相手の性自認や性表現が何であるかは関係なく、どんな状態の人でも平等に愛することができる方を指します。
これは男性・女性だけでなく、Xジェンダーのようにどちらにも当てはまらない方も含めて恋愛対象となります。
自分がXジェンダーだと感じ、男性・女性はもちろん同じXジェンダーの人にも好意を抱くという方は、パンセクシャルに当てはまるでしょう。
バイセクシャル
バイセクシャルとは男女どちらの性に対しても恋愛感情を抱く方のことです。
パンセクシャルと異なるのは、あくまでも男性・女性に対して恋愛感情を抱く場合であり、この中にXジェンダーのような性的マイノリティは含まれていません。
もちろん性的マイノリティの方が身の回りにおらず、男性や女性のみと関わっているために、自身をバイセクシャルであると考えている方も少なくありません。
バイセクシャルは男女にとらわれず相手の容姿や性格といった「その人そのもの」を見ることができる点が特徴です。
どちらかといえば男性/女性が好き、などと偏りがあることもあり、必ずしも好む男女の割合が平等であるとは限りません。
アセクシャル
アセクシャルとは、他人に対して恋愛感情を抱かない方を指します。友情や家族愛のような感情はあっても、性的欲求がない場合はアセクシャルかもしれません。
アセクシャルだからといって周りに関心がないとは限らず、あくまでも恋愛関係に発展しないことだけが特徴といえます。
アセクシャルに似た言葉として「ノンセクシャル」がありますが、これは恋愛感情を抱いていても、性的欲求だけがない場合を指します。
アセクシャルは「恋愛的な好き」も感じない方を指すため、両者の違いを正しく覚えておきましょう。
Xジェンダーの人の割合は?

Xジェンダーについて学んでみても、実際に身の回りに性的マイノリティの方がいなければ、具体的にイメージするのが難しいでしょう。
もちろん性的マイノリティだからといってそれを公開しているとは限らないため、実は身の回りにも様々な方がいて、性自認について悩んでいるかもしれません。
続いては全人口に対し、Xジェンダーの方がどのくらいいるのか、その割合についてご紹介します。
この調査結果はあくまでも概算であり、Xジェンダーに気が付いていなかったり、意図的に隠していたりする方を含めるとさらに多くなるといわれています。
日本では金沢大学・コマニー株式会社・株式会社LIXILの3つが合同で調査を行い、自身の性自認について問いかけました。
その結果トランスジェンダーであると回答したのが全体の2.0%、さらにその中でXジェンダーを自認しているのが52.2%だったと述べています。
すなわち、Xジェンダーを自認している方の割合は全体の1.0%ほどであることが分かります。
この数字を分かりやすく説明すると、100人の人が集まっているとき、少なくとも1人はXジェンダーとなります。
この数字を見ると、自分の周りにもXジェンダーがいる確率が高く、今後関わりを持つ可能性も少なくないことが分かるでしょう。
関連記事:マイノリティ・マジョリティとは? 多様な社会の理解を深めるために
まとめ
Xジェンダーは私たちの身近な存在であり、決して珍しい方々ではありません。
大切なのは彼らがXジェンダーであることを恥ずかしい・隠したいと思うのではなく、男性や女性と同じように公表できる未来を作ることではないでしょうか。
そのための第一歩として正しい理解を持ち、Xジェンダーについてしっかりと知ることが大切です。
怒る前に深呼吸。そのイライラは私にとって役立つの?『幸福になりたいなら幸福になろうとしてはいけない』を読んで実践してみた
Humming編集部メンバーがお届けする書籍コラム。
今回ご紹介する書籍は『幸福になりたいなら幸福になろうとしてはいけない: マインドフルネスから生まれた心理療法ACT入門』。本書で紹介されているACTの手法を日常生活の一場面に取り入れてみました。

夏の陽射しが容赦なく差し込む8月のある日、私は自宅のリビングで息子と向き合っていた。
小学生の息子は夏休み真っ只中。
基本的に家で仕事をしている私は、7月・8月は息子と一緒に過ごす時間が長い。
午前中、私はノートパソコンに向かい仕事に励む一方、息子は夏休みの宿題をする。これが我が家の日課となっていた。
夏休みも終盤に差し掛かり、このままのペースでは息子の宿題は終わらない。私は「毎日、国語算数理科社会、それぞれ毎日3ページずつやらないと終わらないよな……」と焦りを感じていた。しかし、息子に焦る様子は全く感じられない。
25分集中して作業を行い、5分休憩するというポモドーロタイマーをセットして、それぞれがやるべきことをスタートした。しかし、息子は1問解いては立ち上がり、ボールを蹴ったり、ソファーに寝転んで漫画を読んだりと、集中力が続かない様子。本気でやれば1時間で終わるであろう問題に3時間程かかった。
丸つけを始めると、思わずため息がこぼれた。止めもハネも意識されずさらっと書かれた漢字。答えだけが記され、計算過程が全くわからない算数の回答欄。
「あのさ、毎回言っているよね。字をきれいに書こうね、式をちゃんと書こうねって」 私の言葉に、息子は「だって……」と小さな声で答える。 やりとりを繰り返すうちに、「何度言っても直す気がないなら、もう好きにしなよ。困るのは自分だよ」と投げやりな言葉を口にしてしまった。
ここ数日、同じようなやりとりが毎日繰り返され、私は疲れ果てていた。夜になると、さまざまな思いが頭の中をぐるぐると巡り、ひとり反省会が始まる。
「勉強させるのが辛い。そもそも無理やり勉強させることに何の意味があるのだろうか……」
「できていないところばかりでなく、頑張ったところに目を向けてあげたい」
「私がイライラしても状況は悪化するだけ。口出しせずに見守れたらいいのに」
そして最後には必ず、「せっかくの夏休み。息子となるべく笑顔で過ごしたいのに」という思いにたどり着くのだ。
子育てに悩む日々が続く中、
「幸福になりたいなら幸福になろうとしてはいけない」という1冊の本に出会った。マインドフルネスに興味を持ち、タイトルに惹かれてネットでポチッと購入した本だ。
この本で紹介されている心理療法ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)は、ネガティブな考えが浮かんだ時に、まず自分の状態を客観的に見つめ、その感情をありのまま受け入れること(アクセプタンス)が大切だと教えてくれる。そして、「この思考は自分にとって本当に役立つのだろうか」と自問し、自分にとって大切な価値に基づいて行動する(コミットメント)ことを勧めていた。
翌朝、「今日は絶対にイライラしないで子どもたちと笑顔で過ごそう」と決めて1日をスタートした。
しばらくすると、息子がリビングにやってきた。寝起きの息子に「おはよう」と声をかけ、ぎゅーと抱きしめる。「よく眠れたかな?」とたわいのない話をしながら、ソファーに横たわる息子の足をマッサージした。
しばらくすると、娘が起きてきて、すぐさまソファーの陣地争いが始まった。朝から繰り広げられる兄妹喧嘩に、思わず「いいかげんにしなさい」と怒鳴りそうになる。
しかし、ふと我に返る。「今日は笑顔で過ごすんだ!」
そして、本に書いてあったことを意識して、心の中でぶつぶつと呟いてみた。
「私は今怒っているという感情を持っている。朝から兄妹喧嘩が始まりすごくイライラしている。だけど、私が怒りを爆発させたところで、兄妹喧嘩が止まるわけでもないし、自分の気持ちがスッキリするわけでもない。むしろ子どもたちにひどいことを言ってしまって自己嫌悪に陥るかもしれないし、兄妹喧嘩が悪化するかもしれない。つまり、今私が持っている怒りの感情は私にとって良いことをもたらさない…….」
そして、兄妹喧嘩をよそに、目を瞑って3回大きな深呼吸をしてみた。鼻から吸う呼吸で、肺に空気が入っていく感覚を味わい、吐く呼吸でお腹の凹みを感じる。呼吸をするたびに、私の中に渦巻くネガティブな感情が少し外に吐き出された感覚を味わう。足の先から脳味噌まで酸素が行き渡り、イライラしているはずの私の口角がちょっぴり上がったように感じた。
「よし、いったんこの場を離れよう」
キッチンに向い、背後で兄妹の言い合う声が聞こえる中、私は黙々とスイカをカットし始めた。 「今、私はスイカを切っている」 目の前の作業だけに意識を向け、包丁を握る手の感触に集中する。
ダイニングテーブルに、スイカとヨーグルトとパンをセットして、「朝ごはんが用意できたよ」と子どもたちに声をかけた。
むすっとした顔で食卓に座る子どもたち。私は平然とスイカを口に運んだ。 「おぉ、今日のスイカ、甘くて美味しい!」
その言葉に反応するように、子どもたちもスイカを食べ始める。娘は両手を頬に当てて「おいしい〜」のポーズ。息子も親指を立ててグッドサインを送った。
普段なら兄妹の言い合いでイライラしてしまうところを、今日は冷静でいられた。そんな自分に心の中でガッツポーズ。
そして、朝ごはんを終えて娘を保育園に送り届けると、再び息子との時間が始まった。
「今日の目標は?」と息子に尋ねる。
「今日は15時までに1教科2ページずつやる!」
「自分で決めた目標を達成できるように頑張ってね」とソファーでゴロゴロ寝転んでいる息子に声をかけた。
タイムリミットの15時を迎えた。理科と社会と国語、1ページずつしか終わっていないようだ。算数に至っては手付かずだった……。
残念ながら、この時点で私の「今日は絶対にイライラしないで子どもたちと笑顔で過ごそう」という目標は達成できなかった。
「あのさ、自分で決めた目標くらいちゃんと守りなよ。もう少し集中して勉強するべきなんじゃない?…….」息子への説教が止まらない。
しばらく立って、怒りが少しおさまってきた頃に、深く呼吸をした。
「私だって、自分で決めた今日の目標守れてないじゃん」
「私が怒るほど、息子のやる気はなくなっていくよな……」
いろんな思考が頭を巡る。
再び深呼吸をして、今日の自分の言動を客観的に振り返ってみる。
本の内容を実行し続けることはなかなか難しい。
きっと私はこれからも子どもたちに怒ったりイライラしてしまうことがあると思う。だけど、その度にこの本を読み返し、「その思考は私の役に立つの?」と唱えて深呼吸をしてみよう。
書籍紹介:
幸福になりたいなら幸福になろうとしてはいけない: マインドフルネスから生まれた心理療法ACT入門 ラス ハリス (著), 岩下 慶一 (翻訳)
義母の死から悟った、生きることの真髄【Editor’s Letter vol. 11】

| Humming編集長 永野舞麻がカリフォルニアから配信する「Editor’s Letter 」。日々の暮らしで感じた気付きや、人生において大切にしていることを綴っています。 |
2ヶ月前、義母と一緒に楽しんだメキシコ旅行。しかし先日、彼女は突然この世を去りました。まだ77歳。アメリカ女性の平均寿命にも届かぬ年齢でした。
彼女と知り合って20年。共に紡いできた思い出が、まるで掌から零れ落ちる砂のように、あっという間に遠ざかっていくような感覚に襲われました。
今まで人生で経験した「死」の中で一番ショッキングだった義母の死。この突然の喪失は、私に深い衝撃を与えると同時に、人生の本質について深く考えるきっかけとなりました。
人生は沈むことが約束された船旅
義母の死を経験したことで、人生は沈むことが約束された船に乗って航海しているようなものだと気がつきました。
私たちが乗っている船は、嵐に遭遇するかもしれないし、船底に穴が空くかもしれない。最終的には、どの船も必ず海底へと沈んでいくのです。しかし、私たちはその運命を知りながらも、船に乗り込みます。
この避けられない終わりに対して、不安や恐怖を感じる方は多いでしょう。それは自然な感情です。しかし、人生には終わりがあるからこそ、私たちは日々の美しさや楽しさ、そして些細な喜びをより鮮明に感じられる。有限であるがゆえに、一瞬一瞬が輝きを増すのだと私は感じています。
全身全霊で今を生きたい
義母と共に過ごした時間は、長かったのか、短かったのか。
夫に出会って、恋をして、彼のことを心から尊敬するようになる中で、義母の子育てがあったからこそ、今の彼がいるのだと気がつきました。長女を授かってからは、義母のような母親になることが私の目標でした。どんな時も、私のことを尊重してくれ、笑いながらアドバイスをしてくれた義母。上手く子どもたちに接することのできない私を「そんなに自分に厳しくしなくてもいいわよ。あなたは毎日とても頑張っているじゃない」と優しく励ましてくれました。
子どもたちが幼かった頃は、毎年、数ヶ月もある夏休みを同じ屋根の下で過ごしたり、ハワイや日本国内を旅行したり、濃密な時間をたくさん一緒に過ごしました。それでも、義母との思い出を振り返りながら、私は自分に問いかけました。共に過ごした時間、彼女と真剣に向き合って話をできていただろうかと。
私たちは「ながら」生活をしがちです。スマートフォンを見ながら会話をし、他のことや、次の返答を考えながら人の話を聞き、未来の心配や過去を後悔しながら現在を生きています。まっさらな状態でいることは、実はとても難しいことです。
当たり前のように存在していた義母が突然いなくなってしまった。この別れを経験し、人生の儚さを痛感すると共に、限りある人生を後悔せずに生きるためには、 目の前の瞬間に全身全霊で向き合うことが大切だと実感しました。とはいえ、今を大切に生きられたとしても、きっと 「もっとこんなところに行けばよかった、こんな話をすればよかった、こんな料理を作ってあげたかった……」という感情は避けられないのかもしれません。
それでも、これからは、子どもが話しかけてきたときには、その子の言葉一つ一つに耳を傾け、抱きしめるように話を聞いてあげたいし、目の前にいる人、今この瞬間の事柄に100%集中したい。同時に、無理をして「聞いているふり」をするのはやめることにしました。余裕がないときは、「今はちょっと難しいけれど、これが終わったら話を聞くね」と素直に伝える。そうすることで、相手との関係もより誠実なものになるのではないでしょうか。
一方で、キャパシティには限界があります。今と真剣に向き合うためには、時間にも心にも余白が必要です。様々な情報やモノに溢れる現代、私たちは自分のキャパシティを超えた状態で生きているのではないでしょうか。そう感じた私は、35歳を過ぎた頃から、仕事を減らしたり、外出の予定を少なくしたり、余白を意識するようになりました。今後も予定を詰め込みすぎず、今を大切に過ごしていきたいと思っています。
関連記事:辞めることで起こったパラダイムシフト。実は色々なことをやりすぎていた?幸せの鍵はLess is More。 【Editor’s Letter vol.08】
死後の世界には何も持ってはいけない
もう一つ、義母の死を通じて感じたことは、モノやお金に執着することの無意味さです。
先日、遺品整理のために義母の家を訪れた時、日常が突然止まったかのような光景を目にしました。机の上に置かれていた図書館で借りたままの本、冷蔵庫の中の食べかけの食品、制作途中のアート作品、洗濯カゴに入ったままの洋服……、義母の生きていた証がそのまま残されていたのです。今にでも義母が帰ってきそうな風景がそこにはありました。
生きる上で、モノやお金は必要です。 しかし、どんなに集めても、築き上げても、死後の世界には何一つ持ってはいけません。この当たり前の事実を痛感し、頭をガツンと叩かれたような気持ちになりました。生まれてきた時と同じように、死ぬ時は誰しも一人ぼっち。自分の体さえも、この世に残して逝くのです。
「これも私の、あれも私の」
「それも欲しい、これも欲しい」
「お金がないと不安、もっと稼がなければ」
モノや人、お金に執着することに、どれほどの意味があるのでしょうか。最期には全てを手放す運命だということを忘れずに過ごせたのなら、多くの執着や固執をその都度手放せるような気がします。
自分にとって本当に大切なものは何か、今手に入れようとしているものは本当に必要なのかを自問し、心から求める必要最低限のものだけを大切にする。そんな生き方を心がけたいと感じました。
生と死の不思議、そして生きる意味
私たちはどんなに一生懸命生きても、最後には魂が抜け、体は動かなくなり、全てを置いて新たな世界へと旅立っていくのです。そして、この世で所有していたものは次々と片付けられていき、残されるのは、子や孫に引き継がれたDNAと、人々の記憶の中にある思い出だけです。
義母が病に倒れた時、誰もその深刻さを予想できませんでした。わずか1ヶ月半前、私たちは一緒にメキシコで春休みを楽しんだばかりだったからです。海水浴や洞窟探検、美味しいメキシカン料理を堪能した思い出が鮮明でした。
当初、検査をしても心拍の不安定さや酸素不足の原因は分からず、気管支炎と何かのアレルギー症状が重なったのかな……と思っていました。その後、大きな総合病院への移転で希望を感じ、血液検査の結果に絶望しました。それでも、心の底には「回復してまた帰ってくる」という想いがありました。「義母はこのまま帰らぬ人となってしまうんだ。一緒に過ごせる時間はあと1週間しかないんだ」という事実と向き合うことになったのは、組織採取をして検査結果が出た時です。巨大な迷路に迷い込んで、どんなに工夫しても、もがいても、どうやっても抜け出せない。そんな途方もない感覚に襲われました。「このまま死んでしまうなんて絶対に嘘だ」と何度も疑ってみたり、今自分が生きているこの現実を夢のように感じたり、「頭が混乱するとはこのような感覚なんだ」と客観視してみたり。
私たちは無意識のうちに、明日も明後日も明明後日も、人生が永遠に続くかのように思い込んでいます。しかし、つい先日まで一緒に楽しく過ごしていた義母の突然の死は、その思い込みを一瞬にして覆しました。
義母との別れは、深い悲しみと寂しさをもたらすと共に、私たちが日々「生かされている」ことの意味を深く考えさせてくれました。限りある人生だからこそ、今この瞬間を大切にし、愛する人としっかり向き合い、自分にとって本当に必要なものを見極めて欲張ることなく過ごしていきたいです。
生かされていることの意味を考えさせてくれたこと。これは、義母が遺してくれた最後の贈り物なのかもしれません。
子どもの愛情不足サインとは?今すぐできる対処法で親子の絆を深めよう

今日もたくさん子どものことを怒ってしまった……。
私の愛情、ちゃんと子どもに伝わっているかな……。
子育てをしていると、罪悪感や不安を感じることがありますよね。
愛情は目に見えるものではありません。形で図ることもできません。さらに、人によって愛情の受け取り方も様々。だからこそ、子どもへの愛情が足りているかどうかを判断するのは難しいものです。
この記事では、よくある子どもの愛情不足サインや、愛情を伝えるための子どもとの関わり方のヒントをお伝えします。
子どもの発育に必要不可欠な親の愛情とは?
子どもの健やかな成長には、親の愛情が欠かせません。まず大切なのは、子どもに安全と安心を与え、その存在をありのままに受け入れることです。
ありのままを受け入れるとは、他の子と比較することなく、その子の個性を認め、成長を喜ぶことです。
また、子どものさまざまな要求や気持ちをくみ取り、受け止め、応えることも大切です。子どもの感情や行動を否定せず、まずは受け入れる姿勢を持つことで、子どもは「自分は大切にされている」と感じ、安心して成長していけるでしょう。
同時に、成長に合わせて自立を促すことも重要です。例えば、幼児期なら自分で服を選んで着替える、小学生なら学校や習い事の支度を自分で行う、お風呂掃除やゴミ捨てなど家事を手伝うなど、年齢に応じて責任ある行動を任せていきます。
適切な制限を設けることも愛情表現の一つです。就寝時間やスマートフォンの使用時間を決めるなど、子どもの健康や安全を守り、規則正しい生活習慣を身につけさせます。
親自身が良い手本となり、子どもの成長を温かく見守り、必要な時にサポートすること。そして、言葉や行動で愛情を伝えること。これらを通じて、子どもは自分が愛されていると実感しながら、健やかに育っていくでしょう。
愛情不足のサインとは?
では、親からの愛情が不足していた場合、どのようなサインが子どもに現れるのでしょうか。よくある2つの変化をご紹介します。
やる気が出にくくなる
子どもは愛されていると感じると、いろいろなことに挑戦する元気が湧いてきます。一方で、愛情不足の場合、朝布団から出るのが辛くなる、好きだった習い事に行きたがらなくなるなど、やる気が低下することがあります。
愛情を確かめる行動をとる
子どもは、自分が本当に愛されているのかを不安に感じた時、親の愛情を確かめるためにお試し行動をとることがあります。
例えば、いつもより「抱っこして」と甘えん坊になる、わざといたずらをして親を困らせる、親の言うことを全く聞かないなど。「親はこんな自分でも愛してくれるのか?」を試しているのです。
さらに愛情不足の状態が続くと、大人になってからも様々な影響が出る可能性があります。
- 自己肯定感の低下
- 他者を信頼することが難しく、深い人間関係を築くのに苦労する。
- 他者からの評価に過度に依存し、自分の価値を見出すのが難しくなる。
- 特定の人に過度に依存したり、逆に誰とも深い関係を持てなくなったりする。
など。
しかし、これらの状態は、親の愛情不足だけが原因なわけではありません。
例えば、入学・転校・引越し、兄弟の誕生などの環境の変化、受験勉強や友達関係でのストレス、子ども自身の性格や気質など、さまざまな要因が関係していることがあります。
そのため、子どもの変化に気がついた時は、「愛情不足かも.」「私のせいだ」と自分を責める必要はありません。大切なのは、子どもの様子をよく観察し、子どもの変化に気づき、寄り添う姿勢を持つことです。

愛情不足かも?と感じた時の4つ対処法
最近子どもの癇癪が激しい……。
なんだか様子がいつもと違うな……。
もしかして、愛情不足……?
違和感を感じた時には、以下の4つを心がけてみましょう。
「大好きだよ」「ありがとう」言葉で愛情を伝える
言葉で愛情を伝えることは、親子関係を深める最も簡単で効果的な方法です。「あなたのことが大好きだよ」、「生まれてきてくれてありがとう」と素直に表現することで、子どもに直接的に愛情を伝えることができます。
子育てをしていると、ついつい子どものネガティブな面に目を向けがちです。しかし、意識的に子どものちょっとした頑張りや良いところに目を向けて言葉で伝えてあげると良いでしょう。また叱る必要がある時でも、まず子どもの気持ちを聞き、理解しようとする姿勢を示すことが大切です。
スキンシップを大切にする
スキンシップは子どもに安心感を与える重要な愛情表現です。学校に行く前にギュッと抱きしめたり、寝る前に頭を撫でたり、時にはオイルでマッサージしてあげるのも効果的です。
肌と肌が触れ合うことで、愛情ホルモンと呼ばれるオキシトシンが分泌されます。このホルモンは、心身のリラックスを促し、ストレス軽減にも役立ちます。
そのため、スキンシップをすることで、子どもに愛情が伝わるだけでなく、親もより穏やかな気持ちで子育てに向き合うことができるでしょう。
1日10分でもOK。子どもに100%集中する時間を持つ
子どもと向き合う時間を意識的に確保することも効果的です。大切なのは時間の長さではなく質。
例えば、毎日10分間、その子のためだけの時間を確保する。目を見て話を聞いたり、一緒にお絵かきをしたり、その子が望むことを叶えてあげる時間が持てると良いですね。
質の高い時間を親子で過ごすことで、子どもは「自分は大切にされている」と感じることができるでしょう。
自分自身がご機嫌でいること
親自身が心身ともに健康でないと、子どもに十分な愛情を注ぐことは難しくなります。だからこそ、親自身がご機嫌でいることが大切です。美味しいものを食べたり、趣味を充実させたり、たまにはひとりでリラックスする時間を持つことも大切です。
また、親がイキイキとした姿を見せることで、子どもも自分を大切にすることを学んでいくでしょう。
完璧を目指さない、親子で成長することが大切
毎日笑顔で愛情たっぷりに子どもと接したいと思っていても、思い通りにいかないのが現実です。
疲れて余裕がなくなり、子どもにイライラしてしまうときや、仕事に追われて子どもの話をゆっくり聞いてあげられないときもあるでしょう。
しかし、親だって人間です。完璧な人間などいません。だからこそ、自分の不完全さを認めつつ、愛情を伝えながら、親も子どもと一緒に成長していく。それこそが、最高の愛情表現になるのかもしれません。
ポリアモリーの特徴は?浮気と何が違うのか誤解されやすいポイントを解説

現在の社会は、男性・女性といった枠組みを超えた様々な恋愛観が受け入れられ始めています。
LGBTQ+と呼ばれる性的マイノリティの方々に対しても、専用のトイレが作られたり、アンケートにて性別を答える必要がなくなったりといった配慮が見られることが増えてきました。
一方、1990年代頃から始まったとされる「ポリアモリー」は、未だ世界中に受け入れられているとは限りません。
今回はポリアモリーの特徴や招きやすい誤解、本人たちがどのような悩みを抱えているのかについてご紹介します。
ポリアモリーとは?

ポリアモリーとは、複数の相手と恋愛関係にあり、その状態が許容されている状態を指します。
一見浮気のようにも思えますが、複数の相手とそれぞれ合意の上で恋愛をしているため、本人たちの中では何ら問題がないのが特徴です。
周囲に偏見の目で見られることも多く、ポリアモリーであることを隠している方も少なくありません。
日本は古くから一夫多妻制の国であるため、ポリアモリーに対して良い印象を抱かない人が多いという特徴があります。
そもそもポリアモリーという言葉を知らず、単なる浮気だと感じている方も多いでしょう。
ポリアモリーの方々は、こうした偏見の目にさらされながらも、自身の好む生き方を貫いているのです。
そもそもポリアモリーは、1990年代頃をきっかけに広まり始めました。
ギリシャ語の「ポリ(複数)」と、ラテン語の「アムール(愛)」を組み合わせた造語であり、浮気や不倫とは異なる形態として確立されています。
ポリアモリーの生き方を実践している人のことを「ポリアモリスト」、ポリアモリストが形成する家族を「ポリファミリー」などと呼びます。
日本では「複数愛」などと呼ばれることも多いため、覚えておくと良いでしょう。
ポリアモリーの特徴
ポリアモリーが一般的な浮気や不倫と違うのは、大きく分けて3つのポイントがあるためです。
それぞれの特徴をしっかりと理解し、ポリアモリー特有の考え方を理解していきましょう。
全員が合意している
ポリアモリーの特徴として挙げられるもののうち、もっとも大切なのが「それぞれの関係を全員が知っている」という点です。
A子さんがB太さん・C男さんの両方と付き合っていた場合、B太さんとC男さんはお互いの存在を知っており、さらに合意している状態がポリアモリーです。
中にはB太さんとC男さんがA子さんの予定を細かく把握しており、「今日は違う相手と会う日だな」と理解している場合もあります。
A子さんはB太さん・C男さんのいずれにも存在を隠す必要がないため、自然のままに振舞えるのが特徴です。
B太さんに対し、「昨日はC男さんと〇〇をした」と報告することもでき、ストレスのない関係性を築けるでしょう。
また、A子さんというパートナーがいるB太さん・C男さんは、それぞれ別の女性とお付き合いしている可能性もあります。
完全なるポリアモリーでは、B太さん・C男さんのそれぞれがお付き合いしている女性も、この複数愛を理解し、合意していなければなりません。
ポリアモリーに合意できる人はそれほど多いとは限らないため、ポリアモリスト同士が惹かれ合い、大きなコミュニティとなる可能性も高いでしょう。
持続的関係
ポリアモリーは必ずしも身体の関係があるとは限りません。
複数の相手がいることを合意していたとしても、一夜限りの関係ではポリアモリーとは呼べないでしょう。
何ヶ月、何年と関係が続くかは人によって異なりますが、いずれも持続的な関係を目的としており、一般的な恋愛と同じように時間をかけて信頼関係を構築しているのです。
また、ポリアモリストの中には相手へ恋愛感情を抱いている人もいれば、精神的な安心を求めていたり、経済的に支え合ったりする目的の人もいます。
結婚をするつもりはないが老後に一人で暮らすのは心配だという方や、子育てに自信がなく大勢で協力してやりたいと願っている方なども、ポリアモリーに当てはまるでしょう。
相手を所有しない
ポリアモリーでは、相手とパートナー関係にあるのみで、そこに束縛する目的はありません。
いくら複数愛に理解を示していても、相手は独立した考えを持った個人であり、尊重されるべき存在です。
「自分には複数のパートナーがいるが、あなたには自分だけを見ていてほしい」といった考えがあったとしても、相手の考えを理解した上で、お互いが納得できる答えを見出すのが特徴です。
ポリアモリスト同士の間では強固な信頼関係が構築されていますが、その根底にあるのは入念なコミュニケーションです。
相手の気持ちを知り、自分の気持ちを包み隠さずに伝えることで、お互いを尊重した関係性を築けるのではないでしょうか。
ポリアモリーへの誤解

ポリアモリーには複数のパートナーがいますが、日本ではまだまだ一般的な考えではありません。
それ故に周りへポリアモリストであることを明かすと、あらぬ誤解を生む可能性があるでしょう。
ポリアモリーに関する誤解は、口に出してしまうと相手が傷つくようなものばかりです。
相手の恋愛観に疑問を持った場合でも、安易に口に出すことはせず、ポリアモリーに関して正しい知識を付けることが大切です。
性に奔放
ポリアモリーは必ずしも性行為をするための関係ではありません。
身体的な快楽よりも精神的な安心を求めてパートナーを増やす人も多く、性に奔放であるとはいえないでしょう。
中には数々のパートナーと性行為に及ぶ方もいますが、これは私たちが特定のパートナーを選ぶのと同じで、愛する人と身体を重ねたいという思いから来る行動です。
数々の異性と性行為に及びたいだけならば、短期間の間にパートナーをコロコロと変えたり、一夜限りの関係を求めたりするでしょう。
ポリアモリーは通常の恋愛と同じく、会話やデートを重ねてお付き合いへと発展させていきます。
信頼関係を構築して初めて性行為へと繋がっていくため、慎重に性行為へ及ぶ方もたくさんいます。
複数でのセックスがすき
複数のパートナーがいるポリアモリストは、パートナー同士がお互いの存在を知っていたり、時には複数人で会ったりする場合があります。
大勢が属するコミュニティができている場合も多く、同じ考えを持った人が集うため、コミュニケーションも弾みやすいでしょう。
しかし、パートナーが大勢いるからといって、大勢で性行為へ及ぶわけではありません。
複数のパートナーと順番に会い、それぞれ1対1で性行為に及ぶ方がほとんどです。
もちろんグループセックスに同意していれば複数で性行為に及ぶ可能性もありますが、それが全てではないことを覚えておきましょう。
長く続かない
前述のA子さんを例に挙げて考えてみましょう。
A子さんにはB太さん・C男さんというパートナーがいますが、B太さんには別にD美さんという女性が、C男さんにはE奈さんという女性がそれぞれパートナーになっている場合があります。
この場合、A子さんがD美さん・E奈さんに嫉妬してしまい、関係がこじれてしまうのではと考える方も多いのではないでしょうか。
もちろん、ポリアモリスト同士の恋愛であっても、嫉妬により関係が終わってしまうことがあります。
しかしこれがすべてではなく、念入りなコミュニケーションの元、嫉妬の感情とうまく付き合っている人もたくさんいます。
ポリアモリストだからといって長続きしないとはいえず、一般的な恋愛と同じレベルで破局の可能性があるだけなのです。
遊びたいだけ
ポリアモリーを自認する方の多くは、精神的な安心を求めてパートナーを増やしています。
信頼関係を構築した上で性行為に及ぶことはあっても、身体だけで繋がる関係ではないことを覚えておきましょう。
真剣に考える対象が多いというだけで、真剣さの度合いは一般的な恋愛と変わらないため、ポリアモリー=遊びといった考えは間違いです。
関連記事:マイノリティ・マジョリティとは? 多様な社会の理解を深めるために
ポリアモリーの悩み
ポリアモリーを自認し、信頼できるパートナーができても、実際にはさまざまなデメリットに悩まされている方が多いでしょう。
ポリアモリストだからといって好き放題に生きている、と考えるのは間違いで、一人ひとり異なる悩みを抱えているものです。
続いてはポリアモリーならではの悩みをご紹介し、一人ひとりを理解するための準備をしていきましょう。
周囲が理解しづらい
先ほどもご紹介したように、日本をはじめとする各国では複数愛の考えが広まっておらず、周囲の理解が得られにくいといった特徴があります。
中には精神的な病を抱えているのではと、精神科や心療内科の受診を勧められた経験のある方も多いようです。
ポリアモリーを自認するパートナーと出会えた場合でも、家族や友人からの理解が得られず、泣く泣くパートナーとの別れを選ぶ方もいます。
婚姻制度に向かない
ポリアモリストにとって、婚姻制度はどのように利用すべきか頭を悩ませるポイントとなります。
日本では2人目のパートナーと結婚することはできないため、複数のパートナーがいる場合、誰と結婚すべきか迷ってしまうことも多いでしょう。
逢えて誰とも結婚せずにいたり、書類上は1人を選んで結婚をし他のパートナーとは事実婚をしたりといった対応を選ぶ方もいます。
誤解されやすい
周囲に理解されにくいのと同時に、誤解されやすいのも注意したいポイントです。
先ほどご紹介したような性的誤解を中心に、周りから傷つく言葉をかけられたり、不思議だからといって避けられたりする場合があります。
こういった差別は「自分とは違うものを排除する」といった人間の行動が根底にあり、なかなか完全になくせるものではありません。
ポリアモリーを理解するために

ポリアモリストであると公表している人はもちろん、未だ周りに公表できずに困っている人がより過ごしやすい環境を整えるためには、ポリアモリーについてしっかりと理解することが大切です。
身の回りにポリアモリーを自認する方がいたとき、そうでない方と同じように接するためにも、理解すべきポイントを学んでおきましょう。
ポリアモリーについて知る
ポリアモリーの大きな特徴として、「複数人のパートナーと対等に、誠実な関係を結んでいる」という点が挙げられます。
この根底を理解していないが故に、浮気症ではないかと悪口を言ったり、理解ができないと突っぱねたりしてしまうでしょう。
まずはポリアモリーを自認する人々と交流し、その考えについて知ることで、彼らが不誠実な目的で恋愛をしているのではないことが分かるはずです。
嫉妬と向き合う
ポリアモリーは複数のパートナーがいるため、精神状態によっては嫉妬の気持ちが沸き上がってしまう場合があります。
この嫉妬心は見て見ぬふりをしていても始まらず、誠心誠意向き合うことで自分自身の感情を整理することができます。
どうして嫉妬してしまうのか、パートナーにどうしてほしいのかといった希望を口に出し、モヤモヤとした気持ちと向き合ってみましょう。
また、嫉妬心が芽生えたときは、相手とコミュニケーションの機会を増やしてみると良いでしょう。
素直に嫉妬していることを伝え、相手の気持ちを考慮した上で、お互いが納得できる解決策を見出すことが大切です。
浮気との違いを理解する
記事の冒頭からここまでご紹介してきた内容を見ると、ポリアモリーが浮気ではないことが理解できるでしょう。
とはいえ文字や言葉で説明を受け理解した気になっていても、実際にポリアモリストを目の前にしたとき、心が受け付けない場合も考えられます。
どうしても本来の意味でポリアモリーが理解できないと感じた場合は、ポリアモリーを避けるのではなく、反対に積極的な対話をしてみるのがおすすめです。
「ポリアモリストの1人」として捉えるのではなく、「〇〇さん」といった個人で考えることにより、その人の本質を理解できるようになるでしょう。
個人が恋愛に関してどのように考えているのかを知ることで、複数愛全体に対してではなく、目の前の一人へしっかりと向き合えるようになります。
多様性と向き合う
今回ご紹介したポリアモリーは、多様性の中の一部です。男性が男性に恋をしたり、女性が女性に恋をしたりと、現代にはさまざまな恋愛の形があります。
ポリアモリーについて学んだことをきっかけに、様々な恋愛の多様性と向き合ってみると良いでしょう。
関連記事:ノンバーバルコミュニケーションと対人関係|恋愛においての重要性とは
まとめ
未だ日本では一般的ではなく、様々なシーンで誤解を生みやすいポリアモリー。
しかし彼・彼女たちの間では、一般的な恋愛よりも念入りなコミュニケーションが行われ、お互いへのリスペクトが存在しています。
彼ら全体を受け入れようと努力するのではなく、一人ひとりに目を向けて理解を目指すことで、あらゆる恋愛観と向き合えるでしょう。
gd2md-html: xyzzy Fri Aug 02 2024
ナラティブとは?ナラティブアプローチを利用して良好な関係構築

ナラティブ(narrative)とは「物語」という意味を持つ単語ですが、ビジネスシーンでしばしば使われる言葉でもあります。
ナラティブの考え方を用いることで問題をスピーディに解決できるようになるほか、対人関係を円滑に保つためにも重要です。
いかなるコミュニティに属する場合でも、ナラティブアプローチを利用し、誰もが活動しやすい環境を整えてみてはいかがでしょうか。
今回はそんなナラティブがどのように生まれ使われるようになったのか、歴史から理解するためのポイントまでを総合的にご紹介します。
実際に生活の中でナラティブアプローチを利用すべく、基本的な流れについても学んでおきましょう。
ナラティブの意味は?

ナラティブとは、日本語に訳すると「物語」という意味があります。
私たちがイメージする童話のような物語とはいくつかの違いがあり、耳にしただけでは理解が難しい場合もあるでしょう。
まずはナラティブの本質的な意味と、同じく物語という意味を持つ「ストーリー」とは何が違うのかをご紹介します。
ナラティブの概要
ナラティブという言葉は、ビジネスシーンや医療現場など様々な場面で使われています。
職種によっては聞き慣れない場合もありますが、本来はどのようなシーンにおいても活用できる考え方といえるでしょう。
大まかな意味は知っていても、実際に生活の中で活用できている人は少なく、まだまだ浸透しきっていないのも特徴です。
ナラティブの語源はラテン語であり、話す・関連づける・説明するといった意味を持ちます。
つまり、ビジネスシーンや医療現場においては、ナラティブ=物語の力を使って他者へ分かりやすく物事を説明し、購買意欲を掻き立てたり、自分に合う医療を選択しやすくしたりできるのです。
ナラティブを利用する側は自分の主観ではなく、俯瞰的な視点で説明ができるため、自分の理解を深められるのもポイントといえるでしょう。
ナラティブアプローチを用いて説明すると、製品やサービスの概要を淡々と説明するのに比べ、相手の心が動きやすいという特徴があります。
多くの対象に対して一貫した説明をするのではなく、目の前にいる相手のことだけを考えて話ができるのもメリットの一つです。
ナラティブとストーリーの違い
ナラティブと同じような意味を持つ単語として挙げられるのが「ストーリー」です。
どちらも物語という意味を持ちますが、両者には明確な違いがあるため、改めて確認しておきましょう。
ストーリーとは、起承転結がハッキリしており、主人公視点で進む物語を指します。
私たちが普段から触れている小説や漫画・映画などは、ストーリーを意識して作られているものが多いでしょう。
主人公視点での世界観は誰が見ても同じように捉えられやすい一方、主人公以外のところで起きている物事に関しては理解が及びにくいというデメリットがあります。
一方のナラティブは、主人公を含めた出来事の全てを俯瞰的に見ながら、話し手と聞き手が同時に物語を追っていくのが特徴です。
これから先の未来に何があるのかは分からず、話が進むにつれて様々な事象が明らかとなります。
ナラティブはいわば人生のようでもあり、未だ完結していないのもポイントです。
ナラティブはいつから使われるようになった?
ナラティブの考え方が使われるようになったのは、元を辿れば1960年頃のフランスにさかのぼります。
この頃のフランス文学には様々なシーンでナラティブが使われており、読者をより深く物語の世界に取り込み、没頭させられるとして話題になりました。
そんなナラティブを実生活で活用するようになったのは、1980~1990年代が始まりだといわれています。
元は臨床心理学で利用されたことから始まり、一人ひとりの抱えている問題を物語形式で語ることで、様々な視点から解決策を見出すために活用されました。
現在も利用者側・患者側に立つとなかなか気が付かないものの、生活の中でナラティブが利用されている場面は多々存在します。
ナラティブを理解するために

ナラティブを実生活で利用するためには、本質を正しく理解しなければなりません。
背景にある社会構成主義
ナラティブが実際の生活で利用されるようになったのは、1980~90年が最初だといわれています。
文学作品から飛び出したナラティブは、社会構築主義をベースとして発展していきました。
今あるすべての出来事は人間の頭で想像したことだ、と考える社会構築主義は、現在の社会にも広く根付いています。
例えば、片思いをしている男性がいたとします。彼の中でその思いは単なる恋ですが、周りがどう思うかによって状況は大きく変化するでしょう。
周りが彼の思いを応援すると「純愛」になりますが、彼の思いがストーカーだと思われてしまえば、それは「犯罪」になってしまいます。
こういった社会全体の考えが出来事の本質を左右するのも、社会構築主義の特徴です。
しかし私たちは誰もが、少なからず物事に関するフィルターを持っています。
上記のケースでいえば、物事の本質を見ないまま、「男性なのだからどうせストーカーだろう」などと決めつけてしまうことも多いでしょう。
こういったフィルターによって本質が曲げられてしまうことがないよう、俯瞰的に物事を見ながら、もっとも正しい答えを見出していくことがナラティブの役割なのです。
ドミナントストーリーとオルタナティブストーリー
ナラティブを理解するためには、ドミナントストーリーとオルタナティブストーリーについて学ぶ必要があります。
ドミナントストーリーとは、直訳すると「支配的な物語」という意味を持ちます。
ドミナントストーリーは問題を抱えている当事者が感じる内容がすべてであり、他の可能性については触れていません。
「〇〇はこうである」といった思い込みが反映されているため、当事者は変えることができないと信じており、考えが凝り固まってしまっているのも特徴です。
これに対しオルタナティブストーリーは、「代替の物語」という意味の単語です。
固定されたドミナントストーリーに対し、様々な可能性を考慮したオルタナティブストーリーを考えることで、問題に対しあらゆる視点で解決策を講じることができます。
ドミナントストーリーとオルタナティブストーリーを語る際に例として挙げられやすいのが「アリとキリギリス」の物語です。
私たち日本人は幼い頃からの固定観念で、「働き者のアリと怠け者のキリギリスの話」だと思い込んでいます。
これはドミナントストーリーであり、一見これ以外の解釈はないようにも思えます。
しかしオルタナティブストーリーの考え方では、キリギリスは怠け者なのではなく、短い寿命を謳歌するために歌い暮らしていたのかもしれない、と考えます。
キリギリスには病気の友人がおり、彼を勇気づけるために歌うのをやめなかったのかもしれません。
物語の中に書かれていない可能性にも注目し、新たな可能性を考えることが、オルタナティブストーリーの役割です。
モノローグとダイアローグ
モノローグは「一人で語ること」、ダイアローグは「対話をすること」と訳されます。
物語をモノローグで語ると、視点が偏り、ドミナントストーリーのように意味合いが固定されがちです。
語り手の世界観がすべてとなるため、聞き手にも同じようにその世界観が引き継がれるでしょう。
これに対しダイアローグで物語を語るとき、語り手同士の会話の中では、これまでに見られなかった新たな考えが生まれる可能性があります。
その瞬間から物語はあらゆる可能性を含み、どのような展開になるか予想できなくなるでしょう。
ナラティブアプローチとは?

ナラティブが話し手と聞き手によって紡がれる物語である、と説明を受けても、それがビジネスシーンや医療現場でどのように活用されるのか分からない方も多いものです。
まずはナラティブを使ったアプローチ方法がどのような目的で導入されているのか、その役割について確認していきましょう。
ナラティブアプローチの概要
ナラティブアプローチとは、自分と相手が対話する中で様々な可能性を見出し、問題解決へと駒を進めていく方法です。
自分の思い描くドミナントストーリーを大切にしながら、相手の意見を取り入れてオルタナティブストーリーを展開することで、あらゆる可能性に気が付くでしょう。
このとき自分と相手は必ず対等な関係であり、どちらの意見も同じく尊重されなければなりません。
シーンによっては、対話の相手が医師と患者であったり、専門家と一般人であったりと、知識量に差がある可能性も考えられます。
こういった場合でも両者が対等であることは変わりなく、お互いを尊重しながら対話をすることが大切です。
どんな目的で導入されている?
ナラティブアプローチが導入されている場面として分かりやすいのは医療現場です。
医師と患者、もしくは看護師と患者がナラティブアプローチによって対話を行うことで、単なる病気の内容とその治療法を話し合うだけでなく、患者の生活や金銭面への負担、精神状況を踏まえた最適な治療方法を見出すことができます。
医師や看護師側は患者目線での物語を聞くことで、今までに気が付かなかった可能性を考慮し、より負担の少ないケア方法を提案できるでしょう。
これはビジネスシーンでも同じであり、カスタマーを主人公として物語を作成することで、企業側が気が付かない可能性を見出し、より顧客に合った満足度の高いサービスを実現できます。
同じように、教育や福祉シーンでも活用の幅が広がる考え方だといえるでしょう。
ナラティブアプローチの流れ
ナラティブアプローチに関する知識が深まったところで、実際に生活の中で利用する際の流れを確認してみましょう。
今回はビジネスシーンを例に挙げ、問題解決に行き詰まり、良い案の浮かばない状態であると仮定してご紹介します。
ドミナントストーリーを聞く
ナラティブアプローチの目標は、ドミナントストーリーをオルタナティブストーリーへと書き換え、その中であらゆる可能性を見出すことです。
まずは悩んでいる相手とそれぞれドミナントストーリーを作り、お互いに発表し合いましょう。
同じ問題に対処しているにもかかわらず、人によってドミナントストーリーの内容が異なるため、これだけでも新たな気づきがあるかもしれません。
この際に大切なのは、相手がどんな内容を言ったとしても、否定せずに聞くということです。
話の途中で口を挟んだり、「ここは〇〇の方が良い」などとアドバイスしてしまうと、ドミナントストーリーの意味がなくなってしまうでしょう。
問題を外在化する
続いて、ドミナントストーリーを元に問題を外在化していきます。
目に見える形で問題を提起することで、より分かりやすく解決策を講じられるようになります。
今回の場合、もっとも大きな問題は「売れる製品が作れない」ことだとします。
試作品をいくつ作っても上司にOKをもらえなかったり、販売にこぎつけた製品も思うように売れなかったりといった問題が出てくることでしょう。
続いて、その中からもっとも重要な問題を選びます。今回は製品を売る前に、まず社内でOKが出るような製品案を作らなければなりません。
ここに焦点を絞り、第一の目標を立てることで、効率的に問題を解決できるようになります。
反省的な質問をする
続いて、お互いに対し反省的な質問を行います。
時間をかけて編み出した製品案にどうしてOKがもらえないのか、改善すべき点について反省会を行いましょう。
このときの反省点は、具体的であればあるほど良く、さまざまな可能性を見出しやすくなります。
例外的な結果を見出す
質問を投げかけた方は、返答に対しどのような結果が見出せるのかを考えます。
「〇〇という製品が良いと思ったが、却下された」という反省点の中にも、実は予算面で却下されていてもデザインは好評を得ていたり、成功には至っていないものの着眼点は良いと褒められていたりする場合があります。
こういった気づきにくい例外的な結果を見出してあげることで、これまでに気が付かなかった視点から問題にアプローチできるようになります。
オルタナティブストーリーを構築する
ここまでのステップをクリアしたら、いよいよドミナントストーリーに対するオルタナティブストーリーを構築します。
これまでに出た例外的な結果を全て含め、ありとあらゆる道筋を考慮した物語を作りましょう。
実は初期段階で褒められた内容が、製品の完成に大きく貢献してくれる場合もあります。
「〇〇はダメだ」と言われた内容が、実は「△△ならば良い」と捉えることで、新たなアイディアが浮かぶこともあるでしょう。
こういった考えを一人で行うのではなく、対話形式で整理しながら行うことで、より効率的な問題解決に繋がるのです。
ナラティブアプローチのメリット

ナラティブアプローチを定期的に取り入れることは、様々なメリットを生み出します。
今回はナラティブアプローチ導入の参考となるよう、メインとなる3つのメリットをご紹介しましょう。
良好な関係を築きやすい
ナラティブアプローチは他者との対話があって成り立つため、コミュニケーションの機会が増え、対人関係が良好になりやすいのが特徴です。
話し手と聞き手の関係は必ず対等となるため、普段の地位や立場に関わらず、平等に話ができるでしょう。
これまでに会話の機会が得られなかった相手とナラティブアプローチを行うことで、新たな信頼関係の構築にも繋がります。
解決策の幅が広がる
ナラティブアプローチを使って問題に対応することで、これまで気づかなかった解決策を取り入れ、様々な面から取り組めるのがメリットといえます。
目上の人から「こうしなさい」と命令されるのではなく、相手との対話の中でお互いに気づいた可能性を試していくため、自分の意にそぐわない方法であってもスムーズに受け入れられるでしょう。
能動的に実行しやすくなる
ナラティブアプローチを使って見出された解決策に対しては、話し手と聞き手の両方が納得した上で出てきたものであることが多く、より能動的に実行されやすいでしょう。
他者から「こうしなさい」と指示されたことよりも、自分で動こうと決めた解決策の方が、よりやる気が湧いてくるのではないでしょうか。
あらゆるシーンでナラティブアプローチを取り入れることで、日頃の作業効率が上がったり、問題に対しポジティブに対応できたりするのもメリットの一つです。
関連記事:マイノリティ・マジョリティとは? 多様な社会の理解を深めるために
まとめ
ナラティブを使ったアプローチ方法は、医療・教育・福祉などの専門分野はもちろん、ビジネスシーンでも多く使われる手法です。
私たちの身近にある問題を総合的に解決できるようになるため、日頃から積極的に取り入れると良いでしょう。
相手との対等な会話ができる点から、その場の雰囲気を改善し、人間関係を良好に保てる点にも注目してみてはいかがでしょうか。
gd2md-html: xyzzy Fri Aug 02 2024
ポリコレとは?その歴史や問題点、向き合い方を解説

社会にはびこる様々な差別をなくすべく、あらゆる場面で平等が呼びかけられている現代。
その中でもひときわ耳にしやすいのが「ポリコレ」ではないでしょうか。聞いたことはあっても本来の意味を知らずに使っている方も少なくありません。
今回はそんなポリコレが持つ本来の意味を始め、海外と日本におけるこれまでの歴史や、現在指摘されている問題点についてご紹介します。
私たちがポリコレとどう向き合うべきなのか、今後の見通しについても確認していきましょう。
ポリコレとは?

ポリコレとは、「ポリティカルコレクトネス(political correctness)」を略して呼びやすくした単語です。
直訳すると「政治的な正しさ」となりますが、現在は政治以外の場面でも使われることが多いでしょう。
ポリコレが訴えるのは、私たち人間があらゆる違いに悩まされず、皆平等に生きられるような社会です。
人種・性別・年齢・国籍・学歴・障害の有無など、私たちは様々なシーンでマイノリティを除外してしまいがちです。
マイノリティに当てはまる人々を直接傷つけようとしていなくても、無意識のうちに行う差別が人々を傷つけているかもしれません。
ポリコレはこういった差別が自然と行われている社会を正し、誰もが周りを気にすることなく生きられるのが正しい社会の在り方だとしているのです。
ポリコレの考え方は古くから人々の間に根付いていましたが、社会全体を巻き込む運動となったのは、一人ひとりの中に差別に対する意識が芽生え始めたためだと考えられます。
この運動がさらに広がりを見せ、誰しもが差別に対し否定的な考えを持つことで、ポリコレは決して特別な運動ではなくなるでしょう。
ポリコレの歴史
ポリコレの歴史は、海外と日本で大きな違いがあります。
いち早くポリコレの考え方が広まり始めた海外に対し、日本の場合は近年になって初めて社会的現象となりました。
両者の違いを見比べながら、今後のポリコレがどう展開していくのかを予想してみましょう。
海外
世界的なポリコレの発祥は、およそ1900年頃までさかのぼるといわれています。
白人とそれ以外の人種で対立を深めていた地域が多い中、アメリカを中心に差別に対する否定的な考えが広まり始めます。
代表的な変化として挙げられるのが、それまで差別の対象であった「インディアン」が「ネイティブアメリカン」と呼ばれるようになったこと。
目に見える変化があったことで、多くの人が無意識のうちに行っていた差別に気が付くようになったのです。
また、ポリコレがアメリカ発祥とする説に対し、ロシア革命が発祥とする考え方もあります。
こちらはポリコレが持つ本来の意味である「政治的平等」を訴えるための運動であり、どちらが正しいかは分かっていません。
しかし、いずれにしても海外でのポリコレは1900年代と早い段階で広まっており、白人優位主義から脱却することをメインに訴えたものでした。
これが転じて、女性の権利を訴える「ウーマン・リブ運動」など、様々な運動へと繋がっていったのです。
日本
1900年代にポリコレの考えが広まった海外に対し、日本では2010年代に入ってようやく変化が訪れます。
インターネットが広まるにつれてポリコレが浸透し始め、性別や年齢・地位・居住地など様々なシーンで行われる差別について考えられるようになりました。
日本で起こったポリコレの中でも、ひときわ注目を集めたのが男尊女卑に対抗する考え方です。
男性は外で働き女性は家事・育児をするといった考え方に問題があるとして、女性であっても社会に進出し、職場で相応の地位を獲得する権利があると訴える人が多く現れました。
この考え方は、現在も多くの方が訴える「フェミニズム」の始まりでもあります。
ポリコレの身近な具体例

「ポリコレ」という言葉は知っていても、具体的にどのような変化があったのか詳しく理解している方は少ないでしょう。
私たちの身近な場所でも、ポリコレの考えによって様々な変化を遂げたものが多く存在します。
これらが差別を是正するために変化したことを知り、ポリコレについて正しく学ぶことこそが、差別のない未来づくりに必要なことだといえます。
人種における表現
先ほどもご紹介したように、アメリカの先住民は今まで「インディアン」と呼ばれていました。
大航海時代、アメリカをインドと間違えて上陸したことからつけられた呼称であり、現在はポリコレの考えにのっとって「ネイティブアメリカン」へと変更されています。
日本人にとってインディアンとネイティブアメリカンの問題はそれほど身近ではないため、今もインディアンと呼んでしまう方がいますが、差別の歴史を肯定することに繋がるため注意が必要です。
また、白色人種・黄色人種・黒色人種の間で行われる差別も顕著であり、特に黒色人種が被害を受けるシーンが多く見られました。
その際、黒色人種は「ブラック」と呼ばれて差別の対象となっていましたが、現在は「アメリカンアフリカン」と改められています。
日本では色鉛筆やクレヨンのカラーに「肌色」という呼称が使われていましたが、すべての人に当てはまる肌の色ではないといった考えから、「うすだいだい」「ペールオレンジ」などと呼ばれるようになっています。
さらに、近年の美容業界では、「美白」の表現に疑問を唱える方が増えています。
白であれば美しいといった考えを改めるべく、日本では花王株式会社が先頭に立ち、「美白化粧品」などの表現を中止すると発表しました。
性別における表現
性別における表現は、これまで何も考えずに使ってきた方も多いことから、なかなか呼称を改めにくいのが現状です。
この根底にあるのは、「男性はこういった仕事に就くことが多い」「この仕事は女性向きである」といったナチュラルな差別。
性別を問わず自分の目指す仕事に就けるよう、下記のような表現の変更が行われています。
- カメラマン→フォトグラファー
- ビジネスマン→ビジネスパーソン
- 保母→保育士
- 看護婦→看護師
- スチュワーデス→キャビンアテンダント
「マン」と名の付く職業は全て男性を想起させるため、「パーソン」への変更が進められています。
「スポーツマン」なども、現在は「アスリート」と呼ぶ機会が増えているでしょう。
反対に女性を想起させる保母や看護婦なども、男性を含めた呼称として改められています。
指向・思想における表現
マジョリティとマイノリティの差が顕著になりやすいのが「性別」です。
LGBTQ+を始め、すべての人が男性と女性に分けられることはなくなり、書類の性別欄にも変化が見られるようになりました。
「男性・女性・その他・回答しない」など、必ずしも男性と女性のどちらかから選ばなくても良くなったのは、ポリコレによる大きな変化といえるでしょう。
さらに、夫婦のうち男性の方を「主人・亭主」と呼んだり、女性の方を「嫁・奥さん・家内」などと呼んだりすることも、差別的だとして改定が進んでいます。
現在はLGBTQ+同士、または片方がLGBTQ+であることも多いため、相手の性別に関わらず「パートナー」と呼ぶのが一般的です。
映画・ゲームでも使われている?
近年ポリコレに配慮して作られた作品として有名なのが「リトル・マーメイド」ではないでしょうか。
原作は白色人種だと思われる主人公の人魚・アリエルが、実写版では黒色人種の俳優を起用したことで一躍話題となりました。
また、キャラクターを作成して遊ぶタイプのゲームでは、基本となるスキンカラーの種類を増やし、様々な人種に対応できるよう工夫されたものが多数登場しています。
「主人公=白色人種」といった固定観念を捨てることで、誰しもが物語の主人公になることができ、人種における差別をなくす取り組みが広がっています。
関連記事:マイノリティ・マジョリティとは? 多様な社会の理解を深めるために
ポリコレの問題点

近年の社会において重要な考え方であり、良い結果を生むことが多いとされるポリコレ。
影響力の強い芸能人やインフルエンサーはもちろん、一般人であってもSNSなどで考えが瞬時に広まり、多くの人の目に触れるようになりました。
しかし、ポリコレの考え方は時として問題点を生む場合があります。
自分の考えが誰かを傷つけてしまわないよう、現時点で問題視されているポイントについて学んでおきましょう。
言葉狩り
ポリコレの考え方が広まるにつれ、様々な言葉が改められてきました。
先ほどご紹介した「マン→パーソン」の変化など、普段使っている言葉から大きく変更されたものもあり、未だに馴染めずにいる方も少なくありません。
様々な言葉が変化するにつれ、言葉狩りの動きが加速しているのが第一の問題点といえます。
マイノリティを差別する意味で使う場合は良くありませんが、無意識のうちに使ってしまった言葉や、これまでに改定の対象ではなかった言葉に対して、過剰な拒否反応を見せる方が増えています。
たった一度その言葉を使っただけでも、「差別主義者」として批判の的となり、辛い思いをした経験のある方も多いのではないでしょうか。
ポリコレを広める上で大切なのは、私たちが自然と差別を避け、平等な社会を目指すことです。
特定の言葉を嫌うあまりに使った人を激しく非難していては、新たな差別が生まれる原因にもなりかねません。
表現の自由
言葉狩りにも通じる問題点として挙げられるのが「表現の自由」です。
あらゆる方面に配慮するあまりに使える言葉が減り、これまでとは違った表現をせざるを得ないシーンが増えてきています。
これから新しく生まれる作品に対してはもちろん、今まで脚光を浴びた作品を書き直すよう求める声もあり、各所で議論がなされています。
小説・漫画・映画・音楽・絵画など、さまざまなアートで表現の自由が約束されています。
ポリコレに配慮するあまりにアートの道をあきらめたり、素晴らしい作品が世に出ないまま埋もれてしまったりするのは良くありません。
ポリコレの考えと言葉狩り、そして表現の自由の3つがバランス良く存在するために、行き過ぎた排除をやめ、他者に対し優しい気持ちで接することが大切だといえます。
嫌気がさしている
ポリコレに積極的な動きを見せる方がいる一方、それほど興味がなく、どちらでも構わないといった立ち位置の方も少なくありません。
中にはポリコレを訴える声が大きすぎるあまりに、嫌気がさしている方も多いでしょう。
正しく広まるべきポリコレの考え方が、「何だか面倒くさいもの」として捉えられてしまうと、本当の意味で差別をなくすことはできません。
テレビをつけたり新しいゲームをしたり、本を読んだりといった娯楽がすべて過剰なポリコレで埋め尽くされてしまっては、本来の楽しみ方ができずに不満を感じる方が増えてしまいます。
先ほども触れたように、ポリコレと既存の考え方のバランスを取り、どちらに対しても配慮することが必要だといえます。
ポリコレとバランスを取る
「ポリコレ=面倒なもの」といったイメージを払拭し、誰しもが自然とポリコレの考え方ができるようにするには、現時点で使われている言葉や文化とのバランスを取らなければなりません。
下記でご紹介する2点のポイントを参考に、正しい意味でポリコレの考えが広まるように工夫することが大切です。
自由な対話
ポリコレに配慮すべく、日常的に使ってきた言葉の多くが使えない状態は自由とはいえません。
大切なのは相手に配慮する気持ちであり、特定の言葉を使ったからといってただちに悪であると決めつけるのは早計です。
実際に会話をする場合はもちろん、SNS上で顔の見えない相手へコメントをする場合も、相手はもちろんどんな人の目に留まっても良いような書き方を心掛けましょう。
批判的思想
ポリコレに対して批判的な気持ちを持っていても、それが完全に悪だとは言い切れません。
ポリコレが間違った道へ成長しないためにも、常に批判的な思想は必要だといえるでしょう。
もちろんポリコレ同様に攻撃的なワードを用いて相手を傷つけるのではなく、理論的な意見でポリコレの問題点を取り上げ、より良い方向へと導くことが大切です。
まとめ
近年も成長の一途を辿るポリコレの考えですが、SNSを通じて批判を受けたり、特定の表現に対し過剰に反応してしまったりといった問題点にも注意が必要です。
大切なのはマイノリティに対する差別を避けると同時に、今ある表現方法に柔軟な考えを持ち、バランス良く改善を目指すことではないでしょうか。
一人ひとりの考えが異なるのは自然なことであるため、誰しもが自分なりに差別に対する考えをまとめ、小さな行動を積み重ねていくことが重要です。
gd2md-html: xyzzy Wed Jul 31 2024
アフターコロナの新たな居場所:渋谷区が目指す新しい地域のかたち

東京の渋谷といえば、大都会の象徴として知られていますが、その一角に、意外にも住民主体のまちづくりが進むエリアがあるのをご存じでしょうか。その名も「ササハタハツ」—笹塚・幡ヶ谷・初台駅周辺エリアからなるこの場所には、渋谷区民の約4割が暮らしています。ここで繰り広げられているのは、一般的な都会のイメージを覆すユニークなプロジェクトです。
アフターコロナで孤独感が増す人々が多い今、そしてオンラインで何でもできる時代に突入した今、そんなまちづくりがどのような役割を果たしているのか。ササハタハツまちラボの上田事務局長に、その取り組みについて詳しくお話を伺いました。
ーーササハタハツまちラボが2021年から行っている「388 FARM MARCHE」(ササハタハツファームマルシェ)。最近では、5月に行われましたね。
はい、5月12日に第6回目を開催しました。出店数が過去最高の29団体となり、当日は約 2500名が来場してくれました。大人から子供まで幅広い世代に来場していただきましたね。まちラボは、我々が活動をするというよりも、まちづくりをしたいというコミュニティの人たちのために、活動ができるように枠組みを作るなどの支援をしています。
ーー海外でよく見るフリーマーケット(屋外の蚤の市)では、地元の人が無農薬野菜や手作りジャムなんかを売ったりしていますが、「388 FARM MARCHE」も、そういったイベントでしょうか?
ご飯ものを売っている店もありますが、「388 FARM MARCHE」は少しユニークなところがあります。というのも、このイベントでは自分が住むこの地域でこれをやってみたいという人たちが集まり、プロジェクトを作っているからです。地域にこういう課題があるからその解決のための取り組みたいという人だったり、自身の趣味をもう少しつきつめて地域にも貢献したいという人たちの集まりでもあります。
ーーアフターコロナの今、孤独を感じる人が増えているという調査結果も出ています。まちラボの取り組みでは、孤立しやすい一人暮らしの人や高齢者をサポートすることも意識しているのでしょうか?
私たちがサポートしている団体で、特にそういった課題に一役買っていると感じる団体をいくつか紹介させていただきますね。「ママぷらキッズ&ベビー」さんは、妊産婦さんのための運動トレーナーの資格を持った方で構成された団体で、乳幼児親子のための取り組みを展開しています。去年は産後ママのために、赤ちゃんと一緒にできるレッスンや大学の先生を 監修につけて軽い運動プログラムを考案しています。他にも、放課後の子どもたちの居場所を提供したり、夏休み期間中の居場所も提供しています。コロナ禍も活発に活動していた団体で、大勢の方が参加しており地域に大きく貢献していると感じます。

ーー子育て世代のお母さんは、近所とのつながりがないと孤立しがちなので、こういった活動は助かりますね。
他には「ササハタハツ花コミュニティ」という6~7年活動しているところがあります。皆が集まれる場所づくりのためという目的で始まり仲間をどんどん増やしていきました。最近では、活動の規模も拡大し参加者はさらに増え、メンバーたちで様々な企画の担当者を巡回しています。主催者によれば、参加者同志が自然につながっていったとのことでした。この団体は、高齢者、ハンディキャップ持った方、そしてお子さん向けの活動を主に行っており、口コミで広まり人がどんどん増えていったそうです。私たちは、こういう団体が活動を幅広く実施・発信するためのお手伝いをしています。
ーーこういう地域のイベントは、楽しそうだと興味を持ちながらも地域に知り合いもいなく参加を躊躇する人もいるのかなと思います。そう感じている人たちは、まちラボの取り組みをどう活用できるでしょうか?
我々の課題でもあるのですが、「388 FARM MARCHE」をやっていると、少し見るだけでそのまま通り過ぎる人もいます。忙しくて時間がないということもあるかもしれませんが、今後は、より外へ開かれたイベント空間の作り方・オープンな雰囲気醸成が必要なのかもしれません。 ですから、イベントに気軽に立ち寄ってもらうための仕掛けづくりは、今の課題ですね。
一部の人たちだけのイベントではないと理解してもらうための新しい取り組みに「ササハピゼミ」があります。これは、地域で活動をしてみたいけれど具体的にどうやったらいいかわからないという人を対象に、地域で活動した経験のある人たちを講師として迎えた講義と地域のまちづくり活動に実験的にチャレンジするプログラムです。活動のための手段などのアドバイスを行い、地域の新陳代謝を促すためのこの取り組みを、今年度から新しくスタートしました。
ーーアフターコロナとなってオンラインで人と接する機会が増え、パソコン一台あれば人とコミュニケーションがとれます。オンラインで誰とでも会える今の時代に、まちラボの活動がコミュニティに歓迎されるのはなぜでしょう?
我々も「対面がベストだ」とは考えていません。その場に行かないと体験できないこともある一方で、多くの人に気軽に参加してもらいたいという理由で、オンライン形式にしているイベントもあります。対面とオンラインのどちらかを選ぶということではなく、その人の生活スタイルにあった形で、参加しやすいものを選んでいけばいいのではないでしょうか。
ーまちラボがサポートしている対面ならではという活動はありますか?
リアルならではということですと、渋谷区緑道・道路構造物課の事業で玉川上水旧水路緑道に設置した「仮設FARM」というコミュニティ農園があります。これは、緑道にプランターを置き、公募で選ばれた利用者(キャスト)70名が運営しているものです。キャストの人たちが水やりや栽培などの手入れをしている時に、ふらっと立ち寄った犬の散歩をしている人がひと声かけてくれたり、散歩をしている幼稚園の子どもたちが通り過ぎて、実際に野菜を触ってもらえたり、そういうコミュニティが生まれています。そういう場面を見ると農園というリアルの場があってこそ生まれるコミュニティがあるなと感じます。このあたりがリアルで行うことの意義ですね。
ーー日本全国にコミュニティのつながりを強めるための取り組みありますが、ササハタハツまちラボのユニーク性や強みというと、どういうところがあります か?
渋谷区にあるササハタハツのエリアは、渋谷区内の人口の約4割が住んでいる地域です。住宅街でありながら、新宿駅にも近くアクセスしやすい場所にあります。そういったところは強みであり特徴ですね。
また、まちラボが発足する前の2017年度~2019年度にかけて、「ササハタハツまちづくりフューチャーセッション」という多様な人々が集まり、お互いの強みを引き出すためのワークショップや対話を行ってきました。当時の「地域のために何かしたい」「活動したい」といった想いが活動となり、活動同士が繋がり、相乗的にこのエリアのまちの価値を高めています。まちラボのプロジェクトが活発に動いているのも、地域の皆さんが自発的に自分ごととして、これをやりたいと感じている人が多いからです。
ーー前回のインタビューでは、ササハタハツは若い人や高齢者など一人暮らしが多いエリアのため、そういう人たちへのアプローチが課題とのことでしたが、この2~3年で進展はありましたか?
まちづくりの活動の間口はもっと広げていきたいと考えており、去年度から「388 Area Makers(ササハタハツエリアメイカーズ)」という枠組みを作っています。ここでは、すでに活動している人、まちまちづくりに興味がある住民の方など、誰でも参加できるミートアップを開催しています。今後さらに多くの人にも参加してもらえるような機会をどんどん作っています。まちづくりは、住民が積極的に自分ごととして関わることで初めて、継続していけるものだと思います。まちラボは、今後も、地元の皆さんのまちづくりの活動を支援していきます。

ササハタハツまちラボ事務局長として、ササハタハツに関わる全てのみなさんがワクワク・イキイキとやりたいことに取り組めるよう、まちラボ事務局を運営していきます。
前回のインタビュー記事:https://humming-earth.com/mirai/shibuyaku-report/
国境を越えて、生理を理由にチャンスをあきらめない社会を作る【ベアジャパン 髙橋くみさんインタビュー】

生理の日はできることも限られ、気分も落ち込むなど、多くの女性が生理との付き合い方に悩んでいます。そんな女性特有の悩みの解消を目指しているのが、高機能吸水ショーツブランド「ベア ジャパン(Be-A Japan)」。今回のインタビューでは、ベアジャパンの代表取締役CEO、髙橋くみさんに、生理に関するご自身の体験談や、アフリカでの新しい取り組みなどについて伺いました。
「メディアでは『生理セミナーをしている人』と思われているかもしれません」と笑顔で話す髙橋さんからは、「生理が理由で女性があきらめることのない社会」を作るという確固たる意志と自信が感じられました。
ーー髙橋さんが今取り組んでいらっしゃる「女性の幸せ・生き方」について関心を持ったきっかけはありますか?
ロンドンの大学では哲学部だったんです。人権について学んでいく上で、女性の人権や人種差別についてよく考えるようになりました。その後日本に帰国し、外資系の映画会社とアパレル会社で働いてきました。外資ということで日本の伝統的な会社に比べれば自由で、ジェンダーの平等という部分は守られていたように思います。それでも、お茶くみは女性の仕事でした。大学までは、男女一緒に評価されて勉強していたのに、いざ社会に出ると、男女で違いがでてくる社会なのかと強く感じたことが、きっかけのひとつです。
ーー海外生活が長い髙橋さんから見て、女性の生き方という点で、海外らしいエピソードなどありますか?
私は小学校5、6年生をオーストラリアのメルボルンで過ごしました。中学が日本で、高校はオーストラリアの女子高、大学はロンドン、日本に帰って結婚、出産後にアメリカのロサンゼルスに渡る、そんな人生を送ってきました。そこで思うのは、海外生活が長いと言うと、「日本は海外に比べてすごく遅れていますよね」と言われることが多いということ。でもオーストラリアでもイギリスでもアメリカでも、女性の人権が日本より進んでいるのかというと、そうでない部分がたくさんあると思っています。
ーー日本のほうが進んでいると思うのはどんなところでしょう?
日本は、海外に比べて宗教の影響が少ないところだと感じます。例えば、アメリカでは今、中絶の問題があり、カトリック教徒だと避妊の話題すら嫌がる人もいます。その一方で、我々の生理セミナーをテレビや新聞で紹介いただく機会が増えていますが、それは、日本では宗教が大きな問題として扱われないからというのも理由のひとつだと思うんです。ですから、宗教が関わるようなトピックでは、アメリカではNGとされることが多く、女性の権利という点では、意外とアメリカはとても進んでるように見えて実は進みきれていないと感じることがありますね。
ーー生理に関して、海外でのびっくり体験はありますか?
ワオ!と感じた体験で言うと、オーストラリアで小学校6年生の時のことが思い出されます。クラスの女の子が使用した経血がついた生理ナプキンを校庭で体育の授業中に落としたことがあったんです。多分、トイレで捨てられずナプキンをそのままポケットに入れていたので落ちてしまったのでしょう。 「これはなんだ」とみんながわーっと近寄って、担任の男性の先生が真っ赤になり、彼もナプキンを拾えなくて大騒ぎ、という事件が起きました。その後、その女の子は登校拒否になってしまったんです。
ーーそれは、その子にとって辛い出来事ですね。
話しているだけで涙が出てきちゃうほどかわいそうですよね。彼女にとってトラウマだろうしクラスのみんなにとっても、記憶に残る出来事だったと思います。家に帰って、私の母に話したら、生理はあなたにもみんなにもくることなんだから、先生が平然と対応していれば、そんなことにはならなかったよね、とすごく怒ったんですね。
ーー生理がタブーであるのは、日本だけではないということですね。
このオーストラリアでの出来事はいまだに思い出します。どこの世界においても、アフリカでも オーストラリアでも日本でもアメリカでも、生理はどことなくタブーなんです。特に男性は見たこともなければ、触ったこともなければという世界ですからね。こういうことが学校で起きた時、すぐに対応できる先生がいるかというとなかなかいないのではないかと思います。そういう経験を踏まえると、どこの国でも生理がタブーであることは変わりないし、1人1人、女性も男性も含めて、意識を変えていくことで、少しずつ良くできるんじゃないかなと思っています。
ーー3年以上続けて生理セミナーを開催されていますが、生理について女性が話しやすい環境が整ってきたという実感はありますか?
この4年でだいぶ変わってきたと思います。私たちがこのブランドを始めた時に、生理に関するトピックの企画書をテレビ局に提出しプロデューサーさんとお話をさせていただきました。でも、「地上波で生理の話は無理」と言われてしまい、2局からお断りされたんですね。これが4年前のことです。でも今は、我々の生理セミナーの活動もテレビ局に取材いただいたり、新聞で一面カラーで掲載されたりと、すごく変わってきています。

先日は、男子校で行った生理セミナーの記事がヤフーニュースのトップになり700件以上のコメントをもらいました。4年前、ベアの活動がヤフーニュースに掲載された時も900件ぐらいコメントがつきましたが、「なんて卑猥な」など、ネガティブコメントばかりでした。それが、今回のコメントはポジティブなものばかり。ご自分の経験を共有してくれたり、そこに返信してコメントで盛り上がっているのを見て、この4年でずいぶん変わったなと感じました。
ーー生理セミナーを通して、生理への若者の意識の変化などは感じますか?
そうですね。高校生は生理がタブーだという先入観もなくポジティブに素直に聞いてくれることが多いです。逆に大学生だと、恥ずかしがったり、生理ナプキンを見せると茶化してみたりということがありますね。ですから若い頃から、生理は自然現象として女性に起こるもので、生理がなければ人間は生まれない、大事な生殖機能だということを知ることが大切だと感じます。
ーー髙橋さんのお母さまはシングルマザーの経験もあるそうですが、シングルマザーに育てられた経験は、高橋さんの人生観に影響を与えていますか?
女性が社会に出ることはとても大事なことだと思います。女性が収入を得ること、自立することの大切さというのは、母を通じて強く感じました。我々の会社は女性のみで、子供がいるメンバーもすごく多いんです。子供を育てながら仕事をするってすごく大変なことだと思うのですが、 社会として男性も女性もともに自立できることが大事だと思える社会になったらと期待しています。
ーーベアが取り組んでいるエチオピアのプログラムについて教えてください。
社名の『Be-A(ベア)』は、“Girls Be Ambitious” のBeとAをとってつけました。“Boys Be Ambitious(少年よ大志を抱け)”という有名なフレーズがありますが、男の子だけじゃなく女の子や女性も大志を抱ける、という想いで、“Girls Be Ambitious”をブランドのメッセージとして掲げています。
我々のこのエチオピアの活動というのは、弊社が行う「Girls Be Ambitiousプロジェクト」の一つです。このプロジェクトは女性が生理だからといってあきらめない、そんな社会、世界を作っていけたらという想いで行っています。そのために大事なことは、生理に関する知識をきちんと正しく広めていくこと。100人いたら100通りの生理があります。生理痛がある人もない人もいる、眠たくなる人もいればそうでない人もいる、生理の量も人それぞれです。生理についてのそういう情報があまり知られていません。女性も男性もそういう情報をもっと知ることで、あきらめない社会が作れると思っています。2つ目は、生理用品はいろいろなものが出てきていますが、自分に合った生理用品に巡り合えていない女性や、生理用品が使えないという女性も世の中にたくさんいるということ。生理であきらめない社会のためには、生理のもれを気にせず生理期間中も快適に過ごせることが大事です。この2つを主に、我々は活動しています。

ーーエチオピアでも、生理が理由であきらめている女性が日本のように多いんですね。
エチオピアは生理ナプキンを使える女性が36%のみ。それ以外の女性はボロ布などを当てているという現状があります。生理ナプキンを買っている女性も快適に過ごしているわけではなく、ビニール素材のようなむれやすい作りのナプキンを使っています。平均年収が1000ドル未満の国で、生理ナプキンが1パック160円と値段も高いんですね。女性たちにお話を聞くと、頻繁にナプキンの交換もできず極限までナプキンを使っているそうです。その結果かぶれたりもれることがよくあると聞きました。トイレットペーパーも高級品なので、学校や職場のトイレにないのが当たり前の世界。私たちも実際エチオピアを訪問し、トイレットペーパーのない状況で生理期間を過ごすのは不快だろうと感じました。
ーーそういう状況のエチオピアを、ベアジャパンはどのように支援しているのでしょう?
先日、エチオピアを訪問した際に、吸水ショーツを寄贈し生理セミナーも行いました。さらに、吸水ショーツ製造のためのトレーニングを始めます。このプログラムは国連人口基金さんにご賛同いただいて、ご一緒させていただいているプロジェクトです。エチオピアの女性が自分で吸水ショーツを作れば雇用も生まれます。ですから、エチオピアの女性がエチオピアで作った吸水ショーツで過ごせる社会を作るために取り組んでいます。ちょうど今年の4月にトレーニングが始まったところです。
ーー髙橋さんがベアの商品や生理セミナーを通して伝えたいメッセージとは?
「Girls Be Ambitious」というブランドのメッセージそのものですが、私たち人間は生まれたらみんなが大志を持って良いと思うんです。将来、「ボーイズ」とか「ガールズ」とか性別が関係なくなる社会を作りたいですね。今は我々は「女性である」ことに集中して 「Girls Be Ambitious」というプロジェクトをやっていますが、何年後かには、「わざわざガールズと言わなくてもいいよね」「昔はそう言わないといけない世界だったんだね」といえる時代になって欲しいですね。ですから、我々のベアという社名にも、あえて「ガールズ」は使っていません。そういう社会が私たちが目指すべきゴールですね。
前回のベア ジャパンインタビュー記事はこちら:
https://humming-earth.com/mirai/interview03/
ベアジャパン公式HP:https://withbe-a.com
GBA公式HP:https://girlsbeambitious.com/
憂鬱からワクワクへ。働き方の変化は人生を変える

Hummingライター 大浦沙織のコラムをお届けします。
「明日からまた仕事か…」
会社員時代は憂鬱だった日曜日の夜。
しかし、フリーランスになった今、日曜日の夜はワクワクしながら眠りにつき、月曜日の朝、仕事に向き合えることに喜びを感じています。
正社員という安定を手放すことで出会えた、新しい働き方。
私がフリーランスライターになるまでの道のり、そしてこの選択を通じて得た気づきをお伝えします。
安定した会社員から、フリーランスへ
8年前、私は新卒で勤めた会社を辞めました。きっかけは、パートナーの海外転勤。
もしこの転機がなければ、今でも会社員を続けていたかもしれません。安定した職を手放す勇気が私にはなかったからです。
退職後、しばらくは子育てに専念していました。しかし、育児休業から職場に戻る友人たちを羨ましく思ったり、増えない預金残高を見て焦りを感じたり、徐々に「自分の収入が欲しい」「社会とつながりたい」という思いが強くなっていったのです。
とはいえ、子どもはまだ小さいし、我が家は転勤族。今の自分には外に働きにでることは難しいと思い、在宅でできる仕事を探すことにしました。「娘の2歳の誕生日に開業する」。これだけを決めて、様々な可能性を探っていきました。そして、最終的に巡り合ったのがライターの仕事です。
会社員を辞めてから、安定した職を手放したことに不安を感じることもありました。しかし、今思うのは、会社員を辞めたからこそ、今の働き方に出会えたということです。
予期せぬ出来事が、人生の大きな転機となり、新たな可能性を開いてくれました。
「とりあえずやってみる」行動することで未来を切り開く
「際立ったスキルや経験がない私に何ができるのだろうか……」と悩んでいた時、“ママが1ヶ月でWebデザイナーに”という広告が目に留まりました。
「これだ!」と運命を感じた私は、未経験からWebデザイナーを目指すことに決めました。生後3ヶ月の娘を抱っこしながらWebデザインスクールに通い、その後、Webデザイナーとして活動を開始。
しかし、「私はWebデザイナーを名乗って良いのだろうか……」というモヤモヤした感情が拭えずにいました。
そんな中、Webデザインの勉強と並行して始めたブログ運営で、文章を書く楽しさに目覚めました。次第にデザインよりも執筆の仕事に惹かれるようになり、SNSで見つけたライター募集に思い切って応募することに。
そして、勇気を持ってWebデザイナーという肩書きを手放し、「ライター」として活動していくことを決意しました。不思議なことに、「ライター」と名乗ることには違和感がなかったのです。
この経験から感じたことは、好きも嫌いも、得意も苦手も、実際に手を動かしてみなければわからないということ。気になったらやってみれば良いし、やってみて何か違うと思ったら辞めれば良い。行動することで、可能性が広がることを体感しました。
ガムシャラ期を乗り越え、見えてきた仕事の基準
駆け出しの頃は、執筆ジャンルや報酬を気にせずに仕事を受け、目の前の案件に必死に取り組みました。
当時の仕事時間は子どものお昼寝中と家族が寝静まった明け方のみ。スキルも未熟だったので、何をするにも時間がかかり、キャパオーバーに。締め切りが頭から離れず、ストレスから動悸に悩まされることもありました。
しかし、必死に行動することで、少しずつ自分のやりたいことがわかってきたり、自分なりの価格表が作れるようになったり、仕事を選ぶ基準ができてきたのです。
人は歳をとります。睡眠時間を削って働き続けるのは限界があるでしょう。だからこそ、ガムシャラに行動した後には、どんな仕事に関わりたいのか、どんな条件なら気持ちよく働けるのか、どんな人と一緒に働きたいのか……、自分と向き合うことが大切です。
せっかくフリーランスになったのだから、自分が心地よいと感じる働き方を追求していきたいです。
現状維持は後退。学び続けることが大切
「現状維持は後退だと思っている」というフリーランス仲間の言葉が、私の心に深く刻まれています。
AIが急速に進化し、多くの仕事が変化していく今の時代。私たち自身も常にアップデートしていく必要があります。
私は意識的に学びの時間を確保するようにしています。例えば、尊敬する先輩ライターさんのライティング講座を受講したり、書くこと以外の武器を増やすためにカメラの勉強を始めたり。また、AIツールも積極的に活用しています。学び続けることで、自分の可能性が広がると信じているからです。
さらに、心と体の健康維持も重要だと考え、今年からジム通いを始めました。隙間時間に行こうとすると優先順位が低くなりがちです。そこで、ジムに行く日を事前にスケジュールに組み込み、日々の仕事に埋もれないよう心がけています。
もちろん、目の前の仕事をこなすだけで精一杯な日もあります。しかし、自己投資の時間を大切にすることは、長期的には仕事の質を高めることにも繋がるのではないでしょうか。
働き方が変われば、人生が変わる
フリーランスになって実感したのは、働き方の変化が人生を大きく変えるということ。今の私にとって、働く時間と場所を自分でコントロールできるフリーランスの生活はとても心地よく、働くことが楽しいです。
もちろん、いきなり継続の案件がストップしたり、毎月の収入が安定しなかったり、「この先もフリーランスを続けられるかな……」と不安になることもあります。しかし、未来のことは誰にも分かりません。
だからこそ大切なのは、目の前の仕事に全力で取り組むこと、出会えたご縁を大切にすること、自己成長を止めないこと、そして、新たなチャンスを逃さないよう適度な余白を持つこと。
これらを意識しながら、私はこれからも文章を綴っていきます。
多様性の時代に考える「美の基準」との向き合い方

いつまでも美しくありたい。
そのために日々入念にスキンケアをおこなったり、食生活や運動にも気をつける。
でもときどき、誰かがつくった「美の基準」を追い求めていることにふと気づき、疑問を感じる。
ありのままでいいと言われる時代に、人の目を気にして頑張る必要があるのか、そんな想いがよぎることもあるでしょう。
または多様性が認められる一方で、これまで軸にしていたものが揺らいだように感じる人もいるかもしれません。
風の時代を生きる私たちは「美しさ」とどう向き合えばいいのでしょうか。
日本における美の基準
ありのままで美しいという考えが急速に広まりつつも、依然、何らかの「美の基準」が存在していることは確かです。
たとえば「ボディポジティブ」に共感はしていても、どこか言い訳や諦めにも思えて飲み込みきれなかったり。
たとえば「適正体重」が統計的に病気になりにくいと証明されていても、「実際太めに見える体重だから…」と受け入れられなかったり。
無意識に刷り込まれた「美の基準」というのは、なかなか脱ぎ捨てられないものです。
美の基準は国や地域によっても様々ですが、日本で言えば、細身で色白、あるいは目鼻立ちがくっきりした人をいわゆる美人と定義する傾向にあります。
もう一歩踏み込むと、ただ細身ならいいという訳でもなく、ほどよい肉付きで健康的に引き締まったボディラインといった感じでしょうか。
ごく一部ですがこうして羅列してみると、なんとも細かい注文ですよね。
もし「これらを全て兼ね備えた美人と結婚したい!」と声高に言う人が身近にいたら、つい「それは贅沢だよ」と諭したくなるかもしれません。
でも世間では、こうした特徴を兼ね備えたタレントやモデルが、街中の広告塔を飾っているのも事実です。
一方で、当然こうした「一般的な美の基準」に当てはまらなくても、美しいと言われる人もたくさんいます。
ただ、よくよく思い返してみると、それを形容するのに単に「美しい」ということばだけではなく、何かしら違うことばをくっつけることも多い気がするのです。
例えば、個性的とか、エキゾチックとか、あるいは素朴な顔立ちとか。
たしかに「美しい」ということばだけでは、あまりに漠然とするため、キャッチーにしたいのが主な理由だとは思います。
ただ、何となくその裏側に「いわゆる「美の基準」とは少し違うけれど…」というニュアンスも含まれる気がするのは、筆者がひねくれすぎでしょうか。
いずれにせよ、私たちのマインドの奥底に何かしらの「美の基準」が刷り込まれていることは、それに従うかどうかは別としても多くの人が同意することでしょう。
厄介なのは、それを誰が決めたのかも、その根拠も大してはっきりしないことです。
“なんとなく”美しいと思ったから、あるいは”みんな”が美しいと言っているし、たしかにそんな気もするから。
美しさの定義とは、それくらいとてつもなく「ぼんやりしたもの」です。
頭ではそう分かっているのに、ついつい引っ張られて、がんじがらめになってしまう。
ありのままを肯定する「ボディポジティブ」という考えが現れたのも、実体の見えない「美の基準」に振り回され、疲れ果てた結果なのかもしれません。

美しさを追い求めることも肯定されるべき
多様性が叫ばれるようになった一方で、今度は逆に「美の基準」を追い求める人が揶揄されることもあります。
「ありのままで良いのに、なぜそこまで必死になるの?」と。
スキンケアや生活習慣に細かいこだわりがある人、いついかなる時もメイクやファッションに手を抜かない人。
あるいは、年を重ねてもダイエットや体型維持に励み続ける人を見て「若作りして、みっともない」という風潮だってあります。
だけど、必死に美を求めて何が悪いのでしょう。
筆者は、ありのままを受け入れるのと同じくらい、美を追い求めることだって肯定されるべきだと思うのです。
それが本当の意味での多様性ではありませんか?
正直、筆者は、できれば人から綺麗とか、美人とか、可愛いとか、言ってもらえるならどしどし言ってもらいたいタイプです。
他人の評価を求めたくなるのは、自己肯定感が低い証拠と思う人もいるかもしれませんが、美しさを求める理由は必ずしもそれだけとは限りません。
きっかけは「人の目」でも、そうして小ぎれいにした自分がふとショーウィンドウ越しに目に入ると、純粋にテンションが上がるのです。
それでさらに人からも褒めてもらえるなら、これほど自分のご機嫌取りにぴったりな方法はないなと思うのです。
もちろん、疲れていたり気分がのらなければ、徹底的に手を抜いて外出することもあります。
ただ、そんなぼさぼさ姿の自分が目に入ると、さっきとは反対にパッと目をそむけたくなる。
なんとなく堂々とできなくて表情は曇るし、誰に何か責められたわけでもないのに、自分がどんどん惨めに思えて、そそくさと逃げ帰りたくなる。
そのたびに「美しさ」とは、誰のためでもなく自分のためにあるのだと実感するのです。
傍からみたら理解できないこだわりがあったって、常に抜かりなく着飾ったって、いくつになってもストイックに美を追求したっていい。
どうしても手に入れたい理想のパーツや体型があるなら、メスを入れてもらったっていいのかもしれない。
だってそれは全部、自分が「ご機嫌」になるためにやっているのだから。
一見、外見の美しさを追い求めているだけに見えても、これらの行動は「内面」にも大きな変化をもたらします。
それは単に美しくなったから自信がつく、という話だけではありません。
自分の理想に近づくためには、何かしら行動を変える必要があって、さらにそれには「マインド」の改革が必要です。
たとえば運動の時間を増やす、間食や夜更かしを控える、ちょっとした外出でも身なりを整えるように意識する。
あるいは、食品やコスメをちょっと良いものに変える、そのぶん他の支出はちょっと我慢する。
どれも今までとは違う方向へ舵を切ること、つまり負荷がかかるし、時には踏ん張らないといけないことばかりです。
そんなことせずに自分を甘やかしたって、誰も咎めません。
それでもあえて律するのは、そうして努力を積み重ねたという事実そのものが、何より自信につながり、気持ちも前向きになることを知っているからです。
もちろん人から美しいと言ってもらえるのは嬉しいことですが、そう思ってもらえるかはコントロールできないこと。
一方、自分で自分に美しいと言ってあげられるか、そのために努力できるかはコントロールできること。
ストイックに美を追求する人は、この辺りを身をもって実感しているのだと思うのです。
だからこそ自分のために努力している人を、周りが揶揄したり引き止めたりする権利はないと思うのです。
また、こういう文脈で「追い求める」のなら、筆者は実体や根拠のよく分からない「美の基準」ですら、効果的に機能すると考えます。
ぼんやりとでもスタンダードがあれば目指すものが分かって頑張れますし、もしくはそれを軸に自分にあった「美の基準」を相対的に見いだせたりするからです。
だから、必ずしも「美の基準」=悪いことではない。
当然、ひたむきに「美の基準」を追い求める人がいたっていい。
そういう人たちを時代遅れと揶揄していては、いつまでも本当の意味での多様性にはたどり着けません。

人の美の基準に茶々を入れない
誰でもない「自分のため」に美を追い求めるのであれば、同じように美を追い求めている「誰か」にあれこれ口出ししたり、首を突っ込むべきではありません。
自分の権利だけを主張して、周りの人にもそれを認めないのは不公平ですよね。
ただ、頭ではそう分かっても、これは意外と難しいことだったりします。
時代の風向きも相まって、誰かの外見に意見することは、場合によってはハラスメントと捉えられかねませんが、実は自分でも気づかないうちにやっているものです。
たとえば「あなたはこういう体型だから、こういう服のほうが似合う」とか「肌の色味的にこっちのアイシャドウのほうがいい」とか。
おそらく、その多くは「良かれと思って」口をついたことばでしょう。
もう一つ、個人的に例にあげたいのが、痩せ型の人に対することばです。
「ガリガリじゃない、もっとしっかり食べないと!」
「あなたは太るくらいがちょうどいい」
何を隠そう、筆者自身、これまでの人生で幾度となく言われてきたことばです。
そして、未だに肯定的に受け止められないことばでもあります。
自分のために美しさを求めることはいいことと言いましたが、求めたからといって全て手に入るかは別の話です。
筆者の場合、自分でももう少し肉付きが良いほうが美しく見えるし、そうなりたいと思っています。
けれど、体質的になかなか太れません。
でもそれを「太りたい」と口にすると、嫌味だとか贅沢な悩みだと叩かれ、かと思いきや、もっと食べないと不健康に見えるなんて言われるのです。なんともおかしな話ですよね。
「ボディポジティブ」とは、太っていても痩せていてもいい、そういう概念のはずです。
ですが「プラスサイズ」ということばが広まった一方で、その対義語と思われることばはあまり聞きません。
太っている人をみて、何かことば飲み込むよう意識する人は増えたかもしれませんが、痩せている人に対しても同じことをする人はどのくらいいるのでしょうか。
「太ったね、痩せなよ」というのはハラスメントと言われかねませんが、「痩せすぎだよ、ちゃんと食べてる?」というのもハラスメントと言われるとピンとこない人が多いのではないでしょうか。
ただ、かく言う筆者も、無意識に人の「美しさ」に関して口出しをしてしまうことがあります。
あろうことか、自分と同じように瘦せている人に対して、一番嫌う「もっと食べて!」という声をかけることすらあります。
それくらい人は、知らないうちに誰かの「美の基準」に茶々を入れていることがあるのではないでしょうか。
私たちは、自分のことには口を出されたくないくせに、他人のことには口を出したがる。
このことに意識的であるべきだと思うのです。
では外見に関することは、今後一切口にすべきではないのかというと、そういうわけではありません。
純粋に褒めたいときだってありますし、似合うと思うものをフラットに提案したいときだってあります。
実際、それが本人の自信に繋がったり、気づいていない魅力を引き出したり、プラスの面だって当然たくさんあります。
ただ、相手がそのことばをどんな形で受け取りそうか。
ことばを発する前に、それを想像する必要があります。
「美の基準」は、国や地域、時代によってだけではなく、私たち個々によっても異なります。
褒めたつもりが嫌味に捉えられたり、良かれと思っての提案が逆に自信を削いだりすることは、往々にして起こることです。
「相手のため」が必ずしも正しいとは限らないことを、忘れたくないものです。
まとめ
こうして二歩も三歩も引いて見てみると、私たちが振り回されがちな「美の基準」とは、他でもない「私たち」が作り上げているということがよく分かります。
だとしたら、そのしがらみから解放されるためには、やはり私たち自身が少しずつ変わるしかありません。
ただ、ありのままの自分を受け入れるのも、自分のなかに軸を持つのも、人の考えに口を出さないのも、全て聞こえはいいですが決して今すぐ簡単にできることではありません。
いろんな価値観に触れながら、たくさんもがきながら、ときに誰かと本音をこぼし合いながら、少しずつ変わっていけたら十分なのではないでしょうか。
時は金なり。 ドラッグのように中毒性のあるスマホとの付き合い方を見直そう【Editor’s Letter vol.10】
| Humming編集長 永野舞麻がカリフォルニアから配信する「Editor’s Letter 」。
日々の暮らしで感じた気付きや、人生において大切にしていることを綴っています。 |

現代人の必需品とも言えるスマートフォン(以下、スマホ)。手のひらサイズの小さな端末が、私たちの生活に革命的な変化をもたらしました。
スマホさえあれば、世界中の誰とでもリアルタイムで連絡が取れ、わからないことはすぐに調べることができる。社会の情報インフラとして欠かせない存在になった一方で、私たちはいつの間にかスマホに依存し、大切なことを見失ってはいないでしょうか。
通知音が鳴るたびに手が伸びる。無意識のうちにスマホを見てしまう。家族や友人との会話中もついついスマホをチェックしてメールの返信を優先してしまう。そんな経験をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
「便利な道具」のはずのスマホに振り回され、本当に大切なものから目を背けてしまっていないか、一度立ち止まって考えてみませんか。
今回は、私がスマホと距離を置いた理由とそれがもたらした変化についてお話しします。
私を変えた10日間のデジタルデトックス
私がスマホと距離を置きはじめたきっかけは、10日間のリトリート。リトリート中はデジタル機器の使用が一切禁止されていたため、強制的にスマホと距離をとることができたのです。最初は手持ち無沙汰でしたが、日が経つにつれ、スマホがないことによる変化に気づき始めました。目の前の出来事、例えば食べている料理の味や、鳥のさえずり、足元を横切る蟻などに自然と意識が向くようになったのです。情報が過多に入ってこない、余白がある暮らしの心地よさに気づくようになりました。
リトリートを終えて10日ぶりにスマホを手にした時の衝撃は忘れられません。まず、画面の明るさが以前よりもはるかに眩しく感じました。さらに、スマホに自分のエネルギーを吸い取られているかのような不思議な感覚に襲われたのです。実際、スマホを数十分見ただけで頭痛がするようになりました。
その経験に驚き、携帯やパソコンの画面に長時間集中することで、多くのエネルギーを消耗していることに気がついたのです。そこで、意識的にスマホを使う時間を制限することに決めました。
子どもたちと一緒にいる時間は極力スマホを触らない。寝る時はリビングの棚にスマホをしまい、次の朝メディテーションが終わるまでは触れない。さらに、メールやメッセージの通知をOFFに設定しました。スマホに自分の行動を支配されるのではなく、自分が必要な時にのみ、スマホを手にするようにしたのです。

スマホを手放したら、人生が変わる?!
スマホを使う時間と使わない時間の境界線を作ることで、私の生活にはポジティブな変化が表れました。
例えば、寝る前の準備。これまではスマホで調べものをしたり、動画を見たりしながら、顔を洗って、歯磨きをして、着替えをしていたので、1時間ほど時間がかかっていました。それが今では半分以下の時間で終わるようになり、余白が生まれました。
いかにスマホという機械に時間を奪われていたかを体感すると共に、本来の自分のキャパシティの広さに気がついたのです。
また、寝る前にスマホを見なくなったことで、自律神経が整い、メディテーションをしてから眠りにつくまでの時間も短くなり、睡眠の質も高まりました。
さらに、人との関わり方にも変化が表れました。以前は子どもたちに話しかけられた時に、「このメールの返信が終わるまで待って」と言うことが度々あったのです。今思えば、「あなたより、スマホの中の出来事が大切」と表現しているようなものです。しかし今では、目の前にいる相手との時間を何よりも大切にできるようになりました。
すると、学校での出来事や友達とのトラブル、 姉妹喧嘩のこと、自分が感じていることなどを、子どもたちから話してくれることが増えました。私がスマホに集中している代わりに、本を読んだり、趣味のアートやパズルをしていることで、話しかけやすい空間ができたのだと思います。
また驚くことに、私がスマホを手放したことで、これまでは頻繁に行われていたスマホやタブレット端末を模倣した遊びを子どもたちがしなくなったのです。子どもは良くも悪くも周囲の大人の姿を見て育つもの。もし子どもたちにスマホに支配された人生を歩んでほしくないのであれば、まずは周りの大人が手本を示す必要があると強く感じました。
「伝える」ことで、スマホを使わないデメリットを乗り越える
とはいえ、スマホを使う時間を制限することで、急な予定変更や緊急の連絡に気づきにくくなるというデメリットもありました。どちらかと言えば、自分自身への影響というよりも、相手に対してのデメリットと言えるかもしれません。
そのため、よく連絡を取り合う仕事相手や友人には、24時間以内の返信を心がけながらも「私は自分の都合のいいタイミングで連絡するから、あなたも即座に返信しなくて大丈夫。お互いに無理のないペースでやり取りしましょう」と伝えるようにしています。逆に返事を急ぐ時には、「こちらは急ぎの用件なので、できるだけ早めの返信をお願いします」と伝えることもあります。
また、特定の時間帯はスマホを確認し、子どもの学校関連の連絡事項や、仕事上の緊急の連絡にはなるべく対応できるよう心がけています。
必要以上にスマホに時間を奪われないために
スマホが私たちの生活に欠かせない存在となり、即レスが善とされる現代社会において、スマホと距離を置くことは勇気のいることかもしれません。
しかし、完全にスマホを断つことが難しくても、使う時間と使わない時間の境界線を決めて、上手く付き合うことはできると思うのです。例えば、週末や家族団欒の時間、自分の趣味に没頭する時間はスマホから離れる。一方で、仕事上の連絡や緊急の用件には適切に対応するなど。
人生において、時間ほど貴重なものはありません。スマホやパソコンなどの電子機器は私たちの生活を便利にしてくれる、いち道具です。私たちが使う側であり、道具に支配されるようになっては元も子もないのです。
必要以上にスマホに時間を奪われなくなることで、本当に大切なものに時間を使えるようになり、新しい発見や気づきが得られるかもしれません。それはきっとあなたの人生をより豊かなものにしてくれるでしょう。
「本当の自分」が分からない?迷ったときに思い出したい考え方

本当の自分が分からない
「本当の自分」って何なんだろう。
ふと、そんな問いが浮かぶことってありませんか。
親の前、友達の前、職場、パートナーに見せる顔、どれも全部少しずつ違う。
真面目なしっかり者のときもあれば、子どものように甘えたくなるときもある。善良に生きていても、たまに道を踏み外すことだってある。
SNSが当たり前になった現代では、その「顔」の数はさらに増えています。
仕事用、プライベート用アカウント、何も考えずつぶやける、誰にも教えていない裏アカウント。複数アカウントを使い分け、それぞれ違う自分を見せている人も多いのではないでしょうか。
私たちはこんな風に、相手や環境に合わせていろんな顔を使い分けます。
「誰か」のイメージ通りの私でいなきゃ、がっかりされるかもしれないから。それで離れていってほしくないから。
でもそれに疲れ果て、途方に暮れるときもあります。
こんなの私じゃない、素の自分に戻りたい。そもそもいろんな顔を使い分けるなんて、相手も自分も騙しているのと同じではないか。
ずっと変わらない「本当の自分」を貫けたら、どんなに楽だろうか。
だけどもうどれが「本当の自分」なのかも分からない。
そんな葛藤を、誰しも一度は抱えたことがあるのではないでしょうか。
そもそも本当の自分って?
そもそも、私たちが探し求める「本当の自分」ってどんなものなのでしょうか。
自分のなかにある、唯一無二の、確固たる存在。なんとなく、そんなイメージがあるかもしれません。
だからこそ、今は「本当の自分」からかけ離れているとか、周りにも自分にも嘘をついているというような考えが浮かび、私たちは苦しくなります。
でも本当に、「本当の自分」とはたった一つしか存在しないのでしょうか。
一歩引いてその定義を見つめ直してみると、少し心持ちが変わるかもしれません。
「周り」によって形成される
あなたという人間は、あなた自身が感じて考えるからこそ存在しています。
そういう意味では、本当の自分とは「自分のなか」で形成されるように思えるかもしれません。
でも、その感じて考えるということ自体、必ず「周り」と関わっているはずです。
仕事がデキる人に見られたいから、ちょっと背伸びして頑張ろう。家族や親友の前では、ポンコツなところを見せたって平気。
仕事の日は小ぎれいな身なりをするけど、近所のコンビニは伸びきったTシャツでいいや。誰も私を知らないから旅先では、いつもと違う行動や選択をしたくなる。
大人になるとよく「自分で考えて行動しろ」と言われますが、どんなに自分で考えたとしてもその起点はあくまで周りの人や環境にあります。
あの人は雑談多めのほうが仕事の話がスムーズに進む、この人は真面目なタイプだから端的に伝えたほうが良い。
SNSだって同じで、見ている人のタイプを考えて、投稿する内容を調整します。
そんな風に、私たちは常に周りとの関係のなかで自分の立ち居振る舞いを決定しています。
だから「本当の自分」とは、たしかに「自分」ではあるものの、「周り」によって形成される相対的なもの。
相手や環境によってアメーバのように変化する、そもそもの輪郭があいまいなものなのです。
「複数」存在する
世の中には多重人格や八方美人ということばがあり、これらはどちらかというとネガティブな使われ方をします。
誰にでも良い顔をして相手を騙している、そんなニュアンスが含まれていますよね。
さらに、これを裏返すと、あたかも「本当の自分」がたった1つしか存在しないようにも思えます。
常に「本当の自分」でいるべきで、それが人として誠実な振る舞いだ、そんな風にも聞こえてきます。
だから私たちは、自分が「いろんな顔」を持っていることに嫌気が差し、「唯一無二」の本当の自分を見つけようともがく。
でも本当の自分が「周り」によって形成されるのであれば、極端に言えば、関わる人や身を置く環境の数だけ「自分」が存在する可能性があります。
ここから「唯一無二」の本当の自分を定義するのは、かなりハードルが高く感じられませんか?
かといって、いきなり「本当の自分」が複数あることを受け入れろというのも簡単ではありません。だから私たちは悩んでいるのですよね。
では、その「いろんな顔」を全てくっつけたのが「本当の自分」と考えるのはどうでしょうか?
どれだけいろんな顔を使い分けたとしても、その組み合わせだけは唯一無二です。
切り取った一部もその集合体も、どれもが紛れもなく「本当の自分」です。それぞれの仮面を別人と捉えてしまうか、仮面を上手に使い分ける一人の人間と捉えるか。
近くでみるか俯瞰でみるか、問題は視点にあります。
そう考えると、全部ひっくるめて「本当の自分」だということが、少しずつ腑に落ちてくるのではないでしょうか。
「時間」とともに変化する
本当の自分を見失ってしまう要因は、もうひとつあります。それは本当の自分とは「時間」とともに変わるということ。
子どもの頃と大人になった今の自分では、考え方はかなり違うはずです。
子どもの頃は分からなかったことが分かるようになり、子どもの頃はシンプルだったことが複雑に見えることもあります。大事なことと、そうでもないことの基準も変わっているかもしれません。
もっと短いスパンでそれを感じることもあるでしょう。人生において、昨日と今日の価値観が180°ひっくり返ることは、別に不思議なことではありません。
そうした感じ方や考え方の変化にふと気づいたとき、私たちはうろたえてしまいます。「私はこんな人間ではなかったはず」あるいは「これまでなんて人間だったんだろう」と。
でも、過去と今の自分、どちらかが間違っていたのかというと、そうではないはずです。
子どもの頃は子どもなりに、昨日の自分は昨日の自分なりに、そのときの環境や状況に則した「自分」でいたはずです。その環境や状況が変わったから今の自分も変わった、ただそれだけの話です。
本当の自分が「周り」によって形成されるものである以上、時間の経過とともに、環境や付き合う人が変われば「本当の自分」も変わる。
「確固たる」本当の自分が見つからないのは、ある意味、当然のことなのです。

本当の自分を見失ったときのヒント
「本当の自分」とは、何か1つ決まった枠があるわけではないということが、少しずつ理解できてきたかと思いますが、心から腑に落ちるまでには時間がかかるかもしれません。
それに理解したからといって、悩みがすぐに解消されるわけでもないでしょう。はっきりとした輪郭がないものに、不安を抱くのはごく自然なことです。
大切なのは、その不安に飲み込まれず、体勢を立て直すスイッチを知っているかどうかです。
そのスイッチは人それぞれですが、ヒントになりそうな考え方をお伝えしておきます。
いろんな顔の「良い面」に気づく
私たちが確固たる「本当の自分」を探してさまよってしまうのは、そのほうが楽だから。
ものづくりに例えて考えてみましょう。
規格が決まった工場生産なら、同じ品質のものを一度に大量生産できますが、職人の手作りだと、どうしても微妙な差が生じるうえ生産量も限られます。労力、効率を考えると、どう考えても工場生産に軍配が上がりますよね。
工場生産のように、本当の自分にも「規格」があれば、周りに合わせて繊細に調整する必要もなく、余計なストレスも減りそうな気がする。だから、私たちはその型を探したくなる。
では、時間も労力もかかる職人の手作りはダメかというと、そんなわけはありませんよね。1つ1つ微妙に違う風合いは「味」と評価され、多くは生産できないことは「希少性」という価値になります。
だとしたら「本当の自分」も、少しずつ違う顔を「味」、それぞれを見せる相手が限られることを「希少性」ととらえても良いのではないでしょうか?
自分だけに見せてくれる顔があると、人はちょっと嬉しくなります。逆に、いつもとは違う顔や、自分には見せない顔があることを知ると、より惹かれてしまうことだってあります。
いろんな顔を使い分けるのはたしかに疲れますが、それで作られるあなたの魅力があることにも気づいてくださいね。
そしてもう一つ、あなたがいろんな顔を使い分ける理由にも目を向けてください。
相手が気持ちよくいられるように、その場の空気が良くなるように、そして自分が傷つかないように。そのためにはどう振る舞えばいいか、知恵を絞る。
もがきながらもいろんな顔を使い分ける背景には、そんな優しさがあると筆者は考えます。だって、周りのことも自分のこともどうでもいいなら、こんな面倒で疲れることはしないはずです。
たくさんの顔を持つ人は、それだけ優しさや知恵を持っている。
こうしたいろんな顔を持つことの良い面に気づけると、少し「本当の自分」探しの呪縛から解放されるのではないでしょうか。
「不安の原因」を深掘りしてみる
人は意外と、不安の原因を明確に理解していないものです。
漠然と将来が不安、なんとなくこのままじゃ良くない気がする。そんなことってよくありますよね。
「本当の自分」を見失い不安に襲われているときも、その可能性がゼロではありません。そもそもあなたは、なぜ「本当の自分」を見つけたいと感じているのでしょうか。
もしかしたら、何か現状に不満があるのかもしれません。
たとえば、職場では人間関係も仕事もそれなりに上手くいっている。お給料も生活も安定して何不自由ないはずなのに、何となく満たされず「本当の自分」ではない気がする。
実はその背景には「もっとバリバリ仕事をしたい」という野望、あるいは「もっとミニマムな自給自足の暮らしのほうがいい」といった気持ちが隠れているのかもしれません。
あるいは、あなたは今すごく疲れているのかもしれません。
たとえば、ストレートな性格の人が空気を読んで振る舞うことは、出来なくはないけれどかなり疲れることです。
それが今までは職場だけで十分だったのに、何らかの環境の変化で、家庭や友だちと会うときもそうしなくてはいけなくなった。気づいたら、ずっと自分にとって疲れる顔ばかりしている。
だから気張らずいられる「本当の自分」に戻りたい。
こんな風に「本当の自分」探しには、そこに至るまでの原因や過程があるはずです。ただその多くは、ほんの些細な出来事だったり、じんわり変わっていくものだから気づきにくい。
そんなときは、一度紙に書き出して心と頭を整理することも大切です。
なぜ「本当の自分」を見つけたがっているのか?
現状に何か不満があるのか?それとも単にいっぱいいっぱいなのか?
その原因はどこにあるのか?自分で解決できることなのか?
一つずつ地道に深掘りしていくと、意外と具体的な解決策にたどり着くかもしれません。
たとえば、転職活動や異動願い、業務量の調整。あるいは新しい習いごとや家族旅行、旧友との他愛もない話だったり、その解決策は十人十色です。もちろん解決策によっては、すぐには実行できないかもしれません。
でも少なくとも、実体のない唯一無二の「本当の自分」を探し求めるより、遥かに地に足がついていて手を伸ばしやすいものではないでしょうか。
本当の自分は揺らいで当然
いろんな顔があることに嫌気が差しているのに、それ自体を肯定しろだなんて”とんち”のように感じられる内容だったかもしれません。
でも、無理矢理「本当の自分」という枠を作り上げ、そうでないときの自分を否定して苦しむよりは、肩の荷は少し下りるのではないでしょうか。
少しずつ、自分のいろんな顔、そしてそのいろんな顔を持つ自分自身の魅力にも、気づいていってあげてくださいね。
NVCを実践して、よりよい人間関係を築こう!事例で学ぶ非暴力コミュニケーション

子どもがいうことを聞いてくれなくてイライラする。
最近夫婦喧嘩ばかりでしんどい。
部下の教育に頭を抱えている。
このように、家庭や職場での人間関係のストレスに悩まされている方も多いのではないでしょうか。
そんな時、「NVC(非暴力コミュニケーション)」を実践することで、対人関係の問題が改善されたり、解決への糸口が見つかったりするかもしれません
本記事では、NVCついて、具体的な例を交えながら解説していきます。人間関係が好転するヒントを探してみてください。
NVC(非暴力コミュニケーション)とは
「また同じミスを繰り返すの?」
「言うことを聞かないなら、もう知らない!」
こんな風に、ついカッとなって相手を責めたり、見放したりする言葉を発してしまった経験はありませんか?
私たちが日常的に使用する言葉は、時として暴力的に相手や自分自身を傷つけることがあります。
そこで注目したいのが、1970年代にアメリカの臨床心理学者マーシャル・B・ローゼンバーグ博士によって体系化され、提唱されたNVC(非暴力コミュニケーション)です。
NVCは、あらゆる人間関係を、支配や対立、緊張、依存の関係から、自由で思いやりあふれる関係へと変革する方法です。また、私たちの生き方や人生の目的を根本から見つめ直すきっかけにもなるでしょう。
NVCでは、相手の言動に反射的に反応するのではなく、以下の4つの要素を用いて自分の感情を見つめ直し、相手の感情にも耳を傾けることを提案しています。

NVC4つの要素
1. 観察(observation)
NVC第1の要素「観察」は、自分の状態を左右する外的な事実を、「評価を交えずに」明確に認識することです。
例えば、散らかった部屋を見て「あなたは片付けが苦手なのね」と言うのは、観察ではなく評価です。「脱いだ洋服が床に散らばっている。本は開いたまま机に置かれている」のように、事実だけを観察するのです。
2. 感情(Feeling)
NVC第2の要素では、自分の「感情」を表現します。ただし、自分の感情と「いまの自分が思っていること」を区別する必要があります。
例えば、友人との約束が急にキャンセルされたとき、「友達は私のことを大切に思っていないのかもしれない」と考えるのは感情ではなく、相手の行動を自己流に解釈していると言えます。
一方、「約束がキャンセルされてがっかりした。楽しみにしていたから残念だ」というのは、自分の内面の状態を率直に表現した「感情」です。
3. 必要としていること(Need)
NVC第3の要素は、感情の根底にあるニーズを見極め、表現することです。
例えば、パートナーの帰りが遅いことに不満を感じたとき、心の底には「もっと一緒に時間を過ごしたい」といったニーズがあるかもしれません。
4. 要求(Request)
NVC第4の要素は、自分のニーズを満たすために、相手にどのような行動を求めるのかを明確に伝えることです。
例えば、パートナーとのコミュニケーションに不満を感じていた場合。「もっと私の話を聞いて」という曖昧な言い方ではなく、「私が話している時は、スマートフォンを見ずに目を見て聞いて欲しい」と具体的にリクエストを伝えます。
ただし、急ぎでクライアントに返信をしなければいけないなど、相手にも事情があるでしょう。相手の立場に立って理解を示しつつ、状況に応じて柔軟に対応することが大切です。
この4つの要素を意識してコミュニケーションを取ることで、私たちは評価や判断に注意を向けるのではなく、自分の本当の望みを見極め、明確に表現できるようになります。
また、相手の言動の裏にある感情や必要性にも目を向けられるようになることで、お互いを尊重し、相手をより深く理解することができるでしょう。
NVCを使った具体的なコミュニケーション例
NVCを実践する前後では、コミュニケーションの質が大きく変わります。具体的にどのように変化するのか、以下の2つの例を見てみましょう。
「お片付けしなさい!」と子どもに怒鳴ってばかりいる母親のケース
NVCを取り入れる前の伝え方また片付けをしていないじゃない。 あなたのだらしなさにはうんざりよ。 今すぐ片付けなさい! |
NVCによる伝え方
部屋が散らかっていると、私は悲しくて困ってしまうの。(感情) 家族みんなが快適に過ごせる、整理整頓された空間を大切にしたいからなの。(ニーズ) 一緒に片付けをしない?ブロックは専用の箱に入れて、ぬいぐるみは棚に並べて、絵本は本棚に戻してもらえると嬉しいわ。(リクエスト) |
締め切りを守らない部下に困っている男性の上司のケース
NVCを取り入れる前の伝え方また締め切りに遅れたのか。 何度同じミスを繰り返すんだ。 君の仕事ぶりには呆れ果てるよ。 次からは必ず期日を守れ。 |
NVCによる伝え方
先月提出してもらった企画書は締め切りの2日後、今回のレポートは期日を1週間過ぎてからの提出だったね。(事実) 正直、がっかりしているし、チームの信頼関係が損なわれないか心配だよ。(感情) チームのスケジュール管理と生産性を維持するためにも、締め切りを守ることが不可欠だと考えているんだ。(ニーズ) 次回のプロジェクトから、もし締め切りに間に合いそうにない場合は、早めに相談してくれると助かるよ。毎週月曜日の定例ミーティングで進捗状況を報告してもらえれば、問題解決に向けて一緒に取り組めると思うんだ。(リクエスト) |
このようにNVCの4つの要素を意識することで、自分の感情やニーズに向き合い、それを言葉にすることができます。そして、相手の状況を尊重しつつ、明確にリクエストをすることで、お互いを思いやり、理解し合える関係性を築くことができるでしょう。
NVCを習得するには練習が必要
NVCを身につけるには、日々の生活の中で意識的に実践することが大切です。イライラや怒り、悲しみなどのネガティブな感情が湧き上がってきた時こそ、NVCを練習するチャンスと捉えましょう。
ネガティブな感情の奥底には、「相手に理解してほしい」「自分の気持ちを知ってほしい」といった切実な願いが隠れていることがよくあります。そのため、一時的な感情に任せて相手にぶつけるのではなく、自分の感情の根源にあるニーズを見極め、それを具体的な言葉で伝えることが重要です。
また、自分のニーズを理解するだけでも、ネガティブな感情は和らぐものです。NVCの4つの要素を意識することで、自分自身でニーズを満たす方法が見つかるかもしれません。
自分の気持ちに正直に向き合い、相手の立場に立って考えるコミュニケーションを心がけることで、人間関係はより豊かになっていくでしょう。
グレートリセットがもたらす変革とは?経済・環境・社会の未来

私たちが生きる現代社会は、これまで目覚ましい発展を遂げてきました。
特に第二次世界大戦から現代に至るまでの発展は、日本だけでなく世界中が生きやすい社会づくりを目指してきたといえます。
一方、さまざまな発展の裏で危機的状況に陥っている人々や環境があるのをご存じでしょうか。
今回はこれらの危機に対応すべく考え出された「グレートリセット」とは一体どんなものなのか、また実際にグレートリセットが起こった場合はどんな変化があるのかについてご紹介します。
グレートリセットとは?
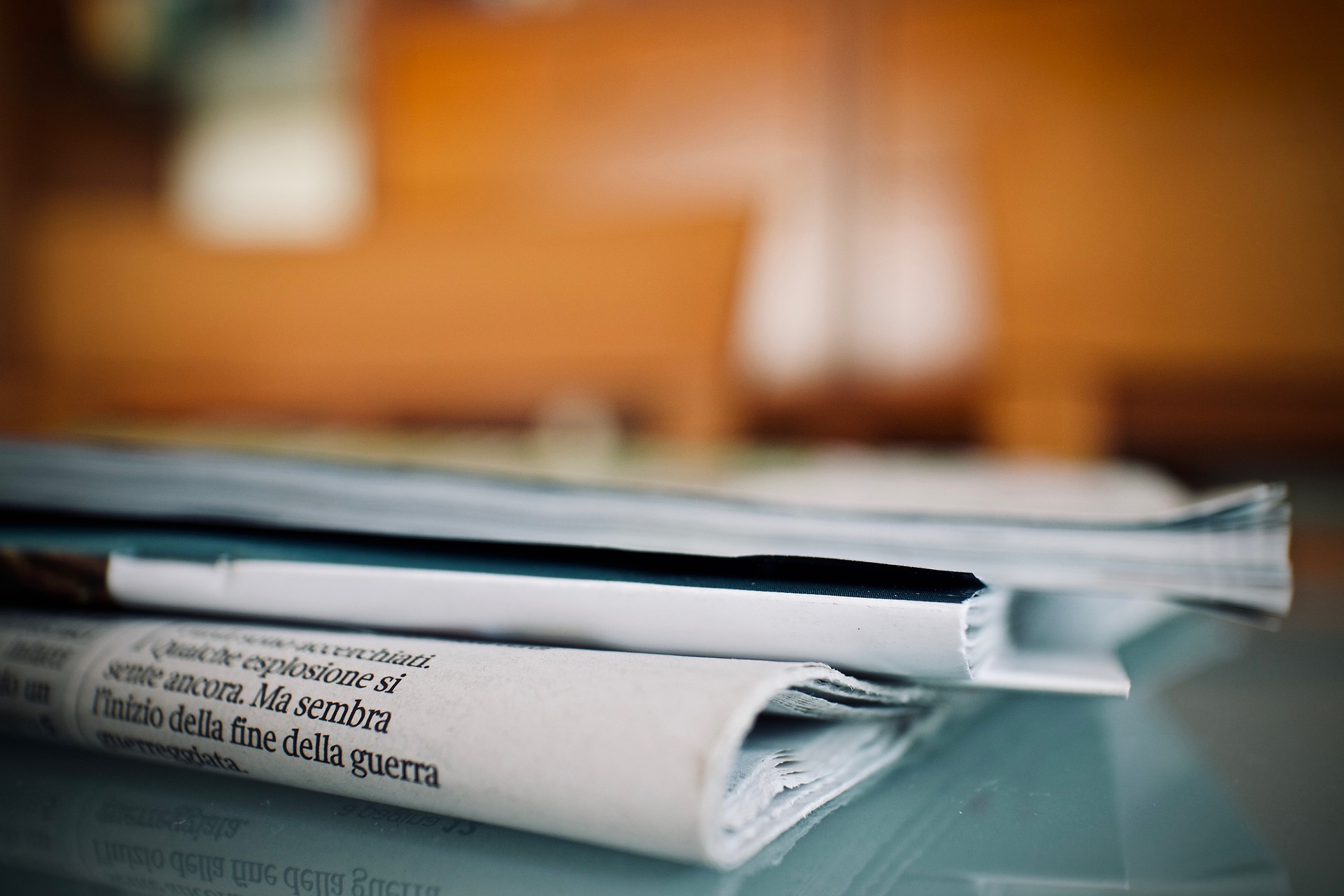
グレートリセットとは、2020年に開かれた世界経済フォーラムにて、クラウス・シュワブ教授が発表した論文に登場した言葉です。
その名の通り「重大な初期化」という意味を持ちますが、具体的には何をどう初期化するのでしょうか。
そもそもグレートリセットの考え方は、さまざまな点で便利になった現代社会において、それらの仕組みを一度リセットすることでより良い社会作りを目指す、といったものです。
そもそもの始まりは世界中で猛威を振るった「COVID-19(新型コロナウイルス感染症)」であり、私たちは非常に大きな打撃を受けました。
感染者数が少なくなった今もCOVID-19による影響は色濃く残っており、今後どう改革が行われるのか、また同じようなパンデミックが起こらないためにはどうすべきなのか議論がなされています。
グレートリセットが推奨されているのはCOVID-19に関連する内容だけではありません。
まずは経済・環境・社会の側面に焦点を当て、それぞれどのようにグレートリセットを行うべきなのか見ていきましょう。
経済的グレートリセット
経済の面でグレートリセットが必要とされているのは、主に労働者の雇用に関する問題が原因です。
世界は時代が進むにつれてロボットなどさまざまな技術を取り入れ、人の負担を軽減すべく進化してきました。
近年ではAIの広まりによって、「近いうちに失われる職業」が話題となるなど、私たち人間が担うべき職に変化が訪れています。
AIは正確かつスピーディな作業が可能であるため、単純作業がメインである職業は人間よりも効率的に仕事ができるでしょう。
さらには自動運転が進めば、タクシーやバスの運転手などもAIで代用される可能性があります。
こういった企業によるAI雇用が積極的に行われると、雇用の機会が減るどころか、現在働いている人々が職を失うリスクが高まります。
AIを運用する職種などが増える可能性も同時に高まりますが、職を失った人々が必ずしもAIを運用できるとは限りません。
また、現代社会で問題視されているのが「違法労働」です。
賃金の発生しないいわゆる「サービス残業」を強要したり、契約時の賃金とは大幅に異なる収入で働かされていたり、指定された日に休みがとれず過労で倒れたりとさまざまな問題が発生しています。
これらの問題はここ数年で始まったものではありませんが、労働基準監督署なども全ての企業の実態を把握しきれず、現在に至るまで問題が浮き彫りになっていないところも多数存在します。
そのため、一度グレートリセットを行い全てを白紙に戻すことで、新たな雇用方法を模索しようというわけです。
環境的グレートリセット
誰しもが自分のことと受け止め、行動していかなければならないといわれているのが「環境問題」です。
例えば生態系に大きな影響を及ぼす海洋プラスチック問題は、このまま進むと2050年にはプラスチックごみが魚の量を上回ると予想されています。
浜辺でごみ拾いなどのボランティアに協力してくれる方もたくさんいるものの、海全体のごみを減らすには至っていません。
また、地球温暖化も大きな問題の一つです。自動車などの乗り物から出る排気ガスはもちろん、可燃ごみを燃やす際にも大量の二酸化炭素が発生します。
これらのガスは通称「温室効果ガス」と呼ばれ、地球の温度を上げて生態系を壊すほか、海面上昇により島国が水没するなどさまざまな影響を及ぼします。
これらの環境問題はもはや、私たち一人ひとりが異なる方向を向き、自分にできることをするだけでは歯止めが利かない事態へと陥ってしまいました。
グレートリセットにより現在のシステムを白紙に戻し、地球全体で環境を守る方法を考えなければなりません。
社会的グレートリセット
グレートリセットで状況を大きく変えなければならないのは、私たちを取り巻く社会も同じです。
私たち人間は誰もが皆平等であり、同じような生活を送れるはずです。
しかし現在の社会はというと、性別や国籍・民族などを理由に所々で差別が行われ、悲しい思いをしている人が多数存在しています。
誰もが根底では「差別をしてはいけない」と分かっていても、経済状況によって生き方に違いが出たり、障害の有無によって生活が異なったりする点は避けられません。
日本人ばかりのコミュニティに一人だけ外国人がいる場合、急に日本人と同じように対応できる方は少ないでしょう。
悪意を持って行われる差別はもちろんのこと、自然に生まれる不平等をなくし、誰もが同じように社会と関わりを持てる日々を目指す必要があります。
グレートリセットによって固定観念や刷り込みを白紙に戻すことも、差別をなくす第一歩といえるでしょう。
関連記事:クリック募金とは?動物や環境に関係する募金サイトまとめ
グレートリセットが起こったらどうなる?

さまざまな問題を抱えている私たちは、グレートリセットによってどのような変化と直面することになるのでしょうか。
単なる「改革」とは異なり、これまでに築き上げてきたシステムが全てゼロからの出発となるため、当然変化の度合いも大きいはずです。
経済・環境・社会のそれぞれにおいてどのような変化が期待されているのか、詳しく見ていきましょう。
経済面
私たちに関係の深い面でいえば、それぞれの企業が実態を透明化し、一人ひとりに対し公正に対応することが大切です。
もちろんこれは一企業だけでなく、社会全体あるいは世界中が、国際的な問題に対し同じように取り組まなければなりません。
そのために創設された国際機関や国際会議を有効に利用し、世界全体が同じ方向を向いて協力し合うことが大切です。
また、これまでは企業が自身の利益を優先とする「株主資本主義」であったのに対し、今後は従業員や顧客・取引先など企業に関わる全ての人が利益を得られるよう配慮する「ステークホルダー主義」へ変わっていくことが予想されます。
これにより違法労働や賃金の未払いが減るだけでなく、未だ株主資本主義を貫く企業が目立つようになり、社会全体の労働環境が改善へと向かっていくでしょう。
企業が自身の利益だけを重視せず、全体を見据えて経営できれば、市場は公平性を保ちやすくなります。
AIの導入によって職を追われても、社会全体で新たな雇用を生み出し、生活難民を減らすことにも繋がるでしょう。
環境面
私たちが地球を守るための第一歩として、燃やしたり埋め立てたりするごみを減らし、再び使えるものは使う、といった「3R」の考え方があります。
- Reduce:リデュース|物の耐久性を高めたり過剰包装をやめたりしてごみを減らす
- Reuce:リユース|詰替え用製品を選んだり不用品を売ったりして物を再び使う
- Recycle:リサイクル|資源ごみを再生利用し新たな製品として使う
これらはあくまでも資源物やごみが出ることを前提として考えられていますが、新たな取り組みとして必要なのが「サーキュラーエコノミー」です。
ごみを資源に回して再生利用するのではなく、そもそも現在ある資源の中でやりくりすることで、新たな廃棄物を減らす効果が期待できます。
これまで私たちは、プラスチックという素材を「便利なもの」としか考えてきませんでした。
それゆえにプラスチックを資源として利用することも、新たにプラスチック製品を生み出すことも悪だとは思わず、意識せずに過ごしてきたはずです。
サーキュラーエコノミーの考えが広まれば、プラスチックの有用性を再認識することに繋がり、「限りある資源」としてより大切に使えるようになるでしょう。
また、ロシアがウクライナを侵攻したことによって、天然ガスをはじめとする資源の価格が高騰し話題となりました。
こういった資源には限りがあり、近い将来枯渇することが分かっています。
石油・天然ガス・石炭などに依存せず、新たなエネルギー生成の方法を見出すことこそ、環境を守るために重要です。
これらの天然資源に頼らずに生きるとなると、私たちの生活はさまざまな方法で生み出された電力によって支えられることとなるでしょう。
自動車のエネルギー源がガソリンから電気や水素へ変わりつつあるように、さまざまな面で変化が訪れるといえます。
社会面
社会面におけるグレートリセットは、人々の間に渦巻く差別の種を無くし、誰もが平等に生きられることを目指します。
第一に経済的な問題などが原因となる「教育」において、いかなる状況に置かれた子どもであっても、同じ年齢で同じ教育を受けられるように均等化することが大切です。
これは大人の場合「就労機会の均等化」に当たり、雇用がない・能力が足りずに雇ってもらえないといったトラブルを無くし、誰でも仕事に就きお金を稼げることを目標としています。
また、これらの目標を達成するためには、人々がお互いの違いを理解し、協力し合うことが大切です。
私たち人間は自分と違う相手に対し「よく分からない」「怖い」といった感情を持ち、それが差別へと繋がっていきます。
人種を超えたコミュニケーションを得ることで、相手を深く理解し、身体の違いや考え方の違い・生活の違いなどを受け入れることが重要といえます。
グレートリセットを実現させるには?
グレートリセットは個人で行うものではないため、実際に行うためには世界中の国々が理解を示す必要があります。
そのため、具体的に何を行うのかも含め、話し合いには長い時間がかかるでしょう。
2050年までに「脱炭素」が完了し、二酸化炭素の排出量がゼロになる未来を目指して環境活動が行われるなど、私たちの身の回りでも少しずつ変化が始まっています。
こういった未来を現実のものとするためには、私たち一人ひとりの意識改革が重要だといえるでしょう。
グレートリセットに備える

グレートリセットは良いことばかりのように思えますが、実際はリセットによって何が起こるか分からない点に注意が必要です。
長い時間がかかるといわれているため、事前にできる限りの準備をしておきましょう。
第一に、グレートリセットが起こることで経済に影響が及び、資産の価値が大幅に変わる可能性があります。
今保有している資産が、数十年後もそのままの価値であるとは限りません。
今のうちから資産運用に関する正しい知識を身に着け、リスクを分散するためにもさまざまな方法で資産を分けておくと良いでしょう。
また、一部の人にとってはグレートリセットによって大きく職務内容が変わったり、場合によっては職を変えることとなったりする場合があります。
慣れ親しんだ仕事から全く新しい仕事へ変わる際は、少なからずストレスがかかることでしょう。
同じ状況に置かれている人と情報を共有し、協力し合って生活することが大切です。
関連記事:寄付による税金の控除とは?ふるさと納税との違いも解説
まとめ
現在のさまざまなトラブルを一掃すべく打ち出された「グレートリセット」案。
便利になった日常の裏で誰かが困っている現状を打破するため、私たちの生活は大きな転換期を迎えるでしょう。
世界中が手を取り合って行われるグレートリセットですが、影響を被ったり、環境に慣れたりするのは私たち一般市民です。
あらかじめ正しい知識を身に着け、来たるその日まで準備をしておくことが大切です。
日常に潜むグルーミング被害|子どもだけでなく大人の被害も

私たち大人だけでなく、子どもであっても常に注意しなければならないのが「性被害」です。
ある日突然被害に遭うケースも多い一方で、親しいと思っていた間柄の人間が牙をむき、消えない傷を負わせる「グルーミング」も問題となっています。
子どもは十分に自分を守ることができないため、大人が性被害の実態とグルーミングについてしっかりと理解し、大切な我が子を守らなければなりません。
今回は幼い子どもをターゲットとする場合はもちろん、大人であっても被害を受けやすいグルーミングについて、具体例を交えながら理解を深めていきましょう。
子どもたちを守るためには一体どうしたら良いのか、私たちがとるべき行動についてもご紹介します。
グルーミングとは?

グルーミングとは、元々動物が行う毛繕いを指す言葉です。
猫が互いの体をなめ合ったり、猿がノミ・ダニを取ってあげたりする行為が該当し、本来悪い意味を持つ言葉ではありません。
彼らのグルーミングは仲間としての絆がそうさせるだけでなく、相手と円滑にコミュニケーションを築き、群れの中で過ごしやすくする目的でも行われています。
一方、今回ご紹介する人間のグルーミングは、正式にいえば「性的グルーミング」「チャイルドグルーミング」などと呼ばれるものです。
目についた子どもを急に襲うのではなく、まずは警戒心を解くために低姿勢で対応し、子どもが慣れてきた頃を見計らって性行為に及びます。
性行為までどれだけ時間をかけようと、親しくなる最終目的が性行為であるならば、それは性的グルーミングに当てはまるでしょう。
恐ろしいのは、自分にとってかけがえのない存在となった大人が、ある日突然不快な行動を迫ってくる点にあります。
子どもにとって信じていた大人に裏切られることは、直接傷をつけられるのと同様に苦しいものとなるでしょう。
中には「この人がやることならば間違いはないはず」と、性行為そのものを容認してしまう子もたくさんいます。
長い時間をかけ、特別な信頼関係を築いた加害者に対し、子どもは「この人を失いたくない」と思うようになります。
性行為に嫌な気持ちを覚えても、不満をいうことで加害者が悲しんでしまったらどうしよう、と考え、口をつぐんでしまう子も少なくありません。
こういった子どもの純粋な心を利用し、未成年に対し犯罪を犯すことこそが、性的グルーミングのもっともたる悪といえるでしょう。
また、性的グルーミングの対象となるのは幼い子どもだけではありません。
性行為を最終目標として被害者の心を懐柔しようと近づく行為は、青年であっても、大人であっても性的グルーミングに当てはまります。
「もう大人だから」と油断せず、自分に近づいてきた相手が何を目的としているのか、冷静な頭で判断しなければなりません。
さらに、性被害の対象となるのは「女性」だけではないことを覚えておきましょう。
幼い男児はもちろん、成人男性であっても被害に遭うケースが増え続けています。
加害者は女性であったり、同じ男性であったりとさまざまであるため、「自分には起こらないだろう」など他人事のように捉えてしまうのは危険です。
関連記事:マイノリティ・マジョリティとは? 多様な社会の理解を深めるために
性犯罪におけるグルーミング

性犯罪におけるグルーミング、すなわち性的グルーミングがどうして恐ろしいのか、さらに深堀りしてみましょう。
先程もご紹介したように、性的グルーミングの対象となるのは幼児から20代・30代の大人までさまざまです。
男性・女性に関わらず被害に遭いやすいため、全ての人が身を守る行動をとらなければなりません。
「自分だけは大丈夫」と安心せず、周りの人とコミュニケーションをしっかりととり、信頼できる相手かどうかの見極めを行いましょう。
近年性的グルーミングによる被害が増えているとはいっても、その数は被害全体のほんの一部だといわれています。
なぜなら、性的グルーミングは被害者自身が被害を受けていることに気が付かず、関係がダラダラと長引きやすいためです。
相手に嫌われたくない子どもが周りに被害を訴えないことも、相手が自分を好いてくれているがゆえの行為だと勘違いしてしまうことも、性的グルーミングが野放しになってしまう理由といえるでしょう。
また、性的グルーミングにおける被害者と加害者の関係は、周りから見ても違和感がなく、被害に気が付きにくいといった点も特徴の一つです。
加害者は頭を使って少しずつ被害者との関係を深めていくため、「急に距離が縮まり親しくなった」「過剰なスキンシップが行われている」といった不自然な点もなく、単に仲の良い関係性だと思われてしまいやすいのです。
性犯罪というと、無理やり行為に及ぶ姿であったり、電車内で痴漢を行ったりといった一方的なものを想像しやすいでしょう。
そのため、一見仲が良く見える性的グルーミングでは、「もしかして性犯罪ではないか」といった考えに及ばず、発見が遅れる可能性が高いのです。
大切なのは私たちが性的グルーミングについて正しい知識を得て、常に「もしかして」といった気持ちでいることです。
子ども、もしくは大切な人の変化にいち早く気が付くためにも、普段からコミュニケーションの習慣をしっかりとつけておきましょう。
グルーミング被害の例

続いて、子どもが対象となる性的グルーミングについて、具体的な例をご紹介します。
学校におけるグルーミング
学校における性的グルーミングでは、加害者となりやすい存在として「教師」が挙げられます。
子どもと距離が近くても周りが違和感に気が付きにくく、また子どもも教師を全面的に信頼しやすいため、時として性被害が起こる場合があります。
学校ではさまざまな子どもが生活しているため、その中からより従順で言いなりになりやすい子どもを選ぶことも容易です。
集団生活になじめず1人でいる子どもなどは標的になりやすく、周囲が気づいたときには既に手遅れであるケースも珍しくありません。
もちろん、学校には教師以外にも養護教諭・守衛・部活の監督やコーチなどさまざまな大人が働いています。
特別練習だといって呼び出したり、特定の生徒のみに声をかけていたりするケースも多いため、周りは注意して見守っていかなければなりません。
インターネットを利用したグルーミング
インターネット上で行われる性的グルーミングを「オンライングルーミング」と呼びます。
主にSNSなどを通じ、感情を吐露する投稿に目をつけ、共感したり寄り添ったりするところから始まります。
家族や友人との関係が上手くいっていない子や、希死念慮のある子などは、SNS上で出会った大人に心を開いてしまうケースが多いでしょう。
オンライングルーミングでは、実際に会って性行為に及ぶ前に、身体の写真を撮って送らせる・ビデオ通話で性的な行為を強要するといった犯罪も目立ちます。
写真や動画をインターネット上で流出されないよう、その後長い間言いなりになってしまう子も多いため、子どもたちにはネットリテラシーをしっかりと身に着けてもらわなければなりません。
地域活動などを利用したグルーミング
近所に親しくしている大人がいたり、よく訪れる公園で頻繁に会う大人がいたりする場合、これらが性的グルーミングに繋がっている可能性も考慮しなければなりません。
遊んでいる子どもに近づいて「何をしているの?」「一緒に遊ぼう」などと声をかける事案は後を絶ちませんが、毎日行く公園に同じ大人がいると、子どもも次第に心を開いてしまいやすいでしょう。
お菓子をくれる・車に乗せるといった行動だけでなく、単なる声掛けであっても子どもに注意を促す必要があります。
家庭内におけるグルーミング
親が子どもを守るのは当たり前のことだと思われていますが、中には家庭内で性的グルーミングが行われるケースもゼロではありません。
家庭内のことだからこそ、「まさかそんなことをしないだろう」といった考えが念頭にあり、被害に気が付くのが遅れる可能性があります。
家庭内での性的グルーミングでは、兄弟姉妹・従兄弟・祖父母・親戚などさまざまな関係性の大人もしくは年上の兄弟が加害者になり得ます。
中には親が直接子どもを懐柔し、性的な行為に及ぶケースもあるでしょう。
こういった実態は近年の日本で実際に行われているものであり、決して過去の出来事ではありません。
家庭内での性的グルーミングが悪質なのは、「子どもは何があっても親を信頼している」という点にあります。
成長した子どもが親を避けることはあれど、幼児や児童など親なしで生きていけない子どもたちは、親に何をされても文句を言わずに耐えてしまうでしょう。
性的グルーミングだけでなく、虐待や育児放棄なども、子どもの純粋さを利用した悪質な犯罪です。
関連記事:知らず知らずに起こっている?ハラスメントの種類や防止方法を紹介
子どもだけでなく、大人の被害は?

性的グルーミングは子どもだけでなく大人も被害に遭う可能性があります。
大人も子どもと同じく、自分が被害に遭っているのに気が付きにくいのが特徴です。
性的グルーミングは一種の「洗脳」であるため、被害者自身がどう行動するかだけでなく、周りがいち早く気が付いてあげることが必要不可欠です。
また、大人の場合は「性的グルーミング」ではなく、洗脳によるさまざまなグルーミングにも注意しなければなりません。
今回ご紹介する具体的なグルーミングの例を参考に、周りの友人や同僚を少し気にかけながら生活してみると良いでしょう。
職場におけるグルーミング
大人の性的グルーミングで多いのが、職場内で起こるものです。
上司が特定の部下だけを贔屓していたり、ミスをすると必ず助けてくれる同僚がいたりと、一見良いことのように思える環境が性的グルーミングに繋がる場合があります。
「あの時助けてもらったから」といった恩があると、いざ性行為が行われそうになっても断り切れず、ダラダラと関係が続きやすいのも特徴です。
また、職場におけるグルーミングの中には、パワハラのようなケースも見られます。
「あの人は良くしてくれるから残業を強制されても仕方ない」「あの時助けてくれたから仕事をしっかり教えてもらえなくても仕方ない」など、理不尽な対応を関係の深さで黙らせようとするのです。
自分が周りとは異なる対応をされていると感じた場合、その人との関係がどうであろうと周りに相談することをおすすめします。
オンライン詐欺
インターネット上で行われる性的グルーミングも、子どもだけのものではありません。
大人の場合は出会い系サイトなどを通じて知り合い、関係を深めながら最終的に性行為へと繋がっていくケースが多く見られます。
また、性的ではないグルーミングの一種として、仲良くなったと思った相手から詐欺へ加担するよう指示されたり、実際に自分が詐欺に巻き込まれたりするケースもあるようです。
「友達を作りたいといって近づいてきたにもかかわらず高額なブレスレットを買わされそうになった」「心配していると見せかけて高額な保険に入らされそうになった」など、さまざまな詐欺に巻き込まれないよう注意が必要です。
洗脳
純粋な人や周りに裏切られた経験のない方などは、自分に良くしてくれた相手が悪いことをするはずがない、と思ってしまいがちです。
優しい心を持った人であれば、違和感を覚えつつも「信じてあげなければ可哀想だ」と傍に居続けてしまうこともあるでしょう。
こういった良心につけ込むことの上手い加害者は、次第に被害者を洗脳し、自分の言うことを聞くように変えてしまいます。
不都合なことでも黙って従い、言われるがままにお金を出したり性行為に及んだりする存在を作るべく、さまざまな手法で近寄ってくるでしょう。
恋愛詐欺
大人のグルーミングに多いのが「恋愛詐欺」です。
あたかも本当に自分のことが好きであるかのように対応しながら、実はお金目当てであったり、性行為が目的であったりと被害者の気持ちを弄ぶ行為が問題視されています。
中には「恋愛詐欺マニュアル」と題し、相手を言葉巧みに騙す方法をまとめて販売する手口もあるようです。
恋愛詐欺もまた、被害者は加害者に恋をしてしまっており、自分から距離を置くのが難しいという特徴があります。
金銭のやり取りや性行為はあれど、自分に寄り添うような言葉やお金のかからないデートなどがほとんどない場合は、グルーミングを疑うと良いでしょう。
お金を取るだけ取って音信不通になったり、妊娠後に姿をくらませてしまったりする悪質な手口も存在します。
長期間付き合っていても結婚の話題が出なかったり、しっかりと避妊をしてくれなかったりする場合も、今後のお付き合いを冷静に検討することをおすすめします。
グルーミングから子どもたちを守るためにできること
大人のグルーミングは自己防衛が鍵となりますが、子どもたちは十分に自分を守ることができません。
まずは子どもとコミュニケーションをとる機会を大切にし、お互いが何でも言い合える関係を目指しましょう。
具体的な被害について相談してもらえなくても、ほんの少しの変化や違和感で被害が判明する場合もあります。
また、子どもと普段近しい関係にある大人は誰なのか、親がしっかりと把握しておくことも大切です。
子どもだけで訪れた公園で知らない人と交流していないか、ネット上で知らない人とやり取りしていないか、逐一チェックしておきましょう。
インターネットの場合は適宜制限をかけるなどして、不特定多数の人と関われないように工夫しておくことも大切です。
このような対策は、時々子どもに「ウザい」と思われてしまうことがあります。
やはり大切なのは、コミュニケーションをとるのが当たり前の毎日を作っておくこと。
過干渉・過保護だと思われないために、子どもが自分の方から1日の出来事を話してくれるようにしておくことが重要です。
関連記事:自己肯定感が低い子供の特徴とは|注意すべき親の発言や行動
まとめ
幼い子どもからティーンエイジャー、大人まで幅広く対象とした悪質なグルーミング。
特に子どもの場合、一度の被害で心が壊れ、精神状態が不安定になってしまうケースも珍しくありません。
親はもちろん周りの大人が一体となり、悪質な犯罪から子どもを守りましょう。
リトリートとは?目的、方法、注意点を解説

私たちが生きている現代社会は、誰しもがしっかりと休息をとり、身体だけでなく心にも寄り添ってあげなければなりません。
常に忙しく目まぐるしい毎日を送っていると、徐々に疲労が溜まり、完全に回復できなくなってしまうでしょう。
そんな忙しい毎日を生きるすべての人に見てほしいのが、近年話題となっている「リトリート」です。
今回はそんなリトリートの意味や目的に加え、行うことでどんな利点があるのか詳しく見ていきましょう。
実際にリトリートを行うときの注意点についても確認し、正しく効果を得られるよう工夫してみてください。
リトリートの意味

日々忙しい毎日を送っている現代人の中には、当日溜まった疲れをその日中に癒せず、疲労を抱えながら頑張っている人もたくさんいます。
出勤日に頑張りすぎてしまうと、休日にいざ好きなことをやろうと思っても、なかなか重い腰が上がらないのではないでしょうか。
そんな現代人に必須ともいえるのが、今回ご紹介する「リトリート」。
「Retreat(退却)」、あるいは「Retreatment(再治療)」という単語から来ており、普段の毎日から一度退却して身体と心を癒そうといった取り組みです。
「そんなことをする時間があったら仕事をしたい」など、タスクに追われて休むことを考えられなくなっている方も少なくないでしょう。
しかし、リトリートをしないままどれだけ頑張っていても、疲れによってパフォーマンスが低下し、より良い仕事ができません。
脳・身体・精神の全てが適宜休息をとることこそ、効率的な仕事ができるようになるのです。
そんなリトリート、実は「これをするべき」といった具体的な行動が決まっているわけではありません。
ひとたび日常から離れ、深くリラックスできることならば、どんなことでもチャレンジできます。
今回ご紹介するのは、数あるリトリートの中でも比較的メジャーであり、誰しもが挑戦しやすい方法です。
自分が深くリラックスできる方法を見つけるためにも、ぜひ最後までご覧ください。
関連記事:エプソムソルトでバスタイムにスキンケア|おすすめの商品を紹介
リトリートの目的

これまでメンタルヘルス分野で重視されてきた「Rest・Relaxation・Recreation」の3つにリトリートが加わったことで、より一人ひとり異なる状況に対応し、全ての人が過ごしやすいよう変化しました。
- Rest(レスト):休息|身体や心を休め、疲れを癒す
- Relaxation(リラクゼーション):くつろぎ|のんびりとした時間の中、穏やかな気持ちで過ごす
- Recreation(レクレーション):余暇活動|疲労を癒すために気晴らしとして行う娯楽
- Retreatment(リトリートメント):再治療|普段と違う環境に身を置き心からリラックスする
これらは精神学上でも重要な行いとされ、働き盛りの世代はもちろん、全ての世代が定期的に取り入れるべきだとされています。
周りが見えないほど仕事に没頭しなければならなかったり、家事や育児に追われて少しずつ疲れや鬱憤が溜まってしまったりする前に、上記3つのRに加えてリトリートの考えも取り入れてみてはいかがでしょうか。
ストレス解消とリラックス
リトリートで得られる効果のうち、もっとも大きなものに「ストレス解消」があります。
私たちが抱えているストレスの内容はさまざまですが、大切なのはストレス源から一度距離を置き、余裕をもって対応することです。
人間関係であったり、忙しすぎる仕事内容であったりと、どんなストレスであっても対面し続けていては解決に至らないでしょう。
リトリートで日々の喧騒から離れ、ストレス源のことを考えずにゆったりとした気持ちで過ごすと、頭の中が整理され物事を正しく判断できるようになります。
心には十分なキャパシティが生まれ、ゆとりをもってストレス源と向き合えるでしょう。
自己成長
リトリートでゆったりとした時間を過ごしていると、頭はスッキリと冴え、さまざまな物事について深く考えられるようになります。
自分を取り巻く環境を見直すのはもちろん、自分自身の行いについても考えを巡らせ、より良い自分を目指せるでしょう。
改めるべき短所だけでなく、伸ばすべき長所についても考えることで、自分を認めながら成長へと繋がります。
心と体の健康促進
リトリートで充実した余暇を過ごすことで、身体的なストレスも解消されやすくなります。
特に頭痛や肩こり・腰痛など慢性化しやすい不調がある方は、悪化する前に休養をとり、身体を労わる時間を設けることが大切です。
さらにはストレスが溜まった状態を長く続けることで、精神的な不調を訴える方も少なくありません。
うつ病などで外出が難しくなる方もいれば、適応障害やパニック障害などストレスが身体の不調となって現れる方、原因が分かりにくいのが難点である自律神経失調症に悩まされる方などさまざまなケースが考えられます。
リトリートではこういった身体・精神の両方をケアし、さまざまな不調を防ぐためにも有効だとされています。
生活している環境によっては定期的にリトリートを行い、健康な身体を目指すことが大切です。
人間関係の改善
私たち人間が相手と良好な関係を築けるのは、適切なコミュニケーションと相手への思いやりがあるためです。
どんなに親しい間柄であっても、横柄な態度で接していれば心を開いてもらえなくなるでしょう。
こういった人間関係を円滑に進めるためにも、定期的なリトリートが必要だといえます。
自分の考えを整理し心に余裕を作ることで、相手のことを考えるスペースが生まれ、正しく評価ができるでしょう。
余裕のなさから生まれるすれ違いが減れば、今まで以上に相手の良さにも気が付きやすくなるはずです。
関連記事:仕事でストレスを感じたらやばい?原因や解消方法をご紹介!
リトリートのメリット

上記で挙げたさまざまな目的を元に行われるリトリートですが、1人で行う場合は誰にも邪魔されることなく、自由な時間を思い切り楽しめるのがメリットといえます。
周りに気を遣う必要がないため、ポジティブなことはもちろん、ネガティブなことについても納得いくまで考えられるでしょう。
普段は文句を言えない相手であっても、リトリート中ならば思う存分嫌だったことを思い返し、今後の対策を練ることも可能です。
また、リトリートは必ず一人でやらなければならないわけではありません。
気の置ける友人や家族、同じ環境に身を置く人たちと一緒にリトリートを行い、問題解決に向けてゆっくりと考えてみるのもおすすめです。
普段過ごしている中ではなかなか伝えられないことも、環境が変わると言い出しやすくなることもあるでしょう。
リトリートの選び方のポイント

リトリートにはさまざまな方法があり、自分が無理なくできるものを選ぶ必要があります。
まずは代表的なリトリート方法を参考に、やりやすいものから試してみると良いでしょう。
ヨガ
ヨガは体幹を鍛えて適度な柔軟を行うことで、凝り固まった身体をほぐす効果が期待できます。
ヨガをしている最中は深くリラックスした状態となるため、余計なことを考えたくない方や、身体を動かすことに集中したい方にもおすすめです。
また、デスクワークをしている方などは特に、日頃汗をかく機会が少なく運動不足に陥っている場合があります。
激しい運動を集中的に頑張るのではなく、ヨガのように長く続けやすいものを選ぶことで、運動を習慣化し健康的な身体を目指すことにも繋がります。
デジタルデトックス
デジタルデトックスとは、一定期間インターネットを遮断するリトリート方法です。
スマートフォンやPCなどを見ていると、さまざまな情報が頭に入ってくるため、脳が疲れやすいのが特徴です。
さらには画面が発するブルーライトによって、ドライアイや眼精疲労が進む点にも注意しなければなりません。
暇さえあれば電子機器を触ってしまうという方は、1日1時間から無理のない程度でデジタルデトックスを始めてみましょう。
ぼんやりと過ごすも良し、紙の本を手に取って活字に触れてみるも良し、スマートフォンに触れないこと以外は何をしても大丈夫です。
数あるリトリート方法の中でも自宅で簡単にできるため、旅行に行っている時間がない方や、今すぐに始めてみたい方にもおすすめです。
温泉
温泉は自宅の湯船とは異なり、素敵な風景とさまざまな効能を楽しめる点が魅力です。
名湯といわれる温泉を巡るのはもちろん、隠れた秘湯を訪れてみるのもおすすめです。
親しい間柄の友達や家族と共に、温泉旅行を計画してみても良いでしょう。
単なる温泉旅行と異なるのは、温泉以外の予定を詰め込み過ぎず、あくまでもリラックスできる旅にする必要がある点です。
ついあれもこれもと行きたくなってしまいますが、緻密なスケジュールを立てるのはやめ、現地で目についたものを楽しむ程度に留めましょう。
肩の力を抜いて旅を楽しめば、普段目に留まらない現地の魅力に気が付けるかもしれません。
森林浴
森林のもたらすリラックス効果は、緑の少ない土地で暮らす人々にとってかけがえのないものです。
山に近い場所に住んでいても、木々の中でゆっくりと過ごす毎日を送っている方は少ないでしょう。
特別な持ち物も必要なく、単に木で囲まれた場所を訪れるだけでも、心がスッと鎮まるのを感じられるはずです。
森林浴がなぜ良いのかというと、木から発生している「フィトンチッド」という成分により、血圧が下がったり自律神経のバランスが整ったりするためです。
森林浴をした日の夜は、普段よりも眠りにつきやすく、良質な睡眠をとれるでしょう。
リトリートの注意点

さまざまな利点のあるリトリートですが、行う際はいくつかの注意点を抑えておく必要があります。
第一に、リトリートは無理なく続けることが大切です。ストレスが溜まって疲れを感じているからといって、「やらなければ」と自分を追い込むのはNGです。
忙しい毎日の中で旅行の時間を確保するために無理をしてしまい、結果として身体を壊してしまっては元も子もありません。
また、リトリートを行っている最中は、ストレス源について冷静に考えられる状態がベストです。
考えを巡らせているうちに気持ちが焦り、よりストレスが発生してしまっては意味がありません。
「リトリートに来ているのだからなるべく早く問題を解決しなければ」と考えるよりも、「束の間の休息だから何か楽しいことを考えよう」と、気楽な気持ちでチャレンジすることをおすすめします。
関連記事:アロマテラピーのやり方や効果とは|おすすめのアロマディフューザーを紹介!
まとめ
日々頑張っているすべての人へ、定期的に試してほしいリトリート。
手軽にデジタルデトックスを行ってみたり、思い切って遠方へ行って静養してみたりと、自分に合った方法を見つけましょう。
電池で動くおもちゃは定期的に電池の交換が必要であり、充電式の家電は使った分だけ電気を貯め込まなければ動きません。
人間も明日を頑張るため、適度な休息をとりながら生活することが大切です。
フェミニズムとは? 歴史、問題、そして解決策

男性は外で働き、女性は家事や育児・介護などを担うのが自然とされていたこれまでの日本。
時代が変わるにつれ、今や働きに出るのも家事や育児をするのも性別を問わず行うべきだとし、男性と女性の差を埋めるための思想が広まってきました。
男女平等を訴えるこの考えは「フェミニズム」と呼ばれ、さまざまなシーンで呼びかけられています。
今回はこのフェミニズムについて詳しく知るとともに、これまでどんな歴史を辿ってきたのかや今後の課題などをご紹介します。
フェミニズムとは?

「フェミニズム」という言葉を辞書で調べてみると、「女性と男性の権利を同等のものとするための主張や運動のこと」だとされています。
由来となったのは女性らしさといった意味を持つ「フェミニン(feminine)」であるため、女性が声を挙げて主張することだと思われがちですが、実はそれが全てではありません。
正しい意味を理解しないままに言葉だけが一人歩きしてしまうと、さまざまな場面でトラブルを生んでしまうでしょう。
フェミニズムが掲げるのはあくまでも「男女平等」であり、「男性軽視」ではありません。
これまで軽視の対象であった女性が声を挙げることで、男性の立場が追いやられるのではないかと思う人がいますが、本来の意味は性別を問わず人々がみな同じ土台に立つことです。
男性を追いやって女性がさまざまな権利を得ても、いずれ男性が声を挙げる時代が来て、問題が繰り返しになってしまうでしょう。
昔と比べると、現代は女性の立場が男性へ近づきつつあるといえます。
しかしそんな中でもフェミニズムの考えが重視されているのは、私たちが産まれたときから刷り込みのようにジェンダーに触れ、それが当たり前だと思ってしまっているためでしょう。
男の子なら青や緑が好きな子が多く、屋外で走り回って遊ぶ。
女の子ならピンクが好きで、おままごとやお絵描きをして遊ぶ、といったように、知らず知らずのうちに固定観念として刷り込みが行われているのです。
そんな固定観念は大人になっても頭を支配し続けるでしょう。
仕事と家事・育児の割合だけでなく、男性は昇進をしても女性は変わらないままであったり、一度産休をとると元のポストに戻れなかったりと職場内環境にも大きな影響を及ぼします。
「女性は男性よりも賃金が低いものだ」「産休をとっても良いように重要な仕事は任せない」といったナチュラルな差別は、現代になっても減ったとはいえません。
フェミニズムの考えは、一部の人が声を上げ続けているだけでは意味がありません。
男性・女性や年齢を問わず、全ての人が意識しなくても男女平等を掲げられるよう、フェミニズムについて深く理解しなければならないのです。
関連記事:マイノリティ・マジョリティとは? 多様な社会の理解を深めるために
フェミニズムの歴史

現代は男性・女性を問わずフェミニズムについて知っている人が増え、後は個人や企業がフェミニズムに対しどう考えていくかが問題となっています。
そんなフェミニズムの思想がいつ生まれ、現代までどのように変容してきたのか、詳しい歴史をご紹介します。
第一波フェミニズム
18世紀以前の世界では、政治に参加するのも、民衆を率いるのも全て男性でした。
女性は家業を手伝ったり、家事・育児をしたりして過ごしており、夢を持ったりいつもと違うことに挑戦したりする人はおらず、みな同じような人生を歩んでいたでしょう。
この頃の女性たちには男性に比べて教育が行き届いておらず、限られた知識の中で生きていました。
学校に行きたいと思っても、許されるのは土地や資産を持ったごくわずかな家の娘のみ。
一般家庭に生まれた娘たちは、自然と生まれた瞬間から生き方が決められてしまっていたのです。
ことの始まりは1789年8月に発表された「フランス人権宣言」。
「第1条 人は、自由かつ諸権利において平等なものとして生まれ、そして生存する。」から始まり、階級制度に悩んでいた人々にとって奇跡のような宣言でしたが、これが主に男性のみをターゲットとして作られていたことをご存じでしょうか。
自由や平等を謳っておきながら、男性と女性はこれまで通り顕著であり、女性は人権宣言後も男性の下で生活をしなければなりませんでした。
これに異議を唱える形で起こったのが「第一波フェミニズム」です。男性ばかりが自由を宣言し、どうして女性は自由に生きられないのかと考えた女性たちが、フランスを中心に抗議運動を開始したのです。
第一波フェミニズムでは女性にも参政権を与えることをメインに訴えが続けられ、20世紀にかけて女性が政治に参加する国が増えていきました。
このとき日本は明治時代であり、作家であり思想家の平塚らいてうらがフェミニズム運動を行っていました。
島国であるはずの日本が世界に取り残されることなく、同じ時代に女性の権利を求めるために声を挙げていたことは、その後の日本にとってかけがえのない一歩であったといえるでしょう。
第二波フェミニズム
長いフェミニズムに関する歴史の中で、第二波と呼ばれるのが1960年頃に起こった「ウーマン・リブ(女性解放運動)」です。
1945年に第二次世界大戦が終了してから、女性たちは男性との差を全て解消し、平等に生きることを目的として声を挙げ始めました。
これは性差によって起こる差別全てを対象としており、「男性だから」「女性だから」といった根本的な差を埋めるために行われたものです。
第二波フェミニズムの大きな特徴として挙げられるのは、フェミニズムと同時に「ウーマニズム」の考えが広まった点にあります。
女性らしさといった意味を持ち性差に関する差別をなくすフェミニズムに対し、ウーマニズムは「女性に対する差別全て」をなくすためのものです。
ウーマニズムの中には、性差による差別、人種による差別、年齢による差別など全ての不平等が盛り込まれていました。
この時期にスポットが当てられていたのは、女性が男性に比べて力が弱く、性的な問題においてはまだまだ弱者であったという点です。
望まぬ妊娠をしても中絶する権利が認められていなかったり、繰り返す性生活の中で身体を壊しても病気だと認められなかったりと、女性たちはさまざまな不平等の上で生活をしていました。
第二波フェミニズムによって女性たちは、徐々に中絶の権利や避妊の権利が与えられ、男性と同じく自分を大切にしながら性を意識できるようになっていくのです。
第三波フェミニズム
圧倒的な不平等の元、男性との差を埋めるために行われてきた第一波・第二波フェミニズム活動。
一方の第三波フェミニズムは1990年代に始まり、「女性とはこういうものである」といった固定観念から脱却するための活動として広まりました。
過激なロックバンドが「女性」という枠を超えて活動し始めると、一般人たちも次々に自分たちの手法で「ありのままの自分」を表現するようになったのです。
第三波フェミニズムの波は世界各国に広まり、現在までその考えが色濃く受け継がれています。
「女性は男性の三歩後ろをつつましく歩くべきだ」といったステレオタイプを捨て、どのような夢を追っても、どのような生き方をしても良いのだとする考えは、女性だけでなく男性にも大きな影響を及ぼすものでした。
フェミニズムの影では「男性は常に家を空けて仕事に勤しむべき」「男性は弱音を吐くべきではない」といった固定観念に苦しんでいた男性も多かったのです。
現在
現在の世界は、フェーズでいえば第四波フェミニズムの中にあります。
長い歴史をもつフェミニズムの考え方ですが、今もなお男女の差が完全になくなったわけではありません。
近年はスマートフォンの普及率も高水準をキープしており、若い世代を中心にSNSで考えを共有するシーンが増えました。
職場で男性との扱いに差を感じて嫌な思いをしたり、性暴力をふるわれた経験があったりと、これまで女性たちが自分の中に秘めていた悩みを匿名で打ち明けられるようになったのです。
世界のどこかに自分と同じ経験をした人がいたり、気持ちに寄り添ってくれる人がいたりするだけでも、抱え込んでいた辛さがふっと楽になるでしょう。
第四波フェミニズムでは、SNSにて「#MeToo運動」が行われました。
これはSNS上で性暴力の被害を訴え、隠された実態を明らかにすることで、社会全体でトラブルを防ぐ目的で行われたものです。
さらには日本国内で「#KuToo運動」なるものも始まり、出勤時にハイヒールを履くことを義務付けられるのはおかしい、といった考えも広まりました。
これまでのフェミニズムと異なるのは、芸能人など声の大きい存在だけでなく、一般人からこのような考えが広まるケースがある、といった点です。
私たちの誰もがフェミニズムに関係があり、辛い思いを発信することで団結力が生まれます。一人で悩まずに同じ悩みをもった人を見つけることで、社会全体の抑止力に繋がるでしょう。
関連記事:社内で円滑にコミュニケーションをとるコツや成功事例を紹介
フェミニズムの抱える問題

フェミニズムを語る上でもっとも注意しなければならないのは、ある「誤解」についてです。
これは一部の過激派に属する人々が、「男女平等」ではなく「女性重視・男性軽視」を訴えているためだといえます。
女性優先車両に間違えて乗ってしまった男性を袋叩きにして追い出したり、何もしていないのに痴漢の容疑をかけられた男性に対し「男性だから仕方ない」と批判してみたりと、さまざまな場面でフェミニズムを履き違えた男性軽視が行われています。
この側面だけを見てしまった人々は、フェミニズムの正しい意味を理解できず、「やっかいな人々」だと勘違いしてしまうことも多いのです。
2024年にSNS上で話題となったのは、「男児は何歳まで女性用トイレを使って良いのか」といった内容です。
防犯上幼い子どもが母親と一緒に女性用トイレを使うシーンも多い中、何歳であっても男性であることには変わりないため、女性用トイレに入ることを禁じてほしいといった声が上がっていました。
中には1人で歩けない乳児であっても男児であれば女性用トイレに入るべきではない、といった声もあり、賛否両論を生んでいます。
繰り返しになりますが、フェミニズムとは男女が平等な立場で生きられる世界を求める考え方です。
女性ばかりが優遇され、男性が損をする社会は平等ではありません。
大切なのは一部だけを見て「アンチ・フェミニズム」になるのではなく、正しい方法で平等を目指すことにあるのではないでしょうか。
関連記事:夫婦仲が悪い原因は?子供に与える影響や改善する方法をご紹介
フェミニズムの正しい知識を身につけよう
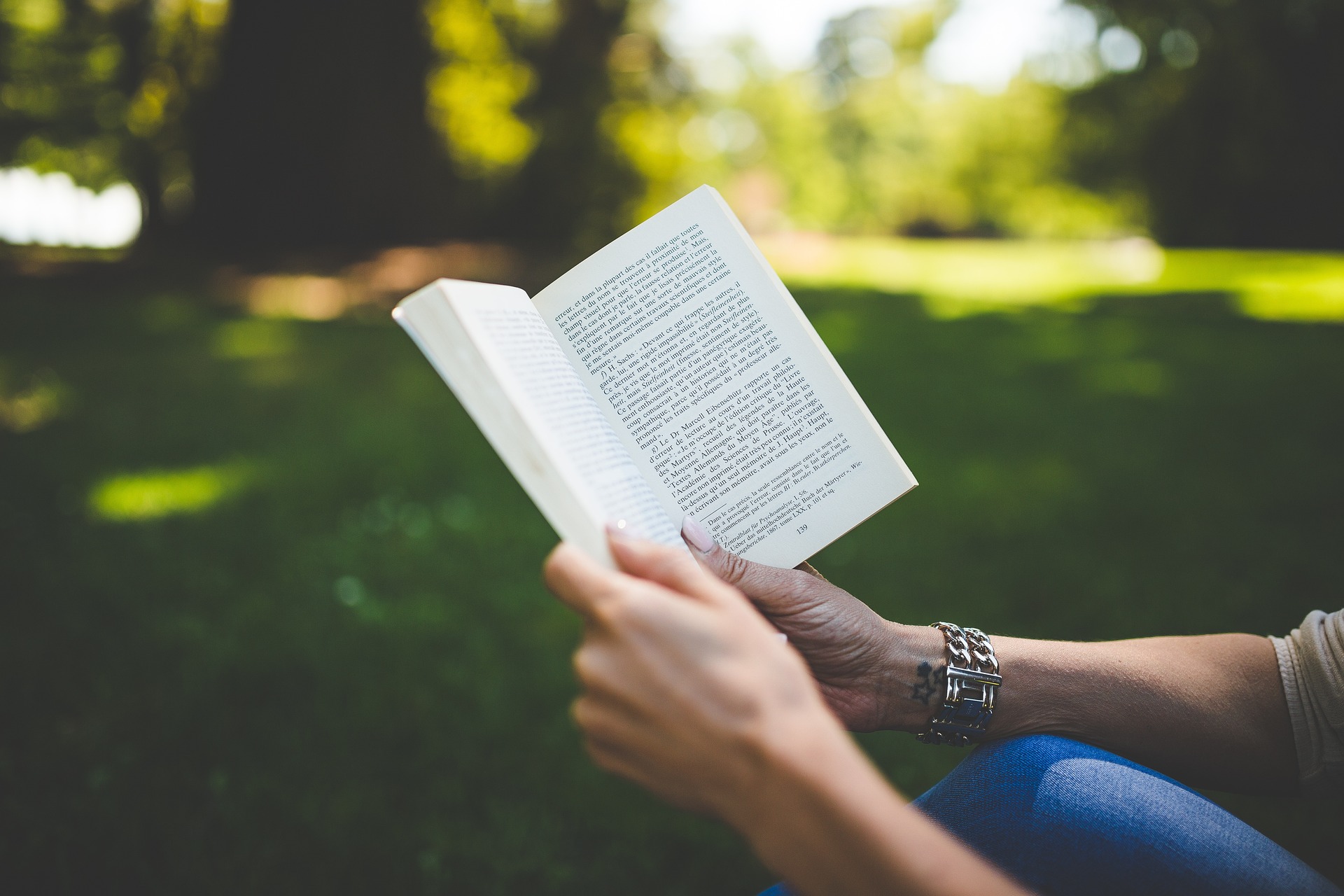
フェミニズム運動について正しく知るためには、まず識者の執筆した本を読むことから始めましょう。
先程も触れたように、SNSで一部の人の声ばかりを見ていると、考えが偏る原因となります。
フェミニズムの考え方も人によって細かく異なるため、根底となる知識を得た後、自分なりにフェミニズムについて考えてみるのが大切です。
また、フェミニズムを自分と関係のないことだと考えず、「自分ならどうするか」を考えるのも良いでしょう。
あなたが女性であれば、これまでに性差が理由で差別された経験や、そのときに感じたモヤモヤした気持ちについて振り返ります。
あなたが男性であれば、妻・兄弟・友人・母親など身近なところにいる女性にどう対応しているのかを振り返りましょう。
フェミニズムの考えを正しく広めるためには、女性だけでなく男性の力も必要不可欠です。
まずは自分の属する小さなコミュニティの中で、男性・女性にとっての差別が起きていないか考えることから始めてみてはいかがでしょうか。
まとめ
さまざまな歴史の中で現代まで発展してきたフェミニズム。
社会全体という大きなコミュニティを変える前に、身の回りからできることを始めましょう。
男性だから、女性だからといった考えを捨てるとともに、未来を生きる子供たちがより過ごしやすい社会づくりが必要です。
21日間のジャーナリングで人生を変えよう

※この記事は、アメリカの記事を日本語に訳したものです。
https://level.game/blogs/can-writing-affirmations-for-21-days-change-your-life?lang=en
「You Can Heal Your Life(あなたは人生を癒すことができる)」というアメリカの作家ルイーズ・ヘイの不朽の言葉には、世界中の人の人生を変えた深い真実が隠されています。それは「アファメーションの力」。つまり、シンプルで前向きな言葉によって、あなたの考え方そのものを変え、夢や願望を実現するための土台を作ることができるのです。数えきれないほどの自己啓発が実験されてきたが、21日間のアファメーションは、私たちを変革するための力強い方法であることがわかってきた。
このアファメーションは単なる希望的観測ではありません。ポジティブな自己イメージを築き、自分にふさわしい人生を引き寄せるために、潜在意識を書き換える方法なのです。
アファメーションとは
アファメーションとは、潜在意識をポジティブにし、ネガティブな思考を取り除き、自信を高めるためのポジティブな文言のことです。常にアファメーションを繰り返し、それを信じることで、ポジティブな変化を起こすことができるのです。「私は〇〇です」という言い方のアファメーションは、あなたの存在意義、そして能力を肯定し、あなたの自己肯定感を高める強力なツールです。こういったアファメーションは、あなたの幸福度を高めポジティブな人生を促すでしょう。
21日間のアファメーション・チャレンジ
ポジティブなアファメーションのやり方としては、毎朝5つのセリフを自分に語りかけるという方法があります。21日間アファメーションを書き続ける理由は、新しい習慣を作るには21日かかるという調査結果に基づいています。この21日間は、あなたの脳をポジティブ思考へといざなうための神聖な期間なのです。毎朝、5つのセリフを自分に語りかけることで、自分の強い決意を確認し、素晴らしい1日の幕開けとなります。
アファメーションの文言を作る
効果的なアファメーションを作るには、「私は〇〇だ」というフレーズから始めましょう。例えば、「私は愛と尊敬を受けるに値する人間だ」とか、「私は自分が思っている以上に強い人間だ」などです。こういうアファメーションは、個人的なもので、前向きな内容で、明確な言い方でなければいけません。さらに、現在形で唱え続けることで、あなたの心は、それがすでに起こっていることであり、未来のことではないと考えるようになります。例えば、もっと創造性を高めたいという人は、「私は想像力に満ちている」というアファメーションの後に文章を書くと、革新的なアイデアが次々と出てくるでしょう。
アファメーションを書くメリット
アファメーションを唱えるのではなく、実際に書くことで、あなたの精神的、感情的、そして肉体的な幸福にも大きな影響を与えることができます。主な効果をいくつか紹介しましょう。
精神的健康の向上: アファメーションは、しばしば不安やうつにつながるネガティブな思考を打ち消すのに役立ちます。ポジティブな結果に焦点を当てることで、より楽観的に物事を考えられるようになります。
自信がつく: 自分の存在意義を定期的に肯定することで、自己肯定感を高めることができます。「私は〇〇」という言葉は、自分への自信を強めるのに特に効果的です。
集中力が高まる: アファメーションを書くことで、目標を常に頭の片隅に置いておくことができ、目標達成に必要な行動を取りやすくなります。
ストレスの軽減: ポジティブなアファメーションは、思考を、心配事をからポジティブな視点へとシフトさせることで、ストレスを軽減することができます。
願望実現: 引き寄せの法則は、肯定的な思考に集中することで、肯定的な人生をもたらすことができるでしょう。アファメーションは、まさにこういった願望実現のためのツールです。
人間関係: 人間関係についてポジティブな発言をすることで、周囲の人と思いやりをもった協力的な環境を育むことができます。
自己回復: ヒーリングのためのアファメーションは、病気や怪我ではなく、健康や癒しに意識を集中させることで、回復や幸福感を促進することができます。
つまり、21日間アファメーションを書き続けることは、大きな自己成長と変容をもたらすための、とてもパワフルな取り組みなのです。この取り組みに必要なのは、ポジティブに変化したいという意欲と、毎日数分だけ行うという決意だけ。このアファメーションを毎日行うことで、人生のあらゆる分野において数えきれないメリットを受け取ることができるでしょう。
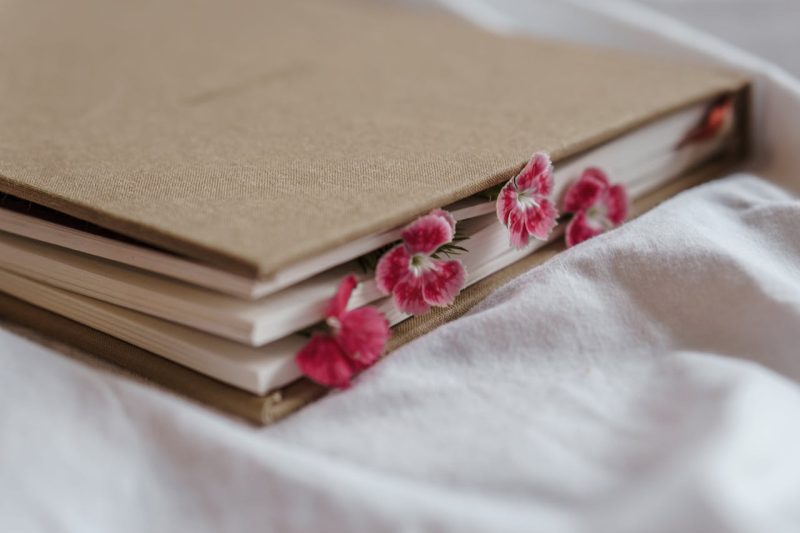
アファメーションを始めるために必要なもの
21日間のアファメーションを書き続けるために必要な道具はペンと紙で十分です。最も重要なのは、心をオープンにし、新しいことにトライする意欲、そして自己改善への決意です。自己肯定感、健康、キャリア、人間関係などの分野で、あなたが深く共感できるアファメーションの言葉を選びましょう。
アファメーションを日常生活に取り入れる
アファメーションを日常生活に取り入れるのは簡単です。日記に書いたり、鏡の前で声に出したり、瞑想中に心の中で繰り返したりして取り入れましょう。大切なことは一貫していることです。例えば「私は毎日癒されています」のようなアファメーションの時は、まるで癒しているような静かな時間に唱えると、特に効果があります。
アファメーションを書くメリット
アファメーションを日常生活にとりこむことは、自分の成長のためにも効果があります。これによって、自分の意思を固め、思考と行動を一致させ、自分は成功に向かっているというマインドセットを育てることができるでしょう。
以下の21日間モデルと、アファメーションの例を参考にしてみてください。
Day 1: あなたがなりたい自分をイメージしてください。
例: 私は自分を誇りに思い、自分のユニークな性格を称えます。
Day 2: 誰かを助けたときのことを書き、それがどんな気持ちになったかを書いてください。
例:私は人の人生に前向きな力を与えています。
Day 3: あなたが今直面している課題を思い浮かべ、それをどう克服するかを考えてください。
例:私には、心が折れても立ち直る力がある。
Day 4: 1年後の自分を思い描いてください。
例:私は明るく成功した未来に向かっています。
Day 5: あなたの人生で乗り越えた困難な時期について、どのように乗り越えたかを書いてください。
例:私の人生には明確な目的がある。私はとても恵まれている。
Day 6: あなたが達成した目標と、それを達成した方法を書いてください。
例: 私は、日々の努力を重ねて目標を達成し、成功を祝うことができます。
Day 7: 失敗が教えてくれた貴重な教訓を振り返ってください。
例:私はどんな経験からも学び、成長します。
Day 8: あなたにインスピレーションを与えてくれる人について書いてください。
例:私は友の偉大さに刺激をうけ、自分も人にインスプレーションを与えられるよう努力します。
Day 9: あなたが恐れていることを思い浮かべ、それにどう立ち向かうかを考えてください。
例: 私は強くて、立ち向かう勇気を持っています。
Day 10: あなたにとっての夢とその意味を書いてください。
例:私は夢を追い求め、一歩一歩夢に近づいています。
Day 11: 他人が言ってくれたあなたへの誉め言葉と、あなたをそれをどう感じたかを振り返ってください。
例: 私は自分の努力や資質を評価され、認められている。
Day 12: あなたの人生で変えたいことについて書いてください。
例:私は自分の人生を自分でデザインしている。
Day 13: 自分が信じられないほど誇らしく感じた瞬間について書いてください。
例: 私は自分の業績を誇りに思っています。
Day 14: あなたが身につけたい習慣とその理由を考えてください。
例:私は毎日、新しく前向きな習慣を身につけています。
Day 15: あなたにとって大切な人間関係について書いてください。
例:すべての人間関係で私は愛に満たされています。
Day 16: あなたが勇気を示した瞬間を振り返ってください。
例:私は勇気があり、自分が信じるもののために立ち上がる。
Day 17: 楽しみにしていることについて書いてください。
例:私は未来が楽しみです。
Day 18: あなたが学びたいスキルとその理由を考えてみてください。
例:私は人生のあらゆる分野で常に学び、成長しています。
Day 19: 今日、どのように自分に優しくできるかを書いてください。
例:私は自分に優しく、癒してあげる価値があります。
Day 20: あなたが安心できる場所について書いてください。
例:私は家族と仲間と一緒にいる時に安心できる。
Day 21:この20日間を振り返り、あなたがどういう成長をしたかについて考えてみてください。
例:私は自分の今までの道のりに感謝し、すべての学びを受け入れます。
アファメーションを書く時間
アファメーションを実践する方法は1つだけではありません。例えば、アファメーションを書くのに最適なのは、1日のうちで邪魔が入らず集中できる静かな時間帯です。多くの人は朝が理想的だと感じているようです。毎朝5行だけ書きながら自分に語りかけることは、自分のマインドに人生の目的意識と前向きな気持ちを植えつけるとても効果的な方法です。ただ人によってはアファメーションを夜に書きたいという人もいるでしょう。いずれにせよ大切なことは、静かな時間を選び、継続して行うことです。
アファメーションだけでなく、毎日瞑想を実践したり、ストレッチをして体調を整えたり、集中力や睡眠のために音楽を聴いたりするのも良いでしょう。ぜひあなたもアファメーションを試して、人生をさらにポジティブに変化させましょう。
マイノリティ・マジョリティとは? 多様な社会の理解を深めるために

2024年現在、日本の総人口は1億2千万人を超えており、誰しもが自分以外の誰かと関わりながら生きています。
そんな大人数のコミュニティで生きるためには、自分の考えだけでなく、周りの考えを柔軟に受け入れることが大切です。
今回は「多様性」の考え方が進む現代において、さまざまな場面で目の当たりにするマイノリティ・マジョリティについて考えてみましょう。
よく見られるマイノリティの種類や具体例を挙げながら、社会に与える影響や問題点に着目してご紹介します。
マイノリティ・マジョリティとは?

マイノリティ(minority)とは、ある事象において少数派となる考え方やその人々を指す言葉です。
元となったマイナー(minor)という単語には「それほど重要ではない」という意味がありますが、マイノリティの場合は重要かそうでないかといった意味は含まれず、単に数が少ないという意味を持ちます。
例えば、自分と相手の2人が話していて意見が対立した場合、どちらかがマイノリティとなることはありません。
しかし10人のうち1人が異なる意見を唱えた場合、それはマイノリティといって良いでしょう。
一方、マイノリティの対義語として挙げられるのがマジョリティ(majority)です。
こちらも元となったメジャー(major)には「重要」という意味がありますが、マジョリティの場合は単に「多数派」という意味になります。
人気アイドルグループの楽曲名にも使われた単語であるため、耳なじみのある方も多いのではないでしょうか。
マイノリティとマジョリティについて話し合うとき、しばしば「マイノリティ=差別の対象」と捉えられる場合があります。
本来の言語にそのような意味がないにもかかわらず、どうしてこのような考えが生まれてしまうのでしょうか。
続いての見出しでは、マイノリティの具体的な例を挙げながら、社会におけるマイノリティの立ち位置についてご紹介します。
関連記事:ノンバーバル(非言語)コミュニケーションの重要性を徹底解説!
マイノリティの種類

一言でマイノリティといってもその種類はさまざまです。
あるコミュニティにおいて多数派だった人も、別のコミュニティに行けば少数派になることがあり、自分がマジョリティ・マイノリティのどちらに属するのかは場所・時間・人数などによって変わります。
これからご紹介するマイノリティの数々は、一部では批判の的となることもあり、社会問題として問題視されています。
自分の属する方だけでなく、周りの意見も柔軟に取り入れ、広い視野をもって問題に取り組むことが大切です。
性的マイノリティ
性的マイノリティ、別名「セクシャルマイノリティ」は、マジョリティ・マイノリティに関する問題の中でもひときわ議題に上がりがちです。
これは相手が性的マイノリティであることが分かりやすく、「自分とは違う」といった意識が芽生え、差別の対象となりやすいことが原因といえます。
近年、性的マイノリティに属する人々は、「LGBTQIA+」と表されることが増えてきました。
- L:レズビアン|女性を恋愛対象とする女性のこと
- G:ゲイ|男性を恋愛対象とする男性のこと
- B:バイ|男女どちらも恋愛対象となる人のこと
- T:トランスジェンダー|身体の性別と反対の性自認を元に恋愛をする人のこと
- Q:クエスチョン/クィア|性自認や性的嗜好が定まっていない人のこと
- I:インターセックス|性的な特徴を持つ部位が一般的な男女の状態に当てはまらない人のこと
- A:アセクシュアル|誰にも恋愛感情を持たない人のこと
上記7つの分類に当てはまらないさまざまな性自認・性的嗜好を含める意味でも、最後に「+」マークをつけて表記されているのを多く見かけます。
中には身体の性別は男性・性自認は女性・なおかつレズビアンであるという、一見して男性が女性に恋をしているのと見分けのつきにくいケースも見られます。
また、男性と女性のどちらにも当てはまらない存在「Xジェンダー」なども増えつつあります。
全方向に愛情を持ち、性別を問わず恋愛ができる「パンセクシュアル」も、近年話題に上がることが多いでしょう。
男性は女性を、女性は男性を愛するのが「マジョリティ」とするならば、これらの性的マイノリティはまだまだ少数です。
しかしLGBTQIA+全体で考えると、人口の約1割程度が当てはまるといわれています。
社会的マイノリティ
社会的マイノリティに当てはまるケースは多種多様であり、誰が該当すると一概にはいえません。
端的にいえば、社会の大きな圧力の中で少数派に押しやられ、発言の権利が失われたり、差別の対象となったりすることが多いといえます。
社会的マイノリティの例として挙げられるのは、ホームレスや貧困層などの経済弱者、身体的・精神的を問わず障害を持つ人たち、女性などです。
特に古い時代は女性への差別がはなはだしく、仕事をする権利が奪われていたり、政治的発言権がなかったりすることも珍しくありませんでした。
こういった社会的マイノリティの考え方をなくし、性別・経済状態・身体的特徴に関わらず同じ生活ができるように配慮していくことが大切です。
エスニックマイノリティ
エスニックマイノリティは、日本語に訳すと「少数民族」となります。
私たちが暮らす日本においては耳なじみの薄い方も多いのではないでしょうか。
世界には190ほどの国がありますが、民族に分けるとその数は数千に上るといわれています。
これらの中には継承する人がいないためになくなりかけている民族もあれば、他民族との結婚を重ねて消滅した民族もあり、その数は常に変動を続けているといって良いでしょう。
日本の場合で考えてみると、大きく分けて3つの民族が存在します。
北海道を中心とするアイヌ民族、本土を中心とする本土人、さらには沖縄を中心とする琉球民族です。
これらのうち、もっとも数が多いのは本土人です。つまり日本においては、アイヌ民族と琉球民族がエスニックマイノリティに当てはまるといえるでしょう。
日本を出て世界に目を向けてみると、日本人は「アジア人」として一括りにされ、黄色人種として差別の対象になることがあります。
肌の色での差別は2020年代に入っても未だなくならず、私たちにとっても決して例外ではありません。
気が付かないうちに差別・偏見を持っていないか、一人ひとりが改めて問題に目を向けて考えてみることが大切です。
宗教的マイノリティ
近年、若い世代を中心に宗教への興味が薄れ、無宗教を掲げる人も増えてきました。
今も日本全体を見れば仏教がもっとも多く、日本ならではの神道が続きます。キリスト教など世界的に多くの信者がいる宗教も、日本の中ではわずか数パーセントしかおらず、宗教的マイノリティに当てはまるでしょう。
無宗教である人も含め、宗教的マイノリティが時として争いを生むケースもあります。
世界ではイスラーム過激派が猛威を振るったことをきっかけに、一般的なイスラム教徒が差別の対象となり、身体的・精神的に傷を負った事件もありました。
宗教的マイノリティでは、「相手のことを良く知らない」「何を考えているか分からない」といった理解の不足から差別や偏見が起こります。
日本国内では関心の薄い問題であるとはいえ、世界的に見れば大きな問題の一つといえるでしょう。
カースト制度
インドで行われているカースト制度について、教科書などで見聞きしたことのある方も多いのではないでしょうか。
カースト制度では国民を以下の5階級に分け、それぞれが異なる扱いを受けています。
- バラモン:司祭
- クシャトリア:王族
- ヴァイシャ:庶民
- シュードラ:隷属民
- ダリット:不可触民
現在インド憲法ではカースト制度が明確に否定されていますが、国民の中では未だに色濃く根付き、差別の対象となっています。
バラモン・クシャトリア・ヴァイシャの3つは上流階級とされていますが、シュードラは下流階級、ダリットに至っては他の階級とコミュニケーションをとることさえ許されていません。
ダリットが少しでも触れたものは不浄であるとされ、他の人が触れるのを禁じているため、「不可触民」と名付けられたといわれています。
これはインドの制度ですが、日本でも一部の地域で同じような風習があり、兼ねてから問題視されてきました。
それがいわゆる「部落差別」。
始まりは江戸時代といわれており、武士や百姓・町人に分類されなかった一部の人たちが差別を受け、その子孫が今もなお差別に苦しんでいるのです。
勘違いされがちなのは、これらの人たちは江戸時代で単に差別に苦しんでいたかといえばそうではありません。
一部の人々は農林業・水産業に従事し、また一部の人々は芸能業に従事するなど、私たちの生活に欠かせない職業に就いていたのです。
つまり彼らの子孫も何ら差別されるいわれはなく、このような差別をなくそうとする試みが続けられています。
経済的マイノリティ
経済的マイノリティとは、その名の通り「経済的に苦しい人々」「貧困層」などを指す言葉です。
時にはホームレスや生活保護受給者であったり、時には年収200万円以下の人を指したりと、場合によってその対象は異なります。
例えば、オフィスでデスクワークを行う人を「ホワイトカラー」、現場で身体を使って作業する人を「ブルーカラー」と呼んだ時代がありました。
これは単に来ている服装のことだけでなく、大学を卒業していなければホワイトカラーにはなれない、一生懸命勉強しなければブルーカラーになってしまう、といった差別的意味合いで使われることも多かったのです。
これに伴い、「ホワイトカラー=高給取り」というイメージが広まりました。
一定以上の収入がある人々が貧困層をあざ笑うとともに、体力を使う仕事を見下す人も増えてしまったのです。
現在はというと、現場で働く人々はそれぞれ異なる資格を持っていることも多く、さまざまなスキルを要する仕事が増えてきました。
これに伴い、職業による差別が徐々に薄れてきたといえるでしょう。
関連記事:友達を作る場所はどこ?社会人で遊ぶ友達がいないのはやばい?
マイノリティ・マジョリティの使い方と具体例

これまでご紹介してきたマイノリティはごく一部であり、私たちの身の回りでもさまざまなシーンで使われています。
マイノリティ・マジョリティの具体例を元に、それぞれのイメージを膨らませてみましょう。
マイノリティの具体例
私たちがイメージしやすいマイノリティに、「左利き」があります。
右利きに比べて数の少ない左利きは全体の1%ほどしかおらず、どちらになるかは脳の発達の影響が大きいといわれています。
左利きだからといって差別を受けるケースはそれほど多くないものの、ハサミやお玉が使いにくかったり、駅の改札を通りにくかったりといった不都合を感じる方も多いようです。
これらの不都合全てに対応するにはまだまだ時間がかかると思われますが、今もなお右利き・左利きに関わらず過ごしやすい設備の導入が検討されています。
左利きと聞くと、「頭が良い」と思われるケースも珍しくないでしょう。
左利きの場合は右脳が発達しており、アーティスティックな感性を持っている方も多いようです。
さらには日常生活で右手を使わなければならない場面も多く、左右の脳をどちらも使っているために処理能力が速いともいわれています。
とはいえこれらの違いは微々たるものであり、個人差も考慮しなければなりません。
「左利きなのにテストの成績が悪い」などといった考えは差別の元となるため、利き手に関わらず同等に考えることが大切です。
マジョリティの具体例
日本人がマジョリティとなるケースとして挙げられるのは、主に日本に住んでいる場合です。
そしてこの場合にマイノリティとなるのは、日本に移り住んできた外国人やハーフの方々です。
学校や職場においてコミュニケーションが難しく、孤立してしまうケースも少なくありません。
こんなとき、マジョリティである日本人がとるべき行動は、マイノリティを特別扱いすることではありません。
日本語でやり取りができないのならば翻訳アプリを使い、生活スタイルに違いがあるのならば寄り添い、周りの日本人と同じように接することが大切です。
関連記事:人間関係が「めんどくさい」「疲れた」と感じる心理や対処法を解説
マイノリティ・マジョリティの影響

マイノリティ・マジョリティの問題は、いかなる場合であってもゼロにすることはできないでしょう。
人々の間で考えが割れたり、出身や職業が違ったりする限り、多数派・少数派の違いはどうしても出てきてしまいます。
問題なのは、時としてマジョリティがマイノリティの考えや生活スタイルを圧倒し、差別の対象として捉えてしまうといった点です。
経済的マジョリティでは家を失う心配がなく、カースト制度上では差別を受ける心配がないなど、マジョリティには一種の特権があります。
これは本人の意思に関わらず自動的に付与されるもののため、気が付かないうちにマイノリティを差別したり、下に見たりしてしまうこともあるでしょう。
私たちが重視しなければならないのは、「マイノリティ=悪」といった考えを根本から捨てることです。
自分と違うからといって悪いわけではなく、数が少ないからといって軽視して良いわけではありません。
冒頭でも述べたように、私たちはいつでもマイノリティ・マジョリティの両方に属しています。
考え方を変え、多数派・少数派に関わらず相手の認識を受け入れることが大切だといえるでしょう。
まとめ
マイノリティとマジョリティが対立してしまうのは、コミュニケーションが不足し、お互いを理解できていないことが原因です。
視野を広く持ち、相手の考えを受け入れることこそが、根本的な差別をなくす第一歩となるでしょう。
私たち人間に与えられたコミュニケーション能力は、相手をけなすためにあるわけではありません。相手を理解するためにその言語を使い、より良い社会を目指していくべきだといえます。
恐れるのは死よりも後悔。今を大切に生きる意味

Humming編集部 條川純のコラムをお届けします。
誰もが必ず経験する「死」。私たちは、大切な人を失う痛みを味わい、いつかは自分自身もこの世を去ります。
死ぬことは怖いというイメージがありますが、本当に死は恐れるべきことなのでしょうか。
最近知った友人の病気や、過去に大切な家族を癌で亡くした経験、そしてテレビやネットで耳にする著名人の訃報など、身近な出来事をきっかけに、私は死について考え続けてきました。そんな中で培ってきた私の死生観について話してみたいと思います。
恐れるのは「後悔」を残して死を迎えること
40歳を目前に、この先の人生を考えると共に、死を意識するようになりました。そして気がついたのは、私は死ぬことよりも、後悔を恐れているということです。
後悔のない人生を歩むためにも、私は他人を尊重し、思いやりを持って接することを大切にしたいと改めて感じています。そうすることが、自分自身の幸福につながると確信しているからです。
また、他人からの評価にとらわれるのではなく、自分自身に集中したいと思っています。
例えば、スマートフォンやソーシャルメディアに依存する生活を送っていると、他者と自分を比較してしまったり、「いいね」の数が気になったり、本当に大切なことを見落としがちです。
どんな情報でも簡単に手に入り、遠く離れた人ともオンラインでコミュニケーションが取れる便利な時代。だからこそ、大切な人に直接会ったり、旅に出て新しい経験をしたり、リアルな交流や体験を大切にしたい。直接的な人とのつながりや、五感を通して得られる生の経験には、かけがえのない価値があるはずです。
人生は一度きり。後悔のない人生を歩むために、自分と向き合い、今この瞬間を大切に生きていきたいです。
大切なひとの死を乗り越えるために
生きている間には、大切な人とのお別れを経験することがあるでしょう。私たちは、愛する人を失った時、計り知れない悲しみと喪失感に襲われます。
以前、親しい友人が親を亡くした時のことを思い出します。彼は耐え難い悲しみに襲われ、その対処法を見出すことができずに、自分自身を傷つけてしまったのです。悲しみの渦から抜け出せない彼を見て、私は死を乗り越える方法について考えさせられました。
現代社会では、家族が亡くなった後、残された親族はすぐに書類作業や法的手続き、請求書の支払いに追われ、死を受け入れる余裕がないことが多いように感じます。
大切な人を失った時には、思い出の場所を訪れたり、写真を眺めたり、故人を偲ぶ時間を持つことが大切です。また、「故人は最後に何を伝えたかったのだろう」と考えたり、「今の自分の生き方を故人が見たらどう思うだろう」と自らを振り返る内省の時間も必要でしょう。心の傷は簡単には癒えないものです。適切なケアを怠ると、その傷は長い間心の奥底に残り続け、私たちを苦しめる可能性があります。
悲しみに寄り添い、故人との思い出を大切にしながら、徐々に新しい日常を築いていくことが、大切な人の死を乗り越えるための健全なプロセスなのかもしれません。
避けては通れない「死」という現実
死は人生の一部であり、恐れるべきことではありません。むしろ、死を受け入れることで、今この瞬間を大切に過ごすことができるでしょう。
大切な人を失ったとき、或いは自分自身の死に直面したとき、悲しみや喪失感にとらわれるのは自然なことです。しかし、そこにとどまるのではなく、亡くなった人との思い出や、自分がこれまで歩んできた人生の旅路を振り返り、感謝の意を込めることが大切なのではないでしょうか。
女性のためのソープに込めた情熱と信念。「女性はもっと自分を大切にしてあげて」【高倉健社長インタビュー 03】

フェムケアという言葉が一般的になる前からこのカテゴリーの商品を手掛けてきたたかくら新産業。同社の挑戦は当時ほとんど知られていなかった経皮吸収という概念に着目したことに始まります。ハミングは今回、フェムケアの先駆者とも言える同社の社長、高倉健さんにインタビューしました。10年以上前からこの分野に取り組んできた高倉さんが、フェムケアを通じて伝えたいメッセージ、日本の女性たちがデリケートゾーンのケアを重視すべき理由をお聞きしました。
ーオーガニック商品を扱うたかくら新産業ですが、フェムケア商品も10年以上前から販売されていますね。どうしてこのフェムケアのアイテムを取り入れたのですか?
弊社はオーガニックのブランド始めて18年ぐらいになります。オーガニックを扱っていくなかで気づいたのは、ケミカル品を悪だと考える人がいるということです。私たちは、ものすごくストイックにオーガニックを追及していますけど、ケミカルが悪とは思っていません。それをちゃんと伝えたいと思いました。今では、経皮吸収という言葉をよく聞きますが、この言葉をを日本に普及させたのは私だと自負しています。なぜなら、私はまだこの言葉が日本で広まる前から経皮吸収に着目していたからです。
オーガニック原料が豊富なオーストラリアで商品を作ろうということになり、オーストラリアの工場に視察に訪れた時のことです。そこで妻が以前に乳がんになったという話をしたら、デオドラントに気をつけているかと聞かれました。「デオドラントに入っているアルミニウムで乳癌リスクが3倍高くなる」「脇はすごく吸収しやすい部位だから、脇に使うものは気を付けて」と教えてもらったんです。日本に戻り、オーストラリアで聞いた「吸収しやすい部位」について文献を探していたら、イギリスで行われた経皮吸収率の調査データを見つけました。
物質が皮膚を通してどのくらい吸収されるかを経皮吸収率と言いますが、これは身体の部位によって違います。腕の内側を1としたとき、頭皮が3.5倍、脇は3.6倍、下顎は14倍も吸収します。では、デリケートゾーンはどうなんだろうと調べたら42倍だったんです。その時にオーガニックに変えるべきなのは、経皮吸収率が一番高いデリケートゾーンでそのための商品を作らなければと思ったのです。
ーなるほど。そういう理由で、経皮吸収率が高い部位に使えるオーラルケアやデオドラント商品も扱っているのですね。
私の会社はフェイシャル商品は1個も作っていません。でも、フェイシャル商品はオーガニックにしても意味がないというわけではありません。ただ、私は人のまねが嫌なんです。誰もやってないことをやりたいですね。
ー「ピュビケア オーガニック」の最初の商品はイタリアで作られたとのことですが?
「ピュビケア オーガニック」がスタートしてから、ブランドのリニューアルは4回していますが、1番最初の商品は、デリケートゾーン商品の開発が進んでいたイタリアで製造しました。例えば、イタリアには、娘が生まれると母親がデリケートゾーンのアイテムの使い方を教えるという文化があるんですね。ある時イタリアの出張で泊まったホテルにあったトイレのビデの中にデリケートゾーン専用のソープが設置されていたのです。それなのに歯ブラシは置いていませんでした。イタリアは、歯ブラシよりもデリケートゾーンのケアの方が優先度が高いのか!と、とてもびっくりしました。翌日、工場でその話をしたら、イタリア人の従業員たちに「デリケートゾーン専門ソープなんて当たり前だよ」と言われました。日本人は身体の全ての部分をボディーソープで洗うと言ったら、「オーマイガッド!」と驚かれましたね。(笑)
ーイタリアでは、身体を同じソープで洗うことが驚かれてしまうことなんですね。
この体験から、デリケートゾーンを大切にするイタリアの習慣を日本にも伝えることが大事だと思いました。しかし、フェムケアアイテムは販売当初は全く日本では売れませんでした。なぜかというと、当時、デリケートゾーンの市場には生理用品しかなかったからです。デリケートゾーン用のソープもミルクもなく、そもそもそういうカテゴリーが存在しなかったので、日本人は誰も知らないわけですよね。そこで「デリケートゾーン・アンバサダー講座」を開催し、デリケートゾ―ンのケアが女性にとってどんなにメリットがあるかを伝えていきました。こういった試みを続けていくと、ケアすることのメリットを徐々に知ってもらえるようになり、フェムケア商品を手にする方が増えていきました。

ー「ピュビケア オーガニック」が他社のフェムケア商品とは違うところは?
まずは、徹底的にエビデンスと安心面にこだわっているところですね。我々は徹底的にオーガニックのものを使っています。例えば、膣の中には善玉菌と悪玉菌がいて、善玉菌がたくさんいると膣内環境が良くなり生理痛もひどくなかったり様々なトラブルになりにくいのです。でも、この膣をゴシゴシと化学品の入ったせっけんで洗うと善玉菌を殺してしまうんです。だから私たちは徹底的な天然成分、オーガニック原料にこだわっています。
また、ソープの泡にもかなりこだわっています。女性のデリケートゾーンの3大悩みは、かゆみ、かぶれ、匂いと言わますが、その半分が雑菌によるものです。さらにアンダーヘアがあると、どうしても雑菌が付着しやすくその状況で、織物シートや生理ナプキンでフタをしているとまさに雑菌パラダイスの状況です。ですから弱酸性の優しい成分で、優しく洗うことが大事です。これが私たちが泡に徹底的にこだわる理由です。
2023年の「ピュビケア オーガニック」のリニューアルでは、世界で初めて、カンジダを予防する商品を出しました。カンジダを性感染症だと思っている方が多いんですが、実はセックスをしてうつるのではなく、カンジダは常在菌でほとんどの人が身体に持っている菌なんです。それがストレスや食事が原因で発症しますが、今まではこのカンジダを予防する方法がありませんでした。
そこで注目されたのがナマコ由来の「ホロトキシン」という成分です。約10年前から研究開発をしている先生とご縁があり、膣カンジダの患者にも効くのではないかということで共同研究をすることになりました。その結果「ホロトキシン入り」のデリケートゾーン用ソープが誕生しました。膣カンジダの症状が出た患者さんにこのソープを使ってもらったところ、88%が継続して使いたいと答え、70%以上がカンジダのかゆみが減ったと答えました。
ー膣カンジダにアプローチするソープが生まれるまでには、長い道のりがあったんですね。
私たちは「ケアからキュア」を目指しています。ただケアしてきれいにするのではなく、キュアという治療に近いこともしていきたいんです。私たちは、デリケートゾーンのパイオニアとして、いつもトップを走っていたい。トップを走るためには、同じような商品を作っていても仕方ないので、病気が治る「キュア」という意識をもってものを作っています。他社とは次元が違う商品を作っています。
ーフェムケアについて男性の高倉さんがこんなにオープンに話してくれることに驚きました。日本では男性が触れにくいトピックだと思うのですが、どうして高倉さんはこれほど率直に話せるのでしょうか?
日本でデリケートゾーンのことをこんなに語れる男性は私くらいでしょう。(笑)女性向けのセミナーでもよく話しますが、男性の私が登壇して最初はびっくりされます。でも私自身は恥ずかしいという意識が全くなく話すので、聞いている女性たちも最後にはたくさんの質問をしてくれます。ものづくりをする時に私が一番大事にしてる言葉を紹介させてください。それは「ミーニング(意味、意義)」という言葉です。私はミーニングがないものは作りたくないし売りたくないと考えています。デリケートゾーンが流行っているから、デリケートゾーンが儲かると思って売るというようなことはミ―ニングがないと考えます。
だからしっかりとしたエビデンスがあり、お客様に納得して喜んで使ってもらえるものを作りたいと思っています。そういう思いで、産婦人科の先生、助産師さんたちとも話をする中で、女性の気持ちを聞いて、女性にとって1番良いものを作ろうという気持ちでやってきたので、 男性であることは自分にとってそんなに特殊なものだとは思っていません。
ー女性の性や、女性の性器を含めた身体と心のウェルビーングに対しての意識改革について日本の社会にどのような変化が必要だと思いますか?
男性のデリケートゾーンは『息子』と親近感のある名前で呼ばれる一方で、女性は『あそこ』と言われる。これは日本でデリケートゾーンの話をすることがタブー視されてきたことを示しています。でも、女性にしか赤ちゃんが産めない、そんなとても大事な場所なのにタブー視されているのはおかしくないですか?だから普通にオープンに語れる世の中になった方がいいと思っていて、そういう社会を作るためにいろんなことを少しずつやっています。
ー「ピュビケア オーガニック」商品を世に出すことで、日本の女性に送りたいメッセージとは?
女性は自分のことをもっと大事にしてほしいというメッセ―ジですね。女性は母性が強いのでどうしても他人優先になりがちです。結婚していたら旦那さん優先、恋人だったら彼氏優先、子供がいたら子供優先というふうに、自分のことをほったらかしでケアできていない方が多いと思うんです。デリケートゾーンはとても大事な場所なのに、見たこともないという女性が多いですよね。産婦人科の先生とよくお話をするんですが、デリケートゾーンに恥垢が溜まっていたりとケアができていない女性が多いそうです。それは自分のデリケートゾーンをしっかりと見ていないからなんですよね。膣はとても大事な臓器の1つなので、外見などの表面上だけではなく、しっかりと自分をケアして愛してほしいですですね。
ーたかくら新産業がこれから挑戦しようとしていることはありますか?海外進出なども視野に?
日本だけでなく世界中の方に幸せになって欲しいので、海外に商品を輸出する海外展開を考えています。ここ5~6年で食品の開発もしてきました。外側にだけ良いものを使っても身体の中は変わらないので、まずは中から変えていかないといけないんです。だから、食べ物に関しても世の中をひっくり返そうと思っていて、ホールフードつまり一物全体食という良い原料をそのまま摂るということを推奨した商品を作っています。人間が何千年も食べているような自然なものを食べていれば副作用もないでしょう。現代は、便利という名のもとに保存料がてんこ盛りに入った加工食品ばかりを食べてきたから病気やうつ、または睡眠障害のある人が多いのです。こういった状況を変えるためにホールフードの食品を作っていきたいです。日本には、こういうものをを作っている人がまだほとんどいないので、なかなか広がりませんが、セミナーを開催したりして日本でもっともっと広げていけたらと考えています。

Profile
高倉健(たかくらけん)
1964年京都府生まれ。たかくら新産業代表取締役社長。西武百貨店渋谷店SEED館の企画担当を経て独立。世界中の化粧品や雑貨ブランドの輸入販売を経て、たかくら新産業を発足。オーガニックブランド「メイドオブオーガニクス」を立ち上げる。
takakura.co.jp/
30代は人生の転換期!?恋愛・健康・性事情まで赤裸々対談

Humming編集部の永野 舞麻と條川 純。もうすぐ40歳を迎える2人が、歳を重ねる中で感じた変化や40代への展望を赤裸々に語り合いました。全く異なるライフスタイルを送る2人に共通していたのは、歳を重ねるごとに感じたポジティブな変化。
恋愛観、健康、セックス論まで、等身大の姿を映し出す赤裸々トークをお楽しみください。
| プロフィール
Humming編集長 永野 舞麻 1984年生まれ。16歳までを日本で過ごした後、海外へ移住。大学で出会ったアメリカ人の夫と結婚し、現在はカリフォルニア在住。3児の母。 高校時代、スイスに住んでいたときに自然の偉大さに触れ、地球環境保全について学び始める。アメリカの美術大学でテキスタイル科を専攻。 今でも古い着物の生地などを使って、子育ての合間に作品を制作し続けている。 |
| Humming編集部Project Coordinator 條川純
1984年生まれ。アメリカ生まれ、アメリカ育ち。現在はひとり暮らしをしながら、生涯を共に過ごせるパートナーを探している。 |
ライフスタイルは十人十色
ーお二人は同じ年ですが、結婚して3人のお子さんがいる舞麻さんと、ひとり暮らしをしている純さん。ライフスタイルはそれぞれ異なりますよね。人生には様々な選択肢があると思いますが、結婚や家族についてどのような考えをお持ちですか?
純:アメリカでは約2人に1人が離婚する時代。離婚は大変そうなイメージがあるので、必ずしも結婚にこだわらず、おじいちゃんおばあちゃんになっても一緒に人生を歩んでいける方と巡り会えたら幸せだと思います。私はそれほど子どもが欲しいとは思っていないので、時間をかけてじっくり相手のことを知りながら、この人だと思える人に出会えたら良いですね。
ただ、年を重ねるほどに自分の気が強くなっているので、そんな私を好きでいてくれる男性がいるのかな……と不安に思うこともあります。理想の相手を探している間に、おばあちゃんになっていたらどうしよう。
舞麻:私はアメリカ人の夫と結婚して14年目になります。夫とは20歳の時に出会って、同棲も遠距離も経験してから結婚しました。
とはいえ、元々結婚願望があったわけではありません。私の両親は離婚しているので、どうせ離婚するくらいなら入籍しなくても良いと思っていたのです。しかし、頻繁に日本とアメリカを行き来していたので、入国審査で手間取るようになり、スムーズに入国するためにという全くロマンチックでない理由で入籍しました。笑
ー純さんは相手のことをよく知ってから結婚を考えたいとのことですが、舞麻さんも同棲・遠距離を経験して、相手のことをよく理解してから結婚に至ったのでしょうか?
舞麻:よく恋愛は3年と言われますよね。誰と恋に落ちてもいつかは冷めるのなら、いつか恋心が冷めた時も、家族として尊敬し愛していける人がいい。それを考えた時にこの人なら!とそう思えたことが夫との結婚の決め手になりました。とはいえ、20年以上連れ添っていても、今でも「この人無理!」と思うこともありますよ。お互いを思いやりながら微調整を続けています。
ー微調整とは?
舞麻:例えば、私たち夫婦は良い関係を保つために別居したこともあるんです。長い間一緒にいると、自分と相手の境界線がなくなってしまい、相手のことなのに、まるで自分のことのように恥ずかしく感じたり、問題視したり、一心同体のようになってしまったからです。一心同体と聞くと聞こえがいいのですが、とてもお節介になってしまったんですね。絶対にこうした方がいいとか、こんな言い方をしない方がいい、とか。
物理的な距離をとることで、お互いを尊重できるようになり、新鮮な気持ちになれました。当時の私たち夫婦にとって別居は必要な選択でした。
実は、結婚前に遠距離恋愛をしていた時は、オープンリレーションシップを試したこともあるんです。
※オープンリレーションシップとは、パートナー以外の人とも身体的・精神的な関係を持つことを、お互いに合意している恋愛形態のこと。ただし、それぞれのカップルによってルールは異なり、お互いの合意の下で行われる。
ーオープンリレーションシップ?!それはアメリカではよくあることなのですか?日本だとあまり耳にしないかもしれない。
純:アメリカでは30〜40代のカップルでオープンリレーションシップをする方が多いと耳にします。実際に私の友人にはオープンリレーションシップを試している夫婦が2組いますよ。オープンな関係になることで、お互いに感謝できるようになり、相手を愛する理由を思い出せたそうです。お互いに納得しているのであれば、良い刺激になるのかもしれないですね。
舞麻:確かに、ずっと一緒にいると、相手の存在に有り難みがなくなり、馴れ合いになってしまうこともありますよね。我が家は今はオープンな関係は望まないけれど、別居したことでお互いを思いやれるようになった経験があるので、相手と一定の距離をとることの大切さは理解できます。
ー夫婦やパートナーと一定の距離をとることは、より良い関係を築くための1つの手段なのかもしれないですね。

歳を重ねるほどに深まる、セックスの満足度
ー女性のセクシュアリティについても扱っているハミングだからこそ、お二人の性生活についてもお聞きしたいと思います。年齢を重ねるにつれて、性に対する考え方に変化はありましたか?
純:性に対する考え方は、20代と30代で、ものすごく変化しました。正直、20代の頃はセックスがあまり好きではなかったんです。痛かったし、そもそも自分の体が好きではなかった。性欲に対して恥ずかしさもありました。しかし、30代半ばからは、セックスを楽しいと思えるようになってきました。
ーそれはどうしてでしょう?
純:新しい人とセックスするたびに、新たな発見があるからです。アメリカ男性の多くは、女性が満足することを最優先に考えてくれるんです。だからこそ、私が喜ぶことを積極的に聞いてくれます。そのおかげで、自分の要望を相手に伝えられるようになり、セックスがより楽しめるようになってきました。
舞麻:私は出産するたびにセックスが気持ちよくなったんです。一人目を出産した後、産む前とは全く違う感覚を味わいました。そのため、出産によって快感が増すものだと思っていました。しかし、純さんの話を聞くと、年齢を重ねたことや経験を積んだことも、セックスの満足度に関係しているのかもしれませんね。
時々、私はセックスそのものを楽しんでいるのか、それとも愛されている、求められていると感じることに喜びを覚えているのか、区別がつかなくなることがあります。肉体的な気持ちよさだけではなく、自分の存在が相手に求められている感覚に心地良さを感じます。
純:その気持ちすごくわかります。私も長く付き合った相手とのセックスは心が満たされます。
ーセックスは、体だけでなく、心も満たされる行為ということですね。歳を重ねるに連れてセックスが楽しめるようになる、歳をとるのも悪いことばかりじゃないですね。
健康面での不安を感じる40代。瞑想で今と向き合う
ーお二人とも、歳を重ねることについて、不安に感じることはありますか?
純:歳をとるに連れて、体が思うように動かなくなっていくことが怖いです。大好きな旅行に行けなくなったら本当に悲しいと思うんですよね。
高齢になると足腰が弱くなるとよく聞くので、35歳からジムに通って本格的に筋トレを始めました。また、バランスの取れた食事を心がけるようにもなりました。
舞麻:私は自分がどんな更年期を迎えるのかが少し不安ですね。私よりも少し年上のママ友でホットフラッシュなどの症状に苦しんでいる方がいて、自分ももうすぐそうなるのかな……とか。先日読んだ本には、更年期は女性ホルモンの減少によって心臓病や動脈硬化のリスクが高まると書かれていて、さらに不安が増しました。
ー歳を重ねると、健康面での不安が増えてきますよね。そういった不安とはどのように向き合っていけば良いのでしょうね。
舞麻:私は、不安を感じた時には、瞑想する時間を増やすようにしています。
なぜなら、瞑想することで過去や未来のことを考えるのではなく、今この瞬間に集中できるからです。起こるか起こらないかわからない未来に不安を感じるよりも、今、確実に起こっていること、例えば自分の呼吸に意識を集めることで気持ちがだいぶ楽になります。
純:私も最近瞑想をするようになりました。Hummingに関わるようになってから、メンタルケアの大切さを実感しています。
過去の経験が自信に繋がり、自分を好きになる
舞麻:私は瞑想やカウンセリングを受けて自分と真正面から向き合うようになってから、自分のことをだんたんと好きになれました。
特別に美人なわけでもないし、モデルのようなスタイルでもない。出産の痕である妊娠線もちょっとあるし、時には家族に厳しく当たってしまうこともあります。それでも、自分と向き合うことで、過去の経験や嫌いな癖など全てを含めた今の自分を受け入れ、認めてあげられるようになりました。
瞑想だけでなく、ジャーナリングやヨガなど、自分と向き合う時間を大切にしている人は、そのままの自分のことを受け入れられている気がします。
純:私も歳を重ねるにつれ、少しずつ自分と向き合う余裕がでてきたなと。若い頃は、背が小さく、腰幅が大きいことにコンプレックスを抱いていましたが、今はジムに通ったり、瞑想したり、自分磨きに力を入れることで昔よりも自分を好きになれました。
また、これまでお付き合いしてきた男性から「あなたは美しいね」と褒めてもらえた経験が積み重なり、自信に繋がっていると感じています。
舞麻:私は子育てを通して自信がついたかな。責任を持たなければいけない大切な存在ができたことで、強くなれたんです。私はこんなに大事な命を世に送り出したんだぞって。出産・子育てを経験したことで、宇宙の偉大さというか、自分のちっぽけさに気がついて、謙虚にもなりました。
ーお二人とも、恋愛や出産・子育てなどを経験することで、自分に自信を持てるようになったのですね。
純:自分に自信が持てるようになったからか、30代後半からは人間関係も楽になりました。人生は短いのだから、合わない人と無理に付き合う必要はないなと。
今いる友達は私に何かあればすぐに駆けつけてくれる、心の通い合った大切な存在です。たくさんの友達がいなくても、深い絆で結ばれた友達がいることに満足しています。

40代のビジョン。自分の幸せ・他者への貢献
ー最後になりますが、これから迎える40代。どのように過ごしていきたいですか?
純:40代はマイペースに楽しく生きたいですね。最近同棲していた彼氏とお別れしたので、引っ越しをして1人暮らしをはじめました。これまで1人暮らしの経験があまりなかったので、今は1人の空間を味わいながら、自分と向き合いたいです。そして、自分らしさを大切にしながら、仕事も頑張って、さらに生涯を共に過ごせるパートナーと出会いたいですね。
舞麻:私は20代は働いてお金を稼ぐことに集中していて、20代の終わりから30代は子育て、そして30代半ばからは内面的なことやスピリチュアルなことに目を向けてきました。
これから迎える40代は自分磨きを続けながら、ボランティア活動などを通して、人のために活動していきたいです。
ホスピスでのボランティアや、シングルマザーが子育てしやすいような環境づくりのサポートなどに関わりたいと思い、登録を進めています。
純:私は自分のために、舞麻さんは誰かのために。だいぶ違いますね……。笑
舞麻:自分のための時間も大切!
ーお二人のお話を伺って、30代半ばを境に、人生に対する姿勢や価値観に変化があったように感じました。過去の経験が自信に繋がり、自分らしい生き方を追求できるようになる。まさに、30代〜40代は人生の転換期と言えるかもしれませんね。これから迎える40代での変化も楽しみですね。
プレイセラピーのやり方や対象となる子供の特徴は?成功事例も紹介

私たち大人が誰かとコミュニケーションをとるときは、言語を使って繊細な気持ちの変化までしっかりと伝えられるでしょう。
しかし子供の場合はそうもいかず、抱えている気持ちを100%読み取るのは難しいものです。
そんな子供たちの精神状態を把握すべく考えられたのが「プレイセラピー」です。
日本語に表すと「遊戯療法」とも呼ばれており、子供にとってさまざまな効果があるといわれています。
今回はそんなプレイセラピーのやり方や対象となる子供の特徴をご紹介しながら、一体どんな効果をもつ療法なのかを探っていきましょう。
プレイセラピーとは?

プレイセラピー(遊戯療法)とは、私たち大人が子供の心を理解するために生み出された方法の一つです。
子供に対する療法は種類が豊富で、どの療法が合っているかはやってみなければ分からない部分も多くあります。
カウンセラーと対話しながらカウンセリングを受けてみましょうといわれても、問いかけに答えられず上手くいかない子も少なくないでしょう。
知らない人の前では緊張してしまったり、自分の気持ちを言葉で表すのが苦手だったりする子供に対し効果的だといわれているのがプレイセラピーです。
子供に好きなように遊んでもらい、その様子を観察することで抱えている気持ちを汲み取るために行われています。
一般的な会話形式のカウンセリングでは緊張してしまう子も、普段遊び慣れたおもちゃがあったり、初めて見るおもちゃに触れたりするうちに自然な態度で接してくれるようになるでしょう。
カウンセラーが時には見守り、また時には一緒に遊んでくれることで、子供もゆっくりと慣れていけるでしょう。
プレイセラピーの効果や狙いは?
プレイセラピーは、一見子供がただ遊んでいるようにも見えるため、どんな効果があるのかイメージしにくい方も多いのではないでしょうか。
プレイセラピーでは、最終的な目標を「子供が自己表現できるようになる」などといった点に定めて行われます。
緊張しがちな子供は肩の力を抜いて他人と関われるように、他人に対し攻撃的な態度をとってしまう子供は気持ちを抑えて他人と関わりやすくなるようにするなど、状況に応じて声掛けの内容を変えていくことが大切です。
最初は黙って遊んでいるだけだった子供も、遊びを通して大人と心を通わせられるようになり、次第に同年代の子供と上手に関われるようになっていきます。
コミュニケーションに不安要素のある子供の中には、やりたいことがあってもどう声をかけて良いか分からなかったり、そもそも自分がどうしたいのか分からなかったりとモヤモヤした気持ちを抱えている子も少なくありません。
遊びを通して自分と向き合い、「自分はこう考えている」「自分はこうしたいと思っている」といった考えがまとまることで、他人との関わりもスムーズにできるようになるでしょう。
関連記事:自己肯定感が低い子供の特徴とは|注意すべき親の発言や行動
プレイセラピーと似ている言葉との違い

プレイセラピーと似ている言葉には、「療育」や「遊び」があります。
一見遊んでいるだけに見えるプレイセラピーが、これらとどう異なるのか見ていきましょう。
療育とは、精神障害・身体障害・知的障害とさまざまな状態の子供が受けるものです。
その内容は子供によって異なりますが、いずれもそれぞれの子供が悩みを解決し、今後社会に出る際に困らないような状態を目指すために行われます。
身体障害がある子には運動療法を、知的障害がある子には知育療法を行うなど、子供に合わせた方法を選ぶことが大切です。
遊びとプレイセラピーは似て非なるものであり、遊びの中で声掛けを行いながら悩みの改善を目指すのがプレイセラピーです。
通常の遊びではケンカをしたときや泣いているときにのみ声掛けをすることも多いですが、プレイセラピーでは子供の様子を見ながら常に声掛けをしていくのが特徴です。
子供にとっては普段の遊びと変わらないため、より肩の力を抜いて過ごせるのがメリットといえるでしょう。
プレイセラピーの対象となる子供の特徴
プレイセラピーを行うのに適しているとされるのは、おおむね3歳頃から小学校卒業程度までの子供たちです。
自分の言葉で少しずつ気持ちを伝えられるようになれば、プレイセラピーを受けても効果が見られやすいでしょう。
また、プレイセラピーの対象となる子供たちは、チック症や吃音症・場面緘黙症などで会話を避けがちな子や、暴力がみられ他人との関わりが上手くいかない子、不登校の子などさまざまです。
年齢に応じて言葉が出にくい子であったり、自閉症・ADHD・アスペルガー症候群などの診断が下りた子であったり、一人ひとりに合った内容で声掛けを行うことで効果が得られやすくなります。
療育の一部として行われるケースも珍しくありません。
これらの悩みを抱えた子供たちは、家でお父さん・お母さんや兄弟と関わっているだけでは悩みが改善されない場合があります。
プレイセラピーを上手く取り入れることで、子供へ負担をかけずにコミュニケーションを取りやすくなるでしょう。
関連記事:自己肯定感が低い原因はプライドが高いから?親のせい?高める方法とは
プレイセラピーのやり方

プレイセラピーを行う際は、大まかな流れに沿って子供一人ひとりへ対応していきます。
まずは子供に日頃過ごしているのと同じ状態で、リラックスして遊んでもらうことから始めます。
これにより子供が抱えている悩みを明らかにし、どういった対応が必要なのかを浮き彫りにしていきます。
普段周りとうまく話せずに一人でいることが多かったり、気に入らないことがあると手が出てしまったりと、実際の様子を見ることで対応策を考えやすくなるでしょう。
続いて、これらの行動を起こすとき、本当は子供がどう考えているのかを考えます。
一人でいるからといって周りと遊びたくないわけではなく、本来であれば声をかけて混ぜてもらいたいと思う子もいるでしょう。
手が出てしまうのにも理由があり、どうやってイライラした気持ちを発散すれば良いか分からないだけかもしれません。
こういった一人ひとりの状況を踏まえ、ここでようやくプレイセラピーの目標を立てられます。
「自分で他人を遊びに誘えるようになる」「イライラしたときは一旦落ち着き、手を出さないようになる」など、無理のない範囲で目指すべき姿を考えることが大切です。
この目標を達成するためにどのような声掛けを行うべきか、時にはお父さん・お母さんも含めて話し合いが行われます。
プレイセラピーでの声掛けは特別難しいものではなく、「お友達を誘うときは何て言ったら嬉しいかな」「叩くと自分の手も痛いから、一度深呼吸してみよう」など子供の気持ちに寄り添うことが一番大切です。
一日で目標を達成する必要はまったくないため、始めたばかりのときは子供と他愛ない会話をするのも良いでしょう。
一緒に遊んでいる中で「この人が楽しい」と思ってもらえれば、自然と会話が続き、気持ちを伝えてくれる子も少なくありません。
関連記事:子供だけでなく家族全員の幸せを考える。悩める親の心を救う確かなメッセージ【保育士 てぃ先生のIt’s My Story】
プレイセラピーの成功事例

プレイセラピーを行っている医療機関や療育施設は非常に多く、成功する場合もあれば別の方法が合う場合もあります。
今回は江戸川大学で行われたプレイセラピーについて、伊藤渚氏がまとめた論文をご紹介します。
本件は小学校2年生の女子児童が学校へ行きたくないと訴えたことで、母親が心配して教育相談を受けたことが始まりです。
周りとのコミュニケーションが上手くいかず、時には手が出て周りと衝突し、2年生に上がったタイミングで学校へ行けなくなってしまいました。
泣いたり怒ったりといった情緒の不安定さが見られ、時には自傷行為に及んでしまうこともあったようです。
当初女子児童はプレイルーム内でのびのびと過ごすことができず、自由にして良いといわれても周りに迷惑をかけないように振舞ったり、ゲームをしても大人を勝たせたりといった「気遣い」が見られました。
髪を口に入れる様子から、落ち着かないことがあっても上手く言葉に出せず、気持ちを閉じ込めてしまうことが伝わってきます。
時間をかけるにつれ、女子児童はゲームで勝ちにこだわったり、のびのびと遊ぶ様子が見られたりするようになりました。
学校でトラブルがあった際にどう考えていたのか、自分の感情も素直に伝えてくれるようになったといいます。
「本当は一緒に遊べる友達がほしい」といった願いも口にするようになり、次第に自傷行為や暴力が少なくなっていきました。
最後まで見られた会話内での「攻撃的表現」においては、大人がごっこ遊びの中で攻撃的な言葉で傷つけられている役を演じることで、自分の周りの環境を客観的に見られるようになりました。
次第に学校での友達ができ、無事肩の力を抜いて生活できるようになるまで、時間はかかったものの彼女が得たものは大きかったといえるでしょう。
このように、プレイセラピーは解決までに長い時間を要することも少なくありません。
逆に言えば、時間をかけて行うことでその子の本質が見えやすくなり、信頼関係を築くことで子供の本当の気持ちを理解しやすくなるのです。
どんな子供でも心の中ではさまざまなことを考え、悩み、葛藤しながら生きています。これらの考えを大人が汲み取り、自然な形での放出を目指すことが重要です。
引用元:人との関わりがうまくいかない子どもとのプレイセラピー【PDF】
プレイセラピーの効果がない子供はいる?
「こんな子供はプレイセラピーを受けるべきではない」といった明確な指針は存在せず、やってみて初めて効果がなかったり、別の方法が合っていることが発覚したりする場合もあるでしょう。
また、自閉症やADHD・アスペルガー症候群といった発達障害が診断されている子供にとって、プレイセラピーが他者との関わりをスムーズにすることはあっても、発達障害そのものを克服できるかといえばそうではありません。
子供にとって良い方法を組み合わせて試し、時間をかけて他者との関わりを促してあげることが重要といえるでしょう。
まとめ
プレイセラピーは通常のカウンセリングとは異なり、遊びながら子供の自立を促せるものです。
堅苦しい話し合いが苦手な子も、好きなことで遊べる時間となれば、肩の力を抜いて過ごしやすいのではないでしょうか。
あくまでも療法の一種として、目標とする状態まで長い時間をかけて進んでいくことが大切です。
ボディポジティブとはどんな意味?日本や海外に与えた影響をご紹介

男性・女性といった性差や年齢に囚われず、ありのままの自分を愛せるように変化しつつある現代。
「こうであるべき」といった理想像は次第に崩れ、誰もが自分を愛せるような世界が来ることが理想とされています。
今回はそんな世界の変化の中で、自分の体をまるごと愛するために生まれた考え「ボディポジティブ」についてご紹介します。
今ある理想像を壊し、自分の体のどこが好きなのかを考えることで、さまざまな良い影響を及ぼします。
良い点だけでなく、ネガティブな意見についてもチェックし、ボディポジティブへの理解を深めましょう。
ボディポジティブとは?

ボディポジティブとは、2010年代に世界へ広まった言葉だといわれています。
それ以前にも体の特徴を愛し、人と比較せずに自分を愛そうとする人々はたくさんいましたが、「ボディポジティブ」という言葉が人々の心を動かしたのも事実です。
ボディポジティブのきっかけは、白人至上主義であった世界に対し反論を唱えた人々が、SNS上で「#BodyPositive」をつけて抗議を行ったことが始まりです。
白い肌、堀の深い顔、スリムで高身長な体型が美しいとされてきた世界において、これらに当てはまらない場合でも自らの体を愛せるようにとの願いを込めて広まりを見せました。
当初は一般人の間で行われていた投稿が、次第に著名人の間でも広まるようになり、結果として世界中で唱えられることとなったのです。
2015年頃になると、アニメ映画の主人公をふくよかな女性に設定したり、有名ブランドがプラスサイズモデルを起用したりといった変化が見られるようになりました。
そして2020年代に入り、これまでに美しいとされてきた価値観は徐々に崩れつつあり、マジョリティ・マイノリティに関わらずありのままの自分を受け入れられる人が増えてきています。
関連記事:20年間の「やせなきゃ」から解放された私が考える『ボディポジティブ』
ボディポジティブが注目されている理由
一般人の間で声が挙げられていたボディポジティブの考え方が世界中に広まることとなったのは、著名人が注目したのが始まりといえます。
一般人であればそのつぶやきは小さなものであり、目に留まる人も少ないのが現実です。
しかし著名人となれば話は別であり、称賛する声もあれば、同時に批判の声も多数集まることでしょう。
これまでにボディポジティブの考えを支持すると公表した著名人の多くは、「太っている」「美しくない」「見たくない」といった批判をはねのけ、堂々と自分を愛している人ばかりです。
そんな凛とした姿に心を打たれ、これまで自分に自信を持てずにいた人が心動かされることもあるでしょう。
ボディポジティブの広まりには、勇気をもって声を挙げた人々だけでなく、著名人の覚悟も欠かせないものであったといえます。
そんなボディポジティブの考え方は、これまで統一された容姿を目標としていたファッション・メイク・ヘアスタイル業界に大きな影響を及ぼしました。
さらには性差や年齢の壁とともに、今後の世界を変える大きな転換点として考えられるようになったのです。
女性が抱える身体のコンプレックス

ボディポジティブでは太っているか痩せているかといった単純な問題だけでなく、多くの人がコンプレックスとして捉えているさまざまな問題から解放され、ありのままの自分を受け入れることを目標としています。
例えば体重が急激に増えた場合などに見られる「ストレッチマーク」や、脂肪とは異なり凸凹とした見た目を気にする人が多い「セルライト」なども多くの女性が悩むポイントです。
ダイエットをして体重が減ってもこれらの症状が消えなければ、結果として自分の体に自信を持てないままになってしまうこともあるでしょう。
また、生まれたときから体にあるシミやあざのことを「バースマーク」と呼びます。特に顔などの目立つ部分にあるものは、取り去りたいと思う女性も多いはず。
中には美容外科や美容皮膚科・形成外科などに通い、治療を受けている方も多いのではないでしょうか。
誕生に絡めていえば、体内の赤ちゃんが成長するにつれ皮膚が引っ張られて起こる「妊娠線」もコンプレックスになりやすいポイントです。
本来赤ちゃんを守り育ててきた証となる妊娠線は決して恥ずかしいものではありませんが、線のない肌に比べて醜く感じてしまい、露出を極端におさえようとする方も少なくありません。
また、性別に関係なく起こりやすい「シミ」も、セルフケアではなかなか消えずコンプレックスとなりやすいものです。
これらのコンプレックスは他人に悪影響を及ぼすものでも、ただちに健康に害があるものでもありません。
これらの症状がある状態を「健康に生きた証」として捉えて受け入れることこそ、ボディポジティブの始まりといえるでしょう。
関連記事:デジタル修正はもう不要! ありのままのあなたが美しい
ボディポジティブが与えた影響
ボディポジティブの考え方は世界各国に広まり、各地に大きな影響を及ぼしました。日本でもボディポジティブの影響は大きく、私たちの生活は徐々に変わりつつあります。
今後の変化を受け入れるためにも、ボディポジティブが各国に与えた影響を見てみましょう。
海外
流行の最先端をゆく名立たるブランドたちは、ボディポジティブの考え方を受けて次々にプラスサイズのアイテムを取り入れるようになりました。
これまでサイズの大きな女性は専用のブランド内でしかファッションを楽しめず、自然とコーディネートの幅は狭まり、窮屈な思いをしていた人も多かったはずです。
有名ブランドが次々に行動を起こしたことで、今では数多くのブランドが豊富なサイズ展開のアイテムを販売しています。
これに伴い注目されるようになったのは、これまで厳しい基準を設けられていたファッションモデルたちです。
彼女たちはいわば「痩せすぎ」といわれるような条件を課せられており、中には栄養不足による死亡例があるなど状況は極めて悪いものでした。
ボディポジティブの考えが広まった後は、各国でモデルに対する厳しい体重制限を緩和し、モデルの低体重化に歯止めがかかったり、プラスサイズモデルが登場したりといった変化が訪れました。
さらにはディズニー映画をはじめ、「主人公は白人である」というイメージを払拭した作品が多く登場しました。
2023年に公開された「実写版 リトル・マーメイド」では主人公アリエル役にアフリカ系アメリカ人のハリー・ベイリー氏が起用されて話題を呼んでいます。
日本
世界に少し遅れ、日本でもボディポジティブに関するさまざまな意見が飛び交いました。
女優・タレントとして活躍する渡辺直美さんが「PUNYUS」を立ち上げたことも大きな変化の一つで、痩せている女性・太っている女性のいずれも同じファッションを楽しめるのが魅力です。
また、ボディポジティブに当てはまるのは体型の差だけではありません。
コスメブランド・資生堂では、病気で両足を切断した経験を持つローレン・ワッサー氏をモデルに起用。
障害の有無にかかわらず誰もが同じようにファッションやコスメを楽しみ、好きな人生を歩むための大きな一歩となりました。
ボディポジティブにネガティブな意見がある理由

ボディポジティブを素敵な考えだとする一方、受け入れられないなどのネガティブな意見も多いのが現状です。
やはり「美しさとは〇〇である」といった固定観念が人々の中から抜けておらず、自分の求めるものと差があるのが理由といえるでしょう。
肌の色が白く痩せていて、歯並びが綺麗で顔立ちが整った女性を多くの人が目指すあまり、理想像とかけ離れた存在を無意識で避けてしまうのです。
また、「ボディポジティブを理由に自分を磨くのを諦めているように思える」といった意見も多く見られます。
多くの女性が少しでも美しくなりたいとダイエットを頑張ったり、日々のスキンケアを欠かさずに行ったりしていますが、それを行わずに「この状態が美しい」という女性を受け入れられない方も多いのではないでしょうか。
さらに、プラスサイズボディの女性に対し、「美しさは関係なく、そもそも不健康である」といった声もあります。
肥満は現代人にとって生活習慣病の大きな原因となるため、標準体重をキープするべきだと考える方も多いでしょう。
ありのままの自分を受け入れた結果、病気になってしまっては元も子もないため、健康に影響を及ぼす場合は医師と相談の上生活を見直すことも必要だといえるでしょう。
関連記事:ボディポジティブ:体重計も投げ出して、ありのままを受け入れる
ボディポジティブ以外にありのままの自分を受け入れる方法

ボディポジティブに限らず、ありのままの自分を受け入れる方法はたくさんあります。
「セルフ・コンパッション」は、自分を労るといった意味の言葉です。
周りの人に優しくできる人は多くいますが、自分自身を心から労れる人は少ないでしょう。
気持ちを紙に書き出して整理したり、目を閉じて自分自身を見つめるための瞑想を行ったりしながら、周りの人と同じように自分を気遣い、褒め、認めることが大切です。
同じような意味の言葉として、自分を愛する「セルフラブ」があります。
自分と深く向き合い良いところを探すために、常に視野を内側に向け、自分中心に考えてみると良いでしょう。
良いことがあったときは素直に自分を褒め、ミスをしたときは次へつなげるために自分を励まします。何も成果を得られなくても、1日を頑張って生き抜いた自分を認めてあげましょう。
「アファメーション」は自己暗示の一種であり、理想を既に達成していると思い込むことでポジティブな気持ちになれる方法です。
「私は成功している」「周りに好かれている」と既に理想が叶ったような文章を作り、自分に向かって宣言することで、心に深く刻み込むことができるのです。
具体的な自分の成功がイメージできるようになり、前向きな毎日を送れるようになるでしょう。
まとめ
ボディポジティブの考え方は、決して世界中の全員に広まったわけではありません。
しかし「自分はダメだ」と思い込むよりも、「そんな自分も好き」と思えた方が、明るく素敵な明日を過ごせるのではないでしょうか。
多くの女性が既にボディポジティブの考えを受け入れ、コンプレックスを自身へと変え、新たな明日へ踏み出しています。
今気になるコンプレックスが理由で前を向けなくても問題ありません。さまざまな世界で活躍する女性たちが、あなたへ勇気と自信をもたらしてくれるでしょう。
まずは自分を大切に。子育てには”Boundary(境界線)”が必要?! 【Editor’s Letter vol.09】
| Humming編集長 永野舞麻がカリフォルニアから配信する「Editor’s Letter 」。
日々の暮らしで感じた気付きや、人生において大切にしていることを綴っています。 |

私が母親になったのは12年前。
右も左もわからない初めての子育て。
「〜しなければいけない」
「〜するべきだ」
自分で作ったルールにがんじがらめになり、子どもと笑顔で接することができない自分を責め続けていました。
そんな私は自分自身と周りとの”Boundary(境界線)”を意識するようになったことで、親子関係に変化を感じるようになりました。
親子であっても、同じ人間ではない。私は私。あなたはあなた。
自分と他者との間に境界線を引くことは、自分のために、そして相手のためにも大切なことなのです。
欲求を押し殺して子どもを優先するのが良い親なのか?!
長女が小さかった頃、私は自分の欲求と限界に気がつけませんでした。自分を押し殺してでも、娘の希望全てを叶えてあげるのが良い母親だと思っていたのです。
子どもはなるべく泣かせてはいけない。
離乳食は一から全て自分で作らなければいけない。
赤ちゃんに着せる衣類は肌に優しいオーガニック素材にこだわるべきだ。
自分の全てを子どものために捧げよう。
当時の私は誰に強いられたわけでもないのに、自分でルールを作り、「子どものためにもっとできるはずだ」「良い母親でいなければ」と自分を追い込んでいました。
しかし、私が良い母親になろうと頑張るほどに、子どもにも夫にもプレッシャーを与え、家族みんなを苦しめていたことにだんだん気がつきました。
他者への優しさは自分を満たしてあげてから
長女が4歳になると彼女自身の主張を言葉にすることも増え、イライラを抑えられずに娘を怒鳴ってしまったり、時には手を挙げそうになったりすることが増えました。
自分の全てを子どものために捧げているのに、結局は私が娘のことを傷つけているのかもしれない……。そんな自分に落胆し、子どもが寝静まった夜にひとり涙を流すこともありました。
その現状を変えたいと思い、夫に勧められて始めたのがセラピーです。
セラピーの時間は毎回子育ての話からスタートしました。当時の私はとにかく子育てのことを話したかった。また、幼少期のトラウマが自分の子育てを通じてフラッシュバックするように溢れ出てきていたので、そのことについても先生にたくさん話を聞いてもらいました。私がどんなに自己嫌悪に陥ったネガティブな話をしても「あなたはこんなにもお子さんのことを愛しているじゃない」「あなたは頑張っているよ」「そんな辛いことが子どもの頃あったのね」と、先生は私の良いところを見つけて言葉にして伝えてくれたり、幼少期に感じた私の想いに同調してくれたのです。
定期的に自分の内を言葉にすること、そしてありのままの自分を誰かから受け止めてもらえることで、まるで玉ねぎの皮が1枚1枚剥がれていくように、自分が本当に求めているものが見えてきました。
たとえば、朝はゆっくりお白湯を飲んだり、趣味のアートをしたり、自分のためだけに時間を使いたい。日中だって疲れた時はゆっくり休憩したい。私には家でのんびりする自分のための時間が必要だったのです。
自分自身が満たされない状態で、周りに手を差し伸べるのは難しいことです。酸素がない状態で酸素ボンベを付けずに他者を助けることはできないですよね。まずは自分の欲求を満たしてあげる。そうすることで誰かのためにも優しさやパワーを注げるということにようやく気がつけました。
自分のための時間がもたらす変化
それ以降、私は常に子ども優先という自分の考え方を改め、自分のための時間も大切にするようになりました。
たとえば、朝6時半までは自分のためだけに時間を使う。「朝6時半まではママは自分の時間を過ごすから、それまでは自分のことは自分でやってね」と子どもたちには伝えています。子どもたちも理解してくれ、早起きした時には、自分でフルーツやグラノーラを食べるようになりました。
日中に少し休憩したい時は、子どもたちには「このカップの中のお茶が空っぽになったら手伝うね」とか「時計の針が30分になったらお話を聞くね」とか「このアラームが鳴るまではママにひとりの時間をちょうだいね」などと伝え、自分のための時間を意識的に確保しています。
子どもたちにイライラして冷たい言葉をかけてしまいそうな時には、「今は優しい気持ちで会話ができそうにないから、落ち着くまで別のところに行くね。落ち着いたら必ず戻ってくるからね」と伝えて歩き去ることもあります。子どもたちが不安を感じないように「必ず戻ってくる」ことを伝えることが大切です。
その他にも、掃除や洗濯などの家事は子どもたちと一緒に行い、子どもたちがいない時間は仕事や趣味に全集中。お手伝いは子どもの自主性を育み、自尊心を高めるとも言われています。子どもといる時間に一緒に家事をやることで、自分の時間が増えて、子どもたちの成長にも繋がる。まさに一石二鳥です。
このように自分のための時間を作ることで、常に誰かのために何かをやっている状態から解放され、イライラすることが減り、子どもとの関係も良い方向に変化していきました。
私は私。あなたはあなた。”Boundary”の重要性
子育てに関する書籍やセラピーを通じて学んだことは、どんなに親しい間柄であっても、「私は私」「あなたはあなた」と境界線を引くことの大切さ。
境界線=”Boundary”。
”Boundary”を大切にすることで、パートナーや子どもを「一個人」としてみることができ、尊敬や尊重の気持ちを忘れずに接することができます。
また、相手からも自分の境界線を踏みにじられることがなくなり、自分の欲求に早く気がつき、満たすことができるでしょう。
私は子育てに境界線を意識するようになってから、心に余裕が生まれ、子どもや夫に怒りや悲しみをぶちまけてしまうことが少なくなりました。
もし、あなたが子育てを辛く感じているなら、”Boundary”を意識して、相手と同意できる境界線を見つけ、それを上手く言葉にして、自分のための時間も大切にして欲しいです。
自分を大切にできるからこそ、他者に対しても真に優しくなれる。私はそう感じています。
デートナイトでロマンチックな夏にしよう

あなたはデートナイトって聞いたことありますか?
デートナイトとは、夫婦やカップルが特別な時間を共有し、お互いの関係を深めるために設ける時間です。通常は、外出して食事や映画、コンサートなどのエンターテイメントを楽しむことが一般的ですが、場所やアクティビティはそれぞれの好みや予算に合わせて選ぶことができます。
あなたが、「パートナーとコミュニケーションがとれていない」「相手との絆をもっと深めたい」「ロマンチックな関係に戻りたい」こういったことに悩んでいるのなら、デートナイトをとりいれてみることをおすすめします。
アメリカで重視される夫婦の関係
アメリカに住んでいた時に、私がびっくりしたのは、子供がいる夫婦が、金曜日の夜を「デートナイト」と決めて、その夜だけはベビーシッターを雇い、夫婦だけでディナーに出かけていることでした。
日本人の母親としては、子供をおいて、夫婦だけで外出するなんて、無責任だな~、そんなこと私にはできない、と感じていました。
アメリカの夫婦は、このデートナイトに限らず、日々の生活のいたるところで夫婦の関係を大切にしています。その一つは、子供が生まれても、新生児の時から子供と夫婦の寝室を分けるところです。夫婦の寝室は夫婦だけの神聖な空間であり、子供と共有する場所ではありません。
日本人の感覚だと、ちょっとやりすぎではないかと思うこともありますが、こういった習慣は、アメリカ人カップルが年を重ねても、いつもロマンティックな関係を築いている秘密なのだなと感じました。
デートナイトのメリット
デートナイトは、夫婦関係をより健全で充実したものにするための素晴らしい手段だと感じます。
まず、忙しい日常生活の中でデートナイトを設けることで、夫婦間の絆を深める時間を確保できます。仕事や家事に追われる日々から解放され、お互いに専念できる時間は、感情的なつながりを強化し、夫婦の絆を深める助けとなります。
さらに、デートナイトは日常のルーティンに変化を与え、新たな刺激や冒険を与えるものでもあります。新しい場所に行ったり新しい体験をすることは、夫婦間の興味を刺激し、お互いをよりよく理解する手助けとなります。また、デートナイトではリラックスして笑い合ったり、共通の趣味や関心事について話し合ったりすることで、コミュニケーションの質を高めることもできます。
また、デートナイトは夫婦の個人的な幸福感を向上させる効果もあります。仕事や家庭のストレスから離れ、お互いを大切に思う時間を共有することで、リラックスして楽しいひとときを過ごすことができます。その結果、夫婦の幸福感があがり、良好な夫婦関係の構築につながるのです。

忙しい毎日にどう取り入れるか
メリットがたくさんありそうなこのデートナイト。あなたの忙しい日々の生活に取り入れやすくするためには、どうしたらよいでしょうか。
まず、日程を計画しましょう。忙しいスケジュールを考慮して、週に一度または二週間に一度の頻度でデートナイトを設けることを目指してみてはどうでしょう。カレンダーに予定を入れることで、デートナイトを優先しようと意識できます。
子供がいる場合は信頼できるベビーシッターや家族に頼ることを考えましょう。子供の世話を頼むことで、夫婦二人だけの時間を確保することができます。予算に合わせて経済的な選択肢を考えることも大切です。高価なデートではなく、予算に合わせたアクティビティや場所を選びましょう。
さらに、日常生活の一環としてデートナイトを取り入れることもできます。例えば、家での特別なディナーや映画鑑賞、散歩やドライブなど、外出しないデートも楽しむことができます。デートナイトは特別なイベントだけでなく、日常の中に組み込むことで継続しやすくなります。
最後に、お互いの関心や好みを考慮して、アクティビティや場所を選ぶことも大切です。共通の趣味や興味を持つイベントに参加したり、新しい経験を共有したりすることで、より充実したデートナイトを楽しむことができます。
デートナイト10のアイデア
- 近くの海、湖、川などに出かけて、子供の頃の水遊びにまつわる思い出をお互い話してみるのはどうでしょう。もちろん、泳ぐことも忘れずに!
- 2人でエクササイズのクラスを受けて一緒に汗をかいてみましょう。
- 遊園地に出かけ、子供に戻ったように2人で楽しみましょう。
- 夏は屋外コンサートに最高の時期。外で音楽を一緒に聞き、忘れられない夜を過ごしましょう。
- ポラロイドカメラを持って、お気に入りの町にくり出しましょう。お互いに写真を撮りあって、2人だけの写真マップを作ってみましょう。
- 行きたいレストランのリストを「この夏に制覇するレストラン」として作り、デートナイトのスケジュールの予定を立てましょう。
- 家でテイクアウトを食べながら映画を見ることが最高の時もありますよね。ジャンケンで勝った人がテイクアウトと映画を選び、2人で家でのんびりと楽しみましょう。
- ハイキングに出かけ、日の出や日の入りを楽しみましょう。
- プラネタリウムに行って、デート気分を楽しみながら宇宙について一緒に学びましょう。
- 2人で実現したい夢のリストを一緒に作って、2人の未来プランをたてましょう。
デートナイトをとりいれていつもと違う夏に
10のリストから、どれかさっそくやってみたいと思うものはありましたか?
私自身、子供が生まれても夫とは「父と母」ではなく「あなたと私」として、お互いいつまでもドキドキするような関係を維持したいと思い、月1くらいの頻度で、2人でデートナイトに出かける時間をとっています。意識的にこういった時間を作ることのメリットは、予想以上でした。
デートナイトは夫婦関係をより良くしながらお互いの幸福感をあげるために重要です。忙しい日常から離れ、お互いを大切にする時間を作ることで、より深い絆を築くことができます。
あなたもぜひ、デートナイトを取り入れてみてはいかがでしょう。
フランスのセックスセラピストに聞く、セックスを楽しむために一番大切なこと【カミ―ル・バタリオンさんインタビュー】

フランスは、性についてオープンな国として知られています。しかし、カップルたちも様々なセックスの悩みを抱えているようです。今回、ハミングは長年セックスセラピストとして活躍するカミール・バタリオンさんに話を伺いました。
カミールさんは、10代の頃に性の問題に関心を持ち、カップルのセックスライフの悩みに真摯に向き合ってきました。フランスでは比較的リベラルな価値観が浸透していますが、それでもセックスの悩みは避けられないのが実情のようです。
カミールさんは、セックスの悩みを抱えた時の最初の一歩は、パートナーとのコミュニケーションだと言います。フランスから届くカミールさんのアドバイスは、あなたのセックスライフをより豊かにするヒントとなるでしょう。
ーなぜセックスセラピストになろうと思ったのですか?
よく聞かれる質問です。16歳の時にセックスセラピストに関する本を読んで感銘を受けたのがきっかけです。その本から、カップルにとって性的なつながりが大切であることがわかったので、性的な悩みを持つ人を手伝うような仕事をしたいと思いました。ただ、当時は性に関する仕事に詳しい知り合いなどもいないし、そういうことに関心を持つこと自体をを恥ずかしく感じていました。「まあ、年をとって40歳くらいになった時にまた考えようか」なんて思っていました。でもその後、アメリカのサンフランシスコで暮らす機会があり、ここで「他人がどう見ているかを気にしないマインド」を身に着けて、25歳の時に長年の夢だったセックスセラピストになることができました。
ーあなたの肩書は「セクソロジスト」ですが、「セックスセラピスト」との厳密な違いはありますか?
国によって異なりますが、フランスでは、セクソロジストは大学で研究をする人、セックスセラピストは大学ではなく私的な機関などでその分野についてのスキルを習得した人です。そういった訓練方法の違いがありますが、どちらも、セックスに関する皆さんの悩みを解決するためのお手伝いをするということに変わりはありません。
ーあなたのクライアントがセックスに対して感じる一般的な悩みや課題について教えてください。
私のクライアントのほとんどは主に3つの理由から私のところを訪れます。性欲がないこと、次の2つは女性に多いんですがセックスに痛みを感じること、そして、セックス中にオーガズムを感じることができないという3つです。
ーそれらの悩みは、どのような原因から生じることが多いと考えますか?
その理由には社会的なプレッシャーと心理的なプレッシャーの2つがあります。まずは、「セックスとはこうあるべき」と私たちの考えをコントロールしようとする社会からの圧力です。セックスに関する「正常」がどういうものか、身体のイメージ、性的表現などに関しての見えない圧力がありますよね。それから、心理的な面では、セックスライフにブレーキをかけてしまうのがストレス、不安、トラウマなどの心理的な圧力です。これは、自己肯定感とも関係してきますね。
ー フランスでは、セックスや性に対して日本よりもオープンなイメージがありますが、それは正しいですか?そういうセックス観は、フランスのカップルの性生活にどのような影響を与えていると思いますか?
私はフランス人でありさらにセクソロジストという仕事をしているので、「あなたは、きっとセックスを愛する最高の恋人だろう」と言われます。(笑) もちろん、フランス人の中にはセックスが大好きな人もいますが、そうでない人だってもちろんいて、これは個人によりますね。ただ、フランスではセックスに関してオープンに話すことができて、セックスに関して話題にすることが普通のこととして一般的に受け入れられているという文化がありますね。
テレビや雑誌などのメディアでは性に関する話題がつきないし、インターネット上で多くの人が友達とセックスについて話していますよ。特にフランスの女性はセックスについて話すのが大好きなんです。あとは、フランスの学校の性教育の状況も年々改善されているように思います。フランスでは、積極的に学校で性教育が行われていますよ。
ーセックスについてなかなか話題に出しにくいというカップルたちにはどういうアドバイスをしますか?
多くの人がセックスについて話しにくいと感じていると思います。だって、恋愛関係にある相手とセックスについて話すなんてこれ以上居心地が悪いことはないですよね。多くの夫婦やカップルがセックスについて話すことができないでいるのが現状です。
でも、ここで大切なことは何よりもコミュニケーション。恥ずかしがり屋な人にとってコミュニケーションをとることが難しいことはよくわかります。でも、コミュニケーションがとれなければ、相手を理解することすらできません。だから、まずはコミュニケーションの大切さを忘れないでほしいです。でも、私のセッションに来る女性たちの中には、パートナーとセックスの話なんて一度もしたことがないと言う人もたくさんいます。「セックスライフで取り組むべき課題があることはわかっているのに、話せないんです…」と。こういうカップルほど、まずは最初の一歩として、会話を始める必要があります。
そして、相手とセックスについて話すことができれば、それはとても意義深くて素直に相手に向き合える時間となるでしょう。セックスについて率直に話すことができないカップルが、お互いが幸せになれるセックスをすることはとても難しいと思います。

ーセックスという行為は、男性を喜ばせるものというイメージがあります。
セックスについて考えるとき、私たちは気持ち良い前戯、男性の勃起、陰部への挿入などを思い浮かべると思います。つまり、「セックス=挿入行為」というイメージがあるんです。私がクライアントに伝えたいのは、このセックスに関するイメージを変えましょうということです。セックスには、挿入するという行為以上の意味があります。
例えば、実験でわかっていることの1つは多くの女性が、身体の別の部位へのやさしい刺激によって快感を得られるということがわかっています。例えば、クリトリスですね。まずは、一般的な私たちが持つセックスのイメージを変える必要があります。
ーなるほど。私たち女性がセックスをもっと楽しめるようになるためのアドバイスはありますか?
女性がもっとセックスを楽しめるようにするには3つあります。セックスでの自己肯定感を高めること、セックスに関する知識を身につけること、そして自分の身体をもっと知ることです。
1つ目のセックスにおける自己肯定感とは、自分の身体に自信を持つことです。それができると自分がどういったセックスをしたいかを相手にも伝えられるようになります。そうすれば、セックスをもっと楽しめるようになるでしょう。セックスにおける自己肯定感を高めることを最優先に取り組んでみてください。
2つ目は、セックスの知識をつけることです。これによって自分の体が何をすれば喜ぶのかを理解することにつながります。つまり、セックスの時間を存分に楽しむために必要な、あなただけのツールを見つけることができます。
3つ目は自分の身体をよく知るということです。身体がどんな刺激を欲しているのか知って、その刺激を受け取り楽しめるようにしましょう。セックスを本当に楽しむためには自分の身体についてもっと知ることが大切なんです。だから、本当にセックスを楽しむためには、体がどう感じているかを意識して、必要に応じてセックスの仕方を調整していきましょう。
セックスを楽しめていないな、と感じたら、相手とセックスをする前に、自分で練習しておきましょう。セックスの最中にどうやって呼吸をしたらいいかを意識してみたり、セルフプレジャーをしてみたり、あなたの体を探求しておけば、相手とセックスをするときにずっと楽になります。
ーすでに結婚している夫婦たちにも、セックスセラピーのセッションを受けることを勧めますか?
もちろんです。最近は、結婚する前にセッションを受けに来るカップルも増えているんですよ。「来年結婚するんだけど、自分たちの関係がちゃんと軌道にのっていけるかを確認したくて」「セックスについて、もっとちゃんと話し合っておきたいから」と言ってセッションに来られます。
研究結果でも出ていますし、私が今まで見てきたケースでも言えることですが、結婚や妊娠などの人生のビッグイベントの前でも、気になる悩みを抱えていたら、早めにセッションに来るほうが、後から取り組むよりも早く解決できることが多いんです。なぜなら、それによって問題を解決するためのツールを早い段階で手に入れることができ、自信がつき、自分で何とかできるようになったり、周りに助けを求めることができるようになるからです。どんなカップルにも、少なくとも年に一度は、セッションを受けることをお勧めします。
セッションに来ると、パートナーとセックスについて話さざるおえない状況になりますよね。パートナーとセックスについて話すことのメリットは、その会話をすることで「2人の関係が重要である」というあなたの意思を相手に伝ることになることです。そうでしょう?私たちの関係はとても重要だから、これを優先課題として今まさに取り組んでいると伝えているようなものです。その結果、セックスに対する満足度も自然と高まるでしょう。
ーセックスについて話すことがまだ恥ずかしいと感じている方へのメッセージはありますか?
あなたがセックスを楽しみたいのなら、まず大切なことは自分が何を望んでいるかを知ることです。それがわかれば、自分の体を探求することも、自分がどういったことをしたいのかを表現することも恥ずかしくなくなります。
セックスに関する著名な研究者であるエミリー・ナゴスキーさんはこう言っています。「あなたにひとつだけ覚えておいてほしいことがある。人生はセックスを楽しまないで過ごすににはあまりにも短いものです。だからセックスを存分に楽しもう」本当にその通りだと思います。人生は一度きり。セックスを楽しまないなんてもったいないですよ。

Profile:
カミ―ル・バタリオン
性別や性的指向に関係なく、個人やカップルが親密さの課題を克服し、スローセックスアプローチを通じて自己や他者とのより多くの喜びとつながりを育む新しい道を切り開く手助けをしています。フランスで心理学の学士号を取得し、ベルギーで家族と性の科学の修士号を取得しました。
Podcast: A Frenchie talks about sex
https://www.camillebataillon.com/en/sex-therapy/
今日から始める、不安解消のための瞑想法

インターネットやSNSの発達により、私たちは世界中の情報を瞬時に手に入れられるようになりました。便利な反面、膨大な情報に振り回されてしまうことも……。
SNSで流れる友人の幸せそうな投稿を見て、自分の人生と比べてしまったり、ニュースで報道される出来事に不安を感じたり、気がつかないうちに心が疲れてしまうことがあるのではないでしょうか。
そんなときには、一度立ち止まって、自分自身と向き合ってみることが大切です。心の中に溜まったざわつきを手放し、内なる平穏を取り戻す。その1つの手段が「瞑想」です。
そもそも、瞑想とは
瞑想とは、自分自身の心と向き合い、内面を見つめるための方法の一つ。自分の心の状態を客観的に観察するためのツールと言えるでしょう
瞑想の方法は様々ですが、基本的には、静かな場所に座り、目を閉じ、呼吸に意識を向けることから始まります。瞑想中は、仕事の心配事、昨日の出来事、今日のやることなど、様々な考えや感情が頭の中に浮かんでくるものです。
最初はこれらの雑念を追い払おうとしがちですが、瞑想の目的は、雑念を無理に消し去ることではありません。むしろ、雑念をそのまま受け入れ、まるで空を流れる雲を眺めるように、客観的に観察することが大切なのです。
例えば、仕事の心配事が頭に浮かんできたら、「私は仕事の心配をしているな」と認識し、その考えにはあまり深入りせず、ゆっくりと呼吸に意識を戻します。このように、雑念をあるがままに受け入れ、静かに観察する練習を重ねることで、次第に自分の心の動きを客観視できるようになっていきます。
とはいえ、「瞑想を日々の生活に取り入れたい」と思っても、何から手をつけたらいいのかわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、誰でも気軽に始められる簡単な瞑想法をいくつかご紹介します。
初心者OK。今日から始める5つの簡単瞑想方法
1日5分、何もしない時間を作る
忙しい現代社会では、仕事に家事に育児と、毎日やることが山積みで自分と向き合う時間が後回しになりがちです。
だからこそ、意識的に自分と向き合う「無になる時間」を日々の中に取り入れてみましょう。最初は5分間でも大丈夫。継続することで少しずつ変化を感じることができるでしょう。
例えば、寝る前や起きる前の5分間、ベッドの上に寝転がり、目を閉じます。吸う息で腹部を膨らませ、吐く息で腹部を凹ませる。呼吸は心を落ち着けるための強力のツールです。ゆっくりと深呼吸をしながら、呼吸に意識を向けてみましょう。
最初のうちは、5分間でも長く退屈に感じるかもしれません。しかし、これを習慣づけていくうちに、次第に瞑想に集中できるようになり、心が落ち着いてくるはずです。
感じたことをノートに書き出す

朝目覚めた直後、まだボーっとしている間に、頭の中に浮かんでくる様々な思いを、そのままノートに書き出してみましょう。これは「モーニングページ」と呼ばれる手法で、頭の中をスッキリとさせ、一日をフレッシュな気持ちで始めるのに効果的です。
ノートを開いたら、思いつくままに書き始めます。例えば、「昨日は夜遅くまで仕事をしていたから、まだ眠い…」「今日は友人との約束があるから、楽しみだな」「最近運動不足だから、今日は公園を散歩しよう」など、何でも構いません。
大切なのは、文章の形式や見た目にこだわらず、自分の感情や思考を自由に表現すること。スペルの間違いや文法の誤りを気にする必要はありません。目安は3ページ。頭の中を言葉にして、ペンを走らせてみてください。
「モーニングページ」を毎朝続けていくことで、自分の思考パターンや感情の変化に気がつけるようになるでしょう。
ヨガをする
ヨガは心身のバランスを整える古代からの知恵です。ポーズに合わせて深く呼吸をすることで、体に酸素を十分に取り込み、老廃物を排出できます。同時に、呼吸に意識を向けることで雑念が消え、心が静まっていくのを感じられるでしょう。
今では、YouTubeでも様々なヨガのレッスンを気軽に受けることができます。
「朝ヨガ」や「夜ヨガ」といった、時間帯に合わせたプログラムや「自律神経を整えるヨガ」など、特定の目的に特化したプログラム、また、5分や10分といった短時間で完結するレッスンも多数あります。
これなら忙しい日々の中でも、隙間時間を見つけてヨガができるでしょう。ヨガを通して、心身のバランスを整え、不安感を和らげていきましょう。
瞑想グッズを取り入れる

瞑想を始めるにあたって、専用のグッズを取り入れるのも一つの方法です。香りや視覚的なアイテムなど、自分に合ったグッズを探してみましょう。
たとえば、アロマディフューザーを使って、お気に入りの香りを部屋に広げるのも効果的です。ラベンダーやカモミールなどのリラックス効果のある精油を使えば、心が落ち着き、瞑想に集中しやすくなります。
他にも、ビー玉が流れるオブジェを眺めているだけで今に集中できる商品なども販売されています。視覚的に心を落ち着けるアイテムを自宅に飾り、「無になる習慣」を作るのも一つの方法です。
不安に襲われたときは、瞑想の力を借りよう
不安感に襲われたとき、私たちは「あの時こうしていれば…」「もし〜だったらどうしよう」といった考えを繰り返し、ネガティブな思考から抜け出せなくなることがあります。
そんなときこそ、瞑想の力を借りてみましょう。深呼吸をして今この瞬間に意識を向け、不安な感情をそのまま受け止めるのです。
最初は難しく感じるかもしれませんが、毎日5分でも自分自身と向き合う時間を持つことで、徐々に瞑想が習慣化され、不安への対処法が自然と身についていくでしょう。
心の平穏を取り戻す第一歩は、自分自身と向き合うことから始まるのです。
「腟のケアは40代からでも遅くない」 鍼灸師の栗本夏帆先生に聞く腟ケアの最初の一歩

あなたは、腟まわりのケアをしていますか?ハミングは今回、『うるおいの腟レッチ』の著者で、鍼灸師の栗本夏帆先生に、腟のケアについて聞きました。生理痛やセックスレス、更年期障害のことと同じように、腟についてもっとオープンに話すことが大切だという栗本先生。どうして腟ケアが必要なのか、具体的にはどんなことから始めたら良いのか、また最近のお勧めのフェムケアアイテムについて教えていただきました。
ーー 栗本先生には2022年にもインタビューをさせていただき、(インタビュー記事はこちら)病気になる前に対策をとる“未病治”という考え方を教えていただきました。この“未病治”の意識はどうしたら日常生活に取り入れることができるでしょう?
“未病治”というのは病気になる前の段階のことです。例えば、 ぎっくり腰になってからではなく、ぎっくり腰にならないようメンテナンスのために鍼治療をしておくというふうに、病気になる前に予防することを“未病治”と言いますが、この考え方はぜひ多くの方に知ってほしいと思います。“未病治”のために実際にできることとしては、まず自分自身のことを知るということでしょう。例えば、自分の腟がどういう状況かを鏡で見ておく、ということ。そうすると、何か変化があった時にすぐ気づけて病院に行こうとか、保湿をしてみようとすぐの判断ができ、大きなトラブルになる前に気づけるようになります。
ーー “未病治”のためにも腟のケアが大切なんですね。ただ、多くの女性にとって、腟は普段の生活で見る機会もなく、あえて刺激せずとも静かに守っておけばいいのではと考える人も多いように思います。なぜ、腟ケアが必要なのでしょう?
腟まわりは意識をして取り組まないと鍛えることが難しく、また年齢とともにどうしても衰えててしまう部分だからです。加齢とともに筋力が衰えると血流も悪くなり、乾燥するので、傷つきやすくなります。その結果、感染症にかかったりとトラブルの原因になってしまうんですね。だから、将来的にこういうトラブルが起きるんだよということを知っておいたうえで、今できることは何かと考えることが重要です。筋力が衰えることで起きる臓器脱や子宮脱という怖い病気がありますが、こういった病気の予防にもなります。日常生活の悩みとして多いのは尿漏れがありますね。腟ケアは尿漏れの予防にもなります。
ーー 栗本先生は腟まわりのケアとして、清潔にする、保湿する、 筋力をつけるの3つが大切だとお話されています。今まで腟まわりのケアを意識したことがない人が、まず最初にできることは何でしょう?
まずは清潔にするということですね。最初は、ソープを切り替えるのが1番取り入れやすいと思います。お風呂で腟まわりを洗うソープを、刺激が弱くデリケートゾーンのph値に合わせたタイプのものを使うということからスタートしてみると良いでしょう。腟専用のソープにするのが面倒だったり、コスト的に厳しいという方は、腟まわりのph値に合わせた全身にも使えるソープがあるので、そういうものに切り替えるのも良いでしょう。そうするだけでも腟まわりの乾燥を防げますし、清潔にすることを自然と意識して洗えるようになるでしょう。そうすると、臭いや蒸れもなくなり、雑菌の繁殖から起きる病気の予防につながります。

ーー 栗本先生は、腟を清潔にするためにはアンダーヘアをカットした方が良いと提言されていますが、なぜでしょう?海外では、女性のアンダーヘアの脱毛が一般的でびっくりしました。
私はアンダーヘアは全部なくて良いと思っています。なぜなら、その方が腟まわりをきれいに洗えて、保湿もしやすく、さらに蒸れません。またこの部分の変化にも気づきやすくなり、良いことづくしです。日本でも最近はVIO脱毛のように、昔よりは脱毛が認知されていますが、海外では性やフェムテック系の知識がより浸透していますね。生理を迎える時に親がちゃんと話したり、学校でもピルが普通に販売されているところもあったりと、小さい時から性について触れる機会が多いと、アンダーヘアをカットすることも自然にできるのではないかと思います。
ーー 前回のインタビューでは、 腟まわり専用ソープをおすすめのフェムケアアイテムとしてご紹介いただきました。最近の栗本先生のおすすめのアイテムは?
私が最近はまっているのが、「アミ―コットンライナー」という使い捨ての布のおりものシートです。
他のおりものシートと何が違うかというと、通気性が一般のおりものシートの176倍以上と言われていて、夏など暑い時に感じる蒸れを全く感じなくなったんです。最近もまとめ買いしましたよ。
ーー 腟は年齢とともに衰えるとのことですが、これから更年期を迎える世代の女性にとって、今さら腟ケアは遅いのではと感じる人もいます。そういった年代でも、腟ケアを始めて効果はあるのでしょうか?
効果はあります。ですから、気づいた時にすぐに始めてもらいたいですね。何歳からでも遅くないですし、40代から始めておけば、50歳前後で来る更年期への心の準備にもなります。腟まわりのことを知ることで、更年期の症状の勉強にもなりますから、腟ケアは40代からでも全く遅くないですよ。
ーー 栗本先生は、子どもが小さい時からの性教育の大切さについてお話されています。私も7歳の娘に生理について伝えたいと思うのですが、どう話したら良いのかわかりません。親が子どもと性についてもっと気軽に話ができるようにするには、どんな工夫ができると思いますか?
私は小学生くらいの時から、母親に「どうやって生まれたの?」などとよく聞いていたんです。その好奇心に対して親から「そんなこと聞いちゃダメ」と言われていたら、その時の私は子どもなりに、これはあまり聞いてはいけない内容なのだと思ったでしょう。私の親にはそういう意識が全くなかったことがとても大きかったですね。だから、お子さんが疑問に思った時に、親はそれにふたをしないということがポイントかなと思います。子どもの好奇心を大切にしてあげて、性について当たり前のように話してみるのが良いのではとは思います。
ーー 親が、性について話してはいけないって思っていると、それは子どもにも伝わるので、まず親の意識から変えていかないとですね。
まずは、親御さんが知識を得るというのが大事だと思います。そうしていけば、「お母さんは今日こういうことを知ったよ~」という感じで、お子さんと共有することができます。「女性の体にはこれからこういうことが起きるから、こういう風に準備していこうね~」などと、知識として伝えていくのが良いと思います。

ーー 栗本先生が総括をされているグラン治療院には「フェムケア鍼灸」というメニューがありますが、これはどういった鍼灸ですか?
はい、「フェムケア鍼灸」は更年期や生理痛の症状などに悩まれている方のための身体全身の鍼灸治療です。女性特有のこういった悩みに、鍼灸が効果があるということを知らない方がすごく多いので、それを知ってもらうきっかけに「フェムケア鍼灸」という名前にしました。この鍼灸では、女性ホルモンを調節したり、体の水分バランスや気の流れを整えたりと、悩みに沿ったツボを整えることができます。女性の悩みにフォーカスした鍼灸院として、2022年の10月には、池袋にyuragi鍼灸院がオープンしましたが、現在はこちらでフェムケア鍼灸をご提供しています。
ーー 「オンライン鍼灸」もありますが、鍼灸はオンラインでも受けられるのですか?
はい。「オンライン鍼灸」はオンラインでつながって、私たちが指示するつぼにシールを貼っていただくという方法です。予約いただいた段階で、ご自宅にツボ刺激ができるシールをお送りをし、ご予約日にそのシールを使って、悩みのツボを相談しながら、ここに貼りましょうと指導をさせていただくのが「オンライン鍼灸」です。こちらは、新型コロナ禍にスタートしましたが、遠方の方、小さなお子さんがいる方や介護中の方などひとりで気軽に外出できない方のニーズに答えられていると感じますね。

ーー グラン治療院が予定している、今後の新しい取り組みはありますか?
はい。骨盤底筋群を鍛える機械の導入を進めています。骨盤底筋群を鍛えることで、尿漏れ予防にもなるのですが、ここは自分ではなかなか鍛えにくい身体の部分なんです。この機械に座ると磁気の刺激を受けて筋肉が動くので、実際にどのあたりに力をいれれば骨盤底筋群を鍛えられるのかわかり、自分でもトレーニングがしやすくなります。この機械は、現在(2024年5月現在)は横浜スパイアス院でキャンペーン価格にて体験ができます。今後は他の店舗でもこの機械を導入し、座るだけで骨盤底筋が鍛えられるメニューを用意していく予定です。
栗本さんの書籍:『うるおいの腟レッチ』
栗本夏帆 著 ¥1,760/光文社

Profile
栗本夏帆(くりもとかほ)
鍼灸師、温活士、鍼灸院『グラン』統括院長。(一社)日本鍼灸協会理事、(一社)日本フェムテック協会常任理事なども務める。女性の心と身体の健康のための学びや相談の場を提供し関連商品のアドバイザーや、フェムテックの啓蒙を行っている。著書に『うるおいの腟レッチ』(光文社)。
https://biyoshinkyu.net/
Instagram @kaho_kurimoto
40歳を目前に考える、限られた人生の過ごし方

Humming編集部 條川純のコラムをお届けします。
久しぶりに会った友人の子どもの成長に、時の流れの速さを実感する今日この頃。40歳を間近に控え、これまでよりも時間の尊さを感じるようになりました。
私は少し前、2年間交際した彼との別れを経験しました。彼は優しく、私のすべてを受け入れて愛してくれた人。しかし、一緒にいる期間が長くなるに連れて、彼の内面の複雑さを知り、別れを選ばざるを得ませんでした。
けして傷つけられたわけではなく、それどころか彼からたくさんの優しさをもらっていた私。別れを意識しはじめてからは、「私がわがままなだけなのかも……」「ありのままの彼を受け入れるべきなのでは……」と罪悪感を感じることもありました。
しかし、悩んだ末に自分の本心に従うことを決め、その結果、彼を深く傷つけてしまったのです。
この経験を機に、過去を振り返り、これからの人生の過ごし方を深く考えるようになりました。
| Humming編集部Project Coordinator 條川純
1984年生まれ。アメリカ生まれ、アメリカ育ち。現在はひとり暮らしをしながら、生涯を共に過ごせるパートナーを探している。 |
流れのままに生きてきた39年間
これまでの人生を振り返ると、私は大きな人生の決断に関して、いつも流れに身を任せるタイプでした。特に恋愛においては、相手の優しさに惹かれ、深く考えることなくお付き合いを始めることが多かったのです。
そういった傾向は、中高時代に感じたコンプレックスが影響しているように思います。私は中学高校の4年間を日本のインターナショナルスクールで過ごしました。そこにいたのはスラリとした美人ばかり。アメリカで生まれ育ち、これまで食事のカロリーや自分の体型を気にせずに過ごしてきた私とはまるで異なっていたのです。
さらに、日本ではスリムで可愛い女の子が男の子から人気を集めていました。いつも友達の影に隠れる私。当時は自分自身をまるで「みにくいアヒルの子」のように感じ、寂しさを感じていたのです。
そんな経験から、男性に優しくされると嬉しさのあまり、深く考えずにお付き合いをしてきました。「私のことを好きになってくれなんて……」という思いが強かったからです。
若さゆえの未熟さから、最終的には自分のことも、相手のことも傷つけてしまうこともありました。
とはいえ、良いことも悪いことも経験したからこそ、今の私がいる。これまでの自分の選択を後悔しているわけではありません。
しかし、40代を間近に控え、さらに彼との別れを経験したことで、今後の自分はどんな人生を歩んでいきたいのかを深く考えるようになったのです。
40歳を目前に考える自分の生き方
広くて綺麗な豪邸に住んだり、高級車を所有したり、ブランド物で着飾ったり、私はそういったことを望んでいるわけではありません。私が求めているのは自分の心に正直に生きること。
仕事においては、情熱を注げる環境を自ら選び、目標に向かって全力で取り組みたい。そして、おばあちゃんになるまで働き続けるのが理想です。
恋愛面では、一生を共に過ごしたいと思える相手と出会い、愛し合い、サポートし合って穏やかに生きていきたい。
そして、人生の終わりを迎える時には、自分に対して「頑張ったね」と言えるような、後悔のない人生を歩みたいと強く願っています。
そのためにも、これからは流れに身を任せて生きるのではなく、キャリアも友情も恋愛関係も、これまでよりも慎重に選択していきたい。人生はあっという間に過ぎ去っていくから、限られた時間をより有意義に過ごしたいからです。
特に恋愛においては、付き合ってから「なんだか違うかも……」ということが起こらないよう、お付き合いをする前にもっと相手のことを知る努力をしたいと思っています。
人生の主人公は自分自身
自分が本当に大切にしたいものは何か。
どんな人生を歩みたいのか。
40歳を目前にした今、私はこんな問いを自分自身に投げかけています。
人生は有限。私たちは毎日着実に死に近づいています。死を意識して生きていくことは、不吉なことや悪いことではないと私は思います。むしろ、限られた時間をどう生きるかを考える良いきっかけになるのではないでしょうか。
どんなに慎重に生きていても、人生には思わぬ出来事や困難があるでしょう。それでも、失敗を恐れずに挑戦し、うまくいかない時は方向転換する勇気を持つ。そして何よりも自分らしく生きることを大切にする。人生の主人公は自分自身なのだから。
あなたはどんな人生を歩んでいきたいですか?
辞めることで起こったパラダイムシフト。実は色々なことをやりすぎていた?幸せの鍵はLess is More。 【Editor’s Letter vol.08】
| Humming編集長 永野舞麻がカリフォルニアから配信する「Editor’s Letter 」。日々の暮らしで感じた気付きや、人生において大切にしていることを綴っています。 |

綺麗な服を着飾るのが好きだった。
人脈を作るために積極的にランチに出かけた。
出張で世界中を飛び回っていた。
振り返れば、私はいつも自分の表面的なことを磨くことに力を注ぎ、忙しない日々を過ごしていました。
どちらかと言えば、派手で騒がしくて、外交的。そんな私が今では約1年間の時を経て、段々と外出を極力減らし、家の中で静かに瞑想をしています。
内と向き合う時間を大切にする。自分が大切だと思っていたことを辞めることを決断する。選択肢が少なくなることで、迷いが減り、穏やかな心で過ごせる時間が増えました。さらに、これまで気がつかなかったことに目が向けられるようにもなったのです。
40歳を目前にして起こったパラダイムシフト。
そのきっかけは何だったのか?内と向き合うことで現れた変化とは?私の体験談をお話します。
現状を受け入れ潔く辞めた海外出張
数年前までの私は、仕事や旅行で世界中を行き来したり、知人とランチに出かけたり、忙しない日々を送っていました。頻繁に会議のために日本へ、ケニアへ映画の撮影に行った帰りに、ロンドンに寄ってミーティング。来月も出張と家族旅行を合わせてニュージーランドへ行く予定になっていました。毎月スケジュール帳はいつもぎっしりと予定で埋め尽くされていました。
先月、予定していた日本出張の少し前のこと。体調を崩し、やむなく全ての予定を一度キャンセルすることを決断したのです。
もちろんキャンセルすることに対して、約束していた人たちへの後ろめたさや残念な気持ちもありました。しかし、自分の置かれたありのままの現実を受け入れ、入れていた予定を全て潔く”手放す”ことで、時間にも心にも余裕が生まれ、自分自身に思わぬ変化が現れたのです。
何事も”始める”のも勇気がいるけれど、”辞める”のには更に勇気がいる。しかし、4年前から始めたメディテーションで段々と自分の内側が変わりつつあったところに加えて、少し前に体験したヴィパッサナーリトリートで「大きな流れに逆らわず、今を受け入れることの大切さ」を体感していたからこそ、潔く”手放す”選択ができました。
内向的な自分を知ることで出会った心の平穏
ごちゃごちゃしていたスケジュールが綺麗になったことで、生活のリズムが整いました。
毎日、同じ場所、同じ時間に瞑想できるようになったことも相まって、性格までも少し大人しくなり、これまでは気がつかなかった日常の中の静寂に目が向けられるようになったのです。また、静かで落ち着いた空間を心地よいと感じるようになり、一人きりの時間を寂しいと感じる代わりに、エンジョイするようになりました。
たとえば、「水が欲しいのかな」とか、「この部屋の光加減が合うんだな」とか、植物が求めているものがわかるようになったり、私が静かになることで、子どもたちから話してくれることが増え、また、自分も静かに周りを観察するようになり、子どもたちの心の内や思考をより深く知れたり。
さらに、家にいる時間が増えたことで、趣味のアートもこれまで以上に充実しています。
遠方への出張を辞めたり、知り合いとのランチの機会を減らしたり、最初は周りと疎遠になるのではないかと不安を感じることもありました。しかし、辞めてみれば意外にも気持ちはスッキリ。これまでは必要以上に動き回っていたことに気がついたのです。
外に出なくても必要な情報は得られるし、会いたい人にはピンポイントで会えればいい。
これまで外交的だった私が、内向的になったことで、パラダイムシフトがおきたのです。
パラダイムシフトとは?
パラダイムシフトとは、考え方や価値観が根本的に変わること。
人は無意識のうちに特定の視点や信念に固執し、そのフィルターを通して日々を過ごしているのです。しかし、パラダイムシフトが起こると、これまでの「当たり前」が覆され、新しい見方や考え方ができるようになります。
この変化は小さな瞬間から始まり、次第に生活全体に影響を及ぼします。パラダイムシフトは私たちに新しい可能性を示唆し、人生に深みをもたらす大切なプロセスだといえるでしょう。
“Less is More”が人生における幸せの鍵
20世紀に活躍したドイツ出身の建築家、ミース・ファン・デル・ローエが残した言葉“Less is More”。これは「シンプルなデザインを追求することによって、より美しく豊かな空間が生まれる」という、彼の建築家としての信念を表した言葉です。
「少ない方が豊かである」という意味あいのこの言葉は、建築のみならず、人生を幸せに過ごすためにも重要な思想だと私は実感しています。
なぜなら、多くのものや情報に溢れた現代、便利な反面、膨大な選択肢に迷いや悩みが生じやすく、心身が疲弊するからです。
だからこそ、大切なのは選択肢を極力減らすこと。辞めること・やらないこと、自分の中に基準を持つこと。選択肢が減ることで迷うときや悩む時に使う思考の量が少なくなり、心穏やかに過ごすことができるのです。
もちろん、これまであたり前にしてきたことを辞めたり、習慣を変えるのは勇気がいることです。しかし、何かを手放し余白が生まれるからこそ、本当に大切なことに気がつけたり、新たなご縁に出会えたり、新しい可能性が広がるものです。
体調を崩し、海外出張をキャンセルしなければいけない。一見ネガティブに思えるこの出来事が、私にパラダイムシフトを起こし、”Less is More”の重要性に気がつかせてくれました。
生理前は性欲が強くなる?ムラムラした時の対処法!

男性にとっても、そして女性にとってもさまざまなタイミングで顔を出す「性欲」。
中でも女性の場合はさまざまな要因で性欲が増減するため、自身の身体をしっかりと把握して向き合っていくことが大切です。
性欲の増減に大きく影響を及ぼす「生理周期」についても、正しい知識を身に着けておきましょう。
今回は女性の性欲が生理前になると強くなる原因や、ムラムラした気持ちにどう対処すべきなのかについてご紹介します。
私たちの身体でホルモンがどうはたらいているのか、性欲の強弱とどう関係しているのかにも焦点を当ててみましょう。
性欲が強くなることには性ホルモンが影響している?

女性の性欲が強くなるのは、さまざまな性ホルモンが影響しています。
代表的な3つの性ホルモンを挙げ、それぞれどんなはたらきをしているのか確認してみましょう。
まず、女性の性欲に直接的な影響を与えているのが「テストステロン」です。
男性ホルモンの一種ですが女性でも分泌されており、筋肉や骨を丈夫に保つはたらきを担っています。
テストステロンは副腎や卵巣から分泌されており、性欲を高めることでパートナーと円滑な関係を保ったり、適切な時期に妊娠ができるよう身体を整えたりしています。
テストステロンの分泌は20代がピークだといわれており、通常は自然と減少していくでしょう。
40代以降テストステロンの分泌量が著しく減ったり、手術で副腎や卵巣を切除したりした場合、性欲の減少にもつながります。
また、女性ホルモンの一種である「エストロゲン」も、性欲の高まりに影響を及ぼしています。
エストロゲンには妊娠しやすい身体に整える役割があり、スムーズに性行為ができるよう膣を濡らしたり快感を高めたりしています。
その他肌や血管を健康的に保つためにも重要な成分で、女性らしい丸みを帯びた体つきになるのもエストロゲンの影響です。
思春期を迎える10代中盤頃から分泌量が増え始め、テストステロン同様20代がピークになるといわれています。
その後は次第に減少し始め、閉経とともにほとんど分泌されなくなっていくでしょう。
もう一種類の女性ホルモン「プロゲステロン」は、性欲を弱める方向にはたらく成分です。
テストステロンやエストロゲンのはたらきで性欲が高まり、無事性行為ができた後は、身体が妊娠を継続するための準備に入ります。
受精卵が育つために子宮内膜が厚くなったり、乳腺が発達して授乳の準備が行われたりと身体にはさまざまな変化が起こります。
それに伴い「PMS(月経前症候群)」に挙げられる不眠やイライラ・頭痛などに悩まされる方も多く、1ヶ月の中でもっとも性欲がおさまる時期といえるでしょう。
つまり女性の場合、元々の体質や性格・環境などが影響するのはもちろん、1ヶ月の中でも性欲に大きな変化があることが分かります。
「何だかムラムラする」「性的なことばかり考えてしまう」と感じたときは、自分が生理中・卵胞期・黄体期のどれに当てはまるのか考えてみましょう。
卵胞期には卵胞ホルモンであるエストロゲンが、黄体期には黄体ホルモンと呼ばれるプロゲステロンが分泌されているため、タイミングによって性欲に違いがあることに気がつけるでしょう。
関連記事:女性の性欲の真実! 年齢ごとの自然な変遷と幸せへのヒント…
女性の性欲が強くなるタイミング

生理周期によって性欲の強弱に差が出やすい女性ですが、中でもどんなタイミングで性欲にピークが訪れるのか知っておくと安心です。
自分の排卵周期や生理周期と照らし合わせながら、およそ何日後にピークが訪れるのか考えてみましょう。
まずは先ほどもご紹介したように、テストステロンやエストロゲンが分泌されやすい「排卵日前後」が性欲の高まりやすい時期といえます。
排卵日前後は1ヶ月の中でもっとも妊娠が成功しやすいタイミングといわれており、ここに合わせて性欲を高めることでよりスムーズに性行為ができるでしょう。
このシステムはいわば子孫繁栄に欠かせないものであり、人間に古くから備わっている機能といえます。
また、三大欲求の一部である「性欲」と、一見関係のないように見える「食欲」は、それぞれ影響し合っていることをご存じでしょうか。
性欲と食欲は脳の同じ場所で管理されており、両者が同時にピークを迎えることはありません。
性欲が高まっているときはお腹が空いているのを忘れ、逆に空腹時はムラムラした気持ちになりにくいのです。
さらに、私たちが食事をすると、身体は入ってきた食べ物を消化する役割を全うしようとします。
脳を含めたさまざまな部分が消化に集中するため、満腹時もそれほど性欲が強くなりにくいでしょう。
食事から約2時間ほど経つと胃の中に食べ物がなくなり、再び性欲が高まるようになります。
パートナーと性行為を考えている場合は食事直後を避け、消化が終わってからチャレンジするのがおすすめです。
▶︎セックスレスの原因とは?|なりやすい夫婦の特徴や解消法を解説
女性の性欲がなくなるタイミング

生理周期はもちろん、食事のタイミングによっても増加する傾向にある女性の性欲。
一方で性欲が失われやすいタイミングを知っておくことで、自身の欲求とうまく付き合えるようになります。
第一に、パートナーとの性行為で性交痛があった場合、女性の性欲は急速に失われてしまいます。
膣内が十分に塗れていない場合や、パートナーからのスキンシップが激しすぎる場合、膣内が感染症を引き起こしている場合などさまざまな原因が考えられます。
性行為中に性欲がなくなってしまうと、その後の行為が苦痛にすら感じられてしまうでしょう。
痛みに対しパートナーからの配慮が得られない場合、セックスレスに繋がる可能性もあります。
また、過度な疲労やストレスを感じている場合、脳に十分な余裕がなく、性欲に繋がらない場合があります。
一時的な疲労で数日間性欲が湧かない分には問題がないものの、数週間・数ヶ月と続けばパートナーとの関係にも影響を及ぼしかねません。
疲労やストレスを癒すのに脳や体が全力を注いでいる状態であるため、まずはストレスの原因を突き止め、上手な解消法を探すのが大切です。
続いて、妊娠や出産を経験した女性も、一時的に性欲が失われることがあります。
赤ちゃんを産んだ直後の女性がパートナーと距離を置きたくなるのも、性欲の減退が原因だといわれています。
出産後の女性は育児に全力を注ぐのはもちろん、自身の身体を回復させなければなりません。
出産は交通事故に遭うよりも身体に衝撃を与えるといわれているため、性欲が二の次になってしまうのも不思議ではないでしょう。
妊娠や出産後はパートナーとよく話し合い、欲求とうまく付き合っていくことが大切です。
さらに、服用する薬の中には一部性欲が失われるものがあります。
代表的なものとしては抗うつ薬が挙げられますが、日常的に服用するものの中にも性欲減退に注意しなければならないものがあります。
薬の服用でパートナーとの関係が悪化しないよう、事前に副作用についてしっかりと確認しておきましょう。
個人差とその影響

これまでは多くの女性に当てはまる原因についてご紹介してきましたが、これらはあくまでも目安であり、実際は人によって性欲の程度に大きな違いがあります。
「男性だから」「女性だから」と型に当てはめて考えるのではなく、パートナーの特徴をしっかりと見て判断することが大切です。
性欲に影響を与える性ホルモンの分泌は、主に20代や30代がピークだとご紹介しました。
しかしこれも個人差があり、30代までピークが来ない方もいれば、ほとんど分泌されないまま一生を終える人も珍しくありません。
こういった文章を読んで「自分と違う」と不安にならず、周りと比べることなく自分の性欲と向き合っていきましょう。
また、かつては多くの女性が子育てを中心とした人生を送っており、5人以上の子どもを出産する方も珍しくありませんでした。
3歳差で産んだ場合でも、全ての子どもが20歳を迎えるまでには42年の月日が必要であり、職には就かず閉経を迎える女性が多かったのです。
つまりほとんどの女性が同じような生活を送っているために、ホルモンバランスや性欲のピークにもそれほど差がなく、周りと自分を比べる必要もそれほどありませんでした。
一方の現在はというと、子どもの数はもちろん、そもそも妊娠・出産を行わない女性も増えてきました。
さまざまな理由があって不妊になってしまったり、結婚をせず仕事に邁進する女性がいたりと、その生き方は千差万別です。
当然ライフスタイルも一辺倒ではなく、抱えているストレスも人それぞれ。これにより、従来の女性と比べると性欲の増減も個人差が大きいといえるでしょう。
慌ただしい現代社会を生きる全ての女性は、「こうでなければならない」という指針を捨て、自分と向き合う時間を作ることが大切です。
▶︎40代の女性は性欲が強い?なくなる?その違いや性欲の対処法について
性欲増加に対する対処方法

性欲がいつピークを迎えるのかは人によって異なるとはいえ、生理周期でいえば排卵日から生理前にかけて徐々にムラムラすることが増えるでしょう。
時には仕事や勉強に集中できなくなったり、パートナーと意見が合わず衝突してしまったりすることもあります。
自分の性欲とうまく付き合っていくために、性欲の高まりを感じたときは、素直に身をゆだねてみるのもおすすめです。
パートナーとタイミングが合えば良いですが、そうでなければセルフプレジャーにチャレンジし、時間をとって欲求を満たしてみましょう。
指で行ったり、グッズを使ったり、動画を見たりとさまざまな方法があるため、自分の満足できる方法を選ぶと良いでしょう。
セルフプレジャーの良いところは、性行為に不満がある方も自分の好きなように取り組めるため、身体が満足しやすい点にあります。
肌が重なるだけで幸せになれる性行為とは異なるものの、また違った意味で充足感を得られるでしょう。
どうしたらさらに満足できるのか、触る場所を変えながら何度も試してみるのがおすすめです。
また、性欲を抑えるためには運動をするのも一つの方法です。運動をして筋肉を使うと、テストステロンが多く消費されます。
性欲の高まりに影響を及ぼすテストステロンが運動によって減少すれば、一時的に性欲を感じにくくなるでしょう。
スポーツに勤しんでいる間は余計なことを考えにくくなるため、頭をスッキリと整理させたい方にもピッタリです。
さらに、幸せホルモンである「セロトニン」を分泌させ、満足度を高めるのも良いでしょう。
セロトニンは適度な運動や日光を浴びることで生成されやすくなるほか、大豆製品や乳製品・肉類などに多く含まれる「トリプトファン」を摂取することでも増えるのが特徴です。
気持ちを落ち着けてうつ状態を緩和するためにも大切な成分の一種であるため、ストレスフルな毎日を過ごす人ほど積極的に摂取すると良いでしょう。
関連記事:生理後は性欲が強くなる?生理周期別の性に関する過ごし方を紹介
心と身体が心地いい状態を保とう!
女性の身体はまだまだ不思議な面がたくさんあり、性欲一つとっても解明されていないことばかりです。
年代であったり、はたまた生理周期によるホルモンバランスであったりとさまざまなことが影響するため、これらを加味した上で上手に付き合っていきましょう。
大切なのは自身の性欲を正しく理解し、上手く発散し、パートナーと話し合ってタイミングを合わせることです。
精神的にも身体的にも無理のない状態を続けることが、ストレスを軽減し心地良く過ごせる第一歩となるでしょう。
▶︎50代女性の性欲事情|閉経後や更年期との関連性についても
女性の性欲の真実! 年齢ごとの自然な変遷と幸せへのヒント…

私たち人間はホルモンの影響で性欲が高まったり、逆になくなったりすることがあります。
これは男性・女性に関わらず起こる現象であり、ホルモンの量に応じて性欲が高まる時期が異なります。
「女性だから性欲がないだろう」といったイメージを抱く人も多いですが、それは間違いであることを覚えておきましょう。
今回はそんな女性の性欲について、人よりも性欲が強く心配している方や、性欲が高まるとどうなるのか知りたい方に向けた情報をご紹介します。
年代によっても大きく異なるため、自身の現状をイメージしながら見てみると良いでしょう。性欲に関して何らかのストレスを感じている方も、ぜひ最後までご覧ください。
性欲が強すぎるのは異常?

そもそも性欲とは、一体どうして高まったりなくなったりするのでしょうか。
「ホルモンの影響」とはいっても、目に見えないホルモンがどうはたらいているのか想像しにくい方も多いはず。
まずは男性ホルモン・女性ホルモンそれぞれのはたらきを見てみましょう。
男性ホルモン「テストステロン」は、その名前から男性の体内でしか分泌されないと思われがちですが、実は女性の筋肉や骨を丈夫に保つためにはたらく成分でもあります。
女性の場合は排卵日付近で多く分泌され、気持ちを興奮させ性欲を高めるといわれています。
排卵日近辺は女性がもっとも妊娠しやすい期間でもあるため、本能の一貫として性欲が高まるのです。
また、女性ホルモンの一種である「エストロゲン」は、膣内の潤いを保ったり、性行為への感受性を高めたりといったはたらきを担っています。
女性は性欲が高まると膣内に粘液が分泌され、性行為の痛みが軽減されるようにできています。
この粘液分泌を担っているのがエストロゲンであり、リラックスして性行為を行うためには必要不可欠な成分といえるでしょう。
つまり、これらのホルモンが正しく分泌されている状態であれば、誰であっても性欲が訪れるといえます。
「自分だけ性欲が強いのではないか」という悩みを抱える女性も多い一方、デリケートな悩みは周りに相談しにくいもの。
誰も他の女性がどう考えているのかを知らないだけで、実は多くの女性に性欲があり、決して異常なことではないのです。
性欲が強いことは、いわば体の機能が正常であり、健康である一つの指針となります。
中にはパートナーと欲求のレベルが合わなかったり、周りと比べて自分が変だと感じてしまったりするケースもありますが、性欲が強いからといって自分を責めるのはやめましょう。
時にはセルフプレジャーを取り入れたり、パートナーとタイミングを合わせたりして、上手に発散していくことが大切です。
関連記事:性欲を抑えるにはどうすればいい?具体的な方法とデメリットについても
年齢とともに変わる女性の性欲

少なからず個人差はあるものの、女性の性欲は年齢によって大きく異なるのが一般的です。
今性欲が強かったり、逆に全くなかったりする場合も、今後変化が訪れる可能性も大いに考えられるでしょう。
現在の年齢と以下の内容を参考に、大まかな性欲の変化を確認してみてはいかがでしょうか。
かつて”男性の性欲のピークは20~30代・女性の性欲のピークは40~50代”という情報が広まり、男女の差からパートナーとの性行為が上手くいかなくなるのではないかと思われていました。
女性が性行為に積極的になった頃には男性が消極的になっており、意見の相違から浮気や不倫に走る人も増える、といった意見も珍しくありません。
しかし近年では、研究の結果”女性の性欲も20~30代にピークを迎える”との情報が主流となりました。
先ほどご紹介した男性ホルモン「テストステロン」の分泌ピークは20~40代、女性ホルモン「エストロゲン」の分泌ピークは20~30代であることから、この時期に性欲が高まるのも自然なことだといえるでしょう。
その後は自然に性欲が減少していき、閉経とともにほとんどなくなるといわれています。
とはいえ、女性の性欲は男性のものとは少し異なり、ホルモンだけでなくそのときの気分や環境によっても大きく異なります。
パートナーが優しい言葉をかけてくれたときや、キスやハグなどのスキンシップをとったときなど、ホルモン分泌に関係のないシーンでも性欲が高まることがあります。
つまり20~30代のピーク時であっても環境が整っていなければ性欲には繋がらず、逆に40代以降であっても環境次第では性欲が続くでしょう。
一般的に、女性ホルモンの分泌が活性化しバランスが崩れがちな思春期や、ホルモンが減る更年期は性欲の波も大きく変化します。
ホルモン量が安定する20~30代の成人期になるまでは、上がったり下がったりする性欲に惑わされず、気持ちを落ち着けて過ごすことが大切です。
性欲が強くなる原因

続いて、女性の性欲が強まるメカニズムをもう少し詳しく見てみましょう。第一に、女性の性欲は生理周期によって大きく変化します。
生理のサイクルを生み出しているのは2種類の女性ホルモンで、これらが交互に分泌されることで月経が起きる仕組みです。
先ほどご紹介した「エストロゲン」は別名卵胞ホルモンと呼ばれ、体が妊娠するための準備を整える役割があります。
一方の「プロゲステロン」は黄体ホルモンと呼ばれ、妊娠を継続するためにさまざまなはたらきを担っています。
月経が終わるとエストロゲンの分泌量が徐々に増え始め、代謝が上がるのと同時に性欲も高まっていきます。
排卵期となる月経後1週間前後を目安に、気分も良くなり生き生きとした毎日を過ごせるでしょう。
エストロゲンの分泌が主流であるため、体が妊娠するための準備を行っており、積極的に性行為がしたくなる時期です。
パートナーとタイミングを合わせるなら、体的にも精神的にも排卵日周辺を狙うと良いでしょう。
排卵日が終わるとエストロゲンが徐々に減少し、代わりにプロゲステロンの分泌が増えていきます。
妊娠に備えて乳腺が発達したり子宮内膜が厚くなったりするのに加え、気分の落ち込みやイライラなど精神的な変化も訪れるでしょう。
特に月経前はこれらの症状が顕著になり、悪化すると「PMS(月経前症候群)」と呼ばれます。
プロゲステロンが分泌されている間は気持ちが不安定になりやすいため、一般的に性欲が落ち着く方が多いでしょう。
性欲が強く悩んでいる方であれば、「ホルモンが分泌されなければ良いのでは」と考えても不思議ではありません。
事実、極度のストレスやダイエットなどの身体的影響が原因でホルモンが正しく分泌されず、生理不順や性欲減少が起こるケースも多く見られます。
しかしこれらは何らかのトラブルを引き起こしやすく、性欲だけがうまく減少してくれるとは限りません。
生理不順によって妊娠しにくくなるなど長期的なトラブルの原因にもなるため、自身でホルモン量を調整しようとするのはやめましょう。
性欲の抑え方

仕事や勉強をしているのに性的なことを考えてしまったり、パートナーが望むよりも多く性行為をしたくなったりと、性欲が強く悩んでいる方も少なくありません。
単にモヤモヤとした気持ちに蓋をするのではなく、他のことに意識を向けるなどして上手に付き合っていくと良いでしょう。
性欲を抑えるのにおすすめの方法の中でも、もっとも手軽に取り入れられるのが「運動」です。
良い気分転換になるだけでなく、男性ホルモンであるテストステロンが筋肉の増強に使われて減少するため、性欲を感じにくくなるといわれています。
運動や筋トレを続けていると見た目にも変化が訪れ、理想のプロポーションを目指せるのも嬉しいポイント。
性欲のコントロールとダイエットが両立でき、まさに一石二鳥の方法といえるでしょう。
また、没頭できるような趣味を見つけてみるのもおすすめです。
手持無沙汰になると性的なことを考えやすくなりますが、頭の中が別のことでいっぱいになっていれば性欲の入る隙がなくなります。
ハンドメイドで一つの作品を完成させてみたり、小説や漫画で物語の世界に入り込んだりと、長時間真剣に取り組める趣味を探してみましょう。
思い切って外出し、スポーツをしたり映画を見たりすることで、性欲よりも満足感が上回ることも多いでしょう。
さらに、性欲は食事内容でもコントロールが可能です。
まずは性欲を抑えて幸福感をアップさせる成分・セロトニンを分泌させるために、「トリプトファン」と呼ばれる栄養素を積極的に摂取しましょう。
豆腐や味噌などの大豆製品や牛乳・バナナなどに多いだけでなく、カツオ・シイタケ・昆布などの出汁が出る食品にも豊富に含まれています。
セロトニンの分泌促進によって精神が安定しやすくなるため、PMSなど生理前のトラブルに悩んでいる方にもおすすめです。
男性ホルモンであるテストステロンの分泌を正しく行うためには、女性ホルモンと似たはたらきをする「イソフラボン」を摂取するのも大切です。
イソフラボンは大豆製品に多く含まれているため、豆腐や味噌などを摂取するとトリプトファンと同時に取り入れられるため効率的です。
テストステロンが多すぎずバランスの良い状態を保てるため、長期的な健康にも繋がるでしょう。
性欲をコントロールして正しく向き合う

性欲は翻弄されすぎても良くないものの、完全になくなれば良いというわけではありません。
自身の生活や体調と性欲がバランス良く共存することで、ストレスのない毎日を過ごせるでしょう。
性欲が強すぎて悩んでいる方の場合、可能であればパートナーと真剣に話をするのが大切です。
女性は精神的に満たされることで性欲をコントロールできるため、単に性行為の回数を増やすだけでなく、キスやハグといったスキンシップをとってみるのもおすすめです。
別々で過ごすプライベートタイムを大切にしながら、普段よりも少し傍で過ごす時間を多くとってみてはいかがでしょうか。
また、パートナーが近くにいない場合や疲れているなどでタイミングが合わない場合などは、セルフプレジャーを上手に取り入れてみましょう。
自分の手で触れるのに抵抗がある方は、セルフプレジャー用に開発されたグッズを使ってみるのもおすすめです。
性行為では幸せホルモンであるオキシトシンが分泌されることで身体的にも精神的にも満足感がありますが、セルフプレジャーは人の目を気にすることなく自分の好きなように行えるのがメリットです。
性行為でなかなかオーガズムに達することがない方も、セルフプレジャーであれば可能な方も多く、性行為とは違った意味での満足感が得られるでしょう。
関連記事:女性の性欲の真実! 年齢ごとの自然な変遷と幸せへのヒント…
性欲の理解を深め、より豊かな日々を
「女性が性欲を感じるなんて恥ずかしい」「性欲のことなんて言い出しにくい」と感じる女性も多いもの。
もちろんデリケートな話題のため周りや自分に配慮が必要ですが、一方で性欲があることは悪いことではなく、誰にでも起こりうる自然なことだと覚えておきましょう。
あなたの周りにいる女性も、口には出さないものの性欲に関する悩みを抱えているかもしれません。
大切なのは自身の性欲を無視せず、正しく向き合うことです。時にはパートナーと話し合いながら、適度に自身の欲求へ応えてあげましょう。
女性は年代や生理周期によっても性欲が大きく異なるため、今の自分がどの位置にいるのかを把握し、性欲についての正しい知識を備えておくことをおすすめします。
性欲への悩みが解消されると、前向きで活き活きとした生活を送れるようになります。まずは自身の性欲を発散するため、運動や食事を含めたさまざまな方法を試してみてはいかがでしょうか。
フェムテックで更年期の悩みを解決!女性の健康革命到来!

近年、仕事をする上での性差は徐々になくなりつつあり、男性であっても女性であっても同じように重要なポストに就いたり昇進を目指したりできるようになりました。
とはいえ、女性ならではの健康課題を完全に無視することはできません。
仕事上ではもちろん、日頃生活する上でも女性特有のトラブルに悩まされている方が多いのではないでしょうか。
月経痛であったり、更年期であったりと人によってトラブルの種類や程度が異なるため、なかなか周りに相談できず抱え込んでしまう方も少なくありません。
今回はそんな女性特有の悩みの中で、年齢を重ねるにつれ気になり始める「更年期」に焦点を当ててみましょう。
女性の健康に寄り添ってくれる「フェムテック」についても、具体的な製品・サービスを挙げながらご紹介します。
フェムテックを通じて一人で抱え込んでいた悩みを解決し、より生き生きとした毎日を目指しましょう。
フェムテックとは?

フェムテック(Femtech)とは、女性(Female)と技術(Technology)を組み合わせて生まれた言葉です。
その名の通り女性のために開発されたテクノロジーを指しており、女性ならではの悩みに寄り添う製品やサービスが多数登録されています。
女性ならではの悩みといっても、その種類や程度は人それぞれ。
単に月経一つとっても、量が多く悩んでいる方もいれば月経痛が生活に影響を及ぼしている方、PMSの症状が強く出て困っている方などさまざまなケースが考えられます。
周りに相談しようと思っても、同じ悩みを抱えている人が見つからず共感してもらえないことも少なくありません。
そんな全ての悩める女性にチェックしてほしいのがフェムテックに登録されている製品やサービスです。
具体的には以下のような悩みに対応しており、自分の体の状態に合った製品やサービスが見つかるでしょう。
- 月経
- 不妊治療
- 出産
- 育児、子育て
- 婦人科系疾患
- 女性向けケアアイテム
- セクシャル・ウェルネス
例えば不妊治療について悩んでいる方がいたとしましょう。
周りの女性は軒並み妊娠・出産を経験しており、その小さなコミュニティ内でマイノリティになってしまうことを心配しています。
出産を経験した女性に不妊治療の大変さを相談しようと思っても、「大変だね」と言ってもらえることはあっても、本当の大変さをイメージするのは難しいでしょう。
こんなときにフェムテック製品やサービスをチェックすると、同じく不妊治療について悩んでいる女性が多くいるのに加え、不妊治療中の女性が使えるカウンセリングや仕事との両立サポートなどさまざまなサービスが見つかります。
フェムテックに登録されている製品やサービスでは、どんな悩みを抱えている女性も決してマイノリティではなく、いわば「当たり前」と考えられています。
悩み自体を解決するためにサポートを受けるのはもちろん、自分が何に悩んでいるのかを知るきっかけにもなるでしょう。
自身が利用するだけでなく、企業が導入することで女性の望まない退職を防ぐことにも繋がります。
今回はさまざまな健康課題の中でも、「更年期」に注目して該当する製品やサービスをご紹介します。
「株式会社YStory」が運営するサービス「JoyHer」は、更年期の女性だけをターゲットにしたサポートアプリです。
京都大学の教授と共同開発を行い、更年期の女性が自身の症状について検索したり、同じような悩みを持っている人を探したりといった使い方が可能です。
専門家によるコラムも多数掲載されているため、これまでに気が付かなかった新しい知識を手に入れられるでしょう。
今日の体調を細かく入力することで自分のパターンをまとめて確認でき、自分でできるセルフケアの方法も細かく探ることができます。
「株式会社ジョコネ。」では、更年期の悩みを抱えながらも仕事にしっかりと取り組みたい女性のための企業です。
更年期が原因でパフォーマンスが半分以下に下がってしまう女性も多い中、当事者である女性にとってはもちろん、企業にとっても相談窓口を設けています。
更年期症状の改善を目指すとともに女性一人ひとりが自信を取り戻し、改善後は再びキャリアを目指せるよう、今後もさまざまなサービスの展開が期待されています。
「株式会社産業経済新聞社」では、オンラインコミュニティ「フェムトーク」を運営し、更年期症状に悩む女性が仲間を見つけるためのサポートを行っています。
例え家族や友人の中で同じ悩みを持つ仲間が見つからなかったとしても、匿名で利用できる掲示板上で話題を共有することで、一人ひとりの悩みを解決するためにみんなで協力できます。
自分でトピックを立てたり、既に立っているトピックに参加したりと、人によってさまざまな使い方ができるのも魅力といえるでしょう。
今回はわずかな製品やサービスをピックアップしてご紹介しました。その他の製品やサービスは、ぜひ一度フェムテックの公式サイトからご確認ください。
女性の健康に対する日本の現状

かつての日本では、女性は妊娠・出産があることから重要なポストに就けなかったり、男性よりも低い賃金で雇われたりするのが当たり前でした。
中には女性であることを理由に面接で落とされるなど、理不尽な思いをしてきた方も少なくないでしょう。
近年は女性であっても人生のほとんどを育児が占めることはなく、育児が終わってから仕事に復帰したり、育児中でも仕事に勤しんだりする方も多いもの。
かつての考え方からアップデートし、女性の働き方について新たに考えることこそが、女性と企業の成長に繋がるでしょう。
女性の社会進出を阻む健康課題の中には、「定期的に来るPMSや月経痛」であったり、「数年間の休業が必要となる出産・育児」であったりと人によってさまざまです。
今回ご紹介している更年期も、頭痛やめまいが起きることもあれば、熱っぽさや動悸が激しくなるホットフラッシュが起こることもあります。
これらすべての症状が出る方もいれば単独の症状に悩む方もいるため、全ての女性をひとくくりに考えるのは良くありません。
また、いわゆる「更年期障害」といわれる症状以外にも、肌の乾燥や生活習慣病の増加、乳がん・子宮体がんなどのリスクにも注意しなければなりません。
これらの悩みが常態化することでうつなどの精神疾患リスクも高まるため、少しでも「普段と違う」と感じたことがあれば専門家に相談しましょう。
これらの症状は、更年期のない男性や症状の軽い女性から見れば大変さが分からず、時には甘えだと思われてしまうことがあります。
企業の中には、未だに体調不良で休む際は診断書の提出が義務付けられているなど、更年期のように病気ではない症状では休みにくい体制が敷かれているところもあります。
有給を使い切って欠勤扱いになってしまったり、欠勤が積み重なって昇給に影響が出たりすることも多いでしょう。
こういった場合、女性はもちろん企業が迅速にフェムテックの製品やサービスをチェックし、女性への対応を見直さなければなりません。
中には法人向けのカウンセリングサービスを展開し、更年期を迎えた女性への対応方法やキャリア育成などの相談にのってくれるものもあるため、必要に応じて導入を検討する必要があるでしょう。
更年期の症状とフェムテックの役割

「更年期」というワードは聞いたことがあっても、具体的にどんな症状が出るのかイメージができない方も多いのではないでしょうか。
これから更年期を迎える40代前後の方々をはじめ、パートナーの健康を意識したい男性の方、女性の健康と職の両立を叶えたい企業役員の方などのために、更年期で考えられる症状の例をご紹介します。
- 神経系の症状:頭痛、めまい、不安感、うつ症状、イライラ、眠れないなど
- 血管系の症状:ほてり、のぼせ、動悸、発汗、息切れ、むくみなど
- 内臓系の症状:吐き気、胃痛、胃もたれ、便秘、下痢、喉の渇きなど
- 運動器官系の症状:肩こり、腰痛、関節痛、末端痛、しびれ、だるさ、失禁など
- 生殖機能系の症状:月経痛、月経異常、性交痛など
上記で挙げただけでも、これだけの種類の症状が更年期の女性を襲うこととなります。
中でも頭痛や吐き気などは多くの方が共感しやすい症状ですが、夜に眠れなくなったり途中で頻繁に起きてしまったりといった睡眠障害やイライラなどの精神症状は周りに伝わりにくいでしょう。
また、更年期特有の症状に「ホットフラッシュ」があります。
これは5分未満の体温上昇と発汗・動悸などが繰り返し引き起こされるものであり、当事者にとっては非常に体力を奪われるものですが、周りからは「単に暑がりなだけ」と思われてしまいがちです。
ホットフラッシュが原因で休みをもらいたいと申し出ても、なかなかスピーディには受理されないでしょう。
もちろん他の症状を挙げても辛いものばかりで、一つであればまだしもさまざまな症状が同時に起こる可能性も大いにあります。
このような耐え難い症状の数々は、決して自分だけでなく、多くの女性が悩んでいるものです。
フェムテックの製品やサービスから自分に合ったものを選択し、更年期症状による辛さを少しでも軽減できるよう工夫しましょう。
「株式会社よりそる」が運営する更年期アプリ「よりそる」は、スマートフォン一つでどこからでも利用できるサービスです。
女性用とカップル用の2種類から選択でき、カウンセリング・座談会・会員同士のチャットなどを利用して自分の症状に合った対策を見つけることができます。
会員向けのデジタルコンテンツも充実しており、病院の探し方から自分でできるセルフケアの方法までしっかりと寄り添ってもらえるでしょう。
「fermata株式会社」が運営するネットショップ「fermata」では、更年期を迎えた女性が密かに使いたいと願っている製品が多数展開されています。
周りに相談しにくかったり、実店舗で買うのが恥ずかしかったりする製品でも、製品画像や説明文を見れば手に取るように詳細が分かるでしょう。
多くなったり少なくなったりする月経に対応しやすい月経カップや、動いた瞬間に漏れてしまう切ない失禁に対応しやすい吸水ショーツ、さらにはホルモンの影響で日々変動する性欲に対応してくれるセルフプレジャーアイテムなど、希望の製品が見つかりやすいでしょう。
フェムテックへの期待

一人で我慢することが普通になってしまった女性たちにとって、急に「フェムテック」といわれてもどうすべきか迷ってしまうのではないでしょうか。
女性たちが正しくフェムテックの考えを取り入れるのと同時に、社会全体がフェムテックを理解することで、女性の社会進出がよりスムーズに進むでしょう。
単にフェムテックといわれる製品やサービスを次から次へと取り入れるのではなく、医学的根拠が伴った信憑性の高い情報を選ぶことが大切です。
また、最後には女性が自分で正しい情報を選べるよう、専門家によるカウンセリングなど正しい自己判断へナビゲートしてもらえるサービスも重要です。
数ある製品やサービスの中から”自力で”正しいものを選ぶ力をつけるため、一部だけの情報に惑わされず、多方面から情報を仕入れることが大切です。
2020年代に入ったとはいえ、女性の健康に対する意識や対応はまだまだ完全とはいえません。
女性は自身の体調をしっかりと認識できるよう、パートナーや企業は女性を正しく気遣えるよう、まずは「フェムテック」というワードを覚えておくことが大切です。
いずれは男性・女性にかかわらず体調を考慮し休みのとりやすい企業が増えたり、女性が自身の体調不良を包み隠さずに伝えられたりといった未来を社会全体で目指し、本来の意味での「男女平等」が期待されています。
関連記事:メンタルがやばいサインとは?メンタルの不調で休むのは甘え?
まとめ
かつての更年期症状は、女性が晩年期に迎えるものであり、その後の人生は寿命を迎えるためのものとして考えられていました。
一方現在はというと、更年期は女性の人生で折り返し地点に当たり、その後も長く生きていくこととなります。
つまり更年期をより過ごしやすいものにすることこそ、人生の後半が充実するポイントとなるでしょう。
フェムテックの考え方は、今更年期に悩んでいる女性はもちろん、男性やこれから更年期を迎える若い世代の女性にとっても決して無視できないものです。
正しい知識と対処法や関わり方を身に着けることこそが、過ごしやすい社会への第一歩となるでしょう。
アメリカのメディテーションコーチに聞く、初心者のあなたが始めやすいメディテーションとメディテーションを習慣化する秘訣~ブレンダ氏インタビュー

アメリカの有名人などが取り入れていることで、日本でも広がってきた「メディテーション」。あなたはメディテーションをしていますか?またはメディテーションに興味はあるけれど、やり方がわからないと感じていますか?
ハミングは今回、アメリカのメディテーションコーチであるブレンダさんに、メディテーションをすることでどういった効果が得られるのか、そして気軽にメディテーションを始められる方法とブレンダ氏が特におすすめする「書くメディテーション」について聞きました。
メディテーションを継続していく方法など、すでにメディテーションをしているあなたにも参考になる情報がもりだくさん。メディテーションを続けていったことで、人生全般に心の余裕が生まれたというブレンダ氏。いったいどのように日々の生活にメディテーションを上手に取り入れていったのでしょう。
−− まずはメディテーションとは何かについて教えてください。そして、あなたがメディテーションを行うとき、どんな効果を期待して行っていますか?
例を挙げて説明しましょう。メディテーションは、スポーツととても似ていると言えるでしょう。スポーツとひとことで言っても様々なスポーツがあるように、メディテーションにも様々な手法やスタイルがあります。約80種類のメディテーションがあると言われていますが、私は個人的にはもっと多くあると思います。
メディテーションをすることで、私たちは、忙しい日々でも、熟考するための時間と空間をつくることができるのです。
メディテーションをすることで自分自身とより親密な関係を持つことができるのです。つまり、自分の思考をよりよく理解できるようになるということです。メディテーションというと、人が座っている姿を思い浮かべると思いますが、人は頭の中で多くの思考が次から次へと出ては消えていく、それが普通の生き物ですから、実はじっと座っているというのは心地がよい状態ではないのです。
でも、スポーツで体を鍛えるのと同じように、メディテーションをすることで、自分の思考に気づき自分自身との密接な関係を築くことができるんです。
ーー メディテーションはなんだか難しそうだと感じる人が、もっと気軽にメディテーションを始められる方法はありますか?
メディテーションという、一見、専門的にも聞こえるこの言葉を使わないほうがいいかもしれませんね。メディテーションではなくて、「自分のための静かな時間を少し作る」という風に考えてみるのはどうでしょう。たった5分間だけでいいので、音楽やスマートフォンのスイッチをオフにして、自分の部屋を見回してみてください。または、静かな部屋に座って、あなたのお気に入り雑誌の写真を見て、あなたの頭にどんな思考が出てくるか待ってみましょう。まずは、こんなことから始めてみてはいかがでしょう。
もうひとつの私のおススメはジャーナリングです。手で紙に書くことで、自分が心の中で感じていることをよりよく理解できるようになります。このジャーナリングも自分の思考を感じるための行為なので、一種のメディテーションと言えるでしょう。
よく写真でみるような、大自然を背景にして流れる川の横にある岩の上に座ってメディテーションしている姿はとてもかっこよく見えるかもしれません。でも、こうやって集中しているように見える人の頭の中をのぞくと、今晩の夕食メニューや食料品の買い物リストのことを考えているということがよくあるものです。自分の今感じていることに全神経を集中させることは簡単ではありません。ですから、ジャーナリングのように自分の考えを書き出すことで、自身の思考により集中できるでしょう。
集中するのがどうしても難しいという場合は、ガイド付きメディテーションを選ぶといいでしょう。聞いているだけで、次は何をすればいいのか教えてくれるので、メディテーションが初めての人にはとっかかがつかめるでしょう。他の手法としては、呼吸に意識を向ける方法もあります。雑念が浮かんできたら、呼吸に意識を向けましょう。
他には、『ヴェーダメディテーション』という手法もあります。これは、雑念が出てきたらマントラを唱える方法です。自分の中から出てくる思考から逃げても結局またその思考は戻ってきますので意味がありません。ですから、私はこのメディテーションをよく行います。メディテーションの最初に、まず自分の思考を観察して理解することから始める、そんなメディテーションです。
ーー ジャーナリングについてもう少しくわしく教えてください。あなたはどういうきっかけでジャーナリングを始めたのですか?
ジャーナリングは「書くメディテーション」とも言えるでしょう。なぜなら、ジャーナリングを行うことは、自分の感じたことや体験を、しっかりと受け止める場所を作るようなものだからです。人生のさまざまな場面でどうしたら良いかわからなくなった時、ジャーナリングをすることで、自分が次のステップとして何をしたらよいかのヒントに近づくことができるでしょう。
あなたの意識を導いてくれる役割を果たすのです。個人的にも、私はこの、書くメディテーションがとても好きです。座ってメディテーションをしていると、出てくる思考にどう対処したらいいかわからなくなり、コントロールできなくなることがあります。でも、ジャーナリングならそんな時は、ノートをいったん閉じて思考を休ませることができます。
または、誰かに手紙を書くふりをするというのも良いでしょう。例えば、あなたが何か悩みを抱えていたら、なぜ悩んでいるのかについて、架空の相手に対してそれを説明する手紙を書いてみるんです。こうすることで、自分の悩みを第三者に知ってもらうために客観的に見ることができますし、偏りのない見方をすることで、この課題が自分にどんなメッセージを送っているのかにも気づくことができるでしょう。
ーー あなたがヨガを始めたのは、あなたの職場でヨガのレッスンがきっかけとのことですが、会社が社員のためにヨガやメディテーションなどの活動を取り入れることは重要だと考えますか?
ヨガには昔から興味があったのですがやったことはありませんでした。でも、会社の同僚がヨガをやっていると聞いて、私もやってみようと勇気をもらったんです。その後、私自身がヨガの先生になり、メディテーションを学ぶようになり、結果的にヨガが私の人生を大きく変えることになりました。ですから会社は、社員がもっと人生を楽しめるようにサポートするという意味でも、ヨガを社員に提供するべきだと思います。
ーー 新しいことに挑戦することへの恐れとどのように向き合っていますか?
私自身は、新しいことに挑戦することはワクワクすることだと思います。人が未知の世界に足を踏み入れることを怖いと感じる理由は、私たちは将来起きることをコントロールできないと感じているからでしょう。将来、何が起こるかなんて誰にもわからないですよね。だからまずは、その事実を受け入れることが大切です。
メディテーションを定期的に続けていくと、金銭的なものから自分を解き放つことができるようになります。そうすると、あなた自身と密接につながっているという感覚が芽生え、人生全般に対してもっと余裕が生まれるでしょう。例えば、もし何かに失敗したとしても、それを失敗ととらえるのではなく、次回にうまくやるための学びの場だったと考えられるようになるでしょう。
ーー メディテーションを学んで、何か大きな変化はありましたか?
ヨガを始める前の私は、とても不安で自意識過剰、いつもストレスを抱えていました。今でもストレスを全く感じないわけではありませんが、以前の自分と比べると劇的に変わったと思います。当時は、健全ではない人間関係をずるずるとひきづっていましたが、メディテーションを始めてからは、この状況を変えようと行動できるようになり、人間としてももっと成長したいと思うようになり、新しいなことにもどんどん挑戦するようになりました。
たった数回のメディテーションで、大きな効果や変化を望む人が多いですが、実際には、そういった変化を得るためには長い時間がかかるものです。
ーー メディテーションをしていて、心から気持ちいいと感じられるようになるまで、どのくらいかかりましたか?
私の場合は1~2年くらいです。日々の習慣にするために、歯磨きなど毎日していることの合間にメディテーションをするようにしています。ただ、メディテーションからあなたが感じられる変化は、ごくささやかなものであるということも理解してほしいのです。明らかにわかるような大きな変化が一瞬で現われる、ということではないんです。友人と食事をしているときに洞察力が高まったり、過剰な反応をしなくなったりと、自分の中にそういったしなやかさが少しずつ生まれるんです。
ーー メディテーションを続けたいのにサボってしまいがちな人に、どんなアドバイスをしますか?
さきほど、歯磨きの例をあげましたが、普段やっていることの合間にやってみるのはどうでしょうか。朝いつもトイレに行くのなら、トイレでいつもより数分長く座って呼吸に集中してみるというのはどうでしょう。メディテーションについてすぐに理解しようとする必要もありません。毎日のルーティンにどう組み入れるかが大切です。
また、静かな場所でメディテーションする必要もありません。もちろんそれが理想ではありますが、走り回る子どもや、おしゃべりしている同僚が近くにいてもメディテーションはできます。今あなたのいる環境で、メディテーションできる時間を見つけることが大切なんです。
ーー メディテーションを始めたいけれど、ちょっと怖いなと不安に思っている人にアドバイスはありますか?
好奇心を持つことがとても大切だと思います。メディテーションが何かわからなくても、自分の周りで起きていることに好奇心を持ち、観察し、それを受け止めてみましょう。今この瞬間に集中してみてください。メディテーションにはいろいろな種類があるので、自分がこれならできそうと感じるものからまずはトライしてみてください。メディテーションに関する本を手に取るとか、メディテーションの先生を見つけるとか、あなたの次のステップが何であれ、まずは好奇心を持つことからスタートしてみてはいかがでしょう。
プロフィール

ブレンダ・ウマナは、ヨガ、マインドフルネス、パブリック・ヘルスの専門家としてキャリアを築いてきたウェルネス提唱者です。コロンビア大学で公衆衛生の修士号を取得した彼女の今後の目標は、自分の知識やプラクティスを共有し、誰にとっても親しみやすくすることです。
彼女はAmazonで「Meditation on Paper」というタイトルの本をリリースしました。
「ごきげん」が人生を変える!更年期のホリスティックケア 【ホリスティックビューティ協会・岸紅子さんインタビュー】
「最近、急に汗をかくようになった」
「ちょっとしたことでイライラしてしまう」
「ドライアイが酷くなったかも」
ホルモンバランスが急激に変化する更年期。50歳前後になると多くの女性が、様々な心身の不調に悩まされる時期を迎えます。
更年期を快適に過ごすためには、この時期の変化を理解し、備えることが大切です。
今回、更年期のホリスティックケアについてお話を伺ったのは、NPO法人日本ホリスティックビューティ協会代表理事の岸紅子さん。
ホリスティックとは何なのか、更年期に悩む方が今からできる対処法、そして更年期を迎える前の方が心がけるべきこと、岸さんがごきげんでいるために大切にしていることなどを教えていただきました。
人生をごきげんに生きるためのヒントを探してみてください。
ホリスティックに生きることが幸せの鍵?!
—— 岸さんが考える「ホリスティック」とはどのような意味でしょうか?
岸さん:ホリスティックとは、その人全体を意味します。人の魅力は肌が綺麗とか、スタイルが良いとか、目が大きいとか、部分的な美しさではなく、「スガタ」「カラダ」「ココロ」の相乗により成りたつものなのです。
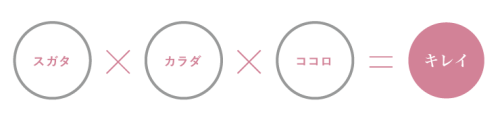
さらに、私たちは地球環境や宇宙とも繋がっています。全ては繋がり合い、循環しているシステムの中にある。それを理解することがホリスティックに生きることだと考えています。
—— 岸さんは、日々の生活の中でどのような時にホリスティックを感じるのでしょうか。
岸さん:ホリスティックに生きるということは、一つ一つの行動や物事に「これがホリスティックである」とラベルを貼る必要はありません。大切なのは、自分と周りの繋がりを常に意識し、感謝の気持ちを持って日常を送ること。
例えば、私たちが毎日当たり前のようにしている呼吸も、酸素があるからこそできるのです。その酸素を作ってくれているのは、森林やサンゴなどの生物たち。また、毎日いただく食事も、土壌微生物が土を肥やしてくれて、植物が育ち、農家の方々が丹精込めて育ててくれるからこそ食卓に並びます。私たちは決して自分一人で生きているわけではありません。
さらに、自分自身もこの大きなエコシステムの中の欠かせないピースの一つであり、この世界の尊さを次世代に繋いでいく役目があると考えています。
このような認識を持つことで、日々の何気ない行動にも感謝の気持ちを持てるようになり、自分自身もかけがえのない存在だと実感できるのです。
—— 岸さんが、ホリスティックを意識するようになったきっかけを教えてください。
岸さん:きっかけはいくつかありますが、大きなものは自分の病気と子どものアレルギーです。
私は27歳の時に喘息を発症し、その後も子宮内膜症など様々な病気を経験しました。働き盛りの女性が一生懸命働いているだけなのに、次々と病気になっていく。これっておかしいと思ったんです。
色々と調べるうちにわかったのは、私たちが何気なく口にしている食品の裏側や、便利な生活の陰で起きている環境問題など。知らないと避けられないこと、知っていれば防げたことがたくさんあったと気がついたのです。
それと同時に生きていること自体が奇跡であることを実感しました。
—— ご自身の病気やお子様のアレルギーを経験される前は、どのような生活をされていたのでしょうか?
岸さん:病気になった時は仕事を頑張っていた時期だけれど、特段不摂生をしていたわけではありませんでした。ただ、振り返って思うのは、ないものばかりに目を向けて、たくさんの「〜せねばならない」に苦しんでいたなと。
良い学校にいかなければいけない、一生懸命働いてお金を稼がなければいけない、辛いことをすれば報われるなどの固定概念があったのだと思います。
そういった忙しない日々を過ごしていると、自分の周りにある小さな幸せに気が付けないんですよね。
—— ホリスティックを意識することで、小さな幸せに気がつき、ココロもカラダも変化していったのですね。
自分の周りの「ある」ものに目を向けられるようになったことで、物事を俯瞰して見られるようになり、仕事も子育ても肩肘を張らずにできるようになりました。
いつかは死んでしまうのだから、ごきげんに生きたい。そういったマインドで過ごせるようになりました。
カラダの仕組みを知ることは自分を大切にする一歩

—— ホリスティックを意識するために、どのようなことからスタートしたのでしょうか。
岸さん:まず、臓器や細胞など、カラダの仕組みを理解することから始めました。
「なぜ目が見えるのか」「匂いが嗅げるのはどういうことなのか」「食べたものがどのように消化され、排出されるのか」など、一つ一つの身体現象を学ぶことで、私たちの体がいかに素晴らしいのかがわかってきます。
例えば、手を上げるというような単純な動作も、ロボットで再現しようとすると膨大な電力を必要とするんですよ。
カラダの素晴らしさを知ることで、自然と自分自身をリスペクトする気持ちが芽生えてくるのです。そこから少しずつ、自分を認め、大切にできるようになりました。
ホリスティックビューティー協会の生徒さんたちを見ていても、カラダの仕組みを理解することで自己革命が起きているのを感じています。
——生徒さんは、どのような悩みを抱えて参加される方が多いのですか。
岸さん:若い頃と比べて体調が変わってきたと感じている方や、妊活に取り組んでいる方、妊娠中の方、更年期を目前に不安を抱えている方などが多いです。
ホリスティックビューティー協会で学ぶことで、生理と向き合いながら仕事でパフォーマンスを保つ方法や、妊娠しやすい体作り、自然育児について、更年期を心地よく過ごすためにできること……、誰か1人でも知っていると家族みんなの役に立てるような知識をお伝えしています。
「ごきげん」でいることで更年期が変化する?!
——生徒さんの中にも更年期前後の方がいらっしゃるのですね。更年期は何歳くらいから始まるのでしょうか?
岸さん:更年期の始まる年齢には個人差がありますが、一般的には45歳〜55歳ぐらいまでの期間が「更年期」と呼ばれています。平均すると50歳くらいです。卵巣の機能が徐々に衰えていく、いわば卵巣の「卒業年齢」とも言えます。
更年期になると、エストロゲンという女性ホルモンが急激に減少していくことが原因で、心身に様々な不調を引き起こすことがあるんです。
——どのような症状に悩まれる方が多いのでしょうか?
岸さん:更年期によく見られる症状として、ホットフラッシュがあります。急に体が熱くなって、それが引くと今度は寒くなったりするんです。
また、イライラしたり、閉経に向けて生理が不安定になったり、肌はもちろん、目や口の中、デリケートゾーンなどが乾燥するドライシンドロームも多いです。デリケートゾーンが乾燥することで性生活に悩む方もいます。中には、帯状疱疹に苦しむ方もいるんです。
——いろいろな不調が現れるのですね。更年期に悩んでいる方が今から取り入れられるケアについて教えて欲しいです。
岸さん:まず伝えたいのは、更年期は辛いかもしれませんが、ある程度期間が決まっているということです。果てしない地獄の苦しみではありません。
更年期の症状を和らげるのに、アロマ、漢方、鍼灸はとても力になってくれます。ホルモン作用のあるアロマもあるので、取り入れてみるのも良いでしょう。
(※)乳がんなどの病歴がある方は、ホルモン作用のあるアロマなどについて、医師に相談してから使用を検討しましょう。
また、急激に減少する女性ホルモンを、オキシトシンやセロトニンなどの他のホルモンで補ってあげることも大切です。
例えば、オキシトシンは、ハグをしたり、ペットを撫でたり、推し活をしたりすることで分泌が促進されます。好きなドラマを見てときめくのもおすすめです。
セロトニンを増やすなら、運動が効果的です。朝しっかり起きて、太陽の光を浴びながら体を動かすのが良いでしょう。
そして、自分でできるケアとしては、デリケートゾーンケア、いわゆるフェムケアもぜひ取り入れていただきたいです。
——『フェムケア』、最近よく耳にします。デリケートゾーンをケアすることでどんなメリットがあるのでしょうか?
岸さん:まず、フェムケアを行うことで、デリケートゾーン自体のプルプル感やツヤ感を実感できるでしょう。また、女性ホルモンの分泌を促すことで、全身の潤いや肌の弾力、ハリにも好影響を与えます。
そしてもう一つ、フェムケアは骨盤底筋を鍛える効果もあります。骨盤底筋は、更年期以降の女性の健康を大きく左右する筋肉なんです。
骨盤底筋が衰えてくると、臓器脱や尿漏れなどが起こりやすくなります。実際、70代以降の日本人女性の一番多い手術が、臓器脱を戻す手術だと言われているのです。尿漏れが原因で、オムツ生活を余儀なくされて自尊心が傷付いたり、匂いが気になって外出を控えるようになったり。家にこもりがちになることで認知症のリスクも上がると言われているんです。
そのため、フェムケアは更年期以降の健康的な生活を送るための土台作りにも繋がります。
——更年期に悩む方向けのケアについてお聞きしましたが、これから更年期を迎える方が今からやっておくべきことはありますか?
岸さん:若いうちから自分なりのごきげんの作り方を見つけておくことが、更年期を上手に乗り越えるコツだと私は考えています。
というのも、ごきげんでいることで、セロトニンやオキシトシンが分泌されるからです。
楽しいことをしたり、夢中になれることに打ち込んだり、人と心地よい関係性を築いたり。そういった日々の積み重ねが、未来の自分への贈り物になるはずです。
心地よい生活は自分で創り出す

——岸さんは自分がごきげんでいるために、日々やっていることはありますか?
岸さん:私は読書が好きなので、本を読む時間を大切にしています。
また、今は東京と山梨の2拠点生活をしているので、山梨では自然と触れ合ったり、畑で野菜を育てるのも楽しみの一つです。やっぱり自然に触れると、心がワクワクして、リフレッシュできますね。
仕事に関しては、好きな人と働くこと、ワクワクする仕事をすることを心がけています。
残りの人生はそんなに長くないと思っているので、何かに耐えて過ごしたくはない。心地よい生活を自分で創っていきたいと思っています。
——好きな人と働く。自分のワクワクすることをする。すごく素敵ですね。とはいえ、世の中には会社勤めで自分に選択権がなく、職場に嫌な人がいたり、やりたくない仕事をやらなければいけなかったりする方が大半なのかなと。現状に不満を抱えている人たちが自分をごきげんにするためにできることは何だと思いますか?
岸さん:まず理解すべきは、今の状況は自分で選択しているということです。本当に嫌なのであれば、環境を変えることもできるはず。何かしらの理由で今の環境から離れられないのであれば、状況を少しでも良くするためにできることを考えるのが大切なのではないでしょうか。
そのためにも、運動をしたり、マインドセットを整えたりすることが重要です。瞑想やヨガで自分自身と向き合う時間を持つのも良いですし、書道のように集中できる時間を持つのも効果的だと思います。
日々忙しいからこそ、自分のための時間を意識的に作ることが大切です。
そして、もう一つのおすすめは断食です。
断食は、体内の老廃物を排出し、細胞の修復を促進してくれるんです。セロトニンの分泌量も高まるので、更年期の女性にもおすすめですよ。
断食明けにおかゆを食べる時は、本当に幸せを実感できます。断食をすることで、デトックスをしながら日常のありがたみを再認識できるでしょう。
私は半年に1回のペースで、3日間の断食をするようにしています。定期的に断食をすることで、心身ともにリフレッシュできますよ。
すべての女性が「ごきげん」に生きられる世界を作りたい
——最後に、ホリスティックケアを取り入れることで岸さんが目指していることについて教えてください。
岸さん:私は、すべての女性がごきげんに生きられる世界を作りたいと思っています。歳を重ねても、健康でQOLを下げずに、ごきげんに暮らせたら幸せですよね。
自分のカラダを知ること、周りとの繋がりや循環を理解すること、つまりはホリスティックな生活を送ることで、それが叶うのだと伝えていきたいんです。
実は、私たちのカラダは借り物なんです。魂が宿る入れ物みたいなもので、神様から預かっているものだと私は考えています。だからこそ、なるべく良い状態を保ちながら、長めに借りられたらラッキーだなって。その間にいろんな経験や体験をするのが人生です。
いつかは役目を終えて、大切に使わせていただいたカラダをお返しする時が来ます。そうしたら、このカラダは地球に還るんですよ。タンパク質や炭素、酸素、水素、窒素など、様々な元素に分解されて、また次の命の一部になっていく。
つまり、自分のカラダを大切にすることは、巡り巡って地球全体を大切にすることに繋がります。
そんな壮大な循環の中で、ごきげんに暮らす人を増やすお手伝いができたら、これほど嬉しいことはありません。
プロフィール

岸 紅子(Kishi Beniko )/ ウェルネスプロデューサー
NPO法人日本ホリスティックビューティ協会代表理事
環境省「つなげよう、支えよう森里川海」アンバサダー
サステナブルコスメアワード審査員長
自身や家族の闘病経験をもとに、2006年にNPO法人日本ホリスティックビューティ協会(HBA)を設立。多数の美容・健康・医療関係者とともに女性の心と体のセルフケアの普及につとめ、資格検定や人材育成を行う。また、自らも自然治癒力や免疫力を引き出すためのウェルネス講座を幅広く実施。
環境アクティビストとしても、ライフスタイルを通じた人にも地球にも優しい循環アクションを多く提言している。
パーマカルチャーデザイナー、発酵食スペシャリスト、味噌ソムリエの一面も持つ。
NPO法人日本ホリスティックビューティ協会(HBA)の詳細はこちら
<岸さんがおすすめするフェムケアアイテム>
フェミニン メディソープ/Pubicare organic
https://takakura.co.jp/products/1370/
フェミニンミスト/明日 わたしは 柿の木にのぼる
https://store.ashita-kaki.com/products/002-1
デリケートゾーン保湿オイル/ヴァージノル®︎
エプソムソルトでバスタイムにスキンケア|おすすめの商品を紹介

お風呂が好きな方ならば、誰もが一度は「入浴剤」を入れたことがあるのではないでしょうか。
体を温めたり、お気に入りの香りに包まれたりと、素敵な製品がたくさん販売されています。
そんな入浴剤好きの方にぜひ使ってほしいのが「エプソムソルト」です。
単なる入浴剤とは異なり、さまざまな効果が期待できる優れもの。毎日の入浴時間がより有意義なものになるはずです。
今回はそんなエプソムソルトの詳しい効果についてご紹介しながら、効果があるといわれる根拠や注意点などを併せてみていきましょう。
エプソムソルトの効果とは

エプソムソルトとは、その名の通りイギリスの「エプソム」地方で産出された粒子のことです。
厳密にいえば塩ではなく「硫酸マグネシウム」ですが、海水に含まれており、見た目が塩にそっくりなことからその名が付きました。
発見されたのは約500年も前であり、当時から現地の人々の健康を支えてきた一品です。
そんなエプソムソルト、実は単に体を温めるだけでなく、さまざまな効果が期待されています。
数十分の入浴で複数の効果が一度に期待できるとあれば、多くの人が試してみたくなるのではないでしょうか。
デトックス効果
エプソムソルトは海に多く含まれる、ミネラルの一種・硫酸マグネシウムでできています。
硫酸マグネシウムには温浴効果があり、通常のお湯に入るときに比べて体が芯から温まりやすいのがポイント。
硫酸マグネシウムが溶けたお湯は浸透圧が変化し、体内の水分が汗となって排出されていきます。
普段エアコンのついた室内にいることが多ければ多いほど、汗をかく機会が少なくなり、体の新陳代謝が上手くはたらかなくなります。
細胞が新しく生まれるのを阻んでしまい、ターンオーバーが乱れ、肌トラブルなどさまざまな影響を及ぼすでしょう。
定期的に入浴で汗をかくことは、体内のサイクルを正常化し、老廃物を排出したり新たな細胞を生み出したりすることに必要不可欠なのです。
むくみの解消
エプソムソルトに炭酸ガスを組み合わせた製品を入浴時に使うと、炭酸ガスが血管を広げ、硫酸マグネシウムが温めることで血行が促進されるといわれています。
血流が滞ってむくんだ状態のふくらはぎなども、じっくりと温めることで改善されやすいでしょう。
お湯の中でできるマッサージなどを組み合わせれば、より一層むくみ解消に役立ちます。
1日立ちっぱなしや歩きっぱなしでむくんだ脚は、そのままにしてしまうと翌日さらなる疲れを生んでしまいます。
日々の積み重ねで改善できなくなる前に、入浴時のむくみ対策が重要といえるでしょう。
美肌効果
ほとんどの人が知らない硫酸マグネシウムの特徴として挙げられるのが「経皮吸収される」という点です。
肌に吸収された硫酸マグネシウムは「アシルセラミド」という成分の生成をサポートする役割を担っています。
このアシルセラミドは水分を保持するセラミドとしての役割はもちろん、バリア機能を高め、乾燥や摩擦・紫外線などのダメージから肌を守ってくれるのが特徴です。
シミやシワ・ニキビなど、どんな肌トラブルであっても大切なのは「強固な土台を作ること」です。
セラミドによって作られた強い肌の土台は、さまざまな肌トラブルを防ぎ、健康な肌への第一歩となるでしょう。
必要に応じて医薬品や化粧品で補いながらも、基本となるセラミド補給は忘れずに行うことが大切です。
筋肉痛の軽減とストレス解消
マグネシウムのもつ抗炎症作用は、運動による筋肉痛を和らげ、翌日のパフォーマンス改善に役立つといわれています。
既に痛みが出ている場合はもちろん、過度な運動をした日の入浴にエプソムソルトを使えば、明日明後日の筋肉痛を防ぐことにも繋がるでしょう。
また、体の芯から温まることで、ストレスの原因となるホルモン「コルチゾール」が減少するという報告があります。
エプソムソルトによって効率的に温まれば、忙しく短時間のみの入浴で済ませがちな方でもストレスが解消されやすいでしょう。
抗炎症作用によって肩こりや腰痛が和らげば、日頃感じる小さなストレスを防げるのも魅力的なポイントです。
睡眠の質の向上
日中一生懸命活動し昂った神経は、マグネシウムのはたらきでしっかりと鎮めてあげましょう。
ぬるめのお湯にエプソムソルトを入れて浸かることで、副交感神経が優位になり、眠りにつきやすくなります。
一度眠った後も起きにくくなり、気持ちの良い状態で朝を迎えられるでしょう。
スムーズに眠りに入るためには、温まった体から次第に熱が逃げ、体温が下がる過程が必要です。
となれば、眠る前にしっかりと体を温め、逃げるべき熱を蓄えておかなければなりません。
眠る1~2時間前までに入浴を済ませ、理想のタイミングで眠れるよう工夫してみてはいかがでしょうか。
運動パフォーマンスの向上と回復促進
エプソムソルトを入れたお風呂で筋肉の凝りや痛みを軽減することで、翌日のパフォーマンス向上につながります。
筋機能や神経機能の回復を手助けしてくれるため、毎日のようにトレーニングを行っている方や、明日に疲労を持ち越したくない方にもおすすめです。
エプソムソルトの科学的根拠は?

ここまでご紹介した内容を見ると、エプソムソルトがまるで薬のように優れた物質であるかのように思えます。
良い点が多数挙げられる一方、本当に効果があるのかと疑問視する声があっても不思議ではないでしょう。
エプソムソルトのもつはたらきについては、過去にバーミンガム大学を始めさまざまな論文が提出されています。
エプソムソルトが実際に経皮から吸収されるのか、また筋肉の痛みや疲労を軽減するはたらきがあるのかなど、それぞれの効果について説明されています。
しかし、現在の日本でエプソムソルトは「化粧品」として販売されています。
つまり、医薬品や医薬部外品とは異なり、現状のトラブルを改善する力は認められていないということ。
今後起こりうるトラブルを予防したり、現状を維持したりするための製品だと定義されているのです。
そのため、エプソムソルトの効果として紹介されているものは、いずれも個人差があることを覚えておかなければなりません。
全ての人にまったく同じ効果が現れることはないため、継続しながら様子を見たり、さまざまな製品を試したりすることが大切です。
関連記事:頭も身体も心も目を覚ます⁈冷たい水風呂でメンタルヘルスが改善!
エプソムソルトの注意点は?

さまざまな嬉しい効果をもつエプソムソルトですが、使用する際はいくつかの注意点を確認しておかなければなりません。
正しい使用方法を守り、悪い影響が出ないように工夫しながら使いましょう。
入浴時間の制限
ぬるめのお湯に30分から1時間程度ゆっくりと浸かる方も多いですが、エプソムソルトを入れた場合は長くても20分程度に留めるのが理想的です。
普段よりも発汗作用が促進されているため、長時間の入浴は体への負担になりかねません。
10分から20分を目安に、ダラダラと入り続けないよう注意しましょう。
飲酒後の使用禁止
エプソムソルトの有無にかかわらず、飲酒後の入浴は好ましくありません。
血行が良い状態でさらに体を温めることになるため、アルコールが一気に体内を巡り、酔いが強く出てしまうでしょう。
エプソムソルトの血行促進作用がはたらけば、危険な状態になることも考えられます。
また、アルコールが体内を巡るだけでなく、心臓が過剰にはたらくことで発作を起こしやすくなります。
体内の血流が上がって脳に血がいかなくなると、貧血を起こして転倒し、頭を強打する可能性もゼロではありません。
入浴前の飲酒は微量であっても避け、入浴後しばらくしてから楽しむのがおすすめです。
使用期限の確認
一般的なエプソムソルトは、使用期限が3年前後に設定されているものが多く、通常の入浴剤に比べ期間が長いのが特徴です。
期間を空けて使う場合は特に、使用期限が切れていないか確認してから使いましょう。
仮に使用期限が切れたエプソムソルトを使っても、ただちに影響があるわけではありません。
とはいえ、肌トラブルの原因となることも考えられるため、肌が弱い方やアレルギーを持っている方などは特に注意が必要です。
アレルギー反応に注意
具体的にエプソムソルトがアレルギー源となることはないものの、季節の変わり目でかゆみが出たり、アトピーが悪化したりといった可能性もゼロではありません。
特に初めて使う場合は、肌に異変がないか確認しながら行いましょう。
二の腕の内側などの柔らかい部分を使って、パッチテストを行ってから使うのも大切です。
溶け残りの確認
エプソムソルトは通常サラサラとした質感ですが、時として団子状に固まってしまうことがあります。
品質に問題はなく、お湯に入れればすぐに溶けることがほとんどですが、稀にお湯が少ない場合などは溶け残りが出る可能性もあるでしょう。
溶け残りがある湯船にそのまま入ると、エプソムソルトが大量に肌に触れ、思わぬトラブルを生む可能性があります。
しっかりと溶けて粒が残っていないことを確認してから入浴することが大切です。
関連記事:アロマテラピーのやり方や効果とは|おすすめのアロマディフューザーを紹介!
エプソムソルトの選び方

続いて、実際にエプソムソルトを選ぶときに注目したいポイントを4つご紹介します。
エプソムソルトといってもその種類はさまざまで、豊富な製品から一つを選ぶ必要があります。製品の特徴を見極め、使いやすい一品を選びましょう。
内容量で選ぶ
エプソムソルトの中には、大容量タイプや個包装タイプなどさまざまな製品が登場しています。
毎日欠かさず使いたい方は大容量タイプを、なるべく品質を保ちながら気分に合わせて使いたい方は個包装タイプを選ぶと良いでしょう。
他の入浴剤をいくつか揃え、今日はどれにしようか悩みながら決めるのもおすすめです。
香りで選ぶ
無香料のイメージが強いエプソムソルトですが、さまざまな香りの製品が発売されており、見た目にも可愛らしいため迷ってしまいがちです。
ローズやラベンダーといったフローラル系の香りもあれば、ミントやレモンなどの爽やかな香りのものもあるため、好みの一品が見つかりやすいでしょう。
気分や季節などさまざまなシーンに合わせて選べるよう、いくつかの種類を揃えておくと便利です。
成分で選ぶ
単にエプソムソルトのみを使った製品もあれば、香りや色を付けるために添加物を使用しているものもあり、どれが良いとは一概にはいえません。
純粋なエプソムソルトを使いたいのか、香りや色を含めてリラックスしながら使いたいのかによって製品を選ぶと良いでしょう。
用途で選ぶ
先ほどもご紹介したように、エプソムソルトはさまざまな効果が期待できます。
リラックスや睡眠の質改善を目指すのか、筋肉のケアをしながらパフォーマンスの工場を目指すのかなど、用途に応じて適切なものを選びましょう。
無香料・保存料不使用のものの中には赤ちゃんから使える製品もあり、家族みんなで有意義なバスタイムを過ごすのにおすすめです。
おすすめのエプソムソルトを紹介
最後に、数あるエプソムソルトの中からおすすめの製品を3種類ご紹介します。
BASSPA エプソムソルト (金木犀 3kg)
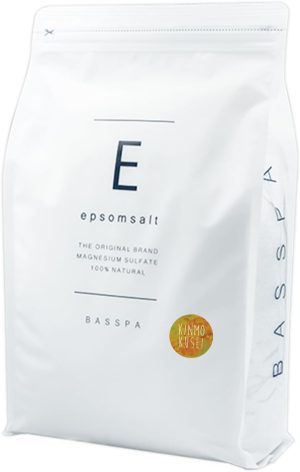
ひのきや柚子といった心落ち着く香りから、イランイランやホワイトムスクのように優しく甘い香りまでさまざまな種類のあるBASSPAのエプソムソルト。
こちらの金木犀は特に人気の一品で、本物の金木犀のような柔らかく芳醇な香りを楽しめます。
防腐剤や着色料は一切使用しておらず、肌に触れる成分に気を配っている方にもおすすめです。
アコール エプソムソルト 100g 5袋

1972年からエプソムソルトの製造・販売を手掛けるアコールが自信をもっておすすめする一品です。
無香料のシンプルなエプソムソルトは、好みを選ばずどんなシーンでも活躍するのがポイント。
1回分ごとに個包装になっているため、持ち運びがしやすく旅行バッグに忍ばせておくのもおすすめです。
香料や着色料は全て無添加であり、肌に優しいのも嬉しいポイントといえるでしょう。
EPSOPIA エプソピア(600g+増量200g)

約45回分のエプソムソルトがセットになったお得な製品です。全て国産の成分のみを使用しており、品質にこだわって作られているのがポイント。
計量スプーンが入っているため、1回分の量が分かりやすく誰でも手軽に使えるでしょう。
安全性の基準として食品と同じレベルを採用しており、赤ちゃんとの入浴時にもおすすめです。
【まとめ】エプソムソルトで至福のバスタイムを
肌が生き生きとしたり、筋肉のパフォーマンスがアップしたりとさまざまなメリットがあるエプソムソルト。
普段の入浴剤の代わりにサッと入れるだけで、手軽に健康を目指せるでしょう。
自分に合った香りや色のエプソムソルトを見つけ、より有意義なバスタイムを過ごしてみてはいかがでしょうか。
アロマテラピーのやり方や効果とは|おすすめのアロマディフューザーを紹介!

素敵な香りが部屋いっぱいに広がり、気分が上がるアロマテラピー。
単に良い香りを楽しむだけでなく、さまざまな嬉しい効果が期待できることでも知られています。
お気に入りの香りを見つけるとともに、お悩みや環境に合った香りを探してみるのもおすすめです。
今回はアロマテラピーが一体どんな効果を持っているのか、また自宅で簡単にできるアロマテラピーのやり方についてご紹介します。
専門的な知識がなくても、気軽に楽しめる方法を知っているだけで、普段の生活がより一層素敵なものになるでしょう。
アロマテラピーの効果について

「アロマテラピー」とは、単に良い香りを嗅いで素敵な気持ちになるだけではありません。
「セラピー」と名の付く通り、香りを使った「療法」であるため、正しく使うことでさまざまな効果が期待できます。
どんな香りアイテムでも良いわけではないため、本来の効果を発揮できるものを選ぶ必要があります。
まずはアロマテラピーが私たちにどんな嬉しい効果をもたらしてくれるのか、一つひとつ確認していきましょう。
香りの種類によっても細かな効果が異なりますが、今回は多くの香りに見られるメイン級の効果についてご紹介します。
リラックス効果
アロマテラピーの効果でもっとも有名なのは、気持ちを落ち着かせ、深くリラックスさせてくれることではないでしょうか。
1日の終わりに楽しむことで疲れた体と心を癒し、明日を頑張るための休息をもたらしてくれます。
ドキドキした気持ちを抑える鎮静効果も期待でき、緊張してしまいがちなシーンの前などにも役立つでしょう。
数あるアロマの中でも、リラックス効果が高いとされているのが「ラベンダー」「オレンジ」「ベルガモット」「カモミール」などです。
いずれもふんわりと甘くやさしい香りが特徴で、プライベートスペースや寝室で使うのがおすすめです。
集中力の向上
勉強や仕事を頑張りたいと思っても、音や光などさまざまな要因で集中がそがれてしまうことがあります。
そんなときはアロマテラピーで、頭をスッキリさせてみてはいかがでしょうか。
集中力が高まると同時に、机に向かう時間が増えたり、思考力が向上したりする効果も期待できます。
意識を勉強や仕事に100%向けることで、普段よりもパフォーマンスが上がり、成績や結果が良くなる可能性も高いでしょう。
具体的に使うなら「ローズマリー」「ペパーミント」「レモン」「ユーカリ」などのアロマがおすすめ。
いずれも鼻にスッと入り、爽快感のある香りを楽しめます。
睡眠の質の向上
深くリラックスする効果に加え、睡眠の質を上げる効果も期待できるアロマテラピー。
先ほどもご紹介したラベンダーなどに加え「サンダルウッド」「ヒノキ」などグリーン系の香りを選ぶのもおすすめです。
入眠する前に少し香りを嗅ぐだけで、入眠しやすくなったり、途中で置きにくくなったりといった効果が期待できるでしょう。
そもそも私たちが上手く眠るためには、交感神経に代わって副交感神経が優位になり、昂った神経を鎮めてリラックスしなくてはなりません。
とはいえ直前まで仕事をしていたり、明るい部屋でテレビを見ていたりすると、副交感神経がはたらかずなかなか眠りにつけなくなってしまうでしょう。
寝る前は早めに部屋を暗くし、お気に入りのアロマオイルを使ってリラックスできる時間を作ります。
スマートフォンはなるべく使わず、間接照明の中でゆったりとした時間を過ごしましょう。
1日のことを振り返る時間として、日記をつけたり音楽を聴いたりして過ごすのもおすすめです。
免疫機能の向上
季節の変わり目や風邪・インフルエンザなどが流行る冬場などは特に、免疫力を上げてトラブルに強い体を作りたいものです。
大人はもちろん、学校で感染症をもらいやすい子どもたちにとっても、アロマオイルで免疫機能を向上させましょう。
子どもがいる家庭でアロマテラピーを行う場合、大人が楽しむときに比べて香りを控えめにすることが大切です。
免疫力をアップし感染症予防に役立つアロマは「ユーカリ」「ティーツリー」「タイム」「ペパーミント」などハーブ系の香りが挙げられます。
スッキリとしていて嗅ぎやすく、頭が冴えることから、子ども部屋にもピッタリのアロマといえるでしょう。
これらのアロマは自律神経のはたらきを整え、免疫力だけでなくアレルギーや炎症にも強いといわれています。
花粉症の症状が出やすい春・秋なども含め、1年を通して使えるのが魅力的です。
消化促進
つい食べ過ぎてしまったり、脂っこいものを食べたりすると、消化不良になり胃もたれや胸やけがする場合があります。
食べたものの内容はもちろん、胃腸のはたらきが弱っている場合も、消化不良を起こしやすいでしょう。
一見胃腸とアロマは関係がないようにも思えますが、実際に消化を促進する効果が期待できるアロマもたくさん存在します。
消化促進にピッタリなのは「レモン」「オレンジ」など柑橘系のアロマオイル。
副交感神経のはたらきを活性化させ、食べたものをしっかりと消化できるようはたらきかけてくれます。
他にも、ラベンダーなどリラックスできるアロマで、ストレス性の胃痛を鎮める効果が期待できます。
ペパーミントなどの爽やかなアロマは、吐き気や胃もたれを回復させたりと、症状によっておすすめのアロマが異なります。
肌の健康促進
肌の健康を保つためのアロマオイルは種類が多く、それぞれのお悩みによって選ぶ必要があります。
下記の代表的なアロマを参考に、自分に合うものを探しましょう。
- 抗炎症作用:ラベンダー、カモミール、ティーツリー、パルマローザなど
- 抗アレルギー作用:パイン、レモングラス、ユーカリなど
- 細胞の成長促進作用:フランキンセンス、ゼラニウム、ネロリなど
ニキビなどの炎症が気になる場合は抗炎症作用のあるアロマを、花粉症の時期などに肌荒れが起こりやすい場合は抗アレルギー作用を選びます。
その他シミやシワなど、さまざまなトラブルに効果的なのが「細胞の成長促進作用」をもつアロマであり、健康な細胞が生まれやすくなる点が魅力的です。
関連記事:20年間の「やせなきゃ」から解放された私が考える『ボディポジティブ』
自宅でできるアロマテラピーのやり方

「専門的な知識がなければできない」と思われることも多いアロマテラピーですが、実は誰でも簡単に自宅で始められる楽しみの一つです。
一度材料を用意してしまえばしばらくの間楽しめるため、まずは一種類のアロマから始めてみてはいかがでしょうか。
ディフューザーを使用する
アロマディフューザーは、アロマオイルの入ったビンに専用のウッドスティックを差し、スティックがアロマを吸い込んで空気中に香りを広げる方法です。
場所をとらないため、玄関やトイレなどの狭い空間でも活躍してくれるでしょう。
一度飾った後はしばらく香り続けるため、いつでも素敵な香りを楽しみたい方におすすめです。
また、ガラスのビンにウッドスティックを差し込むだけで使えるため、その手軽さも大きな魅力の一つ。
インテリアとしても活躍するため、雰囲気がグッとオシャレになるでしょう。
ゆっくりと揮発してくれるため、強い香りが苦手な場合や、子どものいる家庭でも使いやすいタイプです。
アロマバス
入浴中に楽しめるアロマであり、リラックスタイムのお供としても活躍するタイプです。
ゆっくりと香りを楽しむために、普段よりも少しだけお湯の温度を下げ、のぼせないように注意しましょう。
お湯に直接アロマオイルを垂らして使うため、肌からはもちろん、揮発したアロマを吸い込むことでアロマが効果的にはたらいてくれます。
アロマオイルを湯船に入れるときは、およそ200L程度のお湯に3滴から5滴程度が理想です。
濃度の高いアロマオイルは直接肌に触れると荒れやすいため、必ず適切な量を守って使いましょう。
アロマスプレー
一瞬だけ香りを楽しみたいときや、消臭効果を利用したいときには、アロマオイルを水で希釈したアロマスプレーを使ってみてはいかがでしょうか。
お手持ちのスプレーボトルに入れておけば、どこでも気になる場所で使用できます。
キッチンやトイレなどはもちろん、車内の消臭剤としても活躍してくれるでしょう。
アロマスプレーは、精製水と無水エタノールを2:1の割合で混ぜたものにアロマオイルを垂らして作ります。
精製水40mlに無水エタノール20mlの場合、入れるアロマオイルは20滴~25滴程度。分離しやすいため、使う前によく振っておきましょう。
アロマスプレーの効果は永遠ではないため、作ってから1ヶ月程度で使い切るのがおすすめです。
できるだけ小さめのスプレーボトルを用意し、短期間で使い切れるよう工夫しましょう。
車内など気温が上がる場所に置いておくのは避け、冷暗所で保存するのが大切です。
トピカルアプリケーション(直接肌に塗布)
リラックス目的で使用するアロマの一部は、直接肌に塗布して使うことがあります。
これを「トピカルアプリケーション」と呼び、正しい濃度で使うことで疲れを和らげたり、快眠できたりといった効果が期待できます。
とはいえ、高濃度のアロマを直接肌につけてしまうと、肌荒れや赤みなどの原因になりかねません。
アーモンドオイルやホホバオイル・スクワランオイルなど、保湿目的のオイルで希釈し、刺激を抑えて使いましょう。
トピカルアプリケーションでアロマを塗布する場所は、首の後ろや手首などさまざまです。
頭や目が疲れているときはこめかみに塗ると、香りがふんわりと広がりリラックスできるでしょう。
アロマキャンドル
アロマオイルが練り込まれたキャンドルは、溶けるにつれてゆっくりと香るのが特徴です。
強すぎないため、香りが苦手な方でも安心して楽しめるでしょう。
使用時は火がついている間、子どもやペットが触れないように注意しなければなりません。
私たち人間は、炎が揺れている様子を見ていると気持ちが落ち着き、リラックスできるといわれています。
このことから、リラックス系のアロマとキャンドルの組み合わせは、まさにベストコンビといえるでしょう。
寝る前にゆっくりと炎を眺める時間をとれば、深く良質な睡眠がとりやすくなります。
アロマテラピーの効果を手軽に高めるディフューザーの選び方

アロマテラピーを手軽に楽しめるとして人気の「ディフューザー」。
さまざまなタイプがあるため、使いたい部屋や使いやすさなど選び方のポイントを抑えておく必要があります。
一度購入すれば長く使えるものも多いため、気に入る一品を選びましょう。
タイプで選ぶ
アロマディフューザーは、大きく分けて以下の4種類に分けられます。
| 種類 | 仕組み | おすすめの
場所 |
|
| 加熱式 | キャンドル
電気 |
オイルを温めて
香りを拡散させる |
寝室 |
| 超音波式 | – | 水にオイルを浮かべて
水蒸気状に拡散させる |
リビング |
| 噴射式 | アロマドロップ
ネブライザー |
振動させてアロマを
霧状に拡散させる |
リビング |
| 気化式 | リードディフューザー
アロマストーン |
染み込ませたアロマを
気化させて使う |
玄関
トイレ |
各種類ごとに違った使い方があり、香りの広がり方も大きく異なるため、自分に合ったものを想像しながら選ぶのがおすすめです。
部屋のサイズに合わせて選ぶ
広い部屋で使いたいのか、はたまた限られた場所だけを香らせたいのかによっても、選ぶべきアイテムが異なります。
リビングやダイニングなど広い場所で使いたい場合、香りの広がりが速く広範囲で楽しめる超音波式や噴射式を選ぶのがおすすめ。
部屋の隅にいても香りを感じやすく、オフィスなどでも使いやすいでしょう。
プライベートスペースなど、他の場所に香りを広げずに楽しみたい場合は加熱式や気化式を選びましょう。
いずれもふんわりと強すぎない香りが長時間楽しめるため、リラックスしたいときや頭をスッキリさせたいときなどさまざまなシーンで活躍してくれます。
タイマー機能の有無で選ぶ
電源に繋いで使う超音波式ディフューザーの中には、タイマー機能がついた便利な製品も登場しています。
特にお昼寝や就寝時に使いたい場合、設定した時間になると自動で電源がOFFになるのが魅力的。
つけっぱなしにならず、電気代やアロマオイルの節約にも繋がります。
ライト機能で選ぶ
ディフューザーそのものにライト機能がついており、夜間の間接照明として使えるものもあります。
寝る前の数分間をリラックスして過ごしたい方や、読書・日記などのお供にアロマオイルを使いたい場合など、一人でゆっくりと過ごす時間に活躍してくれるでしょう。
温かみのある電球色や温白色のライトを選び、特別な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。
また、赤や青などさまざまなカラーのライトがつき、部屋の電気を消すことで素敵に仕上がるものもあります。
超音波式のディフューザーなどは、水に反射した光がゆらゆらと揺れ、幻想的な空間になるでしょう。
デザイン性を重視する
アロマディフューザーを選ぶとき、シンプルでどんなインテリアにも映えやすい製品もあれば、こだわりのデザインが魅力的な製品もあります。
せっかく選ぶのであれば、毎日使いたくなるような素敵なデザインのものを探してみるのがおすすめです。
メンテナンスのしやすさを重視する
先ほどご紹介した中で、もっともメンテナンスがしやすいのが「アロマストーン」です。
石に数滴ずつアロマオイルを垂らして使うため、汚れが少なく綺麗な状態が長持ちするでしょう。
これに対し、頻繁にお手入れが必要となるのが超音波式ディフューザーです。
水にオイルを垂らすため、季節によってはカビの原因となる可能性があります。中に入れる水は定期的に交換し、清潔さを保つことが大切です。
価格の手頃さを重視する
アロマストーンやリードディフューザーなど比較的リーズナブルなものもあれば、超音波式や噴射式など少しリッチなものまでさまざまな製品があります。
アロマオイルの価格も含め、なるべく長く楽しめるものを選ぶと良いでしょう。
また、加熱式や気化式の中にも、工芸品として扱われているものや有名ブランドのものなど、リッチな製品が数多く登場しています。
普段使っているものよりも少し豪華なディフューザーを選び、特別な時間を過ごしてみるのもおすすめです。
関連記事:頭も身体も心も目を覚ます⁈冷たい水風呂でメンタルヘルスが改善!
おすすめのアロマディフューザーを紹介!

最後に、数あるアロマディフューザーの中から特におすすめのものを4種類ご紹介します。
Minidiva アロマランプ・ナイトライト アロマディフューザー

手のひらサイズのコンパクトなネブライザー式アロマディフューザーです。
シンプルな3つのボタンで操作がしやすく、自分使いとしてはもちろんギフトとしてもおすすめの一品。
昼間は通常通りに、夜はナイトライトを使いながら、さまざまなシーンで活躍してくれるでしょう。
木目調の本体とガラスがシンプルな中にも遊び心を感じさせ、どのお部屋に置いてもオシャレなインテリアアイテムとして活躍してくれます。
Kahuro アロマストーンセット【天然石 400g+アロマオイル10ml+led台座1台+ガラス1本】

ガラスの器に大小さまざまなアロマストーンが詰まった豪華な一品です。
自然が産んだ天然石を使っており、デコボコとした質感が光に当たって幻想的な空間を作り出します。
暖色→乳白色→暖色+乳白色と3つのモードを使い分けられ、お部屋の雰囲気に合わせて使えるのが魅力的。
6種類のアロマを配合したオリジナルエッセンスが付属しており、届いたその日から楽しめます。
アロマセット【アロマストーン400g+Cedarwood Essential Oil 10ml+ガラス1本】

天然の水晶をアロマストーンとして使い、香りだけでなく視覚でも楽しめる一品です。
爽やかなグリーンのカラーを引き立たせるよう、ガラスの器は限りなくシンプルを追求。
アロマストーンのイメージに合うサンダルウッドのアロマオイルが付属しており、心の奥底からゆったりとした気持ちにさせてくれます。
寝室や書斎など、コンパクトな空間で特別なひと時を過ごす際に活躍してくれるでしょう。
MUJI 無印良品 超音波うるおいアロマディフューザー

コロンと丸い形状が可愛らしく、どんな部屋にも合いやすいシンプルな一品です。
中には水を入れられるようになっており、好きなアロマオイルを数滴垂らすだけで香りが部屋一面に広がります。
便利なタイマー機能付きであるのに加え、温かみのあるオレンジ色のライトが周りを優しく照らしてくれるでしょう。
デコボコが少ないためお手入れがしやすく、いつでも清潔な状態を保てます。
【まとめ】アロマテラピーで気分を上げよう
気持ちの面ではもちろん、身体的にもさまざまな影響を与えてくれるアロマテラピー。
その日の気分に合わせて適切なものを選べるよう、いくつかのアロマオイルを揃えておくのもおすすめです。
さらには使いたいお部屋のサイズや印象に合わせたディフューザーを選ぶのもポイント。
今回ご紹介したさまざまな点を参考に、素敵なアロマライフを送ってみてはいかがでしょうか。
ジャーナリングのやり方は?日記との違いや効果について

日々さまざまなことを頭の中で考えていると、結論がなかなか出なかったり、考えすぎてイライラしてしまったりすることもあるでしょう。
誰かと会話するのとは違って、自分の中でだけ考えを巡らせるのは、良い点もあれば悪い点もあるものです。
そんなとき、頭の中を整理するために必要なのが「ジャーナリング」です。
定期的にジャーナリングを行うことで、自分が今何を考えているのか、何をしたいと思っているのかを正しく理解できるでしょう。
今回はジャーナリングがもたらす効果や日記との違い、詳しいやり方についてご紹介します。
ジャーナリングの効果とは
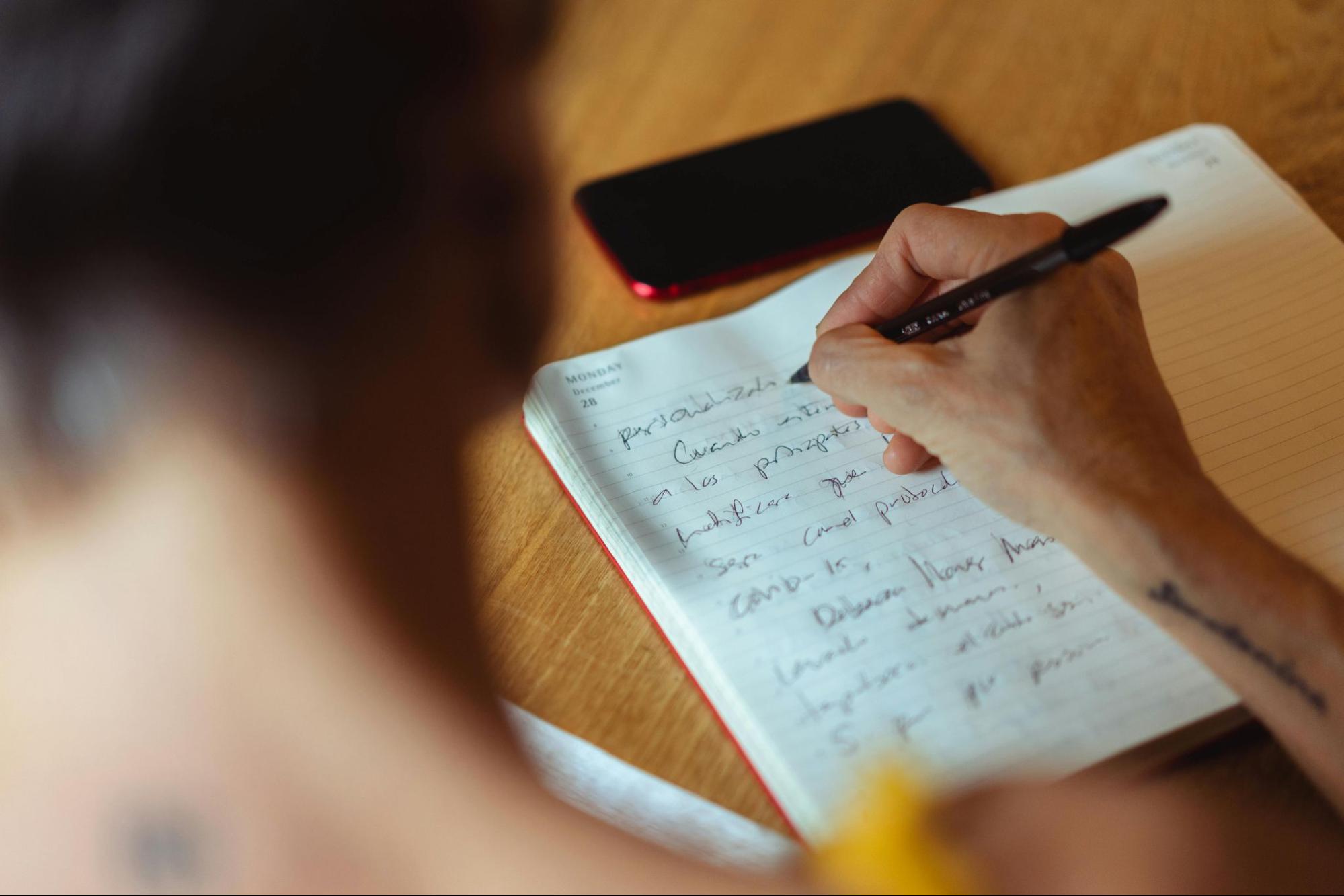
ジャーナリングは、頭の中に浮かんだことを深く考えず、そのまま紙に記していく方法です。
口を閉じて頭の中で考えを巡らせるよりも、自然と浮かんだ気持ちが現れやすいのが特徴です。
ジャーナリングをすると、想像しなかった本当の気持ちに気が付いたり、大したことではないと思っていたら実は重要なことだと分かったりします。
そのため、誰もが一度はチャレンジすべき方法ともいえます。
そんなジャーナリングですが、実は自分の気持ちを深く見つめなおすことで、さまざまな効果を発揮してくれます。
それぞれの効果について詳しくチェックし、日々のルーティンに組み込むことをおすすめします。
ストレスの軽減
理由はないのに落ち込んでしまったり、無性にイライラしたりといった心の不安定さを引き起こすストレス。
軽微なものであれば問題ありませんが、小さなストレスが積み重なったり、急に大きな負担がかかったりするとさまざまな弊害を生んでしまいます。
心の不安定さだけでなく、身体的なトラブルが起こることも珍しくありません。
肌が荒れたり髪が抜けやすくなったり、時には重大な病気を発症する可能性もあります。
ジャーナリングを定期的に行うと、自分の深層心理と向き合うことになり、ストレスの原因や解決策を見出しやすくなります。
ストレスについて深く悩んでしまうのではなく、普段考えが及ばない思考の深いところまで探ることで、よりスムーズにストレスを解決できるでしょう。
また、私たちがストレスを感じているとき、脳は不安やネガティブな思考でいっぱいの状態です。
無理やり楽しいことを考えようと思ってもうまくいかないのは、脳に考える隙間が無いのが理由です。
つまり、ジャーナリングでこの隙間を作ってあげることで、ポジティブな思考が自然と生まれやすくなるでしょう。
免疫機能の向上
辛い出来事を自分の中で抱えたまま過ごしていると、ストレスにより体にさまざまな弊害が生まれやすくなります。
これをジャーナリングでうまく発散してあげることで、不安や焦燥感を抱きにくくなるでしょう。
不安や焦りといった感情が長く心を支配していると、自律神経に大きな影響を及ぼします。
自律神経は私たちの意識と関係のないところで、常に体を動かしてくれている神経のこと。
呼吸や心臓の拍動などさまざまな役割を担っているため、バランスが乱れるだけでも体調の悪化につながってしまいます。
自律神経のはたらきが乱れることで、免疫力が低下するのも注意しなければならないポイントの一つ。
単なる風邪にかかりやすくなったり、一度感染した病気が治りにくくなったりするため、単なる風邪だと軽視できなくなるでしょう。
ジャーナリングでストレスを発散することで、免疫力の低下を防ぎ、健康な体を保つことにも繋がるのです。
抑うつ症状の軽減
上手く外に吐き出せない不安や焦りを抱えた状態が続くと、落ち込んだ状態から浮上しにくくなり、抑うつ状態へと進行してしまいます。
このまま対処をしなければ本格的なうつ病になる可能性も高いため、単なる落ち込みだと思わず、体からのSOSをしっかりと受け止める必要があります。
抑うつ状態はあくまでも「一時的な気分の落ち込み」であり、ここで落ち込んでいる原因と向き合うことで気分の切り替えが可能です。
原因を一つずつ頭の中で考えるのではなく、自分が奥底で何を考えているのかを確かめるためにもジャーナリングを試してみましょう。
自己認識の向上
「自己認識」とは、自分の気持ちや状態をしっかりと把握できている状態を指します。
自分が今何を考えているのか、どんな気持ちでいるのかを第三者目線で理解できれば、不安やイライラなどさまざまな感情をコントロールできるでしょう。
ジャーナリングで思い浮かんだ感情を書き留め、書いた文章を改めて確認することで、これまでに気が付かなかった感情が目で見て分かるようになります。
自分が今ポジティブなのかネガティブなのかを知るだけでも、行動に大きな違いが生まれるでしょう。
「今日はもっと頑張れそうだから」と仕事に取り組んでみる。「今日はしっかり休んだ方が良いだろう」と早めに布団に入る。
といったように、その日の気持ちに合わせた行動がとれるはずです。
記憶力の向上
ジャーナリングで普段の感情を書き出すと、脳に隙間ができ、より重要なことを考えるだけの余裕が生まれます。
ポジティブな感情とネガティブな感情では、圧倒的にネガティブな方が頭を占める割合が多いもの。
これらをうまく発散し、脳に空きを作ることで、さまざまな思考ができるようになるでしょう。
脳に余裕ができれば、記憶力の向上にも繋がります。
試験の前などはもちろん、普段から人の名前を覚えにくい方や、忘れものが多い方にもジャーナリングが向いているといえるでしょう。
小さな感謝への気づき
不安や焦りなどネガティブな感情で頭がいっぱいになっていると、その他のことに目が向きにくくなり、視野が狭まってしまいます。
周りから向けられた気持ちにも気が付きにくくなり、知らないところでトラブルを生んでしまうこともあるでしょう。
ジャーナリングによって頭の中がクリアになると、周りからの気持ちに素直に応えられるようになります。
日常に潜んでいる小さな「ありがとう」にも気が付きやすくなり、毎日を少し優しい気持ちで過ごせるでしょう。
反対に自分も周りに優しくできるようになり、不要なトラブルを防ぐことにも繋がります。
関連記事:アンガーマネジメントのやり方|「意味ない」と言われる理由とは?
ジャーナリングと日記の違いは?

「自分の気持ちを書き出す」という点において、ジャーナリングも日記も同じように見えます。
日記であれば、既に毎日書いている方も多いのではないでしょうか。
ジャーナリングと日記の違いを明確にしておくことで、それぞれを使い分け、より効率的に気持ちの整理ができるようになるでしょう。
ジャーナリング
ジャーナリングは、ノートを目の前にして思い浮かんだすべての気持ちをつらつらと書いていくものです。
「これは書かない方が良いかな」などと深く考える必要はなく、ただ思ったことを全て書いていきましょう。
これにより気持ちを整理したり、奥深くに隠れていた自分の気持ちに気づけたりといった効果が望めます。
真面目な人であれば、ジャーナリングを行うときに「日記にならないように」「気持ちを整理するために」と効果を求めるため一生懸命になってしまうでしょう。
丁寧に書きたい日記とは異なり、肩の力を抜いてチャレンジするのがおすすめです。
日記
日記とは、1日の中で起きた出来事や行動をまとめておくものです。
そのときに感じた気持ちを書くのも良いですが、メインとなるのは「何があったか」であり、気持ちに重点を置いていないのが特徴といえるでしょう。
特別な出来事があった日だけ日記をつけ、普段通りの日には何も書かないという方も少なくありません。
日記を書くときは、ジャーナリングとは異なり、内容を選びながら読み返したくなる文章を書くのがおすすめです。
寝る前にあたたかいものを飲みながら書くなど、1日の終わりのルーティンとして続けてみるのもおすすめです。
関連記事:メンタルブレイクした時はどうすればいい?診断方法や治し方を紹介
ジャーナリングのやり方

続いて、ジャーナリングのやり方を詳しくご紹介します。準備段階からこだわることで書くのが楽しくなり、より長く続けられるでしょう。
用具を準備する
基本的に、ジャーナリングは紙とペンさえあればどこでも始められます。
チラシの裏に書くのも良いですが、気に入ったデザインのノートや筆記具を選ぶことで、より楽しくチャレンジできます。
この後ご紹介するおすすめアイテムの見出しでは、ジャーナリングにピッタリの素敵な日記帳をピックアップしています。
お気に入りのアイテムを見つけるためにも、参考にしてみてはいかがでしょうか。
リラックスする
ジャーナリングを行う場合、できるだけリラックスした気持ちで行うことが大切です。
あたたかい飲み物を用意したり、入浴後に行ったりと、落ち着いて書けるタイミングを選びましょう。
できるだけ自分の気持ちに集中できるよう、1人になれる場所を選んだり、テレビを消したりといった工夫をするのもおすすめです。
テーマを決める
思ったことは何でも書いて良いのがジャーナリングですが、だからといって書くことが思いつかない場合も多いでしょう。
そんなときはテーマを決め、お題に沿って気持ちを整理していくのもおすすめです。
例えば、今日の1日を振り返り、良い行いや悪かったことについて考えてみるのも良いでしょう。
今自分を取り巻く環境について考え、仕事が自分に向いているのか、今後どう成長していきたいのかを考えるのもおすすめです。
不安や焦りの原因を探るために、思い切って最近あった嫌なことについて深堀りしてみるのも効果的です。
書き始める
実際にノートへ書き始めると、次から次へと書きたいことが出てきてしまい、いつまで書けば良いか分からなくなることもあるでしょう。
あらかじめ何分間で書くのかを決めておき、その中で気持ちの整理を行うことが大切です。
実際に書き始めた後は、途中でペンを置くことなく、キリの良いところまで書いてしまわなければなりません。
途中で食事をとったり入浴したりするのではなく、集中して気持ちと向き合う時間を作るのが良いでしょう。
内容を振り返る
納得のいくところまで文章が書けたら、一度全て読み返す時間をとります。
無意識のうちに書いていた文章までしっかりと確認することで、自分の気持ちを可視化し、冷静に分析できるでしょう。
これまでに気が付かなかった点があれば、その部分を抜き出して整理しておくのもおすすめです。
また、ジャーナリングで書いた内容はその日だけでなく、1週間後、1ヶ月後など定期的に確認すると良いでしょう。
その日からどう気持ちや状況が変わったのか、今後どう変えていきたいのかをイメージしながら、今の気持ちと照らし合わせてみるのが効果的です。
習慣化する
ジャーナリングは一度書いて終わりではなく、定期的に取り組むことで頭の中を整理できます。
毎日必ず取り組む必要はありませんが、休日に取り組んでみたり、1ヶ月を振り返ってみたりと、チャレンジするスパンを決めておくと良いでしょう。
ジャーナリングは「やらなければならない」ものではないため、スケジュールに組み込んできっちりと行う必要はありません。
ストレスが溜まってきたり、楽しいことを考えられなくなったりしたときの対処法として、頭の隅に置いておくと良いでしょう。
関連記事:メンタルがやばいサインとは?メンタルの不調で休むのは甘え?
ジャーナリングの気分を上げてくれるおすすめの日記帳4選

最後に、ジャーナリングにチャレンジするときにおすすめの素敵な日記帳を4種類ご紹介します。
ラコニック(Laconic) スタイルノート マンダラチャート A5
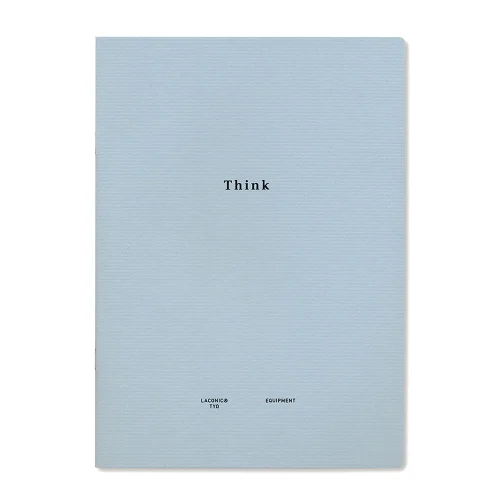
一般的な罫線のノートではなく、自分の気持ちと向き合うための特殊なチャートがついた日記帳です。
さまざまな視点から目標達成を目指す「9×9」
関係性を整理するのに役立つ「座標軸」
考えの広がりを意識できる「同心円チャート」
イラストを交えてイメージを整理できる「4コマ・メモ」
この4種類が特徴です。それぞれ自分に合った使い方ができるため、楽しみながらメモをとれるのが魅力的です。
いろは出版(Iroha Publishing)BREATH DIARY【BLUE】
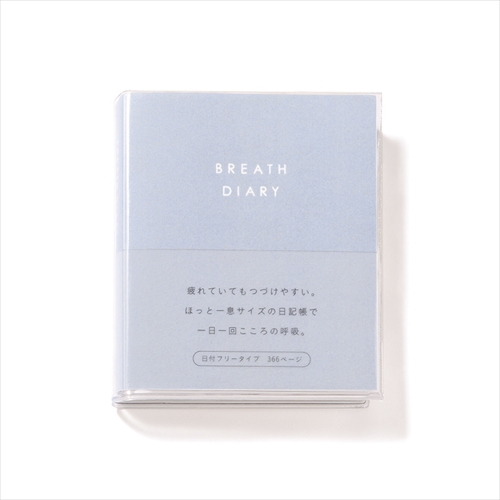
シンプルで使いやすいデザインで、持ち歩くのにもピッタリな日記帳です。
ドットが印刷されたタイプのため、好きな大きさで文字を書けるのはもちろん、イラストを描きたいときにも活躍してくれるでしょう。
最後のページには日記のネタが記載されており、書くことに迷ったときのヒントとしても使えます。
手のひらに乗る程度の小さなサイズ感で、文字をたくさん書くのが難しい人にもおすすめです。
ミドリ(MIDORI)日記 きまぐれA
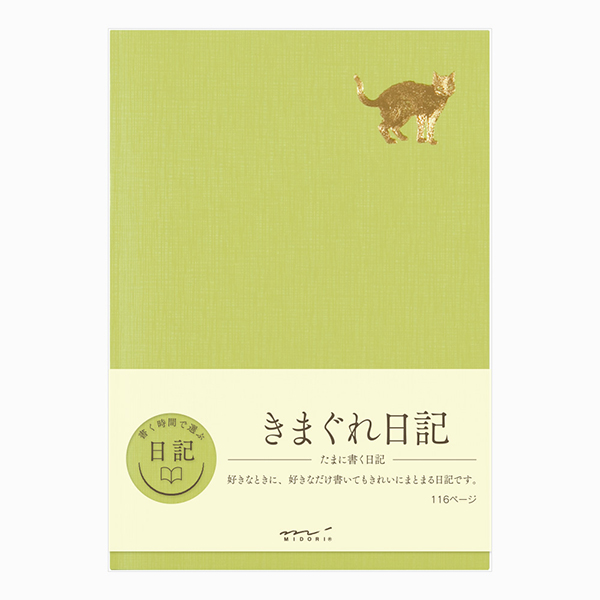
「きまぐれ日記」という名のこちらは、書きたいときに書きたい分だけ使える便利な日記帳です。
日付が印刷されていないため、取り組むと決めた日にだけ向き合えるのが魅力的。
1日分しっかり埋めるのも良し、2日・3日分を使ってたっぷりと書くのも良し、その日の気分に合わせて使えます。
ミドリ 日記 3分 黄色
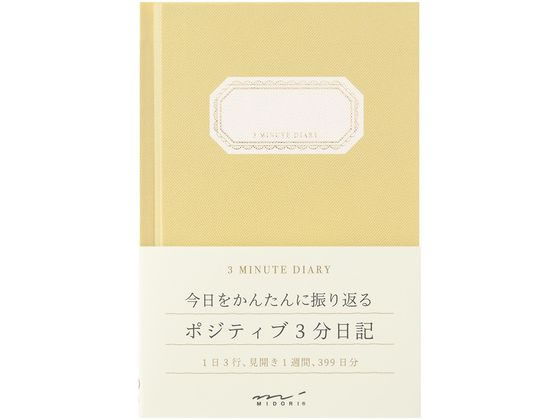
気分がパッと明るくなるようなイエローカラーの日記帳です。
1日分は3行と少なく、たくさん書くのが負担に感じる方も取り組みやすいでしょう。
もちろん数日分を一気に使い、書きたいことを十分にアウトプットするのもおすすめです。
しっかりとした作りの表紙・裏表紙がついており、特別感も満載。自分だけが見る大切なノートとして保管しておくと良いでしょう。
【まとめ】ジャーナリングの習慣で人生を豊かに
耳慣れない言葉であることも多い「ジャーナリング」ですが、実際に取り組んでみると難しくはありません。
ジャーナリングは、自分の深いところにある気持ちと向き合える画期的な方法です。
カウンセリングを受けたり、医療機関を受診したりすることなく試せるため、不安を取り除く第一歩としてチャレンジしてみると良いでしょう。
今回ご紹介した方法やおすすめの日記帳などを参考に、自分の生活に合ったジャーナリングを試してみてはいかがでしょうか。
メンタルブレイクした時はどうすればいい?診断方法や治し方を紹介

忙しい日々を送っている現代人ならば、誰もが一度は気持ちが落ち込んだり、頑張る気力がなくなったりした経験があるのではないでしょうか。
「単なる気持ちの変化だから」と対処せずに過ごしてしまうと、なかなか這い上がれずに辛い日々を送ることになりかねません。
今回はそんな状態を指す言葉「メンタルブレイク」に注目し、自己診断の方法や治し方をご紹介します。
メンタルブレイクの意味とは?

「メンタルブレイク」とは、直訳で「精神崩壊」という意味を持つ言葉です。
医療用語ではなく、いわゆる造語として2000年代初め頃から広まり始めました。
当初は大型掲示板サイト「2ちゃんねる」にて精神を病んだ人を指す言葉として使われていました。
近年は誰しもがなりうる、辛い状態を意味する言葉へと変化しつつあります。
掲示板サイトをきっかけに生まれたメンタルブレイクというワードは、徐々に女子高生を中心としたSNSで使われるようになりました。
何か嫌なことがあったり、やる気が出なかったりといった心情を「メンブレした」と表し、共感やなぐさめの言葉をもらうのが一般的。
当時は、ほんの少し落ち込んだ程度の状態を指す言葉として使われていたのです。
現在は大人でもメンタルブレイクという言葉を知っている人が多く、重いうつ状態などを表す際にも使われつつあります。
面白半分で使う言葉から、自身や周りを労わるために必要な言葉へと進化しつつある言葉といえるでしょう。
一部では「メンタルダウン」という言葉も同様の意味として使われています。
メンタルブレイクの症状は?

一言でメンタルブレイクといっても、人によって症状はさまざまです。
「あの人とは違うから私はメンタルブレイクではない」「この症状があるからメンタルブレイクだ」
というわけではなく、あくまでも普段の自分と比べてどのように変化したかをチェックすると良いでしょう。
下記でご紹介するメンタルブレイクの症状は、実際に体験した人の多い症状の一例です。
下記以外にも気になる症状がある場合は、自分の症状と照らし合わせて確認することをおすすめします。
何もしていないのに気分が落ち込む
何か特別なことがあったり、傷ついたりした経験があって気分が落ち込むのは自然なことです。
しかし「何もしていないのにどんよりとした気持ちになる」「うまく笑えなくなる」
このような場合は、メンタルブレイクの症状の一つといって良いでしょう。
日々の小さなストレスが積み重なるなど、自分では気が付かないレベルのきっかけがメンタルブレイクを引き起こすことがあります。
何も悲しいことがなかったからといって、気持ちが落ち込んでいる状態を見逃さないようにしましょう。
とはいえ、何もきっかけがない場合、気分が落ち込んでいることに気が付くのは難しいものです。
少しでも「あれ?」と感じることがある場合は、一度ゆっくりと時間をとって自分の状態を見つめなおしてみるのがおすすめです。
落ち込んだ気持ちに見て見ぬふりを続けてしまうと、その後ちょっとした出来事でさらに落ち込んだり、外に出るのが難しくなったりすることがあります。
自分では分からないことも、周りが気づいてくれる可能性があるため、信頼できる人に相談するのも良いでしょう。
何をするにも気力が出ない
仕事や家事などを頑張ろうと思っても、なぜか気力がわかずに先延ばしにしてしまったり、重い腰が上がらなかったりした経験のある方も多いのではないでしょうか。
もちろん仕事や家事に苦痛を感じていれば、自然と気力がわかなくなるもの。
普段はしっかりと取り組んでいても、季節の変わり目や生活習慣の変化などでやる気がフェードアウトしてしまうこともあるでしょう。
気力が出ない状態は、いわば「誰にでもあること」として放置してしまう人が多い症状です。
とはいえ、どんな症状にも何かしらの理由があるはずで、何もないのに気力がわかない状態は危険です。
メンタルブレイクでは、自身が気が付かない要因が積み重なっていることが多いです。
「自覚がないままなぜか気力が出ない」「やる気が出ない」などの状態は、決して無視しないようにしましょう。
もちろん、気力が出ないと思ったら実際には風邪の引き始めだったり、ホルモンバランスが乱れていたりすることもあります。
心の問題だけでなく、体の不調で考えられる原因がないかもチェックするのがおすすめです。
いつもなら何でもないことに対してイライラする
メンタルブレイクの症状は、気持ちが落ち込むだけではありません。
普段ならば気にすることがないような些細な出来事に対して、過剰に気持ちが高ぶってしまうケースも考えられます。
家族の何気ない一言に反論してしまったり、イライラがおさまらずに何事も楽しめなかったりする場合は、上記同様メンタルブレイクを疑いましょう。
この「イライラ」という症状は、自分が精神的に疲れていることが分かりにくい症状の一つでもあります。
普段温厚な人が何日もイライラしていたり、激しい言葉遣いに変わったりするのに気が付いた場合は、さりげなくフォローしてあげると良いでしょう。
主に女性の場合、ホルモンバランスの乱れが原因でイライラがつのることがあります。
メンタルブレイクを疑うと同時に、月経周期などを確認し、体に不調がないか確認することも大切です。
胸がドキドキして息苦しい
心の問題だと捉えられがちなメンタルブレイクですが、気持ちの変化によって身体的な症状が出ることも少なくありません。
代表的な症状の一つに「胸がドキドキする」「息苦しい」というものがあります。
病院で検査をしても異常がなく、ストレスが原因だといわれた経験のある方も多いのではないでしょうか。
朝起きた瞬間に胸がつまるような感じがしたり、寝るために横になると息がしにくくなったりと、人それぞれ症状が異なるのも特徴です。
場合によっては息苦しさが強くなり、うまく息が吸えず「過呼吸」になるケースもあります。
口元に袋を当てて二酸化炭素を取り込むことで落ち着くといわれていますが、経験がなければ焦ってしまう人も多いでしょう。
過呼吸は息をゆっくりと吐いたりうつ伏せで横になったりするのに加え、周囲に人がいる場合は会話をすることで落ち着く可能性があります。
息苦しさは決して軽視せず、常に対処法を考えておくことが大切です。
熟睡できず夜中に何度も目が覚める
メンタルブレイクの間は体にストレスがかかり、自律神経のはたらきも乱れやすくなります。
通常、起きている間は交感神経が、眠るときには副交感神経が優位になるはずの人体ですが、自律神経がうまく働かない場合この限りではありません。
夜にもかかわらず気持ちが昂ったり、夜中に目が覚めて寝付けなくなってしまったりする場合は、病気を疑うとともにメンタルケアも行うと良いでしょう。
眠りに関する悩みがある場合、まずは起きている間の行動を改善してみるのがおすすめです。
無理に眠ろうとするのではなく、朝起きてすぐに日光を浴びたり、適度な運動をしたりして体のサイクルを整えましょう。
眠る前は熱すぎないお湯にゆっくりと浸かったり、就寝の3時間前までに食事を済ませたりといった工夫も大切です。
また、眠りに関する悩みが続けば続くほど、心身ともにさまざまなトラブルが起こりやすくなります。
必要に応じて医療機関を受診したり、睡眠導入剤を処方してもらったりと、専門家に相談することをおすすめします。
関連記事:ジャーナリングのやり方は?日記との違いや効果について
メンタルブレイクの自己診断をしてみよう

医療機関を受診する前に、自己診断によるメンタルブレイクの見分け方を試してみましょう。
以下のようなチェックポイントを参考に、当てはまるものがいくつあるかで見極めを行います。
- 気分の変動が激しいか?
- 睡眠に問題はないか?
- 仕事や日常活動に対するモチベーションは?
- 食欲に変化はあるか?
- 社会的な関わりに変化はあるか?
- 集中力や判断力に問題はないか?
- 自己評価に変化はあるか?
- 不安や恐怖を感じることは増えたか?
先ほどご紹介した気分の落ち込み・イライラや、睡眠不足などの項目に加え「漠然と不安や恐怖を感じるか」といったポイントまでさまざまなものがあります。
一見して関連性のない質問にも思えますが、これらは全てメンタルブレイクの一例として多くの人が苦しんでいる症状です。
例として、精神疾患の一つ「うつ病」を挙げてみましょう。
気持ちの落ち込み、不安感、だるさ、暴力行為や希死念慮など、人によって症状に大きな違いが見られます。
症状が重い場合は引きこもりになったり、専門病院に入院しなければならなかったりすることもあるでしょう。
これに対しメンタルブレイクは「一時的な気持ちの問題」と片付けられてしまい、うつ病などの精神疾患に比べ軽視される傾向にあります。
何の対処もしないままでは別の疾患を併発しかねないため、先ほどご紹介したチェックポイントを受診の目安として活用しましょう。
自己診断は、あくまでも参考程度にしかなりません。
本来の原因や対処法は一人ひとり異なるため、専門医と時間をかけて話し合うことをおすすめします。
関連記事:ネガティブ思考は病気?うつ病との違いや治し方を解説
メンタルブレイクしたときの治し方は?

人によって原因や症状が異なるメンタルブレイクは、基本的に専門医と治し方について相談するのがベストです。
いつでも相談できるよう、最寄りの精神科や心療内科を調べておくと良いでしょう。
一方で、自分で症状を軽くするための対処法もいくつか存在します。
これらは根本的な問題を解決するわけではないため、一時的な対処法として覚えておくのがおすすめ。
時間や気持ちに少しでも余裕ができたときには、自身を悩ませている原因を探りましょう。
気持ちを声に出してみる
メンタルブレイクをしているときは、多くの人が自分の状態を正しく把握できていません。
「まだ大丈夫だろう」と思っていたり、これだと思う原因が間違っていたりすると、結果として症状を長引かせてしまうでしょう。
そのため、まずは考えていることを全て口に出してみるのがおすすめです。
何を話すか考えることもなく、ただつらつらと気持ちを声に出してみるだけです。
そこに誰かがいても良いですし、1人のときでもかまいません。
頭の中で考えを巡らせていても、良い結果が生まれにくいどころかどんどんとネガティブな方向へ進んでしまいがちです。
アウトプットすることで気持ちを整理することにもつながるため、独り言のようにつぶやいてみると良いでしょう。
また、どうしても声が出せない環境にいる場合は、手当たり次第紙に書き出してみるのもおすすめです。
書いたものを見直しながら、自分が本当に抱えている気持ちを探っていきましょう。
どうしたいのか考えてみる
気持ちをアウトプットできるようになったら、一体自分がどうしたいのかを考えてみましょう。
仕事関連の気持ちを多く吐き出した場合「自分はその仕事でどんなポストに就きたいのか」
あるいは「辞めてしまいたいのか」といった希望する未来をイメージするのが重要です。
人間関係に悩んでいるのであれば、相手とどんな関係になりたいのか想像してみましょう。
例え非現実的な内容であっても、自分の希望を具体的に思い描くことが大切です。
自分がどうしたいのかを考えるとき、周りの人間の目を気にする必要はありません。
「〇〇さんがこうすべきだと言ったから」「こうすると皆に迷惑がかかるから」といった前提を捨て、自分が心地良く過ごせる選択は何なのかを探りましょう。
肉体的な健康を維持する
メンタルブレイクから脱却するためには、心はもちろん体の健康が必要不可欠となります。
心の辛さを重視するあまり、体の健康をおろそかにしてしまえば「疲れがとれにくい」「風邪をひきやすい」など日常にさまざまな影響が出てしまうでしょう。
その結果、毎日がイメージ通りに過ごせなくなれば、新たなメンタルブレイクを引き起こす可能性もゼロではありません。
肉体的な健康は、精神的な健康の土台となります。
睡眠・食事・運動の3つをバランス良く整え、心と向き合うだけの余裕を身に着けましょう。
急にこれまで続けてきた生活をガラリと変える必要はないため、できることから少しずつ始めていくことが大切です。
ネガティブな事柄を避ける
メンタルブレイクに悩まされている間は、ネガティブな事柄をできるだけ避けると良いでしょう。
例え今抱えている悩みとはまったく異なることであったとしても、ネガティブな事柄に引っ張られて気持ちがさらに沈んでしまう可能性があります。
例として、悩んでいる人の相談にのったり、困っている人とともに苦しんだりするなど、周囲の空気がどんよりするような場所に行くべきではありません。
負の感情が大きくなり、周りを巻き込んでしまう可能性もあるでしょう。
まず自分が十分な余裕をもつことが、誰かを助けるための第一歩となるはずです。
上記を習慣化する
これまでご紹介した1から4までの内容は、数回試しただけで何かが大きく変わるわけではありません。
これらを習慣化し、自分の生活に組み込んでいくからこそ、自分の力でメンタルブレイクを脱却するきっかけとなるでしょう。
その後は専門家の力を借りながら、本来の生活に戻るまでのリハビリを行う必要があります。
関連記事:メンタルがやばいサインとは?メンタルの不調で休むのは甘え?
【まとめ】メンタルブレイクした時は無理しない

人によってさまざまな症状があり、原因を突き止めるだけでも難しいのがメンタルブレイクです。
日々の中で少しずつ自分と向き合いながら、明るい気持ちを取り戻すために対処法を続けていきましょう。
メンタルブレイクは単に原因を取り除いたり、楽しい経験をしたりするだけで完治させることはできません。
決して無理をすることなく、必要に応じて専門家の手を借りながら、少しずつ前を向いていくことが大切です。
性欲を抑えるにはどうすればいい?具体的な方法とデメリットについても

日常生活の中で、ふとした瞬間に沸き起こる性欲。
パートナーとタイミングが合えば良いですが、そうでなければ一旦性欲を抑えなければなりません。
本記事では、性欲を抑える具体的な方法をピックアップすると同時に、注意点やデメリットについてもご紹介します。
性欲を抑える意義

性欲を抑えようとは思っていても、思うようにいかずもどかしい思いをしたことがある方も多いのではないでしょうか。
まずは性欲が高まったとき私たちの体の中では何が起こっているのか、具体的なメカニズムを紐解いていきましょう。
また、性欲を抑えることでどんなメリットがあるのかも併せてご紹介します。
性欲が高まるメカニズムとその影響
私たちの体には、男性ホルモンと女性ホルモンが共存し、それぞれ異なるはたらきをしています。
男性であっても女性ホルモンは持っていますし、女性の中でも男性ホルモンがはたらいています。
このバランスは常に保たれていますが、時折男性ホルモンである「テストステロン」の分泌量が増えることで性欲が高まるといわれています。
とはいえ、テストステロンが直接脳に関与し性欲を高めているわけではありません。
テストステロンの分泌量が増えると、脳から「ドーパミン」と呼ばれる物質が分泌されます。
ドーパミンは別名「幸せホルモン」ともいわれており、興奮や幸福感を誘う物質の一つ。これが血液中に増えると、ムラムラとした気持ちになりやすいのです。
テストステロンの分泌は、十分な睡眠をとったり、適度な運動をしたりすることで活性化します。
他人と会話することでも分泌が促進するため、相手が大切な人であればより分泌量が増えるでしょう。
男性ホルモンと呼ばれることから男性のみ分泌されると思われがちですが、女性の性欲や興奮にもテストステロンが関わっています。
また、女性がもっとも妊娠しやすいといわれる排卵日前後は、テストステロンが増加し興奮が高まる時期でもあります。
テストステロンは「フェロモン」の分泌を促進する作用もあるため、異性を誘うためにも役立つ時期といえます。
性欲を抑制することの精神的、身体的メリット
性欲を抑制すると、精神的・身体的にさまざまなメリットがあります。
- パートナーとタイミングが合わなくてもイライラせずに済む
- 自慰行為にかける時間を省ける
- 気持ちに余裕が生まれる
- 仕事のパフォーマンスが上がる
- 必要なタイミングで性行為ができる
巷では性欲を抑制することで髪質・肌質が変わるなどのメリットも噂されていますが、医療的根拠がなく全ての人に当てはまるとはいえません。
主なメリットとしては、性欲に支配される時間が減ることや、性欲の発散に悩まされることがないといったものが挙げられるでしょう。
性欲を抑える具体的な方法

続いて、性欲を抑えるために有効といわれる方法についてご紹介します。
これらの方法はあくまでも一例であり、人によってはいくら試しても性欲が抑えられなかったり、反対に性欲がゼロになってしまったりすることもあるでしょう。
他人の例を参考にし過ぎることなく、自分の体と相談しながら進めていくことが大切です。
運動と筋トレに励む
運動や筋トレに没頭していると、性欲のことを忘れられると感じる人も多いといわれています。
普段健康のために行う運動よりもほんの少しハードなメニューを選ぶと、体が疲れて性行為に及ぶ体力がなくなるでしょう。
疲れて休みたいと思っている間は、気持ちが性欲に傾くことも少なくなるはずです。
また、運動や筋トレを習慣化すれば、体を引き締めたり健康になったりと良いことづくめなのもメリットといえます。
自慰行為に長い時間を割いてしまい、後からやりたいことができずに後悔してしまうケースも少なくありません。
まずは1日10分程度から、集中して運動する時間をかくほしてみましょう。
趣味に没頭する
運動が苦手な方など、できるだけ体を動かしたくないと感じる場合も多いでしょう。
こういう場合は、自分の好きなことや趣味に没頭してみるのもおすすめです。
何か集中できるものであれば何でも良いため、作品を作るも良し、本の世界に浸るも良し、さまざまな楽しみ方があります。
とはいえ、忙しい毎日を送る現代人であれば、趣味に没頭する時間がなかなか取れないかもしれません。
自分のもっとも好きなことのほかに、短時間でできる楽しみを探してみるのも良いですね。
好きなカフェでコーヒーを1杯頼んでみたり、帰り道に音楽をかけてみたりと、ほんの少しの楽しみを見つけてみてはいかがでしょうか。
瞑想で集中力を高める
性欲で頭がいっぱいになっていると、仕事に集中できずミスをする可能性があります。
別のことを考えられなくなり、他人との会話がうまくいかなくなることもあるでしょう。
これでは通常の生活に支障が出てしまうため、集中力を高めるため瞑想にチャレンジするのが効果的です。
瞑想は毎日1分程度からスタートすると良いでしょう。楽な姿勢で目を瞑り、深い呼吸を心掛けます。
息を吸ったり吐いたりすることに気持ちを向けているうちに、余計な考えが頭から抜け、深く集中できるようになります。
なるべく長期間継続するためにも、日々同じ時間に瞑想を組み込み、ルーティン化するのがおすすめです。
生活習慣の改善に努める
普段よりも長く起きていたり、ダラダラと過ごす時間が増えてしまったりすると、その分性的なことを考える時間も長くなってしまいます。
リラックス目的で時間を確保するならば良いですが、何もすることがなくただだらける時間はできるだけ短くしましょう。
朝食を抜いたり、睡眠時間を削ったりといった生活習慣の乱れも、正すべきポイントの一つです。
日々バランスの良い生活を送っていると、自立神経のはたらきも正常になり、過度な性欲に支配されにくくなります。
適度な性欲とうまく付き合っていくためにも、バランスの良い食事・適度な運動・良質な睡眠の3つを重視した生活を続けましょう。
関連記事:生理後は性欲が強くなる?生理周期別の性に関する過ごし方を紹介
性欲を抑える上での工夫と注意点

性欲を抑えたいと思っても、むやみに我慢すれば良いというわけではありません。
性欲を抑える上での注意点を参考に、無理のない範囲でチャレンジしてみましょう。
自慰行為の健全な利用
性欲を抑えるために、性行為や自慰行為を完全に避けてしまう人も少なくありません。
しかし、今まで行ってきたものが急になくなってしまうと体がついていけず、より性欲が高まってしまう可能性があります。
パートナーとのタイミングが合わず性欲をコントロールしたいときは、適度に自慰行為を行うと良いでしょう。
健全な自慰行為の回数といっても、適切なタイミングは人によって異なります。
1日のうち長い時間を割いてしまったり、そのことしか考えられなくなったりするのは良くありません。
しかし、1日1回程度の自慰行為ならば生活に支障をきたしにくいでしょう。
大切なのは「0か100か」という考えで性行為を避けるのではなく、適度に発散しながら自分の体と付き合っていくことです。
1人になれる時間がある場合は、満足できる最小限の時間を使って自分と向き合ってみてはいかがでしょうか。
視覚的・思考的刺激の抑制
性欲を抑えたいと思っていても、性的なサイトや雑誌などを見てしまっては、元も子もありません。
性欲をコントロールしたいと思っている期間は特に、視覚から刺激を受けることがないよう注意しましょう。
時にはスマートフォンを置き、読書や映画に没頭してみるのもおすすめです。
また、何も見ていなくてもついそのことを考えてしまい、思考が止まらなくなることで性欲が湧いてしまうことも多々あります。
この機会に新たな資格を得る勉強を始めたり、新たな趣味を探してみたりと、別のことで頭をいっぱいにしてみるのも一つの方法といえるでしょう。
社会的・健康的な影響を考慮
この後にご紹介する「性欲を抑えるデメリット」でも触れますが、性欲を抑えた状態が長く続くと、社会的・健康的に影響を及ぼす可能性があります。
まず男性の場合、性欲を抑えることでパートナーとの関係が悪くなったり、その手の会話を避けることで周りと話が合わなくなったりといった弊害が考えられます。
さらには長期間射精をしないことで、精力減退や射精障害、男性ホルモンの低下といった身体トラブルが起こる可能性もあるでしょう。
これらのリスクをしっかりと理解した上で性欲を抑え、コントロールすることが大切です。
女性の場合、男性に比べて身体トラブルの可能性は低いのが特徴です。
しかしパートナーに求められてもその気になれず関係が悪化したり、妊娠のタイミングを逃したりといったリスクもゼロではありません。
関連記事:40代の女性の性欲が強い原因とは?性欲がなくなる場合との違いや対処法
性欲を抑えるデメリットは?

過度な性欲は時間や考える力を奪ってしまいますが、性欲を抑えすぎることで起こりうるデメリットも意識しなければなりません。
いずれにしても「やりすぎ」や「抑制のしすぎ」はできるだけ避け、適度に発散することが大切です。
過剰な抑制による精神的ストレス
抑制を始めたころにありがちなのが、過剰に我慢を重ねることでストレスになり、イライラしやすくなったり周りに当たり散らしてしまうといったトラブルです。
家族や知人と衝突し、関係が悪化してしまうこともあるでしょう。
しかし性欲には波があるため、落ち着いているときはイライラしてしまう自分を責め、逆に落ち込んでしまうことも少なくありません。
浮き沈みの激しい性格になり、周囲から距離を取られてしまう可能性もあります。
性欲を抑制するときは、必ず発散の方法を探しておかなければなりません。
適度な自慰行為も一つの方法であると同時に、運動や趣味で発散するのもおすすめです。
自分の気持ちを溜め込んでしまわないよう、息抜きができる時間はしっかりと確保しておきましょう。
社会的な偏見や誤解
性欲を抑制しパートナーとの性行為を控えていると、周囲に対しあらぬ誤解を生む可能性があります。
単に性欲をコントロールしたいだけだとしても「不仲なのではないか」「子どもができないのではないか」といった噂が次々に生まれてしまうでしょう。
これらを一つひとつ訂正することもまた、ストレスの原因になりかねません。
また、社会には性欲をコントロールできないあまり「誰でも良いから」と犯罪行為に手を染める人が一定数存在します。
過度な抑制によって性欲が爆発してしまい、痴漢や暴行に及ぶ事件もあるでしょう。
こういった事件に対する世間の目は冷たく、性欲を抑制しているというだけで「こういった思想があるのではないか」と思われる危険性があるのです。
性欲を抑制することは決して悪いことではないものの、周囲の人間に打ち明ける時には注意が必要です。
信頼できる関係の人にのみ話し、あらぬ疑いをかけられないよう工夫しなければなりません。
健康への潜在的影響
性欲を過度に抑えることで、男女ともにイライラしてしまったり、パートナーとの関係が悪化したりといった影響が出ることをご説明しました。
一方で男性の場合、身体的影響から健康に被害が出ることもあります。
長期間射精をしないことで古くなった精液が溜まり、健康的な精子が作られなくなったり、上手く射精ができなくなったりといったリスクが高まるでしょう。
いざ妊娠を考えたとき、男性側のトラブルで妊娠に至らないケースも珍しくありません。
一説によれば、男性は少なくとも週に一度のペースで射精することが理想だといわれています。
これ以上回数が減ると上記のようなトラブルが起きたり、前立腺がんのリスクが上昇したりと良いことがありません。
適度な回数・適度なタイミングを意識し、完全にゼロを目指すのはやめておきましょう。
【まとめ】性欲を抑えることのメリットとデメリットを理解しよう
性欲を抑えることにはさまざまなメリットがあると同時に、覚えておかなければならないデメリットもたくさん存在します。
大切なのは「0か100か」ではなく、自分の体や生活リズムと相談しながら適度に性行為・自慰行為を行うこと。
未来の健康を損なわないためにも、自分の性欲と上手に付き合えるよう工夫してみてはいかがでしょうか。
ネガティブ思考は病気?うつ病との違いや治し方を解説

周りの人と比べて自分はネガティブ思考だ、と感じている方も多いのではないでしょうか。
中にはネガティブな気持ちが消えず、うつ病など精神的な病に当てはまるのではと不安に思っている方もいるでしょう。
今回はそんなネガティブ思考はどうして生まれてしまうのか、精神疾患との違いも踏まえながらご紹介します。
ネガティブ思考を脱却するための方法も併せてチェックしていきましょう。
ネガティブ思考は病気なのか?

端的にいえば、ネガティブ思考自体が何かの病気に当てはまることはありません。
しかし、精神疾患の中には気持ちが落ち込んでしまったり、長い間明るい気持ちになれず引きこもってしまったりするものもたくさんあります。
ネガティブ思考は決して放置して良いものではなく、さまざまな病の原因になりかねないことを覚えておきましょう。
ネガティブ思考の怖いところは、単に悲しいことを考えるだけに留まらず、どんどんと悪い思考が続いて脱出できなくなってしまうという点です。
ネガティブ思考がループし始めると、趣味や自分の好きなことも心から楽しめなくなり、毎日を生きる活力さえ奪われてしまうでしょう。
自身がネガティブ思考であることを正しく認識し、脱出するための手を考えることが大切です。
ネガティブ思考が止まらないのはなぜ?

ネガティブ思考が止まらずに悩んでいても、その原因が本人にあるとは限りません。
これまでの環境や子ども時代の育てられ方など、外的要因が積み重なってネガティブ思考を形成している可能性も考えられます。
ネガティブ思考だからといって自分を過度に責めることなく、正しい原因を探っていきましょう。
ネガティブ思考が止まらずに頭の中が悪い内容でいっぱいになってしまうことを、「ぐるぐる思考」「反芻思考」などと呼びます。
まずはこれらの思考がどうして始まってしまうのか、考えうる原因をご紹介します。
ついつい嫌なことや過去の失敗を思い出す
日々の生活のなかで、つい嫌だった経験を繰り返し思い出してしまう人も多いのではないでしょうか。
「黒歴史」などと呼ぶこともあり、思い出すことに恐怖を抱いている人もいるでしょう。
過去の嫌な経験と同じシーンに出会ったとき、嫌だった気持ちを思い出すのは自然なことです。
しかし、何の関係もないのにふと頭をよぎったり、過去の失敗を思い出していたたまれない気持ちになる経験が多いと、何をするにも楽しめなくなってしまうでしょう。
また、過去の失敗を思い出すのと同時に「どうしてあの時こうしなかったんだろう」
「ああしておけば失敗することはなかったのに」といった後悔が同時に襲ってくることがあります。
過去は変えられないため、通常であれば今後同じミスをしないよう注意すれば良いのですが、ネガティブ思考の場合はそれだけに留まりません。
いつまでも同じ失敗について後悔を重ね、前に進めなくなってしまう人も珍しくないのです。
認知の歪み
「認知の歪み」という言葉は、精神科医・アーロン=ベック氏が提唱したものです。
何か失敗をしてしまったとき、通常の精神状態であればミスを振り返り、今後どうすれば良いのか解決方法を模索し始めるはず。
しかし、認知に歪みがあり正しい判断ができなくなっていると、全てが悪く思えてきてしまうのです。
認知の歪みは、自分のことを正しく認識できず、長所に目が向かなくなってしまいます。
自分の短所ばかりが気になるようになり、何をする際も「どうせできないから」と目を背けてしまうようになるでしょう。
何事も白か黒かで判断するようになり「できないものはできない」と諦めてしまうのも、認知の歪みに当てはまります。
少しの失敗があると全てがダメになったと感じたり、計画通りにいかないと全て投げ出してしまったりと、過度な完全主義に周りが振り回されてしまうこともあります。
ストレス
どんなにポジティブな思考の人でも、過度にストレスが溜まった状態では、正しい思考ができません。
仕事や家事・育児など忙しい日々を送る現代人の中には、知らず知らずのうちに少しずつストレスが溜まっている人も珍しくないでしょう。
その日のストレスはその日のうちに解消しなければ、感情にも影響を与えてしまいかねません。
ストレスの怖いところは、多くの人がその存在を無視してしまいがちだという点です。
誰もが少なからずストレスを抱えている現代社会では、少し嫌なことがあったくらいですぐに対処しようと考える人は少ないもの。
そうして積もりに積もったストレスが気持ちをよどませ、ネガティブ思考へと繋がってしまうのです。
疲労
日々を送る上での軽度な疲労であれば、すぐにネガティブ思考のループへと繋がる危険性は低いでしょう。
しかし、忙しい毎日で疲労がとれなくなったり、ストレスの溜まりやすい環境で蓄積された疲労であったりする場合は、精神への影響も強いといえます。
体が疲れている状態で無理に頑張ろうとすれば、ネガティブ思考が止まらなくなるのも不思議ではありません。
疲労が原因によるネガティブ思考の反芻は、悪化する前に原因を取り除いてあげる必要があります。
過重労働が原因であれば転職を、家事や育児が占める割合が大きい場合はパートナーと話合うなど、根本となる原因を模索しましょう。
1日の疲労をその日のうちに癒せるようになれば、自然と頭の中がクリアになり、ポジティブな考えが生まれやすくなります。
自尊心が低い
ネガティブ思考の中でもとりわけ注意しなければならないのが「自尊心の低さ」です。
失敗してしまったときに自分を顧みるのは必要なことですが、チャレンジする前から「どうせ自分にはできない」と諦めてしまうのは良くありません。
誰もが最初から自尊心が低くなることはなく、親からの声掛けや失敗したときのフォローなどが原因であることが多いでしょう。
「あなたはどうせできない」「何をしてもダメな子」「失敗したのはお前のせい」などと育てられれば、大人になっても自分を信じられないのは当然です。
自尊心が限りなく低いと感じる場合は、一度自分の幼少期を振り返ってみると良いでしょう。
幼少期に問題がない場合は、上司の態度やパートナーの発言なども影響しやすいポイントとなります。
少なくとも、自尊心の低さは自分だけが原因であるわけではありません。自分を責めすぎず、思い切って環境を変えてみるのも方法の一つです。
他人からの低評価
自尊心の低さにも通じるものがありますが、他人から正しく評価されない状態が続くと、ネガティブ思考がループする原因となります。
良い行いをしたにもかかわらず評価されなかったり、ミスを自分一人に押し付けられたりした経験のある方も多いのではないでしょうか。
人は誰でも、自分を自分で評価するだけに留まらず、周りからの目を気にしながら生きています。
努力したことや時間をかけて行ったことなどを周りから正しく評価されてこそ、頑張りが報われ次へのやる気となるのです。
他人からの低評価が続くと、自尊心が低くなり「自分ではできない」と考えるようになります。
モチベーションが上がらず失敗することも多くなり、再び他人から低い評価をつけられるといった悪循環に陥ってしまうでしょう。
関連記事:メンタルがやばいサインとは?メンタルの不調で休むのは甘え?
ネガティブ思考とうつ病の違い

ネガティブ思考が続くと「自分はうつ病ではないか」と考える人も多いでしょう。
精神疾患の代表的存在であるうつ病は、今も多くの人が苦しんでいる病の一つです。
うつ病は自分一人が頑張っても治ることがなく、精神科や心療内科で正しい治療を受けなくてはなりません。
実際にうつ病の症状にはネガティブ思考が含まれており、気持ちが沈んだ状態が続いたり、自分を責めたりする人も珍しくありません。
しかし、ネガティブ思考が続くからといって、必ずしもうつ病に当てはまるわけではありません。
病気ではない単なる思考である場合もあれば、うつ病以外の疾患が隠れている場合もあるでしょう。
気持ちが落ち込みやすいからといって自己判断でうつ病を疑うよりも、専門家に正しく判断してもらうことが大切です。
さらに、うつ病と診断されていても、特に気持ちの落ち込みや自尊心の低さといった症状が見られないケースもたくさんあります。
患者一人ひとりによって症状が大きく異なり、対処法も異なるのが精神疾患の難しいところ。
治るまでにも時間がかかりやすいため、通うのに負担がかかりにくく、相談しやすい医師を探す必要があります。
ネガティブ思考の治し方はある?

うつ病など、さまざまな精神疾患によりネガティブな思考になってしまう場合は、専門家と一緒に治療法を考える必要があります。
人によって適切な治療法は異なりますが、使われることの多いものには「認知行動療法」「マインドフルネス」などが挙げられます。
また、ネガティブ思考を治すためには、医師による治療だけでは不十分です。
自分でできることを試しながら、生活習慣を正していくことこそ、ポジティブ思考への第一歩といえるでしょう。
認知行動療法
認知行動療法は、うつ病をはじめとするさまざまな精神疾患に効果が得られやすいとして多くの医療機関で注目されている治療法です。
先ほども触れた「認知の歪み」を正し、ネガティブ思考から脱却するためにも役立つといわれています。
通常、私たちが何かに挑戦するとき全て完了したならば「良かった」何一つとして終わらなかったのであれば「ダメだった」
半分終わったならば「半分はできた」と捉えるでしょう。
しかし、認知に歪みがあると、例え半分は終わっていたとしても「全てできなかったのだからこの半分は無意味だ」と感じてしまうのです。
認知行動療法では、まずこの歪みに本人が気づくことから始まります。
専門家による指摘を受けながら考え方を正し、自然と「半分はできた」という考えに近づけていくことが目標です。
このようなバランスの良い考え方は多くの場面で必要となるため、認知の歪みを正すことでさまざまな疾患に対応できると考えられているのです。
マインドフルネス
私たちがネガティブ思考に陥るとき、そのほとんどは過去の失敗を後悔していたり、未来で挑戦することに不安を覚えていたりするでしょう。
マインドフルネスでは、瞑想をすることで「現在の自分」に焦点を当てることを目的としています。
目を閉じて楽な姿勢をとり、自分の呼吸に集中することで意識をクリアに保てるでしょう。
気持ちが落ち着くような音楽をかけながら瞑想することで、心の深いところからリラックスしてみるのもおすすめですよ。
リフレーミング
リフレーミングとは、偏った考え方をしてしまうネガティブ思考に対し、別の考え方に気が付くことで思考の幅を広げる治療法です。
一つのタスクに対して「終わっている」「終わっていない」
このように極端に考えるよりも「半分終わっているから後はもう少しだ」という新たな考えに気が付くことが大切です。
自分の気持ちが全てではなく、新たな考え方も取り入れることで、自分の中に眠っているポジティブな気持ちにも気が付きやすくなるでしょう。
書き出し
ネガティブ思考のループに陥ってしまうと、頭の中で考えが巡り始め、他のことが考えられなくなってしまいます。
悪い内容で頭がいっぱいになるため、嬉しいことや楽しいことがあっても喜ぶ気持ちが入り込む隙がありません。
そこで、自分の気持ちを整理するためにも、思ったことを何でも紙に書きだしてみるのがおすすめです。
一度紙に書いてアウトプットした内容は再び深く思考せずに済むため、次第に頭の中に余裕が生まれてくるでしょう。
ここで紙に書く内容は、周りのことを考える必要も、誰かに気を遣う必要もありません。
自分もしくは医師だけが見られる内容として、どんなことでも気にせず書き留めていきましょう。
イベントなどに積極的に参加
ネガティブ思考で頭がいっぱいになってしまうのは、ほとんどが一人で過ごしている時間ではないでしょうか。
誰とも会話をせず自分に意識を向けているからこそ、悪い内容が頭を占め、ループから抜け出しにくくなってしまいます。
そんなときは、自分が参加しやすいイベントを探し、いつもとは違う環境に身を置いてみるのがおすすめです。
これまで会ったことのない人と積極的に関わることで、過去にとらわれず新たな考えが浮かびやすくなります。
数々のイベントを主催している病院もあるため、同じネガティブ思考に悩んでいる人と話す機会も探しやすいでしょう。
自分一人で抱え込むのではなく、周りを頼りながら少しずつ改善を目指すことが大切です。
運動
適度な運動を続けることは、ネガティブ思考から脱却するために重要なポイントといえます。
体を動かすと脳から「セロトニン」と呼ばれる物質が分泌されます。
これはドーパミン・オキシトシンと並んで「三大幸せホルモン」と呼ばれており、精神を安定させるはたらきを担っています。
セロトニンは、喜んだときに分泌されるドーパミンや、不安を感じたときに分泌されるノルアドレナリンの量をコントロールするためにもはたらいています。
不安に支配されやすい人にとっても、セロトニンは必要な物質といえるでしょう。
運動を行う上で大切なのは、「なるべく継続する」ということです。初日に過剰な運動を行うのではなく、まずは数分単位から始めましょう。
健康的な生活習慣を維持
身体的な健康にとってはもちろん、メンタルを強く保つためにも、生活習慣の改善は必要不可欠です。
夜更かしや朝食を抜く、好きなものだけを食べるといった生活習慣の乱れは、栄養不足や睡眠不足を引き起こします。
これが続けば続くほど精神は不安定になり、ネガティブ思考から抜け出せなくなってしまうのです。
まずは食事や入浴・睡眠の時間を揃え、毎日同じサイクルで生活できるように調整してみましょう。
朝起きたらすぐにカーテンを開け、日の光を浴びて脳を活性化させます。
タンパク質・脂質・炭水化物・ビタミン・ミネラルのバランスを考えながら、偏りのない食生活を心掛けることも大切です。
関連記事:メンタルブレイクした時はどうすればいい?診断方法や治し方を紹介
【まとめ】ネガティブ思考は病気ではない
ネガティブ思考は決して病気ではないものの、放置すればさまざまな精神疾患を発症する可能性があります。
「これが自分だから」と諦めるのではなく、生活習慣を整えながら頭の中を整理してみましょう。
時には専門家に相談し、自分に合った対策を模索することも大切です。
重要なのは、ネガティブ思考も「自分の一部」だと考えること。
ネガティブになってしまう自分が悪いのではなく、あくまでもポジティブなことを考える余裕がないだけだと理解しましょう。
たくさんの時間をかけながら、無理することなく治療に挑んでみてはいかがでしょうか。
カルマとは?意味をわかりやすく解説|カルマを背負うとはどういうこと?

さまざまな占いにチャレンジしたことがある方や、スピリチュアルの世界に興味がある方ならば、一度は聞いたことがあるであろう「カルマ」
なんとなく意味を想像するものの、詳しい内容までは知らない人も多いでしょう。
今回は「カルマ」というワードについて、その意味を詳しくご紹介します。
「カルマが重い」「カルマを背負う」など、よく耳にする言葉についてもチェックしていきましょう。
カルマの意味とは?わかりやすく解説

カルマは、インドで使われていたサンスクリット語が由来になっているといわれており「作用」「行為」などといった意味で浸透していました。
インドの宗教観では、自分の行いが運命を決めるといわれ、良いことをすれば良い人生を、悪いことをすれば悪い人生を歩むと信じられています。
「カルマ=行為」とするならば、良いカルマが良い人生を、悪いカルマが悪い人生を導くといっても過言ではないでしょう。
これが転じて、仏教でもカルマという言葉が使われ始めます。
中国が発祥である仏教では、カルマを「業」という言葉で表し、インドの宗教と同じく私たちの行動全てを指す言葉として使われてきました。
行動の中には体を動かすものだけでなく、頭で考えたり、口に出したりするものも含まれています。
すなわち、どのような生き方をしてきたかで、その後の未来が決まることを指しているのです。
現代を生きる私たちは、どんなに相手を憎く思っていても、相手にそれが伝わらなければ良いと考えるでしょう。
気持ちが悟られないように作り笑いを浮かべるのも、決して珍しいことではないはずです。
しかし、カルマと運命の考え方では、例え心の中で思ったことであっても、その後の運命を大きく左右すると考えられています。
むしろ体でとった行動や、口に出した言葉よりも、誰にも知られず考えたことの方が運命に影響しやすいといわれているのです。
つまりカルマとは、インドや中国・日本などのさまざまな神様が唱える共通の認識。
どんな神様であっても悪行は決して許されず、自分の運命という形で返ってくると教えてくれているのです。
関連記事:マインドフルネスと瞑想の違いや初心者におすすめのやり方を徹底解説!
カルマを背負うとはどういうこと?

先ほどご紹介したカルマの本質を思い浮かべながら、スピリチュアルの世界でよく耳にする「カルマを背負う」という言葉の意味を考えてみましょう。
人は誰でも、良い行いをした人は良い人生を、悪い行いをした人は悪い人生を歩んでいるはずです。
即ち「自分の行い=カルマ」を背負いながら残りの人生を歩むという意味で、「カルマを背負う」という言葉が使われているのです。
悪い意味に捉えられがちな言葉ですが、決して悪行だけを意味するわけではありません。
同じような言葉に「業を背負う」があります。こちらは悪行を背負って生きることを意味し、悪い状態を指すときに使われる言葉です。
いずれにしても、人類は誰しもが今世、あるいは前世のカルマを背負って生きていると考えられます。
そして現在の行いこそが、未来や来世の人生を決める大きなきっかけとなることも間違いないでしょう。
カルマが重い人の特徴とは?

「カルマ」という言葉は、時として「カルマが重い」などと使われることがあります。
カルマには人によって重いもの・軽いものが存在しており、重いものはすなわち「乗り越えなくてはならない壁が高いこと」を指します。
主に悪い意味で使われることが多く、それだけこれまでの人生で悪行を繰り返してしまったということになります。
悪行を繰り返していても、重いカルマを背負って生きていくうちに、カルマが軽くなり良い人生を歩める可能性が出てきます。
もちろん、その後どれだけ善行を積むかによっても異なりますが、カルマが重いからといって全てが終わってしまうわけではないことを覚えておきましょう。
自分のカルマが重いのか、はたまた軽いのかを正しく理解することはできません。
現在の自分自身を振り返りながら、身に起こった出来事からカルマの軽重を推測することが大切です。
ネガティブな出来事が頻繁に起こる
特に悪い行いをしていないにもかかわらず、ネガティブな出来事ばかり起こると感じる場合があります。
これは、前世やこれまでの人生で悪いカルマが溜まり、それを背負っている状態だと考えられます。
前世やこれまでの人生で行った出来事は、その多くが同じ形で自分に返ってくるといわれています。
つまり、誰かに悪口を頻繁に言っていた人であれば、同じように現在誰かから悪く言われている可能性が高いということ。
物を盗んでいた人は、自分の大切なものを失いやすくなっているでしょう。
進展しない人生
振り返ればありきたりな人生で、良くも悪くも進展がないと感じる場合も、同じようにカルマが重いと考えられます。
進展がないということは、即ち自分がどんなことにも無関心であったといえます。
周りの人にも興味がなければ、自分自身についてもそれほど考えることがないなど、向上心がない状態であるといえるでしょう。
放置してしまえば今後も同じような状態が続き、誰かの記憶に残りにくいさみしい人生で終わってしまうかもしれません。
精神的な不安定さ
同じ出来事を経験していても、精神的に強い人とそうでない人では、受け止め方が大きく異なるでしょう。
もちろん幼少期の育てられ方や遺伝的要素も加わっているものの、カルマが重い人ほど精神的に不安定であるといえます。
通常であれば簡単に乗り越えられる壁でも、精神的に不安定な人は苦労することが多いでしょう。
日常生活でもさまざまな試練に挑む必要があり、ストレスが溜まる一方。出口が見えず、思うように頑張れない人も少なくないはずです。
しかし「こんな状態も過去の自分が起こした行動の結果である」というのがカルマの考え方です。
肉体的な不調
精神的な弱さのほか、体が弱かったり病気にかかっていたりといった肉体的不調も、カルマによる影響が強く出るポイントの一つです。
特にカルマの影響が強いのは、生まれ持った病気や障がいについて。
前世で他人を傷つけた経験がある人に多く見られ、現世では他人を傷つけることなく周囲に頼りながら生きていかなければならないという教えでもあります。
過去の経験からの解放が困難

いつまでも過去の経験がトラウマになっており、解放されずに悩んでいる人も多いのではないでしょうか。
中でも自分の行動が原因でトラウマになってしまった物事に対しては、カルマが大きく影響しているといわれています。
これは先ほどご紹介した「精神的不安定」にもつながります。
通常であれば過去の失敗を乗り越えて強くなっていくものの、不安定であるがゆえに失敗から立ち直ることができないケースがあります。
過去に人の失敗を笑ったり、蔑んだりした経験がある場合、同じように自分も苦しめられる可能性があるのです。
自己否定的な思考
カルマが重い人は、軽い人に比べ自分に自信がないことが多いといわれています。
それがゆえに自分を傷つけたり、何かと自分を下げた発言をしたりと、否定的な思考が抜けなくなってしまうのです。
自分の良さが見つからないだけでなく、他人からせっかく褒められていても「お世辞だろう」と素直に受け取れないケースも多々見られます。
前世で誰かを深く傷つけたり、侮辱する言葉を使っていたりすると、現世では自分が蔑む対象として認識されてしまうのです。
他人への過度な批判や嫉妬
重いカルマを背負っている人は、自分に自信が持てないあまり、他人に嫉妬することが多くなります。
自分にないものを持っている人が羨ましく見えたり、相手の努力を見ずに結果だけを妬んだりと、周りが気になって仕方がなくなるのです。
その結果、他人を過度に批判し周りから疎まれることもあるでしょう。
物質的な損失や金銭問題
過去にさまざまな悪行を行ってきた人の場合、現世でカルマが及ぼすのは精神や肉体に関することだけではありません。
大切にしていたものを偶然失うことになったり、友人や家族との別れを経験したりと、幾度となく損失の機会が訪れるでしょう。
また、カルマが重い人は金銭面でもうまくいかなくなるといわれています。
上手くやりくりができず借金を抱えることになるなど、生活が回らなくなるほどの問題を抱える人も珍しくありません。
スピリチュアルな悩み
過去にさまざまな悪行を積み重ねてきた場合、言葉では説明できないような事柄に悩まされることがあります。
人間関係や金銭面といった分かりやすい悩みではなく、「いつも見られている気がする」「心霊現象が起きた」といった科学的に説明できない悩みを抱えている人も。
こういった事象にはすぐに対処できる方法がないため、結果として長い間同じ悩みに苦しむ人もいるようです。
カルマの法則とは?
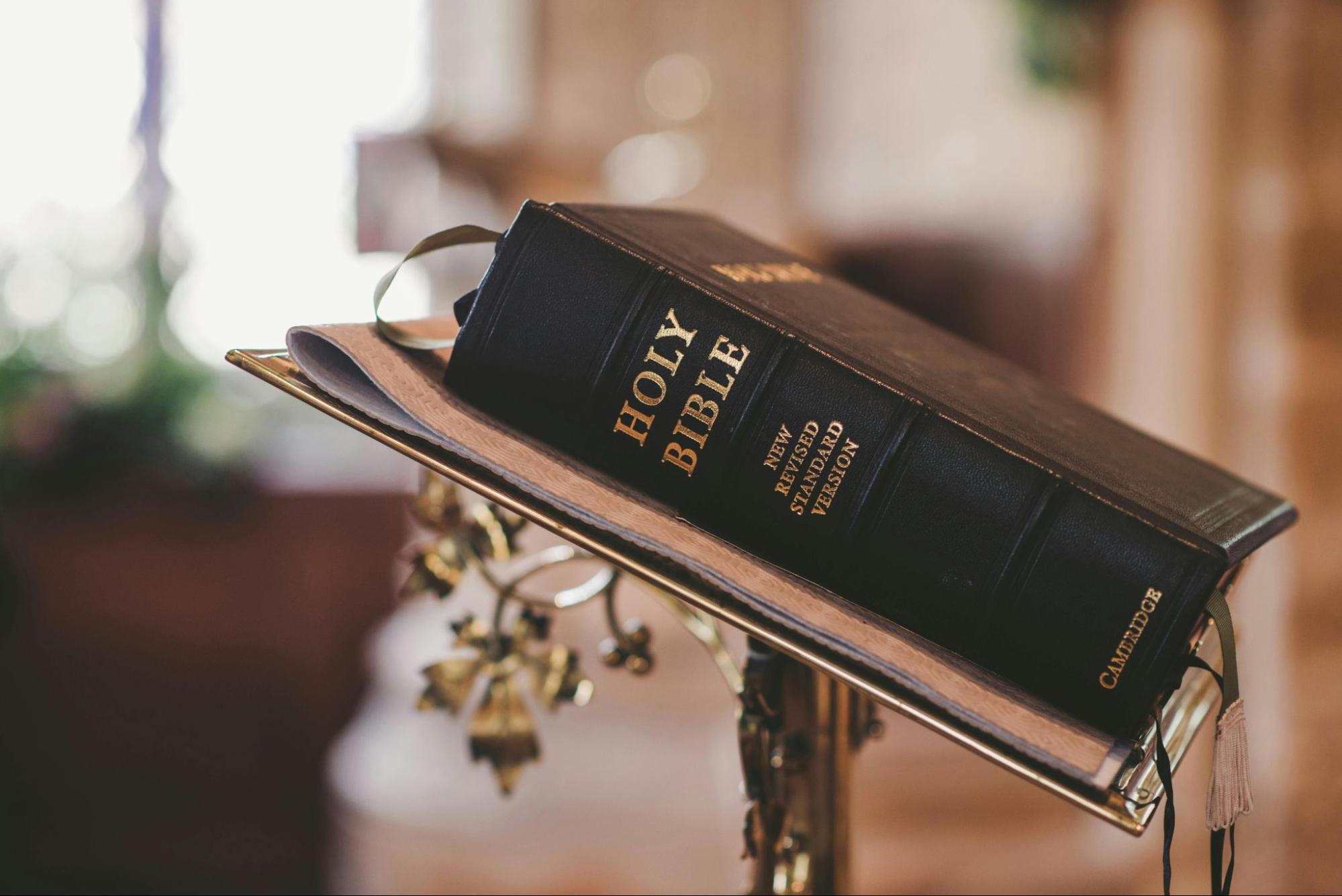
続いて、こちらも耳にすることが多い「カルマの法則」について詳しく見てみましょう。
カルマの法則の概要について
カルマの法則とは、すなわちこれまでにご紹介してきた内容を端的に述べた「自分の行いは自分に返ってくる」という内容を指します。
言い返せば「良い人生を送りたければ良いことをしなさい」という教えの一つ。
悪いことをしてはいけないという戒めであると同時に、人生の指南書としても活躍しているのです。
同じような言葉として「因果応報」があります。
四字熟語でありながら仏教用語でもある言葉で、カルマ同様善悪はすべて自分に返ってくるという意味を持ちます。
このように、言葉は違えど世界中で同じような考えが浸透しており、私たちはその教えの中で生きているのです。
恩恵を得るための方法
カルマの法則を知って恩恵を得るためには、以下の手順で自分を変えていくのがおすすめです。
- 気持ちを変える
- 言葉を変える
- 行動を変える
先ほどもご紹介したように、カルマの良し悪しを決めるのは行動だけに留まりません。
もっとも重視されるのは「気持ち」であり、最初に変えなければならない点でもあります。
まずは自分や他人に対する否定的な気持ちを変え、ポジティブに過ごすことから始めましょう。
気持ちが整ってから、言葉や行動を変えてみても遅くはありません。
関連記事:ジャーナリングのやり方は?日記との違いや効果について
自分のカルマを知る方法は?

一般的に、自分のカルマについて詳しく知る方法はありません。
過去にどんなことをしていて現在があるのか、想像しながら行いを正していくほかないのです。
続いては、そんなカルマを想像するために重要な3つのポイントについてご紹介します。
自分の人生を振り返ってみる
自分のカルマを正しくイメージするためには、これまでの人生を詳細に振り返ってみることが大切です。
失敗や悲しかった出来事などは、思い出に残りやすいです。それらについてどう考えたのか、結果として何が起こったのかなどを細かく振り返ってみましょう。
必要に応じてメモを取りながら、当時のことをできるだけハッキリと思い出すことが大切です。
こうして過去の自分を掘り出していくと、カルマによる影響が目に見えやすくなります。
前世や過去の行いが良かったのか悪かったのか、はたまたカルマが重いのか軽いのかなどを判断する参考にしてみてはいかがでしょうか。
自分の感情と向き合う
カルマを知るために重要なポイントの一つに「感情」があります。
先ほども触れたように、カルマを構成しているもっとも大きなポイントが感情です。
自分が思い描いた感情とは別の気持ちが表れたり、気持ちとは裏腹な行動をとってしまったりしたときは、カルマによる影響が強く出ていると考えて良いでしょう。
この感情は、過去の誰かがあなたに向けていた感情であるといえます。
現在の行動について良い気持ちがあるのならば、あなたは良いカルマを持っている証拠。逆であるならば、今後の感情や行動を見直す必要があるでしょう。
人間関係を見直す
周囲の人間とどのような関係を築いているかも、カルマの良し悪しを判断するポイントになります。
その人が好きか嫌いかといったシンプルな問題だけでなく、これまでの日々でどのような関係になれたのかを詳しく思い返してみましょう。
あなたの周りに良い人が多いならば、過去の善行が今に表れているといえます。
逆にあなたにとって不都合な人間関係が多い場合は、重いカルマを背負っていると判断できます。
自分が悪くなくても相手のトラブルに巻き込まれたり、困難なお願いを頻繁にされたりする場合は、感情や行動を改める必要があるかもしれません。
関連記事:スピリチュアルカウンセラーとは|本物になるためにはどうすればいい?
カルマの意味についてのまとめ
どんな人でも必ず、前世やこれまでの自分が歩んできた人生がカルマとなって現れているはずです。
それが良いことであれば引き続き来世へとつなげ、悪いことであれば今断ち切るために努力しましょう。
悪いカルマを断ち切るための努力は、きっとあなた自身を成長させてくれるはずです。
また、悪いカルマの中でも重いカルマだと感じる場合、自分が背負っているものについて専門家に相談するのもおすすめです。
電話占いや対面占いなど、自分が利用しやすい方法で相談すると良いでしょう。
メンタルがやばいサインとは?メンタルの不調で休むのは甘え?

仕事や家事・育児・介護などさまざまな面において、毎日忙しい時間を過ごしている現代人。
一日の終わりにしっかりと休息をとったり、時には自分の好きなことを思い切りやったりする時間がとれれば良いですが、慌ただしい毎日の中ではそう上手くいかないものです。
今回は、普段頑張っている全ての人に向け、メンタルのバランスが崩れるときの見分け方をご紹介します。
チェック項目や不調時の対処法を確認し、明日を元気に過ごすための参考にしてみてはいかがでしょうか。
メンタルがやばいサインとは?セルフチェック項目

「何だか不調が続いている」「気持ちが落ち込んで戻らない」など、メンタルのバランスが崩れるとさまざまな症状が見られます。
悲しい出来事があって、少しの間落ち込むくらいならば通常の範囲内です。
しかし、落ち込んだ状態があまりにも長く続いたり、悲しい出来事がないのに気持ちが不安定になったりする場合は、メンタルに影響が出ている可能性があります。
まずは自分で自分の状態をしっかりと把握するために、以下の項目を確認してみましょう。
当てはまるものが多ければ多いほど、メンタルにダメージを受けている可能性が高まります。
- 持続する悲しみや気分の低下
- かつて楽しんでいた活動への興味喪失
- 食欲や体重の変化
- 睡眠障害
- 疲労感やエネルギーの欠如
- 価値のなさや過剰な罪悪感の感覚
- 集中力の低下
- イライラ感や怒りの増加
- 社会的な場からの撤退
- 説明できない身体的症状
- 死や自殺の考え
何日経っても気持ちが晴れなかったり、これまで楽しんでいた活動がどうでも良いと感じたりするなど、メンタルの不調はさまざまな弊害を生んでしまいます。
仕事に集中できずミスを頻発したり、理由もなくイライラして周りと軋轢を生んでしまったりと、人間関係に影響が出ることもあるでしょう。
その結果過ごしにくい日々が続き、さらに心を病んでしまう人も少なくありません。
さらには、上記のような心の問題だけでなく、体重減少や睡眠障害が発生する場合もあります。
身体的な問題がないにもかかわらずこのような症状があらわれた場合は、一度精神科や心療内科などの専門家に相談しましょう。
メンタルにダメージを受けた状態が長く続けば、死にたいと考えるようになるなど重大なトラブルの原因にもなりかねません。
具体的に自殺の方法を考えてしまうなど、強い不安がある場合も必ず専門家を受診するようにしましょう。
関連記事:メンタルブレイクした時はどうすればいい?診断方法や治し方を紹介
メンタルの不調の原因は?

続いて、メンタルが不調になるのは一体なぜなのか、多くの人に当てはまる原因について見てみましょう。
一言でメンタルが病んでいるといっても、その原因や解決策は人それぞれです。
自分に合った方法を探すためにも、自分がなぜダメージを受けているのかをハッキリ知ることが大切です。
ストレス
仕事や家事・育児・介護など、さまざまな理由で忙しい毎日を送っている現代人。
どんな生活をしている人も、少なからずストレスを感じているものです。
適度なストレスは生活にメリハリが出る場合もありますが、多大なストレスを受けることや、小さなストレスが積み重なったままでいるのは良くありません。
多大なストレスは、原因となる出来事を防がなくてはなりませんが、小さなストレスは避けきれない場合も多いでしょう。
こういう場合は、適度に肩の力を抜き、リラックスできる時間を確保することが大切です。
種類の違うストレスであっても、発散しない限りは体に溜まり続けてしまうもの。
結果として心身に影響が出る前に、自分に合った発散方法を見つけましょう。
また、自分で望んだ仕事をしているときや、可愛い我が子を育てているときなど、自分が楽しいと思っていても少なからずストレスが発生しています。
ミスをしないように、子どもを危険に晒さないようになどといった緊張感もストレスに繋がるため、「ストレスを受けないようにしよう」と努力しすぎないことが大切です。
生活習慣の乱れ
朝食を抜いたまま出かけたり、毎日寝る時間がバラバラだったりと、理想的な生活習慣を送れていないとメンタルに影響が出やすくなります。
不規則な生活を送っている場合は、食事や睡眠の時間を毎日同時刻に揃えるだけでも気持ちが落ち着きやすくなるでしょう。
乱れた生活習慣が続くと、交感神経・副交感神経のバランスが崩れ、働くべきときに働けなくなってしまいます。
夜眠る前なのに交感神経が優位になり睡眠不足になったり、日中副交感神経がはたらいて異常な眠気を催したりと、生活に支障が出ることも少なくありません。
また、「自律神経失調症」のように原因不明の症状に悩まされる可能性もあります。
呼吸や血圧の上昇・下降などを司る自律神経がうまくはたらかなければ、息苦しさや熱っぽさ、めまいや吐き気などさまざまな症状があらわれるでしょう。
これらを短時間で治すのは難しく、専門家とともに長い時間をかけて治療を行わなければなりません。
人間関係の問題
メンタルに影響を及ぼす原因の中でも、多くの人が抱えているのが「人間関係の問題」ではないでしょうか。
職場内であったり、子どもの学校や幼稚園・保育園で親同士が関わったり、はたまた家庭内の関係であったりとその状況はさまざまです。
どんな状況においても100%好かれる人間が存在しないように、誰しもがどこかで嫌な思いをしているといっても過言ではありません。
大切なのは、嫌な思いをしたときに「どれだけ気にせずにいられるか」という点。
心に余裕があれば受け流すこともできますが、自分に自信がないなどの理由で過度に気にしてしまう人も多いでしょう。
また、人間関係の問題は自分一人が悩んでも解決できないのが難点です。
問題を解決しようとはたらきかけることも、何もせずにじっと耐えることも、どちらの場合も自分にとってのストレスとなってしまうでしょう。
周囲に頼れる人がいる場合は、必要に応じて相談や巨力を求めるなど、自分一人で抱え込まないことが大切です。
経済的問題
十分な貯蓄がなかったり、借金をしていたりといった経済的な問題も、メンタルに影響を及ぼす大きな原因の一つです。
物価が軒並み高騰する中、毎日の食費に気を配っている方も多いのではないでしょうか。
こういったやりくりを続けることや、突発的に起こる大きな出費、未来の経済環境に不安を覚えることでさえもストレスとなってしまうでしょう。
例え十分に貯蓄ができていたとしても、子どもの学費や将来仕事ができなくなったときのことなどを考え出せばキリがありません。
過度な節約で疲れてしまうことのないよう、肩の力を抜いた生活を心掛けましょう。
職場環境

仕事にやりがいを感じられなかったり、不得意な仕事でミスをしてしまったりといった職場環境も、見直さなければならないポイントの一つといえます。
人間関係に問題がなかったとしても、過剰な残業や休日出勤などで心身ともに疲弊してしまう人も珍しくありません。
場合によっては転職も考えながら、自分の職場について見直してみることをおすすめします。
遺伝的要因
病気そのものが血縁から引き継がれることはないものの、精神的な病が発症するかどうかは遺伝的要因も大きいといわれています。
親族にうつ病がいる場合、そうでない場合と比べて発症リスクが数倍高まったという研究結果も存在します。
もちろん遺伝がすべての要因ではないものの、家族に精神疾患を経験した人がいる場合はより一層注意すると良いでしょう。
参考:うつ病は遺伝するの?精神科専門医が分かりやすく解説します
身体的健康問題
メンタルにダメージを負う原因は、心の問題だけではありません。
単なる風邪で気持ちが落ち込んでしまうこともあれば、重大な病をきっかけにうつ病を同時発症してしまう例もたくさんあります。
体の健康は心の健康といっても過言ではなく、「咳が出る」「鼻が詰まる」といった軽微な症状であっても気持ちが落ち込んでしまうのです。
不調が長く続けば続くほど、落ち込んだ状態も長引いてしまいかねません。
忙しい人であればつい後回しにしてしまう通院も、なるべく早い段階で検討すると良いでしょう。
心理的トラウマ
過去に経験した出来事がトラウマとなり、メンタルを傷つけている可能性もあります。
自分で気づいているトラウマであれば避けられますが、中には知らないうちに心の奥深くへ刻み込まれているものもあり、一概にはいえません。
例えば、自動車事故を経験した人であれば、以前と比べて車に乗るのが怖いと感じても不思議ではないでしょう。
プレゼンテーションで失敗した経験から、多くの人の前で話すのが苦手になる人も珍しくありません。
こういった心理的トラウマは短期間で改善するのが難しいため、まずは自分のトラウマを理解し、原因を探ることから始める必要があります。
薬物やアルコールの乱用
日本で禁止されている薬物はもちろん、市販の医薬品を飲みすぎたり、多量のアルコールを継続して摂取したりする場合も、メンタルに大きな影響を及ぼします。
脳に大きなダメージを与える薬物を日常で目にすることはありませんが、市販の医薬品やアルコールは誰でも手軽に手に入るものばかり。
依存することがないよう、適量を守らなければなりません。
医薬品やアルコールを乱用すると、次第に依存するようになり、それがなくては生活ができない状態になる可能性があります。
自力で抜け出せない状態になるケースも珍しくないため、医薬品は用法容量を守り、アルコールは適度な量を楽しみましょう。
情報過多
メンタルについて調べてみると、驚くほど多くの情報がヒットします。
この中から正しいものを選びとり、自分に必要な情報だけを利用しなければならないため、調べているだけで疲れてしまっても不思議ではありません。
どんな情報を調べるときであっても、私たちには正しいものを判断する力が求められています。
気持ちに余裕がないときほどネットの沼にはまってしまいがちですが、焦りや不安を感じているときはスマートフォンを置き、目や頭を休ませてあげることも大切です。
関連記事:ネガティブ思考は病気?うつ病との違いや治し方を解説
メンタルの不調になったらどうすればいい?

続いて、メンタルの不調を感じたとき、私たちがとるべき行動について確認してみましょう。
自分の感情を受け入れる
自分がどんな感情をもっていたとしても、それは自分だけのものであり、周りに非難されてはいけません。
例え周りに受け入れられにくい内容であっても、自分だけは感情を認めてあげましょう。
「こんなことを言ったら嫌われるかもしれない」「恥ずかしくて周りに打ち明けられない」といった内容も、自分の中で消化することに問題はありません。
声に出してみたり、日記に書いてみたりと、自分だけが知るアウトプット方法を探すのがおすすめです。
十分な休息をとる
どんな原因でメンタルがダメージを受けていても、まずは十分に休息をとることから始めましょう。
時にはやるべきことを後回しにしてでも、睡眠やボーっとする時間を確保することが大切です。
十分に休息をとり、体が万全の状態になってから原因について考えても遅くありません。
まずは体の不調を防ぐためにも、睡眠時間を長めにとってみてはいかがでしょうか。
趣味やリラックスできる活動をする
十分な休息をとると同時に、自分の好きなことや趣味に費やす時間を確保することも大切です。
他のことを気にせず没頭できる趣味があれば、メンタルを回復させ、不調を治すきっかけとなるでしょう。
体を思い切り動かすも良し、黙々と作品を作るも良し、心から楽しめる活動を見つけてみると良いでしょう。
運動をする
普段から運動する習慣が身についている人ならば良いですが、そうでなければ軽度な運動を取り入れてみるのもおすすめです。
急に負荷の大きな運動を始めるのではなく、10分間のストレッチや1kmのウォーキングなどできることから始めましょう。
ダイエットなどとは違い、毎日必ず運動をしなければならないわけではありません。
「やらなければならない」と無理をするのではなく、あくまでも気分転換として軽い運動を選択肢に加えてみてはいかがでしょうか。
健康的な食生活を心がける
丈夫な体作りとしてはもちろん、心を安らかに保つためにも、健康的な食生活は必要不可欠です。
過度な食事制限や野菜ばかりのメニューを続けるのではなく、栄養バランスの整った食事を心掛けましょう。
1週間のうち1日は好きなものを食べる日に定めるなど、やる気を保つための工夫も大切です。
睡眠の質を向上させる
メンタルを回復させるために、十分な休息は必要不可欠です。つまり、良質な睡眠をとることこそが健康への第一歩といっても過言ではないでしょう。
単に睡眠時間を長くするだけでなく、ゆったりとした寝巻きに変えたり、室温を調整したりして睡眠の質を高めてあげるのもおすすめ。
夜中に何度も起きることなく、朝までぐっすりと眠れる睡眠が理想的です。
人との繋がりを大切にする
メンタルに影響しがちな人間関係をトラブルのないものにするために、普段から周囲との関係を良好に保っておくことが大切です。
苦手な人にも笑顔を保つ必要はありませんが、不要なトラブルを防ぐために適度な距離を保ちましょう。
人との繋がりを大切にする上では、自分の気持ちを素直に話せる相手を見つけるのも重要です。
何かあったときに相談できる相手がいれば、強い不安や焦りなどの感情も緩和されやすいでしょう。
マインドフルネスや瞑想を試す
目を閉じて自分の気持ちに集中する瞑想をはじめ、現在の出来事に関して深く考えるきっかけとなる「マインドフルネス」もメンタルを安定させるために役立つ方法の一つです。
一人になれる場所で、まずは数分間から自分と向き合う時間を作りましょう。
自分が何を望んでいるのか、何に悩んでいるのかを深く知ることで、メンタルが不安定になる回数や頻度を減らすことに繋がります。
専門家に相談する
これまでご紹介してきた内容は、あくまでも自己判断であったり、自分でできるメンタルケアが中心でした。
しかし、自分自身と向き合い悩みを解決するということは、簡単そうに見えてなかなか難しいもの。
こういうときは、精神科医や心療内科医・臨床心理士・カウンセラーなどの専門家に話を聞いてもらうのがおすすめです。
薬を使った治療法の他にも、カウンセリングや心理療法によるケアにもチャレンジできるでしょう。
専門家は数ある症例や経験の中から、一人ひとりの状態を見抜いて適切なケアを施してくれます。
一人で悩む前に、まずは相談から試してみることをおすすめします。
メンタルの不調で休むのは甘え?

少し前までの日本では、身体的な不調であればともかく、周りが気づきにくいメンタルの不調で仕事を休むのは甘えだといわれていました。
「うつ病は甘え」「メンタルを病む人はサボりたいだけ」などと言われ、さらに自分自身を追い込んでしまう人も決して少なくなかったのです。
現在は、企業カウンセラーが導入されたり、細かいハラスメント規則が定められたりと、これまでよりも心理的な面でのケアに力を入れる企業が増えてきました。
もちろん全ての企業ではないものの、昔に比べメンタルの不調でも休みやすい環境へと近づきつつあるでしょう。
とはいえ、メンタルの不調は周りからすると辛さが分からず「休むほどのことなのか」といわれてしまいがちです。
必要に応じて医師に診断書を書いてもらったり、カウンセリング結果を提出したりして、周囲にも状況をしっかりと把握してもらうことが大切です。
【まとめ】メンタルがやばいサインを感じたら無理は禁物
私たちが過ごす日常の中では、メンタルにダメージを与えるような出来事がたくさん潜んでいます。
避けられるものは避けながら「やばい」と感じたときはすぐに自分自身を守りましょう。
今回ご紹介した対処法を試しながら、無理をせずに過ごすことが大切です。
メンタルの不調は軽視されがちですが、時として長く落ち込んだ状態から抜け出せなくなるなどのリスクがあります。
専門家を味方につけながら、自分に合った対処法を探していきましょう。
アンガーマネジメントのやり方|「意味ない」と言われる理由とは?

近年、「アンガーマネジメント」に対する注目が高まっています。
その一方で、アンガーマネジメントが「意味ない」と言われることも少なくありません。
そこで、この記事ではアンガーマネジメントのやり方や考え方について解説します。
また、なぜアンガーマネジメントが「意味ない」と言われるのか、その理由についても見ていきましょう。
アンガーマネジメントとは?
アンガーマネジメントとは、アメリカで生まれた怒りと上手に向き合うための心理的なトレーニングです。
アンガーマネジメントの目的は「怒らないこと」と思われがちですが、それはアンガーマネジメントの本来の目的ではありません。
アンガーマネジメントでは、必要があるときに適切に怒れることが目標です。
犯罪者の更生プログラムであったアンガーマネジメントは、近年一般化されてきました。
多くの人が怒りのコントロールができるようになるため、アンガーマネジメントを取り入れています。
アンガーマネジメント能力の診断方法
アンガーマネジメント能力の診断方法は、主に次の2つです。
- 自己診断のためのチェックリスト
- 日本アンガーマネジメント協会の無料診断
それぞれの診断方法について、以下で見ていきましょう。
自己診断のためのチェックリスト
以下に、自己診断をするためのチェックリストを用意しました。
ぜひ、自身にアンガーマネジメント能力があるかをチェックしてみてください。
- 自分が怒っているときにそれを自覚することができる
- どういった状況で怒りの感情が沸き起こるか理解している
- 怒りを表現する際の適切な言葉や行動の選択ができる
- 挑発に対して耐えることができる
- 自分の感情を正確に認識することができる
- 対立や不和の状況でのコミュニケーションをとることができる
- 他者の視点を理解し、共感を示すことができる
- 怒りを覚える状況に対して適切な解決策を見つけ、実行できる
- 自分の感情を鎮めるための方法を持っている
- 怒りの発生後に自己反省を行う習慣がある
- 行動の結果を評価し、将来的な改善点を見つける意欲がある
当てはまる項目が多ければ多いほど、アンガーマネジメントの能力が高いと言えるでしょう。
日本アンガーマネジメント協会の無料診断
日本アンガーマネジメント協会の無料診断を受けることでも、自身のアンガーマネジメント能力をチェックできます。
以下のページから、日本アンガーマネジメント協会のLINE公式アカウントをお友だち登録すると診断できます。
上記のチェックリストとあわせて活用してみてください。
アンガーマネジメントのやり方

アンガーマネジメントには、次の5つのやり方があります。
- 深呼吸
- 他のことを考える
- 運動する
- 相手の立場を考えてみる
- 専門家の支援を求める
それぞれのやり方について以下で見ていきましょう。
深呼吸
アンガーマネジメントのテクニックに「深呼吸をする」があります。
怒りを覚えると、私たちの呼吸は速く浅くなりやすいのです。
深呼吸をすることで、速く浅い呼吸を落ち着けることができ、それと同時に怒りの感情もだんだんとおさまってきます。
特に、深呼吸をする際には、吐く息を長くすることを意識すると、よりリラックスしやすくなるでしょう。
他のことを考える
他のことを考えることも、アンガーマネジメントのテクニックの1つです。
たとえば、学生時代の楽しかった思い出や、仕事で褒められたことなどを思い返してみてください。
ポジティブな内容を思い返すことで、喜びや嬉しさなどの怒りと反対の感情が生まれ、怒りをおさめられます。
また、怒りの対象が目に入らないようにすることもおすすめです。
その場から離れたり、目を瞑ったりして怒りの対象から目をそらすことでも、怒りの感情をおさめられるため、ぜひ試してみてください。
運動する
運動には身体的な健康だけでなく、精神的な健康にもプラスの効果があることが多数の研究結果により明らかになっています。
特に、週3回以上の有酸素運動をおこなうことで、その効果は大きくなります。
有酸素運動に該当するのは、ウォーキングやジョギング、水泳など。
身体的な健康と精神的な健康の両方が手に入るため、週3回以上を目安に軽めの運動を取り入れてみてください。
相手の立場を考えてみる
相手の立場を考えてみることもおすすめです。
いざ相手の立場に立ってみると、相手の言動について理解でき、怒りがおさまる場合があります。
また、相手の考えを否定ばかりしていると、どんな状況でも相手の考えを受け入れられなくなってしまう可能性があります。
しかし、時には柔軟な考え方をもち、相手の考えを取り入れることも大切。
考えの柔軟さを手に入れるためにも、相手の立場を考えてみることはおすすめです。
専門家の支援を求める
今までに紹介した4つ以外にも、アンガーマネジメントにはさまざまなテクニックがあります。
しかし、それらを自分自身で実行し、アンガーマネジメントをおこなうのは簡単ではありません。
「自力での実行が難しい」と感じたら専門家の支援を求めるのも1つの手段です。
それぞれの人にあわせて適切なテクニックを紹介してくれて、アンガーマネジメントができるまで伴走してくれます。
ぜひ信頼できる専門家を見つけて、支援を求めてみてください。
関連記事:【怒りを抑える】アンガーマネジメントのテクニックや方法をご紹介!
アンガーマネジメントにおける「6秒ルール」とは?

アンガーマネジメントには「6秒ルール」というテクニックもあります。
6秒ルールとは、怒りが湧いてきたら、6秒だけ数えて怒りが静まるのを待つことです。
6秒ルールで心を落ち着けるには、心の中で1から6をゆっくりと数えることが大切です。
怒りに反射せず、少しでも時間を空けることで、怒りをおさめられやすくなります。
アンガーマネジメントは意味ない?胡散臭い?
「アンガーマネジメントは意味があるの?」
「アンガーマネジメントって胡散臭いものでしょ?」
アンガーマネジメントに対して、このような疑問を抱えている方もいるかもしれません。
たしかに、アンガーマネジメントを学んでも怒りの感情はなくならないため、「怒りの感情をなくす」点では意味がないと言えるでしょう。
しかし、アンガーマネジメントの目的は、怒りの感情を「コントロール」することにあります。
目的を間違えずに地道に実践することで、徐々に怒りの感情がコントロールできるようになり、必要のない場面で怒ることを減らせるようになるでしょう。
子どものアンガーマネジメントについて
アンガーマネジメントは「大人向けのもの」と無意識のうちに認識している人も多くいるかもしれません。
しかし、子どもがアンガーマネジメントを身につけることも重要です。
子どもが感情に任せて行動してしまうと、良好な人間関係の構築が難しくなります。
特に、子どもの時期に人間関係がうまくいかないと、失敗経験を大人になっても引きずってしまう可能性があります。
そのため、子どももアンガーマネジメントを通して、相手とのコミュニケーションの取り方を身につけることが大切です。
関連記事:【誰でもできる】マインドセットの意味や使い方を簡単に解説!
アンガーマネジメントの実践例
筆者が接客業のアルバイトをしていたとき、お客さまからクレームをつけられたことがありました。
いちゃもんと言うべき内容であったため「なぜ自分が怒られなければいけないのか」とお客さまに対して怒りを覚えましたが、立場上、お客さまに反論することはできません。
また、反論したところで更なるトラブルを生むだけであるため、反論しても意味がありません。
深呼吸した後に「今は我慢だ」と自分に言い聞かせ続けていると、だんだんと怒りがおさまってきて、お客さまの言い分を冷静に聞けるようになりました。
状況を察した店長が駆けつけてくれて、代わりに対応してくれたおかげで、その場は事なきを得ました。
深呼吸したり、気持ちを落ち着ける言葉を自分自身に対して言い続けたりしたことにより、不必要に怒ることを回避。
怒りを覚えても、アンガーマネジメントを活用することで、大きなトラブルに発展せずに済みました。
【まとめ】アンガーマネジメントをマスターしよう
アンガーマネジメントをマスターすることで、怒りの感情をコントロールできるようになります。
深呼吸や運動、6秒ルールなどを用いて、アンガーマネジメントをマスターできるようにトレーニングしてみてください。
もし自分の力だけでアンガーマネジメントをマスターするのが難しいと感じた場合は、専門家に支援を求めることもおすすめです。
ぜひアンガーマネジメントをマスターし、良好な人間関係を築いていきましょう。
生理前の情緒不安定の対策|彼氏への伝え方はどうすればいい?

「生理前に情緒不安定にならないようにしたい!」
「生理前に起きる情緒不安定のせいで、彼氏との関係が悪化したらどうしよう」
このような悩みや疑問を抱えている方がいるのではないでしょうか。
この記事では、生理前の情緒不安定の対策や彼氏への伝え方について解説します。
生理前の情緒不安定はなぜ起こる?
生理前に起こる情緒不安定は、PMS(月経前症候群)の症状である可能性が高いと言えます。
PMSの症状には、身体的なものから精神的なものまでさまざまな種類があります。
PMSの症状を引き起こしているのは、エストロゲンとプロゲステロンといわれるホルモンです。
エストロゲンとプロゲステロンは、排卵後に多く分泌される一方、月経が近くなると急激に分泌量が低下します。
分泌量の急激な変化が脳内ホルモンなどに影響を及ぼすことにより、身体的・精神的不調が引き起こされると考えられています。
20代〜30代に多く見られる症状であり、生理周期および卵巣機能が正常でも症状を引き起こすことがあるため、辛いときは無理せず、婦人科に相談してみてください。
関連記事:女性の情緒不安定の治し方は?生理との関係や落ち着く方法を解説
生理前の情緒不安定の対策法は?
生理前の情緒不安定には、次の7つの対策法があります。
- 適切な栄養摂取
- 定期的な運動
- 十分な睡眠
- カフェインとアルコールの摂取を控える
- 良好なコミュニケーション
- 趣味や楽しい活動に時間を割く
- 専門家の助けを求める
それぞれの対策法について、以下で見ていきましょう。
適切な栄養摂取
女性ホルモンの効果が薄くなることで、生理前に情緒不安定になってしまうことがあります。
情緒不安定を改善するには、カルシウムとマグネシウムの摂取がおすすめです。
カルシウムとマグネシウムは、大豆製品や緑黄色野菜に多く含まれるため、ぜひこれらの食材を多めに摂るようにしてみてください。
定期的な運動
定期的な運動も、生理前に起きる情緒不安定の改善に効果があります。
激しい運動をする必要はなく、ジョギングやウォーキングなどの軽めの運動で十分です。
1日30分程度の軽めの運動を週3日するだけで、症状が改善する可能性があります。
隣の駅まで歩いてみたり、いつもバスに乗るルートの一部を歩いてみたりして、定期的な運動習慣を身につけてみてください。
十分な睡眠
生理前に起きる情緒不安定を改善したい場合は、十分な睡眠を心がけてみると良いでしょう。
月経前や月経中は、健康な女性であっても睡眠の質が低下してしまう可能性があります。
そのため、月経前や月経中の時期は、意識的に十分な睡眠ができるように心がけると良いでしょう。
寝る直前までスマートフォンやパソコンを使わないなど、できることから始めてみることをおすすめします。
カフェインとアルコールの摂取を控える
カフェインとアルコールの摂取を控えることも効果的です。
カフェインなどの刺激物を接種することで、神経が緊張したり興奮したりしてしまいます。
神経を落ち着かせてリラックスするために、コーヒーやお茶などカフェインが入っている飲み物は控えてみましょう。
また、アルコールなど体の不調の原因となる食べ物・飲み物を控えることも大切です。
規則正しい生活を送ることで、少しでも症状が改善できるようにしてみましょう。
良好なコミュニケーション
生理前に起きる情緒不安定の改善には、良質なコミュニケーションを取ることも効果があります。
たとえば、家族や親しい人には、PMSの症状が出てしまって情緒不安定になってしまう可能性があることを事前に伝えておくと良いでしょう。
そのうえで、情緒不安定になってしまったときに「やってほしいこと」も伝えておくことがおすすめです。
たとえば「ひとりにしてほしい」「家事を手伝ってほしい」「大目に見てほしい」などが考えられます。
情緒不安定のことを打ち明けるのは、勇気が必要かもしれません。
あなたと親密な関係を築いている人は理解してくれるので、勇気を出して打ち明けてみましょう。
趣味や楽しい活動に時間を割く
生理前に起きる情緒不安定を改善するには、ストレスを低減させることが効果的です。
そのため、精神的に疲れてしまうことがあったら、趣味や楽しい活動に時間を割いてリラックスしてみてください。
趣味や楽しい活動を通してリラックスすることで、ストレスを低減でき、生理前の情緒不安定が改善する可能性が高まるでしょう。
あらかじめ趣味や楽しい活動をする日時を決めておき、それを楽しみに日常生活を送ってみるのもおすすめです。
専門家の助けを求める
以上の6つで症状が改善しない場合は、専門家の助けを求めてみるのも良いでしょう。
婦人科を受診することで、薬を用いた治療を受けられる可能性があります。
精神安定剤や抗うつ薬、経口避妊薬、GnRHアゴニストなど、さまざまな種類の薬があるため、ぜひためらわずに専門家に相談してみてください。
関連記事:イライラして眠れない時はどうする?原因や対処方法を解説
生理前の情緒不安定に効く食べ物

ここでは、生理前の情緒不安定に効く食べ物について解説します。
ホルモンバランスを整える栄養素や気分を安定させる食べ物、避けたい食べ物について見ていきましょう。
ホルモンバランスを整える栄養素
ホルモンバランスを整える栄養素には、次のようなものがあります。
- カルシウム
- マグネシウム
カルシウムやマグネシウムは、女性ホルモンのバランスを整える役割が期待できます。
大豆製品や緑黄色野菜などを摂取することで、情緒不安定が改善しやすくなるでしょう。
また、ビタミンやミネラルも摂取すべき重要な栄養素です。
生理前に限らず、若い人の中にはビタミン・ミネラルが不足している人が多くいます。
摂取すべき栄養素をきちんと摂ることが心の健康にもつながるため、サプリメントなども用いて必要な栄養素を摂るようにしてみましょう。
気分を安定させるおすすめの食べ物
カルシウムやマグネシウム、ビタミンB6には気分を安定させる効果があります。
そのため、前述したように、大豆製品や緑黄色野菜を食べることで、気分を安定させやすくなるでしょう。
特に大豆製品は、女性ホルモンと類似した働きをするイソフラボンも摂取できるため、ぜひ摂取したい食べ物です。
また、次のような食べ物からもカルシウムやマグネシウム、ビタミンB6を摂取できます。
- カツオ
- レバー類
- ナッツ類
- 海藻類
加えて、ビタミンEが接種できるアーモンドなどもおすすめですので、ぜひ積極的に摂取してみてください。
避けたい食べ物とその理由
一方、次のようなものが含まれる食べ物は避けたほうが良いでしょう。
- カフェイン
- 塩分
- アルコール
情緒を安定させるためには、自律神経を整えることが大切です。
しかし、カフェインには自律神経を乱しやすくする作用があるため、カフェインの摂取により気分が安定しない可能性があります。
また、塩分やアルコールなどの生活習慣を乱す成分を摂取することで、代謝が悪くなる可能性もあります。
そのため、カフェインや塩分、アルコールの摂取を控え、健康的な食生活を送るように心がけてみましょう。
生理前の情緒不安定で泣く原因と対策
生理前に情緒不安定になってしまい、泣いてしまうこともあるかもしれません。
この症状は「PMDD(月経前気分不快障害)」と呼ばれています。
PMDDの症状が起きる原因は、PMSと同じく女性ホルモン分泌量の急激な変化にあります。
PMDDの症状を改善するには、PMSと同じように規則正しい生活リズムで過ごし、適度に運動することが大切です。
また、婦人科で薬を処方してもらったりピルを服用したりすることでも症状の改善が期待できます。
困ったら、無理に自分で解決しようとせず、婦人科などの医療機関に相談するようにするとよいでしょう。
関連記事:ストレスを解消するにはどうすればいい?ハグがおすすめな理由も解説
生理前の情緒不安定の彼氏への伝え方はどうすればいい?
彼氏には、生理前の情緒不安定であることを正直に打ち明けることをおすすめします。
不機嫌な態度をとったり涙が止まらなくなったりするなど、冷静さを失ってしまうことや、急激な気分の変化によりドタキャンする可能性があることを理解してもらいましょう。
彼氏に打ち明けるのをためらってしまうことがあるかもしれませんが、信頼関係を悪化させず、むしろ信頼関係を深めるためにも、きちんと打ち明けてみてください。
薬を使った生理前の情緒不安定の治療

生理前の情緒不安定に対しては、薬を使った治療ができます。
医療機関に相談する前に、市販薬で解決したい場合は「プレフェミン」を試してみてください。
プレフェミンは、日本で唯一購入できるPMSの市販薬です。
いつでも使用できるわけではなく、低用量ピルの服用中である場合や女性ホルモンに関連する病気の既往歴がある場合などは使用できません。
その他にも注意点が複数あるため、用量・用法をきちんと確認してから使用するようにしましょう。
プレフェミンで症状が改善できない、もしくはプレフェミンを服用したら副作用が出てしまった場合、医療機関へ相談してください。
医療機関では、あなたの症状に合わせた薬を処方してもらえます。
自分で無理に解決しようとせず、専門家の意見を聞きながら症状改善に取り組んでみましょう。
ピルが原因で情緒不安定で泣くことがある?
ピルを飲み始めたばかりの頃は、ホルモンバランスの変化により情緒不安定になることがあります。
場合によっては泣くなどの症状が現れることもありますが、3ヶ月ほど飲み続ければ気分が安定しやすくなる場合がほとんどです。
しかし、症状が辛い場合、もしくは4ヶ月以上経過しても症状が改善しない場合は、ピルとの相性が悪い可能性があります。
ピルを処方してくれた医師と相談し、トラブル解決をするようにしてください。
【まとめ】生理前の情緒不安定の対策は人それぞれ
生理前の情緒不安定への対策方法は、人それぞれです。
1つの対策方法を試しても症状が改善しない可能性もありますが、その場合は他の対策方法を試してみてください。
また、生理前の情緒不安定により彼氏との関係悪化を避けるには、事情をきちんと伝え、理解してもらうことがおすすめです。
事情をきちんと伝えれば、関係悪化を防げるばかりでなく、気を遣ってくれるようになり、さらなる信頼関係の構築につながる可能性もあるでしょう。
ノンバーバルコミュニケーションと対人関係|恋愛においての重要性とは

言葉以外でおこなうコミュニケーションを「ノンバーバルコミュニケーション」と呼びます。
ノンバーバルコミュニケーションの具体例は、ジェスチャーやアイコンタクト、表情の変化など。
ノンバーバルコミュニケーションを効果的に使えると、コミュニケーションがスムーズにできるようになります。
そこで、この記事では、ノンバーバルコミュニケーションと対人関係について解説します。
恋愛におけるノンバーバルコミュニケーションの重要性についても解説していますので、ぜひ最後までお読みください。
ノンバーバルコミュニケーションの重要性
言葉を使わないノンバーバルコミュニケーションは、コミュニケーションにおいて次のようなメリットが得られるため、重要視されています。
- 言葉を補える
- 安心感を与えられる
- 相手を理解しやすくなる
ノンバーバルコミュニケーションを用いるとコミュニケーションがスムーズにできるのは、メラビアンの法則から明らかになっています。
メラビアンの法則とは、コミュニケーションで相手から受け取る情報の内訳が、言語情報が7%、非言語情報が93%であることを明らかにしたもの。
そのため、ノンバーバルコミュニケーションを使って非言語情報を充実させることで、相手とのコミュニケーションがスムーズにできるようになるのです。
関連記事:コミュ力を上げるにはどうしたらいい?鍛える方法を解説
ノンバーバルコミュニケーションの例
ノンバーバルコミュニケーションの例として、次の7つが挙げられます。
- 身体言語(ボディランゲージ)
- アイコンタクト(視線)
- ボディタッチ(接触)
- プロクセミクス(空間の使い方)
- パラランゲージ(声の特性)
- 物理的な外観
- 表情の微細な変化
それぞれのノンバーバルコミュニケーションについて、以下で見ていきましょう。
身体言語(ボディランゲージ)
身体言語(ボディランゲージ)を用いることで、話の内容に補足ができます。
言葉だけでは伝わりにくい場面でボディランゲージを使用できれば、言いたいことのニュアンスや自分の思い、考えを正確に伝えやすくなります。
特に、Web会議などのカメラを通したコミュニケーションでは、反応が薄く感じられることが多いため、ボディランゲージを強く意識することがおすすめです。
しかし、ボディランゲージを多用すると、ボディランゲージばかりが気になって話の内容が頭に入らないこともあるため、適度に使用するようにしてください。
アイコンタクト(視線)
アイコンタクト(視線)も、ノンバーバルコミュニケーションの例の1つです。
視線がズレていると、話し手の場合には「自分の話に自信がないのかな」と、聞き手の場合には「話に興味がないのかな」と思われてしまいます。
一方、視線を相手の目に向けて話したり聞いたりすることで、相手とコミュニケーションを取ろうとする意志を伝えられます。
視線ひとつで印象がガラッと変わるため、話すときは「相手の目を見る」ことを心がけてみてください。
ボディタッチ(接触)
ボディタッチ(接触)もノンバーバルコミュニケーションの一例に挙げられます。
もちろん、関係性が深まっていない相手にいきなりボディタッチすることは控えたほうが良いでしょう。
しかし、関係性の深い子どもを抱きしめたり、仲間の背中をポンと叩いて励ましたりするなどのボディタッチは取り入れてみることがおすすめです。
中でも握手は取り入れやすく、ビジネスの場面でもよく用いられるため、握手から始めてみるのが良いでしょう。
プロクセミクス(空間の使い方)
ノンバーバルコミュニケーションでは、プロクセミクス(空間の使い方)を意識することもあります。
たとえば、会食の場における座席配置を意図的に考えることで、コミュニケーションが取りやすくなることがあるでしょう。
また、過度に近づくのではなく適度な距離感を保つことで、相手のパーソナルスペースを脅かすことなく、気持ちよくコミュニケーションが取れるようになります。
ぜひ空間の使い方にも気をつけて、コミュニケーションを取ってみてください。
パラランゲージ(声の特性)
パラランゲージ(声の特性)も、コミュニケーションに大きな影響を与えます。
相手に好印象を与えたい場合、普段の会話よりも1トーン高くしたり、落ち着いてゆっくりハッキリと発音したりすることが大切です。
声色ひとつで自分の印象がガラッと変わるため、明るい印象をイメージして1トーン高く話してみてください。
また、相手との距離感を考えて、大きすぎず小さすぎない声で話すことで、相手が違和感を抱くことなく、スムーズにコミュニケーションが取れるでしょう。
物理的な外観
服装をはじめとする物理的な外観(見た目)も、ノンバーバルコミュニケーションでは重要な要素です。
フォーマルな場なのかカジュアルな場なのかによって適切な服装や化粧、アクセサリーなどが異なります。
また、明るい印象を与えたいのか、真面目な印象を与えたいのかによっても、適切な見た目は異なります。
TPOを意識し、場や目的にふさわしい見た目にするようにしましょう。
表情の微細な変化
表情の微細な変化にも気をつかうと、円滑なコミュニケーションがしやすくなります。
私たちは、感情が表情に現れやすいことから、相手が発する言葉のニュアンスを表情を通して読み取っています。
同じ言葉であっても、表情次第でポジティブな言葉にもネガティブな言葉にも変化するのです。
そのため、自分の思いや考えが伝わりやすくするために、表情を意識的に作ることをおすすめします。
関連記事:社内で円滑にコミュニケーションをとるコツや成功事例を紹介
ノンバーバルコミュニケーションの効果

ノンバーバルコミュニケーションには、次の6つの効果があります。
- 感情の伝達
- 親密度の向上
- 非言語的な同意や反対の表明
- 社会的地位や権威の表示
- 嘘や欺きへの疑い
それぞれの効果について、以下で見ていきましょう。
感情の伝達
ノンバーバルコミュニケーションには、感情を伝達する効果があります。
言葉だけでは「嬉しい」「悲しい」などの感情が伝わりづらいこともあります。
しかし、ボディタッチや声の特性、表情の変化などのノンバーバルコミュニケーションを用いることで、自分の感情を伝えやすくなるでしょう。
言葉の内容だけでなく感情も伝えたい場合は、ノンバーバルコミュニケーションを使うことをおすすめします。
親密度の向上
ノンバーバルコミュニケーションは、親密度の向上にも効果があります。
たとえば、相手と視線を合わせて見つめ合ったり、あえて近い席に座ったりすることで、相手との距離感を縮めやすくなります。
ある程度関係性が深まった後に、ボディタッチなどのテクニックを利用することで、さらに親密度を向上させることも可能です。
相手との親密度を向上させたい方は、ノンバーバルコミュニケーションを積極的に利用してみてください。
非言語的な同意や反対の表明
ノンバーバルコミュニケーションを用いることで、非言語的な同意や反対の表明もできます。
相手の話に対してうなずけば、「話を聞いていますよ」「あなたの考えに同意します」という考えを伝えられます。
一方、首を傾げたり眉間にしわを寄せたりすると、相手の話に反対、または同意していないという考えを伝えられるでしょう。
社会的地位や権威の表示
ノンバーバルコミュニケーションによって、マイナスの印象を与えてしまうことがあります。
たとえば、イスにふんぞりかえって座ったり、腕組みをして仁王立ちしていたりすると、社会的地位の高さや権威を見せつけていると捉えられがちです。
相手に見下されないように、わざと社会的地位や権威を表示することもあります。
しかし、一般的な場面では社会的地位や権威を表示することによるメリットが大きくないため、これらの行為はなるべく避けることをおすすめします。
嘘や欺きへの疑い
相手が「嘘をついていたり欺いていたりするかもしれない」と疑うこともノンバーバルコミュニケーションで表現できます。
たとえば、目を細める、頬杖をつく、腕組みをするなどが疑っていることを表す仕草として用いられます。
相手に言葉で直接伝えなくても、仕草から嘘や欺きが見抜かれていることを伝えられれば、余計なトラブルに巻き込まれずに済む可能性が高くなるでしょう。
このように、ノンバーバルコミュニケーションにはさまざまな効果があるため、ぜひ活用してみてください。
恋愛におけるノンバーバルコミュニケーション

ノンバーバルコミュニケーションは、恋愛においても大きな効果をもたらします。
たとえば、次のような要素が揃っていると、異性に好印象を与えられるでしょう。
- 清潔感のある外観に整える
- 話すときに視線が合う
- 口角を上げ爽やかな笑顔をする
一方、視線を合わせられなかったり、ボソボソっと自信なさげに話したり、猫背だったりすると、異性に好印象を与えるのは難しくなります。
また「気まずい空気を作らないようにしなければ!」と思ってしまい、愛想笑いを多用してしまうと、自信のなさが伝わってしまうでしょう。
このように、恋愛ではノンバーバルコミュニケーションが異性との関係に大きく影響します。
「異性と良い関係を築きたい」「恋を成就させたい」と考えている方は、ぜひノンバーバルコミュニケーションをマスターしてみてください。
ノンバーバルコミュニケーションの注意点
ジェスチャーを用いることで、話の内容を補足するテクニックがあります。
しかし、文化圏が違えばジェスチャーが表す意味が異なります。
たとえば、欧米では親指を立てる行為(サムズアップ)は「OK」という意味を表し、日本人も同じように使う場面が多くあるでしょう。
しかし、中東や南米、西アフリカなどの一部の地域では「侮辱」の意味を表します。
このように、異文化コミュニケーションでジェスチャーを使うときには、ジェスチャーが持つ意味に注意してください。
関連記事:ノンバーバル(非言語)コミュニケーションの重要性を徹底解説!
【まとめ】ノンバーバルコミュニケーションをマスターして人間関係を円滑に
ノンバーバルコミュニケーションをマスターすると、表現が豊かになります。
自分の考えや思いを相手に正確に伝えられるようになるだけでなく、恋が成就する確率も高まります。
普段の癖もノンバーバルコミュニケーションに含まれるため、身につけることは簡単ではないでしょう。
しかし、日頃から意識して取り入れることで、少しずつ上達しマスターできるようになりますので、ぜひ今日から試してみてください。
ぬいぐるみの寄付はどこがいい?おすすめの寄付団体と注意点

「使わなくなったぬいぐるみを寄付したいけど、どこに寄付すればいいのかな?」とお悩みではありませんか?
「捨てるのはもったいないから寄付したい」と思っても、ぬいぐるみ寄付の経験がなく、どこに寄付したらいいのかわからない方もいるでしょう。
そこで、この記事ではぬいぐるみの寄付はどこがいいのかを紹介します。
おすすめの寄付団体や、ぬいぐるみ寄付の際の注意点も解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
ぬいぐるみの寄付とは
ぬいぐるみは寄付できます。
今まで使っていた思い出のぬいぐるみを処分せず、新たな持ち主に使ってもらうことで、お互いWin-Winの関係を築けるでしょう。
また、寄付先によっては、ぬいぐるみを寄付するだけでなく各種団体への支援もおこなわれます。
たとえば、「いいことシップ」では、ぬいぐるみを入れた段ボール1箱につき100円を指定した団体に寄付しています。
このように、ぬいぐるみを寄付することで、さまざまな社会貢献ができるでしょう。
ぬいぐるみ寄付の方法
ぬいぐるみを寄付するには、以下の3つの方法が考えられます。
- 保育園や孤児院への持ち込み
- NPO団体への郵送
- 買取・回収サービスの利用
それぞれのやり方を以下で見ていきましょう。
保育園や孤児院への持ち込み
1つ目は、保育園や孤児院への持ち込みです。
近くにある保育園や孤児院に直接連絡し、ぬいぐるみの寄付を受け付けているのかを確認してみてください。
寄付を受け付けている場合、ぬいぐるみのサイズや状態が問題ないか、いつ引き渡しができるのかなども確認しておくと良いでしょう。
新品のぬいぐるみでなければ寄付を受け付けていない場合や、引き渡しできる日時に指定がある場合もあります。
そのため、事前に確認したうえで寄付をするようにしましょう。
また、保育園や孤児院によっては、Amazonのウィッシュリストからの寄付を受け付けている場合もあります。
費用はかかりますが、必ず寄付できる方法であるため、あわせて検討してみてください。
NPO団体への郵送
2つ目は、NPO団体への郵送です。
NPO団体の中には、ぬいぐるみを寄付したい人からの寄付を受け付けて、ぬいぐるみが欲しい保育園などにぬいぐるみを送る活動をしている団体があります。
自分で保育園や孤児院に「寄付を受け付けているか?」と確認する必要がないうえ、寄付するぬいぐるみが「新品でなければダメ」などの制限もないため、簡単に寄付できます。
しかし、NPO団体に郵送する際の送料は負担しなければいけないため、注意が必要です。
具体的に、どのNPO団体がぬいぐるみの寄付を受け付けているのかは後ほど解説します。
買取・回収サービスの利用
3つ目は、買取・回収サービスの利用です。
ぬいぐるみを買い取ってもらい、売却により得たお金を保育園や孤児院に寄付する方法です。
お金を寄付したほうが、ぬいぐるみを寄付するよりも幅広い方法で活用できます。
特に、「ぬいぐるみを寄付したい!」というより「ぬいぐるみを使って良いことに役立てたい!」と考えている方におすすめの方法です。
関連記事:クリック募金とは?動物や環境に関係する募金サイトまとめ
ぬいぐるみを寄付する際の注意点

ぬいぐるみを寄付する際には、以下の3点に注意してください。
- 破損・汚れ
- におい
- 寄付先の条件
それぞれの注意点について、以下で見ていきましょう。
破損・汚れ
ぬいぐるみの破損・汚れは必ずチェックしておきましょう。
保育園や孤児院では、寄付されたぬいぐるみをすべて使うのではなく、破損・汚れの少ないぬいぐるみだけを選んで使います。
そのため、破損・汚れのあるぬいぐるみも送ってしまうと、保育園や孤児院の職員がぬいぐるみのチェックをする手間が大きくなってしまいます。
寄付する前に、ぬいぐるみの破損・汚れをチェックし、綺麗なものだけを送るようにしましょう。
におい
ぬいぐるみのにおいも、要チェックです。
破損・汚れと同じく、においのついたぬいぐるみは保育園や孤児院では使われません。
もし、においのついたぬいぐるみを寄付してしまうと、保育園や孤児院がそのぬいぐるみを処分しなければなりません。
処分するにも手間や費用がかかるため、なるべくにおいのついたぬいぐるみを避けて送るようにしましょう。
寄付先の条件
寄付先によっては、寄付するぬいぐるみに条件が設けられている場合があります。
たとえば、ぬいぐるみの状態について、汚れてても問題ないとする寄付先もあれば、新品のみ受け付けている寄付先もあります。
条件に反するぬいぐるみを送るのは迷惑になるので、事前に条件を確認してから寄付するようにしてください。
関連記事:ランドセル寄付は無料でできる?迷惑にならない方法と支援団体まとめ
ぬいぐるみの寄付はどこがいい?

ぬいぐるみの寄付はどこにすれば良いのでしょうか?
ここでは、次の4つの寄付先を紹介します。
- エコトレーディング
- リボーンプロジェクト
- いいことシップ
- セカンドライフ
それぞれの寄付先について見ていきましょう。
エコトレーディング
エコトレーディングは、寄付されたぬいぐるみをタイやフィリピンにあるリサイクルショップへ販売する活動をおこなう企業です。
そこで得た利益の一部を、国内のNPO法人やタイやフィリピンにある孤児院などに寄付しています。
また、日本国内でのぬいぐるみの販売もおこない、児童養護施設や被災地復興支援、ボランティア活動などに充てています。
事前連絡せずに郵送するだけで寄付できるほか、直接持ち込むこともできるため、ぜひ活用してみてください。
リボーンプロジェクト
リボーンプロジェクトは、不用品の寄付を受け付けて、発展途上国に輸出したり売り上げの一部を寄付してワクチン提供をしたりするプロジェクトです。
ぬいぐるみをはじめとする不用品を無料で発送できるため、気軽にぬいぐるみを寄付できます。
また、ミャンマーやラオスなどの子どもたちにポリオワクチンを寄付し、命を落とす子どもたちを減らす取り組みにも協力できます。
空き箱がない場合、専用回収キットを購入できるため、ぜひ活用してみてください。
いいことシップ
いいことシップは、不用品寄付をおこなっている団体です。
寄付した実績を公表しているうえ、自分が選択した支援団体への寄付もできるため、安心して寄付できるでしょう。
事前連絡不要の郵送と、事前連絡必須の持ち込みの2種類から寄付方法を選べるため、ぜひ活用してみてください。
セカンドライフ
セカンドライフは、寄付されたぬいぐるみを児童養護施設・保育園・海外に届けているNPO法人です。
国内外にかかわらず、ぬいぐるみと遊びたい子どもたちの元に届けられています。
また、ぬいぐるみは寄付するだけでなく、供養することも可能です。
月1回、人形やおもちゃ、お守りなどと共に供養しているため、ぬいぐるみへの感謝を伝えたい方は供養を選択してみてください。
ぬいぐるみの寄付を送料無料でできる?

ぬいぐるみの寄付を郵送でおこなう場合、基本的には送料がかかります。
しかし、次の方法を使えば送料無料でぬいぐるみの寄付ができます。
- 送料無料の寄付団体を利用する
- 持ち込み可の寄付団体を利用する
それぞれの方法について見ていきましょう。
送料無料の寄付団体を利用する
1つ目は、送料無料の寄付団体を利用する方法です。
寄付団体にぬいぐるみを送る場合、一般的には送料がかかりますが、リボーンプロジェクトなど、一部の寄付団体では送料無料で送ることができます。
なお、送料無料で送る場合には、発送方法の指定など条件があるため、事前に確認した上で利用するようにしてください。
持ち込み可の寄付団体を利用する
2つ目は、持ち込み可の寄付団体を利用する方法です。
たとえば、エコトレーディングやいいことシップなど、一部の寄付団体では持ち込みできます。
自分で寄付団体にぬいぐるみを持ち込めば、ガソリン代などはかかりますが、送料自体はかかりません。
なお、持ち込む場合、指定された時間内に届ける必要があるため、事前に持ち込み可能な時間帯を把握しておきましょう。
関連記事:寄付による税金の控除とは?ふるさと納税との違いも解説
ぬいぐるみの寄付が「怪しい」と言われる理由は?
ぬいぐるみの寄付が「怪しい」と言われる理由は、一部の業者が詐欺まがいのサービスを運営していることにあります。
たとえば、寄付されたぬいぐるみを転売して、大きな利益を得ているサービスがあります。
無料で寄付したものが転売されてしまうのは、寄付した側からすると気持ちのいいものではありませんよね。
このような詐欺まがいのサービスに寄付しないためには、口コミをチェックするのがおすすめです。
口コミは、サクラを使用しにくいSNSをチェックすると良いでしょう。
また、送料以外にもさまざまな料金を請求してくる業者や、ホームページに問い合わせ先が載っていない業者、運営状況が不明瞭等の業者は要注意です。
【まとめ】ぬいぐるみの寄付で救われる子どもたちがいる
国内外問わず、「ぬいぐるみが欲しい」「ぬいぐるみと遊びたい」という子どもたちがたくさんいます。
ぬいぐるみを処分してしまうのではなく、ぜひ有効的に活用してくれる保育園や孤児院、寄付団体に寄付してみることがおすすめです。
また、寄付団体の中には、販売した売り上げの一部をワクチンの寄付などもおこなっています。
ぬいぐるみ寄付を通して、世界中にいるたくさんの子どもたちの生活を手助けできるため、ぜひぬいぐるみの寄付をしてみてください。
当メディアの姉妹団体のNPOハミングバードも社会貢献につながる様々な活動を行っています。
完璧主義を辞めたい!楽に生きるための10個の方法

「完璧主義を辞めたい!」
「完璧主義から抜け出したら楽になるのになぁ」
このように考えたことがあるのは、一度や二度ではないでしょう。
完璧主義には自分を苦しくしてしまう面が多くあるため、完璧主義を辞めたい、治したいと考えるのも無理はありません。
そこで、この記事では完璧主義を辞める方法について解説します。
完璧主義を辞めて楽に生きるための10個の方法を紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
完璧主義を辞める方法は?
完璧主義を辞めるには、次の10個の方法を試してみてください。
- 加点方式で考える
- 「まぁ、いいか」を口癖にする
- 物ごとの優先順位をつける
- 合格点を超えた自分を褒める
- 自身を肯定的に評価する
- 全て自分でやろうとせず人に任せる
- うまくいかなくても自分を責めない
- 自己肯定感を上げる
- 環境を変える
- こだわりがないことにチャレンジしてみる
以下では、それぞれの方法を具体的に見ていきましょう。
加点方式で考える
完璧主義を辞めるには、加点方式で考えることがおすすめです。
完璧主義に陥っている人は、自分の「足りない部分」に目を向けて、減点方式で自分を評価しがちです。
しかし、自分の「できたこと」に目を向けて、加点方式で自分を評価すれば、ポジティブな感情を抱くことができ、完璧主義を辞められるようになるでしょう。
「まぁ、いいか」を口癖にする
完璧主義に陥っている人は、物ごとを完璧に遂行できないと満足できなくなっています。
しかし、何ごとも完璧にできるような人など、まずいません。
そこで、「まぁ、いいか」を口癖にして、ある程度の出来で満足することができるようにすることで、完璧主義から抜け出しやすくなります。
完璧にできていなくても、ある程度完了した時点で「まぁ、いいか」を口に出してみるなどして、習慣づけることをおすすめします。
物ごとの優先順位をつける
完璧主義から抜け出すには、物ごとの優先順位をつけることがおすすめです。
「あれもこれもやらなければ!」と思ってしまうと、どのタスクから片付ければよいのかわからなくなり、結果としてどれも中途半端に終わってしまいます。
そこで、緊急性・重要性の高いタスクを優先的に処理することで、やらなければいけないことを着実に終わらせられるようになります。
ぜひ物ごとに優先順位をつけて、完璧主義から抜け出せるようにしましょう。
合格点を超えた自分を褒める
完璧主義から抜け出すには、合格点を設けることがおすすめです。
完璧主義の場合、「ひとつのミスも許されない」という態度で物ごとと向き合ってしまいます。
しかし、100%ミスなくできることなどほとんどなく、誰でもミスを犯します。
そのため、「ここまでできればOK」という合格点を設けておくことで、完璧を求めてしまう癖をなくしていけるでしょう。
自身を肯定的に評価する
完璧主義に陥ってしまったら、自身を肯定的に評価してみてください。
前述した「合格点を超えた自分を褒める」ことは、肯定的に評価するための1つの手法です。
また、間違えたり失敗したりしても、挑戦した自分を褒めることも、1つの例として挙げられます。
肯定的に評価する点は、些細なことでも構いません。
むしろ些細なことでも肯定的に評価することで、ポジティブに考えられるようになり、徐々に完璧主義から抜け出せるようになるでしょう。
全て自分でやろうとせず人に任せる
全てを自分で背負うのではなく、人に任せてみることもおすすめです。
もし、「全て自分でやったほうがうまくいく」と考えているのであれば、その考えは誤解である可能性が高いです。
本当に自分でやらなければいけないことは一部分だけであり、多くの部分は他の人に任せられる場合が多くあります。
無理して自分でやろうとするのではなく、周囲の人や代行サービスなどを利用して、人に任せてみることをおすすめします。
うまくいかなくても自分を責めない
たとえうまくいかなくても、自分を責めないようにしてください。
誰でも失敗をするものであり、失敗を経験としてもう一度チャレンジすることも可能です。
また、失敗した原因が自分のミスではなく、他人や周囲の環境の影響にある場合もあります。
そのため、「失敗=悪」と考えて自分を責めるのではなく、うまくいかなかった原因を突き止めて、もう一度チャレンジしてみてください。
自己肯定感を上げる
自己肯定感を上げることも、完璧主義への対策として効果的です。
自己肯定感を上げるには、積極的に「自分の良い点」に目を向けることが大切です。
また、苦手なことよりも好きなことや得意なこと、やりたいことを積極的に行う方が自己肯定感を上げやすくなります。
自己肯定感が上がれば、前向きな気持ちになれるため、徐々に完璧主義から脱却できます。
「自分の良い点」に目を向けることは大変なことかもしれませんが、できる範囲で少しずつ取り組んでみると良いでしょう。
環境を変える
海外移住をするなど、環境を変えることもおすすめです。
今までと同じ環境で過ごしていると、自分の常識の範囲内でしか物事を考えられません。
しかし、思い切って日本から離れてみると、まったく違う環境での生活となるため、当然ながら日本での常識が通用しなくなるでしょう。
日本では常識として「〇〇しなければならない」と考えられていることも、海外に出ればもっとラフに考えている人が多くいるかもしれません。
海外移住とまではいかなくても、都会に暮らしている人は田舎に移住したり、田舎に暮らしている人は都会に移住したりすることもおすすめです。
環境を変えず、自分の中だけで変化させるのは困難であるため、ぜひ環境を変えて新たな生活をスタートしてみてください。
こだわりがないことにチャレンジしてみる
最後におすすめするのは、こだわりがないことにチャレンジしてみることです。
理想像を追い求めてしまうことで、完璧主義に陥ってしまうことが多くあります。
しかし、こだわりがなければ明確な理想像も存在しないため、完璧主義に陥りにくいのです。
中でも、運動や副業などの目に見えてプラスの効果が得られるものがおすすめです。
ぜひ、今まであまり触れてこなかったような、こだわりがないことにチャレンジしてみてください。
完璧主義の自己診断表

以下に、完璧主義の自己診断表を用意しました。
10項目のうち、どの程度当てはまるのかを確認してみてください。
- 小さなミスも許せない
- 常に最高の成果を求める
- 他人の評価を過度に気にする
- 仕事やタスクに無理な時間を費やす
- 失敗を極端に恐れる
- 自己批判が多い
- 他人にも高い基準を求める
- やり直しや完璧にするために余計な時間をかける
- 自分の成果に満足しない
- タスクの完了よりも過程の完璧さを重視する
できないくせに完璧主義な場合はどうすればいい?
「できないくせに完璧主義な自分を変えたい」と考える方もいるでしょう。
その場合でも、前述したような対策により完璧主義を抜け出せるようになります。
くわえて、次のコツを意識すると、より完璧主義から抜け出しやすくなります。
- 自分の強みを知る
- 合格点を低めに設定する
- 助けを求める
- 「なんとかなるさ」と考える
自分ができる分野、得意な分野を見つけることが大切です。
できない分野で挑戦せず、自分の強みとなる分野で挑戦したほうが失敗する確率を減らせるでしょう。
また、合格点は低めに設定することがおすすめです。
100点や80点などの高い目標を合格点に掲げてしまうと、合格点を超えられず、完璧主義から抜け出せなくなってしまいます。
さらに、「できない」と感じたら助けを求めることも忘れないでください。
「あなたひとりでやらなければならない」ことは多くないので、必要があれば遠慮せず助けを求めるようにしましょう。
そして、もし失敗してしまった場合でも、後から挽回すればなんとかなる場合が多くあります。
失敗したことにクヨクヨするより、「なんとかなるさ」と考え、そのあとのフォローアップについて考えたほうが結果としてうまくいくでしょう。
関連記事:アンガーマネジメントのやり方|「意味ない」と言われる理由とは?
完璧主義な女性の特徴

完璧主義な女性には、次のような特徴があります。
- 努力家
- ストイック
- 負けず嫌い
- 何事も計画的に
- 仕事が丁寧
- 人望が厚い
どれも良いことに見えますが、完璧主義に陥ってしまう女性の特徴でもあるのです。
それぞれの特徴について、見ていきましょう。
努力家
1つ目の特徴は、努力家であることです。
完璧主義の人は「目標をなんとしてでも達成しよう!」という強い意志を持っています。
そのため、多少の困難があっても物事をやり抜ける力があります。
ストイック
2つ目の特徴は、ストイックであることです。
完璧主義の人は90点では満足できず、常に100点を目指します。
100点を目指すために自分を律することができるため、完璧主義の人はストイックな特徴を持つのです。
負けず嫌い
3つ目の特徴は、負けず嫌いであることです。
自分から見た視点で完璧を目指すだけでなく、客観的に見ても完璧な状況を目指します。
他人に負けていては完璧とは言えないため、完璧主義の人は負けず嫌いにもなるのです。
何事も計画的
4つ目の特徴は、何事も計画的であることです。
物事を円滑に進められるように完璧に準備をするため、細かなタイムスケジュールに至るまで計画を立てます。
行き当たりばったりで物事を進めることがなくなるため、無駄な時間を過ごしたり余計なストレスを抱えたりすることがなくなるでしょう。
仕事が丁寧
5つ目の特徴は、仕事が丁寧なことです。
常に完璧を求めるため、些細なミスにも敏感であり、仕事を丁寧に進めることができます。
そのため、重要な資料の作成などミスが許されないような仕事に向いています。
人望が厚い
6つ目の特徴は、人望が厚いことです。
完璧主義の人は、仕事が丁寧であり責任感も強いことから、信頼されやすい特徴があります。
「この人に任せれば一生懸命取り組んでくれる」という評価を受けているため、人望が厚く大役を任されることもあるでしょう。
完璧主義の人はうつになりやすい?
完璧主義の人は、うつになりやすいと言えます。
完璧を目指す中で、自分に厳しくなってしまったり、気軽に物事に取り組めなくなったりしてしまいます。
また、自分のダメな部分にばかり目が向いてしまうため、自分を責めてしまう傾向にもあるのです。
このような原因から、完璧主義の人はメンタルを壊しやすく、うつになりやすいと言えるでしょう。
【まとめ】完璧主義を辞めたいなら自分を認めてあげよう
完璧主義を辞めるには、自分を認めてあげることが大切です。
できないことに目を向けるのではなく、今までにできたことや挑戦した気持ちなどに目を向けることで、少しずつポジティブな気持ちを感じられるようになります。
これまでの考え方を変えることは簡単なことではありませんが、できることから少しずつ取り組んでみてください。
夫婦カウンセリングは意味ない?おすすめ?効果について解説

夫婦が抱える問題はさまざまで、ときには家族や親友にも相談できず一人で抱え込んでしまうこともあるでしょう。
そのような場合、夫婦カウンセリングを受けるのも有効な方法のひとつです。
本記事では、夫婦カウンセリングによってどのような問題を解決できるのか、カウンセリングを受けるときに注意しておきたいポイントなどをご紹介します。
夫婦カウンセリングとは

夫婦カウンセリングとは、夫婦関係で生じた亀裂を修復したり、今後夫婦が歩むべき方向性などについてカウンセラーへ相談し、アドバイスを受けるカウンセリングのことです。
夫婦カウンセリングは夫または妻の一方のみが相談に訪れるケースもあれば、夫婦揃ってカウンセリングを受けるケースもあります。
カウンセラーは夫婦の間に立って中立的かつ公平な立場で判断するため、客観的な第三者の視点から有効なアドバイスが受けられます。
夫婦カウンセリングの目的

夫婦カウンセリングを受ける目的は、大きく分けて夫婦間でのトラブル解決と関係向上があります。
夫婦間のトラブル解決
夫婦間で特に多いトラブルとして、以下の3つが挙げられます。
モラハラ・DV
夫から妻、あるいは妻から夫に対して、日常的に暴言・暴力が繰り返されている場合、夫婦カウンセリングを受けることで夫婦関係の修復につながる可能性があります。
浮気・不倫
浮気や不倫といった不貞行為に悩んでいる場合、基本的には夫婦間で話し合いが必要になります。
このような行為が繰り返される場合は夫婦カウンセリングを受けることで、第三者の立場から今後の方向性についてアドバイスを受けられます。
金銭トラブル
夫婦で貯蓄していたお金を夫または妻が無断で使い込んでしまったり、生活費をギャンブルやお酒に費やしてしまうなどの金銭トラブルも少なくありません。
夫婦カウンセリングを受けることでお金の使い方を見直したり、トラブルの具体的な解決策をアドバイスしてもらえることもあります。
夫婦の関係向上
上記のような深刻なトラブル以外でも、夫婦カウンセリングは有効です。
日常生活のちょっとしたすれ違いや、気になっていることを解消し、夫婦関係をより良いものにするために役立つケースもあります。
上記のような深刻なトラブルだけでなく、日常生活のちょっとしたすれ違いや気になっていることを解消し、夫婦関係をより良いものにするために夫婦カウンセリングが役立つケースもあります。
会話の頻度
仕事や家事が忙しい毎日を送っていると、夫婦での会話が自然と少なくなっていくことも珍しくありません。
夫婦カウンセリングを受けることで会話の頻度が増え、夫婦の絆が強くなることもあります。
スキンシップ
セックスレスなどスキンシップ不足が原因で、夫婦仲が悪化することもあります。
お互いにとって心地良いと感じるスキンシップの方法を、夫婦カウンセリングを通して学ぶことができ、お互いの愛情に気づくきっかけにもなるでしょう。
家事・育児について
家事や育児の負担が偏っていると小さな不満が積もっていき、夫婦仲が悪化する原因になります。
第三者のカウンセラーが同席する場で家事や育児についての不満を打ち明けることで、冷静な話し合いができ今後の方向性も見えてくるでしょう。
夫婦カウンセリングのメリット

夫婦関係を改善するためにはさまざまな方法がありますが、そのなかで夫婦カウンセリングを受けるメリットは何があるのでしょうか。
第三者視点からのアドバイスをもらえる
夫婦カウンセリングの場には、公平な立場からさまざまなアドバイスを行う第三者の専門家が参加します。
感情に流されず、問題を客観的かつ冷静に分析してくれるため、夫婦がそれぞれ相手の立場を理解しやすくなります。
また、自分たちが気づいていない視点や、解決策を提供してくれることも期待できるでしょう。
知人には話しづらいことを相談できる
夫婦間の悩みは非常にデリケートな問題も多く、親しい友人や自分の親・きょうだいに対しても打ち明けられないこともあるでしょう。
カウンセリングはほかの人に聞かれることのない、プライバシーが確保された環境で行われます。
また、カウンセラーも多くの夫婦の問題を解決してきたプロであり、どのような問題・悩みであっても受け止めてくれます。
この安心感の中で、お互いの深層心理や根本的な問題に迫ることができ、解決の糸口を見つけられる可能性があります。
今後に向けて建設的な話ができる
夫婦カウンセリングでは過去に起こった事実だけでなく、今後どうしていくかといった将来に向けても焦点を当てます。
夫婦はお互いに今後どうなっていきたいのか、将来への期待や願望を共有し冷静に対話することができます。
関連記事:夫婦の円満を保つ秘訣|冷めていく夫婦の共通点とは?
夫婦カウンセリングを受ける際のポイント

せっかく夫婦カウンセリングを受けても、その心構えができていなければ、冷静な話し合いができずに終わってしまいます。
夫婦カウンセリングを受ける際にはどういった点に注意すべきなのでしょうか。
感情的にならない
カウンセリングでは夫婦が抱える核心的な問題に切り込むこともあり、つい感情的になって暴言を吐いたり、お互いに激しい口論に発展するケースも少なくありません。
しかし、これでは冷静な話し合いができず建設的な対話が進みません。
どのような話題に対しても感情的にならず冷静さを保つことを意識し、カッとなりそうになったら深呼吸をして落ち着きを取り戻しましょう。
相手の話に耳を傾ける
カウンセリングではお互いの意見や感情を尊重し合うことが大切です。
たとえば、相手が話している最中に割って入ってしまうと、そこから口論がヒートアップするケースもあります。
相手の話に最後まで耳を傾け、理解しようとする姿勢がコミュニケーションの改善に繋がります。
できるだけ夫婦揃って受ける
夫婦カウンセリングは夫または妻の一方が相談に訪れるケースもあります。
特にDVやモラハラに悩んでいる場合、はじめから夫婦二人でカウンセリングに訪れるのは難しいことも多いでしょう。
しかし、カウンセリングは夫婦の共同作業であり、お互いが同じ情報を共有することが重要です。
できるだけ揃ってカウンセリングを受けることで、お互いの認識のズレを修正し、夫婦関係の改善に向けて一貫性のあるアプローチが可能です。
夫または妻の一方だけが出席する場合でも、2回目、3回目のカウンセリングには夫婦揃って参加する方法を模索してみましょう。
どんな夫婦が理想か共有する
夫婦カウンセリングは、夫婦の問題や愚痴を言い合う場ではなく、今後どうなっていきたいのか理想像を話し合い、共有することが大切です。
未来に向けた前向きな話し合いをすることで、夫婦が目指す具体的な目標や期待を共有し、より具体的なアクションプランを立てやすくなります。
関連記事:夫婦喧嘩でやってはいけないこととは?子供への悪影響も解説
夫婦カウンセリングは意味ない?効果なし?

夫婦カウンセリングにはさまざまなメリットがある一方で、「カウンセリングを受けても効果がない」、「意味がない」といった意見を目にすることもあります。
そもそも夫婦カウンセリングは、夫婦揃ってカウンセラーに相談したりアドバイスを貰ったりすることが大切です。
どちらか一方だけがカウンセリングを受けても、十分な効果が得られないことも多いのです。
また、たとえば妻が夫婦関係を改善したいと考えていても、夫にその意志がないとカウンセリングを受けても思うような効果が得られないこともあるでしょう。
さらに、カウンセリングを受ける側の問題だけでなく、カウンセラーの質や相性も重要です。
相談者が話す内容を最後まで聞いてくれなかったり、相談者の人格を否定するようなカウンセラーに当たってしまうと、カウンセリングを受けたことを後悔する人もいるようです。
夫婦カウンセリングの口コミを紹介
実際に夫婦カウンセリングを受けた人は、どのような感想・印象を抱いているのでしょうか。いくつか口コミをご紹介します。
新婚の夫婦関係を改善する糸口が見つかった
「新婚であるにもかかわらず、夫婦喧嘩が絶えず悩んでいました。
すごく分かりやすく説明していただけたので、やるべきことがクリアになって目の前が開けたような気分です。教えていただいたことを真剣に実行してみます。」
夫婦関係の悩みで混乱した状態でも真摯に話を聞いてくれた
「ずっと夫婦関係のことで苦しんでいました。不安で辛くて悲しくて、正直死んだ方がマシだと思うほどでした。
そんな状態で電話をもらったのですが、今まで思っていたことを180度変えられるようなお話でびっくりしました。
苦しくて苦しくて胸につかえていたものが取れたような感覚で涙が出そうでした。こんなに心がふっと軽くなったのはいつぶりでしょうか。
ずっと優しく包み込むような声で話してくださりました。
私の話は思い出した事をあれこれと話していたので、支離滅裂なところもあったかもしれませんが、落ち着いて話もできました。本当に救われた気持ちです。」
穏やかなカウンセラーが丁寧かつ親身になって答えてくれた
「カウンセラーの雰囲気がとても穏やかで癒やされました。
まだ自分の心の中で浄化されてない気持ち(悲しかったり、自分への癒やしなど)もあるので100%頑張りますとは言えません。
しかし、できる限り自分を大切にするというのと、相手に居心地の良い場所を作る努力はしてみようと思います。
1つずつの質問にも丁寧に答えて頂いて助かりました。とても親身になってアドバイスしてくださり、嬉しかったです。
またこれから何かあれば、メールでお話をきいてくださるということもとても助かります。」
まとめ
夫婦間が抱える問題やトラブルは親しい人に対しても相談しにくく、一人で悩みごとを抱え込んでしまう人も少なくありません。
特にモラハラやDV、不貞行為、金銭トラブルなど深刻な問題は早急に対処しなくてはならず、対応が遅れるほど深刻化していきます。
「誰に相談すれば良いのか分からない」、「身近な人に心配をかけたくない」などの悩みを抱えている方は、夫婦カウンセリングを受けてみるのもひとつの方法といえるでしょう。
信頼できるカウンセラーを探すためにも、実際にカウンセリングを受けた人の口コミや感想も参考にしてみてください。
セクササイズとは?やり方やメリットを徹底解説

ダイエットや美容にはさまざまな方法がありますが、多くの場合辛く感じてしまうものです。
しかし、快感を得ながらトレーニングと同じような効果を得られる方法として「セクササイズ」が注目されています。
セクササイズとは何か、具体的なやり方や効果を高めるためのポイントを詳しく解説します。
セクササイズとは?

セクササイズとは、性行為の「セックス」と「エクササイズ」をかけ合わせた造語です。
その名の通り、有酸素運動や無酸素運動の要素をセックスに取り入れ、性行為を通してダイエットや健康効果を得る方法・手段を指します。
セックスでは快楽を得るために一定の時間にわたって激しい動きをしたり、体位によっては普段使わないさまざまな筋肉が刺激されることもあります。
そのため、セックスをした翌日は筋肉痛が現れるという方も多いのではないでしょうか。
単に有酸素運動や無酸素運動を繰り返すだけでは飽きてきたり、トレーニングそのものが苦痛になったりすることも多いものです。
しかし、セクササイズであればセックスのやり方次第でトレーニング効果が得られる可能性があります。
セクササイズのメリット

セクササイズに取り組むことでどういったメリットが得られるのでしょうか。
幸福感を得られる
セックスはエンドルフィンが放出され性的快感が得られるとともに、体を動かすことでセロトニンとよばれる幸せホルモンも分泌され幸福感が得られます。
筋トレ効果がある
セクササイズはさまざまな部位を動かすため、全身の筋肉を刺激し筋力を強化します。筋力がつくと基礎代謝もアップしダイエット効果が得られます。
体力や持久力の向上によって、セックスそのもののパフォーマンスが上がり性的満足度を高められることもあります。
ストレス解消
セックスの際に意識的に体を動かし筋肉を刺激することで、ストレスホルモンを低減しメンタルを安定的に保てます。
美容にも効果的
セクササイズによって体を意識的に動かすと血行が促進され、むくみの解消や肌の健康を保つ効果も期待できます。
また、ダイエット効果はもちろんのこと性的刺激が加わることで女性ホルモンが多く分泌され、アンチエイジング効果も見込めます。
膣トレにもなる
性行為の際、男性の快感を高めるために女性は膣を意識的に締めることも多いです。
セクササイズによって女性が積極的に体を動かすと、骨盤やその周辺の筋肉を鍛え、膣の締まりを良くすることもできます。
睡眠の質が向上する
激しい運動をしたときや、肉体的な疲労が溜まっている日には寝付きが良く、朝までぐっすりと寝られるものです。
セクササイズも同様で、セックスによってさまざまな筋肉を刺激することで睡眠の質が向上していきます。
マンネリ解消につながる
セックスがマンネリ化している夫婦やカップルも少なくありません。
セクササイズによって普段と違う体位を試すことで、普段とは違った性的刺激や快感が得られマンネリ解消につながっていくでしょう。
関連記事:頭も身体も心も目を覚ます⁈冷たい水風呂でメンタルヘルスが改善!
セックスの消費カロリーは?

ダイエットを目的としてセクササイズに取り組む場合、セックスによってどの程度のカロリーが消費されるのか気になる方も多いでしょう。
まず、セックスの最中は男女ともに体を一定間隔で動かしますが、1回あたりの平均時間(6分)で換算すると、消費カロリーはわずか21kcalといわれています。
人によっても時間は異なるため、これよりも消費カロリーが低い人もいれば多い人もいるでしょう。
ただし、セックスの際に絶頂に達した場合、1回あたり60〜100kcal程度が消費されるといわれています。
セックス中の単純な動き(運動)によって消費されるカロリーに比べると格段に多いのです。
以上のことをまとめると、セックスによって絶頂に達しなかった場合には21kcalが消費されるのに対し、絶頂に達した場合には1回あたり80〜120kcalが消費されるということになります。
セクササイズで効率良くカロリーを消費するには
セクササイズで効率よくダイエットを行うためには、動きによって消費されるエネルギーを増やすことが重要となります。
今回は、女性がセクササイズに取り組む際のポイントを主な体位別に解説しましょう。
正常位の場合
女性が仰向けになり足を広げる正常位では、両足に少し力を入れた状態で男性の腰からお尻のあたりを挟みこむようにしましょう。
これによって太ももの筋肉が鍛えられると同時に、腰周りの引き締めにも効果が見込めます。
また、女性がわずかに腰を上げた姿勢をキープすることで腹筋や背筋も鍛えられます。
騎乗位の場合
仰向けの男性に跨る騎乗位も、太ももの筋力アップに有効です。
特に女性優位の体位であるため動きをキープしやすく、セクササイズにおすすめの体位でもあります。
男性側が動くケースもありますが、そのような場合には上半身を前に倒し腕を立てたままキープすることで太ももや腹筋を鍛えられます。
後背位の場合
女性が四つん這いになった状態の体位は後背位、またはバックともよばれます。
後背位のポイントは、上半身をうつ伏せのように寝かせるのではなく腕を立てた姿勢をキープすることです。これにより腕立てと同じ姿勢になり二の腕を鍛えられます。
また、男性側が突き出す際に腰に力を入れることで、骨盤およびその周辺の筋肉を鍛えられ、骨盤の歪みにも効果があります。
立ちバックの場合
女性が立った状態でお尻を突き出す立ちバックは、体勢を崩さないよう足で踏ん張る必要があるため、主に太ももやふくらはぎなどに効果が見込めます。
立ちバックに慣れていない女性は、壁や柱などに手をつけて支えにするのもおすすめです。
この際、できるだけ腕を伸ばし同じ姿勢をキープすることで、二の腕の筋力アップにも効果が見込めます。
側位の場合
側位とは、女性が横向きに寝た状態で片足を上げる体位です。
正常位よりも太ももに負荷がかかるため、左右の向きを変えながら試してみましょう。
対面座位の場合
対面座位は座った男性の上に女性が跨り、お互いが向き合った状態の体位です。
どの部位よりも密着感がありお互いの顔が見えるため人気があります。
対面座位では騎乗位と同様に女性側に主導権があるため、一定の動きをキープすることで太ももや腹筋などの部位を鍛えられます。
関連記事:フェムケアのやり方は?更年期に実践すべき膣マッサージの方法を紹介
セクササイズの注意点

セクササイズは正しい知識や認識のもとで行うことが大切です。特に注意しておきたい3つのポイントをご紹介しましょう。
過度の効果に期待しない
セクササイズといえども、一度のセックスで消費されるカロリーは限られています。また、相手の体調や気分次第ではセックスそのものができない日もあるでしょう。
セクササイズを実践したからといって「◯kg痩せられる」という保証はなく、思い通りの効果が得られないことも少なくありません。
セックスの強要に注意
セックスはあくまでも相手の同意があって初めて成り立つものです。
ダイエット効果や健康効果があるからといって、相手に無理にセクササイズを強要してしまうと二人の関係に亀裂が生じることもあります。
相手が嫌がっている場合には強要しないようにしましょう。
怪我のリスク
セクササイズの効果を高めようとするあまり、慣れない体位を無理に試したり、あまりにも長時間にわたる性行為をしたりするとケガをするリスクがあります。
自分と相手の体力・筋力とも相談しながら、無理のない範囲で楽しみましょう。
セクササイズの体験談
実際にセクササイズを体験した女性は、どのような印象を抱いているのでしょうか。最後に女性の体験談をご紹介します。
「食べ過ぎで太ってしまったためダイエットを決心しました。
しかし、食べるのが好きなこともあり、無理な食事制限はしたくない。好きなことをしながら痩せたいと考えていたところ、セクササイズを知りました。
騎乗位を中心に私自身が動ける体位を選び、一定間隔で動きを止めないように意識します。
そうしているうちに全身にじっとりと汗をかいてきて、これを今後も継続していけば確かにダイエット効果がありそうだなと感じました。」
まとめ
有酸素運動や無酸素運動を意識しながら行う性行為をセクササイズとよび、ダイエット効果や美容効果などが期待できる方法として注目されています。
正常位や騎乗位、後背位(バック)など定番の体位でも、トレーニングを意識して行うことで太ももや腹筋、二の腕、腰回りなどに効果が期待できるでしょう。
ただし、慣れない体勢で長時間行うとケガをするリスクがあるため、慣れないうちは決して無理はしないようにしてください。
また、セックスは相手の同意があって初めて成立するものであるため、セクササイズを相手に強要することは避けましょう。
あなたの寄付が幸せを紡ぐ。自分をも幸せにする「誰かのために」【Editor’s Letter vol.07】

Humming編集長 永野舞麻がカリフォルニアから配信する「Editor’s Letter 」。日々の暮らしで感じた気付きや、人生において大切にしていることを綴っています。
毎月欠かさず行っているとある団体への寄付。
その行動がどのように誰かの未来を変えているのか、その真実を自らの目で見るために、私はインドのバラナシへと向かいました。
世界では推定5000万人が、強制労働や性的搾取など、奴隷制の犠牲になっている現実を知っていますか?
(※参考:現代奴隷制の世界推計)
特にインドでは、貧困や社会的な格差が奴隷問題を助長し、多くの人々が過酷な状況下で働かざるを得ない現実があります。
私は今回インドで人々が奴隷から解放される瞬間を目の当たりにしました。自由を手に入れたことで、人々の目には輝きが戻ったのです。
自分の寄付が誰かの笑顔に繋がることを体感し、私自身も大きな幸せを感じることができました。
寄付したお金の行先とは?!奴隷解放の瞬間を目にしたインドへの訪問

2023年10月、定期的に寄付を行っているとある団体からの声がけで、奴隷解放を後押しするためにインドのバラナシに向かいました。
私が訪れた村々には劣悪な環境で地主に仕えて働く、いわゆる奴隷がたくさんいました。
村の人々は土の上に建てられた木造の家で、ハンモックのようにロープをはったベッドで寝ています。
電気も通っていないので、明かりは焚き火のみ。
食事も牛の糞を固めて乾かしたものを燃やして作り、水は井戸から汲み上げられたものを使います。
お金は1週間の給付金が地主からもらえますが、それもほんのわずか。
幼い頃からずっとまともに栄養を摂れないため、大人であっても背が低く、痩せ細っている。
いつ生まれたのか出生証明書がないので年齢は不明。また、誰との間に授かったかわからない赤ちゃんを抱っこしている女の子もいました。
私はそこで、6ヶ月前までは地主に仕えて苦しんでいたひとりの女の子に出会いました。
どうして奴隷になってしまったのか、そして何がきっかけとなり奴隷から解放されたのか、話を聞くことができました。
彼女はとある村で家族と貧しい暮らしをしていました。
ある日「良い仕事があるよ」と言われ、その人を信じて家族で村から200キロも離れた場所に連れて行かれたのです。
もちろん良い仕事があるというのは全くの嘘。奴隷にするための口実でした。
そこでは、ご飯をろくに食べられなかったり、作ったご飯を蹴り飛ばされるなどの嫌がらせをされたり、意味もなく夜中に叩き起こされたりしました。
ひどい環境の中で長時間休みなく働くことを強いられていました。
そんな環境に耐えられなくなり、ある晩、意を決して家族でその村から逃げ出したのです。しかし、途中で彼女とお姉さん以外は地主に捕えられてしまいました。
家族を助けるためにも彼女たちは必死で逃げました。そして、その途中に奴隷解放に力を注いでいる慈善団体のメンバーに出会ったのです。
彼女たちは微かな望みをかけてその団体に「家族を救って欲しい」と助けを求めました。とはいえ、団体は彼女たちがどの村に住んでいたのかすらわかりません。
1ヶ月ほどかけて事実確認のための調査を行い、場所を特定して彼女たちが奴隷にされていた村を訪れました。
そこで目にしたのは、狭い一室に閉じ込められていた彼女の家族でした。
地主から「奥さんを連れ戻さなければ生き埋めにしてやる」と脅され、部屋の外には生き埋めにするための穴が掘られていました。
助けに行くのがあと少し遅れていたら、きっと彼女の夫や両親は殺されていたことでしょう。
彼女が地主から逃げ、勇気を持って自分たちが置かれている状況を団体に話したことで、彼女の家族は地主から解放されることができました。
今では、国からお金を借りて畑を耕し、育てた野菜を市場で売ったり、イケアなどで販売しているようなジュートのマットなどを作って、企業に買い取ってもらったりしています。
彼女達は、自分たちで生活費を稼ぎながら自由を手にして暮らしています。
自分の現状を知ることの大切さ
「どうして警察に助けを求めないのか?」、疑問に思う方がいるかもしれません。
インドではカースト制度の考えが根強く残っています。
そのため、カーストが低い人たちは、自分よりもカーストが上の人たちと話をすれば痛めつけられるかもしれない恐怖に怯えているのです。
さらには、メディアに触れる機会がないため、自分たちが地主からされていることが違法行為であることさえ知りません。
現地の奴隷解放運動をしている人たちに話を聞くと、最初は彼らを助けるために村を訪れても口を聞いてくれないと言います。
学校を建てて、子どもたちのお昼ご飯を食べられるようにしてあげるから、子どもを学校に送るようにと、まず説得します。
そして「私たちはあなたを傷つけるようなことはしない」と信頼してもらえてようやく話をしてくれるようになると。
「奴隷制度が違法であること」、「あなた達がこんなひどい扱いを受けるのは当たり前ではないこと」、「自分たちで地主に今の状況から解放するように訴えられること」
「警察に助けを求められること」を彼らに伝えていきます。
そうすることで、奴隷として生きていた彼らは自らの力で「もう、正当な賃金なしでは働かない」と地主に訴え、奴隷から解放されていくのです。
毎月の寄付は誰かの人生を変えている
私は、人々が奴隷から解放される瞬間を目の当たりにし、毎月の寄付が誰かの人生を変えるきっかけになれていることを、自分の目で確認することができました。
出会った時は、ひどい環境下での労働を強いられ、絶望に満ちた目をしていたひとりの女の子。
自由を手に入れてからは明らかに表情が明るくなり、まるで希望の光が照らしているかのように目が輝いていたのです。
どんなに絶望の中にいても人は希望を取り戻せる。生命の強さを感じずにはいられませんでした。
辛い環境で生きる人々に手を差し伸べることができて、本当に良かったと心から感じています。

「誰かのため」は自分さえも幸せにする
日本ファンドレイジング協会が発行する寄付白書2021によると、2020年時点での日本の個人寄付総額は「1兆2,126億円」。10年前と比べると2.5倍ほど増加しているものの、同年のアメリカの寄付額(34兆5,948億円)と比べると30分の1ほどです。
また、イギリスの慈善団体「チャリティーズ・エイド・ファンデーション(CAF)」の2022年の調査では、日本の「世界人助け指数」は119ヵ国中118位。宗教的な背景や税制上の待遇などが要因となり、寄付文化が他国に比べて根付いていない状況と言えるでしょう。
人は「他の人が幸せになることを望む生き物」です。自分のために鞄を買ったり、美味しい食事を味わったり、もちろんそれも自分にとっての幸せです。
しかし、利己的なことだけで幸せを感じ続けるには限界があるものです。
利他性と幸福度の関係にまつわるさまざまな実験や研究が、世界中で行われています。
お金を自分のために使った人と、他人のために使った人とでは、後者の方が明らかに幸福度が高いといった研究結果も出ています。
あなたが自分以外に関心を寄せるものは何ですか?たとえば、子ども、動物、医療、環境保全、災害・復興支援など。
自分の関心を探り、今の自分にできる範囲で寄付やボランティアを始めてみるのもおすすめです。
誰かのためにとる行動は、自分自身を幸せにする近道なのです。
関連記事:クリック募金とは?動物や環境に関係する募金サイトまとめ
相談2:スクリーンタイム(テレビの見過ぎ)の悩み (7歳〜小学生高学年向け)

読者からの相談:
子どものスクリーンタイムについて悩んでいます。
子どもがテレビやスマートフォンを見る時間が長すぎないかと心配しています。
そのため、最近は「テレビを見る時間は1日30分まで」と決めています。
最近では子どもたちが外から帰ってくると「30分見ていい?」朝起きると「30分見ていい?」と聞いてくるようになりました。
テレビの時間を制限することで、子どもがさらにテレビに執着しているような気がします。
子どものスクリーンタイムの悩みをどうしたらいいか知りたいです。
ジョアンナさん:
これはよく聞く悩みで、多くの親や教師たちにとっても大きな関心事です。
スクリーンタイムが長すぎることは若者の健康に良くないことは多くの人がわかっていますが、この課題にどうやって対応すればいいかは、よく議論になりますね。
この問題に悩んでいる多くのご両親に私は強く共感します。
「スクリーン」(テレビ、スマートフォン、アイパッド、電車の中や街角の広告など)に囲まれた生活をしている現代社会において、この問題の解決は簡単ではありません。
良質なスクリーンタイムとは何かを判断するのも難しいですよね。
例えば親戚とのフェイスタイムならいいのか?教育番組を見るのは良いのか?など。こういうのもスクリーンタイムですからね。
米国小児科学会(American Academy of Pediatrics)は、1歳半未満の子どもにはスクリーンタイムを一切与えないことを推奨しています。
また、2歳から6歳までは(教育番組のような)「質の高い」スクリーンタイムを1時間以内にすることを推奨しています。
忙しくて疲れている親が、テレビに子守りをしてもらいたいと思う気持ちはわかります。
でも、それによって生じる、子どもの成長と発達への代償はあまりにも大きすぎるのです。
幼い子どもたちがスクリーンばかり見過ぎることは、子どもたちから自分で何かを作り出す力、想像力を奪うことになります。
こういうことを踏まえると、スクリーンタイムを30分に制限することは、とても合理的なことだと思います。
親として最も大切な役割は、子どもに明確なルールをしっかりと示すことです。
子どもは、その時その時に欲しいものを手に入れるために、あらゆる努力をするものです。
駄々をこねて泣いてみたり、叩いてみたり、もっと勉強するからと交渉をしてきたり。これに対して怒る必要はありません。
子どもは親と一緒に決めた約束事を守ることを続ける中で、いずれ自分や物事の限界を知り、良い決断をすることについて多くを学んでいくからです。
30分という制限を与えることで、子どもたちは、いつスクリーンタイムを使うかの判断について学ぶことができます。
もしかしたら、子どもが朝一番にその日のスクリーンタイムを使い、夕方にはスクリーンタイムがないことにがっかりしたり、怒ったりするかもしれません。
その場合は、子どもの残念だと思う気持ちにまず共感をしてあげてから、明日は違う選択をしてもいいかもしれないと話し合う機会にすればいいのです。
最初のうちは、子どもが不満に思うかもしれません。
でも 「ルールは守らなければならない」ということをあなたがはっきりとした態度で示し続ければ、そのうち子どもは否定的な反応は止めるでしょう。
制限を設けることは「自分の」時間をいつ使うかを子どもにある程度コントロールさせることになります。
つまり、子どもがある程度のコントロールと自主性を持つことができるということです。
また、あなたがいう「執着」は、「スクリーン」がいかに中毒性のあるものであるかを示していますね。
スクリーンタイムが終わると、とにかくまたやりたくなるということも研究結果でわかっているそうです。
スクリーンの中毒性を考えると、これからの人生において、様々な依存性のあるものから距離をとる練習になるかもしれません。
タイマーをかけたり口頭で「あと5分」「あと1分」と知らせてあげると、次のことに移行することが難しい子どもには大きな助けになります。
また、30分をスタートする前に、スクリーンタイムが終わったら何をするのかを先に考えて気持ちの準備をしてから遊び始めるのも効果的です。
私の子どもたちは、大人になってから、子ども時代に家にテレビがなかったことを私に感謝してきました。
幼い頃、常にテレビに接していた友人たちが、やることを思いつかず手持ち無沙汰な時間を過ごしていました。
その間、私の子どもたちは自分たちに無限の想像力や発明力があることに、よく驚いていました。
スクリーンタイムに固執しなかった私の子どもたちは、決して「退屈」することはなかったんです。
もうひとつ伝えたいことがあります。それは私たち大人がスマートフォンという「スクリーン」にどれだけの時間を費やしているかということです。
小さな子どもたちは、親がいつもスクリーンを見ているのに、なぜ自分だけが制限されるのだろうと不思議に思っています。
あなた自身がどれくらいスクリーンタイムを使っているのか、それが子どもにどのような影響を与えているのか、考えておくとよいでしょう。
子どもは模倣の生き物ですから、自分の鏡のような存在だと思っておくといいでしょう。
体を動かすゲームや遊び、自転車に乗ること、パズル、アートプロジェクト、本を読むこと、音楽を聴くことなどは、子どもたちが楽しめる最適なアクティビティですね。
こういった活動は、大人になっても自由な時間を楽しく過ごすための良い習慣として続くでしょう。

子どもたちは、とても想像力豊かな生き物です。
ただの段ボール箱ですら、とてもクリエイティブなものに変身させることができます。
家、レストラン、車、船、消防車、診察室、学校の部屋、ロケット、ホテルなど、私自身が、段ボールで作られた数え切れないほどの作品を見てきました。
私たちは、子どもたちの大きな創造力を奪うことはしたくはありません。
人間の脳が受け身な状態を作り出すスクリーンタイムに多くの時間を費やすのは、子どもにとって多くのリスクがあります。
子どもの心と体に秘められている大きな可能性を全力でサポートしていきましょう!
最後に、段ボールにまつわるすばらしい思い出を共有させてください。
私はあるプロジェクトで家にテレビがない子どもたちのために、大きな段ボールでテレビをつくったことがあります。
この時に子どもたちはすべてのテレビ番組を自分たちで制作しました!
私たち大人は子どもの作ったニュース、バラエティ、ダンス発表会の番組の鑑賞会に招待されました。
手作りの衣装や小道具がどんどん増え、番組はより手のこったものになっていきました。大きな創造力に私たち大人の心は温まったものです。
子育ては非常に難しい仕事です。大人はいつも試されているのです。
自分が正しい育児の道を歩んでいると思ったら、自信を持ってしっかりと歩めばいいのです。
目先の楽さや、大変さ、その場しのぎに言うことを聞かせたり、周りの目にこだわるより、大切なことがあります。
子どもをクリエイティブで、バランスのとれた優しい人間に育てるという長期的な目標も持つことが、何よりも大切なのです。

ジョアンナ・ウィギントン氏
助産師として600人以上のお産に携わる。
教育者であり、アーティスト。北カリフォルニア在住。
20年以上にわたりオルタナティブ教育施設であるカスパー・クリーク・ラーニング・センターを創設・指導してきた。
現在はNPO組織Flockworksの活動に参加し、子供や教師をサポートしている。アートの力を広めるためのプログラムを展開中。
すべての人がアーティストであるという強い信念を持ち、若者から年配の人までが創造力を探求する機会を作り出している。
関連記事:相談1:子供の心を垣間見る方法 (3歳〜小学生低学年向け)
ピンクリボン運動とは?ピンクリボンの日はいつ?バッジはもらえる?

毎年秋の季節になると、ピンクリボン運動がニュースとして報じられ、一度は目にした方も多いのではないでしょうか。
乳がんに関する運動という漠然としたイメージはあるものの、どういった活動が行われているのか具体的には分からないという方も多いはずです。
そこで本記事では、ピンクリボン運動とは何を目的にしたどういった活動なのか、基礎知識として押さえておきたいことをご紹介します。
ピンクリボン運動とは

ピンクリボン運動とは、乳がんの予防・早期発見・早期治療を周知・促進することを目的とした啓蒙活動です。
この活動の歴史は40年以上におよびます。
1980年代に乳がんで家族を亡くした遺族が「このような悲劇が繰り返されないように」という強い願いを込めて、ピンク色のリボンを作ったことが始まりです。
現在では、このピンク色のリボンが乳がんの予防や早期治療を促すトレードマークにもなっており、日本でも認知度が高まっています。
ピンクリボン運動の歴史
そもそも、なぜピンクリボン運動はこれほどまでに拡大していったのでしょうか。
ピンクリボン運動が始まった1980年代のアメリカでは、乳がんの発症率は女性の8人に1人と非常に高く、死亡率も高い病気として知られていました。
このような社会的背景もあり、一人のがん患者の遺族が願いを込めて作ったピンク色のリボンは、多くの女性の共感を呼ぶこととなったのです。
日本でピンクリボン運動が拡大し始めたのは2000年代初頭からで、乳がん啓発のためのウォーキングイベントが各地で開催され一気に認知度が高まりました。
また、東京都内ではレインボーブリッジや東京タワーといったランドマークが、ピンク色にライトアップされます。
公的機関もピンクリボン運動をバックアップしてきた歴史があります。
日本人の乳がん罹患数

日本における乳がんの実情はどのようになっているのでしょうか。
国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」によると、2019年に乳がんと診断された数は97,812例におよび、このうち97,142例が女性となっています。
また、死亡数は2020年のデータで14,779人。うち女性は14,650人に達しています。
上記のデータを見てもわかる通り、乳がんは男性よりも圧倒的に女性の罹患率が高い傾向にあります。
ちなみに、一口にがんといってもさまざまな種類がありますが、部位別の罹患数を見ると女性は圧倒的に乳がんが多く、二位の大腸がんとは約3万件の差があります。
また、乳がんは30代から40代にかけて急激に発症リスクが高まり、子育てや仕事に従事している女性がある日突然がん宣告を受けるケースが少なくありません。
10万人あたりの女性の罹患率は150例、死亡率は23.1例にも達することから、いつ罹患してもおかしくない病気なのです。
かつて、がんといえば治療が難しい病気という認識が一般的でしたが、現在は早期発見さえできれば十分治療は可能であり、日常生活に戻れる可能性があります。
「自分は大丈夫だろう」、「自覚症状がなく体調にも異変がないため問題ないだろう」と決めつけるのではなく、定期的にがん検診を受けることが大切です。
関連記事:【ストレス解消】セルフケアの種類を紹介|意味や方法についても解説
ピンクリボンの日はいつ?

ピンクリボン運動の期間に合わせて、がん検診を受けてみるのもおすすめです。
ピンクリボン運動発祥の地であるアメリカでは、毎年10月が乳がん早期発見強化月間としてさだめられています。
日本でもこれに合わせて10月が「乳がん月間」に定められており、自治体や医療機関などが主体となり乳がんに関するさまざまなイベントが開催されています。
これまで乳がんに関する知識がなかった方や、検診を一度も受けたことがないという方は、乳がんに関するセミナーやシンポジウムなどに参加してみるのもおすすめです。
毎月19日は「ピンクの日」
上記以外にも毎月19日は「ピンクの日」として定められています。
ピンクリボン運動の一環として、ブレスト・アウェアネス推奨キャンペーン(乳がんのセルフチェックを推奨するキャンペーン)が実施されています。
乳がんの検診には時間も費用もかかるため、頻繁に検査は受けられないという方も多いでしょう。
そのような場合には、乳房のセルフチェックを行い異常がないかを確認する習慣をつけてみるだけでも、早期発見につながることがあります。
関連記事:ストレスを解消するにはどうすればいい?ハグがおすすめな理由も解説
ピンクリボン運動のバッジはもらえる?
ピンクリボン運動では、活動しているさまざまな人が、胸にトレードマークであるピンクリボンのバッジを付けている姿を目にすることがあります。
これは一般的に販売されているものではなく、ピンクリボン運動を行っている団体へ寄付をしたり、さまざまなイベントへ参加したりすることでもらえる場合があります。
たとえば、認定NPO法人 乳房健康研究会では、1口500円の寄付でバッジが進呈されていますが、団体によっても進呈の条件が異なり、必ずしももらえるものではありません。
まとめ
1980年代にアメリカで始まったピンクリボン運動は、2000年代に日本でも広がりを見せ、現在でも毎年運動が続いています。
がんと聞くと生活習慣や遺伝などが原因としてクローズアップされがちですが、誰であっても発症のリスクはあります。
かつては不治の病として知られてきた”がん”ですが、現在では適切な治療を行えば寛解が見込め日常生活に戻ることもできます。
そのためには早期発見が重要であり、特に若い方は病気の進行も早いため定期的な検診が不可欠です。
「ピンクリボンの日」や乳がん月間などのタイミングに合わせて乳がんへの理解を深め、まずは検診を受けることから始めてみましょう。
クリック募金とは?動物や環境に関係する募金サイトまとめ

「社会貢献のために募金を行いたい」
しかし、経済的な余裕がなくお金を出すのが難しい、あるいは募金活動が行われている現地まで出向くことが難しいという方も多いのではないでしょうか。
そこで、手軽にできる方法・手段として「クリック募金」があります。
本記事では、クリック募金とは何か、基本的な仕組みや代表的な募金サイトの例もいくつかご紹介します。
クリック募金とは?

クリック募金とは、Webサイトにアクセスするだけで募金できる仕組みのことを指します。
通常、募金といえば店頭や街頭の募金箱に現金を寄付したり、募金を受け入れている対象の口座に直接お金を振り込んだりする方法が一般的です。
しかし、クリック募金は手持ちの現金を寄付するのではなく、対象のURLをクリックするだけで誰でも手軽に募金ができます。
また、クリック募金に対応しているサイトは動物の保護を目的としたものや、環境保護を目的としたものなど、募金の使いみちによってもさまざまです。
クリック募金の仕組み
インターネットを利用した募金のなかには、ネットバンキングやクレジットカード、QRコード決済などを活用した募金システムもあります。
たびたびクリック募金と混同されがちです。
冒頭でもご紹介した通り、クリック募金は寄付をする人が金銭を負担することは一切ありません。
実際に寄付をするのは、クリック募金のWebサイトを運営している企業や団体です。
たとえば「1クリックあたり◯円」といったように、アクセス数に応じて募金額を取りまとめて寄付を行います。
個人にとっては「寄付をしたいものの経済的な余裕がない」、「仕事が忙しく、募金のために街に出かける時間的な余裕がない」という場合でも手軽に社会貢献ができます。
また、企業や団体においては、募金の寄付先が公的機関など一定の条件をクリアすれば、寄付した分を損金として計上でき会計上のメリットも大きいです。
クリック募金は近年注目され、対象サイトも徐々に増えています。
関連記事:寄付による税金の控除とは?ふるさと納税との違いも解説
クリック募金のメリット

クリック数に応じて企業や団体が取りまとめて寄付をするクリック募金は、その仕組み上、企業や団体にとってメリットが少ないと思われがちです。
しかし、実際にはクリック募金は寄付をする個人はもちろんのこと、サイトを運営する企業や団体にとってもさまざまなメリットがあります。
社会貢献になる
企業や団体がクリック募金のシステムを提供する目的としては、社会貢献活動による企業イメージのアップや、企業そのものの宣伝効果が見込めるためです。
社会貢献活動にはボランティア活動や物資の提供、災害救援活動などさまざまなものがありますが、従業員の数が少ないと活動を継続していくことができません。
クリック募金であれば、上記のような直接的な支援でなくとも間接的な支援が可能です。
また、クリック募金の数が増えるということは、自社のサイトへアクセスする人が増え認知度が高まることも意味します。
社会貢献活動に積極的に参加しつつ、自社の認知度アップにもつながるという意味で、企業にとってはメリットが大きいのです。
支援者に金銭的負担がない
個人にとっての最大のメリットは、金銭的負担をせずとも社会貢献ができるという点です。
何らかの形で社会の役に立ちたいと考えていても、経済的に苦しい状況だと募金に回せるだけのお金を確保できず、歯がゆい思いをしてしまいます。
しかし、クリック募金であれば自分自身がお金を拠出することなく、誰でも簡単に支援ができます。
誰でもすぐに行える
仕事で忙しい毎日を送っていると、募金活動を行っている現地まで出かける時間を確保できないこともあります。
しかし、募金サイトであればインターネット環境さえあればいつでも、どこでも手軽に社会貢献ができます。
関連記事:「寄付」と「寄附」の違いは何?「寄贈」との違いや使われる場面を解説
動物に関するクリック募金サイトまとめ

ここからは、実際に運営されている募金サイトをいくつかご紹介します。
まずは、動物愛護団体の活動を支援するために運営されている募金サイトとして、以下の2つがあります。
| 募金サイト | 特徴 |
| すばらしき毎日 | 個人が運営する募金サイト。2006年に開設された個人ブログで、1クリック=1円の募金が可能。
クリック募金のリンクも一覧として掲載されており、複数のサイトで横断的に募金することも可能。 |
| おやゆび | 通販サイトの運営企業が開設した募金サイト。
クリック数に応じてネットショップの売上の一部を動物愛護団体へ寄付。また、動物愛護関連のふるさと納税もサイト内で紹介。 |
環境に関するクリック募金サイトまとめ

環境保護に関するクリック募金サイトは以下の5つがあります。
| 募金サイト | 特徴 |
| ふじさわ エコ日和 | 神奈川県藤沢市が運営しているWebサイトで、「環境クリック募金」のタブを選択すると募金サイトのリンク集が掲載されている。11のサイトが登録されており、各リンクをクリックしアンケートを記入することで1回5円の募金が可能。 |
| みどりのよこすかチャリティークリック | 神奈川県横須賀市が運営する募金サイト。登録企業は5社あり、簡単なアンケートに回答後各社のリンク先をクリックすることで募金が完了。 |
| デュプロ グリーンプロジェクト | 印刷機メーカーのデュプロ社が運営する募金サイト。募金は循環型社会の実現に向けて森林保全活動に役立てられる。
「緑の募金」や災害復興支援事業など一定の期間を設定してクリック募金が実施されている。 |
| こおりやま環境ワンクリック募金 | 福島県郡山市が運営している募金サイト。地元企業3社が協賛し、1クリックあたり5円の寄付が可能。サイトに設置された各社のバナーをクリックし、アンケートに回答するだけで簡単に募金できる。 |
| 環境教育へのクリック募金 | 北海道にある札幌市環境プラザが運営する募金サイト。札幌の子どもたちの環境教育資金を提供するために開設され、市内7社の企業が協賛。
1クリックあたり5円の寄付が可能。 |
まとめ
クリック募金とは、支援者自らがお金を寄付するものではなく、Webサイトにアクセスすることで1回あたり数円程度の寄付を行える仕組み。
実際の寄付金は企業や団体が支出することになりますが、企業の社会貢献活動の一環として取り組めるほか自社の認知度アップにもつながるため、メリットは大きいです。
一口にクリック募金といっても、動物愛護活動を目的としたものや、環境保護活動に役立てるものなど、さまざまな種類があります。
当メディアの姉妹団体のNPOハミングバードも社会貢献につながる様々な活動を行っています。
今回紹介した募金サイトも、参考にしてみてください。
夫婦の円満を保つ秘訣|冷めていく夫婦の共通点とは?

「最近、夫婦喧嘩が増えてきた」、「夫(妻)の考えていることが分からない」など、夫婦関係に悩みを抱く方は少なくありません。
夫婦仲が冷めていく原因は人それぞれですが、ある共通点が見られることも多いものです。
本記事では、なぜ夫婦関係は悪化していくのか、円満な夫婦関係を維持していくための秘訣も合わせてご紹介します。
円満な夫婦の特徴とは

夫婦関係を円満に保つにはどういったことが大切なのでしょうか。円満な夫婦に共通して見られる特徴をいくつかご紹介します。
お互いの価値観を尊重している
どれだけ親しい人であっても、自分と全く同じ価値観や考えの人は存在しません。
自分の価値観を押し付けてしまうと、相手の反発を招き夫婦関係にも亀裂が生じることがあります。
お互いに価値観や考えが異なることを理解し尊重し合うことが大切です。
日頃から感謝を伝えている
長い間夫婦生活を共にしていると、「ありがとう」という言葉を伝えなくても相手は分かってくれているだろうと考えがちです。
しかし、言葉にしなければ気持ちは伝わらないことも多いため、感謝の気持ちを言葉にすることが大切です。
思ったことは言葉にする
感謝の気持ちだけでなく、相手に対する愛情や尊敬している部分、あるいは直してほしいところなど、思ったことや感じたことがあれば言葉として伝えましょう。
円満な関係を維持しやすくなります。
二人だけで過ごす時間を持っている
子どもができたり毎日の仕事で忙しい日々を送っていると、夫婦という関係性が徐々に薄れていくことがあります。
そのため、結婚記念日やお互いの誕生日などの記念日だけでも二人で過ごす時間を作ることが大切です。
お互いを信頼しあっている
夫婦として支え合って生活していくためには信頼関係が不可欠です。
相手のことをあえて深く詮索せず、信頼していると示すことにより、相手も「この人のことを裏切ってはいけない」と感じ、理想的な夫婦関係が維持できます。
スキンシップをとっている
夫婦関係を維持するうえで日々のスキンシップは重要です。
相手に直接触れることで愛情を再確認し、円満な夫婦関係が維持できているというケースは少なくありません。
喧嘩しても引きずらない
長い夫婦生活を送っていると、価値観や考え方の違いから喧嘩になることもあるでしょう。
一度も喧嘩をすることなく穏やかな生活を送れているという夫婦は圧倒的に少ないはずです。
それでも円満な関係を維持できているのは、喧嘩をしたとしても長く引きずることなく、お互いが歩み寄っている夫婦が多いためです。
それぞれに趣味がある
夫婦関係に限ったことではありませんが、相手に対して興味を抱くことは、良好な人間関係を維持するための基本といえます。
お互いのことに興味をもっている夫婦は、髪型やファッションなど些細な変化にも気づきやすいです。
「女(男)として見られている」という意識が働くと、円満な夫婦関係を維持しやすいものです。
記念日を大切にしている
結婚記念日や誕生日など、大切な記念日を忘れることで、夫婦関係に亀裂が生じるケースは少なくありません。
相手のことを大切に思っている夫婦は、記念日に食事をしたり外にデートに出かけたりすることが多いものです。
夫婦仲がギクシャクする原因は?

夫婦仲がうまくいかない、ギクシャクしていると感じる原因はさまざまですが、代表的なものをいくつかご紹介しましょう。
夫が家事や育児に非協力的
夫または妻が家事や育児に協力的でないと、夫婦のどちらかに負担が偏りがちになります。
日々の暮らしのなかで小さな不満が溜まっていくと、相手に対して些細なことで腹を立てるようになり、夫婦仲が徐々に悪化していきます。
金銭的な事情
十分な収入が得られないと生活費を切り詰めていかなければならず、なかには結婚したことを後悔するケースもあるでしょう。
相手を非難するような発言がある
相手の人格を否定する言葉を投げかけることはモラハラにあたり、夫婦の信頼関係を構築することも難しくなります。
本人にしてみれば何気なく発した一言のつもりでも、相手は大きく傷つき夫婦関係に亀裂を生じさせるケースもあります。
金銭感覚の違い
十分な収入を得ていたとしても、金銭感覚の違いが結婚後に発覚するケースもあります。
たとえば、ギャンブルに毎月大金を注ぎ込んでいたり、外食や交際費に多額の支出があると、夫婦生活を続けていくことに不安を感じ関係が悪化することもあります。
浮気・不倫の発覚
浮気や不倫が発覚したとき、相手のことを信頼していただけにそのショックは大きいものです。
それまでの夫婦生活は何だったのかと絶望し、この先夫婦関係を維持していくことはできないと判断することもあるでしょう。
関連記事:夫婦仲が悪い原因は?子供に与える影響や改善する方法をご紹介
冷めていく夫婦の共通点

上記とは反対に、関係が冷めていく夫婦にはどういった共通点が見られるのでしょうか。
コミュニケーションが少ない
夫婦生活が長く続くと、お互いが当たり前の存在になり、コミュニケーションが自然と減っていくケースも少なくありません。
しかし、会話の量が少ないと夫婦といえども相手が何を考えているのか分からなくなり、心理的な距離が広がっていくことも多くなります。
あいさつや感謝の言葉がない/少ない
コミュニケーション不足とも関連しますが、毎日のあいさつや感謝の言葉が少なくなることもポイントとして挙げられます。
「おはよう」、「ただいま」、「ありがとう」といった一言はコミュニケーションのきっかけにもなります。
この一言が出てこないと、自然とコミュニケーション不足に陥ってしまいます。
共通の趣味や話題がない
夫婦の間で趣味や価値観が合わないと、盛り上がる共通の話題もなく自然と会話が続かなくなります。
会話を引き出そうとして話題を振っても、そもそも相手が興味を抱いていないと鬱陶しく感じ、ますます冷え切った夫婦仲になることもあるでしょう。
愛情が一方通行になっている
夫婦の一方が愛情を抱いていたとしても、相手がそれに応じない場合、夫婦関係のバランスが崩れてしまいます。
やがてその愛情が鬱陶しく感じたり、重いと感じたりして夫婦仲が冷めていくこともあるでしょう。
勢いで結婚してしまった
冷静な考えや相手に対する深い理解がないまま、感情の勢いで結婚した場合、その後の生活を続けるなかで問題が浮き彫りになり、関係が冷めることがあります。
義理の家族との関係性が悪い
相手の両親やきょうだい、親族と良好な関係を築くことができないと、自然と距離を置きたくなるものです。
配偶者にしてみれば、自分の家族をないがしろにされた気分になり夫婦仲に悪影響を及ぼすこともあるでしょう。
関連記事:セックスレスの離婚率はどれくらい?レスにならないための方法とは
夫婦の円満を保つための秘訣

円満な夫婦関係を保っていくためには、どういった点に注意すれば良いのでしょうか。日頃から実践したい秘訣をご紹介します。
会話する時間を増やす
どんなに些細なことでも、夫婦で会話を交わす時間を増やしましょう。
たとえば、「今日仕事でこんなことがあった」、「子どもがこんなことを言っていた」、「◯◯というテレビ番組が面白かった」など、話題は何でも構いません。
そこからさまざまな話題に発展しコミュニケーションのきっかけとなるでしょう。
お互いに干渉しすぎない
たとえば、残業で帰宅が遅くなった相手に対し浮気を疑うような言動をしてしまうと、お互いに不信感が生まれ信頼関係が崩れてしまいます。
信頼し、あえて深い詮索をしないことで「この人を裏切ってはいけない」という気持ちが芽生え、円満な夫婦関係が維持しやすくなります。
日頃から感謝の言葉を伝える
「ありがとう」という感謝の言葉を意識的に投げかけてみましょう。
感謝の言葉を掛けられて不快になる人はおらず、夫婦仲を改善するための第一歩にもなります。
最初の一言を発するには勇気が要ることもあると思いますが、繰り返し投げかけることで信頼関係が構築され、夫婦円満につながっていきます。
相手を思いやる
相手を尊重し思いやる気持ちも夫婦円満の重要な秘訣です。
自分と異なる意見や考え方で対立したとき、なぜそのような意見をもつのか相手の立場で考えてみましょう。
スキンシップをとる
長い夫婦生活のなかでセックスレスになることも珍しくありませんが、そのような場合でも手を繋いだりハグをしたりすることが習慣になっている夫婦も多いです。
一緒に食事をする
コミュニケーションの場として食事の時間は特に重要です。
仕事が忙しいときでも、相手の帰宅に合わせて食事をとるなど、できるだけ落ち着いて話せる場を設けましょう。
二人で過ごす時間を作る
より夫婦の仲を深めるためには、二人きりの時間をつくることも心がけましょう。
休日は二人で食事やドライブに出かけたりすることで、独身時代を思い出し夫婦の愛情が深まっていくこともあります。
記念日を大切にする
結婚記念日や誕生日など特別な日は夫婦二人でお祝いを欠かさないようにしましょう。
仕事や家事、子育てに忙しい毎日を送っていると記念日を忘れがちになりますが、スマホのカレンダーに登録しておくなどの工夫も有効です。
お互い一人の時間も大切にする
夫婦といえどもつねに一緒の生活を送っていると、精神的に疲れてくることもあります。
そこで、あえて一人の時間をつくることで適度な距離感が生まれストレスのない生活を送ることができます。
一人で過ごせる書斎や趣味の部屋をつくったり、一人で散歩やショッピングに出かけたりするのも気分転換になるはずです。
喧嘩してもすぐに仲直りする
些細なことで喧嘩をしたとしても、後に引きずることなくすぐに仲直りをするよう心がけましょう。
相手が折れないと感じたら、ときには自分から謝ることも大切です。
関連記事:夫婦関係を修復するためのきっかけ|絶対にやってはいけないこととは?
夫婦円満の秘訣に関する名言を紹介
最後に、夫婦円満のために覚えておきたい言葉をいくつかご紹介します。
ゲッターズ飯田(お笑いタレント・占い師)
「『頼れる』と思って一緒になったら、頼りないのが男で、『弱い』と思って一緒になったら、強いのが女ってもの。」
笑福亭鶴瓶(落語家・お笑いタレント)
「ハッピーワイフ、ハッピーライフ」
所ジョージ(お笑いタレント・シンガーソングライター)
「俺が妻と結婚したのは、妻の笑顔が長い時間みたいから。
今、妻を笑顔にしてあげられていないなら、笑顔にしてあげられていない俺がすべて悪い。」
岡本太郎(芸術家)
「自分の惚れた女にケチするヤツは許せない。」
フグ田マスオ(「サザエさん」登場キャラクター)
「たまには羽を伸ばしておいで。タラちゃんは僕がみるよ。」
野原しんのすけ(「クレヨンしんちゃん」主人公)
「悪いことしたら、ごめんなさいって言うんだゾ。幼稚園じゃみんなそうしてるゾ。」
まとめ
お互いに信頼し愛情をもって暮らしている夫婦でも、些細なことで言い合いになったり大喧嘩に発展することもあるでしょう。
このようなトラブルが頻繁に繰り返されると、徐々に夫婦仲は冷え切っていき最悪の結末になることも予想されます。
円満な夫婦関係を維持していくためにも、今回ご紹介した秘訣を参考に普段の生活を見直してみましょう。
ヴィパッサナー瞑想リトリート体験談。リトリート中に感じた恐怖体験とその後の変化とは【Editor’s Letter vol.06】
Humming編集長 永野舞麻がカリフォルニアから配信する「Editor’s Letter 」。日々の暮らしで感じた気付きや、人生において大切にしていることを綴っています。
ある日の深夜、全身の皮膚が毛羽立つような恐怖に襲われました。
真夜中、突然のサイレンに驚いて起き上がると、ビービービーと大きな音が鳴り響いているのです。
「どこかで核爆発が起きたに違いない……」
これまで感じたことのない不安や恐怖心が押し寄せてきました。
けれど、周りを見渡すと部屋の外は静まりかえっている。なんと、サイレンは自分の耳の中だけで鳴り響いていたのです。
忘れもしないこの体験は、ヴィパッサナーリトリート8日目の出来事。
これは今まで心の奥底に溜めた気持ちが浄化され、穏やかな心に近づくための通過点だったのです。

観察することで変革を起こすヴィパッサナーとは?
ヴィパッサナーとは、2500 年以上前にゴーダマ・ブッダによって再発見されたメディテーション法。
感覚や呼吸に集中し、その瞬間のありのままの自分を観察することで、不安、怒り、嫉妬、執着、悲しみなどのあらゆる心の濁りを取り除き、浄化を図ります。
穏やかで充実した人生を築くための手段として、ヴィパッサナーは世界中で受け入れられています。
※詳細はこちら
なぜリトリートに参加しようと思ったのか

私がメディテーションを始めたのは、今から3年ほど前、世界的なパンデミックが起こりはじめた頃。当時は1回20分のマントラ瞑想を朝と午後の1日2回行っていました。
自宅でメディテーションをしていると、家族が話しかけてきたり、子どもが膝に座ってきたり、兄弟喧嘩がはじまったり、そういう状況の中でもメディテーションを続けるのが、ある意味与えられた試練だとはわかっていても、100%自分の内と向き合うことはなかなか難しい。自分だけの時間をしっかりと確保して、本格的にメディテーションを体験してみたいという想いが日に日に募っていきました。
そこで興味を持ったのが、数あるメディテーションの中でも特に厳しいと噂のヴィパッサナー。
ヴィパッサナーの合宿に参加することで何が得られるのかあえて深くは調べないまま、自宅から3時間半ほど車を走らせ、北カリフォルニアのヴィパッサナーセンターへ向かいました。
※ヴィパッサナー瞑想の合宿は世界各国で開催されており、日本では京都と千葉に合宿センターがあります。
他者との会話やアイコンタクトさえも禁止される、自分と向き合う10日間
合宿期間は10日間。いただく食事は朝昼2回の菜食と夕方にフルーツやお茶をほんの少し。毎朝4時に起床し、休憩を挟みながら1日10時間以上メディテーションを行います。
合宿期間は外の世界との接触は完全に遮断され、もちろんスマートフォンやテレビなどデジタルの使用は禁止。さらには人と会話することや誰かと目を合わせること、メモを書くこと、本を読むことさえも許されません。
最初の3日間は、鼻の周りの感覚を研ぎ澄ませて呼吸に意識を向けるアーナパーナというメティテーションをひたすら行い、自分の内と向き合う訓練をします。
4日目に、ついに、全身の感覚に意識を張り巡らせるヴィパッサナーに移ります。まずは鼻まわりからスタートし、頭から顔の各パーツ、肩、腕、手、胸、背中、腹、脚と体全体を1つ1つスキャンするように意識を集中させ、空気の重みや服に触れている感触、脈を打つタイミングを感じていきます。
さらにメディテーション中に絶対に動いてはいけない時間が1回1時間、1日に3回あります。ストロングメディテーションと呼ばれているその時間中は、どんなに体が痛くなっても、鼻がかゆくなっても動いてはいけません。慣れるまでは辛い時間ですが、これを行うことで痛みやかゆみなどの不快な感覚も現れては消える、「世の中に起こる全てのことは永遠には続かない」という感覚を体感し、どんな時でも心の平静さを保つ訓練ができるのです。

メディテーション中に突如現れた幼少期のトラウマ
合宿中、自分の全身の繊細な感覚と真剣に向き合うことで、過去に蓄積された身体や心の中のネガティブな要素が変容し、何かしらの形で現れることがあります。
4日目のメディテーション中のこと。幼少期のトラウマが突如私の心に現れ不意に涙が溢れたのです。
この日から始まったヴィパッサナー瞑想。決められた一定の時間は絶対に動いてはいけないにも関わらず、隣の方は体を掻いたり、寝息を立てていたり。
「私を含め、周りのみんなはこんなに頑張ってメディテーションしているのに、どうしてこの人は…」、ネガティブな感情が沸き起こりました。
不思議なことに、そのイラつきが私の幼少期の記憶と結びつき、当時から内に秘めていた想い、悲しみ、願望、様々な気持ちが現れたのです。
私には3歳年の離れた妹がいます。幼い頃、私は両親に褒めてもらいたくて懸命に家の手伝いをしたり、駄々をこねずに言われたことをきちんとこなしたり、わがままを言わずに欲しいものを我慢をしたり、愛されたい一心でいました。一方で、妹はニコニコ、そこにいるだけで親から愛情を注がれる。
「私だって、ありのままの私を愛して欲しかった……」
そんな素直な心の内がメディテーション中に自然と湧き起こり、涙が止まらなくなりました。
これまでアメリカに移住してから何年もセラピーに通い、たくさんの幼少期の親子関係、姉妹関係のトラウマを掘り返しては癒してきていたので、未だに、こんなにも鮮明な気持ちが現れたことに驚きを隠せませんでした。
合宿中は辛い記憶が蘇ったり、得体の知れない恐怖に襲われたりすることもありました。しかし、最終日には「もう少しこのメディテーションリトリートを続けていたい」そんな気持ちになっていたのです。
リトリート後に満ちた愛情と優しさ
10日間のリトリートを終えて家に帰ると、こんなに誰かを愛おしいと思ったのは初めてではないかというほどの「ピュアな愛」が自分から溢れ出ているのを感じました。
家族との会話。一緒に味わう食事。全てが愛おしい。まるで自分の周りの空気全体が愛のベールとなり家族を包み込んでいるような感覚です。
以前だったらイライラしてしまったような子どもたちや夫とのやりとりの瞬間も、イラつきどころか逆に愛を持った接し方ができたり、ただ抱きしめているだけなのに涙が溢れてくるような愛情を感じたり。
さらにリトリートを終えて1週間ほどは、自然と自分の呼吸に意識が向けられ、目を開けたままメディテーションしている状態が続いたのです。イメージとしては、大嵐で海は大荒れなのに、その中を静かに進む船のように落ち着いた気持ちで過ごすことができました。
この不思議な感覚は徐々に薄れていきましたが、あの感覚は今でも忘れることはありません。
ヴィパッサナー瞑想リトリートの10日間は、まるで人生の縮図
人生において全ては永遠には続かない。痛みも苦しみも、もちろん幸せも。だからこそ、今この瞬間を存分に感じよう。そのような気づきを私にもたらしてくれたヴィパッサナー。
普段、私たちは脳からの情報や声に振り回され、落ち込んだり、怒ったり、幸せを感じたり、良くも悪くも感情に左右されがちです。
メディテーションを通じて、呼吸や感覚に意識を集中し、脳から送られる過多な情報を一旦遮断する。それによって物事がより鮮明に見え、エネルギーを本当に大切なものだけに注ぎ込むことができるようになることを体感できました。
幸せは案外身近にあって、今を感じることから生まれてくるのかもしれません。物事の見方、捉え方が変われば人生が変わる。それを教えてくれた貴重な10日間でした。
新しい感覚や目線で自分の人生を味わいたい方には、ヴィパッサナーは大きなヒントや変わるきっかけを与えてくれるでしょう。
ボディポジティブ:体重計も投げ出して、ありのままを受け入れる

あなたは「ボディポジティブ」という言葉を聞いたことがありますか。
英語を直訳すると「体を前向きに」つまり、あなたのありのままの体型を受け入れてあげようというメッセージで、欧米を中心に広まった考え方です。
あなたは、今まで自分の体型とどう向き合ってきましたか?
自分の体をありのままに受け入れることができていますか?それとも、もっと変わりたいと思っていますか?
なぜボディポジティブが大切なのか、どうやったら私たちがありのままを受け入れることができるのか
「ボディ・ポジティブ (Body Positive: A Guide to Loving Your Body)」の著者、女性のエンパワーメントを目指したマインドセット・コーチでもあるエミリー・ローレンさんに、ハミングの條川純が聞きました。
どうして世の女性たちは「やせること」を追求するようになったのか、体型の悩みをどう解消できるのか、子どもにボディポジティブの考えを伝える方法について。
新しい視点で考えるきっかけとして、エミリーさんとの対談をぜひお楽しみください。
🔻エミリーさんとの対談動画はこちら🔻
「やせているほうが良い」は本当?

−−日本では、『女性はやせているべき』という社会的プレッシャーがあります。私たちはこういうプレッシャーにどう接していけばいいのでしょう。
日本に限らず、やせなきゃ、というプレッシャーはどの国にもありますよね。
まず、なぜ世間には「やせていることが良い」という基準があるのでしょう。
歴史をさかのぼってみると、「細い体」は世界の植民地化の歴史や欧米へのあこがれからスタートし、これが商業化へとつながっていることがわかります。
つまり、体型への不安な気持ちを利用することがお金もうけになると知った企業が、メディアを利用して女性の不安をあおるようになった、こういう歴史があるのです。
こうして作られたのが「やせていることが良い」という考えです。
お金もうけのために私たちの体型が利用されているのだと知ることは「やせる」ことにこだわらない強さを持つための最初の一歩になるでしょう。
−−残念なことに、日本では夫が妻の体型を批判することは普通です。どうすれば、夫婦がケンカをすることなく、この問題に一緒に取り組めると思いますか?
体型に関する会話は、お互いを尊重するためにするべきものですよね。
だから体型を批判されたのであれば、まずしっかりと「あなたの発言に私はとても傷つく」と率直に伝えましょう。
こういうパートナーの悩みを抱えるあなたにまず伝えたいことがあります。
それは、見た目の美しさだけを見ている人と一生を過ごしたいですか?ということです。
私たちはみんな年をとって見た目は変化していくんですよ。一緒に幸せに年をとっていけるような、そんな人と一緒にいたいと思いませんか。
ただ、相手が単にあなたの健康を心配して言っているというケースもあるでしょう。太っていることが健康的ではないと、多くの人が思っているからです。
でも、太っている人がみんな不健康だということではありません。だから、太ることへの恐怖や差別について学ぶことはとても重要なのです。
🔻エミリーさんとの対談動画はこちら🔻
体重計を捨てたから見える世界

−−体型の悩みがある人は、どういったことを日々の生活に取り入れたらよいでしょうか?
まずは鏡にうつるあなたを見つめることから始めましょう。
あなたの体に自信が持てないなら、あなた自身をほめる言葉を小さな紙に書いて鏡に貼っておくといいですよ。
写真にうつる自分の見た目が好きじゃないわ、と思ったときにも、これをやってみてください。
写真にうつるあなたをそのまま受け入れて、これが私なんだ、と思ってほしいんです。こうすればするほど、あなたは見た目に自信をもてるようになります。
もちろん、こんな風にあなたを受け入れられるようになるまでには時間がかかりますが、焦らずに続けてみてほしいんです。
自分を肯定して受け入れていくことで、自信がついていくでしょう。あなたの中に現われるどんな小さな心の変化も大事にして、あなたのがんばりをほめてあげてください。
さらにSNSをうまく活用する方法もあります。SNSはやせたい気持ちを助長する悪影響がある一方で、自分の体を大切にするためのツールとして使えます。
普段から、あなたが心地よくなれるようなメディアを見るように意識してみてください。
ボディポジティブに関する本、ボディポジティブのメッセージを発している人のインスタグラムをフォローする、などです。
日々どういったメディアに触れているかは、あなたが自分の体についてどう感じるかに大きな影響を及ぼすからです。
さらにみなさんに伝えたいことは、体型の悩みは浮き沈みが激しいということです。特に女性はホルモンの影響もあるため身体はいつも変化しています。
だから、自分が感じることをそのまま受け入れてあげて、例え自信が持てない時でも、それが自分の価値だとは考えないようにすることがとても大切なのです。
−−あなたは、時には自分を前面に出したり、キャラクターを作り上げたりと自分の『分身』をつくることで、体型の問題に前向きに取り組めると提言していますね。
具体的には、どんな風に自分の分身と向き合っているんですか?
まず、あなたがどんな人になりたいかを決めるんです。そして「本当にその人になったかのようにふるまう」それだけです。
私がボディポジティブの問題で声を上げているからといって、私が体型の悩みを全て解決したというわけではありません。
でも自分の体型が自分の価値を決めないことを知っている人物としての役を演じていこうと決めたのです。
だから、この役を演じるほど信念もさらに強くなり、社会が持つ偏った美の基準にも力強く接することができるんです。

−−健康のためにはやせていたほうが良いという考えもあります。
ボディポジティブが主張する自由な体型で良いのだという意見も大切だし、このあたりの矛盾はどう考えますか?
この矛盾について考える時に一番大切なことは、あなたの「体重」の数値が、必ずしも「健康」を示すものではないということです。
例えば、運動をすると筋肉がつき体重が増えますが、これは不健康になったというわけではありませんよね。
だから、ボディポジティブとはあなたが心地よく感じられているのかをどうかを考えるものなのです。
「やせたい」と感じること自体を恥ずかしく思う必要もありません。
なぜなら、私たちは、やせることがあたりまえだというメッセージを送り続ける社会に生きているからです。
こういった社会からのメッセージと戦うのは簡単ではありません。
あなたの体型に関してプレッシャーを感じるのは普通のことですが、恥ずかしく感じる必要はないのです。
ですから「あなたが心地よくなるため」というゴールを明確にして、「体重」と「健康」の2つを分けて考えてみてください。
こうやって区別することで、健康的で心地よくいることが、どれだけ精神面に良い影響を与えているか、長い目で見ると実感できるでしょう。
私はダイエットする人が苦手なのではなく、ダイエット文化が嫌いなんです。
「体重」と「健康」が密接にリンクしていることが問題なのです。
例えば運動や、健康的な食事など、自分が気分が良くなることを継続した結果、体重が減るということもあります。でも体重が減らなくても良いんです。
一番大切なことは精神的・肉体的に健康であることで、見た目ではないのです。
私がお勧めするのは、「やせなさい」と脅迫してくる道具、つまり体重計を捨てることです。
体重の数値に苦しむ代わりに、食べたものが自分の体に浸透していくのが心地よいかどうか、そういう違った視点から体と付き合ってみましょう。
🔻エミリーさんとの対談動画はこちら🔻
子どもにボディポジティブをどう教えるか

−−子どもが自分の体型についても自己肯定感を高められるようにするために、親はどんなことができますか?
自身が体型で苦しんできた大人は、子どもたちにもボディポジティブを教えるのが難しいでしょう。
無意識にその苦しみを子どもにも受け継いでしまうからです。でも、対処のしかたはたくさんありますよ。
ひとつは、親である自分の体についても否定的な言葉を使わないということです。
特に幼い子どもたちはなんでも聞いています。だから大人は、自分の体型に悩んでいても、子供の前では言わずに心の中にしまっておきましょう。
他人の体型も一緒です。ほめ言葉であっても「あなた最近やせた?」とは言わないようにしましょう。
これは「やせていることに価値がある」と子どもに伝えているようなものです。
さらに、大人の私たちが、子どもたちの外見以外のことにもっと目を向けてあげましょう。
「子供が得意なこと」例えば、思いやりがあるとか、気が利くとか、そういうことの方がもっと重要であることを子供たちに知ってもらうのです。
最後に最も大切なこと、それは子どもが小さい時から、メディアで見るステレオタイプについてしっかりと話しをすることです。
太ることへの恐怖やダイエット信仰は、私たちの文化にしみ込んでいます。だからこそ、この課題について子どもと一緒に考えることが大切です。
こうすることで、子どもが自信を持ち、体型に関する試練に直面したときに力強く対応できるようになります。
ですから、SNSで見る内容は事実ばかりではないと教えることが重要です。現代は画像がとても簡単に加工できる時代です。
他人に受け入れられるために自分を変える必要はない、ということを子供に強く伝えましょう。
「やせなきゃ」が心に与える影響

−−体型の悩みからくるメンタルヘルスの初期症状にはどんなものがありますか?
自分を批判しすぎたり、自分に否定的な言葉ばかりかけたり、孤独を感じたり、引きこもりになるこういった行動がないか注意してみましょう。
特に気がつきやすいのは、食生活が突然に変わる場合です。
また、以前は楽しんでいたことに興味がなくなったり、常に心配になったり、突然悲しくなるなどの変化に気づくことがあります。
そんなときは自分の中で留めずに、客観的に見ることのできる周りの誰か話しやすい人、できればメンタルヘルスのプロフェッショナルに話してみることをお勧めします。
私自身、食生活が乱れ、ネガティブな考えにとらわれていた時期がありました。でも、ボディポジティブの考え方を知り人生が変わりました。
だから、このことをもっと多くの人にも伝えたいんです。だってこの考え方を知るだけで、大きな力をもらえるのですから。
−−今も体型に悩む世界中の女性へのメッセージは?
最も大切なことは、あなたはひとりぼっちではないということです。
あなたと同じつらい体験をした人がこの地球上には必ずいるんです。だから、そういうコミュニティや、あなたをサポートしてくれる人たちを見つけましょう。
そして、自分が欲しいものを求めるためにまずは最初の一歩を踏み出しましょう。
あなたの体をそのまま受け入れ、自分に正直になりましょう。あなたならできます。あなたはひとりぼっちじゃないんです。

エミリー・ローレン・ディック
エミリー・ローレン・ディックは、女性のエンパワーメントを目標としたクリエイティブ・マーケター、作家、活動家そしてマインドセット・コーチでもある。
http://www.instagram.com/realhappydaughter
http://www.happydaughter.com
彼女の著書は、アマゾンを含む多くの場所で入手できます。出版社のHPリンクはこちら:
https://www.familius.com/book/body-positive/
新しい年への挑戦!人生の目的を発見してそれを生かしていく方法

新しい年が始まりましたね!
たくさんの方が、新しい目標や挑戦に向けてスタートしようと意気込んでいるのではないでしょうか。
そこで、今回はそんなあなたに向けて、自分の生きる意味を見つけてより幸福な人生を築く手助けとなる、Calliopeが提供するプログラムをご紹介します。
ーーCalliopeについて教えてください。
マーラ:私たちのプログラムには主に3つあります。
ひとつは、一緒に瞑想をすることで、参加者が自らの内側に意識を向け、人生の目的を明確にするためのクラスです。
人生の目的がはっきりした後には、私たちが考案したプログラムが役に立つでしょう。それが2つ目です。
人生の目的がわかったあなたにとって、それを土台として、あなたの関わる地域コミュニティで実際に行動に移すことができるようサポートするプログラムです。
この2つが、Calliopeが個人向けに提供しているプログラムです。
3つ目は、企業向けのワークショップです。

ここでは、企業が進むべき目的を明確にし、その目的に向かってメンバーが一丸となって意欲的に関わることができるような環境を作るためのサポートを提供しています。
こういった取り組みが大切な理由。
それは、私たち人間は本来、自分自身よりもっと大きな目的やゴールを見出すと、その実現のために自分だけが持つ特別な才能を発揮することができる生き物だからです。
Calliopeでは、あなたが人生に明確な目的をもたらすためのこういった3つのプログラムを提供しています。
これは、私たち自身が今まで多くのことを学び失敗をし、大きく成長してきた結果できあがったプログラムです。
ーーどういうきっかけで、このプログラムをスタートしたんですか?
桃子:そもそもの原点は「アート」にあると言えます。
なぜ私たちがCalliopeをスタートしたかというと、マーラと私がともにアートを大切にしているからです。
私たちは、この世界を、もっと調和がとれて思いやりに満ちた場所にしたいと望んでいますが、そのためにはアートを日常に取り込むことが必要だと考えています。

私たちが社会に対して、最も効果的に貢献できる方法はなんだろうと考えた時に、Calliopeが生まれました。
私たちの信念は、私たちひとりひとりが地球上のすべての人たちと触れあい、それぞれが最も美しいと思う形を自分の方法で世界に示すことで、この社会は自然と変わっていくというものです。
私自身は小さい時から自然が大好きで、大学では環境科学を専攻し、土地保全やコミュニティ・スペースに関するNGOの仕事もしていました。
でも、こういった活動だけでは自然とつながる社会を作っていくためには十分ではないと感じたんです。
当時は、自分の活動が社会を変えられると信じるマインドセットがまだ私の中で整っていなかったんです。
そのため、まずは自分に変化を起こす力があることに気づくために瞑想をしたり、自分のパッションがどこにあるのかについて学びました。
そしてこの私たちの体験を、おなじような悩みを抱える他の人たちとも分かち合いたいと強く思いました。

人は誰もが変革者であると言うことに気づいた私たちは、社会に貢献できる方法をたくさんの人と分かち合いたいと思いました。
これがCalliopeをスタートした理由です。
マーラ:Calliopeのクラスはオンラインで行うので、世界中の人たちとつながることができることもこのプログラムの特徴ですね。
例えば桃子は東京、私はカリフォルニアに住んでいてお互い遠く離れていますが、こうやってグローバルなつながりを築くことができる時代なんです。
そして大切なことは、オンラインで学んだことを、自分の地域コミュニティで行動に移すことです。
つまり、オンラインで学んで、オフラインで実行するというハイブリッドなアプローチなんです。
桃子:プログラムを始めて実感しているのは、同じ考えや価値観を持った人たちが集まると、本当に大きな力が生まれるということです。
例えば、私が日本で育っていた頃は、環境や自然について気にかけている人はほとんどいませんでした。
このCalliopeのプログラムに参加することで、あなたは、思いもよらないバックグラウンドを持った人や遠く離れた場所に住む人たちと出会うことができます。
あなたと多くの共通点がある仲間たちに出会いきっと驚くことでしょう。
また「あの人ができるのなら、私にもできるかもしれない」そんな風に、仲間から勇気ももらえるんです。

ーーCalliopeという名前の由来は?
マーラ:「Calliope」という言葉自体は、ギリシャ語の女神という意味で、ギリシャ神話に登場する女神のようです。
桃子が『ハミングバード(※ハチドリという意味)』という名前の組織をちょうど立ち上げた頃でした。
環境問題を考えることをミッションにしたこのハミングバードの関連プロジェクトとしてスタートしたのがCalliopeでしたが、その後は独自でプログラムを立ち上げ、活動を始めました。
名前を決める時に、我々が重視したのは、自然との調和をイメージさせる優しい響きで、さらにハミングバードとつながりのある名前にするということでした。
ーーこのプログラムを受講した後には、どんな変化を期待できますか?
桃子:プロジェクトでは、まず参加者に、それぞれが取り組みたいプロジェクトを決めてもらいます。
つまり、自分にとって重要で本当に関心があるものを考え、プログラムが終了するまでに何を達成したいかという、ビジョンやゴールを設定してもらうんです。
過去の参加者の例をご紹介しましょう。
例えば、幼稚園の先生をしている40代の女性は、小さい頃から土をいじることやガーデニングに興味があったそうです。
彼女は仕事柄、普段から子どもたちと過ごす時間が多いので、「私のパッションを子どもたちと共有したい」というプロジェクトに決めました。
最初は小さな規模で幼稚園のスペースを使って子どもたちとガーデニングをスタートしましたが、結果的には、大学で大規模なガーデニングのプロジェクトを実現するまでになりました。
「自分の夢が実現しました!」と彼女はとても興奮していました。

私自身も彼女のプロジェクトから大きな感動をもらいました。
人々がお互いに支え合うことで、その人の人生に魔法が起きる、Calliopeではこういったストーリーを実現することができます。
参加者たちは、最初は特にプロジェクトの具体的なアイデアを持っているわけではないのです。
でも、私たちのプログラムを体験して実感してほしいことは、オープンマインドな心で好奇心を持って参加すれば、あなたの目の前にも魔法が起きるということです。
このプログラムを終えた時には「私は世界に変化を起こす変革者である」と確信を持てるようになってほしいんです。
なぜなら、私たちは、絶望を感じたり、自分には何の力もないと弱気になりがちな時代を生きているからです。
だから、自信をもって自分の中のパワーを感じてもらうことがプログラムの最終的なゴールです。

ーーCalliopeではこれからどういったプログラムが用意されていますか?
マーラ:現在は毎月、『Self-Discovery Classes』という自己発見のクラスを提供しています。
ここでは、グループ瞑想を通して自分自身と向き合うことができます。
さらに、毎年いくつかの大きなプログラムも開催しています。
そのうちのひとつが『purpose to action programs』という目的を実際の行動に移すための12週間のプログラムです。
あなたがどの地域に住んでいても、参加できるように設定されています。
そして、purpose to action programsは1月30日からスタートします。
興味がある人は、私と桃子による「イントロコール」に参加してみてください。
何か行き詰まりを感じていて、それを乗り越えたいと思っている人がいたら、私たちはあなたのコーチになり、サポートすることができるでしょう。
プログラムがどんなものか見てみたい人は、リンクを貼っておきますので、そこからのぞいてみてくださいね。
登録はこちらから:https://calendar.google.com/
Calliope
マーラ・ワルドホーン:Calliope共同設立者。
参加者が人生の目的について立ち止まり、内省できるようにデザインされたワークショップやプログラムを担当している。
Mindfulness and Meditation Teacher Certification Program(マインドフルネスと瞑想の指導者認定プログラム)を修了し、15年間ビジネス・コーチ、スタートアップ企業の経営者として働いてきた。
荻原桃子(おぎはらももこ)
社会起業家。1992年東京都生まれ。英国のQueen Marry Univeristy にて環境学科修了。
自然と人のつながりに興味を持ち、自然保護団体や、Community Garden、オーガニック農業を行う畑で働く。
Community Garden では、子供たちに自然との繋がるを作るために、教育補助業務も行った。
日本に帰国後、メンタルヘルスの大切さを実感し、日本に住む難民や、がん患者にヨガを指導。
現在は自然環境・社会問題の改善を目標にウェルビーイングのツールを使った、グルーブコーチングスタイルのオンラインプログラムを提供するCalliopeを設立。
アフリカで学んだ「愛にあふれた時代から今の日本が学べること」 ~SHOGENインタビュー

ハミングの監修者でもあるSHOGENは、日本で注目をされているアフリカンアートのペンキ画家。
彼の作品には「生きるのって、楽しい!」というメッセージがあふれています。
もともとは大手化粧品会社で働いていたSHOGEN。
タンザニアの伝統絵画であるティンガティンガとの運命的な出会いが彼の人生を変えました。
その後、彼は一人でタンザニアに渡り、村人たちと共に生活しながら絵の修行に励みました。
SHOGENが村で学んだことは絵画だけにとどまりませんでした。
帰国後の彼のアーティストとしての活動の源となっているのは、村長から聞いた「今の日本人が忘れてしまった本来の日本人の生き方」でした。
タンザニアの村に伝えられる、私たち日本人の本来の使命や、忙しい日々を送る私たちでも取り入れられる幸せに生きるヒントなどをSHOGENに聞きました。
日本人なら誰でも心揺さぶられる遠いアフリカからのメッセージを、ぜひお楽しみください。
🔻SHOGENのInterview動画はこちら🔻
みんなで生きていく時代

ーータンザニアで学んだことの中で、SHOGENにとって1番大切に感じていることは何ですか?
『これからの時代は、血がつながっていない家族がみんなで生きていく必要がある』というメッセージです。
日本では、核家族だったり、隣の家の人の顔もわからない、母親が倒れたら家庭が崩壊する、という状況の家庭も多いと思うんです。
こういう「社会の中でどうやって生きていったらいいの?」という疑問へのヒントは、アフリカにたくさんありました。
「みんなで生きていく」というのはアフリカの人たちは当たり前に日常からやっていることなんです。
でもこの考え方は日本の人でも「懐かしいな」という感覚を持つ人は多いと思います。
「昔、ひいおじいちゃんやひいおばあちゃんが言っていたな〜」なんて感じる人も多いでしょう。
ーーSHOGENが住んでいた村の村長のおじいさんが夢の中で日本人とつながっていたことから、愛にあふれた時代の日本について教えてもらったとのことですね。
SHOGENが村で聞いた日本とは?
僕が村長から言われたことは「日本人が日本人としての魂を思い出す必要がある」ということです。
日本の歴史の中で1万5000年の間、日本には生きとし生ける全ての者を愛し、すべてのものから愛され続けてきた時代があります。
その時代に亡くなった人には、差し傷とか切り傷がなかったんだよと言うんです。
おそらく縄文時代のことを言っているのだと思います。
村長から「今の日本人の血に一番深く刻み込まれている記憶は何だと思う?」と聞かれたんです。
「それは何?」と聞いたら、「それは『愛され続けた記憶』だ」というんですよ。
日本のご先祖様は、1万5000年もの間、争いもなく愛と平和であふれていた時代を生きてるんですよね。
だからその時の記憶をもう一度思い出してほしいと。
つまり、自分が普段からやっている所作や行動を愛し続けることで、愛され続けた記憶がよみがえってくるということなのです。
今までは、物質的な豊かさを求めてきたから、自然破壊とか環境汚染から来る肉体と精神の分離から、うつになったり自殺をしてしまう人が増えてきてしまったというんです。
これからの時代は、もうそれではいけないとみんなが分かっているので、これからは心の時代に入らないといけないと村長は言うんです。
心の時代に入るにあたり「愛され続けた日本人が、もう一度自分を愛して、世界中のみんなに愛されるということはどういうことなのか、
愛するということはどういうことなのかを伝えてほしい」ということを村長は言っていました。
ーー経済的には日本よりも貧しいと言われるアフリカですが、アフリカを訪れる多くの日本人が「アフリカの人はとても幸せそう」と言います。
SHOGENがアフリカで暮らした経験から、この理由はなぜだと思いますか?
僕自身、タンザニアに住んでいると、幸せを感じられるようになったんです。
それは村での生活スタイルに理由があったのだと感じます。
つまり本来、人間がやっていたであろう「 日の出とともに起きて、日没とともに寝る」ということを実際にやっていたらすこぶる健康になったということです。
こういった暮らしをしていたら、幸せを感じる余裕が生まれてきました。
日本では、深夜でも電気はついているし、どんなに遅い時間でも仕事ができてしまいますよね。
そんな生活に慣れていた僕が「あきらめる時間が来ることの幸せ」を村長から教えてもらったんです。
この「あきらめる時間」が来ると割り切れるんです。みんなで「はい、今からもう休みね」という時間に入れることが、すごく幸せだったなと思います。
🔻SHOGENのInterview動画はこちら🔻
日が出ているうちに家族の顔が見たい

ーー日本の忙しい人たちが生活レベルをタンザニアの村のように大きく変えることはできないかもしれません。
日本にいる私たちでも幸せになるために生活に取り入れられることはありますか?
ことですね。
日本の小学校に行くと、給食の時間は20分ぐらいです。中学校とかになると10分というところも聞きます。
でも食事は、生きていくために大切な時間です。じっくりと食材を味わえる時間が短すぎるので、これが今の日本の一番の問題だと思います。
食事をゆっくりじっくり味わえなくなったら、生活そのものがおろそかになります。
現代の「効率よく、無駄を省いて、時短で」という考え方にもつながってくるかもしれないですね。
食事を味わえていないということは、生活も味わっていないということ。
給食時間が短いということは、そういう「味わえない」日本人を生み出しているということなんじゃないかと思います。
ーー忙しい日本の私たちは「食事をゆっくりとる」ということも、しっかり意識しないと難しいかもしれませんね。
僕が住んでいたタンザニアの村では、仕事はみんな、お昼過ぎの3時半に終えるんです。
僕の絵の先生も、キリンの足の模様をあと5つだけ描いたら終わるのに、書き終わる前に「3時半になるから帰る」と言うんですよね。
「あとちょっとで終わるのに、なんで終わらせないんですか?」と聞いたら、「早く家に戻らないと、家族の顔が見られないから」と言うんです。
村には電気がないので、夜になると真っ暗になり、家族の顔は朝まで見ることができないんですね。
「自然の光がまだある、明るいうちに家族の顔が見たいから早く帰るんだよ」と言われた時に、僕は『自分の中で本当に大切なことは何だろう』と考えるようになったんです。
だから、本当に大切なものが見えてきたら、生活の仕方も変わると思うんです。
仕事のやり方をすぐに変えることは難しいかもしれないけれど、プライベートとか休日の過ごし方、そういうところから、まずは日々をじっくり味わうことを意識してみたらどうでしょう。
🔻SHOGENのInterview動画はこちら🔻
キラキラ輝く楽しそうな大人を見せよう
ーーそんなアフリカでの生活から一変して、SHOGENが日本の生活に戻るのは大変でしたか?
僕があまりにもわからない人間だったんで、村長にもよく言われていたことがあります。
「お前が明日もし死ぬとしたら、最初に考えるのは、自分の人生は自分らしかっただろうかということだろう」
「だから、もういい加減に自分のために生きればいいんだよ」って。
自分の心が幸せで満たされて初めて、喜びや幸せのおすそわけが、周りにいる人に届くんだと言われたんです。
タンザニアでそういうことを考えながら暮らした後、久しぶりに日本の生活に戻ってまず感じたことがあります。
それは、自己犠牲の上に幸せが成り立っていると考える人が今の日本には多いということです。
自分が犠牲になれば周りの人が喜んでくれると思っていたり、そう思っている自覚がなくても、そういう行動をとっている人が多いと感じます。
ーー私も母親になって、子どもに「ママは幸せを感じながら生きているよ」という姿を見せることの大切さに気づきました。
自分を大事にして楽しんでいる大人の姿をそのまま子どもに見せることに抵抗のある人もいるかもしれませんね。
タンザニアで印象的だったのは、村で壁に絵を描こうという時に、我が子を押しのけて大人たちが壁の前を占領した時です。
その大人の姿を見て、子どもたちは「早く大人になりたい!」と言っていたんです。
これがまさに今の日本に足りないところだと思います。

キラキラ輝く大人の背中を見ている子どもたちが少なすぎるのです。
子どものための英会話教室やレッスンだと言って「子どものため」が多すぎると感じます。
アフリカに住んでると、すごく楽しそうな大人をたくさん見るんです。
日本には思いっきり遊んでいる大人が少なすぎるんです。
大人がもっとおもいきり自分をオープンにして遊ぶという姿を子どもたちに見せることが、今の日本に大切なんじゃないかなと思います。
ーーブンジュ村の人が今の日本を訪れたら、なんと言うでしょう?
「しんどい」と言うでしょう。
ずっとみんなが仕事ばかりをしているところとか、 慌ただしく生活をしているところとかを見たら「日本の人たち…今日もきついだろうな」って言うでしょうね。
ーーもしもまたタンザニアの村を訪れるとしたら、日本からどんなプレゼントを持っていきますか?
品種のいいスイカの種でしょうか。
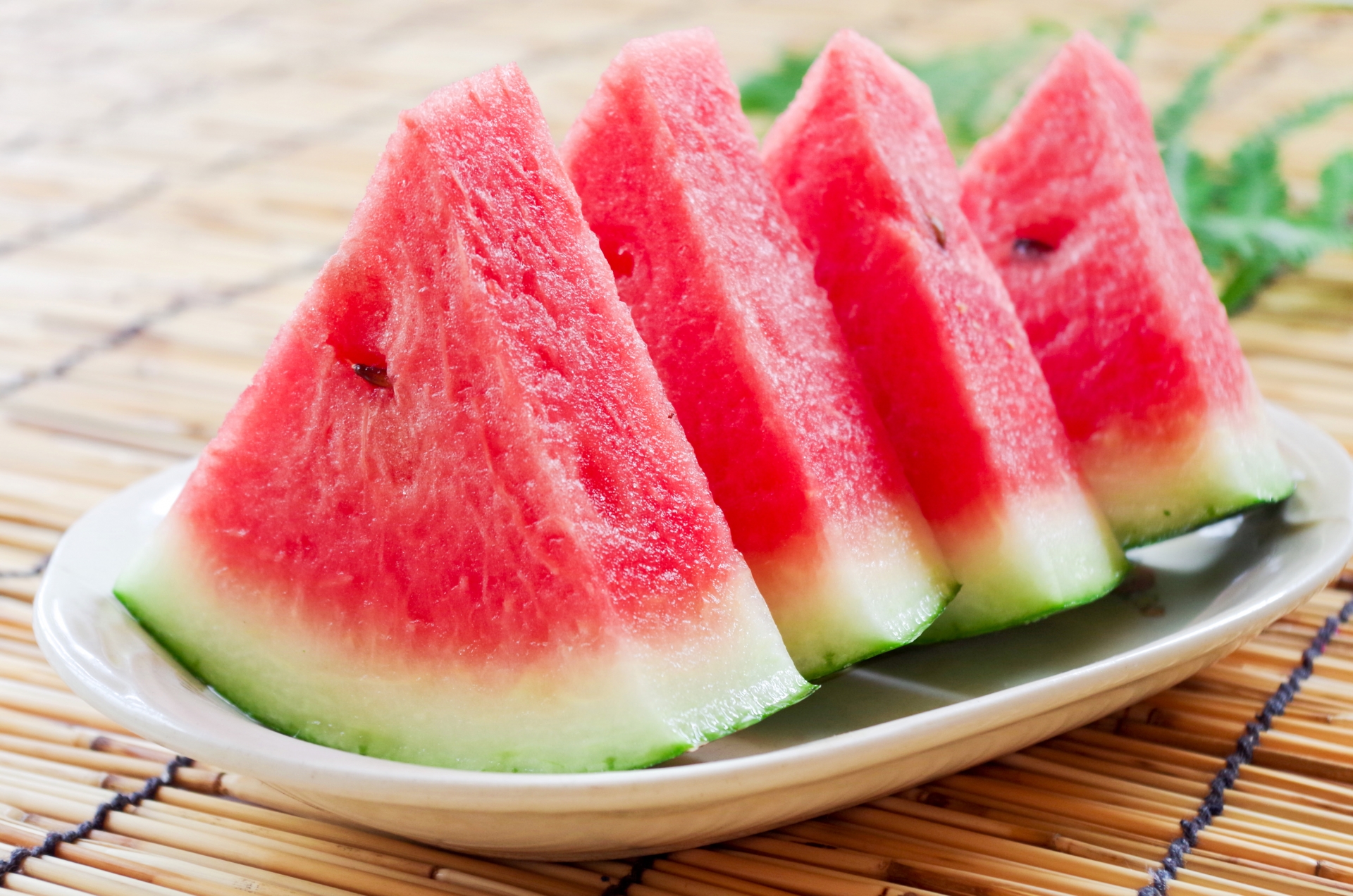
スイカはアフリカが原産だと聞きましたが、タンザニアのスイカは、僕から見ると品質が最高とは言えないものでした。
スイカを切ると、食べられない白い皮の部分が分厚かったりするんです。だから、日本からプレゼントするなら、スイカの種かな。
でも、それはおせっかいかもしれないですね。
基本的にブンジュ村の人たちは、心が満たされているので「何もいらん」っていつも言うんですよね。
村の畑では、ナス、オクラやトマトなど夏野菜がとれるし、ハリネズミや鳥を捕まえて食べるから、全てがそこにあるんです。
だから「欲しいものは?」って聞かれても、村の人たちは「うーん。何もいらん」と言うでしょうね。
時間を気にせずご飯を食べる時間の幸せ
ーーそんなSHOGENが、今一番幸せを感じる瞬間は?
血のつながっていないみんなとご飯を食べている時です。
時間を気にせず、ご飯を食べながら話をしている時に、 すごく幸せだなと感じます。
あとは、自分も自然の一部としてこの大地から生まれてきたんだと思い出しながらアーシングをしている時にすごく幸せを感じますね。
※アーシング=素肌や裸足になって、身体と大地が直接つながる事
ーーアーシングは、どうやってとりいれていますか?
裸足になって土を踏んだり、大地にゴロンと寝転がったりみたいなことをしています。
タンザニアの村の子どもたちにもよくアーシングに誘われていました。
例えば、雨が降り出したら空を見上げて口を開けてね、雨を食べたりするんです。
そうすると、大人たちも外に出てきて、みんなで口を開けて雨を食べるんですよ。
こういう、ほっこりする時間がアフリカでは多かったなと思い出します。
ーーこれから力をいれていきたい活動は何ですか?
これからやりたい活動としては、学校のアート活動があります。
ごみ収集車や町営バス、学校の壁などにみんなで絵を描いて、新しい自分を見つけていくというプロジェクトです。
あとは障害者の子たちとのアート活動ですね。
すでに活動している方とのコラボも積極的にしていきたいです。
先日も静岡の「心のままアート」というアートが好きな子どもや障害を持ってる子どもたちと一緒に絵を描きました。
みんなで集合写真撮ろうという時に、ある子がスキップをしながらカメラの前を横切ったんです。
そんなところをみんなで見ていた時に「あー、別にそうであっても良いよね。心のままで良いよね」と思ったんです。
集合写真を撮ると言われて、 みんなで横に並ばなくても良いんだと。
この横切る子の姿を見た時に、みんながそれぞれに、その瞬間に楽しいことしていたら良いんじゃないと、思えたんですよね。
みんなが寄り添って集える場、そういう場所作りができたらと思っています。
ーーSHOGENには私たちのウェブマガジン、ハミングにも執筆者、監修者として関わってもらっています。
ハミングの読者に伝えたいメッセージをぜひ教えてください。
ハミングは、たくさんのお母さん方も見てくださっているマガジンだと思います。
そういったお母さんたちが心から寄り添ってなんでも話せる、 ハミングはそういう場所になれると思います。
まさに、血がつながっていないみんなが心からつながり合い、出会える場所ですね。
悲しいニュースからあなたの心を守るためのマインドフルネス

あなたは普段、テレビやネットのニュースをどれくらいチェックしていますか?
最近では楽しい話題よりも、戦争や人道的な災難などの悲しい出来事が目立つように感じませんか?
こうした悲しいニュースを続けて見ることが、あなたにどのような影響を与えているでしょうか。
世界の動向を追いながらも、心の負担を軽減する方法について、アメリカでも議論が交わされています。
今回は、アメリカでかかれた記事を参考にして、どのように対処できるかをご紹介します。
ひどいニュースに心が張り裂ける日々
10月にイスラエルとハマスの戦争のニュースが流れ始めると、私はスマートフォンにくぎづけになりました。
次から次へと報道されるニュース記事を読みながら私は泣いていました。
誘拐されたり殺されたりした人たちの記事を読むたび、被害者が誰かの子どもであることを思い、その子の母親が今どうしているかを想像して泣いていたのです。
残念なことに、この重苦しさは、たまにだけ押し寄せる感情ではないのです。
学校での銃乱射事件であれ、自然災害であれ、戦争であれ、私たち人間の体験には、心が痛む瞬間があまりにも多いのです。
そして、こういうニュースによって、私たちは恐怖や不安、そして悲しみにおしつぶされそうになります。
ニュースを読むのをやめればいいのにと思いながら、世界で起きていることをしっかりと知っておきたい自分と葛藤をしています。
そんな私が一番疑問に感じていることは、マインドフルネスの観点です。
悲劇的な出来事が起こるとすぐにSNSなどで多くの情報を収集できる時代です。
そういった出来事にしっかりと目を向けることと、自分の心を守ることのバランスをどう取ればよいのでしょう。
そこで、臨床心理学者であり、セルフ・コンパッションの専門家でもあるテクラ・ブランダー・ロス(以後、テクラ博士)に聞いてみました。
悲しみを理解する
ニュースによって感じる恐怖、悲しみ、不安などの感情と向き合い、それを乗り越えるためには、この感情の性質を理解することが重要だとテクラ博士は指摘します。
ニュース記事を読んで感じる悲しみは、博士によれば「私たちの世界で起きている痛みや苦しみ全てに対する悲しみです。
こういう悲しみにどう対処するかの訓練を学校で受けた人はほとんどいないでしょう」。
しかし、自分の家族や友人がそのニュースの悲劇の影響を受けていないなら、私たちは誰のことを思って悲しんでいるのでしょう?
テクラ博士は苦しみを比較しないようにと念を押します。
「人と比較するのではなく、出来事をしっかりと認識することに努めましょう」と博士は言います。
誘拐された子どもの記事を読んで、その母親のことを思って悲しまずにいられないはずはありません。
自分の子どもが今どこにいるのかわからない苦悩を、想像せずにはいられません。
私が直接に体験していなくても、ニュースで読んだ事件の当事者について感情を強く揺さぶられることは普通でしょう。
どれだけニュースを摂取しているかに気づく
自分がニュースの第三者として行動することで「洞察力と気づき」を意識することができます。
テクラ博士によれば、洞察力と気づきは、幸福のために大切な2つのポイントであり、自分の人生にもっと積極的に参加するために大切なものです。
テクラ博士は、ニュースを読むのを止めるのではなく、私たちのニュースの消費のしかたにもっと気を配るようにと提案します。
あなたがニュースを見る前に、こういった質問を自分に投げかけてみましょう。
- あなたは今、新しい一日を始めるために目を開けたばかりですか?
- あなたは今、心身を休めるために目を閉じたばかりですか?
- あなたは今、仕事中であり、ストレスを感じていますか?
- あなたは今、身体が緊張したり、不快に感じたりしていませんか?
もしこれらの質問のどれかに「はい」と答えたなら、それは今、辛いニュースを見るのに最適なタイミングではないかもしれません。

立ち止まってみる
いったん立ち止まる、つまり今がニュースを見るタイミングではないと判断するという考えは、ただの自己満足に過ぎないと思う人もいるかもしれません。
これに対してテクラ博士は「世間では思いやりの気持ちを持つことが、ただの自己満足だという誤解があります。
しかし、自分と他者への思いやりとは、今この瞬間に感じていることにしっかりと気づいて、優しさや愛を表現することでもあります」。
私たちのように立ち止まる選択肢すらもない人が、この世界にはたくさんいることにも注意をしてみましょう。
何世紀にもわたる抑圧、不正、暴力の中を生きている人々にとって、ニュースは直接彼らの身に迫る脅威を示しています。
テクラ博士はこうアドバイスします。
「今度ニュースを見て、悲しんだり、怒りがこみあげてきた時には、いったん立ち止まり、その時の自分の感情を観察してください。
その痛みがどのように自分の身体に感じられるかに意識を向け、その痛みを感じるのは自分だけではないこと。
そして、その痛み自体もすぐに変化することを、自分に言い聞かせましょう」。
博士はまた、感情をコントロールしようとすることは、天気をコントロールしようとすることと同じだと指摘します。
「自分の経験をコントロールしたり否定したりするより、思いやりの気持ちを持って起きている事実をそのまま受け止めてみましょう」。
写真やビデオのない記事にとどめる
臨床心理学者でハーバード医学部の教授でもあるスパーリング氏は、音声や映像が非常にダイレクトに私たちの心に訴えるものであると強調します。
「誰かが苦しんでいるのを見たり聞いたりすることは、あなたの精神にダメージを与えます」。
写真や動画のないニュース記事のほうが、読者へのインパクトという観点では、より親しみやすいでしょう。
また、教授はニュースを見る回数を意識して制限することを勧めています。
ニュースを見る時間をあらかじめ決めておくことで、ネガティブな内容のニュースを見続けることを避けられるとスパーリング氏は言います。
マインドフルネスのためのシンプルな方法
見るのがつらいニュースを目にした時、なぜそのニュースを見ているのかを意識することも忘れないでください。
記事や動画をクリックする前に一度立ち止まって、テクラ博士がこれから提案する、マインドフルに前進するための方法を考えてみましょう。
まず、ニュースを見る前に、あなたがこれ以上の苦しみを受け入れることができる状態か自問してください。
もし苦しみを受け入れる余裕がないなら、どうすればその苦しみを認めることができるか、どうすれば自分にもっと優しくなれるか、どうすれば今この瞬間に仲間とつながることができるかを考えてみましょう。
つらいニュースを読みながら、両手を心臓に持っていき、今までトラウマになった体験を認めましょう。
地上とつながる(グラウンディング)ための呼吸をし、そのニュースを見て感じる悲しみをより深く認識しましょう。
ここで可能なら、身体を休めてください。他人の苦しみに寄り添う前に、自分自身をいたわってあげることを忘れないでください。
「私だって完璧ではないです。あなたはニュースを読むべきでない、なんて私が言う権利はありません。
大切なことは、いつ、どのようにして、あなたがニュースを消費しているかということです」とテクラ博士。
日々、あなたがどうやってニュースを見ているかにもっと意識を向けることで、心がおしつぶされるようなニュースへの反応を自分でコントロールできるでしょう。
例えば、朝起きてベッドに寝転がりながらスマートフォンに届いたニュースを見る前に、深呼吸をしてみましょう。
そしてあなたがニュースを読む準備ができているかどうかを自問する、そんな簡単なことからできるのです。
そして、その答えが「いいえ」である人がとても多いのです。
残念ながら、恐ろしいニュースはすぐにはこの世界から無くならないでしょう。
しかし、私たちがニュースをどうやって受け入れるかについてもっと意識することで、私たち自身や仲間をサポートすることができるでしょう。
※関連リンク:この記事はThe Good Tradeの英語版をはじめ、別の英語の記事を参照しています。各出典に対するリンクは以下になります。
脱・依存体質。自分の価値や幸せは自分が決めるもの

大好きな彼と一緒に暮らしはじめて幸せの絶頂。それなのに、なんだか胸騒ぎが止まらない。
毎週金曜日、彼は飲みに出かけたまま朝帰りをする日が増えた。いけないとわかりつつ、こっそり彼の携帯に手を伸ばした。
そこにはとある女性とのやりとりが残っていた。
「ずっと大好きだよ」
このメールを見た瞬間から彼のことが信じられなくなった。いや、だいぶ前から「もしかしたら……」と疑っていたのだ。
不安が確信に変わって以降、連絡がつかない時は不安になって鬼のように彼に電話をした。不安を消すために、友達との約束を断って、できる限り彼と一緒に過ごすようになった。
そんな日々から10年以上たった今。当時を振り返って思うのは、自分自身が彼に依存していたということだ。
誰かへの依存は、相手の心を引き離し、自分自身を苦しめるのだ。
誰かに依存していると、常に不安がつきまとう
「依存」とは、「他に頼って存在、または生活すること」を意味します。
依存体質になってしまうと、他者から評価されることで自分の価値を見出し、安心感を得るようになります。
さらに、他者の期待に応えようとするあまり、過度に承認を求めたり、尽くした相手から見返りがないと不安を感じてしまうのです。
例えば、一緒に暮らす彼のために美味しいご飯を作って待っていたのに、彼から「今日は飲みに行くから帰りが遅くなる」と連絡が入った場合。
恋愛に依存していると「あなたのために頑張ってご飯を作ったのに、食べてくれないなんてひどい。私は大切にされていないんだ……」と気持ちが落ち込みます。
さらに、彼の帰りが遅くなるほど、誰とどこにいるのかが気になり不安で何も手につかない。
夢中になれるほど好きな人がいるのは素敵なことです。
しかし、他者に過度に依存することで、自分の心の安定が他人次第となり、常に不安がつきまとうようになります。
自信のなさや未来への不安が依存の引き金に

人はどうして誰かに依存してしまうのでしょうか?
「私には彼しかいない」
「彼と別れてしまったら、この先結婚できないかもしれない」
「離婚したら生活できない」
など……、多くの場合は、自信のなさや未来への不安から生じるのではないでしょうか。
脱・依存体質。自分の幸せは自分で決めよう
では、自分に自信を持ち、未来への不安を減らすためにはどうしたら良いのでしょうか。筆者の体験談を踏まえてご紹介します。
自分磨きをする
「変えられるのは自分だけ」とよく言いますよね。他人に変化を求めるのは想像以上に難しいこと。だからこそ、向き合うべき相手は自分自身です。
例えば、毎日フェイスパックをしてスキンケアに力を入れてみるとか、毎朝10分でも良いから運動して心と体を整えるとか、英語の勉強をしてスキルを身につけるとか。
継続して変化が現れることで、少しずつ自分に自信が持てるようになるかもしれません。
夢中になれるものを見つける
誰かのためにではなく、自分のために夢中になれることを見つけましょう。
大切なことは
彼のために料理をがんばりたい
子どものために働き方を変えたい
など、誰かのためにではなく、「自分のために」夢中になれることを見つけることです。
楽しさややりがいを感じる趣味を見つけることで、誰かに依存しなくても充実感が得られるでしょう。
自分で生きていけるだけの経済力を身につける
「夫婦関係がうまく行かずに離婚を考えているけれど、仕事をしていないから経済的にパートナーを頼るしかない」
そのようなお悩みを抱えている方もいるかと思います。
もしあなたが収入がないことに少しでも不安を感じているのなら、自分で稼ぐ力を身に着けることが大切です。
もちろん、なんらかの理由があって外に働きに出るのが難しい方もいるでしょう。
しかし、今の時代、スマートフォンやパソコンさえあればできることがたくさんあります。
すぐに収入に繋がることが難しくても、ブログを書いてみたり、SNSで好きなことを発信してみたり、ハンドメイドが得意であれば出品してみたり。
できる範囲で未来の自分への投資をすることで、少しずつ自信がつき、未来への不安が和らぐでしょう。
遠い未来ではなく、今に目を向ける
誰しも未来のことはわかりません。だからこそ、遠い未来のことを心配しすぎるよりも、今の自分にとっての幸せを考えてみましょう。
「笑う門には福来たる」というように、今の自分がご機嫌でいることで、素敵なご縁やラッキーが舞い込んできて、未来が良い方向に変わっていく可能性があります。
自分の中に幸せの軸を持つ
誰かに合わせすぎたり、相手の都合の良いように動くと、自分自身が消耗して辛くなります。
自分以外の誰かに依存するのではなく、自分の中に幸せの軸を持つ。そして遠い未来よりも今を大切に生きる。
人生で1番長く共に過ごすのは、自分自身です。まずは自分を大切に。
自分が幸せになる方法を追求するのはわがままなことではありません。自分を大切にできるからこそ、自分の大切な人を思いやることができるのではないでしょうか。
「寄付」と「寄附」の違いは何?「寄贈」との違いや使われる場面を解説

「社会をより良くしたい」「暮らしやすい街をつくりたい」「子どもたちに質の高い教育を受けさせたい」
これらを実現するためにはさまざまな方法がありますが、そのうちのひとつに寄付があります。
しかし、ニュースや新聞、行政機関からの文書などを見ると、「寄付」と「寄附」と異なる表記が用いられていることがあります。
これらの違いは何なのか、また混同しやすい言葉との違いもご紹介しましょう。
「寄付」と「寄附」の違いは?

公的機関や社会的意義のある事業などに対し、金銭やモノを提供する行為を寄付とよびます。
社会貢献の一環として寄付を行う個人や企業も多いです。
特に自然災害の多い日本では地震や台風などが起こるたびに、多くの人・企業から寄付が寄せられることが少なくありません。
それほど寄付という言葉は広く社会に浸透していますが、表記の仕方として「寄付」以外にも「寄附」というものもあり、どちらが正しいのか戸惑ってしまうこともあります。
結論からいえば「寄付」と「寄附」は同じ意味を指す言葉であり、どちらの漢字を使用したとしても間違いではありません。
ただし、両者は使用される場面が異なり、一般的にはシーンに応じて使い分けられています。
「寄付」を使うべき場面と「寄附」を使うべき場面とは

では、「寄付」と「寄附」はどのような場面に応じて使い分けられているのでしょうか。
一言でいえば、公的な書面や法令に関する文言に用いるかどうか、という点です。
たとえば、国や自治体が発行する文書、確定申告などで提出する税務関係の書類などには「寄附」が用いられます。
たとえば、身近な事例として「ふるさと納税」を活用し自治体に寄付を行った場合です。
「ふるさと納税」で、所得税や住民税などの控除を受けることができますが、その金額は確定申告書の「寄附金控除」という欄に記載します。
また、政治団体や政党への献金のルールを定めた政治資金規正法においても「寄附」という表記がなされています。
大学や研究機関などが国・自治体などから受領したお金についても「寄附金」としてその内訳や金額が報告されています。
このように、公的な文書や法令に関する書類として記載する際には「寄附」を用いるのが一般的です。
一方、たとえばテレビのニュース番組や新聞、雑誌などのように一般的な場では「寄付」が用いられます。
そのため、私たちが日常生活のなかで目にするのは「寄附」よりも「寄付」のほうが多いのです。
「寄贈」との違いは何?

寄付と似た言葉に「寄贈」があります。
一度は目にしたことがあるものの、日常生活ではあまり使うことがないため明確な違いがよく分からないという方も多いのではないでしょうか。
両者が決定的に異なるのは、贈る”もの”が違うという点です。
冒頭でもご紹介した通り、寄付は社会貢献の一環として公共性の高い団体や事業に対し、金銭やモノを贈る行為を指します。
これに対し、寄贈はモノを贈る行為を指し、金銭は含まれません。
たとえば、子どもたちの教育に役立ててもらうために学校へ金銭を提供した場合、寄贈ではなく寄付と表現されます。
一方、金銭ではなく学習教材や書籍、タブレット端末などの現物・物品として提供した場合には、寄贈または寄付と表現されます。
| 寄付 | 寄贈 | |
| 金銭を贈る | 〇 | × |
| 物品を贈る | 〇 | 〇 |
「寄付金」「義援金」「支援金」の違い

阪神淡路大震災や東日本大震災など、大きな災害が起こった際には復興を支援するために多くの寄付が寄せられることが少なくありません。
このような善意のお金は「寄付金」とよばれることもあれば「義援金」や「支援金」と表現されることもありますが、それぞれどういった違いがあるのでしょうか。
義援金とは
義援金とは、被災地および被災者に対して直接渡される金銭のことを指します。
個人や企業が直接被災者に手渡すとなると手間がかかり現実的ではありません。
そのため、日本赤十字社や政府など公的機関がお金を集めた後、被災状況や被災者の数などに応じて分配する仕組みとなっています。
義援金は集められたお金がすべて被災地に届けられるという意味では大変意義のある支援方法といえます。
しかし、個別に公平に分配しなければならないことから手元に届くまでには時間を要するという問題もあります。
支援金とは
支援金とは、被災地での救援活動や支援活動を行うNPOやNGOといった団体に渡す金銭のことを指します。
復興を支援するという大きな目的は義援金と共通していますが、支援金はあくまでも各種団体の活動を支援するためのお金です。
そのため、必ずしも義援金のように直接的に被災地支援に使われるとは限りません。
また、支援金を集めている団体のなかには、どういった活動にいくらを使ったのか正確に情報を公開していないところも存在します。
寄付金とは
寄付金とは、上記で紹介した義援金や支援金を含む広い意味を指す言葉です。
冒頭でもご紹介した通り、社会貢献に役立てるために贈るお金であれば寄付金とよばれ、義援金や支援金などのように災害からの復興に限定されるものではありません。
そのため、たとえば政治団体や政党へ提供するお金や、ふるさと納税も寄付金にあたります。
まとめ
今回ご紹介してきたように、「寄付」と「寄附」は基本的に同じ意味を指す言葉です。
ただし、一般的には「寄付」と表記されることが多い一方で、法律や行政など公的な文書および場面では「寄附」と表記されることが多く、シーンに応じて使い分けられています。
私たちが日常生活で使用する分には、基本的にどちらを使っても間違いではありません。
また、寄付と似た意味をもつ言葉も多く混同することも多いため、今回ご紹介した内容を十分に理解し正しく使い分けるよう心がけましょう。
ドネーションとは?寄付との違いや考え方を解説

さまざまな社会課題を解決するための「ドネーション」という活動を聞いたことはあるでしょうか。
本記事では、ドネーションとはどういった活動なのか、寄付や寄贈との違い、国によって異なるドネーションの考え方や現状などもあわせて詳しくご紹介します。
ドネーションとは?

ドネーション(donation)とは、金銭やモノ、サービスなどを無償で提供する行為全般を指す言葉です。
何らかの見返りを求めたり、自分自身の利害に関係する人や団体にお金やモノ、サービスを提供するのではなく、社会福祉や社会貢献など公共の目的であることが前提となります。
また、日本国内においては個人や企業に対する直接的な寄付ではなく、慈善団体や非営利団体などへの金銭および物的支援などを意味する言葉として用いられることもあります。
ドネーションと寄付の違いは?

「金銭やモノ、サービスなどを無償で提供する行為」と聞くと、寄付をイメージする方も多いのではないでしょうか。
実際に辞書でドネーション(donation)という単語を調べてみると、「寄付」や「寄贈」、「助成」といった言葉に直訳されることがわかります。
そのため、基本的にはドネーション=寄付という意味に捉えて問題はありません。
国によっても異なるドネーションの考え方

ドネーション、すなわち寄付に対する考え方は国籍や宗教、価値観、時代などによっても大きく変わります。
昨今の日本では大規模な災害が起こるたびに多くの寄付金が集まり復興に役立てられています。
それ以外の平時においても継続的に寄付をしているという方は、決して多くないのではないでしょうか。
日本ファンドレイジング協会が発行している「寄付白書」のデータによると、
2016年時点での寄付総額は日本が7,756億円であるのに対し、米国は実に30兆6,664億円、イギリスでは1兆5,035億円にものぼります。
極端に日本人の寄付額が少ない背景には、日本では戦後の高度経済成長期から多額の税収が確保され、社会インフラや社会保障制度が整備されてきたという歴史があります。
すなわち、社会課題は基本的に税金で賄われるのが当然という意識があると考えられるのです。
さらに、物理的な面から見てみると、日本はバブル経済の崩壊から30年以上にわたって景気が低迷しています。寄付をしたくても経済的な余裕がない、自分自身の生活で精一杯という人が多いことも大きな要因として考えられるでしょう。
一方、海外に目を向けてみるとどうでしょうか。
たとえばキリスト教においては、毎月の収入に対して1割程度を寄付するといった聖書の教えがあります。
当然、個人の経済状況によっては1割の寄付が難しいこともありますが、自分のできる範囲で継続的に寄付を続けている敬虔なクリスチャンも少なくないのです。
また、米国ではこれまで順調に経済成長を続けており、現時点においてもGDPは世界一位を死守しているばかりか、30年前と比較して約4倍の経済規模にまで成長しています。
このように、日本と世界の国々でドネーションの考え方が異なるのは、文化的、宗教的、歴史的な背景などさまざまな要因が考えられます。
しかし、日本においても近年利用者が増えている「ふるさと納税」などの影響もあり、徐々に寄付総額は上昇傾向にあります。
詐欺には十分に注意しよう

ドネーションや寄付を受け入れている団体は数多く、たとえばNPO法人や非営利団体はもちろんのこと、一般企業などにも広がっています。
しかし、なかには活動に共感してくれた人の善意や良心に付け込もうとする詐欺行為も横行しています。
ドネーションをしたつもりが反社会的組織の資金になっていたり、思わぬトラブルに巻き込まれたりするケースもあります。
災害義援金などのように被災者や被災地に直接届けられるドネーションの活動もあれば、災害支援金などのように活動団体に寄付することで間接的に困っている人を助ける方法もあります。
いずれにしても、ドネーションとして金銭やモノを贈る際には、どのような支援団体がその活動を行っているのかを調べておくことが大切です。
支援団体の名称や所在地、連絡先はもちろんのこと、普段の活動内容やバックグラウンドなどもWebサイトやSNSなどでチェックしましょう。
内容が曖昧で理解できない場合には支援を見送るといった判断も必要です。
まとめ
ドネーションとは金銭やモノ、サービスなどを無償で提供する行為であり、寄付や寄贈などと同じ意味を指します。
また、社会課題に取り組む慈善団体や非営利団体などに対し、金銭および物的な支援を行う意味でドネーションという言葉が使い分けられることもあります。
日本は欧米に比べて寄付の文化が醸成されているとはいえず、社会課題は税金によって解決されるものという意識が根強いです。
しかし、昨今頻発している大規模災害や感染症など国難ともいえる状況が続くなかで、徐々に国民の意識が変わってきているのも事実です。
それを裏付けるように寄付総額も増加傾向にあります。
善意につけ込んで金銭を搾取しようとする個人や団体も存在することから、ドネーションや寄付を行うときには支援団体の情報をしっかりと調べ、トラブルや詐欺被害に巻き込まれないようにしましょう。
当メディアの姉妹団体のNPOハミングバードも社会貢献につながる様々な活動を行っています。
もし宜しければご覧になってください。
ヘアドネーションは迷惑で意味ない?おすすめの長さや送り先を紹介

事故や病気、治療の副作用などにより、毛髪が抜けて精神的に落ち込む人も少なくありません。特に子どもや若い女性は大きなショックを受けやすく、それが原因で精神的に塞ぎ込んでしまうこともあります。
このような課題を解決するために、近年「ヘアドネーション」とよばれる活動が注目されています。ポジティブな意見がある一方で、「迷惑」、「意味がない」といわれることもありますが、果たしてそれは本当なのでしょうか。
ヘアドネーションとは?

ヘアドネーションとは、カットした自分自身の毛髪を寄付する活動のことです。
ヘアドネーションによって寄せられた毛髪は、病気や事故などの後遺症、あるいは治療の副作用などによって毛髪が抜けて悩んでいる方のために、医療用ウィッグを作る材料として用いられます。
海外で始まったヘアドネーションの活動は近年日本でも広がりを見せはじめており、ヘアドネーションに賛同する美容院や団体が増加しています。
ヘアドネーションは迷惑?意味ない?
日本でも活動の輪が広がりつつあるヘアドネーションですが、インターネットやSNSなどで調べてみると「迷惑」や「意味がない」といったネガティブな声も少なくありません。果たしてそれは本当なのでしょうか。
このような声が上がる背景や理由としては、ヘアドネーションが偏見や差別を助長する可能性があることが指摘されます。
すなわち、「髪の毛はあることが当たり前であり、事故や病気によって毛髪が失われた人は医療用ウィッグを身につけるべきだ」という考えを押し付けてしまうため、ヘアドネーションは迷惑な行為にあたるというものです。
自分の毛髪を寄付する人にとっては、「困っている人のために良いことをした」と感じていても、その心理の根底には「髪の毛を失った人がかわいそう」という差別や偏見の意識があるケースが少なくありません。
しかし、差別や偏見がなくなり周囲の見方が変わったとしても、当事者にしてみれば髪の毛を失ったことに絶望し精神的に塞ぎ込んでしまうことはあるでしょう。それをひとつの個性として受け入れるにしても、ある日突然気持ちを切り替えられるものではなく一定の時間を要します。
ヘアドネーションに対する考え方は人によっても異なり、ネガティブな意見も間違いとはいえません。しかし、精神的な支えや自信を取り戻すためにも、医療用ウィッグを必要としている人は少なくないのが現状です。
ヘアドネーションの方法

ヘアドネーションの活動に賛同し、自分の毛髪を寄付したいと考えた場合、どのような手順で行えば良いのでしょうか。
基本的な手順は以下の通りです。
- ヘアドネーションに賛同している美容室を探す
- カットした毛髪を束ねる
- 毛髪を梱包する
- ヘアドネーション活動を行っている団体宛に送付する
カットした毛髪を発送する際には宅配業者の指定はありませんが、基本的に送料は自己負担となります。
また、髪の毛がしっかりと束ねられていないと輸送の際にバラバラになってしまい、医療用ウィッグの材料として使用できなくなるため、ゴムでしっかりと束ねておきましょう。
ヘアドネーションに必要な長さは“31cm以上”

ヘアドネーションにおいてもうひとつ重要なポイントが、髪の毛のカットの仕方です。
美容室や理容室などで髪の毛をカットする場合、一般的には数cmまたは数mm単位で少しずつカットしていくのが一般的です。しかし、ヘアドネーションで寄付できる毛髪は「31cm」以上の長さが条件として定められています。
そのため、美容室でカットをお願いする際には、この要件に対応できるかどうかを事前に確認しておく必要があります。
もし、近所で対応可能な美容室が見つけられない場合には、以下のサイトで検索してみるのもおすすめです。
サロン検索システム:https://www.jhdac.org/search/index.php
寄付する毛髪は、極端なダメージが加わっていなければカラーやブリーチ済であっても問題ありません。ただし、毛髪を梱包する前にはしっかりと乾かし、水分を取り除いておく必要があります。
水分を含み濡れたままの髪の毛を梱包すると、内部でカビや雑菌が繁殖し医療用ウィッグの材料として使用できなくなるため注意しましょう。
ヘアドネーションでおすすめの送り先
ヘアドネーションはさまざまな団体が活動を行っています。トラブルを防止しスムーズな寄付を行うためにも、実績が豊富で信頼性の高い団体を選ぶことが大切です。
そこで、初めての方にもおすすめの3団体をご紹介しましょう。
JHD&C
特定非営利活動法人Japan Hair Donation & Charityは通称「JHD&C」とよばれ、ヘアドネーション活動を行っているNPO法人です。
2009年に開始した活動は今年で15年目を迎え、これまで累計742個もの医療用ウィッグを製作・提供してきた実績があります。
また、JHD&Cの活動に賛同するサロンの数は2,387店にもおよび、その支援の輪は年々広がりを見せています。
JHD&Cへ毛髪を送る際には、以下2つの宛先から選択できます。
【送付先】
1.〒530-0022
・大阪市北区浪花町13-38 千代田ビル北館7A
・NPO法人JHD&C事務局
2.〒640-8226
・和歌山市小人町29番地
・和歌山市あいあいセンター福祉交流館3F
・和歌山市社協・ボランティアセンター内 白百合美容室係
【宅配業者】
指定なし
※追跡機能のある送付方法(日本郵便のレターパック、宅配便など)を推奨
【URL】
https://www.jhdac.org/hair.html
つな髪
「つな髪」は、大阪府にある医療用ウィッグの製造・販売事業者グローウィングが運営しているヘアドネーションプロジェクトです。
これまで累計15万6,000人もの人に毛髪の寄付をいただいており、それらをもとに1,600個以上の医療用ウィッグを無償で提供してきました。
また、つな髪のプロジェクトに賛同したサロンは800店舗におよび、寄付をしたい方に向けてサロンの紹介も行っています。
【送付先】
・〒530-0001
・大阪府大阪市北区梅田3丁目3−45 マルイト西梅田ビル5F
・(株)グローウィング つな髪
【宅配業者】
・レターパック(日本郵便)
・宅急便コンパクト(ヤマト運輸)
・普通郵便(日本郵便)
※追跡機能のある送付方法(日本郵便のレターパック、宅配便など)を推奨
【URL】
https://www.organic-cotton-wig-assoc.jp/
NPO法人HERO
NPO法人HEROは東日本大震災をきっかけに設立され、オリジナルヒーロー「破牙神ライザー龍」を通してさまざまなボランティア活動を行っています。
ヘアドネーション活動は2016年からスタートし、小児がんの子どもたちに笑顔を取り戻してもらうために医療用ウィッグを無償で提供しています。
【送付先】
・〒981-8003
・宮城県仙台市泉区南光台2丁目13-1
・NPO法人HERO
・ヘアドネーションプロジェクト係
【宅配業者】
指定なし
※追跡機能のある送付方法(日本郵便のレターパック、宅配便など)を推奨
【URL】
https://hairdonation.hero.or.jp/hair/
まとめ
ヘアドネーションは毛髪を寄付することで医療用ウィッグの製作に役立ててもらう活動ですが、見方を変えると「髪があって当たり前」という差別や偏見を助長しかねず、ネガティブな意見が根強く存在します。
しかし、事故や病気、治療によって髪の毛を失った当事者にとっては、医療用ウィッグがあることで自信を取り戻し、生きる希望を見いだす人がいることも事実です。
そのような人のために、自分の髪の毛を提供したいといった意見や行動は決して批判されるものではありません。
もし、これからヘアドネーションに取り組んでみたいと考える方は、今回ご紹介した手順を参考にしてみてください。
当メディアの姉妹団体のNPOハミングバードも社会貢献につながる様々な活動を行っています。
ランドセル寄付は無料でできる?迷惑にならない方法と支援団体まとめ

小学校入学にあたっての必需品ともいえるランドセルですが、子どもの成長につれて役目を終えるとタンスの肥やしになってしまいがちです。
丈夫な作りで質が高く、処分するにももったいないと感じる方にはランドセルの寄付がおすすめです。
本記事では、ランドセルを寄付するための方法や手段、寄付にかかる費用や条件なども詳しくご紹介します。
ランドセル寄付は無料でできる?

ランドセルは小学校への入学準備品として揃えますが、6年間使用した後は廃棄したり押入れに保管しておいたりすることが多いものです。
また、近年ではランドセルを6年生まで使用することなく、高学年になるとリュックやバッグなどに切り替えるというケースも珍しくありません。
ランドセルはもともと丈夫な革でできていることから、小学校を卒業するタイミングでもまだまだ使用できるものが多く、廃棄するのはもったいないと感じる方も多いでしょう。
そこで、使わなくなったランドセルは支援団体などを通すことで無料で回収・寄付することができます。
迷惑にならないランドセル寄付の方法は?

古くなった衣類やファッション小物類を有効に活用するために、「困っている方に寄付をしたい」といった善意は最大限尊重されるべきです。
しかし、さまざまな支援施設の現状を見てみると、最低限の衣食住は保障されているケースが多く、特に衣類はニーズと供給のミスマッチが生じやすい傾向が見られます。善意のつもりで寄付をした品物が、受け取る側にとっては頭を悩ませる原因になることもあります。
ランドセルの寄付も例外ではなく、たとえば児童養護施設などにはさまざまな年齢の子どもが暮らしていますが、小学校への入学を控えた子どもの人数は限られています。加えて、過去に「タイガーマスク現象」が注目されたこともあり、毎年新品のランドセルが寄付されている施設も少なくありません。
そのようななかで古くなったランドセルを寄付したとしてもニーズがマッチしづらく、反対に施設側へ大きな負担をかけてしまう可能性すらあるのです。
では、迷惑をかけることなくランドセルを寄付するためには、どういったニーズを汲み取れば良いのでしょうか。
ひとつの例としては、国内ではなく海外に目を向けてみることがおすすめです。海外では日本のようにランドセルを通学用カバンとして使用する習慣はありませんが、ランドセルに使用されている丈夫な素材は極めてニーズが高く、リサイクルすることで魅力的な製品に生まれ変わります。
児童養護施設などに匿名または実名でランドセルを贈る行為は、決して非難されるものではありません。しかし、結果として施設側の負担を増やしてしまうという現実がある以上、できるだけ支援団体を通して寄付をすることが理想的といえるでしょう。
ランドセル寄付は持ち込みOK?

支援団体にランドセルを寄付する場合、どのような方法・手段をとれば良いのでしょうか。
支援団体によっても寄付の仕方はわずかに異なりますが、基本的にはランドセルをダンボールに入れ、指定の住所まで宅配便で送る必要があります。
しかし、ランドセルが入るダンボールとなるとそれなりのサイズのものを用意しなければならず、送料もかかってしまいます。
そこで、近隣に寄付を受け付けている支援団体がある場合、送料を節約するために窓口へ直接持ち込みたいと考える方も多いでしょう。
結論からいえば、窓口への直接の持ち込みが禁止されている団体が多い一方で、条件付きで受付が可能な団体もあります。
支援団体は限られた人員で運営しているケースが多く、窓口や集荷センターにおいて常時対応できるスタッフがいるとは限らないためです。そのため、持ち込みにあたっては以下の情報を事前に伝えておく必要があります。
- 持込予定の日時
- 持込予定の集荷センター(窓口やセンターが複数ある場合)
- 持込予定の品物の種類
- 持込予定の箱数
支援団体ではランドセル以外にもさまざまな品目の寄付を受け付けているため、品物の種類や箱数は正確に伝えておきましょう。
また、あくまでも上記は一例であり、支援団体によっても受け入れ条件は異なるため必ず利用規約を確認しておくことが大切です。
【無料あり】ランドセル寄付ができる支援団体まとめ

ランドセルの寄付に対応している支援団体にはどのようなところがあるのか、いくつかの例をご紹介します。
1.リボーンプロジェクト
「リボーンプロジェクト」は、使用しなくなったものを海外で販売し、その売上を寄付する活動を行っている支援団体です。
寄付金はポリオワクチンの接種に充てられ、これまで27万人以上の世界の子どもを救ってきました。
寄付の対象となる品目はランドセルをはじめとして春夏用の衣類、おもちゃ、調理器具、アクセサリー、服飾小物、スポーツ用品、楽器など多岐にわたります。
一方、布団や日本人形、CD/DVD、家具・家電、冬物の衣類や靴など、受け入れNGの品目もあるためご注意ください。
【費用】
送料負担のみ
※専用回収キット(2,600円)購入の場合は送料無料
【送付先】
〒501-2571 岐阜県岐阜市太郎丸向良162
株式会社GoodService
058-229-5238
【配送業者】
専用回収キット利用の場合は佐川急便で発送
それ以外は配送業者の指定なし
【持込の可否】
NG
【URL】
https://www.kataduke-kaitori.com/reborn/donate/school-bag/
2.KIFUcoco
「KIFUcoco」もさまざまな不用品をリユースすることで現金化し、日本赤十字社をはじめとしたさまざまな支援団体に寄付を行っている団体です。
希望の寄付先があれば指定することもできるほか、事前申込をすることで直接の持込にも対応できます。
食品や液体、古い家電製品など回収できない品目もあるためご注意ください。
【費用】
送料負担のみ
【送付先】
〒731-0214
広島市安佐北区可部町大字桐原822
kifucoco
【配送業者】
指定なし
【持込の可否】
OK(事前連絡が必要)
【URL】
https://kifucoco.com/kifu/category_stationery/stationery_school_bag/
3.いいことシップ
「いいことシップ」は一般社団法人いいことファームが運営している支援団体で、北海道から九州まで全国の拠点に集荷センターや窓口を設置しています。
ランドセルをはじめとした不用品の回収は送料負担のみで、事前の連絡さえ行っていれば集荷センターへの持込にも対応できます。
複数の拠点から最寄りの集荷センターを選択できるため、送料が節約できるのも大きなメリットといえるでしょう。
【費用】
送料負担のみ
【送付先】
以下4拠点のいずれか
〒252-0244 神奈川県相模原市中央区⽥名2242-1
TEL:0120-976-329
いいことシップ 横浜集荷センター
〒577-0004 大阪府東大阪市稲田新町2-2-7
TEL:0120-976-329
いいことシップ 大阪集荷センター
〒651-2404 兵庫県神戸市西区岩岡町古郷1459-1
TEL:0120-976-329
いいことシップ 神戸集荷センター
※家具は受付不可
〒005-0004 札幌市南区澄川4条2-4-12澄川88ビル2F
TEL:0120-976-329
いいことシップ 札幌集荷センター(株式会社クローバーズ)
【配送業者】
指定なし
【持込の可否】
OK(事前連絡が必要)
【URL】
https://eco-to-ship.jp/area/ransel/tokyo/
4.ジョイセフ
ジョイセフはアフガニスタンへランドセルの寄付を行っている支援団体です。
基本的に寄付に対応しているのはランドセルのみですが、中に未使用の鉛筆やノート、消しゴム、下敷きなどの学用品を入れて贈ることもできます。
また、指定倉庫までの送料に加えて、海外輸送費および現地での配布活動費としてランドセル1個あたり1,800円の寄付金も振込が必要です。
【費用】
1,800円+倉庫までの送料
※書き損じはがきでの寄付も可。62円はがきの場合50枚以上(2024年3月1日以降は81枚以上)
【送付先】
〒143-0001
東京都大田区東海4-7-7
鴻池運輸 大井物流営業所内
サンライト「ジョイセフランドセル」係
※書き損じハガキの送付先は以下
〒160-0003
東京都新宿区四谷本塩町12-3 AOIビル3階
ジョイセフ「ランドセル・学用品はがき」係
【配送業者】
指定なし
【持込の可否】
NG
【URL】
https://www.joicfp.or.jp/jpn/donate/support/omoide_ransel/donation/
5.JIYU
「JIYU」は海外の学校に通う子どもたちに対し、文房具や学用品、ランドセルの寄付を行っている支援団体です。
輸送コストなどの問題もありスタッフが現地まで趣き手渡しで届けており、学用品以外のリユース品についても現金化し全額を寄付しています。
寄付品を送る際には、送料とは別途ダンボール1箱あたり1,000円以上の寄付をお願いしており、「寄付申し込みフォーム」から必要情報を入力してから発送します。
【費用】
ダンボール1箱あたり1,000円以上+送料
寄付金入金先
■ゆうちょ銀行
11310-03910171(普通:一三八店 口座番号:0391017)
口座名義:トクヒ)ジユウ
特定非営利活動法人JIYU
■現金書留
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-23-1
ニューステートメナー418号
NPO法人JIYU事務局
【送付先】
茨城県竜ケ崎市
※詳細な住所はフォームから申込後表示
【配送業者】
指定なし
【持込の可否】
NG
【URL】
まとめ
ランドセルは小学校を卒業すると用途がなくなり、再利用も難しいものです。しかし、だからといって押入れに保管しておくのも場所をとったり、処分に困ったりすることもあるでしょう。
そのようなお悩みを抱えている場合には、ランドセルの寄付を検討してみてはいかがでしょうか。海外では質の高い日本のランドセルのニーズが高く、さまざまな支援団体が寄付を受け入れています。
当メディアの姉妹団体のNPOハミングバードも社会貢献につながる様々な活動を行っています。
それぞれの寄付の条件や費用、配送先なども比較しながら、自分自身にとって利用しやすい支援団体に託してみましょう。
寄付による税金の控除とは?ふるさと納税との違いも解説

国や自治体、あるいは学校、医療機関など、公的機関や施設に対して寄付をすることで所得税が軽減される場合があるのをご存知でしょうか。
また、寄付と聞くと「ふるさと納税」をイメージする方も多いと思いますが、一般的な寄付金控除とふるさと納税にはどういった違いがあるのか疑問に感じる方も多いはずです。
そこで本記事では、寄付によって受けられる税金の控除の仕組みやルール、計算方法などもあわせて詳しくご紹介します。
「特定寄附金」を支払うと税金が控除される

会社員の場合は給与、個人事業主や経営者の場合は売上から経費を差し引いた利益に対して所得税が課税されます。
所得税は累進課税という仕組みが採用されており、基本的に所得金額が大きい人ほど課税割合も高くなる仕組みとなっています。しかし、同時にさまざまな控除も用意されており、これらをうまく活用することにより税負担軽減できます。
一定の寄付金を支払った際に控除される「寄附金控除」もそのひとつで、国税庁のタックスアンサーには以下のように掲載されています。
”納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。”
引用:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.html
「寄付金」と聞くと募金や義援金などをイメージする方も多いと思いますが、税金の控除の対象となるのはあくまでも「特定寄附金」に該当するものに限られ、必ずしもすべての寄付金が控除の対象とはならないため注意が必要です。
特定寄附金の範囲は?
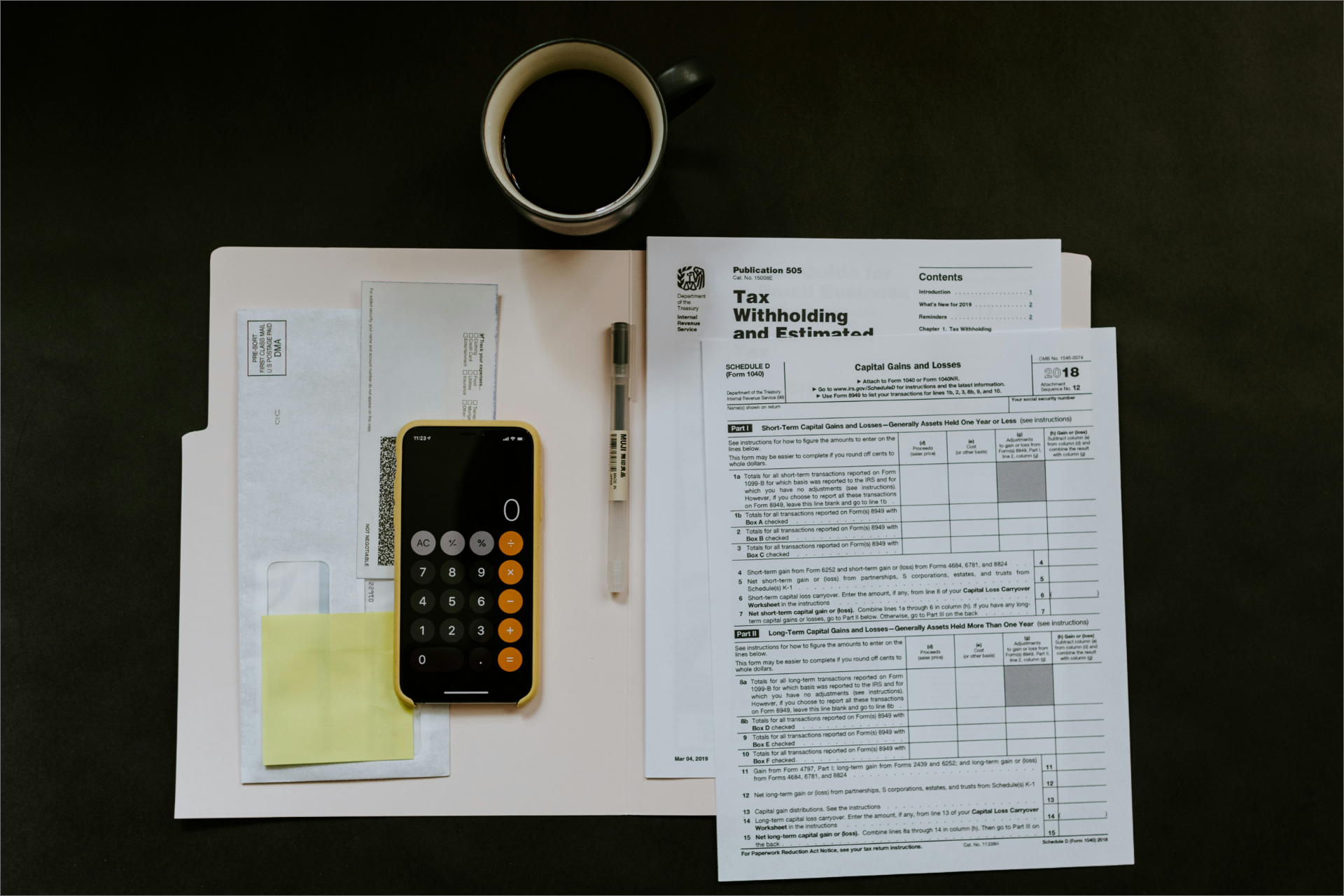
では、所得税の控除対象となる「特定寄附金」とはどのようなものなのでしょうか。国税庁では以下のいずれかに該当するものを特定寄附金と定義しています。
- 国、地方公共団体に対する寄付金
- 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人または団体に対する寄付金
※「一般に広く募集されているもの」かつ「緊急性と公益性が高いと財務大臣が指定したもの」 - 特定公益増進法人(独立行政法人、社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人、日本赤十字社など)に対する寄付のうち一定のもの
※教育・科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他の公益の増進に著しく寄与すると認められた特定公益増人法人に対する寄付金 - 特定公益信託のうち、その目的が教育・科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すると認められる一定の公益信託の信託財産とするために支出した寄付金
- 政治活動に関する寄付金
※寄付をした人に特別の利益がおよぶもの、政治資金規正法に違反するものを除く - 認定特定非営利法人等(認定NPO法人等)に対する寄付金
※寄付をした人に特別の利益がおよぶものを除く - 特定新規中小会社により発行される特定新規株式を、払込みにより取得した金額のうち一定の金額(800万円まで)
上記の内容を簡単にまとめると、特定寄附金として認められる重要なポイントは公益性の高さといえるでしょう。
たとえば、「クラウドファンディングで特定の人やお店、企業を支援するために寄付をした」というのは特定寄附金とみなされず、税金から控除することもできません。
また、寄付先がNPO法人や社会福祉法人、公益社団法人などであったとしても、寄付金の用途や募集の仕方などによっては特定寄附金としてみなされないケースも想定されるため注意が必要です。
寄付金の控除額は?

実際に支払った金銭が特定寄附金に該当する場合、どの程度の割合が寄附金控除として認められるのでしょうか。
まず前提として覚えておきたいのが、税金の控除には所得金額から差し引く「所得控除」と算出された納税額から差し引く「税額控除」の2種類があるということです。
そして、「寄付金特別控除」に該当する場合は両者のいずれかから選択でき、それ以外の寄付金控除は所得控除が適用されます。
所得控除の場合の寄付金控除額算出方法
- 「年間の寄付金額」または「総所得金額×40%」のいずれか低い金額-2,000円
税額控除の場合の寄付金控除額算出方法
- (年間の寄付金額-2,000円) × 30~40%
たとえば、年間の所得金額500万円の人が、ある政党(政治資金団体)に対して10万円を寄付した場合のシミュレーションは以下の通りです。
【所得控除の場合】
10万円-2,000円=9万8,000円
【税額控除の場合】
(10万円-2,000円)×30%=2万9,400円
控除額を見れば所得控除のほうが金額が大きいですが、税額控除は算出された納税額から上記の金額を差し引くため、条件によっては税額控除のほうがより高い節税効果を見込めるケースが多いのです。
ただし、上記のいずれかから選択できるのは「寄付金特別控除」に該当する場合に限られ、主な対象の寄付先としては政治資金団体および政党、公益財団法人・公益社団法人、認定NPO法人などに限られます。
ふるさと納税との違いについて

寄付金控除と聞くと、昨今利用者が増えている「ふるさと納税」を連想する方も多いのではないでしょうか。
両者は税制上似た仕組みであり混同してしまうケースも少なくありませんが、控除の対象や申告の手続きなどに大きな違いが見られます。
控除の違い
寄付金控除の場合、上記で紹介した通り年間の寄付金額または総所得金額の40%にあたる金額から2,000円を差し引いた分が所得金額から控除され、所得税が算出されます。
これに対し、ふるさと納税は寄付額から2,000円を差し引いた全額が控除の対象となるほか、加えて住民税の特別控除も適用されるという大きな違いがあるのです。
すなわち、寄付金控除は所得税のみ、ふるさと納税は所得税+住民税から控除が受けられるため、ふるさと納税のほうが高い節税効果が期待できることを意味します。
確定申告の違い
年末調整の対象となっている会社員であっても、寄付金控除を受けるためには確定申告を行わなければなりません。
しかし、ふるさと納税の場合は「ワンストップ特例制度」が利用でき、一定の条件を満たしていれば確定申告の煩雑な手続きが必要なく控除や還付が受けられます。
ただし、ふるさと納税は寄付金控除との併用も可能であり、この場合は年末調整が対象の会社員であっても確定申告を行わなければなりません。
寄付金控除の計算シミュレーションはこちら
寄付金控除によって所得税の節税効果が得られるとはいっても、どの程度の金額が低減できるのか、おおよその目安を知っておきたいという方も多いでしょう。
大前提として、最終的な納税額は所得金額や配偶者の有無、その他さまざまな控除の内容、条件によっても変わってきます。
ただし、所得金額と寄附金額をもとにおおよその控除割合や控除額をシミュレーションすることは可能です。
たとえば、課税所得(給与所得控除後の金額から所得控除の額の合計額を差し引いたもの)が400万円の方が1年間で5万円の寄付を行った場合、所得控除の場合で9,600円、税額控除では1万9,200円が寄付金控除として受けられます。
また、寄付額が10万円であった場合には所得控除で1万9,600円、税額控除で3万9,200円、20万円では所得控除が3万9,600円、税額控除で7万9,200円と上がっていきます。
すなわち、所得控除であれば寄附金額に対して約2割、税額控除は約4割程度の節税効果が得られる計算になります。
寄付金控除のシミュレーションは以下のサイトにアクセスし、課税所得金額と寄附金額を入力することで概算を求められるためぜひ参考にしてみてください。
https://kikin.keio.ac.jp/simulator/
まとめ
所得税の算出にあたっては、一定の条件を満たす寄付を行った場合に控除が受けられる寄付金控除があり、これを活用することで税負担を軽減できます。
ただし、すべての寄付が控除の対象として認められるものではなく、国や自治体をはじめとして、公的団体や公的機関、そして公益性がある用途などに限定されています。
現在、ふるさと納税の利用者が増えていますが、寄付金控除に比べると住民税の特別控除も受けられる違いがあるためメリットは大きいといえるでしょう。
寄付金控除を活用し税負担を軽減したいと考えている方は、今回紹介したシミュレーションも参考にしながら、ふるさと納税とも比較し検討してみてください。
フェムケアのやり方は?更年期に実践すべき膣マッサージの方法を紹介

デリケートゾーンの悩みをはじめとして、生理痛や更年期障害など女性特有の悩みは多いものです。
これを解決するために、フェムケアとよばれる言葉が現在注目されています。本記事では、フェムケアとはどういった概念なのか、フェムケア製品の種類や具体的な方法などを詳しくご紹介します。
フェムケアとは

フェムケアとは、女性を意味する「feminine(フェミニン)」と「care(ケア)」を組み合わせた言葉です。
すなわち、女性の健康や身体のケアをすることがフェムケアであり、それらをサポートする製品やサービスなどの総称としてこの言葉が使われるようになりました。
具体的には、生理や妊娠、更年期などを原因とした女性特有のさまざまな体調不良をケアし、QOLを向上させていくことを目的としています。
▶︎生理後は性欲が強くなる?生理周期別の性に関する過ごし方を紹介
フェムケアが注目されている理由
フェムケアは近年になって登場した言葉であり、社会的にも徐々に認知されつつあります。
しかし、生理や妊娠、更年期といった女性特有の体調不良や悩みは古くから存在しており、なぜ今のタイミングでフェムケアが注目されるようになったのか疑問に感じる方も多いはずです。
この背景には、女性の社会進出が進み、結婚や出産を経ても働き続ける女性が増えていることが挙げられます。
たとえば、生理や更年期に伴う体調不良が慢性化していると、生産性や働く意欲が低下するほか、出勤そのものが苦痛になり会社を退職せざるを得ないケースも出てくるでしょう。
また、近年の日本では少子化の影響もあり深刻な人手不足が続いていることもあり、性別や年齢にかかわらず労働力の確保は重要な課題となっています。
女性のQOLを向上させると同時に、体調不良に悩むことなく優れたパフォーマンスを発揮できるよう、フェムケアは注目されているのです。
フェムケアの効果・メリット

フェムケアに対応した製品やサービスを利用することで、どういった効果・メリットが得られるのでしょうか。
ホルモンバランスの正常化
人間の身体はホルモンバランスが適切に維持されていることで健康を保っています。
しかし強い生理痛や月経サイクルの乱れ、あるいは更年期障害などによってさまざまな不調が発生すると、それが強いストレスとなりさらにホルモンバランスが悪化していくという悪循環に陥ります。
フェムケアによってデリケートゾーンを中心に適切なケアを行うことで、ホルモンバランスが正常化し不調が改善していくこともあります。
デリケートゾーンの黒ずみやニオイ解消
デリケートゾーンの状態は個人差があるほか、年齢によっても変化していくことがあります。
たとえば、20代・30代の段階ではデリケートゾーンからの分泌液の量が多いことや、蒸れや皮脂、汗なども原因となってニオイに悩む方が少なくありません。
また、年齢を重ねていくとデリケートゾーンに黒ずみが生じ、コンプレックスを抱く方もいます。
そこで、たとえばVIO脱毛をしたり、蒸れが生じにくい下着を着用するなど、さまざまなフェムケア製品やサービスを試すことで解消できる可能性があるのです。
性生活の改善・充実
デリケートゾーンに悩みやコンプレックスを抱えていると、それが原因でパートナーに嫌われてしまうのではないかと心配になり、性生活にも影響を及ぼすことがあるでしょう。
フェムケアを利用することでコンプレックスが解消され、パートナーと円満な関係を維持できる可能性があります。
フェムケアとフェムテックの違い

フェムケアと似た言葉として「フェムテック」があります。フェムケアと同様、近年注目を集めていますが、両者はどのような違いがあるのでしょうか。
フェムテックは「feminine(フェミニン)」と「technology(技術)」を組み合わせた言葉です。
一言でいえば、ITをはじめとした先進のテクノロジーを活用したフェムケアの製品やサービスなどをフェムテックとよび、それ以外はフェムケアに分類されます。
フェムテックの代表例としては、月経サイクルを記録しておくためのスマホアプリや、オンラインでのピル処方、卵子凍結サービスなどが挙げられます。
また、女性が性的快感を得るために用いられるセルフプレジャートイなどもフェムテックの代表的な例として注目されています。
つまり、フェムケアという概念の一部としてフェムテックがあるというイメージです。
▶︎フェムテックとは?主な商品や市場規模、フェムケアとの違いを解説
どんな人にフェムケアはおすすめ?
フェムケアは年齢を問わず、さまざまな悩みを抱えている女性におすすめです。
具体的には、以下のような悩みを抱えている場合には早めにスタートすると良いでしょう。
- 生理痛が辛く仕事を定期的に休んでしまう
- おりものや分泌物の量が多く下着がすぐに汚れてしまう
- デリケートゾーンのニオイが気になる
- 排卵日や生理周期を簡単に予測しておきたい
- 更年期障害に悩んでいる・または更年期を迎える不安がある
- 尿もれで悩んでいる
- パートナーとの性交渉を楽しみたい
- セルフプレジャーを楽しみたい
▶︎セルフプレジャーとは?美容効果を紹介!どんな人におすすめ?
フェムケアのやり方・マッサージ方法

フェムケアには具体的にどういった方法・ツールがあるのでしょうか。また、手軽に自分でできるマッサージの方法もご紹介します。
生理用品
生理用品といえばナプキンやタンポンなどが定番ですが、おりものシートや月経カップなども選択肢のひとつになります。
吸水性や素材、形状にも違いがあり、これらをうまく使い分けることで生理中でも快適な生活を送れるでしょう。
下着
デリケートゾーンの蒸れやニオイが気になる方は、下着にこだわってみるのもおすすめです。
特に、コットンやシルクなどは高価ですが、その分通気性が高く肌触りも良いため、着用感も快適です。
また、薄く軽い素材のため摩擦によって生じる黒ずみも抑えられます。
洗浄
デリケートゾーンのニオイを防ぐためには、洗浄剤の成分や洗い方を見直すことも大切です。
現在では刺激の低いデリケートゾーン専用のボディソープも販売されており、これを使用することで悩みが解決できる可能性もあります。
また、洗浄の際には強く擦らず、たっぷりの泡を手にとって優しく洗い流すようにしてください。
保湿
デリケートゾーンの脱毛や除毛、あるいは生理用品や下着で強い刺激が加わった場合、デリケートゾーンが乾燥し荒れることがあります。
こちらも、保湿力の高いボディソープを使用することで適度な潤いがうまれ、炎症やただれ、かぶれの防止につながります。
膣トレ
膣の緩みや尿もれなどが気になる方は、膣のトレーニング「膣トレ」に挑戦してみるのも良いでしょう。
「ケーゲル体操」とよばれるトレーニングが有名で、尿道から肛門、膣のあたりに力を入れて締めた後、10秒程度キープしゆっくりと緩めます。
机に手を置いた姿勢、仰向けの姿勢、椅子に座った状態、四つん這いの姿勢のいずれかで上記のトレーニングを5セット程度繰り返してください。
膣マッサージ
膣マッサージも膣の緩みを改善するために有効な方法です。
人差し指か中指に専用オイルを塗った後、膣の中にゆっくりと指を入れます。指を膣壁に沿うように密着させ、回しながらマッサージします。
フェムケアが更年期以降にも必要な理由
更年期になると閉経を迎え、生理や妊娠などによる体調の悪化もないことから「フェムケアは必要ないのでは?」と考える方もいるでしょう。
しかし、閉経を迎えることで女性のホルモンバランスは大きく変化し、更年期障害となって現れることも多いのです。
また、閉経後は膣壁が硬くなったり膣からの分泌液が減少するなどして、性交痛の原因になることもあります。
このような悩みを解消し、パートナーとも円満な関係を維持するためにも、更年期以降もフェムケアに取り組むことが重要です。
▶︎50代女性の性欲事情|閉経後や更年期との関連性についても
まとめ
デリケートゾーンの悩みは他人には相談しにくいことから、病院を受診せず一人で悩みを抱えるケースが多いものです。
しかし、フェムケアという言葉が広く社会に浸透しつつある今、女性特有の悩みはさまざまな方法で解決できる可能性が高いです。
正しいフェムケアの方法や自分に合った製品を選び、いきいきとした生活を送りましょう。
フェムテックは更年期の女性におすすめ?商品や市場規模を解説
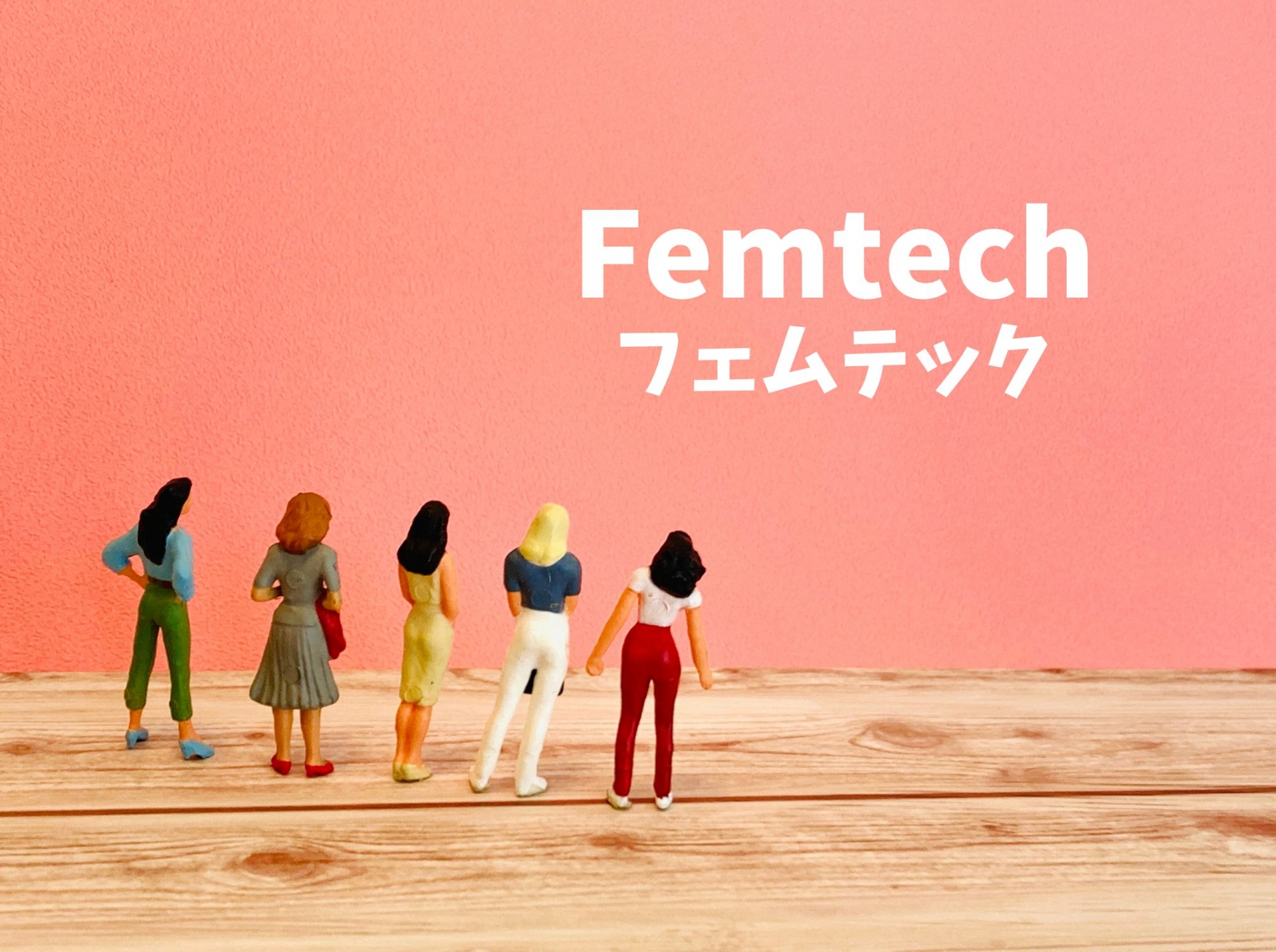
近年、「◯◯テック」という言葉をよく耳にするようになりました。
フィンテックやヘルステック、フードテックなどが代表的ですが、これ以外に「フェムテック」というものもあります。
女性の社会進出により新たに生まれた言葉ですが、フェムテックとは具体的にどのようなものを指すのでしょうか。
商品やサービスの事例、混同しやすいフェムケアとの違いについてもご紹介します。
フェムテックとは

フェムテックとは、「feminine(フェミニン)」と「technology(技術)」を組み合わせた言葉で、テクノロジーを活用し、女性特有の身体的な悩みや不調を改善するための製品やサービスのことを指します。
具体的には生理痛や生理不順、妊娠や出産にともなう体調の変化、更年期障害などの悩みを解消するための製品やサービスが代表的です。
▶︎40代の女性は性欲が強い?なくなる?その違いや性欲の対処法について
フェムテックが広がりつつある背景
女性の身体の悩みは古くから存在していたにもかかわらず、なぜ近年になってフェムテックが注目されるようになったのでしょうか。
その背景には、女性の社会進出が広がってきたことが挙げられるでしょう。結婚や出産を経ても仕事を続けるケースは一般的になりましたが、その一方で生理痛や更年期障害によって仕事のパフォーマンス低下に悩む女性も少なくありません。
人手不足が続く日本において女性の活躍は不可欠なものとなっており、働きやすい環境を実現するためにもフェムテックを導入する企業は増えているのです。
また、それにあわせてフェムテックの市場規模も拡大し、2025年には全世界で5兆円規模にまで成長すると予想されています。
▶︎生理後は性欲が強くなる?生理周期別の性に関する過ごし方を紹介
更年期の女性にとってフェムテックが必要な理由

更年期になると閉経し生理痛に悩むこともなくなるため、フェムテックは必要ないのではないかと感じる方もいるでしょう。
しかし結論からいえば、フェムテックはあらゆる世代の女性に関係するものです。冒頭でも紹介した通り、フェムテックは更年期障害にともなう身体の不調や悩みを改善するうえでも有効です。
近代の日本は、医療技術の発達や健康志向の高まりなどによって健康寿命が伸びていますが、一見健康そうにみえる女性でも更年期障害をはじめとしたさまざまな健康不安を抱えていることがあります。
そのような方にとって、フェムテックを利用することで年齢を重ねても健康な毎日を送れる手助けとなるのです。
▶︎50代女性の性欲事情|閉経後や更年期との関連性についても
フェムテックの効果やメリット

フェムテックは具体的にどのような悩みや症状を緩和する効果があるのでしょうか。また、それによって得られるメリットもあわせてご紹介します。
生理周期や排卵日の予測が可能
専用のスマホアプリを活用することで、生理周期や排卵日を簡単に予測することができます。スマホで正確に管理することで、万が一生理が遅れている場合には早い段階でそれに気付くことができるでしょう。
更年期障害の緩和
更年期障害ではさまざまな症状が起こりますが、なかでも心理的な不安や頭痛などが代表的です。
たとえば、フェムテックの一環として女性ホルモン製剤を注入することにより、ホルモンバランスが改善され不定愁訴の解決につながるケースもあります。
性交痛の緩和
更年期を迎えると心身の不調が起こるばかりではなく、閉経に伴い膣の分泌液の量が減ったり膣壁が硬くなったりすることで、性交渉の際に痛みを感じることがあります。
人によっても痛みの出方や程度は異なりますが、あまりにも強い痛みが出てしまうと性交渉そのものが苦痛に感じることもあるでしょう。
その結果、配偶者やパートナーとの関係に亀裂が生じる可能性もあります。
フェムテック製品のなかには性交痛を緩和する特殊なツールも販売されており、これを活用することで痛みの緩和につながります。
セルフプレジャーやフェムテックとの違い
フェムテックに関する製品やサービスを調べると、「セルフプレジャー」というワードも一緒に目にすることが少なくありません。
そもそもセルフプレジャーとは何か、フェムテックとは何が違うのかをご紹介します。
フェムテックとセルフプレジャー
セルフプレジャーとは、自分自身の身体の一部を触ったり刺激を与えたりすることで、性的快感を得る行為のことです。一般的には「自慰行為」や「マスターベーション」などといわれることが多いです。
たしかに、セルフプレジャーの際に使用するアイテムもフェムテック製品の一部であり、製品のバリエーションも豊富に用意されています。
つまり、フェムテックとセルフプレジャーは関連性はあるものの、意味の上では全く違う言葉です。
▶︎セルフプレジャーとは?美容効果を紹介!どんな人におすすめ?
フェムテックとフェムケア
フェムテックに似た言葉や概念としてフェムケアがありますが、こちらは「feminine(フェミニン)」と「care(ケア)」を組み合わせた言葉で、テクノロジーに依存しない一般的なケアの手法や製品などを指します。
ただし、両者には明確な基準はなく、フェムケアの一部としてフェムテックが位置づけられています。
▶︎フェムケアとは?やり方やマッサージをご紹介!更年期以降は?
フェムテックの主な商品やサービス

フェムテックの製品やサービスとして提供されている代表的な例をいくつかご紹介しましょう。
月経に関する商品・サービス
生理のタイミングを記録・把握したり、生理中の時期を快適に過ごすためのフェムテックは以下の通りです。
◆生理周期や排卵日の予測アプリ◆
専用のスマホアプリを活用することで、生理周期や排卵日を簡単に予測することができます。スマホで正確に管理することで、万が一生理が遅れている場合には早い段階でそれに気付くことができるでしょう。
◆吸水ショーツ◆
吸水性の高い専用のショーツを着用しておけば、生理用ナプキンを忘れた日でも安心です。また、通常のショーツよりも優れた抗菌・防臭効果を発揮するためニオイに悩む方にとっても嬉しいでしょう。
妊娠・不妊治療に関するサービス
妊娠や不妊をサポートするためのフェムテックサービスも充実しています。
◆卵子凍結サービス◆
女性の社会進出が進む一方で晩婚化も進行しており、30代後半や40代になってから結婚する方も珍しくありません。
しかし、年齢を重ねるにつれて妊娠がしにくい身体に変化していき、子どもが欲しいのになかなか授からないと悩む女性は多く存在します。
このような問題を解決するために、将来に備えて自分の卵子を凍結・保管しておくサービスが登場しています。
これを利用することで、本来であれば妊娠の可能性が低くなる40代になってからも体外受精によって子どもを授かれる可能性があるのです。
更年期をサポートする商品・サービス
更年期に現れるさまざまな症状を緩和するためのフェムテックもあります。
◆サプリメント◆
ホルモンバランスが乱れがちな更年期においては、大豆イソフラボンをはじめとした女性に嬉しい成分が配合されたサプリメントがおすすめです。
更年期に差し掛かった際に現れる心身の変化を緩やかにし、身体の内側からサポートすることができます。
◆骨盤底筋のトレーニングアイテム◆
更年期に差し掛かると骨盤底筋とよばれる部位が歪み、体型が変化していくことがあります。
これを鍛える専用のトレーニングアイテムを活用することで、骨盤底筋の歪みが解消されシェイプアップ効果も期待できるでしょう。
まとめ
女性の社会進出が進むなかでフェムテックの市場規模は年々拡大しており、今後さらに注目度は高まっていくと考えられます。
女性である以上、生理や妊娠、更年期といった身体の悩みは起こりうるもので、いかにこれらを緩和しQOLを上げていけるかが重要となります。
今回紹介した代表的な商品やサービス以外にも、今後新たなフェムテックが登場すると考えられるためぜひ注目していきましょう。
【ヘアドネーション】自分で送る手順や必要な長さの条件をご紹介!

自分自身のカットした髪の毛を寄付するヘアドネーションをご存知でしょうか。
米国発祥のヘアドネーションは、日本国内でも社会貢献の一環として徐々に認知されるようになり、女性を中心に寄付に取り組む人が増えています。
ヘアドネーションを行うにはどうすれば良いのか、寄付できる髪の毛の条件や送り方なども詳しくご紹介します。
ヘアドネーションとは

ヘアドネーションとは、カットした髪の毛を寄付することを指します。
ヘアドネーションを受け付けている団体があり、その団体を通して寄付をするのが一般的です。日本ではジャパンヘアードネーションアンドチャリティー(JHD&C)という団体が有名で、多くの美容室と連携しながらヘアドネーションに取り組んでいます。
寄付された髪の毛は医療用ウィッグの材料として使用され、病気や事故などさまざまな事情によって必要とされる人に贈られています。
ただし、ウィッグに使用する以上、ある程度の髪の長さが必要であるなど細かな条件があり、すべての人が寄付できるとは限りません。
ヘアドネーションを必要としている人たち

そもそも、医療用ウィッグという言葉を初めて耳にした人も多いのではないでしょうか。
ウィッグと聞くとファッション分野で使用されるアイテムというイメージが強いですが、なぜ医療用ウィッグが必要なのか、どういった人に贈られているのかを見ていきましょう。
脱毛症の人
先天的な病気のひとつに、髪の毛をはじめとした体毛が抜け落ちてしまう病気があります。これは先天性脱毛症とよばれ、産まれたときから体毛が極端に薄いケースや、一部分だけが局所的に生え揃わないケースなどさまざまです。
これが原因で強いコンプレックスを抱いたり、精神的に落ち込んでしまう人もいることから、ヘアドネーションによって作られた医療用ウィッグが活躍します。
がん治療中の人
抗がん剤による治療を行うと、副作用として大量の体毛が抜け落ちることがあります。
特に若年層や女性の方にとってはショックが大きく、精神的に塞ぎ込んでしまうことも少なくありません。
そこで、医療用ウィッグを着用することで自信を取り戻し、前向きに治療を受けられるようになるのです。
事故などで毛髪を失った人
病気だけでなく、事故によって頭部に外傷を負った方のなかには、大きな傷や手術が原因で毛髪が生えてこなくなるケースもあります。
こちらも特に若年層の方や女性にとってはショックが大きく、命が助かったとしても塞ぎ込んでしまうのも無理はありません。
医療用ウィッグを着用することで、自信を取り戻し前向きに生きる活力となるでしょう。
ヘアドネーションは意味ない?ネガティブな意見がある理由
ヘアドネーションは、多くの方が善意の気持ちをもって髪の毛を寄付しています。
しかし一方で、「ヘアドネーションには意味がない」、「迷惑な行為なのではないか」と捉える人も存在します。
彼らの意見を代弁するならば、私たちのなかに「髪の毛はあって当たり前」という先入観があり、無意識のうちに差別的な見方をしている可能性があるのではないかという問いかけになっています。
すなわち、「毛髪がないから可哀想」という気持ちから、髪の毛を寄付して医療用ウィッグを作ってもらうのは良いことだと一方的に思い込んでいるのではないか、ということです。
そもそも髪の毛がないことに対して偏見や差別がなければ、周囲の視線を気にすることなくありのままの自分で過ごすことができます。
また、四六時中ウィッグを装着していると頭部が蒸れて炎症を起こすケースや、真夏の時期には熱中症のリスクも高まります。
もちろん、脱毛や無毛に悩む人のなかには、医療用ウィッグがあって救われたという人も多いでしょう。そのため、決してヘアドネーションそのものを否定するものではなく、髪の毛を寄付すること自体が悪というわけでもありません。
重要なのは、「すべての人にとって髪の毛があることは当たり前」という意識を捨て、どのような人に対しても差別や偏見をもたずに接することができる世の中の風潮をつくることです。
少なくともヘアドネーションを行う人は、無意識のうちに差別や偏見の気持ちをもっていないか、あらためて自分を振り返りつつ寄付を行うことが求められるのです。
ヘアドネーションに必要な条件

ヘアドネーションを行うためにはさまざまな条件があると説明しましたが、具体的にどういった内容なのでしょうか。
まず、ヘアドネーションへの参加条件として年齢や性別、国籍などは関係ありません。そのうえで、切った髪の毛が以下の条件を満たしている必要があります。
1.髪の長さが31cm以上であること
医療用ウィッグの製作にあたっては、世界的な基準として12インチの長さが必要であると定められています。12インチは30.48cmに相当することから、最低でも31cm以上の毛髪であることが条件となります。
ちなみに、寄付する分の髪の毛をカットする料金は基本的に0円ですが、ドネーション後にはヘアスタイルを整える必要があり、これには正規の施術料が発生します。
2.極端なダメージヘアでないこと
極端なダメージが加わった髪の毛は、引っ張る力が少し加わっただけで切れてしまい、医療用ウィッグには適しません。
3.完全に乾燥していること
濡れた状態、または湿った状態の髪の毛はカビや細菌が繁殖しやすく、せっかく寄付をしても医療用ウィッグの材料として使用できなくなります。
そのため、ヘアドネーションとして送る前には十分に髪の毛を乾かしておく必要があります。
ヘアドネーションの送り方や手順

実際にヘアドネーションはどのような手順で行われるのでしょうか。
1.美容室を探すして予約
ヘアドネーションはすべての美容室やサロンで対応できるとは限りません。
普段利用しているお店がある場合には、ヘアドネーションに対応できるかを確認しておきましょう。
もし美容室が見つからない場合には、JHD&Cの活動に協力している「賛同サロン」がおすすめです。
賛同サロンはJHD&CのWebサイトでも検索できます。
サロン検索システム:https://www.jhdac.org/search/index.php
2.ドネーションカットを依頼する
予約した美容室を訪れ、「ドネーションカットをお願いします」と申し出てください。
3.寄付する毛髪の長さを決めてカットしてもらう
寄付する分の髪をカットしてもらいます。
ドネーション後に残る髪の長さをもとにヘアスタイルも調整しなければならないため、どの程度の長さをカットするかは美容師と相談しながら慎重に決めましょう。
また、髪の毛が濡れたり湿ったりしていると雑菌が繁殖する原因になるため、ドネーションカットの前には髪を濡らさないことが重要です。
4.ドナーシートへ記入
ドナーシートとは、寄付者の性別や年齢、居住地、髪の状態などを記載する書類のことで、JHD&CのWebサイトで書式をダウンロードできます。
なお、ドナーシートの記入は必須ではなく、無理に全ての項目を埋める必要はありません。
5.髪の毛を発送する
髪の毛は美容室やサロンから発送することはできず、ドナー自身が個別に送らなければなりません。
カットした髪の毛を束にまとめてゴムなどで縛り、封筒に入れて発送します。ラップで巻く、台紙にテープで貼り付ける、髪の毛の切り口に接着剤を塗って束にするといった束ね方はNGのため注意してください。
なお、発送先は以下の通りです。
- 〒530-0022
- 大阪市北区浪花町13-38 千代田ビル北館7A
- NPO法人JHD&C事務局
または
- 〒640-8226
- 和歌山市小人町29番地
- 和歌山市あいあいセンター福祉交流館3F
- 和歌山市社協・ボランティアセンター内 白百合美容室係
まとめ
ロングヘアを思い切ってカットしようと考えている方は、社会貢献の一環としてヘアドネーションを検討してみましょう。
特に背中や腰のあたりまで伸びている長い髪は、医療用ウィッグを製作するための貴重な材料となります。
ヘアドネーションに賛同している美容室も多いため、近隣に対応してくれるお店がある場合には美容師へ相談してみましょう。
ストレスマネジメントとは?やり方や具体例を紹介

人間関係の悩みや仕事のノルマ、病気やケガなど、私たちが生活していくうえではさまざまなストレスを感じることが多いものです。
ストレスとは無縁の生活は理想ともいえますが、現実的に考えて一切のストレスを排除することは難しいのも事実です。
そこでぜひ実践していただきたいのが、ストレスと上手に付き合うためのストレスマネジメントです。本記事ではストレスマネジメントについて、やり方や具体例を紹介します。
ストレスマネジメントとは?

ストレスマネジメントとは、ストレスをうまく処理しながら付き合っていくことを指します。
私たちが社会生活を送るうえでは、仕事のプレッシャーや人間関係、家族・親族関係、子育てなど、さまざまなストレスが存在します。
あまりにも強いストレスがかかり続けると、メンタルの不調をきたしたりさまざまな病気の発症リスクが高まるといった問題が生じますが、一切のストレスから開放された生活を送るのは現実的に考えて難しいものです。
そこで、ストレスと上手に付き合っていくストレスマネジメントを理解し、実践することが求められるのです。
▶︎【ストレス解消】セルフケアとはなにか?意味・種類・方法について解説
人間がストレスを感じる仕組みや理由
ストレスマネジメントを実践するためには、そもそもなぜ人間はストレスを感じるのか、基本的なメカニズムを理解しておく必要があります。
ストレスとは、一言でいえば「ストレッサーが原因で引き起こされる心身のストレス反応」と表現できます。
ストレッサーとはストレスを引き起こす根本原因のことであり、それによって引き起こされるストレス反応もさまざまです。
主に以下のような種類に分けられます。
身体的ストレッサー
- 睡眠不足
- 身体の不調 など
心理・社会的ストレッサー
- 職場やプライベートの人間関係
- 残業
- 通勤
- 仕事のノルマ など
物理的ストレッサー
- 気温・湿度
- 明るさ
- 騒音
- 悪臭 など
科学的ストレッサー
- タバコ
- アルコール
- 薬物 など
環境的ストレッサー
- 天候
- ウイルス
- 花粉 など
また、主なストレス反応は以下に分類できます。
身体的反応
- 動悸
- めまい
- 不眠
- 食欲不振
- 頭痛
- 疲労感 など
心理的反応
- うつ
- 不安
- イライラ
- 集中力低下
- 物忘れ
- うっかりミスの多発 など
行動的反応
- 暴飲暴食
- 喫煙量の増加
- 暴言・暴力
- 性欲減退
- 生産性の低下 など
ストレスマネジメントとアンガーマネジメントの違い

心理学において「◯◯マネジメント」とよばれる概念は複数あります。そのなかでも、ストレスマネジメントと並んで耳にすることの多いのがアンガーマネジメントです。
アンガー(anger)とは日本語で「怒り」を意味する言葉であり、アンガーマネジメントとは怒りの感情を適切にコントロールする概念や手法を指します。
アンガーマネジメントと聞くと怒らないための方法と誤解されることが多いですが、あくまでも怒りをコントロールしながらうまく付き合っていくことを目的としています。
ストレスマネジメントもストレスをなくすものではなく、上手に付き合っていくための概念であることから、両者は似ている部分もあるといえるでしょう。
ただし、上記でも説明した通り、ストレスマネジメントは「ストレス」に対して、アンガーマネジメントは「怒り」という感情を対象としている点が決定的に異なります。
▶︎【怒りを抑える】アンガーマネジメントのやり方・テクニックをご紹介!
ストレスマネジメントを行う効果やメリット

ストレスマネジメントを実践することで、どういった効果が得られるのでしょうか。また、それによるメリットもあわせて解説します。
自分の状態を客観的に把握できる
毎日仕事をこなしていると、忙しさのあまり自分にストレスがかかっていることに気付かない人もいます。
ストレスマネジメントを行うことで自分を客観的に分析でき、ストレスの状態やその原因などが分かり、自身の生活を見つめ直すきっかけになるでしょう。
心身の健康を保てる
日々の生活のなかで大きなストレスがかかり続けていると、それが原因で心身に不調をきたすこともあります。
ストレスマネジメントに取り組むことで、心身に不調をきたす前の段階で適切な対処ができ、精神疾患や病気などのリスクを未然に防げるでしょう。
仕事の生産性やパフォーマンス低下を防げる
ストレスに気付かない状態のまま、あるいはストレスを我慢し続けた状態で仕事を続けていると、パフォーマンスが低下し本来の能力を発揮できないこともあります。
その結果、生産性が低下したり、ケアレスミスを連発して周囲に迷惑をかけたりすることもあるでしょう。
ストレスマネジメントを実践すれば、ストレスとうまく付き合いながら仕事をこなすことができ、生産性やパフォーマンスの低下を防止できます。
▶︎ストレスを発散させるメリットとは?解消方法と合わせてご紹介!
ストレスマネジメントの具体例

ストレスマネジメントは仕事やプライベートなど幅広いシーンで役立ちます。いくつか具体例をご紹介しましょう。
職場
ノルマや締め切り、プロジェクトの進行、職場の人間関係など、どのような職種であっても少なからずストレスは存在するものです。
ストレスマネジメントを実践することで、大きな目標やプレッシャーがかかるなかでもストレスとうまく付き合いながら業務を遂行でき、社内あるいは取引先などからも信頼を得られるでしょう。
恋愛
恋愛においては、交際中の相手と価値観や考え方が異なることでストレスを感じたり、交際そのものが長続きせず自己嫌悪に陥ったりすることもあるでしょう。
ストレスマネジメントを実践することで、相手の立場に立って物事を考えられるようになったり、相手と真正面から向き合うことでお互いを深く知る機会にもなります。
夫婦喧嘩
結婚して夫婦として生活をともにしていくと、恋愛とは別のストレスを感じることもあります。
たとえば、家事や育児などの役割分担を決めたとしても、相手のやり方や分担の割合などに不満を感じストレスになることもあるでしょう。そのような不満が蓄積していくと、やがて爆発し、夫婦喧嘩に発展する可能性があります。
夫婦でストレスマネジメントを実践することで、お互いにストレスが蓄積する前に話し合いながら不満を解消し、円満な関係を維持できるでしょう。
▶︎夫婦喧嘩をしたときに仲直りする方法は?子供への悪影響も解説
ストレスマネジメントのやり方
ストレスマネジメントは大きく分けて「セルフモニタリング」と「ストレスコーピング」という2つの方法があります。
それぞれの実践方法をご紹介しましょう。
セルフモニタリング
セルフモニタリングとは、自分自身の状況を客観的に把握する方法です。
- ストレッサーと感じるモノ・コト
- ストレスが生じたときに自分がどう感じているか
- ストレッサーによってどのようなストレス反応が出ているか
上記の項目をそれぞれ紙に書き出し整理することで、ストレッサーを明確化すると同時にどのようなストレス反応が現れているかを把握できます。
ストレスコーピング
ストレスコーピングとは、ストレッサーへ適切に対処することでストレス反応や負担を軽減する方法です。
【問題焦点型コーピング】
仕事のプレッシャーや残業などがストレッサーとなっている場合には、問題焦点型コーピングが有効です。
仕事量の調整や応援の要請など、問題に対して具体的な解決法・対策を立てていきます。
【情動焦点型コーピング】
起こっている問題そのものに対してではなく、自身の考え方や捉え方、気持ちなどを変えることで負担を軽減する方法です。
マイナスの側面ばかりでなくプラスの側面を注視したり、第三者へ相談に乗ってもらい不安や悩みを吐き出すといった行動が情動焦点型コーピングにあたります。
【ストレス解消(発散)型コーピング】
ストレス解消(発散)型コーピングは、その名の通り自分なりの方法でストレスを解消し、身体的な不調や心理的な負担を軽減する方法です。
睡眠や休養はもちろんのこと、運動やマッサージ、エステ、趣味を楽しむといった行為が代表的です。
▶︎仕事でストレスを感じたらやばい?原因や解消方法をご紹介!
まとめ
現代人にとってストレスとは無縁の生活を送るのは難しく、仕事やプライベートにかかわらずさまざまなストレスと付き合っていかなくてはなりません。
ストレスの感じ方も人それぞれで、なかにはストレスがかかっているのにそれに気付かないまま過ごしているケースもあるでしょう。
ストレスと上手に付き合いながら、仕事やプライベートを充実させるためにはストレスマネジメントを実践するのも有効です。
夫婦喧嘩でやってはいけないこととは?子供への悪影響も解説

夫婦生活を送っていると些細なことが理由で口論をしたり、夫婦喧嘩に発展することもあります。長く円満な夫婦生活が続く時期もあれば、「最近夫婦喧嘩が増えてきた」と感じる時期もあるのではないでしょうか。
そのようなとき、できるだけ早期に仲直りをするにはどういった方法があるのか、また、夫婦喧嘩が子供に与える影響なども併せてご紹介します。
よくある夫婦喧嘩の原因

夫婦喧嘩はどのようなことが発端で起こることが多いのでしょうか。
お互いの性格や考え方などによって原因はさまざまですが、典型的なものをいくつかご紹介しましょう。
家事の分担
共働き世帯が増えている昨今、特に多く聞かれるのが家事の負担割合などに関する夫婦喧嘩です。
たとえば、残業で帰宅が遅くなったにも関わらず、先に帰宅していた夫または妻が食事やお風呂の用意をしていなかったりすると口論になることも珍しくありません。
反対に、平日は仕事が忙しいからとはいえ、休みの日に家のことを一切何もせずゴロゴロしているだけの夫に妻が不満を募らせるといったケースもあるでしょう。
家計に関すること
結婚生活ではお互いの金銭感覚のズレが原因となって夫婦喧嘩に発展することもあります。
たとえば、ブランド物の洋服やアクセサリー、家電製品、趣味の物など、高額な商品を相談することなく購入するとトラブルに発展することもあるでしょう。
夫の行き過ぎた飲み会への出費やタバコ、パチンコ、競馬なども家計を脅かす要因となることが多いです。
子育てに関すること
子育てに関する方針や考え方の違いも夫婦喧嘩の原因となることがあります。
子どもの将来を思うあまり、本人が希望していないのに習い事や塾に通わせたり、進学先や就職先を決めたりするケースもあるようです。
もう一方の親が子供の意思を尊重したいというタイプである場合に、対立してしまうことが予測されます。
相手の話し方や態度
話を聞く真摯な姿勢が見られないと、自分の話をきちんと聞いてくれているのか不安になることもあります。
また、本人にそのつもりはなくても、相手のことを見下したり小馬鹿にしたような態度に見られることもあり、それが夫婦間に亀裂を生じさせるケースがあります。
家族や親族の問題
お互いの両親や親族などが原因で夫婦喧嘩に発展することも決して少なくありません。
たとえば、配偶者に対して相談をしないまま両親と同居することを決めたり、配偶者に対して自分の両親の介護を押し付けたりするケースが代表的です。
些細なこと
客観的に見れば些細なことが夫婦喧嘩の引き金になるケースは多いものです。
たとえば、自分のために買ってきた飲み物や食べ物を勝手に開封された、趣味のコレクションに勝手に触られた、間違って食器を割ってしまった、などです。
このようなケースでは、日頃の小さな不満が積み重なり、ある日突然些細なことが引き金となって夫婦喧嘩に発展することが多い傾向にあります。
▶︎夫婦仲が悪い原因は?子供に与える影響や改善する方法をご紹介
夫婦喧嘩で仲直りする方法

夫婦関係を円満に保つために、もし夫婦喧嘩が発生したらどのように仲直りをすれば良いのでしょうか。
自分から先に謝る
夫婦喧嘩が起こったとき、自分から謝るのは気が引けてしまい、ズルズルと不機嫌な態度を長引かせてしまうことがあります。
しかしたいていの場合、夫婦喧嘩はどちらかが一方的に悪いというわけではなく、お互いにそれぞれ原因があることが多いものです。客観的に自分を振り返り、悪い部分があった場合には素直に謝ることが大切です。
自分から話しかける・挨拶をする
喧嘩中はお互いに気まずい雰囲気になり、無視をしたり視線を合わせなかったりする時間が続いてしまいます。
このような状態を打破するためには、あえて自分から積極的に話題を振ったり挨拶をしたりすることも有効です。
たとえば、「おはよう」や「ただいま」、「今日のご飯は何が食べたい?」など、自然な日常会話を心がけましょう。
スキンシップをとる
素直な謝罪とコミュニケーションで心を開けるようになったら、スキンシップをしてさらに距離を縮めていきましょう。
たとえば、仲直りの印として握手をしたり、「ごめんね」と素直に謝ったうえでハグをしたりするのも有効です。
ただし、挨拶をしても相手が無視しつづけていたり、不機嫌な態度が続くようであれば無理なスキンシップは逆効果になる可能性もあるため注意が必要です。
相手の好きなものを買ってくる
誠意のある謝罪の仕方として、相手の好きなものを買ってくる方法もあります。
たとえば、ケーキなどのスイーツやお酒、あるいは外食に誘ってみるのも良いでしょう。
ただし、こちらもスキンシップと同様、謝罪の言葉がないままプレゼントだけを贈っても、「モノで釣ろうとしている」と感じられ逆効果になる可能性があるため注意しましょう。
▶︎夫婦関係は修復できる?よくある破綻のきっかけや修復方法を紹介
夫婦喧嘩で仲直りをするときにやってはいけないこと

上記とは反対に、仲直りをするためにやってはいけないNG行動をご紹介します。
自分を押し通す
夫婦喧嘩の原因がたとえ相手にあったとしても、自分が正しいことを押し通すような態度では平行線に終わってしまいます。
たとえば、自分も相手に対して言い過ぎた部分はなかったか、強い口調で相手を否定しなかったかなど、反省すべき点がないかを振り返ってみましょう。
相手を論破しようとする
激しい口論となったとき、相手を言い負かそうとする人もいるのではないでしょうか。
しかし、論理的に反論したり正論で相手を追い詰めたとしても、元通りの夫婦関係に戻れるケースはきわめて少ないでしょう。
相手が論理的には納得したとしても、感情の面ではさらに大きな亀裂を生じさせる可能性もあります。
重要なのは相手を論破したり正論で言い負かしたりすることではなく、お互いに歩み寄り相手を理解しようとすることです。
一時の感情で離婚を口にする
激しい夫婦喧嘩でヒートアップしてくると、感情に身を任せるように「離婚」という言葉を口にしてしまうこともあります。
夫婦間において離婚というワードは極めて重く、最後のカードともいえます。
それだけに相手の口から離婚の言葉が出てきてしまうと、それを聞いた瞬間に一気に熱が冷め、愛情が失われていく可能性があるでしょう。
▶︎モラハラ夫は特徴やどんな発言をする?対処法や子供への影響も解説
夫婦喧嘩が子供に与える悪影響

子どもがいる家庭で夫婦喧嘩が起こると、その姿を目にした子どもにさまざまな悪影響がおよぶおそれがあります。
具体的にどういった影響が考えられるのか紹介しましょう。
親に対する恐怖心が生まれる
普段は子どもに対して優しく接しているにもかかわらず、夫婦喧嘩が始まると口調や声のトーン、表情などが一変し、子どもにとっては全く違う一面に映ることがあります。
これにより、子どもは「自分のパパとママは怖い人なんだ」と感じるようになり、親に対する恐怖心が生まれてしまいます。
自分のせいで喧嘩をしているのだと感じる
多くの場合、子どもはなぜ夫婦喧嘩をしているのか原因が分からず、戸惑ってしまうものです。
また、自分を放置したまま口論している姿を見ると、子どもは「自分は大切にされていない」、あるいは「自分のせいで喧嘩をしているのではないか」と不安に感じるケースもあります。
その結果、両親に対して甘えることができなかったり、自分の心を閉ざしてしまったりする子どもも少なくありません。
心身の不調をきたす
夫婦喧嘩によって心に大きな傷やトラウマができると、心身にさまざまな不調をきたすケースもあります。
たとえば、自分は周りの人に愛されないと感じると、友達とうまく遊べない、あるいはコミュニケーションをとることすらできなくなる可能性もあるでしょう。
また、ストレスから頭痛や腹痛、吐き気などの症状が現れることも珍しくありません。
▶︎自己肯定感が低い子供の特徴や言動とは|注意すべき親の発言や行動
夫婦喧嘩をした後の子供に対するフォロー
子どもの前で感情的になり、夫婦喧嘩をしてしまったときにはどういったフォローが必要なのでしょうか。
もっとも重要なのは、子どもに対して真摯に謝ることと、気持ちを真正面から受け止めることです。
たとえば、「怖い思いをさせてごめんね」と謝った後で子どもを抱きしめたり、「あなたのせいで喧嘩をしたわけではないからね」と説明することも忘れないようにしましょう。
そのうえで、子どもが泣いている場合には「怖かったよね」、「嫌だったよね」といった言葉をかけながら、泣き止むまでその場を離れず寄り添ってあげてください。
まとめ
夫婦といえども自分の本心や考え方をすべて理解しているとは限らず、すれ違いが生じることで夫婦喧嘩に発展することもあります。
些細なことでの対立や喧嘩はどの夫婦にも起こり得るものですが、重要なのはいかに早く仲直りをして夫婦間の亀裂を修復できるかということです。
また、子どもがいる家庭では夫婦喧嘩がさまざまな悪影響を及ぼすことも考えられるため、子どもへのフォローも忘れないようにしましょう。
寂しさは自分と向き合うきっかけ。4つの解消法をご紹介

夫の転勤に伴って仕事を辞めた。
それから約1年半、私は子育てに専念した。
歩きたい盛りの子どもと一緒に公園に通う日々。今しかできない子育てを楽しんでいた。
しばらくすると、一緒に遊んでいたママ友たちが次々と育児休業を終えて復職していった。
子どもを寝かしつけた後、おもちゃで散らかったリビングを見渡しながらぼんやり考える。
「私はこのままで良いのかな」
「子どもが大きくなった時、私の人生はどうなるのかな」
当時の私は、社会から取り残されたような寂しさ、そして漠然とした将来への不安を感じていた。
寂しさは、誰しもが抱える当たり前の感情
寂しさは、人間にとって避けては通れない感情の1つ。
楽しそうに子育てをしている人も、仕事でバリバリ活躍している人も、お金に不自由せずに好きなものが何でも手に入る人でも、どんな人でも寂しさを感じる時があるのではないでしょうか。
寂しさは単なるネガティブな感情だけではありません。私たちが社会や他者と繋がり、理解され、愛されることへの自然な欲求から生まれるものであり、時に人の心を揺さぶり、自らを見つめ直すきっかけにもなるものです。
寂しさを感じた時の4つの解消法
美味しいものを食べて、たくさん寝て、まずは体を満たす
寂しさは時に、自分と向き合うきっかけにもなります。しかし、疲れが溜まっている時や、ストレスを抱えている時、ホルモンバランスが乱れている時などにもやり場のない寂しさを感じることがあるでしょう。
そういった時には、まずは心身のバランスを整え、ポジティブなエネルギーを取り戻すことが第一です。
家事を放り投げて寝てしまったり、お金もカロリーも気にせずに食べたいものを食べてみたり。そうすることで、翌朝には悩んでいたことが嘘のように、気持ちが切り替わっていることもあるでしょう。
寂しさの原因を言語化する
感情を言語化することは、寂しさと向き合う第一歩。
私は子育てに専念している時に感じた寂しさの根っこにあるものを紙に書き出してみました。
- 減り続ける自分の貯金残高。収入がないことが不安
- 夫の働いたお金で自分のものを買うことに気がひける
- 子育てや家事をしても、誰からも褒めてはもらえない。家事ができていないことを責められるのが辛い
- 子どもが成長した後、私には何が残るのだろう
出てくる、出てくる、寂しさの原因となる不安や不満が。その結果「働いて収入を得ること」が私の寂しさを解決することに繋がるという決断にいたり、再び働くことを決意しました。
自分の気持ちを言葉にすることで、その感情の原因となる問題や課題を具体的に捉えることができます。紙に書いたり、日記をつけたり、誰かに話を聞いてもらったりすることで、寂しさの解決策や対処法が見えてくるかもしれません。
他者に依存しない
他者への過度な依存は寂しさを強化する要因の1つと言えます。
例えば、子どもだけに依存していると、子どもが成長して巣立った後の人生に不安を感じるだろうし、子どもが大きくなって一緒にお出かけしてくれなくなった時に寂しさを感じるでしょう。
配偶者や恋人だけに依存していたら、メールの返信がないと強い不安にかられることや、相手がいない時に寂しさを感じることがあるでしょう。
そういったことを避けるためには、まずは自分自身と向き合い、内なる充実感を見つけることが大切です。中学校の頃に好きだったダンスをもう一度はじめてみるとか、美容に力を入れて自分磨きをしてみるとか、ブログをはじめて発信してみるとか。
他者に依存せずに自分自身が夢中になれることを見つけることで、自己満足感を高め、充実感を味わうことができるでしょう。趣味を通じて新しい仲間との出会いにも恵まれるかもしれません。
他者と比べない。SNSから遠ざかってみる
「隣の芝生は青い」ということわざがあるように、他者は自分よりも魅力的に見えるもの。自分と他者を比較することは、寂しさを引き起こす原因の1つになります。
特に、SNSが普及した今、他者の光り輝く瞬間を目にする機会が増えました。
「家族仲が良くて羨ましいな」
「あの子は子どもが生まれたんだ」
「あの子とあの子が遊んでいる。私は誘われていない」
「素敵なお家に住んでいるな」
など、他者がうらやましく思えることがありますよね。そういう時はSNSから距離を置くことも大切です。
そして比べるべきは他者ではなく、過去の自分。そうすることで、自己成長や喜びを感じ、他者との比較から生じる寂しさを軽減できるでしょう。

寂しさは自分と向き合うきっかけ
寂しさを感じることは、弱さや不完全さではなく、むしろ人間らしさの表れです。
寂しいという感情を避けるのではなく、むしろ受け入れ、向き合う。そうすることで、自分自身の内面の豊かさに気がつき、成長への一歩を踏み出すことができるでしょう。
寂しさが訪れた時には、目を背けるのではなく、その感情を探求し、内なる自分との対話を通じて、新たな可能性を見つけ出してみてください。
ストレスを解消するにはどうすればいい?ハグがおすすめな理由も解説

仕事や家事、子育て、人間関係など、私たちが生活するうえではさまざまなストレスの原因が存在します。
心身の健康を保つためにも、ストレスを感じたら溜め込まずに発散させることが大切ですが、いくつかの方法を試してみたものの効果が実感できず悩んでいる方も少なくありません。
そこで今回は、ストレス解消の正しい方法やポイントを中心に詳しく解説します。
人間がストレスを感じる仕組み

多くの人は、仕事やプライベートにおいてストレスを感じることがありますが、そもそもどういったメカニズムでストレスは生じるのでしょうか。
一言で表すと、何らかの事象や出来事が原因となってメンタルを圧迫し、心身に悪影響を及ぼすことでストレスを感じるようになります。
ちなみに、ストレスの原因となる事象や出来事、あるいはモノや人のことをストレッサーとよびます。
私たちが社会生活を送るうえで、ある程度のストレスはつきものといえますが、あまりにも強いストレスが加わるとその負荷に耐えられなくなり、心身ともに限界を迎えることもあるのです。
▶︎イライラして眠れないのはなぜ?原因や対処方法についてご紹介
ストレスを感じやすい要因とは

ストレスの原因となるストレッサーにはさまざまなものがあります。また、ストレスを感じる程度も人によって異なるほか、性別によってもストレッサーの傾向が異なることがあります。
具体的にどのようなことがストレッサーとなり得るのか、具体例を紹介しましょう。
仕事におけるストレッサー
仕事においてストレスの原因になりやすいものとしては、以下が代表的です。
- 長時間労働
- 高すぎる目標・ノルマ
- やりがいの少ない仕事
- 適性に合わない仕事
- 納期・締め切り・スケジュール
- 通勤・満員電車
- オフィスの環境(騒音・室温・湿度など)
- ハラスメント行為
- 部下の育成・指導
- 人事異動・転勤・昇進
上記は性別を問わず多くの人にとってのストレッサーになり得る内容です。一昔前までは、上司や先輩からの厳しい指導などが原因でストレスを感じる若手社員も多くいましたが、近年ではハラスメント対策に力を入れる企業も増えたことから、厳しい指導ができず部下の育成や指導に頭を悩ませる管理職側がストレスを抱えているケースも。
プライベートにおけるストレッサー
仕事以外に目を向けると、以下のようなストレッサーが代表的です。
- 家族や親類の不仲
- 子育て・介護
- 経済的困窮
- 金銭トラブル
- 近所付き合い
- 友人関係
- 恋愛
- 病気・怪我
- 不規則な生活
- 室内環境(騒音・室温・湿度など)
特に多いのが家族や親類、友人、近隣住民との人間関係で、些細なことが原因で不仲やトラブルに発展しストレスの根源となることもあります。
また、長引く不況によって経済的な困窮や金銭トラブルにつながることも多く、ときには自分一人では解決が難しくなるケースもあるでしょう。
▶︎仕事でストレスを感じたらやばい?原因や解消方法をご紹介!
性別によって異なるストレスの感じ方
男性と女性で分けて考えたとき、ストレスの感じ方やストレスとの付き合い方にも差が生じる傾向があります。
男性のストレスの感じ方
男性の場合は弱音を吐いたり他人に頼ったりすることでネガティブに捉えられるのではないかと感じ、本音を出しづらくなります。
ストレスをなかなか打ち明けられず内に溜め込んでしまうケースも多いことから、心身ともに限界に近づいた頃にやっと病院を受診する方が少なくありません。
女性のストレスの感じ方
女性の場合、対人関係を敏感に捉える方が多く、特に職場においては人間関係がストレッサーとなり退職につながるケースも少なくありません。
また、ストレスがホルモンバランスに影響を与えやすく、自律神経の不調や睡眠不足、生理不順などの症状に直結しやすいことも大きな特徴として挙げられます。
▶︎人肌が恋しいってどういうとき?意味や心理、対処方法をご紹介!
ストレスを発散させるメリット
ストレスを感じると心身にさまざまな影響を及ぼすことから、その前に発散することが大切です。
健康を維持できる
ストレス発散の最大のメリットは、心身の健康を維持できることです。
過剰なストレスがかかると、ホルモンバランスが乱れ自律神経に影響を及ぼし、睡眠不足や頭痛、便秘、下痢などの症状に悩まされることがあります。さらに悪化すると、脱毛や神経性胃炎など重篤な症状につながっていきます。
これらを防ぐ意味でも、定期的にストレスを発散することが大切です。
人間関係の改善
ストレスによってイライラや不安が増大すると、良好な人間関係を維持できなくなることもあります。
たとえば、家族や友人、知人などにイライラをぶつけてしまうことで、自然と自分の周りから人が離れていってしまいます。
しかし、適度にストレスを発散できていれば円滑なコミュニケーションがとれるようになり、人間関係に悩むこともなくなるでしょう。
ストレスを溜め込むデメリット

ストレスを発散するためにはさまざまな方法がありますが、誤った方法をとってしまうと逆効果になる場合もあります。
たとえば、飲酒や喫煙などは一時的に気持ちを和らげ、リラックスできたと感じることもありますが、過度に依存しすぎると体調を崩したり、さまざまな病気の発症リスクも高めることになります。
ストレス発散の正しい方法を身につけることが何よりも大切です。
ストレスを解消する方法とは

正しいストレスの解消法にはどのようなものがあるのでしょうか。日常生活のなかで手軽に実践でき、無理なく継続できる方法をいくつかご紹介しましょう。
屋外に出る
天気の良い日にはできるだけ外に出て、日光を浴びることを心がけましょう。日光を浴びることでセロトニンとよばれるホルモンの一種が分泌され、幸福で前向きな気持ちになります。
ストレッチ・運動
デスクワークが多く屋内で過ごす時間が多い場合には、長時間座ったままの姿勢を維持していると血行が悪くなりがちです。
そこで、こまめに立ったり散歩をしたりすることで運動不足を解消でき、さらにはセロトニンも分泌されやすくなります。
睡眠
睡眠不足はホルモンバランスの乱れにも直結し、ストレスをさらに悪化させる要因になります。そのため、十分な睡眠時間を確保し、睡眠の質を向上させることも大切です。
就寝前にはスマートフォンやPC、テレビなどを観ないようにしたり、体型に合った寝具選びも重要です。
趣味
趣味の時間をつくることもストレス解消につながります。仕事やプライベートで悩みを抱えていても趣味に没頭することで気分転換にもなり、ストレスを軽減できるでしょう。
ただし、ギャンブルやお酒などは逆効果であり、健康上の問題や経済的な困窮といった新たなストレスを生み出すリスクもあるため注意が必要です。
▶︎人肌が恋しいってどういうとき?意味や心理、対処方法をご紹介!
泣くことやハグはストレス解消になる?

意外と知られていないストレス解消法として、泣くことやハグなどもあります。
泣くことがストレス解消につながる理由
感動的な映画やドラマを観たり、美しい音楽を聴いたりしたとき、感情が揺さぶられ涙を流すことがあります。
このとき私たちの体内では副交感神経が活性化し、身体はリラックスした状態になります。
辛い出来事があったときでも、泣くことで気持ちがスッキリとした経験がある方も多いのではないでしょうか。
そのため、ストレスを強く感じて辛い気持ちのときは、感動的な映画やドラマ、音楽などに触れて徹底的に泣くことも効果的です。
ハグがストレス解消につながる理由
さまざまな不安によってストレスを感じている場合にはハグも効果的です。
恋人や家族、親友など、心を許せる人にハグをしてもらうと、安心感に包まれ癒されたり、不安が軽減したという経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
これは、好きな人や信頼できる人に包まれることで、私たちの体内ではドーパミンやオキシトシンとよばれる幸せを感じるホルモンが分泌されるためです。
そのため、ストレスによって押しつぶされそうになったとき、信頼できる人にハグをしてもらうようお願いすることもおすすめです。
▶︎スキンシップにはどんな効果がある?良好な関係性を維持するためのポイントとは
まとめ
私たちが生きていくうえでストレスは避けて通れないものであり、一切のストレスを感じたことがない人は存在しません。
適度なストレスは仕事のパフォーマンスを向上させるなどの効果もありますが、過度なストレスがかかってしまうと心身の健康に悪影響を及ぼすこともあるのです。
ストレスを解消する方法が見つからない、さまざまな方法を試してみたもののストレスが軽減できないという方は、今回紹介した方法を参考にしてみてください。
仕事でストレスを感じたらやばい?原因や解消方法をご紹介!

世の中にはさまざまな仕事がありますが、どんな仕事であっても少なからずストレスは感じるものです。ストレスの度合いが大きいと、体調不良などさまざまな症状として現れることもあるため、原因を理解し適切に対処することが大切です。
本記事では、仕事でストレスが溜まった際にどのような影響が現れるのか、ストレスの解消方法などもあわせてご紹介します。
仕事でストレスを感じる原因

仕事のなかでストレスを感じるのはどのような瞬間なのでしょうか。代表的な6つの原因をご紹介しましょう。
人間関係
特に多い原因として挙げられるのが職場における人間関係の悩みです。
たとえば、上司や先輩社員からハラスメント行為を受けている、同僚から仲間外れにされる、後輩から信頼されていないなど、人間関係の悩みにはさまざまなものがあります。
労働時間
長時間労働によってプライベートの時間が確保できないこともストレスの大きな要因になります。
最近では働き方改革によって残業時間が厳しく規制されるようになりましたが、職種や役職によっては依然として長時間労働を強いられているケースも少なくありません。
給与
仕事に見合った給与が貰えていないと、経済的に困窮し生活が立ち行かなくなります。その結果、「今の仕事を続けていても報われるのか?」と感じるようになり、将来に対する不安が増大しストレスが募っていきます。
仕事内容
人は誰でも向き不向きがあり、仕事の適性にも直結することがあります。自分自身の適性に合っていない仕事を続けていても、思うような成果が得られずストレスを感じることも少なくありません。
将来への不安
仕事を続けていくモチベーションは人によってさまざまですが、将来のキャリアプランもそのひとつに挙げられます。しかし、いくら頑張っても正当な評価を得られないと、昇進や昇給が見込めず将来への不安が増大していきます。
目標やミッション
多くの企業・組織では、持続的な成長を実現するために目標やミッションが設定されます。しかし、あまりにもそのハードルが高く非現実的な内容であると、「どうせ無理だろう」と諦めの気持ちが強くなり、仕事そのものがストレスに感じられるようになります。
▶︎イライラして眠れないのはなぜ??原因や対処方法についてご紹介
仕事でストレスを感じやすい人の特徴

仕事においてストレスを感じる背景には、上記で挙げた仕事内容や周囲の環境、待遇などが原因となっていることが多いですが、それらに加えて個人の性格や価値観、考え方などが影響している場合もあります。
どのような人が特にストレスを感じやすいのでしょうか。
責任感が強い人
仕事において責任感をもつことは大切なことですが、あまりにも責任感が強すぎると自分一人で全てを抱え込んでしまうケースもあります。
たとえば、自分が所属する課やチームのなかで大きなミスがあったとき、自分に大きな責任があると思いこんでしまいストレスを抱える人もいるでしょう。
また、責任感が強い人ほど上司や先輩、同僚などの周囲の人に相談できず、さらにストレスを増大させることもあります。
心配性な人
仕事において些細な失敗やミスも許されず、完璧に遂行しなければならないと考える人も少なくないのではないでしょうか。もちろんそのような心構えは大切なことですが、ミスを恐れるあまり同僚や部下に仕事を任せられず、自分ひとりで抱え込んでしまうケースも少なくありません。
特に心配性な人ほどこのような傾向が強く、知らず知らずのうちにストレスが増大していることも多いです。
感情をうまく表現できない人
人は生まれ育った環境や周囲の人の考え方や価値観、コミュニケーションの仕方など、さまざまなことが影響して人格や性格が形成されていきます。
なかには明るい性格の人もいれば、寡黙で感情の起伏が少ない人もいるでしょう。しかし、感情表現が苦手な人の場合、自分を押し殺してまで周囲の人に無理に合わせようとしてストレスを溜め込むこともあります。
▶︎社内で円滑なコミュニケーションを取るコツや活性化の成功事例を紹介
仕事でストレスを感じるとどんな影響が出るのか
仕事においてストレスはつきものであり、多くの人はストレスとうまく付き合いながら日常生活を送っています。しかし、あまりにもストレスの度合いが大きいと、精神や身体にさまざまな影響が現れることがあります。
精神への影響
ストレスによって現れやすいのが精神への影響です。
特に仕事が原因でストレスを感じていると、無意識のうちに「職場に行きたくない」、「辞めたい」といった言葉を発するようになります。
また、このほかにも些細なことでイライラする、他人から掛けられた何気ない一言が原因で気分が落ち込む、ちょっとした物音や光などの刺激が加わることで必要以上に驚いたり、緊張を覚えたりすることもあるようです。
このように、感情や感性が敏感になったと感じたときには、ストレスによる影響を疑ったほうが良いかもしれません。
身体への影響
ストレスが増大していくと、精神からやがて身体へと影響が拡大していくことがあります。
具体的な症状としては、頭痛や吐き気、眠れない(不眠)、その他原因不明の体調不良などが挙げられ、場合によっては鬱(うつ)と診断されることもあるでしょう。
体調不良や何らかの異常が現れたとき、ストレスが原因であると自覚できない人も少なくありません。そのような場合、注射や点滴、服薬などで治療を行ったとしても改善されず悩み続ける人も多いのです。
仕事のストレスがやばいと感じたときは

仕事のストレスが増大し、上記で挙げたような精神面や身体面への影響が出始め「やばい」と感じたら、できるだけ早めに病院を受診したり、産業医からのカウンセリングを受けたりすることが大切です。
このように自分自身で異常に気づき、必要な対処ができれば健全な状態を取り戻せる可能性は高いでしょう。
しかし、なかには仕事においてストレスを感じることは当たり前であり、休養をとったり病院を受診したりするのは「甘え」であると考える方もいます。また、ストレスそのものを自覚できず、そのまま放置してしまうケースも考えられるでしょう。
これは大変危険であり、場合によっては重度のうつ病を発症したり、睡眠障害や胃潰瘍といった病気を発症するリスクもあります。
仕事において適度なストレスやプレッシャーがあることでパフォーマンスが向上することは事実ですが、過度のストレスによって何らかの症状や悪影響が現れた際にはしっかりと治療やカウンセリングを受けることが欠かせないのです。
▶︎ストレスを発散させるメリットとは?解消方法と合わせてご紹介!
仕事のストレスを解消する方法について

仕事のパフォーマンスを向上させるためには、ストレスとどのように付き合い、解消していけば良いのでしょうか。おすすめのストレス解消法や軽減の方法を紹介します。
些細なことでも相談する
仕事のストレスは小さなことが積み重なって増大していき、やがて自分では抱え込めない状態に達することもあります。
このような事態にならないためにも、同僚や上司、部下などに気軽に相談できる関係性を構築しておくことが大切です。
仕事を分担・協力してもらう
仕事量があまりにも多くストレスを感じている場合には、同じ課やチームのなかで仕事を分担し協力してもらうことも大切です。
特に、課内やチーム内のメンバーで業務量に偏りが生じている場合には、上司へ相談し、仕事を割り振ってもらうことで負担が軽減されるでしょう。
このとき重要なのは、単に仕事を押し付けるのではなく、相手のことを信頼しているからこそ大切な役割を任せたいと伝えることです。これによって仕事に対するやりがいを感じられるようになり、良好な関係が構築されます。
適度な運動を心がける
デスクワークで長時間座ったまま仕事をしていると、気持ちが停滞しストレスが蓄積されていきます。そこで、適度な休憩を挟みつつストレッチや散歩など運動を心がけることでストレスが低減されます。
食事を楽しむ
仕事仲間と食事を楽しむのもストレス解消において有効な方法のひとつです。
仕事の場面では厳しい顔を見せる人も、プライベートな場面では穏やかで優しい一面が垣間見られることもあるでしょう。人間性を理解するうえでも、食事をともにする時間は大切にしたいものです。
食事と一緒にお酒を楽しむ場面も多いと思いますが、過度にアルコールを摂取してしまうと健康上のリスクを増大させ、新たなストレスや不安の原因になる可能性もあります。
また、お酒の席での失敗が人間関係を悪化させる要因になる可能性もあることから、あくまでもお酒は適量を心がけましょう。
▶︎ノンバーバル(非言語)コミュニケーションの重要性とは?一例も紹介
まとめ
仕事内容や職場の人間関係、職場の環境など、仕事におけるストレスの原因となるものはさまざまです。ストレスが一切存在しない仕事や職場は極めて稀であり、多くの人はストレスとうまく付き合いながら仕事に励んでいます。
しかし、ストレスの度合いが強すぎると仕事に悪影響を及ぼすことも事実であり、ときには体調不良など身体的な症状となって現れることもあります。
このような事態を防ぐためにも、ストレスによって何らかの異常が現れたときには、早めに病院を受診することが大切です。
イライラして眠れない時はどうする?原因や対処方法を解説

ストレスが溜まりイライラしていたり、不安や悩みを抱えていたりすると、ベッドや布団に入っても眠れないことがあります。
このような不眠や睡眠不足に悩む人は多く、なかには睡眠導入剤などが手放せないほど重症化するケースも。
本記事では、イライラして眠れないのはなぜか、根本原因として考えられることや、安眠を手に入れるための対処法も含めてご紹介します。
イライラして眠れない原因

ベッドや布団に入ってもイライラが続き、なかなか眠りにつけない、あるいは眠りが浅く慢性的な睡眠不足に陥ってしまうのはなぜなのでしょうか。考えられる4つの原因をご紹介します。
周囲の環境
寝つきが悪い、睡眠が浅くぐっすり眠ることができない理由として、周囲の環境が起因しているケースがあります。
たとえば、家の外を走る車やバイク、電車などの騒音が大きい部屋や、街灯や看板の光が差し込む明るい環境はイライラの原因となり、睡眠を妨げてしまいます。
ストレス
イライラの原因として特に大きいのがストレスです。たとえば、職場の人間関係や仕事への重圧、経済的な問題、将来への不安など、ストレスの根本原因にはさまざまなものがあります。
また、仕事をしていない専業主婦や定年退職を迎えた方であっても、旦那や妻、親、子どもをはじめとした家族との関係によってはストレスを抱え、ぐっすりと眠れないこともあります。
ホルモンバランスの乱れ
特に女性に多い悩みとして挙げられるのがホルモンバランスの乱れによって生じる不眠です。
ホルモンバランスが崩れると些細なことでイライラするようになり、さらに不眠の症状を悪化させることもあるでしょう。
また、女性の場合は生理やその日の天候、生活習慣などが原因となることもあります。
精神疾患
うつ病や適応障害、パニック障害といった精神疾患も不眠の症状を引き起こすことがあります。
ストレスやホルモンバランスの乱れが悪化することで精神疾患に至るケースがあり、その代表的な症状の一つが不眠です。
精神疾患は決して特別なものではなく、生活環境やその人の性格や考え方などによって誰にとっても発症リスクがあります。
イライラして眠れない日が長期間にわたって続いている場合には、精神疾患の可能性も考えたほうが良いかもしれません。
▶︎ストレスを発散させるメリットとは?解消方法と合わせてご紹介!
イライラして眠れないとどんな悪影響が出るのか

睡眠不足に悩む現代人は多く、「自分だけではないはず」と安心している方も多いのではないでしょうか。
しかし、イライラによって眠れない日が続くと、さまざまな悪影響が出てくることがあります。
慢性的な疲労
本来、睡眠は日中の活動によって蓄積した疲労を回復する役割があります。しかし、睡眠不足や浅い眠りが続いてしまうと横になったとしても疲れが取れず、慢性的な疲労を感じるようになります。
具体的には、朝起きたときに全身に倦怠感が残っていたり、身体のさまざまな部位に痛みや違和感が持続的に残ったりすることもあります。
集中力・注意力の低下
睡眠は肉体的な疲労だけでなく、脳の疲労も回復するという重要な役割があります。
私たち人間は日中の時間帯にさまざまな活動を行い、視覚や聴覚などから膨大な情報を得ています。これらの記憶を整理するためにも睡眠は不可欠な行為といえるのです。
しかし、十分な睡眠がとれないと脳は十分な休息をとることができず、日中の時間帯に集中力や注意力の低下を招くこともあります。
免疫力の低下
睡眠の最中には成長ホルモンが分泌されており、私たちの身体をつくったり、自己修復を促したりする役割を果たします。
しかし、十分な睡眠がとれていないと成長ホルモンの分泌が阻害され、免疫力が低下していきます。
その結果、身体の成長スピードが遅くなったり、病気にかかりやすくなったりする可能性もあるのです。
精神疾患の悪化
睡眠不足はうつ病や自律神経失調症、適応障害といった精神疾患の代表的な症状であり、多くの人が悩まされています。
不眠をそのままの状態で放置しておくと、疲労が蓄積するなどしてメンタルの調子も崩しやすくなり、さらなる精神疾患の悪化を招くことも。
「うつ病などの病気が治れば睡眠不足も自然と治るだろう」と考えるのではなく、まずは不眠の状態を改善することが大切です。
▶︎仕事でストレスを感じたらやばい?原因や解消方法をご紹介!
イライラして眠れないときのNG行為は?

イライラとした気持ちが先立ってしまい寝つきが悪いとき、ついやってしまいがちな行動が眠りを妨げている可能性もあります。
具体的にどういった行動が逆効果なのか、NG行為の一例をご紹介しましょう。
スマホの画面を見る
眠れないときに、ついやってしまいがちなのがスマホやタブレット端末などを操作する行為です。
たとえば、SNSや動画サイト、電子書籍などを見ているうちに眠くなることもありますが、多くの場合は明るい画面を見ることで交感神経が刺激され、興奮や緊張状態を招きます。
そのため、就寝の数十分前にはできるだけ部屋を暗くし、スマホやタブレットには一切触れないことが大切です。
「早く寝なければ」と焦る
翌朝早く起床しなければならないのに深夜までなかなか寝つけず、気持ちが焦ってしまい翌朝まで寝られなかったという経験はないでしょうか。
質の良い睡眠は身体がリラックスしている状態が不可欠であり、「早く寝なければ」という焦りの気持ちが出てしまうと身体も緊張し、さらに寝つけないという悪循環に陥ってしまいます。
特に時計を頻繁に見ると焦りの気持ちが増幅することから、身体をリラックスさせ時計には意識を向けないことが大切です。
飲酒
どうしても寝つけないとき、つい頼ってしまいがちなのがお酒です。
少量のアルコールを摂取すると、一時的には身体がリラックスして眠くなることは事実です。
しかし、アルコールには利尿作用があるほか、アルコールを体内で分解する過程で交感神経が刺激され、途中で覚醒することがあるのです。
また、身体は休息できていたとしても、脳は十分な休息がとれずに疲労が蓄積することもあります。そのため、イライラして眠れないときでも就寝前の飲酒は避けたほうが良いでしょう。
▶︎人肌が恋しいってどういうとき?意味や心理、対処方法をご紹介!
イライラして眠れないときの対処法

イライラとした感情が湧いてきて寝つきが悪いとき、どのようにすれば安眠を手に入れられるのでしょうか。有効な対処法をいくつかご紹介します。
運動やスポーツで身体を動かす
良質な睡眠を確保するには身体をリラックスさせることが不可欠です。そのために有効なのが、日中の時間帯に運動やスポーツを行って身体を動かすことです。
これにより、適度な疲労が生まれベッドや布団に入ったときに入眠しやすくなるでしょう。
ちなみに、運動の時間がとれない方や運動が苦手な方は、就寝前に軽いストレッチや筋力トレーニング、散歩などをしてみるのもおすすめです。
入浴時間を考慮する
入浴は副交感神経を刺激し、リラックス効果を高める働きがあります。
ただし、長時間にわたって熱すぎるお湯に浸かったりシャワーを浴びたりすると逆効果なため、38℃前後のぬるま湯に浸かってじっくり身体を温めることを意識してみましょう。
なお、安眠効果を高めるためには就寝の1時間半から2時間前を目安に入浴するのがおすすめです。
リラックス効果のある食べ物を摂取する
眠れないときには温かいミルクを飲むのが良いとされていますが、これ以外にもリラックス効果を高め、スムーズな眠りに導く食べ物があります。
主にたんぱく質やビタミンB群、マグネシウムなどの栄養素が効果的とされており、たとえばバナナや豆乳などが該当します。
寝具の見直し
生活習慣に気をつけているにもかかわらず、なかなか安眠効果が得られない場合には、寝具が合っていない可能性も考えられます。
枕やマットレス、布団などは、自分の体型に合った寝具を選ぶことが大切です。また、体温が下がると睡眠の質も低下してしまいます。保温性が高く、全身をカバーできる寝具を選びましょう。
▶︎一人暮らしは寂しい?孤独を感じる瞬間や寂しさを解消する方法を紹介
まとめ
毎日決まった時間にベッドや布団に入っているにもかかわらず、イライラして眠れないと悩んでいる方は少なくありません。
特に、翌朝早い時間に出社しなければならないときや、予定が入っているときに眠れないと気持ちが焦ってしまい、さらに眠れなくなってしまいます。
このような悪循環を断ち切るためにも、できるだけリラックスした状態でベッドや布団に入ることが大切です。
不眠や睡眠不足に悩んでいる方は、今回紹介した対処法を参考にしてみてください。
一人暮らしは寂しい?孤独を感じる瞬間や寂しさを解消する方法を紹介

大学への進学や就職・転職など、人生の転機ともいえるタイミングで一人暮らしをスタートする方は少なくありません。
しかし、環境が大きく変化するなかで慣れない一人暮らしを始めると、不安や孤独感、寂しさを感じる方も多いものです。
本記事では、一人暮らしのなかで寂しさを感じる瞬間やその原因、寂しさを解消するための方法もあわせてご紹介します。
一人暮らしを始めたばかりの方はもちろん、これから一人暮らしを検討している方も、ぜひ参考にしてみてください。
人が孤独を感じる原因

人は誰でもふとした瞬間に孤独や寂しさを感じるものです。なぜこのような気持ちを抱くのか、考えられる原因をいくつかご紹介しましょう。
人との関わりが少ない
人は自分一人で生きていけず、さまざまな人と関わりをもちながら生活を営んでいます。身近なところでは親や姉弟、親戚、学校の友人、職場の仲間などが挙げられます。
しかし、極端に人との関わりが少ない生活を送っていると、社会から取り残されたような錯覚に陥り孤独を感じることがあります。
他人と比較してしまう
人は良くも悪くも他人と比較してしまいがちです。たとえば、交友関係が広い友人や、若くして結婚し子どもを授かった人を羨ましく感じることもあるでしょう。
一方、自分自身に目を向けたとき、友人の少なさや結婚相手に巡り会えないことに引け目を感じ、孤独感に苛まれることがあります。
環境の変化
進学や就職、転勤など、さまざまな事情によって周囲の環境が大きく変わることがあります。それまで仲の良かった友人とも離れ、一から交友関係をスタートさせなければなりません。
しかし、周囲に知らない人が多いと関係を築くまでに時間がかかるほか、慣れない環境に対する不安もあって孤独感を増長させてしまいます。
熱中できるものがない
交友関係の広い人は、仕事や学校以外にもスポーツや音楽、釣り、ゴルフなど、趣味のコミュニティに属しているケースが多いです。
しかし、このように熱中できるものがないと休日に誰とも会う予定がなく、仕事以外のコミュニティがないため孤独を感じやすくなります。
セロトニン不足
セロトニンとはホルモン物質の一種であり、気持ちを前向きにさせたり幸福を感じさせたりする働きがあります。
セロトニンは太陽の光を浴びることで生成されますが、たとえば天気が悪く外出ができないときや、家の中に籠もったままだと孤独を感じやすくなります。
また、運動不足もセロトニンの分泌を減少させる要因になります。
▶︎人肌が恋しいってどういうとき?意味や心理、対処方法をご紹介!
一人暮らしで寂しいと感じる瞬間

一人暮らしをしている人は特に孤独感や寂しさを感じやすい傾向があります。どのようなシーンで寂しさを感じることが多いのか、具体的な事例をいくつかご紹介しましょう。
帰宅したときに誰もいない
仕事や学校から帰宅したとき、家族がいれば部屋の明かりが点いていたり、「おかえり」と声を掛けてくれます。
しかし、一人暮らしの場合は自分で明かりをつけ、声を掛けてくれる人もいないため、慣れないうちは孤独や寂しさを感じてしまうこともあるでしょう。
一人での食事
食事は一人で摂るよりも、家族や友人など大勢で食卓を囲んだほうが美味しく感じられるものです。また、その日あった出来事や共通の話題で盛り上がれるため、孤独や寂しさを感じにくくなるでしょう。
しかし一人暮らしの場合、仕事帰りにコンビニやスーパーなどに立ち寄って食材を購入してから帰宅し、家で一人食べることも多いため、孤独や侘しさを感じてしまいやすいです。
イベントや行事を一人で過ごすとき
クリスマスや年末年始、父の日・母の日、お盆など、一年を通してさまざまなイベントや行事があります。
多くの家庭では、それぞれのイベントに合わせて豪華な食事を家族で囲みますが、一人暮らしの場合はそのような機会がなかなかありません。
友人を自宅に招いてパーティーや食事会を開くこともありますが、家庭をもっている人はなかなか誘いづらいこともあるでしょう。
また、仕事が忙しいと実家に帰省する時間や経済的な余裕もなく、一人暮らしの孤独感を一層倍増させてしまいます。
体調を崩したとき
風邪やインフルエンザなどの病気や、骨折や捻挫などの怪我をしたとき、自宅で安静に過ごさなければならないケースもあるでしょう。
同居する家族がいれば食事の用意や洗濯、お風呂の準備などの身の回りの世話をしてくれますが、一人暮らしの場合は全て自分でこなさなくてはなりません。
また、体調が悪化すると「自分に万が一のことがあった場合、異変に気づいて助けてくれる人はいるだろうか」と不安な気持ちになりがちです。
一人暮らしが寂しくて泣いてしまう理由
大学への進学や就職、転職などのタイミングで一人暮らしをスタートさせたとき、猛烈な孤独感や寂しさを感じ泣いてしまう方も少なくありません。
なかには、一人暮らしに憧れていたにもかかわらず、いざアパートやマンションに一人になると自然と涙がこぼれてくる人もいます。なぜこのような感情になるのでしょうか。
慣れない環境で不安がある
特に大きい理由として挙げられるのは、環境が大きく変わることです。
実家からアパートやマンションへと引っ越すことで住環境が変わり、今まで当たり前にいた両親や兄弟とも別々に暮らさなくてはなりません。
家を出るときに「いってきます」、帰宅したときに「ただいま」と声を掛けても反応がないと、あらためて一人であることを実感し寂しさを覚える方も多いようです。
また、環境の変化という意味では、住環境だけでなく職場や学校などの違いも大きいでしょう。
特に学校を卒業して新社会人として一人暮らしを始めたときには、自分を取り巻くあらゆる環境が変わることで一層の不安を感じるようになります。
相談できる人がいない
孤独感や不安、寂しさを感じていたとしても、それを気軽に相談できる人が身近にいれば気持ちが楽になるものです。
しかし、家族や友人に対して「一人暮らしをしてみたい」といったことを口にしていた場合、後になって寂しいと弱音を吐くことに気が引けてしまい、辛い気持ちを自分ひとりで抱え込んでしまう方もいます。
あまりにも精神的な負担が増大してしまうと、自分自身ので心の整理がつかなくなり、自然と涙がこぼれてくることがあります。
一人暮らしで寂しさを感じたときの解消方法

慣れない一人暮らしは孤独感や寂しさがつきものです。しかし、どうしても寂しさが解消できず精神的に落ち込んでしまう場合、どのような解消方法があるのでしょうか。
笑って明るい気持ちを取り戻す
寂しさや孤独感は笑うことで解消できることが多いです。
精神的に落ち込んでいるときに無理に笑顔をつくるのは辛いことですが、お笑い番組やマンガ、映画などを観て現実を忘れて笑ってみるのもひとつの手といえるでしょう。
外に出かける
寂しさや孤独感はセロトニン不足によって引き起こされることもあります。どうしても前向きな気持ちになれないときには、意識的に外に出かけるようにしましょう。
外出に抵抗がある場合には、カーテンと窓を開けて室内で日光浴をしてみるのもおすすめです。
趣味を見つける
熱中できるものがなく、休日になると部屋の中に引きこもりがちになる方は、趣味を見つけるのもおすすめです。
たとえば、映画館に立ち寄って最新の映画を楽しんでみたり、ライブハウスやフェスなどに行って音楽を楽しんでみるのも良いでしょう。
映画館やライブに一人で参加するのは抵抗がある方も多いと思いますが、一人だからこそさまざまな人との交流がしやすく、同じ趣味を持つ者同士で人脈が広がっていきます。
自分から積極的に話しかけてみる
コミュニケーションが苦手な人見知りの方は、どうしても自分から話しかけにくく、交友関係を築くのに時間を要することが多いと思います。
しかし、相手も同じようなことを思っているケースも多く、勇気を振り絞って自分から話しかけることで一気に打ち解け、会話が弾むものです。
そのため、相手から話しかけられるのを待つのではなく、自分から積極的に話しかけてみましょう。初対面の場合、自己紹介から入ると自然に会話のラリーを続けやすいでしょう。
本心を正直に打ち明ける
一人暮らしで寂しい気持ちを打ち明ける際には、古い付き合いの友人や家族など、信頼できる人がおすすめです。
弱みを見せるようで相談しにくいと感じる方もいるかもしれませんが、あえて素直な気持ちを言葉に出すことで本気で心配してくれ、親身になって相談に乗ってくれるはずです。
また、そのような相談をすることで一層絆が強くなり、これまで以上に強固な信頼関係を構築できるでしょう。
▶︎スキンシップにはどんな効果がある?良好な関係性を維持するためのポイントとは
まとめ
一人暮らしに憧れを抱く人は多いですが、実際にアパートやマンションで生活をスタートすると孤独感や寂しさを強く感じるようになるものです。
これはその人のメンタルの弱さや脆さが引き起こすものではなく、周囲の環境や気候、時期なども影響します。
一人暮らしに寂しさを感じたときには、できるだけ明るい気持ちになれるよう意識的に笑顔をつくることや、積極的に外に出てさまざまな人とコミュニケーションをとることが有効です。
それでも自宅に帰ると寂しさが襲ってくることも多いため、家族や親友など、信頼できる人に本心を打ち明ける勇気も大切です。
一人暮らしが寂しいと感じるのは決して特別なことではなく、当然の心理といえるでしょう。また、一人暮らしに慣れていくと寂しい気持ちも軽くなっていき、自分のペースで快適な生活を送れるようになります。
それまでの不安定な期間を乗り切るためにも、今回紹介した内容を参考にしてみてください。
人肌が恋しい女性心理とは?対処方法をご紹介!

肌寒い季節や大型のイベントシーズンを控えた時期、あるいは幸せそうなカップルや夫婦を見たときなど、ふと「人肌が恋しい」と感じたことはないでしょうか。
なぜ私たちは人肌が恋しいと感じるのか、その深層心理を探るとともに、人肌が恋しいと感じたときの対処方法もご紹介します。
人肌が恋しいの意味とは?

秋から冬にかけて肌寒さを感じるようになると、「人肌恋しい季節」などと表現されることがあります。
「人肌が恋しい」という言い回しはこれ以外にもさまざまな場面で耳にすることがありますが、本来どういった意味で使われる言葉なのでしょうか。
そもそも「人肌」とは、人の肌という直接的な意味を指すものではなく、人の温もりや体温などを意味します。
たとえば、握手をしたときやハグをしたときなど、自分以外の人に直接触れると温もりがあり、安心感を得られるものです。
すなわち、人肌が恋しいというのは、信頼できる人や愛する人の温もりを感じることで、不安や寂しさを払拭し安心感を得たいという心理を指す言葉といえるでしょう。
特に、秋から冬にかけて寒くなると日照時間が少なくなり、私たちの体内で生成されるホルモンの一種であるセロトニンも減少しがちになります。
セロトニンが減ると不安や寂しさを感じやすくなることから、寒い季節には物理的に温もりを感じるだけでなく、安心感も得たいという心理が働くのです。
▶︎一人暮らしは寂しい?孤独を感じる瞬間や寂しさを解消する方法を紹介
人肌が恋しくなる瞬間

人肌が恋しいという言葉はさまざまなシーンで使用されますが、具体的にどういった場面が多いのでしょうか。
肌寒い季節
冒頭でも紹介した通り、秋から冬にかけて肌寒さを感じるようになると、孤独感や寂しさが押し寄せてきて人肌が恋しくなることがあります。
特に、12月から1月にかけてはクリスマスや年末年始と大きなイベントが控えていることもあり、一層人肌が恋しくなる傾向があります。
体調を崩したとき
風邪やインフルエンザにかかったときや、重い病気にかかって入院を余儀なくされたときなど、人は誰しも不安を感じるものです。
自分に寄り添ってくれる人がいれば不安も低減されるため、身体が弱っているときほど本能的に人肌が恋しくなります。
精神的な疲労が溜まっているとき
精神的な疲労も人肌が恋しくなる大きな要因になります。たとえば、仕事や勉強を頑張っているのに誰からも評価されないと、自分の存在意義が分からなくなり不安や寂しさ、虚しさが増大します。
そのようなとき、そばにいて見守ってくれたり、認めてあげる人がいれば精神的にも救われることから、人肌が恋しいと感じるようになります。
失恋したとき
精神的な疲労とも関連が高い項目ですが、失恋したときも人肌が恋しくなる傾向があります。
特に、信頼していた恋人に裏切られて別れた場合、精神的なダメージは図り知れず、一人では立ち直ることが難しいため誰かに寄り添ってもらいたいと考えるのは当然のことです。
また、実際に付き合ってはいなかったとしても、自分の想いが相手に届かなかった場合、ショックが大きく人肌が恋しいと感じるようになります。
身近な人が交際・結婚したとき
近年では男女ともに価値観が多様化しており、なかには結婚を望まない人も少なくありません。一方で、良縁に恵まれなかったり、経済的な問題などで結婚したくてもできない人も多く存在します。
そのような人にとって、兄弟や親友、同僚など、身近な人が結婚し幸せな家庭を築くと、猛烈な寂しさや孤独感を感じ人肌が恋しくなることがあります。
将来の不安を感じたとき
現代は社会が大きく変化しており、将来を見通すことが難しい世の中になっています。
経済的な問題はもちろんのこと、災害や感染症、テロ、戦争など、社会を根幹から揺るがす大きな出来事がいつ発生してもおかしくない状況にあります。
万が一の事態が発生したとき、一人で生きていくのは極めて困難であり、ときには誰かの助けが必要になることもあるでしょう。
将来のことを考えると、強い不安感を覚え人肌が恋しくなる人も少なくありません。
▶︎スキンシップにはどんな効果がある?良好な関係性を維持するためのポイントとは
女性が人肌恋しくなる心理

「人肌が恋しい」という言葉を聞くと、自分に対して好意を抱いている、あるいは助けを求めているのではないかと感じる人も少なくありません。
男女によって深層心理は異なることが多いですが、具体的にどのような違いがあるのでしょうか。まずは女性が人肌恋しくなる心理を考えてみましょう。
好意を抱いている
女性から「人肌が恋しい」という言葉を聞くとドキッとする男性も多いと思います。女性のなかには、意中の男性に振り向いてもらうためにこのような言葉を伝える方も少なくありません。
特に女性は男性に対して積極的にアプローチしたり、直接的な言葉で好意を伝えたりするのが苦手な人もいます。
必ずしも好意を寄せられているというわけではないでしょうが、少なくとも悪くは思われていないと考えて良いでしょう。
精神的な不安を抱いている
「人肌が恋しい」という言葉はさまざまな意味に捉えられるため、必ずしも好意を伝えているとは限りません。
たとえば、仕事で大きなミスをしたり、プライベートでショックな出来事があったとき、不安を覚え誰かにそばにいてほしいと感じることもあるでしょう。
そのようなとき、信頼できる人にこのような言葉で伝える人もいます。
イベントシーズンを控え寂しさを感じている
クリスマスや年末年始などの大型イベントを控えた時期になると、一人でいることに不安や寂しさを覚える方も少なくありません。
そのようなとき、異性同性を問わず自然と「人肌が恋しい」という言葉が出てくることもあります。
▶︎生理後は性欲が強くなる?生理周期別の性に関する過ごし方を紹介
男性が人肌恋しくなる心理
男性の場合、どのような心理で「人肌が恋しい」という言葉を使用することが多いのでしょうか。
基本的には、女性と同様に好意を伝える手段や、精神的な不安や寂しさを訴える言葉として使われることが多いようです。
ただし、その人とどのような関係性であるかも重要なポイントとなります。たとえば、恋人や友人、兄弟、同僚など、信頼している間柄では上記のような意味合いとして使われることが多いでしょう。
しかし、初対面の人や久しぶりに会った友人、顔見知り程度の人など、十分な信頼関係が築かれていないにもかかわらず、「人肌が恋しい」といった言葉を掛けてくる男性は、下心がある場合も多いです。
いきなりこのような言葉をかけてくる男性がいたら十分注意し、場合によっては距離をとることも考えましょう。
人肌が恋しくなったときの対処方法

さまざまな事情によって人肌が恋しいと感じた場合、寂しさや孤独感、不安を紛らわせるにはどのような対処方法が有効なのでしょうか。
仕事を入れる
プライベートの悩みや寂しさを抱えているときには、それを忘れる手段として仕事に没頭する人も多いです。
シフトや残業などで仕事量を調整できる場合には、あえて仕事を多めに入れて余計なことを考えないようにするのもおすすめです。
運動をする
人肌が恋しいと感じているときは、精神的なストレスが蓄積していることが多いです。
ウォーキングやジョギング、筋力トレーニング、ストレッチなど、適度な運動をすることでストレスや不安感が解消され、前向きに考えられるようになります。
美味しいものを食べる
運動をした後は、美味しいものを食べたり適量のお酒を楽しむのもおすすめです。
気の合う友人や家族など、信頼できる人を食事に誘って楽しむことで孤独感や寂しさが解消され、気分転換にもなるでしょう。
趣味に没頭する
プライベートが充実していないと人肌が恋しく感じやすいものです。特に休日になると一歩も外から出ず引きこもっている方は要注意です。
できるだけ外に出て、時間を忘れて没頭できる趣味を見つけることで寂しさが解消されます。
寝る
夜になると寂しさや孤独感は増大し、特に人肌が恋しいと感じるようになります。
そのため、できるだけ早めにベッドに入り、考え事をする前に寝るのもひとつの方法です。
入眠前にはスマホの画面を見ず、入浴後90〜120分程度でベッドに入るとリラックスした状態になりスムーズに眠れます。
▶︎ストレスを発散させるメリットとは?解消方法と合わせてご紹介!
まとめ
仕事やプライベートが充実していても、ふとした瞬間に「人肌が恋しい」と感じることはあります。
その人の性格や考え方、生活環境、季節など、さまざまな要因が考えられますが、悲観的になりすぎると悪い方向へ進んでしまいます。
また、異性から「人肌が恋しい」と相談されたとき、捉え方を間違えてしまうとさまざまな誤解を生んだりトラブルに発展したりすることもあるでしょう。
人肌が恋しいと感じたときには、仕事や趣味に没頭したり、ストレスを解消するなどして適切に対処することが大切です。
オフザマットヨガ「ヤマ・ニヤマ」を 知って自分らしく生きよう(後編)

Photo by Nguyen Thu Hoai on Unsplash
今回は、前回の『オフザマットヨガ「ヤマ・ニヤマ」を知って自分らしく生きよう(前編)』でご紹介した『ヤマ』に引き続き、『ニヤマ』についてのお話です。
ニヤマは勧戒(かんかい)を表す言葉で、わかりやすく言うと「すべき行い」といったところでしょう。「心地よく生きたい」ということは誰しもが願うこと。心地よさを外側に求めることも多い現代ですが、実は心地よさは自分の中にあるということを、ニヤマを実践することで気づくことができます。
今の自分にもっと満足したい、平安な暮らしを送りたい、他人と比べる生き方から卒業したいという方はぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
シャウチャ(清浄)
必要なものなのかそうではないのか、あるいは、食事や生活習慣によって体の内側をきれいにし、心の清浄をしていくことを指します。
例えば、イライラしていている時、部屋の中を見回して見て下さい。散らかっていたり、埃がたまっているなんてことも多くないでしょうか。(筆者はよくあります)気持ちが不安定な時には、まずは身の回りの整理整頓や、掃除をしてみると、気持ちがスッキリし、それだけで満たされた気分になることも。
食べ物も同じで、ジャンクフードばかり食べていると罪悪感を感じたり、体が重くなったりすることもありますよね。一方で体が喜ぶもの、必要としているものを選択することで体も清浄され、軽やかさや疲れが取り除かれるなんてこともあるかもしれません。
サントーシャ(知足)
サントーシャは、満足すること。日本語で言う「足ることを知る」と同義で、今ここにあるもので満足すること、そして目の前で起こっている出来事や人、事実をありのままに受け入れることを指します。人は満足心を知らない限り、ずっと何かを求め続けます。何かを求め続けるということは、心が休まることから遠のくことになります。
特に現代では、SNSで他人と比べることも少なくありません。「○○さんは、あれを持っている」「○○さんは、こんな生活をしている」など欲望を掻き立てられることも決して珍しくありません。しかし、まずは自分がすでに充分満たされていることを知り、感謝することが、このシャントーシャの考え方です。
「あれが足りない、これも欲しい」を「あれもある、これもある」と言い換えてみるとよいかもしれません。また、1日1回、誰かに感謝する習慣をつけるのも良い行いです。
タパス(苦行)
苦痛は、多くの人が避けたいと思うものかもしれません。一方で、ヨガでは苦痛を引き起こす原因や振る舞い、感覚をありのままに受け止めることが勧められています。つまり、人生の様々な困難や問題を受け入れる強さを養うことを指しています。ここでポイントとなるのが我慢や諦めではなく、自分で納得して受け入れること。
苦痛の内容によっては時間がかかることもあるかもしれませんが、今あるもの、環境、人間関係は何らかの理由があって、必然的におきていること。例え苦しくても、これを乗り越えたら、きっと今よりももっと強く、更に満たされた自分になれることを忘れないでいましょう。
スワディヤーヤ(読誦)
読誦とは、必要なことはすべて、もともと自分の中にあるということ、それに気づくプロセスを指します。つまり、気づきをくれる本を読み、得た知識を実践して、人として成長していきましょうということ。
毎日学ぶ姿勢を忘れずにいれば、人は必ず新しい発見や気付きを得ることができます。それが自分自身の成長に繋がり、心地よい暮らしへと導いてくれます。
ちなみにヨガでは、色々な本を読むよりも、1冊の本を何度も繰り返し読むことが勧められています。知識量は多い方が良いと言われることも多いですが、心地よく生きていくために必要なことは、量ではなく質ではないでしょうか。1度読んだ本でも、2度目、3度目と回数を重ねていくことで理解が深まりますし、その時々の状況によって響き方も変わってくるのも同じ本を読み続けることの醍醐味です。
イシュワラプラニダーナ(神への祈念)
イーシュワラは「宇宙を動かしているもの」、プラニダーナは「自分を明け渡すこと」を意味します。「神様に祈りを捧げて、全てを受け入れること」と言うと分かりやすいかもしれません。
自分は一人だけの力で生きているわけではないことを、神への祈りを通して実感し、謙虚な姿勢を忘れないでいましょう。
例えば、インドでは呼吸は神様から与えられたギフトとされています。当たり前ですが、呼吸ができなければ、私たちは生きていけませんよね。自分が生かされている、存在していることは、すべて自分だけではなく多くの人や動植物、環境などのおかげ。当たり前のことほど見落としがちになってしまいますが、そういったことに気づかせてくれる、自分なりの神への祈りとなる習慣を身につけると良いでしょう。祈りを習慣にすることが難しい場合は、例えば毎朝呼吸を意識したヨガの練習(太陽礼拝がおすすめ)や呼吸法、呼吸に意識を向けた瞑想などもGoodです。
不安なきもちとの上手なつきあい方
*この記事は、社交不安症(ソーシャル・エンザイアティー)を経験したアメリカ人の筆者の記事をもとにしたものです。

ごく日常的な場所でこんなことはありませんか?
例えば、スーパーに買い物に行った時。
シャンプーを選ぶのに時間がかかりすぎている自分をみんなが変な人だと思って見ているかもしれない。ずっと買い物かごが空っぽの状態でこの人は何をやっているんだろうと思われているかもしれない。レジに並びながら、あちらのレジのほうが進み具合が早いけど、あちらに行ったら優柔不断だと思われるかもしれない。
こんな風に、人に見られている場面で何かをすることをとても不安に感じることはありませんか? 批判されたり間違ったことを言っていないかと不安になり、人と関わることを避けがちになるこの社交不安症、最近は日本でも耳にするようになりました。
でも、私たちはこんな不安に支配される必要はないんです。ちょっとしたコツをつかめば、社交不安症の人も満足のいく社会生活を送ることができます。その方法を紹介したいと思います。
自分の内面をよく見てみる
内面への働きかけは、社交不安症に対処するのに大切ですが、これは簡単なことではありません。なぜなら、たいていの場合、他人からどう見られているかを気にしなくなるには時間がかかりますし、自分ではどうしようもないことに不安を感じていることが多いからです。
内面をよく見るためには、自分の思考や感情、リアクションにあなたがもっと注目することが不可欠ですが、これには、かなりの練習が必要となります。その点で、瞑想やマントラを唱えることは、自分自身をグラウンディング(自分と地球のつながりを感じてエネルギーのバランスを取ること)させ、気持ちを落ち着かせるのに役立つでしょう。
不安を感じたときにぜひくり返してほしいおすすめのフレーズがあります。
「他人がどう思うかなんて気にしていない」
実際、私は他人がどう思っていようが、私が喜ぶことをするほうが好きなんだとやっと気づいた時に、この言葉の重みを改めて強く実感しました。このフレーズを自分に言い聞かせることで、私は不安になった時にこの自分の軸に立ち戻ることができるのです。
自分に語りかけるフレーズは自分に合ったものを自分で作ればいいんです。不安な思考がまたぶり返して戻ってくることはありますし、社交不安が完全に消えなくてもいいんです。自分の意識を内側に向ければ向けるほど、不安の度合いは対処しやすくなっていくでしょう。
一緒にいて安心できる友人を見つける

社交不安症の人は、友だちが多すぎると精神的に疲れがちです。その代わり、信頼できる小さな友達の輪を持っていればそれで良いのです。そういう友達は、社交的な場でも、あなたがある程度のスペースを必要としていることをわかってくれています。
人と距離を置いたり、友人との予定をキャンセルすることは、相手に対して失礼だと思う必要はありません。自分自身を主張することは、健全な人間関係のために必要なセルフケアです。そして、あなたが必要とするスペースを友だちが理解してくれるとき、あなたは大切にされていて安全な場所にいるのだと安心することができるでしょう。
とはいえ、信頼できる友だちを見つけることは難しいことです。新しい友だちを作るときは、自分の興味や慣れ親しんだ空間に身をゆだねてみましょう。例えば、いつも行くカフェの店員さんが世間話を始めたら、いつもより少し長居して、その会話の行く末を見守ってみましょう。または、会社の同僚があなたと気が合いそうな友達を紹介すると言ってきたら、それに素直に応じてみましょう。こうやって日々のちょっとした新しいことを受け入れることで、ささやかながらも満足のいく社会生活を送ることができます。
いつでも退出できるようにする
これは、社交不安症の人に対する一番のアドバイスです。例えば、あなたが人と会う時には、すぐにその場を離れることができるような公共の場やカフェのようになじみのある場所でするようにしましょう。プレッシャーを感じたり辛くなりそうだったら、その場を離れることができるとわかっていれば、安心して気持ちのコントロールができます。
こういう「逃げられる」手段を用意しておくことを恥じるべきでないし、その手段を実際に使うことも恥じるべきでありません。イベントに30分しかいられなかったとしても、それでいいんです。実際にイベントに顔を出して、不安と向き合っただけであなたは褒められるべきがんばりをしたのです。
自分に優しくする
社交不安が思うようにすぐに解消されないとしても、それはまったく普通のことです。「それは、あなたが目に見える結果が出るのを欲するあまり、改善を急ぎすぎたからかもしれないし、社交の場でもっと練習をしたほうがいいということかもしれない」と精神科医のドーン・ポッター博士は指摘する。
パニック発作であれ何であれ、何が反応の引き金になったのかを後からしっかりと確認することも大切です。「どうすればそのことについて違う考え方ができるか、どうすれば次にその状況を変えることができるか、こういうことを考えてみましょう」とポッター博士は提案する。「例えば、コンサートで大勢の人に囲まれてパニックになったとしましょう。次回は、後ろや通路側の席に座るとか、不安を感じたら、出口の近くに行くなどです」
ポッター博士は、一般的に人は他人のことなどそれほど考えていないとも言います。「私たちは、次に自分が何を言おうか、自分が何をしようか、そうやって自分のことを考えるのに忙しいのです」「あなたが自分について強く感じている不安な要素は、他人にはほとんど目立たないことであることが多いのです」
周りのサポートを受け入れる

社交的な場面で不安を感じ、助けが必要かもしれないことを周りに認めるのは、恥ずかしく屈辱的なことかもしれません。特に友人や恋人に、特別なサポートが必要かもしれないと伝えることは、大きな支えになります。「人は親しい人と社交的な場所にいれば、より快適に感じるものです」とポッター博士は言う。
親しい相手と一緒にいることは、社会不安症の人が時間をかけて自立していくのを助けることになります。信頼できる友だちや家族が、社会不安のあるあなたを自然に会話に引き込んであげるという方法もあります。「ああ、サラがそのテーマについて何か言いたいことがあるみたいだよ。彼女はそのトピックに興味があるみたい」こうやってあなたの殻を破ってくれることで、あなたをサポートすることができるでしょう。ただし、社交不安症の人は、自分が何か言わなければならない状況に追い込まれるのを嫌がることがありますから、事前に話し合っておきましょう。
日本のこれから
社交不安の症状を訴える日本人の割合は、アメリカ人のそれと比べると8分の1と少ないという調査もでています。これには、会議や授業では上司や先生など人の話を聞いていればよかったという日本の社会的背景があるのかもしれません。
ただ、そんな日本も、職場や学校などの生活で自分から発言することが重視される社会へと変化しています。そんな時に不安を感じることがあれば、自分に対して優しく、他人との比較をやめ、周囲のサポートを受け入れて充実した人間関係を築いていくことが、社交不安を乗り越える道となるでしょう。
参考:
・https://www.thegoodtrade.com/features/how-to-deal-with-social-anxiety/
・https://health.clevelandclinic.org/how-to-overcome-social-anxiety/
五感五行美容とプラネタリーヘルス 地球があなたを美しくする『プラネタリーヘルス』

この世界は全て調和で成り立っています。私たちの身体も実は地球と一体なのです。
この考えに基づいた『プラネタリーヘルス』とは、地球全体の健康を守るための「答え(解決策)」を見つけ、私たち人間の健康も含めてサポートする取り組みのことです。これには、私たちの意識や行動を変えて、地球や地球上の生態系との関係を考えながら、社会が適切な形で進んでいく姿を探求することが含まれます。
この「人と地球のエコシステム」のために、私が長年とりくんできた美容活動でできることは、人間の健全な健康と美を維持することだと考えています。
わかりやすい例を出してみましょう。私たちの体は、地球の状態が変わることで影響を受けます。例えば、気温や湿度の変化が体調やお肌に影響を与えることがあります。環境が壊れると、フロンなどの物質がオゾン層を破壊し、皮膚がんのリスクが高まります。だから、私たちは日焼け止めを使うことの重要性に気づき、皮膚を守るという意識も高まっています。地球が壊れると、私たちの体や肌も影響を受けやすくなるのです。
ここで、私の長年の経験で生まれた五感五行美容メソッドについて簡単に説明させてください。このメソッドは東洋医学が元になっています。ここでいう五感とは、視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚という感覚機能で、外の世界を感じるのに使います。また、五行というのは、木・火・土・金・水の5つの元素から成り立ち、このバランスが身体や肌の基盤となっています。
身体は小宇宙と考えられ、ツボの数も365で、1年と同じ数字になります。東洋医学では、全てが陰と陽の調和というサイクルで動いていると考えられています。つまり、私たちの身体は、地球上のさまざまなものと共存しているのです。
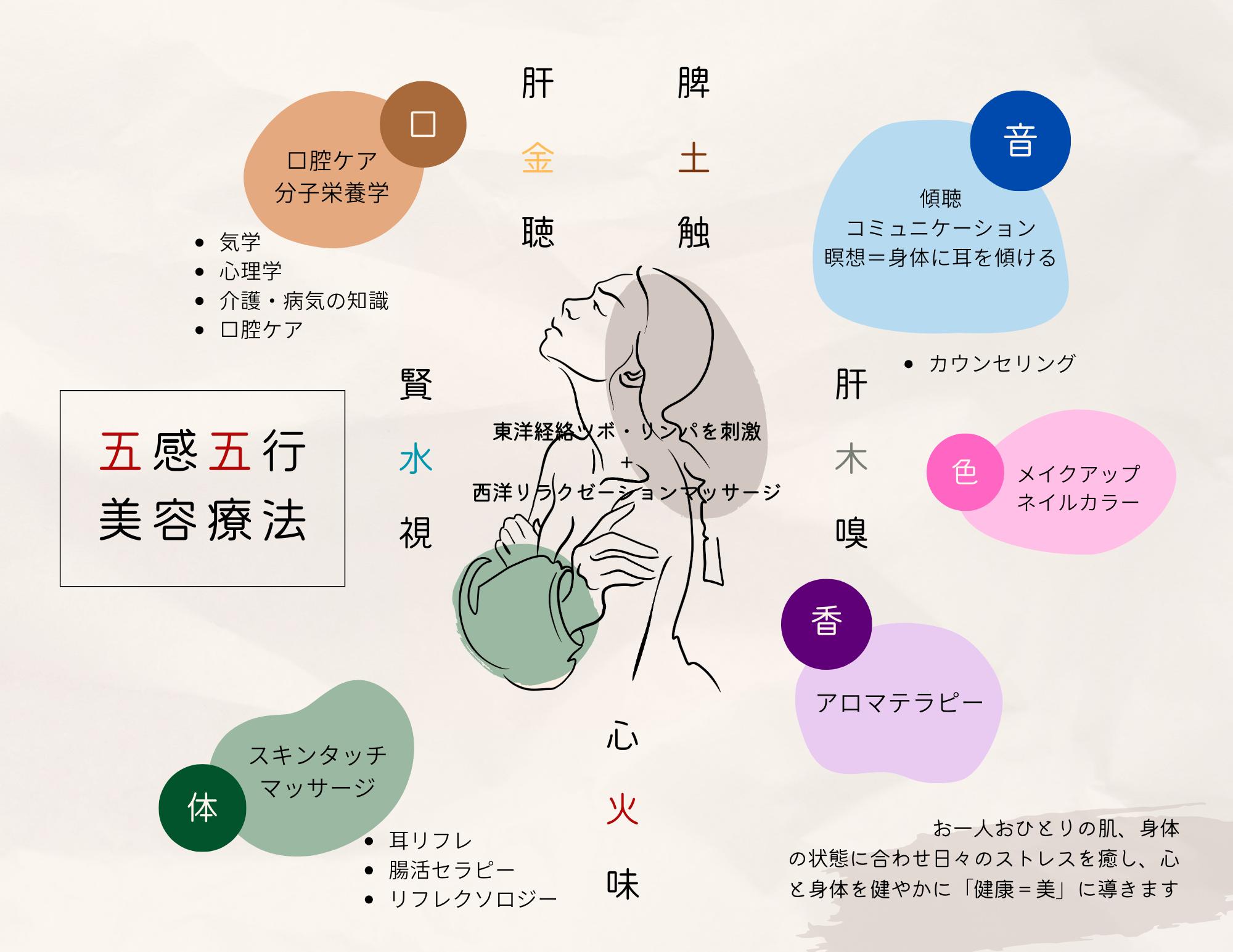
私たちの身体が共存しているもののひとつに細菌があります。なかでも土壌菌は人間の体の中心となる「腸」と最も深い関係があります。
人間の腸の中には、腸内フローラと呼ばれる細菌が住んでいます。この腸内フローラは、私たちが生きていく上で欠かせないものです。腸の中では、悪い影響を与える菌(悪玉菌)、良い影響を与える菌(善玉菌)、中立の影響を与える菌(日和見菌)のバランスが保たれており、これが物質代謝や免疫調整に関与し、健康な身体を維持しています。
ところが近年、農薬などによって土の栄養が失われ、野菜の栄養価が減少する問題が深刻化しています。野菜に土がついた状態で買うことも少なくなってきました。このような状況が、新たな腸のトラブルであるリーキーガットやシーボの発生と関係があるのかもしれません。地球の状態が悪化していることも、これに影響している可能性が考えられます。
五行の理論で言うと、土は身体の中で胃と脾臓(ひぞう)に対応します。胃は「顕在意識」であり、自覚的に意識して働く部分です。一方で、脾臓は「潜在意識」とされ、自覚できない意識や行動に関係します。顕在意識は自分で意識して行動することができますが、潜在意識は自覚できない心や行動に影響を与えます。
胃が「表」、脾臓が「裏」とされる理由は、胃が外から見える部分であり、脾臓が内側に位置しているためです。口の中の口腔内細菌叢(こうくうないさいきんそう)は、消化管の入り口に位置し、腸内フローラに影響を与え、人間の健康維持に大きく関わります。細菌は地球と人体をつなぐ役割を果たしており、そのバランスが地球と人体の健康に良くも悪くも影響を与えるのです。
地球環境を含めた栄養を考えて、身体と地球の循環を大切に考えなければなりません。
東洋医学では、私たちが親から受け継いだ先天的なエネルギーと、食べたものや周囲の環境から得る後天的なエネルギーの2つが重要視されています。しかし、現代では遺伝子を変えることが可能な時代になりました。
これらすべてが「食事と環境」に関係しています。環境を壊さず、共存できるように心掛けることが、地球の健康であり、私たち自身の美と健康につながっていくと考えています。
子どもの自由な発想を生かして正解!【Editor’s Letter vol.05】

「朝ご飯できたよー!」
「ママー、今日はサンドイッチ作ってランチボックスに入れてー。」
「今日は誰がアフターケアだっけ?お稽古事は何時から?」
朝のどこか慌ただしい会話の中、静かに三女が2階から降りてきたと思うと、キッチンカウンターに座わり用意されていた朝ご飯を黙々と食べ始めました。なんだか食べずらそうで、動きがぎこちない。
よくよく見てみると、靴下を足にだけではなく、手にもはいているではありませんか。私はその滑稽な姿にクスクスと笑いをこらえるのに必死でした。なんでそんなこと思いつくのかなー笑
自分のあたりまえを押しつけない
きっと以前の、まだ長女だけを育てていた過去の私だったら、「靴下は足に履くものでしょう。汚いからご飯のときに手にはめて食べないよ。」なんて言っていたのではないでしょうか。
こんなに自分を笑わせてくれるユーモアにも気がつかずに・・・。「靴下が汚い」という概念は私が38年間生きてきた中で培った概念。
決してそれを子どもの自由な発想の中に植え付けるということはしなくてもいいのです。
いつかこの子が汚いと思ったらやめればいいし、誰も他にやっている人がいないから恥ずかしいと思ったらそのタイミングでやめたらいいんだと思います。
そして、それが好きな好意だったら少し変わってるけど、飽きるまでずっと続けたらいいだけのことです。
そんな小さなことに、いちいち目くじらを立てなくてもいいと気がつけたのは、アメリカにある小さな、そしてとてもリベラルなこの町に移住して、まわりのママ友たちや義理の母が、子供たち一人一人を大人と同じように、尊敬し、尊重した接し方をする、その姿を何度も何度も見せてくれたからです。
シュタイナー教育でいつも言うのは「子どもは模倣の生き物」。
真似っこが大好きな子どもたちだから、大人や親が、こんな風に食事をしたら素敵だと思う姿やマナーで日々食事をしていたら、いつかはそれが子どもたちの身についているのだよと教えてくれました。
だから、言葉であーでもない、こーでもないと小言を言うな、というわけです。
でも、それがなかなか難しいのです。
何度も言いすぎては、「ママ、言いすぎちゃった。本当はこういうふうにもっと短く丁寧に言えばよかったね。次はそうするね。またチャレンジしてみる。」これの繰り返し。

そっと見守るだけで良い
それでも母親になって11年目。不安や疑問はたくさんあっても、自分の信じる子育ての道を試行錯誤、右曲折しながらも進んできて、やっと自分のスタイルの育児が見えてきたなーと思うのでした。
完璧じゃないかもしれないし、日本の周りの人たちから見たら常識外れなのかもしれない。
でも、誰よりも、娘たちと真正面から向き合っているという自負と、何があっても最後まで子供たちの気持ちと行動を受け止めるという母としての覚悟があるから今の自分の子育てに揺るがない自信があるのだと感じます。
子供は子供らしくいさせてあげたらいい。育て急がなくていい。大きくなるのはゆっくりとそれぞれのペースでいい。
だから親って漢字は「立ってる木の影から見る」と書くのです。
育児は、そっと黙って見守ってあげたら良いのであって、その子の人生の主人公である子供本人に取って変わって、自分の価値観を声だかに、また常識という名の社会の価値観を代弁してまでコントロールをしなくても良いのです。
どんなに守ろうとしても子供たちは社会の波に揉まれて自分を形成していくのだから、先を見越して、こうならないように、ああならないように、と親の不安感で子供を縛り付けなくてもいいし、もっともっと自由に育ったら素晴らしと思っています。
それに、心配事の9割は起こらないというではありませんか。
起こるか起こらないかわからない、自分の頭の中の想像力、予想力で作られた心配事でがんじがらめにされながら生きても、自分も子どもも幸せにならないな、とつくづく最近思うのです。
ハッピーになれる場所で休憩しよう
本当に子供のためを思っての言葉がけなのか、それとも自分の不安感や恐怖感、トラウマからきているものなのか?それも常に見極めることが大切です。
私は、小言をぐちぐち子供たちに言い出してしまったら「ママ、イライラしてきてしまったみたいだから、少し黙るね。」と言って子供たちから距離をおく。
子供たちも、「あ、オッケー」と言って私をそっとしておいてくれる。
また、姉妹喧嘩がはじまった時も、「優しい言葉が出てこないみたいだから、それぞれのハッピーになれる場所へ行って、ハッピーになったら戻ってこよう」という。
そうすると、喧嘩も4割はエスカレートせずに済みます。
自分が行動で示して、子どもたちにもリマインドをする。これの繰り返し。
私の家の合言葉は”Happy Kids Do Better”(幸せな子どもたちはより良く行動します)です。
自分自身に置き換えてみても、上司などに叱られてしょぼんとしている時より、「君を信じていくからね。できる限りを尽くしてみてほしい。」と言われた方がやってみようという気持ちが湧いてきませんか?

子育ての答えは自分の中
子どもたちの気持ちやモチベーションも同じだと思うのです。
周りの人と比べて劣るところを指摘されてばかりより、以前の自分と比べて成長したり変化したりした部分に気がついてもらえた方が、さらに工夫してみよう、もう少し努力してみようと自然に思うものです。
最近なんだか小言が多いな、ついつい頭ごなしに叱ってしまうな。
そう思うようになったら、一度立ち止まって、バイブルのように読み込んでいる育児本を再度覗き込んだり、通っているシュタイナーの学校の先生に相談してみたり、自分の日記を読み返してどうやって乗り越えたっけ?と思い出してみたりして、気持ちを切り替えてまた子どもたちと向き合うようにしています。
子育てには終わりも答えもないから本当に面白い。
結局必ずと言っていいほど、答えはすでに自分の中にあるんですけどね。
「子育ては自分育て」というけれど、本当にその通りだなと思います。
真摯に向き合えば向き合うほど、自分が育つな、と感じます。
精一杯の愛をくれる子どもたちに同じくらい精一杯の愛で応えたいから、今日も一日、工夫工夫をこらしながら、言葉を大切に選びながら、失敗してキレたりもしながら、過ごしたいと思います。
夫婦仲が悪い原因は?子供に与える影響や改善する方法をご紹介

結婚したばかりの頃は円満であったにもかかわらず、時間の経過とともに夫婦仲が悪化していくケースは珍しくありません。
「最近夫と会話をしていない」、「妻から無視されるようになった」など、悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。
本記事では、夫婦仲が悪くなるのはどういった理由が考えられるのか、改善するための方法やポイントもご紹介します。
夫婦仲が悪くなる原因・理由

夫婦仲が悪化する原因はさまざまで、なかには些細なことがきっかけで不仲になるケースも少なくありません。典型的なのが以下のような原因です。
生活のすれ違い
共働き世帯の場合、夫婦それぞれの勤務形態や労働時間が異なるケースも多いため、休日や帰宅時間などがずれてしまい、夫婦生活にすれ違いが生じることがあります。
たとえば、朝起きたときに夫がいない、夜帰宅しても妻が残業のため一人で食事を摂ることが多いなど、顔を合わせる時間が減っていくと、「なんのために結婚したのだろう」と感じ夫婦仲が悪化することもあるでしょう。
浮気歴がある
夫または妻のいずれかに浮気歴や不倫歴がある場合、それがきっかけで夫婦仲に亀裂が入ることが多くあります。
一方、一度は浮気や不倫を許したものの、時間の経過とともに不満が溜まっていき、些細なことがきっかけでケンカの原因になるケースも少なくありません。
家事や育児の負担
家事や育児の負担割合も夫婦仲を悪化させる要因のひとつになり得ます。
たとえば、夫の立場では十分家事を行っているつもりでも、実際にはその大半を妻が担っているケースは珍しくありません。
子どもがいる家庭の場合、夫が普段育児をできず妻に頼らざるを得ないことも多いです。
義実家との関係性
夫または妻の両親と良好な関係性が構築できていないと、それがストレスとなり夫婦仲を悪化させる原因になることもあります。
たとえば親の介護が必要になり義両親との同居生活が始まると、夫または妻の一方にばかり負担が押し付けられ、夫婦仲が悪化するケースも考えられるでしょう。
経済的な問題
長引く不況の影響もあり、共働きであるにもかかわらず経済的に困窮する家庭も少なくありません。
その結果、「別の人を選んでいたら余裕のある生活が送れていたかもしれない」と考えるようになり、夫婦仲が悪くなることもあるでしょう。
価値観の違い
お互いに異なる人生を歩んできた二人が夫婦として共同生活を送るとなると、些細なことで価値観や考え方に違いが見られることもあります。
一つひとつは小さいことでも、それが積み重なっていくと大きなストレスになり、夫婦仲に亀裂を生じさせる原因にもなるでしょう。
▶︎モラハラ夫は特徴やどんな発言をする?対処法や子供への影響も解説
仲が悪い夫婦の特徴

夫婦関係はそれぞれの家庭によって異なるため、第三者から見て一概に不仲と断定することはできません。しかし、夫婦関係に亀裂が入り仲が悪い夫婦には、共通して見られる特徴もあります。
すべてのケースに当てはまるとは限りませんが、典型的な特徴をいくつかご紹介しましょう。
笑顔が少ない
夫婦仲が悪くなると、お互いに嫌悪感を覚えるようになり、一緒に暮らすことがストレスに感じてきます。その結果笑顔を見せることが減り、つねに無表情か不機嫌な態度を見せるようになります。
夫と妻両方がこのような態度を示すこともあれば、どちらか一方が不機嫌な態度で接するケースもあります。
会話がない
笑顔が少ないだけでなく、会話を交わすこともストレスに感じるため、自然とコミュニケーションが減っていきます。
また、夫か妻いずれかが話しかけても、一方が無視をするなどして会話が成り立たないことも少なくありません。
セックスレス
子どもの誕生などがきっかけで、夫が妻のことを女性として見られなくなる、あるいはその反対のケースもあります。
お互いのことを異性というよりも家族の一員として見るようになり、セックスレスに陥る夫婦も多いようです。
また、夫または妻はセックスを求めているのに、相手はそれに応じてくれないというケースもあります。
その結果、円満な夫婦関係が維持できなくなり、不仲に陥る夫婦も少なくありません。
喧嘩が多い
長い夫婦生活を送る過程で、お互いの嫌な部分が見えてくるようになることもあるでしょう。
新婚当初はお互いを尊重し許せていたことも、家族の一員として見るようになるとストレスに感じ、やがてケンカに発展してしまうケースもあります。
日常的にケンカが続くようになると「これ以上の結婚生活に耐えられない」という結論に至る夫婦も少なくありません。
▶︎セックスレスの原因とは?|なりやすい夫婦の特徴や解消法を解説
夫婦仲が悪いまま一緒に暮らす悪影響

夫婦仲が悪化した状態でも、別居や離婚といった結論が出せず躊躇してしまう夫婦も少なくありません。しかし、かといって夫婦仲が悪いまま同居を選択しても、さまざまな悪影響が考えられます。
仕事のパフォーマンス低下
家庭は本来、安らぎを感じリラックスできる場です。しかし、夫婦仲が悪いと家庭のなかでもつねにストレスを感じ、精神的に安らぐことができません。職場でも家庭の不安が頭をよぎり、仕事に集中できなくなるでしょう。
その結果、仕事で単純ミスを頻発したり、仕事中に居眠りをしたりとパフォーマンスの低下を招くおそれがあります。
健康面への影響
本来、精神的な安らぎの場である家庭がストレスの根源になってしまうと、現実逃避のためアルコールに頼ってしまう危険性があります。
その結果、重度のアルコール依存症となり、健康を害するリスクも高まるでしょう。
また、うまくストレスが発散できない状態が続くとメンタルの不調をきたし、うつ病や統合失調症などを発症するリスクも高まります。
熟年離婚の可能性
夫婦仲が悪い状態が続いたとしても、子どものことを考え離婚を踏みとどまる夫婦は少なくありません。
しかし、子どもが成長し独立すると、あらためて自分自身の人生を見つめ直すきっかけになり、結果として熟年離婚にいたるケースも多いのです。
▶︎セックスレスになると離婚率が上がる?レスにならないための方法とは
夫婦仲が悪いと子供にどんな影響を与える?

夫婦仲の悪化は当事者である夫婦2人の問題だけではありません。特に子どもがいる場合、重大な悪影響を及ぼす可能性があるのです。
夫婦間で日常的にケンカが繰り返されると、子どもは「いつか自分にも危害が加えられるのではないか」と怯えてしまいます。
また、些細なことで怒られるのではないかと考え、自然と自信を喪失していくことも考えられるでしょう。
その結果、親だけでなく周囲の人も恐れるようになり、人間不信に陥る可能性があります。
▶︎自己肯定感が低い子供の特徴や言動とは|注意すべき親の発言や行動
夫婦仲を改善させる方法
夫婦関係が悪化したからといって改善が不可能というわけではなく、実際に関係を修復できた夫婦も存在します。
夫婦仲を改善するにはどういった方法があるのでしょうか。
言葉で伝える
夫婦生活が長くなると、お互いに「わざわざ言わなくても分かるだろう」、「自分の気持ちは伝わっているはず」と考えがちです。
しかし、夫婦といえども自分以外の本心は分からないものです。そのため、たとえば感謝の気持ちや愛情、幸せだと感じたときには、それを素直に言葉で表現しましょう。
夫婦仲が悪いと自分から切り出すことに抵抗を感じる方も多いと思います。
しかし、感謝の言葉を日常的に心を込めて繰り返し伝えることで、徐々に気持ちが伝わり夫婦仲の修復につながっていく可能性は高いです。
相手を理解する努力をする
自分から言葉や態度で表現する以外にも、相手の心を汲み、理解しようとする姿勢が必要です。
たとえば、感謝の気持ちや愛情などを言葉で伝えたとしても、相手が素直に受け取ってくれないと夫婦仲は改善できません。
なぜ、夫または妻はこういった言葉を掛けたのか、相手の立場に立って気持ちを汲み取ることを心がけましょう。
夫婦の時間をつくる
生活のすれ違いなどによって夫婦仲が悪くなっている場合には、少しでも夫婦で過ごす時間をつくるよう工夫してみましょう。
たとえば、残業で帰宅が遅くなった場合でも「おやすみ」の挨拶を交わしたり、シフトの調整や有給休暇を取得して外に出かけるなど、できる範囲で時間を合わせることが大切です。
はじめから「休暇をとってほしい」や「早く帰ってきてほしい」と要望するだけでは反発を招くおそれもあるため、まずは自分から調整し時間をつくるようにしましょう。
過度に干渉しない
相手の言動で気がかりな部分があると責め立てたくなるものです。たとえば、「どうしてそんなに残業が続いているのか?」、「どうして部屋が汚いままなのか?」などといった言葉がそれにあたります。
しかし、これが発展していくと相手の行動を逐一監視するようになり、さらに夫婦関係が悪化する可能性があります。
このような否定的な言葉を投げかけないことはもちろんですが、相手のことを信頼し過度に干渉しないことも夫婦仲を修復するためには不可欠です。
ただし、干渉しないというのはコミュニケーションをおろそかにしたり、相手に興味を示さないということではないため注意しましょう。
▶︎スキンシップにはどんな効果がある?良好な関係性を維持するためのポイントとは
まとめ
新婚当初は仲睦まじい夫婦であったにもかかわらず、夫婦生活が長くなるにつれて関係が悪化し、一緒にいること自体がストレスに感じてしまうケースも少なくありません。
夫婦といえども別人格である以上、お互いのことをすべて理解できるとは限らないものです。
夫婦仲が悪化すると「もう修復は不可能なのではないか」、「離婚するしかないのでは」と考えがちですが、今からでも関係を取り戻せる可能性は十分あります。
今回紹介した方法を参考に、まずは自分自身の行動を変え、相手に気持ちが伝わるよう動いてみましょう。
聞き上手になるには?自分の話をしないのが正解?

「人の話を聞くのが苦手で自分のことばかり話してしまう」、「他人の話に興味が湧かず、質問をするのが苦手」という人も多いのではないでしょうか。
コミュニケーション能力を高めるうえで聞き上手になることはとても大切であり、円滑な人間関係を構築するうえでのポイントとなります。
本記事では、聞き上手の人にはどういった特徴があるのか、聞き方のコツや話し上手との違いについても解説します。
聞き上手とは

聞き上手とは、相手が自然と話したくなるようなコミュニケーションをとることを指します。
たとえば、対面で会話をするとき、相手の目を見ずにスマホを操作しながら聞き流している人と、目を見て、ときには相槌を打ちながら真剣に話を聞いてくれる人がいた場合、後者のほうが話しやすいと感じるでしょう。
相手の話に耳を傾け、真摯な姿勢で聞くということはコミュニケーションの基本であり、聞き上手な人ほどコミュニケーション能力が高いといえるのです。
また、このように真摯に話を聞くことは「傾聴」ともよばれ、聞き上手は傾聴力が高いとも表現されます。
▶︎苦手な人でもコミュ力を上げる方法はある?鍛えるメリットも紹介!
聞き上手になるメリット

傾聴力を高め、聞き上手になることは、日常生活においてさまざまなメリットがあります。具体的にどういったメリットがあるのか、代表的なものをいくつかご紹介しましょう。
相手の本音を引き出しやすくなる
聞き上手であるということは話しやすい雰囲気をつくることでもあり、相手は安心して本音や心の内をさらけ出すことができます。
人間関係において相手を傷つけることを恐れ、本音を言い出せず悩む人も少なくありません。
聞き上手になることで相手は自分に対して本心をぶつけることができ、自分のなかで改善すべき点や相手からの要望が分かれば、お互いにストレスを感じることも少なくなるでしょう。
周囲の人に頼られる存在になる
本音を話しやすい聞き上手な人には、さまざまな人が相談をしたくなるものです。
相談の内容によっては有効な解決策やアドバイスができないことも多いですが、話をじっくり聞くだけでも精神的な負担が軽減され、楽になることは少なくありません。
「困ったときにはあの人に相談しよう」といったように、周囲の人から頼られる存在になることで人望が高まります。
同時に、自分が困ったときや悩みを抱えるときに助けてくれる人が現れるかもしれません。
信頼関係を構築できる
聞き上手になることで、自分自身への信頼度も高まっていきます。
たとえば、ビジネスの場面においては取引先や顧客が抱える課題や悩みに寄り添うことで信頼感を得られ、新規顧客の開拓やビジネスパートナーとの連携も可能になるでしょう。
社内だけでなく社外からの評価も高まり、重要なポジションや役割を任せてもらえる可能性があります。
▶︎社内で円滑なコミュニケーションを取るコツや活性化の成功事例を紹介
聞き上手と話し上手の違い

聞き上手と似た言葉に「話し上手」があります。両者にはどのような違いがあるのでしょうか。
話し上手とは
話し上手とは、相手の理解度や認識の度合いに応じて、分かりやすく丁寧に話をすることを指します。
たとえば、これまで化粧の経験がない中高生に対して、メイクや化粧品の専門的な話をしても理解が追いつかないことが多いため、まずはどういったスキンケアアイテムがあるのか、下地と乳液の違いやメイク道具の使い方などから説明しなければなりません。
自分がもっている知識や理解度を前提に、「これくらいは知っているだろう」といった認識で話を進めるのではなく、相手に合わせて話の内容を組み立てていくことが話し上手な人の特徴です。
また、専門的で内容が伝わりづらい場合には、比喩表現や例え話なども駆使して、分かりやすく伝えようとする特徴もあります。
話し上手な人は聞き上手でもある
聞き上手と話し上手は一見すると対極的なスキルであると捉えられがちですが、古くから「話し上手は聞き上手」ということわざもある通り、密接な関係があります。
分かりやすいように話を組み立てたり、話し方を変えたりするということは、まず相手の状況を知る必要があるのです。
また、話している最中に相手が疑問を感じているような表情を見せた場合、どこが分からないのか具体的に聞き出す必要があるでしょう。
このように、話し上手であることは、大前提として相手に寄り添う姿勢が大切であり、そのためにも聞き上手であることが求められるのです。
▶︎ノンバーバル(非言語)コミュニケーションの重要性とは?一例も紹介
聞き上手の間違った認識
聞き上手の定義や意味を間違って捉えると、コミュニケーションがうまくいかず会話がなかなか弾まないこともあります。
特に多いのが、以下のような誤った認識です。
自分の話をしない
聞き上手と聞くと、「相手の話を聞いていれば良い」と捉え、自分から話をする必要はないと考える人も少なくないでしょう。しかしこれは誤った認識であり、聞き上手とはいえません。
相手にしてみれば、一方的に自分ばかりが話しているように感じてしまい、「この人は本当に理解しているのか」、「自分に共感してくれているのか」と不安を覚えられてしまいます。
質問ばかりする
上記とは反対に、質問ばかり投げかけるのも聞き上手とはいえません。
相手が話している最中に多くの質問を投げかけてしまうと話が横道に逸れていってしまい、本題を見失うことがあります。
また、あまりにも質問をしすぎてしまうと、相手にしてみれば理詰めのように責められていると感じることもあり、それ以上話をしたくなくなる可能性もあるでしょう。
話の流れで時折質問を投げかけるのは有効ですが、タイミングや質問の量には注意が必要です。
聞き上手な人の特徴

聞き上手な人にはどういった特徴があるのでしょうか。人によって話の聞き方は異なりますが、代表的な特徴をいくつかご紹介します。
笑顔で話を聞いてくれる
聞き上手な人の多くは、自然と話しかけたくなるような雰囲気があります。
自然体で話を聞いてくれることはもちろん、笑顔でいることが多く親しみを感じやすいです。
適度な相槌を打ってくれる
話しやすい雰囲気をつくるうえでは、適度な相槌も重要なポイントといえます。
聞き上手な人の多くは、相手が話している途中で「うん、うん」、「へぇー」、「なるほど」、「その通りだね」といった相槌を打ちます。
これにより、相手は自分が話す内容を理解してくれている、あるいは共感してくれていると感じ、次の言葉を発しやすくなるのです。
話を否定せず共感してくれる
会話の途中で話を否定しないのも聞き上手な人の特徴です。
もちろん、人によって考え方や価値観は異なり、すべての意見が一致するとは限りません。しかし、そのような場合であっても、聞き上手な人はあえて否定せず最後まで耳を傾けてくれます。
また、自分と意見が一致する場合には共感の意思を示してくれます。
相手に興味を示す
相手に心地よく話をしてもらうためには、自分が相手に対して興味をもっていることを示す必要があります。
ときには自分の専門外のことや興味がない話をされることもあるかもしれません。
しかし、分からないことがあれば素直に質問したり、自分と共通点のありそうな内容が出れば掘り下げて聞いたりすることで、会話が盛り上がっていく可能性もあるでしょう。
▶︎スキンシップにはどんな効果がある?良好な関係性を維持するためのポイントとは
話の聞き方や受けとめ方のコツ
相手の話を真摯に聞いているつもりでも、聞き方や話の受けとめ方によっては誤解が生じる可能性もあります。
話を聞くうえで注意しておきたいポイントやコツを紹介しましょう。
先入観をもたない
円滑なコミュニケーションをとるために、先入観が邪魔になることがあります。
たとえば、入社して間もない友人や同僚から「仕事を辞めたい」と相談されたとき、「我慢が足りないのだろう」といった先入観をもってしまうと、相手に悪い印象をもってしまい共感できなくなってしまいます。
できるだけ先入観を捨て、ニュートラルな立場で耳を傾けるようにしましょう。
自分の主張を押し付けない
人によって価値観や考え方は異なるため、ときには意見が食い違う場合もあるでしょう。
つい自分の意見や主張を押し通したくなりますが、相手から「この人には理解してもらえない」と思われてしまうため、このような行動はとるべきではありません。
もし異なる意見を示す場合でも、相手を否定するのではなく、「◯◯さんの意見はとても理解できる。一方で見方を変えてみると、◯◯という考え方もあり得るかもしれないね」といったように、気付きを与えるような言い方に留めておきましょう。
共感の姿勢を示す
上記でも紹介しましたが、聞き上手になるためには共感の姿勢が不可欠です。
具体的には、「そうだよね」、「なるほど」といった適度な相槌を打ちながら、自分なりに話を整理し理解した内容を繰り返したり、表現を変えて「これはつまり◯◯ということだよね?」など繰り返すことも必要です。
ただし、あまりにも大げさな相槌や共感は、わざとらしく見えたり嫌味として捉えられることもあるため注意しましょう。
▶︎友達の作り方|場所と手順を社会人から学生ごとに分けて解説!
まとめ
円滑なコミュニケーションを図るうえで、聞き上手になることは重要です。コミュニケーションが苦手と感じている人のなかには、「聞き上手になりたい」という人も多いでしょう。
「話し上手は聞き上手」ということわざもある通り、話し上手になるためには聞き上手であることも求められます。
聞き上手な人の特徴を参考にしながら、コミュニケーション力を高めるためにどういった行動を意識すればよいのか、できることから少しずつトレーニングしていきましょう。
社内で円滑にコミュニケーションをとるコツや成功事例を紹介

さまざまな人が働く企業・組織において業務を円滑に遂行していくために、社内コミュニケーションは欠かせない要素です。
しかし、思うようにコミュニケーションがとれず悩む社員や、組織としてどういった対策を講じれば良いか分からず悩んでいる経営者や人事担当者も多いでしょう。
そこで本記事では、社内コミュニケーションを活性化するためのコツや成功事例などを中心に解説します。
社内コミュニケーションの重要性とは

社内コミュニケーションの活性化を目指す企業は少なくありません。なぜ多くの企業で社内コミュニケーションは重要視されているのでしょうか。考えられる理由を紹介します。
多様化する働き方に対応するため
近年、多くの企業ではテレワークが導入されるようになり、オフィス以外のさまざまな場所で働く光景は当たり前となりました。
しかし、従来は同じオフィスのなかで気軽に声をかけることができましたが、テレワークとなるとメールやチャット、電話をかけたりするのも面倒に感じ、自然とコミュニケーションが減ってしまいがちです。
その結果、連携不足によって重大なミスにつながることもあるでしょう。社内コミュニケーションを活性化することで、多様な働き方のなかでも連携を強化しミスの削減にもつながっていきます。
多様な価値観をもった社員同士が快適に働くため
従来の日本社会は終身雇用や年功序列型の人事制度が主流でしたが、現在は雇用の流動化が進み転職は珍しいものではなくなりました。
その結果、さまざまな業種、職種を経験した多様なキャリアをもつ人材が同じ会社に集まることもあります。
社員によって仕事に対する考え方や価値観が異なるため、ときには軋轢を生み出すこともあるでしょう。
社内コミュニケーションを活性化し、社員同士がお互いを知ることで円満な人間関係を構築でき、快適な労働環境につながっていきます。
▶︎苦手な人でもコミュ力を上げる方法はある?鍛えるメリットも紹介!
社内コミュニケーションにおける課題

社内コミュニケーションを活性化しようと考えても、さまざまな課題があり、思うように進んでいかないケースもあります。
具体的にどのようなことが問題となり得るのか、典型的な例を紹介しましょう。
コミュニケーション環境の整備
働き方が多様化するなかで社内コミュニケーションを活性化するためには、対面以外で気軽に会話ができる環境を整備しなくてはなりません。
従来のようにメールや電話でも最低限のコミュニケーションはとれますが、「忙しいのではないか」、「仕事の邪魔になるのではないか」と考え、躊躇してしまうこともあります。
そのため、メールよりも気軽にやり取りできるビジネスチャットや、顔がよく見えるWeb会議システムなどの整備が求められます。
しかし、必要な機材やツールを新たに揃えなければならず、コスト面の負担が増大します。
細かなニュアンスの相違
ビジネスチャットやWeb会議システムなどを導入しても、対面によるコミュニケーションに比べると細かな表情や仕草までは確認しづらいものです。
その結果、本来の意味とは違ったニュアンスで伝わってしまったり、相手が誤解したまま話が進んでいったりすることもあります。
世代間における価値観のギャップ
企業や組織ではさまざまな世代の人が働いており、それぞれの世代によって価値観や考え方にギャップが生じることもあります。
たとえば、管理職や経営層を担うことが多い40代以上の世代は、長年にわたってオフィスへ出社して働く習慣が根付いており、オンラインでのコミュニケーションにうまく対応できないと感じる人も少なくありません。
一方、20代や30代といった比較的若い世代は、社会人になる前から身近にインターネットを活用してきた世代でもあり、オンラインでのコミュニケーションを受け入れやすい人も多いです。
▶︎ノンバーバル(非言語)コミュニケーションの重要性とは?一例も紹介
社内コミュニケーションを活性化させるメリット

社内コミュニケーションを活性化することで、企業にとってはどのようなメリットがあるのでしょうか。
情報共有の不足や連携不足を解消できる
社内コミュニケーションが活性化すると、働く場所が変わっても気軽に連絡を取り合い、些細なことも相談できる体制が整います。
また、電話や対面でのコミュニケーションでは口頭で伝えた内容が残らず、忘れてしまうこともありますが、チャットなどを活用することでテキストデータとして残り、連携不足を解消できるでしょう。
社員のモチベーションを向上できる
仕事の悩みや職場の人間関係などを気軽に相談できる先輩や上司、同僚などがいれば、有効なアドバイスを受けられることも多いものです。
社員コミュニケーションを活性化することで、些細なことでも相談できる社員同士の関係性が構築でき、前向きに仕事に取り組めるようになるでしょう。
部署間での連携が強化できる
組織の規模が大きくなればなるほど、どの部署がどういった業務を行っているのか分からなくなることも少なくありません。
社内コミュニケーションを活性化できれば、部署にかかわらずさまざまな社員との交流が生まれるため、仕事で困ったときに他部署に助けを求めたり気軽に相談したりと、横の連携が強化されます。
▶︎知らず知らずに起こっている?ハラスメントの種類や防止方法を紹介
社内で円滑にコミュニケーションをとるコツ
さまざまな人とコミュニケーションをとりたいと考えているものの、どう接したら良いか分からず戸惑う人も少なくありません。
社内におけるさまざまなシチュエーションに応じて、円滑なコミュニケーションをとるためのコツを紹介します。
会議でのコミュニケーションのコツ
会議において重要なのは、参加者に分かりやすく説明し内容を理解してもらうことです。
そのためにもプレゼンや資料の説明においては、できるだけ結論から先に述べ、簡潔に話をまとめることが大切です。
また、会議では質問が上がらず本当に理解しているのか不安になることもあるでしょう。
参加者にしてみれば、最初の質問で挙手をするのは緊張するため、「◯◯さんは、ここまでの説明で分からないところはありませんか?」など、何人かに指名をしてみるのも有効です。
上司と部下のコミュニケーションのコツ
パワーハラスメントなどを恐れ、部下と思うようにコミュニケーションがとれていないと悩む上司も少なくありません。
円滑なコミュニケーションを実現するうえでは、部下をむやみに否定するのではなく、まずは良い部分を探し褒めることを意識しましょう。
そうすることで、部下にしてみれば自分は認められていると感じ、信頼関係を構築しやすくなります。
そのうえで、改善すべきところがあれば「◯◯を◯◯のように改善すればさらに良くなる」と優しい声のかけ方を意識しながらアドバイスをすることで、適切なマネジメントが実現できます。
部署間におけるコミュニケーションのコツ
部署やチームが異なると目に見えない壁のようなものを感じ、話しかけづらいと感じるものです。
しかし、このように感じているのは他部署の社員も同様であり、話しかけられるのを待っていてもなかなかコミュニケーションは生まれません。
そのため、自分から積極的に話しかけていくことが大切です。たとえば社内イベントや交流会など、他部署の社員と交流できる場に参加してみると良いでしょう。
▶︎聞き上手になるには?話し上手との違いや話の聞き方のコツを紹介
社内コミュニケーションの活性化で成功した事例

上記で紹介した内容は、コミュニケーションを円滑にするために社員一人ひとりができることです。しかし、社内全体のコミュニケーションを活性化するためには、組織としての取り組みも重要です。
具体的にどういった成功事例があるのか、代表的なものをいくつかご紹介しましょう。
全社員が利用できる交流の場を設置
周りの社員が真剣に仕事をしている執務スペースで、雑談のような会話は抵抗を抱くものです。
また、執務スペースにこもった状態だと他部署の人と交流が生まれにくく、社内コミュニケーションの活性化にもつながりません。
そこで、休憩スペースやカフェ、バーなど、部署にかかわらず全社員が気軽に利用できる交流の場を設ける企業も多いです。
社内イベントの実施
社内コミュニケーションの活性化を目的として、社内イベントを実施する企業もあります。
イベントの種類はさまざまで、たとえばスポーツ大会やバーベキュー、社員旅行、飲み会、ランチ会などが代表的です。
このようなイベントでは、上司や同僚、部下の普段の仕事では見せないような意外な一面を見られるほか、普段交流がない他部署の人と自然と会話が生まれるきっかけにもなります。
ただし、これらのイベントを休日や業務終了後などに行う場合には、強制参加とはせずあくまでも任意参加とすることが前提となります。
経営層からの動画メッセージ配信
企業や組織の規模によっては、経営層とコミュニケーションをとれる機会が少なく、どのような方針・考え方で経営をしているのか社員に伝わりづらいこともあります。
社員一人ひとりとコミュニケーションができる規模の組織であれば対面での会話も有効ですが、それが難しい場合には動画メッセージなどで経営層の考え方や方針を伝える方法もあります。
まとめ
働き方の多様化やさまざまなバックグラウンドをもった人材が増えていることから、円滑に仕事を進めるためにも社内コミュニケーションの活性化は欠かせないものです。
社員同士が密に連携し情報共有の漏れをなくすことも大きな目的としてありますが、仕事の悩みを気軽に相談できる関係性をつくり、社員のモチベーションを向上させる意味でも社内コミュニケーションは重要です。
社員一人ひとりが実践できるコミュニケーションのコツを紹介しましたが、それ以外にも企業や組織として実践できることは数多くあります。
社内コミュニケーションの活性化を実現するためにも、まずはできることから実践していきましょう。
コミュ力を上げるにはどうしたらいい?高める方法を解説
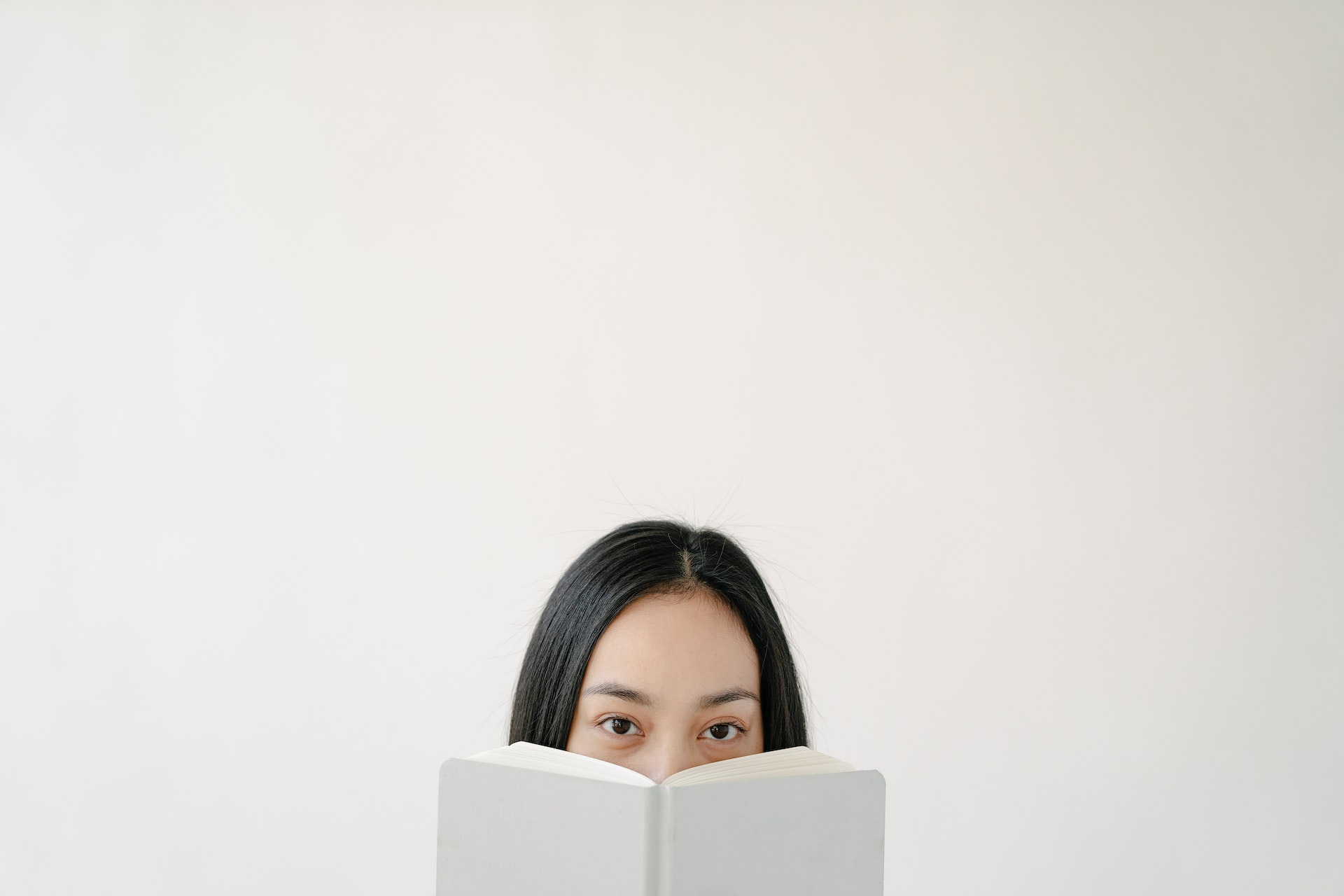
SNSや掲示板などにおいて、コミュ力(コミュニケーション能力)が低くて悩んでいるという声を多く目にします。
親しい友人や家族、恋人とは気兼ねなく話すことができても、初対面の人や職場の上司、同僚、取引先などとうまくコミュニケーションをとるのは難しいですよね。
そこで本記事では、コミュ力に自信がないと悩む人に向けてコミュ力を上げる方法をご紹介します。
現代でコミュ力が重要視される理由

なぜ近年になって「コミュ力」という言葉が生まれるほどコミュニケーション能力が重要視されるようになったのでしょうか。
厚生労働省が調査した「若年者の就職能力に関する実態調査」の結果を見ても、85.7%もの企業が採用時に重視する能力としてコミュニケーション能力を挙げています。
▶︎楽しくコミュ力をアップ
この背景には、働き方の多様化や職場環境の変化などが考えられます。たとえば、近年多くの企業でテレワークが導入されるようになり、メールやチャット、Web会議などでやり取りする光景は珍しくなくなりました。
しかし、対面でのコミュニケーションに比べ、より緊密なコミュニケーションをとっていないと話の意図が伝わりづらく、仕事においてさまざまなトラブルや連携ミスを生じさせる原因にもなります。
これはビジネスの場面に限らず、プライベートにおいても共通していることから、これまで以上にコミュ力は重要視されるようになったと考えられます。
▶︎ノンバーバル(非言語)コミュニケーションの重要性とは?一例も紹介
コミュ力が低い人と高い人の特徴

コミュ力が低い人と高い人を比較した場合、両者にはどのような特徴・違いがあるのでしょうか。
周囲からの視線の感じ方
コミュ力が低い人の多くは、周囲の人から自分がどのように見られているのか過剰に気にしすぎてしまう特徴があります。
たとえば、「自分が発言することで場の雰囲気が悪くなるのではないか」、「的外れなことを言って変に思われているのではないか」と感じます。その結果、自然と発言する機会が減っていき、周囲の人との関係性も希薄になっていくことがあるのです。
これに対しコミュ力の高い人は、積極的に自分の意見を発信し、周囲の人から理解してもらおうとします。
また、相手の態度や表情にわずかな変化があったとしても、あまり深読みせずコミュニケーションを図ろうとする傾向も見られます。
周囲の人に対する興味
もうひとつの違いは、周囲の人に対する興味です。
コミュ力の低い人は、他人に対して興味をもてなかったり、話をするだけ無駄のように感じたりすることもあります。「どうせ自分のことは分かってくれない」といった諦めや、そもそも一人でいることが好きで、必要以上の関わりを持とうとしない人も多いのです。
これに対しコミュ力の高い人は、自分のことを相手に理解してもらおうと考えると同時に、相手の人にも興味を示すことが多くあります。
たとえば、初対面の人であってもさまざまな話題を振って自分との共通点を見つけ出そうとしたり、興味のある話題に対してさまざまな質問をして話を深掘りしようとすることも多いです。
周囲の人への心配り
コミュ力と聞くと「話が上手な人」や「口が達者な人」、「明るい人」といったイメージをもたれがちですが、決してそればかりではありません。
コミュニケーションは相手が存在して初めて成立するため、お互いが心地よく話せる関係でなければならないのです。
コミュ力が低い人の場合、自然と早口になったり難しい専門用語を多用したりして、自分のペースで話すことも多く見られます。しかし、相手にとっては聞き取りづらかったり、難しい話で内容についていけないと感じることもあるでしょう。
これに対しコミュ力の高い人は、相手の様子をうかがいながら会話のペースを落としたり、分かりやすい表現で噛み砕いて会話をしたりすることも多いです。
▶︎スキンシップにはどんな効果がある?良好な関係性を維持するためのポイントとは
コミュニケーションが苦手な人でもコミュ力を上げることはできる?
コミュ力は生まれ持った才能や個人の性格によって決まるものと考える方も多いのではないでしょうか。
たしかに、積極的にコミュニケーションをとろうとする子どももいれば、引っ込み思案や人見知りでうまくコミュニケーションをとれない子どもも存在します。
しかし、結論からいえば大人になってからもコミュ力を高めることは十分可能であり、「自分はコミュ障だから無理」、「もともとコミュニケーションが苦手だから」と諦める必要はありません。
これは自分自身の性格や人格を変えるというものではなく、ちょっとした心がけや考え方を意識しながら、トレーニングをすることで変わっていきます。
▶︎友達の作り方|場所と手順を社会人から学生ごとに分けて解説!
コミュ力を鍛えるメリット

トレーニングによってコミュ力を高めることで、どのようなメリットがあるのでしょうか。
円滑な人間関係が維持できる
コミュ力が低いと、せっかく仲良くなっても自然と友達が離れていってしまったり、過去に一緒に働いていた仲間と疎遠になったりすることも少なくありません。
また、何気ない一言が原因で人間関係をこじれさせてしまうこともあるでしょう。
コミュ力を鍛えるということは、周囲の人がどう感じるかを見極め、心配りできる力を高めることでもあります。
交友関係を広げられる
コミュ力を高めると、現在の人間関係を維持すると同時に新たな交友関係を広げていくことにもつながります。
たとえば、共通の友人として知り合った初対面の人や取引先の担当者、新たに配属された同僚や部下などとコミュニケーションをとり、短い期間でも信頼関係を構築できるでしょう。
困ったときに助けてもらえる仲間ができる
ビジネスの場面はもちろん、プライベートにおいてもさまざまな悩みや困りごとを抱えることがあります。
たとえば、「初めてのプロジェクトで経験がなく、何から手をつければ良いのか分からない」、「ある友人とケンカをしてしまい、仲直りのきっかけがつくれない」など、悩みは人それぞれ異なります。
コミュ力が低いと、他人に頼ることができず一人で抱え込んでしまうケースも多いですが、コミュ力を高め良好な人間関係が構築できていれば、周囲の人に素直に悩みを打ち明け、助けを求めることもできます。
▶︎聞き上手になるには?話し上手との違いや話の聞き方のコツを紹介
コミュ力を上げる方法

コミュ力はトレーニング次第で高めていけると紹介しましたが、具体的にどのような方法があるのでしょうか。その一例をご紹介します。
自分から挨拶をする
挨拶はコミュニケーションの基本であり、会話のきっかけにもなります。
たとえば職場に出勤したときや友人との待ち合わせ場所に合流したときなど、自分から積極的に挨拶をするように心がけましょう。
コミュニケーションが苦手で話題を振ることが難しくても、自分から挨拶をすることで雰囲気が明るくなることも多いです。
相手の話を傾聴する
傾聴とは、相手に共感しながら真摯な姿勢で話を聞くことを指します。
コミュニケーションが苦手な方は、まず相手の話を傾聴することから始めてみましょう。真剣に話を聞いてくれていると感じると、多くの人は気持ちよく話題を提供し、会話が弾むことも多いものです。
具体的には、相手の目を見ながら話を聞き、ときには適度な相槌やオウム返しをすることも有効です。
相手の話を否定しない
相手の話を真剣に聞いていると、ときには間違った内容や自分とは相容れない意見を耳にすることもあるでしょう。
しかし相手の話を遮ったり、直接的に強い言葉で否定するのは避けたほうが良いでしょう。まずは相手の話を最後まで聞き、そのうえで自分の意見を整理し簡潔に伝えることが大切です。
重要なのは相手を否定するのではなく、「自分はこう思う」といったように、あくまで自分自身を主語に意見を表明することです。
相手との共通点を見つける
積極的なコミュニケーションを心がけているにもかかわらず、話が盛り上がらないと悩んでいる方は、相手との共通点を見つけてみましょう。
たとえば、趣味や仕事、出身地、年齢などの共通点から話題を振ったり、質問を掘り下げていくことで話が盛り上がることも多いです。
相手と話のテンポを合わせる
自分から話をする際には、相手の状況を確認しながらテンポを調整することも大切です。
また、相手が早口であるにもかかわらず、自分がゆっくりしたペースで話しているとお互いにストレスを感じることもあるため、相手にペースを合わせて話すことも意識しましょう。
比喩表現を用いる
自分の理解度をベースに話を進めてしまうと、相手の理解度が追いつかず「置いてけぼりにされている」と感じられることも少なくありません。
専門的な内容や複雑な内容を話す場合には、相手に理解してもらえるよう比喩表現や例え話をするのもおすすめです。
相手を名前で呼ぶ
コミュ力を高めるためには自分に対して親しみを感じてもらい、話しやすい雰囲気をつくることも大切です。
そのためのテクニックとして、相手のことを名前で呼びかけるという方法があります。自分の名前を呼んでもらうことで相手は親しみを感じやすく、徐々に距離も縮まっていきます。
関係性によっては、いきなり名前を呼ぶことに抵抗を感じることも多かったり、そもそも何と呼べば良いか分からないことも多いでしょう。
そのような場合には、相手に対して「何と呼べば良いですか?」と質問してみるのもおすすめです。
▶︎【シーン別】人間関係がめんどくさいと感じる心理や対処法を解説
まとめ
ビジネスの場面はもちろん、プライベートにおいてもコミュ力は欠かせない能力のひとつです。
コミュニケーションが苦手でコミュ力が低いと悩む方も少なくありませんが、今からでも高めていくことは十分可能です。
今回紹介したトレーニング方法の例を参考に、少しずつできる範囲で継続していきましょう。
ノンバーバル(非言語)コミュニケーションの重要性を徹底解説!

ノンバーバル(非言語)コミュニケーションは、日常生活のさまざまな場面で信頼関係を構築するためにきわめて重要な役割を果たします。
本記事では、ノンバーバルコミュニケーションとはなにか、基本的な内容を紹介するとともに、その種類や具体的な行動の例、日常生活のなかで活用できる場面も併せて解説します。
ノンバーバル(非言語)コミュニケーションとは

ノンバーバルコミュニケーションとは非言語コミュニケーションともよばれ、その名の通り言葉以外の情報や感情を伝達するコミュニケーションの方法を指します。
たとえば、「おはようございます」という挨拶を例にとっても、笑顔で元気な挨拶をしたときには好印象を抱かれやすいですが、小さい声で相手の目を見ないまま挨拶をした場合、暗い印象を抱かれたり、ときには体調が悪いのではないかと心配されたりすることもあるでしょう。
このように、同じ言葉を伝えたとしても、言葉以外の要素によって相手が抱く印象や意味合いは大きく変わってくることから、円滑な人間関係を築くためにもノンバーバルコミュニケーションは重要です。
ノンバーバルコミュニケーションを構成する要素としては、身体的な動きや顔の表情、目の動き、声のトーンなど、さまざまなものが含まれます。
▶︎苦手な人でもコミュ力を上げる方法はある?鍛えるメリットも紹介!
メラビアンの法則とノンバーバルコミュニケーションの関係性
ノンバーバルコミュニケーションの重要性を裏付けるものに、米国の心理学者であるアルバート・メラビアンが提唱した法則があります。これは「7-38-55ルール」、または「3Vの法則」ともよばれます。
メラビアンは「コミュニケーションにおいて言葉から受け取る情報はごくわずかで、視覚や聴覚から得られる情報が多くを占める」ことを提唱しました。
具体的にはその人の見た目や表情などが全体の55%、声の大きさや話し方などが38%、そして言葉そのものから受け取る情報は全体の7%程度にすぎないという内容です。
実に9割以上がノンバーバルコミュニケーションで占められており、特に強い影響力をもっていることがわかります。
ノンバーバル(非言語)コミュニケーションの重要性

学術的な側面では上記で紹介した通り、ノンバーバルコミュニケーションが重要であることがわかりました。では、実際のビジネスの場面や日常生活において、ノンバーバルコミュニケーションはどのように役立っているのでしょうか。
細かいニュアンスを伝える
ビジネスや日常生活のなかでメールやチャットなどのテキストメッセージをやり取りすることも多いですが、文章だけでは真意が伝わりづらいこともあります。
たとえば、相手の話を理解したことを伝えるためには「了解しました」と短い文章でも意味は伝わりますが、相手との関係性によっては冷たい印象をもたれてしまう可能性もあるでしょう。
電話や対面など、ノンバーバルコミュニケーションが可能な環境であれば、声のトーンや表情などから細かいニュアンスも伝えられるでしょう。
相手に対して安心感を与える
上記で紹介したような最低限の情報をやり取りするコミュニケーションでは、機械的で冷たい印象をもたれるばかりか、お互いの心情が分からず不安を抱くこともあります。
その結果、本音でコミュニケーションが取りづらくなり、なんとなく話しかけづらい雰囲気やコミュニケーション不足が生まれる可能性もあるでしょう。
ノンバーバルコミュニケーションが可能な環境にあれば、そのような不安もなくなりお互いが安心して話し合うことができます。
相手の状況を理解する
コミュニケーションにおいて重要なのは、自分が言いたいことや伝えたいことを一方的に話すのではなく、相手が理解しているかどうか様子を見ながら会話をすることです。
もし、話の内容が理解できていないときは困った表情や首をかしげるなどの仕草が見られることもあります。一方で、十分話が理解できていれば、頷く回数が増えたり、相手の目を見ながら話を聞き入ったりすることが多いです。
ノンバーバルコミュニケーションでは相手の様子を確認しながら話を進めることができ、認識の齟齬が起きにくくなります。
▶︎聞き上手になるには?話し上手との違いや話の聞き方のコツを紹介
ノンバーバル(非言語)コミュニケーションの効果
細かなニュアンスや感情を伝えたり、相手に対して安心感を与えたり、さらには相手の状況を理解するうえでもノンバーバルコミュニケーションは欠かせません。
これらを総合的に考えると、ノンバーバルコミュニケーションによって得られる効果は信頼関係を構築し、良好な人間関係を維持できるということです。
お互いの認識の齟齬を防ぐことでビジネスでもプライベートでもトラブルを防止できるほか、安心感を与えることでお互いに本音で話せる環境が整います。
また、相手の理解度に応じて表現や伝え方を変えることで、お互いのことを理解し合え、誤解を招く心配もなくなるでしょう。
▶︎スキンシップにはどんな効果がある?良好な関係性を維持するためのポイントとは
ノンバーバル(非言語)コミュニケーションの種類と例

ノンバーバルコミュニケーションには具体的にどういった種類があるのでしょうか。
身体動作
身体動作とは、いわゆるボディランゲージともよばれるものです。
言語が異なり言葉が通じない間柄であっても、身振り手振りを交えることで意思疎通が図れるという特徴があります。
たとえば、「はい」、「いいえ」という言葉を発さなくても、頷いたり首を横に振ったりすることで意思表示をすることも可能です。
身体の特徴
身体的な特徴としては、身だしなみを含めた外見的な特徴を指します。具体的には、髪型や髪の色、体型などが挙げられます。
たとえば、清潔感のある髪型の人は好印象を抱かれやすいといったものもノンバーバルコミュニケーションのひとつといえるでしょう。
接触行動
接触行動とはその名の通り、身体の一部に触れる行動を指します。
たとえば、相手に対して親しみや好意を伝える際、言葉だけでなく握手やハグなどをすることで気持ちが伝わりやすいです。これも代表的なノンバーバルコミュニケーションのひとつといえます。
近言語
近言語とは、主に声の大きさやトーン、会話のスピード、相槌などを指します。
相槌のなかには頷きも含まれますが、近言語の場合は「えぇ」、「あぁ」などといった言葉が挙げられます。
プロクセミクス
プロクセミクスとは、相手との距離感や距離の取り方を指します。
たとえば、日本人の場合は初対面や顔見知り程度の人とは一定の距離を空けがちですが、親しくなっていくと徐々に物理的な距離も縮んでいきます。
人工物の使用
人工物とは、一般的に衣服やアクセサリー、メイクなどを指します。
友人や家族など親しい人と会うときにはラフな格好、仕事場や取引先、フォーマルな場で人と会うときにはスーツなどを着用するのが一般的です。
このようなTPOを考慮することで、相手に対して敬意を払っていたり親しみを感じているといったサインになり、ノンバーバルコミュニケーションのひとつといえます。
環境
環境とは、その名の通り部屋の照明や温度などを指します。
一見ノンバーバルコミュニケーションとは無関係のように思われますが、たとえば冷房や暖房を入れて快適な温度に設定しておくことで、相手を快く迎え入れるという意思を表示できます。
ノンバーバル(非言語)コミュニケーションを活用できる場面

ノンバーバルコミュニケーションはさまざまな場面で欠かせないコミュニケーション手段であることがわかりましたが、具体的にどのようなシーンで活用できるのでしょうか。
ビジネス
ビジネスの場面では上司や取引先、顧客などに複雑な内容を説明をしたり、商談でプレゼンを行ったりすることも多くあります。
一方的に説明をするのではなく、相手の表情や仕草をうかがうことで、疑問に感じていることや不安を引き出すことができるでしょう。
円滑なコミュニケーションによって認識の齟齬をなくし、トラブルを未然に防止することにもつながります。
▶︎社内で円滑なコミュニケーションを取るコツや活性化の成功事例を紹介
友人関係
プライベートな場面では、良好な友人関係の構築・維持にも役立ちます。
たとえば、帰省の際に久しぶりに会った同級生や親友に対し、握手をしたりハグをしたりすることで言葉以上の親しみを表現できます。
また、会話の際に積極的に相槌をうったり、目を見て話したりすることで、相手への信頼を示すこともできるでしょう。
夫婦関係
同じ家のなかで暮らす時間が長くなっていくと、お互いのことを男性または女性として見られなくなり、夫婦関係に溝ができることもあります。
そこで、たとえば服装の雰囲気を変えてみたり、アクセサリーを身に着けたりすることで新鮮な印象に映り、夫婦のコミュニケーションが増える可能性もあるでしょう。
また、相手の話にはきちんと耳を傾けたり、目を見て話すといったことも夫婦間に求められる基本的なノンバーバルコミュニケーションのひとつです。
恋愛
恋愛においても夫婦関係のノンバーバルコミュニケーションと共通する部分は多いです。
ただし、好意を抱いている人がいて、これから交際に発展させていきたいという場合には、接触行動やプロクセミクスなどが重要といえます。
たとえば、複数人で食事や飲み会に行ったとき、あえて対面や横の席を確保することで距離が縮まり、好意を抱いてもらえる可能性もあるでしょう。
また、会話のなかで話が盛り上がったとき、自然と膝や腕、肩などにタッチすることも有効な場合があります。ただし、執拗な接触行動は相手を不快にさせる可能性もあるため注意が必要です。
▶︎【シーン別】人間関係がめんどくさいと感じる心理や対処法を解説
まとめ
非言語コミュニケーションともよばれるノンバーバルコミュニケーションは、円滑なコミュニケーションを行ううえで欠かせないものであり、さまざまな種類があります。
特に日本語はわずかな表現の違いで相手を不快にさせたり、誤解を生じさせてしまう可能性もあるため、特に重要なコミュニケーション手法といえるでしょう。
ビジネスの場面はもちろんのこと、友人関係や夫婦関係、さらには恋愛関係に発展させるうえでも役立ちます。
正しい知識を理解したうえで、ノンバーバルコミュニケーションを日常生活に役立てていきましょう。
鉄美人

私たち人間にとって、鉄とは必要不可欠な存在です。なぜなら心と身体とお肌の美しさの根源は、実は鉄にあるからです。
地球が誕生した46億年前。当時、海の色は赤く、鉄やミネラルが豊富だったといわれています。強い酸性の環境では、生物は存在できなかったため、生命が発生するには何度も進化が必要でした。そして約42億年前に人類が誕生したと考えられています。
地下では物質を還元し、地上では酸化を繰り返して分子を作り出し、このプロセスによって炭素、窒素、水素、酸素などの元素が生まれたといわれています。そして、これらの元素は月の間質サイクルを経て形成されました。
私たちの身体の仕組みを考えるとこの分子はとても大切です。というのも、分子は全ての食材に含まれており、この分子の濃度が細胞の機能を左右するからです。私たちの身体は60%の水分とタンパク質、脂肪、微量元素でなりたっています。そして、その中でも最近注目を集めているのが鉄なのです。
この鉄は、私たちの身体の中でどんなお仕事をしてくれているのでしょう。
酸素が不足すると、私たちは集中力がなくなり、息切れ、動悸、肩凝り、冷え、脱毛、目の下のクマ、浮腫みなどの症状が出ます。女性の多くが鉄不足といわれるように、月経で毎月鉄を失い、また出産や過度な運動でも鉄が消費されます。健康だと自負している方でも、こういった悩みを持っている方は多いのではないでしょうか?
私自身も、40代で子宮筋腫からひどい貧血になりました。筋腫ができた場所が悪く、2センチの筋腫でしたが毎月オムツをするほどの出血量でした。ただ人間の精神力は偉大でエステの仕事も家事も全て普通にこなし、階段や坂が辛い程度でした。病院で血液検査をするとヘモグロビン5.5フェリチン10というひどい数値で、医者にびっくりされるほどでした。しかし、鉄の注射を打ってもらうと身体が温かくなり元気になる感覚が戻ってきたのです。
この鉄の注射の威力に興味を持ち、自分で調べてみたところ、この鉄の注射が実は、身体を老化させるものだったと知り、これがきっかけで「分子栄養学(オーソモレキュラー)」の勉強を始めました。
それまでは、鉄が不足していると貧血が起こると考えられていましたが、この分子栄養学では少し考えが違ったのです。分子栄養学は、体内に必要な分子を正しい濃度で維持するために、適切な量の栄養素を摂取することで、健康を維持し、病気を改善することができるととらえています。
貧血予防には鉄だけを補えばよいわけではなく、タンパク質を摂取する必要があります。そしてこのタンパク質を吸収するためにビタミンBが必要になります。このビタミンBは、赤身の魚や、ヒレ肉やささみなどの脂が少ない肉類や、バナナやパプリカ、さつまいも、玄米などにも比較的たくさん含まれています。
さらに美容上では、老化を防ぐビタミンCもプラスすることで、血色が良く透明感もありふっくらと張りのあるお肌が期待できます。
幼児虐待などかわいい我が子への虐待やネグレクトも、鉄不足でやる気がなくなり精神的にうつになっていることが原因であるということも学びました。
このように、精神の安定にまで関わってくる鉄分ですが、この鉄のメインのお仕事は、吸収されたあと、ヘモグロビンとなって酸素をはこんだり、筋肉中に酸素を蓄えることです。
元気で心も身体も活動し続けるには、大切にしなくてはならない存在だということですね。
ぜひ検査をされるときには、脾臓や肝臓、骨髄などに使われてある貯蔵鉄まで調べて、しっかりと鉄のある身体で血液を促し、美しく輝いてください。
プロフィール:寒川友恵

表参道にてリラクゼーションエステティックサロン『プルミエエワール』主宰。
『健康=美』をコンセプトに分子整合栄養学を取り入れた健康管理、体の内側から溢れる美しさを引き出す美容家。
2022年に医療福祉・高齢者にQOLの向上、IADL・ADLの低下予防と向上。
2025年、超高齢化社会に向けてお一人お一人がその方らしく『健康で美しく老う』をコンセプトに介護美容療法協会、キュアエステセラピー&キュアエステセラピスト設立、活動中。
健康は美をコンセプトに美容情報を配信しています。
Cure Beauty 寒川友恵
最小限の努力で1日を健やかに過ごす?アーユルヴェーダ的朝のセルフケア

Photo by bruce mars on Unsplash
皆さんは、朝はどのように過ごされていますか?「早起きは三文の徳」ということわざがありますが、アーユルヴェーダでも、朝の過ごし方が大切であると考えられています。
今回は、アーユルヴェーダ初心者だった頃の筆者が、朝のセルフケアに取り入れはじめたものを中心にご紹介します。朝の目覚めをスッキリさせたい方や、1日をエネルギッシュに過ごしたいという方の参考になれば嬉しいです。
▶︎アーユルヴェーダって何?どうやったらすんなり今の生活に取り入れられる?
アーユルヴェーダの朝の過ごし方
筆者は、もともとどちらかと言うと朝型人間でした。(夜は9時前には就寝します)けれど、いくら睡眠時間が長くても、日によって寝起き状態はまちまち。特に月経前の寝起きは本当に辛いものでした。アーユルヴェーダの知恵を参考にしたセルフケアを取り入れ、しばらくたった今では、程度の差こそあれ、以前に比べてだいぶスッキリした朝を過ごすことができるようになりました。
筆者が最初にはじめたアーユルヴェーダの朝の過ごし方は、ベットの中での「自己観察」です。その日の睡眠の質はどうだったのか、寝起きはどうなのか、また体の調子はどうなのかなど。分析やジャッジする必要はないので、ただ朝のありのままの状態を観察します。
朝一番の自己観察はシンプルすぎてつい軽んじてしまうかもしれませんが、これがその日一日の生活の質を左右するかなめと言っても過言ではないと筆者は考えています。その日の朝の心身の状態をきちんと把握することで、朝の限られた時間を有効に使うことにもつながります。「朝はゆっくり過ごした方がいい」というのは分かってはいても、時間に追われがちな現代人には、そのような優雅なことばかり口にすることは難しい場合もありますよね。
最小限の努力で、1日を健やかに過ごすために、ぜひベットの中で数分間自分の体や心の観察をしてみて下さい。その後、その日の調子を見ながら、あるいは時間的余裕を考慮しながら、セルフケアをしていきましょう。
ベットの中で伸びをする
もし、体のだるさを感じたり、スッキリしないと感じたら、ベットの上で寝たまま「伸び」をします。両腕を頭の上に伸ばして、大きく息を吸いながら全身を伸ばします。背中をそらせ(アーチ)ても構いません。
体の隅々まで新鮮なエネルギーが行き渡るのを感じてみてください。これを数回続けます。長い時間(人によっては短いかもしれませんが)、おやすみモードだった体に起き上がるサインを送ってあげるつもりで行います。いきなりベットから起き上がるよりも、体がほんの少し軽く感じるでしょう。
舌磨き
体の調子に関わらず、多くの方に行ってほしいのが「舌磨き」。美容家も取り入れているということで最近よく話題になっていますが、アーユルヴェーダでは睡眠中に皮膚や口腔内に体内の老廃物が出ると言われています。現代医学においても、岡山大学の研究で舌苔(したごけ/ぜったい)にはアルデヒトという発がん物質が蓄積されていることが明らかになっています。舌苔を除去することで、アルデヒドも減少するのではないだろうかと言われています。その他にも舌苔を除去することで、口臭や口腔内の病気なども未然に防ぐことが期待できると言われています。多くのメリットがあるこの舌磨き、ぜひやってみてはいかがでしょうか。
舌苔を除去するための舌磨きには、市販の金製あるいは銀製のタングスクレイパーを使用するのがおすすめ。もし手に入らない場合は、スプーンで代用も可能です。舌苔の多さは、老廃物の多さが比例していると考えられるため、舌苔の量や質(どんな色なのか、感触、ニオイなど)も観察しましょう。
水分補給
口腔内がきれいになったら、水分補給をします。一般的に、アーユルヴェーダでは白湯がおすすめされていますが、体質によってはお水でも可。体がほてりやすい、熱を持ちやすい、または代謝が良い人は白湯よりもお水の方が良いとされています。しかしキンキンに冷えたお水ですと、お腹を下してしまう可能性がありますので、常温のお水が理想的です。
メディテーション / ジャーナリング
メディテーションには様々な種類があり、またアーユルヴェーダでは体質によってもおすすめのメディテーションが異なります。けれど、最初のうちは難しいことや習わしについては深く考えなくてもOK。あなたが無心になれる瞑想法を1日3分ずつで良いので実践してみて下さい。初心者の方は、静かな落ち着ける場所に座って目をつむり、呼吸することに意識を向けてみて下さい。お気に入りの音楽をBGMにするのがおすすめです。
あるいは、朝から雑念が多いという方は、メディテーションの練習を行うと逆に辛い時間を過ごすことになるかもしれません。そんな時は、「書く瞑想」と呼ばれるジャーナリングがおすすめ。頭の中に思い浮かんだことを遠慮なく書きます。
朝食前に軽い運動
運動はわたしたちの心身のバランスを保つために必要不可欠なものですよね。運動に適当な時間は、朝食前と言われています。特に、気だるい朝をお過ごしの方は、体の中に溜まった毒素を発散するためにもぜひ体を動かしてみましょう。また、食前の軽い運動は排便効果にも役立つと考えられています。
運動は、全身をバランスよく動かすものが理想的。アーユルヴェーダでは、ヨガの練習がおすすめされていますが、その他にウォーキングなども有効。しっかりと手を振り足を動かして散歩してみましょう。体の中に溜まった重たいものが発散されると同時に、頭がスッキリする感覚があるかもしれません。
自分に合ったセルフケアを
いかがですか?朝は何かと忙しい時間ですのでなかなか全てをこなすことは難しいかもしれませんが、まずはできそうなことからはじめてみてはいかがでしょうか。毎日続けていくことで、少しずつ変化がみえてくると思います。
皆さんが、素敵な朝を、そして素敵な1日を過ごすことを心から願っています。
▶︎アーユルヴェーダで重要な消化力とは?体も心もデトックスして気分をあげよう!
アーユルヴェーダで重要な消化力とは?体も心もデトックスして気分をあげよう!
約5,000年前にインドで発祥したとされるアーユルヴェーダの中で、とりわけ重要なのが「消化力」。もう少し噛み砕いていうと、アーユルヴェーダはデトックスファーストといったところでしょうか。「腸活」というとより身近でイメージしやすいかもしれません。その考えは、体の中に余計なものを溜めないで、心身の健康を安定させることを大切にしています。
今回は、アーユルヴェーダアドバイザーの筆者が、実践して本当に効果のあったアーユルヴェーダ的デトックス方法をご紹介します。便秘に悩んでいる方や、疲れやすかったり、気分の落ち込みがあるなど、何となくの不調に悩まされている方の参考になれば嬉しいです。
消化力とは?
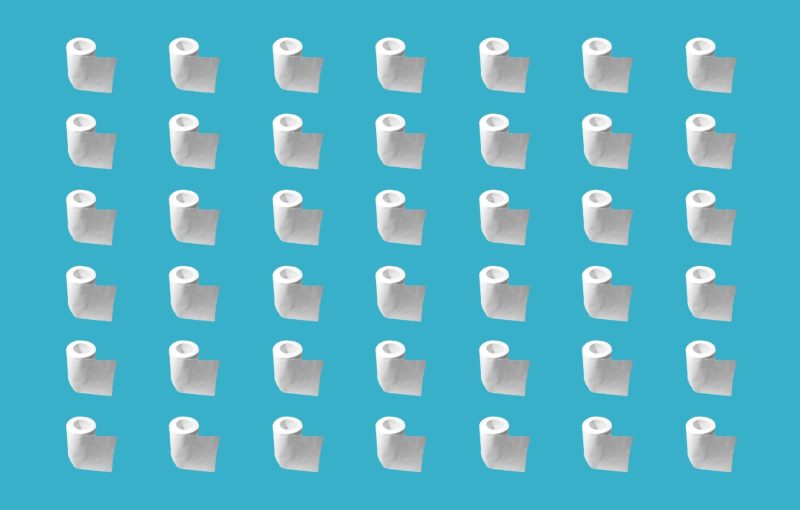
Photo by Nik on Unsplash
「消化力」とは、食べものや感情を消化する力のこと。
アーユルヴェーダでは、消化力が弱いと未消化物が残り、体に「毒」が溜まると考えられています。この毒が、心や体の不調に繋がってしまうのです。
例えば、ベースメイクを思い浮かべてみてください。いくら完璧にファンデーションを塗ったとしても、お肌にニキビがあったり、肌がたるんでいれば、満足のいくキレイを見せることはできないと思いませんか?
それは、体の外側だけでなく内側も同じ。体の中、あるいは心の中にも毒を溜め込んでおけば、いくら良いものを取り入れたとしても身になることはありません。
現代の風潮として、良いもの(オーガニックフードや、ホールフード、スーパーフード、サプリなど)を”取り入れる”ということは多く見られますが、”出すこと”は、あまり重視されないことが多いかもしれません。実際、筆者もそうでした。
消化力の弱かった頃に筆者は、体に良いとされるものを多くとるようにしていましたが、なかなか思ったような結果を得ることはできませんでした。それどころか、心身の不調は増すばかり。便通は悪い上、食後のお腹の張り、ガスやゲップなど消化トラブルに常に悩まされる状態。また、ひどい時にはお肌はくすみ、たるみが気になることも。頑張れるけれど、慢性的に疲れが取れずに、そのせいでイライラして周りに当たってしまうこともしばしば。取り入れることよりも、余計なものを出すことに注力するようになると、みるみる不調は消えました。もちろん、常に一定して活力にみなぎっているわけではありません。それでも消化力を意識する前よりも、快適に暮らすことができるようになりました。
以下は、アーユルヴェーダで言われる毒が体に溜まっている人に表れやすい症状です。一つでも当てはまる項目があれば、次に紹介するアーユルヴェーダ的デトックス方法を試してみると良いかもしれません。
- にきび、吹き出物ができやすい
- お肌が乾燥しやすい
- むくみやすい
- 舌に白い舌苔(ぜったい:舌に付く細菌のかたまり)が溜まっている
- 口内炎、口角炎ができやすい
- 目が充血しやすい
- 目の下にクマがある
- 体臭や口臭が気になる
- 便通が悪い(便秘 /出づらい・出るのに時間がかかる/ 残便感がある/ゆるい/下痢)
- 月経痛がある / 月経不順
- 尿の色が濃い
- 肩こりや関節痛がある
- 集中力が持続しない
アーユルヴェーダ的朝のデトックス方法

Photo by David Mao on Unsplash
アーユルヴェーダには1日を通して、様々なデトックス方法がありますが、筆者がおすすめしたいのは朝のデトックス。寝ている間に蓄積した未消化物を除去できたり、また朝のうちに排便を促すことでスッキリと1日をスタートすることができます。
日の出前に起きる
アーユルヴェーダでは、日の出前の起床がおすすめされています。起床後1時間程度で、便意を感じることが多いと言われていますので、スッキリとした排便を促すためにも、朝は余裕を持って起きることが◎。
西洋医学でも、起床後には、朝日を浴びると体内時計がリセットされ自律神経が整い腸内環境が整うとも言われています。
口内ケア
朝、太陽の光を浴びた後に行いたいのが、口内ケアでデトックスです。
まずは「舌磨き」をして、舌苔を除去しましょう。アーユルヴェーダでは、夜寝ている間に、体の中を巡った未消化物は舌の上に溜まり、これを放置すると、体内に毒として吸収されてしまうと考えられています。また口臭予防にもなり、口の中がスッキリしますよ。舌磨きには、市販のされているタングスクレイパーあるいは、スプーンで代用も可能。歯ブラシでこすると苔を押し込んでしまう可能性があるのでおすすめしません。
その後、歯ブラシをして、最後に「オイルプディング」をするのがおすすめです。これは一度加熱した白ごま油を使ったうがいで、歯茎のマッサージをする効果がある他、感染症、声がれ予防、口内炎の改善効果も期待できると言われています。白ごま油以外に、ココナッツオイルやオリーブオイルでも可。その場合は、加熱はしなくても大丈夫です。
白湯
口腔内がキレイになったら「白湯」を飲んでみましょう。朝の白湯は、排泄を促し、消化力を高めます。白湯の温度は、湯冷ましから50度程度が理想ですが、体調にあわせて調整して下さい。
また更なるパワーを感じたい方は、生姜白湯もおすすめです。生姜には胃腸の機能促進や毒素の排出など消化力を上げる効能が期待できると言われています。よく洗った生姜を食品保存容器にいれて全体が浸るくらいまでミネラルウォーターを注ぎ、一晩冷蔵庫で置いたら完成。飲む時は、適温に温めて飲んで下さい。
ヨガ / 呼吸法
時間の余裕がある場合は、ヨガや呼吸法の練習をおすすめします。体を適度に動かすことで血流が促進されて、腸の動きも良くなります。また呼吸法は腹式呼吸が◎。 腹式呼吸は横隔膜を大きく動かし、腹部内の圧力が高まります。その圧力が排便をサポートしてくれる効果が期待できます。
いかがですか?アーユルヴェーダのデトックス方法は、お金をかける必要はありません。もしかしたら、最小限の努力で最大限の効果を実感できるかもしれません。
特に夏の時期は、胃腸が冷えやすく消化力が下がってしまうケースが非常に多いです。もし、気になるものがあったら、ぜひ明日からでもはじめてみてはいかがでしょうか。
▶︎最小限の努力で1日を健やかに過ごす?アーユルヴェーダ的朝のセルフケア
「セルフプレジャー」はマインドフルネス
最近よく耳にする「セルフプレジャー」という言葉。
以前はタブーとされ、女性が話しにくいトピックでしたが、実はセルフプレジャーは健康と密接な関係があります。
ハミングの代表の永野 舞麻(ながの まあさ)が、セックス・セラピストのジョーダン・ルロ博士に、セルフプレジャーが、どうして女性にとって大切なのか聞きました。
男性が一人で 楽しむものというイメージのあるセルフプレジャーですが、実は女性がうまくとりいれることで、綺麗なお肌、健康な身体、バランスのとれた心だけではなく、幸福感も得られるというメリットがあると博士は言います。
そして、パートナーとのセックスを楽しむ上でも自分の身体の好き・嫌い、気持ちい・気持ち良くないを学ぶことはとても大切なのだそうです。
あなたのセックス観を変えるような新しい考え方を提案してくれた博士とのインタビューをお楽しみください。

セルフプレジャーの目的はオーガズムに達することではない

永野:日本でも、セルフプレジャーということが注目されていますが、博士の考えるセルフプレジャーとは?
まず知っておいてほしいことは「セルフプレジャー」がオーガズムに達することだけが目的ではないということです。セルフプレジャーを体感することで、私たちは、オーガズム以外にも多くの楽しみを体験することができます。
永野:私たちは、「オーガズムを感じなければ、満足なセックスでない」と考えがちです。でも先生が指摘したように「セルフプレジャー」にはオーガズム以上のもっと広い意味があるんですね。
そうです。「セックスの目的はオーガズム」と考えると、セックスの楽しみが減ってしまいます。そういう風に目標を設定するとプレッシャーを感じてしまいますよね。これでは、身体も心も緊張してしまいセックスを十分に楽しめなくなります。
最も楽しいセックスとは、目標を持たずに行うセックスだと思ってください。自分の体をどう動かすかなど一切考えないで「今この時」「この瞬間」に気持ちを集中して、楽しむのです。
永野:女性がセルフプレジャーをすることのメリットは何ですか?
セルフプレジャーをすると、オキシトシンやドーパミン、エンドルフィンのような体に良い化学物質が放出され、それが免疫機能を改善させることは研究でわかっています。また、オーガズムは、生理痛を和らげ、睡眠の質をあげ、ストレスも緩和します。セルフプレジャーを生活に取り入れることで、健康面で多くのメリットがあるのです。
▶セルフプレジャーとは?美容効果を紹介!どんな人におすすめ?
セックスのイメージを変えるセルフプレジャー

これをふまえて、セルフプレジャーのメリットについて考えてみましょう。
まず、オーガズムという点で、男女間には大きな差があります。一般的に、セックスとは女性の性器への挿入からスタートし、男性がオーガズムに達して終わる、というものです。 女性がオーガズムに達したかどうかは、考慮されていませんね。
女性がオーガズムに達したふりをする傾向にあるのはこれが理由です。つまり、女性がオーガズムを感じたかどうかは、重視されていないのが今の社会です。相手をがっかりさせたくないと感じる女性は、オーガズムを感じたふりをして、相手をハッピーにさせようとします。
これが、現代社会の、または映画やメディアで描写されるセックスシーンの典型です。
つまり「セックス」=「男性の快楽」という構図です。
だから男女の間には、オーガズムという点で大きなギャップがあるのです。
▶セックスレスの原因とは?|なりやすい夫婦の特徴や解消法を解説
セルフプレジャーの楽しみを知らないのは人生の楽しみを見過ごしているようなもの
このギャップを埋めるためにも、女性がセルフプレジャーすることがとても重要なんです。セックスとは男性の快楽がすべてではないのです。
だから、女性がセルフプレジャーすることは、女性自身がセックスの快楽を感じ、自分の体について、もっと知ることができるというメリットがあるんです。
自分が気持ちよくなる方法を知らないなんて、人生における大きな楽しみを見過ごしているようなものです。自分がどうしたら気持ちよくなれるのか、何が気持ちいいのかを知ることは女性にとっても大切です。
▶40代の女性は性欲が強い?なくなる?その違いや性欲の対処法について
セルフプレジャーは「恥」ではない
永野:アメリカで友達が自分の好みのセックストイについて恥じらいもなく気ままに話しているのを聞いて、驚いたことがあります。日本ではまだ、セルフプレジャーについてオープンに話しにくい状況です。もっとオープンに話せる社会を実現するためには、どんなサポートが必要でしょうか。
あなたが今言った「恥」がまさに確信をついていますよね。これが、セルフプレジャーに関して誰でも感じる「恥」。だからセックスについてオープンに会話できないのです。
この「恥」をなくしていくためには、幼少期から性教育を始めることが必要です。
今の思春期の性教育というと、セックスによる感染症や望まない妊娠についてなど実用的なことばかり。でも性教育は、セックスの楽しさやパートナーとの関係を築く方法など、もっと包括的であるべきです。
また、セックスは「健康状態」のカテゴリーの1つとして考えるべきです。かかりつけの医者に行き健康状態を聞かれた時に、性的な健康状態についても聞かれ、頭痛や息切れと同じ様に「性的な健康上の心配はありませんか?」と医者に聞かれる、そんなイメージです。
性的な健康が、学校の科目に組み込まれ、医者では健康分野に組み込まれれば、セックスやセルフプレジャーについて話すことが「恥」ではなく、当たり前のことになります。
セックスを楽しむことを女性が自分に許可できるような社会へ
永野:女性がセックスを楽しむことへの社会的偏見には、どう対処すればいいのでしょうか?
この偏見という意識をはずすための「性の健康の6原則」があります。
あなたがパートナーとセックスする時、または1人でセルフプレジャーするときに、この6つの価値観に従っているか自問してみてください。
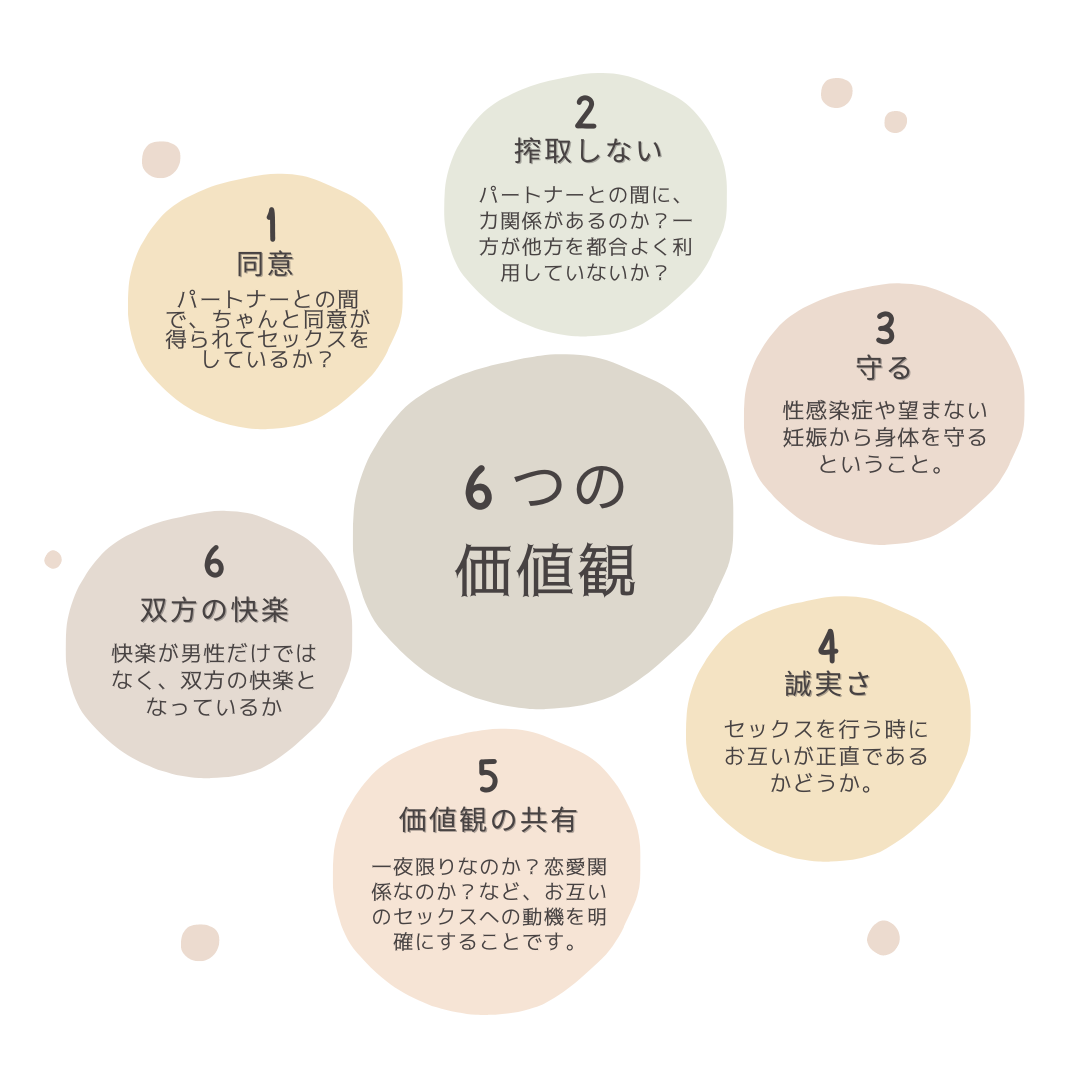
- 同意:パートナーとの間で、ちゃんと同意が得られてセックスをしているか?
- 搾取しない:パートナーとの間に、力関係があるのか?一方が他方を都合よく利用していないか?
- 守る:性感染症や望まない妊娠から身体を守るということ。
- 誠実さ:セックスを行う時にお互いが正直であるかどうか。
- 価値観の共有:つまりセックスをする時に、何のためにセックスをしているか明確にするということ。一夜限りのセックスなのか?新しい恋愛関係の始まりなのか?お互いのセックスへの動機を明確にするということです。
- 双方の快楽:快楽が男性だけではなく、双方の快楽となっているか。

6つ目の「双方の快楽」は特に重要です。つまりセックスは男性だけではなく、女性も喜びを感じるものであるということです。
また、快楽の定義は人それぞれです。例えば、ある人にとってはオーガズムかもしれないし、他の人にとっては感情的な結びつきかもしれません。異なっていていいんです。
この6つの原則をみんなが尊重している社会をイメージしてください。
そんな社会が実現すれば「セックスの快楽のギャップ」の問題も解消されるでしょう。そうすれば、セックスをもっと安心してできるようになると思うんです。その結果、女性が「セックスを楽しむ」ということをもっと自分に許可できるようになると思うのです。
永野:セルフプレジャーを行うことは、ベッドの上で自由に自己表現ができることにもつながるのでしょうか?
もちろんです。自分が何が気持ちいいのかわからなければ、相手にも伝えることはできませんよね。 セックスをしている最中ではなく、お互い落ち着いた雰囲気で話しあえるタイミングでパートナーとセックスについて話すことをお勧めします。
例えば、週末に、普段のセックスについてどう思うか、セックス中にやってみたいこと、やりたくないことはあるか、など相手に率直に聞いてみるのです。
パートナーとこういう時間が作れたら、セックスについてお互いが感じていることを話し合う安全な空間をつくることができます。そのためには、そもそも自分がどうしたら気持ちよくなるのか自分の体のことをわかっていないと、相手に伝えることもできません。
永野:セルフプレジャーをした後に孤独や恥ずかしさを感じることから、セルフプレジャーを避ける女性もいます。どうすれば、より多くの女性が安心してその一歩を踏み出すことができるのでしょうか?
私のクライアントでも、セルフプレジャーをして孤独や恥ずかしさを感じてしまうという悩みを持つ人はいますよ。
それが本当に「孤独」なのかどうか、もう一度考えてみて欲しいです。セルフプレジャーの時間は「私との大切な時間」、誰にも邪魔されない、自分を見つめることができる特別な時間です。
一人でハイキングに行ったり、一人でコーヒーを飲みに行ったりするのと同じです。
自分の体と向き合える一人の時間は「孤独な体験」ではなく、「自分自身を知るための素晴らしい時間」と考え方を変えてみましょう。
永野:自分のことをもっと知る必要があるのですね。そして、パートナーとオープンに話すことで、安全な空間をつくることができますね。最後に、日本の皆さんと世界の人たちにメッセージをお願いします。
大切なことは、セルフプレジャーはあなたの身体、それから心の健康に良いということです。自分が何を気持ちいいと感じるのかをぜひ知ってみてください。セルフプレジャーは、自分のことをもっと知る素晴らしい機会なんです。
▶女性の性欲について解説!性欲がない女性の理由もご紹介!
デジタル修正はもう不要! ありのままのあなたが美しい

あなたは、今の身体をそのまま受け入れ、愛おしく感じることができていますか?
日々がんばっているあなたの身体に対する思い、普段はどのように考えているでしょうか。
- 「セルライトがあるから、足の見えるパンツは履くのはちょっと…」
- 「出産してから、おなかのたるみが気になる。もうビキニは着られないな」
そんなことを感じたことはありますか?
ハミングでは8月は「ボディポジティブ」をテーマにして、さまざまな企画を展開しています。
あなたが抱く身体への思いについて考えるきっかけとして、今回は、アメリカの下着ブランドAerie(以下「エアリー」)をご紹介します。
エアリーは、「ボディポジティブ」のパイオニア的な存在。なぜなら、この概念が世の中全体に広がる前から、「自分をありのままに受け入れる」という考えを強く発信してきたブランドだからです。
多くの女性が共感するエアリーの取り組みを通して、あなたの身体をありのままに受け入れてあげることの大切さを考えてみませんか?
🔻ボディポジティブに関する動画はこちら🔻
リアルな自分って?
エアリーのウエブサイトにはこう書かれています。
- 「エアリーは、本当のあなたが輝くデザインを作ります」
- 「本物であること、❝リアル❞ が何よりも美しい 」
エアリーは「ボディポジティブ」というブランドの理念を2014年からいち早く取り入れ「ありのままの体型で良い」というメッセージを広告にも反映させてきました。
エアリーのオンラインサイトには、いろんな体型、肌の色、サイズのモデルたちの堂々とした姿があり、より現実的で親しみやすい美のイメージを見せています。
こうやって、友達にいそうな体型のモデルたちを紹介することで、エアリーは、自分をありのままに受け入れるという価値観を世界の女性たちに広めています。
▶自分を認める方法|認めることの難しさや自己肯定感との関係性を解説

デジタル修正しない
エアリーを「ボディポジティブ」の代表的ブランドとしている特徴のひとつは、『モデル画像のレタッチをしない』という宣言です。
公式サイトによれば、2014年以来、モデルの画像のレタッチは一切していないそうです。
長年ファッション業界では当たり前だった『画像を理想的なイメージに修正する』というやり方に挑むこのアプローチは、当時、とても大きな反響を呼びました。
エアリーのオンラインサイトを見ると、モデルたちが、自分たちと同じような体型の人達だと感じるでしょう。
エアリーはこうやって修正なしのリアルなモデルを起用することで、「あなたはそのままで良い」「何も修正する必要などない」「一人ひとりの個性を讃えよう」という明確で力強いメッセージを送っています。
私たち女性特有の特徴でもあるストレッチマーク、セルライト、バースマーク、シミ、にきび、妊娠線。こういったものを否定する、時代遅れともいえる美の基準に対して、エアリーはきっぱりと「NO」をつきつけています。
エアリーのモデルたち自身も、インタビューなどでこういった女性の特徴は「恥ずべきことではない」と語っています。
▶メンタルヘルスを向上させるセルフケア方法。自分と向き合う時間を増やそう
プラスサイズも豊富
エアリーが「ありのままのあなた」を応援するという宣言は、商品のラインナップを見ても納得できます。
エアリーは、さまざまな体型の女性に対応できるよう、豊富なサイズバリエーションを提供しています。
プラスサイズを豊富に取り入れることでエアリーは、体型に関係なく、すべての人がスタイリッシュで快適な服を手に入れる権利があるという当たり前のことを示しているのです。
エアリーの取り組みは、こういった女性が隠したくなる特徴に対してだけではありません。
2019年には、障害を持つ女性や車いすの女性モデルを起用し、多様性のある社会を作ろうというメッセージを積極的に送っています。
こういった、女性のエンパワーメントを強化していくエアリーが、世界中の女性たちから指示されていることは、その売り上げの推移からもわかります。
完璧なボディの女性たちをモデルに起用している大手の下着ブランドである「ヴィクトリアズ・シークレット」を急ピッチで追い上げ、2021年時点での売り上げは全米で第2位となっています。
🔻ボディポジティブに関する動画はこちら🔻
あなたはそのままでOK
エアリーのアプローチに触れ、私が率直に感じたのは、「ありのままを受け入れる」という考え方の重要性と同時に、その難しさです。
40代になった私の悩みといえば、最近特に目立つようになった顔のシミ。メイクの時にはこのシミをどう隠そうかということを第一に考えてしまいます。
年齢を重ねるごとに、私たちは、若い頃とは異なる悩みが浮上してくるもの。
そんな時、エアリーが私たち女性にやさしくなげかける「ありのままでいい」という理念は、まさに30~40代の私たちに響く、自信を持って受け入れることが大切なメッセージではないでしょうか。
自分の中にある、どんなに小さな特徴も、隠したくなるような部分も含めて、年を重ねてきた経験や時の流れが紡いできた独自の美しさです。
これは、自分の成長の証しであり、他人にはない独自の個性を示すものでもあるという考え方もできます。
エアリーの商品は、日本でもオンラインサイトで購入ができます。
▶”自分らしく生きる”とは?|仕事や恋愛で自然体で過ごせる方法を紹介
頭も身体も心も目を覚ます⁈冷たい水風呂でメンタルヘルスが改善!

あなたは「コールド・プランジ(Cold Plunge)」という言葉を耳にしたことがありますか。
直訳すると「冷たい水に飛び込む」、つまり水風呂のことです。
最近、SNSでインフルエンサーたちが投稿している動画、凍るような冷たい水風呂に入っているアレです。
グウィネス・パルトロウ、ヴィクトリア・ベッカムやレディー・ガガなど多くのセレブがこのトレンドに乗っています。
しかし、健康ブームにのっているこの水風呂、実際にはどのくらい体に良いのでしょうか?
また、どういう人がやると効果的なのでしょう?
実は、最近の研究で、水風呂は健康面だけでなく、メンタルにも有益であることがわかってきています。
水風呂って体に良いの?
英語でいう、この「コールド・プランジ」には、冷たいシャワーを浴びたり、冷たい海で泳いだり、専用の冷水浴槽を使ったりすることも含まれます。
アスリートの中には、身体の回復を促すために冷水を利用する人もいます。
実際、人類は何世紀にもわたって、さまざまな治療効果のために、さまざまな形で冷水を利用してきました。
スポーツ医学の医者であるマーク・スラボー医学博士は、「臨床的には、1時間以上の激しい運動をするすべての患者にとって、水風呂に体を浸らせる療法は、炎症や痛みの軽減に役立つことがわかりました」と話す。
体への影響は納得できるが、それでは、メンタル面でのメリットについてはどうなのだろう?
▶セルフプレジャーとは?美容効果を紹介!どんな人におすすめ?
メンタルにも効果がある?
理学療法士であるオコン・アンティア氏は、「冷たい温度にさらされると、身体は鎮痛剤の役割をするエンドルフィンを分泌します。また、冷たい温度は、身体のストレスを安定させるなどの長期的な効果もある」と指摘します。
「温度が急降下することで、精神的なタフさと規律が鍛えられます。これは心のトレーニングのようなもので、快適なゾーンから押し出され、不快なことに対処することを教えてくれます」。
実際に水風呂を試した多くの人たちからも、水風呂によって不安やうつ病の改善に大きな変化があったという声が聞かれます。
新しい研究で、オレゴン大学のミンソン博士は、参加者(全員が精神的に健康であると報告した)のストレスホルモンであるコルチゾールのレベルが、冷たい水に浸かった後に低下し、その後3時間まで低いままであることを発見しました。
また、冷たい水に浸かった後、参加者たちは、ネガティブな感情を抱くことが少なくなり、気分が良くなったという報告も出ています。
氷の入った浴槽に座ることと気分が良くなることがどのように関係しているのか、正確なことはまだ解明されていません。
しかし、数分間、冷水に浸るというような、つらいことを成し遂げるという行為には、精神衛生上の効果がある可能性はあると、精神科医エレン・ヴォラ医学博士は言います。
水の中に入り、不快感を感じながらも水の中にとどまることは、困難に立ち向かい目標を達成した自分の能力を信じる結果になります。
「(水風呂は)私たちの人生で起こる挑戦の予行演習になります」とヴォラ博士は説明しています。
とんでもなく冷たい水に体を浸すことは、過去や未来について考えるのではなく、今起こっていることに集中するための活動としても役立ちます。
セラピストのケリー・マッケンナ氏は、「不安な思いを抑えられるのは、今を生きているときです」と説明しています。
「今この瞬間に集中することは、不安に対する非常に強力な対処法です。よって冷水に浸かることは不安を軽減するのにまさに有効なんです」。
うつ病の最も一般的な症状のひとつは、「何も楽しくない」と感じることです。
大好きな食べ物もワクワクしないし、好きな番組もつまらなくなります。
しかし、適度な運動という形で身体に少しストレスを与えるだけで、そのような感情が軽減されることがわかっているとヴォラ博士。
「水風呂につかることも身体的なストレスになるので、同じことができる可能性があります」
水風呂とメンタルヘルスの関係に関する研究はまだ必要で、いかに有効かに関する研究は限られているものの、水風呂への期待は今後も高まる可能性があると言えるでしょう。
ただ、冷水を浴びることは、メンタルヘルスの専門家に診察してもらうことの代わりにはなりません。
「日常生活に支障をきたすような不安や憂鬱を感じている人は、メンタルヘルス治療を受けることが重要です」と、臨床ディレクターのジェイ・サーレ博士は指摘します。
▶感情の起伏が激しい人や少ない人の特徴|上手にコントロールする方法とは

リスクは?
健康な人であれば、水風呂にそれほどリスクはありませんが、何らかの持病がある人は、水風呂に入る前に医師に相談すべきでしょう。
高血圧や低血圧など心臓血管に問題のある人は、特にリスクが高いとスラボー博士。
「寒冷療法の衝撃が動悸やその他の心臓合併症を引き起こす可能性があります」。
健康な人であっても、水風呂は血圧を上昇させたり、ショックを引き起こしたりする危険性があります。
また、冷水に浸かる時間が長すぎると、凍傷や低体温症になる危険性も。
自宅でのやり方
最初は少しずつ始めることが大切です。
スラボー博士は、まずは2分間くらいの短い入浴から始めて、徐々に長くしていくことを勧めています。
すぐに氷水の入ったバケツに飛び込む必要もありません。スラボー博士は「15度(セ氏)くらいのぬるめのお湯から始めて、短時間つかる」ことを勧めています。
ウェルネスコーチのクイグリー氏は「冷水浴の効果は期待できますが、すべての人に合うとは限りません」と指摘します。
また、彼女は冷たいシャワーを浴びることに抵抗があっても、健康上の利点に興味があるのであれば、15度前後の涼しいシャワーを浴びることをお勧めしています。
これだけでも、ストレスの軽減やエネルギーの高まりを実感できるでしょう。
▶セルフ・コンパッションとは?やり方やマインドフルネスとの違いを解説
日本のサウナブーム
日本でも最近はサウナがはやっていますね。
その影響を受け、身の回りでも手軽に水風呂に挑戦するチャンスが広がっています。
健康や美容に注目する人々にとって、この機会は見逃せません。
ただ、このトレンドを単なる一過性のものとして追いかけるだけでなく、長く続けられるあなたなりの方法を模索することが重要です。
大事なのは、自分に合ったペースで取り組むこと。
日本では、まず水シャワーが、日々の生活に組み込みやすい健康法になるかもしれません。
流行を取り入れつつ、自分らしい方法で健康な未来を築いていけると良いですね。
参考:The Benefits of Cold Plunges For Mental Health – The Good Trade
参考:https://www.wondermind.com/article/cold-plunge-benefits/
相談1:子供の心を垣間見る方法 (3歳〜小学生低学年向け)

読者からの相談:
子供たちとのコミュニケーションについて悩んでいます。
3歳と6歳の子供がいます。子供たちが学校から帰ってくると 「今日、学校はどうだった?」とか「友だちと何をしたの?」など質問をしていますが、子供たちは 「別に」「特になにもない」と短い答えで済ませることが多いです。
子供がもっと答えやすいように、質問のしかたを変えてみるべきでしょうか。それとも、「そうなのね」とだけ返事をして、そっとしておくべきでしょうか?
ジョアンナさんの回答:
多くの親が抱く疑問ですね。幼い子供たちは、「今この瞬間」に集中しているものです。 自分の人生が今動いているということに全神経がいっています。 つまり、多くの子供たちにとって、家に帰って来た時には、学校での出来事はすでに過去のものとなっています。
子供にとって何かとても重大だと感じたことが起きた時には、そのことを親に伝えたがるものです。しかし「普段の生活」の詳細を話すことが大切だとは思っていないことが多いでしょう。
さらに、とても幼い子供の場合は、自分が今日した活動の全てを、親のあなたがすでに知っていると思い込んでいる場合もあるのです。
アドバイスの1つとしては、回答に制約を設けないオープンエンドの質問をすることで、会話が始まることもあります。例えば、こんな風に声をかけてみたらどうでしょうか。
- 今日、学校で絵を描いた人はいるのかしら?
- 今日、とってもおいしいおやつを持ってきた人はいるのかな?
- 学校では、手びょうしやダンスをしながら歌を歌うの?
- 今日、お友達の〇〇ちゃんは学校に来たかな?
- 今日は、学校でおもしろいお話を聞いたかな?
- 今日は少し雨が降っていたね。おそとには行けたかな?
- 学校で鬼ごっこをしたりする?
- もし、あなたの一日の絵を描くとしたら、どんな絵にしたいかな?
また、1日中、学校で過ごした子供は、ゆっくりする時間も必要になります。
幼い子供たちにとって、社交的に集団行動に合わせる学校での1日はとても疲れる時間です。また、内気で内向的な子供にとっては、さらに負担を大きく感じるかもしれません。そういう子にとって、家に帰ってきてから、しばらくは会話をしたり、社交的に振る舞うのはおっくうに感じるかもしれません。そういう場合は、おやつを食べたり、静かな時間を過ごしたりするのが良いかもしれませんね。
「今、何をしたい?」と聞くと、ちゃんと教えてくれる子もいます。少しリラックスできた後なら、パズルをしたり絵を描いたりなどの別の遊びをしながら、気軽に話をしはじめることもあるでしょう。
私の住むここアメリカでは、例えば家族がそろった夕食時に、みんなでその日のことを話す時間を設けている家庭もありますよ。その日に一番良かったこと、一番いやだったこと、一番楽しかったことや一番つらかったこと、または最も楽しかったことや最も退屈だったことなど。
ここでとても重要なのが、「静かに聞く」という姿勢です。

質問やアドバイス、リアクションなども控えて、心から子供の言葉に耳を傾けることを徹底します。例え、子供の話がトンチンカンだったとしてもです。
子供たちは、親が自分の言いたいことをすでに知っていると思ったり、親にだめだと言われると感じれば、沈黙する傾向があります。子供がこの場は自分の本音を話しても安全な空間なんだと思えるようにすることが最も大切です。
もし、何かコメントをしたければ、子供の言ったことをリフレーミングしてみましょう。
「今日は〇〇なことを感じた日だったのね」「今日は、〇〇があったのね」など、聞いた言葉をリピートするだけで十分です。
そして、家族のみんなが参加することで、自分の一日についてシェアすることが習慣になり、子供の心の内側が少しずつ垣間見ることができるようになりますよ。
子供のペースはゆっくりです。また習慣の変化も1日2日試したからと言って起こりません。ゆっくり気長に楽しみながら少しずつ起こる変化を観察していってみてくださいね。

ジョアンナ・ウィギントン氏
助産師として600人以上のお産に携わる。
教育者であり、アーティスト。北カリフォルニア在住。
20年以上にわたりオルタナティブ教育施設であるカスパー・クリーク・ラーニング・センターを創設・指導してきた。
現在はNPO組織Flockworksの活動に参加し、子供や教師をサポートしている。
アートの力を広めるためのプログラムを展開中。すべての人がアーティストであるという強い信念を持ち、若者から年配の人までが創造力を探求する機会を作り出している。
女性の性欲について解説!性欲がない女性もいる?
「性欲」という言葉を聞くと、一般的には男性のほうが強いイメージをもたれがちです。
一方で、性欲が強いと自覚している女性も存在し、人知れず悩みや不安を抱えている方も少なくありません。
女性が性欲について知ることは、自分の身体と向き合うためにも大切なことです。
本記事では、女性の性欲が強くなる、または低くなる理由や原因と、性欲をうまくコントロールするためのポイントも紹介します。
女性の性欲と男性の性欲に違いはある?

性欲とは性的欲求のことであり、一般的に肉体的な接触や性行為を求める欲求を指します。
食欲・睡眠欲に並ぶ人間の三大欲求のひとつであり、私たちが子孫を残していくために不可欠な存在でもあります。
一般的に性欲は女性よりも男性のほうが強いと言われることが多いですが、女性にも性欲は存在します。
性欲は人間の本能的な欲求ではありますが、なぜ性欲が高まるのか、そのメカニズムについてはさまざまな研究がされており、完全に解明できてはいません。
しかし、近年の研究において、女性の場合は「オキシトシン」が、男性は「テストステロン」とよばれるホルモン物質が性欲に影響を与えることがわかっています。
オキシトシンとは別名愛情ホルモンともよばれ、人間同士の接触やスキンシップによって分泌されます。
このことから、男性の場合は主に視覚的な情報によって性欲が高まるのに対し、女性の場合はパートナーや恋人との接触によって性欲が高まっていくという違いがあります。
また、男性の場合は比較的短時間で性欲が高まっていく傾向にありますが、女性の場合はスキンシップを図るなかでじっくりと時間をかけて性欲が高まっていく傾向が見られます。
▶︎セックスレスの原因とは?|なりやすい夫婦の特徴や解消法を解説
女性の性欲が強くなる時期や原因

女性にも男性と同様に性欲は存在しますが、性欲が高まる時期やタイミングなどに違いが見られます。
どのようなことが原因で性欲が高まるのか具体的に紹介しましょう。
生理周期
女性の性欲は生理周期に大きく影響を受けます。
一般的に生理が終わった直後から排卵日にかけて性欲が強くなるケースが多いですが、生理前の時期になると性欲は徐々に落ち着いてくる傾向があります。
ただし、これには個人差があり、なかには生理前のタイミングで性欲が強くなるという女性も少なくありません。
年齢や性交渉の経験
性交渉の経験がない、または少ない女性の場合、セックスそのものに恐怖や不安を感じ、性欲が高まりにくい傾向があります。
しかし、年齢とともに性交渉の経験を重ねていくと、徐々に快感を得やすくなりセックスに積極的になる女性も少なくありません。
満腹時
男性の場合、空腹時に性欲が高まりやすい傾向があるのに対し、女性は満腹時に性欲が高まる傾向があります。
これは、女性の性欲を刺激する中枢神経が満腹中枢を刺激する場所に近いためであると考えられています。
▶︎生理後は性欲が強くなる?生理周期別の性に関する過ごし方を紹介
女性で性欲が強いことはよくないことなの?
性欲が強くセックスを求める欲求は男性のほうが強いイメージがあり、女性と性欲の強さはイメージとして結びつかない方も多いのではないでしょうか。
しかし、これまでも紹介してきたように女性にも性欲は存在し、個人差はあるものの性欲が高まることは決して異常なことではありません。
セックスに依存し日常生活に支障をきたすほどでなければ、マスターベーションやパートナーとの性交渉で性欲をうまく発散し付き合っていくことが大切といえるでしょう。
▶︎40代の女性は性欲が強い?なくなる?その違いや性欲の対処法について
性欲がない女性の原因や理由

性欲の強さには個人差があり、男女ともに性行為に対する欲求がそれほど高くない人も存在します。
しかし、生まれ持った体質や性格以外にも、性欲が低い女性にはさまざまな原因が考えられます。
疲労・ストレス
肉体的な疲労やストレスが溜まっていると、性交渉に対するモチベーションが高まらず性欲が湧いてこない傾向があります。
これは女性に限らず男性にもいえることであり、しっかりとした休息やストレスの原因を取り除くことで解決できるケースがほとんどです。
性交痛
性交痛とはその名の通り、セックスの最中に感じる痛みのことを指します。
性交痛が生じる原因はさまざまですが、特に多いのは濡れにくく挿入がうまくいかないというケースです。
また、パートナーとの肉体的な相性がマッチせず痛みを感じることもあるようです。
妊娠・出産
妊娠や出産は性欲に大きな影響を及ぼします。
一般的に妊娠初期と妊娠後期、および出産後は性欲が低下していくとされています。
薬の服用
服用している薬の種類によってはホルモンバランスが崩れ、性欲が低下することがあります。
特に多いのがピルの服用です。
生理痛の緩和や避妊のためにピルを服用する機会が多いと、性欲の低下を招くケースも少なくありません。
性欲がない・湧かないときの対処法
性欲の低下はさまざまな原因によって引き起こされることがわかりましたが、これを放置しておくとパートナーや恋人との間に亀裂が入ることもあります。
そのような事態を招かないためにも、どのような対処法が有効なのでしょうか。
休息やストレスの発散
疲労やストレスが原因で性欲が低下している場合には、まずはしっかりと休息をとり身体を休ませることと、ストレスを発散することが大切です。
特にストレスの緩和に向けては、ストレスの原因となっていることを取り除くことが有効ですが、現実的に考えて難しい場合も多いでしょう。
そのような場合には、適度な運動をしたり、好きな音楽や映画、ドラマなどを楽しむなど、ストレスとうまく付き合っていく方法を試してみましょう。
性交痛を緩和するための工夫
性交痛によって性欲が低下している場合には、潤滑ゼリーを使用したり、痛みを感じにくい体勢を試してみるなどの工夫が効果的です。
パートナーとの話し合い
性欲の低下は誰にでも起こりうるものであり、パートナーから求められたからといって無理に付き合おうとするとストレスを感じてしまいます。
また、最悪の場合、パートナーに対する愛情や好意が低下する可能性もあるでしょう。
このようなすれ違いをなくすためにも、パートナーと十分に話し合い、お互いに思いやりをもって接することが大切です。
▶︎セックスレスになると離婚率が上がる?レスにならないための方法とは
女性が性欲と上手に向き合う方法とは
性欲が湧きづらい、または性欲の波が大きいことに悩みを抱える女性は少なくありません。
性欲は人間の本能でもあり、自分自身でコントロールすることは難しいものです。
しかし、性欲の高ぶりを抑えたり、セックスに対するモチベーションを上げるためにできる工夫は存在します。
性欲が強く抑えたいと感じるときには、マスターベーションやパートナーとの性交渉で発散するのがベストですが、それ以外にもスポーツなどで身体を動かしてみるのも有効です。
反対に、性欲が低いことに悩んでいる方は、無理のない範囲でパートナーと少しずつスキンシップを図ってみるのもおすすめです。
はじめのうちは性欲が低いと感じていても、スキンシップをはかるうちに徐々に気持ちが高ぶってくることもあります。
▶︎セルフプレジャーとは?美容効果を紹介!どんな人におすすめ?
まとめ
個人差はあるものの女性にも性欲は存在し、さまざまなタイミング・原因によって性欲が高まることがあります。
また、反対にちょっとしたことが原因で性欲は低下し、それが原因でパートナーや恋人との関係に亀裂が生じる可能性も少なくありません。
性欲が低い、または高いことに悩みを感じている方は、今回紹介した内容を参考にしながらうまくコントロールする方法を試してみましょう。
生理後は性欲が強くなる?生理周期別の性に関する過ごし方を紹介
女性の性欲には個人差があるほか、さまざまなタイミングによって性欲が強まったり減退したりすることがあります。
なかでも大きな影響を与えるとされているのが生理です。
本記事では、生理前と生理後で性欲はどのように変化していくのか、また、性欲が高まる理由や解消する方法なども解説します。
女性の性欲に関係するエストロゲンとは

性欲についてはさまざまな研究が行われていますが、なかでもエストロゲンとよばれる物質が性欲に大きな影響を与えていることがわかっています。
エストロゲンとは女性ホルモンの一種であり、女性の生殖器系や二次性徴、さらには身体の健康に多くの影響を与えています。
エストロゲンの分泌量が多いほど性欲は高まり、反対に分泌量が減ると性欲も減退していきます。
一般的に生理が終わった直後から排卵日にかけてはエストロゲンの分泌量が増えるため、性欲は高まる傾向が見られます。
反対に、妊娠初期および妊娠後期、出産後、更年期にはエストロゲンの分泌量が減るため、性欲も減退していく傾向にあります。
ただし、これらはあくまでも一般的な傾向であり、性欲の強さや波には個人差があります。
生理前に性欲が強くなる理由
性欲が強くなる背景には、相手に対する愛情や恋愛感情といった心理的な側面と、環境的な要素などが複雑に絡み合っています。
これらに加えて、生理的な側面から見てみると生理周期によってホルモンの分泌量が変化し、それが性欲を刺激しているケースもあります。
女性は生理周期のフェーズに応じてホルモンレベルが変化します。
一般的に、エストロゲンの分泌量がもっとも高くなるのは排卵期とされており、これが直接的な原因となって性欲を高めると考えられています。
排卵期とは、生理が始まる2週間程度前にあたります。
排卵期には妊娠の可能性が高くなることから、生物学的に考えてもこの時期に性欲が高まるのは当然のことといえるでしょう。
▶︎セックスレスの原因とは?|なりやすい夫婦の特徴や解消法を解説
生理後に性欲が強くなるのはメンタルが原因?

生理前や排卵期に性欲が強くなるのは、あくまでも一般的な傾向に過ぎず、必ずしもすべての女性がそうとは限りません。
なかには、生理後に性欲が強くなるケースもあるでしょう。
そのため、生理前の排卵期ではなく生理後に性欲が高まるからといって悩む必要はなく、あくまでも個人の体質の違いなどと捉えて問題ありません。
生理後に性欲が強くなる理由にはさまざまなものがありますが、なかでも多いのがメンタル面の影響です。
生理中は強烈な生理痛や体調不良に悩む女性も多く、精神的にも落ち込むケースが少なくありません。
また、セックスやマスターベーションをしたいのにもかかわらず、生理中にはその欲求が抑制された状態になってしまいます。
しかし、生理が終わった後はそれらの悩みから解放され、性欲が一気に高まるという方も少なくありません。
▶︎感情の起伏が激しい人や少ない人の特徴|上手にコントロールする方法とは
生理後に性欲が強くなる人の割合
女性の性欲が高まるタイミングは個人差があると紹介しましたが、生理前と生理後を比較するとどの程度の割合なのでしょうか。
さまざまなアンケート結果があり、その多くはほぼ半々の割合となっていますが、両者を比較してみると生理前のほうがわずかに高い傾向が見られます。
詳しく見ると、「生理前」と回答した女性の多くは「体調が変化し本能的に性欲が高まる」と回答しています。
反対に、「生理後」と回答した女性は、「生理が終わったという解放感があるから」という方や、「生理前はイライラしてセックスのモチベーションが上がらない」といった意見もありました。
▶︎40代の女性は性欲が強い?なくなる?その違いや性欲の対処法について
生理周期と性欲の推移

性欲の波は生理の周期と密接な関係があると紹介しましたが、一連の周期でどのように変化しているのでしょうか。
生理前から排卵、生理中、生理後のそれぞれのフェーズに分けて解説します。
生理前まで
前の排卵期が過ぎるとエストロゲンの分泌量が徐々に減っていき、それとともに性欲も減退していきます。
ただし、全く性欲がないというわけではなく、パートナーや恋人との接触やスキンシップなどによって性欲が高まるケースも少なくありません。
生理中
生理中は経血の影響もあり、セックスやマスターベーションが物理的に難しいほか、そもそもモチベーションが高まりにくいこともあり性欲は低い傾向にあります。
生理後から排卵前まで
生理後から排卵前の段階では、徐々にエストロゲンが増加し性欲が高まっていきます。
また、先ほども紹介した通り、辛い生理が終わったという解放感から性欲が一気に高まる女性も少なくありません。
排卵期
排卵日の前後2日間程度は排卵期とよばれ、子宮から卵子が放出されるため妊娠しやすいタイミングともいえます。
個人差はありますが、子孫を残すために本能的に女性の身体は敏感になり、性欲もピークに達するとされます。
▶︎50代女性の性欲事情|閉経後や更年期との関連性についても
生理前と後の性欲を解消させる方法
生理前と生理後では、性欲が高まる理由やメカニズムにも違いがあることがわかりました。
では、それぞれのタイミングで性欲を発散・解消するためにはどういった方法が効果的なのでしょうか。
生理前の性欲処理方法
排卵期に性欲はピークに達しますが、生理前のタイミングにかけて徐々にストレスを感じたり、イライラしたりすることもあります。
そのため、排卵期はパートナーとじっくり前戯を楽しみながら愛情のあるセックスを楽しんだり、お互いに試してみたいプレイや体位などに挑戦してみるのもおすすめです。
一方、生理が近づいてくると気が立ってくることもあるため、パートナーを傷つけないためにもしっかりと自分の体調を説明し、休息をとることも大切です。
どうしても性欲を抑えきれない場合には、パートナーとのセックスではなくマスターベーションで処理するという方法もあります。
生理後の性欲処理方法
生理後のタイミングは辛い生理が終わり、気分も高揚し解放感に満ち溢れることが多いです。
そのため、生理中に我慢していたプレイなども存分に楽しむことができます。
また、生理前のタイミングではいつ生理が来るか不安な気持ちがあり、プレイに集中できないことも多いですが、生理後はそのような心配がないため、多少は激しいプレイで性欲を発散できるでしょう。
▶︎セックスレスになると離婚率が上がる?レスにならないための方法とは
まとめ
性欲の強さや波についてはデリケートな問題であり、恋人や友人であっても相談することに抵抗を感じてしまいます。
女性にも性欲は存在し、性欲が強いことは決して異常ではありません。
また、生理をはじめとしてさまざまなタイミングで性欲の波はあり、日常生活に支障をきたさない程度であれば悩む必要はないでしょう。
生理前と生理後それぞれのタイミングで性欲が高まる理由は異なるため、パートナーと相談しながら適切に性欲を解消する工夫を心がけてみましょう。
セックスレスの離婚率はどれくらい?離婚するべきか?夫が拒否するのはなぜ?
長年にわたって生活をともにしている夫婦間にはさまざまな問題が生じることも多く、最悪の場合離婚に発展するケースも少なくありません。
なかでも、特にデリケートな問題のひとつに「セックスレス」があります。
実際にセックスレスが原因で離婚に至る夫婦も存在するなかで、有効な解決策や予防策にはどのようなものがあるのでしょうか。
セックスレスの離婚率はどれくらい?

セックスレスを理由に、実際に離婚に踏み切る夫婦はどれくらいいるのでしょうか。
極めてデリケートな問題のため正確な調査結果やデータは少ないですが、ある調査によればセックスレス夫婦の74.2%は離婚に至るというデータがあります。
ただし、これは欧米での調査であるため文化や家族観などの違いもあり、日本で同様のデータが得られるとは限りません。
しかし、セックスは夫婦関係を維持していくうえで重要なコミュニケーション、スキンシップのひとつであることは間違いないでしょう。
セックスレスでも円満な関係を維持できる夫婦はいますが、それが多数派とは限りません。
そのため、セックスレスの夫婦とそうでない夫婦を比較した場合、前者のほうが離婚のリスクが高まるというのは自然な見方ともいえるでしょう。
関連記事:夫婦喧嘩でやってはいけないこととは?子供への悪影響も解説
セックスレスで離婚は認められるのか

基本的に離婚は双方の合意があれば認められます。
しかし、すべてのケースがそうとは限らず、夫または妻が離婚を希望しているものの、相手がそれを認めない場合もあります。
このようなとき、裁判など法的な手続きを経ることで離婚を成立させる方法もあります。
民法では、離婚が認められる原因として以下の7つを定めています。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄(正当な理由なく夫婦の同居や協力、扶養義務を放棄すること)
- 3年以上の生死不明
- 強度の精神病
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由
このうち、「⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由」は抽象的な表現のためさまざまな解釈ができます。
結論からいえば、セックスレスは上記の原因に該当すると判断され、離婚が認められる可能性があります。
実際の判例においても、以下のようなケースにおいて離婚や慰謝料請求が認められています。
- 結婚後一度もセックスがなく、結婚前の段階で夫は妻に対して性交不能であることを告知していなかった
- 結婚した当初はセックスがあり子どももできたが、その後一方的に夫(または妻)から拒否されるようになった
関連記事:夫婦関係は修復できる?よくある破綻のきっかけや修復方法を紹介
セックスレスで離婚率が上がってしまう原因

セックスレスによって夫婦関係が壊れ、離婚につながってしまう理由についてもう少し詳しく考えてみましょう。
浮気のリスクが高まる
夫または妻がセックスを求めているのに対し、相手が拒否してしまうと不満が溜まってしまいます。
また、「自分は愛されていない」と感じ、ほかの人からの愛情を求めてしまうこともあるでしょう。
さらに、何らかの不満が溜まって浮気に走り、結果として夫婦間でのセックスレスに至るケースも少なくありません。
相手のプライドを傷つける
自分からパートナーに対してセックスを求めているのに、相手から拒否されてしまうと、「男性(または女性)としての魅力がなくなったのではないか」と感じ、プライドが傷つくことがあります。
男性または女性としての自信がなくなり、セックスそのものに恐怖心を抱いてしまうこともあるでしょう。
同時に、愛情をもって接していたパートナーに対し、プライドを傷つけられたことが憎しみの感情に変わっていく可能性も考えられます。
相手に対する不信感が募る
セックスを拒否する理由はさまざまで、なかには「仕事や家事、育児で疲れているから」、「加齢に伴い性欲そのものが減退したから」という人も少なくありません。
しかし、そのような理由を説明しないまま一方的にセックスを拒否してしまうと、パートナーは「浮気しているのではないか」と疑いの目を向け、不信感を募らせるケースもあります。
また、疑われた側からしてみても、「自分は家族のために頑張っているのに…」と不満を抱くこともあるでしょう。
その結果、夫婦間に修復しきれないほどの亀裂が生じてしまい、最悪の場合離婚に至る可能性も出てきます。
関連記事:セックスレスの原因とは?|なりやすい夫婦の特徴や解消法を解説
セックスレスかもしれない夫婦の特徴や兆候

セックスの頻度は個人や夫婦間によっても異なるため、セックスレスと感じる基準はあいまいです。
では、セックスレスに至る夫婦やカップルにはどのような特徴や兆候が見られるのでしょうか。代表的なパターンをいくつか紹介します。
夫婦間のスキンシップやコミュニケーションが減っている
長年にわたって一緒に暮らしていると、その暮らしが当たり前となってしまい、夫婦関係がマンネリ化することがあります。
結婚前や新婚当初はさまざまな話をしたりスキンシップを積極的にとっていたにもかかわらず、それが減ってしまうと愛情を感じられなくなり、やがてはセックスレスに陥る可能性があるのです。
セックスそのものが淡白
セックスに対する価値観は男女または個人によっても異なります。
ありがちなのは、パートナーに快感を与えるという心配りがなく、自分が快感を得られればそれで良いというケースです。
セックスそのものが淡白に終わってしまい、愛情表現やスキンシップが成立せずに自然とセックスから遠ざかってしまうこともあります。
仕事や家事が忙しく夫婦の時間をとれない
疲労やストレスが蓄積すると、セックスを楽しむ余裕がなくなってしまいがちです。
特に仕事や家事が忙しいとパートナーとのライフサイクルがずれてしまい、夫婦で過ごす時間そのものが確保できなくなることもあるでしょう。
セックスレスで離婚するべきか?

セックスレスで離婚するべきかどうかという問題は、一概にどちらが良いとは言い切れません。
しかし、最終的にどうなるかは分からないにしても、お互いに後悔する結末になってしまうのは絶対に避けたいところ。
セックスレスになったからといって夫婦関係が破綻してしまったと判断して、すぐに離婚と考えるのは少々早計であるといえるでしょう。
基本的には、まずは話し合いからということになるでしょうが、セックスレス解消への糸口を見つけ出そうと夫婦で協力することが大切です。
夫が拒否するようになるのはなぜ?

セックスレスの原因は、夫か妻のどちらかがセックスを拒否するところから始まることが多いですが、ここでは、夫が拒否する場合によくある理由を見ていきましょう。
妻を女性として見られなくなってしまった
長年生活を共にすることで、妻のことを親兄弟のような意味での“家族”や、子どもができると“母親”として見てしまい、セックスの対象として意識できなくなるケースは少なくないようです。
妻が夫に対して抱く「ときめきやドキドキ感」を感じられなくなってしまうのと似た感覚かもしれません。
子作りへのプレッシャーが強い
そもそも大前提としてセックスは生殖行為ですが、我々人間にとってはスキンシップの一環や愛を確かめ合う行為という側面が強いです。
ムードを高めることで男女ともに得られる快楽も高まりますが、子作りが目的となってしまうと一気に作業感が出てしまい、心の底から楽しめなくなることもあるようです。
特に近年の日本は晩婚化や高齢出産のリスクなどが問題となっているため、こうしたプレッシャーを受ける機会が必然的に多くなっています。
疲れ果ててセックスどころではない
30~40代くらいになると、多くの人が仕事が最も忙しい時期であり、毎晩遅くにへとへとの状態で帰宅するということも珍しくないでしょう。
セックスは時間も体力も使う行為であるため、このような生活を送っていると、なかなかセックスどころではないという人がいるのも仕方ないことです。
近年は共働き世帯も増えており、夫が早く帰宅できた日に限って妻の帰りが遅く、結局セックスするタイミングがないということもあるでしょう。
加齢で精力が減退してしまった
男性の性欲のピークは10~20代ほどとされており、その後は緩やかに減退していくことが研究結果から明らかになっています。
実際には30代くらいまでは性欲の強い人も多いですが、勃起力という点で20代までと比べて衰えを感じることも少なくないようです。
また、先述したように仕事の疲れなどと相まって性欲より睡眠が優先となってしまうことが多いと考えられます。
セックスは面倒なので一人で処理したい
男性にとってセックスにおいて最も快感を感じられるのは射精のタイミングであり、女性は快楽そのものよりも行為全体のムードを大切にするといわれています。
男性全員に当てはまる話ではありませんが、正直にいうと前戯は面倒で、さっさと挿入して射精したいと考える人も中にはいるでしょう。
このように考える男性は次第にセックスが面倒と感じるようになり、拒否するようになることがあると考えられます。
セックスレスにならないための方法や対策

セックスレスに至らないようにするためには、どのような方法や対策を心がけるべきなのでしょうか。
スキンシップやコミュニケーションを増やす
意識的にスキンシップやコミュニケーションを増やすことを心がけましょう。
お互いの目を見て会話をしたり、パートナーの良い部分をさり気なく褒める、感謝の気持ちを伝えたりすることで円満な夫婦関係につながり、自然とセックスレスが解消される可能性があります。
お互いに思っていることを話し合う
肉体的な衰えやセックスに対するモチベーションの低下など、セックスレスに至る原因は夫婦によってもさまざまです。
セックスレスに陥りそうなとき、自分自身の状況をパートナーに打ち明けられないことも多いですが、ありのままを話し合うことによって理解してもらえる可能性があります。
また、パートナーからそのような相談を受けたときには、相手を尊重し無理を強いない気遣いも大切です。
夫婦カウンセリングを受けてみる
セックスレスに関する漠然とした不安がある方や、夫婦間でセックスに関する悩みを抱えており解決方法が分からない場合には、カウンセリングを受けてみるのもひとつの方法です。
夫婦間の問題解決をサポートする専門のカウンセラーや医師も存在し、問題の根本原因を探りながら認知行動療法などによって解決に導きます。
関連記事:セックスセラピーとは|カウンセリングの内容や受けられる場所は?
セックスレスを解消した夫婦の体験談

セックスレスは離婚の原因にもなるとお伝えしてきましたが、世の中にはさまざまなアプローチでこの問題を解決してきた夫婦がいます。
ここではその体験談の一部を紹介します。
一度距離を置いた
一度距離を置き、一緒にいる時間が減ったことで、一緒に過ごす夜が貴重と感じるようになりました。“今晩しなければ、今週はもうできない”という気持ちが芽生えて、いつの間にかセックスレスが解消していました。
思い出のホテルへの宿泊がきっかけとなった
10回目の結婚記念日に挙式をしたホテルでの宿泊が、私たちの間の誤解を解くきっかけになりました。険悪になり始めた頃のことについて話し合い、互いに謝罪することで、わだかまりが解け、次第に夫婦関係も回復していったと思います。
EDであることをカミングアウトした
EDに悩んでいたけど、全てを打ち明ける覚悟をしました。妻も受け入れてくれて挿入にこだわる必要はないんだと気づき、さまざまな愛撫を楽しむようになりました。その結果、私たちの関係は大きく改善したと思います。
まとめ
日本では3組中1組の割合の夫婦が離婚に至っており、その原因はさまざまです。
今回紹介したセックスレスのように、他人に相談しづらいデリケートな問題もあるでしょう。
しかし、だからといって一人で悩む必要はなく、まずはパートナーに対してありのままを相談し、夫婦で乗り越えようとすることが大切です。
どうしても解決が難しい場合には、専門のカウンセラーや医師に相談するなどの方法もあります。
モラハラ夫の特徴は?人格否定の言葉を一覧で紹介
結婚生活を送っていると、独身時代では見えなかった一面が見えてくることもあります。
特に多く聞かれるのが、モラハラ(モラルハラスメント)にあたるような言葉の暴力です。
本記事では、夫からのモラハラに悩む女性に向けて、モラハラ夫にはどんな特徴があるのか、モラハラの一例や子どもへの影響、正しい対処法について解説します。
モラハラ夫の特徴

モラルハラスメント(モラハラ)とは、精神的な暴力や嫌がらせなどによって、相手の尊厳を傷つける行動を指します。
モラハラは特に夫婦間で問題になるケースが多く、夫から妻に対して行われるモラハラが多いですが、妻から夫に対して行われるパターンもあります。
モラハラを繰り返す夫には、主に以下のような特徴が見られます。
支配欲が強い
モラハラ行為をする夫は、自分の思う通りに妻をコントロールしたいという支配欲が強い傾向があります。
自己中心的
妻の気持ちや心情は顧みることなく、夫自身の思いや考えを優先する傾向が見られます。
また、自分の意見や考えを強制し、妻に対して選択の自由を与えないこともあります。
感情の制御が難しい
ちょっとした出来事やタイミングで怒りが頂点に達し、感情を適切に処理できないことがあります。
人格否定
妻本人の人格や能力を否定する言葉を頻繁に投げかける傾向があります。
▶︎知らず知らずに起こっている?ハラスメントの種類や防止方法を紹介
モラハラ夫の発言例
モラハラ夫は自己中心的で感情の抑制が難しいといった特徴がありますが、具体的にどういった言葉を発するのでしょうか。
一例を紹介します。
ミスや失敗を執拗に責め立てる例
- 「また同じミスを繰り返すなんて、お前は何を考えているんだ?」
- 「こんな簡単なこともできないのか?教えたはずだろう?」
- 「何度同じことを言わせるんだ?一度で理解しろよ」
ミスや失敗をしたとき、それを指摘したり正しい方向に導くのは夫婦として当たり前のことですが、強い口調や何度も責め立てる行為はモラハラにあたる可能性が高いでしょう。
人格を否定する発言の例
- 「お前の考えはいつも間違っている」
- 「お前は役立たずだ」
- 「誰もお前のような人間を必要としないだろう」
ミスや失敗をしたり、間違った意見を述べたりしたときには、その事実を冷静に諭すことが大切です。
しかし、妻本人の人格を否定するような強い言葉を日常的に投げかけていると、モラハラにあたる可能性があります。
大声で怒鳴る例
- 「お前はいつも全てを台無しにする!」
- 「何もかもお前のせいだ!」
- 「いつもお前のせいで俺の時間を無駄にしている!」
大きな声や音を出されると、誰しも恐怖を感じ萎縮してしまうものです。
大声で怒鳴るという行為は、上記のセリフに該当しなかったとしても、その行為自体がモラハラとみなされる可能性があります。
▶︎情緒不安定になると泣くのはなぜ?|情緒不安定になりやすい人や原因とは
モラハラ夫かもしれないチェック項目

一口にモラハラ(モラルハラスメント)といってもさまざまなパターンがあり、人によっても言動は異なります。
モラハラをする夫にはどういった特徴が見られるのか、代表的なポイントは以下の通りです。
- 妻が楽しく会話をしていると気に入らない態度を見せたり、不機嫌になる
- 明らかに夫に落ち度があるにもかかわらず、妻に謝らない
- 妻のミスや失敗を執拗に責め立てる
- 気に入らないことがあったり、機嫌が悪かったりすると妻を無視する
- 嘘をつく
- 妻および妻の家族や友人の人格を否定する言葉を言う
- 過度な嫉妬・依存・束縛
- 大声で怒鳴る・わざと大きな音を出す
- 妻の仕事を無理やり辞めさせる
- 家族や友人との交遊を制限する
上記はあくまでも一例に過ぎず、細かく見ていくとこれ以外にもモラハラにあたる言動や行動はあります。
自分の夫がモラハラを行っているのか、よくわからない場合には、上記の特徴にどの程度該当しているのかをチェックしてみましょう。
もし、該当項目が多ければモラハラ夫である可能性が高いかもしれません。
モラハラ夫になりやすい人の特徴や原因
結婚したばかりの頃はうまくいっていたのに、結婚生活を送るうちにモラハラ行為が行われるようになるケースが少なくありません。
どういった人がモラハラ夫になりやすいのか、その特徴や原因についても紹介しましょう。
自尊心が低い
もともと自尊心が低い人のなかには、他人を否定したり支配したりすることで自己肯定感を満たすケースがあります。
結婚前の段階ではパートナーに対してそのような言動をしていなくても、第三者に対して否定的な言葉や言動を繰り返している場合、結婚後にモラハラ夫へと変貌する可能性は否定できません。
幼少期の家庭環境や周囲の環境
幼少期や思春期の家庭環境や、周囲の環境がモラハラの原因となることがあります。
たとえば、幼少期に親などから虐待・ネグレクトを受けた経験がある人や、適切な教育を受けてこなかった人の場合、周囲の人との接し方に戸惑い人間関係にさまざまな影響を与えるケースがあります。
偏った思想・価値観
偏った思想や価値観がモラハラの原因になることもあります。
たとえば、男性が強く支配的であるべきという価値観に囚われすぎていると、現代社会の価値観とはマッチせずそれがストレスを生み、モラハラを悪化させる要素になることもあるでしょう。
▶︎感情の起伏が激しい人や少ない人の特徴|上手にコントロールする方法とは
モラハラ夫による子供への影響

モラハラ夫が子供に与える影響は深刻で、時には子どもの精神や健康にも影響を及ぼす可能性があります。
具体的にどういった影響が考えられるのか紹介しましょう。
自尊心の低下
親から自分自身を否定される言葉を投げかけられた子どもは、つねに否定的な見方をするようになり、「自分はだめな人間だ」と感じ自尊心の低下を招きます。
精神的な不安・障害
モラハラを受けた子供は精神状態が不安定になる可能性があり、不安や抑うつといった状態が続きます。
あまりにも酷いモラハラを受けた場合、PTSD(心的外傷後ストレス障害)を引き起こすおそれもあり、精神的に立ち直るまで長い時間を要する可能性もあるでしょう。
人間関係のトラブル
モラハラを受けた子供はつねに否定的な見方をするようになりますが、それは自分自身だけでなく、第三者に対しても向けられることがあります。
自宅の外でも親の言動を真似するようになり、やがて友人や知人との人間関係が悪化しさまざまなトラブルを引き起こす可能性もあるでしょう。
▶︎自己肯定感が低い子供の特徴や言動とは|注意すべき親の発言や行動
モラハラ夫への対処法・仕返しはしてもいい?
自分自身がされてきたことを振り返ると、夫に何らかの仕返しや制裁をしたくなる気持ちも理解できますが、仕返しは絶対に避けるべきです。
モラハラ夫への対処を一歩間違うと、場合によっては危害を加えられたり、余計に関係がこじれてしまう危険があるためです。
では、どのような対処が正しいのでしょうか。
自己認識をする
モラハラは物理的な虐待とは異なり、はっきりと見える証拠がないほか、夫の言い分によっては「自分にも悪いところがあるのかもしれない」と錯覚しがちです。
実際に悪いところがあったとしても、執拗に責め立てたり、人格を否定するような言葉を投げかける行為は立派なモラハラであり、自分がその被害に遭っているとしっかり認識することが何よりも大切です。
証拠の記録
可能であれば、万が一に備えてモラハラ行為が行われている状況を記録しておきましょう。
具体的には、メールやチャットなどのテキストデータ、モラハラ行為を収めた動画や写真のほか、日記も立派な証拠になり得ます。
安全な場所に避難する
モラハラ行為がエスカレートし、自分自身に危害が及んだり、精神的に限界を迎えそうになったときには、安全な場所に避難することも考えてください。
実家はもちろんのこと、信頼できる友人の家、ホテルなどが一般的ですが、ほかにもDV被害者を守るためのシェルターなどもあります。
支援を求める
モラハラは一人で解決することが難しい問題です。
夫婦間の問題だからといって一人で抱え込んでしまうと、夫からのモラハラ行為がさらにエスカレートし、警察沙汰になることも十分考えられます。
一人で悩むのではなく、まずは信頼できる友人や家族などに相談し、必要であれば心理カウンセラーや専門家、地域の支援団体などに頼ってみるのもひとつの方法です。
▶︎夫婦関係は修復できる?よくある破綻のきっかけや修復方法を紹介
まとめ
モラハラという言葉は聞いたことがあっても、自分の夫が行っている行為がモラハラにあたるのか分からず、自分の考え過ぎなのではないかと捉えてしまうケースも少なくありません。
もし、「夫からモラハラを受けているかもしれない」と感じたときには、今回紹介したチェック項目や発言例、対処法を参考にしながら、自分自身を守るための行動に移してみてください。
友達を作る場所はどこ?社会人で遊ぶ友達がいないのはやばい?
「自分には友達とよべる存在がいない、または少ない」と感じ、友達作りに苦手意識をもっている方も多いのではないでしょうか。 特に社会人になると学生時代の友達と遊ぶ機会も減り、友達の数が減っていくケースも少なくありません。 そこで本記事では、新たに友達を作るためにはどういった方法があるのか、友達作りに適した場所も紹介します。
友達を作るメリット
 そもそも、友達を作ることは私たちが生活を送るうえでどういったメリットがあるのでしょうか。
そもそも、友達を作ることは私たちが生活を送るうえでどういったメリットがあるのでしょうか。
楽しい時間を共有できる
友達と過ごす時間はかけがえのないものであり、笑いや喜び、楽しみを提供し、人生を豊かなものにしてくれます。 このような時間は決してお金で買うことはできず、何物にも代えられない幸福感を得られるはずです。
第三者の視点でアドバイスが受けられる
人は誰でも長所と短所があり、本人が気づかないことも少なくありません。 だからこそ客観的な立場から指摘やアドバイスをしてくれる友達の存在は大きく、自分自身の成長にもつながっていきます。
不安・悩みの低減
私たちが生活していくうえではさまざまなストレスがあり、不安を感じることが少なくありません。 また、仕事や私生活における悩みを抱えることも多く、中には家族に話せないような悩みもあるでしょう。 そのようなとき、友達の存在は非常に大きく、話を聞いてもらうだけでも精神的な不安や悩みを低減できる場合もあります。
友達がいなくても作ることができる?
友達がいない、または少ない人のなかには「自分にはこの先、友達ができないのではないか」と感じるケースもあるでしょう。 しかし、結論からいえば、現在友達がいない、あるいは少ない状態であっても、具体的な行動を起こしていけば必ず新たな友達を作ることは可能です。 決して悲観的になる必要はなく、焦らず自分のペースでさまざまな人とコミュニケーションをとりながら、信頼できる友達を見つけていきましょう。
▶︎【シーン別】人間関係がめんどくさいと感じる心理や対処法を解説
学校での友達の作り方とは
 友達と聞くと、幼馴染や学生時代から付き合いのある古い友人関係をイメージすることも少なくありません。 では、中学生や高校生が学校で友達を作るためには、どういった方法があるのでしょうか。
友達と聞くと、幼馴染や学生時代から付き合いのある古い友人関係をイメージすることも少なくありません。 では、中学生や高校生が学校で友達を作るためには、どういった方法があるのでしょうか。
共通の趣味をもつ人を見つける
中学生や高校生は特に多感な世代であり、ゲームや音楽、スポーツなど、さまざまなことに興味をもちます。 人によっても興味をもつ事柄やコンテンツは異なりますが、知らない人と距離を近づけるためには共通の趣味に関する話題を切り出してみると良いでしょう。 もしかすると、同じように共通の趣味をもつ仲間を紹介し交友関係が広がっていく可能性もあります。
他人を尊重する
学校という場は社会の基本を学ぶ場でもあり、コミュニケーションのとり方もそのひとつです。 友達を作るためには、相手を尊重する気持ちと姿勢が何よりも大切です。 「尊重」という言葉は抽象的でわかりにくいですが、具体的には相手の話を最後まで聞く、悪口を言わない、相手のことを否定しないことなどが挙げられます。 尊重する気持ちがないと、相手は警戒心を抱いてしまい、信頼できる仲間になろうという気持ちが薄らいでいってしまいます。 たとえ友達という関係にならなかったとしても、クラスの一人ひとりに対して尊重する気持ちをもっていれば好印象を抱かれ、良好な人間関係を構築できるはずです。
▶︎自己肯定感が低い子供の特徴や言動とは|注意すべき親の発言や行動
社会人の友達の作り方とは
学校を卒業し社会人になると、仕事や家事、子育てなどで時間がとれず、新たな友達を作る機会も減ってきます。 そのような状況下でも友達を作りたいと考えた場合、どういった方法があるのでしょうか。
友達を作りたい場所に出かけてみる
社会人の場合、新たな人脈を作ろうと考えても会社と家の往復ばかりで、出会いが見つからないケースも少なくありません。 そこで、まず大切なのは自分から積極的に外に出て、友達を作れる場所を見つけることです。 共通の趣味で盛り上がれる人や、同世代の友達が欲しい場合には、そのような人が集まりそうな場所を探してみるのが友達作りの第一歩となるでしょう。
こまめに連絡をとる
友達という深い関係になかったとしても、知人や顔見知り程度の人も多いはずです。 もし、その中に「この人と仲良くなりたい、友達になりたい」と感じる人がいれば、積極的に連絡を取り合ったり、声をかけて連絡先を交換したりしましょう。 こまめに連絡を取り合うことでお互いのことがより深く理解でき、友達に発展していく可能性も出てくるでしょう。
仕事を頑張る
就職や転職を機に上京した場合、新たな環境のなかで仕事を覚えなくてはなりません。
そのため、まずは新たな仕事に慣れるためにも、仕事に集中しましょう。
プライベートのことは忘れ仕事に取り組むことで、時間が経つのを忘れ充実感を得られるでしょう。
また、同僚や上司とのコミュニケーションも生まれ、職場のなかで交友関係が広がっていくことで孤独感が解消できるかもしれません。
友達を作るのにおすすめの場所

社会人にとって、新たに友達を作るためには自分から外に出て出会いを探すことが大切であるとお伝えしました。 しかし、これだけでは抽象的で、どこに出かければ良いのか分からないという方も多いでしょう。 友達を作るのにおすすめの場所として、いくつかの例を紹介します。
スポーツジム
運動不足の解消や体力作り、ダイエットなどを目的としてスポーツジムに通っている人も多いのではないでしょうか。 スポーツジムは週に数回、定期的に通うケースが多いほか、仕事終わりや週末など決まった時間帯に通うことが多いはずです。 通っているうちに自然と顔見知りの人も増えてくるため、少しずつ仲良くなって新しい友達ができる可能性もあるでしょう。
サークル・カルチャースクール
社会人になっても趣味を楽しんだり、新たなことに挑戦したりするために、サークルやカルチャースクールに通う人も少なくありません。 同じ趣味をもっていたり、共通の目標に向かって努力している人の集まりでもあるため、自分から積極的に声をかけることで友達の関係に発展していく可能性は高いでしょう。
異業種交流会
さまざまなことに興味があり、あえて自分とは知らない世界の人と友達を作ってみたいと考える方もいるでしょう。 そのような場合には、異業種交流会に参加してみるのもおすすめです。 ビジネスを目的として参加している人も多いですが、純粋に新たな人脈を作るために参加している人も少なくありません。 自分自身が在籍している組織や業界、業種とは文化の異なる人と交流することで、新たな発見をしたり魅力的な人に出会える可能性があります。
ライブハウス・音楽フェス
音楽が趣味の人であれば、ライブハウスや音楽フェスなどに行ってみるのもおすすめです。 一人で行くことに抵抗を感じる方も多いですが、実際に会場に行ってみると一人でも楽しんでいる人は意外と少なくありません。 何よりも共通の趣味をもっているため、勇気を出して自分から話しかけることで話が弾み、友達を作れる可能性があります。
▶︎セルフ・コンパッションとは?やり方やマインドフルネスとの違いを解説
アプリやゲームで友達を作るのはアリ?
スマートフォンでも気軽にできるオンラインゲームが発達し、プレイヤー同士で直接交流できるようになりました。 また、近年ではマッチングアプリのユーザーも多く、自宅にいながら多くの人とコミュニケーションをとることができます。 一見すると便利なツールのように思われますが、これらの方法で友達を作る際にはリスクや危険があることも覚えておかなくてはなりません。 たとえば、アプリ上では同性だと思ってやり取りしていたのに、実際に会ってみたら異性がやってきて、さまざまなトラブルに巻き込まれるリスクもあるでしょう。 アプリやゲームで仲良くなったからといって、すぐに会おうとするのではなく、本当にその人が信頼できる人物であるかを見極めることが大切です。
異性の友達を作り方
同性の多い職場や学校などに在籍している場合、異性とコミュニケーションをとる機会が極端に少ないという方も多いでしょう。 もし、異性の友達を作りたいときには、上記で紹介したスポーツジムやサークル、カルチャースクール、異業種交流会などに出かけてみるのもおすすめです。 また、合コンや街コン、友人の結婚式も異性の友達を作るための絶好の場所といえます。 ただし、自分自身は友達を作りたいと考えているのに、相手によっては恋人や結婚相手を探しているというケースも少なくありません。 お互いの認識違いによってトラブルに発展しないよう、十分にコミュニケーションをとることが求められます。
▶︎愛情表現の言葉とは?|愛してるよりも愛が伝わる方法を紹介
まとめ
友達が少ない方にとって、一から人脈を築いていくことは大変で面倒に感じてしまうものです。 しかし、だからといって家に引きこもっていたり、友達作りを放棄してしまうと、悩みは解決できないままになってしまいます。 今回紹介した友達作りの方法やおすすめの場所を参考にしながら、まずは一歩を踏み出す勇気をもち、行動に移してみましょう。
友達がいないってやばいこと?寂しいと感じた時の対処法
休日やイベントがあるときなど、街を見渡すと楽しそうに友達同士で楽しんでいる人を見かけます。
そのような光景を目にしたとき、友達とよべる存在がおらず寂しい気持ちになった経験はないでしょうか。
本記事では、友達がいなくて悩んでいる方に向けて、寂しさを感じたときの対処法などを詳しく解説します。
友達がいないと寂しく感じるとき

普段は一人でいるのが当たり前に感じていても、友達がいないことを寂しく感じる瞬間は存在します。
具体的にどういったときに寂しさを感じやすいのか、代表的な例をいくつか紹介しましょう。
一人暮らし
大学や専門学校へ進学したタイミングや、社会人になったタイミングで一人暮らしをする方も少なくありません。
友達を自宅に招いて食事やお酒、ゲームなどを楽しむことも多いですが、友達がいないとそのような体験ができず、寂しさを感じることがあるでしょう。
結婚式
結婚式では日頃からお世話になっている友達や知人を招いて祝ってもらうのが一般的です。
しかし、友達がいないと特別な日を共有する人が少なく、寂しいと感じるかもしれません。
成人式・同窓会
成人式や同窓会は、学生時代をともに過ごした仲間と再会する貴重な機会でもあります。
友人同士で青春時代を懐かしんだり、近況報告をして盛り上がったりするのが定番ですが、友達がいないと成人式や同窓会の場に行くこと自体が億劫に感じたり、そもそも呼ばれなかったりして自然と疎遠になってしまいがちです。
学校
学校は社会生活やルールを学ぶ場でもあり、友達がいると学校生活がより楽しく有意義に感じられるものです。
しかし、学校で友達ができないと孤独を感じ、学校へ行くこと自体に恐怖を覚えるケースも少なくありません。
▶︎【シーン別】人間関係がめんどくさいと感じる心理や対処法を解説
友達がいない人の特徴

友達がいない、または少ない人は、その人の性格や過去の経験、さらには現在の生活状況などが影響を及ぼすことがあります。
一概に全ての人に当てはまるものではありませんが、具体的にどういった特徴が見られるのか解説しましょう。
内向的な性格
内向的な性格の人は自分自身の世界に引きこもり、自分から他者と積極的に交流をしようとしない傾向が見られます。
内向的な性格の人は、他者と一緒にいるよりも一人でいることを好むため、友達ができたとしても自然と疎遠になっていきやすい傾向にあります。
コミュニケーションが苦手
コミュニケーションが苦手な人も友達が作りにくく、一人になりがちな傾向にあります。
一口にコミュニケーションといってもさまざまで、たとえば感情の表現が苦手な人もいれば、共感の意思を伝えるのが苦手な人、相手が話す言葉の真意を汲み取ることが苦手な人など、多種多様です。
自尊心が低い
自分に自信がなく、自尊心が低い人は友人関係を築くのが難しく感じることがあります。
たとえば、外見にコンプレックスを抱いている、極端に相手に気を遣ってしまう、過去に大きな失敗やいじめを受けた経験があるなど、自尊心が低くなる要因はさまざまです。
自尊心が低すぎると、「自分にはどうせ友達ができない」と諦め、他者との交流を断ってしまうケースもあります。
友達がいない人の割合
「友達がいない」と自覚している人のなかには、自分と同じような境遇にある人はどの程度存在するのか気になってる方も多いはずです。
特に、2020年に入ってからはコロナ禍もあり、友達を作る機会や友達と会う機会も減ったことから、このような悩みを抱える人が増えたことは想像に難くありません。
BIGLOBEが2022年9月に実施した調査によると、「友達がいない」と回答した人の割合は40代がもっとも多く、52.0%でした。
次いで20代の49.8%、30代の49.0%と続きます。
一方、もっとも割合が少なかったのは10代で、35.0%という結果になりました。
社会人になると友達がいなくなる?
上記の結果から見えてくるのは、10代に比べて20代以上が「友達がいない」と感じていることです。
20代といえば大学や専門学校などを卒業し、社会人として働き始める年代であり、さらに30代や40代になると結婚をして子育てが忙しくなっていきます。
学生時代の友達と再会したり、新しく友達を作って遊んだりする時間も作りにくく、自然と友達と疎遠になっていくケースも多いようです。
また、仮に自分自身が結婚をしなかったとしても、周囲の友達が次々と結婚や出産をしていくと、自分から友達を誘いにくくなってしまうケースも少なくありません。
▶︎友達の作り方|場所と手順を社会人から学生ごとに分けて解説!
毒親育ちは友達がいない?
友達がいない、または少ない人は、本人の価値観や考え方、性格や言動などに原因があるケースもあれば、周囲の環境が要因となっているケースもあります。
そのなかでも、典型的な例ともいえるのが親との関係性です。
いわゆる「毒親」のもとで育った子どもは、友達付き合いに親が口を挟んできたり、親から酷い言葉や暴力を繰り返されたりすることで、人間不信となることがあります。
自分以外の人を信じることができなくなり、つねに怯えたような性格になることで、友達になりたい人が現れてもそれを拒否してしまうのです。
もちろん、毒親のもとで育った子どものなかにも、友達ができて良好な人間関係を構築している人も大勢います。
一方で、友達がいない人の家庭環境は、必ずしも良好とはいえないケースが多いものです。
▶︎自己肯定感が低い子供の特徴や言動とは|注意すべき親の発言や行動
友達がいなくて寂しいと感じた時の対処法

友達がいないことで寂しいと感じたとき、自分自身のメンタルを安定させるためにどういった対処法が効果的なのでしょうか。
オンラインで交流してみる
寂しさを感じるときは友達を作ることがベストな対処法といえますが、すぐに他人と信頼関係を築くことは難しいものです。
また、いきなり対面でのコミュニケーションをとることに抵抗を抱く方も多いでしょう。
そこで、まずはSNSなどを通してさまざまな人と交流してみるのがおすすめです。
親しくしていた友人に連絡してみる
オンラインであったとしても、顔の見えない知らない人と交流することに抵抗を抱く方もいるかもしれません。
そのような場合には、学生時代の友人や以前働いていた職場やアルバイト先の同僚など、親しくしていた人に連絡をとってみるのもおすすめです。
久しぶりに連絡をもらうと嬉しい気持ちになる人は多く、そこから話が弾んで友達としての関係が再スタートする可能性もあるでしょう。
外に出かけてみる
友達がいなく寂しい気持ちはあるものの、SNSで交流したり、仲が良かった人に連絡するといったアクションを自分からとることは勇気がいるものです。
あくまでも自然な形で友達を作りたいと考える方は、自宅の中にいるのではなく、できるだけ外に出かけてみることが第一歩となります。
たとえば、飲食店の店員さんに声をかけられて話が弾み、常連さんを紹介してもらい交友関係が広がっていくことも考えられるでしょう。
▶︎セルフ・コンパッションとは?やり方やマインドフルネスとの違いを解説
友達がいないことってやばいことなの?
「友達がいない」と聞くと、なんとなく暗い人というイメージをもたれがちです。
たしかにコミュニケーションが苦手で、自分から話しかけることができずに友達をつくれなかったという方もいるでしょう。
しかし、だからといって悲観的になりすぎることはありません。
上記でも紹介したように、「友達がいない」と回答した人は決して少なくなく、「自分だけがおかしい、やばい」などと考える必要はないのです。
まとめ
友達がいない、少ないと、普段は一人で快適な生活ができていても、ふとしたときに寂しさを感じることがあります。
友達がいないことを気にするあまり、さらに自分の殻に閉じこもってしまう人も少なくありません。
しかし、友達をつくりたいと考え、行動に移すことで、考え方や価値観のあう友達は必ず見つかるはずです。
決して悲観的にならず、焦らず自分のペースで少しずつ行動を起こしていきましょう。
人間関係が「めんどくさい」「疲れた」と感じる心理や対処法を解説
友人や職場の同僚、サークルの仲間など、それまで良好な関係を構築してきたにもかかわらず、ある日突然人間関係が「めんどくさい」と感じることはないでしょうか。
さまざまな理由や原因がありますが、なぜこのような瞬間が訪れるのでしょうか。
本記事では、その心理や背景、どのようなシーンが考えられるのかを紹介します。
人間関係がめんどくさいと感じる瞬間

私たちが社会生活を送るうえで、人間関係がめんどくさいと感じるのはどのようなときなのでしょうか。
典型的な例を紹介します。
職場の人に気を遣わなければならないとき
職場で円滑に仕事を進めていくためには、上司や同僚、部下などに気を遣わなければならない場面も多いものです。
特に昨今ではパワハラやセクハラといったハラスメント行為が問題視されることも多く、立場に関係なく言葉遣いや言動、接し方に注意しなければなりません。
自分自身を否定されたとき
ビジネスの場面に限らず、プライベートにおいても人間関係をめんどくさいと感じることもあります。
特に、第三者から自分に対して否定的な言葉を投げかけられたときや、陰口が耳に入ってきたときなど、その人と信頼関係を築くことが面倒に感じてしまいます。
相手が不機嫌な態度をとってきたとき
自分自身は良好な人間関係を築きたいと考えているにもかかわらず、相手が不機嫌な態度をとってしまうケースもあります。
このような場合、相手の機嫌を損なわないよう過度に気を遣わなければならないため、めんどくさいと感じることも少なくありません。
人間関係がめんどくさいと感じるときの心理
どのような人であっても、初対面のときには相手と仲良くなりたい、良好な関係を築きたいと考えることが多いものです。
その状態から、どのような心理が影響して人間関係がめんどくさいと感じるようになるのでしょうか。
我慢や無理をしてしまう
良好な人間関係を築くために、自分自身が我慢をしたり無理をしたりするケースもあります。
たとえば、相手と考え方や意見が異なっていたとしても、波風を立てないようにするあまり自分の意見を押し殺してしまうと、本音が言い合えなくなってしまいます。
その結果、相手の言動や価値観までもが理解できなくなり、人間関係そのものがめんどくさいと感じてしまうのです。
相手に嫌われたくない
自分自身が我慢をしたり無理をしたりするのは、波風を立てないようにするのと同時に、無意識のうちに相手から嫌われたくないという心理も働いています。
自分の本音を言ってしまうと相手が怒り、喧嘩になってしまうのではないかと過度に恐れるという経験はないでしょうか。
そのようなことがあると、やがて人間関係そのものに疲れてしまい、めんどくさいと感じるようになります。
▶︎ネガティブ思考をやめたい方へ|止まらない原因やレベル診断、改善方法をご紹介
人間関係がめんどくさいと感じるシーン

私たちの日常生活では、さまざまなことが原因となって人間関係に亀裂を生じさせます。
めんどくさいと感じるのは具体的にどういったシーンがあるのか、職場や学校、私生活における一例を紹介しましょう。
職場・アルバイト先
職場やアルバイト先では、多くの人々と協力しながら仕事を進めなければならないため、人間関係が複雑になることがよくあります。
上司と部下、同僚間のコミュニケーションはもちろん、予期しない変更への対応、競争、さらには職場でのハラスメントなど、これらすべてがストレスを生み出し、人間関係を「めんどくさい」と感じさせる原因となり得ます。
学校
学校においても、友人同士の関係、クラス内のいじめ、恋愛の問題、さらには教師との対立など、人間関係が複雑化しめんどくさいと感じることがあります。
ネトゲ・SNS
ネットゲームやSNSでは相手の顔が見えないことから、オンライン上でチームの対立やプレイヤー間のコミュニケーションの問題、特定の個人に対するハラスメントや嫌がらせが発生することもあります。
ママ友・パパ友
幼稚園や保育園、学校などのコミュニティにおいても、親同士の人間関係がこじれることがあります。
たとえば、価値観の違いや子育てに対する考え方・スタイルの違い、根拠のない噂や偏見、または子ども同士での問題などが原因となることが多く、ママ友やパパ友同士の人間関係をこじらせ、めんどくさいと感じさせる原因となり得ます。
▶︎友達の作り方|場所と手順を社会人から学生ごとに分けて解説!
人間関係がめんどくさいと感じるのは病気なのか
それまで良好な関係を築いていたにもかかわらず、ちょっとしたことが原因である日突然人間関係がめんどくさく感じられることもあります。
しかし、急激に態度が変わってしまうと周囲に驚かれたり、自分自身を振り返ってみてもなぜそのような心境に変化したのか不安に感じてしまうこともあるでしょう。
あまりにも態度が変わってしまうと、「自分は精神的に問題を抱えているのではないか」、「メンタル面での病気なのではないか」と思ってしまう人も少なくありません。
たしかに、うつ病や適応障害など、さまざまな病気が原因で人間関係がめんどくさく感じることも多いですが、必ずしも病気にかかっているとは断言できません。
少しでも不安を感じたら、一人で悩みを抱えるのではなく、メンタルクリニックなどを受診し専門医に診てもらうことが大切です。
▶︎マインドフルネスをやってはいけない人の特徴|PTSDやうつ病の人は危険?
人間関係をめんどくさいと感じやすい人の特徴

人間関係をめんどくさいと感じやすい人には、さまざまな特徴が見られることがあります。
内向的な性格
内向的な性格の人は、大人数のグループや団体での行動が苦手で、避ける傾向があります。
人数が多ければ多いほど、多方面に気を遣わなければならず精神的に消耗することから、社会的な接触を避け単独または少人数で行動しがちです。
感受性の高い人
高い感受性を持つ人は、他人の言動や感情の変化を敏感に察知しようとします。
他人からのなにげない一言に傷ついたり気にしたりすることが多く、そのたびにエネルギーが消費され、やがて人間関係そのものをめんどくさいと感じるようになります。
完璧主義者
完璧主義の傾向にある人は、自分自身はもちろんのこと他人に対しても高い基準を設定しがちで、それが満たされないと不満を感じることがあります。
他人のちょっとした言動が気になってしまい、やがて「この人といると疲れてしまう」と感じ、人間関係がうまくいかない原因をつくってしまいます。
▶︎感情の起伏が激しい人や少ない人の特徴|上手にコントロールする方法とは
人間関係がめんどくさいと思った時の対処法

価値観や考え方の相違、性格のミスマッチなど、人間関係がめんどくさいと感じる原因はさまざまです。
そのような感覚に陥ったとき、どう対処すれば良好な人間関係を維持できるのでしょうか。
相手の良い部分を探す
人間関係がめんどくさいと感じるのは、相手の悪い部分や気に食わない部分が目に入ったときが多いはずです。
相手のことをそれ以上嫌いになったり、受け付けたくないと感じることのないよう、良い部分に目を向けてみることが大切です。
相手の言葉や意見を聞いてみる
人間関係のトラブルに陥ったとき、自分の意見を押し通そうとするのではなく、相手の言葉や意見にも耳を傾けることも大切です。
相手の言葉を聞くことで、自分の間違っていた部分や直すべきところに気づき、再び良好な関係を取り戻せることもあるでしょう。
適度な距離をとる
人間関係がめんどくさく感じる要因が相手ではなく自分自身にあり、それを自ら認識できているケースもあると思います。
そのような場合には自分の心を整理するためにも、相手と一定の距離をとって冷静になることも大切です。
▶︎セルフ・コンパッションとは?やり方やマインドフルネスとの違いを解説
まとめ
誰しも人間関係がめんどくさく感じる瞬間はあるものです。
しかし、だからといって一時的な心情の変化で関係を切ったり、絶縁を言い渡したりすることで後悔するケースもあるでしょう。
まずは、なぜ人間関係がめんどくさいと感じるようになったのかを客観的に振り返り、適切な対処法を試してみましょう。
セルフコンパッションとは?やり方やマインドフルネスとの違いを解説
仕事で失敗をしたり、人間関係がうまくいかなかったりすると、必要以上に深刻に捉えてしまうことはないでしょうか。
そんな悩みを解消するための方法として、ありのままの自分を受け入れながら自身に対して思いやりの心を向ける「セルフコンパッション」という考え方があります。
本記事では、セルフコンパッションを実践するうえでのポイントやトレーニング方法、混同しがちなマインドフルネスとの違いについても解説します。
セルフコンパッションとはどんな意味?

コンパッション(compassion)とは、日本語に直訳すると「思いやり」や「慈悲」、「同情」といった意味を表す言葉です。
すなわち、セルフコンパッションとは、他人に対して思いやりや慈悲の心をもつように、自分自身に対しても同じような心を向け、大切にすることを指します。
セルフコンパッションの構成要素
セルフコンパッションを実践するためには、以下に示す3つの構成要素が重要です。
自己親切
自己親切とはその名の通り、自分自身に対して優しい心をもち、理解・肯定することです。
失敗や困難な状況に直面したときでも、自分自身を批判したり否定したりするのではなく、肯定的・前向きに捉えることが自己親切であり、セルフコンパッションの実践につながっていきます。
共有の人間性
共有の人間性とは、自分も含めて誰しも完璧な存在ではなく、必ず失敗したり困難を経験したりするという認識です。
「こんな失敗やミスをしているのは自分だけだ=自分はダメな人間だ」と捉えるのではなく、誰しも一度は大きな失敗をするものであり、多くの人が共通して経験するものであると理解することは、セルフコンパッションの実践にあたって重要なポイントです。
マインドフルネス
マインドフルネスとは、自分自身の感情や経験を現実的にとらえ、ありのままの事実として受け入れたうえでストレスを低減する方法です。
辛いことがあると現実から逃げたくなり、無理に忘れようとする方も多いですが、そのような行為が反対に混乱を招くこともあります。
マインドフルネスを実践することにより、冷静に現実を受け入れ自分自身を肯定する第一歩となります。
▶︎友達の作り方|場所と手順を社会人から学生ごとに分けて解説!
セルフコンパッションの効果・メリット

セルフコンパッションを実践することにより、私たちの日常生活においてどのような効果やメリットが得られるのでしょうか。
3つのポイントをもとに解説します。
自尊心や幸福度の向上
セルフコンパッションを実践することにより、抑うつや不安の症状を軽減し、生活の満足度を高めることができます。
その結果、自尊心や幸福感を向上させ、精神的な健康を手に入れ充実した生活を送ることができるでしょう。
精神的ダメージからの早期回復を促す
私たちは生きていく以上、さまざまな困難に直面することがあります。
しかし、あまりにもショックな出来事が起こってしまうと、精神的な回復に時間を要し日常生活に戻れなくなることも少なくありません。
セルフコンパッションを実践できれば、自分自身に対する優しさと理解を示すことにより、困難や挫折を乗り越える力が増します。
自己啓発と成長を促す
自分自身に対して批判や否定的な考えをもっていると、成長や変化の機会があったとしても「どうせ自分には無理だ」、「自分は変われない」と感じてしまいがちです。
しかし、セルフコンパッションを実践できていれば、自分自身の失敗や欠点に対しても優しさや理解を示すことができ、自己改善に向けた動機付けにもなります。
セルフコンパッションが重要視される理由
セルフコンパッションはもともと心理学の分野で使われていた言葉でしたが、近年になってビジネス分野や一般社会にも広まりを見せています。
なぜセルフコンパッションは注目され、重要視されるようになったのでしょうか。
仕事のストレス
ビジネスの社会では競争が厳しく、慢性的なストレスを感じることが少なくありません。
目標やノルマ達成のプレッシャーはもちろん、時間的な制約や職場の人間関係など、さまざまな要素がストレスの原因となります。
セルフコンパッションを実践できれば、これらのストレスを和らげ、万が一失敗やミスをしたとしても受け入れ、自己批判を減らすことができます。
同時に、仕事や職場に対する満足度を高めたり、良好な人間関係の構築にも役立つでしょう。
私生活のストレス
私生活においても自己批判に陥ることが少なくありません。
考えられる要因は自分の容姿や能力、人間関係、ライフスタイルなど多岐にわたり、自尊心と幸福感を低下させることがあります。
セルフコンパッションを実践することにより、私生活の面でも自己批判から解放され、自己価値感と幸福感を高めることができるでしょう。
将来への不安
激動の社会において、雇用環境の変化や経済状況、自分自身のキャリアなど、将来に対する不安を抱く方も少なくありません。
また、このような社会情勢に起因した悩みだけでなく、自分自身の健康や家族の幸せなどがストレスの原因になることもあるでしょう。
セルフコンパッションは、これらの不安を和らげるためにも重要であり、将来への不確実性を受け入れ、その上で現状を最善に生きるための原動力となります。
▶︎【シーン別】人間関係がめんどくさいと感じる心理や対処法を解説
セルフコンパッションとマインドフルネスの違い
セルフコンパッションを構成する要素のひとつとしてマインドフルネスを紹介しましたが、厳密にいえば両者は異なる概念です。
セルフコンパッションとは、冒頭でも紹介した通り、自分自身に対して思いやりや慈悲の心を向け、大切にすることを指します。
自己批判や自己否定をするのではなく、精神的な健康を保つために自己認識や自己受容、自己愛を育んでいきます。
これに対してマインドフルネスとは、自分自身の感情や経験を現実的にとらえ、ありのままの事実として受け入れたうえでストレスを低減する方法を指します。
マインドフルネスはセルフコンパッションを実践するために重要なものであり、お互いに補完し合う関係にある存在といえるでしょう。
▶︎マインドフルネスをやってはいけない人の特徴|PTSDやうつ病の人は危険?
セルフコンパッションのやり方・トレーニング方法

実際にセルフコンパッションを実践するためには、どのようなトレーニングに取り組めば良いのでしょうか。
スージングタッチ
スージングタッチとは、自分自身の身体の一部を優しく触れたり、撫でたりするトレーニングです。
たとえば、胸を撫でる、手をお腹の上に置く、膝を両腕で抱え込む、頭を優しく撫でるといった行為が該当します。
さまざまな部位に触れてみながら、自分自身が安心し落ち着く方法を試してみましょう。
ボディスキャン
ボディスキャンとは、自分自身の身体に意識を集中させるトレーニングです。
具体的には、足や腕などの部位で末端から意識を集中させ、徐々に体幹に近づけていく方法が一般的です。
足の場合は、つま先から足首、すね、ふくらはぎ、膝、太もも、お尻といったように、身体の中心部に向けて意識を変えていきましょう。
慈悲の瞑想
もっとも手軽にできるトレーニングとして慈悲の瞑想があります。
具体的には、胸またはお腹に手を当てながら「自分自身が健康でありますように」、「悩みがなくなりますように」といった言葉を自分に語りかけます。
大きな失敗をしたり困難にぶつかったりしたとき、冷静な判断力を失ってしまうケースも少なくありません。
しかし、瞑想を習慣づけることで困難な状況に陥っても気持ちが楽になり、自分自身に対する否定的な考えを払拭できます。
▶︎感情の起伏が激しい人や少ない人の特徴|上手にコントロールする方法とは
セルフコンパッションを取り入れている企業の実例
セルフコンパッションは基本的に個人が行うものですが、従業員の生産性向上やストレス低減を目的として組織に取り入れている企業も存在します。
なかでも有名なのが、今や世界を代表するIT企業として成長したAppleです。
故スティーブ・ジョブズ氏は座禅や瞑想を習慣づけていたことでも有名ですが、Appleという会社としても従業員に瞑想を推奨し、セルフコンパッションのトレーニングを取り入れています。
▶︎知らず知らずに起こっている?ハラスメントの種類や防止方法を紹介
どんな人にセルフコンパッションは向いているのか
セルフコンパッションはあらゆる人にとって有効なトレーニングであり、取り組むことにデメリットはありません。
しかし、より高い効果を実感してもらうためにも、以下のような人に適しています。
- 自分自身に否定的な人
- 慢性的なストレスを抱えている人
- マネジメント職や経営者
特にマネジメント職や経営者は、仕事へのやりがいを感じる一方で担う責任も大きいため、バーンアウト(燃え尽き症候群)に陥る人も少なくありません。
セルフコンパッションを実践し自分自身を適切に管理することで、仕事へのモチベーションを維持しながら邁進することができます。
▶︎自己肯定感が低い人の原因とは|実はプライドが高い?親のせい?
まとめ
私たちが生活していくうえで、失敗をしたり困難にぶつかったりすることは必ずあるものです。
しかし、過度に失敗を恐れたり、困難を回避しようとすると成長が見込めなくなることもあるでしょう。
大切なのは、苦しい状況に陥っても前向きに捉え、立ち直る力を身につけることであり、そのためにもセルフコンパッションの実践は大切です。
メンタルヘルスマネジメント検定とは?日程や合格率を解説
ヘルスケア市場が大きくなっている「成長産業」であり市場規模の拡大が見込まれる業界です。
経済産業省 によると、ヘルスケア業界の市場規模(2017年調査)は、2016年は約25兆円、2020年は約28兆円、2025年には約33兆円になると推計されています。
参照元:M&Aベストパートナー
そんなヘルスケア市場の中、でも社会人にとって大きな影響をもたらす1つがメンタル面でのヘルスケアです。
社会人は職場ではさまざまな立場の人と一緒に働かなければならず、考え方や価値観の違いから人間関係がうまくいかないこともあります。
また、膨大な仕事に追われ、大きなストレスを感じている方も多いでしょう。
このようなメンタル面での不安や不調は仕事にも影響を与え、生産性の低下や休職・退職を余儀なくされることもあります。
そこでおすすめしたいのが、メンタルヘルスマネジメント検定とよばれる資格の取得です。
メンタルヘルスマネジメント検定とはどういった資格なのか、取得することで何に役立てられるのか、勉強のコツなども含めて詳しく解説します。
▶︎メンタル心理カウンセラーとは?資格を活かせる現場や学習内容も解説
メンタルヘルスマネジメント検定とは?
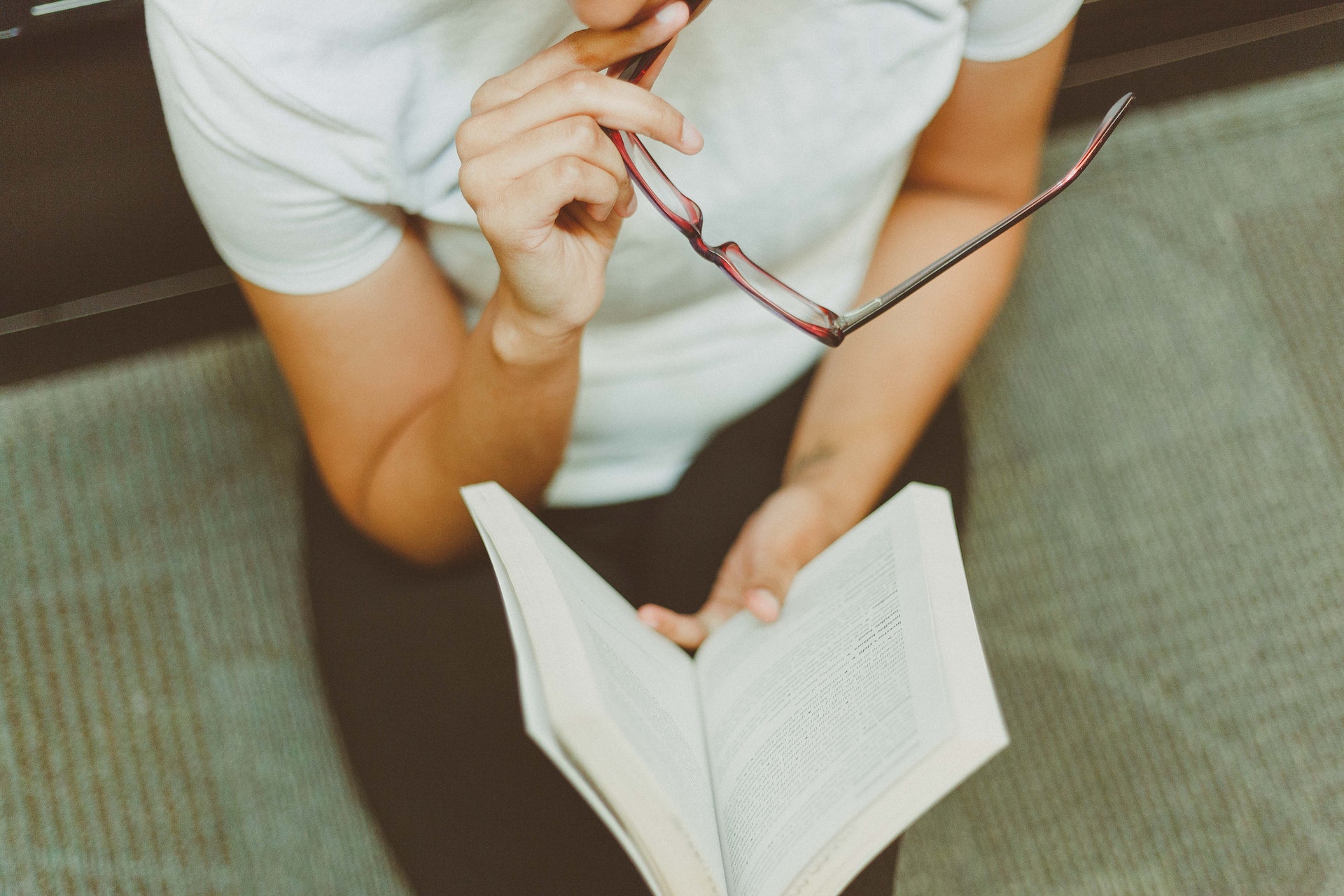
メンタルヘルスマネジメント検定とは、大阪商工会議所と施行商工会議所が主催している民間資格です。
労働者のメンタルケアを職場内で実践するために、必要な知識や正しい対処方法を習得することを目的に運用されています。
長引く不況によって経済的な問題を抱える人も多く、また、職場のストレスや人間関係の悩みなど、さまざまな要因が重なり心理的な不調を訴える人も少なくありません。
精神的なストレスや不安は仕事のパフォーマンスにも影響し、企業として生産性の低下を招くリスクもあることから、社員のメンタルヘルスケアは重要な取り組みといえるのです。
社員のメンタルケアを正しく実践するためにも、メンタルヘルスマネジメント検定を通して正しい知識を習得することが求められます。
メンタルヘルスマネジメント検定は全国15都市の指定会場で一斉に実施される公開試験と、企業や団体、学校などで受験日程を任意に設定し受験できる団体特別試験があります。
このうち、公開試験の試験概要は以下の通りです。
【主催】
- 大阪商工会議所・施行商工会議所(後援:日本商工会議所)
【受験資格】
- 学歴・年齢・性別・国籍を問わず誰でも受験可能
【受験料】
- Ⅰ種(マスターコース):11,550円(税込)
- Ⅱ種(ラインケアコース):7,480円(税込)
- Ⅲ種(セルフケアコース):5,280円(税込)
【2023年度の試験日程】
- 【終了】2023年11月5日(日):Ⅰ種(マスターコース)・Ⅱ種(ラインケアコース)・Ⅲ種(セルフケアコース)
- 2024年3月17日(日):Ⅱ種(ラインケアコース)・Ⅲ種(セルフケアコース)
【試験時間】
- Ⅰ種(マスターコース):前半(選択問題)2時間 後半(論述問題)1時間
- Ⅱ種(ラインケアコース):2時間
- Ⅲ種(セルフケアコース):2時間
なお、団体特別試験の場合はⅡ種・Ⅲ種のみが対象となり、受験料はⅡ種が5,980円、Ⅲ種が4,220円となっています。
メンタルヘルスマネジメント検定の3コース
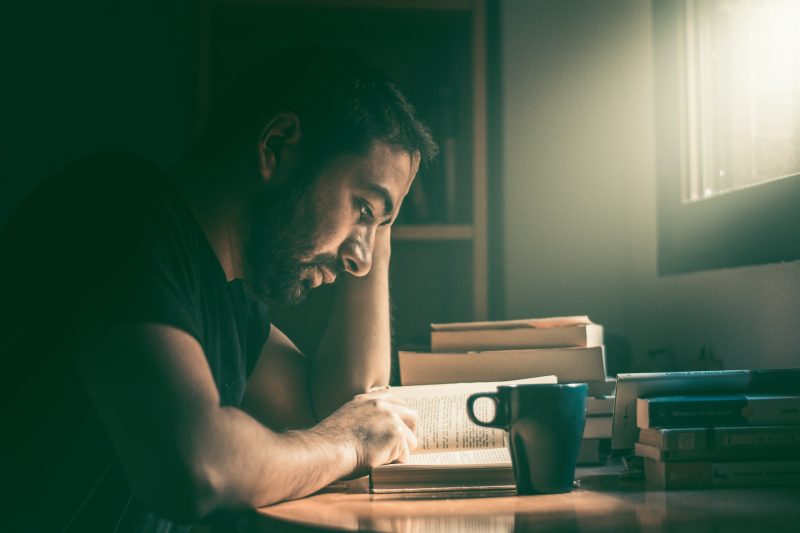
試験概要でも紹介した通り、メンタルヘルスマネジメント検定にはⅠ種(マスターコース)・Ⅱ種(ラインケアコース)・Ⅲ種(セルフケアコース)の3つのコースが用意されています。
それぞれの違いについて詳しく解説しましょう。
Ⅰ種(マスターコース)
Ⅰ種のマスターコースは、社内や組織内におけるメンタルヘルス対策を推進することを目的として、主に人事労務管理スタッフや経営幹部を対象に行われる試験です。
この試験に合格した場合の到達目標は以下のように設定されています。
- 「自社の人事戦略・方針を踏まえたうえで、メンタルヘルスケア計画、産業保健スタッフや他の専門機関との連携、従業員への教育・研修等に関する企画・立案・実施ができる。」
▶︎メンタルヘルスマネジメント検定試験の概要についてはこちら
Ⅱ種(ラインケアコース)
Ⅱ種のラインケアコースは、特定の部門内および、上司の立場から部下のメンタルヘルス対策を推進することを目的として、管理職やマネージャー、リーダーを対象に行われる試験です。
この試験に合格した場合の到達目標は以下のように設定されています。
- 「部下が不調に陥らないよう普段から配慮するとともに、部下に不調が見受けられた場合には安全配慮義務に則った対応を行うことができる。」
▶︎メンタルヘルスマネジメント検定試験の概要についてはこちら
Ⅲ種(セルフケアコース)
Ⅲ種のセルフケアコースは、社員が自分自身のメンタルヘルス対策を適切に推進するために、一般社員を対象に行われる試験です。
この試験に合格した場合の到達目標は以下のように設定されています。
- 「自らのストレスの状況・状態を把握することにより、不調に早期に気づき、自らケアを行い、必要であれば助けを求めることができる。」
▶︎メンタルヘルスマネジメント検定試験の概要についてはこちら
メンタルヘルスマネジメント検定の出題範囲
メンタルヘルスマネジメント検定は3つのコースが存在しますが、試験内容にはどのような違いがあるのでしょうか。
出題範囲や内容の違いについて詳しく紹介しましょう。
Ⅰ種(マスターコース)
Ⅰ種のマスターコースは、3つのコースのなかでも特に出題範囲が広く、以下の9項目が対象となっています。
- 企業経営におけるメンタルヘルス対策の意義と重要性
- メンタルヘルスケアの活動領域と人事労務部門の役割
- ストレスおよびメンタルヘルスに関する基礎知識
- 人事労務管理スタッフに求められる能力
- メンタルヘルスケアに関する方針と計画
- 産業保健スタッフ等の活用による心の健康管理の推進
- 相談体制の確立
- 教育研修
- 職場環境等の改善
いち従業員や管理職、リーダーという立場からではなく、経営者や人事として社内全体を俯瞰して考える必要があり、相談体制や教育研修、職場環境の改善といった内容も範囲に含まれます。
配点および合格基準は以下の通りです。
【配点】
①選択問題 100点
②論述問題 50点
【合格基準】
①②の得点の合計が105点以上
※ただし、論述問題の得点が25点以上
Ⅱ種(ラインケアコース)
Ⅱ種のラインケアコースは、Ⅰ種のマスターコースに次いで広範囲の7項目が出題されます。
- メンタルヘルスケアの意義と管理監督者の役割
- ストレスおよびメンタルヘルスに関する基礎知識
- 職場環境等の評価および改善の方法
- 個々の労働者への配慮
- 労働者からの相談への対応 (話の聴き方、情報提供および助言の方法等)
- 社内外資源との連携
- 心の健康問題をもつ復職者への支援の方法
管理職やリーダーとしてどのように部下に接したら良いのか、一人ひとりへの配慮や相談への対応方法、支援方法なども学びます。
配点および合格基準は以下の通りです。
【配点】
選択問題 100点
【合格基準】
70点以上
Ⅲ種(セルフケアコース)
Ⅲ種のセルフケアコースは、以下の6項目が出題されます。
- メンタルヘルスケアの意義
- ストレスおよびメンタルヘルスに関する基礎知識
- セルフケアの重要性
- ストレスへの気づき方
- ストレスへの対処、軽減の方法
- 社内外資源の活用
社員個人を対象とした試験であることから、メンタルヘルスケアの重要性や対処方法など基礎的な内容が中心となっています。
配点および合格基準は以下の通りです。
【配点】
選択問題 100点
【合格基準】
70点以上
メンタルヘルスマネジメント検定の合格率
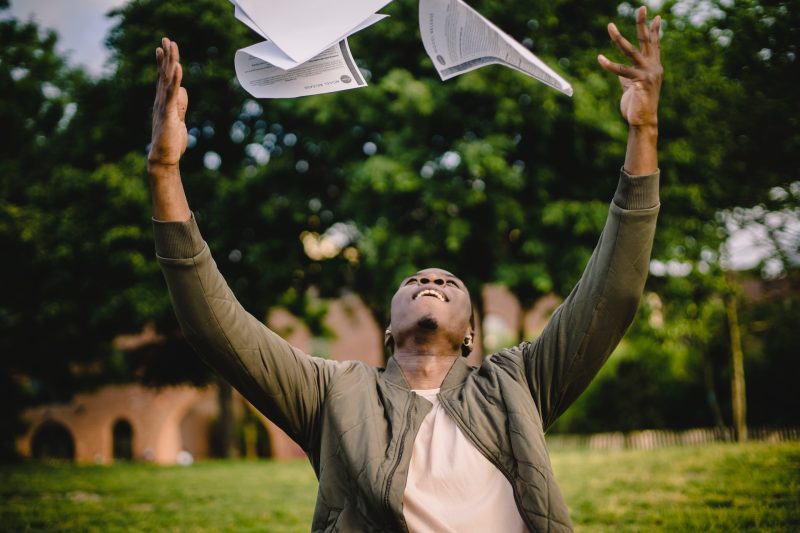
一口に検定試験や資格試験といっても、試験によって難易度は異なります。
メンタルヘルスマネジメント検定の場合、どの程度の合格率なのでしょうか。
大きな傾向を見ると、Ⅲ種(セルフケアコース)がもっとも合格率が高く、Ⅱ種(ラインケアコース)、Ⅰ種(マスターコース)と上位になるほど合格率は下がっていきます。
試験の実施年度によっても多少の差はありますが、たとえば2022年度の試験結果は以下の通りです。
【第34回試験】 2023年3月19日(日)
Ⅱ種(ラインケアコース) 実受験者(11,918人) 合格者数(6,444人) 合格率(54.1%)
Ⅲ種(セルフケアコース) 実受験者(5,035人) 合格者数(3,995人) 合格率(79.3%)
【第33回試験】 2022年11月6日(日)
Ⅰ種(マスターコース) 実受験者(1.628人) 合格者数(287人) 合格率(17.6%)
Ⅱ種(ラインケアコース) 実受験者(10,998人) 合格者数(6,401人) 合格率(58.2%)
Ⅲ種(セルフケアコース) 実受験者(5,458人) 合格者数(3,787人) 合格率(69.4%)
過去の複数回のデータを分析してみても、Ⅰ種の場合は15〜20%前後、Ⅱ種が50〜60%、Ⅲ種が60〜80%程度の合格率で推移しています。
▶︎心理カウンセラーになるには?武器となる資格や仕事内容も解説
メンタルヘルスマネジメント検定を取るとどんなことに活かせる?
メンタルヘルスマネジメント検定を取得するメリットとしては、社員の健康維持や職場環境の改善につながることが挙げられるでしょう。
たとえば、強いストレスや精神的な不調を抱えている人のなかには、自分から悩みを打ち明けられなかったり、どう対処すれば良いのか分からないというケースも少なくありません。
メンタルヘルスマネジメント検定を取得していれば、そのような精神的な不調をきたしている人に対し、一言声をかけ、相談に乗ることもできるでしょう。
その結果、精神的な問題で退職や休職に至る社員を減らし、働きやすい職場をつくることができます。
メンタルヘルスマネジメント検定に合格するための勉強のコツ
メンタルヘルスマネジメント検定に合格するためには、主に公式テキストの内容を繰り返し学習する方法と、受験対策講座を受講する方法があります。
公式テキストはⅠ種・Ⅱ種・Ⅲ種それぞれのコース専用のものが販売されており、メンタルヘルスマネジメント検定の公式サイトで購入手続きが可能です。
また、同じく公式サイトではⅠ種からⅢ種までの受験対策講座の情報も掲載されています。
テキストを使った独学だけでは内容が把握しきれない方や、効率的に試験範囲を学習したいという方は受験対策講座の受講も検討してみましょう。
まとめ
メンタルヘルスマネジメント検定は民間資格であり、医師免許のような高度な専門資格ではありません。
しかし、企業のなかには資格取得を推奨するケースも多く、実際に毎年多くの方が受験しています。
この資格を取得することで、自分自身の精神的な不調やストレスと向き合い適切な対処ができるほか、周囲の社員にも目を配り働きやすい職場が実現できるはずです。
経営層や人事担当者、管理職やリーダー、一般社員など、会社や組織で働く方であれば多くの人におすすめの資格です。
スキンシップにはどんな効果がある?良好な関係性を維持するためのポイントとは
親しい友人や恋人同士では、日常的に体の一部に触れたり、お互いに密着したりすることで関係性が深まっていくこともあります。
このように、お互いが触れ合う行為をスキンシップとよびますが、なかにはスキンシップが苦手な人も存在します。
本記事では、スキンシップにはどのような効果があるのか、スキンシップをとる心理的な理由、スキンシップが苦手な人との接し方なども詳しく解説します。
スキンシップとは何か

スキンシップとは、一般的に「触れ合い」や「交流」といった意味として用いられる言葉です。
その名の通り、人と人とが物理的に密着したり、手で触れたりする行為のことを指します。
一口にスキンシップといってもさまざまなものがありますが、代表的な例でいえば以下のような行為が挙げられるでしょう。
- 握手をする
- 軽くボディタッチをする
- 頭を撫でる
- 肩を抱き合う
- 抱擁する
- 手をつなぐ
- キスをする
握手はビジネスの場面でもよく見られるほか、親しい友人や家族などであればボディタッチや頭を撫でる、肩を抱き合うといった行為も少なくないでしょう。
友人から恋人へ発展していくと、手をつないだりキスをしたりといったスキンシップも増えてくるはずです。
このように、その人との関係性によってもスキンシップの種類は異なります。
▶︎感情の起伏が激しい人や少ない人の特徴|上手にコントロールする方法とは
スキンシップの効果

スキンシップをとることでどういった心理的効果が得られるのでしょうか。
安心感や幸福感を高める
スキンシップをとることで、脳からオキシトシンとよばれるホルモンが放出されます。
オキシトシンは「愛情ホルモン」や「絆ホルモン」ともよばれており、安心感を生み出すとともに、幸福感を高める効果があることもわかっています。
ストレスと不安の軽減
スキンシップによって身体的な接触をはかることで心拍数や血圧を下げ、ストレスホルモンの分泌量を下げることもあります。
その結果リラクゼーションの効果が高まり、ストレスや不安感の軽減にも貢献します。
自己肯定感の向上
スキンシップの一種である、頭を撫でられる、肩を抱き合う、抱擁するといった行為は、本能的に「愛されている」、「守られている」といった感情を生み出します。
すなわち、自分自身が愛され、守られるべき大切な人間であることを認識し、その結果自己肯定感や自尊心を高められる可能性があるのです。
▶︎【自己受容】弱くてダメな自分を認めて受け入れるトレーニング方法
スキンシップをとる心理
なぜ人間は親しくなるほどスキンシップをとろうとするのか、その理由について心理学の観点から解説しましょう。
愛情表現
私たちの一般的なコミュニケーション手法として言語がありますが、それだけでは相手に自分自身の愛情や気持ちが伝わらないケースも少なくありません。
たとえば、恋人に対して「愛してる」と言葉で発したとしても、どこまで本気なのか分からないこともあるでしょう。
しかし、言葉で伝えると同時に、手を握ったり抱擁したりすることで精一杯の愛情を表現できます。
また、そもそも言葉の通じない赤ちゃんや幼い子どもに対しては、パパやママが抱きしめるだけで本能的に「守られている」と安心感を与えられ、愛情のコミュニケーションをとることもできます。
他者とのつながりを強めたい
人は本来社会的な生き物であり、他者とのつながりを求めるのは本能でもあります。
スキンシップによって他者との関係性を強化できることを本能的に知っていることから、より親しくなりたい場合に自然とボディタッチが増える傾向があるのです。
下心がある
スキンシップをとるのは上記で紹介したようなポジティブな理由ばかりとは限りません。特に男性に多いのが、下心が見え隠れするケースです。
女性のなかには、肩や腕などへの軽いボディタッチ程度であれば許容できる方もいるかもしれません。
しかし、男性側に下心がある場合、それを受け入れてしまうとどんどんエスカレートしていく可能性もあります。
また反対に、女性にしてみれば、軽いボディタッチは気に留めておらず無意識にするケースも少なくありません。
スキンシップが苦手な人も

人と触れ合ったり、密着したりといったスキンシップは、人によってもさまざまな捉え方があります。
なかには、自分からスキンシップをとるのが苦手と感じる方や、関係性次第ではスキンシップをとられることに大きな拒絶感を抱く人もいます。
十分な関係性を築けていない
初対面の人や顔見知り程度の人の場合、スキンシップをとることに強い抵抗感を抱く人は少なくありません。
たとえば、欧米人の場合は握手やハグ、キスといった挨拶の文化があり、日常的にスキンシップをとる機会があります。
しかし、日本にはそういった文化がなく、ハグやキスといったスキンシップは特に関係性が深い人でないと抵抗感を抱かれるでしょう。
自己肯定感が低い
親しい友人や恋人であったとしても、スキンシップが苦手と感じる人も存在します。
理由はさまざまですが、特に典型的なのは自己肯定感が低いケースです。
たとえば、自分自身に強いコンプレックスがあると、「スキンシップをとることで相手を不快な気分にさせるのではないか」、「相手から拒絶されるのではないか」などと考えてしまい、スキンシップを敬遠してしまうことも少なくありません。
▶︎自己肯定感が低い子供の特徴や言動とは|注意すべき親の発言や行動
第三者からの目が気になる
恋人同士であるにもかかわらず、スキンシップをとるのが苦手と感じる人の場合、周囲からの目が気になるというケースもあります。
たとえば、外出先で手をつないだり、二人で並んで歩いたりするのも周囲からの視線が気になってしまう人もいます。
異性との交流に慣れていない
これまでの人生において、異性と交流をする機会が少なかった人の場合、恋人や異性の友達ができたとしても、どうスキンシップをとれば良いのか分からないケースもあります。
本人にはスキンシップをしたいという気持ちがあったとしても、「相手に嫌われたらどうしよう」、「どの程度までのスキンシップをするべきかわからない」と感じてしまい、行動に移せないことも多いようです。
スキンシップをとるうえでのポイント・注意点
スキンシップは人間関係をより深めるために有効な方法ですが、その一方でスキンシップのやり方を間違えてしまうと大きな溝を作ってしまうことにもなりかねません。
スキンシップをとるうえで、押さえておきたいポイントや注意点を解説しましょう。
相手との関係性に応じて考える
十分な関係性が築けていない人とのスキンシップは、トラブルを避けるためにも慎重に判断する必要があります。
たとえば、欧米のように初対面の人にハグやキスをすると、相手は驚いてしまい抵抗を示すこともあるでしょう。
まずは言葉のコミュニケーションから関係を深めていき、徐々に握手や軽いボディタッチをしながら様子を伺うことが大切です。
相手に寄り添う
自己肯定感が低い人や、自分自身に強いコンプレックスを抱いている人、異性との交流に慣れていない人に対しては、無理にスキンシップをとることは厳禁です。
このような人は、特に相手との距離感を大切している傾向が強いことから、相手のペースに寄り添って距離を近くしていくようにしましょう。
たとえば、いきなり物理的な距離を縮めようとするのではなく、「ここ、座っていい?」と聞いてみるだけでも相手の警戒心が解け、徐々に関係性が深まっていくはずです。
周囲の視線が目につかない場所でスキンシップをとってみる
第三者からの視線が気になる人に対しては、多くの人の目に触れるような場所でスキンシップをとるのではなく、落ち着いて話せる個室タイプの飲食店や映画館などを選ぶようにしましょう。
スキンシップは相手のことを第一に考えよう
スキンシップには不安感の低減や幸福度のアップなどさまざまな効果があることから、愛情表現のひとつとして有効な手段です。
しかし、なかにはスキンシップが苦手という人や、うまくスキンシップがとれずに悩んでいる人も少なくありません。
自分自身のペースでスキンシップをとるのではなく、まずは相手のことを第一に考え、不快や不安を感じさせないよう配慮することが大切です。
豆腐メンタルとはどんな意味?原因や治し方を徹底解説
わずかなことに傷つき、精神的に立ち直れなくなることを指す「豆腐メンタル」という言葉があります。
なぜ豆腐メンタルとよばれるのか、その理由や由来について解説するとともに、豆腐メンタルの人に見られる傾向や特徴、豆腐メンタルを改善するためのポイントなども詳しく紹介します。
豆腐メンタルとは

豆腐メンタルとは一般的に、精神的に弱く傷つきやすい人のことを指す言葉です。
その名の通り、豆腐のように崩れやすく脆いことから豆腐メンタルとよばれることがあります。
豆腐メンタルという言葉は心理学やメンタルヘルスの世界で用いられてきた言葉ではなく、もともとはインターネットの掲示板やSNSなどで使用されるスラングとして発展してきました。
インターネット黎明期はごく限られたコミュニティや界隈でのみ使用されていましたが、2010年代に入りインターネットユーザーが爆発的に増加したことにより、一般のユーザーにも受け入れられるようになり定着した言葉です。
ちなみに、豆腐メンタルとは対照的に精神的に強い人のことは、「鋼のメンタル」や「こんにゃくメンタル」とよばれることがあります。
こんにゃくが例に出される理由としては、弾力性が強く、わずかな刺激や物理的な力に屈することなくもとの形を保とうとする性質があるためです。
▶︎心理カウンセラーになるには?武器となる資格や仕事内容も解説
豆腐メンタルの原因は?

豆腐メンタルは一言で表すと「精神的に弱い人」のことですが、どういったことが原因で精神的に弱くなってしまうのでしょうか。
失敗やミスを過度に恐れる
わずかな失敗やミスを極度に恐れるあまり、精神的に弱くなってしまう傾向があります。
ちょっとしたミスでも必要以上に自分を追い詰めてしまい、精神的に立ち直るために長い時間を要します。
これは精神的な安定を維持するための自己防衛本能のようなもので、失敗を恐れるあまり新しいことに挑戦したり、興味や関心を抱かなくなることもあります。
自己肯定感が低い
自己肯定感が低いことも豆腐メンタルの人に見られる共通の特徴といえます。
自己肯定感とは、簡単にいえば自分自身を積極的に受け入れ、肯定する心理や感情のことを指します。
たとえば仕事で失敗やミスを犯したとき、「自分はダメな人間だ」、「自分はこの仕事に向いていない」と深刻に考えすぎてしまうことがあります。
ネガティブ思考
ネガティブ思考に陥ってしまいがちな人は精神的に脆いことが多いです。
この背景には、過去に犯した失敗がトラウマのように残っていることが考えられます。
その結果、何か新しいことに挑戦しようとするときに以前の失敗が頭をよぎり、「どうせ自分には無理だろう」と後ろ向きに考えてしまう傾向にあるのです。
また、「絶対にうまくいく」と考えて挑戦したものの、結果として失敗に終わってしまうとショックも大きく、立ち直るのに時間がかかってしまいます。
そのような状態にならないために、豆腐メンタルの人はネガティブに考えることで無意識のうちに予防線を張っているともいえるのです。
コミュニケーションが苦手
他人と積極的にコミュニケーションをとることが苦手だと、徐々に疎外感を感じるようになり、豆腐メンタルとなってしまうことがあります。
相手のことをよく知らない状態でコミュニケーションをとる際には、誰しも自然と警戒心をもってしまうものです。
しかし、あまりにもその気持ちが強すぎると、「無視されたらどうしよう」、「不審に思われたらどうしよう」といった考えが先行してしまい、話しかけることすらできなくなるケースもあります。
▶︎メンタル心理カウンセラーとは?資格を活かせる現場や学習内容も解説
豆腐メンタルを克服したほうが良い理由
メンタルの問題は人それぞれの価値観や考え方に起因することが多いものです。
豆腐メンタルを個性やその人の価値観と片付ける見方もありますが、精神的な弱さを放置しておくことで当事者である自分自身が苦しむことも少なくありません。
たとえば、仕事において上司や先輩社員が適切な指導・アドバイスをしたつもりでも、豆腐メンタルの人にしてみれば「叱られた」「責められた」と感じることもあります。
このような齟齬があると、職場の人間関係に支障をきたしたり、働きづらいと感じ退職に至ることもあるでしょう。
豆腐メンタルを克服することで良好な人間関係を維持するとともに、仕事の面においても自分自身を成長させる原動力となるのです。
▶︎ネガティブ思考をやめたい方へ|止まらない原因やレベル診断、改善方法をご紹介
豆腐メンタルを克服するためのポイント

豆腐メンタルは個人の価値観や考え方にも大きく左右されるものであり、一朝一夕に克服できるものではありません。
しかし毎日の生活を送るうえで、ちょっとしたポイントに注意するだけで精神的な強さを手に入れられる可能性もあります。
小さな目標達成を積み上げる
失敗やミスを過度に恐れる原因として、過去の経験からトラウマになっているケースが少なくありません。
そこで重要なのは、成功体験を積み上げることです。
大きな目標を達成したとき、それが自信につながることは多いですが、大きな目標を掲げるということは失敗のリスクも伴います。
そのため、いきなり大きな目標を設定するのではなく、達成の実現性がある小さな目標を積み上げ、段階を踏んでいくのが有効です。
自分自身の強みや長所を把握する
自己肯定感を高めることは豆腐メンタルを克服するための第一歩でもあります。
自己肯定感が低い人は、自分自身の悪いところばかりに目がいきがちです。
しかし、誰にでも長所や強みは存在します。
まずは自分自身の長所や強みを書き出しながら整理してみることで、自信がつき自己肯定感を高められる可能性があります。
誰にとっても失敗やミスは起こるものだと理解する
失敗を過度に恐れ、ネガティブ思考に陥りやすいときには、考え方や価値観を根本から変えていく必要があります。
すなわち、失敗やミスをしない人は存在せず、誰にとってもあり得ることを理解する必要があります。
これにより、過去の失敗やミスにとらわれ精神的に落ち込むことも減り、ポジティブな姿勢を保ちやすくなるでしょう。
ネガティブな言葉をポジティブな言葉に言い換える
ネガティブ思考が癖になり豆腐メンタルに陥っている人は、日々の言動を客観的に振り返ってみましょう。
たとえば、「どうせ無理だ」、「きっと失敗する」、「自分はダメな人間だ」といった思考が頭の片隅にあると、自然とネガティブな言葉が口癖のように出てきてしまうものです。
そのようなネガティブな言葉は避け、ポジティブな言葉に言い換えることを意識してみましょう。
たとえば、「どうせ無理だ」ではなく、「以前失敗したところを克服できれば、きっと成功するはずだ」と考えを転換することで、良い意味での自己暗示にかかり成功を引き寄せられる可能性もあります。
▶︎【自己受容】弱くてダメな自分を認めて受け入れるトレーニング方法
豆腐メンタル
豆腐メンタルは精神的に弱い人を指すネットスラングとして誕生し、現在では一般社会でも広く用いられるようになりました。
メンタルの強さは人によってもさまざまで、ちょっとしたことにショックを受ける人も少なくありません。
しかし、日常生活を送るうえでさまざまなポイントに注意するだけでも、豆腐メンタルは少しずつ改善され克服できる可能性もあります。
今回紹介した方法の一例をぜひ参考にして、取り組んでみてはいかがでしょうか。
メンタル心理カウンセラーとは?資格や仕事内容も解説
心理カウンセラーになるために必須となる資格や免許はなく、スキルや経験さえあれば誰でも目指せる職業です。
しかし、だからこそキャリアアップのために、スキルを客観的に評価してもらえる資格の取得は有効です。
本記事では、民間資格である「メンタル心理カウンセラー」について詳しく解説します。
メンタル心理カウンセラーはどんな資格?
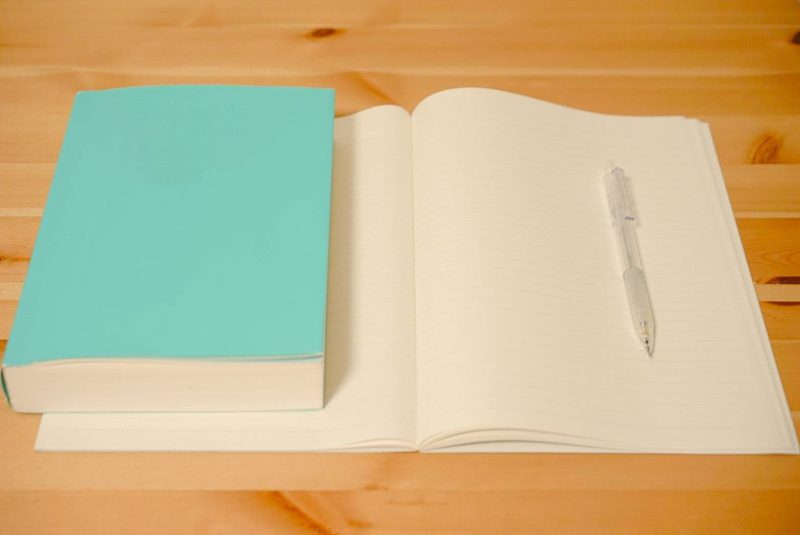
メンタル心理カウンセラーとは、一般財団法人日本能力開発推進協会が認定している民間資格です。
「JADP認定メンタル心理カウンセラー」ともよばれ、心理カウンセラーとして活躍するために必要な知識や技能の程度を証明することができ、キャリア開発において大きな武器となる資格のひとつといえます。
現代社会において、さまざまなストレスを抱える人は少なくありません。
人々の悩みや不安を解消するためにも心理カウンセラーの需要は高まっており、メンタル心理カウンセラーの資格を取得することで活躍の場が広がっていきます。
大前提として、心理カウンセラーになるために必須となる資格や免許はありませんが、採用時にメンタル心理カウンセラーの資格を持っていれば大きな武器になることは間違いないでしょう。
ちなみに、心理カウンセラーにとって有用な資格は数多く存在しますが、メンタル心理カウンセラーは学歴を問わず通信講座でも取得できるため、受験のハードルが比較的低い資格といえます。
▶︎心理カウンセラーになるには?武器となる資格や仕事内容も解説
メンタル心理カウンセラーの資格が活かせる現場

心理カウンセラーはさまざまな場で活躍できる専門職ですが、メンタル心理カウンセラーの資格を取得すれば具体的にどのような現場で活かされるのでしょうか。
医療・介護の現場
病気やケガなどの治療が長期化すると、精神的に不安定になる人も少なくありません。
また、介護の現場では施設に入居する利用者がストレスを抱えたり、介護をする家族が悩みや不安を抱えたりすることも少なくありません。
心理カウンセラーとして患者や利用者やその家族とコミュニケーションをとり、相談に乗ることで不安やストレスを緩和することができます。
教育現場
いじめや不登校などに悩む児童・生徒は多く、子どもの悩みや不安を解消するためにも心理カウンセラーは欠かせない存在です。
教育現場で働く心理カウンセラーはスクールカウンセラーともよばれ、最近では公立学校でも配属されるケースが少なくありません。
一般企業
一般企業においてもメンタル心理カウンセラーの資格は大いに役立ちます。
職場の人間関係やハラスメントに悩む人の心理的ケアを行うカウンセラーは産業カウンセラーともよばれ、メンタルヘルス対策の一環として採用する企業も少なくありません。
また、メンタル心理カウンセラーの資格をもっていれば、カウンセラーとしての仕事ばかりではなく、管理職やリーダー、人事部門などにおいてマネジメント力の向上にも役立てられます。
▶︎感情の起伏が激しい人や少ない人の特徴|上手にコントロールする方法とは
メンタル心理カウンセラーの取得に必要な時間

メンタル心理カウンセラーは専門的な資格であることから、取得には膨大な学習時間を要するのではないかと不安に感じる方も少なくありません。
実際にどの程度の学習時間を要するのか、今回は通信講座を受講するケースをもとに紹介しましょう。
メンタル心理カウンセラーの想定学習時間は20時間
メンタル心理カウンセラーの通信講座では、およそ20時間程度のカリキュラムが組まれています。
大学や大学院へ通う学生とは異なり、通信講座の場合は多くの方が仕事の合間を見つけながら学習をするケースがほとんどです。
毎日無理なく学習することを考えると1日1時間程度が目安となるため、だいたい20日間でカリキュラムを終えられる計算になります。
もちろん、20日間だけでは試験範囲を網羅的に理解できないことも考えられるため、必要に応じて過去問題に挑戦したり、分からないところやつまづいた部分を重点的に復習する時間も必要でしょう。
そのため、少なくとも1ヶ月間程度は学習時間を確保しておく必要があります。
メンタル心理カウンセラーの難易度
メンタル心理カウンセラーの合格基準は70%以上の得点率となっており、難易度がそれほど高い試験ではありません。
心理カウンセラーの関連資格のなかでも初級者向けに位置しており、テキストや教材に沿って学習しておけば初学者でも十分合格を目指せるでしょう。
▶︎【自己受容】弱くてダメな自分を認めて受け入れるトレーニング方法
メンタル心理カウンセラーの学習内容

メンタル心理カウンセラーの資格を取得するうえで、具体的にどういったカリキュラムを学ぶ必要があるのでしょうか。
通信講座で提供されているテキストや教材をもとに、主な学習内容の一例を紹介します。
心理学の基礎
心理カウンセラーとして専門性を身につけるためには、心理学の基礎から学ぶ必要があります。
心理学はどのような歴史を経て発達してきたのか、社会心理学や発達心理学といった分野を網羅的に学ぶとともに、自分自身のストレスチェックも行いながら心理学への理解を深めていきます。
カウンセリングの基礎
心理カウンセラーにとって必要な実践的な学習として、カウンセリングの基礎があります。
そもそもカウンセリングとは何か、何を目的として行うのか、さらには「インテーク面接」や「積極的傾聴」、「来談者中心療法」、「ロジャーズ理論」といった具体的な方法を学びます。
カウンセリングのルール
カウンセリングの基礎を理解できたら、実際にカウンセリングを行う際に守るべきルールも身につけていきます。
カウンセリングの時間や話しやすい環境をつくるためのテクニック、相談者との信頼関係を構築するためのポイントなどもこの範囲に含まれます。
開業方法
心理学やカウンセリングを一通り学んだら、心理カウンセラーとして開業するための方法や流れについても学習します。
どのような開業スタイルがあるのか、開業にあたって不可欠なコンセプトや理念、カウンセリング料金の決め方、事業計画の立て方など実務的な内容を学んでいきます。
メンタル心理カウンセラーの取得にかかる費用
メンタル心理カウンセラーにかかわらず、専門的な資格を取得する際に多くの方が気になるのはコストの問題ではないでしょうか。
メンタル心理カウンセラーは一般財団法人日本能力開発推進協会が主催している試験であり、大前提として、受験するためには協会が認定する教育訓練において全カリキュラムを修了している必要があります。
そのため、メンタル心理カウンセラーの取得にかかる費用は大きく分けて通信講座の受講料と試験の受験料となります。
- 通信講座受講料:38,600円(税込)
- 受験料:5,600円(税込)
上記にある通り、通信講座の受講料は通常38,600円ですが、申し込むタイミングによってはキャンペーンで割引となるケースも多く、3万円以下の料金で受講できる可能性もあるので活用してみましょう。
メンタル心理カウンセラーを取得しキャリアアップにつなげよう
これから心理カウンセラーを目指す方にとって、メンタル心理カウンセラーの資格を取得することは大きな武器になるでしょう。
数ある資格のなかでも初級に位置しており、比較的難易度は低いといえますが、しっかりと学習しておかないと合格は難しいことも事実です。
キャリアアップのために、まずはメンタル心理カウンセラーの取得を目指してみましょう。
▶︎スピリチュアルカウンセラーとはどんな職業?誤解されやすい職業との違い
心理カウンセラーになるには?武器となる資格や仕事内容も解説
ストレスの多い現代社会において、人々が抱える悩みや不安を解消するための相談に乗る「心理カウンセラー」という職種のニーズが高まっています。
これから心理カウンセラーになりたいと考える方にとっては、どういった資格や免許が必要なのか疑問に感じることもあるでしょう。
そこで本記事では、心理カウンセラーになるための条件について解説するとともに、心理カウンセラーの仕事内容や武器となる資格なども紹介します。
心理カウンセラーとは

心理カウンセラーとは、相談者のさまざまな悩みや問題をヒアリングし、相談に乗ることで心理的な側面から支援をする専門職です。
社会生活を送るうえでストレスは切っても切り離せない問題であり、精神的な疾患や不安を抱える人は少なくありません。
実際に心療内科や精神科といったメンタルヘルスクリニックを受診する人は多く、精神疾患は大きな社会問題にもなっています。
精神疾患を治療するのは精神科医をはじめとした医師の仕事ですが、精神疾患を予防するためにも心理カウンセラーの役割は大きく、現代社会になくてはならない存在ともいえるのです。
これまで心理カウンセラーは医療機関などに所属し、患者にとっては相談できる場所が限られていました。
しかし、昨今では学校や企業など多くの場所に心理カウンセラーが在籍するようになったことから、社会からのニーズが高まっています。
▶︎メンタル心理カウンセラーとは?資格を活かせる現場や学習内容も解説
心理カウンセラーの主な仕事内容

心理カウンセラーは具体的にどのような仕事をするのでしょうか。
冒頭でも紹介した通り、心理カウンセラーの活躍の場は広がっており、それによっても仕事内容は変わってきます。
医療機関・クリニック
精神科や心療内科といったメンタルケアを担う医療機関では、精神科医に並んで心理カウンセラーは欠かせない職種です。
直接的な治療は医師が担いますが、心理カウンセラーは治療中の不安や悩みなどの相談に乗り、早期回復をサポートします。
また、内科や外科、産婦人科といった一般的な診療科においても、患者本人やその家族のケアをするために心理カウンセラーが派遣されることがあります。
学校
教育現場では、いじめや不登校、人間関係の悩みなどを抱える児童・生徒が少なくありません。
そのような悩みや心の傷を回復させるためにも心理カウンセラーは不可欠な存在です。
ちなみに、教育現場に配属される心理カウンセラーは「スクールカウンセラー」ともよばれます。
企業
学校と同様、企業においてもさまざまな悩みを抱える人は存在します。
特に、パワハラやセクハラといった深刻な悩みを抱えているにもかかわらず、解決できないまま放置しておくと職場環境が悪化し人材の流出につながるおそれもあるでしょう。
また、残業が続き精神状態が悪化したり、大きな仕事のプレッシャーがストレスとなり生産性が低下したりといったケースもあります。
このように、職場における悩みやストレスを解消するためにサポートする心理カウンセラーを「産業カウンセラー」とよびます。
福祉施設
児童相談所や児童福祉施設にはさまざまな境遇の子どもがおり、なかには心に大きな傷を抱えているケースも少なくありません。
また、子どもだけでなく、高齢者施設においてもストレスを感じる利用者や、介護疲れに悩む家族もいます。
このように、福祉施設の利用者が抱える心の問題に向き合うのも心理カウンセラーの大切な仕事のひとつです。
その他公的機関
警察署や刑務所、少年院などにも心理カウンセラーが配属されることがあります。
犯罪被害に遭った人や、犯罪・非行を起こした人に対し心理的なサポートをするのが主な仕事であり、いち早く元の社会生活に戻るために重要な役割を果たします。
▶︎感情の起伏が激しい人や少ない人の特徴|上手にコントロールする方法とは
心理カウンセラーになるための条件・スキルの習得方法

心理カウンセラーは医師とは異なり、特定の資格や免許が必須というわけではありません。
専門的な知識やスキル、経験を持っていれば、誰もが心理カウンセラーとして活躍できます。
ただし心理カウンセラーとして評価され、実際に仕事に活かそうと考えた場合、知識やスキルを客観的に証明できなければ難しいといえるでしょう。
多くの心理カウンセラーは、以下のいずれかの方法でキャリアをスタートさせています。
大学や大学院で学ぶ
専門的な知識を身につけるためには、大学や大学院で学ぶ方法が一般的です。
心理学を学べる大学を選ぶことで、心理カウンセラーに必要な知識を身につけられるほか、国家資格である公認心理師の受験資格を得られるメリットもあります。
特に、10代、20代と若いうちから心理カウンセラーになることを目標としている方は、大学や大学院へ進学することでキャリアの道が開けてくるでしょう。
民間のスクール・通信講座で学ぶ
民間のスクールや通信講座で学ぶ方法もあります。
大学や大学院に比べると入学のハードルが低く、授業料などコスト面でもメリットが大きいといえるでしょう。
また、通信講座であれば社会人になってからでもカリキュラムを受けやすく、仕事をしながらでも心理カウンセラーに必要な資格取得に挑戦できます。
▶︎【自己受容】弱くてダメな自分を認めて受け入れるトレーニング方法
心理カウンセラーとして武器になる資格
心理カウンセラーとして活躍していくうえで、どういった資格が武器となるのでしょうか。
代表的な資格を3つ紹介しましょう。
公認心理士
公認心理士とは国家資格のひとつであり、2018年に新設された比較的新しい資格です。
心理カウンセラーの武器となる唯一の国家資格であることから、多くの方がこの資格を取得し業務に役立てています。
公認心理士を取得することで、心理査定やカウンセリング、さまざまな情報提供の活動などを担えるようになります。
臨床心理士
臨床心理士とは、公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定している民間資格です。
臨床心理士を取得するためには、「協会が指定する大学院を修了し、所定の条件を満たしている」または「臨床心理士を養成する専門職大学院を修了」といった条件が設定されているため、ほかの資格に比べると受験のハードルは高いです。
しかし、臨床心理士を取得すればスクールカウンセラーの専門職としても認定されるため、心理カウンセラーとしての道が開けてくるでしょう。
メンタル心理カウンセラー
メンタル心理カウンセラーは、一般財団法人日本能力開発推進協会が認定している民間資格です。
その名の通り、心理カウンセラーに求められる知識やスキルを証明するための資格であり、心理カウンセラーとして採用する際にこの資格の有無を問われるケースも少なくありません。
ただし、メンタル心理カウンセラーは通信講座でも取得できることから、ほかの資格に比べると受験のハードルは低いといえるでしょう。
武器となる資格を取得し心理カウンセラーを目指そう
職場や学校、その他あらゆる場面においてストレスを抱えがちな現代社会において、心理カウンセラーは不可欠な存在であり、ますます需要が高まっています。
相談者に寄り添い、話をじっくり聞くことが心理カウンセラーには求められ、人の役に立ちたいと考える方に向いている職業といえるでしょう。
心理カウンセラーになるために資格や免許は必須ではありませんが、これからキャリアをスタートさせたいと考える方は、客観的にスキルを証明できる資格の取得がおすすめです。
▶︎スピリチュアルカウンセラーとはどんな職業?誤解されやすい職業との違い
スピリチュアルカウンセラーとは|本物になるためにはどうすればいい?
霊的な能力を用いてさまざまな人の悩み・不安解消に導く「スピリチュアルカウンセラー」という職業があります。
しかし、これだけを聞くと「怪しい」「胡散臭い」といったイメージをもつ方も少なくありません。
本記事では、スピリチュアルカウンセラーとはどういった職業なのか、誤解されやすい職業との違いやスピリチュアルカウンセラーになるための方法なども詳しく解説します。
スピリチュアルカウンセラーとは

そもそも「スピリチュアル」とは、日本語に直訳すると「霊的な」、「霊魂に関するさま」といった意味を指します。
すなわち、スピリチュアルカウンセラーとは、霊的な力によって相談者のさまざまな悩みや不安を解消する専門家のことを指します。
霊的な力と聞くと、いわゆる霊感商法のように、不安を煽りお金をだまし取るなどの被害に遭うのではないか、または怪しい職業といったイメージを抱かれがちです。
たしかに、霊的な力は多くの人の目に見えるものではないことから、「胡散臭い」、「怪しい」と感じられることも多く、霊的な力をもっていないのにお金を儲けようとする悪質な人も存在します。
しかし、スピリチュアルカウンセラーは民間の資格も存在し、これを持っておくことで客観的にその能力や信頼性を証明でき、初めてカウンセリングを受ける人に対しても安心感を与えることができるのです。
▶︎心理カウンセラーになるには?武器となる資格や仕事内容も解説
スピリチュアルカウンセラーと誤解されやすい職業
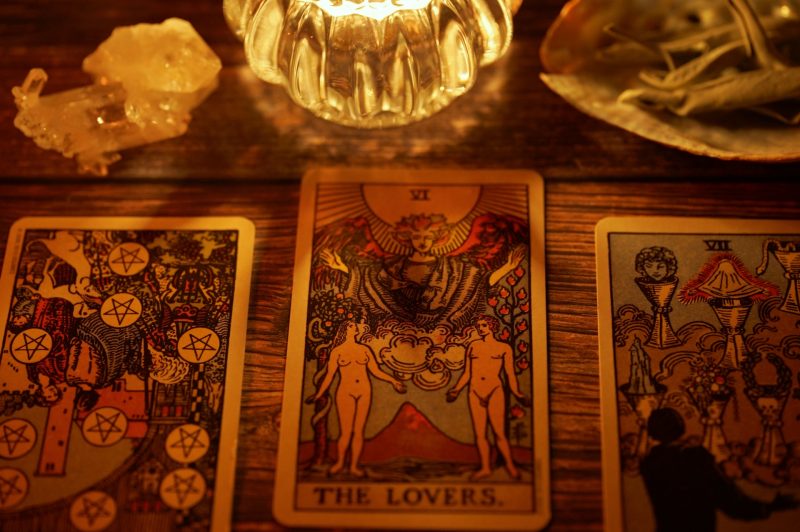
霊的な力をもって人々の悩みや不安を解消すると聞くと、占い師や霊能者といったさまざまな職業をイメージする方も多いと思います。
実際に同じような行為を行うケースもありますが、スピリチュアルカウンセラーとはどのような違いがあるのでしょうか。
占い師との違い
スピリチュアルと聞くと神秘的な力をイメージしがちで、特に占い師と混同する方も少なくありません。
実際にスピリチュアルカウンセラーのなかにも、占いができる、あるいは占いを得意とする人も存在しますが、本質的には異なる存在です。
スピリチュアルカウンセラーはあくまでもカウンセリングを中心に行うため、相談者が何に悩んでいるのか、何を相談したいのかを丁寧にヒアリングします。
一方、占い師は一方的なアドバイスや助言をするケースも多く、必ずしもカウンセリングを行えるとは限りません。
霊能者との違い
霊能者とは、霊魂が存在するとされている世界、いわゆる霊界と交信し、霊からのメッセージを自分なりに解釈して伝える専門家のことです。
日本ではスピリチュアルカウンセラーという言葉よりも、霊能者という名称のほうが浸透しているため分かりやすいでしょう。
イタコとの違い
イタコとは、青森県を中心とした東北地方で口寄せを行う人のことを指します。
口寄せとは、亡くなった方の霊をイタコ自身に乗り移らせ、亡くなった方自身の言葉として発する行為を指します。
イタコは霊界との交信をするだけでなく、自分自身に乗り移らせるという点が大きな特徴といえるでしょう。
チャネラーとの違い
チャネラーとは、日本における霊能者と同じような存在であり、霊界との交信によってさまざまな情報を得る「チャネリング」を行う人を指します。
スピリチュアルカウンセラーは相談者の悩みや不安を取り除くということを目的として活動しますが、チャネラーはあくまでも霊界との交信を行える人という違いがあります。
▶︎メンタル心理カウンセラーとは?資格を活かせる現場や学習内容も解説
スピリチュアルカウンセラーへの主な相談内容

日本ではあまり馴染みのないスピリチュアルカウンセラーという職業ですが、具体的にどういった悩みや相談を受けることが多いのでしょうか。
恋愛・結婚相談
意中の相手がいるものの、なかなか一歩を踏み出せないという人は多いものです。
そのようなとき、スピリチュアルカウンセラーは深層心理を読み解き、霊界との交信をしながら有効なアドバイスをすることができます。
また、すでに交際相手がいる場合、どうしたら結婚できるか、相手は自分のことを受け入れてくれるかといった悩みや不安を抱くことがあるでしょう。
そのような場合も、スピリチュアルカウンセラーは相談者からさまざまなことをヒアリングし、効果的なアドバイスができます。
仕事や将来に関する相談
将来やりたいことが分からない、あるいはどのような仕事が向いているのか分からない、今の仕事をこのまま続けていくべきかなど、仕事や将来に関する相談も少なくありません。
占い師のように「この会社に入りなさい」、「◯◯の道が向いています」といったようなアドバイスではなく、あくまでも相談者の意思や潜在的な考え、価値観などを引き出したうえでアドバイスを行います。
人生におけるあらゆる悩み
仕事や恋愛以外にも、人生にはさまざまな悩みがあります。
たとえば、「経済的に困窮しているためお金持ちになりたい」、「人間関係がうまくいかず孤立してしまう」など、人によって悩みの内容は異なります。
スピリチュアルカウンセラーは、このような漠然とした悩みに対しても丁寧に質問を繰り返して掘り下げていき、その人の考えや価値観をしっかりと理解したうえで有効なアドバイスを送ることができます。
しかし、これだけを聞くと一般的なカウンセラーとの違いが分からないと感じる方も多いでしょう。
カウンセリングをするのはあくまでも本人の意思を確かめるためであり、霊界との交信結果をそのまま相談者へ伝えるわけではないのです。
スピリチュアルカウンセラーは相談者が知りたいことや本当に解決したいことは何か、潜在的にどういった結論を求めているのかなどを理解したうえで助言を行うため、相談者のことを第一に考えています。
▶︎感情の起伏が激しい人や少ない人の特徴|上手にコントロールする方法とは
本物のスピリチュアルカウンセラーになる方法

スピリチュアルカウンセラーになるためには、医師や弁護士のように資格や免許が必須というわけではありません。
霊界との交信ができる人であれば、霊能力者や占い師のように誰でもスピリチュアルカウンセラーを名乗ることができます。
しかし、本当に信頼できるスピリチュアルカウンセラーになるためには、専門的な資格をもっておいたほうが有利になるのは間違いありません。
たとえば、一般社団法人スピリチュアルマスターアカデミーでは、「認定スピリチュアルカウンセラー資格」という民間資格を発行しています。
この資格は独学で受験することもできますが、より効率的に勉強するためには「スピリチュアルマスター養成講座」や専門学校、スクールに通う方法もおすすめです。
スピリチュアルカウンセラーに向いている人
霊能力・霊感があったとしても、すべての人がスピリチュアルカウンセラーに向いているとは限りません。
そもそもカウンセラーという仕事は人とのコミュニケーションが不可欠であることから、他人に対して興味や関心があり、人と接するのが好きな方がスピリチュアルカウンセラーに向いているでしょう。
コミュニケーションと聞くと自分自身の考えや意見を述べる話し上手な人というイメージをもたれがちですが、実際には人の話をしっかり聞いて理解できることが何よりも重要です。
一流のスピリチュアルカウンセラーになるために
スピリチュアルカウンセラーは日本における霊能者やイタコとも近い存在ではありますが、相談者とのコミュニケーションを大切にしカウンセリングに重点を置いているという大きな違いがあります。
多くの相談者が訪れるスピリチュアルカウンセラーは、霊界との交信ができるという特殊な能力に加えて、相談者のことを第一に考えている点が挙げられます。
信頼できるスピリチュアルカウンセラーになるために、専門的な資格の取得とコミュニケーション力の向上にも努めてみましょう。
深呼吸は脳にどんな効果がある?やりすぎは危険?
緊張したときや興奮状態にあるとき、落ち着きを取り戻すために深呼吸をすることがあります。
なぜ深呼吸をするだけで心を落ち着かせることができるのでしょうか。
また、深呼吸にはリラックス効果以外にもさまざまな効果があるとされていますが、それは具体的にどういったものなのでしょうか。
本記事では、深呼吸の正しいやり方や注意点なども含めて詳しく解説します。
深呼吸をすると落ち着くのはなぜ?

パニックに陥ったとき、ゆっくりと深呼吸をすることで心が落ち着くことがあります。
なぜ深呼吸をすると落ち着きを取り戻すことが多いのでしょうか。
酸素の供給
理由は単純で、深呼吸をすることで、より多くの酸素を体内に取り入れられるためです。
酸素は脳や筋肉の活動に欠かせないものであり、適切な酸素供給が行われることで脳の機能が改善され、集中力や冷静な判断力を取り戻すことができます。
集中力を高められるため
深くゆっくりとした呼吸に集中することで、心の中の不安やストレスに意識を向ける余裕が生まれます。
これにより、一時的ではあるものの外部の刺激や心配事から離れ、心を静めることができます。
心理的な効果
私たちはこれまでの経験から、深呼吸をすることで精神的な落ち着きを取り戻すことができるという知識を得ています。
実際に深呼吸にはリラックス効果がありますが、それに加えて「落ち着きを取り戻せる」という自己暗示的な効果もあり、ストレスや不安を緩和することができるのです。
▶︎感情の起伏が激しい人や少ない人の特徴|上手にコントロールする方法とは
深呼吸の効果
深呼吸をすることで、医学的にどのような効果が認められているのでしょうか。
代表的な効果をご紹介します。
ストレスの軽減・リラックス効果
深呼吸はストレスの緩和に効果的です。
深くゆっくりとした呼吸は副交感神経を刺激し、リラックス効果を高めます。
これによりストレスホルモンの分泌が抑制され、心身の緊張を緩和してくれます。
深呼吸によってリラックス効果が得られると、一定の心拍数や呼吸数に調整し落ち着いた状態をもたらしてくれるのです。
セロトニンの増加
セロトニンとは、心の安定や幸福感に重要な役割を果たす神経伝達物質であり、「幸せホルモン」ともよばれています。
深呼吸をすることで酸素が増えると、脳からのセロトニンの生成や放出が促進されると考えられています。
セロトニンが増加すると、後ろ向きな思考や悩み、不安が解消され、心が平穏な状態を維持しやすくなります。
血圧の変化
ゆっくりと深い呼吸をすることで、血液中の酸素濃度が上昇し、血管が拡張されます。これにより、血圧が下がる効果が期待できます。
また、深呼吸は交感神経と副交感神経のバランスを整える働きがあり、副交感神経の優位性が増すことも血圧を下げることにつながります。
▶︎【自己受容】弱くてダメな自分を認めて受け入れるトレーニング方法
深呼吸はどんな人におすすめ?

深呼吸は医学的に見てもさまざまなメリットをもたらす行為といえます。
健康効果を考えたとき、深呼吸はどのような人に適しているのでしょうか。
高齢者
高齢者は一般的に身体的機能が衰え、運動量も減少するため、呼吸が浅くなる傾向があります。
意識的に深呼吸を取り入れることで、酸素供給を増やし肺機能を改善することができるでしょう。
また、高血圧に悩まされている高齢者も多いですが、深呼吸をすることで血管が拡張され、血圧を正常値に戻す効果も期待できます。
うつ病やパニック障害など精神疾患を抱えている人
深呼吸は自律神経の調整に効果が期待でき、交感神経と副交感神経のバランスを整える働きがあります。
これにより精神状態を安定化させ、不安やストレスの軽減に貢献します。
また、深呼吸はセロトニンの増加を促進する働きもあります。
これにより、抑うつ症状を緩和できるため、うつ病やパニック障害の症状に悩まされている人にもおすすめです。
緊張しやすい人
深呼吸にはリラックス効果があるため、緊張しやすい人にもおすすめの習慣です。
たとえば、人前に出て話すときや取引先との商談、スポーツの試合の前などに深呼吸をすることで、本来の自分の力や持ち味を発揮できるでしょう。
また、過度に緊張している状態では注意力が散漫になり、本来ではあり得ないミスや間違いを起こすこともあります。
そのようなときも深呼吸に集中することで緊張や心配事から一時的に離れ、集中力を高めることができるはずです。
睡眠の質を改善したい人
ベッドに入ってもなかなか寝付けず、慢性的な睡眠不足に悩まされている人も少なくありません。
また、睡眠時間は確保できているものの、睡眠の質が悪く熟睡できない人もいます。
ベッドに入ってから深呼吸を行うことで、交感神経と副交感神経のバランスを整え、睡眠の質を改善するのに役立ちます。
▶︎マインドフルネスをやってはいけない人の特徴|PTSDやうつ病の人は危険?
深呼吸のやりすぎは危険?
精神的な効果はもちろん、身体的にもさまざまな効果がある深呼吸ですが、過度に意識するあまり深呼吸をやりすぎてしまうと効果を低減させるばかりか、身体にとってもさまざまな悪影響を及ぼすことがあります。
深呼吸をすると大量の酸素が体内に吸収されます。それと同時に、体内の二酸化炭素が外に排出されていきます。
二酸化炭素と聞くと私たちの身体に不要なものというイメージがありますが、決してそのようなことはなく、酸とアルカリのバランスを適度に保つ役割をもっているのです。
深呼吸をしすぎてしまうと、本来必要であった二酸化炭素まで排出されてしまい、酸とアルカリのバランスが崩れ頭痛やめまいなどの症状を引き起こすことがあります。
深呼吸の正しいやり方

Close-up of a woman’s hands on her chest while doing breathing exercises
では、深呼吸の効果を高めるためにはどうすれば良いのでしょうか。
正しい深呼吸のやり方と、適切な回数や頻度について解説します。
正しい深呼吸の方法
- 椅子に座っている場合は、背筋を伸ばして軽く目を閉じ、腹部に手を添えてください。
- また、立っている場合は力を入れずにリラックスした状態で腹部に手を添えます。
- 深呼吸と聞くと思い切り息を吸い込むイメージがありますが、むしろ意識しなければならないのは息を吐くことです。
- 頭のなかで3秒数えながら息をゆっくり吐き出してみましょう。
- その後、同じように3秒数えながら鼻から息を吸い込みます。
この一連の流れを5~10分程度繰り返してください。
ただし、気分が悪くなったり息苦しさを感じるようであれば無理をせず中断しましょう。
深呼吸の適切な頻度
深呼吸のやりすぎは身体に悪影響をもたらすと紹介しましたが、どの程度の頻度を心がけるべきなのでしょうか。
結論からいえば、上記の一連の流れを1日1セット5~10分程度繰り返すだけで十分です。
その日の体調や個人の体質によっても適切な回数、頻度は異なるため、自分にとって心地よいと感じる範囲で行いましょう。
まとめ
緊張状態を緩和しリラックス効果を得るために、深呼吸は手軽な方法のひとつです。
深呼吸は単にリラックスするだけでなく、集中力を高めたり血圧を抑えたりといった効果も期待できます。
日常生活に取り入れたい習慣のひとつですが、深呼吸のしすぎは本来必要な二酸化炭素を排出してしまい、頭痛やめまいなどの症状を引き起こすこともあります。
今回紹介した正しい深呼吸の方法を実践し、自分自身にとって心地よい回数、頻度で無理なく続けてみてください。
セックスセラピーとは|カウンセリングの内容や受けられる場所は?

夫婦間やパートナー同士の愛情表現やコミュニケーションを図る方法として、セックスは重要な手段のひとつです。
しかし、身体的あるいは精神的な問題や悩みが原因となって、セックスがうまくできず困っている人も少なくありません。
そのような方におすすめしたいのが、セックスセラピストによるセックスセラピーとよばれる治療法です。
セックスセラピーとは何なのか、セックスセラピストにはどういった相談・治療が可能なのか、セックスセラピーを受けられる場所などもあわせて解説します。
セックスセラピーとは

セックスセラピーとは、セックスに関するさまざまな悩みや障害をカウンセリングし、改善に向けた治療を行う行為です。
性行為をしようとしても身体的な問題や精神的な問題によって性行為ができず悩んでいる方も少なくありません。
セラピーと聞くと悩みや不安を聞いて精神面からサポートすることをイメージする方も多いですが、セックスセラピーはメンタル面だけでなく、フィジカル面での物理的な治療も担うことが大きな特徴です。
▶セックスレスの原因とは?|なりやすい夫婦の特徴や解消法を解説
海外でセックスセラピーが注目されている理由
日本ではあまり馴染みのないセックスセラピーですが、海外では徐々に広まっており、セックスセラピーを受けている著名人も少なくありません。
では、なぜ海外でセックスセラピーが注目されているのでしょうか。
性医学の発達
これまで医療の世界では、セックスそのものを対象とした研究はほとんど行われてきませんでした。
しかし、近年では性科学の研究が行われるようになり、医学教育のカリキュラムとしてセックスに関する科目が含まれるようになりました。
セックスの悩みを相談できる人がいない
病気や怪我、精神的な悩みなどは人に話を聞いてもらうこともできますが、セックスに関する話題は非常にデリケートであり、不安や悩みがあったとしても相談しにくいものです。
これは信頼できる友人や夫婦間であっても同様であり、悩みを一人で抱え込んでしまうことも少なくありません。
セックスに関する悩みを解消することは、心身ともに健康的でQOLの高い生活を送るうえでも重要なことです。
他人に相談できないデリケートな悩みを解消するためにも、セックスセラピーは注目されています。
▶40代の女性は性欲が強い?なくなる?その違いや性欲の対処法について
セックスセラピーの相談内容

セックスセラピーでは具体的にどのような相談に乗ってもらえるるのでしょうか。
性行為にあたってよくある悩みや代表的な相談内容を紹介しましょう。
身体的な悩み
男性の場合は勃起不全(ED)が代表的な悩みとして挙げられるほか、女性の場合も挿入時に痛みを感じたり、うまく挿入できなかったりという身体的な悩みを抱えている場合があります。
セックスレスの状態が長く続いている
特定のパートナーはいるものの、たとえば結婚をしてからわずか数年でセックスレスになったり、相手からセックスを拒否されたりすることもあります。
そのセックスレスの原因は何なのか、セックスセラピーを通して相談し解決につなげることもできます。
セックスの経験がなく不安
これまでの人生においてセックスの経験がない場合、交際相手ができたり結婚を意識する相手ができたとき、うまくセックスができるか、相手を満足させられるかといった不安が付きまといます。
セックスセラピーでは、相手にとっても自分にとっても満足のいくセックスをするために、正しい知識を身につけることができます。
セックスそのものに恐怖を感じる
身体的な悩みや不安はもちろんですが、過去にあった辛い経験が原因となり、セックスそのものに恐怖を感じることがあります。
セックスセラピーでは専門家のカウンセリングにより、セックスに対する恐怖心を払拭していきます。
▶︎セックスレスの原因とは?|なりやすい夫婦の特徴や解消法を解説
セックスセラピーはどのような治療をするのか

セックスに関する悩みや不安を払拭するとはいっても、セックスセラピーではどのような治療を行うのか疑問に感じる方も多いでしょう。
まず、前提として覚えておきたいのは、セックスセラピーでは、その場で衣服を脱いで性行為やそれに近い行為をするということはまずありません。
あくまでも専門家が相談に乗り、セックスに関する正しい知識やアドバイスを提供する場と認識しておく必要があります。
性機能不全の治療
身体的な治療としてもっとも多いのは、性機能不全の治療です。
男性の場合は勃起不全(ED)や早漏、女性の場合は膣狭窄や膣の乾燥などが挙げられます。
性機能不全の原因はさまざまで、加齢にともなうホルモン分泌量の低下や、心理的な要因が関係していることもあります。
カウンセリングによって性機能不全の原因を突き止め、必要に応じて行動療法や薬の処方、心理療法などを行います。
心理療法
性機能不全を広い意味で捉えると、セックスに対する嫌悪感や性欲の喪失、過剰性欲なども含まれます。
これらは身体的な原因が背景にあることもありますが、精神的な問題が隠れていることも少なくありません。そのような場合、専門家のカウンセリングによって心理療法も行われます。
特に、過去に経験した辛い出来事が原因となっている場合、安心して話せる場を設けて話を聞き、徐々に改善を目指していきます。
▶︎セルフプレジャーとは?美容効果を紹介!どんな人におすすめ?
セックスセラピーはどんな人におすすめ?
日本でも少しずつ浸透しつつあるセックスセラピーは、一言でいえばセックスに関して何らかの悩みを抱えている人におすすめです。
上記でも紹介した通り、男性の場合は勃起不全や早漏、女性の場合は膣狭窄や膣の乾燥といった身体的な悩みを抱えている人が代表的でしょう。
また、心理的な要因によってセックスレスに陥っている人や、セックスそのものに拒絶反応を示す人、性欲の喪失または過剰性欲に悩んでいる人にもおすすめです。
セックスセラピーは、人に言えないデリケートな悩みや不安を安心して相談できるメリットがあり、当然のことながら相談者のプライバシーは厳重に守られます。
セックスセラピーはどこで受けられるの?
日本におけるセックスセラピーは海外に比べて一般的ではなく、受診できる病院やクリニックも限られています。
セックスセラピーに対応できる病院を調べるときには、セックスカウンセラーやセックスセラピストが日本性科学会(JSSS)のWebサイトで公開されているので、「セックスカウンセラー・セラピスト一覧」を参考にしてみるのがおすすめです。
2023年6月時点では、セックスカウンセラーは全国に13名、セックスセラピストは32名が在籍しています。
セックスセラピーが受けられるクリニックは産婦人科や泌尿器科、精神科などがメインであり、身体的な悩みであれば産婦人科および泌尿器科、心理的な悩みであれば精神科に相談してみるのも良いでしょう。
まとめ
欧米では徐々に注目されているセックスセラピーですが、日本ではまだまだ知名度が低く、受診できる場所も限られています。
セックスに関する悩みや不安は人に相談しにくいこともあり、一人で抱え込んでいるケースも少なくありません。
しかし、間違った知識や治療法で悪化させないためにも、まずは専門家に相談し適切な治療法を選択することが大切です。
50代女性の性欲事情|閉経後や更年期との関連性についても

50代にさしかかると、女性は更年期や閉経を迎えます。
なかには、この年齢を境にセックスレスに陥り、夫婦間の関係やコミュニケーションに悩む女性も少なくありません。
50代になると性欲が低下する女性が多いのはなぜなのかを解説するとともに、性欲が高まる人との違いや、更年期や閉経後も人生を楽しむ方法なども紹介します。
▶40代の女性は性欲が強い?なくなる?その違いや性欲の対処法について
50代女性の性欲事情で多い悩み
ジェックス株式会社が2020年に調査した「Japan Sex Survey」によると、セックスをする目的として男性は半数以上が「性的な快楽のため」と回答しているのに対し、女性は半数以下に留まっていることが分かっています。
なかでも女性の場合は50代が20.8%、60代になると16.4%と極めて低く、年齢を重ねると性欲が大幅に低下していく傾向が見られます。
では、なぜこのような傾向が見られるのでしょうか。
閉経にともなう性交痛
大きな要因のひとつとして、閉経が考えられます。
女性の場合、40代後半から50代に入ると卵巣の機能が消失し月経が停止します。
これを閉経とよび、女性ホルモンの分泌量が著しく減少するのです。
その結果、腟内で分泌される体液の量が減り、潤滑性がなくなることで性交痛を伴うことがあります。
快楽を得られにくくなり、セックスそのものを苦痛に感じ性欲が低下していきます。
介護による時間の制約や疲労
50代になると子育てからは解放されますが、その代わりに親の介護という問題も出てきます。
自分や夫婦の時間を確保したくても、介護疲れによってセックスどころではなくなり、パートナーから求められても面倒に感じることも多いようです。
体力の低下
さらに、30代や40代と比べると加齢にともない体力も低下していき、セックスそのものが疲れると感じることもあるようです。
このように、閉経といった身体のメカニズムが影響していることもあれば、時間的な制約や体力的な問題など、さまざまな要因が複合的に絡み合い、性欲の低下を引き起こしている可能性が考えられるのです。
▶セックスセラピーとは|カウンセリングの内容や受けられる場所は?
▶︎夫婦関係は修復できる?よくある破綻のきっかけや修復方法を紹介
50代女性のセックス頻度
性欲が低下したり、セックスそのものが面倒に感じたりするのは自分だけなのだろうかと、悩みや不安を感じる方も少なくありません。
実際に50代女性はどの程度の頻度でセックスをしているのでしょうか。
「Japan Sex Survey」によると、50代女性の1年間のセックス回数は「1年以上なし」と回答した割合がもっとも多く65.8%、次いで「年数回」が13.7%、「月2〜3回」が8.2%、「月1回」が8.1%と続いています。
このデータからも分かる通り、実に9割以上の女性は月に多くても数回という頻度であり、週1回以上の頻度でセックスをしているのは全体の1割にも満たないことが分かります。
▶︎40代の女性は性欲が強い?なくなる?その違いや性欲の対処法について
閉経後や更年期で性欲が強くなる人と弱くなる人の原因

日本人女性の平均的な閉経年齢は51歳といわれており、この前後5歳、すなわち40代半ばから50代半ばを更年期とよびます。
女性の身体的なメカニズムに着目したとき、性欲の低下は閉経と関連性が高い可能性があることが分かりますが、一方で閉経や更年期を経て性欲が徐々に高まっていく女性も存在します。
その違いは何なのか、考えられるポイントを詳しく解説しましょう。
性欲が強くなる原因
更年期を迎えて性欲が強くなる女性は、以下のような原因が考えられます。
男性ホルモンの相対的な増加
性欲が高まるメカニズムは、男性ホルモンが影響しているといわれています。
実は男性ホルモンは男性の体内にのみ存在するものではなく、女性にもわずかに存在しています。
しかし、女性の場合は女性ホルモンの分泌量が圧倒的に多いことから、男性ほど性欲が強くないといわれています。
しかし、更年期に差し掛かり、閉経が近づくと徐々に卵巣機能が低下し、女性ホルモンの分泌量が減っていきます。
このとき男性ホルモンの分泌量は変化しないため、相対的に女性ホルモンと男性ホルモンの比率が変化し、性欲が強くなるといわれているのです。
妊娠する不安の低下・消失
女性がセックスに対して不安を抱く理由のひとつに、妊娠のリスクが挙げられます。
子どもが欲しいといった理由があれば別ですが、そのような希望がない場合、セックスによって望まぬ妊娠をする恐れがあるため、積極的にセックスしたい女性というのは少ないのです。
しかし、更年期や閉経によって卵巣機能が低下すると、妊娠に対する不安が低下していき、快楽を楽しめるようになります。
性欲が弱くなる原因
上記とは反対に性欲が弱くなる人は、これまでも紹介してきたように、女性ホルモンの減少によって腟内に潤いがなくなり性交痛を伴うケースが考えられます。
また、卵巣機能の低下により、「子どもを産める身体ではなくなった」と感じ、セックスそのものに価値を見いだせなくなる女性もいます。
このように、女性ホルモンの減少という直接的な原因は同じであるものの、その人のセックスに対する考え方や価値観、体質などが性欲やセックスに対するモチベーションを左右しているといっても過言ではないのです。
▶︎セックスレスの原因とは?|なりやすい夫婦の特徴や解消法を解説
閉経・更年期後でも人生を楽しく送る方法

女性ホルモンの減少と聞くと、閉経や更年期によって女性としての魅力が失われたと感じ、ネガティブな気持ちになる人もいるかもしれません。
また、それが原因でセックスから自然と遠ざかってしまう方もいるでしょう。
このような後ろ向きな気持ちでは人生を楽しむことが難しく、さらに魅力が低下していくことも考えられます。
では、閉経や更年期後も人生を楽しむために、どういった方法があるのでしょうか。
▶セックスセラピーとは|カウンセリングの内容や受けられる場所は?
おしゃれを楽しむ
閉経によって月経が停止することを、ポジティブにとらえることもできます。
たとえば、生理痛やナプキンの処理が不要になることはもちろんですが、月経のときには汚れを付けないように避けていた白い服やスカートなども、閉経後は気兼ねなく楽しめるようになるでしょう。
アクティブに活動してみる
月経中はプールや温泉などを楽しめないといった女性ならではの悩みもあります。
また、激しい運動も避ける必要があるでしょう。
しかし、月経が終わればスケジュールを気にすることなくプールや温泉、スポーツを存分に楽しむことができ、アクティブで前向きな気持ちを維持できるでしょう。
セックスの工夫
閉経や更年期を経てセックスがなくなってしまうと、夫婦間の関係やコミュニケーションがうまくいかないこともあります。
まずはパートナーに対して自分の状況を伝えて理解してもらい、無理をしないことが重要です。
そのうえで、新たなセックスの形に挑戦してみるのもおすすめです。
たとえば、挿入する行為だけがセックスではなく、撫でたり触れたりするだけでも性的欲求を満たせることがあります。
▶︎人生を変える最高の『セルフプレジャー』を見つける9つのステップ
まとめ
今回紹介してきたように、一般的に女性は50代になると性欲が低下していき、セックスそのものが面倒に感じることも少なくありません。
これは更年期や閉経にともなう女性ホルモンの分泌量低下が影響していると考えられますが、一方で性欲が増す女性も存在します。
あくまでも個人差があり、性欲が弱い・強いからといって極端に悩む必要はありません。
更年期や閉経後も人生を楽しむ気持ちが何よりも重要であり、そのためにも今回紹介した方法を試してみてください。
40代の女性の性欲が強い原因とは?性欲がなくなる場合との違いや対処法

人の三大欲求のひとつである性欲。
性欲の強さには個人差があり、またデリケートな問題でもあるため、悩みを抱えていたとしても相談しづらいものです。
一般的に、女性の場合は40代に性欲が強まるといわれることも多いですが、はたして本当なのでしょうか。
また、男性と比較した場合、性欲の強さや傾向にはどのような違いが見られるのでしょうか。
本記事では、女性の性欲が高まる年代や対処法について詳しく解説します。
女性の性欲のピークはいつ?

あくまで個人差はあるものの、男性と女性を比較した場合、性欲がピークに達する年齢には差があるとされています。
男性の場合は10代から20代にかけて性欲がピークに達するのに対し、女性の性欲は40代にピークを迎えるといわれています。
ジェックス株式会社の調査「Jex Sex Survey」によると、セックスをする目的として「性的な快楽のため」と回答した女性は40代が突出して高く、32.3%に達しています。
では、なぜ男女で性欲がピークに達する年齢が異なるのでしょうか。
その背景には、たとえば夫婦間でのセックスレスが続き我慢できなくなる、人生経験を積んだことにより男性を口説くのに心理的抵抗がなくなったなど、さまざまな理由があるでしょう。
しかし、科学的な観点から見てみると、性欲の増加には男性ホルモンが大きく影響していると考えられます。
そもそも男性ホルモンは女性にも存在しており、若いうちは女性ホルモンが優位ですが、卵巣機能の衰えとともに女性ホルモンは減少し、男性ホルモンが優位になります。
これによって、性欲のピークを迎える時期は男性と女性でズレが生じると考えられているのです。
▶セックスセラピーとは|カウンセリングの内容や受けられる場所は?
40代女性の年間の平均セックス回数
では、40代女性は1年間でどの程度セックスを行っているのでしょうか。
「Jex Sex Survey」によると、もっとも割合が高かったのは「1年以上なし」が46.8%、次いで「年に数回」が17.6%、「週1回」が14.9%という回答でした。
このデータではセックスそのものの頻度は20代、30代に比べて低い傾向が読み取れますが、夫婦間でのセックスレスが続いていたり、特定の相手がいなかったりと、さまざまな要因が考えられます。
▶︎夫婦関係は修復できる?よくある破綻のきっかけや修復方法を紹介
40代女性は性欲が強いといわれる理由

40代女性が性欲が強いとされているのは、冒頭で紹介したように、男性ホルモンの影響が大きいといえるでしょう。
しかし、それ以外にも生活環境や価値観の変化なども挙げられます。
20代、30代とは異なり、一般的に40代になると子育てのもっとも大変な時期が終わり、子どももある程度大きくなって生活環境が落ち着く時期でもあります。
これまでの生活をあらためて振り返ったタイミングで、女性としての自己認識や自己肯定感が高まり、性的な欲求や好奇心が高まると考えられているのです。
また、それだけでなく、これまでの人生のなかで性交渉を繰り返してきた結果、自分自身の性的嗜好や相手のニーズがわかるようになり、より満足度の高いセックスを求めるようになることも大きな要因として考えられるでしょう。
40代女性で性欲がなくなる人の原因
上記とは対照的に、40代女性のなかには以前と比べて性欲が低下してきた、またはなくなったと感じる人も少なくありません。
その背景にはどういった理由が考えられるのでしょうか。
ストレス・疲労
結婚や出産をしたタイミングによっては、40代といえども子育てのピークで日々の生活を送るだけで手一杯というケースも少なくありません。
特に晩婚化が進んでいる現在では、30代半ばや後半で結婚するケースも珍しくなく、その場合40代前半でも子どもが幼稚園や保育園に通っている場合もあるでしょう。
忙しい生活や仕事、家庭の責任などが原因でストレスや疲労が溜まり、性欲を減退させることがあります。
パートナーとの関係
結婚相手やパートナーが自分よりも年上である場合や、結婚生活があまりにも長いと、パートナーの性欲が減退していったり、自然とセックスと遠ざかったりすることもあります。
人によっては、それがきっかけとなり性欲が抑えきれなくなることもありますが、一方で自分自身までも性欲が低下することがあります。
それだけでなく、夫婦間におけるコミュニケーションの欠如や関心の不一致など、心理的な面も性欲の減退につながることがあるようです。
身体的な変化に対する不安
年齢を重ねていくと、多くの人は身体的にさまざまな変化が見られるようになります。
たとえば、美しいプロポーションを維持していたものの、結婚や出産を経て体型が崩れてきた場合、自信がなくなり相手からの目を気にするようになります。
そのような不安が性欲の低下につながることがあるようです。
▶︎セックスレスの原因とは?|なりやすい夫婦の特徴や解消法を解説
40代女性で性欲が強い人となくなった人との違い

上記を踏まえて、40代女性で性欲が強い人と性欲が減退する人にはどういった違いが見られるのでしょうか。
自己肯定感の高さ
自己肯定感が低い人ほど、身体的な変化に対して自信をなくしがちです。
若い頃の自分と比較してしまい、性に対しても消去的になってしまいます。
一方、自己肯定感の強い人は、加齢にともなう身体的な変化も受け入れ、前向きに考えられるようになります。
その結果、セックスに対しても前向きかつ積極的に受け入れようとし、性欲も高まっていく傾向が見られます。
心身の状態
性欲の強い人の多くは、心身ともに健康な状態にあり、ストレスや疲労も少ない傾向が見られます。
悩みがない、またはストレスとうまく付き合っている分セックスを受け入れる余裕があり、強い快感を求めようとします。
一方で、性欲が低下した人は、ストレスや疲労が原因で心身のバランスが崩れている場合が少なくありません。
性欲が抑えられないときの対処法
40代女性のなかには、年齢を重ねるとともに性欲が増していき、ときには抑えられなくなることもあるでしょう。
しかし、トラブルや病気のリスクを考えると不特定多数とのセックスは避けるべきであるのは当然のことです。
では、具体的にどのような対処法が考えられるのでしょうか。
パートナーとのセックス
まずは結婚している方の場合であれば、パートナーに正直に打ち明けたうえで、パートナーとのセックスで性欲を解消するのがベストです。
年齢を重ねるたびに性欲が高まっていることや、抑えられない感覚についてオープンに打ち明けコミュニケーションをとりましょう。
ただし、パートナーに対して無理強いをするのではなく、お互いが思いやりをもってバランスを取ることが何よりも大切です。
セルフプレジャー
パートナーによっては身体的あるいは体力的な問題でセックスをすることが難しい場合もあります。
そのようなときにはセルフプレジャーによって性的欲求を満たすことも有効です。
セルフプレジャーとは、いわゆる自慰行為やマスターベーションのことを指します。
セルフプレジャーを経験している女性は意外にも多く、その方法も指を使ったり専用のグッズを使ったりと多種多様です。
▶︎人生を変える最高の『セルフプレジャー』を見つける9つのステップ
まとめ
女性は40代になると卵巣機能の低下によって男性ホルモンが増え、それによって性欲が高まるといわれています。
また、子育てが一段落したタイミングで生活に余裕ができたり、自己肯定感が高まったりすることも性欲が高まる一因と考えられます。
もし、性欲が抑えきれず困っているという場合には、パートナーとコミュニケーションをとったり、セルフプレジャーで処理する方法も考えてみましょう。
究極の快楽を感じたいあなたへ:タントラ式セックスのやり方

映画でよく見るセックスのシーンを思い出してみてください。
素早く簡単に行われてオーガズムを感じることが究極の目的のように描写されていることが多いでしょう。
しかし、このセックスによって2人の親密度も増したと思いますか?
インドで生まれた思想「タントラ」の考えをベースにしたタントラ式セックスは、こういった従来のセックスとは異なるものです。
つまり、心のつながりを重視した居心地のよいセックスで深い結びつきを唯一の目的としたものなのです。
タントラ式セックスは、性行為を単に身体的な体験として捉えるのではなく、感情的で精神的なものと位置づけています。
「タントラ式セックスの心(The Heart of Tantric Sex)」の著者ダイアナ・リチャードソンはこう説明しています。
「私たちは絶頂に達することがセックスをする理由だと考えています」
その結果、私たちは絶頂を期待して目的志向的になり、私たち自身やパートナーがそれに到達しなかった場合にがっかりします。
タントラ的セックスはこの絶頂を目的としたものでなく、パートナーと「いまに集中すること」を目的としています。
「タントラ式セックスは、超越的で感情的で、さらには精神的な親密さを生み出します」とセックス・セラピストのモリ―・ペップ氏。
実は、あなたはすでにタントラ式セックスの一部を経験したことがあるかもしれません。
例えば、性交中のアイコンタクトや親密なマッサージなどが、タントラ式セックスの一部なのです。
それでは、自宅でタントラ式セックスを行う方法について詳しく学んでいきましょう。
タントラ式セックスとは?

Photo by We-Vibe Toys on Unsplash
タントラとは、サンスクリット語で「織り合わせる」という意味。
単体で使われる場合、ヒンドゥー教や仏教の伝統を指し、宇宙との一体感を得たり、すべてのものに神の存在を見出すことを重視しています。
タントラには、ヨガ、祈り、マントラ、タントラ経典の研究など、性的ではない実践も多く含まれます。
呼吸法、ゆっくりとしたタッチ、オーガズムを感じるタイミングを遅らせるなどのテクニックを用いたタントラ式セックスは、パートナーのエネルギー的なつながりを強化し、より深い存在感と至福感をもたらすことを目指すものです。
「タントラ式セックスのゴールは、マインドフルなセックスを通じて、より高い意識の状態になることです」とペップ氏は説明しています。
タントラ式セックスはパートナーともできますし、一人でもできます。
大切なことは、性行為を行っている時のマインドセットです。
儀式化されたアプローチを取ることで、セックスは単なる肉体的な行為以上のものになります。
パートナー、自分自身、そして宇宙とのつながりを深め、癒され、リラックスすることができます。
▶セックスレスになりやすい夫婦の特徴とは|原因や解消法を解説
タントラ式セックスのメリットは?
タントラ式セックスはカップルの性的な問題を解消するのに役立ちます。
心理学の雑誌『Psychology Today』によると、セックス中にオーガズムを感じる女性は約50%~70%。
一方で男性の約96%がオーガズムを感じています。
タントラ式セックスは、ゆっくりとしたペースで進めながらプレッシャーを取り除くことが目的で、男性の勃起時間を延長するのにも役立ちます。
また、リラックス感も増すため女性もオーガズムを感じやすくなります。
そして、性器だけに特化しないので予想以上の至福を経験することができます。
つまり、タントラ式セックスは全身へのアプローチのため、オーガズムも全身で感じられることがあるのです。
セックス・セラピストのジャネット・ブリト博士は、タントラ式セックスについて、カップルのつながりを深める以上のメリットがあると指摘します。
ゆっくりとしたペースで呼吸と優しいタッチに焦点を当てるため、セックスがうまくできたかという不安を軽減するのにも役立つと話しています。
「いまここにいると意識することが重要で、うまくできたかどうかはそこまで問題ではないのです」
リチャードソン氏は、マインドフルなセックスのために2~3時間を割くことをお勧めしています。
これにより、セックス中に瞑想状態にゆっくりと入り、タントラ式セックスのメリットの1つである「長時間の愛撫」を楽しむことができます。
セックスライフに満足しているカップルでも、タントラ式セックスの原則を試してみることでメリットがあるかもしれません。
セックスに十分な時間を割き、期待感を高め、いまに集中し、ペースを落とし、新しい体位を試してみましょう。
そうすることで、長年よりそってきたパートナーとさらに親密になるような、ドキドキする全く新しいセックスを体験することができます。
▶40代の女性は性欲が強い?なくなる?その違いや性欲の対処法について
タントラ式セックスの練習を始める方法

こんなセックスにトライしてみる方法を順番に見ていきましょう。
雰囲気を作る
パートナーとタントラ式セックスについて話してから、実際にやってみる時間をつくりましょう。
ここでは、準備すること自体が興奮を高めます。
儀式のように静粛にシャワーを浴び、居心地の良いまたはセクシーなものを着用しましょう。
そしてスマートフォンの音をミュートにし、キャンドルや芳香剤、柔らかい枕や毛布、音楽、またはチョコレートのような誘惑をそそるおやつを用意してください。
雰囲気を作るために役立つものを準備してのぞみましょう。
アイコンタクトを保つ
長時間のアイコンタクトは、2人をおどろくほど親密な仲にさせてくれる効果があります。
「アイコンタクトをして、いまここに集中してください」とペップ氏もアドバイスしています。
まずはアイコンタクトを続けてみることから始めましょう。
5分のタイマーをセットし、お互いに向かい合って座るか抱きしめるかして、タイマーが終了するまでお互いの目を見つめます。
衣服を着ていても裸でも構いません 。
大切なのは、お互いの存在を認識しそこで生まれる感情を認めることです。
呼吸と身体をリラックスさせる
パートナーと一緒に座っている時に、深呼吸をして緊張を解放してください。
神経系を落ち着かせ、通常のセックス中にはあまりできない方法で相手とつながることがゴールです。
座った体位を試す
座位とも呼ばれる座った体位は、お互いを抱きしめるか性器を刺激するかに関係なく、最初に試すのに最適な体位です。
この伝統的なタントラの体位は、私たちの内側にある神聖な男性性と女性性を象徴する、シヴァとシャクティの結合を表します。
ただし、この座った体位では、パートナーの性別は関係ありません。
一方が足を組んで座り、もう一方は、相手の膝の上に座ってから腰に抱きついて向かい合います。
この体位では、呼吸をしたり、見つめたり、挿入したりと何でも行うことができます。
重要なのは、自分を解放して気持ちが良いと感じることです。
陰部の感触に注目するのではなく、ゆっくり動いてお互いの身体を感じることで、どんな体位でもタントラ式セックスとなります。
陰部の刺激を遅くすると、どのような感情が開放されるか試してみましょう。
それは、おいしい食事を味わうのと同じです。ぜひ、すべての感覚を楽しみましょう。
アイコンタクトは重要ですが、自分の身体の感触をより感じるために、目を閉じても良いでしょう。
相手に自分がどう感じているか言葉で伝えることは、タントラ式セックスでも効果があります。
自分が感じていることをパートナーに伝えることで、お互いがいまこの時を感じることができます。
▶セックスセラピーとは|カウンセリングの内容や受けられる場所は?
ひとりでも試せるタントラ
一人でも、タントラ式セックスを試す方法はたくさんあります。
そして最終的なゴールはオーガズムを感じることではありません。
1人でやってみてもいいですし、一部だけ試してみるでもいいのです。
瞑想
瞑想は自分を後ろ向きにしているものから解放される素晴らしい方法です。
ただし、あなたのエネルギーが出ていくのを放っておくのではなく、地に足をつけることを意識しましょう。
自分のエネルギーを地球に向けて流すイメージで瞑想をしてみましょう。
そして、そのエネルギーを身体中に広げて、自分自身に力を与えてください。
▶【簡単】メディテーション(瞑想)のやり方・意味|マインドフルネスとの違いは?
セルフマッサージ
セルフマッサージを全身に行うことで、より豊かな経験を得ることができます。
好きなオイルやローションを全身に塗りましょう。
オイルやローションを塗りながら腹部、股間、内もも、腕、首、胸をマッサージしてみましょう。
セルフプレジャー
1人でタントラを試すことは、必ずしもオーガズムを感じるということではありません。
そうではなく、自分の身体を探索し、自分にとって何が快感なのか理解する時間にしてください。
新しい方法で自分を触ってみたり、ゆっくりとなでてみたり、自分で遊ぶ方法を見つけてみましょう。
▶セルフプレジャーとは?美容効果を紹介!どんな人におすすめ?
■What Is Tantric Sex? – The Good Trade
■Tantric Sex: 26 Tips on How to Practice, Positions to Try, and Mo
完璧主義な女性の特徴を紹介|うつの原因になるって本当?

完璧主義の定義はさまざまなものがありますが、一般的には「自分自身や周囲に対して高すぎる水準・目標を求めること」といえます。
完璧主義の人は周囲からの評価を気にしすぎたり、過度に失敗を恐れたりする傾向も見られます。
完璧主義に陥ってしまうのはなぜなのか、完璧主義な女性に見られる特徴や、うつ病をはじめとした精神疾患につながる理由についても解説します。
完璧主義になってしまう原因

完璧主義に陥ってしまうのは、個人の性格や価値観によるものと片付けられがちです。
しかし、それ以外にもさまざまな原因が考えられます。
家庭環境の問題
子どもの頃に育った家庭環境や親の教育方針、子育て方法が完璧主義の原因となることがあります。
たとえば厳格すぎる親のもとで教育を受けた子どもは、失敗することを過度に恐れるようになります。
また、努力して一定の成果を出したとしても子どもを褒めることが少ないと、わずかな妥協も許せない完璧主義になることもあるようです。
失敗が許されない社会的風潮
個人に対して高い水準を求める社会的風潮も完璧主義に陥る原因となることがあります。
行き過ぎた競争社会や成果主義の中では、わずかな失敗やミスが評価に大きく関わってくるため、つねに完璧でなければならないと感じる人が増えてしまうのです。
過去の失敗体験
過去に大きな失敗やミスをした経験が原因となって、完璧主義の考え方に陥ることもあります。
特に、大勢の前で失敗やミスをしたり、それを指摘されたりした場合、本人はそれが恥ずかしいと感じ、同じ失敗を繰り返さないために完璧を追求しがちです。
>>【ストレス解消】セルフケアとはなにか?意味・種類・方法について解説
完璧主義な女性の特徴

女性のなかには、自分自身の完璧主義な性格に悩んでいる人も少なくありません。
一方で、自分のことを完璧主義であると自覚できていないケースもあります。
自分自身の性格を客観的に判断するためにも、完璧主義の女性にどういった特徴が見られるのか紹介しましょう。
プライドが高い
完璧主義という性格をポジティブにとらえると、「負けず嫌い」と言い換えることもできます。
しかし、ときには周囲から「プライドが高い人」であると認識されることもあります。
自分とは違う意見や考え方をもつ人に対し敵意を向けたり、自分自身の失敗を決して認めようとしなかったりといった性格が特徴的です。
また、プライドが高いあまりに他人に対してお願いをすることができず、一人で仕事を抱え込んでしまうこともあります。
他人と自分を比較しがち
自分自身の成果や特性を他人と比較しがちなことも完璧主義の女性に見られる傾向です。
他人は他人であると割り切って考えることが難しく、周囲と自分を比較しては劣っていると感じることがしょっちゅうあります。
その結果、本来もっている自分の価値を見失う原因となることも少なくありません。
ストレスを溜め込みやすい
完璧主義な人ほど周囲からの目が気になったり、自分の悪いところばかりが目につくようになりストレスを溜め込みがちです。
また反対に、自分が簡単にできる仕事を他人ができていないと、それに対して苛立ってしまうこともあります。
>>【変わりたいあなたへ】自分を変えることは難しい?変われる方法や習慣
完璧主義な女性の長所・メリット

完璧主義はあまり良くないイメージをもたれがちですが、仕事をするうえでは長所として活かせるポイントもあります。
目標達成へのこだわりや意識が強い
完璧主義な人ほど、自分自身が設定した目標または会社から提示された目標に対し、「なんとしてでも達成しなければならない」という強いこだわりと意識をもっています。
目標を達成できるかどうかはその人のスキルや経験も影響しますが、それ以上に「絶対に達成する」という意識が重要です。
その日の実績や予算までの進捗状況を考え、目標達成に向けた具体的なアクションや取り組みを講じられるようになります。
責任感が強い
完璧主義な人は責任感も強く、自分に与えられた仕事やミッションを最後までやり遂げようとします。
困難な状況にあったとしても途中で投げ出すようなことはせず、最後まで自分のベストを尽くし粘り強く取り組むことができるのはメリットといえるでしょう。
細部にも目を配ることができる
完璧主義な人は、自分自身だけでなく周囲の人がとっている行動にも高い水準を求める傾向があります。
細かい部分にまで目を配ることができ、わずかな作業の不備やミスも見逃さず対処できます。
完璧主義な女性の短所・デメリット
上記とは対照的に、完璧主義の女性には短所といえるポイントもあります。
ストレスを感じやすい
仕事やプロジェクトが順調に進んでいるときには問題ありませんが、トラブルやミスなどが発生し業務の達成が困難になったときに、人一倍大きなストレスを感じてしまいます。
それだけでなく、ミスや失敗の原因が自分にあると考え、過度に責め立ててしまうことも少なくありません。
その結果、精神的に疲弊し、さまざまな疾患に陥るケースもあるのです。
スピーディーな意思決定が苦手
完璧主義な人はスピーディーな意思決定が難しいという短所もあります。
大きな決断が求められるとき、完璧主義な人は「決断が間違ったらどうしよう」、「リスクや危険性について見落としている部分はないか」などと不安に感じてしまい、決断を先送りにしがちです。
その結果、プロジェクト全体の進捗に影響したり、新たなビジネスチャンスを逃したりすることもあるのです。
>>【自己受容】弱くてダメな自分を認めて受け入れるトレーニング方法
完璧主義はうつの原因になる?

完璧主義は精神的にもさまざまな影響を与えることがあり、それがうつ病の原因になる可能性もあります。
完璧主義な人は自分に対して高い水準を求め、ときには達成が難しい目標を立てることもあります。
同時に、ミスや失敗を恐れるあまり、目標を達成できなかったときには自分を責める傾向があります。
自己批判や過度のストレスによって、自尊心や自己肯定感の低下、無力感などを感じてしまい、うつ病の発症につながる可能性があるのです。
また、このような病気を発症しなかったとしても、日々の生活そのものに疲れてしまい、「辛い」「しんどい」と感じることもあります。
ただし、完璧主義の人の全てがうつ病を発症するというわけではなく、遺伝的な要因や環境的な要因、個人の性格なども影響するとされています。
>>情緒不安定な女性に多い症状とは|対処法についても紹介
完璧主義をやめたいときの治し方
完璧主義を克服しようと考えたとき、どのような治し方が効果的なのでしょうか。
自分自身を受け入れる
まずは自分自身の長所と短所を把握し、それを受け入れることから始めましょう。
人は誰でも長所と短所があり、完璧な人は存在しません。
すべてのことを完璧にこなそうとしても現実的ではないことを知り、失敗やミスをすることは当たり前であると認識することが大切です。
自分に対して過度に厳しくするのをやめて、ありのままを受け入れる姿勢に変えることが完璧主義からの脱却につながっていきます。
>>自分を認める方法|認める難しさや自己肯定感との関係性を解説
仕事やタスクの優先順位を決める
すべての仕事やタスクを完璧にこなそうとするのではなく、優先順位を決めて取りかかるようにしましょう。
優先度や重要度の高い仕事から取り組むことで、特に重要な部分でのミスや失敗を抑え、メリハリのついた仕事ができるようになります。
>>【誰でもできる】マインドセットの意味・使い方をわかりやすくご紹介!
専門医による治療を受ける
過度な完璧主義によって自分自身に大きなストレスがかかっていたり、周囲の人に悪影響を与えている場合には、専門医による治療を受けることも検討しましょう。
完璧主義を克服する方法としてはカウンセリングや心理療法、認知行動療法などがあります。
特に認知行動療法は、自分自身の言動を客観的に振り返ることにより、どのような言動が問題となっているのかを分析し修正することができます。
まとめ
完璧主義は個人の性格的な問題だけでなく、家庭環境や過去の経験などさまざまな要因が複雑に絡み合っているケースが少なくありません。
ときには完璧主義がポジティブに作用することもありますが、ネガティブにとらえられるケースも多いのが実情です。
完璧主義を克服したい、やめたいと感じる方も多いと思いますが、焦れば焦るほど空回りして逆効果となってしまうこともあります。
そのため、自分自身で対処が難しいと感じた場合には、専門医による治療を受けることも検討してみてください。
知らず知らずに起こっている?ハラスメントの種類や防止方法を紹介

ハラスメントとは、相手に対して嫌がらせをする行為を指します。
一口に嫌がらせといってもその行為はさまざまであることから、ハラスメントにはいくつかの種類があります。
また、自分自身ではハラスメント行為と認識していなくても、相手にとってみれば不快に感じる言動も少なくありません。
そこで今回は、ハラスメントにはどのような種類があるのかを紹介するとともに、ハラスメント防止に役立つ対策の一例も紹介します。
ハラスメントの種類:会社や職場

会社や職場で発生しがちな代表的なハラスメントには、以下のようなものがあります。
なお、以下で挙げるハラスメントは、いずれも職場内だけでなく宴席や移動中の車内などにおいても認められます。
セクシャルハラスメント
異性または同性に対して性的な嫌がらせをする行為をセクシャルハラスメントとよびます。
身体の一部を触る行為や、下ネタを大声で発する、職場に性的なポスターを掲示することなどがセクシャルハラスメントの行為に該当します。
上司や部下などの関係性によっては断りきれないケースもあるため、相手が明確に嫌がっていなかったとしてもセクシャルハラスメントにあたるおそれがあります。
パワーハラスメント
身体的・精神的な苦痛を与える行為全般をパワーハラスメントとよびます。
暴力や暴言はもちろんのこと、相手を侮辱する言動や威嚇する行為、無視する行為などもパワーハラスメントにあたります。
また、パワーハラスメントは上司から部下などに対して行われるものというイメージがありますが、実際には同僚同士や部下から上司に対してもパワーハラスメントが認められる場合があります。
カスタマーハラスメント
顧客から従業員に対して理不尽な要求や悪質なクレームなどを行うことをカスタマーハラスメントとよびます。
たとえば、顧客が店員を恫喝・脅迫したり、正当な理由がないにもかかわらず損害賠償請求を行ったりすることがカスタマーハラスメントに該当します。
アルコールハラスメント
お酒の飲めない人や拒否している人に対して飲酒を強要したり、嫌がらせをする行為をアルコールハラスメントとよびます。
たとえば、一気飲みを強要したり、拒否しているにもかかわらずグラスにお酒を注いだりする行為もアルコールハラスメントにあたります。
ハラスメントの種類:女性

女性に対して行われることの多いハラスメントには以下のようなものがあります。
マタニティハラスメント
妊娠や出産をした女性に対する嫌がらせ行為をマタニティハラスメントとよびます。
たとえば、検診を受診するために休んだ人に対して悪口を言ったり、無理に仕事を押し付けたりする行為などがマタニティハラスメントに該当します。
マタニティハラスメントは会社や職場内だけでなく、町内会やPTAといったコミュニティ内で発生するケースも少なくありません。
ジェンダーハラスメント
「女性(男性)なのだから○○すべき」といったような、女性らしさ・男性らしさを強要する行為をジェンダーハラスメントとよびます。
たとえば、女性に対して「結婚・出産は○歳までにすべき」や「女性はつねにきれいであるべき」といった言動や、女性にのみお茶汲みをさせる行為もジェンダーハラスメントに該当します。
ジェンダーハラスメントはマタニティハラスメントと同様、会社や職場だけでなく、さまざまなコミュニティ内や仲間内でも発生することがあります。
ゼクシャルハラスメント
結婚に踏み切らない女性に対して嫌がらせをしたり、プレッシャーを与えたりする行為をゼクシャルハラスメントとよびます。
たとえば、「いつまで独身でいるつもり?」、「いつになったら結婚するの?」といった言葉を投げかけたり、結婚情報誌をわざと目につくところに置いたりする行為もゼクシャルハラスメントにあたります。
なお、女性だけでなく男性に対する上記のような行為もゼクシャルハラスメントに該当します。
ハラスメントの種類:夫婦
夫婦間で起こるハラスメントには以下のようなものがあります。
モラルハラスメント
相手が嫌がる言動をとり、不快感を与える行為をモラルハラスメントとよびます。
夫婦間においては、たとえば相手に対して家事ができていない、収入が少ないことを執拗に叱責したり、出された食事に手をつけない、生活に必要な金銭を渡さない、相手のことを無視することなどがモラルハラスメントに該当します。
また、上記のような明確な理由や意図がなくても、相手の人格を否定するような言葉を投げかける行為も立派なモラルハラスメントにあたります。
>>夫婦関係は修復できる?よくある破綻のきっかけや修復方法を紹介
ハラスメントの種類:家庭

モラルハラスメントは夫婦間だけでなく、子どもや親も含めた家庭内で起こる場合もあります。
モラルハラスメント
子どもに対するモラルハラスメントの具体例としては、勉強ができないことを執拗に叱責する行為や、食事を与えない、子どものことを無視する、「バカ」、「生まなければよかった」といった暴言を吐くことが該当します。
また、親に対するモラルハラスメントも同様に、暴力的な言動や行為、人格を否定するような言葉を投げかける行為のほか、介護が必要であるにもかかわらず世話をしなかったり、施設への入所を拒否したりする行為もモラルハラスメントにあたります。
>>自己肯定感が低い子供の特徴や言動とは|注意すべき親の発言や行動
ハラスメントの種類:学校
学校におけるハラスメントにはどのようなものがあるのでしょうか。
アカデミックハラスメント
おもに大学教授が権力を濫用し、学生に対してさまざまな嫌がらせをすることをアカデミックハラスメントとよびます。
たとえば、教授の個人的な好みによって特定の生徒・学生の評価を決めたり、優遇または冷遇したりする行為や、学生に対して性的関係を迫ったりする行為もアカデミックハラスメントに該当します。
レイシャルハラスメント
特定の人種や国籍、出身地などに該当する人に対し、嫌がらせをする行為をレイシャルハラスメントとよびます。
たとえば、外国籍の人だけを仲間外れにする行為や理不尽な要求・命令をする行為、特定の出身地の人を無視する行為、そのような人に対し暴言を浴びせる行為などがレイシャルハラスメントに該当します。
レイシャルハラスメントは教授や先生から行われるケースもあれば、仲間やクラスメイト同士で行われる場合もあります。
ハラスメントの防止方法

自分自身が意図せず、知らない間にハラスメントに該当する行為を行っていることもあります。
ハラスメントに対する世間の見方が厳しくなっているなかで、ハラスメント行為を防止するためにはどういった対策が求められるのでしょうか。
ハラスメント対策の研修や講義を行う
職場や学校でできる方法としては、ハラスメント対策の研修や講義を行うことが挙げられます。
自社にノウハウや知見がなくても、ハラスメント対策を専門に扱う外部の企業や団体があります。
全ての従業員や学生に対しハラスメント防止の意識を高めてもらうためにも、研修や講義の実施は有効です。
ハラスメント行為に対する判例を学ぶ
ハラスメントは絶対にやってはいけない行為であると説明しても、必ずしも抑止力になるとは限りません。
そこで、ハラスメント対策の研修や講義と合わせて、具体的な判例について学んでもらうこともおすすめです。
たとえば、セクシャルハラスメントやパワーハラスメントの加害者がその後どのような処分を受けたのか、自社だけでなく他社の事例も含めて学ぶことで、従業員や学生は自分ごととして捉えられるようになります。
社内や学校内に相談窓口を設置する
ハラスメントの実態は複雑なことが多く、客観的に実情を把握することが難しいケースも少なくありません。
そこで、実際にハラスメントを受けている人が個別に相談しやすいよう、専用の相談窓口を設置することも有効な対策です。
相談した事実や相談者の情報は厳密に守ることはもちろんですが、相談したことで不利益が及ばないように配慮することも重要です。
相手を配慮した言動を心がける
上記で紹介した対策は職場や学校などでは可能ですが、コミュニティ内や家庭内では難しい場合も多いでしょう。
私生活において重要なのは、つねに相手のことを配慮した言動を心がけることです。
自分が同じような言動をされたときにどう感じるか、相手の立場に立って考えてから言葉を発したり行動に移したりすることで、ハラスメントは防止できるでしょう。
>>【怒りを抑える】アンガーマネジメントのやり方・テクニックをご紹介!
まとめ
一口にハラスメントといってもさまざまな種類があります。
かつては一般的であった行動や言葉も、時代の変化とともにハラスメントと認識されるようになりました。
だからこそ、自分自身の普段の言動がハラスメントに該当していないかを振り返ることが大切です。
女性の情緒不安定の治し方は?生理との関係や落ち着く方法を解説

ご自分の性格を、「いつもイライラしたり、急に泣きたくなったり、気持ちが不安定になりやすいかも」と悩んでいる女性の方は、意外に多いのではないでしょうか。
感情の起伏が激しい状態を「情緒不安定」と呼び、女性がお悩みになるケースが多いです。
情緒不安定な人に多く見られる特徴や正しい対処法について解説します。
なぜ女性は情緒不安定になりやすいのか

情緒の安定は主に、身体的要因、心理社会的要因が関係しています。
まずはこれら2つの要因について解説していきます。
身体的要因
身体的な要因で一番に挙げられるのは、ホルモンバランスです。
特に女性は月経周期によってエストロゲンやプロゲステロンなどのホルモン分泌量が短期間で変化しています。
これらのホルモンは、私たちの精神面にも影響を与えるため、その乱高下によって情緒が不安定になることがあります。
心理社会的要因
仕事やプライベートでの人間関係、結婚や出産による環境の変化。
女性は家庭や仕事、人間関係などさまざまな場面でストレスを抱えやすい傾向があります。
特に、家庭と仕事の両立や、男女の役割分担の不均衡などがストレスを引き起こし、情緒が不安定になることが少なくありません。
また現在の日本の社会全体の特徴として、自分がどう思うか、の自分軸より、まわりと自分を比較する他者評価に比重が置かれている傾向があります。
そのため、まわりと自分を比較して落ち込んでしまうことも、気持ちが不安定になる要因となっているかもしれません。
関連記事:完璧主義はうつの原因にもなる?完璧主義な女性の特徴を紹介
女性が情緒不安定になる原因や時期

女性が情緒不安定に陥る原因のひとつに、ホルモンバランスの変化があります。
これは一定の周期や時期になると現れやすくなります。
生理前・生理中
生理前および生理中にはPMS(月経前症候群)とよばれる症状が現れます。
個人差はあるものの不安やイライラ、気分の落ち込みなどによって情緒が不安定になりやすいことがわかっています。
なお、生理後はホルモンバランスが安定し、生理前や最中に比べると比較的情緒が安定します。
排卵日
排卵日とは、卵巣から卵子が放出される時期のことを指します。
排卵日の頃は女性ホルモンの一種であるエストロゲンの分泌量がピークに達するため、生理中と並んで情緒不安定になりやすい時期とされています。
妊娠初期
妊娠初期もまた、ホルモンバランスが大きく変化するタイミングです。
生理中や排卵日と異なり、妊娠にともなう吐き気や体調不良、出産への不安なども影響していることがあり、気分がさらに不安定になることがある点に留意しましょう。
更年期
更年期になると卵巣機能が衰え女性ホルモンが低下することで、全体のホルモンバランスも乱れがちです。
それにともない、イライラや情緒不安定、不安感、抑うつ症状などが現れることも少なくありません。
さらに、年齢を重ねていくことで身体的な衰えや美的感覚に対する不安や怖れも加わり、ストレスが増大することもあります。
関連記事:ネガティブ思考をやめたい方へ|止まらない原因やレベル診断、改善方法をご紹介
情緒不安定な女性に多い特徴

もちろん全員に当てはまるわけではありませんが、情緒不安定な女性に共通している特徴がいくつかあります。
自分ではなかなか気づきにくいこと多いものです。あらためてチェックしてみましょう。
感情の起伏が激しい
普通なら悩んだりイライラしないような些細なことにも、不安やいら立ちを覚えてしまう。
そんな感じが数週間続くときは、少し心が疲れている証拠です。
明確なストレスや不安の原因が明確でなくとも、情緒不安定になることがあります。
そのような自分が嫌になり、さらに悪化するケースも少なくありません。
物事をネガティブに考えがち
何でもかんでも後ろ向きに捉えがちな人は、常に心配事を複数抱えているのと同じようなメンタルの状態であり、情緒不安定に陥りやすいです。
また、他人から褒められたとしても素直に受け入れられず、「何か裏があるのではないか?」などと考えてしまうため、たとえ何らかの成果を上げたとしても、いつまでも自己肯定感を高められません。
繊細な性格
他者からの何でもないような一言で傷ついてしまうことの多い繊細な性格の人も、情緒不安定の素養を持っているといえるでしょう。
また、このタイプの人は感受性や共感力が強いことも多く、自分とは直接関係のないこと、たとえばニュースで目にした凶悪事件などについても心を痛めて情緒が不安定になってしまうことがあります。
一人でいるのが苦手
「一人でいるのが苦手だ」という人は、全員ではありませんが、依存傾向が強いケースが多いです。
誰かと一緒にいるときは情緒が安定していても一人になると急に不安感が襲ってくることがあります。
睡眠障害に悩まされている
情緒不安定な時は、不安やストレスによって睡眠に悪影響を及ぼすことがあります。
睡眠の質や時間は肉体的な健康に関係しているのはもちろん、メンタル面にも大きな影響を与えているというのは有名な話でしょう。
夜中に目が覚めてしまったり、寝付きが悪くなることが典型的な症状として挙げられます。
関連記事:感情の起伏が激しい人や少ない人の特徴|上手にコントロールする方法とは
情緒不安定になると泣くのはなぜ?

情緒不安定になると、意味なく泣いてしまうことがあります。
強いストレスや不安を感じているとき、脳の扁桃体とよばれる領域が活性化しやすくなることが知られています。
扁桃体は脳のなかでも感情的な情報を処理するための領域です。
ストレスや不安感などの緊急性の高い情報が集中的に処理されることで、悲しみの感情が引き出され、本人は泣きたくないにもかかわらず、自然と涙が出てくるようになるのです。
また、緊張感が高まることで自律神経のバランスが崩れ、交感神経が優位に働き、涙腺が刺激されます。
その結果、本人の意図とは関係なく涙が出てくることもあります。
関連記事:情緒不安定になると泣くのはなぜ?|情緒不安定になりやすい人や原因とは
情緒不安定になったときの治し方・落ち着く方法は?

気持ちが不安定になったとき、どのように対処すればよいのでしょうか。
深呼吸をする
すぐにその場でできるおすすめの方法が深呼吸です。
情緒不安定になる要因には、ストレスや不安感の増大といった精神的な面が多くあります。
ゆっくりと深呼吸をすることで副交感神経が優位になり、次第にリラックスし、ストレスや緊張を和らげることができるのです。
適度な運動をする
時間に余裕があれば、ウォーキングや軽いランニング、筋力トレーニングなど、体を動かすことをおすすめします。
これまで国内外の多くの研究から、適度な運動はストレスの原因となるホルモンを減らし、前向きな気分にする効果があることが示されています。
十分な休息
身体的な疲労だけでなく精神的な疲労を緩和するために、十分な休息をとることも必要です。
まずは十分な睡眠時間を確保します。
リラックスできる音楽を聞く、温かい飲み物を飲む、少し低めの温度にしたお風呂に浸かるなどして休息の時間を確保しましょう。
自分の感情を書き出したり声に出してみたりする
自分自身がどのような状況にあるのか、どんな気持ちで困っているのか、何に苦しんでいるのかについて、紙にペンで書き出したり、実際に声に出してみるのもおすすめです、
書き出すパターンでは自分の気持ちを視覚化することができ、声に出すパターンでは音の情報として耳に入るため、客観視がしやすくなります。
自分が考えていることを客観視することで、解決方法が見つかったり、意外と小さなことで悩んでいたことに気付くこともあるでしょう。
専門家へ相談する
自分でさまざまな工夫をしてみても改善されない場合には、専門家へ相談することを検討しましょう。
心理カウンセラーやセラピストに相談することで、話を聞いて共感してもらえる安心感が得られ、感情や状況が整理されるでしょう。
その結果、有効な対処法を見つけられる可能性があります。
関連記事:【自己受容】弱くてダメな自分を認めて受け入れるトレーニング方法
情緒不安定な女性との接し方
相手が情緒不安定なときは、急に怒り出したかと思うといきなり悲しんだりと、相手の感情に振り回され、戸惑ってしまうことがあります。
ついつい相手の感情や口調に同調し、こちらも売り言葉に買い言葉、となってしまいがち。
そうなるとお互いヒートアップし、冷静なコミュニケーションがとれなくなってしまいます。
そのため、こちらは努めて冷静に対処しましょう。その際は丁寧なコミュニケーションを心がけることが大切です。
柔らかな口調で話し、相手の話をよく聞くことで相手に安心感を与えることができます。
また、相手の気持ちや立場に共感し、理解を示すことも重要です。
落ち着いて丁寧なコミュニケーションをしようと思っても、相手の感情がおさまらず興奮状態が続くこともあります。
そのような場合には、相手が落ち着くための時間を与え、一定の距離を取りましょう。
まとめ
女性はさまざまな要因により情緒不安定になりやすく、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
自分の気持ちが不安定だなと感じたら、立ち止まってゆっくり深呼吸をしたり、適度な運動をしたり、心地よい休息を心がけるなど、まずはご自分を大切にしてあげてください。
どうしても症状が改善しないときや、悪化しているなと感じられる場合には、メンタルヘルスの専門家へ相談することもご検討ください。
夫婦関係を修復するためのきっかけ|絶対にやってはいけないこととは?

「最近、夫婦の会話が少なく関係が冷え切っている」、「相手に対して強い嫌悪感や不満を抱くようになった」など、夫婦関係に悩んでいる方は決して少なくないでしょう。
このような状況に置かれたら、関係の修復は難しいのではないかと感じてしまうかもしれません。
一方で、夫婦関係の修復に成功し良好な関係に戻すことができたという夫婦もいらっしゃいます。
本記事では、夫婦関係に疲れ破綻してしまう理由やきっかけ、関係が壊れやすい夫婦の特徴を紹介するとともに、すぐに実践できる関係修復の方法についても解説します。
夫婦関係に疲れてしまう理由

結婚生活を送るなかで、夫婦関係に疲れてしまうのはどういった理由があるのでしょうか。
人によっても原因はさまざまですが、特に多く見られる3つの原因を紹介します。
家事や育児に協力的ではない
共働き世帯が増えているなかで、夫婦で家事や育児を分担することは一般的になりつつあります。
かつてのように夫は働きに出て、妻は専業主婦という世帯はごく一部となっているなかで、「家事や育児は妻の仕事」という固定観念を夫がもっていると、家事育児の負担が妻にばかり集中してしまい、不満が溜まっていきます。
感謝の気持ちを表さない
夫婦でなくとも対人関係において感謝の気持ちを常に忘れず、それを表現するのは大切なことですが、身近な家族やパートナーが相手となると、ついおろそかになりがちです。
「言わなくてもわかってくれるだろう」という甘えやいつもそばにいて慣れてしまっていることから、感謝の気持ちを表さなくなっているカップルはくれぐれも注意しましょう。
日々の生活に刺激がない
付き合い始めの頃は一緒にいる時間が刺激的でワクワクした間柄でも、数年、数十年と時間が経つにつれて、そばにいるのが当たり前となり、悪い意味で空気のような存在になることも。
また、日々の仕事や家事、育児に時間が取られすぎてしまうと、次第に夫婦の時間を持つ機会が減り、刺激を感じられなくなることも少なくありません。
>>セックスレスになりやすい夫婦の特徴とは|原因や解消法を解説
夫婦関係が破綻してしまうきっかけとは
夫婦関係が破綻してしまうきっかけはさまざまで、ケースによると言わざるを得ないでしょう。
たとえば、どちらか、もしくは両方の不貞行為やDVなど、深刻な問題によって破綻する場合もあれば、第三者には些細なことと思われがちなものでも、当事者にとって大きな意味を持ち、それが破綻のきっかけになることがあります。
特に後者の場合、まわりは「そんなことで別れる必要はないのではないか」というかもしれません。しかし当事者にとっては許容できない場合も多々あります。
また、長い共同生活や子育てのなかでは、小さな不満が少しずつ積み重なっていくもの。
それらが自分でも知らず知らずのうちに心の中に溜まっていき、ほんの些細な出来事や投げかけられた言葉が破綻のきっかけになることもあるでしょう。
関係が壊れやすい夫婦の特徴
夫婦関係が壊れ、別居や離婚に至ってしまう………。
そんなケースとなるカップルにはどのような特徴が見られるのでしょうか。
コミュニケーション
夫婦間でのコミュニケーションが十分でなかったり、意思疎通がうまくはかれない対話の仕方だと、お互いが考えていることや気持ちをうまく共有することができません。
それにより、誤解やストレスが蓄積すると破綻の要因となる場合があります。
価値観が異なる
結婚生活を送るなかでお互いの価値観や性格の違いが明らかになり、それによって夫婦関係が長続きしないことがあります。
夫婦とはいえ、それぞれが個性をもった人間。意見や考え方、性格が全く同じという人は存在せず、長い夫婦生活を送るなかでは当然軋轢が生じることもあるでしょう。
本来であればお互いを尊重し合い、理解しようとすることで関係性を維持していきますが、あまりにも価値観が異なると修復不可能な関係となっていくケースもあります。
期待のズレ
夫婦間では、たとえば妻が夫に対して「家事を手伝ってほしい」と考えていたり、反対に夫は妻に対して「パートに出て家計を助けてほしい」と考えたりすることもあります。
しかし夫婦間でパートナーに対する期待値が異なっていると、お互いの期待を理解できずに不満がたまることがあります。
これを精神療法の用語では「役割期待のずれ」といいます。
たとえば先ほどの家事の例で言うと、夫は「ゴミ出しや子どもと遊ぶ時間を作っているから問題ないだろう」と考えていても、妻は「夫が家事を一切手伝ってくれない」と感じているような場合です。
>>自己肯定感が低い子供の特徴や言動とは|注意すべき親の発言や行動
夫婦関係の修復は不可能?

一旦関係性がこじれると、もとの関係に修復するまでには時間を要したり、修復が難しくなる場合もあります。
夫婦関係の修復が不可能なケースとしては、夫と妻それぞれに嫌悪感があり、お互いが関係修復を望んでいない場合や、どちらかの性格が頑固で関係修復に対して同意できない場合などが挙げられます。
また、夫婦間で暴力やDVといった問題が生じているケース、たびたび不貞行為を繰り返す、といった場合も、夫婦関係の修復が難しい要因になるでしょう。
一方、夫婦のどちらかが関係修復を強く望んでいたり、お互いの悪い部分も受け入れようとする前向きな姿勢が見えたりすると、再びもとの夫婦関係へ修復できる可能性があります。
夫婦関係を修復する方法
関係を修復したいという意思があっても、相手を説得したり信頼を取り戻すことは簡単ではありません。
具体的にどのような方法が有効なのか、その一例をご紹介しましょう。
話し合いの場を設ける
まずは夫婦がじっくりと話し合える場を設けることが大切です。
夫婦関係が壊れている場合、日頃のコミュニケーション量も質も少なく、お互い不満を抱えているケースも少なくありません。
なぜ自分が不満に感じているのか、相手は何を考えているのか、お互いが説明することが関係修復の第一歩となります。
話し合いの場ではできるだけ感情的にならず、落ち着いて話すことがきわめて重要です。
まわりに人がいる環境を選んだり、話し合いのはじめに「お互いが落ち着いて話す」ことを約束してから始めるのもおすすめです。
自分の気持ちを手紙に書く
自分自身では話し合いたいと思っていても、相手がそれを望まないケースもあるでしょう。
また、その場ではなかなかうまく言葉が出てこなかったり、ついつい感情的になってしまいがち。
そのようなときには、自分の気持ちをメッセージに書き、相手に読んでもらう方法もおすすめです。
自分が反省すべきところがあれば素直に謝り、関係修復を望んでいるということを書きましょう。
はじめのうちは読んでもらえなかったり、相手からの反応がなかったりすることもあるでしょう。
しかし、2回、3回と手紙を渡すうちに相手の心境も変化し話し合いに向けた土壌が整ってくることも考えられます。
また自分の気持ちを書き出すことで、自分の考えや気持ちの整理にもつながります。
相手に対して完璧を求めすぎない
夫婦関係が壊れる要因のひとつに、期待のズレがあると紹介しました。
その多くは、相手に対する期待が高すぎることで裏切られたと感じ、悪い印象を抱いてしまうことが原因となります。
ここで大切になってくる考え方が、相手に完璧を求めすぎないことです。
心理学では完全主義、という言葉を用いますが、この完全主義は、気分障害などの精神疾患につながる要因であることが分かっています。
対人関係でも仕事や生活においても、完全を求めてしまうと、自分も相手も窮屈になるからです。
パートナーに対しても、「これくらいできて当たり前」とか「やってもらって当然」と思いすぎている可能性はありませんか?
相手が自分の期待値ほどのことをしてくれなかったとしても、まずは取り組んでくれたことに対して感謝してみましょう。
感謝や労いの言葉を伝える
お互いに感謝の気持ちを言葉で伝えるようにしましょう。
たとえば、残業続きで帰宅が遅くなった相手に対しては、「遅くまで仕事おつかれさま」といった労いの言葉をかけたり、家事を担当してくれた相手に対しては「ご飯を作ってくれてありがとう」といった感謝の言葉を積極的に伝えましょう。
関係が長くなってくると「わざわざ言わなくても分かっているだろう」と考えがち。しかし実際はそうではありません。
たとえ分かっていても、言われるとうれしいものです。
また、コミュニケーションが減ると相手の考えていることが分からなくなり、不安に陥るケースもあります。
感謝や労いの気持ちはいくら伝えても伝えすぎることはないと考え、心を込めて言葉にしてみてください。
>>愛してるよりも愛が伝わる愛情表現の言葉とは?伝え方も紹介
夫婦関係を修復したいときにやってはいけないこと

関係を修復したい気持ちが強いあまりに、とった行動が逆効果になってしまうこともあります。
夫婦関係の修復にあたってあまり望ましくない行動を紹介しましょう。
自分の意見や考え方を相手に押し付けること
自分自身では夫婦関係の修復を望んでいたとしても、相手はまだその段階ではないケースもあります。
そのような状況のなかで、自分の気持ちや考えだけを相手に強く押し付けてしまうと、逆に反感を招くこともあります。
話し合いの場では相手の意見や考えを十分汲み取ったうえで、ときには聞き役に徹することも大切です。
本当の意味での傾聴はとても難しいですが、話を聴いてもらえて嬉しくない相手はいません。
いつもより長く相手の話に耳を傾け、共感しようと心がけることで、次第に相手は心を開き、いつしかこちらの考えや気持ちにも耳を傾けてくれるようになるでしょう。
自分自身を責めすぎること
夫婦関係が壊れてしまった経緯によっては、自分にその原因があると考え責めすぎてしまうこともあります。
仮に自分に原因があった場合、反省をすることは重要です。
しかし、必要以上に自分を責めすぎてしまうと、相手は「この人のことを幸せにはできないかもしれない」と感じ、悪い結果に結びつくこともあります。
自分自身と向き合いしっかり反省したら、もうおしまい。
過去のことを振り返り続けるのではなく、今どうするのがベストか、そして今後どうしていくのがいいか、に考えをシフトし、できるだけ前向きな意見を出し合うことが関係修復には非常に大切になります。
>>【怒りを抑える】アンガーマネジメントのやり方・テクニックをご紹介!
まとめ
夫婦関係が一度壊れてしまうと、お互いに意地を張り合って謝ることができなかったり、関係修復のきっかけがつかめなくなったりすることもあります。
夫婦関係が破綻する理由はさまざまで、必ずしもすべてのケースにおいて修復したほうが良いとは限りません。
しかし、どちらか一方が関係修復を望んでいたり、反省の気持ちをもっていたりすれば、もとの関係性に戻れる可能性は十分あります。
今回紹介した夫婦関係修復の方法も参考にしながら、実践できることから挑戦してみましょう。
マインドフルネスと瞑想の違いや初心者におすすめのやり方を徹底解説!

自分自身と向き合うことで、集中力や生産性の向上、不安やストレスを緩和するための手法としてマインドフルネスが注目されています。
さまざまなメリット・効果が期待できるマインドフルネスですが、なかには危険な行為であるという言説を目にすることがあります。
マインドフルネスにはどのような危険があるのか、やってはいけない人の特徴や、初心者が取り組む際の注意点などもあわせて解説します。
マインドフルネスとは

マインドフルネスとは、瞑想や呼吸法などを用いて自分の感情や思考と向き合う手法のことです。
精神統一の一種であり、日本では似たような考え方が1,500年以上前から存在していたともされています。
実際に「マインドフルネス」という言葉を生み出し、世に広めたのはマサチューセッツ工科大学医学部教授のジョン・カバット・ジン博士。
その後同大学にてマインドフルネスセンターの創設にも関わったジン博士は、もともと宗教色の強かったマインドフルネスを一般人にも取り組みやすいメソッドに落とし込み、概念や理論を確立しました。
現代では医療の臨床現場で取り入れられているほか、世界中の企業でも取り入れられている例があります。
マインドフルネスと瞑想の違い

マイインドフルネスと瞑想はとても良く似たものとしてしばしば語られますが、大きな違いとして目的が挙げられます。
マインドフルネスは、現在目の前で起こっている事柄に対しての注意力や集中力を最大限に研ぎ澄ますための手法として用いられることが多く、そのため社内の生産性アップのために企業にも取り入れられているケースがあるのです。
それに対して、瞑想は頭の中から一切の雑念を振り払うことで思考を一度リセットし、心の平穏を得ることが主な目的となります。
両者ともに目を閉じて呼吸に集中するなど、やり方に共通する点もありますが、目的がそもそも違うというということを頭に入れておくと良いでしょう。
初心者にもおすすめのマインドフルネスのやり方

マインドフルネスにはさまざまなメリットがあることから、これから挑戦してみたいと考える方も多いでしょう。
リスクを避けつつマインドフルネスの効果を最大限高めるためには、どのようなポイントに注意すべきなのでしょうか。
環境を整える
マインドフルネスを行う場所は、静かで落ち着いた環境が理想的です。テレビやラジオ、屋外の音が届きづらい静かな部屋で行いましょう。
また、着用する衣服や座る椅子、座布団なども重要です。
できるだけ締め付けが少なくリラックスできる衣服を選び、無理のない姿勢で座れる椅子や座布団を用意しましょう。
短時間からスタートする
マインドフルネスの上級者ともなると、数時間以上も瞑想に取り組む人もいます。
しかし、初心者がいきなり何時間も瞑想をするのは辛く感じてしまい、挫折する原因にもなるでしょう。
そのため、まずは数十秒、数分といった短時間からスタートすることがおすすめです。
短い時間からはじめ、瞑想に慣れてきたら徐々に時間を伸ばしていくことで、無理なく続けられるはずです。
毎日継続する
マインドフルネスの効果を実感するためには、毎日継続的に実践することが大切です。
上記でも紹介した通り、1日あたり数十秒、数分と短時間でも、とにかく毎日続けて習慣化することを意識しましょう。
トレーナーやコーチの指導を受ける
マインドフルネスによって気分が悪くなったり、危険な状態に陥らないようにするためにも、トレーナーやコーチの適切な指導を受けることも大切です。
特に初心者の場合、自分でも気付かないうちに瞑想によって危険な状態に陥ることがあります。
専門のワークショップやオンラインプログラムなどを利用し、正しい練習方法を習得しましょう。
体調が悪いときは無理をしない
マインドフルネスは毎日継続することが重要であると紹介しましたが、健康上の不安がある場合は別です。
身体の倦怠感や吐き気、頭痛などの症状があるときや、なんとなく気分が優れないときにマインドフルネスを行うと悪化させるおそれもあるため、決して無理は禁物です。
関連記事:アファメーション(ポジティブな自己暗示)のやり方・効果について解説
マインドフルネスの効果とは
マインドフルネスを行うことで、以下のような効果が期待できます。
集中力が高まる・神経が研ぎ澄まされる
仕事や勉強に集中したいと考えていても、周囲のことに気が散ってしまい集中力が続かない人にはマインドフルネスがおすすめです。
マインドフルネスの練習を通して自分自身と向き合うことで、少しずつではありますが注意力や集中力を高めることができるようになるでしょう。
ストレス耐性の向上
マインドフルネスを継続していると、目の前の事柄に意識を集中させることに徐々に慣れていきます。
その結果、無駄な思考や他のものごとにいちいち気が散るといった機会が少なくなり、ストレス耐性の向上が期待できるでしょう。
睡眠の質の改善
日頃からマインドフルネスを行っていることにより、ホルモンバランスや交感神経と副交感神経のバランスが整い、免疫力の改善や血圧の低下などが見られたとの報告もあります。
これらは副次的な効果ではありますが、睡眠の質を向上させることに寄与するでしょう。
マインドフルネスを行うと覚醒度が高まる可能性があるため、就寝直前は控えるようにしましょう。
関連記事:【簡単】メディテーション(瞑想)のやり方・意味|マインドフルネスとの違いは?
【体験談】マインドフルネスはやばい?続けた結果どうなったか

私がマインドフルネスを始めたきっかけは、日々のストレスと忙しさに追われる生活から少しでも逃れたいと思ったからです。最初はどのように始めたらいいのか、正直迷いましたが、瞑想や日常の小さな行動に意識を向けることからスタートしました。
例えば、食事をする時や歩いている時、そして夜眠りにつく前に、その瞬間瞬間に意識を集中させるようにしました。
数週間続けた後、私の生活にはいくつかの変化が現れ始めました。まず驚いたのは、夜の寝つきが良くなったことです。
以前はどれだけ疲れていても、なかなか寝付けないことが多かったのですが、マインドフルネスを実践するようになってからは、心が穏やかになり、ぐっすり眠れるようになりました。
さらに、日常でイライラすることが減り、ストレスを感じることが少なくなりました。何か予期しないことが起きても、以前よりも落ち着いて対応できるようになったのです。
特に心に留めているのは、「今、この瞬間に意識を向ける」ことの大切さです。私たちはしばしば、過去の後悔や未来の不安に気を取られがちですが、マインドフルネスを通じて「今」に集中することの価値を学びました。それが意志力や集中力を高め、緊張する局面でも落ち着いていられるようになった理由です。
しかし、マインドフルネスにはデメリットもあります。私の場合、感情の起伏が少なくなり、以前ほど感情的なリアクションが少なくなったと感じています。これはある意味で冷静さを保つことができるようになったとも言えますが、時には「感情を感じること」の重要性も思い出させられます。
それでも、マインドフルネスを続けて良かったと心から思っています。イライラすることがあっても、自分を責めることが少なくなりました。
また、ストレスを感じた時にそれに気づき、早く平常心に戻れるようになったのは大きな進歩です。完璧を目指すのではなく、自分自身を受け入れ、瞬間を大切にするマインドフルネスの心得は、私の日々の生活を豊かにしてくれています。
マインドフルネスの副作用・危険性
マインドフルネスは比較的安全で危険性が少ない手法であるとされています。
しかし、実はすべての人にとって安全とも限らず、人によっては危険や副作用をもたらすこともあるのです。
具体的な危険性や副作用には以下のようなものがあります。
トラウマの再体験・フラッシュバック
瞑想を行っていると、過去に経験した辛い出来事やトラウマが浮かび上がることがあります。
人によっては自分自身の過去と対峙し、辛い出来事やトラウマをうまく処理できることもあるでしょう。
しかし、マインドフルネスを行ったことによってさらなる苦痛をともなうケースも少なくありません。
不安・パニック
マインドフルネスでは瞑想や呼吸法によって、深い自己観察を行います。
この過程において、不安やパニックを増幅させることがあります。
このような副作用は、過去または現在に精神的な問題を抱えたことのある人に多く見られます。
無気力・無関心
マインドフルネスを継続していくことで現実逃避に陥ってしまい、何事にも関心を示さなくなったり、無気力になったりすることがあります。
このような症状は自己観察のしすぎによって起こることが少なくありません。
関連記事:【自己受容】弱くてダメな自分を認めて受け入れるトレーニング方法
マインドフルネスをして気持ち悪くなる人がいる?
マインドフルネスによる副作用では、上記のような精神的なもの以外にも、生理現象として現れるケースもあります。
ありがちな副作用としては、気分が悪くなったり、吐き気や咳が止まらなくなるというものです。
人によっては車酔いのような感覚に陥ることもあるようです。
ただし、マインドフルネスを行っているすべての人がこのような状態に陥るものではなく、現れる症状の程度も人によって異なります。
気分が悪くなる人は一人でマインドフルネスを実践しているケースが多いようで、専門のトレーナーやプロのコーチなどのサポートを受けることで症状が緩和されたり、全く症状が現れなくなることもあるようです。
マインドフルネスをやってはいけない人の特徴

マインドフルネスは多くの人にとって安全なトレーニング方法といえます。
では、上記で紹介したような危険性や副作用のリスクが高まるのはどういった人なのでしょうか。
マインドフルネスをやってはいけない人の特徴を4つ紹介しましょう。
精神疾患を抱えている人
うつ病や統合失調症、強迫性障害、双極性障害といった精神疾患を抱えている人の場合、マインドフルネスに取り組むことによって自分自身の嫌な部分ばかりが見えてきて病状を悪化させるリスクがあります。
これらの病気で治療中の方は、担当医やセラピストと相談してからマインドフルネスに取り組むようにしましょう。
PTSD(心的外傷後ストレス障害)の症状がある人
過去に体験した辛い出来事がきっかけとなり、PTSDの症状が表れるようになった人もマインドフルネスは避けるべきです。
瞑想中に過去の出来事やトラウマ、それにともなう辛い感情が引き起こされる可能性があるためです。
PTSDの症状を悪化させる可能性があることから、マインドフルネスに取り組む際には担当医やセラピストと相談しましょう。
自傷行為や自殺企図の経験がある人
過去に自傷行為や自殺企図の経験がある人もマインドフルネスを行うべきではありません。
瞑想によって心の痛みや悲しみを引き起こすことがあり、再び過去と同じ状況に陥る可能性があるためです。
心身症状を抱えている人
専門医による治療や診断は受けていないものの、日常生活のなかでたびたび不安感に襲われる人や、パニック発作や過呼吸などの心身症状が表れる人もマインドフルネスには向いていないかもしれません。
明確な診断を受けていない以上、自分だけの判断でマインドフルネスを行ってしまうと、症状を悪化させさらに重篤な状態に陥る可能性もあります。
関連記事:感情の起伏が激しい人や少ない人の特徴|上手にコントロールする方法とは
まとめ
ストレスや不安が多い現代社会において、マインドフルネスがさまざまなメディアに取り上げられ、SNSでも多くのユーザーが情報を発信しています。
一見すると誰もが手軽に取り組める手法に感じられますが、実際にはマインドフルネスによって危険や副作用が生じることもあり、細心の注意を払うことが大切です。
もし、マインドフルネスの方法が分からなかったり、トレーニングに不安を感じたりする場合には、専門のトレーナーやコーチの指導を受けながら挑戦してみてください。
アーユルヴェーダって何?どうやったらすんなり今の生活に取り入れられる?

アーユルヴェーダは、約5,000年前にインドで発祥した東洋医学の一つとされています。
「医学」と耳にすると「医者に任せるもの」「自分には関係のないもの」と思われがちですが、アーユルヴェーダは、病院で行われる医療という側面だけではなく、今の生活に取り入れ心身を健康にするための家庭での養生法としての側面を持ちます。
もう少し噛み砕いて言うと、セルフケアといったところでしょうか。
今回は、今すぐ始められるアーユルヴェーダをご紹介します。
養生法としてのアーユルヴェーダ
「健康」と聞くと、どんなことをイメージしますか?
風邪を引かない、病気にならない、いつまでも若々しい体でいること…色々なことが思い浮かんでくるのではないでしょうか。
以下が、WHO(世界保健機関)による「健康」の定義です。
“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. “
(健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的 にも、すべてが 満たされた状態にあることをいいます。)”
現代社会では、診断はつかないけれどなんとなくの不調を抱えている人も少なくありません。
アーユルヴェーダでは、健康の定義として、とりわけ幸福感を重視しています。
また「幸福とは”なる”ものではなく、幸福であることに”気づく”こと」と考えている点もキーポイントです。
では、どのようにして今、充分に幸せであることを噛みしめることができるのでしょうか。
アーユルヴェーダでは、理論と実践方法をベースに個々の持つ性質を知って、バランスを整えていきます。
けれど、性質は常に変化していくものではあります。
例えば、年齢によって体調は変化していきますし、季節によっても快調な時とそうでない時があることに気づきませんか?
あるいは、もう少し細かくみていくと、朝と夕方で、体の軽さが違うと感じる人もいるかもしれません。
また、理論や法則ばかりにこだわらず、自身の心身の感覚に尋ねながらケアを行うことも、とても重要になってきます。
自分にとって快適であることが第一で、養生法として無理なく続けていくことも可能になってくるというわけですね。
今の生活にアーユルヴェーダを取り入れるためのファーストステップ
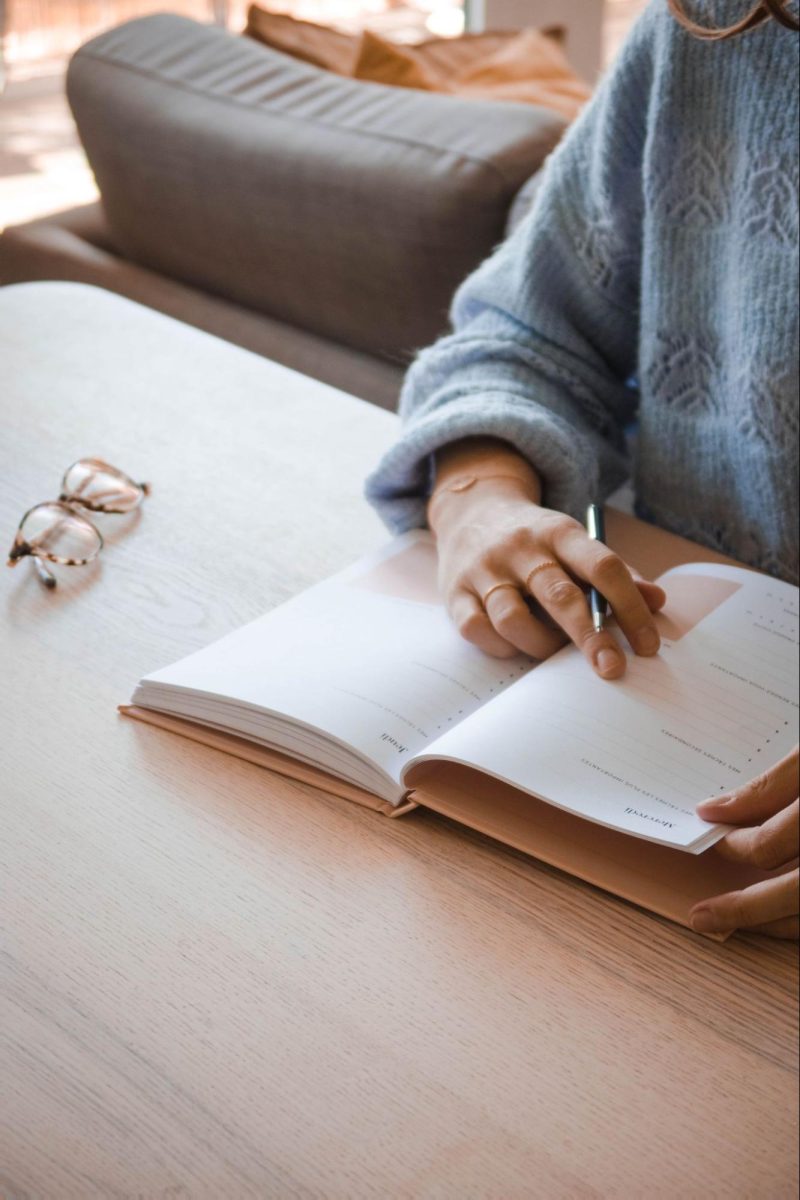
Photo by Covene on Unsplash
アーユルヴェーダを調べていくと、大抵の場合「体質診断」にたどり着くと思います。
それも自分の心身を把握するためのアーユルヴェーダを今すぐ取り入れるための方法の一つではありますが、前述した通り、性質は常に変化していくものです。
また、診断結果によって「私はこの体質だから!」と決めつけてしまい理論的になってしまう可能性も。
例えば「この体質だから、これは食べては駄目」と制限をかけてしまう人も多くいますが、無理は禁物です。
ですので、まずは、自分自身で今どういった体と心の状態かを客観的に把握するための簡単な方法として、以下を参考に寝る前に「自分日記」をつけるのがおすすめです。
食べたもの / 飲んだもの
いつ、どこで、何を、どのように食べたのか記録します。
(eg: 朝食: 家で、食パンとコーヒーを家族と一緒に話しながら食べた)
運動 / セルフケア
その日に行った運動やセルフケアを記録します。
(eg: ヨガ、瞑想、家族と電話、オイルマッサージ)
気分 / 体調
その日の気分や体調を記録します。
原因が分かる場合は、それも記録します。
(eg: 気分が沈みがちだった。前の日に仕事でヘマをしたから。そのせいか、お腹の具合が朝からあまりよくなかった。)
睡眠
就寝時間や起床時間、睡眠の質を記録。
(eg: 就寝時間23時 起床時間6時半、夜中に何度か目覚めた。)
1日の終わりに、自分自身と向き合うことで、自分が今幸せかどうかということにも気づくことができるかもしれません。
また、自分が調子の良いとき、悪い時の傾向(どんなものをよく食べているか、どんな運動やセルフケアをしているか)などを把握することもできます。
これをしばらく続けた上で、アーユルヴェーダ的なセルフケア方法を快適なレベルで取り入れていくのが良いのではないでしょうか。
ミニマリストになってマインドフルネスな生活を手に入れる方法

あなたは、ミニマリスト的な生活を目指していますか?
少ないものに囲まれて暮らす生活が見直されていますが、どうしてミニマリストになることが良いのでしょうか?
それは、ものや人間関係を整理し、あなたにとって「最も価値があるものや人」に囲まれたライフスタイルを送ることで、本当の心の安心・安定が手に入れられるからです。
Photo by Radu Florin on Unsplash
ものを減らすことの効用
ミニマリストになることでどんなメリットがあるのでしょう。
ミニマリストになるメリット①
まずは、ストレスの軽減です。
ものが多いと、それらを整理することに、日々、時間とエネルギーを費やし、心が常にざわざわと落ち着かず忙しくなります。
つまり根本的な持ちものの量を減らすことで、部屋を整える必要が少なくなり、いつもものたちから責められているような「使って」と懇願されているような感覚がなくなり、心が落ち着くのです。
最小限のもので生活することで、必要最低限のものだけに集中しストレスを減らすことができます。
ミニマリストになるメリット②
2つ目は、自分についての理解が深まるという点です。
自分が何を大切にしているかを見つけることができるのは、自分自身と対話をしているときだけ。
持ちものを整理し、どれが必要でどれが不要かを判断することで、現在の自分に対する認識が高まるのです。
さらに、断捨離によって、不必要なものにとらわれることなく、本当に重要なことに集中できるようになります。
自分の持ちものや時間、お金の使い方に注意を払い、意識的に日々の生活で選択をすることにより、より充実した人生を歩むことができるでしょう。
ミニマリストになるメリット③
3つ目は、財政的な自由に近づくこと。
必要なものだけに優先的にお金を使うことで、貯蓄を増やし財政的な自由を目指すことができます。
また、本当に気に入ったものだけを集め、長く大切に使うことにより、消費物や廃棄物を減らすことは、より環境にやさしいライフスタイルを実現することにもつながります。
消費主義の今の時代、私たちは多くのものを所有しています。
しかし、身の回りのたくさんのものによって、あなたの人生の真の意味が埋もれてしまいがちなのです。
ですから、日常生活において、整理整頓をすることでクリアな心と幸福感を生み出すことができるのです。
まずは何からスタートできるか
それでは、どうしたらこのミニマリストの生活を実現できるのでしょうか?
特に、大きな違いがでるのは私たちの家です。
あなたの家を自由と感謝の聖域にするためには、シンプルな状態にしておくことが大切です。

Photo by Deconovoon Unsplash
イメージしてみてください。
清潔で白い壁の家で目をさまし、シンプルで整頓されたクローゼットから服を選び、きれいに整理されたキッチンで朝ごはんを作るような生活を。
掃除がメンタルヘルスに与える影響とは?心も部屋もスッキリさせる方法
とても素敵な情景が浮かびますが、こんな完全なミニマリストの生活をしなくても良いのです。
少し片付けをして、日常生活をシンプルにすることで、マインドフルネスな心境を手に入れることができるのです。
それでは、さっそく今日から、あなたも捨てたりリサイクルしたり寄付したりできるアイテムを紹介します。
今日から手放してみようアイテム30選
【寝室】
- 数か月ずっと着ていない服
- クリーニング屋でもらったハンガー
- イベントでもらった無料のTシャツ
- 未使用のスポーツウェア
- もうサイズが合わない靴
- 1年以上着用していないアクセサリーやバッグ
- 使わない枕
【キッチン】
- 使わない料理本 (使うレシピだけメモしておきましょう)
- 積み重なっているたくさんのエコバッグ
- 子供が使っていた幼児期の食器
- お祝いでもらった使わない食器類
【バスルーム】
- メイクなどのサンプル用品
- 使わないマニュキュア
- 使用期限の切れた日焼け止め
【オフィス】
- もう必要ない古い書類
- もう使わないマニュアル
- 古い新聞や雑誌
- 期限切れの割引クーポン
- もう読んだ本
- 使わないケーブル関連
- 使用済のノート
- もう使わない古いパソコン
【その他】
- 使わないキャンドル
- 壁に飾っていないアート
- 使っていないブランケット
- 使わないゴミ箱
- 子供たちが小さい時に使っていた古いおもちゃ
- 使わないヨガマット
- もう見ることがない古いDVDやCD
- 使わない延長コード
あなたのゴミが誰かの宝物に
こういったアイテムのほとんどは、私たちの家にひっそりと積み上がっていきます。
ボタン、紙袋、レシート、段ボールなど、保存しておくつもりで残しておいたものが、不必要なものの山となってしまうことはよくあります。
その一方で、あなたのゴミは他の人の宝物かもしれません。
あなたが使っていないアイテムについては、友達と交換してみるのはどうでしょう。
それによって、ごみを減らす代わりにあなたにとっての宝物を手に入れるかもしれません。
断捨離とは、つまるところ「優先事項がなにか」に関するものではないでしょうか。
つまり、手放すこと、そして私たちが何に時間やお金を使うのかについて注意深く考えることです。
ものではなく経験を買い、必要のないものは友人から借りてみるでもいいでしょう。
あなたにとって真に重要な人やものに焦点を当てて、量を減らして質を向上させてみてください。
ものを少なくしても、人生を充実させることはできるのです。
自分を変える方法を解説|良い行動や習慣とは

「自分を変える」と聞くと、多くの方は難しいのではないかと感じるのではないでしょうか。
また、実際に変わりたいと思っても、具体的に何から始めれば良いのか悩むことも少なくないはずです。
そこで、本記事では変わりたいと思っている方に向けて、どういった方法が有効なのか、日々どういった習慣を心がければ良いのかも含めて具体的に紹介します。
自分を変えるために重要な自己認識力とは

自分を変えるために重要な要素として、自己認識力というものがあります。
自己認識力とは、自分の性格や考え方などの特性を理解する力のことです。
自己認識力を高められれば、自分にとって大切な価値観や考え方が客観的に理解できます。
そのうえで自分を変えるためにはどういった価値観を取り入れるべきか、反対に手放すべき価値観や考え方なども見えてくるでしょう。
一口に自己認識力といっても、大きく分けると「内面的自己認識」と「外面的自己認識」の2つが存在します。
➀内面的自己認識とは
内面的自己認識とは、自分の真の姿を理解・認識することを指します。
たとえば、自分自身では内向的な性格であると認識していたものの、初対面の人とも短期間で打ち解けられたとき、意外と社交的な面もあると実感した経験はないでしょうか。
自分自身が認識している姿と、本当の自分の姿との差異が少ないほど、内面的自己認識力が高いといえるでしょう。
②外面的自己認識とは
外面的自己認識とは、第三者から自分がどのように見られているかを理解することを指します。
上記の例でいえば、自分自身は内向的な性格であると認識している一方で、第三者からは社交的な人であると認識されているケースもあるでしょう。
こちらも、本人と第三者との認識にズレが少ないほど、外面的自己認識力が高いといえます。
▶︎【変わりたいあなたへ】自分を変えることは難しい?変われる方法や習慣
自分を変えるために必要なステップ
自分を変えるためには、まずは自己認識力を高めることが第一歩となります。
そのために必要な4つのステップを紹介しましょう。
①他者からの意見を求める
外面的自己認識を確認するために、他者から自分はどう認識されているのか、意見を求めましょう。
できるだけ率直な意見を出してもらうことが重要であり、厳しい意見が出されたとしてもそれを受け入れる勇気と覚悟が必要です。
もし、漠然としていて相手が答えに困っているようであれば、「自分では◯◯だと思っているんだけど、◯◯さんから見てどう感じる?」といったように、具体的に問いかけてみるのも良いでしょう。
②うまくいったこと・幸せに感じたことの振り返り
これまでの人生や仕事のなかで、うまくいったことや幸せに感じたことを思い出してみましょう。
そのときに、自分でどのような行動を起こしたか、他者とどのようなコミュニケーションをとっていたか、どのような思考・考え方・価値観をもっていたかなど、自分について思いつくことを何でも良いので書き出してみます。
そうすることで、どのような行動をすれば成功体験を得られるかが自分の中で整理されるようになるでしょう。
③うまくいかなかったことを内省する
次に、上記とは反対に、うまくいかなかったことを思い出してみましょう。
たとえば、仕事で大きなミスを犯してしまったときのことや、友人とケンカをしてしまったときなどを思い出し、そのときにどういった言動をとっていたのか書き出してみます。
過去の自分の行動を客観的に見ることで、次に同じ失敗をしないようにどうすればよいのかを考えることが成長へとつながるでしょう。
④何を変えるべきかを考える
うまくいかなかったことの内省のなかで、何が原因だったのかを考えてみます。
原因がよく分からないときには、他者から見た自分や、うまくいったことや幸せに感じたこととの比較で、どういった言動の違いがあったのかを参考にしてみましょう。
そのうえで、自分のなかの何を変えると状況が良い方向に変わっていくのかを考えてみます。
▶︎【自己受容】弱くてダメな自分を認めて受け入れるトレーニング方法
自分を変えることは難しいのか
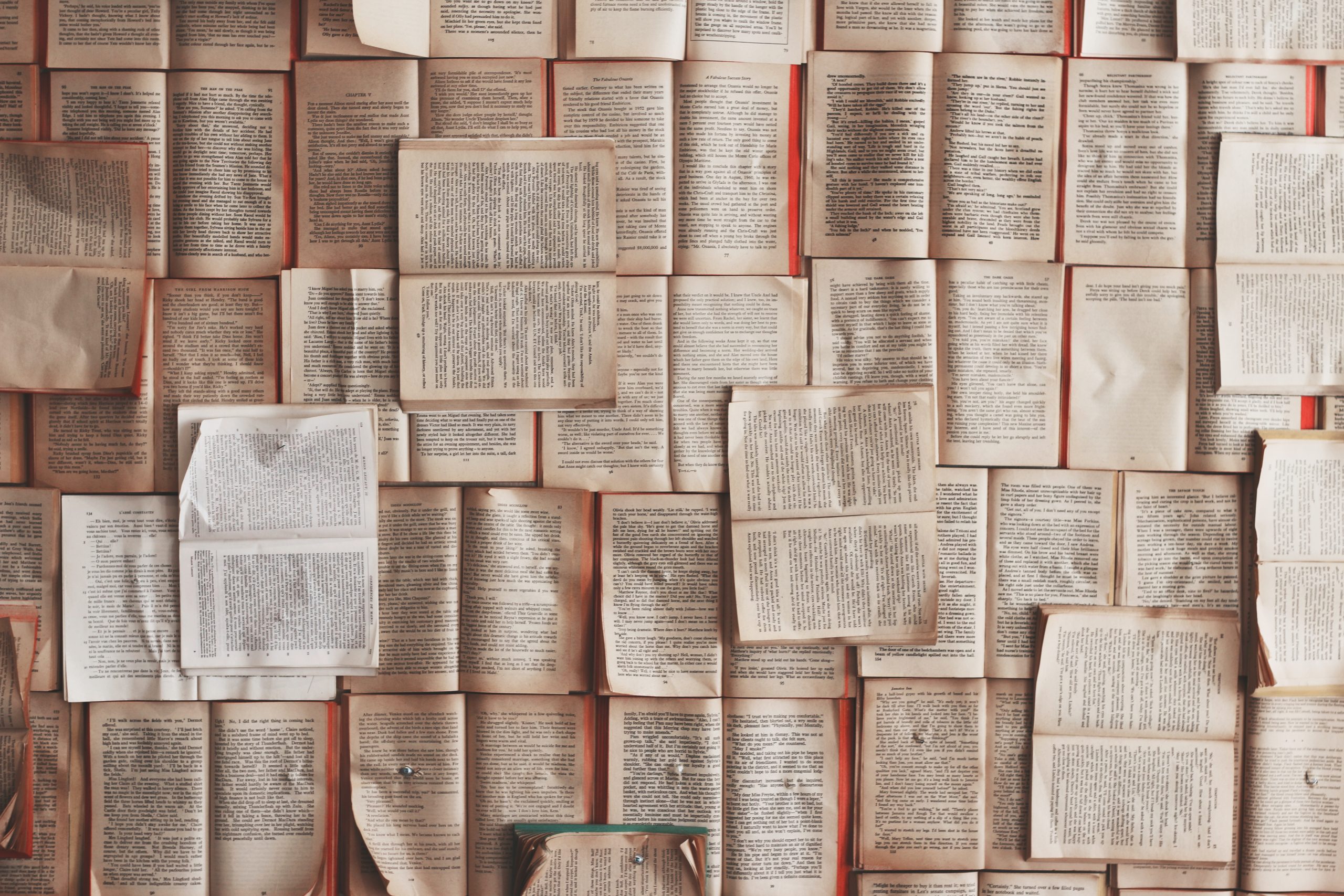
人の性格や価値観は、育った環境やそれまでの経験、周囲の人との関係性など、さまざまな要因が関係しながら長年にわたって形成されるものです。
それだけに、自分を変えるのは無理・しんどいと感じたり、ときには恐怖を覚えることもあるかもしれません。
自分を変えるには時間や手間がかかることはもちろんですが、性格や価値観が変わることで自分の周りから人が離れていってしまうのではないか、と感じる方も少なくないでしょう。
しかし、人間関係を維持しつつ自分自身を良い方向へ変えていくことは決して不可能ではありません。
ある日突然性格や考え方を変えることは難しいですが、日々の習慣や行動に意識を向け、徐々に自分を変えていきましょう。
自分を変えると人生がどう変化するのか
実際に自分を変えることができた場合、仕事や私生活にどういった変化が現れるのでしょうか。
恋愛面において現れる変化も含めて詳しく解説します。
①仕事の変化
仕事に対するモチベーションが上がらず、マンネリ化している方も多いのではないでしょうか。
また、今の仕事が自分に合っていないと感じている方も多いでしょう。
そのような場合は上司からの評価も得にくく、さらにモチベーションが下がっていく悪循環に陥ることがあります。
自分を変えることができれば、日々の業務を自分なりに改善しようと前向きに考えられるようになり、それが行動となって現れます。
上司の見る目も変わり、新たな業務にアサインされたり、役職を任されたりすることもあるでしょう。
また、同僚や部下も頼りにするようになり、仕事そのものに対するやりがいを感じられるようになります。
②恋愛・私生活の変化
自分を変えることで、恋愛を含めた私生活にもさまざまな変化が現れることがあります。
たとえば、ネガティブ思考をポジティブに切り替えることで自然と笑顔が増えていき、話しかけやすい雰囲気に変わってくることもあります。
それまで顔見知り程度であった人からも声をかけられ、交友関係が広がっていくかもしれません。
また、ポジティブな思考になることでいきいきとした表情や雰囲気に変わり、異性から見ても魅力的に映るでしょう。
その結果、新しい恋人ができたり、交際相手と良好な関係を構築できる可能性もあります。
▶︎セルフラブとはどんな意味?自分を愛す方法や自己肯定感との違いを解説
自分を変える具体的な方法

実際に自分を変えようと考えても、具体的に何から始めれば良いのか分からないという方も多いでしょう。
そこで、自分を変えるためにすぐにでも実践できる方法をいくつか紹介します。
①見た目を変える方法
自分を変えるための第一歩として、取りかかりやすいのが外見を変えることです。
これは何も「整形手術を受けろ」と言っているわけではありません。
たとえば、ロングヘアからショートカットに変えてみたり、髪を明るい色に変えてみたりするだけでも気分が変わり、それが性格や言動などに波及することがあります。
髪型だけでなく、黒やグレーといった暗めの服から白やピンク、イエローといった色のアイテムを効果的に取り入れるだけでも印象が変わります。
さらに、外見的なコンプレックスを抱いていたり、自分に自信がなかったりすると自然と猫背になっていくことも多いため、つねに背筋を伸ばすことを心がけるだけでも堂々とした態度に見えるでしょう。
②性格を含めた内面を変える方法
性格や考え方、価値観などの内面を変える方法はいくつか存在しますが、付き合う人を変えてみることがおすすめです。
たとえば内気でネガティブな性格の場合、自分と同じような人のほうが一緒に過ごしていて楽に感じることもあるでしょう。
しかし、あえて自分と正反対の人とコミュニケーションをとることで、これまで避けてきたような人とも交友関係が広がり、新たな考え方や価値観に巡り合えることもあります。
③行動を変える方法
行動を変えるために特におすすめなのは、手本となる人を真似してみることです。
たとえば、人見知りを改善したい場合には、社交的で交友関係が広い人をモデルにし、普段どのような振る舞いをしているのか、話し方なども注意深く観察してみましょう。
手本となる人を意識的に観察することで、自分自身の言動も徐々に影響されてくることがあります。
自分を変えるために効果のある良い習慣
自分を変えるためには、ちょっとした習慣を心がけるだけでも効果が見込める場合があります。
たとえば、早寝早起きを心がけることもそのうちのひとつです。
十分な睡眠時間が確保できていないと、精神的に不安定になったりネガティブな気持ちになったりすることも多く、自分を変えようと思ってもモチベーションが維持できなくなります。
また、SNSの閲覧や投稿が日課となっている方も多いと思いますが、ネガティブな話題や乱暴な言葉を目にすることもあるため、一定の距離を保ったり、ときには“SNS断ち”をしてみるのもひとつの方法です。
▶︎【ストレス解消】セルフケアとはなにか?意味・種類・方法について解説
まとめ
自分を変えるためには、まず自己認識力を高め、自分自身を客観的に把握することが第一歩となります。
これまでの人生や経験を振り返りつつ、内省するとともに、今後何を変えていけば良いのかを具体的に考えてみましょう。
また、ヘアスタイルやファッションといった外見を変えてみたり、付き合う人や自分にとっての手本となるような人を見つけ観察してみるのも具体的な行動としておすすめです。
“自分らしく生きる”とは?|仕事や恋愛で自然体で過ごせる方法を紹介

自分らしく生きることは、充実した人生を送っていくために重要なポイントといえます。
しかし、そもそも「自分らしく生きる」とはどういったことかわからない方も少なくないでしょう。仮にわかっていたとしても、そのような生き方を送ること自体が難しいと感じる方も多いはずです。
本記事では、自分らしく生きることが難しく感じる理由や、自分らしく生きるための方法、コツも含めて解説します。
自分らしく生きるとはどういうこと?
そもそも「自分らしく生きる」とは、人によってもさまざまな解釈があると思います。
一般的には、「自分の気持ちや考え方、価値観などに正面から向き合い、正直に生きていくこと」といえるでしょう。
たとえば、趣味に没頭することはもちろんですが、自分にしかできない仕事を続けること、好きなことを仕事にして生計を立てていくことなども自分らしい生き方といえるでしょう。
私たちが生きていくうえでは、「こうあるべき」といった世間一般の常識や同調圧力のようなものが数多くあります。
たとえば、「◯歳頃までには結婚をしたほうが良い」、「結婚をしたら子どもをつくるべき」といった価値観をもっている人もまだまだ少なくありません。
しかし、そのような考えや価値観に縛られすぎてしまうと、自分の人生を周囲に無理に合わせようとしてしまい、生きづらさを感じることもあるでしょう。
自分らしく生きるためには、世間や周囲の考え方に対して無理に自分を合わせる必要はないのです。
▶︎セルフラブとはどんな意味?自分を愛す方法や自己肯定感との違いを解説
自分らしく生きることに難しさを感じる原因や理由
自分らしく生きたいと考えているものの、実際にそれを実行しようとすると現実的には難しいと感じるケースも少なくありません。
では、なぜそのように感じてしまうのでしょうか。
①周囲からの視線が気になる
自分らしく生きていくということは、客観的に「自由奔放な人」と見られてしまう可能性があります。
友人や知人、仕事仲間など、それまで付き合ってきた人のなかにも、価値観や考え方が合わないと感じ疎遠になってしまう人も出てくるでしょう。
また、他者からの評価が気になってしまい、自分らしく生きることが難しいと感じるケースもあります。
②自己肯定感が低い
自己肯定感とは、自分自身を認め評価することです。
自己肯定感が低い人は、「自分はダメな人間だ」という考えが根底にあり、卑屈な考えに囚われることがあります。
自己肯定感が低い状態で自分らしく生きようと考えても、「どうせ自分には無理だろう」という考えが先行し、行動に移すことすらできなくなるでしょう。
▶︎自己肯定感が低い子供の特徴や言動とは|注意すべき親の発言や行動
③そもそも”自分らしさ”が分からない
人生における夢や目標がなく、なんとなく今の生活を続けている方も多いでしょう。
しかし、そのような状態で自分らしく生きようと考えても、そもそも何が“自分らしさ”なのかが分からず、理想像も浮かんできません。
まずは自分自身と向き合い、心の奥底ではどういった人生が理想なのかを考え、自分らしさとは何かを見つけることから始める必要があります。
▶︎【ストレス解消】セルフケアとはなにか?意味・種類・方法について解説
自分らしく生きている人の特徴

自分らしく生きている人にはどういった特徴が見られるのでしょうか。
仕事はもちろん、プライベートや家庭生活における特徴も紹介します。
①楽しく仕事をしている
仕事をして収入を得ることは生きていくうえで不可欠です。
だからこそ、自分らしく生きていくためには仕事を楽しむことが重要です。
子どもの頃からの夢であった仕事に就いていたり、仕事をしていくなかでやりがいや魅力を感じることをひとつでもいいので見つけてみましょう。
日々の生活が充実したものに感じられ、自分らしく生きていくための活力になるはずです。
②家族の協力を得ながら家事や子育てをしている
仕事にやりがいや楽しさを感じられても、家事や子育ても両立しようとすると自分の時間が確保できず、疲労やストレスが蓄積されていきます。
特に女性の場合、家事や子育てを一人で背負うのではなく、家族の協力を得ながら分担することで負担を軽減できるでしょう。
自分だけの時間が確保できれば、趣味や興味のあることに取り組め、自分らしい生き方を実践できるはずです。
③恋愛やプライベートも充実している
仕事が辛かったとしても、自分を理解してくれる恋人やパートナー、友人がいればプライベートが充実します。
仕事で溜まったストレスも軽減でき、自分らしい生き方を実践できていると感じられるでしょう。
また、仕事にやりがいを感じていたとしても、仕事だけの毎日を送っていると何を目的に働いているのか見失ってしまうこともあります。
そのため恋愛やプライベートを充実させることが重要なのです。
自己中やわがままとの違い
「自分らしく生きる」と聞くと、自己中心的やわがままといった負のイメージを抱く方もいます。
しかし、これらは異なる概念であり、自分らしく生きることは決してネガティブなものではありません。
①自己中とは
自己中、または自己中心的とは、「自分のために他人が動いてくれる、合わせてくれる」と認識していることをいいます。
自己中な人は自分の希望を叶えるために他人をコントロールする傾向がありますが、自分らしさをもっている人は他人をコントロールしようとしません。
②わがままとは
わがままとは「自分本位で気ままに行動すること」を指し、自己中と似た部分があります。
自分らしさをもっている人は、自分のなかに「私はこれが好き」、「私はこう考える」といった軸のようなものがあります。
仮に他人と意見が合わなかったとしても、相手を非難したり責め立てたりすることはありません。
しかし、わがままな人は、自分の考えや希望を相手に押しつけてでも通そうとします。
ときには相手や周囲の人に迷惑をかけることもあるのが“わがまま”です。
自分らしく生きることでどんな影響やメリットがあるのか

自分らしく生きることで、人生にどういったメリットやポジティブな影響があるのでしょうか。
➀ストレスが減る
周囲の人からの視線や意見にばかり気を向けてしまうと、自分らしさを見失ってしまい人生そのものが窮屈に感じられることもあるでしょう。
しかし自分らしさを常に忘れず、大きな軸として持っておくことで、生きづらさを感じにくくなりストレスも低減されます。
②新たなことに挑戦するモチベーションが高まる
ストレスが減って自分らしさを取り戻すことができれば、自然と自信がもてるようになります。
仕事へのモチベーションも高まり、新しい仕事や業務へ挑戦できるようになったり、新たな趣味をスタートさせ生きがいを見つけたりすることもできるでしょう。
自分らしく生きるための方法3選
人生をより充実させていくために、自分らしく生きるにはどういった方法があるのでしょうか。
➀自分を大切にする
まずは自分を最優先に考え、大切にすることを心がけましょう。
これは自己中心的やわがままになるという意味ではなく、あくまでも自分を尊重するということです。
たとえば、疲労が溜まっているのに飲み会に誘われたとき、無理に付き合うのではなくきちんと参加できない理由を説明して、断る勇気も大切です。
②自分にとって本当に大切なものを考える
自分らしさとは何かを考えたとき、その人が大切にしている考え方や価値観などが根底にあるはずです。
本当に大切なものを考えることで、自分らしさを見失うことなく生きていくヒントが得られます。
たとえば、家族と過ごす時間を何よりも大切に考えている場合には、ワークライフバランスを考慮した仕事や職場を選択する必要があるでしょう。
③自分の弱さを個性として受け入れる
人は誰しも弱点や欠点、コンプレックスなどがあり、完璧な人は存在しません。
自分らしく生きていくためには、弱みを欠点として認識するのではなく、個性として受け入れることも重要です。
何事もポジティブにとらえることで生きづらいと感じることも少なくなり、自分の強みを活かせるようになるでしょう。
▶︎【自己受容】弱くてダメな自分を認めて受け入れるトレーニング方法
自分らしく生きるためにやめた方がいい習慣や思考
日頃から行っている習慣や考え方、癖などが自分らしく生きることを阻害していることもあります。
特に注意すべき悪い習慣や思考としては、以下のようなものが挙げられます。
- 他人と自分を比較する
- 自分自身を否定する・責める
- 周囲からの目や評価を気にしすぎる
- 失敗することを過剰に恐れる
上記の習慣や考え方は自分らしさを見失う原因にもなるため、意識的に改善していくことを心がけましょう。
▶︎【変わりたいあなたへ】自分を変えることは難しい?変われる方法や習慣
まとめ
自分らしく生きることは一見すると簡単なように見えて、実際には難しいものです。
普段無意識にとっている行動や考え方が、自分らしく生きることを阻害している可能性もあるため、普段の行動を一つずつ振り返ってみるのも良いでしょう。
ストレスを低減し、人生をより充実したものにするためにも、今回紹介した自分らしく生きる方法を実践してみてください。
【自己受容】弱くてダメな自分を認めて受け入れるトレーニング方法

精神的な安定を手に入れたり、自分自身を成長させるために、まずは「自分を受け入れる」ことが重要であるといわれることがあります。
しかし、そもそも自分を受け入れるとはどういうことなのでしょうか。
本記事では、「自己受容」のトレーニング方法や、自分を受け入れることで得られるメリットなども詳しく解説します。
自己受容=自分を受け入れる
自己受容とはその名の通り、自分自身のことを現状を踏まえて受け入れることです。
自己受容において重要なのは「現状を踏まえて」という部分であり、これはすなわち、自分自身にとって嫌な部分やネガティブな部分も含めて受け入れることを意味します。
たとえば、身体的特徴や経済状況、職業、学歴など、人によってはコンプレックスや不満を抱いているものもあるでしょう。
しかし、自分自身の努力や行動によって変えられるものもあれば、努力ではどうしようもないものもあります。
物理的に変えることが不可能、または困難なものがあっても、それも含めて自分が置かれている状況であると理解し受け入れることを自己受容といいます。
▶︎”自分らしく生きる”とは?|仕事や恋愛で自然体で過ごせる方法を紹介
自分を受け入れることが難しい/できない原因
上記でも解説した通り、自己受容を一言で表すとすれば「自分を受け入れること」です。
しかし、言葉で表すのは簡単でも、自分を受け入れることは難しい、または受け入れられないと感じる方も少なくありません。
それはなぜなのでしょうか。下記で解説します。
➀自分の弱みやコンプレックスを認めたくないため
ひとつめの理由は、自分を受け入れることで、弱みやコンプレックスに感じている部分を認めてしまうためです。
たとえば、結婚や出産などのタイミングで体型が変わり、太ってしまうこともあるでしょう。
本人のなかでは「ダイエットをすればもとの体型に戻る」という未練にも似た意識も強く残っているはずです。
将来的に弱みやコンプレックスを改善できるという思いが強いほど、ありのままの自分を受け入れることが難しくなります。
②自分の成長を否定することになるため
自己受容によって弱みやコンプレックスを認めるということは、自分にとっての成長を諦めたり否定したりすることも意味します。
上記の例では、自分を受け入れた時点で「ダイエットをしてもどうせ諦めてしまう」、「失敗に終わる」という結論にたどり着くこともあるでしょう。
ありのままの自分を受け入れることをポジティブにとらえられず、諦めや成長の否定といったネガティブな方向で考えてしまうケースも少なくありません。
自分を受け入れるメリットや影響

自分を受け入れることで、どういったメリットがあるのでしょうか。
自分自身だけでなく、周囲に与える影響についても詳しく解説しましょう。
➀失敗を恐れず前向きな行動につながる
ありのままの自分を受け入れられれば、失敗を恐れずに前向きな行動を取れるようになります。
たとえば、ダイエットに挑戦して途中で挫折したとしても、必要以上に落ち込むこともなく、次に失敗しないためには何を改善すべきかを考えられるようになるでしょう。
ダイエットに限らず、新たな挑戦には失敗がつきものです。
ありのままの自分を受け入れることで、前向きな行動につなげられます。
②他者に寛容になれる
自分を受け入れることで、自分自身にはもちろん他者に対しても寛容な気持ちで接することができます。
ほかの人が失敗しても過度に責め立てることなく、穏やかな気持ちで見守ることで、良好な人間関係やチームワークが維持できるでしょう。
これは決して他人に期待を寄せていなかったり、諦めたりしているわけではありません。
あくまでも、自分を受け入れることで心に余裕が生まれ、他人に対しても寛容な気持ちで接することができるという意味です。
③自分に自信がもてる
自分を受け入れられない人は、一度でも失敗や挫折をしてしまうと「自分は悪い人間だ」、「情けない」といった負の意識が高ぶってしまい、落ち込んでしまいがちです。
しかし、ありのままの自分を受け入れることができれば、多少のミスや失敗、挫折があっても必要以上に落ち込むこともなく、改善点を次々と発見して成功に近づけていきます。
繰り返し何度も挑戦しているうちに成功を収めることも増え、それが自信にもつながっていきます。
▶︎セルフラブとはどんな意味?自分を愛す方法や自己肯定感との違いを解説
自分を受け入れられている人の特徴
自分を受け入れられている人はどういった特徴があるのでしょうか。
2つのポイントを紹介します。
①自分にも他人にも優しい
自分を受け入れることで他者に寛容になれると紹介しましたが、これは自分自身に対しても同じことがいえます。
少しの失敗をしてもネガティブに捉えず、肯定的に受け止めたうえで自分自身に対して前向きな言葉をかけられるでしょう。
②ストレスを溜めることなく精神が安定している
自分を受け入れられない人は、理想の自分と現実の自分とのギャップに悩み、ストレスを感じやすくなります。
しかし、ありのままの自分を受け入れることでそのようなストレスを感じることもなくなり、つねに精神的に安定している傾向が見られます。
▶︎【ストレス解消】セルフケアとはなにか?意味・種類・方法について解説
自分を受け入れることと、他者受容・開き直り・自己肯定感との違い

自分を受け入れる「自己受容」と似た言葉として、他者受容や開き直り、自己肯定感などがあります。
それぞれどういった意味の違いがあるのか解説しましょう。
①他者受容とは
他者受容とは、自分ではなく相手の気持ちを受け入れることを指します。
両者は対極的な概念のように感じられますが、自分を受け入れられるようになれば、他者の気持ちも受け入れられるようになるでしょう。
②開き直りとは
開き直りとは、自分が間違いを犯していたにもかかわらず、それを正当化したり相手に対して謝罪せず横柄な態度をとったりする行為を指します。
自己受容は、自分の間違いを認めたうえで受け入れるという前提があることから、開き直りとは全く異なる概念といえるでしょう。
③自己肯定感とは
自己肯定感とは、文字通り自分自身を肯定する感情のことを指します。
「自分はダメな人間だ」という気持ちが強いと自己肯定感は高まらず、ネガティブな思考に陥っていきます。
まずはありのままの自分を受け入れることによって、悪い面があったとしても良い面も評価できるようになり、自己肯定感につながっていきます。
すなわち、自己肯定感を高めるために自己受容は必須といえるのです。
▶︎自己肯定感が低い子供の特徴や言動とは|注意すべき親の発言や行動
自分を受け入れるためのトレーニング方法やコツ
「自分を受け入れる」と聞いても漠然としており、具体的にどうすれば自己受容ができるのか分からない方も多いでしょう。
特に意識しておきたいのは、周囲と自分を比較しないことです。
たとえば、営業成績や学歴、収入、結婚または子どもの有無など、他人と比較することで自分が優越感に浸ったり、劣等感を抱いたりすることがあります。
しかし、どちらが上、または下であると意識しないようにすることで、ありのままの自分を否定することなく受け入れられるようになります。
これは決して簡単なことではありませんが、つねに頭の片隅に置いておき、他人と比較しないことを意識して徐々に自己受容を高めていきましょう。
▶︎【ポジティブな自己暗示】アファメーションのやり方・効果について解説
まとめ
ありのままの自分を受け入れるということは、ダメな自分を肯定するような気持ちになり抵抗を抱く方も多いでしょう。
しかし、失敗したとしても前向きな行動をとれるようになったり、良好な人間関係を築けるようになったりと、さまざまなメリットもあります。
他人と比較することをやめ、自分と向き合うことを日常生活で意識し、徐々に自己受容を高めていきましょう。
監修者紹介

– アフリカンペイントアーティストSHOGEN(ショウゲン)-
タンザニアの小さな村で描かれるティンガティンガというペンキアートに心惹かれ、
日本での生活を捨て、なんの伝手もないまま単身アフリカへ・・・
現地で生活をしながらキャンバスだけなく、警察車両やホテル内の壁画に描くなど、
動物と子供を共存させた作風で独自の表現を追及する。
ティンガティンガ創始者Edward Saidi Tingatingaがおこなっていた“人々を幸せにする絵”への到達を目指す。
日本に制作の場を移した後は、キャンパスだけにとらわれない多方面での活躍を続けている。
生きる喜びを描くペンキ画家
アフリカンペイントアーティストSHOGEN(ショウゲン)オフィシャルサイト
メディテーションの意味とは?瞑想やマインドフルネスとの違いは?

ものごとをネガティブにとらえてしまい、いつまでも引きずってしまう方は多いのではないでしょうか。
このようなネガティブ思考を改善するための方法のひとつに、メディテーション(瞑想)があります。
本記事では、ネガティブな人でも自己肯定感を高めるために、普段からできるメディテーション(瞑想)の方法について解説します。
メディテーション(瞑想)の意味とは?
メディテーション(瞑想)とは、精神を集中させるためのトレーニングのことを指します。
日本語では瞑想とよばれることも多く、定期的に行うことで心身ともに健康な状態をつくり上げます。
もともと瞑想は仏教の世界で広く取り入れられており、本来は真理や悟りを拓くために行われてきた歴史があります。
真理や悟りを拓くためには瞑想以外にもさまざまな修行が必要であり、私たちにとっては難しいものだと捉えられがちです。
しかし、メディテーション(瞑想)は誰にでも手軽にできるトレーニングです。
視覚や聴覚などの一切の外部刺激を断ち、静かな空間で瞑想をすることで自分自身と向き合う時間ができ、精神的な安定と前向きな気持ちにつながっていくのです。
▶︎【ストレス解消】セルフケアとはなにか?意味・種類・方法について解説
メディテーション(瞑想)とマインドフルネスの違い
メディテーション(瞑想)と似た概念として、マインドフルネスとよばれるものがあります。
どちらも精神を集中させ、メンタルを安定的に維持することを指しますが、厳密にいえば両者にはわずかな違いがあります。
メディテーション(瞑想)は精神を集中させるためのトレーニングであり、具体的な方法として瞑想があります。
これに対しマインドフルネスとは、現在起こっている事柄や行動に対し意識を集中させる行為を指します。
両者の違いを一言で表すとすれば、メディテーション(瞑想)の最中に実践する行為がマインドフルネスといえるでしょう。
すなわち両者は密接に関連しており、メディテーション(瞑想)を習得することでマインドフルネスの効果も得られるというわけです。
メディテーション(瞑想)の効果
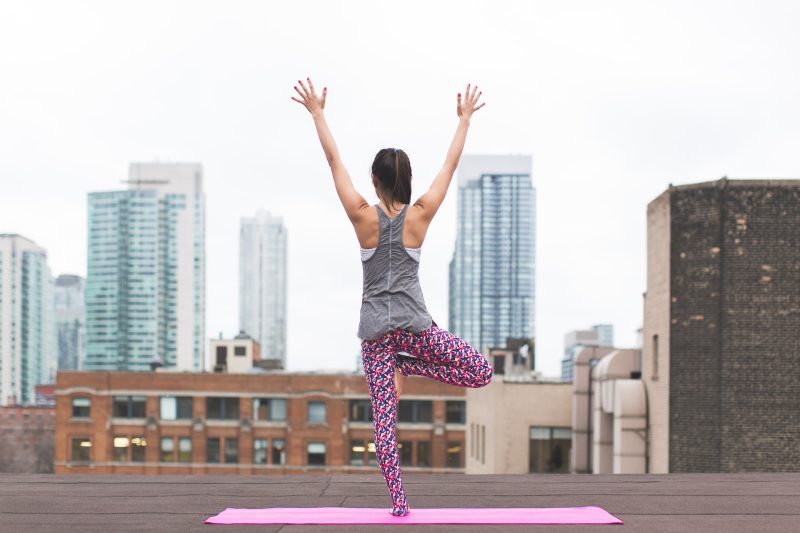
メディテーション(瞑想)は1回行ったからといって劇的な変化が見られることはありません。
メディテーション(瞑想)を習慣化し毎日のように実践することで、さまざまな効果が得られるようになります。
ここではメディテーション(瞑想)の代表的な3つの効果を紹介しましょう。
①ストレスの緩和
まずはストレスの緩和が挙げられます。
社会生活を送るうえで、人とのつながりや仕事は避けて通れないものです。
しかし、人間関係や仕事が原因で少なからずストレスを感じることもあり、人によってはそれが精神的負担としてのしかかってくるケースもあるでしょう。
メディテーション(瞑想)を習慣化することにより、自分自身と向き合い精神を落ち着かせ、ストレスを緩和することができます。
②集中力の向上
仕事に集中しなければならないのに、ほかのことが気になってなかなか進まないといった悩みをもつ方も多いのではないでしょうか。
そのようなとき、メディテーション(瞑想)を実践することで雑念を取り払うことができ、目の前の仕事に集中することができます。
メディテーション(瞑想)は時間や場所に関係なくすぐに実践できることから、仕事を始める前に習慣づけることでパフォーマンス向上が期待できます。
③過食・暴飲暴食の防止
ストレスの根本的な原因を解決できなかったり、ストレスとうまく付き合うことができていないと、必要以上の食事を摂取する過食や暴飲暴食の症状が現れることもあります。
食生活は健康の基本であり、偏った食生活を改善できないと肥満や重篤な病気などにつながるおそれもあります。
メディテーション(瞑想)を実践することにより、ストレスが緩和され健康的な食生活を送れるようになるでしょう。
▶︎ 【怒りを抑える】アンガーマネジメントのやり方・テクニックをご紹介!
メディテーション(瞑想)のやり方

メディテーション(瞑想)はいつでもどこでも、簡単に始められます。
どういった方法・手順で行うのか、基本的な流れを紹介しましょう。
①できるだけ静かな場所に移動する
まずは、できるだけ静かな場所に移動しましょう。
周囲の人から話しかけられたり、物音がうるさい場所では集中の妨げになるため、はじめのうちは静かな場所で実践するのがおすすめです。
たとえば、仕事の合間にメディテーション(瞑想)を行いたくなったら、トイレや休憩スペースなどに移動するのも良いでしょう。
②背筋をまっすぐにして座る
メディテーション(瞑想)は無理のないリラックスできる姿勢で行うのが前提となりますが、このとき重要なのは背筋を曲げないよう意識することです。
背骨に沿って長い棒が刺さっていることをイメージしながら、背筋を伸ばして座りましょう。
③呼吸のみに集中する
静かな場所で背筋を伸ばした状態で座ったら、目を閉じて呼吸のみに集中します。
メディテーション(瞑想)の時間は明確に決められていませんが、はじめのうちは数分程度、慣れてきたら10分程度の時間に挑戦してみましょう。
なお、呼吸のみに集中しようと考えていても、無意識のうちにほかのことを考えてしまう場合もあります。
その場合でも、焦らずに呼吸へ意識を向けるようにしてください。
④1週間に数回のペースで継続する
メディテーション(瞑想)で重要なのは、できるだけ長い時間にわたって呼吸のみに集中することと、定期的に継続し習慣化させることです。
毎日継続することは難しくても、1週間のうち数回のペースで継続していくことがおすすめです。
▶︎【自己受容】弱くてダメな自分を認めて受け入れるトレーニング方法
メディテーション(瞑想)を実際にしていた著名人
メディテーション(瞑想)を仕事や私生活に取り入れ、実際に成功を収めた著名人も少なくありません。
①スティーブ・ジョブズ(Apple創業者)
Appleの創業者である、故スティーブ・ジョブズ氏は、禅に精通していたことは有名なエピソードですが、仏教を学ぶなかでメディテーション(瞑想)も積極的に取り入れていたといいます。
メディテーション(瞑想)によって精神を統一し、心を落ち着かせることで革新的なアイデアを生み、無駄がなく一切の妥協を許さない製品づくりにも生かしていました。
②イチロー(元プロ野球選手)
2019年にメジャーリーグを引退したイチロー氏は、試合が始まる前に入念なストレッチとメディテーション(瞑想)を行うのがルーティーンであったといいます。
特に、メディテーション(瞑想)の時間は数十分にもおよび、毎日必ず試合に向けて精神を研ぎ澄ましていたようです。
ここぞというときに結果を残し、長年にわたってメジャーリーグの第一線で活躍できたのもメディテーション(瞑想)の賜物といえるのかもしれません。
メディテーション(瞑想)は自己肯定感アップにつながる?
メディテーション(瞑想)に取り組むことは精神的・肉体的にもさまざまな効果があると紹介しました。
メンタル面において特に重要な効果といえるのが、自己肯定感のアップです。
自己肯定感とは、その名の通り自分自身を受け入れる感覚のことを指します。
自分自身というのは、長所だけでなく短所も含まれます。
すなわち、自己肯定感が高い人は自分自身の良い部分と悪い部分を客観的に把握できており、そのうえで前向きにとらえているのです。
メディテーション(瞑想)は、マインドフルネスによって自分自身と向き合う行為ともいえます。
そのため、これを毎日のように習慣づけることによって自分の長所と短所が客観的に把握できるようになり、短所を長所に変えるにはどうすれば良いかが具体的に見えてくることもあるのです。
▶︎【ポジティブな自己暗示】アファメーションのやり方・効果について解説
まとめ
メディテーション(瞑想)の手順や方法そのものは簡単ですが、わずか数分だけであっても雑念を取り払い呼吸のみに集中することは意外と難しいものです。
はじめのうちはさまざまな事柄が頭に浮かんできて集中力が続かないこともあると思いますが、その都度呼吸に意識を向けるようにすれば効果は高まっていくはずです。
まずは2〜3分程度、週に数回を目安にメディテーション(瞑想)を継続してみましょう。
ネガティブな人でもできる自己肯定感を高める方法や習慣とは?
仕事やプライベートでうまくいかないことがあったとき、「自分はダメな人間だ」と感じる方も少なくありません。
このように自分のことを否定しがちな人は自己肯定感が低い傾向にありますが、考え方を少し変えてみるだけでも自己肯定感を高めることは可能です。
本記事では、ネガティブな人でも普段からできる自己肯定感を高める方法について詳しく解説します。
そもそも自己肯定感とはなにか

自己肯定感とは、その名の通り「自分自身を肯定できる考えや価値観、感覚」のことを指します。
人間である以上、誰しもが得意不得意な分野があったり、長所と短所が存在します。
自己肯定感で重要なのは、自分自身の長所はもちろんのこと、不得意なことや短所なども受け入れ肯定できることです。
個人の性格によって自己肯定感が高い人もいれば低い人も存在します。
また、生まれ持った性格だけでなく、これまでの人生においてどういった環境で育ってきたか、どのような人と接してきたかによっても自己肯定感の高さは大きく左右される傾向にあります。
▶︎セルフラブとはどんな意味?自分を愛す方法や自己肯定感との違いを解説
自己肯定感が高い人の特徴や言動

では、自己肯定感が高い人には具体的にどういった特徴や言動が見られるのでしょうか。
共通して見られる代表的な特徴をいくつか紹介します。
①長所と短所を客観的に把握できている
自分自身の長所だけでなく、短所も客観的に把握できています。
冒頭でも紹介した通り、長所も短所も受け入れることが前提となることから、自己肯定感の高い人はありのままの自分を把握できている傾向が見られます。
②周囲に流されない
自己肯定感が高い人は自分に自信をもっている傾向があり、周囲の意見に流されにくいという特徴があります。
たとえほかの人と意見が異なっていても、自分の意見ははっきりと明確にもっており、周囲に影響されることがありません。
これは周囲と対立するという意味ではなく、あくまでもほかの人の意見は受け入れたうえで、自分自身の意見や立場を明確にするということです。
③新しいことに興味を抱きやすい
自己肯定感が高い人は、失敗を恐れず新しいことに挑戦しようという意欲が高い傾向にあります。
新しいことを始めるにあたって失敗はつきものですが、挑戦の過程における失敗をネガティブにとらえることなく、むしろ失敗を原動力として突き進むことができます。
関連記事:【ストレス解消】セルフケアとはなにか?意味・種類・方法について解説
普段から自己肯定感を高める方法や習慣はある?

自分自身を振り返ってみたとき、自己肯定感が低いことを認識してしまうと、さらに落ち込んでしまう方も少なくありません。
では、このような状況を打破するために、自己肯定感を高める方法や習慣はあるのでしょうか。
普段の生活で意識しておきたいポイントをいくつか紹介します。
①失敗をネガティブにとらえない
仕事でミスをしたり、新しいことに挑戦してみたもののうまくいかなかったとき、ネガティブな気分に陥ることもあるでしょう。
しかし、いつまでも失敗したことを引きずったままになっていると、さらに仕事のパフォーマンスが低下することもあります。
失敗したから自分にはこの仕事が向いていないと考えるのではなく、「次に失敗しないための勉強になった」と考え方を変えてみましょう。
②短所を長所に言い換えてみる
自己肯定感が低い人は、自分自身の短所ばかりが気になってしまい自己嫌悪に陥りがちです。
しかし、短所ととらえるのではなく、長所に言い換えてみることで自己肯定感を高められる場合もあります。
たとえば、「コミュニケーションをとるのが苦手」と考えている方のなかには、自分から話題を振ることが苦手というケースも少なくありません。
そこで、相手の話をじっくり聞くことができる「聞き上手」であると言い換えれば、自分の新たな長所として見えてくることもあるでしょう。
③自分の思いや意志と向き合う
周囲の意見に流されやすい人ほど自己肯定感が低い傾向が見られます。
そこで、自分自身と正直に向き合い、思いや意志をはっきりさせてみましょう。
「意見が分かれることで、周囲と対立するのではないか」と心配になる方も多いため、はじめのうちは意見を表明できなくても良いです。
しかし、心の中だけでも思いや意志を明確にしておくことで、徐々に周囲に対し意見を表明できるようになり、自己肯定感も高まっていくはずです。
関連記事:【自己受容】弱くてダメな自分を認めて受け入れるトレーニング方法
自己肯定感が低い人は高めることが難しいのか?
自己肯定感はその人の性格や育ってきた環境によっても左右されると紹介しました。
そのため、大人になってから自己肯定感を高めることは難しいのではないかと感じる方もいるでしょう。
しかし、結論からいえば、もともと自己肯定感が低い人であっても、ものの見方や考え方を少し変えるだけで自己肯定感を高めていくことは十分可能です。
ある日突然、自己肯定感が高まり劇的に改善されるといったことは難しいですが、日頃の習慣や考え方の癖を客観的に振り返り、意識するだけでも自己肯定感は徐々に高まっていきます。
大人と子供では自己肯定感の高め方は違う?
大人だけではなく、子どものなかにも自己肯定感という概念は存在します。
大人の場合は自分自身の考え方や習慣などを客観的に振り返り、自分自身で改善していくことも可能ですが、子どもの場合は親のサポートが必要な場合もあります。
特に幼少期から小学生くらいの子どもは、自己肯定感という言葉すら理解できないため、親の立場からサポートが求められるでしょう。
子どもの自己肯定感を高めるためには、短所を必要以上に責め立てたり、他者と比較しないことが重要です。
たとえば、「なぜこんな簡単な問題も解けないの?」や「◯◯君はテストで90点も取った」といった言葉を投げかけてしまうと、子どもは自分自身を否定された気持ちになり、自己肯定感が下がっていきます。
短所を責め立てるのではなく、「こうすれば良くなる」といった前向きなアドバイスをしたり、長所を褒めて伸ばしていくことが重要です。
関連記事:自己肯定感が低い子供の特徴や言動とは|注意すべき親の発言や行動
自己肯定感が高まると仕事やプライペートにどんな影響を与えるのか

自己肯定感を高めることは、仕事やプライベートなどあらゆる面でさまざまなメリットがあります。
具体的にどういった影響が考えられるのか、代表的な3つのポイントを紹介しましょう。
①人生そのものが充実する
自己肯定感が高まると、なにかに失敗しても前向きに考えられるようになります。
失敗を恐れないようになれば、新しいことに挑戦する意欲も自然と湧いてくるでしょう。
その結果人生そのものが充実したものに感じられ、幸福感も得られます。
②良好な人間関係を構築できる
自己肯定感が高い人ほど、ほかの人が失敗やミスをしても過度に責め立てたりせず、寛容であり続けることができます。
相手の話をじっくり聞き、受け入れることで良好な人間関係を構築できるでしょう。
もし自分自身が困ったときでも、信頼できる人が周りにいれば、いざというときに助けてくれることもあります。
③ものごとを客観的かつ冷静に考えられる
自己肯定感が高まると、自分が何か失敗やミスをしたとしても冷静に振り返ることができます。
反省すべき点は反省することで、二度と同じようなミスが起こらないように有効な対策も講じられるでしょう。
その結果、仕事のパフォーマンスも向上していきます。
まとめ
自己肯定感を高めるのは決して簡単なことではありません。
それだけに、なかなか自分自身の性格や考え方を変えられずに悩み、さらに自己肯定感を下げてしまう方も多いです。
しかし、自分自身の短所を長所を言い換えてみたり、必要以上にネガティブ思考に陥らないように意識するだけでも、徐々に自己肯定感を高めていくことは可能です。
まずは考え方の癖や習慣を変えることから始めてみましょう。
【アファメーション】ポジティブな自己暗示のやり方や効果について解説

高い目標や自分が理想とする姿を実現するためには、まず意識の変革が求められます。
そこで重要なのが、アファメーションとよばれる概念です。
「肯定的な自己暗示」ともよばれるアファメーションは、どのように実践するのでしょうか。
また、どのような場面・状況で活かすことができるのかもあわせて紹介しましょう。
アファメーション(肯定的な自己暗示)の意味とは?

アファメーションとは、日本語で「肯定的な自己暗示」や「肯定的な自己説得」とも表現されます。
たとえば、陸上競技の選手が100メートル走でどうしても11秒を切ることができず悩んでいるとき、「どうせ無理だろう」という心理がはたらいていると目標をクリアすることは難しいものです。
しかし、「自分なら絶対にできる」と繰り返し言い聞かせることで、徐々に目標に近づき、やがてはクリアできることもあります。
このように、ポジティブな言葉を自分自身に投げかけ、自己暗示をかけて良い方向へ導くことをアファメーションとよびます。
実際にアファメーションを取り入れたことで成功をもたらした著名人やスポーツ選手も存在しており、夢を実現するために日常生活に取り入れやすいこともあって近年注目されるようになりました。
▶︎セルフラブとはどんな意味?自分を愛す方法や自己肯定感との違いを解説
アファメーション(肯定的な自己暗示)の効果
日常生活でアファメーションを実践することで、さまざまな効果が得られる可能性があります。
具体的にどういった効果が期待されるのか、代表的なものを3つ紹介しましょう。
①RAS
RASとは「Reticular Activating System」の略称であり、人間の脳にもともと備わっている機能のひとつです。
たとえば、朝の占いで「今日のラッキーカラーが赤である」と知ったとき、無意識のうちに赤色のものが目に入るようになったという経験はないでしょうか。
このように、さまざまな情報の中から優先的に意識される脳のフィルターのような働きをRASとよびます。
アファメーションを実践することでRASの機能が働きやすくなり、目標をクリアするために何をすべきか、無意識のうちに行動につながっていきます。
②プラシーボ効果
プラシーボ効果とは医療・製薬業界で用いられる専門用語であり、日本語では偽薬効果ともよばれます。
すなわち、処方された薬のなかに有効な成分が入っていなかったとしても、効果があるものだと患者が思い込んで薬を摂取することにより、症状が改善されるという効果です。
思い込みによってもたらされる結果ともいえ、ポジティブな考えをもつことで状況を改善したり、目標を達成したりする原動力になることがあります。
③ピグマリオン効果
ピグマリオン効果とは、「◯◯さんは仕事ができて優秀な人である」と思いながら第三者が接することで、本人のパフォーマンスが向上する効果です。
RASやプラシーボ効果は本人が思い込むことによってポジティブな効果が得られますが、ピグマリオン効果は第三者が本人に対して期待をかけることがきっかけとなって肯定的な自己暗示をかけることができます。
▶︎【変わりたいあなたへ】自分を変えることは難しい?変われる方法や習慣
アファメーション(肯定的な自己暗示)は意味がないといわれる理由

アファメーションについては、実際に効果が出たという体験やポジティブな意見をもつ方がいるのに対し、「効果がない」、「実践しても意味がない」とネガティブな意見をもつ方も少なくありません。
その背景にはさまざまな理由が考えられますが、特に多いのが本人のネガティブな思い込みです。
たとえば、「思い込みだけで成果が変わるのはあり得ないだろう」という考えのもとでアファメーションに取り組んでも、ネガティブな自己暗示にとらわれてしまい成果が見込めません。
また、アファメーションの正しい方法を把握しないまま取り組んでも、思うような成果が出ないことがあります。
▶︎自己肯定感が低い子供の特徴や言動とは|注意すべき親の発言や行動
アファメーション(肯定的な自己暗示)のやり方・かけ方

アファメーションによって成果を最大化するためには、どういったやり方で進めていけば良いのでしょうか。
基本となる方法と手順を解説します。
①夢や目標を言語化する
まずは、なりたい自分をイメージして言葉として表現します。このとき重要なのは、ネガティブな言葉を使用せずポジティブな言葉に言い換えることです。
たとえば、「仕事でミスをしない」ではなく、「仕事をマスターしメンバーから頼られる存在になる」などの表現を心がけましょう。
②声に出して読む
夢や目標を言語化できたら、実際に声に出して読み上げてみましょう。
声に出して読み上げることで視覚だけでなく聴覚も刺激され、より高い自己暗示の効果が期待できるようになります。
③夢や目標を書き出し目につきやすい場所に貼る
夢や目標をできるだけ大きな紙に書いて、目につきやすい場所に貼っておきましょう。
毎日声に出して読みやすいようにすることはもちろんですが、仕事や私生活の合間にもつねに目に入れておくことで、アファメーションの効果が高まります。
▶︎ネガティブな人でもできる自己肯定感を高める方法や習慣とは?
アファメーション(肯定的な自己暗示)の実践で注意するべきこと
自分がなりたい姿をイメージし、夢や目標を設定することはアファメーションにおいて重要です。
しかし、あまりにも現実とかけ離れた内容だと、「どうせ無理だろう」という潜在意識が生まれてしまい逆効果になることもあります。
たとえば、野球経験のない人が「プロ野球選手になる」と夢を掲げても、あまりにも漠然としていて何から始めれば良いのか分かりません。
そのため、まずは自分がクリアできる可能性がある目標を設定し、徐々に高い目標や理想像へと更新していくことが重要です。
また、「アファメーションのやり方」のなかでも紹介しましたが、目標はネガティブな言葉で表現するのではなく、ポジティブな言葉に言い換えて表現することも覚えておきましょう。
▶︎【簡単実践】メディテーション(瞑想)のやり方|マインドフルネスとの違いは?
アファメーション(肯定的な自己暗示)はどのような場面や状況で効果を実感できるのか

継続的にアファメーションに取り組むことによって、さまざまな成果や効果が実感できるようになります。
たとえば、これまでは「どうせ無理だろう」と考えていたことも、アファメーションによって毎日のように「自分ならできる」と言い聞かせた結果、徐々に目標に近づいていくこともあります。
アファメーションに取り組んだその瞬間、または翌日など短期間で成果が現れるとは限りませんが、徐々に目標に近づいていく感覚は身につくはずです。
たとえば、営業部門でトップの成果を上げるなど、中長期的な目標を掲げてアファメーションに取り組んだとき、長い目で見ると仕事に対する行動や意識が徐々に変わっていき、成果に結びつくこともあるでしょう。
まとめ
自己暗示をするだけで成果が変わるのか疑問に感じる方も多いでしょう。
しかし、アファメーションに継続的に取り組むことによって、日々の行動や意識が知らないうちに少しずつ変わってきて、結果として目標に近づくこともあります。
ポジティブな言葉として言語化し、それを目で見たり、声に発したりすることがアファメーションにおいては重要です。
「どうせ無理だろう」と考えるのではなく、「自分ならできる」という信念をもって行動することが成功への第一歩となります。
監修者紹介

– アフリカンペイントアーティストSHOGEN(ショウゲン)-
タンザニアの小さな村で描かれるティンガティンガというペンキアートに心惹かれ、
日本での生活を捨て、なんの伝手もないまま単身アフリカへ・・・
現地で生活をしながらキャンバスだけなく、警察車両やホテル内の壁画に描くなど、
動物と子供を共存させた作風で独自の表現を追及する。
ティンガティンガ創始者Edward Saidi Tingatingaがおこなっていた“人々を幸せにする絵”への到達を目指す。
日本に制作の場を移した後は、キャンパスだけにとらわれない多方面での活躍を続けている。
生きる喜びを描くペンキ画家
自己肯定感が低い子供の特徴とは|注意すべき親の発言や行動

昨今、SNSを中心に「毒親」や「親ガチャ」という言葉が流行るようになりました。
それだけ親が子どもに与える影響は大きく、ときには自己肯定感のような人格形成に関わることもあります。
そこで本記事では、「自己肯定感という言葉は聞いたことがあるもののよく分からない」という方に向けて、具体的にどういった意味を指すのか、自己肯定感が低い子どもはどういった特徴が見られるのか、また、自己肯定感が低くなる原因もあわせて解説します。
自己肯定感が低い子どもの特徴や言動

自己肯定感とはその名の通り、自分自身を肯定できる考え方や感覚のことを指します。
人の性格や育った環境などによって、自己肯定感が高い人もいれば低い人も存在するのです。
特に子どもの場合、親の教育の仕方や接し方などによっても自己肯定感は大きく左右されます。
さて、自己肯定感が低い子どもにはどういった特徴が見られるのでしょうか。
①自分自身と他人を比較しがち
人間は誰でも長所と短所があり、自分自身の長所を肯定したり認めたりすることは簡単です。
しかし、自己肯定感の低い子どもは、自分自身と他人とを比較してしまい、特に短所がよく目につくようになります。
たとえば、「◯◯さんはテストで80点をとったのに、自分は60点しかとれなかった。だから自分はダメだ」といったように、自己嫌悪に陥ることが少なくありません。
②周囲の目を気にしがち
自己肯定感が低い子どもは、自分で自分を認めてあげることができないため、周囲から良い評価を得ることで安心する傾向が見られます。
あまりにも周囲の目を気にしすぎてしまうと、自分自身を押し殺してまで「良い自分」を演じようとする傾向も見られます。
その結果、自分の意見や考えに自信をもてなくなり、周囲に流されやすくなることもあるのです。
③失敗を過度に恐れる傾向がある
自己肯定感が低い子どもは、少しのミスや間違いでも自己嫌悪に陥りやすく、失敗を過度に恐れる傾向が見られます。
特に、新しいことにチャレンジする際に失敗はつきものですが、自己肯定感が低いと、これ以上自分を嫌いになりたくないと感じ、新しいことに挑戦する意欲すらなくなることもあります。
▶自己肯定感とは?|意味や似ている言葉との違いをわかりやすく解説
自己肯定感が低い子どもの原因が親といわれる理由

自己肯定感が低くなる理由のひとつとして、育った環境が挙げられることがあります。
なかでも親から受ける影響は大きく、子どもへの接し方ひとつで自己肯定感が高くなることもあれば、低くなることもあるのです。
近年、「毒親」という言葉を目にする機会が増えてきました。
子どもに対して悪影響を及ぼす、その名の通り「毒」のような存在の親のことを指します。
たとえば、子どもの考えや個性を一切認めることなく否定し続けてしまうと、子どもは「自分は悪い人間なんだ」と感じるようになり、自分に自信がもてなくなってしまいます。
親としては、立派な子どもに育ってほしいと願うあまり、このような行動をするケースもありますが、子どもにしてみれば自分の存在そのものを全否定されているような感覚になるでしょう。
子どもは親を選ぶことができないことから、自己肯定感が高くなるのも低くなるのも親次第であり、「親ガチャ」という言葉で表現されることもあります。
子どもの自己肯定感に強く関わるのは父親と母親どちらか?
かつての日本では、父親が働きに出て家計を支え、母親が専業主婦として子育てや家事に専念するという家庭が一般的でした。
しかし、昨今では共働き世帯が当たり前となり、子育ても母親と父親が協力して取り組むという考えが一般的となっています。
子どもの自己肯定感は、子育てのなかで子どもとコミュニケーションをとる時間が多い親ほど影響を与えやすいといえるでしょう。
そのため、父親と母親のどちらが子どもの自己肯定感に影響を与えやすい、と一概に判断できるものではありません。
▶︎セルフラブとはどんな意味?自分を愛す方法や自己肯定感との違いを解説
自己肯定感が低い子供が成長するとどうなってしまうのか

幼少期や学生のうちは自己肯定感が低くても、大人になるにつれて自分に自信がもてるようになり、自己肯定感が高くなっていくだろうと考える親もいるかもしれません。
実際に、幼少期に厳しいしつけを受けたものの、大人になってからは自己肯定感を取り戻し、立派に成長する人も少なくありません。
しかし、あまりにも厳しすぎるしつけをしてしまうと、自己肯定感が低いまま子どもが成長してしまうことがあるのです。
自己肯定感が低い状態で成人すると、ものごとを自分で決められなかったり、他者とコミュニケーションをとることに恐怖を覚えたりすることもあります。
その結果、人付き合いに苦手意識をもつようになり、周囲から孤立してしまう人も出てくるでしょう。
また、自分に自信がもてないため就職をしても仕事についていけず、充実した社会人生活が送れないといった事態になることも考えられます。
▶︎ 【怒りを抑える】アンガーマネジメントのやり方・テクニックをご紹介!
自己肯定感を下げてしまうかもしれない親の発言や行動

親であれば誰しもが自分の子どもには立派に育ってほしいと願うものです。
しかし、親が良かれと思ってとった行動や言葉が、子どもにとっては思いのほかショックに感じ、自己肯定感を下げてしまうこともあります。
具体的にどういった言動が子どもの自己肯定感を下げてしまうのか、いくつか例を出しながら解説しましょう。
「どうしてできないの?」などと責める
大人にしてみれば簡単に見えることでも、子どもにとっては難易度が高いことは数多くあります。
親にしてみれば、なぜ自分の子どもが簡単なことをできないのか苛立ってしまうこともあるでしょう。
しかし、だからといって「どうしてできないの?」といったように責め立ててしまうと、子どもは何もできなくなり自信をなくしてしまいます。
他者と比較する
子どものやる気を引き出すために、良かれと思って他者と比較してしまう親も少なくありません。
たとえば、「◯◯君はテストで90点を取ったんだって」と言った場合に、友達に負けないために努力する子どももいれば、自信をなくしてしまう子どももいます。
また、親自身の幼少期と比較して、「自分は運動が得意だったのに、なぜあなたは苦手なの?」といった言葉も自己肯定感を下げる要因となることがあります。
長所を褒めない
もともとの性格で自己肯定感が低い子どもであっても、良いところを褒めることで自己肯定感が高まっていくことがあります。
しかし、親が子どもを認めようとせず褒める言葉を投げかけないと「自分はダメな子どもだ」と感じるようになり、ますます自己肯定感が下がっていってしまいます。
▶自己肯定感が低い人の原因とは|実はプライドが高い?親のせい?
まとめ
自己肯定感の低い子どもは自分と他者を比較したり、周囲の目を気にしすぎたりする傾向があります。
自己肯定感が低くなる理由には個人の性格も影響しますが、幼少期に親がどのように接してきたかも重要なポイントとなるのです。
厳しいしつけのつもりでとってきた行動が、結果として子どもの自己肯定感を下げることにならないよう、長所を褒めてさらに伸ばすなど、日頃の行動を意識してみましょう。
【怒りを抑える】アンガーマネジメントのテクニックや方法をご紹介!

仕事や日常生活のなかで、ちょっとしたトラブルや自分が思うようにいかなかったとき、怒りの感情が湧いてきてしまう方は少なくありません。
怒りやすい性格が災いすると、周囲から人が離れていってしまうこともあるでしょう。
そこで本記事では、怒りを適切にコントロールするアンガーマネジメントについて、具体的な方法やテクニックを紹介します。
アンガーマネジメントとはなにか?
アンガーマネジメントとは、怒り(アンガー)を適切に管理(マネジメント)しコントロールすることです。
たとえば、部下が指示を聞かなかったり、相手から失礼な言葉を投げかけられたりしたとき、人は誰でも不快な気持ちになり、同時に怒りの感情が湧いてくることがあります。
しかし、感情に身を任せて怒りをあらわにするのではなく適切にコントロールできれば、ビジネスがうまくいったり、良好な人間関係が構築できたりする場合があります。
ただし、怒りというのは必ずしもマイナスの感情ではなく、場面によっては怒りを表したほうが良いこともあるでしょう。
たとえば、自ら立てた目標に対して実績が届かなかったとき、悔しさのあまり自分自身に怒りの感情が湧いてくることもあります。
このような場合、素直に感情を表に出すことで怒りや悔しさが原動力となり、次回は目標の達成に近づくこともあるでしょう。
そのため、アンガーマネジメントとは単に怒りを抑えるという意味ではなく、あくまでも感情をコントロールできるようにするためのトレーニングなのです。
▶︎【ストレス解消】セルフケアとはなにか?意味・種類・方法について解説
怒りの感情を持つのはなぜ?人間が怒るメカニズム

そもそも、私たちに怒りという感情が芽生えるのはなぜなのでしょうか。
アンガーマネジメントを学ぶうえでは、怒りのメカニズムを正しく理解しておく必要があります。
怒りが芽生える仕組みを一言でいえば、「それまで期待していたことや理想、自分のなかの価値観などを裏切られた」と感じた場合に生じる感情といえます。
たとえば、部下は上司の指示を聞くことは当たり前という前提がありますが、上司が出した指示が明らかに誤っていたり、論理的でなかったりすると、それに従わない部下も出てくるでしょう。
このような場合、上司は部下に裏切られたと感じ、怒りの感情が湧いてきます。
一方、部下にしてみれば上司だからといって明らかに誤った指示に従う理由はないと考え、さらに反発心や怒りの感情が芽生えてくることもあります。
このように、怒りという感情の原因を探っていくと、根本は些細な行き違いや理解不足といった場合も珍しくないのです。
▶︎【自己受容】弱くてダメな自分を認めて受け入れるトレーニング方法
「怒る」・「叱る」・「注意する」それぞれの違い

「怒る」に似た行為として、「叱る」や「注意する」といった行為もあります。
これらはどういった違いがあるのでしょうか。
ここではアンガーマネジメントにあたって覚えておくべきポイントを紹介します。
①「怒る」とは
感情をあらわにして不満を吐き出すことを「怒る」といいます。
相手のことは一切考えず、あくまでも自分の感情や主張を最優先にぶつける行為です。
②「叱る」とは
相手が間違った言動をとったときなどに、強い口調で厳しく正しいことを伝える行為を「叱る」といいます。
受け取る側の感じ方はいったん置いておいて、感情に身を任せるのではなく、あくまでも相手のために指導するという点で「怒る」と明確な違いがあります。
③「注意する」とは
「叱る」のように強い言葉ではなく、相手の間違った言動を正すために冷静に言葉で伝えることを「注意する」といいます。
相手のために指導するという点では「叱る」と共通していますが、言葉のトーンや伝え方に大きな違いがあります。
▶︎”自分らしく生きる”とは?|仕事や恋愛で自然体で過ごせる方法を紹介
怒り別タイプ診断
一口に「怒り」の感情といっても、人によってさまざまなタイプが存在します。
大まかに分けると、以下の6タイプが挙げられるでしょう。
- 公明正大タイプ:正義感が強く道徳心が高いため、ルール違反やマナー違反をしている人を見ると怒りが湧いてくる
- 博学多才タイプ:向上心が強く完璧主義で、自分にも他人にも厳しいため、考えや価値観が違う人に対して怒りが湧いてくる
- 威風堂々タイプ:自分に自信をもっている一方、プライドが高いため、自分が低い評価を受けた場合などに怒りが湧いてくる
- 天真爛漫タイプ:自分に正直でストレートに物を言うタイプのため、言動が制限される環境下でストレスや怒りが湧いてくる
- 外柔内剛タイプ:表面上は穏やかだが、強い信念をもっているタイプのため、自分の信念やルールに反した出来事があるとストレスや怒りが湧いてくる
- 用心堅固タイプ:真面目で慎重に行動するタイプで、自分と他人を比較しがちなことから、妬みや怒りの感情を抱きやすい
一般社団法人日本アンガーマネジメント協会では、アンガーマネジメント診断を公開しています。
これは、12個の質問に回答し点数を計算することで、上記で示した6種類の怒り別タイプを診断できるというものです。
怒りを抑えるアンガーマネジメントのやり方・テクニック

怒りという感情を適切にコントロールするといっても、条件反射的に感情が爆発してしまい難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。
そのような方に向けて、怒りをコントロールするための具体的な方法やテクニックを2つ紹介しましょう。
①6秒ルール
アンガーマネジメントのなかでも特に有名なのが、6秒ルールとよばれる方法です。
これはその名の通り、怒りの感情が湧いてきたら条件反射的に反応するのをグッとこらえて、まずは6秒待ってみるというものです。
一定時間、怒りの感情を意識的に抑えることにより、冷静かつ客観的に状況を判断できるようになり、感情的に怒りが爆発するのを抑制できる場合があります。
また、どうしても怒りが収まらない場合でも、条件反射的に反応するのに比べると理性的に自分の意見や主義を伝えられ、建設的なコミュニケーションがとれるはずです。
②その場から離れる
どうしても激しい怒りに駆られ、6秒間待っても怒りがコントロールできそうもない場合には、一時的にその場から離れてみるのも有効な方法です。
たとえば、SNSやチャットなどで第三者から自分を侮辱する発言やメッセージを受け取った場合、即座に反応するのではなく、一旦アプリを閉じて仕事や趣味に取り組んでみましょう。
また、対面で相手に対して怒りの感情が湧いてきたら、一旦トイレなどに立って1人になる時間を設け、冷静になれるよう心がけてみましょう。
▶︎【簡単実践】メディテーション(瞑想)のやり方|マインドフルネスとの違いは?
アンガーマネジメントを習得することでどんなメリットがある?
人間には喜怒哀楽の感情があり、それらを表に出すことは決して悪いことではありません。
しかし、怒りの感情はマイナスにとらえられることが多く、怒りやすい人は他人とコミュニケーションがとりづらかったり、ときにはハラスメント行為とみなされたりすることもあるでしょう。
アンガーマネジメントを習得し、自分自身の怒りを適切にコントロールできるようになれば、円滑な人間関係を構築できるほか、職場でのトラブルも防止できるはずです。
▶︎【ポジティブな自己暗示】アファメーションのやり方・効果について解説
まとめ
怒りをコントロールすると聞くと難しいように感じる方も多いかもしれません。
しかし、今回紹介した6秒ルールや、その場から一時的に離れるというのは比較的簡単にでき、アンガーマネジメントにおいて一定の効果が期待できる方法といえるでしょう。
仕事やプライベートの人間関係に悩んでいたり、ちょっとしたことで怒りやすくなったと感じている方は、ぜひ今回紹介した方法を試してみてはいかがでしょうか。
土地のパワーも恵みに! 唯一無二のオーガニックコスメ
肌や体に良いもの、使い心地が良いもの、気分が上がるもの・・・コスメや美容ツールを上手に取り入れて、Hummingな毎日を送りたい。
美容ライター 荒木奈々さんがおすすめをご紹介します。
いろいろな国や地域のニッチなオーガニックコスメが続々登場

セレクトショップに並んでいない海外オーガニックスキンケアが、ECサイトなどで手軽に入手できる時代。
ニッチなコスメブランドの上陸が今後ますます増えそうですよね。
スキンケアを選ぶ際は肌にどう働きかけてくれるかが重要ですが、オーガニックコスメは物語も奥深く、そこにも興味をそそられます。
そこで今回はその土地柄を生かしたオーガニック&ナチュラルコスメをご紹介。
My select 01:フィンランド流のシンプル ラグジュアリーのヘヌア

世界幸福度指数、5年連続第1位(国連「持続可能な開発ソリューション・ネットワーク(SDSN)」調べ)の国といえば、北欧・フィンランド! そんなフィンランドから今年上陸したのが、オーガニックスキンケアのヘヌアです。
ブランド名のヘヌアとは、大切な人とハグをした時のように、この上なく満たされた感覚を表すフィンランドの方言。
創始者はフィンランドで育った姉妹。キレイになるための化粧品で肌トラブルを起こしたことに疑問を持ち、ナチュラルで高品質なスキンケアを作りはじめたのが、化粧品業界で働いていた妹のイェンニ。
そして複数の企業のCEOを経験していた姉のアヌが経営に加わり、2018年に誕生。
“シンプルなのにラグジュアリー”、“サステナブルこそラグジュアリー”を提唱するヘヌアの製品は、精製水、添加物、シリコン、人工香料、染料などは使用せず、フィンランドをはじめ、北欧で親しまれてきたベリー類や白樺樹液など森のスーパーフードから美容成分を採用しています。
そういえばサウナ大国のフィンランドでは、約2000年前から用いられていたというヴィヒタがありますが、あれは白樺の若い枝葉を束ねたものなんですよね。
体を叩くだけでなく、バスルームにつるしたり、湯船に浮かべたりもするとか。
そんな白樺の樹液は自然の濃縮ビタミンウォーターといわれ、フィンランドでは飲用もされているそうですよ。
ちなみにスキンケアは精製水(水)がもっとも多く含まれていますが、ヘヌアでは精製水ではなく、春先に採取した白樺樹液(バーチサップ)などを使用。
これによって濃い潤いを実現しています。

ヘヌア トナー 100ml ¥12,300/キャンドルウィック
ブランドのスターアイテム「ヘヌア トナー」は、水の代わりに天然白樺樹液やローズウォーターを配合。
さらにセイヨウアカマツの樹皮から採れるパインツリーエキスをブレンド。
肌にハリを与え、生き生きとした輝きをもたらす化粧水は、数々の美容アワードを受賞しています。
「ヘヌア トナー」のような水を使わない化粧水をはじめ、固形シャンプーなどウォーターレス製品は、環境問題の点からも注目を集めてます。
WWFによると、3年後の2025年には、世界人口の3分の2が清潔な飲料水の不足に悩まされるという報告もあるのです。

ヘヌア フェイシャルオイル 15ml ¥14,300/キャンドルウィック
もうひとつの濃厚アイテム「ヘヌア フェイシャルオイル」は、11種の植物オイルが中心の天然成分100%。
フィンランドの食生活にも欠かせない素材を美容成分として用いており、潤いを与えるオーツ麦オイル、肌を落ち着かせるシーバックソーンオイル、色ムラをケアしながら小じわにもアプローチするリンゴンベリーシードオイルなどがメイン成分です。
特にリンゴンベリーはビタミンA、B、C、E、Kに、食物繊維、カルシウムやマグネシウムなどミネラルも豊富に含むスーパーフード。
リンゴンベリー種子由来のオイルには、ターンオーバーをサポートするフルーツ酸なども入っているので、肌にフレッシュな輝きもプラスしてくれます。
本国ではミラクルビタミンオイルという製品名がついているだけあって、「ヘヌア フェイシャルオイル」はオールマイティな手応え。
ライトな感触のオイルは化粧水が乾かないうちになじませるのがおすすめだそうで、よりふっくら、弾力のある肌へと導いてくれます。

環境への優しさを追求したというスタイリッシュなパッケージデザインで、2019年にはヨーロピアンデザインアワードを受賞しているそうです。
再生紙で作られた外箱は緩衝材要らず、1枚に広がる仕様なので捨てるときに煩わしさがありません。
フィンランドはSDGs達成度ランキング1位(ドイツ最大財団のベルテルスマン財団と持続可能な開発ソリューション・ネットワーク(SDSN)2021年発表)の評価も得ていますよね。
ヘヌアではフィンランド国内で製造、すべての製品がエコサート認証と動物実験を行わないプログラムのリーピングバニー認証を取得しています。
また故郷フィンランドへの恩返しも積極的で、バルト海の環境保全に取り組むジョン・ヌルミネン財団への寄付なども行っているそうです。
My select 02:お茶で洗う! 台湾の伝統を再発掘した茶籽堂

韓国コスメに続いて、台湾コスメの人気も上々。
“体を冷やさないために白湯を飲む”“自然を大切にする”など、身体や環境を大切にする文化が根付いている台湾発のコスメは、肌や環境に優しいことがお約束。
そのため環境に配慮したパッケージ、NO動物実験を掲げるヴィーガン商品がもともと多いらしいのです。
また、若い起業家の活躍も目立つ台湾コスメ。
台湾の伝統を守りつつ、「若い世代がつくる新しいコスメ」はどれも斬新で眩しいです。
日本未発売・未上陸のブランドも多数、ショップ数32,000点以上という、台湾発・アジア最大級のグローバルサイトのピンコイで見つけたのが茶籽堂(チャズタン)。
「土地の良さを広めること」を使命として、お茶の実(茶籽)を特徴成分に。台湾などで古くから伝わるものの廃れがちだった「お茶で洗う」という文化に着目したり、台湾の苦茶油文化の発展にも努めているブランドです。
日本でいうところの米とぎ汁!? 茶籽堂は創設者の父が、家族がお茶の粉で食器を洗っていたときにもっと使いやすい商品を作ってあげたい、ということから開発がスタート。
現在は台湾に自社農園を3か所持ち、無農薬で茶の実や植物を栽培しています。
 茶籽堂 肖楠葉ハンドソープ 330ml ¥3,290/ピンコイ(※価格は為替レートにより変動する場合があります)
茶籽堂 肖楠葉ハンドソープ 330ml ¥3,290/ピンコイ(※価格は為替レートにより変動する場合があります)
ソープ類には台湾産の肖楠葉(しょうなんは)エキスも配合されています。
ハンドソープはラベンダー、コリアンダーシード、パチョリ、ジュニパーベリーのエッセンシャルオイルのいい香りもポイント。
すっきりとした洗浄と同時に、肌の潤いバランスを整えてくれます。
 茶籽堂 水芙蓉ハンドクリーム 30ml ¥2,870/ピンコイ(※価格は為替レートにより変動する場合があります)
茶籽堂 水芙蓉ハンドクリーム 30ml ¥2,870/ピンコイ(※価格は為替レートにより変動する場合があります)
ハンドクリームも充実していて、肌タイプ×なりたい別に4種。
「水芙蓉ハンドクリーム」は、苦茶油やローズヒップ種子など6種の植物オイルと3種の植物エキスを配合。
肌を柔らかく整えながら、明るい手元へ。
年々クオリティが高くなっているホテルアメニティですが、茶籽堂も台湾のホテルのアメニティに採用されているそうです。
茶籽堂/ピンコイ
https://jp.pinkoi.com/store/chatzutang
世界にはまだまだ知らないオーガニックコスメが。いろいろ探してみるのも楽しいはず!
大切な人と快適な着心地をシェア。
「UNOHA」からユニセックスラインが登場
グローバルスポーツメーカー、アシックスより誕生したライフスタイルブランド「UNOHA」(ウノハ)から、ブランド初のユニセックスラインが登場。機能性ウエアからラウンジウエアまで、秋の行楽シーズンに大活躍のアイテムをご紹介します。
大切な人とシェアしたいユニセックスライン

今秋UNOHAでは個性や内面の美しさに着目し、内面の平等“Spirit of Equality”をテーマにユニセックスラインを展開。果てしなく広く繋がりゆく空や海からインスピレーションを得て、ディープブルーをキーカラーとしたアイテムがラインナップ。
家族やパートナーと洋服をシェアする楽しさの背景には、環境に配慮した地球に優しいものづくりがあります。
着こなしの幅が広がる2WAYジャケット

ジャケット¥36,300、トップス¥9,900、パンツ¥19,800

こちらはペットボトル由来のリサイクルポリエステルを使用したツイル素材のジャケット。マットな生地感のソリッド面と中わた入りキルティング面の2WAY仕様で、その日の気分に合わせて楽しめます。ストレッチ性を備えた快適な着用感とモダンな佇まいが魅力的。
インディゴカラーの洗練セットアップ

ジャケット¥23,100、パンツ¥24,200、トップス¥9,900、シューズ¥15,400
紡績工場で発生する大量の繊維くず(落ちわた)を再生した倉敷のデニムファクトリーの生地を約98%採用したデニムシャツジャケット、セットアップで着られるスリムフィットデニムパンツには厳しい基準のもと栽培されたオーガニック由来の原料を90%以上使用。深めのポケット付きで、ウエストに付属した2つのボタンによりサイズ調節が可能です。生地段階でのバイオ加工によって調整されたインディゴカラーで、男女問わず使いやすいデザインに。
上質なワンマイルウェアは大人のマストアイテム

トップス¥9,900、パンツ¥19,800
何枚あっても嬉しいTシャツは天竺素材を使用し、柔らかく優しい肌触り。後ろ身頃の切替デザインが洗練された印象を与えます。ウエストがドローストリング仕様になったリラックスフィットパンツは、体を締め付けない快適な穿き心地でありながら、きれいめに着こなせます。
リサイクルレザーのクラシックムードなシューズ

シューズ¥15,400
国内外で支持されるアシックスのシューズ。UNOHAでは、履き心地の良さはもちろん、タウンユースしやすい上品なデザインのシューズが揃います。
写真はアッパーにレザーの端材を使用したソフトな質感のリサイクルレザーと、クラシカルなムード漂うガムソールが特徴のスケートボードタイプ。インナーソール表面はコルク素材になっており、ナチュラルなムードに。ゴールドのチップをあしらったスペアシューレースが付属しています。
10月1日(土)~10日(月・祝)の期間に、代官山 蔦屋書店2号館 1 階の建築・デザインフロアにて、10月5日(水)~11日(火)の期間は、大阪タカシマヤ 1 階 グッドショックプレイスにてユニセックスラインをはじめメインコレクションの新作や定番コレクションが並ぶポップアップストアが開催予定。
ブランド名の「UNOHA」には、卯の花のように人々のココロとカラダのバランスを大切に、日常に寄り添いながらファッションやライフスタイルを提供するという想いが込められています。ユニセックスラインが加わり、幅広いライフスタイルに適応するUNOHAの世界観をぜひ体験してみて。
向かうべき場所へ、進む強さを持って【山口乃々華 / コトノハ日和 vol.08】
言葉があるから伝えられること、伝わること。そこから広がっていく思考、癒し、つながり、希望、愛情・・・深くて力強いもの。女優 山口乃々華が、心に舞い落ちてきた“コトノハ(言葉)”を拾い集めて、じっくりと見つめ、ゆっくりと味わい、思いのままに綴っていく連載。さあ、一緒に元気になりましょう。
顔をいつも太陽のほうにむけていて。影なんて見ていることはないわ。

9月が終わろうとしてる。私は今、ミュージカル『SERI〜ひとつのいのち』の絶賛稽古中である。10月6日から東京@博品館劇場にて、10月22日から大阪@松下IMPホールにて公演するミュージカルなのだが、私にとっては初の主演を務めさせていただく大事な大事な作品。
毎日、カンパニーのみなさんと心、声、体を合わせて、初日に向けて積み上げている。少しだけ作品について話をさせてもらうと、私が演じる千璃という役は、両眼性無眼球症と知的障害を抱えた女の子。そんな子供を授かった両親との家族3人の物語である。それ以外にもさまざまな問題があり、乗り越えなければならない壁がたくさんあるのだが・・・。
何よりもこの作品には原作があり、実話である。そのことを考えながら観ていただくと、あまりに大変な現実に、心がポキッと折れそうで、目を背けたくなるようなシーンもあると思う。毎日がジェットコースターのように不安定。止まりたくても止まれない。涙を流しながらも、絶対に目を逸らさずに家族みんなで進み続ける姿から、生きていく強さをきっと感じてもらえるはず。そんな運命を背負った家族の日々を体験してもらえるのではないか、と思う。ぜひ、劇場でお会いしましょう。しっかり宣伝(笑)。
今まで私は、「言葉」の力や「言葉」が教えてくれるものの多さに何度も助けられてきた。真夜中、友達との電話であーだこーだおしゃべりして悩みが軽くなっていくこと、背中を押されるような言葉をそっとかけてくれた人を大切に思ったり、大好きな漫画を何回も読んだり、集中すればするほど鮮明な物語を私に見せてくれた本など。どれをとってもたくさんの言葉たちがある。
今の私に響く「言葉」を思い浮かべると、顔を合わせて話していたことより、スマホを通して聴く友人の声や、活字になったメッセージを読んだり、何かを通して伝わってきたもののほうが、印象強く残っている気がする。
もしかしたら会って話しているときは何を言ってくれたかよりも、もっと他のことに気を取られていたのかもしれない。例えば、視線や仕草、服装とか、その場の空気も。あとは、何を食べているのか、飲んでいるか、とか。他のことを考えず、言葉だけに集中できたことってあんまりない。だから、「言葉」が「言葉」だけのまま伝わってくると、余計なものなく理解できるのかもしれない。
話は戻るが、千璃を演じているとき、目からの情報はほぼないに等しく、言葉を話すことなく、想いを言葉で伝えることもほぼしない。私が演じさせてもらう時間、それを役として生きるというのならば、千璃ちゃんの一生に比べたらほんの少しの間だけれど、その世界を生きさせてもらっている。普段の私よりも、どこか広く全身で捉えて湧き上がってくる想いには、無駄なものが入り込んでこないからか、心地よい。いつもより情報を得る手段は少ないのに、感じるものが多い。そんな自分の心を私は疑っていない。
その経験からか、五感すべてを当たり前に使いながら交わす言葉より、向こう側を想像し、言葉に集中する方がより心の深いところまで理解が行き届く気がしている。じっくりと自分に溶かしていこうとする感覚は嫌な言葉でない限り、すんなりと染みわたる。
久しぶりに会う友人と面と向かって話しているとき、いろいろなところに意識が散ってしまう。それは、話がつまらなくて飽きている・・・とかそういうことではなく、目に入った情報からついいろんなことを考え、思ってしまう。相手のふとした視線の動きから、考えを汲み取ってしまって、少しずつ神経が削れて、疲れる。その人や場に慣れるまで、以前よりも時間がかかるようになった気はする。それが良いのか悪いのかわからないけれど。
役を演じるにあたって勉強になるかもしれないな、と思って読んだヘレン・ケラーの自伝漫画があった。それは、小学校の図書室にあったようなもの。たぶん小学生のときに読んだ。
そんな、ヘレン・ケラーが残した言葉で、何かいいものないかなと思って調べてみたら、たくさんの素晴らしい言葉があった。
そのなかで、私の心に響いた2つの言葉。
「顔をいつも太陽のほうにむけていて。影なんて見ていることはないわ」
前向きに生きなさいよ!と背中を押してくれるようなこの言葉。ついつい、影・・・自分の心の落ち込みや後悔に飲み込まれ自信をなくしてしまうけれど、向かうべき場所へ、進む強さを持っていられそう。
太陽はいつも空高くにある。顔を上げて、堂々と進んでいく姿を写す影は、自分ではなく、他の誰かに見てもらえたら、それでいいのかもしれない。
「はじめはとても難しいことも、続けていけば簡単になります」
続けていけばいつかはきっと、簡単になる。と世界を努力で切り拓いていったヘレン・ケラーの言葉には、説得力がある。
私も、挑戦することをいつまでも恐れないでいたいと思う。
そんなにすぐに時は経たない。ぼーっとしていたら、夜になっているけど、頑張っているときは案外時間はゆっくり過ぎてくれるな、と感じている。「続ける」ということは「時間をかける」ということ。焦らずに一つひとつを十分に確かめながら続けていきたい。
・・・・・・
なんと、今回でこの連載「コトノハ日和」はおしまい。たったの8回でしたが、毎月自分と向き合ういい機会でした。
今年も残すところあと3ヵ月。これを読んでくださっているあなたも、そして私も毎日毎日、心がしっかりと動き、幸せだなと感じる日々でありますように。
うれしくて飛び跳ねるような気持ちの先に、暗闇のトンネルが思ったよりもながーくあったとしても、それも全部いいと思えるもんだな、と思う。
生きてるな、幸せだな、と。
なんて、今年を総括するにはまだ少し早いけれど、今日まで過ぎた日々を思うと、やっぱり満ちていた、と思う。
それではまた会う日まで。
山口乃々華

Profile
山口乃々華(やまぐちののか)
2014年からE-girls主演のオムニバスドラマ「恋文日和」第7話にて主演を務め女優業をスタート。映画『イタズラなKiss THE MOVIE』シリーズ、ドラマ・映画『HiGH & LOW』シリーズほか、2020年には『私がモテてどうすんだ』のヒロイン役など、数々の作品に出演。 2020年末までE-girlsとしての活動を経て、2021年より女優業として本格的に活動を開始。2021年3月、初のミュージカル『INTERVIEW~お願い、誰か助けて~』、同8月にはミュージカル『ジェイミー』、2022年3~4月はミュージカル『あなたの初恋探します』でヒロインを演じた。ドラマ「ビッ友×戦士 キラメキパワーズ」(テレビ東京系)に出演。書籍『ののペディア 心の記憶』(幻冬舎文庫)も好評で、文章を書くことも好き。2022年10月にはconSept Musical Drama #7『SERI〜ひとつのいのち』でミュージカル初主演を務める。
https://www.ldh.co.jp/management/yamaguchi_n
Instagram @yamaguchi_nonoka_official
森カンナ「たった一人で自分に吹く爆風を受ける」【連載 / ごきげんなさい vol.12】
俳優 森カンナさんが日々の生活のなかで見つけたこと、感じた想いを綴る連載エッセイ「ごきげんなさい」。自分を“ごきげん”にするためのヒントを探しましょう。

「show認欲求」
私が一年のなかで一番好きな季節。秋がやってくる。秋刀魚、牡蠣、梨、柿、松茸、葡萄、栗。くぅー。たまらん。四季があって旬な食べ物があるってなんて幸せなことなのだ。
あー、温泉にも行きたいなぁ。サウナにも行きたいなぁ。あっ美術館とかもゆっくり周りたいなぁ。と、あれこれやりたいことがぽんぽんと浮かんでくる。
というのも、数日前、また一つの作品を無事に撮り終わり、達成感で絶賛ホッとしてる週間だ。
しばらくはSNSを封鎖し、台詞を覚えるのに集中していた。SNS封鎖は外からの情報も入ってこないし、携帯との距離も置けるのでとてもいい。
兎にも角にもSNS時代! 私が通うご飯屋さんのお父ちゃんも、SNS反対派だったのに今や写真が映えるポイントを考えていたり、こないだはドラマの宣伝で音楽に合わせて、フリを踊ってみたりもした(照)。
とにかくSNSを有効活用しよう!の時代だ。
だが、一方でプライベートでのSNS疲れをしている人が増えてきていると思う。私の友人も忙しいときに、友達がみんなで楽しく遊んでいるインスタを見ては凹んでいた。のちに、インスタを卒業したら随分と楽になったらしい(笑)。
いやぁSNSとの距離ってとても難しい。私は最近何をあげていいのか分からなくて、絶賛迷子気味である。
そんなSNS迷子な私だけれど最近少し思うことがある。
例えば、自分は今満たされている。自分は愛されている。自分にはお金にも時間にも余裕がある。自分はこんなにも頑張っている。みたいな、こういったいわゆる分かりやすい「幸せ」とか「努力」みたいなことを他人に託してしまっている気がする。
つまり、本来「自分」がどう思うか、感じるかだけでいいのに、家族、周りの友達、フォロワーがどう思うか、彼らに認められること、が自分のすべてになっている人が多い気がする。
キラキラなSNSばかりを見ていると、見失ってしまうのも良く分かるが。
コロナ前は一人で海外旅行に行ったりしていたのだが、その旅で出会う目が飛び出るかと思うくらいの美味しい食べ物、凄い景色、美術館で鳥肌が立つような作品に出合ったときに、誰ともシェアせず、たった一人で自分に吹く爆風を受けるあの感覚は忘れない。
誰にもシェアせず、誰の目も気にせず、まずは目の前の物、人と向き合って自分がどう感じるか。まず最初にたった一人で感じる何かを大切にしていきたいと思う。
話は変われど、こちらの連載「ごきげんなさい」全12回、1年間続けてきたHummingでの連載が今回でラストになります。
そして、そして、GINGERにお引越しします!(詳細はまたお知らせします)
場所は変われど、これからもどうぞ宜しく。
それではみなさん、ごきげんなさい!

最近見つけた近所の魚屋さんが最高で、魚ばかり食べている。天然のモノばかりでお刺身もふわふわ。やはりどんな美味しい店のご飯より、家で食べるご飯が一番美味しい。
Profile
森カンナ(もりかんな)
俳優。富山県出身。映画やドラマなど数々の作品に出演。2021年には、自身初舞台となった蓬莱竜太演出『昼下がりの思春期たちは漂う狼のようだ』で、600人のなかからオーディションによって選ばれ、観客を魅了した。2022年は、フジテレビ4月期月9ドラマ『元彼の遺言状』1話・2話にゲスト出演、フジテレビ2週連続ドラマ『ブラック/クロウズ~roppongi underground~』にレギュラー出演、7月期カンテレ月10ドラマ『魔法のリノベ』の1話にゲスト出演した。
https://kannamori.com/
Instagram @kanna_mori
◆【ポジティブな自己暗示】アファメーションのやり方・効果について解説
◆【簡単実践】メディテーション(瞑想)のやり方|マインドフルネスとの違いは?
◆ネガティブな人でもできる自己肯定感を高める方法や習慣とは?
畑でいのちが産み出され、育まれる【イケてる農家「イケベジ」の農日誌Vol.4】
新潟県・佐渡島と兵庫県・淡路島を中心に自然栽培農家を営む「イケベジ」。今回はイケベジ発起人の一人、いもたろうさんが畑を営むことで体験したこと、学んだことをお届けします。今回はイケベジが行うリトリート「育ベジ」のおはなし。
共に育むという感覚を思い出せる場「育ベジ」

「育ベジ」。私たちがイケベジでの活動をスタートしてからずっと大切にし続けている「育む」という在り方から生まれた、イケベジならではのリトリートです。今までのような企画イベントにある参加者と主催者として互いが関わるのではなく、全員が参加者であることで「共に育む」という感覚を思い出せる場を目指しています。そのなかで自然と関わり、畑に触れることで新たな出来事やご縁が生まれていく流れは毎回違ってとても面白い展開ばかりです。
来月も佐渡島で育ベジを実施する予定です。仲間が約半年に渡り、育んでくれたお米たちが収穫のときを迎えます。たった一粒からたくさんの粒が実るお米の在り方は本当に美しいです。それはお米を主食としてきた日本人が大切にしてきた在り方が詰まってるともいえそうです。ぜひ自身の手で稲刈りを体験して欲しいなと思います。

写真は今月の始めに、僕らが育むホーリーバジル畑での「育ベジ」の様子です。初めましての方もいらっしゃったので、僕も含め、少し緊張感があるなかで始まったのですが、畑に訪れた瞬間から自然と緊張がなくなりました。気づいたら大地の上で安らぎ、自由に自分自身を表現する皆さんの姿がとても印象的でした。なかには持ってきた楽器を奏でたり、自然音に身を委ねながらアカペラを披露してくれたり、畑が豊かさに溢れていました。
それぞれがその瞬間、産み出したものを素直に放っていく姿は美しかったです。
目には見えないですが、畑を通してありのままのいのちに触れ、きっと心のなかの滞りが抜けて巡り出したんだと思いました。
ホーリーバジルも間違いなく喜んでいることでしょう。育ベジで改めて畑をやってきて良かったなと思えたのは個人的にも嬉しかったです。
畑とはいのちが産み出され、育まれている「場」

畑とはいのちが産み出され、育まれている「場」です。そこに私たちは微力ながらその巡り、つまり「循環」に携わらせていただくことで私たち自身も常に産み出し、育んでいることに気付かされます。私たちも自然と変わらない、いのちを産み出し育む美しい存在なのです。
いのちへの信頼があると、どんな生きものにも存在する揺らぎ、動きに逆らうことなく生きることができると思います。揺らぎ、動きというのは、私たちの意識に関わらず営み続けている生命活動のことです。例えば心臓は動き続けていますし、呼吸をし続けることで空気が出たり、入ったりしています。水も流れていないと腐敗します。エネルギーも形を変えながら、巡り続けています。心に浮かぶ気持ちも変わりゆくと思います。暮らしも住む場所や人間関係で変わりますよね。言い出したらキリがないのですが、いのちは何事も変わりゆくなかで最善、最適化してくれます。目的や理想があっても良いですが、それに執着することなく、時に変わり続けても良いんだと自分自身を許し、受け入れてみてください。
自分のいのちに委ね生きることは自分自身を信頼すること

産み出された場は豊かさを生み、そして豊かさは共に育まれていく。そしてそれは一つのいのちから始まる。私たちそれぞれが自分のいのちを根っこから信頼して、自身が持っているリズムを受け入れて生きていきましょう!
忘れそうになったらいつでも思い出しにイケベジ畑へ来てくださいね。「育ベジ」の情報もInstagramに掲載予定です。
Profile
いもたろう
イケベジ発起人、育み人。淡路島で「農」を通じて多くの「いのち」に触れる体験から、人も同じようにありのままで生きていくことで豊かになれると思うようになる。2021年春、友人とともに人も自然も共に育む場「イケベジ」をスタート。大学での講演活動や「命の繋がり・巡り」をテーマにした「育ベジRetreat」などありのままで生きる世界を広める活動を続けている。実は料理好きで、マクロビを取り入れた「いも飯」はイケベジの人気コンテンツ。
https://ikevege.com/
見えない価値に光を。「M_(エムアンダーバー)」が届けるエシカルファッション
アパレル業界では「大量生産・大量消費・大量廃棄」が社会的に問題提起されています。こうした問題に目を向け、生産から廃棄までのサイクルのなかで、環境や労働問題も含めた広い視野を持ち、サステナビリティの実現を目指す企業やブランドが増えています。
今回ご紹介するのは人気ブランド、マウジーから誕生した生産背景や素材にこだわり、作り手の想いを大切にする大人の女性へ向けた新ライン「M_(エム アンダーバー)」です。
うわべだけではない、見えない価値にスポットを当てる服作り

ブランド名にある下線(アンダーバー)は、強調する言葉に引かれる記号。MOUSSY(=M)の先にある“空白”の強調を意味しています。SDGsにおける「つくる責任」に向き合い、廃棄物の削減や持続可能な開発、自然と調和したライフスタイルの情報、それらに意識を持てる未来を目指して誕生しました。
目に見える服のデザインや価格だけでなく、生産背景や作り手の想いなど、見えにくいところにスポットを当てる“see the unseen”をテーマに、オーガニックコットンやノンミュールジングウール、リサイクル原料を使用するなど環境を配慮した素材を選択。森林保全や水質保全につながる製品作りに注力しています。
トレンドにとらわれない次世代のスタンダード
着心地の良さだけでなく、シンプルでありながらひとクセあるデザインが人気の秘訣。10代から20代の頃にマウジーを愛用していたお客様が年齢を重ね、M_の服を手に取ってくださっているそう。
学びの秋にSDGsをもっと身近に。京都「GOOD NATURE STATION」がSDGsツアーをスタート!
9月25日(日)は、国連で持続可能な開発目標SDGsが採択された記念日。SDGsという言葉は知っていても、具体的にどのような目標が掲げられているのか、私たちが日常的にできることは何だろう・・・と疑問を持っている人も少なくないのではないでしょうか。今回はSDGsの項目について学び、より身近なものにできる機会をご紹介します。
体験を通して理解を深めるSDGs

“信じられるものだけを、美味しく、楽しく。人も地球も元気にする「GOOD NATURE」なモノ・コトが集まる場所” というコンセプトのもと、京都中心部の河原町に誕生した複合型商業施設「GOOD NATURE STATION」。
同施設内にあるホテル「GOOD NATURE HOTEL KYOTO」は利用者のウェルビーイングを重視するWELL認証v1、建物設計の観点から環境資源の持続性を評価するLEED認証を、世界で唯一、ホテル版評価基準による同時取得を実現。ホテルを含む施設全体でサステナブルな取り組みや建築など、隅々まで“GOOD NATURE”に向けたこだわりが溢れています。
そんな「GOOD NATURE STATION」で「ひとりひとりに本当の意味でSDGsを“自分ごと化”してほしい」という思いから、SDGs採択記念日に合わせて完全予約制のSDGsツアーとして本格的に始動。

SDGsツアーでは複合型商業施設「GOOD NATURE STATION」の1F〜4Fで、施設館長やホテル支配人、専属のコンダクターが実際に行われているサステナブルな事例を解説。一般公開されていないコンポスト見学や、商品作りの裏話まで、ここでしか味わえないコンテンツが目白押しです。
「京都観光ついでに少しだけ」「地元京都市民としてじっくり知る」「宿泊ついでに施設をゆっくり回りたい」などお客様の要望に合わせ、Aプラン(90分/1人¥6,000)、Bプラン(60分/1人¥4,000)を用意。Aプランでは、オリジナルのフェアトレードカカオ使用のチョコレートとカカオティーの試食も。両プランともにお土産付き。
参加には実施日の60日前までの予約をお忘れなく。「GOOD NATURE HOTEL KYOTO」に宿泊の際はもちろん、新たな気付きや学びを得る旅を楽しんでみてはいかがでしょうか。
GOOD NATURE STATION
https://goodnaturestation.com/
穏やかでいたい!そんなときのブレイクアイテムとは?
肌や体に良いもの、使い心地が良いもの、気分が上がるもの・・・コスメや美容ツールを上手に取り入れて、Hummingな毎日を送りたい。美容ライター 荒木奈々さんがおすすめをご紹介します。
気分を落ち着かせる香りや成分に頼ってみる!

日々のストレス、どうやって発散していますか? 意識していても、イライラ、モヤモヤ、落ち着かないといったセンシティブな状態に陥ることってありますよね。ストレスを溜めすぎないためにも、ちょこちょこブレイクしなければ! そこでお試ししたいのが、やはりビューティ関連のアイテム。コーヒーを飲むように、いい香りのコスメや機能派成分のアイテムでちょっとひと息。毎日のいろんなシーンに取り入れて、心も肌も穏やかさをキープしたいのです。
My select 01:シゲタ パリのメディテーションキットで自分自身を取り戻す!

ナチュラル系のコスメを使ったことがないという友人にSHIGETA PARIS(シゲタ パリ)のオイルセラムをプレゼントしたら、「香りがすごくいいし、肌にハリと明るさが戻った気がする」と喜ばれたことがあります。シゲタ パリはナチュラルコスメでありながら、トリートメント効果も高く、何より人を笑顔にするブランド。そう気付いてから、元気がほしいときはここへ!
シゲタ パリはセラピストのCHICO SHIGETAさんがプロデュースするクリーンビューティーブランド。パーソナルコーチとしてフランスで活躍しているときに独自のメソッドを開発、パーソナルセッションで使用していた独自のエッセンシャルオイルを自宅でも使いたいという要望から、2006年にオイルを製品化したのがはじまりです。
「驚きのある、オーガニック」をメッセージとするシゲタ パリ。限りなくナチュラルであることにこだわりながら、フランス国立科学技術センターと共同でオーガニック有効成分の研究にも努め、独自のオーガニック成分特許の取得なども実現しています。
現在スキンケア、メイクなど100以上の製品が用意されていますが、ブランドのマスターピースはCHICOさんオリジナルブレンドのエッセンシャルオイル! オイル=ベタつくというイメージを覆すべく、ヘーゼルナッツやマカダミアナッツなど、美容効果とライトな感触にこだわったオイルを厳選。#頭痛、#目の疲れ、#首・肩のコリ、#疲れ・・・など、お悩みに合わせて、オイル×メソッドでアプローチできるのもこのブランドの特徴です。
新商品は「トウキョウシャイン メディテーションキット」。長引くコロナ禍で不安を抱えているユーザーさんが多いこと、またメディテーションというようにゆっくりと穏やかな時間を持ちたいという人にも向けて作られたのが、シャワーミストとロールオンタイプのエッセンシャルオイルのリチュアルケアです。
2品の香りは共通で、瞑想の質を高めるフランキンセンスとサンダルウッド、マインドを満たしてくれるシダーウッド、リラクゼーションを促すクラリセージといったこだわりの調合。

ミストは顔や空間にシュッとスプレー。シャワーというようにマイナスイオンに包まれるかのようで、目がパッと覚める! 淀んだ気持ちや空気も浄化してくれそうです。肌を落ち着かせたいときのリフレッシャーとしてもおすすめ。

ロールオンタイプのオイルは、まず胸のあたりにオン。さらに手のひらに円を描くようにつけてから、手首にもコロコロと塗布。香りを嗅ぎながら呼吸すれば、深いリラクゼーションも叶えてくれます。
自分と向き合う瞑想タイムもサポートするキット。瞑想といってもいろいろあるそうで、おすすめは大好きな人をイメージしながらのメディテーション。するとハッピーで満たされるそう。
最適なお手入れ時間というのは特になく、続けることのほうが大事とのことなので、私は仕事中の合間に。
シゲタ パリ
https://shigetaparis.jp/
My select 02:CBD ブランの美味しいCBDですっきり

オーガニックやナチュラルコスメ好きならよく耳にしているはず。欧米で注目を集め、数年前から日本のビューティ界でもトレンドとなっている成分がCBD(カンナビジオール)です。ヘンプ(麻)特有のカンナビノイドという成分の1つで、医療の分野での研究も盛ん。世界中でCBDの有効性が報告されており、CBDを含むコスメやサプリメント、お菓子類なども増えていますよね。CBD は身体や心のECS(エンドカンナビノイドシステム)へのアプローチが期待されています。
ECS(エンドカンナビノイドシステム)とは、人間の身体に備わっている身体と心の調整機能で、体内のホメオスタシスを維持しようとする機能です。すなわち、ECSをうまく機能させることで、認知機能、感情、不安、食欲などを正常に保つ効果が期待されています。(CBD ブランの資料より)
ストレス緩和やリラックス作用に優れているといわれるCBD。ただ製品の種類も増え、手軽に購入できるようになっているので、その安全性や効果はしっかり見極めたいところです。
百貨店のイベントなどで今注目を集めているCBDブランドが、CBD ブラン。スイスの成分分析認証機関を経て、厚生労働省で輸入許可を得たTHC(テトラヒドロカンナビノール)を一切含まないCBDのみを使用するメイドインジャパンブランドで、現在はCBDオイルとCBDグミの2品を展開中。
CBDオイルは舌下に数滴垂らして摂取しますが、私の場合、はじめてのCBDオイルが苦く感じ、苦手に。CBD ブランのオイルは見た目が可愛らしいですし、味にもこだわっているとのこと。レモンフレーバーで美味しいのです。

CBDの摂取も肌のお手入れと同様に継続が大事。CBD ブランではその効果を感じてもらったうえで、継続使用してほしいという想いから、オイルは1本あたり15%(1,500mg)、グミは一粒に40mgという高い含有量にもこだわっています。
オイルとグミ、両方とも舌の裏に1~2分ほど溜めておいて。そうすることによって吸収が早まるらしいのです。いつでもどこでも食べられるグミはグレープとピーチの2種類が用意されています。私は甘酸っぱいグレープが好み。

ブランド名の「blanc(ブラン)」は、空白や白という意味があるフランス語。
マルチタスクで脳がフル稼働、落ち着きたい、余裕を持ちたいというときは、CBD ブランのオイルやグミを!
CBDブラン
https://cbd-blanc.jp/shop
My select 03:エンドカのCBDボディオイルで肌も心も穏やかに

もう1つ、CBDアイテムをご紹介。
CBDオイル界のパイオニアブランドといえば、デンマークで設立されたエンドカ。
「人類にとって有益なナチュラルでオーガニックな良薬を探す旅と研究」を続けていたというエンドカの創業者ヘンリー氏は科学者であり、また彼の家系は最高品質のヘンプの栽培をしていたことから、ヘンプの可能性を発見したというのがヒストリー。
種子や繊維を活用するため、日本などでも古くから栽培されていたヘンプ。そもそもヘンプは土壌を除染する能力が高く、土の良い、悪い、どちらの成分も吸い取る性質があるとか。そこでエンドカでは、“From seeds to shelf(種から店頭まで)”をポリシーに自社農園で栽培。ヘンプの種子から育成し、プロダクトの製造、店頭まですべてのプロセスが自社で管理されています。100%オーガニックな製品で、医療機関などでも利用されているとか。しかも2030年までに、すべての一般家庭に、塩やにんにくと同じレベルまでCBD製品を流通させたいと意欲的。
ヘンプの成熟した茎と種子から特殊な方法で抽出するエンドカのCBD。アイコンのオイルが若い世代を中心に人気のようですが、CBDは乾燥などの刺激から肌を保護する効果も期待されているので、カサカサしやすい今の時期はCBD配合のスキンケアも頼りになりそう。このボディオイルをはじめ、ボディバター、リップクリームなど、エンドカのコスメはオーガニックの国際基準のエコサートを取得済み。

CBD FACE & BODY OILは、CBDをはじめ、オーガニックアプリコットオイル、ベルガモットオイルほか、栄養豊富な食品グレードの成分で構成。ビタミンAやE、オレイン酸を豊富に含んでいるので、刺激から肌を守って、つややかな肌が育めそうです。すっきり感のあるほのかな香り、ライトなオイルテクスチャーはなじみもよく、全身どこでもオン。CBDは睡眠を誘発するという働きもあるそうなので、私は夜のお手入れの最後に使用を。肌と一緒に心のリズムも整えてくれるはず。
「オーガニックを超えて、サステナブルへ」がブランドのポリシー。CBD製品の生産過程で残ったものは牛の餌などに使用、利用できない廃棄物は電機や暖房用のバイオガスに変換するなど、できるだけごみを出さないという独自のグリーンアクションも積極的なブランドです。
ビープル エンドカ
https://store.biople.jp
気分のアップダウンはどうしてもあるもの。だから今、穏やかになれる、ひと息できるアイテムが気になります。
秋を豊かにする草木染のススメ【現代美術家 山本愛子 / 植物と私が語るときvol.4】
染色を中心に自然素材や廃材を使い、ものの持つ土着性や記憶の在り処をテーマとした作品を制作する現代美術家、山本愛子さんの連載 。第4回目は草木染の研究にいそしむ山本さんが、秋がいっそう楽しくなる季節の草木染をご紹介。
実り多き秋の楽しみ
まだ蒸し暑さが残りますが、風が涼しくなってきましたね。秋生まれだからか、四季のなかで秋が1番好きです。考えごとも、染色の制作も、一年のなかで1番よくはかどります。涼しくて快適なこれからの季節はじっくりと物事を考えたり、ものづくりをはじめてみるには絶好の季節。今回はそんな「芸術の秋」にぴったりな草木染の世界を、私の活動のなかから3つご紹介したいと思います。
1.キンモクセイ染め
秋の香りといえばキンモクセイ。キンモクセイには、昔から体内の酸化を防ぐ抗酸化作用があると言われ、食用花として愛されてきました。香りや食、薬用で重宝されているキンモクセイ、実は草木染めでも美しい色に染まります。

こちらは街の公園で剪定されたキンモクセイの葉っぱを区役所からいただいて、染色ワークショップをしたときの様子です。葉っぱを細かくちぎって、鍋でクツクツと煮込み、染料液をつくります。

キンモクセイの色素がたっぷりの染料液に布を入れて、30分ほど煮込みます。

参加者それぞれが持ち寄った古着などが、金木犀の花のように輝かしい黄色が染まりました! 剪定されて通常は捨てられてしまう枝葉が、染色を通して生活を彩ってくれるのです。
もしもご自身の街で捨てられてしまう植物を見かけたら「それください!」と言って草木染めに挑戦してみてはいかがでしょうか。私はよくそうやって植物をゲットしています(笑)!
2.タマネギ染め
涼しくなってきて、鍋やスープ料理の出番が増えてきます。家庭でよく使うタマネギの皮をコツコツためると、草木染が楽しめることをご存知でしょうか。

こちらの写真はタマネギの皮で染めたウールのマフラーです。草木染は動物繊維によく染まる性質を持っているので、ウールやシルクなどはとてもよく染まります。初心者の方は特にシルクが染めやすくてオススメです。
3.庭木をいろいろ染めてみる
庭や近所の植物で草木染をしてみたいと考えたことはあるでしょうか? どんな植物にも色素はあるので、庭木を剪定して草木染を楽しむことができます。
先日とある方から「大切な実家を手放すことになったので、引っ越す前に思い出の庭木で草木染をしたい」というご相談を受け、引っ越し直前のご自宅に伺うという機会がありました。

庭の枝をカットする様子。引っ越し直前なので段ボールがたくさん。(c)Yusuke Ono
記念樹として植えたキンモクセイ、家主の方が大好きなバラなど、思い出の詰まった植物を選んで草木染に挑戦。

煮込んでいる様子。(c)Yusuke Ono
モミジ、バラ、サクラ、ウメ、キンモクセイ・・・思い出がたくさん詰まった植物を煮込んで染めていきます。

染まった布で生まれたカーテン。(c)Yusuke Ono
最終的にはこんなに美しいカーテンが完成! 新居の窓のために染めた布をパッチワークしました。手放すことになった家の庭の草木が、新居を彩ってくれました。お引っ越しで庭は持っていけないけど、庭の思い出を見える形で持っていくことができたと喜んでくれました。
キンモクセイのふとした香りのように。キッチンで生まれるタマネギの皮のように。窓の外のお庭のように。草木染は人にとって身近なものだと私は思っています。これを読んでくれたあなたが、少しでも草木染って面白いなと思ってくれて、植物を見つめる視点がちょっと増えて、この秋をより味わえますように。
日常からトリップできる癒し空間で、身も心も穏やかに!【渡辺知夏子のエシカルスポットNavi. vol.11】
普段の何気ない暮らしのなかで、サステナブルなアクションが出来たら素敵だと思いませんか? エシカルなライフスタイルを提案しているレストランやショップを、自身もウェルビーイングな生活を心掛けているというモデル渡辺知夏子さんがナビゲートする連載。第11回目はイギリス発祥の老舗オーガニックコスメブランド、ニールズヤード レメディーズの表参道本店『NEAL’S YARD GREEN SQUARE(ニールズヤード グリーン スクエア』です。
NEAL’S YARD GREEN SQUARE

なかでも本店の表参道店は、まるでイギリスを訪れたかのような、ニールズヤードレメディーズの世界観を思う存分に体感できる場所。店内に一歩足を踏み入れれば、そこにはアロマの香りに癒されるリラクゼーション空間が広がり、日常を忘れられるひとときを過ごせます。

ニールズヤードのアイコンともいえる、ブルーボトルのプロダクツが美しくディスプレイ。
実は、ここ表参道本店は、商品の取り扱いだけでなく、食やサロン、スクールと、多方面からホリスティックなライフスタイルを楽しむことができる複合施設。100%再生可能エネルギーを使用し、日常から少し離れ、自分のココロや身体の声に耳を傾けることができます。

「インナーケアに特化した施設を目指し、ここ表参道店をオープンしたのが2003年。サロンは、ストレスフルな肌心体を癒す特別な場所。ブラウンライスは、食の大切さに気付き、健康になり、五感を目覚めさせる場所。スクールは植物のチカラを自分のチカラにするための学びの場所。そのすべてが揃っている空間が、表参道本店です。
イギリスにある本店のコヴェントガーデンをイメージした店舗には、コスメだけでなくアロマオイルやハーブなど品揃えも豊富。実際、創業者のロミー・フレイザーが『この店舗こそ、私の想いを一番体現している』と明言しているほどです」
そう教えてくれたのは、表参道店のマネージャーを務める二ノ宮倭子さん。学生時代から身体不調に悩む日々を送り、ニールズヤードと出会って人生が大きく変化。その思いを多くの人に広めるために、ここで働くことを決意したのだそう。

素敵な笑顔で取材に応えてくださった二ノ宮さん。
「植物のチカラで肌心体が良い方向に変化していくことを実際に体感しているスタッフが在籍しておりますので、私どもはお
また、こちらのショップでは、緑豊かなディスプレイやブルーボトルのシャンデリアなど、心身を解放できる心地よい空間づくりにもこだわっています。アロマハーブを学べるディスカバリースペースも設置しているので、この店舗に足を運ぶだけで日常から少し離れ、

ちなみにお店には、オープン当初から通い続ける常連の方はもちろん、身体の不調を訴える方や、さらにコロナ禍以降は、香りの癒しを求めて来店する方も増えているそう。
「室内で過ごす時間が長くなったことで、身の回りに気を配る方が増えたように感じます。数あるアロマブランドのなかでも、厳選されたフレッシュなオーガニックを使い、環境に配慮した製品づくりをしている私どものブランドに賛同してくださる方も多く、とても喜ばしい限りです」

豊富なラインナップのアロマコーナー。ディフューザーもさまざまなタイプが揃っています。
また、ショップの中庭を挟んで、レストラン「BROWN RICE」を併設。玄米と有機野菜を取り扱った、ヴィーガン和食料理が提供されています。

「メインとなる食材は国産でこだわりの食材を使用しています。日本人の体質に合っているだけでなく、地産地消の精神や和食を語るうえで欠かせない五味・五法を取り入れた料理で、体と心を慈しみながら地球にも優しい食文化の提供を目指しています」

さり気なく和テイストのディスプレイを施した居心地のいい店内。
食材選びはもちろん、調理法や見た目の美しさ、さらに器にもこだわっていると語るのは、ジェネラルマネージャーの多屋徹夫さん。

オープン当初からスタッフとして携わる多屋徹夫さん。
「全国の農家さんから上質な旬の野菜を届けてもらっているため、
また、ガーデンスペースでもお食事を楽しむこともできるので、ちょっとした旅気分を味わうこともできます」

ショップとレストランの中間にある中庭で食事を楽しむことも可能。
「ご提供しているメニューすべてがヴィーガンなので、自家製デザート
日頃から愛用している大好きなブランド。天然アロマの香りに癒されます

趣味のダイビングなどを通じて、美しい自然を守っていくことの大切さを実感している知夏子さん。環境に優しいライフスタイルを実践することはもちろん、肌に触れるものも出来る限り自然由来のものにしたいと、こだわりを持っています。
「スキンケアアイテムも使っていますが、自宅で使用するアロマはこちらのブランドがほとんど。スタッフの方のアドバイスがとにかく丁寧なので、そのときの体調などを相談しながら選んでいます」
普段は自宅の近所にある店舗に足を運ぶため、表参道店は初体験。心地よいアロマの香りが漂う店内をゆっくりと見てまわりました。

入り口付近には、おすすめの製品のディスプレイが。この日並んでいたのは、日本人のリクエストで13年前に登場したというベストセラー「ウーマンズバランス」シリーズより、今季発売されたばかりの新製品のボディケアアイテムでした。

早速手に取って、香りや使い心地を体感。
「コロナ禍以降はテスターを手に取れる機会が減っていましたが、少しずつ以前のようなスタイルに戻ってきた気がします。ニールズヤードはテクスチャーや香りにもこだわっている製品が多いので、購入前に実際にお試しできるのはうれしいですね」と知夏子さんは人気のウーマンズバランスのボディオイルを手に取って、香りと使い心地の良さを確かめていました。

店内には、スキンケアやボディケアはもちろん、アロマオイル、ハーブティ、さらにフラワーエッセンスなど、さまざまなアイテムが揃っています。
「いろいろ目移りしちゃって、選べないかも(笑)。何時間でも滞在できそうです」と知夏子さん。

なかでも人気の高い製品はこちら。〈左から〉ウーマンズバランス マッサージオイル 100ml ¥3,740、フランキンセンス インテンス リフトクリーム 50g ¥15,400、グッドナイト ピローミスト 45ml ¥3,140、ブレンドエッセンシャルオイル ウーマンズバランス 5ml 2,970円、アロマチャームNYR ¥990
ニールズヤードの代名詞ともいえるアロマオイル。製品名の脇に植物の写真も添えられているので、選ぶときの指針にも。

フラワーエッセンスの種類も豊富。ここまで揃っているのは、表参道本店ならでは。

また、こちらの店舗では愛犬用のシャンプーとコームも販売。「これ欲しい~! 買って帰ろうかな」と、愛犬家の知夏子さんは興味津々でした。

数あるアイテムのなかで、知夏子さんが今回一番気になったというのがハーブティー。他店ではティーバッグの提供になりますが、こちらでは茶葉の販売が行われています。ちょっとしたプレゼントにも喜ばれそう。

選ぶ際には、パッケージに表示されている成分の解説をはじめ、実際の効能についてスタッフから細かく説明してもらえます。
疲れが取れない、眠りが浅い、スッキリしたいなど、体調の悩みやなりたい気分を伝えて、今の自分の合ったハーブティーを選ぶことができます。

スタッフから説明を伺い、知夏子さんが気になってピックアップしたフレーバーがこちら。〈左から〉ハピネス80g(表参道本店限定)¥3,240、ビューティフルスキン 80g ¥3,456、ウーマンズウェルネス 80g ¥3,456。※ほかの店舗はティーバッグタイプ(12包入り)での販売。
ハーブティーのセレクトを済ませたら、おすすめスキンケアのレクチャーも。

落ち着いた空間で、気になるプロダクツについてレクチャーいただきました。ちょっとした疑問などにも丁寧に説明をしてくださり、アイテムについてきちんと理解したうえで納得して選ぶことができます。安心してショッピングできることも◎。
ショップを存分に堪能したあとは、待望のレストランへ! 知夏子さんは日頃から玄米生活を続けていることもあり、こちらのお店にも興味があったのだそう。

「旬の食材をすぐにお客様に提供できるよう、調理は店内のオープンキッチンで行われているんですよね。ちょっとお邪魔かと思いつつ、気になる料理の過程を覗き見しちゃいました」

キッチン周りにはレモンの酢漬けや唐辛子など、手作りの調味料がインテリア感覚で配置されていてとってもおしゃれ。
そして、週替わりの主菜1品、惣菜2品、漬物がセットになった一汁三菜セットをオーダー。ふっくら炊き上げた玄米ご飯と味噌汁もセットになった、食べ応えのあるランチメニューです。

伝統的な製法で作られた特製の味噌を使ったお味噌汁は、ほどよい塩味とまろやかな口当たりで、ほっこりした気分に。

一汁三菜セット ¥1,900(土日祝は+¥500、季節の前菜付き)
しっかりお腹を満たしたところで、今度は中庭に場所を移してデザートタイムに。
選んだのは一番人気の豆腐のレモンケーキ。多屋さんおすすめのほうじ茶カモミールも一緒に。

「見た目も食感もまるでレアチーズのようなデザートは、乳製品を一切使用していないとは思えないほどの奥深さ。添えられたレモンが酸味を引き立て、後味もすっきり!
一緒に出されたほうじ茶カモミールは、香ばしさのなかにほんのりと甘みが感じられます。ケーキとの相性も完璧です!」

豆腐のレモンケーキ ¥750、ほうじ茶カモミール ¥850
スキンケアやアロマ、さらにはハーブについてしっかり学んだあとに、体に良い食事を思う存分に堪能! 知夏子さんは、多忙な毎日で疲れた心身を完全にリセットできた様子。

肌で触れ、体に取り入れ、ポジティブな毎日をサポートする『NEAL’S YARD GREEN SQUARE』。丁寧なスキンケアの施術を受けたい方にはサロン、さらにアロマやハーブの知識についてもっと深く学びたい方にはスクールも併設されています。自分にぴったりのホリスティックライフが必ず見つかるこの場所で、よりウェルビーイングな心地よい生活に役立つアイテムを見つけてみませんか?
「ニールズヤード レメディーズ 表参道本店」
東京都渋谷区神宮前5-1-17
03-5778-3706
https://www.nealsyard.co.jp/
「ブラウンライス カフェ」
東京都渋谷区神宮前5-1-8 1F
03-5778-5416
https://www.nealsyard.co.jp/brownrice/
〈衣装〉白プルオーバー ¥12,100、チャコールカーディガン ¥24,200/MICA&DEAL チェックラップスカート ¥29,920/O’Neil of Dublin ラタン×レザーミニバッグ ¥18,700/VIOLAd’ORO
SHOP LIST
MICA&DEAL https://mica-deal.com/
O’Neil of Dublin https://www.landwards.co.jp/
VIOLAd’ORO https://violadoro.jp/
“物”を超えた価値をもたらす、ずっと手放せないもの【写真家 宮本直孝のお気に入りLIST】
その道のプロに聞く、今の自分に必要なお気に入りアイテム。今回は、写真家 宮本直孝さんに3つの大切なアイテムを見せていただきました。
ポートレート写真、その強さと原動力
社会的なメッセージを込め、日本在住のウクライナ人や医療従事者、パラリンピック選手などのポートレート写真をオープンスペースで展示する試みを続ける写真家の宮本直孝さん。その原点にあるのは、世界的に著名な写真家、オリビエーロ・トスカーニとの出会いでした。そして一流の写真を追い求めてきた宮本さんが大切にしているものとは?
台湾で人生を仕切り直す。自分らしい地図の描き方【元タカラジェンヌ 中原由貴の衣食住遊学】
いつも元気で幸せそうなひとは、自分の周りに“楽しいこと”を育てる種をまいています。そんな魅力的な方にHummingなライフスタイルのトピックスを伺うシリーズ記事「わたしの衣食住遊学」。今回登場するのは、宝塚歌劇団を卒業後に台湾に移住し、現地で芸能活動を続けている中原由貴さんです。
飛び込んだ場所で、もう一度、夢を見つけたい

台湾生活の模様はSNSを通して発信中。写真はインスタグラムで紹介した、台北の街を背景に撮影した一枚。
宝塚歌劇団の月組で男役として活躍し、6年ほど前にを卒業した中原さんは、台湾に活動拠点を移して2年半。移住の理由はひと言でいうと「すべての環境を変えてしまえ、と思った」。それは彼女にとって、宝塚後の第二の人生をどう生きていくかの模索と葛藤を経て至った結論でした。
「宝塚に入団して舞台に立つことがずっと目標だったので、20代で人生最大の夢を叶えてしまったことになるんです。なので、どうしてもそれ以上の夢を描きづらくて。私は4年間ぐらいずっと探し続け、なかなか見つけられずにいました」。
趣味で習っていた中国語。そして以前にオーディションで台北を訪れた際に得た、うれしい手応え。日本で見つからないなら、いっそのことすべての環境を変えて、想定外の何かをつかみたい。思いきって飛び込んだ新生活で、芸能活動を続けながらダンスを教えたりと、その基盤は着々と固まりつつあります。
「衣」
“女性”を取り戻すプロセスで見つけた自分らしさ

宝塚時代は、“カッコいい女性”というよりも、男役としてまさに“男性”として振舞っていましたから、退団直後は、普通に女性らしい格好をすると、どうしようもなく違和感がありました。舞台上では女性を持ち上げたりして、腕の筋肉もしっかりついていましたから、体型的にも女性の服がしっくりこない。大股で歩くのは当たり前、ドアの開け方一つとっても、明らかに男性的でしたから、身についたものは意識しないと抜けませんでした。
宝塚に入団する前の17歳で私の“女性歴”はいったん止まっていて、10代後半から20代がすっぽりと抜けてしまっているわけです。女性はこんなときにどんな行動を取るのだろう?ということも含めて、退団してから後天的に学びました(笑)。

よく着けているのは、揺れるタイプのピアス。ハンドメイドのものが好きで、元宝塚の先輩が手掛けているネットショップで購入することも。
ファッションも立ち居振る舞いも試行錯誤を経て、私はやはり可愛いフェミニンな着こなしよりも、大人っぽくてカッコいい女性像が好きだなと再確認。華やかな舞台に立っていたことも影響しているかもしれませんが、まず鮮やかな色の服を手に取る傾向がありますね。トップスは白で、ボトムスにブルーやオレンジの華やかなロング丈のフレアースカート、が定番スタイルです。
台湾の夏はとにかく暑くて、日本の春や秋のような時季がほとんどないからでしょうか、ファッションにあまり関心がない人が多いようです(ちなみに冬はそれなりに寒いです)。私も思いきりラフなスタイルの日もありますが、人に会うなど何か予定があるときはきちんと感を心掛けています。おしゃれをする楽しさを忘れないように。
「食」
美味しい台湾ごはんに魅せられて

よく利用するお店の麻辣火鍋は、龍の持ち手が付いているいかにもな中華ふうの鍋で、真ん中が普通のスープ、周りが麻辣のスープに。
台湾は、三食外食をすることが当たり前という文化で、キッチンがない家もあるほど。理由を尋ねると「外で食べたほうが便利で安いから」とのこと(確かに激安なんですよ)。皆さん朝早くから外に出て行きますし、朝食をいただけるところもいーっぱいあります。
私のお気に入りの台湾ごはんは、麻辣火鍋、そして烤鴨(いわゆる北京ダック)。これは激安というよりは、ちょっと贅沢する日の食事ですね。
麻辣火鍋は、辛いだけでなく山椒の香りが効いた絶妙な味わいの鍋です。山椒が舌にピリピリと残り、これがたまらなくてクセになる美味しさ。
烤鴨はまるっと一羽が運ばれてきて、目の前で切りさばいてくれます。セイロでサーブされる蒸したてのクレープ生地に鴨肉をのせて、薬味とともに自分好みでカスタマイズ。好きなだけいただけるので、ついつい食べ過ぎてしまいます。

行きつけのお店は、烤鴨を肉厚に切り分けてくれる。とにかく絶品。
自炊するときは、やはり日本食。体のことを考えて、野菜と鉄分は意識して摂るようにしています。台湾のごはんはバラエティに富んでいて本当に美味しいのですが、やはり油っぽいので、食べ過ぎると太ります。体は日本人ですから(笑)、ひじきとか出汁巻き卵などを無性に欲するときがありますね。台北じゅうを歩き回って、ひじきを購入できるお店を一軒だけ探し出しました。
こちらに来て、日本食の基本ともいえるお出汁の素晴らしさ、食材や調理法がいかにヘルシーであるかを再認識。和食がユネスコ無形文化遺産に登録されたことも、あらためて納得できました。
「住」
アロマで得る、癒しとパワーチャージ

リラックスしたい夜、集中して勉強や調べものをしたいときなどには、アロマを焚いています。台湾でも無添加のものや有機野菜が注目され始まっていて、天然素材を使ったアイテムをたくさん目にするようになりました。私が選んでいるのも、台湾産の天然素材から作られている台湾アロマです。

こちらのお香のお店は、200年の歴史を持った超老舗「金吉利香鋪」。7代目社長が効能と香りをていねいに説明してくれて選びやすい。
迪化街という地区に、漢方などを売る店が並んでいるエリアがあるのですが、そこで手作りのお香を手に入れています。お店の方いわく、日本人観光客にも人気とのこと。購入時は、全種類に火をつけてもらって一つひとつ匂いを確かめて吟味。リラックス効果、元気が出る香り、空気を浄化してくれる香り、ユニークなものでは「お金持ちになれる香り」なんていうものもあります(笑)。私は特定の香りに決めているわけではなく、その時々の気分に合ったもの、必要な香りを選んでいます。

夜、アロマを焚いて、身も心もリラックスしながら、頭のなかでいろいろな思いを巡らせる時間を設けています。たとえば、仕事で成功している自分を想像して、気持ちをワクワクさせたり。そうすると、次にこの香りをかいだだけで、ワクワクする気持ちがよみがえって、心地よさに包まれるわけです。アロマは気分転換にも、パワーチャージにも役立ち、私の一人時間に欠かせない要素になっています。
「遊」
ローカルなお楽しみ、夜市と公園

この日は、南機場夜市という、観光客の少ないとってもローカルな夜市へ。
台湾を旅したことがある方はご存じかと思いますが、夜市での食べ歩きは台湾ならではのお楽しみ。移住する前にも5、6回は旅行で訪れましたが、ガイドブックに載っている有名な夜市に行ったことしかなくて。こちらに住んでから、実はどこにでも夜市があることを知りました。観光客が知らない、おすすめの夜市もたくさんあります。

「曉迪筒仔米糕」というお店の看板メニュー、筒仔米糕(筒形のおこわ)。
夜市の楽しさは?と聞かれたら・・・屋台村に行くイメージでしょうか。現地では、夜食を楽しみに行く感覚で利用している人も多いです。食事のあとに、そこに夜市があるからちょっと寄ってく?みたいな感じ。台湾の人がみんな好きな豬血糕(豚の血を固めて作られた餅)を1本買って、歩きながら食べている光景が日常。いつも活気があって、眺めているだけでも楽しいです。

淡水の金色水岸という公園にて。夕陽がきれいに見えると人気のスポット。
もう一つ、人がよく集っている場所が公園。あちらこちらに公園があって、そこでおしゃべりしている人たちの輪をよく見かけます。楽しそうに情報交換をしていて、主な話題は・・・やはりグルメねた! 皆さんとにかく美味しいものを食べることが大好きで、グルメ情報が飛び交っています。日々のニュースも5つのネタが紹介されるとしたら、1つは必ず、どこに何のお店がオープンしましたというグルメの話題なんですよ。
今はこんなふうに、ローカルな場所でリアルな文化に触れるのが楽しくて。街や人々の様子に触れながら、たくさんの知識を得ています。
「学」
ダンスを教えることで得る学び

ブランドのイメージモデルを務めている、台湾資生堂のBENEFIQUEの広告撮影より。モデルの仕事にはダンスの経験も活かされている。
台湾でCMや広告モデルの仕事をしながら、ダンスを教えています。移住して半年経ったころにオファーをいただいたときは、中国語でダンスを教えるなんて無謀だ!と本当に自信がなくて。日本でも中国語を学んでいたとはいえ、いざ台湾に住んでみると、わからない、聴き取れない、話せない。まだそんなレベルのときに降ってわいたお話だったので、興味はありつつも、適当に教えるのも嫌だし・・・と悩みました。でも私のポリシーでもあるのですが、悩んでもしかたないことは悩まない、悩んでいても意味がない。やるか、やらないかというときは、少しでも興味があるならば、やっちゃえと。そこから毎週末にダンスを教える生活がもう2年も続いています。

こちらは、コンパスという携帯ゲームのCM撮影現場での1カット。
私の生徒さんは、下は10歳ぐらいから50代ぐらいまでの幅広い層で、皆さん宝塚のファン。パンデミック以前は3年に一度のペースで、台湾でも宝塚公演が行われていましたので、有難いことに熱心なファンがたくさんいらっしゃいます。
私が教えているのは、宝塚のメソッドをベースにしたものなので、かなり特殊なダンス教室かもしれません。基本的には皆さんダンス初心者で、大好きな宝塚に何らかの形で触れたいということがきっかけになっています。だからといって、ただ楽しいだけではなくて、私としては宝塚の舞台が厳しいレッスンがあってこそ成り立っているんだということも知ってもらいたくて。
宝塚の舞台では、ダンスは一人で踊るものではなく、みんなと一緒に組んでやるものだということを伝えながら、他の人とのバランスの取り方とか、なぜ今うまく動けなかったのかを自分で考えてもらったり、一歩深いところまで感じてもらえるように指導を工夫しています。

ダンスレッスン中の1枚。教える側も教わる側も、楽しみながらも真剣!
そんな想いが届いたのか、彼女たちも本気で取り組んでくれて、その成長ぶりを肌で感じられるようになったし、そこには達成感も生まれています。誘い合って自主稽古までしていて、そんな生徒たちの真剣な姿が、私自身の達成感にもなっているのです。手探りでスタートしましたが、今は絆や信頼感も出来上がっていると思っています。
今後は宝塚的なダンスだけでなく、さらに広げていきたくて。台湾にはジャズダンスの教室がほぼないので、開拓していきたいし、根付かせたいという気持ちもあります。日本から講師も招いて、プログラムをつくっていこうかなどあれこれと計画中。ダンスを通じて、日台をつなげていきたいですね。
本来はやったことがないことをゼロから学ぶのが好きなのですが、宝塚の舞台を10年間経験して、そこで学んだこと、その基盤を活かせることが、今の私が輝ける道かなと思っています。自分のペースでオーディションを受けながら芸能の仕事を続けられる環境も有難く、一つに絞らずにいろんなことに挑戦して進めることで、可能性が何倍にも広がっていくと思っています。自分にしかできないことを見つけてこそ、ここに来た意味もあるし、居続ける意味を感じています。
台湾に移り住んだことを「正解だった」と答えたその力強さに、中原さんの今の生活の充実ぶりがうかがえます。日本では探し続けても見つけられなかったワクワク感を、ようやく台湾で感じているーー。思いきった選択が新しい扉を開いた今、「まだ何かを成し遂げたわけではないけれど、思う方向へ向かっていると思えています」と語る彼女の未来は、真っ直ぐで迷いがありません。

Profile
中原由貴(なかはらゆうき)
東京都出身。元タカラジェンヌ。宝塚歌劇団に92期生として入団し、10年間在籍。月組の男役スター 煌月爽矢として人気を得る。2016年に退団後は、女優、タレントとして芸能活動を続け、2019年に台湾へ。芸能活動と並行してダンスを教えるなど活躍の場を広げている。
Instagram @Nakahara.yuuki
Twitter @Yuuki_Nakahara
旅のパートナーに!サボテンを原料にしたヴィーガンレザーバッグ
トラベルブランド「Aww(アウ)」から発表された「Cactus Vegan Leatherコレクション」は、サボテンを原料にしたたヴィーガンレザーを使用しています。エシカルとおしゃれが両立した注目の新作をご紹介!
サボテンの葉からつくるカクタスレザーとは

サボテンは、貧しい土俵や水が少ない環境でも育つ耐久性に優れた植物、といわれています。
今回、Awwが採用したヴィーガンレザーは、メキシコ・DESSERTO社のプロダクト。ここはサボテン農場を持ち、灌漑システムや農薬を一切使わずに、雨水で育てるオーガニック農法を行っているそう。成長したサボテンの葉を収穫してカクタスレザーをつくり、また成長を待って収穫するというサステナブルなモノづくりを実現しています。

カクタスレザーの製造は、その過程で環境負荷が少ないこともエシカルポイント。出来上がったカクタスレザーは、柔軟性、耐水性、伸縮性、通気性に優れていて、リアルレザーと比べても遜色ない仕上がり。究極のエコ素材なのです。
エシカルなだけではありません!機能性もパーフェクト

きっと、言われなければこのバッグがヴィーガンレザーだと気付かない人も多いことでしょう。しかもこのコレクションの魅力は素材だけではないのです。“旅のパートナー”として、とっても頼もしい機能性。なかでも注目してほしいのが、2タイプ登場したボストンバッグです。
週末旅行や出張に役立つ大容量ボストンバッグ

写真のブラックのほか、ホワイト、ベージュの全3色展開。¥21,500
こちらの「Cactus Vegan Leather Weekend Boston Bag」は、W44 ×H34×D15cm(ハンドストラップ55cm)という大きめサイズ。1~2泊のトラベルバッグにおすすめです。
ジェンターレスなフォルムとデザインなので、カップルやファミリーで共有も可能。オフィス用バッグとしても活躍してくれます。
内側には収納ポケットがたくさん! PCケースも備えていてるので、使い勝手も抜群です。

ちなみに、1つのバッグに2枚のサボテンの葉が使われていて、このバッグを選ぶことでCO2を11,640gほど削減できるそう。
旅先の街歩きにもぴったりのミニボストンバッグ

写真のベージュのほか、ブラック、ホワイトの全3色展開。¥12,800
もう1つは「Cactus Vegan Leather Mini Bag」で、W21 ×H15×D8cm(ハンドストラップ31cm)の小ぶりなタイプ。トラベルシーンでは機内持ち込み用バッグとして、旅先の街歩きではセカンドバッグとして大活躍間違いなし。
ミニバッグというネーミングながら、収納力も高く、ポケットも充実。ジップで広くオープンできる仕様なので、持ち物の整理も簡単。開け口が2つに分かれていて、使いやすさを考えた配慮が行き届いています。

こちらは1つのバッグに1/2枚のサボテンの葉を使用、このバッグを選ぶとCO2を2,710gほど削減することにコミットできます。
Awwは2020年に誕生したトラベルブランドで、スーツケースを軸にこだわりたっぷりのトラベルアイテムを展開。ご紹介した「Cactus Vegan Leatherコレクション」は、2つのボストンバッグのほかに同じくカクタスレザーを使った「Cactus Vegan Leather Luggage Tag」、リサイクルポリエステル素材で作ったトラベルポーチセット「Recycle Polyester Packing Cube(4size set)」も発売中です。秋の旅計画を考えつつ、トラベルバッグもよりエシカルで、使いやすいものにシフトを検討しましょう!
フェムケアを始めるチャンス。デリケートゾーンケアブランド「I’m La Floria」がポップアップストアを開催
からだと向き合い、自分を知るためのデリケートゾーン&セルフケアブランド『I’m La Floria』が9月2日(金)より、松屋銀座6階ランジェリー売場プロモーションスペースにてポップアップショップを開催。商品について詳しく知ることができ、「フェムケアを始める絶好のチャンスです!
“習慣化”には手軽さが第一。普段のボディケアと同じステップでケア

自分の一部である性ともっとオープンに向き合い、身近に感じることのできるシンプルな毎日のセルフケアを提案する「I’m La Floria」。すべての商品がデリケートゾーンだけでなく全身に使え、デリケートゾーンのケアを習慣にしやすい商品開発に注力しています。
ポップアップショップ期間中の9月2日(金)、3日(土)、4日(日)、9日(金)、10日(土)、11日(日)の6日間は、多くの女性たちのデリケートゾーンケアの悩みに寄り添ってきたアイム ラフロリアのスタッフが接客にあたり、デリケートゾーンのお悩み相談から、アイテムのおすすめの使用方法などを聞くことができます。
人や環境を想う製品づくり

「ボディウォッシュ」「ボディクリーム」「デリケートブライトニングセラム」は、それぞれに肌に優しい天然由来の成分を90%以上使用。弱酸性のボディウォッシュは、少量でよく泡立ち、たっぷりの泡でデリケートゾーンの気になるニオイを軽減。毎日無理なく使用できる使い心地の良さにこだわっています。
「I’m La Floria」では、デリケートゾーンケアアイテムが性別や年齢問わず誰にとっても使いやすいものになるよう、定番商品のパッケージや原料をリニューアル。容器やショッパーは環境負荷の少ないものをセレクトし、ボトルは再生可能な植物由来の成分を使った「バイオプラスチック」を優先的に活用。そのほかにも、紙資材を可能な限り削減し、森林保全やフェアトレードに対応するバナナペーパーを導入するなど、環境に配慮した取り組みを進めています。

ポップアップショップでは、「バランシングボディオイル」を含む¥5,500以上(税込)の購入でコットンパンティライナー(3枚入、非売品)のプレゼントが。肌あたりの良さを考慮したコットン100%の日本製。カーボンニュートラルに配慮して生産され、さらに生分解され自然に還る、使い捨てタイプでありながら環境負荷の少ないプロダクトです。さらに¥7,700以上(税込)購入すると、バスソルト(80g、非売品)がプレゼントされます。
まだまだ自分の目で見て、触れて、知る機会の少ないフェムケア商品。この機会にぜひ立ち寄ってみてください。
『I’m La Floria』ポップアップショップ
日程:2022年9月2日(金)~2022年9月11日(日)
場所:松屋銀座6階ランジェリー売場プロモーションスペース
https://im-official.com
この秋注目!スキンケア級のファンデーションたち
肌や体に良いもの、使い心地が良いもの、気分が上がるもの・・・コスメや美容ツールを上手に取り入れて、Hummingな毎日を送りたい。美容ライター 荒木奈々さんがおすすめをご紹介します。
今時ファンデーションは、究極のながらケア!
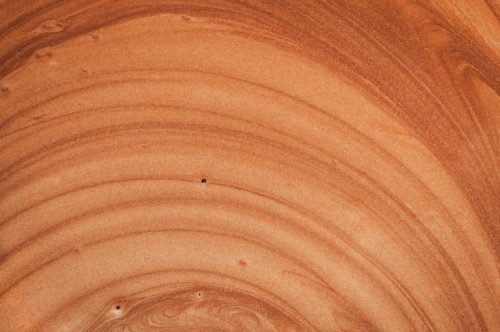
ファンデーションでスキンケア? ひと昔前まではファンデーションを塗る=肌に悪いなんて言われていましたし、いまだにそういう意識は少なからずあるよう。でも昨今のファンデーションは日中の肌をケアする効果がスキンケア級、その働きかけはシーズンごとに進化しているとも。ファンデーションは目に見えない外的刺激から肌を守ってくれる砦。しかも朝から晩までつけているわけですから、よりトリートメント効果があるものを選びたいのです。
My select 01:持ち運べるスキンケア!B.Aのクッションファンデ

B.A セラムクッションファンデーション SPF20・PA++ 全5色 各¥14,850(セット価格)/ポーラ
以前はパウダータイプ派が断然多かったそうですが、今はリキッド&クリーム、クッションに人気がシフトしているというファンデーション。2、3個持ちは当たり前で、その日の気分によって肌を着替えるという人も多いのでは?
忙しい朝手早く仕上げたいときや外出先では、クッションファンデが大活躍です。
1985年にエイジングブランドとして誕生したB.A。アイコンアイテムのローションを中心に「大人になったらB.Aを使ってみたい」なんて声も聞こえる、誰もが憧れるブランドですよね。そんなポーラ最高峰ブランドB.Aから、今期ブランド初のクッションファンデが誕生。B.Aではベースメイクを「日中のエイジングケア」と掲げ、スキンケア同様の考え方で研究を重ねているそうです。
新製品の「B.A セラムクッションファンデーション」のキャッチは、「私の居場所を、オアシスにする。」。強烈な紫外線、空気の汚れ、ストレスなど、見えない外的・内的刺激にさらされている日中の肌は、過酷をきわめています。だからたどりついたのが、「日中の過酷な肌環境をポジティブに変換し、美しさに変える」という発想。つまり、環境を味方にしてしまうというコンセプト!
スキンケアレベルのファンデーションはもう珍しくないかもしれません。でもB.Aベースメイクの感動は、肌をキレイに見せるとか、美容成分がたっぷり入っている、だけではないよう。
このクッションファンデは、空気中の水分を肌に取り込んで逃がしにくいヴェールをつくったり、肌にダメージを与える空気中のガスを分解したり、太陽光のロングUV-Aを肌の輝きに変換したり、肌に良いといわれる赤色光を通過させたりなど、他にはない画期的な手応えばかり。しかも水面のような、水ハリ艶が長時間まとえる演出も。
みずみずしさのお手本は、B.Aローション! クッションファンデ内のゲルにB.Aスキンケアと共通の美容成分入りの水系成分が内包されていて、肌に触れた瞬間、水風船が弾けるようにゲルが弾けて、中の美容成分が放出。スポンジでポンポンすると、ヒタヒタでみずみずしい潤いに満たされます。
同時に、ゲル膜が肌に均一にフィットし、粉体(色素)も整列。みずみずしいクッションファンデは、つけたそばからヨレてしまうのが心配ですが、B.Aのクッションファンデはフィット感も抜群。なじんだ後は塗ったことを忘れるくらい、手で触ってもベタつき感がありません。マスクに付いてしまう失敗も減りそうです。
B.Aのクッションファンデはカバー力も見事で、頬のあたりの肝斑っぽいもやっと感もひと塗りで目立たなくしてくれます。若い肌から大人の肌、肌質も問わず、つるんとしたハリ艶のある肌へ。
香りや感触も官能的なB.A。スキンケアなどアイテムごとに香りが異なっていて、「シプレフローラルアレンジメント」という、お手入れを重ねるごとに花束になっていくしかけが。クッションファンデは、みずみずしい植物をイメージした「アクア」の香り。つけるたびに、香りで、触感で、肌がオアシス。まさに持ち運びたいスキンケアです。

ポーラは2029年で創業100年! そこをサステナビリティゴールの節目に、「未来に、次世代に環境をつなぐアクション」として人、社会、経済、そして地球環境のため、化粧品業界初の取り組みなどにも果敢に挑戦。またB.Aでは、年を取ること(エイジング)=ネガティブという意識をチェンジする活動も行っていて、「年齢を重ねることは人生の可能性を広げていく」という「AGEBILITY(エイジビリティ)」を提唱。年を取るのは怖くない!ことになる未来はポーラから!
My select 02:KANEBOの美容液ファンデーションで嬉々肌へ

カネボウ ライブリースキン ウェア SPF5・PA++(オークルD:SPF5・PA+/オークルE:SPF7・PA++)全8色 30g 各¥11,000/カネボウインターナショナルDiv.(9月9日発売)
スキンケア、メイクブランドと発信は異なっても、どのファンデも美容成分たっぷり。肌仕上がりのクオリティも高く、カバーと透明感という相反する効果を両立するものまであります。カネボウのファンデーションはさらにその先、人柄まで美しくなる!?
カネボウでは「人はなぜファンデーションを塗るのか?」という原点に戻り、キレイな肌になることで自分を好きになり、さらに人柄までキラキラするという良循環を生むことに着目。美容液ファンデーション「ライブリースキン ウェア」で仕上がるのは、「嬉々肌」という存在までキラキラした肌!
その肌を仕上げる技術がライブリースキンテクノロジー。
1. 粉体顔料をカラーオイル化
粉感はまったくなし。潤ったような艶をもたらしながら、時間とともにくすんでくるのを防止。
2. 独自開発の透明ジェルを採用
肌を構成する成分となじみのいい素材によって、つけ心地の良さを実現。肌に吸い付くように密着するから、表情を変えてもファンデーションがヨレにくくなります。
まず驚いたのがテクスチャーのキメ細かさ。そしてファーストタッチに2度目の驚き。フルフルのジェルのような感触で、肌にのばすとリキッドのように伸び広がりがスムーズ。ネーミング通り、ライブリーなツヤと色によって、生き生きとした柔軟な肌に仕上げてくれます。
保湿力だって優秀です。ジェルに美容液成分を抱え込ませた保湿成分「モイスチャーセラムコンプレックス」を配合。ほぼ美容液のようで、朝から夕方まで潤いをしっかりキープしてくれます。
化粧下地、コンシーラー、フェイスパウダーは不要。「素肌に化ける」というファンデーションの本質を体現できる「ライブリースキン ウェア」は、肌に広げるとどこからどこまで塗ったか一目じゃわからないほど、均一でなめらか。なので、重ね付けしても目立たず、気になる部位だけに塗る部分用ファンデーションとしても重宝します。
カネボウのもう1つのお気に入り、日中用クリームとのコンビで、お出かけ肌は万端です。
黒のパッケージが印象的なKANEBO製品。洗顔料などはシェアコスメとしても人気とか。全プロダクトが「使いやすさ」や「わかりやすさ」に配慮したユニバーサルデザイン発想。「ライブリースキン ウェア」は、キャップのユニークな動きにも注目です。
カネボウインターナショナルDiv.
kanebo-global.com
My select 03:ずっとつけていたくなる、ランコムの極上クリームファンデ

アプソリュ タン サブリムエッセンス クリーム 全2色 35ml 各¥18,150/ランコム
高級ファンデーションは、肌悩みを抱える大人のため・・・だけのものではない!? 若い肌の間でも¥10,000超えのファンデーションが人気とか。トリートメント効果の高いファンデーションを未来の肌の投資に!
でも1つ疑問が。スキンケアクリームのようにたっぷり塗るわけではないファンデーションで、スキンケア効果はそこまで期待できるものなの?
今シーズンのスキンケア級ファンデーションのなかで、ひと際オーラを放っているのが、ランコムの「アプソリュ タン サブリムエッセンス クリーム」。ダイヤモンドカットのガラス製のパッケージで、佇まいからして贅沢です。
ブランド最高峰のラグジュアリースキンケア「アプソリュ」の美容成分50%と、クリーミィな色素50%の黄金バランスからなるクリームファンデで、採用されている美容成分だけ見ると、ほとんど高級クリーム! アプソリュの共通成分、南フランスの高原で有機栽培される「アプソリュパーペチュアルローズ ™」の特許取得のエキスは、すぐれた抗酸化作用、さらにハリ不足の肌へのアプローチが期待できるそう。美肌演出はもちろん、使い続けることで美肌を育んでくれるはず。

クリーミィなテクスチャーは、着け心地も極上です。肌に溶け込むようになじんで、厚塗り感はないのにきちんとカバー、ふっくらとしたハリまでメイクしてくれます。また通気性がある膜なので、肌はしっかり呼吸ができる設計。しかも自然なツヤ感とライトアップ効果をもたらす24金も配合されており、塗ったそばから明るいツヤ肌に仕上がります。シェードはアジア人の肌色のために開発されたピンク系の2色。シアーからミディアムまで好みのカバーも演出できます。
そういえばラグジュアリーブランド、ランコムのサステナブルは壮大です。「次の10年間が地球の命運を分ける」というテーマのなかで、いくつものアクションが稼働していますが、身近なところでは、空き容器回収ボックスの設置が昨年から日本でもスタート。またスキンケアやフレグランスの全品が2025年までに詰め替えだったり、再充填ができる容器にスイッチされるそうですよ。
ファンデーションを塗っていると早く脱ぎたい感覚がありましたが、今は逆につけているほうが心地良いものが多いこと! とにかく毎シーズンのファンデーションの進化、知っておいて損はありません。
サイエンス×自然の恩恵美容で肌をしっかりリカバリー
肌や体に良いもの、使い心地が良いもの、気分が上がるもの・・・コスメや美容ツールを上手に取り入れて、Hummingな毎日を送りたい。美容ライター 荒木奈々さんがおすすめをご紹介します。
夏のお疲れ肌にも応える! 最先端ナチュラルコスメ

自然由来のコスメ=肌に優しいわけではないといわれます。過酷な環境で生きる自然由来の素材はそれ自体がパワフルで神秘的。その恵みを活かしているのがナチュラル&オーガニックコスメで、今時はラグジュアリーやドクターコスメにも肩を並べる頼りがいのあるものがとても増えています。心地良いと感じられるだけでも十分に肌に効いている気がしますが、そこにサイエンスの裏付けがあると、なおさら信頼できるし、続けられますよね。そこで今回は、今の肌を任せたい2つのコスメブランドにフォーカス!
My select 01:サイエンスの裏付けあり。アンティポディース
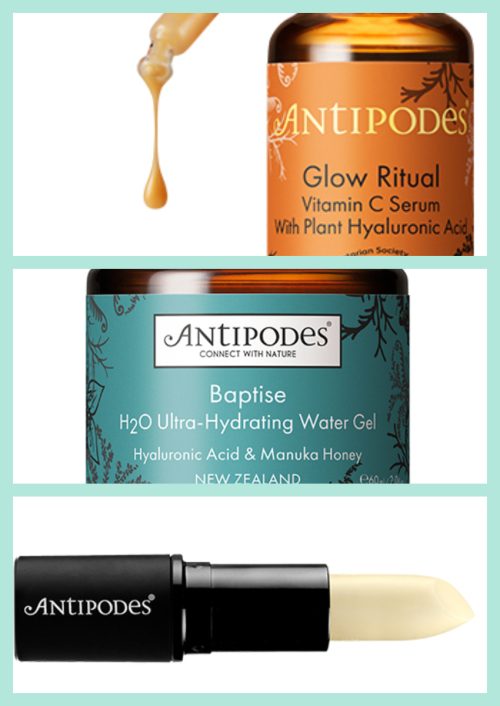
今年、SNSや雑誌などでブレイクしているのが、ニュージーランド発のアンティポディース。2004年に設立されたナチュラル&オーガニックブランドで、アンティポディースとはオーストラリアとニュージーランドを示すそう。
スキンケア開発のインスピレーションは、もちろんニュージーランドの植物たち。大自然で育つ栄養豊富な素材をベースにしたコスメは、それだけでも力強いものですが、それぞれのアイテムはニュージーランドのオーガニック機関バイオグロの認証、英国ベジタリアンソサエティのベジタリアン認証やヴィーガン認証なども取得。ニュージーランドの美容素材といえば、マヌカハニーやキウイシードオイルが有名どころですが、アンティポディースではハラケケ、ママク黒シダ、カワカワといったニュージーランドの伝統的な植物も扱っているのがユニーク。
またこのブランドは、創設者であるエリザベス・バーバリッチさんが医療系の企業で務めていたことから、自然と科学の架け橋になるブランドとして、ナチュラルスキンケアの一段上のレベルを目指したという背景があります。そのためアンティポディースでは、科学的な視点から効果を実証。エビデンスをしっかり持つオーガニック認証コスメというのはまだまだ少なく、その分野のパイオニアブランドでもあります。
カカドゥ・プラムのビタミンCを配合した美容液

グロウ リチュアル Cセラム 30ml ¥6,380/アンティポディース
夏終わりの肌はお疲れモード。シミが濃くなってるし、くすみがちだし、毛穴も開いているし、小じわも増えた気が・・・。そのお悩みに一気に働きかけてくれる成分といえば、やっぱりビタミンC。それを味方にしたスキンケアは多数ありますが、ナチュラル&オーガニックコスメでお探しながら、アンティポディースのスキンブライトニング ラインをチェック。
メイン素材は、カカドゥ・プラム。自然界でもっともビタミンCを多く含むスーパーフルーツといわれ、その含有量はオレンジの100倍とも。オーストラリア原産で、強力な日差しのもとで生育するカカドゥ・プラムから採取されるエキスは、優れた抗酸化力を発揮します。アンティポディースでは、この天然由来のビタミンCの肌を明るくする効果を証明済み。
開発に約2年を費やした「グロウ リチュアル Cセラム」は、カカドゥ・プラムのエキスに、植物性のヒアルロン酸、ブランドのアイコン成分であるブドウの種子やキウイフルーツの皮から採取したヴィナンザ グレープ&キウイを配合。それからレチノールに代わる成分として注目のバクチオールまで入っていて、ツヤと一緒になめらかさもプラスしてくれます。日中の肌をケアする成分がふんだん、オレンジ色のキラキラしたテクスチャーは自然なハイライター効果ももたらすので、朝の美容液として最適です。マンダリンとバニラの甘い香り。
さっぱりでも濃厚に潤う、マヌカハニーのジェル

バプタイズH2Oウルトラ ハイドレーティング ウォータージェル 60ml ¥4,950/アンティポディース
紫外線によって肌の水分は奪われがち、集中的に潤いを与えなければ! そんなときは「バプタイズH2Oウルトラ ハイドレーティング ウォータージェル」を。
アンティポディースのアイコン成分、ニュージーランドのマヌカハニーを配合。さらに植物由来のヒアルロン酸や、高保湿が期待できるハイビスカス、ハラケケ、ママク黒シダをイン。“肌を水に浸す”がテーマのジェルだけあって、つけた瞬間ヒヤッとします。ピンク色のプルプルのテクスチャー、乾燥で潤いがなじみにくくなっている肌にもスルスルと浸透。荒れがちな肌も癒してくれます。暑い日は冷蔵庫で冷やしておいて、それを塗布するのもおすすめだそう。
アンティポディースは、香り成分の選定も独特で、専任の調香師がブレンド。このジェルは、ローズの華やかな香りです。
それからスキンケアのほとんどのボトルが、再生利用が可能なガラス瓶。リバース、リユース、リサイクルもしっかり掲げています。
スーパーフルーツの栄養成分入りリップケア

キウイシードオイル リップコンディショナー 4g ¥2,420/アンティポディース
唇にもエイジングケアが必要と気がつき、最近は潤いケア+αのリップケアをパトロール中。
アンティポディースのリップケア「キウイシードオイル リップコンディショナー」は、ブランド人気No.1のアイクリームと同じ、ニュージーランドで育つスーパーフルーツ、キウイフルーツの恵みが自慢。キウイフルーツ種子油にはビタミンCがたっぷり含まれているので、潤いを与えながら、気になる縦ジワにまでアプローチしてくれます。他にも栄養リッチなスーパーフード、アボカドのオイルも配合。
乾燥しやすいのでしっかり潤わせたい反面、ベタつくなどの違和感のあるリップケアは不満。そんなニーズにも応えてくれるリップケアは、季節を問わず使えるし、口紅の下地としても有能。
アンティポディース
https://jp.antipodesnature.com
My select 02:海洋由来の最先端成分を採用するアルゴロジー
.jpg)
エステメニューの中でいちばん好きなのがタラソテラピー。そういうわけで、タラソがキーワードのコスメがどうしても気になるのです。
フランス・ブルターニュで発祥したタラソテラピーに着想を得て、1987年に誕生したアルゴロジー。エステのみの販路から、2021年に日本でリローンチ。ALGOLOGIE(海藻学)というブランド名通り、海藻や海洋植物の技術を応用したコスメを揃えていて、じわじわと注目を集めているようですよ。
アルゴロジーの拠点は、ブルターニュの自然保護区域内。2つの海流が合流するというとても珍しいビオトープ(生態系環境)で、その海水では800種以上の海洋生物が生息しているとか。その恵みを生かしたブランドの特長成分は、特許を取得している海洋性プレミックス成分ALGO4®。褐藻のワカメエキスや塩生植物など植物幹細胞を含む4つの海洋成分で構成され、ハリを与えるなどエイジングケアが期待できます。
海の恵みがたっぷり。肌を底上げするセラムブースター
.jpg)
アルゴロジー ハイドラセラム ブースター 15m ¥3,740、30ml ¥6,710/アルゴロジー(NISHIKIN)
植物と同様、謎めいている海洋由来の成分。その分野でアルゴロジーがリードしている理由は、世界有数の藻類の研究機関とタッグを組んでいるから。30年以上の研究実績のもと原料の有効性をしっかり確認、100%メイド・イン・フランスで、海洋由来成分の100%をブルターニュ地方で調達しています。ブルターニュにある5つ星ホテルの「タラソ&スパ」でも、アルゴロジーの製品がフェイシャルトリートメントで使用されたりしているそう。
世界で2分に1本売れているというアルゴロジーのスターアイテムが「アルゴロジー ハイドラセラム ブースター」。ALGO4®をはじめ、ブースター成分としてのヒアルロン酸Na、イモセミルエキス、アッケシソウを配合。とろんとした感触のセラムで、ごわごわになっている角質を潤いで整えながら、次に使う化粧水の浸透を高めてくれます。爽やかなマリンフローラルの香りも魅力。天然由来成分95%。ミニサイズもあります。
シーウォーターがベースのクレンジング&保湿

アルゴロジー ミセラー クレンジング ウォーター 200ml ¥3,960/アルゴロジー(NISHIKIN)
角質がごわごわになっている夏終わりは、拭き取り洗顔にもトライ。クレンジングと化粧水の機能がひとつになった2in1のアイテムは、ササッと汚れをオフしたいとき、クレンジングバームや濃厚なパックをストレスなく落としたいときにも重宝。
自然由来成分を96%使用の「アルゴロジー ミセラー クレンジン クレンジング ウォーター」のベースウォーターは、ブルターニュの海水! それだけで気持ちよさそうですが、そのままを使っているわけではなく、海水をろ過してピュアな水にし、そこにブルターニュの海水のミネラル(海塩)をブレンドしたシーウォーターが使われています。洗浄成分は植物由来の界面活性剤、保湿成分としてALGO4®やココナッツオイルから抽出されたグリセリンを配合。
こちらの香りもマリンフローラル。朝の洗顔ウォーターとして使うと、肌も気分もしゃきっとして気持ちがいい!
タラソトリートメントが自宅で叶うボディオイル

アルゴロジー タラソ ボディオイル 125ml ¥6,600/アルゴロジー(NISHIKIN)(9月1日発売)
タラソトリートメントの本場、ブルターニュで開発された「アルゴロジー タラソ ボディオイル」が、今秋解禁に。コンセプトは「内側からハリのある引き締まったボディメイク」。ヘーゼルナッツ種子油、シダー油、レモン果皮油といった引き締め作用をもたらすオイルに、タラソ成分のヒバマタエキスなどを配合。マッサージしやすいテクスチャーで、自分の手でお手入れしているのに、プロにほぐしてもらったかのようなすっきり感覚。使い続けることで、引き締まったボディラインにアプローチしてくれるとのこと。
ゼラニウム、レモングラス、シダーウッドのフレッシュなアロマは、しばらくすると柔らかな香りへと変化。ライトフレグランスとして使うのも良さそう。またALGO4®も配合。乾燥している日焼け肌のサンケアとして、またシャワーオイルやバスオイルにも使えます。
「タラソ ボディオイル」は自然由来成分を99%使用していますが、アルゴロジーでは海洋由来成分にこだわり、すべてのアイテムが自然由来成分95%以上。海の環境の守り、負荷をかけないために、ブルターニュの海のそばにある工場で原料の調達から生産までが管理されています。
アルゴロジー
https://algologie.jp
肌悩みに働きかけてくれるナチュラル&オーガニックコスメはいくつもありますが、より実感のあるものでケアしたいですよね。この2ブランドを覚えておいて。
セルフラブの意味とは?やり方・自己肯定感との違いを解説

幸福度を高める方法のひとつとして、近年SNSなどで「セルフラブ」が話題となっています。
言葉のニュアンスはイメージできるものの、詳しい意味までは理解できていないという方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、セルフラブとはどういった意味なのか、セルフラブの実践方法や似た言葉との違いについても詳しく解説します。
セルフラブの意味とは?

セルフラブとはその名の通り「自分自身を愛すること」を意味します。
難しい言葉でいえば「自己肯定感を高めること」とも表現できますが、自分を否定することなく、ありのままを受け入れることがセルフラブの本質といえるでしょう。
他人と自分とを比べたとき、「自分はダメな人間だ」、「◯◯さんに比べて自分は◯◯が劣っている」と感じることはないでしょうか。
このように自分自身を否定してしまうと、人生そのものの幸福度が下がってしまいます。
セルフラブを心がけることによって、自分らしい生き方が見つけられるようになり、人生の幸福度が上がっていきます。
▶︎【ストレス解消】セルフケアとはなにか?意味・種類・方法について解説
セルフラブの効果やメリット
セルフラブを意識することで幸福度が上がっていくと紹介しましたが、なぜそのような効果が見込めるのでしょうか。
セルフラブのメリットをもう少し具体的に解説しましょう。
①自分に自信がもてる
「自分はダメな人間だ」と感じてしまうと自分に対して自信がなくなり、それまで得意だったこともできなくなるケースがあるでしょう。
しかし、セルフラブを意識し自分を愛せるようになると、他人と比較したときに自分自身の悪い部分や弱みを痛感して落ち込むこともなくなるでしょう。
その結果、自分に自信がもてるようになり、それまで不得意だったことも克服できる可能性もあるでしょう。
②寂しさを感じることが減る
自分を愛することができないと、他者に依存しがちで、つねに誰かと一緒にいないと不安になったり寂しさを感じたりすることがあります。
しかし、セルフラブによって自分自身を愛せるようになると、他者がいなくても一人の時間を有意義に過ごせるようになるでしょう。
③コミュニケーションが円滑になる
自分を愛するということは、他者と比較する必要がなくなり、自分自身にも相手に対しても寛容でいられることを意味します。
ありのままを受け入れることで、相手は安心して心を開くことができ、信頼を置き本音でコミュニケーションを図れるようになるでしょう。
④感情をうまくコントロールできる
自分に自信がないと、相手のちょっとした言動が気になってしまい、不快な感情が湧いてくることがあります。
しかし、セルフラブを意識することで自分自身のなかに心の余裕が生まれ、イライラしたり怒りっぽくなったりすることもなくなるでしょう。
⑤人脈が広がる
自分に自信をもち、相手に対しても寛容でいられる人には、自然と多くの人が寄ってくるものです。
これまで以上に交友関係が広がり、さまざまな人脈を形成できるでしょう。
将来何らかの事情で自分が困ったとき、助けてくれる大切な友人や知人が見つかる可能性もあります。
▶︎【変わりたいあなたへ】自分を変えることは難しい?変われる方法や習慣
セルフラブができている人の特徴

その人の性格や考え方、価値観などによっては、普段からセルフラブを実践できている方も存在します。
では、セルフラブが実践できている人にはどういった特徴が見られるのでしょうか。
①ポジティブな言動が多い
セルフラブができている人の多くは、ネガティブな事象が起こっても後ろ向きに捉えるのではなく、つねにポジティブで前向きな言動の傾向が見られます。
②自分自身の長所・短所を客観的に理解している
セルフラブは自分自身の短所に目を瞑ったり、見てみぬふりをするということではありません。
あくまでも長所と短所を客観的に理解していることが前提としてあり、そのうえでありのままを受け入れるという特徴があります。
③他者に優しく接している
セルフラブができている人は自分自身を受け入れると同時に、他人のことも受け入れる傾向が見られます。
見方を変えれば他者に対して優しく接するということでもあり、決して他人の短所や悪い点を責め立てるようなことはしません。
④一人で過ごす時間を大切にしている
ありのままの自分を受け入れるためには、客観的に自分を見つめることが不可欠です。
そのためにも、あえて一人で過ごす時間をつくり、客観的な視点に立って向き合っています。
また、セルフラブができている人は自分を他人と比較したり、他人に依存する必要もないため、一人で過ごす時間そのものが好きというケースも珍しくありません。
セルフラブとナルシズム・自己肯定感との違い
セルフラブと似た意味をもつ言葉に「ナルシズム」や「自己肯定感」があります。
これらはどういった意味があり、セルフラブとはどのような違いがあるのでしょうか。
①ナルシズムとは
ナルシズムとは、日本語では「自己愛」とも直訳されますが、セルフラブとは根本的に異なる概念です。
ナルシズムの特徴は、自分自身のみを愛すること、自分を必要以上に良く見せようとすることです。
セルフラブは自分自身を客観的に見つめ、ありのままを受け入れることを指しますが、ナルシズムは自分自身を過大評価する傾向があります。
また、ナルシズムは人から良く思われたいという気持ちが強いため、自慢をして他人の気を引こうとする傾向も見られます。
②自己肯定感とは
自己肯定感とは、その名の通り「自分自身を肯定する考え方」であり、ありのままの自分を受け入れたり、認めたりすることを指します。
冒頭でセルフラブとは「自己肯定感を高めること」と紹介した通り、自己肯定感とセルフラブはほとんど同じ概念といえます。
▶︎【自己受容】弱くてダメな自分を認めて受け入れるトレーニング方法
セルフラブのやり方・方法について

もともとネガティブ思考が強い人にとって、自分自身を肯定するセルフラブは簡単にできるものではないと感じがちです。
しかし、日常生活のちょっとした心がけや習慣を変えるだけでセルフラブを実践することは可能です。
①自分のことを整理してみる
まずは自分の強みと弱みを客観的に把握するために、自分自身と向き合いながら整理してみましょう。
強みや得意なこと、好きなことを書き出した後、弱みや不得意なこと、苦手なことを書き出してみましょう。
②ポジティブな言葉に言い換える
苦手なことや不得意なことに取り組むときや、仕事がうまくいかないときなど、つい弱音を吐きたくなることもあるでしょう。
そこで、「自分ならできる」、「大丈夫」という言葉に言い換えることにより、自分に自信が持てるようになります。
▶︎【ポジティブな自己暗示】アファメーションのやり方・効果について解説
セルフラブに悪影響を与える行動や習慣
セルフラブに取り組むにあたっては、ネガティブな言動を避けることが何よりも重要です。
ネガティブな言葉を発するようになると、まるでそれが呪文のように自分を苦しめてしまい、「自分はダメな人間だ」と無意識のうちに認識するようになります。
これではセルフラブと真逆の効果となってしまうため、上記で紹介したようにポジティブな言葉に言い換えることを意識してみましょう。
▶︎ネガティブな人でもできる自己肯定感を高める方法や習慣とは?
セルフラブをすることで人生にどんな影響がでるのか
セルフラブに取り組むことで、私たちの人生の幸福度は向上していきます。
たとえば、経済的な問題が解決できたとしても、自分に自信がない状態だと悪い部分だけを意識してしまい、幸福度は低いままとなります。
しかし、セルフラブに取り組むことで自分に自信がもてるようになると、多少の問題があったとしても前向きに捉えられるようになるでしょう。
このように、セルフラブは幸福度を高めるためにも有効な方法のひとつといえるのです。
まとめ
セルフラブとは、自分自身を肯定的に捉え、ありのままを受け入れることを意味します。
セルフラブを実践することで、自分に自信がもてるようになり、他人に依存することなく一人でいても寂しさを感じることがなくなるなど、さまざまなメリットがあります。
まずは自分自身のことを客観的に把握することがセルフラブの第一歩であり、ネガティブな言動をポジティブなものに変えていくことが重要です。
【ストレス解消】セルフケアの種類を紹介|意味や方法についても解説

心身の健康を維持するためには、自分自身の体調のわずかな変化に気付くことが重要です。
そのための方法のひとつとして、セルフケアがあります。
今回の記事では、セルフケアとはどういった意味を指すのか、セルフケアの種類とそれぞれの違い、すぐにでも実践できるセルフケアの方法などを解説します。
セルフケアとはどんな意味?
セルフケアの「セルフ」とは「自分・自己」といった意味を指し、「ケア」は「世話・管理」といった意味を指します。
すなわち、セルフケアとは自分自身の世話をしたり、健康管理をしたりすることであり、一言で表すとすれば「自己管理」にあたるでしょう。
また、日本看護学会では、セルフケアを以下のように定義しています。
「セルフケアとは、対象がよい健康状態を維持するために、みずから実施する日常生活上および健康管理上の行動をいう」
病気やケガをしないように心がけることはもちろんですが、身体的な健康維持だけでなく、ストレスをうまくコントロールしながら精神的な疾患を予防することもセルフケアのひとつといえるでしょう。
▶︎【変わりたいあなたへ】自分を変えることは難しい?変われる方法や習慣
セルフケアの重要性やメリット
一人ひとりがセルフケアを行うことで、どういったメリットがあるのでしょうか。
もっとも大きいポイントとしては、健康管理において問題が起こる前に対策することで、病気やケガの防止につながる点です。
仕事や家事、育児などに忙しい毎日を送っていると、自分自身の体調の変化や健康に向き合う時間がとれず、異変に気付かないこともあります。
その結果、自分でも気付かないうちに病気が進行してしまい、取り返しのつかない状態になることもあるでしょう。
また、これは心理的なストレスも同様であり、知らないうちに精神疾患を患っているケースもあります。
精神疾患が進行し重症化すれば、治療に取り組んでもなかなか改善できず長期化するおそれもあるのです。
このような事態を防ぐためには、日頃からセルフケアに取り組み、自分自身の体の異変やストレスと向き合い、現状を把握することが重要といえます。
早い段階で自分自身の体で起こっている変化に気付くことができれば、早期の治療につながり重症化を防げるメリットがあるでしょう。
▶︎”自分らしく生きる”とは?|仕事や恋愛で自然体で過ごせる方法を紹介
企業や会社でセルフケアが注目されている理由

セルフケアは健康管理の意識が強い個人はもちろんですが、企業においても注目され始めています。
健康管理は社員個人が自主的に取り組むものというイメージもありますが、現在多くの企業では「健康経営」がキーワードとなっており、さまざまな取り組みが行われるようになりました。
また、日本ではさまざまな業種・企業において人手不足が深刻化しており、健康上の理由で離職するケースも少なくありません。
企業が社員に対してセルフケアに関する専門的な知識や方法などを伝えることで、社員の健康維持につながり離職率の低下にも貢献できるでしょう。
セルフケアの7つの種類
一口にセルフケアといってもさまざまな種類があります。
セルフケアを実践するうえで参考にしておきたい7つの種類をそれぞれ解説しましょう。
①身体的セルフケア
身体的な健康を実現するためのセルフケアを身体的セルフケアとよびます。
身近なところでは感染症の予防なども身体的セルフケアにあたるでしょう。
②感情的セルフケア
自分自身の感情を客観的に意識しながら観察し、管理することを感情的セルフケアとよびます。
企業が実施するストレスチェックなども感情的セルフケアに役立ちます。
③社会的セルフケア
仕事やプライベートなど、自分自身が社会のなかで生きていくうえでどのように人と付き合っていくかを考え、実践することを社会的セルフケアとよびます。
気持ちが乗らない場合や人付き合いが苦手な場合などは、無理につながりをもつ必要はありません。
④精神的セルフケア
精神的セルフケアは自分自身と向き合う時間を作りながら、興味のあることや気分転換になるようなことを実践するセルフケアです。
7種類のなかでも特に重要で本質的なセルフケアともいえるでしょう。
人によっても実践方法はさまざまで、一概にどれが正解というものはなく自分自身にマッチした方法を選ぶことが重要です。
⑤職場のセルフケア
普段の働き方や職場環境などを見直し、働きやすい職場をつくることが職場のセルフケアにあたります。
働き方を変えると聞くと個人レベルでは対処しづらいのではないかと捉えられがちですが、個人単位でできることも意外と多いものです。
⑥経済的セルフケア
理想的な暮らしや夢を実現するために、自分自身の経済状況を正確に把握することを経済的セルフケアとよびます。
⑦心理的/パーソナルセルフケア
私たちが生きるうえでは仕事だけでなく、充実した私生活も重要なポイントとなります。
また、人生のなかで実現したい夢や目標を定めることで、どういったキャリアを歩むべきか見えてくるでしょう。
このように、自分自身の私生活も含めて人生と向き合う時間をつくることが心理的もしくはパーソナルセルフケアにあたります。
▶︎【自己受容】弱くてダメな自分を認めて受け入れるトレーニング方法
セルフケアの具体例や実践方法

セルフケアにはさまざまな種類があることがわかりましたが、これらを実践するうえではどういった方法があるのでしょうか。
具体例をいくつか紹介します。
①身体的セルフケア
- たばこの量を減らす・禁煙する
- 適度な運動を習慣づける
- 食事のバランスを見直す
- 十分な睡眠時間を確保する
②感情的セルフケア
- ネガティブな気持ちにならないよう前向きな言葉を発する
- 自分自身を過度に責めすぎず優しくする
- 励ましてくれる人やポジティブな言葉をかけてくれる人と付き合う
③社会的セルフケア
- 地域のコミュニティに所属し近所付き合いを行う
- 興味のある分野や趣味のサークルに顔を出してみる
- 人付き合いが苦手なため、最低限のコミュニティにのみ所属する
④精神的セルフケア
- 1日に10分程度、瞑想の時間をつくる
- 毎日の出来事を日記に書き留めておく
- 読書を習慣づける
⑤職場のセルフケア
- デスクの上を整理し、使用頻度の高いものはすぐ取り出せるようにしておく
- ToDoリストを作成しておく
- 作業のみに集中的に取り組む時間を決めておく
⑥経済的セルフケア
- 家計簿をつけてムダな支出がないかを見直す
- 貯金や資産運用を始めてみる
- 友人から金銭的な援助を求められても、経済的余裕がない場合はきっぱりと断る
⑦心理的/パーソナルセルフケア
- 身につけたいスキルや知識をリスト化する
- 本業とは関連がなくても興味のあることに没頭してみる
- 読書や勉強などスキルアップの時間を確保する
セルフマネジメントやセルフラブとの違い
セルフケアと似た意味をもつ言葉として、セルフマネジメントやセルフラブがあります。
混同されることも多いこれらの言葉について、どういった違いがあるのか解説しましょう。
セルフマネジメントとは
自分自身の感情や行動、思考を制御することをセルフマネジメントとよびます。
たとえば、仕事でミスをしたとき、原因は何だったのかを的確に捉え、同じミスをしないようにフォローすることで自分自身の成長につながっていきます。
セルフマネジメントのなかにはキャリアデザインやメンタルヘルスケア、アンガーマネジメントといったさまざまな要素が含まれ、これらは仕事を円滑に進めていくために重要なものです。
これに対しセルフケアは、あくまでも自分自身の心身の健康を維持するための管理であり、目的が異なります。
セルフラブとは
セルフラブとは、自分自身を過度に責め立てたり否定したりせず、ありのままを受け入れ認めることを指します。
セルフケアは心身の健康のために具体的な行動を起こしてケアするのに対し、セルフラブはマインドや考え方といった内面的なケアをするのが大きな違いといえるでしょう。
▶︎セルフラブとはどんな意味?自分を愛す方法や自己肯定感との違いを解説
セルフケアができていないとどんな悪影響があるのか
セルフケアに取り組むことで、体調のわずかな変化に気づき病気の早期発見、早期治療につながります。
しかし、セルフケアができていないと、原因不明の体調不良に陥ることも多く、仕事に対するモチベーションが上がらなかったりパフォーマンスが低下したりして仕事にも悪影響を及ぼすことがあるでしょう。
これは個人の問題にとどまらず、企業としても生産性の低下を招くおそれがあるのです。
まとめ
セルフケアは一人ひとりが取り組むものであり、特に企業や組織においてはストレスとうまく付き合っていくうえで不可欠なものです。
セルフケアにはさまざまな種類があり、すぐにでも実践できるものも少なくありません。
今回紹介した実践方法の例も参考にしながら、少しずつでもセルフケアに取り組んでみましょう。
ヨガがメンタルヘルスに良いと言われる理由|ヨーガって本当はどういう意味?
「ヨガ」と聞いてどんなイメージを持ちますか?
「ポーズ」「健康法」「瞑想」「生き方」など、人によって異なるイメージを持っているかもしれません。
そして、そんな奥深さがあることもヨガの魅力ではないでしょうか。
ヨガの練習を続けていくことで、他のエクササイズやリラックス法では感じることができない体と心、そして精神の向上と安定を得ることもできます。
今回は、そんなヨガとは何なのか、またその効果として挙げられるメンタルヘルスとヨガの関係について解説します。
ヨーガとは?

ヨガの世界では「悟り(サマーディ)」を最終目標にしています。
そして、その悟りまでの過程で得られるものすべてをヨガと呼びます。
では悟りとは何でしょうか?
悟りとは、全てのことから解放され、形や時を超えた境地のこと。
現代ではポーズのイメージの強いヨガですが、その悟りの境地までの練習過程には呼吸法や瞑想法、チャンティング、マントラ、祈り、さらにはオフザマット(Off the mat / ヨガマットの外、マットのない時)など、ヨガ的な実生活の行いも含まれます。
現代生活では、こうした追求を積み重ねていくとことで悟りの境地にたどり着くまでに得られる恩恵が非常に多く、それが多くの人にヨガが愛されている理由ではないでしょうか。
例えばヨガを行うことで体力がつき、体の巡りも良くなります。
また、女性であれば年齢とともに衰えてくる骨盤底筋群なども鍛えることができるので、尿もれトラブルを予防したり、緩和してくれることもあるでしょう。
もちろん精神的な面でも安定しやすい心を育て、現代社会を生きやすくしてくれます。
◆【簡単】メディテーション(瞑想)のやり方・意味|マインドフルネスとの違いは?
◆アファメーション(ポジティブな自己暗示)のやり方・効果について解説
ヨガを続けることがメンタルヘルスに良い影響がある

たくさんの恩恵があるヨガの練習ですが、中でもメンタルヘルスの向上に非常に役立つと言われています。
ヨガ文献で世界最古の古典書である『ヨガスートラ』には以下のように記されています。
“心の作用を止滅させることがヨーガである”
もう少し噛み砕いて言うと、ヨガの練習を続けることで心の動き(モヤモヤやイライラ、不安といったメンタルヘルスに悪影響を及ぼすものなど)に左右されなくなるというわけです。
もちろん、一度や二度ヨガのポーズをしたからといってすぐできるわけではありません。
また前述した通り、ヨガはポーズの練習だけでなく、呼吸法や瞑想、またヨガ哲学に則ったヨガ的な実生活を送ることが大切です。
こうした健康的なライフスタイルを選択し慣れ親しんでいくことで、心の動きに左右されなくなったり、自分の体や心に起こっていることを客観的に観察できるようになってくるのです。
そして、ジャッジせずに“ありのままの自分”を受け入れられるようになります。
もちろん、ヨガ単独で深刻な心の病を解決できるわけではないことを覚えておかなければなりません。
一方で、医療や心理的ケアの補助として続けていくことは十分に役立つと言えるでしょう。
◆”自分らしく生きる”とは?|仕事や恋愛で自然体で過ごせる方法を紹介
【自分のことがわからないで苦しい方へ】自分を理解する方法をご紹介

仕事や私生活が順調なときはそれほど意識することはありませんが、何らかの問題や課題に直面したとき、自分がわからなくなり、見失ってしまうことがあります。
自分が得意なこと、強みであると認識していたことに対しても自信を失ってしまうと、生きる気力すら湧いてこなくなることも。
そこで本記事では、「本当の自分がわからない」という悩みを持つ方に向けて、自分を理解するための対処法を紹介します。
「自分がわからない」という心理状態
人の心や精神は複雑で、家族や親友、恋人といった親しい間柄にあったとしても、他人の心理を完全に理解することは難しいものです。
しかし、本人が自分自身のことをすべて理解しているかと言われれば、必ずしもそうとは言い切れません。
たとえば、ふとした瞬間に自分は何者なのかが分からなくなったり、自分の強みや長所を見失ったりして、人生に対して悲観的になってしまうこともあります。
このように、自分のことがわからない心理状態に陥ってしまうと、人によっては感情が動かなくなったり、自分に対して「怖い」、「苦しい」といった感情を抱いたりするケースも多いのです。
「自分で自分のことがわからない」という心理状態に陥ったことがない人にとっては、当事者の気持ちや感覚を理解するのは簡単なことではありません。
そのため、家族や友人、恋人同士であっても、さまざまな軋轢を生むケースがあります。
自分がわからなくなる2つの原因
自分で自分のことがわからなくなるのは、幼少期の環境や人間関係、それまでの経験、性格、価値観など、さまざまなことが要因として考えられます。
断定することは難しいですが、主に考えられる原因をいくつか紹介しましょう。
①自己主張をすることが苦手
自分自身の考えや意見などを主張することが苦手で、周囲に流されやすい人ほど、自分がわからなくなりがちです。
たとえば、幼少期に親から過度なしつけや干渉をされてきた人のなかには、自分の意見を言っても否定されたり、親の指示通りに動くことが癖になっているケースもあります。
そのような環境で育ってきた人が学校を卒業して社会に出たとき、自分自身の意見や考えを主張できず、その結果として自分を見失ってしまうことがあるのです。
②周囲に助けを求めることが多い
自分自身で物事を決められない、または行動を起こすことが苦手な人ほど、周囲の人に助けを求める場面が多いものです。
しかし、つねに周囲の意見やアドバイスだけを参考にしてしまうと、自分の意見や考えをもてなくなることもあるでしょう。
その結果、自分はどうしたいのかわからなかったり、何を考えているのか見えずに悩んでしまうケースがあるのです。
◆【ストレス解消】セルフケアとはなにか?意味・種類・方法について解説
毒親育ちは自分がわからない人が多い?

子どもに対して過度に干渉・管理したり、自分の価値観を押し付けたりしてストレスを与える親のことを毒親といいます。
また、このような精神的な支配だけでなく、暴力などによって物理的に支配しようとするのも毒親の特徴です。
毒親のもとで育った子どもの多くは、上記でも紹介した通り自分の意見や考えを否定されることを知っています。
そのため、自分の意見や考えを通そうとするのではなく、親の指示や意見に従うようになります。
親の指示通りに動くことが、自分自身を守る術であると認識しているためです。
しかし、そのような環境下で育ってしまうと、自分の意見を発すること=悪いことである、と誤った認識が定着するケースもあります。
その結果、成人して社会に出たとき、自分がどういった人間であるのかがわからなくなることが多いのです。
自分がわからないとどんな場面で困るのか
自分がわからないと、仕事はもちろん私生活の面でもさまざまな問題や困りごとが起こります。
具体的にどういった場面で困難に直面するのか、代表的な例を見てみましょう。
①就職活動や転職活動がうまくいかない
ひとつ目は、就職活動や転職活動への影響です。
就職活動や転職活動では、エントリーシートや面接で自分自身の適性や強み、弱みを含めて説明する必要があります。
どういった適性や強みを業務に活かせるのか、そのうえで入社後にどのように貢献できるのかをアピールすることで、採用に結びつけられるためです。
しかし、そもそも自分のことがわかっていないと、選考の段階でアピールできず不採用になってしまう可能性があります。
②仕事が長く続かない
就職活動や転職活動に成功し企業へ入社できたとしても、また別の問題に直面することがあります。
それは、仕事そのものが長く続かず、短期間で転職を繰り返してしまうことです。
就職先や転職先を選ぶ際、自分に合った仕事を見つけるには自分自身の適性や長所、短所を把握することが第一歩となります。
しかし、自分がわからないとそのような分析もできず、さまざまな仕事を転々と繰り返してしまうことも少なくありません。
③恋人や友人ができない
私生活の面では、人間関係がうまく構築できないといった問題が生じることがあります。
自分のことがわかっていないと、意見や考え方をうまく表現することができません。
その結果、周囲の人からは「何を考えているのかよくわからない人」といった印象を抱かれてしまい、自然と距離を置かれてしまうことも。
恋人や友人をつくりたくても、他人とうまくコミュニケーションがとれずに孤立してしまうケースがあるのです。
◆自己肯定感が低い子供の特徴や言動とは|注意すべき親の発言や行動について
自分がわからないで苦しい時の対処法

自分のことがわからず悩んでいる方は、どのように問題を解決していけばよいのでしょうか。
いくつか有効な対処法を紹介します。
①自分を否定しない
もっとも重要なのは、自分で自分のことを否定せず、肯定的にとらえることです。
自分がわからないことで、さまざまな弊害や問題が生じてしまうのは仕方のないことです。
しかし、だからといって「そんな自分はダメな人間だ」と責める必要は一切ありません。
自分がわからなくなるのは、本人の意志の問題というよりは、それまで育ってきた環境や周囲の人間関係などが大きく影響しているケースが少なくありません。
そのため、自分のせいだと考える癖はやめて、心のなかで前向きな言葉に置き換えて考えてみましょう。
たとえば、自己主張をするのが苦手だと感じている方は、「周囲への配慮ができる」ととらえてみましょう。
考え方や捉え方を転換するだけで、少しずつ自信を取り戻すことができます。
②周囲の人に打ち明けてみる
自分のことがわからず悩んでいる人は、素直に周囲の人に打ち明けてみるのもひとつの方法です。
たとえば、親や兄弟、親友など、信頼できる人に打ち明けることで、ほかの人から見てあなたはどう映っているのか、客観的な意見を聞けるかもしれません。
自分ではネガティブに考えすぎていたことも、実際には周囲の人から見ればポジティブに映っている場合も多いものです。
第三者からの意見や考えを聞くことで、自分はどんな人間なのかがわかり自信を取り戻すきっかけになる可能性もあるでしょう。
③新たなことにチャレンジしてみる
仕事や趣味など、これまで経験したことのない新たなことにチャレンジしてみるのもおすすめです。
たとえば、キャリアアップに役立つ資格の取得に向けて勉強したり、興味のある仕事を副業としてやってみたりするのも良いでしょう。また、新たな趣味を楽しんでみるのもおすすめです。
新たなことにチャレンジしてみることで、自分でも知らなかった新たな一面が見えてくることもあり、自分自身を知るきっかけになるかもしれません。
自分を理解する・知ろうとする方法について
自分のことを理解し、詳しく知ることは一見すると簡単そうに見えますが、意外と難しいものです。
自分がわからないと悩んでいる方には、これまで紹介してきた内容以外にも、自分らしく生きることや、自己受容などさまざまな方法が効果的です。
以前に公開している「自分らしく生きるとは?」や「自己受容」などの記事もあわせてお読みいただき、参考にしてみてください。
◆【自己受容】弱くてダメな自分を認めて受け入れるトレーニング方法をご紹介
◆”自分らしく生きる”とは?|仕事や恋愛で自然体で過ごせる方法を紹介
まとめ
自分がわからないことは決して本人だけの責任ではなく、さまざまな要因が影響しているケースがあります。
そのため、決して自分を責めるのではなく、自分を受け入れたうえで前向きに考えることが重要です。
具体的には、新しい仕事や趣味にチャレンジしてみることもおすすめですが、ときには周囲の人に思い切って打ち明け、相談することも考えてみましょう。
【誰でもできる】マインドセットの意味や使い方を簡単に解説!
大きなプロジェクトを成功させ仕事で成果を上げるため、さらには人間として成長していくために、「マインドセット」とよばれる概念が重要です。
初めて耳にした方、または言葉は聞いたことがあるものの、詳しい意味は分からないという方も多いでしょう。
そこで本記事ではマインドセットとは何か、また、マインドセットを理解するメリットや活用できる場面、使い方なども詳しく解説します。
マインドセットの意味とは?

マインドセットとは、個人の性格や生まれ育った環境、経験、人間関係などをもとに形成された、固定化した考え方や価値観、行動の癖などを指します。
マインドセットは本来、心理学で用いられてきた専門用語でしたが、近年では人材育成の観点から注目されるようになり、ビジネス業界でも耳にするようになりました。
なお、心理学においてマインドセットは個人の考え方を指すニュアンスとして用いられますが、ビジネス業界では企業そのものの社風や風土を示す言葉としても用いられることがあります。
◆ヨガがメンタルヘルスに良いと言われる理由。ヨーガって本当はどういう意味?
マインドセットを理解することで得られるメリット
マインドセットが近年注目されるようになった背景としては、時代が急激に変化していることが挙げられます。
従来の社会では、多くの人が同じ価値観や考え方を共有する傾向にありました。
働き方やキャリア形成の変化はもっとも身近な一例といえるでしょう。
従来は新卒入社後、定年退職まで同じ会社で勤め上げる終身雇用制度が一般的であり、多くの人がそれを当たり前の働き方として受け容れてきました。
しかし、近年では転職が当たり前となり、副業やフリーランスとして活動するケースも珍しくありません。
これは働き方に対する価値観が変化した証ともいえるでしょう。
自分自身のマインドセットを理解することにより、価値観や考え方が時代にマッチしたものになっているかを客観的に把握できるほか、それらを意識することでマインドセットを柔軟にさせていくことも可能というメリットがあるのです。
マインドセットの2種類

一口にマインドセットといっても、実は「成長型」と「固定型」とよばれる2種類に分けることができます。
それぞれどういった違いがあるのか解説しましょう。
① 成長型
成長型とは、「成長マインドセット」または「グロースマインドセット」ともよばれます。
成長型のマインドセットを有している人は、「自分自身の能力・スキルは後天的なものであり、努力次第で向上させていける」という考えをもっています。
成長意欲に溢れ、何事にも積極的に挑戦し継続的に努力する傾向が見られます。
変化の激しい時代においては、一度身につけたスキルや能力があったとしても、それが一生役に立つとは限りません。
しかし、そのような状況であっても、成長型のマインドセットがあれば時代に即したスキルや能力を身につけることができるでしょう。
◆ポジティブ思考になる方法|うざいと言われる理由やプラス思考との違いは?
② 固定型
固定型とは、「硬直マインドセット」や「停滞型マインドセット」ともよばれます。
成長型とは対照的に、「自分自身の能力・スキルは先天的なものであり、努力をしても向上できない」という考えをもっています。
努力では何も解決しないという考えが根底にあるため、成長意欲に乏しく努力をしようとしません。
また、仕事やプライベートで何らかの問題が発生しても、他人に責任をなすりつけようとしたり、不正をしたりして解決を図ろうとします。
◆ネガティブ思考をやめたい方へ|止まらない原因やレベル診断、改善方法は?
マインドセットが怪しいと言われる理由
マインドセットを学んだり身につけたりするために情報を調べていくと、「怪しい」、「胡散臭い」といったネガティブな意見を目にすることもあります。
それはなぜなのでしょうか。
①目に見えるものではないから
もっとも大きな理由として挙げられるのは、マインドセットそのものが目に見えず、学んだ本人にしか分からないためです。
上記で紹介した通り、たとえば固定型のマインドセットをもっている人が、さまざまな書籍や研修、セミナーなどを通して成長型のマインドセットを習得できたとしても、その成果は本人にしかわかりません。
見た目が変わったり、試験の結果が良くなるなど客観的に判断する材料がないことから、本当に効果があるのか懐疑的な見方をしてしまうケースが多いのです。
②高額な費用のセミナーが存在するから
マインドセットを学ぶためのセミナーや研修のなかには、高額な受講料が請求されるものも少なくありません。
上記でも紹介したように、受講を検討している段階では客観的に効果を証明できるものがなく、懐疑的な見方をされてしまいます。
そのような、本当に効果があるか分からないにもかかわらず、高額な受講料を目にしてしまうと、率直に「怪しい」と感じることは決して不思議ではありません。
マインドセットの使い方や活用できる場面

マインドセットを理解することで、ビジネスおよび日常生活ではどういったことに役立つのでしょうか。
①ビジネスにおける使い方
ビジネスでは、入社間もない新入社員から実務の主力となる中堅社員、組織を引っ張っていく管理職やリーダーまでさまざまな立場においてマインドセットは役立ちます。
たとえば、新入社員の場合は、社会人としてのマインドセットを身につけることでビジネスパーソンとしての自覚と責任感が高まり、主体的に仕事へ取り組めるようになるでしょう。
また、中堅社員の場合は仕事に対してポジティブなマインドセットを身につけることで、次のステップに向けた成長意欲を高められるはずです。
管理職やリーダーの場合は、一般社員よりも広い視野に立って考えるマインドセットを身につけることで、組織全体の利益につながる行動や考え方ができるようになるでしょう。
②日常生活での使い方
日常生活においては、新たな価値観や考え方を学びマインドセットとして取り入れることで、ストレスを緩和し幸福度を高められます。
たとえば、他人に対して「こうあってほしい」といった理想があると、思い通りにならなかったときに苛立ちやストレスを感じてしまいます。
しかし、そもそも自分と他人は異なる存在であり、思い通りにならないというマインドセットが身についていれば、ストレスを感じることもなくなるでしょう。
これにより、良好な人間関係を築くこともできます。
◆アファメーション(ポジティブな自己暗示)のやり方・効果について解説
誰でもできるマインドセットのやり方

マインドセットを変えると聞くと、一人では難しいのではないかと感じてしまいます。
しかし、実際には正しい手順や方法を知っておけば、誰でも手軽に取り組むことができるのです。
①理想や目標を言語化する
はじめに、自分自身がどうなりたいのか理想の姿をイメージし、目標を言葉にして書き出します。
「ネガティブ・後ろ向きな性格を直したい」という漠然としたイメージがある場合には、「人付き合いを積極的にできる、社交的でポジティブな性格にしたい」など、具体化したほうが良いでしょう。
②毎日記録をつける
理想や目標に向けて毎日漠然と取り組むのではなく、記録をつけるようにしましょう。
日記のように記録することを習慣化することで、着々と目標に近づいていくことを自然と意識できるようになります。
③理想や目標に向けて実行する
設定した目標をクリアするために何に取り組むべきなのかを考え、すぐに実行に移します。
たとえば、上記で挙げた「人付き合いを積極的にできる、社交的でポジティブな性格にしたい」という目標に対しては、「1日◯人以上に挨拶をする」など、簡単なことから始めてみましょう。
④第三者から指摘してもらう
友人や知人など、信頼できる第三者から、自分自身の行動で改善したほうがよい部分がないかを指摘・アドバイスをもらいましょう。
たとえば、自分では明るく挨拶をしているつもりでも、相手にとっては声が小さく聞き取りづらかったり、表情が固く不自然な笑顔であったりすることもあります。
無意識のうちに癖が出ていることもあるため、第三者から指摘してもらうことは重要です。
◆【簡単】メディテーション(瞑想)のやり方・意味|マインドフルネスとの違いは?
マインドセット以外にも知ってほしい思考・メンタルケア
自分自身の思考を客観的に見つめ直したり、正しいメンタルケアを実現するうえでマインドセットは有効な概念のひとつです。
しかし、マインドセット以外にも、たとえばアンガーマネジメントやセルフケア、アフォメーションなどさまざまな概念も存在します。
仕事やプライベートを充実させるためにも、マインドセットと合わせて以下の記事も参考にしてみてください。
>>合わせて読みたい<<
◆【怒りを抑える】アンガーマネジメントのやり方・テクニックをご紹介!
◆【ストレス解消】セルフケアとはなにか?意味・種類・方法について解説
◆アファメーション(ポジティブな自己暗示)のやり方・効果について解説
まとめ
仕事はもちろん、プライベートにおいても人間同士の付き合いやコミュニケーションは欠かせないものです。
しかし、人によっても物事に対する考え方や価値観は異なり、それが原因でさまざまなトラブルに発展することもあります。
このような事態を防ぐためにも、まずは自分自身がどういったマインドセットをもっているのか把握することが第一歩といえます。
ネガティブ思考をやめたい方へ|止まらない原因やレベル診断、改善方法をご紹介
仕事やプライベートにおいて、なぜかいつも悪い方向に考えてしまい、ネガティブ思考に陥ってしまう方も多いのではないでしょうか。
ポジティブ・ネガティブといった概念は、その人の性格や考え方、価値観などに影響するものと捉えられがちですが、実際には人間関係や環境が大きく影響している場合がほとんどです。
そこで本記事では、ネガティブ思考から脱却したいと考えている方に向けて、ネガティブ思考に陥る原因や診断方法、ポジティブ思考へと変化させるための方法も紹介します。
ネガティブ思考が止まらない原因

ネガティブ思考が癖になっている人は本人の性格や価値観の問題もありますが、それ以外にもさまざまな原因が関係していると考えられます。
どういったことがネガティブ思考の原因になりがちなのか、代表的なものを3つ紹介しましょう。
① 大きな挫折や失敗を味わった経験がある
仕事やプライベートで過去に大きな挫折や失敗をした経験がある人は、そのことが頭から離れずネガティブ思考に陥ってしまうことがあります。
たとえば、受験に失敗したり大学を留年した経験や、仕事でミスをして大損害を会社に与えてしまった経験などは、自分でも思い出したくないほど辛いものです。
しかし、ふとした瞬間にこれらを思い出してしまうと、自分自身が嫌になり延々とネガティブ思考が止まらなくなってしまいます。
② 人間関係の悩み
自分自身の過去だけでなく、周囲を取り巻く人間関係もネガティブ思考の原因になることがあります。
たとえば、自分に対して否定的な言葉を投げかけてくる人がいると、「自分はダメな人間なんだ」と考えるようになり、自然とネガティブ思考に陥っていきます。
③ 生活習慣
普段の生活習慣がネガティブ思考を招くこともあります。
特に注意したいのが、日中に睡眠をとって夜に活動する夜型の生活です。
日光を浴びる機会が極端に減ることで、セロトニンとよばれる物質が体内で生成されにくくなります。
セロトニンは幸福感を得るために重要な物質であり、これが不足すると自然とネガティブ思考に陥っていくことがあるのです。
◆ポジティブ思考になる方法|うざいと言われる理由やプラス思考との違いは?
ネガティブ思考とマイナス思考の違い
ネガティブ思考と似た言葉に「マイナス思考」があります。
両者は同じようなニュアンスで使われることも多いですが、どういった違いがあるのでしょうか。
マイナス思考とは、その名の通りものごとをマイナスの方向、すなわち悪い方向に考えてしまうことを意味します。
ネガティブ思考もある意味ではマイナス思考ともいえますが、状況に応じて考え方が変化することが大きな違いといえるでしょう。
ものごとが不利な状況にあるときに、悪い方向に考えてしまうのをネガティブ思考といいますが、マイナス思考は状況にかかわらず悪い方向に考えるという点で大きく異なります。
◆自己肯定感が低い子供の特徴や言動とは|注意すべき親の発言や行動について
ネガティブ思考が嫌われる・うざいと言われる理由

ネガティブ思考の人は周囲から良く思われにくく、嫌われたり「うざい」、「鬱陶しい」と感じられたりすることがあります。
それはなぜなのでしょうか。
もっとも大きな理由として挙げられるのは、ネガティブ思考が周囲に悪影響を与えてしまうことがあるためです。
たとえば、職場の同僚や仲間がいつも不平不満を撒き散らしていると、全体の仕事に対する士気が低下してしまいます。
その結果、生産性が下がりボーナスの査定や人事評価にも悪影響を与えてしまうでしょう。
仕事は決して楽なものではありませんが、そのなかでもやりがいを見いだしたり、楽しみながら仕事をしたいと考える人は多いものです。
ネガティブ思考の人がいると、仕事そのものへの妨げになることから、嫌われたり「うざい」と感じられたりするのです。
ネガティブ思考のレベル別診断
ネガティブ思考・ポジティブ思考は人間であれば誰しも備わっているものです。
あるときはポジティブ思考であったのに、その翌日になると後ろ向きな気持ちになってネガティブ思考に陥ってしまうケースもあるでしょう。
重要なのは、自分自身がどの程度のポジティブ思考・ネガティブ思考の傾向があるのかを知っておくことです。
大まかな傾向を知っておけば、自分自身の考え方の癖をもとに正しい方向に導いていけるでしょう。
そこで参考にしてほしいのが、ネガティブ思考のレベル別診断です。
一口にネガティブ思考といっても、人によってその程度はさまざまです。
以下の診断を行うことで、自分自身がどの程度のレベルにあるのかを客観的に調べられます。
マイナス思考診断
ポジティブorネガティブ度診断! あなたは前向き?ネクラ?
あなたはどちら?ポジティブorネガティブ診断
ネガティブ思考の診断サイトは上記以外にもさまざまなところがあるため、複数のサイトの診断結果を参考にしてみるとよいでしょう。
ネガティブ思考が仕事や恋愛で与える影響

ネガティブ思考をもっていると、仕事や私生活にどういった影響が及ぶのでしょうか。
ここでは仕事面で与える影響の一例と、恋愛面で与える影響の一例をそれぞれ紹介します。
①仕事面で与える影響
仕事面への影響としては、上記でも紹介した通り、部署やチーム全体における仕事への士気低下が考えられます。
「どうせ無理だ」、「目標は達成できないだろう」といった気持ちの同僚がいて、毎日のようにそういった後ろ向きな言葉が飛び交っていると、本来やる気のある社員までもがネガティブ思考に陥ってしまい生産性が低下します。
一方、そのようなネガティブな言葉に惑わされることなく仕事に取り組む社員もいますが、ネガティブ思考の社員を鬱陶しく感じてしまい、職場全体の雰囲気や人間関係が悪くなることもあります。
②恋愛面で与える影響
ネガティブ思考は恋愛面においてもさまざまな影響を与えます。
ネガティブ思考の人の多くは、自分に自信がなかったり、自虐的になる傾向があります。
自信がなく、極度に自分自身を卑下するような人は、異性からも魅力的に映らず恋愛対象外と見られてしまうことも。
また、すでに恋人や好きな人がいたとしても、相手のわずかな言動の変化や言葉に傷ついてしまったり、少しでも連絡が途切れるとしつこく問い詰めてしまったりと、信頼関係を築くことが難しくなる場合もあるでしょう。
ネガティブ思考は他者にもうつる?
ネガティブ思考は他者に感染するようにうつっていくことがあります。
たとえば、職場やコミュニティ内で誰かが他人の悪口や噂話を切り出したとき、それに便乗するように話が盛り上がったという経験はないでしょうか。
また、SNSでも毎日のようにネガティブなワードがトレンドに上がっています。
もともとはポジティブ思考な人であっても、ネガティブ思考に触れ続けることで悪い方向へ影響を受けるという研究結果も出ているのです。
ネガティブ思考を改善する方法

ネガティブ思考が癖になっている人のなかには、ポジティブ思考へと切り替えていきたいと感じることも多いでしょう。
そこで、ネガティブ思考を改善するために習慣づけたい方法の一例を紹介します。
①自分を責めすぎない
ネガティブ思考を改善するための第一歩は、自分で自分のことを認めてあげることです。
自分がもっているネガティブな側面を否定してしまうと、さらにネガティブ思考に拍車がかかってしまいます。
そのため、まずはありのままの自分を否定せず受け容れることが重要です。
◆【自己受容】弱くてダメな自分を認めて受け入れるトレーニング方法をご紹介
②人間関係を見直す
次に、人間関係を見直すことです。
周囲にネガティブ思考な人が多い場合には、できるだけ距離を置くようにし、ポジティブ思考な人と積極的に交流をもつことを心がけましょう。
ポジティブ思考の人の言動や考え方を真似することで、ネガティブ思考から徐々に脱却していける可能性があります。
③成功体験を積み重ねる
最後のポイントとしては、仕事やプライベートにおいて小さな成功体験を積み重ねていくことです。
たとえば、いきなり大きなプロジェクトや売上目標を立てても現実的ではなく、「さすがにこれは無理かも…」とネガティブな気持ちになるでしょう。
そこで、1ヶ月後や1週間後、1日ごとの目標を具体的に設定します。
どのような小さなことでも、目標を達成できたという成功体験を積むことでポジティブ思考に変化していきます。
◆ネガティブな人でもできる自己肯定感を高める方法や習慣とは?
まとめ
ネガティブ思考に陥るのは決して本人だけの問題ではなく、人間関係や環境などさまざまな要因が関係していることが多くあります。
そのため、自分自身を責める必要はなく、まずはありのままの自分を受け入れることが重要です。
ポジティブ思考になるには?|うざいと言われる理由やプラス思考との違いをご紹介
人の考えや価値観はさまざまで、もともと前向きな性格の人もいれば、後ろ向きな性格の人もいます。
ポジティブ思考・ネガティブ思考とよばれることもありますが、特にネガティブ思考な人のなかには「ポジティブ思考に変わりたい」と考えることもあるでしょう。
そもそも、ネガティブ思考な人がポジティブ思考に変わることはできるのか、そのためにはどういった方法が効果的なのかも含めて詳しく解説します。
ポジティブ思考の意味

ポジティブ思考のポジティブ(positive)とは、「明確」や「積極的」、「自信のある」といった意味を指す言葉です。
また、陰・陽の「陽」を指す言葉でもあり、前向きな意味合いとして用いられることが多いです。
「ポジティブ」はすでに日本語でも定着しており、前向きな様子を指す言葉として日常的に用いられます。
すなわち、ポジティブ思考とは積極的かつ前向きな考え方や価値観のことを指します。
反対に、消極的で後ろ向きな考え方はネガティブ思考とよばれ、こちらも私たちの日常的な言葉として多く用いられています。
ポジティブ思考とプラス思考の違い
ポジティブ思考と似た意味を指す言葉にはさまざまなものがあります。
なかでも混同しやすいのが「プラス思考」ではないでしょうか。
プラス思考とは、ものごとを良い方向に考えることを意味します。
たとえば、大学入試やスポーツの試合、就職の採用面接などに臨む前は誰もが緊張し、結果がどうなるのか不安に感じるものです。
このとき、自分の良い面だけをイメージし「きっとうまくいく」と自分に言い聞かせ、自信をもって臨めるようにするのがプラス思考の人の特徴です。
反対に、自分の悪い面だけが頭をよぎり、「自分には無理かもしれない」、「負けるかもしれない」と悪い方向に考えてしまうのをマイナス思考といいます。
ポジティブ思考と同じように見えますが、プラス思考は「自分の良い面だけを見る」という面で大きな違いがあります。
あえて良い面だけを見ることで、悪い状況・不利な状況であっても前向きに考えられ、悪い流れを断ち切ることもできるでしょう。
◆自己肯定感が低い子供の特徴や言動とは|注意すべき親の発言や行動について
ポジティブ思考のメリット・デメリット

ポジティブ思考の特性をもっていることで、どういったメリットがあるのでしょうか。
また、反対にデメリットとして考えられることはないのかもあわせて解説しましょう。
ポジティブ思考のメリット
ポジティブ思考のメリットは主に以下の2点です。
①心身の健康を維持しやすい
ものごとをネガティブな方向に考えてしまうと、「自分はダメな人間だ」という自己嫌悪に陥ってしまいます。
また、少しの失敗を後に引きずりやすく、過去のことに悩み前に進めなくなることもあるでしょう。
このような考え方の癖がついてしまうと頑張りたくても体がなかなか動かなかったり、精神疾患を患ったりすることもあります。
しかし、何事も前向きにとらえるポジティブ思考が備わっていると、過去のことや失敗したことは割り切って考え、心身の健康を維持できるようになるでしょう。
②自己実現に向けて努力できる
仕事やプライベートにおいて、自分自身が理想とする姿や実現したい夢などを抱くことも多いはずです。
ポジティブ思考が備わっていると、自分がありたい姿や目標を実現するために何が必要なのかを考え、前向きに努力する原動力が生まれます。
「どうせ無理だろう」と考えるのではなく、「これをすれば実現できる」といった考える癖が身につき、少しずつ自己実現が近づいてくるはずです。
ポジティブ思考のデメリット
ポジティブ思考が備わっていることは決してメリットばかりではなく、ときにはデメリットとして捉えられることもあります。
①楽観的・無責任な人だと誤解されることがある
仕事やプライベートにおいて深刻な問題が起こったとき、ものごとを前向きに捉えることは決して悪いことではありません。
しかし、その程度が極端だと、チームや仲間から「考えが楽観的すぎる」、「無責任な人だ」と捉えられてしまう可能性もあります。
②頑張りすぎてしまう
ポジティブ思考の人の多くは、「逆境のなかでも前向きにいよう」と考えがちです。
しかし、そのようなことを意識しすぎてしまうと、疲労やストレスが溜まっていて休息が必要なのにもかかわらず、無理して頑張ってしまうケースも少なくありません。
ポジティブ思考な人の特徴とは
人は誰でも前向きな気持ちになることもあれば、後ろ向きな気持ちになることもあります。
両方の側面をもっていることから、自分はポジティブ思考なのかネガティブ思考なのか分からなくなることもあるでしょう。
では、ポジティブ思考の人にはどういった特徴があるのか、いくつか例を出しながら紹介します。
①外交的・社交的な性格
ポジティブ思考な人の多くは、人とコミュニケーションをとるのが得意で外交的・社交的な傾向が見られます。
たとえ人と意見や価値観が違っても、それをネガティブに捉えて自分や相手のことを責め立てることもなく、良好な人間関係を構築できます。
②柔軟で臨機応変な考えをもっている
社交的な性格であることにも関連していますが、ポジティブ思考な人は自分の意見や価値観に固執するのではなく、柔軟で臨機応変な考え方をもっています。
自分の意見ははっきりともっているものの、たとえ相手が180度異なる意見であったとしてもそれを受け容れ、理解しようとします。
③感情の起伏が穏やかで安定している
ものごとを後ろ向きに捉えてしまうと、意見が異なるときに自分が否定されたと感じるようになり、感情的になる人も少なくありません。
しかし、ポジティブ思考な人は決してそのような考えではなく、それぞれの考えを尊重できるようになります。
その結果感情の起伏が穏やかで、すぐに怒ったり不機嫌になったりすることがありません。
◆アファメーション(ポジティブな自己暗示)のやり方・効果について解説
ポジティブ思考がうざいと言われる理由

「ポジティブ思考」というワードを検索すると、検索候補に「うざい」という言葉が出てくることがあります。
これは、少なからず「ポジティブな人は苦手・鬱陶しい」と感じている人が存在することの証明といえるでしょう。
では、なぜ「ポジティブ思考がうざい」と感じられるのでしょうか。
特に大きな要因として考えられるのが、押し付けられているように感じてしまうということです。
たとえば、病気で寝込んでいる人に対して、元気な人が「体を動かせば元気になるよ」と言っても逆効果であり、むしろ反発を招くでしょう。
これと同様に、落ち込んでいる人に対してその人の気持ちを察することなく、「今のままではダメだよ」といった言葉を投げかけてしまうと、「自分の気持ちを理解してくれていない」と捉えられることもあります。
自分自身が前向きでいようと意識することは大切ですが、それを他人に押し付けてしまうと逆効果となることがあるのです。
◆【自己受容】弱くてダメな自分を認めて受け入れるトレーニング方法をご紹介
危険なポジティブ思考?「トキシック・ポジティビティ」とは
他人に対して前向きな思考を押し付けたとき、ポジティブ思考が「うざい」と捉えられることがあると紹介しました。
実はこのような行為は「トキシック・ポジティビティ」とよばれ、誰しもが無意識のうちに行っている可能性があるのです。
「トキシック・ポジティビティ」とは、臨床心理学者であるJaime Zuckerman博士が提唱したもので、以下のように定義されています。
「トキシック・ポジティビティとは、心の痛みを抱えていたり、困難な状況にあっても、ポジティブな考え方をするべき、または、私が大嫌いな言葉『ポジティブなバイブス』だけを発信するべきだ、という自分または他者による決めつけのことである。」
上記で例に挙げたような、「体を動かせば元気になるよ」といった言葉や、「後ろ向きな考えではなく、前向きに考えよう」といった言葉も、その人が置かれている状況や捉え方次第ではトキシック・ポジティビティに該当します。
重要なのは、ありのままの自分自身を否定することなく受け入れることと、ポジティブ思考を他人に強要しないことです。
ポジティブ思考になるためのトレーニング方法

どのような状況下でも前向きにいられるのは理想的であり、自分もポジティブ思考を身につけたいと考える方も多いでしょう。
そこで、日常生活のなかでも手軽にできるトレーニング方法をいくつか紹介します。
①日光を浴びる
朝起きたらまずカーテンを開け、日光を浴びるようにしましょう。
デスクワーク中心の仕事でも、意識的に窓を開けたり外を散歩したりして、日光を浴びることを心がけます。
日光を浴びることで、私たちの体内ではセロトニンとよばれる物質が生成されます。
これは幸福度を高めるために重要なホルモンであり、ポジティブ思考を維持するために欠かせない存在です。
②趣味を楽しむ
仕事や家事・育児に忙しくても、自分自身の時間は定期的に確保し趣味を楽しみましょう。
緊張状態が長く続くと脳が疲労し、前向きな思考を維持することが難しくなります。
家族や同僚の協力を得ながらでも、趣味の時間を確保することは重要です。
③理想像や目標を具体化する
前向きな姿勢を維持していくためには、自分が理想とする姿や目標を具体化し、常にイメージとして持ち続けていくことも重要です。
④言葉を言い換える
ネガティブ思考に陥っている場合、日常生活のなかで自然と後ろ向きな言葉を発していることがあります。
そこで、たとえば「どうせ無理だろう」は「もしかしたらできるかもしれない」、「疲れた・辛い」は「休みまであと◯日」といったように、ポジティブな言葉に言い換えてみましょう。
◆【誰でもできる】マインドセットの意味・使い方をわかりやすくご紹介!
ネガティブ思考でもポジティブ思考に変われるのか
ポジティブ思考・ネガティブ思考といった特性は、その人の性格や価値観などにも影響されます。
しかし、決してそれだけではなく、上記で紹介したような習慣を意識付けるだけでも変わることができます。
「自分はネガティブ思考だから変われないだろう」ということはなく、ネガティブ思考であると自覚していても努力次第でポジティブ思考へと変わっていくことは十分可能です。
◆ネガティブ思考をやめたい方へ|止まらない原因やレベル診断、改善方法は?
まとめ
ネガティブ思考が日常生活のなかで癖になっていると、ポジティブ思考な人を目にしたときに自分との違いを見せつけられ、自己嫌悪に陥ることもあります。
しかし、ポジティブ思考も度が過ぎてしまうと「うざい」、「鬱陶しい」と感じられることもあるため、他人に考えを押し付けないことが何よりも大切です。
もし、ネガティブ思考な自分自身をポジティブ思考へ変えていきたいと考える方は、今回紹介した習慣を参考に、取り組んでみてはいかがでしょうか。
自分を見失う人の特徴や原因|本来の自分を取り戻す方法は?

時として自分自身のアイデンティティーや価値観を見失い、自己評価が低下してしまう「自分を見失う」状態に陥ることがあります。
そこで、今回は「自分を見失う」人の特徴や原因、そして本来の自分を取り戻す方法についてご紹介します。
「自分を見失う」の意味とは
一般的に「自分を見失う」とは、自分自身の本来の考え方や価値観、自己イメージ、目標や希望など、自分自身の基盤となるものがわからなくなったり疑わしくなったりする状態を指します。
つまり、自分自身がどのような存在であるかを見失ってしまうことを意味します。アイデンティティーの喪失とも言い換えられるでしょう。
最近調子が悪いと感じていたり、何かに失敗してしまったときはもちろん、成功者や人生がうまく行っている人も自分を見失ってしまうケースがあります。
>>【自分がわからないことで苦しい方へ】自分を理解する方法をご紹介
自分を見失う原因は?
自分を見失う原因は様々なものが考えられます。
例えば、仕事や学校、恋愛、ママ友との関係などからのストレスや心理的な負荷、疲労や睡眠不足、周囲の環境の変化、自分自身の状態や人生の転機などが挙げられます。
また、社会的な価値観や周囲の人々からの影響によって、自分自身がどのような存在であるか見失ってしまうこともあります。
以下に代表的な原因をいくつか挙げてみます。
環境の変化
引っ越しや転職など、生活環境や社会的な立場が変わることで、価値観が変わってしまうことがあります。
これは決して悪いことではありませんが、そうなると、「今まで自分が信じていたものは何だったのか…」となり、自分を見失うことにつながってしまうことがあります。
ストレスや疲労
ストレスや疲労が長期間続くと、自分自身に向き合う精神的な余裕がなくなってしまいます。
その結果、自分自身が抱える問題や目標に向き合う力が低下し、自分自身を見失うことにつながるのです。
自己評価の低下
自己評価が低下することで、自分自身の存在価値や目的意識を見失うことがあります。
過去の失敗や失敗への恐怖、周りと比べて自分自身が劣っていると感じることが、自己評価の低下を引き起こす原因となるケースが多いです。
目的意識の不明確化
自分自身が達成したい目標や人生の目的を見失ってしまうことで、自分自身が目指すべき方向性がわからなくなることがあります。
他にも自分自身を見失ってしまう原因は多数あるため、「これが原因です」と一概には言えません。
一人ひとりが自分を見失ってしまった原因を理解し、本来の自分を取り戻すための具体的な方法を見つけることが大切です。
>>【自己受容】弱くてダメな自分を認めて受け入れるトレーニング方法
自分を見失う人の特徴

自分を見失っている人には、以下のような特徴が見られることがあります。
自分自身の意見や思考がわからない
自分自身が何を求めているのかわからなくなってしまうと、自分自身の思考や行動が停滞することがあります。
また、自分自身の意見や感情を表現することができず、周囲の人々に合わせることが多くなり、自分というものがなくなってしまったかのような感覚に陥るのです。
自己評価が低く、自分自身を否定的に捉えている
自分自身に自信がないと、自己評価が低くなってしまうものです。
自分自身を否定的に捉えてしまい、自分自身を批判的な目で見がちな方は注意しましょう。
自分自身の夢、人生に望むものや目標が見えていない
自分自身にとって本当に大切なものや、望むべき目標が見えていないことがあります。
急いで結論を出す必要はないので、自分自身の価値観や人生の方向性について考えることが必要になってくるでしょう。
自分自身の思考や行動が停滞している
自分自身の思考や行動が停滞してしまい、新たな発想やアイデアを生み出すことができなくなってしまうことがあります。
そうなると「自分は何も生み出せない虚無な人間だ」という思考に苛まれ、自分自身を見失ってしまうことにつながります。
周囲の人々に合わせることが多く、自分自身の意見や感情を抑えてしまう
周囲の人々との調和を保つことが大切であると考えてしまい、自分自身の意見や感情を抑えてしまうケースです。
「自分の意見を主張できなかった…」と必要以上に自責的になってしまうと、自分自身を見失ってしまうでしょう。
自分を見失っているかもしれない「見失い度診断」

自分を見失っているかどうかを自己診断するために、以下の質問に対して「はい」「いいえ」で答えてみましょう。
- 自分自身が何をしたいのかがわからないことがある
- 自分自身の考えや意見を周囲に伝えることができないことがある
- 自分自身の目標や希望が定まっていないことがある
- 自分自身の好き嫌いや感情を抑えることが多いと感じることがある
- 自分自身を否定的に捉えることが多いと感じることがある
もし、上記の質問に対して「はい」が多かった場合は、自分自身を見失っている可能性があります。
自分自身を見失っているかどうかを自己診断する際には、以下の質問にも答えてみましょう。
- 自分自身の過去や現在、未来について考えたとき、ワクワクするようなことはあるか?
- 自分自身が得意なこと、好きなことを自己評価できるか?
- 自分自身が抱えるストレスや不安について、周囲の人に相談することができるか?
これらの質問にも「はい」が少ない場合は、自分自身を見失っている可能性があります。
自分自身が何を求めているのかを見つめ直し、自分自身の意見や感情を大切にすることが大切です。
自分を見失うとどんな影響があるのか
自分を見失ってしまうと、以下のような影響が出ることがあります。
- ストレスや不安が増大することがある
- 自己肯定感が低下し、自分自身を否定的に捉えてしまうことがある
- 自分自身の意見や思考がわからなくなり、自分自身の人生や将来についての目標や希望が見えなくなることがある
- 自分自身が何をしたいのかがわからなくなり、行動が停滞してしまうことがある
- 自分自身が抑えている感情が蓄積し、爆発してしまうことがある
- 周囲の人々からの影響を強く受けやすくなり、自分自身の考えや感情を表現できなくなってしまうことがある
恋愛
自分を見失うと、自分の価値観や好みがわからなくなり、自分に合ったパートナーを選ぶことが難しくなる可能性があります。
子育て
自分を見失うと、自分自身が満たされずストレスがたまり、子育てに集中できなくなる可能性があります。
転職活動・仕事
自分を見失うと、自分が何をしたいのかがわからなくなり、自分に合った転職先や職場を選ぶことができなくなる可能性があります。
高校生・中学生
自分を見失うと、自分が何をしたいのかがわからず、進路選択に迷い、後悔することがあるかもしれません。
また、自己肯定感が低下し、学業に集中できなくなる可能性があります。
これらの影響は、自分自身や周囲の人々、そして社会全体に与える影響も大きいことがあります。
自分自身を見失っていることで、自分自身の可能性や才能を発揮できず、人生を十分に楽しむことができなくなってしまうことがあります。
自分を見失った時の自分を取り戻す方法とは

自分自身を見失ってしまった場合には、以下のような方法が有効です。
- 自分自身について考える時間を作ること
- 自分自身が何をしたいのか、自分自身の価値観や思考を整理すること
- 自分自身が興味を持つことや得意とすることを探すこと
- 周囲の人々からの影響を受けず、自分自身の考えや感情を表現すること
- 自分自身が望む将来像を描くこと
- 専門家のサポートを受けること
これらの方法を実践することで、自分自身を見失っていた状態から抜け出し、自分自身の人生を楽しむことができるようになることがあります。
ただし、自分自身を見失う原因は人それぞれ異なるため、自分自身に合った方法を見つけることが大切です。
>>【ストレス解消】セルフケアとはなにか?意味・種類・方法について解説
まとめ
自分自身を見失ってしまう人の原因や特徴について解説しました。
自分を見失う原因としては、自分の人生に不安を感じたり、周囲の期待に応えようとしすぎたりすることが挙げられます。
また、自分を見失うと、恋愛や子育て、転職活動、仕事、高校生などに悪影響を及ぼす可能性があります。
自分を取り戻す方法としては、自分自身と向き合い、自分の価値観や好みを見つめ直すことや、自分のために時間を作ることが大切です。
愛してるよりも愛が伝わる言葉とは?上手な伝え方を紹介

愛情表現の言葉を伝えることは、健康的な関係を維持するために重要であり、直接伝えることが望ましいです。
愛情表現を表す言葉には多くの種類があり、適切な言葉を選ぶことが大切です。
本記事では、愛情表現を表す言葉の種類や、「愛してる」よりも愛が伝わる愛情表現の言葉をご紹介します。
愛情表現の言葉を相手に伝えるメリット
愛情表現の言葉を相手に伝えることは、健康的な関係を維持するために非常に重要です。
相手に愛情を表現することで、相手は自分を大切に思ってくれていると感じ、 自己肯定感が高まります。
また、愛情表現の言葉は、相手との信頼関係を構築し、ストレスを軽減する効果があります。
愛情表現の言葉を相手に伝えるメリットは、その他にもたくさんあります。
まず、愛情表現の言葉を相手に伝えることで、相手との絆が深まります。
相手が自分を愛してくれていると感じることで、より強い絆が生まれ、相手との関係がより良いものになります。
また、愛情表現の言葉をかけられることにより、相手が自分を理解してくれていると感じることができます。
相手が自分を理解してくれていると感じることで、自分自身もより自信を持つことができます。
さらに愛情表現の言葉は、相手とのコミュニケーションを円滑にする効果があります。
相手が自分を理解してくれていると感じることで、コミュニケーションがスムーズになり、ストレスや不安を減らすことができます。
以上のように、愛情表現の言葉を相手に伝えることは、健康的な関係を維持するために非常に重要です。
相手に自分の気持ちを正直に伝え、相手との絆を深めることで、より良い関係を築くことができるでしょう。
>>ネガティブな人でもできる自己肯定感を高める方法や習慣とは?
愛情表現の言葉は直接言うべき?

結論から言うと、愛情表現の言葉は直接言うことが重要です。
間接的に伝える方法もありますが、直接伝えることで、相手が本当に大切な存在であるということを明確に伝えることができます。
間接的な方法をとると相手に伝わらない恐れがあるため、直接言うことが望ましいという側面もあります。
さらに、愛情表現の言葉を直接言うことで、相手にとっては非常にありがたく、喜ばれることが多いです。
愛情表現の言葉を聞くことで、相手が自分を大切に思ってくれていると感じることができ、自己肯定感が高まることがあります。
ただし、伝え方や受け取り方によっては誤解を招くこともあります。
愛情表現の言葉を言うことは大切ですが、普段からしっかりコミュニケーションをとることも忘れないようにしましょう。
また愛情表現の言葉は、相手の状況や気分によって適切なタイミングを見極めて伝えることが大切です。
相手が不安定な状況にある場合や落ち込んでいる場合には、タイミングを考慮して伝えるようにしましょう。
そうすることであなたが相手を心から思いやっていることが伝わり、信頼関係がより強化され、より良い関係を築くことができます。
愛情表現を表す愛の言葉の種類

愛情表現を表す言葉には、多くの種類があります。
代表的なものとしては下記が挙げられます。
- 「愛してる」
- 「大好き」
- 「ありがとう」
- 「一緒にいると癒される」
- 「一緒にいることが楽しい」
また、相手の性格や状況に合わせて、独自の言葉を作ることもできます。
さらに、愛情表現は行動や態度でも示すことができます。
- 一緒に過ごす時間を大切にする
- 相手の話を聞いて理解する
- 困っていたら手を差し伸べる
- 優しく触れる
- 笑顔で接する
上記は一例ですが、言葉以外にも様々な形で愛情を表現することができます。
また、言葉で相手に伝える場合には相手が理解しやすく、明確な言葉を選ぶことが重要です。
相手にとって分かりにくい言葉を使ってしまうと、伝えたいことが伝わらず、逆に相手を不安にさせることもあるでしょう。
また、相手が受け取りやすい言葉を選ぶことで、より深いコミュニケーションができ、より良い関係を築くことができます。
愛情表現を表す言葉や行動を選ぶことは、相手との関係を深め、より良いコミュニケーションを築くために不可欠なことといえるでしょう。
自分自身の気持ちを正直に表現し、相手を理解し尊重することが、より良い関係を築くための第一歩となります。
愛してるよりも愛が伝わる言葉とは?

「愛してる」という言葉は愛情表現の中でも代表的なものですが、その他にも伝え方によってはより愛が伝わる言葉があります。
例えば、「あなたと一緒にいると幸せだ」「いつもそばにいてくれてありがとう」といった言葉は、相手に対する感謝の気持ちが込められており、より深い愛情を表現することができます。
さらに、相手のことを思いやる言葉も、愛が伝わる言葉の一つです。
「疲れたら休んでね」「大丈夫、一緒に乗り越えよう」といった言葉は、相手を支える気持ちが込められており、相手にとって安心感や信頼感を与えることができます。
また、相手の良いところを褒める言葉も、愛が伝わる言葉の一つです。
「あなたの優しさにいつも癒されてるよ」「あなたの才能は本当にすごい」といった言葉は、相手が自分を認めてくれていると感じ、自己肯定感を高めることができます。
さらに、愛を伝えるには単語だけでなく、声のトーンや表情、身体言語など、言葉以外の要素も重要です。
相手に対して優しく微笑む、手を握って見つめる、抱きしめるなど、身体言語で相手に愛を伝えることもできます。
愛が伝わる言葉は、相手の心に深く響くものです。
相手が感じる愛情をより深く、より具体的に表現することで、より良い関係を築くことができるでしょう。
自分自身の気持ちを正直に表現し、相手を思いやり、尊重することが、愛情表現の重要なポイントとなります。
愛情表現の言葉の上手な伝え方とは
愛情表現の言葉を上手に伝えるためには、以下の点に注意することが大切です。
- 相手に合った言葉を選ぶ
- 自分の気持ちを正直に伝える
- 相手の表情や反応をよく見る
- 相手が伝えた言葉に対して、適切な返答をする
さらに、以下の点にも注意することが重要です。
まず、相手に合った言葉を選ぶことが重要です。
相手が受け取りやすい言葉や相手が理解しやすい言葉を選ぶことで、より伝えたい気持ちが相手に届きやすくなります。
また、相手の性格や状況に合わせて、伝え方を変えることも大切です。
次に、自分の気持ちを正直に伝えることが重要です。
相手にとって重要なことや、自分自身の気持ちを正直に伝えることで、相手との信頼関係を構築することができます。
その際、相手の表情や反応をよく見ることで、相手がどのように感じているのかを読み取るようにしましょう。
もし相手が困っているのに同じ方法で愛情表現し続けるのは、ただの押し付けになってしまいます。
最後に、相手が伝えた言葉に対して、適切な返答をすることも大切です。
相手が伝えた言葉に対して、素直な気持ちを伝えることで、より深いコミュニケーションができるようになります。
愛情表現の言葉を上手に伝えることは、相手との関係を深め、より良いコミュニケーションを築くために不可欠なことです。
相手に対して自分自身の気持ちを正直に伝え、相手を思いやり尊重することが、より良い関係を築くための第一歩となります。
愛情表現が苦手・恥ずかしいときはどう伝えればいいのか

愛情表現が苦手・恥ずかしいと感じる場合、以下のような方法を試してみましょう。
1.文字で伝える
直接伝えることが難しい場合は、メールや手紙などの文字で伝える方法もあります。
文字であれば、自分の気持ちをゆっくりとまとめることができ、相手のペースで受け止めてもらえるため、伝えやすいというメリットがあります。
2.行動で示す
愛情表現は言葉だけでなく、行動でも示すこともできます。言動に行動が伴なっていなければマイナスに作用することすらあります。
例えば、相手の好きなものをプレゼントする、手料理を作ってあげる、一緒に過ごす時間を大切にするなど、相手に対する思いやりや配慮を行動でも示すようにしましょう。
3.直接伝えるのを少しずつ練習する
愛情表現が苦手・恥ずかしいと感じる場合は、直接伝える練習をしてみましょう。
少しずつ伝え方を変えたり、相手に話しかける回数を増やしたりすることで、少しずつ慣れて自信をつけることができます。
また、相手が自分の気持ちを知っていることで、相手との関係がより深まる可能性があります。
以上の方法を試して、自分に合っていて、かつ相手が喜ぶ伝え方を見つけましょう。
愛情表現は相手との関係をより深めるために欠かせないものであるため、少しずつでも続けていく努力が必要です。
4.その背景を考える
愛情表現をしづらいと感じてしまうのは、過去の経験や自己肯定感の低さ、相手への不安や緊張感など、様々な要因が考えられます。
自分自身が何を恐れているのか、自分の感情を理解することで適切な対処法を見つけましょう。
相手とのコミュニケーションを通じて自分自身が成長できれば、自己肯定感を高めることができる場合もあります。
相手との関係を深めるためには、まずは自分自身を受け入れ、自分自身を大切にすることが大切です。
愛情表現が苦手・恥ずかしいと感じる場合でも、少しずつでも行動を起こし、自分自身の成長につなげられるようにしましょう。
相手との関係をより深めるために自分自身が積極的になり、コミュニケーションを続けていくことが望ましいです。
>>【変わりたいあなたへ】自分を変えることは難しい?変われる方法や習慣
まとめ
愛情表現を上手に伝えるためには、相手に合った言葉を選び、自分の気持ちを正直に伝え、相手の表情や反応をよく見て、適切な対応をすることが大切であることが伝わったでしょうか?
もし、愛情表現が苦手・恥ずかしいと感じる場合は、文字や行動で伝える方法を試してみるか、直接伝えることを少しずつ練習してみましょう。
メンタルヘルス対策を怠るデメリット|企業や地域が取り組むべき課題とは

現代社会においてメンタルヘルスの重要性が注目されています。
これは、社会の変化やストレス要因が増加していることが背景にあります。
- 長時間労働
- 過剰な情報や情報過多
- 社会的孤立
- 貧困
- 人間関係の問題
- 不安やストレス
上記のように原因が多様化し、メンタルヘルスの問題が深刻化していることが考えられるでしょう。
>>情緒不安定になると泣くのはなぜ?|情緒不安定になりやすい人や原因とは
メンタルヘルスの対策をするべき理由

メンタルヘルスの対策をすることは、個人だけでなく社会全体にとっても重要な課題です。
メンタルヘルスが悪化すると、生産性の低下、職場や学校でのトラブルやハラスメント、家庭内暴力など、様々な社会問題を引き起こすことがあります。
また、メンタルヘルスの悪化による身体的な病気のリスクも高まるため、予防や早期対応が必要です。
メンタルヘルスの対策を怠るデメリット
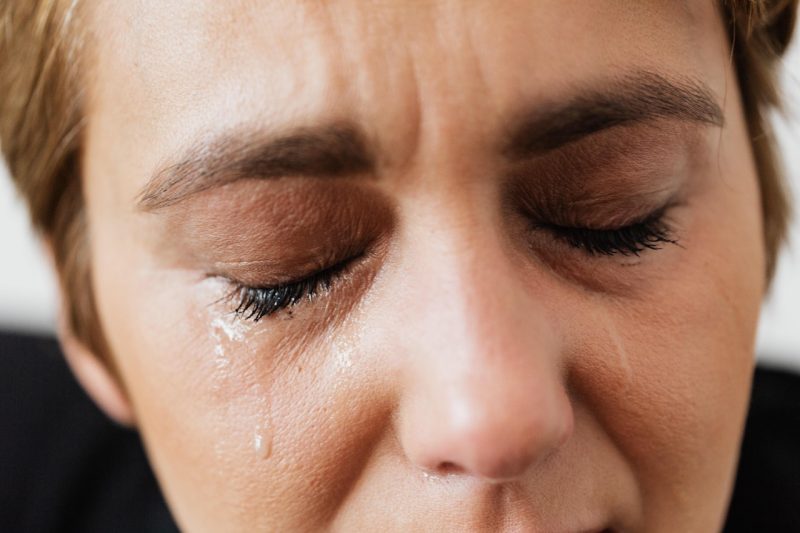
メンタルヘルスの対策を怠ると、深刻なメンタルヘルスの問題が引き起こされる可能性があります。
うつ病や不安障害、パニック障害などの精神疾患に陥り、社会生活や職場生活が困難になることがあります。
最悪の場合は社会的孤立や自殺などにつながることも珍しくありません。
メンタルヘルスとセルフケアとの違い

メンタルヘルスの対策には、セルフケアが重要な役割を担います。
セルフケアとは自分自身の健康や心の健康を維持するために行う、日常生活の中での様々な取り組みのことです。
一方、メンタルヘルスは精神疾患の治療や予防を含む、より専門的な対応が必要な問題です。
セルフケアを行うことで、メンタルヘルスのリスクを低減することができます。
>>メンタルヘルスを向上させるセルフケア方法。自分と向き合う時間を増やそう
>>【ストレス解消】セルフケアとはなにか?意味・種類・方法について解説
企業や地域によるメンタルヘルスの対策事例

メンタルヘルスの対策には、個人だけでなく企業や学校、地域社会など、様々なレベルでの取り組みが必要です。
具体的な対策事例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 職場や学校でのストレスマネジメントプログラムの導入
- メンタルヘルスの問題に対する啓発活動やカウンセリングサービスの提供
- フレックスタイム制度やテレワーク制度など、働き方改革の推進
- スポーツやレジャー、趣味など、リラックスする時間を確保することの推奨
- 地域の交流イベントやボランティア活動など、社会的なつながりを作ることの推奨
これらを取り入れることで、メンタルヘルスに悩まされる人を少しでも減らす努力が必要となるでしょう。
個人でできるメンタルヘルスの対策方法

個人でも、メンタルヘルスのリスクを低減するために、以下のような対策を行うことができます。
- 睡眠をしっかりとること
- 食生活を改善すること
- ストレスを発散する時間を確保すること
- 人間関係を大切にすること
- リラックスするための趣味やスポーツを見つけること
- 自己肯定感を高めること
- 何かを始める前にリラックスするための瞑想や深呼吸を行うこと
- 定期的な健康診断を受けること
これらの対策を継続的に行うことで、ストレスや不安、うつ病などのメンタルヘルスの問題を予防することができます。
>>ヨガがメンタルヘルスに良いと言われる理由。ヨーガって本当はどういう意味?
情緒不安定になると泣くのはなぜ?|情緒不安定になりやすい人や原因とは

急に情緒が不安定になり、突然泣きたくなることはないでしょうか。
自分でも理由が分からないのに、突然涙が溢れてくることもあるでしょう。
なぜ、こういったことが起こるのでしょうか。
本記事では情緒不安定について詳しく解説し、泣いてしまう理由やうつ病との違い、情緒不安定になりやすい人の特徴や原因、そして、情緒不安定になったときの対処法についてもお伝えします。
情緒不安定とはどのような精神状態なのか
情緒不安定とは、急激な気分の変化や感情の不安定さを特徴とする精神状態のことです。
感情の変化が激しく、一瞬で機嫌が変わることがあります。
そのため、周りの人からは「気分屋」と見られることがあるかもしれません。
また、自己評価が極端に変化し、自己否定感や孤独感を感じることもあります。
情緒不安定になる人には、ストレスに弱い人や心の傷を持つ人が多い傾向が見られます。
そのほか、日常的なストレスや疲れも情緒不安定の原因となることがあります。
このような状態が続くと、生活に支障をきたすこともあるでしょう。
例えば、職場や学校での人間関係がうまくいかなくなったり、社交的な場面に苦手意識を持つようになったりすることもあります。
そうなる前に、早めの対処が必要です。
>>感情の起伏が激しい人や少ない人の特徴|上手にコントロールする方法とは
情緒不安定になって泣く理由

情緒不安定になると、自己評価が低下して、自分に自信を持てなくなることがあります。
自分自身に対して厳しく、完璧主義者のような性格の場合、思い通りにいかないことや失敗をすることがストレスとなり、泣いてしまうこともあります。
また、過剰に人の評価を気にし、批判や拒否に強い不安感を抱くこともあります。
このような場合、他者とのコミュニケーションがストレスとなり、感情のコントロールができなくなっている状態であると考えられます。
この状態になると、自分を責めたり悲しい思い出に取り憑かれたりすることがあり、それが泣く原因になります。
さらに、女性の場合はホルモンの影響も原因になることがあります。
女性は、月経前症候群(PMS)や更年期障害により、ホルモンバランスが乱れることがあり、気分の変化や情緒不安定を引き起こすことがあります。
情緒不安定になると泣く以外でどのような症状があるのか

情緒不安定になると、泣くこと以外にも、以下のような症状が現れることがあります。
- 怒りっぽくなる
- イライラしたり、落ち着きがなくなる
- 不安感を強く抱く
- 無気力になる
- 自己嫌悪や罪悪感を感じる
- 自殺願望を持つ
情緒不安定の症状としてよく見られるのは、怒りっぽくなったり、イライラしたりすることが挙げられます。
小さなことで怒りが爆発してしまったり、人に対して攻撃的な態度をとったりすることもあるでしょう。
また、不安感を強く抱くようになったり、何をするにも不安を感じるようになったりすることもあります。
うつ状態となり何もする気力が起きず、日常生活に支障をきたす例も見られます。
また、自己嫌悪や罪悪感を感じるようになり、自分を責めたり、否定的な思考に陥ることがあるのも特徴です。
最悪の場合、自殺願望を持つこともあるでしょう。
不安が原因で睡眠障害を発症したり、食欲不振になったりと、精神面だけでなく体調面への影響が生じることも珍しくありません。
情緒不安定になる人は精神的なサポートを必要とする場合があります。早期に専門家に相談し、適切な治療を受けることが大切です。
>>ネガティブ思考をやめたい方へ|止まらない原因やレベル診断、改善方法をご紹介
情緒不安定になると泣く人はうつ病なのか

情緒不安定になると泣く人が必ずしもうつ病であるとは限りません。
うつ病は、気分が長期間にわたって落ち込んだり、生活に支障をきたすような病気です。
一方、情緒不安定になる人は、気分が急激に変化し、自己評価や人間関係に苦しみを感じることが多くあります。
情緒不安定になる人は、うつ病とは異なる疾患であり、それぞれに異なる対処が必要となります。
ただし、情緒不安定になることが原因でうつ病になることもあるため注意が必要です。
>>ネガティブな人でもできる自己肯定感を高める方法や習慣とは?
情緒不安定になりやすい人の特徴や原因

情緒不安定になりやすい人の特徴や原因には、以下のようなものがあります。
- 過去に心的外傷を受けた経験がある人
- 遺伝的な要因がある人
- ストレスに弱い人
- 人間関係でのトラブルや孤独感が強い人
- 自己肯定感が低い人
- 薬物乱用やアルコール依存症のある人
また、人間関係でのトラブルが多く、感情のコントロールが苦手で、自分自身に対して厳しい人や、完璧主義的な性格の人も情緒不安定になりやすいとされています。
情緒不安定になりやすい人の特徴や原因には、他にも以下のようなものがあります。
- 自分自身の感情や気持ちを理解することが難しい人
- 過去にトラウマを抱えている人
- 子供時代に愛着障害を経験した人
- 脳の機能や化学物質のバランスが異常な人
- 自己防衛のために感情を鈍らせることができない人
- 不安感や恐怖感を感じやすい人
これらの特徴や原因が複合的に作用することで、情緒不安定になる可能性が高まります。
しかし個人差があり、同じ境遇だからといって必ずしも全ての人が情緒不安定になるわけではありません。
情緒不安定になったときの対処法

情緒不安定になったときの対処法には以下のようなものがあります。
- 専門家の診断を受けること
- 自己肯定感を高める
- ストレスを軽減するために、リラックスした時間を過ごすこと
- 感情をコントロールするトレーニングを行うこと
- 自分自身と向き合い、自分自身を許すこと
- 健康的な食事や運動を行うこと
情緒不安定になったときは、周囲の人に自分の気持ちを伝えることが大切です。
自分一人で抱え込まず、身近な人や専門家のサポートを受けましょう。
治療には薬物療法や認知行動療法、精神療法などがあります。
情緒不安定になったときの対処法を実践してみて、それでも改善が難しければ専門家へ相談してみましょう。
自己判断による対処は逆効果になることケースが極めて多いです。
自己肯定感を高めるためには、自分の良いところや過去の成功体験などを振り返り、自分自身にポジティブなメッセージを送ることが大切です。
また、ストレスを軽減するためにはリラックスした時間を過ごすことが有効です。
ヨガや瞑想、アロマテラピーなど、自分に合った方法でリラックスしましょう。
感情をコントロールするトレーニングは、認知行動療法などを通じて行うことができます。
また、自分自身と向き合い、自分自身を許すことで自己受容力が高まります。
健康的な食事や運動を行うことも、情緒不安定になったときの対処法として効果的です。
十分な栄養素を摂取することで、身体の調子を整えることができます。
治療には、薬物療法や認知行動療法、精神療法などがあります。
専門家に相談して、自分に合った治療方法を選ぶことが重要です。
自分一人で抱え込まず、周囲の人や専門家のサポートを受けることで、回復に向けた一歩を踏み出しましょう。
まとめ
情緒不安定になると、泣くこと以外にも怒りっぽくなったりイライラしたり、自己嫌悪や罪悪感を感じたりすることがあります。
このような症状が現れた場合は、専門家の診断を受け、自己肯定感を高めたり、ストレスを軽減したりすることが必要です。
また、身近な人や専門家のサポートを受けることも大切です。
治療には薬物療法や認知行動療法、精神療法などがあります。早めの対処で心の健康を維持しましょう。
自分を認める方法|認めることの難しさや自己肯定感との関係性を解説
自分を認めることができない人は少なくないかと思います。
自己評価が低く、自分自身を肯定することができない人もいます。
しかし、自分を認めることは、自己肯定感を高め、より良い人生を送るための第一歩と言えます。
この記事では、自分を認めることの意味やその難しさの原因、自己肯定感との関係性について解説します。
また、自分を認める方法や効果、自己受容との違いについても述べていきます。
自分自身を肯定し、ポジティブな人生を送るためのヒントが満載ですので、ぜひ最後までお読みください。
「自分を認める」ことの意味とは

「自分を認める」とは、自分自身の感情や考え方、行動などを受け入れ、肯定的に評価することです。
これは自己受容感覚とも呼ばれます。自分を認めることは自己肯定感を高め、心の健康につながる重要なことです。
自分自身を受け入れることで、他人を受け入れることができるようになり、寛容な心を持つことができます。
そのため自分を認めることは、他人との関係性にも良い影響を与えます。
さらに、自分を認めることは自己成長にもつながります。
自分の強みや弱みを認め、自分自身を客観的に見ることができるようになることで、自己改善に取り組むことができます。
自分を認めることは、ポジティブな人生を送るために必要不可欠なスキルの一つといえるでしょう。
>>【自分がわからないことで苦しい方へ】自分を理解する方法をご紹介
自分を認めることが難しい原因

「さあ自分を認めましょう」といってすぐにできるほど、自分を認めることは簡単なことではありません。
自分を認めることが難しい原因としては、以下のようなものが挙げられます。
過去のトラウマやネガティブな体験
過去に体験したトラウマやネガティブな経験は、自分を認めることを難しくします。
これらの経験が自分自身に対して否定的な考えを持ってしまう引き金となり、自己否定感情を引き起こします。
他者との比較
他者と比較して自分自身を評価することも、自分を認めることを難しくします。
自分自身が他人と比較して劣っていると感じると、自己否定感情が高まります。
そのため、ついつい他者と比較してしまう人は、自分自身を肯定的に評価することができなくなることがあります。
社会的な圧力
社会的な圧力も、自分を認めることを妨げる原因の一つです。
社会的な圧力は、人々がどのような行動をとるべきかについての規範や期待を形成することがあります。
これにより、自分自身の欲求や価値観に照らし合わせた行動をとることが難しくなる場合があります。
自己肯定感が高いと自分を認めやすいのか

自己肯定感は、子ども時代の育て方や周囲からの評価などによって形成されるといわれています。
自己肯定感が低い人は、過去のトラウマや失敗経験、周囲からの否定的な評価などが原因で、自分自身を否定的に見る傾向があります。
しかし、一度下がってしまった自己肯定感を高めることは可能です。
そのためには自分自身に対して肯定的な言葉をかけることや、自分自身を褒めることが効果的です。
また、他人からの肯定的な評価を受け入れることも、自己肯定感を高めることにつながるでしょう。
自己肯定感が高くなると、自分自身に対する肯定的な感情が増えるため、自分を認めることが容易になります。
自己肯定感を高めることで自分自身を認める機会が増えれば、自信を持って行動できるようになるでしょう。
>>ネガティブな人でもできる自己肯定感を高める方法や習慣とは?
自分を認めることと自己受容の違いは?

「自分を認めること」と「自己受容」は似たような意味を持つ言葉で、どちらも自分自身を受け入れることを意味します。しかし、これらには微妙な違いがあります。
自己受容とは、自分自身を受け入れることで自分に優しくなり、自分の過ちや欠点を受け入れ、自分自身を許すことを意味します。
自己受容によって、自分自身に対する批判的な思考を減らすことができ、自分に対して寛容になります。
これによって自分自身を信頼し、自分自身の気持ちや思考に耳を傾けることができるようになるでしょう。
一方、「自分を認める」とは、自分自身の良いところや能力、成果を認めるなど、行動した結果や可視化できるものを評価することを意味します。
自分を認めることで、自分自身を高く評価し、自信を持つことができます。
自分を認めることによって、自分自身を肯定し、ポジティブな自己イメージを作ることができるのです。
>>【自己受容】弱くてダメな自分を認めて受け入れるトレーニング方法
自分を認める方法や習慣はある?

自分を認める方法や習慣には以下のようなものがあります。
- 毎日自分でできたことを振り返り、自分自身に褒め言葉を言う
- 自分にとって大切なことや得意なことを書き出し、自分の強みを確認する
- 失敗しても自分自身を責めず、反省して次に活かす
- 自分を甘やかすわけではないが、自分に対して優しく接することを忘れずに
- 自分の感情や気持ちに正直に向き合い、自分を受け入れる
- 自分自身を愛することも大切
自分を認める方法や習慣としては、毎日自分自身に褒め言葉を言うことが効果的です。
例えば自分にできたことを振り返って、その成果を自分自身で褒めたり、目標を達成したことを自分自身で認めることが大切です。
また、自分にとって大切なことや得意なことを書き出し、自分の強みを確認することも大切です。
自分自身が何を得意としているかを知ることで、自己肯定感を高めることができます。
失敗した場合でも自分自身を責めず、反省して次に活かすことが大切です。
自分に対して厳しく接することもあるかもしれませんが、自分に対して優しく接することも忘れないようにしましょう。
自分の感情や気持ちに正直に向き合い、自分を受け入れることが大切です。
自分自身を愛することも大切であり、自分自身を大切にすることが、自分自身を認めることにつながります。
>>ポジティブ思考になる方法|うざいと言われる理由やプラス思考との違いをご紹介
自分を認めることでどんな効果やメリットがあるのか

自分を認めることによる効果やメリットには、ストレスや不安の軽減、自己肯定感の向上、自信や幸福感の向上などがあります。
自分自身を認めることで自分自身に対する信頼感が高まり、自分自身に対してポジティブな気持ちを持つことができるようになるでしょう。
自分を認めることによる効果やメリットには、具体的に以下のようなものがあります。
ストレスや不安の軽減
自分自身に対する批判的な思考が減り、心の負担が軽くなるため、ストレスや不安が緩和されることがあります。
自己肯定感の向上
自分自身を認めることで、自己肯定感が向上します。
自分自身に自信を持つことができるようになり、自分自身の能力や価値を肯定的に見ることができるようになります。
自信や幸福感の向上
自分自身を認めることによって、自信がつき、自分自身に対してポジティブな気持ちを持つことができるようになります。
また、自分自身を認めることによって、幸福感も向上することがあります。
自分自身が幸せであることを認めることで、周りの人々との関係も良好になることがあります。
>>感情の起伏が激しい人や少ない人の特徴|上手にコントロールする方法とは
まとめ
自分を認めることは、自分自身を受け入れ、自己肯定感を高め、ストレスや不安を軽減し、自信や幸福感を向上させる効果があります。
自分に対して厳しいこともあるが、自分に対して優しく接することを忘れず、自分自身を愛することが大切です。
自分自身を認め、受け入れることで、自分自身に対する信頼感が高まり、自分自身に対してポジティブな気持ちを持つことができます。
感情の起伏が激しいのは病気?治したい場合の対処法について徹底解説
感情に身を任せて烈火のごとく怒っていたかと思えば、次の瞬間には急に悲しんだりと、感情の起伏が激しい人は存在します。
自分自身でも改善したいとは思っているものの、うまく感情がコントロールできず悩んでいる人もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、自分の感情とうまく向き合い、感情の起伏をコントロールするためにはどうすればいいのか解説します。
「感情の起伏が激しい」とは
そもそも感情の起伏とはどういった意味を指すのでしょうか。
喜怒哀楽という四文字熟語があるように、私たちの感情は「喜び・怒り・哀(悲)しみ・楽しみ」などさまざまな状態に分けられます。
さまざまな出来事に応じて私たちの感情は変化していきますが、この変化こそが「感情の起伏」とよばれるものです。
そして、感情が極端に変わりやすいことを一般的に「感情の起伏が激しい」と表現します。
関連記事:情緒不安定になると泣くのはなぜ?|情緒不安定になりやすい人や原因とは
感情の起伏が激しくなる原因

感情の起伏が激しいという言葉そのものは一言で表すことができますが、そうなってしまう原因はいくつか考えられます。
ここではその原因について見ていきましょう。
ストレスの蓄積
ストレスとは無縁の生活を送っていると、精神的な余裕が生まれて安定します。
しかし、日々の生活のなかでストレスが蓄積していくと、精神的な余裕がなくなり感情のコントロールも失ってしまいます。
緊張の糸が常に張り詰めた状態にあるため、自分の思い通りにいかないことがあったりすると大きなショックを受けて悲しんだり、怒りの感情が生まれてしまいやすいのです。
肉体的疲労の弊害
肉体的な疲労が蓄積していくとストレスが溜まりやすくなり、感情のコントロールを失う原因になり得ます。
自分自身に対して元気であると言い聞かせていても、肉体的に限界が近づいてくるとメンタルも徐々に張り詰めるようになり、感情が爆発することがあるでしょう。
生まれ持った気質
先述したように環境要因によって後天的に感情の振れ幅が大きくなっていくことが多いですが、もともと生まれ持った気質として感情の起伏が激しいケースもあります。
このパターンは生活を変えただけでは改善しにくいことも多く、臨床心理士への相談など、特別なアプローチが必要となる場合があります。
関連記事:ポジティブ思考になる方法|うざいと言われる理由やプラス思考との違いは?
感情の起伏が激しい女性の特徴

自分自身の感情の起伏が激しいことについて自覚しており、何とか改善したいと考えている人は女性に多いようです。
ここでは、感情の起伏が激しい女性の特徴について述べていきます。
精神的に未熟
人は成長するにしたがって社会性というものを身につけていき、その場その場で自分自身の感情を表に出して良いものか判断がつくようになっていきます。
しかし、年齢に関係なく精神が未成熟な大人になってしまうと、視野の狭い考え方をしてしまったり自分以外の人の立場を考慮することができず、ときに場を弁えず怒りや悲しみの感情を露わにすることがあります。
愛情が不足して育った
両親や周囲の人から十分な愛情を受けることなく育ってきた人の中には、自分の存在を認知してほしいという心理から、感情を爆発させ他人の気を惹こうという行動が見られることも。
また、少し違ったパターンとして、「自分は誰からも愛されない存在」として卑屈になり、周囲の人の気づかいにも素直になれず、幼稚な振る舞いを見せることもあるでしょう。
自己評価や自己肯定感が低い
自己評価や自己肯定感が低い人は抑うつっぽい状態になるか、感情の起伏が激しくなるかで二極化するパターンが多いです。
他人と比較しがち
近年ではSNSや動画サービスが普及した影響もあり、世界中あるいは身近な人の充実した日々や世界観、成功を簡単に垣間見ることができるようになりました。
これらを真に受けて自分自身の境遇と比較し、「あの人は自分より若いのにこんなにお金を稼いで良い生活をしている」「隣のクラスのあの子は顔が綺麗でスタイルも良く、イケメンの彼氏までいる」などと考え、少しずつ精神がすり減っていってしまいます。
仕事や家庭におけるさまざまなプレッシャー
社会に出るとさまざまなしがらみが付きまとうのは、ある意味仕方のないことともいえます。
例えば仕事で成果を出したいと考えているが、親や親戚からは早くに結婚することを求められていたり、友人や交際相手と上手くいかないなど、挙げればキリがないでしょう。
現代では、こうした日常生活のプレッシャーに押しつぶされて感情の起伏が激しくなるケースも珍しくありません。
こだわりが強く神経質
こだわりが強い人や神経症気質の人も、行き過ぎると感情の起伏が激しくなりがちです。
よく完璧主義の人は常に何事にも全力で取り組むため、理想と現実のギャップを突き付けられた際の反動によってうつになりやすいといわれますが、それに近い感覚といえるでしょう。
こだわりのあることや許せないことが自分の中で一定のラインを越えてしまうと、一気に感情が爆発することがあるようです。
ストレス解消として
本当は感情を抑えようと思えば抑えられるのに、あえて感情をさらけ出すことでストレスを解消しようとする人もいます。
このタイプは本当にごく少数であると考えられますが、最もタチの悪いタイプといえるでしょう。
感情の起伏が激しいことによる周囲への影響

感情の起伏が激しいと自分自身が疲れたり人間関係が悪化したりするだけでなく、周囲にもさまざまな悪影響が及ぶことがあります。
精神的な疲労
感情の起伏が激しい人が身近にいると、できるだけ穏やかに過ごすために気を遣ってしまうものです。
たとえば、ランチや飲み会へ誘う際にも声を掛ける順番に配慮したり、失礼な言い方をしないよう細心の注意を払ったりしなければなりません。
しかし、このような行動は精神的な疲労を感じやすく、ストレスの種にもなり得ます。
また、ランチや飲み会へ出席するメンバーも常に気を配らなければならず、楽しむことができません。
業務効率・生産性の低下
感情の起伏が激しいと、仕事に直接的な影響を及ぼすこともあります。
たとえば、ちょっとしたことで怒りやすい人には気軽に声を掛けづらく、仕事の依頼や相談が後回しになることも考えられるでしょう。
その結果、重要な連絡や相談が遅れたり、連絡漏れが発生したりして生産性に影響することも。
また、感情の起伏が激しい部下がいると、ちょっとした言葉の行き違いでハラスメントが疑われることもあるでしょう。
部署・チーム内での雰囲気や人間関係が悪くなり、業務が停滞する原因を招く可能性があるのです。
関連記事:【誰でもできる】マインドセットの意味・使い方をわかりやすくご紹介!
感情の起伏が激しいのを治したい場合の対処法

感情の起伏が激しいのを治したいと思っていても、具体的にどのようなことから取り組めば良いか分からない方もいるでしょう。
ここでは、感情をコントロールするためのポイントについて述べていきます。
自分自身を深く理解する
どのような状況、どのような言葉によって自分の感情が突き動かされやすいのかを理解することが重要です。
これらを客観的に分析することで、実際にその状況が訪れたときの対処が今よりも容易になります。
また、客観的に見直す過程で、自分の感情を突き動かすものが実は意外と大したものではないことを悟り、冷静に対処できるようになることもあるでしょう。
ストレスを定期的に発散する
ここまでの内容で、ストレスを溜め込みがちな人は感情の起伏が激しくなりやすく、適度にストレスを解消できる方法を持っている人はそうではないことが分かりました。
周囲に当たり散らしたりするという意味ではなく、趣味に没頭したり運動したり好きな物を食べたりと、誰の迷惑にもならずにストレスを発散する方法はいくつもあります。
そのため、定期的にストレスを発散できる場を作ることで、感情の起伏が激しくなるリスクをある程度抑えられるでしょう。
感情が動きやすい状況を回避する
先ほどは、自分自身の感情が何によって動かされやすいのか理解することで、その状況に対処できるようになるとお伝えしました。
しかし、いくら客観視しようとしても、人間であればどうしても折り合いをつけられないものも存在するでしょう。
そういったものに対しては、そもそも目や耳に情報すら入れないようにするほかありません。
例えば、どうしてもタバコを吸う人が許せないのであれば、喫煙席のあるお店には入らないようにするなど、自分自身の行動を変えることも必要です。
関連記事:【怒りを抑える】アンガーマネジメントのやり方・テクニックをご紹介!
感情の起伏と上手に向き合うために必要なこと
感情の起伏を穏やかにするためには、まずストレスを溜め込まないことを意識してみましょう。
ストレスが溜まってきたら、スポーツや趣味などを楽しんで発散することも重要です。
また、ストレスの原因となることを避けるのも有効な対策のひとつです。
苦手な人とのコミュニケーションを最低限に留めたり、ストレスが溜まりやすい場所に足を踏み入れないことも大切です。
まとめ
さまざまな状況に応じて感情が変化するのは当たり前のことであり、時と場合によって感情を表に出すのは悪いことではありません。
しかし感情の起伏が激しいと自分自身が苦しむほか、周囲の人にもさまざまな悪影響を及ぼすことがあります。
ストレスとうまく付き合い、アンガーマネジメントなどを参考にしながら自分自身と向き合うことで改善していきましょう。
自己肯定感が低い原因はプライドが高いから?親のせい?高める方法とは
自己肯定感が低いと自分自身を正当に評価できず、自信を持つことができなくなってしまいます。
自己肯定感の低さは、様々な要因が影響しているとされます。
本記事では、自己肯定感が低い人の原因や特徴、プライドが高いといわれる理由、向いている仕事や上げる方法などについて掘り下げていきます。
自己肯定感が低い人の原因

自己肯定感が低い原因としては下記が挙げられます。
- ネガティブ志向
- 素直でない
- コンプレックスがある
- 他人と比較しがち
ネガティブ志向
何に対しても否定から入るようなネガティブ志向な人は自分自身に対してもマイナスな評価を下すことが多い傾向があります。
他人から批判や指摘を受けた際も、自己肯定感が低い人は自分自身を必要以上に責め、行動することをやめてしまいがちです。
反対に自己肯定感が高い人は、批判や指摘を前向きに捉えられるため成長につながりやすく、さらに自己肯定感が高まるという良いサイクルの中に身を置いているといえるでしょう。
素直でない
自己肯定感が低い人は、他人から良い評価を受けた時に、概して「そんなことはない」と否定しがちです。
もしくは表面上では笑顔で対応しても、心の中では「何か裏があるのではないか?」「どうせ社交辞令なんだろうな」などと考えてしまい、素直に受け入れられません。
その結果、せっかく他人からの評価は悪くないのに自己肯定感の向上につながらないという人は意外と多いものです。
コンプレックスやトラウマがある
自分自身の容姿や境遇などに何らかのコンプレックスを抱えている場合も、自己肯定感が低くなりやすいです。
過去にトラウマがある場合も同様です。
コンプレックスやトラウマを忘れるというのは一筋縄ではいかないので、その他の部分で補填する必用があるでしょう。
他人と比較しがち
特に多いのがSNSなどで成功者の投稿を目にして自分の境遇と比べてしまい、「自分は何をやっているんだろう…」となってしまうパターンです。
「上には上がいる」という言葉がある通り、どんな人でも、比べれば自分より良い境遇に置かれている人は無数に存在します。
しかし自己肯定感が高い人は「他人は他人、自分は自分」という考え方ができるので、わざわざ自分と他人を比較して落ち込むようなことは極めて少ないです。
▶自己肯定感とは?|意味や似ている言葉との違いをわかりやすく解説
自己肯定感が低い人の特徴

自己肯定感が低い人の特徴としては、以下のようなものが挙げられます。
- 自分に自信がない
- 自分を否定的に評価する
- 失敗やミスを自分のせいだと責める
- 他人と比較して自分が劣っていると感じる
- 自分に対する期待が低く、自己実現を諦めている
- 批判や非難に敏感で、傷つきやすい
- 人の評価や承認を求める傾向がある
- 自分を省みることができず、自己否定的な思考に固執する
- 新しいことに挑戦することをためらう
自己肯定感が低い人は、これらの特徴が強く出る傾向があります。
しかし、自己肯定感を高めることで、これらの特徴を改善することができるとされています。
▶自己肯定感が低い子供の特徴や言動とは|注意すべき親の発言や行動
自己肯定感が低い人はプライドが高い?

自己肯定感が低い人が、実はプライドが高いとされることがあります。
自己肯定感が低い人は自分に自信がなく自分を過小評価する一方で、他人からの批判や否定に過剰に反応してしまう傾向があります。
このような人は、自分にとって都合の悪いことを認めることができず、自分自身を正当化しようとする傾向があるため、プライドが高いと言われるのです。
また、自己肯定感が低い人は自分に対して厳しい傾向があるため、自分自身が達成したことに対して過剰に自責的になることがあります。
これは、深層心理としては自分が思っていたほど優秀でないということを認めたくないためであるとされています。
しかし、プライドが高い人は自分自身を過大評価することもあるため、本質的には自己肯定感が低いのに、そう見えないというケースも多くあります。
自己肯定感が高まると、自分自身を客観的に評価できるようになり、プライドが高くなりすぎることも防げるでしょう。
自己肯定感が低い人は親に影響されるか

自己肯定感が低い人は、親の影響を受けることがあるとされています。
例えば、親からの厳しい言葉や批判的な態度、過保護な育て方などが、子どもの自己肯定感を低下させる原因となることがあります。
また、親自身が自己肯定感が低い場合、それが子どもにも影響を与えることがあるとされています。
しかし、必ずしも親が原因であるわけではありません。
自己肯定感は個人差や環境によって異なるため、他にも様々な要因が影響している可能性があります。
自己肯定感を高めるためには、親が子どもに対して積極的に肯定的な言葉をかけたり、自己決定権を尊重するなどの育て方が有効とされています。
また、自己肯定感を高めるためには、自分自身での努力やアクションも必要となります。
▶自己肯定感が低い子供の特徴や言動とは|注意すべき親の発言や行動
自己肯定感が低い人がめんどくさいといわれる理由

自己肯定感が低い人がめんどくさいと言われる理由は、いくつか考えられます。
まず、自己肯定感が低い人は、自分に対する不安や不満を抱えやすく、それを周りの人にぶつけてしまうことがあります。
また自分に対して厳しく、周りの人にも同じように厳しく接することがあるため、他人とのコミュニケーションがうまくいかないこともあります。
さらに、自己肯定感が低い人は自分自身がどう思われているかを気にしすぎる傾向があります。
そのため、他人からの批判や否定に対して敏感に反応してしまうことがあり、それが周りの人にとって迷惑となることがあります。
自己肯定感を高めるための方法を学び、自分自身を客観的に見ることができるようになれば、人間関係の改善も期待できるでしょう。
自己肯定感を高めると恋愛や仕事は上手くいく?

自己肯定感が低い人の恋愛傾向は、以下のような特徴があります。
まず、自己肯定感が低い人は自分に自信がなく、相手に依存する傾向があります。
そのため、相手に対して過剰な期待を持ち、相手からの反応に敏感になってしまうことがあります。
また、自己肯定感が低い人は自分自身に対して否定的な考えを持ちやすく、相手にも同じような否定的な考えを抱いてしまうことがあります。
そのため相手に対して過剰に批判的になり、相手の言動に対して過剰に反応してしまうことがあります。
さらに、自己肯定感が低い人は自分自身を受け入れることができず、自分自身に嘘をついたり自分を偽ったりすることがあります。
そのため、相手との関係においても相手に対して自分を偽ってしまうことがあります。そうなるとパートナーに対して偽りの自分を見せ続けれければならず、精神的に参ってしまうこともあるでしょう。
しかし、自己肯定感が低い人でも恋愛を楽しむことができます。
自分自身を受け入れ、自分自身に対する批判的な考えを改めることができれば、相手との関係もより良いものになることが期待できるでしょう。
子供の自己肯定感を高める方法とは

子供の自己肯定感を高めるには、以下のような方法があります。
褒めること
子供が何か良いことをした場合、褒めることが大切です。
ただし、褒めすぎると逆効果になる場合もあるので、ほどほどに褒めるようにしましょう。
子供が頑張ったことを具体的に褒めてあげるのがおすすめです。
自己決定権を尊重すること
子供に自己決定権を与えることが大切です。
例えば、選ぶものや遊ぶものを自分で決めさせたり、自分のやりたいことを自由にさせてあげましょう。
子供が決定したことが他人に迷惑をかけることであったり、倫理的に間違っていることである場合に初めて親が介入しましょう。
失敗を受け入れること
失敗をしたときに、子供を責めないようにしましょう。
失敗は誰にでもあることであり、それを受け入れることが大切です。また、失敗から学ぶことができるということを教えてあげましょう。
手伝いを頼むこと
子供に手伝いを頼むことで、自己肯定感を高めることができます。
手伝いを通じて、自分でできることが増え、自己肯定感が高まるからです。
興味を持たせること
子供に興味を持たせることも、自己肯定感を高めることができます。
例えば、子供が興味を持っていることについて、一緒に調べたり、取り組んだりすることが大切です。
これらの方法を取り入れることで、子供の自己肯定感を高めることができます。
まとめ
自己肯定感が低い人は、子供の頃の経験や親からの影響、失敗体験などから自分自身を否定する傾向があります。
しかし、自己肯定感を高めることで、自信を持って生きていくことができます。自己肯定感を高めるためには、自分の強みを見つけることや自分に対して優しく接することが大切です。
また、子供の自己肯定感を高めるためには、褒めることや肯定的な言葉をかけること、自己決定権を尊重することなどが有効です。
自己肯定感が高まると、人生においてさまざまな困難に立ち向かう力が身につき、幸福感や充実感を得ることができます。
監修者紹介

– アフリカンペイントアーティストSHOGEN(ショウゲン)-
タンザニアの小さな村で描かれるティンガティンガというペンキアートに心惹かれ、
日本での生活を捨て、なんの伝手もないまま単身アフリカへ・・・
現地で生活をしながらキャンバスだけなく、警察車両やホテル内の壁画に描くなど、
動物と子供を共存させた作風で独自の表現を追及する。
ティンガティンガ創始者Edward Saidi Tingatingaがおこなっていた“人々を幸せにする絵”への到達を目指す。
日本に制作の場を移した後は、キャンパスだけにとらわれない多方面での活躍を続けている。
生きる喜びを描くペンキ画家
自己肯定感を高める8つの習慣や言葉を紹介
自己肯定感とは自分自身を受け入れ、自分を大切に思える感覚のことです。
この自己肯定感は人間関係や仕事、恋愛などのあらゆる面において大きな影響を与えます。
本記事では自己肯定感の高め方や習慣、行動についてご紹介します。
自己肯定感を高めることは可能なのか

結論から言うと、自己肯定感を高めることは可能です。
自己肯定感は自分自身に対するポジティブな考え方や、自己価値を肯定する感覚です。
この感覚は、習慣や考え方を変えることで向上させることができます。
自己肯定感を高めるには、まずは自分の強みを見つけることが大切です。
自分が得意なこと、好きなことを見つけ、それを伸ばすことが自己肯定感を高めるための近道です。
また、失敗や間違いを恐れず自分自身を受け入れることも重要です。
自分自身を受け入れ、自分を愛し、自分を許すことができたときに自己肯定感が高まります。
さらに、自分自身を褒めることも有効です。
自分自身に対して肯定的な言葉をかけることで、自己肯定感が高まります。
また、他人からの批判は自己肯定感の低下につながってしまうような気がしますが、それを真摯に受け止め、今後への改善案として前向きに受け入れることができるようになれば、より自分自身を成長させ、価値を高めることになるでしょう。
これらのことを習慣化することで、自己肯定感を高めることができます。
▶自己肯定感とは?|意味や似ている言葉との違いをわかりやすく解説
自己肯定感を高めることのメリット

自己肯定感を高めることには様々なメリットがあります。
まず、自己肯定感が高まると自分自身を肯定的に見ることができるため、自信を持って行動することができます。
自分に自信がある人は自分の意見をしっかりと主張することができ、自分のやりたいことに積極的に取り組むことができます。
また、失敗や挫折に対しても前向きに取り組むことができ、成長することができます。
さらに、先ほども述べたように自己肯定感が高い人はストレス耐性が向上します。
ストレスに対する抵抗力が高いため仕事や学校でのプレッシャーにも強く、うつ病や不安障害の発症率が低くなるとされています。
また、自己肯定感が高い人は、人間関係も良好です。
自分自身を肯定的に見ることができるため、他人にも同じように接することができます。
そのため友人や家族とのコミュニケーションが円滑になり、良好な関係を築くことができます。
以上のように自己肯定感を高めることよるメリットをまとめると以下のようになります。
- 自信を持って行動できるようになる
- ストレス耐性が向上する
- 人間関係が良好になる
▶︎セルフラブとはどんな意味?自分を愛す方法や自己肯定感との違いを解説
自己肯定感を高めるのに効果的な8つの習慣や行動

自己肯定感を高めるためには、以下のような習慣や行動が効果的です。
ポジティブな自己イメージを持つこと
自分の良いところを認め、自分に対してポジティブな考え方を持つことが大切です。
毎日の積み重ねで、自分に対するポジティブなイメージが定着していきます。
認知行動療法(CBT)を取り入れること
認知行動療法は、自分の考え方や行動を変えることで、自己肯定感を高める手法です。
自分の考え方や行動について客観的に見直すことで、ポジティブな自己イメージを持つことができます。
ノートに書き込むこと
毎日自分の良いところや成果をノートに書き込むことで、自己肯定感を高めることができます。
自分の成長を実感することができ、自信に繋がるでしょう。
賞賛されたときは素直に受け取ること
自分の良いところや努力を認められたときは、素直に受け取りましょう。
自分に対する評価が高まるため、自己肯定感を高めることができます。
目標を設定し、達成すること
目標を設定し、その達成過程で自分自身の成長を実感することができます。
達成感や自信に繋がり、自己肯定感を高めることができます。
自分自身を適切に評価すること
自分自身を適切に評価することが大切です。
過度な自己評価は自己肯定感を下げる原因となるため、客観的に自分自身を評価することが必要です。
自分に優しく接すること
自分に対して優しく接することで、自己肯定感を高めることができます。
自分自身に対して厳しすぎることは避け、自分の良いところを認め、自分に対して優しく接しましょう。
自分自身を比較しないこと
他人と比較して自分自身を評価することは避けましょう。
自分自身と過去の自分自身を比較して、自分自身が成長していることを認めたり、目標に向かって進んでいることを意識することで、自己肯定感を高めることができます。
自己肯定感を高めることができる言葉

自己肯定感を高める言葉は人によって異なりますが、以下のような言葉が一般的に有効とされています。
- 「自分ならできる」という言葉を自分にかける。
- 「自分は大丈夫だ」という言葉を自分にかける。
- 「自分を信じる」という言葉を自分にかける。
- 「自分には価値がある」という言葉を自分にかける。
- 「自分は素晴らしい人間だ」という言葉を自分にかける。
- 「自分には才能がある」という言葉を自分にかける。
- 「自分は成功することができる」という言葉を自分にかける。
- 「自分は幸せな人間だ」という言葉を自分にかける。
これらの言葉は、自分自身に対してポジティブなメッセージを送ることで、自己肯定感を高めることができます。
また、言葉だけでなく行動によっても自己肯定感を高めることができます。
具体的な習慣や行動については、前述した通り、自分自身に合ったものを選択することが大切です。
自己肯定感を高めると恋愛や仕事は上手くいく?

自己肯定感を高めることは、恋愛や仕事において上手くいく可能性を高めることがあります。
自分自身を肯定的に評価できるようになると、自分に自信を持って行動することができるようになります。
恋愛においては、自分に自信を持っている人はより魅力的に見えるため、自分に合ったパートナーを見つけやすくなるでしょう。
また、仕事においては自分自身を肯定的に評価することで、自分の能力に見合った仕事を選び、仕事に取り組む姿勢が前向きになることがあります。
しかし、自己肯定感が高いからといって、必ずしも成功するとは限りません。
自己肯定感を高めることは、あくまでも自己成長のための一つの手段であり、それ自体が目的ではないということを心にとどめておきましょう。
▶スキンシップにはどんな効果がある?良好な関係性を維持するためのポイントとは
子供の自己肯定感を高める方法とは

子供の自己肯定感を高める方法は、声かけや子育ての中での態度や行動によって大きく影響されます。
まずは子供が自己肯定感を育てるために、親が自己肯定感を持つことが重要です。
親が自分を肯定する姿勢を見せることで、子供も自分自身を肯定することができるようになります。
また、子供が自分でできることを認めてあげたり、賞賛してあげたりすることも大切です。
例えば、小さなことでも「すごいね」と褒めたり、「ありがとう」と感謝の気持ちを伝えたりすることが、子供の自己肯定感を高めることにつながります。
一方で、否定的な言葉や比較をする言動は、子供の自己肯定感を低下させることがあります。
例えば、「○○ちゃんはもっと上手にできてるよ」と比較したり、「もう一回やりなさい」と言われると、自分自身の能力に自信を持てなくなってしまうでしょう。
そのため、子供の自己肯定感を高めるためには自分で考え判断し、行動することを尊重し、積極的な声かけや肯定的な態度を心がけることが大切です。
▶自己肯定感が低い子供の特徴や言動とは|注意すべき親の発言や行動
まとめ
自己肯定感を高めることは心理的健康や幸福感を促進する上で重要であり、習慣や言葉を使って実現できます。
具体的には下記のような考え方が大事です。
- 自分に寛容になること
- 感謝の気持ちを持つこと
- 自分自身に対して肯定的な言葉をかけること
- 自分の成功を認めること
- 自分自身を比較しないこと
また、子供の自己肯定感を高める方法としては、声かけや子育ての方法を改善することが挙げられるでしょう。
自己肯定感が高まると恋愛や仕事でも積極的に行動でき、自分自身の人生をより充実したものにすることができます。
監修者紹介

– アフリカンペイントアーティストSHOGEN(ショウゲン)-
タンザニアの小さな村で描かれるティンガティンガというペンキアートに心惹かれ、
日本での生活を捨て、なんの伝手もないまま単身アフリカへ・・・
現地で生活をしながらキャンバスだけなく、警察車両やホテル内の壁画に描くなど、
動物と子供を共存させた作風で独自の表現を追及する。
ティンガティンガ創始者Edward Saidi Tingatingaがおこなっていた“人々を幸せにする絵”への到達を目指す。
日本に制作の場を移した後は、キャンパスだけにとらわれない多方面での活躍を続けている。
生きる喜びを描くペンキ画家
自己肯定感の意味をわかりやすく解説|自己評価や自尊心との違いとは?
はじめに
自己肯定感とは、自分自身を肯定することができる心の状態のことを言います。
ちなみに読み方は「じここうていかん」です。
本記事では、自己肯定感の意味や、自己評価、自尊心といった似ている言葉との違いをわかりやすく解説します。
自己肯定感の意味とは

自己肯定感とは、自分自身を受け入れ、自分を肯定する感覚や信念のことを指します。
つまり、自分に対して自信を持ち、自分の価値や能力を認めることができる精神的な状態のことを指します。
自己肯定感が高い人は、自分自身に対して常にポジティブな感情を持ち、前向きな気持ちでいることができます。
一方で、自己肯定感が低い人は自分自身に対してネガティブな感情を持ち、自分を否定したり卑下したりする言動が目立ちます。
自己肯定感は人間関係や仕事、学業など、あらゆる面において重要な役割を果たします。
自己肯定感と似ている言葉との違い
自己肯定感と似ている言葉には、「自己評価」や「自己効力感」、「自尊心」などがありますが、それぞれ微妙なニュアンスの違いがあります。
自己評価
読んで字の通り自分自身に対する評価を表す言葉で、自分がどの程度価値があると思っているかを示します。
自己効力感
自己肯定感とは異なり、自己評価は自分の能力や行動に対する評価も含む言葉です。
自分が目標を達成する能力を持っているという信念や自信のことで、自己肯定感と同様に自己信頼感に関連しています。
自己効力感は特定の行動や目標に対する信念を示すのに対し、自己肯定感はさらに幅広い感情や自己の総合的な評価について述べるものです。
自尊心
自分自身に対する感情的な反応を指す言葉で、自分自身に価値があると感じることを意味し、自己肯定感と同様の意味合いがあります。
自尊心は感情的な反応を示すのに対し、自己肯定感は、より理性的で認知的な評価に重点が置かれるというのが違いです。
自己肯定感を高めるべき理由

自己肯定感を高めるべき理由としては、自分自身や周りの人々との関係性を改善することが挙げられます。
自己肯定感が低いと自分を責めることが多くなり、自信を持てなくなります。
他人からの良い評価を素直に受け取れなくなることもあるため、しばしば自分自身や周りの人々との良好な関係性を築くことが難しくなります。
自己肯定感が高い人は自分自身に自信を持っており精神的な余裕が生まれるため、自分だけでなく周りの人々にも気を配ることができ、良好な人間関係を保つことができます。
また、自己肯定感が高いと、ストレスや不安を感じることが少なくなり、健康的な生活を送ることができるとされています。
自己肯定感を高めることで自分自身を肯定し、ポジティブな心理的影響を受けられるようにしましょう。
自己肯定感は環境に左右されやすい

自己肯定感は環境によって左右されることがあります。
例えば家庭環境が悪かったり、周りの人が否定的な言葉を投げかけたりすると、自己肯定感が低下することがあります。
また、社会的な価値観やイメージが強く反映されるSNSなども、自己肯定感に影響を与えることがあるとされています。
そのような環境の中で自己肯定感を高めるためには、自己肯定感を強化するプログラムやセルフヘルプ本などを利用することが有効とされています。
▶自己肯定感が低い子供の特徴や言動とは|注意すべき親の発言や行動
自己肯定感はSNSに影響される

近年SNSの普及に伴い、自己肯定感に与える影響が注目されています。
SNSを利用することで、自分の投稿やアップロードした写真に「いいね!」や「コメント」が付くことで、一時的な自己肯定感を得ることができます。
しかし、SNSには自分と他人との比較が容易になるというデメリットもあります。
自分の投稿に「いいね!」が少ない場合や、他人の投稿に比べて自分が魅力的でないと感じた場合には、逆に自己肯定感を低下させる可能性があります。
また、SNSでは加工した写真や美しい風景、成功した自分をアピールする傾向があり、それによって現実とのギャップを感じ、自己肯定感に低下につながるケースも多いようです。
SNSの利用方法によっては自己肯定感を高めることも下げる可能性もあるので、適切な使用方法を心がけることが重要です。
自己肯定感が高い人と低い人の違い

自己肯定感が高い人と低い人の違いは様々な面で見られます。
以下は自己肯定感が高い人の特徴です。
- 自分に自信があり、自分の能力や価値を肯定的に捉える
- 失敗や批判に対しても前向きに捉え、自分の成長の機会として受け止める
- 他人と比較することにあまりこだわらず、自分が望む方向に向かって自分自身を発展させようとする
続いて自己肯定感が低い人の特徴を見ていきましょう。
- 自分に自信がなく、自分の能力や価値を過小評価してしまう
- 失敗や批判に対して消極的になり、自分自身を責めたり、自信を喪失してしまう
- 他人と比較してしまい、自分自身を否定したり妬んだりする
以上のように、自己肯定感が高い人と低い人では、たとえ全く同じ状況に置かれていたとしても、自分自身の現状をどのように認識し、今後どのようにアプローチしようと考えるかが大きな違いとなるでしょう。
▶自己肯定感が低い人の原因とは|実はプライドが高い?親のせい?
まとめ
自己肯定感には「自分を肯定することができる力」という意味もあります。
自己肯定感は他人からの評価や環境の影響を受けやすく、概して低くなりがちですが、高い自己肯定感を持つことことができれば自信を持ち、ストレスを軽減することができます。
また、SNSなどの外部環境も自己肯定感に影響を与えることがあるとされています。
自己肯定感が低い人はついつい他人と比較してしまいがちです。そのため、SNSを見て自己肯定感が下がってしまうことが多いのであれば、一度離れてみるというのも選択肢の一つでしょう。
自己肯定感を高めるためには、自分自身を否定的に捉えないようにすることや、自分が得意なことを活かすことが大切です。
監修者紹介

– アフリカンペイントアーティストSHOGEN(ショウゲン)-
タンザニアの小さな村で描かれるティンガティンガというペンキアートに心惹かれ、
日本での生活を捨て、なんの伝手もないまま単身アフリカへ・・・
現地で生活をしながらキャンバスだけなく、警察車両やホテル内の壁画に描くなど、
動物と子供を共存させた作風で独自の表現を追及する。
ティンガティンガ創始者Edward Saidi Tingatingaがおこなっていた“人々を幸せにする絵”への到達を目指す。
日本に制作の場を移した後は、キャンパスだけにとらわれない多方面での活躍を続けている。
生きる喜びを描くペンキ画家
アフリカンペイントアーティストSHOGEN(ショウゲン)オフィシャルサイト
セルフプレジャーとは?美容効果を紹介!どんな人におすすめ?
はじめに
『セルフプレジャー』は雑誌やWEBメディアなどでよく目にするようになってきた話題の言葉で、俗な言葉で表現するならば「女性のオナニー」のことを指します。
しかし、性的な快楽を得ること以外にどんな効果があってどんな人におすすめなのかを知っている人は少ないのではないでしょうか?
本記事では、セルフプレジャーの意味や効果、使い方などを詳しく紹介します。
セルフプレジャーとは

セルフプレジャーとは、冒頭でも述べたように「マスターベーション」や「オナニー」、「自慰」などの意味合いで使われる事が多く、自分自身で性的な快感を得ることを指します。
女性にとっても自分自身で性的な快感を得ることはストレス解消やリラックスに繋がることがあるため注目されています。
具体的にはバイブレーターなどの玩具を使用したり、指を使って自分自身で快感を得る方法があります。
自分自身に快感を与えることで自分の身体をより理解し、自信やセクシュアリティーに繋がることもあります。
女性にとってセルフプレジャーは自己愛の一つであり、自分自身を大切にすることができる方法の一つです。また、ストレスや不安を解消することができるとも言われています。
一方でセルフプレジャーを行うことに罪悪感を感じてしまう人もいますが、自分自身を責めたりすることはしないでください。
自分自身を愛し、自分の身体に優しく接することは女性にとって大切なことだと言えます。
セルフプレジャーの効果について

セルフプレジャーは自分自身で性的な快感を得ること以外にも、健康や心理面への影響が注目されています。
セルフプレジャーによって得られる効果は以下の通りです。
ストレス解消
セルフプレジャーは、ストレスや不安を解消するための自己療法として知られています。
性的な快感を得ることで、リラックス効果が得られるとされています。
睡眠の改善
セルフプレジャーによって緊張を解きほぐすことで、睡眠の質を改善することができます。
自己肯定感の向上
自分自身に性的な快感を与えることにより、自己肯定感が向上すると言われています。
自分自身を愛し、大切にすることができるため、自信につながるとされています。
心身の健康維持
セルフプレジャーによって性的な欲求を満たすことで、心身の健康を維持することができると言われています。
また、性的な快感により免疫力の向上にもつながるとされています。
パートナーシップの向上
セルフプレジャーによって自分自身の身体についてより理解を深めることができ、パートナーシップにも良い影響を与えると言われています。
自分自身の性的な好みを知ることで、パートナーとのセックスライフが充実することが期待できます。
美容効果
セルフプレジャーによって脳内ホルモンのエンドルフィンが分泌されることで、リラックス効果が得られるとともに肌のターンオーバーが促進され、美肌効果が期待できます。
自分に自信を持っている女性はより美しく見えます。そのためセルフプレジャーを行うことで自分自身を愛し、自己肯定感を高めることが女性の美容につながるというわけです。
自分自身の健康や美容のためにも、適度なセルフプレジャーを行うことが大切です。
セルフプレジャーに使う物
セルフプレジャーにおいて女性が使用する物は多岐にわたります。
一般的に使用される物としては、以下のようなものがあります。
バイブレーター
最も一般的に使用されるセルフプレジャーの道具です。
振動させることで、クリトリスや膣内を刺激することができます。
大きさや形状、強さ、振動パターンなどが様々なものがあります。
ディルド
膣内に挿入することで、内部を刺激することができる道具です。
バイブレーターと異なり振動機能はないため、よりリアルな感触を求める方に適しています。
ビーズ
膣内に挿入することで、快感を得ることができる道具です。
挿入する際に膣内を刺激するため、女性器のトレーニングにも適しています。
これらの道具は、自分自身の性的な欲求を満たすために使用されます。
ただし使用方法によっては体に負担をかけたり傷つけたりすることがあるため、適切な方法で使用することが大切です。
また、強い刺激に慣れすぎてしまうと性行為で得られる快感が弱まってしまう点には注意しましょう。
使用前には、説明書や注意書きをしっかりと読み、適切な方法で使用することが大切です。
セルフプレジャーはどんな人におすすめ?

結論から言うと、セルフプレジャーはどんな人にとってもおすすめです。
特に、忙しい現代人やストレスを感じやすい人、健康に興味がある人、美容に興味がある人にとっては特に効果的です。
健康や美容に関心がある人は、セルフプレジャーを行うことで自分自身をケアすることができ、より健康的で美しい生活を送れるようになるでしょう。
セルフプレジャーは誰にでも簡単に取り入れることができるため、ぜひおすすめしたい美容方法です。
まとめ
セルフプレジャーは美容効果やストレス解消効果が期待できることから注目を集めています。
また、自己肯定感アップにもつながることから、心の健康にも良いと言われています。
セルフプレジャーを取り入れ、充実した生活を送りましょう。
セックスレスの原因とは?|なりやすい夫婦の特徴や解消法を解説
最近では、夫婦間での『セックスレス』が社会的な問題として注目されるようになっています。
この記事では、セックスレスの定義や原因、解消法などについて分かりやすく説明していきます。
セックスレスはどのくらいの期間から?定義について

セックスレスの定義は様々ありますが、一般的によく言われているセックスレスは、夫婦やパートナー同士が長期間、性的関係を持たずに暮らす状態を指します。
セックスレスと感じる期間や頻度には個人差があるので、その具体的な期間や頻度は人によって感覚や価値観が異なるため曖昧ですが、一般的には1か月以上性的な接触がない状態がセックスレスとされている事が多いです。
セックスレスになる原因やきっかけ

セックスレスになる原因は、以下のように様々な要因が考えられます。
- ストレスや疲れ
- 仕事や育児などの忙しさ
- 健康上の問題、性的な問題やトラブル
- パートナーとのコミュニケーション不足
- パートナーへの不満や不信感
- 性的な価値観や好みの違い
- 精神的な問題、うつ病や不安障害など
- 環境の変化、引っ越しや転勤など
- 年齢やライフステージの変化に伴う性欲の低下
- 家庭内暴力や虐待などの問題
中でもストレスや疲れ、仕事や子育てなどの忙しさ、年齢の影響、性格や体質の違い、セックスへの興味や欲求の減退などが多く挙げられています。
また、セックスに関するトラウマや過去の浮気・不倫などの精神的な問題がセックスレスの原因になることもあります。
▶40代の女性は性欲が強い?なくなる?その違いや性欲の対処法について
セックスレスになりやすい夫婦の特徴

セックスレスになりやすい夫婦の特徴を以下で紹介します。
コミュニケーション不足
パートナーとのコミュニケーションが不足しており、意見や感情を共有できていない。
ストレスや疲れ
仕事や育児、家事などで忙しくストレスがたまっている。
不満や不信感
パートナーに対して不満や不信感を持っており、セックスに対するモチベーションが低下している。
性的な問題やトラブル
性的な問題やトラブルがあるため、セックスに積極的になれない。
年齢やライフステージの変化
年齢やライフステージの変化により、性欲が低下している。
性的な価値観や好みの違い
パートナーとの性的な価値観や好みが合わないため、セックスに対する意欲が低い。
体調不良や健康上の問題
体調不良や健康上の問題があるため、セックスに積極的になれない。
精神的な問題
うつ病や不安障害などの精神的な問題があるため、性的な欲求が減退している。
環境の変化
引っ越しや転勤などの環境の変化により、セックスに対する意欲が低下している。
家庭内暴力や虐待
家庭内暴力や虐待があるため、セックスに対する意欲が低くなっている。
上記の中でも特に多いと言われている『セックスレスになりやすい夫婦の特徴』としては、お互いのコミュニケーションが不十分であることや、ストレスや疲れがたまりやすい仕事や生活環境に身を置いていること、それぞれの性格や性格の不一致、そして性的な問題を抱えていることです。
セックスレスになると離婚率は上がるのか

セックスレスが離婚の原因となるかどうかは専門家の間でも意見が分かれていますが、一般的にはセックスレスが夫婦の関係性に悪影響を与えることがあるため、離婚の要因の一つとして考えられています。
3万人以上を対象に行った夫婦関係における研究の発表によると、セックスレスになった夫婦の約74.2%が離婚になったという結果が出ています。
米国の新聞では、セックスレスの夫婦の離婚率が約70%と報告された例もあります。
米国の離婚率は約50%ですが、セックスレスの夫婦のみを対象にすると、その数字が約70%に上昇するという結果は一定の説得力があるでしょう。
これを日本の離婚率(約30%)に適用すると、セックスレスの夫婦では離婚率が約40%になると予測できます。
このように長期間にわたってセックスレスが続くと、パートナー同士の愛情や信頼が失われ、相手に対する不満や不信感が増大し、最終的には離婚を選択する夫婦も少なくありません。
また、ストレスや不安がたまり、パートナー同士のコミュニケーションが悪化することもあるでしょう。
しかし、セックスレスが離婚の直接の原因となるかどうかは、夫婦の関係性や問題解決能力、セックスレスの期間や原因、子育ての状況などによって異なります。
そのため夫婦が協力してコミュニケーションを改善し、問題を解決することでセックスレスを克服することも可能です。
▶セックスセラピーとは|カウンセリングの内容や受けられる場所は?
セックスレスにならない為に心がけること

セックスレスにならないためには、以下の点に注意することが重要です。
1.コミュニケーションを大切にする
夫婦の間でコミュニケーションが取れていないとお互いの性的なニーズを把握することができず、セックスレスに陥ることがあります。
日常的に会話をすることでお互いの気持ちや希望を共有し、セックスを含めた性生活をより充実させることができます。
2.ストレスを軽減する
ストレスがたまると、性欲や性的な興奮が低下することがあります。
夫婦でストレスを共有したり、ストレスを解消する方法を考えることが大切です。
例えばスポーツをする、趣味を楽しむ、マッサージに行くなど、リラックスするための時間を持つのが有効です。
3.健康的な生活習慣を維持する
健康的な生活習慣を維持することで、セックスに必要な体力や性機能を維持することができます。
規則正しい生活リズムを作る、バランスのとれた食事を心がける、適度な運動をする、睡眠時間を確保するなど、健康的な生活を心がけることが重要です。
4.セックスを優先する
忙しい生活の中でセックスを後回しにしてしまうと、セックスレスになってしまうことがあります。
夫婦でセックスを優先し、時間を確保することが大切です。
例えば、定期的なデートや旅行を計画することで夫婦での時間を確保し、セックスを含めた性生活を充実させることができます。
5.セックスのバリエーションを増やす
同じ性行為ばかりでは、飽きが来てセックスレスになることがあります。
夫婦で新しい性行為を試みたり、セックスの場所や時間帯を変えたりすることで、セックスに対する興味を持続させることができます。
ただし、お互いが嫌がるような行為は避け、お互いが楽しめる形でセックスを行うことが重要です。
以上の項目を参考にしてセックレスにならないように気をつけましょう。
セックスレスになってしまってからの解消法とは

セックスレスに陥ってしまった夫婦が解消するためには、お互いにコミュニケーションを図り、相手の気持ちや考えを理解することが大切です。
以下に、セックスレスの解消法をいくつか紹介します。
まずは大前提として、相手に優しく接することが大切です。
日常生活での些細な感謝の気持ちや、お互いにサポートすることが性生活の回復につながる場合があります。
また、夫婦で一緒に過ごす時間を増やすことも効果的です。
一緒に旅行に行ったり、趣味を共有したりすることで、お互いの親密度が高まり、性的な関心を取り戻すことができます。
また、ストレスを解消することも重要です。
ストレスを抱えていると性的な欲求が減退する傾向があります。
ストレスを減らすために運動や趣味に時間を割いたり、瞑想やヨガなどのリラックス法を取り入れることがおすすめです。
さらに、夫婦でセックスレスに陥った原因を話し合うことも重要です。
自分が何を望んでいるか、どのような問題があるかを正直に伝え、相手の考えや感情を尊重することが必要です。
相手に対する理解や共感を深めることで、お互いが満足できる解決策を見つけられるでしょう。
妻・夫が拒否をした場合はどうすればいい?

妻や夫がセックスを拒否することは、夫婦関係に大きな影響を与えます。
しかし、拒否されたときには相手を責めたり強要したりすることは避けるべきです。
何よりも相手がセックスを望まない理由を理解することが重要です。
もしも拒否されてしまった場合、まずは相手に対して安心感を与えることが大切です。
お互いにコミュニケーションを図り、相手の気持ちを聞き出すことで、問題の解決につながることがあります。
また、相手に対してプレッシャーをかけることなく何を望んでいるのかを理解することが重要です。
相手の気持ちや状況を理解し、お互いに寛容な心で向き合いましょう。
また、セックスレスになる前にコミュニケーションを大切にすることが重要です。
お互いにストレスや不満を感じた場合はすぐに話し合い、解決策を模索するようにしましょう。
また、セックスレスを解消するためには専門家のアドバイスやサポートを受けることも役立ちます。
セラピーを受けたりセックスセラピストに相談することで、お互いに満足のいくセックスライフを取り戻すことができるでしょう。
▶セックスセラピーとは|カウンセリングの内容や受けられる場所は?
まとめ
セックスレスは夫婦関係に深刻な影響を与えることがあります。
セックスレスになる原因はさまざまであり、解消するためにはお互いにコミュニケーションを取り、相手の気持ちを理解することが重要です。
自分たちだけでは解決の糸口が見つからない場合は、専門家のアドバイスやサポートを受けることも検討してみましょう。
そもそもセックスレスを未然に防ぐため、常日頃からお互いにコミュニケーションを大切にすることが重要です。
夫婦関係を良好に保つためには、セックスに限らずお互いの気持ちや状況を理解し、お互いに協力して問題を解決することが何よりも大切なのです。
幸福度が上がる瞑想方法。楽に続けられる、続けてこそ実感する!
今、あちこちで注目されている瞑想。その理由は、集中力、メタ認知力、直感力、自律神経を整える、うつ病の改善、脳の休息など様々な効果が立証されているから。
しかも、誰でも取り入れることができます。
今回は、ヨガにおいても重要な練習方法である瞑想の基本と練習方法をご紹介します。
ヨガにおける瞑想

最近、様々な場所で注目されている瞑想。約4,000年前からあると言われているヨガでも、瞑想は悟りまでの練習過程のひとつです。ヨガにおいての瞑想を噛み砕いて言うと「自分の内側とつながる」といったところでしょうか。
私達は、自分のことをよく知っているようで、実はあまり理解していないことが多いものです。例えば「お金が欲しい。お金がもっとあれば幸せになれるはずだ」と思っていたけれど、実際にお金を手に入れても、喜びは一瞬で終わってしまうことも珍しくありません。
自分よりもお金をたくさん持っている人は幸せそうに見えたのに不思議ですよね。これは、私達が普段の生活を生き抜くために五感が常に外側に向いた状態にあるから、とヨガでは考えられています。
そこで、五感を自分の内側に向けて、心身の気づきを得るということが瞑想の目的になります。目を閉じて、目、鼻、耳、口、皮膚がえた情報を自分の内側で感じ取り、自分を見つめ直すことが、ヨガにおける瞑想の重要なポイントです。
瞑想方法

Photo by Paolo Nicolello on Unsplash
ヴィッパーサナ瞑想
ヴィッパーサナとは「ものごとをありのままに見つめる」という意味です。練習方法は、心に起こることをジャッジせずに、感情や感覚をかみしめる、というものです。そして、次に起こる心の動きを同じように感じ取っていきます。
「瞑想=無心」とイメージする方は多いですが、感情や考えが次々に起こることはいたって一般的。雑念をどのように整理していくかが瞑想の始まりです。
例えば「どうしてこんなことばかり考えるの?」と突き詰めていくと、たいした悩みではないことに気づけることも。私達の脳は、何かを考えずにはいられないようになっています。気になることや考えが止まらないのであれば、それをまず受け入れることからはじめてみましょう。
TM瞑想
TMとはタランセンデンタル・メディテーションの略称で、日本語では「超越瞑想」と呼びます。
練習方法は、まず、床あるいは椅子に腰掛けてリラックスし、シンプルなマントラを心の中で唱えることから始まります。マントラとは、サンスクリット語で「文字」「言葉」を意味しますが、漢文に訳すと真言と言われています。意訳すると、心を落ち着かせるために唱える短い言葉といったところ。
サンスクリット語のマントラにはいくつかありますが、自分自身で安心できるような短い言葉や文などを唱えるのでも◎。例えば、「今日はどういった1日過ごしたいか、その1日に当てはまる言葉はどんな言葉か。」など考えてマントラを決めても良いでしょう。
トラタク瞑想
トラタク瞑想は、ろうそくの炎を見つめて、心を落ち着かせる瞑想方法。一般的に、瞑想と言えば目を閉じて練習するイメージが強いかもしれません。しかしトラタク瞑想は、ろうそくなどのツールを用いて、それに集中する練習方法なので、集中しにくい人におすすめ。
まずリラックスした状態で座り、1〜2メートル離れた場所にろうそくを置きます。ろうそくは目の高さに合わせます。火をつけたら、炎に集中し自然な呼吸で心を落ち着かせていきます。ポイントは目の力をいれないこと。そのうちに、ろうそくと自分との境目がなくなっていき、頭の中が静かに整っていく感覚があるかもしれません。
ヨガニードラ
「眠りヨガ」とも言われる瞑想方法です。仰向け(シャヴァーサナ/ 屍のポーズ)の体勢を作って、練習を行います。音声ガイドに従い、身体の緊張を緩めるボディリラクゼーションを行い、身体の細かい部位に意識を向け、心身ともに深いリラクゼーションを体験していきます。
この瞑想は、睡眠の質を高める効果が期待でき、就寝前などに練習をするのがおすすめ。
瞑想は毎日練習すると効果的

Photo by Dingzeyu Li on Unsplash
毎日、同じ時間に同じ場所で瞑想を練習するのが、より効果的。そういった習慣ができあがってくると、その時間、その場所に身を置くだけで、いい気分になれたり、活力があふれてくるようになります。日々のコンディションを整えるためにぜひ、毎日、自分にあった瞑想を練習してはいかがでしょうか。
タンザニアで学んだ「自分に許可を出して幸せになる」方法
「なかなか自分に許可が出せない」
普段の生活の中で、こんな風に感じることって意外と多くないでしょうか。
「あのお化粧、私の歳にはあわないよね」
「あんなこと、私がやったら周りの人に笑われちゃうかな」
興味があっても、自分には無理だと無意識にブレーキをかけていることはありませんか?
でも、自分に「やってもいいよ」という小さな許可を出すだけで、それは自分が望む幸せに1歩近づいているのです。なぜなら、自分を止めているブロックというのは、自分が心の奥で、本当はやりたいと思っていることだったり、ずっと気になっていることだったりするからです。自分をとめているブロックは、自分の本質を映しだしていることが多いのです。
私はここタンザニアで、今まで自分になかなか出せなかった小さな許可を出したことで、長い間感じたことのない幸せな気持ちになりました。この記事を読むと、あなたも日々の生活にちょっとした勇気をとりいれる方法がわかり、日常をさらに幸せにするヒントが見つかります。
「私にはムリ」と思ったアフリカ布との出会い

タンザニアに来て、まず私の目を引いたのは「キテンゲ」というアフリカ布を身にまとったタンザニア人女性の美しさ。この「キテンゲ」は、赤、青、黄色などのカラフルな色と、動物やフルーツなどの大胆な柄が特徴的なデザインの布です。
タンザニア人女性の肌の色に、この明るい色が絶妙なコントラストでとても素敵なのです。
でも、日本人のわたしが着るには、キテンゲは派手すぎて無理だなあ、と考えていました。その一方で、日本人を含む外国人の友達が、このキテンゲのワンピースを上手に着こなしている姿をみて「うらやましいな」「わたしもトライしてみたいな」とも感じていました。
そうはいっても、今まで黒、白、ネイビー色などの無難な色を着ていたわたし。もう40代だしこんなカラフルな色を着たら周りからどう見られるだろう、とやはり抵抗がありました。
ある日、友達がアフリカ布を買いに行くということで私も一緒についていきました。そこで出会ったキテンゲの美しさに改めて魅了されたわたし。気付いた時には、買う予定のなかったキテンゲを自分用に購入していました。そこからは、もう早かったのです。
すぐに仕立て屋さんに娘とわたしのおそろいのワンピースを作ってもらい、あこがれていたキテンゲのワンピースが出来上がりました。はじめての娘とおそろいのワンピースを手にいれた私。まるで宝物を手に入れたようにワクワクしていました。娘からの「一緒に着ていこうよ」の一言にさらに勇気をもらい、早速このワンピースを着て出かけました。友達に「とても似合うよ」とほめてもらったわたしは、服をほめてもらってくすぐったいような、でもほんわかと幸せな気持ちをかみしめる少女に戻っていました。
タンザニアの女性の味方

最初はハードルが高いと感じていたこのキテンゲのワンピースですが、少しの勇気で自分も着用してみたら、大きなときめきとワクワク感と予想しなかった幸せを感じることができました。
こんな外国人の私に幸せをもたらしてくれたキテンゲは、タンザニアでも女性の味方です。
キテンゲは、タンザニアではカバンや小物などにも使われている布ですが、圧倒的に女性のワンピースとして活躍しています。男性優位のタンザニア社会で、このキテンゲはタンザニアの女性のエンパワメントにとても重要な役割を担っています。
例えばクリスマスのようなイベントでは、女性たちが同じ柄のキテンゲでおそろいのワンピースを着て女性たちの団結と強さを表現します。また、自分の娘たちが5~6歳くらいになると、母親は初めてのキテンゲをプレゼントし娘の幸せを願います。出産する女性たちの必需品にもキテンゲが含まれます。赤ん坊が産まれた時に最初に新しい命を包む神聖な布がキテンゲなのです。
キテンゲは、タンザニア人女性が着用して自己表現をする手段であり、男性優位の社会で女性が強く自立していくための仲間のような存在なのです。
自分を解放するための「許可」
こんなキテンゲから、大きな幸せを得ることができた私は、「40代なんだから、こういう色の服を着るべき」という固定観念から解放され、自分に許可を出すことができました。
あなたも普段の生活の中で、ずっと気になっていたけど勇気がでないこと、こんなことしたら恥ずかしい、……と自分に許可を出せていないことはありませんか。
とっても小さな勇気で小さなステップを踏んでみることで、おもいもよらない大きな幸せを感じることができるものです。ぜひ一度トライしてみてくださいね。
想像力が羽ばたくアート展で、心を刺激する内なる旅へ
芸術の秋が近づいてきました。作品を観て、そのときの気分で解釈したり、自分の思うままに感じ取って心の栄養にすることがアートの楽しさ。もうすぐ開催予定のアート展をご紹介します。
紙がこんなに表情豊かだなんて

いろいろな形で丸まったり、曲線を描いてしなったりーー不思議な文様をなしている白い素材。これ、平面素材である紙を使ったペーパーアートです。
ヘア&メイクアップアーティストとして活躍するRyujiさんが新たに手掛ける作品は、髪ならぬ「紙」。実験的にスタートしたクラフトワークが写真家の目に留まり、広告に起用されるなど、今その作品に注目が集まっています。
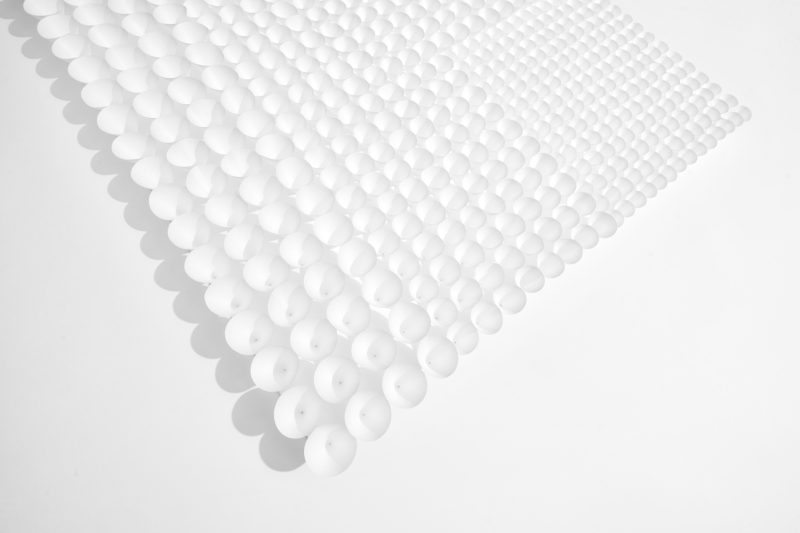
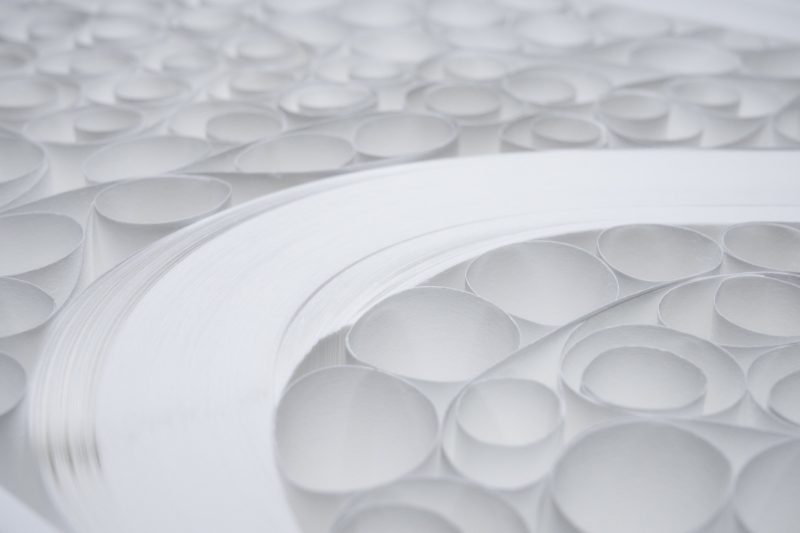
神事などに使われることも多い白い紙には「浄化」の意味があるとされ、今回Ryujiさんが白い紙にこだわったのも、白が「私たちの心に静寂と安寧をもたらしてくれる」からだそう。
白い紙を切り、曲げたり、たわませたり、貼りあわていくプロセスは、基本、すべて手作業。細かな手仕事、微調整の妙、全体のバランスを整えて、アート作品として成立させること。そこには、ビューティークリエイターとして培われたセンスと技が存分に活かされています。
観る者にゆだねられた楽しみ方、感じ方

そんな白い紙が生み出す偶然、そして不完全なフォルム。だからこそ、そこに存在する独特の美しさは新鮮で特別ーー。実際に作品を鑑賞できる機会が、9月に訪れます。それが、Ryujiさんの最新の作品が展示されるアート展『立方体の秩序と円錐の不調和』。
今回のアート展は、航空写真の第一人者として知られる写真家Michael Hitoshiさんとの合同展。彼とRyujiさんのコラボレーション作品の展示も予定されています。
Michael Hitoshiさんの写真は、ヘリコプターで5000フィート上空から眼下の街並みを真俯瞰でとらえたドラマティックな作品。いつもと異なる視点から眺めるその光景が、観る者に新しい視点を授け、感情を揺さぶります。

「それぞれが自分の心の内側で感じることを大切にしてほしい」というRyujiさんからのメッセージ。ぜひ、構えず、自由に。新しいアートとの出合いと、そこから生まれる自分のなかの変化を楽しんでください。
『立方体の秩序と円錐の不調和』
会期:9月1日〜9月11日(11時〜19時)
場所:田中八重洲画廊
http://garou.tanakatochikanri.com/
Profile
Ryuji(りゅうじ)
ヘア&メイクアップアーティスト。東京でフリーランスとして活動した後、2000年に渡米。ニューヨークを拠点に、ヨーロッパ各国で活躍。2009年より東京に拠点を移し、著名人のヘア&メイクを担当するほか、化粧品メーカーの開発アドバイザーや、グローバルに展開する美容室グループのクリエイティブディレクターを務める。メイクアップを駆使した写真やインスタレーションの作品展を開催するなど、アーティスティックな活動も多い。
Instagram @ryujimake
Michael Hitoshi(まいけるひとし)
写真家。上空から真俯瞰で撮影を行う、世界で前例のない作風で知られる。2009年に発表した”Checker board” シリーズを皮切りに、2013年に発表した “LINE” シリーズは、写真界のアカデミー賞と言われるインターナショナルフォトグラファーアワード(USA)スペシャル部門 最優秀賞を受賞。各国で数々の賞を受賞し、全世界で高い評価を得ている。
Instagram @michaelhitoshi_official
この世の恋をしたことがあるみんなに【山口乃々華 / コトノハ日和 vol.07】
言葉があるから伝えられること、伝わること。そこから広がっていく思考、癒し、つながり、希望、愛情・・・深くて力強いもの。女優 山口乃々華が、心に舞い落ちてきた“コトノハ(言葉)”を拾い集めて、じっくりと見つめ、ゆっくりと味わい、思いのままに綴っていく連載。さあ、一緒に元気になりましょう。
君は僕に愛されたという事実を 金ピカのバッジにして胸にはって 歩いていくんだよ
「この場所から」(詩集『わかりやすい恋』銀色夏生 著) より一部抜粋

叔母が住んでいた埃っぽい部屋の中。
本棚に収まりきらず山積みになった本が、狭い部屋で足の踏み場をなくしている。それに加えて暑い。蒸し暑い。「夏生さんの詩集、ここにあるよ〜」と叔母が紹介してくれた。
適当に何冊か選んで手に取ってみた。どれも表紙は色褪せて、古びていて、もう何十年もそこに眠っていたかのような(実際そうだった)・・・なんて言ったら怒られるのだが、本当にちゃんと時間が経っているのを感じて、この詩集たちをまだ少女だった叔母が読んでいたんだなぁと思うと、ちょっとかわいくて面白い。
そんな“銀色夏生コーナー”の中から、選んだこの詩集。
『わかりやすい恋』。
これは思春期のことを指しているのだろうか? 気持ちを隠すことができないほど、心も脳みそも慌ただしく騒いでしまう恋を、私は想う。うーん。私の恋もまだ“わかりやすい”に入るのだろうか。
それとも、経験とともにどんどん“わかりやすい”が増えていく、ということなのだろうか。だとしたら、このタイトルの意味は思春期ではないことになる。もしかして、“わかりやすい恋をする人”ということなのだろうか。なんて、考えた。
「この場所から」はこの詩集に収められた一篇。
私の心に留まったフレーズの、「君は僕に」というその”僕”が、私にとって、大好きでこの世から居なくなったらたまらなく苦しい大事な人だと想像する。
「愛されたという事実」。それは空想でも、妄想でも、眠っているときに見る夢でもなく、事実。
事実は時にむなしいこともある。
けれど、恋をしていたあの時間を思い返す今となっては、そんな記憶なんて、とっくに放り投げていた。
そっと目を瞑って心臓に手を当てれば、当たり前のようにあの時間が蘇ってくる。呼吸、鼓動、体温、匂い。ふわっと柔らかい笑顔に、奥が深い瞳。
火照った心と、安心が一緒になることなんてあるんだと知った“事実”。
それから、詩の中に出てくる「金ピカのバッジ」。
きっと、私にしか見えていない、みんなには秘密のバッジなのだ。誇り高き金ピカのバッジ。
私は嬉しくて何度も何度も見つめるだろう。
それにしても、”僕”はすごいなぁと思う。
金ピカのバッジで私を簡単支配できてしまうのだから。
言葉に特別な魔法をかけるのなんて、きっと彼にとっては朝飯前。何てことないのだ。
“僕”には、いつだって追いつけない。
でも、追いつけないままでいいのかもしれない。
愛されたことを誇りに思い、そんな人に出会えたことを嬉しく感じている。
そんな幸せを想像した詩だった。
自分の生命の終わりよりも、大切な人の生命が終わる方がずっとこわいと感じる日々のなかで、胸にはる、金ピカバッジが、この世の恋をしたことがあるみんなに必要だなぁ、と私は思う。

山口乃々華(やまぐちののか)
2014年からE-girls主演のオムニバスドラマ「恋文日和」第7話にて主演を務め女優業をスタート。映画『イタズラなKiss THE MOVIE』シリーズ、ドラマ・映画『HiGH & LOW』シリーズほか、2020年には『私がモテてどうすんだ』のヒロイン役など、数々の作品に出演。 2020年末までE-girlsとしての活動を経て、2021年より女優業として本格的に活動を開始。2021年3月、初のミュージカル『INTERVIEW~お願い、誰か助けて~』、同8月にはミュージカル『ジェイミー』、2022年3~4月はミュージカル『あなたの初恋探します』でヒロインを演じた。ドラマ「ビッ友×戦士 キラメキパワーズ」(テレビ東京系)に出演。書籍『ののペディア 心の記憶』(幻冬舎文庫)も好評で、文章を書くことも好き。2022年10月にはconSept Musical Drama #7『SERI〜ひとつのいのち』でミュージカル初主演を務める。
https://www.ldh.co.jp/management/yamaguchi_n
Instagram @yamaguchi_nonoka_official
備えておきたい女性向け防災グッズ。
被災中の生理ケアにも対応する衛生用品キット
9月1日は、防災の日。日ごろからいざという時に備えて、防災グッズは準備できていますか? 衛生用品は被災時に体を清潔に保ち、不快感によるストレスを軽減してくれる必需品です。今回は女性にとって心強い防災グッズ「災害用レディースキット」をご紹介します。
自分を信じて進む先に、オリジナルな道がある【ヴィンテージバイヤー 荒木和の衣食住遊学】
いつも元気で幸せそうなひとは、自分の周りに“楽しいこと”を育てる種をまいています。そんな魅力的な方にHummingなライフスタイルのトピックスを伺うシリーズ記事「わたしの衣食住遊学」。今回登場するのは、イギリスでアンティークやヴィンテージのバイイングを行う傍ら、ネイリスト、刺繍作家としても活動中の荒木和さんです。
渡英の目的は点と点をつなげ、線にすること

刺繍は今までの人生で一番熱が入るもの。「刺繍をネイルにのせてみたい」と思い立ってネイルの資格を取得。
大学卒業後、文具雑貨業界で雑貨やヴィンテージのバイイングなどに携わってきた荒木さん。6年前、語学留学で初めて訪れたイギリスには、荒木さんの感性をくすぐるものが溢れていました。個性豊かな花や植物が当たり前に街中に存在し、アンティークやヴィンテージマーケットでたった一つの宝物に出合い、無料開放された美術館で数々の芸術品をじっくりと堪能する・・・「30歳になるまでに絶対にまたここに戻ってくる」と心に誓い帰国したそう。
昨年夏にその想いが叶って念願の再渡英を果たし、現在はロンドン在住。バイヤー、ネイリスト、刺繍作家と幅広く活動し、興味や好奇心の赴くままに挑戦してきた経験をつなぎ、“唯一無二の仕事”を築くための通過点に立っています。
「衣」
周りの目を気にせず、心のままに装うこと

チェルシーフラワーショーに出かける日は、花柄ワンピースがお決まり!?

ロンドンは多くの人種で溢れ、さまざまな文化的背景を持つ人がいます。そういった点からなのか、何が「普通」であるということがかなり曖昧です。よく個人主義の国だといわれますが、必要以上に人に干渉することがないと感じます。ここでは「あなたの好きなように」という空気を感じるから、他人の目を気にせず、好きな服を好きなように着て自分らしく楽しんでいます。
行く先々でよく目にするのは、花柄ワンピースを着た女性たち。お出かけやデートとなると花柄ワンピースを選ぶ人が多いように感じます。特に春先のショップでは「こんなに花柄のバリエーションって存在するんだ!」と驚くほど種類豊富に展開されていました。

私も感化され、ピンク地に緑のハートとバラ模様というかなり派手なワンピースを買いました(笑)。イギリスには各地に「チャリティーショップ」と呼ばれるお店があります。慈善事業団体が運営していて、市民から寄付された中古の服や日用品、本などを販売しており、ショップスタッフの多くはボランティアで、売り上げは慈善事業活動に充てられます。日常の中でそういった活動への理解を深めながら、お金をかけずにおしゃれを楽しんでいる人が多い印象です。

1930年頃に作られたクリスタルビーズのアクセサリーに一目惚れ。

小さな店構えからは想像しがたい量の食器が所狭しと並ぶアンティークショップ。
定期的に蚤の市が開催されたり、アンティークショップも多く、ものを大切にして受け継ぐ習慣が根付いています。アンティークやヴィンテージの買い付けをしていると、素晴らしいジュエリーに出合います。特にアールデコ期のジュエリーが好きで、良いものを見つけるとつい自分のコレクションに。
「食」
食を彩る英国ヴィンテージ食器

お気に入りのヴィンテージ食器。
イギリスに来てから食器に興味を持つようになりました。「ストーク=オン=トレント」といって17世紀から陶器産業が盛んな地方があり、ウェッジウッドやスポードなど名だたるブランドがここから生まれています。アンティークやヴィンテージに携わる仕事をしているため、自然と古い食器を目にすることが増え、販売するもの以外に自分用にも買うようになりました。金箔で豪華絢爛なバラ模様のティーカップなどもアンティークであるのですが、あまりにも私のライフスタイルとはかけ離れているので、素朴な花柄で現代の生活にも合うデザインのものをよく選んでいます。

スーパーマーケットでも簡単に手に入るヴィクトリアサンドウィッチ。価格も手頃でおうちカフェが充実。ラズベリーやブルーベリーなどのベリー類がよく売られていて、ケーキやビスケットと一緒に盛りつければ、ちょっと贅沢な気分に。

スーパーマーケットではスコーンミックスが売られているので、スコーンを焼いて自家製ジャムを添えて。
そうして手に入れたお気に入りの食器でいただくおやつは格別。イギリスの定番お菓子、ヴィクトリアサンドウィッチを食べて以来、イギリスの焼き菓子に興味を持ち、自分でも時々焼くようになりました。イギリスの焼き菓子は簡単なのに素朴で美味しく、気軽にティータイムを楽しめるのが良いところ。甘いもの好きの人も多く、スーパーマーケットの菓子材料コーナーはかなり充実しています。特別な日は大好きなホテルやカフェのアフタヌーンティーに行くこともありますが、自分で好きなお菓子を手作りし、友人と共有する時間も大好きです。
「住」
癒しと楽しみをくれる街並み

ふと目線を上げるとカラフルな花々が。それだけで癒されます。

ショーウィンドウに飾られた愛らしい春の花。
ロンドンは世界有数の都市でありながら自然豊か。季節の移り変わりを肌で感じられ、仕事後や休日にどこか遠くに行かなくても近場でリフレッシュできる機会に恵まれています。テムズ川沿いは絶好のお散歩コースです。
イギリスには新しく建物を建てるのにも、例え自分の家の庭に生えている木であっても許可なく切ってはいけないなど、自然を保護するため厳しいルールがあります。そのためロンドンの47%は緑地なのだそう。野生のリスやキツネを見かけることもしばしば。そんな自然に近いイギリスでは、花を飾る習慣が根付いていて、お店のショーウィンドウに季節の花が飾られていたり、街中にフラワーボウルが吊るされていたりと、いつでも目を楽しませてくれます。


私も自室の窓際を飾るようになりました。ロンドンは家賃がとても高く、シェアハウスが一般的。家具が備え付けのところが多いため、必ずしも自分の趣味ではない部屋をどのようにして居心地良くするか工夫をしながら暮らしています。昨年は窓際に季節の花とヴィンテージやカードを組みあわせてハロウィンには飾りかぼちゃ、クリスマスにはヤドリギを吊るしてイルミネーションを施したり、刺繍作品を飾って楽しみました。
「遊」
“遊び”ながら磨かれる刺繍

初めて販売したのは女の子の顔を刺繍した立体的なブローチ。
学生時代に刺繍に目覚め、独学でスキルを磨いてきた刺繍。きっかけは大学一年生の頃、芸術祭で刺繍のブローチを販売したことでした。そのときが刺繍をするのは初めてで、図書館で初心者向けの本を借りて見よう見まねでステッチを覚えて制作したのですが、嬉しいことに評判がとても良かったのです。

ブロッコリーをモチーフにした立体刺繍。色の見え方など細かく忠実に再現。

その後も刺繍で絵本を作ったり、スタンプワークという立体刺繍の技法を習い、百貨店などで刺繍のアクセサリーを販売したりと制作活動を続け、数をこなしていくうちにスキルアップしていきました。今振り返ると自分の表現方法を早いうちから見つけられたのだと思います。小さくて細かいものが好きなこと、一針一針コツコツ縫った線が絵になり形になる楽しさ。刺繍を始めて10年以上経ちますが、つくづく自分の性分に合っているなと感じます。

ウォレス・コレクションは、ヨーロッパらしい空間も見どころ。

彫刻がたくさん見られるサー・ジョン・ソーンズ博物館。小さな博物館ですが、一点一点興味深い作品ばかり。
イギリスはインスピレーションを得るのに絶好の国だと感じています。私の作品は植物やフルーツ、野菜などの自然物をモチーフにすることが多いですが、美術館や本屋さん、アンティークショップや古い建築、植物園などに遊びに行くと「次はこんなモチーフを作ってみよう」とひらめきます。ほとんどの美術館は入館無料のため、休日は美術館巡りを楽しんでいます。お気に入りは、リチャード・ウォレス卿などによって収集された15世紀から19世紀にかけての芸術作品などが展示されている「ウォレス・コレクション」、イギリスの建築家 ジョン・ソーンズ氏の私邸博物館「サー・ジョン・ソーンズ博物館」。

広大な敷地の国立公園、リッチモンドパークは「あれ?こんなところがあったんだ」と訪れるたびに発見がある場所。
ロンドンは見るところが多く、行きたい場所リストは常に更新され、週末はどこへ行こうかと探す必要はないほど。例え近場であっても隠れた場所に素敵なイングリッシュガーデンを見つけたり、面白いアールデコの建築があったりと探検する甲斐があります。
「学」
オリジナルな仕事を見つける学びの旅


買い付けのために足を運ぶアンティークやヴィンテージマーケット。良い品に出合ったときの喜びは快感!
6年前、ロンドンで半年間の語学留学をしました。その半年間はいろいろな国籍の友達が集まる小さな世界地図のような空間で、言葉に言い表せないほど濃密な時間を過ごしました。彼らから刺激を受けたり、限られた時間のなかで美術館や歴史的価値のある場所を旅したりと、忘れられない思い出が詰まった日々です。帰国後は渡英前から働いていた文具雑貨の会社に戻り経験を積み、昨年、目標としていた30歳で渡英するチャンスを掴みました。

オンラインショップで取り扱っているのはジュエリーや食器が中心。小さな物のなかに、大きなときめきが詰まっています。
再渡英後の一年間は英語を学び直し、仕事を見つけることから始まり、行ったことのなかった場所を巡ったりインプットの日々でした。季節を一周したここからはこれまでの経験を「私にしかできない仕事にする」という目標に向かって邁進していくターンだと感じています。今年5月にはイギリスで買い付けたヴィンテージ食器やジュエリーを販売する自身のオンラインショップをスタート。刺繍はよりイギリスらしいデザインを探求しながら制作しています。
自然を心から愛し、長い歴史のなかで受け継がれてきたものを大切にするイギリスの地で、自分自身と向き合い、たくさんのことを吸収して形にしていきたいです。
巡りが鈍化中と感じたら・・・!夏のむくみをケアするレスキューコスメ
肌や体に良いもの、使い心地が良いもの、気分が上がるもの・・・コスメや美容ツールを上手に取り入れて、Hummingな毎日を送りたい。美容ライター 荒木奈々さんがおすすめをご紹介します。
オイル、ローション、入浴剤・・・いろいろなアイテムでむくみを防止

仕事柄、1日中座りっぱなし。気がつくと脚がパンパンにむくんでいて、昼間からだるい~ことがよくあります。むくみは1年中のトラブルですが、私の場合は夏がもっとも深刻な気が。エアコンの効いた部屋で仕事をしていて動かないことが要因だと思われます。それもよくないと思ってエアコンを切ってみたりしますが、今度は暑くて水分をたくさん摂ったりするので、それがまたむくみの原因に・・・。このむくみのだるさから解放されたい! そんなときに頼りにしているのがこちら。
My select 01:アヴェダのクールなボディオイルでマッサージ

クーリング バランシング オイル 50ml ¥4,180/アヴェダ
体調が悪かったり、塩分を多めに摂った翌日は顔がパンパン、奥二重が一重に! 体の不調がむくみとなって顔に出やすいタイプでしたが、大人になったら今度は体のむくみが酷い・・・。
女性は筋肉量が少ないため、体内の巡りがもともと鈍くなりやすく、むくみやすいといわれます。むくみを感じにくいといっても、実は巡りが滞っていて、本来排出されるべき水分が滞留している場合も。
美容家さんに“すっきりしたいときにはコレ!”と教えてもらったのが、アヴェダの「クーリング バランシング オイル」。アヴェダのアロマオイルはいくつか種類がありますが、爽快な感触の「クーリング バランシング オイル」は、夏のボディケアの一軍。水色のテクスチャーも涼しげです。
アヴェダではペッパーミントのアロマシリーズが人気だそうで、「クーリング バランシング オイル」は、気分をリフレッシュさせるオーガニック ペパーミントにブルーカモミールもブレンド。爽やかさにとことんこだわった設計になっています。ブルーカモミールは、カモミールのなかでも鎮静作用に優れている貴重なエッセンシャルオイルです。
ベタベタが気になる夏もサラッとしたオイルなら問題なし。「クーリング バランシング オイル」のベースは、肌なじみのいいオーガニックのヒマワリオイルを採用。浸透が早いので、クーリング感も素早く堪能できます。マッサージすることで、滞っている巡りも即座にブースト。パンパンなふくらはぎ、背中や肩など凝っている部分や運動後の疲れた脚に塗りながらマッサージしたり。お湯を入れた洗面器にオイルを数滴垂らして、即席の足浴もおすすめです。

クーリング バランシング オイル 7ml ¥3,520/アヴェダ
生理前だけではありません。手全体がだるく、手指がむくみがちではありませんか? 手首まわりも筋肉の緊張で血行不良になりやすいそうですよ。
「クーリング バランシング オイル」のもう1つのうれしい提案が、いつでもどこでもクーリングケアできるロールオンタイプ。手の甲の親指と人差し指の付け根にある合谷(ごうこく)をはじめ、耳の付け根の後ろにある翳風(えいふう)のツボ、リンパが詰まっている膝裏やデコルテのあたりにコロコロ。首筋になじませたりといろいろな部位をスースーさせています。指を使ってポーズをとるHAND YOGAする際も手肌に塗布して香らせて。「クーリング バランシング オイル」の香りは、思考をすっきりするポーズと相性が良いそう。
2021年に100%ヴィーガンにスイッチしたアヴェダについては以前のコラムでも触れましたが、アヴェダのエッセンシャルオイルの約95%がオーガニック認証済みのもの、自然生体を揺るがすことなく野生の原材料も採取。「クーリング バランシング オイル」も100%自然界由来成分でつくられています。
My select 02:見えない湿布!? フランシラのボディローション
-500x750.jpg)
フランシラ 土管のおやじ 100ml ¥8,690/フランシラ&フランツ
フィンランドで300年以上続くハーブ農園、フランシラの森。フランシラでは1981年からアイテムの製造をスタート、使用されている原料のほとんどがその土地で栽培されているものになります。「すべてはウェルビーイングのために」をブランド理念に掲げ、コスメにおいては「自然なものをそのまま受け入れる」がコンセプト。
フィンランドの過酷な環境で育つ素材は、それ自体がパワフルなもの。そのためアロマセラピー(香り成分)、フィトセラピー(植物成分)、ホメオパシー(同種成分)、フラワーセラピー(花のエネルギー)の4つの植物成分からなるフランシラのコスメは、そのどれもが独特のパワフルさを放っています。ハンドピックや低温圧搾法など手間をかけて成分を採取。色素や香料の調整は一切行っておらず、文字通りナチュラルブレンドのアイテムが揃っています。
アーシングできるピート、クレンジングエマルジョン、2色セットのコンシーラーなど、フランシラの傑作のなかで特に印象的なのが、ハーブボディローション「土管のおやじ」。
どかんのおやじ? 16世紀に実在したという森のセラピスト(シャーマン)、オヤンおじさん調合の薬草レシピから再現されたローションで、どかんのおやじとはオヤンおじさんのニックネーム。フランシラだけがレシピの継承を許され、「土管のおやじ」として受け継いでいるのです。

オヤンおじさんが目印のボトルのラベルとパッケージ。
香り成分はジュニパー、ペパーミント、タイム、ウインターグリーンなど。ウインターグリーンは成分の99%がサリチル酸メチルという非常に珍しいハーブで、湿布薬などによく用いられていますよね。ふくらはぎの頑固なむくみには、こちらをフリクション。またこわばっている肩や首にもすり込みます。
関節の痛みなどにもアプローチできるらしく、フィンランドではケア施設などの施術でも使用されているようです。「土管のおやじ」にまつわる感動的な実話も多く、2013年にはフィンランドの健康・ケアアイテムに贈られるケア製品大賞も受賞しています。
ローションタイプで、ただ塗るだけ。ベタつきも気にならないので、ストッキングの上からもつけられます。敏感肌の方やお子さんに使う場合は、水で薄めて使用したりするのが良さそうです。
フィンランドは世界一環境汚染が少ないといわれる国。ゴミの分別は20年以上前から広まっていて、各家庭に種類別に5~6個のゴミ箱があるのが普通とか。環境に対する意識が高い国で、またオーガニックコスメも豊富にあるなかで支持されるフランシラ。「土管のおやじ」は、フィンランドのほとんどの薬局で手に入るそうですよ。
フランシラ
https://www.frantsila.jp/
My select 03:水分停滞をケアするポール・シェリーのバスオイル

ポール・シェリー シルエット ハイドロ バスオイル 150ml ¥7,700/ピー・エス・インターナショナル
ハーブ療法家5代目のポール・シェリー氏が、1978年にスイスで立ち上げたポール・シェリー。ハーブオタクのブランドで、ハーブの産地にもこだわり、代々伝わるハーブ療法のレシピをもとに、植物のエネルギーを生かしたアイテムを発表。サロンなどのトリートメントで多く取り扱われるフィトアロマブランドです。
サロン効果をセルフケアでも手軽に楽しめるのが、バスオイルシリーズ。むくみ対策の「シルエット ハイドロ バスオイル」をはじめ、リラクゼーション、PMS、冷え、ハリの全5種から、悩みや目的別に合わせてチョイスできます。
こんな症状はありませんか?「汗をかきにくい」「トイレに行く頻度が少ない」「夕方サンダルを脱ぐと跡がついている」「体が重く感じる」「太ももがタポタポしている」。1つでも当てはまるようだったら、体内に水分が滞留していて、うまく排出できていないかもしれません。私は全部に心当たりがあります・・・。
「シルエット ハイドロ バスオイル」に配合されている主なハーブは、温浴効果による水分排出を助けるジュニパー、香りによって心身のバイタリティを高めるセイボリーや、疲労もケアするハーブのラベンダー。バスオイルですから扱いは簡単。キャップ2杯程度をバスタブに入れて、お湯をかき混ぜて全身浴するだけですっきり感を味わえます。お気に入りは泡風呂。バスオイルを入れてシャワーで勢いよくお湯を注ぐと軽く泡立ち、心地良い森林の香りで満たされます。

むくみ対策は、入浴による発汗や血流促進によるもの。リラクゼーション、PMSは香りの効果によるもの。妊娠中、授乳中の方は使用をお控えください。
気になるむくみはその日のうちにリセットしないと、たるみやセルライトになってしまう可能性も。ただ入浴するだけでむくみケアが簡単にでき、すっきり系バスオイルはこの夏も大活躍です。
ポール・シェリー
https://paulscerri.jp/
My select 04:巡り体質に改善。重炭酸温浴が叶うホットタブ

薬用 HOT TAB WELLNESS 全3種[医薬部外品]¥990~¥6,930/ホットタブ
暑い日に熱い湯船には入りたくないという人にお伝えしたいのが、ぬるま湯でも巡りを高める入浴法。炭酸のパワーを借りれば、ぬるめのお湯でも血流促進、体内の巡りは良くなるのです。
炭酸風呂って最初だけブクブク。無香料、無着色だと何の変化も見えないけれど、普通のお湯と何が違うのでしょうか? 炭酸泉とは、炭酸ガス(CO2)が溶け込んでいるお湯のこと。重炭酸入浴剤HOT TAB(ホットタブ)シリーズの主成分は、自然由来の重曹、クエン酸、ビタミンCの3つで、発生した炭酸ガスは湯の中で重炭酸イオンと水素イオンに瞬時に変化するため、炭酸ガスはほとんど発生しないのだとか。また、通常の炭酸泉は酸性ですが、ホットタブの炭酸泉は、血液や水道水と同じ中性のpH値。しかも日本の水道水は世界一塩素濃度が高いといわれ、「HOT TAB」を入れることで、デリケートな肌が気になる塩素もカット。肌にやさしい湯ざわりに。
「HOT TAB WELLNESS」はレスケミカルな入浴剤、従来品よりビタミンCの濃度が10%も高まり、より美肌効果が期待できるようにも。36℃以上41℃以下のぬるめのお湯に3錠を入れて、15分以上(できれば30分程度)の入浴がメーカーおすすめの“健康浴”。ややぬるいかなと感じるお湯でも炭酸入浴剤が溶け込んでいるので、体温を芯から上昇させ血流を促進させることができます。慢性的なむくみ体質の方は、こちらを用いて入浴そのものを見直すのも手。
しかも積極的に血流を促すので、有酸素運動と同じようなエネルギーの消費効果も期待できるそうですよ。
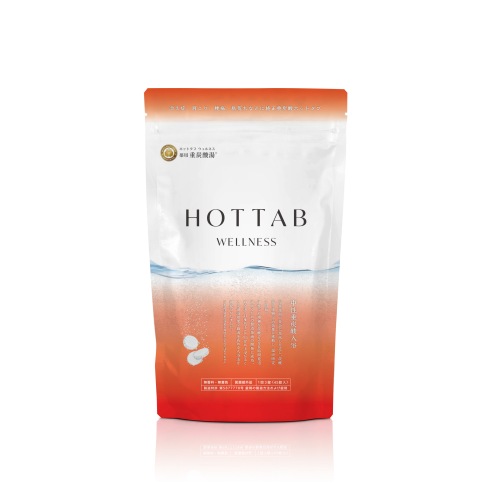
45錠で15日分。
クエン酸や重曹によって肌の汚れを浮き上がらせる作用もあります。ホットタブのテーマにあるのが、NUCSS(Not Using chemical Soap & Shampooの略)(ナクス)で、肌や体に刺激となる化学合成洗剤による洗いすぎを防ぎ、体を清潔に洗浄する役目も持つホットタブ。クエン酸や重曹はクリーニング剤でもよく聞く成分ですが、浴槽が汚れにくい点もうれしいのです。
私たちが地球にできるサステナビリティ=健康でいること。
平均体温は36.5度であることが健康の基本だそうで、ホットタブでは、重炭酸温浴による健康促進活動を普及させることで、2030年までに家族の医療費50%削減を目標に掲げています。
ホットタブ
https://hottab.co.jp
たかがむくみと侮らないほうが良さそう。次のトラブルを引き起こす可能性もあるのです。健康にもつながっていくものだから、引き続きむくみケアを注視したいです。
生理中も心晴れ。どんな日も私に寄り添う「Nagi」の吸水ショーツ
生理期間中に感じやすいストレスや不調。それらを緩和してくれる救世主的アイテムとして、愛用者が増えているのが吸水ショーツです。今回はフェムテックブランド「Nagi(ナギ)」が手がけるスポーツ用の吸水ショーツ「Nagi SPORTS」をご紹介します。
暮らしのなかで物語を育む、エターナルな愛用品【森岡書店 店主 森岡督行のお気に入りLIST】
その道のプロに聞く、今の自分に必要なお気に入りアイテム。今回は、森岡書店 店主 森岡督行さんに3つの大切なアイテムを見せていただきました。
時の流れを慈しむ、独自の審美眼
「一冊の本を売る本屋」というユニークなコンセプトで、銀座に店を構える森岡督行さん。昭和初期の歴史ある建造物にある店内では週替わりで一冊の本と、その本にまつわるギャラリーを展開、人と情報が集まる場として進化を続けています。そんな文化発信地の中心にいる森岡さんが、ずっと変わらず大事にしているアイテムとは?
体調を崩しやすい季節に。
立ち寄り蒸し屋「Mushiya」でスキマ時間に温め美容
眉ティントやあぶらとりウォーターパウダーなど、斬新なアイデアコスメが次々とヒットしているコスメブランド「Fujiko」(フジコ)がよもぎ蒸しサロンをプロデュース。キレイになりたい!をベースにしながら、女性特有のさまざまな悩みに寄り添うサロン「Mushiya」(ムシヤ)とは?
1時間の温めケアで心身ともにリフレッシュ

体を温め、血流を促すことで美容や健康、リラックス、デトックスを目的に人気を集めているよもぎ蒸し。薬草を煮出した蒸気を膣から粘膜吸収させていくことで産後の肥立ちが良くなるとされ、韓国では古くから産後ケアとして取り入れられていた伝統的な民間療法です。腕の内側を1とした場合、約42倍の吸収率といわれる膣の粘膜から、薬効成分を含んだ蒸気を体内に浸透させることで顔や身体に現れる女性特有の悩みや不調の軽減が期待できるといわれています。

落ち着いた雰囲気の居心地のいい個室。
「Mushiya」は“立ち寄り蒸し屋”をコンセプトに、約1時間でカウンセリングから着替え、蒸し、メイク直しができる設計。メイクルームでは「Fujiko」をはじめとする株式会社かならぼが手がける「BIDOL」「4U」のコスメが自由に使えたり、アイロン、ドライヤー類などを完備。よもぎ蒸し後、そのまま仕事に戻ったり、遊びに出かけられるのも通いやすいポイント。

BASICブレンド¥4,000、季節ブレンド¥4,000、Specialブレンド¥6,500を用意。
薬草には韓国韓方よもぎブレンドと純国産よもぎブレンドを使用し、さまざまなお悩みに合わせた、9種類のこだわりのブレンドを用意。子宮/自律神経/免疫/ダイエット/美肌のお悩みに合わせた5種のBASICブレンド、季節ブレンドが1種、本気でキレイを目指したい方にオススメのSpecialブレンドが3種。使用する水は不純物を極力カット。蒸し窯は黄土を採用し、電気窯とは一味違うじんわりと身体の芯から温まるような心地良さを味わうことができます。
そして忙しく限られた時間のなかでも、簡単に、思う存分リラックスできる空間づくりにもこだわりあり。個室で誰にも邪魔されることなく、瞑想をしたり、自分だけの時間を過ごせます。
サロンオープンを記念して9/8までの期間、全メニューが20%オフになるキャンペーンを実施中(初回のみ)だそう。内と外との気温差により、体に負荷がかかり体調不良を起こしやすい季節。気軽に立ち寄れるよもぎ蒸しで、キレイと健康を叶える温活を始めてみては?
Mushiya
東京都渋谷区恵比寿西1-17-1えびす第一ビル8F
03-6433-7876
https://mushiya.salon/
脱プラスチック!毎日使う歯ブラシこそ、サステナブルな選択を。
地球環境に優しいものを選びたい。そう思っていてもいきなり身の回りのものをすべて切り替えるのは難しいですよね。そんなときはまず、使用頻度が高い日用品から見直していきましょう。なかでも毎日使う歯ブラシは消耗品。今回はプラスチックごみを減らし、環境を守る北欧生まれの竹製歯ブラシをご紹介します。
オーラルケアを楽しく、より心地良く!

歯ブラシは、3ヵ月ごとの交換が推奨されています。世界では毎年100億以上ものプラスチックのオーラルケア製品が消費されており、そのほとんどが最終的に埋め立て地や海へと捨てられているそう。完全に自然分解されることのないプラスチックごみは、増え続ける一方なのです。自然環境を守るべく、プラスチックごみを減らす代替資源のひとつとして注目されているのが、生分解性100%である竹です。竹には天然の抗菌作用があり、栽培中に肥料や殺虫剤などの化学薬品が必要ないというメリットもあります。
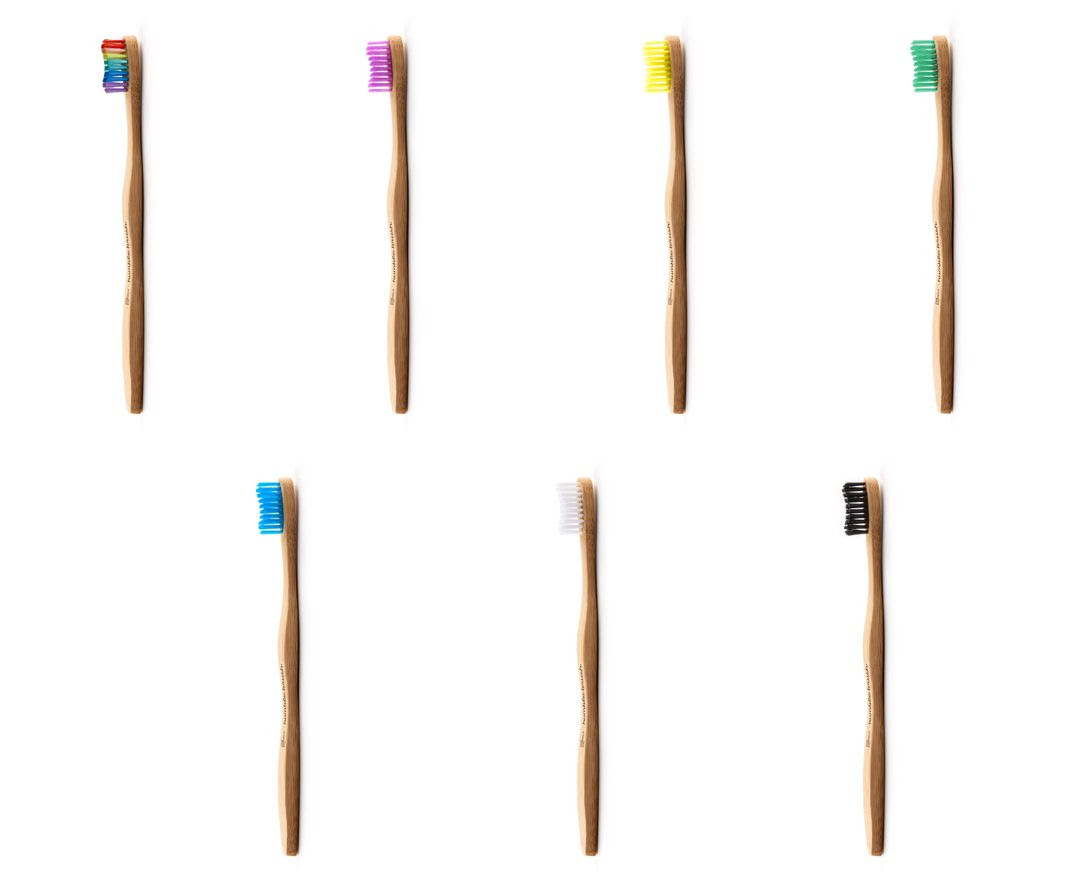
スウェーデン発のオーラルケアブランド「THE HUMBLE CO.」(ザ ハンブル コー)の歯ブラシは柄の部分に竹材、ブラシ部分は植物由来原料を使用したバイオベースナイロンを採用。バイオベースナイロンのブラシは柔らかく、口の中を傷つけず、磨き心地も抜群! 有害な化学物質を含まず、子供から大人まで安心して使えるのが特徴です。
目に入るたびにハッピーな気分になれそうなカラフルなブラシがあれば、歯磨きタイムがもっと楽しくなるはず! 機能的でありながら、北欧らしいデザインセンスが魅力的。

こちらはジューシーなフレーバーを楽しみながら、しっかりと汚れを絡め取ることができるデンタルフロス。従来のフロスに使用されている、ゼラチンやPFC(加フッ素化合物)を使用せず、天然のキャンデリラワックスをフロスにコーティング。ワックスには天然のナチュラルフレーバーに加え、樺の木からとれたキシリトールを配合し、すっきり爽快な使い心地を実現。外装にはディスペンサー代わりになる再利用可能な紙製のパッケージを。
歯科医師のノエル・アブデイエム氏が手掛けるザ ハンブル コーは、世界中の何千もの店舗や歯科医院で取り扱われています。支援が必要な地域に住む世界中の子供たちの口腔ケア支援を行うNGO団体、ハンブルスマイル財団の活動にも貢献。オーラル製品の寄付をはじめ、口腔ケアの知識や手段を提供しているそうですよ。
生涯を通して健康な歯と身体を維持するために欠かせないオーラルケア。地球環境や未来を想った優しい製品で、毎日コツコツ、楽しくケアを続けましょう!
THE HUMBLE CO.
https://thehumbleco.jp/
新宿三丁目のヴィーガンカフェで、極上パンケーキに舌鼓【渡辺知夏子のエシカルスポットNavi. vol.10】
普段の何気ない暮らしのなかで、サステナブルなアクションが出来たら素敵だと思いませんか? エシカルなライフスタイルを提案しているレストランやショップを、自身もウェルビーイングな生活を心掛けているというモデル渡辺知夏子さんがナビゲート。今回は、オーナー自身の食環境がきっかけでヴィーガンショップをオープンさせたという『AIN SOPH. Journey(アインソフ ジャーニー)新宿』をご案内します。
AIN SOPH. Journey 新宿

今回お邪魔させていただいたのは、新宿三丁目にあるヴィーガンカフェ『AIN SOPH. Journey(アインソフ ジャーニー)新宿』。駅のC5番出口から地上に出ると目の前に現れる、緑に囲まれた雰囲気のあるビルが目印です。

香り高いスパイスやハーブをふんだんに使った、季節のベジタブル料理が楽しめると評判のこちらのお店。そんななかでも人気メニューとなっているのが、ヴィーガン通にはおなじみ、ヴィーガンとは思えないクオリティの「天上のヴィーガンパンケーキ」です。
また、VEGAN AWARD 2022で金賞を受賞した「ティラミス」もとっても有名。著名人にもファンの多いこのカフェの一号店である銀座店がオープンしたのは2009年と、実に10年以上にわたり支持されてきた歴史があります。

「オープン当時からヴィーガンメニューを提供していますが、最初は“ヴィーガン”という言葉を知らない人が多かったため、あえてメニューにもヴィーガンという言葉を使うのを避けていました。そこから10年以上経ち、現在は多くの人がヴィーガンや自然食に関心を寄せるようになっています。ナチュラルでヘルシーな食の提供に役立てていることを、今はとても誇りに思っております」
そう語るのは、AIN SOPH. Journeyのオーナー白井由紀さん。ヴィーガンショップをオープンさせたのは、自身の食環境が大きく関係しているのだそう。

取材に対応してくださったオーナーの白井由紀さん。
「10代の頃に留学したカナダのとある地域が、たまたまヴィーガン文化が強く根付いた場所だったんです。そこで初めて、ヴィーガン食に触れる機会ができたのですが、私はわりと抵抗なくなじむことができました。それは、父方の実家が真言密教の家系で、以前から精進料理などを口にする機会が多かったことも影響していたのかもしれません。
そのカナダ留学中に、環境問題をはじめ、宗教などの信条、動物愛護などの理由で、動物性食物を避ける方が世界中には数多く存在することを知りました。そのような方々が、思想の違いでテーブルを別にするのはとても寂しい。そんな思いから、ヴィーガンの方はもちろん、それ以外の方も楽しく食卓を囲める空間づくりをしようと決意しました」

ヴィーガンということで食材に制限はあるものの、「一般の食事以上の美味しさやバリエーションをお届けできるよう努力を重ねてきました」と語る白井さん。その甲斐もあって、現在は本店の銀座や新宿三丁目店のほかにも、池袋店や京都店、さらにはフランチャイズ店も続々とオープン。食生活をより豊かに、楽しいものにするために、店内の内装にも心を配っています。
「新宿店は、異国にタイムトラベルしたような空間づくりがコンセプトになっております。食器はモロッコから直接取り寄せたものを使い、照明などにもこだわりました」

シンプルな内装の中に無国籍なインテリアを配置して、リラックスできる雰囲気に。
料理の内容だけでなく、店を訪れていただくからには、食事すること自体を楽しむことが大前提。空間づくりにもおもてなしの心を込める、そんな思いが多くのお客様に愛されている所以なのかも。
白井さんに、初心者でも挑戦しやすいヴィーガンライフについて伺ってみると、明日からでも真似できそうなアイデアが!
「週末だけ動物性食物を控える『ゆるベジタリアン』から初めてみるのはいかがでしょう。ヴィーガンは無理に強いるものではなく、自分を大切にしたり、その先にある世界や大切な人を愛する気持ちの方が重要なのです。時には瞑想を取り入れてみたり、ゆったりとした気持ちをもってトライするのがベストです」
初訪問の知夏子さんが、人気メニューを網羅

ヴィーガンレストランといえば、広尾や青山など、外国人居住者の多い街にあるイメージですが、今回訪れたのは新宿三丁目。
「最初は意外な場所だなと思いましたが、よくよく考えてみたら新宿も外国人居住者の多い街。さらにいろんな国の人が多く集う多国籍エリアなので、ヴィーガンのお店が長年人気があるのも納得です」と知夏子さん。
入り口から続く階段を降りると、白を基調とした落ち着いた空間が広がっています。1階にはテイクアウトの焼き菓子やスイーツカウンターがあり、イートインスペースは地下1階と2階にも。混雑する時間帯でも、ゆっくりと食事を楽しめそう。

こちらは2階。シンプルながら居心地のいい空間は、世代を問わず好評です。
席に着く前に店内を一巡した知夏子さん。そこで、テイクアウトできるコーナーの焼き菓子に添えられたプレートを熟読。
「こちらで使っている食材には肉、魚、乳製品、白砂糖を使わないのはもちろん、自然農や無農薬の食材を、なるべく日本製にこだわって作っていると明記されています。このコンセプトは、とても大切ですよね」

さていよいよ、実食へ。1階奥のテーブル席に移動します。自然光がたっぷり入る窓際は、居心地の良い空間。まずは、ランチで一番人気のサラダ&デリランチをオーダー。

「まず最初に驚いたのが、ボリューム感! 色とりどりの旬の野菜がプレートいっぱいに盛り付けられていて、さらにソイミートの唐揚げやキッシュ、玄米と、食べ応え満点!」

「正直なところ『食べきれないのでは?』と思いましたが、心配無用でした(笑)。とにかく新鮮な野菜がとても美味しくて! プレート全体のバランスも良くて、一つひとつが味わい深いです」

季節の野菜は蒸したものからフレッシュなものまで、厳選された7種類をトッピング。さらに日替わりデリを3種類乗せて、玄米ライスもしくはバケットをチョイス。鮮やかな見た目も食欲をそそります。サラダデリランチ¥1,630
ランチセットのドリンクには、産地選びにもこだわっているという日本製のハーブティーをチョイス。ドリンクは、ハーブティーの他に、オーガニックコーヒーや紅茶を楽しむことも。ハーブティーは日によって提供される茶葉が変わります。

この日のハーブティーは月桃茶。ショウガのような爽やかな味わい。セットドリンク¥330
ランチを堪能した後は、いよいよお楽しみの、「天上のヴィーガンパンケーキ」の登場。ランチセットのドリンクとともにいただきます。

「フワッフワの生地にチーズの香りが楽しめるパンケーキ。こんなにチーズを感じるのに、乳製品を一切使っていないだなんて本当に驚き! 自家製アイスクリームやフルーツとの相性も素晴らしいです。トッピングは季節ごとに変わるので、訪れるたびにオーダーしてしまいそう」

研究に研究を重ね、卵を一切使わずにフワフワのもちもち食感を実現。季節のフルーツも添えられた、華やかで美しい一品です。

そして最後に、人気のティラミスも試食させていただくことに。

ティラミスはオンラインショップでも購入可能。4セット、6セットのいずれかを選択。4セット¥ 3,320、6セット ¥4,770(送料別)
VEGAN AWARD 2022金賞を受賞した「ティラミス」は、口に入れた瞬間にとろけるような極上の美味しさ。!
「マスカルポーネ風ソイクリームチーズの濃厚な味わいと、リキュールとコーヒーの絶妙な組み合わせ! 隠し味の伊予柑ピールで、爽やかな風味も楽しめます。VEGAN AWARD金賞というのも納得の美味しさです」

取材後は、白井さんとのヴィーガントークがさらに盛り上がり、今回もまた、たくさんの学びを得たという知夏子さん。ヴィーガンな人、ヴィーガンに関心がある人だけでなく、食事をヘルシーにしたい人、人気のスイーツを楽しみたい人にもおすすめのこちらのお店。オンラインショップも充実しているので、ぜひ一度AIN SOPH. Journeyの幸せな味を体験してみて。
「AIN SOPH. Journey新宿」
東京都新宿区新宿3-8-9 新宿QビルB1階、1階、2階
050-3503-8688
https://www.ain-soph.jp/journey-shinjuku
太陽も海風も色になる、奄美大島の泥染め【現代美術家 山本愛子 / 植物と私が語るときvol.3】
染色を中心に自然素材や廃材を使い、ものの持つ土着性や記憶の在り処をテーマとした作品を制作する現代美術家、山本愛子さんの連載 。草木染の研究にいそしむ山本さんが、さまざまな土地を訪れ、そこで出合った植物についてつづっていきます。第3回目は奄美大島の泥染めをご紹介。
風土により培われる個性
先日、ずっと行ってみたかった奄美大島へ行ってきました。北方と南方を結ぶ交流の接点「海のシルクロード」とも呼ばれる奄美大島。大島紬、泥染めなどの染織でも有名です。今回の滞在では、染色工房「金井工芸」の金井さんに泥染めを教えていただきました。

はじめは「泥でどうやって染めるの?」というのが純粋な疑問でした。天然染色では、「藍染め」や「タマネギ染め」のように染料にする植物が染めの名称になります。しかし泥染めの場合は異なります。泥染めの泥は、染料を繊維に定着させる役割を果たしていて、繊維を染める染料は、車輪梅(シャリンバイ)という木から煮出した色素です。車輪梅にはタンニンが豊富で、泥の中の鉄分がタンニンと反応していくことで、深い色が布に定着していくそうです。

金井さんの「奄美は紫外線も強く海風が強いから、シャリンバイが自身を守るためにタンニンを豊富に生成している。奄美大島の風土で強く育ったシャリンバイだからこそ、泥染めにしたときに濃く染まる」というお話が印象的でした。風土と色彩の関係を、現地で日々感じ取っている金井さんの言葉は心に響きます。


奄美大島を訪れ、私の肌も焼けました。海風が肌や髪に刺激を与え、ここに住んだら皮膚が強くなりそうだなと感じました(笑)。夜ご飯には地魚の美味しさが胃袋に染みました。植物も、私たち人間も、外の環境によって中身が培われていくのだなぁとひしひし感じます。「紫外線と海風が車輪梅のタンニンを増やしているんだ」と聞いたとき、目に見えないことでよく実感が湧かなかったけれど、染色によってそれが目に見える形になったときに、「あぁ、これが奄美の自然が生んだ色なんだな」と腑に落ちる瞬間があったのです。

染色は私に旅をさせてくれます。作業をするために手を動かし、原料を見るために足を運び、さまざまな土地に向かわせる旅。そうして染まった色を見て、車輪梅、泥、紫外線、海風などの自然を感じる心の旅。
奄美大島にはこの秋にもう一度行き、さらに現地の染織と植物についてを深堀りしていくのでまたお付き合いよろしくお願いします!

日常に輝きを。私らしさを引き出す「HANA TAJIMA FOR UNIQLO」のドレスコレクション
ニューヨークを拠点に活躍する英国⽣まれのファッションデザイナー、ハナ・タジマとユニクロのコラボレーションライン「HANA TAJIMA FOR UNIQLO(ハナ タジマ フォー ユニクロ)」の新作ドレスコレクションが到着。着るだけで理想の自分に一歩近づく、優雅さと快適さを兼ね備えたアイテムは必見です!
「私」の魅力を引き立てるドレス

デザイナー・HANA TAJIMA氏が手がけたのは、凛とした美しさを放つ上品で軽やかなワンピース。柔らかくドレープ感のあるレーヨン・リヨセル、光沢に深みのあるサテン、温かみのあるフランネルの3つの素材を軸に、優れたカッティング技術とディテールへのこだわりが詰まったシンプルかつエレガントな仕上がりが特徴。
光と上手く付き合いたい。デジタル時代のコスメ選び
肌や体に良いもの、使い心地が良いもの、気分が上がるもの・・・コスメや美容ツールを上手に取り入れて、Hummingな毎日を送りたい。美容ライター 荒木奈々さんがおすすめをご紹介します。
外では紫外線、家の中でもブルーライト。肌は光を浴びまくり!?

紫外線は肌に悪影響! そういろいろなメディアで騒がれているのに、中学校の教科書をパラパラ見ていたら、「紫外線には日焼けを起こす作用がある」程度の記述のみ。学校ではやっぱり正しい美容法なんて教えてくれません(笑)。肌の老化の約7、8割は光老化が原因といわれており、それには紫外線以外の光も含まれてるようで・・・。私の場合は、明らかにデジタルデバイス使用が増えている!ため、その環境にあわせて光対策アイテムもマークすることに。
My select 01:ソロスなら、デジタルほか、外的要因のダメージを帳消し

朝から晩までパソコン前にはりつき、夜はスマホで1、2本、映画かドラマを見るのが普段の日。相当なデジタル沼にハマっていますが、なかなか抜け出せません。でもSOLOS(ソロス)の登場でハッとしました。平均年収は変わっていませんが、30年前と比べて大きく変わったデジタル環境。デジタル要因のブルーライトダメージが肌に蓄積されているかも・・・。
2022春デビューのソロスは、デジタル×ウェルネスビューティを視点に、洗顔料、ローション、フェイスクリームの3ラインで、デジタル社会の「内」と「外」のダメージにアプローチするスキンケアブランド。オリジナルメソッドは “ACPB”CYCLEというA:Awareness・・・気づく(デジタル端末に囲まれてのダメージに「気づく」)、C:Clean・・・浄化する(洗顔料)、P:Prepare・・・整える(ローション)、B:Barrier・・・バリアする(フェイスクリーム)。
デジタル端末の「内」への影響といえば、脳疲労、自律神経の乱れなど。光を見ていつもよりもチラチラ、眩しいと感じるときは自律神経が乱れているらしく・・・。
その「内」に対応するのが、自然療法士によって調合されたソロスのオリジナルの香りです。アイテム共通の精油にはシダーウッドを。さらにアイテムごとに、クラリセージ、ジュニパー、ゼラニウム、ベルガモット、フランキンセンス、ラベンダー、レモンから選定した、リラックスリフレッシュのアロマ。その香りをかぐととても安らぐ♪ そんな日は、逆に“疲れていたんだな”と気づくこともできそう。

ソロス フェイシャルウォッシュ 150ml ¥3,300/ソロス
「ソロス フェイシャルウォッシュ」は泡で出てくるフォームタイプ。キメ細かい泡で、肌をプッシュするだけでもフゥーとため息をついてしまうくらい癒やされます。同時にレモンとベルガモットの柑橘系のエッセンシャルオイルと、シダーウッド、ジュニパーの奏でる香りで気分もクリアに。植物由来の洗浄成分によってベタつきのもともしっかり吸着、洗いあがりの肌は思いのほか爽快です。
ソロスはメンズビューティでも注目の的。泡立てが苦手な男女ともにシェア。
「外」への影響は光老化に着目。紫外線だけでなく、人に見える可視光線のブルーライトや近赤外線も危ぶまれる光。太陽光にも含まれるブルーライトは、パソコンやLEDからも発せられるといわれますよね。ただ太陽光に比べて、デジタルデバイスなどが放つブルーライトは超微量とか。そこまで怖がらなくてもよさそうですが、チリつも! 浴びまくりなら用心したいですね。

ソロス フェイスクリーム 30g ¥4,620/ソロス
ブランドの推しは「ソロス フェイスクリーム」。デジタルのブルーライトだけでなく、あらゆる光ダメージから肌を守るために、ソロスが厳選したのは、ビタミンKを豊富に含む沖縄素材の海ぶどうとヨモギ。さらにシアバター、ノニ、白金など優れた抗酸化でおなじみの成分がたくさん。また、ビタミンEやビタミンAを含む、天然の日焼け止めと呼ばれるラズベリーシードオイルも含有。クラリセージ、ラベンダー、シダーウッドの調香は、デジタルストレスによる緊張をやわらげ、穏やかな気分に導いてくれます。
石油系成分不使用、キャリーオーバー成分不使用などを約束しているソロスでは、“フレッシュ”を届けたいという試みから、パッケージには製造年月日の表示、大量生産をしていません。
ソロス
https://solos-cosmetics.jp/
My select 02:くすみに寄り添う、ナチュラグラッセのメイクアップクリーム

ナチュラグラッセ メイクアップ クリームカラープラス SPF44・PA+++ 全2色 各30g 各¥3,080/ネイチャーズウェイ
天然由来成分がベースで、高SPF、素肌を美しく仕上げる下地は?と尋ねられることがあったら、思いつくのが、ナチュラグラッセの人気者「メイクアップ クリーム」。100%天然由来原料の使用、SPF44・PA+++の高いプロテクト機能、そしてもとからキレイな素肌に演出する逸品!
そこにカラー補正機能を追加しているのが、「メイクアップ クリーム カラープラス」。化粧下地、ライトファンデーション、日焼け止め、ブルーライトカット、保湿美容液、カラー補正を任された1本6役。スキンケア発想のメイクアップクリームといわれるだけあって、ブランドの共通成分オリーブ、ホホバ、サジーのミックスオイルをベースに、高温多湿のアマゾンで生育する必須脂肪酸を含むサチャインチ、山梨県の自社農場で栽培しているゼニアオイなどの保湿成分が高配合されています。
水系と油系の絶妙バランスによって、エマルジョンと美容液のいいとこどり。美容液のように軽くスーッとのびるつけ心地、肌にフィットするとエマルジョンで仕立てたようなムチッとハリも感じる肌に。
また、「メイクアップ クリーム」のフォーカスしたい機能がブルーライトカット。ブルーライトを含む太陽の光を朝浴びることで、わたしたちは体内時計の誤差をリセットできるといわれています。でもその光は、紫外線よりも波長が短くエネルギーが強く、しかもデジタルものからも少なからず発生・・・。
「メイクアップ クリーム」は、ブルーライトから肌を守るためにルテインという成分に着目。「メイクアップ クリーム カラープラス」は、ブルーライトカット99.2%(第三機関実施試験結果より)を実現しています。

くすみが気になる肌にはラベンダーピンク、赤みが気になる肌にはミントグリーン
それから「メイクアップ クリーム カラープラス」は光を味方にするのも得意。ラベンダーピンクのほうは、カラーそのものの補正機能に加え、偏光ピンクパールと偏光イエローゴールドパールをイン。パールのソフトフォーカス効果によって、気になるくすみ感をなかったことに。透明感と血色感を演出しながら、ワントーン明るい肌に仕上げてくれます。ミントグリーンは、赤みをカバーするグリーンの効果に、偏光グリーンパールによって色ムラや毛穴の影もカバー。
どす黒かったり、青っぽかったり、黄色ぽかったり…くすみの種類はさまざまなので、その日のくすみ感によって2色を使い分けるのもおすすめ。
ナチュラルグラッセは、日本の自然化粧品のパイオニア、ネイチャーズウェイのオリジナルメイクブランド。2008年デビュー、100%天然由来原料の使用にこだわってアイテムを開発しています。今回紹介したオールインワンアイテムをはじめ、下地、ファンデ、コンシーラーまでベースメイクが充実。全アイテム石けんで落とせる処方が助かる!
ネイチャーズウェイ(ナチュラグラッセ)
https://online.naturesway.jp/naturaglace/
My select 03:抗酸化ケアもチェック。イニスフリーの導入美容液

グリーンティーシード セラム N 80ml ¥3,190/イニスフリー
肌や体の酸化をすすませるという紫外線やブルーライト。光とともに生きるのが自律神経を乱さない策であり、理想といいますが、光の中に朝から晩までいる現代人は、抗酸化対策が欠かせませんよね。
インナーケアでは緑茶を飲むのがよいと聞きますが、表面からのケアはチャ葉エキスがたっぷりのイニスフリーもチェック。
エココンシャスビューティーブランド、イニスフリーは、ユネスコ世界自然遺産にも登録されているチェジュ島の恵みが贅沢。そのブランドのアイコンアイテムがご存じ“3秒セラム”。 洗顔後に3秒以内で塗るのがルールの導入美容液「グリーンティーシード セラム N」です。
韓国のチェジュ島にある自社の茶畑では、約20年で3,301品種の緑茶を栽培。そのなかでスキンケアに適した美容茶葉を厳選し、オリジナルのダブルスクイーズ製法によって、チャ葉エキスを抽出しています。さらに、緑茶乳酸菌プロバイオティクスとプレバイオティクス、ポストバイオティクスの3種を合わせた独自のテクノロジー、グリーンティートライバイオティクス™と、5種のヒアルロン酸などがセラムには配合されています。
この時季の肌のゴワゴワ感にアプローチしながら、肌の潤いバリア力を強化。あらゆる光、外敵刺激に負けない肌へと整えてくれそう。

グリーンティーシード モイストライン 全6種 ¥2,600~¥3,300
この夏からパッケージも刷新。「グリーンティーシード セラム N」のボトルにはリサイクルガラスを使用し、化粧水やクリームなどのキャップはリサイクルプラスチックが採用されています。8月11日(木)からは「グリーンティーシード セラム N」の売上の一部を森林保全活動に取り組む一般社団法人「more trees」に寄付する、「innisfree FOR more trees」キャンペーンを実施中。期間中に「グリーンティーシード セラム N」を購入すると、ヒノキのアロマブロックのプレゼントも。この機会に3秒セラムもお試しを。

イニスフリー
https://www.innisfree.jp
気づいていてもなかなか減らないデジタルとのお付き合い。ブルーライトのケアをやるとやらないとでは、数十年後に差が出るかもしれません!
ラボグロウンダイヤモンドとは? アルティーダ ウードのエシカルジュエリー
ジュエリーブランド「ARTIDA OUD(アルティーダ ウード)」から、色鮮やかなカラーのラボグロウンダイヤモンドをあしらったチャームが登場! チャームの魅力とともに、同ブランドが力を入れているサステナブルな活動をご紹介します。
ダイヤモンドの新しい選択肢

「raw beauty = ありのままの美しさ」をコンセプトに、神秘的かつオリエンタルなジュエリーを展開する「ARTIDA OUD」。中間業者によるコストを可能な限り排除することで、原石や金属が持つ素材本来の美しさを最大限引き出したハイクオリティなジュエリーを、手に取りやすいプライスで販売しています。
新作のチャームは、安全かつ地球環境に優しいラボグロウンダイヤモンドを採用。天然のダイヤモンドが地中で数千年から数億年の時をかけて育まれるのに対し、ラボグロウンダイヤモンドは高度な技術により、その形成過程をラボラトリー(工房)の中で再現することでわずかな期間で成長が実現可能に。
天然のダイヤモンドとの違いは生育環境のみ。成分や構造は天然のダイヤモンドとまったく同じで、国際的な鑑別機関による鑑定書も発行されます。環境配慮や紛争との関わりを持たない点で今世界中から注目を集めています。

チャーム ¥18,700~¥22,000
天然採掘では希少価値の非常に高いカラーダイヤモンドも、ラボグロウンダイヤモンドで作り出すことができるように。新作のチャームにはこの珍しいカラーラボグロウンダイヤモンドや、研磨の際に出る粉のカケラさえも余すことなく神秘的なモチーフに敷き詰められています。

魔除けのシンボル「evil eye」を象った人気のモチーフ。目の中心に施したカラーラボグロウンダイヤモンドがポイント。

夜空に煌めく新月と星々を象ったモチーフ。左は煌めく新月をイメージして、ラボグロウンダイヤモンドを研磨する際に出る粉のカケラを敷き詰め輝きをプラス。右は3色のカラーラボグロウンダイヤモンドを星に見立てた、煌びやかなチャームに。

イエローとピンクのカラーラボグロウンダイヤモンドを、シンプルに一粒添えたデザイン。ラボグロウンダイヤモンドを研磨する際に出る粉のカケラを縁取りに敷き詰めて。
ARTIDA OUDは自社製品の地金、およびジュエリーパーツのリサイクルを行うなどのサステナブルなものづくりはもちろんのこと、社会貢献や環境に配慮した活動にも注力。対象商品1点につき、最大¥1,100がお客様の選択した団体に寄付される「“I am” ドネーションプロジェクト」を実施しており、寄付先は医療支援、途上国支援、森林保全から選べます。
※チャームは同プログラムの対象商品ではありません。
ダイヤモンドの美しさはそのままに、安全かつ地球に優しいラボグロウンダイヤモンド。これからの新しい選択肢に加えてみては?
ARTIDA OUD
https://www.artidaoud.com
感動の瞬間をどれだけキャッチできるか。それが人生の原動力【シンガーソングライターAK Akemi Kakiharaの衣食住遊学】
いつも元気で幸せそうなひとは、自分の周りに“楽しいこと”を育てる種をまいています。そんな魅力的な方にHummingなライフスタイルのトピックスを伺うシリーズ記事「わたしの衣食住遊学」。今回は、NYを拠点に世界デビューを果たし、多岐にわたり活躍するシンガーソングライターAK Akemi kakiharaさんに登場していただきました。
いつまでも新しい夢に向かって前に進みたい

東京お台場で開催されたBody & Soulでの凱旋ライブの様子。
日本で作詞作曲家、アーティストとして成功を手にしながらも、新たな挑戦を求めてNYに移住。今、世界を視野にシンガーソングライターとして活躍するAKさん。この春にリリースされた新曲の「Beautiful You」もヒット中で、その透き通る歌声とオリジナリティ溢れるメロディが多くの人々を魅了しています。楽曲制作やレコーデイングと、多忙な日々を送るなかで、東日本大震災の追悼式展を主催したり、アフリカ難民の子供たちへのサポート活動を精力的に続けています。そんな彼女に、人々に癒しをもたらしながら、自身も日々を豊かにと心を砕く日常について伺いました。
「衣」
まとうことでもらえるエネルギーを楽しむ

肌ざわりのいいレースで着心地がすごく良く、シルエットもお気に入りだという、セルフポートレートのドレス。繊細なレースやメッシュを使ったフェミニンなスタイルが得意なブランド。© Romi Uchikawa
服が大好きで、白やピンク、ナチュラルな色のものを着ることが多いです。年齢を重ねるほどに、一生のなかで自分が着こなせる服の数は限られていくのだと思うと、もっとおしゃれを楽しみたい、いろんな色やデザインにチャレンジしてみたいと思うようになりました。
服選びの際には、オーガニックコットンやリサイクル糸を使っているかなど品質や素材も必ずチェックしますが、まず第一に、試着したときの肌に触れた感じ、服の質感や着心地にこだわっています。何よりも、着たときに自分がどう感じるかを大切にしたいのです。
フッションには、80年代、90年と、年代によってその時々の流行りがあったと思いますが、今の時代はいろんなものがミックスされていて、今までだったらこれは選ばなかったなというようなアイテムにもトライしてみたいと思うようになりました。

ブラウスは、NYを拠点に活躍中のデザイナーキャロライン・コスタス。遊び心のあるバルーンスリーブが目を引く。素材も気持ち良く、ほどよいストレッチの効いたパンツはラグ&ボーン。レコーディング中は長時間缶詰になるので、着心地の良さは必須。服はそのときに創っている音楽の雰囲気や歌詞に没入しやすいアイテムを自然に選んでいることが多いそう。
以前だったら、このデザイナーのこのデザインがカッコいい、おしゃれとかそういう目線だったのが、最近は、デザイナーの気持ちとか、その服が作られた背景に興味があります。デザイナーがどういう気持ちでこの服を作ったのかを、考えながら着るのも楽しい。
服も音楽も、ものを“つくる”という意味では過程は似てると思います。まっさらな白いキャンバスの上にアイデアを重ねて、思い描いているものを形にしていく。デザイナーが服を作っているときの背景を想像したり、作り上げたときの喜びやエネルギーが伝わってくると感動します。
「食」
料理を作ることは癒し、もてなすことは歓び

友達を招いてディナーパーティーを催すこと、誰かのお祝いごとをホストしておもてなしすることが大好きです。テーブルセッティングはパーティーのコンセプトによって変わりますが、どんな構成にするのかを考えるのも楽しくて!
とにかく料理すること自体も大好き。仕事柄、曲の制作に没頭していることが多いので、その間は集中するし、緊張が続きます。どこかでブレイクを取りたいときに、料理することが最大の息抜きでもあり、癒しの時間。とにかく無心になれますね。

アスパラガスのスープ。野菜を中心にできるだけ旬のものを使い、ヘルシーであることをベースにしているそう。
食べるものが体をつくっていると信じているし、美味しくてヘルシーなものを食べて健康になれるなら最高でしょ? せっかく自分の手で作るならば、できるだけヘルシーなものにしたいと心がけていて、オーガニック、ヴィーガン、グルテンフリーの素材を積極的に取り入れています。
材料は、基本的に野菜が中心で、どれだけフレッシュでナチュラルなものを自分の体に取り込めれるかを常に考えています。油はオリーブオイルがメイン。塩、砂糖はできるだけ避けて、水はたっぷり摂ります。

パーティーのテーマに合わせてケーキのデザインもAKさんが考案。写真はマシュマロを使い、ウサギをデコレーション。中にはピーチコンポートのサプライズを。
友達や家族を私の料理でおもてなしするのは、至福の喜びです。「ひとと一緒に食事をすることはすごく大事なこと」と、とあるひとから言われたことがありましたが、本当にそうだなと実感しています。私の作った料理を食べて「美味しい」と言ってもらえることと、私の音楽を聴いて「癒されました」って言ってくれることは一緒。ひとを幸せな気分にできたら、私自身が幸せなのです。
「住」
五感に響く、自然からのインスピレーション

ニューヨークから飛行機で45分、ナンタケット島というマサチューセッツ州の東海岸沖に小さな島があります。NYで生まれ育った夫(ダニー・クリビット)が、子供のころから夏を過ごしていた島で、ダニーのママであり、私の義理の母が移住したこともあり、今も時間ができると年に一、二度は必ず訪れています。古き良きアメリカという雰囲気で、自然あふれるのどかな島。

ナンタケット島の代表的な家屋。木の温もりを感じられる造りで、配色は白、グレーなどナチュラル系。ノスタルジックな自然に溢れていて、美しい草木、花に囲まれている家が多い。写真の白い花は、AKさんが大好きなライム・ハイドレンジャー(ライム色の紫陽花)。
私は『Summer of 42』(邦題『おもいでの夏』)という映画の世界観が大好きで、ナンタケット島はそのロケーションと似ているんです。映画の舞台はニューイングランドの島なのですが、ナンタケットも“南のニューイングランド”と言われているんですよ。美しい水と砂浜、そして、メインの街並みは石畳でとてもノスタルジック。薬局やジューススタンドも、どこか懐かしい風情です。そんな、自然とノスタルジックが融合した世界観は、私の故郷を思い出させて、どこか懐かしく、切なくもあるのです。
私が生まれたのは、広島県福山市の駅家町というところで、家の周りには自然がいっぱい。山と川、そして緑に囲まれて育ったので、ナンタケットにいると子供時代の思い出がよみがえります。自然と親しんで育った私には、花の香り、海の香り、自然の音や風、太陽の光ーーがとても必要だと感じています。

NYブルックリン、ウイリアムズバーグにある自宅の窓からの眺め。目の前にはイーストリバーが広がっています。
小さいころには、れんげを摘んで首飾りを作るとか、干し草を積んでベッドでにしたり・・・そういうときの匂いや感触は、私の五感に大きく影響していて、記憶に刻まれています。自然が私の心に与えてくれるインスピレーションはとても大きいのです。NYにいても、無意識に空を見上げたり、自宅の窓から目の前に広がるイーストリバーの景色を飽きることなく眺めたり、川の流れや光や風を感じて生活しています。
「遊」
音楽は私にとっての心の遊び場

ブルックリンのウイリアムズバーグにて。撮影の合間に、置かれていたストリートピアノを見つけて弾き始めるAKさん。 ©Romi Uchikawa
映画音楽やジャズが好きな父の影響で、家には音楽が溢れていました。5歳からエレクトーンを習って、『シェルブールの雨傘』や『男と女』などの映画音楽を弾いて、ちょっとおませな子供でした。私が8歳のときに、クロスオーバーと呼ばれたエウミール・デオダートの『プレリュード』を父が買ってきて、そのアルバムを聴いたことが私の運命を変えました。深く心を打たれて、“私もこんな曲を創りたい!”と思い、8歳からエレクトーンで曲を創り始めました。創った曲はボサノバ。デオダートにそっくりな曲でした(笑)。

NYにあるマスタリングスタジオ「Sterling Sound (スターリングサウンド)」でレコーディングの最終プロセス、マスタリング中の一枚。
そのころはまだ、将来音楽が仕事になるなんて思ってもいなくて、ただ“こんな曲を創りたい”という気持ちで心の赴くままに創っていました。詩は10歳くらいから書いていて、中学3年の時には“将来はシンガーソングライターになりたい”と決意。高校の学祭などでパフォーマンスもするようになり、日芸(日本大学芸術学部)の大学3年、21歳でデビュー、それまで書き留めていた曲でデビューアルバムをつくりました。
私には、音楽を創ること = 仕事という感覚はあまりなかったですね。音楽は好きだし、曲を創ること自体も好きで、気が付いたらそれが自然に仕事になっていました。音楽って「自分が楽しめないと人にも楽しんでもらえない」と思っているので、まずは自分が心から大好きと思えて、楽しめることが大事だと思っています。

写真奥は、夫でDJのダニー・クリビットさん。
「楽しい」「切ない」「うれしい」「悲しい」「幸せ」ーーそういうすべての感情を音楽で表現できる。そして、その音楽を奏でてるとき、聴いてるとき、その感情に浸れるのです。
例えば、ダンスミュージックを聴いてると自然に踊りたくなるし、ロマンチックな曲を聴いてると恋心をくすぐられて、誰かに恋をしたくなるかもしれない。音楽には心を豊かにしてくれる魔法がいっぱい。心のビタミン剤でもあり、エモーションの宝庫であり、音楽は私にとって「心の遊び場」のようなもの。そして、曲を創るためのレコーディングスタジオは、フィジカルな遊び場という感じかな。
「学」
子供たちから気付かされる夢と可能性の大切さ

アフリカ、ガーナのボナイリ村にあるMY DREAM.org(mydreambridgethegap.webs.com)代表 原ゆかりさんが作ったMY DREAMスクールの子供たちと一緒にコンサートをするAKさん。
東日本大震災がきっかけで、それ以降、被災地を何度も訪問してボランティアとして現地に出向いてコンサートを行いました。そこで、子供たちとの触れ合いを続けるなか、もっと彼らを支援したいという気持ちが芽生えて、2013年に「I FOR DREAM」というプロジェクトを立ち上げました。それが、私の「世界中の子供たちの夢とモチベーションを育てる支援」の始まりでした。
そんな折に、子供支援への情熱を分かち合い、DREAMという共通のテーマでアフリカの子供支援をしている元外交官の原ゆかりさんと出会いました。そしてアフリカの子供たちのために曲を創る機会をいただいたのです。
世界の子供たちの未来が、家族、友達、愛、そして、感動の瞬間であふれ、夢が叶うことを願って、「夢は叶う」というメッセージを込めた『MY DREAM』という曲を完成させました。そしてこの歌を通して、世界の子供たちをつなぐ「MY DREAMソングプロジェクト」を展開しました。

アフリカのボナイリを訪問したとき、無垢で純粋な子供たちがとても生き生きとしていて、喜びと幸せが溢れていることを感じました。誰かと自分を比べることもなく、困難な状況や過酷な環境であっても、そこにあるもの、自分の周りにあるものを素晴らしいと思える気持ちで満たされている。どんな場所からも、アイデアと情熱と実行力があれば、何かを生み出すことができる。物事は、捉え方一つであり、夢や願いごとは叶えることができるのだと気付かされました。
有名な例え話ですが、コップの水をこぼしてしまったときに、残った半分の水を見て「半分しかない」と思うか、「半分も残っている」と思うか。私はできるだけ「半分もある」っていう気持ちでいたいというのが根底にあります。人生はその人の感じ方や捉え方次第で、幸せだと感じるか否かも、そのひとの心の判断次第。何事もポジティブに捉えていきたいと思います。
ボナイリの子供たちにとって、夢や可能性を持つことが、希望の原動力になっているのを見て、いつまでも夢に向かって前に進み続けるということを彼らからも学びました。そして、諦めずに前に向かって進んでいくことで、幾つになっても学びを得ることができるのだと思っています。

被災地でもあった福島県相馬市、みなと保育園の園児たちと。”夢はきっと叶う”というメッセージを込めた『My Dream』という曲を創り、コンサートを開催。
私の人生で大切にしているものは、家族、友達、愛、そして感動の瞬間をどれだけキャッチできるか。大切なひとたちと分かち合う貴重な体験や時間を幸せだと感じることができるのも、自分の心がそれを幸せだと感じるチカラがあってこそ。感動をキャッチできるかどうかは、自身の感受性次第ですから。自分自身や心の在り方をどのように保ち、成長させるか。私にとってそれは一生の学びです。
音楽の才能を最大限に活かして、ひとを癒し、ひとを癒すことで自身が癒され、喜びを見出しているAKさん。その姿が、衣食住遊学のすべてを大切に、“感動すること”に積極的であることが、日々の充実と幸せにつながることを伝えてくれます。あらゆる感情を表現できる音楽で、彼女が世界に向けて語り掛けるメッセージにも注目していきましょう。
森カンナ「なぜ年齢に縛られているのだろう」【連載 / ごきげんなさい vol.10】
俳優 森カンナさんが日々の生活のなかで見つけたこと、感じた想いを綴る連載エッセイ「ごきげんなさい」。自分を“ごきげん”にするためのヒントを探しましょう

「歳の数」
あるときふと自分の名前がネットニュースに上がっているのを見つけた。
森カンナ(34)が〇〇〇〇(30)と〇〇〇〇(45)にどうたらこうたらみたいな感じで名前の隣に丁寧に年齢をご紹介してくれていた。
思えば、日本のメディアはほとんど、人の名前と一緒に年齢が表記される。海外では考えられないことだろう。
一体なぜ日本人はこんなにも年齢に縛られているのだろう。
確かに、日本語にはものすごく細かい敬語がある。
この人には敬語を使うべきなのかタメ語でいいのか。という精査をしなければならないのも分かる。だがそれと、この日本人の何ともいえない、年齢に囚われている感は別だと思う。
この話をアメリカ人の友人に話してみた。
友人もずっと不思議に思っていたらしい。「日本人は気付いてないと思うけど、とにかく年齢の話が好きだよね〜」と・・・。
確かに、アラサー、アラフォー、アラフィフ、美魔女、イケオジ、結婚適齢期。みたいな年齢にまつわる不思議な言葉もたくさんある。
ドラマや映画でも、35歳崖っぷちヒロイン!運命の相手が現れるのか!?-ーみたいなのもよ〜く目にする。いや、まったくもって崖っぷちではないだろ・・・と思いながら、日本のこのロリコン文化にうんざりしたりする。
年齢を重ねることで人は成長するし、経験も積める。幅も視野も広がる。なのに何故、生きた年の数字が増えていくだけのことを、こんなにもネガティブに受け止めている人が多いのか。
私はそんなことを気にするよりも、年齢を重ねるにつれて滲み出てくる人相を気にした方がよっぽどいいと思う。
政治家の方でも政治家になりたてのころと現在の人相の違いに驚くことがある。
年齢を重ねるたびに、心のなか、魂がどんどん目や口の外側にあらわれ出す。どんなに取り繕ろっても、いろんな手段で顔年齢を巻き戻そうとしても、滲み出ているので嘘はつけなくなると思っている。
自分自身でもパッと鏡に映った顔を見ると、おっ良い顔をしてるじゃん!ってときと、何というひどい顔をしていたんだ!とびっくりするときがある。
何歳からおばさんかしら?なんて考えるより、毎日気持ちよく、“良い顔で生きるには”を考えて、年齢を重ねていきたいものだ。
それではごきげんなさい(^_^)

私の友人の菊乃、堺小春姉妹の母の岡田美里ちゃん! いつもキラッキラな笑顔で出迎えてくれる。こんなふうに歳を重ねていきたいと、会う度に思う。本当に素敵な人だ。
Profile
森カンナ(もりかんな)
俳優。富山県出身。映画やドラマなど数々の作品に出演。2021年には、自身初舞台となった蓬莱竜太演出『昼下がりの思春期たちは漂う狼のようだ』で、600人のなかからオーディションによって選ばれ、観客を魅了した。2022年は、フジテレビ4月期月9ドラマ『元彼の遺言状』1話・2話にゲスト出演、フジテレビ2週連続ドラマ『ブラック/クロウズ~roppongi underground~』にレギュラー出演。そして、先日スタートした7月期カンテレ月10ドラマ『魔法のリノベ』にも1話ゲスト出演した。
https://kannamori.com/
Instagram @kanna_mori
ピンクを楽しむ!ファッションとチャリティを結ぶプロジェクト
2010年よりスタートした「ユナイテッドアローズ」のチャリティプロジェクト『united LOVE project』は、今年で12年目。国内外の注目ブランドとコラボレーションしたアイテムを展開し、その売上の一部をチャリティに役立てています。
愛と感謝をPINKカラーにのせて

「ファッションを楽しみながら、チャリティを」という想いを軸に、ユナイテッドアローズが毎年テーマを掲げて取り組んでいるこのプロジェクト。2022年秋冬は“LOVE,GRATITUDE(愛と感謝)”がシーズンテーマ。愛と感謝をPINKカラーで表現したアイテムを「BATONER」「HAVEL studio」「Mfil」「Pheeta」「To & Co」「babaco」の6ブランドとコラボレーション。魅力的なラインナップが話題です。
発表されているチャリティの内容は下記のとおり。
プロジェクト商品の売上の一部(1点につき¥500)は、昨今のウクライナ情勢を受け、特定非営利活動法人UNHCR協会を通し、国内外への避難生活を強いられているウクライナの方々に対する緊急支援に役立てられます。
但し、ウクライナでの緊急支援に必要な資金が確保できた場合、皆様から寄せられた募金は、UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)が世界各地で実施する避難を余儀なくされている人々への救援支援に充てられます。
8月5日(金)からの一般販売に先駆け、UA オンラインでは先行予約もスタートしているのでぜひチェックして!
どのピンクでおしゃれを楽しむ?
6ブランドから発表されたアイテムは、ワンピース、トップス、シューズ・・・といろいろ。自分のスタイルに合うピンクをセレクトできます。

¥31,900
Pheeta(フィータ)のワンピース
淡いピンクのレースワンピースは、IRENEシリーズのレース生地を使用した別注オーダーアイテム。一枚で着るもよし、レイヤードしてもよし、羽織りとしても使える一枚。付属の細いドローストリングを調整し、ウエストを絞って好みのシルエットで着こなして。

¥52,800
HAVEL studio(ハーヴェル スタジオ)のスカート
“とにかくカラーで楽しむ、日常はドラマチック”をテーマにしているハーヴェル スタジオ。このブランドならではの、目が覚めるようなPINKのタキシードスカートが登場。過去に展開していた復刻アイテムの別注オーダーです。ハリ感のある生地が生み出す美しいシルエット、バックスタイルのボックスタックにも注目。

¥37,400
Mfil(エムフィル)のブラウス
ブランドで定評のあるタイプライター生地を使用した、別注オーダーのピンクブラウスは主役級のインパクト。タックを配したフレアスリーブ、スタイリッシュなスタンドカラー、首後ろにはミニマルなリボンのあしらいも。

¥20,900
BATONER(バトナ―)のタンクトップ
思わず触りたくなる柔らかな風合いの、起毛をほどこしたタンクトップ型のニット。こっくりしたPINKも魅力的。一枚での着こなしも可能なほどよいフィット感、もちろんシャツやカットソーとレイヤードしても素敵にキマります。

¥6,380
babaco(ババコ)のソックス
このプロジェクトに合わせて、定番の3色セットソックスをデザイナーセレクトのカラーで別注オーダー。ピンクはもちろん、レッド、シルバーと、コーディネートを考えるのが楽しくなる3カラーです。ギフトにもおすすめ!

¥33,000
To & Co(トゥーアンド コー)のシューズ
人気シューズブランドとのコラボで生まれたベルジャンシューズ。アッパーにあしらわれた小さなリボンがアクセントに。リボンとパイピングのブラックと、印象的なピンクのコントラストが絶妙!
ファッションを通じて、誰かの、何かの役に立つことができたら! ぜひ、このプロジェクトをきっかけにしてみて。
ユナイテッドアローズ
united LOVE project 2022
火照った身体をクールダウン! この夏食べたいひんやりヴィーガンスイーツ
地球環境や人に配慮したヴィーガンスイーツ。最近ではチョコレートやケーキなど、味にも見た目にもこだわった個性豊かな商品が登場しています。今回ご紹介するのは連日の暑さが吹き飛ぶような、ひんやり美味しいヴィーガンスイーツです。
果物の美味しさをまるごと!ヴィーガン・ソルベ

シングル¥450、ダブル¥840(店内イートイン)
「私たち生活者のみならず、世界や社会にとってもWell(よい)」という意味を込めたウェルフード&ドリンクを提供する「imperfect表参道」では、環境負荷の低いオーガニック栽培による国産の果物を使用したソルベを発売。
乳成分を使用せず、グルテンフリー、ヴィーガン。白砂糖や保存料も含まず、素材の美味しさをギュッと詰め込んだジューシーな味わいを楽しめます。

〈左から〉伊予柑、レモネード、グレープフルーツ 1本あたり¥400
ソルベの種類は、伊予柑、レモネード、グレープフルーツの3種類。皮由来の苦みがほど良く加わり上品な甘みが引き立つ「伊予柑」や、レモンの酸味とアガベシロップの甘みが絶妙な「レモネード」は、スーパーフードと呼ばれるスピルリナ由来の鮮やかなブルーがインパクト満点! そして「グレープフルーツ」は、果物を丸かじりするようなすっきりと爽やかな味わい、酸味のパンチがクセになるはず。
オンラインショップでは、6本入り(¥2,400)と9本入り(¥3,500)のボックスを販売中。自宅用のストックに、ギフトにもぜひ!
imperfect表参道
https://www.imperfect-store.com/
有機カシューナッツベースのアイスクリーム&フローズンヨーグルト

〈左から〉アイスクリーム チョコレート、抹茶各¥500、フローズンヨーグルト 甘酒¥450、ストロベリー ¥500
100%植物由来、100%自然由来、国産食材または有機輸入食材の使用、大豆不使用、グルテンフリーというサステナブルな製造にこだわるヴィーガンフローズンブランド「TOKYO VEG LIFE frozen」。
この夏登場した有機カシューナッツをベースとしたアイスクリームとフローズンヨーグルトは要チェック! アイスクリームはオイル無添加ながら、クリーミーで濃厚な味わいを実現。フレーバーはバニラ、チョコレート、抹茶、ストロベリー、ブルーベリーを展開中です。
フローズンヨーグルトは、RAW&砂糖不使用にこだわった自然発酵のカシューヨーグルトを氷菓に。そのままアイスとして、解凍してヨーグルトとしても味わえるので、2つの美味しさを堪能できるのも◎。ヨーグルトのみのプレーン、自然栽培玄米麹の甘酒を練り込んだ甘酒、フレッシュな信州産いちごを練り込んだストロベリー、自社工房のある長野県茅野市産の生ブルーベリーを使用したブルーベリーからセレクトできます。
同ブランドをプロデュースするヴィーガン、ヨガ、エコをテーマとしたYouTubeチャンネル「TOKYO VEG LIFE」もチェックしてみてくださいね。
TOKYO VEG LIFE frozen
https://frozen.tokyoveglife.jp/
こだわりのひんやりヴィーガンスイーツを食べて、暑い夏を乗り切りましょう!
新レフィル習慣。捨てたくない、カスタマイズできる容器を選択
肌や体に良いもの、使い心地が良いもの、気分が上がるもの・・・コスメや美容ツールを上手に取り入れて、Hummingな毎日を送りたい。美容ライター 荒木奈々さんがおすすめをご紹介します。
スキンケア、ベース、メイクも!お気に入りはレフィルでおかわり

日用品や文房具は詰め替え用、いわゆるレフィルが充実していましたが、今やそっちが主役!? 先日ドラッグストアの洗剤コーナーに行ったら、本体よりもレフィルの陳列がほとんどです。コスメではもともとパウダーファンデや、アイブロウなど棒ものはレフィルが昔からありましたけど、最近はその提案がより積極的。しかもドラッグストアコスメだけでなく、プレステージのスキンケアやメイクでもレフィル購入できるものが増えています。プラ減の意味もありますが、何よりそのケースや中身に惹かれてレフィル使いしたくなるものをチェックしてみました。
My select 01:レフィルシェアでもリードするエリクシール

〈左から〉エリクシール ホワイト クリアローション セット T Ⅱ BR[医薬部外品](本体(特製ドラえもんデザイン170ml)+つめかえ用 150ml)¥6,820、エリクシール ルフレバランシング ウォーターセット Ⅰ BR本体(特製ドラえもんデザイン168ml)+つめかえ用 150ml)¥5,170(ともに編集部調べ)/資生堂(ともに数量限定品)
環境省から化粧品業界で初めて「エコ・ファースト企業」に認定されるなど、どこよりも早くエコ活動に着手してきた資生堂。プラスチック資源循環促進法が施行された今年、各社さまざまな取り組みを掲げていますが、資生堂はつめかえ用商品のアクションを通じてプラスチックごみの削減に配慮。グローバルサステナビリティキャンペーンの一環として用意されたのが、エリクシール特製「ドラえもん」デザインの化粧水セット・乳液セットです。
その紹介前にエリクシールをざっとおさらい。1983年に誕生したエリクシールは、“つや玉”をキーワードに、スキンケア市場で15年連続トップを突き進むエイジングケアブランドで、 “おしろいミルク” “みずクリーム”など発売される新商品はどれも大ヒット。リピ買い必至なのが2019年発売の「つや玉ミスト」ではないでしょうか。累計出荷個数200万個(資生堂調べ:2019年11月~2022年2月までのメーカー累計出荷実績)を記録するベストセラーで、スプレーするだけで頬にすぐつや玉ができると大好評!
そんなエリクシールの次の話題が、永遠の愛されキャラ、ドラえもんがデザインされた3Dボトル! 「毎日使う化粧品をつめかえて使用する」ことを習慣づけられるようにということで、つめかえ用のパッケージもセットされています。限定セットは全4種。美白&エイジングケアシリーズ「エリクシール ホワイト」のクリアローション、クリアエマルジョン、さらにファースト エイジングシリーズ「エリクシー ル ルフレ」のバランシング ウォーター、バランシング ミルクがあります。

適量で出てくるディスペンサー仕様。
美白有効成分4MSK配合。潤いによる透明感と同時にハリをもたらす化粧水「エリクシール ホワイト クリアローション」のボトルは、清潔感のあるニュアンスピンク。キャップ部分が立体のドラえもんになっています。中身を使い終わったら、キレイに洗って、しっかり乾かすという手間があるものの、愛らしすぎるボトルは捨てたくないし、使うたびに嬉しい気分になれそうです。ちなみに化粧水の場合、つめかえ用だと本体ボトルの容器重量と比べてプラスチックの使用を約85%も削減できるとか。
エリクシールのつめかえ提案は2012年に開始。現在の売上構成比をみてみると、日本市場では化粧水・乳液のつめかえ用の普及率は2割程度、それに対してエリクシールではつめかえ用のシェアが約6割ととても高いそう(資生堂調べ)。昨年より海外チャンネルでもレフィルを導入、エリクシールの主力製品はつめかえ対応を2025年までに予定しているそうですよ。
~大切な人との未来のために、今、私たちができること。~をメッセージに掲げているエリクシール。オリジナルの「ドラえもん」スペシャルムービーもあり、「22世紀からのメッセージVol.1~プラスチックごみはどこへ?〜編」「Vol.2~未来はどうなる?〜編」が公開中。(https://www.shiseido.co.jp/elixir/sustainability/)
エリクシール
https://www.shiseido.co.jp/elixir/
My select 02:クッションの限定パッケージもおしゃれなナーズ

ピュアラディアント プロテクション アクアティックグロー クッションファンデーション ケース 02396 ¥1,430(数量限定品)、ピュアラディアント プロテクション アクアティックグロー クッションファンデーションSPF50+/PA+++ レフィル(スポンジ付)¥5,170/ナーズ
クッションファンデが大好きで、リピートしているのがナーズの「ピュアラディアント プロテクション アクアティックグロー クッションファンデーション」。ナーズにはアイコニックなクッションファンデが輝き違いで2タイプあり、そのうちのひとつがピュアラディアント。ナーズ史上最多の60以上のアワードを受賞しています。
みずみずしいフレッシュなつけ心地が快感ですし、手早くグローなツヤ肌になれるところがお気に入り。しかもこのクッションファンデは、紫外線から肌を徹底的に守るSPF50+/PA+++なうえ、独自の「360°ディフェンステクノロジー」が搭載されており、PM2.5など大気中のちりやほこりの付着を軽減、PCなどから発せられるブルーライト対応成分配合と環境ストレスを寄せ付けないプロテクト力が優秀なのです。
また保湿成分の中心は、ヒアルロン酸Na。潤いをしっかり保持してくれるので、日中の肌はベタベタしないのに乾きにくい。頬にあるうっすらとしたシミは、重ね付けしてカバーしています。決して厚くならず、色ムラだけを目立たなくして、素肌をいかした均一な肌トーンに。
既存パッケージもベージュトーンでおしゃれですが、このベストセラーのクッションファンデのためだけに作られる限定パッケージというのがあって、昨年のホリデー限定のメタリックピンクに引き続き、今回はゴールドのケースが登場。無駄を省いたシックなデザインながら、アクセサリーのようなハイスタイル。化粧直し用としても持ち運びたくなりますし、金運も上がりそう(笑)。新しいコスメを買うとそれだけでキレイのテンションが上がりますが、おしゃれな限定パッケージを日々使うのも気分がアップしますよね。

ナーズは日本上陸21周年、大成功を収めているアーティストブランド。フランソワ・ナーズの独創的なクリエイションから生まれた、リップやチークが揃うORGASM(オーガズム)シェードやライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト Nは名品中の名品です。
今年に入ってスキンケア、パウダー、ファンデーションと「ライトリフレクティング」シリーズを拡充。2022年上半期のベスコスでも新商品の「ライトリフレクティング セッティング パウダー ルース N」が話題になっていました。
「ライトリフレクティングシリーズ」のベースメイクは、タルク、アルコール、パラベンといった肌に負担をかける成分を極力排除しているそう。またパッケージもリサイクルが可能なビンで提案。外装はすべて紙素材にするなど、環境配慮の取り組みも見直されているそうです。
My select 03:カスタマイズも可能なセルヴォークのアイシャドウ

ヴァティック アイパレット 全5種(写真は03)¥6,820/セルヴォーク(8月5日発売)
モデルビジュアル使用のアイテムを大人買いしてしまいそう・・・セルヴォークの2022AWのメイクアップコレクション『Surge of Energy “Butterfly Effect”』に発売前から釘づけです。
1st Collectionとして、レッドニュアンスのアイブロウ、アイライナー、マスカラ、さらにシアーブラックのリッププライマー、モードなネイルポリッシュが登場。8月5日(金)発売の2nd Collectionでは、アイシャドウが大きくリニューアルされます。
アイシャドウは4色セットと単色がラインナップされているのですが、ひと塗りで洗練モードを演出する色や配色はそのままに、セルヴォークお得意の自然のエナジーを湛えたラインナップへ。絶妙なくすみ感を帯びているのに、にごりのないクリアな発色、ただのせるだけで抜け感のある今っぽい目元に仕上がります。また植物由来オイルを高配合し、粉感レスも実現。単色のぼかしも、複数の色をのせても、存在感のある美しい目元が際立ちます。
ため息をついてしまうくらい、アーティスティックなグラデーション! キーアイテムの4色アイシャドウ「ヴァティック アイパレット」は、セルヴォークの原点であるテラコッタにレッドニュアンスを加えた03「ネオテラコッタ」がメインカラーです。4色セットですがノールール。全色塗っても頑張った感じに仕上がらないのがさすが。

ヴァティック アイパレットと共通のパッケージ。カスタム パレット(ケース)¥1,650/セルヴォーク(8月5日発売)
さらにパッケージも改良され、1番のポイントは容器を捨てないためのレフィラブルメイクアップ。セルヴォークのネイルコレクションですでに採用されていますが、このグレーブラックの容器は環境に配慮した材質で、サトウキビ由来のバイオPET配合の樹脂が使われています。お好みの4色をカスタマイズできるから捨て色もなし。お気に入りカラーが底をついたら元の色や新しい色を再セットして。

ヴァティック アイズ 全17色 各¥2,200/セルヴォーク(8月5日発売)
それから同時発売の「ヴァティック アイズ」は、単色アイシャドウとして、レフィルとしても。シャイニーカラー、ディープカラー、メインカラーの3質感の全17色。早く減ってしまうパレットのキーカラーも、ここにラインナップされているのでおかわりも安心です。「ヴァティック アイズ」のパッケージがユニークで、竹とサトウキビの搾りかすのバカスからなるパルプモールドという素材。生分解性の特長もあるそう。レフィルのパッケージは捨てることを考えてのものが多いけれど、こちらは見た目がスタイリッシュ。開閉の仕様が扱いやすいのでこれをコレクションするのもいいかもしれません。

光の粒が神秘的。こぼれるラメのシャイニーカラーは3色展開。(左から01、02、03)

まぶたを鮮やかに彩るメインカラーは全11色。温かみのあるカラーが充実。(左から04、06、07、10、14)

優しい影色。目元の立体感を引き出すディープカラーは全3色。(左から18、20)
セルヴォーク
https://celvoke.com/
安いから、もったいないから、というレフィル選択もあるけれど、捨てたくない容器やカスタマイズできる容器をコレクションするのもコスメの楽しみですね♪
オーストラリアから届く、ヴィーガンフレンドリーな注目ブランド
毎日の暮らしをクリーンに心地よく過ごすために欠かせないホーム&エアケアアイテム。せっかくならデザインや機能性はもちろんのこと、「使ったときにご機嫌になれる」お気に入りを選びたいもの。今回はエコ先進国オーストラリアのメルボルン発のエシカルブランドをご紹介。ヴィーガンフレンドリーなこだわりが詰まっています。
美しい自然と植物のチカラを日々の暮らしにも

オーストラリアのメルボルンで2021年春に誕生した「GREEN NATION life」。ブランドを立ち上げたのはメルボルンに住む2人の女性、Fiona (フィオナ)さんとAlanna(アランナ)さん。日用品業界で25年以上のキャリアを積んだ彼女たちがインスピレーションを得たのは、日々暮らすオーストラリアの美しい自然と植物でした。
「自分たちが本当に使いたいものを自分たちの手で」

「GREEN NATION life」ーーブランド名の由来にもなっているグリーンネイションとはオーストラリアのことを指しています。ご存じのとおり、オーストラリアは手つかずの自然がいくつも世界遺産に登録されていて、エネルギーに満ちあふれた大地を擁し、海に囲まれた自然豊かな国。それは「人間に汚されていない原始的な自然、グリーンネイションのよう」とフィオナさんとアランナさんは表現しています。「オーストラリア産」だからこそ叶えられる高い品質に、プライドを持って商品作りに臨んでいるのです。
「自分たちが本当に使いたいものを自分たちの手で」「天然由来で環境にやさしい、 カスタムメイドホームケア&エアケア商品を、みんなに」ーーそんなこだわりが、すべての原点になっています。
環境への配慮に満ちた製品作り

このブランドが届けてくれるクリーニングアイテムは、98%以上天然由来で安全安心、かつ見た目も素敵で、香りも贅沢。それもそのはず、自分たちが使いたくなるもの、家族や友達の家で使える安心なものを基準に製品作りをしているから。
メルボルンで製造されている商品は、すべて最高品質の材料のみを使用していて、全商品の成分を開示しているところも信頼できるポイントです。そして、エココンシャスなオーストラリア発ですから、サステナビリティと環境保護にもきちんとアプローチしています。
パッケージは100%リサイクルされたものを使用していて、100%リサイクルOK。環境へのやさしさと思いやり、使い続けるためのアイデアはさすがです!
おすすめ1:ホームクリーニングアイテム

ファーストステップとしておすすめしたいのが、ホームクリーニングアイテム。天然成分の洗浄剤とエッセンシャルオイルが入っています。出しっぱなしにしてもサマになるおしゃれなパッケージは、100%リサイクルプラスチックボトルで、かつラベルレスなデザイン。環境課題にもなっている埋め立て地での廃棄物の蓄積を減らすこと、ラベルレスでゴミ自体を増やさないことを目指しているのだそう。
食器洗い用洗剤「ディッシュウォッシングリキッド」、洗濯用洗剤「インティメイトランドリーウォッシュ」、掃除用洗剤「マルチクリーナー」がラインナップ。

ディッシュウォッシングリキッド500ml ¥2,200
環境のためにすぐにできるアクションとして、まずは毎日の食器洗いからエコシフトを。スイートオレンジ&レモングラスの「ディッシュウォッシングリキッド」は、爽やかな柑橘類の香りにうっとり。オーストラリアの特定地域にのみ生息するというスーパー果実カカドゥプラムエキスを配合。ビタミンCたっぷりで、手荒れを防いでくれるので毎日の食器洗いにうれしいかぎり。
おすすめ2:ルームフレグランス

こちらは、天然素材にこだわり、エッセンシャルオイルをふんだんに使用しているルームフレグランスシリーズ。ナチュラルでさりげなく印象的な香りは、部屋をスパのようなリラックス空間に変身させてくれます。オーダーメイドのレイヤードフレグランスやエッセンシャルオイルを配合しているという贅沢なこだわりにもうっとり。
気軽に使える「ルーム&リネンスプレー」、ギフトにもぴったの「リードディフューザー」や「ウッドウィックソイキャンドル」がラインナップ。

リードディフューザー 120ml ¥3,960
なかでもこちらの「リードディフューザー」は、シンプルなデザインで置く場所を選ばず、インテリアにスッとなじむスタイリッュなルックス。
香りのバリエーションは〈オーストラリア〉レモンマートル&パイン、〈アウェイクン〉レモングラス&ライム、〈コンテント〉ブラックベリー&パチョリの3つ。いずれもユーカリやローズマリーなど、オーストラリアの美しい風景が思い浮かぶ心地よい香りです。
サステナブルな商品作りが共感を呼んでいる「GREEN NATION life」。自然の恵みに感謝しながら愛用することで、日々の生活だけでなく、気持ちもよりウェルビーイングになりましょう。
GREEN NATION life
https://greennationlifejp.com/
紙包装のサステナブルナプキンで、デリケートな期間を快適に
生理用品がますます多様化している昨今、「エリス 素肌のきもち」シリーズにパッケージと個包装にエリス初の“紙包装”を採用した新製品が誕生。オンラインショップとショッピングサイト限定で発売中です。
夏ケアの大定番。冷やし系コスメで、肌や体をクールダウン!
肌や体に良いもの、使い心地が良いもの、気分が上がるもの・・・コスメや美容ツールを上手に取り入れて、Hummingな毎日を送りたい。美容ライター 荒木奈々さんがおすすめをご紹介します。
汗をかきやすい、かきにくい肌にも涼感コスメがおすすめ

夏になったら追加投入しているのが、冷やし系コスメ。私の場合、汗をかきにくいタイプで、夏は内側に熱がこもっているような状態に。上手に熱を放出できないからか、外出から帰宅した後に鏡を見ると、顔がまだらに赤くなっていることがあります。そんなほてった肌はもちろん、頭皮や体にも賢く涼感ケアを取り入れたい! 冷やし系コスメは今や夏ケアの風物詩で、種類も多岐に出回っていますよね。すでに猛暑が続いたり、また気候が不安定で湿度が高めな今夏、バテないためにもクールダウンをお任せしたいアイテムをご紹介します。
My select 01:韓国発の清涼感シャンプーで、クール&クリアに

クンダル クールアンドクリアシャンプー 500ml ¥1,650(編集部調べ)/韓国高麗人蔘社(限定品)
気温が高くなると皮膚温も上昇。すると汗や皮脂量も増えるから、毛穴も開くし、ベタつきやニオイも気になるように。特に頭皮は熱がこもりやすいので、冷やし系シャンプーが大活躍。自分では気付きにくいですが、紫外線を浴びやすい頭頂部もジリジリ・・・。
冷房などエアコンの設定温度が家族間で合わない、なんて話をよく聞きますが冷やし系シャンプーもそう(笑)。男性たちはキンキン系の冷やし系シャンプーがお好みのようですが、爽快感が強すぎるのも考えもの。なかにはびっくりするほどの清涼感で、顔についたりしたら大変! スースーと刺激の強いひんやり感がしばらく続くなんてものも。
クールダウンしたいけれどマイルドなものがいいという方には、「KUNDAL(クンダル)」の「クールアンドクリアシャンプー」を。クンダルは2016年デビューの韓国発のナチュラルデイリートータルケアブランドで、ヘアケアの累計販売数はなんと6,000万個以上を記録。
ブランド名は、ドイツ語でアートや芸術という意味の「KUNST」と、先住民アボリジニの言葉でマカダミアナッツを意味する「KINDAL KINDAL」の造語で、オーストラリアが原産国のマカデミアの実が持つ潤い補給力と保湿力に着目しているのでその名がついたそう。そのマカデミアナッツ入りのトリートメントは、ツヤツヤな髪になると大評判。ハマってしまう人続出で、SNSでも話題です。
クンダルはシャンプーの種類も豊富で「クールアンドクリアシャンプー」は夏の限定、しかも日本のみで販売中。ユーカリやティーツリーの葉、メントールから抽出した成分を配合し、クール感をもたらしながら、バランスが崩れがちな頭皮環境を整えてくれます。
また頭皮や髪に刺激となる13種の成分フリーで、植物由来の界面活性剤を5種類配合。この時季のデリケートになりやすい頭皮を見つめたpH5.0~6.0、弱酸性タイプ。地肌や髪にやさしいうえに、クリアな洗浄が叶います。さらに保湿成分としてパンテールをはじめ、40種類の植物由来エキスに、7種類の植物由来油を採用。固くなりがちな頭皮を柔らかく整えてくれるので、使い続けることで毛髪環境も健やかに。

香り立ちも豊かなクンダルのシャンプー。
地肌温度が高いの? シャンプーしても何となく頭皮がすっきりしないという感覚があったのですが、こちらにスイッチしてからはさっぱりリフレッシュ。クンダルのシャンプーといえば、生クリームのようにモコモコな濃密泡が自慢。テクニックレスでサロンのようなシャンプー体験ができると同時に、涼感で頭皮をしっかり洗えている感じが気持ちいいのです。
後頭部から上に向かって、頭皮マッサージを意識しながら丁寧に洗浄。もっとひんやり感がほしいという方は、冷水でシャンプーするといいそうです。洗い上がりはクール&クリア、次に噂のマカデミア入りトリートメントを使うと驚くほどなめらかな指通りに仕上がります。
人工的な美しさより、“本来の美しさ”を追い求めるクンダル。ヴィヴィッドな装いとは裏腹に肌にやさしい植物由来成分を中心に、自然親和的なコスメアイテムは韓国本国で数多くのアワードを受賞しているそうですよ。
韓国高麗人蔘社
http://kundalglobal.com/
My select 02:#冷え冷えソープでお風呂上がりが快適

ドクターブロナー マジックソープ ペパーミントセット(237ml+59ml)¥1,320/ネイチャーズウェイ(数量限定販売中)
夜お風呂から出て、ちょっと動いただけでじんわりと汗をかいてしまう・・・そんな日々には#冷え冷えソープ「ドクターブロナー マジックソープ ペパーミント」はいかがでしょうか。“エアコンいらず”もテーマの天然メントールのソープは、節電を心掛けたいこの夏の要チェックアイテムでもあります。
ドクターブロナーの起源は、1858年誕生のドイツの石けんメーカー。世界初のリキッドソープを発明、そして1948年に世界平和などを掲げるオールワンビジョンの企業理念のもと、カリフォルニアにて設立。アイコン製品のマジックソープは22年連続全米売上No.1(2000年~2021年、米国ナチュラルソープ市場/SPINS社調べ)!
天然由来成分100%のオーガニックソープで、その名の通り、顔やボディだけでなく、何でも洗えるソープとして知られています。水の量加減によって、10通りの使い方が提案されていて、
1 for Face 2~3滴をよく泡立てて使用。デリケートな肌にも◎。
2 for Body 小さじ2杯程度で全身洗浄ができる。
3 for Shaving 4~5滴をしっかり泡立ててからシェービングを。
4 for Hand wash 手洗いでは2~3滴が適量。
5 for Dishes 食器用洗剤の代用にも。ソープ1:水10の割合で薄める。
6 for Laundry 食べこぼしなど、衣類の部分汚れに。量は汚れに合わせて。
7 for Fabric accessories 布マスクやエコバッグなど布製品の手洗いに。
8 for Brush 肌に触れるメイクブラシの洗浄にも。ソープ1:水4。
9 for Cleaning フローリングやトイレの床拭きに。ソープ1:水10の割合で薄めて。
10 for Dogs 愛犬のシャンプー用としても最適。
高い生分解性も特徴のマジックソープ。環境保護のための規約が定められている公園はたくさんありますが、なかでも厳しい基準の米国国立公園グランドキャニオンでも使用を推奨されているとか。最近では野菜や果物洗いに使われる方も多いそうですよ。
マジックソープは11種類のフレグランスがラインナップされていますが、夏におすすめのひんやり感触のペパーミントは、ブランド設立時から製造されているロングセラー。現在はインドで栽培&フェアトレードで調達されているオーガニックミント油(香料)が使用されています。しかもそのミントは、気候変動を抑制することで注目を集める「リジェネラティブ・オーガニック農法」で生育。
またドクターブロナーは信頼の証として、米国農務省が定めるUSDA Organicのオーガニック認証をはじめ、13種類の安心・安全・地球保護に関する認定・認証マークを取得。そこまでこだわりを持つブランドはそうはないかも。

今なら Sサイズ付の数量限定セットで購入が可能。
ドクターブロナーは「人間も動物も植物も、同じ地球という名の船に乗るひとつの家族」と説き、たくさんのサステナブルな活動を先駆けで行ってきたブランドで、プラスチック容器や再生紙などの製品パッケージの使用は15年以上前から。全製品100%リサイクルプラスチックボトルが採用されているのはすごいこと!
ドクターブロナー
http://www.drbronner.jp
My select 03:日中は冷やしペーパーで肌やボディをひんやり

ハッピーデオ ボディシート 極冷 全2種 各36枚入 ¥495/マンダム
毎年夏になると多くの国産ブランドが、清涼系コスメやグッズを発表。そんななかでも冷感研究でリードするのがマンダムで、2020年からは“マンダム「清涼部」”という活動などを通じてさまざまな情報を発信しています。独自の知見と技術から見出した、ユニークな涼感テクニック「クールハック」は必見で、試したい工夫がいっぱい。
そのマンダム「清涼部」から届いたニュースで気になったのが、心理学の専門家が語る“暑さとイライラ”の関係。気温30℃を超えたあたりから、人は心理的・行動的において問題が起こる可能性があり、暑さはイライラなど攻撃的な感情を生じやすくするそう。暑いとやる気もなくなるし、集中力も低下するし・・・。そんなとき「冷たさ、清涼感を感じる」ことも有効な対処法なのだそう。
マンダムの「ハッピーデオ」シリーズのボディシートは、この時季に気になる汗のベタつきをケアする以外に、角質ケアやPM2.5や花粉の付着をオフする3 in 1シートとして人気。しかもマンダムでは皮膚における感覚刺激に着目し、オリジナルの「Kai-tech(快 テック)技術」によって、“快適”と感じるクール感を追求しています。
簡単にいうと冷たいおしぼりや汗拭きシートなどで顔や体を拭くとそれだけでも気持ちいいですが、より“快適”さにこだわっているのがマンダム。シート類を複数展開しており、そのうちの1つ「ハッピーデオ ボディシート 極冷」は-3℃のキーンとしたクールな体感。30℃超えの日中はこちらで汗を拭きつつ、涼感ケアを。香りはシャープミントとウォータリーシトラスの2種。クール感&清々しい香りで、知らず知らずのイライラ気分も一緒にリセットできそう。
それから夏場のマスク着用は、暑苦しいし、息苦しい! 歩きハンディファンやクールリングも昨今よく見かけますが、ムレやほてり、汗も気になる顔はどう涼ませよう・・・というときには、「ハッピーデオ」シリーズの顔用シートもチェック。
メイクの上からも使えるフェイスシートで、汗皮脂吸着パウダーと皮脂吸着パウダーを新配合。新処方によってほど良くクールダウン、ベタつきやテカリケアへの対応がパワーアップしています。ハンカチサイズなのも使いやすく、メイクをしているときに使う場合は、優しく押さえるように使うのがコツ。汗と余分な皮脂だけを吸着して、サラサラな肌に。

ハッピーデオ フェイスシート 全2種 各20枚入 ¥308/マンダム
マンダム「清涼部」のクールハックによると、お出かけ前にドライヤーなどでじんわり汗をかいてしまったときなどにもフェイスシートの使用がおすすめだそう。2~3秒肌にのせるとシャキッとして、汗もひいてきます。メイク前にも行うと、ひんやりとして毛穴もキュッ、メイクのノリもよくなるはず。もっと冷感がほしいときには冷蔵庫で冷やしておくのも◎。手軽な涼感ケアを取り入れて、その都度モチベーションをアップ!
ちなみにフェイスシートは、環境配慮として外装なしに。これによってプラスチック10%以上の削減が叶っているそう。
マンダム
https://www.mandom.co.jp/
年々、過酷になってくる日本の夏。涼を楽しめるコスメやグッズを用いて、肌、体、そして心も夏バテしませんように。
話題のCBDをヴィーガンカフェで!心も体も上向きに【渡辺知夏子のエシカルスポットNavi. vol.09】
普段の何気ない暮らしのなかで、サステナブルなアクションが出来たら素敵だと思いませんか? エシカルなライフスタイルを提案しているレストランやショップを、自身もウェルビーイングな生活を心掛けているというモデル渡辺知夏子さんがナビゲート。今回は、食べるマインドフルネスとして注目されているCBDを取り扱ったヴィーガンカフェ『HEMP CAFE TOKYO(ヘンプ カフェ トウキョウ)』をご紹介します。
HEMP CAFE TOKYO

今、世界中で注目を集めている「CBD」をご存知ですか? CBDとはカンナビジオールの略称で、大麻草に含まれる成分の1つ。大麻草と聞くとドラッグをイメージする人が多いと思いますが、それは大麻草に含まれる別の成分です。
CBDには心身の不調改善やホルモンバランスの調整をする働きがあるとされ、近年では医療の分野など、さまざまなシーンで使用され始めています。もちろん、日本でも合法的に使用することが可能。このCBDにいち早く着目したのが、恵比寿にある『HEMP CAFE TOKYO』です。

店内は白を基調にポップなインテリアをアクセントにしたカジュアルな雰囲気。
「CBDの摂取方法はいくつかありますが、ここではヘンプシードやCBDオイルを使って食品から摂り入れてもらうようにしています。また、提供するメニューはすべてヴィーガン。健康に気を配っている方からイスラム教徒の方、そして美容に関心の高い方もよく来店されます」と語るのは、オーナーの宮内達也さん。前職は消防士という、異色のキャリアの持ち主です。

HEMP CAFE TOKYOオーナー 宮内達也さん。物腰柔らな雰囲気と気さくな人柄で、スタッフからの信頼も厚い。
「昔から食べることが大好きで、実は中学生までは肥満気味でした。高校では運動部に所属したことでだいぶ体を絞ることができ、さらに就職後は消防士という職業柄かなり筋肉質な体型に。それでも食べることへの探究心は衰えることがなく、暇を見つけては料理を作る毎日だした。
最初は自己流でレパートリーを増やしていたのですが、それだけでは飽き足らず、休日にはフレンチのお店で料理人としてアルバイトをするまでに(笑)」
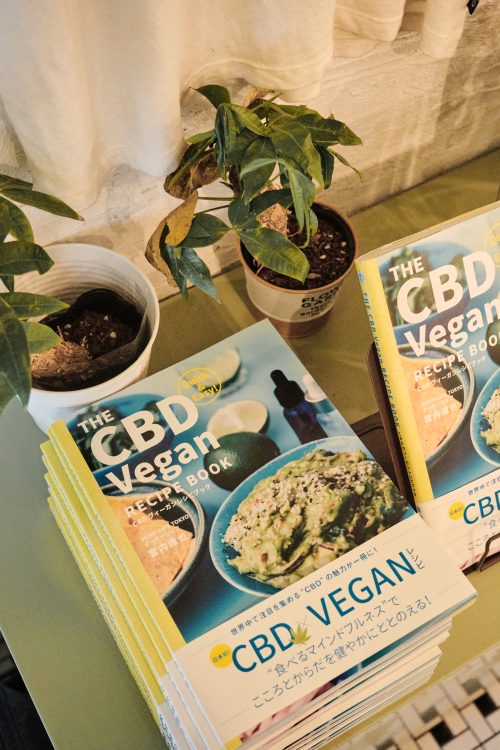
CBDやヴィーガンについてより深く知ってもらうために、クラウドファンディングを利用して制作された書籍。オリジナルレシピをたくさん掲載。
しばらくは二足のわらじ生活を続けていたものの、自分の店を持ちたいという願望が抑えきれず、消防士を退職。翌年にはお店をオープン。そして、CBD&ヴィーガンの専門店と決めていたことには、大きな理由がありました。

つい長居してしまいそう、居心地のよいソファ席。
「消防士を辞めてからは筋肉が落ちてしまい、リバウンドしてしまったのです。そのときに巡り合ったのが、ローフードシェフの加藤馨一氏。そこでCBDの存在を知るようになりました。
健康というのは肉体だけでなく、精神面も整っていなければ意味がないので、その両方を一緒に口にすることができるのはコレしかない!と思いました」

店内に置かれているアルコールはすべてオーガニック。オリジナルビールも販売されています。
オープン当初はCBDの認知度が低かったこともあり、主原料のヘンプを店名に掲げることに。そのため、大麻を扱っているお店と勘違いされ、ちょっとしたトラブルに見舞われたことも今では笑い話に。
そんな宮本さんの思い入れたっぷりのお店で提供される食事は、さすがフランス料理仕込みだけあって、どのメニューもおしゃれなうえに味も格別!

店内の壁に描かれているグラフィックは、新世代アーティストとしてラルフローレンやディーゼルの店内アートなどを手がけるCOIN PARKING DELIVERYの作品。彼もこのお店の常連。
「見た目へのこだわりはもちろん、食材にもしっかりとこだわって作っています。おかげさまで料理のファンも段々と増えてきて、アスリートの方も多く集まるように。最近ではエシカルな意識の高い方々にも、足を運んでいただけるようになりました。
いつ来てくださっても飽きることのないよう、これからも新メニュー作りに精進するつもりです。この店を訪れた方に楽しい食体験をしてもらうーーということは、オープン当初から変わらない目標です」
美の賢人の間で話題のCBDを初体験!

自他ともに認める健康マニアの千夏子さん。もちろんCBDの存在は知りつつも、まだ口にしたことはなかったのだそう。
「CBDは原液をスポイトで数滴口にするのが主流だと思うのですが、苦くて不味いイメージが強くて。『良薬口に苦し』とは言うものの、継続するのは難しいなと思ってしました。でも、料理やドリンクで摂り入れられるなら楽しめそう!」

心を躍らせて扉を開けると、目の前にはリラックス感あふれる明るい空間が広がっています。おしゃれなインテリアに加え、スタッフの皆さんがとても気さくな印象。
さらにいろいろなCBDアイテムがディスプレイされていて、定番のオイルは数種類が並んでいます。初心者でも口にしやすいグミも販売中。他にも店舗オリジナルのTシャツやグッズが。

ヘンプとオーガニックコットンを使用したオリジナルTシャツは、何回洗濯しても全然ヘタらないと、隠れたヒット商品とのこと。手軽にヴィーガン料理が食べられる、レトルト食品もあります。

こちらのコーナーも、全てCBD関連の商品。「オイル、グミやキャンディなど品揃えが豊富。スタッフの方全員がCBDに詳しくて、オイルも試飲することができるので失敗することもなさそう」と知夏子さんは気になるアイテムをいくつも見つけた様子でした。
ゆったりと寛げるのが人気のソファ席を案内されると、早速気になる食事をいただくことに。

ジャンルは無国籍料理なのだそう。どれも美味しそうで、迷いながら吟味するのも楽しい時間。
いろいろ悩んだ末、最初にオーダーしたのは、ランチタイムで一番人気という石焼ビビンバ。

「ヴィーガンのビビンバなんて聞いたことがなかったので、これは絶対にオーダーしようと決めました。カラフルな見た目で香りも良く、しかも食べるとコクと深みを感じます。これでお肉を一切使っていないとか、あり得ないです!(笑)」

焙煎玄米ライスの上に特製ミート、自家製キムチ、人参ナムル、チーズをふんだんに乗せ、オリジナルマヨネーズで味付け。石焼韓国風ビビンバ ¥1,680
期待していた以上の味に驚いた千夏子さん。次は、メキシカンフードを数種類オーダーし、パーティー気分を味わうことに!

「どれもシェアしやすいボリューム感で、お酒のおつまみにもピッタリ! 普段はあまりアルコールを飲みませんが、こちらのお料理に合わせてつい飲みたくなってしまいますね」

早速、オリジナルのCBD恵比寿ビールを片手に乾杯! CBDが25mg含まれた名物ビールなのだとか。爽やかな見た目どおり、フルーツのような味わいとスッキリとした喉越しに大満足。
こちらのビールにも、すべてのドリンクにCBDドロップを+¥300で追加オーダーすることが可能です。

「宮本さんイチオシのタコス。自家製のチリコンカンの甘辛さとさっぱりとしたライム果汁の相性がバッチリですね! これを目当てにお店に通う人がいるというのも頷けます」

「ブリトーの美味しさも、ぜひ体感してほしい。アボカドたっぷりのサワークリームをモチモチの生地にディップ。見た目以上に、食べ応えも抜群です」と知夏子さん絶賛の一品。

〈右上から時計回りに〉CBD恵比寿ビール ¥1,200、焼肉エスニック春巻き ¥1,280円、ハラミとアボカドと自家製サルサのタコス ¥500(注文は2ピースから)、メキシカンブリトー ¥1,680
美味しい食事とお酒を堪能したら、やっぱり最後はスイーツを!
選んだのは、味にコクを出すため、なんと醤油麹を使っているという名物のチョコレートケーキ。カカオニブをふんだんに使用しているのも特徴なのだとか。
「アーモンドクランチのような食感とメープルシロップで味つけられた優しい甘味で、手が止まりません! 食後にいただいても重たさがなくて、ペロリと完食です」

醤油麹のCBD RAW(生)チョコレートケーキ(CBD10ml)¥1,080
お腹いっぱいになるまで食べても罪悪感を感じることのないローカロリーフードに加え、美味しいお酒も楽しめる渋谷の隠れ家的カフェは、千夏子さんのお気に入りスポット確定!

食事を楽しみながら、ストレス削減もできるだなんてうれしい限り。カジュアルデートから女子会まで、あらゆるシーンにぴったりの空間で、癒しの時間を過ごしてみてはいがか?
HEMP CAFE TOKYO
東京都渋谷区東3-17-14 クリスティエビス 8F
03-6427-1984
https://hempcafetokyo.com/
〈衣装〉トップス¥24,200、スカート¥41,800/ともにランバン オン ブルー(レリアン) サンダル¥55,000/ロトゥセ(リエート)
SHOP LIST
ランバン オン ブルー https://www.lanvin-en-bleu.com/
ロトゥセ https://lottusse.com/en/
自分時間を大切にする沖縄旅。自然に癒され元気になれるホテルステイ!
日々のオーバーワークで、気付かないうちに疲れがたまっていませんか? 体の疲労は心にも影響が出てしまいます。ストレスから解放され、自分を癒すなら、やはり旅が最適。ウェルビーイングなホテルステイでゆったりとした時間を過ごすのが、今みんなが求めている旅のスタイルです。
そこで過ごすだけで癒される。そんなホテルへ

夏、そして秋と、旅が楽しいシーズンが続きます。移動距離は短く、でも非日常感を存分に味わいたいーーという理由もあって、今まで以上に注目度が高まっている旅先が沖縄。今回、Hummingがピックアップしたのは沖縄本島、やんばるの入り口にグランドオープンした「オリエンタルホテル 沖縄リゾート&スパ」。
限られた時間のなか、あれこれ欲張りすぎずにホテルステイをメインに楽しむーーそんなリトリートな旅にぴったりです。
癒されポイント1:ぬちぐすいな沖縄フードで元気になる

沖縄に「ぬちぐすい」という言葉があります。「ぬち」は「命」、「ぐすい」は「薬」の意。美味しいものを食べると元気になれるのも、命の薬であるぬちぐすいなごちそうのおかげです。旅先では郷土色を感じるごはんをいただくことは、大きな楽しみ。地産地消はぬちぐすいなごちそう条件のトップかもしれませんね。
その地域で採れた新鮮なものを、新鮮なうちに美味しくいただいてパワーチャージできるだけでなく、それは地元の生産者を応援することにもつながります。そしてそこには、輸送にかかる燃料や二酸化炭素の排出量を削減できるという背景も。
地産地消の食材をいただくことは、観光客にとって、取り組みやすく多幸感を覚えるエシカル消費でもありますね。

レストラン名の「QWACHI(クワッチー)」は、沖縄の方言で「ごちそう」の意。
オリエンタルホテル 沖縄リゾート&スパのレストラン「QWACHI(クワッチー)」では、朝ごはんから地元食材をふんだんに使用した沖縄料理のオンパレード。
今や沖縄のソウルフードとして人気のポークたまごおにぎり、沖縄では給食でも出されるというタコライスまで! 他にも、沖縄そばの麺を使用したうちなー焼きそば、ゆし豆腐など、クワッチーなものばかりです。

夜ごはんにも沖縄産の食材を使用した多くの料理が並びます。ゴーヤの漬物やサラダの具、ドレッシングに至るまで、沖縄の野菜やフルーツが使用されています。
なかでも毎週金曜日の朝に開催される「やんばる朝市」で購入した野菜を使った料理は大好評。やんばる朝市は、女性農業者が農業推進のため設立した「やんばる朝市かあちゃんの会」と、地元ホテルのシェフが中心となっている「やんばる料理研究会」がタッグを組んで行っている、ホテルや飲食店向けの朝市です。
10年以上前から始まっているこのエシカルな活動、無理しない範囲で行っていることが持続可能な取り組みにつながっていることにも素晴らしさを感じます。
名護市内の小さな公民館で行われる週に一度の朝市で、顔の見える作り手から旬の新鮮野菜を買い付け、QWACHIの地元色あふれる料理が生み出されているのです。その料理が出来た背景に思いを馳せながらいただくと、あらたなスパイスが加わり、より深い味わいを感じられます。
癒されポイント2:海を眺めているだけの贅沢時間

こちらはクラブツインの部屋。落ち着いたインテリアは、クラシカルで大人な薫り。
非日常の極上体験ができるホテルステイ。どんな部屋で寛ぐのかーープライベート空間となる部屋選びは、ホテルステイのなかでも重要なエレメントです。
オリエンタルホテル 沖縄リゾート&スパの部屋は、ルームカテゴリーを問わず、どの部屋も44㎡以上の広さがあります。しかも、すべての部屋が東シナ海をのぞむオーシャンビュー。そしてその景観を堪能できるように、海や自然を独り占めできる最高のテラスが用意されています。

部屋の先端に張り出したクリスタルテラスは、天井から床まで窓が大きく取られ、とても明るくて開放的。テラスの座り心地のいいソファに寝そべって、目の前に広がる紺碧の海や、やんばるの森から地続きの豊かな緑をただただ眺めているだけでも、気分が軽やかになってリフレッシュできます。
時間とともに色合いを変えていく海や空の移ろいは、ずっと眺めていても見飽きることがありません。美しい景色を味わえるこのテラスで、読書したり、コーヒーブレイクしたり、うたた寝したり。予定を詰め込まない、のんびり過ごす時間が何よりも贅沢なのです。
癒されポイント3:水と戯れ、スパを最大限に楽しむ

短時間ではもったいない、時間をかけてゆつくりと楽しみたい気持ちのいいスパエリア。
心と体に癒しをもたらし、リラックス効果をアップしてくれるスパ。このホテルのスパエリアには、ジェットバスをはじめとした5つのバスに加え、ドライサウナも完備されています。
ジェットバスでほどよく強めの水圧で筋肉を解きほぐし、バイブラバスの気泡で体を包み込んでマッサージ効果を堪能、さらにアロマバスにてやさしいアロマオイルの香りに癒されてしまいましょう。さらに、アウトドアバスで爽やかな風と青空の開放感に浸り、ドライサウナ後にクールバスへ直行してととのい体験も! たゆたう水と一体となり、体と心が元気を取り戻していくことを実感できます。
癒されポイント4:体を動かしながら、自然との一体感を

ホテル自慢のガーデンプールは、全長170mという圧巻のスケール。沖縄県内最大級の広さを誇ります。太陽の光を浴びたら、プールで泳いでクーリング。ここから眺めるサンセットも格別です。リゾートならではの醍醐味を存分に味わいましょう。

プールがにぎわう前の朝のひとときに、プールサイドでNY発祥のハンモックヨガ体験を。アウトドアで行うヨガは、開放感にあふれ、気持ちのいい気分転換に。肌を撫でる清々しい風を感じ、波の音を聞きながら、ゆっくりと体を伸ばし、動かしていきます。この心地よさは、クセになりそう!

充実したアクティビティのなかでも、特におすすめなのがこちら。ホテルエントランスを出てか10分も歩かずたどり着いた、亜熱帯植物が生い茂る水辺。ここでビッグサップ体験ができるのです。サップを漕ぎながら進み、やんばるのパワーをダイレクトに感じられるスペシャルなアクティビティです。

幹にある模様が小判のように見え、触るとお金持ちになるといわれるシダのヒカゲヘゴや、高木のイタジイなど、やんばるの森に息づく植物からもエネルギーをもらえるはず。
癒されポイント5:エシカルなおもてなしに触れる

ロビーラウンジでみかける赤茶色のざらっとした質感の素朴な陶器は、地元の陶芸家の作品。各客室にも同じ作家のプレートが置かれています。その土地ならではのアイテムに触れ、鑑賞できるのもうれしい限り。
独特の風合いを持つこちらの作品は、沖縄の土に豚の血を混ぜて焼かれているそう。土に還る素材だけ使用した、サステナブルな陶器なのです。

客室内で目にしたコーヒーカップが置いてある木のトレー。こちらは、やんばるの木からつくられたもの。


ホテルのロビーエリアに特設されたアメニティスベース「Arin Krin(アリンクリン)」。部屋に用意されたアメニティ以外に、ゲストが必要なものを自由にピックアップできます。沖縄石鹸は、それぞれが使う分だけ削って部屋で使うという仕組み。ゲストのスタイルと好みを考えた選択肢の広さと、無駄を減らすためのエシカルな試みが両立しています。
さりげなくエシカルな活動に取り組んでいる様子に気付くと、このホテルを選んで正解!と誇らしい気持ちに。長く自然と人が共存して暮らしてきたやんばる地域にあるからこそ、エシカルな、そしてサステナブルな取り組みにも積極的なのでしょう。

数日のステイでも、やんばるの自然に触れて自分を癒し、リトリートできるオリエンタルホテル 沖縄リゾート&スパ。ゆったりと過ごす時間のなかで、本来の自分を取り戻す旅に出かけてみませんか。
オリエンタルホテル 沖縄リゾート&スパ
沖縄県名護市喜瀬1490-1
https://www.okinawa.oriental-hotels.com/
タフでしなやか。まるで本革のようなサボテン由来のヴィーガンレザーバッグ
環境配慮の観点から、リンゴの皮やパイナップルの葉の繊維など植物性素材を使ったヴィ―ガンレザーが増えています。なかでも新たに注目を集める原料は、サボテン! 今回はビューティ&ユース ユナイテッドアローズ が展開するサボテン由来のヴィ―ガンレザー「Desserto®」(デザート)を用いたバッグをご紹介します。
植物由来の新素材、サボテンレザーのバッグ

〈写真上から〉ハンギング ポーチ/バッグ ¥6,600、ジッパー ポーチ/バッグ ¥6,600、スクエア ポーチ/バッグ ¥6,600
そもそもヴィ―ガンレザーとは動物の皮を使用せず、革の質感や見た目を再現させた素材。「サボテン」と聞くと、あのとげとげとした見た目を想像する方も多いかもしれませんが、柔らかくしなやかな手触りで、ふわっと軽いのがサボテンを原料としたヴィ―ガンレザー「Desserto®」の特徴。
こちらはそのレザーと、植物由来のバイオポリウレタンを使用したエコフレンドリーなバッグです。本革のような上品さがありながら、手頃な価格帯も魅力的!
「Desserto®」の製造を手がけるのは、メキシコ・グアダラハラに拠点を置く「Adrian and Marte」(エイドリアン アンド マルテ)社。試行錯誤の末、成熟したサボテンの葉を収穫し、それをすりつぶしたものを天日干しにした後、特殊加工を施すという方法を考案。すべての工程で天然由来成分のみを使用しています。動物性製品ではないため、動物実験も行う必要がないエシカルな観点から生まれた新素材です。
太陽を味方に! ユナイテッドアローズPR担当が選ぶエシカルアイウェア
本格的な日差しの強さを感じる今日このごろ。紫外線対策にも本腰を入れたいシーズンの到来です。夏に欠かせないアイテムといえば「サングラス」ですよね。今回はサステナブルな発想でものづくりに取り組む、パリ発のアイウェアブランドを、ユナイテッドアローズPRの田中駿也さんにご紹介いただきました。
環境への配慮が行き届いたアイウェア

2010年、フランス・パリで誕生した世界初のサステナブルコンセプトアイウェアブランド「WAITING FOR THE SUN(ウェイティングフォーザサン)」。「エコ&リサイクル」をテーマに、素材にはウッドファイバーから作られたバイオアセテートや土に還るバイオアセテート、リサイクルされたメタルフレーム、ニッケルを含まずアレルギーを発症しにくいベータスティールのフレームなどを使用しています。
また、メガネを包装するビニール状の資材はタピオカの原料であるキャッサバからできており、付属の外箱、ハードケース、レンズクロスなどはすべてリサイクルされた素材から生産。

〈写真上〉CGS×WFTS Stiff E15 ¥30,800、〈写真下〉CGS×WFTS Auguste E2 ¥22,000
「こちらはユナイテッドアローズが展開する『カリフォルニアジェネラルストア』の別注。ブルーのレンズカラーがポイントです。海を連想させるような爽やかな印象を与え、ビーチスタイルにハマります」(田中さん)

1997年のオープン以来、米国西海岸のサーフカルチャーを日本に広めた伝説的サーフショップとして知られる「カリフォルニアジェネラルストア」は、昨年ユナイテッドアローズが商標権を継承し移転リニューアル。湘南・鵠沼シーサイドに店を構える新生「カリフォルニアジェネラルストア」では、人と環境にやさしい暮らしのアイテムをラインナップし、サステナブルなライフスタイルを提案。

ショップスタッフは出勤前とサーフィン後のルーティンにビーチクリーンを組み込み、鵠沼海岸の美化活動にも取り組んでいるそう。また、サーフィン&ヨガレッスンを不定期開催し、健康的なライフスタイルを習慣化するためのサポートも行っています。
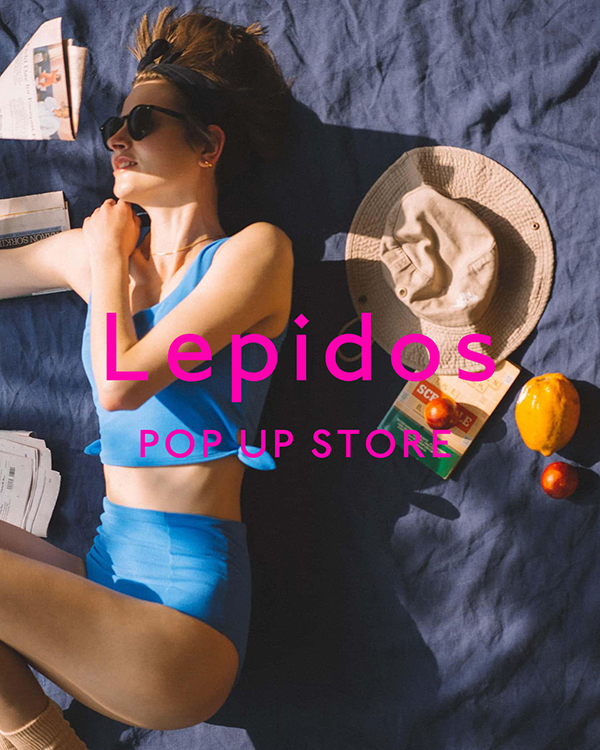
7月5日(火)~7月19日(火)の期間には、ユナイテッドアローズのオリジナルスイムウェアレーベル「Lepidos」のポップアップストアを開催。夏のレジャーシーンで大活躍のアイテムが揃います。「カリフォルニアジェネラルストア」別注アイテムもお見逃しなく!
さまざまなアプローチで、地球環境を守るための努力を重ねる企業やブランド。新たにモノを買うとき、製品づくりの背景や取り組みへの理解を深め、連携することで“持続可能な暮らし”の実現に近づきます。この夏は地球にやさしいサングラスを相棒として迎え入れてみませんか?
WAITING FOR THE SUN
https://waitingforthesun.shop/
カリフォルニアジェネラルストア
https://store.united-arrows.co.jp/brand/cgs/
いい仕事は “遊び”から生まれるという法則【シェフ 市原沙織の衣食住遊学】
いつも元気で幸せそうなひとは、自分の周りに“楽しいこと”を育てる種をまいています。そんな魅力的な方にHummingなライフスタイルのトピックスを伺うシリーズ記事「わたしの衣食住遊学」。今回登場するのは、スウェーデンに移住し、ストックホルムのレストランでエグゼクティブシェフとして活躍する市原沙織さんです。
日常の好奇心が仕事のモチベーションとアイデアを生む

PHOTO = Tove Henckel
スウェーデンを代表するトップシェフたちと肩を並べて活躍する日本人シェフの市原さん。さまざまな受賞歴をもち、ベストシェフを決定する「Årets Kock」と呼ばれるガストロノミーコンペティションでは、毎年審査員としても選ばれる実力の持ち主です。
スウェーデンのシェフたちが選ぶ「ベストなシェフ」のランキングでも、毎年上位に入るように、スウェーデンでは市原さんの創る料理に魅了される人が続出しています。

感性豊かな彼女が創る料理は、日本人としてのバックグラウンドから得たアイデアとスウェーデンで学んだテクニックを織り交ぜた、独創的なノルディック× ジャパニーズキュイジーヌ。女性らしく繊細で、旬の素材の味を生かした一品は、市原さんがキッチンの指揮を取るファインダイニング「ICHI」で体験できます。

華やかなキャリアをもつ一方、プライベートでは一児の母として奮闘中の市原さん。娘さんやたくさんの友人、同僚たちに囲まれて、シンプルで充実した日々を過ごしています。
「衣」
仕事ではこだわりのブラックコーデ、プライベートは色鮮やかに

PHOTO = Isak Berglund Mattsson-Mårn
1日のほとんどの時間をブラックのTシャツとパンツと靴、そしてエプロンをつけて過ごしています。私のレストランのシェフたちは、準備中はみんながこのスタイル。2年前に娘を出産してからは夜のレストラン営業時間に出る機会を減らし、新しい料理の試作と仕込みに従事しています。そのためレストラン営業中のユニフォームを着ることも少なくなり、このブラックカラーのスタイルで過ごす時間が一番長くなりました。
毎日のことなので「動きやすい!」が必須条件なのですが、何でもない全身ブラックでも好きなアイテムを身につけて気持ちが上がるようにしてます。
例えばTシャツは好きなブランドAcne Studios、パンツはセカンドハンドで見つけたパッチワーク風のものを、革靴は靴底のグリップがよくて厨房仕事に向いているDr. Martens。好きなものでも、丈夫で長く使えるアイテムを意識して選んでいます。

その反動か、プライベートの服では一つどこかに色を加えるようなスタイルを好むように。数年前までは私生活も全身モノトーンカラーでミニマルなデザインのものを着ていました。でも娘が生まれてから、子供服のロリーポップみたいなカラフルな色合いに魅了されてしまって。色や柄の持つエネルギーや、それらが放つイメージやオーラっていいものだなと。
もちろん奇抜すぎると飽きがきやすいので、いいなと思ったもののなかでも、歳を重ねても長く着ることができそうなものを選ぶようにしています。ストックホルムの街中で見かけるおしゃれなマダムたちにインスピレーションを受けることも。「カラーアイテムをこんなふうに着こなせるポップなおばあちゃんになりたい!」と、自分でもびっくりするくらい思いきった色を買うこともあります。
「食」
“みんなと楽しく食べること”を通して、インスピレーションを得る
私が料理人として働きたいと思ったきっかけは、友人たちと食卓を囲んだときのあの雰囲気が好きで好きでたまらなかったから。だから食事はいつも誰かと一緒に楽しみたいですね。
今は2歳の娘と二人暮らしで、どうすれば娘が食べてくれるか・・・が毎食の課題として立ちはだかっていますが、それでも日々一緒に食事をする相手がいるのは幸せなことだと実感しています。

娘の離乳食期には、いかにシンプルに野菜の味を凝縮させたピューレを作るかにはまり、その一部は気に入ってお店のメニューに反映させたこともあります。小さな身体のこと、環境のことをいつも考えて、材料選びをするように心がけています。

PHOTO = Reiko Tsukue
春から秋にかけて、友人や同僚とアパートの中庭でバーベキューをすることも大好きです。いろんな食材を焼きながら、みんなでおしゃべりをしながらワイワイと賑やかに食べています。昨夏のBBQでは、ハーブオイルをたっぷり含ませて炭火焼きにした茄子がたまらなく美味しいことを発見して、お店のメニューに採用したりも。

BBQパーティーでヒントを得て、茄子をアレンジしてメニューにしたもの。
友人を招いて一緒に食事をすることも大好きです。たいしたものを作るわけでもなく、簡単にさっと作って一緒に食べるだけ。でも結局それが一番美味しいんですよね。

PHOTO = Magnus Skoglöf
お店で一生懸命アイデアを形にして料理を作るけれども、友人たちとのそんな食事を通して「原点」にかえるんです。「原点」とは、できるだけ無駄を削ぎ落としてシンプルでピュアなもの、ストレートに美味しいと感じられるものを作るよう心がけることです。

娘の離乳食からアイデアを得たじゃがいもの変形版に、キャビアを合わせた一品。
私の食は、仕事のアイデアづくりといつも隣り合わせ。人が集まって、自分の好きな環境で一緒に美味しいと思えるものをシェアすることが、自分にとってはエネルギーとインスピレーションの源になるのだと思います。“遊ぶように仕事をしろ”とはよくいったもので、私は遊べば遊ぶほど、おそらくとてもいい仕事ができるような気がします(笑)。
「住」
古いものに手を加えながら作る、理想の住まい
1年半前に今のアパートに引っ越してから、自分で工夫をして手を加えることが楽しいと思うようになりました。アパートは1943年築で、スウェーデンのその時代に主流だったデザインの愛らしさが残っているのが特徴です。
引っ越した当時は子供部屋はボロボロで使える状態ではなかったため、友人の助けを借りて床や桟張り、壁塗りまですべてを初めて体験し、リノベーションをしました。

〈左〉一から作り上げた子供部屋、〈右〉大型のシェルフを使い勝手よいサイズに。
リビングにあるシェルフは、スウェーデンのセカンドハンドのサイトで購入したもの。とても景色の良い豪邸に住むおじいさんから500kr(およそ¥7,000)とという破格の値段で買い取りました。

大きくて四角かったシェルフを解体して部屋の形に合わせて、子供が落書きをしてもいいように一部分を黒板として使える塗料で塗ってみました。

椅子も中古で購入したものに自分でペイントしたり、前のオーナーさんが置いていった寝室の電気の傘には、内側からドライフラワーをペタペタと張りつけてアレンジをしたり。

もちろん新しいものや洗練されたデザインも素敵で魅力的ですが、私は古いデザインの良さにどうも心惹かれるらしく、さらに自分で手を加えたことで、ものがこんなに愛おしくなるなんて!と感じています。
ものが完成するまでの時間もひっくるめて愛おしく、それを思い出すたびに幸せな気分に。「弥桜(娘)がこの壁に油性マジックで落書きしちゃったからここを黒板にしようと思ったんだよなぁ」とか「子供部屋は近所の友人夫婦が快く床張りを助けてくれてなかったら、一体どうなってたんだろう」とか。
やりたいアイデアや欲しいものばかりが頭のなかで膨らんで、なかなか思うように時間をかけられないのが現実ですが、ゆっくり自分の思い描く住まいを作っていきたいです。
「遊」
自分の好奇心に忠実に
自然の中を散歩したり、ものづくりをしたり、ちょろっと楽器を弾いてみたり、ボルダリングやバレエ鑑賞に行ったり。そのときの気分が向くままに、フワッといろいろなことをして気分転換をしようと試みています。

最近はまっていることは、ストックホルムの文化センターで見つけて、思わず購入してしまったカホンを叩くこと。楽しくて叩いているのに、スッキリもしちゃう優れもの。叩いて音を出すという行為は、多かれ少なかれストレス発散の効果があるようです。

PHOTO = Tove Henckel
音楽を聴いたり弾いたり歌ったりは、気持ちが前向きになるから好きですね。職場でも、いつもジャンルを問わず音楽を流しながら仕事をしています。お店にはさまざまな国出身のスタッフたちがいますが、J-POPがかかればみんな口ずさみ、それはなかなか愉快な光景です。

外でゆっくり過ごす時間も大好き。スウェーデンの冬は長く厳しいので、暖かい季節は外のベンチに座ってゆっくり過ごすだけでとても幸せを感じます。金曜日の帰宅後に、娘とフルーツを外で食べたり、コーヒーを入れたマグを持って中庭に出たり、友人とワイングラス片手にベンチで寛ぐのも至福のひとときです。
「学」
新しい学びで気付く、これからの自分の未来

おそらく学校を出てからの14年間、学びは数えられないほどあったのですが、先日本当に「勉強」をする機会がありました。予習をして、授業を受けて、テストを受ける。いわゆる典型的な学生フォーマットの学びを、何十年ぶりに体験しました。内容は日本酒。WSETというロンドンに拠点が置かれたワイン&日本酒の教育機関による資格です。まだ合否の結果が出ていないのですが(笑)。
出産前まではお酒に弱いこともあって、料理人として恥ずかしいのですがなかなか興味が湧かずにいたんです。それが今になって突然、なんて美味しいんだろう!って。
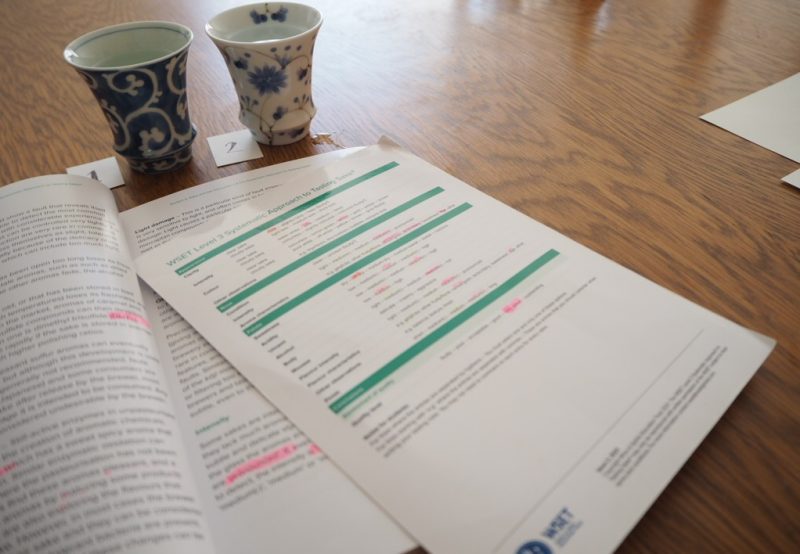
せっかくなのでもう少し知識を深めたいと思い、3日間のプログラムに挑みました。日本酒について、ある程度のことはわかっていると思ったら大間違いで、英語で記された教科書を開けてみれば、酵素分解のことから何まで辞書を引かなくてはまったく理解できない深い話で冷や汗が出ました。久しぶりに何かを暗記しようとしたり、必死で理解しようと頑張りました。
でもテストが終わった後は達成感もあり、なんだか気持ちがよくて。まだ勉強できるんだ、ということを改めて実感。

ICHIをオープンしてから今年の10月で早5年になります。レストランを立ち上げるというプロセスのなかで間違いなく多くのことを学んできました。でも、料理を作り上げること、新しいものを作り出すこと、アウトプットすることに精一杯だった気もします。
この2年間でライフスタイルも仕事の仕方もガラリと変わり、これからどのように自分のキャリアと私生活を充実させていけるかが今、自分のなかで大きな課題となっています。
味はもちろん、スタイルやプレゼンテーションまで、とびきりのセンスの良さが問われるストックホルムという場所で、シェフとして確固たるポジションを築いている市原さん。今回の記事であらためて自身を振り返り「今後の自分のことを考える良ききっかけとなりました」という彼女の視線は、今だけでなく、しっかりと“これから”にも注がれています。遊びも学びも、美味しいものを創るというゴールにつながっている。その手が創り出す美しい一皿ひとさらを、いつか味わってみたいものです。
オールヴィーガンで人と地球にやさしく。 SABONの限定アフタヌーンティー
イスラエル発ナチュラルコスメブランドSABONのフラッグシップストア「SABON l’Atelier SPA」(サボン アトリエ スパ)にて、SABONヴィーガンアフタヌーンティーカフェが期間限定オープン。大好評のメニュー内容をご紹介します。
ヘルシーで美味しい“オールヴィーガン”メニュー


カフェではSABON「プチマルシェ リミテッドコレクション」の限定発売を記念し、“人と地球にやさしい”をテーマにしたオールヴィーガンのアフタヌーンティーを提供中。クリームマフィン、ガレット、パイなどのメニューは動物性原料を含まないオールヴィーガン。またさまざまな理由により市場に出回ることのない「エシカルフルーツ」で作る日替わりジャムを添えたり、まだ美しいにもかかわらず廃棄されるロスフラワーをデコレーションに採用したりと、サステナブルな取り組みにも注目です。

セットのオーガニックドライフルーツティーは「プチマルシェ リミテッドコレクション」のワイルド・ペアーをイメージしたルイボスティーベースのものなど、全3種類を楽しむことができます。

お土産には「プチマルシェ リミテッドコレクション」からワイルド・ペアー、ジンジャー・オレンジ、ラベンダー・アップルのいずれかの香りの「シルキーボディミルク」(50ml)! 自宅に帰ったあとも贅沢な時間を味わえそう。
いよいよ夏本番。もぎたて果実が集い、活気づいた日曜日のマルシェを思わせるアフタヌーンティーで、パワーチャージしませんか?
SABON l’Atelier SPA「SABON VEGAN AFTERNOON TEA CAFÉ ~Petit Marché Limited Collection」
東京都目黒区上目黒1-17-3
価格:6,050円/1名(税・サービス料込)
期間:2022年7月13日(水)まで開催中
予約:https://sabon.resv.jp/
※予約をおすすめ。予約なしでも空き状況に応じて利用できます。
森カンナ「最強おばさんになるために」【連載 / ごきげんなさい vol.09】
俳優 森カンナさんが日々の生活のなかで見つけたこと、感じた想いを綴る連載エッセイ「ごきげんなさい」。自分を“ごきげん”にするためのヒントを探しましょう。

「学び」
学生時代、ほんと~に勉強が嫌いだった。
絶え間なく続くこの時間は一体、将来の何につながるのだろうか、これを覚えて何になるんだろうか。の、想いが止まらなくて、まったくもって頭に入ってこなかった。
あれ、もしかして教科書に睡眠薬でも練り込まれていますか?と思うほどに教科書を開いた瞬間眠くなっていた。
ましてや中学一年生くらいから、仕事を始めちゃったもんで、この仕事以外の選択肢を持ってこなかった。
なので、いい高校、いい大学に入りたい。いい会社に入りたい。などと思ったこともなく、テストで良い点数を取ったとて・・・こんなことを学んだとて・・・と毎日繰り返される時間が苦痛でしょうがなかったのを覚えている。
そんな学びアレルギーだった私が、大人になった現在、ものすごく学びたい欲に駆られている。
身体の経絡について、植物療法について、本当の栄養学。などと、もちろん自分の好きな身体にまつわることばかりだが、今学びたいことがたくさんある。
他にも着物の着付けが出来るようになるといいなぁ。もっと英語をマスターできるといいなぁ。とか取得したいこともたくさん。
そのなかでも今一番ゾッコンなのがピラティスだ。
しばらく運動をしていなかった私は、ある日自分の身体がまったく巡っていないことに気が付いた。
私のなかで巡っている身体とは、身体のなかのポンプがきちんと稼働していて血が足先、指先まできちんと通っている。水はけもよく、水分も心地よく流れていて、肌も水分たっぷりなぷりっとした状態。
なんとなくだが、そんなイメージ。
そんな、とっても氣が良い身体と正反対だった私の身体をここ最近一生懸命、巡らせている。
以前は何もしなくともある程度整っていたが、やるのとやらないではこんなにも違いが出る歳になってきたんだなぁと実感している。
だがその分、変化も分かりやすくてそれはもう楽しくて楽しくてたまらない。そしてピラティスはとても深い。ちょっとやそっとでは習得出来ない。
いつかピラティスマスターとなって、ばっちり整った、巡る身体をどこかでお披露目出来るくらいまでに整えてみせたいとピラティスの先生と企んでいる。
そう思うと、何かが出来るようになったり、分かるようになる楽しさをもっと知っていたなら、学生時代の私の学びアレルギーも少しはマシだったかもしれないな。と思う。
そして学びがどんどん深く広がっていくといろんなことに派生して、新しい発見につながって、自分の興味があることを見つけられたり、また新しい世界に出会えてたのかも知れない。
よし、今からでも遅くない。
将来いろんな草鞋を履いた最強おばさんになるために学びを止めないでみよう。

6月22日、34歳の誕生日を迎えた。愛すべき仲間たちが祝ってくれた。これといって何も変わらないが歳を重ねるということ、私は何だか好きだ。
Profile
森カンナ(もりかんな)
俳優。富山県出身。映画やドラマなど数々の作品に出演。2021年には、自身初舞台となった蓬莱竜太演出『昼下がりの思春期たちは漂う狼のようだ』で、600人のなかからオーディションによって選ばれ、観客を魅了した。2022年、フジテレビ4月期月9ドラマ『元彼の遺言状』1話、2話にゲスト出演。そして、6月28日(火)深夜24:55から2週連続OAとなるフジテレビドラマ『ブラック/クロウズ~roppongi underground~』(※関東ローカル)に、あゆみ役で出演する。
https://kannamori.com/
Instagram @kanna_mori
知れば知るほど、私の人生は豊かになっていく【小泉里子 / 未来に続くBOOKリスト vol.9】
あなたの本棚には、これからの人生で何度も読み返したい本が何冊ありますか? モデル 小泉里子さんの連載エッセイ「未来に続くBOOKリスト」。読書好きの里子さんが、出合ってきた本のなかから“ずっと本棚に置いておきたい本”をセレクトしてご紹介します。
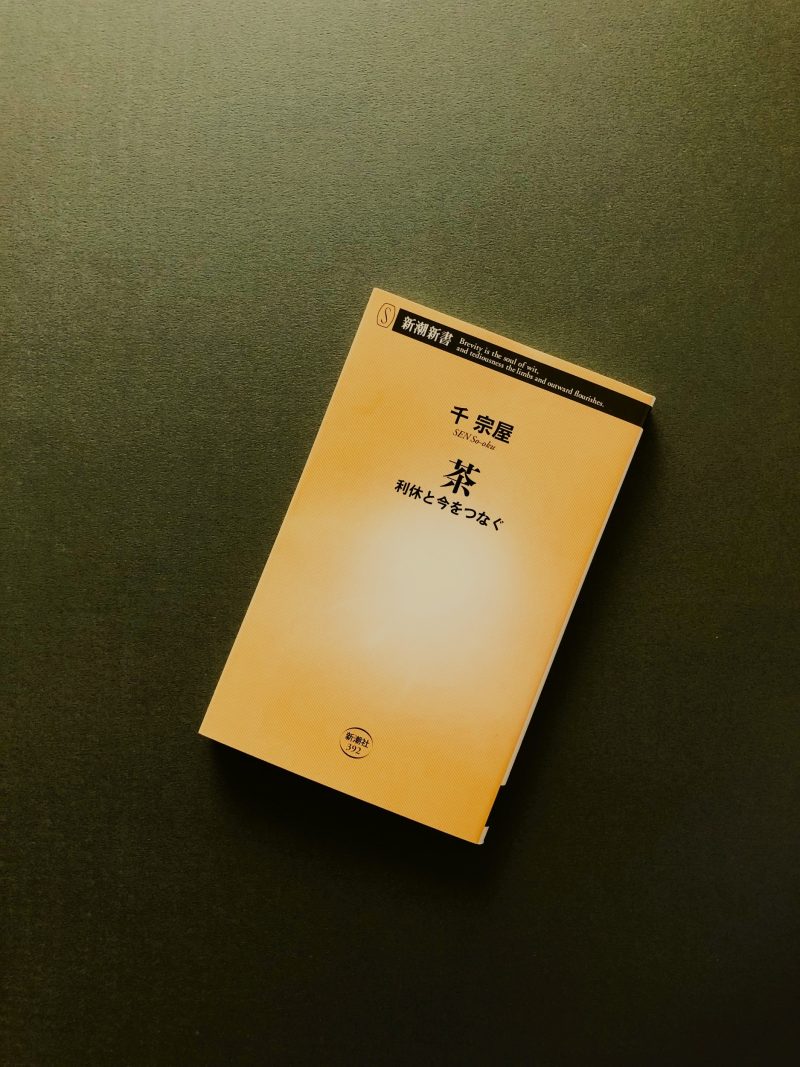
BOOK LIST_09
『茶 ー利休と今をつなぐー』
ジャンル=趣味・実用 千宗屋 著/新潮新書(新潮社)
この本は、私の本棚に長いこと置かれてはいたけど、つい最近まで読んだことがなかった1冊でした。いつかお茶の世界を知りたいとは思いつつも、その敷居の高さやしきたりの奥深さを敬遠して、何となくページを開けずにいました。でもいつか自然と読みたいと思うタイミングがやってくるんじゃないかと待ち続けていたのです。
鎌倉を散策してるときに、とある茶室と出合いました。そこはしばらく使われていないとのことでしたが、畳は新しくいい香りがして、まだ肌寒い季節でしたが、通り抜ける風が気持ちよく何とも心地のいい時間を過ごしました。「この空間でお茶を点ててみたい」ーーふとそんな気持ちになったのです。お茶をいただくのではなく、点てる方。いきなりハードル高めで挑もうとしている自分が心配になりますが、夢は大きく勝手に膨らんでおります。
そんなときに、ずっと本棚の片隅に『茶』と書かれた本があったなと思い出し、ついに読むきっかけができたのです。
「茶」といえば、千利休。利休を知らずにして「茶」は語れない。と、こんな私でもそこは分かりますが、それ以外、恥ずかしながら茶のことはまったく学んでこなかったので、すべて一からの学びです。
まずは、イメージを膨らませるために、映画『利休にたずねよ』を観賞。時代背景を理解してから、最初の1ページ目を開きました。
この本の著者、千宗屋さんは三千家のうちの一つ、武者小路千家の十五代次期家元。表千家と裏千家だけかと思っていた、どうしようもない私をお許しください。そして読み始めると、茶の知識が皆無だった私にも予想外に面白く、時間を忘れて一気に読んでしまったほどです。
「茶」に対する堅苦しいイメージが一新したというか、もちろん最低限の心得は必要だと思いますが、何よりも「茶」を楽しむ心意気が大切なのだということ。ただただ作法を身につけたいのではなく、道具だけを重んじるのでもなく、「お茶を飲む」という日常を楽しむこと。そして主客がそれぞれ思いやりの気持ちで交わすものだということ。・・・などを知りました。
この本読んで、とても印象的だったところがあります。
「高価な名品ばかりを並べる必要はありません。場がきれいに清められ、それぞれのものが、いかにも生き生きと組み合わされ、お互いが引き立て合うように飾られていて、主客の呼吸と間合いがうまく計られ、すべてがあるがまま自然に運ばれていくけれども、見所もある」
ーーまさに「わびさび」の世界だと感動すらした一文でした。
私が日常を送るなかで、こんなふうに過ごせたら素敵だなと思うことでもあります。
生活水準から夫婦のあり方、ファッションに至るまで、持っているものをすべて見せていくのではなく、自分や相手が気持ちよくお互いを引き立て、丁寧に過ごす、そしてそれが自然にこなせる魅力ある人。
この言葉にはすべてにおいて通ずるところがあると思いました。お茶の世界を知れば知るほど、私の人生は豊かになっていくような、そんな気持ちになります。
小さい頃から3 時のお茶の時間が必ずありました。私の実家は自営業で、従業員の皆さんにお茶を入れて出すのが当たり前の日常でもありました。今は、主人と息子と毎日お茶をします。慌ただしい毎日のなかで、唯一ゆっくりとした時間が流れる瞬間です。
20 代のときにアフタヌーンティーに夢中になり、30 代はお煎茶を習い、40 代はなかなか手を出せなかったお抹茶の世界へ。
一つの葉からこんなにも幅広く奥深い世界が広がってるものは、他にないと思います。まだまだのぞいただけのお抹茶の世界ですが、楽しみで仕方ないです
『茶 ー利休と今をつなぐー』(ちゃ りきゅうといまをつなぐ)
利休の末裔がつづる、生活文化の総合芸術としての「茶」。茶の湯の歴史、利休について、茶道具や茶室に関する丁寧かつわかりやすい説明など、ビギナーにも茶事の面白さを伝え、興味を高めてくれる一冊。

Profile
小泉里子(こいずみさとこ)
15 歳でモデルデビュー。数々のファッション誌で表紙モデルを務め、絶大な人気を誇り、広告やテレビ番組でも活躍。着こなすファッションはもちろん、ナチュラルでポジティブな生き方が同世代の熱い支持を得ている。2021年2月には第1子となる男児を出産し、同5月より生活の拠点をドバイに移す。ドバイでの生活や子育てにもさらに注目が集まっている。仕事、プライベート、ドバイでの生活を綴った著書『トップモデルと呼ばれたその後に』(小学館)も好評。
http://tencarat-plume.jp/
Instagram @satokokoizum1
「モノを“育てる”という至福」【ユナイテッドアローズ田中駿也さんの5年選手、10年選手】
物を大切に、長く使い続けることはサステナブルなライフスタイルの基本。おしゃれ業界人が愛用する「5年選手」と「10年選手」、そしてこれからじっくりと育てていきたいNEWアイテムへの愛を語っていただきます。今回お話を伺ったのはビューティ&ユース ユナイテッドアローズ PRの田中駿也さん。
スタイルを格上げしてくれる上質シャツ

― 5年選手を教えてください。
エイチ ビューティ&ユースのシャツです。
― このアイテムとの出合いは?
南青山にあるショップで購入しました。ブランドの立ち上げ当初から展開している根強い人気があるオリジナルのシャツで、ショップスタッフは全員持っているんじゃないかと思うほど、ブランドのアイコン的なアイテムでもあります。僕は白を購入してから着心地と汎用性の高さに魅了されて、カラーやサイズ違いで何枚も持っています。
最近ではワイドシルエットが定番化されていますが、5年前はこのゆったりとしたシルエットが新鮮でした。ドレスシャツに使われるトーマスメイソン社のブロード生地を使用していて、上品さとカジュアル感を併せもつバランスが絶妙。シャツは普遍的なアイテムだからこそ、少し質の高いものが欲しいという声に応えるようなアイテムです。
心がほぐれる田植えリトリート【イケてる八百屋「イケベジ」の農日誌vol.1】
新潟県・佐渡島と兵庫県・淡路島を中心に自然栽培農家を営む「イケベジ」による連載がスタート! 野菜を育てる栽培過程、土の中の微生物、自然環境、スタッフの気配りなど、目に見えない細部にこだわり、真摯に取り組むことを、“美しい・イケてる”と定義し活動中です。新しいことを面白がりながら挑戦していく彼らの活動のなかに、「人生がもっと豊かに、楽しくなる」ヒントが見つかるはず。
植物も人も“ありのまま”の姿は美しい
はじめまして! イケてる八百屋「イケベジ」のいもたろうと申します。今月から僕たちが育んでいるイケベジについてご紹介させていただきます。

イケベジは、昨年春からスタートした農を通じて“ありのままで在ること”の美しさから芽吹いたコミュニティです。従来の組織にあるルールやセオリーを尊重しつつ、各個人が人生を謳歌することで生まれるご縁や世界を楽しみ、育んでいく活動をしています。
現在は佐渡・淡路島を中心に生産活動を行い、東京・渋谷で開催される青山ファーマーズマーケットや駒沢公園周辺で、自然とアートから派生した「The gallery IKEVEGE」を拠点にさまざな活動を展開。農に限らず、自然から発生した美しいモノ・コト・ヒトが集まり、常に新しいご縁や世界が産まれる面白い場になっています。
多くのいのちに触れ、育む暮らし
第一回目は僕自身のお話も少しだけ。
神奈川県・横浜生まれで、現在は兵庫県淡路島でホーリーバジルの畑を営んでいます。今から約6年前に淡路島とのご縁がつながり、自然栽培と呼ばれる農業の在り方と出逢いました。当時の僕は、農業に関する知識や経験はほぼゼロ。しかしながら、農家やお客さんだけでなく、地域も自然も豊かになっていく自然栽培の可能性に魅了されて、農業の世界へ飛び込むことに。

大自然の中で多くのいのちと触れ合い、食べ物を育む暮らしは想像以上に豊かで、自分が育んだお野菜を食べて生きることは、ヒトとして自然な感覚を思い出すきっかけになりました。そして今では淡路島での暮らしをベースに、僕自身が体感したことをさまざまな形で発信させていただいています。
最高に心地よい田植え体験

さて、イケベジでは小さなお子様から大人まで農業体験ができるリトリートを提供しています。先日は2回目となる田植えリトリートを佐渡島で行いました。周りには自然のリズムに沿って生きているいのちがたくさん。それぞれのいのちが奏でるハーモニーを五感を通じて受け取ることで、一人ひとりのなかに宿る自然な感覚へ還っていく。淡路島とはまた違ったリズムが佐渡島には流れていて、とても心地良い場所です。
リトリートではまず田植えを行う前に、島を見守り続ける神様へのご挨拶へ向かいます。森の中にある参道を進み、境内へ入らせていただくと樹齢1,000年といわれる御神木が僕らを出迎えてくださりました。創立1,200年が経つ神社の神様は、自然と人が調和し育み合える暮らしを、長い間見守り支えてくださっているのだなと感じました。
そして神様へのご挨拶を済ませた夜は、五穀豊穣を祈願する佐渡の伝統芸能「鬼太鼓」をみんなで鑑賞。いよいよ明朝から田植えがスタートです!

品種は「亀ノ尾」という、コシヒカリやササニシキなどの銘柄米を生んだ品種改良の交配親としても知られるお米です。約100年前に山形県でほとんどの稲が冷害に見舞われた折に、阿部亀治さんという方が偶然見つけた3本の元気な稲から創選されたそう。そんな貴重な種を、淡路島の先輩農家さんが分けてくださったのです。まさにいのちのリレーです。そんな素晴らしいいのちの恵みが詰まった稲を3本手に取り、大切に植えていきます。
初めて田んぼに触れたときの気持ち良さ、聞こえて来る風や木々が揺れる音、そして鳥の鳴き声。目の前に広がる美しい緑を彩る野草たちのおかげで、とても穏やかな気持ちで田植えができました。ここから約5ヵ月、周りの大自然とともに育まれる稲の生長が楽しみでたまらないです。秋には稲刈りリトリートも開催予定です。一緒に稲刈りをしましょう!
Profile
いもたろう
イケベジ発起人、育み人。淡路島で「農」を通じて多くの「いのち」に触れる体験から、人も同じようにありのままで生きていくことで豊かになれると思うようになる。2021年春、友人とともに人も自然も共に育む場「イケベジ」をスタート。大学での講演活動や「命の繋がり・巡り」をテーマにした「育ベジRetreat」などありのままで生きる世界を広める活動を続けている。実は料理好きで、マクロビを取り入れた「いも飯」はイケベジの人気コンテンツ。
https://ikevege.com/
愛せる自分を探し出し、認めて、受け入れる【山口乃々華 / コトノハ日和 vol.05】
言葉があるから伝えられること、伝わること。そこから広がっていく思考、癒し、つながり、希望、愛情・・・深くて力強いもの。女優 山口乃々華が、心に舞い落ちてきた“コトノハ(言葉)”を拾い集めて、じっくりと見つめ、ゆっくりと味わい、思いのままに綴っていく連載。さあ、一緒に元気になりましょう。
あなたってどんな人?

梅雨時期に入りました。じめっとした重たい空気の日もありますが、気持ちは明るく! スッキリと過ごしたいものですね。
最近、アメリカのとあるリアリティ番組を観ることにはまっている。10年以上続いているその番組の内容は、個性豊かな選ばれし表現者が集まり、自己アピールをし、スターになることをレースで競うというもの。精神的にも、技術的にも、根性的にも、たくさんの武器を備えているように見えるクイーンたち。例えレースに負けたとしても、いつだって胸を張って、堂々たる存在感を放っていた。その姿は本当にかっこいい。
番組内では、常に自己表現の具体的説明を求められる。創造的であり、自信たっぷりと、こちらをワクワクさせるユーモアを加えつつ、上手に言葉を選び伝えていた。それは、完成された物語の主人公として語っているようだった。
随分と前の話なのだが、とある面談で「あなたってどんな人なの?」と問われたことがあった。気楽な雰囲気だけれど、まったく逆の空気も感じる特殊な状況も相まって、私はすぐに答えられず、頭のなかに潜ってしまった。
“私ってどんな人なんだろう。よくわからない”
これがそのときに思った本音で、でもそんなことは言えず、困ったことがある。
あのとき、クイーンたちのように、“自分”を語ることができたならよかったのに。
しかし、人はいろんな面を持っていると思う。仕事をしているとき、プライベートのとき。友達といるのか、ただ居合わせた人なのかで、気の遣い方だって変わるだろう。
ものすごく特殊な人は、ずっと一つの面だけで生きられるのかもしれないけれど。(私とたくさんの時間を共有した人のなかで、そんな人は一人もいなかった)
みんなきっと、どこかしらで“いつも通りの私”が何層かに分かれているように感じているのではないだろうか。
そんななかで、他人に自己を説明する、というのはやはり簡単なことではない。
どんな人なの?と聞かれるシチュエーションをもう一度想像してみた。
そう質問してくる相手は、私を知らない他人である。時間をゆっくりかけて理解し合うような間柄ではない。そんな私がどんなふうに自己を表現するのか、を知りたいのかもしれない。
そう考えると、クイーンたちのように、自分を見せたいように見せることは一つの答えなのでは、と思う。
毎日をそのとおりに生きなければならないわけでもないし、絶対に違うことをしちゃいけないという約束でもない。更新される部分があったっていい。少しばかりは、なりたい自分、こうありたいという希望を交えて語ったとしても、それだって私の人間性を表すものといえるだろう。
そして、長い時間をかけながら愛せる自分を探し出し、認めて、受け入れることが大事なのではと思った。
そのリアリティ番組の最後に、MCが言う言葉がある。
「自分を愛せなければ、他の人も愛せない」
自分を愛せていると、確信できない私は、まだまだ人生の途中なのだと思い知らされる。
うまく生きられない自分が嫌になることもあるけれど、愛せる自分になるための努力と、そんな自分と向き合う時間を過ごしていきたい。他人に合わせるのではなく、私の幸せを感じていきたい。
それができてから、やっと本当の意味で、他の人を愛せるようになるのだと教わる。自分だけの世界より、それはもっと素晴らしいだろう。
他の人をもっと愛せるようになりたい。拒む世界から、手をつなぐ世界へ。ありのままの私で、嘘をつかない私で、もっと自由な私で。

Profile
山口乃々華(やまぐちののか)
2014年からE-girls主演のオムニバスドラマ「恋文日和」第7話にて主演を務め女優業をスタート。映画『イタズラなKiss THE MOVIE』シリーズ、ドラマ・映画『HiGH & LOW』シリーズほか、2020年には『私がモテてどうすんだ』のヒロイン役など、数々の作品に出演。 2020年末までE-girlsとしての活動を経て、2021年より女優業として本格的に活動を開始。2021年3月、初のミュージカル『INTERVIEW~お願い、誰か助けて~』、同8月にはミュージカル『ジェイミー』、2022年3~4月はミュージカル『あなたの初恋探します』でヒロインを演じた。ドラマは現在「ビッ友×戦士 キラメキパワーズ」(テレビ東京系)に出演中。書籍『ののペディア 心の記憶』(幻冬舎文庫)も好評で、文章を書くことも好き。2022年7月には舞台『オッドタクシー』に出演、10月にはconSept Musical Drama #7『SERI〜ひとつのいのち』でミュージカル初主演を務める。
https://www.ldh.co.jp/management/yamaguchi_n
Instagram @yamaguchi_nonoka_official
未来を見据えたエシカルメニュー!アルマーニ / リストランテの挑戦
「もったいない」が世界で広く知られる言葉となり、フードロスが地球環境に悪影響をもたらしていることは周知の事実。食品の廃棄を減らすための取り組みは、個人、企業を問わず、意識の高まりをみせています。そんななか、昨年注目を集めたのが、アルマーニ / リストランテの「ロスフードメニュ ー」でした。この夏、フードロス食材を救う試みに加え、新たなテーマも掲げた新メニューが登場し、 再び話題をさらっています。
新メニュー「サステナビリティ」とは?

デザイナーのジョルジオ・アルマーニ氏が監修をつとめるイタリアンレストラン、アルマーニ / リストランテ。ミラノ、ドバイ、ニューヨーク、東京の4都市にあり、エリアごとの特色を活かしたこだわりのメニューが展開されています。
東京のアルマーニ / リストランテは、日本の四季折々の旬食材を使用したコース料理が特徴的。世界中の美食家たちから愛されているレストランです。
2021年に、フードロスバンクとタッグを組み、フードロス食材が主役のコースメニュー「ロスフードメニュー」を発表。エグゼクティブシェフを務めるカルミネ・アマランテ氏は、このメニューづくりをきっかけに日本の農業や食材、地球環境に対してより深い関心を持ち、食材を扱う立場としての使命を強く感じたのだそう。
その熱意が形となり、新メニュー「サステナビリティ」の誕生へとつながりました。現代社会が抱えるあらゆる問題に焦点を当てたというスペシャルメニューは、とても興味深い内容になっています。
3つの「サポート」をテーマにした新メニュー
新メニューはその名も「サステナビリティ」。3つの「サポート」をテーマに掲げています。
それは「日本米のサポート」「地方のサポート」、そして「フードロス食材のサポート」。 新メニューには、日本の農業や食材が抱える課題を解決するためのアイデアがたくさん!
テーマ1 : 日本米のサポート

日本人のソウルフード的存在ともいえるお米。しかしながら昨今は、日本人のお米離れが進み、国内での需要や消費量は減る一方・・・。そして残念なことに、多くのロスが生まれています。しかも、お米を食べる人が少なくなったことで米農家が廃業に追い込まれるケースもあるのだとか。
今回の「サステナビリティ」 メニューでまずフィーチャーされたのが、日本米。 イタリアンレストランでリゾットを作る場合、通常は空輸されたイタリア米を使うことがほとんど。そこを日本米で提供するというチャレンジが成されています。リゾットの美味しさの決め手でもあるアルデンテの食感を残すため、シェフ自らフードロスバンク提供の日本米をいくつも試食し、さらにその日本米に適した調理方法を考案したのだそう。
日本米を使用するということは、調達を遠距離空輸に頼らない、つまり短距離のフードマイレージになるということもエシカルポイント。味はもちろん、環境にもやさしい一皿といえます。
テーマ2 : 地方のサポート

最高の食材を求めて日本の全国各地を訪れることをシェフとしてのライフワークとしているアマランテ氏。「地方のサポート」をテーマの一つに選んだところも、彼らしい着眼点です。
今回、食材選びのスポットとして彼が選んだのは、北陸地方。コース内で使用されるメインの食材は、すべて北陸産のものというこだわりぶりです。「サステナビリティ」コースでは、この先も季節ごとに異なるエリアに注目して、日本各地方からの魅力あふれる食材を使ったメニューを完成させていく予定だとか。ぜひシーズン毎に訪れて、四季折々の味わいを楽しんでみたいですね。
テーマ3 : フードロス食材のサポート

能登 にあるNOTO高農園の野菜たち。
味は良いのに、形やキズなど見た目の問題で通常ルートで出荷ができず、廃棄されてしまうーーそんな食材を救うべく、コース内の料理にも可能な限り使用しているそう。
今回のメニューについては、さらに徹底した“ゼロロス”を実現。調達された食材は、野菜の切れ端なども出汁として使用するなど、そのすべてを無駄にしない工夫がなされています。
さて、3つのテーマを知ったところでいよいよ本題! 「サステナビリティ」メニューは全6皿、その内容をみてみましょう。
旬野菜を20種類以上使った「高農園のサラダ」

その日に届いた、美味しい旬野菜を日替わりで取り入れるという贅沢なサラダ。つまりレストランを訪れるたびに、いただける野菜が異なるので、まさに“一期一会”なサラダというわけです。パセリが香る「サルサヴェルデ」ソースでいただきます。
サラダの野菜たちは、伝統野菜も手掛けるNOTO 高農園のもの。化学肥料は使わず、畑に無理のない輪作栽培を採用しているそうです。
フォトジェニックな「スモーク ハマチ」

前菜の一皿は、アートのように美しいこちら。福井県産のハマチに塩をふり、適度に⽔分を抜いてからスモーク。旨味をギュッとを閉じ込めたハマチを、スライスしたラディッシュで巻いて、ポロネギのフリットをトッピングしています。ソースは酸味の効いたセビーチェソース。
過剰漁獲にならず、 サステナブルな漁業を可能にするという“定置網漁”ーーつまり環境にやさしい漁法で⽔揚げされた魚を使用しています。
厳選した新潟産米の「スナップえんどうのリゾット」

生産量日本一の新潟県産米を厳選して配合した「れすきゅう米」を使用したリゾット。お米のロスをサポートします。
野菜の切れ端から丁寧に取った出汁でお米を煮詰め、グリーンピースのピューレ、パルメザンチーズをからめて、繊細かつ濃厚な味わいに。仕上げにオーガニック卵のポーチドエッグをトッピング! ナポリの伝統的なパスタ 、パスタエピゼッリからインスピレーションを得たという、歴史と新しさを一皿で実感できるリゾットです。
香りも一緒に楽しむ「鰆の炭火焼 クレソンソース」

メインは、福井県のプライドフィッシュに選ばれし鰆(さわら)の料理。鰆は炭⽕で焼いた後、さらに藁焼きで⾹りづけされていて、その⾹ばしさは感動もの。鰆の下にはグリーンアスパラのスライスが敷かれ、コントラストの美しさも食欲をそそります。アスパラガスの切れ端部分で取った出汁に、エシャロット、ポロネギ、クレソンを合わせたソースも絶品!
感動のアイスキャンディ「とみつ金時」

福井県の農園 フィールドワークスで収穫されるさつま芋「とみつ金時」を使用したプレドルチ。スティックタイプのアイスキャンディの登場に、テーブルでは思わず歓声が上がりそうです。アイスキャンディは、上部分はとみつ金時のアイスクリーム、下部分はベルガモットのシャーベットと2つの味で構成され、甘さと酸味のバランスが抜群。
味は良いのに、形や大きさに難ありという理由で通常の販売ルートからハジかれてしまったとみつ金時を、ペースト状にして保存していたものが使用されています。
忘れられない味になる「いちご 酒粕」

デザートは、⽯川県のいちご「紅ほっぺ」と福井県産の「⿊⿓」の酒粕という美味しいコラボレーション。外側はフレッシュないちご、内部には、形を理由に出荷できないいちごのピューレをシャーベットにしたものと、酒粕を使⽤したジェラートが隠れています。
酒粕は常温だと数ヵ⽉しか保存が効かないため、⿊⿓酒造ではロスを防ぐために酒粕を蒸留して焼酎をつくるなど有効活⽤に取り組んでいるそう。いちごはマイクロ⽔⼒発電による電⼒を使⽤して地域と共⽣している、いちごファームHakusanのものを使用しています。
一皿ごとに美味しさのサプライズがある、新しいコースメニューは全6皿で¥12,000(税込・サ別)。フードロス食材のレスキューにつながるだけでなく、その味わいから食材一つひとつのパワーを感じることができます。そして、日本にこんなにも豊かな食材があることにも感動するはず。「サステナビリティ」な料理を通じて、たくさんの発見と学びを得られる素晴らしい食時間を、ぜひ体験してください。
※メニュー「サステナビリティ」は8月末まで提供予定です。
アルマーニ / リストランテ
東京都中央区銀座5-5-4 アルマーニ / 銀座タワー 10階&11階
03-6274-7005
https://www.armani.com/ja-jp/experience/armani-restaurant/
藍の庭からひろがる世界【現代美術家 山本愛子 / 植物と私が語るときvol.1】
染色を中心に自然素材や廃材を使い、ものの持つ土着性や記憶の在り処をテーマとした作品を制作する現代美術家、山本愛子さんの連載がスタート! 草木染の研究にいそしむ山本さんが、さまざまな土地を訪れ、そこで出合った植物についてつづっていきます。第一回目は『藍』にまつわるのお話。
vol.1『藍』がつなぐ輪
このコラムを「植物と私が語るとき」と名付けてみました。草木染をしていると、植物の新たな一面に気付きます。普段は目に見えない葉や枝の内側に潜んでいた色素が染めの工程で現れたり、その色素に含まれる抗菌効果や保温効果などの効能を体感したり。染めを通した視点から植物を見つめてみると、今まで見えてこなかった色や力、風土など、さまざまな背景が見えきます。見えていなかったものが見えてくるとき、それが「植物と私が語るとき」だと思うのです。
さて、これから私は、北は北海道美瑛町、南は奄美大島まで、植物のリサーチにむかう予定です。いろいろな土地からこのコラムをお届けしたいと思っていますが、第一回目はまず私の庭のお話から始めたいと思います。

庭のタデ藍
2020年春、自然豊かな土地へ引っ越したことをきっかけに自宅の庭で菜園をはじめました。普段の生活で食べる野菜と一緒に、自身の制作に使用する染料となる原料も自給自足をしてみようと思い、藍染めの原料になる「藍」を育ててみることにしました。

藍で染めた布
「藍」の神秘。「藍」は、ある特定の植物ではなく、世界に何種類もの「藍」が存在するのです。どういうこと?と思うかもしれません。普通、タマネギ染めなら「タマネギ」が原料ですし、ヨモギ染めなら「ヨモギ」が原料です。どちらもある特定の植物です。しかし藍染めに使用する「藍」は、タデ科の藍もあれば、アブラナ科の藍、マメ科の藍、キツネノマゴ科の藍など、科も形もまったく異なる藍色の成分をもつ植物の総称です。藍染め独特の不思議な在り方だと思います。藍染めが世界中で重宝される理由の一つは、たくさんの科で藍染めが可能なため、あらゆる風土に適応できるということにあるかもしれません。日本では、インド洋から6世紀頃に伝来した「タデ藍」が多く栽培されています。

近隣の方を招いて藍染会を行なっています。
庭ではこのタデ藍を育てています。春に種を蒔き、夏には近隣の皆さんと藍染めを楽しみます。秋に種を収穫し、冬の間に土を整えておきます。使いきれないほどたくさんの種が穫れるので、欲しい方にはお裾分けをすることも。庭から獲れた種が人から人へ渡って旅をして、今では北海道の広大な土地や、東京港区という都心ど真ん中のプランターや、伊豆の離島の畑など、たくさんの場所で、それぞれの環境で、藍が育てられています。なんというか、自分の庭が拡張されていくような、自分の風土と世界の風土がつながっていく感覚。この感じがとても好きです。それは、私と他人の境界が滲むような感覚でもあり、とても愛おしい感覚です。
-800x535.jpg)
乾燥した藍。ここから種を収穫します。

藍の種
次回は、私の庭の種が育てられている北海道美瑛町からお届けします。
丁寧な手仕事を支える、暮らしの軸【料理家 麻生要一郎のお気に入りLIST】
その道のプロに聞く、今の自分に必要なお気に入りアイテム。今回は、料理家 麻生要一郎さんに3つの大切なアイテムを見せていただきました。
毎日の生活に欠かせない自分らしい流儀
じんわりと心にしみる、優しい味が人気を集める麻生要一郎さんのお弁当。屋号を付ける暇もなく、クチコミで広まっていったという撮影現場やイベントでのお弁当やケータリングに加え、インスタグラムで発信する毎日の食卓の様子もほのぼのと癒されます。みんなの心を惹きつける味わいはどこから生まれる? 麻生さんの日常や仕事を支えるエッセンシャルアイテムを拝見。
肌、髪、ボディとお出かけ前に使う夏のミストコスメ
肌や体に良いもの、使い心地が良いもの、気分が上がるもの・・・コスメや美容ツールを上手に取り入れて、Hummingな毎日を送りたい。美容ライター 荒木奈々さんがおすすめをご紹介します。
スプレータイプなら忙しい朝でも簡単にひと吹き

朝はキレイに仕上がっていたのに何で?と、オフィスで鏡を見てがっかりすることがあります。どうやってもメイクは崩れるし、髪はパサパサになるもの・・・。そうはいっても少しでもキレイを長持ちさせたい。そこで、いざお出かけ! その前に、使って良かった、使わないと損かもしれない的なオプションケアをご紹介。この時期にぴったりな、肌、髪、ボディに仕込んでおくと良いアイテムを見つけました。
My select 01:空気汚れからも肌を保護。定番のフィックスミスト
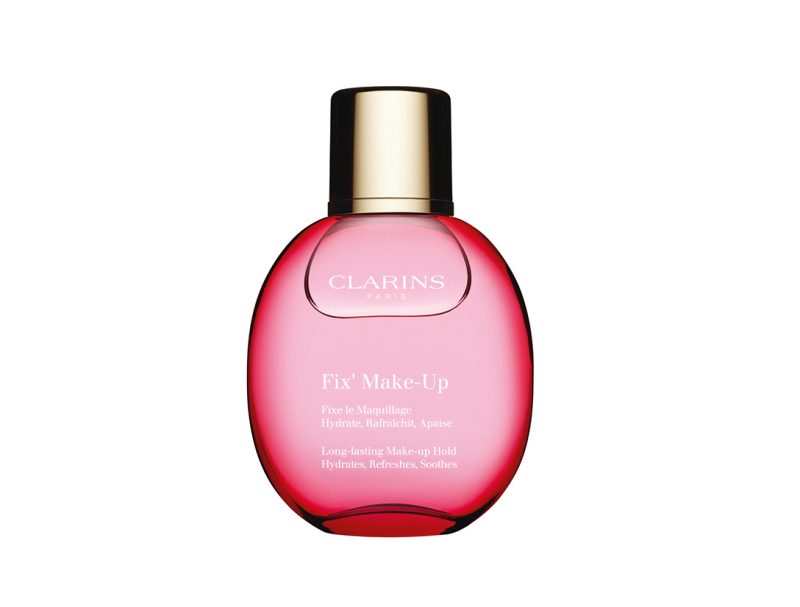
フィックス メイクアップ 50ml¥4,400/クラランス
つけるのを忘れると何だか不安・・・。そのくらいみんなの定番になっているのが、朝のメイク仕上げのフィックスミスト。マスク着用でメイク崩れを気にしているなら、絶対にハズせないアイテムです。
フィックス=定着ですから、やはり頼りになるのはベースメイクブランド作のものでしょうか。最近は保湿やリフレッシュ効果を備えた二層式やナチュラル系など、お好みのタイプや香りが選べるようになっています。
このカテゴリーで知っておきたいのが、クラランスの「フィックス メイクアップ」。マスク着用以前からのロングセラーで、唯一無二のフィックスミストです。
そもそもクラランスのコンセプトはひと言でいうと“プラント&サイエンス”で、このミストはメイクをフィックス、美しい仕上がりを長持ちさせるだけじゃない手応えも頼りになるのです。まずはそのキーワードから機能をおさらい。
- フィックス
キメ細かいミストが肌にふんわりフィット。守りのヴェールを形成し、メイク崩れしにくい肌へ。メイクの仕上げに顔から30cmくらい離して使うのがコツ。 - 保湿
天然由来のアロエ(アロエベラ液汁/保湿)を配合。瞬時に潤いをチャージすると同時に、肌を落ち着かせるスージング効果も発揮。日中スプレーすると逆に乾いてしまう、なんてことは一切なし。みずみずしい肌へ。 - リフレッシュ
どのタイミングで使ってもベタつき感がないのは、極小微粒子マイクロミストのおかげ。香り成分にダマスクローズ(ダマスクバラ花水)×グレープフルーツを採用。使うたびに肌がシャキッと目覚めるだけでなく、気分もうっとり。 - アンティポリューション
クラランス自慢の働きかけで、「フィックス メイクアップ」にはチャ葉エキス、ラプサナコムニス花/葉/茎エキスからなるアンティポリューション コンプレックスを配合。植物由来の成分で大気汚染による肌内ダメージをケア。またチリ、ほこりなどもカット。
使うシーンは朝だけでなく、日中乾燥が気になったとき、気分転換したいときにも。また「フィックス メイクアップ」は、都会に住む肌や季節の変わり目肌、揺らぎやすい肌などにも必携なのです。
その肌にスプレーしたい理由は、上記のアンティポリューション対策が徹底されているから。クラランスでは保湿系のスキンケアから、肌を守るUVケアまで、アイテムごとにアンティポリューション コンプレックスが処方されています。要は大気汚染から肌を保護するというアプローチですが、花粉症のようにあからさまにトラブルがあらわれるわけではないので、肌トラブルを引き起こすほど空気って汚れているの?なんて思ったりもしますが、見えないからこそやっかい。できるだけ回避すべきで・・・。
なぜクラランスは空気にこだわるのか? クラランスのインスピレーションの源はアルプスの自然にあるそう。1966年アルプスのハーブを配合したクレンジングの開発をきっかけに、環境と生物多様性を守り尊重することをブランドフィロソフィーに。クラランスはアルプスの中央、海抜1,400メートルの山々に囲まれたオープンエアの研究所&自社農園「ドメーヌクラランス」を設立しています。そこは大気や土壌汚染とは無縁の地で、自生植物の宝庫。土地を耕す際は、大地に負担をかける機械など使用せず、伝統農法の馬耕だそう。ちなみにクレンジングをはじめ、2020年以降に発売されたアルプスハーブを使用した一部の製品は「ドメーヌクラランス」で栽培された、100%オーガニックのハーブが使用されてます。つまりキレイな空気で育った植物はそれだけでパワフル!
空気が澄んでいない都会に住んでいますから、肌はそのぶんストレスだらけ。そういう意味でもクラランスの「フィックス メイクアップ」にお世話になりっぱなし。ベタつきで崩れやすい肌も、カサカサな感じに崩れる肌も、オールタイプの肌に使えます。ハンドプレスは不要、あっという間にフィックスします。
クラランス
www.clarins.com
My select 02:夕方になってもパサパサしない。髪にはオイルミスト

ラ・カスタ プロフェッショナル ヘアエステ CMCコンディショニング ローション 150ml ¥2,200(サロン専売品)/アルペンローゼ
以前、パーツモデルさんに日焼けについてヒアリングしたら、UVカットものは使っていないと回答。“乾燥しているから余計に日焼けする。だから私は保湿ケアをたっぷり塗る”。なるほど~。それ以来、夏こそ保湿ケア重視を実践。それは髪にもいえることなのです。
紫外線は髪表面のキューティクルに相当なダメージを与えるといわれます。キューティクルは魚のうろこに例えられますが、ダメージを抱えたキューティクルは開きっぱなし、はがれたり、かけたりしてしまっているそうで、そのスキ間から髪の内部成分やカラー色素が流出。そうなるとパサつくし、ツヤがなくなるし、指どおりも悪く。帽子をあまりかぶらないので、確かに夏は髪のパサパサ感が強い、しかもカラーの褪色も夏が一番早い気が・・・。
そこにはUVカットだけでなく、ダメージの連鎖に働きかける根本解決が必要。「ラ・カスタ プロフェッショナル ヘアエステ CMCコンディショニング ローション」は、髪のCMCを補強するアウトバストリートメント。CMCとは細胞膜複合体(Cell Membrane Complex)の略で、髪の外側(キューティクル)と内側(コルテックス)を密着させている接着剤のような働きを持つそう。水分や栄養の通り道になるのですが、日々のシャンプーやドライヤーでも損傷してしまうデリケートな構造。
「ラ・カスタ プロフェッショナル ヘアエステ CMCコンディショニング ローション」は、CMC類似成分や、紫外線や大気汚染など環境ストレスをケアする独自のコンプレックス植物成分LP-GRを配合。保湿・補修・保護をする髪のための化粧水で、乾燥している髪にもスーッと浸透し、サラサラな手触りに。オイル入りなので軽い塗膜効果をもたらし、キューティクルを保護(疎水化)。内部の流出も外部の侵入もブロックしてくれます。
洗髪後、ブロー前にいろいろなタイプのヘアケアを使っていますが、紫外線対策には水分と油分を補う保湿ケアが必須ということで、お出かけ前のブローにはコレ。一目惚れならぬ、一回惚れ。ユーカリ、オレンジ、ローズマリー、セイヨウハッカのハーバルシトラスアロマが爽やか、しかもトリガーハンドルで扱いやすいのも嬉しいのです。スプレーしておくと、夕方の髪が広がりにくい! これさえあればの夏のヘア保湿に個人的に認定。
ラ・カスタ プロフェッショナルのブランドテーマは「美しい『人と地球環境』」で、2006年に誕生、サロン専売品、つまりプロフェッショナル専用のアイテムを取り扱っています。オーガニック植物原料をできる限り使用し、目利きのプロが求めるワンランク上の仕上がりを目指しているそう。水にもこだわるラ・カスタ プロフェッショナルは髪に良いといわれる軟水、信州あづみの野の地下水、いわゆる北アルプス天然水がベース。また研究から製造までメイドインジャパン。SDGsの取り組みは国産ヘアケアメーカーでも随一といわれており、北アルプス製造工場の屋根のソーラーパネルも圧巻です。またウォーターガーデンなどもある美しい庭園、「ラ・カスタ ナチュラル ヒーリング ガーデン」も隣接し、要予約ですが色鮮やかな木々や花々の中を散策することができます。
ラ・カスタ プロフェショナル
https://pro.lacasta.jp
My select 03:朝の強い紫外線もカット。クールなUVミスト

ハレマオ UVカットスプレー LT COOL SPF50+・PA++++ ¥1,320/デミ コスメティクス(サロン専売品・限定品)
自転車の送り迎えって本当に肌が焼けますよね。我が家はたった5分程度なのに、夏が終わる頃にはビーサンの跡がくっきり。焼けやすいのは足や手の甲と、首の裏、デコルテ、それから耳で、うっかり日焼けの最重要ポイントです。ですから玄関にUVスプレーを常備。塗りにくいこれらの部分を中心に、忙しい朝にシューッと大活躍です。
サマーケアブランドのHalema’o(ハレマオ)は、ひんやり系のシャンプーを夏が来るたびに愛用していました。そのハレマオが、初夏にサステナブルブランドへとリニューアル。同時に、スーパーウォータープルーフ処方×クールタイプのUVカットスプレーなどの新アイテムも追加。
シリーズの特徴成分は保湿効果をもたらすレモンバーム。またすべてのアイテムに、消臭効果に優れたカキタニンエキスを配合。プロテクト効果に、美肌効果、さらに気になる夏のニオイもケアしてくれるのです。レモンバームは循環型農法で栽培されたものだそうで、残渣も肥料として活用しているそうですよ。
ハレマオとはハワイ語で“緑の家”、家族でシェアできる設計になっています。またユニークなのが香りの提案。今回限定の全10品は、すべて異なる夏の香りです♪
UVカットスプレーは2タイプ用意されています。手にしたのはハレマオらしいクールな使用感の「UVカットスプレー LT COOL」。ハレマオではクールタイプのレベル分けがされていて、このスプレーは10段階中の5レベル。ほどよいひんやり感です。朝からジリジリの暑い日にもSO COOL! 汗にも流れにくいスーパーウォータープルーフタイプなので、自転車通だけでなく、野外でのスポーツ、フェスなどのお出かけシーンにもぴったり。しかも独自特許成分でタバコのニオイなどもカットできるそう。
ボディのUVだけでなく、髪にも使用可能。髪に使えば広がりや紫外線による褪色も防止できる機能派です。顔にももちろん使えます。ライム×ティーツリーのフレッシュなグリーンの香りが魅力。重ね付け、お直し用の日焼け止めとしても便利です。
ハレマオ
https://www.demi.nicca.co.jp/halemao/
手を汚さないのも嬉しいスプレータイプ。夏は崩れたくない、乾きたくない、焼きたくないからぜひ!
「選び抜いたアイテムをずっと大切に」【ユナイテッドアローズ平井美帆さんの5年選手、10年選手】
物を大切に、長く使い続けることはサステナブルなライフスタイルの基本。おしゃれ業界人が愛用する「5年選手」と「10年選手」、そしてこれからじっくりと育てていきたいNEWアイテムへの愛を語っていただきます。今回お話を伺ったのはビューティ&ユース ユナイテッドアローズ PRの平井美帆さん。
ベーシックななかに個性が光るパンプス

― 5年選手を教えてください。
メゾンマルジェラのローヒールパンプスです。
― このアイテムとの出合いは?
6(ROKU)の店舗で購入しました。メゾンマルジェラの代名詞とも言える足袋ブーツが欲しかったのですが、自分には似合わないと思っていたんです。そこで出合ったのがこのパンプス。ベーシックな黒パンプスでありながら、アイコニックな4本のホワイトステッチが目を引くデザインにビビっときました。
― 靴選びのこだわりは?
身長が157cmと低めというのもあって、ヒールを履くことが多いです。靴はたくさん所持していますが慎重に吟味してから購入しているので、飽きて手放すようなことはなく、ずっと履き続けたいと思っているものばかりです。
― どんなコーディネートに取り入れたいですか?
私にとってファッション小物は、カジュアルなスタイルを格上げするための重要な存在。ハイ&ローアイテムをミックスしたスタイルが好きなので、このパンプスならTシャツやデニムに合わせたいです。カジュアルにもきれいめにも合うのでシーズン問わずヘビロテしています。
私らしさが詰まった永遠の“It Bag”

― 10年選手を教えてください。
セリーヌのラゲージです。
― このアイテムとの出合いは?
今もセリーヌのアイコンバッグとして愛され続けるラゲージシリーズは、10年前には世界中のセレブリティやファッショニスタが愛用し、爆発的人気を集めていました。当時ユナイテッドアローズでセリーヌを取り扱っており、原宿店で見つけたのがこのバッグです。人とかぶらない異素材を組み合わせたデザインに一目惚れをして、勢いで購入しました。
― お気に入りポイントを教えてください。
流行り廃りなくその時々のスタイルにマッチします。革が馴染んできたものの、さすがに作りがよく、まだまだ使い続けられそうです。
― 10年間使い続けるなかで気づきはありましたか?
購入当時、20代だった私にはハイブランドのバッグが浮いてしまっていたかもしれませんが、年齢を重ねていくたびに似合うようになったと感じています。しばらく慎重に扱っていましたが、くたっとした風合いが出たほうが私らしく持てると思い始めてから、細かいことはあまり気にせずに使うようになりました。
トレンドを押さえた大人カジュアルを追求

シャツ ¥19,800/ロク、パンツ ¥26,400/スティーブン アラン、サンダル ¥13,200/ビューティ & ユース ユナイテッドアローズ
― 最近はどんなアイテムを購入しましたか?
6(ROKU)でボタンダウンシャツを手に入れました。
― 購入の決め手は何ですか?
メンズライクなディテールにときめきました! シアー素材による透け感や、ハリ感のあるきれいめシルエットがほど良い女性らしさを引き出してくれます。綿100%で着心地も良いです。
― どんなコーディネートを楽しみたいですか?
今の時期はトレンドのグルカパンツを合わせることが多いです。夏はハーフパンツとヒールサンダルを合わせたり、タンクトップをインして羽織りとしても活用したいです。ネイビーはカジュアルだけど品があってよく手に取るカラーです。
好きという気持ちに真っすぐに生きる【モデル 桐山マキの衣食住遊学】
いつも元気で幸せそうなひとは、自分の周りに“楽しいこと”を育てる種をまいています。
そんな魅力的な方にHummingなライフスタイルのトピックスを伺うシリーズ記事「わたしの衣食住遊学」。
今回はモデルとしてCMや雑誌で幅広く活躍するほか、保護犬の保護活動をライフワークにしている桐山マキさんにご登場いただきます。
愛する犬たちのために考え、行動する日々

そのエレガントな佇まいと美しさから、ナショナルクライアントの広告出演も多い人気モデル 桐山さん。
プライベートではパートナーと一緒に、現在は3匹の犬と暮らす、賑やかで楽しい毎日を送っています。
愛犬たちは保護環境から迎え入れ、それぞれ異なるルートを経て彼女のもとにやって来ました。
そんな桐山さんのおしゃれや健康へのこだわり、愛犬たちとの愛情あふれる日常とは?

「衣」
一生ものアイテムを探し続けていく
デザインもシルエットもできるだけシンプルであるということが、やはり長く着続けられるポイントなので、服選びにおいてそこはいつもしっかりと意識しています。デザイン性が高すぎるといつか飽きてしまうし、流行りの素材はその時期が過ぎると着こなしづらくなって、なかなか長く着ることが難しいですよね。
素材は、カシミアやコットンが好きです。コットンはバシャバシャと洗ってデイリーに着られるラフさも、くたくたの味わい深い風合いになって自分に馴染んでいくプロセスもいいですよね。20年選手のロンTも活躍しています。
そんななかで出合った一生ものアイテムの一つが、古着屋さんで見つけたエルメスのヴィンテージコート。いわゆる“マルジェラ期”のもので、私はもともとマルジェラが好きなのでビビッときてしまいました(笑)。
カシミア100%で、羽織ったときの軽さと、肌触りと、ジェンダーレスなシルエットにもう感動してしまって。気軽に買えるプライスではなかったのですが、一生大切に着よう!と心に決めて購入しました。ここまで惚れ込めるアイテムには、なかなか出合えませんから、これは運命だなと。
>>【自己受容】弱くてダメな自分を認めて受け入れるトレーニング方法

週末だけオープンする古着屋さんで運命的に出会った。
何度も試着して、羽織るたびに「これだ!」という気持ちが強くなったそう。
このコートで出掛けたときは、帰宅後に毎回きちんとブラシをかけ、特別扱いしてクローゼットの外にディスプレイしています。そこにあって、ただ目に入るだけで自分のモチベーションが上がります。
以前は古着にあまり興味がなかったのですが、最近はとらえ方が変わりました。本当に良いものを時代を超えて使っていく、誰かから受け継いで、もしかしたらいつかまた誰かに受け継ぐかもしれないから大切に扱うー-そんな循環は、素敵なことだなと思って。
今では、自分好みのアイテムと出合えそうな古着屋さんを定期的に覗いたりしています。
もう一点、同じくエルメスのプティアッシュというトートも、これからずっと付き合っていきたいバッグとして手に入れました。
私が愛用しているのは、バーキンやケリーを制作をする過程で本来は捨てられてしまうレザーをフェルトに貼って、新しい命を吹き込まれたエシカルなアイテムです。
>>メンタルヘルスが注目されている理由|不調になったときの対策を紹介

表と裏でも表情が異なっていて、ませに唯一無二の存在感。
バッグのパーツが型抜きされた跡がまるでアート作品のようで、その背景からして同じものは存在せず、このシリーズのバッグはそれぞれが世界で一つだけというのも魅力なのです。
友人のスタイリストから「おしゃれはサイジングがすべて」と聞いて以来、必ず試着して確認しています。サイズが合わないせいで着心地がしっくりこないと、結局は着なくなり無駄になってしまいますから。今どきのゆるっとしたアイテムも、きちんと自分の体型に合ったゆるっと加減なのかを見極めて、着こなしたときに全体のバランスが縦長に見えるようにすることがこだわり。後ろ姿もしっかりと確認しています。

月1のファスティングは、Delifasの大田市場の農家さんから直送される無農薬の新鮮な野菜たちで胃腸から元気に。
「食」
内臓を休め、いたわり、健やかに!
本格的に食にこだわり始めたのは、30歳を過ぎてから。もともとアレルギー体質だったこともあり、ここでしっかりと改善したいと思ったのと、腸とアレルギーはとても密接に関係しているから、そこから見直さないと治らないよと言われたこともあって。
朝は起きがけにミネラルウォーターを飲む、発酵ものを意識して摂る、腸活、温活、食品の添加物をチェックする・・・一つひとつをより気を付けるようになって、口にするもので体ができているのだということを再確認しました。内臓を休めるために、ファスティングも月一回のタームで実行しています。
それまでは間食をしがちだったのが、ファスティングのおかげで、半端な時間に何か食べたくなるということがなくなりました。いくつかの方法を試してみましたが、人からすすめられた“食べながら”できるファスティングを取り入れています。朝にスープ、昼にサラダ、夜にまたスープという消化のいいメニューで、農家さんから送られてくる3日間のセットがあるんですよ。もちろん期間中は空腹感がありますが、3日目にはもう慣れて比較的平気になります。間食がなくなるだけでなく、お酒の量も減るし、眠りも深くなって目覚めもとってもよくなりました。
腸を活動させて体を健康にするには、菌の働きが大事なので、ぬか漬けをつくったり、味噌づくりにも挑戦しています。この前初めて出来上がったのですが、あ~こんなに美味しいんだと感動しました。

初めて自分でつくった味噌がこちら。仕込んでから10ヵ月ほど寝かせて完成するそう。
定期的にリセットすることで、舌が敏感になったというか、あるべき状態に戻ったのか、食べ物の味がよくわかるようになった気がします。添加物が多いものを食べると、頭が痛くなることも。そんな変化も感じています。
>>”自分らしく生きる”とは?|仕事や恋愛で自然体で過ごせる方法を紹介

リビングの癒しの存在、エバーフレッシュは育て始めてからかれこれ10年も経つそう。
神奈川県の植物屋さんで購入。当初は半分くらいの大きさだったのが、ここまで成長。
今では「一心同体感!」とまで感じている大切な存在に。
「住」
植物とも会話しています
自宅にはいくつもグリーンを置いて、育てています。
増やそうと思って探しているわけではないのですが、それこそ服と同じで、出かけた先で『わ、このコ、連れて帰りたい!』と、運命的に出合って増えていく感じです。
少し前の出来事なのですが、私が体調を崩してしまい数日間ほど寝込んでしまったことがありました。体調が復活した直後に、いつも話しかけて大事にしているエバーフレッシュがぐったりと元気を失くしているのを見て驚いてしまって。たくさんの葉が床に落ちてしまい、枝も下を向いて垂れていて・・・。何だか私の代わりに悪いものを吸ってくれたのかなとか、寝込んでいた間は声をかけてあげられなかったので、そのせいで元気失くしたのかな・・・と思ったり。
エバーフレッシュは、朝は「おはよ~」ってかんじに葉が開いて、夜になると眠るように閉じるので、まるで人間みたい。元気がないときは見た目ですぐにわかるし、“生きてる”ってかんじがリアルに伝わってきます。植物だけど会話ができる相手という感覚なんですよね(笑)。毎朝、このコの様子を見て挨拶するのが私の日課です。
>>【誰でもできる】マインドセットの意味・使い方をわかりやすくご紹介!

〈上〉宮古島のホテル、イラフスイニて。
〈下〉ジャングルのような野性的な植物群に癒されるドッグカフェ、パニパニ。
「遊」
自然と触れ合う旅でリラックスする
一緒に暮らしいるココワカメさんという、元野犬だったうちの愛犬は宮古島のシェルター(SAVE THE ANIMALS)出身です。いつか里帰りさせてあげたいなと考えていたら、メディアの取材でそれが実現できました。シェルターの取り組みも記事で紹介していただけて。
この取材が私にとって初めての宮古島訪問で、愛犬と一緒に行く旅だったこともあり、イラフスイという犬も泊まれるホテルのお世話になりました。犬にもうれしいサービスが用意されていて、本当に快適でした。
宮古島は車がないと移動ができないので、犬OKのレンタカーを利用して、パニパニというジャングルみたいにグリーンに囲まれた素敵なドッグカフェを訪問。ここはもう、近くに住んでいたら毎日通いたくなるような気持のいい場所で、足元は砂浜なので素足で過ごせるし、生い茂った緑に囲まれていて、食事も美味しくて、最高でした。
私は田舎育ちなので自然の中で過ごすこと、とくに緑が多い場所で植物の生命力に触れるととっても癒されるんですよね。
>>ヨガがメンタルヘルスに良いと言われる理由。ヨーガって本当はどういう意味?

「学」
犬が好きという気持ちが、情熱を生む
もともと私の実家(桐山さんは大阪出身)では、子供のころから犬と一緒の暮らしが当たり前だったという背景があります。東京に来たばかりのころは犬と暮らせる環境ではなかったので、保護犬のボランティアに参加して犬と触れ合っていました。
そんななかで、保護された犬たちの現実を目の当たりにして、虐待されたり、遺棄された犬たちを保健所から引き揚げてきたときに、彼らの怖がって怯えた様子を見て衝撃を受けました。実家で保護犬を飼っていた経験もあったのですが、そのコの比ではないほど、パニックに陥っている犬もいて。この現実をきちんと知っておくべきだなと思ったんです。
そこから自分ができることを少しずつでもできたらいいなと思って活動を続けています。私自身は、現在は3匹の保護犬出身の犬たちと暮らしています。最初に家族になった小春ちゃんとは「ペットのおうち」という里親さんを見つけるサイトで出会って、何回かの面接を経て引き取りました。2匹めは、宮古島のシェルターからやって来たココワカメさん。3匹めのぶーちゃんは、保護犬の一時預かりボランティアという形で我が家に来てもらっています。ぶーちゃんが加わったことで、ココワカメさんの心が急速に開いていって、言葉で表せないくらいに明るくなったんです。

〈左から〉ココワカメさん、小春ちゃん、ぶーちゃん。
人間と犬だけでなく、犬同士の関係にも変化があって、家族の絆が確実に深まっていることを実感しています。
ココワカメさんのような野犬出身の保護犬は、とても難しいところがあります。うちに来たばかりのころはテーブルの下から怯えて出てきてくれなくて。散歩に連れて行っても安心できないからなのか、外で排泄ができないんですよね。そんな様子を見て、最初のうちは『大丈夫だよ』『出ておいでよ~』なんて声をかけて構っていたんですが、それがよくないのかなと思って、構いすぎるのをやめてみたんです。そうすると逆に、ひょいっとテーブルの下から出てきたりして(笑)。
こちらの、こうした方がいいだろうという思い込みに対して、それは違います、それは求めてません・・・みたいな返しを感じたので、その意思表示をきちんと読み取って、距離感を急いで縮めようとせず、時間をかけて少しずつ歩み寄ったほうがいいんだなということも学びました。今はどういう様子かなと細やかに観察して、想像して、互いにアイコンタクトもできるようになって。そうやって一つずつ信頼関係を深めていくように努めています。
満たされていないと、こういう行動するんだなとか、我慢させちゃったかなと思うときはごめんねと伝えたり。日々、いろいろなことを犬たちから教えられているなと思います。
>>【ストレス解消】セルフケアとはなにか?意味・種類・方法について解説

5月半ばに、表参道のギャラリー5450 the GALLERYにて保護犬譲渡会を開催。
桐山さんは会場費の提供やPR活動に携わりました。
私は今、保護犬のこと、保護されるまでの虐げれていた環境についても、たんさんの方に知ってもらうことが、動物と幸せに暮らせる社会にしていくために必要だと思って活動しています。その流れで、保護犬の譲渡会の企画も始めました。
犬のために何かをしたいという気持ちに突き動かされていて、それは「好きだからやりたい」という強い想いが原動力。とはいえそれは、人に対して押しつけになってはいけないなと思っています。情報を正しく広く発信して、ペットを探している方たちに保護犬という選択肢もあるなと、とにかく知ってもらうことが大事だなと考えています。動物と人がピースフルに暮らせる世界が広がっていくことを願って、何か少しでも役に立つことができたらうれしいですね。
犬と人間は、互いに愛情を感じ合い、気持ちを交わせる家族。彼らに寄り添いアクションを起こすことは、桐山さんにとって必然であり、一匹でも多くの犬を幸せにできればという希望へと向かっています。揺るぎない情熱と「やりたい」に真っすぐに進むその行動力は、周りの心を動かし、環を広げ、さらなる大きな変化へとつながっていくはずです。
>>【変わりたいあなたへ】自分を変えることは難しい?変われる方法や習慣

Profile
桐山マキ(きりやままき)
大阪府箕面市出身。2005年、雑誌「PINKY」の専属モデルとして、モデルデビュー。
『美しい着物』などさまざまな雑誌や、国連の出版物などの表紙・誌面で活躍中。また、パリ、NY、ハンガリーをはじめとする世界のショーにも多数出演。
現在 、アメリカン・エキスプレス、ホットヨガスタジオLAVA、ヤクルト等、11社のCMに出演中。また、自らの経験を活かして、保護犬をめぐる啓発活動をファッションやライフスタイルを通して展開している。
Instagram @maki_kiriyama
お手軽ギフトとして最適。貰えると嬉しいシートマスク
肌や体に良いもの、使い心地が良いもの、気分が上がるもの・・・コスメや美容ツールを上手に取り入れて、Hummingな毎日を送りたい。美容ライター 荒木奈々さんがおすすめをご紹介します。
効果も頼りになるシートマスクがギフトの条件

このところ食事に誘われる機会も増え、2、3年ぶりに会う友人も。気の利いたギフトを持参したいと思っていますが、自分で美味しいと思ったもの、使って良かったものの中から、相手を想ってのギフトを用意。みんなが喜んでくれるのがやっぱりコスメで、何でもない日に手軽に渡せるものといったらシートマスク! 貰えたらきっと嬉しいシートマスクを選んでみました。
My select 01:プルプルの快感で、ハリ復活。ファミュのシートマスク

ファミュ ドリームグロウマスク PF 30ml ×6枚入 ¥4,620/アリエルトレーディング
大人の会話で盛り上がるのが肌のこと。20代からシミが気になり、次に小ジワ、くすみ、その後は毛穴の目立ちと順当に衰え問題に直面。そんな大人肌へのギフトは、やはりエイジングケアのシートマスク。数あるエイジング系の中でもギフトに選びたいのは、韓国コスメのファミュ作。それはなぜかというと・・・。
肌トラブルだらけで下がりがちなテンンションを盛り上げることから始めたい大人肌。ファミュは、オーガニック認証を受けた原料を採用している正統派のナチュラルコスメでありながら、ラグジュアリーを追求したビジュアルのギャップがありそうでなかった! キレイになれそう、というマインドにも誘ってくれます。
4年の研究開発を経て、2015年にデビューしたファミュ。ブランド名は「女性」の「femme」と「変化」の「mue」を掛け合わせた言葉だそうで、全製品が女性の美しく変化する瞬間に立ち会ってくれるような働きかけ。“東洋の薔薇”といわれるカメリア(ファミュでは済州島の特産物の椿を採用)をアイコンの花とし、その他花々の恵みをアプローチごとに厳選しているナチュラル×サイエンスの融合コスメで、日本のみならず、アメリカ、イギリスにもチャンネルを持っています。
前置きが長くなりましたが、そんなファミュでの推しシートマスクは、目利きのプロたちのお気に入りコスメとして、その名が必ず挙がる「ドリームグロウマスク PF」。オーロラのパッケージが目印で、4タイプのうちPFは(PLUMP・FIRM)の略、ハリ・エイジングケア用。アデノシンやヒアルロン酸を配合し、乾燥はもちろん、気になる小じわやたるみへの集中ケアが期待できます。
またシートマスクの効果はマスクの素材に左右されることに着目し、ファミュでは世界特許の「ドライバイオセルロース」を採用。それはココナッツ発酵エキスから抽出した極細繊維を編み込んだ100%天然由来素材。しかも無菌状態で保存料・防腐剤不使用な上、この素材による体感が6つもあるそう。
- 乾きにくい
ゲル化するマスクで水分が蒸発しにくく、肌に効率よく潤いを補給。 - 浮いてこない
極薄で肌に吸い付くように密着。 - ケバ感レス
ふんわり柔らかい肌当たり。3D状に繊維を編み込んでいるので、微細な空気穴があり、閉塞感もありません。 - 気持ちいいクーリング感
シートの潤い保持力が高く、肌を穏やかに整えてくれます。 - 潤いのちストレッチ効果
15分くらい貼り付けていると、シートがタイトになり、肌へのホールド感が高まってリフトアップ。 - 角質ケア
セルロースが不要な角質や皮脂を吸着するので、はがした後は明るい肌へ。
香りは予想に反して花ではなく、シトラスの香りですが、そこが甘すぎなくて好み。美容液たっぷりのプルプルなマスクで、大人も満足できるトリートメントを!
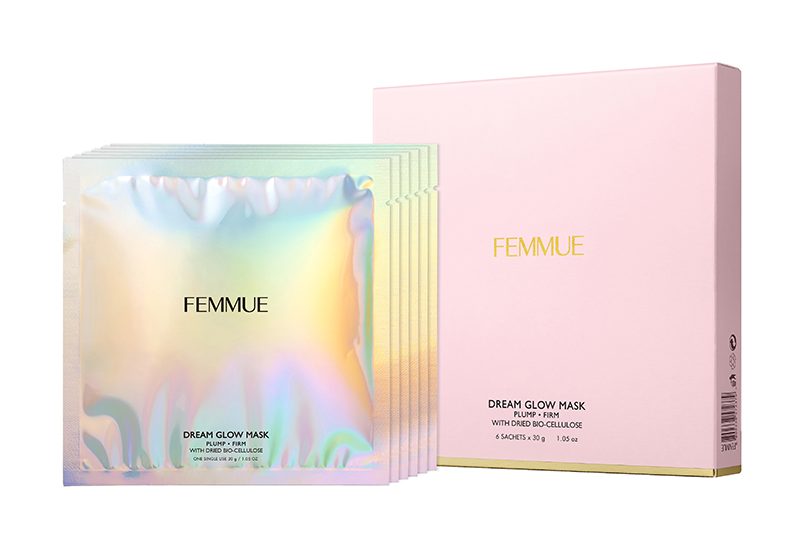
ピンクの外箱はニスやプラスチックコーティングを排除した「環境のためを考慮した」最小限の仕様。
韓国コスメはサステナブルの活動で他国をリードしているといわれますが、ファミュも創業時より「環境にやさしく」をモットーにした、クリーンビューティを提唱しています。プラスチックの使用は必要最低限に抑え、95%以上ガラス容器を採用。クルエルティフリー、水不足への取り組み支援、ショップでの容器回収等々、化粧品ブランドならではのサステナブルはほぼ実践中!
ファミュのシートマスクはギフト需要も多く、1枚ずつ渡したいとき用のギフト封筒(6枚入り¥300)もあります。
ファミュ
www.femmue.jp
My select 02:肌も心もごきげんに! ミラリの水彩柄シートマスク

ミラリ 6種類mirariセット ¥3,740/Beauty Thinker
会うたびに美味しい手土産を持ってきてくれる後輩がいます。センスのいいこだわりの品を用意してくれて、その心配りまでが嬉しい! たかがギフトではありません。センスがいいって思われたいから、迷ったらコレ。
mirari(ミラリ)シートマスクもMADE IN KOREA。プロデュースは日本で行っているそうですが、さすがマスク大国の韓国製コスメ、こちらのシートも独創的!
ミラリは、フランスの国際認証「EVE VEGAN」取得のヴィーガンコスメブランド。ブランド第一弾のアイテムがこちらのフェイシャルトリートメントマスクで、中身が見える透明パウチがおしゃれ。でもこの透明にはワケがあり、エキスやシートを劣化させないための最新技術なんだそう。
その日の肌やその日の気分に合わせて選べる全6種類が用意されています。
人工香料を含まず、天然エッセンシャル・オイルで香りづけ。各々異なる穏やかな癒やしの香りです。#01~04は蓮の3Dのエアメッシュ・シート、#05はツボクサのヴィーガンシート、#06は5重レイヤーの天然シートと目的別でシート素材も違います。
今回は個人的にお気に入りの#04、#05、#06をご紹介。ミラリのシートマスクは想いをのせたプロダクト名になっているので、そのネーミングから直感で選ぶのもおすすめですよ。

ミラリ more rest 25g ×5枚入/Beauty Thinker
#01~04に採用されてるのが、蓮の3Dのエアメッシュ・シート。蓮の葉と種のエキスから抽出した極細繊維を丁寧に編み込んだ100%ナチュラルシートで、水分保持力が高く低刺激、シートそのものにタンパク質が含まれているのが特徴です。どんな肌タイプとも相性の良いシートは、ヨーロッパのエコ繊維認証の厳格な検査試験で「OEKO-TEX®」の一等級も取得。小さな蓮の花模様がプレスされているのもかわいいです。
#04 more restは上記のシートに、~肌はもちろん、心の中までゆっくり休むことができますように~という願いを込めて、ツボクサエキスやウンシュウミカン果皮エキス、ティーツリー葉エキスなど、肌をいたわる天然植物由来成分がたっぷり含浸されています。肌を落ち着かせたい、健やかになりたい、それからハリ不足が気になるという方へ。

ミラリ more calm down 30g ×5枚入 ¥2,750/Beauty Thinker
#05 more calm downのツボクサのヴィーガンシートは、韓国でヴィーガン認証を取得。タイガーズハーブとも呼ばれるツボクサの葉と茎をすりおろして作られた素材で、長時間、肌に美容成分を浸透させることができるのが長所。イタドリ根エキスやオウゴン根エキス、ドクダミエキスなど漢方的な成分がたっぷり。敏感になりがちな肌をカームダウン、透明感もプラスします。#05 more calm downのテーマは~肌はもちろん、心の中に安定と平和が戻ってきますように~。目を閉じると森の中にいるようなグリーンのアロマテラピー。

ミラリ more love myself 40g ×5枚入 ¥3,300/Beauty Thinker
#06 more love myselfはその通りご自愛シートマスク。~自分自身のことをもっと愛するための贅沢な時間になりますように~という想いが込められ、40gの大容量! それを可能にしたのが100%自然由来の薄いシートを5枚重ねた天然シートで、ふわふわの肌触りなのに高密着。センチフォリアバラ花エキス、ハス花エキス、フリージアエキスなどに加え、エイジングケア成分のAmino Acid complexを配合したミルキィーなテクスチャーで、翌朝の肌はたっぷり睡眠したようなしっとり、もっちり肌に。ちなみに5重レイヤーの天然シートも蓮の3Dのエアメッシュ・シート同様、「OEKO-TEX®」の一等級品です。

ナチュラル×アーティなミラリのシートマスクは、エストネーション、ロンハーマン、バーニーズ ニューヨークなどこだわりのセレクトショップでも購入ができます。6種類が1 枚ずつ全部入っている「6種類mirari セット」もあり、ギフトに大人気とか。友達と会うときには複数をもっていき、選んでもらうのも楽しいかも。
mirari
https://mirari.jp
My select 03:肌サウナでほっこり♪ ON&DOのホットマスク

ON&DOホットマスク 3包 ¥1,320/MTG
ギフトですから、ちょっと変わったシートマスクも喜ばれそう。チョイスしたいのは、ON&DO(オンアンドドゥー)のホットマスク。ON&DOは美顔器のリファでおなじみのMTGが提案するビューティブランドで、肌・体・心のベストバランスを“温肌”と定義し、不規則なライフスタイルなどで“温肌”をキープできなくなっている肌に寄り添う、さまざまなプロダクトが展開されています。
ON&DOのホットマスクは、何かある日や肌の落ち込みを感じる日のスペシャルケアとして。開封するとすぐに温感モードになるので扱いも簡単です。耳にかけるタイプで、肌をすっぽり。じんわりほっこりの温感にうっとりします。温感効果の継続は約15分、サウナは苦手ですが、肌サウナのようなホットマスクタイムはあっという間。何度も使ってもおかわりしたくなる心地よさです。
そうはいっても暑い夏に温活ケア!? 紫外線によってくすみがちですし、一年中巡りも悪くなっていますから、定期的に取り入れるのがおすすめ。
ON&DOのルーツは長崎県・五島列島のヤブツバキにあります。冬の寒い時期に咲く椿の花の酵母に着目し、ストレス耐久という特性があるその酵母をスキンケアに応用。独自美容発酵液「温酵母(サッカロミセス/(ツバキ花エキス/アテロコラーゲン)発酵液(保湿剤)」は全ラインナップに配合されているそうです。ちなみにON&DOではツバキの葉、花、果皮、果実、種子、枝まで無駄なく美容成分として生まれ変わらせています。

ON&DOミルキーフェイスマスク 5包 ¥3,850/MTG
ブランドが提案する、ホットマスクとミルキーフェイスマスクのW使いもお試しを。最初にのせるミルキーフェイスマスクは、椿油(エモリエント剤)と椿花細胞水(ツバキ花汁(保湿剤)を乳液化したものを含浸。水分とオイル分がバランスよく配合されているので、潤いを与えながら、クリームのお手入れ後のようなしっとり柔らかい肌も叶います。単独使用でも透明感がアップしますが、ホットマスクを併用すると、スチームマスク効果で、ふんわりより明るい肌へ。巡りも一気に良くなり、理想的な温肌に。
ON&DOでは地球や社会が抱えるアンバランスに向き合うことを使命とし、 “容器アップサイクル”“自然保護”“エンパワーメント”の3つからなる温肌アクションを遂行。もともとON&DOでは、ふるさとである五島列島の里山整備などを手掛けていますが、最近では海洋プラスチックごみにまつわるビーチクリーン活動にも着手。海洋プラスチックごみは、五島列島も抱える問題。拾うことで終わりにするのではなく、さらにその海洋プラスチックごみをディッシュなど魅力的なプロダクトへ再生するという新たな取り組みにも熱心です。
ON&DO
on-and-do.jp
香り系は好き嫌いもあるので難しいところがありますが、個性的なシートマスクはウケもよさそう。でもこちらはギフトなら何でもウェルカムですが(笑)。
夏の装いに映える!
ヘレンカミンスキーのエシカルなサマーハット
強い日差しを感じる日が増えてきた今日このごろ。日除けに最適なサマーハットをご紹介します。こだわりの帽子で、おしゃれに紫外線対策をしませんか?
クラフトマンシップが光る、夏のマストハブ

1983年にオーストラリアで誕生したライフスタイルブランド、ヘレンカミンスキー。最高品質でサステナブルな天然繊維“ラフィア”を使用し、ハンドクラフトで丁寧に編み込んだラフィア・ハットは多くのセレブリティに愛されるブランドの代名詞として知られています。
耐久性と柔軟性に富んでいるラフィア。ハットはコンパクトに折り畳んでも形が崩れにくく(※)、さらにUPF50+の高い紫外線防止効果が備わっているため、夏のお出かけやレジャーに欠かせないアイテムなのです。
※すべての商品ではありません。

Bloom ¥35,200
2022年春夏コレクションは、クラシックかつロマンティックなムード。象徴的なのはイタリア製グログランリボンをあしらった遊び心のあるシリーズ。甘美なカラーリングのリボンが視線を惹き付けます。

Tove¥26,400
レトロな雰囲気漂うラウンドクラウンハットやバケットハットは、淡いカントリーチェックがほど良くリラックス感を演出。リバーシブルで楽しめる自由度の高いアイテムです。
ヘレンカミンスキーは、ブランド創業当時より自然を大切にするというオーストラリアに根付く文化と同様に、ラフィアの原木を傷つけない持続可能な収穫の実践や、二酸化炭素排出量の抑制、強制労働等のないサプライチェーンの構築など、環境配慮とCSRに高い水準を設け、サステナビリティを重んじたコレクションを制作。
長く愛用できる「ロングライフ」な製品づくりに注力し、高水準の原材料と技術によって製品自体の耐久性を高めるほか、リペアサービスも備えています。
上質かつ機能的なヘレンカミンスキーのラフィアハット。どんなスタイルにもマッチする飽きのこないデザイン、そして創業時から培われてきた誠実なモノづくりの姿勢が、私たちが愛着を持ってずっと使い続けたくなる秘訣なのではないでしょうか。
ヘレンカミンスキー ギンザシックス店
03-6264-5573
https://www.helenkaminski.co.jp/
森カンナ「きっと私は丸裸でいるんだと思う」【連載 / ごきげんなさい vol.08】
俳優 森カンナさんが日々の生活のなかで見つけたこと、感じた想いを綴る連載エッセイ「ごきげんなさい」。自分を“ごきげん”にするためのヒントを探しましょう。

「友達」
先日、撮影現場で女子スタッフさんたちに「カンナさんってなんでそんなに友達が多いんですか?」「友達ってどうやってつくればいいんですか?」と、友達に関する質問攻めにあった。
どうやらみんな友達がなかなか出来ないらしい。
友達をつくるということをあまり深く考えたことがなかったが、そういえばよく「カンナってほんと友達が多いよねぇ」と言われる。
確かに自分でも多いと思う。
私の父はかなりの転勤族で、小学校は二校、中学校は三校を渡り歩き、いろんな学校の制服を着て、いろんな給食を食べてきた。
もちろん初登校の日は緊張していたが、いつも転校初日にはもうその足で新しくできた友達と遊びに行くほど、打ち解けるのが早かった。
この仕事を始めてからも、初めて会う役者さんと撮影終わりでご飯を食べに行ったりと、とにかく親しくなるのが早い。
そしてよくあることなのだが、初めて会う人も含め友人に「これは誰にも言ってないんだけど・・・」と、その人がこれまで秘めてきたことを打ち明けられる。
何故なのか・・・。
自分なりに分析したり友達に聞いてみたりした結果、あまりうまく説明出来ないが、きっと私は丸裸でいるんだと思う。本当、つねにスッポンポン!
人に対してあまり変な氣も遣わない。
氣を遣われてるな〜って思うとなんだか疲れてくるし、こっちも遣わないといけないのかな?って思ってくる。
もちろん遣わないといけないときもあると思う。
けれど、氣が遣えていい人だな〜!とか、変な奴! 頭おかしい奴!とか何と思われても、正直どうだっていいと思っている。
周波数が合わない人と無理矢理に仲を深めようと思っても難しい話だし、合う人はソリが合って氣が合って勝手に仲が良くなっていくんだと思う。
友達といると疲れるという人もいるが、合わない人といるのはそりゃ疲れる。
そういうときは離れて一人で居れば良い。
決定権はすべて自分自身にあって、自分の“気持ちいい”を最優先に行動するといいのだと思う。
人間って自分たちが思っている以上に物凄い生き物で、会った瞬間にその人の情報を読み取って判断するらしい(キスも菌を交換して相手の情報を読み取っているらしい。ただ今、絶賛菌の勉強中。その話はまた今度・・・)。
なのでこちらが変な氣を遣わず素っ裸でいると、きっと相手にもそれが伝わって、では私も失礼して・・・と相手もどんどん服を脱ぎだすみたいな。
そりゃこの世界にいると、どんどん厚着して仕上げに鎧を着てみたいな人がほとんどだ。でもそれも自分を守るために必要だったりもするし。全裸スタイルはケガをしたりもすることも多いが、何だかあれこれ考えずに済む。
私は人間が好きだ。
とにかく人を愛して、信用して関わっていきたいと思っている。
例え、それで傷付いたとしても、傷付けるようなことをする人と共鳴する部分が自分にもあったのだから、自分の責任だと思っている。
誰のせいでもなく、すべては自分の責任だ。
これからもそうやって覚悟を持って人と交わっていきたいと思っている。
友達について、人付き合いについてお困りの方。
皆さんも是非、一度素っ裸に。

はぁー! 早く友人たちと海外に行ってぶぁぁって遊びたいなー!って、よく海外旅行写真を見て振り返る。みんなでいろんなとこ行ったなぁ。2019年みんなでグアムに行ったときの写真。誰だか分かるかな? 笑
Profile
森カンナ(もりかんな)
俳優。富山県出身。映画『地獄の花園』『鳩の撃退法』、TBS『プロミス・シンデレラ』、フジテレビ『ラジエーションハウスII』など、数々の映画やドラマに出演。2021年には、自身初舞台となった蓬莱竜太演出『昼下がりの思春期たちは漂う狼のようだ』で、600人のなかからオーディションによって選ばれ、観客を魅了。放映中のフジテレビ 月9ドラマ『元彼の遺言状』(毎週月曜21時~)1話、2話にゲスト出演した。
https://kannamori.com/
Instagram @kanna_mori
みんなで使える!美容ライターお気に入りのシェアコスメ
肌や体に良いもの、使い心地が良いもの、気分が上がるもの・・・コスメや美容ツールを上手に取り入れて、Hummingな毎日を送りたい。美容ライター 荒木奈々さんがおすすめをご紹介します。
コスメをシェアすることがフツーの時代到来

ここ最近、確立されたジャンルといえばシェアコスメ。でも振り返ると幼いときは家族みんなで青缶のクリームを使っていましたし、学生の頃は母の高級コスメを拝借していた思い出が。シェアコスメというワードがなかった時代から、そういえば家族でいろいろなコスメを共有していたものです。そして今、より時代のニーズに合ったシェアコスメが続々登場。パートナーや親子でシェアしているお気に入りのコスメ、その一部をご紹介します。
My select 01:お手入れ初心者のパートナーと一緒に使うセラム

ネス エッセンス ストラータ 25ml ¥6,600/UGONESS Inc.
「流行りのスキンケアやベースメイクって何ですか?」と男子高校生に尋ねられることがあります。若い世代はジェンダーレス、ボーダーレスが定着している印象ですし、男子女子と関係なく、美容に興味を持っている方が多いようです。
一方で大人の男性は、ボディソープで顔を洗うのがいまだに普通!? また恥ずかしさもあるのか「俺はいいよ」とスキンケアに消極的な様子。でも逆にやってこなかった分、大人の男性がスキンケアに目覚めると相当な変化を感じられるそうですよ。特に日焼け全盛時代を過ごしたパパたちは、たるみやシミの出現も深刻ですから、このブームにぜひ乗っていただきたい!
2022年春に誕生した「ness(ネス)」は、美容感度が高い男性に推したいとヘアメイクさんから教えてもらったブランド。「男らしさ、女らしさ、年齢などのさまざまな既成概念を解放し、一人ひとりのウェルネスを高めていく」ことをモットーにしており、誰もが自然にケアする時代を予感させてくれます。
「化粧品でもない、美しくなるためでもない、自分があるべき姿、なりたい姿になるスタンダートなエチケットを提案する」というのがブランド開発時の想い。美容液、化粧下地、そして秋に加わるパウダーの3品のシンプルステップで、「らしさ」を引き出してくれます。スキンケアは美容液1本で完了。ミニマムなお手入れですから、多忙な女性向け、そしてコスメ慣れしていない、お手入れをめんどくさいと思っている男性も続けやすそうです。
1日の間に微妙にズレてしまうという体内の時計遺伝子。朝の光を浴びることでリセットされるといわれますが、肌のリズムを司るといわれる細胞時計(生体内に存在するサーカディアンリズムのこと)は睡眠不足などによって乱れたままに。すると肌の調子は崩れがちになります。そこに着目した美容液「ネス エッセンス ストラータ」は、どんな肌にも合うエイジレス設計で、中心成分に白ブドウ果実由来エキス(保湿成分)配合。不規則な生活で落ち込みがちな大人の肌を、本来のリズムに整え、調子のいい肌へ。使い続けることで刺激にも負けない、揺るがない肌へと導いてくれます。
朝と夜、洗顔後のクリアな肌に2~3プッシュ。水のようにライトなテクスチャーは、手のひらでマッサージするように塗布します。乾燥しがちな肌にもスルスルと浸透し、たった一回の使用でキメが整いふっくらもっちり。シェービングトラブルしやすい肌にも使えます。

クリアなアンバーのパッケージもジェンダーレス。
ファッション、ウェルネス、インテリア、ライフスタイルといった業界のボーダーレスも狙っているそうで、コスメでありながら見た目はフレグランスのように上品。またコスメの甘いニオイが苦手というパートナーも、虜になる爽やか香りです。
肌の土台を整える美容液は1本でも頼りになりますが、なじみがいいので私はいつものお手入れに追加投入。キメが整うので、化粧ノリもアップ♪
My select 02:毛穴トラブル続発の思春期肌とシェアするクレイ洗顔

ハン クリアクレイウォッシュ 130g ¥2,000/ビーバイ・イー
洗顔料も家族でシェアするコスメのひとつ。個人的な観察になりますが、毛穴が目立つようになるのは思春期を迎える小学校高学年くらい。しかも高校生になると毛穴の黒ずみやニキビが気になってきますから、毎日の洗顔ケアが欠かせません。さらに代謝がいいからでしょうか。汚れや皮脂が一日で溜まることを物語るよう、洗顔料を使って洗った日、使わなかった日は明らかにわかるほどです。そうはいってもまだまだデリケートな肌。優しい洗顔料をシェアしたいのです。
ママバターは長年お世話になってきたブランド。天然シアバターをメイン成分とし、赤ちゃんの肌から、デリケートな大人肌にもぴったりな保湿シリーズです。この春にはジェンダーレスをテーマにしたスキンケアブランド「hän(ハン)」をプロデュース。ママバターのやさしい処方を引き継ぎながら、「誰でも使える、誰かと使える」がキーワード。
ブランド名の「hän(ハン)」とは、フィンランド語。彼や彼女を意味し、すべての人を示す単語なのだそう。コスメはクレンジング、ウォッシュ、ローション、コンシーラーの4品が揃っており、男女ともに悩んでいる人が多いという毛穴トラブルにフォーカス! そしてテカリが気になる夏の肌、ベタつきやすいパートナーの肌、毛穴汚れによるトラブルが気になる思春期の肌にもマッチするのがこちら。
「ハン クリアクレイウォッシュ」は、植物由来のビタミンC誘導体(保湿成分)、クレイ(吸着成分)、炭(吸着成分)が配合されており、頑固な毛穴汚れやベタつきの原因となる余分な皮脂をすっきりオフしてくれます。さらに肌を清らかに整えるツボクサ葉/茎エキス、ユーカリ葉エキス、アロエベラ葉エキス、ホップエキスの4つの植物成分も配合。クレイ洗顔というと取り去るパワーが強いイメージですが、こちらは新感覚。ママバターのアイコン成分オーガニックシアバターが採用されているので、ツッパリ感のないしっとりとした洗い上がり。透明感のある明るい肌を洗うたびに実感できます。

のせた瞬間ややひんやりする、なめらかなクレイテクスチャー。
シトラスミントの天然精油が入っているので、爽やかな香りが広がります。毛穴の黒ずみが気になるときは、少し厚めに塗って部分的にクレイパックを。
そうそう初回限定のパッケージは、クリエイティブディレクターのDaichi Miura氏によるデザインで、オリジナルのポジティブワードがプリントされています。このバージョンが入手できるのは今だけのようです。
ハンはシリコーンや合成香料など9つのフリー成分を約束。さらにママバター発信だけあって、未来のためのエシカルな取り組みも丁寧です。ママバターやハンの全アイテムに配合されている「オーガニックシアバター」は、SDGsの17の目標のうち、1(貧困をなくそう)、10(人や国の不平等をなくそう)、12(つくる責任 つかう責任)に着目。トレーサビリティ可能な原料で、現地アフリカで生産されています。もちろん原料、商品製造、発売に至る過程においての“NO ANIMAL TESTING”も実現。それからパッケージに記載はないようですが、バイオPETのエコ容器が使われています。
ハン(ビーバイ・イー)
www.bxe.co.jp/brand/han
My select 03:子供との外遊びに大活躍。UV&アウトドアスプレー

UV&アウトドアスプレー SPF20・PA++ 80ml ¥2,200/ママベビー
ナチュラルコスメにスイッチした理由はいろいろあると思いますが、子供を持ったときにコスメを見直したという人は多いはず。肌が触れ合うから自分が使うコスメはやさしいものがいいし、ましてやベビーに直接使うものは厳選したい。そんな方々から選ばれているのが、イタリア発のオーガニック&ヴィーガンブランドのMammaBaby(ママベビー)です。
ママベビーは70年の歴史がある医療機関向けの製薬会社が開発。創業者の娘さんが重度のアトピーだったことがきっかけとなり生まれたブランドだそうで、良質なのはもちろん、シャンプーやベビーオイルなど「こういうのが欲しかった」というママニーズに応えたアイテムが満載です。
子供にもUVケアを塗るのを習慣にしている方はほとんどだと思いますが、ぐずったりしてつけるのを拒否されることも多々。さらに虫よけスプレーを追いかけながらスプレーする・・・。しっかりケアしてあげたいのに、ちゃんと塗れているか不安ですよね。そこで猛烈におすすめしたいのが「UV&アウトドアスプレー」。正直、もっと早く出合いたかった!
5年の歳月をかけて開発したという独自のテクノロジーによって、日焼け止めのキー成分である酸化チタンを100%植物成分でコーティングすることに成功。ノンケミカル&ノンシリコンで、赤ちゃんや敏感な大人肌を紫外線のリスクから守ってくれます。また今年注目の海を汚さない日焼け止めでもあり、海洋生態系に影響する化学物質は一切入っていません。

子供の手にも持ちやすいコンパクトサイズ。
UVケアと同時にアウトドア対策ができるように、ティーツリー葉油、アオモジ果実油などを配合。自然由来100%で新生児から使えるとことんやさしい処方です。また虫よけ剤としてよく知られるDEET(ディート)はジエチルトルアミドのことで、子供には使用回数が制限されている成分。「UV&アウトドアスプレー」はディートを含む14の無添加処方。ベタつくこともなく、サラッとしっとり。お湯だけで落とせるので、肌残りの心配もありません。とにかく1回のスプレーでUVケア&アウトドア対策のW機能がうれしすぎる!
ママベビーのサステナブル活動もリスペクトしたいところで、例えば従来破棄されていた容器のほか、生産前後の不良品の使い道にも注目。どういうことかというと、容器を作る際、色の切り替えによって5%程度の容器が不良品になり、それらはすべて破棄されているのだとか。その不良品も積極的に活用することで、日本での容器廃棄ゼロを目指しているそうです。また地球と人とのウェルネス、安全について、独自のアクションもあり。特に環境再生型農業の推進と、女性の活躍の場を広げる自由な働き方の見直しに力を入れているそう。
それから新たな取り組みがユニーク! 子供の肌や髪のトラブルの疑問を解決してくれるAI簡易診断「皮膚科専門医のLINE無料診断」を開設していて、「お風呂後に発疹が出た~」など、病院にすぐ行くまでもなさそうな皮膚疾患のSOSは、先にこちらで情報を得ると心強いかも。まずはママベビー公式LINEでお友だち登録を。
ママベビー
https://mammababy.jp/
「これ良かったね」「次はあれを使ってみたい」などとシェアコスメを使うことで会話も増えるかも!? 年齢や性別問わずのシェアコスメ、これからも要注目です。
スヌーピーとその仲間たちと一緒に、楽しくエコ生活を始めませんか?
世界中で愛されるスヌーピーとその仲間たち「PEANUTS (ピーナッツ)」と、Afternoon Tea LIVINGの新作コラボアイテムが6月1日(水)より販売スタート! キャラクターの愛らしさ満点のアートや、人や地球への思いやりのメッセージをあしらったサステナブルな商品が登場します。
「思いやり」の大切さに気づく

原作コミック『ピーナッツ』には、ピーナッツの仲間たちの視点で思いやりの気持ちの大切さが描かれています。そんな彼らをお手本に、「Care for Yourself (自分への思いやり)」「Care for Each Other(お互いへの思いやり)」 、そして「Care for the Earth (地球への思いやり)」という3つの思いやりの輪を広げるため、“TAKE CARE WITH PEANUTS”プロジェクトとして生産者や環境に配慮した商品作りの取り組みが世界的に展開されています。
国内での取り組みの一つが、今回のAfternoon Tea LIVINGとのコラボレーション。各アイテムには、「PALE BLUE DOT(地球について思う気持ち)」「“HERE YOU ARE.. ”(みんなでどうぞの気持ち)」「HOW PLANTS GROW(植物や生き物を大事にする気持ち)」「DEAR CHERISH(お互いを愛しむ気持ち)」のメッセージが描かれています。私たちの日常を彩るハートフルなアイテムのなかから、Humming編集部がオススメをピックアップ!
使うたびに心温まるエコグッズ

ショッピングバッグ¥1,760 © 2022 Peanuts
スヌーピーの寝姿を見るだけで気持ちが和む、再生ポリエステルを使用したショッピングバッグ。最近はレジ袋の有料化により、出かけるときはマイバッグ持参が習慣になっている方も多いのでは? ふとした瞬間に地球のこと、大切な誰かのことを想うきっかけをくれそうなバッグをメインバッグに忍ばせて。

バンブータンブラー(本体にバンブー素材を使用)¥1,980、シリコーンストロー3本セット¥1,320、シリコーンストローコネクター¥770 © 2022 Peanuts
自然素材の竹を使用することで、合成樹脂の使用量を減らした環境にも優しいバンブータンブラー。軽くて割れにくく持ち運びにも便利なので、キャンプやピクニックなどのアウトドアシーンで大活躍の予感! シリコーン製のストローやストローコネクターは洗って繰り返し使用できるので、資源の節約にも。

カトラリーセット¥1,760 © 2022 Peanuts
ランチタイムに欠かせない、持ち運びに便利なカトラリーセット。お気に入りのマイカトラリーやマイ箸を持つことで、使い捨てをやめるきっかけにもなるはず。
購入者限定!オリジナルポストカードをプレゼント

店舗限定デザイン

オンラインストア限定デザイン
6月1日(水)から、『PEANUTS』アイテムのみ¥4,400以上購入した先着5,000名(全国合計)に、4枚セットのオリジナルポストカード(非売品)のプレゼントが用意されています。再生紙を使用したサステナブルなポストカードで、店頭と公式オンラインストアの2種類のデザインがあります。どちらも手に入れたくなる可愛さ!
※なくなり次第、終了となります。
※お一人様1点限り。
※公式オンラインストアでは運用が異なります。
※アフタヌーンティー・ティールームでは本キャンペーンは実施していません。
アイテムにあしらわれたメッセージは、年齢や国籍、言語などを問わず、世界中の誰もが心に留めておきたい言葉ばかり。本当に大切なことを思い出させてくれるグッズとともに、今日から楽しくエコ生活を始めましょう♪
TAKE CARE WITH PEANUTS×Afternoon Tea LIVING
https://shop.afternoon-tea.net/shop/e/efeature-takecarewithpeanuts/
共感と気付き。今の私へと導いた、シャネルの言葉【小泉里子 / 未来に続くBOOKリスト vol.8】
あなたの本棚には、これからの人生で何度も読み返したい本が何冊ありますか? モデル 小泉里子さんの連載エッセイ「未来に続くBOOKリスト」。読書好きの里子さんが、出合ってきた本のなかから“ずっと本棚に置いておきたい本”をセレクトしてご紹介します。
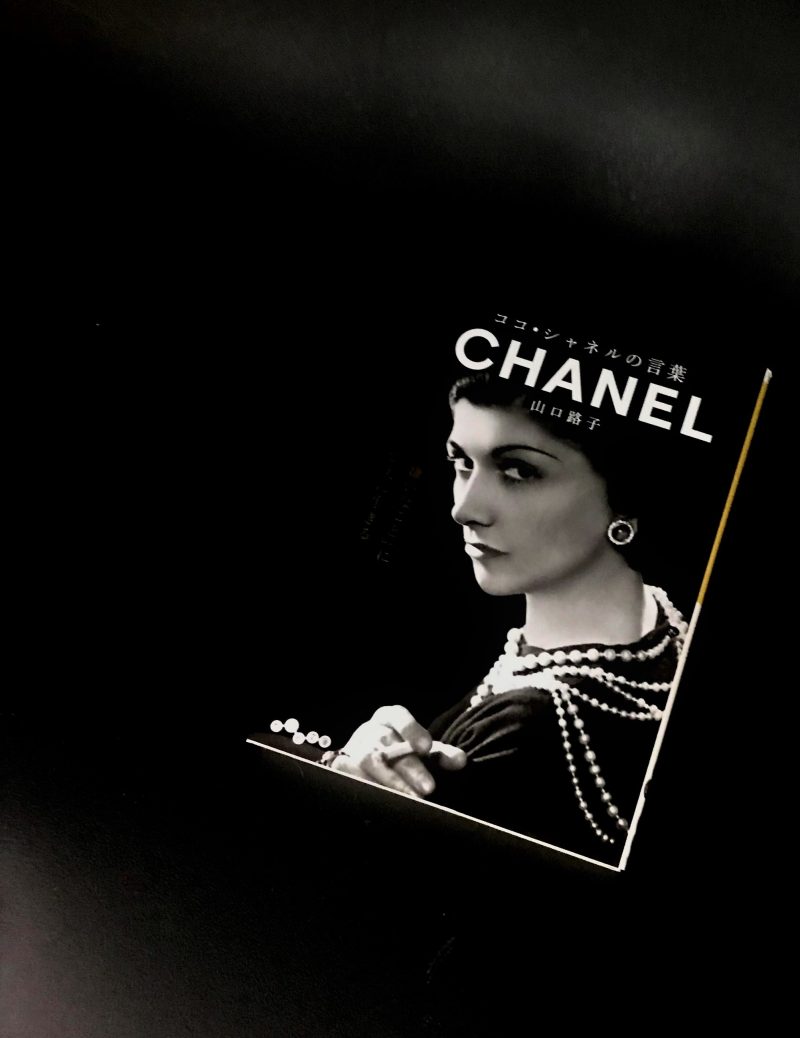
BOOK LIST_08
『ココ・シャネルの言葉』
ジャンル=エッセイ 山口路子 著/だいわ文庫(大和書房)
シャネルのバッグを持つことが憧れでした。それは今も変わらずに存在する憧れ。
こんなにも長く女性の憧れであり続けるブランドであるということ。その理由は、この本のなかにたくさん詰まっていました。
「私はモードではなく、スタイルを作り出したのです」という彼女の言葉。ガブリエル・シャネルが作り出したスタイルは、発表した当初、あの時代においては、何とも風変りで“へんてこりん”と思われてしまうようなものだったのかもしれないけれど、徐々に彼女の作り出すスタイルに世界中の女性が引き込まれ魅了されていったのはご存じのとおり。それは、今私たちが生きてる時代も同じで、彼女のスタイルはずっと生き続けています。
シャネルに関する本は数多く出版されていて、大好きで何冊も読みましたが、なかでも何度も読み返しているのがこの一冊です。言葉集なので、パッと開いたところを読んで、その都度シャネルの言葉に励まされたり、気付きをもらったり。シャネルは生涯独身で、恋多き女性だったものの一度も結婚には至らなかったのですが、これだけの成功を収めたパワーのほとんどすべては仕事に注がれていたのかな・・・と勝手に想像してしまいました。
本のなかで見つけた「強い男でなければ私と一緒に暮らすのはとても難しい。そしてその人が私よりも強ければ、私がその人と暮らすことは不可能なのだ」ーーこの言葉に私は異常に反応してしまいました。何度も読んでいる本なのに、そのときの私にものすごく響いたのです。
それは、自分の矛盾に気付いたという気分。思わず「そうなのー!」と叫んでしまいました。
男の人に頼るというのは、強い女の一番むず痒いところ。本当の本当、心の奥底では実は頼って生きてみたいけれど、それ以上に仕事が大好きで、どうしても譲れないものが出てきてしまう、そして自分でも時にコントロールできなくなる矛盾。そんな苦しみがシャネルもあったのかと思うと、お茶して語り合ってみたいとめちゃくちゃ思ってしまいました(笑)。
5年前、私自身がそんな矛盾で悩んでいたとき、シャネルのこの一節を読んで、もはや結婚は望まず、一人の人生を歩んでいくか、なんて思ってみたりもして。再婚して子供も欲しいけれど、男性を潰してしまうほどの自分の強さ、でも強い男性がいいと思っている自分もいて、でも自分より強いと嫌で・・・。あ~、こりゃややこしい女だわ~と思ったのですが、私にはシャネルほどの功績はなかった・・・とお門違いとすぐに気付きました(笑)。
気付いた私は今、主人に頼り息子も生まれ、今までとはまったく違う人生を送っています。仕事への気持ちも180 度変わりました。それが良いのか悪いのか、その答えは私のなかにあります。
私は、私よりも強い男の人と出会い、ともに人生を送ることにしました。そんな答えを教えてくれたのは、ガブリエル・シャネルなのです。
『ココ・シャネルの言葉』(ここ・しゃねるのことば)
かつてないスタイルを生み出し、世界中の女性たちを熱狂させ、今もなお多くの人を魅了し続けているブランド、シャネル。ココ・シャネルが残した数々の言葉を、美、恋愛、ファッション、仕事、人生の5つのパートに分けて紹介し、その言葉に託された想いや秘められた意味を解き明かした一冊。

Profile
小泉里子(こいずみさとこ)
15 歳でモデルデビュー。数々のファッション誌で表紙モデルを務め、絶大な人気を誇り、広告やテレビ番組でも活躍。着こなすファッションはもちろん、ナチュラルでポジティブな生き方が同世代の熱い支持を得ている。2021年2月には第1子となる男児を出産し、同5月より生活の拠点をドバイに移す。ドバイでの生活や子育てにもさらに注目が集まっている。仕事、プライベート、ドバイでの生活を綴った著書『トップモデルと呼ばれたその後に』(小学館)も好評。
http://tencarat-plume.jp/
Instagram @satokokoizum1
着る服で元気になる!アッタミカの色と柄の魔法
何だか体や心が疲れている朝。クローゼットのなかから、少しでも気分が上がる服を探してみるーー。着るだけで、自分に自信を持てたり、ハッピーな気持ちになれたり。誰にでもそんな服があると思うし、そんなパワーが宿った服ともっと出合いたいですよね。今回ご紹介する「attamica(アッタミカ)」は、そう、まさに“元気が出る服”なのです。
職人ワザが作り出す、アートのような服
![]()
「アッタミカ」は今春から本格的にスタートした、小さなアトリエから発信されるブランドです。サステナブルなモノヅクリに取り組むRICCI EVERYDAYのファブリックをメインに使用し、そこからの製造工程、型紙、裁断、縫製はすべて日本で行っています。

リボンフラワードレス(ブルーxオレンジxチョコレート) ¥35,200
メイド・イン・ジャパンにこだわる背景には「日本人の器用さ、まじめさ、正確さなどから生まれる高い日本の技術を後世にきちんと伝承していきたい」という想いがあるそう。高い技術を誇る日本の職人さんは、高齢化が進み、また業界的にも海外生産が主流になっていることもあり、職人さんの数も工場も少なくなっている現状があるのです。

ダブルフラワー ドレス(イエローxピンクxグリーン)¥33,000
目が覚めるような色使い、そして独特の柄。この美しいプリントを主役にした服づくりには、パターンのどの部分をメインに選ぶかのセンスも大切ですし、何よりもパーツとパーツの柄合わせがキモ。それこそ、職人さんの経験と器用さが必須。仕上がったドレスは、まるでアート作品のように360度美しいのです!
自分だけでなく、周りの人も楽しく
![]()
ブランドのメインアイテムは、プリントの魅力を最大限に活かしたドレスたち。ボディラインを拾わず、さり気なくカバーしてくれるシルエットは、着る人の体型を問わず、エイジレスで、シーンも選びません。
色も柄もとにかく素敵で、着ている自分自身だけでなく、着こなしているあなたを目にした人も明るい気分になりそうなパワーを持っています。

ダブルフラワー ドレス(フーシャピンク)¥33,000
ワックスプリントの生地は、ノーアイロンでOK。シワが目立ちにくく、インナーの透けや響きも気にならなくてラクチン! それでいて、きちんと見えも叶います。

リボンフラワー ドレス(ターコイズブルーxイエローオーカー) ¥35,200
ブランド名の「アッタミカ」はイタリア語で女友達を意味する「amica (アミカ)」 からインスパイアされた言葉で、「いつも寄り添ってくれる明るい女友達のような服」という気持ちが込められているのだとか。
一枚ずつ丁寧につくられているから、大量生産はできません。オンラインショップでは、SOLD OUTの文字が出てしまうことも多いのですが、次はどんなアイテムが登場するのかな・・・と楽しみながら頻繁に覗いてみて。タイミングよく「これは、私のドレスだ!」と一目ぼれする一点に出合えることを期待しましょう!
attamica
https://attamica.com/
自然との遊びは想定外の連続だから楽しい【現代美術家 山本愛子の衣食住遊学】
いつも元気で幸せそうなひとは、自分の周りに“楽しいこと”を育てる種をまいています。そんな魅力的な方にHummingなライフスタイルのトピックスを伺うシリーズ記事「わたしの衣食住遊学」。今回は主に染色技術を用いて創作活動を行う現代美術家、山本愛子さんに教えていただきました。
自然と隣り合わせの生活で、心も身体ものびやかに

『あわいのはた』-2021年

『生々流転』-2019年
自然素材や廃材を使い、ものの持つ土着性や記憶の在り処をテーマとした作品を制作している山本さん。海、山、川、花や緑など、昔ながらの豊かな自然環境に恵まれた神奈川県横須賀市を拠点に活動し、自らが畑で育てた植物や生活圏に生息する野草から染料を生成することにも注力しています。

『BORO – Blues #2』-2019年
山本さんはインドネシアや中国など、アジア各国の地域で滞在制作を経験。各国の染色技術に触れるうちにどこでも同じように染まる化学染料よりも、その土地にしかない草木で染める文化に刺激されたうえ、自然豊かな土地に身を置いたことで草木染への興味、関心が芽生えたそう。
「衣」
草木で自分の衣服を染める

桜の枝で染めた服。
作品制作などで草木染をよく使い、余った染料で自分の服を染めて楽しんでいます。染料に使用する草木は、自分で育てたり、採取したり、あるいは剪定した枝葉を知人からいただいたりと、その土地の風景やいただいた人の顔がみえるものをよく使っています。自分の服が、そういった思い出のある草木に染まっていくのはシンプルに心地いいです。着るたびに「これは近所の方にもらった梅の枝だったな」とか「2年前に自分で育てた藍の葉だな」とかファッションと記憶が結びついてくるんです。この感覚は、染色をしている身として、貴重で独特な体験なのかもしれないなと思います。

また、草木染の服はお薬のような存在でもあります。草木には抗菌効果や保温効果など、それぞれに効能があります。古来、薬草などを体内に取り入れて身を守ることを「内服」、体にまとって身を守ることを「外服」と考えられていたそうです。草木染の衣服はまさに「外服薬」。視覚的に楽しむだけではなく、体をケアしてくれる優れものです。
「食」
私の元気のモトは自家製野菜!

コロナ禍のステイホームをきっかけに家庭菜園をはじめました。固定種を仕入れて、ナス、トマト、じゃがいも、たまねぎ、オクラ、ピーマン、かぼちゃ、大豆、ゴーヤ、大根、ねぎ、レタス・・・欲張ってたくさんチャレンジしています。といっても、ほとんど手をかけず、種をまいたら基本的には放ったらかしです。無肥料無農薬の自然栽培を行っています。自力で育った野菜たちは、大小さまざま、個性的なカタチで愛おしく、食べるといつも元気になります。朝ご飯には、庭のレタスをちぎって、オリーブと塩をふってワイルドに食しています(笑)。
調理の際に出た野菜くずはコンポスターに入れて堆肥化。自然からの生命を得た素材が持つ循環性や土着性を考える作品制作と同じように、日々の暮らしのなかでも“循環”を意識したいと思っています。
「住」
DIYで暮らしやすい空間を探求中

プランターを制作中。仲間と一緒に和気あいあいと作業しています!
パートナーと一緒にDIYをしながら、常にいじりながら暮らしやすさを模索し続けています。ゆっくりお茶ができる場所が欲しくなってウッドデッキを自作したり、作品制作に使う道具の収納に困ったらロフトを自作したり。リビングのダイニングテーブルも、「あと5cmくらい低いほうがいいね」という話になり自分たちで作ったり。
何となく合いそうなものを買い集めてきても、ちょっとだけ合わないと気になってしまうタイプなので、欲しいと思ったものをその場所に合わせて作るときちんと空間に収まるし、愛着も湧き、暮らしやすさにつながっていくような気がしています。
「遊」
“自然”との遊びはライフワークでもある

子供たちと一緒に藍染に使用する藍の葉を採取。
自宅に友達を呼んで、庭でBBQをしたりお茶をする会を月1くらいで行っています。自然の中で、ただ一緒にご飯を食べておしゃべりをして、周辺を散歩するだけという遊びの時間。庭で食事をして山を歩く、というのが好きです。食事をしていると食の話題になりますし、自然に囲まれた場所を歩いていると生き物や植物の話題になることが多く、「人間」以外の話題が自然と湧き出てくる感じが楽しいです。
人間関係の話や仕事の話が嫌いというわけではありませんが、現実社会もネットの世界も、人間中心の話題があまりにも多すぎるように感じます。だからこそ、自然が相手の遊び時間を作るのは大切だなと感じます。
-800x600.jpg)
藍染ワークショップの様子。自然豊かな場所で遊びながら染色を行います。
庭の目の前が小道になっているので、誰かが犬の散歩やハイキングでよく前を通ります。そういう方たちと、たわいもないおしゃべりをするときも、たいてい自然の話です。「あそこの山でふきのとうが出たから食べられるよ」とか「あっちでホタルが見えるよ」とか、「彼岸花がたくさん咲いたから見にいこうよ」とか。自然の中で生きているひとたちは遊び上手、誘い上手だなぁと思います。老若男女だれでも、ホタルが光っているのを見たいと願うはず、と思うのです。
人間にはコントロールできない“自然相手の遊び”は、みんなが楽しめる遊びが生まれ、同時に「これ以上進むと道が崩れて危険だ」「これをしたら川が汚れてホタルがいなくなっちゃうからやめようね」といった、人間が踏み込んではいけないボーダーラインも見えてきます。遊びが教えてくれることは底知れないです。
「学」
植物を研究して、私たちを取り囲む環境を意識する

藍染の研究。植物の品種や生育環境によって多様な表現を生みます。
いま、「植物にまつわる創造力」に興味があります。草木染の衣服の「外服」「内服」の話にも関わるのですが、人間が植物の効能を服用するという意味では、染色や薬学、食や農業には、多くの接点があると感じます。植物は、外敵や周囲の環境から身を守るために自ら効能を生み出しているため、植物を知ることは、その土地の風土、土着性を読み解くことにつながります。
草木染においても、この土着性は色や技法として現れます。植物をはじめとした自然の力を借りなければ成立しない草木染という行為は、自分の力が及ばないものを意識し、自分以外への創造力を働かせる行為です。この「自分以外への創造力を働かせる」というのは自然との遊びの話のように、人間中心的な現代において、とても大切な行為なのではないかと感じています。

染料として使用するヤシ科のビンロウの種子を乾燥した檳榔子(びんろうじ)は漢方の生薬に用いられています。
今年は「植物にまつわる創造力」をテーマに、北海道から奄美大島まで、染織工房、農家さん、植物博士を訪ねてリサーチの旅をしようと考えています。そして、リサーチを経て何かアウトプットできるように計画中です。それがアート作品になるのか、ワークショップになるのか、はたまた一冊の本になるのかは、まだ自分でも決めていません。リサーチをしながら、こういうカタチに残したいと思えるものを探っていこうと思っています。
目まぐるしい生活のなかでは見逃しがちな自然の美しさやかすかな変化・・・。山本さんの作品には繊細さと力強さをあわせ持つ植物、そして自然とのつながりを感じ、自分自身の生活と向き合うきっかけを得られるのではないでしょうか。
6月からは山本さんがリサーチの旅での体験を中心に、日々の発見をレポートする連載がスタート。「ここに行ってみるといいよ」などおすすめスポット情報も随時募集中だそうです。どんな出会いが待っているのか、乞うご期待!
自分でみつける。この場所で生きていく理由【山口乃々華 / コトノハ日和 vol.04】
言葉があるから伝えられること、伝わること。そこから広がっていく思考、癒し、つながり、希望、愛情・・・深くて力強いもの。女優 山口乃々華が、心に舞い落ちてきた“コトノハ(言葉)”を拾い集めて、じっくりと見つめ、ゆっくりと味わい、思いのままに綴っていく連載。さあ、一緒に元気になりましょう。
好きな場所をみつけて生きていく

今年のGW、皆さまいかがお過ごしでしたか? 三年ぶりに規制のないGW。私は両親と共に母の実家に行きました。ゆっくりと数日間を過ごせたのは、とっても久しぶりで。うーんと羽を伸ばし、そこでの時間を満喫してきました。
朝方に聴こえてくるのは、鳥たちの声。
あぁそうだったなぁって、記憶がよみがえった。
私がまだ小学生で、もしこれが夏休みの朝だったら、飛び起きて、朝ごはんを急いで食べて、外で汗だくになりながら遊んでいたけれど。今の私はとにかく眠くて、たまらなかった。
しかし変わらずに心地の良い朝。さぁ、ゆっくり休んでいいですよ。と神から許されたような気分になりました。思う存分二度寝をして、飽きたら起き上がるのです。
それからリビングに行けば、家族の誰かしらが起きていて、「おはよう〜」と言いながら、それぞれの寝癖をチェック。見事な大爆発。
そこにある当たり前な日常に包まれるのは、とても心地がいい。私、そんなに疲れているわけでも、凹んでるわけでもないのだけれど、癒されました。
そんな数日を過ごした帰り道は「あー! 頑張らなきゃな」と思う。しっかり遊んだし。気持ちをシャキッとするスイッチをオンにして取り戻さないといけない。東京はいつのまにか、静かにじっくり沼に足を取られるような場所だということを、私はまだ忘れてはいけない。
そんな気持ちにさせる東京というものは、私を知らぬ間に”夢中”で埋め尽くしてくれている。そんなパワーがある。だから頑張れているのかもしれない。
強くて眩しい。
強くて眩しいから私はここ東京が”好き”なんだと、少し離れて分かった。
いろんな人がいて、いろんな生き方がある。
ここで生きるのが好きな私を、この場所を選んでいるのは私自身なんだということを、あらためて思い出させてくれました。すべてを、もう一度愛さないとなぁ、なんて思うGWでした。
銀色夏生さんの『すみわたる夜空のような』という詩集のなかに「この中で」という詩があります。
「この中で」
この中で
好きな場所を
ぐるっとみわたしてみつけるあのすみ
あたたかく沈みこんでるような
静かに落ち着く場所いつも
今いるこの中で
目の前のこの中で
好きな場所をみつけて
生きていくこの中だったらここ
とここじゃないとはもう言わない
(銀色夏生 『詩集 すみわたる夜空のような』/角川文庫より)
この詩集を読んでいると、古いアルバムをめくっているような気持ちになった。それが、私のアルバムなのか、違う誰かのものなのかはわからないけれど、懐かしくて、ちょっと心の古傷が痛む。
一見、この詩で書かれていることと、私が抱いた“今いる場所”への想いは異なっているようだけれど、でも私なりの解釈はしっかり重なっている。
「この中で」の詩は、「好きな場所をみつけて生きていく」というのがお気に入り。
自分の好きが、「この中で」味方になる。
今を見つめて、ここじゃないなんて、思うことなく、この場所を選んで、ここにいる私。
だから、”ここ”で、私は、私らしく生きていきたい。

Profile
山口乃々華(やまぐちののか)
2014年からE-girls主演のオムニバスドラマ「恋文日和」第7話にて主演を務め女優業をスタート。映画『イタズラなKiss THE MOVIE』シリーズ、ドラマ・映画『HiGH & LOW』シリーズほか、2020年には『私がモテてどうすんだ』のヒロイン役など、数々の作品に出演。 2020年末までE-girlsとしての活動を経て、2021年より女優業として本格的に活動を開始。2021年3月、初のミュージカル『INTERVIEW~お願い、誰か助けて~』、同8月にはミュージカル『ジェイミー』、2022年3~4月はミュージカル『あなたの初恋探します』でヒロインを演じた。ドラマは現在「ビッ友×戦士 キラメキパワーズ」(テレビ東京系)に出演中。書籍『ののペディア 心の記憶』(幻冬舎文庫)も好評で、文章を書くことも好き。2022年7月、舞台『オッドタクシー』への出演が決定。
https://www.ldh.co.jp/management/yamaguchi_n
Instagram @yamaguchi_nonoka_official
アヴェダのヘアケアで、夏の終わりに髪を老けさせない!
肌や体に良いもの、使い心地が良いもの、気分が上がるもの・・・コスメや美容ツールを上手に取り入れて、Hummingな毎日を送りたい。美容ライター 荒木奈々さんがおすすめをご紹介します。
頭皮ケア&補強ケアがポイント。髪の雰囲気チェンジ計画

「どうしてこんなに髪がパサパサでゴワゴワになっちゃたの?」と母親にいわれてハッとしたことがあります。もともとクセ毛なものの、そういえば髪にもっと艶があったし、サラサラだったはず・・・。年齢を語るパーツといえば、手元や首。いえいえ、髪だって顕著だと思うのです。自分では後ろ髪が見えないので、そうやって指摘され、ようやく気合いを入れてお手入れするように。また、髪は夏の間に年を取るといいますから、今からがヘアケアの強化シーズン。年齢は関係なく、健やかな髪をキープするには夏のヘアケアが重要です。まずはAVEDAのアイテムでお手入れの仕切り直しを!
My select 01:頭皮ケアにパドル ブラシは必携

パドル ブラシ ¥4,070/アヴェダ
適当に乾かしてオイルをつければさまになる感じのヘアスタイルを続けていたので、ブラッシングをする機会が極端に減っていたのです。でも髪の専門家にヒアリングするたびに「ブラッシングが大切である」と諭されるし、そういえば艶ありグレーヘアの祖母はいつもブラッシングしていたことを思い出して、これはやらなきゃ!と最初に手にしたのが、アヴェダの「パドル ブラシ」。ここでブラッシングの心地よさにはまり、今ではさまざまな種類のブラシをコレクション(笑)。
ブラッシングは髪をとかす、からまりをほぐすだけじゃない! いろいろな効能を教えてくれたのがこの「パドル ブラシ」です。広い面が特徴で、頭皮に心地いい刺激を与えてくれるスカルプケアブラシのロングセラー。こだわりのひとつが弾力性で、頭皮に押し付けるとプシューと穴から空気が抜け、ポンポンとたたいたり、グリグリしたりする際、気持ちいいマッサージができるのです。ブランドおすすめのブラッシングによるスカルプケアは、縦、横、全体の面を使っての5ステップ。お手入れ後は頭皮のつまりがほぐれるようで血行が良くなり、すっきりします。
肌はマッサージしすぎると負担になってだめ、筋肉に沿ってなどいろいろな制約ごとがありますが、頭皮はそこまでナイーブではないそうで、マッサージをして血行を促進することが、健やかな髪を育むために重要なんだとか。美容機器のヘッドスパも気持ちいいですが、ブラシによるスカルプケアはいつでもどこでもできて便利です。私は頭頂部にあるツボ、百会(ひゃくえ)あたりが疲れるとガチガチに固くなるで、イタ気持ちいいくらいの圧をかけるようにして念入りにほぐしています。ネトフリを見ながらも、ブラシでグリグリ。
もちろん「パドル ブラシ」は通常のブラシとしても優秀。ピンの並びは縦一列、横は互い違いに配列されているので、もつれやからまりを無理なくほどくことができます。適度にテンションがかかるように計算された長い柄は、ストレートブローを叶えるための策。1本持っておくと本当に便利です。髪のほこりや汚れをスムーズに落とすために、シャンプー前もこちらでブラッシングを。
My select 02:細毛・抜け毛悩みには専用のエッセンス

インヴァディ アドバンス ヘア&スカルプ エッセンス 150ml ¥9,020/アヴェダ
髪は1日平均100本ほど抜けるといわれます。でも洗髪後にごそっと抜けたりすると、なんだか不安になりますよね。アヴェダ調べによると薄毛は世界共通のお悩みだそうで、日本でも30代の5人に1人が薄毛・抜け毛のトラブルを抱えている(5NBBAサロンユーザー調査2016年度版)そうですが、時を経てそのお悩み人口は拡大しているのでは? そもそも男女ともに20歳後半から髪は細くなり、女性はホルモンの分泌が減る40歳前後から、髪の本数が少なくなるとも。またダイエットなどによる血行不良や栄養不足、日々のストレスも髪の生成と成長を妨げる要因なので、大人特有の悩みというわけでもなく・・・。
アヴェダの不動のアイテムが、インヴァディ アドバンスシリーズの「ヘア&スカルプ エッセンス」。この製品の人気の背景には、「髪が抜けやすい」「髪が細くなった」「艶がない」「前髪が少なくなった」「ボリューム不足」「分け目が目立つようになった」などの声が多いことが伺えます。
インヴァディ アドバンスシリーズは、ジンセンやオーガニック ターメリックからなるアーユルヴェーダ由来の薬草ブレンド、頭皮コンディショニング成分複合体に加え、クレアチン、アデノシンリン酸、米国特許取得の独自成分カルニチンを配合。さらに「ヘア&スカルプ エッセンス」には、ストレス因子から髪を守るタンジェリンピール(マンダリンオレンジ果皮エキス)など10種の成分が追加されています。
1日1回、濡れた髪、乾いた髪、どちらにも使うことができ、頭皮と髪の根元に約16プッシュをひたひたにスプレーし、指の腹で揉み込むようにマッサージしながら塗布します。もちろん「パドル ブラシ」を使ってのマッサージでもOK。ミント×ローズマリーのフレッシュなアロマや、頭皮が活性化されるようなジンジンとする感覚もクセになるはず。
頭皮の理想の柔らかさは桃程度とよくいわれますけど、スカルプエッセンス+マッサージによって、巡りが良くなると硬さはしだいに変わってきます。ちなみに頭頂部にトラブルが多いのは体の中でも末端のため、血液からの栄養も届きにくいとか、重力によって髪が引っ張られるとかいろいろ要因があるもよう。
エッセンスを使い続けることで頭皮の状態を健やかに、次にはえる髪のハリ・ボリュームアップが期待できそうです。頭皮マッサージを習慣にすると、顔もシャープに一石二鳥!
My select 03:刺激を感じやすい日はロングセラーの定番シャンプー

シャンピュア ナーチュアリング シャンプー 250ml ¥2,420/アヴェダ
今でこそプロフェッショナルなシャンプーが百貨店やオンラインで手に入るようになりましたが、それ以前のシャンプーは家族で使うトイレタリー品。ですから世界中のヘアサロンやスパのプロフェッショナルに信頼されているブランド、アヴェダが手軽に購入できるようになったのは画期的だったに違いなく・・・。私の初めてアヴェダはこのシャンピュアのシャンプーでした。
紫外線を浴びすぎたり、ストレスを感じていたり、寝不足だったりが原因!? 同じカラーリング剤を使っているのに、しみる日とまったくしみない日があります。肌同様、頭皮も日によって調子が変わると思うのですが、デリケートな地肌の日は、アヴェダのロングセラー、シャンピュアのシャンプーに帰ります。アヴェダには500種類以上の製品がありますが、シャンピュアシリーズは、オーガニック ラベンダーやオーガニック イランイランなど25種類の花と植物のエッセンスを使用したアロマがとても華やかで、30年間愛されてきたブランドのザ・名品。
そういえばシャンプーでは髪の汚れを落とすだけでなく、地肌をしっかり洗うことが大事といわれます。しかも芳醇な香りに包まれるシャンプーだと、毎日の当たり前のケアも格別に丁寧になります。
そのシャンピュアのシャンプーですが、3年前に刷新。自然界由来成分を95%以上&シリコンフリー処方となっています。
1978年アメリカで誕生したヘアケアブランド、アヴェダは当初よりヴィーガンマインドが根付いていましたが、使用している900種類以上の成分すべての見直しに着手。そして3年をかけて、昨年スキンケアからヘアケアまでの全商品が100%ヴィーガン処方となりました。「製品づくりから社会還元まですべての活動を通して、命あふれるわたしたちの地球を大切に守り続けること」がアヴェダのミッション。1989年に気候変動や水不足など持続可能性を脅かす問題に関する企業の取り組みを推進する非営利団体(アヴェダ資料より)のセリーズ原則に賛同し、署名した初の民間企業でもあります。その後も独自のサステナ基準をいくつも立ててきましたが、100%風力発電で製品を製造するなど、化粧品会社として初めての取り組みがアヴェダにはいくつもあります。
My select 04:ダメージヘアにはマスク。生まれ変わったかのような艶髪に

ボタニカル リペア インテンシブ マスク ライト 150ml ¥5,280/アヴェダ
元来細く、乾燥ぎみ。枝毛ができやすく、ダメージを抱えやすいことはわかっています。でもやめられない、やめたくないカラーリング。しかも昨年はブリーチもしたので、夏の間は紫外線による退色も気になります。もちろんダメージケア向けのトリートメントは数本常備。その1本がアヴェダのダメージケアシリーズ、ボタニカルリペアの「インテンシブ マスク ライト」です。
100%ヴィーガンということは、ミツロウ、ハチミツ、絹、ケラチン、グリセリン、植物性ではないスクワレン、ラノリン、コラーゲン、カルミンなどを排除。それってとても企業努力のいること。それでいて高機能なアヴェダのボタニカル リペアは、6年以上のボタニカル成分研究のもと、ヴィーガンで98%自然界由来成分が採用されています。髪は一度ダメージを受けるとそのままのびていくことになりますが、このマスクはその場の補修だけでなく、今後のための補強ケアのアプローチも。
髪の内部のコルテックス、表面のキューティクル、さらに保護膜のような働きを持つFレイヤーの3層に着目し、低分子の植物由来成分「ボタニカル ボンド テクノロジー」によって、髪の奥に成分を届け、内と外から補強・補修。トリートメント・マスクと多数用意されていますが、ライトの軽い、シルクのような仕上がりが好み。1回の使用で、艶のある髪に導いてくれます。カラーセーフ処方で、髪の色褪せも防止。
UVヘアケアも必須になる時期ではありますが、実は髪や頭皮が潤いで満たされていると、それだけで紫外線ダメージを寄せつけないことにもなるそうですよ。ですからまずは健やかな状態に導くことが、夏の髪に年を取らせない基本。覚えておいて。
アヴェダ
www.aveda.jp
自分を整え、パワーを引き出す3つの源泉【アーティスト 佐々木香菜子のお気に入りLIST】
その道のプロに聞く、今の自分に必要なお気に入りアイテム。今回は、アーティスト 佐々木香菜子さんに3つの大切なアイテムを見せていただきました。
クリエイティビティを支える、意外なモノ
アーティスト、イラストレーターとして商品パッケージからアート作品、ライブペインティングなど多岐にわたり活躍を続ける佐々木香菜子さん。今年4月、5月は東京、韓国で、そして6月には故郷である仙台で今までにない規模の個展が開催されるなど、アート活動に注力中の佐々木さんが愛用しているものとは? 彼女の美容、食への探求心にも注目です。
思わず「セ・ボン 美味しい♪」を連発!通いたくなる、パリ気分のオーガニックカフェレストラン【渡辺知夏子のエシカルスポットNavi. vol.07】
普段の何気ない暮らしのなかで、サステナブルなアクションが出来たら素敵だと思いませんか? エシカルなライフスタイルを提案しているレストランやショップを、自身もウェルビーイングな生活を心掛けているというモデル渡辺知夏子さんがナビゲート。今回は、南青山のファストカジュアルレストラン『CITRON Aoyama(シトロン アオヤマ)』をご紹介します。
フレンチサラダバー「CITRON Aoyama」

東京メトロ銀座線・外苑前駅のすぐ近く。ラグジュアリーホテルや有名ショップ、一流企業が立ち並ぶ通りの一角に、カジュアルなカフェレストラン「CITRON Aoyama(シトロン 青山)」はあります。
さまざまな種類の味わい豊かなフランス料理と、国産で最高級の有機栽培野菜を材料にしたテイラーメイドのサラダが特徴で、フランスの家庭料理をヒントに、ヘルシーでバランスの取れた彩り鮮やかなメニューを提供。オーガニックで健康的なベジタリアン料理の新しいスタイルを目指しています。

メニューにディスプレイされた大量のレモン!
「CITRON」とはフランス語で「レモン」のこと。その言葉どおり、店内には数々のレモンが飾られています。ちなみに名前の由来となったレモンは、フランス人オーナーのジョナサン・ベルギッグ氏が飼っていた愛犬、フレンチブルドッグの「レイモンド」の愛称なのだとか。

「僕がベジタリアンになったきっかけも、レイモンドが関係しています。ある日、大好きなレイモンドと子豚の姿が瓜二つであることに気づき、豚肉を食べられなくなってしまったんだ。
さらに肉や魚を食べる食生活に疑問を持つようになってしまって。だって僕はすべての動物を愛しているから! それでベジタリアンになることを決意したんだ」

店名の由来になったフレブル、レイモンドのフィギュア。看板犬としてお店の人気者でしたが、3年前に虹の橋を渡ってしまったのだそう。現在は新しく家族を2匹お迎え。新たな看板犬としてお店に立つ日が来るかも?
そして2013年から日本での生活をスタートさせると、外出先の食事で悩まされることに。
「どの店に行っても、料理の中には必ず肉や魚が入っているんだよ。日本でベジタリアンとして生活を送ることの難しさを実感したんだ。欧米はもちろん、他外国では庶民的なレストランでもベジタリアン向けの食事が必ず用意されているけれど、この国は違ったんです」

常連客の間で人気の高いキッシュも、肉や魚は不使用。種類は2週間ごとに入れ替わるので、いろんな味を楽しむことができます。
今でこそ日本人でもベジタリアン人口は増えているものの、10年前といえばかなり少数派。当時は肉や魚を扱わないレストランは、数えるほどしかなかったのだそう。
「だから自分でお店を開くことにしたんだよ。外苑前駅を選んだのは、外国人居住者が多いという情報を耳にしたから。彼らのなかには、自分と同じベジタリアンが必ず存在すると思っていたからね。ただ、この前衛的なコンセプトがなかなか受け入れてもらえず、テナント探しはひと苦労だったよ」

愛犬家にうれしい、ペットフレンドリー。
数々の試練を乗り越え、2015年にようやく開店させた『CITRON Aoyama』は、ベジタリアン仲間やクチコミを通して瞬く間に人気店に。
そしてこのレストランでは、地域のNPO活動にも率先して参加しています。レジ付近に設けられた特設スペースにはパンフレットや名刺などが所狭しと置かれており、さまざまな情報を提供。さらに、毎月利益の1%をAFJ※に寄付して、積極的に社会貢献活動を行なっています。

今回の取材で気さくに対応してくださった、オーナーのジョナサン・ベルギッグさん。
※AFJ(Animal Friends Japan)は、新潟を中心に活動するNPO法人。日本各地で引き取り手のない犬や猫を救い、お世話をしながら新しい家族を見つけることに力を注いでいる団体です。
以前から大ファン!見た目も美しくて味も量も大満足

数年前からライトヴィーガン生活を送っている知夏子さん。
「30代になってから体調の変化を気にするようになって、食生活の見直しをするようになりました。自炊したり、外食でも食材を気にしてメニューを選ぶようにしたり。また、ある一定期間は、肉や魚、小麦を極力避けて生活するように。こうすることで、体がリセットされるんです」

以来、都内のベジタリアン専門店やヴィーガンショップに足繁く通うようになったそう。なかでも『CITRON Aoyama』は、お気に入りのレストラン。
「以前からこちらにはよく通っています。サラダがとてもボリューミィで、食べ応え抜群。食材の種類も豊富で、味も『これで肉や魚は不使用?』と思わせるくらいコクや深みがあるんです。

そして、なによりお店の雰囲気がステキ! 店内にはオーナーが選んだインテリアがあちらこちらに飾られていて、細かいところにまでいろんなこだわりが感じられます。とにかく、眺めているだけで楽しい気分に♪」

お店に入るとすぐに目に飛び込んでくるのが、色とりどりの野菜やトッピングがディスプレイされたサラダ・バー。知夏子さんは、常連だけあって慣れた様子でサラダをオーダー。今回はサラダランチを選択しました。

サラダのトッピングは、なんと20種類以上! 有機栽培野菜を中心に旬の食材を取り入れいているため、季節ごとに食材が入れ替わります。

ミックスリーフをベースに、選んだトッピングを乗せてもらい、仕上げにドレッシングをたっぷり注いで完成。ドレッシングは4種類から選べます。

トッピングのセレクトに自信がない人は、おまかせサラダを選択することもできます。こちらはその一例。
なかでも一番人気なのが、右下の「サラダ シトロン」。自家製ドライトマトにキアヌ、木綿豆腐、アボカド、自家製ファラエル、レンズ豆を加えた、華やかな見た目が特徴のサラダ。ドレッシングはフレンチベースに醤油を加えた、パリ-東京ドレッシング。

オーダーを終えたら、プレートを持って2階へ。
コンクリートを基調としたシックな内観のゆとりのある空間が広がっています。席は自分が好きな場所を選ぶシステム。

おまかせサラダ(もしくはオーダーメイドサラダ・トッピングは4点)スープ、パン付き ¥1,380

「大きめのボウルに旬の野菜がたっぷり! これにスープとドリンク、バケットもつくから食べ応えがあります。新鮮な野菜の味と食材を生かしたドレッシングの相性も抜群です」
さらにお店のおすすめ、キッシュも味見させていただきました。

キッシュセット(キッシュ、スープ、サイドサラダ付き)¥1,380 キッシュは、2種類から1点セレクト。
「まるでスポンジケーキのような厚み! 生地がフワッフワだから、ナイフがスッと入って、簡単にカットできますね。お野菜がたっぷり入っているのでボリューム満点だけど、とってもヘルシー。キッシュにセットされるサラダは日替わりで、今日は私の大好きなコールスローでした」

〆にいただくデザートは、人気ナンバーワンのレモンタルトと自家製レモネードを。

レモンタルト(ランチデザートセット価格)¥460、自家製レモネード(ランチドリンクセット価格)¥340
取材時は、オーナーのジョナサンさんがサーブしてくださいました。
「鮮やかなレモンカラーで、見た目からして美味しそう! レモンの風味と甘味のバランスが絶妙で、たまらない一品ですね。ランチを食べた後でも、ペロリといただけそう(笑)。
コールドドリンクには紙ストローを採用しているなど、細かい部分にまで環境に配慮しているところもステキですよね」

美味しい食事を楽しみながら、地球にも社会にもやさしい活動を支援できるこちらのレストラン。興味のある方、ぜひ一度足を運んでみて。
CITRON Aoyama
東京都港区南青山2-27-21 セイリンビル1F/2F
03-6447-2556
http://citron.co.jp/
※Uberでの注文も可能。オンラインショップも展開中。また、2階の店舗はプライベートのセミナーや音楽イベント、誕生日会として使用することもできます。
〈衣装〉ロゴTシャツ¥9,900、黒ウォッシュドデニムシャツ¥19,800、グリーンオーバーダイストレートパンツ¥20,900/以上MICA&DEAL バッグ ¥20,900/VIOLAd’ORO サンダル(CLASS FEVER)¥3,600/Ipanema
SHOP LIST
MICA&DEAL https://mica-deal.com/
Ipanema https://ipanemajapan.com/
VIOLAd’ORO https://violadoro.jp/
5月15日に開催♪テーマは“循環”。
ポップアップイベント「In the Loop」へGO!
2022年5月15日(日)、循環型デザインやサステナビリティをテーマとしたポップアップイベント「In the Loop 」が、東京・渋谷のFabCafe Tokyoにて開催されます。
新しいライフスタイルを体感しながら、“つながり”が生まれる場所

「In the Loop」 は、循環型デザインや持続可能性を追求したアイデア、製品、サービスを創っていくためのポップアップコミュニティ。イベントでは共通の意識や熱意を持つ国内外で活動する人々、クリエイター、スタートアップ、企業などがグッズ販売やワークショップ、フード&ドリンクの提供を通じて、新しい“つながり”を育みます。ここからは今回のイベントで体験できる4つのアクティビティをご紹介!
デザイン性の高いサステナブルグッズが集結!

せっかくお買い物をするなら、今まで通りおしゃれを楽しみながら、地球に優しいものを選んでいきたいーーそんな想いに応える「LAERSTERENN(ラエステレン)」、「Rus Jewelry(ラス)」、「Mikan bags(ミカン)」の3ブランドによるスタイリッシュなサステナブルグッズが集うマーケットを開催。
日本初のワンヴィーガン・エシカルアクセサリーブランドとして2020年にスタートした「LAERSTERENN」は、丈夫なだけでなく、柔軟で軽くて通気性にも優れたパイナップルレザーグッズを販売。2017年にNYでスタートしたジュエリーブランド「Rus Jewelry」ではリサイクルシルバーをアップサイクルしたジュエリー、「Mikan bags」はアンティークの着物生地を使用したバッグを販売します。
物々交換でモノの寿命を延ばす

衣類や雑貨を“交換”という形で循環させる取り組みとして、不要になった服やモノを持ち寄り新しい服やモノと出合う物々交換型イベント、スワップマーケットを実施。物々交換は昔から脈々と受け継がれてきた文化ですが、環境への影響を減らすことができるアイデアとして今改めて注目されています。自分がもらって嬉しいと思う最高のアイテムを持ち寄って、新たなお気に入りとの出合いを楽しみませんか?
会場にはEDWINがジーンズの回収ボックスを設置。ブランドや状態を問わず穿かなくなったジーンズを受け付けています。この機会に「アップサイクル」の取り組みに参加してみて。
キャンドルづくりワークショップ


マインドフルネスアーティストとして活躍中の市川波美さんは、無着色の大豆ワックスを原材料に使用したキャンドル製作を主催。大豆ワックスからつくるキャンドルは、石油を使用していないため環境に優しく、すすや煙も出にくいため身体にも優しいキャンドルです。廃棄予定のドライフラワーや、酸化して使えなくなったコーヒー豆などをキャンドルに入れて、自分だけのキャンドルを作りましょう!
ヴィーガンフードの美味しさを発見!


会場ではバラエティに富んだヴィーガンフードを提供。100%植物性のフードブランド「LOVEG」のシェフ、今井慎治さんが手がけるヴィーガン麻婆豆腐、ヴィーガンチーズブランド「TOKYO VEG LIFE faux-mage」のチーズセット、「Joey’s Donuts」のヴィーガンドーナツが登場。ヴィーガンフードの可能性を感じる個性豊かな食を体験してください。
人にも環境にも優しいサステナブルなグッズやヴィーガンフード、ドリンクなどに興味があっても、探さないとなかなか見つからないと感じている人も多いかもしれません。「In the Loop」を通して、さまざまな取り組みを行うクリエイターや企業と出合いながら、楽しく知っていくことができます。5月28日(土)にはFabCafe Nagoyaでも同イベントを開催(コンテンツ内容は異なります)。関西方面の方はチェックしてみてください!
In the Loop
日時/2022年5月15日(日)11:00-16:00
場所/FabCafe Tokyo(東京都渋谷区道玄坂1-22-7 道玄坂ピア1F)
参加費/入場の際に会場で1ドリンクオーダー制(マイカップ・ボトル、マイ食器、エコバッグ持参を推奨。 スワップマーケット、ワークショップ、フード&ドリンクは別料金となります)
https://fabcafe.com/jp/
“目の前にあるもの”の美しさに気づくチカラ【素敵な二人のタカラモノ拝見】
蚤の市で見つけた掘り出し物、小さい頃から愛用している分身のようなアイテムー-年月を超えて大切にされてきた品々は暮らしに豊かなストーリーを添えてくれます。おしゃれに暮らす素敵な方々に「いつまでも大切にしたいアイテム」を見せていただきました。今回は、現代アートをこよなく愛するお二人の3つの“タカラモノ”をご紹介します。
美しさを見つけ、愛でる喜びを教えてくれた品々
現代アートをこよなく愛し、自宅にはたくさんのアートが飾られていて、アーティストとの親交も深い、ショウゴさんとミナさんご夫婦。ビジネスをいくつも手掛けてきたショウゴさんは「現代アートもビジネスも共通点があります。それは何でもないように見える目の前の環境から、個性や美しさを発見するチカラだと思います」と語ります。そんなお二人に、あえて現代アート以外のタカラモノを見せてもらいました。
ストックホルムから届いたオーガニックコスメブランドの本気
新商品の情報は続々とアップデートされますが、そのなかから気になるものを見つけ出すのはなかなか大変。自分のもの選びの“キーワード”を決めておけば、最初の段階で迷うことはなさそうです。Hummingな暮らしを目指す方ならきっと「オーガニック」は気になるキーワードですよね。今回は、日本に初上陸したオーガニックコスメをご紹介します。
7つのマニフェストを掲げる「マナシ 7」
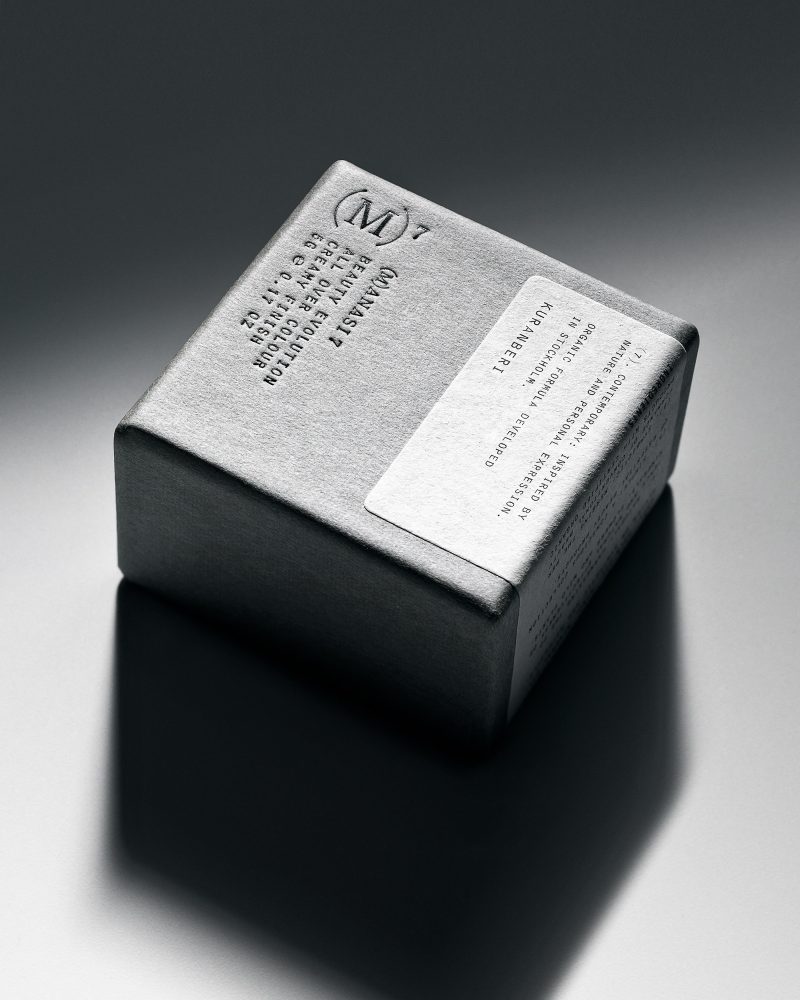
MANASI 7(マナシ 7)というネーミング、ストックホルム発のブランドと聞いて意外と感じますが、「マナシ」はメイクアップアーティストであり、化粧品の開発者、そしてブランドの創業者であるスザンヌ・ペーションのインド名。彼女はインドで生まれで、スウェーデンに養子として迎え入れられたのだそう。
そんな彼女が2018年にストックホルムで創業した「マナシ 7」 は、“エシカルで持続可能な製品の小規模生産にこだわったプレミアムなオーガニックコスメブランド”として現地でも知られた存在。7という数字がブランド名についているのは、7つのマニフェストを掲げているから。どんなマニフェストなのか、このブランドを知るうえでとても重要なので、見てみましょう。
7つのマニフェスト
1:SLOW 水の消費や廃棄など環境へのインパクトを最小限に抑えるために持続可能なペースでの小規模生産を行います。
2:SELECT 美しく健康であり続けるために、成分やコンポジションなど品質において妥協のないセレクトを行います。
3:PURE 自然と調和しながらエシカル調達された持続可能な原料を厳選して使用します。
4:NATURAL 野生植物や天然ミネラルなどクリーンな原料を使用し、豊富な栄養素を含有量の高いレベルで実現します。
5:SIMPLE タイムレスで多目的にカスタマイズして誰もが自由に自分らしさを表現することができるカラーコレクションを展開します。
6:SYMBIOTIC 容器やパッケージにおいても再生可能な素材を開発。成分、容器やパッケージ全て100%生分解性で、自然共生を目指します。
7:CONTEMPORARY 洗練されたカラーパレットで自分らしさ溢れるコンテンポラリーなバランスを引き出します。
ブランドの情熱が伝わってくるマニフェスト。ローンチスタートからうれしいほどのバリエーションがあり、まさに“自由に自分らしさを表現”できそうです。そして原材料の透明性をウェブサイトで公開していることでも、その製品づくりへの本気度が明白。
では、いったいどんなアイテムが届いたのでしょうかー-。豊富なラインナップから、編集部の気になるものをピックアップしました。
気になるアイテム1:万能使いできる「ALL OVER SHINE」

ALL OVER SHINE 全2種 15g 各¥6,930
なめらかなテクスチャーで、口元、頬、目元などあらゆるフェイスゾーンに使えるオールオーバーシャイン。水分を補給しつつ、ベタつかず、潤いとナチュラルな輝きをもたらしてくれます。
使い方はいろいろ。保湿バームあるいはグロスとして唇に。目尻や頬骨など顔のハイポイントにプラスしてハイライターに。ファンデーションとしてスキンエンハンサーと混ぜ合わせて使ったりしても◎。バッグに一つ入れておきたい万能選手です。
気になるアイテム2:確実に気分が上がる「ALL OVER COLOUR」

ALL OVER COLOUR 全16色 5g 各¥6,490
次に注目したいアイテムは、自然然採取の原料を使用したリッチでクリーミィなテクスチャーが魅力のオールオーバーカラー。16色のバリエーションは、どれも試したくなる魅惑のラインナップです。

こちらのビジュアルのカラーはBISQUE。使いやすいヌーディベージュ。
リップ、チーク、アイシャドウとしてポイントメイクに使える優れもの。カスタムシェードのために混ぜ合わせて使用することも可能です。指先につけて、トントントン。自分好みの使い方、テクニックを見つけてください。
気になるアイテム3:4つのシェードが1つになった「CUSTOM EYE AND BROW QUAD」

CUSTOM EYE AND BROW QUAD 6.7g ¥9,130
ワンカラーで使用するよりも、より印象的で洗練された目元を演出してくれる4つのシェードを1つにまとめたコストパフォーマンスの高いアイテム。
認証オーガニックパウダーと植物由来のスクワランをベースにしたプレストパウダーは、肌馴染みの良さも秀逸です。

EARTH AND CLAYというネーミングで、タルクフリーのテクスチャーと厳選されたソフトアイボリー、ほのかなアッシュブラウン、コールドアンダートーンのクラッシュブラウン、そしてブラックに近い深みのあるシェードの4カラーで構成されています。ブランドからの提案は、ソフトアイボリーをベースまたはハイライトとしてほかの3つのシェードで目、眉毛、ラッシュラインをシェーディングして特徴づけて、とのこと。もちろん、使い方は自由です! 自分の思いのままに、楽しんで。
そのほかにも、自然由来の原料を使用したノンオイリーなブロンズライター、認証オーガニックとワイルドクラフテッド原料を使用したストロボライターやシルクグロウパウダーなど、気になるアイムテが目白押しです。
自然界と日本の文化にインスパイアされたというマナシ 7のコレクション。水資源の消費と環境への影響を最小限に抑えながら、自然の恵みを詰め込んだオーガニック製品は、使うたびに私たちの気持ちをポジティブにしてくれるチカラがあります。ぜひ自分らしくカスタマイズして、メイクアップの楽しさを享受しましょう!
MANASI 7
https://www.manasi7.com
※日本ではLIFE&BEAUTY ほか、セレクトショップにて販売中。
GYUTAEさんを幸せに導いたメイクの可能性【気になるあのひとに10の質問】
オリジナルなスタイルを持って生きている素敵なひとに聞く、10のQuestion。心や暮らしの豊かさは、ブレない生き方や考え方が築くもの。内面から輝くひとはどのようなことに目を向け、何を実践しているのかーー心地よく、充実した毎日を生きるためのヒントを探ります。
今回は、YouTubeを中心に活動する美容クリエイター、メイクアップアーティストのGYUTAE(ギュテ)さんにクエスチョン! 10代から全身脱毛症を患い、髪やまつ毛、眉毛など全身の毛が生えないというハンデを負いながら、メイクを通じて発信されるコンプレックスと共に生きる方法は幅広い世代から共感を集めています。
「メイクが自分を好きにさせてくれた」
Q01 メイクを始めたきっかけは?
僕が中学生のころ、東方神起の元メンバー、ジュンスさんのファンでした。彼がソロデビューした際、メイクで大胆にイメチェンした姿を見て「男性でもメイクでこんなに顔が変わるんだ」と衝撃を受けたと同時に、男性がメイクするからこそ醸し出される妖艶な雰囲気に惹き付けられ、メイクに挑戦しました。
Q2 最近熱中して取り組んだことは?
今年3月に初エッセイ『無いならメイクで描けばいい』を出版しました。僕はこだわりが強くて、悪くいうと人に任せられないタイプ(笑)。撮り下ろしの巻頭グラビアは、自分でヘア&メイク、スタイリングを担当しました。表紙は耽美なメイクを施した男性が煌びやかなジュエリーを身に着けることで、僕がジュンスさんを見て感じたように、脳裏に残るような強いヴィジュアルを目指しました。
エッセイでは、脱毛症やいじめなどの辛い経験から学んだこと、そしてメイクの可能性や楽しさを伝える美容クリエイターとしての現在までをせきららに綴っています。過去を振り返るとネガティブな記憶がどうしても強く残りがちですが、周りに助けれられながら今があることも実感しました。だから今は本を出す前よりも、あまり過去に縛られていないように感じます。
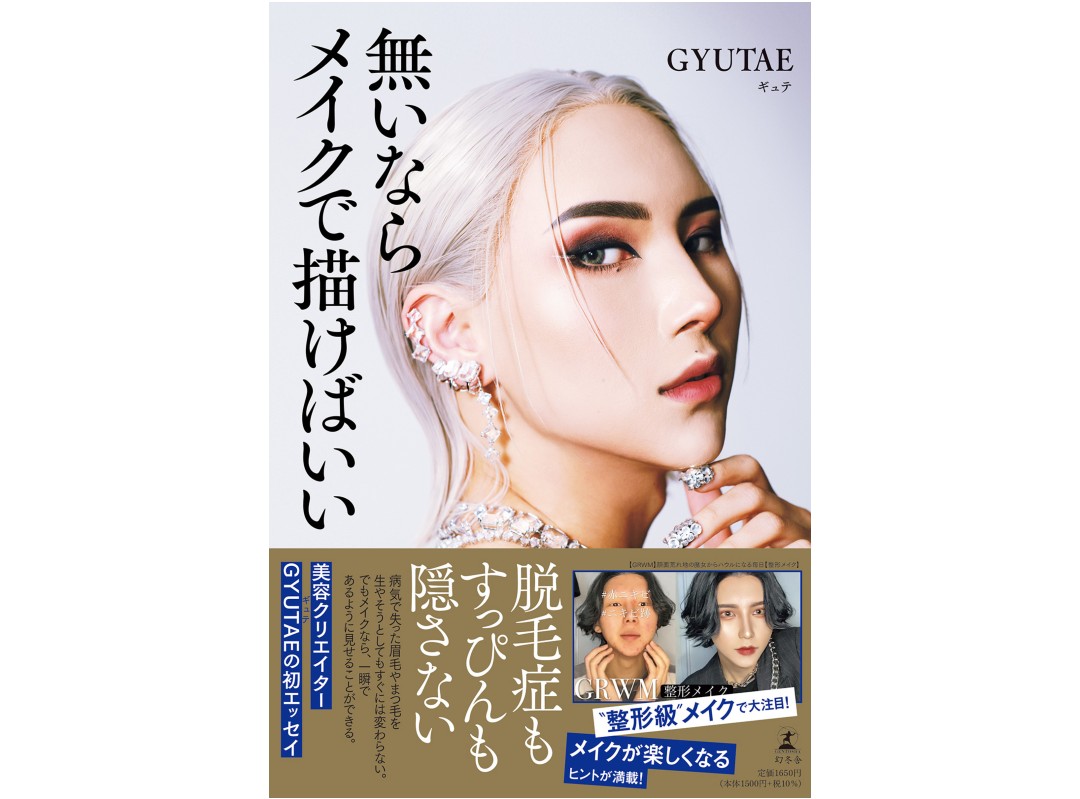
GYUTAEさん初のエッセイ本。『無いならメイクで描けばいい』 GYUTAE(ギュテ)著 /幻冬舎
Q3 今までの人生でターニングポイントになった出来事は?
アパレルショップ「スピンズ(SPINNS)」の広島店で働き始めたことです。スピンズは服装、髪型、髪色、メイクなど何でも自由で、個性豊かなスタッフ揃い。それまではさまざまな感情や規則に縛られて自分らしさを出せずにいたけれど、働き始めてから堂々とメイクをするようになって、自分に似合うメイクも研究。このころから自分のことを好きになりました。

スピンズ時代のGYUTAEさん。
Q4 最近のマイブームは何ですか?
キラキラしたもの! 僕は服装もメイクもすべて、男も女も関係なく自由なものという考え。「男性だから」という概念を覆したくて、あえて大振りのキラキラとした華やかなアイテムを身に着けるのが気に入っています。

キラキラのスワロフスキーネイルがお気に入り。
「マインドや環境が変われば、言葉も人間関係も変わる」
Q5 大切にしている言葉は?
「類は友を呼ぶ」。周囲の人は自分自身を映し出す鏡だと思っています。僕が上京したてのころ、上手くいかないことが多く、周囲に不平不満を漏らしていました。するとそういう話が好きな人が集まってくるんですよね。だからお酒の席でも悪口大会みたいになってしまう(笑)。努力が足りないから成功しないのに、愚痴や悪口を言っている自分が嫌いでもありました。
スピンズ時代を経て、自己否定から自己肯定するようになると、自然と不平不満を漏らすこともなくなり、僕の周りにはハートフルな人たちが集まってきたんです。マインドや環境が変われば、言葉も人間関係も変わります。僕がハッピーなら、周りもハッピー。そんなふうに良い影響が広まっていくとうれしいです。
僕を応援してくださるファンの皆さんのことを、GYUTAE MATE(ギュテメイト)と呼んでいます。Youtubeのメイク動画ではメイクスキルや考え方、悩みなど僕のありのままを発信していて、「類は友を呼ぶ」のとおり、僕と同じような経験をされていたり、何か悩みを抱えている方が多く集まってきます。動画配信後のコメントに励ましの声をいただいたり、逆にSNSを通して僕のもとに集まったお悩み相談にのったり・・・ファンというよりお互いを助け合っている大切な存在。
動画を上げるたびに「なんで眉毛ないの?」といったコメントも増え、嫌われるんじゃないかと反応が怖かったけれど全身脱毛症であることを告白しました。皆さんから温かいコメントをいただいた一方で「病気を売りにしている」というコメントがあったんです。ちょうど仕事でも悲しい出来事があったタイミングと重なって、かなり落ち込みました。それで『聞いてほしい事。僕は脱毛症の人ですか?メイク上手い人ですか?』という動画を投稿。その動画には「ギュテくんの人柄やメイクが好きで観にきています」「“病気だから可哀想だ”と思って観にきたこと一度もありません!」などのコメントをいただいて、ギュテメイトの皆さんの言葉にすごく支えられました。言葉の言い回しや視点を変えるだけでマイナスに見えていたこともプラスに変わる。そんな経験から、言葉をとても大切にしています。
Q6 今、挑戦してみたい“新しいこと”は?
本のタイトル『無いならメイクで描けばいい』のとおり、描くことが得意なので特殊メイクにどんどんチャレンジしたいです。自分の頭のなかにあるメイクアイデアを、より魅力的に表現できるように撮影技術も磨いていきたいと思っています。

GYUTAEさん=眉メイクといわれるほど好評の“眉毛の描き方”動画。徹底研究によるメイクテクニックは必見!
Q7 今、欲しいものは?
大容量のクローゼットが欲しいです。メイクと同じくらいファッションが好きなんです。今はクローゼットやタンスの中に収まっていない洋服がたくさんある状態で、着なくなった服は部屋着としては着られそうだとしばらく保管していたのですが、結局出番なし。先日思い切って整理しました。
ストレス発散方法がお買い物。洋服選びの基準は、スタイルアップするかどうか。「合いそう」では買わず、必ず試着します。コスメにおいても、自分でちゃんと使っていいものを皆さんにご紹介したいので、実際に使って細かくチェックします。
Q8 仕事をするうえで手放せない「三種の神器」を教えてください。
コスメ、スマートフォン、リングライト。僕のメイクは“30時間崩れないメイク”とうたっているので、常備しているコスメはマーシュフィールドのフェイスパウダーと、ディオールのマキシマイザーだけです。

こだわりが詰まった愛用品。仕事現場には大量のコスメを持ち込みます。
Q9 地球のために実践している、ちょっとイイコトを教えてください。
コスメは使い切る前に飽きてしまったり、次のコスメを試したくなり、そのうちに品質が劣化して罪悪感を持ちつつもゴミ箱行き・・・なんて経験もあると思うのですが、最後まで使い切ってから次を使うように心がけています。
Q10 2030年までに実現したい夢やテーマを教えてください。
今よりも僕自身の知名度をあげて、メイクやファッションを中心にさまざまなプロデュース商品を世の中に送り出せたらいいなと思っています。「メイクでこんなに変われるんだ!」という体験は自信につながります。僕の活動を通してメイクの可能性を知り、たくさんの人が自分に自信を持てるようになったらうれしいです。
ずっと調子のいい肌のワケ。朝クリームを始めませんか?
肌や体に良いもの、使い心地が良いもの、気分が上がるもの・・・コスメや美容ツールを上手に取り入れて、Hummingな毎日を送りたい。美容ライター 荒木奈々さんがおすすめをご紹介します。
隠れ乾燥肌が多い春夏。ハリ不足の肌はクリームケアを重視

暑くなってくるとないがしろにしがちなのが、油分のお手入れ。そうでなくてもオイルやクリームなどベタベタするお手入れは苦手、という方はいまだに多いようです。私はあるとき、ヘアメイクさんにおすすめされて朝クリームにトライ。化粧ノリはよくなるし、何より夕方まで乾かない! 一年中朝クリームが手放せなくなりました。特に春夏の肌は汗をかくので肌内が乾燥していることに気付きにくく、インナードライに陥りがち。これからの季節もクリームは必須ですよ。
My select 01:「胎脂」に着想を得た、肌なじみ抜群の朝クリーム

カネボウ クリーム イン デイ SPF20・PA+++ 40g ¥8,800/カネボウインターナショナルDiv.
お出かけすることが減り、ファンデーションを塗らない日も増えました。そんななか、変わらない習慣が、朝クリームを塗ること。スキンケアの延長で、SPFのプロテクト効果があるってとても便利。
KANEBO作のクリームは、デイ、ナイトの2種類があって、ピンクパッケージの旧作から愛用しています。日中用の「カネボウ クリーム イン デイ」は、うっとりするほどのなめらかな使用感。ベスコスを多数受賞、美容のカリスマたちから支持されていることでもよく知られていますよね。
化粧品ブランドにはそれぞれ強みがありますが、カネボウ化粧品はクリームの処方やパウダー技術で一線を画し、こちらのクリームはメーカーが長年研究している胎脂に着想を得ています。胎脂とは体内の赤ちゃんを刺激から守っている保護膜で、潤いを抱え込む働きもあるそうです。それをヒントに開発されたのが、クリームに配合されている「ベビーソフトオイル処方」。
未熟な赤ちゃんの肌を包むヴェールは、バリア機能が弱いデリケートな肌にも欲しかった潤い。溶け込むように肌にスルスルと広がっていくと、フッと指どまりを感じる瞬間があります。お手入れの最後に使えば見えないヴェールを肌の上に形成、それが化粧ノリを高めてくれ、夕方まで乾燥を防いでくれます。肌の水分・油分のバランスも整うようで、逆にテカリにくい肌にも。
潤い感が満足できるスキンケアクリームで、SPF20・PA+++というプロテクト効果を持っているのがこのクリームの魅力。茶花がアクセントのフレッシュフローラルの香りも朝の気分にマッチします。

しかもこの朝クリームは 、“化粧上地”として使えるのも斬新。日焼け止めやファンデーションの上からのせてもよれずになじむテクスチャーなので、こちらで日中の潤い直し。みずみずしいクリームを乾燥しがちな目の下などに足せば、肌の内側から溢れ出るようなフレッシュなツヤがまとえます。
KANEBOは「I HOPE.」をテーマに、美だけでなく、希望を発信するグローバルブランド。2020年にリブランディング、スキンケアは「ライフインテリジェンス」という希望をもとに、取り巻く環境にも適応する肌の強さと美しさをサポートするアイテムを続々発表しています。朝クリームの守ってくれている感は一度使うと虜になるもの、またクレンジングや洗顔、UVケアもときめく使い心地。
カネボウ化粧品といえばカウンセリング! 店頭活動も変わらず丁寧ですが、そこで利用していた使用済みタブレットは寄付を通して、子供たちの未来を創るIT教育活動へ支援しているそう。そんな希望を生むアクションも賛同したいですよね。
KANEBO
kanebo-global.com
My select 02:日中モイスチャライザーで、保湿体力をつける
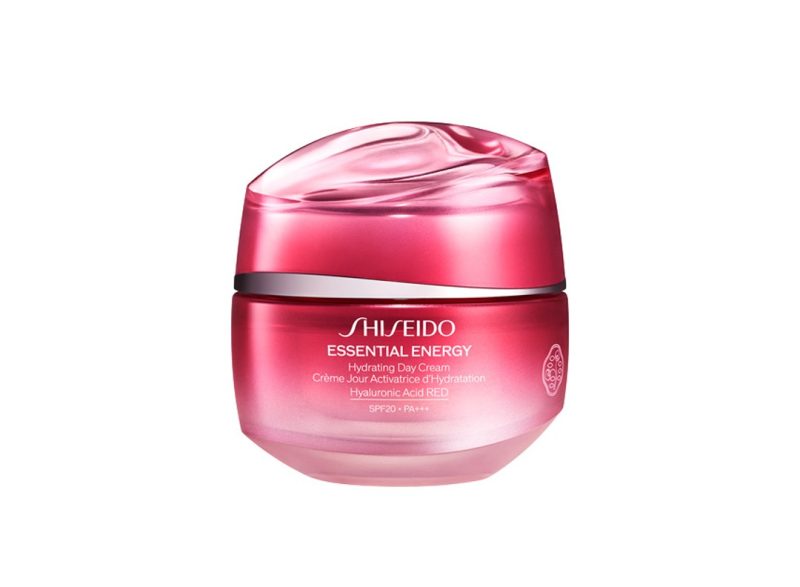
エッセンシャルイネルジャ ハイドレーティング デークリーム SPF20・PA+++ 50g ¥7,150/SHISEIDO
こちらのデークリームもSPF付き、逸品と評判です。“つけてもつけても乾燥する”という負のスパイラルにはまっているのは、保湿体力が低下しているせい。今年リニューアルしたSHISEIDOの保湿シリーズ「エッセンシャルイネルジャ」は、肌の中に眠る可能性に着目。
潤いを与えるだけでなく、自ら潤える肌になることがお手入れの目標。理想の肌に近づくために、SHISEIDOが着目したのは“血管”の役割。そもそも血管は栄養や潤いのもととなる水分を、身体のすみずみまで運ぶ働きがありますよね。でも血管壁がもろくなっていると、適材適所に成分を届けられない場合があるとか。血管は加齢だけでなく、乾燥や紫外線などの影響も受けるそうで・・・。そこから誕生したのが“The Lifeblood™”というビューティーコンセプト。その考えがベースとなっているスキンケアは、エッセンシャルイネルジャシリーズやアルティミューンシリーズ。そのため、2ブランドはレッドピンクのグラデパッケージが共通なのです。
クリームにはオリジナルの保湿成分、REDヒアルロン酸GLを配合。乳液とクリームを兼ね備えたモイスチャライザータイプで、デークリームは水が弾けるよう。鈍くなりがちな肌感度も高めてくれ、使うたびにピュアなみずみずしさが染み渡ります。角層のすみずみまで素早く浸透し、潤いがそのままハリ感に。紫外線から肌をプロテクトするSPF20・PA+++、乾燥小じわを目立たなくする効果もあります。香りは爽やかなフローラル・シトラス。淡いピンクの色味&パール配合でトーンアップも演出。全方位から生命感あふれる、調子のいい肌に見せてくれます。
創業150年に及ぶ、日本を代表するグローバルブランド資生堂ですから、サステナブルのプロジェクトも大事業。特設サイトには“MOTTAINAI:美しい地球環境へ” “HARMONY:美しい社会へ”“EMPATHY:美しい一人ひとりへ”という3つの柱が紹介されています。MOTTAINAIの活動ではリデュース、リユース、リサイクル、リプレイス、さらに地球への敬意を示すリスペクトの5Rで、2025年までに100%持続可能なパッケージの実現を目指しています。またブランドのアイコン美容液のアルティミューン パワライジング コンセントレートは、使い終わったボトルをフラッグシップストアに持参すると、洗浄・充填してくれる他にはないリフィルサービスも。それらは資生堂のSBAS(Sustinable Beauty Actions)のほんの一部。ご興味のある方は#ShiseidoSBASからチェック!
SHISEIDO
https://brand.shiseido.co.jp/
My select 03:潤い、ふっくら、軽やかなキールズの王道クリーム

クリーム UFC 49g ¥4,620、123g ¥8,250/キールズ
世界で4秒に1個(2021年キールズ販売実績による)のセールスを誇る、キールズのNo.1が「クリームUFC」。朝用というわけではないけれど、ライトなクリームは季節や肌質を問わず、モーニングケアにも活躍。一度使うと、使わない日が不安になるという声多し!
2005年デビューのクリームは、たちまちブランドのアイコン製品に。2019年には天然由来成分の配合&軽やかな使用感はそのままに、浸透時の肌への負担を軽減するべく、処方を厳選しリニューアルされました。ベタつきがトラブルの要因になる敏感肌を含め、すべての肌タイプの方に使えると、さらにシェアを拡大中。
正式名称はUFC(ULTRA FACIAL CREAM)。それを別に読み解くと、U=潤い、F=ふっくら、C=軽やか、なんだそう。U・・・皮脂成分に類似し、肌なじみがいいといわれるオリーブ由来のスクワランや、水分保持力が高いアンタークチシンを配合。水分をフルチャージ。F・・・6種の天然由来を配合。内側から弾むようなハリのある素肌へ。C・・・クリームとは思えない、乳液のような軽やかなテクスチャーがポイント。
ベタつきにくいのに、しっかり保湿できるのが長所。特に顎、頬、おでこと乾燥しやすいエリアへのアプローチが高いこと! マスク着用によるトラブル部位にも頼りになりそうです。
もちろん朝だけでなく、夜使っても、翌朝の肌はふっくらモチモチ。イキイキとした明るい肌にその場でなりたい日は、キールズの公式サイトでおすすめされているホットタオルケアを。適量よりも2~3倍のクリームをなじませて、レンジで温めたタオルを顔にひらり。スキンケアのラストに試すと潤いの浸透をより実感でき、洗顔前に行えばくすみもオフされクリアな肌へ。

1851年ニューヨークのアポセカリーが発祥のキールズ。お客さまと一緒に取り組んでいくコミュニティ活動「FUTURE MADE BETTER」は、“スキンケアからアースケアをはじめよう”がスローガン。6つのポリシーがあり、そのあゆみのひとつが、2019年より地域社会に還元するサステナビリティ活動を日本で始動させたこと。公式オンラインストアでアクションに賛同するクリックを押したり、店頭でショッピングバッグを辞退すると、1回につき10円が、音楽家の坂本龍一氏が代表の森林保全団体「more trees」に寄付されます。そのパートナーシップから生まれたのが、鳥取県智頭町にある「キールズの森」。20年、30年後が楽しみな植樹アクションも本格的に始まっています。
現在、各社が積極的に取り組んでいる製品容器の回収。キールズでは2015年といち早くスタートさせ、累計120万個以上のリサイクルが集まったそうです。またその回収容器は、クリームのスパチュラなどにリユース。今でこそグローバルでもフツーのショッピングバックの有料化の試みは、日本のキールズから始まったそう。
キールズ
http://www.kiehls.jp
保湿の基本は、油分のお手入れ。そっくりバリアになりすますことで、紫外線などの刺激を跳ね返すことができ、日焼けしにくい肌へと整います。そういう意味でも春夏に朝クリームを!
人との縁やつながりを結んだ、大切なものたち【素敵な彼のタカラモノ拝見】
蚤の市で見つけた掘り出しもの、小さい頃から愛用している分身のようなアイテムー-年月を超えて大切にされてきた品々は暮らしに豊かなストーリーを添えてくれます。おしゃれに暮らす素敵な方々に「いつまでも大切にしたいアイテム」を見せていただきました。今回は、ワイン商を営む八田さんの3つの“タカラモノ”をご紹介します。
大切な人から受け継いだものと、ものがきっかけで広まった出会いと
ワイン商としてワインや食にまつわる輸入卸や店舗プロデュースなどを手掛ける八田さん。「タカラモノを見せてください」とお願いすると、ファッションアイテムばかりが登場しました。けれどそれは単なるファッションアイテムではなく、人と人をつなぐきっかけになったものばかり。ご縁を大切にしてきた八田さんだからこそ大切にしてきたタカラモノです。
現代アートの“感じ方”を教えてくれた事典です【小泉里子 / 未来に続くBOOKリスト vol.7】
あなたの本棚には、これからの人生で何度も読み返したい本が何冊ありますか? モデル 小泉里子さんの連載エッセイ「未来に続くBOOKリスト」。読書好きの里子さんが、出合ってきた本のなかから“ずっと本棚に置いておきたい本”をセレクトしてご紹介します。
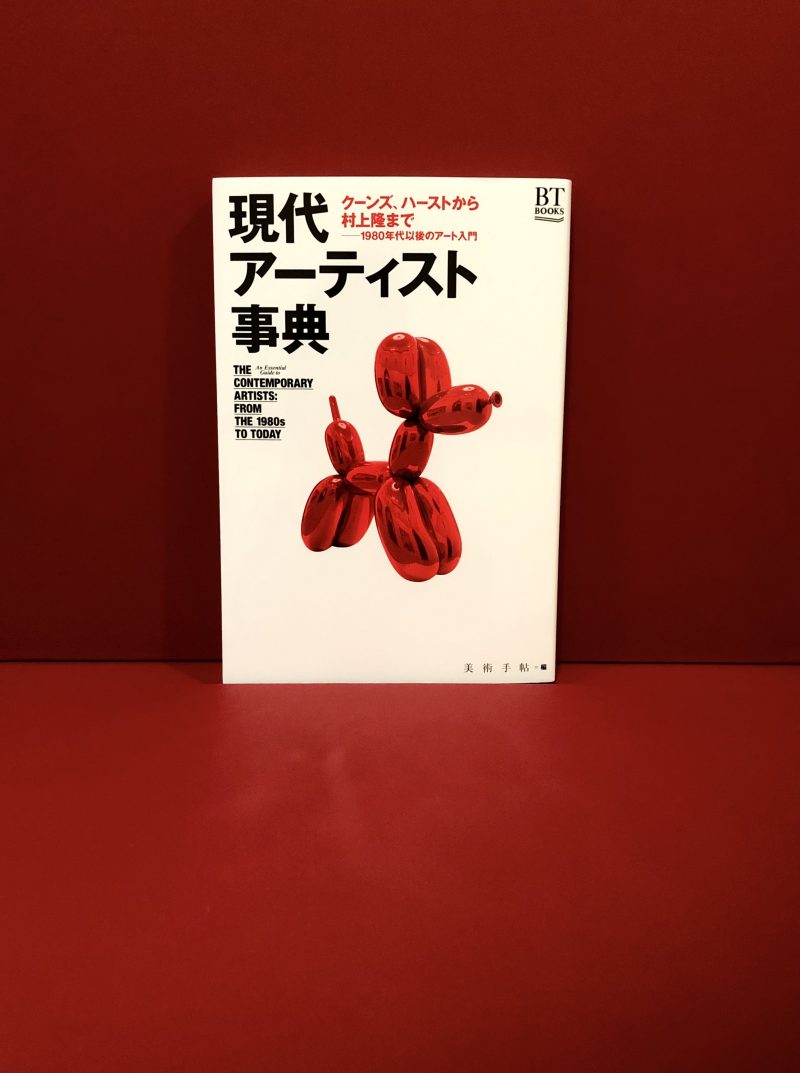
BOOK LIST_07
『現代アーティスト事典』
ジャンル=アート 美術手帳 編/美術出版社
事典と聞くと分厚くて重い参考書的なものを思い浮かべるかもしれませんが、今回紹介するのは、持ち歩くことができ、気軽に読める現代アーティストを紹介した事典です。
私と現代アートの出合いは、かれこれ15年前くらい。友⼈のマツこと松⼭智⼀⽒との出会いから始まりました。
NYで暮らす彼が東京で個展を開催すると聞いて、そこに訪れたのがきっかけ。以来プライベートでも家族ぐるみのお付き合いになりました。NYのマツのスタジオに遊びにいっては、テストの紙に⾊を塗らせてもらったり、たくさんのアシスタントが壁⼀⾯ほどの⼤きさの作品を制作したりを間近で⾒て、現代アートという未知の世界に⼀気に引き込まれました。
ある日、そんな私をマツ夫婦があの歴史あるオークションハウスSothebyʼs (サザビーズ)に誘ってくれたのです。マンハッタンの71 丁⽬とヨークアベニューが交差する角にあるサザビーズのビルでは、オークション前にビューイングといって、出品作品を品定めができる期間があって、しかも誰でも無料で入場でき、アート作品を間近で観ることができるんです。
っと! まーそんな説明を受けながら、そのときはさっぱり理解出来ないくらいにまだまだアートの世界に疎かった私。⾔われるがまま待ち合わせの場所に⾏き、初めてサザビーズを訪れたわけですが、⼊⼝からして異様な空気を感じずにはいられませんでした。
アベニュー沿いには⾼級⾞がずらりと並び、世界の富豪を顧客に持つアートアドバイザーたちが、すごい勢いで出たり⼊ったりしている回転ドアで、私は⼀⽣グルグルと回り続けてしまいそうなくらい圧倒されてしまいました。今や現代アートは巨額なビジネスになっていますが、そのパワーを実感。数⽇後には、ここで数⼗億、数百億が動く・・・そんな世界を垣間⾒れるワクワクが⽌まりませんでした。
いざ、作品を観始めると、マツは⼀つひとつ丁寧に作品やアーティストについて教えてくれました。まだまだ無知だった私にとって、ほぼほぼ初めて聞く名前や作品でしたが、今振り返ってみると、そうそうたるメンバーの作品を⽬にしました。
この本の表紙にもなっているJeff Koons(ジェフ・クーンズ)やDamien Hirst(ダミアン・ハースト)、Jean-Michel Basquiat(ジャン=ミシェル・バスキア)など。今でも⼀気にこれだけの作品を観ることが出来たのはこのときだけ。この⽇を境に点と点を結ぶように、この本を読みながらアーティストと作品を覚えていくのですが、会場では初めて観る作品を⽬の前に、⼩さく横に書かれた落札予想⾦額にも度肝を抜かれ、ビルを出たとき、しばらく現実社会に戻るのに時間がかかりましたよ(笑)。
⼀番印象的だったのは、キャンバスをただカッターで斜めに切った作品が⾼額な予想⾦額をつけていたこと。「これは⼀体・・・」という気持ちが無意識に声に出てしまったほど、謎すぎました。そして、私でもできる!と⾃信を持ってしまいました(笑)。
マツ夫婦に「謎すぎる〜」と連発していたら、「アートはやったもん勝ちだからね」と⾔われ、後⽇、私にもできる“今までにないもの”を考えてみたけれど、凡⼈にはそんな閃きは皆無でした・・・。
そんな「やったもん勝ち」と⾔ってしまっていいのかわからないけれど、現代アートって、それぞれのアーティストの世界に招待されている感覚で、それをなんで?と問う⽅が違和感で。私がその作品がもたらす意味とか考えても無駄なのかなと思います。
作品の前に⽴ち、ただただ受け⼊れる。
それが私の現代アートとの関わり⽅。この本をきっかけに、そんなふうに現代アートを感じるようになりました。
どんなアーティストがいるのか、現代アートがどのように変化してきたのかを知れるアート⼊⾨としては、最適な⼀冊。まずは、たくさんのアーティストを知ること! かつての私のようにアート初心者の方、ここから始めてみませんか?
『現代アーティスト事典 クーンズ、ハーストから村上隆までーー1980年代以後のアート入門』(げんだいあーてぃすとじてん)
1980年代以後の現代アートの流れを、わかりやすく丁寧に解説。アーティストやその代表作品についてだけでなく、各時代背景やその解釈まで学べる“永久保存版”。オールカラーで写真も豊富。眺めているだけでも楽しく、美術展にも携帯したい一冊です。

Profile
小泉里子(こいずみさとこ)
15 歳でモデルデビュー。数々のファッション誌で表紙モデルを務め、絶大な人気を誇り、広告やテレビ番組でも活躍。着こなすファッションはもちろん、ナチュラルでポジティブな生き方が同世代の熱い支持を得ている。2021年2月には第1子となる男児を出産し、同5月より生活の拠点をドバイに移す。ドバイでの生活や子育てにもさらに注目が集まっている。仕事、プライベート、ドバイでの生活を綴った著書『トップモデルと呼ばれたその後に』(小学館)をリリース。
http://tencarat-plume.jp/
Instagram @satokokoizum1
森カンナ「私たちはどこまでいってしまうのだろうか?」【連載 / ごきげんなさい vol.07】
俳優 森カンナさんが日々の生活のなかで見つけたこと、感じた想いを綴る連載エッセイ「ごきげんなさい」。自分を“ごきげん”にするためのヒントを探しましょう。

「Too much」
変な夢をみた。
簡単に話すと、頭の中に携帯を入れ込んでいる“携帯人間”になる手術をするかしないか決めなくてはいけなくて、時間もどんどんなくなっていくなか、決断しなくてはならない。手術すると決めた人たちから麻酔の液体を耳から流し込まれて、目の前で手術が始まる。
みたいな夢で、起きた後30分くらいぼーっと考え込んでしまった。
きっとこの夢をみる数日前に、Netflixのドキュメンタリー&ドラマで「監視資本主義 デジタル社会がもたらす光と影」という作品を観たせいだとは思うのだが、なんだかすごく恐ろしかった。
でもよく考えると私たちは今、どんどんと携帯人間に進化していっている。
文章を書いてるときの漢字の出てこなさにも驚くし、ナビが連れて行ってくれるから道も覚えない。
昔は、家族や大切な人の携帯番号は何個も記憶していたし、携帯を開いてもやることはあまりなかった。
もちろん人の生活を写真や動画で覗くことも、人がふと思った呟きを目にすることもなかった。
友だちと会ったときには聞いてないこと、話してないこともいっぱいだったし、買い物も買いに行かないといけない場所もたくさんあって、足をたくさん動かした。
あぁ・・・進化と退化は同時に起きているんだ。と何ともいえない気持ちになる。
便利な世の中になっていく代償は思っているより大きいのかもしれない。
私たちはいったい、一日にどのくらいの時間スクリーンを見ているのだろう。
思えば、コーヒーショップでコーヒーを頼んで待っている間、エレベーターを待っている間、電車を待っている間。移動してる間。
ちょっとの隙があれば携帯を触っている。
携帯を触っていなくとも、最近はタクシー、電車、エレベーターの中、至るところにスクリーンがあって、ちょっとの時間でもすかさず目に入ってくる広告。無意識で情報が頭に刷り込まれていく。
今後、今じゃ想像もつかないような場所に画面が取り付けられていく予感・・・。
そしてテレビにパソコン。
とにかくデジタルだらけだ。
その情報の質に対してもそうなのだが、このToo muchな情報社会で生きていくからには、ただただ流れてくる情報を受けとるだけの受け身だといけないんだと、コロナが始まって以来、深く考えるようになった。
自分から能動的に、質のいい情報源を見つけていかなければならない。
さぁ、これからどんどん加速するデジタル社会、人間はどこまでいってしまうのだろうか・・・。
いやはやいやはや。

自然な場所を欲する日々。思い立って朝から砂浜を裸足で歩いて、犬たちと寝転がっていた。何も考えずにぼーっとする時間がないとね。
Profile
森カンナ(もりかんな)
俳優。富山県出身。映画『地獄の花園』『鳩の撃退法』、TBS『プロミス・シンデレラ』、フジテレビ『ラジエーションハウスII』など、数々の映画やドラマに出演。2021年には、自身初舞台となった蓬莱竜太演出『昼下がりの思春期たちは漂う狼のようだ』で、600人のなかからオーディションによって選ばれ、観客を魅了。放映中のフジテレビ 月9ドラマ『元彼の遺言状』(毎週月曜21時~)1話、2話にゲスト出演。
https://kannamori.com/
Instagram @kanna_mori
ボディケアが楽しい季節♪ 体も気分もすっきり整えたい!
肌や体に良いもの、使い心地が良いもの、気分が上がるもの・・・コスメや美容ツールを上手に取り入れて、Hummingな毎日を送りたい。美容ライター 荒木奈々さんがおすすめをご紹介します。
洗う、磨く、引き締める。自然と続けられる春夏のボディケア

ズボラな性分なので、ボディケアはおざなりになりがち。だから肌見せの季節はチャンスで、ボディケアを楽しむと同時に、見直すいい機会だと思っています。興味があるボディケアは、洗う、磨く、引き締めるの3品。続けるのが課題ですから、春夏向きの清々しい香り&感触の日々使うのが楽しみなものをチョイスし、自然と手がのびるように。 “整う”感覚になれるとサウナが絶賛ブームですが、この3品は手軽なボディケアでありながら、すっきり “整う”気分も味わえそうです。
My select 01:ヌメリ保湿が面白い。新時代の爽快ボディソープ

ソープオブボディ・01-G 300ml ¥3,920/オブ・コスメティックス
いつからでしょうか、肌が水を弾かなくなったのは。学生のころ、油抜きダイエットをして肌がカッサカサなのを友人に指摘されたことを覚えていますが、今は一年中カサカサ。とはいえ、汗ばむ季節の保湿は苦手。そこには今トレンドの洗いながら潤す系のボディソープがてきめんで、オブ・コスメティックスの新ボディソープは、そのカテゴリーの新星。
もともとボディソープ選びを重要視していませんでした。しかし、オブ・コスメティックスのボディソープに初めて出合ったとき、たかが消耗品、そこまでこだわらなくても・・・という価値観が180度変化。あの日からオブ・コスメティックスのボディソープのクールタイプを使うのが春夏の習慣になっています。何より洗うのが楽しいのです♪
ヘアケア好きならきっと体験済みのオブ・コスメティックス。美容師さんが立ち上げたブランドで、“ナチュラルであること”をモットーに1988年に商品開発に着手。現在ヘアアイテムを中心に、100以上の製品をラインナップしているそうです。髪の悪者とされていたシリコンの代わりに、保湿成分リピジュアを世界でいち早くヘアケアに採用したのはここ!
ヘアケアの使用感はさすがサロン発のクオリティ。ボディソープも秀逸で、クールタイプは、ミントブルーのテクスチャーがなんとも美しいのです。また爽快コスメがここまで流行っていなかった当時、ミント×グレープフルーツの香りとミントの穏やかな清涼感にヤミツキに。オブ・コスメティックスの液体は、クリアなボトルに茶、黄、緑など色がとても鮮やか。これは天然由来成分の色なのだそう。ほのかな香りは天然の精油がベースです。
そんなお気に入りのボディソープがこの春、リニューアル! 環境、加齢、ダイエット・・・肌を乾燥させる原因はたくさんあり、ボディのカサカサに悩んでいる方は多いはず。そこでオブ・コスメティックスが着目したのは、“ヌメリ感(しっとり感)”。「洗い流すものなのに、潤う」をキーワードに、植物由来の角質保湿成分「糖誘導体(ペンタバイティン)」を新たに含め、従来品よりも潤い実感がパワーアップ。一度のせたら流れない潤いで、ターンオーバーによってしか除去されないそう。つまり洗いながら、日ごとに潤う肌が育まれます。水滴が転がるようになったら、皮膚のバリアも強化され健やかな肌になったサイン!
新ボディソープはこのクールタイプのほか、しっとり度、香り別で選べる全4種。クールタイプはアロエや海藻などの保湿成分も配合されており、オブ・コスメティックス独自の保湿指針、しっとり度は6満点中の星3つではありますが、春夏の肌にはこのしっとり度がちょうど良く、クール感と保湿感を両立。
ちなみに衣類洗剤は強い洗浄力を条件に選んだりしますが、肌用は高い洗浄力である必要はありません。こちらのボディソープの洗浄成分は糖類やアミノ酸など植物由来、肌に優しい弱酸性タイプ。石けん成分入りのキュッキュッとした洗いあがりに慣れていると、最初は多少の違和感があるかもしれませんが、クリーミー泡は泡切れもいいので、すすぎ残しなく、残るのはヌメリ感だけ。ボディソープでコツコツと保湿・・・ズボラな私に、忙しい人にもうれしい提案です。

ソープオブボディ・01-HS 300ml ¥3,920/オブ・コスメティックス
春夏は紫外線や汗でデリケートな肌になりやすいという方は、天然由来成分を厳選したパラベンフリータイプもおすすめです。こちらはフランキンセンス・スイートオレンジ・ラベンダー・クラリセージ・ローズマリー・サイプレス・ゼラニウムといった7種類のブレンド精油の香りも魅力。しっとり度は星4つ。秋冬はしっとり度星満点のダマスクローズの香り、しっとり度星5つのマグノリアの香りもぜひ要チェック。
帰宅後、寝る前、出掛ける前にもときどきのお風呂好きの我が家は、ボディソープの消費がハンパないので、スタンダードサイズ300mlよりお財布に約20%優しい、リフィルサイズ800mlを。プラスチック削減にも微力ながら貢献。
オブ・コスメティックス
http://www.ofcosmetics.co.jp/
My select 02:ロングセラーの限定スクラブで、つるすべパーツをキープ

甘夏の香りは7月31日(日)までの期間・数量限定販売
冬のかかとの乾燥も酷ですが、春夏は人目につくぶん、かかと、ひじ、ひざのザラつき、黒ずみは放っておけません! お手入れ不足をすぐに帳消しにしたいから、専用ケアを。
“Oh!Baby”の愛称で知られるハウス オブ ローゼのボディ スムーザーは、発売から30年以上の超ロングセラー。累計販売個数1,200万個(2021年10月末までの定番品、限定品を含むボディ スムーザーの累計)を記録、クチコミサイトなどでも不動の人気ですよね。シーズンごとに限定品が用意されますが、今年は「甘夏の香り」が登場。
パーツケアは塩や軽石、スクラブの素材もさまざまあります。 “Oh!Baby”のスクラブは温泉に含まれている塩(えん)など、もともと自然界に存在する成分を採用。水に溶けるため環境には無害ですし、ポリエチレンなど生分解性がない成分を一切使用していないところもぜひ再注目を。
“Oh!Baby”は温泉に含まれる3種のスクラブを独自の生産方法でペースト状に。体温で柔らかく、溶ける処方になっています。だからなでるようにつけるだけで、肌に負担をかけず、つるつるすべすべ肌へ。また角質を柔らかくほぐすアルカリ単純温泉水(角質柔軟成分)や、肌をすべすべに整えるシルク(保湿成分)なども配合。

ボディ スムーザー AN 350g ¥1,650/ハウス オブ ローゼ
限定のボディ スムーザーは、有機JAS認証を取得した熊本産「甘夏ネロリ」由来の美容成分、ナツミカン花水、ナツミカン花エキスなどがたっぷり。その花はアップサイクル原料。美味しい実をつけるには花を剪定する必要があるそうで、その無駄になるはずの花を化粧品原料に有効利用しているそうです。
手のひらで水を加えて練ってからのせるのがコツ。ひじ、ひざ、かかとはもちろん、個人的にはサンダルで汚れがちな足元、ザラつきが気になるヒップラインやワキにも塗布。甘夏のいい香りに包まれながら、明日のお出かけ準備を。
甘夏の香りシリーズはボディ スムーザー以外にも、ボディソープやボディ用化粧水、ハンドクリームも同時発売。そちらもお見逃しなく。
ハウス オブ ローゼ
https://www.houseofrose.co.jp/
My select 03:引き締め、潤い、ハリケアまで叶うピンクオイル

ロルロゼ ピンクフィット ボディオイル 100ml ¥5,500/メルヴィータ(4月27日発売)
セルライト、むくみ、脂肪・・・向き合わずにいるとどんどん蓄積、理想のボディからかけ離れてしまうことに。そこで春夏きっかけに本気のアプローチを。でもスリミング系ってなかなか続けられないのが本音で・・・。
引き締め系のボディケアをお探しなら、まずはメルヴィータのピンクオイル「ロルロゼ ピンクフィット ボディオイル」。進化するたびに大喝采のピンクオイルは、雑誌などのコスメ賞受賞数が96冠(2014年4月~2021年12月ロルロゼ ボディケアシリーズ世界累計)というから、それだけで試す価値がありそうです。
カフェインの8倍といわれる脂肪分解アプローチを持つピンクペッパー、脂肪の蓄積をケアするブラックペッパーの2大成分に、今年のピンクオイルは抗酸化力に優れているといわれるクランベリーオイルを新配合。種子を低温圧縮し抽出したオーガニッククランベリーエキスは、肌への有用成分が豊富なため、またの名をミラクルベリーとも。引き締めるだけでなく、弾力もプラスしてくれるので、使い続けることでメリハリのある肌が目指せそう。
ボディオイルはベタつきが難点。けれど、ドライオイル処方なので心配無用。塗ってすぐに洋服を着ることができるくらい肌なじみがいいのです。フレッシュなスパイシーシトラスの香りもスリミングの効きを引き上げ、使うたびに肌も気分もすっきり、晴れやかに。

ロルロゼ ピンクフィット ボディオイル 100ml ¥5,500/メルヴィータ(4月27日発売)
ところでオイル美容のエキスパートと称されるメルヴィータは、生物学者であり養蜂家のベルナー・シュビリア氏が1983年に創業したフランス発のオーガニック認証コスメブランド。世界各国から1,000種類以上の植物を取り扱っており、このピンクオイルは厳選の99%自然由来成分です。
ただ自然由来のものを扱っているから安心で終わりではなく、メルヴィータは環境配慮のための原料の見直しも真摯。一例をいうと、化粧品ほか、食用などでも人気のMCTオイル。パームヤシやココヤシなどから抽出されますが、近年の需要の高まりで、生産地のインドネシアのスマトラ島では、ヤシ科の植物の生産を増やすために、約30年で50%ほどの熱帯雨林が農地になっているとか。結果、生物多様性の喪失、地球温暖化への影響も疑われています。そんな背景からメルヴィータでは、ボディオイルなどに使用するMCTオイルの処方を再検討、代わりにひまわりオイルの使用量を増やすなどしているそうですよ。
サステナブルを重視した4R(リデュース、リユース、リサイクル、リプレース)活動や、「環境への完全ゼロインパクト」も提示。メルヴィータはクレンジングや洗顔もブランドの人気製品ですが、そちらの水を汚さない化粧品づくりも注目度大です。
メルヴィータ
https://jp.melvita.com/
ボディケアは肌や心を整えるスイッチケア。しかも春夏はボディのキレイを磨くチャンスです。夏の終わりまで続けることを目標に、ボディケアをもっと堪能してみませんか。
お出かけシーズンの相棒候補に!
「Teva」の最旬スポーツサンダル
衣替えが進み、新作フットウェアが気になる時季。近年はリサイクル素材や自然素材を使用する、サステナブルなシューズが続々と登場しています。そこで今買って晩夏まで長く使える、注目サンダルをご紹介します!
春夏に履きたいサステナブルな一足

アウトドアシーズンの足元に欠かせないスポーツサンダル。その草分け的存在となったのが、1984年創業の米国発のフットウェアブランド「Teva(テバ)」。リサイクル素材を使用した製品づくりから、水の使用量やパッケージの削減まで環境負荷軽減のためのさまざまな取り組みを行っており、2020年には主要なストラップをトレーサブルで検証可能なプラスチックから作られた、速乾性、耐久性に優れ、地球環境に優しい米国Unifi社のREPREVE®100%再生ポリエステルウェビング(100%リサイクルプラスチック素材)を使用したものにシフト。これにより、ペットボトル4000万本以上が埋立廃棄物にならずに、有効活用されています。

UNIVERSAL SLIDE 各¥6,380
2010年代に人気を博したスライドサンダル「UNIVERSAL SLIDE(ユニバーサル スライド)」が、前述のリサイクル素材にアップデートして復活。面ファスナー仕様でフィット感を調整しやすく、着脱もしやすいのがポイント。
カーブしたEVAミッドソールが土踏まずをサポートし、ラバーアウトソールは耐久性とグリップ性に優れています。
屋外・屋内を問わず履けるデザインで、ワンマイルシューズとしても便利。メンズは服を選ばないベーシックカラー、ウィメンズは肌馴染みの良いクリーンなアースカラーのそれぞれ3色展開です。

REVIVE 95 SLIDE ¥8,800
こちらは1995年に発売した「King Thong」のリバイバルモデル「REVIVE 95 SLIDE (リヴァイブ 95 スライド) 」。ソフトなつま先部分で指擦れもなく、足の出し入れがスムーズ。しっかりしたEVAフットベッドは土踏まずをサポートするカーブにより、一日中快適な履き心地を実現。アウトソールはスパイダーラバーで濡れた路面でも優れた耐久性とトラクションを発揮し、水辺での着用にも◎。

FLATFORM UNIVERSAL 各¥8,580
人気の厚底タイプには新色が登場。ヒールの高さ約4.5cmの「FLATFORM UNIVERSAL (フラットフォーム ユニバーサル)」は、今から楽しめるソックス&サンダルコーディネートにもぴったり! 足のニオイを緩和する抗菌加工が施されていて、汗をかく夏場も安心です。
アウトドアからタウンユースまで汎用性の高い「Teva」のサンダル。気軽に履けて、足が疲れにくく、間違いなく出番が多くなるはず。本格的な素足の季節が始まる前に、ぜひチェックしてください。
デッカーズジャパン
https://jp.teva.com
私の背中を押してくれる、4つの単語【山口乃々華 / コトノハ日和 vol.03】
言葉があるから伝えられること、伝わること。そこから広がっていく思考、癒し、つながり、希望、愛情・・・深くて力強いもの。女優 山口乃々華が、心に舞い落ちてきた“コトノハ(言葉)”を拾い集めて、じっくりと見つめ、ゆっくりと味わい、思いのままに綴っていく連載。さあ、一緒に元気になりましょう。
まずは近況報告から
私は先日まで「あなたの初恋探します」というミュージカル作品に出演させていただき、そのことで頭がいっぱいいっぱいの日々でした。そしてなんとか無事に、4月17日の千秋楽を終えることができました。とっても楽しい作品で、たくさんの笑顔が生まれる素晴らしい時間でした。
しかしながら、私にとっては2月の終わりから始まったこの闘い・・・闘いなんて言葉はまったく似合わない爽やかな作品なのに、何というか、個人的にはやはり自分との闘い!という感覚で。心から軽やかにスキップできるほどの余裕もなく、ずーっと一歩一歩を慎重に踏み出しているような気持ちになった日々でした。
でも、春のこの爽やかな晴れ晴れとした空気に目一杯励まされたし、何よりも私の周りの方々が、環境が、心の奥底から支えてくれていました。本当にいつもいつも支えてもらってばかりの私。そのことについても、このままでいいんだろうか?と悩んだりしましたが、気が付きました。悩んでる時点で、まだまだ人のことをケアする立場というステージには、辿り着けていないのです。仕方ない! 時には素直に甘えさせてもらいながら、生きていく所存でございます。
自分のことで目一杯な私をいつかは卒業して、客観的に、もっと広く、もっと全体をを見渡せるような人になりたいです。
さて、春の目標発表(?)が終わったところで! 今月ご紹介したい「コトノハ」へ。

The special secret of making dreams come true can be summarized in four C’s.
They are Curiosity, Confidence, Courage, and Constancy.
夢を叶える秘訣は、4つの「C」に集約される。それは「Curiosity (好奇心)」「Confidence( 自信)」「Courage ( 勇気)」そして「Constancy(継続)」である。ーWalt Disney
今回は、ウォルト・ディズニーのこの言葉について。
ウォルト・ディズニーが創りだした世界観や伝えているメッセージが好きで、いつかディズニープリンセスの声優を務めることが夢でもある私は、Twitterやネット上でよく引用紹介されているこの名言をみて、ドキドキした。
他にもいろいろな名言があるのだけれど、今の私にはこれがしっくり。
何かに向かっていくとき、叶えたいと努力をするとき、そのときのパワーは本当に心を輝きで満たしてくれて、自分に追い風が吹くような、そんな感覚がある。それはここにある「好奇心」からなのだろうか。やりたくて仕方ない! 今すぐ取り組んでみたい!とムズムズしてしまうとき、私はその物事にすごく集中できる。
そして、「自信」。
これは、私にとってすごく難しいことのように思える。しかし今までも、きっとこれからも「できる気がする!」と飛び込み、チャレンジすること自体は大好き。
一生懸命取り組んでいくのだが、その先で失敗を繰り返したり、なかなか成長できなかったりすると、どうしても不安になってしまう。壁にぶつかるのは当たり前だとわかっていも、そんな不安定なときに何かキツいことを言われたら、ふらぁーっと倒れていってしまいそうになる。
しかし、そんなことに負けちゃいけない!といつだって立ちあがろうとするのは、とっても長い目で見たら、私はいつかやれるはずだー-なんて、そんなふうに思えている私がいるからかも。もしかして、これが「自信」なのか?と思う。
「勇気」そして「継続」。
「できないなら、難しいかもね」「大丈夫? どうしていくつもりなの?」などなど。相手側は特別、こちらを責めてるつもりはないだろう言葉。しかし、言葉のなかに隠れている若干の怒りや呆れの棘がグサリと心臓と脳みそに刺さってくるときがある。
うるさい! どっかいけ! そう思っても、全然だめ。もうやめた方がいいかな? 諦めようか。人に迷惑をかけてまで、やり続ける意味があるのだろうか・・・? 本当、何にもできないな! 向いてないなぁ!と自分でその棘を猛毒にして、ぐりぐりぐりぐりと、えぐっていくのが私の思考回路。もはやそうするのが好きなんじゃ!?と思うほど。
毒が全身に回ったころには、とことん落ち込んでいるのだが、そんなときこそ「勇気」と「継続」だと思う。もう一度、立ち上がって勝負する勇気を。そして、諦めずにとにかく継続すること。どうせ、いつかはケロッと立ち直ってしまえるから、腐らないでいたいなと思う。
夢を叶える秘訣は、4つの「C」に集約される。
どうだろう、本当にこれらを大切にしていたら、夢が叶うのだろうか。まだわからないけれど、読むまではしょぼくれていた私も、やる気が湧くのだから、すごい言葉だと思う。
春は、何かと変化の多い季節。どうか周りに流されすぎず、自分の気持ち、意思を大切に過ごしていきたい。

Profile
山口乃々華(やまぐちののか)
2014年からE-girls主演のオムニバスドラマ「恋文日和」第7話にて主演を務め女優業をスタート。映画『イタズラなKiss THE MOVIE』シリーズ、ドラマ・映画『HiGH & LOW』シリーズほか、2020年には『私がモテてどうすんだ』のヒロイン役など、数々の作品に出演。 2020年末までE-girlsとしての活動を経て、2021年より女優業として本格的に活動を開始。2021年3月、初のミュージカル『INTERVIEW~お願い、誰か助けて~』、同8月にはミュージカル『ジェイミー』、2022年3~4月はミュージカル『あなたの初恋探します』でヒロインを演じた。ドラマは現在「ビッ友×戦士 キラメキパワーズ」(テレビ東京系)に出演中。書籍『ののペディア 心の記憶』(幻冬舎文庫)も好評で、文章を書くことも好き。4/30(土)22:30から放送の特集ドラマ「昭和歌謡ミュージカル また逢う日まで」(BS プレミアム・BS4K)に夏木和香役で出演。
https://www.ldh.co.jp/management/yamaguchi_n
Instagram @yamaguchi_nonoka_official
楽しすぎる!クイズで遊びながら、SDGsを学べるボードゲーム
「SDGs」が「Sustainable Development Goals」の略であること、そして2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標であることは広く知られています。その内容は17のゴール、169のターゲット、232の指標から構成され、地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓っています。この世界的取り組みについて、未来を担う子供たちが、そして今を改善すべき大人たちも、“自分ゴト”として理解するのに役立つボードゲームが登場して話題です。
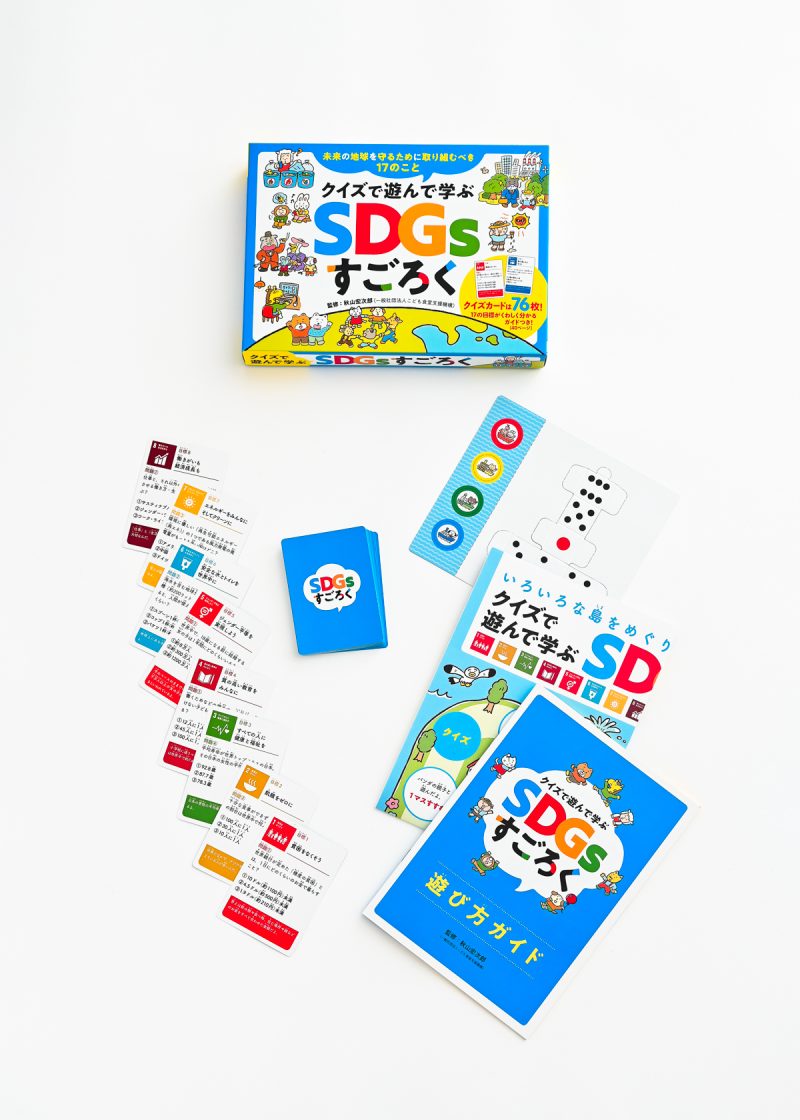
遊びながら、大切なことを学ぶ
発売されたボードゲームは、誰でも簡単に挑戦できる「すごろく」。サイコロを振って、出た目の数だけコマを進めてゴールを目指します。早くゴールできた人が勝者になるという、お馴染みの遊び方です。

『クイズで遊んで学ぶ SDGsすごろく』は、ゴールに向かう途中で「クイズ」マークのマスに止まったらSDGsに関するクイズに挑戦。クイズカードを1枚ひいて、カードに書かれているクイズに答えます。「SDGsチャレンジ」マスに止まったら、SDGsの身近な課題についてを考えて発表します。
クイズカードは全76枚! どんな内容か見てみましょう。
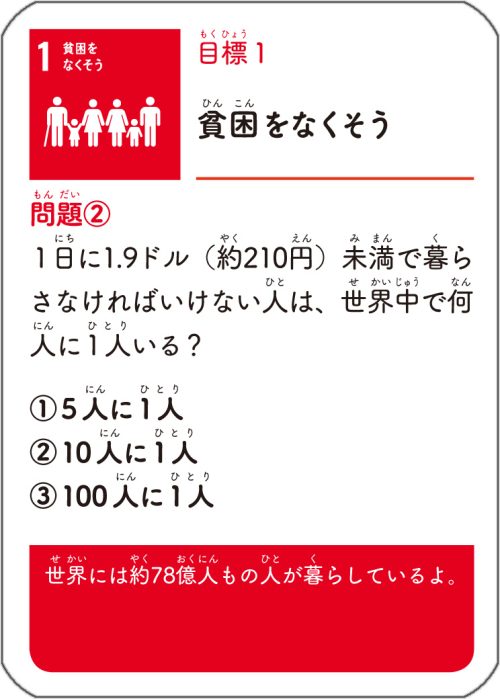
たとえばこちらのクイズカードはSDGsの目標1「貧困をなくそう」に関連した出題。「1日に1.9ドル(約210円)未満で暮らさなければいけない人は、世界中で何人に1人いる?」というクエスチョン。ヒントも載っています。「世界には約78億人もの人が暮らしているよ」ーーさて、あなたは正解をご存じでしょうか。
答えは三択です。
①5人に1人
➁10人に1人
➂100人に1人
正解はーーこの記事の最後でご紹介しますね。
「SDGsチャレンジ」のマスには、どんなことが書かれているかというとーー。

「『持続可能な自然環境や人、社会のためになる商品』ってどんな商品かな? 考えて発表しよう!」「水不足が起こらないよう、おうちで水を節約する方法を考えて発表しよう!」ーーなど、全部で7つの「SDGsチャレンジ」マスが用意されています。発想豊かな子供たちからどんな答えが飛び出すのか、楽しみですね。
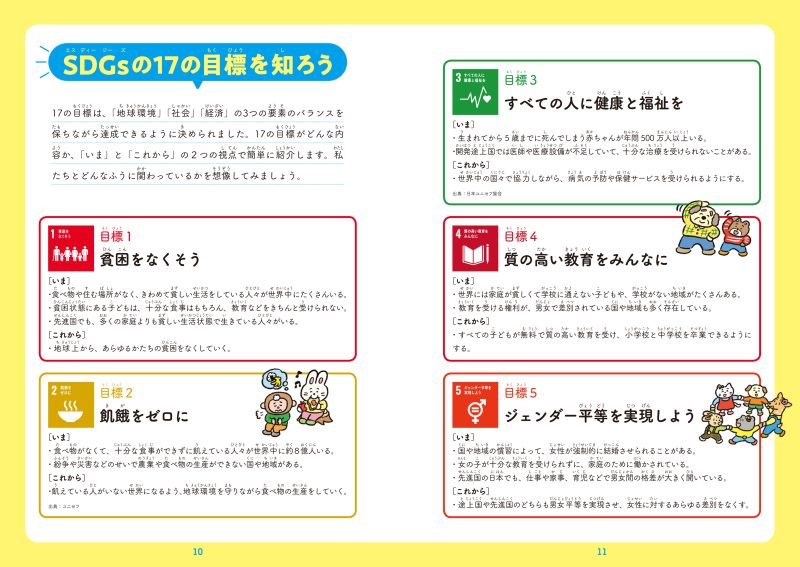
付属の遊び方ガイドには、クイズの進め方、答えと解説だけでなく、「SDGsって何だろう」「SDGsの17の目標を知ろう」というページもあり、子供たちに伝わりやすい優しい言葉で説明が書かれています。
このボードゲームの監修は、一般社団法人 子ども食堂支援機構の代表理事であり、SDGsオンラインフェスタ・ソーシャルイノベーションディレクターの秋山宏次郎さん。商品の売り上げの一部は、こども食堂支援機構を通じて、全国のこども食堂支援のために使われるそう。
遊び方ガイドはもちろん、ゲームの箱、すごろくシート、クイズカード、組立式のサイコロ、コマチップまで、すべて紙製(商品の一部には、森林資源に配慮してFSC認証を受けた紙を使用しています)。そして文章中の漢字には、全部に読みがなが振られています。
さて最後に、前述のクイズの答えはーー「➁10人に1人」です。世界全体で7億人以上の人が、極度の貧困状態なのです。そのうちの約半数ともいえる3億5600万人が子供たち。この数字を知るだけで、自分も何かアクションを起こさねばという気持ちになりますよね。
親子で、子供同士で、考えながら、語り合いながら、知識を取り入れながらゴールを目指すことができるボードゲーム。きっと、たくさんの“学び”と“発見”があるはずです。
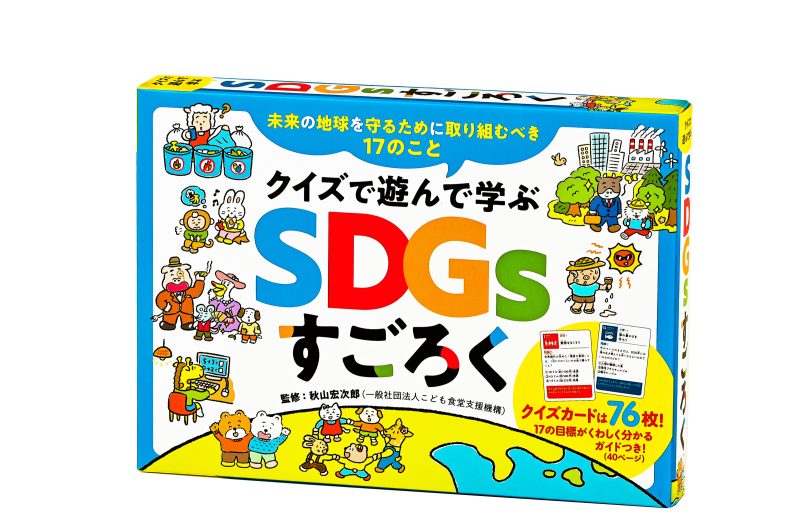
『クイズで遊んで学ぶ SDGsすごろく』¥1,980/幻冬舎
監修/秋山宏次郎(一般社団法人 こども食堂支援機構)
イラスト/田中チズコ
対象年齢/8歳以上 対象人数/2~4人
※全国の書店、玩具店、雑貨店、ネット書店にて販売中
春夏のお守り。ニオイ不安を打ち消すリフレッシュコスメ
肌や体に良いもの、使い心地が良いもの、気分が上がるもの・・・コスメや美容ツールを上手に取り入れて、Hummingな毎日を送りたい。美容ライター 荒木奈々さんがおすすめをご紹介します。
エチケットでもあり、自信もくれる!この3つでマインドケアも

“スメルハラスメント”という言葉が一時期取り上げられていましたが、強い弱いに関係なく、ニオイに違和感を持つときがありますよね。相手のニオイも気になるけれど、特に春夏は自分のニオイが気になります。他人は気付いていないかもしれないけれど、ニオイに不安を感じると集中できなくなったり。とはいえコンプレックスとは思われたくないから、ひっそりケアしたい・・・。汗をかかない、無臭な方はいませんので、ネガティブなマインドもケアしてくれるようなリフレッシュコスメを手に取ってみませんか。
My select 01:Z世代や敏感肌に。ゼットエマのリフレッシュケア

〈左から〉ゼットエマ リフレッシュロールオン デオカールズ、同 デオボーイズ 各50ml 各¥1,870/BCL
思春期臭、加齢臭・・・一生のうち何度か体臭が強くなる時期があるそうです。例えば脇にはアポクリン腺という汗腺があり、思春期のころにそれが急激に発達。そのためニオイが強くなりやすいというのが思春期臭の簡単なメカニズムです。そこでニオイに敏感なZ世代におすすめしたいのが、フランス発のオーガニック認証コスメティックブランド、Z&MA(ゼットエマ)のリフレッシュコスメ。
ゼットエマは2017年にデビュー。“No Petrol、Just Beauty(石油系成分フリーで、美しく)”をフィロソフィーとし、エシカル志向とPOPな世界観で20代をメインに支持されているそう。現在ヨーロッパを中心に、世界14ヵ国で展開されています。
刺激が強い、パウダーが脇のシワに白く残る、ベタベタする、洋服のシミになりやすい・・・エチケットコスメにありがちなデメリットは見当たらず、こちらはノンストレスな“ガールズ&ボーイズのための自然派リフレッシュロールオン”。肌の刺激となるアルミニウム塩フリー、パラベンやシリコーンなど12の成分を不使用、さらにヴィーガン対応となっています。デリケートなガールズ、ボーイズたちの肌を見つめたナチュラル処方、敏感肌にも安心して使えるタイプ。ガールズ、ボーイズともに99%自然由来で、ガールズは全成分30%、ボーイズは全成分31%がオーガニック原料です。
ニオイケアのアプローチは、汗そのものを抑えたり、ニオイ菌の繁殖を抑えたりなどさまざまあります。このゼットエマは気になる汗のニオイをフレッシュな香りで、カバーするアプローチ。個人的にはお化粧直し同様、適度に塗り直しするのがおすすめです。コロンとおしゃれなパッケージで、年齢問わず携帯もしやすいです。
ガールズの香りはレモンやベルガモット、ミントの香りにラベンダーやコリアンダー、パチョリなどがブレンドされたリラックスハーブの香り。アロエベラ葉エキスとゼニアオイ花エキス配合で、乾燥で硬くなりがちなワキの肌をなめらかに整えてくれます。
ボーイズはベチパーやオークが入ったウッディオークの香り。ガールズよりも肌をすっきり、キュッと引き締めるような作用をもたらします。
それからフランスビューティに興味がある人に朗報! ゼットエマを取り扱うBCLでは、5つのフランス発コスメブランドを展開しており、フランス経済の国際化を促進するフランス政府機関「在日フランス大使館 貿易投資庁―ビジネスフランス」の後援を受けたプロジェクト「サステナプラス」をこの春にスタートさせています。“サステナブル”“エシカル”“フェムテック”などをキーワードにSDGsにつながっていく・・・新しい時代のフランスコスメ、フランス式ライフスタイルなどをチェックできますので、そちらもお見逃しのないよう。
My select 02:アスレティアの薬用デオドラントはアクティブ派へ

リフレッシング デオドラントミスト [医薬部外品] 100ml ¥3,850/アスレティア
ジャパンブランドで特に百貨店コスメにはまだまだ少ない、徹底的なクリーンなモノづくりで注目されるアスレティアは、ストレス過多な現代人に合わせて3つのプロダクトがラインナップされています。そのうちの「active&go」は、“からだを動かす喜びを知る”アクティブライフを好む人へ新しい美しさを提案。機能的なヘアケア、ボディケアが揃っており、そこに加わったのが待望の薬用デオドラント。
注目したのは汗。そもそも汗は体温を調整するという重要な役割を担っているものなのに、かけば悩みになってしまうからやっかいなのです。こちらは制汗剤(制汗アルミニウム塩)非配合。汗を抑えるという働きかけではなく、「汗殺菌ラスティングテクノロジー」によって、汗のなかのニオイのもとをブロックします。つまり、かいた汗のニオイをクリーンに変化させて、美しい汗へ!
メントール配合で、ほど良いひんやり感。みずみずしいミストはベタつくこともなく、すばやく揮発します。肌触りはサラサラなのに、ゲル状となってフィットするので、感覚はなくてもニオイケア効果は長く持続します。
それから顔を洗うと水分が一気に蒸散するように、汗をかくと肌からは潤いが逃げていきます。そのため汗をかいたらこまめの保湿がマスト。こちらは独自の複合保湿成分ビオ エナジェティック コンプレックス(アシタバエキス、紫蘇エキス、米発酵液、濃グリセリン)、サクラ葉エキス、ビワ葉エキスなど植物由来の保湿成分を配合。汗をかいても肌の潤い環境をキープしてくれます。ちなみに採用されているアシタバと紫蘇は、アスレティアの共通成分。土壌づくりから情熱を注ぐ、循環型農園で栽培されているこだわりの素材です。
思いっきり汗をかくって気持ちいい! その感覚忘れがちですが、汗をかくことはデトックス作用があるといわれますし、スポーツシーンなど無理に汗を止める必要がないときは、このデオドラントでニオイだけケアを。
スプレータイプのミストは、パウダーレスなので白残りもありません。逆さ使いもできるので汗でベタベタしやすい背中などにも簡単に塗布できます。
香りは天然植物精油を厳選。ジュニパーベリー、ローズマリー、レモン、ユーカリプタス、セダーウッドなど草原のような香りが清々しい。
アスレティアのサステナブルな取り組みといえば、ガラスカレット(製造時に不適合などとされたガラスを再生利用したもの)をボトルに採用していることなどが注目を浴びています。また容器の回収ではプラスチックなどを持参してもOKで、次の資源として循環させるプログラムを実施。しかも容器は洗浄せずとも、中身が空の状態なら受け付けてもらえますよ。
対象店舗に持参すると、容器1個につき提携団体の公益財団法人日本自然保護協会へ寄付。店頭ではお好きなサンプル3点のプレゼントも。
それからアスレティアのクリーンビューティーの新たな取り組みとして、まずはオイルから成分詳細情報公開(トランスペアレンシー)がスタート。クリーンビューティー先進国の欧米ではすでにトランスペアレンシーが常識になりつつありますが、アスレティアでも全成分の表示はもちろん、各成分の配合目的、由来といった詳細情報まで、徐々に開示されていくそうです。
アスレティア
www.athletia-beauty.com
My select 03:頑固なオトナ臭対策には、ロート製薬のデオコ
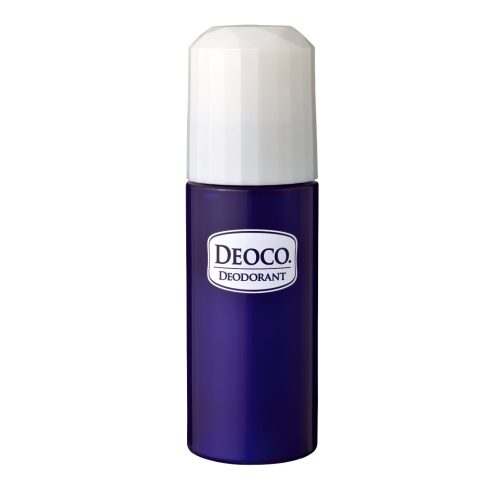
デオコ薬用デオドラントロールオン [医薬部外品] 150g ¥990(編集部調べ)/ロート製薬
体臭は、汗や皮脂などが細菌や酸化によって分解されることで発生。そのニオイのもとは水に溶けやすいため洗い流すことができますが、加齢臭の原因といわれる成分2-ノネナールは水に溶けにくく、洗い流しにくいといわれています。また女の子特有の甘い香りは、加齢臭のもとをマスキングできることがわかっています。
そんな話を聞いてから何度もリピートしているのが、デオコの制汗剤。2018年にオトナ女性のニオイ対策ブランドとしてローンチされたデオコは、「~ニオイまでキレイに~」のキャッチやTVCMでもおなじみですよね。インスタグラムで#DEOCOを検索すると、さすがグローバル展開中のロート製薬発! 世界中で愛用されているようです。
ロート製薬のニオイ研究の集大成ともいうべきデオコシリーズ。目薬研究で培った微生物や菌をコントロールする殺菌技術と、塗り薬や日焼け止めから見出された密着技術を応用しており、気になるニオイを消すだけでなく、ニオイ悩みが起きないようにするのもデオコの頼もしいところ。
デオコの制汗剤は、殺菌成分でニオイの原因菌をカット、制汗成分で汗を抑える、白泥(吸着剤:カオリン)がニオイのもととなる皮脂を吸着するという3つの効果に、さらに潤い成分としてビタミンC誘導体が配合されています。ニオイをエイジレスにする技は、年齢とともに減少するラクトンを含有する香料の手応えです。
スウィートフローラルの香りは懐かしさも感じる、甘いのに清潔感のある独特な香調。一度かいだらデオコの香りと気づくはず。
環境配慮には程遠いような制汗剤ですが、そこは国連グローバル・コンパクトにも参加する日本を代表する企業の提案。こちらのパッケージもきちんとバイオマスプラスチック素材が採用されています。
バイオマスプラスチック
植物由来の原料を使っているため、微生物に分解されて自然に還ることで生態系に悪い影響を与えません。焼却しても、大気中のCO2濃度が上昇しないため、地球温暖化防止にも役立ちます。(ロート製薬、肌ラボHPより抜粋)
ただし制汗剤ですから、機内には持参できません。飛行機に乗るお出かけのときはお留守番を。デオコは女性だけでなく、ジェンダーレスで支持されているのもユニークですし、私的にも目が離せないシリーズです。
デオコ
https://jp.rohto.com/deoco/
ニオイケアは毎日の相棒、一生のケア。お気に入りの香り&機能のアイテムを見つけて、この春夏を快適にポジティブに過ごしましょう。
極上の履き心地だけじゃない。いくつもの感動を運んできてくれる靴
Humming編集スタッフでの情報交換で「この前、とてもいい靴を見つけて」と名前が挙がったのが、今回ご紹介する「Öffen(オッフェン)」。まず驚かされるのは、その軽さ。そして、足にまったく負担を感じない履き心地。しかも“環境に優しい”をテーマに掲げているだけあって、環境に配慮したリサイクル素材を可能な限り使用し、製造工程もなるべくミニマムにすることで二酸化炭素の排出を抑制するなど、エシカルなモノづくりを実現しています。このブランドの魅力、ぜひ知っておきましょう。
J-WAVE×Hummingで伝えていきたいこと。新番組がスタート!
4月は新年度のスタートで、いろいろなことをリフレッシュするタイミングです。Hummingも新しいことに挑戦して、今まで以上に多くの方にアプローチしていきたいと計画中。その1つとして、J-WAVEの番組でコーナーを担当することになりました。ぜひ、皆さんにもキャッチしていただければと思います!
日曜日の朝、一緒に“目覚めましょう”

Photo by dominik hofbauer on Unsplash
J-WAVEにて毎週日曜日の朝6時~9時にオンエアされる新番組『ARROWS』。このタイトルには「不安の多い現代社会において、この番組がポジティブな未来を目指す矢印に」という意味が込められていて、“よりよい未来のために今できるアクションを見つけていく新ワイドプログラム”が展開されます。Hummingが掲げている「A lifestyle in creating colorful earth」もポジティブに未来を目指すことが大前提。とてもシンパシーを感じるタイトルです。
ということで、この『ARROWS』のプログラムのなかにHummingがコーナーが誕生します!

Photo by Imani Bahati on Unsplash
「Humming SUSTAINABLE ACTION」は、日曜日の朝に“未来について考える時間”を持っていただくためのワンコーナーです。SDGs、エシカルアクション、マインドフルネス・・・などをテーマに、私、社会、世界、地球について考えるきっかけをつくっていきます。
このコーナーは8時35分から5分間。日曜日を充実させるために、ぜひ早起きをして耳を傾けてください。気持ちよく目覚めて、そして一緒に“地球にイイコト”にも目覚めましょう!
Hummingでは番組で取り上げたトピックスを、より深掘りしてご紹介していく記事も掲載予定。こちらもあわせてお楽しみに!
新番組は気になるテーマが満載です

『ARROWS』のナビゲーターを務めるのは、音楽ユニット「チャラン・ポ・ランタン」のメンバーで、世代を超えたファンを持つ、ももさん。現代社会のいろいろなテーマに対して、彼女がどのように想いや考えを伝えてくれるのか、とても楽しみです。
この番組では、さまざまな世代からのリアルボイスを集めて分析紹介する「OUR VOICES」や、 未来を担う子供たちを応援する「J-WAVEこどもみらいプロジェクト」との連動コーナーなど、“聴きどころ”がたくさん。
ポジティブな未来に向けて何か始めたくなる、きっとそんな刺激をもたらしてくれるはず。どうぞ、ご期待ください!
J-WAVE
https://www.j-wave.co.jp/
森カンナ「繰り返してきた失敗から抜け出した今」【連載 / ごきげんなさい vol.06】
俳優 森カンナさんが日々の生活のなかで見つけたこと、感じた想いを綴る連載エッセイ「ごきげんなさい」。自分を“ごきげん”にするためのヒントを探しましょう。
自由なマインドでドレスアップを。
ジョエブが提案する、楽しむお呼ばれ服
「疲れたときこそ、いつも以上におしゃれする」「頑張る日はカラフルな服を着る」・・・こんなふうにファッションで自分のご機嫌をとるという人は少なくないはず。
今回ご紹介するのは、自分らしく今を生きる女性の気分に合わせたドレスアップスタイルを提案するブランド「ジョエブ」。同ブランドのディレクターを務める三條場夏海さんが考える、固定概念にとらわれず、体型にも左右されない自由なファッションとは?
“わからない”を解消して、楽しむマインドに

従来の結婚式の形式や格式にとらわれない、自由なスタイルの結婚式が増えています。そんななか、より自由なマインドでドレスアップを楽しみたいと思う一方で、何を着たら良いかわからない・・・というゲストが増えているそう。そんな悩める女性たちに手を差し伸べるのが「ジョエブ」です。
結婚式のお呼ばれウェアを中心に、オケージョンシーンで着られるドレスやそこから派生するアイテムを展開。女性が女性であることに大きな喜びを感じられますようにと願いを込め、乙女ゴコロをくすぐる花柄や刺繍、パール、レースなどヴィンテージライクなディテールやシルエットを、今着たいテイストで提案しています。

上半身のフィット感とフレアーシルエットのバランスにこだわり、可憐さとモダンな印象を両立。sugar gather ワンピース ¥26,400/ジョエブ
ディレクターの三條場さんは、2019年6月に開催されたビームス初の社内新規事業コンテストで優勝。結婚式に参列する女性たちへ向けて、ビームスの商品をキュレーションし、ドレス選びの基準や、知りたい情報を届けるオンラインサービス「ビームス サロン」の開始と同時に、ブランドをローンチしました。
自身のInstagramに集まった同世代の女性たちからの声がアイデアソースになったそう。
「周囲で結婚ラッシュが始まり、結婚式に出席する機会が増えていました。参列スタイルをInstagramに投稿すると、『どのブランドのドレスですか?』『ヘアセットの詳細が知りたいです』など、普段のコーディネート投稿の何倍ものお問い合わせが来ていたんです。『何を着たらいいのかわからない』と悩む女性の多さを実感しました。また、結婚式は花嫁が主役だけれど、その空間を彩ってお祝いムードを作るのが参列者の役目なんじゃないかと感じたことがきっかけとなりました」
悩みに寄り添い、一緒に作り上げていく
「タイムレスな名品は自信をくれる」
【UNDERSON UNDERSON 森田雅子さんの5年選手、10年選手】
物を大切に、長く使い続けることはサステナブルなライフスタイルの基本。おしゃれ業界人が愛用する「5年選手」と「10年選手」、そしてこれからじっくりと育てていきたいNEWアイテムへの愛を語っていただきます。今回お話を伺ったのは、UNDERSON UNDERSONプレスの森田雅子さん。
「本物」に触れる時間の大切さに気付く

― 5年選手を教えてください。
バーバリーのトレンチコートです。
― このアイテムとの出合いは?
30歳の節目に大きな買い物がしたい思い、一生モノとの出合いを求めて、バーバリーのお店を訪れました。どんなシーンでも着やすいオーソドックスな形のトレンチコートが一着欲しいと思って選びました。
私の地元の神戸では、質の良いものを購入して、自分の子供や孫に受け継ぐ文化が根付いているように感じます。それがとても素敵だなと思っていて、私もなるべく長く愛せるものに投資する買い物の仕方を意識しています。
- 購入後、どんな気持ちになりましたか?
「本物を知る」という体験を買ったような感覚でした。アパレル業界で働いていて、配慮の行き届いた接客を目指していましたが、ハイメゾンでのお買い物は接客から購入後のアフターフォローまで素晴らしく、学ぶことが多かったです。それに世界中で愛され続ける名品は、着るだけで自信を与えてくれますね。
― どんなコーディネートを楽しみたいですか?
ボーダーのトップスにデニム、トレンチコートを羽織り、王道のフレンチスタイルを楽しみたいです。
普遍的な価値を持つ、上質な日常着
高山都さんが見つけた、自分を幸せにする方法【気になるあのひとに10の質問】
オリジナルなスタイルを持って生きている素敵なひとに聞く、10のQuestion。心や暮らしの豊かさは、ブレない生き方や考え方が築くもの。内面から輝くひとはどのようなことに目を向け、何を実践しているのかーー心地よく、充実した毎日を生きるためのヒントを探りましょう。今回は、モデルやラジオパーソナリティー、商品プロデュースなど多彩な顔を持つ高山都さんにクエスチョン!
「自分のご機嫌をとるのは、自分」
Q01 ストレス解消法は?
気分をすっきりさせたいときはランニングをします。
走るきっかけは、お仕事で「ハーフマラソンに出ませんか?」と声をかけていただいたことでした。中学、高校時代の体育の成績はずっと「2」で、運動が大の苦手だった私が走ることに爽快感を覚えるなんて思ってもみませんでした。

当時は、仕事の方向性などについていろいろと悩んでいた時期だったので、これは一つのチャンスだ!と思ってトライすることに。ハーフマラソンを走りきったら、気持ちのいい達成感があって。もっと走りたい!と欲が出たし、「やればできる」という自信につながりました。気付けばもう12年も続けていることになるんです。走っているときは一人だから、自分自身と向き合う時間。ランニングはマインドをリセットするにもぴったりです。
ストレス解消もそうですが、自分の機嫌をよくすることができるのは、結局自分なのだと思っています。
たとえば、元気が出ないなぁ・・・というときは、気分を上げるために素敵な服を選んで着てみたり。普段からオンとオフを切り替えるためにも、外出するときは背筋がのびるようなワンピースやシャツを着ることが多いです。自分を奮い立たせたいときは、おしゃれすることをより意識していますね。
◆【ストレス解消】セルフケアとはなにか?意味・種類・方法について解説
Q02「幸せだな」と思う瞬間は?

仕事が終わって家に帰り、ビールを飲むときです(笑)。ビールのあとはワインや日本酒をあけることもありますね。お酒だけを飲むことはなくて、ご飯もセット。お酒に合うメニューをあれこれ考えて作ることも幸せな時間。
Q03 お気に入りのレストランを教えてください!
参宮橋にある「レガーロ」というイタリア料理のお店です。いいことがあった日も、そうじゃない日も、ここに行くと気持ちがシャキッとして元気が出ます。堅苦しい雰囲気のお店ではないのですが、おしゃれをして行きたい場所でもあるので、何を着ようかなと考える時間もテンションが上がって好き。大切な友だちのお祝いごとなどにも利用することが多いのですが、友だちにも「おしゃれをしてきてね」と伝えています。

お料理はどれも美味しくて、訪れるたびに「生きていてよかった!」と思えるほど。シェフをはじめ、スタッフの方たちが料理に対して真摯に向き合っていることがまっすぐに伝わってきて、私も頑張ろうという気持ちになります。気軽に通えるようなお値段ではないので、仕事を頑張ったご褒美のようなものですね。
Q04 今、欲しいものはありますか?
おしゃれな電動自転車! 坂の多い街に住んでいるので、食材の買い出しをしたあとが大変で。電動自転車があればラクに荷物が運べるようになりそう。
Q05 今まで旅をしたなかで、一番好きな場所は?
パリです。初めて訪れたのは2019年の秋でした。仕事で立ち寄っただけだったのですが、その2ヵ月後に一人旅で10日ほど滞在しました。当時ありがたいことに常にスケジュールがいっぱいで、お休みがなかなかとれず・・・。このままでは心身ともにパンクしそうだったので、思いきって休みをとらせてもらいました。

観光をしたいというよりは、そこに住んでいるかのように生活をしたいと思ったので、アパルトマンを借りて過ごしました。マーケットで野菜や肉を買って料理をしたり、花を買って部屋に飾ったり。パリの街をランニングもしましたね。蚤の市でうつわや雑貨を見るのも宝探しみたいでワクワクしました。フランス語は全然できないけれど、笑顔で「ボンジュール」とあいさつするうちに、お店のスタッフと仲良くなれたのも楽しかった。

以前の私だったら、失敗を恐れてチャレンジできなかったと思います。でも、20代後半から始めたマラソンやラジオの仕事で、失敗は恥ずかしいことではなくて、自分のエネルギーになると気付けた。そこから、“何でもやってみる精神”になって、10日間のパリ生活でも、もっと失敗や恥ずかしいことをして強くなりたいと思ったんです。でも楽しすぎて失敗が物足りなかったので(笑)、コロナが収束したら、まずはパリに行きたいですね。
「強くてしなやかで、チャーミングな女性に憧れる」
Q06 自分の生き方に大きな影響を与えてくれたひとは?
迷ったとき、それから私のターニングポイントにいつも声をかけてくれるのが料理家の寺井幸也さんです。最初の本(『高山都の美 食 姿 「したたかに」「自分らしく」過ごすコツ。』/双葉社)を制作している時期に、結婚を約束していた彼とお別れをしてしまい、どん底を経験しました。かわいそうな女には見られたくないと、気持ちを奮い立たせてはいましたが、友人たちからするとウジウジしているように見えたんでしょうね。そんなときに彼から「いつまでもめそめそして、幽霊みたいな女にひとは寄ってこないよ」と言われて。ハッとして、前に進むきっかけになりました。
今もへこんだときや挫折をするたびにこの言葉を思い出します。大人になるにつれて、はっきりと助言してくれるひとは少なくなるから、とっても大事な存在。いつも彼には背中を押してもらっています。
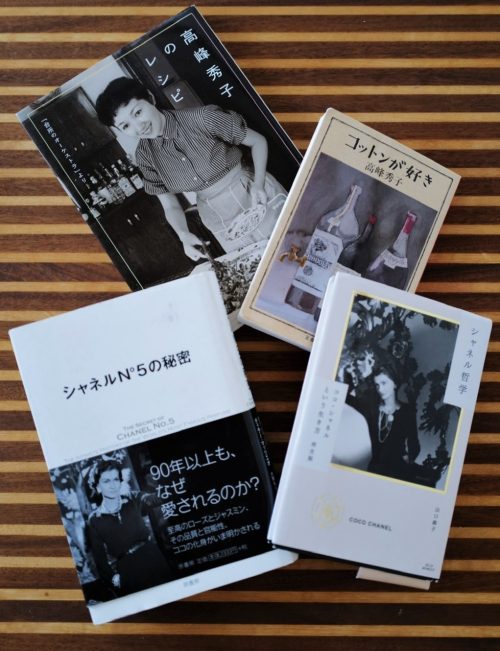
私もこういう女性になりたいという憧れの存在は、高峰秀子さんとココ・シャネル。阿川佐和子さんも大好き。3人に共通しているのは、強くてしなやかでチャーミングなところ。高峰さんは、エッセイを読んで好きになりました。『コットンが好き』が特にお気に入りで、うつわや小物の使い方に刺激をいただいています。
Q07 大切にしている言葉を教えてください!
「笑っていれば風向きは変えられる」。10年ほど前の誕生日に「都はいつも笑っていることで、いい方向に風を吹かせているから、そのまま頑張れ」と友人からもらったメッセージを大切にしています。今は、サインを書くときに添えているほど。私の座右の銘でもあるけれど、誰かの心に残ってそのひとの大切な言葉になればうれしいなと思っているんです。バトンを渡すような感覚ですね。
Q08 お気に入りの本を3冊挙げるとしたら?
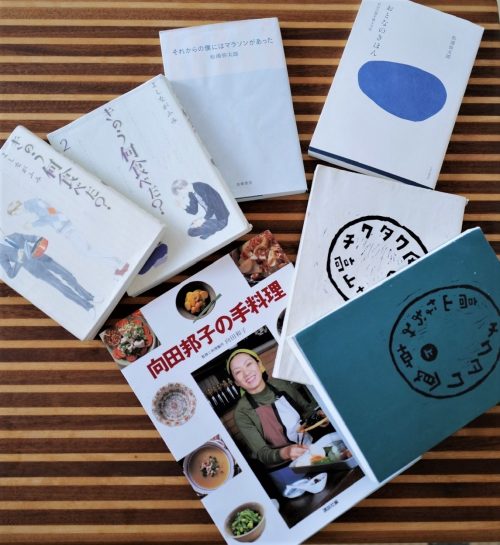
うーん、3冊に絞るのが難しいな。松浦弥太郎さんの『おとなのきほん 自分の殻を破る方法』と『それからの僕にはマラソンがあった』は、繰り返し読んでいる本です。2冊とも、はじめはみんなゼロからのスタートで、できないことは恥ずかしいことではないから続けることが大事だよと教えてくれる本です。読むたびに元気が出ます。
向田邦子さんの手料理を紹介した妹の和子さんの本『向田邦子の手料理』も、何度も興味深く読んでいます。脚本家、小説家、エッセイストとして忙しく活躍されながら、料理が上手でうつわにもこだわりがあったそうです。家庭料理のレシピとエピソードが素敵なんです。
それから、よしながふみさんの『きのう何食べた?』は、読んでいるとおなかが空いてくる本。高山なおみさんの『チクタク食卓』もお気に入りです。食にまつわる本が好きですね。
友だちや仕事仲間と本の話をするのも好きです。「この本、面白かったよ」と勧めてもらった本を読むことも多いです。読書には、知らないことを知る楽しさがありますね。
「愛されるものをつくりたい」
Q09 地球のために実践している、ちょっとイイコトを教えてください!
「なんとなくで物を選ばない」ことでしょうか。
うつわや雑貨が好きだし、おしゃれも好きなので、物を買わない選択はできないからこそ、本当に必要なものなのか、愛せるものなのかを基準に選んでいます。

安かったからとか、流行っているからと“何となく”で買ってしまうと、使わなかったり、すぐに飽きてしまいそう。家にはたくさん物があるけれど、どれも愛しているし、長く使っている大切なものばかりです。
今日着ているシャツは、フィービー・ファイロがクリエイティブディレクターをしていたときの「セリーヌ」のもので、ヴィンテージショップで出合った1枚です。当時の私には手が届かなかったけれど、巡り巡って私のもとにやってきました。試着をしたら驚くほどぴったりで、一緒にいた友人も「都っぽいね」と褒めてくれて、大切に着たい服だと思えました。誰かが手放したものを、大事に使うこともちょっとイイコトですよね。

I.T’.S. internationalと都さんのスペシャルコラボで実現したデニム。
服のプロデュースのお仕事もさせてもらっていますが、自己満足にならないように、“愛される服”を作りたいと思って臨んでいます。簡単には捨てられない、捨てたくない、大事にしたいーーそう思っていただけるものづくりも私のテーマの一つです。
Q10 2030年までに実現したい夢は?
愛されるものづくりにつながりますが、皆さんに大事にしてもらえるもの、こと、空間をプロデュースする会社を今年スタートさせようと準備しています。
本の発売時に全国の蔦屋さんでポップアップショップをやらせてもらったことが、きっかけです。私が愛用している調味料や好きな作家のうつわなどを集めて、私の書籍と一緒に販売をしました。うれしいことに、たくさんのお客さんが来てくださって。私もできるだけお店に立って接客をしたのですが、一人ひとりに合ったお皿を選ばせてもらうのがとても楽しくて、本当にいい経験になりました。

高山さんのセンスが詰まった書籍『高山 都の美食姿』は、大好評につき4冊を数えるまでに。
自分でセレクトしたものを集めてお店を開くことがまず第一歩。海外に行けるようになったら、パリに買い付けに行きたいですね。2030年には店舗数が増えていたらいいなと思うし、飲食店もオープンしていたいです!
石けんでオフできるのがうれしい!春夏の秀逸ミネラルパウダー
肌や体に良いもの、使い心地が良いもの、気分が上がるもの・・・コスメや美容ツールを上手に取り入れて、Hummingな毎日を送りたい。美容ライター 荒木奈々さんがおすすめをご紹介します。
優しいだけじゃない、春夏の肌がミネラルパウダーに頼りたい理由

体に必須のミネラル。ただし肌にのせるミネラルは食べるものとは違って、肌に負担をかけない、天然の鉱物の使用を意味しています。ミネラルパウダーはクレンジング不要で石けんで簡単に落とせるのが肌にも環境にも優しいし、今どきのミネラルパウダーはトリートメント効果に、プロテクト力、肌色補正と機能面もますます優秀。この春夏、一緒に過ごしたいミネラルパウダーとは?
My select 01 塗り直し用。MiMCのポンポンタイプ

ナチュラルホワイトニングミネラルパウダーサンスクリーン(ポンポンタイプ)[医薬部外品]SPF50+・PA++++ 全2色 各¥6,930/MiMC(限定販売中)
崩れにくい日焼け止めはたくさんありますが、朝塗っただけで一日を過ごすのはやっぱり無理。うっかり日焼けを防ぐには塗り直しがマストです。できれば2、3時間に一度! そのために携帯したいのが、メイクの上からも重ねられる“ポンポンUVパウダー”の定番、MiMC(エムアイエムシー)のもの。
MiMC は2007年に女性の科学者が立ち上げた国産コスメブランドで、「自然の力で女性たちの本来の輝きを引き出す」がコンセプト。天然ミネラルと植物美容成分で作られたベースメイクを中心に、スキンケア、メイクまでラインナップ、ミネラルファンデーションはコンパクトタイプのクリーム、リキッド、プレスト、パウダーと肌に合わせて選べるように4種類も用意されています。
ミネラルファンデーションは一般的にマイカ、酸化亜鉛、酸化チタンが使われており、MiMCではスキンケアミネラルといわれる酸化亜鉛の質や種類、量にこだわっているのが特徴的。もちろん防腐剤や合成着色料など、肌に負担をかける成分は一切入っていません。パウダータイプはブランドのなかでも長年愛されている一品で、ポンポン式は手を汚したくない外出先や、時短で仕上げたいときなどに活躍。
春夏シーズンに限定発売されるポンポンタイプのUVパウダーは、肌の刺激となりやすい紫外線吸収剤を使用せず、SPF50+・PA++++のカット力を発揮。しかもこの春夏の「ナチュラルホワイトニングミネラルパウダーサンスクリーン(ポンポンタイプ)」は、日中美容液のようなトリートメント効果が自慢。美白有効成分ビタミンC誘導体(ビタミンCリン酸Mg)&肌荒れ防止有効成分のグリチルレチン酸ステアリルのW有効成分のほかにも、肌のくすみの原因となる糖化に着目した植物美容成分などが配合されています。

〈左〉肌を明るく整えるクリアピンク、〈右〉重ねるほどに透明感をプラスするクリアベージュ。
ピンクとベージュの2つのカラーは、メイクアップアーティストが監修。そのためテクニックレスでも色ムラ、くすみ、毛穴もふんわりカバーし、重ねるほどに美しい仕上がりを演出できます。「日中の日焼け止め」と「美白・保湿のスキンケア」を叶える美容液UVパウダーは、ファンデーションを塗る日、塗らない日、さらに日当たりばっちりのレジャーの日にも肌にポンポン♪

美白有効成分はエラグ酸を採用。また湯原温泉水も配合。そのアルカリ性単純水にはさまざまなミネラルが含まれている。メラノリセット[医薬部外品] 30ml ¥9,570/MiMC
そうそう、MiMCといえば、女性に対する社会貢献活動もリスペクトしたいブランド。創業時からの取り組みが、今日のサステナブルの活動につながっていて、たとえばコスメを通じて途上国の女性をサポートするコフレプロジェクトなどにもいち早く賛同されていました。最新のサステナブルトピックスは「ナチュラルホワイトニングミネラルパウダーサンスクリーン(ポンポンタイプ)」と同日発売の100%天然の薬用美白美容液「メラノリセット」。宮古島産のアロエエキスが配合されているのですが、その売り上げの一部は宮古島の珊瑚礁保護NPO団体へ寄付されるそうです。
My select 02 ニオイも軽減するエトヴォスのボディ用

ミネラルUVボディパウダー SPF40・PA+++ 8g ¥3,300/エトヴォス(限定販売中)
“何となく肌に悪い”・・・そんな負のイメージがどこか拭いきれない日焼け止めやベースメイク。エトヴォスのそれらはミネラル系、スキンケア感覚で使えるもので、なかでも毎年春夏に登場するミネラルUVシリーズを心待ちにしている人は多いはずです。
ミネラルには種類があって、紫外線、ブルーライト、近赤外線から肌を守る働きを持つものが。そんなミネラルの性質を生かし、エトヴォスのミネラルUVシリーズは毎シーズン進化しています。肌をキレイに見せる2つのミネラルと、潤いを保つミネラルを増量したのが今回のポイント。フェイス用、ボディ用があります。
たとえば、ベタつきを抑えてサラサラさせたい春夏のボディは、パウダーをのせると潤いが奪われてしまって逆にカサカサしてしまうことがありますよね。特にミネラルは粉状のため皮脂や水分を吸収し、乾燥をまねいてしまうことがあるそうですが、このシリーズはマイカというミネラルを保湿成分でコーティング。特にヒアルロン酸(保湿成分)などで包んだパウダーを増量することで、しっとりなめらかな密着感を実現しています。もちろん余分な皮脂を吸着するミネラルのシリカやサンゴパウダーを配合しているので、じとじとせず清潔な肌もキープ。
それからうれしいのが香りの作用。イランイランの精油によって、汗や皮脂などニオイをさりげなくカバーしてくれます。独自のミネラルブレンドで叶った機能派パウダーは、珊瑚の白化の原因と考えられている紫外線吸収剤は使用せずのノンケミカル処方で高い紫外線防御力を保持。専用のクレンジングも不要です。
毎年変わるパッケージデザインもおしゃれ! 2022年バージョンは北海道生まれの絵描き・リー イズミダ氏とのコラボパッケージで、山や川、海や花などをイメージ。ワンシーズンで使い切る、ボディ用ミネラルパウダーです。
エトヴォス
https://etvos.com/
My select 03 プチプラ名品。イニスフリーのテカリケア

〈上から〉ノーセバム ミネラルパウダー N ¥825、同 モイスチャーパウダー N ¥1,056/ともにイニスフリー
汗なの? テカリなの? マスクしているから目に入りやすい他人のおでこ。自分も見えているおでこを涼しげに見せたくて思い出したのが、イニスフリーのノーセバムパウダー。
韓国のチェジュ島の恵みをふんだんに使ったスキンケアやベースメイクでおなじみのイニスフリー。誕生から22年、プチプラ分類に入るブランドでありながら数多くの名品を残しており、ノーセバム ミネラルパウダーは、全世界で累計販売数5,500万個を記録しているベストセラーです。ちなみにこのラインは、チェジュ島の太古から流れる溶岩海水生まれのミネラル塩と、天然のミントエキス(メンタアルペンシス葉)がメイン素材。ファミリーを年々増やし、ミネラルパウダーも皮脂を抑えるタイプ、皮脂ケアも保湿もするタイプなど数種ありますが、不動の人気が「ノーセバム ミネラルパウダー N」で、昨年に従来品の余分な皮脂としっかり吸着する働きかけはそのままに、クリーンな処方に刷新されました。
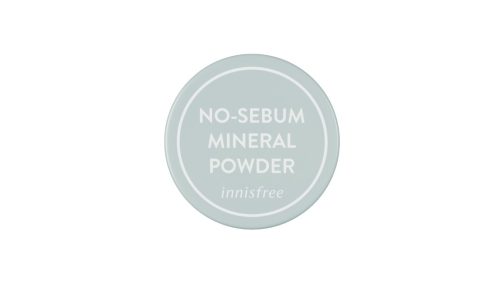
皮脂吸着パウダーとミネラル皮脂コントロールパウダー入り。そこまでのオイリーではないので、おでこや小鼻など、皮脂が出やすい部分に仕込みます。ひと塗りで毛穴のボツボツまでカバーされるのを感じられ、サラサラですべすべ肌に。また日中のくすみの原因は余分な皮脂による酸化が原因らしいので、夕方くすみやすいという人もぜひ。明るい肌がキープできるはずです。また裏技的にチークやアイブロウの前にパウダーを塗っておくのもおすすめです。皮脂による崩れが抑えられて、塗りたての発色が長持ちしますよ。
いつか行ってみたいチェジュ島! ユネスコ世界自然遺産に登録されていて、手つかずの自然が多く残るといわれていますよね。そこが原点であり、「肌に休息を与える島」という意味を持つイニスフリーは、“PLAY GREEN”と “SHARE GREEN” とエコ活動も活発。2012年から「イニスフリーの森」を作るグローバルプロジェクトをスタートさせ、チェジュ島の原生林をはじめ、世界8ヵ国の森林保全にも積極的です。また「紙のかわりにマイハンカチを」というスローガンを2010年から掲げ、オリジナルのハンカチを提案したり。サステナブルは小さな努力が大切だよ、安価でもいいものはいいなど、いろいろな側面でハッとさせられるブランドです。
イニスフリー
https://www.innisfree.jp/
ミネラルパウダーとは自然の恵みをいかした有能アイテム。落とすのも簡単だし、肌への負担が少ないので、好みの機能で自分に合うミネラルパウダーを探してみてはいかがでしょうか。
森カンナ「だらだらモードから脱出する方法」【連載 / ごきげんなさい vol.05】
俳優 森カンナさんが日々の生活のなかで見つけたこと、感じた想いを綴る連載エッセイ「ごきげんなさい」。自分を“ごきげん”にするためのヒントを探しましょう。
別府から届く入浴剤で、幸せに浸る“温泉”時間を
温泉に浸かった瞬間に、思わず口からもれてしまう「ハ~」という深呼吸。寒い一日の終わりに、自宅のお風呂でも「ハ~」できたら最高ですよね。この冬に発売された「HAA for bath」は大分県別府温泉の湯の花を原料にした、本物志向の入浴剤。その魅力をフィーチャーします。
“限りなく天然温泉に近い入浴剤”の背景

まるでスイーツのようなおしゃれなパッケージが目を引く「HAA for bath」。可愛い顔をして、その中身はかなりの本格派。原料は別府温泉でおよそ350年前からつくられている“湯の花”で、職人さんの手によって大切に、丁寧に育てられた“温泉の結晶”です。
別府市の明礬(みょうばん)温泉地区は、地面のおよそ30cm下に温泉脈がある地熱地帯。ここに建てられたわら葺き屋根の小屋の中で、夏場は40日以上、冬場は60~70日という時間と手間をかけて、別府独自の湯の花が作られています。温泉の沈殿物などを採取する通常の方法ではなく、“湯の花小屋”で結晶を作り出すというこの特殊な製造技術は、国の重要無形民俗文化財に指定されている、世界唯一の手法なのです。

小屋の地面には、地表から噴出する温泉ガスの蒸気が均等に小屋内にいきわたるように栗石で石畳がつくられ、その上に土地特有の青粘土が敷き詰められています。温泉ガスの蒸気が栗石のすき間から青粘土の中に入り、ガス中の成分と青粘土の成分が結晶したものが、別府湯の花。湯の花の結晶は、1日1ミリずつしか成長しないそう。
「HAA for beath」は、この貴重な“手作りの湯の花”ありきで生まれた入浴剤。
じっくり時間をかけて作られた湯の花に別府の温泉水を混ぜて不純物を取り除き、湯の花エキスを精製、抽出。このままだと肌への刺激が強いため、有効成分であるセスキ炭酸ナトリウムやホウ酸を混ぜて熟成させ、強酸性から弱アルカリ性に変化させています。

湯の花作りから入浴剤が完成するまでのプロセスは、およそ3ヵ月! 作り手の想いが詰まったアイテムなのです。
優しい肌触りのなめらかな湯質

「HAA for bath」をお湯に入れるとーー白く濁って、とろりとしたお湯に変化。まるで温泉さながらの気分を味わえます。ミネラル成分が肌の表面をやさしく覆ってくれるので、体の熱が逃げにくく、お風呂上りも体がぽかぽか。素材そのままの無香料で仕上げられているので、子供から大人まで使いやすいのもうれしい限り。

日常使いにおすすめな約15回分の大容量パック。「HAA for bath」 900g ¥5,830
風呂釜やバスタブをいためてしまう原因となるイオウを含まない製法で、毎日使っても安心。上の写真の約15回分の大容量パックはお得な定期便購入もあるので、ハマった方にはそちらがおすすめ。約3回分のお試しセット(¥1,290)もあります。

約10回分のセットは、ギフトにもぴったり。「HAA for bath 日々」60g×10個入り ¥5,280
小分けにされた入浴剤の包み紙の裏に、日記のような短い文章が綴られてる「HAA for bath 日々」。バスタブに浸かりながら、“誰か”が書いた文章を読み、書き手の想いに触れてみて。体だけでなく、心も温まるはず!
“別府愛”が生み出した「HAA」

「別府の街の魅力は、日常のなかに温泉が溶け込んでいるところ」と語る池田さん。湯煙が立ち上る別府の街を背景に。
「HAA」の代表を務める別府出身の池田佳乃子さんは、東京と別府のデュアルライフを実現している女性。東京と別府を行き来しながら、“湯治”をコンセプトにしたライフスタイルブランド「HAA」を立ち上げました。

別府の地層や温泉からなる湯の花は、有限ともいえる自然資源。そして職人さんによる湯の花小屋での湯の花作りも、時間と体力、技術を要する大変な仕事です。資源と文化をどのように守り、持続可能にしていくかーー池田さんは、未来を見据えながら今後の展開を考えているそうです。
「日常生活に、深呼吸を届ける」ことをミッションにスタートした「HAA」。別府温泉まで足を伸ばす時間はないけれど、おうちで温泉の癒しを得られる入浴剤で、「ハ~」を連呼してしまう幸せな時間にトリップしてみて。
森カンナ「結婚という幸せの噛みしめ方」【連載 / ごきげんなさい vol.04】
俳優 森カンナさんが日々の生活のなかで見つけたこと、感じた想いを綴る連載エッセイ「ごきげんなさい」。自分を“ごきげん”にするためのヒントを探しましょう。
森カンナ「それでも生きていかにゃならんし。2021の振り返り」【連載 / ごきげんなさい vol.03】
俳優 森カンナさんが日々の生活のなかで見つけたこと、感じた想いを綴る連載エッセイ「ごきげんなさい」。自分を“ごきげん”にするためのヒントを探しましょう。
森カンナ「もしかしたら、本当の私はもっと・・・?」【連載 / ごきげんなさい vol.02】
俳優 森カンナさんが日々の生活のなかで見つけたこと、感じた想いを綴る連載エッセイ「ごきげんなさい」。自分を“ごきげん”にするためのヒントを探しましょう。
自分も環境も美しくあるために。エシカルなメイクアイテムを選択
いつまでも前向きに楽しく暮らしていくために、美しく歳を重ねていきたいもの。そのためには、意識して自分に手をかけてあげることも大切です。あなたの心地よい毎日をサポートする、自分にも環境にも優しいコスメをご紹介します。今回は、よりエシカルに生まれ変わったSHIRO のメイクアップコレクション。
SHIRO のエシカルな新メイクアップコレクション

地球が生み出した限りある資源。環境への負荷を最小限にするために、捨てられてしまうものや、あらゆる素材を恵みに変えること。そして、生産者の思いを紡ぎ、伝えることで、関わっているすべての人を笑顔にして、100年先の世界も幸せにしたい・・・。
そんな想いから、SHIROはメイクアップコレクションをリニューアル。もともと箱なし製品をエシカル割として販売することで、環境にもお財布にも負担をかけない取り組みをはじめ、さまざまな努力をしていましたが、さらにエシカルな視点でパッケージデザインとカラーを刷新。
製品に使用するプラスチック量の削減、付属ブラシの廃止、カラーごとの量の調整や、長く最後まで使えることにこだわったカラーラインナップなど、より環境に配慮したアイテムに生まれ変わって登場しました。

ジンジャーリップスティック 全7色 各 ¥4,400、エシカル割(箱なし製品) ¥4,268/SHIRO
とろけるようなテクスチャーのリップは、何度も塗り直したくなるような使い心地。保湿成分である高知県の矢野農園でつくられる香り高いジンジャーとガーナ産の未精製シアバターを配合。唇の荒れや縦ジワをケアし、ぷるんとした潤いを与えます。

エッセンスリップオイルカラー 全8色 各 ¥3,850、エシカル割(箱なし製品) ¥3,735/SHIRO
メイクするたびにさわやかなゆずが香るオイルリップは、人気の3色に、仕上がりの異なる5 色がプラス。唇に潤いを与えてケアしながら、透明感のあるカラーで抜け感のある唇に仕上げてくれます。

ジンジャーアイシャドウパレット 全4種 各 ¥7,480、エシカル割(箱なし製品) ¥7,256/SHIRO
人気のジンジャーアイシャドウパレットは、指で馴染ませやすい質感に仕上げることで付属のブラシを廃止。また、スリムなデザインに変更することで、パッケージに使用するプラスチックの量を削減。パレット内の4色は色に合わせた質感を採用し、そして色ごとに量を調整することで、最後まで使い切りやすくしたそう。

亜麻ネイル 全13色、トップコート、ベースコート 各¥2,640、エシカル割(箱なし製品) ¥2,561/SHIRO
爪を健やかに保つアマニ油をベースに配合した亜麻ネイル。既存の人気色にベーシックな7色を加え、トレンドにとらわれないカラーラインナップに。長く愛用してもらうことで、ゴミの削減に貢献します。
ホリデーコレクションは、プラスチックフリー!

シアアイシャドウ&ハイライターパレット 全3種 〈上から時計回りに〉1K01 スパークルイエロー、1K02 メタリックカッパー、1K03 ヌードローズ 各¥5,940/SHIRO ※11月18日数量限定発売
ホリデーシーズンに登場するのは、メイクをするときのワクワクするした気持ちを高める、ラメとパールのきらめく質感が楽しめるパレット。ホリデー仕様のアイシャドウに、華やかな艶めきを与えるゴールドのハイライターを組み合わせた3種類のカラーがラインナップ。
パレットは紙でできていて、使用後は燃やせるゴミに。また、ラメにはプラスチックフリーの素材を利用し、環境にも配慮。ホリデーシーズンが終わっても長く使えるカラーやパレットのデザインが特長です。
これからもエシカルなものづくりを目指して

「自分たちが毎日使いたいものをつくる」というシンプルな想いからスタートしたコスメブランドである、SHIRO。自社内に開発から販売まですべての機能を持ち、創業当初からエシカルな信念に基づいたものづくりを続けています。
その使命の一つが、国内外から見つけ出した、厳しい自然が育んだ素材の力を最大限に引き出すスキンケアやコスメ、フレグランスを提案すること。その代表ともいえるのが、SHIROの人気No.1美容液「がごめ昆布美容液」。

がごめ昆布美容液 60ml ¥6,050/SHIRO
もともと捨てられるはずだった昆布の岩肌の部分を利用して作られたという保湿成分、ガゴメエキスを配合。余計なものは加えず、ほぼ水とガゴメエキスでできているという、シンプルなものづくりがなされている製品なのです。
ちなみに、がごめ昆布は限られた海域の水深が深い海で生育している貴重な昆布で、真昆布などの一般的な「だし昆布」と比べ、圧倒的に「とろみ」が強いのが特徴。SHIROは、昆布の岩肌の部分のとろみ成分が、昆布の表面と同じように、肌表面でも水分をたくわえて保持し保水力を発揮してくれることを発見。この力を生かすことができないかと、創業当初からスキンケア開発を続けた結果、誕生したのだそう。
選んだものが環境への配慮につながり、そして私たちの未来につながっていく––持続可能な社会を実現するために、コスメを選ぶときにも、エシカルな選択をしていきましょう。
SHIRO
https://shiro-shiro.jp/
井上咲楽さんに聞く、丁寧な暮らしの秘訣【気になるあのひとに10の質問】
オリジナルなスタイルを持って生きている素敵なひとに聞く、10のQuestion。
心や暮らしの豊かさは、ブレない生き方や考え方が築くもの。
内面から輝くひとは日々どのようなことに目を向け、何を実践しているのか––
心地よく、充実した毎日を生きるためのヒントが見つかるはず。第一回目はタレントの井上咲楽さんにお話を伺いました。
「手作りしたものに触れると、丁寧に生きた気持ちになります」
Q1 最近幸せだと感じたことは?
自分一人のために使っている時間に幸せを感じます。以前は一人暮らしが寂しいと感じていたけれど、今はそれがすごく贅沢だなと思っていて。パワーアップするためにジムで鍛えたり、お風呂上がりにボディクリームを塗ったり、自炊して自分のためにご飯を作ること、そして好きなものづくりに集中できること・・・まさに至福の時間です。
それから食べ物で季節を感じたときにも幸せな気分に。コロナ禍で閉塞感が続いたなかでも、旬の食材から四季を感じることで、“時間は進んでいる”と感じることができました。
Q2 おうち時間の楽しみは?
作ること、何かを生み出すことが大好きです。最近は蜜蝋ラップを手作りしたり、お笑いコンビ・ミキの昴生さんにお子さんが生まれたのでスタイを作ってプレゼントしました。何か気になったものがあると、すぐに「これ、作れないかな」という発想になるんです。
私はいつも、自分の力で生きていきたいなと考えていて。自分の力で生きるというのはいわゆる自立した女性というよりも、自給自足のサバイバー的目線です(笑)。だから自分の手で作り出すことに意味があって。作り置きを活用したりして、家に帰ってきて自分で作ったにらダレを豆腐にかけて食べているだけでホッとします。「今日も自分で作ったもので生活した」と少し丁寧に生きた気分になれます。
>>”自分らしく生きる”とは?|仕事や恋愛で自然体で過ごせる方法を紹介

手作りの蜜蝋ラップ
Q3 最近のビッグニュースは?
昨年トレードマークだった太眉をカットしてから、これまで以上に仕事もプライベートも充実して、人生が大きく変わりました。ファッション誌や美容誌の撮影など新しい仕事も増え、今年の9月15日にはファーストフォトブック『さよならMAYUGE』を発売しました。

Instagram(@bling2sakura)より。
実はこのフォトブックに収録した写真はすべてレタッチなし。撮影日までに筋トレや食事、肌管理に気を使ってきました。トレーニングではお尻を重点的に鍛えたのでぜひ見てほしいですね。
ひたすら自分を追い込むのではなく、リラックスしながら体づくりに取り組めたので、仕事しながらでも上手く鍛えられたと思っています。今もジムには通い続けていて、レッグプレスでようやく100キロ上がるようになりました!

『さよならMAYUGE』より。撮影/曽根将樹(PEACE MONKEY)
Q4 自分のスタイル(生き方、こだわり)に大きな影響を与えたひとやものは?
芸能界入った頃からエレファントカシマシさんの曲をよく聴いています。働く上でのモットーは、流すように仕事をしないこと。どんなに忙しい日でも一つひとつの仕事に対してきちんと立ち止まって、丁寧に向き合いたいです。仕事前にしっかりと気合いを入れたいときに曲を聴くと、前向きな気持ちになれます。
それから母の影響も大きいです。SDGsへの関心が高まるなか、私の暮らし方をサステナブルな暮らしとして取り上げていただく機会が増えました。私の日常生活にある知恵や工夫は実家での暮らしで身についたもので、どれも私にとっては当たり前のことですが、驚かれることが多いです。
例えば食器や調理器具に油やソースなどが残ったまま洗わず、ボロボロになった服やタオルを切ったウエスで拭き取ってから流しに入れます。そうしないと母にものすごく怒られて(笑)。また、田舎はゴミ出しにお金がかかるので、日ごろからあまりゴミを出さないこと、ゴミは小さくしてから捨てるよう言われていました。牛乳パックもきちんと開いてから分別してリサイクルに出したり、開いた牛乳パックをまな板代わりに活用してから捨てたり。
ベジブロスを作るために野菜の皮や芯などは捨てないようにし、玉ねぎの皮で洋服を染めることも。薪ストーブに手のひらサイズの石を入れて、それを新聞紙に包んでカイロ代わりにしていました。
家族間にはゴミになるのはもったいない、何か使えないかという発想で工夫して最後まで使い切る意識があったと思います。

着なくなった洋服を裂いてウエスに。
Q5 最近言われてうれしかった言葉は?
美容系の仕事が増えたこともあり、友達に「このときの化粧品、何使ってるの?」「最近出たコスメで何を狙ってるの?」と聞かれるのはうれしいですね。また、私のInstagramの投稿に対する皆さんからのコメントも日々の活力になっています。投稿したコスメの購入報告や、何気なく載せた料理写真に「作りました!」とコメントをくださったり。自分の発信することが、皆さんの行動の小さなきっかけになれていると思うとうれしいです。
「好きなことを追求し続けて、いろいろな仕事にチャレンジしたい」
Q6 今欲しいものは?
活版印刷機が欲しいです。子供の頃に家族で「井上家新聞」を作っていました。例えば「今月は月見団子食べました」など家族の思い出を残していたのが懐かしくて、もし印刷機が手に入ったら「今月の自分!〜咲楽出版」のような冊子を作りたい! 完全に自己満足です(笑)。
Q7 挑戦してみたい“新しいこと”は?
太眉に頼れない今、自分の力で、積極的にいろいろなことにチャレンジしていきたい気持ちでいっぱいです。例えば発酵食品などの保存食や、何かの手作りキットを出してみたいです。雑誌の表紙を飾ったり、トークライブも実現できたらいいなと構想中です。
最近は政治への関心や昆虫食のことなど、今までやってきたことの点と点が少しずつつながって、線になってきたように思います。自分本来の関心事や暮らしが自然と仕事に結びついたり、仕事内容が自分の好きなことや興味がある分野ということも多く、ますますやりがいを感じます。
>>自己肯定感とは?|意味や似ている言葉との違いをわかりやすく解説

自作の“選挙ノート”を手に街頭演説を聞く咲楽さん。選挙期間中は各選挙区の候補者の選挙戦を追う。
Q8 好きな場所は?
地元である栃木県の益子町は落ち着きますね。ものづくり、暮らしづくりの里としてわざわざ益子町に移住される作家さんもいらっしゃるほどで、作品や制作風景を見るだけで私も創作意欲が湧きますし、原点に戻って頑張ろうと思えます。益子町は都会のように欲しいものが簡単に手に入るわけではないですが、“足りない”くらいが自分は合っているなあと。ぬくもりに溢れるだけではなく、生き抜く力のある場所だと感じます。
Q9 地球のために実践している、ちょっとイイコトを教えてください。
プラスチック容器ではなく瓶入りのものを購入することが多いです。ご飯を温めるときはお茶碗の上にお皿をかぶせてラップの使用頻度を減らす工夫を。それと、3年ほど前から卵の殻のうす皮を利用して化粧水を手作りしています。

長年作り続けている手作りの化粧水。
Q10 2030年までに実現したい、あなた自身の夢やテーマを教えてください。
地元の古民家や使われていない建物をコツコツと改装して、自分のアトリエ兼カフェを作るのが夢です。普段から甘酒やしょうゆ麹など発酵食品を作ったり、昆虫食は昆虫食仲間に分けてもらったり、自分で購入して料理に取り入れています。アトリエ兼カフェでは昆虫食をおしゃれに見せたり、発酵食品や保存食をいっぱい出したいです。
ちなみに初めての昆虫食はハチの子とコオロギで、食べる前は少し構えましたが、美味しくてすっかりハマりました。昆虫食は美味しさもさることながら、原型を残した状態で出てくることが多く、より食材に命を感じられる良さがあります。食育にもいかせる部分はあるのではないかなと思っています。
>>【変わりたいあなたへ】自分を変えることは難しい?変われる方法や習慣
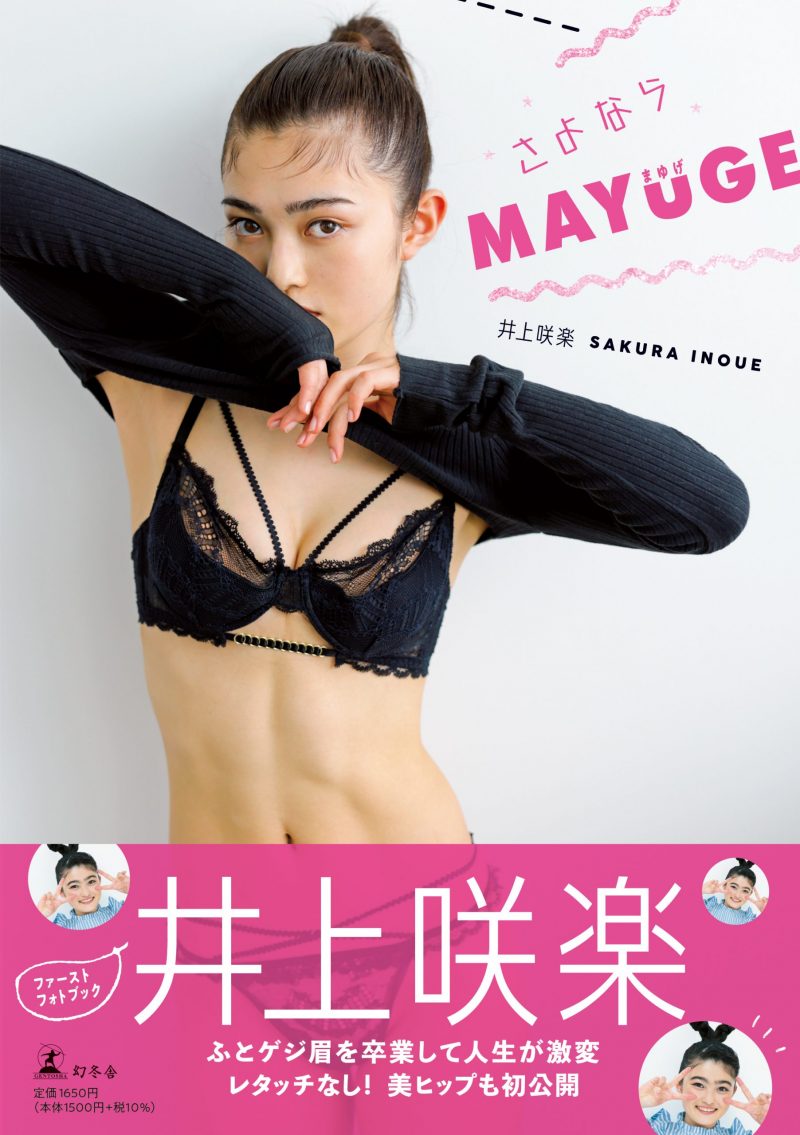
昨年末にトレードマークだった「ゲジ眉毛」を整えたら、「人生が好転し、新たな世界が見えてきた」というファーストフォトブック。この本のために鍛えたレタッチなしのリアルなボディ、眉毛の秘密、丁寧な暮らし、ボディメイクの裏側も紹介。これまで語られなかった人生の転機、今の気持ちを収録したロングインタビューなど、井上咲楽のすべてが詰まった一冊。
『さよならMAYUGE』¥1,650 井上咲楽 著/幻冬舎
>>Amazonで購入する

Profile
井上咲楽(いのうえさくら)
1999年10月2日生まれ、栃木県出身。
第40回ホリプロタレントスカウトキャラバン特別賞でデビュー。
バラエティ番組のほか、女性誌のモデルやグラビアなど活躍の場を広げている。
趣味は昆虫食や国会傍聴、発酵食健康アドバイザーの資格を持つ。

