人間関係を円滑に保つ方法|不安を力に変える実践ステップ

苦手な相手からの突然のメッセージ。それだけで気分が沈んだり、イライラしたりしてしまう。そんな経験はありませんか?
私たちは、苦手な相手が身近にいるだけで、ストレスや不安を感じることがあります。
本記事では、人間関係でストレスを感じた時に取ってしまいがちな行動パターンと、人間関係をできるだけ円滑に保つための方法を紹介します。
人間関係を悪化させる、よくある3つの反応パターン

人間関係でストレスを感じたとき、私たちの反応は大きく3つのパターンに分けられます。
① 攻撃的に返すタイプ
イライラした気持ちをそのままぶつけて、きつい言葉を返したり、強い態度を取ってしまうケースです。
その瞬間はスッキリするかもしれませんが、後から後悔することが多いでしょう。
② 無視・回避するタイプ
面倒に感じて、メッセージを無視したり、スマホを置いて気持ちをそらす行動です。
そのときは少し楽になりますが、問題は何も解決せず、関係がさらに悪化することもあります。
③ 何もできなくなるタイプ
どう対応していいか分からず、何も言えずに黙り込んでしまうケースです。
一時的には自分を守ろうとする反応ともいえますが、状況が変わらず、問題が長引く原因になることもあります。
関連記事:境界線を見直せば人間関係がラクになる|今日から始める距離感の整え方
反応パターンは状況や相手によって変わる

人間関係のストレスに対する反応は、場面や相手によって異なります。
たとえば、職場では攻撃的に反応しがちでも、プライベートでは逃げる傾向がある人や、友人とのやり取りでは無視するタイプでも、家族との問題になると攻撃的に反応してしまう人などです。
自分の反応パターンに気づくことが第一歩

反応の仕方は相手や状況によって変わるものです。しかし、どんな場面でも共通していえるのは、無意識の反応が人間関係を悪化させるということです。
その悪循環を断ち切るには、まず自分の反応パターンに気づくことが重要です。
人間関係にストレスを感じた時の自分の反応パターンを知るためには、「何を考え」「どう感じ」「どんな行動を取ったか」を整理してみましょう。
【反応パターンを整理するステップ】
- 不快感を覚えた具体的な状況を思い出す
- そのときの「思考」「感情」「行動」を紙に書き出す
- それらがどのようにつながっていたのかを振り返る
関連記事:パッシブ・アグレッシブな行動をやめて、素直に自分の気持ちを伝える方法
まとめ
人間関係のトラブルやストレスは、誰にでも避けられないものです。
ですが、自分の反応パターンに気づき、その流れを整理することで、不安や怒りに振り回されず、冷静に状況に向き合うことができるようになります。
人間関係をできるだけ円滑に保つためにも、まずは今日から、自分の内面を冷静に見つめ直す時間をつくってみてください。
境界線を見直せば人間関係がラクになる|今日から始める距離感の整え方

「なぜか人間関係に疲れてしまう」
「距離の取り方がわからない」
そんな悩みを抱えていませんか?
その悩み、境界線がうまく引けていないことが原因かもしれません。
境界線とは、相手との距離を保ちながら、自分自身を守るための“見えない線”。
この記事では、健全な境界線の築き方を7つのステップでわかりやすく解説します。
境界線とは?

境界線は、自分と他人の間に「何がOKで、何がNGか」を伝えるための明確なサイン。
相手を遠ざけるためではなく、健全な距離を保ちつつ、自分の気持ちや価値観、行動の自由を守る役割を果たします。
境界線があることで得られる6つのメリット
- 自立心が育ち、依存的な関係を防げる
- 相手との接し方に対する期待が明確になる
- 自分の意思を尊重し、自己肯定感が高まる
- 精神的・身体的な安心感を保てる
- それぞれの責任範囲がはっきりする
- 自分の欲求や感情が他人と混ざらなくなる
これらのメリットから、境界線が「人間関係を断ち切る線」ではなく、「より良い関係を築くための土台」であることがわかります。
自分自身を理解し、相手との関係に安心感を持つためにも、境界線を意識することが重要です。
関連記事:たとえ変化しても、パートナーと共に成長していくには
境界線の種類とは?人間関係に必要な5つのカテゴリー

境界線は「ただの線引き」ではありません。
人間関係における境界線にはさまざまな種類があり、状況や相手によって必要なタイプが異なります。
ここでは、よく見られる5つの境界線について、具体例を交えて解説します。
1. 身体的な境界線
身体的境界線とは、自分の体や空間に対する感覚的な快適さを守るための線です。
たとえば、ハグよりも握手の方が安心できるという人は、身体的な境界線を自然に意識しています。
「長時間の外出は疲れるから途中で休憩を入れたい」
「私の部屋に入るときはノックしてほしい」
このように、自分が心地よくいられる範囲を相手に伝えることが大切です。
2. 性的な境界線
性的境界線は、同意や快適さを尊重するために欠かせません。
パートナーとの間でも「言わなくてもわかる」は通用しません。
「性的なスキンシップはお互いが心地よいときにしたい」
「避妊や頻度についてきちんと話し合いたい」
恋人同士や夫婦であっても、境界線の確認は関係を深めるための重要なコミュニケーションです。
3. 感情的な境界線
感情的な境界線とは、自分の気持ちや心の平穏を守るためのものです。
人の話を聞くのは大切ですが、他人の感情に振り回されすぎると、自分自身が疲れてしまいます。
「仕事中は深刻な話は避けてほしい。集中したいから」
「断ったことで怒られても、それは私の責任じゃないと思っている」
感情を切り離す力も、健全な人間関係には必要です。
4. 金銭的・物質的な境界線
お金や物を貸す場面では、相手との関係が悪化することも少なくありません。
特に「断れない性格」の人は、後から不満をため込むケースもあります。
「充電器は貸すけど、使い終わったら戻してね」
「申し訳ないけど、お金は貸せない」
自分が納得できない貸し借りは、後のトラブルの原因になります。
5. 時間に関する境界線
時間的な境界線は、日々の生活や仕事の効率、自分のリズムを守るために必要です。
相手に合わせすぎていると、自分の大切な時間が奪われてしまいます。
「平日の昼間は忙しいので連絡は控えてもらえると助かる」
「週末は自分の趣味の時間を大切にしたい」
自分の時間を優先することは、わがままではなく自分を大切にする行動です。
境界線は相手によって柔軟に調整する必要がありますが、自分の中に「これは譲れない」という軸を持つことが何より大切です。
境界線は変化するもの|関係や状況に応じた見直しのポイント

境界線は人間関係の深まりや、ライフステージの変化によって、少しずつ変化していきます。
たとえば、付き合い始めの恋人との関係と、10年目の夫婦では、お互いに求める境界線が違って当然です。
また、引っ越し、転職、出産、病気など、人生のイベントによっても、今までうまくいっていた境界線が合わなくなることがあります。
なぜ境界線を見直すことが大切なのか?
- 境界線が古いままだと、現在の自分の価値観や状況とズレてしまう
- 相手も変わっていくため、一方的にルールを固定すると摩擦が起きやすくなる
- 定期的な見直しによって、お互いにとって無理のない関係が保てる
境界線は“線”ではなく、“対話のきっかけ”とも言えます。
変化に気づいたら、それを相手と共有することで、むしろ関係が深まることもあります。
境界線の変化例:こんなとき、見直しが必要です
|
以前の境界線例 |
変更後の境界線例 |
| 家族に対して「必要ならお金を出す」と言っていた | 収入が減ったので「今は経済的に支援できない」と伝える |
| 同僚の頼みを断れず、週末も手伝っていた | 子どもが生まれたため「土日は家族優先」と伝える |
| 友人の愚痴を毎日のように聞いていた | 精神的に負担が大きくなり、「週に1回程度にしてほしい」と伝える |
| パートナーに合わせて週に何度もセックスをしていた | 自分のペースが変わったため、「他の形の親密さも大切にしたい」と提案する |
| 親族にガレージを貸していた | 自分の荷物を置くために「そろそろ引き取ってもらえますか」と頼む |
こうした調整は、「わがまま」ではなく、変化に適応するための柔軟な対応力です。
見直しのときに大切なこと
- まずは自分自身の変化に気づくこと:「今まで通りだと苦しい」と感じたら、それが見直しのサインです
- 相手にわかりやすく伝えること:「変わった理由」を冷静に説明することで、相手の理解が得られやすくなります
- 一方的に決めつけないこと:話し合いを通じて、新しいルールを一緒に作っていく意識が大切です
境界線は、あらかじめ完璧なものを作る必要はありません。
むしろ、大切なのは変化を受け入れ、必要に応じてアップデートする柔軟さです。
状況に応じて境界線を見直すことは、自分を守るだけでなく、相手との関係をより健全に保つための前向きな選択となります。
関連記事:心も関係も整える:自宅で始めるカップル&ファミリーカウンセリング
不健全な境界線とは?その特徴と背景にある心理

これまで、健全な境界線が人間関係にとっていかに大切かを見てきました。
しかし現実には、「境界線をうまく引けない」、「そもそも意識したことがない」という人も多いのではないでしょうか。
境界線がうまく引けていない状態が続くことで、知らず知らずのうちにストレスや不満が蓄積していることもあります。
ここでは、不健全な境界線の具体的な特徴と、その背景にある心理について解説します。
不健全な境界線の2つのパターン
境界線がうまく機能していない状態には、大きく分けて次の2つの傾向があります。
① 過剰に厳しい(硬すぎる)境界線
- 感情を一切共有しない
- 他人との距離を極端にとる
- 援助や親しみを拒否しがち
このタイプの人は、「自分のことは誰にも知られたくない」「誰にも頼れない」という思いを抱えていることが多く、結果的に人間関係が孤立しやすくなります。
② 緩すぎる(曖昧すぎる)境界線
- 断れない/頼まれるとNOが言えない
- 他人の感情を過剰に引き受ける
- 自分のスペースや時間を犠牲にする
この状態では、「自分を大切にするより、相手に好かれることが大事」という心理が強く、心身ともに消耗しやすくなります。
なぜ不健全な境界線になってしまうのか?
境界線がうまく引けない背景には、性格や家庭環境、過去の経験などが関係していることがあります。
ここでは、不健全な境界線が生まれる典型的な心理的要因を見ていきましょう。
コントロール欲求
相手を操作する手段として、意図的に境界線を硬くしたり、感情を遮断することがあります。
たとえば、「話しかけないで」と言いながら、相手を試しているようなケースです。
拒絶されることへの恐れ
「本音を出したら嫌われるかも」「要求を伝えたら関係が壊れるかも」という不安から、自分の境界線を守ることを後回しにしてしまいます。
境界線教育の欠如
育った家庭で個人の境界線が軽視されていた場合、そもそも「境界線を守る」という概念を学べていないことがあります。
親や兄弟にプライバシーを尊重してもらえなかった経験が、影響していることもあるでしょう。
八方美人・過剰な同調性
人に嫌われるのが怖くて、つい過剰に合わせてしまう。
「断るなんて申し訳ない」「もっと頑張らなきゃ」と思い、自分の限界に気づけなくなってしまいます。
低い自己肯定感
「自分には意見を言う価値がない」「相手を優先しなければ認めてもらえない」という思い込みが、境界線を曖昧にさせます。
周囲も境界線の曖昧さを当然だと受け止めてしまい、さらに境界が軽視される悪循環になります。
気をつけたい「助けすぎ=イネイブリング」の落とし穴
誰かが依存症や精神的な問題を抱えているとき、心配からつい過剰に手を差し伸べたくなることがあります。
しかし、これが「イネイブリング(過剰な援助)」となると、本人が問題に向き合う機会を奪ってしまいます。
たとえば、
- 飲酒運転で捕まった家族の代わりに罰金を肩代わりする
- ギャンブルの借金を内緒で立て替える
- パートナーの対人不安を理由に、会話や対応を代行してしまう
一見「優しさ」に見えても、それは相手の成長や回復を妨げる行為になる可能性があります。
相手の思いを受け止めながらも、必要以上に背負いすぎない距離感が健全な境界線と言えるでしょう。
境界線を設定する4つのステップ

健全な境界線の必要性は理解できても、「どうやって伝えればいいのか分からない」「うまく断れない」と感じている人は多いのではないでしょうか。
この章では、境界線を築くための基本ステップを4つに分けてご紹介します。
ステップ1:自分が何を望んでいるかを明確にする
境界線とは、「自分の快・不快を理解すること」から始まります。
まずは、自分がどんな価値観を持ち、どんなことにストレスを感じるのかを把握することが大切です。
たとえば以下のような問いを自分に投げかけてみてください。
- どんな人との関係に安心感を覚えるか
- どういう態度や言動に不快感を覚えるか
- 「こうしてもらえると嬉しい」と思うことは何か
この自己理解があってこそ、「何をどこまで許容するのか」という境界線を見極めることができます。
ステップ2:相手に伝えるタイミングと言葉を選ぶ
境界線は、一人で完結するものではなく、相手に伝えることで初めて機能します。
まず、伝えるタイミングは「お互いが落ち着いているとき」を選びましょう。
喧嘩の最中や疲れているときに話すと、感情的に受け取られやすく、誤解や反発を招きやすくなります。
また、「Iメッセージ」を使って、自分の気持ちを主語にして伝えることが効果的です。
(例)
×「あなたっていつも部屋に勝手に入ってくるよね」
○「私は、部屋に入るときはノックしてもらえると安心するんだ」
さらに、なるべく具体的な言葉を使うこともポイントです。
「もう少し配慮してほしい」よりも、「夜10時以降は電話を控えてほしい」と伝えたほうが、相手にも意図が伝わりやすくなります。
ステップ3:境界線を守るための姿勢を持つ
一度伝えたからといって、すぐに境界線が守られるとは限りません。
特に今まで曖昧な関係だった相手に対しては、こちらが「本気でそう望んでいる」ことを示す必要があります。
相手が忘れていた場合には、「もしかしたら伝わっていなかったかもしれないけど……」と優しく再度伝えるようにしましょう。
もし境界線を破られた場合は、「これが続くようなら○○する」といったように、自分なりの対応や行動をあらかじめ決めておくと安心です。
そして何より、自分自身がそのルールを一貫して守ることが大切です。
こちらがあいまいな態度をとっていると、相手にもその意図が伝わりにくくなります。
ステップ4:相手の境界線も尊重する
境界線は一方的なものではありません。
自分の気持ちを大切にするのと同じように、相手の気持ちや価値観も尊重することが、信頼関係を築くうえで欠かせません。
たとえば、相手から「今は話したくない」と言われたときに無理に問い詰めたり、「今日はひとりで過ごしたい」と言われたときに不満をぶつけたりしないなど。
こうした小さな配慮が、互いに安心できる関係をつくっていきます。
また、相手が勇気を出して境界線を伝えてくれたときには、それを否定せずに受け入れる姿勢を持ちましょう。
関連記事:パッシブ・アグレッシブな行動をやめて、素直に自分の気持ちを伝える方法
境界線を伝えた後の反応と向き合い方

境界線を伝えることは、少なからず勇気が必要です。
だからこそ、伝えたあとに相手から否定的な反応が返ってくると、「伝えなければよかったのでは……」と不安になることもあるでしょう。
しかし、境界線を設定することは、相手との関係性を健全に整えるための必要なプロセスです。
相手の反応に一喜一憂しすぎない
境界線を伝えたとき、相手が驚いたり、動揺したり、あるいは怒りやショックを表すことがあります。
これは、その人がこれまで「暗黙の了解」だと思っていたルールが崩れるように感じているからです。
ですが、相手が戸惑うのは当然のこと。
それだけあなたとの関係が近かった証拠とも言えます。
伝えた内容が正当であり、自分にとって必要なものであれば、反応に振り回されすぎないようにしましょう。
相手の気持ちも尊重しながら確認する
否定的な反応が返ってきたときには、一方的に押し通すのではなく、相手の意見にも耳を傾けてみましょう。
たとえば、「このお願いって、あなたにとって負担に感じる?」といった問いかけをすることで、相手も自分の気持ちを言葉にしやすくなります。
ここで大切なのは、譲るための確認ではなく、「お互いの立場を理解し合う」こと。
コミュニケーションが成立することで、より建設的な関係性が育まれていきます。
否定されても境界線を引き下げない
残念ながら、すべての人があなたの境界線を尊重してくれるとは限りません。
ときには「そんなのわがままだ」と否定されたり、「前は平気だったのに」と責められたりすることもあるかもしれません。
そのようなときは、相手に合わせて境界線を引き下げるのではなく、自分の感情や限界を守る姿勢を崩さないことが大切です。
誰かに理解されないことと、自分の判断が間違っていることは別問題です。
あなたが大切にしたいものや、守りたい気持ちがあるなら、それを否定する必要はありません。
境界線を保つことに罪悪感を持たない
「嫌われたらどうしよう」「気まずくなったら申し訳ない」と感じる気持ちも自然なものです。
しかし、自分を犠牲にしてまで関係を続けることは、長い目で見ればどちらにとっても健全とは言えません。
境界線を持つことは、わがままでも冷たい行為でもなく、むしろ「関係を長く続けたい」という誠実な姿勢の表れです。
自分の正直な気持ちを丁寧に扱うことが、相手への誠意にもつながっていきます。
まとめ|境界線を意識することで、人間関係はもっとラクになる
人間関係の中で境界線を意識することは、自分を守るためだけでなく、相手とより良い関係を築くための大切な手段です。
曖昧な境界線は、無理な我慢や誤解を生み、やがてストレスや不満へとつながります。
一方で、健全な境界線があれば、お互いの距離感に安心感が生まれ、自立と信頼を両立した関係が築けます。
境界線は一度引いて終わるものではありません。
日々の関わりや変化に応じて、相手と対話しながら見直し、調整していくものです。
そしてそれは、自分自身を大切にし、相手も尊重するという姿勢の表れでもあります。
「うまく言えない」「気まずくなりたくない」といった気持ちがあっても大丈夫。
まずは小さな違和感に気づき、自分の感覚を信じることから始めてみましょう。
トラウマボンドとは?モラハラやDVから抜け出せない理由と対処法

「なぜ、あんな人なのに離れられないんだろう?」
そう思ったことはありませんか?
恋人や配偶者からのモラハラやDVに苦しんでいるのに、なぜか離れられない。
それには「トラウマボンド(Trauma Bond)」という深い心理的な結びつきが関係している可能性があります。
この記事では、トラウマボンドとは何か、その原因とサイン、そして断ち切る方法までを、心理学の知見とともに詳しく解説します。
トラウマボンドとは?

トラウマボンドとは、暴力やモラハラなどの虐待行為を繰り返す相手に対して、強い依存や愛着を感じてしまう状態を指します。
最初は優しかった相手が突然暴力的になり、また優しくなる。
この「愛と恐怖のサイクル」を繰り返すことで、脳が混乱し、「離れたいのに離れられない」状態になります。
こんな関係は要注意|トラウマボンドの兆候

トラウマボンドが形成されていると、以下のような特徴が見られることがあります。
1. 虐待と優しさが繰り返される
暴言や無視、威圧的な態度などで精神的に追い詰められたあと、急に優しい言葉をかけられたり、プレゼントを渡されることがあります。
激しい言動のあとに突然見せる優しさは、強く心に残り、「今度こそ相手が変わってくれるかもしれない」と感じさせます。
相手が変わる可能性にすがる気持ちが積み重なることで、関係から抜け出すのがどんどん難しくなっていくのです。
2. 相手に支配されている感覚がある
一緒にいると、相手の顔色ばかり気にしてしまう。
自分の意思で行動できなくなってくる。
このように相手に支配されているように感じる関係も、トラウマボンドの特徴のひとつです。
3. 離れようとすると不安でいっぱいになる
たとえひどいことをされても、離れようとすると「でもまだ愛しているかも」「一人になるのが怖い」と感じてしまうことがあります。
これは、相手に対する感情的依存が深まっているサインです。
なぜ離れられないの?トラウマボンドが起こる仕組み

生理的メカニズム
暴言や威圧的な態度を受けると、体は「危険だ」と感じて緊張状態になり、心拍が上がり、心は不安や恐怖でいっぱいになるでしょう。
そんな不安な状態の直後に、相手が急に優しく声をかけてきたり、謝ったりすると、強い安心感や安堵を覚えることがあります。
この落差によって、脳はその優しさを特別なものだと錯覚し、さらに強く優しさを求めるようになっていきます。
その結果、たとえ再び傷つけられても、「また優しくしてくれるかもしれない」という期待が生まれ、関係を断ち切る判断を鈍らせてしまうのです。
こうして、虐待と優しさが交互に繰り返されることで、依存が強まり、トラウマボンドはより深く根づいてしまうのです。
心理的背景
子どもの頃に親から虐待や無視をされて育った人は、大人になってからも、支配されたり傷つけられたりする関係を無意識に選んでしまうことがあります。
苦しいはずの関係でも、どこかで「これが普通」と感じてしまい、安心してしまうことがあるのです。
トラウマ関係から抜け出す方法|回復へのステップ

トラウマボンドを断ち切るには、ただ物理的に離れるだけでは不十分です。
心の中に根づいた「離れられない理由」を少しずつ解きほぐしていくことが、真の回復につながります。
ここでは、回復に向かうための具体的なステップを4つ紹介します。
1. 関係の真実を受け入れる
まずは、「これは普通の恋愛ではない」と認めることから始めましょう。
暴言や無視、コントロールされるような言動が繰り返されている関係は、本来の健全な人間関係とは言えません。
しかし、優しかった頃の記憶が残っていたり、「自分にも悪いところがあるのでは」と思っていたりすると、現実を直視するのが難しくなることがあります。
そんなときは、日記を書くことが有効です。
その日にあったこと、相手の言葉、自分の気持ちを簡単でいいので書き残してみてください。
時間をおいて見直してみると「あれ?これっておかしいかも」と気づくことがあります。
第三者の視点で見ることで、自分の置かれている状況を客観的に見つめ直すきっかけになります。
2. 自分を責めない
「自分が悪いからこんなふうに扱われるのかも」と思ってしまうことはありませんか?
理不尽な言動を受け続けていると、次第に「自分さえ我慢すればうまくいくのでは」「相手が怒るのは自分のせいだ」と、自分を責める考え方が癖になってしまうことがあります。
しかし、虐待や支配的な態度は、どんな理由があっても正当化されるものではありません。
あなたが何か失敗したとしても、それは暴言を浴びせられたり、人格を否定されたりしていい理由にはなりません。
どんなときも、あなたには尊厳があり、守られる権利があります。
そんなときは、自分を責める代わりに、自分自身に優しく声をかけてみましょう。
たとえば、「自分は悪くない」「自分は大切に扱われていい存在だ」といった言葉を、心の中で何度も繰り返します。
最初は違和感があっても、続けるうちに少しずつ自己否定の思考がやわらいでいくことがあります。
3. 完全に連絡を断つ
トラウマボンドから回復するうえで、相手との連絡を断つことは非常に重要です。
相手とやり取りを続けていると、優しい言葉や謝罪があるたびに心が揺れてしまい、関係に引き戻されてしまう可能性が高くなります。
まずは、LINEやSNS、電話など、あらゆる連絡手段をブロック・削除することを検討してみてください。
必要があれば自身の電話番号を変更するのもひとつの方法です。
また、相手の投稿やアカウントを見ないようにするだけでも、心の動揺を減らすことができます。
もし同居している場合や、子どものことで連絡をとる必要がある場合は、信頼できる第三者や専門家を介してやり取りする方法を考えてみましょう。
自治体の相談窓口や、女性支援団体、弁護士、カウンセラーなどが力になってくれることもあります。
しかし、連絡を断つのは簡単なことではありません。
「まだつながっていたい」と感じてしまう自分を責める必要はありません。
ただ少しずつ、自分の心と生活を守る選択肢を増やしていくことが、回復への第一歩になります。
4. 専門家のサポートを受ける
トラウマボンドのように深く結びついた関係から抜け出すのは、一人の力だけでは難しいことがあります。
相手と距離を取ろうとするたびに迷いが生じたり、「自分が悪いのでは?」と自責の念にとらわれたりすることもあるでしょう。
そんなときは、ためらわずに心理カウンセラーや臨床心理士など、専門家の力を借りましょう。
トラウマや虐待に詳しい専門家は、どのような関係のパターンに巻き込まれやすいのかを理解し、抜け出すための道筋を示してくれます。
また、サポートを受ける中で、自分にとって安全な人間関係の築き方や、心の境界線(バウンダリー)を守るスキルも少しずつ身についていきます。
心の傷は時間とともに癒えていくものです。
安心して話せる場を持つことが、回復への大きな一歩につながります。
サポートを受けられる窓口(日本国内)
■ DV相談プラス(内閣府)
電話番号:0120-279-889(24時間対応、通話料無料)
チャット相談:正午~午後10時(10か国語対応)
■ よりそいホットライン(一般社団法人 社会的包摂サポートセンター)
電話番号:0120-279-338(24時間対応、通話料無料)
女性支援専門ライン:ガイダンス後に「3」を選択
詳細:https://www.since2011.net/yorisoi/n3/
■ 女性の人権ホットライン(法務省)
電話番号:0570-070-810(平日8:30~17:15)
詳細:https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken108.html
■ 女性相談支援センター全国共通ダイヤル(厚生労働省)
電話番号:#8778(はなそう なやみ)
詳細:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40452.html
関連記事:ジャーナリングのやり方は?日記との違いや効果について
よくある質問(FAQ)

Q:トラウマボンドと共依存の違いは何ですか?
A:共依存は「相手を助けることで自分の価値を感じる」という相互依存的な関係ですが、トラウマボンドは「加害と優しさの繰り返しによって形成される一方的な執着関係」です。
両者は似ている部分もありますが、関係性の力のバランスに大きな違いがあります。
Q:トラウマボンドは恋愛以外でも起こりますか?
A:はい、恋愛関係に限らず、親子・職場・友人関係などでも起こる可能性があります。
特に、上下関係や依存が強い関係性では、トラウマボンドが生じやすい傾向があります。
Q:トラウマボンドから回復するまでには、どのくらいの時間がかかりますか?
A:回復には個人差がありますが、数ヶ月から数年にわたることも珍しくありません。
時間をかけて自己理解を深め、安心できる人間関係を築いていくことで、少しずつ執着や自責の感情が和らいでいきます。
Q:相手と離れる決意をしても不安でいっぱいです。
A:そう感じるのは自然なことです。
「本当にこれでよかったのか」「一人でやっていけるだろうか」といった気持ちが湧いてくるのは、関係が長く続いているほど当然の反応です。
ただ、その不安な気持ちに流されて元の関係に戻るのではなく、不安と向き合い、安心できる方法を少しずつ身につけていくことが回復への鍵になります。
まとめ|「離れられない」は、あなたのせいじゃない
トラウマボンドは、誰にでも起こり得る心理的メカニズムです。
あなたが今、苦しいのは「弱いから」ではありません。
それだけ深く人を信じたり、愛したり、傷ついたりした経験があったという証です。
そして、その苦しみから抜け出す道は必ずあります。
焦らずにまずは、一歩踏み出す勇気を持ってみましょう。
アタッチメント理論とは?4つのスタイルと日常での活かし方

恋愛関係で、相手の距離が少しずつ離れていくのを感じたとき、
私たちは無意識に「振られるくらいなら、自分から終わらせたほうが楽だ」と考えてしまうことがあります。
傷つくのが怖くて、心を守ろうとする防衛本能が働くからです。
こうした防衛本能が働く背景には、子ども時代の愛情体験が影響していると考える心理学理論があります。
それが「アタッチメント理論」です。
この理論を知ることで、私たちは自分の無意識の反応を理解し、新しい選択肢を持てるようになるかもしれません。
アタッチメント理論とは
「人生の最初の2年間で、『愛し方』の基本パターンは形づくられる」。
この考えを提唱したのが、心理学者ジョン・ボウルビィとメアリー・エインスワースです。
アタッチメント理論では、幼いころに親や養育者と築いた関係性が、大人になったあとの恋愛や人間関係に大きな影響を与えるとされています。
その影響の現れ方は、4つのアタッチメントスタイルに分類されます。
関連記事:パッシブ・アグレッシブな行動をやめて、素直に自分の気持ちを伝える方法
アタッチメントスタイルの4タイプ

1. 安定型(Secure)
親密な関係に安心感を持ち、自分の気持ちや境界線を素直に伝えられるタイプです。
問題が起きても、冷静に話し合いで解決しようとする傾向があり、信頼関係を築くことに前向きです。
2. 回避型(Avoidant/Dismissive)
極端に自立を重視し、他人に頼ることを避けようとするタイプです。
感情表現が苦手で、親密さに対して距離を取ろうとします。
恋愛や友情など親密な関係でも、相手に弱みを見せたり助けを求めることを避け、自分の中だけで感情や問題を処理しようとする傾向があります。
3. 不安型(Anxious/Preoccupied)
愛情や承認を強く求め、相手の反応に敏感になるタイプです。
不安から過剰な行動に出やすく、関係が壊れることへの恐れを強く抱えています。
相手にしがみつこうとする傾向があります。
4. 混乱型(Disorganized/Fearful-Avoidant)
親密さを求めながらも、同時にそれを恐れてしまうタイプです。
近づきたい気持ちと、距離を取りたい気持ちの間で大きく揺れ動きます。
人間関係の中で一貫した行動が取りにくいことがあります。
アタッチメントスタイルは変えられる

「私は回避型だから、もう変われない」
そんなふうにあきらめる必要はありません。
アタッチメントスタイルは、日々の小さな行動で少しずつ変えていくことができるからです。
ここからは、アタッチメント理論を活かして、自分自身と向き合いながら、よりよい人間関係を育てるためのヒントを紹介します。
1. 日常の「コネクションのサイン」に気づこう
心理学者ジョン・ゴットマンとジュリー・ゴットマン夫妻による研究では、長続きする夫婦には、ある共通点があることがわかりました。
それは、日常の中で交わされる「小さなつながりのサイン」を大切にしていることです。
たとえば、仕事帰りに「きれいな夕焼けだね」と声をかけたり、ソファで肩にそっと頭を乗せたりといったささやかな行動が、「あなたとつながりたい」というサインになります。
こうしたサインに気づき、きちんと応えることが、深い絆を育てるカギになるのです。
回避型傾向のある人が、突然の電話に戸惑う場合は、無視するのではなく「あとでかけ直すね」と一言伝えるだけでも十分です。
また、混乱型傾向のある人がパートナーとの距離感に迷ったときは、「少し休んでから、また一緒に過ごそう」と伝えるなど、自分に無理のない範囲で応える工夫をしてみましょう。
2. 体のサインに耳を澄ませる
体は、心よりも先に危険を察知し、守ろうと反応する性質を持っています。
そのため、不安や緊張を感じたときには、胸がざわついたり、胃がきりきり痛んだり、さまざまなサインが体に現れます。
アタッチメントスタイルによって、不安を感じやすい場面や反応の出方には違いが見られます。
たとえば、不安型の人は、相手からの返信が遅れるだけでも強い不安を感じやすい傾向があります。
こうした体のサインに意識を向けることが、感情との健全な向き合い方につながります。
3. セーフワードを取り入れる
親密な会話や感情的なやり取りが高まりすぎたときに、緊張を和らげる方法として「セーフワード」を活用する手段があります。
セーフワードとは、感情的に負担を感じた際に、あらかじめ決めておいたキーワードで「一時的な休憩」を申し出るための合図です。
例えば、セーフワードとして「タイム」という単語を決めておき、会話中に「タイム」と伝えた場合、互いに30分間クールダウンの時間を取るといったルールを設定しておきます。
この間に自己調整や内省を行い、落ち着いた状態で話し合いを再開することができます。
アタッチメントスタイルによって、本音や弱さを見せたときの反応は大きく異なります。
安定型のアタッチメントスタイルを持つ人は、自分の感情を表現しても受け入れられるという安心感を持っています。
一方、回避型や混乱型のスタイルを持つ人は、過去の経験から「本音を見せると傷つけられるかもしれない」という不安を抱きやすく、感情を出すことに慎重になります。
事前にセーフワードとその運用方法を話し合っておくことで、衝突の場面でも安心感を保ち、冷静かつ建設的なコミュニケーションを続けることができるでしょう。
4. 相手への共感力を育てる
相手の言動に対して、「なぜこの人はこんな反応をするのだろう?」と疑問に思うことがあるかと思います。
アタッチメントスタイルの理解は、相手の行動背景を読み解く大きな助けになります。
人は幼少期の家庭環境や体験から多くの影響を受けて成長します。
幼少期に身につけた「生き延びるための行動パターン」は、大人になった後も無意識のうちに行動や反応に表れやすくなります。
作家デイヴィッド・ブルックス氏は著書『How to Know a Person: The Art of Seeing Others Deeply and Being Deeply Seen』の中で、「思いやりの目で他者を見るなら、人は誰もが苦しみながらも懸命に人生を航海している存在だとわかる」と述べています。
相手の行動を一方的に批判するのではなく、「育ってきた背景に基づく理由がある」と受け止める姿勢が、人間関係に柔らかさをもたらします。
相手の内面を理解するためには、具体的な質問を重ね、興味を持って丁寧に話を聞くことが大切です。
また、相手が自身について語るときには、その感じ方や視点を尊重し、否定せずに受け入れる姿勢を持ちましょう。
相手の語る物語を尊重することで、関係性には温かさと深みが生まれます。
5. 自分自身に優しさを向ける
アタッチメントスタイルを見つめ直すときに大切なのは、「自分を責めないこと」です。
回避型でも、不安型でも、混乱型でも、どのスタイルも、過去の自分が生き延びるために身につけた、大切な方法です。
たとえ今、そのアタッチメントスタイルが生きづらさをもたらしていたとしても、過去の自分にとっては最善の選択だったことに変わりはありません。
過去の自分を責めるのではなく、「今まで守ってくれてありがとう。これからは違う選択もできる」と、優しく伝えてあげましょう。
過去の努力を認めることから、変化は始まります。
関連記事:ラディカルアクセプタンスを受け入れる方法|変えられないことを受け入れる
まとめ:アタッチメント理論を日常に活かすために
アタッチメント理論は、単なる心理学の知識にとどまりません。
恋愛、友情、仕事など、日常のあらゆる人間関係に深く影響を与えています。
日々の中で生まれる小さな気づきと行動の積み重ねによって、誰もがより安定したアタッチメントスタイルへと近づくことができます。
今日、どんな小さな一歩を踏み出せそうでしょうか。
日常の中で、相手の気持ちに寄り添う、体のサインに耳を傾ける、セーフワードを取り入れるなど、あなたにできる小さな行動を見つけて実践していきましょう。
参考文献
アタッチメントスタイルによるセラピストへの感受の差異について
パッシブ・アグレッシブな行動をやめて、素直に自分の気持ちを伝える方法

「別にいいけど」
「なんでもないよ」
そう言いつつも、心のどこかでモヤモヤが残っていたり、不満をためこんでしまった経験はありませんか?
相手を責めるつもりはなくても、はっきり言えなかった気持ちがため息や沈黙、遠回しな言葉になって表れてしまう。
このような行動は、心理学では「パッシブ・アグレッシブ(受け身的攻撃性)」と呼ばれています。
実は、パッシブ・アグレッシブは無意識のうちにやってしまう人も多く、家庭や職場など、身近な人間関係の中で頻繁に見られる傾向があります。
本記事では、パッシブ・アグレッシブな態度の具体例や、その原因、そしてそれを乗り越えて素直に気持ちを伝えるための実践的な方法までを詳しくご紹介します。
パッシブ・アグレッシブとは?

パッシブ・アグレッシブ(受動的攻撃性)とは、直接的な表現を避け、間接的な方法で不満や怒りを示すコミュニケーションスタイルです。
例えば、「はいはい、分かりました」と皮肉っぽく返事をしたり、頼まれたことをわざと後回しにしたり、明らかに無視をするような態度がこれにあたります。
一見すると表面的には冷静に見えますが、実際には怒りや不満を間接的にぶつけている状態です。
このような言動は、相手にとっては理由が分からずストレスを感じやすく、結果として対話が成立しにくくなるため、人間関係に大きな溝を生んでしまいます。
パッシブ・アグレッシブな行動の例
- 頼まれた仕事をわざと遅らせる
- 皮肉や嫌味を言う
- 無視や冷たい態度を取る
- 約束を守らない
- 他人の成功を素直に喜べない
上記に該当するような行動は、表向きには対立を避けるために行われるケースが多いものの、受け手には「冷たくされた」「嫌われたのかもしれない」といった不安やストレスを与えます。
特に職場や家庭といった日常的に接する関係では、「何を考えているのかわからない」「話しかけづらい」と感じさせてしまい、コミュニケーションの断絶や、関係がぎくしゃくする原因になります。
なぜパッシブ・アグレッシブな行動を取ってしまうのか?

パッシブ・アグレッシブな行動の背景には、以下のような心理的要因が存在します。
1. 対立を避けたいという気持ち
日本の文化では、和を重んじる傾向が強く、対立を避けることが美徳とされています。
そのため、自分の意見や感情を直接的に表現することに抵抗を感じ、間接的な方法で不満を示すことがあります。
2. 自己主張への不安
自己主張をすることで、相手に嫌われるのではないかという不安から、自分の意見や感情を抑え込んでしまうことがあります。
その結果、間接的な方法で不満を表現するようになります。
3. 過去の経験
過去に自己主張をした際に、否定されたり、無視されたりした経験があると、再び同じような経験をすることを恐れて、パッシブ・アグレッシブな行動を取ることがあります。
パッシブ・アグレッシブな行動がもたらす影響

パッシブ・アグレッシブな言動によって職場で信頼を失ったり、家庭内で会話が減ったりといった状態が続くと、次第に人との関係を築くことがストレスになってしまいます。
人と関わるのを避けるようになり、自分の感情を押し殺す生活が当たり前になってしまえば、心のバランスを崩すのも時間の問題です。
結果的に、生活のあらゆる場面で楽しさや充実感を感じにくくなり、孤立や不安を深めることにもつながっていきます。
パッシブ・アグレッシブを克服する方法

パッシブ・アグレッシブな行動を克服するためには、以下のような方法が有効です。
1. 自分の感情を認識する
まず重要なのは、「いま自分はどんな気持ちなのか」に気づくことです。
「イライラ」
「悲しさ」
「期待外れ」
といったマイナスな感情を無視せず、「自分はこう感じている」と認識する習慣を持ちましょう。
自分の気持ちを正しく理解できれば、言葉で表現する準備が整います。
2. アサーティブ(自己主張的)な伝え方を学ぶ
アサーティブとは、相手を傷つけず、自分の気持ちも抑え込まずに伝えるコミュニケーションスタイルです。
例えば、「私はこう感じている」「こうしてもらえると助かる」というように、「非難せずに自分の希望を明確に伝える」方法を練習します。
これにより、相手にも伝わりやすく、すれ違いを防げます。
3. 少しづつ練習する
急に自分の気持ちをすべて正直に話すのは難しいものです。
例えば、飲み物の注文や日常のちょっとしたお願いなどから、「こうしたい」と口に出す練習をしてみましょう。
小さな成功体験を積むことで、徐々に自信がついていきます。
4. 専門家のサポートを受ける
もし「どうしても自分の気持ちが言えない」「過去の経験が原因で話せなくなっている」と感じる場合は、心理カウンセラーなど専門家の支援を受けるのも一つの選択肢です。
安全な場で対話を重ねることで、自己表現のトレーニングができます。
まとめ|パッシブ・アグレッシブを卒業し、自分の声に素直になるために
パッシブ・アグレッシブな態度は、自分の感情を直接伝えられないもどかしさや、対立を避けたいという思いから生まれる行動パターンです。
しかし、この習慣を続けていると、自分自身にも相手にもストレスがたまり、誤解や不満が積み重なってしまいます。
大切なのは、感情を否定せずに受け入れ、それを適切な言葉で伝えるスキルを育てていくことです。
アサーティブなコミュニケーションを少しずつ実践していけば、「察してほしい」という不安から解放され、自分の思いを正直に伝える力が身についていきます。
すべてがすぐにうまくいくわけではありませんが、小さな一歩を積み重ねることで、人間関係は必ず変わっていきます。
まずは今日から、自分の気持ちに耳を傾け、「言葉にする」ことに挑戦してみてください。
その選択こそが、よりよい関係を築く第一歩となるはずです。
「リマレンス」と片思いの違いとは?執着的な恋と健全な恋の境界線

片思いって、もっと楽しいものじゃなかった?
好きな人のことで頭がいっぱいになるあの感覚。ちょっと切なくて、でもどこか心が温まるような気持ち。けれど、その「好き」が苦しさや不安、執着心に変わったとき、それはもしかすると、「リマレンス」という状態かもしれません。
この記事では、近年SNSでも話題になっているリマレンスの正体と、健全な片思いとの違い、そしてそこから抜け出すためのヒントを、専門家の意見を交えて解説します。
リマレンスとは何か?ただの片思いとは違う、心の依存

「リマレンス(limerence)」という言葉を初めて聞いた人も多いかもしれません。これは1979年、心理学者ドロシー・テノフが自身の著書『Love and Limerence』の中で紹介した、“恋愛における強い執着心”を指す心理学の用語です。
リマレンスは、一言でいえば「感情的な見返りを強く求める執着状態」です。自分でも止められないほどの強い思い込みや理想化、相手のちょっとした反応に過敏になる精神状態が特徴です。相手に恋をしているように見えて、実はその人自身ではなく、「その人に満たしてもらいたい気持ち」に執着している状態と言えるでしょう。
恋愛感情のようでいて、どこか苦しく、そして終わりが見えない。これが、一般的な片思いとの大きな違いです。
関連記事:「愛の言語」で解決!愛しているのに伝わらない。愛されているのかわからない。愛情のミスマッチを防ぐ秘訣
リマレンスに陥りやすい人と、その背景

日本ではまだ「リマレンス」という言葉は広く知られていませんが、それに近い感情として、「報われない片思い」「執着的な恋愛」「恋愛依存」といった言葉で語られることがあります。
TikTokでリマレンスについて発信しているクリエイターのダニエル・ウォルターは、リマレンスを「不安型愛着や自信のなさ、うつ傾向といった精神状態からくる、“相手を理想化した非現実的な恋愛の執着”」と表現しています。
実際、リマレンスに陥りやすいのは以下のようなケースが多いとされています。
- 幼少期に感情的なニーズが満たされなかった
- ネグレクトや虐待など、愛情の欠如を経験している
- 不安障害やうつ、PTSD、OCD(強迫性障害)などを抱えている
- 相手が自分に何をくれるかに強く期待しやすい
複雑性PTSDの支援活動を行っているアンナ・ランクル氏は、YouTubeなどで「Crappy Childhood Fairy(つらい子ども時代からの回復を支援する妖精)」という名で情報発信を行っており、次のように語っています。
「子どもの頃に十分な愛情を受け取れなかった人は、大人になってからも、愛情表現が乏しい相手や、心の距離を感じさせる人に惹かれてしまうことがあります。これは心理的な罠の一つです」
誰しも一度は、会話をほとんど交わしたことのない相手に惹かれ、頭の中で理想的な恋愛関係を空想した経験があるかもしれません。現実では距離を取りながらも、心の中では親密な関係を思い描き、気づけば強い執着へと変わっていることもあります。それは恋愛というより、現実から目をそらすための心の逃避といえるでしょう。
片思いとリマレンスの違い。「恋」か「幻想」か

片思いは、本来もっと自由で楽しいものです。相手を少しずつ知っていく過程にときめきを覚えたり、共通点を見つけて嬉しくなったり。たとえ実らなくても、自分の世界が広がる経験になります。
対してリマレンスは、
「相手に振り向いてもらえないのに、なぜか気持ちが強くなる」
「相手を知らないのに、運命を感じてしまう」
「SNSを何度もチェックしてしまう」
など、制御不能な思考と感情に振り回されます。
恋愛・人間関係のコーチであるニコール・コラントーニは言います。
「健全な片思いとリマレンスの違いは、その感情があなたの生活や心にどう影響を与えるかです」
片思いは自分らしさを取り戻すきっかけになりますが、リマレンスは自分を見失うきっかけになります。感情の深さではなく、「その恋があなたをどう変えるか」が大きな分かれ目です。
リマレンスの執着はどう変化していく?よくある3つのプロセス

リマレンスは、相手への執着や理想化が強く続く状態ですが、それが永遠に続くとは限りません。
ある出来事や心の変化によって、少しずつ気持ちの熱が和らいだり、方向が変わったりすることがあります。
ここでは、リマレンスへの執着が少しずつ弱まっていくときによく起きる、3つの変化を紹介します。
1. 現実に触れて、気持ちが冷めていく
相手との距離が縮まり、実際に関係が始まったり、相手の素の部分を知ったりすると、頭の中で理想化していたイメージとのズレが生まれます。
たとえば、「思ったより普通の人だった」「合わない部分が見えてきた」といった現実に触れることで、自然と気持ちが落ち着いていくことがあります。
これは「叶ったから満足」ではなく、「幻想が現実に置き換えられた」ことによる感情の変化です。
2. 反応がないまま、気づけば関心が薄れている
好きになっても、相手から連絡が来ない、話しかけられない、目も合わない、そんな一方通行の状態が続くうちに、次第に気持ちが冷めていくことがあります。
はっきりとした区切りがあるわけではなく、ある日ふと「そういえば最近、気にならなくなってたな」と気づくような感覚です。
相手は何もしていないのに、自分の気持ちばかりが膨らんでいく。そのギャップに疲れてしまい、自然と気持ちが離れていくこともあります。
3. 別の誰かに惹かれていき、自然と距離ができる
新しく気になる人が現れると、それまで強く執着していた相手の存在が徐々に薄れていくことがあります。
ただし、これはあくまで気持ちの“対象”が変わっただけで、リマレンスが解消されたわけではありません。同じように理想化や執着を繰り返してしまう可能性もあります。
リマレンスへの執着は、時間や状況の変化で自然と弱まることもあります。
けれど、「また似たような相手に惹かれている」「今回も一方通行だった」と感じることがあるなら、それは“相手が変わっただけ”で、心の癖は変わっていないという可能性もあります。
リマレンスを繰り返す人の多くは、「なぜあの人に執着したのか?」「自分はどんな感情を求めていたのか?」という内側の問いに向き合うことなく、 “次の相手”に気持ちを移してしまいます。
本当にリマレンスから抜け出したいなら、目の前の人ではなく、自分自身の心の奥を見つめるところから始める必要があるのかもしれません。
まとめ:「好き」がつらいなら、それは恋ではない
恋愛のエネルギーは本来、あなた自身を輝かせるものです。
けれど、それが不安や依存、自己否定に変わったとき、その恋はあなたを壊しかねません。
リマレンスのループから抜け出したとき、
「あれは恋じゃなかった」「本当に欲しかったのは、安心感だった」ときっと気づくはずです。
好きな人がいるのは素敵なことです。
しかし、その気持ちがあなたを傷つけているなら、一度立ち止まってみてください。
その恋があなたを大切にしてくれているか。それが、見極めるべき本当の指標です。
遠距離恋愛を続けるために大切な4つのこと~離れていても心をつなぐヒント~

「彼を待つ意味って、本当にあるのかな」
「ちゃんと想ってくれてるのか、不安になる」
「もしかして、私だけが頑張ってるんじゃない?」
遠距離恋愛には、見えない不安がつきまといます。
会いたいときに会えず、当たり前のような日常が手に入らない。
そんな中でも、遠距離恋愛をしているふたりが関係を続けるにはどうすればいいのでしょうか。
私はこれまでに3回、遠距離恋愛を経験してきました。
その中で気づいた、遠距離を乗り越えるために大切なことを4つご紹介します。
ふたりで楽しみにできる予定を持つ

遠距離恋愛中のふたりにとって、最もつらいのは「この先どうなるのか」が見えなくなることです。
「次に会えるのはいつだろう」
「気持ちは変わっていないのかな」
「私たち、本当にうまくいくのかな」
このような疑問が頭の中に何度も浮かび、不安を大きくしていきます。
だからこそ、お互いが共通して楽しみにできる予定を持ったり、“ふたりの未来”につながる目標を共有したりすることが大切です。
たとえば、次に会える日を決めたり、将来の転職や引っ越し、一緒に住むための準備を話し合ったりすることです。
遠距離恋愛中のふたりには、「今は離れているけど、ちゃんと一緒になれる日が来る」と信じられる希望が何よりの支えになります。
関連記事:「愛の言語」で解決!愛しているのに伝わらない。愛されているのかわからない。愛情のミスマッチを防ぐ秘訣
決めつけず、冷静にコミュニケーションを取る

距離があると、相手のことがよく見えなくなります。
その結果、ちょっとしたことで疑ったり、不安になったりしてしまいます。
たとえば、SNSに知らない異性の名前があるだけで気になったり、いつもより連絡が遅いだけで「何かあったのかな」と思ってしまったり。
また、逆に相手を理想化しすぎてしまうこともあります。
普段会えないぶん、良い部分ばかりを想像してしまい、実際に会ったときにギャップに戸惑うこともあるでしょう。
そんなときこそ、「自分の感情を信じすぎないこと」が大切です。
わからないことは想像せず、素直に相手と話すことが何よりの解決になります。
遠距離恋愛をしているふたりだからこそ、率直な言葉で気持ちを伝えることが、心の距離を縮める鍵です。
連絡は「義務」ではなく「自然体」で
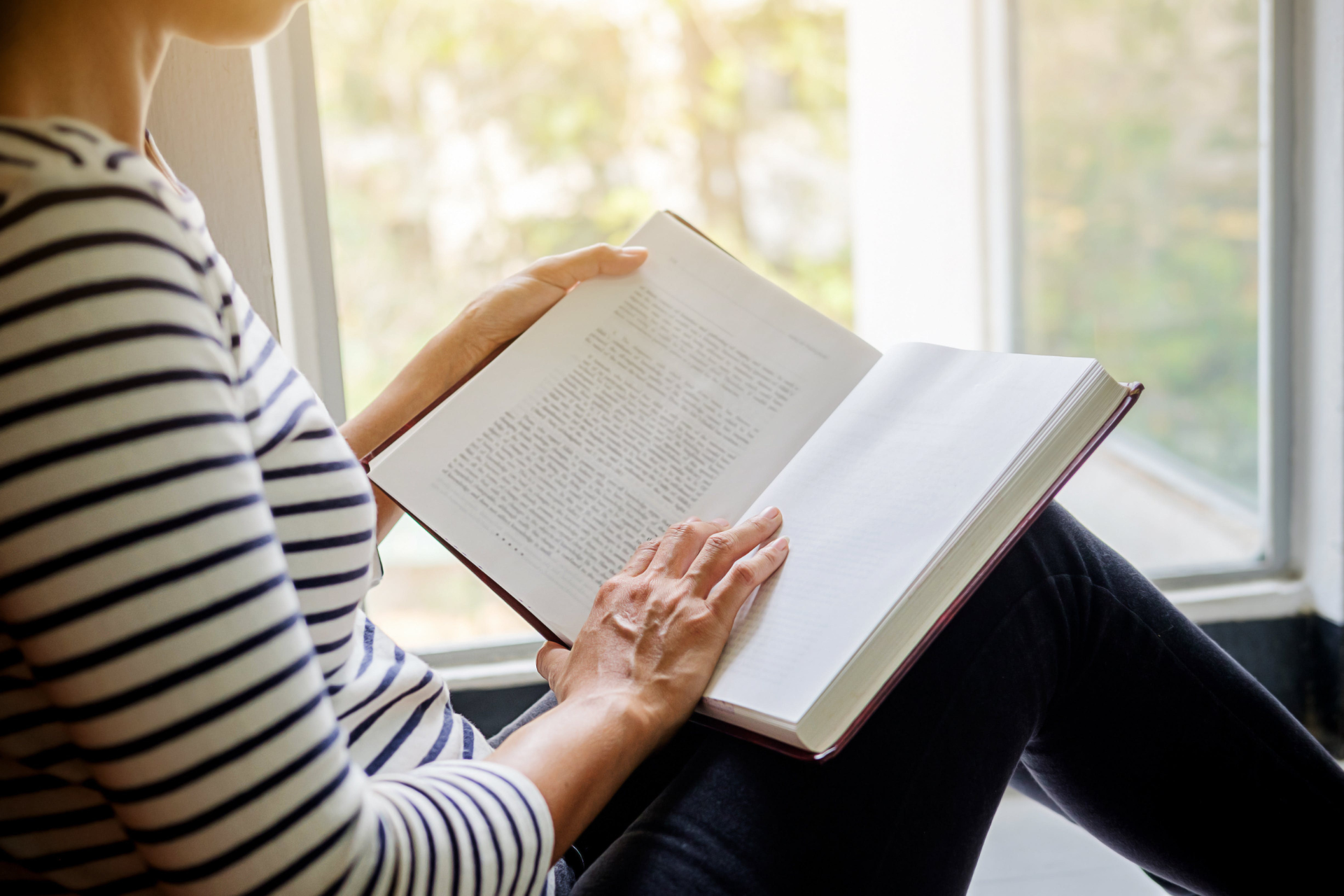
多くのカップルが、遠距離を乗り越えるために「毎日電話しよう」「週に〇回は連絡しよう」とルールを決めます。
もちろん、会話の時間を大切にする姿勢は素敵です。
ですが、会話が義務になってしまうと、次第に負担になってしまうこともあります。
忙しい日や疲れている日には、無理して連絡を取らなくてもかまいません。
話したいときに話す、聞きたいときに聞く。そのくらいの気持ちでちょうど良いでしょう。
会話が少なくなってきたと感じたときは、不安な気持ちを素直に話してみましょう。
ただし、相手の生活や気分に合わせて、少し距離を置くことも必要なときがあります。
遠距離恋愛のふたりだからこそ、「連絡の回数よりも質」を意識し、お互いの気持ちに寄り添う余白を持っておきましょう。
距離は「一時的なもの」と信じること

遠距離恋愛は、ずっと離れたままでは続けていけません。
心に希望を持つためには、「いつか一緒になれる」という現実的なビジョンが必要です。
お互いの将来がまったく別方向を向いているなら、いくら好きでも関係は難しくなります。
「一緒に住む」
「同じ街で働く」
「留学や転職のタイミングを合わせる」
など、どんな形であれ、ふたりの未来が交わる道筋が必要です。
私自身、将来の話をきちんとしないまま曖昧にしていたことがあります。
その結果、お互いの気持ちやタイミングがずれてしまい、最終的には別れを選ぶことになってしまいました。
逆に、今のパートナーとは「1年以内に同じ街に住める見込みがないなら、連絡はやめよう」と最初に話し合いました。
その半年後には、実際に移住を決め、お互いの生活を調整しながら未来を築き始めました。
遠距離恋愛のふたりには、愛情だけでなく「行動する覚悟」が必要です。
おわりに:遠距離恋愛中のふたりが絆を深めていくために

私自身の経験から言えば、遠距離恋愛を続けるのは簡単なことではありません。
会えない時間の中で、相手を本当に知ることは難しく、理想と現実のギャップに苦しむこともあるでしょう。
それでも私は「やってみる価値はある」と思っています。
たとえ失敗しても、自分自身の愛し方や信じ方、相手との向き合い方を深く学べるからです。
遠距離恋愛中のふたりでも、お互いに向き合い、信じ合い、支え合う努力を続ければ、普通のカップル以上に強い絆を育てられると私は信じています。
焦らず、無理せず、ふたりだけのペースで歩んでいきましょう。
離れていても、心がつながっていれば、その恋はきっと続いていきます。
ミソジニーが女性に与える精神的負担と問題|女性が蔑視される原因とは?

日本をはじめとする世界各国では、古くから女性が蔑視されてきた歴史があります。
その差別は未だゼロになったとはいえず、様々な場面で女性に精神的負担を与えているでしょう。
今回は女性蔑視を指す「ミソジニー」について、引き起こされる問題点や解決のためにできる対策についてご紹介します。
ミソジニーとは?

ミソジニーとは、ギリシャ語の「misos(憎しみ)」と「gune(女性)」が合わさってできた造語だといわれています。
意味は「女性に対する差別や嫌悪感・蔑視」であり、規模の大小にかかわらず全てがミソジニーに当てはまります。
女性が嫌いだと声を大にしてコメントしている方はもちろんのこと、普段は女性の味方であったり、自身が女性であったりする場合もミソジニーの考えに当てはまる可能性があるため、誰もが他人事と考えずに理解を示すことが大切です。
例えば、ミソジニーの代表的な例として「男性による女性軽視」が挙げられるでしょう。
古くから日本は男尊女卑の歴史があり、女性は男性よりも劣った存在であるとされてきました。
この慣習は現在廃止されていますが、「男性は女性よりも優れている」といった考えが全くなくなったわけではないでしょう。
また、女性が抱くミソジニーは、「女性とはこういうものである」といった固定観念に当てはまらない女性に対し、「あの人は変わっている」などと嫌悪感を抱くといったケースが挙げられます。
髪を短くカットしボーイッシュな髪型をしている方や、育児を男性に任せて毎日仕事をしている女性などに対し、「女性らしくない」と違和感を覚える方もまだまだ多いのではないでしょうか。
つまり、堂々と女性を差別しているわけではなくても、深層心理として女性を蔑んでいる方が多いといえます。
この考え方がなくならない限りは、ミソジニーの考えを持つ「ミソジニスト」がゼロになることはないでしょう。
関連記事:ルッキズムの意味とは?やめたいけどどうしようもない?
ミソジニーが引き起こす問題と精神的負担
自分の心の中で思うだけであれば問題ないことも、声に出してしまったり、同じ考えを持つ仲間を見つけてしまったりすると大きな問題へと発展してしまいます。
続いてはミソジニーがどのような問題を引き起こし、女性へどのような精神的苦痛を与えているのかについてご紹介します。
性的被害や暴力
ミソジニーの考え方が一般的なものとなった結果、「女性が自分に振り向いてくれないから」「性行為を拒否されたから」などといった理由で性的暴力や一般的な暴力をふるうケースが横行しています。
女性たちにとってそんなつもりはなかったとしても、加害者側からすると「女性が自分よりも下の立場である」といった深層心理があるため、拒否されたことを素直に受け入れることができません。
丁寧に断ったつもりでも、馬鹿にされたと感じてこのようなトラブルに発展してしまうことが多いでしょう。
雇用や教育環境の格差
雇用機会均等法など、様々なルールができ男性と女性の雇用や教育の格差がなくなりつつあります。
とはいえ女性の存在を蔑視するミソジニストたちにより、世界では未だに女性の職や学業が奪われ続けています。
女性だからという理由で子守りをさせられ学校に通えなかったり、家事や育児を一人で任され家の外に出る機会をもらえなかったりする家庭も少なくありません。
日本はというと男女の格差がなくなったようにも見えますが、男女間ではまだまだ明確な賃金格差があります。
役職に就く女性の数も男性に比べて少なく、昇格の機会も多いとはいえません。
結果として女性は自分に対する評価を上げられず、日々少しずつストレスが溜まってしまうでしょう。
社会的な地位の格差
雇用の格差にも通じるところがありますが、男性と女性では社会的な地位にも格差が生じています。
コミュニティの大小にかかわらず、リーダーと呼べるポジションに就くのはほとんどが男性でしょう。
趣味の集まりであったり、子どもの幼稚園・保育園のPTA活動であったり、様々な場所で男性がリーダーシップを発揮しています。
もちろん、男性が先頭に立つことが悪いわけではありません。
問題なのはその場にいる女性にトラブルがないにも関わらず、誰しもが自然と女性を排除し、男性を重要ポジションへと推薦してしまうことにあります。
この場合は女性自身もサッと身を引き、自分が先頭に立つことをイメージできていないのも問題の一部といえるでしょう。
こういった格差が引き起こす孤立感は、女性に精神的苦痛を与えてしまいます。
職場においても地域のコミュニティにおいても、女性の意見が通らずに苦しい思いをした方も多いのではないでしょうか。
賃金の格差
女性と男性では、全く同じ内容の職に就いていても、賃金に差が生まれやすいといわれています。
これは誰かが意図的にそうしようとしているよりも、昔からの慣習でそうなっている場合が多く、根深い問題の一つといって良いでしょう。
女性は男性よりも体調不良になりやすかったり、出産や育児で休暇をとる可能性が高かったりすることを理由として挙げている企業もありますが、これでは両者の立場を平等にしているとはいえません。
結果として男性よりも賃金が安い女性の方が、積極的に育休を取ったり、家事育児の割合を増やしたりしなければならない状態も珍しくありません。
こうなった場合さらに労働時間が減り、重要なポストへの道は遠ざかってしまうでしょう。
ミソジニーを巡る問題は一つひとつが分かれているように見えて、実はそれぞれが繋がっており、社会全体で女性を蔑視するシステムが構築されてしまっています。
これを改善するのは多くの時間が必要ですが、決して諦めてはならないでしょう。
ミソジニーが発生する原因

何故私たちの中にミソジニーの考えが生まれてしまうのかというと、その多くは古くからの慣習が原因といえるでしょう。
男女平等を目指すとは言いつつも、現在までに男尊女卑の文化が消え去ったとはいえません。
こうした文化は知識として私たちの頭に残り、考えや行動に大きな影響を及ぼしているのです。
また、私たち一人ひとりがこうした差別問題に関心を向けているわけではないことも、ミソジニーがなくならない原因といえます。
近年は学校教育の中で差別について取り上げることもあるなど、徐々に関心を寄せる人が増えてきています。
「私は関係ない」と思わず、自分や大切な人に関係することだと捉えれば、自然と問題に対する姿勢が変わっていくのではないでしょうか。
ミソジニーとミサンドリーの違い
ミソジニー(女性蔑視)の対義語として、ミサンドリー(男性蔑視)という言葉があります。
女性の差別をなくすために動かなければならないのはもちろんのこと、同様に男性も差別されて良い対象ではありません。
どちらかを持ち上げるのではなく、双方が平等に過ごすことができる社会作りが大切です。
ミサンドリーは男性へ嫌悪感を抱くことを指し、「男性とはこうである」といった固定観念が原因となります。
「男性だから料理なんてできないはず」「男性だから女性の気持ちなんて分かるはずがない」といった決めつけが、自然と男性を見下すことに繋がっているかもしれません。
その結果、ミサンドリーという言葉を知らない方が、男性蔑視に苦しんでいる可能性もあります。
一方、ミソジニーとミサンドリーでは決定的な違いがあります。
それはミソジニーが雇用機会の減少や賃金の安さといった差別が問題視されているのに対し、ミサンドリーを原因とする明確な差別はそれほど表に出てこず、社会全体の問題とはなっていないという点です。
女性専用車両に間違えて乗った男性が大バッシングを受けるなどの事例も報告されていますが、そもそもが女性を守るための車両であるため、避難されるべきは男性だといった意見もあります。
現時点では、ミサンドリーを原因とする大きな問題が表面化していないため、どうしてもミソジニーに注目が集まりやすいのが現状です。
大切なのはミソジニーに対し真摯に向き合うのに加え、ミサンドリーの意味を知り、自らが無意識のうちに差別をしていないかどうか確認することといえます。
ミソジニーなどの性差別がない の社会を目指すためにできること

ミソジニーやミサンドリーなど、性別によって生まれる差別がない社会を目指すためには、私たち一人ひとりが意識を変えていかなければなりません。
これからご紹介する4つのポイントをおさえ、自分から誰かを差別することがないよう注意しながら生活を送りましょう。
暴力やセクハラへの対策
ミソジニーに関する問題としてもっとも深刻なのは、性暴力やセクハラの横行です。
加害者を減らすことができれば問題はありませんが、現状はそうもいかないでしょう。
まずは被害を受けた方がすぐにしかるべきところへ相談できるよう、手厚いサポートを受けられる体制を整えておくことが大切です。
現在日本ではカウンセリングや精神科・心療内科での治療、警察による捜査など様々な面からの支援を受けることができるため、ためらわずに利用しましょう。
必要に応じて弁護士などの法的機関へ支援を依頼することも大切です。
職場の雇用条件や待遇の改善
個人では難しいものの、それぞれの企業が取り組む課題として挙げられるのが雇用条件の均等化です。
雇用条件は経験やスキルに応じて変化を持たせるべきであり、性別によって差別されて良いものではありません。
もちろん男女の違いだけでなく、正社員や契約社員・派遣社員・パートタイマーなど、雇用の種類に応じて明確な差をつけることもNGです。
また、近年は男性の育児休暇取得が推進されており、実際に取得した実績のある企業も増えてきています。
近年の傾向として夫婦は共働きであることが多く、その分育児も協力して行う家庭が増えているため、男性であってもパートナーを支える目的で育児休暇の取得を目指すと良いでしょう。
その結果、男性と女性の休暇取得が一律となり、雇用条件に差が生まれにくくなります。
女性の地位向上
2022年には女性活躍推進法などの内容が一部改正されるなど、徐々に女性の地位向上に向けた動きが加速しています。
女性であっても役職や重要なポストを目指せるよう、職場と家庭を両立しながら働ける環境づくりが進められています。
もちろんこの活動には男性の協力も必要不可欠となるため、企業全体が一丸となって行動する必要があるでしょう。
重要ポストに就いた女性の情報や、男性の育児休暇取得率などを公式サイトで公開している企業も多いため、気になる方はチェックしてみることをおすすめします。
その他
これまでに挙げた内容は、個人が動いたからといってすぐに変化が訪れるものではありません。
一方、もっとも大切な行動といえるのが、「私たち一人ひとりの意識改革」ではないでしょうか。
日々の中で何気なく考えてしまう「男性だから」「女性だから」といったワードを捨て、性別に関係なく相手を一人の人間として考えることが大切です。
もちろん性別だけでなく、生まれや年齢・学歴・趣味などあらゆる面で人を差別することがないよう、相手の個性を尊重する考え方が重要です。
まとめ
ミソジニーは明日すぐにでもなくすことができるものではありません。
何百・何千といった女性蔑視の歴史の中で、今このときが転換期となるよう、私たち一人ひとりの意識を変えていく必要があるでしょう。
ルッキズムの意味とは?やめたいけどどうしようもない?

私たちの思考に深く根付いてしまっている「ルッキズム」
良くないことだとは分かっていても、やめるにやめられない方がほとんどなのではないでしょうか。
今回はルッキズムの概念や歴史に目を向けながら、具体的にどのような点が問題となり得るのかについてご紹介します。
ルッキズムとは?

ルッキズムとは、特定の容姿を「美しい」「格好いい」などと称することで、そうでない人のことを自然と差別する考え方のことです。
他者を美しいと思う基準は人それぞれですが、相手の価値を外見だけで判断したり、内面を見ずに決めつけたりするのも立派なルッキズムの一部です。
私たちは普段、それほど意識することなく相手を容姿で判断しています。
声を大にして「イケメンが好き」「美女が好き」と言うことはなくても、パートナーにするならば容姿の整った人が良いと思う方が多いでしょう。
どれだけ優しい人がいたとしても、自分の好みに合った容姿をしていなければ、内面の優しさを知ろうとは思わないのではないでしょうか。
このように、ルッキズムは知らず知らずのうちに私たちの心に強く根付いています。
今すぐにルッキズムをやめようと思っても、そう簡単に気持ちを変えるのは難しいでしょう。
そもそもルッキズムが自分の中にあることに気が付いていない方も多いため、社会全体がルッキズムを脱却するのはさらに長い時間がかかると予想されます。
とはいえ、ルッキズムが進むあまり、内に秘めた能力が正当に評価されない社会は間違っています。
ルッキズムを当たり前のものとせず、私たち一人ひとりが相手の本質を見抜く力を持つことが大切です。
関連記事:ガスライティングとは?実例や被害者への影響について解説
ルッキズムの背景と歴史
私たち人類は二足歩行を始めたときからルッキズムに支配されていたわけではありません。
どこでどのようにルッキズムが生まれ、どのように当たり前のものとなったのか、その歴史を紐解いて見ましょう。
言葉自体は1970年代のアメリカ発祥とされる
ルッキズムという言葉は、「look(見た目)」と「~ism(主義)」のワードが組み合わさったものです。
これは1970年代のアメリカが発祥と言われており、これまでの外見至上主義に名前が付いた瞬間でもありました。
さらに具体的にいえば、ルッキズムという言葉を使い始めたのはアメリカの日刊紙・ワシントンポスト。
ルッキズムという造語を紹介した上で、外見の違いに関する差別的な扱いが問題視されているとの記述がありました。
つまり、1970年代から既にルッキズムに問題点があるといわれており、「どうにかしなければならない」といった動きが進んでいたことが分かります。
一般人同士がパートナーを見つけるときだけでなく、受験や就職など人生を左右する場面で容姿が優遇されることがいかに不平等かを説いていたのです。
ルッキズムの発祥には諸説あるため、上記は一説にすぎません。しかし、外見至上主義が早い段階から問題視されていたことは間違いないといえそうです。
美の基準が確立されたことによる広まり
古い時代の日本では「うりざね顔」と呼ばれる色白で面長の顔が美しいとされるなど、各時代において様々な美の表現がありました。
明治時代に学生が使っていた教科書には、「美人はその外見が故に得をすることが多く性格が悪くなりやすいが、そうでない人は好かれようと一生懸命生きるため性格が良い」との記載があったそう。
つまりこの時代には多くの人が同じ美の基準を持っており、美しい人を妬む気持ちも少なからず持ち合わせていたのでしょう。
また、欧米の文化が流入し始めた明治時代では、これまでの閉鎖的な文化とは異なり、社交の場に顔を出す人が増えました。
その結果相手のパートナーを見定める機会が増え、家柄や職種同様、見た目の美しさも話の種になることが多くなったのです。
2000年代以降は特に顕著に
時代と共に変化を見せてきたルッキズムの考え方ですが、2000年代以降は特に顕著なものとなりました。
「美しさとはこうである」といった特定の美がメディアによって取り上げられたり、SNSを通じて美しい人が話題になったりしたことで、大衆の中で美の基準がハッキリと固まってきたのです。
近年は美の基準に少しでも近づきたい方を対象に、格安で受けられる美容整形の広告を目にする機会も多いでしょう。
多くの方があらゆる手段を用いて美を目指すことは悪いことではありません。
しかし、元々の良さを捨て、平均的な美しさを求めるあまり、大勢が同じような風貌になってしまうのも問題です。
「美とは〇〇である」といった決めつけを捨て、自分の容姿に良いところを見つけるのも大切なことなのではないでしょうか。
ルッキズムの問題点
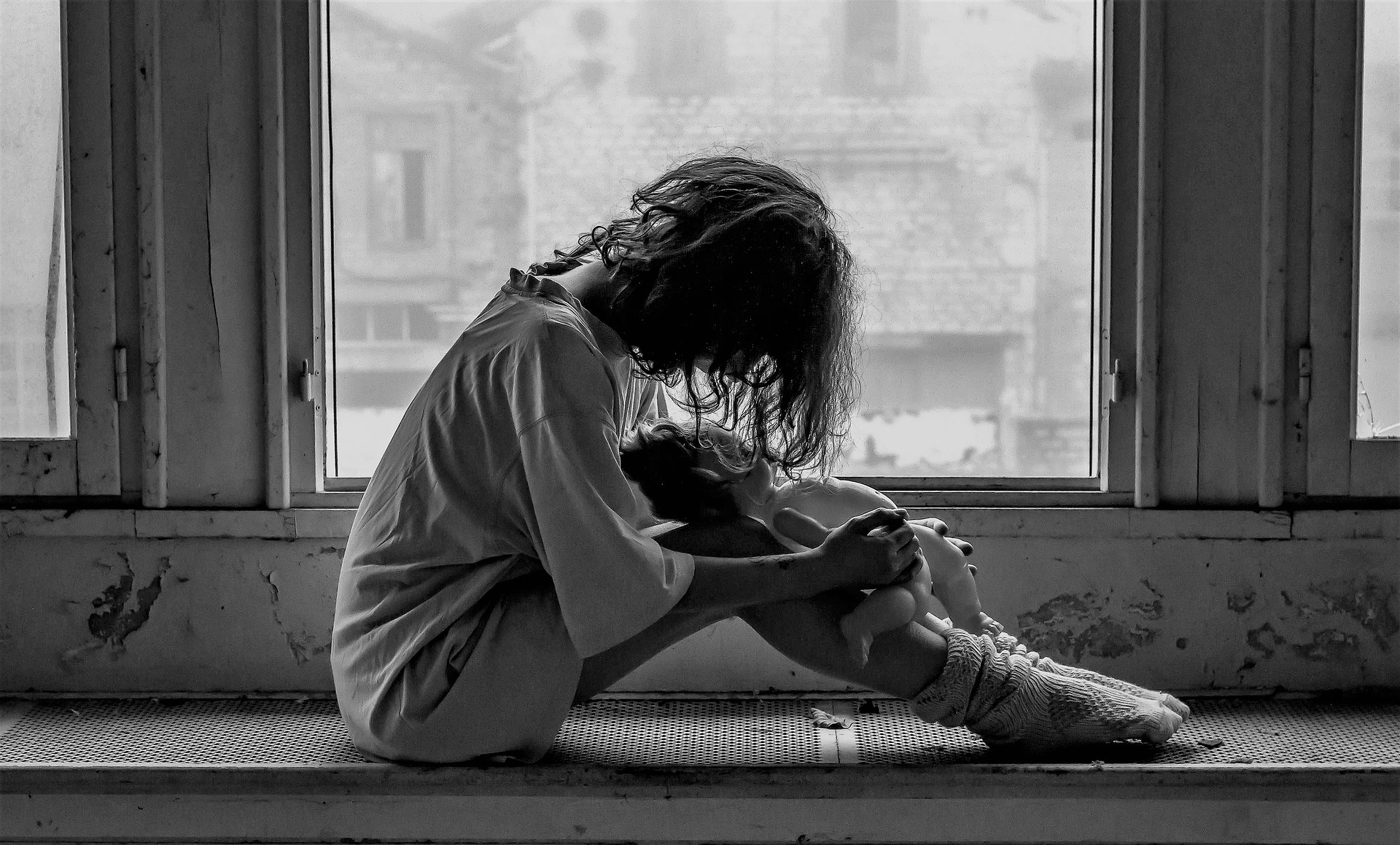
良いものではないと分かっていても、どうして良くないのかを具体的に考える人の少ないルッキズム。
この考えが蔓延り続けることで一体どんな問題があるのかを正しく知っておきましょう。
差別やいじめが助長される
ルッキズムによって外見に差があるとみなされた人々は、時として差別やいじめの対象となる場合があります。
物事の善悪が分からない子どもたちの間ではもちろんのこと、時には大人の間でもひどいいじめが起こり、被害者に大きな影響を及ぼしています。
本当は話し好きなのに外見を気にして会話ができず仲間が作りにくくなっていたり、優れた能力を持っていても発揮する場を与えてもらえず何もできないと思われてしまったり、容姿によって損をした経験のある方も多いはずです。
こういった差別やいじめは、「差別」や「いじめ」というワードを使っているからこそありふれたことのように思えますが、いわば犯罪の一種であることを忘れてはいけません。
中にはこういった差別やいじめを苦に命を絶ってしまう方もいるため、私たち一人ひとりが例外なく、自分の一言の重みを実感して生活しなければならないのです。
能力が正当に評価されない
ルッキズムに関する日本の歴史で少し触れたように、かつては「美人は性格が悪い」「そうでない人は性格が良い」といった偏見がありました。
現在は逆で、見た目が美しくないとみなされた人は上司や先輩から正当な評価を受けられず、能力が眠ったままになっている可能性があります。
これは当人にとって辛いことであるのに加え、企業や社会全体にとっても大きな損失となるでしょう。
自分の能力について正しくアピールできる人であれば良いですが、中にはそうでない人もたくさんいます。
見た目に関わらず、その人がどんな能力を持っているのか、フィルターを通さずに見てみることが大切です。
心理的な健康問題に発展している
美への欲求が多くの人の心に影響を及ぼすことはもちろんですが、時としてその感情が健康問題として現れる場合があります。
特にルッキズムを気にしていない方であれば問題ないようなことでも、周りの目が気になる方や、過去に容姿について嫌なことを言われた経験のある方は過剰に反応してしまうでしょう。
結果として大勢の人がいる場所に恐怖を感じたり、鏡を見ることが怖くなったりといった症状が出やすくなるのです。
また、近年の女性を中心に、「痩せている=美しい」といった考え方が広まっているのも問題の一つです。
「男性よりも痩せていなければならない」「周りの女性はもっと痩せている」といった強迫観念にかられ、本来痩せる必要がないにもかかわらず過剰なダイエットをしてしまう方も少なくありません。
その結果、過食症・拒食症といった食事面でのトラブルや栄養失調、生理不順などの健康問題が現れやすくなってしまうでしょう。
関連記事:子どもの愛情不足サインとは?今すぐできる対処法で親子の絆を深めよう
ルッキズムの解消に向けた対策と取り組み

ルッキズムは一朝一夕でなくせるものではありませんが、このまま放置しても良い考えではないため、日々少しずつ意識を変化させていかなければなりません。
いずれ社会からルッキズムの考えがなくなるよう、一人ひとりができることを始めていくと良いでしょう。
教育・啓蒙活動と意識改革
第一に、ルッキズムが自然と身についてしまうのは、子どもの頃からの刷り込みが原因だといえます。
「痩せている方が美しい」「目がパッチリ大きい方が綺麗」といった考えを子どもに植え付けてしまわないよう、早い段階から「誰しもがみんな違ってみんな良い」といった教育を行うことが大切です。
子どもたちは良いことも悪いこともすぐに吸収してしまうため、大人の身勝手な発言でその後の人生が左右されないよう、子どもの前での会話は特に注意しましょう。
また、多くの大人が自分の考えを見直し、ルッキズムが招く影響を正しく知ることも大切です。
何の気なしに発言した一言が誰かの運命を変えてしまうこともあるため「誰かを傷つけないように」といった曖昧な行動ではなく、「ルッキズムを無くす」といった明確な目標を持つべきです。
メディアの役割の変化
私たちの思想に大きな影響を与えるメディアを使って、ルッキズムの廃止を訴えることも効果的だといえます。
これまでメディアといえば、美しいと評判の俳優や女優・モデルなどを使い、私たち一般人が彼らのような美しさを目指すよう誘導してきました。
もちろんこれは悪意の元行われたことではありませんが、現に私たちの間にはルッキズムが蔓延り、辛い思いをしている人がいます。
特定の人を美しいと持ち上げるのではなく、様々な外見の人をポジティブに取り上げることも良い傾向の一つです。
特定のタイプばかりがテレビに出演しているのを見れば、それに当てはまらない人は自然と自分が美しくないと感じてしまうでしょう。
あらゆるタイプの人を全て平等に「美しい個性」として紹介することで、自分の外見そのものを愛し、自信を持てるようになるのではないでしょうか。
また、お笑い芸人の容姿をいじって笑いに変える文化もまだまだ消えたとはいえません。
一部の人からは笑いが取れるものの、ある人たちからは不快な目で見られてしまうでしょう。
容姿をいじることなく、単純な笑いのセンスで仕事がもらえるよう、メディア全体が変わって行く必要があるのかもしれません。
制度改革による対策
就職などで個人の能力よりも外見が重視されてしまうのを防ぐために、公平な基準を設けておくことも大切です。
これまで「美しい」とちやほやされてきた人は、他者とのコミュニケーションに強く、面接でもハキハキと話せることでしょう。
反対に外見を貶された経験があれば、初対面の相手とイメージ通りの会話ができなくても無理はありません。
こうした差別を取り除くため、各企業が公平な採用基準を設けることが推奨されています。
もちろんコミュニケーションスキルも基準の一つとなりますが、容姿を基準に加えることなく、その人個人の能力をしっかりと見られるような評価を行う必要があるでしょう。
もちろん容姿以外にも、生まれや年齢・性別などでの差別も撤廃するべきだといえます。
特定のイベントの廃止やルールの変更
近年になっても様々なシーンで盛り上がりを見せる「ミスターコンテスト」や「ミスコンテスト」
学校内で行われるものもあれば、全国から美しいと評判の少年少女が集まって競い合うものまで様々です。
もちろん普段の生活や他の魅力も合わせて評価が行われますが、その大半は容姿によって決定されるでしょう。
もしも本当にルッキズムをやめるのであれば、ミスコンそのものを廃止するべきだといえます。
しかし単純に容姿で競い合うのではなく、「〇〇部門」というようにカテゴリを分け、様々な人が1位を狙えるようにするのも良いでしょう。
過度にルッキズム反対を唱えて逆に差別されてしまわないよう、周りが受け入れられやすいプランを提案することが重要です。
ルッキズムをやめたいけどやめられないのはどうしようもない?

先ほどもご紹介したように、ルッキズムはやめようと思ってやめられるものではないでしょう。
自分一人だけが変わっても、周りの環境が変わらなければ、結果として差別やいじめはなくなりません。
インターネットで検索すると、同じように「やめたいけどやめられない」と感じ、声に出せない悩みを抱えながら辛い思いをしている人が多いのが分かります。
ルッキズムに関して大切なのは、「今の自分の気持ちを無視しない」ということではないでしょうか。
ルッキズムが良くないと感じるのも、どうしてもやめられないと悩むのも全て大切な自分の気持ちです。
これらに嘘をついてまでパートナーを選んだり所属する団体を決めたりすると、後々辛くなるのは自分です。
自分の本当の気持ちを尊重しながら、それでもルッキズムが良くないと感じた自分を褒めてあげましょう。
まとめ
ルッキズムは古くから世界中の人々に根付いており、それぞれの地域で異なる美の基準があるのが分かります。
すぐになくすのは難しくても、ルッキズムが推進されるべきでない考えだと知っておくだけで、あらゆる場面での差別をなくすことに繋がるでしょう。
ガスライティングとは?実例や被害者への影響について解説

私たちが他者と関わりを持つとき、その全てが対等であるとは限りません。
どちらかが目上でもう片方が目下の立場になることもありますが、そこには相手への思いやりや尊敬の意が必要となるでしょう。
今回ご紹介する「ガスライティング」は、一方がもう片方を一方的に支配し、感情や行動を抑制する問題行動の一種です。
自身や身の回りの人がガスライティングによる被害を受けないためにも、目的や実例・影響について知っておきましょう。
ガスライティングとは?

ガスライティングとは精神的な虐待の一種であり、相手に間違った情報を植え付け、正しい行動や認識ができないように誘導する問題行動です。
家族や友人関係など親しい間柄で起こる場合もあれば、クラスや職場内など複数人によって行われる場合もあり、被害者は重大なダメージを受けてしまいます。
暴力のように目に見える形で行われることが少ないため、周りはもちろん被害者自身がガスライティングに気が付かず、長年苦しい思いをさせられるケースも珍しくありません。
例えば、仕事でミスをしてしまった部下を上司が叱責するシーンで考えてみましょう。
ミスの原因を探りながら部下の失態を叱り、次のミスが起こらないように対策を考える場合、ガスライティングのような問題は起こりません。
必要な情報だけを伝えて改善策を講じることが重要であり、ミスをしたことだけを責めていても解決には至らないでしょう。
一方、ミスの根本的な原因を無視し、「お前の根性が悪いためだ」「高卒は何をやらせても使えない」などと部下の精神にダメージを与えるような叱責の方法はどうでしょうか。
今回のミスでは部下の性格に問題があったわけではないにもかかわらず、生まれ持った性格や育ちを責め、ミスの責任を押し付けようとしています。
この場合は間違った情報で相手を支配している上司が、部下に対しガスライティングを行っているといえます。
このように、ガスライティングでは「現実とは異なる情報」を相手に正しいと思いこませ、自分の思い通りに支配しようとするのが特徴です。
上記の例では部下が「自分は根性が悪く使えない人間だ」と思い込んでしまうことで、さらなるミスが増えたり、塞ぎ込みがちになったりと様々な影響が出るでしょう。
何をするにも上司の言いなりになり、結果として立派な支配関係が成り立ってしまいます。
こういった状態が続くと、被害者は何も悪いことをしていないにも関わらず、「自分は悪だ」などと正しい判断ができなくなってしまいます。
問題となった上司に対してだけでなく、周りに対してもネガティブな感情しか抱くことができず、人間関係の悪化を招いてしまう点にも注意が必要です。
ガスライティングを行う目的は?
加害者となる側が、被害者に向けてガスライティングを行う目的とは一体何なのでしょうか。
意識的に相手を支配しようとしている人もいれば、無意識のうちに自分を優位に立たせ、相手を破滅に追い込もうとしている加害者もいます。
いずれの場合も、ガスライティングの特徴にいち早く気づき、なるべく早い段階で身を守ることが重要です。
自主的な服従状態に追い込む
ガスライティングの加害者は、相手を服従させ、優越感に浸ることを目的としています。
無理やり自分の言うことを聞かせるのではなく、あくまでも被害者が自主的に服従するよう仕向けることで、より上の立場から相手を見下すことを目指しています。
自分の行いが間違っていると指摘されたり服従を拒否されたりすると逆行し、さらなる暴言を吐くようになるため、被害者は次第に抵抗することを諦めるようになるでしょう。
破滅へ誘導
ガスライティングは単純な支配とは異なり、相手が自立心を失い、自分なしでは何もできないといったレベルまで落ちてしまうことを目的としています。
言うことを聞かせたり思い通りに行動させたりといった序盤から、正しい判断ができず社会に適合できなくなる終わりまで、執拗に追い続けるのです。
特に身内や恋愛・友情関係においては執拗なガスライティングが行われることが多く、周りに打ち明けることもなく苦しんでいる被害者がたくさんいるといわれています。
ガスライティングとモラハラ・ストーカーとの違い

ガスライティングという言葉は未だ社会に浸透していないため、「モラハラ」や「ストーカー」と同義であると捉える方も少なくありません。
モラハラやストーカーとどのように違うのか、それぞれの定義を確認しておきましょう。
モラハラとの違い
モラハラとは「モラルハラスメント」の略称であり、主に言葉によって相手の尊厳を奪い、精神的に傷つける問題行動の一種です。
意見が食い違う相手に対して必要以上に声を荒げて怒鳴ったり、相手の人格を否定するような言葉を投げつけたりと、モラルが備わっている人であればしないであろう過激な言動が特徴です。
直接相手に暴力をふるうことはないものの、大きな音を立ててドアを閉める・物を壊すなどして相手へ恐怖を与える行動もモラハラの一種だといえます。
モラハラがガスライティングと異なるのは、モラハラの方が比較的問題が明るみに出やすいといった点です。
モラハラの被害者は被害を受けたことを実感しやすく、周りにも相談しやすいでしょう。
会社やクラスといった場所でのモラハラであれば、被害者よりも周囲が先に声を上げる場合も見られます。
一方のガスライティングは、被害者はもちろん周りも気が付かないようなスピードで徐々に精神を追い詰めていく点に注意が必要です。
被害者は知らず知らずのうちに加害者から離れられなくなり、気が付いたときには手遅れとなっていることも多いでしょう。
周りから見ると加害者と被害者の関係が非常に良好に見える場合もあり、なかなか問題が露呈しにくいといった危険性があります。
ストーカーとの違い
相手を自分の好きなように支配したい、といった感情は、ガスライティングだけでなくストーカーにも当てはまります。
相手が好きで仕方がない、または相手が自分のことを好いていると思い込んだ結果、行動を監視したり過度に連絡を取ったりしてしまうのがストーカーの特徴です。
中には相手が自分の恋人だと思い込んだ加害者が、被害者が異性といるのを発見し、勢い余って暴力に及ぶケースも珍しくありません。
ガスライティングもストーカー同様に相手へ強い執着を見せますが、その根底にあるのは「相手を服従させたい」といった思いであり、恋愛感情とは異なります。
ストーカーはあくまでも相手に振り向いてほしくて行うケースが多いのに対し、ガスライティングは相手の人生を破滅させ、とことん追い込むことを目的としています。
「相手に幸せになってほしい」といった思いは一切なく、嫌がらせの数々は全て自分の快楽のために行われているのが特徴です。
ガスライティングの実例
続いて、実際に起こったガスライティングの実例をご紹介します。
先程もご紹介したように、ガスライティングは被害者が自覚しにくいといった危険性があります。
これからご紹介する実例に当てはまるケースはないか、身の回りをイメージしながらご覧ください。
疑心暗鬼に陥らせる
ガスライティングで頻繁に見られるのが、何もしていない人に対して不安になるような言動を行うことで、「自分が悪いのではないか」と疑心暗鬼に陥らせる行動です。
例えばある日会社で重要な書類の紛失事件が起こったとします。
Aさんは何もしていないはずのBさんに対し、「そういえばこの前Bさんがその書類を持っていたよね」と話しかけます。
Bさんは身に覚えがないものの、Aさんがあまりにもハッキリと断言するため、「もしかしたら自分が書類をなくしたのではないか」と不安に感じてしまいます。
このように、Aさんにとって書類を紛失したのが誰であるかは関係なく、「Bさんをいじめてやろう」「困らせてやろう」といった考えだけで行動しているのが特徴です。
このような出来事が繰り返されると、Bさんは次第に自信を失い、何事にも挑戦できなくなってしまうでしょう。
わざと侵入した痕跡を残す
先程の例を引き続き見ていきましょう。
書類の紛失事件をBさんになすりつけて困らせようと考えたAさんは、事前にBさんが犯人であると疑われるように仕掛けます。
Cさんが出張に行った際に職場で配ったお土産をBさんが机に置いたのを見て、Aさんはこれをこっそりと隠してしまうのです。
Bさんはお土産がないことに気が付きますが、Cさんになくしたとはいえず、モヤモヤとした気持ちで過ごすこととなるでしょう。
そんな折に書類の紛失事件が明るみに出ます。Aさんは先程同様にBさんを疑い、同時に「前もCさんのお土産をなくしてたよね」と発言しました。
これによって職場のメンバーからは、「人からもらったものをなくすなんて、きっとBさんが書類をなくしたんだろう」といったイメージを持たれることとなるでしょう。
このように、被害者を疑心暗鬼に陥らせるため、わざと証拠を残すのもガスライティングのやり口です。
これにより、加害者から受けるガスライティングだけでなく、周りからも孤立しやすくなってしまうといった危険性があります。
偶然を装う
ガスライティングでは、被害者が加害者に精神的な依存を見せるのが特徴です。
そのためには被害者と加害者がより近しい関係になる必要があり、お互いの物理的な距離は縮まっていくでしょう。
AさんはさらにBさんを追い詰めるため、職場のメンバーと共謀してBさんの行動を監視します。
職場内だけでなく、外出先などでも偶然を装って姿を現し、Bさんのプライベートを侵食していきます。
Bさんは怪しんで職場のメンバーに相談しますが、Aさんと共謀しているメンバーが口を割ることはありません。
結果、BさんはいつもAさんに監視されていると思い込むようになり、外出自体を怖がり、ひきこもるようになってしまいました。
このとき、AさんはBさんに対し「いつも監視している」と伝えたわけではありません。あくまでもBさんが勝手な思い込みで苦しんでいる、といった状況を作り出すため、偶然を装って行動を監視しているのです。
嘘を吹き込む
AさんはBさんを孤立させ、さらに自身への依存を高めるために嘘を吹き込むようになります。
「〇〇さんがBさんのことを苦手だって言っていた」「Bさんは仕事ができないから重要な案件を任せられないと上司が言っていた」など、根も葉もない嘘を吹き込んでBさんの不安をあおります。
さらには「皆には内緒だけど、特別に教えてあげる」などと伝えることで、Bさんは周りのメンバーに相談ができなくなり、たった一人で悩むこととなってしまいました。
このような嘘はガスライティングにおいてよくあるケースであり、被害者は簡単にこの嘘を信じてしまいます。
加害者は最初から嘘を信じるような純粋な人や、周りになかなか相談できない内向的な人を狙ってガスライティングを行うのです。
行動の邪魔をする
ガスライティングの手口として最後にご紹介するのが「行動の邪魔をする」といった点です。
Bさんが職場でしようとすることを端からAさんが邪魔をしていくため、Bさんは思い通りに動くことができません。
それどころかAさんの指示通りに動くよう強制され、いつしかAさんがいなければ何もできないようになってしまうのです。
関連記事:マイノリティ・マジョリティとは? 多様な社会の理解を深めるために
ガスライティングの被害者への影響

ガスライティングでは、ときに被害者に対し社会復帰できないレベルの重大な影響が及ぶ可能性があります。
こういった最悪のケースを防ぐためにも、自身や周囲がガスライティングの可能性を疑い、日々確認しながら過ごすことが大切です。
精神的影響とトラウマ
ガスライティングの被害者は自身を信じることができなくなり、自分が何をすれば良いのか、どう生きていけば良いのか分からないといった不安に襲われることとなります。
自分で自分の意思を決められないため、職場や学校でのコミュニケーションがうまく取れなくなり、結果として外出できず引きこもりになってしまうケースも少なくありません。
こうしたガスライティングの被害者は、加害者による抑圧が終わった後も、しばしば被害についてフラッシュバックしてしまうことがあります。
嫌な思いをした場所に足を踏み入れることができなくなったり、パニック症状やうつ症状が現れたりと、精神的にも身体的にも弊害が起こってしまうでしょう。
長期的な健康への影響
ガスライティングの被害者は精神疾患を抱えやすいほか、不眠・イライラ・焦り・便秘や下痢といった症状が慢性的に現れるようになったり、思うように食事がとれなくなったりする場合があります。
こういった状況が続くと健康を害し、様々な病気にかかりやすくなってしまうでしょう。
外出の機会が減ると日光を浴びる回数が減り、骨や歯がもろくなったり、皮膚病にかかりやすくなったりする可能性が高まります。
一度でもガスライティングによる被害を受けてしまうと、被害者はこういった身体症状が現れていても、すぐに医療機関を受診できない場合があります。
一人暮らしなどで周りに頼れる人がいない場合や、周りに不調を隠してしまう場合などは特に、症状が長引く可能性が高いといえます。
社会的孤立
ガスライティングでは加害者が被害者を孤立させる目的で様々な行動を起こします。
辛いことがあっても頼る人がおらず、結果として加害者に依存するしかない状態を作り上げているのです。
周りがガスライティングに気が付かなければ、被害者は永遠と一人で苦しむことになるでしょう。
また、加害者の巧妙な手口によって孤立した被害者は、自分だけでなく周りも信用できなくなってしまいます。
うまくいって加害者とは別の環境に移動できたとしても、心から周りを信じることができず、結果として孤立してしまうケースが多々見られます。
ガスライティングに仕返しすることはできる?
ガスライティングを受けていることに気が付いたり、周りにいる人が被害者なのではないかと感じたりしたとき、誰でも一度は「仕返しをしたらいいのではないか」と考えることでしょう。
ガスライティングに対し仕返しをすることは可能なのか、リスクと共にご紹介します。
仕返しのリスク
ガスライティングの加害者に対し、同じような方法で仕返しをすることはおすすめできません。
何故なら加害者は既に被害者に対して優位に立っていると思い込んでおり、仕返しをするようなそぶりを見せると直ちに攻撃を開始してくると考えられるためです。
今までよりも強い言葉でなじったり、周りから孤立させたりするだけでなく、今度は暴力などを用いて支配しようとするかもしれません。
また、被害者が加害者に仕返しをしたことが原因で、「喧嘩両成敗」となってしまう可能性があります。
周りに相談しても「どっちも悪いね」と済まされてしまい、被害者の無念は晴れないでしょう。
仕返しを考える前にできること
ガスライティングに対しては、仕返しをする前にまず「周りに相談」することが大切です。
なるべく加害者から距離のある知人に、第三者目線で判断してもらうと良いでしょう。
時には精神科医や臨床心理士・カウンセラーなど、専門家に協力を求めるのも大切です。
加害者の言動が度を過ぎていると感じたり、距離を取ろうとしてもうまくいかなかったりする場合は、法的措置を検討するのも一つの手です。
辛い現状を変えるため、受けた被害は全て証拠を残しておきましょう。
チャットのトーク画面を保存したり、音声データを残したり、壊されたものをそのまま保管しておいたりするのも重要です。
ガスライティングから身を守るための対処法

ガスライティングを受けたと感じたときは、ただちに立ち向かうのではなく、まず自分の身を守る行動をとることが大切です。
これからご紹介する5つの対処法を頭に入れておき、万が一の際にしっかりと判断できるように心掛けておきましょう。
1.第三者に助けを求める
ガスライティングは加害者と被害者が一対一の関係になったり、複数人の加害者に対し少数の被害者が攻撃を受けたりすることが多いとされています。
ガスライティングに当てはまる行動を見たり、実際に受けたりした場合は、すぐに第三者の助けを借りましょう。
先程もご紹介したように、必ずしも加害者に近しい人を選ぶ必要はありません。
時には家族を、またある時には上司や先生など立場が上の人を巻き込んで、加害者の言動をチェックしてもらうことが大切です。
2.起きやすい場所を避ける
ガスライティングは個室などの閉鎖空間で起こることが多いため、加害者と二人きりになるような状況をできるだけ避けるのがおすすめです。
自分のいない間に何かされているのではないかと心配な方は、自分のデスクやロッカーにしっかりと鍵をかけるなどの対策を行うのも良いでしょう。
集団で行うガスライティングを避けるためには、一定期間その集団から離れてみても良いでしょう。
普段一緒にいるグループから少しの間離れたり、別の人と一緒にいるようにしたりするだけで、被害を抑えることに繋がります。
加害者が家族や友人内にいる場合は、プライベートの時間をしっかりと確保し、なるべく同じ空間で過ごさないよう工夫することをおすすめします。
3.加害者を無視する
ガスライティングの被害者になりやすいのは、相手の発言を無視できず、つい言うことを聞いてしまう心の優しい人です。
どんなにひどいことを言われていても強く反発できず、加害者に自信を与えてしまうでしょう。
嫌なことをされたとき、加害者を無視する強さを持つことも大切です。嫌なことをされてまで、相手に嫌われないようにと振舞うのは得策ではありません。
さりげなく相手から距離を取ったり、嫌な話題を変えたりするだけでも、ガスライティングの被害を最小限に抑えられるでしょう。
4.証拠を集める
最終手段として専門家に相談するため、ガスライティングで受けた被害は全て証拠を集めておくことが大切です。
メッセージや写真・録音など、様々な形で証拠を残しておくことで、被害の全貌を明らかにすることができます。
加害者が無意識で行っていたことも含めてしっかりと責任を負わせるためにも、辛い中ではあるものの、証拠を失ってしまわないように注意しましょう。
こういった精神的被害は、被害者の日記も証拠になる場合があります。
その日されたことや嫌だったことを時系列順に書き留め、風化させないように保管しておきましょう。
5.専門家・専門機関への相談
被害が甚大な場合や、加害者に更生の兆しが見られない場合は、専門家へ相談することをおすすめします。
既に被害者に身体的・精神的症状が出ている場合は、精神科や心療内科を受診しましょう。
医薬品の服用やカウンセリングなど、被害者一人ひとりに合った治療を選択できます。
また、社内でのトラブルは上司や人事へ、家庭内でのトラブルはDV支援施設など、それぞれ役割の異なる施設がたくさんあります。
どこに相談すべきか分からない方は、弁護士に話を聞いてもらうのもおすすめです。
関連記事:人間関係が「めんどくさい」「疲れた」と感じる心理や対処法を解説
まとめ
ガスライティングは一人の被害者の人生を狂わせてしまう悪質な行為です。
自身が被害を受けないように注意するだけでなく、周りに苦しんでいる人がいないかどうか確認しておくのも大切です。
ガスライティングの特徴や実例・困ったときの相談先などをイメージし、万が一の際に備えましょう。
義母の死から悟った、生きることの真髄【Editor’s Letter vol. 11】

| Humming編集長 永野舞麻がカリフォルニアから配信する「Editor’s Letter 」。日々の暮らしで感じた気付きや、人生において大切にしていることを綴っています。 |
2ヶ月前、義母と一緒に楽しんだメキシコ旅行。しかし先日、彼女は突然この世を去りました。まだ77歳。アメリカ女性の平均寿命にも届かぬ年齢でした。
彼女と知り合って20年。共に紡いできた思い出が、まるで掌から零れ落ちる砂のように、あっという間に遠ざかっていくような感覚に襲われました。
今まで人生で経験した「死」の中で一番ショッキングだった義母の死。この突然の喪失は、私に深い衝撃を与えると同時に、人生の本質について深く考えるきっかけとなりました。
人生は沈むことが約束された船旅
義母の死を経験したことで、人生は沈むことが約束された船に乗って航海しているようなものだと気がつきました。
私たちが乗っている船は、嵐に遭遇するかもしれないし、船底に穴が空くかもしれない。最終的には、どの船も必ず海底へと沈んでいくのです。しかし、私たちはその運命を知りながらも、船に乗り込みます。
この避けられない終わりに対して、不安や恐怖を感じる方は多いでしょう。それは自然な感情です。しかし、人生には終わりがあるからこそ、私たちは日々の美しさや楽しさ、そして些細な喜びをより鮮明に感じられる。有限であるがゆえに、一瞬一瞬が輝きを増すのだと私は感じています。
全身全霊で今を生きたい
義母と共に過ごした時間は、長かったのか、短かったのか。
夫に出会って、恋をして、彼のことを心から尊敬するようになる中で、義母の子育てがあったからこそ、今の彼がいるのだと気がつきました。長女を授かってからは、義母のような母親になることが私の目標でした。どんな時も、私のことを尊重してくれ、笑いながらアドバイスをしてくれた義母。上手く子どもたちに接することのできない私を「そんなに自分に厳しくしなくてもいいわよ。あなたは毎日とても頑張っているじゃない」と優しく励ましてくれました。
子どもたちが幼かった頃は、毎年、数ヶ月もある夏休みを同じ屋根の下で過ごしたり、ハワイや日本国内を旅行したり、濃密な時間をたくさん一緒に過ごしました。それでも、義母との思い出を振り返りながら、私は自分に問いかけました。共に過ごした時間、彼女と真剣に向き合って話をできていただろうかと。
私たちは「ながら」生活をしがちです。スマートフォンを見ながら会話をし、他のことや、次の返答を考えながら人の話を聞き、未来の心配や過去を後悔しながら現在を生きています。まっさらな状態でいることは、実はとても難しいことです。
当たり前のように存在していた義母が突然いなくなってしまった。この別れを経験し、人生の儚さを痛感すると共に、限りある人生を後悔せずに生きるためには、 目の前の瞬間に全身全霊で向き合うことが大切だと実感しました。とはいえ、今を大切に生きられたとしても、きっと 「もっとこんなところに行けばよかった、こんな話をすればよかった、こんな料理を作ってあげたかった……」という感情は避けられないのかもしれません。
それでも、これからは、子どもが話しかけてきたときには、その子の言葉一つ一つに耳を傾け、抱きしめるように話を聞いてあげたいし、目の前にいる人、今この瞬間の事柄に100%集中したい。同時に、無理をして「聞いているふり」をするのはやめることにしました。余裕がないときは、「今はちょっと難しいけれど、これが終わったら話を聞くね」と素直に伝える。そうすることで、相手との関係もより誠実なものになるのではないでしょうか。
一方で、キャパシティには限界があります。今と真剣に向き合うためには、時間にも心にも余白が必要です。様々な情報やモノに溢れる現代、私たちは自分のキャパシティを超えた状態で生きているのではないでしょうか。そう感じた私は、35歳を過ぎた頃から、仕事を減らしたり、外出の予定を少なくしたり、余白を意識するようになりました。今後も予定を詰め込みすぎず、今を大切に過ごしていきたいと思っています。
関連記事:辞めることで起こったパラダイムシフト。実は色々なことをやりすぎていた?幸せの鍵はLess is More。 【Editor’s Letter vol.08】
死後の世界には何も持ってはいけない
もう一つ、義母の死を通じて感じたことは、モノやお金に執着することの無意味さです。
先日、遺品整理のために義母の家を訪れた時、日常が突然止まったかのような光景を目にしました。机の上に置かれていた図書館で借りたままの本、冷蔵庫の中の食べかけの食品、制作途中のアート作品、洗濯カゴに入ったままの洋服……、義母の生きていた証がそのまま残されていたのです。今にでも義母が帰ってきそうな風景がそこにはありました。
生きる上で、モノやお金は必要です。 しかし、どんなに集めても、築き上げても、死後の世界には何一つ持ってはいけません。この当たり前の事実を痛感し、頭をガツンと叩かれたような気持ちになりました。生まれてきた時と同じように、死ぬ時は誰しも一人ぼっち。自分の体さえも、この世に残して逝くのです。
「これも私の、あれも私の」
「それも欲しい、これも欲しい」
「お金がないと不安、もっと稼がなければ」
モノや人、お金に執着することに、どれほどの意味があるのでしょうか。最期には全てを手放す運命だということを忘れずに過ごせたのなら、多くの執着や固執をその都度手放せるような気がします。
自分にとって本当に大切なものは何か、今手に入れようとしているものは本当に必要なのかを自問し、心から求める必要最低限のものだけを大切にする。そんな生き方を心がけたいと感じました。
生と死の不思議、そして生きる意味
私たちはどんなに一生懸命生きても、最後には魂が抜け、体は動かなくなり、全てを置いて新たな世界へと旅立っていくのです。そして、この世で所有していたものは次々と片付けられていき、残されるのは、子や孫に引き継がれたDNAと、人々の記憶の中にある思い出だけです。
義母が病に倒れた時、誰もその深刻さを予想できませんでした。わずか1ヶ月半前、私たちは一緒にメキシコで春休みを楽しんだばかりだったからです。海水浴や洞窟探検、美味しいメキシカン料理を堪能した思い出が鮮明でした。
当初、検査をしても心拍の不安定さや酸素不足の原因は分からず、気管支炎と何かのアレルギー症状が重なったのかな……と思っていました。その後、大きな総合病院への移転で希望を感じ、血液検査の結果に絶望しました。それでも、心の底には「回復してまた帰ってくる」という想いがありました。「義母はこのまま帰らぬ人となってしまうんだ。一緒に過ごせる時間はあと1週間しかないんだ」という事実と向き合うことになったのは、組織採取をして検査結果が出た時です。巨大な迷路に迷い込んで、どんなに工夫しても、もがいても、どうやっても抜け出せない。そんな途方もない感覚に襲われました。「このまま死んでしまうなんて絶対に嘘だ」と何度も疑ってみたり、今自分が生きているこの現実を夢のように感じたり、「頭が混乱するとはこのような感覚なんだ」と客観視してみたり。
私たちは無意識のうちに、明日も明後日も明明後日も、人生が永遠に続くかのように思い込んでいます。しかし、つい先日まで一緒に楽しく過ごしていた義母の突然の死は、その思い込みを一瞬にして覆しました。
義母との別れは、深い悲しみと寂しさをもたらすと共に、私たちが日々「生かされている」ことの意味を深く考えさせてくれました。限りある人生だからこそ、今この瞬間を大切にし、愛する人としっかり向き合い、自分にとって本当に必要なものを見極めて欲張ることなく過ごしていきたいです。
生かされていることの意味を考えさせてくれたこと。これは、義母が遺してくれた最後の贈り物なのかもしれません。
子どもの愛情不足サインとは?今すぐできる対処法で親子の絆を深めよう

今日もたくさん子どものことを怒ってしまった……。
私の愛情、ちゃんと子どもに伝わっているかな……。
子育てをしていると、罪悪感や不安を感じることがありますよね。
愛情は目に見えるものではありません。形で図ることもできません。さらに、人によって愛情の受け取り方も様々。だからこそ、子どもへの愛情が足りているかどうかを判断するのは難しいものです。
この記事では、よくある子どもの愛情不足サインや、愛情を伝えるための子どもとの関わり方のヒントをお伝えします。
子どもの発育に必要不可欠な親の愛情とは?
子どもの健やかな成長には、親の愛情が欠かせません。まず大切なのは、子どもに安全と安心を与え、その存在をありのままに受け入れることです。
ありのままを受け入れるとは、他の子と比較することなく、その子の個性を認め、成長を喜ぶことです。
また、子どものさまざまな要求や気持ちをくみ取り、受け止め、応えることも大切です。子どもの感情や行動を否定せず、まずは受け入れる姿勢を持つことで、子どもは「自分は大切にされている」と感じ、安心して成長していけるでしょう。
同時に、成長に合わせて自立を促すことも重要です。例えば、幼児期なら自分で服を選んで着替える、小学生なら学校や習い事の支度を自分で行う、お風呂掃除やゴミ捨てなど家事を手伝うなど、年齢に応じて責任ある行動を任せていきます。
適切な制限を設けることも愛情表現の一つです。就寝時間やスマートフォンの使用時間を決めるなど、子どもの健康や安全を守り、規則正しい生活習慣を身につけさせます。
親自身が良い手本となり、子どもの成長を温かく見守り、必要な時にサポートすること。そして、言葉や行動で愛情を伝えること。これらを通じて、子どもは自分が愛されていると実感しながら、健やかに育っていくでしょう。
愛情不足のサインとは?
では、親からの愛情が不足していた場合、どのようなサインが子どもに現れるのでしょうか。よくある2つの変化をご紹介します。
やる気が出にくくなる
子どもは愛されていると感じると、いろいろなことに挑戦する元気が湧いてきます。一方で、愛情不足の場合、朝布団から出るのが辛くなる、好きだった習い事に行きたがらなくなるなど、やる気が低下することがあります。
愛情を確かめる行動をとる
子どもは、自分が本当に愛されているのかを不安に感じた時、親の愛情を確かめるためにお試し行動をとることがあります。
例えば、いつもより「抱っこして」と甘えん坊になる、わざといたずらをして親を困らせる、親の言うことを全く聞かないなど。「親はこんな自分でも愛してくれるのか?」を試しているのです。
さらに愛情不足の状態が続くと、大人になってからも様々な影響が出る可能性があります。
- 自己肯定感の低下
- 他者を信頼することが難しく、深い人間関係を築くのに苦労する。
- 他者からの評価に過度に依存し、自分の価値を見出すのが難しくなる。
- 特定の人に過度に依存したり、逆に誰とも深い関係を持てなくなったりする。
など。
しかし、これらの状態は、親の愛情不足だけが原因なわけではありません。
例えば、入学・転校・引越し、兄弟の誕生などの環境の変化、受験勉強や友達関係でのストレス、子ども自身の性格や気質など、さまざまな要因が関係していることがあります。
そのため、子どもの変化に気がついた時は、「愛情不足かも.」「私のせいだ」と自分を責める必要はありません。大切なのは、子どもの様子をよく観察し、子どもの変化に気づき、寄り添う姿勢を持つことです。

愛情不足かも?と感じた時の4つ対処法
最近子どもの癇癪が激しい……。
なんだか様子がいつもと違うな……。
もしかして、愛情不足……?
違和感を感じた時には、以下の4つを心がけてみましょう。
「大好きだよ」「ありがとう」言葉で愛情を伝える
言葉で愛情を伝えることは、親子関係を深める最も簡単で効果的な方法です。「あなたのことが大好きだよ」、「生まれてきてくれてありがとう」と素直に表現することで、子どもに直接的に愛情を伝えることができます。
子育てをしていると、ついつい子どものネガティブな面に目を向けがちです。しかし、意識的に子どものちょっとした頑張りや良いところに目を向けて言葉で伝えてあげると良いでしょう。また叱る必要がある時でも、まず子どもの気持ちを聞き、理解しようとする姿勢を示すことが大切です。
スキンシップを大切にする
スキンシップは子どもに安心感を与える重要な愛情表現です。学校に行く前にギュッと抱きしめたり、寝る前に頭を撫でたり、時にはオイルでマッサージしてあげるのも効果的です。
肌と肌が触れ合うことで、愛情ホルモンと呼ばれるオキシトシンが分泌されます。このホルモンは、心身のリラックスを促し、ストレス軽減にも役立ちます。
そのため、スキンシップをすることで、子どもに愛情が伝わるだけでなく、親もより穏やかな気持ちで子育てに向き合うことができるでしょう。
1日10分でもOK。子どもに100%集中する時間を持つ
子どもと向き合う時間を意識的に確保することも効果的です。大切なのは時間の長さではなく質。
例えば、毎日10分間、その子のためだけの時間を確保する。目を見て話を聞いたり、一緒にお絵かきをしたり、その子が望むことを叶えてあげる時間が持てると良いですね。
質の高い時間を親子で過ごすことで、子どもは「自分は大切にされている」と感じることができるでしょう。
自分自身がご機嫌でいること
親自身が心身ともに健康でないと、子どもに十分な愛情を注ぐことは難しくなります。だからこそ、親自身がご機嫌でいることが大切です。美味しいものを食べたり、趣味を充実させたり、たまにはひとりでリラックスする時間を持つことも大切です。
また、親がイキイキとした姿を見せることで、子どもも自分を大切にすることを学んでいくでしょう。
完璧を目指さない、親子で成長することが大切
毎日笑顔で愛情たっぷりに子どもと接したいと思っていても、思い通りにいかないのが現実です。
疲れて余裕がなくなり、子どもにイライラしてしまうときや、仕事に追われて子どもの話をゆっくり聞いてあげられないときもあるでしょう。
しかし、親だって人間です。完璧な人間などいません。だからこそ、自分の不完全さを認めつつ、愛情を伝えながら、親も子どもと一緒に成長していく。それこそが、最高の愛情表現になるのかもしれません。
ポリアモリーの特徴は?浮気と何が違うのか誤解されやすいポイントを解説

現在の社会は、男性・女性といった枠組みを超えた様々な恋愛観が受け入れられ始めています。
LGBTQ+と呼ばれる性的マイノリティの方々に対しても、専用のトイレが作られたり、アンケートにて性別を答える必要がなくなったりといった配慮が見られることが増えてきました。
一方、1990年代頃から始まったとされる「ポリアモリー」は、未だ世界中に受け入れられているとは限りません。
今回はポリアモリーの特徴や招きやすい誤解、本人たちがどのような悩みを抱えているのかについてご紹介します。
ポリアモリーとは?

ポリアモリーとは、複数の相手と恋愛関係にあり、その状態が許容されている状態を指します。
一見浮気のようにも思えますが、複数の相手とそれぞれ合意の上で恋愛をしているため、本人たちの中では何ら問題がないのが特徴です。
周囲に偏見の目で見られることも多く、ポリアモリーであることを隠している方も少なくありません。
日本は古くから一夫多妻制の国であるため、ポリアモリーに対して良い印象を抱かない人が多いという特徴があります。
そもそもポリアモリーという言葉を知らず、単なる浮気だと感じている方も多いでしょう。
ポリアモリーの方々は、こうした偏見の目にさらされながらも、自身の好む生き方を貫いているのです。
そもそもポリアモリーは、1990年代頃をきっかけに広まり始めました。
ギリシャ語の「ポリ(複数)」と、ラテン語の「アムール(愛)」を組み合わせた造語であり、浮気や不倫とは異なる形態として確立されています。
ポリアモリーの生き方を実践している人のことを「ポリアモリスト」、ポリアモリストが形成する家族を「ポリファミリー」などと呼びます。
日本では「複数愛」などと呼ばれることも多いため、覚えておくと良いでしょう。
ポリアモリーの特徴
ポリアモリーが一般的な浮気や不倫と違うのは、大きく分けて3つのポイントがあるためです。
それぞれの特徴をしっかりと理解し、ポリアモリー特有の考え方を理解していきましょう。
全員が合意している
ポリアモリーの特徴として挙げられるもののうち、もっとも大切なのが「それぞれの関係を全員が知っている」という点です。
A子さんがB太さん・C男さんの両方と付き合っていた場合、B太さんとC男さんはお互いの存在を知っており、さらに合意している状態がポリアモリーです。
中にはB太さんとC男さんがA子さんの予定を細かく把握しており、「今日は違う相手と会う日だな」と理解している場合もあります。
A子さんはB太さん・C男さんのいずれにも存在を隠す必要がないため、自然のままに振舞えるのが特徴です。
B太さんに対し、「昨日はC男さんと〇〇をした」と報告することもでき、ストレスのない関係性を築けるでしょう。
また、A子さんというパートナーがいるB太さん・C男さんは、それぞれ別の女性とお付き合いしている可能性もあります。
完全なるポリアモリーでは、B太さん・C男さんのそれぞれがお付き合いしている女性も、この複数愛を理解し、合意していなければなりません。
ポリアモリーに合意できる人はそれほど多いとは限らないため、ポリアモリスト同士が惹かれ合い、大きなコミュニティとなる可能性も高いでしょう。
持続的関係
ポリアモリーは必ずしも身体の関係があるとは限りません。
複数の相手がいることを合意していたとしても、一夜限りの関係ではポリアモリーとは呼べないでしょう。
何ヶ月、何年と関係が続くかは人によって異なりますが、いずれも持続的な関係を目的としており、一般的な恋愛と同じように時間をかけて信頼関係を構築しているのです。
また、ポリアモリストの中には相手へ恋愛感情を抱いている人もいれば、精神的な安心を求めていたり、経済的に支え合ったりする目的の人もいます。
結婚をするつもりはないが老後に一人で暮らすのは心配だという方や、子育てに自信がなく大勢で協力してやりたいと願っている方なども、ポリアモリーに当てはまるでしょう。
相手を所有しない
ポリアモリーでは、相手とパートナー関係にあるのみで、そこに束縛する目的はありません。
いくら複数愛に理解を示していても、相手は独立した考えを持った個人であり、尊重されるべき存在です。
「自分には複数のパートナーがいるが、あなたには自分だけを見ていてほしい」といった考えがあったとしても、相手の考えを理解した上で、お互いが納得できる答えを見出すのが特徴です。
ポリアモリスト同士の間では強固な信頼関係が構築されていますが、その根底にあるのは入念なコミュニケーションです。
相手の気持ちを知り、自分の気持ちを包み隠さずに伝えることで、お互いを尊重した関係性を築けるのではないでしょうか。
ポリアモリーへの誤解

ポリアモリーには複数のパートナーがいますが、日本ではまだまだ一般的な考えではありません。
それ故に周りへポリアモリストであることを明かすと、あらぬ誤解を生む可能性があるでしょう。
ポリアモリーに関する誤解は、口に出してしまうと相手が傷つくようなものばかりです。
相手の恋愛観に疑問を持った場合でも、安易に口に出すことはせず、ポリアモリーに関して正しい知識を付けることが大切です。
性に奔放
ポリアモリーは必ずしも性行為をするための関係ではありません。
身体的な快楽よりも精神的な安心を求めてパートナーを増やす人も多く、性に奔放であるとはいえないでしょう。
中には数々のパートナーと性行為に及ぶ方もいますが、これは私たちが特定のパートナーを選ぶのと同じで、愛する人と身体を重ねたいという思いから来る行動です。
数々の異性と性行為に及びたいだけならば、短期間の間にパートナーをコロコロと変えたり、一夜限りの関係を求めたりするでしょう。
ポリアモリーは通常の恋愛と同じく、会話やデートを重ねてお付き合いへと発展させていきます。
信頼関係を構築して初めて性行為へと繋がっていくため、慎重に性行為へ及ぶ方もたくさんいます。
複数でのセックスがすき
複数のパートナーがいるポリアモリストは、パートナー同士がお互いの存在を知っていたり、時には複数人で会ったりする場合があります。
大勢が属するコミュニティができている場合も多く、同じ考えを持った人が集うため、コミュニケーションも弾みやすいでしょう。
しかし、パートナーが大勢いるからといって、大勢で性行為へ及ぶわけではありません。
複数のパートナーと順番に会い、それぞれ1対1で性行為に及ぶ方がほとんどです。
もちろんグループセックスに同意していれば複数で性行為に及ぶ可能性もありますが、それが全てではないことを覚えておきましょう。
長く続かない
前述のA子さんを例に挙げて考えてみましょう。
A子さんにはB太さん・C男さんというパートナーがいますが、B太さんには別にD美さんという女性が、C男さんにはE奈さんという女性がそれぞれパートナーになっている場合があります。
この場合、A子さんがD美さん・E奈さんに嫉妬してしまい、関係がこじれてしまうのではと考える方も多いのではないでしょうか。
もちろん、ポリアモリスト同士の恋愛であっても、嫉妬により関係が終わってしまうことがあります。
しかしこれがすべてではなく、念入りなコミュニケーションの元、嫉妬の感情とうまく付き合っている人もたくさんいます。
ポリアモリストだからといって長続きしないとはいえず、一般的な恋愛と同じレベルで破局の可能性があるだけなのです。
遊びたいだけ
ポリアモリーを自認する方の多くは、精神的な安心を求めてパートナーを増やしています。
信頼関係を構築した上で性行為に及ぶことはあっても、身体だけで繋がる関係ではないことを覚えておきましょう。
真剣に考える対象が多いというだけで、真剣さの度合いは一般的な恋愛と変わらないため、ポリアモリー=遊びといった考えは間違いです。
関連記事:マイノリティ・マジョリティとは? 多様な社会の理解を深めるために
ポリアモリーの悩み
ポリアモリーを自認し、信頼できるパートナーができても、実際にはさまざまなデメリットに悩まされている方が多いでしょう。
ポリアモリストだからといって好き放題に生きている、と考えるのは間違いで、一人ひとり異なる悩みを抱えているものです。
続いてはポリアモリーならではの悩みをご紹介し、一人ひとりを理解するための準備をしていきましょう。
周囲が理解しづらい
先ほどもご紹介したように、日本をはじめとする各国では複数愛の考えが広まっておらず、周囲の理解が得られにくいといった特徴があります。
中には精神的な病を抱えているのではと、精神科や心療内科の受診を勧められた経験のある方も多いようです。
ポリアモリーを自認するパートナーと出会えた場合でも、家族や友人からの理解が得られず、泣く泣くパートナーとの別れを選ぶ方もいます。
婚姻制度に向かない
ポリアモリストにとって、婚姻制度はどのように利用すべきか頭を悩ませるポイントとなります。
日本では2人目のパートナーと結婚することはできないため、複数のパートナーがいる場合、誰と結婚すべきか迷ってしまうことも多いでしょう。
逢えて誰とも結婚せずにいたり、書類上は1人を選んで結婚をし他のパートナーとは事実婚をしたりといった対応を選ぶ方もいます。
誤解されやすい
周囲に理解されにくいのと同時に、誤解されやすいのも注意したいポイントです。
先ほどご紹介したような性的誤解を中心に、周りから傷つく言葉をかけられたり、不思議だからといって避けられたりする場合があります。
こういった差別は「自分とは違うものを排除する」といった人間の行動が根底にあり、なかなか完全になくせるものではありません。
ポリアモリーを理解するために

ポリアモリストであると公表している人はもちろん、未だ周りに公表できずに困っている人がより過ごしやすい環境を整えるためには、ポリアモリーについてしっかりと理解することが大切です。
身の回りにポリアモリーを自認する方がいたとき、そうでない方と同じように接するためにも、理解すべきポイントを学んでおきましょう。
ポリアモリーについて知る
ポリアモリーの大きな特徴として、「複数人のパートナーと対等に、誠実な関係を結んでいる」という点が挙げられます。
この根底を理解していないが故に、浮気症ではないかと悪口を言ったり、理解ができないと突っぱねたりしてしまうでしょう。
まずはポリアモリーを自認する人々と交流し、その考えについて知ることで、彼らが不誠実な目的で恋愛をしているのではないことが分かるはずです。
嫉妬と向き合う
ポリアモリーは複数のパートナーがいるため、精神状態によっては嫉妬の気持ちが沸き上がってしまう場合があります。
この嫉妬心は見て見ぬふりをしていても始まらず、誠心誠意向き合うことで自分自身の感情を整理することができます。
どうして嫉妬してしまうのか、パートナーにどうしてほしいのかといった希望を口に出し、モヤモヤとした気持ちと向き合ってみましょう。
また、嫉妬心が芽生えたときは、相手とコミュニケーションの機会を増やしてみると良いでしょう。
素直に嫉妬していることを伝え、相手の気持ちを考慮した上で、お互いが納得できる解決策を見出すことが大切です。
浮気との違いを理解する
記事の冒頭からここまでご紹介してきた内容を見ると、ポリアモリーが浮気ではないことが理解できるでしょう。
とはいえ文字や言葉で説明を受け理解した気になっていても、実際にポリアモリストを目の前にしたとき、心が受け付けない場合も考えられます。
どうしても本来の意味でポリアモリーが理解できないと感じた場合は、ポリアモリーを避けるのではなく、反対に積極的な対話をしてみるのがおすすめです。
「ポリアモリストの1人」として捉えるのではなく、「〇〇さん」といった個人で考えることにより、その人の本質を理解できるようになるでしょう。
個人が恋愛に関してどのように考えているのかを知ることで、複数愛全体に対してではなく、目の前の一人へしっかりと向き合えるようになります。
多様性と向き合う
今回ご紹介したポリアモリーは、多様性の中の一部です。
男性が男性に恋をしたり、女性が女性に恋をしたりと、現代にはさまざまな恋愛の形があります。
ポリアモリーについて学んだことをきっかけに、様々な恋愛の多様性と向き合ってみると良いでしょう。
関連記事:ノンバーバルコミュニケーションと対人関係|恋愛においての重要性とは
まとめ
未だ日本では一般的ではなく、様々なシーンで誤解を生みやすいポリアモリー。
しかし彼・彼女たちの間では、一般的な恋愛よりも念入りなコミュニケーションが行われ、お互いへのリスペクトが存在しています。
彼ら全体を受け入れようと努力するのではなく、一人ひとりに目を向けて理解を目指すことで、あらゆる恋愛観と向き合えるでしょう。
gd2md-html: xyzzy Fri Aug 02 2024
ナラティブとは?ナラティブアプローチを利用して良好な関係構築

ナラティブ(narrative)とは「物語」という意味を持つ単語ですが、ビジネスシーンでしばしば使われる言葉でもあります。
ナラティブの考え方を用いることで問題をスピーディに解決できるようになるほか、対人関係を円滑に保つためにも重要です。
いかなるコミュニティに属する場合でも、ナラティブアプローチを利用し、誰もが活動しやすい環境を整えてみてはいかがでしょうか。
今回はそんなナラティブがどのように生まれ使われるようになったのか、歴史から理解するためのポイントまでを総合的にご紹介します。
実際に生活の中でナラティブアプローチを利用すべく、基本的な流れについても学んでおきましょう。
ナラティブの意味は?

ナラティブとは、日本語に訳すると「物語」という意味があります。
私たちがイメージする童話のような物語とはいくつかの違いがあり、耳にしただけでは理解が難しい場合もあるでしょう。
まずはナラティブの本質的な意味と、同じく物語という意味を持つ「ストーリー」とは何が違うのかをご紹介します。
ナラティブの概要
ナラティブという言葉は、ビジネスシーンや医療現場など様々な場面で使われています。
職種によっては聞き慣れない場合もありますが、本来はどのようなシーンにおいても活用できる考え方といえるでしょう。
大まかな意味は知っていても、実際に生活の中で活用できている人は少なく、まだまだ浸透しきっていないのも特徴です。
ナラティブの語源はラテン語であり、話す・関連づける・説明するといった意味を持ちます。
つまり、ビジネスシーンや医療現場においては、ナラティブ=物語の力を使って他者へ分かりやすく物事を説明し、購買意欲を掻き立てたり、自分に合う医療を選択しやすくしたりできるのです。
ナラティブを利用する側は自分の主観ではなく、俯瞰的な視点で説明ができるため、自分の理解を深められるのもポイントといえるでしょう。
ナラティブアプローチを用いて説明すると、製品やサービスの概要を淡々と説明するのに比べ、相手の心が動きやすいという特徴があります。
多くの対象に対して一貫した説明をするのではなく、目の前にいる相手のことだけを考えて話ができるのもメリットの一つです。
ナラティブとストーリーの違い
ナラティブと同じような意味を持つ単語として挙げられるのが「ストーリー」です。
どちらも物語という意味を持ちますが、両者には明確な違いがあるため、改めて確認しておきましょう。
ストーリーとは、起承転結がハッキリしており、主人公視点で進む物語を指します。
私たちが普段から触れている小説や漫画・映画などは、ストーリーを意識して作られているものが多いでしょう。
主人公視点での世界観は誰が見ても同じように捉えられやすい一方、主人公以外のところで起きている物事に関しては理解が及びにくいというデメリットがあります。
一方のナラティブは、主人公を含めた出来事の全てを俯瞰的に見ながら、話し手と聞き手が同時に物語を追っていくのが特徴です。
これから先の未来に何があるのかは分からず、話が進むにつれて様々な事象が明らかとなります。
ナラティブはいわば人生のようでもあり、未だ完結していないのもポイントです。
ナラティブはいつから使われるようになった?
ナラティブの考え方が使われるようになったのは、元を辿れば1960年頃のフランスにさかのぼります。
この頃のフランス文学には様々なシーンでナラティブが使われており、読者をより深く物語の世界に取り込み、没頭させられるとして話題になりました。
そんなナラティブを実生活で活用するようになったのは、1980~1990年代が始まりだといわれています。
元は臨床心理学で利用されたことから始まり、一人ひとりの抱えている問題を物語形式で語ることで、様々な視点から解決策を見出すために活用されました。
現在も利用者側・患者側に立つとなかなか気が付かないものの、生活の中でナラティブが利用されている場面は多々存在します。
ナラティブを理解するために

ナラティブを実生活で利用するためには、本質を正しく理解しなければなりません。
背景にある社会構成主義
ナラティブが実際の生活で利用されるようになったのは、1980~90年が最初だといわれています。
文学作品から飛び出したナラティブは、社会構築主義をベースとして発展していきました。
今あるすべての出来事は人間の頭で想像したことだ、と考える社会構築主義は、現在の社会にも広く根付いています。
例えば、片思いをしている男性がいたとします。
彼の中でその思いは単なる恋ですが、周りがどう思うかによって状況は大きく変化するでしょう。
周りが彼の思いを応援すると「純愛」になりますが、彼の思いがストーカーだと思われてしまえば、それは「犯罪」になってしまいます。
こういった社会全体の考えが出来事の本質を左右するのも、社会構築主義の特徴です。
しかし私たちは誰もが、少なからず物事に関するフィルターを持っています。
上記のケースでいえば、物事の本質を見ないまま、「男性なのだからどうせストーカーだろう」などと決めつけてしまうことも多いでしょう。
こういったフィルターによって本質が曲げられてしまうことがないよう、俯瞰的に物事を見ながら、もっとも正しい答えを見出していくことがナラティブの役割なのです。
ドミナントストーリーとオルタナティブストーリー
ナラティブを理解するためには、ドミナントストーリーとオルタナティブストーリーについて学ぶ必要があります。
ドミナントストーリーとは、直訳すると「支配的な物語」という意味を持ちます。
ドミナントストーリーは問題を抱えている当事者が感じる内容がすべてであり、他の可能性については触れていません。
「〇〇はこうである」といった思い込みが反映されているため、当事者は変えることができないと信じており、考えが凝り固まってしまっているのも特徴です。
これに対しオルタナティブストーリーは、「代替の物語」という意味の単語です。
固定されたドミナントストーリーに対し、様々な可能性を考慮したオルタナティブストーリーを考えることで、問題に対しあらゆる視点で解決策を講じることができます。
ドミナントストーリーとオルタナティブストーリーを語る際に例として挙げられやすいのが「アリとキリギリス」の物語です。
私たち日本人は幼い頃からの固定観念で、「働き者のアリと怠け者のキリギリスの話」だと思い込んでいます。
これはドミナントストーリーであり、一見これ以外の解釈はないようにも思えます。
しかしオルタナティブストーリーの考え方では、キリギリスは怠け者なのではなく、短い寿命を謳歌するために歌い暮らしていたのかもしれない、と考えます。
キリギリスには病気の友人がおり、彼を勇気づけるために歌うのをやめなかったのかもしれません。
物語の中に書かれていない可能性にも注目し、新たな可能性を考えることが、オルタナティブストーリーの役割です。
モノローグとダイアローグ
モノローグは「一人で語ること」、ダイアローグは「対話をすること」と訳されます。
物語をモノローグで語ると、視点が偏り、ドミナントストーリーのように意味合いが固定されがちです。
語り手の世界観がすべてとなるため、聞き手にも同じようにその世界観が引き継がれるでしょう。
これに対しダイアローグで物語を語るとき、語り手同士の会話の中では、これまでに見られなかった新たな考えが生まれる可能性があります。
その瞬間から物語はあらゆる可能性を含み、どのような展開になるか予想できなくなるでしょう。
ナラティブアプローチとは?

ナラティブが話し手と聞き手によって紡がれる物語である、と説明を受けても、それがビジネスシーンや医療現場でどのように活用されるのか分からない方も多いものです。
まずはナラティブを使ったアプローチ方法がどのような目的で導入されているのか、その役割について確認していきましょう。
ナラティブアプローチの概要
ナラティブアプローチとは、自分と相手が対話する中で様々な可能性を見出し、問題解決へと駒を進めていく方法です。
自分の思い描くドミナントストーリーを大切にしながら、相手の意見を取り入れてオルタナティブストーリーを展開することで、あらゆる可能性に気が付くでしょう。
このとき自分と相手は必ず対等な関係であり、どちらの意見も同じく尊重されなければなりません。
シーンによっては、対話の相手が医師と患者であったり、専門家と一般人であったりと、知識量に差がある可能性も考えられます。
こういった場合でも両者が対等であることは変わりなく、お互いを尊重しながら対話をすることが大切です。
どんな目的で導入されている?
ナラティブアプローチが導入されている場面として分かりやすいのは医療現場です。
医師と患者、もしくは看護師と患者がナラティブアプローチによって対話を行うことで、単なる病気の内容とその治療法を話し合うだけでなく、患者の生活や金銭面への負担、精神状況を踏まえた最適な治療方法を見出すことができます。
医師や看護師側は患者目線での物語を聞くことで、今までに気が付かなかった可能性を考慮し、より負担の少ないケア方法を提案できるでしょう。
これはビジネスシーンでも同じであり、カスタマーを主人公として物語を作成することで、企業側が気が付かない可能性を見出し、より顧客に合った満足度の高いサービスを実現できます。
同じように、教育や福祉シーンでも活用の幅が広がる考え方だといえるでしょう。
ナラティブアプローチの流れ
ナラティブアプローチに関する知識が深まったところで、実際に生活の中で利用する際の流れを確認してみましょう。
今回はビジネスシーンを例に挙げ、問題解決に行き詰まり、良い案の浮かばない状態であると仮定してご紹介します。
ドミナントストーリーを聞く
ナラティブアプローチの目標は、ドミナントストーリーをオルタナティブストーリーへと書き換え、その中であらゆる可能性を見出すことです。
まずは悩んでいる相手とそれぞれドミナントストーリーを作り、お互いに発表し合いましょう。
同じ問題に対処しているにもかかわらず、人によってドミナントストーリーの内容が異なるため、これだけでも新たな気づきがあるかもしれません。
この際に大切なのは、相手がどんな内容を言ったとしても、否定せずに聞くということです。
話の途中で口を挟んだり、「ここは〇〇の方が良い」などとアドバイスしてしまうと、ドミナントストーリーの意味がなくなってしまうでしょう。
問題を外在化する
続いて、ドミナントストーリーを元に問題を外在化していきます。
目に見える形で問題を提起することで、より分かりやすく解決策を講じられるようになります。
今回の場合、もっとも大きな問題は「売れる製品が作れない」ことだとします。
試作品をいくつ作っても上司にOKをもらえなかったり、販売にこぎつけた製品も思うように売れなかったりといった問題が出てくることでしょう。
続いて、その中からもっとも重要な問題を選びます。
今回は製品を売る前に、まず社内でOKが出るような製品案を作らなければなりません。
ここに焦点を絞り、第一の目標を立てることで、効率的に問題を解決できるようになります。
反省的な質問をする
続いて、お互いに対し反省的な質問を行います。
時間をかけて編み出した製品案にどうしてOKがもらえないのか、改善すべき点について反省会を行いましょう。
このときの反省点は、具体的であればあるほど良く、さまざまな可能性を見出しやすくなります。
例外的な結果を見出す
質問を投げかけた方は、返答に対しどのような結果が見出せるのかを考えます。
「〇〇という製品が良いと思ったが、却下された」という反省点の中にも、実は予算面で却下されていてもデザインは好評を得ていたり、成功には至っていないものの着眼点は良いと褒められていたりする場合があります。
こういった気づきにくい例外的な結果を見出してあげることで、これまでに気が付かなかった視点から問題にアプローチできるようになります。
オルタナティブストーリーを構築する
ここまでのステップをクリアしたら、いよいよドミナントストーリーに対するオルタナティブストーリーを構築します。
これまでに出た例外的な結果を全て含め、ありとあらゆる道筋を考慮した物語を作りましょう。
実は初期段階で褒められた内容が、製品の完成に大きく貢献してくれる場合もあります。
「〇〇はダメだ」と言われた内容が、実は「△△ならば良い」と捉えることで、新たなアイディアが浮かぶこともあるでしょう。
こういった考えを一人で行うのではなく、対話形式で整理しながら行うことで、より効率的な問題解決に繋がるのです。
ナラティブアプローチのメリット

ナラティブアプローチを定期的に取り入れることは、様々なメリットを生み出します。
今回はナラティブアプローチ導入の参考となるよう、メインとなる3つのメリットをご紹介しましょう。
良好な関係を築きやすい
ナラティブアプローチは他者との対話があって成り立つため、コミュニケーションの機会が増え、対人関係が良好になりやすいのが特徴です。
話し手と聞き手の関係は必ず対等となるため、普段の地位や立場に関わらず、平等に話ができるでしょう。
これまでに会話の機会が得られなかった相手とナラティブアプローチを行うことで、新たな信頼関係の構築にも繋がります。
解決策の幅が広がる
ナラティブアプローチを使って問題に対応することで、これまで気づかなかった解決策を取り入れ、様々な面から取り組めるのがメリットといえます。
目上の人から「こうしなさい」と命令されるのではなく、相手との対話の中でお互いに気づいた可能性を試していくため、自分の意にそぐわない方法であってもスムーズに受け入れられるでしょう。
能動的に実行しやすくなる
ナラティブアプローチを使って見出された解決策に対しては、話し手と聞き手の両方が納得した上で出てきたものであることが多く、より能動的に実行されやすいでしょう。
他者から「こうしなさい」と指示されたことよりも、自分で動こうと決めた解決策の方が、よりやる気が湧いてくるのではないでしょうか。
あらゆるシーンでナラティブアプローチを取り入れることで、日頃の作業効率が上がったり、問題に対しポジティブに対応できたりするのもメリットの一つです。
関連記事:マイノリティ・マジョリティとは? 多様な社会の理解を深めるために
まとめ
ナラティブを使ったアプローチ方法は、医療・教育・福祉などの専門分野はもちろん、ビジネスシーンでも多く使われる手法です。
私たちの身近にある問題を総合的に解決できるようになるため、日頃から積極的に取り入れると良いでしょう。
相手との対等な会話ができる点から、その場の雰囲気を改善し、人間関係を良好に保てる点にも注目してみてはいかがでしょうか。
gd2md-html: xyzzy Fri Aug 02 2024
ポリコレとは?その歴史や問題点、向き合い方を解説

社会にはびこる様々な差別をなくすべく、あらゆる場面で平等が呼びかけられている現代。
その中でもひときわ耳にしやすいのが「ポリコレ」ではないでしょうか。
聞いたことはあっても本来の意味を知らずに使っている方も少なくありません。
今回はそんなポリコレが持つ本来の意味を始め、海外と日本におけるこれまでの歴史や、現在指摘されている問題点についてご紹介します。
私たちがポリコレとどう向き合うべきなのか、今後の見通しについても確認していきましょう。
ポリコレとは?

ポリコレとは、「ポリティカルコレクトネス(political correctness)」を略して呼びやすくした単語です。
直訳すると「政治的な正しさ」となりますが、現在は政治以外の場面でも使われることが多いでしょう。
ポリコレが訴えるのは、私たち人間があらゆる違いに悩まされず、皆平等に生きられるような社会です。
人種・性別・年齢・国籍・学歴・障害の有無など、私たちは様々なシーンでマイノリティを除外してしまいがちです。
マイノリティに当てはまる人々を直接傷つけようとしていなくても、無意識のうちに行う差別が人々を傷つけているかもしれません。
ポリコレはこういった差別が自然と行われている社会を正し、誰もが周りを気にすることなく生きられるのが正しい社会の在り方だとしているのです。
ポリコレの考え方は古くから人々の間に根付いていましたが、社会全体を巻き込む運動となったのは、一人ひとりの中に差別に対する意識が芽生え始めたためだと考えられます。
この運動がさらに広がりを見せ、誰しもが差別に対し否定的な考えを持つことで、ポリコレは決して特別な運動ではなくなるでしょう。
ポリコレの歴史
ポリコレの歴史は、海外と日本で大きな違いがあります。
いち早くポリコレの考え方が広まり始めた海外に対し、日本の場合は近年になって初めて社会的現象となりました。
両者の違いを見比べながら、今後のポリコレがどう展開していくのかを予想してみましょう。
海外
世界的なポリコレの発祥は、およそ1900年頃までさかのぼるといわれています。
白人とそれ以外の人種で対立を深めていた地域が多い中、アメリカを中心に差別に対する否定的な考えが広まり始めます。
代表的な変化として挙げられるのが、それまで差別の対象であった「インディアン」が「ネイティブアメリカン」と呼ばれるようになったこと。
目に見える変化があったことで、多くの人が無意識のうちに行っていた差別に気が付くようになったのです。
また、ポリコレがアメリカ発祥とする説に対し、ロシア革命が発祥とする考え方もあります。
こちらはポリコレが持つ本来の意味である「政治的平等」を訴えるための運動であり、どちらが正しいかは分かっていません。
しかし、いずれにしても海外でのポリコレは1900年代と早い段階で広まっており、白人優位主義から脱却することをメインに訴えたものでした。
これが転じて、女性の権利を訴える「ウーマン・リブ運動」など、様々な運動へと繋がっていったのです。
日本
1900年代にポリコレの考えが広まった海外に対し、日本では2010年代に入ってようやく変化が訪れます。
インターネットが広まるにつれてポリコレが浸透し始め、性別や年齢・地位・居住地など様々なシーンで行われる差別について考えられるようになりました。
日本で起こったポリコレの中でも、ひときわ注目を集めたのが男尊女卑に対抗する考え方です。
男性は外で働き女性は家事・育児をするといった考え方に問題があるとして、女性であっても社会に進出し、職場で相応の地位を獲得する権利があると訴える人が多く現れました。
この考え方は、現在も多くの方が訴える「フェミニズム」の始まりでもあります。
ポリコレの身近な具体例

「ポリコレ」という言葉は知っていても、具体的にどのような変化があったのか詳しく理解している方は少ないでしょう。
私たちの身近な場所でも、ポリコレの考えによって様々な変化を遂げたものが多く存在します。
これらが差別を是正するために変化したことを知り、ポリコレについて正しく学ぶことこそが、差別のない未来づくりに必要なことだといえます。
人種における表現
先ほどもご紹介したように、アメリカの先住民は今まで「インディアン」と呼ばれていました。
大航海時代、アメリカをインドと間違えて上陸したことからつけられた呼称であり、現在はポリコレの考えにのっとって「ネイティブアメリカン」へと変更されています。
日本人にとってインディアンとネイティブアメリカンの問題はそれほど身近ではないため、今もインディアンと呼んでしまう方がいますが、差別の歴史を肯定することに繋がるため注意が必要です。
また、白色人種・黄色人種・黒色人種の間で行われる差別も顕著であり、特に黒色人種が被害を受けるシーンが多く見られました。
その際、黒色人種は「ブラック」と呼ばれて差別の対象となっていましたが、現在は「アメリカンアフリカン」と改められています。
日本では色鉛筆やクレヨンのカラーに「肌色」という呼称が使われていましたが、すべての人に当てはまる肌の色ではないといった考えから、「うすだいだい」「ペールオレンジ」などと呼ばれるようになっています。
さらに、近年の美容業界では、「美白」の表現に疑問を唱える方が増えています。
白であれば美しいといった考えを改めるべく、日本では花王株式会社が先頭に立ち、「美白化粧品」などの表現を中止すると発表しました。
性別における表現
性別における表現は、これまで何も考えずに使ってきた方も多いことから、なかなか呼称を改めにくいのが現状です。
この根底にあるのは、「男性はこういった仕事に就くことが多い」「この仕事は女性向きである」といったナチュラルな差別。
性別を問わず自分の目指す仕事に就けるよう、下記のような表現の変更が行われています。
- カメラマン→フォトグラファー
- ビジネスマン→ビジネスパーソン
- 保母→保育士
- 看護婦→看護師
- スチュワーデス→キャビンアテンダント
「マン」と名の付く職業は全て男性を想起させるため、「パーソン」への変更が進められています。
「スポーツマン」なども、現在は「アスリート」と呼ぶ機会が増えているでしょう。
反対に女性を想起させる保母や看護婦なども、男性を含めた呼称として改められています。
指向・思想における表現
マジョリティとマイノリティの差が顕著になりやすいのが「性別」です。
LGBTQ+を始め、すべての人が男性と女性に分けられることはなくなり、書類の性別欄にも変化が見られるようになりました。
「男性・女性・その他・回答しない」など、必ずしも男性と女性のどちらかから選ばなくても良くなったのは、ポリコレによる大きな変化といえるでしょう。
さらに、夫婦のうち男性の方を「主人・亭主」と呼んだり、女性の方を「嫁・奥さん・家内」などと呼んだりすることも、差別的だとして改定が進んでいます。
現在はLGBTQ+同士、または片方がLGBTQ+であることも多いため、相手の性別に関わらず「パートナー」と呼ぶのが一般的です。
映画・ゲームでも使われている?
近年ポリコレに配慮して作られた作品として有名なのが「リトル・マーメイド」ではないでしょうか。
原作は白色人種だと思われる主人公の人魚・アリエルが、実写版では黒色人種の俳優を起用したことで一躍話題となりました。
また、キャラクターを作成して遊ぶタイプのゲームでは、基本となるスキンカラーの種類を増やし、様々な人種に対応できるよう工夫されたものが多数登場しています。
「主人公=白色人種」といった固定観念を捨てることで、誰しもが物語の主人公になることができ、人種における差別をなくす取り組みが広がっています。
関連記事:マイノリティ・マジョリティとは? 多様な社会の理解を深めるために
ポリコレの問題点

近年の社会において重要な考え方であり、良い結果を生むことが多いとされるポリコレ。
影響力の強い芸能人やインフルエンサーはもちろん、一般人であってもSNSなどで考えが瞬時に広まり、多くの人の目に触れるようになりました。
しかし、ポリコレの考え方は時として問題点を生む場合があります。
自分の考えが誰かを傷つけてしまわないよう、現時点で問題視されているポイントについて学んでおきましょう。
言葉狩り
ポリコレの考え方が広まるにつれ、様々な言葉が改められてきました。
先ほどご紹介した「マン→パーソン」の変化など、普段使っている言葉から大きく変更されたものもあり、未だに馴染めずにいる方も少なくありません。
様々な言葉が変化するにつれ、言葉狩りの動きが加速しているのが第一の問題点といえます。
マイノリティを差別する意味で使う場合は良くありませんが、無意識のうちに使ってしまった言葉や、これまでに改定の対象ではなかった言葉に対して、過剰な拒否反応を見せる方が増えています。
たった一度その言葉を使っただけでも、「差別主義者」として批判の的となり、辛い思いをした経験のある方も多いのではないでしょうか。
ポリコレを広める上で大切なのは、私たちが自然と差別を避け、平等な社会を目指すことです。
特定の言葉を嫌うあまりに使った人を激しく非難していては、新たな差別が生まれる原因にもなりかねません。
表現の自由
言葉狩りにも通じる問題点として挙げられるのが「表現の自由」です。
あらゆる方面に配慮するあまりに使える言葉が減り、これまでとは違った表現をせざるを得ないシーンが増えてきています。
これから新しく生まれる作品に対してはもちろん、今まで脚光を浴びた作品を書き直すよう求める声もあり、各所で議論がなされています。
小説・漫画・映画・音楽・絵画など、さまざまなアートで表現の自由が約束されています。
ポリコレに配慮するあまりにアートの道をあきらめたり、素晴らしい作品が世に出ないまま埋もれてしまったりするのは良くありません。
ポリコレの考えと言葉狩り、そして表現の自由の3つがバランス良く存在するために、行き過ぎた排除をやめ、他者に対し優しい気持ちで接することが大切だといえます。
嫌気がさしている
ポリコレに積極的な動きを見せる方がいる一方、それほど興味がなく、どちらでも構わないといった立ち位置の方も少なくありません。
中にはポリコレを訴える声が大きすぎるあまりに、嫌気がさしている方も多いでしょう。
正しく広まるべきポリコレの考え方が、「何だか面倒くさいもの」として捉えられてしまうと、本当の意味で差別をなくすことはできません。
テレビをつけたり新しいゲームをしたり、本を読んだりといった娯楽がすべて過剰なポリコレで埋め尽くされてしまっては、本来の楽しみ方ができずに不満を感じる方が増えてしまいます。
先ほども触れたように、ポリコレと既存の考え方のバランスを取り、どちらに対しても配慮することが必要だといえます。
ポリコレとバランスを取る
「ポリコレ=面倒なもの」といったイメージを払拭し、誰しもが自然とポリコレの考え方ができるようにするには、現時点で使われている言葉や文化とのバランスを取らなければなりません。
下記でご紹介する2点のポイントを参考に、正しい意味でポリコレの考えが広まるように工夫することが大切です。
自由な対話
ポリコレに配慮すべく、日常的に使ってきた言葉の多くが使えない状態は自由とはいえません。
大切なのは相手に配慮する気持ちであり、特定の言葉を使ったからといってただちに悪であると決めつけるのは早計です。
実際に会話をする場合はもちろん、SNS上で顔の見えない相手へコメントをする場合も、相手はもちろんどんな人の目に留まっても良いような書き方を心掛けましょう。
批判的思想
ポリコレに対して批判的な気持ちを持っていても、それが完全に悪だとは言い切れません。
ポリコレが間違った道へ成長しないためにも、常に批判的な思想は必要だといえるでしょう。
もちろんポリコレ同様に攻撃的なワードを用いて相手を傷つけるのではなく、理論的な意見でポリコレの問題点を取り上げ、より良い方向へと導くことが大切です。
まとめ
近年も成長の一途を辿るポリコレの考えですが、SNSを通じて批判を受けたり、特定の表現に対し過剰に反応してしまったりといった問題点にも注意が必要です。
大切なのはマイノリティに対する差別を避けると同時に、今ある表現方法に柔軟な考えを持ち、バランス良く改善を目指すことではないでしょうか。
一人ひとりの考えが異なるのは自然なことであるため、誰しもが自分なりに差別に対する考えをまとめ、小さな行動を積み重ねていくことが重要です。
gd2md-html: xyzzy Wed Jul 31 2024
憂鬱からワクワクへ。働き方の変化は人生を変える

Hummingライター 大浦沙織のコラムをお届けします。
「明日からまた仕事か…」
会社員時代は憂鬱だった日曜日の夜。
しかし、フリーランスになった今、日曜日の夜はワクワクしながら眠りにつき、月曜日の朝、仕事に向き合えることに喜びを感じています。
正社員という安定を手放すことで出会えた、新しい働き方。
私がフリーランスライターになるまでの道のり、そしてこの選択を通じて得た気づきをお伝えします。
安定した会社員から、フリーランスへ
8年前、私は新卒で勤めた会社を辞めました。きっかけは、パートナーの海外転勤。
もしこの転機がなければ、今でも会社員を続けていたかもしれません。安定した職を手放す勇気が私にはなかったからです。
退職後、しばらくは子育てに専念していました。しかし、育児休業から職場に戻る友人たちを羨ましく思ったり、増えない預金残高を見て焦りを感じたり、徐々に「自分の収入が欲しい」「社会とつながりたい」という思いが強くなっていったのです。
とはいえ、子どもはまだ小さいし、我が家は転勤族。今の自分には外に働きにでることは難しいと思い、在宅でできる仕事を探すことにしました。「娘の2歳の誕生日に開業する」。これだけを決めて、様々な可能性を探っていきました。そして、最終的に巡り合ったのがライターの仕事です。
会社員を辞めてから、安定した職を手放したことに不安を感じることもありました。しかし、今思うのは、会社員を辞めたからこそ、今の働き方に出会えたということです。
予期せぬ出来事が、人生の大きな転機となり、新たな可能性を開いてくれました。
「とりあえずやってみる」行動することで未来を切り開く
「際立ったスキルや経験がない私に何ができるのだろうか……」と悩んでいた時、“ママが1ヶ月でWebデザイナーに”という広告が目に留まりました。
「これだ!」と運命を感じた私は、未経験からWebデザイナーを目指すことに決めました。生後3ヶ月の娘を抱っこしながらWebデザインスクールに通い、その後、Webデザイナーとして活動を開始。
しかし、「私はWebデザイナーを名乗って良いのだろうか……」というモヤモヤした感情が拭えずにいました。
そんな中、Webデザインの勉強と並行して始めたブログ運営で、文章を書く楽しさに目覚めました。次第にデザインよりも執筆の仕事に惹かれるようになり、SNSで見つけたライター募集に思い切って応募することに。
そして、勇気を持ってWebデザイナーという肩書きを手放し、「ライター」として活動していくことを決意しました。不思議なことに、「ライター」と名乗ることには違和感がなかったのです。
この経験から感じたことは、好きも嫌いも、得意も苦手も、実際に手を動かしてみなければわからないということ。気になったらやってみれば良いし、やってみて何か違うと思ったら辞めれば良い。行動することで、可能性が広がることを体感しました。
ガムシャラ期を乗り越え、見えてきた仕事の基準
駆け出しの頃は、執筆ジャンルや報酬を気にせずに仕事を受け、目の前の案件に必死に取り組みました。
当時の仕事時間は子どものお昼寝中と家族が寝静まった明け方のみ。スキルも未熟だったので、何をするにも時間がかかり、キャパオーバーに。締め切りが頭から離れず、ストレスから動悸に悩まされることもありました。
しかし、必死に行動することで、少しずつ自分のやりたいことがわかってきたり、自分なりの価格表が作れるようになったり、仕事を選ぶ基準ができてきたのです。
人は歳をとります。睡眠時間を削って働き続けるのは限界があるでしょう。だからこそ、ガムシャラに行動した後には、どんな仕事に関わりたいのか、どんな条件なら気持ちよく働けるのか、どんな人と一緒に働きたいのか……、自分と向き合うことが大切です。
せっかくフリーランスになったのだから、自分が心地よいと感じる働き方を追求していきたいです。
現状維持は後退。学び続けることが大切
「現状維持は後退だと思っている」というフリーランス仲間の言葉が、私の心に深く刻まれています。
AIが急速に進化し、多くの仕事が変化していく今の時代。私たち自身も常にアップデートしていく必要があります。
私は意識的に学びの時間を確保するようにしています。例えば、尊敬する先輩ライターさんのライティング講座を受講したり、書くこと以外の武器を増やすためにカメラの勉強を始めたり。また、AIツールも積極的に活用しています。学び続けることで、自分の可能性が広がると信じているからです。
さらに、心と体の健康維持も重要だと考え、今年からジム通いを始めました。隙間時間に行こうとすると優先順位が低くなりがちです。そこで、ジムに行く日を事前にスケジュールに組み込み、日々の仕事に埋もれないよう心がけています。
もちろん、目の前の仕事をこなすだけで精一杯な日もあります。しかし、自己投資の時間を大切にすることは、長期的には仕事の質を高めることにも繋がるのではないでしょうか。
働き方が変われば、人生が変わる
フリーランスになって実感したのは、働き方の変化が人生を大きく変えるということ。今の私にとって、働く時間と場所を自分でコントロールできるフリーランスの生活はとても心地よく、働くことが楽しいです。
もちろん、いきなり継続の案件がストップしたり、毎月の収入が安定しなかったり、「この先もフリーランスを続けられるかな……」と不安になることもあります。しかし、未来のことは誰にも分かりません。
だからこそ大切なのは、目の前の仕事に全力で取り組むこと、出会えたご縁を大切にすること、自己成長を止めないこと、そして、新たなチャンスを逃さないよう適度な余白を持つこと。
これらを意識しながら、私はこれからも文章を綴っていきます。
NVCを実践して、よりよい人間関係を築こう!事例で学ぶ非暴力コミュニケーション

子どもがいうことを聞いてくれなくてイライラする。
最近夫婦喧嘩ばかりでしんどい。
部下の教育に頭を抱えている。
このように、家庭や職場での人間関係のストレスに悩まされている方も多いのではないでしょうか。
そんな時、「NVC(非暴力コミュニケーション)」を実践することで、対人関係の問題が改善されたり、解決への糸口が見つかったりするかもしれません
本記事では、NVCついて、具体的な例を交えながら解説していきます。人間関係が好転するヒントを探してみてください。
NVC(非暴力コミュニケーション)とは
「また同じミスを繰り返すの?」
「言うことを聞かないなら、もう知らない!」
こんな風に、ついカッとなって相手を責めたり、見放したりする言葉を発してしまった経験はありませんか?
私たちが日常的に使用する言葉は、時として暴力的に相手や自分自身を傷つけることがあります。
そこで注目したいのが、1970年代にアメリカの臨床心理学者マーシャル・B・ローゼンバーグ博士によって体系化され、提唱されたNVC(非暴力コミュニケーション)です。
NVCは、あらゆる人間関係を、支配や対立、緊張、依存の関係から、自由で思いやりあふれる関係へと変革する方法です。また、私たちの生き方や人生の目的を根本から見つめ直すきっかけにもなるでしょう。
NVCでは、相手の言動に反射的に反応するのではなく、以下の4つの要素を用いて自分の感情を見つめ直し、相手の感情にも耳を傾けることを提案しています。

NVC4つの要素
1. 観察(observation)
NVC第1の要素「観察」は、自分の状態を左右する外的な事実を、「評価を交えずに」明確に認識することです。
例えば、散らかった部屋を見て「あなたは片付けが苦手なのね」と言うのは、観察ではなく評価です。「脱いだ洋服が床に散らばっている。本は開いたまま机に置かれている」のように、事実だけを観察するのです。
2. 感情(Feeling)
NVC第2の要素では、自分の「感情」を表現します。ただし、自分の感情と「いまの自分が思っていること」を区別する必要があります。
例えば、友人との約束が急にキャンセルされたとき、「友達は私のことを大切に思っていないのかもしれない」と考えるのは感情ではなく、相手の行動を自己流に解釈していると言えます。
一方、「約束がキャンセルされてがっかりした。楽しみにしていたから残念だ」というのは、自分の内面の状態を率直に表現した「感情」です。
3. 必要としていること(Need)
NVC第3の要素は、感情の根底にあるニーズを見極め、表現することです。
例えば、パートナーの帰りが遅いことに不満を感じたとき、心の底には「もっと一緒に時間を過ごしたい」といったニーズがあるかもしれません。
4. 要求(Request)
NVC第4の要素は、自分のニーズを満たすために、相手にどのような行動を求めるのかを明確に伝えることです。
例えば、パートナーとのコミュニケーションに不満を感じていた場合。「もっと私の話を聞いて」という曖昧な言い方ではなく、「私が話している時は、スマートフォンを見ずに目を見て聞いて欲しい」と具体的にリクエストを伝えます。
ただし、急ぎでクライアントに返信をしなければいけないなど、相手にも事情があるでしょう。相手の立場に立って理解を示しつつ、状況に応じて柔軟に対応することが大切です。
この4つの要素を意識してコミュニケーションを取ることで、私たちは評価や判断に注意を向けるのではなく、自分の本当の望みを見極め、明確に表現できるようになります。
また、相手の言動の裏にある感情や必要性にも目を向けられるようになることで、お互いを尊重し、相手をより深く理解することができるでしょう。
NVCを使った具体的なコミュニケーション例
NVCを実践する前後では、コミュニケーションの質が大きく変わります。具体的にどのように変化するのか、以下の2つの例を見てみましょう。
「お片付けしなさい!」と子どもに怒鳴ってばかりいる母親のケース
NVCを取り入れる前の伝え方また片付けをしていないじゃない。 あなたのだらしなさにはうんざりよ。 今すぐ片付けなさい! |
NVCによる伝え方
部屋が散らかっていると、私は悲しくて困ってしまうの。(感情) 家族みんなが快適に過ごせる、整理整頓された空間を大切にしたいからなの。(ニーズ) 一緒に片付けをしない?ブロックは専用の箱に入れて、ぬいぐるみは棚に並べて、絵本は本棚に戻してもらえると嬉しいわ。(リクエスト) |
締め切りを守らない部下に困っている男性の上司のケース
NVCを取り入れる前の伝え方また締め切りに遅れたのか。 何度同じミスを繰り返すんだ。 君の仕事ぶりには呆れ果てるよ。 次からは必ず期日を守れ。 |
NVCによる伝え方
先月提出してもらった企画書は締め切りの2日後、今回のレポートは期日を1週間過ぎてからの提出だったね。(事実) 正直、がっかりしているし、チームの信頼関係が損なわれないか心配だよ。(感情) チームのスケジュール管理と生産性を維持するためにも、締め切りを守ることが不可欠だと考えているんだ。(ニーズ) 次回のプロジェクトから、もし締め切りに間に合いそうにない場合は、早めに相談してくれると助かるよ。毎週月曜日の定例ミーティングで進捗状況を報告してもらえれば、問題解決に向けて一緒に取り組めると思うんだ。(リクエスト) |
このようにNVCの4つの要素を意識することで、自分の感情やニーズに向き合い、それを言葉にすることができます。そして、相手の状況を尊重しつつ、明確にリクエストをすることで、お互いを思いやり、理解し合える関係性を築くことができるでしょう。
NVCを習得するには練習が必要
NVCを身につけるには、日々の生活の中で意識的に実践することが大切です。イライラや怒り、悲しみなどのネガティブな感情が湧き上がってきた時こそ、NVCを練習するチャンスと捉えましょう。
ネガティブな感情の奥底には、「相手に理解してほしい」「自分の気持ちを知ってほしい」といった切実な願いが隠れていることがよくあります。そのため、一時的な感情に任せて相手にぶつけるのではなく、自分の感情の根源にあるニーズを見極め、それを具体的な言葉で伝えることが重要です。
また、自分のニーズを理解するだけでも、ネガティブな感情は和らぐものです。NVCの4つの要素を意識することで、自分自身でニーズを満たす方法が見つかるかもしれません。
自分の気持ちに正直に向き合い、相手の立場に立って考えるコミュニケーションを心がけることで、人間関係はより豊かになっていくでしょう。
フェミニズムとは? 歴史、問題、そして解決策

男性は外で働き、女性は家事や育児・介護などを担うのが自然とされていたこれまでの日本。
時代が変わるにつれ、今や働きに出るのも家事や育児をするのも性別を問わず行うべきだとし、男性と女性の差を埋めるための思想が広まってきました。
男女平等を訴えるこの考えは「フェミニズム」と呼ばれ、さまざまなシーンで呼びかけられています。
今回はこのフェミニズムについて詳しく知るとともに、これまでどんな歴史を辿ってきたのかや今後の課題などをご紹介します。
フェミニズムとは?

「フェミニズム」という言葉を辞書で調べてみると、「女性と男性の権利を同等のものとするための主張や運動のこと」だとされています。
由来となったのは女性らしさといった意味を持つ「フェミニン(feminine)」であるため、女性が声を挙げて主張することだと思われがちですが、実はそれが全てではありません。
正しい意味を理解しないままに言葉だけが一人歩きしてしまうと、さまざまな場面でトラブルを生んでしまうでしょう。
フェミニズムが掲げるのはあくまでも「男女平等」であり、「男性軽視」ではありません。
これまで軽視の対象であった女性が声を挙げることで、男性の立場が追いやられるのではないかと思う人がいますが、本来の意味は性別を問わず人々がみな同じ土台に立つことです。
男性を追いやって女性がさまざまな権利を得ても、いずれ男性が声を挙げる時代が来て、問題が繰り返しになってしまうでしょう。
昔と比べると、現代は女性の立場が男性へ近づきつつあるといえます。
しかしそんな中でもフェミニズムの考えが重視されているのは、私たちが産まれたときから刷り込みのようにジェンダーに触れ、それが当たり前だと思ってしまっているためでしょう。
男の子なら青や緑が好きな子が多く、屋外で走り回って遊ぶ。
女の子ならピンクが好きで、おままごとやお絵描きをして遊ぶ、といったように、知らず知らずのうちに固定観念として刷り込みが行われているのです。
そんな固定観念は大人になっても頭を支配し続けるでしょう。
仕事と家事・育児の割合だけでなく、男性は昇進をしても女性は変わらないままであったり、一度産休をとると元のポストに戻れなかったりと職場内環境にも大きな影響を及ぼします。
「女性は男性よりも賃金が低いものだ」「産休をとっても良いように重要な仕事は任せない」といったナチュラルな差別は、現代になっても減ったとはいえません。
フェミニズムの考えは、一部の人が声を上げ続けているだけでは意味がありません。
男性・女性や年齢を問わず、全ての人が意識しなくても男女平等を掲げられるよう、フェミニズムについて深く理解しなければならないのです。
関連記事:マイノリティ・マジョリティとは? 多様な社会の理解を深めるために
フェミニズムの歴史

現代は男性・女性を問わずフェミニズムについて知っている人が増え、後は個人や企業がフェミニズムに対しどう考えていくかが問題となっています。
そんなフェミニズムの思想がいつ生まれ、現代までどのように変容してきたのか、詳しい歴史をご紹介します。
第一波フェミニズム
18世紀以前の世界では、政治に参加するのも、民衆を率いるのも全て男性でした。
女性は家業を手伝ったり、家事・育児をしたりして過ごしており、夢を持ったりいつもと違うことに挑戦したりする人はおらず、みな同じような人生を歩んでいたでしょう。
この頃の女性たちには男性に比べて教育が行き届いておらず、限られた知識の中で生きていました。
学校に行きたいと思っても、許されるのは土地や資産を持ったごくわずかな家の娘のみ。
一般家庭に生まれた娘たちは、自然と生まれた瞬間から生き方が決められてしまっていたのです。
ことの始まりは1789年8月に発表された「フランス人権宣言」。
「第1条 人は、自由かつ諸権利において平等なものとして生まれ、そして生存する。」から始まり、階級制度に悩んでいた人々にとって奇跡のような宣言でしたが、これが主に男性のみをターゲットとして作られていたことをご存じでしょうか。
自由や平等を謳っておきながら、男性と女性はこれまで通り顕著であり、女性は人権宣言後も男性の下で生活をしなければなりませんでした。
これに異議を唱える形で起こったのが「第一波フェミニズム」です。
男性ばかりが自由を宣言し、どうして女性は自由に生きられないのかと考えた女性たちが、フランスを中心に抗議運動を開始したのです。
第一波フェミニズムでは女性にも参政権を与えることをメインに訴えが続けられ、20世紀にかけて女性が政治に参加する国が増えていきました。
このとき日本は明治時代であり、作家であり思想家の平塚らいてうらがフェミニズム運動を行っていました。
島国であるはずの日本が世界に取り残されることなく、同じ時代に女性の権利を求めるために声を挙げていたことは、その後の日本にとってかけがえのない一歩であったといえるでしょう。
第二波フェミニズム
長いフェミニズムに関する歴史の中で、第二波と呼ばれるのが1960年頃に起こった「ウーマン・リブ(女性解放運動)」です。
1945年に第二次世界大戦が終了してから、女性たちは男性との差を全て解消し、平等に生きることを目的として声を挙げ始めました。
これは性差によって起こる差別全てを対象としており、「男性だから」「女性だから」といった根本的な差を埋めるために行われたものです。
第二波フェミニズムの大きな特徴として挙げられるのは、フェミニズムと同時に「ウーマニズム」の考えが広まった点にあります。
女性らしさといった意味を持ち性差に関する差別をなくすフェミニズムに対し、ウーマニズムは「女性に対する差別全て」をなくすためのものです。
ウーマニズムの中には、性差による差別、人種による差別、年齢による差別など全ての不平等が盛り込まれていました。
この時期にスポットが当てられていたのは、女性が男性に比べて力が弱く、性的な問題においてはまだまだ弱者であったという点です。
望まぬ妊娠をしても中絶する権利が認められていなかったり、繰り返す性生活の中で身体を壊しても病気だと認められなかったりと、女性たちはさまざまな不平等の上で生活をしていました。
第二波フェミニズムによって女性たちは、徐々に中絶の権利や避妊の権利が与えられ、男性と同じく自分を大切にしながら性を意識できるようになっていくのです。
第三波フェミニズム
圧倒的な不平等の元、男性との差を埋めるために行われてきた第一波・第二波フェミニズム活動。
一方の第三波フェミニズムは1990年代に始まり、「女性とはこういうものである」といった固定観念から脱却するための活動として広まりました。
過激なロックバンドが「女性」という枠を超えて活動し始めると、一般人たちも次々に自分たちの手法で「ありのままの自分」を表現するようになったのです。
第三波フェミニズムの波は世界各国に広まり、現在までその考えが色濃く受け継がれています。
「女性は男性の三歩後ろをつつましく歩くべきだ」といったステレオタイプを捨て、どのような夢を追っても、どのような生き方をしても良いのだとする考えは、女性だけでなく男性にも大きな影響を及ぼすものでした。
フェミニズムの影では「男性は常に家を空けて仕事に勤しむべき」「男性は弱音を吐くべきではない」といった固定観念に苦しんでいた男性も多かったのです。
現在
現在の世界は、フェーズでいえば第四波フェミニズムの中にあります。
長い歴史をもつフェミニズムの考え方ですが、今もなお男女の差が完全になくなったわけではありません。
近年はスマートフォンの普及率も高水準をキープしており、若い世代を中心にSNSで考えを共有するシーンが増えました。
職場で男性との扱いに差を感じて嫌な思いをしたり、性暴力をふるわれた経験があったりと、これまで女性たちが自分の中に秘めていた悩みを匿名で打ち明けられるようになったのです。
世界のどこかに自分と同じ経験をした人がいたり、気持ちに寄り添ってくれる人がいたりするだけでも、抱え込んでいた辛さがふっと楽になるでしょう。
第四波フェミニズムでは、SNSにて「#MeToo運動」が行われました。
これはSNS上で性暴力の被害を訴え、隠された実態を明らかにすることで、社会全体でトラブルを防ぐ目的で行われたものです。
さらには日本国内で「#KuToo運動」なるものも始まり、出勤時にハイヒールを履くことを義務付けられるのはおかしい、といった考えも広まりました。
これまでのフェミニズムと異なるのは、芸能人など声の大きい存在だけでなく、一般人からこのような考えが広まるケースがある、といった点です。
私たちの誰もがフェミニズムに関係があり、辛い思いを発信することで団結力が生まれます。
一人で悩まずに同じ悩みをもった人を見つけることで、社会全体の抑止力に繋がるでしょう。
関連記事:社内で円滑にコミュニケーションをとるコツや成功事例を紹介
フェミニズムの抱える問題

フェミニズムを語る上でもっとも注意しなければならないのは、ある「誤解」についてです。
これは一部の過激派に属する人々が、「男女平等」ではなく「女性重視・男性軽視」を訴えているためだといえます。
女性優先車両に間違えて乗ってしまった男性を袋叩きにして追い出したり、何もしていないのに痴漢の容疑をかけられた男性に対し「男性だから仕方ない」と批判してみたりと、さまざまな場面でフェミニズムを履き違えた男性軽視が行われています。
この側面だけを見てしまった人々は、フェミニズムの正しい意味を理解できず、「やっかいな人々」だと勘違いしてしまうことも多いのです。
2024年にSNS上で話題となったのは、「男児は何歳まで女性用トイレを使って良いのか」といった内容です。
防犯上幼い子どもが母親と一緒に女性用トイレを使うシーンも多い中、何歳であっても男性であることには変わりないため、女性用トイレに入ることを禁じてほしいといった声が上がっていました。
中には1人で歩けない乳児であっても男児であれば女性用トイレに入るべきではない、といった声もあり、賛否両論を生んでいます。
繰り返しになりますが、フェミニズムとは男女が平等な立場で生きられる世界を求める考え方です。
女性ばかりが優遇され、男性が損をする社会は平等ではありません。
大切なのは一部だけを見て「アンチ・フェミニズム」になるのではなく、正しい方法で平等を目指すことにあるのではないでしょうか。
関連記事:夫婦仲が悪い原因は?子供に与える影響や改善する方法をご紹介
フェミニズムの正しい知識を身につけよう
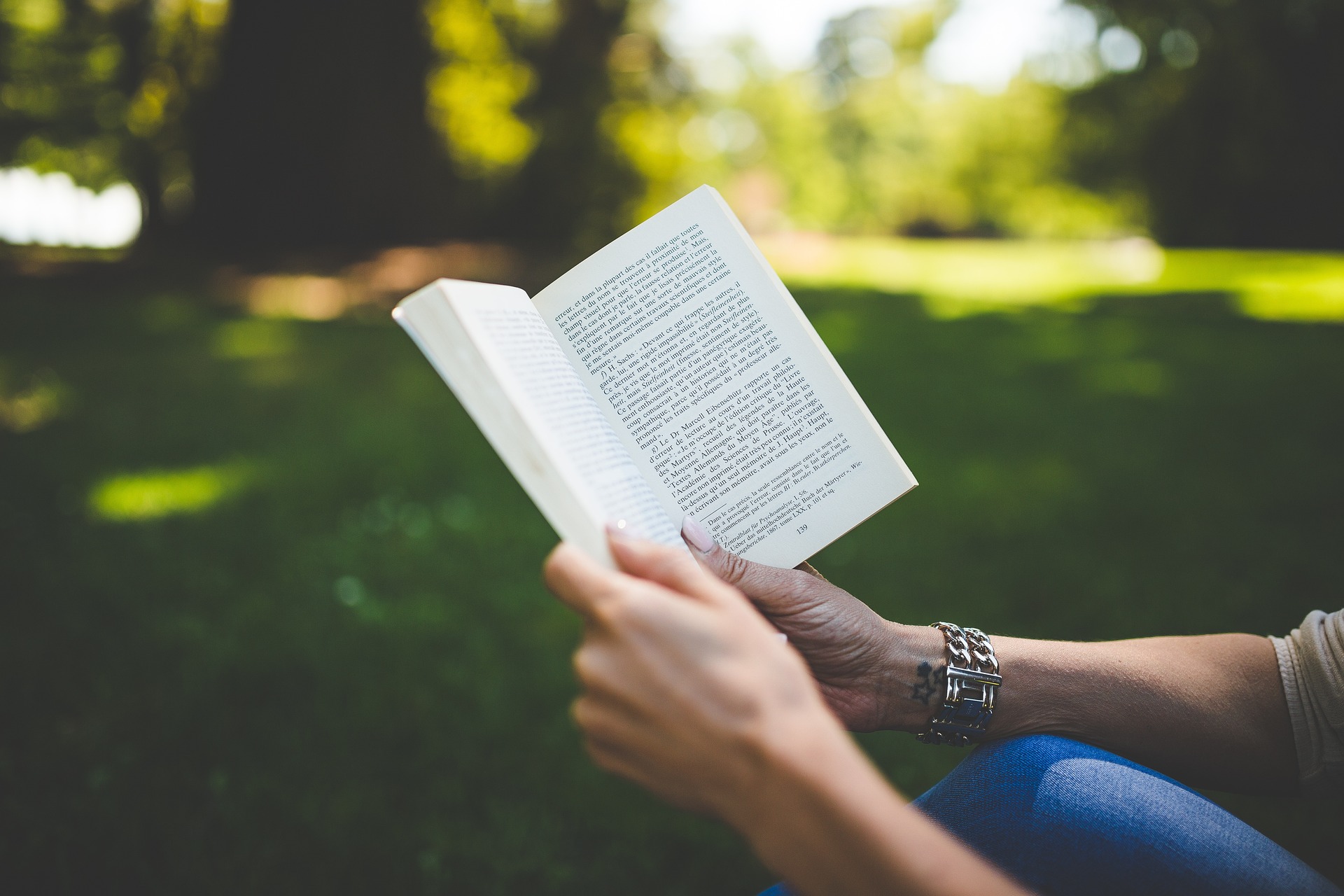
フェミニズム運動について正しく知るためには、まず識者の執筆した本を読むことから始めましょう。
先程も触れたように、SNSで一部の人の声ばかりを見ていると、考えが偏る原因となります。
フェミニズムの考え方も人によって細かく異なるため、根底となる知識を得た後、自分なりにフェミニズムについて考えてみるのが大切です。
また、フェミニズムを自分と関係のないことだと考えず、「自分ならどうするか」を考えるのも良いでしょう。
あなたが女性であれば、これまでに性差が理由で差別された経験や、そのときに感じたモヤモヤした気持ちについて振り返ります。
あなたが男性であれば、妻・兄弟・友人・母親など身近なところにいる女性にどう対応しているのかを振り返りましょう。
フェミニズムの考えを正しく広めるためには、女性だけでなく男性の力も必要不可欠です。
まずは自分の属する小さなコミュニティの中で、男性・女性にとっての差別が起きていないか考えることから始めてみてはいかがでしょうか。
まとめ
さまざまな歴史の中で現代まで発展してきたフェミニズム。
社会全体という大きなコミュニティを変える前に、身の回りからできることを始めましょう。
男性だから、女性だからといった考えを捨てるとともに、未来を生きる子供たちがより過ごしやすい社会づくりが必要です。
マイノリティ・マジョリティとは? 多様な社会の理解を深めるために

2024年現在、日本の総人口は1億2千万人を超えており、誰しもが自分以外の誰かと関わりながら生きています。
そんな大人数のコミュニティで生きるためには、自分の考えだけでなく、周りの考えを柔軟に受け入れることが大切です。
今回は「多様性」の考え方が進む現代において、さまざまな場面で目の当たりにするマイノリティ・マジョリティについて考えてみましょう。
よく見られるマイノリティの種類や具体例を挙げながら、社会に与える影響や問題点に着目してご紹介します。
マイノリティ・マジョリティとは?

マイノリティ(minority)とは、ある事象において少数派となる考え方やその人々を指す言葉です。
元となったマイナー(minor)という単語には「それほど重要ではない」という意味がありますが、マイノリティの場合は重要かそうでないかといった意味は含まれず、単に数が少ないという意味を持ちます。
例えば、自分と相手の2人が話していて意見が対立した場合、どちらかがマイノリティとなることはありません。
しかし10人のうち1人が異なる意見を唱えた場合、それはマイノリティといって良いでしょう。
一方、マイノリティの対義語として挙げられるのがマジョリティ(majority)です。
こちらも元となったメジャー(major)には「重要」という意味がありますが、マジョリティの場合は単に「多数派」という意味になります。
人気アイドルグループの楽曲名にも使われた単語であるため、耳なじみのある方も多いのではないでしょうか。
マイノリティとマジョリティについて話し合うとき、しばしば「マイノリティ=差別の対象」と捉えられる場合があります。
本来の言語にそのような意味がないにもかかわらず、どうしてこのような考えが生まれてしまうのでしょうか。
続いての見出しでは、マイノリティの具体的な例を挙げながら、社会におけるマイノリティの立ち位置についてご紹介します。
関連記事:ノンバーバル(非言語)コミュニケーションの重要性を徹底解説!
マイノリティの種類

一言でマイノリティといってもその種類はさまざまです。
あるコミュニティにおいて多数派だった人も、別のコミュニティに行けば少数派になることがあり、自分がマジョリティ・マイノリティのどちらに属するのかは場所・時間・人数などによって変わります。
これからご紹介するマイノリティの数々は、一部では批判の的となることもあり、社会問題として問題視されています。
自分の属する方だけでなく、周りの意見も柔軟に取り入れ、広い視野をもって問題に取り組むことが大切です。
性的マイノリティ
性的マイノリティ、別名「セクシャルマイノリティ」は、マジョリティ・マイノリティに関する問題の中でもひときわ議題に上がりがちです。
これは相手が性的マイノリティであることが分かりやすく、「自分とは違う」といった意識が芽生え、差別の対象となりやすいことが原因といえます。
近年、性的マイノリティに属する人々は、「LGBTQIA+」と表されることが増えてきました。
- L:レズビアン|女性を恋愛対象とする女性のこと
- G:ゲイ|男性を恋愛対象とする男性のこと
- B:バイ|男女どちらも恋愛対象となる人のこと
- T:トランスジェンダー|身体の性別と反対の性自認を元に恋愛をする人のこと
- Q:クエスチョン/クィア|性自認や性的嗜好が定まっていない人のこと
- I:インターセックス|性的な特徴を持つ部位が一般的な男女の状態に当てはまらない人のこと
- A:アセクシュアル|誰にも恋愛感情を持たない人のこと
上記7つの分類に当てはまらないさまざまな性自認・性的嗜好を含める意味でも、最後に「+」マークをつけて表記されているのを多く見かけます。
中には身体の性別は男性・性自認は女性・なおかつレズビアンであるという、一見して男性が女性に恋をしているのと見分けのつきにくいケースも見られます。
また、男性と女性のどちらにも当てはまらない存在「Xジェンダー」なども増えつつあります。
全方向に愛情を持ち、性別を問わず恋愛ができる「パンセクシュアル」も、近年話題に上がることが多いでしょう。
男性は女性を、女性は男性を愛するのが「マジョリティ」とするならば、これらの性的マイノリティはまだまだ少数です。
しかしLGBTQIA+全体で考えると、人口の約1割程度が当てはまるといわれています。
社会的マイノリティ
社会的マイノリティに当てはまるケースは多種多様であり、誰が該当すると一概にはいえません。
端的にいえば、社会の大きな圧力の中で少数派に押しやられ、発言の権利が失われたり、差別の対象となったりすることが多いといえます。
社会的マイノリティの例として挙げられるのは、ホームレスや貧困層などの経済弱者、身体的・精神的を問わず障害を持つ人たち、女性などです。
特に古い時代は女性への差別がはなはだしく、仕事をする権利が奪われていたり、政治的発言権がなかったりすることも珍しくありませんでした。
こういった社会的マイノリティの考え方をなくし、性別・経済状態・身体的特徴に関わらず同じ生活ができるように配慮していくことが大切です。
エスニックマイノリティ
エスニックマイノリティは、日本語に訳すと「少数民族」となります。
私たちが暮らす日本においては耳なじみの薄い方も多いのではないでしょうか。
世界には190ほどの国がありますが、民族に分けるとその数は数千に上るといわれています。
これらの中には継承する人がいないためになくなりかけている民族もあれば、他民族との結婚を重ねて消滅した民族もあり、その数は常に変動を続けているといって良いでしょう。
日本の場合で考えてみると、大きく分けて3つの民族が存在します。
北海道を中心とするアイヌ民族、本土を中心とする本土人、さらには沖縄を中心とする琉球民族です。
これらのうち、もっとも数が多いのは本土人です。
つまり日本においては、アイヌ民族と琉球民族がエスニックマイノリティに当てはまるといえるでしょう。
日本を出て世界に目を向けてみると、日本人は「アジア人」として一括りにされ、黄色人種として差別の対象になることがあります。
肌の色での差別は2020年代に入っても未だなくならず、私たちにとっても決して例外ではありません。
気が付かないうちに差別・偏見を持っていないか、一人ひとりが改めて問題に目を向けて考えてみることが大切です。
宗教的マイノリティ
近年、若い世代を中心に宗教への興味が薄れ、無宗教を掲げる人も増えてきました。
今も日本全体を見れば仏教がもっとも多く、日本ならではの神道が続きます。
キリスト教など世界的に多くの信者がいる宗教も、日本の中ではわずか数パーセントしかおらず、宗教的マイノリティに当てはまるでしょう。
無宗教である人も含め、宗教的マイノリティが時として争いを生むケースもあります。
世界ではイスラーム過激派が猛威を振るったことをきっかけに、一般的なイスラム教徒が差別の対象となり、身体的・精神的に傷を負った事件もありました。
宗教的マイノリティでは、「相手のことを良く知らない」「何を考えているか分からない」といった理解の不足から差別や偏見が起こります。
日本国内では関心の薄い問題であるとはいえ、世界的に見れば大きな問題の一つといえるでしょう。
カースト制度
インドで行われているカースト制度について、教科書などで見聞きしたことのある方も多いのではないでしょうか。
カースト制度では国民を以下の5階級に分け、それぞれが異なる扱いを受けています。
- バラモン:司祭
- クシャトリア:王族
- ヴァイシャ:庶民
- シュードラ:隷属民
- ダリット:不可触民
現在インド憲法ではカースト制度が明確に否定されていますが、国民の中では未だに色濃く根付き、差別の対象となっています。
バラモン・クシャトリア・ヴァイシャの3つは上流階級とされていますが、シュードラは下流階級、ダリットに至っては他の階級とコミュニケーションをとることさえ許されていません。
ダリットが少しでも触れたものは不浄であるとされ、他の人が触れるのを禁じているため、「不可触民」と名付けられたといわれています。
これはインドの制度ですが、日本でも一部の地域で同じような風習があり、兼ねてから問題視されてきました。
それがいわゆる「部落差別」。
始まりは江戸時代といわれており、武士や百姓・町人に分類されなかった一部の人たちが差別を受け、その子孫が今もなお差別に苦しんでいるのです。
勘違いされがちなのは、これらの人たちは江戸時代で単に差別に苦しんでいたかといえばそうではありません。
一部の人々は農林業・水産業に従事し、また一部の人々は芸能業に従事するなど、私たちの生活に欠かせない職業に就いていたのです。
つまり彼らの子孫も何ら差別されるいわれはなく、このような差別をなくそうとする試みが続けられています。
経済的マイノリティ
経済的マイノリティとは、その名の通り「経済的に苦しい人々」「貧困層」などを指す言葉です。
時にはホームレスや生活保護受給者であったり、時には年収200万円以下の人を指したりと、場合によってその対象は異なります。
例えば、オフィスでデスクワークを行う人を「ホワイトカラー」、現場で身体を使って作業する人を「ブルーカラー」と呼んだ時代がありました。
これは単に来ている服装のことだけでなく、大学を卒業していなければホワイトカラーにはなれない、一生懸命勉強しなければブルーカラーになってしまう、といった差別的意味合いで使われることも多かったのです。
これに伴い、「ホワイトカラー=高給取り」というイメージが広まりました。
一定以上の収入がある人々が貧困層をあざ笑うとともに、体力を使う仕事を見下す人も増えてしまったのです。
現在はというと、現場で働く人々はそれぞれ異なる資格を持っていることも多く、さまざまなスキルを要する仕事が増えてきました。
これに伴い、職業による差別が徐々に薄れてきたといえるでしょう。
関連記事:友達を作る場所はどこ?社会人で遊ぶ友達がいないのはやばい?
マイノリティ・マジョリティの使い方と具体例

これまでご紹介してきたマイノリティはごく一部であり、私たちの身の回りでもさまざまなシーンで使われています。
マイノリティ・マジョリティの具体例を元に、それぞれのイメージを膨らませてみましょう。
マイノリティの具体例
私たちがイメージしやすいマイノリティに、「左利き」があります。
右利きに比べて数の少ない左利きは全体の1%ほどしかおらず、どちらになるかは脳の発達の影響が大きいといわれています。
左利きだからといって差別を受けるケースはそれほど多くないものの、ハサミやお玉が使いにくかったり、駅の改札を通りにくかったりといった不都合を感じる方も多いようです。
これらの不都合全てに対応するにはまだまだ時間がかかると思われますが、今もなお右利き・左利きに関わらず過ごしやすい設備の導入が検討されています。
左利きと聞くと、「頭が良い」と思われるケースも珍しくないでしょう。
左利きの場合は右脳が発達しており、アーティスティックな感性を持っている方も多いようです。
さらには日常生活で右手を使わなければならない場面も多く、左右の脳をどちらも使っているために処理能力が速いともいわれています。
とはいえこれらの違いは微々たるものであり、個人差も考慮しなければなりません。
「左利きなのにテストの成績が悪い」などといった考えは差別の元となるため、利き手に関わらず同等に考えることが大切です。
マジョリティの具体例
日本人がマジョリティとなるケースとして挙げられるのは、主に日本に住んでいる場合です。
そしてこの場合にマイノリティとなるのは、日本に移り住んできた外国人やハーフの方々です。
学校や職場においてコミュニケーションが難しく、孤立してしまうケースも少なくありません。
こんなとき、マジョリティである日本人がとるべき行動は、マイノリティを特別扱いすることではありません。
日本語でやり取りができないのならば翻訳アプリを使い、生活スタイルに違いがあるのならば寄り添い、周りの日本人と同じように接することが大切です。
関連記事:人間関係が「めんどくさい」「疲れた」と感じる心理や対処法を解説
マイノリティ・マジョリティの影響

マイノリティ・マジョリティの問題は、いかなる場合であってもゼロにすることはできないでしょう。
人々の間で考えが割れたり、出身や職業が違ったりする限り、多数派・少数派の違いはどうしても出てきてしまいます。
問題なのは、時としてマジョリティがマイノリティの考えや生活スタイルを圧倒し、差別の対象として捉えてしまうといった点です。
経済的マジョリティでは家を失う心配がなく、カースト制度上では差別を受ける心配がないなど、マジョリティには一種の特権があります。
これは本人の意思に関わらず自動的に付与されるもののため、気が付かないうちにマイノリティを差別したり、下に見たりしてしまうこともあるでしょう。
私たちが重視しなければならないのは、「マイノリティ=悪」といった考えを根本から捨てることです。
自分と違うからといって悪いわけではなく、数が少ないからといって軽視して良いわけではありません。
冒頭でも述べたように、私たちはいつでもマイノリティ・マジョリティの両方に属しています。
考え方を変え、多数派・少数派に関わらず相手の認識を受け入れることが大切だといえるでしょう。
まとめ
マイノリティとマジョリティが対立してしまうのは、コミュニケーションが不足し、お互いを理解できていないことが原因です。
視野を広く持ち、相手の考えを受け入れることこそが、根本的な差別をなくす第一歩となるでしょう。
私たち人間に与えられたコミュニケーション能力は、相手をけなすためにあるわけではありません。相手を理解するためにその言語を使い、より良い社会を目指していくべきだといえます。
プレイセラピーのやり方や対象となる子供の特徴は?成功事例も紹介

私たち大人が誰かとコミュニケーションをとるときは、言語を使って繊細な気持ちの変化までしっかりと伝えられるでしょう。
しかし子供の場合はそうもいかず、抱えている気持ちを100%読み取るのは難しいものです。
そんな子供たちの精神状態を把握すべく考えられたのが「プレイセラピー」です。
日本語に表すと「遊戯療法」とも呼ばれており、子供にとってさまざまな効果があるといわれています。
今回はそんなプレイセラピーのやり方や対象となる子供の特徴をご紹介しながら、一体どんな効果をもつ療法なのかを探っていきましょう。
プレイセラピーとは?

プレイセラピー(遊戯療法)とは、私たち大人が子供の心を理解するために生み出された方法の一つです。
子供に対する療法は種類が豊富で、どの療法が合っているかはやってみなければ分からない部分も多くあります。
カウンセラーと対話しながらカウンセリングを受けてみましょうといわれても、問いかけに答えられず上手くいかない子も少なくないでしょう。
知らない人の前では緊張してしまったり、自分の気持ちを言葉で表すのが苦手だったりする子供に対し効果的だといわれているのがプレイセラピーです。
子供に好きなように遊んでもらい、その様子を観察することで抱えている気持ちを汲み取るために行われています。
一般的な会話形式のカウンセリングでは緊張してしまう子も、普段遊び慣れたおもちゃがあったり、初めて見るおもちゃに触れたりするうちに自然な態度で接してくれるようになるでしょう。
カウンセラーが時には見守り、また時には一緒に遊んでくれることで、子供もゆっくりと慣れていけるでしょう。
プレイセラピーの効果や狙いは?
プレイセラピーは、一見子供がただ遊んでいるようにも見えるため、どんな効果があるのかイメージしにくい方も多いのではないでしょうか。
プレイセラピーでは、最終的な目標を「子供が自己表現できるようになる」などといった点に定めて行われます。
緊張しがちな子供は肩の力を抜いて他人と関われるように、他人に対し攻撃的な態度をとってしまう子供は気持ちを抑えて他人と関わりやすくなるようにするなど、状況に応じて声掛けの内容を変えていくことが大切です。
最初は黙って遊んでいるだけだった子供も、遊びを通して大人と心を通わせられるようになり、次第に同年代の子供と上手に関われるようになっていきます。
コミュニケーションに不安要素のある子供の中には、やりたいことがあってもどう声をかけて良いか分からなかったり、そもそも自分がどうしたいのか分からなかったりとモヤモヤした気持ちを抱えている子も少なくありません。
遊びを通して自分と向き合い、「自分はこう考えている」「自分はこうしたいと思っている」といった考えがまとまることで、他人との関わりもスムーズにできるようになるでしょう。
関連記事:自己肯定感が低い子供の特徴とは|注意すべき親の発言や行動
プレイセラピーと似ている言葉との違い

プレイセラピーと似ている言葉には、「療育」や「遊び」があります。
一見遊んでいるだけに見えるプレイセラピーが、これらとどう異なるのか見ていきましょう。
療育とは、精神障害・身体障害・知的障害とさまざまな状態の子供が受けるものです。
その内容は子供によって異なりますが、いずれもそれぞれの子供が悩みを解決し、今後社会に出る際に困らないような状態を目指すために行われます。
身体障害がある子には運動療法を、知的障害がある子には知育療法を行うなど、子供に合わせた方法を選ぶことが大切です。
遊びとプレイセラピーは似て非なるものであり、遊びの中で声掛けを行いながら悩みの改善を目指すのがプレイセラピーです。
通常の遊びではケンカをしたときや泣いているときにのみ声掛けをすることも多いですが、プレイセラピーでは子供の様子を見ながら常に声掛けをしていくのが特徴です。
子供にとっては普段の遊びと変わらないため、より肩の力を抜いて過ごせるのがメリットといえるでしょう。
プレイセラピーの対象となる子供の特徴
プレイセラピーを行うのに適しているとされるのは、おおむね3歳頃から小学校卒業程度までの子供たちです。
自分の言葉で少しずつ気持ちを伝えられるようになれば、プレイセラピーを受けても効果が見られやすいでしょう。
また、プレイセラピーの対象となる子供たちは、チック症や吃音症・場面緘黙症などで会話を避けがちな子や、暴力がみられ他人との関わりが上手くいかない子、不登校の子などさまざまです。
年齢に応じて言葉が出にくい子であったり、自閉症・ADHD・アスペルガー症候群などの診断が下りた子であったり、一人ひとりに合った内容で声掛けを行うことで効果が得られやすくなります。
療育の一部として行われるケースも珍しくありません。
これらの悩みを抱えた子供たちは、家でお父さん・お母さんや兄弟と関わっているだけでは悩みが改善されない場合があります。
プレイセラピーを上手く取り入れることで、子供へ負担をかけずにコミュニケーションを取りやすくなるでしょう。
関連記事:自己肯定感が低い原因はプライドが高いから?親のせい?高める方法とは
プレイセラピーのやり方

プレイセラピーを行う際は、大まかな流れに沿って子供一人ひとりへ対応していきます。
まずは子供に日頃過ごしているのと同じ状態で、リラックスして遊んでもらうことから始めます。
これにより子供が抱えている悩みを明らかにし、どういった対応が必要なのかを浮き彫りにしていきます。
普段周りとうまく話せずに一人でいることが多かったり、気に入らないことがあると手が出てしまったりと、実際の様子を見ることで対応策を考えやすくなるでしょう。
続いて、これらの行動を起こすとき、本当は子供がどう考えているのかを考えます。
一人でいるからといって周りと遊びたくないわけではなく、本来であれば声をかけて混ぜてもらいたいと思う子もいるでしょう。
手が出てしまうのにも理由があり、どうやってイライラした気持ちを発散すれば良いか分からないだけかもしれません。
こういった一人ひとりの状況を踏まえ、ここでようやくプレイセラピーの目標を立てられます。
「自分で他人を遊びに誘えるようになる」「イライラしたときは一旦落ち着き、手を出さないようになる」など、無理のない範囲で目指すべき姿を考えることが大切です。
この目標を達成するためにどのような声掛けを行うべきか、時にはお父さん・お母さんも含めて話し合いが行われます。
プレイセラピーでの声掛けは特別難しいものではなく、「お友達を誘うときは何て言ったら嬉しいかな」「叩くと自分の手も痛いから、一度深呼吸してみよう」など子供の気持ちに寄り添うことが一番大切です。
一日で目標を達成する必要はまったくないため、始めたばかりのときは子供と他愛ない会話をするのも良いでしょう。
一緒に遊んでいる中で「この人が楽しい」と思ってもらえれば、自然と会話が続き、気持ちを伝えてくれる子も少なくありません。
関連記事:子供だけでなく家族全員の幸せを考える。悩める親の心を救う確かなメッセージ【保育士 てぃ先生のIt’s My Story】
プレイセラピーの成功事例

プレイセラピーを行っている医療機関や療育施設は非常に多く、成功する場合もあれば別の方法が合う場合もあります。
今回は江戸川大学で行われたプレイセラピーについて、伊藤渚氏がまとめた論文をご紹介します。
本件は小学校2年生の女子児童が学校へ行きたくないと訴えたことで、母親が心配して教育相談を受けたことが始まりです。
周りとのコミュニケーションが上手くいかず、時には手が出て周りと衝突し、2年生に上がったタイミングで学校へ行けなくなってしまいました。
泣いたり怒ったりといった情緒の不安定さが見られ、時には自傷行為に及んでしまうこともあったようです。
当初女子児童はプレイルーム内でのびのびと過ごすことができず、自由にして良いといわれても周りに迷惑をかけないように振舞ったり、ゲームをしても大人を勝たせたりといった「気遣い」が見られました。
髪を口に入れる様子から、落ち着かないことがあっても上手く言葉に出せず、気持ちを閉じ込めてしまうことが伝わってきます。
時間をかけるにつれ、女子児童はゲームで勝ちにこだわったり、のびのびと遊ぶ様子が見られたりするようになりました。
学校でトラブルがあった際にどう考えていたのか、自分の感情も素直に伝えてくれるようになったといいます。
「本当は一緒に遊べる友達がほしい」といった願いも口にするようになり、次第に自傷行為や暴力が少なくなっていきました。
最後まで見られた会話内での「攻撃的表現」においては、大人がごっこ遊びの中で攻撃的な言葉で傷つけられている役を演じることで、自分の周りの環境を客観的に見られるようになりました。
次第に学校での友達ができ、無事肩の力を抜いて生活できるようになるまで、時間はかかったものの彼女が得たものは大きかったといえるでしょう。
このように、プレイセラピーは解決までに長い時間を要することも少なくありません。
逆に言えば、時間をかけて行うことでその子の本質が見えやすくなり、信頼関係を築くことで子供の本当の気持ちを理解しやすくなるのです。
どんな子供でも心の中ではさまざまなことを考え、悩み、葛藤しながら生きています。
これらの考えを大人が汲み取り、自然な形での放出を目指すことが重要です。
引用元:人との関わりがうまくいかない子どもとのプレイセラピー【PDF】
プレイセラピーの効果がない子供はいる?
「こんな子供はプレイセラピーを受けるべきではない」といった明確な指針は存在せず、やってみて初めて効果がなかったり、別の方法が合っていることが発覚したりする場合もあるでしょう。
また、自閉症やADHD・アスペルガー症候群といった発達障害が診断されている子供にとって、プレイセラピーが他者との関わりをスムーズにすることはあっても、発達障害そのものを克服できるかといえばそうではありません。
子供にとって良い方法を組み合わせて試し、時間をかけて他者との関わりを促してあげることが重要といえるでしょう。
まとめ
プレイセラピーは通常のカウンセリングとは異なり、遊びながら子供の自立を促せるものです。
堅苦しい話し合いが苦手な子も、好きなことで遊べる時間となれば、肩の力を抜いて過ごしやすいのではないでしょうか。
あくまでも療法の一種として、目標とする状態まで長い時間をかけて進んでいくことが大切です。
まずは自分を大切に。子育てには”Boundary(境界線)”が必要?! 【Editor’s Letter vol.09】
| Humming編集長 永野舞麻がカリフォルニアから配信する「Editor’s Letter 」。
日々の暮らしで感じた気付きや、人生において大切にしていることを綴っています。 |

私が母親になったのは12年前。
右も左もわからない初めての子育て。
「〜しなければいけない」
「〜するべきだ」
自分で作ったルールにがんじがらめになり、子どもと笑顔で接することができない自分を責め続けていました。
そんな私は自分自身と周りとの”Boundary(境界線)”を意識するようになったことで、親子関係に変化を感じるようになりました。
親子であっても、同じ人間ではない。私は私。あなたはあなた。
自分と他者との間に境界線を引くことは、自分のために、そして相手のためにも大切なことなのです。
欲求を押し殺して子どもを優先するのが良い親なのか?!
長女が小さかった頃、私は自分の欲求と限界に気がつけませんでした。自分を押し殺してでも、娘の希望全てを叶えてあげるのが良い母親だと思っていたのです。
子どもはなるべく泣かせてはいけない。
離乳食は一から全て自分で作らなければいけない。
赤ちゃんに着せる衣類は肌に優しいオーガニック素材にこだわるべきだ。
自分の全てを子どものために捧げよう。
当時の私は誰に強いられたわけでもないのに、自分でルールを作り、「子どものためにもっとできるはずだ」「良い母親でいなければ」と自分を追い込んでいました。
しかし、私が良い母親になろうと頑張るほどに、子どもにも夫にもプレッシャーを与え、家族みんなを苦しめていたことにだんだん気がつきました。
他者への優しさは自分を満たしてあげてから
長女が4歳になると彼女自身の主張を言葉にすることも増え、イライラを抑えられずに娘を怒鳴ってしまったり、時には手を挙げそうになったりすることが増えました。
自分の全てを子どものために捧げているのに、結局は私が娘のことを傷つけているのかもしれない……。そんな自分に落胆し、子どもが寝静まった夜にひとり涙を流すこともありました。
その現状を変えたいと思い、夫に勧められて始めたのがセラピーです。
セラピーの時間は毎回子育ての話からスタートしました。当時の私はとにかく子育てのことを話したかった。また、幼少期のトラウマが自分の子育てを通じてフラッシュバックするように溢れ出てきていたので、そのことについても先生にたくさん話を聞いてもらいました。私がどんなに自己嫌悪に陥ったネガティブな話をしても「あなたはこんなにもお子さんのことを愛しているじゃない」「あなたは頑張っているよ」「そんな辛いことが子どもの頃あったのね」と、先生は私の良いところを見つけて言葉にして伝えてくれたり、幼少期に感じた私の想いに同調してくれたのです。
定期的に自分の内を言葉にすること、そしてありのままの自分を誰かから受け止めてもらえることで、まるで玉ねぎの皮が1枚1枚剥がれていくように、自分が本当に求めているものが見えてきました。
たとえば、朝はゆっくりお白湯を飲んだり、趣味のアートをしたり、自分のためだけに時間を使いたい。日中だって疲れた時はゆっくり休憩したい。私には家でのんびりする自分のための時間が必要だったのです。
自分自身が満たされない状態で、周りに手を差し伸べるのは難しいことです。酸素がない状態で酸素ボンベを付けずに他者を助けることはできないですよね。まずは自分の欲求を満たしてあげる。そうすることで誰かのためにも優しさやパワーを注げるということにようやく気がつけました。
自分のための時間がもたらす変化
それ以降、私は常に子ども優先という自分の考え方を改め、自分のための時間も大切にするようになりました。
たとえば、朝6時半までは自分のためだけに時間を使う。「朝6時半まではママは自分の時間を過ごすから、それまでは自分のことは自分でやってね」と子どもたちには伝えています。子どもたちも理解してくれ、早起きした時には、自分でフルーツやグラノーラを食べるようになりました。
日中に少し休憩したい時は、子どもたちには「このカップの中のお茶が空っぽになったら手伝うね」とか「時計の針が30分になったらお話を聞くね」とか「このアラームが鳴るまではママにひとりの時間をちょうだいね」などと伝え、自分のための時間を意識的に確保しています。
子どもたちにイライラして冷たい言葉をかけてしまいそうな時には、「今は優しい気持ちで会話ができそうにないから、落ち着くまで別のところに行くね。落ち着いたら必ず戻ってくるからね」と伝えて歩き去ることもあります。子どもたちが不安を感じないように「必ず戻ってくる」ことを伝えることが大切です。
その他にも、掃除や洗濯などの家事は子どもたちと一緒に行い、子どもたちがいない時間は仕事や趣味に全集中。お手伝いは子どもの自主性を育み、自尊心を高めるとも言われています。子どもといる時間に一緒に家事をやることで、自分の時間が増えて、子どもたちの成長にも繋がる。まさに一石二鳥です。
このように自分のための時間を作ることで、常に誰かのために何かをやっている状態から解放され、イライラすることが減り、子どもとの関係も良い方向に変化していきました。
私は私。あなたはあなた。”Boundary”の重要性
子育てに関する書籍やセラピーを通じて学んだことは、どんなに親しい間柄であっても、「私は私」「あなたはあなた」と境界線を引くことの大切さ。
境界線=”Boundary”。
”Boundary”を大切にすることで、パートナーや子どもを「一個人」としてみることができ、尊敬や尊重の気持ちを忘れずに接することができます。
また、相手からも自分の境界線を踏みにじられることがなくなり、自分の欲求に早く気がつき、満たすことができるでしょう。
私は子育てに境界線を意識するようになってから、心に余裕が生まれ、子どもや夫に怒りや悲しみをぶちまけてしまうことが少なくなりました。
もし、あなたが子育てを辛く感じているなら、”Boundary”を意識して、相手と同意できる境界線を見つけ、それを上手く言葉にして、自分のための時間も大切にして欲しいです。
自分を大切にできるからこそ、他者に対しても真に優しくなれる。私はそう感じています。
40歳を目前に考える、限られた人生の過ごし方

Humming編集部 條川純のコラムをお届けします。
久しぶりに会った友人の子どもの成長に、時の流れの速さを実感する今日この頃。40歳を間近に控え、これまでよりも時間の尊さを感じるようになりました。
私は少し前、2年間交際した彼との別れを経験しました。彼は優しく、私のすべてを受け入れて愛してくれた人。しかし、一緒にいる期間が長くなるに連れて、彼の内面の複雑さを知り、別れを選ばざるを得ませんでした。
けして傷つけられたわけではなく、それどころか彼からたくさんの優しさをもらっていた私。別れを意識しはじめてからは、「私がわがままなだけなのかも……」「ありのままの彼を受け入れるべきなのでは……」と罪悪感を感じることもありました。
しかし、悩んだ末に自分の本心に従うことを決め、その結果、彼を深く傷つけてしまったのです。
この経験を機に、過去を振り返り、これからの人生の過ごし方を深く考えるようになりました。
| Humming編集部Project Coordinator 條川純
1984年生まれ。アメリカ生まれ、アメリカ育ち。現在はひとり暮らしをしながら、生涯を共に過ごせるパートナーを探している。 |
流れのままに生きてきた39年間
これまでの人生を振り返ると、私は大きな人生の決断に関して、いつも流れに身を任せるタイプでした。特に恋愛においては、相手の優しさに惹かれ、深く考えることなくお付き合いを始めることが多かったのです。
そういった傾向は、中高時代に感じたコンプレックスが影響しているように思います。私は中学高校の4年間を日本のインターナショナルスクールで過ごしました。そこにいたのはスラリとした美人ばかり。アメリカで生まれ育ち、これまで食事のカロリーや自分の体型を気にせずに過ごしてきた私とはまるで異なっていたのです。
さらに、日本ではスリムで可愛い女の子が男の子から人気を集めていました。いつも友達の影に隠れる私。当時は自分自身をまるで「みにくいアヒルの子」のように感じ、寂しさを感じていたのです。
そんな経験から、男性に優しくされると嬉しさのあまり、深く考えずにお付き合いをしてきました。「私のことを好きになってくれなんて……」という思いが強かったからです。
若さゆえの未熟さから、最終的には自分のことも、相手のことも傷つけてしまうこともありました。
とはいえ、良いことも悪いことも経験したからこそ、今の私がいる。これまでの自分の選択を後悔しているわけではありません。
しかし、40代を間近に控え、さらに彼との別れを経験したことで、今後の自分はどんな人生を歩んでいきたいのかを深く考えるようになったのです。
40歳を目前に考える自分の生き方
広くて綺麗な豪邸に住んだり、高級車を所有したり、ブランド物で着飾ったり、私はそういったことを望んでいるわけではありません。私が求めているのは自分の心に正直に生きること。
仕事においては、情熱を注げる環境を自ら選び、目標に向かって全力で取り組みたい。そして、おばあちゃんになるまで働き続けるのが理想です。
恋愛面では、一生を共に過ごしたいと思える相手と出会い、愛し合い、サポートし合って穏やかに生きていきたい。
そして、人生の終わりを迎える時には、自分に対して「頑張ったね」と言えるような、後悔のない人生を歩みたいと強く願っています。
そのためにも、これからは流れに身を任せて生きるのではなく、キャリアも友情も恋愛関係も、これまでよりも慎重に選択していきたい。人生はあっという間に過ぎ去っていくから、限られた時間をより有意義に過ごしたいからです。
特に恋愛においては、付き合ってから「なんだか違うかも……」ということが起こらないよう、お付き合いをする前にもっと相手のことを知る努力をしたいと思っています。
人生の主人公は自分自身
自分が本当に大切にしたいものは何か。
どんな人生を歩みたいのか。
40歳を目前にした今、私はこんな問いを自分自身に投げかけています。
人生は有限。私たちは毎日着実に死に近づいています。死を意識して生きていくことは、不吉なことや悪いことではないと私は思います。むしろ、限られた時間をどう生きるかを考える良いきっかけになるのではないでしょうか。
どんなに慎重に生きていても、人生には思わぬ出来事や困難があるでしょう。それでも、失敗を恐れずに挑戦し、うまくいかない時は方向転換する勇気を持つ。そして何よりも自分らしく生きることを大切にする。人生の主人公は自分自身なのだから。
あなたはどんな人生を歩んでいきたいですか?
生理前の情緒不安定の対策|彼氏への伝え方はどうすればいい?

「生理前に情緒不安定にならないようにしたい!」
「生理前に起きる情緒不安定のせいで、彼氏との関係が悪化したらどうしよう」
このような悩みや疑問を抱えている方がいるのではないでしょうか。
この記事では、生理前の情緒不安定の対策や彼氏への伝え方について解説します。
生理前の情緒不安定はなぜ起こる?
生理前に起こる情緒不安定は、PMS(月経前症候群)の症状である可能性が高いと言えます。
PMSの症状には、身体的なものから精神的なものまでさまざまな種類があります。
PMSの症状を引き起こしているのは、エストロゲンとプロゲステロンといわれるホルモンです。
エストロゲンとプロゲステロンは、排卵後に多く分泌される一方、月経が近くなると急激に分泌量が低下します。
分泌量の急激な変化が脳内ホルモンなどに影響を及ぼすことにより、身体的・精神的不調が引き起こされると考えられています。
20代〜30代に多く見られる症状であり、生理周期および卵巣機能が正常でも症状を引き起こすことがあるため、辛いときは無理せず、婦人科に相談してみてください。
関連記事:女性の情緒不安定の治し方は?生理との関係や落ち着く方法を解説
生理前の情緒不安定の対策法は?
生理前の情緒不安定には、次の7つの対策法があります。
- 適切な栄養摂取
- 定期的な運動
- 十分な睡眠
- カフェインとアルコールの摂取を控える
- 良好なコミュニケーション
- 趣味や楽しい活動に時間を割く
- 専門家の助けを求める
それぞれの対策法について、以下で見ていきましょう。
適切な栄養摂取
女性ホルモンの効果が薄くなることで、生理前に情緒不安定になってしまうことがあります。
情緒不安定を改善するには、カルシウムとマグネシウムの摂取がおすすめです。
カルシウムとマグネシウムは、大豆製品や緑黄色野菜に多く含まれるため、ぜひこれらの食材を多めに摂るようにしてみてください。
定期的な運動
定期的な運動も、生理前に起きる情緒不安定の改善に効果があります。
激しい運動をする必要はなく、ジョギングやウォーキングなどの軽めの運動で十分です。
1日30分程度の軽めの運動を週3日するだけで、症状が改善する可能性があります。
隣の駅まで歩いてみたり、いつもバスに乗るルートの一部を歩いてみたりして、定期的な運動習慣を身につけてみてください。
十分な睡眠
生理前に起きる情緒不安定を改善したい場合は、十分な睡眠を心がけてみると良いでしょう。
月経前や月経中は、健康な女性であっても睡眠の質が低下してしまう可能性があります。
そのため、月経前や月経中の時期は、意識的に十分な睡眠ができるように心がけると良いでしょう。
寝る直前までスマートフォンやパソコンを使わないなど、できることから始めてみることをおすすめします。
カフェインとアルコールの摂取を控える
カフェインとアルコールの摂取を控えることも効果的です。
カフェインなどの刺激物を接種することで、神経が緊張したり興奮したりしてしまいます。
神経を落ち着かせてリラックスするために、コーヒーやお茶などカフェインが入っている飲み物は控えてみましょう。
また、アルコールなど体の不調の原因となる食べ物・飲み物を控えることも大切です。
規則正しい生活を送ることで、少しでも症状が改善できるようにしてみましょう。
良好なコミュニケーション
生理前に起きる情緒不安定の改善には、良質なコミュニケーションを取ることも効果があります。
たとえば、家族や親しい人には、PMSの症状が出てしまって情緒不安定になってしまう可能性があることを事前に伝えておくと良いでしょう。
そのうえで、情緒不安定になってしまったときに「やってほしいこと」も伝えておくことがおすすめです。
たとえば「ひとりにしてほしい」「家事を手伝ってほしい」「大目に見てほしい」などが考えられます。
情緒不安定のことを打ち明けるのは、勇気が必要かもしれません。
あなたと親密な関係を築いている人は理解してくれるので、勇気を出して打ち明けてみましょう。
趣味や楽しい活動に時間を割く
生理前に起きる情緒不安定を改善するには、ストレスを低減させることが効果的です。
そのため、精神的に疲れてしまうことがあったら、趣味や楽しい活動に時間を割いてリラックスしてみてください。
趣味や楽しい活動を通してリラックスすることで、ストレスを低減でき、生理前の情緒不安定が改善する可能性が高まるでしょう。
あらかじめ趣味や楽しい活動をする日時を決めておき、それを楽しみに日常生活を送ってみるのもおすすめです。
専門家の助けを求める
以上の6つで症状が改善しない場合は、専門家の助けを求めてみるのも良いでしょう。
婦人科を受診することで、薬を用いた治療を受けられる可能性があります。
精神安定剤や抗うつ薬、経口避妊薬、GnRHアゴニストなど、さまざまな種類の薬があるため、ぜひためらわずに専門家に相談してみてください。
関連記事:イライラして眠れない時はどうする?原因や対処方法を解説
生理前の情緒不安定に効く食べ物

ここでは、生理前の情緒不安定に効く食べ物について解説します。
ホルモンバランスを整える栄養素や気分を安定させる食べ物、避けたい食べ物について見ていきましょう。
ホルモンバランスを整える栄養素
ホルモンバランスを整える栄養素には、次のようなものがあります。
- カルシウム
- マグネシウム
カルシウムやマグネシウムは、女性ホルモンのバランスを整える役割が期待できます。
大豆製品や緑黄色野菜などを摂取することで、情緒不安定が改善しやすくなるでしょう。
また、ビタミンやミネラルも摂取すべき重要な栄養素です。
生理前に限らず、若い人の中にはビタミン・ミネラルが不足している人が多くいます。
摂取すべき栄養素をきちんと摂ることが心の健康にもつながるため、サプリメントなども用いて必要な栄養素を摂るようにしてみましょう。
気分を安定させるおすすめの食べ物
カルシウムやマグネシウム、ビタミンB6には気分を安定させる効果があります。
そのため、前述したように、大豆製品や緑黄色野菜を食べることで、気分を安定させやすくなるでしょう。
特に大豆製品は、女性ホルモンと類似した働きをするイソフラボンも摂取できるため、ぜひ摂取したい食べ物です。
また、次のような食べ物からもカルシウムやマグネシウム、ビタミンB6を摂取できます。
- カツオ
- レバー類
- ナッツ類
- 海藻類
加えて、ビタミンEが接種できるアーモンドなどもおすすめですので、ぜひ積極的に摂取してみてください。
避けたい食べ物とその理由
一方、次のようなものが含まれる食べ物は避けたほうが良いでしょう。
- カフェイン
- 塩分
- アルコール
情緒を安定させるためには、自律神経を整えることが大切です。
しかし、カフェインには自律神経を乱しやすくする作用があるため、カフェインの摂取により気分が安定しない可能性があります。
また、塩分やアルコールなどの生活習慣を乱す成分を摂取することで、代謝が悪くなる可能性もあります。
そのため、カフェインや塩分、アルコールの摂取を控え、健康的な食生活を送るように心がけてみましょう。
生理前の情緒不安定で泣く原因と対策
生理前に情緒不安定になってしまい、泣いてしまうこともあるかもしれません。
この症状は「PMDD(月経前気分不快障害)」と呼ばれています。
PMDDの症状が起きる原因は、PMSと同じく女性ホルモン分泌量の急激な変化にあります。
PMDDの症状を改善するには、PMSと同じように規則正しい生活リズムで過ごし、適度に運動することが大切です。
また、婦人科で薬を処方してもらったりピルを服用したりすることでも症状の改善が期待できます。
困ったら、無理に自分で解決しようとせず、婦人科などの医療機関に相談するようにするとよいでしょう。
関連記事:ストレスを解消するにはどうすればいい?ハグがおすすめな理由も解説
生理前の情緒不安定の彼氏への伝え方はどうすればいい?
彼氏には、生理前の情緒不安定であることを正直に打ち明けることをおすすめします。
不機嫌な態度をとったり涙が止まらなくなったりするなど、冷静さを失ってしまうことや、急激な気分の変化によりドタキャンする可能性があることを理解してもらいましょう。
彼氏に打ち明けるのをためらってしまうことがあるかもしれません。
むしろ信頼関係を深めるためにも、きちんと打ち明けてみてください。
薬を使った生理前の情緒不安定の治療

生理前の情緒不安定に対しては、薬を使った治療ができます。
医療機関に相談する前に、市販薬で解決したい場合は「プレフェミン」を試してみてください。
プレフェミンは、日本で唯一購入できるPMSの市販薬です。
いつでも使用できるわけではなく、低用量ピルの服用中である場合や女性ホルモンに関連する病気の既往歴がある場合などは使用できません。
その他にも注意点が複数あるため、用量・用法をきちんと確認してから使用するようにしましょう。
プレフェミンで症状が改善できない、もしくはプレフェミンを服用したら副作用が出てしまった場合、医療機関へ相談してください。
医療機関では、あなたの症状に合わせた薬を処方してもらえます。
自分で無理に解決しようとせず、専門家の意見を聞きながら症状改善に取り組んでみましょう。
ピルが原因で情緒不安定で泣くことがある?
ピルを飲み始めたばかりの頃は、ホルモンバランスの変化により情緒不安定になることがあります。
場合によっては泣くなどの症状が現れることもありますが、3ヶ月ほど飲み続ければ気分が安定しやすくなる場合がほとんどです。
しかし、症状が辛い場合、もしくは4ヶ月以上経過しても症状が改善しない場合は、ピルとの相性が悪い可能性があります。
ピルを処方してくれた医師と相談し、トラブル解決をするようにしてください。
【まとめ】生理前の情緒不安定の対策は人それぞれ
生理前の情緒不安定への対策方法は、人それぞれです。
1つの対策方法を試しても症状が改善しない可能性もありますが、その場合は他の対策方法を試してみてください。
また、生理前の情緒不安定により彼氏との関係悪化を避けるには、事情をきちんと伝え、理解してもらうことがおすすめです。
事情をきちんと伝えれば、関係悪化を防げるばかりでなく、気を遣ってくれるようになり、さらなる信頼関係の構築につながる可能性もあるでしょう。
ノンバーバルコミュニケーションと対人関係|恋愛においての重要性とは

言葉以外でおこなうコミュニケーションを「ノンバーバルコミュニケーション」と呼びます。
ノンバーバルコミュニケーションの具体例は、ジェスチャーやアイコンタクト、表情の変化など。
ノンバーバルコミュニケーションを効果的に使えると、コミュニケーションがスムーズにできるようになります。
そこで、この記事では、ノンバーバルコミュニケーションと対人関係について解説します。
恋愛におけるノンバーバルコミュニケーションの重要性についても解説していますので、ぜひ最後までお読みください。
ノンバーバルコミュニケーションの重要性
言葉を使わないノンバーバルコミュニケーションは、コミュニケーションにおいて次のようなメリットが得られるため、重要視されています。
- 言葉を補える
- 安心感を与えられる
- 相手を理解しやすくなる
ノンバーバルコミュニケーションを用いるとコミュニケーションがスムーズにできるのは、メラビアンの法則から明らかになっています。
メラビアンの法則とは、コミュニケーションで相手から受け取る情報の内訳が、言語情報が7%、非言語情報が93%であることを明らかにしたもの。
そのため、ノンバーバルコミュニケーションを使って非言語情報を充実させることで、相手とのコミュニケーションがスムーズにできるようになるのです。
関連記事:コミュ力を上げるにはどうしたらいい?鍛える方法を解説
ノンバーバルコミュニケーションの例
ノンバーバルコミュニケーションの例として、次の7つが挙げられます。
- 身体言語(ボディランゲージ)
- アイコンタクト(視線)
- ボディタッチ(接触)
- プロクセミクス(空間の使い方)
- パラランゲージ(声の特性)
- 物理的な外観
- 表情の微細な変化
それぞれのノンバーバルコミュニケーションについて、以下で見ていきましょう。
身体言語(ボディランゲージ)
身体言語(ボディランゲージ)を用いることで、話の内容に補足ができます。
言葉だけでは伝わりにくい場面でボディランゲージを使用できれば、言いたいことのニュアンスや自分の思い、考えを正確に伝えやすくなります。
特に、Web会議などのカメラを通したコミュニケーションでは、反応が薄く感じられることが多いため、ボディランゲージを強く意識することがおすすめです。
しかし、ボディランゲージを多用すると、ボディランゲージばかりが気になって話の内容が頭に入らないこともあるため、適度に使用するようにしてください。
アイコンタクト(視線)
アイコンタクト(視線)も、ノンバーバルコミュニケーションの例の1つです。
視線がズレていると、話し手の場合には「自分の話に自信がないのかな」と、聞き手の場合には「話に興味がないのかな」と思われてしまいます。
一方、視線を相手の目に向けて話したり聞いたりすることで、相手とコミュニケーションを取ろうとする意志を伝えられます。
視線ひとつで印象がガラッと変わるため、話すときは「相手の目を見る」ことを心がけてみてください。
ボディタッチ(接触)
ボディタッチ(接触)もノンバーバルコミュニケーションの一例に挙げられます。
もちろん、関係性が深まっていない相手にいきなりボディタッチすることは控えたほうが良いでしょう。
しかし、関係性の深い子どもを抱きしめたり、仲間の背中をポンと叩いて励ましたりするなどのボディタッチは取り入れてみることがおすすめです。
中でも握手は取り入れやすく、ビジネスの場面でもよく用いられるため、握手から始めてみるのが良いでしょう。
プロクセミクス(空間の使い方)
ノンバーバルコミュニケーションでは、プロクセミクス(空間の使い方)を意識することもあります。
たとえば、会食の場における座席配置を意図的に考えることで、コミュニケーションが取りやすくなることがあるでしょう。
また、過度に近づくのではなく適度な距離感を保つことで、相手のパーソナルスペースを脅かすことなく、気持ちよくコミュニケーションが取れるようになります。
ぜひ空間の使い方にも気をつけて、コミュニケーションを取ってみてください。
パラランゲージ(声の特性)
パラランゲージ(声の特性)も、コミュニケーションに大きな影響を与えます。
相手に好印象を与えたい場合、普段の会話よりも1トーン高くしたり、落ち着いてゆっくりハッキリと発音したりすることが大切です。
声色ひとつで自分の印象がガラッと変わるため、明るい印象をイメージして1トーン高く話してみてください。
また、相手との距離感を考えて、大きすぎず小さすぎない声で話すことで、相手が違和感を抱くことなく、スムーズにコミュニケーションが取れるでしょう。
物理的な外観
服装をはじめとする物理的な外観(見た目)も、ノンバーバルコミュニケーションでは重要な要素です。
フォーマルな場なのかカジュアルな場なのかによって適切な服装や化粧、アクセサリーなどが異なります。
また、明るい印象を与えたいのか、真面目な印象を与えたいのかによっても、適切な見た目は異なります。
TPOを意識し、場や目的にふさわしい見た目にするようにしましょう。
表情の微細な変化
表情の微細な変化にも気をつかうと、円滑なコミュニケーションがしやすくなります。
私たちは、感情が表情に現れやすいことから、相手が発する言葉のニュアンスを表情を通して読み取っています。
同じ言葉であっても、表情次第でポジティブな言葉にもネガティブな言葉にも変化するのです。
そのため、自分の思いや考えが伝わりやすくするために、表情を意識的に作ることをおすすめします。
関連記事:社内で円滑にコミュニケーションをとるコツや成功事例を紹介
ノンバーバルコミュニケーションの効果

ノンバーバルコミュニケーションには、次の6つの効果があります。
- 感情の伝達
- 親密度の向上
- 非言語的な同意や反対の表明
- 社会的地位や権威の表示
- 嘘や欺きへの疑い
それぞれの効果について、以下で見ていきましょう。
感情の伝達
ノンバーバルコミュニケーションには、感情を伝達する効果があります。
言葉だけでは「嬉しい」「悲しい」などの感情が伝わりづらいこともあります。
しかし、ボディタッチや声の特性、表情の変化などのノンバーバルコミュニケーションを用いることで、自分の感情を伝えやすくなるでしょう。
言葉の内容だけでなく感情も伝えたい場合は、ノンバーバルコミュニケーションを使うことをおすすめします。
親密度の向上
ノンバーバルコミュニケーションは、親密度の向上にも効果があります。
たとえば、相手と視線を合わせて見つめ合ったり、あえて近い席に座ったりすることで、相手との距離感を縮めやすくなります。
ある程度関係性が深まった後に、ボディタッチなどのテクニックを利用することで、さらに親密度を向上させることも可能です。
相手との親密度を向上させたい方は、ノンバーバルコミュニケーションを積極的に利用してみてください。
非言語的な同意や反対の表明
ノンバーバルコミュニケーションを用いることで、非言語的な同意や反対の表明もできます。
相手の話に対してうなずけば、「話を聞いていますよ」「あなたの考えに同意します」という考えを伝えられます。
一方、首を傾げたり眉間にしわを寄せたりすると、相手の話に反対、または同意していないという考えを伝えられるでしょう。
社会的地位や権威の表示
ノンバーバルコミュニケーションによって、マイナスの印象を与えてしまうことがあります。
たとえば、イスにふんぞりかえって座ったり、腕組みをして仁王立ちしていたりすると、社会的地位の高さや権威を見せつけていると捉えられがちです。
相手に見下されないように、わざと社会的地位や権威を表示することもあります。
しかし、一般的な場面では社会的地位や権威を表示することによるメリットが大きくないため、これらの行為はなるべく避けることをおすすめします。
嘘や欺きへの疑い
相手が「嘘をついていたり欺いていたりするかもしれない」と疑うこともノンバーバルコミュニケーションで表現できます。
たとえば、目を細める、頬杖をつく、腕組みをするなどが疑っていることを表す仕草として用いられます。
相手に言葉で直接伝えなくても、仕草から嘘や欺きが見抜かれていることを伝えられれば、余計なトラブルに巻き込まれずに済む可能性が高くなるでしょう。
このように、ノンバーバルコミュニケーションにはさまざまな効果があるため、ぜひ活用してみてください。
恋愛におけるノンバーバルコミュニケーション

ノンバーバルコミュニケーションは、恋愛においても大きな効果をもたらします。
たとえば、次のような要素が揃っていると、異性に好印象を与えられるでしょう。
- 清潔感のある外観に整える
- 話すときに視線が合う
- 口角を上げ爽やかな笑顔をする
一方、視線を合わせられなかったり、ボソボソっと自信なさげに話したり、猫背だったりすると、異性に好印象を与えるのは難しくなります。
また「気まずい空気を作らないようにしなければ!」と思ってしまい、愛想笑いを多用してしまうと、自信のなさが伝わってしまうでしょう。
このように、恋愛ではノンバーバルコミュニケーションが異性との関係に大きく影響します。
「異性と良い関係を築きたい」「恋を成就させたい」と考えている方は、ぜひノンバーバルコミュニケーションをマスターしてみてください。
ノンバーバルコミュニケーションの注意点
ジェスチャーを用いることで、話の内容を補足するテクニックがあります。
しかし、文化圏が違えばジェスチャーが表す意味が異なります。
たとえば、欧米では親指を立てる行為(サムズアップ)は「OK」という意味を表し、日本人も同じように使う場面が多くあるでしょう。
しかし、中東や南米、西アフリカなどの一部の地域では「侮辱」の意味を表します。
このように、異文化コミュニケーションでジェスチャーを使うときには、ジェスチャーが持つ意味に注意してください。
関連記事:ノンバーバル(非言語)コミュニケーションの重要性を徹底解説!
【まとめ】ノンバーバルコミュニケーションをマスターして人間関係を円滑に
ノンバーバルコミュニケーションをマスターすると、表現が豊かになります。
自分の考えや思いを相手に正確に伝えられるようになるだけでなく、恋が成就する確率も高まります。
普段の癖もノンバーバルコミュニケーションに含まれるため、身につけることは簡単ではないでしょう。
しかし、日頃から意識して取り入れることで、少しずつ上達しマスターできるようになりますので、ぜひ今日から試してみてください。
夫婦カウンセリングは意味ない?おすすめ?効果について解説

夫婦が抱える問題はさまざまで、ときには家族や親友にも相談できず一人で抱え込んでしまうこともあるでしょう。
そのような場合、夫婦カウンセリングを受けるのも有効な方法のひとつです。
本記事では、夫婦カウンセリングによってどのような問題を解決できるのか、カウンセリングを受けるときに注意しておきたいポイントなどをご紹介します。
夫婦カウンセリングとは

夫婦カウンセリングとは、夫婦関係で生じた亀裂を修復したり、今後夫婦が歩むべき方向性などについてカウンセラーへ相談し、アドバイスを受けるカウンセリングのことです。
夫婦カウンセリングは夫または妻の一方のみが相談に訪れるケースもあれば、夫婦揃ってカウンセリングを受けるケースもあります。
カウンセラーは夫婦の間に立って中立的かつ公平な立場で判断するため、客観的な第三者の視点から有効なアドバイスが受けられます。
夫婦カウンセリングの目的

夫婦カウンセリングを受ける目的は、大きく分けて夫婦間でのトラブル解決と関係向上があります。
夫婦間のトラブル解決
夫婦間で特に多いトラブルとして、以下の3つが挙げられます。
モラハラ・DV
夫から妻、あるいは妻から夫に対して、日常的に暴言・暴力が繰り返されている場合、夫婦カウンセリングを受けることで夫婦関係の修復につながる可能性があります。
浮気・不倫
浮気や不倫といった不貞行為に悩んでいる場合、基本的には夫婦間で話し合いが必要になります。
このような行為が繰り返される場合は夫婦カウンセリングを受けることで、第三者の立場から今後の方向性についてアドバイスを受けられます。
金銭トラブル
夫婦で貯蓄していたお金を夫または妻が無断で使い込んでしまったり、生活費をギャンブルやお酒に費やしてしまうなどの金銭トラブルも少なくありません。
夫婦カウンセリングを受けることでお金の使い方を見直したり、トラブルの具体的な解決策をアドバイスしてもらえることもあります。
夫婦の関係向上
上記のような深刻なトラブル以外でも、夫婦カウンセリングは有効です。
日常生活のちょっとしたすれ違いや、気になっていることを解消し、夫婦関係をより良いものにするために役立つケースもあります。
上記のような深刻なトラブルだけでなく、日常生活のちょっとしたすれ違いや気になっていることを解消し、夫婦関係をより良いものにするために夫婦カウンセリングが役立つケースもあります。
会話の頻度
仕事や家事が忙しい毎日を送っていると、夫婦での会話が自然と少なくなっていくことも珍しくありません。
夫婦カウンセリングを受けることで会話の頻度が増え、夫婦の絆が強くなることもあります。
スキンシップ
セックスレスなどスキンシップ不足が原因で、夫婦仲が悪化することもあります。
お互いにとって心地良いと感じるスキンシップの方法を、夫婦カウンセリングを通して学ぶことができ、お互いの愛情に気づくきっかけにもなるでしょう。
家事・育児について
家事や育児の負担が偏っていると小さな不満が積もっていき、夫婦仲が悪化する原因になります。
第三者のカウンセラーが同席する場で家事や育児についての不満を打ち明けることで、冷静な話し合いができ今後の方向性も見えてくるでしょう。
夫婦カウンセリングのメリット

夫婦関係を改善するためにはさまざまな方法がありますが、そのなかで夫婦カウンセリングを受けるメリットは何があるのでしょうか。
主なメリットとして以下などが挙げられます。
- 第三者視点からのアドバイスをもらえる
- 知人には話しづらいことを相談できる
- 今後に向けて建設的な話ができる
これらのメリットについて解説しましょう。
第三者視点からのアドバイスをもらえる
夫婦カウンセリングの場には、公平な立場からさまざまなアドバイスを行う第三者の専門家が参加します。
感情に流されず、問題を客観的かつ冷静に分析してくれるため、夫婦がそれぞれ相手の立場を理解しやすくなります。
また、自分たちが気づいていない視点や、解決策を提供してくれることも期待できるでしょう。
知人には話しづらいことを相談できる
夫婦間の悩みは非常にデリケートな問題も多く、親しい友人や自分の親・きょうだいに対しても打ち明けられないこともあるでしょう。
カウンセリングはほかの人に聞かれることのない、プライバシーが確保された環境で行われます。
また、カウンセラーも多くの夫婦の問題を解決してきたプロであり、どのような問題・悩みであっても受け止めてくれます。
この安心感の中で、お互いの深層心理や根本的な問題に迫ることができ、解決の糸口を見つけられる可能性があります。
今後に向けて建設的な話ができる
夫婦カウンセリングでは過去に起こった事実だけでなく、今後どうしていくかといった将来に向けても焦点を当てます。
夫婦はお互いに今後どうなっていきたいのか、将来への期待や願望を共有し冷静に対話することができます。
関連記事:夫婦の円満を保つ秘訣|冷めていく夫婦の共通点とは?
夫婦カウンセリングを受ける際のポイント

せっかく夫婦カウンセリングを受けても、その心構えができていなければ、冷静な話し合いができずに終わってしまいます。
夫婦カウンセリングを受ける際にはどういった点に注意すべきなのでしょうか。
主な注意点として以下などが挙げられます。
- 感情的にならない
- 相手の話に耳を傾ける
- できるだけ夫婦揃って受ける
- どんな夫婦が理想的か共有する
これらの注意点について解説していきます。
感情的にならない
カウンセリングでは夫婦が抱える核心的な問題に切り込むこともあり、つい感情的になって暴言を吐いたり、お互いに激しい口論に発展するケースも少なくありません。
しかし、これでは冷静な話し合いができず建設的な対話が進みません。
どのような話題に対しても感情的にならず冷静さを保つことを意識し、カッとなりそうになったら深呼吸をして落ち着きを取り戻しましょう。
相手の話に耳を傾ける
カウンセリングではお互いの意見や感情を尊重し合うことが大切です。
たとえば、相手が話している最中に割って入ってしまうと、そこから口論がヒートアップするケースもあります。
相手の話に最後まで耳を傾け、理解しようとする姿勢がコミュニケーションの改善に繋がります。
できるだけ夫婦揃って受ける
夫婦カウンセリングは夫または妻の一方が相談に訪れるケースもあります。
特にDVやモラハラに悩んでいる場合、はじめから夫婦二人でカウンセリングに訪れるのは難しいことも多いでしょう。
しかし、カウンセリングは夫婦の共同作業であり、お互いが同じ情報を共有することが重要です。
できるだけ揃ってカウンセリングを受けることで、お互いの認識のズレを修正し、夫婦関係の改善に向けて一貫性のあるアプローチが可能です。
夫または妻の一方だけが出席する場合でも、2回目、3回目のカウンセリングには夫婦揃って参加する方法を模索してみましょう。
どんな夫婦が理想か共有する
夫婦カウンセリングは、夫婦の問題や愚痴を言い合う場ではなく、今後どうなっていきたいのか理想像を話し合い、共有することが大切です。
未来に向けた前向きな話し合いをすることで、夫婦が目指す具体的な目標や期待を共有し、より具体的なアクションプランを立てやすくなります。
関連記事:夫婦喧嘩でやってはいけないこととは?子供への悪影響も解説
夫婦カウンセリングは意味ない?効果なし?

夫婦カウンセリングにはさまざまなメリットがある一方で、「カウンセリングを受けても効果がない」、「意味がない」といった意見を目にすることもあります。
そもそも夫婦カウンセリングは、夫婦揃ってカウンセラーに相談したりアドバイスを貰ったりすることが大切です。
どちらか一方だけがカウンセリングを受けても、十分な効果が得られないことも多いのです。
また、たとえば妻が夫婦関係を改善したいと考えていても、夫にその意志がないとカウンセリングを受けても思うような効果が得られないこともあるでしょう。
さらに、カウンセリングを受ける側の問題だけでなく、カウンセラーの質や相性も重要です。
相談者が話す内容を最後まで聞いてくれなかったり、相談者の人格を否定するようなカウンセラーに当たってしまうと、カウンセリングを受けたことを後悔する人もいるようです。
夫婦カウンセリングの口コミを紹介
実際に夫婦カウンセリングを受けた人は、どのような感想・印象を抱いているのでしょうか。いくつか口コミをご紹介します。
新婚の夫婦関係を改善する糸口が見つかった
「新婚であるにもかかわらず、夫婦喧嘩が絶えず悩んでいました。
すごく分かりやすく説明していただけたので、やるべきことがクリアになって目の前が開けたような気分です。教えていただいたことを真剣に実行してみます。」
夫婦関係の悩みで混乱した状態でも真摯に話を聞いてくれた
「ずっと夫婦関係のことで苦しんでいました。不安で辛くて悲しくて、正直死んだ方がマシだと思うほどでした。
そんな状態で電話をもらったのですが、今まで思っていたことを180度変えられるようなお話でびっくりしました。
苦しくて苦しくて胸につかえていたものが取れたような感覚で涙が出そうでした。こんなに心がふっと軽くなったのはいつぶりでしょうか。
ずっと優しく包み込むような声で話してくださりました。
私の話は思い出した事をあれこれと話していたので、支離滅裂なところもあったかもしれませんが、落ち着いて話もできました。本当に救われた気持ちです。」
穏やかなカウンセラーが丁寧かつ親身になって答えてくれた
「カウンセラーの雰囲気がとても穏やかで癒やされました。
まだ自分の心の中で浄化されてない気持ち(悲しかったり、自分への癒やしなど)もあるので100%頑張りますとは言えません。
しかし、できる限り自分を大切にするというのと、相手に居心地の良い場所を作る努力はしてみようと思います。
1つずつの質問にも丁寧に答えて頂いて助かりました。とても親身になってアドバイスしてくださり、嬉しかったです。
またこれから何かあれば、メールでお話をきいてくださるということもとても助かります。」
まとめ
夫婦間が抱える問題やトラブルは親しい人に対しても相談しにくく、一人で悩みごとを抱え込んでしまう人も少なくありません。
特にモラハラやDV、不貞行為、金銭トラブルなど深刻な問題は早急に対処しなくてはならず、対応が遅れるほど深刻化していきます。
「誰に相談すれば良いのか分からない」、「身近な人に心配をかけたくない」などの悩みを抱えている方は、夫婦カウンセリングを受けてみるのもひとつの方法といえるでしょう。
信頼できるカウンセラーを探すためにも、実際にカウンセリングを受けた人の口コミや感想も参考にしてみてください。
相談2:スクリーンタイム(テレビの見過ぎ)の悩み (7歳〜小学生高学年向け)

読者からの相談:
子どものスクリーンタイムについて悩んでいます。
子どもがテレビやスマートフォンを見る時間が長すぎないかと心配しています。
そのため、最近は「テレビを見る時間は1日30分まで」と決めています。
最近では子どもたちが外から帰ってくると「30分見ていい?」朝起きると「30分見ていい?」と聞いてくるようになりました。
テレビの時間を制限することで、子どもがさらにテレビに執着しているような気がします。
子どものスクリーンタイムの悩みをどうしたらいいか知りたいです。
ジョアンナさん:
これはよく聞く悩みで、多くの親や教師たちにとっても大きな関心事です。
スクリーンタイムが長すぎることは若者の健康に良くないことは多くの人がわかっていますが、この課題にどうやって対応すればいいかは、よく議論になりますね。
この問題に悩んでいる多くのご両親に私は強く共感します。
「スクリーン」(テレビ、スマートフォン、アイパッド、電車の中や街角の広告など)に囲まれた生活をしている現代社会において、この問題の解決は簡単ではありません。
良質なスクリーンタイムとは何かを判断するのも難しいですよね。
例えば親戚とのフェイスタイムならいいのか?教育番組を見るのは良いのか?など。こういうのもスクリーンタイムですからね。
米国小児科学会(American Academy of Pediatrics)は、1歳半未満の子どもにはスクリーンタイムを一切与えないことを推奨しています。
また、2歳から6歳までは(教育番組のような)「質の高い」スクリーンタイムを1時間以内にすることを推奨しています。
忙しくて疲れている親が、テレビに子守りをしてもらいたいと思う気持ちはわかります。
でも、それによって生じる、子どもの成長と発達への代償はあまりにも大きすぎるのです。
幼い子どもたちがスクリーンばかり見過ぎることは、子どもたちから自分で何かを作り出す力、想像力を奪うことになります。
こういうことを踏まえると、スクリーンタイムを30分に制限することは、とても合理的なことだと思います。
親として最も大切な役割は、子どもに明確なルールをしっかりと示すことです。
子どもは、その時その時に欲しいものを手に入れるために、あらゆる努力をするものです。
駄々をこねて泣いてみたり、叩いてみたり、もっと勉強するからと交渉をしてきたり。これに対して怒る必要はありません。
子どもは親と一緒に決めた約束事を守ることを続ける中で、いずれ自分や物事の限界を知り、良い決断をすることについて多くを学んでいくからです。
30分という制限を与えることで、子どもたちは、いつスクリーンタイムを使うかの判断について学ぶことができます。
もしかしたら、子どもが朝一番にその日のスクリーンタイムを使い、夕方にはスクリーンタイムがないことにがっかりしたり、怒ったりするかもしれません。
その場合は、子どもの残念だと思う気持ちにまず共感をしてあげてから、明日は違う選択をしてもいいかもしれないと話し合う機会にすればいいのです。
最初のうちは、子どもが不満に思うかもしれません。
でも 「ルールは守らなければならない」ということをあなたがはっきりとした態度で示し続ければ、そのうち子どもは否定的な反応は止めるでしょう。
制限を設けることは「自分の」時間をいつ使うかを子どもにある程度コントロールさせることになります。
つまり、子どもがある程度のコントロールと自主性を持つことができるということです。
また、あなたがいう「執着」は、「スクリーン」がいかに中毒性のあるものであるかを示していますね。
スクリーンタイムが終わると、とにかくまたやりたくなるということも研究結果でわかっているそうです。
スクリーンの中毒性を考えると、これからの人生において、様々な依存性のあるものから距離をとる練習になるかもしれません。
タイマーをかけたり口頭で「あと5分」「あと1分」と知らせてあげると、次のことに移行することが難しい子どもには大きな助けになります。
また、30分をスタートする前に、スクリーンタイムが終わったら何をするのかを先に考えて気持ちの準備をしてから遊び始めるのも効果的です。
私の子どもたちは、大人になってから、子ども時代に家にテレビがなかったことを私に感謝してきました。
幼い頃、常にテレビに接していた友人たちが、やることを思いつかず手持ち無沙汰な時間を過ごしていました。
その間、私の子どもたちは自分たちに無限の想像力や発明力があることに、よく驚いていました。
スクリーンタイムに固執しなかった私の子どもたちは、決して「退屈」することはなかったんです。
もうひとつ伝えたいことがあります。それは私たち大人がスマートフォンという「スクリーン」にどれだけの時間を費やしているかということです。
小さな子どもたちは、親がいつもスクリーンを見ているのに、なぜ自分だけが制限されるのだろうと不思議に思っています。
あなた自身がどれくらいスクリーンタイムを使っているのか、それが子どもにどのような影響を与えているのか、考えておくとよいでしょう。
子どもは模倣の生き物ですから、自分の鏡のような存在だと思っておくといいでしょう。
体を動かすゲームや遊び、自転車に乗ること、パズル、アートプロジェクト、本を読むこと、音楽を聴くことなどは、子どもたちが楽しめる最適なアクティビティですね。
こういった活動は、大人になっても自由な時間を楽しく過ごすための良い習慣として続くでしょう。

子どもたちは、とても想像力豊かな生き物です。
ただの段ボール箱ですら、とてもクリエイティブなものに変身させることができます。
家、レストラン、車、船、消防車、診察室、学校の部屋、ロケット、ホテルなど、私自身が、段ボールで作られた数え切れないほどの作品を見てきました。
私たちは、子どもたちの大きな創造力を奪うことはしたくはありません。
人間の脳が受け身な状態を作り出すスクリーンタイムに多くの時間を費やすのは、子どもにとって多くのリスクがあります。
子どもの心と体に秘められている大きな可能性を全力でサポートしていきましょう!
最後に、段ボールにまつわるすばらしい思い出を共有させてください。
私はあるプロジェクトで家にテレビがない子どもたちのために、大きな段ボールでテレビをつくったことがあります。
この時に子どもたちはすべてのテレビ番組を自分たちで制作しました!
私たち大人は子どもの作ったニュース、バラエティ、ダンス発表会の番組の鑑賞会に招待されました。
手作りの衣装や小道具がどんどん増え、番組はより手のこったものになっていきました。大きな創造力に私たち大人の心は温まったものです。
子育ては非常に難しい仕事です。大人はいつも試されているのです。
自分が正しい育児の道を歩んでいると思ったら、自信を持ってしっかりと歩めばいいのです。
目先の楽さや、大変さ、その場しのぎに言うことを聞かせたり、周りの目にこだわるより、大切なことがあります。
子どもをクリエイティブで、バランスのとれた優しい人間に育てるという長期的な目標も持つことが、何よりも大切なのです。

ジョアンナ・ウィギントン氏
助産師として600人以上のお産に携わる。
教育者であり、アーティスト。北カリフォルニア在住。
20年以上にわたりオルタナティブ教育施設であるカスパー・クリーク・ラーニング・センターを創設・指導してきた。
現在はNPO組織Flockworksの活動に参加し、子供や教師をサポートしている。アートの力を広めるためのプログラムを展開中。
すべての人がアーティストであるという強い信念を持ち、若者から年配の人までが創造力を探求する機会を作り出している。
関連記事:相談1:子供の心を垣間見る方法 (3歳〜小学生低学年向け)
夫婦の円満を保つ秘訣|冷めていく夫婦の共通点とは?

「最近、夫婦喧嘩が増えてきた」、「夫(妻)の考えていることが分からない」など、夫婦関係に悩みを抱く方は少なくありません。
夫婦仲が冷めていく原因は人それぞれですが、ある共通点が見られることも多いものです。
本記事では、なぜ夫婦関係は悪化していくのか、円満な夫婦関係を維持していくための秘訣も合わせてご紹介します。
円満な夫婦の特徴とは

夫婦関係を円満に保つにはどういったことが大切なのでしょうか。
円満な夫婦に共通して見られる特徴についてご紹介します。
お互いの価値観を尊重している
どれだけ親しい人であっても、自分と全く同じ価値観や考えの人は存在しません。
自分の価値観を押し付けてしまうと、相手の反発を招き夫婦関係にも亀裂が生じることがあります。
お互いに価値観や考えが異なることを理解し尊重し合うことが大切です。
日頃から感謝を伝えている
長い間夫婦生活を共にしていると、「ありがとう」という言葉を伝えなくても相手は分かってくれているだろうと考えがちです。
しかし、言葉にしなければ気持ちは伝わらないことも多いため、感謝の気持ちを言葉にすることが大切です。
思ったことは言葉にする
感謝の気持ちだけでなく、相手に対する愛情や尊敬している部分、あるいは直してほしいところなど、思ったことや感じたことがあれば言葉として伝えましょう。
円満な関係を維持しやすくなります。
二人だけで過ごす時間を持っている
子どもができたり毎日の仕事で忙しい日々を送っていると、夫婦という関係性が徐々に薄れていくことがあります。
そのため、結婚記念日やお互いの誕生日などの記念日だけでも二人で過ごす時間を作ることが大切です。
お互いを信頼しあっている
夫婦として支え合って生活していくためには信頼関係が不可欠です。
相手のことをあえて深く詮索せず、信頼していると示すことにより、相手も「この人のことを裏切ってはいけない」と感じ、理想的な夫婦関係が維持できます。
スキンシップをとっている
夫婦関係を維持するうえで日々のスキンシップは重要です。
相手に直接触れることで愛情を再確認し、円満な夫婦関係が維持できているというケースは少なくありません。
喧嘩しても引きずらない
長い夫婦生活を送っていると、価値観や考え方の違いから喧嘩になることもあるでしょう。
一度も喧嘩をすることなく穏やかな生活を送れているという夫婦は圧倒的に少ないはずです。
それでも円満な関係を維持できているのは、喧嘩をしたとしても長く引きずることなく、お互いが歩み寄っている夫婦が多いためです。
それぞれに趣味がある
夫婦関係に限ったことではありませんが、相手に対して興味を抱くことは、良好な人間関係を維持するための基本といえます。
お互いのことに興味をもっている夫婦は、髪型やファッションなど些細な変化にも気づきやすいです。
「女(男)として見られている」という意識が働くと、円満な夫婦関係を維持しやすいものです。
記念日を大切にしている
結婚記念日や誕生日など、大切な記念日を忘れることで、夫婦関係に亀裂が生じるケースは少なくありません。
相手のことを大切に思っている夫婦は、記念日に食事をしたり外にデートに出かけたりすることが多いものです。
夫婦仲がギクシャクする原因は?

夫婦仲がうまくいかない、ギクシャクしていると感じる原因はさまざまですが、代表的なものをご紹介しましょう。
夫が家事や育児に非協力的
夫または妻が家事や育児に協力的でないと、夫婦のどちらかに負担が偏りがちになります。
日々の暮らしのなかで小さな不満が溜まっていくと、相手に対して些細なことで腹を立てるようになり、夫婦仲が徐々に悪化していきます。
金銭的な事情
十分な収入が得られないと生活費を切り詰めていかなければならず、なかには結婚したことを後悔するケースもあるでしょう。
相手を非難するような発言がある
相手の人格を否定する言葉を投げかけることはモラハラにあたり、夫婦の信頼関係を構築することも難しくなります。
本人にしてみれば何気なく発した一言のつもりでも、相手は大きく傷つき夫婦関係に亀裂を生じさせるケースもあります。
金銭感覚の違い
十分な収入を得ていたとしても、金銭感覚の違いが結婚後に発覚するケースもあります。
たとえば、ギャンブルに毎月大金を注ぎ込んでいたり、外食や交際費に多額の支出があると、夫婦生活を続けていくことに不安を感じ関係が悪化することもあります。
浮気・不倫の発覚
浮気や不倫が発覚したとき、相手のことを信頼していただけにそのショックは大きいものです。
それまでの夫婦生活は何だったのかと絶望し、この先夫婦関係を維持していくことはできないと判断することもあるでしょう。
関連記事:夫婦仲が悪い原因は?子供に与える影響や改善する方法をご紹介
冷めていく夫婦の共通点

上記とは反対に、関係が冷めていく夫婦にはどういった共通点が見られるのでしょうか。
コミュニケーションが少ない
夫婦生活が長く続くと、お互いが当たり前の存在になり、コミュニケーションが自然と減っていくケースも少なくありません。
しかし、会話の量が少ないと夫婦といえども相手が何を考えているのか分からなくなり、心理的な距離が広がっていくことも多くなります。
あいさつや感謝の言葉がない/少ない
コミュニケーション不足とも関連しますが、毎日のあいさつや感謝の言葉が少なくなることもポイントとして挙げられます。
「おはよう」、「ただいま」、「ありがとう」といった一言はコミュニケーションのきっかけにもなります。
この一言が出てこないと、自然とコミュニケーション不足に陥ってしまいます。
共通の趣味や話題がない
夫婦の間で趣味や価値観が合わないと、盛り上がる共通の話題もなく自然と会話が続かなくなります。
会話を引き出そうとして話題を振っても、そもそも相手が興味を抱いていないと鬱陶しく感じ、ますます冷え切った夫婦仲になることもあるでしょう。
愛情が一方通行になっている
夫婦の一方が愛情を抱いていたとしても、相手がそれに応じない場合、夫婦関係のバランスが崩れてしまいます。
やがてその愛情が鬱陶しく感じたり、重いと感じたりして夫婦仲が冷めていくこともあるでしょう。
勢いで結婚してしまった
冷静な考えや相手に対する深い理解がないまま、感情の勢いで結婚した場合、その後の生活を続けるなかで問題が浮き彫りになり、関係が冷めることがあります。
義理の家族との関係性が悪い
相手の両親やきょうだい、親族と良好な関係を築くことができないと、自然と距離を置きたくなるものです。
配偶者にしてみれば、自分の家族をないがしろにされた気分になり夫婦仲に悪影響を及ぼすこともあるでしょう。
関連記事:セックスレスの離婚率はどれくらい?レスにならないための方法とは
夫婦の円満を保つための秘訣

円満な夫婦関係を保っていくためには、どういった点に注意すれば良いのでしょうか。
日頃から実践したい秘訣をご紹介します。
会話する時間を増やす
どんなに些細なことでも、夫婦で会話を交わす時間を増やしましょう。
たとえば、「今日仕事でこんなことがあった」、「子どもがこんなことを言っていた」、「◯◯というテレビ番組が面白かった」など、話題は何でも構いません。
そこからさまざまな話題に発展しコミュニケーションのきっかけとなるでしょう。
お互いに干渉しすぎない
たとえば、残業で帰宅が遅くなった相手に対し浮気を疑うような言動をしてしまうと、お互いに不信感が生まれ信頼関係が崩れてしまいます。
信頼し、あえて深い詮索をしないことで「この人を裏切ってはいけない」という気持ちが芽生え、円満な夫婦関係が維持しやすくなります。
日頃から感謝の言葉を伝える
「ありがとう」という感謝の言葉を意識的に投げかけてみましょう。
感謝の言葉を掛けられて不快になる人はおらず、夫婦仲を改善するための第一歩にもなります。
最初の一言を発するには勇気が要ることもあると思いますが、繰り返し投げかけることで信頼関係が構築され、夫婦円満につながっていきます。
相手を思いやる
相手を尊重し思いやる気持ちも夫婦円満の重要な秘訣です。
自分と異なる意見や考え方で対立したとき、なぜそのような意見をもつのか相手の立場で考えてみましょう。
スキンシップをとる
長い夫婦生活のなかでセックスレスになることも珍しくありませんが、そのような場合でも手を繋いだりハグをしたりすることが習慣になっている夫婦も多いです。
一緒に食事をする
コミュニケーションの場として食事の時間は特に重要です。
仕事が忙しいときでも、相手の帰宅に合わせて食事をとるなど、できるだけ落ち着いて話せる場を設けましょう。
二人で過ごす時間を作る
より夫婦の仲を深めるためには、二人きりの時間をつくることも心がけましょう。
休日は二人で食事やドライブに出かけたりすることで、独身時代を思い出し夫婦の愛情が深まっていくこともあります。
記念日を大切にする
結婚記念日や誕生日など特別な日は夫婦二人でお祝いを欠かさないようにしましょう。
仕事や家事、子育てに忙しい毎日を送っていると記念日を忘れがちになりますが、スマホのカレンダーに登録しておくなどの工夫も有効です。
お互い一人の時間も大切にする
夫婦といえどもつねに一緒の生活を送っていると、精神的に疲れてくることもあります。
そこで、あえて一人の時間をつくることで適度な距離感が生まれストレスのない生活を送ることができます。
一人で過ごせる書斎や趣味の部屋をつくったり、一人で散歩やショッピングに出かけたりするのも気分転換になるはずです。
喧嘩してもすぐに仲直りする
些細なことで喧嘩をしたとしても、後に引きずることなくすぐに仲直りをするよう心がけましょう。
相手が折れないと感じたら、ときには自分から謝ることも大切です。
関連記事:夫婦関係を修復するためのきっかけ|絶対にやってはいけないこととは?
夫婦円満の秘訣に関する名言を紹介
最後に、夫婦円満のために覚えておきたい言葉をいくつかご紹介します。
ゲッターズ飯田(お笑いタレント・占い師)
「『頼れる』と思って一緒になったら、頼りないのが男で、『弱い』と思って一緒になったら、強いのが女ってもの。」
笑福亭鶴瓶(落語家・お笑いタレント)
「ハッピーワイフ、ハッピーライフ」
所ジョージ(お笑いタレント・シンガーソングライター)
「俺が妻と結婚したのは、妻の笑顔が長い時間みたいから。
今、妻を笑顔にしてあげられていないなら、笑顔にしてあげられていない俺がすべて悪い。」
岡本太郎(芸術家)
「自分の惚れた女にケチするヤツは許せない。」
フグ田マスオ(「サザエさん」登場キャラクター)
「たまには羽を伸ばしておいで。タラちゃんは僕がみるよ。」
野原しんのすけ(「クレヨンしんちゃん」主人公)
「悪いことしたら、ごめんなさいって言うんだゾ。幼稚園じゃみんなそうしてるゾ。」
まとめ
お互いに信頼し愛情をもって暮らしている夫婦でも、些細なことで言い合いになったり大喧嘩に発展することもあるでしょう。
このようなトラブルが頻繁に繰り返されると、徐々に夫婦仲は冷え切っていき最悪の結末になることも予想されます。
円満な夫婦関係を維持していくためにも、今回ご紹介した秘訣を参考に普段の生活を見直してみましょう。
脱・依存体質。自分の価値や幸せは自分が決めるもの

大好きな彼と一緒に暮らしはじめて幸せの絶頂。それなのに、なんだか胸騒ぎが止まらない。
毎週金曜日、彼は飲みに出かけたまま朝帰りをする日が増えた。いけないとわかりつつ、こっそり彼の携帯に手を伸ばした。
そこにはとある女性とのやりとりが残っていた。
「ずっと大好きだよ」
このメールを見た瞬間から彼のことが信じられなくなった。いや、だいぶ前から「もしかしたら……」と疑っていたのだ。
不安が確信に変わって以降、連絡がつかない時は不安になって鬼のように彼に電話をした。不安を消すために、友達との約束を断って、できる限り彼と一緒に過ごすようになった。
そんな日々から10年以上たった今。当時を振り返って思うのは、自分自身が彼に依存していたということだ。
誰かへの依存は、相手の心を引き離し、自分自身を苦しめるのだ。
誰かに依存していると、常に不安がつきまとう
「依存」とは、「他に頼って存在、または生活すること」を意味します。
依存体質になってしまうと、他者から評価されることで自分の価値を見出し、安心感を得るようになります。
さらに、他者の期待に応えようとするあまり、過度に承認を求めたり、尽くした相手から見返りがないと不安を感じてしまうのです。
例えば、一緒に暮らす彼のために美味しいご飯を作って待っていたのに、彼から「今日は飲みに行くから帰りが遅くなる」と連絡が入った場合。
恋愛に依存していると「あなたのために頑張ってご飯を作ったのに、食べてくれないなんてひどい。私は大切にされていないんだ……」と気持ちが落ち込みます。
さらに、彼の帰りが遅くなるほど、誰とどこにいるのかが気になり不安で何も手につかない。
夢中になれるほど好きな人がいるのは素敵なことです。
しかし、他者に過度に依存することで、自分の心の安定が他人次第となり、常に不安がつきまとうようになります。
自信のなさや未来への不安が依存の引き金に

人はどうして誰かに依存してしまうのでしょうか?
「私には彼しかいない」
「彼と別れてしまったら、この先結婚できないかもしれない」
「離婚したら生活できない」
など……、多くの場合は、自信のなさや未来への不安から生じるのではないでしょうか。
脱・依存体質。自分の幸せは自分で決めよう
では、自分に自信を持ち、未来への不安を減らすためにはどうしたら良いのでしょうか。筆者の体験談を踏まえてご紹介します。
自分磨きをする
「変えられるのは自分だけ」とよく言いますよね。他人に変化を求めるのは想像以上に難しいこと。だからこそ、向き合うべき相手は自分自身です。
例えば、毎日フェイスパックをしてスキンケアに力を入れてみるとか、毎朝10分でも良いから運動して心と体を整えるとか、英語の勉強をしてスキルを身につけるとか。
継続して変化が現れることで、少しずつ自分に自信が持てるようになるかもしれません。
夢中になれるものを見つける
誰かのためにではなく、自分のために夢中になれることを見つけましょう。
大切なことは
彼のために料理をがんばりたい
子どものために働き方を変えたい
など、誰かのためにではなく、「自分のために」夢中になれることを見つけることです。
楽しさややりがいを感じる趣味を見つけることで、誰かに依存しなくても充実感が得られるでしょう。
自分で生きていけるだけの経済力を身につける
「夫婦関係がうまく行かずに離婚を考えているけれど、仕事をしていないから経済的にパートナーを頼るしかない」
そのようなお悩みを抱えている方もいるかと思います。
もしあなたが収入がないことに少しでも不安を感じているのなら、自分で稼ぐ力を身に着けることが大切です。
もちろん、なんらかの理由があって外に働きに出るのが難しい方もいるでしょう。
しかし、今の時代、スマートフォンやパソコンさえあればできることがたくさんあります。
すぐに収入に繋がることが難しくても、ブログを書いてみたり、SNSで好きなことを発信してみたり、ハンドメイドが得意であれば出品してみたり。
できる範囲で未来の自分への投資をすることで、少しずつ自信がつき、未来への不安が和らぐでしょう。
遠い未来ではなく、今に目を向ける
誰しも未来のことはわかりません。だからこそ、遠い未来のことを心配しすぎるよりも、今の自分にとっての幸せを考えてみましょう。
「笑う門には福来たる」というように、今の自分がご機嫌でいることで、素敵なご縁やラッキーが舞い込んできて、未来が良い方向に変わっていく可能性があります。
自分の中に幸せの軸を持つ
誰かに合わせすぎたり、相手の都合の良いように動くと、自分自身が消耗して辛くなります。
自分以外の誰かに依存するのではなく、自分の中に幸せの軸を持つ。そして遠い未来よりも今を大切に生きる。
人生で1番長く共に過ごすのは、自分自身です。まずは自分を大切に。
自分が幸せになる方法を追求するのはわがままなことではありません。自分を大切にできるからこそ、自分の大切な人を思いやることができるのではないでしょうか。
夫婦喧嘩でやってはいけないこととは?子供への悪影響も解説

夫婦生活を送っていると些細なことが理由で口論をしたり、夫婦喧嘩に発展することもあります。
長く円満な夫婦生活が続く時期もあれば、「最近夫婦喧嘩が増えてきた」と感じる時期もあるのではないでしょうか。
そのようなとき、できるだけ早期に仲直りをするにはどういった方法があるのか、また、夫婦喧嘩が子供に与える影響なども併せてご紹介します。
よくある夫婦喧嘩の原因

夫婦喧嘩はどのようなことが発端で起こることが多いのでしょうか。
お互いの性格や考え方などによって原因はさまざまですが、典型的なものとして以下などが挙げられます。
- 家事の分担
- 家計に関すること
- 子育てに関すること
- 相手の話し方や態度
- 家族や親族の問題
- 些細なこと
これらの原因についてご紹介しましょう。
家事の分担
共働き世帯が増えている昨今、特に多く聞かれるのが家事の負担割合などに関する夫婦喧嘩です。
たとえば、残業で帰宅が遅くなったにも関わらず、先に帰宅していた夫または妻が食事やお風呂の用意をしていなかったりすると口論になることも珍しくありません。
反対に、平日は仕事が忙しいからとはいえ、休みの日に家のことを一切何もせずゴロゴロしているだけの夫に妻が不満を募らせるといったケースもあるでしょう。
家計に関すること
結婚生活ではお互いの金銭感覚のズレが原因となって夫婦喧嘩に発展することもあります。
たとえば、ブランド物の洋服やアクセサリー、家電製品、趣味の物など、高額な商品を相談することなく購入するとトラブルに発展することもあるでしょう。
夫の行き過ぎた飲み会への出費やタバコ、パチンコ、競馬なども家計を脅かす要因となることが多いです。
子育てに関すること
子育てに関する方針や考え方の違いも夫婦喧嘩の原因となることがあります。
子どもの将来を思うあまり、本人が希望していないのに習い事や塾に通わせたり、進学先や就職先を決めたりするケースもあるようです。
もう一方の親が子供の意思を尊重したいというタイプである場合に、対立してしまうことが予測されます。
相手の話し方や態度
話を聞く真摯な姿勢が見られないと、自分の話をきちんと聞いてくれているのか不安になることもあります。
また、本人にそのつもりはなくても、相手のことを見下したり小馬鹿にしたような態度に見られることもあり、それが夫婦間に亀裂を生じさせるケースがあります。
家族や親族の問題
お互いの両親や親族などが原因で夫婦喧嘩に発展することも決して少なくありません。
たとえば、配偶者に対して相談をしないまま両親と同居することを決めたり、配偶者に対して自分の両親の介護を押し付けたりするケースが代表的です。
些細なこと
客観的に見れば些細なことが夫婦喧嘩の引き金になるケースは多いものです。
たとえば、自分のために買ってきた飲み物や食べ物を勝手に開封された、趣味のコレクションに勝手に触られた、誤って食器を割ってしまったなどです。
このようなケースでは、日頃の小さな不満が積み重なり、ある日突然些細なことが引き金となって夫婦喧嘩に発展することが多い傾向にあります。
関連記事:夫婦仲が悪い原因は?子供に与える影響や改善する方法をご紹介
夫婦喧嘩で仲直りする方法

夫婦関係を円満に保つために、もし夫婦喧嘩が発生したらどのように仲直りをすれば良いのでしょうか。
仲直りする方法として以下などが挙げられます。
- 自分から先に謝る
- 自分から話しかける・挨拶をする
- スキンシップをとる
- 相手の好きなものを買ってくる
ここからは、仲直りする方法についてご紹介しましょう。
自分から先に謝る
夫婦喧嘩が起こったとき、自分から謝るのは気が引けてしまい、ズルズルと不機嫌な態度を長引かせてしまうことがあります。
しかしたいていの場合、夫婦喧嘩はどちらかが一方的に悪いというわけではなく、お互いにそれぞれ原因があることが多いものです。
客観的に自分を振り返り、悪い部分があった場合には素直に謝ることが大切です。
自分から話しかける・挨拶をする
喧嘩中はお互いに気まずい雰囲気になり、無視をしたり視線を合わせなかったりする時間が続いてしまいます。
このような状態を打破するためには、あえて自分から積極的に話題を振ったり挨拶をしたりすることも有効です。
たとえば、「おはよう」や「ただいま」、「今日のご飯は何が食べたい?」など、自然な日常会話を心がけましょう。
スキンシップをとる
素直な謝罪とコミュニケーションで心を開けるようになったら、スキンシップをしてさらに距離を縮めていきましょう。
たとえば、仲直りの印として握手をしたり、「ごめんね」と素直に謝ったうえでハグをしたりするのも有効です。
ただし、挨拶をしても相手が無視しつづけていたり、不機嫌な態度が続くようであれば無理なスキンシップは逆効果になる可能性もあるため注意が必要です。
相手の好きなものを買ってくる
誠意のある謝罪の仕方として、相手の好きなものを買ってくる方法もあります。
たとえば、ケーキなどのスイーツやお酒、あるいは外食に誘ってみるのも良いでしょう。
ただし、こちらもスキンシップと同様、謝罪の言葉がないままプレゼントだけを贈っても、「モノで釣ろうとしている」と感じられ逆効果になる可能性があるため注意しましょう。
関連記事:夫婦関係は修復できる?よくある破綻のきっかけや修復方法を紹介
夫婦喧嘩で仲直りをするときにやってはいけないこと

上記とは反対に、仲直りをするためにやってはいけないNG行動があります。
- 自分を押し通す
- 相手を論破しようとする
- 一時の感情で離婚を口にする
これらのやってはいけないことについて紹介しましょう。
自分を押し通す
夫婦喧嘩の原因がたとえ相手にあったとしても、自分が正しいことを押し通すような態度では平行線に終わってしまいます。
たとえば、自分も相手に対して言い過ぎた部分はなかったか、強い口調で相手を否定しなかったかなど、反省すべき点がないかを振り返ってみましょう。
相手を論破しようとする
激しい口論となったとき、相手を言い負かそうとする人もいるのではないでしょうか。
しかし、論理的に反論したり正論で相手を追い詰めたとしても、元通りの夫婦関係に戻れるケースはきわめて少ないでしょう。
相手が論理的には納得したとしても、感情の面ではさらに大きな亀裂を生じさせる可能性もあります。
重要なのは相手を論破したり正論で言い負かしたりすることではなく、お互いに歩み寄り相手を理解しようとすることです。
一時の感情で離婚を口にする
激しい夫婦喧嘩でヒートアップしてくると、感情に身を任せるように「離婚」という言葉を口にしてしまうこともあります。
夫婦間において離婚というワードは極めて重く、最後のカードともいえます。
それだけに相手の口から離婚の言葉が出てきてしまうと、それを聞いた瞬間に一気に熱が冷め、愛情が失われていく可能性があるでしょう。
関連記事:モラハラ夫は特徴やどんな発言をする?対処法や子供への影響も解説
夫婦喧嘩が子供に与える悪影響

子どもがいる家庭で夫婦喧嘩が起こると、その姿を目にした子どもにさまざまな悪影響がおよぶおそれがあります。
具体的にどういった影響が考えられるのでしょうか。
- 親に対する恐怖心が生まれる
- 自分のせいで喧嘩をしているのだと感じる
- 心身の不調をきたす
ひとつずつご紹介しましょう。
親に対する恐怖心が生まれる
普段は子どもに対して優しく接しているにもかかわらず、夫婦喧嘩が始まると口調や声のトーン、表情などが一変し、子どもにとっては全く違う一面に映ることがあります。
これにより、子どもは「自分のパパとママは怖い人なんだ」と感じるようになり、親に対する恐怖心が生まれてしまいます。
自分のせいで喧嘩をしているのだと感じる
多くの場合、子どもはなぜ夫婦喧嘩をしているのか原因が分からず、戸惑ってしまうものです。
また、自分を放置したまま口論している姿を見ると、子どもは「自分は大切にされていない」、あるいは「自分のせいで喧嘩をしているのではないか」と不安に感じるケースもあります。
その結果、両親に対して甘えることができなかったり、自分の心を閉ざしてしまったりする子どもも少なくありません。
心身の不調をきたす
夫婦喧嘩によって心に大きな傷やトラウマができると、心身にさまざまな不調をきたすケースもあります。
たとえば、自分は周りの人に愛されないと感じると、友達とうまく遊べない、あるいはコミュニケーションをとることすらできなくなる可能性もあるでしょう。
また、ストレスから頭痛や腹痛、吐き気などの症状が現れることも珍しくありません。
関連記事:自己肯定感が低い子供の特徴や言動とは|注意すべき親の発言や行動
夫婦喧嘩をした後の子供に対するフォロー
子どもの前で感情的になり、夫婦喧嘩をしてしまったときにはどういったフォローが必要なのでしょうか。
もっとも重要なのは、子どもに対して真摯に謝ることと、気持ちを真正面から受け止めることです。
たとえば、「怖い思いをさせてごめんね」と謝った後で子どもを抱きしめたり、「あなたのせいで喧嘩をしたわけではないからね」と説明することも忘れないようにしましょう。
そのうえで、子どもが泣いている場合には「怖かったよね」、「嫌だったよね」といった言葉をかけながら、泣き止むまでその場を離れず寄り添ってあげてください。
まとめ
夫婦といえども自分の本心や考え方をすべて理解しているとは限らず、すれ違いが生じることで夫婦喧嘩に発展することもあります。
些細なことでの対立や喧嘩はどの夫婦にも起こり得るものですが、重要なのはいかに早く仲直りをして夫婦間の亀裂を修復できるかということです。
また、子どもがいる家庭では夫婦喧嘩がさまざまな悪影響を及ぼすことも考えられるため、子どもへのフォローも忘れないようにしましょう。
寂しさは自分と向き合うきっかけ。4つの解消法をご紹介

夫の転勤に伴って仕事を辞めた。
それから約1年半、私は子育てに専念した。
歩きたい盛りの子どもと一緒に公園に通う日々。今しかできない子育てを楽しんでいた。
しばらくすると、一緒に遊んでいたママ友たちが次々と育児休業を終えて復職していった。
子どもを寝かしつけた後、おもちゃで散らかったリビングを見渡しながらぼんやり考える。
「私はこのままで良いのかな」
「子どもが大きくなった時、私の人生はどうなるのかな」
当時の私は、社会から取り残されたような寂しさ、そして漠然とした将来への不安を感じていた。
寂しさは、誰しもが抱える当たり前の感情
寂しさは、人間にとって避けては通れない感情の1つ。
楽しそうに子育てをしている人も、仕事でバリバリ活躍している人も、お金に不自由せずに好きなものが何でも手に入る人でも、どんな人でも寂しさを感じる時があるのではないでしょうか。
寂しさは単なるネガティブな感情だけではありません。私たちが社会や他者と繋がり、理解され、愛されることへの自然な欲求から生まれるものであり、時に人の心を揺さぶり、自らを見つめ直すきっかけにもなるものです。
寂しさを感じた時の4つの解消法
美味しいものを食べて、たくさん寝て、まずは体を満たす
寂しさは時に、自分と向き合うきっかけにもなります。しかし、疲れが溜まっている時や、ストレスを抱えている時、ホルモンバランスが乱れている時などにもやり場のない寂しさを感じることがあるでしょう。
そういった時には、まずは心身のバランスを整え、ポジティブなエネルギーを取り戻すことが第一です。
家事を放り投げて寝てしまったり、お金もカロリーも気にせずに食べたいものを食べてみたり。そうすることで、翌朝には悩んでいたことが嘘のように、気持ちが切り替わっていることもあるでしょう。
寂しさの原因を言語化する
感情を言語化することは、寂しさと向き合う第一歩。
私は子育てに専念している時に感じた寂しさの根っこにあるものを紙に書き出してみました。
- 減り続ける自分の貯金残高。収入がないことが不安
- 夫の働いたお金で自分のものを買うことに気がひける
- 子育てや家事をしても、誰からも褒めてはもらえない。家事ができていないことを責められるのが辛い
- 子どもが成長した後、私には何が残るのだろう
出てくる、出てくる、寂しさの原因となる不安や不満が。その結果「働いて収入を得ること」が私の寂しさを解決することに繋がるという決断にいたり、再び働くことを決意しました。
自分の気持ちを言葉にすることで、その感情の原因となる問題や課題を具体的に捉えることができます。紙に書いたり、日記をつけたり、誰かに話を聞いてもらったりすることで、寂しさの解決策や対処法が見えてくるかもしれません。
他者に依存しない
他者への過度な依存は寂しさを強化する要因の1つと言えます。
例えば、子どもだけに依存していると、子どもが成長して巣立った後の人生に不安を感じるだろうし、子どもが大きくなって一緒にお出かけしてくれなくなった時に寂しさを感じるでしょう。
配偶者や恋人だけに依存していたら、メールの返信がないと強い不安にかられることや、相手がいない時に寂しさを感じることがあるでしょう。
そういったことを避けるためには、まずは自分自身と向き合い、内なる充実感を見つけることが大切です。中学校の頃に好きだったダンスをもう一度はじめてみるとか、美容に力を入れて自分磨きをしてみるとか、ブログをはじめて発信してみるとか。
他者に依存せずに自分自身が夢中になれることを見つけることで、自己満足感を高め、充実感を味わうことができるでしょう。趣味を通じて新しい仲間との出会いにも恵まれるかもしれません。
他者と比べない。SNSから遠ざかってみる
「隣の芝生は青い」ということわざがあるように、他者は自分よりも魅力的に見えるもの。自分と他者を比較することは、寂しさを引き起こす原因の1つになります。
特に、SNSが普及した今、他者の光り輝く瞬間を目にする機会が増えました。
「家族仲が良くて羨ましいな」
「あの子は子どもが生まれたんだ」
「あの子とあの子が遊んでいる。私は誘われていない」
「素敵なお家に住んでいるな」
など、他者がうらやましく思えることがありますよね。そういう時はSNSから距離を置くことも大切です。
そして比べるべきは他者ではなく、過去の自分。そうすることで、自己成長や喜びを感じ、他者との比較から生じる寂しさを軽減できるでしょう。

寂しさは自分と向き合うきっかけ
寂しさを感じることは、弱さや不完全さではなく、むしろ人間らしさの表れです。
寂しいという感情を避けるのではなく、むしろ受け入れ、向き合う。そうすることで、自分自身の内面の豊かさに気がつき、成長への一歩を踏み出すことができるでしょう。
寂しさが訪れた時には、目を背けるのではなく、その感情を探求し、内なる自分との対話を通じて、新たな可能性を見つけ出してみてください。
一人暮らしは寂しい?孤独を感じる瞬間や寂しさを解消する方法を紹介

大学への進学や就職・転職など、人生の転機ともいえるタイミングで一人暮らしをスタートする方は少なくありません。
しかし、環境が大きく変化するなかで慣れない一人暮らしを始めると、不安や孤独感、寂しさを感じる方も多いものです。
本記事では、一人暮らしのなかで寂しさを感じる瞬間やその原因、寂しさを解消するための方法もあわせてご紹介します。
一人暮らしを始めたばかりの方はもちろん、これから一人暮らしを検討している方も、ぜひ参考にしてみてください。
人が孤独を感じる原因

人は誰でもふとした瞬間に孤独や寂しさを感じるものです。
なぜこのような気持ちを抱くのか、考えられる原因は以下などが挙げられます。
- 人との関わりが少ない
- 他人と比較してしまう
- 環境の変化
- 熱中できるものがない
- セロトニン不足
これらの原因についてご紹介しましょう。
人との関わりが少ない
人は自分一人で生きていけず、さまざまな人と関わりをもちながら生活を営んでいます。
身近なところでは親や姉弟、親戚、学校の友人、職場の仲間などが挙げられます。
しかし、極端に人との関わりが少ない生活を送っていると、社会から取り残されたような錯覚に陥り孤独を感じることがあります。
他人と比較してしまう
人は良くも悪くも他人と比較してしまいがちです。
たとえば、交友関係が広い友人や、若くして結婚し子どもを授かった人を羨ましく感じることもあるでしょう。
一方、自分自身に目を向けたとき、友人の少なさや結婚相手に巡り会えないことに引け目を感じ、孤独感に苛まれることがあります。
環境の変化
進学や就職、転勤など、さまざまな事情によって周囲の環境が大きく変わることがあります。
それまで仲の良かった友人とも離れ、一から交友関係をスタートさせなければなりません。
しかし、周囲に知らない人が多いと関係を築くまでに時間がかかるほか、慣れない環境に対する不安もあって孤独感を増長させてしまいます。
熱中できるものがない
交友関係の広い人は、仕事や学校以外にもスポーツや音楽、釣り、ゴルフなど、趣味のコミュニティに属しているケースが多いです。
しかし、このように熱中できるものがないと休日に誰とも会う予定がなく、仕事以外のコミュニティがないため孤独を感じやすくなります。
セロトニン不足
セロトニンとはホルモン物質の一種であり、気持ちを前向きにさせたり幸福を感じさせたりする働きがあります。
セロトニンは太陽の光を浴びることで生成されますが、たとえば天気が悪く外出ができないときや、家の中に籠もったままだと孤独を感じやすくなります。
また、運動不足もセロトニンの分泌を減少させる要因になります。
関連記事:人肌が恋しいってどういうとき?意味や心理、対処方法をご紹介!
一人暮らしで寂しいと感じる瞬間

一人暮らしをしている人は特に孤独感や寂しさを感じやすい傾向があります。
どのようなシーンで寂しさを感じることが多いのか、具体的な事例として以下などがあります。
- 帰宅した時に誰もいない
- 一人での食事
- イベントや行事を一人で過ごすとき
- 体調を崩したとき
これらの瞬間について紹介しましょう。
帰宅したときに誰もいない
仕事や学校から帰宅したとき、家族がいれば部屋の明かりが点いていたり、「おかえり」と声を掛けてくれます。
しかし、一人暮らしの場合は自分で明かりをつけ、声を掛けてくれる人もいないため、慣れないうちは孤独や寂しさを感じてしまうこともあるでしょう。
一人での食事
食事は一人で摂るよりも、家族や友人など大勢で食卓を囲んだほうが美味しく感じられるものです。
また、その日あった出来事や共通の話題で盛り上がれるため、孤独や寂しさを感じにくくなるでしょう。
しかし一人暮らしの場合、仕事帰りにコンビニやスーパーなどに立ち寄って食材を購入してから帰宅し、家で一人食べることも多いため、孤独や侘しさを感じてしまいやすいです。
イベントや行事を一人で過ごすとき
クリスマスや年末年始、父の日・母の日、お盆など、一年を通してさまざまなイベントや行事があります。
多くの家庭では、それぞれのイベントに合わせて豪華な食事を家族で囲みますが、一人暮らしの場合はそのような機会がなかなかありません。
友人を自宅に招いてパーティーや食事会を開くこともありますが、家庭をもっている人はなかなか誘いづらいこともあるでしょう。
また、仕事が忙しいと実家に帰省する時間や経済的な余裕もなく、一人暮らしの孤独感を一層倍増させてしまいます。
体調を崩したとき
風邪やインフルエンザなどの病気や、骨折や捻挫などの怪我をしたとき、自宅で安静に過ごさなければならないケースもあるでしょう。
同居する家族がいれば食事の用意や洗濯、お風呂の準備などの身の回りの世話をしてくれますが、一人暮らしの場合は全て自分でこなさなくてはなりません。
また、体調が悪化すると「自分に万が一のことがあった場合、異変に気づいて助けてくれる人はいるだろうか」と不安な気持ちになりがちです。
一人暮らしが寂しくて泣いてしまう理由
大学への進学や就職、転職などのタイミングで一人暮らしをスタートさせたとき、猛烈な孤独感や寂しさを感じ泣いてしまう方も少なくありません。
なかには、一人暮らしに憧れていたにもかかわらず、いざアパートやマンションに一人になると自然と涙がこぼれてくる人もいます。
なぜこのような感情になるのでしょうか。
主な理由として「なれない環境で不安がある」や「相談できる人がいない」などが考えられます。
これらの主な理由についてご紹介しましょう。
慣れない環境で不安がある
特に大きい理由として挙げられるのは、環境が大きく変わることです。
実家からアパートやマンションへと引っ越すことで住環境が変わり、今まで当たり前にいた両親や兄弟とも別々に暮らさなくてはなりません。
家を出るときに「いってきます」、帰宅したときに「ただいま」と声を掛けても反応がないと、あらためて一人であることを実感し寂しさを覚える方も多いようです。
また、環境の変化という意味では、住環境だけでなく職場や学校などの違いも大きいでしょう。
特に学校を卒業して新社会人として一人暮らしを始めたときには、自分を取り巻くあらゆる環境が変わることで一層の不安を感じるようになります。
相談できる人がいない
孤独感や不安、寂しさを感じていたとしても、それを気軽に相談できる人が身近にいれば気持ちが楽になるものです。
しかし、家族や友人に対して「一人暮らしをしてみたい」といったことを口にしていた場合、後になって寂しいと弱音を吐くことに気が引けてしまい、辛い気持ちを自分ひとりで抱え込んでしまう方もいます。
あまりにも精神的な負担が増大してしまうと、自分自身ので心の整理がつかなくなり、自然と涙がこぼれてくることがあります。
関連記事:女性の性欲について解説!性欲がない女性の理由もご紹介!
一人暮らしで寂しさを感じたときの解消方法

慣れない一人暮らしは孤独感や寂しさがつきものです。
しかし、どうしても寂しさが解消できず精神的に落ち込んでしまう場合、どのような解消方法があるのでしょうか。
寂しさを感じたときの解消法として以下などが効果的なためおすすめです。
- 笑って明るい気持ちを取り戻す
- 外に出かける
- 趣味を見つける
- 自分から積極的に話しかけてみる
- 本心を正直に打ち明ける
では、これらの解消方法について紹介しましょう。
笑って明るい気持ちを取り戻す
寂しさや孤独感は笑うことで解消できることが多いです。
精神的に落ち込んでいるときに無理に笑顔をつくるのは辛いことですが、お笑い番組やマンガ、映画などを観て現実を忘れて笑ってみるのもひとつの手といえるでしょう。
外に出かける
寂しさや孤独感はセロトニン不足によって引き起こされることもあります。
どうしても前向きな気持ちになれないときには、意識的に外に出かけるようにしましょう。
外出に抵抗がある場合には、カーテンと窓を開けて室内で日光浴をしてみるのもおすすめです。
趣味を見つける
熱中できるものがなく、休日になると部屋の中に引きこもりがちになる方は、趣味を見つけるのもおすすめです。
たとえば、映画館に立ち寄って最新の映画を楽しんでみたり、ライブハウスやフェスなどに行って音楽を楽しんでみるのも良いでしょう。
映画館やライブに一人で参加するのは抵抗がある方も多いと思いますが、一人だからこそさまざまな人との交流がしやすく、同じ趣味を持つ者同士で人脈が広がっていきます。
自分から積極的に話しかけてみる
コミュニケーションが苦手な人見知りの方は、どうしても自分から話しかけにくく、交友関係を築くのに時間を要することが多いと思います。
しかし、相手も同じようなことを思っているケースも多く、勇気を振り絞って自分から話しかけることで一気に打ち解け、会話が弾むものです。
そのため、相手から話しかけられるのを待つのではなく、自分から積極的に話しかけてみましょう。
初対面の場合、自己紹介から入ると自然に会話のラリーを続けやすいでしょう。
本心を正直に打ち明ける
一人暮らしで寂しい気持ちを打ち明ける際には、古い付き合いの友人や家族など、信頼できる人がおすすめです。
弱みを見せるようで相談しにくいと感じる方もいるかもしれませんが、あえて素直な気持ちを言葉に出すことで本気で心配してくれ、親身になって相談に乗ってくれるはずです。
また、そのような相談をすることで一層絆が強くなり、これまで以上に強固な信頼関係を構築できるでしょう。
関連記事:スキンシップにはどんな効果がある?良好な関係性を維持するためのポイントとは
関連記事:上京して友達がいないのは普通?寂しさを紛らわす方法7選!|上京ものがたり
まとめ
一人暮らしに憧れを抱く人は多いですが、実際にアパートやマンションで生活をスタートすると孤独感や寂しさを強く感じるようになるものです。
これはその人のメンタルの弱さや脆さが引き起こすものではなく、周囲の環境や気候、時期なども影響します。
一人暮らしに寂しさを感じたときには、できるだけ明るい気持ちになれるよう意識的に笑顔をつくることや、積極的に外に出てさまざまな人とコミュニケーションをとることが有効です。
それでも自宅に帰ると寂しさが襲ってくることも多いため、家族や親友など、信頼できる人に本心を打ち明ける勇気も大切です。
一人暮らしが寂しいと感じるのは決して特別なことではなく、当然の心理といえるでしょう。
また、一人暮らしに慣れていくと寂しい気持ちも軽くなっていき、自分のペースで快適な生活を送れるようになります。
それまでの不安定な期間を乗り切るためにも、今回紹介した内容を参考にしてみてください。
人肌が恋しい女性心理とは?対処方法をご紹介!

肌寒い季節や大型のイベントシーズンを控えた時期、あるいは幸せそうなカップルや夫婦を見たときなど、ふと「人肌が恋しい」と感じたことはないでしょうか。
なぜ私たちは人肌が恋しいと感じるのか、その深層心理を探るとともに、人肌が恋しいと感じたときの対処方法もご紹介します。
人肌が恋しいの意味とは?

秋から冬にかけて肌寒さを感じるようになると、「人肌恋しい季節」などと表現されることがあります。
「人肌が恋しい」という言い回しはこれ以外にもさまざまな場面で耳にすることがありますが、本来どういった意味で使われる言葉なのでしょうか。
そもそも「人肌」とは、人の肌という直接的な意味を指すものではなく、人の温もりや体温などを意味します。
たとえば、握手をしたときやハグをしたときなど、自分以外の人に直接触れると温もりがあり、安心感を得られるものです。
すなわち、人肌が恋しいというのは、信頼できる人や愛する人の温もりを感じることで、不安や寂しさを払拭し安心感を得たいという心理を指す言葉といえるでしょう。
特に、秋から冬にかけて寒くなると日照時間が少なくなり、私たちの体内で生成されるホルモンの一種であるセロトニンも減少しがちになります。
セロトニンが減ると不安や寂しさを感じやすくなることから、寒い季節には物理的に温もりを感じるだけでなく、安心感も得たいという心理が働くのです。
関連記事:一人暮らしは寂しい?孤独を感じる瞬間や寂しさを解消する方法を紹介
人肌が恋しくなる瞬間

人肌が恋しいという言葉はさまざまなシーンで使用されますが、具体的にどういった場面が多いのでしょうか。
主に以下などの瞬間に人肌が恋しいと感じることが多いようです。
- 肌寒い季節
- 体調を崩したとき
- 精神的な疲労が溜まっているとき
- 失恋したとき
- 身近な人が交際・結婚したとき
- 将来の不安を感じたとき
これらの瞬間について紹介しましょう。
肌寒い季節
冒頭でも紹介した通り、秋から冬にかけて肌寒さを感じるようになると、孤独感や寂しさが押し寄せてきて人肌が恋しくなることがあります。
特に、12月から1月にかけてはクリスマスや年末年始と大きなイベントが控えていることもあり、一層人肌が恋しくなる傾向があります。
体調を崩したとき
風邪やインフルエンザにかかったときや、重い病気にかかって入院を余儀なくされたときなど、人は誰しも不安を感じるものです。
自分に寄り添ってくれる人がいれば不安も低減されるため、身体が弱っているときほど本能的に人肌が恋しくなります。
精神的な疲労が溜まっているとき
精神的な疲労も人肌が恋しくなる大きな要因になります。たとえば、仕事や勉強を頑張っているのに誰からも評価されないと、自分の存在意義が分からなくなり不安や寂しさ、虚しさが増大します。
そのようなとき、そばにいて見守ってくれたり、認めてあげる人がいれば精神的にも救われることから、人肌が恋しいと感じるようになります。
失恋したとき
精神的な疲労とも関連が高い項目ですが、失恋したときも人肌が恋しくなる傾向があります。
特に、信頼していた恋人に裏切られて別れた場合、精神的なダメージは図り知れず、一人では立ち直ることが難しいため誰かに寄り添ってもらいたいと考えるのは当然のことです。
また、実際に付き合ってはいなかったとしても、自分の想いが相手に届かなかった場合、ショックが大きく人肌が恋しいと感じるようになります。
身近な人が交際・結婚したとき
近年では男女ともに価値観が多様化しており、なかには結婚を望まない人も少なくありません。一方で、良縁に恵まれなかったり、経済的な問題などで結婚したくてもできない人も多く存在します。
そのような人にとって、兄弟や親友、同僚など、身近な人が結婚し幸せな家庭を築くと、猛烈な寂しさや孤独感を感じ人肌が恋しくなることがあります。
将来の不安を感じたとき
現代は社会が大きく変化しており、将来を見通すことが難しい世の中になっています。
経済的な問題はもちろんのこと、災害や感染症、テロ、戦争など、社会を根幹から揺るがす大きな出来事がいつ発生してもおかしくない状況にあります。
万が一の事態が発生したとき、一人で生きていくのは極めて困難であり、ときには誰かの助けが必要になることもあるでしょう。
将来のことを考えると、強い不安感を覚え人肌が恋しくなる人も少なくありません。
関連記事:スキンシップにはどんな効果がある?良好な関係性を維持するためのポイントとは
女性が人肌恋しくなる心理

「人肌が恋しい」という言葉を聞くと、自分に対して好意を抱いている、あるいは助けを求めているのではないかと感じる人も少なくありません。
男女によって深層心理は異なることが多いですが、具体的にどのような違いがあるのでしょうか。
まずは女性が人肌恋しくなる心理を考えてみましょう。
- 好意を抱いている
- 精神的な不安を抱いている
- イベントシーズンを控え寂しさを感じている
これらの女性が人肌恋しくなる心理について紹介しましょう。
好意を抱いている
女性から「人肌が恋しい」という言葉を聞くとドキッとする男性も多いと思います。
女性のなかには、意中の男性に振り向いてもらうためにこのような言葉を伝える方も少なくありません。
特に女性は男性に対して積極的にアプローチしたり、直接的な言葉で好意を伝えたりするのが苦手な人もいます。
必ずしも好意を寄せられているというわけではないでしょうが、少なくとも悪くは思われていないと考えて良いでしょう。
精神的な不安を抱いている
「人肌が恋しい」という言葉はさまざまな意味に捉えられるため、必ずしも好意を伝えているとは限りません。
たとえば、仕事で大きなミスをしたり、プライベートでショックな出来事があったとき、不安を覚え誰かにそばにいてほしいと感じることもあるでしょう。
そのようなとき、信頼できる人にこのような言葉で伝える人もいます。
イベントシーズンを控え寂しさを感じている
クリスマスや年末年始などの大型イベントを控えた時期になると、一人でいることに不安や寂しさを覚える方も少なくありません。
そのようなとき、異性同性を問わず自然と「人肌が恋しい」という言葉が出てくることもあります。
関連記事:生理後は性欲が強くなる?生理周期別の性に関する過ごし方を紹介
男性が人肌恋しくなる心理
男性の場合、どのような心理で「人肌が恋しい」という言葉を使用することが多いのでしょうか。
基本的には、女性と同様に好意を伝える手段や、精神的な不安や寂しさを訴える言葉として使われることが多いようです。
ただし、その人とどのような関係性であるかも重要なポイントとなります。たとえば、恋人や友人、兄弟、同僚など、信頼している間柄では上記のような意味合いとして使われることが多いでしょう。
しかし、初対面の人や久しぶりに会った友人、顔見知り程度の人など、十分な信頼関係が築かれていないにもかかわらず、「人肌が恋しい」といった言葉を掛けてくる男性は、下心がある場合も多いです。
いきなりこのような言葉をかけてくる男性がいたら十分注意し、場合によっては距離をとることも考えましょう。
人肌が恋しくなったときの対処方法

さまざまな事情によって人肌が恋しいと感じた場合、寂しさや孤独感、不安を紛らわせるにはどのような対処方法が有効なのでしょうか。
主な対処法として以下などが挙げられます。
- 仕事を入れる
- 運動する
- 美味しいものを食べる
- 趣味に没頭する
- 寝る
これらの対処法について紹介します。
仕事を入れる
プライベートの悩みや寂しさを抱えているときには、それを忘れる手段として仕事に没頭する人も多いです。
シフトや残業などで仕事量を調整できる場合には、あえて仕事を多めに入れて余計なことを考えないようにするのもおすすめです。
運動をする
人肌が恋しいと感じているときは、精神的なストレスが蓄積していることが多いです。
ウォーキングやジョギング、筋力トレーニング、ストレッチなど、適度な運動をすることでストレスや不安感が解消され、前向きに考えられるようになります。
美味しいものを食べる
運動をした後は、美味しいものを食べたり適量のお酒を楽しむのもおすすめです。
気の合う友人や家族など、信頼できる人を食事に誘って楽しむことで孤独感や寂しさが解消され、気分転換にもなるでしょう。
趣味に没頭する
プライベートが充実していないと人肌が恋しく感じやすいものです。特に休日になると一歩も外から出ず引きこもっている方は要注意です。
できるだけ外に出て、時間を忘れて没頭できる趣味を見つけることで寂しさが解消されます。
寝る
夜になると寂しさや孤独感は増大し、特に人肌が恋しいと感じるようになります。
そのため、できるだけ早めにベッドに入り、考え事をする前に寝るのもひとつの方法です。
入眠前にはスマホの画面を見ず、入浴後90〜120分程度でベッドに入るとリラックスした状態になりスムーズに眠れます。
関連記事:ストレスを発散させるメリットとは?解消方法と合わせてご紹介!
まとめ
仕事やプライベートが充実していても、ふとした瞬間に「人肌が恋しい」と感じることはあります。
その人の性格や考え方、生活環境、季節など、さまざまな要因が考えられますが、悲観的になりすぎると悪い方向へ進んでしまいます。
また、異性から「人肌が恋しい」と相談されたとき、捉え方を間違えてしまうとさまざまな誤解を生んだりトラブルに発展したりすることもあるでしょう。
人肌が恋しいと感じたときには、仕事や趣味に没頭したり、ストレスを解消するなどして適切に対処することが大切です。
不安なきもちとの上手なつきあい方
*この記事は、社交不安症(ソーシャル・エンザイアティー)を経験したアメリカ人の筆者の記事をもとにしたものです。

ごく日常的な場所でこんなことはありませんか?
例えば、スーパーに買い物に行った時。
シャンプーを選ぶのに時間がかかりすぎている自分をみんなが変な人だと思って見ているかもしれない。ずっと買い物かごが空っぽの状態でこの人は何をやっているんだろうと思われているかもしれない。レジに並びながら、あちらのレジのほうが進み具合が早いけど、あちらに行ったら優柔不断だと思われるかもしれない。
こんな風に、人に見られている場面で何かをすることをとても不安に感じることはありませんか? 批判されたり間違ったことを言っていないかと不安になり、人と関わることを避けがちになるこの社交不安症、最近は日本でも耳にするようになりました。
でも、私たちはこんな不安に支配される必要はないんです。ちょっとしたコツをつかめば、社交不安症の人も満足のいく社会生活を送ることができます。その方法を紹介したいと思います。
自分の内面をよく見てみる
内面への働きかけは、社交不安症に対処するのに大切ですが、これは簡単なことではありません。なぜなら、たいていの場合、他人からどう見られているかを気にしなくなるには時間がかかりますし、自分ではどうしようもないことに不安を感じていることが多いからです。
内面をよく見るためには、自分の思考や感情、リアクションにあなたがもっと注目することが不可欠ですが、これには、かなりの練習が必要となります。その点で、瞑想やマントラを唱えることは、自分自身をグラウンディング(自分と地球のつながりを感じてエネルギーのバランスを取ること)させ、気持ちを落ち着かせるのに役立つでしょう。
不安を感じたときにぜひくり返してほしいおすすめのフレーズがあります。
「他人がどう思うかなんて気にしていない」
実際、私は他人がどう思っていようが、私が喜ぶことをするほうが好きなんだとやっと気づいた時に、この言葉の重みを改めて強く実感しました。このフレーズを自分に言い聞かせることで、私は不安になった時にこの自分の軸に立ち戻ることができるのです。
自分に語りかけるフレーズは自分に合ったものを自分で作ればいいんです。不安な思考がまたぶり返して戻ってくることはありますし、社交不安が完全に消えなくてもいいんです。自分の意識を内側に向ければ向けるほど、不安の度合いは対処しやすくなっていくでしょう。
一緒にいて安心できる友人を見つける

社交不安症の人は、友だちが多すぎると精神的に疲れがちです。その代わり、信頼できる小さな友達の輪を持っていればそれで良いのです。そういう友達は、社交的な場でも、あなたがある程度のスペースを必要としていることをわかってくれています。
人と距離を置いたり、友人との予定をキャンセルすることは、相手に対して失礼だと思う必要はありません。自分自身を主張することは、健全な人間関係のために必要なセルフケアです。そして、あなたが必要とするスペースを友だちが理解してくれるとき、あなたは大切にされていて安全な場所にいるのだと安心することができるでしょう。
とはいえ、信頼できる友だちを見つけることは難しいことです。新しい友だちを作るときは、自分の興味や慣れ親しんだ空間に身をゆだねてみましょう。例えば、いつも行くカフェの店員さんが世間話を始めたら、いつもより少し長居して、その会話の行く末を見守ってみましょう。または、会社の同僚があなたと気が合いそうな友達を紹介すると言ってきたら、それに素直に応じてみましょう。こうやって日々のちょっとした新しいことを受け入れることで、ささやかながらも満足のいく社会生活を送ることができます。
いつでも退出できるようにする
これは、社交不安症の人に対する一番のアドバイスです。例えば、あなたが人と会う時には、すぐにその場を離れることができるような公共の場やカフェのようになじみのある場所でするようにしましょう。プレッシャーを感じたり辛くなりそうだったら、その場を離れることができるとわかっていれば、安心して気持ちのコントロールができます。
こういう「逃げられる」手段を用意しておくことを恥じるべきでないし、その手段を実際に使うことも恥じるべきでありません。イベントに30分しかいられなかったとしても、それでいいんです。実際にイベントに顔を出して、不安と向き合っただけであなたは褒められるべきがんばりをしたのです。
自分に優しくする
社交不安が思うようにすぐに解消されないとしても、それはまったく普通のことです。「それは、あなたが目に見える結果が出るのを欲するあまり、改善を急ぎすぎたからかもしれないし、社交の場でもっと練習をしたほうがいいということかもしれない」と精神科医のドーン・ポッター博士は指摘する。
パニック発作であれ何であれ、何が反応の引き金になったのかを後からしっかりと確認することも大切です。「どうすればそのことについて違う考え方ができるか、どうすれば次にその状況を変えることができるか、こういうことを考えてみましょう」とポッター博士は提案する。「例えば、コンサートで大勢の人に囲まれてパニックになったとしましょう。次回は、後ろや通路側の席に座るとか、不安を感じたら、出口の近くに行くなどです」
ポッター博士は、一般的に人は他人のことなどそれほど考えていないとも言います。「私たちは、次に自分が何を言おうか、自分が何をしようか、そうやって自分のことを考えるのに忙しいのです」「あなたが自分について強く感じている不安な要素は、他人にはほとんど目立たないことであることが多いのです」
周りのサポートを受け入れる

社交的な場面で不安を感じ、助けが必要かもしれないことを周りに認めるのは、恥ずかしく屈辱的なことかもしれません。特に友人や恋人に、特別なサポートが必要かもしれないと伝えることは、大きな支えになります。「人は親しい人と社交的な場所にいれば、より快適に感じるものです」とポッター博士は言う。
親しい相手と一緒にいることは、社会不安症の人が時間をかけて自立していくのを助けることになります。信頼できる友だちや家族が、社会不安のあるあなたを自然に会話に引き込んであげるという方法もあります。「ああ、サラがそのテーマについて何か言いたいことがあるみたいだよ。彼女はそのトピックに興味があるみたい」こうやってあなたの殻を破ってくれることで、あなたをサポートすることができるでしょう。ただし、社交不安症の人は、自分が何か言わなければならない状況に追い込まれるのを嫌がることがありますから、事前に話し合っておきましょう。
日本のこれから
社交不安の症状を訴える日本人の割合は、アメリカ人のそれと比べると8分の1と少ないという調査もでています。これには、会議や授業では上司や先生など人の話を聞いていればよかったという日本の社会的背景があるのかもしれません。
ただ、そんな日本も、職場や学校などの生活で自分から発言することが重視される社会へと変化しています。そんな時に不安を感じることがあれば、自分に対して優しく、他人との比較をやめ、周囲のサポートを受け入れて充実した人間関係を築いていくことが、社交不安を乗り越える道となるでしょう。
参考:
・https://www.thegoodtrade.com/features/how-to-deal-with-social-anxiety/
・https://health.clevelandclinic.org/how-to-overcome-social-anxiety/
夫婦仲が悪い原因は?子供に与える影響や改善する方法をご紹介

結婚したばかりの頃は円満であったにもかかわらず、時間の経過とともに夫婦仲が悪化していくケースは珍しくありません。
「最近夫と会話をしていない」、「妻から無視されるようになった」など、悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。
本記事では、夫婦仲が悪くなるのはどういった理由が考えられるのか、改善するための方法やポイントもご紹介します。
夫婦仲が悪くなる原因・理由

夫婦仲が悪化する原因はさまざまで、なかには些細なことがきっかけで不仲になるケースも少なくありません。
典型的なのが以下のような原因です。
- 生活のすれ違い
- 浮気歴がある
- 家事や育児の負担
- 義実家との関係性
- 経済的な問題
- 価値観の違い
これらの原因について詳しく紹介しましょう。
生活のすれ違い
共働き世帯の場合、夫婦それぞれの勤務形態や労働時間が異なるケースも多いため、休日や帰宅時間などがずれてしまい、夫婦生活にすれ違いが生じることがあります。
たとえば、朝起きたときに夫がいない、夜帰宅しても妻が残業のため一人で食事を摂ることが多いなど、顔を合わせる時間が減っていくと、「なんのために結婚したのだろう」と感じ夫婦仲が悪化することもあるでしょう。
浮気歴がある
夫または妻のいずれかに浮気歴や不倫歴がある場合、それがきっかけで夫婦仲に亀裂が入ることが多くあります。
一方、一度は浮気や不倫を許したものの、時間の経過とともに不満が溜まっていき、些細なことがきっかけでケンカの原因になるケースも少なくありません。
家事や育児の負担
家事や育児の負担割合も夫婦仲を悪化させる要因のひとつになり得ます。
たとえば、夫の立場では十分家事を行っているつもりでも、実際にはその大半を妻が担っているケースは珍しくありません。
子どもがいる家庭の場合、夫が普段育児をできず妻に頼らざるを得ないことも多いです。
義実家との関係性
夫または妻の両親と良好な関係性が構築できていないと、それがストレスとなり夫婦仲を悪化させる原因になることもあります。
たとえば親の介護が必要になり義両親との同居生活が始まると、夫または妻の一方にばかり負担が押し付けられ、夫婦仲が悪化するケースも考えられるでしょう。
経済的な問題
長引く不況の影響もあり、共働きであるにもかかわらず経済的に困窮する家庭も少なくありません。
その結果、「別の人を選んでいたら余裕のある生活が送れていたかもしれない」と考えるようになり、夫婦仲が悪くなることもあるでしょう。
価値観の違い
お互いに異なる人生を歩んできた二人が夫婦として共同生活を送るとなると、些細なことで価値観や考え方に違いが見られることもあります。
一つひとつは小さいことでも、それが積み重なっていくと大きなストレスになり、夫婦仲に亀裂を生じさせる原因にもなるでしょう。
関連記事:モラハラ夫は特徴やどんな発言をする?対処法や子供への影響も解説
仲が悪い夫婦の特徴

夫婦関係はそれぞれの家庭によって異なるため、第三者から見て一概に不仲と断定することはできません。
しかし、夫婦関係に亀裂が入り仲が悪い夫婦には、共通して見られる特徴もあります。
- 笑顔が少ない
- 会話がない
- セックスレス
- 喧嘩が多い
すべてのケースに当てはまるとは限りませんが、典型的な特徴をいくつかご紹介しましょう。
笑顔が少ない
夫婦仲が悪くなると、お互いに嫌悪感を覚えるようになり、一緒に暮らすことがストレスに感じてきます。
その結果笑顔を見せることが減り、つねに無表情か不機嫌な態度を見せるようになります。
夫と妻両方がこのような態度を示すこともあれば、どちらか一方が不機嫌な態度で接するケースもあります。
会話がない
笑顔が少ないだけでなく、会話を交わすこともストレスに感じるため、自然とコミュニケーションが減っていきます。
また、夫か妻いずれかが話しかけても、一方が無視をするなどして会話が成り立たないことも少なくありません。
セックスレス
子どもの誕生などがきっかけで、夫が妻のことを女性として見られなくなる、あるいはその反対のケースもあります。
お互いのことを異性というよりも家族の一員として見るようになり、セックスレスに陥る夫婦も多いようです。
また、夫または妻はセックスを求めているのに、相手はそれに応じてくれないというケースもあります。
その結果、円満な夫婦関係が維持できなくなり、不仲に陥る夫婦も少なくありません。
喧嘩が多い
長い夫婦生活を送る過程で、お互いの嫌な部分が見えてくるようになることもあるでしょう。
新婚当初はお互いを尊重し許せていたことも、家族の一員として見るようになるとストレスに感じ、やがてケンカに発展してしまうケースもあります。
日常的にケンカが続くようになると「これ以上の結婚生活に耐えられない」という結論に至る夫婦も少なくありません。
関連記事:セックスレスの原因とは?|なりやすい夫婦の特徴や解消法を解説
夫婦仲が悪いまま一緒に暮らす悪影響

夫婦仲が悪化した状態でも、別居や離婚といった結論が出せず躊躇してしまう夫婦も少なくありません。
しかし、かといって夫婦仲が悪いまま同居を選択しても、さまざまな悪影響が考えられます。
- 仕事のパフォーマンス低下
- 健康面への影響
- 熟年離婚の可能性
これらの影響について紹介しましょう。
仕事のパフォーマンス低下
家庭は本来、安らぎを感じリラックスできる場です。
しかし、夫婦仲が悪いと家庭のなかでもつねにストレスを感じ、精神的に安らぐことができません。
職場でも家庭の不安が頭をよぎり、仕事に集中できなくなるでしょう。
その結果、仕事で単純ミスを頻発したり、仕事中に居眠りをしたりとパフォーマンスの低下を招くおそれがあります。
健康面への影響
本来、精神的な安らぎの場である家庭がストレスの根源になってしまうと、現実逃避のためアルコールに頼ってしまう危険性があります。
その結果、重度のアルコール依存症となり、健康を害するリスクも高まるでしょう。
また、うまくストレスが発散できない状態が続くとメンタルの不調をきたし、うつ病や統合失調症などを発症するリスクも高まります。
熟年離婚の可能性
夫婦仲が悪い状態が続いたとしても、子どものことを考え離婚を踏みとどまる夫婦は少なくありません。
しかし、子どもが成長し独立すると、あらためて自分自身の人生を見つめ直すきっかけになり、結果として熟年離婚にいたるケースも多いのです。
関連記事:セックスレスになると離婚率が上がる?レスにならないための方法とは
夫婦仲が悪いと子供にどんな影響を与える?

夫婦仲の悪化は当事者である夫婦2人の問題だけではありません。
特に子どもがいる場合、重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
夫婦間で日常的にケンカが繰り返されると、子どもは「いつか自分にも危害が加えられるのではないか」と怯えてしまいます。
また、些細なことで怒られるのではないかと考え、自然と自信を喪失していくことも考えられるでしょう。
その結果、親だけでなく周囲の人も恐れるようになり、人間不信に陥る可能性があります。
関連記事:自己肯定感が低い子供の特徴や言動とは|注意すべき親の発言や行動
夫婦仲を改善させる方法
夫婦関係が悪化したからといって改善が不可能というわけではなく、実際に関係を修復できた夫婦も存在します。
夫婦仲を改善するにはどういった方法があるのでしょうか。
- 言葉で伝える
- 相手を理解する努力をする
- 夫婦の時間を作る
- 過度に干渉しない
夫婦仲を改善させる代表的な方法を紹介しましょう。
言葉で伝える
夫婦生活が長くなると、お互いに「わざわざ言わなくても分かるだろう」、「自分の気持ちは伝わっているはず」と考えがちです。
しかし、夫婦といえども自分以外の本心は分からないものです。
そのため、たとえば感謝の気持ちや愛情、幸せだと感じたときには、それを素直に言葉で表現しましょう。
夫婦仲が悪いと自分から切り出すことに抵抗を感じる方も多いと思います。
しかし、感謝の言葉を日常的に心を込めて繰り返し伝えることで、徐々に気持ちが伝わり夫婦仲の修復につながっていく可能性は高いです。
相手を理解する努力をする
自分から言葉や態度で表現する以外にも、相手の心を汲み、理解しようとする姿勢が必要です。
たとえば、感謝の気持ちや愛情などを言葉で伝えたとしても、相手が素直に受け取ってくれないと夫婦仲は改善できません。
なぜ、夫または妻はこういった言葉を掛けたのか、相手の立場に立って気持ちを汲み取ることを心がけましょう。
夫婦の時間をつくる
生活のすれ違いなどによって夫婦仲が悪くなっている場合には、少しでも夫婦で過ごす時間をつくるよう工夫してみましょう。
たとえば、残業で帰宅が遅くなった場合でも「おやすみ」の挨拶を交わしたり、シフトの調整や有給休暇を取得して外に出かけるなど、できる範囲で時間を合わせることが大切です。
はじめから「休暇をとってほしい」や「早く帰ってきてほしい」と要望するだけでは反発を招くおそれもあるため、まずは自分から調整し時間をつくるようにしましょう。
過度に干渉しない
相手の言動で気がかりな部分があると責め立てたくなるものです。
たとえば、「どうしてそんなに残業が続いているのか?」、「どうして部屋が汚いままなのか?」などといった言葉がそれにあたります。
しかし、これが発展していくと相手の行動を逐一監視するようになり、さらに夫婦関係が悪化する可能性があります。
このような否定的な言葉を投げかけないことはもちろんですが、相手のことを信頼し過度に干渉しないことも夫婦仲を修復するためには不可欠です。
ただし、干渉しないというのはコミュニケーションをおろそかにしたり、相手に興味を示さないということではないため注意しましょう。
関連記事:スキンシップにはどんな効果がある?良好な関係性を維持するためのポイントとは
まとめ
新婚当初は仲睦まじい夫婦であったにもかかわらず、夫婦生活が長くなるにつれて関係が悪化し、一緒にいること自体がストレスに感じてしまうケースも少なくありません。
夫婦といえども別人格である以上、お互いのことをすべて理解できるとは限らないものです。
夫婦仲が悪化すると「もう修復は不可能なのではないか」、「離婚するしかないのでは」と考えがちですが、今からでも関係を取り戻せる可能性は十分あります。
今回紹介した方法を参考に、まずは自分自身の行動を変え、相手に気持ちが伝わるよう動いてみましょう。
聞き上手になるには?自分の話をしないのが正解?

「人の話を聞くのが苦手で自分のことばかり話してしまう」、「他人の話に興味が湧かず、質問をするのが苦手」という人も多いのではないでしょうか。
コミュニケーション能力を高めるうえで聞き上手になることはとても大切であり、円滑な人間関係を構築するうえでのポイントとなります。
本記事では、聞き上手の人にはどういった特徴があるのか、聞き方のコツや話し上手との違いについても解説します。
聞き上手とは

聞き上手とは、相手が自然と話したくなるようなコミュニケーションをとることを指します。
たとえば、対面で会話をするとき、相手の目を見ずにスマホを操作しながら聞き流している人と、目を見て、ときには相槌を打ちながら真剣に話を聞いてくれる人がいた場合、後者のほうが話しやすいと感じるでしょう。
相手の話に耳を傾け、真摯な姿勢で聞くということはコミュニケーションの基本であり、聞き上手な人ほどコミュニケーション能力が高いといえるのです。
また、このように真摯に話を聞くことは「傾聴」ともよばれ、聞き上手は傾聴力が高いとも表現されます。
関連記事:苦手な人でもコミュ力を上げる方法はある?鍛えるメリットも紹介!
聞き上手になるメリット

傾聴力を高め、聞き上手になることは、日常生活においてさまざまなメリットがあります。
具体的にどういったメリットがあるのか、代表的なものは以下などです。
- 相手の本音を引き出しやすくなる
- 周囲の人に頼られる存在になる
- 信頼関係を構築できる
これらのメリットについてご紹介しましょう。
相手の本音を引き出しやすくなる
聞き上手であるということは話しやすい雰囲気をつくることでもあり、相手は安心して本音や心の内をさらけ出すことができます。
人間関係において相手を傷つけることを恐れ、本音を言い出せず悩む人も少なくありません。
聞き上手になることで相手は自分に対して本心をぶつけることができ、自分のなかで改善すべき点や相手からの要望が分かれば、お互いにストレスを感じることも少なくなるでしょう。
周囲の人に頼られる存在になる
本音を話しやすい聞き上手な人には、さまざまな人が相談をしたくなるものです。
相談の内容によっては有効な解決策やアドバイスができないことも多いですが、話をじっくり聞くだけでも精神的な負担が軽減され、楽になることは少なくありません。
「困ったときにはあの人に相談しよう」といったように、周囲の人から頼られる存在になることで人望が高まります。
同時に、自分が困ったときや悩みを抱えるときに助けてくれる人が現れるかもしれません。
信頼関係を構築できる
聞き上手になることで、自分自身への信頼度も高まっていきます。
たとえば、ビジネスの場面においては取引先や顧客が抱える課題や悩みに寄り添うことで信頼感を得られ、新規顧客の開拓やビジネスパートナーとの連携も可能になるでしょう。
社内だけでなく社外からの評価も高まり、重要なポジションや役割を任せてもらえる可能性があります。
関連記事:社内で円滑なコミュニケーションを取るコツや活性化の成功事例を紹介
聞き上手と話し上手の違い

聞き上手と似た言葉に「話し上手」があります。
両者にはどのような違いがあるのでしょうか。
話し上手とは
話し上手とは、相手の理解度や認識の度合いに応じて、分かりやすく丁寧に話をすることを指します。
たとえば、これまで化粧の経験がない中高生に対して、メイクや化粧品の専門的な話をしても理解が追いつかないことが多いため、まずはどういったスキンケアアイテムがあるのか、下地と乳液の違いやメイク道具の使い方などから説明しなければなりません。
自分がもっている知識や理解度を前提に、「これくらいは知っているだろう」といった認識で話を進めるのではなく、相手に合わせて話の内容を組み立てていくことが話し上手な人の特徴です。
また、専門的で内容が伝わりづらい場合には、比喩表現や例え話なども駆使して、分かりやすく伝えようとする特徴もあります。
話し上手な人は聞き上手でもある
聞き上手と話し上手は一見すると対極的なスキルであると捉えられがちですが、古くから「話し上手は聞き上手」ということわざもある通り、密接な関係があります。
分かりやすいように話を組み立てたり、話し方を変えたりするということは、まず相手の状況を知る必要があるのです。
また、話している最中に相手が疑問を感じているような表情を見せた場合、どこが分からないのか具体的に聞き出す必要があるでしょう。
このように、話し上手であることは、大前提として相手に寄り添う姿勢が大切であり、そのためにも聞き上手であることが求められるのです。
関連記事:ノンバーバル(非言語)コミュニケーションの重要性とは?一例も紹介
聞き上手の間違った認識
聞き上手の定義や意味を間違って捉えると、コミュニケーションがうまくいかず会話がなかなか弾まないこともあります。
特に多いのが、以下のような誤った認識です。
- 自分の話をしない
- 質問ばかりする
これらについて解説します。
自分の話をしない
聞き上手と聞くと、「相手の話を聞いていれば良い」と捉え、自分から話をする必要はないと考える人も少なくないでしょう。
しかしこれは誤った認識であり、聞き上手とはいえません。
相手にしてみれば、一方的に自分ばかりが話しているように感じてしまい、「この人は本当に理解しているのか」、「自分に共感してくれているのか」と不安を覚えられてしまいます。
質問ばかりする
上記とは反対に、質問ばかり投げかけるのも聞き上手とはいえません。
相手が話している最中に多くの質問を投げかけてしまうと話が横道に逸れていってしまい、本題を見失うことがあります。
また、あまりにも質問をしすぎてしまうと、相手にしてみれば理詰めのように責められていると感じることもあり、それ以上話をしたくなくなる可能性もあるでしょう。
話の流れで時折質問を投げかけるのは有効ですが、タイミングや質問の量には注意が必要です。
聞き上手な人の特徴

聞き上手な人にはどういった特徴があるのでしょうか。
人によって話の聞き方は異なりますが、代表的な聞き上手な人の特徴は以下の通りです。
- 笑顔で話を聞いてくれる
- 適度な相槌を打ってくれる
- 話しを否定せず共感してくれる
- 相手に興味を示す
これらの特徴について詳しくご紹介します。
笑顔で話を聞いてくれる
聞き上手な人の多くは、自然と話しかけたくなるような雰囲気があります。
自然体で話を聞いてくれることはもちろん、笑顔でいることが多く親しみを感じやすいです。
適度な相槌を打ってくれる
話しやすい雰囲気をつくるうえでは、適度な相槌も重要なポイントといえます。
聞き上手な人の多くは、相手が話している途中で「うん、うん」、「へぇー」、「なるほど」、「その通りだね」といった相槌を打ちます。
これにより、相手は自分が話す内容を理解してくれている、あるいは共感してくれていると感じ、次の言葉を発しやすくなるのです。
話を否定せず共感してくれる
会話の途中で話を否定しないのも聞き上手な人の特徴です。
もちろん、人によって考え方や価値観は異なり、すべての意見が一致するとは限りません。
しかし、そのような場合であっても、聞き上手な人はあえて否定せず最後まで耳を傾けてくれます。
また、自分と意見が一致する場合には共感の意思を示してくれます。
相手に興味を示す
相手に心地よく話をしてもらうためには、自分が相手に対して興味をもっていることを示す必要があります。
ときには自分の専門外のことや興味がない話をされることもあるかもしれません。
しかし、分からないことがあれば素直に質問したり、自分と共通点のありそうな内容が出れば掘り下げて聞いたりすることで、会話が盛り上がっていく可能性もあるでしょう。
関連記事:スキンシップにはどんな効果がある?良好な関係性を維持するためのポイントとは
話の聞き方や受けとめ方のコツ
相手の話を真摯に聞いているつもりでも、聞き方や話の受けとめ方によっては誤解が生じる可能性もあります。
話を聞くうえで注意しておきたいポイントやコツとして以下などが挙げられます。
- 先入観をもたない
- 自分の主張を押し付けない
- 共感の姿勢を示す
それぞれ紹介しましょう。
先入観をもたない
円滑なコミュニケーションをとるために、先入観が邪魔になることがあります。
たとえば、入社して間もない友人や同僚から「仕事を辞めたい」と相談されたとき、「我慢が足りないのだろう」といった先入観をもってしまうと、相手に悪い印象をもってしまい共感できなくなってしまいます。
できるだけ先入観を捨て、ニュートラルな立場で耳を傾けるようにしましょう。
自分の主張を押し付けない
人によって価値観や考え方は異なるため、ときには意見が食い違う場合もあるでしょう。
つい自分の意見や主張を押し通したくなりますが、相手から「この人には理解してもらえない」と思われてしまうため、このような行動はとるべきではありません。
もし異なる意見を示す場合でも、相手を否定するのではなく、「◯◯さんの意見はとても理解できる。一方で見方を変えてみると、◯◯という考え方もあり得るかもしれないね」といったように、気付きを与えるような言い方に留めておきましょう。
共感の姿勢を示す
上記でも紹介しましたが、聞き上手になるためには共感の姿勢が不可欠です。
具体的には、「そうだよね」、「なるほど」といった適度な相槌を打ちながら、自分なりに話を整理し理解した内容を繰り返したり、表現を変えて「これはつまり◯◯ということだよね?」など繰り返すことも必要です。
ただし、あまりにも大げさな相槌や共感は、わざとらしく見えたり嫌味として捉えられることもあるため注意しましょう。
関連記事:友達の作り方|場所と手順を社会人から学生ごとに分けて解説!
まとめ
円滑なコミュニケーションを図るうえで、聞き上手になることは重要です。
コミュニケーションが苦手と感じている人のなかには、「聞き上手になりたい」という人も多いでしょう。
「話し上手は聞き上手」ということわざもある通り、話し上手になるためには聞き上手であることも求められます。
聞き上手な人の特徴を参考にしながら、コミュニケーション力を高めるためにどういった行動を意識すればよいのか、できることから少しずつトレーニングしていきましょう。
社内で円滑にコミュニケーションをとるコツや成功事例を紹介

さまざまな人が働く企業・組織において業務を円滑に遂行していくために、社内コミュニケーションは欠かせない要素です。
しかし、思うようにコミュニケーションがとれず悩む社員や、組織としてどういった対策を講じれば良いか分からず悩んでいる経営者や人事担当者も多いでしょう。
そこで本記事では、社内コミュニケーションを活性化するためのコツや成功事例などを中心に解説します。
社内コミュニケーションの重要性とは

社内コミュニケーションの活性化を目指す企業は少なくありません。
なぜ多くの企業で社内コミュニケーションは重要視されているのでしょうか。
考えられる理由として「多様化する働き方に対応するため」や「多様な価値観を持った社員同士が快適に働くため」などが挙げられます。
これらの理由について紹介します。
多様化する働き方に対応するため
近年、多くの企業ではテレワークが導入されるようになり、オフィス以外のさまざまな場所で働く光景は当たり前となりました。
しかし、従来は同じオフィスのなかで気軽に声をかけることができましたが、テレワークとなるとメールやチャット、電話をかけたりするのも面倒に感じ、自然とコミュニケーションが減ってしまいがちです。
その結果、連携不足によって重大なミスにつながることもあるでしょう。
社内コミュニケーションを活性化することで、多様な働き方のなかでも連携を強化しミスの削減にもつながっていきます。
多様な価値観をもった社員同士が快適に働くため
従来の日本社会は終身雇用や年功序列型の人事制度が主流でしたが、現在は雇用の流動化が進み転職は珍しいものではなくなりました。
その結果、さまざまな業種、職種を経験した多様なキャリアをもつ人材が同じ会社に集まることもあります。
社員によって仕事に対する考え方や価値観が異なるため、ときには軋轢を生み出すこともあるでしょう。
社内コミュニケーションを活性化し、社員同士がお互いを知ることで円満な人間関係を構築でき、快適な労働環境につながっていきます。
関連記事:苦手な人でもコミュ力を上げる方法はある?鍛えるメリットも紹介!
社内コミュニケーションにおける課題

社内コミュニケーションを活性化しようと考えても、さまざまな課題があり、思うように進んでいかないケースもあります。
具体的にどのようなことが問題となり得るのでしょうか。
- コミュニケーション環境の整備
- 細かなニュアンスの相違
- 世代間における価値観のギャップ
これらの典型的な例を紹介しましょう。
コミュニケーション環境の整備
働き方が多様化するなかで社内コミュニケーションを活性化するためには、対面以外で気軽に会話ができる環境を整備しなくてはなりません。
従来のようにメールや電話でも最低限のコミュニケーションはとれますが、「忙しいのではないか」、「仕事の邪魔になるのではないか」と考え、躊躇してしまうこともあります。
そのため、メールよりも気軽にやり取りできるビジネスチャットや、顔がよく見えるWeb会議システムなどの整備が求められます。
しかし、必要な機材やツールを新たに揃えなければならず、コスト面の負担が増大します。
細かなニュアンスの相違
ビジネスチャットやWeb会議システムなどを導入しても、対面によるコミュニケーションに比べると細かな表情や仕草までは確認しづらいものです。
その結果、本来の意味とは違ったニュアンスで伝わってしまったり、相手が誤解したまま話が進んでいったりすることもあります。
世代間における価値観のギャップ
企業や組織ではさまざまな世代の人が働いており、それぞれの世代によって価値観や考え方にギャップが生じることもあります。
たとえば、管理職や経営層を担うことが多い40代以上の世代は、長年にわたってオフィスへ出社して働く習慣が根付いており、オンラインでのコミュニケーションにうまく対応できないと感じる人も少なくありません。
一方、20代や30代といった比較的若い世代は、社会人になる前から身近にインターネットを活用してきた世代でもあり、オンラインでのコミュニケーションを受け入れやすい人も多いです。
関連記事:ノンバーバル(非言語)コミュニケーションの重要性とは?一例も紹介
社内コミュニケーションを活性化させるメリット

社内コミュニケーションを活性化することで、企業にとってはどのようなメリットがあるのでしょうか。
- 情報共有の不足や連携不足を解消できる
- 社員のモチベーションを向上できる
- 部署間での連携が強化できる
これらの活性化させるメリットについて紹介しましょう。
情報共有の不足や連携不足を解消できる
社内コミュニケーションが活性化すると、働く場所が変わっても気軽に連絡を取り合い、些細なことも相談できる体制が整います。
また、電話や対面でのコミュニケーションでは口頭で伝えた内容が残らず、忘れてしまうこともありますが、チャットなどを活用することでテキストデータとして残り、連携不足を解消できるでしょう。
社員のモチベーションを向上できる
仕事の悩みや職場の人間関係などを気軽に相談できる先輩や上司、同僚などがいれば、有効なアドバイスを受けられることも多いものです。
社員コミュニケーションを活性化することで、些細なことでも相談できる社員同士の関係性が構築でき、前向きに仕事に取り組めるようになるでしょう。
部署間での連携が強化できる
組織の規模が大きくなればなるほど、どの部署がどういった業務を行っているのか分からなくなることも少なくありません。
社内コミュニケーションを活性化できれば、部署にかかわらずさまざまな社員との交流が生まれるため、仕事で困ったときに他部署に助けを求めたり気軽に相談したりと、横の連携が強化されます。
関連記事:知らず知らずに起こっている?ハラスメントの種類や防止方法を紹介
社内で円滑にコミュニケーションをとるコツ
さまざまな人とコミュニケーションをとりたいと考えているものの、どう接したら良いか分からず戸惑う人も少なくありません。
社内におけるさまざまなシチュエーションに応じて、円滑なコミュニケーションをとるためのコツを以下のシーン別に紹介します。
- 会議でのコミュニケーションのコツ
- 上司と部下のコミュニケーションのコツ
- 部署間におけるコミュニケーションのコツ
順に紹介しましょう。
会議でのコミュニケーションのコツ
会議において重要なのは、参加者に分かりやすく説明し内容を理解してもらうことです。
そのためにもプレゼンや資料の説明においては、できるだけ結論から先に述べ、簡潔に話をまとめることが大切です。
また、会議では質問が上がらず本当に理解しているのか不安になることもあるでしょう。
参加者にしてみれば、最初の質問で挙手をするのは緊張するため、「◯◯さんは、ここまでの説明で分からないところはありませんか?」など、何人かに指名をしてみるのも有効です。
上司と部下のコミュニケーションのコツ
パワーハラスメントなどを恐れ、部下と思うようにコミュニケーションがとれていないと悩む上司も少なくありません。
円滑なコミュニケーションを実現するうえでは、部下をむやみに否定するのではなく、まずは良い部分を探し褒めることを意識しましょう。
そうすることで、部下にしてみれば自分は認められていると感じ、信頼関係を構築しやすくなります。
そのうえで、改善すべきところがあれば「◯◯を◯◯のように改善すればさらに良くなる」と優しい声のかけ方を意識しながらアドバイスをすることで、適切なマネジメントが実現できます。
部署間におけるコミュニケーションのコツ
部署やチームが異なると目に見えない壁のようなものを感じ、話しかけづらいと感じるものです。
しかし、このように感じているのは他部署の社員も同様であり、話しかけられるのを待っていてもなかなかコミュニケーションは生まれません。
そのため、自分から積極的に話しかけていくことが大切です。
たとえば社内イベントや交流会など、他部署の社員と交流できる場に参加してみると良いでしょう。
関連記事:聞き上手になるには?話し上手との違いや話の聞き方のコツを紹介
社内コミュニケーションの活性化で成功した事例

上記で紹介した内容は、コミュニケーションを円滑にするために社員一人ひとりができることです。
しかし、社内全体のコミュニケーションを活性化するためには、組織としての取り組みも重要です。
具体的にどういった成功事例があるのでしょうか。
- 全社員が利用できる交流の場を設置
- 社内イベントの実施
- 経営層からの動画メッセージ配信
上記の代表的なものをいくつかご紹介しましょう。
全社員が利用できる交流の場を設置
周りの社員が真剣に仕事をしている執務スペースで、雑談のような会話は抵抗を抱くものです。
また、執務スペースにこもった状態だと他部署の人と交流が生まれにくく、社内コミュニケーションの活性化にもつながりません。
そこで、休憩スペースやカフェ、バーなど、部署にかかわらず全社員が気軽に利用できる交流の場を設ける企業も多いです。
社内イベントの実施
社内コミュニケーションの活性化を目的として、社内イベントを実施する企業もあります。
イベントの種類はさまざまで、たとえばスポーツ大会やバーベキュー、社員旅行、飲み会、ランチ会などが代表的です。
このようなイベントでは、上司や同僚、部下の普段の仕事では見せないような意外な一面を見られるほか、普段交流がない他部署の人と自然と会話が生まれるきっかけにもなります。
ただし、これらのイベントを休日や業務終了後などに行う場合には、強制参加とはせずあくまでも任意参加とすることが前提となります。
経営層からの動画メッセージ配信
企業や組織の規模によっては、経営層とコミュニケーションをとれる機会が少なく、どのような方針・考え方で経営をしているのか社員に伝わりづらいこともあります。
社員一人ひとりとコミュニケーションができる規模の組織であれば対面での会話も有効ですが、それが難しい場合には動画メッセージなどで経営層の考え方や方針を伝える方法もあります。
まとめ
働き方の多様化やさまざまなバックグラウンドをもった人材が増えていることから、円滑に仕事を進めるためにも社内コミュニケーションの活性化は欠かせません。
社員同士が密に連携し情報共有の漏れをなくすことも大きな目的としてありますが、仕事の悩みを気軽に相談できる関係性をつくり、社員のモチベーションを向上させる意味でも社内コミュニケーションは重要です。
社員一人ひとりが実践できるコミュニケーションのコツを紹介しましたが、それ以外にも企業や組織として実践できることは数多くあります。
社内コミュニケーションの活性化を実現するためにも、まずはできることから実践していきましょう。
コミュ力を上げるにはどうしたらいい?高める方法を解説
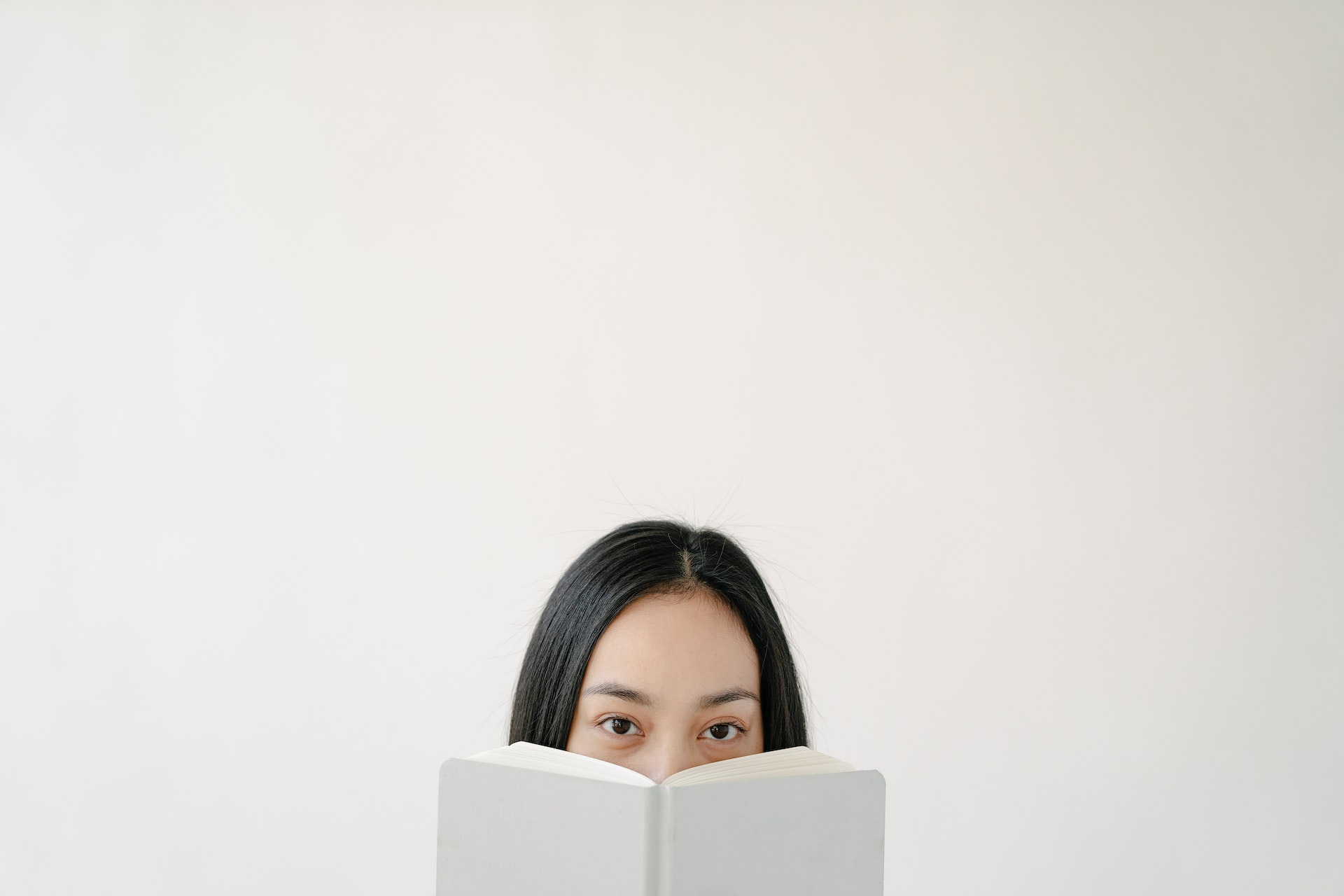
SNSや掲示板などにおいて、コミュ力(コミュニケーション能力)が低くて悩んでいるという声を多く目にします。
親しい友人や家族、恋人とは気兼ねなく話すことができても、初対面の人や職場の上司、同僚、取引先などとうまくコミュニケーションをとるのは難しいですよね。
そこで本記事では、コミュ力に自信がないと悩む人に向けてコミュ力を上げる方法をご紹介します。
現代でコミュ力が重要視される理由

なぜ近年になって「コミュ力」という言葉が生まれるほどコミュニケーション能力が重要視されるようになったのでしょうか。
厚生労働省が調査した「若年者の就職能力に関する実態調査」の結果を見ても、85.7%もの企業が採用時に重視する能力としてコミュニケーション能力を挙げています。
この背景には、働き方の多様化や職場環境の変化などが考えられます。
たとえば、近年多くの企業でテレワークが導入されるようになり、メールやチャット、Web会議などでやり取りする光景は珍しくなくなりました。
しかし、対面でのコミュニケーションに比べ、より緊密なコミュニケーションをとっていないと話の意図が伝わりづらく、仕事においてさまざまなトラブルや連携ミスを生じさせる原因にもなります。
これはビジネスの場面に限らず、プライベートにおいても共通していることから、これまで以上にコミュ力は重要視されるようになったと考えられます。
▶︎楽しくコミュ力をアップ
関連記事:ノンバーバル(非言語)コミュニケーションの重要性とは?一例も紹介
コミュ力が低い人と高い人の特徴

コミュ力が低い人と高い人を比較した場合、両者にはどのような特徴・違いがあるのでしょうか。
具体的な特徴として以下などが挙げられます。
- 周囲からの視線の感じ方
- 周囲の人に対する興味
- 周囲の人への心配り
これらの特徴について紹介しましょう。
周囲からの視線の感じ方
コミュ力が低い人の多くは、周囲の人から自分がどのように見られているのか過剰に気にしすぎてしまう特徴があります。
たとえば、「自分が発言することで場の雰囲気が悪くなるのではないか」、「的外れなことを言って変に思われているのではないか」と感じます。その結果、自然と発言する機会が減っていき、周囲の人との関係性も希薄になっていくことがあるのです。
これに対しコミュ力の高い人は、積極的に自分の意見を発信し、周囲の人から理解してもらおうとします。
また、相手の態度や表情にわずかな変化があったとしても、あまり深読みせずコミュニケーションを図ろうとする傾向も見られます。
周囲の人に対する興味
もうひとつの違いは、周囲の人に対する興味です。
コミュ力の低い人は、他人に対して興味をもてなかったり、話をするだけ無駄のように感じたりすることもあります。
「どうせ自分のことは分かってくれない」といった諦めや、そもそも一人でいることが好きで、必要以上の関わりを持とうとしない人も多いのです。
これに対しコミュ力の高い人は、自分のことを相手に理解してもらおうと考えると同時に、相手の人にも興味を示すことが多くあります。
たとえば、初対面の人であってもさまざまな話題を振って自分との共通点を見つけ出そうとしたり、興味のある話題に対してさまざまな質問をして話を深掘りしようとすることも多いです。
周囲の人への心配り
コミュ力と聞くと「話が上手な人」や「口が達者な人」、「明るい人」といったイメージをもたれがちですが、決してそればかりではありません。
コミュニケーションは相手が存在して初めて成立するため、お互いが心地よく話せる関係でなければならないのです。
コミュ力が低い人の場合、自然と早口になったり難しい専門用語を多用したりして、自分のペースで話すことも多く見られます。
しかし、相手にとっては聞き取りづらかったり、難しい話で内容についていけないと感じることもあるでしょう。
これに対しコミュ力の高い人は、相手の様子をうかがいながら会話のペースを落としたり、分かりやすい表現で噛み砕いて会話をしたりすることも多いです。
関連記事:スキンシップにはどんな効果がある?良好な関係性を維持するためのポイントとは
コミュニケーションが苦手な人でもコミュ力を上げることはできる?
コミュ力は生まれ持った才能や個人の性格によって決まるものと考える方も多いのではないでしょうか。
たしかに、積極的にコミュニケーションをとろうとする子どももいれば、引っ込み思案や人見知りでうまくコミュニケーションをとれない子どもも存在します。
しかし、結論からいえば大人になってからもコミュ力を高めることは十分可能です。
「自分はコミュ障だから無理」、「もともとコミュニケーションが苦手だから」と諦める必要はありません。
これは自分自身の性格や人格を変えるというものではなく、ちょっとした心がけや考え方を意識しながら、トレーニングをすることで変わっていきます。
関連記事:友達の作り方|場所と手順を社会人から学生ごとに分けて解説!
コミュ力を鍛えるメリット

トレーニングによってコミュ力を高めることで、どのようなメリットがあるのでしょうか。
メリットとして以下などあります。
- 円滑な人間関係が維持できる
- 交友関係を広げられる
- 困ったときに助けてもらえる仲間ができる
もうすこし詳しく紹介しましょう。
円滑な人間関係が維持できる
コミュ力が低いと、せっかく仲良くなっても自然と友達が離れていってしまったり、過去に一緒に働いていた仲間と疎遠になったりすることも少なくありません。
また、何気ない一言が原因で人間関係をこじれさせてしまうこともあるでしょう。
コミュ力を鍛えるということは、周囲の人がどう感じるかを見極め、心配りできる力を高めることでもあります。
交友関係を広げられる
コミュ力を高めると、現在の人間関係を維持すると同時に新たな交友関係を広げていくことにもつながります。
たとえば、共通の友人として知り合った初対面の人や取引先の担当者、新たに配属された同僚や部下などとコミュニケーションをとり、短い期間でも信頼関係を構築できるでしょう。
困ったときに助けてもらえる仲間ができる
ビジネスの場面はもちろん、プライベートにおいてもさまざまな悩みや困りごとを抱えることがあります。
たとえば、「初めてのプロジェクトで経験がなく、何から手をつければ良いのか分からない」、「ある友人とケンカをしてしまい、仲直りのきっかけがつくれない」など、悩みは人それぞれ異なります。
コミュ力が低いと、他人に頼ることができず一人で抱え込んでしまうケースも多いですが、コミュ力を高め良好な人間関係が構築できていれば、周囲の人に素直に悩みを打ち明け、助けを求めることもできます。
関連記事:聞き上手になるには?話し上手との違いや話の聞き方のコツを紹介
関連記事:将来への不安があるのは考えすぎ?不安解消への4つのアクション|上京ものがたり
コミュ力を上げる方法

コミュ力はトレーニング次第で高めていけると紹介しました。
では、具体的にどのような方法があるのでしょうか。
- 自分から挨拶する
- 相手の話を傾聴する
- 相手の話を否定しない
- 相手との共通点を見つける
- 相手の話のテンポに合わせる
- 比喩表現を用いる
- 相手を名前で呼ぶ
一例をご紹介します。
自分から挨拶をする
挨拶はコミュニケーションの基本であり、会話のきっかけにもなります。
たとえば職場に出勤したときや友人との待ち合わせ場所に合流したときなど、自分から積極的に挨拶をするように心がけましょう。
コミュニケーションが苦手で話題を振ることが難しくても、自分から挨拶をすることで雰囲気が明るくなることも多いです。
相手の話を傾聴する
傾聴とは、相手に共感しながら真摯な姿勢で話を聞くことを指します。
コミュニケーションが苦手な方は、まず相手の話を傾聴することから始めてみましょう。
真剣に話を聞いてくれていると感じると、多くの人は気持ちよく話題を提供し、会話が弾むことも多いものです。
具体的には、相手の目を見ながら話を聞き、ときには適度な相槌やオウム返しをすることも有効です。
相手の話を否定しない
相手の話を真剣に聞いていると、ときには間違った内容や自分とは相容れない意見を耳にすることもあるでしょう。
しかし相手の話を遮ったり、直接的に強い言葉で否定するのは避けたほうが良いでしょう。
まずは相手の話を最後まで聞き、そのうえで自分の意見を整理し簡潔に伝えることが大切です。
重要なのは相手を否定するのではなく、「自分はこう思う」といったように、あくまで自分自身を主語に意見を表明することです。
相手との共通点を見つける
積極的なコミュニケーションを心がけているにもかかわらず、話が盛り上がらないと悩んでいる方は、相手との共通点を見つけてみましょう。
たとえば、趣味や仕事、出身地、年齢などの共通点から話題を振ったり、質問を掘り下げていくことで話が盛り上がることも多いです。
相手と話のテンポを合わせる
自分から話をする際には、相手の状況を確認しながらテンポを調整することも大切です。
また、相手が早口であるにもかかわらず、自分がゆっくりしたペースで話しているとお互いにストレスを感じることもあるため、相手にペースを合わせて話すことも意識しましょう。
比喩表現を用いる
自分の理解度をベースに話を進めてしまうと、相手の理解度が追いつかず「置いてけぼりにされている」と感じられることも少なくありません。
専門的な内容や複雑な内容を話す場合には、相手に理解してもらえるよう比喩表現や例え話をするのもおすすめです。
相手を名前で呼ぶ
コミュ力を高めるためには自分に対して親しみを感じてもらい、話しやすい雰囲気をつくることも大切です。
そのためのテクニックとして、相手のことを名前で呼びかけるという方法があります。
自分の名前を呼んでもらうことで相手は親しみを感じやすく、徐々に距離も縮まっていきます。
関係性によっては、いきなり名前を呼ぶことに抵抗を感じることも多かったり、そもそも何と呼べば良いか分からないことも多いでしょう。
そのような場合には、相手に対して「何と呼べば良いですか?」と質問してみるのもおすすめです。
関連記事:【シーン別】人間関係がめんどくさいと感じる心理や対処法を解説
まとめ
ビジネスの場面はもちろん、プライベートにおいてもコミュ力は欠かせない能力のひとつです。
コミュニケーションが苦手でコミュ力が低いと悩む方も少なくありませんが、今からでも高めていくことは十分可能です。
今回紹介したトレーニング方法の例を参考に、少しずつできる範囲で継続していきましょう。
ノンバーバル(非言語)コミュニケーションの重要性を徹底解説!

ノンバーバル(非言語)コミュニケーションは、日常生活のさまざまな場面で信頼関係を構築するためにきわめて重要な役割を果たします。
本記事では、ノンバーバルコミュニケーションとはなにか、基本的な内容を紹介するとともに、その種類や具体的な行動の例、日常生活のなかで活用できる場面も併せて解説します。
ノンバーバル(非言語)コミュニケーションとは

ノンバーバルコミュニケーションとは非言語コミュニケーションともよばれ、その名の通り言葉以外の情報や感情を伝達するコミュニケーションの方法を指します。
たとえば、「おはようございます」という挨拶を例にとっても、笑顔で元気な挨拶をしたときには好印象を抱かれやすいですが、小さい声で相手の目を見ないまま挨拶をした場合、暗い印象を抱かれたり、ときには体調が悪いのではないかと心配されたりすることもあるでしょう。
このように、同じ言葉を伝えたとしても、言葉以外の要素によって相手が抱く印象や意味合いは大きく変わってくることから、円滑な人間関係を築くためにもノンバーバルコミュニケーションは重要です。
ノンバーバルコミュニケーションを構成する要素としては、身体的な動きや顔の表情、目の動き、声のトーンなど、さまざまなものが含まれます。
関連記事:苦手な人でもコミュ力を上げる方法はある?鍛えるメリットも紹介!
メラビアンの法則とノンバーバルコミュニケーションの関係性
ノンバーバルコミュニケーションの重要性を裏付けるものに、米国の心理学者であるアルバート・メラビアンが提唱した法則があります。
これは「7-38-55ルール」、または「3Vの法則」ともよばれます。
メラビアンは「コミュニケーションにおいて言葉から受け取る情報はごくわずかで、視覚や聴覚から得られる情報が多くを占める」ことを提唱しました。
具体的にはその人の見た目や表情などが全体の55%、声の大きさや話し方などが38%、そして言葉そのものから受け取る情報は全体の7%程度にすぎないという内容です。
実に9割以上がノンバーバルコミュニケーションで占められており、特に強い影響力をもっていることがわかります。
ノンバーバル(非言語)コミュニケーションの重要性

学術的な側面では上記で紹介した通り、ノンバーバルコミュニケーションが重要であることがわかりました。
では、実際のビジネスの場面や日常生活において、ノンバーバルコミュニケーションはどのように役立っているのでしょうか。
例えば、以下などが挙げられます。
- 細かいニュアンスを伝える
- 相手に対して安心感を与える
- 相手の状況を理解する
それぞれについて詳しく紹介しましょう。
細かいニュアンスを伝える
ビジネスや日常生活のなかでメールやチャットなどのテキストメッセージをやり取りすることも多いですが、文章だけでは真意が伝わりづらいこともあります。
たとえば、相手の話を理解したことを伝えるためには「了解しました」と短い文章でも意味は伝わりますが、相手との関係性によっては冷たい印象をもたれてしまう可能性もあるでしょう。
電話や対面など、ノンバーバルコミュニケーションが可能な環境であれば、声のトーンや表情などから細かいニュアンスも伝えられるでしょう。
相手に対して安心感を与える
上記で紹介したような最低限の情報をやり取りするコミュニケーションでは、機械的で冷たい印象をもたれるばかりか、お互いの心情が分からず不安を抱くこともあります。
その結果、本音でコミュニケーションが取りづらくなり、なんとなく話しかけづらい雰囲気やコミュニケーション不足が生まれる可能性もあるでしょう。
ノンバーバルコミュニケーションが可能な環境にあれば、そのような不安もなくなりお互いが安心して話し合うことができます。
相手の状況を理解する
コミュニケーションにおいて重要なのは、自分が言いたいことや伝えたいことを一方的に話すのではなく、相手が理解しているかどうか様子を見ながら会話をすることです。
もし、話の内容が理解できていないときは困った表情や首をかしげるなどの仕草が見られることもあります。一方で、十分話が理解できていれば、頷く回数が増えたり、相手の目を見ながら話を聞き入ったりすることが多いです。
ノンバーバルコミュニケーションでは相手の様子を確認しながら話を進めることができ、認識の齟齬が起きにくくなります。
関連記事:聞き上手になるには?話し上手との違いや話の聞き方のコツを紹介
ノンバーバル(非言語)コミュニケーションの効果
細かなニュアンスや感情を伝えたり、相手に対して安心感を与えたり、さらには相手の状況を理解するうえでもノンバーバルコミュニケーションは欠かせません。
これらを総合的に考えると、ノンバーバルコミュニケーションによって得られる効果は信頼関係を構築し、良好な人間関係を維持できるということです。
お互いの認識の齟齬を防ぐことでビジネスでもプライベートでもトラブルを防止できるほか、安心感を与えることでお互いに本音で話せる環境が整います。
また、相手の理解度に応じて表現や伝え方を変えることで、お互いのことを理解し合え、誤解を招く心配もなくなるでしょう。
関連記事:スキンシップにはどんな効果がある?良好な関係性を維持するためのポイントとは
ノンバーバル(非言語)コミュニケーションの種類と例

ノンバーバルコミュニケーションにはどういった種類があるのでしょうか。
具体的な種類には以下などが挙げられます。
- 身体動作
- 身体の特徴
- 接触行動
- 近言語
- プロセミクス
- 人工物の使用
- 環境
これらの種類について詳しく紹介しましょう。
身体動作
身体動作とは、いわゆるボディランゲージともよばれるものです。
言語が異なり言葉が通じない間柄であっても、身振り手振りを交えることで意思疎通が図れるという特徴があります。
たとえば、「はい」、「いいえ」という言葉を発さなくても、頷いたり首を横に振ったりすることで意思表示をすることも可能です。
身体の特徴
身体的な特徴としては、身だしなみを含めた外見的な特徴を指します。具体的には、髪型や髪の色、体型などが挙げられます。
たとえば、清潔感のある髪型の人は好印象を抱かれやすいといったものもノンバーバルコミュニケーションのひとつといえるでしょう。
接触行動
接触行動とはその名の通り、身体の一部に触れる行動を指します。
たとえば、相手に対して親しみや好意を伝える際、言葉だけでなく握手やハグなどをすることで気持ちが伝わりやすいです。
これも代表的なノンバーバルコミュニケーションのひとつといえます。
近言語
近言語とは、主に声の大きさやトーン、会話のスピード、相槌などを指します。
相槌のなかには頷きも含まれますが、近言語の場合は「えぇ」、「あぁ」などといった言葉が挙げられます。
プロクセミクス
プロクセミクスとは、相手との距離感や距離の取り方を指します。
たとえば、日本人の場合は初対面や顔見知り程度の人とは一定の距離を空けがちですが、親しくなっていくと徐々に物理的な距離も縮んでいきます。
人工物の使用
人工物とは、一般的に衣服やアクセサリー、メイクなどを指します。
友人や家族など親しい人と会うときにはラフな格好、仕事場や取引先、フォーマルな場で人と会うときにはスーツなどを着用するのが一般的です。
このようなTPOを考慮することで、相手に対して敬意を払っていたり親しみを感じているといったサインになり、ノンバーバルコミュニケーションのひとつといえます。
環境
環境とは、その名の通り部屋の照明や温度などを指します。
一見ノンバーバルコミュニケーションとは無関係のように思われますが、たとえば冷房や暖房を入れて快適な温度に設定しておくことで、相手を快く迎え入れるという意思を表示できます。
ノンバーバル(非言語)コミュニケーションを活用できる場面

ノンバーバルコミュニケーションはさまざまな場面で欠かせないコミュニケーション手段であることがわかりました。
具体的にどのようなシーンで活用できるのでしょうか。
- ビジネス
- 友人関係
- 夫婦関係
- 恋愛
これらのシーンで活用できる場面を紹介しましょう。
ビジネス
ビジネスの場面では上司や取引先、顧客などに複雑な内容を説明をしたり、商談でプレゼンを行ったりすることも多くあります。
一方的に説明をするのではなく、相手の表情や仕草をうかがうことで、疑問に感じていることや不安を引き出すことができるでしょう。
円滑なコミュニケーションによって認識の齟齬をなくし、トラブルを未然に防止することにもつながります。
関連記事:社内で円滑なコミュニケーションを取るコツや活性化の成功事例を紹介
友人関係
プライベートな場面では、良好な友人関係の構築・維持にも役立ちます。
たとえば、帰省の際に久しぶりに会った同級生や親友に対し、握手をしたりハグをしたりすることで言葉以上の親しみを表現できます。
また、会話の際に積極的に相槌をうったり、目を見て話したりすることで、相手への信頼を示すこともできるでしょう。
夫婦関係
同じ家のなかで暮らす時間が長くなっていくと、お互いのことを男性または女性として見られなくなり、夫婦関係に溝ができることもあります。
そこで、たとえば服装の雰囲気を変えてみたり、アクセサリーを身に着けたりすることで新鮮な印象に映り、夫婦のコミュニケーションが増える可能性もあるでしょう。
また、相手の話にはきちんと耳を傾けたり、目を見て話すといったことも夫婦間に求められる基本的なノンバーバルコミュニケーションのひとつです。
恋愛
恋愛においても夫婦関係のノンバーバルコミュニケーションと共通する部分は多いです。
ただし、好意を抱いている人がいて、これから交際に発展させていきたいという場合には、接触行動やプロクセミクスなどが重要といえます。
たとえば、複数人で食事や飲み会に行ったとき、あえて対面や横の席を確保することで距離が縮まり、好意を抱いてもらえる可能性もあるでしょう。
また、会話のなかで話が盛り上がったとき、自然と膝や腕、肩などにタッチすることも有効な場合があります。
ただし、執拗な接触行動は相手を不快にさせる可能性もあるため注意が必要です。
関連記事:【シーン別】人間関係がめんどくさいと感じる心理や対処法を解説
まとめ
非言語コミュニケーションともよばれるノンバーバルコミュニケーションは、円滑なコミュニケーションを行ううえで欠かせないものであり、さまざまな種類があります。
特に日本語はわずかな表現の違いで相手を不快にさせたり、誤解を生じさせてしまう可能性もあるため、特に重要なコミュニケーション手法といえるでしょう。
ビジネスの場面はもちろんのこと、友人関係や夫婦関係、さらには恋愛関係に発展させるうえでも役立ちます。
正しい知識を理解したうえで、ノンバーバルコミュニケーションを日常生活に役立てていきましょう。
相談1:子供の心を垣間見る方法 (3歳〜小学生低学年向け)

読者からの相談:
子供たちとのコミュニケーションについて悩んでいます。
3歳と6歳の子供がいます。子供たちが学校から帰ってくると 「今日、学校はどうだった?」とか「友だちと何をしたの?」など質問をしていますが、子供たちは 「別に」「特になにもない」と短い答えで済ませることが多いです。
子供がもっと答えやすいように、質問のしかたを変えてみるべきでしょうか。それとも、「そうなのね」とだけ返事をして、そっとしておくべきでしょうか?
ジョアンナさんの回答:
多くの親が抱く疑問ですね。幼い子供たちは、「今この瞬間」に集中しているものです。 自分の人生が今動いているということに全神経がいっています。 つまり、多くの子供たちにとって、家に帰って来た時には、学校での出来事はすでに過去のものとなっています。
子供にとって何かとても重大だと感じたことが起きた時には、そのことを親に伝えたがるものです。しかし「普段の生活」の詳細を話すことが大切だとは思っていないことが多いでしょう。
さらに、とても幼い子供の場合は、自分が今日した活動の全てを、親のあなたがすでに知っていると思い込んでいる場合もあるのです。
アドバイスの1つとしては、回答に制約を設けないオープンエンドの質問をすることで、会話が始まることもあります。例えば、こんな風に声をかけてみたらどうでしょうか。
- 今日、学校で絵を描いた人はいるのかしら?
- 今日、とってもおいしいおやつを持ってきた人はいるのかな?
- 学校では、手びょうしやダンスをしながら歌を歌うの?
- 今日、お友達の〇〇ちゃんは学校に来たかな?
- 今日は、学校でおもしろいお話を聞いたかな?
- 今日は少し雨が降っていたね。おそとには行けたかな?
- 学校で鬼ごっこをしたりする?
- もし、あなたの一日の絵を描くとしたら、どんな絵にしたいかな?
また、1日中、学校で過ごした子供は、ゆっくりする時間も必要になります。
幼い子供たちにとって、社交的に集団行動に合わせる学校での1日はとても疲れる時間です。また、内気で内向的な子供にとっては、さらに負担を大きく感じるかもしれません。そういう子にとって、家に帰ってきてから、しばらくは会話をしたり、社交的に振る舞うのはおっくうに感じるかもしれません。そういう場合は、おやつを食べたり、静かな時間を過ごしたりするのが良いかもしれませんね。
「今、何をしたい?」と聞くと、ちゃんと教えてくれる子もいます。少しリラックスできた後なら、パズルをしたり絵を描いたりなどの別の遊びをしながら、気軽に話をしはじめることもあるでしょう。
私の住むここアメリカでは、例えば家族がそろった夕食時に、みんなでその日のことを話す時間を設けている家庭もありますよ。その日に一番良かったこと、一番いやだったこと、一番楽しかったことや一番つらかったこと、または最も楽しかったことや最も退屈だったことなど。
ここでとても重要なのが、「静かに聞く」という姿勢です。

質問やアドバイス、リアクションなども控えて、心から子供の言葉に耳を傾けることを徹底します。例え、子供の話がトンチンカンだったとしてもです。
子供たちは、親が自分の言いたいことをすでに知っていると思ったり、親にだめだと言われると感じれば、沈黙する傾向があります。子供がこの場は自分の本音を話しても安全な空間なんだと思えるようにすることが最も大切です。
もし、何かコメントをしたければ、子供の言ったことをリフレーミングしてみましょう。
「今日は〇〇なことを感じた日だったのね」「今日は、〇〇があったのね」など、聞いた言葉をリピートするだけで十分です。
そして、家族のみんなが参加することで、自分の一日についてシェアすることが習慣になり、子供の心の内側が少しずつ垣間見ることができるようになりますよ。
子供のペースはゆっくりです。また習慣の変化も1日2日試したからと言って起こりません。ゆっくり気長に楽しみながら少しずつ起こる変化を観察していってみてくださいね。

ジョアンナ・ウィギントン氏
助産師として600人以上のお産に携わる。
教育者であり、アーティスト。北カリフォルニア在住。
20年以上にわたりオルタナティブ教育施設であるカスパー・クリーク・ラーニング・センターを創設・指導してきた。
現在はNPO組織Flockworksの活動に参加し、子供や教師をサポートしている。
アートの力を広めるためのプログラムを展開中。すべての人がアーティストであるという強い信念を持ち、若者から年配の人までが創造力を探求する機会を作り出している。
モラハラ夫の特徴は?人格否定の言葉を一覧で紹介
結婚生活を送っていると、独身時代では見えなかった一面が見えてくることもあります。
特に多く聞かれるのが、モラハラ(モラルハラスメント)にあたるような言葉の暴力です。
本記事では、夫からのモラハラに悩む女性に向けて、モラハラ夫にはどんな特徴があるのか、モラハラの一例や子どもへの影響、正しい対処法について解説します。
モラハラ夫の特徴

モラルハラスメント(モラハラ)とは、精神的な暴力や嫌がらせなどによって、相手の尊厳を傷つける行動を指します。
モラハラは特に夫婦間で問題になるケースが多く、夫から妻に対して行われるモラハラが多いですが、妻から夫に対して行われるパターンもあります。
モラハラを繰り返す夫には、主に以下のような特徴が見られます。
- 支配欲が強い
- 自己中心的
- 感情の制御が難しい
- 人格否定
これらの特徴について紹介しましょう。
支配欲が強い
モラハラ行為をする夫は、自分の思う通りに妻をコントロールしたいという支配欲が強い傾向があります。
自己中心的
妻の気持ちや心情は顧みることなく、夫自身の思いや考えを優先する傾向が見られます。
また、自分の意見や考えを強制し、妻に対して選択の自由を与えないこともあります。
感情の制御が難しい
ちょっとした出来事やタイミングで怒りが頂点に達し、感情を適切に処理できないことがあります。
人格否定
妻本人の人格や能力を否定する言葉を頻繁に投げかける傾向があります。
関連記事:知らず知らずに起こっている?ハラスメントの種類や防止方法を紹介
モラハラ夫の発言例
モラハラ夫は自己中心的で感情の抑制が難しいといった特徴がありますが、具体的にどういった言葉を発するのでしょうか。
- ミスや失敗を執拗に責め立てる例
- 人格を否定する発言の例
- 大声で怒鳴る例
これらの一例を紹介します。
ミスや失敗を執拗に責め立てる例
- 「また同じミスを繰り返すなんて、お前は何を考えているんだ?」
- 「こんな簡単なこともできないのか?教えたはずだろう?」
- 「何度同じことを言わせるんだ?一度で理解しろよ」
ミスや失敗をしたとき、それを指摘したり正しい方向に導くのは夫婦として当たり前のことですが、強い口調や何度も責め立てる行為はモラハラにあたる可能性が高いでしょう。
人格を否定する発言の例
- 「お前の考えはいつも間違っている」
- 「お前は役立たずだ」
- 「誰もお前のような人間を必要としないだろう」
ミスや失敗をしたり、間違った意見を述べたりしたときには、その事実を冷静に諭すことが大切です。
しかし、妻本人の人格を否定するような強い言葉を日常的に投げかけていると、モラハラにあたる可能性があります。
大声で怒鳴る例
- 「お前はいつも全てを台無しにする!」
- 「何もかもお前のせいだ!」
- 「いつもお前のせいで俺の時間を無駄にしている!」
大きな声や音を出されると、誰しも恐怖を感じ萎縮してしまうものです。
大声で怒鳴るという行為は、上記のセリフに該当しなかったとしても、その行為自体がモラハラとみなされる可能性があります。
関連記事:情緒不安定になると泣くのはなぜ?|情緒不安定になりやすい人や原因とは
モラハラ夫かもしれないチェック項目

一口にモラハラ(モラルハラスメント)といってもさまざまなパターンがあり、人によっても言動は異なります。
モラハラをする夫にはどういった特徴が見られるのか、代表的なポイントは以下の通りです。
- 妻が楽しく会話をしていると気に入らない態度を見せたり、不機嫌になる
- 明らかに夫に落ち度があるにもかかわらず、妻に謝らない
- 妻のミスや失敗を執拗に責め立てる
- 気に入らないことがあったり、機嫌が悪かったりすると妻を無視する
- 嘘をつく
- 妻および妻の家族や友人の人格を否定する言葉を言う
- 過度な嫉妬・依存・束縛
- 大声で怒鳴る・わざと大きな音を出す
- 妻の仕事を無理やり辞めさせる
- 家族や友人との交遊を制限する
上記はあくまでも一例に過ぎず、細かく見ていくとこれ以外にもモラハラにあたる言動や行動はあります。
自分の夫がモラハラを行っているのか、よくわからない場合には、上記の特徴にどの程度該当しているのかをチェックしてみましょう。
もし、該当項目が多ければモラハラ夫である可能性が高いかもしれません。
モラハラ夫になりやすい人の特徴や原因
結婚したばかりの頃はうまくいっていたのに、結婚生活を送るうちにモラハラ行為が行われるようになるケースが少なくありません。
どういった人がモラハラ夫になりやすいのでしょうか?
- 自尊心が低い
- 幼少期の家庭環境や周囲の環境
- 偏った思想・価値観
その特徴や原因についても紹介しましょう。
自尊心が低い
もともと自尊心が低い人のなかには、他人を否定したり支配したりすることで自己肯定感を満たすケースがあります。
結婚前の段階ではパートナーに対してそのような言動をしていなくても、第三者に対して否定的な言葉や言動を繰り返している場合、結婚後にモラハラ夫へと変貌する可能性は否定できません。
幼少期の家庭環境や周囲の環境
幼少期や思春期の家庭環境や、周囲の環境がモラハラの原因となることがあります。
たとえば、幼少期に親などから虐待・ネグレクトを受けた経験がある人や、適切な教育を受けてこなかった人の場合、周囲の人との接し方に戸惑い人間関係にさまざまな影響を与えるケースがあります。
偏った思想・価値観
偏った思想や価値観がモラハラの原因になることもあります。
たとえば、男性が強く支配的であるべきという価値観に囚われすぎていると、現代社会の価値観とはマッチせずそれがストレスを生み、モラハラを悪化させる要素になることもあるでしょう。
関連記事:感情の起伏が激しい人や少ない人の特徴|上手にコントロールする方法とは
モラハラ夫による子供への影響

モラハラ夫が子供に与える影響は深刻で、時には子どもの精神や健康にも影響を及ぼす可能性があります。
具体的にどういった影響が考えられるのか?
- 自尊心の低下
- 精神的な不安・障害
- 人間関係のトラブル
それぞれ紹介しましょう。
自尊心の低下
親から自分自身を否定される言葉を投げかけられた子どもは、つねに否定的な見方をするようになり、「自分はだめな人間だ」と感じ自尊心の低下を招きます。
精神的な不安・障害
モラハラを受けた子供は精神状態が不安定になる可能性があり、不安や抑うつといった状態が続きます。
あまりにも酷いモラハラを受けた場合、PTSD(心的外傷後ストレス障害)を引き起こすおそれもあり、精神的に立ち直るまで長い時間を要する可能性もあるでしょう。
人間関係のトラブル
モラハラを受けた子供はつねに否定的な見方をするようになりますが、それは自分自身だけでなく、第三者に対しても向けられることがあります。
自宅の外でも親の言動を真似するようになり、やがて友人や知人との人間関係が悪化しさまざまなトラブルを引き起こす可能性もあるでしょう。
関連記事:自己肯定感が低い子供の特徴や言動とは|注意すべき親の発言や行動
モラハラ夫への対処法・仕返しはしてもいい?
自分自身がされてきたことを振り返ると、夫に何らかの仕返しや制裁をしたくなる気持ちも理解できますが、仕返しは絶対に避けるべきです。
モラハラ夫への対処を一歩間違うと、場合によっては危害を加えられたり、余計に関係がこじれてしまう危険があるためです。
では、どのような対処が正しいのでしょうか。
- 自己認識する
- 証拠の記録
- 安全な場所に避難する
- 支援を求める
これらの対処法について詳しく紹介しましょう。
自己認識をする
モラハラは物理的な虐待とは異なり、はっきりと見える証拠がないほか、夫の言い分によっては「自分にも悪いところがあるのかもしれない」と錯覚しがちです。
実際に悪いところがあったとしても、執拗に責め立てたり、人格を否定するような言葉を投げかける行為は立派なモラハラであり、自分がその被害に遭っているとしっかり認識することが何よりも大切です。
証拠の記録
可能であれば、万が一に備えてモラハラ行為が行われている状況を記録しておきましょう。
具体的には、メールやチャットなどのテキストデータ、モラハラ行為を収めた動画や写真のほか、日記も立派な証拠になり得ます。
安全な場所に避難する
モラハラ行為がエスカレートし、自分自身に危害が及んだり、精神的に限界を迎えそうになったときには、安全な場所に避難することも考えてください。
実家はもちろんのこと、信頼できる友人の家、ホテルなどが一般的ですが、ほかにもDV被害者を守るためのシェルターなどもあります。
支援を求める
モラハラは一人で解決することが難しい問題です。
夫婦間の問題だからといって一人で抱え込んでしまうと、夫からのモラハラ行為がさらにエスカレートし、警察沙汰になることも十分考えられます。
一人で悩むのではなく、まずは信頼できる友人や家族などに相談し、必要であれば心理カウンセラーや専門家、地域の支援団体などに頼ってみるのもひとつの方法です。
関連記事:夫婦関係は修復できる?よくある破綻のきっかけや修復方法を紹介
まとめ
モラハラという言葉は聞いたことがあっても、自分の夫が行っている行為がモラハラにあたるのか分からず、自分の考え過ぎなのではないかと捉えてしまうケースも少なくありません。
もし、「夫からモラハラを受けているかもしれない」と感じたときには、今回紹介したチェック項目や発言例、対処法を参考にしながら、自分自身を守るための行動に移してみてください。
友達を作る場所はどこ?社会人で遊ぶ友達がいないのはやばい?
「自分には友達とよべる存在がいない、または少ない」と感じ、友達作りに苦手意識をもっている方も多いのではないでしょうか。
特に社会人になると学生時代の友達と遊ぶ機会も減り、友達の数が減っていくケースも少なくありません。
そこで本記事では、新たに友達を作るためにはどういった方法があるのか、友達作りに適した場所も紹介します。
友達を作るメリット

そもそも、友達を作ることは私たちが生活を送るうえでどういったメリットがあるのでしょうか。
具体的なメリットとして以下などが挙げられます。
- 楽しい時間を共有できる
- 第三者の視点でアドバイスが受けられる
- 不安・悩みの低減
これらの具体的なメリットについて詳しく紹介しましょう。
楽しい時間を共有できる
友達と過ごす時間はかけがえのないものであり、笑いや喜び、楽しみを提供し、人生を豊かなものにしてくれます。
このような時間は決してお金で買うことはできず、何物にも代えられない幸福感を得られるはずです。
第三者の視点でアドバイスが受けられる
人は誰でも長所と短所があり、本人が気づかないことも少なくありません。
だからこそ客観的な立場から指摘やアドバイスをしてくれる友達の存在は大きく、自分自身の成長にもつながっていきます。
不安・悩みの低減
私たちが生活していくうえではさまざまなストレスがあり、不安を感じることが少なくありません。
また、仕事や私生活における悩みを抱えることも多く、中には家族に話せないような悩みもあるでしょう。
そのようなとき、友達の存在は非常に大きく、話を聞いてもらうだけでも精神的な不安や悩みを低減できる場合もあります。
関連記事:友達がいないってやばいこと?寂しいと感じた時の対処法
友達がいなくても作ることができる?
友達がいない、または少ない人のなかには「自分にはこの先、友達ができないのではないか」と感じるケースもあるでしょう。
しかし、結論からいえば、現在友達がいない、あるいは少ない状態であっても、具体的な行動を起こしていけば必ず新たな友達を作ることは可能です。
決して悲観的になる必要はなく、焦らず自分のペースでさまざまな人とコミュニケーションをとりながら、信頼できる友達を見つけていきましょう。
関連記事:【シーン別】人間関係がめんどくさいと感じる心理や対処法を解説
学校での友達の作り方とは

友達と聞くと、幼馴染や学生時代から付き合いのある古い友人関係をイメージすることも少なくありません。
では、中学生や高校生が学校で友達を作るためには、どういった方法があるのでしょうか。
具体的には「共通の持つ人を見つける」や「他人を尊重する」などが挙げられます。
共通の趣味をもつ人を見つける
中学生や高校生は特に多感な世代であり、ゲームや音楽、スポーツなど、さまざまなことに興味をもちます。
人によっても興味をもつ事柄やコンテンツは異なりますが、知らない人と距離を近づけるためには共通の趣味に関する話題を切り出してみると良いでしょう。
もしかすると、同じように共通の趣味をもつ仲間を紹介し交友関係が広がっていく可能性もあります。
他人を尊重する
学校という場は社会の基本を学ぶ場でもあり、コミュニケーションのとり方もそのひとつです。
友達を作るためには、相手を尊重する気持ちと姿勢が何よりも大切です。
「尊重」という言葉は抽象的でわかりにくいですが、具体的には相手の話を最後まで聞く、悪口を言わない、相手のことを否定しないことなどが挙げられます。
尊重する気持ちがないと、相手は警戒心を抱いてしまい、信頼できる仲間になろうという気持ちが薄らいでいってしまいます。
たとえ友達という関係にならなかったとしても、クラスの一人ひとりに対して尊重する気持ちをもっていれば好印象を抱かれ、良好な人間関係を構築できるはずです。
関連記事:自己肯定感が低い子供の特徴や言動とは|注意すべき親の発言や行動
社会人の友達の作り方とは
学校を卒業し社会人になると、仕事や家事、子育てなどで時間がとれず、新たな友達を作る機会も減ってきます。
そのような状況下でも友達を作りたいと考えた場合、どういった方法があるのでしょうか。
- 友達を作りたい場所に出かけてみる
- こまめに連絡をとる
- 仕事を頑張る
これらの方法について詳しく紹介しましょう。
友達を作りたい場所に出かけてみる
社会人の場合、新たな人脈を作ろうと考えても会社と家の往復ばかりで、出会いが見つからないケースも少なくありません。
そこで、まず大切なのは自分から積極的に外に出て、友達を作れる場所を見つけることです。
共通の趣味で盛り上がれる人や、同世代の友達が欲しい場合には、そのような人が集まりそうな場所を探してみるのが友達作りの第一歩となるでしょう。
こまめに連絡をとる
友達という深い関係になかったとしても、知人や顔見知り程度の人も多いはずです。
もし、その中に「この人と仲良くなりたい、友達になりたい」と感じる人がいれば、積極的に連絡を取り合ったり、声をかけて連絡先を交換したりしましょう。
こまめに連絡を取り合うことでお互いのことがより深く理解でき、友達に発展していく可能性も出てくるでしょう。
仕事を頑張る
就職や転職を機に上京した場合、新たな環境のなかで仕事を覚えなくてはなりません。
そのため、まずは新たな仕事に慣れるためにも、仕事に集中しましょう。
プライベートのことは忘れ仕事に取り組むことで、時間が経つのを忘れ充実感を得られるでしょう。
また、同僚や上司とのコミュニケーションも生まれ、職場のなかで交友関係が広がっていくことで孤独感が解消できるかもしれません。
関連記事:地元の友達と疎遠に…?そんな時に効果的な対応方法|上京ものがたり
友達を作るのにおすすめの場所

社会人にとって、新たに友達を作るためには自分から外に出て出会いを探すことが大切であるとお伝えしました。
しかし、これだけでは抽象的で、どこに出かければ良いのか分からないという方も多いでしょう。
代表的なおすすめの場所として以下などが挙げられます。
- スポーツジム
- サークル・カルチャースクール
- 異業種交流会
- ライブハウス・音楽フェス
ここからは、友達を作るのにおすすめの場所を詳しく紹介します。
スポーツジム
運動不足の解消や体力作り、ダイエットなどを目的としてスポーツジムに通っている人も多いのではないでしょうか。
スポーツジムは週に数回、定期的に通うケースが多いほか、仕事終わりや週末など決まった時間帯に通うことが多いはずです。
通っているうちに自然と顔見知りの人も増えてくるため、少しずつ仲良くなって新しい友達ができる可能性もあります。
サークル・カルチャースクール
社会人になっても趣味を楽しんだり、新たなことに挑戦したりするために、サークルやカルチャースクールに通う人も少なくありません。
同じ趣味をもっていたり、共通の目標に向かって努力している人の集まりでもあるため、自分から積極的に声をかけることで友達の関係に発展していく可能性は高いでしょう。
異業種交流会
さまざまなことに興味があり、あえて自分とは知らない世界の人と友達を作ってみたいと考える方もいるでしょう。
そのような場合には、異業種交流会に参加してみるのもおすすめです。
ビジネスを目的として参加している人も多いですが、純粋に新たな人脈を作るために参加している人も少なくありません。
自分自身が在籍している組織や業界、業種とは文化の異なる人と交流することで、新たな発見をしたり魅力的な人に出会える可能性があります。
ライブハウス・音楽フェス
音楽が趣味の人であれば、ライブハウスや音楽フェスなどに行ってみるのもおすすめです。
一人で行くことに抵抗を感じる方も多いですが、実際に会場に行ってみると一人でも楽しんでいる人は意外と少なくありません。
何よりも共通の趣味をもっているため、勇気を出して自分から話しかけることで話が弾み、友達を作れる可能性があります。
関連記事:セルフ・コンパッションとは?やり方やマインドフルネスとの違いを解説
アプリやゲームで友達を作るのはアリ?
スマートフォンでも気軽にできるオンラインゲームが発達し、プレイヤー同士で直接交流できるようになりました。
また、近年ではマッチングアプリのユーザーも多く、自宅にいながら多くの人とコミュニケーションをとることができます。
一見すると便利なツールのように思われますが、これらの方法で友達を作る際にはリスクや危険があることも覚えておかなくてはなりません。
たとえば、アプリ上では同性だと思ってやり取りしていたのに、実際に会ってみたら異性がやってきて、さまざまなトラブルに巻き込まれるリスクもあるでしょう。
アプリやゲームで仲良くなったからといって、すぐに会おうとするのではなく、本当にその人が信頼できる人物であるかを見極めることが大切です。
異性の友達を作り方
同性の多い職場や学校などに在籍している場合、異性とコミュニケーションをとる機会が極端に少ないという方も多いでしょう。
もし、異性の友達を作りたいときには、上記で紹介したスポーツジムやサークル、カルチャースクール、異業種交流会などに出かけてみるのもおすすめです。
また、合コンや街コン、友人の結婚式も異性の友達を作るための絶好の場所といえます。
ただし、自分自身は友達を作りたいと考えているのに、相手によっては恋人や結婚相手を探しているというケースも少なくありません。
お互いの認識違いによってトラブルに発展しないよう、十分にコミュニケーションをとることが求められます。
▶︎愛情表現の言葉とは?|愛してるよりも愛が伝わる方法を紹介
まとめ
友達が少ない方にとって、一から人脈を築いていくことは大変で面倒に感じてしまうものです。
しかし、だからといって家に引きこもっていたり、友達作りを放棄してしまうと、悩みは解決できないままになってしまいます。
今回紹介した友達作りの方法やおすすめの場所を参考にしながら、まずは一歩を踏み出す勇気をもち、行動に移してみましょう。
友達がいないってやばいこと?寂しいと感じた時の対処法
休日やイベントがあるときなど、街を見渡すと楽しそうに友達同士で楽しんでいる人を見かけます。
そのような光景を目にしたとき、友達とよべる存在がおらず寂しい気持ちになった経験はないでしょうか。
本記事では、友達がいなくて悩んでいる方に向けて、寂しさを感じたときの対処法などを詳しく解説します。
友達がいないと寂しく感じるとき

普段は一人でいるのが当たり前に感じていても、友達がいないことを寂しく感じる瞬間は存在します。
具体的にどういったときに寂しさを感じやすいのでしょうか?
- 一人暮らし
- 結婚式
- 成人式・同窓会
- 学校
上記の代表的な例を詳しく紹介しましょう。
一人暮らし
大学や専門学校へ進学したタイミングや、社会人になったタイミングで一人暮らしをする方も少なくありません。
友達を自宅に招いて食事やお酒、ゲームなどを楽しむことも多いですが、友達がいないとそのような体験ができず、寂しさを感じることがあるでしょう。
結婚式
結婚式では日頃からお世話になっている友達や知人を招いて祝ってもらうのが一般的です。
しかし、友達がいないと特別な日を共有する人が少なく、寂しいと感じるかもしれません。
成人式・同窓会
成人式や同窓会は、学生時代をともに過ごした仲間と再会する貴重な機会でもあります。
友人同士で青春時代を懐かしんだり、近況報告をして盛り上がったりするのが定番ですが、友達がいないと成人式や同窓会の場に行くこと自体が億劫に感じたり、そもそも呼ばれなかったりして自然と疎遠になってしまいがちです。
学校
学校は社会生活やルールを学ぶ場でもあり、友達がいると学校生活がより楽しく有意義に感じられるものです。
しかし、学校で友達ができないと孤独を感じ、学校へ行くこと自体に恐怖を覚えるケースも少なくありません。
関連記事:【シーン別】人間関係がめんどくさいと感じる心理や対処法を解説
友達がいない人の特徴

友達がいない、または少ない人は、その人の性格や過去の経験、さらには現在の生活状況などが影響を及ぼすことがあります。
一概に全ての人に当てはまるものではありませんが、具体的にどういった特徴が見られるのか。
- 内向的な性格
- コミュニケーションが苦手
- 自尊心が低い
ここでは、友達がいない人の特徴について解説しましょう。
内向的な性格
内向的な性格の人は自分自身の世界に引きこもり、自分から他者と積極的に交流をしようとしない傾向が見られます。
内向的な性格の人は、他者と一緒にいるよりも一人でいることを好むため、友達ができたとしても自然と疎遠になっていきやすい傾向にあります。
コミュニケーションが苦手
コミュニケーションが苦手な人も友達が作りにくく、一人になりがちな傾向にあります。
一口にコミュニケーションといってもさまざまで、たとえば感情の表現が苦手な人もいれば、共感の意思を伝えるのが苦手な人、相手が話す言葉の真意を汲み取ることが苦手な人など、多種多様です。
自尊心が低い
自分に自信がなく、自尊心が低い人は友人関係を築くのが難しく感じることがあります。
たとえば、外見にコンプレックスを抱いている、極端に相手に気を遣ってしまう、過去に大きな失敗やいじめを受けた経験があるなど、自尊心が低くなる要因はさまざまです。
自尊心が低すぎると、「自分にはどうせ友達ができない」と諦め、他者との交流を断ってしまうケースもあります。
関連記事:情緒不安定な女性に多い症状とは|対処法についても紹介
友達がいない人の割合
「友達がいない」と自覚している人のなかには、自分と同じような境遇にある人はどの程度存在するのか気になってる方も多いはずです。
特に、2020年に入ってからはコロナ禍もあり、友達を作る機会や友達と会う機会も減ったことから、このような悩みを抱える人が増えたことは想像に難くありません。
BIGLOBEが2022年9月に実施した調査によると、「友達がいない」と回答した人の割合は40代がもっとも多く、52.0%でした。
次いで20代の49.8%、30代の49.0%と続きます。
一方、もっとも割合が少なかったのは10代で、35.0%という結果になりました。
社会人になると友達がいなくなる?
上記の結果から見えてくるのは、10代に比べて20代以上が「友達がいない」と感じていることです。
20代といえば大学や専門学校などを卒業し、社会人として働き始める年代であり、さらに30代や40代になると結婚をして子育てが忙しくなっていきます。
学生時代の友達と再会したり、新しく友達を作って遊んだりする時間も作りにくく、自然と友達と疎遠になっていくケースも多いようです。
また、仮に自分自身が結婚をしなかったとしても、周囲の友達が次々と結婚や出産をしていくと、自分から友達を誘いにくくなってしまうケースも少なくありません。
関連記事:友達の作り方|場所と手順を社会人から学生ごとに分けて解説!
毒親育ちは友達がいない?
友達がいない、または少ない人は、本人の価値観や考え方、性格や言動などに原因があるケースもあれば、周囲の環境が要因となっているケースもあります。
そのなかでも、典型的な例ともいえるのが親との関係性です。
いわゆる「毒親」のもとで育った子どもは、友達付き合いに親が口を挟んできたり、親から酷い言葉や暴力を繰り返されたりすることで、人間不信となることがあります。
自分以外の人を信じることができなくなり、つねに怯えたような性格になることで、友達になりたい人が現れてもそれを拒否してしまうのです。
もちろん、毒親のもとで育った子どものなかにも、友達ができて良好な人間関係を構築している人も大勢います。
一方で、友達がいない人の家庭環境は、必ずしも良好とはいえないケースが多いものです。
関連記事:自己肯定感が低い子供の特徴や言動とは|注意すべき親の発言や行動
友達がいなくて寂しいと感じた時の対処法

友達がいないことで寂しいと感じたとき、自分自身のメンタルを安定させるためにどういった対処法が効果的なのでしょうか。
具体的に以下などの対処法が挙げられます。
- オンラインに交流してみる
- 親しくしていた友人に連絡してみる
- 外に出かけてみる
これらの寂しいと感じた時の対処法について詳しく紹介しましょう。
オンラインで交流してみる
寂しさを感じるときは友達を作ることがベストな対処法といえますが、すぐに他人と信頼関係を築くことは難しいものです。
また、いきなり対面でのコミュニケーションをとることに抵抗を抱く方も多いでしょう。
そこで、まずはSNSなどを通してさまざまな人と交流してみるのがおすすめです。
親しくしていた友人に連絡してみる
オンラインであったとしても、顔の見えない知らない人と交流することに抵抗を抱く方もいるかもしれません。
そのような場合には、学生時代の友人や以前働いていた職場やアルバイト先の同僚など、親しくしていた人に連絡をとってみるのもおすすめです。
久しぶりに連絡をもらうと嬉しい気持ちになる人は多く、そこから話が弾んで友達としての関係が再スタートする可能性もあるでしょう。
外に出かけてみる
友達がいなく寂しい気持ちはあるものの、SNSで交流したり、仲が良かった人に連絡するといったアクションを自分からとることは勇気がいるものです。
あくまでも自然な形で友達を作りたいと考える方は、自宅の中にいるのではなく、できるだけ外に出かけてみることが第一歩となります。
たとえば、飲食店の店員さんに声をかけられて話が弾み、常連さんを紹介してもらい交友関係が広がっていくことも考えられるでしょう。
関連記事:セルフ・コンパッションとは?やり方やマインドフルネスとの違いを解説
友達がいないことってやばいことなの?
「友達がいない」と聞くと、なんとなく暗い人というイメージをもたれがちです。
たしかにコミュニケーションが苦手で、自分から話しかけることができずに友達をつくれなかったという方もいるでしょう。
しかし、だからといって悲観的になりすぎることはありません。
上記でも紹介したように、「友達がいない」と回答した人は決して少なくはありません。
「自分だけがおかしい、やばい」などと考える必要はないのです。
関連記事:地元の友達と疎遠に…?そんな時に効果的な対応方法|上京ものがたり
まとめ
友達がいない、少ないと、普段は一人で快適な生活ができていても、ふとしたときに寂しさを感じることがあります。
友達がいないことを気にするあまり、さらに自分の殻に閉じこもってしまう人も少なくありません。
しかし、友達をつくりたいと考え、行動に移すことで、考え方や価値観のあう友達は必ず見つかるはずです。
決して悲観的にならず、焦らず自分のペースで少しずつ行動を起こしていきましょう。
人間関係が「めんどくさい」「疲れた」と感じる心理や対処法を解説
友人や職場の同僚、サークルの仲間など、それまで良好な関係を構築してきたにもかかわらず、ある日突然人間関係が「めんどくさい」と感じることはないでしょうか。
さまざまな理由や原因がありますが、なぜこのような瞬間が訪れるのでしょうか。
本記事では、その心理や背景、どのようなシーンが考えられるのかを紹介します。
人間関係がめんどくさいと感じる瞬間

私たちが社会生活を送るうえで、人間関係がめんどくさいと感じるのはどのようなときなのでしょうか。
典型的な例として以下などが挙げられます。
- 職場の人に気を遣わなければならないとき
- 自分自身を否定されたとき
- 相手が不機嫌な態度をとってきたとき
これらの人間関係がめんどくさいと感じてしまう瞬間について解説しましょう。
職場の人に気を遣わなければならないとき
職場で円滑に仕事を進めていくためには、上司や同僚、部下などに気を遣わなければならない場面も多いものです。
特に昨今ではパワハラやセクハラといったハラスメント行為が問題視されることも多く、立場に関係なく言葉遣いや言動、接し方に注意しなければなりません。
自分自身を否定されたとき
ビジネスの場面に限らず、プライベートにおいても人間関係をめんどくさいと感じることもあります。
特に、第三者から自分に対して否定的な言葉を投げかけられたときや、陰口が耳に入ってきたときなど、その人と信頼関係を築くことが面倒に感じてしまいます。
相手が不機嫌な態度をとってきたとき
自分自身は良好な人間関係を築きたいと考えているにもかかわらず、相手が不機嫌な態度をとってしまうケースもあります。
このような場合、相手の機嫌を損なわないよう過度に気を遣わなければならないため、めんどくさいと感じることも少なくありません。
関連記事:友達がいないってやばいこと?寂しいと感じた時の対処法
人間関係がめんどくさいと感じるときの心理
どのような人であっても、初対面のときには相手と仲良くなりたい、良好な関係を築きたいと考えることが多いものです。
その状態から、どのような心理が影響して人間関係がめんどくさいと感じるようになるのでしょうか。
具体的には「我慢や無理をしてしまう」「相手に嫌われたくない」という心理が影響しています。
これらについて詳しく紹介しましょう。
我慢や無理をしてしまう
良好な人間関係を築くために、自分自身が我慢をしたり無理をしたりするケースもあります。
たとえば、相手と考え方や意見が異なっていたとしても、波風を立てないようにするあまり自分の意見を押し殺してしまうと、本音が言い合えなくなってしまいます。
その結果、相手の言動や価値観までもが理解できなくなり、人間関係そのものがめんどくさいと感じてしまうのです。
相手に嫌われたくない
自分自身が我慢をしたり無理をしたりするのは、波風を立てないようにするのと同時に、無意識のうちに相手から嫌われたくないという心理も働いています。
自分の本音を言ってしまうと相手が怒り、喧嘩になってしまうのではないかと過度に恐れるという経験はないでしょうか。
そのようなことがあると、やがて人間関係そのものに疲れてしまい、めんどくさいと感じるようになります。
関連記事:ネガティブ思考をやめたい方へ|止まらない原因やレベル診断、改善方法をご紹介
人間関係がめんどくさいと感じるシーン

私たちの日常生活では、さまざまなことが原因となって人間関係に亀裂を生じさせます。
- 職場・アルバイト先
- 学校
- ネトゲ・SNS
- ママ友・パパ友
めんどくさいと感じるのは具体的にどういったシーンがあるのか、職場や学校、私生活における一例を紹介しましょう。
職場・アルバイト先
職場やアルバイト先では、多くの人々と協力しながら仕事を進めなければならないため、人間関係が複雑になることがよくあります。
上司と部下、同僚間のコミュニケーションはもちろん、予期しない変更への対応、競争、さらには職場でのハラスメントなど、これらすべてがストレスを生み出し、人間関係を「めんどくさい」と感じさせる原因となり得ます。
学校
学校においても、友人同士の関係、クラス内のいじめ、恋愛の問題、さらには教師との対立など、人間関係が複雑化しめんどくさいと感じることがあります。
ネトゲ・SNS
ネットゲームやSNSでは相手の顔が見えないことから、オンライン上でチームの対立やプレイヤー間のコミュニケーションの問題、特定の個人に対するハラスメントや嫌がらせが発生することもあります。
ママ友・パパ友
幼稚園や保育園、学校などのコミュニティにおいても、親同士の人間関係がこじれることがあります。
たとえば、価値観の違いや子育てに対する考え方・スタイルの違い、根拠のない噂や偏見、または子ども同士での問題などが原因となることが多く、ママ友やパパ友同士の人間関係をこじらせ、めんどくさいと感じさせる原因となり得ます。
関連記事:友達の作り方|場所と手順を社会人から学生ごとに分けて解説!
人間関係がめんどくさいと感じるのは病気なのか
それまで良好な関係を築いていたにもかかわらず、ちょっとしたことが原因である日突然人間関係がめんどくさく感じられることもあります。
しかし、急激に態度が変わってしまうと周囲に驚かれたり、自分自身を振り返ってみてもなぜそのような心境に変化したのか不安に感じてしまうこともあるでしょう。
あまりにも態度が変わってしまうと、「自分は精神的に問題を抱えているのではないか」、「メンタル面での病気なのではないか」と思ってしまう人も少なくありません。
たしかに、うつ病や適応障害など、さまざまな病気が原因で人間関係がめんどくさく感じることも多いですが、必ずしも病気にかかっているとは断言できません。
少しでも不安を感じたら、一人で悩みを抱えるのではなく、メンタルクリニックなどを受診し専門医に診てもらうことが大切です。
関連記事:マインドフルネスをやってはいけない人の特徴|PTSDやうつ病の人は危険?
人間関係をめんどくさいと感じやすい人の特徴

人間関係をめんどくさいと感じやすい人には、さまざまな特徴が見られることがあります。
具体的に以下などの特徴が当てはまることが多いようです。
- 内向的な性格
- 感受性の高い人
- 完璧主義者
これらの特徴について詳しく紹介しましょう。
内向的な性格
内向的な性格の人は、大人数のグループや団体での行動が苦手で、避ける傾向があります。
人数が多ければ多いほど、多方面に気を遣わなければならず精神的に消耗することから、社会的な接触を避け単独または少人数で行動しがちです。
感受性の高い人
高い感受性を持つ人は、他人の言動や感情の変化を敏感に察知しようとします。
他人からのなにげない一言に傷ついたり気にしたりすることが多く、そのたびにエネルギーが消費され、やがて人間関係そのものをめんどくさいと感じるようになります。
完璧主義者
完璧主義の傾向にある人は、自分自身はもちろんのこと他人に対しても高い基準を設定しがちで、それが満たされないと不満を感じることがあります。
他人のちょっとした言動が気になってしまい、やがて「この人といると疲れてしまう」と感じ、人間関係がうまくいかない原因をつくってしまいます。
関連記事:感情の起伏が激しい人や少ない人の特徴|上手にコントロールする方法とは
人間関係がめんどくさいと思った時の対処法

価値観や考え方の相違、性格のミスマッチなど、人間関係がめんどくさいと感じる原因はさまざまです。
そのような感覚に陥ったとき、どう対処すれば良好な人間関係を維持できるのでしょうか。
対処法として以下などが挙げられます。
- 相手の良い部分を探す
- 相手の言葉や意見を聞いてみる
- 適度な距離をとる
ここからは人間関係がめんどくさいと思った時の対処法について詳しく紹介しましょう。
相手の良い部分を探す
人間関係がめんどくさいと感じるのは、相手の悪い部分や気に食わない部分が目に入ったときが多いはずです。
相手のことをそれ以上嫌いになったり、受け付けたくないと感じることのないよう、良い部分に目を向けてみることが大切です。
相手の言葉や意見を聞いてみる
人間関係のトラブルに陥ったとき、自分の意見を押し通そうとするのではなく、相手の言葉や意見にも耳を傾けることも大切です。
相手の言葉を聞くことで、自分の間違っていた部分や直すべきところに気づき、再び良好な関係を取り戻せることもあるでしょう。
適度な距離をとる
人間関係がめんどくさく感じる要因が相手ではなく自分自身にあり、それを自ら認識できているケースもあると思います。
そのような場合には自分の心を整理するためにも、相手と一定の距離をとって冷静になることも大切です。
関連記事:セルフ・コンパッションとは?やり方やマインドフルネスとの違いを解説
まとめ
誰しも人間関係がめんどくさく感じる瞬間は誰しもが経験したことがあるでしょう。
しかし、だからといって一時的な心情の変化で関係を切ったり、絶縁を言い渡したりすることで後悔するケースも少なくありません。
まずは、なぜ人間関係がめんどくさいと感じるようになったのかを客観的に振り返り、適切な対処法を試してみましょう。
スキンシップにはどんな効果がある?良好な関係性を維持するためのポイントとは
親しい友人や恋人同士では、日常的に体の一部に触れたり、お互いに密着したりすることで関係性が深まることがあるでしょう。
お互いが触れ合う行為をスキンシップとよびますが、なかにはスキンシップが苦手な人も存在します。
本記事では、スキンシップにはどのような効果があるのか、スキンシップをとる心理的な理由、スキンシップが苦手な人との接し方なども詳しく解説します。
スキンシップとは何か

スキンシップとは、一般的に「触れ合い」や「交流」といった意味として用いられる言葉です。
その名の通り、人と人とが物理的に密着したり、手で触れたりする行為のことを指します。
一口にスキンシップといってもさまざまなものがありますが、代表的な例でいえば以下のような行為が挙げられるでしょう。
- 握手をする
- 軽くボディタッチをする
- 頭を撫でる
- 肩を抱き合う
- 抱擁する
- 手をつなぐ
- キスをする
握手はビジネスの場面でもよく見られるほか、親しい友人や家族などであればボディタッチや頭を撫でる、肩を抱き合うといった行為も少なくないでしょう。
友人から恋人へ発展していくと、手をつないだりキスをしたりといったスキンシップも増えてくるはずです。
このように、その人との関係性によってもスキンシップの種類は異なります。
関連記事:感情の起伏が激しい人や少ない人の特徴|上手にコントロールする方法とは
スキンシップの効果

スキンシップをとることでどういった心理的効果が得られるのでしょうか。
具体的な心理的効果として以下などが挙げられます。
- 安心感や幸福感を高める
- ストレスと不安の軽減
- 自己肯定感の向上
詳しく紹介していきます。
安心感や幸福感を高める
スキンシップをとることで、脳からオキシトシンとよばれるホルモンが放出されます。
オキシトシンは「愛情ホルモン」や「絆ホルモン」ともよばれており、安心感を生み出すとともに、幸福感を高める効果があることもわかっています。
ストレスと不安の軽減
スキンシップによって身体的な接触をはかることで心拍数や血圧を下げ、ストレスホルモンの分泌量を下げることもあります。
その結果リラクゼーションの効果が高まり、ストレスや不安感の軽減にも貢献します。
自己肯定感の向上
スキンシップの一種である、頭を撫でられる、肩を抱き合う、抱擁するといった行為は、本能的に「愛されている」、「守られている」といった感情を生み出します。
すなわち、自分自身が愛され、守られるべき大切な人間であることを認識し、その結果自己肯定感や自尊心を高められる可能性があるのです。
関連記事:【自己受容】弱くてダメな自分を認めて受け入れるトレーニング方法
スキンシップをとる心理
なぜ人間は親しくなるほどスキンシップをとろうとするのでしょうか?
理由として以下などが挙げられます。
- 愛情表現
- 他者とのつながりを強めたい
- 下心がある
それぞれの理由について心理学の観点から解説しましょう。
愛情表現
私たちの一般的なコミュニケーション手法として言語がありますが、それだけでは相手に自分自身の愛情や気持ちが伝わらないケースも少なくありません。
たとえば、恋人に対して「愛してる」と言葉で発したとしても、どこまで本気なのか分からないこともあるでしょう。
しかし、言葉で伝えると同時に、手を握ったり抱擁したりすることで精一杯の愛情を表現できます。
また、そもそも言葉の通じない赤ちゃんや幼い子どもに対しては、パパやママが抱きしめるだけで本能的に「守られている」と安心感を与えられ、愛情のコミュニケーションをとることもできます。
他者とのつながりを強めたい
人は本来社会的な生き物であり、他者とのつながりを求めるのは本能でもあります。
スキンシップによって他者との関係性を強化できることを本能的に知っていることから、より親しくなりたい場合に自然とボディタッチが増える傾向があるのです。
下心がある
スキンシップをとるのは上記で紹介したようなポジティブな理由ばかりとは限りません。特に男性に多いのが、下心が見え隠れするケースです。
女性のなかには、肩や腕などへの軽いボディタッチ程度であれば許容できる方もいるかもしれません。
しかし、男性側に下心がある場合、それを受け入れてしまうとどんどんエスカレートしていく可能性もあります。
また反対に、女性にしてみれば、軽いボディタッチは気に留めておらず無意識にするケースも少なくありません。
関連記事:情緒不安定な女性に多い症状とは|対処法についても紹介
スキンシップが苦手な人も

人と触れ合ったり、密着したりといったスキンシップは、人によってもさまざまな捉え方があります。
なかには、自分からスキンシップをとるのが苦手と感じる方や、関係性次第ではスキンシップをとられることに大きな拒絶感を抱く人もいます。
スキンシップが苦手な理由として以下などが考えられるでしょう。
- 十分な関係性を築けていない
- 自己肯定感が低い
- 第三者からの目が気になる
- 異性との交流に慣れていない
これらの理由について詳しく解説します。
十分な関係性を築けていない
初対面の人や顔見知り程度の人の場合、スキンシップをとることに強い抵抗感を抱く人は少なくありません。
たとえば、欧米人の場合は握手やハグ、キスといった挨拶の文化があり、日常的にスキンシップをとる機会があります。
しかし、日本にはそういった文化がなく、ハグやキスといったスキンシップは特に関係性が深い人でないと抵抗感を抱かれるでしょう。
自己肯定感が低い
親しい友人や恋人であったとしても、スキンシップが苦手と感じる人も存在します。
理由はさまざまですが、特に典型的なのは自己肯定感が低いケースです。
たとえば、自分自身に強いコンプレックスがあると、「スキンシップをとることで相手を不快な気分にさせるのではないか」、「相手から拒絶されるのではないか」などと考えてしまい、スキンシップを敬遠してしまうことも少なくありません。
関連記事:自己肯定感が低い子供の特徴や言動とは|注意すべき親の発言や行動
第三者からの目が気になる
恋人同士であるにもかかわらず、スキンシップをとるのが苦手と感じる人の場合、周囲からの目が気になるというケースもあります。
たとえば、外出先で手をつないだり、二人で並んで歩いたりするのも周囲からの視線が気になってしまう人もいます。
異性との交流に慣れていない
これまでの人生において、異性と交流をする機会が少なかった人の場合、恋人や異性の友達ができたとしても、どうスキンシップをとれば良いのか分からないケースもあります。
本人にはスキンシップをしたいという気持ちがあったとしても、「相手に嫌われたらどうしよう」、「どの程度までのスキンシップをするべきかわからない」と感じてしまい、行動に移せないことも多いようです。
スキンシップをとるうえでのポイント・注意点
スキンシップは人間関係をより深めるために有効な方法ですが、その一方でスキンシップのやり方を間違えてしまうと大きな溝を作ってしまうことにもなりかねません。
気を付けておきたいポイントや注意点は以下などが挙げられます。
- 相手との関係性に応じて考える
- 相手に寄り添う
- 周囲の視線が目につかない場所でスキンシップをとってみる
ここからは、スキンシップをとるうえで、押さえておきたいポイントや注意点を解説しましょう。
相手との関係性に応じて考える
十分な関係性が築けていない人とのスキンシップは、トラブルを避けるためにも慎重に判断する必要があります。
たとえば、欧米のように初対面の人にハグやキスをすると、相手は驚いてしまい抵抗を示すこともあるでしょう。
まずは言葉のコミュニケーションから関係を深めていき、徐々に握手や軽いボディタッチをしながら様子を伺うことが大切です。
相手に寄り添う
自己肯定感が低い人や、自分自身に強いコンプレックスを抱いている人、異性との交流に慣れていない人に対しては、無理にスキンシップをとることは厳禁です。
このような人は、特に相手との距離感を大切している傾向が強いことから、相手のペースに寄り添って距離を近くしていくようにしましょう。
たとえば、いきなり物理的な距離を縮めようとするのではなく、「ここ、座っていい?」と聞いてみるだけでも相手の警戒心が解け、徐々に関係性が深まっていくはずです。
周囲の視線が目につかない場所でスキンシップをとってみる
第三者からの視線が気になる人に対しては、多くの人の目に触れるような場所でスキンシップをとるのではなく、落ち着いて話せる個室タイプの飲食店や映画館などを選ぶようにしましょう。
スキンシップは相手のことを第一に考えよう
スキンシップには不安感の低減や幸福度のアップなどさまざまな効果があることから、愛情表現のひとつとして有効な手段です。
しかし、なかにはスキンシップが苦手という人や、うまくスキンシップがとれずに悩んでいる人も少なくありません。
自分自身のペースでスキンシップをとるのではなく、まずは相手のことを第一に考え、不快や不安を感じさせないよう配慮することが大切です。
完璧主義な女性の特徴を紹介|うつの原因になるって本当?

完璧主義の定義はさまざまなものがありますが、一般的には「自分自身や周囲に対して高すぎる水準・目標を求めること」といえるでしょう。
完璧主義の人は周囲からの評価を気にしすぎたり、過度に失敗を恐れたりする傾向も見られます。
完璧主義に陥ってしまうのはなぜなのか、完璧主義な女性に見られる特徴や、うつ病をはじめとした精神疾患につながる理由についても解説します。
完璧主義になってしまう原因

完璧主義に陥ってしまうのは、個人の性格や価値観によるものと片付けられがちです。
しかし、それ以外にもさまざまな原因が考えられます。
- 家庭環境の問題
- 失敗が許されない社会的風潮
- 過去の失敗体験
これらの完璧主義になってしまう主な原因について詳しく紹介しましょう。
家庭環境の問題
子どもの頃に育った家庭環境や親の教育方針、子育て方法が完璧主義の原因となることがあります。
たとえば厳格すぎる親のもとで教育を受けた子どもは、失敗することを過度に恐れるようになります。
また、努力して一定の成果を出したとしても子どもを褒めることが少ないと、わずかな妥協も許せない完璧主義になることもあるようです。
失敗が許されない社会的風潮
個人に対して高い水準を求める社会的風潮も完璧主義に陥る原因となることがあります。
行き過ぎた競争社会や成果主義の中では、わずかな失敗やミスが評価に大きく関わってくるため、つねに完璧でなければならないと感じる人が増えてしまうのです。
過去の失敗体験
過去に大きな失敗やミスをした経験が原因となって、完璧主義の考え方に陥ることもあります。
特に、大勢の前で失敗やミスをしたり、それを指摘されたりした場合、本人はそれが恥ずかしいと感じ、同じ失敗を繰り返さないために完璧を追求しがちです。
関連記事:【ストレス解消】セルフケアとはなにか?意味・種類・方法について解説
完璧主義な女性の特徴

女性のなかには、自分自身の完璧主義な性格に悩んでいる人も少なくありません。
一方で、自分のことを完璧主義であると自覚できていないケースもあります。
完璧主義な女性の特徴として以下などが挙げられます。
- プライドが高い
- 他人と自分を比較しがち
- ストレスを溜め込みやすい
自分自身の性格を客観的に判断するためにも、完璧主義の女性にどういった特徴が見られるのか紹介しましょう。
プライドが高い
完璧主義という性格をポジティブにとらえると、「負けず嫌い」と言い換えることもできます。
しかし、ときには周囲から「プライドが高い人」であると認識されることもあります。
自分とは違う意見や考え方をもつ人に対し敵意を向けたり、自分自身の失敗を決して認めようとしなかったりといった性格が特徴的です。
また、プライドが高いあまりに他人に対してお願いをすることができず、一人で仕事を抱え込んでしまうこともあります。
他人と自分を比較しがち
自分自身の成果や特性を他人と比較しがちなことも完璧主義の女性に見られる傾向です。
他人は他人であると割り切って考えることが難しく、周囲と自分を比較しては劣っていると感じることがしょっちゅうあります。
その結果、本来もっている自分の価値を見失う原因となることも少なくありません。
ストレスを溜め込みやすい
完璧主義な人ほど周囲からの目が気になったり、自分の悪いところばかりが目につくようになりストレスを溜め込みがちです。
また反対に、自分が簡単にできる仕事を他人ができていないと、それに対して苛立ってしまうこともあります。
関連記事:【変わりたいあなたへ】自分を変えることは難しい?変われる方法や習慣
完璧主義な女性の長所・メリット

完璧主義はあまり良くないイメージをもたれがちですが、仕事をするうえでは長所として活かせるポイントもあります。
では実際に完璧主義な女性の長所とメリットとしてどのようなことが挙げられるでしょうか。
- 目標達成へのこだわりや意識が強い
- 責任感が強い
- 細部にも目を配ることができる
これらの長所やメリットを詳しく紹介しましょう。
目標達成へのこだわりや意識が強い
完璧主義な人ほど、自分自身が設定した目標または会社から提示された目標に対し、「なんとしてでも達成しなければならない」という強いこだわりと意識をもっています。
目標を達成できるかどうかはその人のスキルや経験も影響しますが、それ以上に「絶対に達成する」という意識が重要です。
その日の実績や予算までの進捗状況を考え、目標達成に向けた具体的なアクションや取り組みを講じられるようになります。
責任感が強い
完璧主義な人は責任感も強く、自分に与えられた仕事やミッションを最後までやり遂げようとします。
困難な状況にあったとしても途中で投げ出すようなことはせず、最後まで自分のベストを尽くし粘り強く取り組むことができるのはメリットといえるでしょう。
細部にも目を配ることができる
完璧主義な人は、自分自身だけでなく周囲の人がとっている行動にも高い水準を求める傾向があります。
細かい部分にまで目を配ることができ、わずかな作業の不備やミスも見逃さず対処できます。
完璧主義な女性の短所・デメリット
上記とは対照的に、完璧主義の女性には短所といえるポイントもあります。
ストレスを感じやすい
仕事やプロジェクトが順調に進んでいるときには問題ありませんが、トラブルやミスなどが発生し業務の達成が困難になったときに、人一倍大きなストレスを感じてしまいます。
それだけでなく、ミスや失敗の原因が自分にあると考え、過度に責め立ててしまうことも少なくありません。
その結果、精神的に疲弊し、さまざまな疾患に陥るケースもあるのです。
スピーディーな意思決定が苦手
完璧主義な人はスピーディーな意思決定が難しいという短所もあります。
大きな決断が求められるとき、完璧主義な人は「決断が間違ったらどうしよう」、「リスクや危険性について見落としている部分はないか」などと不安に感じてしまい、決断を先送りにしがちです。
その結果、プロジェクト全体の進捗に影響したり、新たなビジネスチャンスを逃したりすることもあるのです。
関連記事:【自己受容】弱くてダメな自分を認めて受け入れるトレーニング方法
完璧主義はうつの原因になる?

完璧主義は精神的にもさまざまな影響を与えることがあり、それがうつ病の原因になる可能性もあります。
完璧主義な人は自分に対して高い水準を求め、ときには達成が難しい目標を立てることも…。
同時に、ミスや失敗を恐れるあまり、目標を達成できなかったときには自分を責める傾向があります。
自己批判や過度のストレスによって、自尊心や自己肯定感の低下、無力感などを感じてしまい、うつ病の発症につながる可能性があるのです。
また、このような病気を発症しなかったとしても、日々の生活そのものに疲れてしまい、「辛い」「しんどい」と感じることもあります。
ただし、完璧主義の人の全てがうつ病を発症するというわけではなく、遺伝的な要因や環境的な要因、個人の性格なども影響するとされています。
関連記事:感情の起伏が激しいのは病気?治したい場合の対処法について徹底解説
完璧主義をやめたいときの治し方
完璧主義を克服しようと考えたとき、どのような治し方が効果的なのでしょうか。
自分自身を受け入れる
まずは自分自身の長所と短所を把握し、それを受け入れることから始めましょう。
人は誰でも長所と短所があり、完璧な人は存在しません。
すべてのことを完璧にこなそうとしても現実的ではないことを知り、失敗やミスをすることは当たり前であると認識することが大切です。
自分に対して過度に厳しくするのをやめて、ありのままを受け入れる姿勢に変えることが完璧主義からの脱却につながっていきます。
関連記事:自分を認める方法|認める難しさや自己肯定感との関係性を解説
仕事やタスクの優先順位を決める
すべての仕事やタスクを完璧にこなそうとするのではなく、優先順位を決めて取りかかるようにしましょう。
優先度や重要度の高い仕事から取り組むことで、特に重要な部分でのミスや失敗を抑え、メリハリのついた仕事ができるようになります。
関連記事:【誰でもできる】マインドセットの意味・使い方をわかりやすくご紹介!
専門医による治療を受ける
過度な完璧主義によって自分自身に大きなストレスがかかっていたり、周囲の人に悪影響を与えている場合には、専門医による治療を受けることも検討しましょう。
完璧主義を克服する方法としてはカウンセリングや心理療法、認知行動療法などがあります。
特に認知行動療法は、自分自身の言動を客観的に振り返ることにより、どのような言動が問題となっているのかを分析し修正することができます。
まとめ
完璧主義は個人の性格的な問題だけでなく、家庭環境や過去の経験などさまざまな要因が複雑に絡み合っているケースが少なくありません。
ときには完璧主義がポジティブに作用することもありますが、ネガティブにとらえられるケースも多いのが実情です。
完璧主義を克服したい、やめたいと感じる方も多いと思いますが、焦れば焦るほど空回りして逆効果となってしまうこともあります。
そのため、自分自身で対処が難しいと感じた場合には、専門医による治療を受けることも検討してみてください。
知らず知らずに起こっている?ハラスメントの種類や防止方法を紹介

ハラスメントとは、相手に対して嫌がらせをする行為を指します。
一口に嫌がらせといってもその行為はさまざまであることから、ハラスメントにはいくつかの種類があります。
また、自分自身ではハラスメント行為と認識していなくても、相手にとってみれば不快に感じる言動も少なくありません。
そこで今回は、ハラスメントにはどのような種類があるのかを紹介するとともに、ハラスメント防止に役立つ対策の一例も紹介します。
ハラスメントの種類:会社や職場

会社や職場で発生しがちな代表的なハラスメントには、以下のようなものがあります。
- セクシャルハラスメント
- パワーハラスメント
- カスタマーハラスメント
- アルコールハラスメント
なお、これらのハラスメントは、いずれも職場内だけでなく宴席や移動中の車内などにおいても認められます。
セクシャルハラスメント
異性または同性に対して性的な嫌がらせをする行為をセクシャルハラスメントとよびます。
身体の一部を触る行為や、下ネタを大声で発する、職場に性的なポスターを掲示することなどがセクシャルハラスメントの行為に該当します。
上司や部下などの関係性によっては断りきれないケースもあるため、相手が明確に嫌がっていなかったとしてもセクシャルハラスメントにあたるおそれがあるのです。
パワーハラスメント
身体的・精神的な苦痛を与える行為全般をパワーハラスメントとよびます。
暴力や暴言はもちろんのこと、相手を侮辱する言動や威嚇する行為、無視する行為などもパワーハラスメントにあたります。
また、パワーハラスメントは上司から部下などに対して行われるものというイメージがありますが、実際には同僚同士や部下から上司に対してもパワーハラスメントが認められる場合があるのです。
カスタマーハラスメント
顧客から従業員に対して理不尽な要求や悪質なクレームなどを行うことをカスタマーハラスメントとよびます。
たとえば、顧客が店員を恫喝・脅迫したり、正当な理由がないにもかかわらず損害賠償請求を行ったりすることがカスタマーハラスメントに該当します。
アルコールハラスメント
お酒の飲めない人や拒否している人に対して飲酒を強要したり、嫌がらせをする行為をアルコールハラスメントとよびます。
たとえば、一気飲みを強要したり、拒否しているにもかかわらずグラスにお酒を注いだりする行為もアルコールハラスメントにあたります。
ハラスメントの種類:女性

女性に対して行われることの多いハラスメントには以下のようなものがあります。
- マタニティハラスメント
- ジェンダーハラスメント
- ゼクシャルハラスメント
女性に対して行われるハラスメントについても紹介しましょう。
マタニティハラスメント
妊娠や出産をした女性に対する嫌がらせ行為をマタニティハラスメントとよびます。
たとえば、検診を受診するために休んだ人に対して悪口を言ったり、無理に仕事を押し付けたりする行為などがマタニティハラスメントに該当します。
マタニティハラスメントは会社や職場内だけでなく、町内会やPTAといったコミュニティ内で発生するケースも少なくありません。
ジェンダーハラスメント
「女性(男性)なのだから○○すべき」といったような、女性らしさ・男性らしさを強要する行為をジェンダーハラスメントとよびます。
たとえば、女性に対して「結婚・出産は○歳までにすべき」や「女性はつねにきれいであるべき」といった言動や、女性にのみお茶汲みをさせる行為もジェンダーハラスメントに該当します。
ジェンダーハラスメントはマタニティハラスメントと同様、会社や職場だけでなく、さまざまなコミュニティ内や仲間内でも発生することがあるのです。
ゼクシャルハラスメント
結婚に踏み切らない女性に対して嫌がらせをしたり、プレッシャーを与えたりする行為をゼクシャルハラスメントとよびます。
たとえば、「いつまで独身でいるつもり?」、「いつになったら結婚するの?」といった言葉を投げかけたり、結婚情報誌をわざと目につくところに置いたりする行為もゼクシャルハラスメントにあたります。
なお、女性だけでなく男性に対する上記のような行為もゼクシャルハラスメントに該当するのです。
関連記事:情緒不安定な女性に多い症状とは|対処法についても紹介
ハラスメントの種類:夫婦
夫婦間で起こるハラスメントにはモラルハラスメントがあります。
モラルハラスメント
相手が嫌がる言動をとり、不快感を与える行為をモラルハラスメントとよびます。
夫婦間においては、たとえば相手に対して家事ができていない、収入が少ないことを執拗に叱責したり、出された食事に手をつけない、生活に必要な金銭を渡さない、相手のことを無視することなどがモラルハラスメントに該当します。
また、上記のような明確な理由や意図がなくても、相手の人格を否定するような言葉を投げかける行為も立派なモラルハラスメントにあたるのです。
関連記事:夫婦関係は修復できる?よくある破綻のきっかけや修復方法を紹介
ハラスメントの種類:家庭

モラルハラスメントは夫婦間だけでなく、子どもや親も含めた家庭内で起こる場合もあります。
モラルハラスメント
子どもに対するモラルハラスメントの具体例としては、勉強ができないことを執拗に叱責する行為や、食事を与えない、子どものことを無視する、「バカ」、「生まなければよかった」といった暴言を吐くことが該当します。
また、親に対するモラルハラスメントも同様に、暴力的な言動や行為、人格を否定するような言葉を投げかける行為のほか、介護が必要であるにもかかわらず世話をしなかったり、施設への入所を拒否したりする行為もモラルハラスメントにあたります。
関連記事:自己肯定感が低い子供の特徴や言動とは|注意すべき親の発言や行動
ハラスメントの種類:学校
学校におけるハラスメントにはどのようなものがあるのでしょうか。
主に、アカデミックハラスメントとレイシャルハラスメントがあります。
アカデミックハラスメント
おもに大学教授が権力を濫用し、学生に対してさまざまな嫌がらせをすることをアカデミックハラスメントとよびます。
たとえば、教授の個人的な好みによって特定の生徒・学生の評価を決めたり、優遇または冷遇したりする行為や、学生に対して性的関係を迫ったりする行為もアカデミックハラスメントに該当します。
レイシャルハラスメント
特定の人種や国籍、出身地などに該当する人に対し、嫌がらせをする行為をレイシャルハラスメントとよびます。
たとえば、外国籍の人だけを仲間外れにする行為や理不尽な要求・命令をする行為、特定の出身地の人を無視する行為、そのような人に対し暴言を浴びせる行為などがレイシャルハラスメントに該当します。
レイシャルハラスメントは教授や先生から行われるケースもあれば、仲間やクラスメイト同士で行われる場合もあるのです。
ハラスメントの防止方法

自分自身が意図せず、知らない間にハラスメントに該当する行為を行っていることもあります。
ハラスメントに対する世間の見方が厳しくなっているなかで、ハラスメント行為を防止するためにはどういった対策が求められるのでしょうか。
ハラスメント防止方法として以下などが挙げられます。
- ハラスメント対策の研修や講義を行う
- ハラスメント行為に対する判例を学ぶ
- 社内や学校内に相談窓口を設置する
- 相手を配慮した言葉を心がけえる
これらの対策について詳しく紹介しましょう。
ハラスメント対策の研修や講義を行う
職場や学校でできる方法としては、ハラスメント対策の研修や講義を行うことが挙げられます。
自社にノウハウや知見がなくても、ハラスメント対策を専門に扱う外部の企業や団体があります。
全ての従業員や学生に対しハラスメント防止の意識を高めてもらうためにも、研修や講義の実施は有効です。
ハラスメント行為に対する判例を学ぶ
ハラスメントは絶対にやってはいけない行為であると説明しても、必ずしも抑止力になるとは限りません。
そこで、ハラスメント対策の研修や講義と合わせて、具体的な判例について学んでもらうこともおすすめです。
たとえば、セクシャルハラスメントやパワーハラスメントの加害者がその後どのような処分を受けたのか、自社だけでなく他社の事例も含めて学ぶことで、従業員や学生は自分ごととして捉えられるようになります。
社内や学校内に相談窓口を設置する
ハラスメントの実態は複雑なことが多く、客観的に実情を把握することが難しいケースも少なくありません。
そこで、実際にハラスメントを受けている人が個別に相談しやすいよう、専用の相談窓口を設置することも有効な対策です。
相談した事実や相談者の情報は厳密に守ることはもちろんですが、相談したことで不利益が及ばないように配慮することも重要です。
相手を配慮した言動を心がける
上記で紹介した対策は職場や学校などでは可能ですが、コミュニティ内や家庭内では難しい場合も多いでしょう。
私生活において重要なのは、つねに相手のことを配慮した言動を心がけることです。
自分が同じような言動をされたときにどう感じるか、相手の立場に立って考えてから言葉を発したり行動に移したりすることで、ハラスメントは防止できるでしょう。
関連記事:【怒りを抑える】アンガーマネジメントのやり方・テクニックをご紹介!
まとめ
一口にハラスメントといってもさまざまな種類があります。
かつては一般的であった行動や言葉も、時代の変化とともにハラスメントと認識されるようになりました。
だからこそ、自分自身の普段の言動がハラスメントに該当していないかを振り返ることが大切です。
女性の情緒不安定の治し方は?生理との関係や落ち着く方法を解説

ご自分の性格を、「いつもイライラしたり、急に泣きたくなったり、気持ちが不安定になりやすいかも」と悩んでいる女性の方は、意外に多いのではないでしょうか。
感情の起伏が激しい状態を「情緒不安定」と呼び、女性がお悩みになるケースが多くあります。
情緒不安定な人に多く見られる特徴や正しい対処法について解説します。
なぜ女性は情緒不安定になりやすいのか

情緒の安定は主に、身体的要因、心理社会的要因が関係しています。
まずはこれら2つの要因について解説していきます。
身体的要因
身体的な要因で一番に挙げられるのは、ホルモンバランスです。
特に女性は月経周期によってエストロゲンやプロゲステロンなどのホルモン分泌量が短期間で変化しています。
これらのホルモンは、私たちの精神面にも影響を与えるため、その乱高下によって情緒が不安定になることがあります。
心理社会的要因
仕事やプライベートでの人間関係、結婚や出産による環境の変化など。
女性は家庭や仕事、人間関係などさまざまな場面でストレスを抱えやすい傾向があります。
特に、家庭と仕事の両立や、男女の役割分担の不均衡などがストレスを引き起こし、情緒が不安定になることが少なくありません。
また現在の日本の社会全体の特徴として、自分がどう思うか、の自分軸より、まわりと自分を比較する他者評価に比重が置かれている傾向があります。
そのため、まわりと自分を比較して落ち込んでしまうことも、気持ちが不安定になる要因となっているかもしれません。
関連記事:完璧主義はうつの原因にもなる?完璧主義な女性の特徴を紹介
女性が情緒不安定になる原因や時期

女性が情緒不安定に陥る原因のひとつに、ホルモンバランスの変化があります。
これは以下などの一定の周期や時期になると現れやすくなります。
- 生理前・生理中
- 排卵日
- 妊娠初期
- 更年期
女性が情緒不安定になりやすい時期について紹介しましょう。
生理前・生理中
生理前および生理中にはPMS(月経前症候群)とよばれる症状が現れます。
PMSの症状のうち特に気分の落ち込みやイライラなどの精神症状がひどい場合をPMDD(= Premenstrual Dysphoric Disorderの略で月経前不快気分障害)といいます。
月経前になると特に誘引なく急激に落ち込んで希死念慮まで生じてしまった方が、薬物療法でこういった症状が消失した方を何度も経験しました。
個人差はあるものの不安やイライラ、気分の落ち込みなどによって情緒が不安定になりやすくなるでしょう。
なお、生理後はホルモンバランスが安定し、生理前や最中に比べると比較的情緒が安定します。
排卵日
排卵日とは、卵巣から卵子が放出される時期のことを指します。
排卵日の頃は女性ホルモンの一種であるエストロゲンの分泌量がピークに達するため、生理中と並んで情緒不安定になりやすい時期とされています。
妊娠初期
妊娠初期もまた、ホルモンバランスが大きく変化するタイミングです。
生理中や排卵日と異なり、妊娠にともなう吐き気や体調不良、出産への不安なども影響していることがあり、気分がさらに不安定になることがある点に留意しましょう。
更年期
更年期になると卵巣機能が衰え女性ホルモンが低下することで、全体のホルモンバランスも乱れがちです。
それにともない、イライラや情緒不安定、不安感、抑うつ症状などが現れることも少なくありません。
さらに、年齢を重ねていくことで身体的な衰えや美的感覚に対する不安や怖れも加わり、ストレスが増大することもあります。
関連記事:ネガティブ思考をやめたい方へ|止まらない原因やレベル診断、改善方法をご紹介
情緒不安定な女性に多い特徴

もちろん全員に当てはまるわけではありませんが、情緒不安定な女性に共通している特徴がいくつかあります。
- 感情の起伏が激しい
- 物事をネガティブに考えがち
- 繊細な性格
- 一人でいるのが苦手
- 睡眠障害に悩まされている
自分ではなかなか気づきにくいこと多いものです。
あらためてチェックしてみましょう。
感情の起伏が激しい
普通なら悩んだりイライラしないような些細なことにも、不安やいら立ちを覚えてしまう。
そんな感じが数週間続くときは、少し心が疲れている証拠です。
明確なストレスや不安の原因が明確でなくとも、情緒不安定になることがあります。
そのような自分が嫌になり、さらに悪化するケースも少なくありません。
物事をネガティブに考えがち
何でもかんでも後ろ向きに捉えがちな人は、常に心配事を複数抱えているのと同じようなメンタルの状態であり、情緒不安定に陥りやすいです。
また、他人から褒められたとしても素直に受け入れられず、「何か裏があるのではないか?」などと考えてしまいます、
そのため、たとえ何らかの成果を上げたとしても、いつまでも自己肯定感を高められません。
繊細な性格
他者からの何でもないような一言で傷ついてしまうことの多い繊細な性格の人も、情緒不安定の素養を持っているといえるでしょう。
また、このタイプの人は感受性や共感力が強いことも多く、自分とは直接関係のないこと、たとえばニュースで目にした凶悪事件などについても心を痛めて情緒が不安定になってしまうことがあります。
一人でいるのが苦手
「一人でいるのが苦手だ」という人は、全員ではありませんが、依存傾向が強いケースが多いです。
誰かと一緒にいるときは情緒が安定していても一人になると急に不安感が襲ってくることがあります。
睡眠障害に悩まされている
情緒不安定な時は、不安やストレスによって睡眠に悪影響を及ぼすことがあります。
睡眠の質や時間は肉体的な健康に関係しているのはもちろん、メンタル面にも大きな影響を与えているというのは有名な話でしょう。
夜中に目が覚めてしまったり、寝付きが悪くなることが典型的な症状として挙げられます。
関連記事:感情の起伏が激しい人や少ない人の特徴|上手にコントロールする方法とは
情緒不安定になると泣くのはなぜ?

情緒不安定になると、意味なく泣いてしまうことがあります。
強いストレスや不安を感じているとき、脳の扁桃体とよばれる領域が活性化しやすくなることが知られています。
扁桃体は脳のなかでも感情的な情報を処理するための領域です。
ストレスや不安感などの緊急性の高い情報が集中的に処理されることで、悲しみの感情が引き出され、本人は泣きたくないにもかかわらず、自然と涙が出てくるようになるのです。
また、緊張感が高まることで自律神経のバランスが崩れ、交感神経が優位に働き、涙腺が刺激されます。
その結果、本人の意図とは関係なく涙が出てくることもあります。
関連記事:情緒不安定になると泣くのはなぜ?|情緒不安定になりやすい人や原因とは
情緒不安定になったときの治し方・落ち着く方法は?

気持ちが不安定になったとき、どのように対処すればよいのでしょうか。
具体的には以下などの対処法がおすすめです。
- 深呼吸する
- 適度な運動をする
- 十分な休息
- 自分の感情を書き出したり声に出してみたりする
- 専門家へ相談する
情緒不安定になったときの対処法を詳しく紹介します。
深呼吸をする
すぐにその場でできるおすすめの方法が深呼吸です。
情緒不安定になる要因には、ストレスや不安感の増大といった精神的な面が多くあります。
ゆっくりと深呼吸をすることで副交感神経が優位になり、次第にリラックスし、ストレスや緊張を和らげることができるのです。
適度な運動をする
時間に余裕があれば、ウォーキングや軽いランニング、筋力トレーニングなど、体を動かすことをおすすめします。
これまで国内外の多くの研究から、適度な運動はストレスの原因となるホルモンを減らし、前向きな気分にする効果があることが示されています。
十分な休息
身体的な疲労だけでなく精神的な疲労を緩和するために、十分な休息をとることも必要です。
まずは十分な睡眠時間を確保します。
リラックスできる音楽を聞く、温かい飲み物を飲む、少し低めの温度にしたお風呂に浸かるなどして休息の時間を確保しましょう。
自分の感情を書き出したり声に出してみたりする
自分自身がどのような状況にあるのか、どんな気持ちで困っているのか、何に苦しんでいるのかについて、紙にペンで書き出したり、実際に声に出してみるのもおすすめです。
書き出すパターンでは自分の気持ちを視覚化することができ、声に出すパターンでは音の情報として耳に入るため、客観視がしやすくなります。
自分が考えていることを客観視することで、解決方法が見つかったり、意外と小さなことで悩んでいたことに気付くこともあるでしょう。
専門家へ相談する
自分でさまざまな工夫をしてみても改善されない場合には、専門家へ相談することを検討しましょう。
心理カウンセラーやセラピストに相談することで、話を聞いて共感してもらえる安心感が得られ、感情や状況が整理されるでしょう。
その結果、有効な対処法を見つけられる可能性があります。
関連記事:【自己受容】弱くてダメな自分を認めて受け入れるトレーニング方法
情緒不安定な女性との接し方
相手が情緒不安定なときは、急に怒り出したかと思うといきなり悲しんだりと、相手の感情に振り回され、戸惑ってしまうことがあります。
ついつい相手の感情や口調に同調し、こちらも売り言葉に買い言葉、となってしまいがち。
そうなるとお互いヒートアップし、冷静なコミュニケーションがとれなくなってしまいます。
そのため、こちらは努めて冷静に対処しましょう。その際は丁寧なコミュニケーションを心がけることが大切です。
柔らかな口調で話し、相手の話をよく聞くことで相手に安心感を与えることができます。
また、相手の気持ちや立場に共感し、理解を示すことも重要です。
落ち着いて丁寧なコミュニケーションをしようと思っても、相手の感情がおさまらず興奮状態が続くこともあります。
そのような場合には、相手が落ち着くための時間を与え、一定の距離を取りましょう。
まとめ
女性はさまざまな要因により情緒不安定になりやすく、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
自分の気持ちが不安定だなと感じたら、立ち止まってゆっくり深呼吸をしたり、適度な運動をしたり、心地よい休息を心がけるなど、まずはご自分を大切にしてあげてください。
どうしても症状が改善しないときや、悪化しているなと感じられる場合には、メンタルヘルスの専門家へ相談することもご検討ください。
自己肯定感が低い子供の特徴とは|注意すべき親の発言や行動

昨今、SNSを中心に「毒親」や「親ガチャ」という言葉が流行るようになりました。
それだけ親が子どもに与える影響は大きく、ときには自己肯定感のような人格形成に関わることもあります。
そこで本記事では、「自己肯定感という言葉は聞いたことがあるもののよく分からない」という方に向けて、具体的にどういった意味を指すのか、自己肯定感が低い子どもはどういった特徴が見られるのか、また、自己肯定感が低くなる原因もあわせて解説します。
自己肯定感が低い子どもの特徴や言動

自己肯定感とはその名の通り、自分自身を肯定できる考え方や感覚のことを指します。
人の性格や育った環境などによって、自己肯定感が高い人もいれば低い人も存在するのです。
特に子どもの場合、親の教育の仕方や接し方などによっても自己肯定感は大きく左右されます。
さて、自己肯定感が低い子どもにはどういった特徴が見られるのでしょうか。
①自分自身と他人を比較しがち
人間は誰でも長所と短所があり、自分自身の長所を肯定したり認めたりすることは簡単です。
しかし、自己肯定感の低い子どもは、自分自身と他人とを比較してしまい、特に短所がよく目につくようになります。
たとえば、「◯◯さんはテストで80点をとったのに、自分は60点しかとれなかった。だから自分はダメだ」といったように、自己嫌悪に陥ることが少なくありません。
②周囲の目を気にしがち
自己肯定感が低い子どもは、自分で自分を認めてあげることができないため、周囲から良い評価を得ることで安心する傾向が見られます。
あまりにも周囲の目を気にしすぎてしまうと、自分自身を押し殺してまで「良い自分」を演じようとする傾向も見られます。
その結果、自分の意見や考えに自信をもてなくなり、周囲に流されやすくなることもあるのです。
③失敗を過度に恐れる傾向がある
自己肯定感が低い子どもは、少しのミスや間違いでも自己嫌悪に陥りやすく、失敗を過度に恐れる傾向が見られます。
特に、新しいことにチャレンジする際に失敗はつきものですが、自己肯定感が低いと、これ以上自分を嫌いになりたくないと感じ、新しいことに挑戦する意欲すらなくなることもあります。
▶自己肯定感とは?|意味や似ている言葉との違いをわかりやすく解説
自己肯定感が低い子どもの原因が親といわれる理由

自己肯定感が低くなる理由のひとつとして、育った環境が挙げられることがあります。
なかでも親から受ける影響は大きく、子どもへの接し方ひとつで自己肯定感が高くなることもあれば、低くなることもあるのです。
近年、「毒親」という言葉を目にする機会が増えてきました。
子どもに対して悪影響を及ぼす、その名の通り「毒」のような存在の親のことを指します。
たとえば、子どもの考えや個性を一切認めることなく否定し続けてしまうと、子どもは「自分は悪い人間なんだ」と感じるようになり、自分に自信がもてなくなってしまいます。
親としては、立派な子どもに育ってほしいと願うあまり、このような行動をするケースもあります。
しかし、子どもにしてみれば自分の存在そのものを全否定されているような感覚になるでしょう。
子どもは親を選ぶことができないことから、自己肯定感が高くなるのも低くなるのも親次第であり「親ガチャ」という言葉で表現されることもあります。
子どもの自己肯定感に強く関わるのは父親と母親どちらか?
かつての日本では、父親が働きに出て家計を支え、母親が専業主婦として子育てや家事に専念するという家庭が一般的でした。
しかし、昨今では共働き世帯が当たり前となり、子育ても母親と父親が協力して取り組むという考えが一般的となっています。
子どもの自己肯定感は、子育てのなかで子どもとコミュニケーションをとる時間が多い親ほど影響を与えやすいといえるでしょう。
そのため、父親と母親のどちらが子どもの自己肯定感に影響を与えやすい、と一概に判断できるものではありません。
▶︎セルフラブとはどんな意味?自分を愛す方法や自己肯定感との違いを解説
自己肯定感が低い子供が成長するとどうなってしまうのか

幼少期や学生のうちは自己肯定感が低くても、大人になるにつれて自分に自信がもてるようになり、自己肯定感が高くなっていくだろうと考える親もいるかもしれません。
実際に、幼少期に厳しいしつけを受けたものの、大人になってからは自己肯定感を取り戻し、立派に成長する人も少なくありません。
しかし、あまりにも厳しすぎるしつけをしてしまうと、自己肯定感が低いまま子どもが成長してしまうことがあるのです。
自己肯定感が低い状態で成人すると、ものごとを自分で決められなかったり、他者とコミュニケーションをとることに恐怖を覚えたりすることもあります。
その結果、人付き合いに苦手意識をもつようになり、周囲から孤立してしまう人も出てくるでしょう。
また、自分に自信がもてないため就職をしても仕事についていけず、充実した社会人生活が送れないといった事態になることも考えられます。
▶︎ 【怒りを抑える】アンガーマネジメントのやり方・テクニックをご紹介!
自己肯定感を下げてしまうかもしれない親の発言や行動

親であれば誰しもが自分の子どもには立派に育ってほしいと願うものです。
しかし、親が良かれと思ってとった行動や言葉が、子どもにとっては思いのほかショックに感じ自己肯定感を下げてしまうこともあります。
具体的にどういった言動が子どもの自己肯定感を下げてしまうのか、いくつか例を出しながら解説しましょう。
「どうしてできないの?」などと責める
大人にしてみれば簡単に見えることでも、子どもにとっては難易度が高いことは数多くあります。
親にしてみれば、なぜ自分の子どもが簡単なことをできないのか苛立ってしまうこともあるでしょう。
しかし、だからといって「どうしてできないの?」といったように責め立ててしまうと、子どもは何もできなくなり自信をなくしてしまいます。
他者と比較する
子どものやる気を引き出すために、良かれと思って他者と比較してしまう親も少なくありません。
たとえば、「◯◯君はテストで90点を取ったんだって」と言った場合に、友達に負けないために努力する子どももいれば、自信をなくしてしまう子どももいます。
また、親自身の幼少期と比較して、「自分は運動が得意だったのに、なぜあなたは苦手なの?」といった言葉も自己肯定感を下げる要因となることがあります。
長所を褒めない
もともとの性格で自己肯定感が低い子どもであっても、良いところを褒めることで自己肯定感が高まっていくことがあります。
しかし、親が子どもを認めようとせず褒める言葉を投げかけないと「自分はダメな子どもだ」と感じるようになり、ますます自己肯定感が下がっていってしまいます。
▶自己肯定感が低い人の原因とは|実はプライドが高い?親のせい?
まとめ
自己肯定感の低い子どもは自分と他者を比較したり、周囲の目を気にしすぎたりする傾向があります。
自己肯定感が低くなる理由には個人の性格も影響しますが、幼少期に親がどのように接してきたかも重要なポイントとなるのです。
厳しいしつけのつもりでとってきた行動が、結果として子どもの自己肯定感を下げることにならないよう、長所を褒めてさらに伸ばすなど、日頃の行動を意識してみましょう。
自己肯定感が低い原因はプライドが高いから?親のせい?高める方法とは
自己肯定感が低いと自分自身を正当に評価できず、自信を持つことができなくなってしまうでしょう。
自己肯定感の低さは、様々な要因が影響しているとされます。
本記事では、自己肯定感が低い人の原因や特徴、プライドが高いといわれる理由、向いている仕事や上げる方法などについて掘り下げていきます。
自己肯定感が低い人の原因

自己肯定感が低い原因としては下記が挙げられます。
- ネガティブ志向
- 素直でない
- コンプレックスがある
- 他人と比較しがち
ネガティブ志向
何に対しても否定から入るようなネガティブ志向な人は自分自身に対してもマイナスな評価を下すことが多い傾向があります。
他人から批判や指摘を受けた際も、自己肯定感が低い人は自分自身を必要以上に責め、行動することをやめてしまいがちです。
反対に自己肯定感が高い人は、批判や指摘を前向きに捉えられるため成長につながりやすく、さらに自己肯定感が高まるという良いサイクルの中に身を置いているといえるでしょう。
素直でない
自己肯定感が低い人は、他人から良い評価を受けた時に、概して「そんなことはない」と否定しがちです。
もしくは表面上では笑顔で対応しても、心の中では「何か裏があるのではないか?」「どうせ社交辞令なんだろうな」などと考えてしまい、素直に受け入れられません。
その結果、せっかく他人からの評価は悪くないのに自己肯定感の向上につながらないという人は意外と多いものです。
コンプレックスやトラウマがある
自分自身の容姿や境遇などに何らかのコンプレックスを抱えている場合も、自己肯定感が低くなりやすいです。
過去にトラウマがある場合も同様です。
コンプレックスやトラウマを忘れるというのは一筋縄ではいかないので、その他の部分で補填する必用があるでしょう。
他人と比較しがち
特に多いのがSNSなどで成功者の投稿を目にして自分の境遇と比べてしまい、「自分は何をやっているんだろう…」となってしまうパターンです。
「上には上がいる」という言葉がある通り、どんな人でも、比べれば自分より良い境遇に置かれている人は無数に存在します。
しかし自己肯定感が高い人は「他人は他人、自分は自分」という考え方ができるので、わざわざ自分と他人を比較して落ち込むようなことは極めて少ないです。
関連記事:自己肯定感とは?|意味や似ている言葉との違いをわかりやすく解説
自己肯定感が低い人の特徴

自己肯定感が低い人の特徴としては、以下のようなものが挙げられます。
- 自分に自信がない
- 自分を否定的に評価する
- 失敗やミスを自分のせいだと責める
- 他人と比較して自分が劣っていると感じる
- 自分に対する期待が低く、自己実現を諦めている
- 批判や非難に敏感で、傷つきやすい
- 人の評価や承認を求める傾向がある
- 自分を省みることができず、自己否定的な思考に固執する
- 新しいことに挑戦することをためらう
自己肯定感が低い人は、これらの特徴が強く出る傾向があります。
しかし、自己肯定感を高めることで、これらの特徴を改善することができるとされています。
関連記事:夢が見つからないのはなぜ?夢が見つからないのはダメなこと?|上京ものがたり
自己肯定感が低い人はプライドが高い?

自己肯定感が低い人が、実はプライドが高いとされることがあります。
自己肯定感が低い人は自分に自信がなく自分を過小評価する一方で、他人からの批判や否定に過剰に反応してしまう傾向があります。
このような人は、自分にとって都合の悪いことを認めることができず、自分自身を正当化しようとする傾向があるため、プライドが高いと言われるのです。
また、自己肯定感が低い人は自分に対して厳しい傾向があるため、自分自身が達成したことに対して過剰に自責的になることがあります。
これは、深層心理としては自分が思っていたほど優秀でないということを認めたくないためであるとされています。
しかし、プライドが高い人は自分自身を過大評価することもあるため、本質的には自己肯定感が低いのに、そう見えないというケースも多いです。
自己肯定感が高まると、自分自身を客観的に評価できるようになり、プライドが高くなりすぎることも防げるでしょう。
関連記事:完璧主義はうつの原因にもなる?完璧主義な女性の特徴を紹介
自己肯定感が低い人は親に影響されるか

自己肯定感が低い人は、親の影響を受けることがあるとされています。
例えば、親からの厳しい言葉や批判的な態度、過保護な育て方などが、子どもの自己肯定感を低下させる原因となることがあるのです。
また、親自身が自己肯定感が低い場合、それが子どもにも影響を与えることがあるとされています。
しかし、必ずしも親が原因であるわけではありません。
自己肯定感は個人差や環境によって異なるため、他にも様々な要因が影響している可能性があります。
自己肯定感を高めるためには、親が子どもに対して積極的に肯定的な言葉をかけたり、自己決定権を尊重するなどの育て方が有効とされています。
また、自己肯定感を高めるためには、自分自身での努力やアクションも必要となるでしょう。
関連記事:自己肯定感が低い子供の特徴や言動とは|注意すべき親の発言や行動
自己肯定感が低い人がめんどくさいといわれる理由

自己肯定感が低い人がめんどくさいと言われる理由は、いくつか考えられます。
まず、自己肯定感が低い人は、自分に対する不安や不満を抱えやすく、それを周りの人にぶつけてしまうことがあります。
また自分に対して厳しく、周りの人にも同じように厳しく接することがあるため、他人とのコミュニケーションがうまくいかないこともあるでしょう。
さらに、自己肯定感が低い人は自分自身がどう思われているかを気にしすぎる傾向があります。
そのため、他人からの批判や否定に対して敏感に反応してしまうことがあり、それが周りの人にとって迷惑となることがあります。
自己肯定感を高めるための方法を学び、自分自身を客観的に見ることができるようになれば、人間関係の改善も期待できるでしょう。
関連記事:情緒不安定な女性に多い症状とは|対処法についても紹介
自己肯定感を高めると恋愛や仕事は上手くいく?

自己肯定感が低い人の恋愛傾向は、以下のような特徴があります。
まず、自己肯定感が低い人は自分に自信がなく、相手に依存する傾向があります。
そのため、相手に対して過剰な期待を持ち、相手からの反応に敏感になってしまうことがあるのです。
また、自己肯定感が低い人は自分自身に対して否定的な考えを持ちやすく、相手にも同じような否定的な考えを抱いてしまうことがあります。
そのため相手に対して過剰に批判的になり、相手の言動に対して過剰に反応してしまうことがあります。
さらに、自己肯定感が低い人は自分自身を受け入れることができず、自分自身に嘘をついたり自分を偽ったりすることがあるでしょう。
そのため、相手との関係においても相手に対して自分を偽ってしまうことがあります。
そうなるとパートナーに対して偽りの自分を見せ続けれければならず、精神的に参ってしまうこともあるでしょう。
しかし、自己肯定感が低い人でも恋愛を楽しむことができます。
自分自身を受け入れ、自分自身に対する批判的な考えを改めることができれば、相手との関係もより良いものになることが期待できるでしょう。
関連記事:愛情表現の言葉とは?|愛してるよりも愛が伝わる方法を紹介
子供の自己肯定感を高める方法とは

子供の自己肯定感を高めるには、以下のような方法があります。
- 褒めること
- 自己決定権を尊重すること
- 失敗を受け入れること
- 手伝いを頼むこと
- 興味を持たせること
子供の自己肯定感を高める方法をそれぞれ解説しましょう。
褒めること
子供が何か良いことをした場合、褒めることが大切です。
ただし、褒めすぎると逆効果になる場合もあるので、ほどほどに褒めるようにしましょう。
子供が頑張ったことを具体的に褒めてあげるのがおすすめです。
自己決定権を尊重すること
子供に自己決定権を与えることが大切です。
例えば、選ぶものや遊ぶものを自分で決めさせたり、自分のやりたいことを自由にさせてあげましょう。
子供が決定したことが他人に迷惑をかけることであったり、倫理的に間違っていることである場合に初めて親が介入しましょう。
失敗を受け入れること
失敗をしたときに、子供を責めないようにしましょう。
失敗は誰にでもあることであり、それを受け入れることが大切です。また、失敗から学ぶことができるということを教えてあげましょう。
手伝いを頼むこと
子供に手伝いを頼むことで、自己肯定感を高めることができます。
手伝いを通じて、自分でできることが増え、自己肯定感が高まるからです。
興味を持たせること
子供に興味を持たせることも、自己肯定感を高めることができます。
例えば、子供が興味を持っていることについて、一緒に調べたり、取り組んだりすることが大切です。
これらの方法を取り入れることで、子供の自己肯定感を高めることができます。
関連記事:自己肯定感を高めるに効果的な8つの習慣や方法を紹介
まとめ
自己肯定感が低い人は、子供の頃の経験や親からの影響、失敗体験などから自分自身を否定する傾向があります。
しかし、自己肯定感を高めることで、自信を持って生きていくことができます。自己肯定感を高めるためには、自分の強みを見つけることや自分に対して優しく接することが大切です。
また、子供の自己肯定感を高めるためには、褒めることや肯定的な言葉をかけること、自己決定権を尊重することなどが有効です。
自己肯定感が高まると、人生においてさまざまな困難に立ち向かう力が身につき、幸福感や充実感を得ることができます。
監修者紹介

– アフリカンペイントアーティストSHOGEN(ショウゲン)-
タンザニアの小さな村で描かれるティンガティンガというペンキアートに心惹かれ、
日本での生活を捨て、なんの伝手もないまま単身アフリカへ・・・
現地で生活をしながらキャンバスだけなく、警察車両やホテル内の壁画に描くなど、
動物と子供を共存させた作風で独自の表現を追及する。
ティンガティンガ創始者Edward Saidi Tingatingaがおこなっていた“人々を幸せにする絵”への到達を目指す。
日本に制作の場を移した後は、キャンパスだけにとらわれない多方面での活躍を続けている。
生きる喜びを描くペンキ画家