瞑想はとっつきにくい?初心者の私が実感した無理なく始めて続けるコツ

いろんなことが目まぐるしく変わる時代。
心配ごとは次から次へ増えるし、とにかくストレスだらけの現代社会ですよね。
そんなときは「瞑想」が良いとは最近よく聞きますが、まったくの初心者だとちょっととっつきにくい部分があるのも本音ではないでしょうか。
今回はそんな初心者におすすめの「瞑想」のはじめ方、そして続け方のコツを筆者自身の体験を交えてご紹介します。
瞑想は正直ハードルが高い
瞑想には集中力を高めたり、ストレスを緩和したりと様々な効果があります。
これは決して精神論ではなく、実は瞑想は科学的根拠に基づいたものだということをご存知でしょうか?
実際、瞑想で勉強やスポーツの成績が向上したことを報告する研究もいくつかあるのです。
また、医療現場ではれっきとした治療法として活用されていたりと、海外では特に瞑想が身近で一般的な存在になっています。
最近は日本でも「瞑想」ということば自体はよく聞きますし、著名人やアスリートでも取り入れているという人は増えていますよね。
ただ、そうは言っても、まだまだ心理的ハードルが高いというのも、正直なところではないでしょうか?
まったく触れたことがない人にとっては、宗教っぽい、スピリチュアルっぽい、なんだか怪しいなど、とっつきにくさが拭えないかもしれません。
そもそも日本人にとっては宗教や信仰というもの自体、普段からあまり馴染みがないため、そういうを感じただけで反射的にブロックしてしまうのも無理もないことでしょう。
また、仮にそうした心理的ハードルを越えられたとしても、今度は意外と継続が難しいというケースもあるでしょう。
当サイト含め、ネットで検索すれば、瞑想のやり方を解説している記事はたくさんヒットします。
どの記事でも手順はおおむね同じ。
静かな場所であぐらをかいて目を瞑り、呼吸や自分の内側に集中するという、とてもシンプルなものです。
でもやってみると、シンプルなわりに継続は意外と難しいのです。
数回チャレンジしてみて少し良いかもと思ったものの、気づいたら習慣からフェードアウトしている。
筆者自身、そんな経験を何度もしてきました。
1,2回しただけでは効果を実感しないという意味では、瞑想は筋トレと似ています。
ただ筋トレと異なるのは、外見など何か目に見える変化が現れるのではなく、自分の感じ方や考え方といった内面が少しずつ変化していく点です。
瞑想がもたらしてくれる変化は、注意深く意識していないと見逃してしまうこともあります。
変化が感じられないことを、脳が意識の外に追い出してしまうのは自然なことですよね。
なんなら目に見えて変化が出る筋トレですら、それを感じる前に心が折れて辞めてしまう人も多いわけですから、目に見えた変化を感じにくい瞑想が続かないというのも、おかしなことではないでしょう。
とはいえ、メンタルが揺らぎやすい筆者は、この状況を変えるべく、どうにか瞑想を習慣にしようと何度もトライしつづけてきました。
辞めては再開してのサイクルを繰り返すなかで、だんだんと続けるコツや考え方が見えてきたので、同じような状況の方の参考になればと思いシェアしてみます。

☞メディテーションの意味とは?瞑想やマインドフルネスとの違いは?
瞑想へのハードルを下げるコツ
まず筆者は、一旦「瞑想」という概念そのものから離れてみました。
今から自分は「瞑想」をするのではなく「深呼吸の練習」をするのだと、ことばを変えてみたのです。
「瞑想」にハードルを感じるのであれば、そもそも「瞑想」だと思わなければハードルはグッと下がると思いませんか?
とんちのように聞こえるかもしれませんが、筆者の場合これが意外とハマりました。
呼吸については、瞑想に関する記事でもよく言及されるので、捉え方の違いが分からないと感じるかもしれません。
でもそういった記事の文脈では、あくまで「瞑想の中の呼吸」という位置づけですよね。
そうではなく、本当にただ純粋に「呼吸」だけにフォーカスする。
自分の行為が瞑想かどうかは一旦置いておいて、とにかく自分がどれだけ呼吸できているかに意識を向けるだけ。
「呼吸なんて無意識にしてるでしょ」と思うかもしれません。
ですが、実はしっかり呼吸できていないことって、結構あるのです。
特に現代人はストレスで呼吸が浅くなっていたり、強い緊張を感じたときは、無意識に数秒間息を止めていることすらあります。
でもご存じのとおり、呼吸は生きていくうえで無くてはならないものです。
浅い呼吸だと十分に酸素を体に取り込めず、いつまでも交感神経が優位になってリラックスできず、血圧も上がりやすくなってしまいます。
逆に言えば、しっかり深い呼吸ができれば、それだけで心や体の調子を少し上向けることができる。
たかが呼吸、されど呼吸なのです。
一度、仕事中など、普段の何気ない瞬間に自分の呼吸がどうなっているか意識してみてください。
「深呼吸の練習」の必要性を実感する場面が、きっとあると思います。
そして何より「瞑想」より、単なる「深呼吸の練習」のほうが、心理的ハードルも低く感じられませんか?
それは「深呼吸」であれば、私たちはすでに取り入れたことがあるからです。
人前で話すときの緊張をほぐす深呼吸、遅刻しないよう猛ダッシュしたあとに息を整える深呼吸、イラっとしたときに冷静さを取り戻す深呼吸。
誰しもどれか一つはやったことがありますよね。
ストレスを上手く解消する手段として、日々の呼吸に意識を向ける。
そう捉え方を変えただけでも、筆者の場合は何か小さなステップを乗り越えた感じがしました。
気持ちの問題といえばそれまでですが、習慣化のためにいかに脳を上手く騙すかも大事なコツの一つです。

「深呼吸の練習」を習慣にするコツ
心理的ハードルが下がったら、次の課題は「継続」でしたよね。
ここでは現時点での筆者の考えるベストアンサーを紹介します。
まずは就寝前から始めてみる
まず、深呼吸の練習を始めるのに一番おすすめのタイミングは夜、できれば就寝直前です。
朝の活動前や、仕事の休憩中などちょっとしたスキマ時間でももちろん出来ますが、慣れないうちはどうしても、その後にやらなければならないことなど、あれこれ考えごとが浮かんできます。
その点、就寝直前なら、あとはもう寝るだけ。
やることが残っていない状態のほうがスムーズなので、入浴や歯磨き、スキンケアやストレッチなど、寝る前のルーティーンを全て終え、布団に入ってしまってからが特におすすめです。
横になって全身リラックスして、頭の中で数を数えながら、ただただ深呼吸を繰り返す。
最初はアプリなどのガイドに合わせて行うと、より集中しやすいでしょう。
☞おすすめのアプリ
就寝直前に布団の中で行うことの、もう一つのメリットは考えごと防止です。
夜は何か一つ考えごとが浮かぶと、それがあっという間にネガティブな方向に膨らんでいくもの。
その最初の考えごとすら浮かぶ前に深呼吸に集中することで、不安の渦に飲み込まれて寝付けなくなることを防いでくれます。
自分に合ったスタイルを見つける
と言ったものの、ライフスタイルは人の数だけ存在するので、必ずしも全員にとって就寝直前がベストタイミングとは限りません。
朝、家族全員を送り出したあとのほうが頭も心もスッキリしている、あるいはお昼休みに使う公園のベンチが結構リラックススポットという人もいるかもしれません。
大切なのは自分にとって一番続けやすいタイミングや場所、シチュエーションを見つけることです。
ツールに関しても同じことが言えます。
「瞑想アプリ」をインストールすることで結局またハードルを感じてしまうなら、リラックスできるBGMを小さく流しておくのでもいいでしょう。
筆者も先ほど紹介したようなアプリのガイドを活用していますが、日によっては音声が少し邪魔だなと思ったり、なんとなくペースが合わないと感じられたりもします。
そんなときはガイド音声なしのBGMだけにしたり、お気に入りのプレイリストをタイマー付きで流したり、まったく何も流さず頭の中だけで深呼吸したりと、その日の自分に合わせてスタイルを変えています。
習慣=毎日という思い込みを捨てる
継続、習慣ということばからは、どうしても「毎日やること」をイメージしますよね。
でも例えば、週1回しかジムに行ってなくても、それを何年も続けているならそれは立派な「習慣」といえますよね?
深呼吸の練習も、瞑想も同じです。
まずは心からリラックスできる、金曜の夜から取り入れてみるでもいい。
不定期でも、とにかく気がついたら深呼吸するでもいい。
極端なことを言えば、筆者みたいに辞めては再開しての繰り返しでも、継続していると言えると思っています。
眠れない夜が続けば「そうだ、最近深呼吸の練習サボっていたからだ」と思い出せるくらいには、十分頭と体に染みついているからです。
もちろん、アプリやカレンダーでリマインダーを設定して、毎日継続できることに越したことはありません。
ただそれで苦しくなったり、ストレスを感じたりしては本末転倒ですよね。
どれだけ健康によいことでも、義務に感じた途端、やる気を失うのは当然のことです。
もっとやりたいと思ったら毎日やってみる、逆に何年やっても毎日は無理と思うならやらない。
それくらいで十分です。
まずは気づいたときだけでもOKと自分に許可を出してあげて、ゆるく取り入れるほうが、結局スムーズに習慣化できるものです。

「深呼吸」を意識してみて感じた変化
最後に、とにかくゆるく細長く「深呼吸」や「瞑想」を続けてきた筆者が、少しずつ感じている変化にも触れておきます。
考えごとに飲まれることが減った
筆者は常に考えごとが絶え間なく湧き上がってくるタイプ。
考えごとには最悪のタイミングだといわれる夜は、むしろ一番考えごとをしてしまう時間で、見事に不安の渦に飲まれて眠れなくなるというのがデフォルトでした。
でも、ベッドに入った瞬間に「深呼吸の練習」をするというのを何日か続けると、そのままスムーズに入眠できる日が増えてきました。
始めたばかりは特にやり方がまだ身についていないので、自然とアプリのガイド音声に集中し、その時点で考えごとは強制終了されていたのです。
何度かそういう経験をすると、体や脳も慣れるのか、アプリを使わなくても数回深呼吸しただけで、フッと寝落ちすることもありました。
もちろん、いつも完璧にできるわけではなく、ガイド音声に慣れるとそちらに意識が向きにくくなったり、ストレスが重なった日は考えごとが我慢できなかったりと、気づいたらガイドが終わっていたという日もあります。
それでも「呼吸で考えごとの沼から脱出できる」という成功体験は記憶に残っているので、日中イラっとしたときも、まずは深呼吸してみようという、ある種のお守りを手に入れた感覚があります。
瞑想へのハードルが低くなった
「瞑想」ではなく「深呼吸の練習」という、より身近でとっつきやすい形に変換した結果、習慣としても馴染みやすくなったというのは、ここまででなんとなくお分かりいただけたかと思います。
ただ、予想外だったのが「深呼吸の練習」を続けた結果、とっつきにくさを感じていたはずの「瞑想」にも興味が出てきたことです。
以前は、自分の内面に集中するというのも、考えごとをそのままにして受け入れるのも、なんだかピンときていませんでした。
ましてや数十分も瞑想するなんて絶対無理だし、別世界の話だと思っていました。
でも「深呼吸の練習」をしてみると、意外と時間はすぐに経つし、もしかしたら思っているほどは難しくないのではと思えてきたのです。
しかも今は「就寝前の深呼吸で、気持ちよく入眠できる」くらいの効果ですが、もしもっと踏み込んで「瞑想」ができれば、根本にあるメンタルの揺らぎやすさも、本当に改善できるのかもしれないと感じはじめています。
初めて「瞑想」ということばに出会ったときとはまったく違う感覚で、明らかに心理的ハードルが下がっているのです。
ただ、やはりまだ一歩踏みとどまっている部分があるので、その障壁が何なのかを見極めながら、スムーズに一歩踏み出せるやり方や考え方を模索しているところです。
何かいい方法が見つかったらまた皆さんにもシェアしたいと思います。
まとめ
みんな良いと言っているから、流行っているからというだけで、無理して取り入れても瞑想の効果は発揮されません。
大切なのは自分が納得して、習慣にしていけるかです。
「瞑想」と捉えるか「深呼吸の練習」と捉えるか、どちらが良いかという話ではなく、自分自身が心地よく始めるため、頭と心が拒否反応を起こさないためにはどうしたらいいのか。
今回の記事がそんな道を探すヒントになれば幸いです。
瞑想やマインドフルネスに関連した記事は、やり方の解説やインタビュー記事などたくさんあるので、ぜひ参考にしてみてください。
☞幸福度が上がる瞑想方法。楽に続けられる、続けてこそ実感する!
☞マインドフルネスと瞑想の違いや初心者におすすめのやり方を徹底解説!
怒る前に深呼吸。そのイライラは私にとって役立つの?『幸福になりたいなら幸福になろうとしてはいけない』を読んで実践してみた
Humming編集部メンバーがお届けする書籍コラム。
今回ご紹介する書籍は『幸福になりたいなら幸福になろうとしてはいけない: マインドフルネスから生まれた心理療法ACT入門』。本書で紹介されているACTの手法を日常生活の一場面に取り入れてみました。

夏の陽射しが容赦なく差し込む8月のある日、私は自宅のリビングで息子と向き合っていた。
小学生の息子は夏休み真っ只中。
基本的に家で仕事をしている私は、7月・8月は息子と一緒に過ごす時間が長い。
午前中、私はノートパソコンに向かい仕事に励む一方、息子は夏休みの宿題をする。これが我が家の日課となっていた。
夏休みも終盤に差し掛かり、このままのペースでは息子の宿題は終わらない。私は「毎日、国語算数理科社会、それぞれ毎日3ページずつやらないと終わらないよな……」と焦りを感じていた。しかし、息子に焦る様子は全く感じられない。
25分集中して作業を行い、5分休憩するというポモドーロタイマーをセットして、それぞれがやるべきことをスタートした。しかし、息子は1問解いては立ち上がり、ボールを蹴ったり、ソファーに寝転んで漫画を読んだりと、集中力が続かない様子。本気でやれば1時間で終わるであろう問題に3時間程かかった。
丸つけを始めると、思わずため息がこぼれた。止めもハネも意識されずさらっと書かれた漢字。答えだけが記され、計算過程が全くわからない算数の回答欄。
「あのさ、毎回言っているよね。字をきれいに書こうね、式をちゃんと書こうねって」 私の言葉に、息子は「だって……」と小さな声で答える。 やりとりを繰り返すうちに、「何度言っても直す気がないなら、もう好きにしなよ。困るのは自分だよ」と投げやりな言葉を口にしてしまった。
ここ数日、同じようなやりとりが毎日繰り返され、私は疲れ果てていた。夜になると、さまざまな思いが頭の中をぐるぐると巡り、ひとり反省会が始まる。
「勉強させるのが辛い。そもそも無理やり勉強させることに何の意味があるのだろうか……」
「できていないところばかりでなく、頑張ったところに目を向けてあげたい」
「私がイライラしても状況は悪化するだけ。口出しせずに見守れたらいいのに」
そして最後には必ず、「せっかくの夏休み。息子となるべく笑顔で過ごしたいのに」という思いにたどり着くのだ。
子育てに悩む日々が続く中、
「幸福になりたいなら幸福になろうとしてはいけない」という1冊の本に出会った。マインドフルネスに興味を持ち、タイトルに惹かれてネットでポチッと購入した本だ。
この本で紹介されている心理療法ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)は、ネガティブな考えが浮かんだ時に、まず自分の状態を客観的に見つめ、その感情をありのまま受け入れること(アクセプタンス)が大切だと教えてくれる。そして、「この思考は自分にとって本当に役立つのだろうか」と自問し、自分にとって大切な価値に基づいて行動する(コミットメント)ことを勧めていた。
翌朝、「今日は絶対にイライラしないで子どもたちと笑顔で過ごそう」と決めて1日をスタートした。
しばらくすると、息子がリビングにやってきた。寝起きの息子に「おはよう」と声をかけ、ぎゅーと抱きしめる。「よく眠れたかな?」とたわいのない話をしながら、ソファーに横たわる息子の足をマッサージした。
しばらくすると、娘が起きてきて、すぐさまソファーの陣地争いが始まった。朝から繰り広げられる兄妹喧嘩に、思わず「いいかげんにしなさい」と怒鳴りそうになる。
しかし、ふと我に返る。「今日は笑顔で過ごすんだ!」
そして、本に書いてあったことを意識して、心の中でぶつぶつと呟いてみた。
「私は今怒っているという感情を持っている。朝から兄妹喧嘩が始まりすごくイライラしている。だけど、私が怒りを爆発させたところで、兄妹喧嘩が止まるわけでもないし、自分の気持ちがスッキリするわけでもない。むしろ子どもたちにひどいことを言ってしまって自己嫌悪に陥るかもしれないし、兄妹喧嘩が悪化するかもしれない。つまり、今私が持っている怒りの感情は私にとって良いことをもたらさない…….」
そして、兄妹喧嘩をよそに、目を瞑って3回大きな深呼吸をしてみた。鼻から吸う呼吸で、肺に空気が入っていく感覚を味わい、吐く呼吸でお腹の凹みを感じる。呼吸をするたびに、私の中に渦巻くネガティブな感情が少し外に吐き出された感覚を味わう。足の先から脳味噌まで酸素が行き渡り、イライラしているはずの私の口角がちょっぴり上がったように感じた。
「よし、いったんこの場を離れよう」
キッチンに向い、背後で兄妹の言い合う声が聞こえる中、私は黙々とスイカをカットし始めた。 「今、私はスイカを切っている」 目の前の作業だけに意識を向け、包丁を握る手の感触に集中する。
ダイニングテーブルに、スイカとヨーグルトとパンをセットして、「朝ごはんが用意できたよ」と子どもたちに声をかけた。
むすっとした顔で食卓に座る子どもたち。私は平然とスイカを口に運んだ。 「おぉ、今日のスイカ、甘くて美味しい!」
その言葉に反応するように、子どもたちもスイカを食べ始める。娘は両手を頬に当てて「おいしい〜」のポーズ。息子も親指を立ててグッドサインを送った。
普段なら兄妹の言い合いでイライラしてしまうところを、今日は冷静でいられた。そんな自分に心の中でガッツポーズ。
そして、朝ごはんを終えて娘を保育園に送り届けると、再び息子との時間が始まった。
「今日の目標は?」と息子に尋ねる。
「今日は15時までに1教科2ページずつやる!」
「自分で決めた目標を達成できるように頑張ってね」とソファーでゴロゴロ寝転んでいる息子に声をかけた。
タイムリミットの15時を迎えた。理科と社会と国語、1ページずつしか終わっていないようだ。算数に至っては手付かずだった……。
残念ながら、この時点で私の「今日は絶対にイライラしないで子どもたちと笑顔で過ごそう」という目標は達成できなかった。
「あのさ、自分で決めた目標くらいちゃんと守りなよ。もう少し集中して勉強するべきなんじゃない?…….」息子への説教が止まらない。
しばらく立って、怒りが少しおさまってきた頃に、深く呼吸をした。
「私だって、自分で決めた今日の目標守れてないじゃん」
「私が怒るほど、息子のやる気はなくなっていくよな……」
いろんな思考が頭を巡る。
再び深呼吸をして、今日の自分の言動を客観的に振り返ってみる。
本の内容を実行し続けることはなかなか難しい。
きっと私はこれからも子どもたちに怒ったりイライラしてしまうことがあると思う。だけど、その度にこの本を読み返し、「その思考は私の役に立つの?」と唱えて深呼吸をしてみよう。
書籍紹介:
幸福になりたいなら幸福になろうとしてはいけない: マインドフルネスから生まれた心理療法ACT入門 ラス ハリス (著), 岩下 慶一 (翻訳)
時は金なり。 ドラッグのように中毒性のあるスマホとの付き合い方を見直そう【Editor’s Letter vol.10】
| Humming編集長 永野舞麻がカリフォルニアから配信する「Editor’s Letter 」。
日々の暮らしで感じた気付きや、人生において大切にしていることを綴っています。 |

現代人の必需品とも言えるスマートフォン(以下、スマホ)。手のひらサイズの小さな端末が、私たちの生活に革命的な変化をもたらしました。
スマホさえあれば、世界中の誰とでもリアルタイムで連絡が取れ、わからないことはすぐに調べることができる。社会の情報インフラとして欠かせない存在になった一方で、私たちはいつの間にかスマホに依存し、大切なことを見失ってはいないでしょうか。
通知音が鳴るたびに手が伸びる。無意識のうちにスマホを見てしまう。家族や友人との会話中もついついスマホをチェックしてメールの返信を優先してしまう。そんな経験をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
「便利な道具」のはずのスマホに振り回され、本当に大切なものから目を背けてしまっていないか、一度立ち止まって考えてみませんか。
今回は、私がスマホと距離を置いた理由とそれがもたらした変化についてお話しします。
私を変えた10日間のデジタルデトックス
私がスマホと距離を置きはじめたきっかけは、10日間のリトリート。リトリート中はデジタル機器の使用が一切禁止されていたため、強制的にスマホと距離をとることができたのです。最初は手持ち無沙汰でしたが、日が経つにつれ、スマホがないことによる変化に気づき始めました。目の前の出来事、例えば食べている料理の味や、鳥のさえずり、足元を横切る蟻などに自然と意識が向くようになったのです。情報が過多に入ってこない、余白がある暮らしの心地よさに気づくようになりました。
リトリートを終えて10日ぶりにスマホを手にした時の衝撃は忘れられません。まず、画面の明るさが以前よりもはるかに眩しく感じました。さらに、スマホに自分のエネルギーを吸い取られているかのような不思議な感覚に襲われたのです。実際、スマホを数十分見ただけで頭痛がするようになりました。
その経験に驚き、携帯やパソコンの画面に長時間集中することで、多くのエネルギーを消耗していることに気がついたのです。そこで、意識的にスマホを使う時間を制限することに決めました。
子どもたちと一緒にいる時間は極力スマホを触らない。寝る時はリビングの棚にスマホをしまい、次の朝メディテーションが終わるまでは触れない。さらに、メールやメッセージの通知をOFFに設定しました。スマホに自分の行動を支配されるのではなく、自分が必要な時にのみ、スマホを手にするようにしたのです。

スマホを手放したら、人生が変わる?!
スマホを使う時間と使わない時間の境界線を作ることで、私の生活にはポジティブな変化が表れました。
例えば、寝る前の準備。これまではスマホで調べものをしたり、動画を見たりしながら、顔を洗って、歯磨きをして、着替えをしていたので、1時間ほど時間がかかっていました。それが今では半分以下の時間で終わるようになり、余白が生まれました。
いかにスマホという機械に時間を奪われていたかを体感すると共に、本来の自分のキャパシティの広さに気がついたのです。
また、寝る前にスマホを見なくなったことで、自律神経が整い、メディテーションをしてから眠りにつくまでの時間も短くなり、睡眠の質も高まりました。
さらに、人との関わり方にも変化が表れました。以前は子どもたちに話しかけられた時に、「このメールの返信が終わるまで待って」と言うことが度々あったのです。今思えば、「あなたより、スマホの中の出来事が大切」と表現しているようなものです。しかし今では、目の前にいる相手との時間を何よりも大切にできるようになりました。
すると、学校での出来事や友達とのトラブル、 姉妹喧嘩のこと、自分が感じていることなどを、子どもたちから話してくれることが増えました。私がスマホに集中している代わりに、本を読んだり、趣味のアートやパズルをしていることで、話しかけやすい空間ができたのだと思います。
また驚くことに、私がスマホを手放したことで、これまでは頻繁に行われていたスマホやタブレット端末を模倣した遊びを子どもたちがしなくなったのです。子どもは良くも悪くも周囲の大人の姿を見て育つもの。もし子どもたちにスマホに支配された人生を歩んでほしくないのであれば、まずは周りの大人が手本を示す必要があると強く感じました。
「伝える」ことで、スマホを使わないデメリットを乗り越える
とはいえ、スマホを使う時間を制限することで、急な予定変更や緊急の連絡に気づきにくくなるというデメリットもありました。どちらかと言えば、自分自身への影響というよりも、相手に対してのデメリットと言えるかもしれません。
そのため、よく連絡を取り合う仕事相手や友人には、24時間以内の返信を心がけながらも「私は自分の都合のいいタイミングで連絡するから、あなたも即座に返信しなくて大丈夫。お互いに無理のないペースでやり取りしましょう」と伝えるようにしています。逆に返事を急ぐ時には、「こちらは急ぎの用件なので、できるだけ早めの返信をお願いします」と伝えることもあります。
また、特定の時間帯はスマホを確認し、子どもの学校関連の連絡事項や、仕事上の緊急の連絡にはなるべく対応できるよう心がけています。
必要以上にスマホに時間を奪われないために
スマホが私たちの生活に欠かせない存在となり、即レスが善とされる現代社会において、スマホと距離を置くことは勇気のいることかもしれません。
しかし、完全にスマホを断つことが難しくても、使う時間と使わない時間の境界線を決めて、上手く付き合うことはできると思うのです。例えば、週末や家族団欒の時間、自分の趣味に没頭する時間はスマホから離れる。一方で、仕事上の連絡や緊急の用件には適切に対応するなど。
人生において、時間ほど貴重なものはありません。スマホやパソコンなどの電子機器は私たちの生活を便利にしてくれる、いち道具です。私たちが使う側であり、道具に支配されるようになっては元も子もないのです。
必要以上にスマホに時間を奪われなくなることで、本当に大切なものに時間を使えるようになり、新しい発見や気づきが得られるかもしれません。それはきっとあなたの人生をより豊かなものにしてくれるでしょう。
「本当の自分」が分からない?迷ったときに思い出したい考え方

本当の自分が分からない
「本当の自分」って何なんだろう。
ふと、そんな問いが浮かぶことってありませんか。
親の前、友達の前、職場、パートナーに見せる顔、どれも全部少しずつ違う。
真面目なしっかり者のときもあれば、子どものように甘えたくなるときもある。善良に生きていても、たまに道を踏み外すことだってある。
SNSが当たり前になった現代では、その「顔」の数はさらに増えています。
仕事用、プライベート用アカウント、何も考えずつぶやける、誰にも教えていない裏アカウント。複数アカウントを使い分け、それぞれ違う自分を見せている人も多いのではないでしょうか。
私たちはこんな風に、相手や環境に合わせていろんな顔を使い分けます。
「誰か」のイメージ通りの私でいなきゃ、がっかりされるかもしれないから。それで離れていってほしくないから。
でもそれに疲れ果て、途方に暮れるときもあります。
こんなの私じゃない、素の自分に戻りたい。そもそもいろんな顔を使い分けるなんて、相手も自分も騙しているのと同じではないか。
ずっと変わらない「本当の自分」を貫けたら、どんなに楽だろうか。
だけどもうどれが「本当の自分」なのかも分からない。
そんな葛藤を、誰しも一度は抱えたことがあるのではないでしょうか。
そもそも本当の自分って?
そもそも、私たちが探し求める「本当の自分」ってどんなものなのでしょうか。
自分のなかにある、唯一無二の、確固たる存在。なんとなく、そんなイメージがあるかもしれません。
だからこそ、今は「本当の自分」からかけ離れているとか、周りにも自分にも嘘をついているというような考えが浮かび、私たちは苦しくなります。
でも本当に、「本当の自分」とはたった一つしか存在しないのでしょうか。
一歩引いてその定義を見つめ直してみると、少し心持ちが変わるかもしれません。
「周り」によって形成される
あなたという人間は、あなた自身が感じて考えるからこそ存在しています。
そういう意味では、本当の自分とは「自分のなか」で形成されるように思えるかもしれません。
でも、その感じて考えるということ自体、必ず「周り」と関わっているはずです。
仕事がデキる人に見られたいから、ちょっと背伸びして頑張ろう。家族や親友の前では、ポンコツなところを見せたって平気。
仕事の日は小ぎれいな身なりをするけど、近所のコンビニは伸びきったTシャツでいいや。誰も私を知らないから旅先では、いつもと違う行動や選択をしたくなる。
大人になるとよく「自分で考えて行動しろ」と言われますが、どんなに自分で考えたとしてもその起点はあくまで周りの人や環境にあります。
あの人は雑談多めのほうが仕事の話がスムーズに進む、この人は真面目なタイプだから端的に伝えたほうが良い。
SNSだって同じで、見ている人のタイプを考えて、投稿する内容を調整します。
そんな風に、私たちは常に周りとの関係のなかで自分の立ち居振る舞いを決定しています。
だから「本当の自分」とは、たしかに「自分」ではあるものの、「周り」によって形成される相対的なもの。
相手や環境によってアメーバのように変化する、そもそもの輪郭があいまいなものなのです。
「複数」存在する
世の中には多重人格や八方美人ということばがあり、これらはどちらかというとネガティブな使われ方をします。
誰にでも良い顔をして相手を騙している、そんなニュアンスが含まれていますよね。
さらに、これを裏返すと、あたかも「本当の自分」がたった1つしか存在しないようにも思えます。
常に「本当の自分」でいるべきで、それが人として誠実な振る舞いだ、そんな風にも聞こえてきます。
だから私たちは、自分が「いろんな顔」を持っていることに嫌気が差し、「唯一無二」の本当の自分を見つけようともがく。
でも本当の自分が「周り」によって形成されるのであれば、極端に言えば、関わる人や身を置く環境の数だけ「自分」が存在する可能性があります。
ここから「唯一無二」の本当の自分を定義するのは、かなりハードルが高く感じられませんか?
かといって、いきなり「本当の自分」が複数あることを受け入れろというのも簡単ではありません。だから私たちは悩んでいるのですよね。
では、その「いろんな顔」を全てくっつけたのが「本当の自分」と考えるのはどうでしょうか?
どれだけいろんな顔を使い分けたとしても、その組み合わせだけは唯一無二です。
切り取った一部もその集合体も、どれもが紛れもなく「本当の自分」です。それぞれの仮面を別人と捉えてしまうか、仮面を上手に使い分ける一人の人間と捉えるか。
近くでみるか俯瞰でみるか、問題は視点にあります。
そう考えると、全部ひっくるめて「本当の自分」だということが、少しずつ腑に落ちてくるのではないでしょうか。
「時間」とともに変化する
本当の自分を見失ってしまう要因は、もうひとつあります。それは本当の自分とは「時間」とともに変わるということ。
子どもの頃と大人になった今の自分では、考え方はかなり違うはずです。
子どもの頃は分からなかったことが分かるようになり、子どもの頃はシンプルだったことが複雑に見えることもあります。大事なことと、そうでもないことの基準も変わっているかもしれません。
もっと短いスパンでそれを感じることもあるでしょう。人生において、昨日と今日の価値観が180°ひっくり返ることは、別に不思議なことではありません。
そうした感じ方や考え方の変化にふと気づいたとき、私たちはうろたえてしまいます。「私はこんな人間ではなかったはず」あるいは「これまでなんて人間だったんだろう」と。
でも、過去と今の自分、どちらかが間違っていたのかというと、そうではないはずです。
子どもの頃は子どもなりに、昨日の自分は昨日の自分なりに、そのときの環境や状況に則した「自分」でいたはずです。その環境や状況が変わったから今の自分も変わった、ただそれだけの話です。
本当の自分が「周り」によって形成されるものである以上、時間の経過とともに、環境や付き合う人が変われば「本当の自分」も変わる。
「確固たる」本当の自分が見つからないのは、ある意味、当然のことなのです。

本当の自分を見失ったときのヒント
「本当の自分」とは、何か1つ決まった枠があるわけではないということが、少しずつ理解できてきたかと思いますが、心から腑に落ちるまでには時間がかかるかもしれません。
それに理解したからといって、悩みがすぐに解消されるわけでもないでしょう。はっきりとした輪郭がないものに、不安を抱くのはごく自然なことです。
大切なのは、その不安に飲み込まれず、体勢を立て直すスイッチを知っているかどうかです。
そのスイッチは人それぞれですが、ヒントになりそうな考え方をお伝えしておきます。
いろんな顔の「良い面」に気づく
私たちが確固たる「本当の自分」を探してさまよってしまうのは、そのほうが楽だから。
ものづくりに例えて考えてみましょう。
規格が決まった工場生産なら、同じ品質のものを一度に大量生産できますが、職人の手作りだと、どうしても微妙な差が生じるうえ生産量も限られます。労力、効率を考えると、どう考えても工場生産に軍配が上がりますよね。
工場生産のように、本当の自分にも「規格」があれば、周りに合わせて繊細に調整する必要もなく、余計なストレスも減りそうな気がする。だから、私たちはその型を探したくなる。
では、時間も労力もかかる職人の手作りはダメかというと、そんなわけはありませんよね。1つ1つ微妙に違う風合いは「味」と評価され、多くは生産できないことは「希少性」という価値になります。
だとしたら「本当の自分」も、少しずつ違う顔を「味」、それぞれを見せる相手が限られることを「希少性」ととらえても良いのではないでしょうか?
自分だけに見せてくれる顔があると、人はちょっと嬉しくなります。逆に、いつもとは違う顔や、自分には見せない顔があることを知ると、より惹かれてしまうことだってあります。
いろんな顔を使い分けるのはたしかに疲れますが、それで作られるあなたの魅力があることにも気づいてくださいね。
そしてもう一つ、あなたがいろんな顔を使い分ける理由にも目を向けてください。
相手が気持ちよくいられるように、その場の空気が良くなるように、そして自分が傷つかないように。そのためにはどう振る舞えばいいか、知恵を絞る。
もがきながらもいろんな顔を使い分ける背景には、そんな優しさがあると筆者は考えます。だって、周りのことも自分のこともどうでもいいなら、こんな面倒で疲れることはしないはずです。
たくさんの顔を持つ人は、それだけ優しさや知恵を持っている。
こうしたいろんな顔を持つことの良い面に気づけると、少し「本当の自分」探しの呪縛から解放されるのではないでしょうか。
「不安の原因」を深掘りしてみる
人は意外と、不安の原因を明確に理解していないものです。
漠然と将来が不安、なんとなくこのままじゃ良くない気がする。そんなことってよくありますよね。
「本当の自分」を見失い不安に襲われているときも、その可能性がゼロではありません。そもそもあなたは、なぜ「本当の自分」を見つけたいと感じているのでしょうか。
もしかしたら、何か現状に不満があるのかもしれません。
たとえば、職場では人間関係も仕事もそれなりに上手くいっている。お給料も生活も安定して何不自由ないはずなのに、何となく満たされず「本当の自分」ではない気がする。
実はその背景には「もっとバリバリ仕事をしたい」という野望、あるいは「もっとミニマムな自給自足の暮らしのほうがいい」といった気持ちが隠れているのかもしれません。
あるいは、あなたは今すごく疲れているのかもしれません。
たとえば、ストレートな性格の人が空気を読んで振る舞うことは、出来なくはないけれどかなり疲れることです。
それが今までは職場だけで十分だったのに、何らかの環境の変化で、家庭や友だちと会うときもそうしなくてはいけなくなった。気づいたら、ずっと自分にとって疲れる顔ばかりしている。
だから気張らずいられる「本当の自分」に戻りたい。
こんな風に「本当の自分」探しには、そこに至るまでの原因や過程があるはずです。ただその多くは、ほんの些細な出来事だったり、じんわり変わっていくものだから気づきにくい。
そんなときは、一度紙に書き出して心と頭を整理することも大切です。
なぜ「本当の自分」を見つけたがっているのか?
現状に何か不満があるのか?それとも単にいっぱいいっぱいなのか?
その原因はどこにあるのか?自分で解決できることなのか?
一つずつ地道に深掘りしていくと、意外と具体的な解決策にたどり着くかもしれません。
たとえば、転職活動や異動願い、業務量の調整。あるいは新しい習いごとや家族旅行、旧友との他愛もない話だったり、その解決策は十人十色です。もちろん解決策によっては、すぐには実行できないかもしれません。
でも少なくとも、実体のない唯一無二の「本当の自分」を探し求めるより、遥かに地に足がついていて手を伸ばしやすいものではないでしょうか。
本当の自分は揺らいで当然
いろんな顔があることに嫌気が差しているのに、それ自体を肯定しろだなんて”とんち”のように感じられる内容だったかもしれません。
でも、無理矢理「本当の自分」という枠を作り上げ、そうでないときの自分を否定して苦しむよりは、肩の荷は少し下りるのではないでしょうか。
少しずつ、自分のいろんな顔、そしてそのいろんな顔を持つ自分自身の魅力にも、気づいていってあげてくださいね。
21日間のジャーナリングで人生を変えよう

※この記事は、アメリカの記事を日本語に訳したものです。
https://level.game/blogs/can-writing-affirmations-for-21-days-change-your-life?lang=en
「You Can Heal Your Life(あなたは人生を癒すことができる)」というアメリカの作家ルイーズ・ヘイの不朽の言葉には、世界中の人の人生を変えた深い真実が隠されています。それは「アファメーションの力」。つまり、シンプルで前向きな言葉によって、あなたの考え方そのものを変え、夢や願望を実現するための土台を作ることができるのです。数えきれないほどの自己啓発が実験されてきたが、21日間のアファメーションは、私たちを変革するための力強い方法であることがわかってきた。
このアファメーションは単なる希望的観測ではありません。ポジティブな自己イメージを築き、自分にふさわしい人生を引き寄せるために、潜在意識を書き換える方法なのです。
アファメーションとは
アファメーションとは、潜在意識をポジティブにし、ネガティブな思考を取り除き、自信を高めるためのポジティブな文言のことです。常にアファメーションを繰り返し、それを信じることで、ポジティブな変化を起こすことができるのです。「私は〇〇です」という言い方のアファメーションは、あなたの存在意義、そして能力を肯定し、あなたの自己肯定感を高める強力なツールです。こういったアファメーションは、あなたの幸福度を高めポジティブな人生を促すでしょう。
21日間のアファメーション・チャレンジ
ポジティブなアファメーションのやり方としては、毎朝5つのセリフを自分に語りかけるという方法があります。21日間アファメーションを書き続ける理由は、新しい習慣を作るには21日かかるという調査結果に基づいています。この21日間は、あなたの脳をポジティブ思考へといざなうための神聖な期間なのです。毎朝、5つのセリフを自分に語りかけることで、自分の強い決意を確認し、素晴らしい1日の幕開けとなります。
アファメーションの文言を作る
効果的なアファメーションを作るには、「私は〇〇だ」というフレーズから始めましょう。例えば、「私は愛と尊敬を受けるに値する人間だ」とか、「私は自分が思っている以上に強い人間だ」などです。こういうアファメーションは、個人的なもので、前向きな内容で、明確な言い方でなければいけません。さらに、現在形で唱え続けることで、あなたの心は、それがすでに起こっていることであり、未来のことではないと考えるようになります。例えば、もっと創造性を高めたいという人は、「私は想像力に満ちている」というアファメーションの後に文章を書くと、革新的なアイデアが次々と出てくるでしょう。
アファメーションを書くメリット
アファメーションを唱えるのではなく、実際に書くことで、あなたの精神的、感情的、そして肉体的な幸福にも大きな影響を与えることができます。主な効果をいくつか紹介しましょう。
精神的健康の向上: アファメーションは、しばしば不安やうつにつながるネガティブな思考を打ち消すのに役立ちます。ポジティブな結果に焦点を当てることで、より楽観的に物事を考えられるようになります。
自信がつく: 自分の存在意義を定期的に肯定することで、自己肯定感を高めることができます。「私は〇〇」という言葉は、自分への自信を強めるのに特に効果的です。
集中力が高まる: アファメーションを書くことで、目標を常に頭の片隅に置いておくことができ、目標達成に必要な行動を取りやすくなります。
ストレスの軽減: ポジティブなアファメーションは、思考を、心配事をからポジティブな視点へとシフトさせることで、ストレスを軽減することができます。
願望実現: 引き寄せの法則は、肯定的な思考に集中することで、肯定的な人生をもたらすことができるでしょう。アファメーションは、まさにこういった願望実現のためのツールです。
人間関係: 人間関係についてポジティブな発言をすることで、周囲の人と思いやりをもった協力的な環境を育むことができます。
自己回復: ヒーリングのためのアファメーションは、病気や怪我ではなく、健康や癒しに意識を集中させることで、回復や幸福感を促進することができます。
つまり、21日間アファメーションを書き続けることは、大きな自己成長と変容をもたらすための、とてもパワフルな取り組みなのです。この取り組みに必要なのは、ポジティブに変化したいという意欲と、毎日数分だけ行うという決意だけ。このアファメーションを毎日行うことで、人生のあらゆる分野において数えきれないメリットを受け取ることができるでしょう。
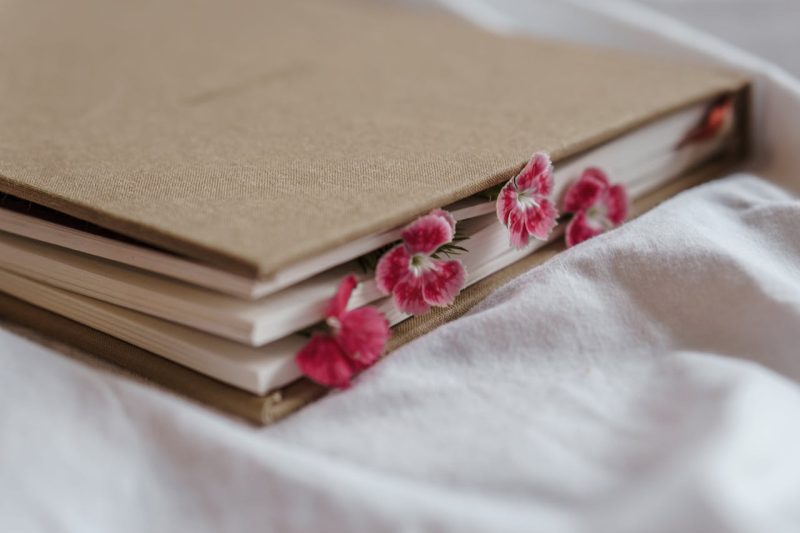
アファメーションを始めるために必要なもの
21日間のアファメーションを書き続けるために必要な道具はペンと紙で十分です。最も重要なのは、心をオープンにし、新しいことにトライする意欲、そして自己改善への決意です。自己肯定感、健康、キャリア、人間関係などの分野で、あなたが深く共感できるアファメーションの言葉を選びましょう。
アファメーションを日常生活に取り入れる
アファメーションを日常生活に取り入れるのは簡単です。日記に書いたり、鏡の前で声に出したり、瞑想中に心の中で繰り返したりして取り入れましょう。大切なことは一貫していることです。例えば「私は毎日癒されています」のようなアファメーションの時は、まるで癒しているような静かな時間に唱えると、特に効果があります。
アファメーションを書くメリット
アファメーションを日常生活にとりこむことは、自分の成長のためにも効果があります。これによって、自分の意思を固め、思考と行動を一致させ、自分は成功に向かっているというマインドセットを育てることができるでしょう。
以下の21日間モデルと、アファメーションの例を参考にしてみてください。
Day 1: あなたがなりたい自分をイメージしてください。
例: 私は自分を誇りに思い、自分のユニークな性格を称えます。
Day 2: 誰かを助けたときのことを書き、それがどんな気持ちになったかを書いてください。
例:私は人の人生に前向きな力を与えています。
Day 3: あなたが今直面している課題を思い浮かべ、それをどう克服するかを考えてください。
例:私には、心が折れても立ち直る力がある。
Day 4: 1年後の自分を思い描いてください。
例:私は明るく成功した未来に向かっています。
Day 5: あなたの人生で乗り越えた困難な時期について、どのように乗り越えたかを書いてください。
例:私の人生には明確な目的がある。私はとても恵まれている。
Day 6: あなたが達成した目標と、それを達成した方法を書いてください。
例: 私は、日々の努力を重ねて目標を達成し、成功を祝うことができます。
Day 7: 失敗が教えてくれた貴重な教訓を振り返ってください。
例:私はどんな経験からも学び、成長します。
Day 8: あなたにインスピレーションを与えてくれる人について書いてください。
例:私は友の偉大さに刺激をうけ、自分も人にインスプレーションを与えられるよう努力します。
Day 9: あなたが恐れていることを思い浮かべ、それにどう立ち向かうかを考えてください。
例: 私は強くて、立ち向かう勇気を持っています。
Day 10: あなたにとっての夢とその意味を書いてください。
例:私は夢を追い求め、一歩一歩夢に近づいています。
Day 11: 他人が言ってくれたあなたへの誉め言葉と、あなたをそれをどう感じたかを振り返ってください。
例: 私は自分の努力や資質を評価され、認められている。
Day 12: あなたの人生で変えたいことについて書いてください。
例:私は自分の人生を自分でデザインしている。
Day 13: 自分が信じられないほど誇らしく感じた瞬間について書いてください。
例: 私は自分の業績を誇りに思っています。
Day 14: あなたが身につけたい習慣とその理由を考えてください。
例:私は毎日、新しく前向きな習慣を身につけています。
Day 15: あなたにとって大切な人間関係について書いてください。
例:すべての人間関係で私は愛に満たされています。
Day 16: あなたが勇気を示した瞬間を振り返ってください。
例:私は勇気があり、自分が信じるもののために立ち上がる。
Day 17: 楽しみにしていることについて書いてください。
例:私は未来が楽しみです。
Day 18: あなたが学びたいスキルとその理由を考えてみてください。
例:私は人生のあらゆる分野で常に学び、成長しています。
Day 19: 今日、どのように自分に優しくできるかを書いてください。
例:私は自分に優しく、癒してあげる価値があります。
Day 20: あなたが安心できる場所について書いてください。
例:私は家族と仲間と一緒にいる時に安心できる。
Day 21:この20日間を振り返り、あなたがどういう成長をしたかについて考えてみてください。
例:私は自分の今までの道のりに感謝し、すべての学びを受け入れます。
アファメーションを書く時間
アファメーションを実践する方法は1つだけではありません。例えば、アファメーションを書くのに最適なのは、1日のうちで邪魔が入らず集中できる静かな時間帯です。多くの人は朝が理想的だと感じているようです。毎朝5行だけ書きながら自分に語りかけることは、自分のマインドに人生の目的意識と前向きな気持ちを植えつけるとても効果的な方法です。ただ人によってはアファメーションを夜に書きたいという人もいるでしょう。いずれにせよ大切なことは、静かな時間を選び、継続して行うことです。
アファメーションだけでなく、毎日瞑想を実践したり、ストレッチをして体調を整えたり、集中力や睡眠のために音楽を聴いたりするのも良いでしょう。ぜひあなたもアファメーションを試して、人生をさらにポジティブに変化させましょう。
恐れるのは死よりも後悔。今を大切に生きる意味

Humming編集部 條川純のコラムをお届けします。
誰もが必ず経験する「死」。私たちは、大切な人を失う痛みを味わい、いつかは自分自身もこの世を去ります。
死ぬことは怖いというイメージがありますが、本当に死は恐れるべきことなのでしょうか。
最近知った友人の病気や、過去に大切な家族を癌で亡くした経験、そしてテレビやネットで耳にする著名人の訃報など、身近な出来事をきっかけに、私は死について考え続けてきました。そんな中で培ってきた私の死生観について話してみたいと思います。
恐れるのは「後悔」を残して死を迎えること
40歳を目前に、この先の人生を考えると共に、死を意識するようになりました。そして気がついたのは、私は死ぬことよりも、後悔を恐れているということです。
後悔のない人生を歩むためにも、私は他人を尊重し、思いやりを持って接することを大切にしたいと改めて感じています。そうすることが、自分自身の幸福につながると確信しているからです。
また、他人からの評価にとらわれるのではなく、自分自身に集中したいと思っています。
例えば、スマートフォンやソーシャルメディアに依存する生活を送っていると、他者と自分を比較してしまったり、「いいね」の数が気になったり、本当に大切なことを見落としがちです。
どんな情報でも簡単に手に入り、遠く離れた人ともオンラインでコミュニケーションが取れる便利な時代。だからこそ、大切な人に直接会ったり、旅に出て新しい経験をしたり、リアルな交流や体験を大切にしたい。直接的な人とのつながりや、五感を通して得られる生の経験には、かけがえのない価値があるはずです。
人生は一度きり。後悔のない人生を歩むために、自分と向き合い、今この瞬間を大切に生きていきたいです。
大切なひとの死を乗り越えるために
生きている間には、大切な人とのお別れを経験することがあるでしょう。私たちは、愛する人を失った時、計り知れない悲しみと喪失感に襲われます。
以前、親しい友人が親を亡くした時のことを思い出します。彼は耐え難い悲しみに襲われ、その対処法を見出すことができずに、自分自身を傷つけてしまったのです。悲しみの渦から抜け出せない彼を見て、私は死を乗り越える方法について考えさせられました。
現代社会では、家族が亡くなった後、残された親族はすぐに書類作業や法的手続き、請求書の支払いに追われ、死を受け入れる余裕がないことが多いように感じます。
大切な人を失った時には、思い出の場所を訪れたり、写真を眺めたり、故人を偲ぶ時間を持つことが大切です。また、「故人は最後に何を伝えたかったのだろう」と考えたり、「今の自分の生き方を故人が見たらどう思うだろう」と自らを振り返る内省の時間も必要でしょう。心の傷は簡単には癒えないものです。適切なケアを怠ると、その傷は長い間心の奥底に残り続け、私たちを苦しめる可能性があります。
悲しみに寄り添い、故人との思い出を大切にしながら、徐々に新しい日常を築いていくことが、大切な人の死を乗り越えるための健全なプロセスなのかもしれません。
避けては通れない「死」という現実
死は人生の一部であり、恐れるべきことではありません。むしろ、死を受け入れることで、今この瞬間を大切に過ごすことができるでしょう。
大切な人を失ったとき、或いは自分自身の死に直面したとき、悲しみや喪失感にとらわれるのは自然なことです。しかし、そこにとどまるのではなく、亡くなった人との思い出や、自分がこれまで歩んできた人生の旅路を振り返り、感謝の意を込めることが大切なのではないでしょうか。
今日から始める、不安解消のための瞑想法

インターネットやSNSの発達により、私たちは世界中の情報を瞬時に手に入れられるようになりました。便利な反面、膨大な情報に振り回されてしまうことも……。
SNSで流れる友人の幸せそうな投稿を見て、自分の人生と比べてしまったり、ニュースで報道される出来事に不安を感じたり、気がつかないうちに心が疲れてしまうことがあるのではないでしょうか。
そんなときには、一度立ち止まって、自分自身と向き合ってみることが大切です。心の中に溜まったざわつきを手放し、内なる平穏を取り戻す。その1つの手段が「瞑想」です。
そもそも、瞑想とは
瞑想とは、自分自身の心と向き合い、内面を見つめるための方法の一つ。自分の心の状態を客観的に観察するためのツールと言えるでしょう
瞑想の方法は様々ですが、基本的には、静かな場所に座り、目を閉じ、呼吸に意識を向けることから始まります。瞑想中は、仕事の心配事、昨日の出来事、今日のやることなど、様々な考えや感情が頭の中に浮かんでくるものです。
最初はこれらの雑念を追い払おうとしがちですが、瞑想の目的は、雑念を無理に消し去ることではありません。むしろ、雑念をそのまま受け入れ、まるで空を流れる雲を眺めるように、客観的に観察することが大切なのです。
例えば、仕事の心配事が頭に浮かんできたら、「私は仕事の心配をしているな」と認識し、その考えにはあまり深入りせず、ゆっくりと呼吸に意識を戻します。このように、雑念をあるがままに受け入れ、静かに観察する練習を重ねることで、次第に自分の心の動きを客観視できるようになっていきます。
とはいえ、「瞑想を日々の生活に取り入れたい」と思っても、何から手をつけたらいいのかわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、誰でも気軽に始められる簡単な瞑想法をいくつかご紹介します。
初心者OK。今日から始める5つの簡単瞑想方法
1日5分、何もしない時間を作る
忙しい現代社会では、仕事に家事に育児と、毎日やることが山積みで自分と向き合う時間が後回しになりがちです。
だからこそ、意識的に自分と向き合う「無になる時間」を日々の中に取り入れてみましょう。最初は5分間でも大丈夫。継続することで少しずつ変化を感じることができるでしょう。
例えば、寝る前や起きる前の5分間、ベッドの上に寝転がり、目を閉じます。吸う息で腹部を膨らませ、吐く息で腹部を凹ませる。呼吸は心を落ち着けるための強力のツールです。ゆっくりと深呼吸をしながら、呼吸に意識を向けてみましょう。
最初のうちは、5分間でも長く退屈に感じるかもしれません。しかし、これを習慣づけていくうちに、次第に瞑想に集中できるようになり、心が落ち着いてくるはずです。
感じたことをノートに書き出す

朝目覚めた直後、まだボーっとしている間に、頭の中に浮かんでくる様々な思いを、そのままノートに書き出してみましょう。これは「モーニングページ」と呼ばれる手法で、頭の中をスッキリとさせ、一日をフレッシュな気持ちで始めるのに効果的です。
ノートを開いたら、思いつくままに書き始めます。例えば、「昨日は夜遅くまで仕事をしていたから、まだ眠い…」「今日は友人との約束があるから、楽しみだな」「最近運動不足だから、今日は公園を散歩しよう」など、何でも構いません。
大切なのは、文章の形式や見た目にこだわらず、自分の感情や思考を自由に表現すること。スペルの間違いや文法の誤りを気にする必要はありません。目安は3ページ。頭の中を言葉にして、ペンを走らせてみてください。
「モーニングページ」を毎朝続けていくことで、自分の思考パターンや感情の変化に気がつけるようになるでしょう。
ヨガをする
ヨガは心身のバランスを整える古代からの知恵です。ポーズに合わせて深く呼吸をすることで、体に酸素を十分に取り込み、老廃物を排出できます。同時に、呼吸に意識を向けることで雑念が消え、心が静まっていくのを感じられるでしょう。
今では、YouTubeでも様々なヨガのレッスンを気軽に受けることができます。
「朝ヨガ」や「夜ヨガ」といった、時間帯に合わせたプログラムや「自律神経を整えるヨガ」など、特定の目的に特化したプログラム、また、5分や10分といった短時間で完結するレッスンも多数あります。
これなら忙しい日々の中でも、隙間時間を見つけてヨガができるでしょう。ヨガを通して、心身のバランスを整え、不安感を和らげていきましょう。
瞑想グッズを取り入れる

瞑想を始めるにあたって、専用のグッズを取り入れるのも一つの方法です。香りや視覚的なアイテムなど、自分に合ったグッズを探してみましょう。
たとえば、アロマディフューザーを使って、お気に入りの香りを部屋に広げるのも効果的です。ラベンダーやカモミールなどのリラックス効果のある精油を使えば、心が落ち着き、瞑想に集中しやすくなります。
他にも、ビー玉が流れるオブジェを眺めているだけで今に集中できる商品なども販売されています。視覚的に心を落ち着けるアイテムを自宅に飾り、「無になる習慣」を作るのも一つの方法です。
不安に襲われたときは、瞑想の力を借りよう
不安感に襲われたとき、私たちは「あの時こうしていれば…」「もし〜だったらどうしよう」といった考えを繰り返し、ネガティブな思考から抜け出せなくなることがあります。
そんなときこそ、瞑想の力を借りてみましょう。深呼吸をして今この瞬間に意識を向け、不安な感情をそのまま受け止めるのです。
最初は難しく感じるかもしれませんが、毎日5分でも自分自身と向き合う時間を持つことで、徐々に瞑想が習慣化され、不安への対処法が自然と身についていくでしょう。
心の平穏を取り戻す第一歩は、自分自身と向き合うことから始まるのです。
辞めることで起こったパラダイムシフト。実は色々なことをやりすぎていた?幸せの鍵はLess is More。 【Editor’s Letter vol.08】
| Humming編集長 永野舞麻がカリフォルニアから配信する「Editor’s Letter 」。日々の暮らしで感じた気付きや、人生において大切にしていることを綴っています。 |

綺麗な服を着飾るのが好きだった。
人脈を作るために積極的にランチに出かけた。
出張で世界中を飛び回っていた。
振り返れば、私はいつも自分の表面的なことを磨くことに力を注ぎ、忙しない日々を過ごしていました。
どちらかと言えば、派手で騒がしくて、外交的。そんな私が今では約1年間の時を経て、段々と外出を極力減らし、家の中で静かに瞑想をしています。
内と向き合う時間を大切にする。自分が大切だと思っていたことを辞めることを決断する。選択肢が少なくなることで、迷いが減り、穏やかな心で過ごせる時間が増えました。さらに、これまで気がつかなかったことに目が向けられるようにもなったのです。
40歳を目前にして起こったパラダイムシフト。
そのきっかけは何だったのか?内と向き合うことで現れた変化とは?私の体験談をお話します。
現状を受け入れ潔く辞めた海外出張
数年前までの私は、仕事や旅行で世界中を行き来したり、知人とランチに出かけたり、忙しない日々を送っていました。頻繁に会議のために日本へ、ケニアへ映画の撮影に行った帰りに、ロンドンに寄ってミーティング。来月も出張と家族旅行を合わせてニュージーランドへ行く予定になっていました。毎月スケジュール帳はいつもぎっしりと予定で埋め尽くされていました。
先月、予定していた日本出張の少し前のこと。体調を崩し、やむなく全ての予定を一度キャンセルすることを決断したのです。
もちろんキャンセルすることに対して、約束していた人たちへの後ろめたさや残念な気持ちもありました。しかし、自分の置かれたありのままの現実を受け入れ、入れていた予定を全て潔く”手放す”ことで、時間にも心にも余裕が生まれ、自分自身に思わぬ変化が現れたのです。
何事も”始める”のも勇気がいるけれど、”辞める”のには更に勇気がいる。しかし、4年前から始めたメディテーションで段々と自分の内側が変わりつつあったところに加えて、少し前に体験したヴィパッサナーリトリートで「大きな流れに逆らわず、今を受け入れることの大切さ」を体感していたからこそ、潔く”手放す”選択ができました。
内向的な自分を知ることで出会った心の平穏
ごちゃごちゃしていたスケジュールが綺麗になったことで、生活のリズムが整いました。
毎日、同じ場所、同じ時間に瞑想できるようになったことも相まって、性格までも少し大人しくなり、これまでは気がつかなかった日常の中の静寂に目が向けられるようになったのです。また、静かで落ち着いた空間を心地よいと感じるようになり、一人きりの時間を寂しいと感じる代わりに、エンジョイするようになりました。
たとえば、「水が欲しいのかな」とか、「この部屋の光加減が合うんだな」とか、植物が求めているものがわかるようになったり、私が静かになることで、子どもたちから話してくれることが増え、また、自分も静かに周りを観察するようになり、子どもたちの心の内や思考をより深く知れたり。
さらに、家にいる時間が増えたことで、趣味のアートもこれまで以上に充実しています。
遠方への出張を辞めたり、知り合いとのランチの機会を減らしたり、最初は周りと疎遠になるのではないかと不安を感じることもありました。しかし、辞めてみれば意外にも気持ちはスッキリ。これまでは必要以上に動き回っていたことに気がついたのです。
外に出なくても必要な情報は得られるし、会いたい人にはピンポイントで会えればいい。
これまで外交的だった私が、内向的になったことで、パラダイムシフトがおきたのです。
パラダイムシフトとは?
パラダイムシフトとは、考え方や価値観が根本的に変わること。
人は無意識のうちに特定の視点や信念に固執し、そのフィルターを通して日々を過ごしているのです。しかし、パラダイムシフトが起こると、これまでの「当たり前」が覆され、新しい見方や考え方ができるようになります。
この変化は小さな瞬間から始まり、次第に生活全体に影響を及ぼします。パラダイムシフトは私たちに新しい可能性を示唆し、人生に深みをもたらす大切なプロセスだといえるでしょう。
“Less is More”が人生における幸せの鍵
20世紀に活躍したドイツ出身の建築家、ミース・ファン・デル・ローエが残した言葉“Less is More”。これは「シンプルなデザインを追求することによって、より美しく豊かな空間が生まれる」という、彼の建築家としての信念を表した言葉です。
「少ない方が豊かである」という意味あいのこの言葉は、建築のみならず、人生を幸せに過ごすためにも重要な思想だと私は実感しています。
なぜなら、多くのものや情報に溢れた現代、便利な反面、膨大な選択肢に迷いや悩みが生じやすく、心身が疲弊するからです。
だからこそ、大切なのは選択肢を極力減らすこと。辞めること・やらないこと、自分の中に基準を持つこと。選択肢が減ることで迷うときや悩む時に使う思考の量が少なくなり、心穏やかに過ごすことができるのです。
もちろん、これまであたり前にしてきたことを辞めたり、習慣を変えるのは勇気がいることです。しかし、何かを手放し余白が生まれるからこそ、本当に大切なことに気がつけたり、新たなご縁に出会えたり、新しい可能性が広がるものです。
体調を崩し、海外出張をキャンセルしなければいけない。一見ネガティブに思えるこの出来事が、私にパラダイムシフトを起こし、”Less is More”の重要性に気がつかせてくれました。
ジャーナリングのやり方は?日記との違いや効果について

日々さまざまなことを頭の中で考えていると、結論がなかなか出なかったり、考えすぎてイライラしてしまったりすることもあるでしょう。
誰かと会話するのとは違って、自分の中でだけ考えを巡らせるのは、良い点もあれば悪い点もあるものです。
そんなとき、頭の中を整理するために必要なのが「ジャーナリング」です。
定期的にジャーナリングを行うことで、自分が今何を考えているのか、何をしたいと思っているのかを正しく理解できるでしょう。
今回はジャーナリングがもたらす効果や日記との違い、詳しいやり方についてご紹介します。
ジャーナリングの効果とは
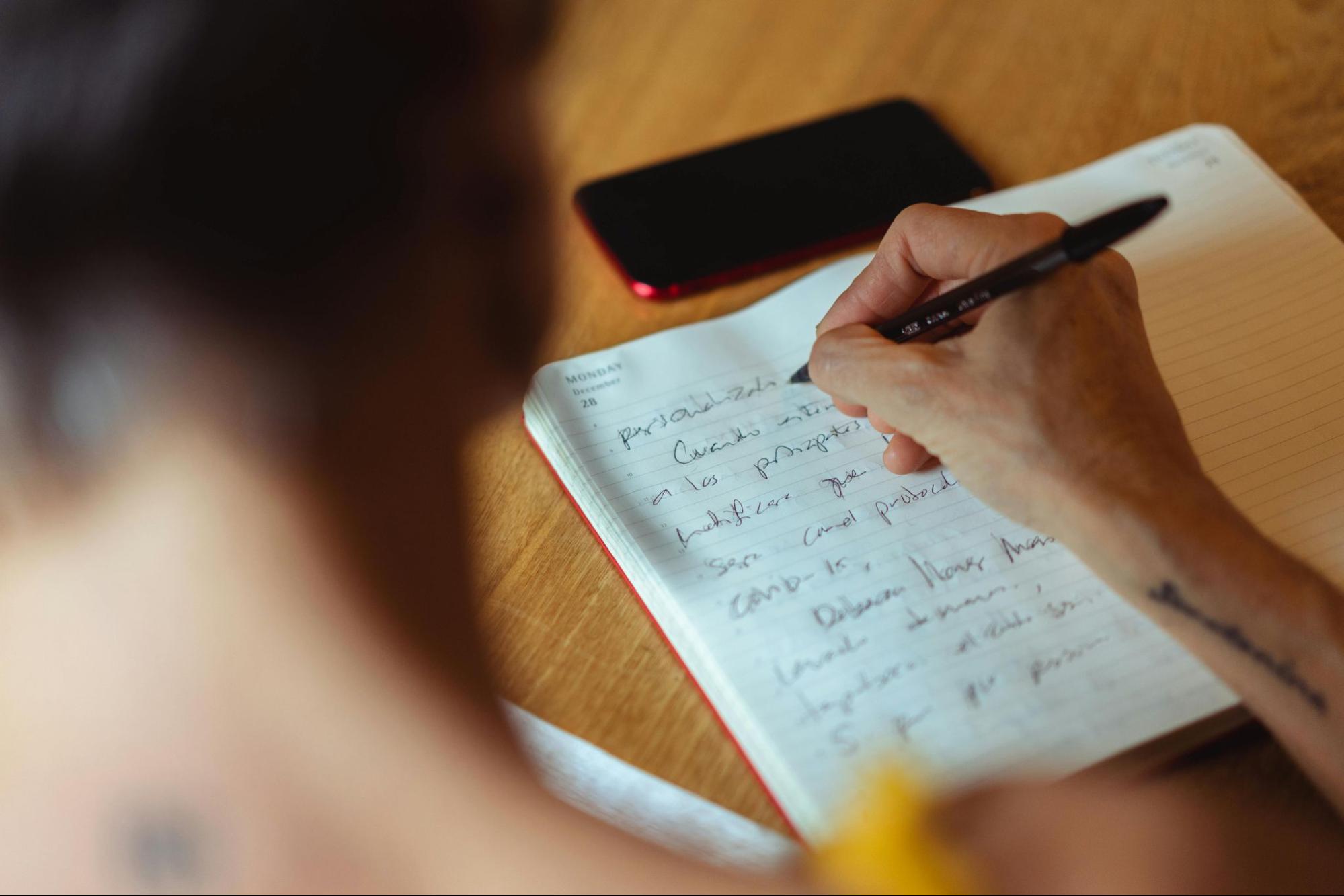
ジャーナリングは、頭の中に浮かんだことを深く考えず、そのまま紙に記していく方法です。
口を閉じて頭の中で考えを巡らせるよりも、自然と浮かんだ気持ちが現れやすいのが特徴です。
ジャーナリングをすると、想像しなかった本当の気持ちに気が付いたり、大したことではないと思っていたら実は重要なことだと分かったりします。
そのため、誰もが一度はチャレンジすべき方法ともいえます。
そんなジャーナリングですが、実は自分の気持ちを深く見つめなおすことで、さまざまな効果を発揮してくれます。
それぞれの効果について詳しくチェックし、日々のルーティンに組み込むことをおすすめします。
ストレスの軽減
理由はないのに落ち込んでしまったり、無性にイライラしたりといった心の不安定さを引き起こすストレス。
軽微なものであれば問題ありませんが、小さなストレスが積み重なったり、急に大きな負担がかかったりするとさまざまな弊害を生んでしまいます。
心の不安定さだけでなく、身体的なトラブルが起こることも珍しくありません。
肌が荒れたり髪が抜けやすくなったり、時には重大な病気を発症する可能性もあります。
ジャーナリングを定期的に行うと、自分の深層心理と向き合うことになり、ストレスの原因や解決策を見出しやすくなります。
ストレスについて深く悩んでしまうのではなく、普段考えが及ばない思考の深いところまで探ることで、よりスムーズにストレスを解決できるでしょう。
また、私たちがストレスを感じているとき、脳は不安やネガティブな思考でいっぱいの状態です。
無理やり楽しいことを考えようと思ってもうまくいかないのは、脳に考える隙間が無いのが理由です。
つまり、ジャーナリングでこの隙間を作ってあげることで、ポジティブな思考が自然と生まれやすくなるでしょう。
免疫機能の向上
辛い出来事を自分の中で抱えたまま過ごしていると、ストレスにより体にさまざまな弊害が生まれやすくなります。
これをジャーナリングでうまく発散してあげることで、不安や焦燥感を抱きにくくなるでしょう。
不安や焦りといった感情が長く心を支配していると、自律神経に大きな影響を及ぼします。
自律神経は私たちの意識と関係のないところで、常に体を動かしてくれている神経のこと。
呼吸や心臓の拍動などさまざまな役割を担っているため、バランスが乱れるだけでも体調の悪化につながってしまいます。
自律神経のはたらきが乱れることで、免疫力が低下するのも注意しなければならないポイントの一つ。
単なる風邪にかかりやすくなったり、一度感染した病気が治りにくくなったりするため、単なる風邪だと軽視できなくなるでしょう。
ジャーナリングでストレスを発散することで、免疫力の低下を防ぎ、健康な体を保つことにも繋がるのです。
抑うつ症状の軽減
上手く外に吐き出せない不安や焦りを抱えた状態が続くと、落ち込んだ状態から浮上しにくくなり、抑うつ状態へと進行してしまいます。
このまま対処をしなければ本格的なうつ病になる可能性も高いため、単なる落ち込みだと思わず、体からのSOSをしっかりと受け止める必要があります。
抑うつ状態はあくまでも「一時的な気分の落ち込み」であり、ここで落ち込んでいる原因と向き合うことで気分の切り替えが可能です。
原因を一つずつ頭の中で考えるのではなく、自分が奥底で何を考えているのかを確かめるためにもジャーナリングを試してみましょう。
自己認識の向上
「自己認識」とは、自分の気持ちや状態をしっかりと把握できている状態を指します。
自分が今何を考えているのか、どんな気持ちでいるのかを第三者目線で理解できれば、不安やイライラなどさまざまな感情をコントロールできるでしょう。
ジャーナリングで思い浮かんだ感情を書き留め、書いた文章を改めて確認することで、これまでに気が付かなかった感情が目で見て分かるようになります。
自分が今ポジティブなのかネガティブなのかを知るだけでも、行動に大きな違いが生まれるでしょう。
「今日はもっと頑張れそうだから」と仕事に取り組んでみる。「今日はしっかり休んだ方が良いだろう」と早めに布団に入る。
といったように、その日の気持ちに合わせた行動がとれるはずです。
記憶力の向上
ジャーナリングで普段の感情を書き出すと、脳に隙間ができ、より重要なことを考えるだけの余裕が生まれます。
ポジティブな感情とネガティブな感情では、圧倒的にネガティブな方が頭を占める割合が多いもの。
これらをうまく発散し、脳に空きを作ることで、さまざまな思考ができるようになるでしょう。
脳に余裕ができれば、記憶力の向上にも繋がります。
試験の前などはもちろん、普段から人の名前を覚えにくい方や、忘れものが多い方にもジャーナリングが向いているといえるでしょう。
小さな感謝への気づき
不安や焦りなどネガティブな感情で頭がいっぱいになっていると、その他のことに目が向きにくくなり、視野が狭まってしまいます。
周りから向けられた気持ちにも気が付きにくくなり、知らないところでトラブルを生んでしまうこともあるでしょう。
ジャーナリングによって頭の中がクリアになると、周りからの気持ちに素直に応えられるようになります。
日常に潜んでいる小さな「ありがとう」にも気が付きやすくなり、毎日を少し優しい気持ちで過ごせるでしょう。
反対に自分も周りに優しくできるようになり、不要なトラブルを防ぐことにも繋がります。
関連記事:アンガーマネジメントのやり方|「意味ない」と言われる理由とは?
ジャーナリングと日記の違いは?

「自分の気持ちを書き出す」という点において、ジャーナリングも日記も同じように見えます。
日記であれば、既に毎日書いている方も多いのではないでしょうか。
ジャーナリングと日記の違いを明確にしておくことで、それぞれを使い分け、より効率的に気持ちの整理ができるようになるでしょう。
ジャーナリング
ジャーナリングは、ノートを目の前にして思い浮かんだすべての気持ちをつらつらと書いていくものです。
「これは書かない方が良いかな」などと深く考える必要はなく、ただ思ったことを全て書いていきましょう。
これにより気持ちを整理したり、奥深くに隠れていた自分の気持ちに気づけたりといった効果が望めます。
真面目な人であれば、ジャーナリングを行うときに「日記にならないように」「気持ちを整理するために」と効果を求めるため一生懸命になってしまうでしょう。
丁寧に書きたい日記とは異なり、肩の力を抜いてチャレンジするのがおすすめです。
日記
日記とは、1日の中で起きた出来事や行動をまとめておくものです。
そのときに感じた気持ちを書くのも良いですが、メインとなるのは「何があったか」であり、気持ちに重点を置いていないのが特徴といえるでしょう。
特別な出来事があった日だけ日記をつけ、普段通りの日には何も書かないという方も少なくありません。
日記を書くときは、ジャーナリングとは異なり、内容を選びながら読み返したくなる文章を書くのがおすすめです。
寝る前にあたたかいものを飲みながら書くなど、1日の終わりのルーティンとして続けてみるのもおすすめです。
関連記事:メンタルブレイクした時はどうすればいい?診断方法や治し方を紹介
ジャーナリングのやり方

続いて、ジャーナリングのやり方を詳しくご紹介します。準備段階からこだわることで書くのが楽しくなり、より長く続けられるでしょう。
用具を準備する
基本的に、ジャーナリングは紙とペンさえあればどこでも始められます。
チラシの裏に書くのも良いですが、気に入ったデザインのノートや筆記具を選ぶことで、より楽しくチャレンジできます。
この後ご紹介するおすすめアイテムの見出しでは、ジャーナリングにピッタリの素敵な日記帳をピックアップしています。
お気に入りのアイテムを見つけるためにも、参考にしてみてはいかがでしょうか。
リラックスする
ジャーナリングを行う場合、できるだけリラックスした気持ちで行うことが大切です。
あたたかい飲み物を用意したり、入浴後に行ったりと、落ち着いて書けるタイミングを選びましょう。
できるだけ自分の気持ちに集中できるよう、1人になれる場所を選んだり、テレビを消したりといった工夫をするのもおすすめです。
テーマを決める
思ったことは何でも書いて良いのがジャーナリングですが、だからといって書くことが思いつかない場合も多いでしょう。
そんなときはテーマを決め、お題に沿って気持ちを整理していくのもおすすめです。
例えば、今日の1日を振り返り、良い行いや悪かったことについて考えてみるのも良いでしょう。
今自分を取り巻く環境について考え、仕事が自分に向いているのか、今後どう成長していきたいのかを考えるのもおすすめです。
不安や焦りの原因を探るために、思い切って最近あった嫌なことについて深堀りしてみるのも効果的です。
書き始める
実際にノートへ書き始めると、次から次へと書きたいことが出てきてしまい、いつまで書けば良いか分からなくなることもあるでしょう。
あらかじめ何分間で書くのかを決めておき、その中で気持ちの整理を行うことが大切です。
実際に書き始めた後は、途中でペンを置くことなく、キリの良いところまで書いてしまわなければなりません。
途中で食事をとったり入浴したりするのではなく、集中して気持ちと向き合う時間を作るのが良いでしょう。
内容を振り返る
納得のいくところまで文章が書けたら、一度全て読み返す時間をとります。
無意識のうちに書いていた文章までしっかりと確認することで、自分の気持ちを可視化し、冷静に分析できるでしょう。
これまでに気が付かなかった点があれば、その部分を抜き出して整理しておくのもおすすめです。
また、ジャーナリングで書いた内容はその日だけでなく、1週間後、1ヶ月後など定期的に確認すると良いでしょう。
その日からどう気持ちや状況が変わったのか、今後どう変えていきたいのかをイメージしながら、今の気持ちと照らし合わせてみるのが効果的です。
習慣化する
ジャーナリングは一度書いて終わりではなく、定期的に取り組むことで頭の中を整理できます。
毎日必ず取り組む必要はありませんが、休日に取り組んでみたり、1ヶ月を振り返ってみたりと、チャレンジするスパンを決めておくと良いでしょう。
ジャーナリングは「やらなければならない」ものではないため、スケジュールに組み込んできっちりと行う必要はありません。
ストレスが溜まってきたり、楽しいことを考えられなくなったりしたときの対処法として、頭の隅に置いておくと良いでしょう。
関連記事:メンタルがやばいサインとは?メンタルの不調で休むのは甘え?
ジャーナリングの気分を上げてくれるおすすめの日記帳4選

最後に、ジャーナリングにチャレンジするときにおすすめの素敵な日記帳を4種類ご紹介します。
ラコニック(Laconic) スタイルノート マンダラチャート A5
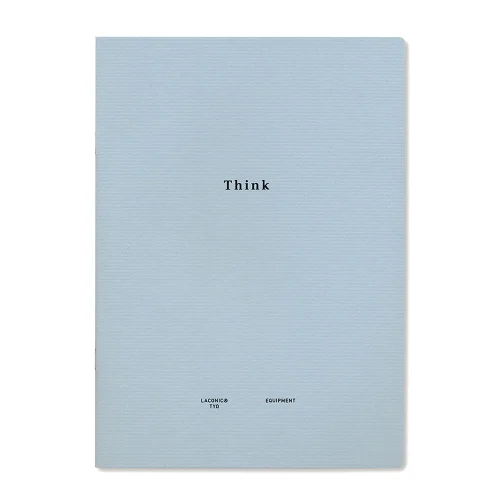
一般的な罫線のノートではなく、自分の気持ちと向き合うための特殊なチャートがついた日記帳です。
さまざまな視点から目標達成を目指す「9×9」
関係性を整理するのに役立つ「座標軸」
考えの広がりを意識できる「同心円チャート」
イラストを交えてイメージを整理できる「4コマ・メモ」
この4種類が特徴です。それぞれ自分に合った使い方ができるため、楽しみながらメモをとれるのが魅力的です。
いろは出版(Iroha Publishing)BREATH DIARY【BLUE】
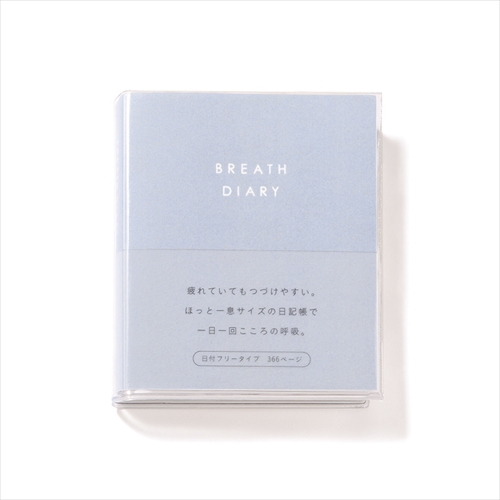
シンプルで使いやすいデザインで、持ち歩くのにもピッタリな日記帳です。
ドットが印刷されたタイプのため、好きな大きさで文字を書けるのはもちろん、イラストを描きたいときにも活躍してくれるでしょう。
最後のページには日記のネタが記載されており、書くことに迷ったときのヒントとしても使えます。
手のひらに乗る程度の小さなサイズ感で、文字をたくさん書くのが難しい人にもおすすめです。
ミドリ(MIDORI)日記 きまぐれA
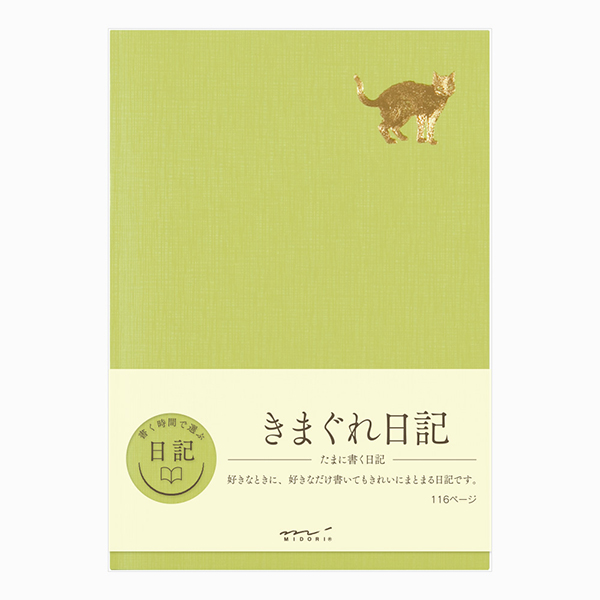
「きまぐれ日記」という名のこちらは、書きたいときに書きたい分だけ使える便利な日記帳です。
日付が印刷されていないため、取り組むと決めた日にだけ向き合えるのが魅力的。
1日分しっかり埋めるのも良し、2日・3日分を使ってたっぷりと書くのも良し、その日の気分に合わせて使えます。
ミドリ 日記 3分 黄色
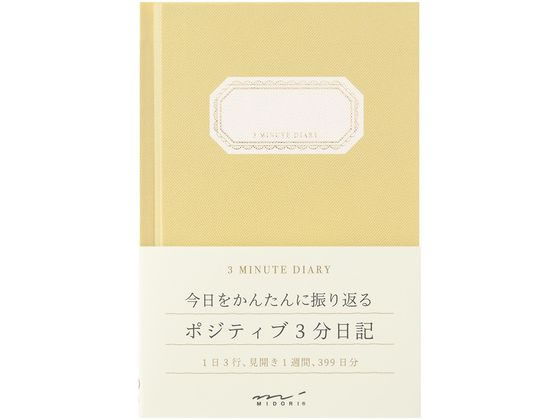
気分がパッと明るくなるようなイエローカラーの日記帳です。
1日分は3行と少なく、たくさん書くのが負担に感じる方も取り組みやすいでしょう。
もちろん数日分を一気に使い、書きたいことを十分にアウトプットするのもおすすめです。
しっかりとした作りの表紙・裏表紙がついており、特別感も満載。自分だけが見る大切なノートとして保管しておくと良いでしょう。
【まとめ】ジャーナリングの習慣で人生を豊かに
耳慣れない言葉であることも多い「ジャーナリング」ですが、実際に取り組んでみると難しくはありません。
ジャーナリングは、自分の深いところにある気持ちと向き合える画期的な方法です。
カウンセリングを受けたり、医療機関を受診したりすることなく試せるため、不安を取り除く第一歩としてチャレンジしてみると良いでしょう。
今回ご紹介した方法やおすすめの日記帳などを参考に、自分の生活に合ったジャーナリングを試してみてはいかがでしょうか。
メンタルブレイクした時はどうすればいい?診断方法や治し方を紹介

忙しい日々を送っている現代人ならば、誰もが一度は気持ちが落ち込んだり、頑張る気力がなくなったりした経験があるのではないでしょうか。
「単なる気持ちの変化だから」と対処せずに過ごしてしまうと、なかなか這い上がれずに辛い日々を送ることになりかねません。
今回はそんな状態を指す言葉「メンタルブレイク」に注目し、自己診断の方法や治し方をご紹介します。
メンタルブレイクの意味とは?

「メンタルブレイク」とは、直訳で「精神崩壊」という意味を持つ言葉です。
医療用語ではなく、いわゆる造語として2000年代初め頃から広まり始めました。
当初は大型掲示板サイト「2ちゃんねる」にて精神を病んだ人を指す言葉として使われていました。
近年は誰しもがなりうる、辛い状態を意味する言葉へと変化しつつあります。
掲示板サイトをきっかけに生まれたメンタルブレイクというワードは、徐々に女子高生を中心としたSNSで使われるようになりました。
何か嫌なことがあったり、やる気が出なかったりといった心情を「メンブレした」と表し、共感やなぐさめの言葉をもらうのが一般的。
当時は、ほんの少し落ち込んだ程度の状態を指す言葉として使われていたのです。
現在は大人でもメンタルブレイクという言葉を知っている人が多く、重いうつ状態などを表す際にも使われつつあります。
面白半分で使う言葉から、自身や周りを労わるために必要な言葉へと進化しつつある言葉といえるでしょう。
一部では「メンタルダウン」という言葉も同様の意味として使われています。
メンタルブレイクの症状は?

一言でメンタルブレイクといっても、人によって症状はさまざまです。
「あの人とは違うから私はメンタルブレイクではない」「この症状があるからメンタルブレイクだ」
というわけではなく、あくまでも普段の自分と比べてどのように変化したかをチェックすると良いでしょう。
下記でご紹介するメンタルブレイクの症状は、実際に体験した人の多い症状の一例です。
下記以外にも気になる症状がある場合は、自分の症状と照らし合わせて確認することをおすすめします。
何もしていないのに気分が落ち込む
何か特別なことがあったり、傷ついたりした経験があって気分が落ち込むのは自然なことです。
しかし「何もしていないのにどんよりとした気持ちになる」「うまく笑えなくなる」
このような場合は、メンタルブレイクの症状の一つといって良いでしょう。
日々の小さなストレスが積み重なるなど、自分では気が付かないレベルのきっかけがメンタルブレイクを引き起こすことがあります。
何も悲しいことがなかったからといって、気持ちが落ち込んでいる状態を見逃さないようにしましょう。
とはいえ、何もきっかけがない場合、気分が落ち込んでいることに気が付くのは難しいものです。
少しでも「あれ?」と感じることがある場合は、一度ゆっくりと時間をとって自分の状態を見つめなおしてみるのがおすすめです。
落ち込んだ気持ちに見て見ぬふりを続けてしまうと、その後ちょっとした出来事でさらに落ち込んだり、外に出るのが難しくなったりすることがあります。
自分では分からないことも、周りが気づいてくれる可能性があるため、信頼できる人に相談するのも良いでしょう。
何をするにも気力が出ない
仕事や家事などを頑張ろうと思っても、なぜか気力がわかずに先延ばしにしてしまったり、重い腰が上がらなかったりした経験のある方も多いのではないでしょうか。
もちろん仕事や家事に苦痛を感じていれば、自然と気力がわかなくなるもの。
普段はしっかりと取り組んでいても、季節の変わり目や生活習慣の変化などでやる気がフェードアウトしてしまうこともあるでしょう。
気力が出ない状態は、いわば「誰にでもあること」として放置してしまう人が多い症状です。
とはいえ、どんな症状にも何かしらの理由があるはずで、何もないのに気力がわかない状態は危険です。
メンタルブレイクでは、自身が気が付かない要因が積み重なっていることが多いです。
「自覚がないままなぜか気力が出ない」「やる気が出ない」などの状態は、決して無視しないようにしましょう。
もちろん、気力が出ないと思ったら実際には風邪の引き始めだったり、ホルモンバランスが乱れていたりすることもあります。
心の問題だけでなく、体の不調で考えられる原因がないかもチェックするのがおすすめです。
いつもなら何でもないことに対してイライラする
メンタルブレイクの症状は、気持ちが落ち込むだけではありません。
普段ならば気にすることがないような些細な出来事に対して、過剰に気持ちが高ぶってしまうケースも考えられます。
家族の何気ない一言に反論してしまったり、イライラがおさまらずに何事も楽しめなかったりする場合は、上記同様メンタルブレイクを疑いましょう。
この「イライラ」という症状は、自分が精神的に疲れていることが分かりにくい症状の一つでもあります。
普段温厚な人が何日もイライラしていたり、激しい言葉遣いに変わったりするのに気が付いた場合は、さりげなくフォローしてあげると良いでしょう。
主に女性の場合、ホルモンバランスの乱れが原因でイライラがつのることがあります。
メンタルブレイクを疑うと同時に、月経周期などを確認し、体に不調がないか確認することも大切です。
胸がドキドキして息苦しい
心の問題だと捉えられがちなメンタルブレイクですが、気持ちの変化によって身体的な症状が出ることも少なくありません。
代表的な症状の一つに「胸がドキドキする」「息苦しい」というものがあります。
病院で検査をしても異常がなく、ストレスが原因だといわれた経験のある方も多いのではないでしょうか。
朝起きた瞬間に胸がつまるような感じがしたり、寝るために横になると息がしにくくなったりと、人それぞれ症状が異なるのも特徴です。
場合によっては息苦しさが強くなり、うまく息が吸えず「過呼吸」になるケースもあります。
口元に袋を当てて二酸化炭素を取り込むことで落ち着くといわれていますが、経験がなければ焦ってしまう人も多いでしょう。
過呼吸は息をゆっくりと吐いたりうつ伏せで横になったりするのに加え、周囲に人がいる場合は会話をすることで落ち着く可能性があります。
息苦しさは決して軽視せず、常に対処法を考えておくことが大切です。
熟睡できず夜中に何度も目が覚める
メンタルブレイクの間は体にストレスがかかり、自律神経のはたらきも乱れやすくなります。
通常、起きている間は交感神経が、眠るときには副交感神経が優位になるはずの人体ですが、自律神経がうまく働かない場合この限りではありません。
夜にもかかわらず気持ちが昂ったり、夜中に目が覚めて寝付けなくなってしまったりする場合は、病気を疑うとともにメンタルケアも行うと良いでしょう。
眠りに関する悩みがある場合、まずは起きている間の行動を改善してみるのがおすすめです。
無理に眠ろうとするのではなく、朝起きてすぐに日光を浴びたり、適度な運動をしたりして体のサイクルを整えましょう。
眠る前は熱すぎないお湯にゆっくりと浸かったり、就寝の3時間前までに食事を済ませたりといった工夫も大切です。
また、眠りに関する悩みが続けば続くほど、心身ともにさまざまなトラブルが起こりやすくなります。
必要に応じて医療機関を受診したり、睡眠導入剤を処方してもらったりと、専門家に相談することをおすすめします。
関連記事:ジャーナリングのやり方は?日記との違いや効果について
メンタルブレイクの自己診断をしてみよう

医療機関を受診する前に、自己診断によるメンタルブレイクの見分け方を試してみましょう。
以下のようなチェックポイントを参考に、当てはまるものがいくつあるかで見極めを行います。
- 気分の変動が激しいか?
- 睡眠に問題はないか?
- 仕事や日常活動に対するモチベーションは?
- 食欲に変化はあるか?
- 社会的な関わりに変化はあるか?
- 集中力や判断力に問題はないか?
- 自己評価に変化はあるか?
- 不安や恐怖を感じることは増えたか?
先ほどご紹介した気分の落ち込み・イライラや、睡眠不足などの項目に加え「漠然と不安や恐怖を感じるか」といったポイントまでさまざまなものがあります。
一見して関連性のない質問にも思えますが、これらは全てメンタルブレイクの一例として多くの人が苦しんでいる症状です。
例として、精神疾患の一つ「うつ病」を挙げてみましょう。
気持ちの落ち込み、不安感、だるさ、暴力行為や希死念慮など、人によって症状に大きな違いが見られます。
症状が重い場合は引きこもりになったり、専門病院に入院しなければならなかったりすることもあるでしょう。
これに対しメンタルブレイクは「一時的な気持ちの問題」と片付けられてしまい、うつ病などの精神疾患に比べ軽視される傾向にあります。
何の対処もしないままでは別の疾患を併発しかねないため、先ほどご紹介したチェックポイントを受診の目安として活用しましょう。
自己診断は、あくまでも参考程度にしかなりません。
本来の原因や対処法は一人ひとり異なるため、専門医と時間をかけて話し合うことをおすすめします。
関連記事:ネガティブ思考は病気?うつ病との違いや治し方を解説
メンタルブレイクしたときの治し方は?

人によって原因や症状が異なるメンタルブレイクは、基本的に専門医と治し方について相談するのがベストです。
いつでも相談できるよう、最寄りの精神科や心療内科を調べておくと良いでしょう。
一方で、自分で症状を軽くするための対処法もいくつか存在します。
これらは根本的な問題を解決するわけではないため、一時的な対処法として覚えておくのがおすすめ。
時間や気持ちに少しでも余裕ができたときには、自身を悩ませている原因を探りましょう。
気持ちを声に出してみる
メンタルブレイクをしているときは、多くの人が自分の状態を正しく把握できていません。
「まだ大丈夫だろう」と思っていたり、これだと思う原因が間違っていたりすると、結果として症状を長引かせてしまうでしょう。
そのため、まずは考えていることを全て口に出してみるのがおすすめです。
何を話すか考えることもなく、ただつらつらと気持ちを声に出してみるだけです。
そこに誰かがいても良いですし、1人のときでもかまいません。
頭の中で考えを巡らせていても、良い結果が生まれにくいどころかどんどんとネガティブな方向へ進んでしまいがちです。
アウトプットすることで気持ちを整理することにもつながるため、独り言のようにつぶやいてみると良いでしょう。
また、どうしても声が出せない環境にいる場合は、手当たり次第紙に書き出してみるのもおすすめです。
書いたものを見直しながら、自分が本当に抱えている気持ちを探っていきましょう。
どうしたいのか考えてみる
気持ちをアウトプットできるようになったら、一体自分がどうしたいのかを考えてみましょう。
仕事関連の気持ちを多く吐き出した場合「自分はその仕事でどんなポストに就きたいのか」
あるいは「辞めてしまいたいのか」といった希望する未来をイメージするのが重要です。
人間関係に悩んでいるのであれば、相手とどんな関係になりたいのか想像してみましょう。
例え非現実的な内容であっても、自分の希望を具体的に思い描くことが大切です。
自分がどうしたいのかを考えるとき、周りの人間の目を気にする必要はありません。
「〇〇さんがこうすべきだと言ったから」「こうすると皆に迷惑がかかるから」といった前提を捨て、自分が心地良く過ごせる選択は何なのかを探りましょう。
肉体的な健康を維持する
メンタルブレイクから脱却するためには、心はもちろん体の健康が必要不可欠となります。
心の辛さを重視するあまり、体の健康をおろそかにしてしまえば「疲れがとれにくい」「風邪をひきやすい」など日常にさまざまな影響が出てしまうでしょう。
その結果、毎日がイメージ通りに過ごせなくなれば、新たなメンタルブレイクを引き起こす可能性もゼロではありません。
肉体的な健康は、精神的な健康の土台となります。
睡眠・食事・運動の3つをバランス良く整え、心と向き合うだけの余裕を身に着けましょう。
急にこれまで続けてきた生活をガラリと変える必要はないため、できることから少しずつ始めていくことが大切です。
ネガティブな事柄を避ける
メンタルブレイクに悩まされている間は、ネガティブな事柄をできるだけ避けると良いでしょう。
例え今抱えている悩みとはまったく異なることであったとしても、ネガティブな事柄に引っ張られて気持ちがさらに沈んでしまう可能性があります。
例として、悩んでいる人の相談にのったり、困っている人とともに苦しんだりするなど、周囲の空気がどんよりするような場所に行くべきではありません。
負の感情が大きくなり、周りを巻き込んでしまう可能性もあるでしょう。
まず自分が十分な余裕をもつことが、誰かを助けるための第一歩となるはずです。
上記を習慣化する
これまでご紹介した1から4までの内容は、数回試しただけで何かが大きく変わるわけではありません。
これらを習慣化し、自分の生活に組み込んでいくからこそ、自分の力でメンタルブレイクを脱却するきっかけとなるでしょう。
その後は専門家の力を借りながら、本来の生活に戻るまでのリハビリを行う必要があります。
関連記事:メンタルがやばいサインとは?メンタルの不調で休むのは甘え?
【まとめ】メンタルブレイクした時は無理しない

人によってさまざまな症状があり、原因を突き止めるだけでも難しいのがメンタルブレイクです。
日々の中で少しずつ自分と向き合いながら、明るい気持ちを取り戻すために対処法を続けていきましょう。
メンタルブレイクは単に原因を取り除いたり、楽しい経験をしたりするだけで完治させることはできません。
決して無理をすることなく、必要に応じて専門家の手を借りながら、少しずつ前を向いていくことが大切です。
ネガティブ思考は病気?うつ病との違いや治し方を解説

周りの人と比べて自分はネガティブ思考だ、と感じている方も多いのではないでしょうか。
中にはネガティブな気持ちが消えず、うつ病など精神的な病に当てはまるのではと不安に思っている方もいるでしょう。
今回はそんなネガティブ思考はどうして生まれてしまうのか、精神疾患との違いも踏まえながらご紹介します。
ネガティブ思考を脱却するための方法も併せてチェックしていきましょう。
ネガティブ思考は病気なのか?

端的にいえば、ネガティブ思考自体が何かの病気に当てはまることはありません。
しかし、精神疾患の中には気持ちが落ち込んでしまったり、長い間明るい気持ちになれず引きこもってしまったりするものもたくさんあります。
ネガティブ思考は決して放置して良いものではなく、さまざまな病の原因になりかねないことを覚えておきましょう。
ネガティブ思考の怖いところは、単に悲しいことを考えるだけに留まらず、どんどんと悪い思考が続いて脱出できなくなってしまうという点です。
ネガティブ思考がループし始めると、趣味や自分の好きなことも心から楽しめなくなり、毎日を生きる活力さえ奪われてしまうでしょう。
自身がネガティブ思考であることを正しく認識し、脱出するための手を考えることが大切です。
ネガティブ思考が止まらないのはなぜ?

ネガティブ思考が止まらずに悩んでいても、その原因が本人にあるとは限りません。
これまでの環境や子ども時代の育てられ方など、外的要因が積み重なってネガティブ思考を形成している可能性も考えられます。
ネガティブ思考だからといって自分を過度に責めることなく、正しい原因を探っていきましょう。
ネガティブ思考が止まらずに頭の中が悪い内容でいっぱいになってしまうことを、「ぐるぐる思考」「反芻思考」などと呼びます。
まずはこれらの思考がどうして始まってしまうのか、考えうる原因をご紹介します。
ついつい嫌なことや過去の失敗を思い出す
日々の生活のなかで、つい嫌だった経験を繰り返し思い出してしまう人も多いのではないでしょうか。
「黒歴史」などと呼ぶこともあり、思い出すことに恐怖を抱いている人もいるでしょう。
過去の嫌な経験と同じシーンに出会ったとき、嫌だった気持ちを思い出すのは自然なことです。
しかし、何の関係もないのにふと頭をよぎったり、過去の失敗を思い出していたたまれない気持ちになる経験が多いと、何をするにも楽しめなくなってしまうでしょう。
また、過去の失敗を思い出すのと同時に「どうしてあの時こうしなかったんだろう」
「ああしておけば失敗することはなかったのに」といった後悔が同時に襲ってくることがあります。
過去は変えられないため、通常であれば今後同じミスをしないよう注意すれば良いのですが、ネガティブ思考の場合はそれだけに留まりません。
いつまでも同じ失敗について後悔を重ね、前に進めなくなってしまう人も珍しくないのです。
認知の歪み
「認知の歪み」という言葉は、精神科医・アーロン=ベック氏が提唱したものです。
何か失敗をしてしまったとき、通常の精神状態であればミスを振り返り、今後どうすれば良いのか解決方法を模索し始めるはず。
しかし、認知に歪みがあり正しい判断ができなくなっていると、全てが悪く思えてきてしまうのです。
認知の歪みは、自分のことを正しく認識できず、長所に目が向かなくなってしまいます。
自分の短所ばかりが気になるようになり、何をする際も「どうせできないから」と目を背けてしまうようになるでしょう。
何事も白か黒かで判断するようになり「できないものはできない」と諦めてしまうのも、認知の歪みに当てはまります。
少しの失敗があると全てがダメになったと感じたり、計画通りにいかないと全て投げ出してしまったりと、過度な完全主義に周りが振り回されてしまうこともあります。
ストレス
どんなにポジティブな思考の人でも、過度にストレスが溜まった状態では、正しい思考ができません。
仕事や家事・育児など忙しい日々を送る現代人の中には、知らず知らずのうちに少しずつストレスが溜まっている人も珍しくないでしょう。
その日のストレスはその日のうちに解消しなければ、感情にも影響を与えてしまいかねません。
ストレスの怖いところは、多くの人がその存在を無視してしまいがちだという点です。
誰もが少なからずストレスを抱えている現代社会では、少し嫌なことがあったくらいですぐに対処しようと考える人は少ないもの。
そうして積もりに積もったストレスが気持ちをよどませ、ネガティブ思考へと繋がってしまうのです。
疲労
日々を送る上での軽度な疲労であれば、すぐにネガティブ思考のループへと繋がる危険性は低いでしょう。
しかし、忙しい毎日で疲労がとれなくなったり、ストレスの溜まりやすい環境で蓄積された疲労であったりする場合は、精神への影響も強いといえます。
体が疲れている状態で無理に頑張ろうとすれば、ネガティブ思考が止まらなくなるのも不思議ではありません。
疲労が原因によるネガティブ思考の反芻は、悪化する前に原因を取り除いてあげる必要があります。
過重労働が原因であれば転職を、家事や育児が占める割合が大きい場合はパートナーと話合うなど、根本となる原因を模索しましょう。
1日の疲労をその日のうちに癒せるようになれば、自然と頭の中がクリアになり、ポジティブな考えが生まれやすくなります。
自尊心が低い
ネガティブ思考の中でもとりわけ注意しなければならないのが「自尊心の低さ」です。
失敗してしまったときに自分を顧みるのは必要なことですが、チャレンジする前から「どうせ自分にはできない」と諦めてしまうのは良くありません。
誰もが最初から自尊心が低くなることはなく、親からの声掛けや失敗したときのフォローなどが原因であることが多いでしょう。
「あなたはどうせできない」「何をしてもダメな子」「失敗したのはお前のせい」などと育てられれば、大人になっても自分を信じられないのは当然です。
自尊心が限りなく低いと感じる場合は、一度自分の幼少期を振り返ってみると良いでしょう。
幼少期に問題がない場合は、上司の態度やパートナーの発言なども影響しやすいポイントとなります。
少なくとも、自尊心の低さは自分だけが原因であるわけではありません。自分を責めすぎず、思い切って環境を変えてみるのも方法の一つです。
他人からの低評価
自尊心の低さにも通じるものがありますが、他人から正しく評価されない状態が続くと、ネガティブ思考がループする原因となります。
良い行いをしたにもかかわらず評価されなかったり、ミスを自分一人に押し付けられたりした経験のある方も多いのではないでしょうか。
人は誰でも、自分を自分で評価するだけに留まらず、周りからの目を気にしながら生きています。
努力したことや時間をかけて行ったことなどを周りから正しく評価されてこそ、頑張りが報われ次へのやる気となるのです。
他人からの低評価が続くと、自尊心が低くなり「自分ではできない」と考えるようになります。
モチベーションが上がらず失敗することも多くなり、再び他人から低い評価をつけられるといった悪循環に陥ってしまうでしょう。
関連記事:メンタルがやばいサインとは?メンタルの不調で休むのは甘え?
ネガティブ思考とうつ病の違い

ネガティブ思考が続くと「自分はうつ病ではないか」と考える人も多いでしょう。
精神疾患の代表的存在であるうつ病は、今も多くの人が苦しんでいる病の一つです。
うつ病は自分一人が頑張っても治ることがなく、精神科や心療内科で正しい治療を受けなくてはなりません。
実際にうつ病の症状にはネガティブ思考が含まれており、気持ちが沈んだ状態が続いたり、自分を責めたりする人も珍しくありません。
しかし、ネガティブ思考が続くからといって、必ずしもうつ病に当てはまるわけではありません。
病気ではない単なる思考である場合もあれば、うつ病以外の疾患が隠れている場合もあるでしょう。
気持ちが落ち込みやすいからといって自己判断でうつ病を疑うよりも、専門家に正しく判断してもらうことが大切です。
さらに、うつ病と診断されていても、特に気持ちの落ち込みや自尊心の低さといった症状が見られないケースもたくさんあります。
患者一人ひとりによって症状が大きく異なり、対処法も異なるのが精神疾患の難しいところ。
治るまでにも時間がかかりやすいため、通うのに負担がかかりにくく、相談しやすい医師を探す必要があります。
ネガティブ思考の治し方はある?

うつ病など、さまざまな精神疾患によりネガティブな思考になってしまう場合は、専門家と一緒に治療法を考える必要があります。
人によって適切な治療法は異なりますが、使われることの多いものには「認知行動療法」「マインドフルネス」などが挙げられます。
また、ネガティブ思考を治すためには、医師による治療だけでは不十分です。
自分でできることを試しながら、生活習慣を正していくことこそ、ポジティブ思考への第一歩といえるでしょう。
認知行動療法
認知行動療法は、うつ病をはじめとするさまざまな精神疾患に効果が得られやすいとして多くの医療機関で注目されている治療法です。
先ほども触れた「認知の歪み」を正し、ネガティブ思考から脱却するためにも役立つといわれています。
通常、私たちが何かに挑戦するとき全て完了したならば「良かった」何一つとして終わらなかったのであれば「ダメだった」
半分終わったならば「半分はできた」と捉えるでしょう。
しかし、認知に歪みがあると、例え半分は終わっていたとしても「全てできなかったのだからこの半分は無意味だ」と感じてしまうのです。
認知行動療法では、まずこの歪みに本人が気づくことから始まります。
専門家による指摘を受けながら考え方を正し、自然と「半分はできた」という考えに近づけていくことが目標です。
このようなバランスの良い考え方は多くの場面で必要となるため、認知の歪みを正すことでさまざまな疾患に対応できると考えられているのです。
マインドフルネス
私たちがネガティブ思考に陥るとき、そのほとんどは過去の失敗を後悔していたり、未来で挑戦することに不安を覚えていたりするでしょう。
マインドフルネスでは、瞑想をすることで「現在の自分」に焦点を当てることを目的としています。
目を閉じて楽な姿勢をとり、自分の呼吸に集中することで意識をクリアに保てるでしょう。
気持ちが落ち着くような音楽をかけながら瞑想することで、心の深いところからリラックスしてみるのもおすすめですよ。
リフレーミング
リフレーミングとは、偏った考え方をしてしまうネガティブ思考に対し、別の考え方に気が付くことで思考の幅を広げる治療法です。
一つのタスクに対して「終わっている」「終わっていない」
このように極端に考えるよりも「半分終わっているから後はもう少しだ」という新たな考えに気が付くことが大切です。
自分の気持ちが全てではなく、新たな考え方も取り入れることで、自分の中に眠っているポジティブな気持ちにも気が付きやすくなるでしょう。
書き出し
ネガティブ思考のループに陥ってしまうと、頭の中で考えが巡り始め、他のことが考えられなくなってしまいます。
悪い内容で頭がいっぱいになるため、嬉しいことや楽しいことがあっても喜ぶ気持ちが入り込む隙がありません。
そこで、自分の気持ちを整理するためにも、思ったことを何でも紙に書きだしてみるのがおすすめです。
一度紙に書いてアウトプットした内容は再び深く思考せずに済むため、次第に頭の中に余裕が生まれてくるでしょう。
ここで紙に書く内容は、周りのことを考える必要も、誰かに気を遣う必要もありません。
自分もしくは医師だけが見られる内容として、どんなことでも気にせず書き留めていきましょう。
イベントなどに積極的に参加
ネガティブ思考で頭がいっぱいになってしまうのは、ほとんどが一人で過ごしている時間ではないでしょうか。
誰とも会話をせず自分に意識を向けているからこそ、悪い内容が頭を占め、ループから抜け出しにくくなってしまいます。
そんなときは、自分が参加しやすいイベントを探し、いつもとは違う環境に身を置いてみるのがおすすめです。
これまで会ったことのない人と積極的に関わることで、過去にとらわれず新たな考えが浮かびやすくなります。
数々のイベントを主催している病院もあるため、同じネガティブ思考に悩んでいる人と話す機会も探しやすいでしょう。
自分一人で抱え込むのではなく、周りを頼りながら少しずつ改善を目指すことが大切です。
運動
適度な運動を続けることは、ネガティブ思考から脱却するために重要なポイントといえます。
体を動かすと脳から「セロトニン」と呼ばれる物質が分泌されます。
これはドーパミン・オキシトシンと並んで「三大幸せホルモン」と呼ばれており、精神を安定させるはたらきを担っています。
セロトニンは、喜んだときに分泌されるドーパミンや、不安を感じたときに分泌されるノルアドレナリンの量をコントロールするためにもはたらいています。
不安に支配されやすい人にとっても、セロトニンは必要な物質といえるでしょう。
運動を行う上で大切なのは、「なるべく継続する」ということです。初日に過剰な運動を行うのではなく、まずは数分単位から始めましょう。
健康的な生活習慣を維持
身体的な健康にとってはもちろん、メンタルを強く保つためにも、生活習慣の改善は必要不可欠です。
夜更かしや朝食を抜く、好きなものだけを食べるといった生活習慣の乱れは、栄養不足や睡眠不足を引き起こします。
これが続けば続くほど精神は不安定になり、ネガティブ思考から抜け出せなくなってしまうのです。
まずは食事や入浴・睡眠の時間を揃え、毎日同じサイクルで生活できるように調整してみましょう。
朝起きたらすぐにカーテンを開け、日の光を浴びて脳を活性化させます。
タンパク質・脂質・炭水化物・ビタミン・ミネラルのバランスを考えながら、偏りのない食生活を心掛けることも大切です。
関連記事:メンタルブレイクした時はどうすればいい?診断方法や治し方を紹介
【まとめ】ネガティブ思考は病気ではない
ネガティブ思考は決して病気ではないものの、放置すればさまざまな精神疾患を発症する可能性があります。
「これが自分だから」と諦めるのではなく、生活習慣を整えながら頭の中を整理してみましょう。
時には専門家に相談し、自分に合った対策を模索することも大切です。
重要なのは、ネガティブ思考も「自分の一部」だと考えること。
ネガティブになってしまう自分が悪いのではなく、あくまでもポジティブなことを考える余裕がないだけだと理解しましょう。
たくさんの時間をかけながら、無理することなく治療に挑んでみてはいかがでしょうか。
カルマとは?意味をわかりやすく解説|カルマを背負うとはどういうこと?

さまざまな占いにチャレンジしたことがある方や、スピリチュアルの世界に興味がある方ならば、一度は聞いたことがあるであろう「カルマ」
なんとなく意味を想像するものの、詳しい内容までは知らない人も多いでしょう。
今回は「カルマ」というワードについて、その意味を詳しくご紹介します。
「カルマが重い」「カルマを背負う」など、よく耳にする言葉についてもチェックしていきましょう。
カルマの意味とは?わかりやすく解説

カルマは、インドで使われていたサンスクリット語が由来になっているといわれており「作用」「行為」などといった意味で浸透していました。
インドの宗教観では、自分の行いが運命を決めるといわれ、良いことをすれば良い人生を、悪いことをすれば悪い人生を歩むと信じられています。
「カルマ=行為」とするならば、良いカルマが良い人生を、悪いカルマが悪い人生を導くといっても過言ではないでしょう。
これが転じて、仏教でもカルマという言葉が使われ始めます。
中国が発祥である仏教では、カルマを「業」という言葉で表し、インドの宗教と同じく私たちの行動全てを指す言葉として使われてきました。
行動の中には体を動かすものだけでなく、頭で考えたり、口に出したりするものも含まれています。
すなわち、どのような生き方をしてきたかで、その後の未来が決まることを指しているのです。
現代を生きる私たちは、どんなに相手を憎く思っていても、相手にそれが伝わらなければ良いと考えるでしょう。
気持ちが悟られないように作り笑いを浮かべるのも、決して珍しいことではないはずです。
しかし、カルマと運命の考え方では、例え心の中で思ったことであっても、その後の運命を大きく左右すると考えられています。
むしろ体でとった行動や、口に出した言葉よりも、誰にも知られず考えたことの方が運命に影響しやすいといわれているのです。
つまりカルマとは、インドや中国・日本などのさまざまな神様が唱える共通の認識。
どんな神様であっても悪行は決して許されず、自分の運命という形で返ってくると教えてくれているのです。
関連記事:マインドフルネスと瞑想の違いや初心者におすすめのやり方を徹底解説!
カルマを背負うとはどういうこと?

先ほどご紹介したカルマの本質を思い浮かべながら、スピリチュアルの世界でよく耳にする「カルマを背負う」という言葉の意味を考えてみましょう。
人は誰でも、良い行いをした人は良い人生を、悪い行いをした人は悪い人生を歩んでいるはずです。
即ち「自分の行い=カルマ」を背負いながら残りの人生を歩むという意味で、「カルマを背負う」という言葉が使われているのです。
悪い意味に捉えられがちな言葉ですが、決して悪行だけを意味するわけではありません。
同じような言葉に「業を背負う」があります。こちらは悪行を背負って生きることを意味し、悪い状態を指すときに使われる言葉です。
いずれにしても、人類は誰しもが今世、あるいは前世のカルマを背負って生きていると考えられます。
そして現在の行いこそが、未来や来世の人生を決める大きなきっかけとなることも間違いないでしょう。
カルマが重い人の特徴とは?

「カルマ」という言葉は、時として「カルマが重い」などと使われることがあります。
カルマには人によって重いもの・軽いものが存在しており、重いものはすなわち「乗り越えなくてはならない壁が高いこと」を指します。
主に悪い意味で使われることが多く、それだけこれまでの人生で悪行を繰り返してしまったということになります。
悪行を繰り返していても、重いカルマを背負って生きていくうちに、カルマが軽くなり良い人生を歩める可能性が出てきます。
もちろん、その後どれだけ善行を積むかによっても異なりますが、カルマが重いからといって全てが終わってしまうわけではないことを覚えておきましょう。
自分のカルマが重いのか、はたまた軽いのかを正しく理解することはできません。
現在の自分自身を振り返りながら、身に起こった出来事からカルマの軽重を推測することが大切です。
ネガティブな出来事が頻繁に起こる
特に悪い行いをしていないにもかかわらず、ネガティブな出来事ばかり起こると感じる場合があります。
これは、前世やこれまでの人生で悪いカルマが溜まり、それを背負っている状態だと考えられます。
前世やこれまでの人生で行った出来事は、その多くが同じ形で自分に返ってくるといわれています。
つまり、誰かに悪口を頻繁に言っていた人であれば、同じように現在誰かから悪く言われている可能性が高いということ。
物を盗んでいた人は、自分の大切なものを失いやすくなっているでしょう。
進展しない人生
振り返ればありきたりな人生で、良くも悪くも進展がないと感じる場合も、同じようにカルマが重いと考えられます。
進展がないということは、即ち自分がどんなことにも無関心であったといえます。
周りの人にも興味がなければ、自分自身についてもそれほど考えることがないなど、向上心がない状態であるといえるでしょう。
放置してしまえば今後も同じような状態が続き、誰かの記憶に残りにくいさみしい人生で終わってしまうかもしれません。
精神的な不安定さ
同じ出来事を経験していても、精神的に強い人とそうでない人では、受け止め方が大きく異なるでしょう。
もちろん幼少期の育てられ方や遺伝的要素も加わっているものの、カルマが重い人ほど精神的に不安定であるといえます。
通常であれば簡単に乗り越えられる壁でも、精神的に不安定な人は苦労することが多いでしょう。
日常生活でもさまざまな試練に挑む必要があり、ストレスが溜まる一方。出口が見えず、思うように頑張れない人も少なくないはずです。
しかし「こんな状態も過去の自分が起こした行動の結果である」というのがカルマの考え方です。
肉体的な不調
精神的な弱さのほか、体が弱かったり病気にかかっていたりといった肉体的不調も、カルマによる影響が強く出るポイントの一つです。
特にカルマの影響が強いのは、生まれ持った病気や障がいについて。
前世で他人を傷つけた経験がある人に多く見られ、現世では他人を傷つけることなく周囲に頼りながら生きていかなければならないという教えでもあります。
過去の経験からの解放が困難

いつまでも過去の経験がトラウマになっており、解放されずに悩んでいる人も多いのではないでしょうか。
中でも自分の行動が原因でトラウマになってしまった物事に対しては、カルマが大きく影響しているといわれています。
これは先ほどご紹介した「精神的不安定」にもつながります。
通常であれば過去の失敗を乗り越えて強くなっていくものの、不安定であるがゆえに失敗から立ち直ることができないケースがあります。
過去に人の失敗を笑ったり、蔑んだりした経験がある場合、同じように自分も苦しめられる可能性があるのです。
自己否定的な思考
カルマが重い人は、軽い人に比べ自分に自信がないことが多いといわれています。
それがゆえに自分を傷つけたり、何かと自分を下げた発言をしたりと、否定的な思考が抜けなくなってしまうのです。
自分の良さが見つからないだけでなく、他人からせっかく褒められていても「お世辞だろう」と素直に受け取れないケースも多々見られます。
前世で誰かを深く傷つけたり、侮辱する言葉を使っていたりすると、現世では自分が蔑む対象として認識されてしまうのです。
他人への過度な批判や嫉妬
重いカルマを背負っている人は、自分に自信が持てないあまり、他人に嫉妬することが多くなります。
自分にないものを持っている人が羨ましく見えたり、相手の努力を見ずに結果だけを妬んだりと、周りが気になって仕方がなくなるのです。
その結果、他人を過度に批判し周りから疎まれることもあるでしょう。
物質的な損失や金銭問題
過去にさまざまな悪行を行ってきた人の場合、現世でカルマが及ぼすのは精神や肉体に関することだけではありません。
大切にしていたものを偶然失うことになったり、友人や家族との別れを経験したりと、幾度となく損失の機会が訪れるでしょう。
また、カルマが重い人は金銭面でもうまくいかなくなるといわれています。
上手くやりくりができず借金を抱えることになるなど、生活が回らなくなるほどの問題を抱える人も珍しくありません。
スピリチュアルな悩み
過去にさまざまな悪行を積み重ねてきた場合、言葉では説明できないような事柄に悩まされることがあります。
人間関係や金銭面といった分かりやすい悩みではなく、「いつも見られている気がする」「心霊現象が起きた」といった科学的に説明できない悩みを抱えている人も。
こういった事象にはすぐに対処できる方法がないため、結果として長い間同じ悩みに苦しむ人もいるようです。
カルマの法則とは?
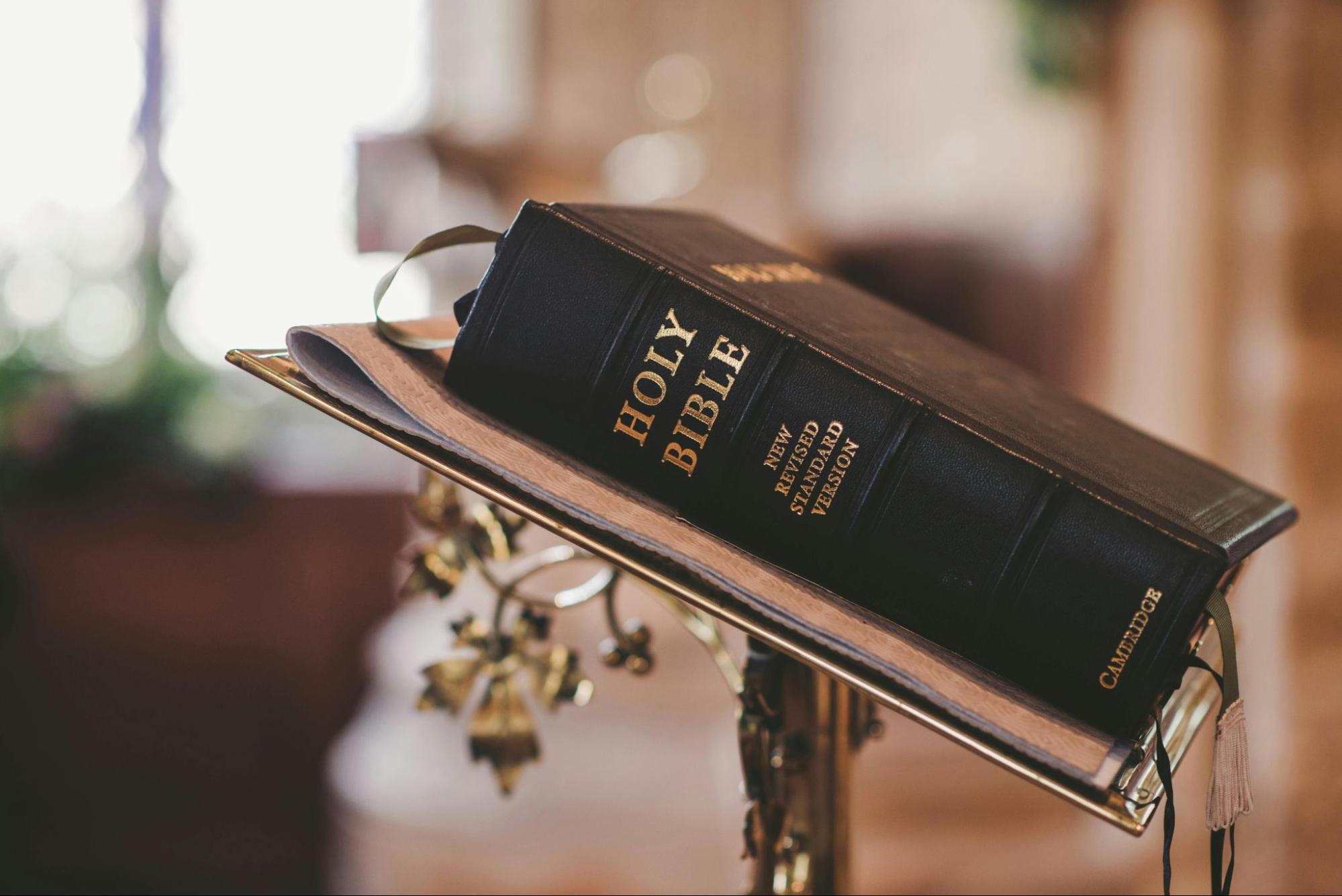
続いて、こちらも耳にすることが多い「カルマの法則」について詳しく見てみましょう。
カルマの法則の概要について
カルマの法則とは、すなわちこれまでにご紹介してきた内容を端的に述べた「自分の行いは自分に返ってくる」という内容を指します。
言い返せば「良い人生を送りたければ良いことをしなさい」という教えの一つ。
悪いことをしてはいけないという戒めであると同時に、人生の指南書としても活躍しているのです。
同じような言葉として「因果応報」があります。
四字熟語でありながら仏教用語でもある言葉で、カルマ同様善悪はすべて自分に返ってくるという意味を持ちます。
このように、言葉は違えど世界中で同じような考えが浸透しており、私たちはその教えの中で生きているのです。
恩恵を得るための方法
カルマの法則を知って恩恵を得るためには、以下の手順で自分を変えていくのがおすすめです。
- 気持ちを変える
- 言葉を変える
- 行動を変える
先ほどもご紹介したように、カルマの良し悪しを決めるのは行動だけに留まりません。
もっとも重視されるのは「気持ち」であり、最初に変えなければならない点でもあります。
まずは自分や他人に対する否定的な気持ちを変え、ポジティブに過ごすことから始めましょう。
気持ちが整ってから、言葉や行動を変えてみても遅くはありません。
関連記事:ジャーナリングのやり方は?日記との違いや効果について
自分のカルマを知る方法は?

一般的に、自分のカルマについて詳しく知る方法はありません。
過去にどんなことをしていて現在があるのか、想像しながら行いを正していくほかないのです。
続いては、そんなカルマを想像するために重要な3つのポイントについてご紹介します。
自分の人生を振り返ってみる
自分のカルマを正しくイメージするためには、これまでの人生を詳細に振り返ってみることが大切です。
失敗や悲しかった出来事などは、思い出に残りやすいです。それらについてどう考えたのか、結果として何が起こったのかなどを細かく振り返ってみましょう。
必要に応じてメモを取りながら、当時のことをできるだけハッキリと思い出すことが大切です。
こうして過去の自分を掘り出していくと、カルマによる影響が目に見えやすくなります。
前世や過去の行いが良かったのか悪かったのか、はたまたカルマが重いのか軽いのかなどを判断する参考にしてみてはいかがでしょうか。
自分の感情と向き合う
カルマを知るために重要なポイントの一つに「感情」があります。
先ほども触れたように、カルマを構成しているもっとも大きなポイントが感情です。
自分が思い描いた感情とは別の気持ちが表れたり、気持ちとは裏腹な行動をとってしまったりしたときは、カルマによる影響が強く出ていると考えて良いでしょう。
この感情は、過去の誰かがあなたに向けていた感情であるといえます。
現在の行動について良い気持ちがあるのならば、あなたは良いカルマを持っている証拠。逆であるならば、今後の感情や行動を見直す必要があるでしょう。
人間関係を見直す
周囲の人間とどのような関係を築いているかも、カルマの良し悪しを判断するポイントになります。
その人が好きか嫌いかといったシンプルな問題だけでなく、これまでの日々でどのような関係になれたのかを詳しく思い返してみましょう。
あなたの周りに良い人が多いならば、過去の善行が今に表れているといえます。
逆にあなたにとって不都合な人間関係が多い場合は、重いカルマを背負っていると判断できます。
自分が悪くなくても相手のトラブルに巻き込まれたり、困難なお願いを頻繁にされたりする場合は、感情や行動を改める必要があるかもしれません。
関連記事:スピリチュアルカウンセラーとは|本物になるためにはどうすればいい?
カルマの意味についてのまとめ
どんな人でも必ず、前世やこれまでの自分が歩んできた人生がカルマとなって現れているはずです。
それが良いことであれば引き続き来世へとつなげ、悪いことであれば今断ち切るために努力しましょう。
悪いカルマを断ち切るための努力は、きっとあなた自身を成長させてくれるはずです。
また、悪いカルマの中でも重いカルマだと感じる場合、自分が背負っているものについて専門家に相談するのもおすすめです。
電話占いや対面占いなど、自分が利用しやすい方法で相談すると良いでしょう。
メンタルがやばいサインとは?メンタルの不調で休むのは甘え?

仕事や家事・育児・介護などさまざまな面において、毎日忙しい時間を過ごしている現代人。
一日の終わりにしっかりと休息をとったり、時には自分の好きなことを思い切りやったりする時間がとれれば良いですが、慌ただしい毎日の中ではそう上手くいかないものです。
今回は、普段頑張っている全ての人に向け、メンタルのバランスが崩れるときの見分け方をご紹介します。
チェック項目や不調時の対処法を確認し、明日を元気に過ごすための参考にしてみてはいかがでしょうか。
メンタルがやばいサインとは?セルフチェック項目

「何だか不調が続いている」「気持ちが落ち込んで戻らない」など、メンタルのバランスが崩れるとさまざまな症状が見られます。
悲しい出来事があって、少しの間落ち込むくらいならば通常の範囲内です。
しかし、落ち込んだ状態があまりにも長く続いたり、悲しい出来事がないのに気持ちが不安定になったりする場合は、メンタルに影響が出ている可能性があります。
まずは自分で自分の状態をしっかりと把握するために、以下の項目を確認してみましょう。
当てはまるものが多ければ多いほど、メンタルにダメージを受けている可能性が高まります。
- 持続する悲しみや気分の低下
- かつて楽しんでいた活動への興味喪失
- 食欲や体重の変化
- 睡眠障害
- 疲労感やエネルギーの欠如
- 価値のなさや過剰な罪悪感の感覚
- 集中力の低下
- イライラ感や怒りの増加
- 社会的な場からの撤退
- 説明できない身体的症状
- 死や自殺の考え
何日経っても気持ちが晴れなかったり、これまで楽しんでいた活動がどうでも良いと感じたりするなど、メンタルの不調はさまざまな弊害を生んでしまいます。
仕事に集中できずミスを頻発したり、理由もなくイライラして周りと軋轢を生んでしまったりと、人間関係に影響が出ることもあるでしょう。
その結果過ごしにくい日々が続き、さらに心を病んでしまう人も少なくありません。
さらには、上記のような心の問題だけでなく、体重減少や睡眠障害が発生する場合もあります。
身体的な問題がないにもかかわらずこのような症状があらわれた場合は、一度精神科や心療内科などの専門家に相談しましょう。
メンタルにダメージを受けた状態が長く続けば、死にたいと考えるようになるなど重大なトラブルの原因にもなりかねません。
具体的に自殺の方法を考えてしまうなど、強い不安がある場合も必ず専門家を受診するようにしましょう。
関連記事:メンタルブレイクした時はどうすればいい?診断方法や治し方を紹介
メンタルの不調の原因は?

続いて、メンタルが不調になるのは一体なぜなのか、多くの人に当てはまる原因について見てみましょう。
一言でメンタルが病んでいるといっても、その原因や解決策は人それぞれです。
自分に合った方法を探すためにも、自分がなぜダメージを受けているのかをハッキリ知ることが大切です。
ストレス
仕事や家事・育児・介護など、さまざまな理由で忙しい毎日を送っている現代人。
どんな生活をしている人も、少なからずストレスを感じているものです。
適度なストレスは生活にメリハリが出る場合もありますが、多大なストレスを受けることや、小さなストレスが積み重なったままでいるのは良くありません。
多大なストレスは、原因となる出来事を防がなくてはなりませんが、小さなストレスは避けきれない場合も多いでしょう。
こういう場合は、適度に肩の力を抜き、リラックスできる時間を確保することが大切です。
種類の違うストレスであっても、発散しない限りは体に溜まり続けてしまうもの。
結果として心身に影響が出る前に、自分に合った発散方法を見つけましょう。
また、自分で望んだ仕事をしているときや、可愛い我が子を育てているときなど、自分が楽しいと思っていても少なからずストレスが発生しています。
ミスをしないように、子どもを危険に晒さないようになどといった緊張感もストレスに繋がるため、「ストレスを受けないようにしよう」と努力しすぎないことが大切です。
生活習慣の乱れ
朝食を抜いたまま出かけたり、毎日寝る時間がバラバラだったりと、理想的な生活習慣を送れていないとメンタルに影響が出やすくなります。
不規則な生活を送っている場合は、食事や睡眠の時間を毎日同時刻に揃えるだけでも気持ちが落ち着きやすくなるでしょう。
乱れた生活習慣が続くと、交感神経・副交感神経のバランスが崩れ、働くべきときに働けなくなってしまいます。
夜眠る前なのに交感神経が優位になり睡眠不足になったり、日中副交感神経がはたらいて異常な眠気を催したりと、生活に支障が出ることも少なくありません。
また、「自律神経失調症」のように原因不明の症状に悩まされる可能性もあります。
呼吸や血圧の上昇・下降などを司る自律神経がうまくはたらかなければ、息苦しさや熱っぽさ、めまいや吐き気などさまざまな症状があらわれるでしょう。
これらを短時間で治すのは難しく、専門家とともに長い時間をかけて治療を行わなければなりません。
人間関係の問題
メンタルに影響を及ぼす原因の中でも、多くの人が抱えているのが「人間関係の問題」ではないでしょうか。
職場内であったり、子どもの学校や幼稚園・保育園で親同士が関わったり、はたまた家庭内の関係であったりとその状況はさまざまです。
どんな状況においても100%好かれる人間が存在しないように、誰しもがどこかで嫌な思いをしているといっても過言ではありません。
大切なのは、嫌な思いをしたときに「どれだけ気にせずにいられるか」という点。
心に余裕があれば受け流すこともできますが、自分に自信がないなどの理由で過度に気にしてしまう人も多いでしょう。
また、人間関係の問題は自分一人が悩んでも解決できないのが難点です。
問題を解決しようとはたらきかけることも、何もせずにじっと耐えることも、どちらの場合も自分にとってのストレスとなってしまうでしょう。
周囲に頼れる人がいる場合は、必要に応じて相談や巨力を求めるなど、自分一人で抱え込まないことが大切です。
経済的問題
十分な貯蓄がなかったり、借金をしていたりといった経済的な問題も、メンタルに影響を及ぼす大きな原因の一つです。
物価が軒並み高騰する中、毎日の食費に気を配っている方も多いのではないでしょうか。
こういったやりくりを続けることや、突発的に起こる大きな出費、未来の経済環境に不安を覚えることでさえもストレスとなってしまうでしょう。
例え十分に貯蓄ができていたとしても、子どもの学費や将来仕事ができなくなったときのことなどを考え出せばキリがありません。
過度な節約で疲れてしまうことのないよう、肩の力を抜いた生活を心掛けましょう。
職場環境

仕事にやりがいを感じられなかったり、不得意な仕事でミスをしてしまったりといった職場環境も、見直さなければならないポイントの一つといえます。
人間関係に問題がなかったとしても、過剰な残業や休日出勤などで心身ともに疲弊してしまう人も珍しくありません。
場合によっては転職も考えながら、自分の職場について見直してみることをおすすめします。
遺伝的要因
病気そのものが血縁から引き継がれることはないものの、精神的な病が発症するかどうかは遺伝的要因も大きいといわれています。
親族にうつ病がいる場合、そうでない場合と比べて発症リスクが数倍高まったという研究結果も存在します。
もちろん遺伝がすべての要因ではないものの、家族に精神疾患を経験した人がいる場合はより一層注意すると良いでしょう。
参考:うつ病は遺伝するの?精神科専門医が分かりやすく解説します
身体的健康問題
メンタルにダメージを負う原因は、心の問題だけではありません。
単なる風邪で気持ちが落ち込んでしまうこともあれば、重大な病をきっかけにうつ病を同時発症してしまう例もたくさんあります。
体の健康は心の健康といっても過言ではなく、「咳が出る」「鼻が詰まる」といった軽微な症状であっても気持ちが落ち込んでしまうのです。
不調が長く続けば続くほど、落ち込んだ状態も長引いてしまいかねません。
忙しい人であればつい後回しにしてしまう通院も、なるべく早い段階で検討すると良いでしょう。
心理的トラウマ
過去に経験した出来事がトラウマとなり、メンタルを傷つけている可能性もあります。
自分で気づいているトラウマであれば避けられますが、中には知らないうちに心の奥深くへ刻み込まれているものもあり、一概にはいえません。
例えば、自動車事故を経験した人であれば、以前と比べて車に乗るのが怖いと感じても不思議ではないでしょう。
プレゼンテーションで失敗した経験から、多くの人の前で話すのが苦手になる人も珍しくありません。
こういった心理的トラウマは短期間で改善するのが難しいため、まずは自分のトラウマを理解し、原因を探ることから始める必要があります。
薬物やアルコールの乱用
日本で禁止されている薬物はもちろん、市販の医薬品を飲みすぎたり、多量のアルコールを継続して摂取したりする場合も、メンタルに大きな影響を及ぼします。
脳に大きなダメージを与える薬物を日常で目にすることはありませんが、市販の医薬品やアルコールは誰でも手軽に手に入るものばかり。
依存することがないよう、適量を守らなければなりません。
医薬品やアルコールを乱用すると、次第に依存するようになり、それがなくては生活ができない状態になる可能性があります。
自力で抜け出せない状態になるケースも珍しくないため、医薬品は用法容量を守り、アルコールは適度な量を楽しみましょう。
情報過多
メンタルについて調べてみると、驚くほど多くの情報がヒットします。
この中から正しいものを選びとり、自分に必要な情報だけを利用しなければならないため、調べているだけで疲れてしまっても不思議ではありません。
どんな情報を調べるときであっても、私たちには正しいものを判断する力が求められています。
気持ちに余裕がないときほどネットの沼にはまってしまいがちですが、焦りや不安を感じているときはスマートフォンを置き、目や頭を休ませてあげることも大切です。
関連記事:ネガティブ思考は病気?うつ病との違いや治し方を解説
メンタルの不調になったらどうすればいい?

続いて、メンタルの不調を感じたとき、私たちがとるべき行動について確認してみましょう。
自分の感情を受け入れる
自分がどんな感情をもっていたとしても、それは自分だけのものであり、周りに非難されてはいけません。
例え周りに受け入れられにくい内容であっても、自分だけは感情を認めてあげましょう。
「こんなことを言ったら嫌われるかもしれない」「恥ずかしくて周りに打ち明けられない」といった内容も、自分の中で消化することに問題はありません。
声に出してみたり、日記に書いてみたりと、自分だけが知るアウトプット方法を探すのがおすすめです。
十分な休息をとる
どんな原因でメンタルがダメージを受けていても、まずは十分に休息をとることから始めましょう。
時にはやるべきことを後回しにしてでも、睡眠やボーっとする時間を確保することが大切です。
十分に休息をとり、体が万全の状態になってから原因について考えても遅くありません。
まずは体の不調を防ぐためにも、睡眠時間を長めにとってみてはいかがでしょうか。
趣味やリラックスできる活動をする
十分な休息をとると同時に、自分の好きなことや趣味に費やす時間を確保することも大切です。
他のことを気にせず没頭できる趣味があれば、メンタルを回復させ、不調を治すきっかけとなるでしょう。
体を思い切り動かすも良し、黙々と作品を作るも良し、心から楽しめる活動を見つけてみると良いでしょう。
運動をする
普段から運動する習慣が身についている人ならば良いですが、そうでなければ軽度な運動を取り入れてみるのもおすすめです。
急に負荷の大きな運動を始めるのではなく、10分間のストレッチや1kmのウォーキングなどできることから始めましょう。
ダイエットなどとは違い、毎日必ず運動をしなければならないわけではありません。
「やらなければならない」と無理をするのではなく、あくまでも気分転換として軽い運動を選択肢に加えてみてはいかがでしょうか。
健康的な食生活を心がける
丈夫な体作りとしてはもちろん、心を安らかに保つためにも、健康的な食生活は必要不可欠です。
過度な食事制限や野菜ばかりのメニューを続けるのではなく、栄養バランスの整った食事を心掛けましょう。
1週間のうち1日は好きなものを食べる日に定めるなど、やる気を保つための工夫も大切です。
睡眠の質を向上させる
メンタルを回復させるために、十分な休息は必要不可欠です。つまり、良質な睡眠をとることこそが健康への第一歩といっても過言ではないでしょう。
単に睡眠時間を長くするだけでなく、ゆったりとした寝巻きに変えたり、室温を調整したりして睡眠の質を高めてあげるのもおすすめ。
夜中に何度も起きることなく、朝までぐっすりと眠れる睡眠が理想的です。
人との繋がりを大切にする
メンタルに影響しがちな人間関係をトラブルのないものにするために、普段から周囲との関係を良好に保っておくことが大切です。
苦手な人にも笑顔を保つ必要はありませんが、不要なトラブルを防ぐために適度な距離を保ちましょう。
人との繋がりを大切にする上では、自分の気持ちを素直に話せる相手を見つけるのも重要です。
何かあったときに相談できる相手がいれば、強い不安や焦りなどの感情も緩和されやすいでしょう。
マインドフルネスや瞑想を試す
目を閉じて自分の気持ちに集中する瞑想をはじめ、現在の出来事に関して深く考えるきっかけとなる「マインドフルネス」もメンタルを安定させるために役立つ方法の一つです。
一人になれる場所で、まずは数分間から自分と向き合う時間を作りましょう。
自分が何を望んでいるのか、何に悩んでいるのかを深く知ることで、メンタルが不安定になる回数や頻度を減らすことに繋がります。
専門家に相談する
これまでご紹介してきた内容は、あくまでも自己判断であったり、自分でできるメンタルケアが中心でした。
しかし、自分自身と向き合い悩みを解決するということは、簡単そうに見えてなかなか難しいもの。
こういうときは、精神科医や心療内科医・臨床心理士・カウンセラーなどの専門家に話を聞いてもらうのがおすすめです。
薬を使った治療法の他にも、カウンセリングや心理療法によるケアにもチャレンジできるでしょう。
専門家は数ある症例や経験の中から、一人ひとりの状態を見抜いて適切なケアを施してくれます。
一人で悩む前に、まずは相談から試してみることをおすすめします。
メンタルの不調で休むのは甘え?

少し前までの日本では、身体的な不調であればともかく、周りが気づきにくいメンタルの不調で仕事を休むのは甘えだといわれていました。
「うつ病は甘え」「メンタルを病む人はサボりたいだけ」などと言われ、さらに自分自身を追い込んでしまう人も決して少なくなかったのです。
現在は、企業カウンセラーが導入されたり、細かいハラスメント規則が定められたりと、これまでよりも心理的な面でのケアに力を入れる企業が増えてきました。
もちろん全ての企業ではないものの、昔に比べメンタルの不調でも休みやすい環境へと近づきつつあるでしょう。
とはいえ、メンタルの不調は周りからすると辛さが分からず「休むほどのことなのか」といわれてしまいがちです。
必要に応じて医師に診断書を書いてもらったり、カウンセリング結果を提出したりして、周囲にも状況をしっかりと把握してもらうことが大切です。
【まとめ】メンタルがやばいサインを感じたら無理は禁物
私たちが過ごす日常の中では、メンタルにダメージを与えるような出来事がたくさん潜んでいます。
避けられるものは避けながら「やばい」と感じたときはすぐに自分自身を守りましょう。
今回ご紹介した対処法を試しながら、無理をせずに過ごすことが大切です。
メンタルの不調は軽視されがちですが、時として長く落ち込んだ状態から抜け出せなくなるなどのリスクがあります。
専門家を味方につけながら、自分に合った対処法を探していきましょう。
アンガーマネジメントのやり方|「意味ない」と言われる理由とは?

近年、「アンガーマネジメント」に対する注目が高まっています。
その一方で、アンガーマネジメントが「意味ない」と言われることも少なくありません。
そこで、この記事ではアンガーマネジメントのやり方や考え方について解説します。
また、なぜアンガーマネジメントが「意味ない」と言われるのか、その理由についても見ていきましょう。
アンガーマネジメントとは?
アンガーマネジメントとは、アメリカで生まれた怒りと上手に向き合うための心理的なトレーニングです。
アンガーマネジメントの目的は「怒らないこと」と思われがちですが、それはアンガーマネジメントの本来の目的ではありません。
アンガーマネジメントでは、必要があるときに適切に怒れることが目標です。
犯罪者の更生プログラムであったアンガーマネジメントは、近年一般化されてきました。
多くの人が怒りのコントロールができるようになるため、アンガーマネジメントを取り入れています。
アンガーマネジメント能力の診断方法
アンガーマネジメント能力の診断方法は、主に次の2つです。
- 自己診断のためのチェックリスト
- 日本アンガーマネジメント協会の無料診断
それぞれの診断方法について、以下で見ていきましょう。
自己診断のためのチェックリスト
以下に、自己診断をするためのチェックリストを用意しました。
ぜひ、自身にアンガーマネジメント能力があるかをチェックしてみてください。
- 自分が怒っているときにそれを自覚することができる
- どういった状況で怒りの感情が沸き起こるか理解している
- 怒りを表現する際の適切な言葉や行動の選択ができる
- 挑発に対して耐えることができる
- 自分の感情を正確に認識することができる
- 対立や不和の状況でのコミュニケーションをとることができる
- 他者の視点を理解し、共感を示すことができる
- 怒りを覚える状況に対して適切な解決策を見つけ、実行できる
- 自分の感情を鎮めるための方法を持っている
- 怒りの発生後に自己反省を行う習慣がある
- 行動の結果を評価し、将来的な改善点を見つける意欲がある
当てはまる項目が多ければ多いほど、アンガーマネジメントの能力が高いと言えるでしょう。
日本アンガーマネジメント協会の無料診断
日本アンガーマネジメント協会の無料診断を受けることでも、自身のアンガーマネジメント能力をチェックできます。
以下のページから、日本アンガーマネジメント協会のLINE公式アカウントをお友だち登録すると診断できます。
上記のチェックリストとあわせて活用してみてください。
アンガーマネジメントのやり方

アンガーマネジメントには、次の5つのやり方があります。
- 深呼吸
- 他のことを考える
- 運動する
- 相手の立場を考えてみる
- 専門家の支援を求める
それぞれのやり方について以下で見ていきましょう。
深呼吸
アンガーマネジメントのテクニックに「深呼吸をする」があります。
怒りを覚えると、私たちの呼吸は速く浅くなりやすいのです。
深呼吸をすることで、速く浅い呼吸を落ち着けることができ、それと同時に怒りの感情もだんだんとおさまってきます。
特に、深呼吸をする際には、吐く息を長くすることを意識すると、よりリラックスしやすくなるでしょう。
他のことを考える
他のことを考えることも、アンガーマネジメントのテクニックの1つです。
たとえば、学生時代の楽しかった思い出や、仕事で褒められたことなどを思い返してみてください。
ポジティブな内容を思い返すことで、喜びや嬉しさなどの怒りと反対の感情が生まれ、怒りをおさめられます。
また、怒りの対象が目に入らないようにすることもおすすめです。
その場から離れたり、目を瞑ったりして怒りの対象から目をそらすことでも、怒りの感情をおさめられるため、ぜひ試してみてください。
運動する
運動には身体的な健康だけでなく、精神的な健康にもプラスの効果があることが多数の研究結果により明らかになっています。
特に、週3回以上の有酸素運動をおこなうことで、その効果は大きくなります。
有酸素運動に該当するのは、ウォーキングやジョギング、水泳など。
身体的な健康と精神的な健康の両方が手に入るため、週3回以上を目安に軽めの運動を取り入れてみてください。
相手の立場を考えてみる
相手の立場を考えてみることもおすすめです。
いざ相手の立場に立ってみると、相手の言動について理解でき、怒りがおさまる場合があります。
また、相手の考えを否定ばかりしていると、どんな状況でも相手の考えを受け入れられなくなってしまう可能性があります。
しかし、時には柔軟な考え方をもち、相手の考えを取り入れることも大切。
考えの柔軟さを手に入れるためにも、相手の立場を考えてみることはおすすめです。
専門家の支援を求める
今までに紹介した4つ以外にも、アンガーマネジメントにはさまざまなテクニックがあります。
しかし、それらを自分自身で実行し、アンガーマネジメントをおこなうのは簡単ではありません。
「自力での実行が難しい」と感じたら専門家の支援を求めるのも1つの手段です。
それぞれの人にあわせて適切なテクニックを紹介してくれて、アンガーマネジメントができるまで伴走してくれます。
ぜひ信頼できる専門家を見つけて、支援を求めてみてください。
関連記事:【怒りを抑える】アンガーマネジメントのテクニックや方法をご紹介!
アンガーマネジメントにおける「6秒ルール」とは?

アンガーマネジメントには「6秒ルール」というテクニックもあります。
6秒ルールとは、怒りが湧いてきたら、6秒だけ数えて怒りが静まるのを待つことです。
6秒ルールで心を落ち着けるには、心の中で1から6をゆっくりと数えることが大切です。
怒りに反射せず、少しでも時間を空けることで、怒りをおさめられやすくなります。
アンガーマネジメントは意味ない?胡散臭い?
「アンガーマネジメントは意味があるの?」
「アンガーマネジメントって胡散臭いものでしょ?」
アンガーマネジメントに対して、このような疑問を抱えている方もいるかもしれません。
たしかに、アンガーマネジメントを学んでも怒りの感情はなくならないため、「怒りの感情をなくす」点では意味がないと言えるでしょう。
しかし、アンガーマネジメントの目的は、怒りの感情を「コントロール」することにあります。
目的を間違えずに地道に実践することで、徐々に怒りの感情がコントロールできるようになり、必要のない場面で怒ることを減らせるようになるでしょう。
子どものアンガーマネジメントについて
アンガーマネジメントは「大人向けのもの」と無意識のうちに認識している人も多くいるかもしれません。
しかし、子どもがアンガーマネジメントを身につけることも重要です。
子どもが感情に任せて行動してしまうと、良好な人間関係の構築が難しくなります。
特に、子どもの時期に人間関係がうまくいかないと、失敗経験を大人になっても引きずってしまう可能性があります。
そのため、子どももアンガーマネジメントを通して、相手とのコミュニケーションの取り方を身につけることが大切です。
関連記事:【誰でもできる】マインドセットの意味や使い方を簡単に解説!
アンガーマネジメントの実践例
筆者が接客業のアルバイトをしていたとき、お客さまからクレームをつけられたことがありました。
いちゃもんと言うべき内容であったため「なぜ自分が怒られなければいけないのか」とお客さまに対して怒りを覚えましたが、立場上、お客さまに反論することはできません。
また、反論したところで更なるトラブルを生むだけであるため、反論しても意味がありません。
深呼吸した後に「今は我慢だ」と自分に言い聞かせ続けていると、だんだんと怒りがおさまってきて、お客さまの言い分を冷静に聞けるようになりました。
状況を察した店長が駆けつけてくれて、代わりに対応してくれたおかげで、その場は事なきを得ました。
深呼吸したり、気持ちを落ち着ける言葉を自分自身に対して言い続けたりしたことにより、不必要に怒ることを回避。
怒りを覚えても、アンガーマネジメントを活用することで、大きなトラブルに発展せずに済みました。
【まとめ】アンガーマネジメントをマスターしよう
アンガーマネジメントをマスターすることで、怒りの感情をコントロールできるようになります。
深呼吸や運動、6秒ルールなどを用いて、アンガーマネジメントをマスターできるようにトレーニングしてみてください。
もし自分の力だけでアンガーマネジメントをマスターするのが難しいと感じた場合は、専門家に支援を求めることもおすすめです。
ぜひアンガーマネジメントをマスターし、良好な人間関係を築いていきましょう。
生理前の情緒不安定の対策|彼氏への伝え方はどうすればいい?

「生理前に情緒不安定にならないようにしたい!」
「生理前に起きる情緒不安定のせいで、彼氏との関係が悪化したらどうしよう」
このような悩みや疑問を抱えている方がいるのではないでしょうか。
この記事では、生理前の情緒不安定の対策や彼氏への伝え方について解説します。
生理前の情緒不安定はなぜ起こる?
生理前に起こる情緒不安定は、PMS(月経前症候群)の症状である可能性が高いと言えます。
PMSの症状には、身体的なものから精神的なものまでさまざまな種類があります。
PMSの症状を引き起こしているのは、エストロゲンとプロゲステロンといわれるホルモンです。
エストロゲンとプロゲステロンは、排卵後に多く分泌される一方、月経が近くなると急激に分泌量が低下します。
分泌量の急激な変化が脳内ホルモンなどに影響を及ぼすことにより、身体的・精神的不調が引き起こされると考えられています。
20代〜30代に多く見られる症状であり、生理周期および卵巣機能が正常でも症状を引き起こすことがあるため、辛いときは無理せず、婦人科に相談してみてください。
関連記事:女性の情緒不安定の治し方は?生理との関係や落ち着く方法を解説
生理前の情緒不安定の対策法は?
生理前の情緒不安定には、次の7つの対策法があります。
- 適切な栄養摂取
- 定期的な運動
- 十分な睡眠
- カフェインとアルコールの摂取を控える
- 良好なコミュニケーション
- 趣味や楽しい活動に時間を割く
- 専門家の助けを求める
それぞれの対策法について、以下で見ていきましょう。
適切な栄養摂取
女性ホルモンの効果が薄くなることで、生理前に情緒不安定になってしまうことがあります。
情緒不安定を改善するには、カルシウムとマグネシウムの摂取がおすすめです。
カルシウムとマグネシウムは、大豆製品や緑黄色野菜に多く含まれるため、ぜひこれらの食材を多めに摂るようにしてみてください。
定期的な運動
定期的な運動も、生理前に起きる情緒不安定の改善に効果があります。
激しい運動をする必要はなく、ジョギングやウォーキングなどの軽めの運動で十分です。
1日30分程度の軽めの運動を週3日するだけで、症状が改善する可能性があります。
隣の駅まで歩いてみたり、いつもバスに乗るルートの一部を歩いてみたりして、定期的な運動習慣を身につけてみてください。
十分な睡眠
生理前に起きる情緒不安定を改善したい場合は、十分な睡眠を心がけてみると良いでしょう。
月経前や月経中は、健康な女性であっても睡眠の質が低下してしまう可能性があります。
そのため、月経前や月経中の時期は、意識的に十分な睡眠ができるように心がけると良いでしょう。
寝る直前までスマートフォンやパソコンを使わないなど、できることから始めてみることをおすすめします。
カフェインとアルコールの摂取を控える
カフェインとアルコールの摂取を控えることも効果的です。
カフェインなどの刺激物を接種することで、神経が緊張したり興奮したりしてしまいます。
神経を落ち着かせてリラックスするために、コーヒーやお茶などカフェインが入っている飲み物は控えてみましょう。
また、アルコールなど体の不調の原因となる食べ物・飲み物を控えることも大切です。
規則正しい生活を送ることで、少しでも症状が改善できるようにしてみましょう。
良好なコミュニケーション
生理前に起きる情緒不安定の改善には、良質なコミュニケーションを取ることも効果があります。
たとえば、家族や親しい人には、PMSの症状が出てしまって情緒不安定になってしまう可能性があることを事前に伝えておくと良いでしょう。
そのうえで、情緒不安定になってしまったときに「やってほしいこと」も伝えておくことがおすすめです。
たとえば「ひとりにしてほしい」「家事を手伝ってほしい」「大目に見てほしい」などが考えられます。
情緒不安定のことを打ち明けるのは、勇気が必要かもしれません。
あなたと親密な関係を築いている人は理解してくれるので、勇気を出して打ち明けてみましょう。
趣味や楽しい活動に時間を割く
生理前に起きる情緒不安定を改善するには、ストレスを低減させることが効果的です。
そのため、精神的に疲れてしまうことがあったら、趣味や楽しい活動に時間を割いてリラックスしてみてください。
趣味や楽しい活動を通してリラックスすることで、ストレスを低減でき、生理前の情緒不安定が改善する可能性が高まるでしょう。
あらかじめ趣味や楽しい活動をする日時を決めておき、それを楽しみに日常生活を送ってみるのもおすすめです。
専門家の助けを求める
以上の6つで症状が改善しない場合は、専門家の助けを求めてみるのも良いでしょう。
婦人科を受診することで、薬を用いた治療を受けられる可能性があります。
精神安定剤や抗うつ薬、経口避妊薬、GnRHアゴニストなど、さまざまな種類の薬があるため、ぜひためらわずに専門家に相談してみてください。
関連記事:イライラして眠れない時はどうする?原因や対処方法を解説
生理前の情緒不安定に効く食べ物

ここでは、生理前の情緒不安定に効く食べ物について解説します。
ホルモンバランスを整える栄養素や気分を安定させる食べ物、避けたい食べ物について見ていきましょう。
ホルモンバランスを整える栄養素
ホルモンバランスを整える栄養素には、次のようなものがあります。
- カルシウム
- マグネシウム
カルシウムやマグネシウムは、女性ホルモンのバランスを整える役割が期待できます。
大豆製品や緑黄色野菜などを摂取することで、情緒不安定が改善しやすくなるでしょう。
また、ビタミンやミネラルも摂取すべき重要な栄養素です。
生理前に限らず、若い人の中にはビタミン・ミネラルが不足している人が多くいます。
摂取すべき栄養素をきちんと摂ることが心の健康にもつながるため、サプリメントなども用いて必要な栄養素を摂るようにしてみましょう。
気分を安定させるおすすめの食べ物
カルシウムやマグネシウム、ビタミンB6には気分を安定させる効果があります。
そのため、前述したように、大豆製品や緑黄色野菜を食べることで、気分を安定させやすくなるでしょう。
特に大豆製品は、女性ホルモンと類似した働きをするイソフラボンも摂取できるため、ぜひ摂取したい食べ物です。
また、次のような食べ物からもカルシウムやマグネシウム、ビタミンB6を摂取できます。
- カツオ
- レバー類
- ナッツ類
- 海藻類
加えて、ビタミンEが接種できるアーモンドなどもおすすめですので、ぜひ積極的に摂取してみてください。
避けたい食べ物とその理由
一方、次のようなものが含まれる食べ物は避けたほうが良いでしょう。
- カフェイン
- 塩分
- アルコール
情緒を安定させるためには、自律神経を整えることが大切です。
しかし、カフェインには自律神経を乱しやすくする作用があるため、カフェインの摂取により気分が安定しない可能性があります。
また、塩分やアルコールなどの生活習慣を乱す成分を摂取することで、代謝が悪くなる可能性もあります。
そのため、カフェインや塩分、アルコールの摂取を控え、健康的な食生活を送るように心がけてみましょう。
生理前の情緒不安定で泣く原因と対策
生理前に情緒不安定になってしまい、泣いてしまうこともあるかもしれません。
この症状は「PMDD(月経前気分不快障害)」と呼ばれています。
PMDDの症状が起きる原因は、PMSと同じく女性ホルモン分泌量の急激な変化にあります。
PMDDの症状を改善するには、PMSと同じように規則正しい生活リズムで過ごし、適度に運動することが大切です。
また、婦人科で薬を処方してもらったりピルを服用したりすることでも症状の改善が期待できます。
困ったら、無理に自分で解決しようとせず、婦人科などの医療機関に相談するようにするとよいでしょう。
関連記事:ストレスを解消するにはどうすればいい?ハグがおすすめな理由も解説
生理前の情緒不安定の彼氏への伝え方はどうすればいい?
彼氏には、生理前の情緒不安定であることを正直に打ち明けることをおすすめします。
不機嫌な態度をとったり涙が止まらなくなったりするなど、冷静さを失ってしまうことや、急激な気分の変化によりドタキャンする可能性があることを理解してもらいましょう。
彼氏に打ち明けるのをためらってしまうことがあるかもしれませんが、信頼関係を悪化させず、むしろ信頼関係を深めるためにも、きちんと打ち明けてみてください。
薬を使った生理前の情緒不安定の治療

生理前の情緒不安定に対しては、薬を使った治療ができます。
医療機関に相談する前に、市販薬で解決したい場合は「プレフェミン」を試してみてください。
プレフェミンは、日本で唯一購入できるPMSの市販薬です。
いつでも使用できるわけではなく、低用量ピルの服用中である場合や女性ホルモンに関連する病気の既往歴がある場合などは使用できません。
その他にも注意点が複数あるため、用量・用法をきちんと確認してから使用するようにしましょう。
プレフェミンで症状が改善できない、もしくはプレフェミンを服用したら副作用が出てしまった場合、医療機関へ相談してください。
医療機関では、あなたの症状に合わせた薬を処方してもらえます。
自分で無理に解決しようとせず、専門家の意見を聞きながら症状改善に取り組んでみましょう。
ピルが原因で情緒不安定で泣くことがある?
ピルを飲み始めたばかりの頃は、ホルモンバランスの変化により情緒不安定になることがあります。
場合によっては泣くなどの症状が現れることもありますが、3ヶ月ほど飲み続ければ気分が安定しやすくなる場合がほとんどです。
しかし、症状が辛い場合、もしくは4ヶ月以上経過しても症状が改善しない場合は、ピルとの相性が悪い可能性があります。
ピルを処方してくれた医師と相談し、トラブル解決をするようにしてください。
【まとめ】生理前の情緒不安定の対策は人それぞれ
生理前の情緒不安定への対策方法は、人それぞれです。
1つの対策方法を試しても症状が改善しない可能性もありますが、その場合は他の対策方法を試してみてください。
また、生理前の情緒不安定により彼氏との関係悪化を避けるには、事情をきちんと伝え、理解してもらうことがおすすめです。
事情をきちんと伝えれば、関係悪化を防げるばかりでなく、気を遣ってくれるようになり、さらなる信頼関係の構築につながる可能性もあるでしょう。
完璧主義を辞めたい!楽に生きるための10個の方法

「完璧主義を辞めたい!」
「完璧主義から抜け出したら楽になるのになぁ」
このように考えたことがあるのは、一度や二度ではないでしょう。
完璧主義には自分を苦しくしてしまう面が多くあるため、完璧主義を辞めたい、治したいと考えるのも無理はありません。
そこで、この記事では完璧主義を辞める方法について解説します。
完璧主義を辞めて楽に生きるための10個の方法を紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
完璧主義を辞める方法は?
完璧主義を辞めるには、次の10個の方法を試してみてください。
- 加点方式で考える
- 「まぁ、いいか」を口癖にする
- 物ごとの優先順位をつける
- 合格点を超えた自分を褒める
- 自身を肯定的に評価する
- 全て自分でやろうとせず人に任せる
- うまくいかなくても自分を責めない
- 自己肯定感を上げる
- 環境を変える
- こだわりがないことにチャレンジしてみる
以下では、それぞれの方法を具体的に見ていきましょう。
加点方式で考える
完璧主義を辞めるには、加点方式で考えることがおすすめです。
完璧主義に陥っている人は、自分の「足りない部分」に目を向けて、減点方式で自分を評価しがちです。
しかし、自分の「できたこと」に目を向けて、加点方式で自分を評価すれば、ポジティブな感情を抱くことができ、完璧主義を辞められるようになるでしょう。
「まぁ、いいか」を口癖にする
完璧主義に陥っている人は、物ごとを完璧に遂行できないと満足できなくなっています。
しかし、何ごとも完璧にできるような人など、まずいません。
そこで、「まぁ、いいか」を口癖にして、ある程度の出来で満足することができるようにすることで、完璧主義から抜け出しやすくなります。
完璧にできていなくても、ある程度完了した時点で「まぁ、いいか」を口に出してみるなどして、習慣づけることをおすすめします。
物ごとの優先順位をつける
完璧主義から抜け出すには、物ごとの優先順位をつけることがおすすめです。
「あれもこれもやらなければ!」と思ってしまうと、どのタスクから片付ければよいのかわからなくなり、結果としてどれも中途半端に終わってしまいます。
そこで、緊急性・重要性の高いタスクを優先的に処理することで、やらなければいけないことを着実に終わらせられるようになります。
ぜひ物ごとに優先順位をつけて、完璧主義から抜け出せるようにしましょう。
合格点を超えた自分を褒める
完璧主義から抜け出すには、合格点を設けることがおすすめです。
完璧主義の場合、「ひとつのミスも許されない」という態度で物ごとと向き合ってしまいます。
しかし、100%ミスなくできることなどほとんどなく、誰でもミスを犯します。
そのため、「ここまでできればOK」という合格点を設けておくことで、完璧を求めてしまう癖をなくしていけるでしょう。
自身を肯定的に評価する
完璧主義に陥ってしまったら、自身を肯定的に評価してみてください。
前述した「合格点を超えた自分を褒める」ことは、肯定的に評価するための1つの手法です。
また、間違えたり失敗したりしても、挑戦した自分を褒めることも、1つの例として挙げられます。
肯定的に評価する点は、些細なことでも構いません。
むしろ些細なことでも肯定的に評価することで、ポジティブに考えられるようになり、徐々に完璧主義から抜け出せるようになるでしょう。
全て自分でやろうとせず人に任せる
全てを自分で背負うのではなく、人に任せてみることもおすすめです。
もし、「全て自分でやったほうがうまくいく」と考えているのであれば、その考えは誤解である可能性が高いです。
本当に自分でやらなければいけないことは一部分だけであり、多くの部分は他の人に任せられる場合が多くあります。
無理して自分でやろうとするのではなく、周囲の人や代行サービスなどを利用して、人に任せてみることをおすすめします。
うまくいかなくても自分を責めない
たとえうまくいかなくても、自分を責めないようにしてください。
誰でも失敗をするものであり、失敗を経験としてもう一度チャレンジすることも可能です。
また、失敗した原因が自分のミスではなく、他人や周囲の環境の影響にある場合もあります。
そのため、「失敗=悪」と考えて自分を責めるのではなく、うまくいかなかった原因を突き止めて、もう一度チャレンジしてみてください。
自己肯定感を上げる
自己肯定感を上げることも、完璧主義への対策として効果的です。
自己肯定感を上げるには、積極的に「自分の良い点」に目を向けることが大切です。
また、苦手なことよりも好きなことや得意なこと、やりたいことを積極的に行う方が自己肯定感を上げやすくなります。
自己肯定感が上がれば、前向きな気持ちになれるため、徐々に完璧主義から脱却できます。
「自分の良い点」に目を向けることは大変なことかもしれませんが、できる範囲で少しずつ取り組んでみると良いでしょう。
環境を変える
海外移住をするなど、環境を変えることもおすすめです。
今までと同じ環境で過ごしていると、自分の常識の範囲内でしか物事を考えられません。
しかし、思い切って日本から離れてみると、まったく違う環境での生活となるため、当然ながら日本での常識が通用しなくなるでしょう。
日本では常識として「〇〇しなければならない」と考えられていることも、海外に出ればもっとラフに考えている人が多くいるかもしれません。
海外移住とまではいかなくても、都会に暮らしている人は田舎に移住したり、田舎に暮らしている人は都会に移住したりすることもおすすめです。
環境を変えず、自分の中だけで変化させるのは困難であるため、ぜひ環境を変えて新たな生活をスタートしてみてください。
こだわりがないことにチャレンジしてみる
最後におすすめするのは、こだわりがないことにチャレンジしてみることです。
理想像を追い求めてしまうことで、完璧主義に陥ってしまうことが多くあります。
しかし、こだわりがなければ明確な理想像も存在しないため、完璧主義に陥りにくいのです。
中でも、運動や副業などの目に見えてプラスの効果が得られるものがおすすめです。
ぜひ、今まであまり触れてこなかったような、こだわりがないことにチャレンジしてみてください。
完璧主義の自己診断表

以下に、完璧主義の自己診断表を用意しました。
10項目のうち、どの程度当てはまるのかを確認してみてください。
- 小さなミスも許せない
- 常に最高の成果を求める
- 他人の評価を過度に気にする
- 仕事やタスクに無理な時間を費やす
- 失敗を極端に恐れる
- 自己批判が多い
- 他人にも高い基準を求める
- やり直しや完璧にするために余計な時間をかける
- 自分の成果に満足しない
- タスクの完了よりも過程の完璧さを重視する
できないくせに完璧主義な場合はどうすればいい?
「できないくせに完璧主義な自分を変えたい」と考える方もいるでしょう。
その場合でも、前述したような対策により完璧主義を抜け出せるようになります。
くわえて、次のコツを意識すると、より完璧主義から抜け出しやすくなります。
- 自分の強みを知る
- 合格点を低めに設定する
- 助けを求める
- 「なんとかなるさ」と考える
自分ができる分野、得意な分野を見つけることが大切です。
できない分野で挑戦せず、自分の強みとなる分野で挑戦したほうが失敗する確率を減らせるでしょう。
また、合格点は低めに設定することがおすすめです。
100点や80点などの高い目標を合格点に掲げてしまうと、合格点を超えられず、完璧主義から抜け出せなくなってしまいます。
さらに、「できない」と感じたら助けを求めることも忘れないでください。
「あなたひとりでやらなければならない」ことは多くないので、必要があれば遠慮せず助けを求めるようにしましょう。
そして、もし失敗してしまった場合でも、後から挽回すればなんとかなる場合が多くあります。
失敗したことにクヨクヨするより、「なんとかなるさ」と考え、そのあとのフォローアップについて考えたほうが結果としてうまくいくでしょう。
関連記事:アンガーマネジメントのやり方|「意味ない」と言われる理由とは?
完璧主義な女性の特徴

完璧主義な女性には、次のような特徴があります。
- 努力家
- ストイック
- 負けず嫌い
- 何事も計画的に
- 仕事が丁寧
- 人望が厚い
どれも良いことに見えますが、完璧主義に陥ってしまう女性の特徴でもあるのです。
それぞれの特徴について、見ていきましょう。
努力家
1つ目の特徴は、努力家であることです。
完璧主義の人は「目標をなんとしてでも達成しよう!」という強い意志を持っています。
そのため、多少の困難があっても物事をやり抜ける力があります。
ストイック
2つ目の特徴は、ストイックであることです。
完璧主義の人は90点では満足できず、常に100点を目指します。
100点を目指すために自分を律することができるため、完璧主義の人はストイックな特徴を持つのです。
負けず嫌い
3つ目の特徴は、負けず嫌いであることです。
自分から見た視点で完璧を目指すだけでなく、客観的に見ても完璧な状況を目指します。
他人に負けていては完璧とは言えないため、完璧主義の人は負けず嫌いにもなるのです。
何事も計画的
4つ目の特徴は、何事も計画的であることです。
物事を円滑に進められるように完璧に準備をするため、細かなタイムスケジュールに至るまで計画を立てます。
行き当たりばったりで物事を進めることがなくなるため、無駄な時間を過ごしたり余計なストレスを抱えたりすることがなくなるでしょう。
仕事が丁寧
5つ目の特徴は、仕事が丁寧なことです。
常に完璧を求めるため、些細なミスにも敏感であり、仕事を丁寧に進めることができます。
そのため、重要な資料の作成などミスが許されないような仕事に向いています。
人望が厚い
6つ目の特徴は、人望が厚いことです。
完璧主義の人は、仕事が丁寧であり責任感も強いことから、信頼されやすい特徴があります。
「この人に任せれば一生懸命取り組んでくれる」という評価を受けているため、人望が厚く大役を任されることもあるでしょう。
完璧主義の人はうつになりやすい?
完璧主義の人は、うつになりやすいと言えます。
完璧を目指す中で、自分に厳しくなってしまったり、気軽に物事に取り組めなくなったりしてしまいます。
また、自分のダメな部分にばかり目が向いてしまうため、自分を責めてしまう傾向にもあるのです。
このような原因から、完璧主義の人はメンタルを壊しやすく、うつになりやすいと言えるでしょう。
【まとめ】完璧主義を辞めたいなら自分を認めてあげよう
完璧主義を辞めるには、自分を認めてあげることが大切です。
できないことに目を向けるのではなく、今までにできたことや挑戦した気持ちなどに目を向けることで、少しずつポジティブな気持ちを感じられるようになります。
これまでの考え方を変えることは簡単なことではありませんが、できることから少しずつ取り組んでみてください。
あなたの寄付が幸せを紡ぐ。自分をも幸せにする「誰かのために」【Editor’s Letter vol.07】

Humming編集長 永野舞麻がカリフォルニアから配信する「Editor’s Letter 」。日々の暮らしで感じた気付きや、人生において大切にしていることを綴っています。
毎月欠かさず行っているとある団体への寄付。
その行動がどのように誰かの未来を変えているのか、その真実を自らの目で見るために、私はインドのバラナシへと向かいました。
世界では推定5000万人が、強制労働や性的搾取など、奴隷制の犠牲になっている現実を知っていますか?
(※参考:現代奴隷制の世界推計)
特にインドでは、貧困や社会的な格差が奴隷問題を助長し、多くの人々が過酷な状況下で働かざるを得ない現実があります。
私は今回インドで人々が奴隷から解放される瞬間を目の当たりにしました。自由を手に入れたことで、人々の目には輝きが戻ったのです。
自分の寄付が誰かの笑顔に繋がることを体感し、私自身も大きな幸せを感じることができました。
寄付したお金の行先とは?!奴隷解放の瞬間を目にしたインドへの訪問

2023年10月、定期的に寄付を行っているとある団体からの声がけで、奴隷解放を後押しするためにインドのバラナシに向かいました。
私が訪れた村々には劣悪な環境で地主に仕えて働く、いわゆる奴隷がたくさんいました。
村の人々は土の上に建てられた木造の家で、ハンモックのようにロープをはったベッドで寝ています。
電気も通っていないので、明かりは焚き火のみ。
食事も牛の糞を固めて乾かしたものを燃やして作り、水は井戸から汲み上げられたものを使います。
お金は1週間の給付金が地主からもらえますが、それもほんのわずか。
幼い頃からずっとまともに栄養を摂れないため、大人であっても背が低く、痩せ細っている。
いつ生まれたのか出生証明書がないので年齢は不明。また、誰との間に授かったかわからない赤ちゃんを抱っこしている女の子もいました。
私はそこで、6ヶ月前までは地主に仕えて苦しんでいたひとりの女の子に出会いました。
どうして奴隷になってしまったのか、そして何がきっかけとなり奴隷から解放されたのか、話を聞くことができました。
彼女はとある村で家族と貧しい暮らしをしていました。
ある日「良い仕事があるよ」と言われ、その人を信じて家族で村から200キロも離れた場所に連れて行かれたのです。
もちろん良い仕事があるというのは全くの嘘。奴隷にするための口実でした。
そこでは、ご飯をろくに食べられなかったり、作ったご飯を蹴り飛ばされるなどの嫌がらせをされたり、意味もなく夜中に叩き起こされたりしました。
ひどい環境の中で長時間休みなく働くことを強いられていました。
そんな環境に耐えられなくなり、ある晩、意を決して家族でその村から逃げ出したのです。しかし、途中で彼女とお姉さん以外は地主に捕えられてしまいました。
家族を助けるためにも彼女たちは必死で逃げました。そして、その途中に奴隷解放に力を注いでいる慈善団体のメンバーに出会ったのです。
彼女たちは微かな望みをかけてその団体に「家族を救って欲しい」と助けを求めました。とはいえ、団体は彼女たちがどの村に住んでいたのかすらわかりません。
1ヶ月ほどかけて事実確認のための調査を行い、場所を特定して彼女たちが奴隷にされていた村を訪れました。
そこで目にしたのは、狭い一室に閉じ込められていた彼女の家族でした。
地主から「奥さんを連れ戻さなければ生き埋めにしてやる」と脅され、部屋の外には生き埋めにするための穴が掘られていました。
助けに行くのがあと少し遅れていたら、きっと彼女の夫や両親は殺されていたことでしょう。
彼女が地主から逃げ、勇気を持って自分たちが置かれている状況を団体に話したことで、彼女の家族は地主から解放されることができました。
今では、国からお金を借りて畑を耕し、育てた野菜を市場で売ったり、イケアなどで販売しているようなジュートのマットなどを作って、企業に買い取ってもらったりしています。
彼女達は、自分たちで生活費を稼ぎながら自由を手にして暮らしています。
自分の現状を知ることの大切さ
「どうして警察に助けを求めないのか?」、疑問に思う方がいるかもしれません。
インドではカースト制度の考えが根強く残っています。
そのため、カーストが低い人たちは、自分よりもカーストが上の人たちと話をすれば痛めつけられるかもしれない恐怖に怯えているのです。
さらには、メディアに触れる機会がないため、自分たちが地主からされていることが違法行為であることさえ知りません。
現地の奴隷解放運動をしている人たちに話を聞くと、最初は彼らを助けるために村を訪れても口を聞いてくれないと言います。
学校を建てて、子どもたちのお昼ご飯を食べられるようにしてあげるから、子どもを学校に送るようにと、まず説得します。
そして「私たちはあなたを傷つけるようなことはしない」と信頼してもらえてようやく話をしてくれるようになると。
「奴隷制度が違法であること」、「あなた達がこんなひどい扱いを受けるのは当たり前ではないこと」、「自分たちで地主に今の状況から解放するように訴えられること」
「警察に助けを求められること」を彼らに伝えていきます。
そうすることで、奴隷として生きていた彼らは自らの力で「もう、正当な賃金なしでは働かない」と地主に訴え、奴隷から解放されていくのです。
毎月の寄付は誰かの人生を変えている
私は、人々が奴隷から解放される瞬間を目の当たりにし、毎月の寄付が誰かの人生を変えるきっかけになれていることを、自分の目で確認することができました。
出会った時は、ひどい環境下での労働を強いられ、絶望に満ちた目をしていたひとりの女の子。
自由を手に入れてからは明らかに表情が明るくなり、まるで希望の光が照らしているかのように目が輝いていたのです。
どんなに絶望の中にいても人は希望を取り戻せる。生命の強さを感じずにはいられませんでした。
辛い環境で生きる人々に手を差し伸べることができて、本当に良かったと心から感じています。

「誰かのため」は自分さえも幸せにする
日本ファンドレイジング協会が発行する寄付白書2021によると、2020年時点での日本の個人寄付総額は「1兆2,126億円」。10年前と比べると2.5倍ほど増加しているものの、同年のアメリカの寄付額(34兆5,948億円)と比べると30分の1ほどです。
また、イギリスの慈善団体「チャリティーズ・エイド・ファンデーション(CAF)」の2022年の調査では、日本の「世界人助け指数」は119ヵ国中118位。宗教的な背景や税制上の待遇などが要因となり、寄付文化が他国に比べて根付いていない状況と言えるでしょう。
人は「他の人が幸せになることを望む生き物」です。自分のために鞄を買ったり、美味しい食事を味わったり、もちろんそれも自分にとっての幸せです。
しかし、利己的なことだけで幸せを感じ続けるには限界があるものです。
利他性と幸福度の関係にまつわるさまざまな実験や研究が、世界中で行われています。
お金を自分のために使った人と、他人のために使った人とでは、後者の方が明らかに幸福度が高いといった研究結果も出ています。
あなたが自分以外に関心を寄せるものは何ですか?たとえば、子ども、動物、医療、環境保全、災害・復興支援など。
自分の関心を探り、今の自分にできる範囲で寄付やボランティアを始めてみるのもおすすめです。
誰かのためにとる行動は、自分自身を幸せにする近道なのです。
関連記事:クリック募金とは?動物や環境に関係する募金サイトまとめ
ヴィパッサナー瞑想リトリート体験談。リトリート中に感じた恐怖体験とその後の変化とは【Editor’s Letter vol.06】
Humming編集長 永野舞麻がカリフォルニアから配信する「Editor’s Letter 」。日々の暮らしで感じた気付きや、人生において大切にしていることを綴っています。
ある日の深夜、全身の皮膚が毛羽立つような恐怖に襲われました。
真夜中、突然のサイレンに驚いて起き上がると、ビービービーと大きな音が鳴り響いているのです。
「どこかで核爆発が起きたに違いない……」
これまで感じたことのない不安や恐怖心が押し寄せてきました。
けれど、周りを見渡すと部屋の外は静まりかえっている。なんと、サイレンは自分の耳の中だけで鳴り響いていたのです。
忘れもしないこの体験は、ヴィパッサナーリトリート8日目の出来事。
これは今まで心の奥底に溜めた気持ちが浄化され、穏やかな心に近づくための通過点だったのです。

観察することで変革を起こすヴィパッサナーとは?
ヴィパッサナーとは、2500 年以上前にゴーダマ・ブッダによって再発見されたメディテーション法。
感覚や呼吸に集中し、その瞬間のありのままの自分を観察することで、不安、怒り、嫉妬、執着、悲しみなどのあらゆる心の濁りを取り除き、浄化を図ります。
穏やかで充実した人生を築くための手段として、ヴィパッサナーは世界中で受け入れられています。
※詳細はこちら
なぜリトリートに参加しようと思ったのか

私がメディテーションを始めたのは、今から3年ほど前、世界的なパンデミックが起こりはじめた頃。当時は1回20分のマントラ瞑想を朝と午後の1日2回行っていました。
自宅でメディテーションをしていると、家族が話しかけてきたり、子どもが膝に座ってきたり、兄弟喧嘩がはじまったり、そういう状況の中でもメディテーションを続けるのが、ある意味与えられた試練だとはわかっていても、100%自分の内と向き合うことはなかなか難しい。自分だけの時間をしっかりと確保して、本格的にメディテーションを体験してみたいという想いが日に日に募っていきました。
そこで興味を持ったのが、数あるメディテーションの中でも特に厳しいと噂のヴィパッサナー。
ヴィパッサナーの合宿に参加することで何が得られるのかあえて深くは調べないまま、自宅から3時間半ほど車を走らせ、北カリフォルニアのヴィパッサナーセンターへ向かいました。
※ヴィパッサナー瞑想の合宿は世界各国で開催されており、日本では京都と千葉に合宿センターがあります。
他者との会話やアイコンタクトさえも禁止される、自分と向き合う10日間
合宿期間は10日間。いただく食事は朝昼2回の菜食と夕方にフルーツやお茶をほんの少し。毎朝4時に起床し、休憩を挟みながら1日10時間以上メディテーションを行います。
合宿期間は外の世界との接触は完全に遮断され、もちろんスマートフォンやテレビなどデジタルの使用は禁止。さらには人と会話することや誰かと目を合わせること、メモを書くこと、本を読むことさえも許されません。
最初の3日間は、鼻の周りの感覚を研ぎ澄ませて呼吸に意識を向けるアーナパーナというメティテーションをひたすら行い、自分の内と向き合う訓練をします。
4日目に、ついに、全身の感覚に意識を張り巡らせるヴィパッサナーに移ります。まずは鼻まわりからスタートし、頭から顔の各パーツ、肩、腕、手、胸、背中、腹、脚と体全体を1つ1つスキャンするように意識を集中させ、空気の重みや服に触れている感触、脈を打つタイミングを感じていきます。
さらにメディテーション中に絶対に動いてはいけない時間が1回1時間、1日に3回あります。ストロングメディテーションと呼ばれているその時間中は、どんなに体が痛くなっても、鼻がかゆくなっても動いてはいけません。慣れるまでは辛い時間ですが、これを行うことで痛みやかゆみなどの不快な感覚も現れては消える、「世の中に起こる全てのことは永遠には続かない」という感覚を体感し、どんな時でも心の平静さを保つ訓練ができるのです。

メディテーション中に突如現れた幼少期のトラウマ
合宿中、自分の全身の繊細な感覚と真剣に向き合うことで、過去に蓄積された身体や心の中のネガティブな要素が変容し、何かしらの形で現れることがあります。
4日目のメディテーション中のこと。幼少期のトラウマが突如私の心に現れ不意に涙が溢れたのです。
この日から始まったヴィパッサナー瞑想。決められた一定の時間は絶対に動いてはいけないにも関わらず、隣の方は体を掻いたり、寝息を立てていたり。
「私を含め、周りのみんなはこんなに頑張ってメディテーションしているのに、どうしてこの人は…」、ネガティブな感情が沸き起こりました。
不思議なことに、そのイラつきが私の幼少期の記憶と結びつき、当時から内に秘めていた想い、悲しみ、願望、様々な気持ちが現れたのです。
私には3歳年の離れた妹がいます。幼い頃、私は両親に褒めてもらいたくて懸命に家の手伝いをしたり、駄々をこねずに言われたことをきちんとこなしたり、わがままを言わずに欲しいものを我慢をしたり、愛されたい一心でいました。一方で、妹はニコニコ、そこにいるだけで親から愛情を注がれる。
「私だって、ありのままの私を愛して欲しかった……」
そんな素直な心の内がメディテーション中に自然と湧き起こり、涙が止まらなくなりました。
これまでアメリカに移住してから何年もセラピーに通い、たくさんの幼少期の親子関係、姉妹関係のトラウマを掘り返しては癒してきていたので、未だに、こんなにも鮮明な気持ちが現れたことに驚きを隠せませんでした。
合宿中は辛い記憶が蘇ったり、得体の知れない恐怖に襲われたりすることもありました。しかし、最終日には「もう少しこのメディテーションリトリートを続けていたい」そんな気持ちになっていたのです。
リトリート後に満ちた愛情と優しさ
10日間のリトリートを終えて家に帰ると、こんなに誰かを愛おしいと思ったのは初めてではないかというほどの「ピュアな愛」が自分から溢れ出ているのを感じました。
家族との会話。一緒に味わう食事。全てが愛おしい。まるで自分の周りの空気全体が愛のベールとなり家族を包み込んでいるような感覚です。
以前だったらイライラしてしまったような子どもたちや夫とのやりとりの瞬間も、イラつきどころか逆に愛を持った接し方ができたり、ただ抱きしめているだけなのに涙が溢れてくるような愛情を感じたり。
さらにリトリートを終えて1週間ほどは、自然と自分の呼吸に意識が向けられ、目を開けたままメディテーションしている状態が続いたのです。イメージとしては、大嵐で海は大荒れなのに、その中を静かに進む船のように落ち着いた気持ちで過ごすことができました。
この不思議な感覚は徐々に薄れていきましたが、あの感覚は今でも忘れることはありません。
ヴィパッサナー瞑想リトリートの10日間は、まるで人生の縮図
人生において全ては永遠には続かない。痛みも苦しみも、もちろん幸せも。だからこそ、今この瞬間を存分に感じよう。そのような気づきを私にもたらしてくれたヴィパッサナー。
普段、私たちは脳からの情報や声に振り回され、落ち込んだり、怒ったり、幸せを感じたり、良くも悪くも感情に左右されがちです。
メディテーションを通じて、呼吸や感覚に意識を集中し、脳から送られる過多な情報を一旦遮断する。それによって物事がより鮮明に見え、エネルギーを本当に大切なものだけに注ぎ込むことができるようになることを体感できました。
幸せは案外身近にあって、今を感じることから生まれてくるのかもしれません。物事の見方、捉え方が変われば人生が変わる。それを教えてくれた貴重な10日間でした。
新しい感覚や目線で自分の人生を味わいたい方には、ヴィパッサナーは大きなヒントや変わるきっかけを与えてくれるでしょう。
悲しいニュースからあなたの心を守るためのマインドフルネス

あなたは普段、テレビやネットのニュースをどれくらいチェックしていますか?
最近では楽しい話題よりも、戦争や人道的な災難などの悲しい出来事が目立つように感じませんか?
こうした悲しいニュースを続けて見ることが、あなたにどのような影響を与えているでしょうか。
世界の動向を追いながらも、心の負担を軽減する方法について、アメリカでも議論が交わされています。
今回は、アメリカでかかれた記事を参考にして、どのように対処できるかをご紹介します。
ひどいニュースに心が張り裂ける日々
10月にイスラエルとハマスの戦争のニュースが流れ始めると、私はスマートフォンにくぎづけになりました。
次から次へと報道されるニュース記事を読みながら私は泣いていました。
誘拐されたり殺されたりした人たちの記事を読むたび、被害者が誰かの子どもであることを思い、その子の母親が今どうしているかを想像して泣いていたのです。
残念なことに、この重苦しさは、たまにだけ押し寄せる感情ではないのです。
学校での銃乱射事件であれ、自然災害であれ、戦争であれ、私たち人間の体験には、心が痛む瞬間があまりにも多いのです。
そして、こういうニュースによって、私たちは恐怖や不安、そして悲しみにおしつぶされそうになります。
ニュースを読むのをやめればいいのにと思いながら、世界で起きていることをしっかりと知っておきたい自分と葛藤をしています。
そんな私が一番疑問に感じていることは、マインドフルネスの観点です。
悲劇的な出来事が起こるとすぐにSNSなどで多くの情報を収集できる時代です。
そういった出来事にしっかりと目を向けることと、自分の心を守ることのバランスをどう取ればよいのでしょう。
そこで、臨床心理学者であり、セルフ・コンパッションの専門家でもあるテクラ・ブランダー・ロス(以後、テクラ博士)に聞いてみました。
悲しみを理解する
ニュースによって感じる恐怖、悲しみ、不安などの感情と向き合い、それを乗り越えるためには、この感情の性質を理解することが重要だとテクラ博士は指摘します。
ニュース記事を読んで感じる悲しみは、博士によれば「私たちの世界で起きている痛みや苦しみ全てに対する悲しみです。
こういう悲しみにどう対処するかの訓練を学校で受けた人はほとんどいないでしょう」。
しかし、自分の家族や友人がそのニュースの悲劇の影響を受けていないなら、私たちは誰のことを思って悲しんでいるのでしょう?
テクラ博士は苦しみを比較しないようにと念を押します。
「人と比較するのではなく、出来事をしっかりと認識することに努めましょう」と博士は言います。
誘拐された子どもの記事を読んで、その母親のことを思って悲しまずにいられないはずはありません。
自分の子どもが今どこにいるのかわからない苦悩を、想像せずにはいられません。
私が直接に体験していなくても、ニュースで読んだ事件の当事者について感情を強く揺さぶられることは普通でしょう。
どれだけニュースを摂取しているかに気づく
自分がニュースの第三者として行動することで「洞察力と気づき」を意識することができます。
テクラ博士によれば、洞察力と気づきは、幸福のために大切な2つのポイントであり、自分の人生にもっと積極的に参加するために大切なものです。
テクラ博士は、ニュースを読むのを止めるのではなく、私たちのニュースの消費のしかたにもっと気を配るようにと提案します。
あなたがニュースを見る前に、こういった質問を自分に投げかけてみましょう。
- あなたは今、新しい一日を始めるために目を開けたばかりですか?
- あなたは今、心身を休めるために目を閉じたばかりですか?
- あなたは今、仕事中であり、ストレスを感じていますか?
- あなたは今、身体が緊張したり、不快に感じたりしていませんか?
もしこれらの質問のどれかに「はい」と答えたなら、それは今、辛いニュースを見るのに最適なタイミングではないかもしれません。

立ち止まってみる
いったん立ち止まる、つまり今がニュースを見るタイミングではないと判断するという考えは、ただの自己満足に過ぎないと思う人もいるかもしれません。
これに対してテクラ博士は「世間では思いやりの気持ちを持つことが、ただの自己満足だという誤解があります。
しかし、自分と他者への思いやりとは、今この瞬間に感じていることにしっかりと気づいて、優しさや愛を表現することでもあります」。
私たちのように立ち止まる選択肢すらもない人が、この世界にはたくさんいることにも注意をしてみましょう。
何世紀にもわたる抑圧、不正、暴力の中を生きている人々にとって、ニュースは直接彼らの身に迫る脅威を示しています。
テクラ博士はこうアドバイスします。
「今度ニュースを見て、悲しんだり、怒りがこみあげてきた時には、いったん立ち止まり、その時の自分の感情を観察してください。
その痛みがどのように自分の身体に感じられるかに意識を向け、その痛みを感じるのは自分だけではないこと。
そして、その痛み自体もすぐに変化することを、自分に言い聞かせましょう」。
博士はまた、感情をコントロールしようとすることは、天気をコントロールしようとすることと同じだと指摘します。
「自分の経験をコントロールしたり否定したりするより、思いやりの気持ちを持って起きている事実をそのまま受け止めてみましょう」。
写真やビデオのない記事にとどめる
臨床心理学者でハーバード医学部の教授でもあるスパーリング氏は、音声や映像が非常にダイレクトに私たちの心に訴えるものであると強調します。
「誰かが苦しんでいるのを見たり聞いたりすることは、あなたの精神にダメージを与えます」。
写真や動画のないニュース記事のほうが、読者へのインパクトという観点では、より親しみやすいでしょう。
また、教授はニュースを見る回数を意識して制限することを勧めています。
ニュースを見る時間をあらかじめ決めておくことで、ネガティブな内容のニュースを見続けることを避けられるとスパーリング氏は言います。
マインドフルネスのためのシンプルな方法
見るのがつらいニュースを目にした時、なぜそのニュースを見ているのかを意識することも忘れないでください。
記事や動画をクリックする前に一度立ち止まって、テクラ博士がこれから提案する、マインドフルに前進するための方法を考えてみましょう。
まず、ニュースを見る前に、あなたがこれ以上の苦しみを受け入れることができる状態か自問してください。
もし苦しみを受け入れる余裕がないなら、どうすればその苦しみを認めることができるか、どうすれば自分にもっと優しくなれるか、どうすれば今この瞬間に仲間とつながることができるかを考えてみましょう。
つらいニュースを読みながら、両手を心臓に持っていき、今までトラウマになった体験を認めましょう。
地上とつながる(グラウンディング)ための呼吸をし、そのニュースを見て感じる悲しみをより深く認識しましょう。
ここで可能なら、身体を休めてください。他人の苦しみに寄り添う前に、自分自身をいたわってあげることを忘れないでください。
「私だって完璧ではないです。あなたはニュースを読むべきでない、なんて私が言う権利はありません。
大切なことは、いつ、どのようにして、あなたがニュースを消費しているかということです」とテクラ博士。
日々、あなたがどうやってニュースを見ているかにもっと意識を向けることで、心がおしつぶされるようなニュースへの反応を自分でコントロールできるでしょう。
例えば、朝起きてベッドに寝転がりながらスマートフォンに届いたニュースを見る前に、深呼吸をしてみましょう。
そしてあなたがニュースを読む準備ができているかどうかを自問する、そんな簡単なことからできるのです。
そして、その答えが「いいえ」である人がとても多いのです。
残念ながら、恐ろしいニュースはすぐにはこの世界から無くならないでしょう。
しかし、私たちがニュースをどうやって受け入れるかについてもっと意識することで、私たち自身や仲間をサポートすることができるでしょう。
※関連リンク:この記事はThe Good Tradeの英語版をはじめ、別の英語の記事を参照しています。各出典に対するリンクは以下になります。
ストレスマネジメントとは?やり方や具体例を紹介

人間関係の悩みや仕事のノルマ、病気やケガなど、私たちが生活していくうえではさまざまなストレスを感じることが多いものです。
ストレスとは無縁の生活は理想ともいえますが、現実的に考えて一切のストレスを排除することは難しいのも事実です。
そこでぜひ実践していただきたいのが、ストレスと上手に付き合うためのストレスマネジメントです。本記事ではストレスマネジメントについて、やり方や具体例を紹介します。
ストレスマネジメントとは?

ストレスマネジメントとは、ストレスをうまく処理しながら付き合っていくことを指します。
私たちが社会生活を送るうえでは、仕事のプレッシャーや人間関係、家族・親族関係、子育てなど、さまざまなストレスが存在します。
あまりにも強いストレスがかかり続けると、メンタルの不調をきたしたりさまざまな病気の発症リスクが高まるといった問題が生じますが、一切のストレスから開放された生活を送るのは現実的に考えて難しいものです。
そこで、ストレスと上手に付き合っていくストレスマネジメントを理解し、実践することが求められるのです。
▶︎【ストレス解消】セルフケアとはなにか?意味・種類・方法について解説
人間がストレスを感じる仕組みや理由
ストレスマネジメントを実践するためには、そもそもなぜ人間はストレスを感じるのか、基本的なメカニズムを理解しておく必要があります。
ストレスとは、一言でいえば「ストレッサーが原因で引き起こされる心身のストレス反応」と表現できます。
ストレッサーとはストレスを引き起こす根本原因のことであり、それによって引き起こされるストレス反応もさまざまです。
主に以下のような種類に分けられます。
身体的ストレッサー
- 睡眠不足
- 身体の不調 など
心理・社会的ストレッサー
- 職場やプライベートの人間関係
- 残業
- 通勤
- 仕事のノルマ など
物理的ストレッサー
- 気温・湿度
- 明るさ
- 騒音
- 悪臭 など
科学的ストレッサー
- タバコ
- アルコール
- 薬物 など
環境的ストレッサー
- 天候
- ウイルス
- 花粉 など
また、主なストレス反応は以下に分類できます。
身体的反応
- 動悸
- めまい
- 不眠
- 食欲不振
- 頭痛
- 疲労感 など
心理的反応
- うつ
- 不安
- イライラ
- 集中力低下
- 物忘れ
- うっかりミスの多発 など
行動的反応
- 暴飲暴食
- 喫煙量の増加
- 暴言・暴力
- 性欲減退
- 生産性の低下 など
ストレスマネジメントとアンガーマネジメントの違い

心理学において「◯◯マネジメント」とよばれる概念は複数あります。そのなかでも、ストレスマネジメントと並んで耳にすることの多いのがアンガーマネジメントです。
アンガー(anger)とは日本語で「怒り」を意味する言葉であり、アンガーマネジメントとは怒りの感情を適切にコントロールする概念や手法を指します。
アンガーマネジメントと聞くと怒らないための方法と誤解されることが多いですが、あくまでも怒りをコントロールしながらうまく付き合っていくことを目的としています。
ストレスマネジメントもストレスをなくすものではなく、上手に付き合っていくための概念であることから、両者は似ている部分もあるといえるでしょう。
ただし、上記でも説明した通り、ストレスマネジメントは「ストレス」に対して、アンガーマネジメントは「怒り」という感情を対象としている点が決定的に異なります。
▶︎【怒りを抑える】アンガーマネジメントのやり方・テクニックをご紹介!
ストレスマネジメントを行う効果やメリット

ストレスマネジメントを実践することで、どういった効果が得られるのでしょうか。また、それによるメリットもあわせて解説します。
自分の状態を客観的に把握できる
毎日仕事をこなしていると、忙しさのあまり自分にストレスがかかっていることに気付かない人もいます。
ストレスマネジメントを行うことで自分を客観的に分析でき、ストレスの状態やその原因などが分かり、自身の生活を見つめ直すきっかけになるでしょう。
心身の健康を保てる
日々の生活のなかで大きなストレスがかかり続けていると、それが原因で心身に不調をきたすこともあります。
ストレスマネジメントに取り組むことで、心身に不調をきたす前の段階で適切な対処ができ、精神疾患や病気などのリスクを未然に防げるでしょう。
仕事の生産性やパフォーマンス低下を防げる
ストレスに気付かない状態のまま、あるいはストレスを我慢し続けた状態で仕事を続けていると、パフォーマンスが低下し本来の能力を発揮できないこともあります。
その結果、生産性が低下したり、ケアレスミスを連発して周囲に迷惑をかけたりすることもあるでしょう。
ストレスマネジメントを実践すれば、ストレスとうまく付き合いながら仕事をこなすことができ、生産性やパフォーマンスの低下を防止できます。
▶︎ストレスを発散させるメリットとは?解消方法と合わせてご紹介!
ストレスマネジメントの具体例

ストレスマネジメントは仕事やプライベートなど幅広いシーンで役立ちます。いくつか具体例をご紹介しましょう。
職場
ノルマや締め切り、プロジェクトの進行、職場の人間関係など、どのような職種であっても少なからずストレスは存在するものです。
ストレスマネジメントを実践することで、大きな目標やプレッシャーがかかるなかでもストレスとうまく付き合いながら業務を遂行でき、社内あるいは取引先などからも信頼を得られるでしょう。
恋愛
恋愛においては、交際中の相手と価値観や考え方が異なることでストレスを感じたり、交際そのものが長続きせず自己嫌悪に陥ったりすることもあるでしょう。
ストレスマネジメントを実践することで、相手の立場に立って物事を考えられるようになったり、相手と真正面から向き合うことでお互いを深く知る機会にもなります。
夫婦喧嘩
結婚して夫婦として生活をともにしていくと、恋愛とは別のストレスを感じることもあります。
たとえば、家事や育児などの役割分担を決めたとしても、相手のやり方や分担の割合などに不満を感じストレスになることもあるでしょう。そのような不満が蓄積していくと、やがて爆発し、夫婦喧嘩に発展する可能性があります。
夫婦でストレスマネジメントを実践することで、お互いにストレスが蓄積する前に話し合いながら不満を解消し、円満な関係を維持できるでしょう。
▶︎夫婦喧嘩をしたときに仲直りする方法は?子供への悪影響も解説
ストレスマネジメントのやり方
ストレスマネジメントは大きく分けて「セルフモニタリング」と「ストレスコーピング」という2つの方法があります。
それぞれの実践方法をご紹介しましょう。
セルフモニタリング
セルフモニタリングとは、自分自身の状況を客観的に把握する方法です。
- ストレッサーと感じるモノ・コト
- ストレスが生じたときに自分がどう感じているか
- ストレッサーによってどのようなストレス反応が出ているか
上記の項目をそれぞれ紙に書き出し整理することで、ストレッサーを明確化すると同時にどのようなストレス反応が現れているかを把握できます。
ストレスコーピング
ストレスコーピングとは、ストレッサーへ適切に対処することでストレス反応や負担を軽減する方法です。
【問題焦点型コーピング】
仕事のプレッシャーや残業などがストレッサーとなっている場合には、問題焦点型コーピングが有効です。
仕事量の調整や応援の要請など、問題に対して具体的な解決法・対策を立てていきます。
【情動焦点型コーピング】
起こっている問題そのものに対してではなく、自身の考え方や捉え方、気持ちなどを変えることで負担を軽減する方法です。
マイナスの側面ばかりでなくプラスの側面を注視したり、第三者へ相談に乗ってもらい不安や悩みを吐き出すといった行動が情動焦点型コーピングにあたります。
【ストレス解消(発散)型コーピング】
ストレス解消(発散)型コーピングは、その名の通り自分なりの方法でストレスを解消し、身体的な不調や心理的な負担を軽減する方法です。
睡眠や休養はもちろんのこと、運動やマッサージ、エステ、趣味を楽しむといった行為が代表的です。
▶︎仕事でストレスを感じたらやばい?原因や解消方法をご紹介!
まとめ
現代人にとってストレスとは無縁の生活を送るのは難しく、仕事やプライベートにかかわらずさまざまなストレスと付き合っていかなくてはなりません。
ストレスの感じ方も人それぞれで、なかにはストレスがかかっているのにそれに気付かないまま過ごしているケースもあるでしょう。
ストレスと上手に付き合いながら、仕事やプライベートを充実させるためにはストレスマネジメントを実践するのも有効です。
セルフコンパッションとは?やり方やマインドフルネスとの違いを解説
仕事で失敗をしたり、人間関係がうまくいかなかったりすると、必要以上に深刻に捉えてしまうことはないでしょうか。
そんな悩みを解消するための方法として、ありのままの自分を受け入れながら自身に対して思いやりの心を向ける「セルフコンパッション」という考え方があります。
本記事では、セルフコンパッションを実践するうえでのポイントやトレーニング方法、混同しがちなマインドフルネスとの違いについても解説します。
セルフコンパッションとはどんな意味?

コンパッション(compassion)とは、日本語に直訳すると「思いやり」や「慈悲」、「同情」といった意味を表す言葉です。
すなわち、セルフコンパッションとは、他人に対して思いやりや慈悲の心をもつように、自分自身に対しても同じような心を向け、大切にすることを指します。
セルフコンパッションの構成要素
セルフコンパッションを実践するためには、以下に示す3つの構成要素が重要です。
自己親切
自己親切とはその名の通り、自分自身に対して優しい心をもち、理解・肯定することです。
失敗や困難な状況に直面したときでも、自分自身を批判したり否定したりするのではなく、肯定的・前向きに捉えることが自己親切であり、セルフコンパッションの実践につながっていきます。
共有の人間性
共有の人間性とは、自分も含めて誰しも完璧な存在ではなく、必ず失敗したり困難を経験したりするという認識です。
「こんな失敗やミスをしているのは自分だけだ=自分はダメな人間だ」と捉えるのではなく、誰しも一度は大きな失敗をするものであり、多くの人が共通して経験するものであると理解することは、セルフコンパッションの実践にあたって重要なポイントです。
マインドフルネス
マインドフルネスとは、自分自身の感情や経験を現実的にとらえ、ありのままの事実として受け入れたうえでストレスを低減する方法です。
辛いことがあると現実から逃げたくなり、無理に忘れようとする方も多いですが、そのような行為が反対に混乱を招くこともあります。
マインドフルネスを実践することにより、冷静に現実を受け入れ自分自身を肯定する第一歩となります。
▶︎友達の作り方|場所と手順を社会人から学生ごとに分けて解説!
セルフコンパッションの効果・メリット

セルフコンパッションを実践することにより、私たちの日常生活においてどのような効果やメリットが得られるのでしょうか。
3つのポイントをもとに解説します。
自尊心や幸福度の向上
セルフコンパッションを実践することにより、抑うつや不安の症状を軽減し、生活の満足度を高めることができます。
その結果、自尊心や幸福感を向上させ、精神的な健康を手に入れ充実した生活を送ることができるでしょう。
精神的ダメージからの早期回復を促す
私たちは生きていく以上、さまざまな困難に直面することがあります。
しかし、あまりにもショックな出来事が起こってしまうと、精神的な回復に時間を要し日常生活に戻れなくなることも少なくありません。
セルフコンパッションを実践できれば、自分自身に対する優しさと理解を示すことにより、困難や挫折を乗り越える力が増します。
自己啓発と成長を促す
自分自身に対して批判や否定的な考えをもっていると、成長や変化の機会があったとしても「どうせ自分には無理だ」、「自分は変われない」と感じてしまいがちです。
しかし、セルフコンパッションを実践できていれば、自分自身の失敗や欠点に対しても優しさや理解を示すことができ、自己改善に向けた動機付けにもなります。
セルフコンパッションが重要視される理由
セルフコンパッションはもともと心理学の分野で使われていた言葉でしたが、近年になってビジネス分野や一般社会にも広まりを見せています。
なぜセルフコンパッションは注目され、重要視されるようになったのでしょうか。
仕事のストレス
ビジネスの社会では競争が厳しく、慢性的なストレスを感じることが少なくありません。
目標やノルマ達成のプレッシャーはもちろん、時間的な制約や職場の人間関係など、さまざまな要素がストレスの原因となります。
セルフコンパッションを実践できれば、これらのストレスを和らげ、万が一失敗やミスをしたとしても受け入れ、自己批判を減らすことができます。
同時に、仕事や職場に対する満足度を高めたり、良好な人間関係の構築にも役立つでしょう。
私生活のストレス
私生活においても自己批判に陥ることが少なくありません。
考えられる要因は自分の容姿や能力、人間関係、ライフスタイルなど多岐にわたり、自尊心と幸福感を低下させることがあります。
セルフコンパッションを実践することにより、私生活の面でも自己批判から解放され、自己価値感と幸福感を高めることができるでしょう。
将来への不安
激動の社会において、雇用環境の変化や経済状況、自分自身のキャリアなど、将来に対する不安を抱く方も少なくありません。
また、このような社会情勢に起因した悩みだけでなく、自分自身の健康や家族の幸せなどがストレスの原因になることもあるでしょう。
セルフコンパッションは、これらの不安を和らげるためにも重要であり、将来への不確実性を受け入れ、その上で現状を最善に生きるための原動力となります。
▶︎【シーン別】人間関係がめんどくさいと感じる心理や対処法を解説
セルフコンパッションとマインドフルネスの違い
セルフコンパッションを構成する要素のひとつとしてマインドフルネスを紹介しましたが、厳密にいえば両者は異なる概念です。
セルフコンパッションとは、冒頭でも紹介した通り、自分自身に対して思いやりや慈悲の心を向け、大切にすることを指します。
自己批判や自己否定をするのではなく、精神的な健康を保つために自己認識や自己受容、自己愛を育んでいきます。
これに対してマインドフルネスとは、自分自身の感情や経験を現実的にとらえ、ありのままの事実として受け入れたうえでストレスを低減する方法を指します。
マインドフルネスはセルフコンパッションを実践するために重要なものであり、お互いに補完し合う関係にある存在といえるでしょう。
▶︎マインドフルネスをやってはいけない人の特徴|PTSDやうつ病の人は危険?
セルフコンパッションのやり方・トレーニング方法

実際にセルフコンパッションを実践するためには、どのようなトレーニングに取り組めば良いのでしょうか。
スージングタッチ
スージングタッチとは、自分自身の身体の一部を優しく触れたり、撫でたりするトレーニングです。
たとえば、胸を撫でる、手をお腹の上に置く、膝を両腕で抱え込む、頭を優しく撫でるといった行為が該当します。
さまざまな部位に触れてみながら、自分自身が安心し落ち着く方法を試してみましょう。
ボディスキャン
ボディスキャンとは、自分自身の身体に意識を集中させるトレーニングです。
具体的には、足や腕などの部位で末端から意識を集中させ、徐々に体幹に近づけていく方法が一般的です。
足の場合は、つま先から足首、すね、ふくらはぎ、膝、太もも、お尻といったように、身体の中心部に向けて意識を変えていきましょう。
慈悲の瞑想
もっとも手軽にできるトレーニングとして慈悲の瞑想があります。
具体的には、胸またはお腹に手を当てながら「自分自身が健康でありますように」、「悩みがなくなりますように」といった言葉を自分に語りかけます。
大きな失敗をしたり困難にぶつかったりしたとき、冷静な判断力を失ってしまうケースも少なくありません。
しかし、瞑想を習慣づけることで困難な状況に陥っても気持ちが楽になり、自分自身に対する否定的な考えを払拭できます。
▶︎感情の起伏が激しい人や少ない人の特徴|上手にコントロールする方法とは
セルフコンパッションを取り入れている企業の実例
セルフコンパッションは基本的に個人が行うものですが、従業員の生産性向上やストレス低減を目的として組織に取り入れている企業も存在します。
なかでも有名なのが、今や世界を代表するIT企業として成長したAppleです。
故スティーブ・ジョブズ氏は座禅や瞑想を習慣づけていたことでも有名ですが、Appleという会社としても従業員に瞑想を推奨し、セルフコンパッションのトレーニングを取り入れています。
▶︎知らず知らずに起こっている?ハラスメントの種類や防止方法を紹介
どんな人にセルフコンパッションは向いているのか
セルフコンパッションはあらゆる人にとって有効なトレーニングであり、取り組むことにデメリットはありません。
しかし、より高い効果を実感してもらうためにも、以下のような人に適しています。
- 自分自身に否定的な人
- 慢性的なストレスを抱えている人
- マネジメント職や経営者
特にマネジメント職や経営者は、仕事へのやりがいを感じる一方で担う責任も大きいため、バーンアウト(燃え尽き症候群)に陥る人も少なくありません。
セルフコンパッションを実践し自分自身を適切に管理することで、仕事へのモチベーションを維持しながら邁進することができます。
▶︎自己肯定感が低い人の原因とは|実はプライドが高い?親のせい?
まとめ
私たちが生活していくうえで、失敗をしたり困難にぶつかったりすることは必ずあるものです。
しかし、過度に失敗を恐れたり、困難を回避しようとすると成長が見込めなくなることもあるでしょう。
大切なのは、苦しい状況に陥っても前向きに捉え、立ち直る力を身につけることであり、そのためにもセルフコンパッションの実践は大切です。
メンタルヘルスマネジメント検定とは?日程や合格率を解説
ヘルスケア市場が大きくなっている「成長産業」であり市場規模の拡大が見込まれる業界です。
経済産業省 によると、ヘルスケア業界の市場規模(2017年調査)は、2016年は約25兆円、2020年は約28兆円、2025年には約33兆円になると推計されています。
参照元:M&Aベストパートナー
そんなヘルスケア市場の中、でも社会人にとって大きな影響をもたらす1つがメンタル面でのヘルスケアです。
社会人は職場ではさまざまな立場の人と一緒に働かなければならず、考え方や価値観の違いから人間関係がうまくいかないこともあります。
また、膨大な仕事に追われ、大きなストレスを感じている方も多いでしょう。
このようなメンタル面での不安や不調は仕事にも影響を与え、生産性の低下や休職・退職を余儀なくされることもあります。
そこでおすすめしたいのが、メンタルヘルスマネジメント検定とよばれる資格の取得です。
メンタルヘルスマネジメント検定とはどういった資格なのか、取得することで何に役立てられるのか、勉強のコツなども含めて詳しく解説します。
▶︎メンタル心理カウンセラーとは?資格を活かせる現場や学習内容も解説
メンタルヘルスマネジメント検定とは?
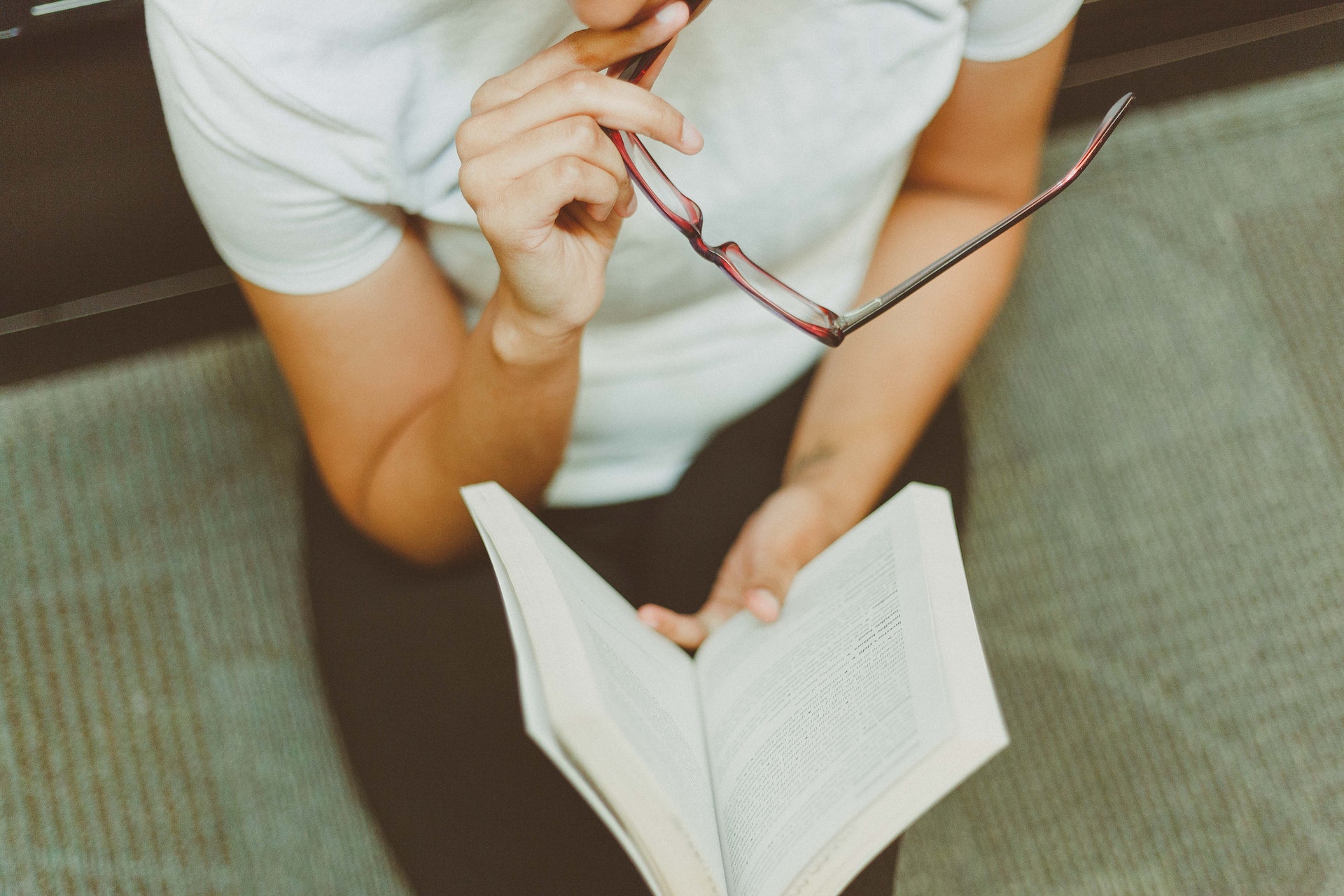
メンタルヘルスマネジメント検定とは、大阪商工会議所と施行商工会議所が主催している民間資格です。
労働者のメンタルケアを職場内で実践するために、必要な知識や正しい対処方法を習得することを目的に運用されています。
長引く不況によって経済的な問題を抱える人も多く、また、職場のストレスや人間関係の悩みなど、さまざまな要因が重なり心理的な不調を訴える人も少なくありません。
精神的なストレスや不安は仕事のパフォーマンスにも影響し、企業として生産性の低下を招くリスクもあることから、社員のメンタルヘルスケアは重要な取り組みといえるのです。
社員のメンタルケアを正しく実践するためにも、メンタルヘルスマネジメント検定を通して正しい知識を習得することが求められます。
メンタルヘルスマネジメント検定は全国15都市の指定会場で一斉に実施される公開試験と、企業や団体、学校などで受験日程を任意に設定し受験できる団体特別試験があります。
このうち、公開試験の試験概要は以下の通りです。
【主催】
- 大阪商工会議所・施行商工会議所(後援:日本商工会議所)
【受験資格】
- 学歴・年齢・性別・国籍を問わず誰でも受験可能
【受験料】
- Ⅰ種(マスターコース):11,550円(税込)
- Ⅱ種(ラインケアコース):7,480円(税込)
- Ⅲ種(セルフケアコース):5,280円(税込)
【2023年度の試験日程】
- 【終了】2023年11月5日(日):Ⅰ種(マスターコース)・Ⅱ種(ラインケアコース)・Ⅲ種(セルフケアコース)
- 2024年3月17日(日):Ⅱ種(ラインケアコース)・Ⅲ種(セルフケアコース)
【試験時間】
- Ⅰ種(マスターコース):前半(選択問題)2時間 後半(論述問題)1時間
- Ⅱ種(ラインケアコース):2時間
- Ⅲ種(セルフケアコース):2時間
なお、団体特別試験の場合はⅡ種・Ⅲ種のみが対象となり、受験料はⅡ種が5,980円、Ⅲ種が4,220円となっています。
メンタルヘルスマネジメント検定の3コース
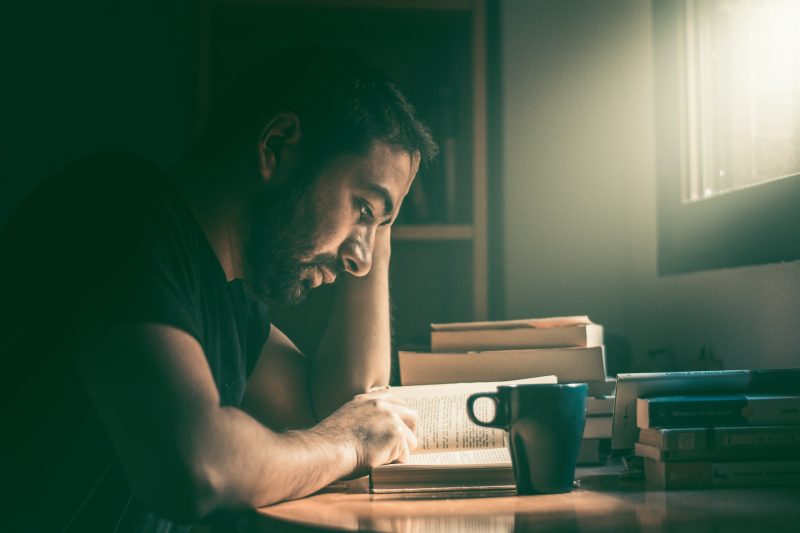
試験概要でも紹介した通り、メンタルヘルスマネジメント検定にはⅠ種(マスターコース)・Ⅱ種(ラインケアコース)・Ⅲ種(セルフケアコース)の3つのコースが用意されています。
それぞれの違いについて詳しく解説しましょう。
Ⅰ種(マスターコース)
Ⅰ種のマスターコースは、社内や組織内におけるメンタルヘルス対策を推進することを目的として、主に人事労務管理スタッフや経営幹部を対象に行われる試験です。
この試験に合格した場合の到達目標は以下のように設定されています。
- 「自社の人事戦略・方針を踏まえたうえで、メンタルヘルスケア計画、産業保健スタッフや他の専門機関との連携、従業員への教育・研修等に関する企画・立案・実施ができる。」
▶︎メンタルヘルスマネジメント検定試験の概要についてはこちら
Ⅱ種(ラインケアコース)
Ⅱ種のラインケアコースは、特定の部門内および、上司の立場から部下のメンタルヘルス対策を推進することを目的として、管理職やマネージャー、リーダーを対象に行われる試験です。
この試験に合格した場合の到達目標は以下のように設定されています。
- 「部下が不調に陥らないよう普段から配慮するとともに、部下に不調が見受けられた場合には安全配慮義務に則った対応を行うことができる。」
▶︎メンタルヘルスマネジメント検定試験の概要についてはこちら
Ⅲ種(セルフケアコース)
Ⅲ種のセルフケアコースは、社員が自分自身のメンタルヘルス対策を適切に推進するために、一般社員を対象に行われる試験です。
この試験に合格した場合の到達目標は以下のように設定されています。
- 「自らのストレスの状況・状態を把握することにより、不調に早期に気づき、自らケアを行い、必要であれば助けを求めることができる。」
▶︎メンタルヘルスマネジメント検定試験の概要についてはこちら
メンタルヘルスマネジメント検定の出題範囲
メンタルヘルスマネジメント検定は3つのコースが存在しますが、試験内容にはどのような違いがあるのでしょうか。
出題範囲や内容の違いについて詳しく紹介しましょう。
Ⅰ種(マスターコース)
Ⅰ種のマスターコースは、3つのコースのなかでも特に出題範囲が広く、以下の9項目が対象となっています。
- 企業経営におけるメンタルヘルス対策の意義と重要性
- メンタルヘルスケアの活動領域と人事労務部門の役割
- ストレスおよびメンタルヘルスに関する基礎知識
- 人事労務管理スタッフに求められる能力
- メンタルヘルスケアに関する方針と計画
- 産業保健スタッフ等の活用による心の健康管理の推進
- 相談体制の確立
- 教育研修
- 職場環境等の改善
いち従業員や管理職、リーダーという立場からではなく、経営者や人事として社内全体を俯瞰して考える必要があり、相談体制や教育研修、職場環境の改善といった内容も範囲に含まれます。
配点および合格基準は以下の通りです。
【配点】
①選択問題 100点
②論述問題 50点
【合格基準】
①②の得点の合計が105点以上
※ただし、論述問題の得点が25点以上
Ⅱ種(ラインケアコース)
Ⅱ種のラインケアコースは、Ⅰ種のマスターコースに次いで広範囲の7項目が出題されます。
- メンタルヘルスケアの意義と管理監督者の役割
- ストレスおよびメンタルヘルスに関する基礎知識
- 職場環境等の評価および改善の方法
- 個々の労働者への配慮
- 労働者からの相談への対応 (話の聴き方、情報提供および助言の方法等)
- 社内外資源との連携
- 心の健康問題をもつ復職者への支援の方法
管理職やリーダーとしてどのように部下に接したら良いのか、一人ひとりへの配慮や相談への対応方法、支援方法なども学びます。
配点および合格基準は以下の通りです。
【配点】
選択問題 100点
【合格基準】
70点以上
Ⅲ種(セルフケアコース)
Ⅲ種のセルフケアコースは、以下の6項目が出題されます。
- メンタルヘルスケアの意義
- ストレスおよびメンタルヘルスに関する基礎知識
- セルフケアの重要性
- ストレスへの気づき方
- ストレスへの対処、軽減の方法
- 社内外資源の活用
社員個人を対象とした試験であることから、メンタルヘルスケアの重要性や対処方法など基礎的な内容が中心となっています。
配点および合格基準は以下の通りです。
【配点】
選択問題 100点
【合格基準】
70点以上
メンタルヘルスマネジメント検定の合格率
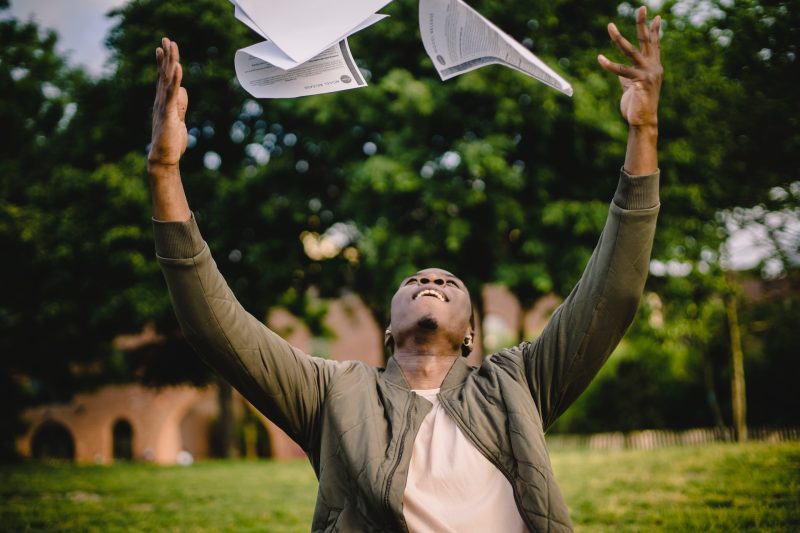
一口に検定試験や資格試験といっても、試験によって難易度は異なります。
メンタルヘルスマネジメント検定の場合、どの程度の合格率なのでしょうか。
大きな傾向を見ると、Ⅲ種(セルフケアコース)がもっとも合格率が高く、Ⅱ種(ラインケアコース)、Ⅰ種(マスターコース)と上位になるほど合格率は下がっていきます。
試験の実施年度によっても多少の差はありますが、たとえば2022年度の試験結果は以下の通りです。
【第34回試験】 2023年3月19日(日)
Ⅱ種(ラインケアコース) 実受験者(11,918人) 合格者数(6,444人) 合格率(54.1%)
Ⅲ種(セルフケアコース) 実受験者(5,035人) 合格者数(3,995人) 合格率(79.3%)
【第33回試験】 2022年11月6日(日)
Ⅰ種(マスターコース) 実受験者(1.628人) 合格者数(287人) 合格率(17.6%)
Ⅱ種(ラインケアコース) 実受験者(10,998人) 合格者数(6,401人) 合格率(58.2%)
Ⅲ種(セルフケアコース) 実受験者(5,458人) 合格者数(3,787人) 合格率(69.4%)
過去の複数回のデータを分析してみても、Ⅰ種の場合は15〜20%前後、Ⅱ種が50〜60%、Ⅲ種が60〜80%程度の合格率で推移しています。
▶︎心理カウンセラーになるには?武器となる資格や仕事内容も解説
メンタルヘルスマネジメント検定を取るとどんなことに活かせる?
メンタルヘルスマネジメント検定を取得するメリットとしては、社員の健康維持や職場環境の改善につながることが挙げられるでしょう。
たとえば、強いストレスや精神的な不調を抱えている人のなかには、自分から悩みを打ち明けられなかったり、どう対処すれば良いのか分からないというケースも少なくありません。
メンタルヘルスマネジメント検定を取得していれば、そのような精神的な不調をきたしている人に対し、一言声をかけ、相談に乗ることもできるでしょう。
その結果、精神的な問題で退職や休職に至る社員を減らし、働きやすい職場をつくることができます。
メンタルヘルスマネジメント検定に合格するための勉強のコツ
メンタルヘルスマネジメント検定に合格するためには、主に公式テキストの内容を繰り返し学習する方法と、受験対策講座を受講する方法があります。
公式テキストはⅠ種・Ⅱ種・Ⅲ種それぞれのコース専用のものが販売されており、メンタルヘルスマネジメント検定の公式サイトで購入手続きが可能です。
また、同じく公式サイトではⅠ種からⅢ種までの受験対策講座の情報も掲載されています。
テキストを使った独学だけでは内容が把握しきれない方や、効率的に試験範囲を学習したいという方は受験対策講座の受講も検討してみましょう。
まとめ
メンタルヘルスマネジメント検定は民間資格であり、医師免許のような高度な専門資格ではありません。
しかし、企業のなかには資格取得を推奨するケースも多く、実際に毎年多くの方が受験しています。
この資格を取得することで、自分自身の精神的な不調やストレスと向き合い適切な対処ができるほか、周囲の社員にも目を配り働きやすい職場が実現できるはずです。
経営層や人事担当者、管理職やリーダー、一般社員など、会社や組織で働く方であれば多くの人におすすめの資格です。
豆腐メンタルとはどんな意味?原因や治し方を徹底解説
わずかなことに傷つき、精神的に立ち直れなくなることを指す「豆腐メンタル」という言葉があります。
なぜ豆腐メンタルとよばれるのか、その理由や由来について解説するとともに、豆腐メンタルの人に見られる傾向や特徴、豆腐メンタルを改善するためのポイントなども詳しく紹介します。
豆腐メンタルとは

豆腐メンタルとは一般的に、精神的に弱く傷つきやすい人のことを指す言葉です。
その名の通り、豆腐のように崩れやすく脆いことから豆腐メンタルとよばれることがあります。
豆腐メンタルという言葉は心理学やメンタルヘルスの世界で用いられてきた言葉ではなく、もともとはインターネットの掲示板やSNSなどで使用されるスラングとして発展してきました。
インターネット黎明期はごく限られたコミュニティや界隈でのみ使用されていましたが、2010年代に入りインターネットユーザーが爆発的に増加したことにより、一般のユーザーにも受け入れられるようになり定着した言葉です。
ちなみに、豆腐メンタルとは対照的に精神的に強い人のことは、「鋼のメンタル」や「こんにゃくメンタル」とよばれることがあります。
こんにゃくが例に出される理由としては、弾力性が強く、わずかな刺激や物理的な力に屈することなくもとの形を保とうとする性質があるためです。
▶︎心理カウンセラーになるには?武器となる資格や仕事内容も解説
豆腐メンタルの原因は?

豆腐メンタルは一言で表すと「精神的に弱い人」のことですが、どういったことが原因で精神的に弱くなってしまうのでしょうか。
失敗やミスを過度に恐れる
わずかな失敗やミスを極度に恐れるあまり、精神的に弱くなってしまう傾向があります。
ちょっとしたミスでも必要以上に自分を追い詰めてしまい、精神的に立ち直るために長い時間を要します。
これは精神的な安定を維持するための自己防衛本能のようなもので、失敗を恐れるあまり新しいことに挑戦したり、興味や関心を抱かなくなることもあります。
自己肯定感が低い
自己肯定感が低いことも豆腐メンタルの人に見られる共通の特徴といえます。
自己肯定感とは、簡単にいえば自分自身を積極的に受け入れ、肯定する心理や感情のことを指します。
たとえば仕事で失敗やミスを犯したとき、「自分はダメな人間だ」、「自分はこの仕事に向いていない」と深刻に考えすぎてしまうことがあります。
ネガティブ思考
ネガティブ思考に陥ってしまいがちな人は精神的に脆いことが多いです。
この背景には、過去に犯した失敗がトラウマのように残っていることが考えられます。
その結果、何か新しいことに挑戦しようとするときに以前の失敗が頭をよぎり、「どうせ自分には無理だろう」と後ろ向きに考えてしまう傾向にあるのです。
また、「絶対にうまくいく」と考えて挑戦したものの、結果として失敗に終わってしまうとショックも大きく、立ち直るのに時間がかかってしまいます。
そのような状態にならないために、豆腐メンタルの人はネガティブに考えることで無意識のうちに予防線を張っているともいえるのです。
コミュニケーションが苦手
他人と積極的にコミュニケーションをとることが苦手だと、徐々に疎外感を感じるようになり、豆腐メンタルとなってしまうことがあります。
相手のことをよく知らない状態でコミュニケーションをとる際には、誰しも自然と警戒心をもってしまうものです。
しかし、あまりにもその気持ちが強すぎると、「無視されたらどうしよう」、「不審に思われたらどうしよう」といった考えが先行してしまい、話しかけることすらできなくなるケースもあります。
▶︎メンタル心理カウンセラーとは?資格を活かせる現場や学習内容も解説
豆腐メンタルを克服したほうが良い理由
メンタルの問題は人それぞれの価値観や考え方に起因することが多いものです。
豆腐メンタルを個性やその人の価値観と片付ける見方もありますが、精神的な弱さを放置しておくことで当事者である自分自身が苦しむことも少なくありません。
たとえば、仕事において上司や先輩社員が適切な指導・アドバイスをしたつもりでも、豆腐メンタルの人にしてみれば「叱られた」「責められた」と感じることもあります。
このような齟齬があると、職場の人間関係に支障をきたしたり、働きづらいと感じ退職に至ることもあるでしょう。
豆腐メンタルを克服することで良好な人間関係を維持するとともに、仕事の面においても自分自身を成長させる原動力となるのです。
▶︎ネガティブ思考をやめたい方へ|止まらない原因やレベル診断、改善方法をご紹介
豆腐メンタルを克服するためのポイント

豆腐メンタルは個人の価値観や考え方にも大きく左右されるものであり、一朝一夕に克服できるものではありません。
しかし毎日の生活を送るうえで、ちょっとしたポイントに注意するだけで精神的な強さを手に入れられる可能性もあります。
小さな目標達成を積み上げる
失敗やミスを過度に恐れる原因として、過去の経験からトラウマになっているケースが少なくありません。
そこで重要なのは、成功体験を積み上げることです。
大きな目標を達成したとき、それが自信につながることは多いですが、大きな目標を掲げるということは失敗のリスクも伴います。
そのため、いきなり大きな目標を設定するのではなく、達成の実現性がある小さな目標を積み上げ、段階を踏んでいくのが有効です。
自分自身の強みや長所を把握する
自己肯定感を高めることは豆腐メンタルを克服するための第一歩でもあります。
自己肯定感が低い人は、自分自身の悪いところばかりに目がいきがちです。
しかし、誰にでも長所や強みは存在します。
まずは自分自身の長所や強みを書き出しながら整理してみることで、自信がつき自己肯定感を高められる可能性があります。
誰にとっても失敗やミスは起こるものだと理解する
失敗を過度に恐れ、ネガティブ思考に陥りやすいときには、考え方や価値観を根本から変えていく必要があります。
すなわち、失敗やミスをしない人は存在せず、誰にとってもあり得ることを理解する必要があります。
これにより、過去の失敗やミスにとらわれ精神的に落ち込むことも減り、ポジティブな姿勢を保ちやすくなるでしょう。
ネガティブな言葉をポジティブな言葉に言い換える
ネガティブ思考が癖になり豆腐メンタルに陥っている人は、日々の言動を客観的に振り返ってみましょう。
たとえば、「どうせ無理だ」、「きっと失敗する」、「自分はダメな人間だ」といった思考が頭の片隅にあると、自然とネガティブな言葉が口癖のように出てきてしまうものです。
そのようなネガティブな言葉は避け、ポジティブな言葉に言い換えることを意識してみましょう。
たとえば、「どうせ無理だ」ではなく、「以前失敗したところを克服できれば、きっと成功するはずだ」と考えを転換することで、良い意味での自己暗示にかかり成功を引き寄せられる可能性もあります。
▶︎【自己受容】弱くてダメな自分を認めて受け入れるトレーニング方法
豆腐メンタル
豆腐メンタルは精神的に弱い人を指すネットスラングとして誕生し、現在では一般社会でも広く用いられるようになりました。
メンタルの強さは人によってもさまざまで、ちょっとしたことにショックを受ける人も少なくありません。
しかし、日常生活を送るうえでさまざまなポイントに注意するだけでも、豆腐メンタルは少しずつ改善され克服できる可能性もあります。
今回紹介した方法の一例をぜひ参考にして、取り組んでみてはいかがでしょうか。
メンタル心理カウンセラーとは?資格や仕事内容も解説
心理カウンセラーになるために必須となる資格や免許はなく、スキルや経験さえあれば誰でも目指せる職業です。
しかし、だからこそキャリアアップのために、スキルを客観的に評価してもらえる資格の取得は有効です。
本記事では、民間資格である「メンタル心理カウンセラー」について詳しく解説します。
メンタル心理カウンセラーはどんな資格?
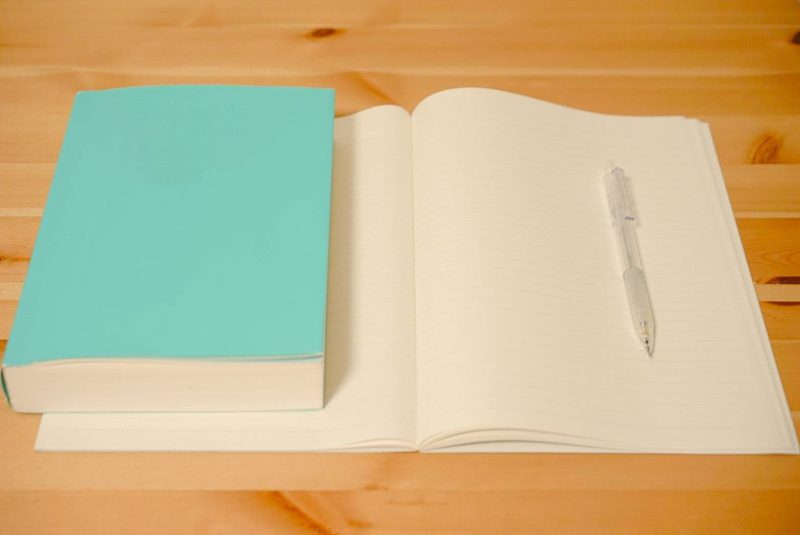
メンタル心理カウンセラーとは、一般財団法人日本能力開発推進協会が認定している民間資格です。
「JADP認定メンタル心理カウンセラー」ともよばれ、心理カウンセラーとして活躍するために必要な知識や技能の程度を証明することができ、キャリア開発において大きな武器となる資格のひとつといえます。
現代社会において、さまざまなストレスを抱える人は少なくありません。
人々の悩みや不安を解消するためにも心理カウンセラーの需要は高まっており、メンタル心理カウンセラーの資格を取得することで活躍の場が広がっていきます。
大前提として、心理カウンセラーになるために必須となる資格や免許はありませんが、採用時にメンタル心理カウンセラーの資格を持っていれば大きな武器になることは間違いないでしょう。
ちなみに、心理カウンセラーにとって有用な資格は数多く存在しますが、メンタル心理カウンセラーは学歴を問わず通信講座でも取得できるため、受験のハードルが比較的低い資格といえます。
▶︎心理カウンセラーになるには?武器となる資格や仕事内容も解説
メンタル心理カウンセラーの資格が活かせる現場

心理カウンセラーはさまざまな場で活躍できる専門職ですが、メンタル心理カウンセラーの資格を取得すれば具体的にどのような現場で活かされるのでしょうか。
医療・介護の現場
病気やケガなどの治療が長期化すると、精神的に不安定になる人も少なくありません。
また、介護の現場では施設に入居する利用者がストレスを抱えたり、介護をする家族が悩みや不安を抱えたりすることも少なくありません。
心理カウンセラーとして患者や利用者やその家族とコミュニケーションをとり、相談に乗ることで不安やストレスを緩和することができます。
教育現場
いじめや不登校などに悩む児童・生徒は多く、子どもの悩みや不安を解消するためにも心理カウンセラーは欠かせない存在です。
教育現場で働く心理カウンセラーはスクールカウンセラーともよばれ、最近では公立学校でも配属されるケースが少なくありません。
一般企業
一般企業においてもメンタル心理カウンセラーの資格は大いに役立ちます。
職場の人間関係やハラスメントに悩む人の心理的ケアを行うカウンセラーは産業カウンセラーともよばれ、メンタルヘルス対策の一環として採用する企業も少なくありません。
また、メンタル心理カウンセラーの資格をもっていれば、カウンセラーとしての仕事ばかりではなく、管理職やリーダー、人事部門などにおいてマネジメント力の向上にも役立てられます。
▶︎感情の起伏が激しい人や少ない人の特徴|上手にコントロールする方法とは
メンタル心理カウンセラーの取得に必要な時間

メンタル心理カウンセラーは専門的な資格であることから、取得には膨大な学習時間を要するのではないかと不安に感じる方も少なくありません。
実際にどの程度の学習時間を要するのか、今回は通信講座を受講するケースをもとに紹介しましょう。
メンタル心理カウンセラーの想定学習時間は20時間
メンタル心理カウンセラーの通信講座では、およそ20時間程度のカリキュラムが組まれています。
大学や大学院へ通う学生とは異なり、通信講座の場合は多くの方が仕事の合間を見つけながら学習をするケースがほとんどです。
毎日無理なく学習することを考えると1日1時間程度が目安となるため、だいたい20日間でカリキュラムを終えられる計算になります。
もちろん、20日間だけでは試験範囲を網羅的に理解できないことも考えられるため、必要に応じて過去問題に挑戦したり、分からないところやつまづいた部分を重点的に復習する時間も必要でしょう。
そのため、少なくとも1ヶ月間程度は学習時間を確保しておく必要があります。
メンタル心理カウンセラーの難易度
メンタル心理カウンセラーの合格基準は70%以上の得点率となっており、難易度がそれほど高い試験ではありません。
心理カウンセラーの関連資格のなかでも初級者向けに位置しており、テキストや教材に沿って学習しておけば初学者でも十分合格を目指せるでしょう。
▶︎【自己受容】弱くてダメな自分を認めて受け入れるトレーニング方法
メンタル心理カウンセラーの学習内容

メンタル心理カウンセラーの資格を取得するうえで、具体的にどういったカリキュラムを学ぶ必要があるのでしょうか。
通信講座で提供されているテキストや教材をもとに、主な学習内容の一例を紹介します。
心理学の基礎
心理カウンセラーとして専門性を身につけるためには、心理学の基礎から学ぶ必要があります。
心理学はどのような歴史を経て発達してきたのか、社会心理学や発達心理学といった分野を網羅的に学ぶとともに、自分自身のストレスチェックも行いながら心理学への理解を深めていきます。
カウンセリングの基礎
心理カウンセラーにとって必要な実践的な学習として、カウンセリングの基礎があります。
そもそもカウンセリングとは何か、何を目的として行うのか、さらには「インテーク面接」や「積極的傾聴」、「来談者中心療法」、「ロジャーズ理論」といった具体的な方法を学びます。
カウンセリングのルール
カウンセリングの基礎を理解できたら、実際にカウンセリングを行う際に守るべきルールも身につけていきます。
カウンセリングの時間や話しやすい環境をつくるためのテクニック、相談者との信頼関係を構築するためのポイントなどもこの範囲に含まれます。
開業方法
心理学やカウンセリングを一通り学んだら、心理カウンセラーとして開業するための方法や流れについても学習します。
どのような開業スタイルがあるのか、開業にあたって不可欠なコンセプトや理念、カウンセリング料金の決め方、事業計画の立て方など実務的な内容を学んでいきます。
メンタル心理カウンセラーの取得にかかる費用
メンタル心理カウンセラーにかかわらず、専門的な資格を取得する際に多くの方が気になるのはコストの問題ではないでしょうか。
メンタル心理カウンセラーは一般財団法人日本能力開発推進協会が主催している試験であり、大前提として、受験するためには協会が認定する教育訓練において全カリキュラムを修了している必要があります。
そのため、メンタル心理カウンセラーの取得にかかる費用は大きく分けて通信講座の受講料と試験の受験料となります。
- 通信講座受講料:38,600円(税込)
- 受験料:5,600円(税込)
上記にある通り、通信講座の受講料は通常38,600円ですが、申し込むタイミングによってはキャンペーンで割引となるケースも多く、3万円以下の料金で受講できる可能性もあるので活用してみましょう。
メンタル心理カウンセラーを取得しキャリアアップにつなげよう
これから心理カウンセラーを目指す方にとって、メンタル心理カウンセラーの資格を取得することは大きな武器になるでしょう。
数ある資格のなかでも初級に位置しており、比較的難易度は低いといえますが、しっかりと学習しておかないと合格は難しいことも事実です。
キャリアアップのために、まずはメンタル心理カウンセラーの取得を目指してみましょう。
▶︎スピリチュアルカウンセラーとはどんな職業?誤解されやすい職業との違い
心理カウンセラーになるには?武器となる資格や仕事内容も解説
ストレスの多い現代社会において、人々が抱える悩みや不安を解消するための相談に乗る「心理カウンセラー」という職種のニーズが高まっています。
これから心理カウンセラーになりたいと考える方にとっては、どういった資格や免許が必要なのか疑問に感じることもあるでしょう。
そこで本記事では、心理カウンセラーになるための条件について解説するとともに、心理カウンセラーの仕事内容や武器となる資格なども紹介します。
心理カウンセラーとは

心理カウンセラーとは、相談者のさまざまな悩みや問題をヒアリングし、相談に乗ることで心理的な側面から支援をする専門職です。
社会生活を送るうえでストレスは切っても切り離せない問題であり、精神的な疾患や不安を抱える人は少なくありません。
実際に心療内科や精神科といったメンタルヘルスクリニックを受診する人は多く、精神疾患は大きな社会問題にもなっています。
精神疾患を治療するのは精神科医をはじめとした医師の仕事ですが、精神疾患を予防するためにも心理カウンセラーの役割は大きく、現代社会になくてはならない存在ともいえるのです。
これまで心理カウンセラーは医療機関などに所属し、患者にとっては相談できる場所が限られていました。
しかし、昨今では学校や企業など多くの場所に心理カウンセラーが在籍するようになったことから、社会からのニーズが高まっています。
▶︎メンタル心理カウンセラーとは?資格を活かせる現場や学習内容も解説
心理カウンセラーの主な仕事内容

心理カウンセラーは具体的にどのような仕事をするのでしょうか。
冒頭でも紹介した通り、心理カウンセラーの活躍の場は広がっており、それによっても仕事内容は変わってきます。
医療機関・クリニック
精神科や心療内科といったメンタルケアを担う医療機関では、精神科医に並んで心理カウンセラーは欠かせない職種です。
直接的な治療は医師が担いますが、心理カウンセラーは治療中の不安や悩みなどの相談に乗り、早期回復をサポートします。
また、内科や外科、産婦人科といった一般的な診療科においても、患者本人やその家族のケアをするために心理カウンセラーが派遣されることがあります。
学校
教育現場では、いじめや不登校、人間関係の悩みなどを抱える児童・生徒が少なくありません。
そのような悩みや心の傷を回復させるためにも心理カウンセラーは不可欠な存在です。
ちなみに、教育現場に配属される心理カウンセラーは「スクールカウンセラー」ともよばれます。
企業
学校と同様、企業においてもさまざまな悩みを抱える人は存在します。
特に、パワハラやセクハラといった深刻な悩みを抱えているにもかかわらず、解決できないまま放置しておくと職場環境が悪化し人材の流出につながるおそれもあるでしょう。
また、残業が続き精神状態が悪化したり、大きな仕事のプレッシャーがストレスとなり生産性が低下したりといったケースもあります。
このように、職場における悩みやストレスを解消するためにサポートする心理カウンセラーを「産業カウンセラー」とよびます。
福祉施設
児童相談所や児童福祉施設にはさまざまな境遇の子どもがおり、なかには心に大きな傷を抱えているケースも少なくありません。
また、子どもだけでなく、高齢者施設においてもストレスを感じる利用者や、介護疲れに悩む家族もいます。
このように、福祉施設の利用者が抱える心の問題に向き合うのも心理カウンセラーの大切な仕事のひとつです。
その他公的機関
警察署や刑務所、少年院などにも心理カウンセラーが配属されることがあります。
犯罪被害に遭った人や、犯罪・非行を起こした人に対し心理的なサポートをするのが主な仕事であり、いち早く元の社会生活に戻るために重要な役割を果たします。
▶︎感情の起伏が激しい人や少ない人の特徴|上手にコントロールする方法とは
心理カウンセラーになるための条件・スキルの習得方法

心理カウンセラーは医師とは異なり、特定の資格や免許が必須というわけではありません。
専門的な知識やスキル、経験を持っていれば、誰もが心理カウンセラーとして活躍できます。
ただし心理カウンセラーとして評価され、実際に仕事に活かそうと考えた場合、知識やスキルを客観的に証明できなければ難しいといえるでしょう。
多くの心理カウンセラーは、以下のいずれかの方法でキャリアをスタートさせています。
大学や大学院で学ぶ
専門的な知識を身につけるためには、大学や大学院で学ぶ方法が一般的です。
心理学を学べる大学を選ぶことで、心理カウンセラーに必要な知識を身につけられるほか、国家資格である公認心理師の受験資格を得られるメリットもあります。
特に、10代、20代と若いうちから心理カウンセラーになることを目標としている方は、大学や大学院へ進学することでキャリアの道が開けてくるでしょう。
民間のスクール・通信講座で学ぶ
民間のスクールや通信講座で学ぶ方法もあります。
大学や大学院に比べると入学のハードルが低く、授業料などコスト面でもメリットが大きいといえるでしょう。
また、通信講座であれば社会人になってからでもカリキュラムを受けやすく、仕事をしながらでも心理カウンセラーに必要な資格取得に挑戦できます。
▶︎【自己受容】弱くてダメな自分を認めて受け入れるトレーニング方法
心理カウンセラーとして武器になる資格
心理カウンセラーとして活躍していくうえで、どういった資格が武器となるのでしょうか。
代表的な資格を3つ紹介しましょう。
公認心理士
公認心理士とは国家資格のひとつであり、2018年に新設された比較的新しい資格です。
心理カウンセラーの武器となる唯一の国家資格であることから、多くの方がこの資格を取得し業務に役立てています。
公認心理士を取得することで、心理査定やカウンセリング、さまざまな情報提供の活動などを担えるようになります。
臨床心理士
臨床心理士とは、公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定している民間資格です。
臨床心理士を取得するためには、「協会が指定する大学院を修了し、所定の条件を満たしている」または「臨床心理士を養成する専門職大学院を修了」といった条件が設定されているため、ほかの資格に比べると受験のハードルは高いです。
しかし、臨床心理士を取得すればスクールカウンセラーの専門職としても認定されるため、心理カウンセラーとしての道が開けてくるでしょう。
メンタル心理カウンセラー
メンタル心理カウンセラーは、一般財団法人日本能力開発推進協会が認定している民間資格です。
その名の通り、心理カウンセラーに求められる知識やスキルを証明するための資格であり、心理カウンセラーとして採用する際にこの資格の有無を問われるケースも少なくありません。
ただし、メンタル心理カウンセラーは通信講座でも取得できることから、ほかの資格に比べると受験のハードルは低いといえるでしょう。
武器となる資格を取得し心理カウンセラーを目指そう
職場や学校、その他あらゆる場面においてストレスを抱えがちな現代社会において、心理カウンセラーは不可欠な存在であり、ますます需要が高まっています。
相談者に寄り添い、話をじっくり聞くことが心理カウンセラーには求められ、人の役に立ちたいと考える方に向いている職業といえるでしょう。
心理カウンセラーになるために資格や免許は必須ではありませんが、これからキャリアをスタートさせたいと考える方は、客観的にスキルを証明できる資格の取得がおすすめです。
▶︎スピリチュアルカウンセラーとはどんな職業?誤解されやすい職業との違い
スピリチュアルカウンセラーとは|本物になるためにはどうすればいい?
霊的な能力を用いてさまざまな人の悩み・不安解消に導く「スピリチュアルカウンセラー」という職業があります。
しかし、これだけを聞くと「怪しい」「胡散臭い」といったイメージをもつ方も少なくありません。
本記事では、スピリチュアルカウンセラーとはどういった職業なのか、誤解されやすい職業との違いやスピリチュアルカウンセラーになるための方法なども詳しく解説します。
スピリチュアルカウンセラーとは

そもそも「スピリチュアル」とは、日本語に直訳すると「霊的な」、「霊魂に関するさま」といった意味を指します。
すなわち、スピリチュアルカウンセラーとは、霊的な力によって相談者のさまざまな悩みや不安を解消する専門家のことを指します。
霊的な力と聞くと、いわゆる霊感商法のように、不安を煽りお金をだまし取るなどの被害に遭うのではないか、または怪しい職業といったイメージを抱かれがちです。
たしかに、霊的な力は多くの人の目に見えるものではないことから、「胡散臭い」、「怪しい」と感じられることも多く、霊的な力をもっていないのにお金を儲けようとする悪質な人も存在します。
しかし、スピリチュアルカウンセラーは民間の資格も存在し、これを持っておくことで客観的にその能力や信頼性を証明でき、初めてカウンセリングを受ける人に対しても安心感を与えることができるのです。
▶︎心理カウンセラーになるには?武器となる資格や仕事内容も解説
スピリチュアルカウンセラーと誤解されやすい職業
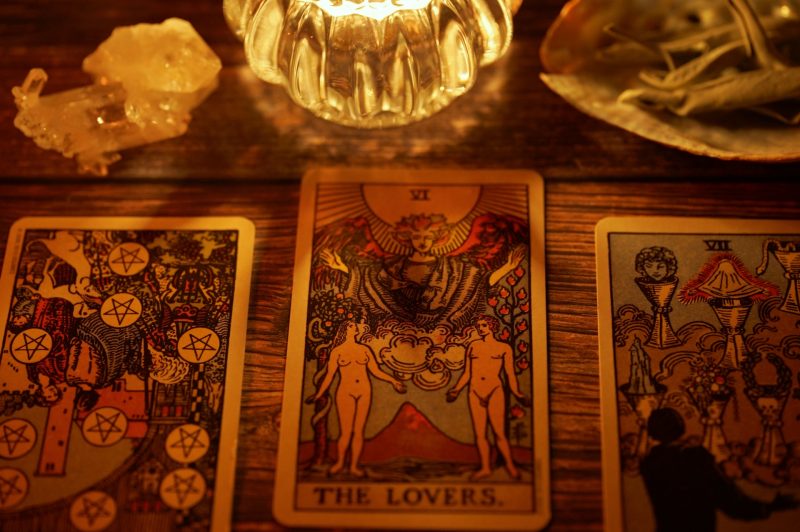
霊的な力をもって人々の悩みや不安を解消すると聞くと、占い師や霊能者といったさまざまな職業をイメージする方も多いと思います。
実際に同じような行為を行うケースもありますが、スピリチュアルカウンセラーとはどのような違いがあるのでしょうか。
占い師との違い
スピリチュアルと聞くと神秘的な力をイメージしがちで、特に占い師と混同する方も少なくありません。
実際にスピリチュアルカウンセラーのなかにも、占いができる、あるいは占いを得意とする人も存在しますが、本質的には異なる存在です。
スピリチュアルカウンセラーはあくまでもカウンセリングを中心に行うため、相談者が何に悩んでいるのか、何を相談したいのかを丁寧にヒアリングします。
一方、占い師は一方的なアドバイスや助言をするケースも多く、必ずしもカウンセリングを行えるとは限りません。
霊能者との違い
霊能者とは、霊魂が存在するとされている世界、いわゆる霊界と交信し、霊からのメッセージを自分なりに解釈して伝える専門家のことです。
日本ではスピリチュアルカウンセラーという言葉よりも、霊能者という名称のほうが浸透しているため分かりやすいでしょう。
イタコとの違い
イタコとは、青森県を中心とした東北地方で口寄せを行う人のことを指します。
口寄せとは、亡くなった方の霊をイタコ自身に乗り移らせ、亡くなった方自身の言葉として発する行為を指します。
イタコは霊界との交信をするだけでなく、自分自身に乗り移らせるという点が大きな特徴といえるでしょう。
チャネラーとの違い
チャネラーとは、日本における霊能者と同じような存在であり、霊界との交信によってさまざまな情報を得る「チャネリング」を行う人を指します。
スピリチュアルカウンセラーは相談者の悩みや不安を取り除くということを目的として活動しますが、チャネラーはあくまでも霊界との交信を行える人という違いがあります。
▶︎メンタル心理カウンセラーとは?資格を活かせる現場や学習内容も解説
スピリチュアルカウンセラーへの主な相談内容

日本ではあまり馴染みのないスピリチュアルカウンセラーという職業ですが、具体的にどういった悩みや相談を受けることが多いのでしょうか。
恋愛・結婚相談
意中の相手がいるものの、なかなか一歩を踏み出せないという人は多いものです。
そのようなとき、スピリチュアルカウンセラーは深層心理を読み解き、霊界との交信をしながら有効なアドバイスをすることができます。
また、すでに交際相手がいる場合、どうしたら結婚できるか、相手は自分のことを受け入れてくれるかといった悩みや不安を抱くことがあるでしょう。
そのような場合も、スピリチュアルカウンセラーは相談者からさまざまなことをヒアリングし、効果的なアドバイスができます。
仕事や将来に関する相談
将来やりたいことが分からない、あるいはどのような仕事が向いているのか分からない、今の仕事をこのまま続けていくべきかなど、仕事や将来に関する相談も少なくありません。
占い師のように「この会社に入りなさい」、「◯◯の道が向いています」といったようなアドバイスではなく、あくまでも相談者の意思や潜在的な考え、価値観などを引き出したうえでアドバイスを行います。
人生におけるあらゆる悩み
仕事や恋愛以外にも、人生にはさまざまな悩みがあります。
たとえば、「経済的に困窮しているためお金持ちになりたい」、「人間関係がうまくいかず孤立してしまう」など、人によって悩みの内容は異なります。
スピリチュアルカウンセラーは、このような漠然とした悩みに対しても丁寧に質問を繰り返して掘り下げていき、その人の考えや価値観をしっかりと理解したうえで有効なアドバイスを送ることができます。
しかし、これだけを聞くと一般的なカウンセラーとの違いが分からないと感じる方も多いでしょう。
カウンセリングをするのはあくまでも本人の意思を確かめるためであり、霊界との交信結果をそのまま相談者へ伝えるわけではないのです。
スピリチュアルカウンセラーは相談者が知りたいことや本当に解決したいことは何か、潜在的にどういった結論を求めているのかなどを理解したうえで助言を行うため、相談者のことを第一に考えています。
▶︎感情の起伏が激しい人や少ない人の特徴|上手にコントロールする方法とは
本物のスピリチュアルカウンセラーになる方法

スピリチュアルカウンセラーになるためには、医師や弁護士のように資格や免許が必須というわけではありません。
霊界との交信ができる人であれば、霊能力者や占い師のように誰でもスピリチュアルカウンセラーを名乗ることができます。
しかし、本当に信頼できるスピリチュアルカウンセラーになるためには、専門的な資格をもっておいたほうが有利になるのは間違いありません。
たとえば、一般社団法人スピリチュアルマスターアカデミーでは、「認定スピリチュアルカウンセラー資格」という民間資格を発行しています。
この資格は独学で受験することもできますが、より効率的に勉強するためには「スピリチュアルマスター養成講座」や専門学校、スクールに通う方法もおすすめです。
スピリチュアルカウンセラーに向いている人
霊能力・霊感があったとしても、すべての人がスピリチュアルカウンセラーに向いているとは限りません。
そもそもカウンセラーという仕事は人とのコミュニケーションが不可欠であることから、他人に対して興味や関心があり、人と接するのが好きな方がスピリチュアルカウンセラーに向いているでしょう。
コミュニケーションと聞くと自分自身の考えや意見を述べる話し上手な人というイメージをもたれがちですが、実際には人の話をしっかり聞いて理解できることが何よりも重要です。
一流のスピリチュアルカウンセラーになるために
スピリチュアルカウンセラーは日本における霊能者やイタコとも近い存在ではありますが、相談者とのコミュニケーションを大切にしカウンセリングに重点を置いているという大きな違いがあります。
多くの相談者が訪れるスピリチュアルカウンセラーは、霊界との交信ができるという特殊な能力に加えて、相談者のことを第一に考えている点が挙げられます。
信頼できるスピリチュアルカウンセラーになるために、専門的な資格の取得とコミュニケーション力の向上にも努めてみましょう。
マインドフルネスと瞑想の違いや初心者におすすめのやり方を徹底解説!

自分自身と向き合うことで、集中力や生産性の向上、不安やストレスを緩和するための手法としてマインドフルネスが注目されています。
さまざまなメリット・効果が期待できるマインドフルネスですが、なかには危険な行為であるという言説を目にすることがあります。
マインドフルネスにはどのような危険があるのか、やってはいけない人の特徴や、初心者が取り組む際の注意点などもあわせて解説します。
マインドフルネスとは

マインドフルネスとは、瞑想や呼吸法などを用いて自分の感情や思考と向き合う手法のことです。
精神統一の一種であり、日本では似たような考え方が1,500年以上前から存在していたともされています。
実際に「マインドフルネス」という言葉を生み出し、世に広めたのはマサチューセッツ工科大学医学部教授のジョン・カバット・ジン博士。
その後同大学にてマインドフルネスセンターの創設にも関わったジン博士は、もともと宗教色の強かったマインドフルネスを一般人にも取り組みやすいメソッドに落とし込み、概念や理論を確立しました。
現代では医療の臨床現場で取り入れられているほか、世界中の企業でも取り入れられている例があります。
マインドフルネスと瞑想の違い

マイインドフルネスと瞑想はとても良く似たものとしてしばしば語られますが、大きな違いとして目的が挙げられます。
マインドフルネスは、現在目の前で起こっている事柄に対しての注意力や集中力を最大限に研ぎ澄ますための手法として用いられることが多く、そのため社内の生産性アップのために企業にも取り入れられているケースがあるのです。
それに対して、瞑想は頭の中から一切の雑念を振り払うことで思考を一度リセットし、心の平穏を得ることが主な目的となります。
両者ともに目を閉じて呼吸に集中するなど、やり方に共通する点もありますが、目的がそもそも違うというということを頭に入れておくと良いでしょう。
初心者にもおすすめのマインドフルネスのやり方

マインドフルネスにはさまざまなメリットがあることから、これから挑戦してみたいと考える方も多いでしょう。
リスクを避けつつマインドフルネスの効果を最大限高めるためには、どのようなポイントに注意すべきなのでしょうか。
環境を整える
マインドフルネスを行う場所は、静かで落ち着いた環境が理想的です。テレビやラジオ、屋外の音が届きづらい静かな部屋で行いましょう。
また、着用する衣服や座る椅子、座布団なども重要です。
できるだけ締め付けが少なくリラックスできる衣服を選び、無理のない姿勢で座れる椅子や座布団を用意しましょう。
短時間からスタートする
マインドフルネスの上級者ともなると、数時間以上も瞑想に取り組む人もいます。
しかし、初心者がいきなり何時間も瞑想をするのは辛く感じてしまい、挫折する原因にもなるでしょう。
そのため、まずは数十秒、数分といった短時間からスタートすることがおすすめです。
短い時間からはじめ、瞑想に慣れてきたら徐々に時間を伸ばしていくことで、無理なく続けられるはずです。
毎日継続する
マインドフルネスの効果を実感するためには、毎日継続的に実践することが大切です。
上記でも紹介した通り、1日あたり数十秒、数分と短時間でも、とにかく毎日続けて習慣化することを意識しましょう。
トレーナーやコーチの指導を受ける
マインドフルネスによって気分が悪くなったり、危険な状態に陥らないようにするためにも、トレーナーやコーチの適切な指導を受けることも大切です。
特に初心者の場合、自分でも気付かないうちに瞑想によって危険な状態に陥ることがあります。
専門のワークショップやオンラインプログラムなどを利用し、正しい練習方法を習得しましょう。
体調が悪いときは無理をしない
マインドフルネスは毎日継続することが重要であると紹介しましたが、健康上の不安がある場合は別です。
身体の倦怠感や吐き気、頭痛などの症状があるときや、なんとなく気分が優れないときにマインドフルネスを行うと悪化させるおそれもあるため、決して無理は禁物です。
関連記事:アファメーション(ポジティブな自己暗示)のやり方・効果について解説
マインドフルネスの効果とは
マインドフルネスを行うことで、以下のような効果が期待できます。
集中力が高まる・神経が研ぎ澄まされる
仕事や勉強に集中したいと考えていても、周囲のことに気が散ってしまい集中力が続かない人にはマインドフルネスがおすすめです。
マインドフルネスの練習を通して自分自身と向き合うことで、少しずつではありますが注意力や集中力を高めることができるようになるでしょう。
ストレス耐性の向上
マインドフルネスを継続していると、目の前の事柄に意識を集中させることに徐々に慣れていきます。
その結果、無駄な思考や他のものごとにいちいち気が散るといった機会が少なくなり、ストレス耐性の向上が期待できるでしょう。
睡眠の質の改善
日頃からマインドフルネスを行っていることにより、ホルモンバランスや交感神経と副交感神経のバランスが整い、免疫力の改善や血圧の低下などが見られたとの報告もあります。
これらは副次的な効果ではありますが、睡眠の質を向上させることに寄与するでしょう。
マインドフルネスを行うと覚醒度が高まる可能性があるため、就寝直前は控えるようにしましょう。
関連記事:【簡単】メディテーション(瞑想)のやり方・意味|マインドフルネスとの違いは?
【体験談】マインドフルネスはやばい?続けた結果どうなったか

私がマインドフルネスを始めたきっかけは、日々のストレスと忙しさに追われる生活から少しでも逃れたいと思ったからです。最初はどのように始めたらいいのか、正直迷いましたが、瞑想や日常の小さな行動に意識を向けることからスタートしました。
例えば、食事をする時や歩いている時、そして夜眠りにつく前に、その瞬間瞬間に意識を集中させるようにしました。
数週間続けた後、私の生活にはいくつかの変化が現れ始めました。まず驚いたのは、夜の寝つきが良くなったことです。
以前はどれだけ疲れていても、なかなか寝付けないことが多かったのですが、マインドフルネスを実践するようになってからは、心が穏やかになり、ぐっすり眠れるようになりました。
さらに、日常でイライラすることが減り、ストレスを感じることが少なくなりました。何か予期しないことが起きても、以前よりも落ち着いて対応できるようになったのです。
特に心に留めているのは、「今、この瞬間に意識を向ける」ことの大切さです。私たちはしばしば、過去の後悔や未来の不安に気を取られがちですが、マインドフルネスを通じて「今」に集中することの価値を学びました。それが意志力や集中力を高め、緊張する局面でも落ち着いていられるようになった理由です。
しかし、マインドフルネスにはデメリットもあります。私の場合、感情の起伏が少なくなり、以前ほど感情的なリアクションが少なくなったと感じています。これはある意味で冷静さを保つことができるようになったとも言えますが、時には「感情を感じること」の重要性も思い出させられます。
それでも、マインドフルネスを続けて良かったと心から思っています。イライラすることがあっても、自分を責めることが少なくなりました。
また、ストレスを感じた時にそれに気づき、早く平常心に戻れるようになったのは大きな進歩です。完璧を目指すのではなく、自分自身を受け入れ、瞬間を大切にするマインドフルネスの心得は、私の日々の生活を豊かにしてくれています。
マインドフルネスの副作用・危険性
マインドフルネスは比較的安全で危険性が少ない手法であるとされています。
しかし、実はすべての人にとって安全とも限らず、人によっては危険や副作用をもたらすこともあるのです。
具体的な危険性や副作用には以下のようなものがあります。
トラウマの再体験・フラッシュバック
瞑想を行っていると、過去に経験した辛い出来事やトラウマが浮かび上がることがあります。
人によっては自分自身の過去と対峙し、辛い出来事やトラウマをうまく処理できることもあるでしょう。
しかし、マインドフルネスを行ったことによってさらなる苦痛をともなうケースも少なくありません。
不安・パニック
マインドフルネスでは瞑想や呼吸法によって、深い自己観察を行います。
この過程において、不安やパニックを増幅させることがあります。
このような副作用は、過去または現在に精神的な問題を抱えたことのある人に多く見られます。
無気力・無関心
マインドフルネスを継続していくことで現実逃避に陥ってしまい、何事にも関心を示さなくなったり、無気力になったりすることがあります。
このような症状は自己観察のしすぎによって起こることが少なくありません。
関連記事:【自己受容】弱くてダメな自分を認めて受け入れるトレーニング方法
マインドフルネスをして気持ち悪くなる人がいる?
マインドフルネスによる副作用では、上記のような精神的なもの以外にも、生理現象として現れるケースもあります。
ありがちな副作用としては、気分が悪くなったり、吐き気や咳が止まらなくなるというものです。
人によっては車酔いのような感覚に陥ることもあるようです。
ただし、マインドフルネスを行っているすべての人がこのような状態に陥るものではなく、現れる症状の程度も人によって異なります。
気分が悪くなる人は一人でマインドフルネスを実践しているケースが多いようで、専門のトレーナーやプロのコーチなどのサポートを受けることで症状が緩和されたり、全く症状が現れなくなることもあるようです。
マインドフルネスをやってはいけない人の特徴

マインドフルネスは多くの人にとって安全なトレーニング方法といえます。
では、上記で紹介したような危険性や副作用のリスクが高まるのはどういった人なのでしょうか。
マインドフルネスをやってはいけない人の特徴を4つ紹介しましょう。
精神疾患を抱えている人
うつ病や統合失調症、強迫性障害、双極性障害といった精神疾患を抱えている人の場合、マインドフルネスに取り組むことによって自分自身の嫌な部分ばかりが見えてきて病状を悪化させるリスクがあります。
これらの病気で治療中の方は、担当医やセラピストと相談してからマインドフルネスに取り組むようにしましょう。
PTSD(心的外傷後ストレス障害)の症状がある人
過去に体験した辛い出来事がきっかけとなり、PTSDの症状が表れるようになった人もマインドフルネスは避けるべきです。
瞑想中に過去の出来事やトラウマ、それにともなう辛い感情が引き起こされる可能性があるためです。
PTSDの症状を悪化させる可能性があることから、マインドフルネスに取り組む際には担当医やセラピストと相談しましょう。
自傷行為や自殺企図の経験がある人
過去に自傷行為や自殺企図の経験がある人もマインドフルネスを行うべきではありません。
瞑想によって心の痛みや悲しみを引き起こすことがあり、再び過去と同じ状況に陥る可能性があるためです。
心身症状を抱えている人
専門医による治療や診断は受けていないものの、日常生活のなかでたびたび不安感に襲われる人や、パニック発作や過呼吸などの心身症状が表れる人もマインドフルネスには向いていないかもしれません。
明確な診断を受けていない以上、自分だけの判断でマインドフルネスを行ってしまうと、症状を悪化させさらに重篤な状態に陥る可能性もあります。
関連記事:感情の起伏が激しい人や少ない人の特徴|上手にコントロールする方法とは
まとめ
ストレスや不安が多い現代社会において、マインドフルネスがさまざまなメディアに取り上げられ、SNSでも多くのユーザーが情報を発信しています。
一見すると誰もが手軽に取り組める手法に感じられますが、実際にはマインドフルネスによって危険や副作用が生じることもあり、細心の注意を払うことが大切です。
もし、マインドフルネスの方法が分からなかったり、トレーニングに不安を感じたりする場合には、専門のトレーナーやコーチの指導を受けながら挑戦してみてください。
自己肯定感を高める8つの習慣や言葉を紹介
自己肯定感とは自分自身を受け入れ、自分を大切に思える感覚のことです。
この自己肯定感は人間関係や仕事、恋愛などのあらゆる面において大きな影響を与えます。
本記事では自己肯定感の高め方や習慣、行動についてご紹介します。
自己肯定感を高めることは可能なのか

結論から言うと、自己肯定感を高めることは可能です。
自己肯定感は自分自身に対するポジティブな考え方や、自己価値を肯定する感覚です。
この感覚は、習慣や考え方を変えることで向上させることができます。
自己肯定感を高めるには、まずは自分の強みを見つけることが大切です。
自分が得意なこと、好きなことを見つけ、それを伸ばすことが自己肯定感を高めるための近道です。
また、失敗や間違いを恐れず自分自身を受け入れることも重要です。
自分自身を受け入れ、自分を愛し、自分を許すことができたときに自己肯定感が高まります。
さらに、自分自身を褒めることも有効です。
自分自身に対して肯定的な言葉をかけることで、自己肯定感が高まります。
また、他人からの批判は自己肯定感の低下につながってしまうような気がしますが、それを真摯に受け止め、今後への改善案として前向きに受け入れることができるようになれば、より自分自身を成長させ、価値を高めることになるでしょう。
これらのことを習慣化することで、自己肯定感を高めることができます。
▶自己肯定感とは?|意味や似ている言葉との違いをわかりやすく解説
自己肯定感を高めることのメリット

自己肯定感を高めることには様々なメリットがあります。
まず、自己肯定感が高まると自分自身を肯定的に見ることができるため、自信を持って行動することができます。
自分に自信がある人は自分の意見をしっかりと主張することができ、自分のやりたいことに積極的に取り組むことができます。
また、失敗や挫折に対しても前向きに取り組むことができ、成長することができます。
さらに、先ほども述べたように自己肯定感が高い人はストレス耐性が向上します。
ストレスに対する抵抗力が高いため仕事や学校でのプレッシャーにも強く、うつ病や不安障害の発症率が低くなるとされています。
また、自己肯定感が高い人は、人間関係も良好です。
自分自身を肯定的に見ることができるため、他人にも同じように接することができます。
そのため友人や家族とのコミュニケーションが円滑になり、良好な関係を築くことができます。
以上のように自己肯定感を高めることよるメリットをまとめると以下のようになります。
- 自信を持って行動できるようになる
- ストレス耐性が向上する
- 人間関係が良好になる
▶︎セルフラブとはどんな意味?自分を愛す方法や自己肯定感との違いを解説
自己肯定感を高めるのに効果的な8つの習慣や行動

自己肯定感を高めるためには、以下のような習慣や行動が効果的です。
ポジティブな自己イメージを持つこと
自分の良いところを認め、自分に対してポジティブな考え方を持つことが大切です。
毎日の積み重ねで、自分に対するポジティブなイメージが定着していきます。
認知行動療法(CBT)を取り入れること
認知行動療法は、自分の考え方や行動を変えることで、自己肯定感を高める手法です。
自分の考え方や行動について客観的に見直すことで、ポジティブな自己イメージを持つことができます。
ノートに書き込むこと
毎日自分の良いところや成果をノートに書き込むことで、自己肯定感を高めることができます。
自分の成長を実感することができ、自信に繋がるでしょう。
賞賛されたときは素直に受け取ること
自分の良いところや努力を認められたときは、素直に受け取りましょう。
自分に対する評価が高まるため、自己肯定感を高めることができます。
目標を設定し、達成すること
目標を設定し、その達成過程で自分自身の成長を実感することができます。
達成感や自信に繋がり、自己肯定感を高めることができます。
自分自身を適切に評価すること
自分自身を適切に評価することが大切です。
過度な自己評価は自己肯定感を下げる原因となるため、客観的に自分自身を評価することが必要です。
自分に優しく接すること
自分に対して優しく接することで、自己肯定感を高めることができます。
自分自身に対して厳しすぎることは避け、自分の良いところを認め、自分に対して優しく接しましょう。
自分自身を比較しないこと
他人と比較して自分自身を評価することは避けましょう。
自分自身と過去の自分自身を比較して、自分自身が成長していることを認めたり、目標に向かって進んでいることを意識することで、自己肯定感を高めることができます。
自己肯定感を高めることができる言葉

自己肯定感を高める言葉は人によって異なりますが、以下のような言葉が一般的に有効とされています。
- 「自分ならできる」という言葉を自分にかける。
- 「自分は大丈夫だ」という言葉を自分にかける。
- 「自分を信じる」という言葉を自分にかける。
- 「自分には価値がある」という言葉を自分にかける。
- 「自分は素晴らしい人間だ」という言葉を自分にかける。
- 「自分には才能がある」という言葉を自分にかける。
- 「自分は成功することができる」という言葉を自分にかける。
- 「自分は幸せな人間だ」という言葉を自分にかける。
これらの言葉は、自分自身に対してポジティブなメッセージを送ることで、自己肯定感を高めることができます。
また、言葉だけでなく行動によっても自己肯定感を高めることができます。
具体的な習慣や行動については、前述した通り、自分自身に合ったものを選択することが大切です。
自己肯定感を高めると恋愛や仕事は上手くいく?

自己肯定感を高めることは、恋愛や仕事において上手くいく可能性を高めることがあります。
自分自身を肯定的に評価できるようになると、自分に自信を持って行動することができるようになります。
恋愛においては、自分に自信を持っている人はより魅力的に見えるため、自分に合ったパートナーを見つけやすくなるでしょう。
また、仕事においては自分自身を肯定的に評価することで、自分の能力に見合った仕事を選び、仕事に取り組む姿勢が前向きになることがあります。
しかし、自己肯定感が高いからといって、必ずしも成功するとは限りません。
自己肯定感を高めることは、あくまでも自己成長のための一つの手段であり、それ自体が目的ではないということを心にとどめておきましょう。
▶スキンシップにはどんな効果がある?良好な関係性を維持するためのポイントとは
子供の自己肯定感を高める方法とは

子供の自己肯定感を高める方法は、声かけや子育ての中での態度や行動によって大きく影響されます。
まずは子供が自己肯定感を育てるために、親が自己肯定感を持つことが重要です。
親が自分を肯定する姿勢を見せることで、子供も自分自身を肯定することができるようになります。
また、子供が自分でできることを認めてあげたり、賞賛してあげたりすることも大切です。
例えば、小さなことでも「すごいね」と褒めたり、「ありがとう」と感謝の気持ちを伝えたりすることが、子供の自己肯定感を高めることにつながります。
一方で、否定的な言葉や比較をする言動は、子供の自己肯定感を低下させることがあります。
例えば、「○○ちゃんはもっと上手にできてるよ」と比較したり、「もう一回やりなさい」と言われると、自分自身の能力に自信を持てなくなってしまうでしょう。
そのため、子供の自己肯定感を高めるためには自分で考え判断し、行動することを尊重し、積極的な声かけや肯定的な態度を心がけることが大切です。
▶自己肯定感が低い子供の特徴や言動とは|注意すべき親の発言や行動
まとめ
自己肯定感を高めることは心理的健康や幸福感を促進する上で重要であり、習慣や言葉を使って実現できます。
具体的には下記のような考え方が大事です。
- 自分に寛容になること
- 感謝の気持ちを持つこと
- 自分自身に対して肯定的な言葉をかけること
- 自分の成功を認めること
- 自分自身を比較しないこと
また、子供の自己肯定感を高める方法としては、声かけや子育ての方法を改善することが挙げられるでしょう。
自己肯定感が高まると恋愛や仕事でも積極的に行動でき、自分自身の人生をより充実したものにすることができます。
監修者紹介

– アフリカンペイントアーティストSHOGEN(ショウゲン)-
タンザニアの小さな村で描かれるティンガティンガというペンキアートに心惹かれ、
日本での生活を捨て、なんの伝手もないまま単身アフリカへ・・・
現地で生活をしながらキャンバスだけなく、警察車両やホテル内の壁画に描くなど、
動物と子供を共存させた作風で独自の表現を追及する。
ティンガティンガ創始者Edward Saidi Tingatingaがおこなっていた“人々を幸せにする絵”への到達を目指す。
日本に制作の場を移した後は、キャンパスだけにとらわれない多方面での活躍を続けている。
生きる喜びを描くペンキ画家
自己肯定感の意味をわかりやすく解説|自己評価や自尊心との違いとは?
はじめに
自己肯定感とは、自分自身を肯定することができる心の状態のことを言います。
ちなみに読み方は「じここうていかん」です。
本記事では、自己肯定感の意味や、自己評価、自尊心といった似ている言葉との違いをわかりやすく解説します。
自己肯定感の意味とは

自己肯定感とは、自分自身を受け入れ、自分を肯定する感覚や信念のことを指します。
つまり、自分に対して自信を持ち、自分の価値や能力を認めることができる精神的な状態のことを指します。
自己肯定感が高い人は、自分自身に対して常にポジティブな感情を持ち、前向きな気持ちでいることができます。
一方で、自己肯定感が低い人は自分自身に対してネガティブな感情を持ち、自分を否定したり卑下したりする言動が目立ちます。
自己肯定感は人間関係や仕事、学業など、あらゆる面において重要な役割を果たします。
自己肯定感と似ている言葉との違い
自己肯定感と似ている言葉には、「自己評価」や「自己効力感」、「自尊心」などがありますが、それぞれ微妙なニュアンスの違いがあります。
自己評価
読んで字の通り自分自身に対する評価を表す言葉で、自分がどの程度価値があると思っているかを示します。
自己効力感
自己肯定感とは異なり、自己評価は自分の能力や行動に対する評価も含む言葉です。
自分が目標を達成する能力を持っているという信念や自信のことで、自己肯定感と同様に自己信頼感に関連しています。
自己効力感は特定の行動や目標に対する信念を示すのに対し、自己肯定感はさらに幅広い感情や自己の総合的な評価について述べるものです。
自尊心
自分自身に対する感情的な反応を指す言葉で、自分自身に価値があると感じることを意味し、自己肯定感と同様の意味合いがあります。
自尊心は感情的な反応を示すのに対し、自己肯定感は、より理性的で認知的な評価に重点が置かれるというのが違いです。
自己肯定感を高めるべき理由

自己肯定感を高めるべき理由としては、自分自身や周りの人々との関係性を改善することが挙げられます。
自己肯定感が低いと自分を責めることが多くなり、自信を持てなくなります。
他人からの良い評価を素直に受け取れなくなることもあるため、しばしば自分自身や周りの人々との良好な関係性を築くことが難しくなります。
自己肯定感が高い人は自分自身に自信を持っており精神的な余裕が生まれるため、自分だけでなく周りの人々にも気を配ることができ、良好な人間関係を保つことができます。
また、自己肯定感が高いと、ストレスや不安を感じることが少なくなり、健康的な生活を送ることができるとされています。
自己肯定感を高めることで自分自身を肯定し、ポジティブな心理的影響を受けられるようにしましょう。
自己肯定感は環境に左右されやすい

自己肯定感は環境によって左右されることがあります。
例えば家庭環境が悪かったり、周りの人が否定的な言葉を投げかけたりすると、自己肯定感が低下することがあります。
また、社会的な価値観やイメージが強く反映されるSNSなども、自己肯定感に影響を与えることがあるとされています。
そのような環境の中で自己肯定感を高めるためには、自己肯定感を強化するプログラムやセルフヘルプ本などを利用することが有効とされています。
▶自己肯定感が低い子供の特徴や言動とは|注意すべき親の発言や行動
自己肯定感はSNSに影響される

近年SNSの普及に伴い、自己肯定感に与える影響が注目されています。
SNSを利用することで、自分の投稿やアップロードした写真に「いいね!」や「コメント」が付くことで、一時的な自己肯定感を得ることができます。
しかし、SNSには自分と他人との比較が容易になるというデメリットもあります。
自分の投稿に「いいね!」が少ない場合や、他人の投稿に比べて自分が魅力的でないと感じた場合には、逆に自己肯定感を低下させる可能性があります。
また、SNSでは加工した写真や美しい風景、成功した自分をアピールする傾向があり、それによって現実とのギャップを感じ、自己肯定感に低下につながるケースも多いようです。
SNSの利用方法によっては自己肯定感を高めることも下げる可能性もあるので、適切な使用方法を心がけることが重要です。
自己肯定感が高い人と低い人の違い

自己肯定感が高い人と低い人の違いは様々な面で見られます。
以下は自己肯定感が高い人の特徴です。
- 自分に自信があり、自分の能力や価値を肯定的に捉える
- 失敗や批判に対しても前向きに捉え、自分の成長の機会として受け止める
- 他人と比較することにあまりこだわらず、自分が望む方向に向かって自分自身を発展させようとする
続いて自己肯定感が低い人の特徴を見ていきましょう。
- 自分に自信がなく、自分の能力や価値を過小評価してしまう
- 失敗や批判に対して消極的になり、自分自身を責めたり、自信を喪失してしまう
- 他人と比較してしまい、自分自身を否定したり妬んだりする
以上のように、自己肯定感が高い人と低い人では、たとえ全く同じ状況に置かれていたとしても、自分自身の現状をどのように認識し、今後どのようにアプローチしようと考えるかが大きな違いとなるでしょう。
▶自己肯定感が低い人の原因とは|実はプライドが高い?親のせい?
まとめ
自己肯定感には「自分を肯定することができる力」という意味もあります。
自己肯定感は他人からの評価や環境の影響を受けやすく、概して低くなりがちですが、高い自己肯定感を持つことことができれば自信を持ち、ストレスを軽減することができます。
また、SNSなどの外部環境も自己肯定感に影響を与えることがあるとされています。
自己肯定感が低い人はついつい他人と比較してしまいがちです。そのため、SNSを見て自己肯定感が下がってしまうことが多いのであれば、一度離れてみるというのも選択肢の一つでしょう。
自己肯定感を高めるためには、自分自身を否定的に捉えないようにすることや、自分が得意なことを活かすことが大切です。
監修者紹介

– アフリカンペイントアーティストSHOGEN(ショウゲン)-
タンザニアの小さな村で描かれるティンガティンガというペンキアートに心惹かれ、
日本での生活を捨て、なんの伝手もないまま単身アフリカへ・・・
現地で生活をしながらキャンバスだけなく、警察車両やホテル内の壁画に描くなど、
動物と子供を共存させた作風で独自の表現を追及する。
ティンガティンガ創始者Edward Saidi Tingatingaがおこなっていた“人々を幸せにする絵”への到達を目指す。
日本に制作の場を移した後は、キャンパスだけにとらわれない多方面での活躍を続けている。
生きる喜びを描くペンキ画家
アフリカンペイントアーティストSHOGEN(ショウゲン)オフィシャルサイト
体調を崩しやすい季節に。
立ち寄り蒸し屋「Mushiya」でスキマ時間に温め美容
眉ティントやあぶらとりウォーターパウダーなど、斬新なアイデアコスメが次々とヒットしているコスメブランド「Fujiko」(フジコ)がよもぎ蒸しサロンをプロデュース。キレイになりたい!をベースにしながら、女性特有のさまざまな悩みに寄り添うサロン「Mushiya」(ムシヤ)とは?
1時間の温めケアで心身ともにリフレッシュ

体を温め、血流を促すことで美容や健康、リラックス、デトックスを目的に人気を集めているよもぎ蒸し。薬草を煮出した蒸気を膣から粘膜吸収させていくことで産後の肥立ちが良くなるとされ、韓国では古くから産後ケアとして取り入れられていた伝統的な民間療法です。腕の内側を1とした場合、約42倍の吸収率といわれる膣の粘膜から、薬効成分を含んだ蒸気を体内に浸透させることで顔や身体に現れる女性特有の悩みや不調の軽減が期待できるといわれています。

落ち着いた雰囲気の居心地のいい個室。
「Mushiya」は“立ち寄り蒸し屋”をコンセプトに、約1時間でカウンセリングから着替え、蒸し、メイク直しができる設計。メイクルームでは「Fujiko」をはじめとする株式会社かならぼが手がける「BIDOL」「4U」のコスメが自由に使えたり、アイロン、ドライヤー類などを完備。よもぎ蒸し後、そのまま仕事に戻ったり、遊びに出かけられるのも通いやすいポイント。

BASICブレンド¥4,000、季節ブレンド¥4,000、Specialブレンド¥6,500を用意。
薬草には韓国韓方よもぎブレンドと純国産よもぎブレンドを使用し、さまざまなお悩みに合わせた、9種類のこだわりのブレンドを用意。子宮/自律神経/免疫/ダイエット/美肌のお悩みに合わせた5種のBASICブレンド、季節ブレンドが1種、本気でキレイを目指したい方にオススメのSpecialブレンドが3種。使用する水は不純物を極力カット。蒸し窯は黄土を採用し、電気窯とは一味違うじんわりと身体の芯から温まるような心地良さを味わうことができます。
そして忙しく限られた時間のなかでも、簡単に、思う存分リラックスできる空間づくりにもこだわりあり。個室で誰にも邪魔されることなく、瞑想をしたり、自分だけの時間を過ごせます。
サロンオープンを記念して9/8までの期間、全メニューが20%オフになるキャンペーンを実施中(初回のみ)だそう。内と外との気温差により、体に負荷がかかり体調不良を起こしやすい季節。気軽に立ち寄れるよもぎ蒸しで、キレイと健康を叶える温活を始めてみては?
Mushiya
東京都渋谷区恵比寿西1-17-1えびす第一ビル8F
03-6433-7876
https://mushiya.salon/
感動の瞬間をどれだけキャッチできるか。それが人生の原動力【シンガーソングライターAK Akemi Kakiharaの衣食住遊学】
いつも元気で幸せそうなひとは、自分の周りに“楽しいこと”を育てる種をまいています。そんな魅力的な方にHummingなライフスタイルのトピックスを伺うシリーズ記事「わたしの衣食住遊学」。今回は、NYを拠点に世界デビューを果たし、多岐にわたり活躍するシンガーソングライターAK Akemi kakiharaさんに登場していただきました。
いつまでも新しい夢に向かって前に進みたい

東京お台場で開催されたBody & Soulでの凱旋ライブの様子。
日本で作詞作曲家、アーティストとして成功を手にしながらも、新たな挑戦を求めてNYに移住。今、世界を視野にシンガーソングライターとして活躍するAKさん。この春にリリースされた新曲の「Beautiful You」もヒット中で、その透き通る歌声とオリジナリティ溢れるメロディが多くの人々を魅了しています。楽曲制作やレコーデイングと、多忙な日々を送るなかで、東日本大震災の追悼式展を主催したり、アフリカ難民の子供たちへのサポート活動を精力的に続けています。そんな彼女に、人々に癒しをもたらしながら、自身も日々を豊かにと心を砕く日常について伺いました。
「衣」
まとうことでもらえるエネルギーを楽しむ

肌ざわりのいいレースで着心地がすごく良く、シルエットもお気に入りだという、セルフポートレートのドレス。繊細なレースやメッシュを使ったフェミニンなスタイルが得意なブランド。© Romi Uchikawa
服が大好きで、白やピンク、ナチュラルな色のものを着ることが多いです。年齢を重ねるほどに、一生のなかで自分が着こなせる服の数は限られていくのだと思うと、もっとおしゃれを楽しみたい、いろんな色やデザインにチャレンジしてみたいと思うようになりました。
服選びの際には、オーガニックコットンやリサイクル糸を使っているかなど品質や素材も必ずチェックしますが、まず第一に、試着したときの肌に触れた感じ、服の質感や着心地にこだわっています。何よりも、着たときに自分がどう感じるかを大切にしたいのです。
フッションには、80年代、90年と、年代によってその時々の流行りがあったと思いますが、今の時代はいろんなものがミックスされていて、今までだったらこれは選ばなかったなというようなアイテムにもトライしてみたいと思うようになりました。

ブラウスは、NYを拠点に活躍中のデザイナーキャロライン・コスタス。遊び心のあるバルーンスリーブが目を引く。素材も気持ち良く、ほどよいストレッチの効いたパンツはラグ&ボーン。レコーディング中は長時間缶詰になるので、着心地の良さは必須。服はそのときに創っている音楽の雰囲気や歌詞に没入しやすいアイテムを自然に選んでいることが多いそう。
以前だったら、このデザイナーのこのデザインがカッコいい、おしゃれとかそういう目線だったのが、最近は、デザイナーの気持ちとか、その服が作られた背景に興味があります。デザイナーがどういう気持ちでこの服を作ったのかを、考えながら着るのも楽しい。
服も音楽も、ものを“つくる”という意味では過程は似てると思います。まっさらな白いキャンバスの上にアイデアを重ねて、思い描いているものを形にしていく。デザイナーが服を作っているときの背景を想像したり、作り上げたときの喜びやエネルギーが伝わってくると感動します。
「食」
料理を作ることは癒し、もてなすことは歓び

友達を招いてディナーパーティーを催すこと、誰かのお祝いごとをホストしておもてなしすることが大好きです。テーブルセッティングはパーティーのコンセプトによって変わりますが、どんな構成にするのかを考えるのも楽しくて!
とにかく料理すること自体も大好き。仕事柄、曲の制作に没頭していることが多いので、その間は集中するし、緊張が続きます。どこかでブレイクを取りたいときに、料理することが最大の息抜きでもあり、癒しの時間。とにかく無心になれますね。

アスパラガスのスープ。野菜を中心にできるだけ旬のものを使い、ヘルシーであることをベースにしているそう。
食べるものが体をつくっていると信じているし、美味しくてヘルシーなものを食べて健康になれるなら最高でしょ? せっかく自分の手で作るならば、できるだけヘルシーなものにしたいと心がけていて、オーガニック、ヴィーガン、グルテンフリーの素材を積極的に取り入れています。
材料は、基本的に野菜が中心で、どれだけフレッシュでナチュラルなものを自分の体に取り込めれるかを常に考えています。油はオリーブオイルがメイン。塩、砂糖はできるだけ避けて、水はたっぷり摂ります。

パーティーのテーマに合わせてケーキのデザインもAKさんが考案。写真はマシュマロを使い、ウサギをデコレーション。中にはピーチコンポートのサプライズを。
友達や家族を私の料理でおもてなしするのは、至福の喜びです。「ひとと一緒に食事をすることはすごく大事なこと」と、とあるひとから言われたことがありましたが、本当にそうだなと実感しています。私の作った料理を食べて「美味しい」と言ってもらえることと、私の音楽を聴いて「癒されました」って言ってくれることは一緒。ひとを幸せな気分にできたら、私自身が幸せなのです。
「住」
五感に響く、自然からのインスピレーション

ニューヨークから飛行機で45分、ナンタケット島というマサチューセッツ州の東海岸沖に小さな島があります。NYで生まれ育った夫(ダニー・クリビット)が、子供のころから夏を過ごしていた島で、ダニーのママであり、私の義理の母が移住したこともあり、今も時間ができると年に一、二度は必ず訪れています。古き良きアメリカという雰囲気で、自然あふれるのどかな島。

ナンタケット島の代表的な家屋。木の温もりを感じられる造りで、配色は白、グレーなどナチュラル系。ノスタルジックな自然に溢れていて、美しい草木、花に囲まれている家が多い。写真の白い花は、AKさんが大好きなライム・ハイドレンジャー(ライム色の紫陽花)。
私は『Summer of 42』(邦題『おもいでの夏』)という映画の世界観が大好きで、ナンタケット島はそのロケーションと似ているんです。映画の舞台はニューイングランドの島なのですが、ナンタケットも“南のニューイングランド”と言われているんですよ。美しい水と砂浜、そして、メインの街並みは石畳でとてもノスタルジック。薬局やジューススタンドも、どこか懐かしい風情です。そんな、自然とノスタルジックが融合した世界観は、私の故郷を思い出させて、どこか懐かしく、切なくもあるのです。
私が生まれたのは、広島県福山市の駅家町というところで、家の周りには自然がいっぱい。山と川、そして緑に囲まれて育ったので、ナンタケットにいると子供時代の思い出がよみがえります。自然と親しんで育った私には、花の香り、海の香り、自然の音や風、太陽の光ーーがとても必要だと感じています。

NYブルックリン、ウイリアムズバーグにある自宅の窓からの眺め。目の前にはイーストリバーが広がっています。
小さいころには、れんげを摘んで首飾りを作るとか、干し草を積んでベッドでにしたり・・・そういうときの匂いや感触は、私の五感に大きく影響していて、記憶に刻まれています。自然が私の心に与えてくれるインスピレーションはとても大きいのです。NYにいても、無意識に空を見上げたり、自宅の窓から目の前に広がるイーストリバーの景色を飽きることなく眺めたり、川の流れや光や風を感じて生活しています。
「遊」
音楽は私にとっての心の遊び場

ブルックリンのウイリアムズバーグにて。撮影の合間に、置かれていたストリートピアノを見つけて弾き始めるAKさん。 ©Romi Uchikawa
映画音楽やジャズが好きな父の影響で、家には音楽が溢れていました。5歳からエレクトーンを習って、『シェルブールの雨傘』や『男と女』などの映画音楽を弾いて、ちょっとおませな子供でした。私が8歳のときに、クロスオーバーと呼ばれたエウミール・デオダートの『プレリュード』を父が買ってきて、そのアルバムを聴いたことが私の運命を変えました。深く心を打たれて、“私もこんな曲を創りたい!”と思い、8歳からエレクトーンで曲を創り始めました。創った曲はボサノバ。デオダートにそっくりな曲でした(笑)。

NYにあるマスタリングスタジオ「Sterling Sound (スターリングサウンド)」でレコーディングの最終プロセス、マスタリング中の一枚。
そのころはまだ、将来音楽が仕事になるなんて思ってもいなくて、ただ“こんな曲を創りたい”という気持ちで心の赴くままに創っていました。詩は10歳くらいから書いていて、中学3年の時には“将来はシンガーソングライターになりたい”と決意。高校の学祭などでパフォーマンスもするようになり、日芸(日本大学芸術学部)の大学3年、21歳でデビュー、それまで書き留めていた曲でデビューアルバムをつくりました。
私には、音楽を創ること = 仕事という感覚はあまりなかったですね。音楽は好きだし、曲を創ること自体も好きで、気が付いたらそれが自然に仕事になっていました。音楽って「自分が楽しめないと人にも楽しんでもらえない」と思っているので、まずは自分が心から大好きと思えて、楽しめることが大事だと思っています。

写真奥は、夫でDJのダニー・クリビットさん。
「楽しい」「切ない」「うれしい」「悲しい」「幸せ」ーーそういうすべての感情を音楽で表現できる。そして、その音楽を奏でてるとき、聴いてるとき、その感情に浸れるのです。
例えば、ダンスミュージックを聴いてると自然に踊りたくなるし、ロマンチックな曲を聴いてると恋心をくすぐられて、誰かに恋をしたくなるかもしれない。音楽には心を豊かにしてくれる魔法がいっぱい。心のビタミン剤でもあり、エモーションの宝庫であり、音楽は私にとって「心の遊び場」のようなもの。そして、曲を創るためのレコーディングスタジオは、フィジカルな遊び場という感じかな。
「学」
子供たちから気付かされる夢と可能性の大切さ

アフリカ、ガーナのボナイリ村にあるMY DREAM.org(mydreambridgethegap.webs.com)代表 原ゆかりさんが作ったMY DREAMスクールの子供たちと一緒にコンサートをするAKさん。
東日本大震災がきっかけで、それ以降、被災地を何度も訪問してボランティアとして現地に出向いてコンサートを行いました。そこで、子供たちとの触れ合いを続けるなか、もっと彼らを支援したいという気持ちが芽生えて、2013年に「I FOR DREAM」というプロジェクトを立ち上げました。それが、私の「世界中の子供たちの夢とモチベーションを育てる支援」の始まりでした。
そんな折に、子供支援への情熱を分かち合い、DREAMという共通のテーマでアフリカの子供支援をしている元外交官の原ゆかりさんと出会いました。そしてアフリカの子供たちのために曲を創る機会をいただいたのです。
世界の子供たちの未来が、家族、友達、愛、そして、感動の瞬間であふれ、夢が叶うことを願って、「夢は叶う」というメッセージを込めた『MY DREAM』という曲を完成させました。そしてこの歌を通して、世界の子供たちをつなぐ「MY DREAMソングプロジェクト」を展開しました。

アフリカのボナイリを訪問したとき、無垢で純粋な子供たちがとても生き生きとしていて、喜びと幸せが溢れていることを感じました。誰かと自分を比べることもなく、困難な状況や過酷な環境であっても、そこにあるもの、自分の周りにあるものを素晴らしいと思える気持ちで満たされている。どんな場所からも、アイデアと情熱と実行力があれば、何かを生み出すことができる。物事は、捉え方一つであり、夢や願いごとは叶えることができるのだと気付かされました。
有名な例え話ですが、コップの水をこぼしてしまったときに、残った半分の水を見て「半分しかない」と思うか、「半分も残っている」と思うか。私はできるだけ「半分もある」っていう気持ちでいたいというのが根底にあります。人生はその人の感じ方や捉え方次第で、幸せだと感じるか否かも、そのひとの心の判断次第。何事もポジティブに捉えていきたいと思います。
ボナイリの子供たちにとって、夢や可能性を持つことが、希望の原動力になっているのを見て、いつまでも夢に向かって前に進み続けるということを彼らからも学びました。そして、諦めずに前に向かって進んでいくことで、幾つになっても学びを得ることができるのだと思っています。

被災地でもあった福島県相馬市、みなと保育園の園児たちと。”夢はきっと叶う”というメッセージを込めた『My Dream』という曲を創り、コンサートを開催。
私の人生で大切にしているものは、家族、友達、愛、そして感動の瞬間をどれだけキャッチできるか。大切なひとたちと分かち合う貴重な体験や時間を幸せだと感じることができるのも、自分の心がそれを幸せだと感じるチカラがあってこそ。感動をキャッチできるかどうかは、自身の感受性次第ですから。自分自身や心の在り方をどのように保ち、成長させるか。私にとってそれは一生の学びです。
音楽の才能を最大限に活かして、ひとを癒し、ひとを癒すことで自身が癒され、喜びを見出しているAKさん。その姿が、衣食住遊学のすべてを大切に、“感動すること”に積極的であることが、日々の充実と幸せにつながることを伝えてくれます。あらゆる感情を表現できる音楽で、彼女が世界に向けて語り掛けるメッセージにも注目していきましょう。
森カンナ「なぜ年齢に縛られているのだろう」【連載 / ごきげんなさい vol.10】
俳優 森カンナさんが日々の生活のなかで見つけたこと、感じた想いを綴る連載エッセイ「ごきげんなさい」。自分を“ごきげん”にするためのヒントを探しましょう

「歳の数」
あるときふと自分の名前がネットニュースに上がっているのを見つけた。
森カンナ(34)が〇〇〇〇(30)と〇〇〇〇(45)にどうたらこうたらみたいな感じで名前の隣に丁寧に年齢をご紹介してくれていた。
思えば、日本のメディアはほとんど、人の名前と一緒に年齢が表記される。海外では考えられないことだろう。
一体なぜ日本人はこんなにも年齢に縛られているのだろう。
確かに、日本語にはものすごく細かい敬語がある。
この人には敬語を使うべきなのかタメ語でいいのか。という精査をしなければならないのも分かる。だがそれと、この日本人の何ともいえない、年齢に囚われている感は別だと思う。
この話をアメリカ人の友人に話してみた。
友人もずっと不思議に思っていたらしい。「日本人は気付いてないと思うけど、とにかく年齢の話が好きだよね〜」と・・・。
確かに、アラサー、アラフォー、アラフィフ、美魔女、イケオジ、結婚適齢期。みたいな年齢にまつわる不思議な言葉もたくさんある。
ドラマや映画でも、35歳崖っぷちヒロイン!運命の相手が現れるのか!?-ーみたいなのもよ〜く目にする。いや、まったくもって崖っぷちではないだろ・・・と思いながら、日本のこのロリコン文化にうんざりしたりする。
年齢を重ねることで人は成長するし、経験も積める。幅も視野も広がる。なのに何故、生きた年の数字が増えていくだけのことを、こんなにもネガティブに受け止めている人が多いのか。
私はそんなことを気にするよりも、年齢を重ねるにつれて滲み出てくる人相を気にした方がよっぽどいいと思う。
政治家の方でも政治家になりたてのころと現在の人相の違いに驚くことがある。
年齢を重ねるたびに、心のなか、魂がどんどん目や口の外側にあらわれ出す。どんなに取り繕ろっても、いろんな手段で顔年齢を巻き戻そうとしても、滲み出ているので嘘はつけなくなると思っている。
自分自身でもパッと鏡に映った顔を見ると、おっ良い顔をしてるじゃん!ってときと、何というひどい顔をしていたんだ!とびっくりするときがある。
何歳からおばさんかしら?なんて考えるより、毎日気持ちよく、“良い顔で生きるには”を考えて、年齢を重ねていきたいものだ。
それではごきげんなさい(^_^)

私の友人の菊乃、堺小春姉妹の母の岡田美里ちゃん! いつもキラッキラな笑顔で出迎えてくれる。こんなふうに歳を重ねていきたいと、会う度に思う。本当に素敵な人だ。
Profile
森カンナ(もりかんな)
俳優。富山県出身。映画やドラマなど数々の作品に出演。2021年には、自身初舞台となった蓬莱竜太演出『昼下がりの思春期たちは漂う狼のようだ』で、600人のなかからオーディションによって選ばれ、観客を魅了した。2022年は、フジテレビ4月期月9ドラマ『元彼の遺言状』1話・2話にゲスト出演、フジテレビ2週連続ドラマ『ブラック/クロウズ~roppongi underground~』にレギュラー出演。そして、先日スタートした7月期カンテレ月10ドラマ『魔法のリノベ』にも1話ゲスト出演した。
https://kannamori.com/
Instagram @kanna_mori
話題のCBDをヴィーガンカフェで!心も体も上向きに【渡辺知夏子のエシカルスポットNavi. vol.09】
普段の何気ない暮らしのなかで、サステナブルなアクションが出来たら素敵だと思いませんか? エシカルなライフスタイルを提案しているレストランやショップを、自身もウェルビーイングな生活を心掛けているというモデル渡辺知夏子さんがナビゲート。今回は、食べるマインドフルネスとして注目されているCBDを取り扱ったヴィーガンカフェ『HEMP CAFE TOKYO(ヘンプ カフェ トウキョウ)』をご紹介します。
HEMP CAFE TOKYO

今、世界中で注目を集めている「CBD」をご存知ですか? CBDとはカンナビジオールの略称で、大麻草に含まれる成分の1つ。大麻草と聞くとドラッグをイメージする人が多いと思いますが、それは大麻草に含まれる別の成分です。
CBDには心身の不調改善やホルモンバランスの調整をする働きがあるとされ、近年では医療の分野など、さまざまなシーンで使用され始めています。もちろん、日本でも合法的に使用することが可能。このCBDにいち早く着目したのが、恵比寿にある『HEMP CAFE TOKYO』です。

店内は白を基調にポップなインテリアをアクセントにしたカジュアルな雰囲気。
「CBDの摂取方法はいくつかありますが、ここではヘンプシードやCBDオイルを使って食品から摂り入れてもらうようにしています。また、提供するメニューはすべてヴィーガン。健康に気を配っている方からイスラム教徒の方、そして美容に関心の高い方もよく来店されます」と語るのは、オーナーの宮内達也さん。前職は消防士という、異色のキャリアの持ち主です。

HEMP CAFE TOKYOオーナー 宮内達也さん。物腰柔らな雰囲気と気さくな人柄で、スタッフからの信頼も厚い。
「昔から食べることが大好きで、実は中学生までは肥満気味でした。高校では運動部に所属したことでだいぶ体を絞ることができ、さらに就職後は消防士という職業柄かなり筋肉質な体型に。それでも食べることへの探究心は衰えることがなく、暇を見つけては料理を作る毎日だした。
最初は自己流でレパートリーを増やしていたのですが、それだけでは飽き足らず、休日にはフレンチのお店で料理人としてアルバイトをするまでに(笑)」
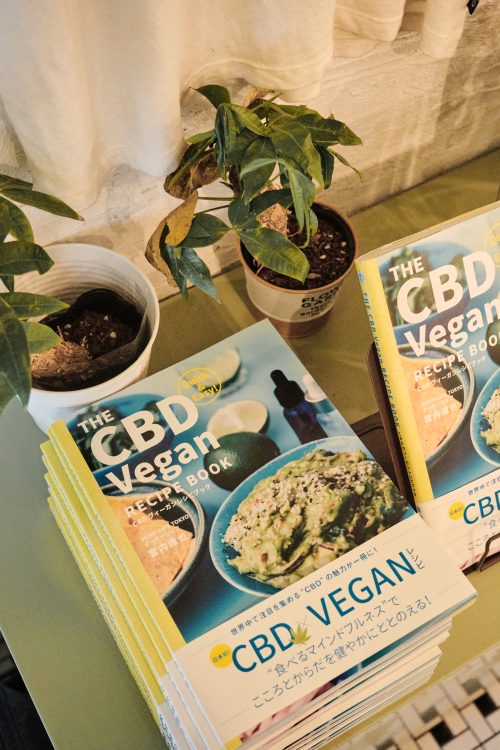
CBDやヴィーガンについてより深く知ってもらうために、クラウドファンディングを利用して制作された書籍。オリジナルレシピをたくさん掲載。
しばらくは二足のわらじ生活を続けていたものの、自分の店を持ちたいという願望が抑えきれず、消防士を退職。翌年にはお店をオープン。そして、CBD&ヴィーガンの専門店と決めていたことには、大きな理由がありました。

つい長居してしまいそう、居心地のよいソファ席。
「消防士を辞めてからは筋肉が落ちてしまい、リバウンドしてしまったのです。そのときに巡り合ったのが、ローフードシェフの加藤馨一氏。そこでCBDの存在を知るようになりました。
健康というのは肉体だけでなく、精神面も整っていなければ意味がないので、その両方を一緒に口にすることができるのはコレしかない!と思いました」

店内に置かれているアルコールはすべてオーガニック。オリジナルビールも販売されています。
オープン当初はCBDの認知度が低かったこともあり、主原料のヘンプを店名に掲げることに。そのため、大麻を扱っているお店と勘違いされ、ちょっとしたトラブルに見舞われたことも今では笑い話に。
そんな宮本さんの思い入れたっぷりのお店で提供される食事は、さすがフランス料理仕込みだけあって、どのメニューもおしゃれなうえに味も格別!

店内の壁に描かれているグラフィックは、新世代アーティストとしてラルフローレンやディーゼルの店内アートなどを手がけるCOIN PARKING DELIVERYの作品。彼もこのお店の常連。
「見た目へのこだわりはもちろん、食材にもしっかりとこだわって作っています。おかげさまで料理のファンも段々と増えてきて、アスリートの方も多く集まるように。最近ではエシカルな意識の高い方々にも、足を運んでいただけるようになりました。
いつ来てくださっても飽きることのないよう、これからも新メニュー作りに精進するつもりです。この店を訪れた方に楽しい食体験をしてもらうーーということは、オープン当初から変わらない目標です」
美の賢人の間で話題のCBDを初体験!

自他ともに認める健康マニアの千夏子さん。もちろんCBDの存在は知りつつも、まだ口にしたことはなかったのだそう。
「CBDは原液をスポイトで数滴口にするのが主流だと思うのですが、苦くて不味いイメージが強くて。『良薬口に苦し』とは言うものの、継続するのは難しいなと思ってしました。でも、料理やドリンクで摂り入れられるなら楽しめそう!」

心を躍らせて扉を開けると、目の前にはリラックス感あふれる明るい空間が広がっています。おしゃれなインテリアに加え、スタッフの皆さんがとても気さくな印象。
さらにいろいろなCBDアイテムがディスプレイされていて、定番のオイルは数種類が並んでいます。初心者でも口にしやすいグミも販売中。他にも店舗オリジナルのTシャツやグッズが。

ヘンプとオーガニックコットンを使用したオリジナルTシャツは、何回洗濯しても全然ヘタらないと、隠れたヒット商品とのこと。手軽にヴィーガン料理が食べられる、レトルト食品もあります。

こちらのコーナーも、全てCBD関連の商品。「オイル、グミやキャンディなど品揃えが豊富。スタッフの方全員がCBDに詳しくて、オイルも試飲することができるので失敗することもなさそう」と知夏子さんは気になるアイテムをいくつも見つけた様子でした。
ゆったりと寛げるのが人気のソファ席を案内されると、早速気になる食事をいただくことに。

ジャンルは無国籍料理なのだそう。どれも美味しそうで、迷いながら吟味するのも楽しい時間。
いろいろ悩んだ末、最初にオーダーしたのは、ランチタイムで一番人気という石焼ビビンバ。

「ヴィーガンのビビンバなんて聞いたことがなかったので、これは絶対にオーダーしようと決めました。カラフルな見た目で香りも良く、しかも食べるとコクと深みを感じます。これでお肉を一切使っていないとか、あり得ないです!(笑)」

焙煎玄米ライスの上に特製ミート、自家製キムチ、人参ナムル、チーズをふんだんに乗せ、オリジナルマヨネーズで味付け。石焼韓国風ビビンバ ¥1,680
期待していた以上の味に驚いた千夏子さん。次は、メキシカンフードを数種類オーダーし、パーティー気分を味わうことに!

「どれもシェアしやすいボリューム感で、お酒のおつまみにもピッタリ! 普段はあまりアルコールを飲みませんが、こちらのお料理に合わせてつい飲みたくなってしまいますね」

早速、オリジナルのCBD恵比寿ビールを片手に乾杯! CBDが25mg含まれた名物ビールなのだとか。爽やかな見た目どおり、フルーツのような味わいとスッキリとした喉越しに大満足。
こちらのビールにも、すべてのドリンクにCBDドロップを+¥300で追加オーダーすることが可能です。

「宮本さんイチオシのタコス。自家製のチリコンカンの甘辛さとさっぱりとしたライム果汁の相性がバッチリですね! これを目当てにお店に通う人がいるというのも頷けます」

「ブリトーの美味しさも、ぜひ体感してほしい。アボカドたっぷりのサワークリームをモチモチの生地にディップ。見た目以上に、食べ応えも抜群です」と知夏子さん絶賛の一品。

〈右上から時計回りに〉CBD恵比寿ビール ¥1,200、焼肉エスニック春巻き ¥1,280円、ハラミとアボカドと自家製サルサのタコス ¥500(注文は2ピースから)、メキシカンブリトー ¥1,680
美味しい食事とお酒を堪能したら、やっぱり最後はスイーツを!
選んだのは、味にコクを出すため、なんと醤油麹を使っているという名物のチョコレートケーキ。カカオニブをふんだんに使用しているのも特徴なのだとか。
「アーモンドクランチのような食感とメープルシロップで味つけられた優しい甘味で、手が止まりません! 食後にいただいても重たさがなくて、ペロリと完食です」

醤油麹のCBD RAW(生)チョコレートケーキ(CBD10ml)¥1,080
お腹いっぱいになるまで食べても罪悪感を感じることのないローカロリーフードに加え、美味しいお酒も楽しめる渋谷の隠れ家的カフェは、千夏子さんのお気に入りスポット確定!

食事を楽しみながら、ストレス削減もできるだなんてうれしい限り。カジュアルデートから女子会まで、あらゆるシーンにぴったりの空間で、癒しの時間を過ごしてみてはいがか?
HEMP CAFE TOKYO
東京都渋谷区東3-17-14 クリスティエビス 8F
03-6427-1984
https://hempcafetokyo.com/
〈衣装〉トップス¥24,200、スカート¥41,800/ともにランバン オン ブルー(レリアン) サンダル¥55,000/ロトゥセ(リエート)
SHOP LIST
ランバン オン ブルー https://www.lanvin-en-bleu.com/
ロトゥセ https://lottusse.com/en/
知れば知るほど、私の人生は豊かになっていく【小泉里子 / 未来に続くBOOKリスト vol.9】
あなたの本棚には、これからの人生で何度も読み返したい本が何冊ありますか? モデル 小泉里子さんの連載エッセイ「未来に続くBOOKリスト」。読書好きの里子さんが、出合ってきた本のなかから“ずっと本棚に置いておきたい本”をセレクトしてご紹介します。
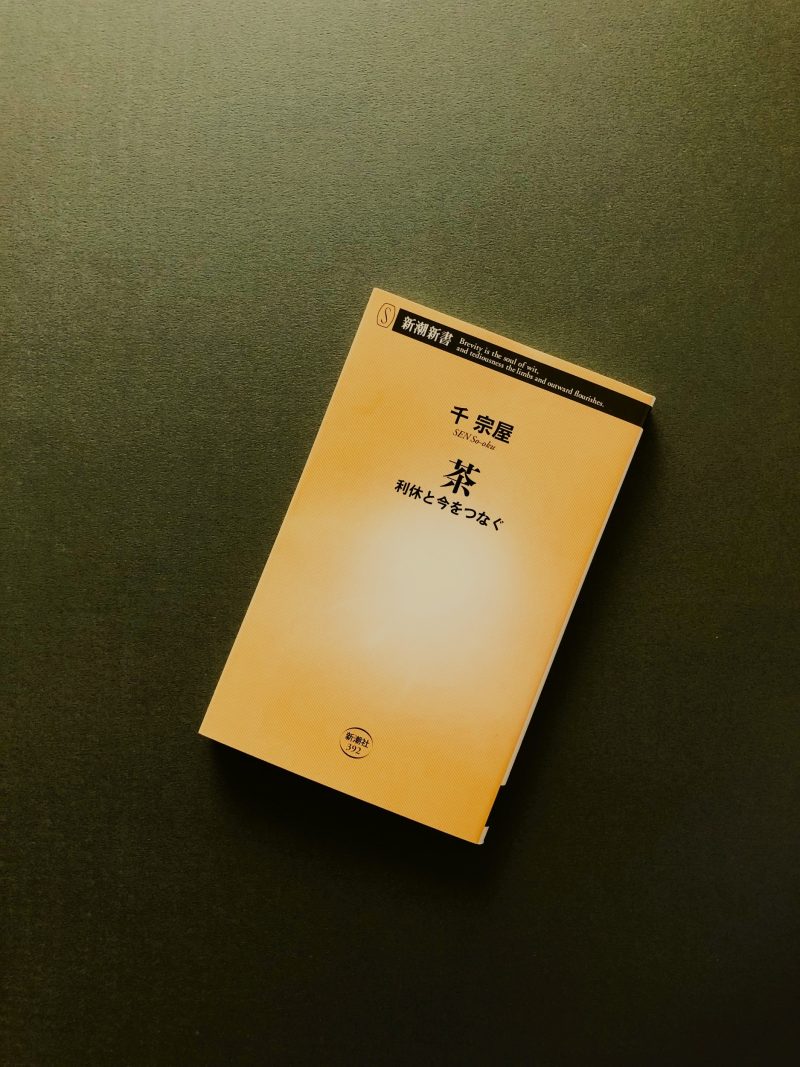
BOOK LIST_09
『茶 ー利休と今をつなぐー』
ジャンル=趣味・実用 千宗屋 著/新潮新書(新潮社)
この本は、私の本棚に長いこと置かれてはいたけど、つい最近まで読んだことがなかった1冊でした。いつかお茶の世界を知りたいとは思いつつも、その敷居の高さやしきたりの奥深さを敬遠して、何となくページを開けずにいました。でもいつか自然と読みたいと思うタイミングがやってくるんじゃないかと待ち続けていたのです。
鎌倉を散策してるときに、とある茶室と出合いました。そこはしばらく使われていないとのことでしたが、畳は新しくいい香りがして、まだ肌寒い季節でしたが、通り抜ける風が気持ちよく何とも心地のいい時間を過ごしました。「この空間でお茶を点ててみたい」ーーふとそんな気持ちになったのです。お茶をいただくのではなく、点てる方。いきなりハードル高めで挑もうとしている自分が心配になりますが、夢は大きく勝手に膨らんでおります。
そんなときに、ずっと本棚の片隅に『茶』と書かれた本があったなと思い出し、ついに読むきっかけができたのです。
「茶」といえば、千利休。利休を知らずにして「茶」は語れない。と、こんな私でもそこは分かりますが、それ以外、恥ずかしながら茶のことはまったく学んでこなかったので、すべて一からの学びです。
まずは、イメージを膨らませるために、映画『利休にたずねよ』を観賞。時代背景を理解してから、最初の1ページ目を開きました。
この本の著者、千宗屋さんは三千家のうちの一つ、武者小路千家の十五代次期家元。表千家と裏千家だけかと思っていた、どうしようもない私をお許しください。そして読み始めると、茶の知識が皆無だった私にも予想外に面白く、時間を忘れて一気に読んでしまったほどです。
「茶」に対する堅苦しいイメージが一新したというか、もちろん最低限の心得は必要だと思いますが、何よりも「茶」を楽しむ心意気が大切なのだということ。ただただ作法を身につけたいのではなく、道具だけを重んじるのでもなく、「お茶を飲む」という日常を楽しむこと。そして主客がそれぞれ思いやりの気持ちで交わすものだということ。・・・などを知りました。
この本読んで、とても印象的だったところがあります。
「高価な名品ばかりを並べる必要はありません。場がきれいに清められ、それぞれのものが、いかにも生き生きと組み合わされ、お互いが引き立て合うように飾られていて、主客の呼吸と間合いがうまく計られ、すべてがあるがまま自然に運ばれていくけれども、見所もある」
ーーまさに「わびさび」の世界だと感動すらした一文でした。
私が日常を送るなかで、こんなふうに過ごせたら素敵だなと思うことでもあります。
生活水準から夫婦のあり方、ファッションに至るまで、持っているものをすべて見せていくのではなく、自分や相手が気持ちよくお互いを引き立て、丁寧に過ごす、そしてそれが自然にこなせる魅力ある人。
この言葉にはすべてにおいて通ずるところがあると思いました。お茶の世界を知れば知るほど、私の人生は豊かになっていくような、そんな気持ちになります。
小さい頃から3 時のお茶の時間が必ずありました。私の実家は自営業で、従業員の皆さんにお茶を入れて出すのが当たり前の日常でもありました。今は、主人と息子と毎日お茶をします。慌ただしい毎日のなかで、唯一ゆっくりとした時間が流れる瞬間です。
20 代のときにアフタヌーンティーに夢中になり、30 代はお煎茶を習い、40 代はなかなか手を出せなかったお抹茶の世界へ。
一つの葉からこんなにも幅広く奥深い世界が広がってるものは、他にないと思います。まだまだのぞいただけのお抹茶の世界ですが、楽しみで仕方ないです
『茶 ー利休と今をつなぐー』(ちゃ りきゅうといまをつなぐ)
利休の末裔がつづる、生活文化の総合芸術としての「茶」。茶の湯の歴史、利休について、茶道具や茶室に関する丁寧かつわかりやすい説明など、ビギナーにも茶事の面白さを伝え、興味を高めてくれる一冊。

Profile
小泉里子(こいずみさとこ)
15 歳でモデルデビュー。数々のファッション誌で表紙モデルを務め、絶大な人気を誇り、広告やテレビ番組でも活躍。着こなすファッションはもちろん、ナチュラルでポジティブな生き方が同世代の熱い支持を得ている。2021年2月には第1子となる男児を出産し、同5月より生活の拠点をドバイに移す。ドバイでの生活や子育てにもさらに注目が集まっている。仕事、プライベート、ドバイでの生活を綴った著書『トップモデルと呼ばれたその後に』(小学館)も好評。
http://tencarat-plume.jp/
Instagram @satokokoizum1
心がほぐれる田植えリトリート【イケてる八百屋「イケベジ」の農日誌vol.1】
新潟県・佐渡島と兵庫県・淡路島を中心に自然栽培農家を営む「イケベジ」による連載がスタート! 野菜を育てる栽培過程、土の中の微生物、自然環境、スタッフの気配りなど、目に見えない細部にこだわり、真摯に取り組むことを、“美しい・イケてる”と定義し活動中です。新しいことを面白がりながら挑戦していく彼らの活動のなかに、「人生がもっと豊かに、楽しくなる」ヒントが見つかるはず。
植物も人も“ありのまま”の姿は美しい
はじめまして! イケてる八百屋「イケベジ」のいもたろうと申します。今月から僕たちが育んでいるイケベジについてご紹介させていただきます。

イケベジは、昨年春からスタートした農を通じて“ありのままで在ること”の美しさから芽吹いたコミュニティです。従来の組織にあるルールやセオリーを尊重しつつ、各個人が人生を謳歌することで生まれるご縁や世界を楽しみ、育んでいく活動をしています。
現在は佐渡・淡路島を中心に生産活動を行い、東京・渋谷で開催される青山ファーマーズマーケットや駒沢公園周辺で、自然とアートから派生した「The gallery IKEVEGE」を拠点にさまざな活動を展開。農に限らず、自然から発生した美しいモノ・コト・ヒトが集まり、常に新しいご縁や世界が産まれる面白い場になっています。
多くのいのちに触れ、育む暮らし
第一回目は僕自身のお話も少しだけ。
神奈川県・横浜生まれで、現在は兵庫県淡路島でホーリーバジルの畑を営んでいます。今から約6年前に淡路島とのご縁がつながり、自然栽培と呼ばれる農業の在り方と出逢いました。当時の僕は、農業に関する知識や経験はほぼゼロ。しかしながら、農家やお客さんだけでなく、地域も自然も豊かになっていく自然栽培の可能性に魅了されて、農業の世界へ飛び込むことに。

大自然の中で多くのいのちと触れ合い、食べ物を育む暮らしは想像以上に豊かで、自分が育んだお野菜を食べて生きることは、ヒトとして自然な感覚を思い出すきっかけになりました。そして今では淡路島での暮らしをベースに、僕自身が体感したことをさまざまな形で発信させていただいています。
最高に心地よい田植え体験

さて、イケベジでは小さなお子様から大人まで農業体験ができるリトリートを提供しています。先日は2回目となる田植えリトリートを佐渡島で行いました。周りには自然のリズムに沿って生きているいのちがたくさん。それぞれのいのちが奏でるハーモニーを五感を通じて受け取ることで、一人ひとりのなかに宿る自然な感覚へ還っていく。淡路島とはまた違ったリズムが佐渡島には流れていて、とても心地良い場所です。
リトリートではまず田植えを行う前に、島を見守り続ける神様へのご挨拶へ向かいます。森の中にある参道を進み、境内へ入らせていただくと樹齢1,000年といわれる御神木が僕らを出迎えてくださりました。創立1,200年が経つ神社の神様は、自然と人が調和し育み合える暮らしを、長い間見守り支えてくださっているのだなと感じました。
そして神様へのご挨拶を済ませた夜は、五穀豊穣を祈願する佐渡の伝統芸能「鬼太鼓」をみんなで鑑賞。いよいよ明朝から田植えがスタートです!

品種は「亀ノ尾」という、コシヒカリやササニシキなどの銘柄米を生んだ品種改良の交配親としても知られるお米です。約100年前に山形県でほとんどの稲が冷害に見舞われた折に、阿部亀治さんという方が偶然見つけた3本の元気な稲から創選されたそう。そんな貴重な種を、淡路島の先輩農家さんが分けてくださったのです。まさにいのちのリレーです。そんな素晴らしいいのちの恵みが詰まった稲を3本手に取り、大切に植えていきます。
初めて田んぼに触れたときの気持ち良さ、聞こえて来る風や木々が揺れる音、そして鳥の鳴き声。目の前に広がる美しい緑を彩る野草たちのおかげで、とても穏やかな気持ちで田植えができました。ここから約5ヵ月、周りの大自然とともに育まれる稲の生長が楽しみでたまらないです。秋には稲刈りリトリートも開催予定です。一緒に稲刈りをしましょう!
Profile
いもたろう
イケベジ発起人、育み人。淡路島で「農」を通じて多くの「いのち」に触れる体験から、人も同じようにありのままで生きていくことで豊かになれると思うようになる。2021年春、友人とともに人も自然も共に育む場「イケベジ」をスタート。大学での講演活動や「命の繋がり・巡り」をテーマにした「育ベジRetreat」などありのままで生きる世界を広める活動を続けている。実は料理好きで、マクロビを取り入れた「いも飯」はイケベジの人気コンテンツ。
https://ikevege.com/
愛せる自分を探し出し、認めて、受け入れる【山口乃々華 / コトノハ日和 vol.05】
言葉があるから伝えられること、伝わること。そこから広がっていく思考、癒し、つながり、希望、愛情・・・深くて力強いもの。女優 山口乃々華が、心に舞い落ちてきた“コトノハ(言葉)”を拾い集めて、じっくりと見つめ、ゆっくりと味わい、思いのままに綴っていく連載。さあ、一緒に元気になりましょう。
あなたってどんな人?

梅雨時期に入りました。じめっとした重たい空気の日もありますが、気持ちは明るく! スッキリと過ごしたいものですね。
最近、アメリカのとあるリアリティ番組を観ることにはまっている。10年以上続いているその番組の内容は、個性豊かな選ばれし表現者が集まり、自己アピールをし、スターになることをレースで競うというもの。精神的にも、技術的にも、根性的にも、たくさんの武器を備えているように見えるクイーンたち。例えレースに負けたとしても、いつだって胸を張って、堂々たる存在感を放っていた。その姿は本当にかっこいい。
番組内では、常に自己表現の具体的説明を求められる。創造的であり、自信たっぷりと、こちらをワクワクさせるユーモアを加えつつ、上手に言葉を選び伝えていた。それは、完成された物語の主人公として語っているようだった。
随分と前の話なのだが、とある面談で「あなたってどんな人なの?」と問われたことがあった。気楽な雰囲気だけれど、まったく逆の空気も感じる特殊な状況も相まって、私はすぐに答えられず、頭のなかに潜ってしまった。
“私ってどんな人なんだろう。よくわからない”
これがそのときに思った本音で、でもそんなことは言えず、困ったことがある。
あのとき、クイーンたちのように、“自分”を語ることができたならよかったのに。
しかし、人はいろんな面を持っていると思う。仕事をしているとき、プライベートのとき。友達といるのか、ただ居合わせた人なのかで、気の遣い方だって変わるだろう。
ものすごく特殊な人は、ずっと一つの面だけで生きられるのかもしれないけれど。(私とたくさんの時間を共有した人のなかで、そんな人は一人もいなかった)
みんなきっと、どこかしらで“いつも通りの私”が何層かに分かれているように感じているのではないだろうか。
そんななかで、他人に自己を説明する、というのはやはり簡単なことではない。
どんな人なの?と聞かれるシチュエーションをもう一度想像してみた。
そう質問してくる相手は、私を知らない他人である。時間をゆっくりかけて理解し合うような間柄ではない。そんな私がどんなふうに自己を表現するのか、を知りたいのかもしれない。
そう考えると、クイーンたちのように、自分を見せたいように見せることは一つの答えなのでは、と思う。
毎日をそのとおりに生きなければならないわけでもないし、絶対に違うことをしちゃいけないという約束でもない。更新される部分があったっていい。少しばかりは、なりたい自分、こうありたいという希望を交えて語ったとしても、それだって私の人間性を表すものといえるだろう。
そして、長い時間をかけながら愛せる自分を探し出し、認めて、受け入れることが大事なのではと思った。
そのリアリティ番組の最後に、MCが言う言葉がある。
「自分を愛せなければ、他の人も愛せない」
自分を愛せていると、確信できない私は、まだまだ人生の途中なのだと思い知らされる。
うまく生きられない自分が嫌になることもあるけれど、愛せる自分になるための努力と、そんな自分と向き合う時間を過ごしていきたい。他人に合わせるのではなく、私の幸せを感じていきたい。
それができてから、やっと本当の意味で、他の人を愛せるようになるのだと教わる。自分だけの世界より、それはもっと素晴らしいだろう。
他の人をもっと愛せるようになりたい。拒む世界から、手をつなぐ世界へ。ありのままの私で、嘘をつかない私で、もっと自由な私で。

Profile
山口乃々華(やまぐちののか)
2014年からE-girls主演のオムニバスドラマ「恋文日和」第7話にて主演を務め女優業をスタート。映画『イタズラなKiss THE MOVIE』シリーズ、ドラマ・映画『HiGH & LOW』シリーズほか、2020年には『私がモテてどうすんだ』のヒロイン役など、数々の作品に出演。 2020年末までE-girlsとしての活動を経て、2021年より女優業として本格的に活動を開始。2021年3月、初のミュージカル『INTERVIEW~お願い、誰か助けて~』、同8月にはミュージカル『ジェイミー』、2022年3~4月はミュージカル『あなたの初恋探します』でヒロインを演じた。ドラマは現在「ビッ友×戦士 キラメキパワーズ」(テレビ東京系)に出演中。書籍『ののペディア 心の記憶』(幻冬舎文庫)も好評で、文章を書くことも好き。2022年7月には舞台『オッドタクシー』に出演、10月にはconSept Musical Drama #7『SERI〜ひとつのいのち』でミュージカル初主演を務める。
https://www.ldh.co.jp/management/yamaguchi_n
Instagram @yamaguchi_nonoka_official
好きという気持ちに真っすぐに生きる【モデル 桐山マキの衣食住遊学】
いつも元気で幸せそうなひとは、自分の周りに“楽しいこと”を育てる種をまいています。
そんな魅力的な方にHummingなライフスタイルのトピックスを伺うシリーズ記事「わたしの衣食住遊学」。
今回はモデルとしてCMや雑誌で幅広く活躍するほか、保護犬の保護活動をライフワークにしている桐山マキさんにご登場いただきます。
愛する犬たちのために考え、行動する日々

そのエレガントな佇まいと美しさから、ナショナルクライアントの広告出演も多い人気モデル 桐山さん。
プライベートではパートナーと一緒に、現在は3匹の犬と暮らす、賑やかで楽しい毎日を送っています。
愛犬たちは保護環境から迎え入れ、それぞれ異なるルートを経て彼女のもとにやって来ました。
そんな桐山さんのおしゃれや健康へのこだわり、愛犬たちとの愛情あふれる日常とは?

「衣」
一生ものアイテムを探し続けていく
デザインもシルエットもできるだけシンプルであるということが、やはり長く着続けられるポイントなので、服選びにおいてそこはいつもしっかりと意識しています。デザイン性が高すぎるといつか飽きてしまうし、流行りの素材はその時期が過ぎると着こなしづらくなって、なかなか長く着ることが難しいですよね。
素材は、カシミアやコットンが好きです。コットンはバシャバシャと洗ってデイリーに着られるラフさも、くたくたの味わい深い風合いになって自分に馴染んでいくプロセスもいいですよね。20年選手のロンTも活躍しています。
そんななかで出合った一生ものアイテムの一つが、古着屋さんで見つけたエルメスのヴィンテージコート。いわゆる“マルジェラ期”のもので、私はもともとマルジェラが好きなのでビビッときてしまいました(笑)。
カシミア100%で、羽織ったときの軽さと、肌触りと、ジェンダーレスなシルエットにもう感動してしまって。気軽に買えるプライスではなかったのですが、一生大切に着よう!と心に決めて購入しました。ここまで惚れ込めるアイテムには、なかなか出合えませんから、これは運命だなと。
>>【自己受容】弱くてダメな自分を認めて受け入れるトレーニング方法

週末だけオープンする古着屋さんで運命的に出会った。
何度も試着して、羽織るたびに「これだ!」という気持ちが強くなったそう。
このコートで出掛けたときは、帰宅後に毎回きちんとブラシをかけ、特別扱いしてクローゼットの外にディスプレイしています。そこにあって、ただ目に入るだけで自分のモチベーションが上がります。
以前は古着にあまり興味がなかったのですが、最近はとらえ方が変わりました。本当に良いものを時代を超えて使っていく、誰かから受け継いで、もしかしたらいつかまた誰かに受け継ぐかもしれないから大切に扱うー-そんな循環は、素敵なことだなと思って。
今では、自分好みのアイテムと出合えそうな古着屋さんを定期的に覗いたりしています。
もう一点、同じくエルメスのプティアッシュというトートも、これからずっと付き合っていきたいバッグとして手に入れました。
私が愛用しているのは、バーキンやケリーを制作をする過程で本来は捨てられてしまうレザーをフェルトに貼って、新しい命を吹き込まれたエシカルなアイテムです。
>>メンタルヘルスが注目されている理由|不調になったときの対策を紹介

表と裏でも表情が異なっていて、ませに唯一無二の存在感。
バッグのパーツが型抜きされた跡がまるでアート作品のようで、その背景からして同じものは存在せず、このシリーズのバッグはそれぞれが世界で一つだけというのも魅力なのです。
友人のスタイリストから「おしゃれはサイジングがすべて」と聞いて以来、必ず試着して確認しています。サイズが合わないせいで着心地がしっくりこないと、結局は着なくなり無駄になってしまいますから。今どきのゆるっとしたアイテムも、きちんと自分の体型に合ったゆるっと加減なのかを見極めて、着こなしたときに全体のバランスが縦長に見えるようにすることがこだわり。後ろ姿もしっかりと確認しています。

月1のファスティングは、Delifasの大田市場の農家さんから直送される無農薬の新鮮な野菜たちで胃腸から元気に。
「食」
内臓を休め、いたわり、健やかに!
本格的に食にこだわり始めたのは、30歳を過ぎてから。もともとアレルギー体質だったこともあり、ここでしっかりと改善したいと思ったのと、腸とアレルギーはとても密接に関係しているから、そこから見直さないと治らないよと言われたこともあって。
朝は起きがけにミネラルウォーターを飲む、発酵ものを意識して摂る、腸活、温活、食品の添加物をチェックする・・・一つひとつをより気を付けるようになって、口にするもので体ができているのだということを再確認しました。内臓を休めるために、ファスティングも月一回のタームで実行しています。
それまでは間食をしがちだったのが、ファスティングのおかげで、半端な時間に何か食べたくなるということがなくなりました。いくつかの方法を試してみましたが、人からすすめられた“食べながら”できるファスティングを取り入れています。朝にスープ、昼にサラダ、夜にまたスープという消化のいいメニューで、農家さんから送られてくる3日間のセットがあるんですよ。もちろん期間中は空腹感がありますが、3日目にはもう慣れて比較的平気になります。間食がなくなるだけでなく、お酒の量も減るし、眠りも深くなって目覚めもとってもよくなりました。
腸を活動させて体を健康にするには、菌の働きが大事なので、ぬか漬けをつくったり、味噌づくりにも挑戦しています。この前初めて出来上がったのですが、あ~こんなに美味しいんだと感動しました。

初めて自分でつくった味噌がこちら。仕込んでから10ヵ月ほど寝かせて完成するそう。
定期的にリセットすることで、舌が敏感になったというか、あるべき状態に戻ったのか、食べ物の味がよくわかるようになった気がします。添加物が多いものを食べると、頭が痛くなることも。そんな変化も感じています。
>>”自分らしく生きる”とは?|仕事や恋愛で自然体で過ごせる方法を紹介

リビングの癒しの存在、エバーフレッシュは育て始めてからかれこれ10年も経つそう。
神奈川県の植物屋さんで購入。当初は半分くらいの大きさだったのが、ここまで成長。
今では「一心同体感!」とまで感じている大切な存在に。
「住」
植物とも会話しています
自宅にはいくつもグリーンを置いて、育てています。
増やそうと思って探しているわけではないのですが、それこそ服と同じで、出かけた先で『わ、このコ、連れて帰りたい!』と、運命的に出合って増えていく感じです。
少し前の出来事なのですが、私が体調を崩してしまい数日間ほど寝込んでしまったことがありました。体調が復活した直後に、いつも話しかけて大事にしているエバーフレッシュがぐったりと元気を失くしているのを見て驚いてしまって。たくさんの葉が床に落ちてしまい、枝も下を向いて垂れていて・・・。何だか私の代わりに悪いものを吸ってくれたのかなとか、寝込んでいた間は声をかけてあげられなかったので、そのせいで元気失くしたのかな・・・と思ったり。
エバーフレッシュは、朝は「おはよ~」ってかんじに葉が開いて、夜になると眠るように閉じるので、まるで人間みたい。元気がないときは見た目ですぐにわかるし、“生きてる”ってかんじがリアルに伝わってきます。植物だけど会話ができる相手という感覚なんですよね(笑)。毎朝、このコの様子を見て挨拶するのが私の日課です。
>>【誰でもできる】マインドセットの意味・使い方をわかりやすくご紹介!

〈上〉宮古島のホテル、イラフスイニて。
〈下〉ジャングルのような野性的な植物群に癒されるドッグカフェ、パニパニ。
「遊」
自然と触れ合う旅でリラックスする
一緒に暮らしいるココワカメさんという、元野犬だったうちの愛犬は宮古島のシェルター(SAVE THE ANIMALS)出身です。いつか里帰りさせてあげたいなと考えていたら、メディアの取材でそれが実現できました。シェルターの取り組みも記事で紹介していただけて。
この取材が私にとって初めての宮古島訪問で、愛犬と一緒に行く旅だったこともあり、イラフスイという犬も泊まれるホテルのお世話になりました。犬にもうれしいサービスが用意されていて、本当に快適でした。
宮古島は車がないと移動ができないので、犬OKのレンタカーを利用して、パニパニというジャングルみたいにグリーンに囲まれた素敵なドッグカフェを訪問。ここはもう、近くに住んでいたら毎日通いたくなるような気持のいい場所で、足元は砂浜なので素足で過ごせるし、生い茂った緑に囲まれていて、食事も美味しくて、最高でした。
私は田舎育ちなので自然の中で過ごすこと、とくに緑が多い場所で植物の生命力に触れるととっても癒されるんですよね。
>>ヨガがメンタルヘルスに良いと言われる理由。ヨーガって本当はどういう意味?

「学」
犬が好きという気持ちが、情熱を生む
もともと私の実家(桐山さんは大阪出身)では、子供のころから犬と一緒の暮らしが当たり前だったという背景があります。東京に来たばかりのころは犬と暮らせる環境ではなかったので、保護犬のボランティアに参加して犬と触れ合っていました。
そんななかで、保護された犬たちの現実を目の当たりにして、虐待されたり、遺棄された犬たちを保健所から引き揚げてきたときに、彼らの怖がって怯えた様子を見て衝撃を受けました。実家で保護犬を飼っていた経験もあったのですが、そのコの比ではないほど、パニックに陥っている犬もいて。この現実をきちんと知っておくべきだなと思ったんです。
そこから自分ができることを少しずつでもできたらいいなと思って活動を続けています。私自身は、現在は3匹の保護犬出身の犬たちと暮らしています。最初に家族になった小春ちゃんとは「ペットのおうち」という里親さんを見つけるサイトで出会って、何回かの面接を経て引き取りました。2匹めは、宮古島のシェルターからやって来たココワカメさん。3匹めのぶーちゃんは、保護犬の一時預かりボランティアという形で我が家に来てもらっています。ぶーちゃんが加わったことで、ココワカメさんの心が急速に開いていって、言葉で表せないくらいに明るくなったんです。

〈左から〉ココワカメさん、小春ちゃん、ぶーちゃん。
人間と犬だけでなく、犬同士の関係にも変化があって、家族の絆が確実に深まっていることを実感しています。
ココワカメさんのような野犬出身の保護犬は、とても難しいところがあります。うちに来たばかりのころはテーブルの下から怯えて出てきてくれなくて。散歩に連れて行っても安心できないからなのか、外で排泄ができないんですよね。そんな様子を見て、最初のうちは『大丈夫だよ』『出ておいでよ~』なんて声をかけて構っていたんですが、それがよくないのかなと思って、構いすぎるのをやめてみたんです。そうすると逆に、ひょいっとテーブルの下から出てきたりして(笑)。
こちらの、こうした方がいいだろうという思い込みに対して、それは違います、それは求めてません・・・みたいな返しを感じたので、その意思表示をきちんと読み取って、距離感を急いで縮めようとせず、時間をかけて少しずつ歩み寄ったほうがいいんだなということも学びました。今はどういう様子かなと細やかに観察して、想像して、互いにアイコンタクトもできるようになって。そうやって一つずつ信頼関係を深めていくように努めています。
満たされていないと、こういう行動するんだなとか、我慢させちゃったかなと思うときはごめんねと伝えたり。日々、いろいろなことを犬たちから教えられているなと思います。
>>【ストレス解消】セルフケアとはなにか?意味・種類・方法について解説

5月半ばに、表参道のギャラリー5450 the GALLERYにて保護犬譲渡会を開催。
桐山さんは会場費の提供やPR活動に携わりました。
私は今、保護犬のこと、保護されるまでの虐げれていた環境についても、たんさんの方に知ってもらうことが、動物と幸せに暮らせる社会にしていくために必要だと思って活動しています。その流れで、保護犬の譲渡会の企画も始めました。
犬のために何かをしたいという気持ちに突き動かされていて、それは「好きだからやりたい」という強い想いが原動力。とはいえそれは、人に対して押しつけになってはいけないなと思っています。情報を正しく広く発信して、ペットを探している方たちに保護犬という選択肢もあるなと、とにかく知ってもらうことが大事だなと考えています。動物と人がピースフルに暮らせる世界が広がっていくことを願って、何か少しでも役に立つことができたらうれしいですね。
犬と人間は、互いに愛情を感じ合い、気持ちを交わせる家族。彼らに寄り添いアクションを起こすことは、桐山さんにとって必然であり、一匹でも多くの犬を幸せにできればという希望へと向かっています。揺るぎない情熱と「やりたい」に真っすぐに進むその行動力は、周りの心を動かし、環を広げ、さらなる大きな変化へとつながっていくはずです。
>>【変わりたいあなたへ】自分を変えることは難しい?変われる方法や習慣

Profile
桐山マキ(きりやままき)
大阪府箕面市出身。2005年、雑誌「PINKY」の専属モデルとして、モデルデビュー。
『美しい着物』などさまざまな雑誌や、国連の出版物などの表紙・誌面で活躍中。また、パリ、NY、ハンガリーをはじめとする世界のショーにも多数出演。
現在 、アメリカン・エキスプレス、ホットヨガスタジオLAVA、ヤクルト等、11社のCMに出演中。また、自らの経験を活かして、保護犬をめぐる啓発活動をファッションやライフスタイルを通して展開している。
Instagram @maki_kiriyama
自分でみつける。この場所で生きていく理由【山口乃々華 / コトノハ日和 vol.04】
言葉があるから伝えられること、伝わること。そこから広がっていく思考、癒し、つながり、希望、愛情・・・深くて力強いもの。女優 山口乃々華が、心に舞い落ちてきた“コトノハ(言葉)”を拾い集めて、じっくりと見つめ、ゆっくりと味わい、思いのままに綴っていく連載。さあ、一緒に元気になりましょう。
好きな場所をみつけて生きていく

今年のGW、皆さまいかがお過ごしでしたか? 三年ぶりに規制のないGW。私は両親と共に母の実家に行きました。ゆっくりと数日間を過ごせたのは、とっても久しぶりで。うーんと羽を伸ばし、そこでの時間を満喫してきました。
朝方に聴こえてくるのは、鳥たちの声。
あぁそうだったなぁって、記憶がよみがえった。
私がまだ小学生で、もしこれが夏休みの朝だったら、飛び起きて、朝ごはんを急いで食べて、外で汗だくになりながら遊んでいたけれど。今の私はとにかく眠くて、たまらなかった。
しかし変わらずに心地の良い朝。さぁ、ゆっくり休んでいいですよ。と神から許されたような気分になりました。思う存分二度寝をして、飽きたら起き上がるのです。
それからリビングに行けば、家族の誰かしらが起きていて、「おはよう〜」と言いながら、それぞれの寝癖をチェック。見事な大爆発。
そこにある当たり前な日常に包まれるのは、とても心地がいい。私、そんなに疲れているわけでも、凹んでるわけでもないのだけれど、癒されました。
そんな数日を過ごした帰り道は「あー! 頑張らなきゃな」と思う。しっかり遊んだし。気持ちをシャキッとするスイッチをオンにして取り戻さないといけない。東京はいつのまにか、静かにじっくり沼に足を取られるような場所だということを、私はまだ忘れてはいけない。
そんな気持ちにさせる東京というものは、私を知らぬ間に”夢中”で埋め尽くしてくれている。そんなパワーがある。だから頑張れているのかもしれない。
強くて眩しい。
強くて眩しいから私はここ東京が”好き”なんだと、少し離れて分かった。
いろんな人がいて、いろんな生き方がある。
ここで生きるのが好きな私を、この場所を選んでいるのは私自身なんだということを、あらためて思い出させてくれました。すべてを、もう一度愛さないとなぁ、なんて思うGWでした。
銀色夏生さんの『すみわたる夜空のような』という詩集のなかに「この中で」という詩があります。
「この中で」
この中で
好きな場所を
ぐるっとみわたしてみつけるあのすみ
あたたかく沈みこんでるような
静かに落ち着く場所いつも
今いるこの中で
目の前のこの中で
好きな場所をみつけて
生きていくこの中だったらここ
とここじゃないとはもう言わない
(銀色夏生 『詩集 すみわたる夜空のような』/角川文庫より)
この詩集を読んでいると、古いアルバムをめくっているような気持ちになった。それが、私のアルバムなのか、違う誰かのものなのかはわからないけれど、懐かしくて、ちょっと心の古傷が痛む。
一見、この詩で書かれていることと、私が抱いた“今いる場所”への想いは異なっているようだけれど、でも私なりの解釈はしっかり重なっている。
「この中で」の詩は、「好きな場所をみつけて生きていく」というのがお気に入り。
自分の好きが、「この中で」味方になる。
今を見つめて、ここじゃないなんて、思うことなく、この場所を選んで、ここにいる私。
だから、”ここ”で、私は、私らしく生きていきたい。

Profile
山口乃々華(やまぐちののか)
2014年からE-girls主演のオムニバスドラマ「恋文日和」第7話にて主演を務め女優業をスタート。映画『イタズラなKiss THE MOVIE』シリーズ、ドラマ・映画『HiGH & LOW』シリーズほか、2020年には『私がモテてどうすんだ』のヒロイン役など、数々の作品に出演。 2020年末までE-girlsとしての活動を経て、2021年より女優業として本格的に活動を開始。2021年3月、初のミュージカル『INTERVIEW~お願い、誰か助けて~』、同8月にはミュージカル『ジェイミー』、2022年3~4月はミュージカル『あなたの初恋探します』でヒロインを演じた。ドラマは現在「ビッ友×戦士 キラメキパワーズ」(テレビ東京系)に出演中。書籍『ののペディア 心の記憶』(幻冬舎文庫)も好評で、文章を書くことも好き。2022年7月、舞台『オッドタクシー』への出演が決定。
https://www.ldh.co.jp/management/yamaguchi_n
Instagram @yamaguchi_nonoka_official
自分を整え、パワーを引き出す3つの源泉【アーティスト 佐々木香菜子のお気に入りLIST】
その道のプロに聞く、今の自分に必要なお気に入りアイテム。今回は、アーティスト 佐々木香菜子さんに3つの大切なアイテムを見せていただきました。
クリエイティビティを支える、意外なモノ
アーティスト、イラストレーターとして商品パッケージからアート作品、ライブペインティングなど多岐にわたり活躍を続ける佐々木香菜子さん。今年4月、5月は東京、韓国で、そして6月には故郷である仙台で今までにない規模の個展が開催されるなど、アート活動に注力中の佐々木さんが愛用しているものとは? 彼女の美容、食への探求心にも注目です。
私の背中を押してくれる、4つの単語【山口乃々華 / コトノハ日和 vol.03】
言葉があるから伝えられること、伝わること。そこから広がっていく思考、癒し、つながり、希望、愛情・・・深くて力強いもの。女優 山口乃々華が、心に舞い落ちてきた“コトノハ(言葉)”を拾い集めて、じっくりと見つめ、ゆっくりと味わい、思いのままに綴っていく連載。さあ、一緒に元気になりましょう。
まずは近況報告から
私は先日まで「あなたの初恋探します」というミュージカル作品に出演させていただき、そのことで頭がいっぱいいっぱいの日々でした。そしてなんとか無事に、4月17日の千秋楽を終えることができました。とっても楽しい作品で、たくさんの笑顔が生まれる素晴らしい時間でした。
しかしながら、私にとっては2月の終わりから始まったこの闘い・・・闘いなんて言葉はまったく似合わない爽やかな作品なのに、何というか、個人的にはやはり自分との闘い!という感覚で。心から軽やかにスキップできるほどの余裕もなく、ずーっと一歩一歩を慎重に踏み出しているような気持ちになった日々でした。
でも、春のこの爽やかな晴れ晴れとした空気に目一杯励まされたし、何よりも私の周りの方々が、環境が、心の奥底から支えてくれていました。本当にいつもいつも支えてもらってばかりの私。そのことについても、このままでいいんだろうか?と悩んだりしましたが、気が付きました。悩んでる時点で、まだまだ人のことをケアする立場というステージには、辿り着けていないのです。仕方ない! 時には素直に甘えさせてもらいながら、生きていく所存でございます。
自分のことで目一杯な私をいつかは卒業して、客観的に、もっと広く、もっと全体をを見渡せるような人になりたいです。
さて、春の目標発表(?)が終わったところで! 今月ご紹介したい「コトノハ」へ。

The special secret of making dreams come true can be summarized in four C’s.
They are Curiosity, Confidence, Courage, and Constancy.
夢を叶える秘訣は、4つの「C」に集約される。それは「Curiosity (好奇心)」「Confidence( 自信)」「Courage ( 勇気)」そして「Constancy(継続)」である。ーWalt Disney
今回は、ウォルト・ディズニーのこの言葉について。
ウォルト・ディズニーが創りだした世界観や伝えているメッセージが好きで、いつかディズニープリンセスの声優を務めることが夢でもある私は、Twitterやネット上でよく引用紹介されているこの名言をみて、ドキドキした。
他にもいろいろな名言があるのだけれど、今の私にはこれがしっくり。
何かに向かっていくとき、叶えたいと努力をするとき、そのときのパワーは本当に心を輝きで満たしてくれて、自分に追い風が吹くような、そんな感覚がある。それはここにある「好奇心」からなのだろうか。やりたくて仕方ない! 今すぐ取り組んでみたい!とムズムズしてしまうとき、私はその物事にすごく集中できる。
そして、「自信」。
これは、私にとってすごく難しいことのように思える。しかし今までも、きっとこれからも「できる気がする!」と飛び込み、チャレンジすること自体は大好き。
一生懸命取り組んでいくのだが、その先で失敗を繰り返したり、なかなか成長できなかったりすると、どうしても不安になってしまう。壁にぶつかるのは当たり前だとわかっていも、そんな不安定なときに何かキツいことを言われたら、ふらぁーっと倒れていってしまいそうになる。
しかし、そんなことに負けちゃいけない!といつだって立ちあがろうとするのは、とっても長い目で見たら、私はいつかやれるはずだー-なんて、そんなふうに思えている私がいるからかも。もしかして、これが「自信」なのか?と思う。
「勇気」そして「継続」。
「できないなら、難しいかもね」「大丈夫? どうしていくつもりなの?」などなど。相手側は特別、こちらを責めてるつもりはないだろう言葉。しかし、言葉のなかに隠れている若干の怒りや呆れの棘がグサリと心臓と脳みそに刺さってくるときがある。
うるさい! どっかいけ! そう思っても、全然だめ。もうやめた方がいいかな? 諦めようか。人に迷惑をかけてまで、やり続ける意味があるのだろうか・・・? 本当、何にもできないな! 向いてないなぁ!と自分でその棘を猛毒にして、ぐりぐりぐりぐりと、えぐっていくのが私の思考回路。もはやそうするのが好きなんじゃ!?と思うほど。
毒が全身に回ったころには、とことん落ち込んでいるのだが、そんなときこそ「勇気」と「継続」だと思う。もう一度、立ち上がって勝負する勇気を。そして、諦めずにとにかく継続すること。どうせ、いつかはケロッと立ち直ってしまえるから、腐らないでいたいなと思う。
夢を叶える秘訣は、4つの「C」に集約される。
どうだろう、本当にこれらを大切にしていたら、夢が叶うのだろうか。まだわからないけれど、読むまではしょぼくれていた私も、やる気が湧くのだから、すごい言葉だと思う。
春は、何かと変化の多い季節。どうか周りに流されすぎず、自分の気持ち、意思を大切に過ごしていきたい。

Profile
山口乃々華(やまぐちののか)
2014年からE-girls主演のオムニバスドラマ「恋文日和」第7話にて主演を務め女優業をスタート。映画『イタズラなKiss THE MOVIE』シリーズ、ドラマ・映画『HiGH & LOW』シリーズほか、2020年には『私がモテてどうすんだ』のヒロイン役など、数々の作品に出演。 2020年末までE-girlsとしての活動を経て、2021年より女優業として本格的に活動を開始。2021年3月、初のミュージカル『INTERVIEW~お願い、誰か助けて~』、同8月にはミュージカル『ジェイミー』、2022年3~4月はミュージカル『あなたの初恋探します』でヒロインを演じた。ドラマは現在「ビッ友×戦士 キラメキパワーズ」(テレビ東京系)に出演中。書籍『ののペディア 心の記憶』(幻冬舎文庫)も好評で、文章を書くことも好き。4/30(土)22:30から放送の特集ドラマ「昭和歌謡ミュージカル また逢う日まで」(BS プレミアム・BS4K)に夏木和香役で出演。
https://www.ldh.co.jp/management/yamaguchi_n
Instagram @yamaguchi_nonoka_official
森カンナ「繰り返してきた失敗から抜け出した今」【連載 / ごきげんなさい vol.06】
俳優 森カンナさんが日々の生活のなかで見つけたこと、感じた想いを綴る連載エッセイ「ごきげんなさい」。自分を“ごきげん”にするためのヒントを探しましょう。
高山都さんが見つけた、自分を幸せにする方法【気になるあのひとに10の質問】
オリジナルなスタイルを持って生きている素敵なひとに聞く、10のQuestion。心や暮らしの豊かさは、ブレない生き方や考え方が築くもの。内面から輝くひとはどのようなことに目を向け、何を実践しているのかーー心地よく、充実した毎日を生きるためのヒントを探りましょう。今回は、モデルやラジオパーソナリティー、商品プロデュースなど多彩な顔を持つ高山都さんにクエスチョン!
「自分のご機嫌をとるのは、自分」
Q01 ストレス解消法は?
気分をすっきりさせたいときはランニングをします。
走るきっかけは、お仕事で「ハーフマラソンに出ませんか?」と声をかけていただいたことでした。中学、高校時代の体育の成績はずっと「2」で、運動が大の苦手だった私が走ることに爽快感を覚えるなんて思ってもみませんでした。

当時は、仕事の方向性などについていろいろと悩んでいた時期だったので、これは一つのチャンスだ!と思ってトライすることに。ハーフマラソンを走りきったら、気持ちのいい達成感があって。もっと走りたい!と欲が出たし、「やればできる」という自信につながりました。気付けばもう12年も続けていることになるんです。走っているときは一人だから、自分自身と向き合う時間。ランニングはマインドをリセットするにもぴったりです。
ストレス解消もそうですが、自分の機嫌をよくすることができるのは、結局自分なのだと思っています。
たとえば、元気が出ないなぁ・・・というときは、気分を上げるために素敵な服を選んで着てみたり。普段からオンとオフを切り替えるためにも、外出するときは背筋がのびるようなワンピースやシャツを着ることが多いです。自分を奮い立たせたいときは、おしゃれすることをより意識していますね。
◆【ストレス解消】セルフケアとはなにか?意味・種類・方法について解説
Q02「幸せだな」と思う瞬間は?

仕事が終わって家に帰り、ビールを飲むときです(笑)。ビールのあとはワインや日本酒をあけることもありますね。お酒だけを飲むことはなくて、ご飯もセット。お酒に合うメニューをあれこれ考えて作ることも幸せな時間。
Q03 お気に入りのレストランを教えてください!
参宮橋にある「レガーロ」というイタリア料理のお店です。いいことがあった日も、そうじゃない日も、ここに行くと気持ちがシャキッとして元気が出ます。堅苦しい雰囲気のお店ではないのですが、おしゃれをして行きたい場所でもあるので、何を着ようかなと考える時間もテンションが上がって好き。大切な友だちのお祝いごとなどにも利用することが多いのですが、友だちにも「おしゃれをしてきてね」と伝えています。

お料理はどれも美味しくて、訪れるたびに「生きていてよかった!」と思えるほど。シェフをはじめ、スタッフの方たちが料理に対して真摯に向き合っていることがまっすぐに伝わってきて、私も頑張ろうという気持ちになります。気軽に通えるようなお値段ではないので、仕事を頑張ったご褒美のようなものですね。
Q04 今、欲しいものはありますか?
おしゃれな電動自転車! 坂の多い街に住んでいるので、食材の買い出しをしたあとが大変で。電動自転車があればラクに荷物が運べるようになりそう。
Q05 今まで旅をしたなかで、一番好きな場所は?
パリです。初めて訪れたのは2019年の秋でした。仕事で立ち寄っただけだったのですが、その2ヵ月後に一人旅で10日ほど滞在しました。当時ありがたいことに常にスケジュールがいっぱいで、お休みがなかなかとれず・・・。このままでは心身ともにパンクしそうだったので、思いきって休みをとらせてもらいました。

観光をしたいというよりは、そこに住んでいるかのように生活をしたいと思ったので、アパルトマンを借りて過ごしました。マーケットで野菜や肉を買って料理をしたり、花を買って部屋に飾ったり。パリの街をランニングもしましたね。蚤の市でうつわや雑貨を見るのも宝探しみたいでワクワクしました。フランス語は全然できないけれど、笑顔で「ボンジュール」とあいさつするうちに、お店のスタッフと仲良くなれたのも楽しかった。

以前の私だったら、失敗を恐れてチャレンジできなかったと思います。でも、20代後半から始めたマラソンやラジオの仕事で、失敗は恥ずかしいことではなくて、自分のエネルギーになると気付けた。そこから、“何でもやってみる精神”になって、10日間のパリ生活でも、もっと失敗や恥ずかしいことをして強くなりたいと思ったんです。でも楽しすぎて失敗が物足りなかったので(笑)、コロナが収束したら、まずはパリに行きたいですね。
「強くてしなやかで、チャーミングな女性に憧れる」
Q06 自分の生き方に大きな影響を与えてくれたひとは?
迷ったとき、それから私のターニングポイントにいつも声をかけてくれるのが料理家の寺井幸也さんです。最初の本(『高山都の美 食 姿 「したたかに」「自分らしく」過ごすコツ。』/双葉社)を制作している時期に、結婚を約束していた彼とお別れをしてしまい、どん底を経験しました。かわいそうな女には見られたくないと、気持ちを奮い立たせてはいましたが、友人たちからするとウジウジしているように見えたんでしょうね。そんなときに彼から「いつまでもめそめそして、幽霊みたいな女にひとは寄ってこないよ」と言われて。ハッとして、前に進むきっかけになりました。
今もへこんだときや挫折をするたびにこの言葉を思い出します。大人になるにつれて、はっきりと助言してくれるひとは少なくなるから、とっても大事な存在。いつも彼には背中を押してもらっています。
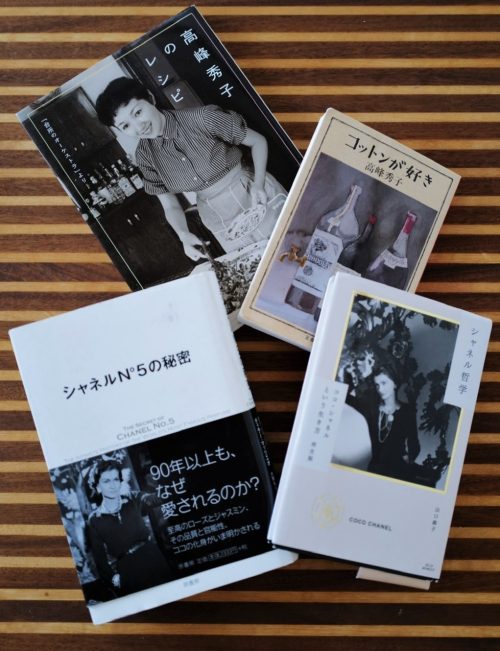
私もこういう女性になりたいという憧れの存在は、高峰秀子さんとココ・シャネル。阿川佐和子さんも大好き。3人に共通しているのは、強くてしなやかでチャーミングなところ。高峰さんは、エッセイを読んで好きになりました。『コットンが好き』が特にお気に入りで、うつわや小物の使い方に刺激をいただいています。
Q07 大切にしている言葉を教えてください!
「笑っていれば風向きは変えられる」。10年ほど前の誕生日に「都はいつも笑っていることで、いい方向に風を吹かせているから、そのまま頑張れ」と友人からもらったメッセージを大切にしています。今は、サインを書くときに添えているほど。私の座右の銘でもあるけれど、誰かの心に残ってそのひとの大切な言葉になればうれしいなと思っているんです。バトンを渡すような感覚ですね。
Q08 お気に入りの本を3冊挙げるとしたら?
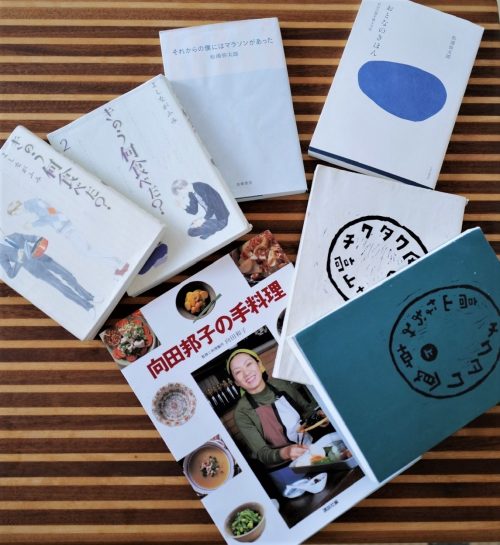
うーん、3冊に絞るのが難しいな。松浦弥太郎さんの『おとなのきほん 自分の殻を破る方法』と『それからの僕にはマラソンがあった』は、繰り返し読んでいる本です。2冊とも、はじめはみんなゼロからのスタートで、できないことは恥ずかしいことではないから続けることが大事だよと教えてくれる本です。読むたびに元気が出ます。
向田邦子さんの手料理を紹介した妹の和子さんの本『向田邦子の手料理』も、何度も興味深く読んでいます。脚本家、小説家、エッセイストとして忙しく活躍されながら、料理が上手でうつわにもこだわりがあったそうです。家庭料理のレシピとエピソードが素敵なんです。
それから、よしながふみさんの『きのう何食べた?』は、読んでいるとおなかが空いてくる本。高山なおみさんの『チクタク食卓』もお気に入りです。食にまつわる本が好きですね。
友だちや仕事仲間と本の話をするのも好きです。「この本、面白かったよ」と勧めてもらった本を読むことも多いです。読書には、知らないことを知る楽しさがありますね。
「愛されるものをつくりたい」
Q09 地球のために実践している、ちょっとイイコトを教えてください!
「なんとなくで物を選ばない」ことでしょうか。
うつわや雑貨が好きだし、おしゃれも好きなので、物を買わない選択はできないからこそ、本当に必要なものなのか、愛せるものなのかを基準に選んでいます。

安かったからとか、流行っているからと“何となく”で買ってしまうと、使わなかったり、すぐに飽きてしまいそう。家にはたくさん物があるけれど、どれも愛しているし、長く使っている大切なものばかりです。
今日着ているシャツは、フィービー・ファイロがクリエイティブディレクターをしていたときの「セリーヌ」のもので、ヴィンテージショップで出合った1枚です。当時の私には手が届かなかったけれど、巡り巡って私のもとにやってきました。試着をしたら驚くほどぴったりで、一緒にいた友人も「都っぽいね」と褒めてくれて、大切に着たい服だと思えました。誰かが手放したものを、大事に使うこともちょっとイイコトですよね。

I.T’.S. internationalと都さんのスペシャルコラボで実現したデニム。
服のプロデュースのお仕事もさせてもらっていますが、自己満足にならないように、“愛される服”を作りたいと思って臨んでいます。簡単には捨てられない、捨てたくない、大事にしたいーーそう思っていただけるものづくりも私のテーマの一つです。
Q10 2030年までに実現したい夢は?
愛されるものづくりにつながりますが、皆さんに大事にしてもらえるもの、こと、空間をプロデュースする会社を今年スタートさせようと準備しています。
本の発売時に全国の蔦屋さんでポップアップショップをやらせてもらったことが、きっかけです。私が愛用している調味料や好きな作家のうつわなどを集めて、私の書籍と一緒に販売をしました。うれしいことに、たくさんのお客さんが来てくださって。私もできるだけお店に立って接客をしたのですが、一人ひとりに合ったお皿を選ばせてもらうのがとても楽しくて、本当にいい経験になりました。

高山さんのセンスが詰まった書籍『高山 都の美食姿』は、大好評につき4冊を数えるまでに。
自分でセレクトしたものを集めてお店を開くことがまず第一歩。海外に行けるようになったら、パリに買い付けに行きたいですね。2030年には店舗数が増えていたらいいなと思うし、飲食店もオープンしていたいです!
森カンナ「だらだらモードから脱出する方法」【連載 / ごきげんなさい vol.05】
俳優 森カンナさんが日々の生活のなかで見つけたこと、感じた想いを綴る連載エッセイ「ごきげんなさい」。自分を“ごきげん”にするためのヒントを探しましょう。
森カンナ「それでも生きていかにゃならんし。2021の振り返り」【連載 / ごきげんなさい vol.03】
俳優 森カンナさんが日々の生活のなかで見つけたこと、感じた想いを綴る連載エッセイ「ごきげんなさい」。自分を“ごきげん”にするためのヒントを探しましょう。
