私が惹かれる「魅力」の正体。目指すのは桃のような女性

「人は『魅力』でしか縛れないんだよ」
最近、知人から言われたその一言が、心に深く刻まれている。
私はときどき、欲張りになる。
もっと愛されたい、とか。
もっと認めて欲しい、とか。
でも、どんなに頑張っても人の気持ちをコントロールすることは難しい。
だったら、相手に求めるよりも、自分を整えるほうがいいのかもしれない。
では、私にとって「魅力的な人」とはどんな人だろう。
大好きで尊敬している人たちのことを思い浮かべながら、私なりの「魅力」を考えてみることにした。
おすすめ記事:「幸せって何だろう?」目指すのは未来を追うより、今を感じる生き方
ホワンとふんわり。やわらかい空気を身に纏っている人
私は空気がふわっとやわらかい人に魅力を感じる。
では、その「やわらかさ」とは何だろう。
大好きな人たちを思い浮かべると、頭に浮かんでくるのは、だいたい笑っている顔だ。「目にはその人の生き方が出る」とよく言うけれど、目に優しさがある人が纏っている空気は、いつもふんわり、やわらかい。
いつもニコニコでいるのは難しいかもしれないけれど、ほんの少し口角を上げるだけでも、身に纏う空気は変えられるかもしれない。
そしてもうひとつ。私の周りにいる空気がやわらかい人たちは、愚痴を言わないし、誰かを否定したり、傷つけたりする言葉を決して使わない。
自分は自分、あなたはあなたと、ちゃんと境界線を持っていて、それぞれの価値観を認めているからなのかもしれない。
空気のやわらかい人と一緒にいると、安心して話ができるし、何を話さずとも近くにいるだけで心地が良いなと思う。

フルーツで例えるなら桃のような人
でも、空気がやわらかい人は、ただ優しいだけではない。
私の大好きな人たちは、穏やかな表情をしているけれど、自分の中にある想いや目標を、はっきりと言葉にできる人たちだ。
こんなことを成し遂げたい。
この想いを伝えたい。
こんな人生を歩みたい。
自分の内側としっかり向き合い、人生の軸を持っている人は素敵だな。
フルーツでたとえるなら、桃のような人だ。やさしい色と、やわらかな手ざわり。なんだかホワホワしているのに、中には、かたーい種がある。
私は、そんなふうに、やわらかさと熱い想いの両方を持っている人に、強く心を動かされる。
「これお願い」がちゃんと言える人
私の周りの尊敬する人たちは、一人で全部を抱え込んでいない。手放すことを徹底しているように思う。
自分がエネルギーを注ぐべきことと、そうでないことを分けているのかもしれない。
だから「これ、お願いしてもいい?」と周りを信頼して、巻き込んでいく。
私はついつい「こんなことをお願いしたら迷惑かな」と考えてしまうけれど、実は、頼られることに喜びを感じている。
大好きな人たちに「さおりさーん、これお願いできる?」なんて言われた時には、うれしくて、顔がニヤけてしまう。大好きな人の力になれるなら、できることは全力でやりたいと思ってしまう。
「人に頼る」ができる人は、やっぱり魅力的だなと思う。
魅力の土台は「経験」なのかもしれない
そしてもうひとつ。私が惹かれる人に共通しているのは、たくさんの経験を重ねていることだ。
本を読んだり、勉強したりして得た知識も大切だと思う。でもそれ以上に、実際に動いて、感じて、その出来事を自分の中で消化している人に、私は強く惹かれてしまう。
うれしかったことや感動した経験はもちろん、しんどかったこと、悲しさ、孤独……そういった時間をたくさん経験して乗り越えてきた人の言葉は、どこかあたたかくて、重みがある。
やわらかさも、想いの強さも、人に頼れるしなやかさも、色々なことを乗り越えてきた経験から生まれているのかもしれない。
だから私も、興味のあることにどんどん挑戦して、気になる場所には出かけて、会いたい人には会いに行こうと思う。そうやって重ねた経験が、いつか私の中にやわらかな魅力を育ててくれたらいいな。そんなふうに思っている。
更年期前後の“いま知りたい”10の疑問に専門家が回答

更年期(平均51歳前後)は、いま大きな注目を集めています。多くの女性がこのホルモンの転換期について率直に語り始め、「何が普通で、何が普通ではないのか」を学び始めています。
その“妹”にあたるのがペリメノポーズ(更年期前期)。閉経に至るまでの数年間にわたる移行期で、心身にさまざまな変化が起こります。しかし、まだ情報不足が続いています。
Hey Perryが主催したイベントでは、専門家たちが集まり、女性が必要な情報にアクセスできるようにするにはどうすべきかが議論されました。そこで寄せられた質問に、医師や看護師が回答しました。
おすす記事:【更年期美容カウンセラー斉藤万奈さんインタビュー】「これって更年期?」もしや、と不安になったあなたへ――専門家が明かす、心と体の変化を乗りこなすヒント
1. そもそもペリメノポーズとは?なぜあまり知られていないの?
ケリー・キャスパーソン医師:
まず「閉経」とは、自然な月経が1年間ない状態を指します。
ペリメノポーズはその数年前から始まります。卵巣のホルモン分泌が徐々に不安定になり、周期的な分泌が弱まる時期です。閉経の2~10年前に始まることがあります。
2. 自分がペリメノポーズかどうかはどう分かる?
血液検査やレントゲンで正確に診断できるものではありません。
30代後半~40代で症状が出始めているなら、臨床的にはペリメノポーズと考えられます。
3. 主な症状は?
症状は人それぞれですが、よくあるのは:
- 「なんだか自分らしくない」感覚
- 疲れやすい
- 睡眠トラブル
- ホットフラッシュ(のぼせ)
- 夜間の発汗
- 頻尿
- 尿路感染症の増加
- 性的変化(潤い不足、痛み)
ホットフラッシュは単なる不快症状ではなく、心疾患リスクとも関連することが分かっています。
4. 「更年期の怒り」は本当?
あります。
エストロゲンやテストステロン、プロゲステロンは脳内神経伝達物質に影響します。ホルモンが減少すると、怒りや不安、うつのリスクが高まることがあります。
5. なぜ体重が増えるの?どう対処する?
体重増加というより、体組成の変化が起こります。筋肉量が減り、脂肪が増えやすくなります。
対策は:
- タンパク質中心の食事
- 運動
- カロリー管理
- 必要に応じてホルモン療法やGLP-1薬の検討
魔法の解決法はありませんが、選択肢はあります。
6. サプリメントは役立つ?
カフェイン、クレアチン、食物繊維、ビタミンD、オメガ3など、食事で不足しているものを補うのは有効な場合があります。

7. 自然な老化なのに治療する必要はある?
「虫歯は自然だから放置しますか?」
卵巣だけ治療しない理由はありません。
現代女性は卵巣寿命より40年も長く生きる時代です。
8. ホルモン療法は乳がんリスクを高める?
大規模研究では、エストロゲン単独療法は乳がんリスクを低下させたという結果もあります。
リスクは、飲酒や運動不足、肥満のほうが大きい場合もあります。リスクとベネフィットを冷静に考える必要があります。
9. テストステロン療法は?
テストステロンは女性にとっても重要なホルモンです。
エネルギー低下、筋肉量減少、自信の低下などがある場合、治療が役立つ可能性があります。
10. 更年期におすすめの食事は?
地中海式のような植物中心の食事が推奨されます。 加工食品を減らし、サステナブルな食生活を心がけることが大切です。
更年期は「終わり」ではなく、移行期
更年期は、衰えのサインではありません。人生の第二章に入るための、通過点。
体は変わります。 でも、あなたの価値は変わりません。
エネルギーが落ちるなら、休んでいい。
怒りが湧くなら、深呼吸していい。
変化を受け入れられなくても、それも自然。
更年期は、「これからどう生きたいか」を静かに問いかける時間でもあるのかもしれません。
ダイエット文化とは?日本女性が知っておきたい本当の影響と6つの対処法

「食べすぎたから明日は抜こう」
「夏までに5kg痩せなきゃ」
「この服を着るにはもっと細くならないと」
こんな言葉を、無意識のうちに自分へ向けていませんか?
SNS、芸能人、雑誌、フィットネス系インフルエンサー
現代の私たちは常に“痩せていることが正解”というメッセージにさらされています。
これこそが「ダイエット文化」です。
おすすめ記事:代謝の健康状態とは?医師が解説
ダイエット文化とは?簡単に言うと
ダイエット文化とは、 「細い=健康」「痩せること=自己管理ができている証」という社会的価値観のこと。
本来、健康とは体重だけで測れるものではありません。
それなのにダイエット文化は、
- 体重計の数字
- 洋服のサイズ
- 見た目の“細さ”
だけを基準にしてしまいます。
日本の若い女性と「やせ」の現実
厚生労働省の「令和5年 国民健康・栄養調査」によると、20代女性の約2割がBMI18.5未満の“やせ(低体重)”に該当しています。
それでも多くの女性が「もっと痩せたい」と感じている。
別の調査では、医学的には標準体重であっても、 自分を「太っている」と感じている女性が7割以上いるという結果もあります。
数字だけを見ると、日本の若い女性は“すでに十分に細い”のです。それでも、心の中では「まだ足りない」と感じてしまう。
それはなぜでしょうか。

「痩せること」は本当に健康?
1940年代に行われた有名なミネソタ飢餓実験では、 健康な男性にカロリー制限を続けた結果、
食べ物への強い執着や抑うつ、不安、イライラなどが生まれました。
長期的なダイエットは、体だけでなく心にも影響を与えることがわかっています。
さらに、体重の増減を繰り返す「ヨーヨーダイエット」は心疾患リスクとも関連するという研究もあります。
私たちは「痩せる=良いこと」と教わってきました。 でも、そう考えることで自分を責め続けていないでしょうか。
ダイエット文化が日本女性に与える影響
1. ヨーヨーダイエット
食事制限 → 一時的に痩せる → リバウンド → 自己嫌悪
このサイクルは心身に大きな負担をかけます。
2. 低い自己肯定感
「まだ足りない」「もっと痩せないと」という思考が止まらない。
3. 摂食障害のリスク
過度な制限や過食の繰り返しは、将来的な摂食障害につながる可能性があります。
4. ホルモンバランスや骨密度への影響
極端なカロリー制限は、生理不順や将来的な骨粗しょう症リスクにも。

ダイエット文化とやさしく距離を取る6つのヒント
1. 数字より体調を優先する
体重よりも、
・睡眠の質
・集中力
・月経の安定
・疲れにくさ
を基準に。
2. SNSの情報を選別する
フォローを見直し、ボディポジティブや専門家アカウントを選ぶ。
3. 「短期間で−5kg」などの誘惑に注意
急激な減量はほぼ確実にリバウンドを招きます。
4. “ダイエット食品”より“自然な食事”
野菜、魚、豆類、ナッツ、オリーブオイルなど、 加工品を食べる頻度をおさえた自然食品を中心に。
5. 食べ物を道徳化しない
ケーキは「悪」ではありません。
食事はエネルギーであり、楽しみでもあります。
6. ボディ・アクセプタンスを学ぶ
「健康はあらゆるサイズに存在する」という考え方を知ること。
体は、敵じゃない
私たちの体は、何年も、何十年も、呼吸し、働き、支え続けてくれている存在。それなのに、「細くならないと認めない」と言い続けるのは、 少しだけ酷かもしれません。
痩せることを目標にする前に、 まずは「今あるあなたの体」を信頼すること。
健康は、ひとつのサイズに収まりません。
あなたの体は、今日もちゃんと生きて、動いて、支えてくれている。それだけで、もう十分に尊いのです。
ファッションは“量より質”。あなたらしさが息づくワードローブのつくり方

クローゼットを開いたときに、「これ好き」と言える服がどれだけあるでしょうか。
トレンドが目まぐるしく変わる今だからこそ、たくさん持つことよりも、本当に気に入った一着を選ぶことが、心地よいワードローブづくりの鍵になります。
質の良いアイテムは、あなたの毎日にそっと寄り添い、自信を育て、長く愛せる相棒になってくれます。ここでは、「量より質」の選択が、どんなふうに毎日を軽やかにしてくれるのかをご紹介します。
おすすめ記事:ファストファッションとは?環境問題・社会問題・未来のサステナブルファッションまで解説
“良い服”ってなんだろう?
良い服の条件は、価格やブランド名だけでは決まりません。
大切なのは、着たときにしっくりくるかどうか。
- 丁寧に縫われている
- 肌に触れたときに気持ちいい
- 素材そのものが長く使える
そんな一着は、流行が変わっても長く寄り添ってくれます。
買い替えが減り、時間もお金も、そして心の余白も生まれていきます。
質の良い服が“個性とスタイル”をつくる理由
量より質を選ぶことで、あなたのスタイルがより明確になり洗練されます。
- 流行に振り回されず、自分だけの定番スタイルが育つ
- 上質なシルエットと素材が、着るだけで自信を与えてくれる
- 1着をさまざまに着回せるので、毎日のコーデが楽になる
また、質の良いブランドはオーダーや丁寧な仕立てを提供していることが多く、
買い物が「大量消費」ではなく、自分らしさを反映した体験へと変わります。

地球にも、自分にもやさしい選択
質の良いアイテムは、長く着られるだけでなく、素材やつくり手の背景が丁寧に扱われていることが多いもの。
- オーガニック素材
- 長持ちする生地
- 大量生産に頼らないものづくり
買う量が減ることで、地球への負担を少しだけ軽くしながら、「本当に好き」と思える物だけに囲まれる暮らしへ近づきます。
ワードローブの革命児:白の防水スニーカー
今、多くの女性に選ばれている“量より質”アイテムの1つが 白の防水スニーカー。
白いのに汚れにくい・天候に強い・どんな服にも合う
という万能さで、1足で何役もこなせる優秀アイテムです。
- 雨の日でも快適で実用的
- シンプルで洗練された白が、どんなコーデにも合う
- お手入れが簡単で、長くきれいに保てる
まさに、「少ない数で最大の価値を発揮する」 という質を重視するファッションを象徴する1足です。

長く愛せるワードローブをつくるために
質を大切にしたワードローブは、“毎年入れ替える服”ではなく、何年経っても着たい服のコレクションへと変わります。
- 長く着られる服を選ぶ
- 時々ワードローブを見直す
- 正しいケアで服を大切にする
こうした積み重ねが、あなたのスタイルと自信、そして環境への優しさを育てます。
まとめ:量より質。それがあなたと地球にとって最良の選択
ファストファッションがあふれる現代ですが、 “本当に好きなものを選ぶ”というシンプルな選択が、 あなたの人生をそっと豊かにしてくれます。
量より質を大切にすることは、 自分を大切にすることでもあり、地球への小さな思いやりでもあります。
あなたらしさが息づくワードローブで、毎日をもっと心地よく。
【エッセイ】長い髪に少し飽きてきた——でも切ることは、もっと深い何かを手放すようで

あの夏のことを思い出す。
2024年、世の中はボブの熱に包まれていた。ヘイリー・ビーバーやゼンデイヤ、リリー・コリンズ——誰もが軽やかなあごラインのボブにしていて、私もその波に乗るつもりだった。
美容室の椅子に座るまでは。
「パリの女の子みたいな、あの潔いボブがきっと似合うはず」
そう思い込んでいたのに、鏡の前に座った途端、自信はふっと溶けてしまった。
“パリ風ボブに憧れて髪を切ったものの、結局中途半端なロブに落ち着き、帰り道にはすでに後悔と「自分らしくない」という違和感を抱えていた。”
勇気を出すはずだったその日は、結局、どっちつかずの“肩につくロブ”で終わってしまった。
サロンを出るときには、すでに小さな後悔が芽生えていて、それでも美容師さんに笑顔で頷きながら「気に入っています」と言った。帰りの車の中、ミラーに映る自分を執拗に覗き込みながら、「これはこれで悪くない」と自分を説得しようとした。でも、その日一日、どうしても“自分じゃない”という違和感が消えなかった。
サロンを出るときには、すでに小さな後悔が芽生えていて、それでも美容師さんに笑顔で頷きながら「気に入っています」と言った。帰りの車の中、ミラーに映る自分を執拗に覗き込みながら、「これはこれで悪くない」と自分を説得しようとした。でも、その日一日、どうしても“自分じゃない”という違和感が消えなかった。
振り返れば、すべてが衝動的だったと思う。
仕事が始まって数ヶ月、自分なりの“大人のスタイル”を見つけなきゃと焦っていた。
大胆に髪型を変えることが、あせりから救ってくれる気がした。
だけど、床に落ちていく自分の髪を見つめながら、気づいてしまった。私にとって髪は、ただの“外見の一部”ではない。もっと深いところで、自分という存在とつながっているものなのだと。
おすすめ記事:がん治療中の脱毛に向き合う方法〜心と体をケアするために〜
ロングヘアは、ずっと私の“居場所”だった
自分の髪を自分で決められるようになってから、私はずっとロングヘアだ。
そのきっかけは、まわりの女の子たちの影響かもしれないし、子どもの頃に大好きだった『リロ&スティッチ』のナニに憧れたせいかもしれない。ハワイに住むいとこの Kuʻuipo の、腰まで届く髪にも心を奪われていた。
“長い髪=美しさ”
知らないうちに、こんな価値観が当たり前になっていたのだと思う。
でも、私のロングヘアには、いつの間にか別の意味が宿り始めていた。
母と過ごした小さな習慣。
卵を混ぜたものを頭皮に塗ってくれた日曜日、キッチンバサミで毛先を1センチだけ整えてくれた夜、写真撮影の前日にきつく編み込んでくれた三つ編み。
思春期に自分の身体に自信を持てなくなった頃、ロングヘアは私を守ってくれる“安心の毛布”になっていた。

髪はアイデンティティと深く結びついている
「髪はアイデンティティとつながる複雑な“言語”のようなもの」
心理学者・アフィヤ・ムビリシャカ博士 の言葉は、私自身の感覚を優しく代弁してくれた。
髪は、文化やルーツ、信念を語る。だからこそ、“自分らしくない髪”は心に小さなずれを生むのだ。
“髪は文化やルーツを映す存在であり、自分らしくない髪型は心のずれを生む——そして20代で、フィリピンのルーツとのつながりを自分の髪の中に見いだした。”
20代になって自分のルーツを探す時間が増えた。母の故郷であるフィリピンとのつながりを、言語でもなく肌の色でもなく、“自分の髪”に見いだした瞬間があった。
いとこの ティファニー が言った、 「私たちのフィリピンの髪、本当にきれいだよ」という言葉が胸の奥に残っている。
フィリピンでは、髪は美しさだけでなく、強さや誇りの象徴だ。
植民地時代、男性の長髪が“抵抗のサイン”だったことも知った。
髪は、ただのファッション以上のもの——物語を宿している。
母の髪の歴史にも、私と同じ“揺らぎ”があった
母はフィリピンのダバオで生まれ育ち、若い頃のハワイ時代も姉妹みんながロングヘアだった。 1990年、アメリカンドリームを追ってNYへ移住したとき、初めて髪をバッサリと切ったという。
「新しい人生をスタートするために、何か変えたかった」
そう言う母の目は、少し誇らしげだった。
髪の長さは、その人の人生の変化を映す鏡なのだと気づく。
それは母にも、私にも当てはまっていた。

もう一度、自分の髪と向き合うために
2020年、パンデミックの不安の中で、私は髪をプラチナブロンドに染めた。
あの時は、変化が必要だった。でも、ブリーチで傷んだ髪を見つめながら、「私はここで何を求めていたんだろう」と思ったこともある。
2022年、ようやく地毛に戻し、健康な髪を育てながら、鏡に映る自分がゆっくりと落ち着きを取り戻していった。
それでも最近、また変化を求める気持ちが揺れ始めた。仕事柄、毎日のようにヘアチェンジするセレブを見ているせいかもしれない。
だけど、スタイリストマーク・タウンゼント の言葉が頭に残る。
「自分のスタイルを知っていることには、誇りがある」
それが、私の迷いにそっとストップをかけてくれた。
そして私は、18ヶ月ぶりに美容院へ行った
今回は、インスピレーション写真をしっかり持って。
美容師さんは、傷んだ毛先を少し整え、頬に沿うレイヤーで表情を明るく見せてくれた。
動きのある軽やかなラインをつくりながらも、私の象徴である“長さ”はきちんと残してくれた。
カットの間ずっと「自分らしさ」を失わせないように寄り添ってくれて、切ってもらうたびに安心が積み重なっていくようだった。
美容院を出たとき、髪が腰に触れる感覚にホッと胸がほどけた。
鏡に映る自分を見つめながら、静かに思った。
ああ、やっと自分に戻れた。
この記事は、以下の記事をもとに翻訳・再編集したものです:
https://www.instyle.com/emotional-attachment-long-hair-embrace-identity-haircut-11881224
2026年版 | 最高のオーガニックコットンTシャツ

オーガニックコットンTシャツは、ミニマルなワードローブの定番アイテム。デニムと合わせても、ジャケットやカーディガンのインナーとしても万能に活躍してくれます。
私たちはいつも、オーガニック素材の使用、公正な労働環境、スローファッションの姿勢など、サステナブルに配慮したブランドに注目しています。
おすすめ記事:ファストファッションとは?環境問題・社会問題・未来のサステナブルファッションまで解説
なぜオーガニックコットンTシャツを選ぶべき?
オーガニックコットンTシャツは、環境にも私たちの肌にもメリットがたくさんあります。
- 化学農薬や合成肥料を使わず栽培されるため、環境汚染を軽減
- 土壌や生態系にやさしい農法で、水の使用量も少なくて済む
- 農家の労働環境に配慮したフェアな生産体制が多い
- 化学薬品不使用のため、肌触りがやわらかく刺激が少ない
環境も肌も心地よい、良質なオーガニックコットンTシャツは、持っていて損のないアイテムです。
おすすめブランド
Reformation
サイズ| XS – XL
価格| ¥5820
何にでも合わせられるクルーネックを探しているなら、Reformationのオーガニックコットン・ヴィンテージTがぴったり。リラックスフィットで、涼しげな着心地。カジュアルにもきれいめにも使えます。
生地はやや薄めなので、白などの淡色は透け感が気になる場合は濃い色か可愛いブラレットを合わせるのがおすすめ。 Reformationはロサンゼルス発のブランドで、サステナブル素材やアップサイクル素材を使用し、公正賃金の環境で生産しています。

Harvest and Mill
サイズ| XS – XL
価格| ¥7352
Harvest and Millの魅力は、オーガニックコットンがアメリカ国内で栽培されていること。紡績・編立・縫製まで、すべてサンフランシスコで行われており、サプライチェーン全体がアメリカ国内に完結しています。
とくにおすすめなのが、オフホワイトのやわらかいクルーネック。無染色・無漂白の自然な白なので、肌に安心して触れられる質感です。

The Classic T-Shirt Company
サイズ| XXS – XXL
価格| ¥15,300
まさに「クラシック」の名にふさわしいブランド。カリフォルニア発で、100%オーガニックコットンにこだわり、シンプルなTシャツを極めています。
シルエットはゆったりめで、身体を締めつけず美しく見えるバランス。生地は適度な厚みがあり、ホワイトでも透け感が少なめ。さらに、豊富なカラー展開と、事前に洗い・縮み加工がされているので、洗濯後にサイズが変わる心配もありません。

Everlane
サイズ| XXS – XL
価格| $30
EverlaneのオーガニックコットンTシャツは、ボーイッシュな雰囲気とフェミニンなシルエットのバランスが絶妙。肌に吸い付くような柔らかさで、ベーシックなのにどこか上品な雰囲気が漂う一着です。
白もほとんど透けず、ボックス型のシルエットはデニムにもショートパンツにも相性抜群。ミニマリストのワードローブにひとつは持っておきたい定番Tシャツです。

まとめ
オーガニックコットンTシャツは、私たちの肌にも環境にもやさしく、長く愛せるワードローブをつくるうえで欠かせない存在です。自分の心地よさを大切にしながら選んだ一枚は、忙しい日々のなかで「これを着ると安心する」という小さな支えにもなってくれるはず。
今回ご紹介したブランドは、どれも丁寧なものづくりとサステナブルな姿勢を大切にしているところばかり。お気に入りの一枚に出会えたら、そのTシャツがあなたの毎日のスタイルにそっと寄り添ってくれますように。
【ハミングが届けるポジティブニュース】失われた「自分の腕」を取り戻す未来。「動く!」と願うだけで、麻痺した腕が再び動き出す

Credit: Vilje Bionics
明日、家族のために夕飯を作ったり、子供と手をつないで歩いたり。 そんな日常のあたりまえの動作が、突然できなくなったら……。そう考えたら、少し怖くなってしまいますよね。
脳卒中は、4人に1人が生涯のうちに経験すると言われています。一命を取り留めても、体に麻痺が残ってしまうことが多く、多くの人が「もう前のような生活は送れない」と今までの生活をあきらめてきました。
“脳卒中による麻痺で日常生活をあきらめざるを得ない人が多い中、ノルウェーのスタートアップが、思い通りに腕を動かせる世界初の腕全体用エクソスケルトンを開発し、新たな希望を示している。”
でも、諦めるのはまだ早い、そう思わせてくれるニュースがノルウェーから届きました。
ノルウェーのスタートアップ企業が、麻痺して動けなくなった腕を、まるで自分の意思に従って動いてくれる「世界初の腕全体用エクソスケルトン(外部骨格)」を開発しました。これはただの機械ではありません。
おすすめ記事:【ハミングが届けるポジティブニュース】世界中でウミガメが増えている? インドの海岸で起きた奇跡のストーリー
「思い」を、ロボットが読んでくれる
この画期的な装置「Vilpower(ヴィルパワー)」を開発したのは、ノルウェーのVilje Bionicsという会社です。これまでの補助器具と何が違うのか、見てみましょう。
「Vilpower」の3つの特徴
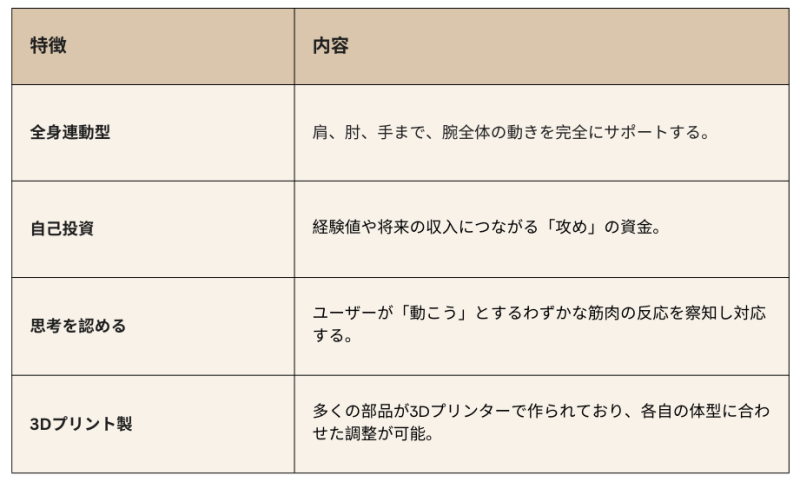
創設者のサイード・ホセイニ氏は、「ユーザーが腕をどう使いたいか『考える』ことで作動する」と語っています。私たちの頭で望んでいることが、そのまま腕の動きに繋がる――まるで魔法のような技術ですよね。
「この腕は、もう他人じゃない」ある女性の感動的な変化
この技術によって、人生が劇的に変わった女性がいます。ヨハン・マリー・ヘムネスさんです。
彼女は2017年に脳出血で倒れ、左半身麻痺が残りました。リハビリでは「歩くこと」に重点が置かれ、腕の回復は後回しにされてしまったそうです。
「自分の腕なのに、言うことを聞いてくれない。まるで他人の腕のように感じて、腕に『ジェニー』という別の名前をつけて呼んでいたんです。動かない腕が邪魔に感じて、切り落としてしまいたいと思ったことさえありました」
こんな彼女がこのロボットアームを装着した瞬間、信じられないことが起きました。
- 体の一部だと感じられるようになった。
- 自分の力で野菜を切ることができた。
- 入れ物のふたを開けることができた。
「これを装着していると、また元の自分に戻った気がする」と笑顔で話します。
2026年、自立に向けた新しい一歩が始まります
現在、40名ほどがこの装置の試用を終了しており、2026年の前半(4月〜6月頃)には、ノルウェーを皮切りに正式な製品として発売される予定です。
開発チームが何よりも大切にしているのは、「自立」です。人の手を借りずに、自分の意志で料理をし、歩くことができるようになることを目指しています。
最新のテクノロジーは、私たちを置いてけぼりにするものではなく、こうして「人間らしさ」を支えるために進化しています。 もし、あなたの周りでリハビリをがんばっている人がいたら、「こんな未来がすぐそこまで来ているよ」とぜひ教えてあげてください。 近い未来は、私たちが想像するよりもずっと明るいかもしれません。
参考記事:‘It Feels Like Me Again’: World’s First Arm Exoskeleton Gives Stroke Patients Independence
女性のエンパワーメントと美容整形──その“矛盾”をめぐる考察

美容整形は女性の自己決定を後押しする力にもなれば、社会が求める不可能な美の基準をさらに強化する存在にもなり得ます。
古代神話から現代のSNSまで、女性の身体は常に「美」と「理想」をめぐる視線にさらされてきました。
この記事では、美容整形の歴史・エンパワーメントの側面・女性へのプレッシャー・メディアの影響という複数の観点から、その複雑な関係性を紐解きます。
おすすめ記事:エイジングケアの新常識:科学・心・美の調和で輝く「タイムレスビューティー」
美の理想はどこから来たのか:女性神話に続く“単一の美の基準”
ユダヤ教神話のリリスやイブ、古代のビーナス像、そしてハリウッド黄金期のマリリン・モンローやオードリー・ヘプバーン。古くから女性は「こうあるべき美」の象徴として描かれ、それは単一化された理想像をつくりあげてきました。
多様性が重視される今でさえ、SNSでは美容整形や特定の美のトレンドが拡散され、別の形で“美の同質化”が加速しています。
美容整形の歴史:古代から現代までの“美の再構築”
美容整形の起源は、古代エジプト・インド・ローマにまで遡ります。
- エジプト:形成術の基礎が生まれた
- インド:鼻の再建術
- ローマ:耳の修復など
- 20世紀:戦争での外傷治療が技術を飛躍的に発展させた
現代の美容整形は、医療技術の進歩によって安全性が向上し、外見の改善と自信回復の手段として定着しました。

エンパワーメントとしての美容整形:自己肯定感を取り戻す手段
自信は人生の幸福度に深く関わるといわれています。美容整形は、コンプレックスを抱える女性にとって自己受容のきっかけになることもあります。
例えば:
- 鼻の形に悩む
- 胸の左右差が気になる
- 妊娠・加齢で変化した体を整えたい
こうした悩みに対し、整形は「ありのままの自分に戻るための手段」として選ばれることがあります。
実際、多くの女性は手術後にこういったことを感じるといいます。
- 外見の満足度が上がる
- 自信が戻る
- 気持ちが前向きになる
芸能人の中にも、率直に整形体験を語る女性たちが増え、 “選択としての整形”が肯定的に語られる場面も広がっています。
しかし、それは同時に“美の圧力”を強化する側面もある
美容整形には、女性のエンパワーメントを支える一方で、次のような問題点も指摘されています。
- メディアやSNSが“理想の顔・体型”を大量に発信
- 「普通の人」がそれに合わせようとするプレッシャー
- 外見が評価軸となり、女性の個性や能力が見えにくくなる
- 「美しくあるべき」という社会的な同調圧力の強化
研究者たちは、この現象を “メイクオーバー社会”と呼び、外見の改造を繰り返す文化の危険性を指摘しています。

美の神話をつくるメディアの影響
SNS・広告・テレビは、女性月間のキャンペーンであっても、美容整形を「欠点を直す手段」として提示することが多くあります。
このメッセージは、とくに若い女性に
- 自分の容姿への不安
- 比較による自己否定
を生み出しやすいと研究で示されています。
メディアは“美の多様性”を広げる力も、“美の固定化”を促す力も持っているため、その影響は非常に大きいのです。
結論:美容整形は女性を自由にするのか?それとも縛るのか?
美容整形は女性に自信や自由を与える一方で、社会が押しつける美の基準を強化し、女性全体としての自己価値を揺らす側面もあります。
だからこそ大切なのは、
- 「自分のための選択」であるか
- 社会の圧力に押されていないか
- 心の健康と情報が整った上で判断しているか
という視点です。
女性の身体は、装飾のためではなく「生きるため」にあり、その身体をどう扱うかは本来、他者が介入すべきではない個人の選択です。
美容整形がエンパワーメントになるかどうかは、あなたがあなた自身の声を聞けているかそこに尽きます。
【エッセイ】「69歳の自分の身体を受け入れられるようになるまで」

「痩せていなければ価値がない」
パトリス・ワーナーは、自分の身体は“完璧ではない”と信じて育ちました。
20代、服のサイズが0だった頃でさえ、彼女は「もっと痩せたい」と願っていました。
サンマルコス(テキサス州)に住む現在69歳のワーナーは、こう振り返ります。
「太ももや、ほかの少しでも大きいと思う部分を批判していました。自分より細いと思う女性を見ると、その体型ばかり気になって、『どうすればああなれるんだろう?』と考えてしまうんです。たとえ、その人が全く違う体質だったとしても。」
“ワーナーは若い頃から「痩せていなければ愛されず、認められない」と信じ込み続け、人生の節々で過度な減量を重ねてきた。”
ワーナーは「友達をつくるためにも、恋人を見つけるためにも、痩せている必要がある」と信じていました。
31歳のとき、博士論文を書き上げたタイミングで出産を経験しました。 「授乳しても勝手に“妊娠前の体重”に戻らなかったことに、すごく腹が立ったんです。」
ワーナーは職場のダイエットプログラムに参加し、産後に増えた体重以上に痩せました。4年後、二人目を出産した後も同じことを繰り返します。
「もう恋人のために痩せようとは思っていませんでしたが、当時は“細くて魅力的であること”が、男性管理職に認められる事や学生から“カッコいい”と思われるために必要だと思っていたんです。」
おすすめ記事:ボディポジティブ:体重計も投げ出して、ありのままを受け入れる
人生の中で、身体イメージは揺れ動くもの
シカゴのセラピスト、サラ・アレン博士はこう説明します。 閉経に伴う体型の変化や体重増加、社会からの“若さと美しさへのプレッシャー”は、女性の身体イメージや自己肯定感に大きな影響を与える、と。
ニュージーランドの約1万5千人を対象とした大規模調査では、年齢を重ねるほど身体イメージは改善する傾向があることが示されました。 19歳より74歳のほうが、身体への満足度が高いという結果でした。
男性は人生を通して女性より身体満足度が高い傾向にあり、20代に少し落ち込むものの、30代以降は徐々に改善。女性はゆっくりではあるものの、60代以降で大きく上向くという結果でした。
更年期:「体重が増えると、また批判される気がしていた」
40代、ワーナーは仕事と子育てで忙しく、徐々に身体が「厚みを増して」いくのを感じ始めました。時間がなかったため、以前ほどの“痩せなきゃ”という強い執着は薄れていたものの、大きめの服を買うと「自分を責めずにはいられなかった」と言います。
極端なダイエットにも手を出しましたが、続かず、減った体重はいつも元に戻ってしまいました。「その失敗の恥ずかしさは、耐えがたいものでした。」
“40代以降のワーナーは忙しさや更年期の影響で体重の増減を繰り返し、そのたびに自分を責めながら苦しいダイエットのサイクルから抜け出せずにいた。”
50代で更年期を迎える頃、子育てがひと段落し、仕事はデスクワーク中心に。体重は増え続け、そのたびに彼女は自分を嫌いになりました。
ここから、体重増減を繰り返すサイクルが何年も続きます。
ダイエット → 痩せる → 停滞する → リバウンド → さらに体重増加
そしてまたダイエットへ…。
「60代まで、この体重と恥の悪循環は続きました。友達やキャリアのために痩せなきゃとは思わなくなったけれど、“太っている自分が判断されている”感覚はずっと残っていたんです。」
研究によると、更年期は多くの女性にとって身体イメージが揺れやすい時期。
体型の変化、睡眠トラブル、月経の乱れなどが自己イメージに影響します。
別の研究では、閉経後の女性のほうが、閉経前の女性より身体満足度は高いという結果もあります。
ニューヨークの臨床ソーシャルワーカー、キャサリン・フェリセッタはこう説明します。
「更年期は、多くの女性が“もう到達できない社会的理想”を手放し、自分の身体を受け入れ始める時期でもあります。」

“体重の科学”を学び、セラピーを受けたことが転機に
65歳の誕生日を控えて、ワーナーは“最後のダイエット”に挑戦。処方薬を使って約16kgも痩せましたが、ひどいめまいが続くようになり、体重はまた戻りました。
その後、彼女は医師を変える決断をします。 前の医師は、副作用があっても薬の継続を強く求め、体重が増えると彼女を責めたためです。
新しい医師と面談し、過食とダイエットの歴史を打ち明けると、セラピーをすすめられました。
彼女は『Health at Every Size』と『Intuitive Eating(直感的食事法)』という本を読み、考え方が一変します。
「ダイエットが身体に“飢餓”として認識され、ホルモンが変化して体重を維持しようとする——この仕組みを知ったとき、本当に解放された気持ちでした。」
痩せていなくても、健康でいることはできる。
痩せていなくても、価値のある存在でいられる。
初めてそう理解できたと言います。
“65歳の挫折をきっかけに医師と向き合い直したワーナーは、直感的食事法や「どんなサイズでも健康になれる」という考えに出会い、長年のダイエット思考から解放され自分の価値を再認識した。”
“セルフコンパッション(自分への思いやり)”を学ぶ
現在、ワーナーの身体イメージは人生で最も安定していると言いますが、それでも“道の途中”。セラピーを通じて、身体を批判する内なる声に気づき、自分をやさしく扱う方法を練習しています。
フェリセッタは言います。「セルフコンパッションは、身体イメージを癒すためには欠かせない考え方です。」
また、彼女は“ボディポジティブ”ではなく“ボディニュートラル”を勧めています。
「“自分の身体の全部を好きでいなければならない”というプレッシャーはよくありません。身体への感謝や中立的な見方で十分なんです。」
おすすめ記事:理想の自己 vs 義務の自己:バランスの取れたアプローチ
「69歳の身体を完全に愛している?」
ワーナーはこう答えます。「いいえ。まだ、痩せられたらいいのにと思うことはあります。」
それでも今の彼女は、これまでで最も身体を受け入れられています。
彼女は言います。
「経済的にも時間的にも、助けを求めて回復できる環境があるのは幸運です。支えてくれる夫がいて、インスタグラムで直感的食事法の専門家たちから励ましをもらえることにも、本当に感謝しています。」
これはhttps://www.everydayhealth.com/emotional-health/how-i-learned-to-accept-my-69-year-old-body/から翻訳したものです
2026年版|おすすめしたいエシカルジュエリーブランド6選

サステナブルでエシカルなジュエリーを探している人は年々増えています。特に2026年は「ローカル発」「女性オーナー」「フェアトレード素材」を扱うジュエリーブランドに注目が集まっています。
丁寧な素材選び、適正な賃金、地域へ還元する仕組み。そんな想いが込められたジュエリーは、毎日身につけても、大切な人へのギフトとしても長く愛せるアイテムです。
サステナブルジュエリーを選ぶべき理由とは?
サステナブルジュエリーとは、環境負荷の軽減・エシカルな調達・透明性のある生産背景を重視したジュエリーのこと。
特に近年は、
- リサイクルゴールド
- リサイクルシルバー
- ラボグロウンダイヤモンド(人工ダイヤ)
- ラボグロウンジェムストーン
の人気が高まっています。
これらは新たな採掘を必要としないため、環境破壊やCO₂排出を大きく減らせるという強みがあります。
採掘による森林破壊・水質汚染・労働搾取などの問題を避けながら、美しさ・品質・長持ちする価値を両立できるのがサステナブルジュエリーの魅力です。
エシカルジュエリーとは?何が「エシカル」なのか
一般的なジュエリー産業は長年、
- 劣悪な労働環境
- 不当な低賃金
- 紛争鉱物の問題
- 児童労働
- 採掘による深刻な環境破壊
といった課題を抱えてきました。
こうした背景に対し、エシカルジュエリーブランドは次のポイントを大切にしながら、より透明で持続可能な仕組みづくりを目指しています。
コンフリクトフリー素材の使用
暴力や人権侵害に関わらない、透明性のあるルートで調達された素材のみを使用。
紛争ダイヤを排除する Kimberley Process(キンバリープロセス) などの国際的な取り組みも基準となっています。
フェアな労働環境の確保
- 適正で公正な賃金
- 安全で健全な職場環境
- 労働者の権利尊重
フェアトレード認証を取得し、サプライチェーン全体で倫理的な労働環境を守るブランドが増えています。
リサイクル素材・ラボグロウン素材の活用
リサイクルゴールドやリサイクルシルバー、ラボグロウンダイヤモンドなどを使用し、新たな採掘の必要性を減らし、環境負荷を大幅に軽減します。
職人技術と地域文化の継承
ローカルの職人や小規模工房と協働し、 伝統技術を守りながら、持続可能な形で次世代へと継承していくことも大切な要素です。
エシカルジュエリーを選ぶことが未来につながる理由
あなたがエシカルジュエリーを選ぶたびに、次のような未来を後押ししています:
- 人権が守られるジュエリー産業
- 透明性のあるサプライチェーン
- 環境破壊を減らす生産体制
- ローカル職人や女性起業家の活躍
- 持続可能な消費文化の促進
ただの「アクセサリー」ではなく、価値ある選択の積み重ねが、より良い産業をつくっていきます。
1. CLED(クレッド)
Best For|アップサイクルガラスのジュエリー
Ethics & Sustainability|アップサイクル/リサイクル素材、ロサンゼルスでのハンドメイド、地域支援、プラスチックフリー包装
Product Range|リング、ネックレス、イヤリング、イヤーカフ、ブレスレット、ヘアアクセ、キーチャーム
Price Range|$35(チャーム)〜 $1,150(ネックレス)
ロサンゼルスの女性主導チームが手がけるCLEDは、「Conscious Lifestyle, Earth Friendly & Ethical Design」を理念とするブランド。採掘された宝石や大量生産のプラスチックに頼らず、廃棄されるガラスをアップサイクルして生まれる“Eco Gems™”が象徴的な存在です。すべて手作業でカット、研磨、成形されるため、色・形が一点ずつ異なる唯一無二の美しさが魅力。ガラスを埋立地から救い出し、宝物へと変えるCLEDは、サステナブルで美しく、メッセージ性の強いジュエリーを求める人にぴったりです。
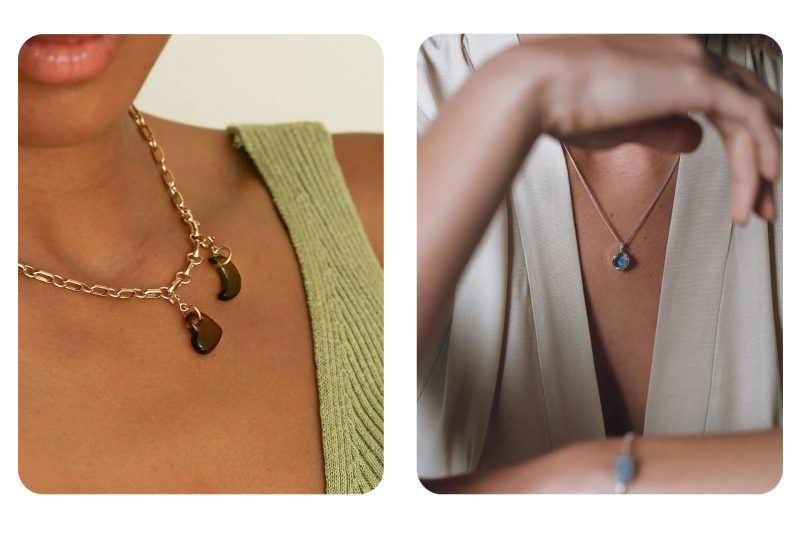
2. Mejuri(メジュリ)
Best For|責任ある調達とリサイクルゴールド
Ethics & Sustainability|倫理的な金属・石、RJC認証のリサイクル/責任調達ゴールド、公正な労働環境、BIPOC・ノンバイナリー支援
Product Range|イヤリング、リング、ネックレス、ブレスレット、アンクレット、エンゲージメントジュエリー、メンズ、ペット用
Price Range|¥7,500(シングルスタッド)〜 ¥10,8500(ダイヤモンドテニスネックレス)
「特別な日だけでなく、毎日つけられるファインジュエリーを」というコンセプトのMejuri。イタリア・インド・韓国など世界中の専門職人が手がけ、伝統的なラグジュアリーブランドのような高い品質を、手の届きやすい価格で提供します。素材には淡水パール、ミネラルストーン、そしてコンフリクトフリーのダイヤモンドなど、責任あるルートから調達されたものだけを使用。ミニマルで洗練されたデザインが揃います。
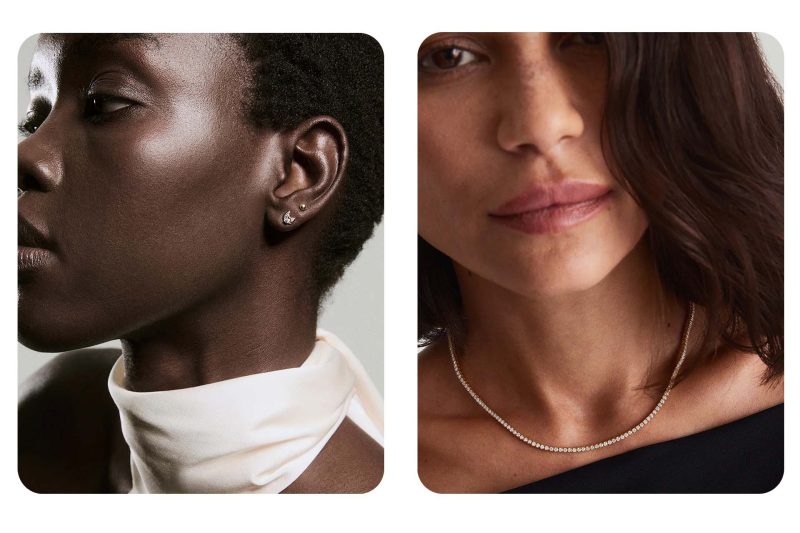
3. Aurate(オーレイト)
Best For|マークアップなしの高品質ファインジュエリー
Ethics & Sustainability|倫理的な労働環境、7代続く職人技、持続可能な調達、コンフリクトフリー、リサイクル素材、社会貢献
Product Range|リング、イヤリング、ネックレス、ブレスレット、アンクレット、エンゲージメントジュエリー
Price Range|¥6,440 (チェーンブレスレット)〜 ¥30,000(ダイヤモンドネックレス)
NYC発のAurateは、100%リサイクルゴールドを使った繊細で美しいジュエリーが人気。歴史的建築のドアノブやブルックリンブリッジから着想を得たデザインは、現代的でありながらクラシックな魅力を持ちます。7代続く職人が仕上げるクラフトマンシップも圧巻。高品質なエンゲージメントピースも揃い、長く愛される“黄金基準”のジュエリーが見つかります。

4. GLDN(ジーエルディーエヌ)
Best For|パーソナライズジュエリー&モダンな家宝級ピース
Ethics & Sustainability|手作り、90%リサイクル素材、利益の10%を寄付、85%が受注生産
Product Range|ネックレス、リング、ブレスレット、イヤリング、アンクレット、セットジュエリー
Price Range|¥4,400(チャーム)〜 ¥15,700(チェーンネックレス)
GLDNは、誕生花・星座・モノグラムなど「大切な人を想うパーソナルなデザイン」が豊富なブランド。ほぼすべてのアイテムにリサイクルシルバー、ゴールドフィル、ローズゴールドフィル、ソリッドゴールドなどの選択肢があり、手頃な価格と持続可能性を両立しています。デイリー使いの華奢なデザインから、受け継ぎたくなる特別なピースまで揃い、どんな人にも“自分だけの一品”が見つかるラインナップです。

5. SOKO(ソコ)
Best For|ケニアの職人が手がけるアートフルなジュエリー
Ethics & Sustainability|B Corp認証、公正取引、アップサイクル素材、テクノロジーで職人を支援
Product Range|イヤリング、リング、ブレスレット、アンクレット、ネックレス
Price Range|¥8,700(スタッキングリング)〜 ¥60,630(チェーンネックレス)
SOKOは、ケニアの職人たちと協働し、グローバルにアクセスできるテクノロジーを使って収入・機会を拡大するフェアトレードブランド。SOKOの職人は平均の5倍の収入を得ているともいわれ、社会的インパクトの高い取り組みが魅力です。建築や部族文化から着想を得たデザインは、ミニマルでありながら力強さを感じる唯一無二の美しさ。唯一無二の存在感を求める人におすすめです。
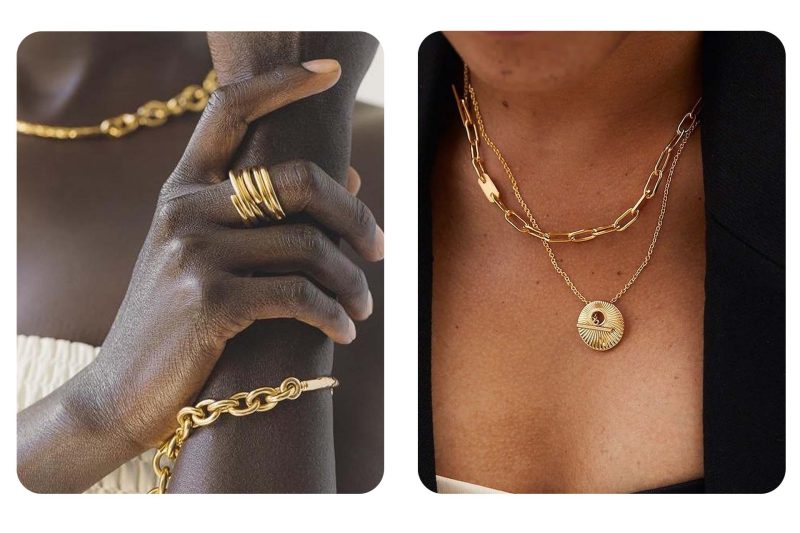
6. Local Eclectic(ローカルエクレクティック)
https://www.localeclectic.com/
Best For|世界中のインディペンデントデザイナーによる一点ものジュエリー
Ethics & Sustainability|スモールビジネス支援、94%が女性創業、リサイクル素材
Product Range|リング、チャーム、ネックレス、イヤリング、ブレスレット、アンクレット、セットジュエリー
Price Range|¥5,500(アンクレット)〜 ¥94,300(ヴィンテージダイヤリング)
Local Eclecticは、女性創業が94%を占める新進デザイナーの作品を集めたユニークなジュエリーハウス。2013年にAlexis Nido-Russoが立ち上げ、今では「他にない一点もの」を探す人に愛される存在に。小規模チームが丁寧に制作・撮影・発送まで行うスタイルで、ハンドクラフトの魅力を最大限に伝えています。ファインジュエリーからデイリーなアイテムまで、ここでしか出会えない逸品が揃います。

まとめ
エシカルジュエリーを選ぶことは、ただ美しいアクセサリーを身につけるだけではありません。それは、環境への配慮や公正な労働への支援、そして職人たちの技術と文化を未来へつなぐ“意思ある選択”です。
今回紹介した6つのブランドは、それぞれ異なるストーリーや哲学を持ちながらも、共通し「より良い世界をつくるジュエリー」であることを大切にしています。
自分のために、大切な人のために、そして地球のために。あなたが次に選ぶひとつのジュエリーが、サステナブルな未来への小さな一歩になりますように。
毎日使える「前向きなモーニング・アファメーション」20選

セルフケアの波に寄り添うということ
セルフケアの波は、私の人生の中で満ちたり引いたりを繰り返してきました。
そして、特に長い“引き潮”(というより厳しい干ばつ)の時期に、私は毎朝こうつぶやいていました。
「私は希望を持っている。私の傷は癒えていく。私は幸せだ。」
心が壊れたように感じていたとき、私はもう一度心を開くことで、かけらを拾い集めるように自分らしさを取り戻しました。 癒しの中に、希望を見つけました。
“ポジティブ・アファメーションは、日常に小さな励ましを取り入れたい人に長く親しまれている、手軽で自由に使える習慣です。”
そして“幸せ”。それは正直、ちょっと願望を込めた言葉だったかもしれません。
それでも唱えるたびに、心の中を探して「いま幸せだと思える何か」を見つけようとしました。
完璧じゃない日でも、小さなよろこびが必ずどこかに隠れていると気づかせてくれる言葉でした。
ポジティブ・アファメーションは、毎日にほんの少し励ましがほしい人にとって、長く愛されてきた習慣です。そして嬉しいことにお金もかからず、自分に合うように自由に使える!
鏡に貼る付箋に書いてもいいし、スマホのメモに保存しておいて落ち込んだときに見返してもいい。 お気に入りを覚えておいて、不安な瞬間にそっと唱えるだけでもかまいません。
あなたがもし今、うつ状態を乗り越えようとしているのなら(できれば専門家のサポートを得ながら)、 あるいはもう少しだけ自尊心を育てたいと思っているのなら、このリストの中からあなたの心に響く言葉が見つかりますように。
今日から使えるアファメーション集
- 助けを求めることは、自分を大切にし、自分をよく知ろうとする気持ちのあらわれです。
- 考えを変えることは、迷いや弱さではなく、自分をよりよくしていこうとするしなやかな強さです。
- 私の選んだことは、これまでの経験のすべてに支えられています。
- 私は自分を励ますように、周りの人にもあたたかい声をかけていけます。
- 私がどんな人なのか——その答えをいちばんよく知っているのは、やっぱり私自身です。
- 私は、欲しいものや必要なものを穏やかに求めていい。
- 私は、心地よさを感じてもいい。
- 私は、がんばる時間と、息をゆるめる時間を、自分なりのバランスで育てていけます。
- 私は今のままでも十分に満たされていて、周りの人はその私を支えてくれる存在です。
- 私は、満たされる感覚に向かって、心が少しずつ軽くなっています。
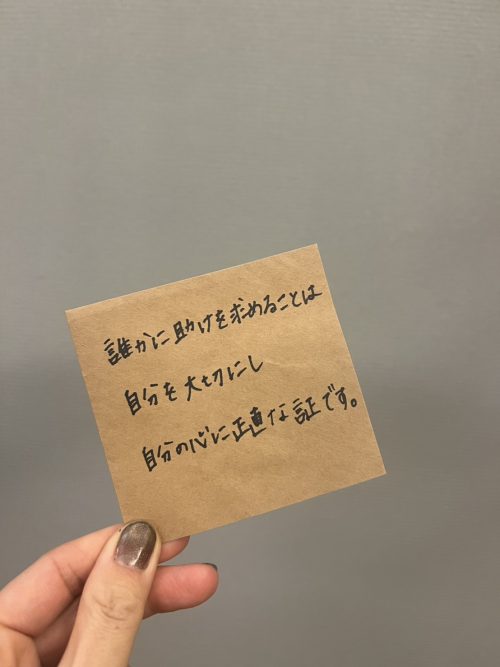
- 私は、自分にとって本当に必要なことに、ゆっくりと取り組んでいます。
- 私はよい方向へと進んでいて、少しずつ、でも確かによくなっています。
- 私は自分のペースで成長しています。
- 私は、私を愛してくれる人たちにやさしく包まれています。
- 私は自分の気持ちを大切に扱い、幸せでいることを選びます。
- 私は、世界からのささやかなメッセージに心を開いています。
- 私は愛される価値のある存在であり、そのままで尊いです。
- 私は、状況に振り回されるだけの存在ではありません。
- 私は癒しを受け取るために、そっと心をひらいています。
- 私は今日という新しい一日を、明るい気持ちで迎えています。
結論:言葉は、心を少しずつ癒す“灯り”になる
セルフケアの波は、人生のなかで満ち引きし続けます。ときには干ばつのように心が枯れてしまう時期もあるけれど、言葉をそっと自分に向けることで、希望や癒し、そして小さな幸せをもう一度見つけることができます。ポジティブ・アファメーションは、そんな“心の再生”を支えてくれるシンプルで優しいツール。完璧じゃない日でも、言葉の力があなたをそっと前へと導いてくれますように。このリストの中から、あなたの心を少しだけ軽くするフレーズが見つかりますように。
【女性と断続的断食】本当に効果ある?女性の体に起こる変化と注意点を専門家が解説

「朝食を抜くだけで代謝が整う」「体重が落ちやすくなる」——
断続的断食(インターミットファスティング)はここ数年、健康法として大きな注目を集めています。
しかし、女性の体はストレスや血糖値の変化、摂食リズムにとても敏感。そのため、男性の研究結果をそのまま女性に当てはめると、むしろ逆効果になるケースも少なくありません。
今回は、ホルモンバランス・PCOS(多嚢胞性卵巣症候群)・持続可能な栄養学を専門とするホリスティック栄養コーチ、Caroline Lalier(キャロライン・ラリアー)が語ります。
女性が断食を始める前に知っておきたい、大切なポイントをまとめました。
おすすめ記事:代謝の健康状態とは?医師が解説
【断食=痩せる】は誤解。女性の体は「食事のリズム」を重要視する
断続的断食は「代謝が上がる」「痩せやすくなる」と語られることが多いもの。ですがキャロラインは、最初にこの誤解を正します。
「女性にとって断続的断食は、必ずしも効果的な減量方法ではありません」
食事を長く抜くことで:
- ストレスホルモンが上がる
- 血糖値が乱れやすくなる
- 体が“省エネモード”に入り、逆に痩せづらくなる
といった反応が起きやすくなります。
体が“飢餓状態かもしれない”と判断すると、脂肪燃焼より生存を優先するモードに切り替わるため、代謝はむしろ低下しやすくなります。

なぜ男性と同じ結果が出ない?女性特有のホルモンとエネルギー需要
断続的断食に関する研究は、男性を対象にしたものが多く、女性にはそのまま適用できません。
キャロライン曰く:
「女性の体は、血糖値とエネルギーの変動にとても敏感です」
女性のホルモンバランスは、一定のエネルギー供給に強く依存しています。
断食などで食事タイミングが不安定になると、
- エストロゲン
- プロゲステロン
- コルチゾール(ストレスホルモン)
などのバランスが乱れ、気分や月経サイクルにも影響が出やすくなります。
ライフステージによっては断食が逆効果。特に妊娠可能年齢の女性は注意
体に負担の大きい断食は、特に妊娠可能年齢の女性にはおすすめできません。
キャロラインはこう断言します。
「生理のある年代は、規則的な食事(タンパク質・良質な脂質・複合炭水化物)が必須です」
排卵や月経リズム、ホルモンシグナルは、食事のリズムに密接に依存しているため、長時間の空腹はそのバランスを崩しやすくなります。

女性に合う“やさしい断食”の考え方:目的は「制限」ではなく「整える」
とはいえ、断食のすべてが悪いわけではありません。
キャロラインは、女性向けの緩やかなアプローチとして:
- 寝る3〜4時間前に食事を終える
- 食間を適度にあけて消化の負担を減らす
- 1日の食事リズムを整えることを優先する
など、「体が心地よく感じられる範囲」で行うことを推奨。
意図は“制限”ではなく、“消化や睡眠の質を整える”こと。
厳しい断食スケジュールより、栄養価の高い食事をバランスよく摂る方がはるかに体に良いと強調しています。
あなたの体が「栄養不足」を訴えているサイン
女性は“お腹が空いた”と感じるより先に、別のサインで不調が出ることが多いもの。
キャロラインはこう注意を促します:
「疲れやすさ、頭痛、イライラ、抜け毛、肌荒れ、体重の停滞は、栄養不足のサインかもしれません」
特に断食と過度な運動、ストレスが重なると、必要なエネルギーが不足し、体の機能に影響が出やすくなります。
あなたの体はあなたの味方。だからこそ、無理をしなくていい
断食は、誰かには合うかもしれない。でも、あなたの体にとってベストかどうかは、あなたの体だけが知っています。
私たち女性の体は、本当に正直です。食事が足りないと、疲れやすくなったり、気分が落ちたり、肌や髪にサインが出てきたり…。それは「もっとやさしく扱ってほしい」という体からのメッセージ。
もし断食を始めてみて、なんとなく調子が悪い、気持ちが不安定、力が入らない。
そんな小さな違和感があるなら、それは“あなたのせい”ではなく、ただ“その方法が合っていないだけ”。
私たちが思っている以上に、女性の体は “安定したエネルギー” を必要としています。
規則正しい食事、やさしい食習慣、そして自分の声に耳を傾けること。それが、あなたの体が最も安心して働ける環境です。
流行の健康法よりも、
「私にとって心地いいか?」
「これで私は元気でいられるか?」
その感覚を、どうか一番大切にしてください。
あなたの体は、あなたの味方。無理をしなくても、ちゃんとあなたを守ろうとしてくれています。だからこそ、あなた自身も体を味方にするような、やさしい選択をしてあげてくださいね。
初めてのジムはこわい。でも大丈夫。セレブトレーナーが教える「ジムの緊張」をゆるめる6つのヒント

初めてジムに足を踏み入れるとき。
目の前に並ぶマシン、慣れない空気、何をしたらいいかわからない不安。
胸がぎゅっと縮むようなあの感じ——実は、とても多くの人が感じています。
“ちゃんとできるかな?”
“変に見えないかな?”
“ここにいていいのかな?”
そんな心の声を抱えたまま立ち止まりそうになるあなたへ。
コートニー・カーダシアンのトレーナーとしても知られる コーチ・ドン・ブルックス(Don-a-Matrix Training) に、はじめての一歩を軽くするヒントを聞きました。
ここでは、ジム初心者にもやさしく寄り添う「プレッシャーゼロの6つのTips」をお届けします。
おすすめ記事:ウォーキングで心も体も健康に
Tip 1:誰もあなたをジャッジしていない
ジムで最も多い不安は“見られている気がする”という感覚。
でもそれは、私たちが勝手に感じてしまう「スポットライト効果」。
コーチ・ドンは言います。
「ほとんどの人は自分のトレーニングに集中している。誰かを見ている暇なんてないよ」
“できそうな人”に見える必要はありません。その場にいるだけで、あなたはもう十分に一歩を踏み出しています。
Tip 2:Day1は“完璧”じゃなくていい
初日こそ頑張らなくちゃ——そう思い込んでしまうのは自然なこと。
でも、本当に大事なのは“来た”という事実。
「Day1は習慣をつくる日。20分歩くだけでも立派なスタート」
成果を出す日ではなく、自分を褒めてあげる日のはじまりです。
Tip 3:トレーナーに頼るのも、勇気のある選択
使い方のわからないマシン、不安なフォーム。
そんなときは数回だけでもトレーナーと動いてみるのが安心。
目的は“上達”ではなく、「この空間に慣れる」ことでOK。
あなたのペースを尊重してくれる人を選びましょう。
Tip 4:マシンの使い方がわからないのは普通です
“これ合ってる…?”
これは、誰もが通る道。
マシンが怖いのは、未知だから。
説明図を見るのも、イスの調整も、ぜんぶ自然なプロセス。
「マシンはあなたに合わせるもの。焦らず少しずつで大丈夫」
Tip 5:ぎこちなさは、成長のサイン
不器用で落ち着かない感覚は、実は“学びの証拠”。
コーチ・ドンはこう断言します。
「今は自信満々に見える人も、全員、この最初のぎこちなさを経験してきた」
誰もがここを通り抜けてきたのです。
あなたもゆっくりで大丈夫。
Tip 6:シンプルなメニューを1つだけ決めておく
「今日は何をしよう…」
その迷いが不安を大きくします。
だからこそ、スクワット10回+ウォーキング10分のような“たった2つ”でOK。
最初のひとつが決まるだけで、心が軽くなり、流れに乗りやすくなります。
ジムは“慣れる場所”。あなたはその最初の一歩を踏み出している
ジムは、初心者が入りづらい場所ではありません。
むしろ、みんなが“はじめて”を通ってきた場所。
今、緊張しながらもここに興味を持っているあなたは、すでに一歩を踏み出しています。
最初はぎこちなくて当たり前。
使い方を間違っても当たり前。
不安を感じるのも当たり前。
でも、ゆっくりと自分のペースで、
“慣れるためだけの一日” を何度でも重ねていいのです。
ジムはあなたを拒まないし、あなたのペースを奪いません。
あなたの体と心が、少しずつ強く軽くなっていく場所。
だから、こわくても大丈夫。
あなたの一歩は、ちゃんと未来につながっています。
【映画レビュー】母性とは選択の重さ~『Abortion: Stories Women Tell』を観て思うこと~
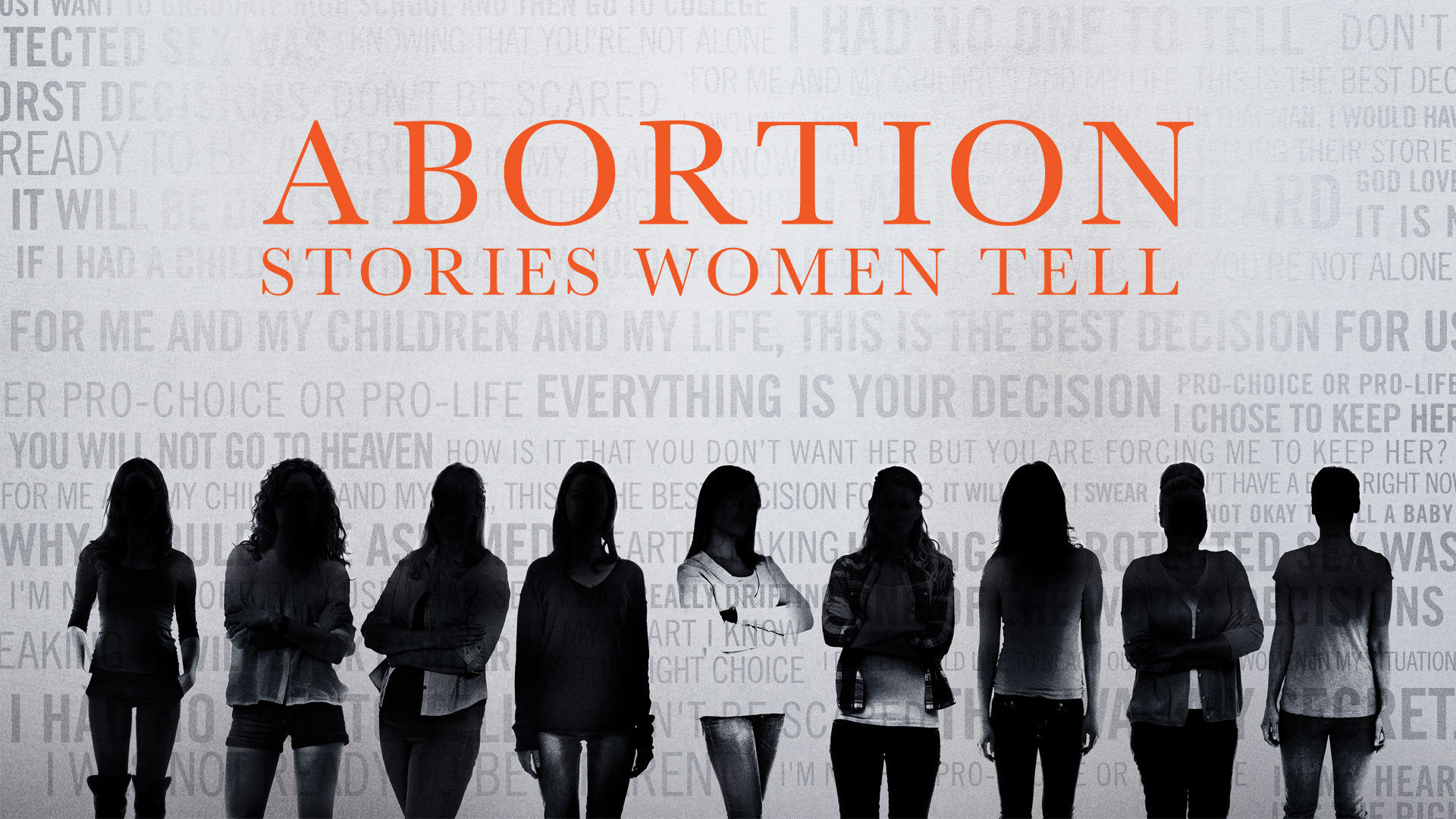
誰も軽い気持ちで来ているわけじゃない
中絶というテーマに向き合うのは、とても大きな勇気がいる。
このドキュメンタリー『Abortion: Stories Women Tell』を観て、胸の奥が何度もざわついたのは、そこに映っていたのが“大きな社会問題”ではなく、ひとりひとりの女性の「生活」と「感情」だったからだ。
彼女たちは皆、自分の人生のどこかで立ち止まり、深く息を吸い込み、そして苦しい選択をしています。 誰も軽い気持ちで来ているわけではないし、正解なんてどこにも存在しない。
おすすめ記事:【映画レビュー】「Strip Down, Rise Up」| ポールダンスを通じて女性が立ち上がるとき
アメリカでは中絶が長く対立の的になり、2022年には、連邦レベルでの中絶の権利が覆され、各州が独自に中絶を禁止・制限できるようになりました。 本作の舞台であるミズーリ州では、中絶は特に強い偏見のなかに置かれています。それは2016年の時点でも同じだったという。(この記事の執筆時点では、ミズーリ州では中絶は依然合法ですが、状況は常に変わり続けています。)
“このドキュメンタリーは、中絶をめぐる政治論争ではなく、厳しい選択に向き合う女性たち一人ひとりの現実と感情を静かに映し出している。”
それでもこの映画が描くのは、賛成か反対か、という二者択一ではない。
そのどちらにも“人生の物語”が背景にあるということ。
反対を唱える女性たちでさえ、そこには悲しみや不安、あるいは過去の影のようなものがひそんでいました。映画は彼女たちを敵として描くことはしない。
ただ、「人として」そこにいる。
私自身の立場をあえて言うなら、私は女性が自分の身体について選ぶ権利を支持している。
しかし「選択を尊重する」という言葉が、反対派の人たちからは、あまりにも軽く聞こえてしまうことも理解しています。まるでマクドナルドのメニューを選ぶかのようだ、と感じてしまう人もいるでしょう。
そして、この映画に出てくる女性たちは、その「軽さ」がまったく当てはまらない現実を教えてくれる。 声は震え、涙をこらえ、手のひらには不安がにじむ。
背負っているものは、悲しみや責任、そして、どうしようもない“現実”。
これを軽々しく語れる人なんて、きっと一人もいない。

写真提供:HBO
女性は、あまりにも多くを背負っている。
「女性らしさ」という名で社会から押しつけられた箱の中には、昔から変わらない期待や役割が詰まっています。
かつてのように親族たちの支えで家庭が成り立つ時代は終わり、いまは多くの女性が自分と子どもを同時に支える必要があります。疲弊と不安が日常に潜むなか、家族の拡大や母性を疑問視する女性たちを責められるでしょうか。限界の中で生きる姿は、とても責められるものではない。
中絶の理由にはさまざまあるけど、多くは「経済的理由」「パートナーとの問題」「健康上の理由」に集約されている。
しかしその背景にあるのは、数えきれないほどの“人としての物語”。裁くのではなく、理解しようとする姿勢が必要ではないでしょうか。
この作品は、どんな決断の背後にも「その状況で最善を尽くそうとする女性」がいることを思い出させてくれる。そして、静かに、やわらかく見守ることこそが、私たちにできる力強い支えのひとつなのだと感じました。
子どもを育てるという現実の重さ
アメリカで子どもを18歳まで育てるには、およそ37万5000ドル(約5,500万円)かかると言われている。 数字だけでは伝わらないが、子育てとは想像以上に重い現実。
映画で最初に登場するエイミーは、30歳。8歳と9歳の子どもを育てながら、週に70〜90時間働いている。これ以上の子どもを育てる余裕はないんです。
時間も、お金も、気力も。
“生活の限界の中で中絶という苦しい選択を迫られるエイミーの葛藤と、女性だけが不当に責められ恥を負わされる社会の偏見を鋭く映し出している。”
彼女の顔には、長年の疲れが刻まれていた。車を運転し、診察室で静かに座る姿には、言葉にできない葛藤が漂う。
それでもエイミーはカメラに向かって、こう言いました。
「なぜ私たちは恥じなきゃいけないの?私は女性として生まれたのに。」
カメラが外の抗議者たちのプラカードを映すと、裸の女性を描いた“侮辱的な”看板が目に入ります。それは、中絶を選ぶ女性はふしだらだという古い偏見を象徴していました。
エイミーは言います。「女性にも欲求や人生がある。でも何かがうまくいかなくなった時、責められるのはいつも私たち。」
本来は二人の行為でできた命なのに、なぜ責任と恥の大半だけが女性に押しつけられるのでしょうか。

写真提供:HBO
暴力、裏切り、そして“選べない選択”
別の女性モニークは、暴力的な夫との生活の中で妊娠が発覚しました。 殴られ、蹴られ、頭蓋骨を割られた過去。その環境で子どもを育てるという選択肢は、彼女にはなかった。
中絶の処置中、優しく手を差し伸べた男性看護師の結婚指輪を見て、「こういう夫もいるんだ」と思ったという。その対比が、胸に痛い。彼女の夫は、中絶から一週間後には「もう忘れろ」と言っただけでした。
また別の女性メルセデスは、恋人が既婚者であることを妊娠後に知った。妊娠したと思った矢先、相手の男性が既婚者で、子どもも責任も負う気がないことを知ります。
彼女はすでに1人娘を育てていて、生活は限界。でもミズーリ州では中絶を受ける前に72時間の待機期間が課されます。3日間の無給休暇を取る余裕はなく、彼女は州外へ向かうしかなかった。
距離を移動して中絶を受ける女性はアメリカでは珍しくありません。
医療への遅れや制限は、命の危険にもつながることがあるのです。
赤ちゃんが生きられないとわかったとき
妊娠中期で、赤ちゃんに致命的な異常が見つかることも。サラは妊娠12週の検査で、赤ちゃんの頭蓋骨が形成されておらず、四肢にも異常がある「羊膜索症候群」であることを知りました。
“致命的な胎児異常によって母体の命まで危険にさらされる状況でも中絶が禁じられる州があるという現実を示し、中絶が“選択”ではなく時に“生存のための医療”であることを強く訴えている。”
子宮内で赤ちゃんが亡くなった場合、母体にも命の危険が及びます。迅速に処置をしなければ、母親が亡くなることもあります。
それほど深刻な状況でも、中絶が禁じられている州は少なくない。
「中絶は選択ではなく、生存のための医療行為」である現実を、この映画は突きつけます。
静かに支え続ける人たち
映画には、診療所の医師や看護師、スタッフが登場する。彼女たちもまた、脅迫や孤立の中で過ごしています。 それでも毎日現場に立ち、傷ついた女性たちの不安を受け止め続ける。
その優しさは、声に出さなくても伝わってくる。
 写真提供:HBO
写真提供:HBO
宗教と罪悪感のあいだで
ミズーリ州を含むアメリカの一部地域では、キリスト教と中絶の議論が強く結びついている。
神を裏切った、と自己嫌悪になる女性もいれば、神の助けを信じて前を向こうとする女性もいる。
宗教に馴染みがない私にとって、キリスト教内でもこれほど多様な解釈や感情があることは興味深いものでした。ある人は「神は中絶を憎む」と叫び、別の人は涙を流しながら「神は慈悲深い」と語る。
反中絶団体のリーダーであるキャシーは、信仰のもとで活動を続ける女性。彼女は中絶禁止法の成立を祝うイベントを準備し、神への感謝を口にします。一見、反対派は冷淡に見えるかもしれないけど、キャシーの表情からは悪意は感じられない。ただ、信じるものに真剣な人として映っていた。
“中絶をめぐるキリスト教的価値観がアメリカでいかに複雑で多様かを示し、信仰ゆえに反対運動を続ける人々もまた、それぞれの真剣な思いや解釈の中で揺れている”
そして彼女自身、「自分は中絶されかけた子だった」と語りました。両親が最終的に中絶を選ばなかったことで、自分は生を得た——その事実が、彼女にとって「命の尊さ」を形作っていると語ります。話す途中でふと視線をそらすその姿には、「もしかしたら私は存在しなかったかもしれない」という淡い悲しみが滲んでいるようだった。
その事実は、彼女の世界の見え方を決定づけている。
人の立場や信念の根っこには、必ず“理由”がある。
痛みや恐怖や希望が、それぞれの方向に人を動かす。
違いの中にあるもの
私たちは、きっと永遠に中絶について完全に意見を一致させることはできない。
けれど、その背景にはほとんどの場合、「恐れ」や「希望」や「経験」があります。
学生団体「Students for Life」で活動する大学生リーガンもそのひとり。討論では落ち着きを保ちながらも、自分の信念をしっかりと語ります。
映画では団体の主張が詳しく説明されていないけど、彼女の言葉や姿勢からは、敵意ではなく「信じているものを伝えたい」という誠実さが感じられました。

写真提供:HBO
意見の対立は、人間社会において避けられないもの。
大切なのは「対立そのもの」ではなく、「対立しているときにどうふるまうか」。
“意見の対立は、人間社会において避けられないもの。大切なのは「対立そのもの」ではなく、「対立しているときにどうふるまうか」。”
しかし診療所の外で抗議する人たちは、まるで女性の心の傷に塩を塗り込むようなやり方で叫び、責め立てる。
ガードマンのシシーは言う。
「人のことばっか気にして、家のことはどうでもいいだろ。」
彼らは何を求めてそこに立ち続けるのだろう?リーガンでさえ、「診療所前での抗議行動は効果がない」と認めています。
進展もないまま炎天下や寒空の下で叫び続けるその原動力は何なのか?
シシーの言うように「ネガティブなことを喜ぶ」のだとしたら、それは本当に“神の意志”なのでしょうか。
その疑問はずっと残ったまま。
女性として、この映画を見て
この作品が心を揺さぶったのは、ここに映る苦しみや葛藤が、女性として私自身も感じてきた現実と重なるからだと思う。
私たちは、望んでもいないのに、あまりにも多くの責任を背負わされています。
子どもか、生活か。
母性か、安定か。
多くの女性は、両方を手に入れる余裕なんて持たされていない。
誰が「子どもを産みたくなかった」などと言えるでしょうか。
彼女たちの中で育っていた命を、何とも思わないはずがない。
そこには深い悲しみがある。
もし状況が違えば、彼女たちの多くは喜んで母になるでしょう。
けれど、子どもであるはずの10代の少女たちが妊娠したとき、彼女たちは突然、“人生を左右する岐路”に立たされる。
子どもを産むか、教育を取るか。
子どもを産むか、身の安全を守るか。
歯列矯正の器具をつけた幼い少女が、母親に言えない理由を小さな声で語る姿。
すでに一児の母である17歳の少女が、また妊娠し、「二人目を育てられるだろうか」と震える声で相談する様子。
胸が痛くない人なんているだろうか。
女性は「母であり、妻であり、恋人であり、社会人であれ」と求められます。
けれど私たちは、ひとりの人間。
すべてを同時に背負うことはできない。
だからこそ、時には「息をつく場所」が必要なのです。
選択するための空間。
存在を許される空間。
自分を取り戻すための空間。
だから、時には少しだけ“呼吸できる場所”が必要なのだと思う。
自分で選ぶための場所。
自分として存在していい場所。
シシーの言葉が、不思議と心に残る。
「すべては自分の選択。神様はみんなを愛してる。」
40代からの不調は「冷え」がサイン。香港の隠れ家サロンで心身を整える「よもぎ蒸し」の力【よもぎ蒸しサロン経営Yuriさんインタビュー】

40代を迎え、以前には感じなかった体の変化を感じることがありませんか?手足の冷えが取れない、夜ぐっすり眠れない、イライラが止まらない……。それはわがままな悩みではなく、変わりゆく体からの大切なサインです。
今回は、香港でよもぎ蒸しサロンを経営するYuriさんに、私たち女性にとってよもぎ蒸しがなぜ良いのか、など大人の女性の体を立て直すヒントを伺いました。
40代の女性を襲う「冷え」と「不調」の正体
ーー 40代に入ると、急に冷えや体の不調を感じる女性が増えます。こうした悩みに「よもぎ蒸し」はなぜ良いのでしょうか?
40代は更年期に向けてホルモンバランスが大きく揺らぎ始める時期です。よもぎ蒸しで体を芯から温めることには、非常に多くのメリットが期待できます。
まず、体が温まることで血液循環がスムーズになります。これによって冷えの解消に繋がるだけでなく、免疫力の向上も期待できますし、何より「よく眠れるようになった」というお声を多くいただきます。また、高いデトックス作用によってお肌の状態が整うという嬉しい変化も期待できますね。
特に40代の方が悩まれる更年期の諸症状の緩和や、生理痛、PMS(月経前症候群)、子宮系のトラブルといった、女性特有のデリケートなお悩みに対して、そっと和らげてくれるような働きかけが期待できるのが、よもぎ蒸しの最大の魅力です。
驚愕の「粘膜吸収」:デリケートゾーンは二の腕の42倍!?
―― 以前、Yuriさんのサロンで「デリケートゾーンの吸収率は二の腕の42倍」というお話をっ聞いて驚きました。
そうなんです。少し専門的なお話になりますが、私たちの皮膚には「経皮吸収」という仕組みがあります。二の腕の吸収率を「1」とした場合、頬や顎は13倍、背中は17倍。そして、デリケートゾーン(膣粘膜)は42倍という、体の中で最も高い数値を示しているんです。
つまり、ここは「良いものも、悪いものも、最も吸収しやすい場所」ということ。だからこそ、普段使う石鹸なども、擦らずに優しい泡で洗う「フェミニンウォッシュ」のような専用のケアが大切になってきます。
よもぎ蒸しでは、この吸収率の高い粘膜にダイレクトにハーブのスチームを当てます。これによって粘膜が活性化され、普段の排泄だけでは出し切れなかった毒素や、古い細胞・角質などの老廃物の排出を促す効果が期待できるのです。
お風呂とは違う「芯」へのアプローチと「自律神経」の調整
―― 体を温めるならお風呂でも良さそうですが、よもぎ蒸しならではの「整う」感覚の正体は何でしょうか。
お風呂との大きな違いは「女性特有の疾患」への特化と「自律神経」へのアプローチです。
現代女性はストレスが多く、常に「交感神経(活動の神経)」が優位になりがちです。これが自律神経の乱れ、つまり不眠や疲労感の原因になります。よもぎ蒸しで温まると血管が広がり、血流が改善されます。すると、リラックスを司る「副交感神経」が刺激され、心身が解き放たれていくんです。
また、筋肉の緊張がほぐれて酸素が全身に行き渡ることで、自律神経失調症特有の症状も和らぐことが期待できます。特によもぎは「子宮に効く」と言い伝えられてきた歴史があり、産後の子宮ケアや不妊、更年期のお悩みにも効果が期待できます。
―― よもぎ蒸しの後に、普段の汗とは違う「サラサラ感」を感じるのも不思議です。
そうですね。運動でかく汗は水分や塩分、アンモニアなどを含む「ベタつく汗」になりやすいのですが、よもぎ蒸しの汗は体幹から芯まで温まることで出る、老廃物を含んだ「質の良い汗」なんです。水銀やヒ素などの有害重金属や、食品添加物の残留物などを排出するデトックス効果が期待できるため、終わった後は驚くほどスッキリしますよ。
効果を実感するための「理想のペース」とは?
―― 忙しい毎日の中で、どのくらいの頻度で通うのが効果がありますか。
初めてよもぎ蒸しを体験される方には、最初の2〜3回はあまり日を空けず来ていただくのがベストだとお伝えしています。理想は「1週間のうちに3回ほど」続けて座っていただくこと。まずは集中して体を温め、巡りのベースを作ってしまうんです。
その後は、週に1回のペースで継続されるのが理想的ですね。ただし、生理中はお座りいただくことができません。生理の期間は避けていただき、ご自身のサイクルに合わせて週1回を習慣にされると、変化が期待できるかと思います。
―― 生理中は完全にお休みしなければならないのでしょうか?
生理中で体調が優れない時は無理をしないのが一番ですが、当サロンでは「足蒸し」というメニューもご用意しています。膣粘膜ではなく、ふくらはぎに蒸気を当てる方法です。粘膜吸収ほどの効率はありませんが、足を温めることでむくみが取れたり、香りでリラックスできたりといった効果が期待できますよ。

本場・韓国の最高品質と日本のホスピタリティ
―― Yuriさんのサロンは、使っている道具へのこだわりがすごいですよね。
ありがとうございます。当サロンで使用している椅子や壺は、本場・韓国の陶芸家が焼き上げた最高級品です。良質な天然黄土を使っているので、熱を加えることで良質な遠赤外線が放出され、お体をより深部から温めることができます。
薬剤も、デトックス・子宮ケア・美肌に特化した配合の無農薬ハーブのみを厳選しています。香りの癒やしも重要で、嗅覚から脳の感情を司る部分へは、わずか0.2秒以下で信号が届きます。良い香りを嗅いで「あぁ、幸せ」と感じる瞬間、すでに体はリラックスモードに切り替わっているんですよ。
―― 香港の大都会にありながら、一歩サロンに入ると「ここは日本?」と感じるような別世界ですね。
外はガヤガヤしていますが(笑)、サロン内では「日本ならではのおもてなし」を大切にしています。海外生活は想像以上にストレスが溜まるものです。言葉の壁を気にせず、日本人である私に体の悩みを打ち明け、心を緩めていただける場所でありたいですね。お客様からは「ここは東京ですか?」なんて言っていただけることもありますね。
Yuriさんが実践する「基本」のセルフケア
―― 最後に、日々忙しく過ごす女性たちへ、Yuriさんが大切にしている習慣を教えてください。
意識的にこういったことをケアしていますね。
1. 朝の白湯: 年中通して、まずは火にかけた白湯を飲む。眠っていた内臓が動き出すのが分かります。
2. 発酵食品と大豆: 香港は外食も多いですが、家では野菜たっぷりの豚汁や納豆、豆乳を欠かしません。イソフラボンや麹の力は、女性の味方です。
3. 睡眠の質: ネットフリックスを夜更かしして見すぎない(笑)。睡眠不足はすべてのパフォーマンスを下げ、メンタルにも影響します。
結局、子供の頃に親から言われていた「よく食べ、よく寝て、体を温める」という基本が、40代以降の体には何よりの薬になるんですよね。年齢を重ねることは、こうした基本に立ち返ることなのかもしれませんね。

Yuriさんプロフィール
香港の湾仔にてよもぎ蒸しサロン経営。ロンドンでの生活を経て2011年に香港に移住。2012年にイメージコンサルティングサロンを始め、2022年からはよもぎ蒸しも導入。外見と内面の両面からキレイになるサロンを運営。
https://www.instagram.com/yomogimushi.hk
自分へのご褒美は「頑張ったから」じゃなくて「ここまで来たから」でいい

大人になってから、「自分を褒める」という行為が、やたらと難しくなった気がします。
学生の頃から、「いやいや上には上がいるし…」と思いがちなタイプではあったんですけど、それでもまだ、勉強にしろ部活にしろ、自分なりに頑張ったことは「頑張った」と認められていたように思います。
でも社会人になってからというもの、「上には上がいる」という比較思考ばかりが強まって、反比例するように自分を認める気持ちはどんどん小さくなっていきました。
例えば、仕事では何か成し遂げたという分かりやすい実績があるわけでもないし、成果や出世を掴み取ろうとがむしゃらに働いてるわけでもない。
これというスペシャリスト的な強みがあるわけでもない。
そんな私って別に大したことないよな、頑張ってる部類の人間ではないよな、みたいな。
おすすめ記事:アートへの敷居が下がったのは”都会”のおかげ
そう思うにつれ、自分を褒めるとか、ご褒美をあげるという行為にどこか後ろめたさがついて回るようになって。
だんだん自分のなかで、メリハリがつかなくなっている感覚があるんです。
シンプルだった学生時代、頑張りの輪郭が一気にぼやけた社会人
何が変わったのか、よくよく考えてみると、学生の頃って自分の頑張りが測りやすかったんだなと思ったんです。
学生の頃は「頑張り」と「ご褒美」が、とても分かりやすくつながってた。
例えば、勉強にしても部活にしても、それぞれ試験や大会という分かりやすい評価軸がありましたよね。
できた、できてないの指標が数値で出てくるって(その是非は一旦置いておいて)、よく考えたら超楽だったんですよ。
しかも試験も大会も定期的なもので、だいたい実施スケジュールが決まっている。
よほどのことがない限り、予定変更ってないですよね。
だからこそ、こちらも計画的に準備ができたし、「今はアクセルを踏む時期」「ちょっと力を抜いていい時期」というリズムが作りやすかった。
しかも、始まりと終わりが明確だから、結果がどうであれ「とりあえずここまでやった」という気持ちの区切りもつけやすくなる。
だから、頑張った自分を労ったり、ちょっとしたご褒美をあげたりすることにも、あまり迷いがなかった気がします。
ところが、社会人になると、その構造が一気に崩れます。
たしかにルーティーンワークはあるし、企画やプロジェクトはスケジュールを引いて計画的に進めることも多いです。
でもそれ以上に、“想定外”が多い。
いくらこっちが計画通りに動いていても、急な方針変更や横やりが当たり前のように入ってくる。
ここまでに終わらせると決めていたことが、いきなり前倒して完成させてくれとか、延期してでも作りこんでくれとか言われたり。
ちゃぶ台返しでゼロから作り直しになったり、はたまたやっぱり中止と言われることだってあります。(ベンチャー勤めの私にとっては、もはやそれが日常ですが)
それにアクセル踏み込んで熱心に取り組んだからといって、それがそのまま評価される保証もない。
むしろ「そこまでやらなくてもよかったのに」と言われることさえあります。
かたや、その場の思いつきで口に出したアイデアが評価される場合もあるし、難なくひょいひょいとやったことに感動されることもある。

学生の頃のように、頑張ったことやその気持ちが、評価や達成感ときれいにつながらない。
そりゃあ社会人は労働力や知恵を提供してお金をもらう身になっているのだから、学生までとは話が変わってくるのは頭では分かってる。
がむしゃらに頑張ればいいというわけではなく、省エネで上手く作れる人が正義なんだという感覚も理解できる。
でもそうなると「何を以て自分を労えばいいのか」が分からなくなっちゃったんですよね。
だって、別にこっちだって頑張っていないわけではないじゃないですか。
やるべきことはちゃんとやっているし、しっかり働いたぶん、疲れだってじわじわ溜まっている。
それでも、その疲れを「功績」としては認めてあげられないんですよね。
こんなの、頑張ったうちに入らない、もっとしゃかりきに動いている人、成果を挙げている人はいくらでもいる。
この「そんなに頑張ってない」という感覚がある以上、自分にご褒美をあげることに、どこか後ろめたさや罪悪感を覚えてしまうのは私だけでしょうか?
結果、疲れているのにちゃんと休めなくて、切り替えたいのに切り替えられない。
アクセルもブレーキも中途半端なまま、だらだら走り続けているような感覚に陥ってしまいます。
「ご褒美」という枠組み自体が窮屈なのかも
じゃあ、もっと頑張ればいいのかというと、そう単純でもありません。
要領よく形にできる人が評価される、「がむしゃらに頑張ること」が必ずしも最適解ではないことを、頭では理解してしまっている状態で、全力で頑張るスイッチを入れるのは、正直至難の業です。
頑張ったご褒美をあげて、自分をちゃんと認めてあげたい。
でももう、そもそも頑張れない。
うわー八方塞がりじゃん。
……と思ってたんですけど、これを書いていてふと気づいたことがあります。
もしかして「頑張ったからご褒美」という構図自体が苦しいのかもしれない、と。
これまでは、頑張ったという「過程」がないとご褒美をあげるべきではないと、無意識に方程式をつくっていました。
けど、必ずしも「頑張り」が評価に直結しない環境にいるのに、それをご褒美の基準にするのってそもそも破綻してない?と思ったんです。
例えば、人生の教訓的な話でもよく出てくるじゃないですか。
自分が描いた結果が出せなくても、そこにたどり着くまでの軌跡は糧になってるんだから、その過程が大事なんだよ的な話。
これはこれで確かに正しいと思います。
だけど、何でもかんでもこれを当てはめるから苦しいのでは?
別に「結果」だけを見て「よし」とすることがあってもいいのでは?と思ったんです。
「ひたすらデータ入力しかしてないけど、プロジェクトは成功したらしい記念」
「途中でちゃぶ台返しされてこっちもヤケクソになったけど、無事、商品はリリースできた記念」
「なんか分からんけど、ぽっと出のアイデアが採用された記念」みたいな。
別に頑張ってはないけど、とりあえず終わりはした!なんか上手くいった!
だからお祝いにちょっといいもの食べたり、だらだらドラマを一気見したり、ゲームに没頭してみる。
「頑張ったかどうか」という過程はあえてジャッジせず、「ここまで来れた」という結果だけにフォーカスする。
これならしっくりくるし、自分のなかでも区切りがつけやすくなるような気がしたんです。

「セーブポイント」は自分でつくる
RPGゲームでも、ちょっと強いボスを倒すと、そこまでの記録を保存して体力を回復するセーブポイントが必ずありますよね。
自分の人生にもそういうポイントを作って、小さなお祝いと休息を取る。
まだ頑張れてないから、ではなく、ここまで来たから、でいい。
それなら気後れや罪悪感もなく、自然に受け入れられるような気がしたので、これからは素直に自分を労う時間を少しずつ増やせそうです。
アクセルとブレーキのメリハリができれば、次に進むためのエネルギーにもなって、なんだかんだ頑張れる人にもなれるのでは……?!と、淡い期待も抱きながら。
セラピストが教える「ガスライターとの性行為」に潜むサインと影響

ガスライティングとは?本来の意味をまず知ろう
最近よく耳にする「ガスライティング」という言葉。
ただし日常的に使われるほど、本来の意味がぼやけてしまうこともあります。
ガスライティングとは、相手の記憶・感情・現実認識を疑わせることで支配しようとする“心理的虐待”のひとつ。
特徴としては:
- 事実の否定や嘘
- 相手の記憶・感情の軽視
- 現実の書き換え
- 相手の不安や弱さを利用した操作
被害者は混乱し、孤立させられ、自己否定が強まることが多く、長期的にメンタルヘルスへ影響します。
そしてあまり語られませんが、性行為や親密な場面でもガスライティングは起こり得ます。
おすすめ記事:夫婦喧嘩でやってはいけないこととは?子供への悪影響も解説
ガスライターとの性行為:どんなサインがある?
「記憶の書き換え」や「感情の否定」によるコントロール
セラピストのフランク氏は次のように説明します。
「ガスライティングは、相手の現実感覚そのものを揺さぶる行為。自分の感覚よりも相手の言葉を信じさせ、支配するためのパターンです」
性や親密な場面では特に以下のように現れます:
- 「それ、君が望んだんでしょ」
- 「大げさだよ」
- 「そんなこと言ってなかったよ」
- 「誤解だよ、混乱してるだけ」
目的はひとつ。 責任を逃れるために相手の境界線を曖昧にし、自分に有利な物語に書き換えること。

性の場面で起こりやすいガスライティングの特徴
ガスライティングはしばしば次の領域で起こります:
✓ 同意(Consent)
嫌がっているのに「本当は望んでたよね」と言い換える。
✓ 境界線(Boundaries)
明確に伝えた「NO」や不快感を否定し、相手を混乱させる。
✓ 欲求や反応(Desire)
相手の気持ちや身体の反応を勝手に解釈し、都合よく書き換える。
こうした行為はすべて相手の自由や主体性を奪うための行動です。
性におけるガスライティングがもたらす影響
ガスライティングはその瞬間だけでなく、長期的にあなたの性や自己認識へ影響を残します。
被害を受けた人が抱えやすい感覚:
- 「私のNOは正しいのかな?」
- 「不快に感じるのは私の問題?」
- 「相手を満足させないといけない」
- 「性は楽しむものではなく、相手に合わせるもの」
- 「もう親密なシチュエーションを避けたい」
- 罪悪感・恥・自信の低下
フランク氏はこう語ります:
「性を楽しむどころか、”管理しなければならない”ものになってしまうケースはよくあります」

性にまつわるガスライティングを受けたときの対処法
1. 自分の“直感”を信じる
ガスライターは多くを操作できますが、胸の奥で「何かおかしい」と感じる感覚までは消せません。
フランク氏のアドバイス:
「困惑・違和感・不安は“過剰反応”ではなく“サイン”。まずはその感覚を大切にして」
直感はあなたを守る大事なセンサーです。
2. 信頼できる人に話す
友人、専門家、支援団体の窓口など、“安全な相手”に自分の経験を話すことが大切です。
「誰かに話すことで、自分の現実感覚を取り戻す助けになります」(フランク氏)
3. 境界線や同意について学び直す
これからの親密な関係で自分を守るためにも、 同意(Consent)や境界線(Boundaries)について学ぶことは有効です。
過去を責めるためではなく、 これからの自分を尊重できるようになるためのステップです。
まとめ:その違和感、あなたを守る大切なサイン
ガスライティングは境界線・同意・欲求など、性の重要な部分を揺さぶり、あなたの現実感を奪います。
もし「何かがおかしい」と感じたなら、それは誤りではありません。
あなたの直感は、あなたを守ろうとしているサイン。 被害を受けたとしても、回復し、自分の感覚を取り戻すことは必ずできます。
【ボディカウントは本当に重要?】“何人と寝たか”より大切なもの──性・価値観・ダブルスタンダードを徹底解説

ボディカウントは重要なのか?いまこそ終わらせたい「人数論争」
「何人と寝たか」で人を判断する——そんな瞬間に、胸の奥がチクッと痛んだことはありませんか?
自分のことを正直に話したのに、相手の表情が変わった。
楽しかった会話が、急に気まずくなった。
「しまった、言わなきゃよかった」と後悔が押し寄せる。
“人数で価値は決まらない——あなたが歩んできた経験には、もっと深い意味がある。この記事では、その視点を取り戻していく。”
それなのに、逆に相手の過去は“武勇伝”みたいに語られる。
気づけば、性の経験にまつわる数字は、 いつだって女性にだけ重くのしかかる——そんな不公平さを感じたことはないでしょうか。
でも、本当は誰の過去も数字なんかで語れるはずがありません。
そこには、勇気や喜びや後悔や、孤独や解放や好奇心……
人それぞれの“ストーリー”が確かに存在しています。
人数で価値は決まらない。
あなたが歩んできた道のりには、もっと深い意味がある。
そのことを、この記事で一緒に取り戻していきましょう。
おすすめ記事:セックスの不満をパートナーとケンカせずに話すには?
ボディカウントが気にされる理由:科学・心理学的な背景
1. 健康リスクへの不安(STIに関する誤解)
スウォンジー大学の進化心理学者 Andrew Thomas博士によると、 性行為をした相手の数が多いほど性感染症リスクが上がるという一般的な認識があるため、 ボディカウントを気にする人が一定数いるといいます。
ただし博士はこうも指摘しています:
「性行為をした人数が少なくてもSTIに感染することはあり、人数が多い人でも安全なセックスを徹底している場合もある」
人数=リスクではないという点が重要です。
2. 浮気の可能性を読み取ろうとする心理
博士の研究によると、 性的パートナーが多い人は「カジュアルセックスへの欲求が高い」と見られやすい傾向があります。
そのため、長期的な関係を求める人は「この人は本当にまじめな関係を求めているのか?」 と不安になることがあるのだとか。
ただしこれは“傾向”に過ぎません。
誰もが当てはまるわけではありません。

3. 社会的な性道徳とダブルスタンダード
性教育の不足、SNSでの言論制限、宗教的・文化的な価値観、そしてインフルエンサーの影響もあり、「性は少ないほうが“価値がある”」という偏見が根強く残っています。
特に女性やマイノリティほど、その影響を強く受けやすいといわれています。
ボディカウントのダブルスタンダード:女性のほうが厳しくジャッジされる現実
多くの女性の声から見えてきたのは、 “男性のほうが人数に寛容と言われながら、実際は女性がより批判されやすい” という矛盾。
例:
- 男性は100人以上と寝ていても「経験豊富」
- 女性は5人で「多い」扱い
- 男性が自分より人数が多い女性に引け目を感じて攻撃的になる
- 男性側の未熟さ・不安から人数を気にするケースが多い
女性の多くは 「人数を気にする男性ほど自分に自信がない」 と感じていることがわかります。
経験が多い=悪い?実は“人数”は能力を示さない
性教育者Ruby Rareはこう断言します:
「経験が多いことがマイナスになる分野なんて他にない」
大切なのは人数ではなく…
- 自分の欲求を理解しているか
- コミュニケーションができるか
- お互いを尊重した関係が築けるか
経験が多い=浮気性
経験が少ない=誠実
といった図式は根拠がありません。

男性側の本音:低いボディカウントに不安を感じる男もいる
一部の男性は「低い人数」のほうに不安を感じると語ります。
- 経験が少ないと“後から遊びたくなるのでは?”
- 性的相性より“今後の不満”を心配する
- 過去の経験数より「良い経験かどうか」を気にする男性も多い
つまり、 男女ともに“人数”ではなく“質”を重視している人が増えている
ということです。
ボディカウントより大切なのは「快感・尊重・つながり」
性教育者のRare氏はこう言います:
「人数に執着することは、あなた自身の性の自由を狭めるだけ」
もっと集中すべきことは:
- どれだけ自分を大切にできたか
- 快感や安心を感じられたか
- 健康的な境界線を築けたか
- 相手とのコミュニケーション
- 自分らしい性のスタイル
“何人と寝たか”では、何も測れません。
まとめ:ボディカウントは重要ではない。大切なのは「あなたがどう感じてきたか」
ボディカウント——この小さな数字に、私たちはどれだけの意味を背負わせてきたのでしょうか。でも本当は、数字が教えてくれることなんてほとんどありません。
大切なのは「何人か」ではなく、 その時どう感じたのか、どんなつながりを求めていたのか、そしてこれからどう生きたいのか。
私たちひとりひとりの性の歴史には、 喜びも、迷いも、痛みも、学びも、すべてが詰まっています。それは数字では測れない、かけがえのない人生の一部です。
だからもし、誰かが“何人と寝たか”という尺度であなたを評価しようとしたら、その人こそ、あなたの物語を受け止められない相手なのだと思ってください。
これから先、あなたが大切にすべきなのは—— リスペクト・安心感・快感・誠実さ・つながり。
数字ではなく、あなたの心と身体がどう感じるか。 その感覚こそが、あなたの価値を決めるいちばん確かなものです。
【センスエイト・フォーカスとは?】カップルの親密さを取り戻すタッチセラピーの効果とやり方

センスエイト・フォーカスとは?カップルに役立つ理由
パートナーとの身体的な親密さが「遠い」「プレッシャーになる」「なんとなくぎこちない」と感じる時、多くのカップルが「何が変わったのだろう?」と不安になります。
・セックスが義務のように感じる
・気持ちが乗らない
・拒否された気がして傷つく
・パフォーマンスへの不安がある
こうした悩みは決して珍しいものではありません。
おすすめ記事:セックスレスの離婚率はどれくらい?離婚するべきか?夫が拒否するのはなぜ?
アメリカのセックスセラピストがよく用いるアプローチのひとつが、 “センスエイト・フォーカス(Sensate Focus)”と呼ばれるタッチエクササイズです。
1960年代にセックス研究者マスターズ&ジョンソンが開発したもので、 性交やオーガズムを目的とせず、 「触れる」「触れられる」ことをゆっくり丁寧に味わい直すことを通して、親密さや安心感を取り戻すセラピーです。
センスエイト・フォーカスの基本:目的と特徴
センスエイト・フォーカスは、期待や結果を手放し、 「好奇心」と「気づき」でタッチを探求する練習です。
- うまくやる必要はない
- 気持ちよくさせる義務もない
- 答えやゴールもない
ただ「今、この瞬間の感覚」を確かめながら触れ合うことで、 パートナーと心身の距離を優しく縮めていきます。
セラピストはこれを、 “身体のためのマインドフルネス”と表現することもあります。

センスエイト・フォーカスのやり方(ステップ別)
1. 非性的タッチ(Non-Sexual Touch)
まずは、胸・性器を避けた部分へのタッチから始めます。
- 肌触り
- 温度
- 圧の強さ
- リラックスしている部分/緊張している部分
触れる側は「相手を満足させる」のではなく、触れている自分の感覚を観察します。触れられる側は、ただ「感じる」ことに集中します。
身体的な安全感を取り戻す大切なステップです。
2. センシュアルタッチ(Sensual Touch)
次は、首・背中・太ももの内側など、やや官能的な“性感エリア”にもゆっくり触れていきます。
ここでもルールは同じ。
性交へ進む必要はありません。
自然に湧いてくる興奮も、湧かない感覚も、そのまま受け止めてOKです。
3. 性的タッチ(Sexual Touch)
十分な安心感が育った段階で、乳房や性器を含むタッチへ進みます。
ただしここでも、
- ゴールは「性交」ではない
- オーガズムは必須ではない
- コミュニケーションと安心感が最優先
というスタンスは変わりません。

センスエイト・フォーカスがカップルに効果的な理由
1. パフォーマンス不安を軽減
「うまくしなきゃ」「満足させなきゃ」という意識は
ストレス反応を引き起こし、逆に性反応を妨げます。
ゴールをなくすことで、 “できる/できない”の枠から自由になれるのが 最大のメリットです。
2. 距離ができた関係の“再接続”をサポート
喧嘩、すれ違い、産後、病気、浮気などで距離ができたとき、性交はハードルが高く感じられることがあります。
センスエイト・フォーカスは、安全で気軽な“やり直しの入り口”として機能します。
3. 痛みや機能の悩みに優しいアプローチ
- 膣の痛み(膣けいれん、外陰部疼痛症など)
- 勃起の悩み
- 性欲低下
こうした性の不安を抱える人にとっても、“快・安心・気づき”を積み重ねながら進む方法はとても有効です。
4. マインドフルネス効果で心のつながりが深まる
忙しさや癖で、私たちはつい無意識に何も考えずに触れてしまいます。
センスエイト・フォーカスは「今ここ」に戻る練習。
- 相手の反応
- 自分の感情
- 呼吸
- 触れたときの微細な変化
これらに気づけるようになり、より深い心のつながりが育ちます。
よくある質問(Q&A)
Q. 性の悩みがないカップルでもやる意味はある?
もちろんあります。
親密さや満足度を高めたい場合にも効果的です。
Q. 効果が出るまでどのくらい?
カップルによります。
数回で変化が出る人もいれば、じっくり時間をかける方が合う人もいます。
Q. 自分たちだけでもできる?
可能ですが、専門のセックスセラピストと進めるとより安全で効果的です。
まとめ:親密さは「完璧」ではなく「気づくこと」から始まる
センスエイト・フォーカスが教えてくれるのは、“もっと頑張ること”ではなく、“もっと感じること”。
触れる・触れられる体験をゆっくり味わい直すだけで、パートナーとのつながりは驚くほど変わります。
もしあなたやパートナーが、「距離を感じる」「プレッシャーが大きい」と悩んでいるなら、
焦る必要はありません。
気づきと安心を育てることで、 再び自然な親密さを取り戻すことは十分可能です。
性欲はなぜ変化する?その理由と今日からできる対処法

性欲はなぜ変化する?その理由と向き合い方
「最近、性欲が落ちた気がする」
「前はもっと自然に感じられていたのに、今はそうでもない」
そんな変化に戸惑ったり、不安になったりしたことはありませんか。
おすすめ記事:セックスの不満をパートナーとケンカせずに話すには?
性欲は、年齢やホルモンだけで決まるものではなく、心の状態、体調、ライフステージ、ストレス、パートナーシップなど、さまざまな要因の影響を受けながら常に揺れ動いています。
つまり、性欲の変化は「おかしなこと」ではなく、今のあなたの心と体が何かを伝えようとしているサインです。
この記事では、性欲・性的興奮・満足感の違いを整理しながら、性欲が変化する主な理由と、今日からできる実践的なケア方法をわかりやすく解説します。
変化を責めるのではなく、理解し、いたわるためのヒントとしてお読みください。
性欲・興奮・満足感の違いとは?
混同されがちなこの3つですが、実は意味が異なります。
-
性欲
セックスに対する「したい」という気持ちや関心。主に心理的要素が大きい。 -
性的興奮
刺激に対する身体の反応。血流増加や潤いなど、生理的な変化が中心。 -
性的満足感
セックスから得られる快感や満足度、オーガズムの有無、自分の性生活への捉え方。
性欲は「頭」、興奮は「体」、満足感は「体験全体」と考えると理解しやすいでしょう。
性欲や満足感が変化する主な理由
性欲の変化は、ホルモンだけが原因ではありません。
複数の要因が重なり合って起こります。
1. ホルモンと身体的要因
- 血流や神経の働き
- エストロゲンの低下
- 痛みや不快感(膣の乾燥、性交痛など)
身体に痛みがあると、脳は無意識に「ブレーキ」をかけ、性欲は自然と下がります。
2. 妊娠・産後・授乳期
妊娠中はホルモン変化や血流増加で性欲が高まる人もいれば、つわりや疲労で下がる人もいます。
出産後や授乳期はエストロゲンが大きく低下し、疲労感や気分の変化、ホルモンの影響で性欲が落ちやすくなります。

3. 更年期・プレ更年期
ホルモンの揺らぎにより、
- 膣の乾燥
- 性交時の痛み
- オーガズムの感じにくさ
などが起こりやすく、結果的に性欲の低下や回避につながることがあります。
4. 薬の影響
一部の低用量ピルや抗うつ薬などは、性欲に影響することがあります。また、うつ状態そのものが性欲低下の原因になる場合もあり、調整が重要です。
5. パートナーシップと心理的要因
- 関係性への不満
- 信頼感の低下
- 慢性的なストレス
これらは性欲や満足感と密接に関係しています。心が安全だと感じられないと、身体は反応しにくくなります。
6. ボディイメージ
自分の体をどう感じているかは、性欲に大きく影響します。妊娠・加齢・自己肯定感の低下などにより「自分は魅力的ではない」と感じると、性への関心が下がることがあります。

性的ウェルネスを支えるためにできること
生活習慣を整える
- 栄養バランスの取れた食事
- 適度な運動
- 質の良い睡眠
これらは性欲だけでなく、全体的な幸福感を高めます。
ストレスケアを習慣に
呼吸法や瞑想などで、
神経系を落ち着かせることは性欲回復の土台になります。
膣の乾燥・不快感には適切なケアを
膣の乾燥がある場合は、非ホルモン性の保湿ケアを取り入れることで、
痛みや不快感が軽減し、性へのハードルが下がることがあります。
セクシュアリティを日常に取り戻す
- セルフプレジャー
- 官能的な感覚に触れる時間
- パートナーとの「つながる時間」を意識的につくる
パートナーがいない場合でも、自分とのつながりを大切にすることは重要です。
一人で抱え込まないことが大切
性欲や性的満足感について悩むことは、とても一般的です。
医療者に相談することで、「自分だけじゃなかった」と安心し、選択肢が広がることも少なくありません。
性について話すことは、恥ずかしいことではなく、自分を大切にする行為です。
まとめ|性欲の変化は、あなたの「不調」ではない
性欲が変わることは、決して異常でも、問題でもありません。
それは、ホルモン、心の状態、体調、ライフステージ、パートナーシップなど、さまざまな要素が重なった結果として起こる自然な反応です。
大切なのは、「前と同じ状態に戻さなければ」と焦ることではなく、今の自分の体と心が何を必要としているのかに気づくこと。
十分な休息、ストレスのケア、身体の不快感への対処、そして自分のセクシュアリティを後回しにしないこと。そうした小さな積み重ねが、性欲や満足感を少しずつ育てていきます。
また、悩みを一人で抱え込む必要はありません。医療者や信頼できる人と話すことで、選択肢が広がり、気持ちが軽くなることもあります。
性欲は、あなたの価値を測るものではなく、心と体の状態をそっと教えてくれるサイン。
比べず、責めず、今の自分を尊重するところから、健やかなセクシュアルウェルネスは始まります。
【ハミングが届けるポジティブニュース】世界中でウミガメが増えている? インドの海岸で起きた奇跡のストーリー
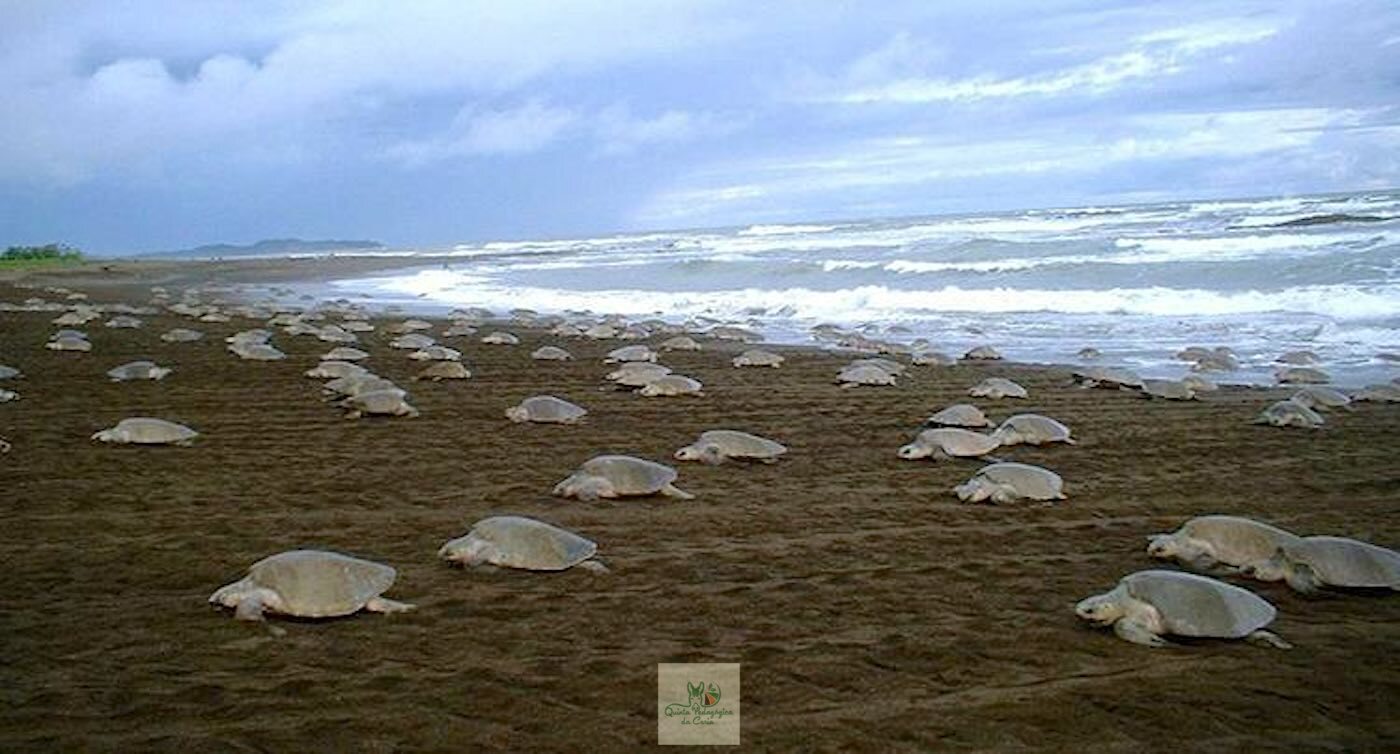
ウミガメ100万の巣が示す希望
夜明けの砂浜に広がる、100万個ものウミガメの巣を想像してみてください。 今、インド西海岸では、絶滅の危機を乗り越えたウミガメたちが驚くほどの生命力を謳歌しています。20年前と比較すると、その数はなんと10倍。
かつて「もう絶滅してしまうかも」とあきらめられていた状況を、人間の手による地道な保護活動が変えました。自然の再生力と、諦めない心が起こした「100万の奇跡」。今回は、その温かなストーリーをひも解いてみましょう。
“インド西海岸でウミガメの巣が20年前の10倍となる約100万個に増え、地道な保護活動によって絶滅の危機から大きく回復したことが明らかになりました。”
最近の報道によると、インド西海岸で確認されたウミガメの巣は約100万個に達したそうです。この数字は20年前と比較して10倍という驚異的な増加です。
「オリーブヒメウミガメ」は世界で最も個体数の多い種ですが、それでも国際自然保護連合(IUCN)によって「※危急種」に分類されています。赤ちゃんガメのうち成体まで生き残れるのは1000匹に1匹という厳しい現実があるため、個体数が多くても油断はできないのです。
※ このままの状態が続くと、絶滅してしまう恐れがある『絶滅危惧種』の一歩手前の状態のこと。
おすすめ記事:【ハミングが届けるポジティブニュース】 「バケツの水をパイプラインへ」スコットランド人男性がネパールにもたらした、水と希望の物語
赤ちゃんガメがつなぐ、希望のフェスティバル
インドのベラスで毎年開催される「ベラス・タートル・フェスティバル」では、昨年4月、数千人の観光客や地元住民が集まりました。赤ちゃんガメが次々とビーチを這い、転がり、よたよたと海に向かう姿を見守り、歓声を上げました。
このフェスティバルは、インドの海岸に巣を作るオリーブヒメウミガメの素晴らしさを広め、保護意識を高めるために、ウミガメを愛する人々によって企画されたものです。
“「ベラス・タートル・フェスティバル」は、ウミガメ保護への理解を広めるために開催され、年間を通した卵の保護や孵化支援の取り組みのもと、観光客と地元住民が赤ちゃんガメの海への旅立ちを見守るイベントです。”
保護活動は年間を通じて綿密に行われています。1月にメスのカメが巣を掘る場所をカメラで記録。その後、ボランティアや自然保護活動家たちが巣を掘り起こし、卵を大きな孵化場に移します。これは、鳥やトカゲ、犬などが海岸線から孵化前の卵を食べてしまうのを防ぐためです。
赤ちゃんガメが孵化して海へ向かう時が来ると、フェスティバルのチームが付き添い、すべての赤ちゃんガメが初めて鱗に塩水を感じ、波の音と観客の歓声に包まれながら海へと旅立っていきます。
現在の成功に至るまでの道のりは長いものでした。インドを代表するウミガメの専門家、カルティク・シャンカー氏は、20年前にはインド全海岸線で確認された巣は約10万個だったと語っています。この10万という数字は多いようにも聞こえますが、赤ちゃんガメの生存率を考えると、個体数の回復には不十分な数字でした。
“ベラスではウミガメ保護のために、巣の記録や卵の移送、海への誘導など年間を通じた取り組みが行われ、海岸開発の禁止や漁業規制、清掃活動などが導入された結果、20年前には10万個だった巣の数が現在では約100万個にまで回復しました。”
シャンカー氏らは、オリーブヒメウミガメがベラスの町から永遠に姿を消したと思っていました。しかし2000年、ビーチで1個だけ卵が発見されました。シャンカー氏は、これは海のどこかにカメがいて、いつかベラスに戻って巣を作ることを意味すると確信しました。
彼は町議会にこの事実を説明し、海岸の建設禁止を含む保護措置の実施を訴えました。この訴えが受け入れられ、ウミガメ保護への第一歩が踏み出されたのです。
海岸建設の禁止に続いて、季節的な漁業禁止、保護海岸区域の設定、そしてビーチをきれいに保つためにスタッフの配置が行われました。ウミガメがクラゲ(カメの大好物)と間違えて食べてしまうプラスチックゴミを海岸から取り除くことも重要でした。
「ある程度の保護措置が講じられたとき、オリーブヒメウミガメは回復しました」とシャンカー氏は話します。この冬の営巣シーズン中に、カメたちは「約100万個の巣を掘りました。これは信じられないほど多い数です」。
アオウミガメが見せた再生の力
この成功はインドだけの話ではありません。昨年10月、世界の国際保護機関であるIUCNは、アオウミガメがもはや「絶滅危惧種」ではないと発表しました。カリブ海からインド洋まで営巣するこれらの優雅な巨大ガメは、1970年代以降、着実に回復を続けています。
IUCNへの勧告を準備したチームの一員であるブライアン・ウォレス氏もこう話します。「私たちはアオウミガメの個体数について非常に心配していた状態から、過去数十年にわたって彼らの数が増加するのを見守ってきました。もちろん、まだ完全に安心できるわけではありませんが、報告書が示しているのは、一般的に言って、正しいことをすれば保護活動は効果を上げるということです」。
“気候変動やプラスチック汚染などの脅威は残るものの、地域住民・科学者・政府の協力により保全が実を結び、1個の卵から始まった希望が100万個の巣へと広がったことは、人間の行動が自然に大きな再生をもたらせることを示しています。”
海にどれだけの数のウミガメが存在するかを正確に知ることは困難です。保護活動家たちは、個体数の代用指標として巣の数を使うしかありません。でも、この巣の数の劇的な増加は、確実に個体数の回復を示しています。
ウミガメの回復は素晴らしいニュースですが、これで安心というわけではありません。気候変動、海洋プラスチック汚染、違法漁業など、ウミガメが直面する脅威は今も存在しています。
インドでの成功は、地域コミュニティ、科学者、ボランティア、そして政府の協力があってこそ実現しました。海岸建設の制限、漁業規制、清掃活動、そして地域住民の意識の向上――すべてが組み合わさって、ウミガメたちに第二のチャンスを与えたのです。
たった1個の卵から始まった希望が、今では100万個の巣へと成長しました。この物語は、諦めずに保護活動を続けることの大切さ、そして人間の行動が自然界にポジティブな変化をもたらせることを教えてくれています。
ジェンダーアイデンティティと代名詞を理解する
多様な性のあり方を知るための基礎ガイド

ジェンダーは「決まった答え」ではなく、対話のプロセス
ジェンダーについて理解するうえで大切なのは、「正解を覚えること」ではなく、対話を続ける姿勢です。
人のジェンダーアイデンティティは、人生のある時点で言語化されることもあれば、時間とともに変化することもあります。昨日までしっくりきていた表現が、明日は合わなくなることもある。それは混乱ではなく、自己理解が深まっているサインでもあります。
だからこそ、「一度聞いたら終わり」ではなく、変化を前提に尊重し続けることが重要なのです。
おすすめ記事:ミソジニーが女性に与える精神的負担と問題|女性が蔑視される原因とは?
ジェンダーは一つではありません。
私たちが当たり前だと思ってきた「男/女」という枠組みは、実はとても限定的な見方です。
このガイドでは、
- ジェンダーとは何か
- 性別との違い
- 代名詞の意味と使い方
- ノンバイナリーやトランスジェンダーについて
を、初めての方にも分かりやすく解説します。
ジェンダーとは何か?
ジェンダーとは、社会や文化の中でつくられた「性別にまつわる考え方・役割」のことです。
たとえば、
- どう話すべきか
- どんな服装が「ふさわしい」とされるか
- 感情をどう表現するか
といった答えは、ジェンダーによって無意識に決めつけられがちです。
アメリカや日本を含む多くの社会では、「男はこうあるべき」「女はこうあるべき」という性別に期待される役割が、幼いころから刷り込まれています。
しかし、これらは生まれつき決まっているものではありません。
ジェンダーは二択ではなく、濃淡のあるものとして存在しています。

ジェンダーと文化・環境の深い関係
ジェンダーの考え方や表現は、文化や社会環境によって大きく左右されます。
ある文化では自然と受け入れられている表現が、別の場所では誤解や偏見の対象になることもあります。
そのため、ジェンダーについて考えることは、「個人の問題」ではなく、「社会のあり方」を見つめ直すことでもあります。
誰かが安心して自分らしく存在できるかどうかは、その人の強さではなく、周囲の環境によって決まることが多いのです。
よくあるジェンダーの思い込みの例
- 女の子はピンク、男の子は青
- 男性は泣かない、女性は感情的
- 男性は攻撃的・論理的、女性は優しく世話好き
これらは文化的につくられたイメージであり、 個人の在り方を決めるものではありません。
代名詞とは?【基礎知識】
代名詞とは、名詞の代わりに使う言葉です。
ジェンダーにおいて、代名詞はその人のアイデンティティを尊重する大切な要素です。
英語でよく使われる代名詞の例
- he / him / his
- she / her / hers
- they / them / theirs(単数でも使われます)
「they/them」は、
- 自分を男性・女性のどちらとも感じない
- 二択に当てはまらない
と感じる人によく使われます。
また、
- he/they
- she/they
のように複数の代名詞を使う人もいます。
「they」は文法的に正しいの?
はい、正しいです。
実は私たちは日常的に単数の「they」を使っています。
例:
「誰かが財布を落とした」
→ I need to find the person who lost their wallet.
歴史的にも、シェイクスピアやエミリー・ディキンソンなどの作家が使ってきました。
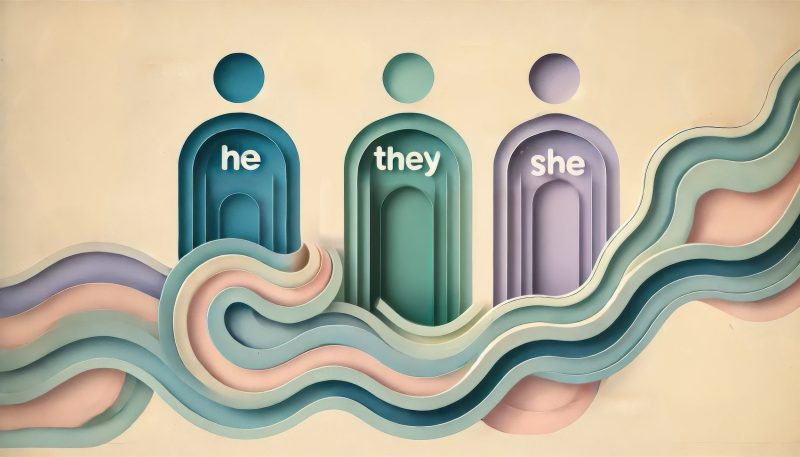
正しい代名詞の使い方
- 自己紹介のときに名前+代名詞を伝える
- 相手の代名詞を覚え、使う
- 間違えたら、簡単に謝って言い直す
過剰に言い訳したり、長く謝る必要はありません。
大切なのは「尊重する姿勢」です。
ジェンダーとセックス(生物学的性)の違い
- セックス(sex):出生時に医師が身体的特徴から割り当てる性
- ジェンダー(gender):自分自身がどう感じ、どう認識しているか
セックスも実は二択ではなく、トランスジェンダーのように、身体的特徴が多様な場合もあります。
ジェンダーの尊重は、メンタルヘルスとも深くつながっている
研究や現場の声からも、自分のジェンダーや代名詞を尊重されることは、心の安全性に直結することが分かっています。
特に若い世代のLGBTQ+の人たちにとって、
- 正しい名前で呼ばれる
- 正しい代名詞を使ってもらえる
という小さな行為は、「自分はここにいていい」という安心感を育てる、大きな支えになります。
言葉はただの記号ではなく、安心をつくるツールでもあるのです。
トランスジェンダー・シスジェンダーとは?
- シスジェンダー:出生時に割り当てられた性と、ジェンダーアイデンティティが一致している人
- トランスジェンダー(トランス):一致していない人
どちらも自然な在り方で、優劣はありません。

ノンバイナリーとは?
ノンバイナリーとは、「男性/女性」という二分法に当てはまらないジェンダーの総称です。
- ジェンダーフルイド
- ジェンダークィア
- バイジェンダー
- ポリジェンダー
など、さまざまな表現があります。
ノンバイナリーの人すべてがトランスと名乗るわけではありません。
ジェンダーに迷っているあなたへ
迷うことは、おかしいことではありません。
自分に問いかけてみてください。
- 生まれたときの性別をどう感じている?
- どんなジェンダーとして見られたい?
- どんな服装・表現が心地いい?
- どの代名詞がしっくりくる?
答えは一つでなくても大丈夫です。
子どもや若い世代にとっての意味
子どもたちは、大人の言動を驚くほど敏感に受け取ります。
大人がジェンダーについて柔軟であること、多様性を自然なものとして扱うことは、「自分らしくあっていい」という許可を次の世代に渡すことでもあります。
ジェンダーの3つの側面
- ジェンダー表現:服装・髪型・振る舞い
- ジェンダーアイデンティティ:自分自身の感覚
- 周囲からの認識:社会がどう見るか
これらは必ずしも一致する必要はありません。

トランジション(移行)について
トランジションには、
- ソーシャル(代名詞・名前)
- 法的(戸籍・書類)
- 医療的(ホルモン・手術)
などがありますが、どれも必須ではありません。
どこまで行うかは、完全に個人の選択です。
言葉とラベルについての大切なこと
- 「transgender」は形容詞として使う
- 「transgendered」は使わない
- 呼び方は必ず本人に確認する
言葉は、人を尊重するために使うものです。
間違えてもいい。大切なのは「どう向き合うか」
ジェンダーや代名詞について、誰もが最初から完璧である必要はありません。
大切なのは、間違えないことではなく、間違えたときの態度です。
素直に認め、言い直し、学び続けること。
その積み重ねが、「安全な人」「信頼できる人」という評価につながっていきます。
最後に
ジェンダーを理解することは、誰かを特別扱いすることではありません。
それは、
人を一人の人として見ること。
相手の言葉を信じること。
そして、尊重を行動で示すこと。
完璧でなくていい。
でも、無関心ではいないこと。
その姿勢こそが、多様な世界をやさしく支える土台になります。
ケーゲル体操とは?30秒でできる尿もれ・性生活をサポートする骨盤底筋トレーニング

たった30秒、道具も不要。病院に行かなくても始められて、尿もれや骨盤の不調、さらには性生活の質向上まで期待できる運動があるとしたら、試してみたいと思いませんか?
それが「ケーゲル体操(骨盤底筋トレーニング)」です。
ケーゲル体操は、骨盤の底にある筋肉(骨盤底筋)を鍛えるシンプルなエクササイズ。正しく行うことで、日常生活からセクシュアルヘルスまで、幅広いメリットが期待できます。
おすすめ記事:セクササイズとは?やり方やメリットを徹底解説
ケーゲル体操(骨盤底筋)とは?
ケーゲル体操とは、骨盤底筋を意識的に収縮・リラックスさせる筋力トレーニングです。
骨盤底筋は以下の役割を担っています。
- 膀胱・子宮・直腸など骨盤内臓器を支える
- 尿・便・ガスのコントロールを助ける
- 姿勢や体幹の安定に関わる
この筋肉が弱くなると、尿もれや骨盤臓器脱などのトラブルが起こりやすくなります。
ケーゲル体操の主な効果・メリット
1. 尿もれ・便もれ・ガスもれの予防・改善
腹圧性尿失禁や産後・加齢による軽い尿もれの改善に役立ちます。
2. 骨盤臓器脱の症状をやわらげる
膣壁が下がる、臓器が下垂するなどの症状の進行を抑えるサポートになります。
3. 性生活の質向上が期待できる
骨盤周りの血流がよくなり、興奮・潤い・感覚の向上につながる可能性があります。
筋肉をコントロールできるようになることで、身体感覚への自信が高まる方も多いです。
ケーゲル体操は女性だけのもの?
いいえ。男性にも効果があります。
- 過活動膀胱の症状
- 尿もれ・便失禁
- 前立腺手術後の回復サポート
男女問わず、骨盤底筋のケアは重要です。
骨盤トラブルがなくてもやっていい?
問題ありません。
骨盤底筋も、腕や脚と同じ「使えば保てる筋肉」です。
ただし、妊娠中や産後、違和感がある場合は、正しい方法で行うことが重要です。誤ったやり方は、かえって不調を悪化させることもあります。

間違ったケーゲル体操で起こりやすいこと
よくある間違いは以下の通りです。
- お尻や太ももに力を入れてしまう
- お腹に力を入れていきむ
- 息を止める
これらは効果がないだけでなく、骨盤臓器脱や尿もれを悪化させる原因になることもあります。
正しい筋肉の見つけ方
ケーゲル体操は、「おしっこをしている途中で止める」感覚に近い運動です。尿の流れをコントロールする筋肉を、締めたりゆるめたりします。まずは、どの筋肉を使うのかを正しく知ることが大切です。
次にトイレに行ったとき、実際に排尿を始めてから途中で止めてみてください。そのとき、女性の場合は膣まわり、男女共通で膀胱や肛門まわりの筋肉がキュッと締まり、内側に引き上がる感覚があるはずです。
これが骨盤底筋です。筋肉が締まる感覚を感じられたら、正しくできています。
このとき、太もも・お尻・お腹の筋肉はリラックスしたままであることが重要です。
それでもよく分からない場合は
以下の方法を試してみてください。
おならを我慢しているところを想像する
女性の場合
清潔な指を膣に入れ、尿を我慢するように筋肉を締めてから、ゆるめます。
筋肉が締まり、上下に動く感覚が指で感じられれば正解です。
男性の場合
清潔な指を肛門に入れ、尿を我慢するように筋肉を締めてから、ゆるめます。
筋肉が締まり、上下に動く感覚があれば、正しい筋肉を使えています。
※排尿中に止める動作は、あくまで筋肉を確認するための方法です。日常的なトレーニングとして繰り返すのは避けましょう。

ケーゲル体操の正しいやり方【基本】
ケーゲル体操の基本は、骨盤底筋だけを意識的に使い、締めて鍛えることです。最初は重力の影響を受けにくい仰向けの姿勢で行うのがおすすめです。
仰向けに寝てリラックスし、片手をお腹に置きます。息をゆっくり吐きながら、お尻・お腹・太ももは力を抜いたまま、骨盤底筋を締めます。
そのとき、「内側に引き上げて、頭の方向へ持ち上げる」イメージをすると分かりやすいでしょう。
膝を立てたり、少しお尻を床から浮かせたりすると、感覚をつかみやすくなる場合もあります。
※息を止めないように注意してください。
手順(基本)
- 仰向けに寝てリラックスする(筋肉はゆるんだ状態)
- 骨盤底筋を内側・上方向に引き上げるように締める
- 3〜5秒キープ(最初は3秒でOK)
- 5〜10秒かけてゆっくりゆるめる
無理をせず、心地よい範囲で続けていきましょう。
ケーゲル体操の「やること」
- 排尿後、膀胱が空の状態で行う
- 尿を途中で止めるときに使う筋肉を意識
- 骨盤底筋を10秒締める → 10秒ゆるめる
- 1日3セット(1セット10〜15回)
ケーゲル体操の「やってはいけないこと」
- 排尿中に何度も尿を止める
- 息を止める
- お腹・太もも・お尻に力を入れる
専門家のサポートは必要?
可能であれば、骨盤底筋専門の理学療法士に指導を受けるのがおすすめです。
正しい筋肉を使えているかを確認し、フィードバックをもらうことで、自己流よりも効果が高いことが研究でも示されています。
まとめ|ケーゲル体操は一生使えるセルフケア
ケーゲル体操は、
- すき間時間でできる
- 年齢・性別を問わず取り入れられる
- 排泄・姿勢・性生活を支える
一生もののセルフケア習慣です。
「今は困っていないから」ではなく、将来の自分の体をいたわるための予防ケアとして、今日から少しずつ取り入れてみてください。
がんばりすぎるあなたへ。立ち止まるきっかけに気づくヒント
| 香港から、ハミング編集部の知子が日常の中の小さな気づきをお届けしていきます。読み終えたあとに、今日の自分がもっと好きになれる。そんな時間になればうれしいです。 |
「私、まだできるかも」人生の折り返し地点での挑戦
香港での生活が始まって、1年がたちました。 こちらの朝は、外に出るだけで元気になれるエネルギーに満ちているんです。
ビクトリアハーバー沿いを吹き抜ける気持ちのいい海風。高層ビルの隙間から零れ落ちる、力強い太陽の光。都会の喧騒をすり抜けて、急な坂道を駆け上がると、目の前にはパッと香港の街並みを見渡せるランニングルートが広がります。

この景色を独り占めしながら駆け抜ける時間は、私にとって何よりの贅沢。
40代後半。人生の折り返し地点を過ぎて、ふとこれからの自分に想いをはせたとき、「もっと自分を試してみたい」「私、もしかしたらまだできるかも?」そんな、静かだけれど熱い欲求がむくむくと芽生えました。今回、私にとってのそれは「香港マラソン」という挑戦でした。
おすすめ記事: タンザニアの女性から教えてもらった「もっとわがままでいい」
いつもなら「完走できればそれでOK!」というお気楽なスタンス。それなのに、なぜか今回は「やるならちゃんとタイムを狙ってみたい」と自分に高いハードルを課していました。若い頃によくあった「やるなら、周りにちゃんと評価されるような数字を出さなきゃ」という気持ちが久しぶりにぐぐっと出てきたんです。
そこから、毎朝の5キロラン、週末のロングラン。ストイックに自分を追い込む日々は、充実しているようでいて、実はちょっとずつ「心の余裕」を削り取っていたのかもしれません。
突然訪れた、体からの「強制終了」
マラソン本番まで2か月後となった、ある日曜日のこと。
前日に25キロという大きな壁を乗り越え、自信がついていた私の右足に痛みが走りました。右の後ろ腿、大臀筋から腿の裏。さらには『ITバンド』と呼ばれる太ももの外側あたりまで……。下半身の一帯に広がる、鈍い痛み。それは、体からの明確な『ストップ』のサインでした。
「ええ!どうして今?」
「あと2か月しかないのに!!」
この焦りが、私をどんどん「みっともない姿」へと変えていきました。ランニングを休まなければならないストレスは、周囲への苛立ちに変わっていきます。
バスの窓から軽やかに走るランナーを見ては「うらやましい」気持ちを通り越して嫉妬したり、痛い足を引きずりながら走る私を軽々と追い越していく小学生ランナーに対して、大人げなく悔しがったり……。

「大好きだった週末のテニスも休んで、マラソンの練習にすべてを捧げてきたのに!」この執着が、私の心を支配していました。今、振り返ればそう気づくことができます。
「お母さん、最近走っていないね~」
心配して声をかけてくれる子どもにすら冷たい態度をとってしまい、つい数週間前に行ったマッサージ店の施術が悪かったのではないかと、誰かのせいにしようとする自分がいました。
「新しい挑戦をして人生をより豊かにしたい」そんな気持ちで始めたマラソンのトレーニングが、いつの間にか自分を追い詰めていたんです。
「手放す」ことで見えてきた、目の前の景色
まだ続く足の痛みと焦りの中でもがきながらも、私は一度、すべてをリセットすることにしました。ある意味、「あきらめ」に近い気持ちでした。
ちょうど友人や親戚が香港を訪ねてきてくれる時期と重なったこともあり、「もう、走ることを考えるのをやめよう」と、自分に許可を出しました。といっても、そう思えるようになるまでには数日間はかかりましたが…。
それまでは「走れない自分」を責めてばかりいました。でも、ランニングシューズをいったんしまい、代わりに今までサボっていた朝と晩のストレッチをていねいにやるようにしました。
朝ランに出かける代わりに家族との朝食の時間を大切にし、香港の街を「走る」のではなく「ゆっくりと歩いて」みました。朝ランを始めてからは、家族との朝食時間を犠牲にしていたことや、香港の景色を心に余裕をもって眺めることもできていなかった。そんなことに気づいたんです。久しぶりに家族とみんなで食べるごはんのおいしいことといったら!

こうやって「走らなければならない」という執着を手放した時、嬉しいことが起きました。
本番まで2週間を切った週末。祈るような気持ちで久しぶりにおそるおそる数キロ走ってみたところ、あんなに私を苦しめていた痛みが、ずいぶんと和らいでいたのです。以前のようにスピードは出せません。距離も、目標としていたものには程遠い。
でも、一歩踏み出すたびに感じる、地面を蹴っているあの感覚。
「あぁ、痛みもなく走れるって、なんて幸せなんだろう」
心の底から、そう思えたのです。今まで走ることは当たり前すぎて、痛みもなく丈夫な脚で走れることを「幸せ」と考えたことなんてありませんでした。
すれ違うランナーたちに、「私、また走れるようになったよ!」と大声で伝えたくなるような、子どもの時に感じたあの喜び。それはタイムを追い求めていた時には味わえなかったなんとも温かい気持ちでした。

立ち止まることは、自分を守ること
私たちはつい、「もっと上へ」「もっと速く」と自分を駆り立ててしまいます。
特に、昭和の時代に育ち責任感の強い女性たちは、がんばることが当たり前になりすぎて、体が発している「休んで」というサインを見落としがち。
もし今、あなたが何かに突き当たっていたり苦しいと感じるのなら、必死に握りしめていた拳をいったんゆるめてみるのもいいかもしれません。
私にいたっては、今回の香港マラソン、タイムはもう気にしません!完走できるかどうかも、当日のお楽しみとします。ただ、こうして健康で動ける体があること。そのことに感謝しながら、香港の街を思いっきり駆け抜けます!
今、がんばりすぎているあなたへ。今日だけは、自分に「お疲れ様」と言って、深呼吸をしてみてくださいね。

【2026版】オーガニックな生理用品を選ぶ理由

見えない「マイクロプラスチック」と私たちの身体の話
生理用品は、毎月、長時間にわたって直接肌や粘膜に触れるもの。
それにもかかわらず、私たちは「何でできているか」をあまり知らないまま使い続けていることが多いかもしれません。
一般的な使い捨てナプキンやタンポンの多くには、石油由来プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレンなど)や、吸収力を高めるための高分子吸収体(SAP)が使われています。これらは便利である一方、使用中や廃棄後にマイクロプラスチックとして環境中に残る可能性が指摘されています。
おすすめ記事:【映画レビュー】ナプキン一枚が変える未来――インドの女性たちの闘い
また、デリケートゾーンは皮膚吸収率が高く、漂白剤・香料・合成素材による刺激が、かゆみや違和感の原因になることも。
だからこそ近年、オーガニック素材・植物由来素材・再利用可能な生理用品に注目が集まっています。
オーガニックな生理用品を選ぶことは、
- 自分の身体をいたわること
- 不要な化学物質への曝露を減らすこと
- 使い捨てゴミやマイクロプラスチックを減らすこと
そのすべてにつながっています。
ここでは、オーガニック&サステナブルな生理用品を厳選してご紹介します。
おすすめオーガニック生理用品6選
1.Flo
こんな人におすすめ|
・ 昼夜しっかりカバーしたい人
・ 多い日や長時間の安心感を求める日
素材|
・100% オーガニックバンブー
・化学物質・漂白剤・染料フリー
ポイント|
B Corp認証ブランド。購入が社会貢献につながる仕組みも支持されている。

2. ソフィ はだおもい オーガニックコットン
こんな人におすすめ|
・初めてオーガニックナプキンを使う人
・敏感肌/かぶれやすい人
素材|
・肌に触れる表面シート:100%オーガニックコットン
・日本製
ポイント |
身近なドラッグストアでも手に入りやすく、「まずは試してみたい」人に最適。やさしい使用感で日常使いしやすい。

3. コットン・ラボ
こんな人におすすめ|
・化学素材をできるだけ避けたい人
・通気性重視の人
素材|
・表面材:オーガニックコットン100%
・吸収体:ポリマー不使用
ポイント|
吸収ポリマーを使わない設計で、ムレにくくナチュラル。布ナプキンと紙ナプキンの中間のような安心感。

4. The Honey Pot
こんな人におすすめ|
・オーガニック+フェムケア意識が高い人
・香りに敏感な人(※ハーブ配合タイプあり)
素材|
・オーガニックコットン
・人工香料・塩素・パラベン不使用
ポイント|
黒人女性が創業したブランド。セルフケアと社会的視点を両立した、フェムテックの代表格。

5. Cora
こんな人におすすめ|
・夜用・多い日用を探している人
・信頼できる認証を重視する人
素材|
・100%オーガニックコットン
・塩素漂白・合成香料不使用
ポイント|
B Corp認証ブランド。購入が社会貢献につながる仕組みも支持されている。

6. Boob
こんな人におすすめ|
・ゴミを減らしたい人
・長期的にコスパを重視したい人
素材|
・オーガニックコットン
・洗って繰り返し使える設計
ポイント|
北欧ブランドらしいミニマル設計。生理との付き合い方を見直したい人に。

まとめ|生理用品は「消耗品」ではなく「セルフケア」
生理用品は、毎月必ず使うもの。
だからこそ、その選択は体調・気分・環境への影響を少しずつ積み重ねていきます。
オーガニックやサステナブルな生理用品は、「完璧を目指す」ためのものではありません。
✔ 今日は体を休ませたい
✔ ちょっと肌にやさしいものを使いたい
✔ 未来の環境に、少しだけ配慮したい
そんな小さな選択の延長線にあるものです。
自分の身体と、これからの世界のために。
あなたに合った、心地よい生理用品が見つかりますように。
外陰部のスキンケア・ルーティンの作り方

デリケートゾーンも「スキンケア」の一部です
生理中を除くと、外陰部のケアについて、じっくり考える機会は意外と少ないかもしれません。
けれど、女性の身体はとても強く、同時にとても繊細。だからこそ、顔や身体のスキンケアと同じように、デリケートゾーンにも丁寧なケアが必要です。
おすすめ記事:生理直前のカラダが教えてくれること――PMSの症状を見逃さないで
このメッセージを広く伝えているのが、クレア・ベルトゥシオ医師。
彼女は、女性のためのスキンケアブランド Medicine Mama のCEO兼チーフ・メディカル・オフィサーです。
「外陰部ケアはスキンケアそのもの。顔の肌を大切にするように、外陰部という美しくデリケートな“皮膚”にも、ケアのルーティンを持つべきです」
外陰部について、まずは正しく知ることから
外陰部と膣は、混同されがちですがまったく別の部位です。
-
外陰部
恥丘、大陰唇・小陰唇、クリトリス、膣口など、外側に見えるすべて -
膣
体内にある器官(自浄作用あり)
重要なのは、外陰部は「皮膚」であるという点。
皮膚である以上、乾燥・摩擦・刺激の影響を受けやすく、外側からの適切なケアが必要になります。

外陰部の肌は、顔以上にデリケート
外陰部の皮膚は、顔と同じくらい、あるいはそれ以上に繊細です。
以下のような要因が、pHバランスや肌状態を乱す原因になります。
- (プレ)更年期
- 産後
- 薬の服用
- 性的活動
- ムダ毛処理
- 下着や衣類の摩擦
ただし、「ケアすれば何でもいい」わけではありません。
顔に使わない洗浄力の強い製品を使わないように、外陰部専用に設計された製品を選ぶことが大切です。
外陰部のケア製品を選ぶときの基本ポイント
バートゥシオ博士が強調するのは、以下の点です。
- 香料・強い化学成分を含まない
- 外陰部特有のpH・常在菌バランスを考慮
- 刺激を最小限に抑えた処方
適切でないケアを続けると、
✔ 乾燥
✔ 弾力の低下
✔ かゆみ・違和感
✔ 感染や親密な時間の痛み
につながることもあります。
外陰部スキンケアの基本ルーティン【3ステップ】
1. 外陰部用モイスチャライザー
天然由来成分でオーガニックな保湿剤は、(プレ)更年期、産後、性行為、脱毛後、医療ケア後の乾燥や刺激をやさしく和らげます。
- 毎日の保湿ケアとして
- 乾燥や違和感を感じたときに
2. 外陰部用ウォッシュ(洗浄)
ココナッツ由来で低刺激の洗浄料は、肌を乾燥させずに汚れを落とし、pHバランスをサポートします。
ポイントは、
✔ 洗浄力が強すぎないこと
✔ うるおいを奪わないこと
3. スクラブ
きめ細かいスクラブは、ムダ毛処理前の肌を整え、埋没毛の予防に役立ちます。
- ビキニシーズンだけでなく通年使用OK
- やさしく、頻度は控えめに
そのほかに大切なケア
健やかな外陰部環境を保つためには、プロバイオティクス、クリーム、入浴剤なども有効です。
これらは、pHバランスと肌バリアの維持を助けてくれます。
まとめ|外陰部ケアは、セルフケアと自己理解の第一歩
外陰部ケアは、単なる美容やトラブル予防ではありません。
それは、自分の身体と向き合い、声を聞き、尊重する時間でもあります。
バートゥシオ博士はこう語ります。
「外陰部ケアは、女性が自分の身体とつながり、
健康について自ら選択をし、
安全で満たされた状態を育むための第一歩です」
デリケートゾーンを大切にすることは、自分自身を大切にすること。今日から少しずつ、あなたの外陰部スキンケア習慣を始めてみませんか。
性欲を高めるには?原因と今日からできる5つの方法

心と体、そして脳から整えるケア
「最近、性欲が落ちている気がする」
そんな悩みは、決して珍しいものではありません。性欲は年齢、ストレス、体調、パートナーシップなど、さまざまな理由で変化します。
おすすめ記事:セックスの不満をパートナーとケンカせずに話すには?
知っておいて欲しいことは、性欲は“戻す・育てる”ことができるということ。
ここでは、ロサンゼルスを拠点に活躍する臨床心理士・セックスセラピストの ケイト・バレストリエリ博士の科学的根拠に基づいたアドバイスをもとに、性欲を高めるための考え方と実践法をご紹介します。
性欲は「スイッチ」ではない
性欲は、オン・オフを切り替えるスイッチのようなものではありません。
多くの場合、複数の要素が重なって生まれる、とても繊細な反応です。
性欲には大きく分けて2つのタイプがあります。
-
自発的な欲求
気持ちが先に高まり、そのあと身体が反応するタイプ -
反応的な欲求
身体の刺激や安心感が先にあり、あとから「したい」という気持ちが生まれるタイプ
どちらが正しい・間違っているということはありません。
大切なのは、自分がどちらの傾向かを知り、性欲が生まれやすい環境を整えることです。

性欲を高めるための5つのポイント
1. 心と体の健康を最優先にする
性欲の低下は、身体や心が「少し休みたい」「ケアが必要」と伝えているサインであることも。
睡眠不足、栄養の偏り、運動不足、慢性的なストレスは、性欲に直接、影響します。
また、特定の疾患や服用中の薬が性欲に影響することもあります。
食事・睡眠・運動のバランスを見直すことは、性的な健康の土台づくりです。
2. 「安心・安全」を感じられているかを見直す
性欲は、意外なほど「安心感」に左右されます。
お金の不安、健康への心配、パートナーへの不信感などがあると、身体は無意識にブレーキをかけます。
過去のトラウマや強いストレスを抱えている場合は、それをケアすることで、性欲に使えるエネルギーが戻ってくることもあります。
信頼関係を築き直す、ペースをゆるめる、気持ちを言葉にする――
それだけで、性的な感覚が少しずつ開いていくことがあります。
3. パートナーとの関係を整える
性欲のタイミングがパートナーと合わないのは、とても自然なこと。
私たちは常に同じ気分・体調でいるわけではありません。
ただし、
・解決されていない不満
・言えなかった気持ち
・けんかの後のモヤモヤ感
こうした積み重ねは、性欲を遠ざけます。
必要なのは「我慢」ではなく、健全なコミュニケーションと感情の整理。
親密さを取り戻せると、性欲も自然と戻るケースは少なくありません。
4. 脳を刺激する(脳は最大の性器)
性欲において、最も重要な器官は「脳」です。
脳が刺激されなければ、身体も反応しにくくなります。
おすすめなのは:
- 官能的な文章・音声・映像に触れる
- ダンスやポールダンスなど、身体感覚を楽しむ
- 性教育やセルフプレジャーについて学ぶ
- ロールプレイや新しいファンタジーを探る
「想像力」と「新鮮さ」は、性欲を育てる大切な栄養です。
5. セクシュアリティに触れる頻度を増やす
「使わない機能は衰えていく」
これは性欲にも当てはまります。
実際のセックスだけでなく、
・自分の身体に意識を向ける
・官能的な気分を味わう
・セルフケアとしての性的時間を持つ
こうした積み重ねが、脳と身体に「性的感覚」を思い出させるのです。
さいごに|性欲は「戻すもの」ではなく、いたわりの中で育つもの
性欲が落ちていると感じると、
「自分はおかしいのかもしれない」
「前みたいに戻らなきゃ」
こうやって、知らず知らずのうちにあせってしまうことがあります。
でも、性欲は決して一定のものではありません。
日々の疲れ、心の揺れ、環境の変化、こういったことに正直に反応しているだけなのです。
大切なのは、無理に高めようとすることではなく、
今の自分に「何が足りていないか」「何を求めているか」に耳を澄ますこと。
しっかり眠ること。
安心できる人とつながること。
自分の身体に、やさしく触れること。
少しだけ、ワクワクする想像をしてみること。
そんな小さな積み重ねの中で、性欲は自然と息を吹き返していきます。
性欲は、あなたの価値を測るものではありません。
それは、心と体が元気かどうかをそっと教えてくれるサイン。
どうか焦らず、比べず、今のあなたをそのまま受けとめて。
あなたのペースで、あなたらしい心地よさを取り戻していけますように。
セキララカードが目指すヘルシーリレーションシップ。会話から、人間関係や社会を変えていく
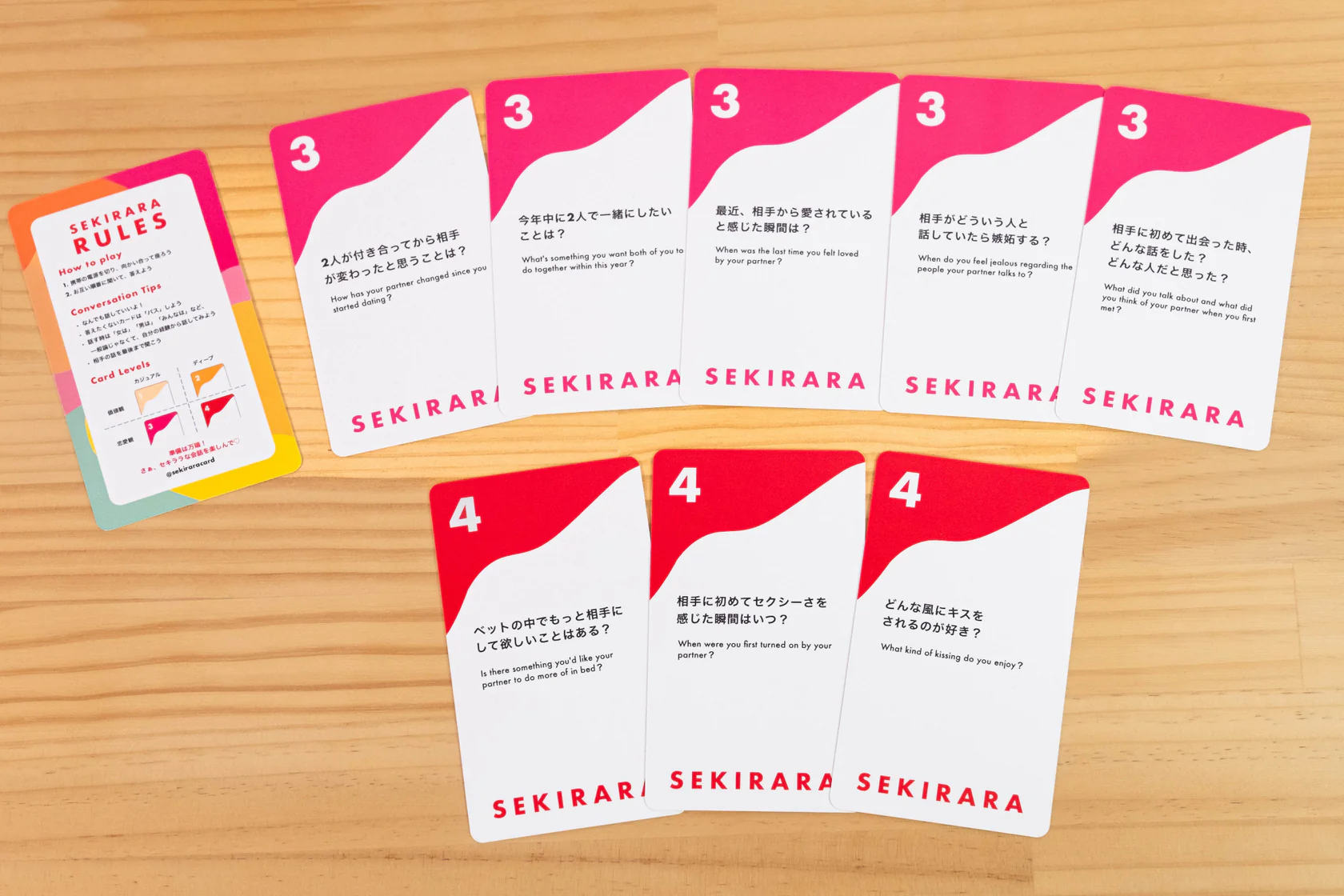
© 2026, セキララカード Sekirara Card
HummingのセレクトECショップでも人気を集めている、身近な人とのコミュニケーションをやさしく後押ししてくれる「セキララカード」。
Humming編集部には、編集長を含め、アメリカを拠点に活動しているメンバーもいます。アメリカでは、カードをきっかけに恋人や友人と会話を深める文化がある一方で、日本では、コミュニケーションカードをあまり見かけません。
おすすめ記事: セキララカードで本音トーク。Humming編集部が試してみた!
「日本にも、こんなツールがあったらいいのではないか」そんな思いから編集部メンバーが探す中で出会ったのが、セキララカードでした。
今回は、株式会社セキララカード代表取締役・藤原紗耶さんに、セキララカード誕生の背景や、このカードを通して目指している世界について伺いました。
本音を言えなかった過去の恋愛が、セキララカードの原点
― セキララカードが生まれた背景には、藤原さんご自身の恋愛経験があるそうですね。差し支えなければ、どんな経験だったのかお話を伺いたいです。
藤原:過去の私は好きな人と楽しい話はできるのに、少し疑問に思うことや、ネガティブな話題は、なかなか口に出せませんでした。
たとえば、「私たちの関係って何?」といった深い話を避け、曖昧な関係を続けてしまったり、本当はセックスをしたくない時でも相手に合わせて応じてしまったり。
「本音を言って相手が離れてしまうくらいなら、言わないほうがいい」。そんなふうに自分を納得させながら、結果的に傷つく恋愛を繰り返していました。
当時はアメリカに住んでいたのですが、転機となったのは、友達が貸してくれた「カップル向けの質問カード」です。それは、パートナーと話すきっかけを自然につくってくれるものでした。
自分から切り出すには勇気がいる話題でも、カードを使えば無理なく言葉にできる。「このカードがあれば、私の恋愛は変わるかもしれない」と希望を感じました。
日本では、こうしたコミュニケーションカードがまだなかったので、「自分で作ろう」と思ったことが、セキララカードの始まりです。
セックスやお金の話が気軽にできるように。20代から熟年夫婦まで、世代を超えて届く声
ー セキララカードのユーザーさんからは、どのような声が届いていますか?
藤原:「付き合う・付き合わない」フェーズにいる20代前半の方たちからは、「セキララカードのおかげで自分からは言いづらかったことを話せるようになった」という声が届いています。
また、結婚や同棲を考えているカップルからは、「 『この人と一緒に暮らせるか』『結婚できるか』を考えるきっかけになった」という話も聞きました。
特に印象的だったのは、長年連れ添ったご夫婦のケースです。「子育てが落ち着き、会話が減っていた中、旅行先でお酒を飲みながらカードを使ってみたところ、普段あまり話さないご主人がたくさん話し始め、家族の雰囲気がとても良くなった」という嬉しいエピソードもありました。
特に、離婚経験のある方はセキララカードの意義を深く理解してくれます。大きな痛みを経験しているからこそ、対話の大切さを実感しているのだと思います。
あとは、世代を問わず、「お金」と「セックス」の話ができることに価値を感じてくださる方が多いです。
― 確かに、お金の話は、自分の人生をそのまま覗かれているような感覚になりますよね。 「今月、何にお金を使ったの?」と聞かれると、特に悪いことはしていないのに、なぜか答えづらい。そんな経験、きっと多くの人があると思います。セキララカードの質問は、どなたが考えているのですか?
藤原: 私が考えたり、海外のカードゲームを参考にしたりすることもあります。大学院で夫婦学やコミュニケーション学を教えている教授にチェックしてもらい、最終決定しています。

© 2026, セキララカード Sekirara Card
パートナーとのいい会話の鍵は「言語化・傾聴・未来」
― 藤原さんが思う、カップル間での「いい会話」の鍵は何だと思いますか?
藤原:大きく分けて、3つあると思っています。
一つ目は、自分の気持ちをきちんと言葉にすること。
たとえば、 「ムカつく」「イライラする」で終わらせてしまいがちな感情を、「どんな言動に対して」「なぜそう感じたのか」まで掘り下げて考えてみる。すると、怒りの感情の奥に、実は寂しさがあったり、過去の経験が重なっていたりすることがあります。
二つ目は、相手の話を最後まで聞くこと。
当たり前のようで、これがなかなかできないことなんです。途中で「でも私は」と口を挟みたくなってしまう。
自分の気持ちを伝えるのと同じくらい、相手の話を受け取る姿勢が大切です。
そして三つ目が、これからどうしたいかを二人で話すこと。
言い合って終わりではなくて、「次に同じことが起きたらどうする?」と未来の話をする。ここまでできると、「話してよかった」と思えるし、二人の関係がより心地よくなると、私は感じています。
― うちの両親も「最後まで聞いてよ」と夫婦喧嘩の時に言っていました。相手の話を最後まで聞くのは、簡単そうで難しいですよね。
どうして私たちは一番近い存在に対してこそ、オープンに、正直に話すことが難しいのでしょうか?
藤原:その人の存在が大切だから、だと思います。
失いたくないからこそ、離れてしまうリスクのある話題は避けたくなる。結局は、相手を失いたくないのと同時に、自分が傷つきたくないからなのかもしれません。
― でも、話さないと、逆に失ってしまうこともありますよね。

© 2026, セキララカード Sekirara Card
すべてのカップルに、会話をするきっかけを
― どんな人にセキララカードを使ってほしいですか?
藤原:世界中のすべてのカップルに使ってほしいです。 婚姻届を出したらセキララカードがもらえるくらいの感覚で。
中でも特に届けたいのは、過去の私のように、自分を犠牲にする恋愛をしている人。 「思いやり」のつもりで我慢を重ねて、苦しくなってしまう。自分を責めてしまう人たちに、「関係は二人でつくっていくものだよ」、「嫌なことは嫌だと言っていいんだよ」ということを、セキララカードを通じて伝えたいです。
カードを眺めるだけで、 「パートナーとは、こういう話題が話せたほうがいいんだ」と気づきがあるかもしれないし、これまで恥ずかしくて避けてきたけれど、セックスの話に興味があると感じる人もいるかもしれません。
セキララカードが、新しい自分を見つけるきっかけになれたら嬉しいですね。
会話から、社会を変えていく。ヘルシーリレーションシップを日本に広げたい
― 最後に、セキララカードが今後目指していることを教えてください。
藤原:まず一つは、セキララカードの種類をもっと充実させることです。 家族向けのものや、チームビルディングに特化したもの。カップル向けでも、結婚前や出産前など、関係性のフェーズごとに分けたカードも作ってみたいですね。
その一方で、私たちが本当に目指しているのは、「ヘルシーリレーションシップ」という考え方や文化を、日本に広げていくことです。
そのためには、カードを作るだけでは足りなくて、「教育」と「エンタメ」の両方が必要です。
教育だけでは、正しさは伝えられても広がりにくい。エンタメだけでは、広がっても深くは浸透しない。だからこそ、この二つを両輪として進めていくことが大切だと思っています。
家庭内DVやデートDV、夫婦関係や親子関係の問題、学校でのいじめ、職場でのパワハラやセクハラ…..。今の社会にある多くの課題は、突き詰めると「人と人との関係」から生まれているものです。
言葉にすることの大切さを、社会全体で共有していかなければ、問題は増えていく一方です。
だからこそ、「ヘルシーな関係は、努力して築けるもの」「察するのではなく、ちゃんと言葉にすること」、そうした価値観を、カードづくりと並行して広げていきたいです。
― 世界的にも課題になっていますが、インターネットが普及したことで、対面で会話をする機会が減っています。特に若い世代では、その傾向が強まっていますよね。だからこそ、会話をすることの大切さを伝えていくことは大切ですね。本日はありがとうございました。
株式会社セキララカードについてはこちら▼
https://sekiraracard.com/
【2026年版】安心して使えるノントキシック&ナチュラル潤滑剤(ルーブ)おすすめ5選

Hummingがセレクトする、ナチュラル&ノントキシック潤滑剤
潤滑剤(ルーブ)は、特別なときのためだけのものではありません。
それは、自分の体の声に耳を傾け、心地よさを取り戻すためのアイテム。
おすすめ記事:性生活の改善ヒント:セックスで「自分が本当に楽しめること」を見つける方法
乾燥や違和感を「仕方ないもの」と我慢するのではなく、
「どうすれば、もっと安心できる?」と問いかけてみる。
Hummingは、そんな小さな選択を応援したいと考えています。
今回セレクトしたのは、
✔ ナチュラル
✔ ノントキシック
✔ フェムケア視点で安心して使える
そんな基準を大切にした潤滑剤たちです。
潤滑剤(ルーブ)は、安全で自然な成分で作られていれば、心と体の両方にやさしいセルフケアアイテムになります。
前戯や優しいマッサージ、エロゲンゾーンへのタッチなど、さまざまなシーンで使えるだけでなく、成分によっては感度を高めたり、心地よさを深めたり、乾燥や痛み、炎症を和らげる助けにもなります。
なぜ「ナチュラルルーブ」を選ぶの?
ナチュラルな潤滑剤を選ぶことは、自分の体をいたわる選択であると同時に、環境にも配慮した選択です。
特に重要なのが pHバランス。
潤滑剤は、私たちの体の自然なpH値に近いことがとても大切です。理想的にはpH4.5前後が望ましく、これにより膣内環境の乱れや感染症のリスクを減らすことができます。
ナチュラルルーブは、多くの場合、
⇒ 刺激の強い化学成分
⇒ 合成香料
⇒ 人工保存料
を含まず、アレルギーやかゆみ、違和感が起きにくいのが特徴です。
アロエベラやココナッツオイルなど、保湿・鎮静作用のある植物由来成分が使われているものも多く、膣の健康をサポートしてくれます。
さらに、環境面でも、生分解性の高い原料やエコなパッケージを採用しているブランドが多く、「動物実験なし」を掲げている点も魅力です。
Hummingのセレクト基準
Hummingでは、以下のポイントを重視して商品を選んでいます。
- 体のpHバランスに配慮していること
- 刺激の強い化学成分・合成香料を使っていないこと
- 植物由来・オーガニック成分を中心にしていること
- ブランドの姿勢(倫理性・サステナビリティ)
「安心して、続けて使えるかどうか」を何より大切にしています。
① The Natural Love Company
特徴| 有機成分99.2%配合
成分| アロエベラ、精製水
値段| ¥6,300
こんな人におすすめ
- はじめてナチュラルルーブを使う
- 水性でクセのない使用感が好き
- 成分の透明性を重視したい
Simply Lubeは、水性タイプのパーソナルルーブで、感度と心地よさを高めることを目的としながらも、一般的な潤滑剤に含まれがちな刺激成分を排除しています。
99.2%がオーガニック成分で、鎮静作用のあるアロエベラを配合。水性・トイセーフ・ヴィーガン認証・コンドーム対応と、安心して使える条件が揃った一本です。

② Foria
CBD Intimacy Sex Oil (CBDインティマシーセックスオイル)
特徴| 原料はわずか2つのみ
成分| オーガニックMCTココナッツオイル、ブロードスペクトラムCBD
値段| ¥6,899
こんな人におすすめ
- リラックスしながら親密さを深めたい
- 感覚の「緊張」をゆるめたい
- オイルタイプが好み
ForiaのCBDルーブ&セックスオイルは、極限までシンプルな処方が特徴。
オーガニックココナッツオイルと、USDA認証・再生農法で育てられたヘンプ由来CBDのみを使用しています。
レビューでも、「感度が高まった」「リラックスできた」といった声が多く、心身をゆるめながら親密さを深めたい人におすすめです。
※オイルベースのため、ラテックス製コンドームとの併用には注意が必要です。

③ The Honey Pot Company
Organic Moisturizing Water-Based Lubricant (オーガニック保湿水性潤滑剤)
特徴| 膣環境をサポートするpHバランス設計
成分| オーガニックアガベエキス、カモミール
値段| ¥2200
こんな人におすすめ
- 乾燥が気になる
- 膣環境(pH)を大切にしたい
- 毎日のフェムケアの延長で使いたい
乾燥を感じたときに手に取りたい、やさしいハーバルウォータールーブ。
刺激になる添加物や香料は一切使わず、オーガニック処方で作られています。
保湿力のあるアガベと、心を落ち着かせるカモミール配合で、 「ベッドルームの中でも外でも、自分に自信を持てる感覚」を大切にしたい人に。
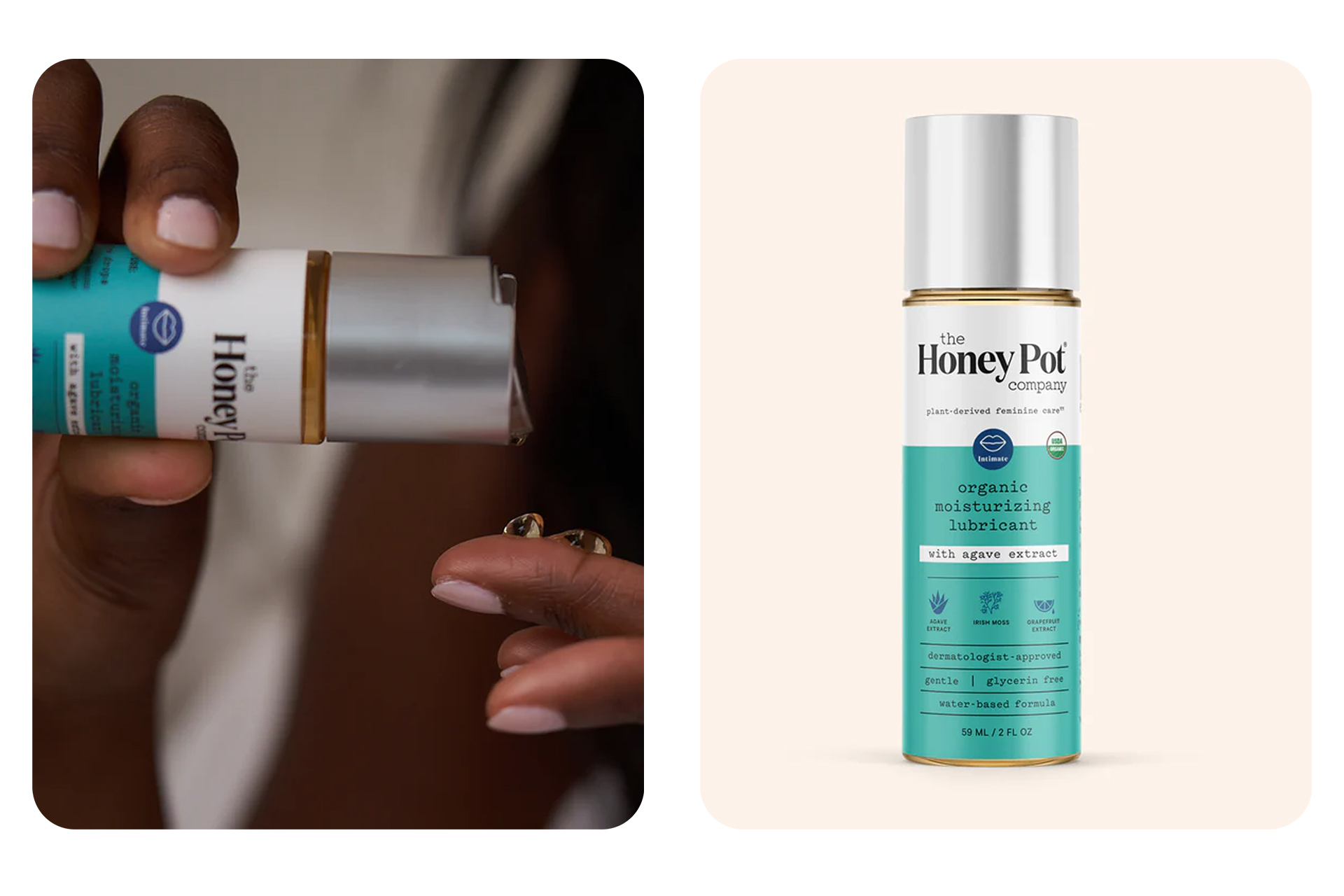
④ Package Free
Radiant Love Lube (ラディアントラブ潤滑剤)
特徴| パラベン・石油由来成分・グリセリン不使用
成分| ホホバオイル、バニラオイル、シナモンオイル
値段| ¥5200
こんな人におすすめ
- 成分も香りも、とことん自然派
- マッサージや前戯にも使いたい
- サステナブルな選択をしたい
Living Libationsによるこのルーブは、100%ナチュラルなオイルベース。
パラベンや石油由来成分、グリセリンを使わず、官能的で温かみのある香りが特徴です。
伸びがよく、食べられるほど安全な成分で作られているため、マッサージや前戯にもぴったり。 サステナブルなライフスタイルを大切にする人にもおすすめです。

⑤ La Nua
Watermelon Mint Water-Based Lubricant (スイカミント風味の水性潤滑剤)
特徴| 植物由来・爽やかな香り
成分| ケルプ(海藻)、クエン酸
値段| ¥4000
こんな人におすすめ
- 軽やかな使い心地が好き
- フレーバー付きルーブに興味がある
- デザイン性も大切にしたい
La Nuaのウォーターベースルーブは、クリーンでナチュラルな原料を使用。
スイカ&ミントのフレーバーがさっぱりと心地よく、使用感も軽やかです。
フロストガラスのボトルと竹製キャップという、美しさとサステナビリティを両立したデザインも魅力。 「使う時間そのものを大切にしたい人」にぴったりの一本です。

まとめ|自分の体にやさしい選択が、心地よさを育てる
潤滑剤を選ぶことは、「快感を足す」こと以上に、自分の体を信頼する練習なのかもしれません。
無理をしない。
我慢しない。
比べない。
その人の体、その人のタイミングに合った心地よさを、安心できる選択肢の中から見つけていく。
Hummingはこれからも、「静かだけれど、確かなフェムケア」を届けていきます。
子どもがいる家庭で、カップルはどうやって親密さを保てばいい?

子どもがいると「二人の時間」がなくなるのは自然なこと
親になってから、パートナーとの親密さが減ったと感じるカップルは少なくありません。
けれどその原因は、愛情や魅力、欲求がなくなったからではないことがほとんどです。
多くの場合、一番の変化は「プライバシーの喪失」です。
おすすめ記事:性生活の改善ヒント:セックスで「自分が本当に楽しめること」を見つける方法
子どもが家にいることで、以前は二人だけのものだった空間や時間が共有されるようになります。「近くに誰かがいるかもしれない」という感覚が続くと、心も体も無意識に緊張し、親密さに身を委ねにくくなります。
これは、関係がうまくいっていないサインではありません。
子育てという、とても自然な環境の変化なのです。
なぜプライバシーは親密さにとって大切なのか
性的な親密さには、時間や機会だけでなく、心理的な安心感が必要です。
プライバシーが不安定だと、脳や神経は常に「警戒モード」に入ります。
この小さな緊張が積み重なることで、
- 今この瞬間に集中できない
- 遊び心やつながりを感じにくい
- 行為が急ぎ足になったり、避けられるようになる
といった状態が起こりやすくなります。
その結果、「もう欲求がなくなったのかも」と誤解してしまうこともありますが、実際には欲求ではなく環境が合っていないだけというケースが非常に多いのです。
乳児・幼児期|予測できる「小さな時間」をつくる
赤ちゃんや幼児がいる時期は、疲労と予測不能さがプライバシーの最大の壁になります。
いつ起きるかわからない、常に気が抜けない、それは当然のことです。
この時期に大切なのは、予測可能性。
- お昼寝中
- 早めの就寝後
- 数分でも「触れ合う時間」を決める
こうした短くても意図的な時間が、親密さをつなぎ止めてくれます。
また、「性行為はこうあるべき」という期待を手放すことも重要です。
短いスキンシップや安心できる触れ合いだけでも、関係は保たれます。

幼児期後半|やさしい境界線をつくる
子どもが成長し、好奇心が強くなると、「入ってこられるかも」という不安が増えてきます。
この時期は、大人の空間にやさしい境界線をつくることが助けになります。
- ノックを教える
- 寝る前のルーティンを整える
- 「今は大人の時間だよ」とシンプルに伝える
大切なのは、恥や罪悪感を与えないこと。
境界線がはっきりすると、親自身の緊張も自然と和らぎます。
小学生期|プライバシーの再定義
子どもが成長すると、夜更かしや自室での時間が増えます。
物理的には離れていても、「聞こえていないか」「気づかれていないか」という不安が残りがちです。
この時期に必要なのは、完璧なプライバシーを求めないこと。
完全な静けさや確実性は、現実的ではありません。
年齢に合った境界線を信頼し、「家に人がいても親密さは可能だ」と再学習することが大切です。
また、エネルギーが残っている夕方や日中に時間をずらすことで、親密さが戻るケースも多くあります。
思春期|大人としての自分を取り戻す
ティーンエイジャーがいる家庭では、物理的なプライバシーはあっても、心理的な抵抗感が生まれやすくなります。
- 気まずさ
- 聞かれているかもしれない不安
- 親である自分と女性・男性としての自分の葛藤
この段階では、親の役割と、大人としての自分を切り分けることが重要です。
閉じたドアやプライバシーを尊重する家庭ルールは、親だけでなく、子どもにとっても健全です。

「完璧なタイミング」を待たないこと
多くのカップルは、「落ち着いたら」「もう少し成長したら」と親密さを先送りにします。
しかし、完璧な条件がそろう時期はほとんど訪れません。
大切なのは、その時期に合った形で続けること。
まれな理想の時間より、小さくても継続的なつながりのほうが、関係を深めてくれます。
専門家のサポートが役立つ理由
プライバシーの問題は、単なる環境の話ではなく、
- 不安
- 欲求のズレ
- コミュニケーションのすれ違い
と深く結びついています。
専門家との対話は、「何がブレーキになっているのか」を安全な場で整理する助けになります。 問題が深刻になる前にサポートを受けることで、距離が広がるのを防ぐこともできます。
親密さは、今の生活の中でも育てられる
子どもがいることで、親密さの形は変わります。
でも、なくなるわけではありません。
長く満たされた関係を続けているカップルは、
完璧な条件を待った人たちではなく、変化に合わせて調整してきた人たちです。
もし今、「プライバシーが一番の壁」だと感じているなら、それはあなただけではありません。
適切な視点とサポートがあれば、親密さは家族の成長とともに、静かに育っていきます。
生理について、もっとオープンに話そう
月経をタブーにしないことが、健康と尊厳を守る第一歩

月経は、私たちの生活のごく自然な一部です。
しかし、その重要性とは裏腹に、いまだに多くの社会で語られにくく、偏見にさらされているテーマでもあります。
Hummingでは、「なぜ月経についてオープンに話すことが大切なのか」、そして「どんな視点を対話に含めるべきか」を掘り下げます。
おすすめ記事:毎月のことだから、もっとやさしく。安全でサステナブルなオーガニック生理用品を選ぶということ
偏見のない、インクルーシブな対話は、生理の貧困やジェンダー不平等の解消につながり、すべての人の健康と尊厳を守る力になります。
世界では、どれほど多くの人が月経を経験しているのか
世界では毎日、3億人以上の女性が月経中であり、毎月では約18億人が月経を経験しています。 それほど多くの人にとって身近な現象であるにもかかわらず、安全な生理用品・衛生的な設備・正しい知識にアクセスできない人は今も非常に多く存在します。
世界全体で、約5億人の女性が十分な月経ケアを受けられていないとされ、これは感染症などの健康リスクにも直結します。
それでも月経は、秘密にされ、恥と結びつけられ、オープンに語られることがほとんどありません。
文化や地域を超えて続く沈黙は、誤解や神話、排除を強め、安全な月経管理をより難しくしているのが現状です。
月経は「不調」ではなく、体のリズム
月経は、妊娠が成立しなかった場合に、子宮内膜の血液や組織が排出される生理的なプロセスで、ホルモンの変化によって調整されています。
安定した月経周期は、
- 気分
- エネルギー
- 睡眠の質
- 代謝・心血管の健康
と深く関係しており、内分泌系がバランスよく機能しているサインでもあります。
月経は、季節の移ろいのようなもの。木の葉が落ち、また芽吹くように、体と心に訪れる自然な波なのです。

なぜ月経は「黙るべきもの」になったのか
月経について話すことが「不適切」「恥ずかしい」とされる社会では、生理に関する悩みや不調を相談すること自体が難しくなります。
その結果、
- 生理中に学校を休まざるを得ない
- 教育や将来の選択肢が狭まる
- 貧困やジェンダー格差が固定化される
といった問題が生まれます。
さらに、月経について語らない文化は、「女性の健康は後回しでよい」という無言のメッセージを社会に送るようなものです。
政治的・経済的に男性が優位な構造の中で、月経への偏見は、女性や多様なジェンダーの声をさらに見えにくくしてしまうのです。
月経を語ることは、誰のためのもの?
私たちは、ジェンダー・地域・年齢を超えた、包括的な月経の対話を提案します。
月経は「女性だけの問題」ではありません。 誰が月経を経験しているのかを尊重し、すべての人が理解し、支える視点が必要です。
また、対話の中では次のような視点も欠かせません。
- 生理の貧困の解消
- 教育・医療資源が限られた地域への配慮
- 気候変動や人道危機下での月経ケア
- 更年期・閉経を含むライフサイクル全体の理解
こうした広い視野が、月経を「一時的な問題」ではなく、人生を通じた健康のテーマとして捉えることにつながります。

教育・政策・テクノロジーの役割
月経についてオープンに話せる社会をつくるには、教育・医療・政策の連携が不可欠です。
- 早期からの包括的な教育
- 医療現場での月経症状への理解とケア
- エビデンスに基づいた政策設計
- 公共キャンペーンによる知識と資源へのアクセス向上
これらは、誤解や偏見を正し、月経を「普通の健康の話題」として位置づける助けになります。
近年では、月経トラッカーや装着可能なデバイス、AIを活用した健康サポートなど、テクノロジーの進化も進んでいます。一方で、個人データのプライバシーや安全性といった倫理的課題にも目を向ける必要があります。
月経について話すことは、未来を変えること
月経は、常に存在してきたにもかかわらず、長く語られてこなかったテーマです。
今こそ沈黙を破り、偏った物語に疑問を投げかけ、誰もが安心して生きられる社会をつくる対話を始めるときです。
月経についてオープンに話すことは、安全・快適さ・尊厳をすべての人に保障するための、大切な一歩。
Hummingは、そんな対話の場をこれからも育てていきます。
親は子どもと「性」についてどう話せばいい?
年齢に合った、正直で安心できる対話のガイド

子どもに性の話をすることに、不安や戸惑いを感じる親はとても多いものです。
「まだ早いのでは?」「間違ったことを言ってしまったらどうしよう」「どこまで話すべき?」
こうした悩みは自然なものですが、年齢に合ったオープンな性の対話は、子どもの将来にとってとても重要です。
おすすめ記事:「親との関係」は、私たちのパートナー選びにどう影響するのか?
研究では、誠実で発達段階に合った性教育を受けた子どもは、大人になってからも 健全な人間関係・自己肯定感・親との信頼関係 を築きやすいことがわかっています。
シカゴで活動するセックスセラピストとして、私は「自信があり、情報に基づいて判断でき、心の健康を大切にできる子どもを育てたい」と願う多くの親御さんをサポートしてきました。
性の話は、1回きりの「大きな話し合い」である必要はありません。
日常の中で少しずつ重ねていく対話でいいのです。
この記事では、親がよく抱く疑問――
「いつ始める?」「何をどう話す?」「不安なときは?」――にお答えします。
いつから性の話を始めるべき?
性の話は、ある日突然「さあ話そう」と切り出すものではありません。
むしろ、もっと静かで、もっと日常的なところから始まっています。
たとえば、
- 自分の身体に名前があること
- 触られたくないときに「いや」と言っていいこと
- 家族のかたちはひとつじゃないこと
こうしたことを伝えるだけでも、それは立派な性教育です。
性の話=性交渉の説明、ではありません。
「自分の身体をどう扱っていいか」「人との距離感をどう感じていいか」
その土台を育てることが、性について話すということなのだと思います。

答えがわからない質問をされたら?
子どもは、思いがけないタイミングで、思いがけない質問を投げかけてきます。
その瞬間、言葉に詰まることもあるでしょう。
でも、答えを知らない自分を責めなくていい。
「わからない」は、失敗ではありません。
「いい質問だね」
「一緒に考えてみようか」
そう言って立ち止まることは、子どもにとって“考えることを許される体験”になります。
完璧な説明よりも、誠実な姿勢のほうが、ずっと心に残ります。
性の話をすると、性行動が早まる?
これはよくある誤解です。
実際には、包括的な性教育を受けた子どもほど、より慎重で責任ある選択をする傾向があります。
研究によると:
- 性行動の開始が遅くなる
- 避妊の使用率が高まる
- 健全なパートナーシップを築きやすい
- 望まない妊娠のリスクが下がる
オープンな対話は「危険」ではなく、「安心と判断力」を育てます。
年齢に合った話し方とは?
性の話は一度きりではなく、成長に合わせて重ねていくものです。
年齢別の例:
幼児期
- 身体の名前
- 触れていい・よくないの感覚
- 同意と境界線
- 家族の多様性
学童期〜プレティーン
- 思春期と身体の変化
- 月経
- 健全な人間関係
- 性の多様性
- 妊娠・出産の基礎
- メディアリテラシー
ティーン
- 合意とコミュニケーション
- 安全なセックス
- 快感と尊重
- デジタル上の同意
- 暴力のない関係性

気まずい質問をされたときの対処法
正直に言えば、どれだけ準備しても、気まずさがゼロになることはありません。
でも、その戸惑いを隠す必要もない。
深呼吸して、少し間を置いて、「聞いてくれてありがとう」と伝えるだけでいい。
大人が落ち着いている姿は、 子どもにとって「この話題は危険じゃない」という合図になります。
同意(コンセント)と健全な関係の教え方
同意は、性の話以前から教えられます。
- ハグの前に聞く
- 「NO」を尊重する
- 「あなたの身体はあなたのもの」
こうした日常の積み重ねが、子どもの安全と主体性を守ります。
ティーンには、積極的な同意やデジタル上の同意についても話していきましょう。
友だちやネットから誤った情報を得ていたら?
今の子どもたちは、早い段階で性情報に触れます。
大切なのは、叱ることではなく、
- 何を見聞きしたかを聞く
- 判断せずに耳を傾ける
- 正しい情報を穏やかに伝える
ことです。
価値観を伝えつつ、恥を与えないには?
家族の価値観は伝えていいものです。
ただし、否定や恐れからではなく、思いやりから伝えましょう。
- 「私たちはこう考えている」
- 「これは私の大切にしている価値」
というメッセージが効果的です。

子どもから聞かれるのを待つべき?
多くの子どもは、親の反応を見て質問を控えます。
だからこそ、親から自然に話題を出すことが大切です。
本や映画、日常の出来事がきっかけになります。
親の性生活について聞かれたら?
好奇心からの質問です。
境界線を教えるチャンスでもあります。
例:
「それは大人のプライベートなことだけど、愛や尊重については話せるよ」
誠実さと適切な距離感の両立が大切です。
正解よりも、関係性を
性の話に、完璧な言い回しはありません。
でも、話そうとする姿勢そのものが、 子どもにとっては何よりのメッセージになります。
間違えてもいい。
言い直してもいい。
沈黙があってもいい。
大切なのは、 「あなたの話を聞く準備がある」という姿勢。
それが、子どもが自分の身体や心を信頼できる未来につながっていくのだと思います。
—
【ハミングが届けるポジティブニュース】「清潔な服を着るだけで、人は変われる」元警官が走らせた一台のバスの物語

「洗濯について聞いてみて」 ある声が導いた新しい支援のかたち
ある声に導かれ、元警察官が始めた移動式ランドリー。ホームレスの人々に無料で洗濯サービスを提供し、清潔な衣服とともに自信も届けています。きれいな服を着ることが、次の一歩を踏み出す力になる――今回は、そんな温かい物語をご紹介します。
“神の声に導かれたと感じた元警察官ウェイド・ミリヤードさんは、ホームレスの人々が洗濯環境に困っている現実を知り、清潔な衣服と自信を届けるために移動式ランドリーを始める決意をしました。”
アメリカのメリーランド州の警察署に勤務していたウェイド・ミリヤードさん(45歳)。ある日、路上生活者が暮らす一角での家族間のもめごとに対応していたとき、「どこからともなく」声が聞こえてきたといいます。それは神からの声だと彼は信じており、その声は「洗濯について聞いてみて」と彼に語りかけました。
おすすめ記事:【ハミングが届けるポジティブニュース】 世界の都市が命を取り戻す物語──100年ぶりによみがえるシカゴ川
ミリヤードさんはその声に従い、対応していたホームレスのカップルに洗濯をどうしているのか尋ねます。すると、二人は近くの小川で洗濯をしているというのです。この出来事が、彼の人生の新たな使命を開く扉となりました。
一杯のコーヒーから始まった、尊厳を取り戻すための洗濯サービス
警察官として働く中で、ミリヤードさんはホームレスの人々と接する機会が多くありました。あるとき、彼はホームレスの男性をコーヒーに誘いました。その男性は、洗濯する場所がないため、衣服も清潔でなく就職面接に行けないと打ち明けました。「これこそ自分がやるべきことだ」とミリヤードさんは強く感じたといいます。
警察官として退職した後の人生について考えていた彼にとって、これが決定的な転機となりました。自分の貯金と寄付金を集め、彼は使われなくなった警察のバスを改造し、移動式ランドリーを作り上げることを決めます。
“元警察官のミリヤードさんは、ホームレスの男性が「洗濯できないため就職面接に行けない」と打ち明けたことをきっかけに、自分にできる支援を見出し、退職後に貯金と寄付金で警察バスを改造した移動式ランドリーを立ち上げる決意をしました。”
2025年1月に警察を退職したミリヤードさんは、数ヶ月の準備期間を経て、念願の移動式ランドリーサービス「フレッシュ・ステップ・ランドリー」を立ち上げました。この元警察バスには、3台の洗濯機と3台の乾燥機が設置されています。
このサービスの使命はきわめて明確。住む場所のない人々に無料で、アクセスしやすく、衛生的な洗濯サービスを提供することで、彼らの自信を取り戻すこと。ミリヤードさんは一円も受け取らず、ただ人々の生活を少しでも良くしたいという思いで活動しています。
一台のバスから、明日へ。支援は今も走り続けている
サービスを利用している男性は、「清潔でいると、気分が良くなる。自分自身に少し誇りを持てるようになる」と語ります。ミリヤードさんも、「ほんの少しでも彼らを後押しできればいい。清潔な服が少しでも助けになるなら、私の使命は果たされたことになる」と話します。
サービス開始からわずか数週間で、このランドリーサービスは900キロ以上の服を洗濯してきました。多くの人々が、就職面接や医療機関の予約、あるいは日常生活を送るための自信を取り戻しています。
“利用者は清潔な服が気分や自尊心を高めてくれると語り、ミリヤードさんも小さな支援で人々の背中を押したいと話しています。”
ミリヤードさんの次の目標は、2台目のバスを導入し、サービスを受けられる人々を倍にすること。特に、安定した住居のない学生たちのための専用バスを用意したいと考えています。
多くの人々がミリヤードさんに連絡を取り、他の場所でもサービスを始めてほしいと依頼しています。現在は1台のバスしかありませんが、彼は着実に活動範囲を広げていく計画です。
「どこからともなく」聞こえたあの声は、今日も一台のバスを動かし続けています。
参考記事:https://www.goodnewsnetwork.org/retired-cop-now-drives-mobile-laundry-van-to-wash-clothes-for-the-homeless/
【映画レビュー】ブラック・バービーが教えてくれる「表現」の力
おもちゃがつくる美の基準、人種的アイデンティティ、そして子どもの頃に「自分を見る」ことが一生に与える影響
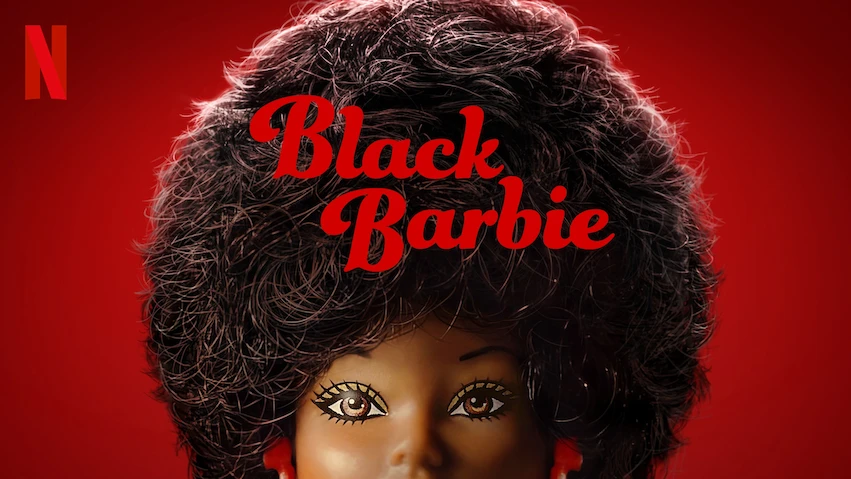
鏡に映る自分を見て、理由ははっきりしないけれど、どこか居心地の悪さを感じたことはありませんか。
女性であれば、その感覚に覚えがある人も多いかもしれません。
では、その違和感を「肌の色」や「生まれ持った人種」が理由で感じたことはありますか。
おすすめ記事:【映画レビュー】ドキュメンタリー『Daughters』を観て、触れること、愛すること——父と娘の再会がもたらす癒し
日本のように比較的均質な社会では、想像しにくい経験かもしれません。けれど「人種のるつぼ」と呼ばれるアメリカでは、人種は否応なくアイデンティティの一部になります。望むかどうかに関わらず、常に意識させられるものです。それは、自分自身をどう見るか、他人からどう見られるか、日常の中でどれだけ安心して存在できるかにまで影響します。
この視点は、身近に感じられないかもしれません。それでもどうか、評価や判断のためではなく、「聴く」つもりで読み進めてみてください。自分の住む場所でありながら、どこか少しだけ世界とズレて浮いているような感覚——その意味に、そっと寄り添ってみてほしいのです。
「人形」が映し出す、見えなかった現実
Netflixのドキュメンタリー『ブラック・バービー』は、このテーマをとても身近な存在——一体の「人形」を通して描いています。
アメリカでは、何世代にもわたって黒人の人々が「見られること」「価値を認められること」「尊厳をもって扱われること」を求めて闘ってきました。その経験は非常に深く、複雑で、私が代弁できるものではありません。私は黒人としてアメリカに生きているわけではないからです。
それでも、「自分の見た目が、世界が決めた“美”の基準に当てはまらない」と気づいたときの、静かな痛みなら、少しはわかる気がします。
『ブラック・バービー』の中心にあるのは、黒人女性たちの物語です。評価されることなく、それでも前に進み続け、次の世代の黒人の女の子たちが、自分自身を誇りをもって映し出せる未来をつくってきた女性たちの物語。そこには、道がなかった場所に道をつくる、という営みがあります。
“子どものおもちゃである人形が長らく白人像に偏ってきたことで、多様な背景を持つ子どもたちが「普通」や「美しさ」の基準から排除され、自分は平均ではないという無言のメッセージを刷り込まれてきた問題を指摘しています。”
人形が子供のおもちゃとして家庭に普及し始めた頃、選択肢はほぼ一つしかありませんでした。長い金髪に青い目の女の子です。長いあいだ、濃い肌の色をした人形は、そもそも存在しなかったり、意図的に排除されてきました。その結果、あらゆる背景を持つ子どもたちが、「これが普通」「これが愛される姿」「これが美しい」という、ひとつの価値観だけを吸収して育ってきたのです。
「存在しない」ということは、確実に心に跡を残します。自分に似た存在を一度も目にしないまま育つと、そのメッセージはとても静かですが、執拗です。
——あなたは“平均の姿”ではない。

その感覚は、時間をかけて、子どもの時のあなたの自分の価値の捉え方に影響を与えます。
この現象は、精神科医ケネス・クラーク博士の有名な研究にも表れています。博士は黒人の子どもたちに、白い人形と茶色い人形を見せ、どちらを好むかを尋ねました。多くの子どもが白い人形を選び、「良い」「きれい」といった肯定的な言葉を結びつけ、茶色い人形には否定的なイメージを与えました。これは「人種的拒絶」と呼ばれています。
子どもたちが反応していたのは、自分自身ではなく、すでに学んでしまった「世界の読み方」でした。まだ幼い年齢で、多くの黒人の女の子は、「自分は美しい存在として見られるものではない」という考えを、知らず知らずのうちに吸収していたのです。
だからこそ、表現は重要なのです。
大きな声で、派手にではなく。
静かに、継続的に、丁寧に。
人生のいちばん最初の瞬間から。
見えなかった私たちが、見える存在になるまで
映画の中で、監督・脚本のラゲリア・デイヴィスは、繰り返しひとつの問いに立ち返ります。
——なぜ、こんなにも小さく、取るに足らないように見えるプラスチックの人形が、子どもたちの自己認識に大きな影響を与えるのか。
私自身も、同じ問いを抱きました。私たちは、人形を「力のある存在」だとは思っていません。でもこの物語の本質は、表現が、気づかぬうちにいかに私たちの中に入り込むか、ということなのです。
デイヴィスと同じように、私も子どもの頃、人形遊びに強い関心はありませんでした。バービーは何体か持っていましたが、大切にしていたわけではありません。遊ぶときは髪を切ったり、マニキュアで体を塗ったりして、どちらかというと「自分を映す存在」ではなく、単なる物として扱っていました。愛着はなかったのです。
けれど、映画に登場する女性たちにとって、バービーはただのおもちゃではありませんでした。それは幼少期の文化的な存在であり、自分自身や未来を想像する手がかりでした。だからこそ、初めて黒人のバービーを目にした瞬間、それは単なる嬉しさではなく、感情が溢れる体験だったのです。
——「やっと、見てもらえた」。
“アジア系アメリカ人として育つ中で、メディアに自分に似た存在や多様な役割がほとんど描かれず、その欠如を疑うこともなく「白人が中心」という価値観を無意識に内面化し、やがて自分自身を肯定しきれない静かな傷を抱えるようになった経験を語っています。”
その感覚——認識されること、安堵すること——は、私自身にもよくわかります。
アジア系アメリカ人として育った私は、テレビや映画で自分に似た女の子を見ることがほとんどありませんでした。たまに登場しても、役柄は限られていました。武道家、着物やチャイナドレスを着た女性、静かで頭のいい「オタク」的な脇役。そこに「私」はいませんでした。
子どもの頃は、人種的アイデンティティや表現の欠如がもたらす影響を言葉で理解することはできません。ただ、目の前の映像をそのまま現実として受け取ります。私は「なぜアジア系の女の子が画面にいないのか」を疑いませんでした。「画面にいるべきなのは白人なのだ」と、無意識に受け入れていたのです。
その静かな認識は、やがて内側に向かいます。鏡を見たとき、外の世界に映し返される自分が見つからないと、心のどこかにひびが入ります。
違和感は憧れに変わり、憧れは比較に変わり、比較はやがて、自分自身への嫌悪に変わっていきます。映画の中で多くの女性が、「黒さ」が“売れない”“好まれない”ものとして扱われてきたことへの苦しさを語っています。私もまた、違う形で同じ思いを抱いていました。
目はもっと大きければよかった。
髪はもっとツヤがあって、
瞳の色はもっと明るければよかった。
丸い鼻も、平たい顔も嫌いでした。
「誰か別の人」になりたかった。

だからこそ、すべての子どもに向けた人形が必要なのです。
自分を映す存在を見ることは、こう語りかけてくれます。
あなたはここにいていい。
捨てられる存在ではない。
例外ではない。
自分の特徴が「浮いた存在」ではなく、ただ他の誰かと並んで存在するものになったとき、心の中で何かがほどけていきます。そして自然と、静かに理解するのです。
——私も、美しい。
ブラック・バービー誕生の裏側にいた人
この映画をラゲリアが制作しようと思った理由のひとつには、彼女の叔母であるビューラ・メイ・ミッチェルの存在があります。ビューラは、バービーを生み出した会社・マテル社で働いた初めての黒人社員でした。
ビューラが育ったのは、アメリカの公民権運動のまっただ中。人種隔離が日常のあらゆる場面に影を落としていた時代です。映画の中で彼女は、「黒人の人形で遊ぶ」という発想自体が頭に浮かばなかったと語ります。欲しくなかったからではなく、選択肢として存在していなかったからです。
やがてビューラは、バービーの生みの親であるルース・ハンドラーと仕事を共にするようになり、二人は友情を築いていきます。その関係性の中で、少しずつ、しかし確実に、ある問いが浮かび上がってきました。
——黒人の人形をつくる、ということはどういう意味を持つのか。
当時、その問いを口にすること自体が革新的でした。会話が始まったという事実そのものが、マテル社の中でビューラが持っていた静かな影響力を物語っています。
1960年代、マテル社は初めての黒人の人形「クリスティ」を発表します。しかし彼女はバービーではありませんでした。バービーの“親友”という位置づけです。確かに前進ではありましたが、その歩みは限定的でした。実際に「黒人のバービー」が誕生するまでには、さらに20年の歳月が必要でした。
見られることの責任、開かれる扉
例外として存在するということは、
常に「他よりも抜きんでていること」を求められるということでもあります。
映画には、さまざまな分野で活躍する黒人女性たちが登場します。アーティスト、アスリート、クリエイター——その多くが、それぞれの分野で「初めて成功した黒人女性」でした。その肩書きは誇らしい一方で、重くのしかかるものでもあります。
「最初の一人」であることは、失敗が許されないというプレッシャーと隣り合わせです。ひとつの間違いが、自分個人ではなく、「後に続くすべての人」を代表してしまうかもしれない。白人でない多くの人にとって、失敗していいという余裕はほとんどありません。
それでも、映画に登場する女性たちはその責任から目を背けません。なぜなら、その重みがどれほど重要かを知っているからです。

「黒い身体で、あの舞台に立つこと自体がプロテストなんです。
自分を含んでいない歴史、
自分のためにつくられていない場所の一部として、そこに立つこと」
そう語るのは、アメリカン・バレエ・シアターで黒人女性として初めてプリンシパル・ダンサーとなったミスティ・コープランドです。彼女は、自分の存在と成功が、次の世代の黒人バレエダンサーたちへの「メッセージ」になることを知っています。
——ここに、あなたの居場所はある。
舞台の上でミスティが成し遂げたことを、ビューラは何十年も前に舞台裏で成し遂げていました。マテル社に自分の居場所を築いたことで、彼女は他の黒人クリエイターたちへの扉を開いたのです。
その後に続いたのが、マテル社初の黒人デザイナー、キティ・ブラック・パーキンスでした。キティは、初めて「本当の意味での黒人バービー」を生み出します。クリスティが単に肌の色を変えただけの存在だったのに対し、キティは顔立ちや表情にまで心を配り、黒人女性をきちんと映し出した人形を実現させました。
それは、名前だけの実現ではありませんでした。
配慮とリスペクトを伴った表現でした。
そしてこの物語が何度も立ち返るのは、
そこにいることと、本当に見られていることの違いです。
進んだ時間と、動かなかった針
年月を経て、ブラック・バービーは何度もアップデートされてきました。それでも、問いは残ります。ビューラがマテル社に入社したあの頃から、私たちの認識は本当に変わったのでしょうか。
その問いを探るために、ラゲリアは14歳の姪・ケイデンをカメラの前に招き、率直な質問を投げかけます。
——ブラック・バービーが主役の単独映画は、実現すると思う?
ケイデンは、少し気まずそうに笑ってから、正直に答えます。
「難しいと思う。だって、私たちは“白人が多数派の世界”に生きているから」
隣に座っていた母親は言葉を失い、静かにこう漏らします。
——娘がこんなふうに感じていたなんて、知らなかった。
この瞬間が示しているのは、時間は何キロメートルも進んだのに、進歩の針はほんの一センチしか動いていないという現実です。
“多様な人形を用いた実験から、現代の子どもたちは美しさを単純に人種で判断しない一方で、見た目によって扱われ方が変わる現実や人種差別をすでに理解しており、本来無邪気でいられるはずの年齢から、不平等な世界で生き抜くための「気をつけ方」を学んでいることが示されています。”
映画の中では、アミラ・サーフィア博士が、ケネス・クラーク博士の研究に着想を得た実験を行います。さまざまな人種的な背景を持つ子どもたちに、多様なバービー人形を見せ、同じような質問を投げかけました。そこで浮かび上がったのは、希望と同時に、見過ごせない現実でした。
現代の子どもたちは、「美しさ」を人種そのもので判断しているわけではありません。彼らは髪型や服、靴といった要素に目を向けます。その一方で、「人種差別」という概念は理解しています。文化や民族、宗教の違いを感じ取り、そして何より、「見た目によって扱われ方が変わる」という事実を知っているのです。
本来なら、ただ子どもでいられるはずの年齢で、多くの子どもたちはすでに「気をつけなければならない世界」を学び始めています。言葉にされないルールを読み取りながら、生き方を調整することを覚えていく。
それは、安全や居場所、受け入れられるかどうかが、決して平等ではない世界で生きるための術でもあります。
だからこそ、私たちがまだ取り組むべき仕事は残っています。
それは、より多くの人形をつくること、より多くのバリエーションを用意することだけではありません。
子どもたちが、こんなにも早く「身を守る方法」を学ばなくていい世界をつくることなのです。
次の世代へ映し返すもの
進歩には時間がかかります。
飛び越えたり、駆け抜けたりはできません。
一歩ずつ、ゆっくり進み、ときには前に進んでいると思った矢先に、後戻りすることもあります。
それでも、歩みを止める理由にはなりません。
マテル社のダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン部門責任者であるメイソン・ウィリアムズは、こう語ります。
「自分が“なれる存在”を、見たことがなければ、人はそれを想像できない」
マテルは、世代を超えてアメリカの文化に深く根づいてきた存在です。一見すると小さな存在——一体の人形——であっても、家庭の日常の中に入り込むからこそ、長く、深い影響を残します。
おもちゃは、子どもにとって世界への最初の窓です。だからこそ、マテルのような企業には、「何を映しだすのか」を意識的に選ぶ責任があります。

アメリカでは、人種や差別といった重たいテーマを企業が扱うことに、必ず反発があります。それでも、このメッセージを発信し続けることには意味があります。それは、これまで語られてこなかった経験が、「存在していいもの」として認められるということだからです。
こうした機会がなければ、多くの人は、有色人種が日々背負っている積み重なる痛みに触れることすらありません。
私たちは同情を求めているのではありません。
理解されること、そしてつながることを求めているのです。
ブラック・バービーが残した本当の意味
映画の終盤、マテル社でインクルーシビティの土台を築いてきた黒人女性たちが、並んで座り、昔を懐かしそうに語り合う場面があります。その姿を見ていると、彼女たち自身が、彼女たちの手で生み出されたブラック・バービーと重なって見えてきます。
ある人にとって、バービーはただのおもちゃかもしれません。
けれど多くの女性にとって、バービーは美しさ、知性、自信、そして可能性の象徴でした。
それらは、この映画に登場する女性たちが体現してきた資質であり、また、日々社会の中で居場所を切り拓いているすべての有色人種の女性たちが持つものでもあります。
私たちは、人種だけで定義される存在ではありません。
私たちは多層的で、複雑で、完全に人間的な存在です。
もし、肌の色や背景によって扱いが変わるかどうかを考えたことがないなら、あなたは「人格そのもの」で判断される世界を知っているということです。その当たり前の公平さ——ありのままの自分として見られること——それこそが、これらの女性たちが目指してきた未来でした。
そしてそれは、次の世代に手渡したいと願った世界でもあるのです。
公式サイト:https://www.blackbarbiefilm.com/
トレーラー:https://youtu.be/T0nwa0sLrhc?si=5ukpjCySEoaFnSvM
30代のキャリア迷子、意地でもクォーターライフクライシスを泳ぎ切る

「クォーターライフクライシス」という言葉を目にしたことがあるでしょうか?
私は最近知った概念なんですが、どうやらざっくり言うと30代前後に漠然とした不安を感じる現象らしいのです。
…うん、思い当たる節がありすぎる。
人生のあらゆる面において、”なんとなく不安”がありすぎる。
そして、私の場合は特に、キャリアについてモヤモヤすることが多く(というか基本常に)、何をやってもどこかしっくりこなくて、ずっと彷徨い続けています。
漠然と「レールから外れた」とか「ドロップアウトしちゃったな」という感覚が、猛烈に襲い掛かってくるというか、いつまでも「ちゃんとした大人」になれていない自分にずっと嫌気が差している感じがすごいんですよね。
おすすめ記事:「本当の自分」が分からない?迷ったときに思い出したい考え方
ゆるふわすぎる職歴がコンプレックス
30代前半にいる私。
周りの「キャリア」を見渡してみると、なんだかカッコイイ大人がたくさんいます。
そろそろいい役職についていたり、自分で何かプロジェクトを立ち上げて大きな実績をつくっていたり、あるいは部下を何人か束ねていたり。
かたや私は、新卒で入った会社は3年程度でうつ退職、その後はフリーランスライターをかじってみたり、1年弱派遣社員として事務員をしてみたり、まーふわふわ漂流している。
“友人の会社で正社員として働いてはいるものの、3年経っても手応えや強いやりがいを感じられず、「このままでいいのか」「自分に合う別の働き方があるのでは」と悩み続けている心境のまとめです。”
そして、最終的に漂着したのは友人のベンチャー企業で、会社という雰囲気が皆無な中で、ゆるゆると働いています。
一応、フルタイム勤務で扱いとしては正社員ですが、友だちの会社というのもあってか、世間一般のいわゆる「普通の正社員」とは違う気がしています。
しかもここでも、もう働き始めて3年は経つのに、未だに何かがしっくりきていません。
環境的にはとても気楽だけど、かといってバリバリやりがいを感じているわけではないし、会社に何か突出した推しポイントがあるわけでもない、でもとりあえずこの場にとどまっている、そんな感覚です。
「今の時代、なんかまだ知らない働き方があるのでは…?」とか「やっぱりフリーランスが性に合う気がするんだよな…」と、仕事の帰り道に、眉間にシワを寄せながら悶々と考える日も多々あります。
でも、ここまでの職歴も十分ふわふわしているのに、心の中ではさらに彷徨い続けているなんて、どれだけゆるふわ系職歴を重ねれば気が済むんだと、そういう自分がまた嫌にもなってくるわけです。

いつまでも子どもみたいなわがままを言ってるようで、胸を張れないんですよね。
適当に歩んできただけのような感じがして、この職歴にちょっとコンプレックスがある。
勉強を頑張って、親にお金出してもらって県外にまで出て、それなりの大学に入ったのに、外国語学部でいろんな言語・文化に触れたのに、その学歴を活かしたキャリアは今までのところほとんどありません。
そういう引け目もあってのコンプレックスなのかも。
かと言って、じゃあ周りのみんなと同じよう、いわゆる普通の会社できっちりしっかり働いたり、社内政治も上手く渡り歩くみたいなことも、今さらできる気がしません。
「あーほんと、どうしたいんだろう私は」
そう漠然と、焦りは募る一方。
「何者でもない」現状が焦燥感を煽る
さらに追い打ちをかけるのが、何者にもなれていない感覚です。
周りを見れば、商社だの銀行だの業界がはっきりしていたり、システムを作ってるとか、営業で契約をもぎ取りまくってるとか、マーケを任されてるとか、採用担当してるとか、やっている仕事が明確な人がほとんどです。
自分の役割や界隈を、おおまかにでも「一言」で言い表せる。
「わたくし、こういう者といいます。こういうことをしています」と、名刺を出されればなんとなくイメージがつく。
かたや私は、業種も職種も一言では言い表せません。
商品企画もすれば、e-ラーニングもやるし、YouTube動画を作ったりもするし、直近ではヘルスケア系の事業を立ち上げているところで、ベンチャーの名に恥じなさすぎるくらい、事業のジャンルがバラバラです。
“語学を学んでいた学生時代には想像もしなかった実務や制度に向き合いながら、幅広く何でもこなしてはいるものの、専門性に自信が持てず、「結局は何者でもないのでは」と感じている葛藤を描いています。”
しかも超少人数の会社なので、全員が企画もマーケも販促も、法務も労務も会計もCSも…etc.ありとあらゆる業務を担っています。
外国語学部に入学したあの時の私は、10年後に、契約書を読み込んだり、税制の仕組みを一生懸命ググって理解しようとする日がくるなんて、これっぽっちも想像してませんでした。
でも、いろんなことをやっているからといって、それぞれのスペシャリストという訳でもありません。
正直、全部付け焼き刃。
分からないなら分からないなりに調べて、それらしい答えを導いて、オフロードをとにかくパワーで強引に進んでいるだけです。
よく言えば、なんでもできるオールラウンダーだけど、本当は「何者でもない」のが実態なんですよね。

「わたくし、こういう者といいます。こういうことをしています」という名刺が作れない、一言でご挨拶ができない。
久々に再会した友だちとの会話であるあるな「仕事、何してるの?」という何気ない質問も、私にとってはまるで面接の受け答えかのよう。
「どうやったら上手く説明できるんだろう…」と手に汗握ってしまいます。
整備されたレールじゃなくても、道は道
そんな感じでキャリアに大コンプレックスを抱えまくりな私ですが、最近ちょっとだけ違う捉え方ができるようになってきました。
人が増えたり社内の環境や体制が少し変わったことで、多少気持ちに余裕がでてきたのかもしれません。
相変わらずオフロードを強引に進み、ガタゴト揺られながらも、ぼんやり遠くの景色を眺めるように、自分のキャリアについても一歩下がって客観的に見えてきた感覚があります。
そして、ちゃんとしたレールを諦めたことで、代わりに得られたものがたくさんあることにも、気づきはじめました。
“多様な生き方や働き方があると実感し、その中から他人任せではなく、自分の意思でこれまでのキャリアや選択を積み重ねてきたのだと気づいたことが大きな変化だと述べています。”
なかでも大きいのは、世の中には多種多様な道があると実感できたこと、そして、その中からちゃんと自分の意思で道を選べるようになったこと。
そもそも、ゆるふわだろうが何だろうが、ここまでの職歴は全部、自分で選びとってきたものなんですよね。
だって、うつで休職した後もどうにか療養して、元のレールに戻る選択肢だってあったんです。
同じ会社でなくても、別の会社でいわゆる「普通の会社員」に戻るチャンスだって、いくらでもあったはずです。
でも当時の私は「いくらレールが整備されてても、また車体を軋ませて走ることになったら嫌」だと、自分のために逃げることを決意しました。
フリーランスや派遣社員も、ただ会社を変えるだけでは根本が変わる気がしないと思ったから、自分に合う働き方を知るためにとった選択肢でした。
自分でやりたいと思って、自分のタイミングで始めて、辞め時も自分で下した。
今のベンチャーだって、何がどうなるか想像なんてまったくできなかった(今もこの先どうなるかあんまり見えてない)けれど、そろそろ心も癒えてきてエンジンをかけ直してみたい時期だったから、一つの経験だと自分で入ることを決めた。
学生の頃のように、目の前にお膳立てされたレールに無思考で乗っかるのではなく、あっちかな?こっちかな?と、自分の頭で考え、胸に手をあて、心の声に耳を傾け、自分の足で進むようになった気がします。
今の自分は、全て自分の選択でできている。
そういうことが、素直に飲み込めるようになってきた気がします。
だから、不満や不安が尽きない状況も、少しずつ「まあ、自分で選んだ結果だし」とか、「気に入らないなら、また違う道を探せばいいんだよ」と思えるようになっています。
あちこち漂流したからこそ、どこへ行ってもなんとかなること、人は簡単には野垂れ死なないから大丈夫だということを、身をもって知ったから。

ちょっと図太くなってきたのかも。
……いや、やっぱりこれも、ベンチャーのオフロードで揉まれたおかげかもしれません。
とりあえずあそこにたどり着くために、どの道でもいいから一旦進んでみる。
岩にぶつかったなら、今度は迂回路を探せばいい。
それだけの話、それの繰り返し。
そういうことを刷り込まれたので、自分の人生においても、同じように考えたらいいんだと思えるようになってきました。
足元の石ころばかり必死に見つめてぎゅーっと狭めていた視界から、ふわっと顔を上げた感じ。
整備されたレールだろうが、オフロードだろうが、道は道。
どんな道でも、ちゃんとどこかにはたどり着くから大丈夫。
そう思えるようになってから、いつまでもちゃんとした大人になれない後ろめたさも、ゆるふわすぎる職歴へのコンプレックスも、少しずつ和らいでいるような気がします。
なんだかいつの間にか、メンタル的にかなりパワーとスタミナがついたみたい。
だとしたら今度は、潮目に身を任せる漂流型から、自分でしっかりオールを握る航海型にもシフトできるかな。
なんならクォーターライフクライシスだって、スイスイ泳ぎ切れてしまうんじゃないかな。
最近の仕事帰りは、そんなふうに少しご機嫌モードが増え、眉間のしわもだいぶ浅くなってきたところです。
今ある家で幸せに暮らす方法|引っ越さなくても心地よさはつくれる

「この家でいいのかな?」と感じたことはありませんか
子どもたちが寝静まった夜、私は床がきしむ場所を避けながら家の中を歩きます。
食器を片づけ、洗濯物をたたみ、キッチンテーブルにキャンドルを灯す。棚の上に置かれていたおもちゃを、そっと元の場所へ戻す——それが一日の終わりの小さな儀式です。
この家に住み始めたのは、結婚前のことでした。
気づけば家族は増え、暮らしは変わり、今では「少し手狭かもしれない」と感じることもあります。それでも、この家にはこれまでの時間と記憶が詰まっています。
おすすめ記事:「モノを手放したら、人生が動き出した。」ミニマリストが実践する、モノ・コト・思考のシンプル化戦略とは【ミニマルなライフを発信するあさこさんインタビュー】
家は、休み、集い、考え、また立ち直る場所。
だからこそ「もっと理想の家だったら…」と思うのは自然なことです。けれど、引っ越しや大きな変化が難しいときでも、今ある家で心地よく暮らすことは可能です。
ここでは、今の住まいで幸せを感じるための実践的なヒントをご紹介します。
家は「人生がいちばん静かに流れる場所」
家は、休む場所であり、集う場所であり、
何度も立て直し、夢を見る場所。
賃貸か持ち家か、広さや築年数に関わらず、
住まいは私たちの感情やリズムに深く影響します。
「もっとこうだったら」
「次はこんな家に住みたい」
そう願う気持ちは自然なこと。
でも、すぐに環境を変えられない時もあります。
そんなとき、暮らしを大きく変えるのではなく、
今の家との関係を、少しだけ変えてみることはできるのかもしれません。
キッチンの一部を片付ける。
ベッド シーツを新しくする。
植物に水をあげる。
それだけで、
家の空気も、自分の呼吸も、少し整うから不思議です。

1. まずは「整える」ことから始める
どんなに理想の家でも、散らかっていれば心は落ち着きません。
片付けは地味に感じるかもしれませんが、幸福感を左右する大切な要素です。
お気に入りの飲み物を用意して、音楽やポッドキャストを流しながら、
ブランケットを整え、キッチンカウンターを少し片づける。
その時間自体を「心地よい行為」に変えてみましょう。
2. 掃除は、気分を変えるいちばん確実な方法
床を拭き、掃除機をかけ、シーツを新しくするだけで、
家の空気は驚くほど変わります。
週末にまとめて掃除するのも、プロの力を借りるのもOK。
清潔さは、安心感と満足感をもたらします。
3. 必要なところだけ、賢くアップデート
すべてを新しくする必要はありません。
本当に使いにくくなったもの、役目を終えたものだけを見直しましょう。
収納用品や家具などは、地域の寄付団体や中古品のお店から入手するのもおすすめです。
長く使える良質なものを、少しずつ迎えることで、暮らしの質は確実に上がります。
4. 比較するのをやめる
SNSやインターネットは、刺激と同時に「比較」を生みます。
他人の家や暮らしを見て、今の住まいが物足りなく感じることもあるでしょう。
そんなときは、意識的に距離を置いてみてください。
満足感は、比べないことで戻ってきます。
5. 感謝できるポイントを書き出してみる
午後の光の入り方、
お気に入りの椅子、
思い出が残るベランダや庭。
どんな家にも「好きなところ」は必ずあります。
それを思い出し、味わうことが、心を今ここに戻してくれます。
6. 空間に「ムード」をつくる
花を一輪飾る。
植物を置く。
キャンドルを灯す。
音楽を流す。
理由はなくていい。
ここが、今のあなたの居場所だから。
幸せは「持つこと」より「向き合うこと」
家を大切にすることは、完璧を目指すことでも、所有を増やすことでもありません。
それは「今ここ」に意識を向けること。
家を整えることは、
自分自身を整えることにもつながっています。
静かな朝も、慌ただしい夕方も、
そのすべてを包み込む場所が、あなたの家。
今ある家に手をかけることは、
暮らしと心の両方を、少しずつやさしく整えていく行為なのです。
自然療法に関するおすすめ書籍5選|暮らしの中で“整える力”を育てるセルフケアガイド

忙しい毎日の中で、体調がゆらいだり、なんとなく不調が続いたりするとき。「できれば薬に頼りすぎず、まずは暮らしの中で整えたい」と感じる人も多いはずです。
そこで役立つのが自然療法(ナチュロパシー/ホリスティックケア) の考え方。食事・睡眠・ストレスケア・ハーブ・アロマなど、身体が本来持つ回復力をサポートするアプローチです。
自然療法(ナチュラルレメディ)とは?
自然療法(Natural Remedies/ナチュロパシー)とは、薬や対症療法だけに頼らず、身体が本来持っている「自己治癒力」を引き出すことを目的としたケアの総称です。
ハーブ、アロマテラピー、食事療法、休養、温熱、呼吸、ストレスケアなど、日常生活の延長線上にある方法を通じて、心と体のバランスを整えていきます。
自然療法の大きな特徴は、「症状そのもの」だけでなく、
- なぜその不調が起きているのか
- 生活リズムやストレス、食事、睡眠はどうか
- 心の状態が体に影響していないか
といった全体像(ホリスティックな視点)を見ることにあります。
なぜ自然療法がいま注目されているのか
現代社会では、忙しさや情報過多、慢性的なストレスによって、はっきりした病名はつかないけれど「なんとなく不調」を抱える人が増えています。
自然療法は、こうしたグレーゾーンの不調——疲れやすさ、眠りの浅さ、PMS、冷え、胃腸の不快感、気分の落ち込み——に対して、日常の中でできる選択肢を増やしてくれる存在です。
また、自然療法は「西洋医学の代わり」ではありません。
必要なときには医療を受けつつ、
・回復をサポートする
・再発を防ぐ
・自分の体を理解する
ための補完的なアプローチとして、多くの人に取り入れられています。
そんな自然療法を学ぶうえで心強い味方になるのが、信頼できる書籍です。ここからは、日本語で読めて、実践にもつなげやすい本を厳選して紹介します。
おすすめ自然療法書籍5選
1) 『ホリスティック家庭の医学療法』
こんな人に:一家に一冊の決定版が欲しい/幅広く知りたい
西洋医学・東洋医学・自然療法を横断的に扱い、症状別に「どんな選択肢があるか」を整理してくれる家庭向けの医学書。
セルフケアだけでなく、「この場合は医療機関へ」という視点も含まれており、自然療法を安心して学びたい人におすすめです。
2) 『自然治癒力を上げる ドイツ「緑の薬箱」』
こんな人に:薬に頼る前の選択肢を知りたい
ドイツの家庭が取り入れている自然療法をもとに、日常の不調への向き合い方を紹介。
「まず休む」「まず温める」「まず整える」という視点が、忙しい現代人のセルフケアの軸になります。
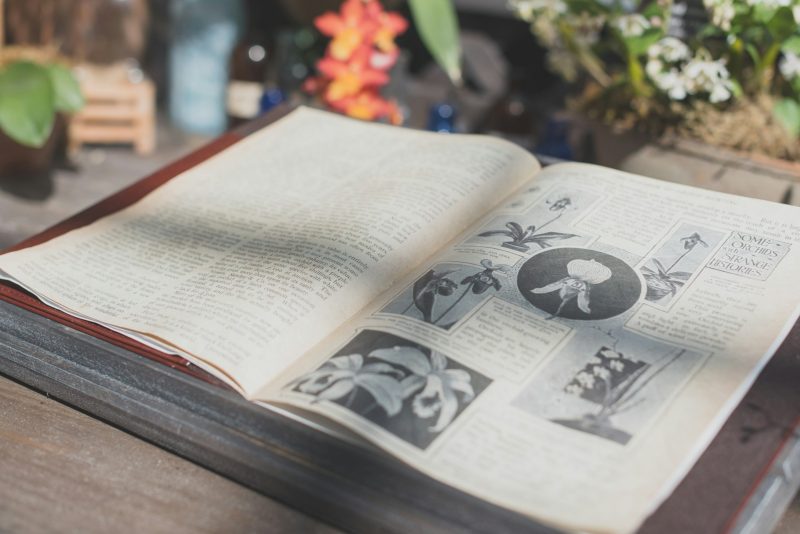
3) 『アロマテラピー外来が教える メディカルアロマ&ハーブのセルフケア事典』
こんな人に:アロマやハーブを実用的に使いたい
医療現場の視点から、アロマやハーブを安全に、現実的に使う方法を解説。
「おしゃれ」ではなく「体調管理」としてアロマを取り入れたい人に向いています。
4) 『緑の薬箱ハーブセラピー わが家でできるハーブ健康法』
こんな人に:家庭での“手当て”を大切にしたい
植物療法を、特別なものではなく暮らしの一部として紹介する一冊。
季節の不調や軽い症状に、ハーブで寄り添う視点が学べます。
5) 『ナチュロパシー マハトマ・ガンディーの自然療法』
こんな人に:自然療法の思想や哲学にも触れたい
テクニックだけでなく、「健康とは何か」「どう生きるか」という視点から自然療法を考えさせてくれる本。
自然療法を“生き方”として理解したい人におすすめです。
自然療法の本を、暮らしに活かすコツ
- まずは1冊を辞書として使う
- いきなり全部やらず、1つだけ試す
- 体調・気分・睡眠などをゆるく記録する
自然療法は、続けてこそ意味があります。
結論|自然療法は「自分を知る」ための入り口
自然療法のいちばんの価値は、「何を使うか」よりも、
自分の体と心の声を聞く習慣を育てることにあります。
疲れていることに気づく。
無理をしていたことを認める。
休むことを、自分に許す。
そうした小さな気づきの積み重ねが、結果的に不調を遠ざけ、回復力を高めていきます。
今回紹介した書籍は、自然療法を“特別なもの”ではなく、
日々の暮らしに根づいたセルフケアとして取り入れるための心強いガイドです。
薬が必要なときは医療の力を借りながら、
その手前にある「整える選択肢」として、自然療法をそっと生活に迎えてみてください。
それはきっと、あなた自身を大切に扱う第一歩になるはずです。
40代からのマネープラン:老後・キャリア・住居…40代女性が抱えるお金の不安を解消する実践ガイド【FPウーマン代表 大竹のり子さんインタビュー】

40代を迎え、将来の老後資金やキャリアの継続など、漠然としたお金の不安を感じていませんか?それは、キャリアやライフプランのターニングポイントに差し掛かり、未来の生活を真剣に見つめ始めたサインかもしれません。
今回は、女性のお金の悩みに寄り添い続けるFPウーマン代表の大竹のり子さんに、忙しい毎日でも無理なく続けられる、お金の健康によい習慣を伺いました。
インタビューから、お金の不安は、実は自分の価値観を棚卸しすることで解決できるかもしれない、という意外な真実も見えてきました。さらに、この悩みから解放されるための具体的な最初のステップについてもお聞きしました。
この機会に、未来の自分を支えるお金の土台を一緒に整えていきませんか。
ーー 40代女性が抱えるお金に関する典型的な悩みには、どのような共通点がありますか?
40代の方々からよく聞かれるお金の悩みとしては、以下の三つがあります。
- 老後資金への不安: 40代に限らないのですが、「老後のお金が思うように貯まらない」「いくら準備すればよいのか」を不安に思っている方はとても多いです。
- 健康とキャリアの継続性: 年齢的にも体の不調を感じ始め、「働けなくなったらどうしよう」という不安や、今の仕事をこの先もずっと続けられるかというキャリアへの懸念が膨らむ時期でもあります。
- 住居に関する決断: 独身の場合、シングルで生きていくための資金計画を真剣に考え始める時期。「家を買うべきか、賃貸のままいくべきか」という、大きな決断に直面して悩んでいる人が少なくありません。
ーー 買い物をする時に、それは「投資」なのか「浪費」なのか、どのように判断すれば良いでしょうか?
買い物を単なる支出で終わらせず、賢く生かすためには、「投資」「消費」「浪費」を区別してお金を使うことが不可欠です。判断基準は、支払った「価格」に対して、ご自身が感じる「価値」の大小です。
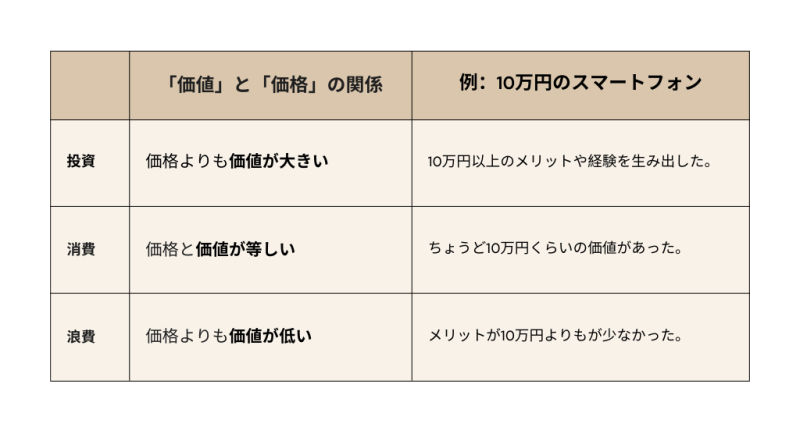
この「価値」は、それぞれの人が購入後にそれを「どう活用したか」「どう感じたか」によって決まります。
これは、スマートフォンのような特別な支出ではなく、日常の買い物であっても同じこと。例えば、安さにつられて大量に買いすぎ、食べきれずに無駄にしてしまった食材の購入費は、いくらお得な価格で買えたとしても「浪費」になりかねません。そのモノやサービスから実際に価格を上回るの恩恵を得られたかを振り返ることが重要です。
ーー 大竹さんのご著書を拝見し、「お土産を買わない」「バッグの中身は七つまでにする」といった提言が、お金の使い方と日々の生き方が密接に関係していると感じました。お金の意識につながるような良い習慣があれば教えてください。
私が個人的に意識していることとして、エンターテイメント(ライブや演劇など)に行く際、できるだけ良い席のチケットを買うということがあります。
もちろん何度も行く場合は別ですが、1回しか行かないであろう貴重な機会なのであれば、遠い席でよく見えなかったり、傍観者のように感じられてしまっては、どのみちお金を使うのに、その一度きりのチャンスの価値を最大限に味わうことができません。もちろん、お財布と相談にはなりますが、せっかく時間とお金を使って行くのであれば、可能な範囲でよい席を買って、その時間を思う存分に味わうことが、結果的に価格<価値という状態につながります。
「まずは安いところから…」というのが常に正解ではない、という考え方ですね。

ーー お金を増やすための「攻め」の資金配分ルール、「2:6:2ルール」について教えてください。
収入の使い道について、手取りの金額を以下の割合で振り分ける「2:6:2ルール」を推奨しています。
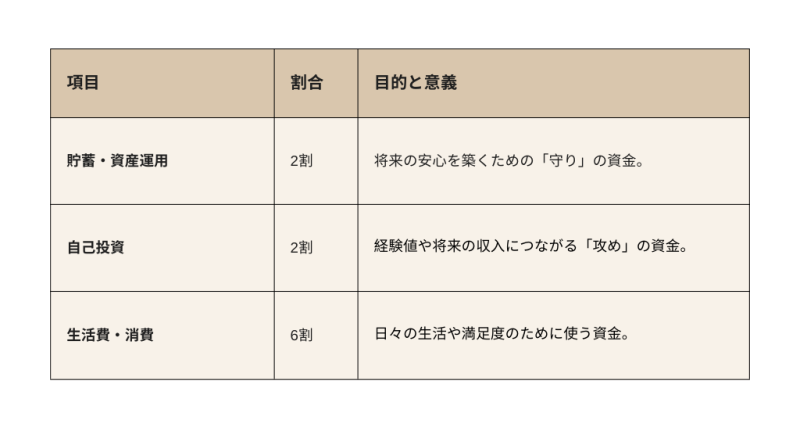
1. 貯蓄・資産運用(2割):守りの基盤
まず、給与が入ったらすぐに2割を「先取り貯蓄」します。「先取り貯蓄」は、貯まる人が共通して行っている王道の貯蓄方法です。この2割を継続すれば、約5年で年収分が貯まり、ライフプランの変化や想定外の事態など、いざという時の土台が築けます。
2. 自己投資(2割):成長への投資
残りの8割のうち、さらに2割を「自己投資」の枠として確保します。多くの人はつい「少しでも多く貯蓄しないと」と余ったお金を貯蓄に回しがちですが、自己投資は将来、より大きなリターン(価値)となって返ってくる可能性をもたらすもの。例えば5万円の出費でも、スキルアップやキャリア向上に自己投資をすれば、将来的にその数倍の収益を生み出します。この2割を意識的に設け、何かしらに使おうと考えることで、将来を見据えた建設的なお金の使い方ができるようになります。
3. 生活費(6割):日々の生活費
残りの6割は、日々の生活のために必要な支出です。貯蓄は別にできているので、この6割の中に収まりさえすれば、日々の生活費はどんな内訳でもOK。自分の価値観に合わせて配分を調整しながらやりくりしましょう。
ーー 将来のお金の不安を解消し、自分らしい人生を送るために、今すぐ始めるべき具体的な行動は何でしょうか?
不安を解消し、豊かな人生を送るための行動は、2つの側面から考えるべきです。
- 収入増につながる自己投資(攻め): キャリアアップやスキル習得など、将来の収入を増やすための自己投資を継続すること。
- 老後資金の準備(守り): NISAやiDeCoなど、公的な制度を賢く活用して老後資金の積立を始めること。
特に老後資金については、「不安の見える化」から始めましょう。「漠然と不安」な状態から抜け出すために、「〇年後までに〇〇万円の老後資金を貯める」と、時期と金額を具体化します。そして、シミュレーションツールを使って、その目標達成に必要な毎月の積立額を算出し、その金額を自動で積立されるように設定してしまうことです。
もちろん、毎月の家計からその金額が貯蓄に回せない場合には、固定費を削減したり、副業を検討したりと対策が必要です。でも、金額を確保でき、自動積立の設定を完了すれば、老後資金の悩みはいったん解決。1年に1回くらいはチェックして見直す必要がありますが、基本的には「忘れて」しまって大丈夫です。これにより、精神的にも安心が生まれ、意識も時間もを現在の生活や自己投資という「攻め」の分野に積極的に使えるようになります。
ーー ハミングはお金について「水のようなもので、貯めるだけでなく流れを重視、使うことでさらに豊かになる」と考えていますが、こういった考えについて、どう思われますか?
お金を水に例える考え方には共感します。お金を貯めてばかりで動かさないままだと水が淀んでしまうように、お金も本来の価値を発揮できません。消費であれ、投資であれ、お金を動かすことで循環が生まれ、価値を生見出していきます。
ただし、ただ使えば良い、というわけではありません。先ほどの投資・消費・浪費の考え方と照らし合わせて、自分にとって価値を最大化できるものに意識的にお金を使っていくことが大切です。
もうひとつお金を使うときに大切にしたい考え方が、「お金を使うことは社会に対する投票行動である」ということ。安さを追求して買うだけではなく、少し高くても想いが込められたよい製品・サービスを利用する、今の時代であれば、少しでも環境問題の抑制につながる製品を意識して買う、ビジョンに共感できる企業のサービスを利用するなど、意識を込めてお金を使うことが、お金をよい形で循環させる鍵と言えます。

大竹のり子
株式会社エフピーウーマン代表取締役
ファイナンシャルプランナー(CFP®認定者・1級FP技能士)
出版社の編集者を経て2005年4月に「エフピーウーマン」を設立。 雑誌、講演、テレビ・ラジオ出演などのほか『お金の教養スクール』を通じて女性がお金の知識をつけることの大切さを伝えている。『なぜかお金に困らない女性の習慣』(大和書房)、『ライフプランから考える お金の増やし方』(ナツメ社)など著書・監修書は70冊以上に及ぶ。
<女性ファイナンシャルプランナーによるお金の総合クリニック>
「エフピーウーマン」https://www.fpwoman.co.jp/
一方、財務省、金融広報中央委員会、東京証券取引所、不動産証券化協会をはじめとする公的機関で、金融や女性活躍の促進についての講演を行うほか、証券会社や銀行、大学等の各種金融機関・教育機関でも精力的に講演活動を行っている。
また、2005年から数年間にわたりエグゼクティブオフィサーとしてネット証券の立ち上げやサービス向上に関わったり、日本証券業協会で金融・証券教育広報委員を務めたりなど、幅広い立場から投資家育成やNISAの普及活動に携わっている。
『老後に破産しないお金の話』(成美堂出版)、『幸せになれるお金の使いかた』(ダイヤモンド社)、『ライフプランから考える お金の増やし方』(ナツメ社)などお金の分野での著書・監修書は約70冊に及ぶ。
野心を手放したら幸せになれる?ー「ハッスルカルチャー」が私たちから奪うもの

勝つために、私たちは何を犠牲にしてきたのか
もしあなたが、「110%出せ」「期待以上をやれ」と言われる職場で働いたことがあるなら、この感覚はきっと身に覚えがあるはずです。
すべては小さな犠牲から始まりました。
残業するためにハッピーアワーを断る。
ネットワーキングイベントに行くためにジムを休む。
ランチを抜いて、午後2時にプロテインバーをかじる。
おすすめ記事:仕事でストレスを感じたらやばい?原因や解消方法をご紹介!
「これさえ乗り越えれば」と、友人にも、パートナーにも、そして自分自身にも言い聞かせていました。
あと1時間。あと1週間。あと1か月だけ。
やがて犠牲は日常になり、気づけばもう誰からもハッピーアワーに誘われなくなっていました。半年間一度も行っていないジムの会費だけを払い続けて。
そして犠牲は、より深く、より痛みを伴うものへと変わっていきました。
野心に取り憑かれ、話題はいつもプロジェクト、プロセス、目標のことばかり。
質問もしない、話も聞かない。今ここにいない。約束されていない「未来」のために生きていました。
少しずつ、人生は薄くなっていく。
「勝つにはこれが必要なんだ」
ハッスルカルチャーとは何か
ハッスルカルチャーとは、常に生産的であること、努力し続けること、成果を出し続けることを美徳とする価値観です。
- 「110%出すのが当たり前」
- 「期待以上を出してこそ評価される」
- 「休む=怠けている」
こうしたメッセージは、職場やSNSを通じて私たちの中に深く刷り込まれています。
一見すると、向上心があり前向きな文化のように見えますが、問題はその代償です。
ハッスルカルチャーが幸福を奪う3つの理由
① 人生が「未来待ち」になる
ハッスルカルチャーのもとでは、幸福は常に「次の達成」の先にあります。
- このプロジェクトが終わったら
- この評価を取れたら
- この目標を達成したら
しかし実際には、達成の喜びは一時的で、すぐに次の課題が現れます。
結果として、今この瞬間を生きる感覚が失われていくのです。
② 人間関係や健康が「犠牲」になりやすい
最初は小さな妥協から始まります。
- 友人との時間を後回しにする
- 運動や食事を削る
- 休息を「無駄」と感じる
やがてそれが常態化し、気づいたときには、人生を支えてくれるものが周囲から消えているという状態に陥ります。
成功のためにすべてを捧げたはずなのに、その成功を一緒に喜んでくれる人がいない——
これはハッスルカルチャーがもたらす典型的な孤独です。
③ 野心が「恐れ」によって動かされる
ハッスルカルチャーの原動力は、しばしば「恐れ」です。
- 失敗したら価値がなくなるのではないか
- 立ち止まったら置いていかれるのではないか
- 成果を出し続けなければ認められないのではないか
この恐れに基づく野心は、決して満足することがありません。 一つ達成しても、すぐに「次」を要求します。
その結果、 成功しても満たされず、休んでも罪悪感が残るという状態が続いてしまいます。

「野心」そのものが悪いわけではない
ここで大切なのは、野心を完全に否定しないことです。
目標を持つことや、成長したいと願うこと自体は、人間にとって自然で健全な欲求です。
問題になるのは、自分を証明するためだけに追いかけているとき、そして幸福を犠牲にすることが前提になっているときです。
目標が人生を豊かにするのではなく、削るものになった瞬間、見直す必要があります。
なぜ「手放す」ことが必要なのか
ハッスルカルチャーから距離を取ることは、「諦め」や「後退」ではありません。
それはむしろ、 自分の時間・健康・人間関係を守るための意識的な選択です。
- すべてを完璧にやろうとしない
- 常に上を目指さなくてもいいと認める
- 成果よりプロセスを大切にする
- 役割や肩書きから自分の価値を切り離す
こうした「手放し」は、自分の人生を取り戻す行為でもあります。
「何もしない時間」にも価値がある
ハッスルカルチャーの世界では、人の価値は生産性と結びつけられがちです。
しかし本来、価値は成果や忙しさでは測れません。
休むこと、立ち止まること、やめることもまた、
自分を大切に扱っているという明確な意思表示です。
幸せは、頑張り続けた先だけにあるわけではない
ハッスルカルチャーは、 「もっとやれ」「まだ足りない」と私たちをせかします。
でも、幸せは常に前方にあるゴールではありません。
今ここで感じられる安心感やつながりの中にも存在します。
頑張ることをやめなくてもいい。 でも、すべてを賭けなくてもいい。
ときには足を止め、手放し、 「もう十分やっている」と自分に言ってあげること。
それは怠けではなく、 長く、健やかに生きるための知恵です。
慢性的な疲労のサインー「疲れている」と「消耗している」はどう違う?

なぜ私たちはこんなにも疲れているのか
仕事、家事、育児、人間関係。
現代社会は、常に動き続けることを前提に設計されています。その結果、多くの人がカフェインで無理やり乗り切り、慢性的な睡眠不足のまま日々を過ごしています。
おすすめ記事:気分転換で心をリセット|心を軽くする習慣づくりとおすすめアイテム
もちろん、忙しい生活の中で「疲れる」こと自体は珍しくありません。しかし中には、休んでも回復せず、生活の質や幸福感そのものを下げてしまうレベルの疲労に悩まされている人もいます。
「ちゃんと寝ているはずなのに、常にしんどい」
「朝起きた瞬間から、もう限界を感じる」
それは単なる疲れではなく、「消耗している」サインかもしれません。
「疲れ」と「消耗」の違い
睡眠は、心身の最適な機能に深く関わっています。体調やメンタルが崩れると、睡眠の質も影響を受けます。
一時的な「疲れ」は、しっかり休めば回復します。 一方で消耗状態は、一晩ぐっすり眠っただけでは回復しません。
消耗とは、長期間にわたって続く慢性的な疲労状態で、日常生活や人間関係、感情の安定にまで影響を及ぼします。心と体の両方が「ずっと限界に近い状態」で動き続けているような感覚です。
現代社会では、仕事・家事・学業などで慢性的な睡眠不足や過労状態が一般化しています。成人の多くが推奨される7〜8 時間の睡眠を確保できていないという報告もあります。
「眠れば大丈夫」と思いがちですが、十分な睡眠をとっても疲れが残る場合、それは単なる疲労ではなく「慢性的な消耗」の可能性があります。
消耗しているときに起こりやすい変化
慢性的な疲労は、身体だけでなく感情や思考にも影響します。
消耗していると、人はイライラしやすくなり、集中力が落ち、防御的になりがちです。
小さな作業が重く感じられ、日常をこなすだけで大きなエネルギーを消耗します。
これは「気あいが足りない」のではなく、心身が助けを必要としているサインです。

あなたは「疲れている」だけ?それとも「消耗している」?
忙しい大人にとって、疲労は当たり前のものになりがちです。実際、多くの成人が推奨されている睡眠時間を確保できていません。
しかし、次のような状態が頻繁に続く場合、単なる疲れを超えている可能性があります。
消耗している可能性のあるサイン
- 起きても疲れが取れない
- 集中力や判断力の低下
- 感情の不安定さ
- イライラ、過度のストレス感
- 頭痛やめまい
- 食欲の異常
- 日常的な疲労感が続く
こうした症状は、単なる睡眠不足だけではなく、心身の健康全般に関わる可能性があります。
消耗の主な原因
消耗の原因は人それぞれですが、大きく分けると精神的要因と身体的要因があります。
精神的には、過労、バーンアウト、長期的なストレスが大きな要因です。仕事だけでなく、家庭、人間関係、将来への不安など、複数のストレスが重なることで消耗は加速します。
また、うつ病や不安障害、双極性障害などのメンタルヘルスの不調も、強い疲労感と深く結びついています。心の問題と消耗は切り離せません。
身体的には、貧血、甲状腺機能低下症、高血圧、心疾患、線維筋痛症、睡眠時無呼吸症候群、慢性疲労症候群などが関連することもあります。
重要なのは、「もっと寝れば解決する」と思い込まないこと。
消耗は、根本原因に向き合わなければ繰り返されます。

慢性疲労と関連疾患について
長期間にわたる深刻な疲労は、慢性疲労症候群(CFS/ME) と呼ばれる状態と関連することもあります。これは休んでも回復しない強い倦怠感が 6 ヶ月以上続く状態とされ、日常生活に支障をきたすことがあります。
慢性疲労症候群は、一般の疲労とは異なり、睡眠を改善しても楽にならないなどの特徴があり、専門医による診断と支援が必要なケースもあります。
消耗感を和らげるためにできること
まず、睡眠の質を整えることは重要な第一歩です。
規則正しい睡眠時間、就寝前のリラックス習慣、カフェインやアルコールを控えるなど、基本的な睡眠ケアは消耗の土台を支えます。
ただし、睡眠だけでは十分でない場合も多くあります。
日中の過ごし方としては、 エネルギーを持続させる食事、水分補給、こまめな休憩、ストレスを下げる呼吸や瞑想、自然に触れる時間が助けになります。
何より大切なのは、自分のエネルギーレベルを基準に1日を組み立てること。
無理に詰め込まず、「今日はここまで」と線を引くことは、回復への重要なステップです。
専門的な支援の重要性
疲労が長期間続き、日常生活に支障が出ている場合は、自己判断で放置せず、医師や専門家に相談することが重要です。慢性疲労症候群や睡眠障害の可能性を含め、正確な診断とサポートは回復に向けた大きな一歩になります。
結論|消耗は「弱さ」ではなく、体からのメッセージ
慢性的な疲労は、怠けや甘えではありません。
それは、心と体が「このままでは続かない」と伝えているサインです。
必要なのは、もっと頑張ることではなく、立ち止まって原因を見つめ直すこと。
専門家の力を借りることも、自分を守る立派な選択です。
消耗しているときこそ、休むことに罪悪感を持たないでください。
あなたの価値は、生産性や忙しさでは決まりません。
回復は、ゆっくりでも確実に進みます。
そしてその第一歩は、「私は今、消耗しているかもしれない」と認めることから始まります。
【ハミングが届けるポジティブニュース】 最高の恩返し。64年間「自分の部屋」を持てなかった母へ贈る安らぎの空間

Credit: Courtesy Anan Duarte
人生の経験を重ねるほど、私たちは母親という存在の「強さ」と、その裏側にある「沈黙の苦悩」を理解するようになります。特に、自分が親になって初めて、「あの時、母はどれだけ大変だったのだろう」と胸を締めつけられる瞬間があるのではないでしょうか。
今回ご紹介するアメリカのアナさん(25歳)と母アネットさん(64歳)の物語は、貧困と不安定な生活の中で、母が娘に与え続けた「揺るぎない愛」、そして娘が大人になって初めて気づいた「誰が母の面倒を見るのか」という問いが、最高の恩返しへと繋がった、心温まる実話です。
おすすめ記事:【ハミングが届けるポジティブニュース】 「バケツの水をパイプラインへ」スコットランド人男性がネパールにもたらした、水と希望の物語
これは、単に部屋をプレゼントした話ではありません。苦労を重ねた母に、娘が「心の平和と新しいスタート」を贈った、家族の物語です。
アナさんの幼少期は、絶え間ない不安定さとの戦いでした。住む家もなく避難所を出入りし、次にどこで眠るのかさえ分からない日々。「本当に落ち着くことがなく、常に移動していました」とアナさんは振り返ります。
“苦労を重ねてきた母に、娘が住まい以上の「心の平和と再出発」を贈った、困難を乗り越える家族の物語です。”
母アネットさんは、父親の重病のため、10代で高校を中退し家族の介護にあたらざるを得ませんでした。英語は第二言語で、頼れる人も少ない中、アネットさんはマクドナルドなどで懸命に働き、二人の生活を維持しました。
アナさんは言います。「いつ何が起こるか分からない、常に不安が付きまとう生活でした。精神的にも疲れ果てる毎日でしたが、私は母がひたむきに働く姿を見て育ちました。その強い精神が、私を支えてくれたのです」。

Credit: Courtesy Ana Duarte
彼らは、安い家賃で借りられる「ボロボロの狭い部屋」を転々としてきました。「そこは『家』というより、次の引っ越しまで生き残るための場所でしかなかった」とアナさんは語ります。
しかし、中学時代、再びホームレス状態に陥ったとき、アナさんは教育こそが貧困から抜け出す唯一の方法だと気づきます。奨学金を得て進学した私立学校で、豊かな家庭の子どもたちに囲まれ、避難所暮らしを隠し、お古の制服を着て登校する日々は、大きな不安と劣等感の毎日でした。それでも彼女は、「いつかもっと良い人生を築く」という希望を心の支えに、学業に専念しました。
アナさんの努力が実を結び、一家の中で初めてとなる大学卒業者となったのです。大学を卒業し、ソーシャルワークの学位を取得したことは、長年の苦難に終止符を打つ決定的な瞬間でした。
現在、アナさんはアメリカ最大のキリスト教系非営利団体の一つで働いています。「貧困に苦しむ人たちを助ける仕事は、私にとって深い意味があります。すべてを失った時の苦しさは、私が誰よりも知っているからです」と彼女は語ります。
“アナさんは、長年の苦難を乗り越えて大学を卒業し安定した仕事に就いたことで、これまで一度も自分の部屋を持てなかった母に「本当の家」と安らぎを贈る恩返しを実現しました。”
この安定した生活の中で、アナさんは母に恩返しをするチャンスを得ます。初めて手に入れた安定したアパートで、家賃や食費を支払えるようになっただけでなく、母に「本当の家」をプレゼントする時が来たのです。
アナさんは、アパートのメインベッドルームを母にプレゼントすることを決めました。その理由はシンプルでした。
「私の母は、生まれてから64年間、一度も自分の部屋を持ったことがないんです」
「母は自分が持てなかったものを全て私に与えようとしてくれましたが、誰がこれから母の世話をするのでしょうか? 私は、大人として親を大切にすることの重要性を強く感じています」この思いが、彼女にサプライズを決行させました。

Credit: Courtesy Ana Duarte
上品に飾り付けられたベッドルームは、アネットさんにとって、まさに64年分の「心の平和と新しい始まり」のシンボルとなりました。
アナさんは言います。「今までの貧困生活は長く、厳しかったけれど、その苦労のおかげで私は強さ、広い視野、そして思いやりの心が身につきました。もし昔の自分に、大学を卒業し、家と仕事、そして母と暮らす未来が待っていると話しても、きっと信じられなかったでしょう。でも、今、私はここにたどり着きました」。
「あきらめずに進み続ければ、いつか振り返ったとき、『やってよかった』と心から思える日が来る」という彼女の言葉は、今を生きる私たちへの力強いメッセージです。
「ハッスルカルチャー」の本当の問題|なぜ頑張り続けても満たされないのか

「時間」との歪んだ関係
数か月前、私はメモにこんな独白を書いていました。
“いつからこうなったのかは分からない。でも今の私は、時間と健全ではない関係を築いてしまっている。”
時間は「無駄にしてはいけない、世界で最も価値のある資源」になり、私は自分の人生のすべての時間を生産的であるかどうかで評価していました。
確かに、時間には限りがあります。永遠に生きられるなら、時間に価値は生まれません。限りがあるからこそ貴重なのです。
でも水と同じで、必死につかもうとすればするほど、指の間からこぼれ落ちていく。足りないと感じれば感じるほど、大切にできなくなっていきました。
「もっと頑張らなかった時間」はすべて無駄。
楽しむことや人付き合いでさえ、効率的でなければ許されない。
これはまさに、ハッスルカルチャーに飲み込まれた状態でした。
目標トレッドミルという罠
目標を追いかけるプロセスは、心理学でいうヘドニック・トレッドミル(快楽順応)とよく似ています。
ヘドニック・トレッドミルとは、良い出来事や悪い出来事が一時的に幸福度を上下させても、最終的には元の基準値に戻ってしまう、という考え方です。
目標達成も同じ構造を持っています
- 短期的には:小さな成功で一時的に気分が上がる
- 長期的には:目標達成後、束の間の高揚感のあとに「次は何?」という空虚さが訪れる
- そして新しい目標を設定し、同じサイクルを繰り返す
つまり、目標トレッドミルはヘドニック・トレッドミルの上に重なって存在しているのです。
そしてその性質は同じく、「もっと欲しい」という尽きない渇望を生み出します。
混乱の正体|なぜ満たされると思ってしまうのか
問題は、目標を追うこと自体ではありません。
問題なのは、目標を達成すれば、人生の土台そのものが良くなると期待してしまうことです。
私たちは無意識にこう思っています。
「もっと達成すれば、もっと幸せになれる」
「いつか、もう頑張らなくてよくなる」
でも実際には、その「追いかける行為」こそが、私たちをトレッドミルに留めているのです。
ここで重要なのが、相対的な目標と究極的な目標の混同です。
-
相対的な目標:お金、影響力、成功、評価
→ 他人と比べるため、終わりがない - 究極的な目標:幸福感、充足感、満足、安心
ハッスルは相対的な目標には有効ですが、
幸福や満足といった究極的な目標には、ほとんど役に立ちません。

「もっと欲しい」という欲望の正体
ハッスルの根底には、常に「もっと欲しい」という感覚があります。
そして「もっと欲しい」と思うことは、今の状態に満足していないという宣言でもあります。
欲望そのものが悪いわけではありません。
でも欲望とは、本質的にこういう契約です。
欲しいものを手に入れるまで、自分は不幸でいてもいい
— ナヴァル・ラヴィカント『The Almanack of Naval Ravikant』より
私たちは日常的に欲望を抱きながら、なぜ満たされないのか不思議がります。
だからこそ、どんな欲望を持つかを慎重に選ぶ必要があるのです。
ナヴァルは、「人生で同時に持つ大きな欲望は一つだけにする」と語ります。
それは同時に、「どこで自分が苦しむことを選んでいるのか」を自覚するということでもあります。
追いかけることと、どう向き合うか
ハッスルの本質を理解したあと、私たちにはいくつかの選択肢があります。
① マインドフルな節度
• 追いかける欲望を意識的に選ぶ
• 同時に抱える目標の数を制限する
② 相対的目標には、明確な終点を
• 数値で測れるゴールを設定する
• なぜそれを達成したいのかを明確にする
• ゴールを動かさない
③ 追い続けること自体を「遊び」にする
• これは終わらないゲームだと理解する
• アップダウンを含めて楽しむ
• 成果ではなく、プロセスを味わう
まとめ|目的地ではなく、地平線としての目標
すべては、ハッスルの正体を理解し、受け入れることから始まります。
そこから先の選択は、すべて「明確さ」の上に成り立ちます。
楽園は、目標と同じで「到達する場所」ではないのかもしれません。
むしろ、私たちが本当はたどり着きたくない、終わりのない地平線。
それは、 「目標を達成するため」ではなく、 「どんな目標でも達成できる自分になるため」に働き、成長し続ける理由なのかもしれません。
感謝の科学|「ありがとう」がホルモン・ストレス・睡眠を整える理由

12月になると、世界中で「感謝」について考える機会が増えます。でも、感謝の力は単なる前向きなマインドセットにとどまりません。
実は感謝は、”私たちの体の化学反応そのものを変える“生物学的な取り組み”でもあるのです。
医学の現場では、「食事は薬」「運動は薬」「睡眠は薬」とよく言われます。そこにもう一つ加えるなら——
感謝こそ、最も過小評価されている“薬”かもしれません。
感謝の気持ちを感じた瞬間、神経系はゆるみ、心拍は安定し、脳は「警戒」ではなく「安心とつながり」へと切り替わります。その小さな「ありがとう」が、ストレスホルモンを下げ、ホルモンバランスを整え、消化や睡眠の質まで支えてくれるのです。
感謝がストレスホルモンを書き換える仕組み
まず、こんな質問をしてみてください。
あなたは日常的に「感謝」を感じていますか?それとも「慢性的なストレス」の中にいますか?
正直なところ、ストレスを感じる練習は誰もが自然にできてしまいます。でも、感謝を習慣として続ける練習は意識しないとできません。
慢性的なストレス状態では、体は常に「戦い・逃走モード」に入り、コルチゾールが上昇し、心拍数が高まり、神経は休まる暇がありません。その結果、疲労感、不安、睡眠障害、炎症といった不調が現れやすくなります。
一方で感謝は、体にこう伝えます。「今は安全だよ」と。
研究によると、継続的な感謝の実践は、
- コルチゾールを最大約23%低下
- 心拍変動(HRV)の改善
- 炎症マーカー(CRP)の低下
といった変化をもたらすことが示されています。
感謝はストレスを消すのではなく、ストレスに対する体の反応そのものを整えるのです。
ホルモンに広がる「感謝の連鎖反応」
私たちのホルモンは、感情の影響を強く受けています。
ストレスが続くと、コルチゾールがエストロゲンやプロゲステロンといった生殖ホルモンを抑制し、甲状腺や血糖バランスにも影響します。
感謝は、その流れにブレーキをかけます。
大切なのは「感謝を考える」だけでなく、体で感じること。
胸があたたかくなる、呼吸が深くなる、肩の力が抜ける——
その身体感覚こそが、神経系に「安心」を伝えます。
すると、
- オキシトシン(絆のホルモン)が増える
- コルチゾールが下がる
- 副交感神経(休息・消化モード)が優位になる
という好循環が生まれます。
消化が整い、エネルギーが安定し、免疫機能もサポートされていきます。

感謝と睡眠の深い関係
感謝の効果が最もわかりやすく現れるのが「睡眠」です。
カリフォルニア大学や米国国立衛生研究所(NIH)の研究では、
感謝を習慣にしている人ほど、寝つきが早く、睡眠時間が長く、目覚めが良いことが示されています。
理由の一つは「不安な思考」の減少。
感謝は、夜中に頭の中でぐるぐる回る不安な思考を中断してくれます。
感謝に意識を向けると、脳の恐怖中枢である扁桃体の活動が落ち着き、感情調整を担う前頭前野が活性化します。その結果、心拍や血圧が下がり、体は「眠っていい状態」へと移行します。
さらに、感謝はセロトニンを増やし、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌もサポートします。
本当に続く感謝習慣のつくり方
感謝は、特別なノートや完璧なルーティンがなくても始められます。大切なのは一貫性です。
科学的に効果がある方法:
- 習慣に紐づける:朝のコーヒー、歯磨き中など、すでにある行動とセットにする
- 感覚的に表現する:「健康に感謝」ではなく「今朝の散歩で足が軽かったこと」と自分の体が感じたことを思い出してみる
- 声に出す・共有する:オキシトシンが増え、安心感が高まる
- その瞬間に気づく:温かい飲み物、子どもの笑い声、静かな時間
- 寝る前に3つ:うまくいったことを思い出すだけで夜のコルチゾールが低下
感謝は「思考」ではなく、全身で行う実践です。
つらいときこそ、感謝は効く
感謝は「全部うまくいっているふり」をすることではありません。
むしろ、しんどいときにこそ、小さな光を見つけるための道具です。
カリフォルニア大学の研究では、感謝を意識的に行うことで、感情の調整や回復力に関わる脳の領域が活性化することが示されています。
涙の中で小さく「ありがとう」とつぶやくこと。
それは、体に「まだ安全だよ」と伝える行為でもあります。
まとめ|日常にある、いちばんやさしい薬
感謝は、特別な日だけのものではありません。
毎日の中で、心と体を整えてくれる、最もシンプルで確かなセルフケアです。
ホルモンを整え、神経系を休ませ、睡眠を深くする——
感謝は、科学に裏打ちされた“無料の薬”。
足りないものに目を向けがちな世界の中で、感謝は私たちを「すでにあるもの」へと連れ戻してくれます。
呼吸、体、人とのつながり、そして生きているという奇跡へ。
_______________________________________________________________________________________
参考・出典(Source Links)
UC Davis Health – Gratitude & Sleep Research
https://health.ucdavis.edu/blog/cultivating-health/gratitude-and-sleep/
National Institutes of Health (NIH) – Gratitude & Well-being
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3010965/
UCLA – Gratitude and Brain Function
https://www.uclahealth.org/news/article/expressing-gratitude-can-improve-your-health
食べ物は情報だった|機能性医学が教えてくれる「食べ方」の本当の意味

食べ物は「栄養」ではなく「情報」
「何を食べたらいいのかわからない」
そんなふうに感じたことはありませんか?
流行の食事法、○○は良い・悪いという情報、季節ごとに変わるルール。
がんばって健康になろうとしているのに、情報が多すぎて、かえって疲れてしまうこともありますよね。
機能性医学(ファンクショナル・メディスン)が大切にしている考え方は、とてもシンプルです。
食べ物は、体へのメッセージ。
食べるたびに、体はちゃんと受け取って、応えてくれています。
体は、食べ物の「意味」をちゃんと理解している
一口食べるごとに、体の中では小さな会話が起きています。
- たんぱく質は「修復してね」という合図
- 食物繊維は「腸内環境を整えよう」というサポート
- 良質な脂は「ホルモンを作ろう」という材料
- 色のある野菜は「細胞を守ろう」という優しいケア
逆に、甘いものや加工食品が多いと、体は少し緊張します。
血糖値が揺れて、眠りや気分にも影響が出ることがあります。
どんな食べ物も、良い・悪いではなく、体にどんなサインを送っているかが大切なのです。
体は食べ物を「コード」のように読み取っている
食べ物を情報として見ると、それは化学の話になります。
科学が示していること
- たんぱく質
筋肉や組織の修復、血糖値の安定、満腹ホルモン(GLP-1、PYY)の分泌を促す - 食物繊維
腸内細菌のエサとなり、短鎖脂肪酸を作り、炎症の抑制や免疫・メンタルの安定に寄与 - 良質な脂質
ホルモンの材料になり、脳機能を支える(脳の約60%は脂質) - 色とりどりの野菜・果物
抗酸化物質を供給し、細胞を守り、解毒経路をサポート - 超加工食品や糖質過多の食事
コルチゾールを上げ、血糖値を乱し、睡眠や気分に影響
どんな食べ物も「中立」ではありません。
それは善悪の話ではなく、「体がどう解釈するか」という情報の話です。

食事はホルモンへのダイレクトメッセージ
ホルモンは、食事の内容にとても敏感です。
- たんぱく質・脂質・食物繊維がそろった食事
→ 血糖値が安定し、炎症が抑えられ、代謝がスムーズに - 超加工食品中心・食事時間が不規則
→ 血糖値の乱高下、コルチゾール上昇、インスリン過剰分泌
これが長く続くと、エストロゲン・プロゲステロン・甲状腺ホルモン・テストステロンにも影響します。
機能性医学が注目するポイント
- ホルモン合成に必要なたんぱく質
- エストロゲン・プロゲステロンを支える脂質
- 解毒を助ける食物繊維
- マグネシウム、亜鉛、ビタミンB群、オメガ3
バランスの取れた食事 = バランスの取れたホルモンはとても正直です。
腸内環境も、あなたの食事を聞いている
私たちは「自分のため」だけに食べているわけではありません。
体内には数兆個の腸内細菌が住んでいます。
- 食物繊維 → 善玉菌が育つ
- 超加工食品 → 炎症を起こしやすい菌が増える
- ポリフェノール(ベリー、ハーブ、カカオ)
→ 腸粘膜の修復を促す
腸は、ホルモン・免疫・メンタルすべての司令塔。
だからこそ、機能性医学では「まず腸から」整えます。
食事は自律神経の体験でもある
食べるスピードや環境も、重要な情報です。
- ゆっくり、落ち着いて食べる
→ 副交感神経(休息・消化モード) - 急いで、スマホを見ながら、立ったまま食べる
→ 交感神経(戦い・逃走モード)
ストレス状態では、どんなに良い食事でも消化・吸収されません。
「安心できない体は、栄養を受け取れない」
食前に深呼吸を数回するだけでも、体は「今は安全」と理解します。

食べ物には、気持ちを癒す力もある
食べ物は、ただ体を満たすだけのものではありません。
誰かと食べるごはん、 思い出の味、ほっとする一杯のスープ。
「おいしい」「うれしい」という気持ちは、体にとっても優しい作用があります。
機能性医学は、楽しみを我慢する食事をすすめません。
体も心も、いっしょに満たすこと。
エネルギーを守る食事という考え方
毎日を動かしてくれているエネルギー工場(ミトコンドリア)も、 食事から力をもらっています。
栄養が足りないと、体は節電モードに。
それが「なんとなく疲れる」「やる気が出ない」につながることも。
完璧じゃなくていいので、
- たんぱく質
- 野菜や食物繊維
- 良質な脂
を少し意識するだけで、体は安心します。
体は、急激な変化より、穏やかな安定が好き。
機能性医学的な食事の考え方
- 食べ物に善悪をつけない
- 血糖値を安定させる
- 意識して食べる
- 腸内細菌を育てる
- 完璧より「パターン」を大切にする
機能性医学は、 「なぜ今の体調なのか」を理解するためのツールです。
食べ物は、体との会話
食事はテストでも、我慢大会でもありません。
体はいつも、
「ちゃんと受け取ったよ」
「今は少し疲れているよ」
と教えてくれています。
私たちは、その声を少しだけ聞いてあげればいい。
食べ物は、
- 薬にもなり
- 安心にもなり
- つながりにもなり
そして、 体が本来持っている力を、そっと思い出させてくれるものです。
今日の一食が、 あなたの体にやさしいメッセージになりますように。
_______________________________________________________________________________________
参考・ソースリンク
Harvard T.H. Chan School of Public Health
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/
National Institutes of Health (NIH) – Gut & Microbiome
https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/gut-microbiome
Cleveland Clinic – Functional Medicine
https://my.clevelandclinic.org/departments/functional-medicine
PubMed(腸内細菌・短鎖脂肪酸)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
Institute for Functional Medicine (IFM)
https://www.ifm.org
自分で決めた締め切りが、生産性を高めストレスを減らす理由

締め切りというと、プレッシャーや追い詰められるイメージを抱きがちです。しかし、実はうまく活用すれば、生産性向上とメンタルの安定に役立つ最強のツールにもなります。とくに「自発的な締め切り(セルフデッドライン)」は、仕事や日常のタスクに集中力をもたらし、心にも余裕を生み出します。
周りから決められた締め切りよりも前に、あえて自分で締め切りを設けることで、効率よく行動できるようになり、予期せぬアクシデントによるストレスを大幅に防ぐことができます。
自分で締め切りを決めるメリット
本来の締め切りギリギリになってしまうと、焦りや不安が一気に押し寄せます。
しかし、自分で締め切りを前倒しにして設定することで…
- 重要度の高いタスクを優先できる
- 余計な先延ばしや無駄な情報収集が減る
- ほどよいプレッシャーが集中力を高める
- 作業を中断することにも慣れ、不測の事態に対応できる
いわば「最後の1分」をあえて手前にずらすことで、生産性が劇的に向上します。
実例:作家が実践したセルフデッドライン術
ジャーナリストで作家のロイ・ピーター・クラーク氏は、
締め切りの2時間前に原稿を提出する「自分ルール」を導入しました。
- 編集者から丁寧なフィードバックを受けられる
- 焦ることなく推敲できる
- 精度の高い記事づくりにつながる
自分で意図的に作った締め切りでも、習慣化することで本物の締め切りのように効果を発揮し、その結果、12年間で6冊もの著書を出版できたと語っています。
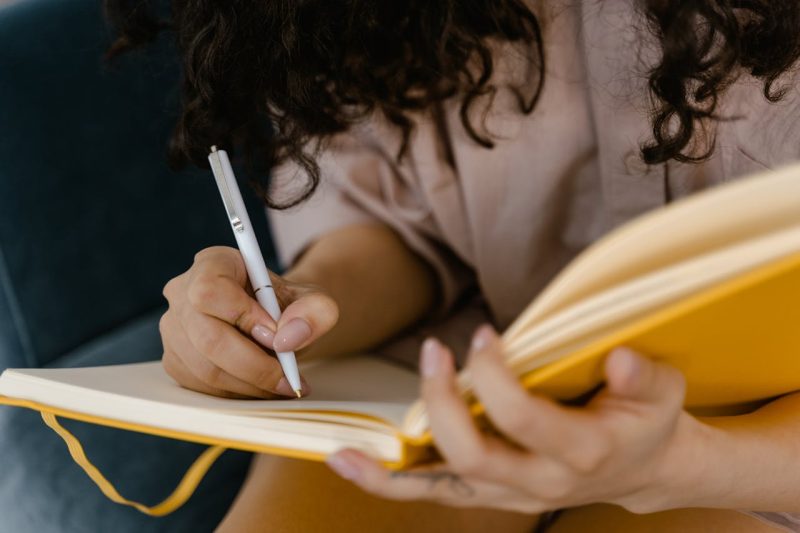
日常の小さなタスクにも活用できる
セルフデッドラインは、仕事だけでなく日々の雑務にも応用できます。
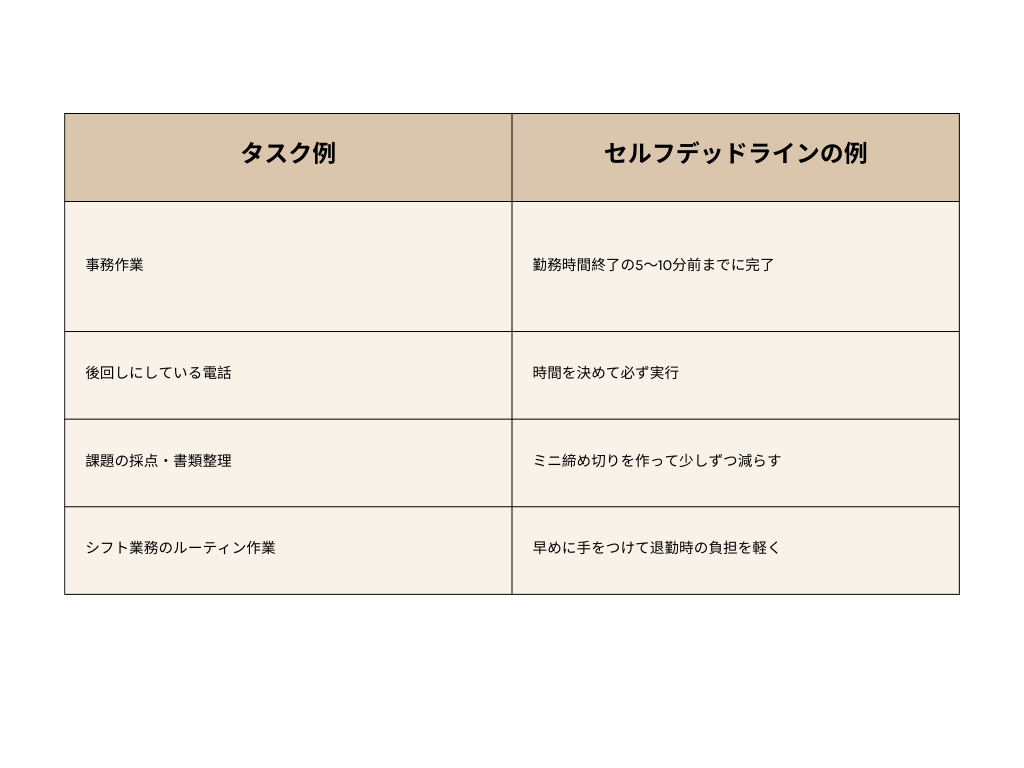
突然のトラブルにも強くなる
前倒しで行動することで…
- Wi-Fiトラブル
- プリンターの紙詰まり
- 仕事の割り込み
- 子どものケア
こうした予測不能の出来事にも冷静に対応できます。
それが強い安心感とストレス耐性につながります。
締め切りを守れない日があってもOK
毎回うまくいかなくても構いません。大切なのは…
- 状況を見直す
- 期限を調整する
- 深呼吸して再スタートする
「完璧でなくていい」という柔軟さが、継続のコツです。
まずは1つ、締め切りを設定してみよう
- 直近のタスクを1つ選ぶ
- 本来より早い締め切りを設定する
- 誰かに宣言することで「やらなくては!」というプレッシャーに
- 完了後に振り返る
小さな一歩が、仕事の質と心の余裕を大きく変えます。
まとめ
セルフデッドラインは時間に追われる側から、時間を味方につける側へ
シフトするための方法です。
先回りの行動が、集中力を高め、ストレスを減らし、
人生にもっとゆとりと満足感を与えてくれます。
なぜ「グランマホビー(おばあちゃんの趣味)」が現代に響くのか — 手を動かすことで得られる心と体のバランス

近年、編み物や刺繍、園芸、料理、パズルなど、かつて「おばあちゃん世代のもの」と言われていた手作業やクラフトが、若い世代の間で再び注目を集めています。スクリーンの前で過ごす時間が増える中、画面を離れて手や頭を動かすことで得られる癒しと安定感が、多くの人々にとって必要とされているからです。
このような“グランマホビー”は、ただの趣味以上の意味をもっています。
- 手を使うことで身体がリラックスモード(副交感神経優位)に入りやすくなる
- 集中と没入によって「今この瞬間」に意識が向き、過去や未来の不安から解放される
- 自分のペースで成し遂げる創造的な行為が「達成感」と「自己肯定感」を育む
つまり、グランマホビーは「癒し」や「自分らしさの回復」をもたらす、現代人にとっての新しいウェルネスの形なのです。
なぜ今、グランマホビーが注目されているのか
現代社会では、情報過多やテクノロジーの急速な進展により、私たちの脳や感覚は常に刺激にさらされています。一方で、多くの仕事はPCスクリーンとキーボード上で完結し、身体を使う機会は減少傾向にあります。
こんな時代だからこそ、 「土を触る」「毛糸を編む」「手で形を作る」といった、手と体と感覚を使う行為が、人々にとって貴重な「癒し」と「安心感」を与えてくれるのです。
UKのメンタルヘルス専門家であるシェリー・ダーはこう語っています。
「編み物やパン生地をこねるような、左右対称のリズムを伴う手作業や、土や毛糸に触れる感覚、そして次に何が起きるか予測ができるなようなアクティビティは、体に“安全”を知らせる。副交感神経を優位にして、休息と回復を促す。」
このように、手仕事は単に“懐かしい”というだけでなく、身体の神経系にポジティブな作用を与えることが、心理療法や神経科学からも支持されつつあります。
代表的な “グランマホビー” 16選
手先を使い、集中とゆったりしたペースをともなう活動は、たくさんあります。たとえば:
- 編み物(ニット)
- かぎ針編み(クロッシェ)
- 刺繍
- ニードルフェルト
- 裁縫/洋裁
- スクラップブッキング・コラージュ
- 絵画・お絵かき
- 手紙・ペン習字
- 料理
- パンやお菓子作り
- 保存食づくり・瓶詰め
- バードウォッチング
- 園芸・ガーデニング
- ジグソーパズル
- ボードゲーム
- カードゲーム
手を使い、頭を使い、五感を使う——それがこういった趣味の本来の力を引き出します。
“グランマホビー” がもたらす心身への効果
ストレス軽減・不安の低減
編み物や園芸、パズルなどは、瞑想に似た効果があるとする研究もあります。
集中力と自己効力感の向上
一つの作業を最後までやり遂げることで、「私はできた」という達成感が得られる。
副交感神経の活性化
ゆったりしたリズムや手指の感覚が、自律神経のバランスを整え、心身をリラックスさせる。
現代の“生産性偏重”からの解放
時間あたりの成果ではなく、「手を動かすことで感じる幸福」「自分で作る喜び」を取り戻せる。
また、これらの活動は「ただ楽しむ趣味」でありながら、日常に“休息”と“癒し”の時間を自然と取り入れる仕組みになります。
初心者でも簡単に始められる“はじめの一歩”
はじめるとき、覚えておきたいのはこの基本:
- 1日5〜10分からで OK — 無理しない、続けやすいリズムを意識
- 完璧を目指さない — うまくできなくても、それでいい。続けることが大切
- 習うなら誰かと一緒に — 祖母や友人、近所の人、コミュニティから学ぶと、さらに楽しさが広がる
- 忙しい日常に“ゆとりの余白”を — 朝のコーヒータイム、夜寝る前、休日のちょっとした時間など
これらを気軽に取り入れるだけで、心が軽く、暮らしが豊かになります。
まとめ
「グランマホビー」は、たんなるノスタルジーではなく、
情報過多・高速化する現代社会を生き抜くための、“心と体を取り戻すライフスタイル” です。
手を動かすことで得られる安心感、ゆるやかな達成感、身体の声に耳を傾ける静けさ。
それらが毎日の生活に生まれるとき、
私たちはただ「長く生きる」のではなく、
「自分らしく、穏やかに生きる時間」を取り戻すことができるのです。
今日、あなたの手が喜ぶ何かを――。
それが、あなたにとっての新しいウェルネスになるかもしれません。
クレコスがつくる、未来につながるオーガニックコスメ。あなたの選択が、社会を優しく変えていく

Humming編集長が京都のGOOD NATURE HOTELで出会った、1本のハンドクリーム。
「自然の香りがする」
「しっとりするのにベタつかない」
その心地よさに一目惚れし、HummingセレクトECショップでの取り扱いが始まりました。
その商品を生み出しているのが、30年以上前から国産原料にこだわり続けてきたオーガニックコスメメーカー「クレコス」。
今回は、株式会社クレコス代表取締役社長・暮部達夫さんに、クレコス誕生秘話や社会課題に向き合う姿勢、そして「QUON(クオン)」ハンドクリームに込めた想いを伺いました。
株式会社クレコスについてはこちら
「QUON(クオン)」についてはこちら
原材料から責任を持って化粧品を作りたい
ー まず、クレコスについてお聞かせください。
株式会社クレコスは、1993年に私の母が創業しました。
当時はまだオーガニックという言葉すら浸透しておらず、自然派化粧品と呼ばれていた時代です。
そんな中で、母が大切にしていたのは「自分の娘が安心して使えるコスメをつくりたい」という想いでした。
ケミカルな成分は使わず、原材料から責任を持って開発・製造する。その姿勢を、創業当時から貫いてきました。
ー 原材料から責任を持つ。まずは何からスタートされたのでしょうか?
一番最初にご縁があったのが、熊本の農家さんです。ヘチマの茎からぽたぽたと垂れる「ヘチマ水」を分けていただくことから、私たちの原材料開発は始まりました。
当時は、化粧品メーカーが原材料から自分たちで作ることは珍しく、農家さんに化粧品の原材料として農産物を提供していただくことも、あまり前例がありませんでした。

ー 原材料探しからスタートされた中で、大変だったことは何でしたか?
一番大変だったのは、農家さんに理解していただくことです。
当時、農家さんにとって農産物はあくまで「食べるためのもの」。 「化粧品の原材料として提供してほしい」とお願いしても、ほとんど相手にされない状況だったからです。
ー 今も、農家さんに直接足を運ぶことは多いのでしょうか。
そうですね。当時から続けてきたコミュニケーションで全国にネットワークができ、今は逆に「地方の農産物を使ってコスメにしてほしい」という依頼も増えました。
全国の農家さんと出会えるので、とても楽しいです。
ー 原材料は国産にこだわっているのでしょうか?
基本的には国産にこだわっています。
クレコスの商品、特にクオンは、全成分の後ろにマークを入れていて、「国産」「自然栽培」「オーガニック」であることが一目で分かるようになっています。
オーガニックをもっと身近に。クオンが目指すのは、社会を良くするコスメづくり
ー クオンのお話が出てきたので、ここからは、クレコスが展開するブランド「クオン」について伺えたらと思います。クオンはどのようなコンセプトのもとで立ち上がったブランドなのでしょうか。
クレコスは40代以上の方向けで、アンチエイジングに特化したブランドです。よりナチュラルな手法で、20代・30代向けのブランドを立ち上げたいと思い、2011年に立ち上げたのが「クオン」です。
「オーガニックのコスメをもっと手軽に使っていただきたい」という想いから、価格にもこだわりました。
さらに、化粧品を作りながら、社会課題の解決に繋がる仕組みをつくることにも注力しています。
ー 社会課題の解決に繋がる仕組みとは、具体的にはどのような取り組みですか?
1つ目は、耕作放棄地を減らすための取り組みです。
農業の現場では高齢化による離農が進み、耕作放棄地が全国で増え続けています。その課題に向き合う中で出会ったのが、奈良県・大和高原で自然栽培のお茶を育てる「健一自然農園」です。代表の伊川健一さんは、おじいちゃんおばあちゃんから受け継いだ耕作放棄地をひとつずつ再生しながら、お茶づくりを続けています。
彼との出会いが大きな転機となり、お茶の葉・実・花など、すべてを買い取ることで農業収入を安定させ、耕作放棄地の解消につなげる仕組みをつくりました。そのため、クオンではお茶を原材料にした製品づくりを広く展開しています。

2つ目は、障害者就労の支援です。全国的に賃金が低いと言われる障害者就労の現場を、少しでも良くしたいという想いがあります。
そのため、お茶のタネを搾って油にしたり、花を蒸留して香りのある水をつくるなど、原材料の加工工程を障害のある方にお願いしています。
3つ目は、日本の森を守る取り組みです。
近年では里山が荒れ、熊が人里に降りてくる問題も深刻化しています。そこで私たちは、間伐した木をパルプ化し、障害者の方たちが手すきした和紙として再生。それをクオンのパッケージに使用しています。

ー 素晴らしい取り組みですね。一個人が「森を守ろう」と思っても、実際に何をしたらいいのかわからないことって多いですよね。使う側としても、商品を選ぶことで社会の一部に関われているようで、すごく嬉しいです。
問題意識はあっても、具体的なアクションにはなかなかつながらない。そういう方もたくさんいるかと思います。
私たちはコスメを長年作り続けているので、品質には自信があります。そこに社会課題を解決する取り組みを掛け合わせることで、「この商品を選ぶことが、誰かの力になるんだ」という購買の動機になれば嬉しいです。

べたつかず、しっとり潤う。天然成分100%ハンドクリームのこだわり
ー 素敵です。クオンのハンドクリームについても伺いたいです。こちらも原材料づくりからこだわっているのでしょうか?
もちろん天然成分100%で作っています。日常で使いやすいアイテムから、オーガニックコスメの良さを感じてもらえたらと想い、開発しました。
基礎化粧品をいきなり変えるのはハードルが高いですからね。このハンドクリームがオーガニックコスメを手にする最初の入口になれたら嬉しいです。
ー クオンのハンドクリームはしっとりするのにべたつかないですよね。
オフィスでハンドクリームを使う方も多いので、「つけてすぐにボールペンが持てる」、べたつきの少ないテクスチャーを目指しました。
それでいて、きちんと保湿感がある。働く女性が気軽に使える使用感を大事にしています。
ー 香りへのこだわりはありますか?
合成香料は使用せず、天然の精油(アロマオイル)だけを使っています。強い香りが苦手な方でも、やさしい天然の香りを心地よく楽しんでいただけます。
ー Hummingの編集長もナチュラルなバラの香りを絶賛していました!
心地よさの先にあるもの。手に取るその一歩が、未来をより良くする
ー 最後に、クレコスの商品を手にとってくださる方へメッセージをお願いします。
クレコスの商品は、オーガニックを使ったことがない方でも、一度手に取っていただければ、その良さを実感していただける自信があります。オーガニックならではのナチュラルな香りや心地よさを感じていただきながら、天然成分でもケミカルに負けない使用感があることを体感してほしいです。
そして、商品には、障害のある子どもたちが原材料づくりに関わってくれていたり、日本の農業や森林を守るための取り組みがあったりと、さまざまな想いも詰まっています。 「この商品を選ぶことで、より良い社会づくりの一部を担えるんだ」と、少しでも想いを巡らせていただけたら嬉しく思います。
🔗 Humming公式セレクトショップでも販売中
QUON(クオン) メルセライザー ハンドクリーム ローズ
QUON(クオン) メルセライザー ハンドクリーム ユズ
ウクライナの壊れたダム跡に広がる巨大な森――命の復活か、それとも危険な時限爆弾か?

Photograph: AP
今も続くウクライナ戦争で、巨大なダム湖が消滅したことをご存知でしょうか。2023年にダムが破壊され、水が引いた後、残されたのはひび割れた泥の土地でした。しかし、そこから信じられないような出来事が起きています。わずか2年で、その場所には新しい森と命が驚くほどの速さで復活しているのです。
これは、自然の持つ力がどれほど強いかを証明する「大きな実験」だと、科学者たちは注目しています。ただ、この美しい復活の裏には、環境を脅かす深刻な問題も隠されているのです。
ウクライナ南部にあるノヴァ・カホフカダムは、2023年に壊されました。その結果、それまで水で満たされていた場所は干上がり、地面がむき出しになりました。ところが2年たった今、その場所には信じられないくらい豊かな自然が戻ってきています。新しい森が広がり、多くの動植物が戻ってきたのです。でも、その未来はまだはっきりしていません。回復した自然が今後どうなるのか、まだ誰にもわからないのです。
かつての湖が大地に戻った
この場所はもともと、ヨーロッパ最大の川であるドニエプル川にできた巨大なダム湖でした。1956年に旧ソ連がこのダムを作ったことで、豊かな自然や文化の場所は水に沈んでしまいました。
しかし2023年、戦争の中でこのダムが破壊され、水が大量に流れ出しました。その洪水で多くの村が壊され、たくさんの人が被害を受けました。さらに、100万人以上の人が飲み水を失う事態にもなりました。
その後、水が引いて干上がった湖の跡地には、ひび割れた土や水に住んでいた生き物の殻が散らばっていました。でも、驚くことにそこにはたくさんの新しい木や植物が育ち始め、今や広大な森ができています。
自然の力が自ら生き返る「大きな実験」
科学者たちは、この場所で起きていることを「大きな自然の実験」と呼んでいます。人の手によって作られたダムが壊れたことで、自然がどのように復活するかを実際に見ることができるからです。
ウクライナの環境保護グループの専門家によると、元のダム湖だった場所に、ヤナギやポプラの木がどんどん生えています。川の水も戻り、絶滅が危惧されていたチョウザメ(高価なキャビアを産む魚)も戻ってきました。イノシシや他の哺乳類も新しい森に姿を見せているのです。
この変化はとても速く、地元の村に住む人々は、今や家の目の前に美しい森が広がっているのを目にしています。かつて湖だった場所に森が広がるなんて、想像できない変化ですよね。

Photograph: Vincent Mundy
自然の復活はヨーロッパでも特別な出来事
この自然の復活は、単なるウクライナだけの問題ではありません。ドニエプル川のこの部分は、ヨーロッパでも最大級の淡水湿地(川や湖のまわりの湿った土地)が形成されるかもしれないと期待されています。
専門家は、この場所を復元できれば、ドナウ川デルタに匹敵する生物多様性(いろんな動植物がいること)を持つ場所になる可能性があると話しています。これは自然環境の回復において、ヨーロッパ全体にとっても重要な意味があります。
でも、まだ安心はできない――「時限爆弾」の危険も
この美しい森や湿地ができている一方で、心配なこともあります。
昔から工場や農業などのせいで、この地域の川や土には重い金属などの有害物質がたまっていました。こうした毒は、長い間ダムの底に沈んでいて、普段は大きな問題にはなっていませんでした。
しかし、ダムが壊れたことで、こうした汚染物質が川や土地に広がり始めました。これらの有害物質は、水や土を汚し、植物や動物を通して人間の体にも悪影響を及ぼす恐れがあります。
例えば、がんやホルモンの異常、肺や腎臓の病気の原因になることもあり、特に食べ物の中で濃縮されると大きな問題になります。
現地での調査が難しい理由
今のところ、この地域は戦争の影響で立ち入りが危険だったり、地雷が残っていたりして、詳しい調査や研究がなかなかできません。
そのため、どのくらい毒が拡散しているかや、自然がどこまで回復しているかはまだよくわかっていないのです。

Photograph: Vincent Mundy
自然回復のチャンスをどうする?
ウクライナの環境グループは、この場所を自然のまま回復させるべきだと考えています。もしそうすれば、広大な自然の森や湿地が残り、多くの動植物が安全に暮らせる場所になるでしょう。
しかし、ウクライナの電力会社は、壊れたダムをまた建て直そうとしています。そうすると、この若い森や湿地は再び水に沈み、壊されてしまいます。
専門家は「ダムを再建することは、この新しい自然を破壊することだ」と強く警告しています。彼らは、この場所の自然を守ることがウクライナの未来を守ることになると信じています。
環境と文化の未来がかかっている
この地域は生態系としてだけでなく、ウクライナの歴史や文化にも深く結びついています。自然を守ることは、ウクライナの独立やアイデンティティを守ることでもあるのです。
また、この地域はヨーロッパの自然保護ネットワークにも含まれており、ウクライナだけでなくヨーロッパ全体が注目しています。
新しい命のリズム
今、ドニエプル川の周りでは、小鳥たちが戻り、川の浅瀬でチョウザメが産卵を始めています。かつての自然のリズムがゆっくりと戻りつつあるのです。
「この場所で何が起こるか、まだ完全にはわからないけれど、自然は驚くほど早く回復している」と研究者は言います。
まとめ
ノヴァ・カホフカダムの破壊は、たくさんの人の生活を奪い、大きな被害をもたらしました。しかし、その後に見られる自然の復活は、科学者たちにとって非常に貴重な「自然の実験」となっています。
これからの課題は、有害物質の問題にどう向き合い、この新しい自然をどう守っていくかです。
この地域の未来はまだ不確かですが、もし守り抜くことができれば、ウクライナだけでなく世界にとってもかけがえのない自然の宝となるでしょう。
参考記事:https://www.theguardian.com/environment/2025/jul/22/in-a-bombed-out-reservoir-ukraine-huge-forest-grown-a-return-to-life-or-toxic-timebomb
女性のためのバイオハック

心と科学で導く、健やかで豊かな生き方
私たち女性の身体は、毎日少しずつ姿を変えながら生きています。
ホルモン変化、生理周期、妊娠・出産、更年期…。
まるで波のように、心と体は常にゆらぎ、
同じ日なんてひとつもありません。
それなのに、私たちはいつも「今日も完璧に」と自分に求めてしまいがち。
少し疲れやすい日も、
なんだか眠れなかった夜も、
理由のわからない不安が胸を締めつける日もある。
✔「気のせい」
✔「年齢のせい」
✔「私が弱いだけ」
そう無理やり片付けてきたことはありませんか?
でも本当は、どれも身体からの大切なサイン。
「もっと私を知ってほしい」と
教えてくれているメッセージなのです。
おすすめ記事 ▶ なんとなく不調の正体は“エネルギー代謝”だった?細胞から整える健康法
女性の体は、いつもサインを送っている
肌がゆらぐ日も、眠れない夜も、なぜか心がついてこない日も。
それらはすべて、「もっと私を整えて」と教えてくれるメッセージ。
実は、女性はすでに 生まれながらのバイオハッカー なのです。
データが示す“寿命”と“健康寿命”のギャップ
たとえ平均寿命が伸びても、「健康に過ごせる年数(=健康寿命)」が伴っていなければ、
その先の日々は、痛みや不調とともに過ごす可能性があります。
- 日本では、女性の平均寿命は約87歳、一方で健康寿命は約75歳 — その差は約12年。
- 世界的にも、寿命と健康寿命の差は拡大傾向にあり、2019年には平均で約9.6年。
- また、女性は骨粗しょう症など、加齢に伴うリスクが男性より高い傾向があります。
つまり「長く生きる」よりも、「健康で生きる年数」をいかに増やすかが、これからますます大切になっているのです。
バイオハックで体との対話が始まる
私が実践したのは、極端な食事制限や過剰な自己管理ではなく、
「自分の体の声を聞く」 というシンプルな行動でした。
たとえば、
- 血糖値のリアルタイム管理(CGM)で、食事や生活習慣が体にどう影響するかを「見える化」。
-
睡眠・食事・運動・休息という 基本の “土台” を整えること。
その結果、肌や消化の不調が改善し、日々の生活が格段に軽やかになりました。

テクノロジーも味方に。ただ無理はしない
バイオハック市場は拡大していますが、
高価なデバイスや過剰な健康法に飛びつく必要はありません。
本当に大切なのは、自分を理解して、自分に必要なケアを選ぶこと。
まずは基本を整えて、そこに合ったツールを “そっと”取り入れる。
それだけで、体は応えてくれます。
まとめ
日本のデータは、私たちに問いかけています:
「長く生きる」ではなく「健康に生きる」未来を、どう選ぶか?
女性は、生まれながら体と向き合う力をもっています。
そこに、科学的な知見と少しの意識をプラスして、
「心地よく、豊かに生きる時間」をできるだけ長く。
── それが、これからの女性のための
新しい “バイオハック” のかたちです。
シルクの足首ウォーマーで「ひなたぼっこしているような温かさ」を

締めつけずにむくみを緩和する足首ウォーマー。
その特徴的な「もこもこ」形状のウォーマーは、なぜこれほど愛され続けているのでしょうか?
Humming公式セレクトECショップでも人気のこの「足首ウォーマー」を手がける「イオンドクター」のブランドマネージャーの藤村さんに、 創業の背景から製品へのこだわり、そして愛用者の声を伺いました。
イオンドクターさんについてはこちら
ーー イオンドクターについて教えてください。
イオンドクターは、もこもことした形状が特徴のレッグウォーマーを主に製造販売している会社です。「天然素材」にこだわり、「締め付けない」「日本製」という点を大切にしています。
ーー 創業のきっかけは?
ちょうど今年で創業25周年を迎えるのですが、創業時に乳がんの手術でリンパ浮腫に悩むお客様からの声がきっかけでした。そのお客様は、圧の強い弾性ストッキングが苦手で、「締め付けず、天然素材で体を温め、むくみが取れるようなものが欲しい」というご要望から製品化がスタートしました。
View this post on Instagram
ーー 商品作りで特にこだわった点は?
大きく2つのこだわりがあります。
1. 天然素材と温かさの秘密:
- ウォーマーの中わたに、天然の鉱物パウダーを吸着させた綿を使用しています。
- このパウダーがご自身の体温に反応し、輻射熱(ふくしゃねつ)という形で熱を体に跳ね返して戻してくれます。
- 外側の生地も、肌に優しいコットン100%やシルク100%など、化学繊維を使わず天然素材にこだわっています。これは、創業のきっかけとなったお客様のように、手術の傷などがある方も安心して使ってほしいという思いがあるからです。
2. 締め付けない工夫:
- 一般的な毛糸のレッグウォーマーとは異なり、この特徴的なもこもことした形が「締めつけない」につながっています。
- 縫製の過程で、肌に縫い目が当たらないように裏側は一切縫い目が出ない形状です。
- 落ちてこないように、表面だけにシャーリング加工を施すことで、程よいホールド感を実現。「包まれているような着用感」で履いていただけるようになっています。
ーー締めつけないのに温かいのはなぜですか?
鉱物パウダーがご自身の熱をエネルギーとしているため、締めつけなくても温まります。電気なども一切使いません。また、製品の構造も工夫されており、実は生地と綿がべったりくっついているわけではなく、間に空間(空気層)がある三層構造になっています。この空気層でもしっかりと保温してくれるのが特徴です。
ーー商品を手に取ってくれた方に、どんな変化を届けたいですか?
まず、着用して「ほっとしていただきたい」という思いが強いです。創業時から「日だまりのような温かさがある」「ひなたぼっこしているような優しい温かさ」と多くの方に言われてきました。じんわりとした、その温かさを感じていただきたいです。

ーー愛用者の方から、具体的にどういった症状が良くなったという声がありますか?
イオンドクターは医療品・医療機器ではないため「治る」といった言及は難しいのですが、愛用者の方からは以下のような声が多く寄せられています。
- 寝つきが良くなり、眠りやすくなった。
- ウエストウォーマーをつけて寝るようになったら、夜中にお手洗いに起きなくなった。
- 生理痛の緩和。
- 妊婦さんの足のつりの予防・緩和(一部の商品は助産師会からの推奨もいただいています)。
ーーどんなアイテムがありますか?特に人気のアイテムは?
「首」がつくところはすべて使っていただけるものがあります。
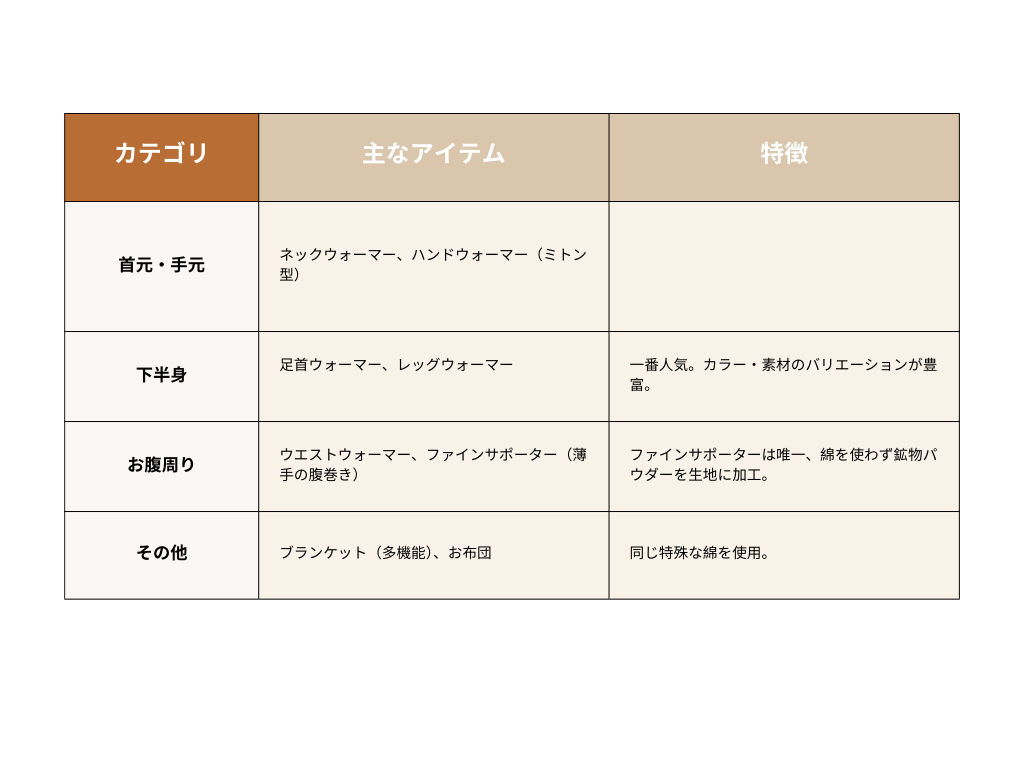
一番人気は、やはり足首ウォーマー、レッグウォーマーです。
ーーどのような方によく使われていますか?
一番多いのは女性です。ただ、最近ではスポーツシーンなどで男性の利用も増えており、一部キッズ商品も展開しています。本当に「皆さん一回はぜひ」という思いです。
ーー口コミで広まっている商品だと伺いましたが、広告などは行っているのでしょうか?
費用をかけての広告は一切やってきていません。一度手にとってくださった方が、娘さんやご両親にプレゼントするなど、口コミで輪が少しずつ広がっています。最近では、女優さん、俳優さん、モデルさんなどの著名人の方々が使ってくださっていることで、より若い層にも届き始めていると感じています。

ーー何年くらい使用できますか?
10年以上同じものを使っているというお客様もいらっしゃいますが、中に入っている綿が水分などを含んで少しずつへたってしまうため、新しいものとの温かさの感じ方に差が出てきます。
目安としては、2年〜3年くらいで買い替えられる方が多い印象です。外側の生地の摩耗が目立ってきたら変えるという方もいます。商品自体はずっと温かいですが、長く使える分、ご自身の感覚や使用頻度に合わせてご検討ください。
イオンドクターのウォーマーは、天然素材・締めつけない構造・中に綿が入った三層構造が大きな特徴です。さらに、職人さんが手間暇かけて手縫いで仕上げてくださっているため、大量生産はできませんが、日本製の丁寧な良さを感じていただけると思います。
見た目は可愛らしく「もこもこ」していますが、実は高性能な技術と職人さんの手仕事が詰まった商品です。「日だまりのような温かさ」をぜひ体験してみてください。
ハミングのウェブサイトでイオンドクターのシルク足首ウォーマーをぜひご覧になってみてください。
🔗 Humming公式セレクトショップでも販売中
https://shop.humming-earth.com/products/silk-ankle-warmer
心と体を整える、ヘルシー&マインドフルな料理本おすすめガイド

忙しさに追われる日々の中で、「何を食べるか」はつい後回しになりがちです。
それでも、食事は私たちの心と体を支える“いちばん身近なセルフケア”。
食材の選び方、調理のプロセス、ひと口を味わう時間。
そのすべてが、わたしたちの気持ちやエネルギーに大きな影響を与えています。
今回Hummingでは、「丁寧に食べる」「自分の体を尊重する」
そんなマインドを大切にした料理本を厳選して紹介します。
和食中心のものから、マインドフルを意識した食事や季節の食事を意識したものまで、
“食べること”を心地よく整えてくれる本ばかり。
自分のペースで、心と体に優しい食生活を始めてみませんか?
ヘルシー&マインドフルな料理本 おすすめリスト
『僕が食べたい和そうざい』笠原将弘
https://books.shufunotomo.co.jp/author/a62135.html
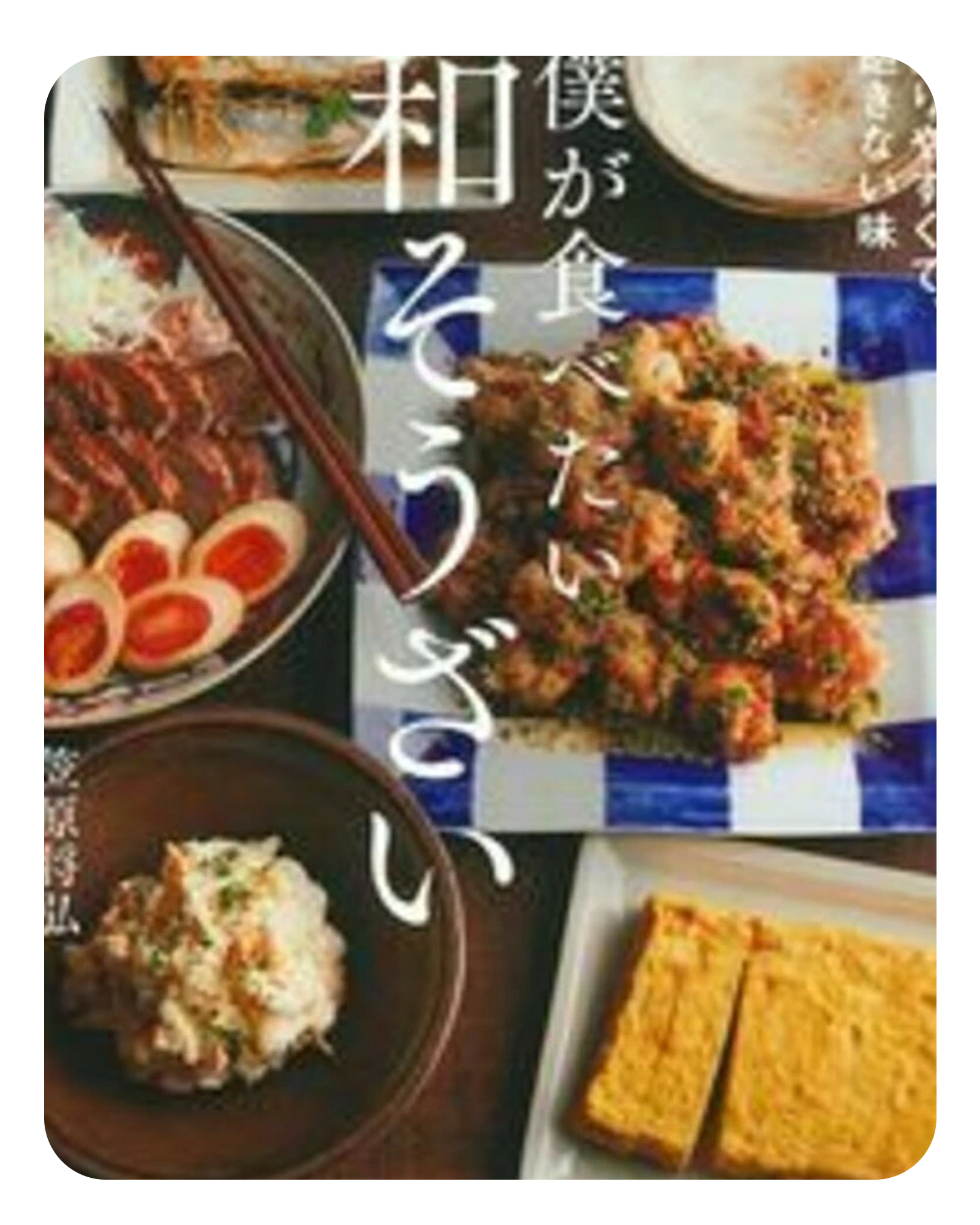
シンプルで体に優しい“和の常備菜”が中心。季節の食材を取り入れたバランスの良いレシピが多く、忙しい人でも無理なく作れる内容です。
こんな人におすすめ:
✔ 時短で健康的な食生活を整えたい
✔ 和食中心の生活をしたい
『おいしい健康の料理本』 おいしい健康編集部
https://oishi-kenko.com/
ジャンル:栄養計算/病院食の専門家監修/データ重視

人気アプリ「おいしい健康」から生まれた一冊。栄養バランスやカロリーが明確で、ヘルシーな和洋レシピが豊富。“食べて整える”を目指す人に。
おすすめポイント:
✔ 管理栄養士監修
✔ 健康診断が気になる人にもぴったり
『一汁一菜でよいという提案』 土井善晴
https://www.shinchosha.co.jp/book/103381/
ジャンル:ミニマル 和食/食の哲学/心の整え方
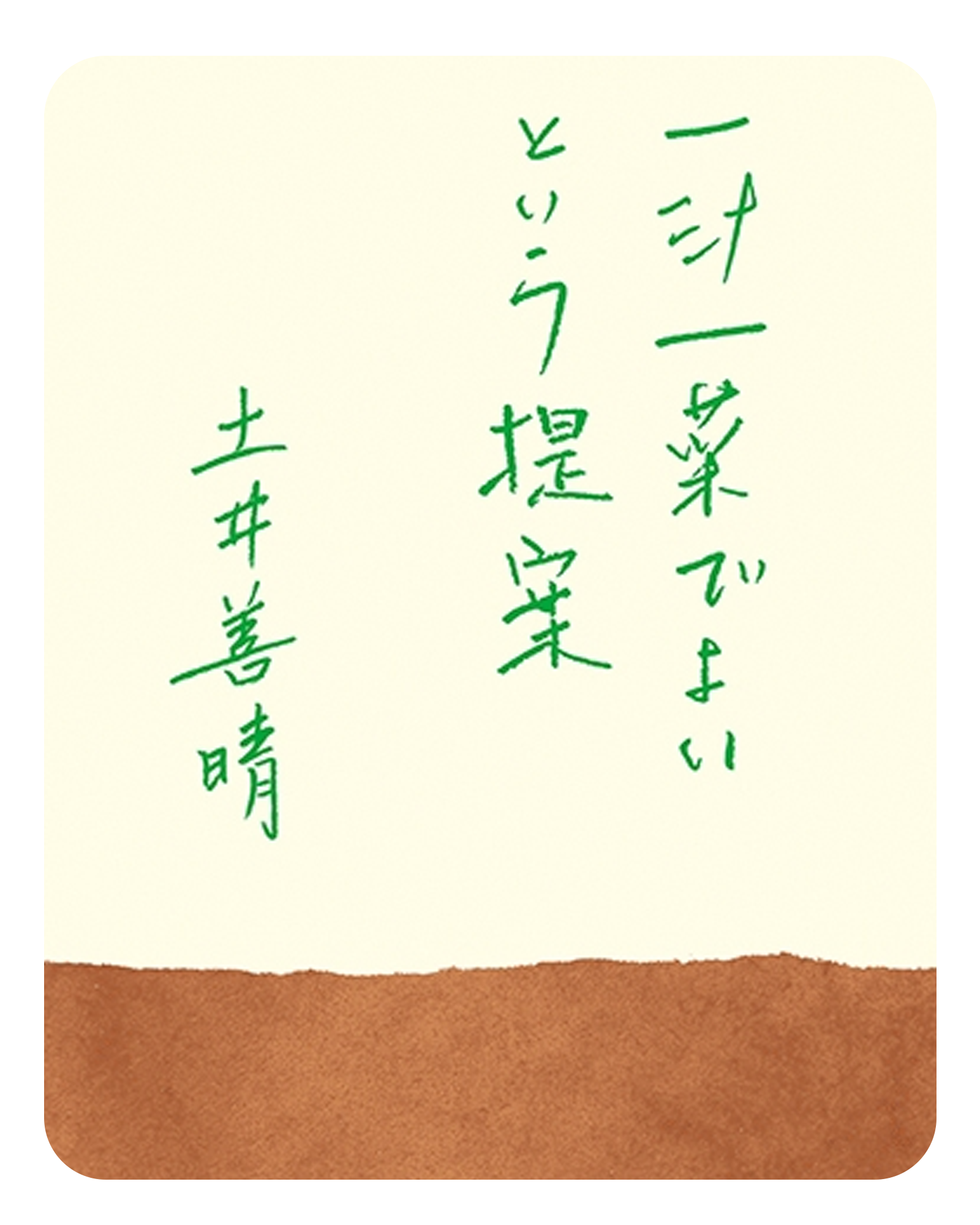
料理本でありながら、「食べるとは生きること」 を考え直させてくれる名著。難しくないレシピと食の思想がマインドフル。
こんな人におすすめ:
✔ “丁寧な暮らし”に興味がある
✔ 食事の概念から整えたい
『きょうの料理 わたしのいつものごはん』 栗原はるみ
https://www.yutori.co.jp/shop/g/gEBXX0006-000/
ジャンル:手軽 × 健康/家庭料理の第一人者
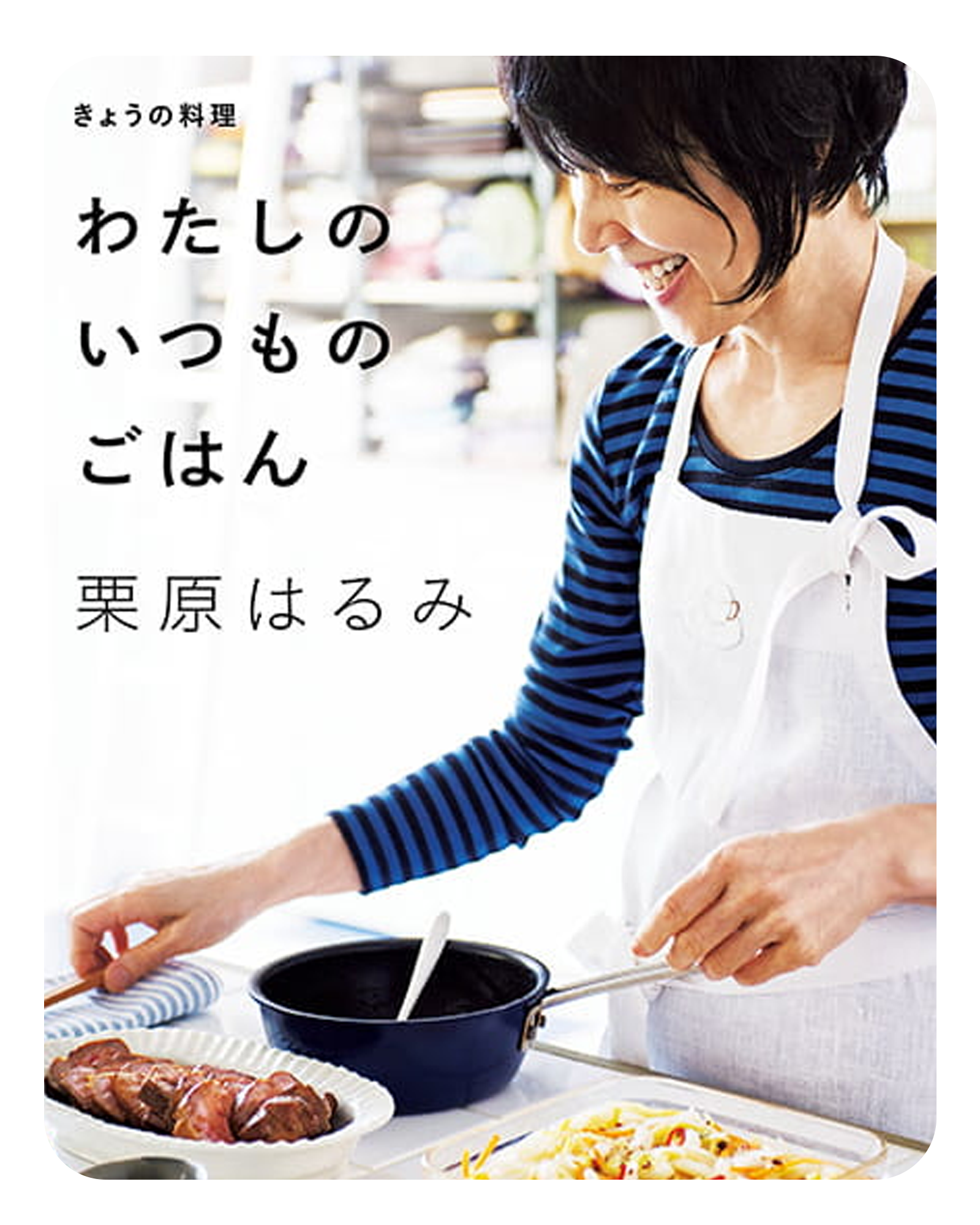
どんな家庭でも再現しやすい、手軽に作りやすいレシピが豊富。「調味料の無駄を減らして、簡単においしく」というマインドが健康的。
おすすめポイント:
✔ 家庭料理のプロの味
✔ 時短なのに心と体が喜ぶごはん
『藤井恵のからだリセットごはん』 藤井恵
https://www.shufu.co.jp/bookmook/detail/9784391164435/
ジャンル:家庭料理 × 健康/作りやすいレシピ
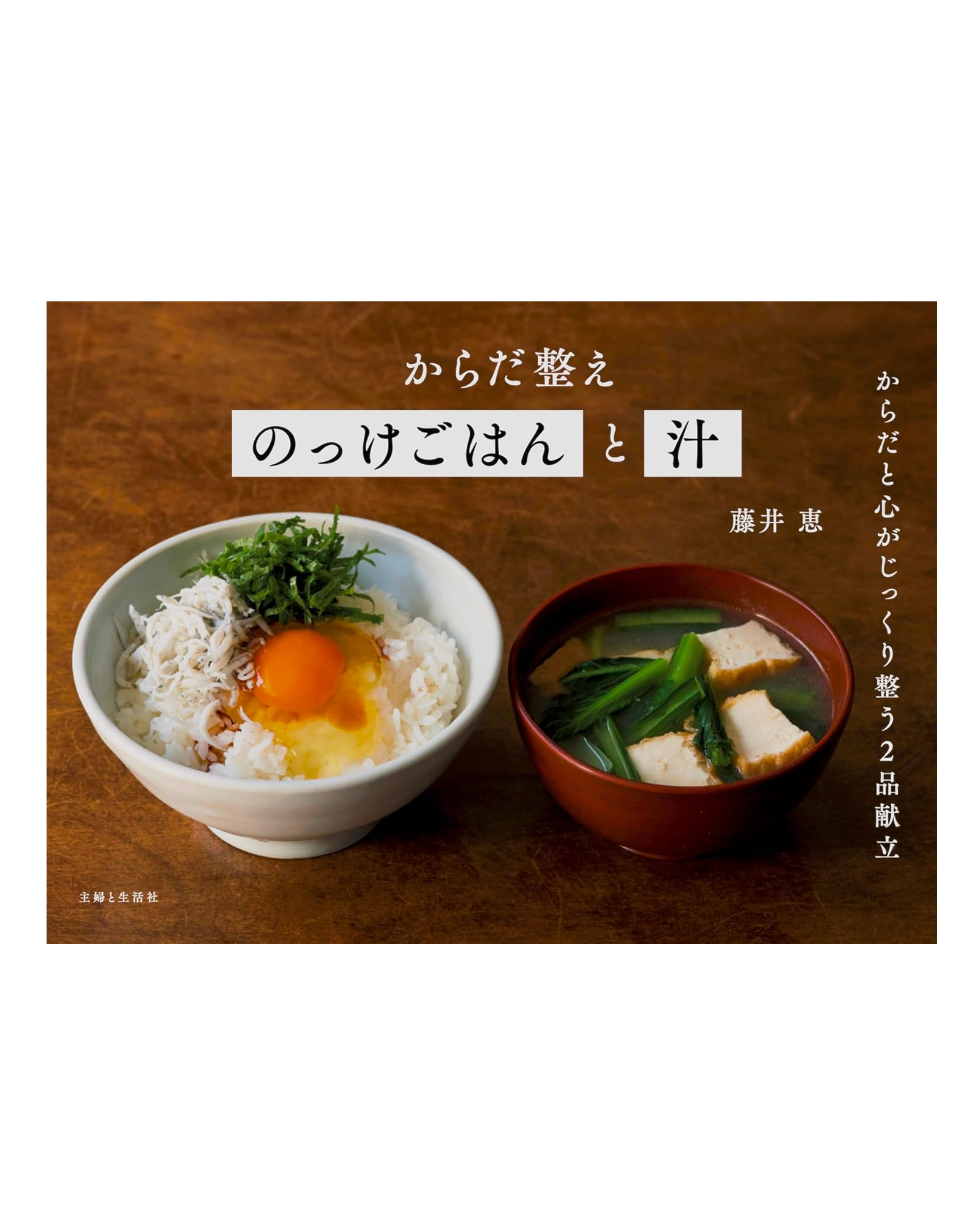
“体に優しい”に特化したレシピ集。調理が簡単で、忙しい人や料理初心者でも続けやすい。
まとめ
食事は、ただ体を満たすための作業ではなく、「今日の自分を大切にするための小さな儀式」でもあります。
忙しい日も、疲れた日も、ほんの少しの工夫で食卓はやさしい場所に変わる。
今回ご紹介した料理本は、
✔ 心を落ち着かせる“丁寧な食事の時間”をつくる
✔ 健康的で満足感のあるレシピに出会える
✔ 食に対する価値観を、自分らしく整えられる
そんな“暮らしの味方”になってくれるはずです。
あなたの食卓が、もっと心地よく、
もっとあなたらしいものになりますように。
【ハミングが届けるポジティブニュース】 世界の都市が命を取り戻す物語──100年ぶりによみがえるシカゴ川

私たちは、ふと目にしたニュースに心が重くなったり、暗い話題に引きずられがちです。でも、視点を少し変え、私たちの暮らしに身近な場所、「水」や「自然」に目を向けると、実は今、世界中で静かに、そして力強く、ポジティブな変化が起きていることをご存知でしょうか?
遠い海の向こう、アメリカの巨大都市シカゴで、人々の意識と行動が100年以上失われていた都市の宝をよみがえらせました。その宝とは、かつて「汚くて、誰も見向きもしなかった」川。私たち一人ひとりの小さな選択が、未来を変える大きな力になる。今回は、そんな心が温まるストーリーをお届けします。
“世界中で暗いニュースに心が沈みがちな中、100年以上汚れて放置されていたシカゴ川が、人々の意識と行動によって再び命を取り戻したように、私たち一人ひとりの小さな選択が自然をよみがえらせる大きな力になることを示すストーリーです。”
中国の長江、フランスのセーヌ川、そしてアメリカのシカゴ川。かつては、生活や産業の利便性を最優先し、汚水を垂れ流すことが当たり前でした。川は、ただの「排水路」で「見えないもの」として扱われていたのです。
鉄道が発達する前、シカゴは船での物流が主流だったため、川は貨物輸送のために運河化されました。川底は掘り起こされ、岸辺は鋼鉄のパネルで囲まれました。これにより、川辺の植物や野生生物の住処は一夜にして消滅。残ったのは、汚染に強いわずかな魚種だけが細々と生きる「巨大な金属とコンクリートの排水路」でした。
あらゆる廃棄物の捨て場所となっていた当時のシカゴ川の悪臭と汚染は、私たちが想像する以上です。シカゴの歴史的建造物の多くが、「川に面した窓がない」という事実は、当時の状況を如実に物語っています。
問題は、ただ汚いということだけではありません。人間の排泄物に含まれる糞便性大腸菌群は、様々な病気の原因となります。さらに、窒素やリンといった過剰な栄養分が水に流れ込むことで、他の生命を窒息させてしまうのです。川は、文字通り「生命を奪う場所」となっていました。

Kayakers on the Chicago River – credit Jrrugg94, CC 3.0. BY-SA
この絶望的な状況を変える大きな転機となったのが、1972年に成立したアメリカの「クリーン・ウォーター法」。この法律は、許可なしの廃棄物の投棄を禁止しました。「排泄物を川に流すのをやめる」という、極めて基本的な一歩が、川の再生の土台となったのです。
さらに行政と市民は惜しみない努力を重ねました。豪雨の際に下水が川に溢れ出すのを防ぐため、下水貯蔵システムを近代化する壮大なプロジェクトに、何百万ドルもの公的資金が投じられました。
“シカゴ川は排泄物や汚染物質で「生命を奪う場所」と化していたものの、1972年のクリーン・ウォーター法と行政・市民の継続的な取り組みによって再生への大きな一歩が踏み出された。”
さらに、市民の草の根の活動も大きな力となりました。Urban Riversのような非営利団体(NPO)は、野生生物を助けるために立ち上がりました。彼らが作った「ワイルド・マイル・エコパーク」は、鋼鉄のパネルで囲まれた川に、浮遊式のトレイルを設置することで、水中生態系のための巨大な浮遊システムを創り出しました。
そして今、その努力は目覚ましい成果となって現れています。かつて最低5種しか確認できなかった魚類は、なんと77種にまで激増。スナッピング・タートル(カミツキガメ)や淡水ムール貝が川に戻ってきています。
最も感動的なニュースは、シカゴ川が100年以上ぶりに市民に水泳を許可する日が目前に迫っているということ。川は「汚染源」ではなく、「生命を育む場」へと大きな変化を遂げたのです。
“100年以上汚染されていたシカゴ川が市民が泳げるほどに回復し、周囲の土地価値や都市の活気まで取り戻した事例は、私たち一人ひとりの意識と行動が深刻な環境問題をも未来へと好転させる力を持つことを示している。”
汚染がなくなり、悪臭が消えた川沿いの土地は、新しい価値を生み出し始めました。川の支流沿いでは、不動産がブームとなり、古い工業団地だった場所は、オフィスや音楽会場に生まれ変わっています。川が、人々に安らぎと散歩の場を提供し、都市に活気と命を吹き込む役割を取り戻したのです。
このシカゴの物語は、遠い異国の話ではありません。私たち一人ひとりが環境に対する意識を少し変えて協力し、法や技術、そして何よりも「自然を取り戻したい」という強い意志を持つことで、どんなに深刻な問題でも解決できることを証明してくれているのではないでしょうか。
参考記事: https://www.goodnewsnetwork.org/chicago-river-follows-the-seine-to-become-biodynamic-and-swimmable-once-again/
感動の子育て。教え込むより導く、 という方法【Editor’s Letter vol.02】
Hummingの編集長 永野舞麻がカリフォルニアから配信する「Editor’s Letter 」。日々の暮らしで見つけたこと、感じたこと、考えたことをシェアします。

共感できる教育法を探して
私たちが、カリフォルニア州北部にあるこの町に住むことを決めた理由の一つに、とても素敵な学校がたくさんあった、ということがあります。
まだ日本に住んでいたときのことですが、長女が1歳半になったころ、お友達に出会えるようにと保育園探しを始めました。夫がアメリカ人ということもあり、インターナショナルスクールもたくさんあたってみましたし、“モンテッソーリ教育”の学校、日本の保育園などなど、十数校回ってみました。
“北カリフォルニアに移住する前、日本で十数校を見学した中で唯一強く心に残った“シュタイナー教育”の保育園に直感的に惹かれたことが、家族がこの町を選んだ大きな理由の一つになっている。”
そのなかで、一校だけ、二人の記憶に鮮明に残った学校がありました。その学校の見学時間内に気がついたことは、子供たちは子供たちらしく遊んでいるのですが、どこか落ち着きが感じられ、何か不思議な安定感があり、先生たちも、声を張り上げて子供たちに言うことを聞かせようとしていないのです。
帰り道、夫と私は同時に「この学校しか考えられないね」と直感で決めた保育園が、“シュタイナー教育”に基づいた方針の高輪シュタイナー子ども園でした。
私自身、保育園をモンテッソーリ教育のところに通わせてもらっていたため、モンテッソーリについては少し知識がありましたが、シュタイナー教育についてはまったく認識がなく、一から本などを買い集めて読んでみました。

「からだ」と「こころ」と「あたま」
シュタイナー教育では7歳ごろまでは「からだ」を、14歳ごろまでは「こころ」を、21歳ごろまでには「あたま」を、この順序に沿って育てるのが大切だと提唱しています。
大人になったときに、子供たちにどんな人になって欲しいかーーを、常々、一緒に話している私たち夫婦にとっては、ぴったりな教育方針だと思いました。
“シュタイナー教育は「からだ・こころ・あたま」を段階的に育てる理念を持ち、夫婦が望む“バランスの取れた自立した人間像”と一致していたため、短期的な成長より長期的なビジョンを重視して子どもと向き合う姿勢に強く共感した。”
相手の気持ちを汲み取れて、責任感があり、自由な心を持ち、地に足が着いていて、想像力に長けた、自立したひと。子供たちが、そんなひとに育っていってくれたらいいなと思っています。
何歳までに自転車が乗れる乗れない、何歳なのにお行儀が良い悪い、学校での勉強ができるできないということよりも、長い目で見た“子供に対するビジョン”をしっかり持って接していくことを心がけています。
身体だけ発達しすぎるのも、感情的になりすぎるのも、頭でっかちになりすぎるのもよくなく、大人になったときに「体と心と頭がバランスのとれていることが大切だ」とシュタイナー教育は考えます。

知能を発達させるのは早ければ早いほどいい、という考え方もあります。私も、以前はそう考えていたこともありました。
幼い子どもに対して、机に座った教育をしようとすると、子供たちは一ヵ所にじっとしていられません。そんなとき、大人たちはーー「ここに座りなさい、これを書きなさい、これを読みなさい」と、段々と命令口調になっていってしまいます。
強制させられた環境で、脳は効率よく学ぶことはできません。
7歳くらいまでの子供たちは、常に体の一部を動かして、何かを触って、肌で感じて「自分はここにいる、地球にいる」という感覚を最大限に感じたい生き物なのだと、三姉妹を育てながら感じています。
何時間もじっとしろ、お行儀よくしろ、座っていろ・・・などと言うのは、「からだ」を一番に育てたい時期には逆効果。幼い子供たちは晴れでも雨でも嵐でも、外に出て肌で痛いほど世界を感じることが、一番大切なのです。

そのため、シュタイナー教育ではテレビ・ビデオ・CDなどは極力見せない、聴かせないようにします。
見ている間、せっかくの「からだ」を育てる時間を「あたま」ばかりを使う時間にしてしまうのと、映像などで頭に入ってきた情報は刺激が強過ぎて、子供たちの限りない想像力に限界を与えてしまうからです。
“シュタイナー教育の「子供は模倣の生き物」という理念に基づき、私たちはテレビやデジタル機器を排し、まず大人が望む行動を実践して見せることで、子どもの想像力と健やかな成長を守る生活スタイルを徹底している。”
「子供は模倣の生き物」。これはシュタイナーの先生たちがよく言うことなのです。
子供たちに外で遊んで欲しけれは、自分がまず外へ行く。
本を読んで欲しければ、自分が本を読む。
歯磨きをして欲しければ、自分がまず歯磨きをして見せてみる。
自分自身が実際に行動して見せてみるだけで、幼い子供たちを促し、実際に行動に移す様子をみることができると、まるで魔法のような感覚を覚えます。
「親の背を見て子は育つ」というのは本当だと感じます。
なので、私たちの家にはテレビを置いていません。私たちがついついテレビを見てしまっていたら、子供たちもきっと同じようにテレビを見たがるでしょう。携帯電話も、できる限り子供たちの前では使わないようにしています。
極端なように思えるかもしれませんが、これくらいの決意と姿勢が子供には理解しやすいと思っています。
焦らない子育て
私も夫も、シュタイナー教育で娘を育てはじめてから、どんなに周りの同じ歳の子供たちが字を読めても、焦らないようにしました。そして、娘に無理に字を読ませたり、覚えさせたりしようとはしませんでした。
“親が焦らず比べず、娘の「学びたいタイミング」を信じて寄り添い続けた結果、9歳で一気に読書の花が開き、興味が内側から湧き上がる瞬間に大人がそっと導くことの大切さを強く実感したエピソードです。”
子供が一番不安になるのは、親が不安になっているとき。どんなときもどっしり構えていようと、心に決めていました。
「興味のあることには時間もかけられるし、集中できる」ということは、大人も子供も同じだと思います。
子供の学びたい気持ちが満杯になったときに起こる、乾いたスポンジがものすごい勢いで水を吸収していくような、その学びたくて仕方のない様は、隣で見ていて気持ちがいいものです。
長女は6歳、7歳、8歳が過ぎても赤ちゃん用の本しか読めなかったけれど、毎晩一緒に本を読むことだけは続けて、決して他のメインストリームの学校に通っている子供たちと比べませんでした。
少しずつ興味が出てきた段階では、標識を読んだり、レストランごっこでメニューを書いてみたり、妹たちに本を読んでみたりしてはいましたが、スラスラ読み書きできるところまでは今一歩進まず、私が一緒に練習してもすぐに飽きてしまうようでした。
9歳になり、コロナ禍で始めたホームスクーリング(学校に通学せず、家庭で学習を行うこと)で出会った先生に恵まれたこともあり、一気に花が開くように文字を読み出しました。
なぜ?どうして?もっと教えて!もっと知りたい!ーー内側から出てくるどうしようもないほどの抑えきれない衝動をうまく使って、学びにつなげていく。それをするのが、親と先生の役目だと感じます。
今では、もう誰が止めても止まりせん(笑)。つい2、3ヵ月前まで絵本を読んでいた子が、今では『ハリー・ポッター』を読んでいる姿には感動を覚えます。
「教え込む」よりも「子供たちの興味が導く方向へ、ベストなタイミングで大人たちが誘導する」
これは、最近私たちが親として目の当たりにした、何にも変えがたい体験でした。
家計管理が劇的にラクになる「ディスクリナリーファンド」という考え方

“予算の中にもう一つの予算”をつくるだけで、暮らしが安定する
家計簿をつけることは、どんな金銭的目標にとっても大切な第一歩です。
でも実は、この“最初の一歩”こそが一番難しいもの。
理由はシンプルで、人生には予測できない支出が山ほどあるからです。
結婚祝い、医療費、急な出費…
1つひとつは小さくても、何度も繰り返しやってきます。
私自身、細かすぎる予算に苦しみ、逆にざっくりしすぎてお金が足りなくなってしまった時期もありました。
その中でたどり着いたのが、
ディスクリナリーファンド(自由枠)という解決法です。
おすすめ記事 ▶ お金との健全な関係を築くために:自分に合った予算管理を見つけよう
ディスクリナリーファンドとは?
毎月の支出を組み立てたあとに設ける、“予測できない支出”専用のお金。
いわば、
✔ バッファー
✔ 心の余裕
✔ 生活の安全装置
として機能してくれます。
カバーできるものは幅広く、
・車の修理
・薬の値上げ
・本や化粧品
・学校の教材
・突然必要になったプレゼント
・季節ごとの買い足し
など、現実的に必ず発生する雑多な支出すべて。
余ったらどうする?
月末に残った自由枠は、あなたの目標に合わせて活用できます。
- 貯金に回す
- 旅行などの目的別の口座へ入れる
- 投資アプリで運用する
- 翌月の自由枠へ追加
- 別カテゴリのオーバー分に充当
自由度が高く、家計のストレスが軽くなります。
いくら設定すべき?
一般的な流れは次のとおり:
- 家賃・光熱費など必須の支出を確保
- 収入の10%以上を貯金へ
- 月ごとにほぼ一定の支出項目を設定
- その残り(または少し控えめの金額)を自由枠に設定
さらに、自分の“お金のクセ”も理解すると効果UP。
- 節約しすぎて友達の誘いを断りがち?
→ 自由枠があれば気軽に楽しめる - 相手への奢りやプレゼントでつい使いすぎる?
→ 自由枠内なら安心して好意を表現できる
数字は何度も調整していい
予算に正解はありません。
ガソリン代のように月ごとに変動するものもあるし、季節で支出が増減することもあります。
ディスクリナリーファンドなら、“毎月違う生活リズム”に柔軟に対応できます。
予想外の駐車違反の罰金も、これがあればパニックにならない。
まとめ
✔ 家計管理のストレスが減る
✔ 突発的な支出に動じなくなる
✔ 貯金や投資も進みやすくなる
✔ 自分に合った家計バランスが見つかる
ディスクリナリーファンドは、小さな工夫で大きな安心をつくる家計管理術。
あなたの暮らしにも、きっと余白と安定をもたらしてくれるはずです。
「時間をお金で買う」価値はある?時間とお金の使い方を見直すためのガイド

忙しさに追われる日々の中で、
「もっと時間があったらいいのに」と思ったことはありませんか?
私たちに与えられた1日は、誰にとっても24時間。
増やすことはできないけれど、 お金の使い方を少し見直すことで “時間をつくる” ことは可能です。
料理、掃除、買い物、片づけ。 やらなきゃいけないことが積み重なっていくと、
心にも体にも余白がなくなっていく。
おすすめ記事 ▶ お金をかけずに予算内で夏を楽しむ方法
お金で換算できない“時間の価値”
お金はまた稼げるけれど、失った時間は戻りません。
家族と過ごす時間、子どもと遊ぶ時間、パートナーとのデートなど、
数字では測れない価値があります。
19世紀アメリカの作家で自然哲学者でもあるヘンリー・デビッド・ソローの言葉にあるように、 「物の価格とは、それに費やした“人生の量”である」
という考え方は、時間の重さを改めて感じさせてくれます。
そんなときこそ、「自分の時間を守るために、お金を使ってもいい」
という新しい視点を持ってみませんか?
お金を払って時間を買うべきタイミングとは?
大切なのは、自分の予算と優先順位に合っているかどうか。
時間を買うことが“価値になる”具体例
- 家事代行を頼んで、子どもとの時間を増やす
- 忙しい日はテイクアウトを利用して、夜の疲れを軽減する
- 食材キットを使って平日の負担を減らす
- 旅行帰りに洗濯代行を頼む
- 食品配達を利用して運動や読書の時間を確保する
こうした選択は、心の余裕をつくり、暮らしを整えてくれます。
ただし、「時間を買う」を言い訳にして浪費しすぎないよう注意も必要です。
時間とお金は“交換”だけではなく、お互いを助け合う
時間をうまく管理すると、無駄な出費が減ったり、お金を上手に管理すると、時間を生むためのサービスを利用できるようになります。
最終的に、お金と時間はどちらも自分の価値観に沿って生きるためのツールです。
時間を買うべきか判断する2つの質問
1. 予算に収まる?
収まらないなら、他の支出を減らせるかを検討。
どうしても無理なら、その支出は見送るべき。
2. その“余った時間”に価値がある?
家族時間・運動・学習・休息など、人生の優先事項に時間を使えるなら“買う価値あり”。
ただ嫌なことを避けたいだけなら、もう少し慎重に判断しましょう。
時間を買うことは、自分を大切にする行為
時間は増やせないけれど、お金の使い方で“暮らしの余白”をつくることはできます。
それは贅沢ではなく、
あなたの心身の健康を守るための優しい工夫。
迷ったときは、
「これは今の自分に優しい選択だろうか?」
と問いかけてみてください。
あなたの時間は、あなたの人生そのものだから。
【映画レビュー】Silver Linings Playbook が描く、喪失と再生のリアリティ

Copyright: © 2012 The Weinstein Company. All Rights Reserved.
悲しみって、本当に不思議な感情ですよね。
最初は静かに寄り添っているのに、気づけば糸みたいにじわじわ広がって、体が動かなくなるくらい重くのしかかってくる。
『世界にひとつのプレイブック(Silver Linings Playbook)』は、そんな“喪失の悲しみ”をどう乗りこえていくかを描いた映画です。2012年に公開されて、話題にもなった作品だから、きっと観たことがある人も多いと思います。私もそのひとり。でも今回久しぶりに観て、前とはまったく違う視点で物語に入り込んでいました。
“『世界にひとつのプレイブック』を久しぶりに観て、登場人物たちの不安定さは“扱いづらさ”ではなく深い悲しみと孤独から来ていたのだと気づいた”
初めて観たときは、正直ほとんどのキャラクターが苦手でした。
みんな怒鳴ってるし、情緒不安定だし、責任逃れするし、ずっと不機嫌。ジェニファー・ローレンスとブラッドリー・クーパーの魅力がなかったら観るのをやめていたかもしれません。
でも今回は、少し立ち止まってみたんです。
声のトーンや仕草、表情のちょっとした揺れまで、ちゃんと観察してみた。
そして苛立つ代わりに、「なんでみんなこんなふうに振る舞うんだろう?」って、考えてみました。
すると気づいたんです。
彼らが“扱いづらい人たち”に見えるのは、ただ、深く傷ついているからなんですよね。
悲しみって、あまりにも痛みが鋭すぎて、世界から切り離されたみたいな孤独に陥ることがある。
そんな状態で“いつもの自分”なんて保てるわけがないんです。
結婚を取り戻したいのは、愛のためか、それとも心を守るためか
パットは、妻の浮気相手を殴りつけてしまい、精神科施設に送られます。しかもそのとき妻は、よりにもよって二人の“結婚式の曲”を流していたという…。暴力は絶対ダメだけど、正直パットに同情してしまう気持ちもわかります。
でも、パットは裏切られたのに「まだ結婚生活はとり戻せる」と思い込んでしまう。ニッキはまだ自分を愛している、自分が変われば何とかなる、と。
パットは双極性障害とアンガーマネージメントの問題を抱えていて、それはずっと胸の奥で静かにくすぶっていたものでした。

Copyright: © 2012 The Weinstein Company. All Rights Reserved.
彼の育った家も安定とは程遠くて、こだわりが強い父親と、なにかと張り合ってくる兄。感情的なケアなんて与えられず、心はずっと雑に扱われ続けてきたんです。だから心は少しずつひびが入り、最後には壊れてしまった。
だからパットが必死に結婚生活を取り戻そうとするのは、“愛”というよりも、トラウマから自分を守るため。
本当は結婚生活が終わっていると認めたくない。認めた瞬間、自分が失ったものの大きさに耐えられないから。
悲しみが深いと、現実を見るより“否定してしまうほうが楽”に感じるときがありますよね。
私たちは痛みに耐えるために、時々“別の現実”を心の中に作り上げてしまうんです。
“パットは裏切りの痛みと長年のトラウマから現実を直視できず、壊れた心を守るために「まだ結婚は修復できる」と思い込んで執着してしまっている”
そしてパットは、夫を亡くして自分なりの悲しみを抱えているティファニーと出会います。二人が最初に話した瞬間から、「あ、この二人は似た者同士だな」とわかるくらい相性がいい。パットがズバズバ物を言えば、ティファニーもすぐに言い返す。彼が彼女の夫について踏み込んだ質問をすれば、彼女は彼のフットボールのジャージをバカにする。
周りから見ればめちゃくちゃ気まずい会話。でも、二人にとってはすごく刺激的なんです。
ようやく“自分の強さに合わせて返してくれる相手”に出会えた感じ。
恥と偏見に覆われた“性”と“怒り”の裏側で、二人が見つけたほんとうのつながり
ティファニーは、孤独と悲しみをごまかすために、人の体温にしがみついてしまった。でも突然パートナーを失ったら、誰かの温もりを求めてしまうのは自然なことだと思う。
でも周りの人たちは、その奥にある痛みを見ようとしない。
パットの怒りは“怖いもの”として避けられ、ティファニーの性にオープンな態度は“都合よく扱えるもの”として見られる。
二人は“変な人”扱いされ、まるで人間じゃなく問題そのものみたいに扱われている。
パットとティファニーはお互いの弱さを理解し始めるけれど、パットはまだ“自分とティファニーの間に線を引きたい”と思ってしまう。
“ティファニーとパットは周囲から“問題のある人”と誤解され続ける中で、お互いの痛みと弱さを理解し合い、ダンスをきっかけに少しずつ心を取り戻していく”
ニッキを理由に距離を置こうとしたり、“ティファニーみたいな人とは…”と傷つくようなことを言ったり。
本当は彼が一番理解できるはずの彼女の痛みに。
人って、あんなにセックスが好きなのに、話題になると途端に恥ずかしがるんですよね。
ティファニーはそこを恥ずかしがらず、自分の セクシュアリティ をちゃんと受け止めていて、パットにもそれを突きつける。

Copyright: © 2012 The Weinstein Company. All Rights Reserved.
「あなたは生きるのが怖いのよ!」と叫ぶシーンがありますけど、まさにその通り。
パットは“ニッキへの悲しみ”に自分を包み込んで、自分の一部を消してしまっていたんです。
そこでティファニーはこう提案します。
「ダンスコンテストのパートナーになってくれたら、ニッキに手紙を届けてあげる」と。
最初は抵抗するけど、やがてダンスという“リズムとルール”がパットの心を落ち着かせていく。
動きに集中することで心が静まり、ようやく“自分の気持ちを感じる余裕”が生まれてくるんです。
悲しみの奥にある小さな希望
多くの人は、この映画を「壊れた二人が互いを癒やしていくラブストーリー」と言います。それも間違いではないし、二人がキスしたシーンで私も思わず笑顔になりました。
でも実はこの映画、もっと深いところを描いている気がします。
地下でひっそり泣いている夫。年金を失って息子に執着してしまう父親。依存症から抜け出そうとしている友人。
みんなそれぞれ傷を抱えて、つまずきながらも前へ進もうとしている。
この映画は“人生のやり直し”や“悲しみの先に続く道”についての物語なんだと思います。
悲しみの渦に飲み込まれたとき、人は簡単に希望を見失う。でも、この映画は「それでも一歩ずつ進んでみよう」と静かに背中を押してくれる。
そして、人の“混乱”を外側からジャッジするのではなく、その奥にある痛みに目を向けようと教えてくれる映画でもあります。
もし初めて観たときの自分に声をかけられるなら、こう言いたいです。
「そのカオスの裏には痛みがあって、その痛みの奥には、確かに癒しの芽があるよ」と。
【コアバリューとは?】自分の価値観の見つけ方と自己理解を深める方法

自分の「大切にしたいもの」を見つけるために
人が自分らしく生きようとするとき、最初に向き合うべきものがあります。
それが 「コアバリュー(価値観)」。
毎日の選択、感情の揺れ、人間関係の心地よさ。
実はそのすべてが、私たちがどんな価値観を大切にしているかによって変わります。
でも、そもそもコアバリューって何?
どうやって見つけるの?
今回は、Hummingらしく“やさしく・ていねいに”その答えを紐解いていきます。
おすすめ記事 ▶ 心の健康を保つための方法
コアバリューとコアビリーフの違い
まず知っておきたいのは、コアバリュー(価値観)とコアビリーフ(信念)は似ているようでまったく違うということ。
● コアビリーフ(信念)
「人は優しい」「世界は危険」などのような、世界の見え方そのもの。
人生経験や環境によって育っていく“根っこ”の部分です。
● コアバリュー(価値観)
「正直さ」「自由」「家族」「成長」など、
“どう生きたいか”を判断するための指標。
信念は世界を見るレンズ。
価値観は、その世界の中で何を大切にするかの基準。
この違いを理解すると、価値観の見つけ方がぐっと明確になります。
コアバリューの見つけ方:実践ステップ
自分の価値観を見つける3つのステップ
STEP 1:気になる言葉をすべて拾う
「誠実」「安心」「自由」「挑戦」…
まずは直感でOK。気になったカードを全部集めてみる。
STEP 2:似ているテーマでまとめる
- 創造性・表現・革新
- 達成・成果・熟達
- 誠実・信頼・正義
並べてみると、自分の“癖”や“傾向”が浮かび上がります。
STEP 3:最終的に5つに絞る
「家族 vs 自律」
「安定 vs 冒険」
自分にとってどちらがより大切か、一つひとつ比べていきます。
ここで初めて、心の奥がはっきりと語りはじめます。

価値観って、実はとても複雑
価値観は美しいけれど、時にとてもあいまいです。
たとえば——
「正直でいたい」と思う一方で、
誰かを傷つけたくない優しさも大切にしたい。
「豊かさ」という言葉にも、
贅沢の意味にも、感謝の意味にもなる。
そして何より、
「優しさ」「思いやり」「忍耐」など、
“良い人そうな価値観”を選びたくなる私たち自身のクセ。
でも、本当に大切なのは
“誰かにとって良い価値観”ではなく、
“自分にとって本当に必要な価値観”を選ぶこと。
ここを間違えると、心がちぐはぐになり、
なんとなく生きづらさを抱えることになります。
Be Honest With Yourself
「こうあるべき」ではなく、「私はどうありたいか」
私は長いあいだ、“理想的な社会人像”にあうように生きていました。
忙しい、ストイック、なんでもこなす。
そういう“優等生のよろい”が、自分を守ってくれると思っていた。
でも結果的に、
一番大切にしたかったものを見失ってしまった。
だからこそ、価値観を選ぶときは
正直であることがいちばん大切。
- 時間の使い方
- 反応の仕方
- 心が動いた瞬間
それらは、あなたが思う以上に“本当の自分”を教えてくれます。
自分の価値観を正しく理解するための方法
1. 自分の時間の使い方を見る
行動は言葉よりも正直です。
2. 反応パターンを振り返る
忠誠心が大事なら、
- 最後に忠誠を示したのはいつ?
- 裏切りの場面にどう反応した?
など具体的に振り返ります。
3. セラピー・対話・日記で深掘りする
自分では気づけない自分の傾向や偏った考え方が見えてきます。
4. 意図を問う習慣を持つ
ヨガ、タロット、読書会など“自分のアイデアを生活で使う”習慣は理解を深めます。
目標は「認知的一貫性」
=信念・言葉・行動がそろった状態のこと。
心が安定し、満足感のある生き方につながります。

“あるべき自分”ではなく“本当の自分”を選ぶ
社会的に良く見える価値観を選ぶと、心が乱れます。
私はかつて“理想の働き方”に合わせて自分を演じ続けた結果、疲弊し、自分を見失いました。
価値観を選ぶときは、徹底的に正直になることが大切です。
5つのコアバリュー(例として)
1. 知恵(Wisdom)
視野の広さ、判断力、自己認識。
感情に飲まれず、複数の視点から物事を見る力。
2. 説明責任(Accountability)
意図と行動の差を縮めるための誠実さ、謙虚さ、責任感。
3. 信頼(Trust)
相手の言葉と行動が一致していること。
完璧さではなく、一貫性と誠実さ。
4. 成長(Growth)
知的・精神的・感情的な発達。
勝ち負けよりも、「前より良くなっているか」を重視。
5. 好奇心(Curiosity)
探求心、柔軟性、学ぶ姿勢。
偏見を減らし、驚きや発見を人生に広げる力。
自分の価値観に沿って生きるということ
価値観を知ることは、自分を愛する方法のひとつ
あなたのコアバリューは、誰とも比べる必要がありません。
同じ言葉を選んでも、解釈は人それぞれでいい。
大切なのは、
その価値観があなたの人生に平和と方向性をもたらすかどうか。
そして価値観は変わってもいいし、成長していってもいい。
今の自分に合ったものを、やさしく選び直せばいい。
あなたがあなたをより深く理解するための
ひとつの小さなきっかけになりますように。
白浮きしない、ベタつかない。“心地よいオーガニック”を追求したluamo(ルアモ)の日焼け止め開発ストーリー

そのオーガニック製品は安全ですか?
実は日本には明確なオーガニック基準がありません。
だからこそ、大切なのは「何を選ぶか」です。
今回お話を伺ったluamo(以下、ルアモ)は、ヨーロッパの厳しいオーガニック基準を土台に、日本人の肌に寄り添った “白浮きしない・ベタつかない” 心地よさを追求し続けているブランド。
そのこだわりが詰まった日焼け止めが、HummingセレクトECショップでも人気の 「ルアモ オールデイプロテクト UVアクアヴェール」 です。
肌が弱い方でも毎日気持ちよく使える理由を、株式会社ロゴナジャパン ルアモ開発チームの飯田さんにお伺いしました。
luamoについてはこちら
株式会社ロゴナジャパンにて取扱いのブランド「LOGONA(ロゴナ)」についてはこちら
白浮きしない。ベタつかない。心地よいオーガニックの日焼け止めを作りたい
ールアモはどんな思いから生まれたブランドなのでしょうか?
私たちロゴナジャパンは輸入代理店として、ロゴナをはじめとするヨーロッパのオーガニックスキンケアを日本に紹介しています。まだ日本でオーガニック認証の選択肢が少なかった頃から、「品質が確かなものを届けたい」という気持ちで取り組んできました。
ただ、ロゴナはヨーロッパを中心としたブランド。スキンケアもメイク品も、白人の肌を基準に作られた処方や色味が多く、日本人の肌には100%フィットしない部分がありました。
たとえば、オーガニックの日焼け止めは、肌にやさしい一方で、「ベタつく」「白浮きする」といった声を日本のお客様からいただくことがありました。
ヨーロッパでは少し日焼けした肌を健康的と捉える文化もあり、年間を通して日焼け止めを使う日本とはニーズが異なります。そこで「日本のお客様にもっと満足いただけるオーガニックの日焼け止めを作りたい」という想いから、ロゴナジャパンのオリジナルブランドとしてルアモが誕生しました。
肌に優しいだけじゃない。こだわったのは使い心地

ー それが、ルアモの日焼け止め「オールデイプロテクト UVアクアヴェール」なんですね。完成に至るまでのストーリーを教えてください。
大きな転機となったのが、「酸化セリウム」という第3の日焼け止め成分との出会いです。
この成分を使うことで、これまで多くのお客様から寄せられていたベタつき・白浮き・伸びの悪さといった課題を、大きく改善できる可能性が見えてきました。
ー「酸化セリウム」は、従来の成分とどのように違うのでしょうか?
従来のオーガニックの日焼け止めには、「酸化チタン」や「酸化亜鉛」 が使われています。酸化チタンは白い成分なので、どうしても白浮きしやすい。ナノ化すれば白浮きは抑えられますが、ナノ粒子は体内に入り込みやすい、環境に流れやすいという懸念もあります。
さらに、酸化チタンや酸化亜鉛は油分が多い仕上がりになりやすく、ベタつきやすい。シリコンを足せばサラッとしますが、肌への負担が大きくなります。
一方、酸化セリウムは水溶性処方と相性がよく、白浮きせずにクリームのように軽く、なめらかな使い心地を実現できます。
ー ルアモ初の商品である「オールデイプロテクト UVアクアヴェール」が完成したとき、開発チームの皆さんはどんなお気持ちでしたか?
3年弱かけて試作と改良を重ね、自分たちが使っても満足できる理想の形に仕上がりました。
「白浮き」や「ベタつき」といったお客さまの悩みにしっかり応えられた実感があり、開発チーム全員が達成感を味わっていました。
ー 開発に3年弱かかったとのことですが、1番大変だったことは何でしょうか?
一番の課題は、SPFの数値を安定して出すことでした。SPFを表示するには専門機関での検査が必要で、時間も費用もかかります。
日常使いならSPF20前後で十分だと言われていますが、実際には「SPFは高い方が安心」と感じる方が多いです。そのため、お客さまの期待に応える数値を安定させることにかなり時間を費やしました。
加えて、「酸化セリウム」で紫外線カット効果を確保する取り組みはまだ事例が少ないので、手探りでの開発が続きました。
ー「オールデイプロテクト UVアクアヴェール」を手に取ってくださる方に、どんな価値を届けたいですか?
ルアモはヨーロッパの厳しいオーガニック基準に合わせて成分を選びつつ、使用感は日本のお客様の要望に応えられるよう、心地よさにもとことんこだわっています。
肌が弱い方やオーガニック派の方に、安心して、気持ちよく、毎日使っていただけるアイテムを届けたいと思っています。

徹底した環境への配慮
ー ルアモは肌へのやさしさに加えて、環境への配慮も大切にされている印象があります。具体的に、どんな点を意識してモノづくりをされているのでしょうか?
環境への配慮は、創業当初からずっと変わらないこだわりです。製品に「石油系の成分は使わない」を基本にしています。
たとえば、
・ナノ化した成分を使わない(体内や環境中に入り込みやすいため)
・マイクロビーズは使わない(海に流れると魚が摂取してしまう)
・紫外線吸収剤は使用しない(海に入ったとき、成分が流れ出てサンゴ礁に悪影響を及ぼすため)
など、環境負荷につながる可能性のあるものは避けています。
さらに、プラスチックごみを増やさないためにも工夫しています。たとえば、メイク品のパレットは木製で、磁石で中身だけを入れ替えられる仕様です。木製ケースは長く使えますし、単色販売にすることで、使わない色が余って捨てられるという無駄もなくなります。

アイブロウペンシルも、プラスチック製の繰り出し式ではなく、木軸のペンシル型を採用しています。
ー 木製のパレット、とても可愛いですね。私もいつも使わない色だけ残ってしまうので、好きな色だけを選んで自分だけのパレットを作れるのはすごく魅力的だと思いました。
ヨーロッパの厳しい基準を満たしたオーガニック製品※

ー 最後にHummingの読者に向けてメッセージをお願いします。
私たちは、肌への刺激が少なく、安心して使えるナチュラル・オーガニック製品をお届けしています。日本では「オーガニック」と名のつく商品が増えていますが、実はオーガニックの明確な基準が整っていないため、何を基準に選ぶべきか分かりにくいのが現状です。
その点、ヨーロッパには原料の配合率や製造過程での環境配慮など、細かい基準が設けられており、それらをクリアしたものだけがオーガニックとして認証されます。
私たちは、長年ヨーロッパのオーガニック製品を扱ってきた経験を生かし、その基準を大切にしながら製品づくりを行っています。
そして同時に、日本のお客様が毎日気持ちよく使えることも重視しています。肌にも地球にもやさしく、使うたびに心地よさを感じられるものを。そんな思いで、これからもオーガニック製品の魅力を伝えていきたいと思っています。
ー オーガニックと書かれているだけで安心してしまいがちですが、日本で販売されているオーガニックにはいろいろな形があることを初めて知りました。「安心して使えるオーガニック」を探している方にとって、ルアモは心強い存在ですね。本日は貴重なお話をありがとうございました。
🔗 Humming公式セレクトショップでも販売中
オールデイプロテクトUVアクアヴェール
UVカラーヴェール ファンデーション
UVパウダーヴェール
※UV製品、パレットを除く
自己肯定感が上がらないのは”逆”アファメーションのせいだった

理解はできても飲み込めないアファメーション
“Fake it till you make it”――上手くいくまで上手くいってるふりをしろ。
英語にはこういう言葉があるそうです。
最近は日本でも、似たような趣旨の話をよく聞くようになった気がします。
アファメーションという言葉で説明されるようなことでしょうか。
例えば、
「あの人みたいになりたい」ではなく、「私はもうあの人みたいになっている」
「こういう生活をしたい」ではなく、「私はこういう生活をしている」
といったように「既にそうなっている」という表現で何度も何度も言い聞かせることで、脳がそれを事実と認識して、本当にそうなるよう行動がプログラミングされてく的な。
同じ主旨の話で、ちょうど先日SNSで見つけた投稿があります。
それは「なりたい」と思っている限り、脳はその「なりたい」という”前提の状態”を保とうとするということ。
…なんだか、一瞬「とんちですか?」って聞き返したくなるような気持ちになりますよね。
どういうことかというと、なりたい自分を「追いかけている状態」をキープしようとしてしまうらしいんです。
なりたい自分に近づく行動ではなく、それを目指している人らしい行動をとるようにプログラムされる。
だって、なりたい自分を実現してしまったら、追いかけられなくなってしまうから。
これらは意思の問題でもなければ、”引き寄せ”みたいな掴みどころのない話とも少し違って、どうやらもう「脳の仕組み」としてそうなっているそうです。
そんな脳科学的に言われると「はーん、なるほどね、だからいつまで経ってもなりたい自分になれないのか~…」と、しぶしぶ腑に落とすしかありません。
無意識に”逆”アファメーションばかりしていた
しぶしぶとはいえ、本当にちゃんと理解はしているんです。
しかも、実体験を伴って。
ただ、私の場合は、残念なことに逆のパターンで起動させているというだけ!(ドヤァ
例えば「なんで私っていつもこうなんだろう…」「気疲ればかりして損だよな」と、暇があれば自分の粗を探して、自分を落としまくっている。
つまり「なりたくない自分」ばかり思い描いて、それをご丁寧に脳みそに刷り込んでいるわけです。
傍から見たら、というか、自分でも精神が安定していて客観的になれるときは、そんなにダメなヤツではないし、むしろ普通によくやってるなと思うこともあります。(年に数回だけど)
だけど、それに気づけたとて「なのに、なんでこんなにも自己卑下しちゃうんだろう…」と、また別の視点から自分を責めるわけです。
これもまた、自己卑下する自分でいなきゃと、脳に前提の状態を保たせていることになりますよね。
自己卑下するにふさわしい私でいなきゃいけないので、自分には粗があることが前提で生きてしまうし、こじつけでもいいから粗ばかり探すようになる。
なんという、粗探しの天才。
そりゃあ、自己肯定感なんて育めるわけがありません。
だからこそ、アファメーションが有効だとか、脳の仕組みを逆手にとるんだって話は身をもって理解している。
ただ、それを上手く活用ができない。
逆張りアファメーションに慣れすぎて、順張りアファメーションが上手くできない。
ネガティブな自分は前述の通り、すぐに何万通りでも想像できるけど、理想を叶えているポジティブな自分は、どうもうまく想像できないわけです。
まあ、よく考えたらそれは至極当たり前の話。
30年以上の年月をかけて、めちゃくちゃ強固な負の思考回路を構築してきたので、ちょっとやそっとで変わるものではありませんよね。

理論以上に大切なのは自分に合う方法に出会えるか
どうしたらいいのか、何から手を付けていいのか分からず、八方塞がりになったので、このテーマをエッセイにもらったのも何かのきっかけと思い、最近、こんな本を読みはじめてみています。
『あなたはあなたが使っている言葉でできている』ゲイリー・ジョン・ビショップ (著)
まださわりしか読めていないのもあってか、正直に言うと「…うーん、結局気持ちってこと?」と思ってしまう節が多々あります。
ただ1つ印象的だったのは「あなたはもうすでに人生に勝っている」というフレーズ。
著者曰く、これは別に気休めでも励ましでもなく、本当に文字通り勝っているんだ、それどころか既に勝ちグセがついているんだと。
「…… は?」って感じですよね笑
私も最初は、まったく意味が分からず思考停止しました。
私の解釈を交えながらざっくり説明すると、人生で起きるものごとは全て、自分が想像した通りに動いている、だから全勝ということらしいのです。
でも、到底そうは思えませんよね。
現に、なんで私はいつもこうなんだろうと日々ふさぎ込んでいるんですから。
どこが勝ち組なのかって話です。
でも、続く説明を読んで納得しました。
ここで言う勝ちの定義は、想定通りになるというだけで、その”想定通り”が全て良いことかどうかはまた別の話なんだそう。
例えば「私はいつも上手くできない」「良い相手に出会えない」「お金が溜まらない」と思うとします。
そう思っている限り、その言葉通りになる、良くも悪くもちゃんと全て想像した通りになる、勝っているとはそういう意味ということなのです。
だから、どう勝ちたいかを正しく設定しないと、勝ちグセをちゃんと自分の目標に向けないといけないということ。
この考え方が、なんだか妙に個人的に腑に落ちたんですよね。
素直に「あーたしかに、じゃあやってみようかな」と思えたんです。
実際、ここ数日、気持ちがネガティブに寄りはじめたり、つい怠けそうになった途端、「おっと?そっちの勝ちでいいのか?」と、早速立ち止まる癖がつきはじめています。
今までアファメーションを咀嚼できなかったのが嘘みたい。
もちろん、アファメーションそのものの理屈が理解できるか、腑に落ちるかは大前提なんですが、こんな風に自分に合う方法や考え方を見つけるのも同じくらい大事だなと思うんです。
思考のように目に見えないものにアプローチしたいときは、特に。
勝ちグセの話だって、人によっては全く腑に落ちなかったり、それこそ気持ちの問題じゃないかと思うでしょう。
だから、どの方法、考え方が優れているかではなく、自分にとって優れた方法、スッと入ってくる考え方に、いかに早く出会えるか。
意外とここを柔軟にできなくて「これも続かなかった…私ってダメだ…」と自己嫌悪を重ねてしまうケースって、結構多いのではないでしょうか?
その方法が、続かなくてもいい。
続かなかったら、続くまで別の方法を探し求めればいい。
いくつか組み合わせてオリジナルメソッドを編み出したっていいんですから。
ちなみに、私の場合は、この勝ちグセの話のほかにも、Mind Movieと呼ばれるものも自分に合う気がしています。
Mind Movieとは理想の未来、セルフイメージを動画にして繰り返し見る習慣なのですが、おそらく私が視覚優位派なタイプなので、しっくりくるんだと思います。
この兆候は学生の頃からあって、教科書を何度声に出して読み上げても、その音や内容は1ミリも記憶に残らない。
でもその代わりに、目で追っていた文字や挿絵の配置とかは、意識しなくてもいつの間にか覚えられるんです。
右側の2つめの段落くらいに書いてあったとか、あのページの次くらいにあったはずとか。
そう思うと、毎朝鏡の前の自分に向かって言い聞かせるような、よく聞くアファメーション方法が効かない、続かないのも納得です。
だって何度話しかけようが、記憶に刷り込まれるのは前向きな言葉ではなく、鏡に映った自分の顔だけなんですもん。(そういえば、むくみとかちょっとした顔の変化には気づけるようになったかも…)
こんな風に少しずつ自分の特性にも気づきながら、アファメーションを取り入れられるようになると、歯車がかみ合ったように急速に変化が起きるのではないかなという気がしてきます。

なりたい自分を”なりたいのまま”にしないために
一度きりの短い人生なんですから、せっかくならなりたい自分をずっと追いかける状態から、ちゃんとそこに到達できるようになりたいですよね。
他人にとって都合のいい私でいたくないし、自分で人生を生きてる感を実感したい、ちゃんと良い方向に全勝したい。
そのためにはこの”たい”を外さなくちゃいけない、というのがアファメーションなのかもしれませんが…まあ急にはできないので。
こうやっていろいろ試す過程も楽しみながら、地道に自分改革を遂行していきたいなと思います。
【2025年版】環境にやさしいサステナブルキャンドルおすすめ5選|香りで整えるエコな暮らし

環境にも心にもやさしい“サステナブルキャンドル”を選びませんか?
忙しい日々の中、ふと灯すキャンドルのやわらかな光と香りは、心をほどく小さな癒しの時間をくれます。
特に近年は、植物由来のワックスや天然精油を使ったサステナブルキャンドルが注目され、環境にも配慮しながら香りを楽しみたいという人が増えています。
大豆ワックス(ソイワックス)やココナッツワックス、再利用できるガラス容器、天然素材の芯など——
キャンドルは気軽に取り入れられる「エコで心地よい暮らし」の第一歩。
そこで今回は、環境や素材に配慮したサステナブルキャンドルを厳選してご紹介します。
あなたのお部屋、バスタイム、瞑想時間に寄り添う特別な一本を、ぜひ見つけてみてください。
サステナブルキャンドルを選ぶポイント
サステナブルキャンドルを選ぶとき、以下の点をチェックすると安心です。
• 植物由来ワックス(大豆・ココナッツ・蜜蝋)
石油由来のパラフィンではなく、再生可能で燃焼がきれいなワックスを選びましょう。
• 天然精油・ナチュラルフレグランス
合成香料やフタル酸類不使用のものは、心にも環境にも◎。
• 安全なウィック(芯)
コットン芯、木芯、紙芯など、無鉛・無金属の芯を使用しているブランドがおすすめ。
リユースできる容器
ガラスジャーやリサイクル素材など、使い終わった後も活用できるものが理想的。
• ブランドの姿勢・透明性
環境配慮・フェアなものづくりへの取り組みも判断材料に。
サステナブルキャンドルおすすめ5選
1. Japanese Rice Bran Wax Candle(高澤ろうそく)|伝統技術×米ぬかワックス
価格: 約¥3,800
URL: https://www.etsy.com/listing/1263098533/japanese-rice-bran-wax-candles-organic?gao=1
石川県金沢の老舗「高澤ろうそく店」が手がける、珍しい 米ぬかワックス(ライスブランワックス) のキャンドル。 自然な明るさと柔らかい色味が魅力で、燃焼がゆっくりなのも特長。
► 100%植物由来ワックス
► 和の静けさを感じる灯り
► ギフトにも人気
こんな人におすすめ:
→ 和の雰囲気が好き、自然素材にこだわりたい方

2. DAMDAM Tokyo – Hiba Soy Candle|“和の香り”を楽しむ大豆ワックス
価格: 約¥5,400
URL: https://damdamtokyo.com/en/products/hiba-soy-candle
東京発のヴィーガンスキンケアブランド「DAMDAM」の大豆ワックスキャンドル。
日本の木“ヒバ”の香りが、森にいるような落ち着きをくれます。
► ヴィーガン&クリーンビューティー
► 天然香料使用
► シンプルで洗練されたデザイン
こんな人におすすめ:
→ 落ち着く木の香りが好き、都会的なミニマルデザインが好みの方

3. +JAPAN Clean Cotton Soy Candle|日本モチーフのソイキャンドル
価格: ¥3,800
URL: https://gohanmarket.com/products/japan-scented-soy-candle-9oz
“日本”をテーマにした香りとデザインが特徴。
大豆ワックスを使用し、クリーンコットンの軽やかさが部屋全体を心地よく整えます。
► シンプルで使いやすい香り
► インテリアとしても可愛い
► 海外ECから日本へ発送対応
こんな人におすすめ:
→ ナチュラルで爽やかな香りが好き、部屋をすっきりさせたい方

4. Aveda (アヴェダ)Shampure Vegan Soy Wax Candle|世界的人気の香りを部屋で
価格: ¥8,400
URL: https://www.aveda.com/product/5346/62093
アヴェダの人気ライン“Shampure”の香りを堪能できるヴィーガンキャンドル。
25種類の植物エッセンスをブレンドした香りは、何度嗅いでも心がほどける名作。
► 100%ヴィーガン大豆ワックス
► 植物由来の精油ブレンド
► 海外発送対応
こんな人におすすめ:
→ 心が落ち着くクリーンな香りが好き、上質なリラックスタイムを求める方

5. Hanayuzu Candle(Yuzu Leaf Co.)|柚子×檜の和モダンブレンド
価格: ¥4,300
URL: https://yuzuleaf.co
ココナッツワックスに、柚子・イランイラン・檜など“和×ボタニカル”をミックスしたユニークな香り。
ほんのり甘く、フルーティーで、上品な余韻が広がります。
► ココナッツワックス+コットン芯
► 香りの評価が高い
► 海外ショップから日本発送可能
こんな人におすすめ:
→ 日本の香りをモダンに楽しみたい、甘さと爽やかさの両方が欲しい方

6. Ritual + Fancy|古代ハーブの知恵に着想を得たキャンドルブランド
価格: ¥5,200
URL: https://shop.humming-earth.com/products/bramble
モミや松、シナモン、オレンジ、クローブが織りなす、ぬくもりあふれるウッディな香り。ほんのりとしたフローラルとアーシーな香りがやさしく包み込みます。
► ウィスキータンブラー型のガラス容器
► 手作業で作られた
► BIPOC女性オーナーブランド
こんな人におすすめ:
→ フルーティーな香りが好きな方へ

サステナブルなキャンドルの楽しみ方
- 瞑想・ヨガのお供に:香りが集中力と落ち着きをサポート
- バスタイムに:灯りが気持ちの切り替えを助けてくれる
- 就寝前のルーティンに:1日の終わりを丁寧に過ごせる
- ギフトに最適:環境にやさしい贈り物は好印象◎
“エコで心地よい時間”を日常に取り入れよう
サステナブルなキャンドルは、
「環境負荷を減らしながら、自分の心を整える」
という、新しいライフスタイルを気軽に始められるアイテムです。
素材・香り・デザインなど、ブランドの想いはさまざま。
ぜひ、あなたの空間や気分にフィットする一本を選んでみてください。
不確実な時代に「行動できる人」になるための6つの方法|メンタルヘルスを守る実践ガイド

近年、私たちはパンデミック、社会的不安、インフレ、政治的対立など、予測不能な出来事に直面し続けています。将来への不安が高まり、ストレスを感じるのも当然のこと。
しかし、不確実な時代だからこそ「自分で選べる行動」に目を向けることが、心の強さ(レジリエンス)を育てる鍵になります。
この記事では、心理学の専門家が提案する「不安な時期にこそ実践したい6つの行動」を分かりやすく紹介します。
ネガティブ思考の連鎖を断ち切る
最悪のシナリオばかり想像してしまうと、まだ起きていない出来事に対して、すでに脅威を感じてしまいます。
そんなときは深呼吸して思考をリセットしましょう。
- 「もしうまくいったら?」という“良い未来”のイメージを意識的に思い描く
- 悪い妄想から一度距離を置く
- 目の前の事実と想像を切り離す
小さな思考の切り替えが、不安の減少につながります。
あえて“予定外”のことをしてみる
不確実性に慣れるには、自分を少しだけ未知の環境に置くことが効果的です。
- 行ったことのない場所へ行く
- 新しい趣味や食べ物に挑戦する
- スケジュールをあえてゆるくする
「未知」に触れる経験は、「私は変化に対応できる」という自信を育てます。
コントロールできる範囲に集中する
コントロールできない物事に囚われるほど、不安は大きくなります。
まずは“自分が動かせること”に目を向けましょう。
- 選挙に行く
- ボランティア活動に参加する
- 地域やコミュニティに関わる
研究では、主体的に行動する人はストレスを感じにくく、寿命が長い傾向があることも示されています。

他人と比較しない
不確実なことへの対応の速さや柔軟さは人によって違います。
「私は弱い」と自分を責める必要はありません。
- 自分のペースで行動してOK
- 解決に時間がかかっても大丈夫
- 自分の感情に寄り添う
比べるべきは「昨日より少しできた自分」です。
“自分なら友人に何と言う?”と考える
自分の悩みを客観視する方法として効果的なのがこの質問。
「もし友達が同じ状況なら、私はどんなアドバイスをするだろう?」
視点を変えることで、冷静な判断や新しいアイデアが浮かびやすくなります。
誰かに“助けてもらう前提”で考えない
誰かに問題を丸投げすると、自分は無力だという気持ちが強まってしまいます。
必要なのは、「解決してもらう人」ではなく、あなたを信じてくれるサポーターです。
- 相談は「解決」ではなく「感情の共有」を目的に
- 助けてくれる人は“支えてくれる人”であり、“代わりに解決する人”ではない
- 小さな一歩を一緒に考えてもらう
自分で行動を選べる感覚が、不安耐性を高めてくれます。
不確実な時代こそ、「行動する力」を育てよう
将来の予測が難しい今、不安を完全になくすことはできません。
だからこそ、
- コントロールできることに集中する
- 小さな一歩を積み重ねる
- 自分の感情に寄り添う
これらが心の余裕を生み、レジリエンス(心が回復する力)を育ててくれます。

不確実な時代でも「自分を大切にする選択」はできる
不安や予測不能な出来事は、これからも私たちの生活に存在し続けます。しかし、だからこそ大切なのは、「外の世界」ではなく「自分の内側」に意識を戻すこと。
ネガティブ思考を手放し、コントロールできる範囲に集中し、小さな一歩を選び続けることで、私たちはどんな環境でも自分らしさを失わずに歩いていけます。
レジリエンスは特別な人だけが持つ才能ではなく、日々の行動の積み重ねで誰でも育てられる力です。
不確実な時代は、私たちが自分自身を深く知り、強く優しくなっていくチャンスでもあります。
今日できる小さな行動を、ひとつだけでも選んでみてください。
参考リンク(Reference):
American Psychological Association(APA)
Stress in America™ 2022: Concerned for the Future, Beset by Inflation
https://www.apa.org/news/press/releases/stress/2022/concerned-future-inflation
他人の幸せを心から喜べないときに──

成功で価値が測られる時代に、心を保つということ
私たちはいま、「どれだけ成功しているか」で価値が判断される社会に生きています。
SNSを開けば、昇進、結婚、マイホーム、出産、旅行…。
友人や知人の“幸せの瞬間”がタイムラインを絶え間なく流れていきます。
本来なら、誰かの幸せを見て「よかったね」と心から祝いたい。
でも現実には、それが焦り・不安・自己否定、そしてときに抑うつ感へと変わってしまうことがあります。
「どうして私だけうまくいかないんだろう」「私は何をしているんだろう」と、気づけば自分を責めてしまう。
けれど、それは“心が弱いから”でも“性格が悪いから”でもありません。
誰かの喜びを素直に受け止められないのは、自分の中にまだ癒えていない痛みや悲しみがあるから。
そんなときこそ、自分を責めるのではなく、「今の心を丁寧に見つめること」が大切です。
まずは自分の心をチェックする
この状況について考えてみてください。
長い間、子どもを授かるために不妊治療を続けていた。
毎月のように訪れる希望と落胆の繰り返し。
少しずつ心も体も疲れていく中で、ある日、親しい友人から妊娠の報告が届いた。
「おめでとう」と返したその瞬間、胸の奥で何かが崩れるような音がした。
涙が止まらなかった。
でも、それは嫉妬ではなかった。
ただ、自分の叶わない願いに対する深い悲しみだった。
「彼女の幸せがうれしくないんじゃなくて、私が悲しいだけ。」
「妊娠報告がつらい女性」──それが自分の新しいアイデンティティだと思い込んでいたが、そうではなかった。
それは、悲しみを整理しながら、他の感情が入る余白をつくっている途中のプロセスにすぎなかったのだ。
たとえば──
- 恋人がいなくて孤独を感じているなら、新しい出会い方を考えてみる
- 仕事が停滞しているなら、小さな挑戦や学び直しを始めてみる
悲しみを無理に消すのではなく、「いまの自分を理解する行動」をとることが、少しずつ心の回復につながります。
無理せず「境界線」を引く勇気を持つ
あなたが今、仕事に行き詰まりを感じているのに、友人が次々と昇進しているなら──
素直に喜べないのは自然なことです。
そんなときは、こう伝えてみてください。
「本当にすごいね! ただ、今ちょっと仕事の話を聞くのがつらい時期で…。少しの間だけ、その話題をお休みしてもいい?」
これは冷たい言葉ではなく、自分の心を守るための優しい選択です。
友人もまた、あなたが無理せずそばにいてくれることを望んでいます。

「おめでとう」を言葉にする力
悲しみや焦りの中にいても、行動として「おめでとう」を伝えることには大きな意味があります。
花を贈る、メッセージを送る、短くても「お祝いの言葉」を口にする。
「たとえ心が追いつかなくても、“喜びの行動”を選ぶことが、未来の自分を助けてくれる。」
喜べない気持ちは一時的なもの。
行動を通して他者とのつながりを保つことで、心のバランスは少しずつ戻っていきます。
「今は喜べない自分」も受け入れて
どんなに努力しても、どうしても喜べない瞬間があります。
友人や周りのグッドニュースを聞くと怒りと悲しみでいっぱいになります。
けれどその感情を押し殺さず、「今の私は悲しい」と認めることで、やがてその気持ちは静かに消えていくんです。
大切なのは、自分の反応を否定しないこと。
他人の幸せを喜べない自分がいても、それは「冷たい人間」ではなく、
「まだ癒えていない人間」なだけです。
幸せも悲しみも、すべては一時的なもの
今は苦しくても、いつかまた笑える日が来ます。
そして今、誰かが幸せの絶頂にいるように見えても、彼女にもいつか迷いや涙の時期が訪れます。
人はみんな、お互いの光と影の時間を支え合いながら生きている。
スピリチュアルの先生であるラム・ダスはこう言いました。
“We’re all just walking each other home.”
―「私たちはみんな、ただ一緒に“帰り道”を歩いているだけなんだ。」
自分にも、人にもやさしく
他人の幸せを喜べないとき、それはあなたが悪い人間だからではありません。
むしろ痛みを知っているからこそ、やがて他人の気持ちに寄り添える人になれるのです。
幸せを発信するときの配慮に気をつけるのもいいかもしれません。
SNSでの投稿や何気ない言葉も、誰かの心を刺激することがあるんです。
だからこそ、自分が幸せな立場にあるときも、
「今、誰かが同じように苦しんでいるかもしれない」と思いを巡らせ、
やさしくあることを忘れないようにしています。
最後にー
私たちは、周りと比べずには生きられない時代に生きています。
それでも、自分を責めるのではなく、
「私は今、悲しいけれど、それでいい」と認めることから始めてみてください。
他人の幸せを喜べないとき、それは心が疲れているサインです。
そんなときこそ、自分をいたわることが“優しさ”の第一歩。
Hummingは、あなたが他人の光に怯えず、自分のペースで心を癒せるように寄り添います。
― Humming Team
【ハミングが届けるポジティブニュース】 「バケツの水をパイプラインへ」スコットランド人男性がネパールにもたらした、水と希望の物語

私たちの日々の暮らしにとって、「水」はあって当たり前の存在。朝起きて顔を洗い、コーヒーをいれ、家族の洗濯をする…。蛇口をひねれば、いつでも清潔な水が出てくる。もしそれが、ものすごく大変な重労働で、毎日何時間もかけて遠くまで汲みに行かなければならないとしたら?想像するだけでも、疲れてしまいますよね。
実は、ネパールには今も、そんな厳しい現実を生きている村がたくさんあります。特に水汲みの重労働は、幼い女の子や女性たちの肩にのしかかっています。
そんなネパールの村に、スコットランドからやってきた一人の男性が、文字通り「奇跡のパイプライン」を敷設し、人々の生活を根底から変えています。彼の名前はイアン・ベントさん。彼の行動のきっかけが、世界中でブームになった「アイス・バケツ・チャレンジ(難病支援のため氷水をかぶる、または寄付するチャリティー運動)」だった、というから驚きです。
おすすめ記事 ▶ 【ハミングが届けるポジティブニュース】 生きものたちが帰ってくる場所──世界のやさしい取り組み
「水を頭から浴びるなんて水がもったいない!」— 熱い怒りが生んだ、画期的なアイデア
イアンさんは長年ネパールで生活し、ビミリ村の人々が抱える深刻な水不足を目の当たりにしていました。そんなある日、彼のもとにSNSで「アイス・バケツ・チャレンジ」の指名が届きます。当時、誰もがやっていたこのチャリティームーブメント。しかし、イアンさんはこの行為に激しく異議を唱えました。
彼の心の叫びは、SNSに投稿された率直なメッセージとなって飛び出します。
“イアンさんは「アイス・バケツ・チャレンジ」に異議を唱え、無駄に水を使う代わりにネパールの村のための井戸掘り支援を呼びかけ、人々に水の尊さと寄付の本質を気づかせた。”
「清潔で飲める水を、ただ頭からぶっかけるなんて、なんてもったいないんだ!こんなこと、全く意味がない!」
そして彼は宣言しました。もし本当に誰かを助けたいと思うなら、その水を捨てる代わりに、「この村の素晴らしい人たちのために、井戸を掘る費用として20ドル、あるいは可能な範囲で寄付してほしい」と。
彼のこの訴えは、当時のブームに「待った」をかけるもので、多くの人々の心に響きました。当たり前のように使っている水への感謝と、恵まれない人々への思いやりを、改めて考えさせてくれたのです。
重労働を体感!ネパールの伝統籠「ドク」で運ぶ、水の重み
イアンさんは、ただ言うだけでなく、自ら行動で示しました。
彼は、ネパールで昔から使われている、頭にバンドをかけて背中で運ぶ伝統的なかご「ドク(DOKU)」を使い、20リットルの水を村まで運ぶという挑戦を発表。この「ドク」は、何時間もかけて重い水を運ぶ女性たちの日常を象徴するものです。
“イアンさんはネパール女性たちの水運びを象徴する「ドク」で20リットルの水を運ぶ挑戦を自ら行い、多くの寄付と共感を集めて「ビミリ財団」を設立し、人々に水不足の現実と支援の大切さを強く伝えた。”
彼の呼びかけに、人々はすぐさま反応しました。数百人から寄付が集まり、その額は数千ドルに達しました。こうして、イアンさんの熱意と人々の善意によって、村に水を届けるための団体「ビミリ財団(The Bimiri Foundation)」が誕生したのです。
さらに、彼の友人たちも、あの過酷な水運びを体験するために「ドク・チャレンジ」に参加。参加者の一人、ジムさんは、「水があたり前にある国から来た私にとって、この重労働は、単なるバケツ一杯どころではない、感情にぐっしりと響く重みがあった」と語っています。

パイプラインが村にもたらしたもの — 蛇口から出る「時間」と「希望」
集まったお金は、ただの井戸掘りだけに終わりませんでした。イアンさんと村の人々は、水を自宅まで届けるための「パイプライン敷設」という、もっと大規模なプロジェクトに挑んだのです。
このプロジェクトが素晴らしいのは、村の全員が参加しているということです。
“イアンさんの呼びかけで始まった支援は村全員参加のパイプライン敷設へと発展し、ビミリ村の全家庭に水道が通って女性と子どもたちの時間と未来を解放し、生活と希望を大きく広げる結果につながった。”
子どもから大人まで、皆が一緒になって水道管を埋めるための溝を掘り、地元のエンジニアが技術指導を行いました。時には、資材を運ぶために道を作ったり、電気を引いたりといったインフラ整備にまで発展しました。まさに、「自分たちの手で未来を創る」という共同作業です。
そして、ついに成果が。ビミリ村の全ての家庭に水道が通り、蛇口から水が出るようになったのです!
これにより、10歳くらいの幼い女の子たちを含む女性たちが、毎日何時間も費やしていた水くみの重労働から解放されました。彼女たちが得たのは、水だけではありません。「時間」です。
得られた時間で、子どもたちは学校で学ぶことができ、女性たちは小さな飲食店を始めたり、家畜を増やしたりと、家族の暮らしを豊かにするための活動に専念できるようになったのです。水が、彼女たちの「可能性」と「希望」を広げたのです。
一人のスコットランド人男性の「もったいない」という怒りから始まった活動は、国境を越え、多くの人々の心を動かし、ネパールの村に命の水を届け続けています。
次の目標はナモブッダ地区全域へ!
最初の村で成功を収めたイアンさんの次の目標は、ビミリ村の周辺にあるナモブッダ地区全域の家庭に、一つずつ蛇口を設置すること。「すでに費用の計算を始めていて、すぐにでも作業を始めたい!」と意欲満々です。
さらに、スコットランドの小学校と連携し、生徒たちがネパールを訪れてイアンさんの活動をサポートし、「人を助けることの大切さ」を学ぶ教育プログラムも計画しています。
一人の男性の勇気ある行動が、世界を動かし、たくさんの笑顔を生んでいるこの物語。
私たちが日々当たり前に使っている「水」について、そして私たちの身近な行動が世界を変える力を持っていることを、改めて教えてくれます。
食べられるお茶『ティート』で、五感を満たすひとときを

食べられるお茶として人気の「ティート」。
お湯を注ぐと、まるで果実のデザートのように華やかな香りが広がります。
Humming公式セレクトECショップでも人気のこの「ティート」を手がける、「TEAtriCO(以下、ティートリコ)」の村田さんに、開発の裏側や商品に込めた想いを伺いました。
TEAtriCO(以下、ティートリコ)さんについてはこちら
美容師さんの想いから生まれた“食べられるお茶”
──まずは、ティートについて教えてください。
村田さん:ティートは、“食べられるフルーツティー”です。お茶の「Tea」と、食べるの「Eat」を組み合わせて名づけられました。
主な材料はドライフルーツとハーブ。カップに茶葉を入れてお湯を注ぎ、5分ほど待つとハイビスカスなどの鮮やかな色がゆっくりと広がり、見た目にも華やかなお茶ができあがります。
飲み終えたあとには、柔らかくなったドライフルーツをそのまま召し上がっていただけます。茶殻が出ないので環境にも優しく、最後のひと口まで楽しめるのがティートの魅力です。
──「お茶を食べる」という発想がユニークですよね。ティートが生まれた背景を教えてください。
村田さん:実はティートは、美容室のサービスティーとして誕生しました。美容室は、自分を整える時間を過ごす特別な場所ですよね。
だからこそ、新しいお店をオープンするときに、「施術の時間以外でもお客様に心地よく過ごしてもらいたい」とスタッフが考えたことが、ティート誕生のきっかけでした。
ですので、ティートリコというブランドが誕生したのは2014年ごろですが、ティート自体はその前から存在していました。
当時の本部は福島にありましたが、製造に適した環境を考えたとき、お茶の本場である静岡が良いだろうということで、静岡に製造部門を移し、そこからティートリコが始まりました。
── 美容師さんのお客様への想いから生まれたお茶なのですね。驚きです!
環境や生産者にも優しい取り組み「エコティートサイクル」
── 私もティートを愛飲しています。ティートなら面倒な茶葉の処理もないし、ゴミも出ないのが最高です。最近、ティートを飲むためにガラスのカップを買ったのですが、お湯を注ぐと、鮮やかな色が広がって、すごく幸せな気持ちになりました。
村田さん:ありがとうございます。香りも味も、見た目も自慢のお茶なので、いろんな方に楽しんでいただけたら嬉しいです。ちなみにどのフレーバーがお好きですか?
── 私は「とちあいか」と「ベリーミックス」を飲んでいます。
村田さん:どちらも人気のフレーバーです。「とちあいか」は市場に出せないフルーツを農家さんから買い取って製造しているプレミアムなティートです。
── ティートリコのWebサイトで拝見しました。「エコティートサイクル」という、環境に優しい取り組みをされているのですよね。
村田さん:エコティートサイクルは、環境への配慮はもちろんですが、何よりも“農家さんの力になりたい”という想いから生まれた仕組みなんです。
果物の中には、形が少し不揃いというだけで市場に出せないものがたくさんあります。どれも農家さんが手間ひまかけて育てた大切な果物なのに、出荷できなければ廃棄せざるを得ない。
そうした果物を買い取らせていただき、ティートという形でお客様に届けることで、少しでも生産者の力になれたらと思っています。
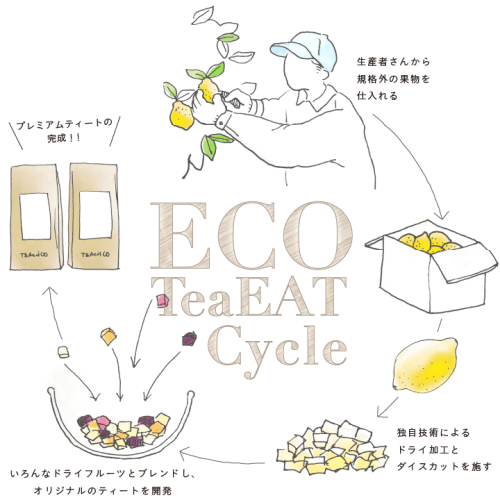
味・香り・彩りのバランス、そして自由な楽しみ方
──ティートを作る上で、特にこだわっていることを教えてください。
村田さん:こだわりは2つあります。
1つ目は「味・香り・彩りのバランス」です。
現在、ティートは14種類あります。その日の気分や好みに合わせて選べるように、甘いフレーバーや酸味の強いものなど、味の系統をバランスよく揃えることを意識しています。
2つ目は「自由に楽しめること」。
ティートは、お湯を注ぐだけで楽しめるお茶です。
紅茶のように英国式の入れ方が決まっていたり、緑茶のようにお湯の温度に気をつけないと渋みが出たり、細かなルールがないので、誰でも簡単に味わうことができます。
たとえば「今日は茶葉を多めにして濃いめにしてみようかな」とか、「スッキリしたいから少なめにしてみようかな」といったように、その日の気分で変えられます。パイナップルとピーチをブレンドしたり、ヨーグルトに混ぜたり、お菓子作りに使ったり……。アレンジの幅が広く、自由に楽しめるのもティートの魅力です。
View this post on Instagram
ギフトにも、自分へのご褒美にも
──ティートをご購入されるお客様には、どんな特徴がありますか?
村田さん:公式オンラインストアでは、20代から60代まで、幅広い世代の女性にご購入いただいています。女性への贈り物として男性の方が購入されることも多いですね。
── 私もティートはギフトにぴったりだと感じています。お友達の家に遊びに行くときなどに持っていけば、「何このお茶?」「可愛い〜」と話題になりそうですよね。自然と会話が弾みそうです。
コンセプトは「ひとときを思うひとしずく」

── ティートを手に取ってくださった方に、届けたい想いを教えてください。
村田さん:今の時代はモノや情報があふれているし、 みんな仕事や家のことで毎日忙しい。スマートフォンでSNSや動画を手軽に楽しめる一方で、ゆっくりと自分と向き合う時間を持つのが難しくなっている気がします。
お茶を淹れるひとときは、そんな忙しい日常の中で“少し立ち止まるきっかけ”になる時間です。特にティートは見た目も可愛く、お湯を注ぐと、ふわっと甘い香りが広がって、五感が満たされていく感覚を味わえます。
だからこそ、自分と向き合う時間を持つきっかけに、ティートがなれたら嬉しいです。
── HummingのセレクトECショップでは、「自分のいちばんの親友は、自分自身」というコンセプトを大切にしています。
ティートリコさんのお話を伺いながら、“自分を大切にする”という想いに深く共鳴しました。ティートを通じて、自分をいたわる時間を楽しむ人がひとりでも増えたら嬉しいですね。
村田さんおすすめのフレーバーは「ペア」と「ルビーオレンジ」。
2025年10月に新しく発売したフレーバーです。
🔗 Humming公式セレクトショップでも販売中
・ベリーミックス
・とちあいか
・ピーチ
音声で聴くならこちら
Spotify:
https://open.spotify.com/episode/5y6FyO50iGu3Jgn3QHC1fG?si=O3NN_yfoSv6C4m2P41kDLw
stand.fm:
https://stand.fm/episodes/690454cc1de4a9fd200ca746
うつを「治療する」シンプルな運動習慣:セラピー並みの効果も

運動がもたらすメンタルヘルス改善 — いつものアクティビティで“こころの癒し”を
うつの波が押し寄せてきたとき、「運動なんて今さら…」と思うかもしれません。でも、最新の研究では、ウォーキング・ジョギング・ヨガ・筋力トレーニングなど様々な運動が、うつ治療としてセラピー(心理療法)と同等の効果を持つ可能性が示されています。
特に、米国では成人の10 ~ 25 %がうつに関わる何らかの症状を経験するとされており、借金・離婚・糖尿病よりも「幸福感」を損なうという指摘もあります。
おすすめ記事 ▶ 初心者のためのワークアウトガイド
運動がうつ改善に効くというエビデンス
- 英国誌 BMJ に発表された ネットワーク・メタ分析(無作為化比較試験218件・14 000人以上対象)では、運動療法がうつ治療の有効な選択肢であることが示されました。
- 国内でも、東京都医学総合研究所などによるレビューで「有酸素運動、ヨガ、筋力トレーニングが特に有効」という報告があります。
- また、働く人のメンタルヘルス改善の現場でもウォーキングや身体活動を習慣にすることでストレス軽減・うつ傾向の改善が見られるという報告があります。
どんな運動が効果的?/どんなやり方でもいい?
効果が特に高かった運動の種類
- ウォーキングまたはジョギング、ヨガ、筋力トレーニングが特に効果が高いとされており、強度がやや高めの運動ほど改善効果が大きいという傾向があります。
- ただし「どれほどの回数や期間が必要か」「どれだけ強度を上げればいいか」は、まだ明確なガイドラインが確立されていないという報告もあります。
“どんな運動”でも“全く運動しない”よりは良い
- 研究では「どれだけ運動したか(回数・分数)はそれほど影響しなかった」「重要なのは“何もしない”よりは動くこと」だという指摘があります。
- つまり、まずは“少し動く習慣”を持つことが鍵です。ハードに始める必要はありません。

運動がうつに効くメカニズム(簡略版)
- 運動により、脳内の神経伝達物質(例:セロトニン、ドーパミン)やホルモン(エンドルフィンなど)が活性化され、気分改善・ストレス軽減につながるという研究があります。
- また、身体を動かすことで「無力感・孤立感」から抜け出しやすくなり、自己効力感(「自分でも動ける」)の回復にも役立つと考えられています。
- 身体的活動は睡眠の質向上・社会的交流促進・日中のリズム改善など、複数の経路からメンタルに良い影響を与える可能性があります。
実践のポイント:続けやすくするために
- 習慣化を目的に:例えば「毎朝10分ウォーキング」「週3回ヨガ」など、まず“できそうな量”から始めましょう。
- 楽しさを優先:好きな音楽を聴きながらウォーキング、友人と一緒に散歩、ヨガや太極拳を体験… 楽しめる形式の方が継続しやすいです。
- 強度を少しだけ上げると◎:軽めの運動でも効果はありますが、少しチャレンジを含めることでより良い効果が期待されます。
- サポートを活用:運動グループに参加、トレーナーを頼る、あるいは家族・友人と一緒に行うことでモチベーション維持に役立ちます。
- 無理はしないで:うつのときは動き出すのも大変です。始めから過度な負荷をかけず、体調・気分に合わせて調整しましょう。
注意点と限界
- 運動だけで“薬を完全に不要”と考えるのは危険です。うつの程度によっては、薬物療法・心理療法との併用が必要です。
- 研究には「バイアスの可能性」「運動内容・期間・強度の統一性が低い」などの課題があり、すべての人に同じ効果が出るわけではありません。
- 身体的な健康状態、既往症、怪我・疾患の有無などから、安全に運動を始めるために医師・専門家に相談することが推奨されます。
- 継続が困難な場合、低強度・短時間の運動でも“まったく動かない”よりは価値があります。
- そして、「今日は無理かも」と思った日こそ、自分を責めずに休むことも大切です
Hummingからー
どんなに小さな一歩でも、それは前進です。
“動けない日があっても大丈夫。”
心が疲れたときこそ、自分を責めるのではなく、優しく包んであげてください。もし外に出られない日があっても、窓を開けて深呼吸をしてみる。 体を少し伸ばしてみる。 その「小さな動き」こそが、心の回復の始まりです。Hummingは、みなさんが自分のペースで心と体を整えていけるように寄り添いながら、日々の暮らしに優しい風を届けていきます。
ペットの力:ヒトと動物のふれあいがもたらす健康効果

人と動物のインタラクション”がもたらす驚くべきメリット
忠実な仲間を家に迎える喜びに勝るものはありません。ペットからの無条件の愛は、単なる癒しを超えて、ストレスの軽減、健康改善、子どもの感情の安定・社会スキルの向上など、さまざまな健康効果をもたらす可能性があります。
おすすめ記事 ▶ クリック募金とは?動物や環境に関係する募金サイトまとめ
ペット普及率と研究の背景
アメリカではおよそ68%の世帯がペットを飼っていると推定されています。
では、どんな人が動物から恩恵を受け、どの種類のペットが健康に良いのでしょうか?過去10年間、アメリカ国立衛生研究所(NIH) は WALTHAM Centre for Pet Nutrition(マース社)と提携し、このテーマを研究資金で支えてきました。
魚からモルモット、犬・猫に至るまで、異なる動物における精神・身体の健康メリットが調査されています。
健康効果の可能性
「人と動物のふれあい」に関する研究はまだ発展途上ですが、一定のポジティブな効果が報告されています。
主な効果は以下の通りです。
- 動物と接することで、コルチゾール(ストレス関連ホルモン)のレベル低下や血圧の低下が示唆されています。
- 動物が孤独感の軽減、社会的支援感の増加、気分の改善を促す可能性があります。
- 特に犬を飼っている場合、日常の身体活動量(散歩などが増えるという研究結果があります。
- また、子どもの発達支援(例:自閉スペクトラム症、ADHD)において、動物との接触が有益であったという報告もあります。
ただし、すべての研究で一貫した結果が出ているわけではなく、「どのペットが」「どのような人に」「どの程度のふれあいがあれば」という条件次第で効果が変わるという指摘も多くあります。
動物が人を助ける場面
動物は、人にとって「安心・支援の源」として機能することがあります。特に「セラピー・ドッグ(治療補助犬)」などはその典型例です。
例えば、尊敬される研究者である Ann Berger 医師は、ガンや終末期疾患を抱える人々とともにマインドフルネス(注意・意図・共感・気づき)を教えていますが、こうしたスキルを動物は「本能的に」提供できる存在だと言います。
教室や病院など、人が緊張・ストレス・不安を抱える場面でも、動物が入ることで「人のそばに静かにいてくれる存在」が安心感を生み、支援的な役割を果たしています。

注意すべきこと:リスクと限界
- 研究の多くが、因果関係を明確にしてはいないことが指摘されています。
- ペットを飼うことが必ずしもすべての人に「健康改善」をもたらすわけではありません。アレルギーや喘息のリスクがある人など、個々の条件によって逆効果になる可能性もあります。
- 動物自身にもストレスや疲労があります。ペットの世話には責任が伴い、「いつでも接して良い」というわけではありません。特に子どもが動物に接する際には「動物がストレスを感じていないか」「適切な距離を保てているか」を教えることが重要です。
ペットを健康パートナーにするためのポイント
- 自分の目的を明確にしましょう:例えば「身体活動を増やしたい」「ストレスを軽減したい」「子どもの社会性を育みたい」など。目的によって適したペットや接し方は異なります。
- 定期的な世話・遊び・散歩など、ペットとの日常のやり取りが鍵となります。
- 動物側の健康・ストレス・安全にも配慮を。動物福祉を考えることが、お互いの関係を健やかに維持するために大切です。
- アレルギーや住環境など、自分自身や家族の条件を確認して、無理のないペットライフを選びましょう。
ペット別の健康メリット比較
犬の場合
主なメリット
- 定期的な散歩などによる身体活動量の増加。例えば、「イヌを飼っている人は、イヌを飼っていない人に比べて余暇に体を動かす活動が約69%多かった」という分析があります。
- 高齢者は「イヌの飼育経験がフレイル発生リスクを約20%減少、要介護・認知症発症リスクを約40%低減」する可能性があるという報告。
- 飼い主の愛着が強いほど身体活動量が高まるという研究も。
注意点
- 散歩の時間や世話の負担があるため、生活リズムや体力・住環境が整っていることが前提。
- アレルギー・衛生面・事故(咬傷など)にも配慮が必要。
猫の場合
主なメリット
注意点
- 散歩などの運動促進効果は犬ほどではないため、身体活動を主目的にするなら補助的になる。
- 室内飼育が基本となるため、住環境(室内スペース・清掃・換気)など準備が必要。
小動物(ハムスター・ウサギなど)の場合
主なメリット
- 小さい生き物とのふれあい・世話・観察という行動自体が「責任感」「共感力」「観察力」「リラックス効果」を育てる機会となる。日本では高齢者のQOL向上や認知機能維持との関連を報じた研究もあります。
- 初めてペットを飼う場合や、住環境・時間に余裕がない場合の「ペット入門」として適している。
注意点
- 体が小さいため、病気・ストレスを見落としやすく、適切なケア(温度・清潔・栄養)が必要。
- 運動量・スキンシップ量だけでメリットを期待するには限界があるため、目的によって選択する。

子ども・高齢者・在宅ワーカー別:ペット活用ガイド
子どもとの暮らし
おすすめのペット&活用法
- 犬:毎日の散歩・餌やり・しつけを通じて「責任感」「社会性」「体力」を育てる。
- 猫・小動物:静かに観察できるため「情緒安定」「集中力」「共感力」を養いやすい。
例:幼児向け保育施設では、本物の犬を置くと「子どもたちは犬に触ったり話しかけたりし、行動が活性化された」という報告あり。
【ポイント】
- ペットを通じた「世話」「観察」「遊び」の流れをルーチンにする。
- 子どものアレルギー・衛生教育(動物に近づくときのルール)を事前に整備。
- ペットの休息時間・逃げ場を確保し、子どもが無理に触らないよう指導。
高齢者との暮らし
おすすめのペット&活用法
- 犬:散歩など定期的な身体活動が、フレイル・認知症予防となるという研究あり。
- 猫・小動物:比較的お世話の負担が少ないため、体力・住環境に制約がある場合に適している。
- ペットと暮らすことで「目的意識」「日々のリズム」「社会的つながり(散歩中の住民交流など)」が生まれ、孤立・鬱予防に好影響。
【ポイント】
- 散歩コース・ペットの体調管理・ペット用医療費などをあらかじめ検討。
- ペットの寿命や、飼えなくなったときの代替プランも視野に。
- ペットが高齢になったときのケア・家族の協力体制も考えておく。
在宅ワーカー・リモートワークとの暮らし
おすすめのペット&活用法
- 犬:定期的に「仕事の合間の散歩」でリフレッシュ&運動習慣化。
- 猫・小動物:静かな環境で一緒に過ごし、仕事の合間に短い休憩タイムとして「撫でる」「観察する」ことでストレス軽減。
日本の調査では、ペットを飼っている人の95%が「ペットはストレス解消に役立っている」と感じているというデータあり。
【ポイント】
- 作業中にペットが邪魔にならないよう、専用スペース・遊び時間をあらかじめ設定。
- ペットによる気分転換を「タイマー・ブレイク」で意図的に導入。
- リモート会議・電話中の騒音や動きを避けるため、ペットの活動時間帯を考慮。
覚えておきたい「ペットと健康」の基本ポイント
- 目的を明確にする:運動増加/ストレス軽減/社会性促進など、自分のニーズに合ったペット選びを。
- 動物側のケアも重視:ペットも疲労・ストレスを抱えるため、休息・適切な扱いが必要。
- アレルギー・住環境・経済的負担も考慮:すべての人・すべてのペットが同様に健康メリットを得られるわけではありません。
- 関係の質が鍵:単なる「飼う」ではなく、適切な交流・絆・世話・観察が“健康メリット”を生み出します。
まとめ
ペットとの関係は、単なる「癒し」や「癒やされる存在」を超えて、私たちの身体的・精神的・社会的な健康にポジティブな影響をもたらす可能性があります。とはいえ、すべての人・すべてのペットが同様に恩恵を受けるわけではありません。ペットを迎える際には、自分の目的・環境・ペットの世話能力・健康リスクなどを総合的に考えて、適切に選ぶことが鍵です。そして、何より「動物と人間、お互いが幸せになる関係」を築くことが最も重要です。
【2025年最新版】サステナブルなエッセンシャルオイル特集: おすすめブランドと選び方

リラックスや集中力アップ、心身のバランスを整える香りのアイテムとして人気の「エッセンシャルオイル(精油)」。
しかし近年では、ただ香りを楽しむだけでなく「環境にも人にも優しいサステナブルなエッセンシャルオイル」を選ぶ人が増えています。
この記事では、エッセンシャルオイルの基本知識から使い方・効果、そして日本国内で購入・発送が可能なサステナブルブランドを厳選してご紹介します。
環境を守りながら、自分の心も癒す香りの選び方を一緒に探していきましょう。
エッセンシャルオイルとは?
エッセンシャルオイルとは、植物(花・葉・木・果皮・根など)から抽出された天然の芳香成分を凝縮したオイルのこと。
香りを通じてリラックスやリフレッシュ効果が期待され、アロマテラピーやスキンケア、空間演出など幅広い用途で使われています。
主なメリット・効果
- ストレス緩和・リラックス効果:ラベンダーやヒノキなどの香りが心を落ち着かせる
- 集中力アップ:ローズマリーやペパーミントで頭をすっきり
- 睡眠の質向上:就寝前の芳香浴でリラックス
- 自然の香りで空間を整える:人工香料に頼らないナチュラルな香りづくり
使用方法の例
- ディフューザーで空間に香りを拡散
- オイルに混ぜてマッサージに使用
- バスタイムに数滴垂らしてリラックス
- コットンやハンカチに染み込ませて持ち歩き
サステナブルなエッセンシャルオイルを選ぶポイント
環境と人に配慮した「サステナブル精油」を選ぶ際は、以下の点をチェックしてみましょう。
- 原料の栽培方法:自然栽培・有機栽培・過剰伐採防止など
- 地域社会との連携:生産地や林業の支援、地域循環型プロジェクト
- 抽出・製造方法の透明性:化学溶剤を使わない蒸留・圧搾製法
- エコパッケージや再利用素材の使用
- フェアトレードや認証マーク(例:有機JAS、ECOCERTなど)
日本で買えるおすすめのサステナブル精油ブランド
1|Kosmic Market(コズミックマーケット)
https://shop.humming-earth.com/
世界中から最良のシングルオリジン、オーガニック、野生採取の原料を探し求めるだけでなく、自身の心身の健康を高める努力を続け、その学びをコミュニティ全体と分かち合っている
おすすめ製品:
- エッセンシャルオイル – ミント(ペパーミント)
ポイント:ペパーミント精油は、スッとした清涼感のある香りが特徴で、気分をリフレッシュし、集中力を高める効果があります。

2|areme(アリーム)
ベトナムと日本の植物を原料に、環境と人に優しい製法で作られるナチュラルアロマブランド。
「自然と共に生きる香り」をテーマに、農薬を使わない栽培や再利用可能なパッケージにもこだわっています。
おすすめ商品
-
Japanese Botanicals Yuzu Essential Oil(ユズ精油)
爽やかで前向きな気分に導く柑橘の香り。 -
Yoshino Hinoki Essential Oil(吉野ヒノキ精油)
森の中を歩いているような深いリラックス感。
ポイント:自然素材の香りを通して、日常に“静かな豊かさ”を届けるブランドです。

3|meet tree(ミートツリー)
岐阜県中津川発、100年以上続く木材屋が立ち上げた森林循環型ライフスタイルブランド。
国産ヒノキやスギを原料にした精油を販売し、木材資源の有効活用と森の再生を両立しています。
おすすめ商品
-
Japanese Air Essential Oils(ヒノキ/スギ/クロモジ)
国産木材を使用。森林浴のような癒しを自宅で体験。
ポイント:ギフトにも最適なパッケージと香りのバリエーションが豊富。
“森の香りを暮らしに取り入れる”ことは、サステナブルライフを象徴するアイテムです。

4|梨之香(Rinoka)
山梨県富士川町を拠点に、実生ゆずや地元ハーブを使った循環型ものづくりを行う香りブランド。
耕作放棄地の再利用や森林整備など、香りを通して地域と自然をつなぐ活動が特徴です。
おすすめ商品
-
実生ゆず精油/芳香蒸留水シリーズ(ゆず・ローズマリー・ミントなど)
地元資源を活かした香りが魅力。クラウドファンディングで人気を集めたシリーズです。
ポイント:自然と人、地域と香りが共生する新しい日本型アロマブランド。
5|doTERRA(アメリカ/“Gift of the Earth”)
https://www.doterra.com/US/en
「地球からの贈り物」という名にふさわしく、倫理的な原料調達(Co-Impact Sourcing)・持続可能なパッケージなどに定評あり。
おすすめ製品
- 標準的な精油単品・ブレンド多数(日本への発送・代理店経由の取扱いも調べると良いです)。
ポイント:自社農園や提携農家との調達体制が整っており、“ブランドとしての信頼性”が高いブランドです。

6|Cliganic(アメリカ/コスト重視&オーガニック)
オーガニック認証を強く打ち出し、価格帯も手頃。大量レビューもあり、エントリーユーザーにも選びやすい。
おすすめ製品
-
Cliganic Organic Aromatherapy Set Top 8:8種のオーガニック精油セット。
ポイント:まずは、続けられそうな精油を気軽に試してみたいというあなたに最適です。

まとめ:香りを選ぶことは、暮らしのあり方を選ぶこと
エッセンシャルオイルは、ただ香りを楽しむものではなく、自分の心や地球の未来を意識する選択でもあります。
サステナブルな精油を選ぶことは、森林保全や地域の循環、公正な取引を支えることにもつながります。
忙しい日々の中で、少し立ち止まり、香りと共に呼吸を整えてみませんか?
あなたの暮らしに寄り添う“サステナブルな香り”が、きっと見つかるはずです。
秋の満月リチュアルのつくり方
心を整え、季節のエネルギーとつながるセルフケアガイド

内省の季節、秋に訪れる“静かな魔法”
夏の喧騒が静まり、空気が少し冷たく感じるようになると、私たちの意識は自然と内側へ向かいます。
キャンドルの灯り、焚き火の音、夜風の匂い——秋は「整える」エネルギーに満ちた季節です。
そんな秋にぴったりなのが、満月のリチュアル(儀式)。
月の満ち欠けは古来より人々の生活と深く結びつき、作物の収穫や祈りの時間を司ってきました。
現代の私たちにとっても、満月は「立ち止まり、自分と向き合う」特別なタイミング。
1年に12回訪れる満月のうち、秋の3回は特にパワフル。
この記事では、秋の満月が持つ意味と、それを日常に取り入れるリチュアルの方法を紹介します。
満月の意味とその力
月は何千年も前から、人の生活を照らし導いてきました。
満月は「豊かさ」「再生」「感情」「変化」の象徴とされ、
古代エジプトでは神聖な儀式の一部として、
ケルトの人々は物語や音楽、火を囲む集いを通して祝っていました。
今でも私たちは、満月を見るとどこか心が静まり、
「自然とともに生きている」という感覚を取り戻します。
秋の3つの満月とその意味
秋の満月は、“外へ”向かっていたエネルギーが“内へ”還る節目を示します。
それぞれの満月には、美しい名前と意味があります。
9月:コーンムーン(Corn Moon)
実りの象徴。夏の豊かさを感謝とともに収穫する時期です。
太陽のエネルギーを抱きしめながら、「この一年、自分の中で実ったもの」を振り返る時間に。
2025年の満月:9月7日(日)
10月:ハーベストムーン(Harvest Moon)
秋分に最も近い満月で、一年の中で最も明るく長く照らす月。
農夫たちはこの月明かりの下で夜通し収穫を行ったといわれています。
感謝と祝福のムーンフェーズです。
2025年の満月:10月6日(月)・スーパームーン
11月:ビーバームーン(Beaver Moon)
冬支度の象徴。
寒さが深まる前に、心と体を整える時期です。
内なる静けさと向き合い、エネルギーを蓄える満月です。
2025年の満月:11月5日(水)

秋の満月におすすめのリチュアル
秋の満月は、成長や拡大を象徴する春夏とは異なり、
「内省」「感謝」「手放し」をテーマにしたリチュアルが最適です。
1. 地域のフェスティバルやマーケットに参加する
満月は本来、人とつながるための月。
地元のマーケットや秋祭りに出かけて、旬の食材や手作りのアイテムを楽しみましょう。
友人や家族と一緒に季節の喜びを分かち合うことで、“今ここ”の幸せを感じられます。
2. 自分だけのスクラップブックをつくる
夏の思い出を振り返り、写真やメモをまとめてみましょう。
アルバムを見返すだけでも「感謝」のエネルギーが高まります。
手書きで「今年の夏、できたこと」を書き出すのもおすすめ。
3. ムーンウォーターをつくる
SNSでも話題のムーンウォーターは、古代から続く月の浄化法。
きれいなガラス瓶に水を入れ、満月の光が届く場所に一晩置くだけ。
翌朝その水を小瓶に移し、お気に入りの精油(フランキンセンス、ベルガモットなど)を数滴加えると、お守りのようなルームスプレーになります。
4. ハーベストムーンの晩餐を開く
満月の日に、親しい人たちと小さな“収穫祭”を。
パンプキンスープやアップルパイ、秋野菜のサラダなど、旬の食材を囲んで食卓を囲みましょう。
最後に「手放したいもの」を紙に書いて、キャンドルの炎で燃やすのもおすすめです。
5. 祖先とつながる時間をもつ
秋は“ご先祖とつながる季節”。
写真を飾り、感謝の気持ちを伝える時間を持ちましょう。
あるいは家族や友人と昔話を語り合うだけでも、
世代を超えた絆と安心感が生まれます。
6. シャドーワーク(内なる影と向き合う)
「シャドーワーク」とは、自分の中にある“影の部分”を見つめる心理的なセルフワーク。
不安、嫉妬、罪悪感、過去の痛みなど——普段は見ないふりをしている感情を
やさしく受け入れる練習です。
ノートにこう書いてみましょう。
- 「最近、避けている感情はなんだろう?」
- 「もう手放していい“思い込み”はある?」
- 「怖いけれど、本当は挑戦したいことは?」
月の光が、あなたの心を照らしてくれます。
リチュアルのあとに
儀式が終わったら、静かにノートを開き、
感じたことや気づきを書き留めましょう。
それはあなた自身の“成長の記録”になります。
夜空に浮かぶ満月を見上げると、
私たちはほんの少しだけ「自然の一部」であることを思い出します。
Hummingでは、リチュアルを“特別な儀式”ではなく、
「日常の中で心を整えるための小さな習慣」として紹介しています。
この秋、月の光に包まれながら、
静かな自分と出会う時間をつくってみてください。
— Humming Team
メディアを「丁寧に」ファクトチェックする方法
情報過多の時代に、自分の“情報消費”を整えるために

情報の洪水が心を疲れさせるとき
SNSやニュースアプリを開くたび、次々と更新される「最新情報」。
便利なはずのこの仕組みが、いつのまにか心の負担になっている――そんな経験はありませんか?
近年の研究では、情報の過剰摂取(インフォメーション・オーバーロード)は不安やストレスを高め、集中力の低下や感情の疲弊を引き起こすと報告されています。
日本ファクトチェックセンター(JFC)も、誤情報や偏向報道が人々の心理的負担や社会的分断を深める要因になっていると指摘しています。
情報と健やかに付き合うには、ただ受け取るだけでなく、“自分で確かめる”姿勢が大切です。ここでは、日々のメディア消費を少し丁寧に見直す方法をご紹介します。
おすすめ記事 ▶ 悲しいニュースからあなたの心を守るためのマインドフルネス
まず“一次資料”/“発信元”をたどる
ニュースを見たとき、「~によれば」「~が報じた」といった表現をチェックし、最初に報じたメディアや当事者にアクセスする習慣を持ちましょう。
例えば、政治や選挙に関する報道では、候補者や政党が“直接”発表している声明や演説、記者会見の映像・全文が元情報となることが多いです。
また、日本では 日本ファクトチェックセンター(JFC)が「ファクトチェック」と「メディア情報リテラシー普及」を二本柱に活動しています。日本ファクトチェックセンター (JFC)+2日本ファクトチェックセンター (JFC)+2
情報の“中継報道”よりも、できるだけ“直接の発信”に近いソースを参照することで、中間フィルターによる歪みを少しでも減らせます。
事実を確認(そのうえで再確認)
メディアや政治家、SNS投稿で目にした「数字」「発言」「データ」などは、ただ読むだけでなく「本当にその通りか?」を確認しましょう。日本語の解説でも「ファクトチェック=公開されている情報の真偽を検証し、共有する行為」と定義されています。
具体的な手順例:
- 公的機関や信頼できる報道機関のデータと比較
- 一次資料(発表・声明・統計)と全文で照らし合わせ
- 情報が最新かどうか確認(古いデータのまま使われていないか)
- 情報源(出典/支援団体/資金源)に偏りや利害関係がないかチェック
日本では、偽・誤情報の拡散に対して「教育・啓発」「ファクトチェッカーの育成」が急務とされています。
ですから、自分自身が“受け手”として、こうした確認プロセスを意識することが、いま特に価値があります。

信頼できる意見を読む・ただしそれを“事実”と同義にしない
信頼できるジャーナリストや分析者の意見を読むことは有益ですが、その人の主張=確かな事実ではありません。
チェックすべきポイント:
- その人/メディアのこれまでのトーンや報道姿勢はどうか?
- 問題発言や利害関係の指摘がないか(名前+「論争」などで検索)
-
「ああ、これに賛成!」と感じたときこそ、反対意見・根拠を探してみる
多くの場合、自分の意見と「いつも同じ側」の情報ばかり消費していると、見えない偏りが育ってしまいます。自分自身の“偏り”を自覚することが、ファクトチェックの大きな第一歩です。
心の健康を守るメディア習慣を
ファクトチェックは“情報のため”だけでなく、“自分を守るため”でもあります。
- ニュースを確認する時間を一日2回程度に制限
- 信頼できる媒体を2~3社に絞る
- 夜寝る前はSNSではなく、読書やストレッチで心を整える
情報を手放す勇気も、ウェルネスの一部です。
最後にー
情報消費の世界では、私たちは“読み手”であると同時に“判断者”です。
国内でも 日本ファクトチェックセンター のように、誰でも学べるメディア情報リテラシー教育プログラムが出てきています。
だからこそ、情報をただ“受け入れる”だけでなく、少しでも“問い”そして“検証する”姿勢を持つことが、これからの時代には欠かせません。
ニュースを通じて世界を知ることができる一方で、誤情報や偏った報道に惑わされないよう、自分自身の“情報収集の筋力”を鍛えていきましょう。
Hummingでは、情報と心のバランスを取ることを“新しいウェルネス”の一形態として考えています。
真実を見極める力は、他人を否定するためのものではなく、自分の心を静めるためのもの。
今日読むニュースが、あなたの中に安心と明晰さを残しますように。
ホリデーブルーを防ぐためのポジティブアクション
心が沈みがちな季節に、自分をやさしく守る方法

情報も感情もあふれる季節に
街に灯がともり、人々が集い、笑顔でプレゼントを交換する。
それが本来のホリデーシーズンの姿かもしれません。
けれど現実は、華やかなイルミネーションの光の裏で、心が少し疲れてしまう人もいます。
周囲の「楽しそうな雰囲気」と、自分の中にある孤独感や焦りのギャップ。
これこそが “ホリデーブルー” と呼ばれる現象です。
日本でも最近では「季節性情動障害(SAD)」という言葉が知られるようになりました。
冬の日照時間の短さや生活リズムの乱れにより、気分の落ち込みや不安、無気力を感じやすくなるといわれています。
なぜホリデーブルーになるの?
冬は、朝起きても外がまだ暗く、仕事を終えて外に出てももう日が暮れている…。
そんな日々が続くと、脳内のセロトニン(幸せホルモン)やメラトニン(睡眠ホルモン)の分泌が乱れ、心のバランスを崩しやすくなります。
さらに、ホリデーシーズン特有のプレッシャーも大きな要因です。
- 「どんな服を着よう?」
- 「どんなプレゼントを贈ろう?」
- 「家族とどう過ごそう?」
といった細かなストレスが積み重なり、「楽しむための季節」がいつのまにか「我慢する季節」に変わってしまうのです。
心を整えるポジティブアクション
整理整頓で“見える世界”を整える
頭の中が散らかっているときは、まず“目に見える場所”を整えるのがおすすめです。
クローゼットを整理して、冬に使う服だけを手前に置く。
デスクの上を片づけて、お気に入りのキャンドルを灯す。
環境を整えることで「自分でコントロールできている」という安心感が生まれます。
小さな“お祭り気分”を取り入れる
部屋を少しだけ飾りつけて、好きな音楽を流してみましょう。
完璧である必要はありません。
誰かと比べず、自分のペースで「小さな祝い」を作ることで、孤独感がやわらぎます。
「悲しみ」や「寂しさ」があってもいい。
その感情を否定せず、“楽しさ”と“切なさ”が共にある季節として受け止めることが、心の柔軟さにつながります。

過去を手放し、今を味わう
昔のクリスマスや家族の記憶が胸を締めつけることもあります。
でも、今シーズンは新しい思い出をつくるチャンス。
お気に入りの香りのキャンドルを灯し、日記や感謝ノートを書いたり、
大切な人へ手書きのメッセージカードを送ってみたり。
あるいは、地域のボランティア活動に参加するのもおすすめです。
人を助けるとき、脳内でドーパミン(幸福ホルモン)が分泌され、気分が自然に上向きます。
無理なく人とつながる
仕事が忙しくてつい「予定がないから残業しよう」と思ってしまうとき、
思い切って友人と会う約束を入れてみましょう。
先に約束をしておくことで、人とつながるきっかけになります。
気の合う人と過ごす時間は、ホリデーシーズン最大の癒しです。
屋外に出て、太陽の光を浴びる
冬はどうしても室内にこもりがちですが、
1日15分でも外の光を浴びることで、体内時計と気分が整います。
太陽光は“天然のセラピー”のようなもの。
外の冷たい空気を感じながら歩くだけでも、心の滞りが軽くなります。
生活リズムを保つ
ホリデー中は特別な予定が続き、睡眠や食生活が乱れがち。
しかし、気分の安定には「いつも通りのリズム」が最も大切です。
- 運動を続ける(ウォーキングやストレッチでもOK)
- 睡眠時間を確保する
- 食事やお酒の量を意識的にコントロールする
運動は抗うつ薬と同じようにセロトニンとドーパミンを増やし、
気分を上向かせる効果があるといわれています。
感情をアルコールで紛らわせない
失恋や喪失の記憶が強く浮かぶ季節でもあります。
けれど、アルコールや薬物は一時的に気分を軽くしても、
脳のセロトニンを減らし、結果的にさらに気分を落ち込ませます。
つらいときは一人で抱えず、信頼できる友人やカウンセラーに話してください。
地域のメンタルヘルスセンターやいのちの電話(0570-783-556)などの相談窓口があります

もし心が苦しいときは
「やる気が出ない」「食欲がない」「何をしても楽しくない」
そんな日が続くときは、無理せず専門家に相談を。
心理士やカウンセラーとの会話は、心の整理にとても効果的です。
話すことで、自分の中の感情を“見える化”できるからです。
助けを求めることは弱さではなく、前に進むための第一歩です。
ホリデーを“整える季節”に
ホリデーシーズンは、がんばるための季節ではなく、“立ち止まり、整えるための季節”。
やることに追われるのではなく、心を整える行動を少しずつ増やすことで、
一年の終わりをやさしく締めくくることができます。
今日できることを、ひとつだけ選んでみましょう。
それが、あなたの冬を少し温かくしてくれるはずです。
最後にー
「楽しそうに見える季節ほど、人は孤独を感じやすいもの。」
Hummingでは、そんな心の揺らぎも含めて“人間らしさ”だと考えています。
ホリデーは、笑顔だけでなく、静かな時間や涙も包み込むもの。
そのどれもが、あなたの物語の一部です。
どうか、今年の冬は少し自分に優しく、
小さな幸せを見つけることから始めてみてください。
— Humming Team
介護者のためのセルフケア:あなた自身を大切にするための4つのヒント

介護をする時に大切なこと
祖母がパーキンソン病だと知ったのは、私がまだ幼い頃でした。
当時はよく分からず、「少しずつ悪くなる病気」だとだけ教えられていました。
アメリカで暮らしていた私は頻繁に会いに行くことができず、数か月ぶりに会うたびに祖母の変化を感じました。母は主な介護者として心身ともに大きな負担を抱え、祖母の体が弱っていくにつれ、母自身の輝きも少しずつ失われていくようでした。
介護は深い愛の表現であると同時に、自分をすり減らす行為でもあります。
だからこそ、“自分をケアすること”が何より大切なのです。
おすすめ記事▶ 心の健康を保つための方法
1. 睡眠を最優先に
介護中はどうしても睡眠が削られがちですが、休息は心と体の基盤です。
- 短時間でも眠れるときに仮眠をとる
- 寝る前のルーティンを作る(洗顔・ハーブティーなど)
- 「完璧な睡眠」を求めない
疲れを我慢しても誰も得をしません。休めるときには、ためらわず休みましょう。
2. 栄養のある食事をとる
介護に集中すると自分の食事が後回しになりがちですが、栄養は心と体のエネルギーです。
- 朝は少しでも何かを食べる
- 間食を常備(ナッツ・フルーツなど)
- 水分と電解質をこまめに摂る
- 料理を簡単にする工夫(宅配・作り置き・周囲の助けを借りる)
“完璧な食事”よりも“続けられる食事”を。

3. 外の空気と小さな喜びを感じる
太陽の光や風を感じることは、心を落ち着かせる自然の力です。
たとえ数分でも、外に出て深呼吸をしてみましょう。
お気に入りのカフェでコーヒーを飲む、庭に出て草花を眺める、ただ空を見上げる——そんな小さな時間が心を回復させてくれます。
4. 誰かに頼る勇気を持つ
「自分が頑張らなきゃ」と思い込んでしまう介護者は多いですが、あなたも支えられる側でいていいのです。
家族や友人に頼ること、地域のサポートを利用することは“甘え”ではなく“必要なケア”です。
支える側の人も、こうした関わりをしてみましょう。
- 「何を手伝えば助かる?」と聞く
- 家事や買い物など具体的なサポートを
- 「介護者として」ではなく「一人の人間として」寄り添う
介護は、愛と優しさの循環
介護は、思いやりと忍耐、そして深い愛で成り立っています。
その中には、介護する人の幸せも含まれています。
どうか、あなた自身にも光を向けてください。
休息、栄養、太陽、そして人とのつながり——それらはすべて、あなたを支えるセルフケアの一部です。
最後にー
介護という言葉の裏には、数えきれないほどの物語があります。
それは愛であり、責任であり、時には静かな孤独でもあります。
Hummingでは、介護を「誰かのために尽くすこと」だけでなく、「自分の心を守ること」としても大切に考えています。
あなたの優しさが、あなた自身を傷つけないように。
今日の小さな休息が、明日の大きな力になりますように。
— Humming Team
【ハミングが届けるポジティブニュース】 「スマホのない子ども時代」を取り戻す!何気ない2人の親の会話から始まった全国規模のムーブメント

私たちにとって、子ども時代の思い出は泥まみれの公園や、友だちとの顔を合わせたおしゃべりではないでしょうか。でも、今やスマートフォンは子どもたちの生活に欠かせない存在となり、その光と影に心を痛めている親も多いはず。
「うちの子はまだだけど、いつまで持たせないでいられるかしら…」
そんなふうに感じていたイギリスの二人の母親のささやかな会話から始まったのが、「スマホのない子ども時代(Smartphone Free Childhood)(以下SFC)」という草の根ムーブメントです。
この活動は、たった一年で数万世帯の家族が参加する全国的なキャンペーンへと爆発的に広がり、学校のルールを変えました。
彼らのメッセージはシンプルで力強いもの。
「子ども時代というのは、スマートフォンに時間を費やすにはあまりにも短い」。
そして提案するのは、「14歳までスマホは持たせない、ソーシャルメディアは16歳まで」という指針です。これは、子どもをアルゴリズムの支配から解放し、子どもの時間を子どもたちの手に取り戻そうという、ポジティブな抵抗の物語。
この驚くべきムーブメントが、どうやって多くの親の心をつかみ、社会を変え始めているのか、今回はその全容をお伝えします。
親の不安が導火線となった、ムーブメントの誕生
SFCの共同創設者であるデイジーさんは、ジャーナリストとしての経験を持つ一人の母親です。彼女が抱いていたスマホに対する不安は、もう一人の母親との何気ない会話で一気に火が付きます。
「うちの子がスマホを欲しがったら、そろそろ買うわ」という友人の言葉に、デイジーさんは強い危機感を覚えました。「このままでは、友達に取り残されると恐れて、多くの子どもたちがスマホを持ち始めるという避けられない現実がある」と。
実際、イギリスでは12歳の子どもの89%が、そして驚くべきことに5歳から7歳の子どもの4分の1がすでにスマホを持っており、初めてスマホを持つ平均年齢はわずか9歳。これは、なんの管理も行き届かない状態で世界が子どもに向けて完全にオープンとなってしまうことを意味します。彼女は「今行動しなければ、手遅れになる」と強く感じ、それが彼女を突き動かす原動力となりました。
スマホがもたらす心の健康への影響
なぜ、これほどまでに親たちは不安を感じているのでしょうか?
デイジーさんたちが指摘するのは、スマホが子どもたちの心にもたらす深刻な影響です。
例えば、暴力的なものや性的なものなど有害なコンテンツに簡単にアクセスできてしまうこと。また、絶え間ない通知によって集中力が妨げられます。平均的なティーンエイジャーは一日に200件以上の通知を受け取り、勉強や趣味、現実の友人関係に集中することが難しくなっています。他にも、テクノロジー企業は、ユーザーを画面に釘付けにすることで利益を得るために設計されたアルゴリズムの罠や、オンラインでのいじめや、見知らぬ大人によるグルーミング(誘い込み)などの報告も後を絶ちません。
その結果、スマホが普及した2010年頃から、ティーンエイジャーの不安やうつ病の発生率が急増していることが、様々な研究者によって指摘されています。

瞬く間に全国へ広がるムーブメント
デイジーさんは、まず友人のクレアさんとともに、同じ不安を抱える親たちが団結するためのワッツアップ(通話アプリ)でグループを作りました。最初はたった3人から始まったこのグループですが、ある晩、彼女がインスタグラムに短い投稿をしたことをきっかけに、まさかの展開を迎えます。
翌朝、彼女がスマホを見た時には、グループは多くの人達のコメントであふれていました。「まるで魔法のように恐ろしい竜巻が、私たちのキッチンにやってきたような気分だった」と当時を振り返るデイジーさん。
彼女たちは、政府の指針もない中で、「地球上で最も強力で説得力のある企業」に向き合い、「私たちは一人じゃない」と感じたい親たちの切実なニーズにまさに火をつけたのです。
親たちの「行動」が社会を変える
この爆発的なエネルギーを目の当たりにし、デイジーさんたちはブランディング会社での仕事やジャーナリストの職を辞め、SFCを現実の組織として立ち上げることを決めました。
ムーブメントの中心にあるのは、「親の約束」と呼ばれる誓約です。これは、「14歳までスマホなし、16歳までソーシャルメディアなし」という姿勢を守り、学校にも同じ方針を奨励してもらうために、親たちが署名するものです。発足からわずか一年ほどで、南極大陸を除くすべての大陸の14万世帯以上の家族がこれに署名しています。
学校にも広がる変化
SFCは、イギリスの地元の学校とも連携して、具体的な変化を生み出しています。
ある学校の校長は、スマホがもたらす問題を目の当たりにし、低学年の生徒を対象に、登校時にスマホを預ける自主的な預け入れ制度を導入しました。その結果、食堂はスマホをいじる生徒でなく、友だちとおしゃべりや笑いを楽しむ、素敵な雰囲気に変わったといいます。
この成功に手応えを感じた学校は、この預け入れ制度を学年ごとに義務化し、最終的には全校に広げる予定です。さらに、この校長はSFCの支援を受けながら、地域の80校中68校を巻き込み、同様の取り組みを推し進めています。

目的は「禁止」ではなく「バランス」
SFCの関係者は皆、自分たちが「アンチ・テクノロジー」や「スマホ反対派」ではないことを強調しています。
「私たちは『スマホを禁止したい親たち』という報道をされることが多いのですが、そんなことは一度も言っていません。テクノロジーは敵ではなく、私たちがそれをどう使うかが問題なのです」。
彼らの目的は、子どもたちがテクノロジーに依存するのではなく、自信を持って使いこなせるように育つことです。彼らは、デジタルスキルを段階的に構築し、子どもたちが常にデジタルとつながっている状態になる前に、「子どもでいられる時間」を多く与えることを信条としています。
実際、SFCはスマホメーカーとも協力し、SNSへのアクセスは遮断しつつ、必須の情報にはアクセスできる「子どもに優しいデバイス」の開発も進めています。
この草の根の力強いムーブメントは、私たち親が抱える静かな不安が、どれだけ大きくポジティブな社会変革のエネルギーになり得るかを示しています。大切なのは、「私たちは一人ではない」と知り、「子ども時代を子どもたちの手に取り戻す」という明確な意志を持つことではないでしょうか。
このムーブメントを見て、ご自身の子育てにおけるスマホとの付き合い方について、改めて問いかけてみませんか?
【レビュー】『Love on the Spectrum』が教えてくれた、本当の「愛し方」

誰だって、一度は夢見たことがあるんじゃないでしょうか。
まるでおとぎ話みたいな恋を。
子どもの頃の私は、少女マンガにすっかり心を奪われていました。
不器用で、ちょっと頼りない男の子が、物語の最後には必ず主人公の女の子に恋をして、
まるでこの世界に彼女しか存在しないかのように見つめる――そんなシーンに胸をときめかせて。
おすすめ記事:【映画レビュー】Minari | ミナリとアメリカン・ドリーム
10歳の私には、それが「恋の理想」そのものだったのです。
でも、大人になるにつれて、恋の形はいろいろあることを知りました。
マンガの中で輝いていた恋は、現実では少し違う。
皮肉屋になったわけじゃないけれど、人の心はそんなに単純じゃないって気づいたんです。
正直でいるほうがきっと楽なのに、私たちはそれを怖がって、
争いも、痛みも、真実も避けてしまう。
そして、「うまくやろう」とついた小さな嘘が、
気づけば大きなもつれになっていく。
“『Love on the Spectrum』を通して、私は「誠実さ」と「静けさ」の中にこそ、本当の愛の優しさがあることに気づかされた。”
30代のある日、Netflixで『Love on the Spectrum』という番組を見つけました。
自閉スペクトラム症の男女が「恋」を探すドキュメンタリー。
最初は、自閉症のことをほとんど知りませんでした。
「スペクトラム」という言葉の通り、人によって度合いが違い、
主にコミュニケーションや人との関わりに影響がある――その程度の知識。
だからこそ、「恋愛」という誰にとっても難しいテーマを、
彼らがどう歩んでいくのかが気になったのです。

観始めたら、あっという間に時間が過ぎていました。
この番組には、描かれ方に対する批判もあると聞きます。
私は「定型発達者」だから、その立場から何か言えるわけではありません。
ただ、出演者の多くが白人で、比較的恵まれた環境にいたことが、
彼らの恋愛経験に影響しているのかもしれないとは思いました。
それでも心を打たれたのは、彼らの「誠実さ」でした。
自分にも、相手にも、家族にも、正直であろうとする姿。
彼らのデートに、相手に対する丁寧さと誠実さを感じました。
言葉を練習したり、服を選んだり、
男性たちは椅子を引いて、相手のためにドアを開けて。
会話はぎこちなく、沈黙も多くて、
「友達でいましょう」で終わることも少なくない。
でも、そこには不思議な温かさがあって、
思いがけない愛が、静かに芽を出していく。
沈黙が苦手な私にとって、その静けさは小さな発見でした。
言葉のない時間の中に、
優しさや真実が、確かに存在しているのです。
“彼らの前向きな姿から、恋において大切なのは自分を責めることではなく、「自分だけの光」を信じることなのだと気づかされた。”
そして何よりも美しかったのは、彼らの「前向きさ」。
うまくいかなくても、涙を流しても、決して諦めない。
「何が悪かったんだろう」ではなく、「きっと縁がなかったんだ」。
その潔さに、私は何度も心を打たれました。
恋愛を求めるとき、私たちはつい自分を責めがちです。
「可愛くないから」「細くないから」「背が低いから」――
そんな理由を並べては、
自分を「足りない」と思い込んでしまう。
でも考えてみたら、そんな風に自分を削ってまで恋をするなんて、
少し悲しいことですよね。
世界には、あなたより綺麗な人も、
賢い人も、魅力的な人もいる。
でもそれでいい。
あなたはあなたにしかなれないし、
その中にしかない光が、ちゃんとあるのです。

番組を見ながら思ったのは、
自閉症の人たちが持つ「シンプルな視点」が、
人間関係の本質をすっと映し出しているということ。
相手に好かれなかったとしても、
それはただの事実であって、
自分の価値とは関係がない。
痛みはあるけれど、必要以上に掘り下げない。
その潔さが、なんだか眩しく見えました。
そして、誰かを好きになったときの彼らの反応――
まっすぐで、純粋で、隠せない。
笑って、飛び跳ねて、全身で「嬉しい!」を表す姿に、
私は高校時代の初恋を思い出しました。
ただ「好き」という気持ちだけでいっぱいだったあの頃。
駆け引きも、言い訳もいらなかった。
ソファの上で笑いながら、
あの頃の胸の高鳴りを、ふと思い出していました。
“『Love on the Spectrum』を通して、愛とは飾らず正直に向き合い、時間をかけて育てていくものだと改めて教えられた。”
この番組の意味をめぐっては、
教育なのか、搾取なのか、エンタメなのか――いろいろと言われています。
でも、私にとっては「学び」でした。
自閉症について学んだこと以上に、
「愛」について教えられた気がします。
愛は、過去の傷や孤独を埋めるためのものじゃない。
作り笑いの中で育つものでもない。
時間をかけて、正直さの中で、ゆっくり育つもの。
相手の良いところも、弱いところも、
まるごと受け入れる準備ができたときにこそ、
愛は静かに根を下ろす。
だから、まずは自分に正直であること。
そして、相手にも誠実であること。
その勇気さえあれば――
愛はきっと、あなたのもとにもやってくる。
過去の失恋が気づかせた、わがままプリンセスすぎた私とパートナーシップの本質

過去の恋愛を振り返って、穴があったら入りたいくらいの恥ずかしさに襲われること、ありませんか?
とはいえ、私はそれほど恋愛経験が豊富ではなく、今も彼氏がいない期間記録を更新中。
過去の恋愛といっても、するめいかをしゃぶるかの如く、同じ思い出を反芻しているだけなのですが…
そのなかに「いや~~あのときの私、わがままプリンセスすぎた…!」と、思い出すたび、恥ずかしさに身もだえする思い出があります。
エスコートしてくれない、年上の彼
私がわがままぶりを発揮してしまったのは、大学時代に付き合っていた先輩と、遠距離恋愛になったときのことです。
彼が先に就職して東京へ行き、私は大阪。
夏休みに会いに行って、数日間彼の家に泊まらせてもらったことがありました。
当然平日は、彼は仕事なので私はひとりで観光するしかなかったのですが、休みの日には一緒に出かける予定にしていたのでそこは特に気に留めず。
むしろ、どんなところに連れてってくれるんだろうかと、ひそかに楽しみにしていました。
おすすめ記事▶ 大人になってから友達を作るのは大変?でも大人になったから築ける友情もある
でも、待てど暮らせどどころか、当日になっても具体的なデートプランの話は一切されず…
そう、よく言えば気の向くままに、悪く言えば行き当たりばったりのデートになったんです。
そんなの、大阪にいた頃と一緒じゃん…
あの頃はそれで充分だったよ…いつでもどこでも行けたから…
でも、久々に過ごす二人の時間なのに…
あなたは住んでても、私はめったに来れない東京なのに…
そんなモヤモヤが、出かけるときから薄っすら溜まっていき、決定打になったのが映画でした。
行き当たりばったりのなかで、前から二人とも気になっていた映画でも見に行くかという流れになったんです。
「日本全国どこでも行ける映画…でもまあまあ、まあ」と、心の中で一旦飲み込む私。
気になってた作品だし、それを彼と一緒に見に行けるのは素直に嬉しいし。
ただ、大ヒット映画だったことと、思い立ったのが直前すぎたせいで、なかなか空席のある映画館も、ちょうどいい時間帯の上映が見つからなくて。
ようやく予約できたものの、少し足を伸ばす映画館で、しかも前方のほうの席しかありませんでした。
見上げるような角度で観ることになって、首が痛いなあとは思いながらも、映画自体は普通に面白くて、上映後も感想を言い合ったりしてそれは純粋に楽しかった。
“年上の彼が自分のためにデートの計画を立ててくれなかったことへの寂しさが積もり、不満として爆発してしまった。”
だけどその後、少し時間が経ってから、ふと話の流れで上映館探しにまごついたことと、バッドコンディションで鑑賞したモヤモヤを思い出してしまい、彼を責めるようなことを言ってしまったんです。
「もっと早く予約してくれてたらよかったのに」的なことをぶつけてしまったんですが、今思えば、映画の座席なんてどうでもよかったんです。
本当に引っかかっていたのは、「私のために段取りしてくれなかった」ことに対する寂しさでした。
映画に限らず、私が訪問することは決まっていたのに、「ここに連れていきたい」「これを見せたい」といったデートプランを彼が考えてくれていないことが、やっぱりずっとしこりになっていたんですよね。
だってさ、年上の彼ですよ。
一足先に社会人、大人になった彼。
こっちはまだ、遠距離をひょいとは会いにいけない大学生。
そんなの、正直エスコートされたいとか、甘やかされたい的な憧れ抱いちゃうじゃないですか。
だから、
「毎週は会えないから!!」
「どっか連れてってくれるの?!くれないの?!」
と、ドリカムの『大阪LOVER』(私たちの舞台は東京だけど)さながらに、小さな不満を募らせ、結果、彼を一方的に責めることになってしまったんだと思います。

ディズニープリンセスだって自力で道を切り拓くのに
そんな感じで、その時の私は、彼に対して「もっとこうしてほしい」「わかってほしい」と求めるばかりでした。
土地勘は彼のほうがあるだろうし、年上だし社会人だし…と、とにかく自分から動くよりも、彼がリードしてくれるのを期待していました。
そんなあの頃の私にツッコみたい。
「いや、どこぞのプリンセスやねん」と。
時代は令和です。(当時はまだ平成ですが)
馴染みのない土地だろうが、なんなら海外だろうが、この手のひらに収まっている便利な電子機器1つで何でも解決する時代です。
美味しそうなお店、面白そうなスポット、見たいもの、行き方、リアルなレビューも全部調べられます。
それを彼がするか、私がするか、二人でするか、その三択。
というか、新社会人になったばかりの彼は、新しい土地で仕事にも生活にも慣れるのに精いっぱいで、毎日必死だったはずです。
今思えば、デートプランを練る余裕なんてそうそうなかったでしょう。
むしろ、彼が仕事中、ひとりで時間を持て余していたのは私のほうです。
“彼の優しさや気遣いに十分満たされていたはずなのに、当時の自分は「もっと特別にしてほしい」と受け身のまま欲を募らせていたことに気づき、今では恥ずかしく思っている。”
ディズニープリンセスだって、自分の足でたくましく道を切り拓いていく時代に、お城のてっぺんの窓辺で優雅に白馬の王子様を待ち続ける、超受動的プリンセスになってた。恥ずかしすぎる。
しかも、彼は何もしてくれなかったわけじゃありません。
滞在中、私は誕生日を迎えたのですが、その日にはおしゃれなレストランを予約しておいてくれたし、プレゼントに手紙まで書いてくれていました。
なんて素敵な彼氏!!!
それだけで十分ありがたいでしょうが!!!
と、当時の私を引っぱたきたい気分です。
それでも、そのときは本気で悪気なく「もっと」を求めていたんだから、恐ろしい話です。
次こそは、お互い与えあえるパートナーに
そんな子どもすぎる不満をぶつけても、彼は私に言い返したり愛想をつかす素振りもなく、むしろ優しく「ごめんね」と謝るだけでした。
もう十分甘やかされていたどころか、私は負担ばかりかけていたのに、そのときは全然気づけなかった。
ようやく気づいたのは、自分が社会人になってからのことでした。
社会に出て、右も左も分からない環境で毎日働いて、生活を紡ぐことが、どれだけエネルギーがいることか。
私は慣れ親しんだ地元に帰って、しかも実家から通える会社に入社したのに、それでもしんどかった。
重い足取りで家路につくなかで、ふと彼の顔が浮かび、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。
“過去の未熟さから彼に思いやりを欠いていたことを今になって悔いながらも、謝るのではなくその痛みを胸に刻み、自分への戒めとして受け止めている。”
彼はきっと、いっぱいいっぱいの中で、それでも私に時間を割いてくれてたのに。
疲れて帰ってきて、家で一人になれる時間がなかったのもしんどかったよな、きっと。
私だったら、帰って彼氏が居て嬉しいのはせいぜい最初の1-2日だけだもん。
3日目くらいからちょっと鬱陶しくなっちゃうし、休みの日はゆっくり家で寝たいわ。
そう思うと、まあまあ骨の折れる彼女だったなと、失笑してしまいます。
でも、気づいたときには、時すでに遅し。
彼とは、私が社会人になる随分前にお別れしてしまっていたので、謝ることも挽回することもできないままです。
何年も経った今も、こうしてたまに申し訳ない気持ちがチクッと心に蘇ります。
でも、これくらいのチクチク、私が彼にぶつけた思いやりのなさに比べたら全然たいしたことありません。
だいたい、今さら謝るのもおかしな話だし、何よりそれは結局自分が許されたい、スッキリしたいだけ。
そんなの、逆にまた彼を傷つけることになります。
だから、このチクチクはそっと胸にしまっておく。
むしろ、これを抱えたまま生きていくことが、自分への戒めになる気がします。

…いや、それはさすがに綺麗事かな。
これで多少、当時の罪滅ぼしにならないかなって邪な気持ちもあるし。
でも、もしいつかまた誰かとお付き合いできたら、次こそ、求める人ではなく、相手を思いやって自分から与えられる人になりたいです。
子どもすぎる私を受け止めてくれた、優しすぎる彼から教わった大事なこの教訓はこれからも忘れずにいたいと思います。
……と言いつつ、書いていたらあまりにも申し訳なさが溢れてきたので、この場を借りてこっそり彼に謝らせてください。
あの時はマジでごめん!!!ほんとありがとう!!!
やわらかく戻る力──大人になってからのレジリエンスの育て方

ひとりっ子として育った私は、誰かと自分の気持ちや体験を共有する機会がほとんどありませんでした。
母はとても厳しく、アメリカで育つ娘に日本的な「ルール」を強く求めました。
幼い私にとって、それはとても怖く、そして混乱に満ちた時間でした。
「二つの文化に属することは美しいこと」——そんな理解にたどり着くには幼すぎて、
6歳の私には、どちらの世界にも完全には馴染めないという、きゅうくつな感覚しかありませんでした。
霧のような混乱の中で、私は「わからないこと」に慣れ、何が起きても自分で解決しようとするスキルを身につけました。
何か辛いことや怖いことがあるたびに、私は心の中でこうつぶやいていました。
「大丈夫、わたしがなんとかする。」
子ども特有の繊細な心を守るため、私は懸命に強がりの壁を築き、“わかっているふり”をしていました。 今振り返れば、それは本当の強さではなく、どこか脆く、不安定な「なんちゃってレジリエンス」だったのです。
レジリエンスとは何か
「レジリエンス」という言葉は、近年よく耳にするようになりました。
研究者であり作家のブレネー・ブラウンが著書『Rising Strong』の中で述べているように、
レジリエンスとは「うまく苦しむ力」——つまり、困難な感情と向き合い、失敗から学び、
意図と自己への思いやりを持って前に進む力を指します。
心理学的には、逆境やトラウマ、強いストレスに直面したときに、うまく適応し回復する力のこと。
それは困難を避けることではなく、しなやかさ・勇気・感情的な強さをもってそれを乗り越える力です。
ある論文ではレジリエンスを “ordinary magic(ありふれた魔法)” と呼んでおり、私はその表現がとても気に入っています。
私自身が好きなのは、レジリエンスを物ごとの性質として捉える考え方です。
つまり、「外からの圧力を受けても元の形に戻る力」「弾力性」や「エネルギーを吸収して放出する柔軟さ」。
別の論文では、この言葉の過剰使用に疑問を投げかけ、
「形を取り戻す前に、まず圧力の原因を取り除くことの大切さ」を説いていました。
この考えに触れたとき、ようやく腑に落ちたのです。
レジリエンスとは「無限に耐える力」ではなく、圧力に耐えたあと、きちんと回復する力。
そして硬くなることではなく、柔らかく戻る力こそが、本当のしなやかさなのだと。
レジリエンスの育て方
アメリカ心理学会(APA)は、次のように述べています。
「レジリエンスを高めるのは筋肉を鍛えるのと同じ。
時間と意識的な練習が必要です。
“つながり・ウェルネス・健全な思考・意味”の4つの要素を意識することで、
困難やトラウマから学び、乗り越える力を強化できます。」
つまり、レジリエンスは一夜にして身につくものではなく、
日々の小さな選択とセルフケアの積み重ねで育つもの。

私が誤解していた「強さ」と「しなやかさ」
私はずっと、レジリエンスを「耐える力」だと思っていました。
どんなにつらくても、倒れずに立ち続けること。
でも実際は、形を取り戻せていなかったのです。
完璧主義はやがて不安障害へと変わり、
「コンパートメンタライゼーション(心の分離)」という言葉を知ったとき、
まるで自分のことだと感じました。
感情を切り離し、見ないふりをすることが、私の生き延びる術でした。
しかしそれは、しなやかさではなく、硬さと分断を育てていたのです。
困難な環境を生き抜くための防衛反応は、
時間が経つとともに、自分を蝕む“古い鎧”になっていました。
本当のレジリエンスを育てるには、
外からの支えと、内側のやさしさの両方が必要なのだと、今ならわかります。
私の「レジリエンス・プラクティス」
大学時代、私にとってのレジリエンス練習は「癒しの時間」でした。
他の学生が自由や冒険を楽しむなか、私は静かに自分を整えていました。
- 朝のノート時間で心を整える
- 友人たちと笑い合う夜を楽しむ
- ジムで体を動かし、食事で自分を養う
- カウンセラーに話を聞いてもらう
こうした小さなセルフケアが、
私の中の「自己信頼」をゆっくりと取り戻してくれました。
大学を早期卒業した頃には、
「努力すること」よりも「自分を慈しむこと」が、
本当の強さだと気づくようになっていました。
大人になってからのレジリエンスの磨き方
40代の今、私は20代で築いたセルフケアをより深く実践しています。
- 批判的な内なる声に気づき、やさしく修正する
- 体・心・人間関係をバランスよく育てる
- 自分を追い詰めず、軽やかに挑戦する
- 真剣になりすぎず、「楽しむ力」を取り戻す
こうした実践が、心の弾力性=レジリエンスを支えています。
レジリエンスとは「痛みに耐える力」ではなく「喜びを感じる力」
レジリエンスとは、「強く立つこと」ではなく、「やわらかい自分に戻ること」。
それは、心が折れそうな瞬間に、自分をそっと抱きしめるような小さな選択の積み重ねです。
泣いても、止まっても、また立ち上がれる。
そんな“しなやかな強さ”こそが、これからの時代を生きる力なのだと思います。
—— Humming 編集部
離婚を乗り越え、自分らしく生きるために

心の回復と新しい人生の始め方ガイド
離婚は、人生の中でも特に心を揺らす出来事のひとつ。
大切な関係が終わるとき、人は深い悲しみと同時に、空白のような静けさに包まれます。
「これからどう生きていけばいいのか」「子どもや家族はどうなるのか」——そんな不安でいっぱいになるのは自然なことです。
けれど、離婚は“終わり”ではありません。
それは、これまで誰かと共有していた人生から、自分自身の人生を取り戻す“再出発”のタイミングでもあります。
ここでは、心理学的な視点と実践的なアプローチを交えながら、離婚を乗り越えて、自分らしく生きるためのヒントをお届けします。
あなたのペースで、一歩ずつ、心を整えていきましょう。
おすすめ記事 ▶ 離婚後に心を癒すための心理学者のアドバイス──どんな年齢でも
1. 離婚は「失敗」ではなく、人生の転機
離婚後、多くの人が「失敗した」「もう立ち直れない」と感じます。
けれど本当は、離婚はあなたの人生を再び見つめ直すチャンス。
悲しみや喪失の中にも、「自分らしく生きる力」を取り戻すきっかけが隠れています。
あなたの物語はここで終わりではありません。ここからが新しい章の始まりです。
2. コントロールできることに目を向ける
離婚すると多くのことを失ったように感じますが、実は「自分で選べること」もたくさんあります。
心の回復力(レジリエンス)や周囲の支え、人とのつながりを意識的に育てることで、ストレスや不安を和らげることができます。
「すべてを完璧に」ではなく、「少しずつ前へ」が大切です。
3. 離婚の進め方を選ぶ
どのように離婚するかは、心の回復にも大きく影響します。
裁判を避け、「調停」「協議離婚」「コラボレーティブ離婚(協働的離婚)」といった方法を選ぶことで、対立ではなく「思いやりと対話」を重視したプロセスを築くことができます。
穏やかな話し合いは、あなた自身にも、子どもたちにもやさしい選択です。

4. SMARTゴールで「新しい自分」をつくる
離婚後の不安定な時期こそ、SMARTゴール(具体的・測定可能・達成可能・関連性・期限設定)を使って、人生を再設計してみましょう。
たとえば:
- 毎日30分のウォーキングを習慣にする。
- 週に一度、友人と食事をしてつながりを保つ。
- 子どもと一対一で過ごす時間をつくる。
- クリスマスや年末は一人で過ごさないように早めに計画する。
小さな達成の積み重ねが、自己肯定感と安心感を育てます。
5. 人とのつながりを再構築する
離婚は社会的なつながりにも影響しますが、同時に「新しい縁」を築くチャンスでもあります。
- 旧友に連絡してみる
- ボランティアや趣味のサークルに参加する
- コーヒーショップの店員さんや近所の人に挨拶する
社会学者マーク・グラノヴェターが提唱した「弱いつながり(Weak ties)」は、幸福感を高め、孤独をやわらげる力があると言われています。
小さな交流を大切にすることで、心が少しずつ温まっていきます。
6. 子どもがいる場合は「思いやりの共同養育」を
離婚後の親同士の衝突(コペアレンティング・コンフリクト)は、子どもにとって最も大きなリスクの一つ。
ここで役立つのが「BIFFメソッド(Brief, Informative, Friendly, Firm)」です。
- Brief(短く):長文ではなく、1〜2段落でまとめる。
- Informative(情報中心に):感情ではなく事実を伝える。
- Friendly(友好的に):皮肉や怒りのトーンを避ける。
- Firm(明確に):できること・できないことをはっきり伝える。
お互いのやり取りを記録できるアプリ(例:Our Family Wizard)を使うのもおすすめです。
穏やかな親同士の関係は、子どもの安心と幸福を守ります。

7. 過去の関係から学び、未来の恋愛を育てる
次の恋愛を始める前に、まずは「自分の過去のパターンを理解すること」が大切です。
なぜあのとき衝突したのか、どんな関係性が心を満たしていたのか。
それを見つめ直すことで、同じ失敗を繰り返さずにすみます。
心理学者ジョン&ジュリー・ゴットマン夫妻の研究によると、健全な関係の土台は次の7つ。
- お互いの世界を知る
- 感謝と尊敬を伝える
- 問題を無視せず向き合う
- 相手の意見を尊重する
- 解決できる問題を話し合う
- 行き詰まりを乗り越える
- 共通の意味・価値をつくる
逆に、「批判・軽蔑・防御・無視」は関係を壊す要因になります。
これらを意識することで、次の恋愛をより健やかに育てることができます。
8. 自分を大切にする「セルフケア」を最優先に
離婚は心にも体にも大きなストレスを与えます。
だからこそ、自分をいたわることは贅沢ではなく必要です。
- よく眠る
- 栄養のある食事をとる
- ヨガや瞑想で呼吸を整える
- カウンセリングやコーチングで心を整理する
「自分をケアする力」が、人生を再び動かすエネルギーになります。
9. 離婚を乗り越える19の真実
- 離婚は失敗ではなく、成長の一形態。
- どんな感情も否定しない。
- セルフケアは最優先。
- 信頼できるサポートを見つけよう。
- 回復のスピードは人それぞれ。
- 焦らず、時間を味方に。
- コミュニケーションを恐れない。
- 未来のビジョンを描く。
- 子どもに「愛されている安心感」を伝える。
- お金の計画を立てて自立する。
- マインドフルネスで心を落ち着ける。
- 幸せは自分の手でつくる。
- 許しは、自分を自由にする鍵。
- 人生は再び美しくなれる。
- 新しい自由を楽しもう。
- 境界線(バウンダリー)を大切に。
- 離婚から学べることは必ずある。
- 本当の「区切り」は自分の中にある。
- あなたは思っている以上に強い。
10. 新しい章を生きるあなたへ
離婚は人生の「終わり」ではなく、「再生の始まり」。
焦らず、自分のペースで、少しずつ前へ進みましょう。
どんな小さな一歩も、確実に未来を変えていきます。
最後にー
あなたの物語は、ここからまた美しく続いていきます。
離婚を経験するということは、同時に「自分を見つめ直す」ということ。
痛みの中にも、新しい可能性が静かに芽生えています。
焦らず、比べず、少しずつ日常を取り戻していく過程そのものが、回復の証です。
今日、あなたが深呼吸をひとつできたなら、それで十分。
明日、少し笑えたなら、それはもう希望の兆しです。
離婚は終わりではなく、“自分の人生をもう一度はじめる日”。
どんな形であれ、あなたがあなたらしく幸せを感じられる未来が、きっと待っています。
—— Humming 編集部より
“Your new chapter starts here.”
参考記事:https://psyche.co/guides/how-to-survive-and-thrive-through-divorce-to-a-new-life-chapter
セキララカードで本音トーク。Humming編集部が試してみた!

今回は“セキララカード”を使って、編集部メンバーが本音トークをしてみました。
セキララカードは、カードに書かれた質問に答えるだけで、自然と心の奥の気持ちが言葉になるコミュニケーションカード。
「本音を話すきっかけがほしい」
「いつもより深く話してみたい」
そんな時にぴったりのツールとして人気を集めています。
Humming編集部は、アメリカ・東京・福岡と、それぞれ離れた場所に暮らしているため、今回は、オンラインで使えるセキララカード for Friendsを使ってプレイしてみました。
離れていても、カード1枚で心の距離がぐっと近づく。そんな体験をお届けします。
セキララカードの詳細はこちら▼
https://shop.humming-earth.com/products/sekirara-couple
Q1. もしお金の問題がなかったら、どこに住みたい?
純:では、セキララカードを始めましょう!今回は職場の人や友達と使えるカードです。カテゴリーには「アイスブレイク」「価値観」「恋愛感」「セックス」がありますが、どれから始めましょうか?
舞麻:価値観がいいです!どうしよう、チームみんなの価値観が違ったら……(笑)
純:では1問目。「お金の問題がなかったら、どこに住みたい?」
美樹:私が理想とするライフスタイルは、たくさんの本に囲まれて、気持ちのいい椅子に座って、サンルームみたいなところで過ごすこと。海が見えたら最高です。年間を通して気候が大きくぶれないところであれば、場所にこだわりはありません。
純:日本以外でも大丈夫?海外だと言葉の壁もありそうですが。
美樹:言葉の壁は、怖くないと言えば嘘になります。でも、今の時代は翻訳アプリもあるし、どうにでもなるのかなと。だから日本以外でもOKです。
沙織:私はお金の心配がなければ、低層階マンションの一番上の部屋に住みたいです。自分の好きなものだけに囲まれて暮らしてみたい!
純:おぉ〜豪華。都会が良いですか?
沙織:うーん、東京が良いです。
純:私はその真逆です。山の中にある大きな別荘でひっそり暮らしたい。犬や猫も好きだから、旦那さんと動物たちに囲まれて、静かに暮らしたいな。舞麻さんは?
舞麻:私は1年を3ヶ月ずつに4分割して、カリフォルニア、ヨーロッパ、日本、ハワイなどのあたたかい場所……みたいな生活がしたいです。その土地に飽きる前に次の場所に行ける、みたいな。どれだけ移動していたいんだろう(笑)。自分を成長させてくれる刺激を求めているのかもしれません。
でも、今は子どもたちの学校があるので、移動しながらの暮らしは難しい。同じ場所で毎日同じことを繰り返す今の生活は、自分にとっては試練であり、成長の場だと感じています。
Q2. 学校で教えてほしかったことは?
舞麻:歴史の楽しさ!学生時代に日本史も世界史も学んだけれど、当時はその面白さがよくわかりませんでした。
大人になってから本を読むようになり、歴史がぐっと身近に感じられるようになりました。
もっと早く歴史の面白さに気がつきたかったです。
純:すごくわかります。学生時代の歴史の授業は、当時の自分には少し難しく、なかなか楽しめませんでした。学生時代は今よりも自由な時間があったので、もっと歴史の本を読めばよかったと感じています。
あとは「お金について」ももっと学びたかったです。クレジットカードの使い方や、借金の仕組みなど、基本的なことを知る機会がないまま大人になってしまいました。
20代の最初は、クレジットカードを使いすぎて借金だらけになった時期も……。親に叱られて、アルバイトを掛け持ちして返済しました。
もし高校や大学でお金のことを学んでいたら、もう少し上手にお金を使えていたかもしれません。お金の教育は本当に大事だと思います。
沙織:私もお金や税金のことを学生時代に学びたかったです。フリーランスになって、自分で確定申告をするようになった時に、「全然わかんない!」と泣きたくなりました。
美樹:私は「自分との約束を守ること」が、どれだけ自分自身を大切にし、ひいては他者を大切にすることにつながるのかを体系的に学びたかったです。というのも、大人になってから、自分との約束を守れなかったことで、痛い思いをした経験がたくさんあるので。
部活に打ち込んでいた人は、目標をやり遂げる達成感を通して自分との約束を守る力を身につけているのかもしれません。でも、部活をやってこなかった人とかは、自分との約束を守る大切さを感じる機会が少ないのかなと。
純:深い!!
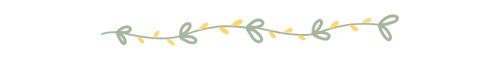
Q3. 子どもの頃の夢は実現しましたか?
舞麻:私はファッションスタイリストかヘアスタイリストになりたいと思っていました。でも叶ってないです(笑)。
今でもおしゃれは好きですが、人のためではなく、自分のために綺麗でいられたら、それで満足!
沙織:私は幼い頃から幼稚園の先生に憧れていましたが、結果的に先生にはなりませんでした。でも、大学では教育学を学び、社会人になってから保育士免許も取りました。今は子育てもできているので、ある意味、幼児教育には関われているのかなと。
美樹:小学生の頃の夢はイラストレーターになることでした。当時はオリジナルキャラクターを作って、クラス新聞を作っていました。今はブランドディレクターをしていますが、過去にはアートディレクションや編集の仕事もしてきたので、夢は叶っているのかもしれません。
舞麻:おー!夢が叶ってる人がいた!
純:子どもの頃の夢は、大人になるにつれて変わることもあります。だから、夢が叶っている人は少ないかもしれません。
私は子どもの頃、「これになりたい」という夢がなかなか定まらなくて、よく変わっていました。中学生の頃の夢は、声優でした。
舞麻:似合うよ!今からでも挑戦したら?!
純:中学生の頃、日本に住んでいた時に、声優学校に1年程通いました。声優にはならなかったけれど、その経験はすごく楽しかった。アメリカ育ちで日本に住んでいた期間もインターナショナルスクールに通っていたので、純日本人の同い年の子たちと話すことが新鮮で。あとは、発声がすごく良くなりました。
Q4. 恋愛において「重い」とは?
舞麻:次は「恋愛感」をやってみない?
純:そうしましょう!では次の質問は「恋愛において重いとは?」
舞麻:重いのは無理!
一同:爆笑www
舞麻:日常の行動が自立していない人は無理です。落ち込んでいる時に精神的な支えになることはできるけれど、基本的に自分のことは自分でできる人がいい。
その点、夫は料理も洗濯も全部自分でできるので助かっています。
あとは、嫉妬も苦手。私は私、あなたはあなた。お互いにちゃんと境界線を持っていたいです。
沙織:私も同じです。「私を幸せにして」みたいな人は重いですね。それぞれが自分の人生を楽しんでいて、その上で一緒にいられるのが理想。35歳を過ぎてから「自分を幸せにできるのは自分だけ」だと痛感しています。
純:うんうん、同感!
美樹:重い人って、“テイカー”ですよね。相手から奪おうとしたり、コントロールしたい気持ちが強い人。
でも、私自身も、まだ重いシーンはたくさんあるなと感じます。
たとえば、パートナーに「もう寝る時間だから寝ようよ」と自分の軸で決めてしまうことって誰にでもありえることだと思うので。
純:私は、自己嫌悪や被害者意識が強い人を重いと感じてしまいます。
苦しいことがあっても、自分で立ち上がる力がある人がいい。「慰めて〜」というタイプの人は、少し苦手です。というのも、私、慰めるのがすごく下手なんです。もちろん話は聞くけれど、最終的には自分の力で立ち上がってほしいですね。
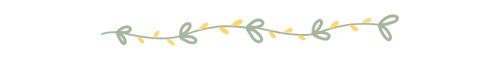
Q5. 両親の関係性は、自分の恋愛観にどう影響している?
純:私の両親は性格が正反対で、喧嘩が多い家庭でした。子どもながらに、2人の間にあまり愛を感じられなかったこともあり、恋愛や結婚にはとても慎重になりました。「この人だ!」と100%思えなければ結婚しないし、その人との子どもも欲しくない。だから、41歳になった今も結婚していません。
舞麻:両親の関係性は自分の恋愛観に影響するよね。
沙織:うちの両親も若い頃は喧嘩が多く、小さい頃は夫婦喧嘩が怖くて兄弟で押入れに隠れていたこともあります。
父は仕事一筋で、子育てはほとんど母が担っていたので、母はきっと大変だったと思います。
でも、父が50歳を過ぎて大病をしてから、夫婦の絆が深まったんです。今では2人で仲良く旅行や食事を楽しんでいます。
そんな姿を見ていると、若い頃は色々あっても、歳を重ねればうまくいくこともあるんだと思えるようになりました。
美樹:私の母は陶器を使ったアーティスト、父は建築士で、それぞれが自分の世界観を大切にしていました。いい感じにお互いに興味がないけれど、仲は良い、みたいな。
ただ、相手が本当に求めている優しさを察するのはお互いに苦手だったようで、求めていない優しさをお互いに降り注いで喧嘩をしていました(笑)。
そんな両親をみて、相手が欲しい優しさをどう汲み取るかが大切なことを学びました。
純:では最後に、舞麻さん!
舞麻:私の両親は、とても仲が良くて、いつもイチャイチャしていました。一方で喧嘩も多く、私が20歳のときに離婚しました。
親の離婚を経験してからは、「あんなに愛し合っていた両親でも離婚するのだから、私は結婚しなくてもいいや」と思うようになりました。
でも、夫と付き合っていたとき、日本に来るたびに入国審査で止められるようになって。
2時間拘束された翌日に入籍しました(笑)。
結婚のきっかけは入国審査でしたが、結婚の決め手は「恋心が落ち着いたあとでも、夫となら一緒にいたい」と思えたからです。
今振り返ると、宇宙の流れに逆らわず、夫と結婚して良かったです。
心を開くきっかけをくれるセキララカード
純:今日は赤裸々に語ってもらって、みんなのことをさらに知れた気がします。
舞麻:楽しかった!
美樹:またやりましょう、これ!
沙織:ミーティングの前とかに短時間でやっても良さそう!
純:セキララカードはただの質問カードではなく、心を開くきっかけをくれるツールですね。読者の皆さんも、ぜひ試してみてください。
Humming公式セレクトECショップはこちら▼
https://shop.humming-earth.com/
「骨密度」は40代から大きくダウン。症状ナシの「骨危機」を防ぐ、医師に聞く「体幹×骨」を鍛える「ゆる筋トレ&食事術」 【整形外科 かおるこHappyクリニックの伊藤薫子院長インタビュー】

「なんだか最近、疲れやすくなった」「昔より体力が落ちた気がする」—40代を迎え、そんな小さな変化を感じていませんか?それは、閉経前後の女性ホルモンの変化に、体が一生懸命対応しようとしているサインかもしれません。
この時期の女性の体は、骨の健康において静かなターニングポイントを迎えています。でも、これは未来のあなたをもっと輝かせるための準備期間でもあります。今回は、ご自身の経験から「骨活」の大切さを知った整形外科医の伊藤薫子先生に、忙しい毎日でも無理なく続けられる、骨の健康によい習慣を伺いました。
この骨活が、実はシワやたるみといった美容のお悩みにもつながっているという意外な真実も。この機会に、未来の自分を支える土台を一緒に整えていきましょう!
「骨活」提唱のきっかけと実体験
ーー 伊藤先生が骨活を提唱されるようになったきっかけは何だったのでしょうか?
私自身、元々は整形外科医として手術をやりたくてこの道に進みました。正直、骨粗しょう症は内科の範疇かなと思っていた時期もあります。
しかし、私が40歳の時、スキーで、すねの骨折をしてしまい、緊急手術を受けた際、先輩の先生から「ああ、もう骨粗しょう症でね、骨がつかないかもしれないね」と言われたんです。半分冗談だったと思いますが、40歳でそんなことを言われたら「え?」ってなりますよね。
それまで骨が折れやすいとか、骨がつかないということを全く意識していなかったのですが、この経験から「やはり骨は大事なんだ」と痛感しました。
特に女性は、閉経後3年から5年ほどの間に女性ホルモンの変化で骨密度が下がるという事実があります。症状は全くないのですが、この段階で予防をすれば、骨密度の低下を緩やかにすることができるのです。
これまでは、骨折をしてから病院で治療し、次の骨折を防ぐための対策を始めるという段階でしたが、今はもっと事前にその危険が分かります。だからこそ、皆さんにその情報を伝え、骨活についてしっかりお話させていただいています。
ーー 骨密度が下がっても症状がないというのは怖いですね。実際に、私たちはどのようなサインに気をつければ良いのでしょうか?
サインは残念ながらないですね。だからこそ、どんな方法でも構いませんので、骨密度を測ってもらって数値化することが一番大切なんです。
“骨密度検査は義務項目ではなく、自分で情報を得て受けに行く必要があるため、特に閉経前や40歳になったら一度は検査を受けてほしいと勧めている。”
ーー 骨密度の検査は、具体的にどうすれば受けられますか?
本来であれば、人間ドックや会社の特定健診、あるいは自治体の検診でも測れることがあるのですが、骨密度検査は義務的な項目に含まれていないことが多いです。
人間ドックでもオプションだったり、自治体によっては40歳から5年おきなどに測れるところが多いですが、自分で情報を取りに行かないと受けられないのが現状です。
内科、婦人内科、婦人科、整形外科など、どんなクリニックでも測れますし、自治体の検診でも可能です。とにかく、閉経前、40歳になったら一度は測っていただきたいと思っています。
ーー 自治体によっては5年ごとというところもあるようですが、先生としてはどれくらいの頻度で測るのが理想でしょうか?
日本人の閉経の平均は45歳から54歳です。まず、40歳になったら節目として一度検査をしていただきたいです。
その後は、やはり閉経後5年までは、できれば毎年、1年に1回は測っていただくと良いと思います。
骨と女性ホルモンの関係
ーー 骨密度が下がる時に症状はないとのことでしたが、日常の疲労感などは骨密度低下と関連がありますか?
疲労感や、手の関節の痛み、膝の痛みといった症状を、骨密度低下のサインではないか、とよく聞かれます。
しかし、これらの症状はどちらかというと、女性ホルモンが減ってきて不安定になっているサインなんです。つまり、女性ホルモンの変動があって少なくなっているということは、骨のバランスも悪くなっているというサインとイコールなんですね。

ーー 更年期の症状と骨密度の低下は連動しているということですね。
はい。更年期の症状というと、ホットフラッシュや気分の落ち込み、不眠などが知られていますが、実は300個ぐらい症状があると言われています。肩こりや腰痛の悪化、手の指のこわばりや痛み、五十肩、変形性膝関節症なども含まれます。
病院に行くほどではないけれど「つらいな」と感じる不定愁訴のほとんどが、女性ホルモンの変動に関係しています。
昔は平均寿命が50歳だったので、50歳で女性ホルモンが少なくなり寿命を迎える時代でしたが、今は50代以降も50年近く生きていきます。その「あと50年をどうやって元気に女性らしく生きるか」ということが、女性にとって最大の課題だと考えています。
筋トレと骨の健康
ーー 50代以降を元気に生きるために、私の周りでも40代の女性が筋トレを始める人が増えています。筋トレは骨の健康にも良い効果があるのでしょうか?
はい。骨が土台にあって、プラス筋肉。骨だけが強くても転んで骨折しますし、筋肉だけでも骨はカバーできません。
骨が弱くなるのが骨粗しょう症、筋肉が弱くなるのはサルコペニアと言われています。これらを防ぐことは、医療業界でも非常に重要視されていますので、筋力はつけてもらいたいです。
“女性ホルモンの減少期には筋力低下や代謝悪化が起こりやすく、無理な筋トレは関節や骨を痛める原因になるため、40代以降はストレッチやピラティスなど無理のない運動が勧められる。”
ーー 筋トレをする上で注意点はありますか?
女性ホルモンが少なくなると、筋力も低下しますし、代謝が悪くなるので太りやすくもなります。筋肉をつけることは良いことですが、間違った方法で無理をしてやると、かえって痛めてしまうことが多いんです。
女性ホルモンは関節をスムーズにする働きもあるため、急激に少なくなる時期に、今まで通り、あるいはさらに負荷をかけて筋トレをすると、痛みが出やすいんですね。
ですから、急に頑張るのではなく、状況を見ながら負荷をかけすぎずにやること、例えばストレッチやピラティスなどがお勧めです。急にバーベルを上げたりするような激しい筋トレは、骨折のリスクもありますので、特に40代からは注意が必要です
ーー 先生ご自身も骨折後に体幹の衰えを感じられたそうですね。
はい。骨折が治った後、駅の階段がうまく降りられなかったんです。骨も関節も悪くないのに、なぜだろうと思ったら、体幹のインナーマッスルが落ちていたんです。
背骨を支えるインナーマッスル(横隔膜、腹横筋、多裂筋、骨盤底筋)がしっかりしていないと、上手に歩けないし、重力に勝てないことが自分の実感としてよく分かりました。
骨活プログラムのエクササイズでは、ガチガチになった体を急に動かすのではなく、まず緩めてあげることを重視しています。特に現代の生活スタイルでは、スマホやパソコンで体が凝り固まっているので、その状態で急に筋トレをすると痛めてしまうからです。
骨を強くするための効果的な運動と食事
ーー 骨を強くするための効果的な運動としては、どのようなものがありますか?
骨に直接刺激を与えるという意味で、一番簡単なのはやはりウォーキング、つまり歩くことだと思っています。かかとなどに刺激が伝わることで、骨を作る細胞である骨芽細胞が全身で活性化されるんです。

ーー ウォーキングのポイントはありますか?
ただ「歩きましょう」と言っても、皆さんの歩き方は様々で、ただ1万歩、2万歩と頑張って歩いても、かえって体を痛めてしまう方もいます。
大切なのは、短い時間で良いので正しい姿勢で歩くことです。
目安としては、週に2回から3回、15分から30分程度(4,000歩から8,000歩程度)で十分です。姿勢としては、みぞおちとおへそを伸ばし、お腹とお尻をキュッと締めて、頭は上から釣られている感じ、目線は前で歩くのが理想です。
疲れてきて姿勢が悪くなるくらいなら、5分でも10分でも、きちんと意識して歩く方が効果的です。この歩き方なら、かかとに刺激があるだけでなく、体幹も意識するので、尿漏れ対策(膣トレ)にもなり、一石三鳥くらいの効果が期待できます。
ーー 忙しい方でも「ながら」でできる運動はありますか?
はい、かかとの上げ下ろしです。地味で高齢者がやるイメージがあるかもしれませんが、とても効果的です。
私がお勧めしているのは、トイレに行ったついでにやることです。洗面台などに手を添えて、真上に上がって、トンと降りるのを1回とします。これを10回を5セット、1日合計50回行います。トイレに5回ほど行けば達成できる回数です。
この時もウォーキングと同じで、体幹を意識し、前のめりにならずに真上に上がることを意識してください。マンションなどで音が気になる方もいるかもしれませんが、歩くのと同じくらいの体重のかけ方でトンと刺激を与えるだけで大丈夫です。
ーー 毎日の食事で意識した方が良い栄養素や食材はありますか?
骨イコールカルシウムというイメージが定着していますが、実は日本人は3食召し上がっていれば、一応1日の必要量(一般は600mg、骨粗鬆症予備軍は800mg)に近いカルシウムは摂れています。
ただし、カルシウムは腸からの吸収率が3割程度と低いんです。
そこで重要なのが、カルシウムの吸収率を上げるためのビタミンDと、骨の材料となるタンパク質です。
ビタミンD:日本人の女性の8〜9割が不足していると言われています。カルシウムの吸収を良くするだけでなく、認知症予防や免疫力アップにも注目されています。
-
- 食材:鮭、サバ缶などの青魚、きのこ類
- 対策:食事から摂るのが難しい場合は、サプリメントを利用したり、ビタミンD入りの卵などの食品を選ぶのも良いでしょう。
タンパク質:骨の材料です。一日に手のひら分くらいのタンパク質を摂ることをお勧めします。肉、魚、卵など何でも良いですが、特に40代以降の女性は吸収しづらいので、積極的に摂りましょう。
ーー 食事の工夫としてはどのようなものがありますか?
カルシウムと何かを一緒に組み合わせて摂ることが大事です。
具だくさんのお味噌汁:
-
- 煮干しをだしにしてそのまま具として食べる(カルシウムが摂れます)。
- 木綿豆腐などの大豆製品(タンパク質、骨密度アップに良いとされるエクオールの材料)を入れる。
- カブの葉や大根の葉など(カルシウムが摂れます)。
骨ブロススープ(ボーンブロススープ):
-
- 鶏手羽先などに塩と水、玉ねぎ、人参などを入れてひたすら煮込んだスープです。タンパク質や骨からの栄養が摂れます。
- 冷凍して作り置きしランチなどに食べるのも簡単で良いですよ。
柑橘類との組み合わせ:
-
- クエン酸やレモン、カボスなどの酸味を一緒に摂ると、カルシウムの吸収率が上がります。例えば、お味噌汁にカボスを一切れ入れたり、小魚を食べるときにレモンをかけたりするのがおすすめです。
骨密度低下のメカニズムと予防策
ーー 閉経前後で骨密度が下がりやすいのは、女性ホルモンが急激に下がってくるからということですが、改めてホルモンと骨の関係を教えていただけますか?
女性ホルモンは、骨を壊す細胞(破骨細胞)と骨を作る細胞(骨芽細胞)のバランスを保っています。閉経後、女性ホルモン(エストロゲン)が約10分の1ぐらいにまで減ってしまうと、このバランスが崩れ、骨を壊す細胞ばかりが働き、作る細胞が間に合わなくなってしまうんです。
その結果、骨密度が下がります。
また、「閉経後3年から5年」で骨密度が下がりやすいと言われるのは、全身の骨が全て入れ替わるのに3年から5年かかると言われているからです。ホルモンが減った状態で骨の入れ替えが進むと、気付いた時には骨密度が下がっている、というイメージですね。
“閉経後にエストロゲンが急減すると、骨を壊す細胞が優位になり骨密度が低下しやすく、特に閉経後3〜5年は骨の入れ替え周期により急激に減少しやすい時期とされている。”
日常生活での「骨活」と美容への影響
ーー 忙しい40代の女性が、日常生活で「これは実践できる」という骨活、運動、食事面での工夫を改めて教えていただけますか?
伊藤先生:
- ウォーキング:15分から30分を週に2〜3回。正しい姿勢を意識し、お腹とお尻を締めて歩く。
- かかと落とし:トイレに行ったついでに10回。洗面台などに手を添え、真上に上がってトンと降りる。
- 食事の工夫:カルシウム、ビタミンD、タンパク質を意識して摂り、特にカルシウムの吸収率を上げる食べ方(酸味と合わせるなど)を工夫する。
- 日光浴:1日15分程度の紫外線を浴びることで、必要なビタミンDの約8割を作ることができます。日傘をさしていても、手のひらなど日焼け止めを塗らない部分だけでも太陽に当てましょう。
- 体のケア:デスクワークの合間に、鎖骨の下や肋骨の間をほぐしてあげたり、深い呼吸を意識して行ったりすることで、凝り固まった体を緩め、インナーマッスルを使いやすくします。

ーー 日に当たるのも骨に良いのですね。
はい。ビタミンDを作るためには、食事以外に皮膚から紫外線(日光浴)で合成する必要があるんです。ただし、シミやシワ、がんなどのリスクもあるので、顔などは日焼け止めを塗って守ってくださいね。
ーー 骨活は美容にも関係するのでしょうか?
伊藤先生: はい、実は深く関係しています。骨密度が下がると、頭蓋骨も骨なので萎縮して(縮んで)きます。そうすると、その上に乗っている筋肉や皮膚がたるんできて、シワやたるみの原因になることが分かっているんです。
骨が元気でなくなると、目の周りのしわや輪っかが大きくなって目がくぼんできたり、顎が小さくなってたるみができたりと、美容面での影響も大きいんです。
ーー 体の健康だけでなく、美容にも繋がるというのは非常に興味深いです。
伊藤先生: ええ。骨が元気になれば、全体的に元気に綺麗になるということなんです。女性がいくつになっても背筋を伸ばして綺麗で元気でいるために、骨活は欠かせないと思っています。
“骨粗しょう症で最も危険なのは背骨や大腿骨の骨折で、命に関わる合併症を招く恐れがあるため、症状がなくても骨密度検査や日常的な「骨活」で早めの予防が重要とされている。”
骨粗しょう症の怖い現実
ーー 最後に、骨活がどれほど大切かお聞かせください。
骨粗しょう症になって一番怖いのは、背骨の圧迫骨折と、足の大腿骨の骨折です。
特に大腿骨の骨折は、高齢者の場合、骨折後1年以内に10%の方が亡くなるという現実があります。手術をしても、肺炎や尿路感染などの合併症で命に関わるケースが少なくないんです。
また、背骨の圧迫骨折は、骨が潰れてそのまま固まってしまうことで、背骨が曲がり、姿勢が悪くなってしまいます。姿勢が悪いだけではなく、飲み込みが悪くなって逆流性食道炎や誤嚥性肺炎を起こしたりする原因にもなります。
「いつのまにか骨折」といって、痛みを感じないまま背骨が潰れ、身長が2〜4センチも低くなることもあります。
症状がないからこそ、皆さんに関心を持ってもらうのは難しいのですが、骨密度を測ること、そして日常のちょっとした意識でできる「骨活」は、将来の生活や命に関わる大切な予防策なんです。
ーー 貴重なお話をありがとうございました。症状がない中で対策するのは難しいと思っていましたが、ウォーキングやかかと落としなど、今日から取り入れられる具体的なアイデアをたくさん伺えました。
無理せず続けられることが大事です。骨だけでなく、女性の体に必要な必須要素なので、続けていれば元気に綺麗になれると思いますよ。

プロフィール:
伊藤薫子
かおるこHappyクリニック院長
⽇本整形外科学会専⾨医
⽇本整形外科学会認定脊椎脊髄病医
2002年東京女子医科大学卒業、同年慶應義塾大学整形外科入局。関連病院勤務を経てアメリカ Cleveland Clinic留学。帰国後、慶應義塾大学病院骨粗しょう症外来担当。2021年7月「いくつになっても背筋を伸ばしてハイヒール」をモットーに「女性のための整形外科 かおるこHappyクリニック」を帝国ホテル東京にて開業。骨粗しょう症の予防として『骨活プログラム』を主宰。全国、海外からも骨密度検査や予防、治療に通院されている患者さんが多数。
HP: https://kaoruko-happyclinic.com/
インスタグラム:https://www.instagram.com/kaorukohappyclinic/
Dr.クロワッサン 一生歩くための骨活。 (MAGAZINE HOUSE MOOK) ムック – 2024/10/7
【ハミングが届けるポジティブニュース】 アマゾンの森から届いたうれしいニュース──火災被害が65%減少

ジョシュア・スティーブンス撮影、NASA地球観測衛星が捉えた2019年のアマゾン山火事
「地球の肺」とも呼ばれるアマゾン熱帯雨林。2019年には世界中のメディアが「燃えるアマゾン」と大きく報じ、その光景に胸を痛めた人も多いでしょう。干ばつや人為的な理由で広がった火災は、森林破壊だけでなく生態系や地球全体の気候にも深刻な影響を与えるとされてきました。
そんなアマゾンから、この9月、希望を感じさせるニュースが届きました。
2025年、アマゾンで火災により失われた森林面積は前年より65%減少し、観測が始まって以来の最小を記録したのです。
昨年の干ばつから一転、今年は雨と人々の努力が守った森
2024年には、アマゾン流域で記録的な干ばつが発生し、数十万エーカーの森林が焼失しました。乾いた大地と強風によって火災はさらに広がり、消火活動も追いつかない状況が続いたのです。
しかし2025年はこの状況が大きく変わりました。環境研究者フェリペ・マルテネクセン氏によれば、今年は「例年以上に強く、長く続いた雨季」が森林を守り、さらに「農民や住民が火の扱いにいっそう慎重になった」ことが火災の減少につながったといいます。
自然の恵みと人々の努力が重なった結果、アマゾンの森はかつてないほど火災から守られたのです。
衛星が捉えた「観測史上最小」の数字
火災の規模は、衛星モニタリングプロジェクト「MapBiomas」によって記録されています。このプログラムは、2019年の大規模火災をきっかけにスタートし、毎年の火災面積を追跡してきました。
そのMapBiomasの最新データによれば、2025年にアマゾンで焼失した森林面積は観測開始以来最も小さく、前年から65%も減少しました。さらにアマゾン流域にとどまらず、ブラジル全土でも火災による焼失面積は前年比54%の減少。ブラジル国内全体でも自然環境の回復が進んでいることがわかります。

COP30を前に「地球の肺」に注目が集まる
今年12月には、ブラジルのベレン市で国連気候変動会議「COP30」が開かれます。このタイミングも象徴的です。開催地はアマゾン流域の都市で、まさに世界中の視線が「地球の肺」に注がれます。
ブラジルのルーラ大統領は「2030年までにアマゾンの森林破壊を終わらせる」との公約を掲げています。今回の数字は、その実現に向けた希望のサインともいえるでしょう。
未来への希望をつなぐ
かつて「燃えるアマゾン」と呼ばれた光景は、世界に無力感を与えました。しかし2025年の成果は、そのイメージを大きく塗り替えます。
アマゾンの森はまだ生きており、守ることができる。人と自然が協力すれば、地球規模の課題にも希望を見いだせる。
このニュースは、そんな力強いメッセージを私たちに届けてくれています。
「内発的モチベーション」とは?

自分の中にある“本当のやる気”を見つける方法
秋になると、周りの自然が私たちに“内側へ目を向ける季節だよ”と語りかけてきます。
太陽は低くなり、光はやわらかく、夕暮れが早まる。
夏の喧騒が静まり、花々が土へと戻る。
自然界は「今は見せびらかす季節じゃない」と教えてくれているのです。
けれど多くの人にとって、秋は“がんばりの季節”でもあります。
新しい服を買い、目標を立て、仕事もプライベートも成果を出したくなる。
年末のイベントシーズンも重なり、心を静める余裕がなくなりがちです。
今年こそは、そんな外向きのエネルギーを少し手放してみませんか。
自然と同じように、自分の内側に意識を向けて、“自分らしい動機”を取り戻す季節にしてみましょう。
モチベーションには2種類ある
心理学では、やる気の源を大きく2つに分けています。
- 内発的モチベーション(Intrinsic Motivation)
自分の好奇心・楽しさ・意義や充実感から生まれる“内側の動機”。 - 外発的モチベーション(Extrinsic Motivation)
報酬・評価・責任・周囲の期待など、“外側の刺激”によって動かされる動機。
臨床心理士のアラティ・パテル氏はこう語ります。
「内発的モチベーションとは、私たちに自然にエネルギーを与えてくれるものです。」
一方で外発的モチベーションも悪いものではありません。
適度なプレッシャーは私たちを成長させる“追い風”にもなります。
しかし、それが“唯一の原動力”になってしまうと、燃え尽きや無力感に陥ることもあるのです。
あなたのやる気は「内側」から?「外側」から?
見分けるのは意外と難しいものです。
社会的な期待や周囲の目が強いと、自分の欲求と他人の期待が混ざってしまいます。
モチベーションコーチのオーラ・マルティネス氏はこう言います。
「クライアントに“何をしたいか”だけでなく、“なぜそれをしたいのか”を尋ねます。
その“なぜ”の部分に、内発的か外発的かの違いが現れます。」
もし答えが「誰かに認められたい」「期待に応えたい」なら、それは外発的動機。
一方で「やってみたい」「心がワクワクする」と感じるなら、それは内発的動機のサインです。
内発的モチベーションを見つける方法
1. 「エネルギーの棚卸し」をしてみる
1週間、自分の行動を記録し、どんな活動がエネルギーを与え、どんな活動が奪うのかを書き出します。
心が軽くなる行動が、あなたの“本当のやる気”を示してくれます。
2. 「恐れ」ではなく「拡がり」で選ぶ
決断をするとき、「怖いから」「嫌われたくないから」ではなく、
“自分の世界が広がるかどうか”を基準に考えましょう。
3. 「誰も見ていなかったら何をするか」を問う
もし誰も評価しないなら、あなたは何をしていたいですか?
その答えの中に、あなたの内発的動機が隠れています。
4. 体の感覚に耳を傾ける
他人の期待で動いているとき、肩がこわばったり、呼吸が浅くなったりします。
反対に、自分の心からの選択は、体が軽くリラックスしているはずです。
外発的モチベーションを手放すために
- “誰の期待なのか”を明確にする
父親?上司?SNSの向こう側にいる他人? それを知るだけで一歩前進です。 - 価値観チェックをする
その目標は自分の価値観に合っているか? 「なんとなく」ならもう一度見直して。 - 少しずつ距離を取る
一気に手放さなくてOK。週1日だけ定時で帰る、SNSを1日見ないなど、小さな変化から。
内発的モチベーションを育てる秘訣
それは自己への思いやり(セルフコンパッション)です。
他人の期待を手放すとき、罪悪感や不安が出てくるのは自然なこと。
キャリアを変えること、生活スタイルを変えること、
「間違っているのでは」と感じても、あなたの感情はあなたのものです。
内発的モチベーションに従うことは、“自分を信じる練習”でもあります。
秋は「手放す季節」
「自然が葉を落とすように、私たちももう必要のない動機を手放すことができます」
― オーラ・マルティネス
秋はリセットと再調整の季節。
ゆっくりと立ち止まり、今の自分に必要なもの・そうでないものを見つめ直す時間をつくりましょう。
やる気を他人の期待に委ねず、自分の“内なる羅針盤”に従うことで、
あなたの人生はもっと穏やかに、もっと自由に動き出します。
同僚は友達ではない12の理由

健全な距離感がキャリアを守り、心の余裕をつくる
「弊社はアットホームな職場です!」
求人広告や社内ミーティングで、こんな言葉を聞いたことはありませんか?
一見ポジティブに聞こえますが、実際にはそうでないことが多いのが現実です。
それは冷たい考えではなく、むしろ自分と相手のためになる大切な真実です。
この記事では、職場の人間関係でよくある誤解と、同僚との健全な距離の保ち方を解説します。
おすすめ記事 ▶ 親しい友人関係における「開かれた、思いやりのある衝突」のすすめ
なぜ「同僚は友達ではない」と言われるのか
ベテラン社会人が「同僚と仲良くなりすぎるな」と言うのは、過去に同じ失敗を経験しているからです。 過剰な信頼やプライベートの共有がトラブルを生むケースは少なくありません。
その忠告は、あなたを傷つけないための“予防線”。
他人の経験を教訓とすることは、キャリアを守る第一歩です。
同僚と「友達」でなくても大丈夫?
もちろんです。
フレンドリーであることと、友達になることは違います。
- フレンドリー=挨拶・雑談・協力・思いやり
- 友達=プライベートの共有・頻繁な連絡・深い感情的なつながり
職場では「良好な関係」を保ちながら、
一定の距離感をキープすることが信頼と評価を高めるカギです。

同僚が友達ではない12の理由
1. その関係は「便利さ」で成り立っている
同僚とのつながりは、近くにいるから成り立っているだけの“距離の近さ”によるもの。
転職すれば自然と消える関係です。
2. 共通点は「ネガティブ」なものかもしれない
不満・愚痴・上司への不信感など、負の感情でつながる関係は長続きしません。
3. 誰もが「自分の利益」を優先する
昇進・評価・成果。職場では誰もが自分の目標を追っています。
競争意識が友情を壊すことも。
4. 全員が善意で動くわけではない
あなたを利用して情報を得たり、自分の地位を守るために近づく人もいます。
5. 相手のことを本当は知らない
仕事中に見せるのは“仕事用の自分”。
本当の性格や価値観までは見えません。
6. 趣味・価値観が違う
仕事の目標は共有できても、プライベートで共通点がないことが多いです。
7. 職場は競争の場
昇格・ボーナス・評価…限られた枠をめぐる競争が友情を歪めることも。
8. 仕事外での優先順位が違う
家族・副業・趣味。人によって仕事後の時間の使い方は全く異なります。
9. 上下関係と権力構造がある
上司や部下と友達のように接すると、誤解やトラブルの原因になります。
10. ゴシップと社内政治が渦巻いている
ちょっとした発言や秘密が“噂話”として広がる危険性も。
11. 転職や異動で関係は簡単に終わる
一緒に働く環境がなくなれば、会話も減り、自然と疎遠になります。
12. 間違った関係があなたの評価を下げる
誰とつるむかで印象が変わります。
悪目立ちする人と一緒にいれば、あなたまで評価が下がる可能性も。
同僚と距離を置くメリット
- 客観的に判断できる:感情に流されず冷静な判断ができる
- トラブルが減る:ゴシップや人間関係の摩擦が少なくなる
- プライバシーが守られる:仕事と私生活をしっかり分けられる
- 集中力が高まる:本来の目標にエネルギーを注げる
- ワークライフバランスが整う:オンとオフを切り替えやすい
- 信頼されるプロになる:公平な姿勢が上司や同僚からの信頼につながる
職場でも本当の友情は生まれる?
もちろんゼロではありません。
お互いにリスペクトがあり、利害を超えて信頼し合える関係なら、
職場発の友情が続くこともあります。
ただし、環境が変われば関係も変わるという前提を忘れずに。
距離ができても、お互いを尊重できる関係が理想です。
まとめ:親しさよりも「信頼感」を育てよう
職場の人間関係は、仕事を円滑に進めるための“協力関係”がベース。
優しさや思いやりは大切ですが、過度な親しさはトラブルのもとになります。
「同僚=友達」ではなく、「同僚=チームメイト」という意識を持つことで、
あなたのキャリアも心の余裕も守られるはずです。
結婚前にしておきたい「お金の話」:将来のパートナーと向き合うための7つのステップ

お金の価値観は、結婚生活において大きな衝突の原因になることがあります。
それでも、多くのカップルは「ロマンチックじゃないから」と、結婚前にお金の話を避けてしまいがち。
でも実は、結婚前に正直なお金の会話をすることこそ、長く安定した関係を築くための第一歩です。
ここでは、ストレスやケンカを避けながら、パートナーと健全な金銭感覚を共有するためのポイントをご紹介します。
① お互いを責めない「オープンな会話の場」をつくる
お金の話はデリケート。借金や収入格差、貯金習慣の違いなど、話題によっては気まずくなることも。
だからこそ、安心して話せる雰囲気づくりが大切です。
- カジュアルなカフェや静かなレストランなど、リラックスできる場所を選ぶ
- 「理解するための会話」であって「責めるための会話」ではないと約束する
- 「チーム」として向き合う姿勢を持つ
② お金の価値観と育った環境をシェアする
人のお金の使い方は、幼少期の家庭環境に大きく影響されます。
まずは、お互いの「お金のバックグラウンド」を理解しましょう。
たとえば:
- 子どもの頃、家庭ではお金をどう扱っていた?
- 自分は“貯める派”それとも“使う派”?
- お金に関して一番ストレスを感じるのはどんなとき?
価値観の違いを知ることで、今後の金銭的トラブルを防ぐことができます。
③ 収入・借金・クレジットなど「すべてをオープンに」
結婚前に必ず話し合うべき項目:
- 収入源:給与、副業、投資など
- 借金:奨学金、カードローン、車のローンなど
- クレジットスコア:信用履歴や借入可能額
お金の「隠しごと」は信頼を損なう原因になります。
もし一方に借金がある場合は、返済計画を共有し、結婚後の影響を明確にしておきましょう。

④ 口座管理をどうする?「共同・別・ハイブリッド」
結婚後の口座管理には3つのスタイルがあります。
-
共同口座
すべての収入と支出を共有。透明性が高い。 -
別口座
各自が自分のお金を管理。自由度が高い。 -
ハイブリッド
生活費は共同口座、その他は個人口座で管理。バランス型。
どの方法が正しいというわけではありません。お互いが心地よく感じるシステムを選ぶことが大切です。
⑤ ライフスタイルと支出の優先順位を合わせる
「何にお金を使いたいか」は人によって違います。
ファッションを重視する人もいれば、旅行や趣味を優先する人も。
話し合うポイント:
- 必要経費と贅沢の境界はどこ?
- 月々どれくらい貯金したい?
- 住宅・車・旅行など大きな買い物はどう計画する?
⑥ 緊急時と将来設計について話し合う
今日の暮らしだけでなく、未来のリスクにも備えておくことが安心のカギ。
- 緊急資金:いざという時にいくら必要?
- 退職後の資金:老後の貯蓄はどのくらいが理想?
- 生命保険・遺産の話:もしもの時、どんな備えをしておく?
⑦ 定期的な「マネーチェックのためのデート」を習慣に
お金の話は一度きりでは終わりません。
月1回または四半期ごとに「マネーについて話すデート時間」を設け、現状を共有しましょう。
- 支出と貯蓄の確認
- 来月・来年の目標設定
- 収入変化や新しい支出の共有
定期的な確認は、信頼関係と安心を保つための習慣です。
お金の話が苦手な人へ
お金の話を避けてしまうのは、恥ずかしさや不安、ケンカへの恐れから。でも、一歩踏み出すことで、相手をより深く理解できます。 少しずつ練習するうちに、お金の会話はきっと自然になっていきます。
最後に:愛とお金は切り離せない
結婚前にお金の話をするのは勇気がいります。
けれど、それは「信頼」と「チームワーク」を育てるための大切なプロセス。
オープンなマネーコミュニケーションが、ふたりの未来をより穏やかで豊かなものにしてくれるはずです。
経験を積んでも自信がつかないのはなぜ?

女性リーダーが「自信」を取り戻すためにできること
「もっと経験を積めば、自信が持てるようになる」
そう思っていませんか?
「昇進したら」「スキルを身につけたら」「資格を取ったら」
きっと自信がつくはず——そう信じて頑張ってきた人は多いでしょう。
けれど実際には、経験を重ねても、思うように自信が育たないことがあります。
むしろ、経験を積むほど「自分にはまだ足りない」と感じてしまうことさえあるのです。
おすすめ記事 ▶ 憂鬱からワクワクへ。働き方の変化は人生を変える
「経験=自信」ではない現実
筆者自身も、トレーニングを受け、昇進し、外から見れば順風満帆なキャリアを築いてきました。
それでも心の中には常に「私で大丈夫だろうか」という不安がありました。
同じように、筆者のコーチングやメンタリングに訪れる多くの人も、
豊富なスキルや実績を持ちながら、自信が持てないことに悩んでいます。
特に、女性や有色人種、マイノリティの人々にとって、
「自信がない」と感じることは、個人の問題ではなく構造的な問題でもあります。
職場の“自信格差”が生まれる理由
多くの研究が示すように、職場では依然としてジェンダーや人種による不平等が存在します。
たとえば:
-
男性には「特定のスキルにもっと自信を持て」と言われる一方で、
女性には「もっと自信を持ちなさい」と漠然とした助言が多い。 - 女性が積極的に意見を述べると「強すぎる」「でしゃばり」と見られてしまう。
- 昇進や評価が、「実力」ではなく「自信がありそうに見えるか」で決まることもある。
つまり、自信が求められる環境そのものが不公平なのです。

自信を持てないのは「あなたのせい」ではない
「もっと自信を持ちなさい」
「堂々としなさい」
そんな言葉を受け取るたび、私たちは「できない自分」を責めてしまいがちです。
でも、本当に変えるべきなのは“あなた”ではなく、“環境”の方です。
低賃金、不当な昇進格差、偏った評価制度。
こうした構造的な不平等が、私たちの自己肯定感や自信を奪っています。
自信がないのではなく、
自信を育てるための安心な土壌が与えられていないだけなのです。
自信を取り戻すための4つのステップ
① 自分の「見られ方」を知る
パフォーマンスレビューやフィードバックを通して、
他者の視点を知ることは有益です。
もしそれが理不尽な評価なら、それはあなたの問題ではなく、
職場の価値観とあなたの価値観が合っていないというサインかもしれません。
② 自分の限界と優先順位を理解する
どれだけ努力しても、構造的な問題は一人では変えられません。
「自信を持つために何を試したのか」「今どこまでエネルギーを使えるのか」
を整理し、自分を追い詰めない範囲で取り組みましょう。
③ 自分の実績を“見える化”する
自分が今まで成し遂げたことをリストアップしてみましょう。
達成したこと、もらった感謝の言葉、成功体験を記録することで、
落ち込んだときに「できている自分」を思い出す助けになります。
④ サポートネットワークを持つ
メンターやコーチ、応援してくれる仲間とのつながりが、
あなたの「支え」になります。
一人で自信をつけるのではなく、共に育てていくという意識を持ちましょう。
「なりきる」ことで自信を育てるという方法も
筆者自身、かつて「もっと自信を持て」と言われ続けてきました。
そのとき実践したのが、“自信に満ちた自分”を演じること。
たとえば、架空の人物「ジュリア」という自信満々なマネージャーを想定して、
会議中に「ジュリアならどうする?」と自問することで、
徐々に新しい行動や考え方が身についていきました。
やがて“演じていた自信”が“自分の中の自信”へと変わっていったのです。
本当の自信は「行動」と「つながり」から生まれる
自信は理論や本の中では育ちません。
行動し、挑戦し、失敗し、それでも立ち上がる——
その積み重ねが、やがて確かな自信になります。
そして、自信は一人で育てるものではなく、
共感し合える仲間との関係の中で育つもの。
完璧なリーダーではなく、
人として信頼されるリーダーであることを目指して。
あなたの中にすでにある“静かな自信”を、少しずつ育てていきましょう。
この記事をもとに執筆しました:
https://www.lenareinhard.com/articles/the-trouble-with-asking-women-to-be-more-confident-building-confidence-at-work
エシカルな婚約指輪ブランド6選

あなたの愛を“誰かの痛み”にしないために。
エシカルな婚約指輪を選ぶということ
婚約指輪を選ぶとき、私たちはつい「デザイン」や「価格」に目を向けがちです。
けれど、その輝きの裏側にある“もうひとつの物語”を知っていますか?
多くのジュエリーは、採掘や製造の過程で環境破壊や労働搾取といった問題を抱えています。
遠い国の誰かの犠牲の上に成り立つ美しさ――そう気づいたとき、
「本当に心から祝福できる選択とは何か」を考えたくなるのです。
エシカルな婚約指輪ブランドは、人にも地球にもやさしい方法で作られたジュエリーを届けています。
リサイクルゴールドや合成ダイヤ、
フェアトレード認証を受けた素材を使うなど、
その輝きは“純粋な愛”を象徴するにふさわしいもの。
これからの時代、「誰が、どんな想いでつくったか」までを選ぶことが、
愛のかたちをより美しくしてくれるのではないでしょうか。
1. Brilliant Earth(ブリリアント・アース)
https://www.brilliantearth.com/
おすすめポイント| コンフリクトフリー(紛争とは無縁の)宝石
特徴| コンフリクトフリーダイヤモンド、エシカルな宝石、合成ダイヤ、リサイクルメタル、フェアマインドゴールド、自分でデザインできるオーダーメイド対応
価格帯| 約$520〜$6,090以上
Brilliant Earth(ブリリアント・アース)は、エシカルジュエリーの先駆けとして知られるブランド。 “Beyond Conflict Free(紛争のない、さらにその先へ)”という理念のもと、業界基準を超えた透明性と倫理的調達を実現しています。
採掘・流通のすべてにおいて厳格なガイドラインを設け、環境に配慮しながら人権を尊重する生産体制を徹底。 天然ダイヤモンド、リサイクルゴールド、リサイクルダイヤモンドはすべて第三者機関による監査と認証を受けており、確かなトレーサビリティを保証しています。
「ダイヤモンドの出どころがわかること」に価値を感じる人にとって、
Brilliant Earthは安心して選べる信頼のブランドです。

2. Mejuri(メジュリ)
おすすめポイント| ジェンダーを問わず楽しめる手頃な価格のリング
特徴| エシカルに調達された合成ダイヤ、カーボンニュートラルの合成ダイヤモンド、リサイクルゴールド&シルバー
価格帯| 約$148〜$3,900
Mejuri(メジュリ)のファインジュエリーは、単なる「上質」以上の存在。
日常使いのアクセサリーだけでなく、すべてのジェンダーに向けた婚約指輪やペアリングも豊富にそろえています。
使用される天然石やダイヤモンドはすべてコンフリクトフリーで、使用するゴールドの約80%はリサイクル素材、残りの20%も責任ある調達先から認証を受けた金属です。
製造はカナダ、インド、イタリア、韓国など世界各地で行われ、職人たちは安全で公正な労働環境のもとで制作に携わっています。
また、Empowerment Fund(エンパワーメント基金)を通じて、女性やノンバイナリーの人々の支援活動にも貢献。
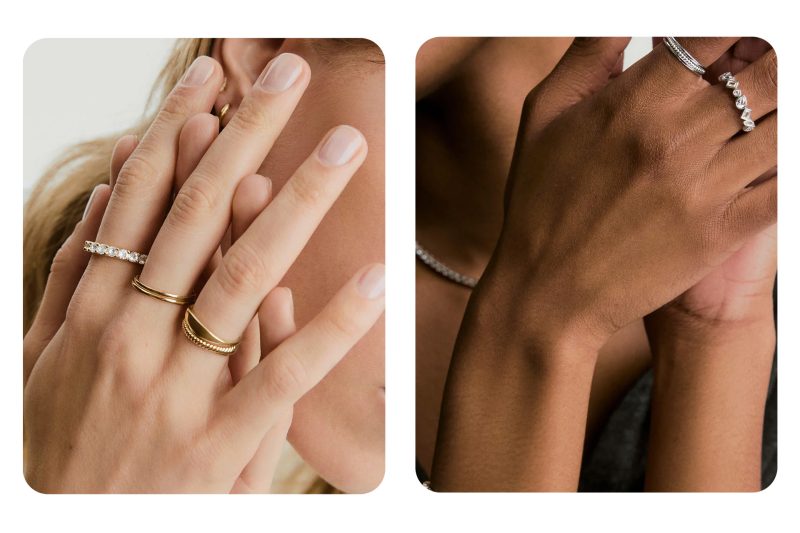
3. Blue Nile(ブルーナイル)
おすすめポイント| ダイヤモンドの生涯アップグレード制度&価格保証プログラム
特徴| 100%責任ある採掘によるコンフリクトフリーダイヤモンド、豊富な宝石オプション、自分でデザインできるリング
価格帯| 約$540〜$18,350以上(セッティング価格)
1999年創業の Blue Nile(ブルーナイル) は、オンライン販売で高品質なダイヤモンドを適正価格で提供したジュエリー業界のパイオニア。
透明性と顧客満足度を最優先に掲げ、販売ノルマのない専門スタッフが一人ひとりに丁寧に対応してくれます。
ニューヨーク本社の職人によってすべての婚約指輪やファインジュエリーがハンドクラフトされており、特別な瞬間を彩る理想のデザインを一緒に作り上げることができます。
Blue Nileで使用されるダイヤモンドは、100%コンフリクトフリーかつキンバリープロセスに完全準拠した倫理的な調達のみ。
さらに、GIA鑑定付きダイヤモンドの生涯アップグレード制度や価格保証(プライスマッチ)制度など、信頼できる購入サポートも充実。
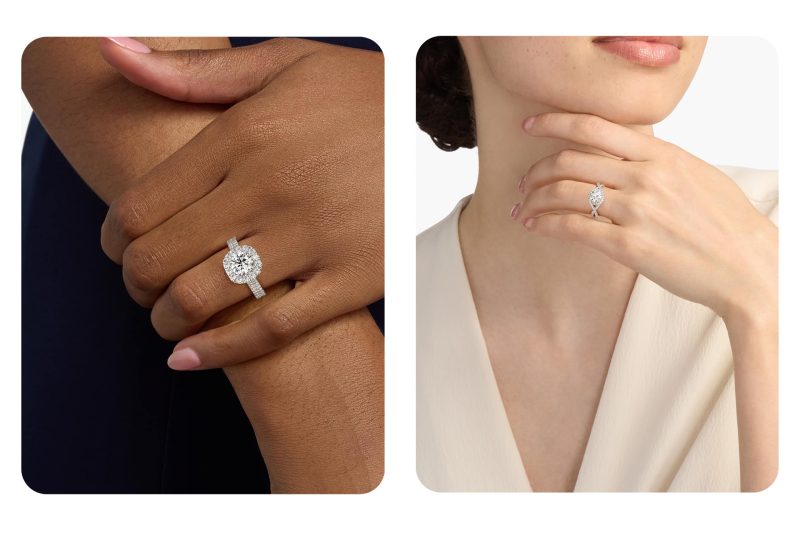
4. Bario Neal(バリオ・ニール)
おすすめポイント| カスタマイズ&クラスターリング(多石デザイン)
特徴| フェアマインドゴールド、トレーサブルな宝石、リクレイムドメタル(再利用金属)、リサイクルダイヤモンド、合成ダイヤ、パーソナライズ対応
価格帯| 約$70〜$11,430以上
フィラデルフィアとブルックリンを拠点とするBario Neal(バリオ・ニール)は、LGBTQ+の権利や結婚平等を長年サポートしてきた女性経営のエシカルジュエリーブランド。
ふたりの関係性をそのまま形にするようなオーダーメイドリングを得意としており、個性を反映させたデザインや、受け継いだジュエリーをリメイクして新たな形に生まれ変わらせることもできます。
素材には、フェアマインド認証のゴールドやトレーサブルな宝石、リサイクルメタル・ダイヤモンドなどを使用。すべて職人の手によって丁寧に仕上げられています。
特に、他では見られない美しいクラスターリング(多石リング)のセンスは圧巻。
「どんな指輪を選べばいいかわからない」という人にも寄り添いながら、
“自分たちらしい愛のかたち”をデザインしてくれるブランドです

5. Aurate(オーレイト)
おすすめポイント| アメリカ製のミニマルなウェディングバンド
特徴| エシカルに調達されたダイヤモンド、合成ダイヤ、リサイクルゴールド、オーダーメイドリング
価格帯| 約$2,400〜$4,500
Aurate(オーレイト)は、「高品質」「適正価格」「社会的責任」――この3つを同時に叶えることを使命に掲げるニューヨーク発のジュエリーブランドです。
同ブランドはキンバリープロセス(紛争ダイヤの排除基準)を超える透明性を実現しており、採掘からニューヨークの工房に届くまで、すべての天然ダイヤモンドを徹底的に追跡。
その出どころが倫理的かつ環境的に健全なものであることを保証しています。
また、希望に応じて合成ダイヤ(合成ダイヤ)を選ぶことも可能です。
すべてのリングには真正証明書(Certificate of Authenticity)が付属し、
売上の一部は教育支援団体「Mastery Charter」や女性リーダー支援団体「She Should Run」などへ寄付されています。
シンプルで洗練されたデザインの裏には、確かな倫理観と社会への想いが息づく。
Aurateは、スタイルと良心の両立を求める人にぴったりのブランドです。
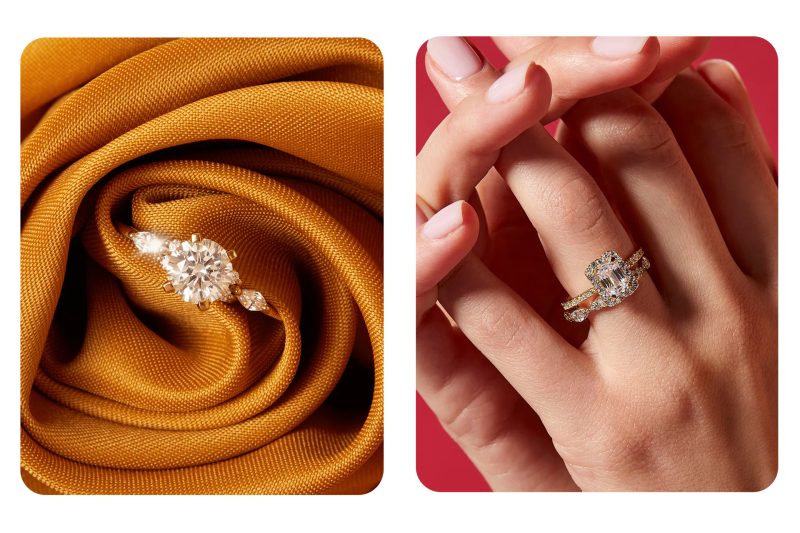
6. Catbird(キャットバード)
おすすめポイント| 多彩なデザイナーとスタイルのバリエーション
特徴| リサイクルゴールド、コンフリクトフリーの宝石、パーソナライズリング
価格帯| 約$230〜$13,800
Catbird(キャットバード)は、ニューヨーク・ブルックリンを拠点に18年以上続く人気ジュエリーブランド。
多くのアイテムはブルックリンの小さな工房でハンドメイドされており、素材にはリサイクルゴールドが使用され、すべての宝石がコンフリクトフリー(紛争のない調達)であることが保証されています。
Catbirdの婚約指輪コレクションには、自社のCatbird Weddingラインに加え、
Erstwhile(アーストワイル)、Gillian Conroy(ジリアン・コンロイ)、Kataoka(片岡義順)など、世界中の注目デザイナーによる作品が多数ラインナップ。
プリンセスや白鳥、フェアリーテイルをモチーフにしたデザインはどれも繊細で美しく、
まるで物語の主人公になったような気分にさせてくれます。
サステナブルで美しい愛の証を探している人にぴったりのブランドです。

本当に“美しい”指輪を選ぶということ
婚約指輪は、愛の象徴であると同時に、 “これからどんな価値観を大切に生きていくか”を映し出す選択でもあります。
誰かの笑顔や地球の未来を犠牲にしない――
そんな思いやりの循環から生まれるエシカルジュエリーは、
身につけるたびにやさしい誇りを感じさせてくれます。
ダイヤモンドの輝きだけでなく、その背景にあるストーリーまでを選ぶこと。
それこそが、これからの時代の“真のラグジュアリー”なのかもしれません。
あなたの愛のかたちが、世界にとってもやさしいものでありますように。
「頑張りすぎてしまうあなたへ」Hummingが届ける、癒しのセルフケアアイテムとは?!【編集部対談】
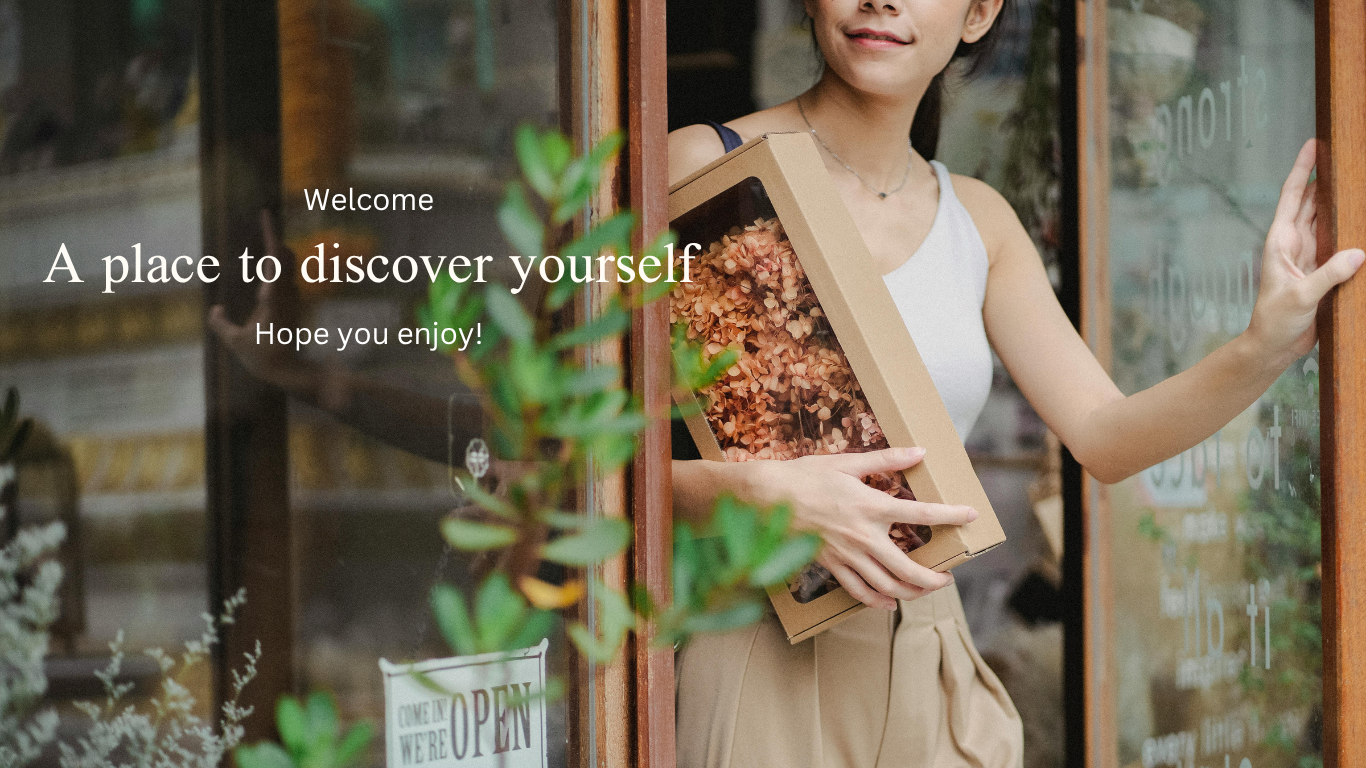
2025年10月13日、HummingのECサイトがOPEN!
コンセプトは「いつも誰かを気づかって、頑張りすぎてしまうあなたへ」。
自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりな、心と体を癒すアイテムを編集部が心を込めてセレクトしました。
今回は、Humming編集部メンバーが、ECサイト立ち上げの想いと、おすすめのアイテムについて語ります。
記事だけじゃ伝えきれない、“本当に良いもの”を形に
舞麻:WebマガジンHummingは「これをやって良かったから、みんなにも試してほしい!」という気持ちで記事を書いています。でも記事だけでは伝えきれないこともあって。
記事を読んで終わりではなく、実際に手に取って暮らしの中で感じてもらいたい。そんな思いから、ECサイトを立ち上げました。
ラインナップは、「これ本当にいい!」と感じて、愛用しているものばかりです。
沙織:Hummingで取り扱っているのは、具体的にはフェムケアソープとかアイマスクとか、セルフケアのアイテムですよね。
舞麻:そうそう。アイマスクは私にとって欠かせないアイテムです。「ナイトライトをつけて寝ると、目を閉じていても体がしっかり休まらない」と聞いてから、寝る時は光を遮断することを意識しています。就寝時はもちろん、飛行機に乗るときなどにアイマスクを使っています。
沙織:Hummingでは、2種類のアイマスクを取り扱っているんですよね。
舞麻:ひとつは持ち運びに便利なシルク素材。軽くて、肌触りが良くて気持ちがいい。目に当たる部分がくぼんでいるのでマツエクが潰れないのもポイントです。

Coming Soon!
もうひとつは重みのあるタイプ。装着すると目にちょうど良い圧がかかるので、リラックスできます。ベッドで横になって使うと深い休息がとれますよ。

沙織:私、最近、夜中に目が覚めて眠れなくて……。アイマスクしてみようかな。
舞麻:それ、更年期のはじまりのサインかもしれません。エストロゲンやプロゲステロンといった女性ホルモンのバランスが崩れると、自律神経が乱れて、夜中に目が覚めやすくなると言われています。
沙織:えーーー、更年期?!この1ヶ月くらいずっと眠れなくて……。
舞麻:30代後半から40代は、プレ更年期に入ってくる時期です。一度ホルモンの数値を調べてみても良いかもしれません。
あとは、ベッドに横になって目を閉じたまま、視線を右・左・右・左とワイパーみたいに動かすのも、眠れない時におすすめです。これは、アメリカの神経科学者アンドリュー・ヒューバーマンが紹介していた方法で、実際にやってみたら本当に良く眠れました!
沙織:今夜やってみます。でも……更年期のはじまりだと思うと、ちょっとショックです。Hummingは“38歳から読みたいWebマガジン”とうたっているので、読者の中には、これから迎える更年期に不安を感じている方や、すでに症状に悩んでいる方も多いかもしれませんね。
舞麻:そうですよね。HummingのECサイトでは、プレ更年期や更年期の悩みに寄り添えるアイテムを意識して選んでいます。
編集長おすすめはシルクの足首ウォーマー
舞麻:私のいちおし商品は「イオンドクターの足首ウォーマー」です。18年以上愛用しています。

シルク素材だから軽くて、着けるとすぐにポカポカと体が温まります。妊娠中にも使っていましたし、生理の時にも欠かせません。持ち運びにも便利なので、ホテルでの会議など、冷える場所では、こっそり着けることもあります。
日本の家は構造的に寒いと言われているので、足元の冷え対策にぴったりなアイテムです。
沙織:在宅ワークをしていると、冬場は本当に足元が冷えるので、私も足首ウォーマーを狙っています!
ちなみにHummingでは、ショートサイズのシルク足首ウォーマーを11,880円で販売予定です。
舞麻:とても良い商品だから、イオンドクターを試してほしいけれど、「ちょっと値段が……」という人は、他のレッグウォーマーでも全然良いです。大事なのは手首や足首を温めること。体の冷え方が全然違うから、本当におすすめです。
女性のリズムに寄り添って。生理とフェムケアに込めた想い
舞麻:Hummingのチームは全員女性です。既婚の人、未婚の人、離婚している人……、いろいろな立場のメンバーがいますが、みんな女性だからこそ、体調の変化や生理のことも自然に話せます。
この間、チームでフェムケアについて話し合う機会があった時に、私の“生理との向き合い方”をシェアしたんです。私は生理の1日目は必ず休むようにしていて、それが自分の体を大切にすることにつながると思っています。そうした考え方は商品の選定にも反映していますし、Webマガジンでも生理について積極的に発信しています。
沙織:先日、舞麻さんがLINEグループに9分くらいのボイスメモを送ってくれたんですよね。私はこれまで、生理で貧血がひどくても、子どもを公園に連れて行ったり、いつも通り家事や仕事をしたり、「生理=休む時期」とは考えたことがありませんでした。だから、「生理の1日目は無理せず休む」という舞麻さんの話が新鮮でした。今まで頑張りすぎていた自分を、少し褒めてあげたくなりました。
日本でも生理休暇のある会社は増えていますが、実際に利用している人はまだ少ないと思います。だからこそ、「生理の時は体を労わってあげるべき時期なんだよ」というメッセージをもっと日本の女性に伝えていきたい。それに合わせて、ECショップではフェムケアのアイテムも充実させていきたいですね。
舞麻:生理があるからこそ、子どもを産むことができる。だから、生理の期間は体を労わり、尊重する大切な時間だと伝えていきたいです。社会の認識が変われば、一人ひとりの行動もきっと変わっていくと思うので。
沙織:フェムケアも、ただ流行っているから取り入れるのではなく、生理を正しく理解したうえで、自分の体と向き合うきっかけになればいいですね。
生理の話は改めて紹介予定なのでお楽しみに。
小さな癒しを日常に。心と体を整えるお茶と香りのアイテムたち
舞麻:私は「生理から生理まで」をひとつのサイクルとして、体や心の調子を見るようにしています。ホルモンの変化でイライラしたり、眠くなったり、気分が上下するのは自然なこと。気持ちが揺らぐ時こそ、自分をいたわる時間をつくってほしいですね。
HummingのECショップで扱っているお茶は、リラックスしたい時にぴったりのアイテムです。
沙織:先日、ティートを飲んでみたのですが、茶葉ごと味わえるからゴミも出ないし、満足感があって気に入っています。

舞麻:ティートは、本来なら捨てられてしまうフルーツを使って作られているんですよね。フードロスの削減にもつながっています。
沙織:Hummingでは他にもヨモギ茶を扱っていますよね。

舞麻:よもぎもすごく大事!
沙織:お茶以外だと、エッセンシャルオイルやシャワースチーマーなど、香り系のアイテムも取り揃えています。

舞麻:エッセンシャルオイルは、毎日のように使っています。ニキビにはティーツリー、咳にはユーカリ、蚊に刺されたらペパーミント。夜はラベンダーオイルで子どもをマッサージしてあげることもあります。香りのリラックス効果は本当に大きいですね。もっと深く学んでみたいと思うくらい、日々助けられています。
沙織:私もエッセンシャルオイルにはすごく興味があります。でも、普段はディフューザーに垂らして使うくらいで、他の使い方をあまり知らなくて。
舞麻:たとえば、ラベンダーなら、ホホバオイルやココナッツオイルに混ぜて使います。ユーカリは、旅行中に咳が出た時にトイレットペーパーに少し垂らして枕元に置いたり。かなりズボラな使い方ですが、効果は抜群です。推奨はされないかもしれませんが、ティーツリーはニキビに直接ちょんちょんと塗ってしまうこともあります。
朝、子どもたちがなかなか起きてこない時は、オレンジやレモン、グレープフルーツなどのシトラスの香りをディフューザーに入れて。ベルガモットを少し足して、香りをアレンジすることもあります。
沙織:そんなに自由に使えるんですね。エッセンシャルオイルの活用方法を知らない人は結構多いような気がします。舞麻さんの使い方、ぜひHummingでもシェアしていきたいです!
舞麻:自由でいいんです。ダメな使い方なんて基本ないと思う。うちはトイレットペーパーに直接ちょんちょんですから(笑)。
西洋×東洋のいいとこ取り。セルフケアを日常に
沙織:あともう一つ使い方を聞きたいのが、今Hummingで取り扱うか迷っているキャスターオイル。お試しで使ってみたのですが、ねっとりしていて、ボディマッサージしようと思ったら難しくて……。

Coming Soon!
舞麻:キャスターオイルは、手のひらに出して伸ばしてから、お腹にやさしく染み込ませるといいですよ。ティッシュに染み込ませてお腹に置くだけでも大丈夫。
卵巣に良性の腫瘍があったママ友が、キャスターオイルを毎日続けて使っていたら、症状が軽くなったという話を聞いたことがあります。
私自身も流産を経験した時に使っていたし、生理の時のケアにもおすすめです。オイルなので、使い方に決まりはなく、体のどこに塗っても安心して使えます。
沙織:なんと万能なオイル!
舞麻:私が大事だと思っているのは「西洋医学と東洋医学のいいとこ取り」。たとえば、がんを東洋医学だけで治そうとするのはリスクが高いかもしれません。でも抗生剤をむやみに使うのも危険です。抗生剤は悪い菌だけではなく、腸内の良い菌も殺してしまうからです。
もちろん命に関わるなら抗生剤に頼るべきですが、「ちょっと風邪だから」とすぐに使うのは考えた方が良いと私は思っています。たとえば、普段から野菜や食物繊維を増やしたり、ヨーグルトや納豆、お味噌といった発酵食品を摂る。泥に触れたりペットと暮らしたりして日常の中で免疫を育てることも大切。
お医者さんに頼る前に、自分でケアできることはする。キャスターオイルも、そのひとつだと思っています。
沙織:キャスターオイル、扱いたいですね。使い方がわからなかったから、まだ仕入れていないので、商品ラインナップに加えたいです。
「買うこと」が応援になる。Hummingのセレクトに込めた想い
沙織:ECサイトで取り扱う商品は、オーガニックであったり、女性経営者が手がけていたりと、背景にもこだわって選んでいるのが印象的です。
舞麻:アメリカでは、女性が社会で活躍することや、対等な賃金を得ることが重視されています。だからこそ、女性が立ち上げたブランドや、小規模でも丁寧にものづくりをしている会社の商品を選んで使おう、という意識が自然と身についてきました。
Hummingで扱っている商品も、そうした背景を持つお店から仕入れているものが多いです。
沙織:商品を買うことが、小さな企業や作り手を応援することにつながる。今はモノがあふれる時代だからこそ、「どこで買うのか」を考えるきっかけになったら良いですね。
疲れた時に遊びにきてほしい
沙織:どんな方にHummingのECサイトに足を運んでもらいたいですか?
舞麻:買うかどうかは別として、「ちょっと疲れたな」「最近、自分をケアできていないな」と感じた時に、気軽にのぞいてもらいたいです。
Hummingを通して、自分をケアすることに時間をかけている人もいるんだと知ってもらえたら嬉しいです。
「自分をケアすることって、悪いことじゃないんだ」「ちゃんと自分を大切にしていいんだ」と感じてもらえたらと思います。
沙織:Webマガジンの記事を読んでいただいて、気になる商品があればECショップに立ち寄ってもらうのもいいですよね。
舞麻:いつか東京や大阪でポップアップもしたいですね。
沙織:いいですね!ぜひやりましょう。
「お金のゆがみ」とは?もしかしてあなたも陥っているかも?

最近、こんなことを感じたことはありませんか?「周りの人が高いレストランばかり行くようになった」「SNSを見ていると、みんな豪華な旅行やブランドバッグを持っている気がする」――。
気づけば、自分も“そのペース”についていかなきゃと感じている。
でも、ふと立ち止まると「本当に私は大丈夫?」「他の人みたいにお金を使えていないのはおかしいの?」と不安になる。
このように、自分の経済状況と現実との間にズレが生じる感覚を「マネーディスモルフィア(お金のゆがみ)」と呼びます。
おすすめ記事 ▶ 時は金なり。 ドラッグのように中毒性のあるスマホとの付き合い方を見直そう【Editor’s Letter vol.10】
お金の現実が見えなくなる「マネーディスモルフィア」とは?
ファイナンシャルセラピストのリンジー・ブライアン=ポドヴィン氏はこう説明します。
「マネーディスモルフィアとは、本人が感じている“お金の状態”と、実際の経済状況との間にある距離のことです。」
これは医学的な診断名ではありませんが、現代社会では多くの人がこの“お金のゆがみ”に影響を受けています。
実際、Credit Karmaの調査によると、ミレニアル世代とZ世代の43%がマネーディスモルフィアを経験しているといいます。
SNSが引き起こす「比較の罠」
SNSでは、他人の消費スタイルがリアルタイムで流れ込んできます。
でも私たちは、その人の年収や背景を知っているわけではありません。
「旅行は実はもらいものだった?」「バッグはレンタル?」と気になるけれど、真実はわからない。
それでも私たちは「自分もそのくらいできるはず」と感じてしまうのです。
こうして、現実よりも「お金が足りない」「もっと稼がなければ」と感じるようになります。
それが「マネーディスモルフィア」の始まりです。

マネーディスモルフィアとお金の不安の違い
「お金への不安」は、実際の支出や貯金などに関して不安を感じる状態。
一方でマネーディスモルフィアは、“他人と比べること”によって現実が歪んで見える状態です。
どんなに収入があっても、「自分は遅れている」「足りていない」と感じてしまう。
実際、年収1000万円以上の人の51%が「毎月ギリギリで生活している」と答えています。
お金は理屈ではなく、感情と深く結びついているのです。
マネーディスモルフィアを手放す5つのステップ
1. 自分の「現実」を見つめ直す
お金を避けずに、今の収支や貯蓄を“ありのまま”に見ましょう。
「見たくない」と思うほど、そこには学びがあります。
2. 感謝の視点を持つ
どんなに小さくても、すでに自分の暮らしを支えてくれているものに目を向けて。
家族や思い出、日々の安心感――それらはお金では買えない“資産”です。
3. 比較をやめるSNSの使い方をする
SNSの「ミュート」「フォロー解除」は立派なセルフケア。
あなたの心をざわつかせる投稿から距離をとることは、決して逃げではありません。
4. 自分の価値観に沿った目標を立てる
「もっと稼ぐ」よりも、「どんな暮らしをしたいか」にフォーカスしてみて。
1〜3個の“自分らしいお金の使い道”を決めるのがおすすめです。
5. 必要であれば専門家に相談する
お金の悩みは、心の課題とつながっていることもあります。
信頼できるファイナンシャルプランナーやセラピストに話してみましょう。
お金との関係を「整える」ことは、自分を大切にすること
マネーディスモルフィアは、単にお金の問題ではなく、自分の価値や幸福の感じ方と深く関係しています。
他人のライフスタイルを基準にするのではなく、
「自分にとって豊かさとは何か?」を問い直すことが、真のマインドフルマネーへの第一歩です。
女性は一人暮らしのほうが幸せ?結婚・同棲に縛られない生き方とは

女性は一人で暮らすほうが幸せって本当?
「結婚した方がいいのは男性。でも女性は無理にする必要はない」――こんな言葉を残したのは、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスの行動科学教授であり、『Happy Ever After』の著者、ポール・ドラン氏です。
彼が引用する調査によると、未婚・既婚・離婚・死別などさまざまな人を比較した結果、もっとも幸福度が高かったのは「未婚で子どものいない女性」でした。
結婚や同棲にはもちろんメリットもあります。経済的な安心感や孤独の軽減などがその一例です。ですが同時に、自由や心の安らぎを制限してしまう可能性もあります。たとえばベッドの真ん中で気兼ねなく眠ること、自分の健康や趣味に十分な時間を使うこと――これらは「一人だからこそできる幸せ」なのです。
おすすめ記事 ▶ 脱・依存体質。自分の価値や幸せは自分が決めるもの
なぜ一人暮らしの女性は幸せで健康でいられるのか?
テキサス州の心理学者キンバー・シェルトン博士は、「家事・育児の負担」を理由に挙げます。
彼女によれば、女性は外で働いていても、男性よりも家事や子育てを多く担い続けているとのこと。仕事を終えた後に料理・掃除・子どもの世話、さらにパートナーのケアまでこなす生活では、自分を労わる時間がほとんど残りません。
その結果、男性は結婚することで健康に長生きする一方、既婚女性は独身女性よりも寿命が短く、幸福度も低いという研究結果があるほどです。
つまり「自分の時間や空間を持てること」が、女性の健康や幸福に直結しているのです。
女性は一度は一人暮らしを経験すべき?
インドで行われた研究では、50〜65歳の中流上層階級の女性たちが一人暮らしをする中で、孤独の中にある自己実現や充実感を見いだしたと報告されています。
社会学者ベラ・デパオロ氏も、著書『Single at Heart』で「独身の喜び」について語り、一人暮らしを楽しむ人の強みとして以下を挙げています。
- 好きなことをひとりで楽しめる
- 他者とのつながりを保てる
- 孤独を「脅威」ではなく「回復の時間」として受け止められる
孤独と聞くとネガティブに思う人もいるかもしれませんが、博士は「lonely(孤独)」と「alone(独り)」は違うと指摘します。新しい趣味や旅行、運動、読書などを通じて、一人時間を楽しむ方法はいくらでもあるのです。

結婚・交際中でも「ひとりで暮らす」は可能?
「結婚しているから」「同棲しているから」一人暮らしができないわけではありません。
カップルでも、家を分けて住む・自宅を区切って別スペースを持つといった工夫で、自分の生活空間と役割を切り離すことができます。あるいは長期の一人旅も、自分のニーズや思考に向き合う方法のひとつです。
ただし、この選択には罪悪感が伴うこともあります。シェルトン博士はこう語ります。
「大事なのは住まいの形ではなく、信頼とコミュニケーション。お互いに合意して信頼を持てるなら、別々に暮らすことは関係を弱めるのではなく、むしろ強めることになります。」
一人暮らしを始めるときの実践ステップ
一人暮らしは、社会的な期待や慣習に逆らう部分があるため、最初は不安や葛藤を感じるかもしれません。そこで役立つステップを紹介します。
- 罪悪感を手放す:その感情の正体が「世間の常識」か「他人の期待」から来ていないかを見直す
- 意思を明確にする:独身や一人暮らしを望むなら、パートナーや相手に誠実に伝える
- サポートを得る:同じ価値観を持つ人や友人と時間を過ごし、孤独ではなく連帯感を感じる
- 専門家に相談する:必要に応じてセラピーを受け、自分の選択に安心感を持てるようにする
まとめ:一人暮らしは「わがまま」ではなく自己保存の選択
一人暮らしを選ぶ女性は、古い「結婚すべき」という価値観から離れ、自分の幸せを自分で選んでいます。
それは時に「わがまま」と呼ばれるかもしれませんが、実際には自分を守るための大切な自己保存のかたちです。
一人の時間を大切にできることは、孤独ではなく自由。
「女性は一人暮らしで幸せになれるのか?」という問いの答えは――YES。それは、自分を最優先できる幸せな選択なのです。
恋愛における嫉妬の乗り越え方|9つの実践的な対処法

大切な人が他の誰かと過ごしているとき、ふと「自分だけ置いていかれた」と感じたことはありませんか?
嫉妬は誰もが避けたい感情ですが、恋愛をしている限り、多くの人が一度は経験するものです。
「嫉妬しない方法を知りたい」
「嫉妬が止まらないときどうすればいい?」
「不安や比較で心が苦しい」
もしそう感じているなら安心してください。嫉妬は関係を壊すものではなく、向き合い方次第で信頼を深めるきっかけにもなります。ここでは、心理学に基づいた嫉妬の原因と対処法をわかりやすく解説します。
おすすめ記事 ▶ たとえ変化しても、パートナーと共に成長していくには
恋愛における嫉妬とは?
嫉妬とは、「大切な人を誰かに奪われるかもしれない」という不安から生まれる感情です。
「羨望(自分も欲しい)」とは違い、「今あるものを失う恐れ」が嫉妬の正体です。
例えば、パートナーが新しい同僚の話を楽しそうにする時や、友人と長く過ごす時に、心がざわつくことがあります。実際には起きていないことを想像してしまい、相手を疑ったり過剰に質問してしまうのも嫉妬のサインです。
嫉妬はなぜ起こるのか?6つの主な原因
嫉妬を感じるとき、その裏側には自分でも気づいていない深い要因が隠れていることがあります。恋愛における嫉妬に向き合うためには、よくある「引き金」を理解することが大きな一歩になります。
不安や自己否定感
自尊心の低さは嫉妬の大きな要因です。「自分は面白くないのでは」「頭が良くないのでは」「魅力的ではないのでは」と思い込むことで、「自分はパートナーにふさわしくない」と感じ、自分を追い詰めたり、疑いの気持ちを抱きやすくなります。
過去の経験
過去に誰かに裏切られたり傷つけられたりした経験は、現在の感情に大きな影響を与えます。かつての出来事が再び起こるのではないかと心配するのは自然なことです。
失うことへの恐れ
大切な人を失いたくない――その思いは誰にでもあります。パートナーを他の誰かに奪われるのではないかという恐怖は、嫉妬心を強くかき立てます。
比較から生まれる嫉妬
パートナーの周りにいる人と自分を比べ、「自分より優れているのでは」と思うことがあります。特にSNSは、他人の「切り取られた理想的な姿」と自分を比較してしまうため、自信を失い、嫉妬を感じやすくなります。
気分や精神状態の影響
気分が落ち込んでいたりストレスが溜まっているときは、敏感になり嫉妬を感じやすくなります。特にうつ病、強迫性障害、不安症などのメンタルヘルスの課題を抱えている場合、嫉妬心が強まることがあります。
オープンなコミュニケーション不足
誤解は恋愛関係ではよくあることで、とくに愛情表現の仕方や愛着スタイルが違うと、相手の意図を読み違えて嫉妬を生みやすくなります。

パートナーが嫉妬しているときの対処法
ときには、嫉妬を感じているのが自分ではなくパートナーであることもあります。そのとき大切なのは、相手をただ「嫉妬深い人」と決めつけるのではなく、嫉妬への対処も関係そのものと同じく“ふたりの共同作業”だと理解することです。忍耐とオープンなコミュニケーションがあれば、嫉妬の瞬間を関係を深めるきっかけに変えることができます。
オープンな会話を促す
パートナーが安心して気持ちを打ち明けられる場をつくりましょう。批判される心配なく、正直に思いを共有できると伝えてあげてください。
批判せずに耳を傾ける
相手が話してくれたときは、遮ったり防御的になったりせず、丁寧に耳を傾けましょう。相手の視点を理解することが何より大切です。
責めない
「あなたのせい」と指をさすのではなく、これからどう一緒に前に進み、絆を強められるかに焦点を当てましょう。
嫉妬を手放す9つの方法
嫉妬を避けて、健全な関係にずっと居座り続ける必要はありません。嫉妬を防いだり、乗り越えたりするためにできる実践的なステップはたくさんあります。
1. 立ち止まって気持ちを見つめ直す
なぜ嫉妬しているのか考えてみましょう。パートナーの行動が原因なのか、それとも自分の心配や不安から来ているのか。ネガティブな自己対話が気持ちに影響していることもあります。
2. パートナーと正直に話す
嫉妬を感じたときは、責めるのではなく正直に気持ちを伝えることが大切です。ケンカをするためではなく、心を開くために。過去の経験から来る不安なら、その怒りやわだかまりを手放すことも必要かもしれません。
3. 一緒に信頼を築く
信頼は関係の土台です。約束を守る、正直でいる、オープンでいる――そんな積み重ねが強い信頼をつくります。
4. 自分に自信をつける
自分に満足できると嫉妬しにくくなります。新しいことを学んだり、趣味に打ち込んだり、自分を大切にすることで自己肯定感を高めましょう。
5. 感謝でポジティブに焦点を当てる
うまくいっていないことではなく、うまくいっていることに目を向けましょう。関係やパートナーに感謝する気持ちは、嫉妬心を和らげます。もし感謝できることが見つからないときは、関係全体を振り返ることも大切です。
6. 誤解を防ぐために境界線を決める
お互いに「何がOKで、何がNGか」をはっきりさせましょう。明確な境界線は誤解を防ぎ、安全と理解の感覚を育みます。
7. 相手を尊重する
パートナーのスマホやメールをのぞくことは信頼を壊します。プライバシーを尊重し、必要なことは相手がきちんと共有してくれると信じましょう。
8. 助けを求める
嫉妬が強すぎて自分ひとりで対処できないときは、友人や専門家に相談してみましょう。外の視点からの助言が助けになることがあります。
9. マインドフルネスを実践して「今」に戻る
「もしパートナーが誰かと…」と未来を心配するのではなく、今この瞬間に意識を向けましょう。マインドフルネスは、嫉妬を悪化させる“もしも”の思考から抜け出す助けになります。
まとめ
嫉妬は「なくす」ものではなく、「うまく扱う」もの。
正しく向き合えば、関係を深めるチャンスに変えることができます。
大切なのは、自分の心を理解すること、パートナーと誠実に向き合うこと。
そうすることで、嫉妬はあなたの幸せを邪魔する存在ではなく、成長のきっかけになるでしょう。
【ハミングが届けるポジティブニュース】 南極から届いた意外な朗報──「氷が増えている」という意外なニュース

「地球温暖化が進み、南極の氷がどんどん溶けている」──私たちが耳にするのは、そんな不安をあおるニュースばかりではないでしょうか。
海面上昇や異常気象のリスクを考えると、確かに深刻な現実があります。しかし、今週世界の科学ニュースをにぎわせたのは、そんな予想とは逆の出来事でした。「南極の氷が増えている」というのです。
おすすめ記事 ▶ 【ハミングが届けるポジティブニュース】 今日も、誰かの優しさが世界を救っている──クレーン運転手が見せた奇跡の救出劇と心温まる贈り物
過去10年の常識を覆す観測結果
中国・同済大学の研究チーム(王巍博士、沈雲中教授ら)は、2021年から2023年にかけて、東南極のウィルクスランドとクイーンメアリーランド地域で、年間平均108ギガトンもの氷床が増加したと報告しました。
1ギガトンは10億トン。108ギガトンといえば、アメリカの空母およそ150万隻分もの重さに相当します。数字だけを見ても想像しにくいですが、それほど膨大な量の氷が新たに積み重なったということです。
従来の常識では、2010年から2020年の間に南極は平均して年間147ギガトンの氷を失っていたとされていました。だからこそ、この氷の増加は驚きをもって受け止められています。
“NASAとドイツ航空宇宙センターの衛星観測により、異常な降雪量の影響で南極の4つの氷河盆地で氷が増加し、年間0.3ミリ分の海面上昇を相殺する可能性があることがわかりました。”
どうやって氷の増減を測るのか?
研究チームは、NASAとドイツ航空宇宙センターが共同で進めている人工衛星「GRACE(重力回復衛星)」と「GRACE-FO」を使いました。この人工衛星は地球の重力の微妙な変化を測定し、その変化から氷の増減を割り出すことができます。
結果、トッテン氷河、モスクワ大学氷河、デンマン氷河、ビンセンス氷河という4つの氷河盆地で氷の増加が確認されたのです。
原因は「異例の降雪量」
氷が増えた背景には、異常に多かった降水量があるとされています。 つまり、雪として降った水分が氷床に厚く積もり、失われる氷の量を上回ったのです。
この結果、年間0.3ミリの海面上昇を打ち消す効果が見込まれるといいます。これは2010年代に観測された海面上昇の約4分の1に相当するインパクトです。
もちろん、科学者たちはこの結果を楽観視していません。観測データは2024年に入ると再び氷の減少が見られたからです。氷の増減は季節変動の影響を強く受けており、増えた年もあれば減った年もあります。その繰り返しの中で、今回のような「増加トレンド」がどこまで続くかは、まだわかっていません。
それでも重要なのは、「南極の氷が一方的に減り続けているわけではない」という事実が明らかになったことです。

地球が見せる「回復力」
南極とグリーンランドの氷床は、世界の淡水の大部分を占めており、海面上昇の最大の理由とされています。だからこそ「氷が増える」という事実は、本来なら海に流れ出して海面を押し上げるはずの水が氷として留まっているため、地球が持つ自然の回復力を示す希望の光ともいえそうです。
気候変動の議論では「残された時間はほとんどない」と言われることが多く、無力感を抱く人も少なくありません。でも、南極から届いた今回のニュースは、そんな私たちに「まだ希望はある」と教えてくれます。
前向きな未来を描くために
南極の氷が増えたのは一時的な現象かもしれません。それでも、このニュースは「自然の変化には想像以上の可能性がある」ことを示しました。私たちにできるのは、自然の力を信じつつ、人間としての努力を重ねること。
南極から届いた意外な朗報は、未来に対して悲観するばかりではなく、「ポジティブな変化を信じる力」を持とうと私たちに語りかけています。
【映画レビュー】老いを抱きしめる美しさ――『About Face』を見て

幼いころ、母に連れられて行く買い物で、私がひそかに心を躍らせていたのは、雑誌コーナーへと抜け出すひとときでした。流行に敏感だったわけでもなく、化粧に興味があったわけでもないのに、あの光沢を放つ表紙たちは、いつも私を惹き寄せました。そこに佇む女性たちは優雅で、静かに私を見つめ返し、私はただ密やかに「いつか自分も」と願っていたのです。
『About Face』は、そんな時代を彩ったスーパーモデルたちを再び呼び戻し、雑誌の表紙を飾り、ランウェイを駆け抜けた彼女たちが、いまどこに立っているのかを描き出すドキュメンタリーです。彼女たちが歩み出したのは、そもそも「キャリア」という言葉が女性には与えられていなかった時代。その姿は、モデルとインフルエンサーの境目が曖昧に溶けていく現代と、鮮やかな対照を成しています。
おすすめ記事 ▶ 多様性の時代に考える「美の基準」との向き合い方
言葉が人生を左右するとき
当時のモデルは、個人として讃えられる存在ではなく、布をまとった「動くハンガー」に過ぎませんでした。けれども時が経つにつれ、人々の視線は衣服から彼女たちの存在へと移っていきます。強いまなざし、彫り深い頬、強い存在感――それを無視することなど、誰にもできなかったのです。
150センチそこそこの背丈で、丸みを帯びた身体を持つ私は、背が高く細身の彼女たちを羨望のまなざしで見つめていました。モデルになることを夢見たわけではない。ただ、もう少しだけ背が高くなりたいと願っていたのです。艶やかに巻かれた髪も、頬にのせられたチークも、すべてが巧みに演出された幻影だとは知りませんでした。あの表紙の裏には、少女たちに向けられたひとつの声が隠されていたのです――「美しい女の子とは、こういうものだ」と。
“たったひとことの言葉が一生心に残り、人を縛ることも解き放つこともある”
映画は、1945年からモデルとして歩み続けるカルメン・デロリフィチェの姿から幕を開けます。
彼女は古い写真を見つめながら、ふと「自分の足を好きじゃない」とこぼします。かつて母に「棺のようだ」と言われたその言葉は、81歳となった今なお、彼女の心に影を落としているのです。ひとつの言葉が、一生を通して響き続ける――その重さに、ただ驚かされます。
言葉はなぜ、これほどまでに深く心の奥底に根を張るのでしょう。どれほど自信を重ねても、決して消えない言葉があります。
私自身も、母から「少しぽっちゃりしているから痩せた方がいいのでは」と何気なく言われた日のことを忘れられません。13歳の頃でした。その瞬間から、私と自分の身体との関係は複雑なものになり、健康でありたい願いと、罪悪感なく食を楽しみたい思いのあいだで、心は揺れ動き続けています。けれど同じ母が「あなたの笑顔はとても素敵ね」と告げてくれた言葉もあり、それ以来、私はためらわず笑うようになりました。その言葉が、笑顔でいることを許してくれたように。
別のモデル、マリサ・ベレンソンは、母から「あなたの顔はモディリアーニの絵のようだ」と言われたことを語ります。彼女は笑ってそう言いましたが、その笑いの奥には痛みが潜んでいました。たとえ悪意のない言葉であっても、深く心を傷つけてしまうのです。
それこそが、モデルという職業の逆説なのかもしれません。称賛よりも欠点を指摘され、身体を細部まで値踏みされる世界。毒のように思える場所でありながら、それでも無数の少女たちが憧れを抱き続けます。なぜなら、ほんのひと握りの選ばれし者は、繰り返し「美しい」と讃えられるから。――美しさは、世界が何度も教えてきたように、扉を開く鍵であるからです。

権力と偏見にかたどられた「美」
「美しい」とは、本当にどういうことなのだろう。
それは幸せをもたらすのだろうか。――着る人の心よりも、世界にどう映るかだけを求められるこの業界で。与えられるのは、ブランドが選んだ化粧。望まれるのは、彼らが描いた完璧な髪型。強いられるのは、作りものの美しい笑顔。
元モデルのキャロル・オルトは言う。
「それは、本当の私ではなかった」と。
モデルとは自分を売るのではなく、服を売る仕事だ――そう言う人もいるだろう。けれど彼女は続ける。
「服を着て生き生きと存在すること。その姿ごとに価値を見いだされること」。
そこにこそ、人間らしい真実が宿るのだと。
“映画は、美と栄光の裏に潜む搾取や人種差別の現実を映し出し、「美しさ」が権力や偏見に左右され続けてきたことを突きつけている”
映画はまた、目を背けたくなる闇をも映し出す。
ドラッグ、セックス、搾取――それらは例外ではなく、日常の風景だった。繰り返されるうちに、人はそれを「普通」と思い込んでしまう。だが、15歳や16歳の少女たちが酒や薬の漂う場へと投げ込まれ、大人の欲望の視線を浴びるその光景は、あまりに見ていて辛い。少女の身体に「女」の姿を映し出し、思春期そのものを奪う――その異様さは、忘れがたい不快さを伴う。
そして、人種の壁もまた、この業界を覆っていた。
有色人種の女性を表紙に載せることをためらう出版社。
ベサン・ハーディソンやパット・クリーブランドは、白人を優遇する世界で、自らの居場所と声を切り拓いてきた。いまなお続くその戦いの中で、ブランドが放つ言い訳は「非白人モデルをどこに置けばいいのかわからない」というもの。しかし、アメリカの街角を一歩歩けば、多様性に満ちた顔があふれている。その言葉がいかに空虚かは明らかだ。
おすすめ記事 ▶ 映画レビュー:「食べて、祈って、恋をして」— 人生で出会う人はすべて意味がある
アジア人としてアメリカで育った私にとって、雑誌に自分と似た顔を見つけることは大きな意味を持っていた。それは単なる「姿」ではなく、「未来」の可能性だったから。
だからこそ、この映画が不都合な真実から目をそらさなかったことを、私は深く評価したい。
美しさとは、決して無垢でも中立でもなかった。常に権力や偏見にかたどられ、「誰が見るに値するのか」という問いにさらされ続けてきたのだ。

時間がくれる、自信という美しさ
『About Face』は、モデル業界の暗い影を映し出しながらも、最後には「美しさ」と「老い」に新しい光を投げかける。
時間とは戦うべき敵ではなく、強さや自信を宿す源である――この映画はそう語りかけてきます。
彼女たちがキャリアを歩み出したのは、まだスマートフォンもSNSも存在しない時代。アルゴリズムが美を決めるのではなく、環境そのものが扉を開く時代でした。イザベラ・ロッセリーニやキャロル・オルトにとって、モデルは夢ではなく、生き延びるための手段であり、あるいは家族や共同体に背を押されて選んだ道でもありました。だからこそ彼女たちの「老い」に対する眼差しには、他者との比較に曇らされない透明さがあり、その語りはどこか清められた祈りのように響きます。
長年にわたる視線と批評にさらされたからこそ、彼女たちは解き放たれる強さを得たのでしょう。仲間の中には若さを追い、かつての個性を消してしまった者もいた。それでも彼女たちは、成熟こそが美であると信じる世代に生きてきた。成熟はつまり「生きてきた証」であり、そのしるしこそが顔に刻まれるのです。
“『About Face』は、若さを追うのではなく人生を抱きしめることで芽生える自信と、老いを祝福すべき美しさとして描き出している”
あるモデルは言いました。
「誰かとあなたを分ける一番大切なもの――それは“表情”なの」
ボトックスや整形があたり前になったこの時代にあっても、その言葉は胸の奥深くに沈みます。映画も、私自身も、美容の選択を否定はしません。人を本当に幸せにするものなら、それが正解だから。けれど、彼女たちを見ているとわかるのです。揺るぎない自信は、若さを留めることからではなく、人生の物語をそのまま抱きしめることから生まれるのだと。
イザベラが語った一言は、特に心に残ります。
「50代になって初めて、自分は美しいと呼ばれるにふさわしいと思えた」と。
その言葉は、私たちへの優しいささやきでもあります。――焦らなくていい、自分の肌の中に安らぎを見つけるには時間がかかるのだと。美しさとは、消え去るものでも忘れ去られるものでもない。むしろ、時間とともに豊かに花開くもの。
結局のところ、『About Face』はファッションの物語ではありません。
それは耐えること、しなやかに生きることの物語。
女性は美しいだけでなく、強い存在である。老いの旅は隠すべきものではなく、祝福すべきものなのだ――この映画は、静かな声でそう教えてくれます。
10分が育む、親子の絆。3姉妹ママが実践する子育て法【編集部対談】
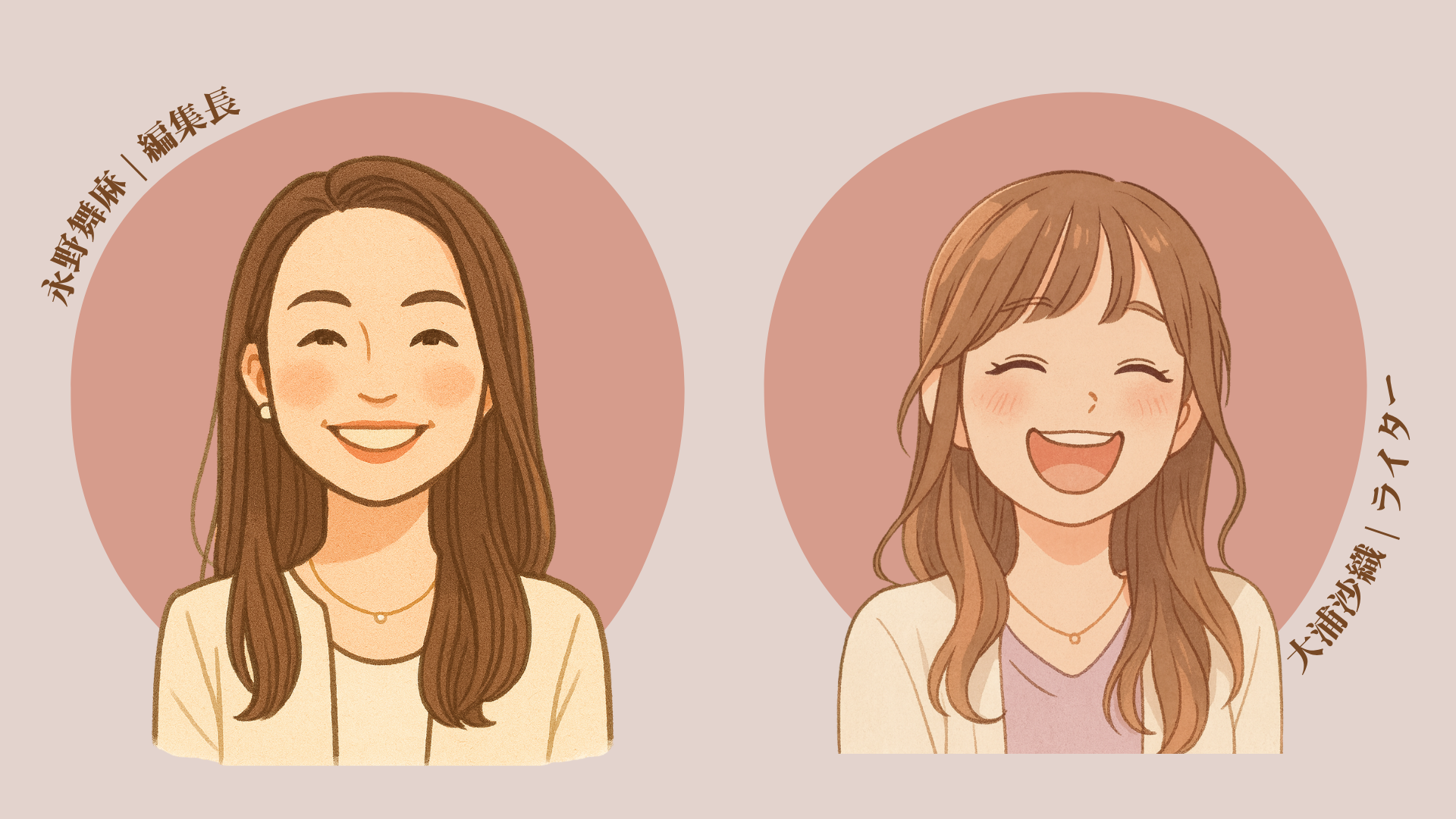
「ママが自分を見てくれている」「聞いてくれている」。
子どもにそう感じてもらえる時間を、私たちはどれだけ持てているでしょうか。
今回は Humming編集部の舞麻(カリフォルニア在住・3姉妹の母)と沙織(東京在住・小学生2人を育てるワンオペママ)が、 “親子の信頼関係を育む10分間”について語り合いました。
編集部のリアルな子育て対談をお届けします。
おすすめ記事 ▶ 子どもとのふたり旅 。24時間以上一緒に過ごすことで見えてくる一面【Editor’s Letter vol.11】
全力で子どもと向き合う10分間
舞麻:我が家では2021年頃から寝る前に子どもたちそれぞれと10分間を過ごすようにしています。
それまでは母親の愛を取り合って姉妹喧嘩が絶えませんでした。私がいない時の方が仲良く遊べるのに、私がいるとネガティブな行動で注目を浴びようとする子がいる。その姿を見て「きっと辛いだろうな」と感じ、対処法を探す中で出会ったのが「1日10分、その子だけの特別な時間をつくる」という考え方でした。
「10分ならできるかも」と思い、取り入れてみることにしました。
沙織:子どもが複数人いると、なかなか子ども一人ひとりと向き合う時間が取れないですよね。10分間はどうやって過ごすのですか?
舞麻:最初の8分は、100%受け身でその子のやりたいことを一緒にやります。色塗りをしたり、こちょこちょ遊びをしたり、一緒に本を読んだり。残りの2分は「バラとトゲ」というシェアの時間。今日悲しかったこと・辛かったこと・嫌だったことを“トゲ”として、嬉しかったことや楽しかったことを“バラ”として話すんです。
「ママのバラとトゲはなに?」と聞かれた時は、その子に関わる出来事を話しています。
沙織:お子さんたちからは、何をしたいとリクエストされることが多いですか?
舞麻:「Tickle Monster(くすぐりモンスター)」という、私がモンスターになってくすぐる遊びをリクエストされることが多いです。
私はくすぐられるのが大嫌いなので、全然共感できないけど(笑)、子どもたちがゲラゲラ笑っていると、つい私も笑ってしまう。子どもたちはママと一緒に笑える時間が嬉しいのかもしれません。
親は、どうしても子どもの健康や安全、将来のことを真剣に考える時間が多いから、子どもとゲラゲラ笑う機会は意外と少ないですよね。

沙織:私は笑うより、怒っていることの方が多いかも……。
舞麻:ある本で「フィジカルな遊びは子どもの心の安定に良い」と読んだことがあります。一緒に体を動かしたり、遊びながら会話したりする方が、子どもにとって記憶に残りやすいとも言われています。うちは親子で柔術を習っているので、技をかけ合ったりすることもありますよ。
沙織: 10分間の時間は、毎日欠かさず続けているんですか?
舞麻:コンサートに行ったり、外食したり、寝る準備が遅くなる日は「バラとトゲ」だけをやることもあります。
でも、子どもたちは「ママだけにシェアしたいこと」があるから、忙しい日でもなるべく時間をつくるように心がけています。
沙織:舞麻さんは3人お子さんがいるから、3人分やったら30分。これを毎日継続する。なかなかできないことですよね。
舞麻:もちろん「今日は疲れたし早く寝たいな」という日もあります。正直、精神力を使うから修行みたいに感じる時もあるくらい。でも、もう習慣になってしまったので、やらないと1日が終わった気がしなくて。まるで「歯を磨かずに寝ちゃった時の気持ち悪さ」みたいな感覚です。
沙織:我が家も兄妹喧嘩が多いから、子どもそれぞれとの10分間を取り入れたいな。でも、寝る前はいつもバタバタだし、下の娘が待てなさそうな……。
舞麻:寝る前の10分間が難しければ、昼間でも、朝でも、どのタイミングでも大丈夫です。娘たちも10分間を始めた頃は、なかなか待てなかったです。コンコンってノックしてみんな入ってきちゃう。そのたびに「今はスペシャルな時間だから、10分間だけ待っててね」と根気強く伝えました。最初は「また来た……」と思うこともあったけど(笑)。1年経った頃にはちゃんと待てるようになりました。
きっと娘たちにとって、この10分間は本当に大切な時間なんだと思います。だからこそ、自分以外の姉妹がその時間を過ごしている時も、「今は待とう」と尊重できるようになったのかもしれません。
沙織:舞麻さんの一番上のお姉ちゃんは今おいくつですか?
舞麻:中1になる歳です。
沙織:中学生は、思春期とか反抗期とか、難しい時期かと思いますが、そういうお年頃でも10分間は嫌がらないですか?
舞麻:私が読んだ専門家の本には「10歳くらいになると、子どもはだんだん親との特別な時間を欲しがらなくなる」と書かれていました。
でも、長女はいまだにこの10分間を大切にしてくれています。

子どもと“人”として向き合う
沙織:子どもたちそれぞれと10分間を過ごすようになってから、何か変化はありましたか?
舞麻:ママに振り向いてほしくて、わざと激しくぶつかり合うことはだいぶ減ったと思います。もちろん姉妹喧嘩がなくなったわけではないけれど。
それぞれが「必ずママと過ごせる時間がある」とわかっているからこそ、安心できるようになったのかもしれません。
沙織:舞麻さん自身にはどんな変化がありましたか?
舞麻:ひとりの人間として、子どもたちを愛おしく感じるようになりました。
「この子はこんなふうに物事を捉えるんだ」とか、「この言い方はユニークだな」とか。純粋に人として興味がわいて、毎日話を聞くのが楽しみです。
沙織:そういう気持ちになると、子どもたちへの接し方も変わりますか?
舞麻:より尊敬や尊重の気持ちを持って、子どもたちと向き合えるようになります。
夫はもともと「子どもだから」ではなく、“人”として接する人なんです。例えば、子どもが「やりたくない」と言うと、「どうしてやりたくないと思うの?」と丁寧に理由を聞く。頭ごなしに「やりなさい」とは言いません。
一方で私は「親の言うことは絶対」という環境で育ったので、「なんでそこで理由を聞くの?」「もっと厳しくした方がいいんじゃない?」と以前は思っていました。でも、10分間を積み重ねるうちに、夫の接し方が理解できるようになりました。
私と沙織さんだって、最初は何も知らない他人。でも、知り合って話を重ねるうちに、お互いのことを発見し合い、少しずつ分かり合えるようになってきましたよね。それと同じで、我が子に対しても「親だから分かっている」と思い込むのではなく、会話を重ねながら関係を築いていく必要があると思います。
“10分間”は未来への先行投資
沙織:確かにそうですよね。知っているつもりになってしまうけれど、我が子だって自分とは違う人間。大人同士が会話を通じて関係を築いていくように、子どもともちゃんと向き合わないと分からないことがたくさんありますよね。
舞麻:そうそう。子どもがシェアしてくれないと気がつけないことが実はいっぱいあるんです。
以前、娘がひとりで寝てくれない時期があって、困ったことがありました。
ある日、娘が「私、眠りに落ちる時にまるで死んでしまうみたいに感じて、ひとりで寝るのが怖いの」と話してくれたんです。その話を聞いた瞬間、「もっと早く言ってよ。一緒に寝ようよ」と思いました。
他にも、寝る前に長女が私の携帯で下の子に何かを見せていたので、「もう寝る時間なのに、どうしてママの携帯を勝手にいじってるの?」と、頭ごなしに怒ってしまったことがあって。
でもその夜の10分間で、長女が話してくれました。「寝なきゃいけないのはわかっていたけど、妹に写真見せる約束をしていたの。ママが嫌がるのはわかっていたけど、妹との約束を守る方が私には大事だったの。ごめんね」と。
その時、ハッとしました。娘は一生懸命考えて行動していたんだって。シェアできるタイミングが来ないと、本音を言えない時があるんですよね。

沙織:子どもだっていろんな思いや考えがあって行動しているのに、つい頭ごなしに叱ってしまうこと、私にもあります。友達や周りの人にはそんなこと言わないのに、どうして我が子にだけ強く言っちゃうんだろうって……。舞麻さんの話を聞きながら、反省ばかりです。
舞麻:私も毎日反省ばかりです。でも、親だって与えられた環境の中で精一杯やっているのだから、必要以上に自分を責める必要はありません。むしろ「私は私のままでいい」と自分を受け入れている姿を見せることこそ、子どもにとって大切な学びになるのだと思います。
だから私は毎日瞑想をして「自分をそのまま受け入れる」練習をしています。
沙織:子育てをしていると、「ちゃんと育てなきゃ」というプレッシャーを定期的に感じます。「子どもが怒りっぽいのは私のせいかな」と不安になることもあって。でも、自分を責めるのではなく、まず自分を認めてあげることが大切ですね。
子どもとの対話の時間を意識して持つこと、私もやってみたいと思います。
舞麻:いきなり毎日は難しいから、週1回からでもいいと思います。今までゼロだったのを1にする、1を2にする……。そうやって少しずつでも大丈夫。例えば「週末の金曜と土曜だけやる」とか、「週1回だから、15分にしよう」とか。
私はこの10分間を、娘たちとの絆を深める“先行投資”だと考えています。将来、娘たちが大きくなったときに「うちの子たち、何を考えているのかわからない……」という状況は避けたい。いつでも「ママに相談できる」と思える関係を築いておきたいです。
人生には、誰にでも予期せぬ困難が訪れます。どうしようもなく辛さを感じたとき、頼れる相手がいる。ひとりで抱え込まなくていい。そう思えるだけで、人は前を向いて生きていけるはず。
娘たちとの10分間の対話は、そのための“生涯続く絆”を育む大切な時間だと信じています。
沙織:子どもたちとの絆を深める“先行投資”!深い!子どもに限らず、夫婦とか身近な人。自分のやりたいことに付き合ってくれる、叶えてくれるってすごく嬉しいですよね。
舞麻:相手の好きなことに寄り添うと、自然と関係が深まるんですよね。夫は古いマニュアル車が大好き。私は車に興味がなく「目的地に着けば何でもいい」タイプなんですが(笑)、あえて「教えて」とお願いして、一緒に運転することもあります。
沙織:子どもに対しても、夫婦でも、「その人のためだけの時間」をつくることって本当に大切ですね。
舞麻:相手のやりたいことに寄り添い、心から耳を傾けて言葉を受け止める。その小さな積み重ねが、信頼関係を育てていくのだと思います。
ウォーキングで心も体も健康に

毎日の一歩が未来を変える
アメリカで育った私は、車が主な移動手段という環境で暮らしていたので、歩くことが日常に組み込まれることはありませんでした。ほんの数分先のおやつを買いに行くときでさえ、当たり前のように車に乗り込んでいたのです。歩くという選択肢はそもそも頭に浮かびませんでした。
大人になって日本を訪れたとき、初めて「どこへ行くにも歩く」という体験をしました。そしてそのときに、歩くことの静かな魅力に気づいたのです。
もちろん、長距離を移動するなら今でも車の方が便利だと思います。でも、歩くことにはまた別の良さがあります。時間がゆっくり流れて、車に乗っていたら決して気づけないような、近所の小さな景色や変化を発見できるのです。
私のように「歩く習慣」がない環境で育った人間からすると、日本の人々はとても恵まれていると思います。子どもの頃から自然と健康的な習慣が身についているのですから。年齢を重ねるにつれて、私は歩くことをこれまで以上に大切に考えるようになりました。身体の健康のためだけでなく、心の健康のためにも。
おすすめ記事 ▶ 運動嫌いの私が「運動はメンタルにいい」を少しずつ信じはじめた話
なぜウォーキングなのか?
運動不足を感じていても、「ジムに通うのは大変」「激しい運動は続かない」と思っている人は多いのではないでしょうか。そんな方におすすめしたいのがウォーキングです。特別な道具も費用も必要なく、今日からすぐに始められるのが最大の魅力。
さらに、ウォーキングは体だけでなく心にも良い影響を与えます。日々のモヤモヤを抱えたまま歩き出すと、歩調と一緒に気持ちが整っていくような感覚を味わえることがあります。これはまさにウォーキング メンタルヘルスの効果です。
ウォーキングの健康効果
ウォーキングは有酸素運動のひとつで、ウォーキングの健康効果は非常に幅広いです。
- 心肺機能を高めることで、心臓病や脳卒中のリスクを軽減
- 血圧やコレステロール値の改善
- 骨の強化やバランス感覚の向上
- 筋力や持久力を高める
- 体脂肪の減少と基礎代謝の向上
- 気分を前向きにし、ストレス解消につながる
また、がんや糖尿病といった生活習慣病のリスクを下げる効果も期待されています。たった1日30分のウォーキングでも、続けることで大きな変化をもたらしてくれるのです。

メンタルヘルスへの効果
ウォーキングは「心の健康」にも大きな効果があります。研究によると、自然の中や太陽の光を浴びながら歩くことで、幸せホルモンと呼ばれるセロトニンが分泌され、気分が安定しやすくなると言われています。
例えば、仕事で疲れたときや人間関係でストレスを感じたとき。散歩に出るだけで頭がスッキリし、前向きな気持ちになれることはありませんか?これこそが散歩がストレスの解消になるのです。ウォーキングを習慣化することで、ストレスに強い心を育てることができます。
日常に取り入れるコツ
「30分歩くのは難しい」という方も心配いりません。10分を1日3回に分けても同じような効果が得られます。忙しい生活の中に小さな工夫を取り入れてみましょう。
- エレベーターではなく階段を使う
- 通勤や通学で1駅前から歩く
- スーパーやコンビニまで歩いて行く
- 犬の散歩を日課にする
- 昼休みにオフィス周辺を軽く歩く
こうした小さな積み重ねが、健康につながっていきます。
続けやすくする工夫
ウォーキングを長く続けるには、「楽しむこと」が大切です。
- 友人や家族と一緒に歩いて会話を楽しむ
- 好きな音楽やポッドキャストを聴きながら歩く
- 毎日ルートを変えて新しい景色を楽しむ
- 季節ごとの自然を観察する
ウォーキングは単なる運動ではなく、自分を癒やす時間、生活を彩る習慣へと変わります。
自分らしいウォーキングを見つける
ウォーキングのいいところは、誰でも、どこでも、今日からすぐに始められること。体力に自信がない人でも、自分のペースで無理なく続けられます。
少しだけ遠回りして帰ったり、休日に自然の中を散策したり。そんな小さな工夫が、ウォーキングの効果を最大限に引き出し、心の安定にもつながります。
「今日は疲れたから歩くのをやめよう」ではなく、「疲れているからこそ歩いてみよう」と思えるようになったとき、ウォーキングはあなたの人生に欠かせない習慣になっているはずです。
まとめ
ウォーキングは、体の健康を守るだけでなく、心を整え、ストレスを和らげる最高のセルフケアです。メンタルヘルスへの効果を感じながら、毎日の小さな一歩を大切にしてみませんか?
今日からできることは、とてもシンプルです。スニーカーを履いて、外に出て、歩いてみること。
その一歩が、散歩 ストレス解消と健康な未来へのスタートラインになります。
年を取ることは”老い”ではなく“更新”のチャンス|30代になって気づいたこと

大学生の頃といえば、若さに物を言わせて遊びたい盛り。
そして、その様子をみて、周りの大人たちが息を吐くように言っていた、
「そんな無茶できるのは若い時だけ」
「年取ったらすぐガタがくるんだから」
「体は資本、健康第一よ」
という言葉たち。
正直、当時の私は全然ピンときてませんでした。
なんせそのときの自分は、ちょっと無理したって1日経てばすぐ復活するし、風邪を引いてもしっかり食べてしっかり寝れば回復するわけですから。
まあそりゃ年を取ったらそれなりに体も衰えるだろうけど、そこまで言うのはちょっと大げさすぎないか?と疑心暗鬼になっていました。
でも、30代を幾ばくか経験した今、かつての大人たちの言葉の意味が痛いほど分かるようになってきたのです。
おすすめ記事 ▶ 心がまぁるくなった30代後半。歳を重ねるってどういうこと?
30代を境に訪れる体の変化
ほんの少し夜更かししただけで、翌朝の顔はぼてっとむくんで化粧ノリも最悪。
昨日の自分と今日の自分は別人なのでは?と思うほど、全身のコンディションがガタ落ちする。
代謝も落ちているから、気をつけないとすぐ体がぷにぷにしはじめて、ボディラインが曖昧になる。
季節の変わり目ですぐ風邪を引いてしまうし、さらには必ずといっていいくらい毎回長引く。以前のように、ぐーすか寝ればスカッと治ることも激減しました。
学生時代の勢いでオールなんてしようものなら、翌日は屍(しかばね)になることが容易に想像できます。
30代は節目とはいえ、人生100年時代で考えればまだまだ若造なはずなのに、早くも激変していく自分の体に直面して、ようやくあの頃の大人たちの気持ちが身に染みて分かるようになりました。
はーーー曲がり角ってこういうことね!
そりゃ衝撃的すぎて、自分たちよりまだ若い人たちに声高に伝えたくなるわ、今から備えておけよと。
「体が資本」という言葉は脅しでも誇張でもなく、リアルな実感からくる親切な助言だったのだとやっと気づきました。
“年齢を重ねることは老いではなく意識や価値観のアップデートであり、食やお酒との付き合い方など日常の選択もより心地よい方向へと変化している。”
年齢による変化は老いではなく、アップデート
かといって、自分に訪れる老いを前に、ただ悲嘆に暮れるだけでは面白くありません。
年を重ねてできなくなったこともあれば、できるようになったことも絶対ある。物事は捉え方次第ですよね。
そういう意味では30代に入って、いろんな意識がアップデートされた気がしています。
例えば「食」。

学生の頃は「安くてお腹が膨れる」が正義で、特に私はお酒をよく飲むタイプだったので、飲み放題があるお店はいつだって最高の選択肢でした。
でも今は「美味しいものを、必要な分だけ、気持ちよく食べたい」という気持ちにシフトしています。
かつては「せっかくの外食だから、思う存分飲むぞ!」と意気込んでいましたが、最近は「よく考えたらそんなに飲まなくていいかも」と素直に感じることも増えました。
最初こそ帰り道では少し物足りない気持ちもしていましたが、だんだん慣れてくると、翌日にも残らないし「ほろ酔い」ってなんて素晴らしいんだ!と思うようになってきました。
でも別に、制限をしているわけではないんです。
シンプルに「今の自分が必要な分だけ」を守っているだけ。
だから、裏を返せば「今日はもう羽目を外して、めちゃくちゃ飲みたい!」と思ったなら、その日は一切我慢しません。
一緒に飲みに出た友だちを深夜まで連れまわすし、翌日は二日酔いで丸一日無駄にして後悔するというのを、学習することなく未だに繰り返すこともよくあります。
旅先ではお腹パンパンになるまで、お金も労力も惜しまず全力でご当地グルメを味わうし、それで胃もたれしても「まあええか」と思える。
いくつになったから、このくらいの量にセーブするとか、もしくは、良いものを食べて舌を肥やすのが年相応とか、そういうことはあまり気にしていなくて、シンプルに30年分のデータから導いた「マイベスト」に従う。
そこを一番大事にしています。
今、自分の体に必要なものは、ちゃんと自分が一番分かっているので。
その声を素直に聞き取れるようになったのも、年齢を重ねたからこその変化かもしれません。
“運動を「義務」ではなく「気分をリフレッシュしてくれるもの」と捉えられるようになり、自然と日常に取り入れるようになった。”
さらに、運動についても考え方が大きく変わりました。
私はもっぱら文化系人間なので、運動にはなじみがなく、「健康のためにやらなきゃいけないもの」という義務感でしかなく、正直、昔から苦手意識しかありませんでした。
運動は疲れるもの、でも将来のためにしぶしぶやるって感じ。
でも今は、運動で気持ちいい汗をかくという感覚が分かるようになってきました。
体を動かす機会そのものが激減した影響も大きいのかもしれませんが、デスクワーク続きでどこか身も心もどんより疲れているときこそ、ちょっと動いてみる。
サクッと5分だけストレッチしたり、コーヒーを買いに行きがてら早歩きで散歩してみたりするだけでも、なんかちょっと血が巡って気分もリセットされる。
運動は疲れるものではなく、むしろリフレッシュしてくれるというのが少しずつ分かってきました。
なので、通勤をウォーキング時間にしてみたり、宅トレやストレッチ、ヨガをやってたりと、昔の自分が見たら信じられないくらい自発的に運動を取り入れるようになりました。
といいつつ、実はどれもイマイチ続かなくて、ちょっと落ち込むこともあるけど…
でも、それも単に今の自分の気分やスタイルに合わなくなっただけと切り替えて、「じゃあ次は何を試してみようかな」と、試行錯誤すること自体も楽しめるようになっています。
ちょうど最近は、ずっと気になっていたピラティスのパーソナルレッスンに通い始めたところで。
みっちりじっくり1時間、誰かと一緒に自分の体に向き合えるのが新鮮で、ちょっと楽しいかもと思えてきています。
まだ習慣にはなっていないけれど、運動の意味付けが「義務感でやる」から「心地よさのため」へと変わってきたことは、自分にとって大きな発見でした。

体が衰えても、心は軽やかでありたい
こうして振り返ると、変わったのは食べ物や運動に対する考え方だけではありません。
体の変化と向き合う中で、これまでの生活や世界がちょっと違うふうに見えてきて。
それなら、今まで自分の領域とは違う、世界線が違うと思っていたことも、最初からシャッターを下ろすのではなく一回は覗いてみてもいいのかもと思えるようになってきたんです。
で、実際、一歩踏み出してみたら意外と楽しかった、性に合うかもと思えた経験も増えてきました。
例えば、これまで「YouTuberなんて自分とは別世界」と思っていましたが、たまたま仕事で機会があって、気づけばYouTubeチャンネルを開設して自分で動画編集までして、チャンネルもそれなりに育っています。
あとは推し活。
ちょっと前まではむしろ理解できない派だったのに、今や推しが2人もいて、追っかけるのに身も心も忙しい状態です。
他にも、昔から歴史が好きだからというだけで世界遺産検定を受けてみたり、声が小さいのを克服したくてボイトレも始めてみたりと、我ながら30代入りたてにしては、まあまあいろんなことを試せている気がします。
しかもこういうことをきっかけに、また新しい世界が広がっていくことも知りました。
ボイトレの先生から仕事を紹介してもらったり、推しの雑談から新しいアーティストを知ったり、自分にはなかった考え方を知れて少し生きやすくなったり。
きっと他にもまだまだ、私が「苦手」「興味ない」「向いてない」って思い込んでることがあるんだろうな。
だからこそ、意識してオープンでいる。
拒絶せず、まずはちょっとだけでも試してみる。
そんな姿勢でいれば、体が衰えても、少なくとも心はいつまでも若々しくいられるんじゃないかなと感じています。
年齢を重ねることは“更新”のチャンス
年を重ねるうちに、いろんなものや人、環境を知っていく、触れていくからこそ、自分のなかの無意識の固定観念にも気づける。
だとしたら、年を重ねることは、柔軟に自分を更新していけるチャンスがあるということではないでしょうか。
単に「老い」と捉えてしまうと、可能性は狭まる一方に感じてしまいますが、むしろ自分らしさを深められる「チャンス」だと思うと、なんだか途端に前向きな気持ちになってきます。
実はこれを書いている今もちょうど誕生日を迎えたところなので、この一年は何をしようか、何を削ぎ落して、どんな新しいことに出会えるだろうかと、また一つレベルアップする気持ちでワクワクしています。
もちろん、大人たちが言っていた「健康第一」という言葉も胸に刻みつつ、「自分にとって心地よいもの」を見つけるアンテナをアップデートしていきたいと思います。
ファストファッションとは?環境問題・社会問題・未来のサステナブルファッションまで解説

ファストファッションとは?
“安くて早い”流行の裏側
街を歩いていて、つい「プチプラ可愛い!」と手に取ってしまう一着。気軽にトレンドを楽しめるのは、ファストファッションのおかげかもしれません。私自身も学生時代や若いころ、値段を気にせず洋服を買えることが嬉しくて、よく利用していました。
でも、便利さの裏で何が起きているのかを知ると、少し見え方が変わってきます。2000年から2014年にかけて衣類の生産量は2倍に、私たち一人あたりの購入量も約60%増加。これは、ファストファッションの仕組みが大きな影響を与えています。
おすすめ記事 ▶ オフィスでも活躍する!サステナブルなファッションブランド8選
ファストファッションの問題点
“着て捨てる”文化が生んだもの
ファストファッションの急成長は、環境や社会に大きな負担をかけています。
- 毎年、生産された衣類の5着中3着が焼却・埋立処分されている
- 繊維生産による温室効果ガスは年間12億トン(国際航空と海運を上回る規模)
- 一部の工場では、低賃金・劣悪な労働環境が続いている
- 安価な服は平均7回の着用で捨てられるとも言われている
こうした課題が若い世代を中心に意識され始め、Z世代やミレニアル世代は「持続可能なファッション」への関心を高めています。

ウルトラファストファッションの台頭
“1日1万点”というスピードの衝撃
ZARAが週単位で商品を投入し始めた1990年代から、さらに進化したのがSheinやTemuといった「ウルトラファストファッション」。
- Sheinは1日最大1万点の新商品を発表
- H&MやZARAよりも半額以下の価格帯
- 米国のZ世代を中心に爆発的な人気
その手軽さと安さは魅力的。でも「本当に必要?」と考えるきっかけにもなります。
サステナブルファッションへの道
“買わない選択”もひとつのスタイル
多くのブランドは2030年の脱炭素目標に遅れており、63%が設定した目標を達成できていません。ですが、進展していることもあります。
- 再生素材や代替素材の普及
- サプライチェーンの脱炭素化への取り組み
- 消費者の意識の変化
私たちが「安くて早い」ではなく「長く着たい」「大切にできる」を基準に選ぶこと。それがファッションの未来を変えていく第一歩になるのだと思います。
まとめ
ファストファッションは、気軽にトレンドを楽しめる素敵な仕組み。でも同時に、環境破壊や労働問題といった影の部分も抱えています。
「この服を選ぶことで、地球や誰かに優しい一歩になるかもしれない」
そんな風に思いながら服を選ぶことが、これからのサステナブルファッションにつながっていきます。
私たちの小さな選択が、未来の大きな変化をつくるのかもしれません。
【ハミングが届けるポジティブニュース】 身近な「米ぬか」がアメリカで大変身!木を切らずに家を彩る新素材とは?

米ぬかが海外でも大活躍しているって知っていますか?
日本では昔から身近な存在で、健康や美容にも使われる米ぬかですが、実はアメリカで大量に捨てられていた米ぬかが、環境を守るための新しい建築資材として生まれ変わっているんです。
普段は気に留めない身近な素材が、世界を救う一歩になっている驚きのストーリーをぜひご覧ください。
おすすめ記事 ▶ 【ハミングが届けるポジティブニュース】 今日も、誰かの優しさが世界を救っている──クレーン運転手が見せた奇跡の救出劇と心温まる贈り物
あの「米ぬか」が、海外で地球を救う素材に変身!
アメリカで毎年200億ポンド(約90万トン)ものお米が生産されている中、その外側を包む硬い「米ぬか(米殻)」は、これまで捨てられてきた大量の農業廃棄物でした。これが、ゴミの山になるだけでなく、環境への大きな負担になっていました。
そして今、最新技術でこの「米ぬか」を建築資材に再生利用する画期的なプロジェクトが進んでいます。アメリカの企業「Modern Mill」が開発した素材『ACRE(エーカー)』は、米ぬかをアップサイクルして作られた、まったく新しい外壁材です。
これがスゴイのは、単なるエコ素材なだけではなく、見た目も手触りも本物の木のように美しく、耐久性も抜群だということ。
“米ぬかを活用したエーカー素材は、デッキやフェンスなどにも使え、熱帯雨林伐採防止や廃棄物削減に貢献しながら、天然木のような強度と美しい色合いを持つ環境に優しい建材です。”
「木を切らずに、本物の木の美しさを」
このエーカーは、外壁以外にも、デッキやフェンスとして使えます。実際、積み荷1パレット分のエーカーを使えば、熱帯雨林の木材1エーカー分(1エーカーは約4,047平方メートルで、サッカー場より少し小さい区画分ほど)伐採を防げるという数字が出ています。2022年だけでも、44,000パレットがアメリカ中の住宅建築に使われ、約4,000トンの米ぬか廃棄物がゴミになるのを防いでいます。
日本人にとっては、身近な存在の米ぬかが海外でこんなに活躍しているなんて、なんだか嬉しいですね。
さらに、米ぬかの「リグニン」という木の主成分に似た成分のおかげで強度もあります。熱帯硬材のチーク(高級家具に使われる木)やアイペ(非常に硬く丈夫な熱帯の木)、そして杉のような上質な木材のような深みのある色合いも表現できるのは、自然素材ならではの魅力です。
価格も現実的で、火災に強い安心感
建築資材としての価格は、1平方フィートあたり10〜12米ドルほどで、無理なく導入できる範囲。しかも、カリフォルニア州の厳しい防火基準をクリアしているので、火災リスクの高い地域でも使える安全な素材です。
実際に、2025年に起きたカリフォルニアの大規模な山火事では、Modern Mill社は20世帯の被災者たちに無償でこのエーカーの外壁材を寄付し支援しました。企業として、環境貢献だけでなく、コミュニティの支援にも本気で取り組んでいるのです。
米ぬかは、ぬか床や入浴、肥料など、日本の暮らしに寄り添ってきた素材。素朴でありながら、体や環境にやさしい力を秘めています。いま世界でも注目される米ぬかを、私たちは昔から身近に使ってきました。その価値を改めて感じ、日々の暮らしに小さく取り入れてみるのもよいかもしれません。
睡眠不足は美容の敵?質を高める習慣

眠らない日本人への「Wake Up Call」
「寝る子は育つ」と昔から言われますが、大人にとっても質の良い睡眠は心身の健康を守る基本です。
それでも、夜11時を過ぎてもSNSをスクロールし続けたり、「6時間寝れば十分」と思って夜更かしをしていませんか?
研究によると、睡眠不足は健康リスクや美容への影響が深刻で、注意力や記憶力の低下はもちろん、うつ病や生活習慣病のリスクを高めることが分かっています。
また、慢性的な睡眠不足は肥満・糖尿病・心疾患・うつ病・認知症など、多くの病気のリスクを高めることもわかっています。
おすすめ記事 ▶ 瞑想をするのにベストな時間は?自分に合ったタイミングで、心と体を整えるヒント
睡眠不足がもたらす健康リスク
睡眠が不足すると、まず脳とメンタルに大きな影響が現れます。感情のコントロールを担う前頭前野がうまく働かなくなり、些細なことでイライラしたり、不安や過敏さが強まったりします。睡眠不足が続けば、うつ病や不安障害のリスクも高まり、相手の表情を正しく読み取る力まで低下してコミュニケーションに悪影響を及ぼすこともあります。
体に対しても影響は深刻です。睡眠時間が5時間以下の人は心疾患のリスクが50%も増加するとされ、免疫力は低下し、風邪をひきやすくなります。消化器系の不調や炎症性腸疾患が悪化することも珍しくありません。さらに、睡眠不足の時間が1時間増えるごとに糖尿病のリスクが9%高まるといわれ、ホルモンのバランスが乱れることで過食が進み、肥満の原因にもなります。
美容の面でも睡眠不足は大敵です。肌のハリやツヤが失われ、しわやたるみ、目の下のくまやシミが目立ちやすくなります。髪もパサつきやすく、顔全体の印象が「疲れている」「老けて見える」と感じられやすくなるのです。つまり、睡眠不足は「美容の最大の敵」と言っても過言ではありません。

女性が眠りにつきにくい理由
実は、女性は男性よりも睡眠不足になりやすいと言われています。その背景には、体のリズムやホルモンの変化、生活習慣の違いが関係しています。
- ホルモンバランスの変化
生理前や更年期にはエストロゲンとプロゲステロンの変動が起こり、眠りの質が低下しやすくなります。特にPMSの時期には、不眠や夜中の中途覚醒が増える女性も少なくありません。 - 妊娠・出産による影響
妊娠中は体調の変化や頻尿、出産後は赤ちゃんの授乳や夜泣きで、まとまった睡眠がとりにくくなります。 - 更年期と睡眠障害
更年期になるとホットフラッシュ(急なほてりや発汗)により夜中に目が覚めやすくなり、慢性的な不眠につながることもあります。 - 社会的な役割の多さ
家事や育児、仕事など「マルチタスク」を抱えることが多い女性は、心配ごとを抱えやすく、寝る前に考えごとが止まらなくなる傾向があります。
女性のための快眠のヒント
- 就寝前はスマホやPCを控え、リラックスできるルーティンを取り入れる
- ハーブティー(カモミールなど)で心を落ち着かせる
- 軽いストレッチや深呼吸で副交感神経を優位にする
- 生理や更年期の不眠は我慢せず、婦人科や睡眠外来に相談する
女性の睡眠不足は、美容やメンタルの不調に直結しやすいため、意識的にケアしていくことがとても大切です。
睡眠の質を改善する快眠習慣
眠りの質を上げるためには、環境づくりから意識してみましょう。寝室は暗く、静かで涼しい環境を心がけ、清潔な寝具で快適に休むことが基本です。毎日同じ時間に寝て起きるようにすると体内時計が整い、休日の「寝だめ」に頼る必要もなくなります。
就寝前のカフェインやアルコールは眠りを浅くする原因になるため、できるだけ控えましょう。日中にはウォーキングやヨガなど適度な運動を取り入れ、朝に太陽の光を浴びることで体内時計をリセットするのも効果的です。こうした小さな習慣の積み重ねが、深く質の高い眠りにつながります。
まとめ:睡眠は「最高の美容法」
「寝なくても大丈夫」と思っていても、睡眠不足による健康リスクは確実に積み重なっていきます。逆に、毎日の睡眠を優先するだけで免疫力は高まり、病気の予防やメンタルの安定、美肌効果といった大きなメリットを得ることができます。
特に女性はホルモンやライフステージによって睡眠が乱れやすいからこそ、快眠の工夫が欠かせません。眠ることは無料でできる最高の健康法であり、美容法でもあります。今日から、あなたの睡眠をもっと大切にしてみませんか?
エイジングケアの新常識:科学・心・美の調和で輝く「タイムレスビューティー」

年齢を重ねることは“失う”ことではなく、“積み重ね”
気づけば肌のハリが少しずつ薄れてきたり、鏡の中に新しいしわを見つけたりすることってありますよね。そんな瞬間に「もう若くないんだ」と感じてしまう方もいるかもしれません。でも本当は、年齢を重ねるということは「美しさが減ること」ではなく、「美しさのかたちが変わること」なんです。
若い頃にはなかった落ち着きや知恵、経験からにじみ出る自信。それこそが、エイジングの過程で手に入る新しい魅力です。この記事では、美肌を守る科学的アプローチと心を整えるマインドセット、そしてタイムレスな美しさを受け入れる考え方をご紹介します。あなたらしい「自然な若々しさ」を一緒に見つけていきましょう。
おすすめ記事 ▶ 40歳を目前に考える、限られた人生の過ごし方
美肌を保つための科学的アプローチ
年齢を重ねても健康で美しい肌を維持するためには、毎日のケアと必要に応じた美容施術を組み合わせることが大切です。
基本のスキンケア
- 紫外線対策:SPF30以上の日焼け止めが必須
- 保湿と角質ケア:乾燥対策と古い角質除去で透明感アップ
- レチノール:コラーゲン生成を促進し、しわ改善に効果的 → レチノールの使い方
先進的な美容成分
- 抗酸化ケア:ビタミンCや最新レチノイドで酸化ストレスから肌を守る
- 目元ケア:目元専用の美容液で小じわ・たるみを集中ケア
美容医療・エステの選択肢
- ボトックス注射:表情じわを和らげ、ナチュラルな若返り効果
- ヒアルロン酸注入:ヒアルロン酸などの注入で、口元や頬のボリュームを取り戻す治療
- レーザー治療:しみ・赤ら顔・小じわにアプローチ
- マイクロニードル&RF治療:肌の再生力を高める → マイクロニードル治療
科学的なアプローチは、正しい知識+信頼できる医師や製品選びがポイントです。
心のエイジングケア:年齢を受け入れるマインドセット

肌や外見に変化を感じたとき、つい落ち込んでしまうのは自然なこと。でも、そこで自分を責める必要はありません。心の持ち方を少しずつ変えていくことで、毎日の気分も大きく変わります。
- 「あっ」と思う瞬間を前向きに
新しいしわを見つけた瞬間を「老いのサイン」ではなく「経験の証」ととらえましょう。 - 本当の自分を隠さない
過度な若作りよりも、自分らしさを大切にすることが魅力につながります。 - 心の声を書き換える
「老けた」と責める声を「今の私も美しい」と優しい言葉に変える習慣を。 - 美の基準を更新する
若さだけが美しさではありません。40代、50代、60代…それぞれにふさわしい美しさがあります。
心のエイジングケアは、外見だけでなく 自己肯定感と生きる力 を育ててくれるものです。
タイムレスビューティーの本質
「アンチエイジング=若さを取り戻す」ではなく、「エイジングビューティー=年齢と共に輝く」へ。
しわやたるみはマイナスではなく、人生の笑顔や涙が刻んだ大切な証。美容医療やスキンケアは「時間を逆戻しするため」ではなく「今の自分をより美しく見せるため」に取り入れるものです。
本質的な美しさとは、
- 科学に裏付けられたスキンケア
- 適度な美容施術でのサポート
- そして「ありのままの自分」を受け入れる心
これらがバランスよく重なったときに生まれるものです。
アンチエイジングから「美しく年を重ねる」へ
年齢を重ねることは、けっして恐れることではありません。それは、経験や知恵、自分らしさが積み重なっていくこと。エイジングケアを通じて肌を整え、心を解放すれば、年を重ねるごとにあなたの魅力は深まっていきます。
「若さ」を追いかけるのではなく、「今の自分」を慈しむ。
そのとき、あなたは 年齢と共に輝くタイムレスビューティー を手に入れるのです。
妊娠中のセルフケアと健康管理で安心なマタニティライフを

妊娠中は、自分の体を整えることが赤ちゃんの健康につながります。そのためには妊娠中のセルフケアと健康管理を意識することがとても大切です。
バランスの良い食事や十分な休養、適度な運動に加えて、定期的な妊婦健診を受けることが安心して出産を迎えるための基本です。また、つわり・むくみ・便秘など妊娠特有の不調も、正しいセルフケアを取り入れることで軽減できます。
葉酸の摂取や体重管理、感染症対策など、日々の生活の中でできる小さな工夫が大きな安心につながります。医師と相談しながら、自分に合った健康管理を続けていきましょう。
おすすめ記事 ▶ 流産を経験した大切な人をどう支えるか
妊娠中に大切なセルフケアと健康管理とは
妊娠中は、自分の体を大切にすることが赤ちゃんの健康にも直結します。そのために欠かせないのがセルフケアと健康管理です。妊婦健診を受けることで、妊娠の経過を確認しながら安心して過ごせます。また、体重管理や栄養バランスを整えることは、妊娠中の不調を防ぎ、出産準備にもつながります。
妊婦健診の重要性と通院スケジュール
妊娠が分かったら、できるだけ早く医師の診察を受けましょう。妊娠初期は4週間ごと、7〜8か月は2週間ごと、臨月は毎週健診があります。血圧や体重、胎児の心音や子宮の大きさを定期的にチェックすることで、異常を早期に発見できます。
体重管理と栄養バランスの考え方
妊娠中の体重増加は個人差がありますが、一般的には10〜13kgが目安です。急激な体重増加は妊娠高血圧症候群のリスクを高めるため、医師と相談しながら管理しましょう。

妊娠中の食事と生活習慣
バランスの取れた食生活は、妊娠中の健康管理に欠かせません。特に葉酸、鉄分、カルシウムは赤ちゃんの発育に必要不可欠です。
妊娠中に避けるべき食べ物と飲み物
生肉・生魚・加熱不足の卵は食中毒のリスクがあります。また、水銀を多く含む魚(サメ、メカジキなど)は控えましょう。アルコールや過剰なカフェインも避けるべきです。
葉酸・カルシウム・鉄分など必須栄養素
葉酸は胎児の脳や神経の発達を助ける栄養素です。サプリメントでの摂取も推奨されています。牛乳や小魚、野菜などを取り入れて、カルシウムや鉄分もバランスよく補いましょう。
妊娠中の運動と休養
適度な運動は妊娠中のセルフケアに役立ちます。ウォーキングやスイミングなど、体に負担をかけない運動がおすすめです。
安全にできる運動(ウォーキング・スイミングなど)
毎日30分程度の軽い運動は、血流を良くし、便秘やむくみの改善にもつながります。激しい運動や転倒のリスクがあるスポーツは避けましょう。
睡眠とリラックスのための工夫
妊娠中はホルモンの影響で眠りが浅くなりやすいです。クッションを活用して横向きで寝ると、リラックスして休めます。
妊娠中によくある不調とセルフケア方法
妊娠中はつわり、便秘、むくみ、気分の浮き沈みなど、さまざまな不調が起こります。
つわり・便秘・むくみの改善法
つわりには少量の食事をこまめに摂ることが有効です。便秘には水分補給と食物繊維、むくみには軽い運動と足を高くして休むことが効果的です。
気分の浮き沈みやホルモン変化への対応
ホルモン変化で気分が不安定になることがあります。パートナーや周囲に気持ちを共有し、必要に応じて専門家に相談しましょう。

妊娠中に避けたい習慣とリスク管理
妊娠中は赤ちゃんを守るために、避けるべき習慣があります。
タバコ・薬物・アルコールの影響
喫煙やアルコールは流産や低体重児、先天性障害のリスクを高めます。薬物はさらに危険で、赤ちゃんに深刻な影響を与えます。
感染症予防と日常生活での注意点
猫のトイレ掃除や生肉の摂取はトキソプラズマ感染の原因となるため避けましょう。手洗いやうがいなど、日常的な衛生管理も大切です。
妊娠中のセルフケアで快適なマタニティライフを
妊娠中の健康管理は、赤ちゃんと自分のための大切な習慣です。医師と相談しながら、日々のセルフケアを積み重ねることで安心して出産を迎えることができます。
医師との相談で安心をプラス
気になる症状や不安があれば、早めに医師に相談しましょう。
毎日の小さな積み重ねが赤ちゃんの健康につながる
バランスの取れた生活を続けることが、母子の健康を守る最良の方法です。
まとめ
妊娠中は、体も心も大きく変化する大切な時期。だからこそ、無理をせず、自分のペースでセルフケアと健康管理を続けていくことが何よりも大切です。小さな積み重ねが、赤ちゃんと自分自身の安心につながります。
毎日の生活の中でできることから始めてみてくださいね。そして、不安や気になることがあれば、ひとりで抱え込まずに、ぜひ医師や周囲の人に相談してみましょう。
安心して笑顔でマタニティライフを楽しめるように、今日からできるケアを一歩ずつ取り入れていきましょう。
頑張りすぎた1人目、肩の力が抜けた2人目。産後に気づいた“自分を大切にする”こと

1人目の産後は、とにかく子どものことを最優先にしていました。「子どもが起きている間は全力で向き合う」「寝ている間に家事をしないと」と、自分でたくさんのルールを作り、身体も心も休まる暇がありませんでした。
その結果、疲れがたまって子どもにイライラしたり、飲み会に出かける夫に不満をぶつけてしまったり。今思えば、自分を追い込みすぎていたのだと思います。
2人目の時は、1人目のときよりも気持ちに余裕があったのか、自然と自分にも意識を向けられるようになりました。子どもへの愛情はもちろん変わらないけれど、「自分の時間も大切にしていい」と思えるようになったんです。
子どもが寝ている時間は家事ではなく、自分のやりたいことをする。そうやって自分を満たすことで、心に余裕を持てるようになりました。
ここからは、私が子育てをする前に知っておきたかった4つのことを紹介します。
おすすめ記事 ▶ まずは自分を大切に。子育てには”Boundary(境界線)”が必要?! 【Editor’s Letter vol.09】
子育てを少しラクにするために伝えたい4つのこと
1. 子どもが寝ている間は全力で自分時間
1人目を育児中の私は、「子どもが起きている時は全力で子どもと向き合う」「子どものお昼寝中は家事の時間」と思い込んでいました。夜は頻回授乳でクタクタなのに、お昼寝の時間に一緒に休むこともせず、産後の体に鞭を打つように無理をしていた気がします。
無理を続けた結果どうなったかというと……我が家の場合、夫婦喧嘩が増えました。夫が一人で自由に過ごす時間を見て「ずるい」と思うようになり、イライラが募ってしまったのです。
でも今振り返ると、洗濯物が多少溜まっていても、床におもちゃが転がっていても、疲れた時はベビーフードに頼っても、全然いいんですよね。完璧じゃなくても子どもは育ちます。
2人目の育児では、思い切って「子どもが寝ている間は全力で自分時間」と割り切ることにしました。お茶を飲みながら本を読んだり、ブログを書いたり。自分の時間を確保することで、肩の力を抜いて子どもと向き合えるようになりました。
2. 誰かに頼ることは“信頼の証”
私はもともと「人にお願いする」のが苦手です。
「迷惑かな」「負担になるかな」と考えすぎて、つい遠慮してしまう。だから子育て中も、夫や親、仲良しのママ友にさえ気軽に頼むことができませんでした。お願いできたのは、本当に大事な用事があるときや、自分が体調不良でベッドから起き上がれないときだけ。38度の熱があっても、起きられるなら葛根湯を飲んで無理して動いてきました。
そんな私に転機があったのは、熱を出して娘を習い事に送れなかった日のこと。ママ友が気づいて声をかけてくれ、事情を話すと「そういう時はいつでも言ってね。一緒に送っていくよ。その方が娘ちゃんも喜ぶし」とさらりと言ってくれたのです。その優しさに、胸がじんわり温かくなりました。
そのとき気づいたのは、「頼ることは悪いことじゃない。むしろ信頼の証なんだ」ということ。よく考えれば、私自身も誰かに頼られると嬉しいし、「助けたい」と思います。だからもっと周りを頼っても大丈夫。もちろん相手が困っているときは、私も頼られる存在でありたい。今はそう思えるようになりました。

3. そのルール、本当に子どものため?
初めての育児の時、今思えば必要のないマイルールにがんじがらめになっていました。
「子どもは19時までに寝かせなければ」
「できるだけ手作りのご飯を用意しなければ」
「午前中は児童館に連れて行かないと」
などなど、自分で作ったルールを守ることに必死になり、気づけば時間に追われて心の余裕がなくなることも多かったです。
でもそのルールは一体誰のためのものだったのか?本当に子どもにとって必要だったのか?今になって振り返ると疑問だらけです。多少寝るのが遅くても翌日ゆっくり過ごせば良いし、手作りご飯が作れない日があっても子どもは元気に育つ。児童館に行けなくても、家で一緒に笑って遊べたらそれで十分。
大切なのは「子どもが元気で、家族が笑顔でいられること」。多少ルールが崩れても大きな問題は起こりません。もっと柔軟に考えて、自分に優しくしてあげればよかったと感じています。
4. 子どもと一緒に早寝して、朝の時間を充実させる
1人目の時、寝かしつけは私にとって一番つらい時間でした。
「子どもが寝たら家事をしよう」「あれも片付けなきゃ」と思えば思うほど、なかなか寝ない子どもにイライラ。小さな声で「早く寝ろよ」なんてつぶやいてしまったこともあります。やっと寝た!と思っても、ベッドを抜け出すと「まま〜」と呼ばれて振り出しに戻ることもしばしば。寝かしつけ=動けない不毛なストレスの時間でした。
でも2人目を産んでからは、子どもと一緒に寝てしまうスタイルに切り替えました。そうすると「早く寝てほしい」と焦る気持ちが減り、イライラもしなくなりました。むしろ私の方が先に寝てしまうこともあるくらい。
子どもと一緒に早寝した分、自然と朝5時には目が覚めるようになり、その時間を「朝活」として自分のやりたいことに使えるようになりました。静かな早朝に好きなことをする習慣は、ストレスを減らすだけでなく、自分時間を充実させる大きな助けになっています。
「子ども」も「自分」も、大切に
初めての妊娠・出産は、わからないことだらけ。だからこそ「ちゃんとしなきゃ」「母親だから頑張らなきゃ」と思いすぎてしまう人も多いのではないでしょうか。私自身も1人目のときはそうでした。
でも実際は、家事が少しくらい滞っても大丈夫。誰かに頼っても大丈夫。母親が少し肩の力を抜いて、自分の時間を大切にすることで、子どもとの時間もより心地よいものになるのだと実感しました。
「子どもを大事にすること」と「自分を大事にすること」、その両方があるからこそ、笑顔で子育てができる。産後すぐのママはもちろん、子育てに奮闘するすべてのお母さんに、この思いが届けば嬉しいです。
女性に多い自閉症の特徴とは?診断が遅れる理由とセルフケア

「昔から人との関わりが疲れる」「周囲には普通に見えるけれど、自分の中では混乱している」――こうした感覚を持つ女性の中には、実は自閉症スペクトラム(ASD)の特徴を持つ人が少なくありません。
しかし、研究によると女性は男性に比べて診断が遅れやすく、多くの人が大人になってから初めて自分の特性に気づくこともあります。ここでは、専門家の意見をもとに 「女性の自閉症の特徴」 と 「診断が遅れる背景」、そして 「自分らしく生きるためのセルフケア」 を解説します。
おすすめ記事 ▶ ラディカルアクセプタンスを受け入れる方法|変えられないことを受け入れる
自閉症とは?
自閉症(ASD)は「脳が世界を処理する仕組みが一般とは少し違う状態」。病気や欠陥ではなく、神経の多様性(ニューロダイバーシティ) のひとつと考えられています。
社会的なコミュニケーションの違い、感覚過敏、こだわりの強さなどが特徴ですが、女性の場合は「外からは見えにくい」ことが多いのです。
女性に見られやすい自閉症の特徴
女性や女の子は、男性や男の子に比べて自閉症の現れ方が異なることが多くあります。そのため 「見過ごされやすい」 のです。
よく見られる特徴
- 周囲に合わせるために、特徴を隠しがちで、疲れやすい
- 社交的に見えても内心は強い不安や混乱を抱えている
- 動物や本、音楽、美術など「社会的に受け入れられやすい特別な興味」を持つ
- 小さな音や光、食感などに敏感で、感覚過敏を「わがまま」「神経質」と誤解されやすい
- 日常のルーティンや予測可能性を強く求める
- 人間関係で断ることができず、燃え尽きやすい
なぜ女性は診断が遅れるのか?
研究によると、女性は男性より平均6年も診断が遅れることが分かっています。
その理由のひとつは、診断基準が主に「男性の典型的な特徴」に基づいて作られてきたから。そしてもうひとつは、女性が「人に合わせること」「良い子でいること」を社会的に求められ、本音を話しにくいからです。

診断を受けることの意味
診断はゴールではなく、自己理解の大きな手がかりです。
- 「本来の自分を隠さなくてもいい」と思える
- 生きづらさの理由が分かり、自己への思いやりが持てる
- 自分に合った環境や支援を見つけやすくなる
- コミュニティや仲間とつながれる
逆に診断されないまま大人になると、慢性的なストレスや燃え尽き、心身の不調を抱えやすくなります。
自閉症の女性に役立つセルフケア
- 本音を隠すことをできるだけ減らし、自分らしい振る舞いをする
- 感覚過敏に合わせた環境(ノイズキャンセリング、柔らかい素材の衣服など)を整える
- 予定や会話をあらかじめ準備し、不安を軽減する
- 自閉症女性のコミュニティや支援ネットワークに参加する
- セラピーを受ける場合は、多様性を肯定する専門家を選ぶ
こうした工夫は小さなことに見えても、毎日のストレスを大きく減らしてくれます。
まとめ|女性の自閉症理解が広がる未来へ
女性における自閉症は、まだまだ理解が進んでいません。ですが、研究や当事者の声が少しずつ広がり、「女性のASD」 への認知は確実に高まっています。
「診断される・されない」に関わらず、自分の特性を理解し、自分に優しい方法で暮らすこと が、何よりも大切なのだと思います。
何歳になっても夢をあきらめないーープロのダンサーが香港ディズニーで見つけた、年齢に関係なく挑戦し続ける秘訣【ダンサー松浦希実さんインタビュー】

香港ディズニーランドのステージで観客を楽しませる日本人ダンサー、松浦希実さん。幼い頃からダンスに夢中になり、東京のテーマパークで経験を積み、単身ニューヨークへ渡った彼女が、今は異国・香港で8年間舞台に立ち続けています。
夢を追いかける過程での葛藤や挫折、プロとしての覚悟、さんの情熱の源とは?年齢や環境に関わらず挑戦し続けることができる秘訣や、毎日を大切に生きるヒントをお聞きしました。
おすすめ記事 ▶ 心の痛みを抱えるあなたに、犬が教えてくれること【アメリカのドッグセラピスト、モニカ・キャラハンさんインタビュー】
_______________________________________________________________________________________
ーー 香港ディズニーランドでは、具体的にどんなお仕事をしているのですか?
パフォーマンスを通じて、ディズニーランドに来園したお客様が、まるで自分もディズニーの世界に入り込んだように感じられるお手伝いをしています。私が今出演している「ミッキー・アンド・ザ・ワンダラス・ブック」というショーは、香港ディズニーランドの中でも特に人気の高いショーの一つです。このショーでは、香港、フィリピン、タイ、台湾、中国、そして欧米、オーストラリア、アメリカ、イギリス、パキスタンなど、たくさんの国から集まったメンバーと一緒にステージを作り上げています。
ーー 小さい頃からダンサーを目指していたんですか?
小さい頃にバレエを始めて、その頃はバレリーナになるのが夢でした。でも、うまくいかないことも多く、だんだんと「私にはバレリーナは向いてないんじゃないかな」と思うようになっていた頃にミュージカルに出会いました。ミュージカルの専門学校で3年間、芝居や歌、ダンスを勉強し、卒業後、いろんなオーディションを受けて事務所が決まりました。
東京ではオーディションに合格して、東京のテーマパークでダンサーとして活動することになったんです。
“東京で8年間ショーやパレードに出演した後にダンスへの情熱を再燃させ、憧れのブロードウェイダンサーたちと同じレッスンを受けながら交流するという、刺激的で忘れられない体験をニューヨークで手にしました。”
ーー そして、ニューヨークから香港へ?
せっかく時間もお金もかけて、ニューヨークでダンスレッスンを受けたり、50本以上のショーを見てきたので、その経験を活かして、日本ではない違う国で英語を使って働いてみたい、踊ってみたいと思うようになりました。
留学期間が終わりに差し掛かったとき、インターネットでオーディション情報を調べていたら、ちょうど帰国する翌日に、香港ディズニーランドのオーディションがあるのを見つけたんです。この機会を逃したら、もう香港へ行く機会はないかもしれないと思って、その場で飛行機のチケットを取りました。ニューヨークから成田、そして翌日に成田から香港へ弾丸で飛んで、オーディションを受けて帰国しました。

ーー ディズニーのダンサーという華やかな世界の裏には、大変なこともたくさんあると思います。これまでで一番大変だったことは何ですか?
一番大変だったのは、やっぱり言葉の壁ですね。言いたいことが伝わらなかったり、逆に相手の言っていることのニュアンスがうまく掴めなかったり…。翻訳機を使ったり、言葉なしでも伝わるように努力したりと、コミュニケーションには苦労しましたね。
そして、もう一つ、日本人特有の「言わなくてもわかるだろう」という感覚は、海外では通用しないと痛感しました。私は伝わっていると思って言わなかったことが、後々トラブルになることもあります。相手からは「言ってなかったじゃないか」と。こっちは「言わなくてもわかるだろう」と思っていたりするんですよね。
でも、そういう経験をして、「思っていることは口に出して伝える」ことの重要性を学びました。遠慮して言わない方がいいかなと思うことも、言った方がいいんだなっていうふうに、だんだん考え方が変わっていきましたね。
ーーダンサーとして大変だったことは?
若い時は、オーディションで悔しい思いをすることも多々ありました。ダンススキルだけじゃなく、スタイルや身長といった外見的な理由で落ちてしまうこともあったので、若い頃はダイエットを頑張ったり、鏡の前でどうしたら自分の体を一番きれいに見せられるかを研究したりしていました。
あとは、自分の実力が足りないと感じることも多かったですね。それを補うために、どうしたらオーディションに受かるだろうと考えて、「人とは違う表現をする」ことを心がけました。ただ振りを正確に踊るだけではなく、表情や表現の仕方で差をつけるように。そして、審査員側が今どんなキャラクターや踊りを求めているのかをいち早くキャッチして、自分がその役にどう入り込めるかを考えながら、一つひとつの壁を乗り越えてきました。
ーーダンサーというお仕事の一番のやりがいは?
一番のやりがいは、やっぱりお客さんの楽しそうな顔を見ることです。ステージ上からもお客さんの表情はよく見えます。特に子どもたちが笑顔でショーを楽しんでくれているのを見ると、「やっていてよかったな」と心から思います。
パレードのように、お客さんとの距離が近いパフォーマンスの時もやりがいを感じますが、今踊っているショーのように、ステージと客席が離れていても、お客さんの反応を感じられるのがすごく嬉しいですね。
あとは、才能あふれる世界中のパフォーマーたちと一緒に仕事ができることも、大きなやりがいです。みんなでウォームアップをしたり、互いの得意なダンスを教え合ったりと、毎日が刺激の連続です。ライバルではなく、一つのチームとしてお互いを高め合っていると感じます。
“現役ダンサーとしてのキャリアに一区切りをつけつつ、子どもたちにダンスを教えたり舞台づくりの裏方として関わったりしながら、踊る喜びと日々の尊さへの感謝を胸に、次世代とともにエンターテインメントを育んでいきたい”
ーー 40代のダンサーとして、体力の維持やモチベーションアップのために工夫していることは?
若い頃はあまり真剣に取り組んでいなかったのですが、やはりこの歳になるとストレッチやコアトレーニングの重要性を強く感じています。最近はショーの練習とは別に、ピラティスやダンベルを使ったトレーニングもするようになりました。
そして何より、体を休めることが大切です。体の回復に時間がかかるようになったので、睡眠時間は最低でも7時間は取るように心がけています。寝る前に足をマッサージしたり、体のケアをしっかりするようにしています。
ーー今年40歳になったばかりの希実さん。今後のキャリアはどう考えていますか?
現役ダンサーとしての活動は、そろそろ一区切りかなと考えています。でも、エンターテインメントへの情熱は変わらず、これからも何らかの形で関わり続けたいです。具体的には、子どもたちにダンスを教えることで次世代を育てたり、裏方としてショー作りに携わったりするなど、舞台の魅力を支える側でも力を発揮できればと思っています。現場で踊るだけでなく、創る側としてもエンターテインメントに貢献していけたらうれしいです。
ちょうど昨日、知り合いに頼まれて久しぶりに子どもたちのレッスンをやったんです。日本にいた頃は、母校の昭和音大付属バレエ教室でミュージカルの講師として教えていた経験もあります。久しぶりだったので、子どもたちと一緒に踊る楽しさやワクワク感を改めて思い出しました。やっぱり、彼らと一緒に体を動かす時間ってすごく特別で、教える喜びが大きいんです。だからこれからは、子どもたちにダンスを教えるクラスもどんどん再開して、彼らと一緒に成長していけたらいいなと思っています。

ステージ右の手前で踊る希実さん
ーー希実さんが「40歳からの人生でいちばん大切にしていること」は何ですか?
若い頃は毎日が当たり前だと思っていましたが、年を重ねると、踊れることも日常の時間も決して当たり前ではないと感じるようになりました。だからこそ、一日一日を大切に過ごし、今この生活ができていることに感謝しながら生きていきたいです。若い頃には気づけなかった日々のありがたさや、瞬間を大切にすることの大切さを、今はしっかり感じていますね。
ーー何かを始めたいけど迷っている同じ年代の女性へのメッセージはありますか?
年齢を重ねてから何かを始めるのは、不安を感じる方も多いと思います。私も30代でダンス留学をした時、「もう遅すぎるんじゃないか」と迷ったことがありました。でも、実際に行動してみると、それが香港で働くきっかけになったように、何歳からでも遅すぎることはないと身をもって感じました。
迷った時こそ、思い切って行動してみることが大切だと感じます。そして、もう一つ大事なのが、やりたいことや興味があることを恥ずかしがらずに周りに話してみること。
私も最初は恥ずかしくて言えなかったのですが、勇気を出して話してみると、周りの人が応援してくれたり、「それならこんな方法もあるよ」とアドバイスをくれたり、思いがけない情報をもらうことができました。
そうやって誰かに話すことで、物事が良い方向に進んだり、新しいチャンスにつながったりする経験をたくさんしてきました。もし今、一歩踏み出せずにいるなら、まずはその気持ちを誰かに話してみることから始めてみませんか。

プロフィール:松浦希実(まつうらのぞみ)
幼少よりバレエをはじめ昭和音楽芸術学院にてミュージカルの基礎学ぶ
卒業後は東宝芸能に所属しイベントや舞台等に出演、出演の傍ら昭和音楽大学附属バレエ音楽教室にてミュージカルダンス講師を務める
2009〜2017年東京某テーマパークにてショーやパレードに出演
退園後ニューヨークのブロードウェイダンスセンターBDCにダンス留学
2018年より現在、香港ディズニーランドのシアターショー”Mickey and the Wondrous Book”に出演中
大人肌におすすめのクリーンメイク|肌に優しいナチュラルコスメで美しく

「昔と同じメイクなのに、なんだかしっくりこない」
「ファンデーションがシワに入り込みやすい」
40代・50代を迎えると、肌の質感やトーンが変化し、従来のメイクでは満足できなくなる方も多いのではないでしょうか。そこで注目したいのが クリーンメイク。
化学成分を極力控え、肌や環境に優しい成分で作られたコスメは、大人肌に自然なツヤと透明感を与え、健康的で若々しい印象を叶えてくれます。
おすすめ記事 ▶ エプソムソルトでバスタイムにスキンケア|おすすめの商品を紹介
クリーンメイクとは?
クリーンメイクとは、肌に負担をかける成分を避け、ナチュラルで安全性の高い成分を使用したコスメで仕上げるメイク方法 のこと。
一般的な特徴は:
- パラベンやシリコンなどの合成添加物を使わない
- オーガニック・植物由来の成分を使用
- 動物実験を行わない
- 環境に配慮したサステナブルな製品
敏感になりやすい大人肌にとっても安心できる選択肢です。
Hummingおすすめのクリーンメイクアイテム
40代・50代から気になる肌悩み。厚塗りで隠すよりも、肌に優しいクリーンメイクを取り入れることで、ナチュラルに美しさを引き出すのがおすすめです。ここでは、大人肌にもぴったりな人気クリーンメイクブランドを6つご紹介します。
1. ILIA(イリア)|スキンケア発想のミニマルメイク
おすすめ:リップオイル、セラムスキンティント
特徴:パラベン・鉱物油・タルク不使用、ナチュラル成分処方
価格帯:$24〜$46

ILIAは「スキンケアベースのクリーンメイク」として注目されているブランド。
マルチユースのクリームやスティックは、肌に優しい成分で作られ、大人肌にもなじみやすい軽い使用感が魅力です。多くの商品にはナチュラルSPFが配合されており、美肌ケアと紫外線対策を同時に叶えるクリーンコスメ。ファンデーションセラムやマルチスティックは、大人のナチュラルメイクに最適です。
2. BOOM!(ブーム)|世代を超えて使えるプロエイジングメイク
https://boombeauty.com/
おすすめ:マルチユーススティック、リップグロス
特徴:エシカル&オーガニック成分を可能な限り使用
価格帯:$24〜$27

メイクアップアーティストでありスーパーモデルのCindy Josephが立ち上げたプロエイジングブランド。
中でも人気の「BOOMSTICK TRIO」は、顔・唇・体などにマルチに使える万能アイテム。40代・50代の大人肌メイクにもフィットし、自然なツヤ感を演出してくれます。
3. RMS Beauty(RMS ビューティー)|自然なツヤ肌を叶える定番クリーンコスメ
https://www.rmsbeauty.com/
おすすめ:ファンデーション&コンシーラー
特徴:オーガニック成分、ナノ粒子不使用、パラベン・フタル酸・硫酸塩フリー
価格帯:$25〜$58

世界的メイクアップアーティストRose-Marie Swiftによって立ち上げられたクリーンメイクの先駆け。 特に「Un Cover-Up コンシーラー」は、厚塗り感のないナチュラルな仕上がりで、エイジングケア世代の肌にもぴったり。
AllureやVogueでも取り上げられる実力派で、大人肌のツヤと透明感を引き出すクリーンメイクブランドです。
4. Saie(サイ)|スキンケアとメイクの融合
おすすめ:肌を整えるファンデーション&グロウ系アイテム
特徴:ホホバオイル、シアバター、ビタミンEなどのナチュラル成分配合
価格帯:$16〜$99
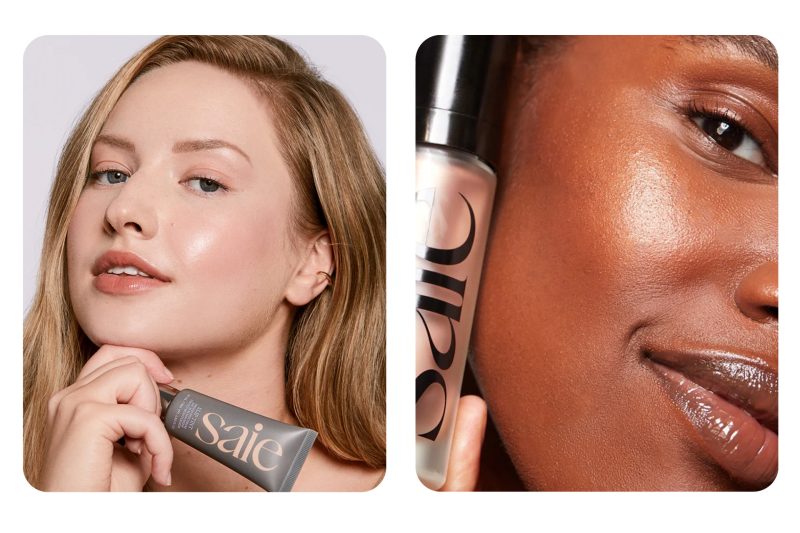
Saieは「クリーン×ラグジュアリー」をテーマに、高性能で肌に優しい処方を実現。Climate Neutral認証やLeaping Bunny認証を取得しており、環境と動物にも配慮しています。
素肌感を引き出す“セカンドスキン”のようなツヤ肌仕上げが、大人女性に人気です。
5. Adorn Cosmetics(アドーンコスメティクス)|エシカルなアイメイクブランド
https://www.adorncosmetics.com.au/
おすすめ:アイメイク製品(アイシャドウ・マスカラ)
特徴:PFASやパラベン不使用、オーガニック成分を可能な限り使用
価格帯:$5〜$72
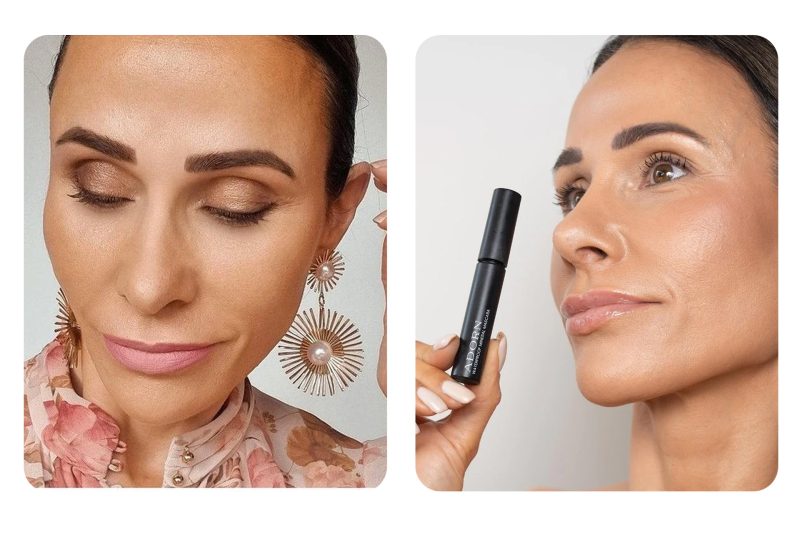
オーストラリア発のAdornは、ラグジュアリーとサステナブルを両立したブランド。環境にやさしい詰め替え用パックを導入し、数千個の容器を廃棄から救っています。
エシカルに製造されたクリーンアイメイクで、大人女性の目元を華やかに彩ります。
6. Gressa Skin(グレッサスキン)|植物オイル配合のスキンケア発想メイク
https://www.gressaskin.com/
おすすめ:美容液ファンデーション、ブロンザー
特徴:ローズヒップオイル、カレンデュラ、カモミールオイル配合
価格帯:$41〜$98
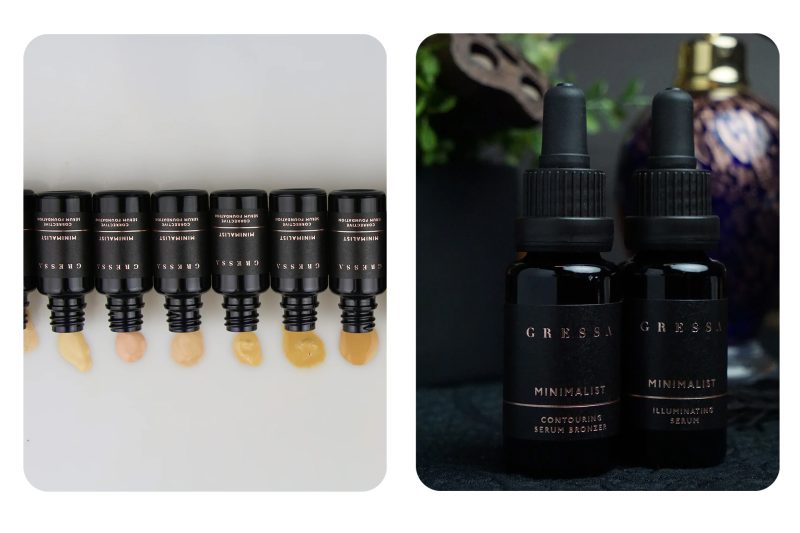
Gressaは、スキンケア効果の高いクリーンコスメとして人気。植物エキスを贅沢に配合し、くすみや乾燥が気になる大人肌を明るくなめらかに整えます。
スキンケアラインも展開しており、メイクと同時に肌をいたわりたい方におすすめ。
まとめ|大人肌こそ「肌に優しいメイク」を
クリーンメイクは、ただのトレンドではなく 肌・健康・環境を守る新しいビューティーの基準。
大人肌の悩みを自然にカバーしながら、素肌を生かした美しさを引き出してくれます。
今日からあなたも、肌に優しいクリーンコスメを取り入れて、ナチュラルで上品な大人の美しさを楽しんでみませんか?
コラーゲンとは?減少の原因と増やす方法を徹底解説|美肌を守る食べ物と習慣

「昔より肌のハリがなくなった気がする」「シワやたるみが気になる」
そんな悩みの原因のひとつが コラーゲンの減少 です。
コラーゲンは肌の弾力を保ち、若々しい見た目を支える大切なタンパク質。年齢とともに減ってしまいますが、食事や生活習慣を工夫することで減少をゆるやかにし、美しい肌をキープすることができます。
ここでは、美容に欠かせないコラーゲンの基礎知識と、増やす方法をご紹介します。
おすすめ記事 ▶ 代謝の健康状態とは?医師が解説
コラーゲンとは?体に欠かせない理由
コラーゲンは体の中で最も豊富に存在するタンパク質で、肌、髪、爪、関節などを支える「接着剤」のような役割を持っています。
- 美肌効果:肌の弾力やハリを保つ
- シワ・たるみ予防:真皮を支え、小じわやほうれい線を軽減
- 傷の修復:細胞の再生を助ける
- 髪や爪の健康:ツヤや強さをサポート
美容だけでなく、健康にも深く関わっているのがコラーゲンです。
コラーゲンが減少する原因
コラーゲンは20代半ばをピークに減少が始まり、特に40代以降は加速します。
主な原因は以下の通り:
- 加齢(エストロゲンの変化による影響)
- 過剰な糖分(糖化現象によりコラーゲンが破壊される)
- アルコールの飲みすぎ
- タンパク質不足
- ビタミンC・銅・亜鉛不足
- 睡眠不足・慢性的なストレス
特に糖の摂りすぎは「肌の弾力を失う大敵」なので要注意です。

コラーゲンを増やすための食べ物
コラーゲンを直接含む食品
- ボーンブロス(骨スープ)
- 魚の皮(低水銀・天然のものがおすすめ)
- グラスフェッドビーフ(牧草牛)
コラーゲン生成を助ける栄養素
- ビタミンC:パプリカ、キウイ、柑橘類、ブロッコリー、ベリー類
- 銅・亜鉛:豆類、ナッツ、種子類
- アミノ酸(グリシン・プロリン):肉、卵
特にビタミンCは「美肌ビタミン」。
体内でのコラーゲン生成を助けるだけでなく、シミやくすみ対策にも役立ちます。
美容のためのライフスタイル習慣
コラーゲンを守るために、次の習慣を心がけましょう。
- 糖質や加工食品を控える
- 良質な睡眠をとる
- ストレスをためない
- 紫外線対策をする(日焼け止め+ビタミンC美容液)
- 適度な運動で血行促進
内側からのケアと外側からのスキンケアを組み合わせることで、より効果的に美肌を維持できます。
まとめ|美肌は日々の積み重ねから
コラーゲンは年齢とともに減少してしまいますが、食べ物や生活習慣を工夫することで“10歳若い肌”を保つことも夢ではありません。
- コラーゲンを多く含む食品をとる
- ビタミンCを食事・サプリ・美容液で意識的に取り入れる
- 糖やアルコールを控え、睡眠・ストレスケアを大切にする
今日からの小さな積み重ねが、未来の美肌をつくります。
あなたも毎日の食事とケアで、若々しいハリ肌を目指しましょう。
女性特有の腸内環境の乱れ|原因と改善のための腸活ガイド

最近、なんとなく「お腹の調子が安定しない」「肌が荒れやすい」「気分の浮き沈みが激しい」と感じることはありませんか? その不調、実は 腸内環境の乱れ が原因かもしれません。特に女性は、月経や妊娠・出産、更年期といったホルモンの変化によって腸内環境が揺れやすい傾向があります。腸は消化だけでなく、ホルモン・免疫・心の健康にも深く関わっているからこそ、日常の小さな不調サインを見逃さないことが大切です。
女性に多い腸内環境の乱れ
「腸内環境 乱れ 原因」を調べてみると、食生活やストレスといった一般的な要因が多く挙げられます。しかし、女性の場合はさらに ホルモンの変動 が大きく関わってきます。
女性の腸は、月経周期・妊娠・産後・更年期といったライフイベントによって常に影響を受けており、これが男性と比べて腸内環境が乱れやすい理由のひとつです。
おすすめ記事 ▶ 本当に”体に良い食事”のレシピはSNSではなく、あなたの中にある
腸内環境 乱れ 原因【女性特有の要因】
月経周期によるホルモン変動
- エストロゲンやプロゲステロンの変化は腸の蠕動運動に影響し、便秘や下痢が起こりやすくなります。
- PMS症状の一部として腸の不調を感じる女性も少なくありません。
妊娠・産後の影響
- 妊娠中はホルモンの変化により便秘や胃腸の不快感が増加。
- 出産後はホルモンバランスが大きく揺れ動き、腸内フローラのバランスも乱れやすくなります。
更年期とエストロゲンの低下
- 更年期に入るとエストロゲンが急激に減少し、腸内細菌の多様性が失われがち。
- その結果、腸内環境の乱れだけでなく、肌荒れや気分の落ち込みなど全身症状に広がります。

腸内環境の乱れが引き起こす女性の不調
- 慢性的な便秘・下痢
- PMSや月経痛の悪化
- 肌荒れ(ニキビ・湿疹・乾燥)
- 不眠や疲労感
- 気分の落ち込み・不安感
- 更年期症状の悪化(ホットフラッシュ・イライラ)
これらの不調は単なる「胃腸の問題」ではなく、腸とホルモン、免疫が深くつながっているサインです。
女性の腸内環境を整えるための改善ポイント
ホルモンを意識した食事
- 発酵食品(納豆、ヨーグルト、キムチ)で善玉菌を増やす
- 食物繊維(野菜、果物、海藻、豆類)で腸のリズムを整える
- オメガ3脂肪酸(青魚・亜麻仁油)で炎症を抑える
ライフステージに合った腸活
- 月経前後:温かい飲み物や消化に良い食事で腸をサポート
- 妊娠中:便秘対策に水分・食物繊維を意識
- 更年期:カルシウム・マグネシウム・ビタミンDを補給し腸と骨の両方をケア
生活習慣の見直し
- 睡眠の質を高めて自律神経を整える
- 適度な運動(ヨガ・ウォーキング)で腸の動きを活発にする
- ストレスケア(瞑想・呼吸法)でホルモンと腸のバランスを保つ
まとめ|女性の腸内環境はホルモンと深く関わっている
「腸内環境 乱れ 原因」は、食事や生活習慣だけでなく、女性特有の ホルモン変化 が大きなカギを握っています。
- 月経周期、妊娠・産後、更年期の影響を知る
- 食生活とライフスタイルを見直し、腸とホルモンを同時にケアする
- 小さな腸活習慣を日常に取り入れる
腸を整えることは、消化だけでなくホルモン・免疫・心の健康までサポートする大切な第一歩。女性の健やかな未来は「腸」から始まります。
【ハミングが届けるポジティブニュース】 郵便配達員とひとりぼっちの犬の絆。亡き飼い主の願いをつないだ奇跡の物語

動物と人間の物語は、いつも読む人の心を温かくします。動物は、忙しい日常に癒しと安らぎをもたらしてくれる存在。
今回は、テキサスの郵便配達員と愛犬の絆が紡いだ、心温まる実話をご紹介します。人生の深い味わいを知るあなたに、きっと響く物語です。
おすすめ記事 ▶ 【ハミングが届けるポジティブニュース】 正直者がもらったごほうび──14歳の少年が拾った財布に込めた優しさと、思いがけない贈り物
テキサスの郵便配達員が、亡き飼い主の愛犬を引き取った奇跡のストーリー
「郵便配達員は犬に嫌われる」というアメリカに昔からあるイメージを覆したのは、米国テキサス州デントンという町に住む郵便配達員イアン・バークさんと、一匹の犬フロイドの実話です。
3年前、バークさんが郵便配達をしていたとき、突然元気いっぱいの子犬が後ろから駆け寄ってきました。その犬はジャーマンシェパードとボーダーコリーのミックスで、名前はフロイド。彼の飼い主はベトナム戦争の退役軍人で、車椅子で生活していました。フロイドはその飼い主にとって、単なるペット以上の存在。介助犬としての役割も果たしながら、飼い主の心の支えでもありました。
バークさんは日々の配達の中でフロイドとその飼い主と親しくなり、フロイドにはいつも優しく接しながらおやつを届けていました。フロイドは人懐っこくて、誰にでもとてもフレンドリーに接します。「フロイドはハグするのが大好き。誰にでも愛くるしい姿で友達のように接してくれるんだ」とバークさんは語ります。
“郵便配達員のバークさんは、飼い主を失いシェルターに預けられていた犬フロイドを引き取り、新しい家族として迎え入れた。”
しかし、1年半前にバークさんの配達ルートが変わり、フロイドとその飼い主との連絡は途絶えました。ある日、悲しい知らせが届きました。フロイドの飼い主が亡くなり、フロイドは市内の動物シェルターに預けられていたのです。
バークさんはすぐにシェルターへ向かい、フロイドの保護期間が切れ新しい飼い主の元に引っ越しできる日を待ちました。そして、ついにフロイドは新しい飼い主であるバークさんのもとへ移ることができました。
動物シェルターの職員であるマギーさんは、「郵便配達員と犬は仲が悪いという古い迷信がアメリカにはありますが、フロイドが素敵な家族を見つけることができて本当に安心しました」と語ります。
バークさんはフロイドの新しい飼い主になることをとても誇りに思い、また動物を家族として受け入れることの責任を真剣に受け止めています。バークさんは郵便配達の仕事中も、相変わらず道で出会う犬たちにおやつを持ってきたり、猫たちにエサを与えたりと動物たちに優しい日々を送っています。
この物語は、全米のメディアの注目を集め、多くの人に動物を保護することの大切さを伝えています。
私たちの日常は、時に忙しさややるべきことへのあせりで心に余裕がなくなりがちですが、動物との出会いはそのすきまに優しい光を差し込んでくれます。
郵便配達員と愛犬の物語は、ただの偶然ではなく、互いを必要とする心が引き寄せた奇跡かもしれません。あなたのすぐそばにも、同じように心を温めてくれる存在がいませんか?
女性の骨密度低下の原因とは?|骨の健康を守る予防と対策

年齢を重ねるにつれて「最近疲れやすい」「腰や膝に違和感がある」と感じることはありませんか? 実はその背景には、女性特有の 骨密度低下の原因 が隠れているかもしれません。骨の健康は目に見えにくいため後回しにされがちですが、50代以上の女性の約半数が骨粗しょう症による骨折を経験すると言われています。仕事、子育て、そして自分の人生を楽しむためにも、今のうちから骨を守ることが未来の自分への大きな投資になるのです。
おすすめ記事 ▶ 運動嫌いの私が「運動はメンタルにいい」を少しずつ信じはじめた話
なぜ女性は骨密度が低下しやすいのか?
「女性 骨密度 低下 原因」を調べる方が増えています。実際に女性は男性よりも骨粗しょう症のリスクが高く、50歳以上の女性の2人に1人が骨折を経験すると言われています。その大きな理由は ホルモンの変化 と 生活習慣 にあります。
- エストロゲンの低下
更年期に入ると女性ホルモンであるエストロゲンが急激に減少します。エストロゲンは骨の分解を抑える重要な役割を持っているため、その低下が骨密度低下の最大の原因です。 - もともとの骨量の違い
女性は男性に比べて骨格が小さく、ピーク時の骨量も少ないため、骨密度が下がりやすい傾向があります。 - 生活習慣の影響
栄養不足、運動不足、過度なダイエット、喫煙や過度な飲酒なども骨の健康を損なう要因です。
骨密度低下を加速させる要因
女性の骨密度が下がる背景には、以下のような「見落とされがちな原因」もあります。
- 慢性的なストレス(コルチゾール増加により骨代謝が乱れる)
- 甲状腺や副腎などホルモンバランスの不調
- 腸内環境の乱れ(栄養吸収がうまくいかない)
- ビタミンD不足(日光不足による)
これらが重なると、40代以降だけでなく30代半ばから骨密度が減り始めることもあります。
骨の健康を守る食事と栄養素

骨密度低下を防ぐには「カルシウムだけ」では不十分です。以下の栄養素をバランスよく摂ることが大切です。
- カルシウム(牛乳・小魚・豆腐など)
- ビタミンD(鮭・卵・きのこ、または日光浴)
- マグネシウム(ナッツ類・海藻・玄米)
- ビタミンK2(納豆・発酵食品)
- たんぱく質(肉・魚・豆・プロテインパウダー)
これらを組み合わせて摂ることで、骨がしっかりと再生され、骨密度の維持につながります。
骨密度を高める運動習慣
骨は「負荷」によって強くなります。特におすすめは:
- 筋力トレーニング(スクワット、腕立て、ダンベル運動)
- ジャンプ運動(トランポリンや縄跳びなどの軽い衝撃)
- ウォーキングや階段の上り下り(毎日の生活で取り入れやすい)
運動は骨密度を上げるだけでなく、転倒防止やバランス力の向上にも役立ちます。
まとめ|女性の骨密度低下を防ぐために
「女性 骨密度 低下 原因」は、ホルモンの変化や生活習慣が大きな要因です。特に更年期以降は骨粗しょう症のリスクが急増するため、栄養・運動・生活習慣の見直し が不可欠です。
- エストロゲンの減少による影響を理解する
- 栄養素(カルシウム、ビタミンD・K2、マグネシウム、たんぱく質)を意識する
- 筋トレやジャンプ運動で骨に負荷を与える
今から始める予防が、10年後、20年後の自分を守る力になります。強い女性には強い骨が必要。今日からできることを一歩ずつ取り入れていきましょう。
オーガニックベビーケアで守る赤ちゃんの肌|無香料ベビーローション敏感肌向けおすすめ

赤ちゃんの敏感肌に必要なケアとは?
赤ちゃんの肌は大人の約半分の薄さしかなく、とてもデリケート。ちょっとした刺激でも赤みや乾燥、かゆみが起きやすいのが特徴です。特に 合成香料や防腐剤入りの製品は刺激になることが多く、肌トラブルの原因になりかねません。
そこで注目されているのが、オーガニックベビーケア。自然由来の成分で作られた製品なら、赤ちゃんの敏感な肌をやさしく守りながら、しっかりと潤いを与えてくれます。
おすすめ記事 ▶ 地球にも赤ちゃんにも優しい:成長をサポートする6つのエコフレンドリーおもちゃ
なぜ「無香料」のベビーローションが安心なの?
- 余計な刺激を避けられる:合成香料は赤ちゃんの皮膚や呼吸器に刺激となることも。無香料なら安心。
- 親子で使える:無香料タイプは大人の敏感肌ケアにもおすすめ。
- 香りが苦手な方にも◎:人工的な香りが気になるママ・パパにも心地よく使えます。
特に「敏感肌向け 無香料ベビーローション」を選ぶことで、肌荒れのリスクを最小限に抑えられるのが大きな魅力です。
無香料ベビーローション 敏感肌向けの選び方
成分チェックが第一歩
シアバター、アロエベラ、ホホバオイルなど、保湿・鎮静効果のある植物成分が入っているかを確認。
オーガニック認証をチェック
USDAやECOCERTなどの認証マークがあると安心。
テクスチャーと使いやすさ
乳液タイプは広範囲に使いやすく、バームタイプは乾燥が気になる部分におすすめ。
敏感肌におすすめの無香料オーガニックベビーローション【編集部セレクト】
The Honest Company(オネストカンパニー)
おすすめ対象:敏感肌用プロダクト
配合成分:カレンデュラ花エキス、カモミール花エキス、シアバター、ヒマワリ種子油
価格帯:¥1,500(おしり洗浄料)〜¥3,600(ヒーリング軟膏)
The Honest Company のベビーケア製品は、すべて天然で安全な成分を使用。特に人気の低刺激オムツは、持続可能に収穫されたフラッフパルプで作られており、環境にもやさしい仕様です。さらに皮膚科医テスト済みの植物由来おしりふきは、キュウリや花エキスを配合し、赤ちゃんのお肌をやさしくケアしてくれます。
小さなお子さまがいるご家庭では「便利さ」が何より大切。特におしりふきは、赤ちゃん特有の予期せぬ小さな汚れに欠かせないアイテムです。正直に言うと、オムツは大きな“爆発”にはあまり耐えられませんが、おしりふきは完璧。やさしく、心地よく、しかもパッケージもとても可愛いのが魅力です。

Pipette(ピペット)
おすすめ対象:トラベル用バーム
配合成分:スクワラン、セラミドNP、ビサボロール
価格帯:700円(エクマローション)〜¥5,200(ミネラルサンスクリーンスプレー)
Pipette のベビースキンケアラインは、最新のサイエンスに基づいた処方で、新生児の敏感な肌を守ることを目的に開発されています。最大の特徴は、サトウキビ由来のスクワラン。これは赤ちゃんが生まれたときに体を覆っている「ヴァーニックス(胎脂)」に似た成分で、自然な保湿力を持ち、繊細な肌に最適です。
さらに、すべての製品は 皮膚科医テスト済み・小児科医承認・EWG認証取得。赤ちゃんのケアをより安心で快適なものにする、安全で効果的なスキンケアアイテムとして高い評価を得ています。
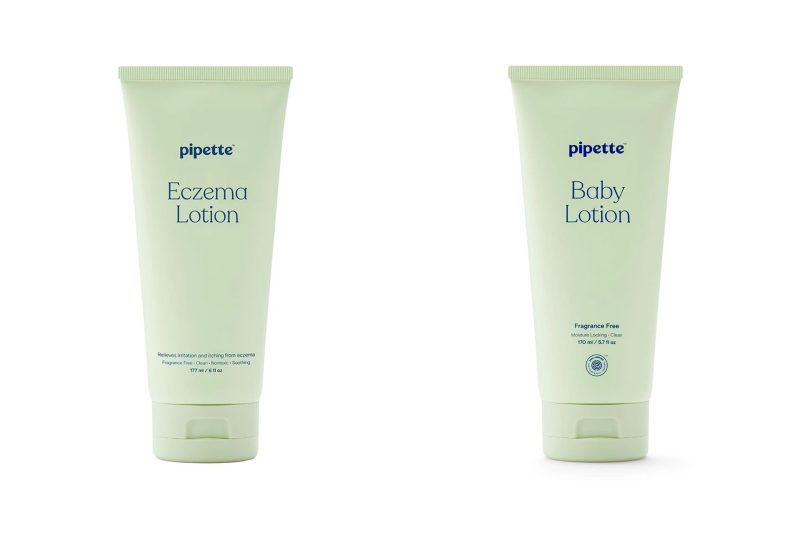
Primally Pure(プライマリーピュア)
おすすめ対象:クレンジング&おむつ替え後のケア
配合成分:マシュマロルート、エミューオイル、ヤギミルク、カレンデュラ・カモミールなどのハーブ、グラスフェッド牛脂、未精製ミツロウ
価格帯:¥2,300(ベビーバー&パウダー)〜¥4,600(ベビーオイル)
赤ちゃんの肌ケアは、本来もっとシンプルで安心できるもの。けれど従来のベビーケア製品では、十分に肌を守りきれないこともあります。そこで誕生したのが Primally Pure Baby。
マシュマロルート、エミューオイル、ヤギミルク、そしてカレンデュラやカモミールといった落ち着かせるハーブを配合。さらにグラスフェッド牛脂や未精製ミツロウといった栄養価の高い天然成分を使用し、赤ちゃんのデリケートな肌をやさしく守ります。
また、強いエッセンシャルオイルを一切使用していないため、敏感肌の赤ちゃんにも安心。多用途で使えるナチュラルケア製品として人気を集めています。

Alaffia(アラフィア)
日本からの購入はこちら(Vitacost)
おすすめ対象:ヘアケア製品&ボディローション
配合成分:シアバター、フルーツオイル
価格帯:¥1,500(ヘアコンディショナー)〜¥2,300(バブルバス)
Alaffia は、西アフリカの地域社会を持続可能にすることを使命とし、未精製シアバターやフェアトレードのバオバブオイルといった在来資源を倫理的に取引することで知られるブランドです。農家には公正な賃金と安全な労働環境を提供し、売上の一部は女性の協同組合や地域プロジェクトの支援に活用されています。
大人向けのボディケアラインでも有名な Alaffia ですが、ベビー&キッズ向けの製品も展開。赤ちゃんの乾燥しやすい肌や髪をやさしく潤し、自然なツヤを与えてくれます。特にシアバター配合のボディローションやフルーツオイルを使ったヘアケアは、敏感肌のケアに最適です。

California Baby(カリフォルニアベビー)
おすすめ対象:湿疹(エクマ)&おむつかぶれケア
配合成分:コロイドオートミール、カレンデュラ花エキス、アロエベラジュース
価格帯:¥1,600(エクマサンプルパック)〜¥6,000(エクマクリームウォッシュセット)
California Baby は、ボディウォッシュからおむつ用軟膏、サニタイザーまで揃う ナチュラルベビーケアの総合ブランド。すべての製品は植物由来で、USDA認証を取得しています。さらにグルテン、ソイ、乳製品、ナッツ類、合成香料は一切不使用。使用される水も4段階の浄化プロセスを経ており、徹底した安全性と純度が魅力です。
また、アメリカ国内のソーラー発電施設で製造され、環境負荷を最小限に抑える取り組みも実践。特に赤ちゃんの湿疹やおむつかぶれに悩む家庭には、ステロイド不使用&第三者機関によるテスト済み のケア製品がおすすめです。

まとめ
赤ちゃんの敏感な肌を守るには、オーガニックベビーケアと無香料ベビーローションが最適。自然由来成分でやさしく保湿し、刺激を最小限に抑えることができます。
オーガニック認証や成分表示をしっかりチェックしながら、赤ちゃんに安心して使える一本を選びましょう。
【映画レビュー】「Strip Down, Rise Up」| ポールダンスを通じて女性が立ち上がるとき

女でいることって、本当にしんどいときがある。
これを読んでいる多くの人もきっと同じように感じていると思う。疲れるんだ。私たちのすべてがジャッジされる――服、声、化粧の量、体重。止まることがない。そして最悪なのは? その基準が、全部男たちが作り出したくだらない「基準」で、社会の隅々にまで染み込んでしまっていること。どこに行っても、何をしても、私たちは「十分じゃない」と言われ続ける。自由に「存在する」ことさえ許されない。
だからこそ、Netflixのドキュメンタリー『Strip Down, Rise Up』は私の胸を強く打った。これは、女性がポールダンスを通じて自分の身体とセクシュアリティを取り戻していく物語だ。多くの人は「ポールダンス」と聞くと即座に「ストリッパー」を連想し、「恥ずかしいもの」として切り捨ててしまう。いまだに性産業が偏見の対象になっているから。でも、このアートの形にはそれ以上のものが詰まっている。確かに肉体的にハードなワークアウトでもあるけれど、それ以上に深く親密なダンスだ。ポールの上で、女性たちは自分の身体や強さ、そしてセクシュアリティと再びつながるための「深い対話の場」を見つけ出すのだ。
おすすめ記事 ▶ 「過去の記憶と向き合う:映画『You Were My First Boyfriend』が教えてくれたこと」
セクシュアリティは恥じゃない
なぜ私たちはセックスをそんなに恐れるのだろう?
ほとんどの人が食べ物や水のように自然にそれを求めている。ほとんどの人が、誰かと一緒に、あるいは一人で、それを楽しんでいる。閉じられた扉の向こうでは、それは許されていて、ほとんど見えない存在。でも、一歩外に出て、自分のセクシュアリティを主張しようとした瞬間、それはタブーになる。恥ずかしいものとされる。その矛盾が、私にはどうしても理解できない。
もちろん、自分のセクシュアリティをプライベートに留めておきたいという気持ちは理にかなっているし、多くの人がそちらを選ぶ。それはその人の自由。でも、違う選択をした人たち――自分のセクシュアリティを堂々と、隠さずに生きようとする人たち――を社会がわざわざ恥ずかしめようとする、その構造こそがおかしいのだ。表現することは黙っていることを否定するものではないし、黙っていることも表現を消し去る理由にはならない。
“セクシュアリティは多くの人にとって自然で大切なものなのに、社会はそれを表に出すことを恥とし、しかし『S Factor』のような場では女性が自分の身体や官能性を取り戻し、本来の自分とつながり直していることが描かれている。”
映画の中で紹介されるのが、「S Factor」というポールダンススタジオだ。創設者は元女優のシーラ・ケリー。彼女はストリッパー役を演じるための役作りでポールダンスを知り、リサーチのつもりがすぐにそれ以上のものへと変わっていった。最初はフィットネスクラスとしてプログラムを作ろうとした――「男性の視線」とは切り離された、自立したワークアウトとして。でも、彼女は気づいた。彼女のクラスに通う女性たちにもっと深い変化が起きていることに。彼女たちはただ筋力をつけているのではなく、長い間「隠すべき」と言われ続けてきた自分の一部――身体、官能を感じること、心の声――を取り戻していたのだ。その気づきがシーラのビジョンを一変させ、「S Factor」は、女性たちが自分自身と新たにつながることができる場へと変わっていった。

失われた自分を取り戻す
私たちが最初に出会うのは、50歳で二人の子どもを持つエブリン。彼女は2年ほど前に夫を亡くし、それ以来ずっと漂うように生きている――かつての自分の殻だけを抱えて。カメラは、キャンディショップの店で働く彼女を追いかける。その声は静かにナレーションとなって響く。「お客さんのお世話はできる。でも車に乗ったら、音楽もない、命もない」。長い迷いの末、彼女は「Strip & Rise」という6か月の初心者向けプログラムに申し込む。これは女性が再び自分自身を愛せるようになるためにデザインされた、S Factor のコースだ。
このクラスに入る多くの女性たちは、何らかの「喪失」の物語を抱えている――自分自身を失った人、身体を失った人、力を失った人。長年S Factorに通うパトリシアは、失恋をきっかけに女性としての価値を疑い、ポールダンスを始めた。免疫疾患を患うジェイミーは、長年自分の身体に居場所を感じられずに苦しんできた。そして元体操選手のメーガン。彼女は子どもの頃、コーチから性的虐待を受け、それ以来、自分の身体が自分のものではなく誰かに奪われたもののように感じてきた。
“S Factor に集う女性たちは喪失や暴力の経験を抱え、自分の身体や女性性を取り戻そうとする中で、社会に植え付けられた恥や抑圧から解放され、自分自身を再発見していく姿が描かれている。”
グループの中には、レイプを生き延びた女性もいた。彼女たちの物語は、言葉にされなくてもクラス全体に流れる痛みとなり、暴力と恥がどれほど深く女性の身体に刻み込まれるのかを思い出させる。
そして私も同じように感じる。女である限り、私の身体は完全に自分のものだと感じられたことがない。常に「見られるもの」として存在してきた――通り過ぎる他人にジャッジされるショーウィンドウのマネキンのように。幼い頃から、私たちの女性性は押し黙らされ、形を変えられ、他人によって決められてきた。何が美しいのか、何が望ましいのか、「やりすぎ」なのか「足りない」のか。そうして大人になるにつれて、その恥をまるで二枚目の皮膚のようにまとい続ける。それは私たちを押しつぶし、エロティシズムも、柔らかさも、炎も奪い去る――やがて、自分自身に属するとはどういう感覚だったかすら忘れてしまうのだ。
恥を解き放つことで始まる回復
S Factorでは、深いトラウマを抱える女性と向き合うことが多いため、インストラクターたちは精神科医に相談しながら指導を行っている。精神科医はこう説明する。「トラウマ回復の鍵は“恥を解き放つこと”。セクシュアリティを取り戻すには、自分のペースで、自分の意思で行わなければならない。なぜなら、その力を奪われ、恥にすり替えられてしまったから。恥はあなたを閉じ込めてしまうけれど、本当は光の中にさらされて解き放たれることを望んでいるのです。」
身体が直接的に侵害された経験があるかどうかに関わらず、ほとんどすべての女性が「存在するだけで恥を負わされる」感覚を知っている。それはあまりに頻繁に繰り返されるため、もはや自分の一部のようになってしまう――毎日着続ける重いコートのように。それを脱ぎ捨てることは、ぎこちなく、痛みすら伴う。なぜならその恥は同時に、絶え間ないジャッジから自分を守る鎧でもあったから。
“アンバーはS Factorの感情を解き放つ生々しいプロセスに耐えられず早々に去り、彼女にとっての力は脆さではなく勝利や規律にあり、その背景には身体を侵害された経験の有無という差も影響していた。”
初日の授業で、シーラは生徒たちにこう警告する。「多くの人は途中でやめたくなるでしょう。このプロセスは恐ろしく、そしてとてもプライベートなものだからです。」その言葉通り、一人の生徒アンバーは、わずか1週間で去ることを決めた。最初のクラスのあと、感情の激しさに圧倒されて車の中で大泣きしてしまったと彼女は認めているのに、Netflixのインタビューで彼女は「12歳の息子に、裸同然の姿で床で身をくねらせている自分を見せたくない」と語った。力を得るどころか、むしろさらけ出され、性そのものに嫌悪感すら感じたように聞こえた。
最初はその反応が理解できなかった――だって彼女はこのクラスがどういうものか知っていたはずだから。でも、彼女を揺さぶったのはポールダンスそのものではなかったのかもしれない。感情を解き放ち、抑え込んできたものを感じろと求められる、その「生々しさ」だったのではないか。
そして、ある意味で私は共感もした。私も感情をあからさまに表現することが苦手で、あのようなむき出しの脆さに囲まれる居心地の悪さを知っている。それでも彼女たちの中にある恐れや怒り、悲しみは、私自身も抱えてきたからこそ、理解できる――自分の身体が自分のものではないと感じる感覚。
けれどアンバーは、少し違っていた。彼女は常にアスリートであり、強くタフであるように鍛えられてきた人間だった。彼女にとってのエンパワーメントは、涙や降伏からではなく、勝利、規則、パフォーマンスから得られるものだった。もしかすると、彼女がこのクラスと繋がれなかったのは、繋がる必要がなかったからかもしれない。あるいは、それは「自分の身体を侵害された経験がない」という特権からきているのかもしれない。

ポールダンスが与える力と再定義
このドキュメンタリーには、複雑な過去を持つポール競技者でありスタジオオーナーのエイミーも登場する。彼女はもともと俳優を目指してロサンゼルスに来たが、生活費を稼ぐために短期間ポルノに出演したことがある。性産業は苛烈だ――人々はその向こう側をほとんど見ようとせず、消費しながらも同時に糾弾する。エイミーはそのスティグマを背負ったが、その時期に出会ったのがポールダンスだった。それは彼女の内側に火をつけ、強さと高揚感をもたらし、最終的に競技的ポールに特化したスタジオを開くきっかけとなった。
また、シルク・ドゥ・ソレイユで活躍したポールアーティストのジェナインにも出会う。彼女は世界を巡り、鍛えられた肉体性、芸術性、そして官能性を融合させた圧巻のパフォーマンスを披露している。彼女の舞台は、ポールダンスが単なる見せ物ではなく「芸術」であることを思い出させてくれる。それはダンスであり、体操であり、動きを通じた物語だ。セクシーであることは確かにその一部だが、それはむしろ力の源だ。そもそも、セクシーであることが罪であるはずがない。魅力的でありたい、自分の官能性とつながりたいと思うのは、人間であること――女性であることの一部なのだから。私たちの身体は強力な表現の道具であり、誰とそれを分かち合うかは私たち自身が選べる。
もちろん、誰もがエイミーやジェナインのようにステージに立ちたいと思うわけではない。しかし、ポールダンスが与えてくれるのは「再びつながる」ためのチャンスだ――女性らしさを感じてもいい、自分のその一部を堂々と受け入れていいのだと思い出させてくれる。映画に登場する多くの女性たちにとって、この実践は命綱のようなものとなった。彼女たちの多くは男性から傷つけられ、虐げられ、小さく扱われ、その痕跡が「価値は男性の視線に収まるかどうかで決まる」と囁き続けてきた。ポールダンスは彼女たちにそれを取り戻させたのだ――「自分の条件」で見られる許可を、自分が女性であることの意味を再定義する力を。
誰もが持つ比類なき美しさ
映画の後半で、エブリンは胸を締め付けるような事実を打ち明ける。夫は一度も「君は美しい」と言ってくれなかったのだ。彼女はずっとその言葉を望んでいたが、夫は言わないまま亡くなってしまった。死後、彼が不倫をしていたこと、そして愛人にはためらいなく「美しい」と伝えていたことを知る。その瞬間、彼女の心は打ち砕かれた。
その痛みを抱えていたのは彼女だけではなかった。ドキュメンタリーに登場する何人もの女性が「妊娠や出産を経てから、自分をセクシーだと感じられなくなった」と告白する。その言葉には重みがある。なぜならそれは、多くの私たちが静かに抱えている現実だから。私たちはしばしば自分に対して最も厳しい批評家となり、他人と比べ、他者からの承認を必死に求めてしまう――男性からも、女性からも、社会からも。
“エブリンや多くの女性が自己価値を他者の承認に縛られて苦しむ一方で、本当の美しさは誰とも比べられない唯一無二のものであり、経験や生き方そのものがその輝きを深めていくのだと語られている。”
けれど真実はこうだ。あなた以上に美しい人はいない。私たち一人ひとりが、比べることのできない唯一無二の美しさを持っている。その美はパートナーによっても、母であるかどうかによっても、他者との関係によっても決まらない。むしろ、そうした経験があなたの存在にさらなる深みと豊かさを与えているのだ。

女性の光を奪わせない
この映画はまた、保守主義――宗教を含む――と性的自由との衝突についても描いている。宗教的な家庭で育ったエイミーは、ポルノ出演の過去を知られ、教会から追放された。彼女が指摘するように、処罰されたのは彼女だけで、裏でポルノを消費している人々は罰せられなかったのだ。
さらに、アリソンというポールインストラクターも登場する。彼女はかつて保守的な男性と結婚していたが、夫は彼女の身体を支配しようとし、SNSに写真を投稿することさえ禁じた。やがてアリソンはそれに逆らい、Instagramアカウントを開設した結果、二人の結婚は終止符を打った。これらの物語はより深い真実を示している――セクシュアリティはスペクトラム上に存在するのだ。すべての人がオープンな表現を価値あるものと考えるわけではないし、それはそれで構わない。しかし、誰も他人の身体の使い方を決める権利は持っていない。
映画の中でシーラはこう語る。「女性が満ちて、豊かになり、爆発的に輝きだすと、それを受け止められない男性もいる。どうやってその事実を受け入れればいいのか、どうやって共に存在すればいいのか、分からなくなるのです。」これは事実だ――女性が変われば、周囲の世界も変わる。
“映画は宗教や保守的価値観と性的自由の衝突を描きつつ、女性が自分の身体とセクシュアリティを自由に表現し合い、互いを支え合うことこそが力と連帯を生むのだという強いメッセージを伝えている。”
もしパートナーがその炎を消そうとするなら、その人の中にあなたの居場所はない。私たちの光は、私たちを見て、敬い、美しいと伝えてくれる人々に囲まれてこそ強くなる。ポールダンスはこの意味で、単なる動き以上のものだ――それはコミュニティである。女性たちは競うためではなく、互いを引き上げ、壊れたピースを再び繋ぎ合わせるために集まる。確かにその結束は強烈で、時に「カルト的」とさえ感じられるかもしれないが、その強さは連帯から生まれるのだ。女性が女性を支えるというラディカルな行為から。
そして私がこのドキュメンタリーから受け取ったメッセージはこれだ――誰も私たちから女性性を奪い、セクシュアリティを黙らせることは許されない。すべての女性は、自分が生きるこの身体を愛し、自分のタイミングで、自分の方法で表現する権利を持っている。だからこそ、あなたの周りにいる女性を愛してほしい。彼女たちに「あなたは美しい」「私たちはあなたはいつも見守っているし、声に耳を傾けている」と伝えてほしい。女性は人生のあらゆる方向から重荷を背負っているのだから――せめて、安全で温かな場所を作ること、それができる最低限のことだ。
更年期に繰り返す膀胱炎(UTI)の原因と自分でできる予防法

更年期に膀胱炎が増えるのはなぜ?
ホルモン変化とエストロゲン低下の影響
更年期に入ると、女性ホルモンであるエストロゲンが大きく減少します。エストロゲンは膣や尿路の粘膜を守る役割を持っていますが、その分泌が減ることで粘膜が薄くなり、細菌感染に弱くなります。その結果、膀胱炎(UTI)が起こりやすくなるのです。
膣や尿路に起こる変化(乾燥・粘膜の弱まり)
膣の乾燥や弾力の低下は、更年期女性に多く見られる症状です。これにより、排尿時の違和感や性交痛が起こるだけでなく、細菌が侵入しやすい状態になり、膀胱炎が繰り返される原因になります。
おすすめ記事 ▶ 【更年期美容カウンセラー斉藤万奈さんインタビュー】「これって更年期?」もしや、と不安になったあなたへ――専門家が明かす、心と体の変化を乗りこなすヒント
GSM(閉経関連泌尿生殖器症候群)とは?
GSM(Genitourinary Syndrome of Menopause)は、更年期から閉経にかけての女性に多くみられる症候群です。膣の乾燥、かゆみ、性交痛、頻尿や尿意切迫といった症状を含み、これが膀胱炎のリスクを高める大きな要因となります。
膀胱炎が繰り返しやすい年齢層とは
若年期(14〜24歳)に多い理由
若い世代では、活発な性生活により膀胱炎が増える傾向があります。性交時に細菌が尿道に侵入しやすいためです。
更年期前後から再び増える背景
加齢に伴うホルモン低下により、膀胱炎は更年期から再び増加します。セックスの有無にかかわらず、ホルモンバランスが乱れることで発症リスクが高まるのです。
閉経後に再発率が急増するデータ
研究によると、閉経前の膀胱炎再発率は19〜36%ですが、閉経後は55%に跳ね上がります。これはホルモン変化による粘膜の弱まりが大きく関係しています。
更年期に繰り返す膀胱炎の症状
頻尿・尿意切迫・排尿時の痛み
典型的な症状は「何度もトイレに行きたくなる」「排尿時に痛みを感じる」といったものです。
性交痛や膣の乾燥との関連
更年期の膣乾燥は性交痛を引き起こすだけでなく、細菌感染を助長し膀胱炎につながります。
生活に与える影響とQOLの低下
頻繁にトイレへ行く、性交を避けてしまうなど、日常生活やパートナーシップに大きな影響を与えることがあります。

Photo by Solving Healthcare on Unsplash
更年期の膀胱炎を予防する自分でできること
水分補給と排尿習慣の見直し
こまめに水を飲み、トイレにいくのを我慢しないことが大切です。尿と一緒に細菌を排出することで感染予防につながります。
膣の乾燥ケア(保湿ジェル・ローションなど)
膣専用の保湿ジェルやローションを使うことで、乾燥や粘膜の弱まりを防ぎ、細菌感染のリスクを軽減できます。
食生活と腸内環境の改善
発酵食品や食物繊維をとり、腸内環境を整えることも免疫力を高める鍵。ビタミンCやクランベリーなども膀胱炎の予防に役立つとされています。
膀胱炎を繰り返さないための生活習慣チェック
- 下着は通気性の良いコットン素材を選ぶ
- 性交後は排尿して菌を流す
- 体を冷やさないよう注意する
これらを意識するだけで、膀胱炎の繰り返しを大きく防げます。
医師に相談すべきサインと治療法
繰り返す膀胱炎は「放置しない」が鉄則
自己判断で市販薬だけに頼らず、再発を繰り返す場合は医師の診断が必要です。
婦人科・泌尿器科での治療オプション
抗生物質による治療のほか、症状に応じた膣の保湿ケア、レーザー治療などの選択肢があります。
ホルモン補充療法(HRT)やその他の治療
必要に応じて、医師がホルモン補充療法(HRT)を提案することもあります。症状が強い場合は、こうした専門的な治療が効果的です。
まとめ|更年期の膀胱炎は予防と早めのケアが大切
- 更年期のホルモン変化は膀胱炎のリスクを高める
- 水分補給や膣ケアなど「自分でできること」で予防可能
- 再発を繰り返す場合は必ず医師へ相談
膀胱炎は「仕方ない」と我慢するものではありません。正しい知識とケアで、更年期を快適に過ごすことができます。
セックスレス解消に自分でできること ひとりのセックスで心と体を満たす方法

セックスレスを自分で解消するには?
セックスは「パートナーとするもの」だけじゃない
多くの人が「セックス=パートナーとするもの」と考えています。そのため、恋人や夫婦関係がないと「セックスレス」だと感じ、満たされない思いを抱きがちです。けれど、性の中心にあるのは本来「自分自身」。自分の心と体を理解し、楽しむことこそが健やかなセックスライフの第一歩です。
最も大切なのは「自分との性的な関係」
セックスレス解消のためにできることは、相手を探すことだけではありません。むしろ「自分との性的な関係」を大切にすることで、満たされる感覚を得られるのです。
おすすめ記事 ▶ セックスレス、会話不足、不倫…パートナーとの悩みを元AV女優がひも解く!【男女コミュニケーション心理士の小室友里さんインタビュー】
ひとりセックスがセックスレス解消につながる理由
マスターベーションが心と体に与える効果
マスターベーションは脳内で幸せホルモン(ドーパミンやオキシトシンなど)を分泌し、気分を高めたりストレスを軽減したりします。これは科学的にも証明されており、日常生活にポジティブな変化をもたらしてくれます。
リラックス&気分を高める「セルフプレジャー」
意識的にひとりセックスを取り入れることで、リラックスの時間を確保し、セルフケアの一部として役立てられます。仕事や人間関係で疲れていても、「自分で自分を癒す」習慣は心の安定につながります。
一人で楽しむことは恥ずかしいことじゃない
文化的に「一人ですること」は話題にしにくいテーマですが、セックスレスを自分で解消する大切な手段です。パートナーに頼らず、自分で自分を満たすことは決して恥ずかしいことではなく、むしろ健康的で自然な行為なのです。

Photo by Rae Angela on Unsplash
自分でできるセックスレス解消の方法
マスターベーションをセルフケアに取り入れる
セックスレス解消の一番シンプルな方法は、マスターベーションを生活の一部に取り入れることです。照明や香りなど、自分が心地よく過ごせる環境を整え、丁寧に楽しむことがポイントです。
エロティカ(官能的な作品)を通じて想像力を広げる
本や音声、映像などのエロティカは、自分の想像力や欲望を広げてくれる強力なツールです。普段は意識しない感覚や気持ちを引き出すことで、ひとりセックスの体験がより豊かになります。
性に関する内省やセラピーで「自分の境界線」を知る
セックスレス解消は、快感を得ることだけではありません。自分の性に対する価値観や境界線を理解することも大切です。必要であれば、セックスセラピーやカウンセリングを取り入れることで、より深い自己理解につながります。
性の「考古学」をしてみる
セックスレスを自分で解消する最初のステップのひとつは、過去の記憶を振り返ることです。たとえば、中学の保健体育で受けたぎこちない性教育や、初めて欲望を感じた瞬間など、自分がどんなメッセージを受け取り、どんな価値観を作ってきたのかを探ってみましょう。
多くの人は「自分を触るのは変なこと」と教えられて育ったり、「セックスは恋愛関係の中でしか意味がない」と信じ込んできたりします。こうした思い込みや古い固定観念は、セックスへの楽しみ方や関わり方に影響を与えているかもしれません。
ここで大切なのは「私はセックスについてどう考えているのか?」「何を教わり、どう感じてきたのか?」と自分に問い直すこと。そして、それが本当に自分の考えなのか、あるいは手放してもいい価値観なのかを見極めることです。こうして古い枠組みを見直すことが、セックスレスを解消するために自分でできる大切な一歩になります。
ひとりセックスについて書いてみる
過去を振り返ることで気づきを得られたら、それを終わりにせず「書くこと」でさらに深めてみましょう。ひとりセックス専用のノートを作ることで、過去だけでなく「今の自分」や「これから望むこと」にも目を向けられます。
そこには最近の体験を書き留めてもいいし、新しい妄想や試してみたいことを書き出してもOKです。具体的に「もっとオーガズムを感じたい」「不安を減らしたい」「自信を持ちたい」「日常の中に快楽の時間をつくりたい」などの目標を書き出すのも効果的です。
必ずしも大きな目標でなくても構いません。たとえば「自分の体に安心して触れられるようになりたい」「長いシングル生活の中で失われていた性とのつながりを取り戻したい」といった小さな気持ちでも十分です。理由は人それぞれですが、専用のノートに書くことで、自分の動機や目的を整理し、セックスレス解消に向けた「自分でできること」をより具体的に理解できます。
ひとりセックスで築く、自分らしいセックスライフ
セックスレスを恐れない考え方
「パートナーがいないから自分はセックスレス」という考え方に縛られる必要はありません。むしろ、ひとりの時間を楽しむことは自立している女性であることの証です。
自分のニーズを知り、自分を優先すること
セックスレス解消において最も大切なのは、「自分の心と体が何を求めているか」を知ること。そして、他人の期待に応えるよりも自分の満足を優先することです。
「ノー」と言える強さがあなたを守る
パートナーがいる場合でも、自分が望まないときに「ノー」と言えることは健全な性関係の基本です。自分を大切にする強さがあれば、セックスレスをただ我慢するのではなく、健やかな形で向き合えるようになります。
まとめ|セックスレス解消は自分でできる
セックスレスを解消するために必要なのは「相手」ではなく「自分自身」です。
- ひとりセックスをセルフケアに取り入れる
- マスターベーションを意識的に楽しむ
- 性に関する理解を深め、自分の欲望や境界線を知る
これらはすべて、「セックスレス 解消 自分でできること」 です。あなたがあなた自身を大切にし、自分の欲望を尊重することこそが、最高のセックスライフにつながります。
SNSで時間を溶かしまくって気づいた「本当に心が満たされるご自愛」のコツ

仕事から帰宅した夜。
「疲れたからちょっと休憩」と、なんとなくスマホを手に取ってSNSを開く。
気がつくと3時間、4時間があっという間に過ぎている。そんな経験、ありませんか?
私はよく、このパターンをやってしまいます。
寝る前の時間や、予定のない休日の昼間にも、平気で数時間溶かしてしまう。
しかも、たいていその後に待っているのは、強烈な自己嫌悪です。やらなければいけない家事も、翌日の仕事への準備も、全く手につかなくなってしまいます。
ところが、同じように「ゆっくり過ごす」時間でも、全く違う結果をもたらすこともあります。
“同じ「ゆっくり過ごす」でも、SNSで時間を溶かすのは自己嫌悪を招く一方、気ままな散歩や寄り道は心を満たし翌日への活力につながることに気づいた体験でした。”
ある時、やるべきことがいろいろ山積みだったにもかかわらず、なんだかどうしようもなく外に出たい気持ちが湧いてきた日がありました。
もういいや!と、すべてを翌日に後回しにして、身支度もそこそこに適当な服を着て、あてもなく散歩に出かけてみたんです。
買う予定もないけど家具屋さんを目指して、その道中もまっすぐ行くわけではなく好きなように寄り道しながら歩き、帰りはたまたま見つけたコーヒーショップに入ったりして、とにかく好きにのんびり過ごす。
しかもそのコーヒーショップで初めて見るケーキに出会って、それがまぁとても美味しくて。それ以降もちょこちょこ買いに行くほど、すっかりお気に入りになりました。
でも何より大きかったのは、その日の帰宅後の気持ちの変化です。
なんて良い一日だったんだろうと心はとても満たされ、後回しにしたことも明日しっかり頑張ろうと前向きな気持ちが自然に湧いてきたんです。
でも別に、SNSをスクロールする時間だって、同じように「ゆっくり過ごした」はずなのに、むしろそっちのほうが体力も使わないし、なぜこんなにも「その後の気持ち」が違ったのでしょうか。
おすすめ記事 ▶ 些細なことにイライラ…HSP気質な私のストレス攻略法
「ただの甘やかし」と「本当のご自愛」の境界線

本当の意味で自分を労われたとき、気分はすぐに前向きになって、なんだか温かい気持ちがしてエネルギーも湧いてくる。
一方、自分を「ただ甘やかしてしまった」ときは、何時間経っても心のモヤモヤは晴れず、むしろ自己嫌悪で状況が悪化することもある。
振り返ってみると、先ほどの例に限らず、どちらのパターンも何度も経験したことがある話です。
でも自分としては、いずれの場合も「何も考えず好きに過ごすことで自分を労わっている」つもりなのに、かたや前向きな気持ちをもたらし、かたや自己嫌悪を誘発する。
なんとも不思議な話です。
で、私なりに考えてみて少し気づいたことがあります。
それは、よくあるSNSはエネルギーを削ぐといったような話ではなく、それ以前に、自分の状態を正確に見極められているかどうかによるのではないかと。
例えば、漠然と気分が落ちていると感じただけで、「なんかもうキャパオーバーなんだろうな」と判断してしまうことがあります。
でも実は、たまたまやるべきことや予定が一気に押し寄せて圧倒されているだけで、本当はまだ余力があるのかもしれない。
そうした考察もしないまま、すぐに「もう無理だ…」と結論づけてしまうから、本当に気分も体もどんどん重くなって、ご自愛タイムが必要なんだと思い込んでしまう。
ちゃんと自分の状態や本当の欲求を見極めないまま、なんとなく「疲れたから休もう」と判断してしまうと、SNSのような手軽な逃げ道に頼ってしまいがちです。
SNSなら、受動的でいても、特に何も考えなくても、時間を消費できるから。
で、こうなるパターンは「甘え」であり、「逃げ」なのではないかと思います。
例としてSNSを挙げましたが、無思考でとりあえず「ご自愛っぽい」ことをするなら、他のことでも同じ結果だと思います。
なんとなく溜まっていたドラマを見ても、積読のままになっていた本を読むことで自分時間を取った気になっても、それが本当にその時自分に必要なご自愛でなければ、さほど満足感は得られないと思います。
“本当のご自愛は自分の状態や欲求を正しく見極めたときに前向きなエネルギーを生む一方、思考停止で選んだ「ご自愛っぽい」行動は甘えや逃げとなり、自己嫌悪を招いてしまうのだと気づいた話です。”
一方、一呼吸置いて自分の状況を冷静に見つめられたら。
「最近、あの仕事結構重かったもんな」
「プライベートもバタバタしてて、ずっと張り詰めてたんだよな」
「私のキャパからしたら結構限界まできてるよな」
そう自分の中で納得できたら、次は自然と「じゃあ今どんな癒しが自分に必要なんだろうか」という思考が浮かんできます。
そうやって、自分の状態を正確に把握するからこそ、適切な対処法が分かって、結果として本当のセルフ・コンパッションになるのではないかと、最近思うのです。
実際、冒頭の散歩に出かけた日は、いろいろ頑張りすぎていたことを自覚していたし、だからこそ、ここでもうひと踏ん張りするより「外に出たい」という自分の欲求に、素直に従うほうが大事だと気づけたんだと思います。
私なりのご自愛タイムには他にも、映画やドラマを見たり、本やゲームに没頭したり、旅行を計画したり、いろんな選択肢がありますが、それぞれやっぱり適切なタイミングがある気がします。
「外に出たい」と思った日に、「もう遅い時間だから」などと理由をつけて、ドラマの一気見でお茶を濁そうとしても、そんなに満たされない。
本当の意味で自分に優しくするということは、今の自分がどういう状態で、何を欲しているのか、ちゃんと理解することなんだと思います。
つまり、良いご自愛と、そうでないご自愛、両者の違いの根本にあるのは「過程」。
どちらも同じ「好きに過ごす時間」だけど、そこに至るまでの経緯、ちゃんと考えてそこに至ったかが、ご自愛の「結果」を大きく左右するのではないかと、最近ヒシヒシと感じるのです。
自分の状態を正しく見極める難しさ

とはいえ、自分の状態を正しく見極めるということ、自分の疲れや頑張りに気づいてあげるのは、思っている以上に難しくもあります。
他人には優しくできても、自分にはなかなか優しくできない理由も、一つはここにある気がします。
だって、実は他人に優しくすることって、意外と簡単じゃないですか?
傍から見ていると、みんなすごく頑張っているように見えるから、「ギアを落としてもいいんじゃない?」と自然に思えます。
でも自分に対しては厳しくて「あの人に比べたらまだまだ」とか、「こないだ自分を甘やかしてしまったから、もっともっと頑張らないと」となる。
これって、完璧主義とか自分に厳しいという言葉で片づけられるものではなく、自分を適切に評価できていないからだと思うんです。
他人の状況は客観的に見ることができるのに、自分の状況となると主観が入りすぎて、「まだ頑張れるはず」という思い込みに囚われて、本当に必要な休息を取れなくなってしまう。
歩みを緩めることを許してあげられない。というか、怖い。
でも心の底では、もう休みたいという本音もある。
…はぁ、正しいセルフ・コンパッションって、ほんとーーーに難しい!!
ただ、逆にいえば、この評価さえきちんとできれば、意外とセルフ・コンパッションは簡単に実践できるものなのかもしれません。
だからこそ、最近は「自分のやったこと」を正しく把握することに重きを置いています。
私が実践していて効果を感じているのは、定期的に自分の状況を書き出して、客観的に見つめることです。
“気持ちが淀んだときは書き出して自分の状態を正しく見極め、その状況に合った対応を取ることで安心感が生まれ、自然と前向きな気持ちに切り替わるのだと気づいた話です。”
漠然と気持ちが淀んでいるように感じたときこそ、一旦立ち止まって自分の状況や気持ちを一つひとつ紐解いてみる。
最近どのくらい忙しかったか、何で忙しかったのか、それは客観的に見ても膨大な仕事量だったのか、もしくは気疲れしていただけなのか、単に予定が重なってキャパオーバーだったのか。
頭の中で考えてもいいのですが、文字にした方が冷静になれるので、とにかく書き殴るのがおすすめです。
ぶわーっと現状を書き出していくと「いや、たしかに最近めっちゃ頑張ってたわ」とか「あれは結構ハードワークだったのでは?」と思えたり、
逆に「いや、そうでもないな。何をすべきか分かってなくて不安なだけだ」とか「整理したらもう少し頑張れるかも」と、冷静に見えてくることもあります。
前者の場合なら、今の自分に必要な癒しは何か自問自答し、それを実現する。
後者なら、どうやったらもうちょっと頑張れそうかを考え、それを実行する。
ただそれだけに、全集中する。
いずれの状況にせよ、それぞれ正しい対処法が取れたら、不思議と(後者の場合でも!)すぐに気持ちは復活するんですよね。
自分の状態を正しく把握して、それに応じた適切な対応を取れたという安心感が、前向きな気持ちを生み出してくれるのかもしれません。
セルフ・コンパッションは技術

Photo by Tijana Drndarski on Unsplash
自分に優しくするというのは、思っているほど簡単ではありません。
ただ自分を甘やかせばいいというわけでも、厳しくすればいいというわけでもない。自分の状態を正しく見極めて、そのときの自分に本当に必要なものは何かを判断する「一つの技術」なのだと思います。
頑張るときは頑張る、休むときは思いっきり自分を甘やかす。
そんなメリハリのある理想的な生活を実現する第一歩は、今の自分がどんな状態にあるのかを、できるだけ客観的に、そして優しい目で見つめることから始まるのかもしれません。
30代でようやく見つけた“性への自信”

17歳で処女を失ったけれど、理想とは程遠い日々だった。
昔からよくある話。男の子が女の子にちょっかいを出し、女の子は彼の魅力に惹かれるけれど、男の子は彼女の体だけを欲しがる。
あの頃の私は世間知らずで経験不足で、男性が女性をセックスのためにあやつれるだなんて知らなかった。セックスは合意の上。でも、その後に何かあると思っていた。デート中に2人で話しができるかもしれないと思ったけれど、彼が残していったのはSNS上のスクリーンネームとメールアドレスだけ。電話番号すら残してくれない男の子だった。
おすすめ記事▶ 女性の性欲の真実! 年齢ごとの自然な変遷と幸せへのヒント…
20代を通してセックスに抱いた不安と誤解
腹立たしく聞こえるかもしれないけれど、今となっては優しい心で振り返ることができる。でも、あの出来事は20代を通して私の性体験を不安と失敗で決定づけたのです。
私はセックスを、道具として関係を深めるものではなく、むしろ交渉の道具として見ていたんです。20代の男の子とのやり取りではいつもセックスをしたいという彼らの願望を感じ、私が異性と関わる時の行動にはその願望に一致するべきという気持ちが反映されていました。
「見た目が良い女の子ではない」と感じながら育った私にとって、セックスは私が女性として求められていると感じられる唯一の時間。
でもほとんど知らない男の子と裸でベッドにいるのは決して心地よく感じられなかった。しかも、ベットの上で女の子を気持ちよくさせるやり方が分からない男の子と寝るのは、大惨事でした。すぐに私は流れに身を任せ、彼の望むことをするという考えに慣れてしまった。その方が簡単だと感じたから。
“20代は失敗や義務感に縛られたセックス体験を通じて自分を見失ったが、30代になり自己理解と自己肯定感を深めたことで、自分を優先しセックスを楽しめるようになった。”
私はいつもみんなに、20代は失敗しても大丈夫と伝えている。20代はそのためにあるもの。失敗から学べば、転んでも立ち上がれる、そんなぜいたくな時間。私は20代の大半はセックスを楽しんでいなかったけど、セックスの回数は多い方だった。セックスは趣味というよりは、義務のように感じていたんです。
大人になり「セックスを義務感でやっている」と認識できるほどに脳が発達した時、自分自身に問いかけるようになりました。「あなたは、ベッドで何をしたいの?」と。そうしたらすぐに自分を守る境界線ができて、男性のすべてのアプローチが良いとは限らないこと、そして、チャンスを逃したように感じても、立ち去ってもいいことをゆっくりと学んだんです。つまり、私は誰よりも自分の気持ちを優先するようになったのです。
30代に差し掛かり、自分を大切にするようになりました。運動量を増やし、健康的な食生活を送り、旅行にも行った。自信がセックスの喜びに繋がることを発見し、驚いた。自分の体型を受け入れられるようになり、20代の経験を通して自分の好き嫌いも理解できるようになりました。
信頼と自己尊重から始まる、大人のセックス
歳を重ねるにつれ、セックスをする相手も大人の男性になり、自分のニーズを最優先に考えてくれる人との付き合いがどんな感じかを学びました。大人になって初めて、セックスは信頼に基づくパートナーシップであり、コミュニケーションが鍵となることを知ったんです。
“40代になった今、過去の経験から自分の心と体の望みを理解し、他人に合わせるのではなく自分を大切にしながらセックスを楽しむことを学んだ。”
パートナーとセックスについて話すのは、時にとても難しいもの。なぜなら、それはまさに自分が鍵をかけた扉の奥にしまい込んでいたものを傷つけることになるからです。簡単に心を開きたくないのは当然。ありのままの自分に優しく、そしてそんな自分を傷つけるような人は拒絶することが大切です。あなたはあなたの人生で一番大切な人であり、あなたを一番尊重してくれる人に心を開くべき。
40代に突入した今、過去の失敗から学んだおかげで、自分の心と体が何を求めているのか、これまで以上にはっきりと分かっている。そして、ベッドの中での自分の見ためや発する声をあまり気にしないようにしようと決めました。なぜなら、男性にとって、目の前の女性が自分と一緒に行為を楽しんでいる姿を見ることほどセクシーなものはないからです。他人の喜びのために生きるには人生は短すぎます。「ノー」と言って、あなたを大切にしてくれる人を待つのもいいのです。
【ハミングが届けるポジティブニュース】 「あの頃の友情が今も毎年届く」81年間、誕生日カードを送り合う女性の物語

毎日がバタバタと過ぎていくなかで、「昔からの友達、元気にしてるかな…」なんてふと考えること、ありませんか?長い年月を経ても変わらず続く絆には、心が温かくなる力があります。
今回ご紹介するアメリカに住むふたりのおばあちゃんは、なんと81年間も、同じ誕生日カードを毎年送りあってきたのです。そんな心あたたまる物語に、きっとあなたも優しい気持ちになれるはずです。
“95歳になったメアリーさんとパットさんは、14歳の誕生日に交わした1枚のカードをきっかけに、81年間ずっと毎年交互に送り合い続けてる。”
学校も別々になり、大人になってからは住む場所も変わったふたりですが、カードのやりとりは決して欠かしませんでした。ある年には郵便事故でカードが行方不明になったものの、パットさんの夫が探し出してくれたほど。これまで世界130か国を旅したというパットさんでも、そのカードだけは手放しませんでした。
おすすめ記事▶ 【ハミングが届けるポジティブニュース】 正直者がもらったごほうび──14歳の少年が拾った財布に込めた優しさと、思いがけない贈り物
カードの内側には恐竜の骨格が描かれており、ふたりはそこに年号を書き、相手の署名を線で消しては送り返す、という独自のルールを守り続けています。恐竜の骨もそろそろ埋まり、いまではカード本体や封筒の余白にも書き込みをするほどに。
そんな二人の長い長い伝統は、ギネス記録にも認められました。60年の節目には最長記録として認定されましたが、オーストラリアの別のペアが61年を記録してからは、一時的に記録が抜かれてしまいました。そこで昨年11月、ふたりの家族が再びギネスの記録申請をしたそうです。
ただし本人たちは、「名声のためではない」と話します。
「ただ、私たちがずっとやってきたことを、これからも続けているだけなの」とパットさん。

高齢になり移動が難しくなったため、ここ数年は直接会えていないふたりですが、カードは変わらず届き続けています。
「今年も届いたわ、とってもうれしいの」と語るパットさん。メアリーさんも、「私が送れなくなっても、子どもたちが引き継いでくれるはず」と語ります。
時を超えて届くたった一枚のカード。その中に詰まっているのは、人生の変化を超えて続く友情の記録です。
人間関係が移ろいやすい今の時代に、「変わらない何か」があることは、どこか希望になりますね。14歳で始まったふたりのおばあちゃんの心のやりとりは、人生の終わりが近づく今もなお、静かに続いています。
あなたにも、ふと手紙を書きたくなるような相手がいませんか?
参考記事:https://www.cbc.ca/radio/asithappens/best-friends-birthday-card-1.7501500
セラピストと親密さを高める役割とは?
カップルや個人がつながり・信頼・性のウェルネスを取り戻す方法

セックスセラピストは、親密さを高めるうえでどんな役割を果たすのでしょうか?
カップルや個人が親密さを高めるためには、心身両面の課題に向き合う必要があります。忙しい現代社会では、性的な不一致や欲求のズレ、コミュニケーションのすれ違いが、親密さを静かにむしばんでいきます。セックスセラピストは、そうした課題に対して、感情面・関係性・身体的な側面を含む包括的なサポートを提供する存在です。
セラピストは、科学的根拠に基づくアプローチと、一人ひとりに寄り添う思いやりのある支援によって、親密さを高めることを専門としています。
“カップルが直面する最も一般的な課題のひとつが、セックスについて率直かつ建設的に話すことができないということです。このコミュニケーションのギャップは、思い込みや不満、感情的な距離を生み、身体的な親密さをさらに難しくしてしまいます。”
おすすめ記事▶ セックスレスの原因とは?|なりやすい夫婦の特徴や解消法を解説
親密さを高めるためのセックスセラピー:身体だけでなく心も整えるアプローチ
セックスセラピーは、性的パフォーマンスだけに焦点を当てるものではありません。心理的・感情的・関係性・身体的側面を統合し、親密さを高めることを目的とした心理療法です。
セラピーでは、次のような課題を抱えるクライアントをサポートしています:
- 性的欲求の低下
- セックス時の痛みや興奮のしづらさ
- セックスに関するコミュニケーションがとりづらい
- セックスへの不安や親密さの回避
- トラウマやストレス、過去の経験による性的自己表現の難しさ
- 子育てや加齢、病気による親密さの変化
クライアントのニーズに応じて、個人またはカップルセッションのいずれか、もしくは両方を通じて親密さを高める支援を行います。
コミュニケーションと感情的な洞察を通して、親密さを高める

カップルがセックスについて率直に話すことができないと、誤解や不満、距離感が生まれ、親密さがさらに損なわれます。
セラピーでは、安心して話せる空間を提供し、次のような取り組みを行います:
- 親密さに関する価値観・境界線・ニーズの明確化
- 強い感情を引き起こすきっかけの理解
- 健全なコミュニケーション方法の練習
- 無意識に抱えている緊張や葛藤の解消
これにより、身体的なつながりだけでなく、感情的なレベルでの親密さを高めることが可能になります。
“親になること、キャリアの変化、病気や加齢などは、自分自身のアイデンティティや身体、パートナーとのつながりに揺らぎをもたらすことがあります。”
人生の転機と親密さの揺らぎ
親になること、キャリアの変化、病気や加齢などは、自分自身のアイデンティティやパートナーとの関係性に影響を与え、親密さを揺るがすことがあります。
セラピーでは、以下のようなテーマに取り組みながら、親密さを取り戻すサポートを行います:
- 産後の身体イメージや欲求の変化
- 慢性疾患や診断後の関係性の変化
- 性的アイデンティティの再発見
- 過去のトラウマからの回復
こうした経験を整理し、自分自身とのつながりを深めることで、親密さを高める土台が築かれていきます。
性的課題への臨床的アプローチで親密さを高める
性交時の痛み、勃起不全、オーガズム困難、欲求の低下などの問題は、しばしば心理的・関係的要因とも結びついています。
セラピーでは、以下のような包括的アプローチを採用しています:
- 性反応サイクルや解剖学に関する心理教育
- 必要に応じた医療専門家への紹介
- トラウマからの不安の軽減法
- 身体と心をつなぐエクササイズ
これにより、症状に対するスティグマを取り除き、安心して性と向き合える環境をつくり、親密さを高めることを可能にします。
親密さを高めるための関係再構築:すれ違いからつながりへ
多くのカップルが、恋人というより「ルームメイト」のように感じてしまっていると語ります。愛情や信頼があっても、情熱やスキンシップが失われた状態です。
セラピーでは以下のような取り組みを通じて、親密さを高める関係づくりをサポートします:
- 感情的・生活的・性的に親密さを妨げている要因の特定
- プレッシャーのないスキンシップの再開
- 愛情とつながりを育む新たな習慣の構築
- 長期的に性的関係を続けるためのアプローチ
性的な断絶はテクニックの問題ではなく、感情的な安全や対話の欠如、長年積み重なった妥協によるものであることが多いです。セラピーは、その根本を見つめ直し、深いレベルでの親密さを再構築する力になります。
あなた自身やパートナーとの関係において、フラストレーションや孤独感を我慢する必要はありません。正しいサポートがあれば、親密さを高めることは、今すぐにでも始められます。
生理直前のカラダが教えてくれること――PMSの症状を見逃さないで

生理直前になると毎回やってくる、イライラやむくみ、腹痛や肌荒れ。
「いつものことだから」とPMSの症状を軽く見たり、現代医療では“正常の範囲”とされることも多いため、気づかないうちに無理をしてしまっている人も少なくありません。
でも、そのPMSの症状、本当に「普通」で済ませてしまって大丈夫ですか?
「何の不調もなく、生理が自然と始まる…くらい快適だったらいいのに」
そんな理想を思い描きながらも、現実は生理直前になると心も体も乱れてしまう…という人も多いはず。
月に一度やってくるサインだからこそ、自分の心と体の声に耳を傾けてみることが大切です。
【おすすめ記事】生理後は性欲が強くなる?生理周期別の性に関する過ごし方を紹介
生理直前に気持ちが不安定になるとき――それ、PMSの症状かも?
落ち込みやイライラ、気分の浮き沈み、不安感など、感情の変化は生理直前に多くの人が経験するごく一般的なPMSの症状のひとつです。
こうした感情の変化が仕事や日常生活に支障をきたすほど強くなる場合、“月経前不快気分障害(PMDD)”と診断されることがあります。PMDDと診断された場合、うつや不安症の治療にも使われる薬が処方されることが多いです。
“生理前の気分の落ち込みやイライラは一般的なPMS症状ですが、日常生活に支障をきたすほど強い場合はPMDDの可能性があり、医療機関での相談が推奨されます。”
ただし、念のために言っておくと、生理直前にパートナーにちょっときつく言ってしまったり、保護犬のCMを見て号泣してしまった――そんな経験だけでPMDDと診断されるわけではありません(誰にでもありますよね)。
PMDDとは、PMSの症状の中でも特に感情の変化が強く、日常生活に明らかな支障を与えている場合に下される臨床的な診断です。もし気分の落ち込みや不安が生理が終わっても続くようなら、ホルモンとは別の原因がある可能性もあるので、一度医療機関で相談してみることをおすすめします。
生理直前に起こるトイレの変化――それもPMSの症状のひとつです

「最近、生理直前になるとお腹の調子が不安定になる…」と感じているなら、それはあなただけではありません。
ガスが溜まったり下痢になったりといった腸の変化は、生理直前のホルモンバランスの影響でよく起こります。これは、プロゲステロンの急激な減少によって、腸の動き(蠕動運動)が活発になり、下痢を引き起こしやすくなるためです。
生理直前のPMSの症状としてよく見られるもののひとつですが、不快な変化をやわらげるには、食物繊維を多くとり、カフェイン、アルコール、辛すぎる食べ物などの刺激物は控えるのがポイントです。
生理直前の「おなかパンパン」感――PMSの症状としての腹部の膨満感
下腹部の膨満感、なんだかお腹が張って重たい感じ…。これもまた多くの人が生理直前に経験するPMSの症状のひとつです。
主な原因は、エストロゲンとプロゲステロンのホルモンバランスが乱れることで体内に塩分や水分が溜まりやすくなることにあります。
“生理前の下腹部の張りや膨満感はPMSの一症状で、ホルモンバランスの変化による水分・塩分の滞留が原因とされ、塩分を控えたりマグネシウムを取り入れることで和らげられます。”
特に生理直前は塩気のあるものを無性に食べたくなる時期ですが、塩分の摂りすぎはむくみを悪化させるので、控えめにするのが理想です。
この時期には、マグネシウムのサプリメントを取り入れてみるのもおすすめ。マグネシウムは電解質のバランスを整えたり、やさしく体内の余分な水分を排出してくれたり、こわばった筋肉をリラックスさせてくれるなど、生理直前の不快なむくみや張りを和らげるのに役立ちます。
生理直前のPMSの症状としての腹痛(生理痛)
生理直前になると、おなかの痛みや鈍い違和感を感じる人は少なくありません。
これは、子宮内膜がはがれ落ちる準備として、体が実際に「子宮の収縮」を起こしているためです。
出産のような激しさはないにしても、体は“何かを外に排出しよう”と動いており、その働きはプロスタグランジンというホルモン様物質によって引き起こされています。
ただし、生理直前の腹痛が日常生活に支障をきたすほど激しく、数日以上続く場合は「子宮内膜症」などの病気が隠れている可能性もあります。
これは、子宮の内膜に似た組織が本来あるべきでない場所に増殖する疾患で、激しい生理痛、卵巣嚢腫、性交痛、腰痛、骨盤痛、不妊など、さまざまな問題を引き起こす可能性があります。
生理直前の腹痛については、「痛みの強さ」と「続く期間」にしっかり目を向けましょう。
・いつもより痛みが強く感じる
・日常生活や仕事に支障が出る
・生理が終わっても痛みが続く
・市販薬が効かない
・毎月のように痛みで学校や仕事を休んでしまう
これらに当てはまる場合は、できるだけ早く婦人科で相談を。早期発見と適切な治療がとても大切です。
生理直前に起こるPMSの症状としての強い疲労感

生理直前に突然やる気が出なくなったり、疲れがどっと押し寄せることはありませんか?
この強い疲労感も、PMSの症状のひとつです。
その背景には、エストロゲンやプロゲステロンの急激な減少によって、セロトニンなどの気分を安定させる神経伝達物質が乱れることが関係しています。
エネルギーが湧かず、普段なら簡単にこなせる仕事や家事すら手につかないような強い倦怠感がある場合、それは月経前不快気分障害(PMDD)のサインである可能性もあります。
「ただの疲れかな」と流さず、気になる場合は医療機関に相談してみることをおすすめします。適切なサポートを受けることで、生理直前のPMSの症状をぐっとラクにできるかもしれません。
生理直前に起こる肌荒れ――PMSの症状としてのサインかも?
生理直前にニキビや吹き出物が増える…そんな肌トラブルに悩まされる人も多いのではないでしょうか。
これはPMSの症状のひとつで、プロゲステロンの減少によって皮脂腺の活動が活発になり、さらにエストロゲンの低下によって、排卵後〜生理前にテストステロンの影響が強く出ることが原因とされています。
“生理前の肌荒れはホルモンバランスの変化によるPMSの一症状で、食生活の工夫で改善が期待でき、症状が長引く場合は医療機関への相談がおすすめです。”
このホルモンバランスの変化が、肌をオイリーにし、吹き出物を引き起こしやすくするのです。
対策としては、食物繊維や抗酸化作用のある食品、オメガ3脂肪酸などを意識的に摂ることで、体内の解毒をサポートし、過剰な皮脂分泌を抑える効果が期待できます。
生理直前に起こるPMSの症状の多くは「よくあること」として見過ごされがちですが、それが長引いたり、日常生活に支障をきたすほど辛い場合は、医療機関でのチェックをおすすめします。
あなたの体が「いつもと違う」とサインを出しているときは、その声にしっかり耳を傾けてあげることが大切です。
※このコンテンツは情報提供のみを目的としており、医師の診断・治療・アドバイスに代わるものではありません。健康上の不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。Humming は本記事における情報に基づくいかなる損害、損失、請求等についても責任を負いかねますので、ご了承ください。
大切な人を亡くしたあなたへ。悲しみは「乗り越える」ものではなく「共に生きる」もの【リヴオンの代表理事 尾角光美さんインタビュー】

突然の別れや予期せぬ喪失。心にぽっかり空いた穴は、深い悲しみに、どう向き合えばいいか分からず、自分を責めることもあるかもしれません。でも、あなたの心に湧き上がるどんな感情も「おかしくない」んです。そして、その悲しみは決して一人で抱え込む必要はありません。今回は、大切な人を亡くした後の心の変化や、悲しみとどう「共に生きていくか」について、グリーフケアを行うリヴオン代表の尾角光美さんに伺いました。
おすすめ記事 ▶ 瞑想をするのにベストな時間は?自分に合ったタイミングで、心と体を整えるヒント
ーー 大切な人を亡くしたとき、落ち込みがちな感情とどう向き合えばいいでしょうか?
まず知っていただきたいのは、「喪失の反応は悲しみや落ち込みだけではない」ということです。例えば、お子さんを亡くした後に仕事を頑張るお父さんや、親を亡くした後に受験勉強に集中する子ども
大切なのは、亡くした直後に様々な感情や反応、影響があるということを知ることです。そして、その反応の多くは「ノーマル」で、自然なものなんです。「グリーフはノーマル」という考え方を広めることを「グリーフのノーマライゼーション」と言いますが、悲しみが深くても、逆に涙が全く出ないとしても、その反応は正常なもので、、自分は「おかしくないんだ」と思うところから始めるのが、グリーフと向き合う上での一本の軸になりますね。
ーー 「知る」ことが大切とのことで、最初はまず何をしたらいいでしょう?
そうですね。ご本人が必要なサポートを探して手を伸ばすのは、亡くした直後はなかなかハードなことなので、周りの人たちが情報などを届けるのがとても大切です。
例えば、私たちのウェブサイトにある「大切な人を亡くした人のための権利条約」はPDFでダウンロードして印刷できるので、「ちょっと参考になれば」とで、さりげなく手渡してみるのもいいでしょう。別に私たちの団体に限らず、「こういうものを見つけたから読んでみたら?いらなかったら別にいいからね」と、相手に選択肢と主導権を渡した上で、手がかりを届けていくのが大切です。
“「私はあなたのお母さんのことを知りたいんだ」ということを示してもらえると、亡くされた方は嬉しいと感じることも多いんです。”
あとは、「積極的関心」を持つこと。亡くなった人のことを知ろうとしたり、亡くした経験をしているその人の「今」を知ろうとすることです。日本人は距離を置くのが礼儀だと思いがちですが、アメリカやイギリスに行くと、初対面でも「お母さん亡くされたって?どうして?」と積極的に聞いてきます。もちろん、聞かれたくない人もいるのですが、それも聞いてみないと相手がどう思っているのかは分かりません。
でも、「私はあなたのお母さんのことを知りたいんだ」ということを示してもらえると、亡くされた方は嬉しいと感じることも多いんです。例えば、「お母さんは名前は何ていうの?」と亡くなった人の名前を聞いてくれること、それは人間だけでなくペットでも同じです。そういった積極的な関心を持ってもらえると、「亡くなって終わりじゃないんだな」と思えるのではないでしょうか。
ーー 尾角さんご自身は、お母様を亡くされたご経験から、現在のグリーフケアの活動へとつながっていったとのこと。当時はどんな心の変化がありましたか?
私は19歳の時に母を亡くしました。当時は、感情の変化はなかったんです。むしろ、うつ病でずっと「死にたい」と言っていた母が亡くなり、それしか選択肢がなかったんだという思いや、自分が「「一緒に死を選んだ」という感覚でした。母親が亡くなる時に止められなかったことを責めるというよりも、共に生きるのが苦しかったので、それしかできなかったんだという思いでしたね。
私にとって、グリーフは感情だけではないということを知れたのも大きかったです。死別後、身体の変化として腰の椎間板ヘルニアになったりした「身体的影響」以外にも、経済的な影響も大きく、大学を何度も中退しそうになり、9年かかって大学の学部を卒業しました。死んだ方がマシだと思った時期もありました。また、親の話をする友達と距離を取ったり、学校に行くのが苦しいと感じたりと「社会的影響」も大きかったんです。

でも幸い、アメリカの「ダギーセンター」という世界最大の遺児支援団体からグリーフのことを学ぶ機会があり、そこで「親が亡くなってホッとした気持ちがあったのはおかしくなかったんだ」とか「身近な人を失って何も感じないこともある」「人間関係に変化が起きるのも自然なことだったんだ」と知ることができたのは、すごく大きな支えになりましたね。
グリーフケアの活動を始めようと明確に思っていたわけではないんです。大学時代に、親を亡くした子どもを支援する団体からのご縁で、自殺で家族を亡くした遺族として行政で講演する機会がありました。そこからたくさんの遺族の方との出会いがあり、活動がスタートしました。
転機は2007年。たまたまGoogleで検索していたら「母の日」の原点が出てきたことでした。ウィキペディアに、亡くなったお母さんの好きだった白いカーネーションを配ったアメリカ人女性が母の日を始めたという話が書いてあって、「なんだ、母親を亡くしている私にとっても母の日は大事な日なんだ」と気づいたんです。それを広めたいという思いから、「母の日プロジェクト」を立ち上げました。
翌年の2008年の母の日100周年にあたり、亡くなったお母さんへ手紙をを募集し、文集を作成したのですが、これに大きな反響がありました。新聞やNHKでも特集していただき、受付の電話がずっと鳴り止まないほどでした。その電話の向こうには、母を亡くして以来、母の日が辛かった人、大嫌いだった人や、虐待を受けていたけれど母と向き合うきっかけをもらった人など、様々な方がいらっしゃいました。この活動は一回きりでは「やめられないな」と感じ、リヴオンという団体を立ち上げることになったんです。
ーー 尾角さんにとって、「死」とはどのような意味がありますか?
とても大きな質問ですね。これまでたくさんインタビューを受けてきましたが、初めて聞かれた質問です。
ありきたりな答えかもしれませんが、私にとって死は「いのちの一部」だと思っています。子どもたちにいのちの授業で「死もいのちなんだ」と伝えると、みんなびっくりするんですよね。やっぱり、「生きる」とか「生まれてくる」ということに意識が向きがちですが、死まであって初めて「いのち」なんです。そして、死してなおそこにはいのちがあり、その亡きいのちとつながることができると私は思っています。
それは、霊能力とか、見えるとかそういう話ではありません。例えば、亡くなった人のことを思って遺品を身につけたり、私にとってはネックレスだったんですけど、ちょっとした日常の中に亡き人のいのち、いのちの一部を感じながら生きている。死がそこにあるからこそ、亡くなった人が残したものになっているんです。
「いのち」の中にも「死」があるし、「死」の中にも「いのち」があると思っています。矛盾しているように聞こえるかもしれませんが、死んでもなお生きているいのちがそこにある。いのちの中にも必ず死を含めていのちが存在する、死なないいのちはない、という両面性があるなと、今自分で説明しながら気づきました。
ーー グリーフケアにおいて大切にしていることは何ですか?
当事者も、支えたいと思う人も、「悲しみをどうしたら楽にできるか」という問いを持つことがあります。でも、多分悲しみの奥にある気持ちって、その人のことを強く思っているからこそ、生まれてくるものだったりするんです。
私には母親を死なせたという罪悪感が今もあるのですが、罪悪感も「母のいのちを助けたかった」という思いがあるから生まれてきているんですよね。だから、私は感情にプラスもマイナスも本当はないと思っていて、人間が勝手にラベルをつけているだけだと考えています。
なので、私たちがグリーフケアで大切にしているのは、どんな感情もジャッジをしないということ、そして、感情の奥にあるものを大事にするということです。感情そのものも、もちろん大事にしますが、表面的なところで判断しないということがとても重要だと思っています。
“私には母親を死なせたという罪悪感が今もあるのですが、罪悪感も「母のいのちを助けたかった」という思いがあるから生まれてきているんですよね”
例えば、東日本大震災の津波で奥様を亡くされた方が、「私が殺したんだ」と自分を責めていたことがありました。でも、それをジャッジせずにそのままに聞いていくと、「自分がそばにいたら助けてあげられたかもしれないのに、私が一緒にいなかったからだ」という話が出てきたんです。その「死なせた」とか「殺した」という言葉の奥には、「助けたい」という計り知れない思いがあったのだと解釈させてもらいました。単純に「あなたが悪いんじゃないですよ、津波が連れ去ったんですよ」と言ったって、何も解決しないし、その人の罪悪感を取り除こうとすると同時に、そこにある大事なものまで聞こえなくなってしまうんです。
私たちはジャッジをしてしまうのが人間なので、大切なのは「ジャッジしている自分に気がついている」ということ。そして、「あ、私ジャッジしてるな」と思ったら、ちょっと「そのままに」この感情を見てみるのはどんな感じなんだろう、とそこを訪ねていくことを大事にしています。
感情を無理になくそうとすると、かえって大きくなるような感覚があります。まるで、お化けを「なくなれ、消えろ、あっち行け」と言えば言うほど、こちらに近づいて大きくなってくるような。ですから「あなたはなんでここにやってきたの?」という感じで、その感情と付き合っていくことをおすすめしています。

ーー 亡くなった大切な人の思い出を風化させずに、感じながら生きていくために、他にできることはありますか?
山のように選択肢や方法があります。亡くしたことを表現する営みを「グリーフワーク」といったりします。ググリーフを大切に、その人自身がグリーフを表現するものすべてをさします。
例えば、誰かに亡くした人の思い出話をすることや、亡き人が好きだった納豆を今日買って食べようとか、日々の日常の食事を通して思い出したり。音楽が好きだった人なら、命日の前に、その人の好きだった曲のプレイリストを作って聴いてみたりするのもいいですね。
最近はAIで故人と話ができるサービスなども出てきていますが、それぞれ表現方法や、亡くした人との関係をを大切にする仕方が違うものです。亡くなった人を想った時に、何をするのが自分にとってしっくりくるのか、それを選んでいくということなんです。
また、日本の文化や宗教的な生活の中にも、グリーフワークはたくさん組み込まれています。お墓参りもそうですし、お彼岸やお盆には亡くなった人が帰ってくると考え、茄子で馬などで乗り物に見立てて作ったりもしますよね。そういった日常の中に、亡くなった人を想う営みはたくさんあるんです。
ーー 私自身、最近、義理の父を亡くしました。小さな子供が二人いるんですが、私は「おじいちゃんはいなくなっちゃったんじゃなくて、天国で見守ってくれているんだよ」と伝えることくらいしかできず…。子どもたちにどう声をかけたらいいか分かりません。
まず知ってほしいのは、子どもであれ大人であれ、亡き人の存在の感じ方は一人ひとり違うということです。大人はつい「お空に行っちゃったよ」「お星さまになって見守っているよ」などと抽象的に説明しがちですが、子どもには子どもなりの実感があります。
例えば「おじいちゃんは今どこにいると思う?」と聞いてみてください。子どもはもっと自由に発想するかもしれないので、もしかしたら「天国の階段の途中で転んでるかも」とか、「土いじりが好きだったから土の中に感じる」なんて答えるかもしれません。
“亡き人の存在の感じ方は多様であることを受け止めてあげてくださいね。”
大人が先に答えを出そうとするのではなく、子どもの話をまず聞くことが大切です。もし話したくなければ「言わなくていいよ」という選択肢も持たせつつ、例えば「おじいちゃんとの思い出で一番嬉しかったことは何?」などと問いかけてみましょう。もしとんかつ屋さんに連れて行ってもらったことが思い出なら、おじいちゃんの誕生日にとんかつ屋さんに行ってみるなど、子どもの感覚を尊重した過ごし方を見つけるのがおすすめです。
亡き人の存在を感じるタイミングや場所は人それぞれです。もしかしたら、蝶々が飛んできたのを見て「あれ、おじいちゃんだったかも」と言うかもしれません。亡き人の存在の感じ方は多様であることを受け止めてあげてくださいね。
ーー 実は私もまだ、義父がこの世からいなくなってしまった現実を受け容れられていない部分があります。来月に、義父のいない家に行き悲しくなってしまうのではないかと、今から心の準備をしているところです。
「受け容れる」というのは、白か黒かではありません。グラデーションのように、心が揺らぎながらで全然いいんですよ。無理に現実を受け容れようとせず、今は距離を取ろうとしている自分をそのまま認めるのもよいのではないでしょうか。
ーー 大切な人を亡くしたことにこれから向き合おうとしている人に、どんな言葉を届けたいですか?
言葉を届けるというよりは、一つの問いを置いておきたいですね。
「あなたにとって、その失ったものを大切にするために、何かちょっと一歩踏み出してみるとしたら、どんなことができそうですか?」
グリーフは「指紋ほどに違う」と言われています。一人ひとり、感じ方も、求めている言葉も違います。だから、私がここで紡ぐ言葉が、ある人にとっては傷つくかもしれないし、ある人にとっては今、心に届くかもしれない、またある人にとっては2年後に届くかもしれない。
ーー リヴオンさんの活動に興味を持った方に、どのようなサポートがあるか教えてください。
具体的な場としては、定期的に、10代から30歳までの死別を経験した若者の集いを、オンラインと京都の現地でそれぞれ行っています。お母さん、お父さん、恋人や婚約者、親友、など、大切な身近な人を亡くした若者たちが、当事者同士で分かち合う場になります。
より幅広い方を対象に行っているのは、「グリーフケア基礎講座」というオンデマンドで受けられる学びの場です。この講座は、自分で自分と向き合うことを目的としていますが、オンラインのオンデマンド動画の向こう側には、一緒にワークをやってくれる人がいたり、私自身も講義をしているので、一人だけど一人じゃない講座を作りました。自分のグリーフに向き合いたいけれど、一人で外に出るのはちょっと…という方には、とてもおすすめです。また、喪失を経験した人を支えたいという方にもぜひご受講いただければと願ってます。
リヴオン: https://www.live-on.me/
Podcast「ゆるやか死生学」 (Spotify)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWfT7GWq-Ow1riGRR1TVnbi0i30HXLpgC (Youtube)

尾角光美 おかく てるみ 一般社団法人 リヴオン代表理事
1983年大阪生まれ。19歳で母を亡くす。あしなが育英会で病気、災害、自殺、テロ等による遺児たちのケアに携わる。2006年自殺対策基本法制定以後、全国の自治体、学校などから講演、研修の講師として呼ばれ、グリーフケア、自殺予防に関して伝え広める。2009年「グリーフケア・サポートが当たり前にある社会」の実現を目指してリヴオンを立ち上げる。石川県小松市勝光寺における「グリーフサポート連続講座」が認められ、寺院とNPOの協働を表彰する浄土宗第5回「共生・地域文化大賞」にて「共生優秀賞」受賞。日本財団国際フェローシップのフェロー5期生に選ばれ、英国に留学、2018年ヨーク大学大学院国際比較社会政策修士号取得。現在英国バース大学の死と社会センターの博士候補生として「成人形成期の親との死別経験による経済的影響」について研究中。現在は主に日本で活動。2023年よりポッドキャスト番組「ゆるやか死生学」を配信中、「死は乗り超えるもの?」「自殺・自死」というテーマで国内外の研究の紹介や、母を亡くした人や僧侶との語り合いなどを行っている。
セックスの不満をパートナーとケンカせずに話すには?
セックスの不満を伝えて、対立ではなく理解につなげる方法

長い関係の中で生まれるセックスの不満は、突然現れるわけでも、自然に消えていくものでもありません。
こういった悩みを抱えたとき、それをパートナーに伝えるのはとても難しく感じられるものです。
「相手を責めているように聞こえるかも」「ケンカになるのでは?」「ちゃんと受け止めてもらえないかもしれない」——そんな不安から、多くのカップルがセックスの不満について話すことを避けてしまいます。でも、その沈黙こそが、ふたりの距離をさらに広げてしまう原因になることも。
セックスの不満は、工夫次第でお互いを責めることなく、むしろ理解やつながりを深めるきっかけにすることができます。大切なのは、伝え方、タイミング、そして思いやり。ちょっとしたコツを押さえれば、ふたりの関係をより親密にする対話が始められます。
“セックスの不満は珍しくなく、多くは関係破綻の兆しではなく気づきのサイン。こじれる原因は内容より伝え方であり、話し合いには安心できる土台作りが大切です。”
セックスの不満を感じても、それはあなただけじゃないし、失敗でもない
まず伝えたいのは、「セックスの不満」を抱えるのは決して珍しいことではない、ということです。
多くのカップルが、ある時点でセックスに関する悩みや不満を経験します。
それは、ストレス、子育てによる疲れ、ホルモンや体調の変化、感情的な距離感、過去のトラウマ、そして単純なリビドーの違いなど、さまざまな理由によって起こります。
セックスの不満があるからといって、「関係が壊れている」わけではありません。
それはむしろ、「何かに気づくタイミング」が訪れているサインなのです。
そして多くの場合、そのモヤモヤがケンカに発展してしまうのは、不満そのものではなく、“どうやって伝えるか”に原因があります。特に、長く我慢していた場合は、感情が爆発しやすくなるもの。だからこそ、セックスの不満について話し合う前には、安心して話せる土台をつくることがとても大切なのです。
セックスの不満を伝える前に、自分の気持ちを整理する

セックスの不満についてパートナーと話す前に、まずは自分自身の気持ちを見つめ直す時間をとってみましょう。
あなたが本当に感じているのは、拒絶されたような気持ち?恥ずかしさ?孤独感?誘うことへの不安?それとも、相手から誘われたときのプレッシャー?
まずはその感情を、書き出してみてください。声に出してみたり、日記に書いたり、信頼できる友人に話したり、セラピーで練習してみるのも効果的です。
セックスの不満を伝えるとき、自分の気持ちを明確にしておくことで、感情的になりすぎず、思いやりを持って冷静に対話を進めることができるようになります。
“批判ではなく「つながりたい」という意図をやさしく伝えることで、相手も受け入れやすく建設的な会話につながる。”
セックスの不満を伝えるときに気をつけたい話し方と伝え方
タイミングを選ぶ(ヒント:ベッドルームでは話さない)
セックスの不満を伝えるなら、セックスの最中や、うまくいかなかった直後などには避けましょう。そういった場面では感情が高ぶりやすく、相手も自分も責められているように感じたり、心を閉ざしてしまいやすくなります。
代わりに、落ち着いた雰囲気でストレスの少ないタイミングを選びましょう。たとえば、散歩中やコーヒーを飲んでいるとき、あるいは事前に「ちょっと話そう」と時間を設けるのもおすすめです。
こんなふうに、やさしく切り出すとスムーズかもしれません:
「最近、からだのつながりが少し減ってるように感じてて…ケンカしたいわけじゃなくて、もっとお互いに近く感じられるように話せたらうれしいなと思って」
このように、“批判”ではなく“つながりたい”という意図を伝えることで、相手も受け入れやすくなり、セックスの不満についても建設的な話し合いにつながりやすくなります。
セックスの不満を伝えるときは、「正す」のではなく「理解しようとする」姿勢で

セックスの不満を感じているときこそ、忘れてはいけないのは、ふたりの間にはそれぞれの感情、不安、期待があるということ。
たとえば、パートナーがセックスに対して距離を感じさせるとしたら、そこにはストレス、不安、プレッシャー、恥ずかしさ、あるいは過去の拒絶体験など、何かしらの理由が隠れているかもしれません。
すぐに結論づけたり、責めたりするのではなく、こんなふうに問いかけてみてください:
- 「最近、私たちのセックスについてどう感じてる?」
- 「気持ちが乗りにくいときって、何か理由があったりする?」
- 「私の言動が理由で、実は言いにくいことってある?」
セックスの不満を話すときにこうした質問をするのは、たしかに勇気が必要です。けれどその分、正直でオープンな対話の扉が開かれるきっかけにもなります。
“セックスの不満は一回で全部解決しようとせず、まずは話し始めることが大事。完璧を目指さず、少しずつ共有していくことで関係も深まっていきます。”
セックスの不満は、一度の会話で解決しようとしないことが大切
セックスの不満や性的なすれ違いは、長い時間をかけて積み重なっていくものです。だからこそ、たった一度の話し合いですべてを解決しようとするのは、現実的ではありません。
むしろそのプレッシャーが、会話を重くさせたり、お互いに緊張を与えてしまうこともあります。大切なのは「これをきっかけに話し始めてみる」という姿勢です。完璧を求めるのではなく、少しずつセックスの不満を共有していくことが、関係を深める第一歩になります。
こんなふうに伝えてみるのもおすすめです:
「今日だけで全部解決しなくて大丈夫。まずはセックスの不満について少しずつ話していけたらと思ってる。」
セックスの不満の背景にある“恥”の感情にも気づく
セックスの不満を話し合おうとしたとき、相手が黙ってしまったり、防御的になることがあります。
その反応の裏には、恥ずかしさや罪悪感、「ちゃんとできていないのでは」という不安が隠れているかもしれません。特に、性についてオープンに話す文化の中で育ってこなかった人には、こうした感情が強く出やすいのです。
相手がそうした反応を示したときは、責めるのではなく、やさしく寄り添う姿勢を持つことが大切です。
「これは正しいとか間違ってるって話じゃなくて、また一緒に心も体も気持ちよくつながりたいと思ってるだけなんだ」
セックスの不満を伝える会話は、ときに勇気がいりますが、その先にはより深い信頼と親密さが待っています。
セックスの不満に行き詰まりを感じたら、専門家のサポートを検討してみる

ときには、いくら自分たちで頑張っても、会話のスキルや工夫だけでは解決できないセックスの不満があります。それは、あなたやパートナーが悪いからではなく、問題の根が深く、自分たちだけで整理するには難しい場合もあるからです。
多くのカップルが、長いあいだセックスの不満を抱えたまま避け続けたり、ストレスや傷ついた気持ちを溜め込んだ末に、セックスセラピーに訪れます。セラピーは、そうした負のパターンに気づき、本当の課題に向き合い、感情的にも性的にも新しいつながり方を築くための安全な場を提供してくれます。
性欲の低下、欲求の不一致、性交時の痛み、パフォーマンスの不安、「ただの同居人のようになってしまった」関係——
どんなセックスの不満にも、サポートはあります。そして、希望もあります。
まとめ:セックスの不満を話すことは、パートナーシップを深める最強の一歩
セックスの不満について話すのは勇気がいることですが、実はそれは相手との関係を大きく前進させる力を持っています。
完璧さでも、回数でも、技術でもありません。
「ちゃんと見てもらえている」「求められている」と感じ、パートナーと安全な心のつながりを築くことこそが、本当の親密さです。
あなたの声を届けるのに、ケンカをする必要はありません。
必要なのは、適切なタイミングと伝え方、そしてやさしさと誠実さを持ってそこに向き合う意志です。
【ハミングが届けるポジティブニュース】 生きものたちが帰ってくる場所──世界のやさしい取り組み

今年の夏は、気候変動の深刻さを感じずにはいられない暑さが続いていますね。私たちが暮らす地球では、環境破壊が続き、当たり前だと思っていた自然が少しずつ失われています。
ホッキョクグマやミツバチといった動物たちも、生きる場所を奪われ、絶滅の危機にさらされていると聞くと、胸が痛む方も多いのではないでしょうか。
「こんなニュースばかりで、正直もう気が滅入ってしまう」「未来に希望なんて持てるの?」そういった声が聞こえてきそうです。
でも実は今、世界のあちこちで、壊れてしまった自然を取り戻そうと粘り強く努力する人たちがいて、その成果が少しずつ現れているのをご存じでしょうか。
イギリスのケンブリッジで開かれた環境保全の会議では、そういった「破壊を食い止め、逆転させた」数々のストーリーが紹介されました。今回はその中から、未来への小さな希望を感じられる取り組みをいくつかご紹介します。
“猛暑が続き、地球規模で自然や動物たちが危機にさらされていますが、世界各地では自然を取り戻そうと努力する人々がいます。”
内戦で荒廃したモザンビークでゾウが復活
例えばアフリカのモザンビーク。1980年代の内戦では、地雷や密猟によってゾウやカバ、シマウマなどが壊滅的な打撃を受けました。しかし現在、複数の保護区域や緑地をつなげて動物の安全な移動経路を確保する取り組みなどの長期的プログラムのおかげで、野生動物の数は内戦前を上回るまでに回復しています。
この取り組みがうまくいった理由のひとつは、地域開発との連携です。女子生徒の教育プログラムなどを同時に進め、地域住民が「保護」に協力したいというモチベーションを高めました。野生動物の保護は、地域社会の発展とも結びつけられるのです。
【おすすめ記事】正直者がもらったごほうび──14歳の少年が拾った財布に込めた優しさと、思いがけない贈り物
イギリスで広がる「野生に戻す」プロジェクト
イギリスもかなりの努力をしています。なんと、「イギリスにはマクドナルドより多くの自然保護区がある」のだそうです!
例えば、スコットランド高地は(アメリカの中でも人口が少ない州である)モンタナ州より人口密度が低く、大規模なリワイルディング(人間の開発や農業、都市化などで失われてしまった自然環境を、人ので「野生が息づく状態に戻す」試み)が進んでいる例です。農業的な生産性が高くない地域だからこそ、大胆な自然再生が可能なのです。
海でも起きている「静かな奇跡」

そして陸上だけでなく、海でも劇的な回復が起きています。
環境ジャーナリストのチャールズ・クローバー氏は、20年前には地球上には「終わりの物語」しかなかったと言います。例えば、彼が最初の書籍を出した2005年頃は、乱獲のせいで魚の資源はほとんど絶滅寸前でした。
しかし、NGOの圧力、漁業者たちの意識変化、そして珍しいことではありますが「政府の行動」がわわさり、状況は一変しました。クローバー氏の2022年の最新の著書は『海のリワイルディングする(Rewilding the Sea)』。その名の通り、今では海を「再び野生化」し、魚たちが戻りつつあるのです。
“かつて絶滅の危機にあった大西洋クロマグロやライム湾の海洋生態系は、科学的管理や底引き網禁止により魚の数が約4倍に増加しました。この成功事例は他地域にも広がり、タイやエンジェルシャークなども回復の兆しを見せています。”
マグロが400%増加し、「サンゴの庭」も回復
大西洋クロマグロは、かつて「最後の一匹まで獲り尽くされてしまう」とまで予測されていた魚ですが、科学的根拠に基づく漁獲管理の導入でマグロの数は400%増加しました。60年以上も見られなかった場所で再び姿を現しつつあるんです。
さらに、イギリス南西部に広がるライム湾。かつては「イングランドのサンゴの庭」と呼ばれた場所ですが、底引き網漁で海底は荒廃していました。16年前に底引き網を禁止した結果、魚の数は4倍に増えました。
このモデルケースは、イギリスやギリシャなどの別の地域でも導入され、同様に期待が持てる成果を上げています。かつて深刻に絶滅が危惧されていたタイやエンジェルシャークも回復の兆しを見せています。
「まだ終わりではない」けれど、希望は確かにある
もちろん、まだまだ課題はたくさんあります。世界中で続く大規模な漁業や開発が、今も多くの海や森を脅かしているのも事実です。
それでも、「もうだめだ」と思われた場所が、きちんと守り方を見直し、人や地域が力を合わせることで、少しずつ命を取り戻している例が増えています。
地雷原を越えて戻ってきた象の群れ、再び色を取り戻したサンゴの海、何十年ぶりに泳ぐマグロの群れ──どれも、科学の知恵や地域の暮らし、国境を越えた協力が生んだ希望の風景です。
「もう終わりだ」と嘆きたくなる今のような時代だからこそ、こうした小さな回復の物語に目を向けてみませんか。
パートナーとポルノを観てみたい? 2人の距離を縮める、50のセクシャルな質問リスト

パートナーと一緒にポルノを観るのって、ちょっとハードルが高く感じるかもしれません。でも、実はそんなに構える必要はないんです。リラックスして楽しむために、2人の会話のきっかけになるようなセクシャルな質問を50個ご用意しました。
正直なところ、カップルでポルノを観るのは勇気がいること。
「どうやって切り出せばいい?」「どんなジャンルが観たいか、恥ずかしい気持ちにならずに話すには?」——そんな不安もあるはず。
そこで今回ご紹介するのは、ポルノをテーマにしたカップル向けの50の質問。
気まずさを和らげて、お互いの欲望や好みを自然にシェアできるようサポートします。2人のコミュニケーションを深めるきっかけとして、ぜひ活用してみてください。
おすすめ記事|安全で満足できるバーチャルセックスの楽しみ方
パートナーとポルノを観たいなら──安心して話し合うためのコツとセクシャルな質問の使い方
タイミングと場所を大切に
パートナーとポルノについて話すなら、そのタイミングがとても大切です。
仕事で疲れていたり、出かける直前の慌ただしい時間に切り出すのは避けましょう。
おすすめなのは、お互いにリラックスできる夜、静かな自宅など、落ち着いて向き合える時間。
この会話は、すでに盛り上がっているときにしかできないわけではありません。
むしろ、こうしたセクシャルな質問を使うことで、パートナーとポルノを自然に楽しむ流れが生まれていきます。
ジャッジのない空間をつくろう
「パートナーとポルノを観てみたい」と思っていても、それを口に出すのは勇気がいるもの。
そんなときこそ、お互いが安心して話せる“ジャッジのない空間”をつくることが大切です。
このセクシャルな質問リストは、関係を深めたり、新しい楽しみ方を共有するためのツールです。 決して相手を責めたり、今の関係に不満があるという意味ではないことを、最初にしっかり伝えましょう。
少し気まずく感じる答えも、正解・不正解はありません。 「はい」「いいえ」で終わらせず、自由に話せる空気をつくってあげてください。
軽めの質問から少しずつ深めて
いきなり大胆な話題から入ると、相手が戸惑ってしまうことも。
まずは軽くて楽しい、ちょっとだけドキッとするような質問からスタートして、
会話の中で少しずつお互いの興味や好みを探っていくのがポイントです。
パートナーとポルノについて話すことは、2人の親密さを高めるひとつの方法。
無理せず、少しずつ、自分たちのペースで楽しんでみてください。
パートナーとポルノを楽しむための、ちょっとセクシーな質問集

Step 1: まずはアイスブレイクから
- いきなり本題に入る前に、まずは会話を温めてくれる軽めで楽しい質問から始めましょう。
- 深刻になりすぎず、自然と会話が盛り上がるような内容ばかりです。
- 秘密の片思いをした架空のキャラクターっている?それは誰?
- 理想のセクシーなシチュエーションってどんな感じ?細かいところまで教えて!
- においをかぐとムラムラする香りってある?
- 自分が一番セクシーに感じる服装ってどんなの?
- 先生とか、立場が上の人に恋したことってある?
- 架空のキャラクターと1日だけ入れ替われるなら、誰になりたい?
- 恋人やパートナーとした、一番衝動的なことって何?
- ロールプレイするなら、どんなシチュエーションが気になる?
- 音楽のプレイリストの中で一番誘惑される曲は?
- 好きな人に関する夢で、一番記憶に残ってるのは?
- 恋愛小説を書くなら、どんなストーリーにする?
- 誰かの気を引くためにやった、一番あざとい・大胆なことは?
- あまりにリアルで、「本当だったらよかったのに…」と思った夢はある?
”この質問リストは、安全でジャッジのない空間の中で、あなたとパートナーが性的ファンタジーを探求する手助けをしてくれます。”
Step 2: 境界線と安心感についての質問
この質問は、パートナーとポルノを楽しむうえで、お互いが無理をせず心地よい範囲で過ごせるようにするためのものです。いきなり深みに飛び込むのではなく、境界線や不安を事前に共有しておくことが大切です。
- 観るとしたら、朝・昼・夜のどの時間帯が好き?
- 絶対に観たくない/触れたくない内容ってある?
- この体験をより安心して楽しめるように、私にできることはある?
- 始める前に、決めておきたいルールや境界線ってある?
- 避けたいテーマやジャンルはある?
- 無理してない?それとも本当に興味があって試してみたい?
- 一緒に観る時間はどのくらいがちょうどいい?
- 一時停止や中止の合図(セーフワード)を決めておくのはどう思う?
- どちらかが楽しめていないとき、どう対応する?
- この体験に対して、期待していることやちょっと不安に思っていることはある?
- 信頼できるクリエイターやサイトってある?
- 事前に「やってOKなこと/NGなことリスト」を作っておくのはどう?
Step 3: セクシャル・ファンタジーと欲望を探るための質問
もっと深く踏み込みたいと思ったら、ここからが本番。
この質問リストは、安全でジャッジのない空間の中で、あなたとパートナーが性的ファンタジーを探求する手助けをしてくれます。
まず大切なのは、「セクシャル・ファンタジー(性的空想)」と「セクシャル・デザイア(性的欲望)」は別物であるということ。
“セクシャル・ファンタジーは、覚醒時に性的興奮をもたらすイメージや思考で、突然浮かぶ場合も意図的に描く場合もあります。”
セクシャル・ファンタジーとは?
「セクシャル・ファンタジーとは、覚醒している状態で感じる性的に興奮するイメージや思考のことです(つまり夢ではありません)。
ファンタジーは突然浮かぶこともあれば、意図的に思い描くこともあります。興奮を高めるため、退屈をまぎらわせるため、リラックスするためなど、理由はさまざまです。
ファンタジーの最大の特徴は、それが性的興奮をもたらすということ。
でも、興奮する=実際にやりたいとは限らないんです。」
——ジャスティン・レミラー博士(キンゼイ研究所フェロー/『Tell Me What You Want』著者)
セクシャル・デザイアとは?
「一方でセクシャル・デザイアは、実際にやってみたいと思っていること。
性的な未来のプラン、叶えたい願望、試してみたいと思っていることを指します。」
——レミラー博士
これから紹介する質問をパートナーと一緒に試すとき、
「これは空想にすぎないのか、それとも実際にやってみたいと思う欲望なのか?」を意識してみてください。
自分にとっての違いを見つけるヒントになります。
- 気分が高まる映画のシーンってある?
- ゆっくりと盛り上がるのが好き? それとも激しめな展開?
- セクシーに感じる言語やアクセントってある?
- ストーリー重視? それともシンプルに始まる方が好き?
- ユーモアがある作品と、真面目な雰囲気、どっちが好み?
- 室内と屋外、どちらのシチュエーションが好み?
- 複数人でのプレイについてどう思う?
- 実際のカップルの動画を観るのはどう感じる?
- タブーや禁断のテーマのファンタジーについてはどう?
- 興味をそそられる特定の関係性や力関係はある?
- 手や足など、特定の体の部位にフォーカスされるのは好き?
- 教育的・学習的な要素を含んだビデオについてどう思う?
- 支配と服従のテーマには興味ある?
- 食べ物を使ったプレイには興味ある?
- クローズアップと全体的な画、どちらが好み?
- 初対面の設定と、関係性のある恋人同士の設定、どちらが好き?
- ファンタジーや超自然的な要素が出てくる作品に興味ある?
- 興奮を感じる声や話し方ってある?
- 性別や役の入れ替えについてどう思う?
- ストーリーの過程を楽しみたい? それとも結末が大事?
ポルノを選ぼう:はじめての「パートナーとポルノ」体験をポジティブにするためのヒント

自分たちに合ったコンテンツを選ぶ
最初に出てきた動画を何となく選ぶのではなく、自分たちに合った内容を意識的に選びましょう。
お互いに安心して楽しめるような、倫理的で合意のある内容がおすすめです。
目的はただ興奮することではなく、本物のつながりを感じる体験を共有すること。
「一緒に楽しむ」ことに重きを置いてみてください。
ムードを整える
観るのはコンテンツだけじゃありません。「どう観るか」も大切なポイントです。
部屋の明かりを少し落として、リラックスできる空間をつくりましょう。
スマホなどの気が散るものは脇に置いて、2人だけの時間に集中してみてください
会話を止めない
一緒に動画を観ながらも、感じたことや好きなシーンについて話すことを忘れずに。
「ここ好き」「こういうのもいいかも」など、途中で動画を止めて会話するのもOK。
そうすることで、ただ観るだけじゃない、双方向で心地よいセクシャルな体験が生まれます。
そのやり取り自体が、とてもセクシーで親密な時間になるはずです。
“どちらかが気まずさを感じたら、一歩引いて、何が不安だったのか、どこが心地よくなかったのかを話し合ってみてください。”
Step 4: 振り返りとつながりのための質問
一緒に観終わったあとは、お互いの気持ちを確認する時間も大切です。
この体験がどう感じられたのか、じっくり振り返ってみましょう。
- 一番ドキドキしたシーンはどこだった?
- 予想外だったことってあった?(良い意味でも、悪い意味でも)
- 実際の体験は、事前に想像していたものと比べてどうだった?
- 今後もっと試してみたいと思ったことはあった?
- 今日の「一緒に観る体験」に点数をつけるとしたら10点中何点?その理由は?
パートナーとポルノを観るときによくある不安とその対処法
- パートナーのどちらかが気まずく感じたら?
それは、すごく普通のことです。誰でも最初はちょっと戸惑います。
どちらかが気まずさを感じたら、一歩引いて、何が不安だったのか、どこが心地よくなかったのかを話し合ってみてください。
そうやって少しずつ歩み寄ることが、本当のパートナーシップを育てる一歩になります。
- 好みが合わなかったらどうする?
好みが違うのは自然なこと。無理に合わせる必要はありません。
2人のちょうどいい“中間”を見つけることが大切です。
そして何より大事なのは、「一緒に楽しもう」とする気持ち。
妥協することも、意外とセクシーだったりしますよ。
- 思ってたようにうまくいかなかったら?
もしちょっと微妙な結果だったとしても、大丈夫。
一度休憩して、お互いにどう感じたかをシェアしてみて。
またタイミングを変えて、心地よく感じられるときにチャレンジすればいいんです。
そもそもパートナーとポルノを観る理由のひとつは、相手の「興奮のツボ」を知ることや、なかなか言い出せない性の好み・願望について話すきっかけをつくることです。
この“発見の時間”に、焦りは必要ありません。
パートナーとポルノを観ることは、恥ずかしいことでも気まずいことでもありません。
むしろ、お互いをもっと深く知り合うためのチャンスです。
今回ご紹介した質問を使って、安心できる楽しい空間をつくりながら、2人だけの新しいつながりを育んでみてください。
毎月のことだから、もっとやさしく。安全でサステナブルなオーガニック生理用品を選ぶということ

生理は、私たちの暮らしの中でごく自然な出来事。
でもその「当たり前」の中に、実はたくさんの選択肢があることを知っていますか?
毎月数日間、肌に直接触れる生理用品。
その選び方ひとつで、私たちの体や心、そして地球にもやさしい影響を与えることができます。
おすすめ記事:【映画レビュー】ナプキン一枚が変える未来――インドの女性たちの闘い
肌に触れるものだから、「オーガニック生理用品」で安心を
市販の使い捨てナプキンには、漂白剤や香料、吸収ポリマーなど、肌に刺激を与える可能性のある成分が含まれていることがあります。 特にデリケートゾーンに長時間触れるものだからこそ、素材の安全性にはこだわりたいところ。
近年注目されているのが、オーガニック生理用品。
オーガニックコットンを使用した布ナプキンや、化学物質フリーの吸水ショーツは、肌への負担が少なく、敏感肌の方にもおすすめです。
生理と環境をつなぐ、オーガニック生理用品で「サステナブル」という選択
使い捨ての生理用品は、プラスチックや化学素材を多く含み、生涯で約1万枚以上が廃棄されるとも言われています。
しかし、オーガニック生理用品はその多くが再利用可能で、ごみの削減にもつながります。
「自分にも、環境にもやさしい選択」をすることは、これからの時代を生きる私たちにとって大切なテーマになっています。
無理せず、オーガニック生理用品で自分らしく始める
「いきなり全部変えるのはちょっと不安…」そんな人は、まずは家で過ごすときだけ布ナプキンを使ってみる、夜用だけ吸水ショーツにしてみる、といった自分のペースでのスタートがおすすめです。
はじめてのオーガニック生理用品でも、今は選択肢が豊富。デザインも機能性も進化していて、きっとあなたに合うものが見つかるはず。
肌にも環境にもやさしい、オーガニック生理用品おすすめ5選
GladRags(グラッドラグス)|アメリカ
オーガニックコットン100%の布ナプキンを提供する、アメリカ・ポートランド発のブランド。洗って繰り返し使える設計で、使い捨てナプキンに代わるエコで安全な選択肢として人気。環境と体へのやさしさを追求しています。
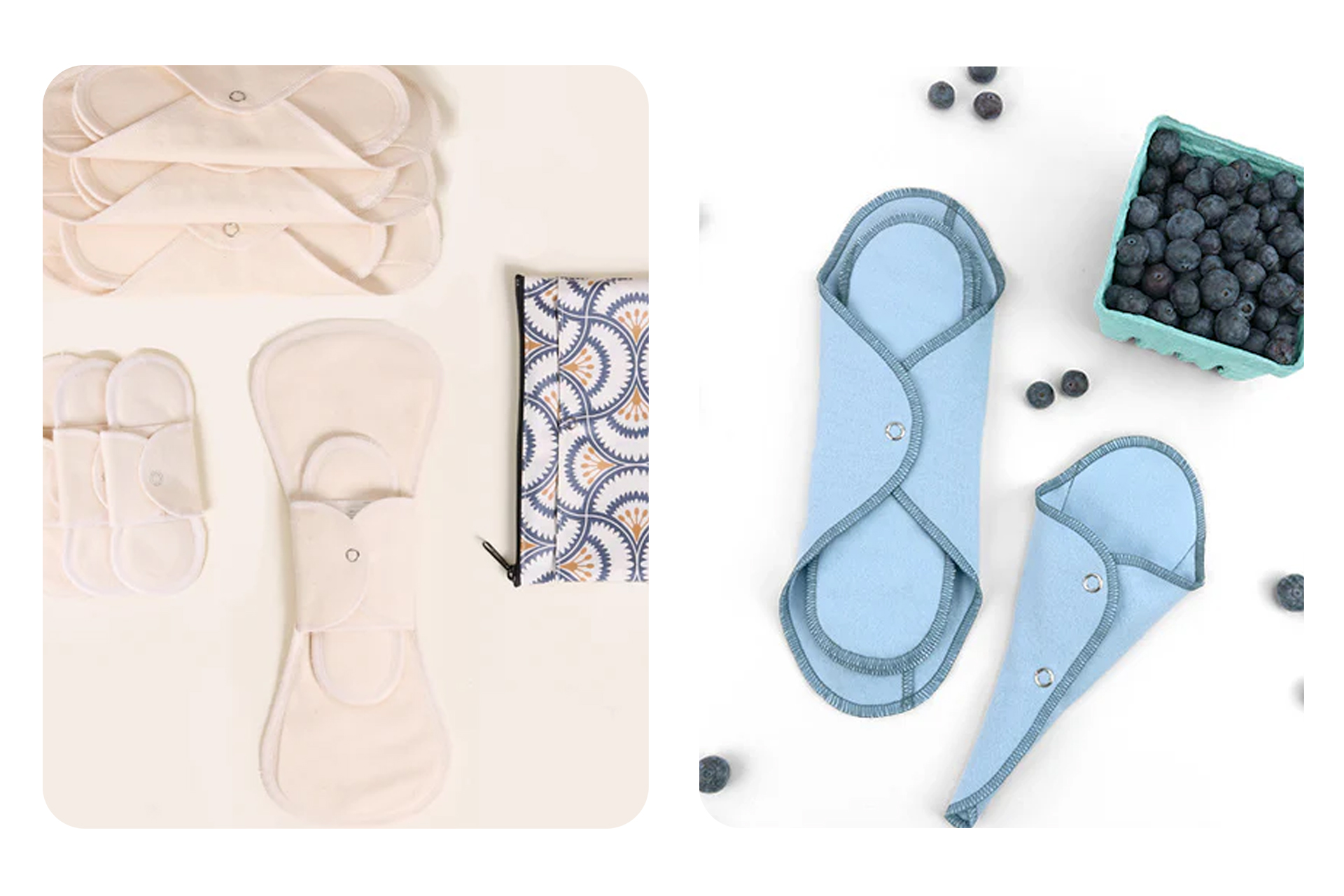
Eco Femme(エコフェム)|インド
インドの女性たちによって作られた、オーガニック布ナプキンブランド。GOTS認証取得、プラスチックフリー。エシカルな雇用と女性支援の側面もあり、使うことで社会貢献にもつながります。

DAME(デイム)|イギリス
サステナブルな生理用品のリーディングブランド。再利用可能な布パッドや、通気性と吸収性に優れたオーガニック吸水ショーツを提供。美しいデザインと高機能性が特徴です。国際配送にも対応。
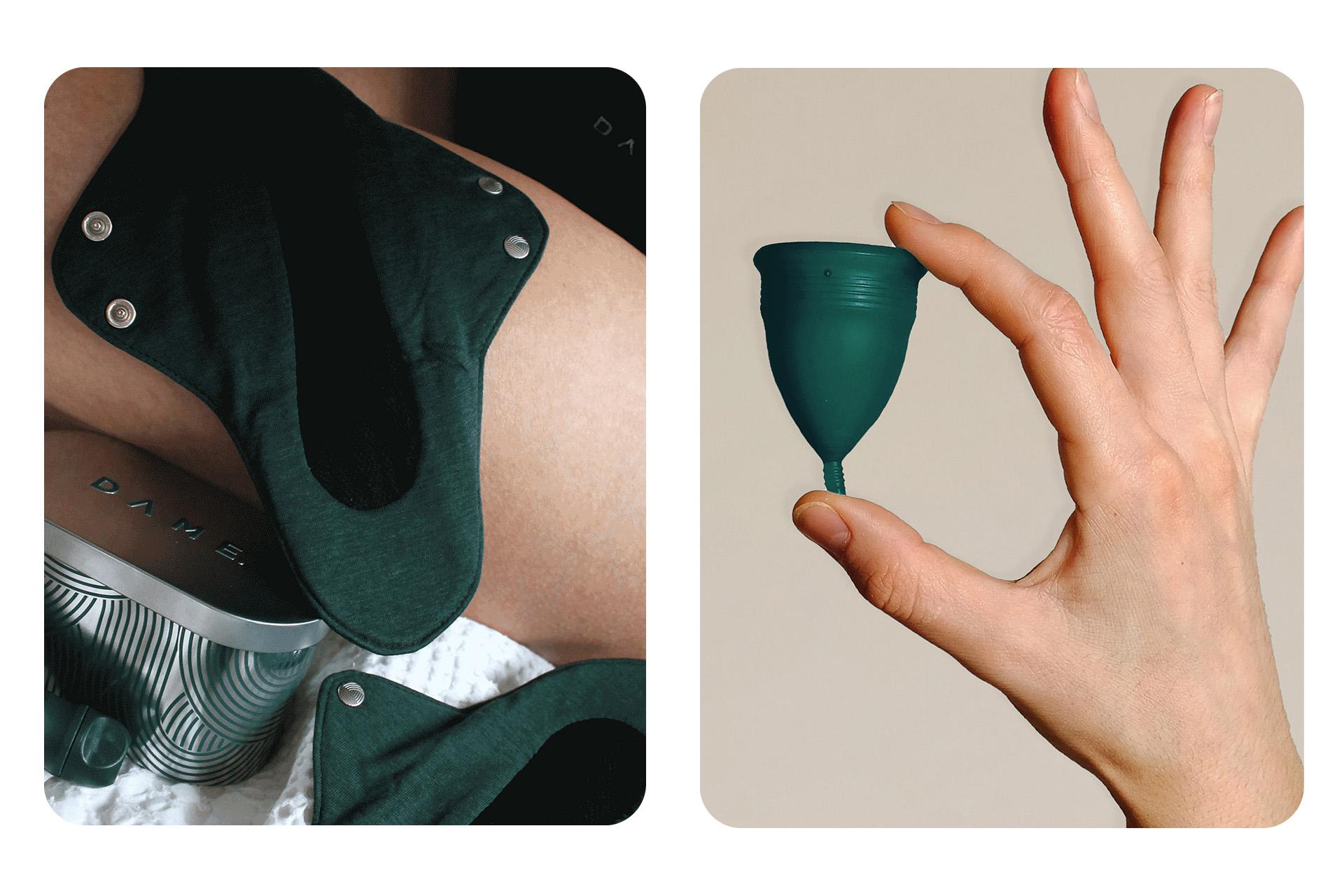
Fermata(フェルマータ)|日本
国内外のフェムテック製品を取り扱うオンラインセレクトショップ。日本製の「Period.」や「Bé-A」、台湾の「Moon Pants」など、安心・安全な吸水ショーツや布ナプキンを厳選して販売。全国送料無料キャンペーンもあり。

Aisle(アイル)|カナダ
布ナプキンや吸水ショーツなど、スタイリッシュかつ実用的な製品を展開。すべての製品はPFASフリーで、長持ちする高品質設計。LGBTQ+フレンドリーなブランドとしても知られています。
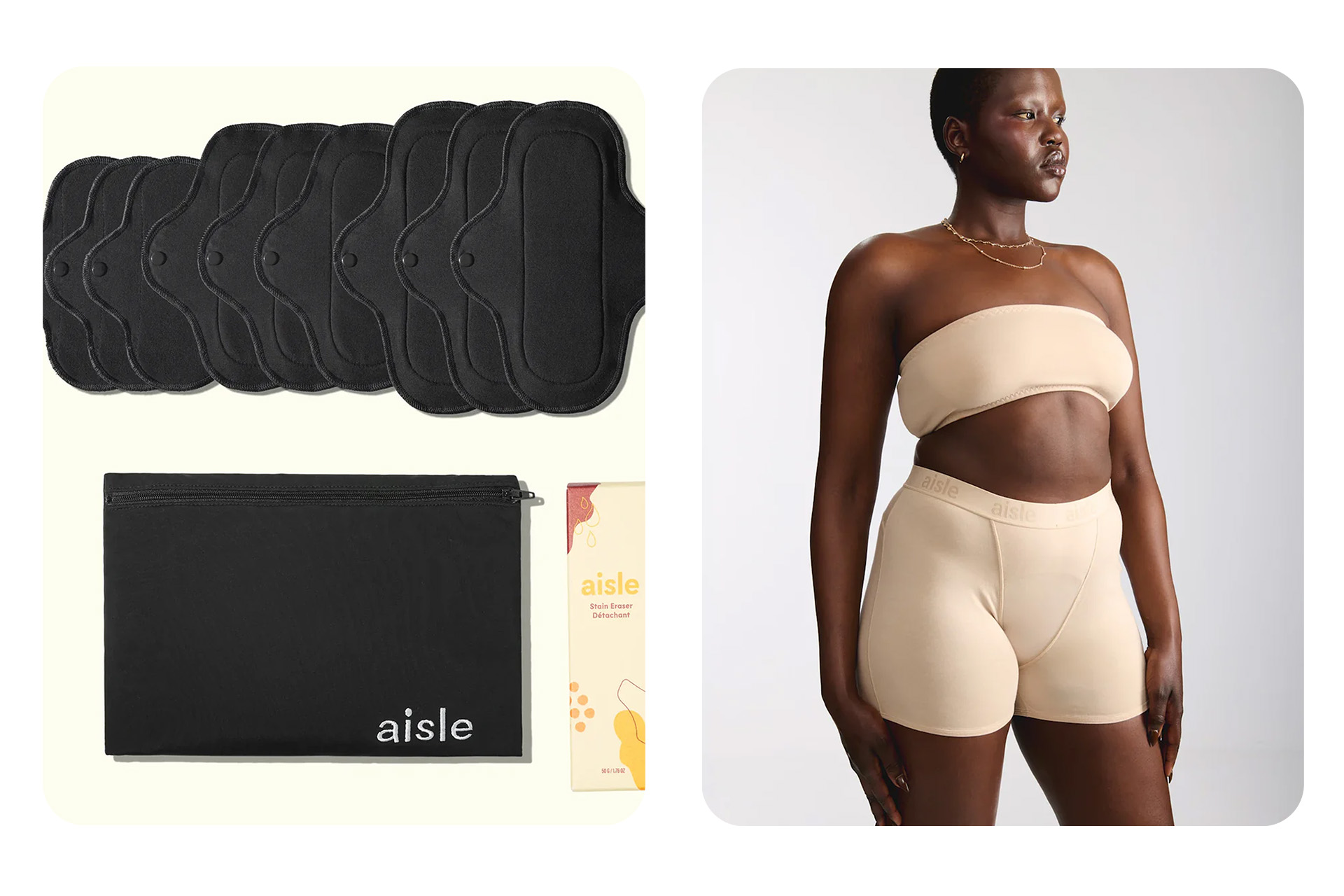
まとめ:自分の身体と、未来のためにできること
生理用品は、単なる道具ではなく、自分の身体に寄り添うパートナーのような存在。
毎月使うものだからこそ、安心できる素材で、心地よく過ごせるものを選びたいですよね。
オーガニック生理用品は、そんな思いに応えてくれるやさしい選択肢です。
今日の小さな選択が、明日の自分や、地球にとっての大きな一歩になるかもしれません
特権階級のためのポルノ – セックスワークをめぐる「自由」と「責任」──フェミニズムの視点から

数年前、私が若き急進的フェミニストだった頃のこと。地元で開催された毎年恒例の「テイク・バック・ザ・ナイト(夜を取り戻そう)」ラリーに参加し、街を行進していました。私たちは通りを練り歩きながら、ときに立ち止まって、男性特権の象徴とされる様々な施設の前でスローガンを叫びました。そのルートの中には、毎年必ず立ち寄る地元のポルノショップがあり、私たちは「ポルノは理論、レイプは実践だ」と声を上げていました。
それからまだ20年も経たないうちに、ポルノ、売春、そして女性の性的な側面を商業目的で搾取することへの従来のフェミニズムの反対姿勢は、大きく揺らぐことになります。「チョイス・フェミニズム」と呼ばれる第三波フェミニズムは、「セックスワーク(性労働)」を正当な雇用形態として捉え、女性のエンパワーメントや性的解放に寄与するものとして肯定しようとしています。
チョイス・フェミニズムは、本質的に女性のセクシュアリティの他の領域にも適用する考え方です。「私の体、私の選択(My body, my choice)」というスローガンがそのまま使われ、女性が自らの意思でセクシュアリティを売る権利があるとされ、その選択はすべて、女性の権利の正当な表現としてフェミニストに支持されるべきだと主張されます。
“多くの人は、セックスワークがタブー視される背景に、女性の性的行動を制限し悪者化する家父長制的な力があると指摘しています。しかし第三波フェミニズムが描く「エンパワメントとしてのセックスワーク」は特権的少数派の経験に偏り、現実の多くの労働環境や搾取の実態からは乖離しています。”
フェミニズムとセックスワーク──誰の物語が語られているのか?
さらに一歩進んで、多くの人々は、セックスワークが社会的にタブー視される背景には、女性の性的行動をコントロールし、セックスを楽しんだり、自らの利益のために性を活用する女性を悪者扱いする、家父長制的な力が深く関係しているとまで主張しています。
セックスワークを「エンパワメント(自己肯定)の選択」として描く際、第三波フェミニズムは、しばしば特権的な少数派の経験に焦点を当てがちです。しかし実際には、彼女たちが業界全体に占める割合はごくわずかです。
売春、ポルノ、ストリップといった異なる実態をもつものが、「セックスワーク」というひとつのカテゴリに一括りにされてしまっています。そして、セックス産業にあえて足を踏み入れるフェミニストたちの多くは、顧客との直接的な関わりが少ない領域に惹かれていきます。そうした分野では、比較的安全な労働環境が整っており、自分の演じる内容や境界線を高いレベルでコントロールできることが多く、実際にセックス行為をともなわない仕事も少なくありません。
もちろん、セックスワークに従事するフェミニストの多くが、搾取にさらされている他の女性たちとの連帯を本気で望んでいることに疑いはありません。しかし問題は、そうした女性たちが語るストーリーが、現実とはかけ離れた、いつでも抜け出せるような“特例的なセックスワーク体験”になってしまうという点にあります。

フェミニズム内部でも、こうした複雑さが無批判に語られているわけではありません。たとえばバーレスク・パフォーマーのキャサリン・フランクはこう書いています。
「私のパフォーマンスがどう解釈されるかを、私は予測も指示もできない。ハイヒール、ストッキング、サスペンダーといった衣装を自覚的に身につけることで、“私は性の対象を装うことを選んでいる”というポストフェミニズム的な主張をしていたとしても、ある男性には単なるセックス対象として映るかもしれない。その解釈が私を否定するわけではないが、男性たちが私のパフォーマンスを勝手に再解釈する力に気づくと、私は我に返る。もし私が意図的に演じている役割が、“女性とはこういうもの”、“娼婦とはこういうもの”、“私とはこういう人間”と捉えられるとしたら――果たして何かが本当に変わったり、覆されたりしているのだろうか?」
この問いは、セックスワークとフェミニズムの関係を考えるうえで、今もなお私たちに深く問いかけてきます。
フェミニズムと「選択」の美化──見えなくなる暴力と二重基準
こうした微妙で深い議論は、残念ながら一般の討論にはほとんど反映されていません。フェミニスト・セックスワーカーたちが語る「エンパワメント」の物語は、セックスワーク擁護派やポルノ業界によって都合よく利用され、ポルノや売春に伴う現実の虐待や搾取を覆い隠すためのツールとなってしまっています。
ごくわずかな人々の経験があたかも業界の標準であるかのように語られ、実際に存在する暴力・強制・トラウマ的な現実は、「本人の選択」という魔法の言葉でまるごと消されてしまうのです。
“フェミニスト・セックスワーカーの「エンパワメント」物語は一部の特例的経験に偏り、業界の暴力や搾取を覆い隠す道具として利用されがちです。”
ここで欠けているのは、「フェミニストによるセックスワークという選択も、場合によっては倫理的に問題があるかもしれない」という視点です。「すべての女性の選択は尊重されるべきだ」とするチョイス・フェミニズムの立場は、かえって女性の道徳的判断力を軽視し、男性に対しては当然求められる社会的・政治的責任を、女性だけが免除されるという二重基準を作り出しています。
このような態度は、結果的に女性を深く見下すものです。私たちは一般に、ある人が「うまくできていなくても」称賛するのは、その人がそれをできたこと自体が驚きに値するときです。たとえば、幼児が人間らしい形の落書きを初めて描いたとき、大人たちはそれをモナリザのように褒め称えます。
同じように、女性がどんな選択をしても「それが選択である」というだけで無条件に称賛されるのだとしたら、女性全体を未熟で判断力の乏しい存在として扱っていることになりませんか?
それが本当に、フェミニズムの目指す尊厳ある平等と言えるのでしょうか。
フェミニズムと「選択」の責任──自由とは何を意味するのか?

深く傷つけられたごく少数の女性にとっては、「お金のために性的に貶められる」という選択が一見“救い”のように見えることがあります。しかし、それは彼女たちがこれまで受けてきた被害を、自ら繰り返すことにつながる可能性もあります。
本当の意味での「自由の回復」とは、こうした女性たちが自らの尊厳を取り戻し、しっかりと自分が納得できる選択ができるようサポートすることにあります。
“真の自由とは、尊厳を取り戻し納得できる選択ができるよう支援することであり、「チョイス・フェミニズム」が全ての選択を無条件に肯定する姿勢は、女性の主体性や倫理的判断を弱める危うさがあります。”
選択は自由な空間の中で行われるものではありません。長年にわたって暴力的に自律性を奪われてきた人が、再び搾取されるような状況に引き寄せられるのは、「それが普通」だと感じてしまうからです。
とはいえ、こうしたケースはごく一部です。
ほとんどの女性は、大人としての倫理的判断力と決断力を十分に持っています。
たしかに、外的・内的な制約が自由を妨げることはあります。けれども、私たちは未熟な存在ではなく、良い選択も、悪い選択もできる存在です。
「チョイス・フェミニズム」は、すべての選択を肯定することで、女性の選択に含まれる道徳的な側面を曖昧にし、結果的に女性の主体性を弱めてしまう危うさをはらんでいます。
なぜなら、ポルノや売春に関わる一部の女性が、「意図的に」選んだ選択であっても、それが倫理的に誤ったものである可能性を、あえて見ないようにしているからです。
本当の意味で女性の「選択」を尊重するとは、それが単なる個人の解放や自己実現ではなく、社会的・政治的に意味を持つ行動であるということです。
主体性とは、自分の内面に留まる力ではありません。他者や社会にも影響を与える、意味ある行動を起こす力なのです。
主体性とは何か──フェミニズムが問うべき「選択」の重み

女性の選択に本当の意味で倫理的重みを認めるということは、それが単なる個人の問題ではなく、男性の選択と同様に社会的・政治的な影響力を持つものとして捉えることを意味します。
主体性とは、単なる「自己肯定」や「解放感」ではなく、自分を超えて広がる影響を持つ“意味ある行動力”です。
たとえば、ある女性が自らを性的対象として売り、それを「私はこれで力を得ている」と主張したとき、彼女はその行動を他者(とくに男性)がどう解釈するかについての倫理的責任から完全には逃れることができません。
“自由とは「何でもできること」ではなく、その選択が他者にどう受け取られるかも含めて責任を負うことです。”
たとえフェミニストが異性愛的な「女性らしさ」に挑むために、意図的に“セックスオブジェクト”の役割を演じたとしても、そのパフォーマンスの意味を観客(とくに男性)は必ずしも共有していないのです。
男性がピープショーに足を運ぶのは、女性のセクシュアリティや欲望の政治性について自己批判的に考えるためではありません。この現実を無視することは、過激な主体性ではなく、危うく自己中心的な無責任です。
ポルノ、売春、セックス産業の倫理的側面に向き合うためには、そこが女性が被害者として搾取される場であると同時に、女性の欲望や権力性が表れる場でもあることを認めなければなりません。
私たちが分析の中から、女性の虚栄心、欲望、男性を性的に支配する力などを取り除いてしまえば、性の領域での女性の道徳的責任について語ることはできなくなります。
それはつまり、女性の自由を矮小化し、本来の尊厳——客観的かつ倫理的・政治的意味を持つ選択を行う力を否定することにもつながるのです。
自由とは「なんでもできること」ではなく、結果に責任を持てることでもあるのです。
※本記事は、米国のカトリック系思想誌『First Things』に掲載されたメリンダ・セルミス(Melinda Selmys)による記事の翻訳です。
メリンダ・セルミスは、『Sexual Authenticity: An Intimate Reflection on Homosexuality and Catholicism(性的オーセンティシティ:同性愛とカトリシズムに関する親密な考察)』および『Slave of Two Masters』の著者です。
【映画レビュー】Minari | ミナリとアメリカン・ドリーム

男であるとはどういうことか?
これは何世代にもわたって問い続けられてきたテーマであり、今でも議論を呼ぶ問いです。
私の父は20代前半に日本からアメリカへと移住し、成功と富を夢見て「アメリカン・ドリーム」を追いかけました。母はそのすぐ後に父のもとへ渡り、ふたりは結婚して家庭を築き、数年後に私は生まれました。
『ミナリ』は、同じように夢を追ってカリフォルニアに移住し、その後アーカンソーの田舎に落ち着いた韓国人家族の物語です。
でも、それは誰の「アメリカン・ドリーム」だったのでしょう?
私にとってこの映画の核となったのは、むしろ静かに描かれる「男性の自尊心」、特に「一家の大黒柱であること」に対する男性の誇りでした。
初めてこの映画について聞いたとき、私は、白人が多数を占めるコミュニティに溶け込もうとする韓国人家族の苦悩が描かれているのだろうと思いました。実際にそうしたテーマもありますが、それは控えめに描かれています。
例えば、教会の女性が母親に「かわいいわね」と微笑んだり、子どもが「なんで顔が平らなの?」と無邪気に聞いたりと、文化的な違いから起きる緊張感を示すシーンはありますが、それが物語の中心ではありません。
私にとってこの映画の核となったのは、むしろ静かに描かれる「男性の自尊心」、特に「一家の大黒柱であること」に対する男性の誇りでした。
夢を追う夫と、現実に疲れた妻――崩れゆく家族のはじまり
物語は、イ家がアーカンソーの農地にある古びたトレーラーハウスに引っ越してくる場面から始まります。母親のモニカは、最初からこの新しい生活に満足していない様子がはっきりと伝わってきます。カリフォルニアに移住した当初、彼女が想像していたものとはまったく違う、何もない風景がそこには広がっていたからです。
モニカは、韓国人コミュニティのあるアーカンソーの都市部に引っ越すことをヤコブに提案します。そこなら、子どもの世話を頼める人や買い物ができるモール、そして何よりも病院があります。幼い息子デビッドには深刻な心臓の病気があり、必要な時にすぐに医者に診てもらえるかどうかは重要な問題です。
しかしヤコブは、50エーカーの農場を築くという自身の夢に固執し、モニカの不安を軽くあしらいます。「ここは誰もいないから子どもたちも大丈夫」と言うのですが、その言葉にはデビッドの健康状態への配慮が感じられません。
「10年間も鶏の性別を判別する仕事をしてきたんだ。もっと良い人生に挑戦する権利がある」
そんなふたりの対立が最悪となったのが、竜巻が接近した夜でした。トレーラーハウスの屋根から水が漏れ、窓はガタガタと揺れ、風が唸り声をあげ、電気は点いたり消えたり。穏やかな気候に慣れたカリフォルニア育ちの家族にとっては、恐ろしい体験でした。
モニカは、恐怖に震えるデビッドとアンを抱きしめます。一方ヤコブはニュースに釘付けになりながら、「避難命令じゃないから大丈夫」と冷静な態度を崩しません。その無関心にも思える態度に、モニカは怒りを爆発させ、ついに激しい言い争いが始まります。
彼女は、夫が自分たちのすべてを夢のために無謀に賭けたと非難します。一方でヤコブは、それは家族のためだと主張します。「10年間も鶏の性別を判別する仕事をしてきたんだ。もっと良い人生に挑戦する権利がある」と。そして彼は懇願するように言います。「新しいスタートをしようって言っただろ。これがそれなんだ。」
でも、疲れ果てたモニカにとって、これが“新しいスタート”とは思えません。彼女は重い気持ちを込めてこう返します。「あなたが求めたスタートがこれなら、私たちに未来はないかもしれない。」
すでに綻びかけていたふたりの結婚生活は、静かに崩れ始めます。

母の静かな孤独と、私のゆれるルーツ
私はよく、母が初めてアメリカに来たとき、どんな気持ちだったのだろうと考えます。私たちの家族は感情についてあまり話すことがなかったので、真実を知ることはもうないかもしれません。でも想像はできます。言葉も通じず、知り合いも誰もいない場所に来て、どれほど孤独で、どれほどもどかしかったか。すべては夫のそばにいるための決断だったのです。
もしかすると、父が自分のビジネスを築こうとしていた頃、母も同じような口論を何度も繰り返していたのかもしれません。
私はアメリカ人なのか?それとも日本人なのか?いつも心のどこかで葛藤していました。
『ミナリ』を観ながら、私は自分の幼少期を何度も重ねていました。両親の言い争いが止まるのを願いながら部屋の外を覗いていたデビッドとアン。私もまた、耳を塞ぎながら、早く静かになってほしいと願っていた子どもでした。ただの子どもだったけれど、大人になることがこんなにも大変だと知っていたら、もう少し違うふうに受け止められたのかもしれません。
時間が経つにつれて、映画の中のトレーラーハウスは徐々にモニカの色に染まっていきます。韓国の装飾品が増え、彼女の心がまだ韓国にあることを静かに物語ります。それは私自身の記憶とも重なりました。
私の実家も日本を思わせるものでいっぱいでした。アメリカで生まれ育ちながら、私は常にふたつの文化の間で揺れていました。母はいつも日本のルーツを大切にし、食事やテレビ番組、日々の習慣を通して、私に“自分がどこから来たのか”を思い出させてくれました。でも家の外に出ると、そこはまったく異なる世界が広がっていて——私はアメリカ人なのか?それとも日本人なのか?いつも心のどこかで葛藤していました。
祖母の優しさとミナリの教え――静かに根を張る強さ
イ家の末っ子であるデビッドも、その葛藤を抱えていました。モニカの母親が韓国から来て子どもたちの世話をすることになったとき、彼は反発します。「あの人は本当のおばあちゃんじゃない」と言い、彼女の匂いについて文句を言います。
その“匂い”という言葉は、移民家庭で育った者にしか分からない感覚かもしれません。私も子どものころ、両親が日本から持ち帰ってきたお土産や、日本から親戚が遊びに来たとき、どこか違う匂いを感じていました。嫌な匂いではありません。でもその“違い”が、私が他のアメリカの友達とはちょっと違う場所から来たことを、静かに教えてくれていたのです。
映画の中で、モニカはたびたび子どもたちが“韓国人であること”を強調します。ある場面では、「あの子はそんな子じゃない、韓国の子よ」とデビッドを擁護します。一方で、祖母は冗談混じりに彼を「ばかなアメリカ人」と呼んだりします。
「ミナリはどこでも育つのよ。お金持ちでも貧しくても、誰でも食べられるし薬にもなる」
そのやり取りの中にも、私は母の姿を重ねずにはいられませんでした。母もまた、自分を形作ってきた文化に必死でしがみつきながら、私の中に自然に日本の伝統を織り込んでいたのかもしれません。言葉や食事、しきたりを通して、私が知らぬうちに、そして私が望んだかどうかに関わらず——“あなたは日本人なんだよ”と静かに伝えていたのだと思います。
デビッドやアンと違って、私は祖母と近くで過ごした記憶がほとんどありません。祖母と一緒に過ごす彼らを見て、少しうらやましくなりました。映画の中での彼女の存在は、とても力強く、そして地に足のついたものでした。家族が「アメリカン・ドリーム」の形をめぐってぶつかり合い、迷い続ける中で、祖母は終始、自分らしさを失わずにそこにいました。
彼女は孫たちを育てるために、はるばる韓国からアメリカへやってきました。息子の夢を支えるために、文句ひとつ言わずに家事をこなし、拒絶の言葉をささやかれながらも、デビッドの隣で床に寝るのです。
年長者を敬う文化の中で育った私にとって、デビッドの態度は少しショッキングでした。どこか「アメリカ的」な反応のように見えました——個人主義的で、遠慮のない振る舞い。彼はついには、祖母にイタズラを仕掛け、ソーダだと偽って自分のおしっこを飲ませるという酷いことまでするのです。祖母が「山の飲み物」と愛おしそうに呼んでいたものなのに。
両親は当然怒りますが、それでも祖母はデビッドをかばいます。ストレスや野心に目が曇っていた大人たちとは対照的に、祖母は愛情と忍耐で彼を包み込みます。
そして、映画のタイトルにもなっている「ミナリ」を紹介するのも祖母です。家のそばの小川にデビッドを連れて行き、「ミナリはどこでも育つのよ。お金持ちでも貧しくても、誰でも食べられるし薬にもなる」と言います。
この言葉は心に残ります。もしかしたら、祖母が伝えたかったのは、「しなやかさ」や「たくましさ」は必ずしも犠牲や苦しみから生まれるものではない、ということだったのかもしれません。本当に価値のあるものは、静かに、あまり多くを求めずに育つのです。

「役に立つ男」であろうとした父と、その背中に重ねた記憶
映画の序盤で、ヤコブは息子に雄のヒヨコが捨てられる理由を説明します。「卵を産まないし、肉も美味しくないからね」と。そしてこう続けます。「だから男は役に立たなきゃいけないんだ。」
この一言に、ヤコブの“男であること”への信念が凝縮されています。彼にとって「役に立つこと」は「生き残ること」と同義であり、自分の価値は、家族を養い、成功し、踏ん張り続けることによって証明されるのです——たとえ自分をすり減らしてでも。
きっと犠牲も後悔もあったでしょう。それでも、何よりもそこには“勇気”があった。それが私の心に残っているものです。
映画の中で、ヤコブは夢の農場にすべてのエネルギーを注ぎ込みます。彼が交流するのはほとんど息子のデビッドだけで、娘のアンにはほとんど目を向けません。モニカと同じように、彼女も脇に追いやられているのです。物語の中心にあるのは、ヤコブの執拗な成功への執着。その姿は痛々しいほどに必死で、見ていて辛くなるほどです。
水が確保できず、野菜を売ることもできない。それでも彼は諦めない。なぜなら、彼にとっての「失敗」はすなわち「価値がない」ということ。つまり、ヒヨコのように「捨てられる存在」になってしまうのです。
ヤコブを見ていて、私は父の姿を思い出しました。
アメリカで最初に始めたビジネスは成功しましたが、二度目の挑戦は失敗に終わりました。両親は詳細を語ることはありませんでしたが、私はある程度、察していました。父は最初のビジネスを手放し、すべてを畳み、日本に帰ることになったのです。
その出来事が彼らにどれほどの影を落としたのか——それは言葉ではなく、顔に刻まれた深いしわや、目の下のクマが物語っていました。
それでも私は、父を「失敗した人」とは思いませんでした。むしろ、今でもずっと誇りに思っています。異国の地で、ゼロからビジネスを始め、未来に賭けるなんて、誰にでもできることではありません。
きっと犠牲も後悔もあったでしょう。それでも、何よりもそこには“勇気”があった。それが私の心に残っているものです。
夢を追う代償と、信じる心の終わり
物語が終盤に差し掛かる頃、祖母が脳卒中に倒れます。この出来事がモニカにとっての転機となり、彼女はついに、母と息子がより良い医療を受けられるようカリフォルニアへ戻る決心をします。
しかし、真に決定的な一撃はその後にやってきます。息子が入院している病院で、ヤコブが現れますが、心配そうな様子ではなく、市場で売るための野菜の入った木箱を抱えていました。モニカは呆然としながら彼を見つめます。この町への訪問は農場のためではなく、息子のためだと、彼女ははっきりと伝えていたのです。
成功を目指すことに罪はありません。誰だって安定した暮らしを望みます。でも、問いかけるべきなのは、「どこまでそれを追いかける覚悟があるか」、そして「そのために、どれだけの手を離してしまうのか」です。
モニカが彼にカリフォルニアへ一緒に戻るよう訴えると、ヤコブは拒みます。「たとえ失敗しても、始めたことはやり遂げなきゃいけない」と彼は言います。
その瞬間、モニカは痛切な現実を悟ります——ヤコブは家族よりも夢を選んだのです。家族と離れるリスクを冒してまで、自分の夢を追いかけることを選んだ。これまで静かに続いていたすれ違いが、激しい言葉の応酬へと変わります。そして、モニカはこう言い放ちます——まるで最後のとどめのように。「もうあなたを信じられない。」
私はこれまでヤコブに対して厳しい目を向けてきましたが、それでも彼の気持ちがわかります。
長男として韓国を離れ、アメリカという異国で生活を始めたものの、喜びのない仕事——鶏の雌雄を見分ける職業に縛られ、彼は息が詰まるような日々を過ごしていたのでしょう。彼は家族のために、そして何より自分自身のために、もっと意義のある人生を求めていたのです。自分には価値がある、自分の人生には意味がある——そう証明したかった。
成功を目指すことに罪はありません。誰だって安定した暮らしを望みます。でも、問いかけるべきなのは、「どこまでそれを追いかける覚悟があるか」、そして「そのために、どれだけの手を離してしまうのか」です。
きっと母も、どこかで同じような悲しみを感じたことがあったのでしょう。それでも彼女は、そこに留まりました。理由はわからないけれど——でも、それもまた、ひとつの強さだったのかもしれません。

燃え尽きた夢のあとに残ったもの——静かに寄り添う家族の強さ
映画が感情的な頂点を迎える中で、回復途中の祖母は、何かの役に立ちたいという一心で動き、結果的に収穫した野菜を保管していた小屋に火をつけてしまいます。体は弱っていても、家族の夢を支えたいという気持ちは消えていなかったのです。
悲しみと混乱の中でも、祖母は“しなやかな強さ”の象徴として描かれます。どんなに厳しい状況でも、希望は残る——彼女はそれを体現する存在でした。
この火事は、物理的にも象徴的にも、彼らの限界を超えるものでした。蓄えた食料とともに、彼らが積み重ねてきた夢までもが燃え尽きてしまった。ヤコブとモニカは呆然と立ち尽くし、祖母は罪悪感を背負ったままその場を去ります。
男性のプライド——とても脆く、それでいてとても大きなもの——は、忍耐強く、安定していて、そして優しさを持ったパートナーに支えられてこそ、形を持って育っていけるのです。
けれど、その破壊の中から、静かで優しい何かが生まれ始めます。それは、言葉ではなく、共有された痛みと、優しさと、理解から生まれた“赦し”でした。
そして物語は、特に説明もなく、イ家が再びアーカンソーでの生活に挑んでいる姿を映し出します。依然として同じ土地に住んでいる。劇的な和解の場面も、明確な決断の描写もないまま。
モニカはヤコブにもう一度チャンスを与えたのか?すべてを受け入れて、この地に留まることを選んだのか?それとも、不完全なままでも“家族であること”を選んだのか?
映画はその答えを示しません。意図的にそうしたのかもしれません。でも私は、心のどこかで結末を求めていました。傷口を縫い合わせるようなシーンが見たかった。
たぶんその感情は、自分の家族の経験に重なるものだったのだと思います。父のビジネスが失敗した後、両親がどうやって立ち直ったのか——その「転機」を私は見たことがありません。ただ、ふたりが何事もなかったかのように静かに一緒にいた。それだけでした。
真実はこうです。男性のプライド——とても脆く、それでいてとても大きなもの——は、忍耐強く、安定していて、そして優しさを持ったパートナーに支えられてこそ、形を持って育っていけるのです。無理に引っ張るのではなく、静かに導くような存在。
そして、ようやく彼がすべてを理解したときに見えるのは、何よりも大切なもの——静かに寄り添い続けてくれた家族の姿です。
セックスしたくないと思うのはなぜ?私に何か問題があるの?
壊れているわけじゃない。そう感じるのは、それだけ繊細で、まっすぐなあなたの証です。

「もうセックスをしたくない」と感じているなら、あなただけではありません。
以前はセックスがワクワクするものだったり、パートナーとのつながりを感じる時間だったりしたかもしれません。あるいは、最初から複雑な感情があった人もいるでしょう。でも今は、避けたいもの、プレッシャーを感じるもの、あるいは全く考えないものになっている——そんな自分に戸惑ったり、不安になったりするかもしれません。そして、多くの人が最初に抱く疑問はこうです。
「私、おかしいのかな?」
その答えは、いいえ。
でも、あなたのその気持ちは、きちんと向き合う価値のある大切なサインです。
セックスへの関心が薄れたり、まったく感じられなかったりするのは、実はとてもよくあること。特に長期的なパートナーシップの中で、仕事、子育て、感情的な負担、そして未解決の関係の問題などを抱えている女性にとっては、なおさらです。これは多くの人がセラピーに訪れるきっかけにもなっています。
では、なぜ性欲は変化するのか?
それはあなたに何を伝えようとしているのか?
そして、セラピストと一緒に取り組むことで、どうすれば自分自身やパートナーとのつながりを取り戻せるのか——
一緒に探っていきましょう。
関連記事:セックスレスの原因とは?|なりやすい夫婦の特徴や解消法を解説
セックスしたくないとはどういうこと?
性欲は、生まれつきの性格のように「固定されたもの」ではありません。人生や人間関係の中で、波のように増えたり減ったりする自然なものです。
だから、セックスへの興味に変化を感じたとしても、それはあなたの「失敗」ではなく、何かのサインかもしれません。
性欲が薄れる理由には、ストレス、怒り、疲労、パートナーとの距離感、あるいは性に対する恥の感情など、さまざまな要因が関係しています。けれど、こうしたサインを「ただの自分の問題」だと決めつけてしまう人は少なくありません。
実際には、性欲というのはとても複雑なもの。
それは、人間関係・感情・ホルモン・心理状態など、いくつもの要素が絡み合ってできています。だからこそ、適切なサポートがあれば、自分に合った形で理解し、取り戻すことも可能です。
また、「性欲が低いこと」と「無性愛」は別のものであることも大切なポイントです。
無性愛とは、ごく少ない、あるいはまったく性的な欲求を感じないという性的指向のひとつで、決して「治すべき問題」ではありません。
人間関係・感情・ホルモン・心理状態など、いくつもの要素が絡み合ってできています。だからこそ、適切なサポートがあれば、自分に合った形で理解し、取り戻すことも可能です。
一方で、性欲の低下は、「以前と違う自分に戸惑っている」「パートナーとの関係に影響が出ている」など、悩みや違和感を伴う場合が多いです。
自分がどちらに当てはまるのかわからないと感じるときは、セラピーを通して丁寧に探っていくこともできます。
好奇心と優しさをもって、自分自身を見つめ直す時間を持つこと。それが第一歩です。

今セックスをしたくない理由とは?
性欲が低下するのには、よくある理由がいくつもあります。以下はいくつかの代表的な例です。
1. 頭の中が常にフル回転(メンタルの負担と圧倒感)
多くの女性にとって、セックスには「時間」だけでなく「心の余裕」も必要です。
やるべきこと、家族のケア、仕事のストレスで頭がいっぱいのとき、今この瞬間に集中したり、身体のつながりを楽しむのは難しくなります。
2. 燃え尽きや感情的な疲労
慢性的なストレスや疲労は、自律神経に大きな影響を与えます。
“生き延びるモード”に入っているとき、身体は性的興奮や親密さよりも、まず休息と回復を優先します。これは「失敗」ではなく、生物学的な反応です。
3. パートナーとの距離感やモヤモヤ
欲望は、安全で安心できるつながりの中で育ちます。
感情的に距離を感じていたり、言えない不満やすれ違い、家事や育児の負担が一方に偏っているような関係では、セックスに前向きになれなくて当然です。
4. セックスがしばらく「心地よくなかった」
過去のセックスが、プレッシャーが強かったり、満たされなかったり、一方通行だったと感じる経験があると、体は「また同じ思いをするかも」と予測してしまいます。
これはあなたが壊れているからではなく、神経系があなたを守ろうとしている証拠です。
5. ホルモンの変化や身体的な要因
更年期、産後の回復期、慢性的な痛み、特定の薬の影響なども、性欲に影響を与えることがあります。
こうした身体的・ホルモン的な変化を理解することは、「問題」として扱うのではなく、癒しとケアのスペースをつくるためにとても大切な視点です。
この状態が続くと、やがて感情的な距離が広がったり、スキンシップが減ったり、「自分は魅力がないのかも」といった自己否定の感情につながることもあります。
「セックスしたくない…」が関係に与える影響とは?
多くのカップルにおいて、性欲の低下は特定のパターンを生み出します。
ひとりが求め、もうひとりが避ける。
そしてふたりとも、拒まれたように感じたり、イライラや戸惑いを抱えたりする——そんな悪循環が生まれてしまうのです。
この状態が続くと、やがて感情的な距離が広がったり、スキンシップが減ったり、「自分は魅力がないのかも」といった自己否定の感情につながることもあります。
セックスがない=関係に問題がある、と考えてしまいがちですが、実はセックスへの興味の低下は、関係そのものではなく、その関係が存在している“環境”に原因があることも多いのです。
そんなとき、セラピーは大きな助けになります。

セラピーが「セックスしたくない」気持ちに寄り添い、つながりを取り戻す手助けに
個人でもカップルでも、セックスセラピーは「性欲との関係性」を深く理解し、自分に優しく向き合うための力強いサポートになります。
必ずしも「危機的な状況」である必要はありません。
「なんだか自分らしくないな」
「前はもっと親密だったのに、今はそれがない」
——そんな小さな気づきがきっかけでセラピーに訪れる人も多くいます。
セラピーで得られるサポートの一例:
● 恥や罪悪感のない、安全な対話の場
「なぜ今セックスをしたくないのか」を無理に説明したり、すぐに解決しなきゃと焦る必要はありません。
経験豊かなセラピストは、あなたの「今ここにある感情」をそのまま大切に扱ってくれます。
● 神経系を整えるためのツール
性欲が低下しているとき、多くの人は無意識に慢性的なストレスや緊張状態にあります。
セラピーでは、マインドフルネスを取り入れた方法などを通じて、自分の身体と穏やかにつながり直すサポートが受けられます。
● カップルで再びつながるための対話サポート
カップルセラピーでは、「セックスしなきゃ」というプレッシャーを和らげ、感情的な親密さを育むことを目指します。
それは、率直な会話の練習や、長年のわだかまりを解消するプロセス、今の2人に合った“つながり方”を再定義することかもしれません。
● 欲望に対する新しい見方を育む
性欲はいつも自然発生的で情熱的とは限りません。
「リラックスできる」「大切にされている」「安心できる」——そんな土壌の上に、ゆっくり芽生える“反応的な欲望”もあります。
セラピーでは、他人と比べることなく、自分にとっての欲望のかたちを丁寧に見つめ直すことができます。
セックスしたくない…でも、どこから始めればいいの?
それで大丈夫です。すべてを完璧に理解している必要なんてありません。
むしろ、セラピーとは「わからないままの自分」にも居場所がある場所です。
「セックスしたくない」と感じること、 パートナーとの関係にモヤモヤがあること、
自分の心や体にピンとこない感覚——そうした違和感や戸惑いも、セラピーでは大切な入り口になります。
セラピーは、あなたの今いる場所から、 無理なく、自分らしい一歩を見つけていくためのサポートです。
セラピーでは、性欲の低下やセックスへの不安、 感情的・身体的なつながりの難しさなど、 個人やカップルが直面するさまざまなテーマに、 安心・丁寧に向き合うことができます。
ひとりでも、パートナーと一緒でも。 「どうしたらいいかわからない」から始めても、もちろん大丈夫。
セラピーは、あなたの今いる場所から、 無理なく、自分らしい一歩を見つけていくためのサポートです。
「セックスしたくない自分」を責める前に──セラピーという選択肢
診断があるわけでも、深刻な危機があるわけでもなくていいのです。
こんなふうに感じているなら、セラピーが助けになるかもしれません:
- 自分の身体や性欲から切り離されたように感じる
- セックスが「選択」ではなく「義務」のように思える
- パートナーと親密さについて話さなくなった
- 自分の性欲の程度について、罪悪感・恥・混乱を感じている
- 親密な時間に、もっと「今ここ」にいて、つながりを感じたいと思っている
あなたの感じていることには意味があります。
その思いを整理する場所として、セラピーはとても有効な手段です。
あなたは壊れてなんかいない。ただ、人間らしいだけ。
性欲の低下は、欠点でも異常でもありません。
それは、心や身体が「ちょっと立ち止まってほしい」と送ってくれているサイン。
そしてそのサインは、多くのセラピーで、癒し・気づき・深いつながりへの出発点になります。
この気持ちを、ひとりで抱える必要はありません。
セラピーは、性との向き合い方や、自分自身・パートナーとの関係を見つめ直す安全な場所です。
「なんだかうまくいかない」「自分でもよくわからない」——そんな曖昧な感覚からでも大丈夫。
今感じていることにそっと寄り添い、あなた自身のペースで一歩ずつ進んでいくために、セラピーは力になれます。
夏休み到来。子どもはワクワク。親はヘトヘト?!この夏の過ごし方を考えてみた

「『夏休み』をテーマに記事を書いてください」とお題をもらってから、「私の夏休みって何だろう?」と改めて考えてみました。
学生時代は心待ちにしていた夏休み。でも、社会人になってからは、夏休みという概念すらなくなってしまったように感じます。
特に母になり、子どもたちが小学生になってからは、「子どもたちの夏休み=母にとっては休めない過酷な季節」の到来になってしまいました。笑
幼い頃の夏の思い出を振り返りながら、子どもたちと過ごす今年の夏の過ごし方を考えてみたいと思います。
大人になってすっかり忘れてしまった、夏休みのワクワク感
正直なところ、母になってからの夏休みは、ワクワクよりも「夏休みが来てしまう……」というネガティブな気持ちのほうが強くなってしまいました。
私は基本的に在宅で仕事をしているので、夏休み中も子どもたちと同じ空間で過ごすことはできます。でも、やっぱり子どもが家にいる状態で集中して仕事をするのは難しい。ひとりで静かな環境でじっくり向き合いたいのです。
だからこそ、子どもたちと一緒に夏を楽しむイベントを考えながらも、夏休みが始まる1ヶ月ほど前から「どうすれば学童に行ってもらえるか」「どんなイベントに申し込めば子どもに家を空けてもらえるか」など、自分の時間をどう確保するかという計画を練り始めています。
祖母の家まで大冒険。非日常にワクワクした夏休みの思い出
大人になってすっかり夏休みのワクワクを忘れてしまったけれど、小学校の頃はどうだったでしょう。
「明日から朝早く起きて学校に行かなくていいんだ!」と、夏休みに入った瞬間に心がふわっと軽くなったのを覚えています。
とはいえ、実際にどんなふうに過ごしていたかは、あまりはっきりとは思い出せません。当時は今のようにスマホで気軽に写真を撮ることができなかったので、記憶はぼんやりと曖昧です。
それでも、強く心に残っている夏の思い出があります。
“子どもの頃、夏休みに姉弟と祖母の家で過ごした1週間の思い出。サンリオショップでのおまけ、プール遊びや漫画部屋、犬の散歩、祖母の怖い話などが心に残っています。今では、祖母も母もこの時間を楽しみにしていたと感じる、大切な夏の記憶です。”
それは小学校3〜4年生の頃。姉と弟と私、子ども3人だけで、千葉の家から埼玉にある母方の祖母(以下、ばぁば)の家に遊びに行ったこと。
片道2時間ほどの道のりを電車を乗り継いで行くのはドキドキでしたが、ちょっぴり誇らしい気持ちにもなりました。
駅に着くと、ばぁばとおばちゃんが迎えに来てくれていて、毎回駅ビルのサンリオショップに寄るのがお決まりコース。買い物をするとレジでキーホルダーのおまけがもらえて、嬉しくて何度も眺めていた記憶があります。
滞在は1週間ほど。家の前のビニールプールで水遊びをしたり、つきたてのお餅をごちそうになったり。ばぁばの家の2階には“漫画ルーム”と呼ばれる部屋があり、そこで好きなだけ漫画を読めるのも楽しかったな。
飼っていたハスキー犬のジャッキーとの散歩や、夜になるとばぁばが面白おかしく怖い話をしてくれたことも、今でも鮮明に覚えています。
今になって思うのは、きっとばぁばは、孫たちが来るこの1週間を楽しみにしてくれていたんだろうなということ。そして、母にとっては子どもたちが不在になるこの1週間が、“自分の夏休み”だったのかもしれません。
この夏の目標は「ごきげん母さん」でいること。頑張りすぎない夏休みを

“夏休みは特別なことをしなくても、小さな非日常が子どもの大切な思い出になる。親は無理せず、自分時間と心のゆとりを確保し、ペースを落として過ごすことが大切。”
幼少期の夏休みを振り返って感じるのは、夏の思い出は決して特別である必要はないということ。
家族みんなで旅行に行けなくたっていい。好きなシロップをいくつか用意して、かき氷パーティーを開いてみたり、大きなスイカをくり抜いてフルーツポンチを作ったり。冷房の効いた部屋で親子でゴロゴロしながら本を読むのも、素敵な時間です。
そして、私の幼少期の思い出のように、子どもたちだけで祖父母の家に遊びに行くのも良いなと思います。ちょっとした非日常が、子どもたちにとっては大きな冒険であり、忘れられない夏になるかもしれません。
だからこそ、「せっかくの夏休みだから、どこか特別な場所に連れていかなきゃ」とか、「毎日たっぷり構ってあげなきゃ」と気負いすぎる必要はないのかもしれません。
それよりも、「なんだか楽しかったな〜」と子どもたちが思ってくれるような、そんな穏やかな夏を目指したい。
そのためには、母である私がまずごきげんでいることが大切だと思っています。
私がごきげんでいるために必要なのは、「自分時間の確保」と「心のゆとり」。
そのために、適度に学童を活用したり、子どもだけのサマーキャンプに申し込んだりしています。どんなに愛おしい存在でも、子どもたちと少し距離をとる時間は、私には欠かせません。
また、心のゆとりを保つために、夏休み中は納期がタイトな仕事は極力入れない、外出が必要な案件はできるだけ控えるなど、いつもより少しペースを落として、余白を持つことを意識しています。
夏は毎年やってくる。だけど、2025年の夏は一度きり
8月の終わり、「平凡な夏休みだったけど、なんだか楽しかったな〜」と子どもたちが思ってくれるように。
そして、「この夏休みは子どもたちと笑顔で過ごせたな」と私自身も振り返って思えるように。
肩の力を抜いて、がんばりすぎずに。この夏を大切に過ごしていきたいと思います。
それは直感?それとも不安?直感と不安の違い

私はほぼ毎日、不安を抱えて過ごしています。頭の中にはいつも何かしらの心配やモヤモヤがあって、目の前の瞬間を心から楽しむことが難しいのです。今、それを少しずつ手放そうと取り組んでいますが、不安という感情は、過去の経験に深く結びついていることが多いと気づきました。
でも同時に、不安は自分を守るための防御反応でもあるのだと思っています。「何かがおかしいよ、注意して」と、身体が教えてくれているサインなのかもしれません。
不安は、私をリラックスから遠ざける存在でもあるけれど、振り返ってみると、人生の大切な節目で冷静な判断を促し、後悔や自己破壊へと向かう道を避けさせてくれた“ガイド”でもありました。だからこそ私は今、不安を和らげる方法を学ぶと同時に、その声に耳を傾ける方法も学んでいるのです。
とはいえ、「直感」と「不安が偽装した直感」を見分けるのは簡単なことではありません。
今回は、この2つの内なるサインが身体にどう現れるのか、それぞれが何を伝えようとしているのか、そしてそれらを区別し、信じる力をどう育てていけるのかについて探ってみました。
関連記事:メンタルブレイクした時はどうすればいい?診断方法や治し方を紹介
直感とは?
直感とは、ふと湧き上がる「内なる確信」、突然のひらめきや、説明できないけれど確かな感覚のようなものです。心理学的には、意識が追いつく前に潜在意識がパターンを読み取り、素早く答えを導き出している状態ともいえます。スピリチュアルな視点では、直感は「高い次元での導き」とされ、自分にとって本当にふさわしい方向へとそっと背中を押してくれる存在です。
不安とは?
一方で、不安は身体に備わった“アラームシステム”のようなものです。心理的には、何か脅威を感じたときに作動する「闘うか、はたまた、逃げるか」の反応です。スピリチュアルな観点では、自分の本質や内なる真実からズレているとき、それを知らせるサインとして現れることもあります。

どうやって直感と不安の違いを見分ける?
1. 体の感覚に意識を向ける
直感は、どっしりと地に足のついたような感覚を伴うことが多いです。たとえそのメッセージが予想外だったり挑戦的な内容だったとしても、どこかに静けさや明晰さが感じられます。それは、恐れや焦りを伴わない“確信”のような感覚です。
それは優しく背中を押してくれるような感覚だったり、小さなサイン、もしくは内なる声がささやくように静かに聞こえてくるものかもしれません。直感は、無理に注意を引こうとはせず、静かに“気づいてほしい”と招くものです。
一方で不安は、しばしば大きく圧倒的なエネルギーを持って現れます。切迫感や混乱、恐れに満ちていて、最悪のケースを想定して頭の中がフル回転しているような状態です。不安は、今この瞬間から引き離し、「もしも…」という無限ループへと引き込んでいきます。
また、不安は身体的な症状として現れることもあります。たとえば、心臓がバクバクする、呼吸が浅くなる、胃のあたりに不快な緊張感を覚える、といった具合です。そしてその声はたいてい大きく、しつこく、無視しようとしても難しいものです。
優しく背中を押してくれるような感覚だったり、小さなサイン、もしくは内なる声がささやくように静かに聞こえてくるものかもしれません。直感は、無理に注意を引こうとはせず、静かに“気づいてほしい”と招くものです。
2. タイミングに注目する
不安は、どんなときでも最悪の未来を想定して繰り返し再生されますが、直感は“いま”明確な判断が必要な場面で、的確なタイミングでやってきます。
直感は、ふとした瞬間に訪れる短くて明快なメッセージであることが多く、時にはシンクロニシティ(意味のある偶然)やサインとともに現れることもあります。
それに対して不安は、過去の記憶を再生したり、未来への恐れを投影したりと、頭の中で何度も同じ不安がこだまし続ける「思考の反響室」のような状態を生み出します。
3. 正しい問いかけをする
「これは、今目の前で起きている現実に対する反応なのか? それとも“もしも”の未来を想像して生まれた恐れなのか?」
こう自分に問いかけてみてください。
また、視覚化のワークも効果的です。直感が導いているように感じる選択を「イエス」と受け入れたと想像してみて、それが心地よく広がる感覚なのか、胸が締めつけられるような窮屈な感覚なのかを感じてみましょう。
直感は、“今”に対して反応します。不安は、想像の中の未来や過去のパターンの中に生きているものです。

感覚で分かる直感と不安の違い
直感はドアが開かれるような感覚。不安は、ドアの向こう側で立ちすくんでいるような感じ。
直感の特徴:
- 静けさ、落ち着き、安定感をもたらす
- たとえ挑戦的な内容でも、中立的またはクリアに感じられる
- 「今、この瞬間」に対して反応する
- 腹の奥の感覚、地に足がついた静けさ、そっと背中を押すような感覚として現れる
- 明晰さや内なる整合性から生まれる
- パッと現れて、静かに消えていく
- ドアが自然に開くような感覚
- 優しく「おいで」と招く
- メッセージがはっきりしていることが多い
- エネルギーが整っているときに流れやすい
不安の特徴:
- 大きくて、切迫感があり、圧倒的に感じられる
- パニックや不安、恐れとして感じられる
- 「もしも〜だったら」と思考がグルグル回る
- 心拍数の上昇、手のひらの汗、浅い呼吸などの身体症状を引き起こす
- 恐れや内なる不一致から生じる
- 同じ考えがループして何度も再生される
- 前に進めず、行き詰まった感覚になる
- 無理に「やらなきゃ」と押してくる
- 反射的な反応として現れる
- 処理されていない感情によって増幅される
“今”にいる練習を重ねれば重ねるほど、自然と直感=あなたの高次の自己につながる声と調和できるようになります。
直感を強化するには?
もし直感が遠ざかっているように感じるなら、それは思考の雑音にかき消されているだけかもしれません。心が静かになるほど、直感の声はよりクリアに響いてきます。
日常的にできる練習:
- 今の気持ちを言語化する:感情に名前をつけることで、自律神経を整える助けになります
- 「今ここ」に意識を向ける:マインドフルネスは、思考のノイズを抑える力になります
- 瞑想する:たった2分でも効果があります
これらの習慣は、思考を静め、自分の内なる声により深く耳を傾ける力を育ててくれます。“今”に集中する練習を重ねれば重ねるほど、自然と直感=あなたの高い次元の自己につながる声と調和できるようになります。
本当のところ、直感も不安もあなたを導くために存在しています。
直感は「本来の自分」へと進むための道しるべ。不安は「いま、どこかがズレているよ」と教えてくれるサイン。
直感を聞くために、不安を消す必要はありません。
ただ、「いま話しているのは、どっちの声か?」を見極めることが大切なのです。
まとめ:直感と不安の違う声
- 直感は静かで落ち着いた感覚。今この瞬間に根ざし、穏やかな確信をもたらす
- 不安は大きく騒がしく、恐れや焦り、身体的な緊張を伴うことが多い
- 見分けるには、体の感覚やタイミングに意識を向けることが大切
- 「これは現実への反応?それとも“もしも”の想像?」と自分に問いかけてみる
- 感情を言語化する、マインドフルネスや瞑想などで心を整える習慣が効果的
- 不安を否定せず、「今、話しているのはどっちの声か?」を見極める力を育てよう
お金をかけずに予算内で夏を楽しむ方法

最近、物価の上昇が続き、食料品は高くなり、家賃も上がっています。多くの人にとって、バケーションや大きなイベントにお金を使う余裕はなかなかありません。天気が良くて、周りの人が夏を楽しんでいるように見えると、なんだか取り残された気分になることも。
私自身も、食費と家賃でぎりぎりの生活をしていて、何日も家にこもることがあります。正直なところ、ちょっとした楽しみのために自由にお金を使う余裕はありません。貯金と出費のバランスを取る生活は、時にプレッシャーを感じるものです。
でも、ここで朗報があります。お金をかけなくても、思い出に残る楽しい夏を過ごすことは十分可能です。ちょっとした工夫と計画次第で、予算を守りながら今の季節を満喫することができるのです。
ここでは、無理せずに夏を楽しむための、シンプルで実践しやすいアイデアをご紹介します。
関連記事:「経済的自由」よりも大切なこと|ファイナンシャル・ウェルネスという考え方
予算内で楽しむなら無料イベントをチェックしよう
「無料イベントって、気が乗らないと行くのが面倒…」その気持ち、よくわかります。無料=気軽に参加できる分、腰が重くなってしまうことも。でも、夏は意外と見落とされがちな“お得なイベント”がいっぱいなんです。
多くの都市では、無料の野外映画上映やコンサート、地元のパーティー、市が主催する各種イベントなどが開催されています。それに、Meetupのグループやランニングクラブ、ハイキンググループ、読書会など、共通の趣味を通じてつながれる集まりも豊富にあります。ぱっと目に入るものばかりではないかもしれませんが、探してみると驚くほどたくさん見つかるはずです。
正直、不安な気持ちもよくわかります。無料イベントって、どんな雰囲気なのか、どんな人が来るのか分からない…そんな“未知”の感じがちょっとハードルに感じることも。でも、無料だからこそ、合わなかったら途中で帰ってもOKという気軽さがあります。今までやったことがないことを試してみたり、普段ならお金がネックで敬遠していた興味にチャレンジしてみるチャンスでもあるのです。
また、金銭的な負担があると集まりにくい友人グループでも、無料イベントなら誘いやすいというメリットもあります。気になるイベントがあったら、気軽に一歩踏み出してみてください。
自分にとって本当に大切なことには、少しはお金を使ってもいいと自分に許可を出すことが大切です。ただしポイントは、「何に使うか」をしっかり見極めること。
予算内で楽しむコツは「選ぶ力」にあり
この夏、お金を節約することが最優先という人も多いと思いますが、「一切のお金を使わない夏」を過ごすのは現実的ではないかもしれません。だからこそ、自分にとって本当に大切なことには、少しはお金を使ってもいいと自分に許可を出すことが大切です。ただしポイントは、「何に使うか」をしっかり見極めること。
たとえば、DJイベントやダンスが大好きな人にとって、それは大切な趣味。でもチケットが5千円もするとなると、毎週行くのは金銭的に厳しくなります。そんなときは、夏の間に本当に観たいアーティストのショーを2〜3回選んで行くことで、高額の出費を、1万〜2万円程度の“楽しみの出費”に抑えることができます。
本当に大事なことや特別な日、ちょっとしたご褒美にお金を使う余地はちゃんとあっていいのです。大切なのは、計画を立てて、「これは自分にとって価値があるか?」という視点で判断すること。自分が何を大切に思っているか、どんな体験に価値を感じるかを把握していれば、そのための予算も立てやすくなり、あとでびっくりするような出費にもならないでしょう。

予算内で楽しむには「余白」も必要
「余白を持つ」といっても、それは“好き放題にお金を使っていい”という意味ではありません。あくまで、必要なときや意味のあるタイミングで、自分にちょっとしたご褒美を許してあげる「心の余裕」と「予算の余裕」のことです。
出費に対して意識していれば、その“余白”を使う場面をあらかじめ決めておくことができ、あとから銀行口座を見てびっくり…というようなことも防げます。あまりにも節約に縛られすぎてしまうと、かえってストレスが溜まったり、反動で浪費してしまうことも。そうならないためにも、「これは予算の範囲内でOK」と自分で決めたうえで、無理のない出費を楽しむことが大切です。
たとえば、もうすぐ大切な誕生日があるとか、頑張って達成したことがあるとか、久しぶりに友達が遊びに来るなど、ちょっとしたお祝いで外食したり、楽しいことをするのは十分に“あり”です。
節約とは、「一切お金を使わないこと」ではなく、「本当に価値のあることのために、計画的にお金を使うこと」。そうすることで、たまに思い切って使うお金にも、より満足感を感じられるようになります。
実際にやってみて思うのは、節約を意識して1杯だけ頼んでも、友達と出かけて楽しい時間を過ごすという体験自体には、まったく支障がないということ。むしろ、帰り際に「今日の出費、ちゃんと抑えられたな」と思える安心感があります。
1杯だけでも満足できる工夫で、予算内で楽しむ外食時間
夏の予算を守るために、あらかじめ計画して特別な日に思い切って楽しむのも良い方法ですが、日常の中でできるちょっとした工夫も、積み重なるとかなりの節約につながります。個人的には、こういった小さな選択が一番大きな効果を感じています。お金って、意識していないと、いつの間にかどんどん消えていくんですよね。
私がよく実践しているのは、「飲みに行くときはドリンク1杯だけにする」こと。これ、本当に侮れません。最初は気づかないうちに、2千円だったはずの会計が、気づけば6千円に膨らんでいた…なんてこと、ありませんか?週1回、たとえそれ以下の頻度でも、積み重なるとかなりの出費になります。
でも、実際にやってみて思うのは、節約を意識して1杯だけ頼んでも、友達と出かけて楽しい時間を過ごすという体験自体には、まったく支障がないということ。むしろ、帰り際に「今日の出費、ちゃんと抑えられたな」と思える安心感があります。
これはお酒だけでなく、外食やカフェ、ブランチなどにも言えることです。メニューを見た瞬間、「どうせ高くなるからついでにドリンクも頼んじゃおう」とか、「ラテ1杯じゃ足りないから2杯にしよう」みたいな気持ちになりがち。でも、そうやって何気なく選んだものが、気づけば会計を倍にしていることも。
その場の「お金の使い方」に意識を向けることは、私にとって大きな節約のコツです。外出も、友達との楽しい時間も、ドリンクも、ちゃんと楽しめる。でも「無理なく楽しめてる」という感覚があるだけで、出費に対する罪悪感もなく、満足感はむしろ増すんです。

ちょっとの準備で予算内で楽しむ1日に
「家に食べ物あるでしょ?」っていうこのセリフ、最も嫌われるフレーズの一つかもしれません。でも、実際その通りなんです!
特に終日外出するような日帰りのお出かけやアクティビティのときには、この考え方が本当に効果的だと感じています。
ビーチに行くときにサンドイッチやグラノーラバーを持たせてくれたお母さんたちって、ちゃんと分かってたんですよね。実際、それだけで長い目で見るとかなりの節約になります。特に、ビーチや公園など外で過ごす時間が長くなる場所では、現地での食べ物が割高になることも多いので、軽食を少し準備しておくだけでも大きな節約につながります。
出かける前にほんの数分使ってスナックを用意するだけで、後々「やってよかった」と思えるはず。しかも、せっかくお金を払ったのにイマイチだった…なんてごはんより、自分が持ってきたものの方がずっと満足できることもありますよ。
まとめ:お金をかけなくても、夏はしっかり楽しめる
節約と楽しさは、決して相反するものではありません。無料イベントへの参加、優先順位を見極めたお金の使い方、ちょっとした“余白”の許可、1杯だけの工夫、そしてスナックを持参するなど、日常の中の小さな選択が、心地よい夏の時間を支えてくれます。
何より大切なのは、「何が自分にとって大切か」を見つめ直すこと。高価な体験をしなくても、大切な人と過ごす時間や、自分らしい楽しみ方に意識を向ければ、心に残る夏はきっとつくれます。
無理せず、自分に優しく、そしてちょっとした工夫を重ねながら、予算内で心から楽しめる夏を過ごしていきましょう。あなたの夏が、豊かで思い出深いものになりますように。
呼吸も空間も心地よく。日本で手に入るナチュラルクリーニングアイテム5選
部屋の掃除はスッキリするもの。でも、洗剤のニオイや手荒れに悩まされることはありませんか?最近では、人にも環境にもやさしい、ナチュラルでノンケミカルな掃除用品が注目されています。しかも、日本国内で購入できたり、海外から配送できたりするものも増えています。

ナチュラルクリーニングとは?
ナチュラルクリーニングとは、合成化学成分を使わずに、自然由来の素材を使って掃除や洗浄を行う方法です。主に重曹(ベーキングソーダ)、クエン酸、酢、セスキ炭酸ソーダ、石けんなどが使われます。これらの素材は環境や人の体に優しく、日常の掃除から洗濯まで幅広く活用されています。
ナチュラルクリーニングのメリット
- 人体にやさしい
化学物質に敏感な人や、小さな子ども、ペットがいる家庭でも安心して使えます。肌への刺激やアレルギーのリスクを減らすことができます。 - 環境への負荷が少ない
天然素材は水に溶けやすく、排水後も環境への影響が少ないため、持続可能な暮らしに繋がります。 - コストパフォーマンスが良い
重曹や酢などは安価で手に入りやすく、少量で多用途に使えるため、経済的です。 - 安心して使える多用途性
キッチン、浴室、トイレ、衣類の洗濯など、さまざまな用途に対応可能。合成洗剤のように場所ごとに製品を分ける必要がありません。 - 香りや成分のカスタマイズが可能
エッセンシャルオイルなどを加えれば、好みの香りや効果をプラスすることもできます。
今回は、私たちが本当におすすめしたい「安心して使えるクリーナー」をご紹介します。
1. ソネット(Sonett)|ドイツ発・日本でも購入可能
おすすめポイント:オーガニック認証済み、100%生分解性、敏感肌にもやさしい処方。
取扱店:Bio c’ Bon、ナチュラルハウス、Amazon、iHerbなど。
おすすめ商品:オールパーパスクリーナー、ランドリーリキッド(センシティブ)

2. ブランチベーシックス(Branch Basics)|アメリカ発・日本配送OK
https://branchbasics.com/
おすすめポイント:1本の濃縮液で家中の掃除ができる万能クリーナー。無香料・植物由来で赤ちゃんのいる家庭にも安心。
購入方法:公式サイト(Branch Basics)から国際配送で注文可能。
おすすめ商品:スターターキット(濃縮液+専用ボトル)、ナチュラルスクラブブラシ

3. マーチソン・ヒューム(Murchison-Hume)|オーストラリア発・日本国内販売あり
https://www.murchison-hume.com/
おすすめポイント:デザイン性も高く、ギフトにも◎。天然由来成分とエッセンシャルオイル使用。
購入先:Biople by CosmeKitchen、楽天、蔦屋家電など。
おすすめ商品:カウンターインテリジェンス(多用途スプレー)、エフォートレスフロアスプラッシュ

4. シャボン玉石けん|日本製
おすすめポイント:無添加・無香料のやさしい処方。赤ちゃんやペットのいる家庭にも安心。昔ながらの製法で作られた信頼のブランド。
購入先:全国のドラッグストア、Amazon、LOHACOなど。
おすすめ商品:台所用せっけん、酸素系漂白剤(洗濯・掃除用)

5. エコストア(Ecostore)|ニュージーランド発・日本国内販売あり
おすすめポイント:詰め替え可能、容器は100%リサイクル対応。ゼロウェイストを目指す人にも人気。
購入先:CosmeKitchen、iHerb、Biopleなど。
おすすめ商品:マルチクリーナー(スプレータイプ)、食器用洗剤(レモングラス)

ナチュラルクリーニングをもっと身近にするヒント
- 重曹(ベーキングソーダ)やクエン酸は、スーパーや100円ショップでも簡単に手に入ります。
- 使い捨てを減らすために、再利用可能なクロスや「スウェーディッシュディッシュクロス」もおすすめ。
- 詰め替え対応のブランドを選んで、ゴミを減らす工夫も◎
おわりに
肌にも環境にもやさしい掃除用品は、家族の健康を守るだけでなく、地球にもやさしい選択。少しずつでも「サステナブルな暮らし」を始めてみませんか?
リアルにできるお酒を減らす方法
頑張りすぎず、お酒を減らす新しい習慣を。

今日は、つい美化されがちだけど、知らないうちに不健康な習慣になりやすい「お酒」について考えてみましょう。
仕事終わりの一杯や、週末のカクテルがごほうびのように感じる人も多いはず。適度に楽しむ分には問題ありません。でも、その「たまのお酒」がいつの間にか習慣化しているなら、ちょっと見直すタイミングかもしれません。
ストレスや日常のルーティン、あるいはハッピーアワーの誘惑など、気づけば私たちはお酒を気分転換の手段として選びがち。でも、毎日のストレスへの対処法としては、必ずしもベストとは言えないのです。
「完全にやめたい」わけじゃないけど、「少し控えたい」と思っているなら——
ここでご紹介する7つのヒントが、賢くお酒と付き合いながら、自分のペースを保つ手助けになるはずです。
お酒を減らすことがちょっと楽しくなる方法
週ごとの上限を決めよう
一見シンプルに思えるかもしれませんが、「1週間で何杯飲んだか」を実際に書き出して記録することで、自分がどれだけ飲んでいるのかが目に見えてわかるようになります。ワインやカクテルの杯数を紙に書き出しておけば、意識もしやすくなります。
そして、決めた上限を守れたときには、自分にちょっとしたごほうびをあげましょう。小さなことでもOK!モチベーションにもつながりますよ。
お酒を減らすときはワインをそのまま飲まずにひと工夫
ワインをスプリッツァーにしよう
ワインを一杯そのまま飲むのではなく、ワインと炭酸水を半分ずつにして割ってみましょう。アルコールは半分になりますが、ワインを飲む満足感はそのまま楽しめます
お酒を減らすには一人で頑張らなくていい
宣言しよう
お酒を減らしたいという気持ちを、親しい友人に伝えてみましょう。口に出して誰かに宣言することで、自分自身への意識も高まり、自然と責任感が生まれます。そして、仲間が応援してくれたり、サポート役になってくれることもあります。もしかしたら、一緒にチャレンジしてくれる人が現れて、一緒にお酒を控える仲間になれるかもしれません。

お酒を減らすコツは“特別な日にだけ”飲むこと
家でのお酒を控えめにしよう
ひとりで家で飲む習慣は、少し寂しいだけでなく、気づかないうちに依存へとつながる危険もあります。週に何杯か飲むと決めているなら、それを外出時や週末など、特別なタイミングに取っておくのがおすすめです。そのほうが楽しみができるし、「がんばったごほうび」として満足感も高まります。
お酒を減らすシンプルな習慣は“1杯ごとに1杯の水”
お酒の合間にお水をはさもう
飲酒中にしっかり水分補給をするのは、とても大切なこと。お酒を一杯飲んだら、その次はお水を一杯飲むようにすると、飲むペースが自然とゆっくりになり、翌日もスッキリ過ごせます。
お酒を減らす第一歩はお気に入りのノンアル探しから
ノンアルコールの代替ドリンクに切り替えてみよう
お酒を飲まなくてもリラックスできる、おいしいノンアルコールのドリンクはたくさんあります。気分転換にもなるし、ストレス発散にも◎。自分好みのものを見つけて、週に1回のお楽しみドリンクとして取り入れてみましょう。
お酒を減らすスイッチは体をちょっと動かすこと
何か別のアクティビティで気をそらそう
ビールやワインに手が伸びそうになったときは、ちょっと散歩に出てみたり、その場でジャンピングジャックを10回やってみたりして、気持ちを切り替えてみましょう。お酒じゃなくても、自分はコントロールできるし、健康的な選択ができるということを思い出させてくれます。最初は難しく感じるかもしれませんが、慣れてくると「飲みたい」という気持ちが少しずつ薄れてくるはずです。きっと後から「やってよかった」と思えるはず。
まとめ
お酒を減らすことは、我慢や制限というよりも、“自分を大切にするための選択肢”のひとつ。
無理せず、自分のペースでできることから始めてみるだけで、心や体に嬉しい変化がきっと訪れます。
今回ご紹介した7つのヒントは、どれも生活に取り入れやすく、ちょっと楽しくお酒との付き合い方を見直せるものばかり。完璧を目指す必要はありません。
「今日は飲まないでみようかな」そんな小さな一歩を重ねながら、自分らしい心地よいバランスを見つけていきましょう。
アートへの敷居が下がったのは”都会”のおかげ

正直に言うと、私は昔からアートに興味があったわけではありません。
両親もそういった場所に特別足を運ぶタイプではなかったので、むしろ、美術館や博物館といった場所は、自分とは縁遠い世界のように感じていました。
美術館と聞くだけでなんとなく敷居が高い感じがするし、特別な知識がないと楽しめない場所のような印象を持っていたのかもしれません。
おすすめ記事 ▶ 音楽で自分のご機嫌をコントロールするヒント&おすすめプレイリスト
「縁遠い存在」だったアートが身近になった
そんな私がアートに興味を持つようになったのは、大学生になってからでした。
大学進学をきっかけに地元広島から関西に出たことで、この環境の変化が、私とアートとの関係を大きく変えました。都会な関西には広島にいた頃よりも、はるかに多くの美術館や博物館があり、「選択肢」が一気に増えたのです。
「○○展」といった企画展示もよく開催されていて、そうしたイベントのチラシや広告を目にしたら、気軽にふらっと寄れるような場所にある。
広島にいた頃は、関西に比べるとそういった選択肢はやはり少なかったので、興味を持つ機会そのものが限られていたのかもしれないことに気づきました。
さらに大きかったのは、大学の友だちの存在です。
彼女たちは、普段の何気ないおしゃべりの最中にも、ごく自然に「この展示見に行ってみたいんよな〜」なんてよく話していたんです。
最初こそ緊張したものの、何度かついていくうちに、私自身もだんだん素直に楽しめるようになっていき、今となっては気になる美術館や企画展には自分一人でも足を運ぶようになりました。
まるで映画を見に行くのと同じような調子で誘ってくるので、アートに馴染みのない私は少し戸惑いました。
そして何より「私なんかが行っても楽しめるのだろうか」という不安も。
実際、誘われるがままについて行ってみても、やっぱり緊張するわけです。
正直なところ、深い考察ができない自分を少し恥ずかしく思うこともありました。
「友だちも、周りにいるマダムたちも、いろいろ感じとってるんだろうな」とか、「よく分かってないのに分かったような顔して回っててごめんなさい……」みたいな(笑)
でも、蓋をあけてみたら意外と友だちも似たような漠然とした感想しか持っていなくて。
帰り道で「あの絵なんかめっちゃ良かったな~!」「あの画家のタッチなんか好きだったわー!」とか、あっけらかんと話すのを聞いて、純粋に自分の感覚で作品を楽しんでいいんだと思えるようになりました。
最初こそ緊張したものの、何度かついていくうちに、私自身もだんだん素直に楽しめるようになっていき、今となっては気になる美術館や企画展には自分一人でも足を運ぶようになりました。
やっぱり環境って大きい。
自分がそれまで触れてこなかったものに、自然と引き寄せられるようになったのは、物理的な環境と友だちの存在が大きかったと思います。
とはいえ、アートに関する知識は相変わらずありません。
今だって、絵画の技法について詳しく語ることもできないし、美術史の流れを理解しているわけでもありません。
だから、作品を見ても感想はいつも「なんとなくすごいな」とか「好きだな」といった、とても漠然としたものになってしまいます。
でも、知識がなくても、その瞬間に感じたことを大切にする。
美しいと思ったら、好きだと思ったら、素直にそのまま感じる。
そんな、ちょっとミーハーな楽しみ方でもいいと分かっただけで、アートとの距離はグッと縮まりました。
「怖い絵展」で気づいたアートの面白さ

《レディ・ジェーン・グレイの処刑》1833年ポール・ドラローシュロンドン・ナショナル・ギャラリー蔵
そうしていろいろとアートに触れる機会が増えていく中で、特に印象に残っているのが「怖い絵展」です。
タイトルのとおり、ただ美しいだけではない、むしろゾッとするような背景を持った絵画を集めた展覧会でした。
一見すると普通の風景画なのに、実は争いの後に幽閉された人の視点で描かれた景色だったり、逆に生首が描かれたいかにも恐ろしい絵画なのに、実はその背景にあるのは愛だったり。
そうした背景を知ったとたん、絵の印象ってガラリと変わるもの。
音声ガイドの語りに耳を傾けながら、ひとつひとつじっくり見て回ったあの時間は、今でも記憶に残っています。
そしてこの「怖い絵展」を通して気づいたのは、私は絵そのものよりも、その「背景」に強く惹かれるタイプなんだということです。
なぜその絵が生まれたのか、作者はなぜこれを描こうとしたのか。
作品そのものの美しさだけではなく、そこにある「ストーリー」こそが、私がアートに惹かれる理由なんだと気づきました。
振り返ってみると、それってアートに限った話ではありませんでした。
目の前にあるものがどうして生まれたのか、どんな背景からそうなったのかを知りたい、紐解きたい、言語化したい。
異国の文化に興味があるのも、最近、世界遺産に夢中になって検定まで受けたのも、それらの背景にある歴史や人々の営みといったストーリーに、私は魅力を感じているから。
はたまた他人や自分の考え、感情にだって、必ずそこに至った過程がある。
目の前にあるものがどうして生まれたのか、どんな背景からそうなったのかを知りたい、紐解きたい、言語化したい。
そういう意味では、全部根っこでつながっている気がしています。
自分らしいアートとの付き合い方
私はおそらく、今後も芸術そのものに詳しくなることはないと思います。知識がないまま、感想はずっと「なんか好き」止まりかもしれません。
でも “見えない部分”に思いを馳せて、その「なんか好き」を深めていく。
それが私なりのアートの楽しみ方だと、今は自信を持って言える気がします。
これからも気負わずミーハー心全開で、目についた美術展には足を運んでみようと思います。
ゴミを減らす4つの方法
身近にできるエコなアクションが、地域社会に大きなポジティブな変化をもたらすことをご存知ですか?

本題に入る前に少しだけ。地球全体として、壊滅的な気候変動や生物多様性の喪失を止めるために、今すぐ行動する必要があります。そして、個人として何かできることはあるのでしょうか?答えは力強い「YES」です!
確かに、企業や政府レベルでの大きな取り組みは必要ですが、私たちの日々の選択にも大きな力があります。ひとつひとつの行動が未来を形づくり、家族や友人と一緒に取り組めば、より大きな変化を生み出すことができるのです。
さて、無駄にする時間はありません。実は、日本では1人あたり1日に約918グラムのゴミを出していることをご存知でしたか?
私たち一人ひとりが、ゴミを減らし環境を守るためにできることがあります。以下のヒントをチェックしてみてください。
関連記事 | 日本におけるゴミ問題の現状は?環境への影響やわたしたちにもできることを紹介
プラスチックごみを減らす、小さな行動の積み重ねを
プラスチックの生産は、気候変動の大きな原因のひとつであり、マイクロプラスチックは自然環境だけでなく人間の健康にも悪影響を与えています。でも、日常生活の多くの必需品が、リサイクルしにくいこの素材に包まれている現状では、どうしたらよいのでしょうか?
がっかりしないでください。まずは、環境保護に取り組む団体とともに、世界のリーダーたちに対して「プラスチック産業以外の、より良い選択肢を消費者に提供してほしい」と声を上げましょう。まずは家庭や地域でできることから始めてみませんか?
お気に入りの再利用アイテムで「おでかけキット」を作る
マイボトルやタンブラー、エコバッグ、マイストローなど、人気の再利用アイテムはたくさんあります。お店によっては、これらを持参することで割引が受けられる場合も。忘れずに持っていくコツは、買い物リストの一番上に書いておくこと。玄関にバッグを置いたり、車に常備しておくのもおすすめです。
リサイクルできるプラスチックを確認しよう
プラスチックは、実はリサイクルがとても難しい素材。テイクアウト容器などをリサイクルに出す前に、自治体のルールを確認しましょう。「リサイクルしてほしい」という願いから分別しても、対象外のものを混ぜてしまうと、かえって悪影響になることもあります。
学校・職場・地域団体でも「使い捨てゼロ」を呼びかけよう
私たちが使い捨てたプラスチックの多くは、地域の川や公園、大切な自然の中に流れ着いています。あなたの住む街でも、プラスチックを減らす活動をしている仲間がいるはず。一緒に行動して、身近な場所から変えていきましょう。
ファストファッションは大量の資源を消費し、マイクロプラスチックの発生や繊維廃棄物の増加など、深刻な環境問題を引き起こしています。
ファッションでゴミを減らそう
ファストファッションは、大量生産・短期間での流行のサイクルに依存しており、膨大な量の天然資源を消費します。また、多くの衣類にはポリエステルなどの合成繊維が使用されており、これがマイクロプラスチックを発生させる原因となっています。マイクロプラスチックは肉眼では見えませんが、有害であり、環境に大きな脅威をもたらしています。衣類の製造過程でもマイクロファイバーやプラスチックが放出されており、現在のままでは繊維の生産量は2050年までに3倍に増えると予測されています。
さらに、ファストファッションは「使い捨て文化」を助長し、数回着ただけで服が捨てられることで、大量の繊維廃棄物が生まれています。捨てられた衣類の何百万トンもの量が埋め立て地に送られ、分解には何百年もかかり、有害な温室効果ガスや毒素が放出されるのです。

買う前に一度立ち止まって考えよう
「賢く買う」とは、「買わないこと」を選ぶことかもしれません。本当に必要なときだけ購入し、環境に配慮して作られたアイテムを選ぶことが、消費を減らす一番の方法です。手作業で少ない資源を使って衣類を作る地元の職人から購入するのも一つの方法。また、倫理的な製造を実践している企業を選ぶことで、長持ちする衣類を手に入れながら、労働者の権利や環境保護にも貢献できます。
あえて中古品を選ぶ
新しいものを買う前に、「誰かが大切に使っていたもの」を選んでみませんか?これは節約にもなります。地元のリサイクルショップを訪れたり、オンラインの地元マーケットでお得な商品を探すのも良い方法です。中古品を購入することで、地域経済を支えながら廃棄物を減らすことができます。
結婚式やお祭りなど、特別な日のための衣類も、購入するのではなく「レンタルする」という選択肢が広まりつつあります。
修理とアップサイクルで衣類を長く使う
アップサイクルとは、古くなったり着なくなった服を、新しくてスタイリッシュなアイテムへと生まれ変わらせること。衣類の修理やアップサイクルは、「流行を追い捨てる」のではなく、「今あるものを大切にする」姿勢につながります。これは、ファストファッションに伴う生産・廃棄による環境負荷を軽減する有効な方法です。破れた箇所や外れたボタン、壊れたファスナーなどは、自分で修理するか、地元の修理専門家に依頼することで、服の寿命を大きく延ばすことができます。
アップサイクルは、自分らしいファッションを表現できるだけでなく、衣類の廃棄を防ぐことにもつながります。アップサイクルされた1枚の服が、埋め立て地に送られるはずだった1枚を救うのです。
ゴミを減らすために、食べものを無駄にしない工夫を
世界では毎年およそ9億3,100万トンもの食べ物が廃棄されています。日本だけでも年間で約233万トンと推計されています。こうした食品廃棄物が埋め立て地に送られることで、温室効果ガスが発生し、気候変動の加速につながっています。以下のヒントを参考に、サステナブルな食生活を始めてみましょう。
食事を計画しよう
あらかじめ献立を立てて、必要なものだけを買うようにしましょう。行き当たりばったりで買い物するのではなく、作りたいレシピをリストアップし、それに必要な材料だけを購入するのがポイントです。また、食べる人数に合わせて適量を調理・提供することも大切です。

食生活を少しずつ見直そう
植物由来の食材を選ぶことで、水質汚染を減らすことができます。肉中心の食事に比べて、植物性の食事は温室効果ガスの排出量が低いのが特徴。すべてを変える必要はなく、少しの変化でも効果はあります!例えば、肉を使わない1食で約500リットル(133ガロン)の水を節約できます。週に1度「お肉なし日」を取り入れたり、植物性の料理を家族や友人と楽しんでみましょう。
また、炭素排出量の少ない食材を選ぶだけでも違いがあります。牛肉の代わりにバイソンや鶏肉を選んだり、牛乳の代わりに植物性ミルクを使うだけで、二酸化炭素の排出量を大幅に削減できます。肉や魚を選ぶときは、再生型農業や持続可能な養殖を実践している生産者のものを選びましょう。
食材の保存と再活用を工夫しよう
余分に購入・調理してしまった場合は、冷凍保存したり、ご近所におすそ分けするのもおすすめ。冷凍食品は忙しい日の強い味方になります。野菜が余ったら、干したりピクルスにしたりして長期保存する方法も。果物はピューレやジャムにアレンジしてみるのも楽しいですよ。野菜の皮や切れ端は冷凍保存して、スープや煮込み料理に使える美味しい自家製だしに活用しましょう。
日常のゴミの話題が、周囲にエコな行動を広げ、地球を守る大きな一歩になります。
ゴミを減らす会話が、地球を救うきっかけに
ゴミの話で地球を救おう!
日常のちょっとした「ゴミトーク」が、実は地球にとって大きな転機になるかもしれません。私たちが普段の生活で排出している二酸化炭素や、日々の習慣が与える影響について話すことで、個人だけでなく、地域や社会全体の視点から「地球にやさしくする方法」が見えてきます。こうした小さな気づきや行動を友人や家族とシェアすることで、周りの人の意識を変えるきっかけとなり、やがてはコミュニティ全体の大きな変化につながっていくのです。
【ハミングが届けるポジティブニュース】 今日も、誰かの優しさが世界を救っている──クレーン運転手が見せた奇跡の救出劇と心温まる贈り物

(left) courtesy photo (right) Glen with his new shed – credit, Bucket List Wishes Charity
毎日忙しく過ぎていく日常の中で、ふと「人のやさしさって、このめちゃくちゃ自分のことだけで忙しい時代にまだ存在するのかしら」なんて思うこと、ありませんか?
そう感じたときにこそ知ってほしい、世界のどこかで本当に起きた「心があたたかくなる」物語をご紹介します。
「今日一日をがんばろう!」そんな前向きな気持ちになれるお話です。
2023年の終わり頃、イギリスの街・レディングで、ある建設現場が火災に見舞われました。煙と風が渦巻く中、逃げ場を失い高層ビルの外側に取り残された作業員──その命を救ったのは、クレーン運転手のグレン・エドワーズさん(66歳)でした。
彼が操作していたクレーンのバスケット(人を乗せてビルの外壁を作業できるかご)を、視界がほとんど見えない状況で的確に操作し、命がけで作業員を救出したのです。バスケットが無事近くに届き、作業員が乗り込んだとき、そこには火と煙、有毒ガスの混ざる過酷な状況が広がっていました。
グレンさんのこの勇気ある行動はニュースとなり、地元では「本物のヒーロー」として語り継がれています。
そんな彼のもとに、ある日、意外な知らせが届きます。彼の勇気ある行動を知った慈善団体から、「あなたの夢を一つ叶えさせてほしい」と申し出があったのです。
この記事もチェック ▶ 【ハミングが届けるポジティブニュース】ミサイルが音楽に変わるなんて。世界にはまだ、優しさと希望がある
この団体は、人生の終わりが見えてきた人たちの「やりたいことリスト」を叶える活動をしている団体なのです。実は、グレンさんは末期がんの診断を受けていたのです。彼はがんの治療をしていましたが再発し、現在は脊髄への転移もあるとのこと。
命がけで他人を救ったその日に、グレンさん自身もがんと闘っていたのです。
でも、グレンさんが団体にお願いしたのは豪華な旅や高価な品ではありませんでした。
「引っ越したばかりの家に新しい床材がほしい」
「庭に物置を置きたい」
それだけでした。「必要なことを叶えてくれれば十分」──彼のその謙虚さに、団体スタッフたちも心を打たれました。
最終的に団体は、床と物置の設置だけでなく、新しいキッチン家電一式や寝具を購入するためのギフト券、さらには釣り旅行までプレゼント。
テレビの取材に対して、グレンさんは火災についてこう語っています。
「煙が本当にひどくて、ほとんど作業員さんの姿は見えなかった。でも、彼には8歳と13歳の娘さんがいるって聞いていたんだ。後日、その子たちから心に響く手紙をもらったんだ。読むだけで涙が出るような内容だったよ」
自分も誰かのために、ちょっとだけやさしくなれるかも
誰かの命を救い、自分の病については語らず、ただ必要なものを求めただけの彼。そんなグレンさんの姿は、「本当の強さ」と「やさしさ」の意味を私たちに教えてくれます。
日々の暮らしの中で、ふと疲れを感じたり、誰かにやさしくする余裕がなくなったりすることもありますよね。でも、世界のどこかで起きているこうした物語を知ると、「自分も誰かのために、ちょっとだけやさしくなれるかも」と思えてきませんか?
小さな親切や思いやりが、こんなにも大きな希望を生む──
今日も一日、私たちらしく、やさしさを忘れずに過ごしてみましょう。
家を整えると、心も整う。おすすめの収納グッズをご紹介

整理整頓は単なる「片づけ」ではなく、心と時間の余白を生む行為。自然素材やエコ設計の道具を使い、より丁寧で地球にもやさしい暮らしへ踏み出しましょう。
整理のコツ3ステップ
- 視覚化する
収納スペースを見える化することで、必要な「あるもの」「要らないもの」が明確になります。 - 手に取りやすくする
良く使うものは取り出しやすく、戻しやすい場所・仕組みを作ることが継続の鍵。 - 心地よさを基準に
美しく機能的で、使っていて「気持ちいい」と感じることが続けられるコツです。
おすすめ収納グッズと注目の製品
1. 無印良品 (Muji)
素材:竹、ラタン、再生プラなど環境配慮素材
特徴:ミニマル&機能的で長く使えるデザイン。紙やプラ包装の削減にも注力
おすすめ:Muji スタッカブル竹収納ボックス — Medium、ウォーターヒヤシンス
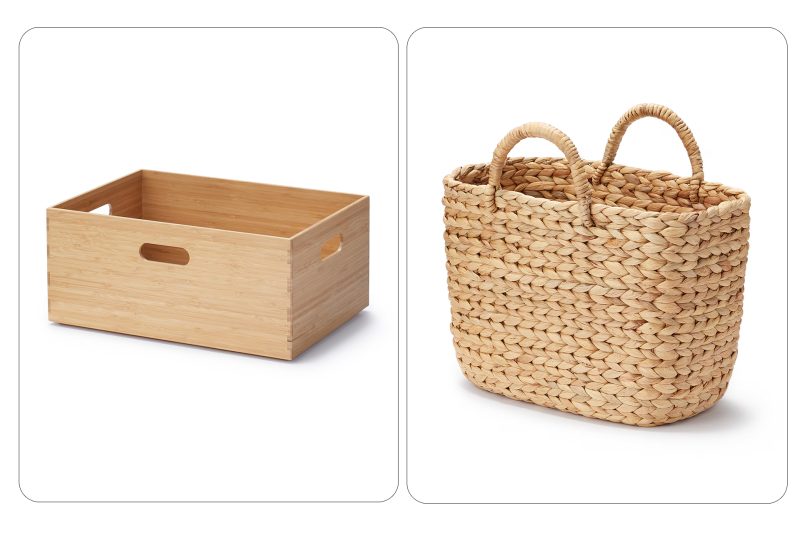
2. Yamazaki Home(山崎実業)
素材:竹、スチール、抗菌塗装
特徴:小スペース対応のスマート設計と機能優先のミニマリズム
おすすめ:竹×スチール収納バスケット、ペン + デスクオーガナイザー

3. Mifuko
素材:ケニアの天然素材による手編み
特徴:アフリカの職人支援と伝統技術継承に貢献
おすすめ:キオンドマーケットバスケット、パンバ フロアバスケット
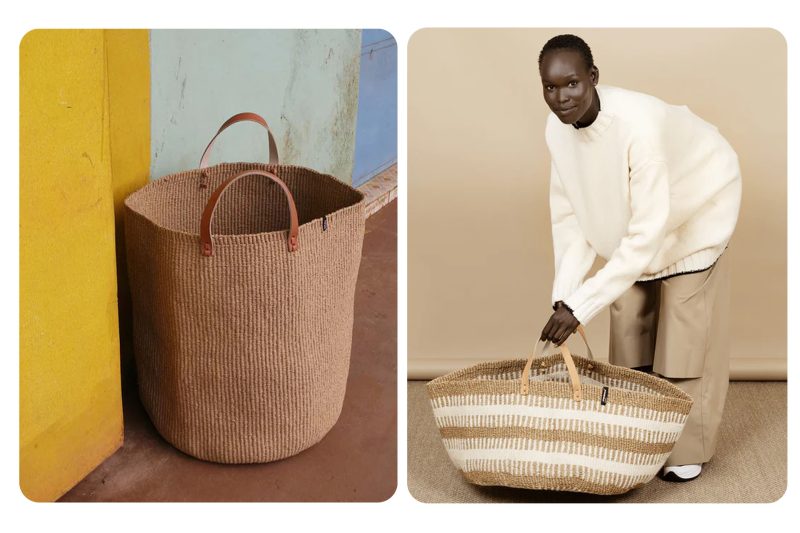
4. Ifuji
素材:国産桜材を使用したハンドクラフト製品
特徴:一生モノの収納箱を手作りで提供
おすすめ:OVAL BOX、RINKA OVAL PLATE

5. Bags By The Ocean
https://www.bagsbytheocean.com/
素材:再生ペットボトル由来のファブリック
特徴:壁面収納に適したハンギング型オーガナイザー

6. Savor
素材:再生ファブリック
特徴:書類整理・小物収納に特化し、アップサイクル素材活用
おすすめ:書類収納ケース、整理ボックス

環境にも自分にも優しい素材と機能性を備えた収納ツールなら、「片づける」ことが安心で楽しい習慣になります。まずは一つ、お気に入りから試してみてくださいね。
仕事を失ったとき、自分や大切な人を支える方法

昨年11月、パートタイムの仕事を解雇されました。その後の数週間はとても辛い時期でしたが、友人や大切な人たちが変わらずにそばにいてくれたことに、本当に救われました。
ただ、仕事を失った直後、まわりの反応は必ずしも自分が思い描いていたものではありませんでした。何かしらの慰めの言葉をかけてくれると思っていた人たちの多くが、逆にその話題を避けるように、他の話をしたり、連絡を控えたりすることがありました。
最初はそうした沈黙に傷つきましたが、今となってはその気持ちもよくわかります。自分も同じ立場だったら、どんなふうに寄り添えばいいのか迷ってしまうと思うからです。
この経験を通して、私は自分自身をどう支えるか、そして仕事を失った大切な人をどう支えるかについて、まさに「実践で学ぶ」時間を過ごしました。ここで得た学びが、今困っているあなたや、将来同じような立場になる誰かの力になれば嬉しいです。
関連記事 | 手放しの法則の本当の効果とは|執着や願いを手放した先に現れる未来
仕事を失った大切な人を、どう支えればいい?
まずは、「どうすればいいか」から考えてみましょう。
大切なのは、あなたがその人について何を知っているかを思い出すこと。たとえば私自身は、人に気持ちを話して「つらかったね」と優しい言葉をかけてもらったり、ぎゅっとハグしてもらったりすることで大きな安心感を得るタイプです。もしあなたの友人や家族が同じようなタイプなら、最初に必要なのは、そっと寄り添って話を聞いたり、「大丈夫だよ」と言ってあげたりすることかもしれません。
反対に、1人で静かに気持ちを整理するのが好きなタイプの人なら、「いつでも話を聞くよ」と伝えるだけで、無理に話をさせたりしないことの方が助けになるでしょう。
セラピストのアーロン・ギルバート氏は、こう語っています。
「最も大切なことは、大切な人のそばにいてあげることです。とてもシンプルですが、実際にはとても難しいことでもあります。誰しも、目の前の問題を解決したくなってしまうものですが、まずは落ち着いて、アドバイスではなく“ただ聞くこと”を意識してみてください。」
仕事を失うと、自尊心が大きく揺らぎます
どんな理由であれ、本人は「自分はどこかで間違った選択をしてしまったのでは」と感じたり、「自分の価値が認められていないのでは」と思いがちです。私自身も、まさにそうでした。
キャリアコーチのジャネル・アブラハム氏はこう言います。
「感情面では、仕事を失う前と変わらずその人は“価値ある存在だ”ということを、何度でも思い出させてあげることが大切です。失業したことは、その人の内面の欠陥ではありません」
そして、最初のショックが落ち着いてきたタイミングで、あなたの「実務的なサポート」がとても力になります。
アブラハム氏によれば、こんなことが役立つそうです:
- 履歴書やLinkedInのプロフィールを一緒に見直す(本人が希望した場合)
- 自分のネットワークで役に立ちそうな人を紹介する
- 求人情報を送るのは、本人が「欲しい」と言ったときだけ(それ以外はプレッシャーになる場合も)
- コーヒーをごちそうしたり、仕事とは関係のない気晴らしに誘って「あなたは仕事だけじゃない」と思い出させてあげる
こうしたサポートが、大切な人の再出発の力になるはずです。

次に、「何を言えばいいか」について:
相手に悪気はなかったのだと思いますが、私が仕事を失ったことにまったく触れず、話題を避ける人たちに対して、当時とても傷ついたのを覚えています。私はむしろ、少しでも話したかったんです。もちろん、何時間も語りたいわけではありませんでしたが、それは間違いなく私の人生で“今、起きていること”でした。だからこそ、その話題を避けられると、「私のことに興味がないのかな」と感じてしまいました。
「周囲の人が仕事を失った大切な人の話題に触れないのは、本人の気持ちを守ろうとしたり、気を紛らわせてあげようとしたりする意図からですが、実際には“苦しいときに寄り添ってくれる存在であること”こそが、一番の支えになります」と、セラピストのギルバート氏は言います。
「本人が話したいかどうかを尊重し、どちらであっても『自分はあなたの味方でいるよ』と伝えることが、真の“そばにいる”という姿勢です。」
ギルバート氏とアブラハミ氏によると、以下のような声かけが有効です:
- 「こんな状況になって、本当に辛いよね。話したかったら、いつでも聞くよ。もちろん、他の話でも全然OKだよ」
- 「すごく大変な時期だよね。もし気持ちを吐き出したくなったら、私は聞く準備ができてるよ」
- 「何か必要なことがあれば、何でも言ってね」
※ギルバート氏は、より具体的な提案をするのも効果的だと言います
例:「明日、夕食を持っていこうか?」「週末、一緒にハイキングに行かない?」「少し休めるように、お子さん見てるよ」など - 「今回のことがあなた自身を決めるものではないよ」
反対に、アブラハミ氏は次のような言葉は避けるべきだとアドバイスしています:
- 「すべてのことには意味があるんだよ」
- 「すぐに次が見つかるって!」
- 「〇〇に応募してみた?」
- 「△△の会社から返事きた?」
たとえ励ますつもりでも、無意識にプレッシャーをかけてしまう可能性があるので注意が必要です。

仕事を失ったあと、自分をどう支えるか?
仕事を失うことは、非常に孤独な体験です。たしかに、友人やパートナー、家族は私のそばにいてくれましたが、LinkedInのフィードをうなだれながら眺めている間、ずっと手を握ってくれるわけではありません(それができたら嬉しいですが)。どんなにつらい経験でも、すべての瞬間にそばにいるのは自分自身。だからこそ、自分をきちんとケアする必要がありました。
正直に言うと、ほとんどの時間はLinkedInを閉じてNetflixを開いたり、PCから離れてホリデーショッピングに出かけたりしていました。専門家の推奨とは言えませんが、それでも少しずつ気持ちが回復していったのです。
キャリアコーチのアブラハミ氏はこう語ります:
「この時期のセルフケアは、甘えではなく“安定・自己への思いやり・回復力”のためのもの。感情を整理し、自信を取り戻し、前に進むための明確さを取り戻す助けになります。これがないと、不安から動きすぎて燃え尽きてしまう可能性があります」
セラピストのギルバート氏もこう付け加えます:
「セルフケアをするかしないかで、仕事を失った体験を乗り越えられるか、それに押しつぶされるかが分かれると言っても過言ではありません」
私たちは、睡眠不足の翌日に気持ちが沈んだり無性に甘いものが欲しくなったりするのをよく知っています。困難な時期こそ、健康的な習慣はさらに重要になります。そうした土台があってこそ、感情を整理し、仕事探しをする準備が整うのです。
ギルバート氏は、睡眠・食事・運動の大切さに加えて、「自分が何を必要としているかを知ること」が鍵だと話します。
「夜にゆったりとお風呂に浸かることかもしれないし、森の中を歩くこと、日記をつけること、あるいは全く違うことかもしれません。『今、この瞬間の私は何を必要としている?』と自分に問いかけてみてください」
そして、その答えが見つかったら——それを実行しましょう。
またアブラハミ氏は、「神経系の安定化」を、失業後の回復への第一歩と位置づけています。その一環として、LinkedInの利用時間に境界線を設けることも含まれています。
解決モード”に入るのではなく、「前職で何を学び、これから何を望んでいるのか」をじっくり考える時間を取ることが大切です。日記を書いたり、コーチングを受けたり、信頼できる友人と話すことが助けになります。
そして最後に必要なのが「自己肯定」。
「あなたの価値は肩書きで決まるものではありません」とアブラハミ氏は強調します。
「もし友人が同じ状況だったら、どんな言葉をかけるか?それと同じように、自分に優しく語りかけてください。あなたにはスキルも価値もあり、これは一時的な“季節”であって、あなたという人を定義するものではありません。」
ガーデニングの効果を深掘りしてみよう

自分で野菜を育てることは、決して新しいアイデアではありません。古代の人々にとって、栄養価の高い食料を安定して確保するためには、家庭菜園が欠かせない存在でした。
時代によって、家庭菜園の必要性は変化してきました。近年では、スーパーで安く簡単に食料が手に入るにもかかわらず、ガーデニングの人気が再び高まっています。
ある調査によると、新型コロナウイルス感染症のパンデミックの最中にはガーデニングへの関心が高まりました。多くの人が自宅で過ごす時間が増え、自然とのつながりやストレスの軽減、食料の確保手段としてガーデニングに注目したのです。
私自身、10年間にわたり、自宅で広い菜園と花壇を手入れしてきました。手間はかかりますが、その分、植物が育っていく様子を見守るのはとてもやりがいのある経験です。
ここでは、私が実感してきた「土に触れること」のさまざまなメリットをご紹介します。
関連記事 | 【初心者向け】ガーデニング入門|何から始めれば良い?
ガーデニング効果で全身運動
一日ガーデニングをすると、全身を使った良い運動になります。草むしりをしながらスクワットやランジのような動きが自然にでき、土や肥料の袋を運ぶことで大きな筋肉群も鍛えられます。耕したり、芝刈り機を使ったりする作業はかなり体力を使います。
ジムでのトレーニングに匹敵するカロリーを消費することも。ガーデニングに不慣れな方は、翌日に筋肉痛を感じるかもしれません。バランス感覚、筋力、柔軟性も高められます。
身体を動かすのが難しい方でも、道具やアイデア次第で無理なく楽しめます。腰に負担があるなら、小さな椅子や高床式の花壇、軽量の鉢や小さな土袋を使うのがおすすめです。
ガーデニング効果で自然と食生活が整う理由
自分で育てた野菜や果物を食べることで、より健康的な食習慣が身につきます。ガーデニングをしている人は、バランスの取れた食生活を意識する傾向が強く、我が家でも、自家製のコーンやポテト、サルサを一年中楽しんでいます。
野菜それぞれに異なる栄養効果があります。ピーマンは抗炎症作用のあるカプサイシンを含み、心臓病予防に効果が。トマトにはビタミンCとカリウム、前立腺がんリスクを下げるリコピンが含まれています。サツマイモは老化予防に役立つβカロテンが豊富。ほうれん草は免疫力を高め、ブロッコリーは細胞を守ります。

自然とつながる毎日とガーデニング効果
屋外で過ごす時間は、身体と心の健康を高めます。外に出ることで深い呼吸が促され、肺の浄化、消化促進、免疫力向上、血中酸素の増加につながります。
また、自然の中にいることで心拍数や筋肉の緊張が緩和され、日光を浴びることで血圧の低下やビタミンDの生成も期待できます。
ガーデニング効果でストレスにサヨナラ
運動全般と同様に、ガーデニングもストレス軽減に効果があります。植物を育て、収穫し、誰かと分け合うプロセスは非常に満足感を与えてくれます。
水やりや草取りといった日課が、心のリズムを整え、心を落ち着けてくれることもあります。私自身、1日の仕事を終えたあと、1時間ほど庭仕事をするのが日課になっています。雑草を抜くことが、思考を整理する時間にもなっています。
土からはじまるガーデニング効果とご近所の輪
ガーデニングは人との交流を育む活動でもあります。ガーデニング好きの人たちは知識や苗を惜しみなく分け合う傾向があり、地域のガーデニング経験者は、初心者へのアドバイスもしてくれます。市民農園では、異なる背景を持つ人々が一つの目標に向かって協力し、自然とつながりが生まれます。
私にとって最も大きなガーデニングの恩恵は、こうした「つながり」でした。春には友人や近所の人と計画を立て、夏には収穫した野菜を交換し、秋にはサルサパーティーで収穫を楽しみます。

ガーデニングを始めるための3つのコツ
- 小さく始めること
最初から広いスペースに挑戦するより、小さな区画からスタートしましょう。無理をするとかえってストレスになりかねません。 -
仲間を見つけること
ガーデニング仲間と知識や経験を共有すると、楽しさが倍増します。 -
適した植物を選ぶこと
地域の気候や環境に合った植物を選ぶことで、成功率が上がり、挫折感を避けることができます。地域の園芸センターや経験者に相談するのもおすすめです。
ガーデニングは、心と体の健康、そして人とのつながりを豊かにしてくれる、素晴らしい習慣です。ほんの小さな一歩から、あなたの暮らしを変える大きなきっかけになるかもしれません。
セックスレス、会話不足、不倫…パートナーとの悩みを元AV女優がひも解く!【男女コミュニケーション心理士の小室友里さんインタビュー】

「パートナーとのコミュニケーションが最近うまくいかない」と感じていませんか?「言いたいことが言えない」「会話が減った」といった悩みは、多くの女性が抱える共通の課題です。
今回、私たちは男女コミュニケーション心理士の小室友里さんにお話を伺いました。小室さんは、かつてアダルト業界でキャリアをスタートさせたという異色の経歴を持つ、コミュニケーションの専門家です。「性」についても率直でユニークな視点をお持ちの小室さんと一緒に、夫婦間のコミュニケーションのあり方、特に「性」が関係する悩みの原因とその解決方について、深く掘り下げていきます。
アダルト業界から学んだ、男女のすれ違いと本当のコミュニケーション
ーーまずはじめに、「男女コミュニケーション心理士」というユニークな肩書きを持つに至ったきっかけを教えていただけますか?
私のキャリアは、30年前にアダルト業界からスタートしました。男女間の深いコミュニケーションをビジネスの出発点とした、少し珍しい経歴と言えるでしょう。その中で気づいたのは、アダルト業界から発信される情報が、一般社会では非常に屈折して受け取られているということでした。
アダルト業界の人間は、AVを「バイブル」や「教科書」として作っているつもりは全くありません。単なるサービス産業の一つ、エンターテイメントの一つとして制作しているのですが、どうやら一般社会では違う解釈をされているらしい。このギャップを埋め、本来の意図をわかりやすく伝えていく必要があると感じたのです。
そこで2015年に「男女コミュニケーション」という表現を使い始め、その後、私自身が「男女コミュニケーション心理士」という資格を作り、取得しました。現在は、男女間のコミュニケーション、ジェンダーの問題、そして女性の社会活躍をテーマに、講演やセミナー、研修を行っています。
ーーアダルト業界でのご経験が、現在の男女間のコミュニケーションに関する気づきにどのように繋がったのでしょうか?具体的にどのような「屈折したイメージ」に気づかれたのですか?
アダルトビデオは、主に男性向けに制作されている作品が多いのですが、その中で表現されている女性の表情やスタイル、アクションが、日常生活の性生活においても当たり前に出てくる反応だと考えている男性が非常に多いことに気づきました。たとえそれが「作られたもの」だと分かっていても、現実でもそうしたアクションやリアクションをしてほしいという願望を持つ方が非常に多かったのです。
この「理想」と「現実」の間の大きなズレこそが、私がアダルト業界での経験を通じて得た大きな気づきでした。
男性からの性に関する悩みは主に「自分がいかない」「立たない」「女性をいかせられない」の3つに分けられます。
ーーその時の気づきや体験は、現在のカウンセリングにどのように活かされていますか?
例えば、男性からいただくご相談は、大まかに分けて3つあります。1つ目は「自分がいかない」、2つ目は「立たない」、つまり勃起に関する身体的な悩みです。そして3つ目が「(相手を)いかせられない」というもの。これは、女性をオーガズムに導けない、潮を吹かせられないといった、自分のスキル不足に関する悩みですね。
驚くべきは、男性がこうしたことで悩んでいる一方で、女性はそこまで求めていないというケースが往々にしてあることです。この男女間の「ズレ」はかなり大きいと感じています。
こうした悩みに対して、私だからこそ答えられることがあると思っています。なぜなら、私は演者側として身をもって現場を体験してきたからです。撮影現場は結構体育会系で、エロい雰囲気なんて全くありません。何分間で何をしなければならないか、アジェンダが明確に決まっているんです。何分後にこういう行為をして、何分後に挿入して、何分後に射精するというように、すべてが作られた映像なんですよ、という話をします。それでも「女性は感じているんでしょ?」と聞かれることもありますが、「いえ、あれは演技であり表現です」とお伝えします。これはなかなか聞けない話ですよね。(笑)

セックスレスの背景にある“触れ合い”の不足
ーー小室さんの元に相談に来られる方の男女比はどのくらいで、一番多い悩みは何ですか?
カウンセラーとしては珍しい立ち位置だと思っていますが、私の場合は男性の相談者が多い傾向にあり、これまで6割が男性でした。最近になってようやく女性が4割に増えてきたという感じです。
男性、女性問わず、お悩みの根幹にはやはり「性」というものがあります。それが細分化されている、というイメージです。
一番多い悩みは、やはりセックスレスですね。そのセックスレスが根幹にあり、そこからマスターベーションの話や、セックスレスの解消、あるいは婚外にパートナーを求めているといった話に細かく分かれていきます。
ーーセックスレスの悩みに対して、小室さんが最初にするアドバイス、最初のステップとは?
相談者の方それぞれなので、まずは詳しくお話を伺わないと分かりませんが、どれだけご夫婦間で日常会話をしているか、ということをお聞きしますね。
その日常会話の中に、例えば手を繋ぐ、肩に触れるといったボディタッチのアクションや、少しセクシュアルな話が入っていますか?というようなヒアリングから始めていきます。
「性は語るべきでない」という文化の中で育った私たちにとって、関係を深める第一歩は、言葉ではなく“そっと触れること”かもしれません。
ーーセクシュアルな話は、なかなか難易度が高いと感じる方も多いと思います。日々の生活の中で、具体的にどんな声かけや、女性から男性へのアプローチの例がありますか?
そうですよね。女性が男性にセクシュアルなアクションを起こすことについて、そもそも日本文化の中では「女性は慎ましくあるべきだ」といった「べき論」で語られてきた部分が多いと思います。私自身も今年50歳になりますが、親世代や祖母世代から「性ははしたない」「言葉にするものではない」といった文化の中で育ってきましたから、いきなりセクシュアルな会話と言われても思いつかないのは当然です。
ですので、日常会話や日常生活の中から、少しずつ入れ込んでいくのが良いでしょう。それも言葉である必要はありません。「ノンバーバルコミュニケーション」、つまり言葉ではないコミュニケーションでも十分可能です。具体的には、指に触れるとか、肩に触れるだけでも、実は性的な接触と捉えられなくはないんです。
特にセックスカウンセリングでは、一番最初は「手に触れる」ことから始めます。それも嫌がるようであれば、まずは「距離感を縮める」ことから。例えばソファに座っていて、どれだけ体同士の距離感を詰められるか、というレベルからスタートします。

「セックスレスと不倫に揺れる心に寄り添う」――女性の相談が増える背景と、その本音とは
ーー先ほど悩みのひとつに「不倫」も多いと伺いました。具体的にどのような内容のご相談が多いのでしょうか?男性の悩みというイメージが強いですが、実際はどうでしょうか?
不倫のご相談は、実は圧倒的に女性が多いんです。これは私のカウンセリングの場合ですが、もともと男性のご相談者が多い中で、不倫のご相談が増えてきたのはここ1、2年ですね。おそらく、私のカウンセリングに関する女性への認知が高まったからでしょう。
ご相談の内容としては、おっしゃる通り、夫とのコミュニケーションのすれ違いやセックスレスが原因になっているケースが多いです。掘り下げていくと、「旦那さんに女として見てもらえなくなった」というお気持ちが非常に強いですね。
ーーそういった悩みに、小室さんはどうアドバイスをされますか?
その方それぞれに寄り添わせていただきますが、必ず聞かなければならないのは、「どうなりたいのか?」ということです。その方にとってのベストな状態は何なのか、というお話はどこかで聞かせていただきます。
なぜなら、相談者の方によっては、もう一度夫と関係を修復したいという方もいれば、正直なところ「夫じゃなくてもいい」という答えが出てくる方もいらっしゃいます。あるいは、夫とは「運命共同体」や「経済共同体」という立場を取れればいい、という方もいます。
その方の未来のゴールが、なんとなくでも見えてこないと、今苦しんでいる状況を一時的に解消したとしても、また同じ悩みに戻ってしまう可能性があります。限られた時間ではありますが、その方が求める未来のゴールを見せていただいてから、「では今、何をしていこうか」というお話をするように心がけています。
多くの女性は「話を聞いてほしい」「今の自分を認めてほしい」という気持ちを抱えて相談に来る傾向があります。
ーー小室さんに相談に来られるということは、不倫を辞めたい、このまま続けてはいけないという意識があって皆さんいらっしゃるのでしょうか?
いいえ、必ずしもそうとは限りません。女性の場合は「聞いてほしい」という気持ちが強いように感じます。そして、「こんな自分」を認めてほしい、という気持ちを強く感じますね。これは男性にも共通することですが。
特に「性」というところが私の強みでもあるので、その「セックスをしている自分」も含め、今の自分を誰かに承認してほしいという気持ちが強いように感じます。
ーーセックスの話は、仲の良い女友達でもなかなか話せない部分だと思います。小室さんのような、現場をご存知の方だからこそ話しやすいというのもあるのでしょうか?
そうですね。私も感じるところですが、近しい関係であればあるほど話せないのが「性」や「セックス」だと思います。似たようなところにお金の話もあるかもしれません。遠ければ遠い人ほど話しやすい、ということはありませんか?例えば、たまたま居酒屋で隣に座った人に飲みながら愚痴程度に話す、といったように。
ーー男性の不倫で悩んでいる方も、やはり女性と同じように「承認してほしい」という気持ちが強いのでしょうか?
承認してほしい、という気持ちは女性と似ていると思います。ですが、男性の場合は心のどこかに「このままじゃまずいよね」という気持ちがあるように感じます。
ーー男女間のコミュニケーションにおける最大の課題とは何でしょう?特に、「女性の価値が男性主導で決まる」という小室さんがご指摘されている社会的な背景について、小室さんが感じる課題を教えてください。
まず女性の方からお話すると、女性は自己承認をすることで、様々な問題が解決していくと感じています。自己承認の中には、自分の「性」への自己承認も含まれます。以前もお話ししたかもしれませんが、女性の性が男性の価値によって「価値づけされている」という現状があります。
女性が自身の価値を自分自身でまだ決めきれていない、という部分ですね。これを「私はこれでいい」と自分で決めてあげることができたら、おそらく性の話だけでなく、家庭のことや仕事のことも、すべて自分で「私、これでいい」と責任を持てるようになると思うのです。
先ほどの不倫の話に戻れば、「不倫をしているこんな自分も、私だからこれでいい」と、何かあった時には私が責任を取ります、という気持ちがあれば、もっと楽に生きられる気がしませんか?もちろん、それには責任だけではなく、家庭のことや経済のことも関わってきますが、そこすらも自分の責任だと置き換えて考えた時に、女性の生き方は変わるのではないかと考えています。

セックスレスや不倫の悩みを根本から見直すには、自己承認を高めることが鍵
ーーやはり「男性からどう判断されるか」「男性にどう思われるか」というところが基準で女性が考えがちな部分は、結婚しても変わらないことが多いと感じます。この自己承認は、どうやったら高められるのでしょうか?
今までの文化に逆らう部分も出てきてしまうので、自分の生き方そのものに一度メスを入れるというか、疑いを持つ時間も当然出てきてしまいますから、決して楽な時間ではないと思います。
まず大切なのは、他の先生方もおっしゃると思いますが、自分で自分を良しとすることです。その一つの方法として、私は「働く」ことだと思います。例えば専業主婦の場合、評価してくれる方はパートナーである夫とお子さんや家族といった、ここからの評価に限られますよね。その評価をいただける場所をもっと広げていくことです。様々な方から様々な評価をいただくことで、それが自分の自信に変わっていくと思うのです。
自己承認の力をつけていく、もっと言えば、他人の力を借りて自己承認をしていくということですね。家の外に出ることで、自分の力が見えてくる、できるようになるという感覚です。
ーー小室さんは女性の社会活躍の分野でもご活躍されていますが、女性がさらに社会進出し、会社でも上の立場になるという傾向は良い流れだとお考えですか?
はい。これは、女性がもっと楽に楽しく生きられるようになるだけでなく、特に日本人男性が抱えてきた「男はこうあるべきだ」という価値観からの解放にも繋がっていくと思うのです。
男性ももっと楽に、もっと自分らしく生きられるようになっていくだろうなと。最終的な結果は多分そこだと思います。女性だけでなく、男性側にとってもですね。
そこには男性も男性で、今までの自分の価値観というものに一度立ち返る必要はあります。「自分が稼ぐことが価値」であり、セックスに置き換えれば「自分が快感を与えることが価値」だという考え方です。
それが、女性も自分の快感や快楽を自分で取りに行く、自分も与える側になる。そうすると、セックスはもっと楽になりませんか?お互いもっと自由な形でリラックスして、お互い与え合える関係、与え合えるセックスができたら、めちゃくちゃ楽しくなりそうじゃないですか。
ーー海外では、そういった性の同等な関係性が一般的な国もありますよね。
私の考えですが、セックスで与え合えるようになると、そこに至るまでに信頼構築が絶対に必要なので、時間もかかります。そうなることで、他の人とのセックスをする理由がなくなっていくんです。つまり、不倫がなくなる、ということです。
そういった、お互いが本当に望むもの、つまり「自分が与えたいもの」ではなく、「お互いが望むもの」をギブできるようになれば、他に行かなくなる。不倫がなくなる。こういうサイクルなのではないかなと思います。セックスというもののイメージが、そう考えると変わってきますよね。
セックスレスや愛情表現に悩む私たちがまずできることは、「ポンコツな自分」を許し、認めることから
ーーセックスや愛情表現に関する私たちが持つ思い込みを手放すために、今日からできる小さな習慣や、日々に取り入れられるちょっとしたことはありますか?
小室友里的な観点でお話させていただければ、「ポンコツでいいんじゃないか」と思っています。だって、できないことはできないし、嫌なことは嫌だし。それを自分で許してあげる、認めてあげることがまず第一段階です。
このポンコツな自分を相手が認めてくれるか、というのはまた別の話なので、それは相手が受け取りやすいように形を変える、言葉を変えるなどして、やはり伝えていく。これが第二段階かなと思います。「受け取ってもらいやすい土壌を作っていく」ということですね。
私もそこそこポンコツなんです。こういう雰囲気で喋っちゃってるので、あまり「ポンコツだね」って言ってもらえないんですけど(笑)。でも、すごくポンコツなんですよね。
ーーでも、「ポンコツでいい」という言葉は、「これでいいんだ」と思わせてくれる落ち着く響きがありますね。
「ダメな人間」と本質的に同じことを言っているんですけど、私は「ポンコツ」という言葉が好きです。
ーー他人が決めた女性としての価値に振り回されず、自分の軸を持って生きていくために、何を心がけたら良いでしょう?
「なんとなく」でやらないことです。自分の軸はこれだ、というものを、やはりどこかで書き出して、それを自分で見ることです。書き出してみると色々なものが出てくるんですよね。自分の価値観、それは恋愛に対しても仕事に対しても、お金に対しても、家庭に対しても、様々な価値観があると思います。これを書き出してみる、見てみる。この作業は、自分軸を作ってくれると思います。
私も実際に書いています。今、めちゃくちゃ書いていますね。手帳でもノートでも何でもいいので、やっぱり手を動かして自分の文字で書き出して、その文字を見ている時間というのが、何よりの自分との対話に繋がっているなと感じます。
ーー最後に、多くの読者が抱える「今さら夫に愛しているなんて言えない」といった悩みを持つ女性に、一つアドバイスがあるとしたらどんなアドバイスになりますか?
「愛している」なんて言えない、という方には、「なんで愛しているって言えないの?」というのを、5回、自分に問いかけてみてください。「なんで?なんで?なんで?」と繰り返していくと、5回目くらいになってくると、「なんで私、愛しているって言えなかったんだろう」というご自身の答えが見えてくるかもしれません。
いきなり「愛している」と言うためにこれをやりましょう、と言っても根本解決にはならないと思うんです。なんで自分は「愛している」と言えなくなったのか、というのを、ご自身が理解してからでないと進めないんですよね。スタートラインに立てないので。
私がお伝えするとしたら、まず自分のスタートラインをしっかり自分が認識しましょう、ということですね。どんな悩みもそうですが、根本の原因やゴールを考えないと、そこで止まってしまいます。
小室さんの温かくも力強い言葉は、長年の経験と深い洞察に裏打ちされたものでした。夫婦間のコミュニケーションの悩みは、一見すると表面的な問題に見えても、その根底には「性」や「自己承認」といった、より深いテーマが隠されていることを改めて感じさせられました。
あなたの「なんで?」の答え、ぜひ一度ご自身と向き合って見つけてみませんか?
______________________

プロフィール
小室友里
日本人がタブー視するセクシュアリティ(性のあり方)を切り口にした新しい視点で、ハラスメント予防法に男女心理の違いを用い、経営者向けの講演、セミナーにて全国各地を訪れている。 講演登壇100回以上、参加者は延べ5,000人以上。
2021年にチャレンジした「女性も男性も『大切な人を傷つけない』性の知識を得て、真に性に向き合える社会へ!」と謳ったクラウドファンディングでは、1ヶ月で197名から350万円の支援金を集め達成率700%を記録。オンラインサロン「女性のためのセックスエデュケーションコミュニティ」を開設。他人の性を否定しない主旨から男性も参加可能にし、男女格差を減らす情報を発信している。
2022年3月、90年代を代表する元セクシー女優として、AV出演被害防止法提出前に国会議員から意見を求められ、可決時の記者会見にもコメントを求められた。世界最大のリファーラルマーケティングチームBNIに所属し、2018年にはBNI主催のナショナルカンファレンス日本大会の総合司会に抜擢されるなど、元セクシー女優のセカンドキャリア構築のパイオニアとしても呼び声が高い。
Instagram:https://www.instagram.com/komuroyuri_official/
著書『結婚が幸せになるための性書』
【ハミングが届けるポジティブニュース】 正直者がもらったごほうび──14歳の少年が拾った財布に込めた優しさと、思いがけない贈り物

朝の支度、子どものお弁当、仕事の準備──忙しさに追われる日々のなかで、ふと立ち止まって思うことはありませんか?
「ちゃんと正直に生きるって、報われるんだろうか?」
目の前の選択が自分の得にならないとき、やさしさや誠実さを貫くのはけっこう難しいもの。
けれど──
誰かのために選んだ「正直」が、人生に思いがけないミラクルを連れてくることもあるんです。今日は、そんな「まっすぐな心が起こした、ちょっと信じられないような素敵な出来事」を、アメリカ・アリゾナ州からお届けします。
2025年5月2日、アリゾナ州チャンドラーの町を、自転車で走っていた14歳の少年、コーディ君。
ふと路上に目をやると、そこに落ちていたのはお財布。中には300ドル(約4万4千円)もの現金とクレジットカード、身分証が入っていました。
ちょうどコーディ君は「電動バイク」を買うためにお金をコツコツ貯めていた最中。それでも彼は、財布の中身に心を動かされることなく、迷うこともなく、すぐにある行動をとりました。
財布に入っていた身分証をスマートフォンで撮影し、それを母親に送ったのです。
「誰かきっと、すごく困ってると思う。だから、すぐに返したほうがいいと思った」
そう語るコーディ君。数年前に父親が財布をなくしたときのことが頭に浮かび、「あのとき、どんなに大変だったか覚えてる。財布って、その人の生活そのものだよね」と振り返ります。
その言葉には、彼のまっすぐな心と想像力がにじみ出ています。
母親のキャリーさんは、息子の行動に心を動かされ、地元のFacebookグループにその出来事を投稿。「うちの息子、ついに「グッドサマリタン(親切な市民)」デビューよ」と。
その投稿が多くの人の目にとまり、感動と称賛の声が集まる中、ある一人の「見知らぬ誰か」が動き出します。
彼は「こんなにも正直で優しい少年がいたなんて」と深く感銘を受け、自分の3,500ドル(約51万円)を使って、コーディ君が欲しかった電動バイクをプレゼントしようと決めたのです。彼はキャリーさんに連絡をとり、「そのバイク、どこで売ってるいのかリンクを教えて」とひとこと。
そして、まもなくコーディ君の元にやってきたのは、つややかな黒いボディがまぶしい、ピカピカの電動バイク。
しかも、そのブランド名がまた奇跡のようで……「インテグリティ・Eバイク」。
そう、「インテグリティ(誠実さ)」を名に持つ会社が作った自転車だったのです。
コーディ君は、今、毎日のように大好きな自転車にまたがって、暑いアリゾナの通りを風のように走っています。
何も見返りを期待せず、ただ「誰かのために」と思ってとった正直な行動。それがめぐりめぐって、彼に最高のプレゼントとなって返ってきたのでした。
世の中にはまだ、ちゃんと「やさしさ」や「誠実さ」が通じる場所がある。そんなことを、コーディ君の小さな勇気が私たちに教えてくれます。
親としても、こんなふうに育ってくれたら…と、少し胸が熱くなりますよね。
目の前にある「ちょっとした選択」に、私たちは毎日、たくさん出会っています。
見て見ぬふりをすることもできるし、少し遠回りでも誰かのためを思って行動することもできます。
その選択の積み重ねが、人生の景色を変えていくのかもしれません。
今日も、自分らしく。ほんの少し、誰かにやさしくできたら、それはもう十分に素敵なこと。
そう思わせてくれる物語でした。
Arizona Teen Returns Lost Wallet Containing $300, Receives Electric Bike He Had Been Saving for
初心者のためのワークアウトガイド

さまざまな種類の運動と、それらを週のルーティンにどう組み込むかを理解することで、運動を始めやすくなります。フィットネスクラスに参加したり、短時間のミニワークアウトを取り入れたりすることで、運動を習慣にすることもできます。
定期的な運動は、健康を維持するためにとても重要な役割を果たします。
短期的には、運動は気分やメンタルヘルス、睡眠の質を改善し、ホルモンバランスの管理にも役立ちます。
長期的には、健康的な体重や筋肉量を維持したり、慢性的な病気のリスクを減らしたりするなど、多くのメリットがあります。
もし「運動を始めたいけど、何から始めればいいのかわからない」と感じているなら、このガイドがおすすめです。ここでは、運動の種類と続けるコツについて詳しくご紹介します。
よくある運動の種類
以下のようなさまざまな運動があります:
- 有酸素運動
心拍数や呼吸数を上げる継続的な動きが特徴です。例:水泳、ランニング、ダンスなど。
- 筋力トレーニング
筋肉のパワーや太さ、強さを高めることを目的としています。例:レジスタンストレーニング、プライオメトリクス、ウエイトリフティング、短距離ダッシュなど。
- カリステニクス(自重トレーニング)
器具を使わず、主に自分の体重で大きな筋肉を動かす運動。中程度の有酸素運動ペースで行われます。例:ランジ、状態起こし、腕立て伏せ、懸垂など。
- HIIT(高強度インターバルトレーニング)
高強度の運動と低強度の運動または休憩を交互に繰り返すトレーニング。
- ブートキャンプ
有酸素運動と筋トレを組み合わせた、高強度で時間ベースのサーキットトレーニング。
- バランス・安定性トレーニング
筋肉の強化と身体のバランス感覚を高めることを目的とした運動。例:ピラティス、太極拳、片足でのエクササイズ、体幹トレーニングなど。
- 柔軟性トレーニング
筋肉の回復、可動域の維持、ケガの予防に効果があります。例:ヨガ、ストレッチなど。

これらの運動は、単独でも、組み合わせて行ってもOK。
大切なのは、自分に合った方法で、楽しく続けられることです。
始めるためのステップ
新しい運動習慣を始める前に、いくつか大切なポイントを押さえておきましょう。
1. 健康状態をチェックする
運動を始める前には、医師に相談し、健康診断を受けることが大切です。
特に、これまであまり激しい運動をしてこなかった方にとっては、事前の確認が非常に重要です。
早めの健康チェックにより、運動中のケガや体調悪化のリスクを未然に防ぐことができます。
また、自分の体力や健康状態に合わせた運動プランを立てやすくなり、必要に応じてトレーナーと連携する際の参考にもなります。
2. 計画を立てて、現実的な目標を設定する
運動を習慣化しようと決めたら、達成可能なステップと目標を含んだプランを立てましょう。
例えば、「5kmを完走したい」という目標があるなら、まずは短い距離から始めて、徐々に距離を伸ばしていくのが効果的です。
小さな達成を積み重ねることで、成功体験がモチベーションにつながり、継続しやすくなります。
3. 運動を「習慣」にする
運動を続けるために最も大切なのは、楽しみながら続けられるルーティンをつくることです。
研究によると、以下のような場合、運動習慣が長続きしやすいとされています:
楽しさを感じられる
体や心への効果を実感できる
習慣化して、定期的に実行している
新しい習慣を作るのは簡単ではありません。特に、今のライフスタイルから大きく変えようとするとハードルが高く感じられることも。
また、「運動する時間がない」と感じている方も多いはずです。
そんなときは、1日のスケジュールを見直して、30分程度の運動時間を組み込めそうなタイミングを探してみましょう。
たとえば、「朝一番」「昼休み」「仕事終わり」などが一般的な運動時間としておすすめです。
もし30分まとめて時間が取れない場合は、「10分のミニワークアウトを1日3回」でもOK!
自分にとって無理のないタイミングで運動を習慣化することで、継続しやすくなります。
一番大切なのは、“あなたに合った方法”を見つけることです。

1週間のサンプル運動プログラム
こちらは器具不要・1日30〜45分で完了する、初心者にも取り組みやすい1週間の運動プログラムです。
ご自身の体力レベルに応じて、強度を調整することも可能です。
月曜日: 40分間の中強度ジョギング、または早歩き
火曜日: 休息日
水曜日: まず10分間、テンポよく歩きます。 その後、以下の2つのサーキットを行いましょう。各サーキットは1分休憩を挟みながら3セット行います(種目間の休憩はなし)。
最後に軽くストレッチを。
サーキット1(3セット)
片足ずつ10回のランジ(交互に)
腕立て伏せ 10回
上体起こし 10回
サーキット2(3セット)
椅子を使ったディップス 10回
ジャンピングジャック 10回
ヒップリフト(お尻上げ)10回
木曜日:休息日
金曜日:30分間のサイクリング または 中強度のジョギング
土曜日: 水曜日と同じ筋トレサーキット、または別の自重トレーニングを実施
日曜日: 40分間のゆったりとした長めのウォーキング
このプログラムは、特別な道具がなくてもできるように設計されており、運動習慣を始める第一歩としておすすめです。
オフィスでも活躍する!サステナブルなファッションブランド8選

働き方が多様化している今、自分らしく心地よい服で働きたいと感じる方も増えてきています。そんな中で注目されているのが、環境や人に配慮した「サステナブルファッション」。今回は、オフィスでもしっかり映えるスタイリッシュでエシカルなブランドを10つご紹介します。
1. EILEEN FISHER(アイリーン・フィッシャー)|アメリカ
シンプルで洗練されたデザインが魅力。オーガニック素材や再生繊維を使用し、リサイクルプログラムも展開。長く着られる上質なアイテムが揃っています。
おすすめ:ゆったりとしたシルクブラウスや、シンプルなウールパンツ

2. Sézane(セザンヌ)|フランス
洗練されたパリ風スタイルが人気。B Corp認証を取得し、環境にも配慮した製造工程が魅力です。エレガントでフェミニンなデザインが豊富。
おすすめ:刺繍ブラウス、タック入りのスラックス

3. ASKET(アスケット)|スウェーデン
ミニマリストにおすすめのブランド。無駄を削ぎ落としたシンプルなデザインと、完全なトレーサビリティが特徴です。価格も透明性あり。
おすすめ:ベーシックな白シャツ、ウールニット

4. The Curated(ザ・キュレイテッド)|ノルウェー/シンガポール拠点
高品質で長く愛せるアイテムを少量生産で展開。オフィスでも映える洗練されたコートや上品なニットが揃っています。
おすすめ:カシミアコート、フィット感のあるリブニット

5. Baukjen(バウキェン)|イギリス
B Corp認証を持つサステナブルブランドで、エレガントかつ実用的なスタイルを展開。オフィスから日常までシームレスに使えるアイテム多数。

6. Reformation(リフォメーション)|アメリカ
https://www.thereformation.com/
LA発の人気ブランド。環境負荷の少ない素材や廃棄布を再利用し、エネルギー効率の高い工場で生産。トレンド感がありつつ、きちんと感のあるデザインが特徴で、セレブにもファン多数。
おすすめ:リラックス感があるドレス、ミディ丈スカート

7. Kowtow(カウタウ)|ニュージーランド
https://us.kowtowclothing.com/
GOTS認証オーガニックコットンのみを使用し、全ての製造過程が倫理的であることを徹底。フェアトレードの先駆け的存在。
おすすめ:クリーンなシャツワンピース、水玉スカート

8. ÉTICA(エティカ)|アメリカ
https://eticadenim.com/
LA発のデニムブランドで、サステナブルな素材とエシカルな労働環境のもとで製作。定番のデニムスタイルを、環境に優しくアップデートしています。
おすすめ:ブラックやネイビーのスリムデニム、シャツと合わせてカジュアルに

サステナブル=地味、というイメージはもう古い! 今ではデザイン性と機能性、そしてエシカルな価値観がすべて両立したブランドが続々登場しています。オフィスでも活躍するサステナブルなアイテムを選ぶことで、自分にも地球にも優しい選択ができます。
お気に入りの一着を見つけて、心地よい毎日を過ごしてみませんか?
【本レビュー】私たちが背負う重さ:『Wild』を読んでの個人的な感想
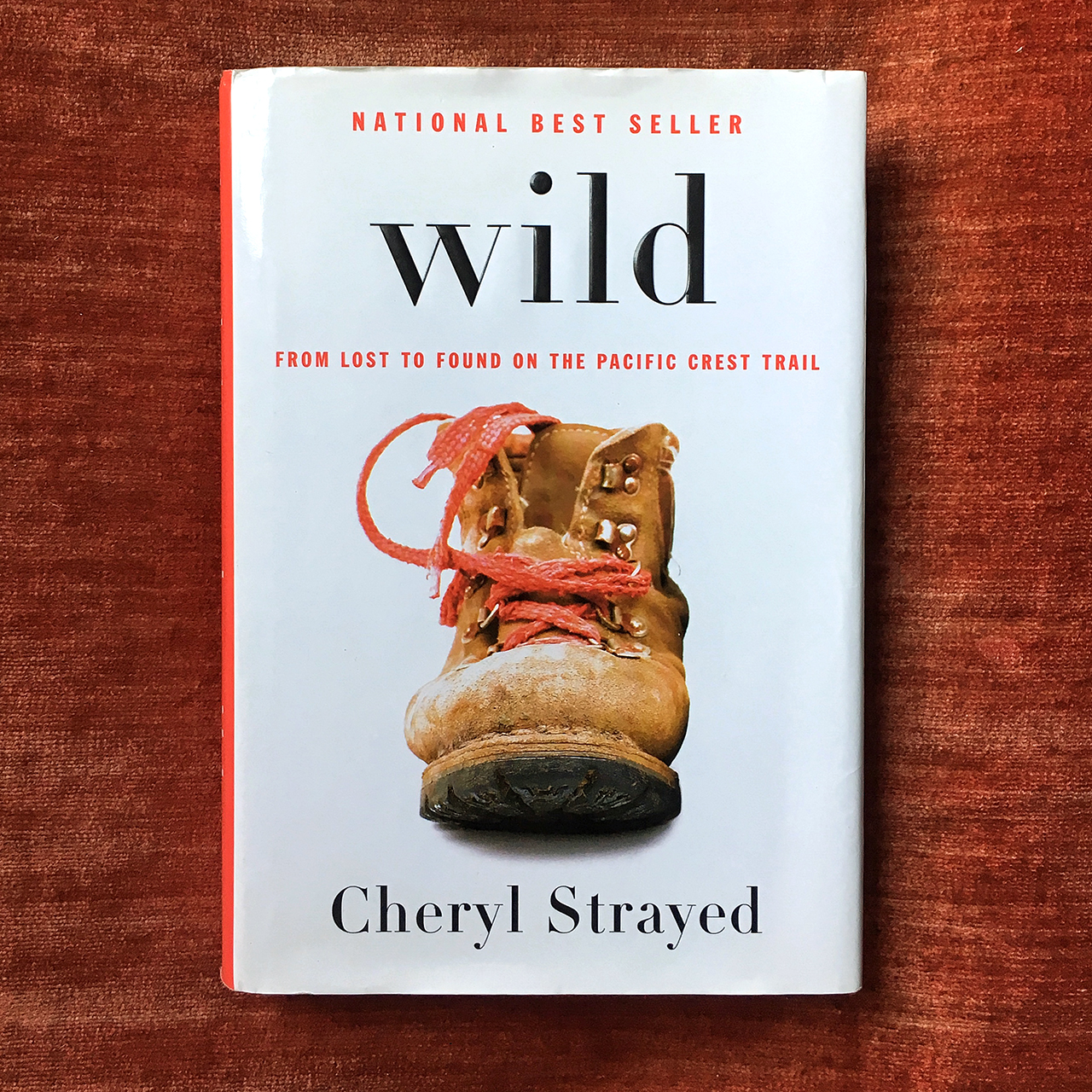
ときどき、心に引っかき傷を残していくような本に出会うことがあります。私にとって、シェリル・ストレイドの『Wild』がまさにそれでした。
一見、私には関係ないように思えるかもしれません。私は結婚したこともないし、母は健在で、ドラッグやアルコールに苦しんだ経験もありません。でも、シェリルの混乱に満ちた、無防備で、生々しい人生の意味を探す旅が、思いがけず私の深い部分に触れてしまったのです。正直に言うと、その感情に出会いたくなかった。
物語は、シェリルが母の死と向き合うところから始まります。彼女はまだ22歳、ようやく大人になろうとしていた頃、最も大切な存在が、がんによって突然奪われようとしていたのです。
「私は22歳だった。彼女が私を妊娠したのも同じ年齢だった。私が彼女の人生に現れたその時に、彼女は私の人生から去ろうとしていた」
母娘の関係は、たとえ健全であっても常に複雑です。説明のつかない、繊細でややこしい感情が、あなただけの記憶に結びついて織り込まれているようなもの。私は母を愛しています。でも、近しいと感じたことはあまりありません。母親と“親友”のような関係を築いている友人たちが、少しうらやましかった。
でも、その距離が私にくれたものもあります。それは、強さや自立心。そして、孤独の中でしか育まれない、静かな平穏。
シェリルと母親との関係もまた、複雑でありながら、深い愛に支えられていました。暴力的な夫と別れた母は、3人の子どもを一人で育てあげます。その後パートナーも見つけ、厳しい暮らしの中でも「あなたは愛されている」と伝え続けました。その静かで確かな愛が、シェリルの世界の土台だったのです。
母の病がわかると、事態はあまりにも早く進行しました。その衰え方は、残酷で容赦がなかったのです。生き生きとして笑っていた母が、少しずつその光を失っていく姿を見ることは、運命に何度も背後から刺されているような苦しみだったのです。
そして母が最期の息を引き取ったとき、シェリルはそばにいませんでした。彼女は弟と妹に、病院に来るよう説得していたのです。きっと最後になるかもしれないから、と。でも、彼らは恐怖と拒絶感に縛られて、来ることができなかったのです。ようやく全員が病院に来たときには、すでに母は亡くなっていました。

その出来事が、彼女を完全に打ちのめしました。深い悲しみが彼女を飲み込み、浮気をし、ドラッグやアルコールに逃げ、自己破壊のスパイラルに陥っていきます。深い喪失をどう処理していいかわからないときに、多くの人がたどる道でもあります。尊厳も、アイデンティティも失い、彼女は「やり直す」ことを選びました。その手段が、米国西海岸を縦断する過酷なハイキングコース「パシフィック・クレスト・トレイル(PCT)」だったのです。
最初は、「ちょっと大げさじゃない?」と思いました。失恋や人生のどん底を癒す手段が、荒野を一人で3か月も歩くこと?いかにも主人公気取りだな、とすら感じました。
もちろん、心が傷ついたときに旅に出る人はたくさんいます。新しい趣味を始める人も。でも、トレーニングもろくにせず、国内でもっとも過酷なハイキングに挑むなんて、無謀にしか見えませんでした。
案の定、準備不足は明らかでした。重すぎて持ち上げられないバックパックに「モンスター」と名付け、靴のサイズも小さすぎて、すぐに足が血だらけに。読んでいて「なんでそんなこともわからないの?」と呆れてしまったほどです。
でも、もしかするとその無鉄砲さこそが、彼女の内面を表していたのかもしれません。彼女はとにかく、自分を縛るすべてから逃げ出したかった。冷静な判断なんてできる状態ではなかった。ただ、何かを変えたかった。
それでも彼女は、歩き続けました。絶望、涙、後悔、あらゆる感情に飲まれながらも、足を止めなかったのです。なぜならこれは、自分に誓った旅だったから。
ここで、私の中の何かが変わりました。
シェリルは、自分を美化しようとしません。むしろ正反対。怒りっぽくて、無計画で、性に奔放で、心がごちゃごちゃ。でも、それって誰しもが一度は経験する姿ではないでしょうか。もしかすると、あなたも今その途中かもしれない。
道中、彼女はさまざまな人に出会います。温かい言葉、ちょっとした食べ物、乗せてもらった車。ほんの小さな助けが、彼女の壊れかけていた「人への信頼」を少しずつ修復していきます。どん底のときに手を差し伸べてくれる存在は、どんなに短い出会いでも、永遠に心に残ります。
彼女がサイズの合わない登山靴を崖から投げ捨てる場面があります。それは象徴的な瞬間でした。もう必要のない自分を手放して、本当の自分に少しずつ近づいていく。それは物理的な軽さだけではなく、心の重荷を下ろしていく過程でもありました。
『Wild』の魅力は、彼女が特別な人ではなかったこと。ハイキングのプロでもなければ、人生をうまく生きていたわけでもない。ただ、自分の人生を立て直したいと願った、ひとりの壊れた女性だったのです。

私自身、ずっと自分で自分を守らなければならない人生を送ってきました。だからこそ、彼女の物語には静かに共鳴しました。私たちは時に、自分を守るあまり、大切な人を傷つけてしまいます。そして、自分自身が傷ついて初めて、愛はちゃんとそばにあったんだと気づくことがあります。
「カリフォルニアが、絹のヴェールのように私の後ろに流れていった。もう自分がバカだとは思わなかったし、“最強のアマゾネス”でもなかった。ただ、私は強くて、謙虚で、自分の内側にちゃんと集まっていた。私も、この世界でちゃんと安全なんだと思えた。」
限界まで自分を追い込むと、謙虚さを思い出します。汗をかき、血を流し、痛みを感じる。それは不快だけど、確かに“生きている”という感覚です。
人から「すごいね」「タフだね」と言われることがありますが、私自身はそんなふうに思ったことはありません。ただ、何度も転びながら立ち上がった、それだけです。
人は痛みに耐えたくないから、自分を変える旅に出ることを恐れます。でもその不快さこそが、感謝や優しさ、謙虚さを教えてくれるのです。
人生は一直線ではありません。失敗し、立ち止まり、道を修正しながら、ようやく「信じられる自分」に近づいていく。シェリルはそれをやったのです。理由がわからなくても、自分を信じて歩き出し、歩き続けました。
彼女は3か月におよぶ長い旅の果てに、オレゴン州の「ブリッジ・オブ・ザ・ゴッズ」にたどり着きました。白いベンチに腰を下ろし、水面を見つめながら、そっとこうつぶやきました。
「それを、ただ“そうあるもの”として受け入れるって、なんて野生的(Wild)なんだろう。」
人と触れ合うことってどうして重要なの?

デジタル化がますます進む現代において、私たちにとって最も大切なつながりの一つである「人との触れ合い」が、日常から静かに消えつつあります。安心感のあるハグ、肩に手を添えるしぐさ、信頼する人とそっと寄り添う――こうした身体的な接触は、私たちの心の健康や「人とつながっている」という感覚に大きな役割を果たしています。しかし昨今、社会的な慣習や文化の変化、そしてパンデミックの長期的な影響によって、安心して触れ合える機会が著しく減少しています。この自分でも気づかないうちに広がる喪失感は、たとえ人に囲まれていても、私たちに孤独感をもたらしています
「触れること」の科学的根拠
人が「触れ合い」を必要とするという研究は数多く存在します。発達の観点から言えば、人間の赤ちゃんは文字通り、触れてもらわないと生きていくことができません。出生直後の肌と肌の接触は、新生児の体温、心拍、呼吸を安定させ、泣く回数を減らすことが示されています。母親もリラックスホルモンやオキシトシンの分泌などが促進されます。
かつてルーマニアの孤児院で行われた研究では、十分なスキンシップを受けられなかった子どもたちのコルチゾール値や成長の度合いが著しく低かったことが報告されました。
また、心理学者ハーロウの有名な実験では、ワイヤー製の母猿と布製の母猿を用意し、赤ちゃん猿が餌を与えてくれるワイヤー母よりも、ぬくもりのある布母に強い愛着を示すことが明らかになりました。生きるために食事は必要ですが、私たちが「人として生きる」ためには触れ合いが不可欠なのです。
その後の研究でも、触れ合いの欠如が不安、うつ、ストレスなどの悪化と強く関係していることが分かっています。触れ合いは神経を鎮め、心拍数を下げ、血圧やストレスホルモンであるコルチゾールを下げてくれます。また、愛着や信頼を高めるホルモン「オキシトシン」も促されます。
PETスキャンを用いた研究では、手を握ってもらうだけで脳のストレス反応が鎮まり、その効果は愛する人との接触の方が大きいものの、見知らぬ人との触れ合いでも有効であることが分かっています。
また、触れ合いは私たちの神経回路にまで影響していると考えられています。触れ合いが不足している人は免疫疾患を抱えるリスクが高まることも分かっています。皮肉なことに、パンデミックのように免疫が試される状況でこそ、本来その機能を支えるはずの触れ合いが最も不足してしまうのです。

触れ合いを日常で増やすには
人との触れ合いがとても重要であることは明らかですが、では実際にどうやってその機会を増やせばいいのでしょうか?たとえ家族や“同じ空間で過ごす人”が身近にいたとしても、パンデミック以前に比べて触れ合いの機会が減っているのは確かです。
研究によると、接触することによるセラピー効果をもっとも効果的に得る方法のひとつがマッサージです。マッサージは、うつ症状の軽減、集中力の向上、免疫機能の強化などに効果があることがわかっています。マッサージが苦手な人は、ネイルやペディキュアなど、触れることが含まれるスパ体験も代わりになるかもしれません。
また、ペットとのふれあいも、人とのタッチに近い効果を持つことがわかっています。たっぷりとなでてあげる時間を持つことで、ストレス緩和につながります。さらに、重みのあるブランケット(加重ブランケット)は人間の手ではないものの、神経系を落ち着かせるという点で同様の効果を持つとされています。前述の実験で登場する赤ちゃん猿になったつもりで、安心感を得てみてください。
相手からの同意が大前提
最後に大切なポイントをひとつ。それは「触れ合いには必ず同意が必要だ」ということです。自分が触れ合いを強く求めているからといって、他人にその提供を強制することはできません。誰かに無理に触れ合いを求めるのは決して正しいことではありませんし、相手が応じなければならない義務もありません。
特に子どもたちにとっては、自分の身体的な境界線を守る大切さを学ぶ機会にもなります。おじいちゃん・おばあちゃんががっかりするかもしれませんが、それでもこの「同意」の大切さを子どもに教えることは、それだけの価値があります。
「きれい」のものさしは、自分で決める。内側からも輝く、私らしい美しさとは?【編集部対談】

年齢や体型、社会の目。美しさにまつわるプレッシャーは、知らず知らずのうちに心と身体を縛っています。
だけど本当は、誰もが自分らしい美しさを持っているはず。
編集部の舞麻と純が、それぞれの視点で「美と身体」について語り合いました。
美しさはもっと多様でいい
純:今回は「美と身体」についてお話ししたいと思います。このテーマは、Hummingの中でも私が特に強い思いを持っているカテゴリーです。
私は12歳から16歳まで日本で暮らしていました。その時期は思春期の真っただ中だったこともあり、体型の変化にとても敏感でした。太ったり痩せたりを繰り返し、自分の体に自信が持てなかったんです。まわりにはスラッとした子が多く、余計にコンプレックスを感じていました。
日本では特に「痩せていること=美しい」という価値観が強く、ガリガリに細い体が称賛されることすらあります。それがアメリカで育ってきた私にはとても不思議で、衝撃的でした。
だからこそ、「体型によって人の価値を決めるような考え方」は、少しずつでも手放していけたらと思っています。
舞麻:確かに、昔はケイト・モスとか、パリス・ヒルトンが人気で、痩せている体型に憧れる人が多かったよね。でも最近は、「ハリのある肌」や「引き締まった身体」などが注目されるようになって、いわゆる「健康美」を目指す女性も増えてきた気がします。
純:舞麻さんが「美と身体」をHummingのカテゴリーに選んだのはどうしてですか?
舞麻:ヨーロッパやアメリカでの暮らしを経験して感じたのは、美しさはもっと多様だということ。
最近では外国人も増えてはいるけれど、日本はまだ日本人が大多数の社会なので、美しさの基準もどうしても似たような基準で比べられがちだと感じていて。
日本基準の美しさだけでなく、もっと広い視点で「美」を見つめ直したいと思いました。
それに年齢を重ねると、身体との向き合い方も少しずつ変わってきますよね。私自身、プレ更年期といわれる年齢に入り、食事や運動だけでなく、「どんな景色を見るか」「誰と過ごすか」といった、心に触れるものもすべてが身体に影響すると実感しています。
だからこそ、これからは見た目だけではない、美しさや健やかさについて、読者のみなさんと一緒に考えていきたいです。
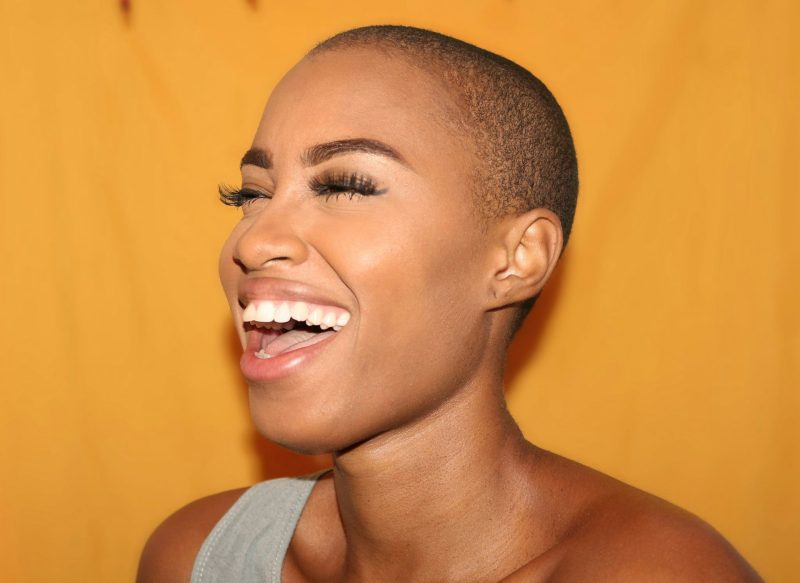
心が整えば、鏡に映る自分も変わる
純:舞麻さんはどんな人に魅力を感じますか?
舞麻:私が魅力的だと感じるのは、外見が整っている人です。整っているというのは、いわゆる美女という意味ではなくて、清潔感があって、服装や立ち居振る舞いがきちんとしていて、「その人らしさ」がにじみ出ている人のことです。
あとは、純粋で人に対して優しさを散りばめられる人や、人生を活き活きと楽しんで、いろんなことに興味を持ってる人、自分のことも人のことも大事にできている人に魅力を感じます。
そういった人に出会うと、「もっと話してみたいな」とか、「また会いたいな」と、自然と思えます。
純:「美」というと、ついメイクや髪型、服装など、見た目ばかりに目が向きがち。でも、内側を整えることも大切ですよね。
私は30代になってようやく、食事や運動を意識するようになりました。年を重ねても元気に動けるように、筋肉をつけたいと思って。
高校生のころはガリガリの体型に憧れていたけれど、今は、人それぞれ生まれ持った骨格があるから、それ以上に細くなるのはむしろ不健康だと思っています。私は背が低く、脚も短く、おしりもしっかりしていますが、「これが私の骨格なんだ」と、ようやく受け入れられるようになりました。
舞麻:私はヒップにボリュームがないから、丸みのある体型の女性を見ると、すごくセクシーで魅力的に感じます。でも、そういう体型の人はジーンズがきつかったり、人目が気になったりするのかもしれないけど。
純:そうなんです!ジーンズを履いてる自分が、好きになれなくて。でも、今は「健康的なご飯を食べて、運動もして、私はこの身体で頑張ってる。これで十分!」と、自分に言い聞かせています。
舞麻:私の好きな本に『水は答えを知っている』という一冊があって、その本には、水は言葉や音に反応すると書かれています。たとえば、優しい言葉やクラシック音楽を聞かせると、水は綺麗な六角形の結晶をつくる。一方で、ネガティブな言葉を聞かせると、うまく結晶ができなかったり、歪な形になったりするそうです。私たちの体の約60%は水分なので、どんな言葉を使うか、どんな言葉を浴びるかで、心にも身体にも影響があるはず。
だから、純が自分に優しい言葉をかけているのは、本当に良いことだと思うし、私も子どもにはできるだけポジティブな言葉で話すようにしています。
純:ポジティブな言葉は、子どもの自信にもつながりますよね。
私は母から厳しい言葉をかけられることが多く、自信が持てるようになるまで時間がかかりました。でも、決して母を責めているわけではなくて、20代は誰でも自分の身体や心に迷う時期。そういう揺らぎも、大人になるプロセスのひとつだったのかなと思います。
舞麻:子どもを産んで感じるのは、どんなにポジティブに子育てをしようと思っても、完璧な子育てなんてできないということ。きっと子どもの心の中には、何かしらのささくれだった気持ちや、「これは嫌だったな」と思う経験があると思うんです。
私も、母親にされて嫌だったことがたくさんあるし、それがしばらくトラウマとして残っていたこともあります。でも、30代になってからは、いつまでも親のせいにして生きていくのは違うと思うようになりました。
ネガティブな感情は体に蓄積されてしまうから、負の感情をどれだけ上手に手放せるかが大切。過去に誰かからされたことも、最終的には自分の責任として受け止めていく。そんな覚悟や、前に進むための「ガッツ」が必要だと思います。
純:私は、発する言葉や心の持ちようも美しさに関係すると思っています。だって、悩んでいたり、イライラしたりしていると、肌も荒れるし、げっそりと疲れた顔になってくるから。「私は大丈夫。頑張ろう!」とポジティブな気持ちだと、肌にもハリが出てくる気がします。
だからこそ、ストレスを感じる時も、落ち込む時もあるけれど、なるべくネガティブな感情に浸りすぎないように意識しています。
舞麻:脳の力は本当に偉大だから、ネガティブな感情をため込まないことは本当に大切。そのためにも、信頼できる友人やパートナーなど、話せる相手がいることがとても重要だと思っています。私はカウンセリングやセラピーを利用することもあります。身近な人だと、どうしてもその人の価値観や考え方が影響してしまうので、お金はかかるけれど、偏りなく話を聞いてくれるプロの存在は貴重です。
「きれい」は誰のため? 自分と大切な人を思いやる身体づくりを
純:「美と身体」について私がいちばん伝えたいのは、「きれい」の基準は人それぞれだということ。そして、美しくなることで誰を喜ばせたいのかを考えてみてほしいです。
私は、自分のためにきれいでいたい。自分の身体を好きになるほど、人生が明るく、楽しくなると思うからです。もちろん、自分だけでなく、大切な人のためにも美しく、健康でありたいですね。
| Humming編集長 永野 舞麻
1984年生まれ。16歳までを日本で過ごした後、海外へ移住。大学で出会ったアメリカ人の夫と結婚し、現在はカリフォルニア在住。3児の母。 高校時代、スイスに住んでいたときに自然の偉大さに触れ、地球環境保全について学び始める。アメリカの美術大学でテキスタイル科を専攻。 今でも古い着物の生地などを使って、子育ての合間に作品を制作し続けている。 |
| Humming編集部Project Coordinator 條川純
1984年生まれ。アメリカ生まれ、アメリカ育ち。現在はひとり暮らしをしながら、生涯を共に過ごせるパートナーを探している。 |
ーーーーー
\ポッドキャストはじめました/
編集部対談の内容はポッドキャストでも配信しています。ぜひ音声でもお楽しみください。
spotify
stand.fm
【更年期美容カウンセラー斉藤万奈さんインタビュー】「これって更年期?」もしや、と不安になったあなたへ――専門家が明かす、心と体の変化を乗りこなすヒント

「更年期」という言葉に、漠然とした不安や、どこかネガティブなイメージを抱いていませんか?実は筆者の私自身もその1人です。多くの女性が経験する自然な体の変化であるにも関わらず、その実態や向き合い方については、あまり知られていないのが現状です。
今回は、更年期カウンセラーの斉藤さんをお迎えし、女性たちが抱える「更年期の悩み」に真正面から向き合います。なぜ更年期症状は起こるのか? そして、心と体が揺らぐこの時期を、どうしたら自分らしく乗り越えられるのか? 斉藤さんご自身の経験も交えながら、具体的なヒントと温かいエールをお届けします。あなたの「更年期」を「幸年期」に変えるためのヒントがありそうです。
ーー 更年期とは一般的に年齢ではいつ頃と考えられますか?
更年期の定義は決まっていまして、閉経を挟んで前5年、後ろ5年のあわせて10年を更年期と言います。最近の閉経の平均年齢が52歳ぐらいと言われていますので、だいたい45~47歳ぐらいから55~57歳ぐらいまでが更年期と考えたらいいかなと思います。
ーー斎藤さんご自身の更年期症状の体験について教えてください。どのような症状があり、どのように自覚されましたか?
私が更年期症状を自覚したのは42歳でした。当時、仕事とプライベートで大きなストレスが約1年間続いていた時期で、夜眠れない、気持ちが落ち込むといった症状を感じていました。ある時、仕事が終わってから一歩も動けなくなり、部屋が暗くなっても電気もつけずにソファに埋もれている状態になり、このままでは本当にうつ病になってしまうと危機感を覚えました。これが「おかしいぞ」と感じたきっかけです。
ーーその症状をどのように乗り越えられましたか?
周囲にいた婦人科の先生や美容家の方に相談したところ、「ホルモンが落ちてくる時期だから、ホルモンを安定させてみては?」とアドバイスされました。そこで低用量ピルを飲み始めたんです。低用量ピルは女性ホルモンを安定させる効果があるので、飲み始めてから体調が劇的に良くなりました。それまではうつ病やストレスだと思っていた症状が、低用量ピルでこんなにも安定し、元気になることができたので、これが更年期の入り口だったのかもしれないと感じました。
ーー更年期は誰にでも訪れるもの?
はい、更年期は思春期や成熟期、老年期があるのと同じように、誰にでも訪れる体のステージなんです。ただ、更年期症状が出るかどうか、どんな症状が出るかは、人それぞれなんですよ。

ーー更年期症状が出るのには、どんな理由があるんですか?
更年期症状が出るのには、大きく分けて3つの要因があるんです。
- 女性ホルモンの減少(卵巣の老化)
一番大きな要因は、女性ホルモンの減少です。卵巣の中に卵の赤ちゃんがたくさん詰まっているんですが、それがだんだん少なくなって、女性ホルモンが分泌されなくなるんです。これは、いわば卵巣の老化ですね。だいたい40代に入ると徐々に始まり、40代半ばくらいから一気に加速していく方が多いです。 - もともとの性格
二つ目は、その方のもともとの性格です。例えば、すごく生真面目で頑張り屋さん、「私がやらなきゃ!」と責任感が強く、抱え込んでしまうタイプの方は、更年期症状が出やすい傾向があります。 - 環境要因
三つ目は、その人の環境要因です。人間関係や生活環境の変化、大きなストレスが重なると、症状が出やすくなります。
よくあるご相談としては、お子さんの受験、夫婦関係の悩み、ご主人の転勤といった家庭の事情。あとは、ご自身のキャリアですね。40代半ばから50代前後で仕事の責任が重くなったり、部下を抱える立場になったりして、ストレスを抱える方も多いです。
これらの3つの要因が重なると、更年期症状が出やすくなるんです。
ーー更年期の症状には、どんなものがあるんですか?
更年期症状って、実は本当に多種多様で、最近は100も200も、いや300もあると言われているほどなんですよ。だから、「これって更年期症状なの?」とご自身では分かりにくいことが多いですし、更年期を受け入れること自体が難しいと感じる方もいらっしゃいます。
また、ストレスがかかっている最中は、それに一生懸命向き合っているから症状が出にくいこともあります。ストレスが落ち着いてから、例えば3ヶ月後とか半年後に、何かしらの不調が出てくるパターンも多いですね。夏の疲れが秋に出る、みたいな感覚に近いかもしれません。
ーー斉藤さんご自身も更年期症状を経験されたとのことですが、どんな変化がありましたか?
そうですね。それまでは特に大きな病気をしたこともなく、メンタルもそんなに弱くないと思っていましたし、仕事も楽しんでいました。でも、不調が出たことで、自分の健康との向き合い方、体との向き合い方を学ぶ大きなきっかけになりましたね。「このままじゃいけないな」と気づかされた感じです。
肌や髪のお手入れももちろんそうですが、私の場合、特にうつ症状が出たことが大きかったです。これまでの心の揺らぎの根本にある、自分のアイデンティティみたいなものをもう一度深く考えるきっかけになりました。これまでの生き方や物事の捉え方、両親や家族との関係など、普段あまり考えなかったことと向き合う時間になったんです。
ーー更年期って、人生の大きな節目のようですね。
まさにそうですね。よく転職や人生の大きな節目に「人生の棚卸し」をすると言いますが、更年期はまさにそのくらいの大きな機会なんです。
私自身、子どもがいないのですが、更年期を迎えた時に「もう子どもを産むことはないんだな」ということを改めて感じました。そして、「あの時違う選択をしていたら、子どもを持てたのかな?」とか、「自分が選んできた人生で今ここにいるけれど、もし違う選択をしていたらどうなっていたんだろう?」なんて、これまでの人生を振り返って、深く考えるようになりました。
今は、女性の生き方って本当に多様ですよね。子どもを持つか持たないか、仕事をするかキャリアを積むかなど、選択肢はたくさんあります。でも、選んだ人生はこれしかないわけです。そう考えた時に、更年期以降の人生、まだ人生の半分くらいしか来ていないから、あと半分どう生きていこうかなって、真剣に考えるようになりました。まさに「第二の人生」とか「セカンドステージ」の始まりだと感じています。
実際、うつ症状が出たことで、カウンセリングに行ったりして、もう一度自分を見つめ直す時間をかなり持ちましたね。

ーー更年期はつらい時期というイメージが強いですが、今後の生き方を考えるきっかけにもなるんですね。
そうなんです。女性の体は、閉経までは女性ホルモンによって守られているんです。病気もしにくいようにできています。毎月生理のたびに心も体も揺らぐ大変さはあるけれど、それがあって人生の半分まで来ました。そして、それがなくなることのちょっとした「解放感」のようなものも感じるんです。
ただ、心も体を守ってくれていた女性ホルモンがなくなることで、今度は「自分の健康をどうやって自分で作っていくか、育てていくか、守っていくか」を考える時期になるんです。
だから、更年期って悪いことばかりじゃないんですよ。私は、人として成熟して、この先さらに良い人生を歩んでいくための準備期間であり、きっかけを与えてくれている場所だと考えています。今年60歳になりますが、そう考えると、これから更年期を迎える方たちには「全然無理じゃないよ!」って心から伝えたいですね。
ーー閉経後に現れる不調や老化を緩やかにするために、40代からやっておくと良いことはありますか?
たくさんありますよ!もちろん「たくさんある」って言うと、ちょっとプレッシャーに感じるかもしれませんが(笑)。
一番大切なのは、本当に基本的なこと、食事と運動と休養を見直すことです。これは、すべての人にとって生活の基盤になる部分ですからね。
1. 食事について:
栄養バランスと「食べ方」が重要です。毎日完璧なバランスの食事を作るのは大変ですが、できるだけ彩り豊かにしたり、加工食品の裏の表示を見て添加物が少ないものを選んだりする意識を持つと良いでしょう。
更年期以降は、太りやすくなったり、コレステロール値が上がってきたりと、体の自然な変化があります。動物性脂肪の摂りすぎには注意したり、自分の体に負担になるようなものはできるだけ避けるように心がけてください。
若い頃と違って、更年期以降は食べてもなかなか身にならない(栄養が吸収されにくい)と感じることもありますし、カロリーだけを見て食事をするのも良くありません。極端なダイエットも体に負担をかけるので、無理なくバランスよく、基本通りの食事を心がけるのがおすすめです。例えば、甘いものの摂りすぎは良くない、というのは言われていますよね。
2. セルフケアについて:
40代になったら、これまで以上にセルフケアをしっかり行う必要があります。今までと同じだと、後から不調が出てきやすくなるかもしれません。
そしてもう一つ、大切なのは自分の弱点を知ることです。例えば、もともと偏頭痛がある方は、生理前のPMSがひどかったり、更年期に入ると偏頭痛がひどくなる傾向があります。そういった自分の弱点を早めに知り、対処しておくことが大事です。免疫も落ちてくるので、自分の体の声に耳を傾けてあげましょう。
ーー斉藤さんご自身が実践されている、おすすめのセルフケアはありますか?
私の場合、もはや「何が特別なの?」って聞かれても分からないくらい、日々の生活に溶け込んでしまっています(笑)。
食事については、昔はローフードを試したり、動物性のものを抜いたり、いろいろな食事方法を試しました。今はとりあえず3食はしっかり食べます。
朝食は、最近はだいたい決まっていますね。最初に野菜サラダ、次にヨーグルトにバナナを入れたもの、そして小さいパンを1個と卵1個、コーヒーです。その日の気分で適当にアレンジしています。和食ももちろん良いと思いますが、私の場合、朝にご飯とお味噌汁だとちょっと重たく感じてしまうので、このスタイルに落ち着きました。
お昼はご飯とお味噌汁と納豆、夜は野菜のおかずと肉か魚、海藻やキノコ類などを食べます。ご飯は食べてもお茶碗半分くらいです。
何を気をつけているかというと、一番最初に野菜を食べること。そして、いきなり炭水化物を摂らないようにしています。朝パンを食べる日は、お昼や夜にパスタなど、炭水化物が重なるものは避けるようにしていますね。
あと、これは私の体の「取扱説明書」のようなものなのですが、ご飯を食べないと便秘になるんです。昔は便秘で何日も出なくても平気だったんですが、50代に入って更年期になってからは、便秘になると本当に苦しくて。どうして便秘になるのかを自分なりに検証した結果、「ご飯」が私には必要だと分かったんです。なので、お米は朝昼晩のどこかで必ず摂るようにしています。だいたいお昼ですね。
それから、オリーブオイルを大さじ1杯は必ずどこかの食事のタイミングで摂るようにしています。そうすると、私の場合は便秘が解消されるんです。
この「ご飯とオリーブオイルと、最初に野菜を食べる」という自分なりのルールのおかげか、20年前、30年前の服が今でも全部着られるんですよ。スカートでもデニムでも。だから、体をキープする意味では、多分間違ってないんじゃないかなと思っています。

ーーご自身の「取扱説明書」を作られているんですね!
そうですね。きっと、更年期はネガティブになることももちろん多いし、自分を「ダメだダメだ」と思ってしまうことも本当によくあります。そんな時は、「どうやって気持ちを切り替えようか」「どうやったら自分の気持ちがちょっと晴れるか」ということを考えるようになりました。例えば、何も考えずにさっさとウォーキングすると、気分転換になったりしますね。
自分の心が何をしたら喜ぶかな?ちゃんと整うかな?ということを考えるのが大事だと思います。自分の取扱説明書を作るというのは、つまり自分をちゃんと観察してあげることなんです。
「私、今どういう気持ちでいるかな?」「私の体がどうして欲しいと思ってるかな?」といったことを、客観的に見てあげられるようになると良いですね。
あと、私は仕事柄、化粧品やサプリメントなど、いろいろなものを試す機会があるので、試した時に「なんかいいな」という気持ちになれるかどうかを大切にしています。皆さんも、いろんな情報をたくさん持っているけれど、それを試した時に「あ、なんかいいな」という自分の声が聞けなくなっていることがあるんじゃないかと思うんです。「口コミに書いてあったから良いはずだ」とかではなく、自分が試した時にどう感じるか、ピンとくるかこないか、というちょっとした感覚をもっともっと大事に拾ってあげることが重要なんじゃないかなと思います。
ーー更年期に差し掛かる前から、ご自身の体と向き合われていたんですか?
いえいえ、そんなことはないと思います。本当に40代に入るまでは、「私がやらなきゃ」とか、世間体や外の目ばかり気にしていました。今思えば、自分らしさみたいなものは本当になかったかな。自分のことは後回しでしたね。
でも、今のように「何かいいな」と自分が好きなことを感じられるようになったのは、まさに更年期のあたりから、もっと自分に目を向けるようになってからです。
「自分を大切にできるのは、自分しかいない」
セルフケアは自分しかできないこと。それに気づいた時に、本当に「自分ファースト」で行こうと思いました。もちろん、環境や状況によっては、なかなかそうはいかない方もたくさんいらっしゃると思います。でも、できる範囲で良いので、周りの人の助けを借りながら、それでも自分をちゃんとケアする「自分ファースト」を少しでも実行できたら良いんじゃないかなと思います。
これはね、訓練なんだと思いますよ。いつも自分を見てあげて、自分の気持ちや心が動く瞬間を見逃さずにキャッチしてあげることです。
ーー「ラマーナ」にいらっしゃるお客様は、更年期に関するどんな悩みを抱えていることが多いですか?
「これって更年期?」というご相談がすごく多いですね。ご自身に起きている症状や不調が、本当に更年期なのかどうかの確認だったり。
あとは、「つらい症状があるけれど、どうしたら改善できるの?」という具体的なご相談も多いです。体の不調よりも、どちらかというとやっぱりメンタル面ですね。気持ちが落ち込んでやる気が起きないとか、ひどい疲労感が抜けないとか、うつ症状、集中力がないといったメンタルのご相談が多いです。
確かに、素人目には「これは更年期障害な気がするけれど、もしかしたら別の症状かもしれない」と判断が難しいですよね。だから、そういう悩みを相談できる場所があるのは心強いと思います。
ーー婦人科での治療についても相談できるんですか?
はい、もちろんできますよ。婦人科での更年期症状や更年期障害の治療についてのお話もよくします。
「婦人科でこういう治療があるよ」「治療にはこういう方法があるよ」といった情報提供ですね。例えば、ホルモン補充療法は婦人科の保険診療で受けられますし、漢方薬も保険で処方してもらえます。あとはプラセンタ注射も更年期治療で保険が適用される場合もあります。
そういった情報を、その方の状態に合わせてお伝えしています。
ーーラマーナでは、どんなサポートをされているんですか?
当サロンにいらっしゃるお客様は、フェイシャルやボディのマッサージといったトリートメントを受けながら、私との会話の中で「最近こういうことがあってね」といったお話をしてくださいます。
そこで、「それ、更年期かもしれないからちょっとチェックしてみましょうか」と、更年期チェックリストでご自身の状態を確認してもらったりします。定期的に来てくださる方には、毎回「最近どう?」と体調を聞きながら、おすすめのサプリメントや生活習慣についてアドバイスしたり、本当に必要そうだと感じたら、「かかりつけの婦人科を持った方がいいよ」と、婦人科のかかり方や選び方についても具体的にアドバイスすることもあります。
ーー友達と話すだけでは終わらない、次のステップが見えるサポートは心強いですね。
これは皆さん、本当によくおっしゃいますね。「友達同士では『更年期だよね、そうかもね』って話すけど、結局何も解決しないんだよね」って(笑)。
もちろん、話すことはとても大切ですよ。女性はコミュニケーションをとってストレスを発散したり、ハハハと笑って免疫を上げたりします。女性ホルモンって、ニコニコ、ウキウキ、ワクワクするホルモンなので、そういう時間を持つことは女性ホルモンの活性にもつながります。
それはすごく良いことなんですが、その先に「更年期に対してどうしたら良いか」という具体的な選択肢が示されるかどうかで、その後の対処が変わってくると思うんです。まさに「取扱説明書」の作り方に関わってくることなので。
治療もあれば、アロマセラピーやハーブ、呼吸法といったセルフケアの仕方もあります。何か一つだけで劇的に良くなるというわけではないから、いろんなものを組み合わせて自分をサポートしていく、持ち上げていくという考え方が大切なんですよね。
_________________________________________________________________________________

斉藤万奈
証券会社で役員秘書として10年間勤務した後、ジュリークショップ青山、新宿伊勢丹BPQCジュリークショップ店長を経て、2002年二子玉川にてエステティックとリラクゼーションのサロン「ラマーナ」をオープン。これまでに15000人の女性の美と健康をサポートしてきた中で、更年期を軽やかに乗り越えることの大切さを実感し、近年は施術やカウンセリングなど更年期ケアに注力している。
2014年より女性ライフクリニック新宿にてメノポーズカウンセリングを担当。
・CIDESCO認定エステティシャン
・IFA認定アロマセラピスト
・NPO法人更年期と加齢のヘルスケア認定メノポーズカウンセラー メノポーズカウンセラーオブザイヤー2022受賞
エステサロン「ラマ―ナ」HP | https://la-marna.jp/ | Instagram
涙活(るいかつ)──涙がくれる、心のデトックス
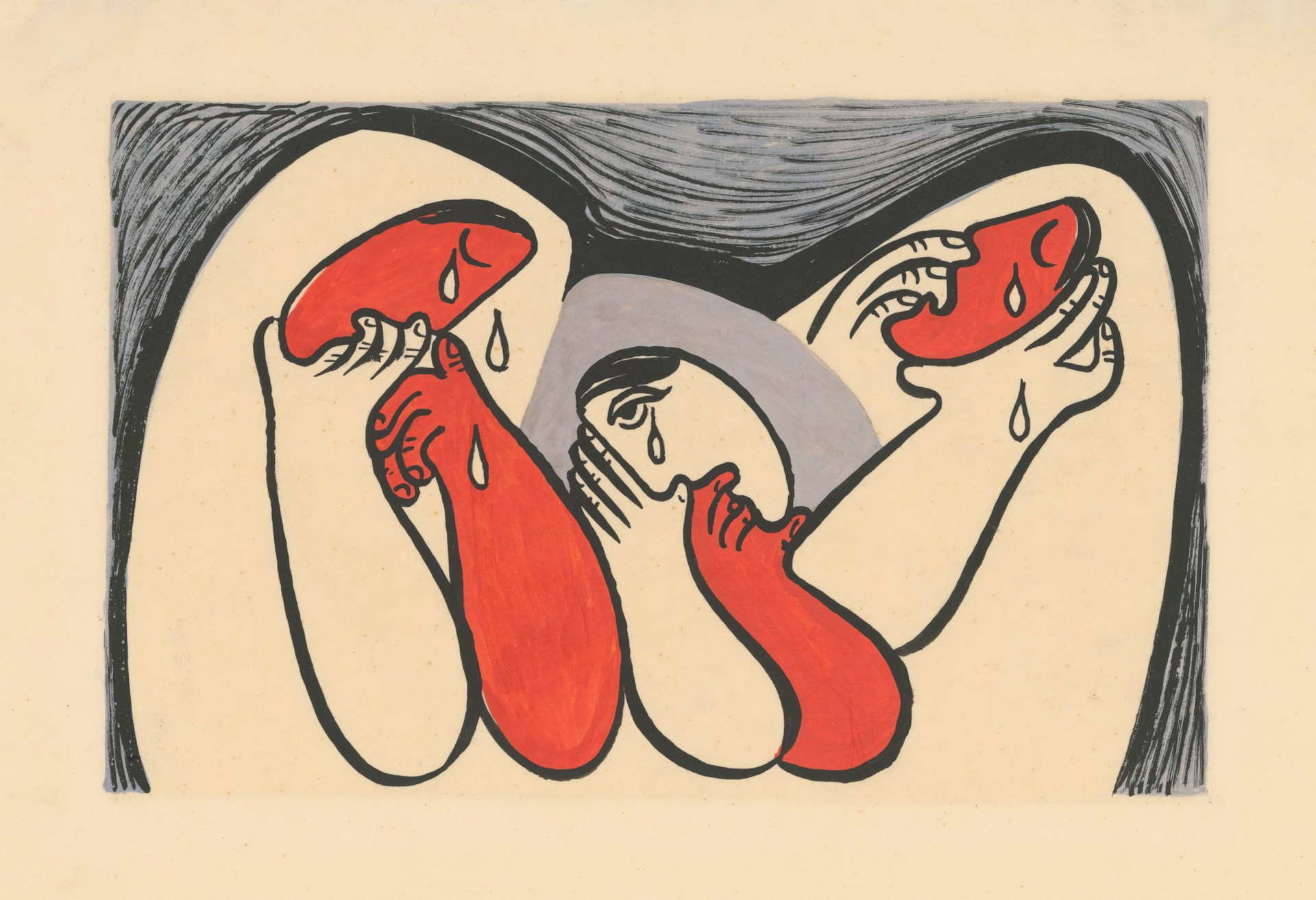
感情が高ぶると、私はいつも涙が出てしまいます。でも子どもの頃は、泣くたびに叱られていたので、いつの間にか「泣くことは弱さの証」だと思うようになりました。それから長い間、人前で涙を見せないようにしてきました。
でも、人生でとてもつらい出来事が起きたとき、もう我慢できなくなりました。チームミーティングの最中、私は思わず泣き崩れてしまったのです。驚いたことに、当時の上司はその場を穏やかに受け止めてくれました。そしてそのとき私が感じたのは、恥ずかしさではなく「安堵」でした。
ずっと心に重くのしかかっていたものが、涙とともに少し軽くなったように感じました。思考は鈍り、やる気も失っていた私にとって、泣くことで少しだけ前が見えるようになったのです。
もちろん、涙が問題を解決してくれるわけではありません。でも、心を整えて、また一歩踏み出す力をくれる。何より、「自分は人間なんだ」と思い出させてくれます。それだけで、十分な意味があると思うのです。
涙活ってなに?
忙しさやプレッシャーに追われる毎日。人はつい、自分の感情にフタをしてしまいがちです。泣きたいのに泣けない、弱音を吐けない──そんなときに、心をそっとゆるめてくれるのが「涙活(るいかつ)」です。
「涙活」とは、意識的に涙を流すことで、ストレスを和らげ、心のデトックスを図る活動のこと。
映画を観たり、感動的な話を読んだり、人と深く語り合ったりして、涙を誘う時間をあえて設けます。2013年頃から日本で広まり、企業の研修やワークショップに導入されることもあります。
涙がもたらす驚きの効果
涙は単なる感情の表れではなく、科学的にも心身に良い影響があることがわかっています。
- ストレスホルモンを排出する
情動による涙には、ストレスホルモン(コルチゾールなど)を体外に排出する働きがあるとされています。 - 副交感神経が優位になり、リラックスモードへ
涙を流すと、副交感神経が優位になり、身体が自然と休息モードに。呼吸も落ち着き、緊張がほぐれます。 - 感情の解放で「自分らしさ」を取り戻す
泣くことで抑えていた感情に気づき、認めてあげられる。これは、自分自身との関係性を回復する第一歩です。

涙活のやり方
涙活は特別な道具や場所がなくても始められます。以下はおすすめの方法です:
- 感動系の映画・ドキュメンタリーを観る
自分の感情に重ねやすい作品を選ぶと、自然と涙があふれてきます。おすすめは『そして父になる』『湯を沸かすほどの熱い愛』『クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶモーレツ!オトナ帝国の逆襲』など。 - 「泣ける話」や手紙を読む・書く
誰かへの感謝を手紙に書いたり、昔の自分宛に手紙を書くと、思わぬ感情があふれることも。 - 涙活イベントに参加する
最近では「涙活セミナー」「涙シェア会」など、他人と一緒に涙を流す体験型のイベントも増えています。共感による癒やしの効果も得られます。
涙を我慢しがちな人へ
「泣くこと=弱さ」と思われがちな文化もありますが、涙は自然な感情の表れであり、むしろそれを受け止める強さが必要です。泣くことで、心のモヤモヤが少しずつ流されていきます。
たとえ涙がポロっと一粒でも、それはあなたの心が自分を守ろうとしている証拠。
最後に──涙は、心のマッサージ
涙活は、自分を甘やかすのではなく、自分にやさしく向き合う時間です。
強くあろうと頑張る毎日だからこそ、ほんのひととき、自分をゆるめてあげることも大切。
「最近、泣いてないな」と思ったら、ぜひ涙活、してみてください。
直感的な意思決定の力

情報過多の時代に生きる今、私たちは「決断疲れ」や「決断の麻痺」に陥りがちです。道に迷うことがなくなったのは、常にGPSが手元にあるから。金曜のデート相手を見つけるのも、ベッドやソファから出ずに済む時代。でも、選択肢は無限にあります。
たとえば、パーティー用のブーツが欲しい?サイズぴったりで火曜までに届く商品が、なんと48,976足もあるのです。
これでは、自分の「内なる声」とのつながりが弱くなるのも無理はありません。
ですが、幸いにも、直感と深くつながり、それを人々に教えることを仕事にしている人たちがいます。たとえば、トランスフォーメーショナル・コーチでエネルギーヒーラー、そして〈Forward with Grace〉の創設者でもあるグレース・エモンズさんは、良くない思考パターンを手放し、内なる“羊飼い”と向き合う方法を探求してきました。
直感的な意思決定って、どんな感覚?
「直感的な意思決定とは、“なぜそれが正しい選択なのか説明できなくても、心の奥でそれだと分かる”感覚に従うこと。
最初に“なんとなく”感じることがあったり、理由は分からないけど“ただ分かる”ということもあります。それが、あなたの直感が語りかけているサインなんです。」とエモンズさんは言います。
ただし、これは簡単なことではありません。
「直感を“スピリチュアルすぎる”と否定する人もいますが、実は直感は、“論理的思考”“権威による知識”“経験による知識”と並ぶ、認知科学においても認められた“4つの知の方法”のひとつなんです。」
ハーバード・ビジネス・レビューの調査によれば、トップCEOたちの85%が、重要な意思決定を直感で下していることも分かっています。
つまり、CEOのように直感を信じることが、実はパワフルな選択方法なのです。
潜在意識は、膨大な情報を処理している
「私たちの潜在意識は、意識的に把握しているよりも27,500倍も多くの情報を処理しています。
その情報を分析し、最適な選択肢を“直感”という形で、まるで銀のトレーに乗せて差し出してくれているのです。」

成功する直感的意思決定の例
- 紙面上は最高でも、心が乗らない仕事のオファーを断る
→ 数ヶ月後にその会社が倒産。直感が正しかった! - 論理では説明できないけど「この人だ」と感じる恋人と出会う
→ 直感が導く深い結びつき。 - 怖いけどワクワクする転居や新しい挑戦にYESと言う
→ 「不安」と「直感」を見極める力が大きな変化を生む。
直感力を高めるトレーニング方法
「最初は小さなことから始めて、自信を育ててください」とエモンズさんはアドバイスします。
- 例:どちらのレストランに行くか、あの服を買うか、直感に聞いてみる
- 自分の“直感のサイン”を感じ取り、その結果を確認することで精度が上がる
慣れてきたら、より大きな決断(パートナー選び、投資、引越しなど)に応用する
直感は、スピリチュアルな“ひらめき”ではなく、自分の深い部分が集めたデータによる「静かな提案」です。
その声に耳を傾けることで、自分の人生に信頼が生まれ、もっと自由に選択できるようになるのです。
些細なことにイライラ…HSP気質な私のストレス攻略法

「何でもかんでもストレス」になる性格
私はいわゆるHSPだと思います。
基本的に、何でもかんでもストレスに感じやすい性格。
誰かのちょっとした素振りや声色、何気ない一言が、のどに刺さった魚の小骨みたいに、地味にずーっと心に残り続けるんですよね。
相手はもう忘れているような些細なことでも、私の中では延々とリピート再生されて、気がつくとその場面をぐるぐると思い返している。
それが知り合いに対してだけでなく、街ですれ違う人、電車で乗り合わせた人、カフェで隣になった人。
そんな、もう二度と会わないかもしれない人のことまで、いちいち気になってしまうんですよね。
そんなだから、自分の言動にも厳しくなります。
相手が不快にならないよう、場の空気を悪くしないよう、いろいろ細かいところに気を遣うわけで、そりゃもう毎日気疲れですよね。
ましてや、相手がそれに気づかない、無下にする、当たり前のような態度を取るなど、思いやりに欠ける言動をされると、そのストレスは一気に膨らみます。
道を譲ったこちらに、目もくれずに電話に夢中になる人や、電車の座席で、荷物も体もギュッと縮めて座るこちらに、スマホを操作する肘をガンガンぶつけてくる人とか。
そんな場面に出くわすと「こっちの気も知らないで…!」と勝手にイライラしてしまうんですよね。
自分でも嫌になっちゃう。
そして、そんな私の様子を見て、周りが言うのは「気にしすぎ」の一言。
そう言われるたび「そんなこたぁ、分かってるんですよ」と、いつも心の中で言い返します。

諦めの境地、性格は変えるものではない
だから、おおらかに、鈍感に生きていけたらどんなにラクだろうと何度思ったことか。
イライラを感じるたびに「気にしない気にしない」とか、「私だって同じような言動をすることがあるじゃない」と言い聞かせ、マインドや思考回路をどうにか変えられないかと試行錯誤した時期もあります。
でも、30年以上この性格と付き合ってきて、はっきりわかったことがあります。
今さらこの性格を変えることは、きっとできない。
というか、そうやって無理に自分を変えようとすることが、また新たなストレスになるんですよね。「なんでいつまでも変われないんだろう」と自分を責めるループに入ってしまって、結局二重に苦しくなる。
だから最近は、その代わりにこういうイライラや感情を、上手く処理してコントロールすることに重きを置くようになりました。
完全にストレスを断ち切ることはどうやっても無理、でも感じたストレスとどう向き合うか、どうやって消化するかは工夫できるはず。そう考えを切り替えたら、少し心が軽くなりました。
性格は変えるものではなく、上手く付き合うもの。
やっとそう思えるようになってきました。
そもそも、この性格で「生きづらさ」を感じる場面は恐ろしくたくさんあるけど、もちろん長所になる場面もあるわけです。
細かなところまで気がつくから防げるミスがあるし、仕事が丁寧とか思慮深いと言われることもある。そうやって見てくれてる人だってちゃんといる。
そう思うとなおさら、性格を変えることに固執しても意味がないようにも思えてくるんですよね。
自分の感じ方や受け止め方を否定せず、「自分は自分」と思ってあげること。
そのうえで、生きづらいと感じる瞬間をいかに減らせるか、逆に、自分の性質に胸を張れる瞬間をどれだけ増やせるかを考えることが、結局は一番ラクな生き方に繋がると思うのです。

ストレスと付き合うには、一旦切り離す
そうしていい意味で諦めの境地に至った今、ストレスやモヤモヤと向き合うために、私が大事にしている習慣があります。
それが「書き出すこと」です。
イライラやモヤモヤって、それに振り回されているうちは何も生み出さないし、害でしかありません。でも、グッと立ち止まって一度冷静に見つめてみると、実はいろんな気づきが詰まっていることも多々あります。
ただ、頭の中だけで考えていると、どうしてもネガティブな方向に飲まれたり、同じところを堂々巡りしてしまいがち。
そんなとき、書くことの一番の効用は、自分の内側を一歩引いた目で見つめ直せることです。
「なんでそう感じたんだろう」「いつもこのパターンかも」「私にはこういう傾向があるのかも」「これが嫌だと思っていたけど、根っこは違うところにあるのかも」
そうやって自分の感情を分析しながら、文章として吐き出すだけで、ちょっと心が落ち着くんですよね。
もちろん、書き出したからといって、現状が何かすぐに解決するわけではありません。むしろ、何も解決しないことのほうが多いです。
でも、文字にして外に出すだけで、自分の中でグルグル渦巻いていた感情が、ほんのちょっとだけ他人事のように、距離を取って見られるようになる。そんな不思議な効果があるのです。
さらに、そうやって言語化した内容を、こういうエッセイや趣味で書いているnoteなどで人に見せると、思いがけず共感してもらえることもあります。
「私もそう思ってました」「まさにそれです」なんてコメントをもらうと、自分だけじゃなかったとか、誰かの気持ちを代弁できたと思えて、いつの間にかストレスも一緒に消化されていく感覚があります。
でも、いつも人様に見せられるような、よそ行きの文章に昇華できるわけではありません。
どうにも整理がつかないときや、どす黒い気持ちや汚い言葉しか浮かんでこないときもあります。
そんなときは、誰にも見せない「吐き出し用ノート」に殴り書きすることもあります。このノートは私にとって、とにかく自分の本音をストレートにぶつけられる安全地帯、シェルターのような場所です。
どす黒い感情も、乱暴な言葉も、すべてOK。ただひたすら自分の本音に耳を傾けて、吐き出すだけの時間――それが私にとっての“ご自愛”になるんですよね。
普段、細かなところまで気を遣いまくる分、何も気を遣わず「”雑”で居られる場所」をつくっておくことは、思っている以上に心を守ってくれています。
(実際、割合でいえば外に出せるエッセイが2、誰にも見せられない吐き出しノートに書くのが8くらいなので、このノートは私にとってかなり重要なストレス発散法です。)

ストレスと付き合うには、自分の「王道」を心得ておく
考えてみれば、書き出すことは昔から無意識にやっていました。学生時代の日記から始まって、何となく思ったことをメモしたり、感情をぶつけるように文字にしたり。
でも、それが自分に一番合う方法だと気づけたのは、実は最近のことなんです。
ストレス解消法といえば、SNSを見ていると本当にいろいろなアイデアが流れてきます。「運動が一番」「アロマを焚くといい」「とにかく寝るのが最強」など、どれも効果がありそうだし、たまに参考にして試してみることもあります。
けれど、誰かの“正解”がそのまま自分にも合うかというと、必ずしもそうとは限らない。
逆にいえば、私が最終的に行きついたのは「書くこと」だけど、それも皆さん全員に効くとは限りません。
いろいろと新しい方法を試すのは大切ですが、同じくらい、自分に合った「王道」のストレス対処法をきちんと知っておくことも大切です。
それが運動でも、瞑想でも、書くことでも、食べることでも、自分に合っていれば何だっていい。
だから、今日も自分なりのやり方で、心に積もった小さな石たちを一つずつ片づけていこうと思います。
怒りの感情を発散する「アンガールーム」は効果的?

アンガールームは、物を壊すことでストレスや怒りを発散するための空間です。
「安全でコントロールされた環境で怒りを表現することで、感情を解放し、ストレスを軽減できる」といった考えに基づいています。
近年では、ちょっとしたレクリエーションや“セルフセラピー”として人気を集めています。
「思いっきり壊してスッキリする」「誰にも迷惑をかけずに発散できる」といった気軽なイメージもあるでしょう。
ですが、メンタルヘルスの研究によると、こうした“怒りの発散”は必ずしも心に良いとは限らないことが分かってきています。
たしかに、アンガールームは安全な環境で怒りを外に出す手段ではありますが、
怒りを物理的に爆発させる行為は、逆に怒りの感情を強化し、悪化させてしまう可能性があるのです。
“カタルシス効果(すっきりする解放感)”があるように思えても、実際にはそうならないことが多く、 むしろ怒りの習慣化や依存的な行動につながることもあります。
アンガールームはどのように機能するの?
アンガールーム(怒りの部屋)では、決められた時間内に壊してもいい物が用意されており、
利用者はそれらを思いっきり破壊することができます。
壊したことに罪悪感を感じる必要もなく、後片付けも不要というのが特徴です。
では、こうしたアクティビティはストレスマネジメントとどう関係しているのでしょうか?
アンガールームは、「カタルシス理論(怒りの浄化理論)」という考え方に基づいています。
この理論によれば、人は怒りやフラストレーションを外に出すことで、その感情が軽減されるとされています。
「イライラを爆発させると、気分がスッとする」と感じる人も多いですが、
こうした行動が本当に長期的に見て健康的なストレス管理法なのか?
効果的なアンガーマネジメントになるのか?という点は、まだはっきりしていません。
たとえば「枕を叩く」「ジムで体を動かす」など、他の方法と比べた場合、どうなのでしょうか?
実のところ、アンガールームがメンタルヘルスに与える影響についての研究はまだ非常に少ないのが現状です。 ただし、近年では一部の研究者が、こうした活動の可能性を模索し始めています。
ある研究では、がん患者にVRを使った仮想の「スマッシュルーム」を体験してもらうという実験が行われました。 その結果は賛否両論で、一部の参加者は「楽しかった」と答えた一方で、
「感情をこんなに公に表現するのは好きじゃない」と感じた人もいました。
中には「物を壊すより、整理したり直したりするほうが楽しかったかもしれない」と答えた人もいたほどです。
こうした結果からも、アンガールームが人にどのような影響を与えるのかを理解するには、さらなる研究が必要だと言えるでしょう。

アンガールームが“本当に”もたらしていることとは?
アンガールームというアイデア自体は、実は昔から存在していたようなものです。
誰でも一度くらいは、「あまりにも怒って何かを壊してしまった」という経験があるのではないでしょうか。
アンガールームに関するデータはまだ少ないものの、
研究者たちは「攻撃性」「フラストレーション」「怒り」といった感情を行動に移したときに
何が起きるかについて、これまでにも調査を行ってきました。
■ 短期的な怒りの発散にはなる可能性がある
アンガールームは、一時的に強い感情を解放する手段にはなるかもしれません。
怒りやイライラを感じているとき、その緊張をどこかにぶつけることで「ちょっとスッキリした」と感じることもあるでしょう。
特にアンガールームの特徴は、身体的にかなりアクティブであるという点です。
バットを振り回したり、ガラスを割ったり、物を壁に投げつけたりすることで、
その瞬間だけは感情が解放されたように感じられるかもしれません。
■ 怒りの不健全な表現を助長する可能性も
怒りを「発散する」ことは、しばしばフラストレーションやストレスを解消する有効な手段と捉えられがちですが、
実際の研究では、身体的な攻撃や暴力によって感情を爆発させることは、怒りをむしろ悪化させるという結果が出ています。
いくつかの研究によれば、 怒りやストレス、フラストレーションを感じたときに身体的に爆発するという反応を繰り返すと、その状態が“習慣”として体に染みついてしまうのです。
一見すると逆効果に思えるかもしれませんが、ちょっと考えてみてください。
もし「怒りをぶつけると気持ちがスッキリする」という経験を何度もすれば、
次に同じような感情を抱いたときも、また攻撃的な行動を取りたくなる可能性が高くなりますよね?
それが無意識のうちに「怒り=暴力で発散」というパターンとして定着してしまうリスクがあるのです。
アンガールームは怒りを増幅させる可能性が高い
アンガールームに行くことが、実際にどんな影響を及ぼすのか——
その短期的・長期的な効果について、信頼できる研究やデータはまだほとんどありません。
しかし、現在までの研究では、「攻撃的な行動」は将来的により攻撃的な行動を引き起こす傾向があることが示されています。
ある研究では、挑発されたあとに攻撃的な行動を取った人が、たしかに直後には「少しスッキリした」と感じることがあると報告されています。
ですが、その効果は一時的なもので、 その後また怒りを感じたときに、今度はさらに攻撃的な反応を取りやすくなることが分かっています。

健康的な代替手段:アンガールームに頼らない怒りの対処法
怒りやフラストレーションの“原因”に目を向けることも重要ですが、それ以外にも、モノに当たる以外のストレスマネジメント法には効果的なものがいくつもあります。
以下のような方法は、怒りやフラストレーションを減らす助けになると科学的にも示されています。
◎ シンプルな方法
- その場を離れる・一度距離を取る(「10数える」は意外と効果的です)
- 深呼吸を意識して行う
- 瞑想やマインドフルネスを試してみる(初心者でもOK)
◎ 認知行動療法的アプローチ(副作用なく効果的)
- 漸進的筋弛緩法:体の各部位を順番にぎゅっと力を入れ、ゆっくりと緩めていくことで、身体的な緊張を解放する方法
- 認知の再構成:物事の捉え方を変えることで、怒りの感じ方をやわらげる思考法
- アサーティブトレーニング(自己表現や人間関係スキルの訓練):感情を押し殺さず、健全な関係を築くためのスキル
- 問題解決スキルの強化:すべての問題がすぐに解決できるわけではありませんが、多くのストレスは能動的な対応で減らせます
- 段階的暴露法:不安などに対して使われる方法ですが、ストレス要因に少しずつ慣れていくことで、心の負担を減らしていきます
- 怒りに関する教育:怒りの仕組みや向き合い方を学ぶことで、怒りに振り回される必要がなくなり、他人を傷つけることも避けやすくなります
- ストレスマネジメント全般の習慣化:ストレスを日常的にうまく扱う力をつけることで、外からの刺激に対しても動じにくくなります
■ アンガールームには“何かしら”のメリットはある?
では、こう思う人もいるかもしれません——
「物を壊すことで怒りが少しでも軽く感じられるなら、それって意味があることなんじゃないの?」
「ストレスが限界に達したときに試してみる価値はあるのでは?」
「土曜の夜に友達と一緒にワイワイやるレクリエーションとしては、むしろ楽しそうじゃない?」と。
たしかに、アンガールームには一定の魅力や利点も存在します。
実際、多くの人が興味を持ち、人気が高まっているのには理由があります。
正しく理解しながら楽しむのであれば、以下のようなメリットも考えられます。
● 新しいことを試したいときに
興味本位で「一度行ってみたい」と思うなら、それも立派な動機です。
軽い運動にもなりますし、ちょっと面白い話のネタにもなるかもしれません。
友達と一緒に行くことで、「こんな体験したよ!」と共有することもできます。
● 誰かと一緒に「つながる」体験として
友達やパートナーと一緒に参加することで、一緒に壊す=一緒に笑う体験になり、
ちょっとした“絆づくり”にもつながる可能性があります。
同じようなストレスを抱えている相手となら、
「分かる〜!」と笑い飛ばすきっかけにもなるかもしれません。
※ただし、その後に攻撃的な習慣がつかないように、他の健全なストレス解消法も並行して意識することが大切です。
● 純粋に「楽しい」から
研究でも、“楽しい時間を持つこと”はストレス軽減や心のバランス維持に重要であることが分かっています。
もし「物を壊すことで笑ってスカッとできる」というのであれば、
それは少なくとも、家でイライラを繰り返し反芻しているより、ずっと健全かもしれません。
前向きな気分になれるなら、一度体験してみるのもアリでしょう。
(もちろん、その後に怒りやストレスと向き合うための他の習慣も身につけていくことを忘れずに!)
瞑想をするのにベストな時間は?自分に合ったタイミングで、心と体を整えるヒント

あなたは瞑想をしていますか?
著者は、朝起きたらするようにしています。……いや、正直に言うと、「するようにがんばっている」のが本音。というのも、瞑想する前についパソコンを開いてしまったり、メールをチェックしてしまったり。気がつけば、もう他のことをしている……なんてこともしょっちゅうです。
そんな時、ふとよぎるのがこの疑問。
「瞑想って、いつするのがベストなんだろう?」
忙しい毎日の中で、つい後回しになってしまいがちな瞑想の時間。でも、どのタイミングで取り入れるかが大切だということもよく聞きます。
今回は、アメリカの記事から「瞑想はいつするのがベストか?」という問いに対するヒントをお届けします。
これを読むと、自分の生活リズムに合った瞑想スタイルがきっと見つかるはずです。
そもそも、なぜ瞑想をするの?
「心を静める」瞑想には、自分を客観的に見つめたり、ストレスの反応を減らしたりと、さまざまなメリットがあります。
瞑想アプリ「Unplug Meditation」の創設者スーズ・ヤロフ・シュワルツ氏はこう言います。
「反応するのではなく応答できるようになり、人をジャッジせずに耳を傾け、ストレスよりも優しさをもって行動できるようになります」
でも、そんな良いことづくめの瞑想も、「毎日続ける」ことが意外と難しい。特に私たち現代人の生活は、常に慌ただしいものです。
だからこそ、自分に合った「ベストなタイミング」を見つけることで、瞑想を習慣にしやすくなります。
朝の瞑想で1日が変わる
科学的にも「朝の瞑想」は続けやすいことがわかっています。
2023年の研究では、朝に瞑想をする人の方が集中度が高く、習慣として定着しやすいという結果が出ています。
アーユルヴェーダの専門家エリン・キャスパーソンさんは、「朝は一日の中で最も静かな時間。たとえ数分でも、心と体の安定につながります」と話します。
シュワルツさんも「朝を逃すと、1日を逃してしまう可能性が高い」と言い、朝の瞑想をすすめています。
朝の瞑想がもたらすもの
朝の瞑想は、自分自身の「軸」を整える時間。
「目覚めてすぐにスマホをチェックしたり、メールを開いたりするのではなく、まず自分の内側に向き合う時間を持つことで、自分らしい1日が始められます」とシュワルツさん。
私たちはつい、「他人のリクエスト」に応えることで1日が始まりがち。でも朝の静かな数分間があるだけで、「今日はこう過ごそう」と自分のペースで1日をスタートできます。

夜の瞑想で、心をしずめて眠る準備を
一方、夜の瞑想は「手放し」の時間。
1日の終わりに、心にたまったストレスやモヤモヤをリセットするのにぴったりです。
シュワルツさんいわく、「夜の瞑想は、心を落ち着かせ、深く長く眠るために効果があります」。 ただし、キャスパーソンさんは「夜は眠気もあるため、集中力が途切れてしまうこともある」と注意もしています。
夜におすすめの瞑想スタイル
1日の出来事を振り返る
感謝することを思い出す
音声ガイド付きのリラクゼーション瞑想
心と体を「おやすみモード」に切り替えるやさしい瞑想が理想的です。
実は午後の瞑想もおすすめ
午後になると、エネルギーが切れてきたり、集中力が途切れてくる人も多いはず。
そんなとき、5〜15分ほどの短い瞑想が、リフレッシュにぴったり。
キャスパーソンさんは「午後の瞑想は、コーヒーの代わりになることも」と話します。
夕方以降の予定に向けて頭をスッキリさせるのにも効果的。ガイド付きの瞑想を取り入れると、集中しやすくなります。
ただし、午後はスケジュールが詰まりがちな時間帯でもあるため、毎日決まった時間をとるのは少し難易度が高めかもしれません。
ハミング編集部5人の瞑想スタイルをご紹介
ちなみに、私たちハミング編集部でも、瞑想はちょっとしたマイブーム。
5人それぞれのスタイルをご紹介します。
永野さん(編集長):
毎朝、朝起きたらまず窓開けて、太陽光の中で10分間次女とメディテーションします。レモンとジンジャー入れたお白湯を飲んで、朝ごはんの前に便を出します!小さなメモ帳を持ち歩いて、感謝を感じたことをどんなに小さくても良いので、その都度書き留めます。夜はまた次女と一緒に10分間メディテーションします。それ以外に日中に1時間一人でメディテーションもするようにしています。
純(オペレーション):
毎朝、起きてから10分間だけ瞑想の時間をとっています。背筋を伸ばして座り、目を閉じて、ただ呼吸に意識を向けるだけ。頭の中にいろんな考えが浮かんできても、それにとらわれずに、静かに「今ここ」に戻るようにしています。この小さな習慣が、1日の始まりを落ち着いた気持ちにしてくれるんです。
さおりさん(ライター):
朝起きたら、ベッドの上でチャイルドポーズをしながら深呼吸をします。
また、スキンケアで化粧水をつけるときには、肌に優しく触れながら目を閉じて呼吸に意識を向けます。
週に1〜2回はヨガのレッスンにも参加。最近はホ・オポノポノも取り入れています。
みきさん(ブランドダイレクター):
皆様と違いちゃんとした瞑想はしてませんが、
添付の音楽を聴きながら入眠する
https://youtu.be/vcqpMAznmX0?si=Eii8lRoEOaGlnwPL
筋トレ週4と有酸素運動しているので、筋トレ終わりにストレッチしながら軽く瞑想、有酸素運動した後に軽く瞑想
ともこ(ライター):
平日の朝起きてすぐ、誘導瞑想の音声を聞きながら20分ほどの瞑想。パソコンやメールを見る前の「朝いち」にやるように意識しています。
あなたにとっての「ちょうどいい瞑想時間」は、どのタイミングでしょうか?
ぜひ、自分なりのスタイルを見つけてみてくださいね。
参考記事:https://www.yogajournal.com/meditation/best-time-to-meditate/
クラフトは私たちを癒してくれるのか? ──心理的な効果を探る

クラフトの世界が、今ふたたび注目されています。
編み物、刺繍、レザークラフト、キャンドル作り、ペーパークラフト、陶芸、ビーズアクセサリー…
クラフトにはさまざまな種類があり、どれも「手を動かす心地よさ」と「完成したときの達成感」が魅力です。
最近では、SNSや動画プラットフォームを通じて、クラフトのアイデアや作り方が気軽にシェアされるようになり、世代や国境を越えてクラフト人気が高まっています。おうち時間が増えたこともあり、「ちょっとやってみたい」と始めた人がその奥深さにはまってしまう…なんてことも珍しくありません。
道具を使って手を動かすうちに、無心になれたり、気分がすっきりしたりすることも。クラフトは、アートのように自由で、自分の「好き」をカタチにできる素敵な時間です。
今回は、そんなクラフトのさまざまな種類や魅力についてご紹介します。あなたにぴったりのクラフトがきっと見つかるはずです。
クラフトがもたらす心理的な効果とは?
1. クラフトは「今この瞬間」に集中することを助けてくれる
「クラフトは、瞑想的な活動にとても近いものです。何かを作っているとき、私たちはその作業に深く没頭し、目の前のことに集中している状態になります。つまり、“今ここ”にいるということなんです」と語るのは、ニュージャージー州とマサチューセッツ州を拠点とする心理療法士のエリース・ロビンソン氏。
今この瞬間に意識を向けることで、心が落ち着き、リラックスしやすくなります。「現代を生きる大人の多くは、常に何かしらのストレス反応の中にいます。つまり、体が常に“戦うか逃げるか”のモードになっているんです」とロビンソン氏は言います。このストレス反応により、ストレスホルモンであるコルチゾールが過剰に分泌されますが、クラフトに集中することでそのレベルを下げることができるほか、幸福感をもたらすホルモンであるドーパミンの分泌も促進されるのです。
不安やストレスを感じたとき、意識をそらす手段にもなる
「不安やストレスを感じていたり、頭の中で考えがぐるぐると止まらないときは、意識を別のところに向けることがとても効果的です。無理に瞑想しようとしてうまくいかないときは、代わりにペンを持って5分だけ落書きをしてみてください。たとえそれがただのグチャグチャな線でもいいんです」と語るのは、アーティストであり、アートとウェルネスの関係性に注目したディレクターのミーガン・マハフィー氏。
「その瞬間、脳は“ペンの動き”や“何を描いているか”に集中しているので、不安の症状に使われるエネルギーや時間が少なくなるんです。」
クラフトは、忙しく混乱した日常から一歩離れ、自分の時間に没頭するチャンスを与えてくれます。ストレスや不安、頭の中の雑音を一時的に横に置いて、作品作りに集中することで、私たちは“フロー状態”に近い感覚を得ることができるのです。

2. クラフトは、自信・自己への思いやり・レジリエンス(回復力)を育む
クラフトをしているとき、私たちはほとんど“何もない状態”から何かを生み出しています。たとえば、毛糸からセーターを編んだり、真っ白な紙に絵を描いたり、粘土の塊からマグカップを作ったり。こうして何もないところから形あるものを生み出すことで、「自己効力感(自分にはやり遂げる力があるという感覚)」が育まれると、心理療法士のロビンソン氏は言います。
「一般的に、自分自身や自分の能力を信じる力が強くなると、自分の“欠点”や“弱点”にばかり意識を向けなくなり、全体的なストレスも減っていくんです」と彼女は話します。
ロビンソン氏によると、自分をより思いやる気持ちやストレスへの反応が減ることで、自信が高まるのです。実際に、創造的な活動(クラフトを含む)に取り組むことで、感情を表現・調整するための貴重な手段が得られ、ストレスのかかる状況でも柔軟に対応できる力が高まると研究でも示されています。
「クラフトをすることで、“失敗しても大丈夫”という感覚が育ちます。人生ってそもそも混沌としていますから、それを受け入れる練習にもなります。物事を少し軽く受け止められるようになるんです」とロビンソン氏。「クラフトは、そういった心のスキルを、リスクの少ない形で自然と脳にインプットする方法なんです」。
さらに、クラフトは問題解決能力を鍛える実践の場でもあります。たとえば、新しい編み方を覚えたり、型紙を調整したりする必要が出てくることも。
「創造性を高めることは、問題解決能力や自己信頼、自尊心を育むことにつながります」と、アート・ガールの創設者であるマハフィー氏は言います。
3. クラフトは、人とつながるきっかけをつくってくれる
クラフトは、コミュニティとつながる素晴らしい方法でもあります。編み物サークルやクラフトクラブ、陶芸教室など、誰かと一緒に創作する機会を通じて、人との関係性が生まれていきます。
「何かを作るイベントに参加して、特に内省的なテーマに応じて作品を作るような場合、人と自然に深いつながりが生まれやすくなります」と、マハフィー氏は話します。「作品を通して自然と会話が生まれ、より深く、満たされたつながりにつながっていくんです」。
人とのつながりを感じることは、帰属意識、目的意識、そして支え合いの感覚を与えてくれます。現代ではコミュニティを見つけるのが難しいこともありますが、クラフトという共通の興味は、その第一歩を踏み出すきっかけになります。
クラフトは、私たちの人生にとって本質的に“いいことづくし”
クラフトは、心を落ち着け、自分自身を信じ、愛する力を育み、人とのつながりを築く手助けをしてくれます。そして何より、とても楽しいのです!
これらすべてが、創造性と自己表現に満ちた、健康で幸せな人生につながっていきます。
とはいえ、すぐに効果が実感できるものではないかもしれません。
「“クラフトを始めたのは先週なのに、まだ効果がない!”というように、すぐ結果が出るわけではないんです。でも、続けていくうちに、自己肯定感や自信、そして自己効力感が確実に育っていきます」とロビンソン氏は語ります。
マハフィー氏は、クラフトや創作を日常的なウェルネスの一部として「練習するもの」と捉えています。
彼女は、毎日のお絵かきのアイディアをシェアし、人々が創造性を日常に取り入れるサポートをしています。ただし、特別なスキルや道具が必要なわけではありません。どんなクラフトでもOKです。
「すべての人が、自分自身に自信を持ち、幸せだと感じる価値があると思います」とロビンソン氏は語ります。
「クラフトは、それを気づかせてくれる素晴らしい方法なんです。」
心と体にやさしい、おすすめのティーブランド9選

日々の忙しさやストレスを少しでも和らげてくれる、そんなひとときに欠かせないのが「お茶」の存在。温かいお茶を一杯飲むだけで、心がふっと落ち着いたり、リフレッシュできたりしますよね。
今回は、そんなリラックスタイムにぴったりの、世界中のおすすめティーブランドを10社ご紹介します。オーガニック素材にこだわったものから、美容や睡眠のサポートになるブレンドティーまで、幅広くピックアップしました。
1. LUPICIA(ルピシア)|日本
世界各国のお茶を取り揃えた日本発の人気ブランド。季節限定のお茶やオリジナルブレンドが豊富で、選ぶ楽しさも味わえます。

2. Pukka(パッカ)|イギリス
https://www.pukkaherbs.com/uk/en/
100%オーガニックでカフェインフリーのハーブティーが中心。心と体を整えるウェルネスブレンドが多く、毎日のセルフケアにぴったり。

3. Yogi Tea(ヨギティー)|アメリカ
アーユルヴェーダの思想をベースにしたブレンドが特徴。ティーバッグのタグには前向きなメッセージが添えられていて、飲むたびに気分が上がります。

4. NINA’S MARIE-ANTOINETTE(ニナス)|フランス
https://www.ninasparis.com/en/home-2/
フランス王妃マリー・アントワネットに由来する華やかな紅茶ブランド。優雅な香りと味わいで特別なティータイムに。

5. Harney & Sons(ハーニー&サンズ)|アメリカ
高品質な紅茶と美しい缶デザインが特徴の老舗ブランド。特にアールグレイやホットシナモンなどのフレーバーティーが人気。

6. Clipper(クリッパー)|イギリス
フェアトレード&オーガニックの原料にこだわったエシカルブランド。環境にも配慮したパッケージで、サステナブル志向の方におすすめ。

7. 茶屋すずわ|日本
静岡発の日本茶ブランド。伝統とモダンが融合した洗練されたデザインと、素材の良さを活かした味わいが魅力です。

8. The Qi(ザ・チー)|アメリカ
バラや菊などの花をまるごと使った「フラワーティー」が話題。見た目も美しく、五感で楽しめるお茶です。

9. T2 Tea(ティーツー)|オーストラリア
カラフルでポップな世界観が人気のティーブランド。紅茶・緑茶・ハーブティーなどジャンル問わず、独創的なブレンドが楽しめます。

幸せの科学:ポジティブなニュースが心と体にもたらす効果

もし、あなたのX(旧Twitter)のタイムラインがネガティブな内容を一切含まない、ポジティブなニュースだけで満たされていたらどうでしょう?
私たちは、心に優しく、前向きになれるニュースを届けようと努力していますが、現実にはSNS上では暴力、自然災害、政治的不安など、暗く落ち込むようなニュースが圧倒的に多くを占めています。
でも、実は気分を明るくし、うつや不安の症状を軽減し、さらには身体の健康にまで良い影響をもたらす方法があるとしたら?
そしてその答えが、すでに私たちの目の前にあるとしたら?
そう、それが「ポジティブなニュース」なのです。
【ハミングが届けるポジティブニュース】ミサイルが音楽に変わるなんて。世界にはまだ、優しさと希望がある
ポジティブなニュースが幸福感に与える影響についての科学的研究
最近の科学的研究では、私たちの感情状態が、日々どんなニュースを見聞きしているかに大きく左右されることがわかってきました。
中でも、ポジティブなニュースに触れることは、心の健康や幸福感に大きな効果をもたらすことが確認されています。
ここで言う「ポジティブなニュース」とは、よくあるお涙ちょうだい系の“良い話”ではありません。
人々や社会の中にある「本当の良さ」を映し出す、心から勇気づけられるような現実のストーリーのことです。
たとえば、気候変動への取り組みで改善が見られていることや、科学の進歩によって人々の寿命が延びていること、そして世界の識字率が過去最高を記録しているといったニュースです。
【ハミングが届けるポジティブニュース】スイスの奇跡:かつて汚染された川が、ヨーロッパで最も美しい都市の遊泳スポットに!
ポジティブなニュースは、うつ症状を軽減する力がある
世界中で、約41%の人が何らかのメンタルヘルスの問題──うつ、不安、慢性的なストレスなど──に悩まされています。
一部の専門家によれば、社会がコロナ以前のような状態に戻るには、少なくとも10年かかるとも言われています。
うつと向き合ううえでの大きな課題のひとつは、「現実をありのままに見ること」が難しくなってしまうことです。現実は良いことも悪いことも混ざっているものですが、ネガティブなニュースばかりを見続けると、偏った世界観が強くなってしまい、「世界は恐ろしい場所だ」といった破壊的な思考が根づいてしまうことがあります。
たとえば、うつ状態の人がネガティブなニュースばかり見ていると、「世界はどんどん悪くなっている」「どうせ何も良くならない」といった極端な思考に陥ることがあります。
もちろん、世界に問題があるのは事実ですが、それがすべてではありません。実際には、世界には驚きや思いやり、優しさ、希望といったポジティブな面もたくさん存在しているのです。ポジティブなニュースに触れることで、よりバランスの取れた現実の見方が身につきます。
もし気分が落ち込んでいるときがあれば、困っている隣人を助けようと立ち上がった人々の話や、地域の小さなビジネスを支えるコミュニティの物語など、心温まるストーリーを読んでみてください。それがあなたの気持ちを少し明るくしてくれるかもしれません。

ポジティブなニュースは、ストレスホルモン「コルチゾール」を減らし、身体の健康にも良い影響を与える
ポジティブなニュースは、心だけでなく体にも直接的な良い影響をもたらすことが研究で明らかになっています。
前向きなニュースに触れることで、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が減少することが分かっており、それによって高血圧や心臓病、さらにはがんといったさまざまな健康リスクの軽減につながるとされています。
コルチゾールは「闘争・逃走反応(fight or flight)」を引き起こすホルモンとも言われており、緊急時に体を守るために分泌されるものです。少量であれば、日々のストレスを乗り越える助けになりますが、過剰になると炎症を引き起こしたり、免疫システムを過剰に刺激したり、うつの原因になることもあります。
つまり、ポジティブなニュースに触れることは、感情面だけでなく、身体面の健康にも良い影響を与えてくれるのです。
【ハミングが届けるポジティブニュース】風がくれた、新しい暮らしのかたち:役目を終えた風力タービンが、小さなマイホームに変身!
ポジティブなニュースは、人とのつながりを深め、孤独感を和らげてくれる
さらに、ポジティブなニュースは人間関係にもポジティブな影響をもたらします。明るいニュースに触れることで、社会的なつながりを感じやすくなり、孤独感が軽減されるという研究結果もあります。
これは、人は嬉しいニュースを自然と誰かと共有したくなる傾向があるためかもしれません。そのシンプルな行動が、人との健やかな関係づくりへとつながっていくのです。
つまり、自分の気持ちが明るくなるだけでなく、周囲とのつながりも深まり、人間関係までポジティブになる——まさに一石二鳥です。
まとめると、「幸せの科学」によって、ポジティブなニュースに触れることが私たちの全体的なウェルビーイング(心身の健康)に良い影響を与えることが証明されつつあります。
でも、これを信じるかどうかはあなた次第。ぜひ一度、自分自身で試してみてください。日々のネガティブなニュースから少し離れて、前向きなストーリーを意識的に探してみてください。
きっと、心も体も「ありがとう」と言ってくれるはずです。
【ハミングが届けるポジティブニュース】オランダの教会がプールに変身!100年の時を経て、笑顔あふれる場所へ
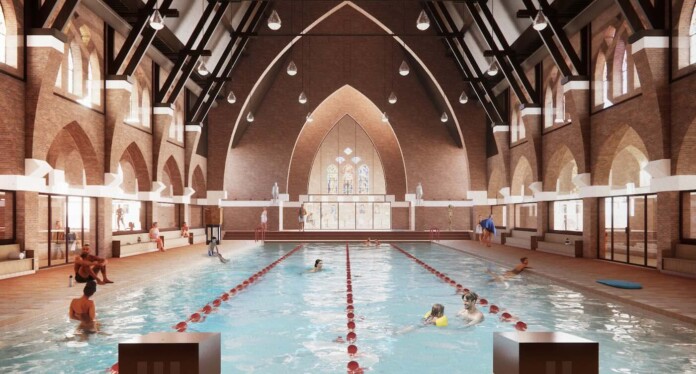
ハミングが届ける今回のポジティブニュースは、オランダからです!
オランダ南部の都市ヘールレンにある、築100年以上の美しい教会「聖フランシス教会」。その重厚な外観と、色とりどりのステンドグラスに包まれた神聖な空間が、なんと「スイミングプール」として生まれ変わることになりました。
その名も「Holy Water(神聖なる水)」。
ユニークなこのプロジェクトは、2023年に礼拝が終了し、空き家となっていた教会を、新しい形で地域に開かれた場へと再生する取り組みです。
教会で泳ぐ!?古き良きと、新しい楽しさの融合
プールとして生まれ変わった教会は、ただの泳ぐ場所ではありません。
ガラスの壁で仕切られたプール空間を囲むように、礼拝堂時代のベンチが再利用されていて、片側はスイマーの休憩用のベンチに、もう片側は観客が使えるバー風のテーブルになっているのです。昔の説教台は、今度はライフガードの見張り台に。教会の記憶が、あちこちで新しい命を得ています。
さらに目を引くのが、水深を自由に調整できる「可動式の床」。
子ども用の浅いプールから、大人向けの本格的な水泳コースまで対応でき、さらには床を完全に上げてしまえば、平らなホールに早変わり。文化イベントや地域の集まりにも使える、多目的な空間になるのです。
なかでも圧巻なのが、薄く水を張った状態。
教会の荘厳な天井やステンドグラスが水面に映り、まるで水の上を歩いているような幻想的な体験ができるのだとか……!

「社会とつながる場所」に、もう一度
プロジェクトの中心人物である建築家ウィニー・マースさんはこう語ります。
「教会の空き家が増えている今、もう一度「人々が集まる場所」として活用する方法を考える必要があるんです。昔の教会がそうだったように、もう一度社会とつながる場所にするというのが、私たちの提案です」
たしかに、ステンドグラスを見上げながら背泳ぎなんて、なんとも贅沢。
朝の水泳教室や、放課後の子どもたちの憩いの場。さらには文化イベントやコンサートまで——教会という神聖な空間が、もっと日常に近づく。そんな未来が想像できます。
歴史を守りながら、やさしくアップデート
もちろん、歴史的建造物としての価値もしっかりと守られています。
天井の木組みやレンガの壁はそのままに、外側から断熱材を加えることでエネルギー効率を保ちつつ、内部の美しさもキープ。
プール空間と他のスペースを分けるガラスの壁は、湿気からステンドグラスや壁画を守るバリアの役割も担っています。照明も、昔の教会で使われていたランプを参考にデザインされていて、4列に並ぶランプがそのままスイミングレーンのガイドにもなっているという工夫っぷり!
また、プールの床や周囲には新しくモザイク模様の床が敷かれる予定で、地域のアーティストとともに、地元の壁画文化を取り入れたデザインに仕上げるそうです。

はじめの一歩は2027年
この教会から生まれたプール、実際に市民が泳げるようになるのは2027年の終わりごろ。
それまでには、設備面や構造面での細かな工事が続きますが、すでに市民の期待は高まっています。
誰もが一度は訪れてみたくなる、ちょっと不思議で、でもどこか心温まる水の教会。
「古き良き」を残しながら、今を生きる私たちの暮らしにそっと寄り添う場所として、世界中の注目を集めています。
今回はオランダから届いた、心がほっこりするニュースでした。
「新しい使い道」って、なんだか希望がある。そんな気持ちにさせてくれるプロジェクトです。
参考:
Extraordinary Reuse of Vacant Church: Transforming into a Public Swimming Pool in the Netherlands
「アイデアガーデン」が持つ秘密の力

「木を植えるのに一番良い時期は20年前。二番目に良いのは今だ」——この中国のことわざを、どこかで聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。確かに前向きなメッセージではあるけれど、「20年前に逃したチャンス」と「今しかないこの瞬間」の二択しかないような、少し窮屈な印象も受けます。現在目の前にあるチャンスや、人生のあゆみというのはもっと複雑なものではないでしょうか。
だからこそ、私は「アイデアガーデン」という静かで素敵な新しい習慣が大好きです。これは、自分のアイデアや目標のために専用の庭のようなスペースを作り、植物を育てるようにゆっくりと育てていくというもの。特に、冬から春にかけての「再生」や「新しい始まり」といった気分にぴったりな過ごし方です。
アイデアガーデンの本質はとてもシンプル。アイデアをためておき、ときどき見直すための場所をつくること。それが進化して、より明確な形になっていくのを見守ります。物理的な引き出しや箱、ファイルでもいいし、パソコンのフォルダやスマホのメモアプリなど、デジタルな場所でもかまいません。大事なのは、アイデアが自由に流れ込んでくるための入口をつくること。できればその場所は、自分だけの「聖域」のようにしておくのがおすすめです。誰にもジャッジされない、あなただけの静かな世界にすることで、アイデアを守り、安心して育てることができます。
そして次は、種をまく番。イメージ、言葉、新聞の切り抜き、写真、メモ、インスピレーションを与えてくれるあらゆるものを、そこに入れていきましょう。そういったものには、今はまだ小さくても、いずれ大きく育つ可能性がある「芽」が隠れているかもしれません。それが目標のためでも、美的なものでも、概念的なものであっても、あるいはその全部でもいい。あなたが「これは種だ」と思うものは、すべてアイデアガーデンにぴったりの種です。
アイデアガーデンの育て方
どんな種を植えたらいいのかわからない?あまり深く考えすぎないでください。実は、「何を入れるべきか」を考えすぎないほうが、いいアイデアが浮かびやすいんです。
自分の身のまわりを見渡してみてください。どんなコンセプトが心に引っかかりますか?そして、なぜそれが気になるのでしょう?よく使う言葉は何ですか?その言葉を使うとどんな気持ちになりますか?やりかけのプロジェクトを完成させたくなるようなモチベーションになる言葉は?自然の中で感動する瞬間は?何度も読み返してしまう記事や本は?それらがあなたの中でどんな感情を呼び起こすかに注目してみてください。
こうした問いに向き合うことで、あなたのアイデアガーデンに植えるのにぴったりな「健やかで豊かな種」を見つけるヒントになります。
どんなものであっても、どこから来たものであっても、その種はあなたの心の奥をワクワクさせるものであるべきです。そして、頻繁に頭に浮かんできたり、「大切に育ててみたい」と思えるものであること。現実の種と同じように、それがどんな風に育つか想像できたり、可能性を感じられるものを選びましょう。その種がどんな花を咲かせるのか、実をつけるのかを思い描くだけでも楽しくなるようなものであることが理想です。
中には、どうしてその種を選んだか説明が長くなるものもあるかもしれません。でも「なんとなく気になったから」という理由でも十分です。大切なのは、自分の直感を信じて選ぶこと。なぜその種を選んだのかを自分なりに理解していれば、それでいいのです。

よい種がいくつか見つかったら、それをガーデンに植えていきましょう。日付を入れたり、ラベルをつけたりして、自分があとで見てわかりやすいように分類しておくと便利です。実際の庭と同じで、どこに何が植わっているかを把握しておくことが、後でそれらを育てていくうえでとても重要になってきます。
アイデアガーデンの提唱者のひとりであり、作家でもあるチャーリー・ギルキーは、「なぜあなたにはアイデアガーデンが必要なのか」という記事の中で、デジタルフォルダを作り、その中に「種」を植えたときの自分の考えを簡単にまとめておくようにしていると書いています。
彼が記録した種の一例が「アイデアを熟成させることと、それにこだわりすぎることの間にある緊張感」というテーマです。このテーマについての短い文章を保存しておき、その中で「アイデアを早く出しすぎると深みがなくなる。でも、抱えすぎると力を失い、忘れ去られてしまう。どのタイミングで放つかを見極めることが大切だ。というのも、すばらしいアイデアは社会的な産物だから」と綴っています。
ギルキーにとって、このアイデアは頭の中で長い間考えていたもの。でも、それを言語化し、アイデアガーデンでじっくり育てることで、初めてその種がどんな芽を出すかが見えてきたのです。
つまり、まずはガーデンの準備をして、種を見つけて、植えることから始めるのです。
でも、それはまだ始まりにすぎません。
アイデアガーデンを育てる
すべての種をアイデアガーデンに植え終えたら、それをアクセスしやすい場所に置いておきましょう。ただし、あまり手の届くところに置いて、つい見てしまわないように。理想は、陽の光が差し込むような美しい場所。でも、デジタルで管理している場合は、そこまで気にしなくても大丈夫です。普通の庭と同じで、邪魔にならず、でもちょっと手を伸ばせば届く場所にあるのが理想です。
そして次にすることは…ガーデンから距離を置くこと!植えた種はしばらくそっとしておきましょう。脳がそれを自然に熟成させるのを待つのです。意識的に見たり、いじったりせず、1ヶ月くらいは放置してみてください。そのあとで改めて見返してみると、アイデアの見え方がまるで違っていて驚くと思います。中には、もはや魅力的に感じなくなっている種もあれば、逆に以前よりも強く輝いて感じられる種もあるはずです。

次は水やりの段階に入ります。まずは、定期的にガーデンを訪れて種に向き合う時間をスケジュールしましょう。週に1回、2週間に1回、月に1回など、自分にとって負担にならず、ワクワクする頻度でOKです。植物と同じで、コンスタントなケアが必要です。
最初の水やりの日には、メモを取れるものを用意しましょう。ノートパソコンでも、ノートでも、付箋でも構いません。最初に種を記録したものと同じものを使うのが理想です。まずはその日の日時を書き、種を一つずつ確認して、それについて自由に書いたり、クリエイティブなアイデア出しをしてみましょう。
やり方は自由です。チャーリー・ギルキーのように、種に関するドキュメントをどんどん膨らませていってもいいですし、その種にイメージできる写真のコラージュやスケッチを作ってもいいのです。集めたオブジェクトなどを水やりの成果としてガーデンに残すのも効果的です。
中には、あまり気が乗らない種もあるかもしれません。その場合は、次回までスキップしても、放置しても大丈夫。大切なのは、自分の中で育っている種を少しずつ追いかけていくことです。
このプロセスを繰り返していくと、アイデアガーデンは本物の庭のように進化していきます。すぐに芽を出してぐんぐん育つ種もあれば、なかなか動きがないものもあるし、長い間眠ったままになるものもあります。ある時点で、新しい種のために古い種を抜いてしまうこともあるでしょう。
でも、どんな形にせよ、アイデアガーデンは常に生きていて呼吸するような存在。あなたの変化し続ける思考とともに成長する、小さなライブラリーになります。水やりのたびに、その成長を確認できる場所です。
もしあなたが望むなら、「収穫のとき」を設けて、育った種とそこから生まれたコンテンツを実際のプロジェクトや活動に移行させてもOKです。または、育成のプロセスそのものを創作のインスピレーションとして使ってもいいし、まったく新しいアイデアガーデンを始めても構いません。
大事なのは、あなたのペースで、あなたらしい方法で、アイデアと向き合い続けることです。
なぜうまくいくのか
ギルキーにとっては、最初のアイデアが「種」になり、それが記事へと成長しました。そしてその記事は「完成した投稿」フォルダへと保存され、役目を終えました。しかし、アイデアガーデンが生み出す果実は、人それぞれ、ガーデンそれぞれ、アイデアそれぞれでまったく異なります。その可能性はとても力強く、無限大。まるで実際の庭と同じように、愛情と手間をかけることで、創造的な成果が生まれるのです。
では、なぜアイデアガーデンはこんなにも効果的なのでしょうか?
それは、「構造」「準備」「熟成」という、創造のプロセスにおいて重要な3つの要素を活用しているからです。
まず、アイデアガーデンには明確な構造があります。柔軟性を持ちつつも、自分でデザインするため、一度コンセプトが固まれば、継続しやすく実行しやすい形になります。
次に、ガーデンを準備する時間が必要です。実はここが一番大変なステップかもしれません。種(アイデア)を集める作業には、少し労力が必要です。でもそれさえ終えれば、あとは熟成の時間に入ります。つまり、最初に蒔いた種を焦らず育てる期間が始まるのです。大きなプレッシャーもなく、既にあるベースに少しずつ加えていくだけでいいのです。
近年、クリエイティブな分野ではアイデアガーデンという考え方が広まりつつあります。果たしてこれは一過性の流行で終わるのか?それとも定着していくのか?――そう問いかけたくなるほど、アイデアガーデンは深く、優しく、そして創造性に満ちたプロセスです。
私にとっては、安心してアイデアと向き合い、自由に試行錯誤できる大切な場所になりました。新しいアイデアが芽を出し、育ち、広がっていくハブのような存在です。
物理的な庭と同じように、アイデアガーデンも「自分にとって心地よいスタイル」でなければなりません。でも、そのスタイルがピタッとはまったとき、本当に魔法のような時間が生まれるのです。
心地よく香る、5つのノン・トキシックなオイル&リードディフューザー

家の中を心地よい香りで満たしてくれるリードディフューザー。けれど、使われているオイルの中には、合成香料や有害化学物質が含まれているものもあるのをご存じですか?特に小さなお子さんやペットがいるご家庭では、安心して使える「ノン・トキシック(無毒性)」な製品を選ぶことが大切です。
今回は、成分にこだわり、自然由来の香りを楽しめる無毒性のリードディフューザーを5つご紹介します。
1. Saje ナチュラルウェルネス アロマリードディフューザー(アンワインド)

Sajeのディフューザーは、100%ピュアなエッセンシャルオイルのみを使用。ストレスを和らげてくれる「アンワインド」ブレンドは、ラベンダーやゼラニウムなどの心地よい香り。グリセリンベースで安全性も高く、香りに敏感な方にもおすすめ。
2. Brooklyn Candle Studio ディフューザー(サンタル)
https://brooklyncandlestudio.com/

ミニマルで美しいパッケージが目を引くBrooklyn Candle Studio。サンダルウッドをベースにしたウッディな香りは、落ち着いた雰囲気を演出します。フタル酸不使用、動物実験なし、ヴィーガン仕様というのも魅力です。
3. Cochine リードディフューザー(ウッディノート&サイプレス)

ベトナムのサイゴン発のラグジュアリーブランド。植物性ベースのオイルを使用し、香りは長持ち。サイプレスやシダーウッドなどのウッディな香りが大人っぽく、リラックスタイムにぴったりです。
4. Maison Louis Marie No.04 Bois de Balincourt リードディフューザー

フランスの伝統的な香水技術を背景にしたヴィーガン&クリーンビューティーブランド。サンダルウッド、シダーウッド、スパイスの絶妙なブレンド。合成香料・パラベン・フタル酸不使用で安心。
5. Plant Therapy リードディフューザー
https://www.planttherapy.com/

アロマテラピー専門ブランドのPlant Therapyによる、100%ピュアなエッセンシャルオイル使用のブレンド。グレープフルーツやレモンのシトラス系で朝にぴったり。子どもやペットにも安心。
香りと安心、どちらも叶える選択を
ディフューザーは、空間を彩るだけでなく、心にも作用するアイテム。だからこそ、体にやさしいものを選びたいですよね。今回ご紹介したアイテムは、どれも成分にこだわった無毒性な製品ばかり。あなたのライフスタイルに合った香りを、ぜひ見つけてみてください。
【編集部対談】情報溢れる今だからこそ、大切にしたい「マインドフルネス」

スマホを見ながらなんとなく食事をすませたり、
次にやることを考えながら大切な人と会話していたり。
「今この瞬間に意識を向ける」、いわゆるマインドフルネスな状態を保つのは、簡単そうで意外と難しいものです。
今回はHummingが「マインドフルネス」について発信している理由や、編集部メンバーが実践しているメディテーション方法について話をしました。
「今ここ」に意識を向けること。それがマインドフルネス
純: Hummingでは「マインドフルネス」「性のはなし」「美と身体」「人間関係」「ライフスタイル」の5つのテーマで情報を発信しています。今回はその中の「マインドフルネス」について話をしていきたいと思います。
舞麻さんがマインドフルネスをテーマに選んだ理由を教えてください。
舞麻:私にとってマインドフルネスとは、「目の前のことに、100パーセント意識を向けること」。たとえば、今、純との会話に100%集中できているかとか、食事のひと口ひと口をちゃんと味わえているかとか。
情報が溢れるこの時代だからこそ、今に集中することはすごく大切。「マインドフルネス」は絶対に扱いたいテーマでした。
Hummingでは、メディテーション(瞑想)やジャーナリングなど、自分と向き合う方法を紹介しています。
純:私もマインドフルネスは本当に大切だと思います。
私は子どもの頃から、テレビを見ながらご飯を食べるのが当たり前の家庭で育ったので、食べることだけに集中すると、そわそわしちゃいます。
電車に乗りながらスマホを見たり、食事をしながらテレビを見たり、「〜しながら」が癖になってしまっているかも。カフェで友達と話している時も、「ちゃんと話を聞こう」と思っているのに、無意識に窓の外を見て人間観察をしてしまうこともあります(笑)。
今この瞬間に意識を向けることは、簡単なようで難しい。だからこそ、マインドフルネスを意識することが大切だと思っています。

無理なく続けるために。自分に合った方法を見つけて習慣に
舞麻:私は、メディテーションをするようになってから、「今」に集中しすぎてしまって、タイマーをかけないと予定をすっかり忘れてしまいます。子どもにも「ママ、迎えに来るの忘れないでね!」と心配されるくらい。だから大事な予定の前には、タイマーが必須!
人間は、習慣の生き物です。 たとえば、認知症の人でも、毎週通っていた場所には自然と行けるくらい、習慣は強い力を持っています。
だからこそ、マインドフルネスを日常に取り入れる習慣ができれば、今この瞬間を大切にする意識が少しずつ育っていくと思います。
純:習慣にできたらすごく楽だけど、習慣にするまでが大変で、諦めてしまうこともあります。だから、継続するためには、自分に合うやり方を見つけることが大切だなと。
私は、座ってじっとするタイプのメディテーションは、正直苦手。だから、週に1〜2回ほど、スマートフォンのアプリでガイドを聞きながら、ひたすら歩いています。いわゆる「ウォーキングメディテーション」です。ジムで運動を始めたときと同じで、最初は少しキツかったけれど、続けていくうちに気持ちが整っていく感じがしています。
「メディテーション」や「瞑想」と聞くと、少しハードルが高そうに思えるかもしれませんが、長時間座り続ける必要はないし、もっと気軽に取り組んでほしいです。
たとえば、ソファに座って目を閉じて心を落ち着かせる。それだけでも立派なメディテーションです。 1日5分でもいい。朝起きてすぐにスマートフォンに手を伸ばす代わりに、呼吸に意識を向けるだけでも変化を感じられると思います。
鼻から空気を吸って、口からゆっくり吐く。深い呼吸を意識するだけでも、脳がマッサージされてるような感覚を味わえますよ。
舞麻:私はけっこうストイックだから、1時間座ってメディテーションをするのが好き。この間ママ友に「前世はお坊さんか尼さんだったんじゃない?」って笑われたくらい。
でも、純が言っているように、自分に合う心地良い方法を見つけることが大切です。
純:1時間も静かに座っていられる舞麻さんはすごいと思います。舞麻さんの家には、3人の娘さんや旦那さん、同居している方、犬もいますよね。そんな中で集中するのは大変なのでは?
舞麻:部屋の扉に「ママは◯時までメディテーションをしています」と張り紙をして、メディテーション中は話しかけられても答えません(笑)。子どもが小さいときは、私の上に乗ってきて集中力が途切れてしまうこともあったけれど、今はこしょこしょ話しているくらいなら気にならなくなりました。

純:娘さんたちも、メディテーションに興味を持っていますか?
舞麻:子どもたちが心配事で頭がいっぱいになってる時には、「5分だけ一緒に座ってみようか」と声をかけて、ブレスワークをしたり、私がガイドをしながらメディテーションをしたりすることもあります。そうすると娘たちも落ち着くようです。
でも、強制はしません。お父さんが脳の研究をしている友人は、メディテーションすることを親から強制されるのが本当に嫌だったと話していました。そんな彼も今ではメディテーションの先生になっていますが、「自分が親になったら、子どもには強制せずに自分がメディテーションする姿勢だけを見せたい」と言っていたのがとても印象的でした。
だから、私もメディテーションすることを娘たちに強制はしない。だけど、心を落ち着ける選択肢の1つとしてメディテーションがあることは、娘たちにも伝わっていると良いなと思います。
「自分のための時間」を少しずつでも、日常に
純:ここまでマインドフルネスについて話をしてきましたが、マインドフルネスのテーマを通じて伝えたいことは「自分のための時間を持ってほしい」ということ。
日常の様々な役割をいったん脇に置いて、 自分と向き合う時間を持つ。その方法は座ってメディテーションをするでもいいし、外に出て少し歩いてみるでもいい。どんな形でもいいから、自分だけの時間をつくって、それを少しずつ習慣にしてもらえたら嬉しいですよね。
舞麻:一人で買い物に行ったり、美味しいご飯を食べに行ったりするのも、もちろん素敵な過ごし方です。でも、「自分のための時間」と「自分と向き合う時間」は、少し意味合いが違うように感じています。
私たちがHummingを通じて伝えたいのは、静かに自分と向き合う時間を、日常の中に少しずつ取り入れていってほしいということです。
自分と向き合うことの大切さを実感してきた私たちだからこそ、その経験をシェアしながら伝えていけたらと思います。
| Humming編集長 永野 舞麻
1984年生まれ。16歳までを日本で過ごした後、海外へ移住。大学で出会ったアメリカ人の夫と結婚し、現在はカリフォルニア在住。3児の母。 高校時代、スイスに住んでいたときに自然の偉大さに触れ、地球環境保全について学び始める。アメリカの美術大学でテキスタイル科を専攻。 今でも古い着物の生地などを使って、子育ての合間に作品を制作し続けている。 |
| Humming編集部Project Coordinator 條川純
カリフォルニアで日本からの移民の両親のもとに生まれ育った私は、まったく異なる2つの文化に触れるという貴重な経験をしてきました。それによって、世界や人との関わりについて幅広い視点を持つことができたと思います。人々が安心して休めたり、心が癒されるような場所があることはとても大切だと思っていて、Hummingがそんな場所になれたらと願っています。 |
ーーー
\ポッドキャスト はじめました/
編集部対談の内容はポッドキャストでも配信しています。ぜひ、音声でもお楽しみください。
spotify
stand.fm
【映画レビュー】ドキュメンタリー『Daughters』を観て、触れること、愛すること——父と娘の再会がもたらす癒し

父親であることの意味とは?――それが刑務所の中の父親である場合、その意味はどう変わるのでしょうか。
ドキュメンタリー映画『Daughters』は、この問いに深く、感情豊かに迫ります。
この作品の中心にあるのは「Date With Dad(父とのデート)」というプログラム。これは収監中の父親たちに、娘とダンスするイベントに参加できるようにするものです。多くの父親たちにとって、数年ぶりに娘を抱きしめたり、目を見て話すことができる貴重な時間になります。
しかし、この感動的な再会の裏側には、見過ごせない現実があります。アメリカでは、黒人男性が圧倒的に高い割合で収監されており、これは社会的・制度的な根深い問題です。
貧困が世代を超えて続き、極端に与えられるチャンスが少ないコミュニティでは、生き抜くために難しい選択を迫られることがあります。多くの黒人男性たちは、「家族を守り、養うためには法を犯すしかない」というメッセージに囲まれて育ちます。彼らがその行為は悪いことだと知らないわけではありません。ただ、多くの場合、それが唯一の選択肢のように感じられてしまうのです。
『Daughters』が映し出すのは、ただの「父親」ではありません。
それは、娘たちのために、そして自分自身のために、その物語を書き換えようとしている「ひとりの人間たち」の姿です。
この映画は、人生における3つの重要な真実を浮き彫りにしています。
第一に、娘と父親の関係は、娘の情緒的な発達において土台となるものです。
第二に、癒されないまま親から子へと受け継がれる世代間のトラウマは、人を壊してしまう可能性があります。
そして第三に、人との触れ合いは、つながりや癒し、成長に欠かせない本質的なものだということです。
物語は、服役中の父親との関係にそれぞれ複雑な想いを抱える4人の少女たちを追います。

物語は、服役中の父親との関係にそれぞれ複雑な想いを抱える4人の少女たちを追います。
最初に登場するのは、5歳のオーブリー。ある夜、彼女が眠っている間に、30人もの警官が家に押し入り、父親を逮捕しました。オーブリーはその場面を目撃していませんが、目を覚ましたときには、父がいないという現実だけが残されていました。
部屋の壁には、彼女が努力を重ねて獲得したカラフルな表彰状がずらりと並んでいます。父から「頑張り続けなさい」と励まされてきた証ですが、それは同時に、彼の不在を常に思い出させる存在でもあります。オーブリーは無邪気に跳ね回り、笑顔で「パパは私が知っている中で3番目に強い人」と誇らしげに語ります。彼女は「7年後に戻ってくる」と信じています。希望に満ちたその瞳の奥には、父の罪の重さをまだ理解しきれていない、静かな悲しみが宿っています。
次に登場するのは10歳のサンタナ。彼女の痛みは、煮え立つように強く、言葉にもその強さがにじみます。
「パパのせいで泣くのはもう嫌。私が選んだことじゃない。」
「次にまた刑務所に入ったら、もう涙は流さない。」
彼女の父は、彼女の人生のほとんどを通して、刑務所と外を行き来してきました。その不安定さが、サンタナの心を硬くしてしまったのです。彼女は拳を握りしめながら歩き、母親がいつも怒っていると話します。サンタナは怒りを鎧のようにまとい、現れないかもしれない父への期待から自分を守っているのです。

続いて11歳のジャアナ。彼女は生まれる前から父が収監されており、会ったことがありません。
「顔も覚えてない。何も知らない。」
無表情でそう語る彼女の言葉は一見冷たいように聞こえますが、その奥には別の種類の喪失感が潜んでいます。――不在から来る喪失ではなく、「最初から失うものすら持っていなかった」という感覚です。
最後は15歳のラジア。彼女は父を恋しく思っています。ベッドに横たわりながら目には涙を浮かべ、「たった15分の通話しか許されないのはおかしい」と不満を漏らします。父の不在は彼女の心の健康に大きく影響しており、ある場面では、母に「もう生きていたくない」と打ち明ける場面もあります。
4人の少女たちは、それぞれ異なる形で、父の不在という重荷を背負っています――希望、怒り、無感覚、そして深い悲しみ。
『Daughters』は、単なる「刑務所」と「親子」のドキュメンタリーではありません。
それは、愛、触れ合い、そしてつながりが、どれほど人間にとって不可欠なものであるかを静かに、しかし力強く語る作品です――とくに、それらが欠けている時にこそ。
刑務所の中でも「そばにいる」という力

「Date with Dad(父とのデート)」は、バージニア州リッチモンドで始まり、12年以上にわたって続いているプログラムです。立ち上げたのは、黒人の女の子たちの自己表現とリーダーシップを育む団体「Girls for A Change」の創設者、アンジェラ・パットン。
アンジェラが少女たちと関わる中で気づいたのは、多くの父親が服役中であるという現実でした。あるとき、数人の少女たちが「父と一緒にダンスパーティーがしたい」と話したことがきっかけで、彼女はその願いを実現へと導きます。それがこのプログラムの始まりです。
ドキュメンタリーでは、このプログラムに参加する十数名の受刑者の父親たちを密着しています。ただし、参加するには「行くだけ」では済みません。彼らはまず、10週間のコーチングプログラムを修了しなければなりません。
映画では、彼らが犯した罪の詳細は明かされません。しかしインタビューでは、社会からのプレッシャーがどれほど自分たちの選択に影響を与えたかを率直に語ります。彼らは責任を放棄しているわけではありません。自分の行動が結果的に刑務所に繋がったことは理解しています。ただ一方で、「選択肢が限られた世界で、自分はどこに向かえばよかったのか?」という問いを投げかけます。
彼らの多くは、父親もまた服役経験があるような家庭で育ってきました。「父のようにはなりたくない」と誓ったはずが、気づけば同じ道をたどってしまった――そう語る男性もいます。ある男性は、父親に「愛してる」と言われたことがないと打ち明けます。「うちの家族は、そういうことを言わないから」と。
「Date with Dad」が提供するのは、ただのダンスパーティーではありません。それは、“つながる時間”であり、“癒しのきっかけ”であり、そして――根深い世代間の連鎖を断ち切るための“最初の一歩”でもあるのです。
なぜ「そばにいること」が大切なのか

赤ちゃんが生まれて最初にすることのひとつは、触れようとすることです。ぬくもりに触れ、安心を感じる——人間は生まれながらにして「つながり」を求める存在であり、触れるという行為は、もっとも基本的でありながら、しばしば見落とされがちな必要なことです。それは父親が愛を伝える手段であり、子どもが「守られている」と感じる瞬間です。特に少女にとって、愛情深い父親の存在は、自信や自己肯定感、感情の成長に大きな影響を与えます。
けれども、親がいなくなる——それが服役によるものでも、その他の事情でも——その不在は心にぽっかりと穴を空けます。子どもはその喪失を完全には理解できなくても、深く感じ取っています。その空白は、混乱や見捨てられた感覚、そして大人になってからの親密さや信頼の問題へとつながることもあります。やがて「愛とは何か」「自分は何を受け取るに値するのか」という問いにも影響していきます。
「Date with Dad」は、こうした現実に正面から向き合うプログラムです。刑務所にいる父親たちと娘たちが、実際に会い、触れ合うことで、父親たちは自身の不在が娘たちに与えた感情的な影響と向き合わされます。そして、ようやく抱きしめられる瞬間は、涙なしには見られないほど心を揺さぶります。
怒りに満ちていたサンタナは「パパ!」と叫びながら、父の腕の中に飛び込みます。その頑なな態度は一瞬で溶け、愛されたかった10歳の少女の姿が浮かび上がります。希望に満ちていたオーブリーは、何度も「7年後だよね?」と父に問いかけ、その再会の約束を信じようとします。父を知らずに育ったジャアナは、距離を縮めようと懸命に向き合い、ラジアは言葉では表せない想いを涙で流しながら、父にしがみつきます。

こうした娘たちの感情と触れたことで、父親たちの心にも変化が生まれます。ドキュメンタリーによれば、「Date with Dad」に参加した男性の95%が、その後再び刑務所に戻ることはありませんでした。ある男性はこう語ります。「ストリートに愛はない。お前の娘だけが、お前を愛してくれる。」
娘たちは、ストリートが決して与えられなかったもの——変わる理由、そばにいる意味、希望——を父親たちに与えてくれたのです。
数年後、ドキュメンタリーは再び彼女たちのもとを訪れます。サンタナの父親は出所し、4年間ずっと彼女のそばにいます。かつて怒りに満ちていた彼女の顔には、明るく無邪気な笑顔が広がり、車内で父と冗談を言い合う姿が映し出されます。時間とともに育まれた絆がそこにはありました。
一方で、かつて希望にあふれていたオーブリーは、8歳になった今、父親がさらに10年間刑務所にいると知り、その心に大きな衝撃を受けます。彼女は無口になり、父と話すことさえ避けるようになります。まるで、父と共に過ごせないという現実が、心の奥に何か大切なものを壊してしまったかのように——。
彼女たちはこれからも長い時間をかけて、父親との複雑な感情を整理していくでしょう。親子の絆は、ただの思い出をつくるだけでなく、自分自身をどう認識し、この世界をどう生きていくかを形づくる大切な要素です。
もし、あなたが親になるのなら、どうか、その愛を確かなものにしてください。励まし、導き、そして何よりも、「どんな時でもそばにいてくれる存在」として、子どもにとっての拠り所であってほしいのです。
デジタル・デトックスで輝く女性へ:ハワイ発の「Radiant Renewal」の魅力

現代の女性は、スマホやPCに囲まれ、常に情報の波にさらされています。特に30代後半以上になると、ホルモンバランスの変化やストレスの影響を感じやすく、心と体の調和を整えることがより重要になります。そんな中、ハミング編集部が注目したのが、アメリカのウェルネスの専門家たちによる「デジタル・デトックス」のリトリートです。
自宅で体験できる本格的なリトリートとは?
「Radiant Renewal: A Digital Wellness Retreat.(デジタル・リトリート)」は、女性の心身の健康をサポートするために設計された4日間のオンラインプログラム。単なるヨガやフィットネスにとどまらず、ホルモン健康、セルフケア、瞑想、ライフスタイル戦略といった多角的なアプローチで、女性がより自分らしく健康に生きるために知っておくべきことやどうやればいいのかを教えてくれます。
特に、ホルモンバランスの変化を迎える年代の女性にとって、心と体のケアは欠かせません。このリトリートに参加することで、日常生活の中で取り組みやすい形でウェルネスを取り入れることができるようになり、参加者が内面から輝くことを目的としています。
デジタル・リトリートの4日間のプログラム内容
このリトリートは、自然界の4つのエレメント(地・火・水・風)に基づいて、毎日異なるテーマで構成されています。
🌿 Day 1 – Earth(地):グラウンディングとホルモンバランス
最初のテーマは「地」。心身を安定させ、地に足をつける感覚を養うことが目的です。
グラウンディングヨガで心を落ち着かせ、体の軸を整える
内分泌(ホルモン)系の基礎知識と、年齢に応じたホルモンケアについて学ぶ
🔥 Day 2 – Fire(火):活力を呼び覚ます
「火」はエネルギーと情熱を象徴し、体を動かすことで内側から活力を引き出します。
ダイナミックなヨガとフィットネスでエネルギーを活性化
女性のライフステージとホルモン変化について学ぶ(更年期、PMSなど)
💧 Day 3 – Water(水):心と体を流れるように整える
「水」のエネルギーを意識しながら、柔軟性と流動性を高めます。
流れるようなヨガとストレッチで体の緊張を解放
ホルモンバランスが崩れると出やすい症状(疲労感、むくみや肌荒れなど)とその対策
🌬️ Day 4 – Air(風):心を解放し、内なる声を聞く
「風」は軽やかさと自由を象徴し、リトリートの最終日には心をクリアにし、自分自身の本当の声を見つめる時間を持ちます。
呼吸を深める瞑想とマインドフルネス
エネルギーを高めるスキンケアとホルモンサポートの実践
参加方法に関する詳細はこちらから:https://www.desibartlett.com/radiant-renewal

なぜ今、デジタル・リトリートなのか?
スマホの通知やSNSに追われる毎日では、無意識のうちにストレスを溜め込みがちです。実際に、過剰なデジタル接触は睡眠の質の低下やホルモンバランスの乱れにつながることが研究でも明らかになっています。
特に30代以上の女性にとって、ホルモンの変化は体調や気分に大きく影響を及ぼします。この時期に適切なケアを行うことで、更年期の症状を和らげ、より快適な日常を送ることができます。
デジタル・リトリートは、こうしたデジタル疲れを解消し、ホルモンバランスを整えるための実践的な方法を学ぶ場でもあります。画面から少し離れ、自分自身の体と心に意識を向ける時間を持つことで、未来の健康にもつながるでしょう。
デジタル・デトックスで、本来の輝きを取り戻そう
デジタル・リトリートは、単なるリラックスの場ではなく、女性が人生の変化を前向きに乗り越えるための知恵と実践方法を学ぶ場でもあります。
デジタルの騒がしさから少し離れ、自分自身のケアに集中する時間を作ることで、より健やかで輝く毎日を手に入れてみませんか?
【ハミングが届けるポジティブニュース】風がくれた、新しい暮らしのかたち:役目を終えた風力タービンが、小さなマイホームに変身!

今回は、「空のヒーロー」だった風力タービンが、地上で「第二の人生」を歩み始めた物語をお届けします。
100メートルの高みで風をつかまえていた彼らが、今度は人のぬくもりを包む小さな家となり、私たちに「ものの価値は使い方次第で変わる」と教えてくれました。
――さて、それでは風が運んできた新しい暮らしのかたちを、のぞいてみましょう。
小さな家に宿る、大きなアイデア
巨大タービンが、地上で温かな明かりをともす「小さな家」に生まれ変わりました。設計したのはオランダ・ロッテルダムの建築事務所 Superuse Studios。使ったのは、ブレード(羽根)を支えるナセルと呼ばれるパーツです。
長さ10メートル・幅3メートル・高さ3メートル――数字だけ聞くとコンパクトですが、実物は一般的なワンルームより少し広いほど。天井が高く、開放感もしっかり。さらに屋根も壁も厚い断熱材で覆われ、オランダの建築基準をクリアしています。
たっぷりの光――三方向に大窓を設け、日中は照明いらず。
本格キッチン――IHヒーター、ワークトップ、収納を備え、自炊派も満足。
快適フルバス――トイレ・洗面・シャワーを一体化し、換気窓で湿気知らず。
「余白」の楽しみ――内装を固定せず、壁紙や家具で自分らしく彩れる設計。
設計者ヨス・デ・クリーガー氏いわく、V80型ナセルは「住める広さ」と「陸送可能なサイズ」の絶妙なバランス。世界に約1万基ある同型タービンが寿命を迎えても、こうした再利用が進めば、エネルギー設備は役目を終えたあとも“第二の人生”を歩み続けられるのです。

「羽根」たちも負けていない
ナセルだけではありません。リサイクルが難しい炭素繊維製ブレードも、おしゃれに再デビュー中。
例えば、再生企業『ReBlade』が廃ブレードでEV充電ステーションの雨よけを製作予定。公共空間インフラとしては世界初と話題になっています。
また『BladeBridge』は13メートルのブレード2枚を橋桁に転用。洪水時にも強い5.5メートルの歩道橋が完成しました。
欧州だけで今後5年間に最大1万4,000枚が解体される見込みですが、クリエイティブな再利用が進めばゴミは資源へと変わります。
エネルギー企業が挑む「解体のその先」
今回ナセルを提供したのはスウェーデンの電力大手 『Vattenfall』。イノベーション担当トーマス・ヨルト氏はこう語ります。
「大型洋上風車が引退を迎える時代に入りました。役目を終えた機械をどう社会に還元するかを考えるのは、私たち人間の責任です」
現時点で量産計画はありませんが、ナセルを活用したい企業には無償提供する方針とのこと。安定供給が難しい部品だからこそ、地域やコミュニティ単位でオーダーメイドの住まいを作る──そんな未来図も描けそうです。
身近な「リユース」を、少しだけアップデート
私たちの手元にも、まだ使えるのに捨てられるものがたくさんあります。洋服をリメイクしたり、家具を修理して長く愛したり。風車のナセルやブレードはスケールこそ大きいものの、発想は同じ。「生まれ変わった姿を想像してみる」ことから始まります。
環境に優しいだけでなく、「これが元タービンなの?」と語れるユニークさも魅力。次に風力発電所のそばを通ったら、空高く回るブレードにちょっと手を振ってみてください。風が運ぶエネルギーは、いつか誰かの温かな暮らしを照らす家になるかもしれません。
住まい選びも“心地よさ”や“ストーリー”を大切にしたくなるもの。役割を終えた風車が第二の人生で届けてくれるのは、電気ではなく「希望の灯り」です。私たちもモノとの付き合い方を少し見直して、地球にも自分にも優しい毎日を紡いでいきませんか。
参照記事:https://www.positive.news/society/the-decommissioned-wind-turbine-that-became-a-tiny-home
たとえ変化しても、パートナーと共に成長していくには

人生には、永遠に続くように感じる季節もあれば、ある朝ふと目覚めて「もう10年も経ったんだ」と気づく瞬間もあります。
自分は年を重ね、変わっていて、昔の自分はもはや遠い記憶のよう。ベッドで横を見ると、隣にいる相手もまた変わっていることに気づきます。それが必ずしも悪いことというわけではありません。ただ、そこにいるのは、かつて恋に落ちたあの人とは少し違う顔をした誰かです。
この文章を読んでいる今、私たち夫婦はメキシコの海辺で乾杯しているところかもしれません。今年で結婚13年目を迎え、初心を振り返るために海辺の旅を計画しました。でも、ここまでの道のりは決して楽なものではありませんでした。
最初の数年は、正直かなり大変でした。恋の熱が冷めて、現実的な生活が始まると、まず私のほうが変わっていきました。20代前半の私はまだ自分がどんな人間なのか、何を信じているのかすら分からない状態。自分の価値観や考え方を見直し始めるのは難しいことですが、新婚生活の中でそれをやるのはなおさら大変でした。
変わったのは考え方だけじゃなくて、好みも、友達も、目標も、夢も全部。自分が誰かもわからないまま、それでも前に進んでいました。夫の変化はもっとゆっくりで、何度かの転職や、自分の信念を見つめ直すことで、彼も少しずつ変化していきました。
それぞれが成長する中で、ふたりの方向がずれていった時期もありました。特に結婚初期の数年間は、お互いのことがよくわからなくなっていたと思います。「またふたりで同じ方向を向ける日は来るのかな?」と不安になることも多かったです。
でも、人は変わるもの。変わらないことのほうが不自然です。様々な経験や困難を経て、人はどんどん新しい自分になっていきます。まるで粘土みたいに、何度も形を変えていく──そしてそれは、パートナーも同じなんです。
一緒にいることがいつも簡単だったわけじゃないけれど、大きな変化の中にこそ「成長」というご褒美があったと思います。簡単ではないけれど、美しくて価値のあるもの。それが、共に変化しながら歩むことの意味だと、私は思っています。
私たちが出会ったのは14年前、コロラドの空があまりに澄んでいた寒い1月の日でした。出会ってすぐに夏のロマンスが始まり、その秋、私が大学のために引っ越したあとも、遠距離恋愛をしてみようと決めました。そしてそれがうまくいき、2年後、再びコロラドの空の下で結婚式を挙げました──今度は雷雲が浮かぶ空の下で。
もちろん、すべての関係が永遠に続くわけではありません。人それぞれ、カップルそれぞれにベストな道があります。私たち夫婦にとっては、「たとえ今のお互いが昔と違っていても、一緒に歩んでいきたい」という気持ちがありました。昔の自分とは違っても、今の自分同士としてまた向き合うことで、新しい関係を築いていけるのだと思います。
そして、私がこの道のりの中で学んだことがいくつかあります。そのヒントをお伝えします。

パートナーと共に成長していくためのヒント
1. 自分にも、相手にも正直でいること
私が結婚して間もない頃、ずっと信じてきた宗教的な価値観に疑問を持ち始めました。そこで、私は夫にその気持ちを伝えることにしました。とはいえ、大きな話し合いを一度したわけではなく、数ヶ月かけて小さな会話を何度も重ねていったんです。最初はとても怖かったし、意見が合わないこともありましたが、自分の内面の変化を見守ってくれる人がいることに安心感を覚えました。そして、このプロセスを共有することで、私たちはむしろより深くつながることができたと感じています。
正直さは、やっぱり大切です。自分自身や大切な人に対して正直でいることで、関係はより健やかに育ちますし、何よりも心の平穏が保たれます。それがたとえ小さな変化──新しく好きになった食べ物でも、宗教を変えたことであっても──パートナーに伝えることで、今のあなたの気持ちや経験を理解してもらえるようになります。そして、相手もまた自分の変化を安心して話せる空気が生まれます。勇気がいることではあるけれど、トライする価値はきっとあるはずです。
2. お互いに興味を持ち続けること
私の夫は、今でも出会った頃と同じように冒険好きでおちゃめな人です。でもこの10年で、趣味も増えたし、政治的な立場も変わったし、海より山が好きになったみたい。人も、関係も、少しずつ変わっていくものですよね。でも、その変化に興味を持ち続けることで、関係は新鮮さを保てます。
「出会った頃の気持ち、思い出してみて」
だからこそ、今もパートナーと“デート”してみてほしいんです。出会った頃のようにワクワクした気持ちで、ちょっとおしゃれして新しいレストランに行ったり、行ったことのない街に旅してみたり。真面目な話も軽い話も、どちらも大切にしていきましょう。

3. 関係の外での「自分の成長」も大切にする
パートナーと一緒に成長することは素晴らしいことですが、それと同じくらい「ひとりの自分」を育てることも大切です。関係は自分を補完するものであって、すべてではありません。まずは自分自身を大切にしなければ、相手をしっかり支えることもできません。
成長のタイミングでは、ひとりの時間を意識的に持つことも必要です。ただの「離れる時間」としてではなく、呼吸を整える時間、変化を整理してクリアな心で戻ってくるためのスペースだと思ってみてください。それは午後の数時間かもしれないし、数日、あるいは数週間という場合もあるでしょう。どんな形であれ、その時間は関係にとってきっとプラスになるはずです。
4. 周囲のサポートに頼る
一緒に成長していくのは、正直、すごく大変なときもあります。そんなときは、信頼できる友人や家族、カップル向けのサポートに頼るのも大切です。どんなカップルも完璧な人ではありません。自分の変化や、相手の変化が理解できずにモヤモヤすることだってあります。
そんなときこそ、周囲の人たちの支えが力になります。同じような経験をしているカップルの友人たち、あるいはカウンセラーなどの専門家の助けを借りるのもひとつの選択肢です。
5. 昔の自分たちを一緒に振り返り、祝福し、そして見送る
最後に。自分や相手が、もう「昔の私たち」ではなくなっていると気づくことには、少し寂しさや悲しみが伴うこともあります。でも、それを受け入れることこそが、自由への第一歩かもしれません。
変化に対処する時間を取るのは大切なことです。ただ、過去に戻ろうとするのではなく、今ここまで歩んできた道のりを振り返ってみましょう。かつての自分たち、あの頃のふたりを誇りに思い、そして必要であれば、その終わりに静かにお別れを告げてもいいんです。過去の自分とパートナーが、今のあなたたちをここまで導いてくれたことに感謝して。
そして今、変化を迎えた新しいふたりとして、再び向き合っていきましょう。
きっとある朝、目を覚ましたときに隣にいるその人が「知らない人」なんかじゃなく、「ずっと愛してきた人」なんだと気づけるはずです。少しだけ変わっただけ。あなたも、相手も。
離婚後に心を癒すための心理学者のアドバイス──どんな年齢でも

1985年に結婚したとき、私は自分が31年後の結婚記念日に離婚するなんて想像もしていませんでした。両親が離婚せずに添い遂げたように、結婚はずっと続くものだと信じていました。
大学院の臨床心理学で初めて結婚セラピーの授業を受けたとき、「若くして結婚した2人が、後に気持ちが離れてしまったらどうなるのか」と先生に聞いたことがあります。そのときは答えを教えてもらえませんでしたが、「気持ちが離れること」が離婚の大きな理由のひとつになるというのは、直感的に理解できました。実際、私の離婚もそうでした。
1990年に個人開業してから、多くの夫婦を見てきました。夫婦間の不満や衝突は、ある日突然起こるのではなく、時間をかけて積み重なるものだということがわかりました。私は妊娠や産後のメンタルヘルスを専門としていたので、子どもが生まれることで、すでにあった問題がより深刻になることや、子どもをきっかけに夫婦関係に亀裂が入るケースを多く見てきました。
私自身は、元夫スティーブと一緒に子育てをうまくやっていました。次女の出産後に彼が仕事を失ったとき、彼が家にいて子どもの世話をし、私が家計を支えることに決めました。それはしばらくうまくいっていましたが、長女の大学進学が近づくにつれて、私ひとりで学費を負担することに不安を感じるようになりました。
そしてある日、スティーブがクライアントの家の屋根から落ち、足首と足を粉砕骨折する事故が起きました。彼は2回の手術と9ヶ月のリハビリを経て仕事に復帰しましたが、私は娘を大学に送り届けるため、母と一緒に車で長距離運転をしていました。
そこから、人生におけるさまざまな変化が重なり、私は離婚を望むようになりました。2014年に聴神経と顔面神経の間にできた良性腫瘍を取り除く手術を受け、2015年には初期の乳がんの治療も経験しました。その頃には、私たちは感情的に完全に離れてしまっており、「これ以上、不幸な結婚生活を続けたくない」と強く感じるようになりました。
離婚が与える心理的影響は、たとえ円満な離婚であっても無視できないものです。私のカウンセリングの現場や私自身の経験でも、離婚の影響は軽度なストレスから、深刻なうつや不安に至るまで幅広く見られました。
離婚という大きなライフイベントの後には、心の整理と癒しのプロセスがあります。そのなかで、自分の居場所を取り戻す感覚、自分の人生に再び責任を持つ感覚、そして新たな自分と出会う経験が生まれてきます。
中には「離婚してスッキリした」と思う人もいれば、しばらくしてから「もしかしたらやり直せるかも」と感じる人もいます。私自身、離婚から1年半経った頃、スティーブへの怒りや失望が落ち着いたタイミングで「もう一度うまくやれないかな」と思ったことがありました。けれど彼から「もうそういう気持ちはない」と言われ、そのときの喪失感はとても大きなものでした。
離婚を通して私が学んだことのひとつは、「喪失」はひとつだけではないということです。パートナーの喪失、共有していた夢の喪失、家族や友人、ペットとの関係の変化、子どもとの時間の変化など、さまざまなかたちの喪失を経験します。

悲しみのプロセスには段階があります。「ショック」「怒り」「対処」「抑うつ・諦め」「受容」です。ただし、これは人それぞれのプロセスであり、必ずしも順番通りに進むわけではありません。行きつ戻りつしながら、少しずつ受け入れへと向かっていくものです。
また、離婚がもたらすのは感情面だけの問題ではありません。多くの人が経済的な変化にも直面します。たとえば、パートナーのどちらかが家計を一手に担っていた場合、もう一方は預金口座の残高やログイン情報すら把握していないということもあります。
また、離婚後に直面するのが「自分とは何者なのか」という問いです。結婚生活では知らず知らずのうちに相手との関係性の中で自分を形づくっていることが多いので、独り身になることでアイデンティティを再構築する必要が出てきます。
私自身はそのプロセスのなかで、マインドフルネスを実践し、本を書き、自分自身を見つめ直す時間を持ちました。結果的に、自分がどんな人間で、どんな時間の使い方を望んでいるのかが明確になり、新しいパートナーと自分らしい関係を築くこともできました。
最後に、自分を癒すためのヒントをいくつか紹介します:
- 離婚は人生の大きな転機であることを認める。
- 栄養・運動・睡眠・ストレス管理など、基本的なセルフケアを大切にする。
- 呼吸法やリラクゼーションなど、ストレスを軽減する方法を日常に取り入れる。
- 子どもがいる場合、子どもの感情に寄り添い、パートナーの悪口を言わないよう心がける。
- 小さなことでいいので、今この瞬間に心地よさを感じる行動をする(音楽を聴く、散歩する、好きな香りを楽しむなど)。
人生には波がありますが、「これもいずれ過ぎ去る」という言葉を心に留めながら、一歩ずつ前に進んでいきましょう。
_________________________________________________________________________________
ダイアン・サンフォード博士は、女性の人生のあらゆる段階において心身の健康をサポートすることを専門とする心理学者です。35年以上にわたり、セルフケアとマインドフルネスを通じて、クライアントが内なる平和と自己理解を深められるよう導いてきました。
彼女自身もバランスの取れたクリアな心を保つために、セルフケアとマインドフルネスを大切にしています。具体的には、ヨガ、瞑想、自然の中を歩くこと、読書、料理、家族や友人と過ごす時間、そして20ヶ月になる孫のキャメロンとの遊びが日々の習慣となっています。
詳しくは、drdianesanford.com をご覧ください。
心も関係も整える:自宅で始めるカップル&ファミリーカウンセリング

カウンセリングというと、「何か問題が起きたときに行くもの」と思われがちですが、実は予防的なケアとしてもとても有効です。特に夫婦や家族など、身近な人間関係では、感情が絡み合いやすく、つい相手の意図を誤解してしまうこともありますよね。
そんなとき、第三者であるカウンセラーが入ることで、お互いの思いや考えを冷静に整理し、より良い関係性を築くためのサポートを受けることができます。以下のようなメリットがあります:
- コミュニケーションの改善
言いたいことがうまく伝わらない、すぐケンカになってしまう……そんな悩みの根本原因を一緒に見つけてくれます。 - 感情の整理と理解
イライラや不安など、自分でも整理しきれない感情を安心して話せる場があるだけでも、心が落ち着きます。 - 相手への理解が深まる
「なぜあの人はそう言ったのか」「どうしてあの態度を取るのか」を、一緒に考えることで、相手への見方が変わることも。 - 関係を修復・強化するチャンスになる
距離ができてしまった関係も、カウンセリングを通じて再びつながるきっかけになることがあります。
カウンセリングは決して「問題がある人が受けるもの」ではなく、「より良く生きたい」「もっとわかり合いたい」という思いを持つすべての人にとって、有益なサポートツールです。
日本で家族や夫婦関係に関する悩みを抱えている方々に向けて、オンラインで利用できるカウンセリングサービスをいくつかご紹介します。これらのサービスは、忙しい日常の中でも自宅から安心して相談できる環境を提供しています。
1. TELL Counseling(テル)
TELLは、英語と日本語を含む多言語でのカウンセリングを提供しており、個人、カップル、家族、子ども、青少年向けのサービスがあります。東京と沖縄に拠点を持ち、オンラインでも全国から利用可能です。経験豊富なセラピストが在籍しており、文化的背景や言語の違いを理解した支援が受けられます。
2. Tokyo Mental Health(東京メンタルヘルス)
東京メンタルヘルスは、個人、カップル、家族向けのオンラインカウンセリングを提供しています。英語と日本語に対応しており、国際的な背景を持つクライアントにも対応可能です。多様な専門家が在籍しており、柔軟な対応が魅力です。
3. NTC(ナラティブ東京カウンセリング)
https://www.ntokyocounseling.com/
NTCは、オンラインでのカップルおよび家族向けカウンセリングを提供しています。セッションは自宅から受けられ、プロのセラピストが関係性の課題に対処するサポートを行います。料金は50分13,200円(税込)で、予約制です。
4. Universal Psychology Japan(ユニバーサル・サイコロジー・ジャパン)
臨床心理士の中村仁美博士が運営するこのサービスは、英語と日本語でのオンラインカウンセリングを提供しています。国際的な背景を持つ子供や家族を対象としており、異文化への適応という課題へのサポートがあります。現在、新規クライアントの受付は2025年6月まで停止中ですが、将来的な利用を検討される方はウェブサイトで詳細をご確認ください。
_________________________________________________________________________________
オンラインカウンセリングは、地理的な制約を超えて、必要なサポートを受けるための有効な手段です。特に、国際的な背景を持つ方や多忙な日常を送る人にとって、自宅から安心して相談できる環境は大きな利点となります。上記のサービスは、それぞれ異なる特徴や専門性を持っていますので、ご自身のニーズに合わせて選択されることをおすすめします。
心の健康は、日々の生活の質を大きく左右します。一人で抱え込まず、専門家のサポートを受けることで、新たな視点や解決策が見つかるかもしれません。ぜひ、これらのオンラインカウンセリングサービスを活用して、より良い生活を築いていきましょう。
流産を経験した大切な人をどう支えるか

この記事は The Good Trade より翻訳されました。
私が20代後半のとき、親友のクリスティンが流産をしました。
彼女は妊娠12週目で、ずっと妊娠を望んでいたところでした。
私はどう対応したらいいのか分からず、何を言えばいいのか、どう言えばいいのか迷いました。
妊娠や出産を経験している友人も少なく、排卵検査薬や妊娠糖尿病、搾乳器のこともよく知らない私にとって、「流産」は未知のもので、ただただ無力感に包まれました。
何よりも、私がいつも支えてもらっていた大切な人に、今度は私が寄り添いたかったのです。
「どんな言葉や贈り物がふさわしいだろう?」
私は、以前同じような立場になった年上の友人にメッセージを送りました。
彼女は、「何か命を育てられるもの――たとえば植物――を贈るのはどう?」と提案してくれました。
その後、私はクリスティンに電話をかけ、心からのお悔やみを伝え、何が必要かを静かに尋ねました。
刺激になりそうな言葉を避けながら、もう1週間ほど経ったころ、小さなかわいらしい植物を贈りました。
「あなたは深く愛されている。赤ちゃんもあなたも大切な存在だった」――そんな想いを込めて。
これが正解だったのかどうかは分かりません。
それがこのテーマの難しさでもあります。
とても身近で、でもタブー視されがちな「流産」。
実際には、妊娠の30%以上が流産に至るという研究もあり、染色体異常や遺伝、母体の健康状態など、原因もさまざまです。
親しい人を支えたいと願うとき、どんな言葉が適切か考えることはとても大切です。
幸いなことに、クリスティン自身も、自らの経験と、流産を経験した人への支援のあり方について、シェアしてくれました。
何を「言うか」「するか」
流産後によく耳にする言葉に、「そのうちうまくいくよ」「そうは言っても…」というフレーズがあります。
たとえば、「そうは言っても妊娠できることがわかったじゃない」とか、「初期だったからまだ良かった」など。
悪気はなくとも、こうした言葉は悲しみを過小評価したり、無効化したりしてしまう危険があります。
クリスティンはこう語ります:
「私が一番つらかったのは、命があった赤ちゃんが、亡くなったという事実でした。
次の赤ちゃんを楽しみにしていることとは別の話なんです。
前の子も、今の子も、それぞれがかけがえのない存在なんです」
だからこそ、「あなたが大切な存在を失ったことを悲しんでいます」「ずっとあなたのことを想っています」――
そんなシンプルで真心のこもった言葉が、何よりの支えになります。
また、流産後は心だけでなく、体の回復も大変です。
クリスティンは子宮内容除去術のあと、「痛み、出血、発熱の中で、感情を整理する余裕なんてなかった」と振り返ります。
さらに、妊娠中の人の約45%が直面すると言われる産後うつも、状況をさらに厳しいものにします。
ですので、気持ちのケアだけでなく、実際のサポート―― 通院の付き添いや家事の手伝い、食事の差し入れなど――も、心に寄り添うかたちとなります。

何が必要か、何が「不要」かを尋ねる
数週間が経つと、どう接していいか分からなくなることもあるかもしれません。
でも、尋ねていいんです。「何ができる?」と聞くことで、正しい答えに近づけます。
とても親しい間柄なら、
「今、どんなふうに支えてほしい?」
「話したい? それとも静かにそっとしておいた方がいい?」
と聞いてみましょう。
特におすすめなのが、連絡するタイミングについても確認すること。
忙しいときや職場で突然連絡を受けると、それだけで心が乱れてしまうこともあります。
クリスティンは、こう言います:
「何人かの友人が、“話したいときはいつでも連絡してね。返せなくても大丈夫だから”とメッセージをくれた。
それが一番ありがたかった」
もし、最近はあまり親しくないけれど、SNSや共通の知人から流産を知ったという場合、直接メッセージを送るのは避けた方がいいかもしれません。
家族に連絡し、お悔やみのカードや贈り物をどこに送ればいいか確認するのもひとつの方法です。
また、あなたが妊娠中だったり、小さなお子さんがいる場合は、特に相手の気持ちや境界線に配慮する必要があります。

ただ「そばにいる」ことが力になる
大切なのは、完璧な言葉を探すことではなく、そばにいることそのものです。
「聞く」だけでも十分な支えになりますし、支援グループやカウンセラーの情報を共有するのも一つの方法です。
また、妊娠していた本人だけでなく、パートナーや子ども、家族も支えを必要としていることを忘れないでください。
小さな気遣いでも、大きな力になります。
偏見をなくすために
流産の話題には、まだ多くの偏見がつきまといます。
出産経験者の5人に1人が流産を経験すると言われていますが、それほど多くの話を耳にすることはありません。
「話さない自由」は尊重されるべきですが、「話したくても話せない」空気をつくってしまっているのも事実です。
クリスティンはソーシャルワーカーとしてこう言います:
「ほかの“喪失”については話すのに、なぜ流産だけはタブーになるのでしょう。
誰かに聞いてほしいのに、“話してはいけない”と感じるのはつらいことです」
社会としても、「12週までは公表しない」文化や、企業の弔意制度において流産が含まれていないといった課題があります。
こうした構造にも目を向け、政策の見直しや啓発活動を通じて支援の輪を広げることも、私たちにできる支援のひとつです。
長期的な支援も大切に
失った命のことを、記念日や年末年始など、ふと思い出すタイミングでそっと気にかけてください。
「ひとりじゃないよ」と伝え続けることが、何よりも心強い支えになります。
人生のどんな喪失も、深く心をえぐるものです。
そして、その悲しみのなかにいる誰もが、「支え」を必要としています。
あなたの大切な人が流産を経験したとき、このメッセージが少しでも支えになり、
「見守られている」「大切にされている」と感じてもらえるきっかけになりますように
【編集部対談】心がふっと軽くなるメディアを目指して。編集部が語る「Humming」の原点
Webマガジン「Humming」を立ち上げてから早2年。立ち上げメンバーである編集部の舞麻と純が、あらためて「なぜHummingを始めたのか」「どんな想いで運営しているのか」を語り合いました。
| Humming編集長 永野 舞麻
1984年生まれ。16歳までを日本で過ごした後、海外へ移住。大学で出会ったアメリカ人の夫と結婚し、現在はカリフォルニア在住。3児の母。 高校時代、スイスに住んでいたときに自然の偉大さに触れ、地球環境保全について学び始める。アメリカの美術大学でテキスタイル科を専攻。 今でも古い着物の生地などを使って、子育ての合間に作品を制作し続けている。 |
| Humming編集部Project Coordinator 條川純
カリフォルニアで日本からの移民の両親のもとに生まれ育った私は、まったく異なる2つの文化に触れるという貴重な経験をしてきました。それによって、世界や人との関わりについて幅広い視点を持つことができたと思います。人々が安心して休めたり、心が癒されるような場所があることはとても大切だと思っていて、Hummingがそんな場所になれたらと願っています。 |

自分と向き合うことで人生は変わる。その経験を伝えるために
純:今日は、WebマガジンHummingを始めた理由や、どんな気持ちで運営しているのかを話していきたいと思います。
舞麻:Hummingを立ち上げたのは、2年前、私たちが38歳のとき。だから、「38歳から読みたいWebマガジン」にしたんですよね。
私はこれまで、いわゆる普通の人生を歩んできたと思っていました。でも、アメリカに移住してから、娘の育児に行き詰まってしまって……。そんなとき、夫から勧められてセラピーを受けてみました。
セラピーの先生との対話の中で、自分の幼少期のトラウマや、心の奥に残っていた傷や怒り、悲しみと、じっくり向き合う時間を持つことができました。過去のつらい出来事も含めて、すべての経験が今の自分をつくっていると気づけたことで、少しずつ自由になって、ありのままの自分を受け入れられるようになっていきました。
そして実感したのが、「自分が変わると、まわりも変わっていく。世界の見え方さえも変わる」ということ。
私がこれまで経験したことを丁寧に紐解きながら言葉にしていくことで、今つらい気持ちを抱えている誰かの心が、ほんの少しでも軽くなるかもしれない。「自分に生まれてよかった」「生きていてよかった」と思える人が一人でも増えたらと思ってHummingを立ち上げました。
読んでくださる方の役に立ちたいという一心で、発信を続けています。
「自分を満たす方法」を知ってほしい

純:自分のことを書くって、勇気がいるし、不安にもなる。でもHummingのライターさんたちは、毎回テーマに真正面から向き合って、赤裸々に書いてくれているよね。私も読むたびに心打たれることが多いです。
私自身も記事を書くことがあるけど、書くことで自分の気持ちが整理できて、「書いてよかった」と思える瞬間があります。読者さんに少しでも共感してもらえたら嬉しいな。
舞麻:日本は「自分を後回しにして誰かのために尽くすのが美徳」みたいな価値観が根強く残っている気がして……。でも、誰かを大切にすることは自分を後回しにすることではないし、自分を大切にしているからこそ、本当の意味で誰かを支えることができる。そういうことをHummingでは伝えていきたい!
お母さん、奥さん、上司、部下、娘……、女性にはいろいろな立場があって、自分を後回しにしがち。でも頑張りすぎると心のコップが空っぽになってしまいます。だからこそ、Hummingでは、まずは自分を満たしてあげていいんだよという感覚、そして自分を満たす方法を伝えていきたいです。
純:女性は何かしらの肩書きや役割を背負っていることが多いから、Hummingは、頑張り続ける女性たちの語り合える場所、ほっとできる居場所になれたらいいよね。
子どもがいる人もいない人も、働くママも専業主婦も、生き方は人それぞれ。私はHummingを通じて、いろんな女性に出会えるのがすごく楽しいです。
舞麻:Hummingは、男性にも協力してもらっているけれど、私たち女性が立ち上げたからこそ、「女性」をとても大切にしている場所だよね。
純:私はアメリカ育ちだから、日本で頑張っている女性を見ていると、「日本って厳しいな……」と感じることも多くて。もちろんアメリカにも厳しさはあるけど、種類が違うというか。
舞麻:私が暮らしているカリフォルニアでは、「ここまではできるけど、これ以上は難しい」と、バウンダリー(境界線)を提示する女性が多いです。
たとえば、子どもの学校行事でも、「全部やります」ではなく、「ここまではできるけど、この先は誰か手伝ってもらえますか?」と言えること。自分で背負いすぎない姿勢が大切だと思います。
純:日本では「できない」と言うことが許されないような空気があるよね。
舞麻:「あの人もそう言ってたし、私も言ってみようかな」と思える空気をHummingがつくっていけたらなって。ずっと我慢していると、身近な人に八つ当たりして、自己嫌悪のサイクルに陥ってしまいがち。だからこそ、バウンダリーを意識することは大事だよね。
でも、私も最初はバウンダリーを持つのがすごく怖かった。夫に「もう無理〜」と伝えることすら、自分のわがままなような気がしていたし、プライドや責任感が邪魔して、なかなか言えなかった。
だけど、「まだ大丈夫」と言い続けていたら、ある日バーンって爆発して、夫とケンカしたり、八つ当たりしたり……。あの悪循環は本当にきつかった。
でも、自分とちゃんと向き合うようになって、他者とのあいだに境界線を持てるようになったことで、今は夫との関係もすごく安定しています。
だからこそ、私のそんな経験も、Hummingに綴っていきたい。今の環境がしんどい、少しでも変えたいと思っている人にとって、Hummingが1歩踏み出すきっかけになれたら、とても嬉しいです。
純:編集部メンバーも、みんな手こずったり、つまずいたりしながら生きている。私たちのリアルな姿をシェアすることで、「ひとりで頑張らなくてもいいんだよ」と伝えていけたらいいよね。
日本のスタンダードに苦しんでいませんか?

舞麻:Hummingが少しユニークなのは、純は日本人だけど生まれも育ちもアメリカ。私は日本で生まれたけれど、ヨーロッパの高校に行って、今はアメリカ人の夫とカリフォルニアで暮らしている。他にもタンザニアや香港での暮らしを経験しているメンバーもいます。
日本にいると、つい「これはOK」「これはダメ」だと白黒つけたくなるけれど、その基準は、あくまでも日本でのスタンダード。知らず知らずのうちに、その枠に自分を押し込めて、苦しくなっていることもあるはず。
でも視野を世界に広げてみると、「ヨーロッパではこういうのもアリだよ」とか、「インドではそれが普通だよ」とか、もっと自由で、多様で、オッケーなことがたくさんあります。
だから、日本のスタンダードにとらわれすぎずに、「こういう考え方もあるんだな」とか、「こういう子育てもアリかも」、「こういう関係性も心地いいな」と、ちょっとでも気持ちがゆるんで、ふっと楽になれる。そんな情報源として、Hummingを読んでもらえたら嬉しいです。
ーーーーー
\音声配信 はじめました/
編集部対談の内容は音声でも配信しています。音声でもお楽しみください。
spotify
stand.fm
家族との関係は悪くないけど、無意識に気を張ってしまう自分もいる

私は一人っ子。
両親からの愛情をひとり占めして育ってきました。
特段裕福な家庭というわけではないけれど、生活に困るようなことはなく、習いごとや行きたい大学などやりたいことはだいたい挑戦させてもらえました。
たしかに、恵まれている環境でした。
だけど、昔からどこか、心の奥には”家族に対する説明のつかないモヤモヤ”があります。
「なんでこんなに満たされないんだろう」と、自分でもうまく言葉にできないまま、今もときどき、その違和感に足をとられそうになります。
生まれ落ちたのは、正反対な父と母の間
母を一言で表すと、とても明るくてよくしゃべる人。そして頑張り屋さんです。
家事は全部ひとりでこなすし、料理も美味しい手の込んだものをパパッとつくってしまう。
忘れ物は多かったりと、ちょっと抜けているところはあるものの、基本的にはとてもしっかりしていて、私にいろんなことを学ばせ、経験させようと常にあれこれ考えてくれていました。
それはそれはたっぷり私に愛情を注いでくれて、小さいころの私はそんな母が大好きでいつもべったりでした。
そうなると、いつの間にか母が絶対的な存在になっていきます。
「母さんがいれば大丈夫。母さんが言うならそれが正しい。」
でも、大きくなるにつれ、世界というのはもっと広く、いろんなもので溢れていることに気づく。
そこに正しさなんてものは存在せず、100人いれば100通りの答えがあって良いということも知る。
そうすると、私の中で母の存在がちょっと揺らぐ。
その愛情がちょっと重たくなってきて、ふとしたときに「あれは母が思い通りにしたかっただけじゃないか?」と思う記憶がちらほら出てくるんですよね。
そうなると、普段の母との会話にも違和感を覚えはじめます。
「結婚は?彼氏は?」と何度もズケズケ踏み込んでくるし、何気ない世間話のなかにも、ちょっと古い考え方や“べき論”を感じ取るようにもなってしまって。
最近はそのエネルギーに生気を吸い取られる感覚もある。
もちろん、母のことは今も好きだし大事だし、尊敬もしています。
でも子どもの頃には気づかなかった一面が見えてくると、途端に付き合い方が分からなくなってきてしまったんですよね。
一方、父はというと母とは正反対。

基本、母のように暇があれば他愛もない話を吹っかけてくることもなければ、こちらが話しかけても最低限の返答しかしない。
……というか、そもそも口を開いてないんじゃないか?
子どもの頃を思い返しても、父がつらつら喋っている風景はほぼ思い出せません。
そんな父の血を強く引いたのか、幼い頃から自分の気持ちを伝えるのが苦手だった私は、とにかく泣き虫でした。
でも、私が泣いていても父は特に声をかけてこない。
母が一目散に駆けつけるから隙がなかったのかもしれないけれど、父が慰めてくれたり、話を聞いてくれた記憶は、少なくとも物心ついてからはありません。
そのぶん、何かで口うるさく怒られたり、たしなめられることも大してありませんでした。
私が、どんな習いごとをはじめようと、辞めようと、どの高校に進学しようと、大学で県外に出ようと、父はまったく口を出さないし顔色一つ変えない。
幼馴染なんて、私が県外に出ると言ったらポロポロ泣いてショックを受けてたのに…!
よく言えば「干渉しない父」でしょう。
でも今思えば、学生の私にとって、一番身近な家族が、実の父親が「何も言ってくれない」のはとても不安で寂しかったんじゃないかと思うんです。
その沈黙に、ひとりで大きな決断を背負っているような、そんな孤独を感じていたような気がします。
そして、いざ本当に県外の大学に進学が決まり、いよいよ旅立つという時も、父が来てくれたのは見送りだけ。
平日だったか私の荷物を出すのに残ってくれたんだか、何か理由があったような気がしなくもないけど、引っ越しについてきてくれたのが母だけというのには、やっぱりどこか寂しさがありました。
それに、積もっていたモヤモヤも相まって、新幹線のなかで思わずメールを打った記憶があります。
「あの時も、あの時も、父さんはなんで何も言ってくれんかったん?」って。
すると、返ってきたのは「やりたいようにやればいいと思っていた」というような内容でした。
テキストですら口下手な父にしては、いろいろ書いて弁明してくれた気はするけれど、当時の(いや、今も)私からしたらこの一言に尽きます。
「それを面と向かって言ってくれ……」
今思えば、何も言わず見守ることが父なりの愛情だったのかもしれません。
それでも、やっぱり言葉にしてもらえなければ、伝わらないことってたくさんあるんですよね。
胃もたれするくらい言葉を浴びせてくる母と、不安になるくらい喋らない父。
そんな両極端な環境で育つうちに、私はどちらかに偏ってはいけない、バランスを取らねば、と無意識に力んでしていたのかもしれません。
全てを育った環境や両親のせいにするつもりではないけれど、”人の顔色を気にしすぎる性格”になった大きな要因の一つではある気がします。

私にとって家族は、一番近くて遠い
もう子どもとは言えない年齢になった今もたまに、この二人の狭間でどんな娘でいればいいのか分からなくなることがあります。
最近は母が企画してくれて家族3人で出かける機会が増えました。
おばあちゃん家以外の家族旅行があまりなかった子ども時代なので、その時間はシンプルに楽しいし、心から笑う瞬間も多々あります。
でも、その途中にふと「なんか……家族、演じてんな」と急に冷徹に客観視してしまう瞬間もあるんですよね。
一番近いはずの家族なのに、たまに突然、まったく分かり合えないものすごく遠い人に感じる、みたいな。
で、何より、大事な家族に対してそう思ってしまう自分にも罪悪感を覚えて、少し疲れる。
こんな感じなので、あまりずっと近くに居すぎるといつかバランスを崩してしまいそうで、今は実家の近くで一人暮らしをしています。
歩いてほんの10分の距離だし、なんなら職場には実家のほうが近いし、いろんな意味でコスパは悪いです。
でもこのほんの10分の距離が、私の心、そして家族仲を守るのにめちゃくちゃ大事な気がするんですよね。
家族の形に正解はない
ふとSNSなどで、幼馴染がその家族ととても仲睦まじそうに旅行したり、一堂に会して親御さんの還暦祝いをしたりする様子を見かけると、その姿が眩しくて「なんで私はこんな風にできないんだろう」と思ってしまうことがあります。
私はいつまで、上手くバランスを取れない子どものままでいるんだろうと、情けなくなることもあります。
だけど、家族の形に正解はないし、私と父と母が良ければそれで良い。
どれだけクセの強い両親でも、その狭間で揺さぶられようとも、家族を大事にしたい気持ちも本物。
それを忘れずに、限りある家族の時間をちゃんと噛みしめられる大人になりたいものです。
「親との関係」は、私たちのパートナー選びにどう影響するのか?

親子関係が恋愛にどう影響するのか
恋人との絆は「趣味や相性が合った偶然の出会い」と思うかもしれません。
しかし心理学的には、親との関係が私たちが惹かれる相手に大きく影響していることが分かっています。
人は胎内にいる時から、養育者の愛情やその欠如によって心の“設計図”が形づくられます。
これは次のような点に影響します:
-
自分自身の捉え方
-
世界の見え方
-
愛や信頼、親密さの感じ方
-
親密な関係に対する期待値
おすすめ記事 ▶ 子どもの愛情不足サインとは?今すぐできる対処法で親子の絆を深めよう
親と似たパートナーに惹かれる理由
愛着理論(アタッチメント・セオリー)とは
心理学の「愛着理論」によると、親や養育者との関係は、私たちが他者との親密さや信頼を築く土台になります。
愛着スタイルには次の4タイプがあります:
-
安定型(secure)
-
不安型(anxious)
-
回避型(avoidant)
-
混乱型(disorganized)
安全で安定した関係で育った人は健全な恋愛関係を築きやすい一方、無視や混乱が多かった場合、その特徴を持つ相手に惹かれやすくなる傾向があります。
無意識に「親に似た人」を求める心理
人は「馴染みあるもの=安心」と無意識に感じやすいため、たとえネガティブな特徴であっても惹かれてしまうことがあります。
トラウマセラピーではこれを「反復強迫(Repetition Compulsion)」と呼び、過去の体験を無意識に繰り返してしまう現象として知られています。

親に似たネガティブな相手ばかり選んでしまうときの対処法
まず「気づくこと」が最初の一歩
このパターンに気づくこと自体が大きな前進です。そこから癒しや変化が始まります。
実践できるステップ
-
親に似たネガティブな特徴をリスト化し、「赤信号」として意識する
-
見た目や肩書きよりも「関係を築く力」があるかどうかを見極める
(誠実さ・感情表現・思いやり・正直さなど) -
ドラマチックな恋愛に惹かれるパターンを見直し、「安心・安定」に魅力を感じる練習をする
まとめ|親との関係を理解することが恋愛の第一歩
同じような恋愛で傷ついたり孤独を感じても、それはあなたひとりの問題ではありません。
まずは「なぜ自分が親に似た相手を選んでしまうのか」に気づき、理解することが重要です。
そして新しい言葉や行動を学ぶことで、健全で安心できる恋愛関係を育むことができます。
最初は不器用でも、やがて自然に身につき、愛をより豊かに感じられるようになるでしょう。
コスタリカでのリトリート体験談。メディテーションを続ける理由とは

Humming編集長の永野舞麻が、コスタリカで開催されたメディテーションリトリートに参加しました。
彼女はなぜリトリートの場所にコスタリカを選んだのか。
メディテーションを続けることで、どんな変化を感じているのか。
編集部メンバーが話を聞きました。
雨に打たれ、ジャングルの中でメディテーション
ーー 舞麻さんは、昨年12月にリトリートでコスタリカに行かれていましたよね。どうしてコスタリカに行こうと思ったのですか?
夫のメディテーションの先生が「今度コスタリカでリトリートをやるよ」と教えてくれて、夫婦で参加することにしました。
これまでは私から「このリトリートに参加してみない?」と夫に提案しても、却下されることが多くて。でも今回は夫から誘ってくれたので嬉しくて!「これはもう行くしかない!」と思って、初めてコスタリカに行ってきました。
ーー 日本ではリトリートにあまり馴染みのない方もいると思います。コスタリカではどのようなことをされたのですか?
コスタリカの自然をたくさん味わってきました。ちょうど雨季の終わり頃に行ったのですが、毎日すごい雨で。土砂降りの中でメディテーションをしたり、日中はハイキングに出かけてウォーキングメディテーションをしたり、みんなでレインフォレストにも行きました。
これまで朝4時半から夜9時半まで一日中メディテーションを行うストイックなリトリートにも参加したことがありますが、今回の先生は「目を閉じて座ることだけがメディテーションではない」という考え方。料理をしているとき、子どもと接しているとき、仕事中、電車や車に乗っているとき、お風呂に入っているとき……、日常のすべての場面でメディテーションはできると教えてくれました。
ーー 以前参加された一日中メディテーションをするリトリートと、今回のコスタリカでのリトリート、どんな違いがありましたか?
以前のリトリートは、食事の時間以外はほぼメディテーション。電子機器やノート、本の持ち込みも禁止で、自分の内側にある雑念や思考をひたすら見つめる時間でした。
一方で、コスタリカでは自然の中でメディテーションをするので、いろんなノイズが入ってきます。目を瞑って呼吸を整えても、目を開いて活動し始めると、また雑念がやってくる。外から入ってくるものをどう受け止めるか、自分の中にどう取り入れるかを練習できました。
ーー ジャングルの中での瞑想。なかなか想像ができないのですが、どのように行うのでしょうか?
たとえばハイキングの最初に「ウォーキングメディテーションをしましょう」と先生が言ってくれて、そのときは足の裏に意識を集中させて、一歩一歩を感じながら歩きます。
最初はみんな黙って集中して歩いているけど、しばらくすると誰かが話し始めて(笑)。後半は普通におしゃべりしながら歩いていました。
ーー コスタリカでのリトリートを経験して何か変化はありましたか?
一番大きな変化は、「予想外のことが起こったときに、過剰な反応をせず、落ち着いて対応できるようになった」ことです。
たとえば、空港から宿まで本来は3時間半で着くはずだったのが、運転手さんのスピードがゆっくりで5時間もかかってしまったんです。宿に到着してから1時間ほどメディテーションをする予定でしたが、それができずに代わりにバスの中でメディテーションをしました。
でも、「こんなところでメディテーションなんて」「予定と違うじゃん」と思うのではなく、現実を受け入れて、次にどう動くかを考えられるようになりました。
あとは、メディテーションの仲間ができました。私の理想は毎朝4時半に起きて、子どもたちが起きる前に1時間メディテーションをすることですが、予定通りにできないことも多くて。でも、コスタリカで出会った仲間と「今日は◯分メディテーションできたよ」とお互いにチャットで報告し合うようになり、思い通りに時間が取れない日でも、できる範囲でいいからやろうと思えるようになりました。
「無」になることは宇宙と繋がること。全ての人やモノに優しくなれる
ーー 自分と向き合う時間を意識的にとる。簡単そうで意外と難しいですよね。
違うメディテーションの先生から「みんな毎日いろんな人とミーティングや商談をするのに、どうして自分と対話する時間は取らないの。自分のことをきちんと知らない状態で、どうやって他の人に自分の意見を言うの。朝一番に、自分と向き合う時間を持つことが大事だよ」と言われたことがあって、すごく納得したんです。
ーー 確かに!でも、私、不思議なんです。メディテーションをして「無」になることが、どうして自分と向き合うことになるのでしょうか?
たしかに、「無になること」と「自分と向き合うこと」は、一見つながっていないように思えるかもしれません。でも、続けてみると少しずつわかってくるんです。
私たちは普段、過去の記憶や思考に引っ張られて、無意識のうちにプレッシャーを感じながら意思決定しています。でも、毎日20分でも30分でも良いからメディテーションを続けていると、「プレッシャーをかけてくるもの」と「自分」のあいだに、ほんの少し隙間ができてきます。その隙間があることで、恐怖や不安といったネガティブな感情だけでなく、「好きな人のことが頭から離れない」みたいなポジティブな感情に対しても、冷静に向き合えるようになります。
感情に巻き込まれすぎず、「本当の自分は、今なにを感じているんだろう?」と立ち止まって考えられるようになる。すると、自分の直感や、本当に大切にしたいことが少しずつ浮かび上がってくるようになるんです。

ーー 舞麻さんはメディテーションを始めてどのくらいで変化を感じましたか?
「あ、変わってきたかも」と感じたのは、メディテーションを始めて2ヶ月くらいです。
「なんとなく優しい自分でいられているな」とか、「話し方が少し落ち着いている気がする」とか、小さな変化が重なっていきました。
メディテーションの習慣を続けていくと、まるで玉ねぎの皮を一枚ずつ剥くように、「永野舞麻」というアイデンティティをはじめ、「母親」「娘」「妻」「編集長」「プロデューサー」……あらゆる役割や肩書きが取り除かれていく。すべてを剥き終わったときに残ってる芯の部分が「本当の私」です。
ーー おっ、なんだか深い!
私が信じていることは、仏教の考えに近いと思っていて。「すべてのことには意味があって、すべてのことには意味がない」。それは矛盾しているけど真理だなって。
科学的に見ると、宇宙にあるすべての物質は「アトム(原子)」でできています。アトムは常に振動している。つまり、動かないもの、変わらないものは存在しないんです。
たとえば、家も、木も、時間が経てば崩れて土に戻ります。私たちの体も心も、日々少しずつ変化していて、今日と明日でまったく同じ「私」なんてありえない。
私とあなたも、目の前にある机やパソコンだって、組み合わせ方が違うだけで同じ物質でできている。そう思うと、「これは私」「あれは他人」って分けようとすること自体が不思議ですよね。
メディテーションをして「無」になれた瞬間は、宇宙と繋がっている状態です。自分より大きな宇宙の一部になれている瞬間に、自由を感じます。私はその状態を少しでも長くするために毎日メディテーションをしています。
ーー 「宇宙と繋がる時間」が長くなると、 舞麻さんにとってどんなメリットがあるのですか?
「無」の感覚でいられる時間が長くなればなるほど、争いごとがバカバカしく思えてくるし、誰かのことをジャッジすることもアホらしくなってくる。みんな同じなのに、どうして批判しあうのって。
私もあなたも、目の前にあるものもみんな一緒なんだって思えたら、心の底から人を愛せるし、全てのものを大切にできます。
たとえば、目の前でのろのろ運転してる車にも、「私がスピードを出しすぎないように、この人が現れてくれたんだな」って、ポジティブ思考になれます。得体の知れない心の底からの愛が溢れ出てくる感じを味わえるんです。
ーー その感覚、味わってみたいです。
でも、それを夫に話すと、「じゃあなんで娘たちに怒るの?」って言われちゃう。常に「無」になって、すべてを愛することは、やっぱり難しい。でも、そんな時間を1秒でも長く持てるように、私はメディテーションを続けています。

しんどい時は10分間のメディテーション。意識的にスピードを落とすことも大切
ーー 舞麻さんの話を聞いて、私もメディテーションに挑戦してみたことがあるのですが、なかなか継続できなくて。
私がやって良かったのは、朝起きたらすぐにメディテーションができるように、ベッドの横に椅子を置いたことです。寒くて起きられないなら椅子にブランケットを置いておくとか。「どこでやろうかな」「寒くてなかなか起きれない」といったハードルを一つひとつ減らしました。
「5分だけでもやろう」と思って椅子に座ると、気がついたら50分くらい座っていたりします。結局、私はメディテーションが好きなんですよね。
ーー メディテーションは毎日やることが大切なのでしょうか?
変化を感じたいのなら、毎日やるのが良いです。できれば、朝と午後の2回。午後はお昼を食べて、お腹が落ち着いた3時くらいがおすすめです。そのタイミングで10分でも良いからメディテーションをすると、体力も気力も夜まで持つんです。
小さな子どもがいると、子どもが寝るまでの夜の時間って「鬼ママ」になりがちですよね。イライラして、パートナーにきつくあたってしまったり。でも、午後にメディテーションをしておくと、気持ちに余裕ができて、踏ん張りがきくんです。
今って、みんなすごく生き急いでるじゃないですか。だからこそ、毎日少しだけでも、意識的にスピードを落とす時間を持つことが大切だと思います。
もし今、「しんどいな」とか「心がパンパンだな」と感じているなら、ショッピングに行くより、友達とお茶をするより、美味しいごはんを食べに行くより、映画を見るより、 私は10分間のメディテーションをおすすめします。
私がメディテーションをするようになって変われたので、きっとどんな人でも変化を感じられると思います。
親しい友人関係における「開かれた、思いやりのある衝突」のすすめ

人生の大半を通して、私は「健康的な関係」とは「衝突がないこと」だと思っていました。
「私たち、一度もケンカしたことないんだよね」なんて、恋人や親しい友人について語るとき、その言葉を「良い関係」の言い換えとして使っていたのです。
でも当時の私は気づいていませんでした。自分の人生に衝突が少なかったのは、偶然なんかじゃなく、私がものすごく一生懸命に、衝突を避けようと努力していたからだということに。
母は私が小さい頃から、「あなたのことは心配していない」とよく言っていました。
「あなたは、どこに植えられてもちゃんと花を咲かせるタイプだから」
私はその言葉が気に入って、それを自分の信条のように受け入れてきました。
柔軟性がある、立ち直る力がある、適応力がある——周囲の人たちは私のことをそう褒めてくれました。私は折り合いをつけられる人間だったし、協調的だったし、本当に“問題解決型”の人間だと思っていました。
でもこういう性質を自分の価値の一部と信じ込んでいたからこそ、それを維持することが実は簡単ではなかったことに気づけませんでした。そして、それには必ずしも“代償がなかった”わけではなかったのです。
何度も(何度も、何度も!)、私は小さな違和感やモヤモヤを見て見ぬふりしてやり過ごすことを選んできました。だって、それに向き合うなんて「サバサバしていない」し、「細かい」とか「面倒な人」って思われるかもしれないから。
たとえば、本当はサラダが食べたかったのに空気を読んでピザに賛成したり(雰囲気壊したくないし!)、誰かの嫌味や傷つく一言を「そんなつもりで言ったわけじゃないよね」と笑って受け流したり。私はいつの間にか、自分の本当の気持ちを飲み込むクセを身につけていました。口に出すより、我慢してやり過ごした方が楽。そう思い込んでいたのです。
「大丈夫。私なら平気」
「これくらいなら我慢できる」
これらが私の口癖で、イヤな気持ちを自分の中で処理して、心地よいことに意識を向けて、自分は“感じのいい人”であり続ける。それが、自分の価値だと信じていたのです。
でも、うまくいかないときもあるんです。
何度目かの「食べたくない重めの食事」や、「傷つくけど大したことじゃない“冗談”」を我慢した後、私は見えないところで少しずつ苛立ちを募らせていきます。気づけば、頭の中でそのときの場面を繰り返し再生しながら、心の中で怒りが燃え始めているのです。
「これが初めてじゃない」
私はそう思いながら、今まで受けてきた失礼な言動や、軽視された出来事のリストを思い出し始めます。私にも、人に優しくしていられる限度がある。そしてその一線を越えると、私は無言の戦闘モードに突入するのです。
ランニング中、シャワー中、通勤中。
私は空想の中で相手を叱りながらひとりで言い返す。
目は前を見据え、心臓はドキドキと鳴り響き、完璧な「正義の正論パンチ」を作り上げては、相手の心をズタズタにする想像をしているのです。
「あなたは、最初から私のことも、他の誰のことも尊重なんてしてこなかった」
「私はもう、あなたの自分への“リスペクト”のために戦いたくないの」
一度この思考に入ってしまうと、その関係はもう元には戻れなくなっていました。そして私の中では、2つのどちらかの結末に向かうしかないと感じていたのです。
ひとつは、その衝突が現実の世界で表に出てくること。もうひとつは、その人との関係が完全に終わること。
でも、たとえ何が起ころうと、私にとっては、「不快な会話をすること」よりはマシに思えました。
だって、「あなたの言葉に傷ついた」とか「私はそうは思わない」と伝えることには、とても大きなリスクがあるように感じていたからです。

もし相手が逆ギレしたら?
軽くあしらわれたら?
「あなたって繊細すぎるよ」と言われたら?
「めんどくさい人だな」と思われて、離れていかれたら?
私が思っているほど、私は柔軟でも協調的でもないとバレてしまったら——そのとき、自分にはもう親しい人間関係なんて残らないんじゃないかと思っていたのです。
衝突?それとも戦い?
今では(そして読んでくれているあなたもきっと)、「私は恐れに支配されていた」とはっきり分かります。でも、セラピストに「初めて衝突を怖いと感じたのはいつですか?」と聞かれたとき、私は驚きました。
私が戸惑っているのを見て、彼女は言い方を変えました。
「衝突が怖くなかった頃を覚えていますか?」
私はさらに混乱し、思わず笑ってしまいました。
「衝突が平気な人なんて、いるんですか?」
彼女は何も言わず、私が自分で答えるのを待ちながら、意味深な微笑みを浮かべました。
でも考えてみると、その問いは私には当てはまらないものでした。
「私はあまり人とケンカしないんです」と言ったとき、私は彼女が褒めてくれるだろうと思っていました。
でも、そうはなりませんでした。
「ご家族とは?」と彼女が尋ねました。「ご両親や兄弟とは?」
子どもの頃、兄と姉とは普通の兄弟喧嘩をしていました。けれど、今はみんな別の場所に住んでいて、特別仲が良いわけでもありません。
お互いあまり連絡を取らず、なんとなくの不満がくすぶっているような距離感。けれど、それが“兄弟ってもの”でしょ?
イライラすることがあっても、わざわざ言い争うほどのことじゃないし。
両親ともケンカしたことはありません。でも、私はもう10年以上も両親の近くで暮らしていません。
思春期の頃、両親はよく口喧嘩をしていて、私もその議論に加わることがよくありました。あの頃特有の情熱と反抗心を抱えて。でも、それって普通のことじゃない?

すると、セラピストがこう言いました。
「あなた、“ケンカ”って言葉をよく使いますね。あなたにとって“衝突”って、“戦い”だと思っていますか?」
……たしかに。
戦いじゃなかったら、それは衝突と呼べるの?
私はその問いを口に出す前に、心のどこかで気づいていました。人と対立する感情や緊張、不快感を「戦い」にしなくても処理する方法があるということに。でも、私はそれを経験したことがなかったのです。
誰かが自分と違う意見を持っていると感じたとき、私は無意識に“先回り”して、それを避けるために自分の意見を控えめにしたり、もっと好かれるように振る舞ったりしていました。
そして、もしその引き出しがもう空っぽになっていて、いつものように柔らかく対応する余裕がなくなっていたら、私は防衛モードに入り、その人との距離を取ることで自分を守ろうとしていました。
そのとき、相手が傷つくかどうかなんて、正直どうでもよかった。
私の中では、もうとっくに“戦い”は始まっていて、
「この関係は“有害”だ」と思い込むことで、離れることを正当化していたのです。
だって、もうたくさん傷ついてきたんだから。
それは——相手のせい。でしょ?
話しながら、自分が言っていることが……あまり良く聞こえないな、とは思っていました。
でも、まさか私が「ただ怖いから」という理由だけで、ちゃんとした関係を壊してきたなんてこと、ある?
これまでの親しい友人たちとの関係を思い返して、私たちがどうやって摩擦を乗り越えてきたかをひとつずつ振り返ってみました。
私の人間関係は、たいていある環境の中で強く、濃く燃え上がるタイプです(学校とか職場とか)。でも、人生の変化とともに自然と離れていったり、逆に長く穏やかに続く炎として残ったりするパターンもあります。
私は、まず軽い話題で距離感を測ったり、少しずつ相手を探ったりはしないタイプ。最初からガツンと深いところに飛び込むタイプで、それを面白がってくれる人が、私の「仲間」です。
大学時代のルームメイトには、「あなたがパーティーを本当に楽しんでる時って、隅っこの席で初対面の人とずーっと話し込んでるときだよね」と言われたことがあります。
ちなみにそのルームメイトとは今でも友達です。しかも、私たちは一度ケンカしています。……めちゃくちゃ激しいやつ。
大声で叫び合う、本気の大ゲンカ。
その前には、ほぼ1学期にわたって続いた「無言の緊張感」がありました。冷蔵庫の中の物の位置をいちいち変えたり、目を合わせないことでお互いの不満を表現するっていう……。
……まあ、それはいい例じゃないかもですね(笑)。
「質問!」
私は30年来の親友にショートメッセージをしました。
「私たちって、今までにケンカしたことある?」
「多分あるけど、“怒ってた”っていうよりは、“すれ違い”だったんじゃない?」と彼女。
確かに、3つくらい「ちょっと気まずかったかも」というエピソードが思い出せるけど、そのうち明確に言葉にして向き合ったのは1つだけ(しかもそれ、メールで……たぶん、ちゃんと話し合ってすらいない)。
以前の私だったら、それを「良い関係の証」と思っていました。
常に同意し合えて、争いのない関係こそ平和。それが理想!って。
でも——

本当に「平和」とは、一方が心の中で静かに戦っている状態のことを言うの?
誰かの“本音”が犠牲になって成り立っている平和に、意味はあるの?
40歳に近づいてきた今、私はようやく見方が変わってきました。
自分が傷ついたり、居心地の悪さを感じたときにそれを隠していたり、相手がそうしているサインを見過ごしていたら、それは関係の中で“誠実でないこと”をしているのと同じ。
それは、ただ自分の「心の平和」を失うだけでなく、関係そのものを損なっているのです。
私は、表面的なつながりには興味がありません。
それなのに、こんなふうに自分の大切な人間関係の「成長」を、無意識のうちに妨げていたのだとしたら、とてもショックです。
だって、私の中で「成長」と「真実」は、一番大事な価値観だから。
「ねぇ、私たち、“健全な衝突”の練習、必要じゃない?」
そう親友にショートメッセージを送ってみました。
数分間、返事がこなくて、私は思わず笑ってしまいました。
「え、ちょっと待って、これでストレス感じてる? すごく感じるんだけど、あなたが今ストレス感じてるの(笑)」
「ははは、感じてるよ!今まさに“衝突”中じゃん!!」
自宅出産は、本能に戻り、体・心に丁寧に向き合う豊かな時間【助産師でバースエデュケーターのNANAKOさんインタビュー】

「自宅出産」と聞くと、どんなイメージが浮かぶでしょうか?特別な人だけが選ぶもの?少し怖い?それとも、どこか懐かしい響きがしますか?
100年前、日本では当たり前だったという「家で産む」という選択。いま改めて、出産を「自分のリズム」で、「自分の空間で」、「自分の力を信じて」迎えたいと望む女性が少しずつ増えています。
今回お話を聞いたのは、第一子から自宅での出産を選んだNANAKOさん。ご自身も助産師であるNANAKOさんが、出産をサポートしてくれた助産師との深い信頼関係や、本能を信じることの大切さ、自宅という安心できる場所だからこそ味わえた「気持ちいいお産」について語ってくれました。
インタビューを行ったのは、自身も自宅出産を経験したHumming編集長の永野舞麻。母として、女性として、心から共感しながら聞いたリアルな声には、自宅出産への先入観をやさしく解いてくれるヒントが詰まっています。
ーー出産って、マラソンみたいに感じます。妊娠前から準備に入り、トレーニングをして体を整えて、出産を迎えるという流れが。
私もそう思います。妊娠することで、今まで以上に、自分の体に目を向けるようになり自分にフォーカスできるようになります。それは、お腹に赤ちゃんがいて、赤ちゃんをしっかり育てるという責任が生まれるからですね。だから、自分を見つめ直して、これからの生活習慣にフォーカスを当てやすくなります。出産は、人生が大きくガラッと変わるきっかけになる、そんなフェーズだと思っています。
ーー私には、娘が3人いて一番上はもうすぐ13歳で生理を考える時期。でも13歳から生理のことを話すのは遅いと思っています。なぜ生理が来るのか、女性の体の神秘について、血が出ることは怖いことじゃない、生理がないと赤ちゃんが生まれてこない、そういう話をしながら、娘たちには生理を自然のこととして受け入れてほしいと考えています。
その考え方は素敵ですね。私の子供はまだ小さくて、そこまで考えたことなかったですが、生理のことは早ければ早いほど、自然に受けいれることができるでしょうね。
ーー出産を通じて女性が得られる精神的な成長変化についてどのように考えていますか?
出産って通過点なんですよね。出産の先にあるのが人生。出産も産後もすごく変化がある部分。自分の体の変化もそうだし、心の変化もそうだし、ドラマのように波があって、落ち込む時もあれば、楽しめる時もあります。
ここで大切なのは「自分が決断する」こと。自分が決断しなきゃいけないことが、お産にも産後の生活にもたくさんあります。だから、自分をどうやって信じて、変化に自分がどう対応していくか、自分のアイデンティティをどう形成していくか、そういうことを妊娠中に学ぶことが大事です。
自分に自信を持って何か決断をできたり、その変化を楽しめたり、潜在的な自分のマインドを育てることで、産後に同じような変化があった時もどう対応していけばいいかわかるようになり、自分にも優しくなれます。
妊娠中に、こういったマインドの整え方を知っていると、自分を責めすぎません。産後はうまくいかないことが当たり前ですが、その時にちゃんと自分に優しい言葉をかけてあげられるようになります。人生で大事になること、つまり、自分や自分の体との向き合い方を経験し構築していける期間が、妊娠・出産だと思っています。
安産だったら嬉しいというのは一般的だと思いますが、私の究極の目的はそこではないんです。どうやって自分と向かい合い、母となる自分の基盤作りができるか、それが大切だと思っています。

ーー私も共感します。子供を産んで、母親になっていくのは、人生で1番難しくて、でも言葉で表せないほどの喜びを味わわせてもらっているプロセスだなと感じますね。
丁寧に人生を生きるということですよね。妊娠して、出産して、子育て期に入って、丁寧に向き合うということを意識できるようになったことも、大きな変化だったと思います。
ーー私は3人目の時に自宅出産をしたいと思ったんですが、NANAKOさんは最初から自宅出産を選んでいますね。どうしてでしょうか?
私が自宅出産を選んだ理由は、原点に戻りたいという気持ちがありました。私が持っている助産師さんのイメージは、「みんなの相談にのる町の産婆さん」「お産をする人はもちろん、若い女の子の恋の相談や、更年期の方の相談にのる産婆さん」でした。100年前は、ほぼ100パーセントの方が自宅出産をしていたということもあり、1番原点に戻れる場所は自宅なのではと思って、自宅出産を選びました。
ーー怖くないかったですか。現在だと、自宅出産につきものが恐怖だと思うんですが、NANAKOさんご自身はそういう恐怖はなかったですか?
恐怖はなかったですね。でも、病院で出産をするとしたら恐怖を感じていたかもしれないです。自宅出産の最大のメリットは、自分の本能をむき出しにできて自分がとりたい姿勢がとれることなど、自由なところです。自宅出産は本能に戻りやすいので、体が何をしたらいいかっていうのを伝えてくれるて、それに従えばいいんです。だから、自分をとことん解放できる自宅出産に、私は恐れはなかったですね。
自宅出産では妊娠中から同じ助産師さんがずっと付き添ってくれるんですよね。病院の妊婦検診とは全く違います。病院の妊婦検診は、長い時間待ち、先生と話せるのは5~10分ほど、必要なことだけ聞かれて、異常がないかのチェックをし、検診終わりということが多いと思うんです。私が受けた妊婦検診は、長い時だと3時間ぐらいあるんですよね。助産師さんが、私が出産する家の中で、赤ちゃんの状態だけではなく、私の体や心の状況を全部を見てくれるんです。
すごく印象に残ってることがあります。初めて助産師さんに会った時に、体を全身タッチされたんですね。頭からつま先まで触ってもらった時に、助産師さんは私をまるっと全部見てくれるんだと感じ、大きな安心感につながったんですよね。助産師さんとの関わり合いや、お産をサポ―トしてくれる人との信頼関係が築けているという感覚が、すごく印象に残っています。
ーーNANAKOさんが提唱している気持ち「気持ちいいお産」について教えてもらえますか。
ホルモンをいかに味方につけてお産を進めるかは、ポジティブなお産だったかどうかに関わってきます。一言で言うと、「フローに入る」ということ。自分がお産の世界にどっぷりはまっている時は、出てほしいホルモンがたくさん出て、逆に出てほしくないホルモンはきゅっと引っ込んでくれるんですよね。
みんながみんな自然にお産のゾーンに入れるかと言えば、残念ながらそうではないんですね。ただこのお産のゾーンは、自宅の方が入りやすいです。自分が安全でリラックスしている時に、このゾーンに入りやすくなるからです。病院やクリニックという環境は、自分のコントロールの範疇に入らないことがどうしても起きてしまうんですよね。
自分の感情と体はつながっているので、不安や緊張があると、体にも無意識に力が入ってしまいます。そうすると痛みを強く感じ、フローが生まれなくなってしまうんですね。フローに入るためには、まずは自分を信頼することです。自分の体と赤ちゃんとそのプロセスを信頼することで、不安が安心に変わり、陣痛を受け入れることができるんですよね。そうすると、体もリラックスするので、出てほしいホルモンもたくさん出てきます。自分が安心して陣痛を受け入れて、リラックスするという循環に入ることができるとお産のゾーンに入れます。
私もこのお産のゾーンに入ったんですが、とても不思議な感覚でした。ふわふわっと半分夢の中、半分現実みたいな感じでした。まるで酔っ払っているような感覚になってたんですよね。子宮口が全部開いてから、出産までには長い時間がかかったんですが、お産のゾーンに入っていたので、時間が長くかかっているとは感じなかったんです。
ゾーンに入ってる時は痛くなかったかと聞かれたら、もちろん痛みはあるけれど、それが苦しくて辛いかって言われたら、全っくそうではないんです。
ーー私も陣痛の時に、自分の中でマントラがありました。「ふうー、強かった。もう1回ください」というもので、何回も自分に言っていました。出産体験を「痛い、もういや!」で終わらせたくなかったので、陣痛の波に乗る気持ちで行っていました。
永野さんのそういう体験をぜひ日本中のこれからお産する女性にも聞いてほしいですね。出産のポジティブな体験って耳に入ってきにくいんです。日本は特にそういう環境だと思っています。テレビや映画で見た出産のシーンが凄まじくて「出産は怖い」と心の奥底に刷り込まれてしまっています。
人工促進剤を使った時の陣痛と自然分娩の陣痛が違うことは科学的にもわかっています。決定的に違うのは、お産を進める人工の促進剤を使った時は、痛みを和らげてくれるエンドルフィンやオキシトシンというホルモンが出にくくなってしまうんですよね。つまり、体にかかる痛みを直接感じやすくなってしまうんです。体から出るホルモンとマインドはつながっているので、促進剤を使ったお産の場合は、特にマインドと体の繋がりを忘れずに意識することがとても大切になっていきます。
ただ、人工的な促進剤を使ったらポジティブなお産ができないかって言ったら、そういうことではないんです。妊娠中から出産の準備をすることで、促進剤を使ったお産も、無痛分娩でも、帝王切開でも、ポジティブなお産はできると思っています。

ーー 私は1人目のお産で挫折感を味わったんです。出産後に家族のみんなに「ごめんなさい」と謝っていたんです。それを見た助産師さんが「どうやって赤ちゃんを産むかが大事なんじゃない。今日からあなたはお母さんになった。この子と生きてくと覚悟を決めることが大事なのよ」と言われて涙が出ました。その人の言葉は今も心の中に残っています。
本当にそうですよね。やっぱりお産はあくまで通過点。妊娠・出産で自分が何を得られたか、それが一番大事だと感じました。
どんな出産でも、私がひとつ伝えておきたいのは、プランBをいつも考えておくことです。私自身も、「自宅出産でこれとこれをやりたい」と考えていましたが、実際できなかったこともありました。自宅出産ができなかった、無痛分娩ができなかった、促進剤を使った、だから失敗だと考るのでなく、お産の知識が備わっていれば、この時に促進剤を使ったのは私と赤ちゃんを守るためだったんだと受け入れることができるようになります。「出産は自分が思った通りにいかなくてもいいんだよ」と私は思っています。
ーー自宅出産の場合、緊急の事態の時に、助産師さんはどう対応してくれるのでしょう?
全部のお産にリスクはあるものですが、自宅出産だとリスクが劇的に上がるかというと、私は出産自体のリスクは逆に減ると思っています。自然な本能をむき出しのお産ほど安全なお産はないと思っているので、リスクはむしろ減っていくと思うんです。ただ、自宅出産では緊急時に病院への移動など、どうしてもタイムラグが大きくなるというのはあります。
ただ、自宅出産では病院には行かないということではなく、妊婦検診も何回かクリニックであったり、助産助産院さんと提携するクリニックで科学的なチェックもしてもらいます。出産で何かあった時すぐに搬送できるように準備をしてくれているし、自宅出産をする助産師さんたちは、緊急事態に対応するスキルを持っています。緊急時の対応も周知している助産師さんがついていてくれるので、そこは安心してほしいところです。
ーー私の自宅出産では、ドゥーラがいてくれて良かったと思います。自宅出産のメリットとして産後直後のケアが個人的には良かったと思いますが、NANAKOさんのご経験からどうですか?
さきほど、自宅出産では、妊婦検診にすごく時間をとってくれたと話しましたが産後も一緒なんです。産後のほうが長かったかな。子宮の回復状況や傷が治っているかなど目に見えるところだけでなく、赤ちゃんと家でどう生活をしているかとか心のケアなど、全部をひっくるめて助産師さんにケアしてもらえました。自分が暮らしているそのままの状態を見てもらい、さりげなく足りないところを補ってもらえたんです。
ーー NANAKOさんはドゥーラをお願いしましたか。
ドゥーラはいなかったです。日本は、「産後ドゥーラ」という存在はありますが、「出産ドゥーラ」になる資格などがまだないんです。特に病院やクリニックで出産する場合は、ドゥーラが出産に付き添うシステムがないんですよね。
ーー日本でも病院出産をしても、病院付きそいのドゥーラがいたら心強いかなと思いますね。
日本にも出産ドゥーラの存在が認められ、広く認知されて、ドゥーラを連れて病院で出産することができたらいいのにと思います。守り神のように、特別な知識がある人がいつも一緒にいてくれることで、不必要な医療介入がもし行われようとしても「ちょっと待って。ちゃんと考えよう」と守ってくれると思います。
ーー女性のこと、体のこと、赤ちゃんのこと最優先に一緒に考えてくれるドゥーラがいると心強いですね。
はい。そうしたら、お母さんにとっても赤ちゃんにとっても「優しい」お産が増えるだろうと思います。沖縄でドゥーラさんたちとお話する機会がありましたが、すごく頑張っていらっしゃって、日本もドゥーラが大活躍する時代がやってくるんじゃないかと期待しています。
ーー私は、出産の実体験について話すことにヒーリング効果があると感じます。自分のお産の経験は、話さない方も多いと思いますが、誰かに話したり、誰かの話を聞くことで、トラウマだった傷が柔らかくなったりする場所があったらいいなと思っています。
トラウマ的な感情があって、フタをしていた方が、少しそのフタを開けて解消できるような、そんな機会があったらいいし、お産のことを話すのが恥ずかしいことでないというのが当たり前になる、そんな風潮があればいいなと思います。
ーー最後にNANAKOさんの提供されてる、「あと100回したくなるお産 “ポジティブバースプログラム”」について教えてください。
私は助産師として、現場でいろんなお産を目にしてきました。
「戦うぞ」という表情で病院にやってきて、ずっと陣痛と戦っているようなお母さんも、お産のゾーンに入りマインドが変わった瞬間に、劇的にお産がハーモニーを育てたように進んでいくところを見てきました。ポジティブなお産をするのに、マインドがキーになるというのを現場で感じてきました。
どうやったらみんながリラックスして病院に来てくれるんだろう、妊娠中に質のいい準備をすることができるだろうと考えた時に、このポジティブバースプログラムの構想が始まりました。私自身がお産をして、あと100回お産をしたいって思うぐらい、幸せだったんですよね。
私が知っている幸せなお産をするレシピを広めたいと思い、自分が出産をして大切だと思ったことをとりいれて作り上げたのがこのプログラムです。出産だけがゴールではなく、産後のその先も、自分が自信を持って生きていけるようなプログラムを作り上げました。
私はヨガの講師をしてるっていうこともあって、体の相談を受けることがあります。お産の後から体型が変わった、尿漏れでパッドが手放せない、垂れたお腹が治らないなど、お産に関わる体のトラブルを聞いてきました。お産に携わっている身として、自分がサポートするお産で女性の体にダメージを与えたくないと思い、骨盤底筋に関する勉強もしプログラムにとりいれています。
一生付き合う体だから、お産がきっかけで、「不具合があるけど産後だからしょうがないよね」と、それが当たり前にならないでほしいと思っています。産後だからこそ輝いて、スポットライトが当たらない部分のケアや、自分の体に優しいお産、そういうところを学べるプログラムです。
_________________________________________________________________________________
ダルボワ南菜子
助産師 ヨガ講師(RYT200) バースエデュケーター ペリネケアアドバイザー
全てのライフステージにいる女性とその家族を支えることを目的にしたプラットホームSANBAROOM創設者。現役助産師としてクリニックで勤務する傍ら、妊娠・出産・産後に関連したワークショップの開催や、ヨガ講師としてマタニティヨガ・産後ヨガの知識を広める活動など行っている。2024年3月に第一子を出産。海とサーフィンと食べることが大好きな新米ママ。
インスタグラム:@sanbaroom
お金との健全な関係を築くために:自分に合った予算管理を見つけよう

〜アプリ派も手書き派も、自分らしいマネープランのすすめ〜
「気づいたら今月も使いすぎていた」「貯金したいのに、何に使ってるのか分からない」
そんな悩みを抱える人は多いのではないでしょうか?
予算管理は、単に「節約すること」ではありません。
それは、「お金との向き合い方を見直すこと」であり、ひいては「自分との関係を見つめ直すこと」でもあります。
お金は、私たちの価値観や暮らし方を映す鏡のようなもの。だからこそ、自分に合った方法で予算を管理することが、ストレスを減らし、人生の質を高める第一歩になります。
この記事では、アプリ派と手書き派、それぞれにおすすめのツールを紹介しながら、予算管理を通してお金との健全な関係を築くヒントをお届けします。
【デジタル派におすすめ】日本で使える予算管理アプリ4選
1. マネーフォワード ME
https://moneyforward.com/

銀行、クレジットカード、電子マネーなどを自動連携してくれる定番アプリ。グラフ表示で収支の把握もしやすく、使い勝手◎。
おすすめ:忙しいけどしっかり家計を管理したい人
2. Zaim(ザイム)
https://zaim.net/
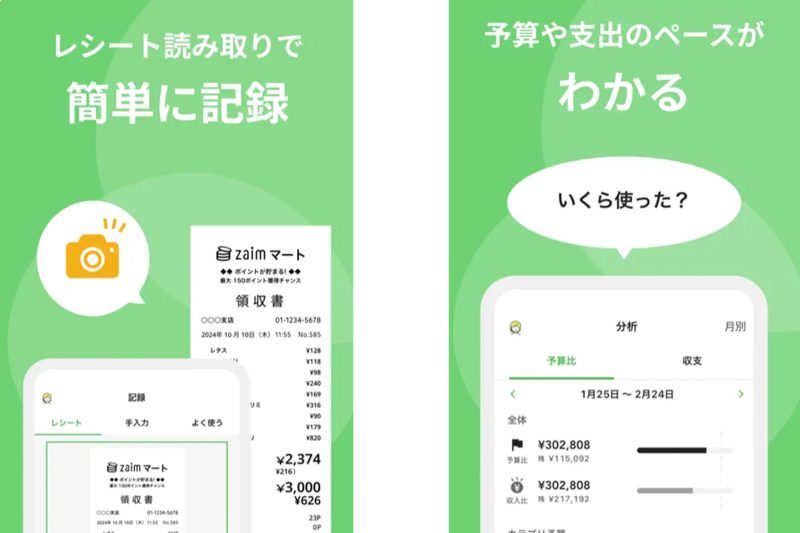
レシート読み取り機能つきで手入力が不要。医療費管理や家族共有もでき、柔らかいデザインで初心者にもやさしい。
おすすめ:家族と家計を共有したい人、アプリ初心者
3. OsidOri(オシドリ)

夫婦やカップルで家計を共有しやすい設計。共通の目標(旅行・引越しなど)を一緒に管理できます。
おすすめ:パートナーと家計管理を始めたい人
4. Moneytree(マネーツリー)
https://getmoneytree.com/jp/home

資産全体を見渡したい人向け。銀行、証券、ポイントまでまとめて管理可能で、セキュリティ面も安心。
おすすめ:貯蓄・投資含めて全体を把握したい人
【アナログ派におすすめ】書いて整える、手書き家計簿の魅力
アプリが便利なのは分かっていても、「やっぱり紙に書く方がしっくりくる」という人も多いはず。
手書き家計簿は、記録という行為を通してお金とじっくり向き合う時間をつくってくれます。
なぜ手書き?
- 記憶に残る:手を動かして書くことで、支出の実感が高まる
- 思考の整理になる:感情や気づきを書き込める
- “自分だけのノート”として愛着が湧く
- デジタル疲れの解消にも◎
手書き派に人気の家計簿ノート3選
1. 『づんの家計簿』シリーズ

インスタ発の人気家計簿。「書くことで整う」シンプルな構成が魅力で、日々の支出を丁寧に記録したい人にぴったり。
おすすめ:細かく見直したい人、書くことが好きな人
2. 無印良品『家計簿ノート』
https://www.muji.com/jp/ja/store/cmdty/detail/4550344296868
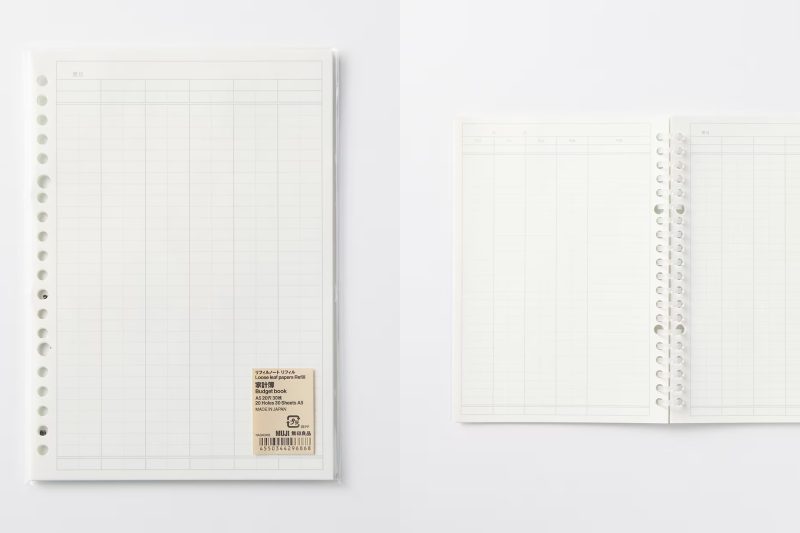
ミニマルなデザインで、月ごとの収支をすっきり記録。余白も多く、自分流にカスタマイズしやすい。
おすすめ:シンプルに続けたい人、初心者
3. フランクリンプランナー 家計簿
https://www.franklinplanner.jp/shopping/form/t05/

目標設定、予算計画、振り返り……すべて詰まった“思考型”の家計簿。ライフプラン全体を見据えた設計です。
おすすめ:計画的にお金を使いたい人、将来を見据えたい人
お金と「対話する」習慣を持とう
お金との関係は、「管理」するものというより、「対話」するものです。
今月は何に一番お金を使った?その出費は、どんな気持ちからだった?
そんなふうに日々の支出を振り返ることで、自分が本当に大切にしたいことや、人生の優先順位が見えてきます。
アプリでも、手書きでも——大切なのは「自分に合った方法を選ぶこと」。
ストレスなく続けられるスタイルを見つけて、自分らしいマネープランを育てていきましょう。
今日から始められる「お金との小さな対話」——まずは1日分だけ記録してみませんか?
その1歩が、もっと自由で安心できる未来へのきっかけになるかもしれません。
【映画レビュー】私たちは何を食べているのか?―フード・インクが問いかける食の現実

Series Art
誰もが健康的な食べ物を手にする権利がある。
そう聞くと、当たり前のことのように思えますよね?
食べることは生きる上で欠かせない行為です。あまりにも日常に溶け込んでいるからこそ、私たちは「その食べ物がどこから来ているのか」、そして「誰がその食をコントロールしているのか」を深く考えることはあまりありません。
ドキュメンタリー映画『フード・インク』は、アメリカの食品業界の知られざる闇を映し出しています。なお、この作品は2009年に公開されたものであり、紹介されている法規制や統計データは、現在では変わっている可能性があります。
アメリカでは、「農家は国の大黒柱である」という言葉があります。
20世紀の、食べ物が当たり前のように手に入る時代に育った私にとって、目の前のレタスを誰が育てたのか、肉がどこから来たのかを深く考えたことはありませんでした。
それは人によっては「特権」とも「無知」とも言えるかもしれません。けれど、そう遠くない昔まで、農家とは家族経営で、自分たちが作るものに誇りを持つ存在でした。今では、それが企業に取って代わられています。
農業のあり方が大きく変わったのは、ファストフードが普及し始めたときです。
マクドナルドはその先駆けのひとつで、手軽に安く提供できる肉の需要を一気に高めました。
ファストフードが急拡大する以前、アメリカの食肉市場においてトップ4社が占めていたシェアはわずか25%でしたが、今ではそのシェアが80%にまで上がっています。
つまり、小規模で独立していた農家はどんどん追いやられているのです。
「限られた土地で、たくさんの食べ物を、安い値段で作る。これのどこが悪いんですか?」
全米チキン協議会のリチャード・ロブ氏はそう語ります。
もちろん、安価な肉を買えることはありがたいことです。
でも、その代償は一体何なのでしょうか?
このドキュメンタリーでは、大手企業と契約している生産者たちの声にも光を当てています。
ヴィンス・エドワーズは、アメリカ最大級の食肉会社タイソンで鶏の飼育を行っています。かつてはタバコ農家でしたが、業界への厳しい批判により廃業を余儀なくされ、今ではタイソンの契約農家として収入を得られることに感謝していると語ります。働き口があること、家族を養えることはもちろん大きな安心です。
でも、こうした大企業が本当に従業員の健康や幸せを気にかけているのでしょうか?

作品の中では、パデュー社と契約するキャロル・モリソンも紹介されます。彼女は、会社からの厳しい態度に苦しみながら働いています。タイソンやパデューのような企業は、運営費をまかなうために農家に借金をさせる仕組みを取っています。その結果、効率を最優先する体制が労働者や動物にとって非常に危険な環境を生み出しています。
一般的な生産者は約50万㌦(7250万円)の借金を抱えながら、年収はたったの1万8千㌦(260万円)程度にとどまります。
では、「農業」と「大量生産」の違いとは、一体なんなのでしょうか?
リチャードのような人々は、鶏を「動物」ではなく「食べ物」として見ています。だからこそ、より効率よく手に入る鶏を作り出す方法を模索するのです。企業は、鶏の肉量を増やすために遺伝子操作を行い、筋肉と内臓のバランスが不自然になってしまっています。
ここで、私自身の葛藤があります。私は肉が好きで、毎日ではないけれど、たまにチキンやビーフを楽しんでいます。
そんな私が、ただ利益を求めて働いている人たちを批判する資格があるのでしょうか?結局食べるのなら、安ければどう飼育されているかなんて関係ないのでは?
でも、私たちが普段気にしない“別のコスト”こそが、長い目で見て私たち自身を苦しめることになるのです。
ご存じですか?2000年代以降に生まれた子どもたちの3人に1人が、将来的に2型糖尿病になる可能性があると言われています。 これはかつてなかったことです。政治的な話にしたくはありませんが、食のコントロールには政治が大きく関わっています。
私たちを守るはずのFDA(アメリカ食品医薬品局)やUSDA(アメリカ農務省)のような組織は、大規模工場の元関係者たちによって運営されていることが少なくありません。こうした監視体制の甘さにより、多くの屠殺場では管理が行き届かず、病気が蔓延する温床となっています。
有名なE.コリ(腸管出血性大腸菌)の集団感染を覚えている方も多いかもしれません。あの感染拡大は、牛に本来の草ではなく、コスト削減のためにトウモロコシを与えたことが原因でした。その結果、子どもを含む多くの命が失われました。 命の重みが、大量生産の“便利さ”によって軽く見られていいはずがありません。

「私たちは、食べ物というこれほど大切なものについて、あまりにも無関心で無知になってしまったのです」
そう憤りを込めて語るのは、ポリフェイス・ファームのオーナー、ジョエル・サラティンです。 彼は倫理的な農法を実践し、働く人や動物たちを敬意をもって扱うことを大切にしています。
彼の言う通り、健康的な食事は「特権」ではなく「権利」であるべきです。
私自身、食べるという行為を「大切な営み」として考えたことはありませんでした。でも、よく考えてみると本当にそうなんです。私たちは企業を信じて、その食べ物を体の中に取り入れているのです。体は一つだけ。命も一つだけ。
だからこそ、大切にしたいし、できる限り良いものを取り入れたい。その願いに、値札がついてはいけないのです。
ここで改めて問いかけたいと思います。
「農業」と「大量生産」の違いは何でしょうか?
農業は、人と人とをつなぐ営みです。
家族が食卓を囲むこと。
良質な食べ物で幸せを届けること。
農業は“人”が中心にあるものです。
けれど、工業型の食品産業はそのつながりを奪ってしまいました。
そこにあるのは、あくまで「利益」が最優先だからです。
安価な肉の裏に、労働者への搾取があってはいけない。
小さな農家が追い出されるような仕組みであってはいけない。
そして何より、私たちの「健康」が犠牲になってはいけないのです。
しかし現実として、健康的な食事は高くつくようになってしまいました。
「誰もが手に入れられるべき」と言っても、それは理想論に聞こえてしまうかもしれません。だからこそ、私たちは食品業界そのものを見直す必要があります。
長い間、大企業は私たちが「何を食べるべきか」「何を食べるべきでないか」を決め、トウモロコシや大豆など特定の作物に依存する市場を作り出してきました。
でも、私たち消費者にも力はあります。
自分の体に何を入れるかを決めるのは、自分自身です。
少し高くても、より良い食材を選べる余裕があるなら、そうすることには意味があります。
大手企業がつくる肉を買わないという選択をする人が一人増えるたびに、
「私たちはそのやり方に賛成していない」という意思表示になるのです。
がん治療中の脱毛に向き合う方法〜心と体をケアするために〜

がん治療と脱毛について
がん細胞のように急速に分裂する細胞を標的とする治療は、毛包のような他の急速に分裂する細胞にも影響を与えることがあります。ただし、すべてのがん治療が脱毛を引き起こすわけではありません。髪が抜ける可能性や、その程度については担当医に相談してください。
化学療法と脱毛
受ける化学療法の種類によっては、完全に脱毛する場合もあれば、髪が薄くなる程度、またはまったく影響がない場合もあります。
化学療法は通常、サイクルを繰り返して行われ、脱毛の程度は使用する薬剤の種類、用量、治療スケジュールによって異なります。
脱毛は頭皮だけでなく、眉毛、まつ毛、胸、脇の下、顔、陰部など、体のさまざまな部位で起こる可能性があります。
化学療法では、頭皮に近い部分で髪が切れるように抜け落ちることもあり、枕やシーツ、または髪をとかしたり洗ったりしたときに抜け毛に気づくことがあります。
脱毛の直前には、頭皮に違和感やかゆみを感じることもあります。治療開始から2〜3週間ほどで脱毛が始まるのが一般的で、短期間(数日間)で大量に抜けることもあります。まつ毛や眉毛は、抜けるまでに少し時間がかかることもあります。
クールキャップ(冷却キャップ)
クールキャップ(頭皮冷却装置)は、脱毛をある程度抑えられる場合があります。血管を収縮させ、頭皮への薬剤到達量を減らすことで効果を発揮します。
ただし、すべての治療施設で提供されているわけではなく、コストが高い場合や効果が限られる場合もあります。また、すべての人に適しているわけではないため、使用を希望する場合は医療従事者に相談してください。
放射線治療と脱毛
放射線治療を受けている部位に毛が生えている場合、その部分の毛が治療中または治療後すぐに抜けることがあります。
治療終了から数週間以内に毛が再生し始めることもありますが、場合によっては永久的な脱毛になることもあります。
脱毛は、あくまで治療を受けている部位に限定されます。たとえば、頭部に放射線を当てている場合は頭髪が、脇の下や胸部に当てている場合は、その部分の体毛が抜けることが予想されます。

脱毛への対応
脱毛によって怒りや不安など、さまざまな感情が湧き上がることがありますが、それは非常に自然なことです。
外見に対する意識が高まる人もいれば、思っていたほど気にならないと感じる人もいます。
コントロールを取り戻すために
脱毛の可能性に備え、気持ちを整理し、対策を立てておくことは助けになります。
- 治療開始前に髪を短くカットして、少しずつ変化に慣れる。
- 段階的に髪を短くするか、抜け始めたタイミングで思い切って坊主にする。
- 周囲の人がどう反応してよいかわからないこともあるので、気まずい場合は「健康のために治療を受けていて、その副作用なんです」と簡単に説明する。
- 子どもが不安を感じている場合は、やさしくサポートする。
- がん患者向けの外見ケアプログラム「Look Good Feel Better」も活用できます。
髪と頭皮のケア
脱毛後は以下を心がけましょう:
- 無香料のローションや保湿剤で頭皮をやさしくマッサージし、乾燥やかさつきを防ぐ。
- 帽子、スカーフ、日焼け止めで頭皮を紫外線から保護する。
- ポリコットン、コットンサテン、バンブー素材など、肌触りのよい枕カバーを使用する。
- 柔らかい帽子やターバンで頭を保温する。
- 脇毛が抜けた場合、香料入りのデオドラントは避ける。
髪が細くなり頭皮が敏感な場合は:
- やさしいシャンプーとコンディショナーを使う。
- 柔らかいブラシでそっと髪をとかす。
- 自然乾燥、または冷風モードでドライヤーを使う。
- ホットカーラー、ヘアアイロンなど高温の器具は避ける。
髪染め、ジェル、ムース、パーマ液などの刺激の強い化学薬品も避ける。

ウィッグとヘッドウェア
脱毛後にウィッグ、帽子、スカーフ、ターバンを選ぶ人もいれば、特に隠さないという選択をする人もいます。
大切なのは、自分が一番心地よく、自信を持てるスタイルを選ぶことです。
- 柔らかい帽子やターバンは快適でおすすめです。
- 広いつばの帽子は日焼け対策にも効果的です。
- スカーフは頭をしっかり覆える長さのものを選びましょう。コットンや軽量ウール、混紡素材が最適で、ナイロンやシルクは滑りやすいので注意が必要です。
- スカーフやターバンは、さまざまなアレンジが可能です。
治療後
脱毛は通常、一時的なものです。
- 化学療法後は、1か月から6週間以内に産毛が生え始めることが多いです。髪は28日ごとに約1cm伸び、治療終了から4〜12か月でしっかりとした髪が戻ってくるでしょう。
- 放射線治療後も、数か月以内に髪が生え始めるのが一般的ですが、受けた放射線量によって回復具合に差が出ることもあります。高線量の場合、髪が完全に戻らず、部分的な脱毛が残ることもあります。
再び髪が生え始めたとき、以前よりもカールしていたり、太さや質感が変わったり、色が異なることがあります。
美容師に相談すれば、薄毛対策や再生中のヘアケアのアドバイスを受けられるでしょう。
また、部分的な脱毛であれば、ヘアスタイルを工夫することでボリューム感を出すことも可能です。ヘアピースを使うのも一つの方法です。頭皮が敏感な場合は、化学薬品よりもヘナや植物由来の染料を使うことをおすすめします。
https://www.cancervic.org.au/cancer-information/treatments/common-side-effects/hair-loss
【ハミングが届けるポジティブニュース】スイスの奇跡:かつて汚染された川が、ヨーロッパで最も美しい都市の遊泳スポットに!

「地球に優しい取り組みは、未来を確かに変えていく」——そんな希望に満ちたストーリーが、スイスから届きました。
不安や問題が絶えないように感じる現代。でも、そんな今だからこそ、世界のどこかで生まれている「静かで確かな前進」に目を向けてみませんか。ハミングでは、そんな「ポジティブなニュース」を大切に届けていきたいと考えています。
今日は、“汚染の川”が“真っ青な美しい川”に変わった、スイスの取り組みをご紹介します。
スイスでは過去数十年にわたり水質改善が行われてきました。その成果はまさに驚くべきもの。現在では、スイスの川や湖はヨーロッパでも指折りの「都市型スイミングスポット」として注目され、多くの人々が水辺でのひとときを楽しんでいます。
ただ、ここに至るまでの道のりは決して平坦ではありませんでした。
汚染と病気に苦しんだ1960年代
1960年代のスイスでは、水質汚染が深刻な社会問題でした。当時は下水処理への投資が少なく、多くの都市や村では生活排水がそのまま川や湖に流されていたのです。美しいはずのジュネーブ湖も、藻が一面に広がり、魚が浮かんで死んでいる——そんな光景が日常でした。
極めつけは、1963年に(スイス南部の村)ツェルマットで発生した腸チフスの集団感染。原因は未処理の下水が飲料水に混入したこと。複数の死者が出て、数百人が病気になりました。この悲劇がきっかけとなり、国を挙げた水質改善プロジェクトが始まったのです。

Soldiers arriving in Zermatt to help out with the typhoid epidemic in 1963. Photograph: Ullstein bild/Getty Images
未来のための投資と市民の声
それからというもの、スイス政府は巨額の資金を下水処理と水質保全に投入。1965年には、下水処理施設につながっている人口はわずか14%でしたが、今ではなんと98%の人々がきちんとした処理を受けた水環境に暮らしています。
「スイスの人々にとって、水の質はとても大切なものです」と語るのは、環境工学会社ホリンガーの廃水処理責任者ミヒャエル・マトル氏。「私たちは、スイスを流れる水を汚さないように細心の注意を払っています」。
現在、スイスは一人当たり年間191ユーロ(約3万円)を水質浄化に使っています。これは例えばイギリスの98ユーロと比べても、実に2倍近い額です。スイスは、国として「きれいな水」を守ることに本気であることがわかります。
「薬剤」まで除去する次世代の処理技術
2016年からは、人体から排出される薬剤(抗うつ剤、糖尿病治療薬や抗生物質など)による水質汚染にも注目が集まっています。これらは従来の下水処理では除去が難しいため、スイスでは「活性炭フィルター」を使った新技術が導入され、なんと80%もの薬剤を除去することが可能に。
この技術を支えているのは、まるで人間の胃腸のように「バクテリアの力」で水中の有機物を分解する高度な施設です。それでも、メディアで「永遠の化学物質」とも呼ばれるPFASなどは、依然として残ってしまうのが課題。そのためスイスは現在、こうした残留物質に対する法整備に取り組んでいます。
世界各国がスイスから学ぶ時代へ
こうしたスイスの取り組みは、隣国にも大きなインパクトを与えています。ヨーロッパ諸国は、スイスの先進技術と運用体制に注目しており、現在では10,000人以上が暮らす地域の下水処理施設に「薬剤除去」の義務化を検討中。スイスが実現した「きれいな水」のビジョンが、いまやヨーロッパ全体に広がろうとしています。

“水辺のある暮らし”が、未来を変える
そして今、スイスの川や湖では、春先の冷たい時期から人々が水辺で楽しむ風景が広がっています。通勤前のひと泳ぎ、家族連れの週末ピクニック、年配のご夫婦の水中ウォーキングなど、それぞれのスタイルで水辺の暮らしを楽しむ姿は、まさに「自然と共に生きるライフスタイル」のお手本です。
この変化は、ひとつの技術革新や政策だけで起きたわけではありません。住民の声、政治の意志、専門家の知恵、そして「未来のためにできることを今やろう」という市民の想いが、長い年月をかけて形になったといえるでしょう。
地球に優しい行動は、決して遠い話ではありません。スイスの川が教えてくれるのは、「環境の奇跡」は、今日から私たちにも始められる、ということだと感じます。
今回ご紹介したトピックは、小さな希望の光のようなもの。
世界にはまだまだ素敵な出来事がたくさんあるのだと、改めて感じさせてくれます。
これからもハミングは、そんな前向きなニュースを丁寧に拾い集めていきます。
参照記事:https://www.theguardian.com/environment/2025/mar/17/from-sewage-and-scum-to-swimming-in-blue-gold-how-switzerland-transformed-its-waterways-aoe?utm_term=67dfcda5f324cd8f0de1daab781f9366&utm_campaign=TheUpside&utm_source=esp&utm_medium=Email&CMP=upside_email
「フェスティバル・ファッション」って、一体どういう意味?

少し過去に戻って、史上最も有名な音楽フェスのひとつ――1969年のウッドストックを思い出してみましょう。ニューヨーク州北部で開催されたこの3日間のイベントは、写真によって永遠に記録され、フェスでのファッションの中でも、特に大きな影響を与え続けているスタイルとして知られています。
フレアパンツ、バンダナ、ビーズのヘッドバンド、フリンジジャケット、クロップトップ、デニム、かぎ針編み、タイダイ柄、そしてサイケデリックなプリント……当時は、政治的メッセージと抗議運動が根付いたヒッピー文化を象徴するスタイルでしたが、現代ではより広く「フェスに行く人たち」のファッションとして定着し、毎年夏の定番トレンドにもなっています。
その影響は、2000年代初頭のグラストンベリー・フェスティバルでのケイト・モスのスタイルにも見られ、さらにはヴァネッサ・ハジェンズやカーダシアン一家が披露したファッションにも受け継がれています。彼女たちは、セレブやインフルエンサー主導の新たなフェス・ファッション時代を築いたのです。
北半球のフェスティバルシーズンの幕開けを告げるコーチェラ(アメリカ最大の音楽&アートフェス)が4月に開催されると、ブランドたちはこぞって「フェス・コレクション」を展開します。そしてその多くは、やはりウッドストック時代のファッションをどこかで感じさせるのです。
Nudie Jeans
Nudie Jeans(ヌーディージーンズ)は、100%オーガニックコットンを使用した衣類をデザインし、その製造過程もしっかりと公開しています。また、無料の修理サービスがあり、中古商品の再販や、着古したアイテムのリサイクルも行っています。

MUD Jeans
オランダ発のデニムブランド、MUD Jeans(マッドジーンズ)は、サステナビリティをブランドの核に据えています。修理サービスに加え、ジーンズを最長1年間レンタルできるサービスも提供しています。GOTS認証のオーガニックコットンと、消費者から回収したリサイクルコットンを組み合わせて使用し、屋外で過ごすのに最適で、しっかりとしたデニムパンツを展開しています。

Christy Dawn
フェスティバルの夜は冷え込むこともあり、Christy Dawn(クリスティ・ドーン)のニットカーディガンは、暖かく過ごすのにぴったりです。このブランドは、農地を再生させる取り組みを支援するだけでなく、再生型素材を使用した衣類づくりを行っており、購入することでサステナブルな未来への一歩を応援できます。

All The Wild Roses
https://allthewildroses.com/
All The Wild Roses(オール・ザ・ワイルド・ローゼズ)は、夢見る人や変化を起こしたい人のための自由な精神を体現するオーストラリアのブランド。製品には最大50%のデッドストック生地(余剰在庫)を使用しており、高品質で長く愛用できるアイテムを提供しています。

Afends
デニムショーツはフェスティバルの定番アイテム。Afends(アフェンズ)のオーガニック&リサイクルコットンを使用したショーツは、イベントが終わった後も別のイベントで使えるでしょう。オーストラリア発のこのブランドは、オーガニックヘンプファッションの先駆者であり、再生可能エネルギーを導入して環境問題にも取り組んでいます。

Veja
https://www.veja-store.com/ja_jp/
Veja(ヴェジャ)はフランス発のブランドで、フェアトレードの靴をデザインしています。GOTS認証コットンなど、環境負荷の少ない素材を使用し、綿花栽培の農家やゴム採取者には世界市場価格の30〜100%高い価格で報酬を支払っています。また、広告に費用をかけないことで、持続可能な取り組みにより多く投資しています。

Parker Clay
Parker Clay(パーカー・クレイ)はアメリカのブランドで、エチオピアの人々の暮らしを向上させ、搾取のない未来を目指しています。「Ellilta Women at Risk」プログラムと提携し、売春の仕事をやめたい女性たちに安定した収入と安全な職場環境を提供しています。また、エチオピアの伝統的な技術や素材、スタイルを守ることで、エチオピアがその美しいルーツを保ち続けられるよう支援しています。
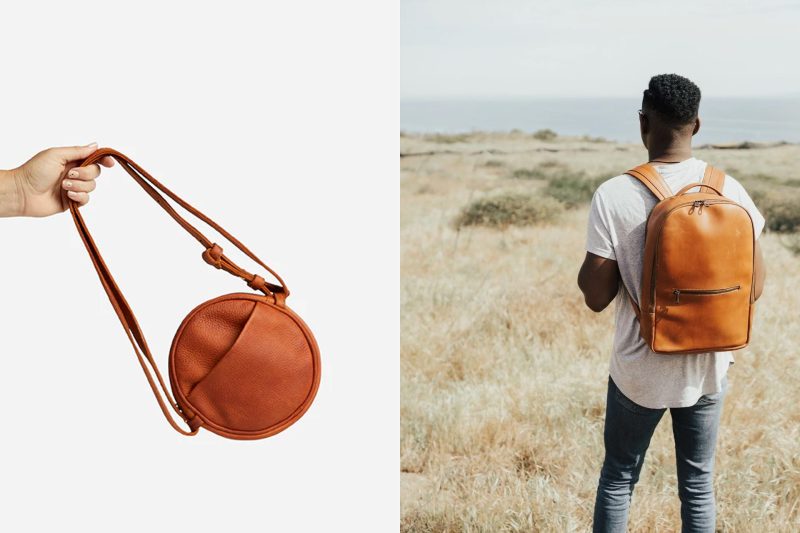
Joyya
https://joyya.com/en-row
Joyya(ジョイヤ)は、インド・コルカタの地域社会において良質な雇用を創出することを目的としたオーガニックアパレルブランドです。もともと2001年にコルカタで始まったこのブランドは、ニュージーランドを拠点に、極度の貧困や人身売買の終焉を目指し、「機会の火花を灯す」ことを使命としています。3つの企業が統合することで設立され、協力することでより大きな成果を上げようとしています。

Article 22
https://article22.com/
ARTICLE22(アーティクル22)のジュエリーは、すべてラオスで地元の職人によって手作業で作られています。素材には、ベトナム戦争時代の爆弾、飛行機の部品、軍需品、その他のアルミくずがリサイクルされています。このバングルには「愛」という言葉が様々な言語で刻まれており、フェスティバル・ファッションの起源とも言えるウッドストックの精神を象徴しています。

マイクロプラスチックは人間の健康に有害ですか?

この分野に関心を持つ方であれば、大量のプラスチックが自然界に散乱している光景に胸を痛めることでしょう。浮遊するプラスチックの島々、プラスチックをヒナに与える鳥たち、プラスチックの輪に絡まるカメなどの話は、心を痛めます。フロリダ州の沿岸部では、プラスチック製の食器、ストロー、タバコの吸い殻、使い捨ての包装材などが浜辺に打ち上げられ、白い砂浜を点々と汚しているのが日常の光景となっています。
使い捨てのプラスチック製品(ペットボトル、タンポンのプラスチック部分、ビニール袋、食品容器、医療廃棄物、ビーチ用のおもちゃ)や、捨てられたプラスチック製品(サングラス、釣り具など)は、水路の奥深くまで入り込み、海洋環境に甚大な被害をもたらし、野生生物を毒し、その美しさを汚染しています。
使い捨てプラスチックが問題であることは理解していても、それを避けるのは容易ではありません。さらに、プラスチック汚染が野生生物に害を及ぼし、命を奪うことは知っていても、それに対して無力感を覚えることもあります。それでは、この同じプラスチックが人間の健康に与える影響について、どれほど心配すべきでしょうか?
マイクロプラスチックとは何か?そしてその発生源は?
石油由来のプラスチックは、1950年代にその多様性と耐久性が家庭で評価されて以来、広く使用されてきました。現代では悪者扱いされることが多いプラスチックですが、医療やヘルスケア分野など、特定の場面では依然として有益です。プラスチックは革新的で命を救う機器の開発を可能にし、無菌状態を保つ手段にもなりました。
しかし現実として、石油由来のプラスチックは生分解されないので、リサイクルできるプラスチックはごくわずかです。私たちの台所や日常生活でその耐久性が重宝されたのと同じ特性が、今や大きな健康と環境の危機を引き起こしているのです。
プラスチックが自然環境に放出されると、それは溶けたり消えたりせず、永遠に残ります。つまり、大きなプラスチックはやがて小さく砕けていき、それがいわゆる「マイクロプラスチック(MPs)」になります。アメリカ海洋大気庁(NOAA)は、マイクロプラスチックを「5ミリメートル未満の小さなプラスチック片」と定義しています。つまり、鉛筆の消しゴムの先より小さなサイズから、肉眼で見えないほど微細なものまでを指します。
マイクロプラスチックには2種類あります。1つは「一次マイクロプラスチック」と呼ばれ、化粧品、洗剤、おむつ、塗料、医薬品などに添加されるプラスチック粒子です(例:スクラブ洗顔料やボディウォッシュに含まれるマイクロビーズ)。また、合成繊維の衣服からはがれたり、塗料から染み出したりする微小なプラスチック繊維もこれに含まれます。一次マイクロプラスチックは、排水口や洗濯機を通じて下水処理場へ流れ込みますが、そのサイズが小さいためろ過をすり抜け、海へと放出されます。
もう一つの「二次マイクロプラスチック」は、多くの人が思い浮かべるタイプで、大きな使い捨てプラスチックやその他のプラスチック製品が分解された結果として発生します。二次マイクロプラスチックは、リサイクルされずに自然に捨てられたり、海や川へ流されたりした結果、太陽光、塩分、波などの厳しい環境によってどんどん細かく砕けていきます。
どのような形であれ、一度環境の中に放出されたマイクロプラスチックは簡単には消えません。その小さなサイズもあって、水、空気、土壌、そして最終的には食物連鎖にまで簡単に入り込んでしまいます。

人間はどのようにマイクロプラスチックにさらされているのか?
人間は様々な経路でマイクロプラスチックにさらされています。たとえば、空気中に漂うマイクロプラスチックの吸入(文字通り、風の中にも含まれています)、プラスチック製品や合成繊維の衣類との接触、そして摂取などです。
「えっ、プラスチックを食べるなんて気持ち悪い!」と思うかもしれません。もちろん、誰もマイクロプラスチックを食べようとは思っていません。しかし、魚介類や貝類を食べたことがある人は、知らないうちにマイクロプラスチックを摂取している可能性があります。海に存在するマイクロプラスチックの量は非常に多く、海洋生物は常にそれらを摂取しています。人間がマイクロプラスチックを摂取する主な経路は魚介類であり、とくに貝類などの「天然の海のフィルター」ともいえる生物には、ヒレのある魚よりも多くのマイクロプラスチックが含まれているとされています。
マイクロプラスチックは水中に限らず、土壌でも発見されており、土壌の生物多様性や陸上の生態系にも脅威を与えています。土壌中の大量のマイクロプラスチックは水の流れや吸収に悪影響を及ぼし、植物の根付きを妨げ、ミミズのような有益な土壌生物がマイクロプラスチックを餌と間違えて死んでしまう原因にもなります。つまり、土壌中のマイクロプラスチックは、私たちが必要とする食料の栽培を難しくすることで、人間の健康にも影響を及ぼしているのです。
さらに残念なことに、私たちがマイクロプラスチックを摂取してしまう最も一般的な方法の一つは、ペットボトルやテイクアウト用容器などの使い捨てプラスチックです。研究者たちは、1リットルサイズのプラスチックボトルに24万個のプラスチックナノ粒子が含まれていることを確認しました。これらは腸や肺を通過して血流や臓器にまで入り込む可能性があります。

では、マイクロプラスチックは人間にとってどれほど危険なのか?
石油由来のプラスチックが人間に広く使われ始めてから70年以上が経ち、今やプラスチックは文字通り私たちの体の一部になりつつあります。マイクロプラスチックが人間の体内に入り、蓄積されることはすでに確認されています。しかし、私たちがどのようにしてそれを吸収し、代謝し、排出しているのか(あるいはまったく排出できていないのか)は、まだ科学的に明らかになっていません。プラスチックの種類も多様であり、人間が接触する形や量も様々であるため、どの程度が有害で、どんな疾患や病気を引き起こす可能性があるのかといった人間の健康に対する直接的な影響についての包括的な研究はまだ不足しています。
ただし、広範囲かつ継続的にマイクロプラスチックにさらされることが、人間の健康に悪影響を及ぼす可能性が高いということは否定できません。
魚や他の動物を対象とした研究では、マイクロプラスチックが体内に入ると循環系を通じて細胞や組織にまで届くことが示されています。また、「マイクロプラスチック曝露の健康影響に関する研究」では、「マイクロプラスチックが体内に蓄積することで、栄養失調、炎症、生殖能力の低下、死亡率の上昇といった様々な悪影響が確認されている」と報告されています。これと同様のことが、人間の体内でも起きている可能性があります。
さらに懸念すべきは、マイクロプラスチックそのものに加えて、それが吸着しているさまざまな有害化学物質も同時に体内に取り込まれるリスクがあるという点です。poison.orgによると、マイクロプラスチックは重金属、ポリ塩化ビフェニル(PCB)、農薬など、環境中の有害な化学物質を吸収する可能性があるとされています。
マイクロプラスチックは細胞に侵入し、消化器系などの生体機能に影響を与えることで、毒素を体内に運び込む可能性があるため、研究者たちはこれが若年性乳がんや大腸がんの増加に関係している可能性や、その他の疾患を引き起こす媒体となっている可能性についても調査を進めています。さらに、空気中のマイクロプラスチックへの継続的な低濃度の曝露は、呼吸器系や循環器系の疾患につながる可能性もあると考えられています。ただし、これらについても人間を対象とした決定的な研究はまだ不足しています。
私たちにできることは何か?
マイクロプラスチックへの曝露をコントロールし、環境から取り除くことを考えるとこの問題の複雑さが見えてきます。
たとえ全ての人がプラスチックとの接触を完全に避け、魚介類を食べるのをやめ、今後一切プラスチック製品を購入しないとしても、マイクロプラスチックは私たちが呼吸する空気や水源の中に依然として存在し続けます。この問題に持続的な効果をもたらすには、「予防」と「除去」の両面からの多角的なアプローチが必要です。
予防の大きな部分は、新たなマイクロプラスチックが環境中に放出されるのを減らすことです。消費者として、私たちは紙、ガラス、竹、天然繊維の衣類など、より環境に優しい選択肢を購入することで貢献できます。
植物由来の「バイオプラスチック」の開発は、従来の石油由来プラスチックの代替として注目されています。これらは自然に分解されるため、マイクロプラスチックにはなりません。しかし、現時点では製造コストが高く、多くの企業で広く採用されていないのが現状です。とはいえ、実現すれば、従来の合成プラスチックよりも低い炭素排出量で済む可能性があります。
すでに存在するマイクロプラスチックを環境から除去することは困難な作業ですが、期待できる研究や技術も進められています。たとえば、電極を使用してマイクロプラスチックを分解し、無害な水分子に変える技術などが探られています。ただし、このプロセスは高コストで、まだ一般化には至っていません。
2019年には、アイルランドのティーンエイジャーが科学コンテストの一環で「フェロフルイド(磁性流体)」という油と磁性粉末を組み合わせた物質を使い、マイクロプラスチックを磁気で引き寄せて除去するというアイデアを発表しました。このシステムは下水処理施設に導入できる可能性があり、一次マイクロプラスチックの回収に効果的とされています。
ドイツの企業では、シリカ(ケイ素)を水に加え、渦を利用してマイクロプラスチックを水面に集めて回収するという方法も開発されています。さらに、カナダのウォータールー大学の研究者と化学工学教授ティザズ・メコンネンは、熱分解を利用してエポキシ樹脂を活性炭に変えることに成功しました。活性炭はナノプラスチックの除去に有効とされています。

私たち個人や家庭レベルでも、マイクロプラスチックへの曝露を減らし、環境負荷を軽減するためにできることがあります:
- 浄水器を導入する:ほとんどの浄水システムは、飲料水中のマイクロプラスチックを除去または大幅に減少させることができます。
- 空気清浄機を使う、もしくは高性能なフィルターを使ったエアコンシステムを使用する(フィルターは定期的に交換)。
- 魚介類、特に貝類の摂取を控える。
- 合成繊維ではなく、天然素材の衣類を購入する。すでに使用された合成繊維製品をリユースするのも有効。
- バイオプラスチックを使用した製品を選ぶ(例:食品包装、おもちゃ、使い捨て食器など)。
- プラスチック袋の代わりにエコバッグを使う。手で持ち運べる場合は袋を断るのもOK。
- 自宅や外出先で使える「マイ食器セット」を用意する(金属のフォーク・スプーン、布ナプキン、再利用可能なストローなど)。
- ペットボトルを避ける。使い捨てであっても、ガラス・アルミ・ステンレス製のものを選ぶ。
- 食品の保存には、プラスチック以外の方法を使う。
- 使い捨てプラスチックを使わない
最後に
日常生活の中で完全にプラスチックやマイクロプラスチックを避けることは、現実的には難しいでしょう。それでも、自分自身や他人がこの問題を認識し、よりよい選択をしようと努力しているのなら自分をほめてあげるきです。たとえ今回の提案のうちひとつだけでも取り入れられたなら、それは前向きな一歩です。
【ハミングが届けるポジティブニュース】ミサイルが音楽に変わるなんて。世界にはまだ、優しさと希望がある

最近、朝の支度をしながらニュースを聞くのが日課になっています。世界のトレンドや日本の動きを知っておきたいと思う反面、フジテレビの不祥事やトランプ氏の関税の話題など、心がざわざわするニュースが多く、「この先どうなるんだろう」と不安になることも。
私にも小さな子どもが二人いるので、将来を思うと胸が締めつけられるような気持ちになることもあります。
でも実は、そんな不安に埋もれてしまいそうな今だからこそ、そっと心に灯をともしてくれるような“希望のニュース”が世界にはたくさんあるんです。
ハミングでは、「ポジティブなニュース」をもっともっと届けたいと思っています。
それは、世界がちゃんと良い方向に進んでいる証かもしれないから。
今日は、“戦争の道具”を“平和の音”に変えた、ウクライナの音楽家の物語をご紹介します。
重たいテーマのように思えるかもしれませんが、きっと読んだあとに、やさしい気持ちになれるはずです。
戦争のミサイルが、「希望の楽器」に変わるまで
この話の主人公は、ウクライナの作曲家ロマン・フリホリウさん。
彼はある日、2022年に自分の国に落ちた未爆発のロシア製ミサイルを目にしました。普通なら「恐怖」や「怒り」の象徴ともいえるそのミサイルに、彼は別の意味を込めたのです。
なんと爆薬を取り除き、チェロのような弦楽器に作り変えてしまったんです。
独特の響きを持つその楽器は、「地獄の矢の声(Hell’s Arrow Voice)」「生まれざる者の歌(Song of the Unborn)」という、戦争の悲しみと再生をテーマにした曲を奏でるために生まれました。
「これは私にとって単なる楽器ではありません。この楽器は、ウクライナの人々が経験した恐怖を象徴しています。この楽器に織り込まれたストーリーと、私たちの苦しみが、この楽器を特別なものしているのです」と彼は語ります。
「痛み」も、「未来への祈り」も、音楽に込めて
この楽器は2024年の秋、イギリスで開かれたチャリティディナーで初めて演奏されました。
その場には、ウクライナからイギリスやアメリカに避難し、勉強を続けている若者たちの支援を願う人たちが集まっていました。
彼の演奏には、キエフのオーケストラ「カメラータ・キエフ」も参加し、会場は静かな感動に包まれたそうです。
「ウクライナの若者たちに教育の機会を与えるため、戦争の遺物を使っています」
「この楽器をいつか博物館に展示して、世界に“ウクライナは強い国で、残酷な歴史を乗り越えた”と伝えたいんです」
フリホリフさんのそんな言葉が、とても印象的です。

Blenheim Palace
子どもたちの未来のために、私たちにできること
この取り組みは、ウクライナの若者たちが将来、国を立て直す力になれるようにという願いから始まっています。
チャリティイベントを支えた「オックスブリッジ財団」の共同代表ヘレン・クラークさんはこう話します。
「今、この瞬間にも苦しんでいるウクライナの人々がいます。でもウクライナはこの紛争を克服するでしょう。私たちは、ウクライナの若者たちが、国の再建のために必要な支援を受けられるようにしたいんです」
戦争という重い現実を前にしても、人は立ち上がることができる。 そして誰かの力になりたいと思う気持ちは、ちゃんと世界に届いている。そんなことを、このニュースは静かに教えてくれると感じます。
小さな希望を見つける目を、私たちは持っている
ニュースに心を痛める日々が続いても、私たちには「いい話に目を向ける力」もあるはずです。そしてそれは、自分や家族、社会を大切に思うやさしい気持ちの表れだと思います。
今回ご紹介したような出来事は、世界が少しずつ良い方向へ進んでいるサインかもしれません。
これからもハミングでは、そんなポジティブなニュースをお届けしていきます。
「世界って、捨てたもんじゃないな」
そんなふうに思える瞬間が、きっと誰かの心を救うと信じて。
_________________________________________________________________________________
参照記事:https://www.bbc.com/news/articles/ckgmp1n982ko
https://www.positive.news/society/deadly-russian-rocket-is-transformed-into-musical-instrument-of-hope/
本当に”体に良い食事”のレシピはSNSではなく、あなたの中にある

We are what we eat ―――― 「私たちの体は、私たちの食べるものでできている」
このことばを聞くたび、本当にその通りだなとしみじみ感じてしまいます。そして、毎日何を食べるかって、実は“自分をどう扱うか”に直結しているなとも思うんです。
今回はそんな視点から、私の食との向き合い方と、ちょっと偏った食への愛を綴ってみます。
食べることは私にとって最重要事項
日々の生活において、私が一番重きを置いているものこそが、毎日の「食事」です。
日常だけでなく旅先でも、観光スポットよりもまず先にグルメスポットばかりリサーチするタイプです。
美味しいものを食べているときが一番幸せ。
美味しいものを食べれば機嫌が直る。
美味しいものをできるだけたくさん食べてから死にたい。
そんな、常に食べることばかり考えている、食への執着100%な人間なのです。
だって、美味しいものの力ってすごいじゃないですか。
まず味、食感、見た目、香り、調理の音、五感を一気に満たしてくれますよね。
そして、舌で味わって体に取り込んで、ただ満腹感を得るだけではなく、「あぁ、美味しい~~!」ってにっこりしている時間に、心まで満たされていく。
万能薬すぎませんか?

もちろん、どうしても忙しくて適当に済ませることもあります。
でもやっぱり、たとえばコンビニで「どれもそんなにそそられないけど時間がないし…」となんとなく手に取ったものは、いくら健康そうなメニューでもイマイチ満足しないんですよね。
お腹はたしかにふくれたはずなんだけど、なぜか食べた気にならないというか、脳と体がちぐはぐというか。
もっと悪いときは、体がむしろだるくなることもあります。
食べ物ってエネルギーになってくれるはずなのに、鉛を飲み込んでしまったのではないかというくらい、逆に体から精力が奪われる。
だから、私は毎食妥協したくないんです。
中途半端に食べて心が満たされないなら、空腹を募らせるほうが良い。
ちゃんとお腹を空かせて、本当に食べたいものを口と胃と心と…全身で楽しむ。それが何よりも幸せなのです。
食べたものが自分を作るって、単に栄養面の話だけではなく、こうした精神面も大きいと私は思います。
何を食べるべきかは体に聞く
そんな、食へのこだわりが強い私ですが、何もとにかく量を食べたいわけではありません。
たしかに「胃袋があと5個くらいあればいいのに…」と思ったことは人生で多々ありますが、大切なのは量より質。
体だけでなく心まで満たしてくれる食事なわけです。
だから、何を食べるか決めるときは必ず「自分の身体」に聞いています。
「何を食べようか~どんな気分かな?」といろんなメニューを脳内でシャッフルカードしながら、自分の体に聞く。
ピンとくるカードにあたるまで、ひたすら自分に問うのです。
例えば、朝起きた時。
半分寝ぼけながらも、頭の中で「どうする?パン食べたい?ごはんの気分?なんか違うよね…作るのもめんどくさいし…」と語りかけ、
「あ、あれだったら食べれるかな?うん……うんうん、いいかも!食べたい!」と、頭の中でピースがハマった瞬間に、急にお腹がちゃんと空き始めて体も頭も起きはじめるんですよね。
仕事中の間食なら「めちゃくちゃ頭使ったから、さすがにチョコオールドファッションとコーヒーのコンボをキメたい」とか、「今の私、絶対塩おにぎりが一番ウマい体だ!」とか。
夜ごはんなら「今日のお腹の空き具合だと、ガッツリこってり食べちゃいたいな、でも後味はさっぱり系がいいからトンカツをポン酢で食べるか!」とか
「いや、朝ごはんっぽいけど今日は白米を漬物でかきこみたい、しかも白菜の漬物!」とか、かなり具体的に思い浮かべます。
そして、自分の体に聞いた通りのものを食べると、これがめちゃくちゃに美味しい。
そのメニューがたとえ素朴な一汁一菜でも、ジャンキーな揚げ物でも一緒。
欲しいものは、心と体がちゃんと知っているんですよね。
今の時代、何が健康にいいとか、これは美肌に効くとか、腸活にはこういう栄養素が必要とか、いろんな情報があふれています。

しかも忙しい現代人には、週末に作り置きしたおかずを、計画的に平日消費したり、いっそメニューを固定化して栄養も調理も最効率化!みたいなSNS投稿も刺さりますよね。
私も「なるほど…」と納得はするんですが、いざ、毎食の選択がそういう外部の情報に引っ張られると、なんだか食事にワクワクしなくなるんですよね。
なんなら、体もあまり健康になった気がしない。
それもそのはず、と私は思えて仕方がありません。
だって、私たちの体の状態は、日々微妙に違うじゃないですか。
内部のコンディションもあれば、外部からの刺激を受けて変化したりもする。一日として全く同じ状態というのはあり得ないですよね。
だとしたら、その日その時、体が必要とする食事だって変わってくると思うんです。
たとえ理論上、最高に栄養バランスが良い食事でも、体の声を聞いたものでないのなら、きっと体だってその食事をスルーして、せっかくの栄養も吸収してくれない。
一方、一見栄養バランスはイマイチそうでも、ちゃんと自分の体に聞いたメニューなら、それを食べれば心も体もハツラツになる。
そんな気がしています。
本当の意味で体に良い食事のレシピは、SNSじゃなくもっと身近、あなたの体が知っているんです。
料理の時間も食事の一部
だから、私は作り置きをあまりしません。
せいぜい作っても次の一食分まで多めに作るとか、日持ちやリメイクが効くおかずを1、2品ほどです。
その理由は、ここまでお伝えした通りです。
休日の午前いっぱい使って頑張って作っても、明日にはそのメニューの気分じゃなくなっている、そんなことがザラにあるからです。
それでも痛むからと作り置きを消費することが義務になった瞬間、ますます食べたくなくなって、何日か後にイヤイヤ口に詰め込むか、食材に謝りながら廃棄するか…
そういうことが重なったので、作り置き生活は諦め、その日、食べたいと思ったものを、その場で作る生活にシフトしました。

もちろん、めちゃくちゃめんどくさいです。毎回ちゃんと自分の体に聞くことのデメリットは、確かにここにあります。
唐突に手作り餃子が大量に食べたくなって、その材料だけスーパーに買いに行かなきゃいけない、しかも包むのに時間もかかる、みたいなことが多々起こります。
最初は、それがとても非効率に思えて「いやいや、次の買い出しまで我慢」と抑え込むこともあったのですが、最近、「いっそその調理の過程すら楽しんでしまえばいいのでは?」と思うようになりました。
実際、体が本当に欲するものを作っているときって、気分もちょっと上がるんですよね。
副菜用の野菜を切りながら「うんうん、いい感じかな~?」と、主菜の火の通り具合を耳で感じたり、「は~いい匂い~早く食べたい!」と蓋を開けてあふれ出た湯気を胸いっぱい吸いこんだり。
時間も手間もかかって、非効率なことに変わりはないんだけど、なんだかんだ毎日楽しんでしまうんです。
自分の体にちゃんと耳を傾けているということが、自己肯定感も高めてくれているのかもしれません。
メニューを考えるときも、作るときも、食べるときも、ずっとそこに意識をフォーカスさせていて、なんだか知らず知らずのうちにマインドフルネスに食事を摂るようになっているのかもしれません。
親の心子知らず
こんな風に食べることが大好きな人間に育ったのは、昔から母が私に「ちゃんとしたものを食べさせる」ことを頑張ってくれていたからかもしれません。
ちゃんと栄養のある美味しいものを、私にたくさん食べさせたいと品数を増やし、新しいメニューにもよくチャレンジしてくれていました。
そんな母の口癖は「女の子は美味しいものを食べとかないと、旦那さんに作ってあげられないからね」。
でも母さん、ごめん。
美味しいものをたくさん食べさせてもらった私は今、日々自分のためだけに料理してるよ!
性生活の改善ヒント:セックスで「自分が本当に楽しめること」を見つける方法

満足のいく性生活を楽しむための第一歩は、「自分が何を心地よいと感じるのか」を知ることです。相手も手がかりがなければ、あなたを満足させるのは難しいもの。とはいえ、多くの人が「自分は何が好きなのか、どうされたいのか」がわからないまま過ごしています。その背景には、文化的なタブーや“性にまつわる恥ずかしさ”が関係していることもあります。
では、自分の「好き」をどうやって見つけていけばいいのでしょう?
ここでは、性生活の改善のヒントとして、自分の快感をもっと深く理解するためのアイデアと、自分に問いかけてみたい質問をご紹介します。
おすすめ記事 ▶ 性欲を抑えるにはどうすればいい?具体的な方法とデメリットについても
ベッドルームで「自分の好き」を見つける実践的なヒント
1. エロティカ(官能的な作品)を読む・観る
「エロティカ」とは、性的に明示的な文学作品や芸術作品のことです。これは、性的な興味を一人で、またはパートナーと一緒に探求するのに役立つツールになります。エロティカには、小説、短編、音声作品、イラストなどさまざまな形式があります。エロティカを探索し、自分がどのような内容に興奮するのかを知ることで、セックスにおいて何を楽しめるかを把握しやすくなります。
2. 自分の体を探求し、マスターベーションをする
パートナーと試す前に、まずは自分自身の体を意識的に触れて探求してみましょう。それは、性器だけでなく、全身を含めた試みであるべきです。例えば、優しいタッチと強めのタッチを試してみたり、自分が「好きなはず」と思い込んでいることを一度手放して、自由に探求してみたりすることが大切です。また、マスターベーションの方法を変えてみるのも良いでしょう。たとえば、狭い範囲への刺激と広い範囲への刺激を試したり、セックストイを使用したり、座った状態と横になった状態を比べたりすることで、新しい発見があるかもしれません。
3. 信頼できるパートナーと実験する
パートナーとのセックスで何を楽しめるかを知る最善の方法は、実際に試してみることです。ただし、自分の好奇心や不安、迷いについて話し合える信頼できるパートナーを選ぶことが重要です。この話題を持ち出す際は、相手が落ち着いて話せる状態であるかを考慮し、考える時間を与えましょう。もし試すことに合意したら、明確な期待値を設定し、「セーフワード(中止の合図)」を決めておくのも良いでしょう。実験が終わった後は、時間をおいて振り返り、また試したいかどうかを話し合いましょう。
ぜひ自分に問いかけてほしいクエスチョン
セックスに対する自分の感情を理解することは、欲求を明確にするのに役立ちます。以下の質問を自問してみることで、自分が求めるものをより深く理解できるかもしれません。
- 自分の体のどの部分に触れられると特に気持ちいいか?
- パートナーに触れられたくない部分はあるか?
- セックストイや小道具をセックスに取り入れることに対してどう感じるか?
- 自分の性的トラウマについて考慮すべき点はあるか?
- 「ダーティートーク(卑猥な言葉)」は好きか?
- 主導権を握りたいか、それともリードされるのが好きか?
- 受ける刺激と与える刺激、どちらをより求めているか?
- セックスを通じてどのような感情を味わいたいか?(愛されていると感じたい、セクシーに感じたい、力強さを感じたい、支配されたいなど)
- どのような性器への刺激が好みか?
- 挿入を望むか?
- セックスの後にどんなケア(アフターケア)があると心地よいか?
まとめ
性生活の改善ヒントのひとつは、「自分がベッドで何を楽しめるのか」を知ること。自己探求や振り返りを通して、自分に合った方法を見つけてみましょう。
性的なトラウマや恥の意識が「自分の好みがわからない」ことにつながっている場合もあります。焦らず、少しずつ自分を知っていくプロセスを大切にしてくださいね。
理想の自己 vs 義務の自己:バランスの取れたアプローチ

人間は自然に自己成長を求め、自分のベストを目指す傾向があります。この「より良くなりたい」という欲求には、しばしば2つの異なる動機が伴います。それが「理想の自己」と「義務の自己」です。「理想の自己」は自分がなりたい姿を、「義務の自己」は自分がなるべきだと感じている姿を指します。この動機は私たちの行動に大きな影響を与える可能性があり、それを理解することは自己成長と幸せのために重要です。
理想の自己
理想の自己とは、私たちがなりたいと願うベストな自分です。それは、達成したい目標や夢を反映したものであり、私たちに成長や努力を促す強い原動力となります。
研究によると、理想の自己に意識を向けることは行動に大きな影響を与えることがわかっています。例えば、理想の自己を意識するよう促された参加者は、健康的な食生活や定期的な運動など、より良い行動を取る傾向がありました(Kiviniemiら, 2011)。また、理想の自己に焦点を当てることで、目標に向かい粘り強く行動することが研究でもわかっています(Oysermanら, 2006)。
神経科学の研究では、理想の自己は前頭前皮質(計画や目標設定に関与する脳領域)と関連していることが示されています。ある研究では、参加者が理想の自己を想像しているとき、現在の自己を想像しているときよりも前頭前皮質の活動が高かったと報告されています(Northoffら, 2006)。これは、理想の自己が自己成長を促す重要な要素であることを示しています。
義務の自己
義務の自己とは、「こうあるべき」と自分が感じている姿です。それは、期待や責任を背負った「こうでなければならない自分」を表します。義務の自己は、責任を果たすための強い動機にもなります。
一方で、義務の自己がネガティブな影響を与えることもあります。自分が期待に応えていないと感じると、人は罪悪感や恥を感じやすくなり、結果として回避したり先延ばしをするなど逆効果の行動を取ってしまうこともあります(Carver & Scheier, 1998)。
神経科学的には、義務の自己は扁桃体(恐怖や不安などの感情処理に関与する脳領域)と関連しています。ある研究では、義務の自己を想像しているときの方が理想の自己を想像しているときよりも扁桃体の活動が高かったと報告されています(Northoffら, 2006)。これは、義務の自己がストレスや不安の原因となり得ることを示しています。

理想の自己と義務の自己のバランス
理想の自己と義務の自己は、異なる影響を持ちつつも、どちらも自己成長と幸福のために不可欠な要素です。理想の自己は希望や夢を、義務の自己は責任や義務を象徴しています。これらをバランスよく持つことで、ストレスを抱えることなく目標を達成することが可能になります。
ある研究では、理想の自己と義務の自己の両方に焦点を当てることで、健康的な行動(運動や食生活の改善)を促す効果があることが示されています(Kiviniemiら, 2011)。
神経科学的にも、両者のバランスを取ることは意思決定や目標設定に関わる腹内側前頭前皮質の活動と関連しています。理想の自己または義務の自己のどちらか一方に集中するよりも、両方を考慮しているときの方がこの領域の活動が高まるという結果が出ています(Northoffら, 2006)。
自己成長と幸福のために
理想の自己と義務の自己を理解し、バランスを取ることは、自己成長と幸福感の向上に大きく貢献します。両方の動機に焦点を当てることで、自分の目標を達成しながら、社会的責任や役割も果たすことができます。
研究によると、自己成長に焦点を当てることで、幸福感や人生満足度が向上することが明らかになっています(King & Hicks, 2007)。また、個人の成長に取り組んでいる人は、前頭前皮質の活動が高いという神経科学的な証拠もあります(Krogerら, 2013)。これは、自己成長が脳の働きや幸福感において重要な役割を果たしていることを示しています。

結論
理想の自己と義務の自己は、それぞれ異なる動機でありながら、どちらも私たちの行動に強い影響を与えます。理想の自己は「こうなりたい自分」、義務の自己は「こうあるべき自分」です。この2つの動機をバランスよく取り入れることで、個人の成長と幸福度がアップします。
行動科学と神経科学の研究は、両方に焦点を当てることが、行動面でも精神面でもプラスの効果をもたらすことを示しています。理想の自己により成長が、義務の自己により責任感が促され、両者の調和が健全な意思決定と目標達成に導きます。
自己成長と義務のバランスを取りながら生きること。それが、より豊かで満足のいく人生への鍵と言えるでしょう。
______________________________________________________________________________________
参考文献(英語)
Carver, C. S., & Scheier, M. F. (1998). On the self-regulation of behavior. Cambridge University Press.
King, L. A., & Hicks, J. A. (2007). Whatever happened to “What might have been”? American Psychologist, 62(7), 625–636.
Kiviniemi, M. T., et al. (2011). Fitting the task and the person. Social and Personality Psychology Compass, 5(12), 960–975.
Kroger, J. K., et al. (2013). Identity status change. Journal of Adolescence, 36(5), 741–752.
Northoff, G., et al. (2006). Self-referential processing in our brain. NeuroImage, 31(1), 440–457.
Oyserman, D., et al. (2006). Possible selves intervention. Journal of Adolescence, 29(4), 687–702.
心がまぁるくなった30代後半。歳を重ねるってどういうこと?
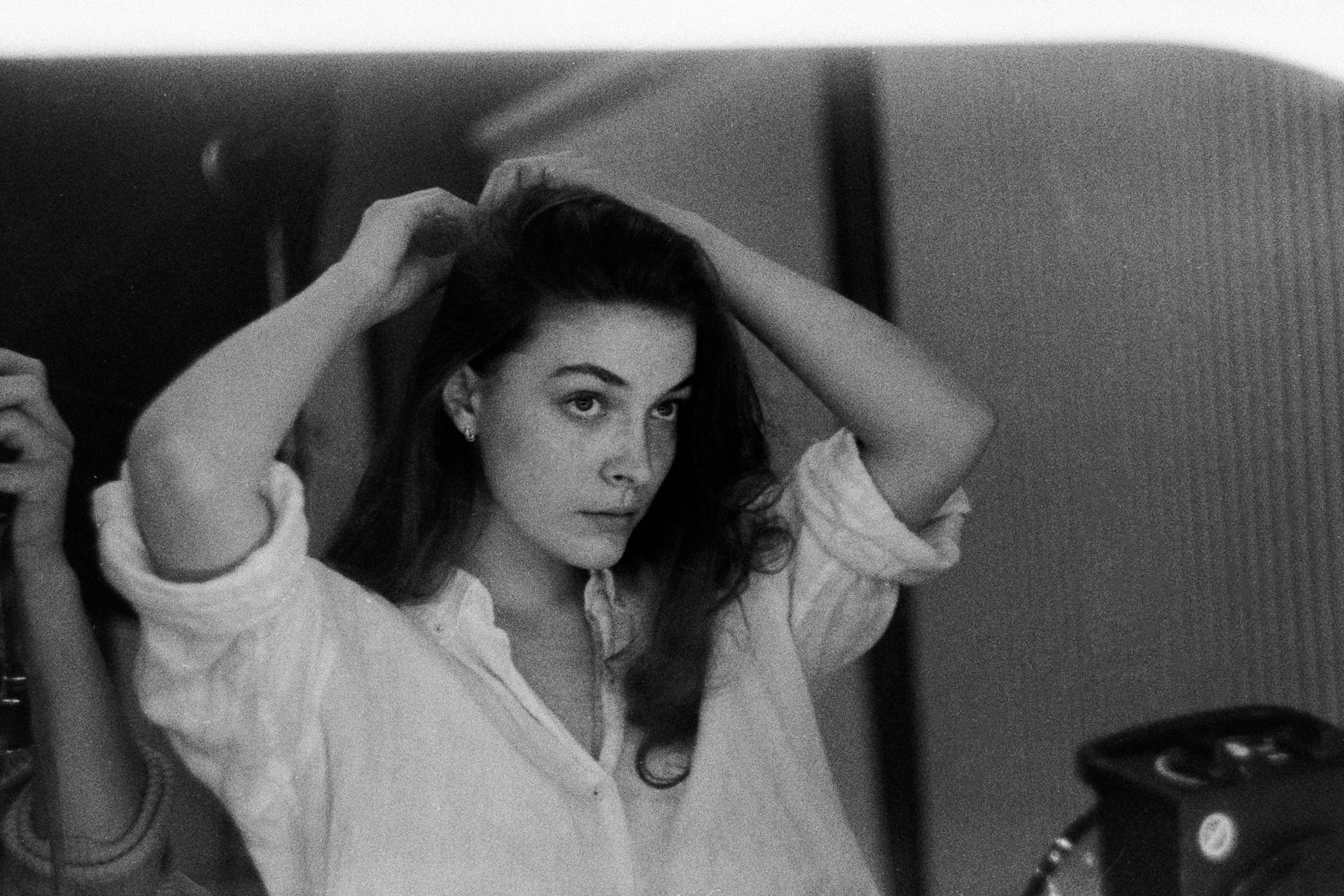
ふらりと立ち寄った書店で手に取った『ココ・シャネル99の言葉』。
そこに書かれていたのは
“女の人生。本番は40歳から。それまでは練習みたいなものよ。そして40歳からが、本当におもしろい”という言葉。
「私の人生はこれからが本番なのか」と思うと、なんだかワクワクしてきました。
歳を重ねるとはどういうことなのでしょう。これまでの人生とこれからについて、あらためて考えてみることにしました。
35歳からヒシヒシと感じる体の変化
20代の頃は、夜更かししても翌日は元気に活動できました。念入りなスキンケアをしなくても肌にはハリがあったし、日焼け止めを塗り忘れてもシミなんて気になりませんでした。
でも、35歳を過ぎた頃、鏡を見てギョッとしました。今まで気にならなかったシミや毛穴がどうしても気になるし、ハリのあったバストも、2人の子どもを母乳で育てた結果、すっかり萎んでしまった……。夜更かしした翌日の午前中は使い物になりません。
自分に時間とお金をかけられるように
一方で、歳を重ねることは、悪いことばかりではありません。35歳を過ぎた頃から、「自分のために時間とお金を使う」ことへの罪悪感が薄れていきました。
スキンケアに時間をかけたり、勇気を出してエステや美容クリニックに行ってみたり、気になっていた下着屋さんに行って、自分にぴったりの補正下着を買ってみたり。忙しい時でも、自分のための時間を確保して、一人で美術館や映画館に行ったり、週1回はヨガに通ったりできるようになりました。
不思議なことに、自分を大切にする時間が増えると、歳を重ねることへの抵抗感も和らいでいきました。身体の変化には逆らえないけれど、歳を重ねることを楽しむという選択肢があることに気がついたのです。

心のまぁるさという贈りもの
先日迎えた38歳の誕生日。「お誕生日おめでとう」とメッセージを送ってくれた友人に、「歳をとるのは身体的にはイヤだけど、心はすごく生きやすくなった気がしてる」と返信している自分がいました。
そう感じられるようになったのは、30代後半になって、少しずつ心がまぁるくなってきたからかもしれません。
人との出会いや、日々の経験を重ねるなかで、いつの間にか考え方が変わってきたように思います。
たとえば——
過去の辛い経験は、今の自分の優しさにつながっている。
他者の不機嫌は、自分のせいではなく、その人自身の問題。
失敗や挫折は、振り返れば最高のネタ。
誰かに好かれようと無理をするより、自分が大切にしたい人を大切にし、自分を大切にしてくれる人を大切にすればいい。
そんなふうに思えるようになったことで、心がふっと軽くなり、生きやすくなりました。
自分を大切にする方法を知ることが大切
でも、歳を重ねたからといって、自然と自分を大切にできるわけではありません。私が自分を愛おしく思えるようになったのは、これまでの経験だけでなく、自分と向き合う方法を他者から教えてもらったからです。
私は30代後半でWebマガジン『Humming』に出会いました。『Humming』を読んだり、編集長の話を聞いたりするうちに、少しずつ自分と向き合う大切さを実感していきました。
この世界には、人生の先輩がたくさんいます。本を読んだり、誰かの話を聞いたり、先輩たちの知恵をちょっと分けてもらうことで、人生はもっと潤うし、直感が研ぎ澄まされていくことを体感しています。
歳を重ねることは自分をより深く知ること
20代の頃は「歳をとりたくない」と思うことも多かったです。でも今は、歳を重ねることも悪くないと思っています。もちろん健康でいられるかな、仕事を続けていけるかな……など、未来への不安もあります。でも、自分がどんな人生をおくっていくのか、楽しみの方が大きいです。
というのも、最近の私は「明日死ぬかもしれない」と思って生きているからです。だったら、起きるかわからない未来のことを悩むのではなく、「今」を大切に、やりたいことはどんどんやって生きたいなって。
歳を重ねるということは、ただ老いていくことではなく、自分自身を深く理解して、より自分らしく、より自由に生きる術を身につけていくプロセスなのかもしれません。
【商品紹介】自然石鹸の魅力を発見:お肌にやさしいナチュラルなケア

合成成分や刺激の強い化学物質があふれる現代において、ナチュラル石鹸への切り替えは、肌をやさしくケアしながら、環境に配慮したライフスタイルを取り入れるシンプルでパワフルな方法です。植物由来のオイル、エッセンシャルオイル、スキンケアに優れた植物成分を使用した手作りの石鹸で、市販の製品に含まれる不要な添加物なしの、ぜいたくな体験となるでしょう。
しかし、ナチュラル石鹸の特別な点とは? どのように肌に良い影響を与えるのか、そしてなぜナチュラル石鹸に切り替えるべきなのか? この記事では、おすすめのナチュラル石鹸を紹介しながら、ナチュラルで手作りの石鹸が、健康なお肌とセルフケアをするすべての人にとって必須のアイテムである理由を探ります。あなたの毎日の洗顔習慣を、至福のリラックスタイムへと変えてみませんか?
お肌にやさしい成分
ナチュラル石鹸は、オリーブオイル、ココナッツオイル、シアバターなどの植物由来のオイルやバターを使用しており、肌の自然な潤いを奪うことなく、しっとりと洗い上げます。敏感肌や乾燥肌の方にもぴったりです。
______________________________________________________________________________________
おすすめ①
WATO
🌿 公式サイト: https://www.watosoap.com/collections/soap
成分: 天然オイル、藍、竹炭、大麻炭、米ぬか、ターメリック、日本酒
WATOは、創設者の母・ノリコさんにインスパイアされた日本人女性&黒人女性が経営するブランドです。彼女は独学で伝統的な石鹸作りを習得し、現在はブランドとしてその技術を活かしています。ヒマワリ油や米ぬか油などのナチュラルオイルと植物由来の染料を使用し、色合いをゼロから調合。自然でこだわり抜かれた石鹸を提供しています。

合成化学物質不使用
市販の石鹸には、硫酸塩(SLS)、パラベン、合成香料が含まれていることが多く、これらは肌を刺激し、乾燥を引き起こす原因になります。ナチュラル石鹸は、その代わりにエッセンシャルオイルや植物エキスを活用し、心地よい香りとスキンケア効果を提供します。
______________________________________________________________________________________
おすすめ②
Meow Meow Tweet
🌿 公式サイト: https://meowmeowtweet.com/collections/soap
成分: 天然オイル、シアバター、エッセンシャルオイル、植物エキス
Meow Meow Tweetは、ココナッツカカオ、ヒノキクローブ、ラベンダーレモン、グレープフルーツミントの4種類の香り豊かな石鹸を使用。ヴィーガン石鹸でもあり、Leaping Bunny認証(動物実験を行わないことを証明するための認証)を取得し、パームオイルフリーで環境にもやさしい紙包装が特徴です。
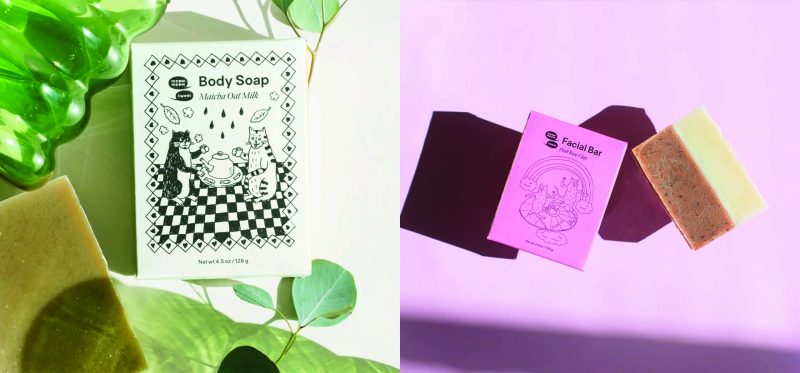
グリセリンをたっぷり含み、保湿力抜群
グリセリンは、水分を引き寄せて肌を潤す天然の保湿成分。市販の石鹸では製造過程で除去されることが多いですが、手作り石鹸にはそのまま残っているため、肌にたっぷりの潤いを与えます。
______________________________________________________________________________________
おすすめ③
Binu Binu
🌿 公式サイト: https://www.binu-binu.com/collections/soap
成分: 天然オイル、シアバター&ココアバター、ココナッツミルク、カオリンクレイ、お茶エキス、エッセンシャルオイル
韓国の伝統的な入浴習慣「セシン」からインスパイアされたBinu Binuの石鹸は、韓国の文化に根付いた「ボリ茶(麦茶)」をベースに作られています。ボタニカル成分とエッセンシャルオイルを組み合わせた8種類のラインナップがあり、ニューヨーク・タイムズ紙やVogueでも紹介された人気ブランドです。

環境に優しく、生分解性あり
ナチュラル石鹸は、環境に配慮した持続可能な成分で作られ、パッケージも最小限または環境にやさしいものを使用しています。
______________________________________________________________________________________
おすすめ④
Wary Meyer
🌿 公式サイト: https://warymeyers.com/collections/bar-soap
成分: 100% 植物性グリセリン
メイン州でハンドメイドの石鹸&キャンドルを作る夫婦ブランド。デザイン性の高いカラフルな石鹸が特徴で、すべて合成洗剤、アルコール、パラベン不使用。バスルームのインテリアやギフトにも最適なアイテムです。

クルエルティフリー&エシカル
ナチュラルソープブランドの多くは、倫理的に正しい方法で原材料を調達し、動物実験をせず、正当な価格で購入するフェアトレードを行っています。
______________________________________________________________________________________
おすすめ⑤
Herbivore Botanicals
🌿 公式サイト: https://www.herbivorebotanicals.com/collections/soap
成分: 天然オイル、炭パウダー、エッセンシャルオイル、カオリンクレイ
ナチュラル&オーガニックのスキンケアで有名なHerbivore Botanicals。炭石鹸やピンククレイ石鹸など、100以上の高評価レビューを誇る高品質な製品を提供しています。

あなたに合ったナチュラル石鹸を見つけよう
乾燥肌、敏感肌、角質ケアが必要な方など、それぞれの肌に合わせたナチュラル石鹸が見つかります。
______________________________________________________________________________________
おすすめ⑥
Upcircle Beauty
🌿 公式サイト: https://us.upcirclebeauty.com/collections/cleansers
成分: グリセリン、ココナッツ酸、シアバター、天然オイル、植物エキス
イギリス発のUpcircle Beautyは、アップサイクル原料を活用したスキンケアブランド。余剰食材を再利用し、天然成分とブレンドした保湿力の高い石鹸を提供しています。
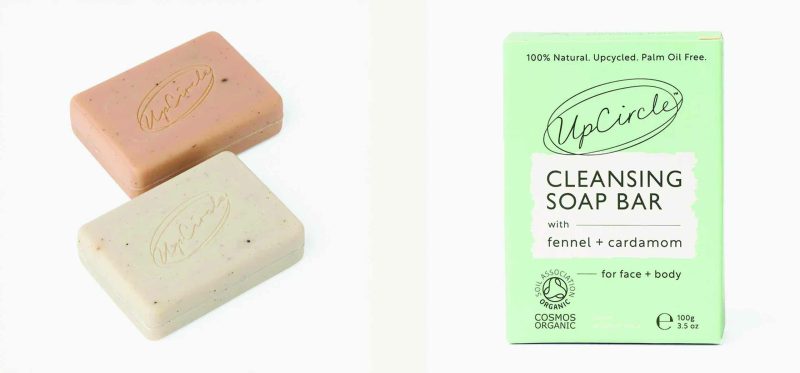
自然石鹸に切り替えて、毎日のバスタイムをより心地よいものにしてみませんか?
代謝の健康状態とは?医師が解説

私が30代前半で乳がんと診断されたとき、それまでの健康に関する考えをすべて見直さなければなりませんでした。突然、これまで考えたことのなかった疑問に直面しました。
- なぜこのようなことが起こったのか?
- 自分の体のために何ができるのか?
- どうすれば、継続できる方法でポジティブに健康を取り戻すことができるのか?
その時、私はナシャ・ウィンターズ博士の『The Metabolic Approach to Cancer(がんに対する代謝的アプローチ)』という本に出会いました。この本は、私の健康や病気に対する理解を根本から変えました。「代謝の健康状態」というワードを、単なる流行の言葉やダイエット方法としてではなく、私たちの体は細胞レベルで機能している土台であると紹介していました。
私は、自分が選択するすべてのこと—食事、運動、ストレス管理—が、体の回復力や健康維持にどのような影響を与えるのか理解するようになりました。この気づきは、私自身の健康管理だけでなく、家族や患者のケアの方法も変えました。
代謝の健康は誰にとっても重要
代謝の健康は、病気を持つ人だけのものではありません。これはすべての人にとって重要です。実際、93%の人々が代謝の面で不健康であり、代謝の問題は今日私たちが直面するほぼすべての慢性疾患の根本原因となっています。アメリカのケイシー・ミーンズ博士の研究によると、この統計は驚くべき結果で、多くの人々が何らかの代謝的な問題を抱えていることを示しています。
代謝の健康が著しく低下すると、代謝症候群を引き起こす可能性があります。これは、心臓病、脳卒中、2型糖尿病のリスクを大幅に高める複数の症状の集まりです。代謝症候群の場合、高血糖、高血圧、腹部脂肪の蓄積、異常なコレステロール値などのリスクがあると診断されます。しかし、これは一夜にして発症するわけではありません。疲労、食欲の変化、血糖値の乱高下、ブレインフォグ(頭の中がふわふわし、認知機能や集中力が低下)などの初期症状が現れ、それが進行すると病気へとつながります。しかし、日々の習慣を少しずつ改善することで、代謝の健康状態を向上させることができるということです。
日常生活における代謝の健康の重要性
多くの人々は、年齢のせいだと思い込んでいる症状が、実は代謝の問題のサインであることに気づいていません。
代謝が低下しているサイン:
- 疲れやすい、または疲れているのに眠れない
- 集中力や記憶力の低下
- 正しい生活をしているのに体重管理が難しい
- 甘いものや加工食品への強い欲求
- 膨満感、逆流、便秘などの消化不良
- ホルモンバランスの乱れ(生理不順、甲状腺の問題など)
- ストレス耐性の低下、常に圧倒される感覚
これらの症状の多くは、血糖値の乱れ、ホルモンバランスの崩れ、炎症など、代謝と深く関わっています。
代謝をサポートする方法
幸いなことに、厳しい食事制限や短期間の対策ではなく、日々の小さな習慣の積み重ねによって代謝を改善できます。
- 加工食品を避け、全粒食をとりいれる
- 食後に軽い運動を取り入れる(15分のウォーキングなど)
- 食事のタイミングを工夫し、朝食や昼食をしっかり摂る
- 睡眠の質を向上させるため、朝日を浴び、ブルーライトを制限する
- 呼吸法や瞑想、自然とのふれあいでストレスを管理する
- 十分な水分を摂り、毒素を避ける
これらの習慣を取り入れることで、日々の活力を高めることができます。

代謝が健康であるために「気づくこと」
何よりも大切なのは、自分の体に注意を払うことです。
- 朝起きたとき、どのように感じるか?
- 食後のエネルギー状態はどうか?
- 睡眠の質は良いか?
これらの小さな変化に気を配ることで、代謝健康を維持し、より充実した人生を送るための第一歩を踏み出すことができます。
あなたの代謝は、毎秒あなたの健康を支えています。それにふさわしいサポートをしてあげましょう。
______________________________________________________________________________________
ジャクリン・トレンティーノ医師は、家庭医療専門医です。女性の健康を専門とし、などのメディアにも取り上げられています。
機能性医学の医者でもあり、自身も乳がんを経験したトレンティーノ医師は、健康問題の根本原因を明らかにすることに情熱を注いでいます。ホリスティックなアプローチを取り入れ、長期的な健康とウェルビーイングをサポートすることをミッションとしています。
お産は「痛い」でなく「気持ちがいい」もの。ドゥーラのサポートで本来の自分に戻った出産体験とは【バースドゥーラの木村章鼓さんインタビュー】

「お産は痛いもの」――そう思っている人は多いかもしれません。でも、今回お話を伺ったバースドゥーラの木村章鼓さんは、「お産はきもちいい体験だった」と語ります。実際に2回の自宅出産を経験し、個人の出産体験には、「女性の人権」や「選択の自由」など、社会的・経済的・文化的側面が大きく関わることを知っていったと話します。
そもそもバースドゥーラとは何をしてくれる人なのか? 産婦さんにどんな変化をもたらすのか? 木村さんの体験を通じて、バースドゥーラがいることで「お産がどう変わるのか」が見えてきました。そして今、日本でも注目を集めるバースドゥーラの役割と、その広がりの理由についても深掘りしていきます。
ーー木村さんは、自宅出産を2回されていますが、どんな体験でしたか?
日本とアメリカで、自宅に助産師さんを招いて水中出産をしました。その経験は「自分の自律性(autonomyオートノミー)を持つことが人生を生きていく上での底力になる」ことを強く感じさせる体験でした。「痛い」「辛い」「怖い」のがお産だと思っていましたが、実は「気持ち良くて、楽しくて、辛くない」ことがとことん腑に落ち、驚きました。こういうお産の文化は、日本ではあまり知られていないのではと思います。
産婦人科医の先生と比べて、助産師さんの存在はあまり認知されていないかもかもしれません。でも、「お産の医療化」という流れの中で、精神的にも肉体的にもお産を支えてきたのは日本の産婆さん、つまり助産師さんだったと思うんです。
私はありがたいことにすばらしい助産師さんに出会い、21年前に素晴らしいお産をさせてもらいました。私一人が体験するだけでいいのだろうかという罪悪感が出るほどだったんです。
それから私もバースドゥーラになりたいと思って、この20年間ずっと走り続けてきました。
ーー多くの女性が、出産は痛いものだと考えますが、そうではなかったのですね?
ミシェル・オダンという80代のフランスの産婦人科医がお産について興味深い調査をしています。彼は若い頃から、フランスの国立病院の中に「野生の部屋」と名付けた部屋を設けました。女性が野生に戻るために部屋を薄暗くし、洞窟の奥にこもったような感覚になれる部屋を作ったんです。すると、この部屋で出産する多くの女性が安産だったのです。この調査から、外部から介入やコントロールされないお産は、本人の野生的部分や五感を発動させ、お産の痛みではなく、質の高い心地よさをを生み出したことがわかりました。
私自身も女性の体について学んでいくうちに、私たちが知らないだけで、女性の体に起きることはこんなに深い意味があり、日本の助産師さんのケアレベルが世界的に見てもそうとう高く素晴らしいものだったということを知り、大きな衝撃を受けました。
ーー日本の助産師さんのケアレベルは世界とどう違うのですか?
日本の助産技術で筆頭に挙げられるのが「会陰保護」です。日本の助産師さんが辛抱強く待てるのは豊かな経験の裏返しでもあります。会陰が和紙のように伸びると、赤ちゃんの頭が産道をくぐってきても割けることなく、外科的な処置の必要もないのです。これは、体にとって健やかで優しく痛みのないお産となります。こういう会陰保護の技術があるのはすごいなと気づきました。
例えば、日本の助産師さんは熱いお湯を洗面器にはって持って来てくれます。その洗面器に清潔なガーゼを浸し、熱いうちにキュッと指先で絞って、女性の会陰に押しくらまんじゅうのような力で押し戻してくれます。それを繰り返すと会陰も慣れ潤いが増し、初産でも会陰は裂けにくくなるものです。そんな風に丁寧に大切に会陰を扱ってもらう経験は「ご神体として大切に体を扱ってもらった」という財産になります。ですから、私は助産師さんに恩返しをしたいし、こういうお産を体験する女性が一人でも増えてほしいと思っています。

「この記事に使用している写真の2、3枚目はすべて2025年春に木村章鼓さんの立ち合った自宅出産(地元の助産師さんたちとの協働)の様子です。レボゾという布を使った手技で妊産婦さんを適宜リラックスさせています」
ーーバースドゥーラと助産師の違いは?
医療者か被医療者かの違いがまずは筆頭に挙げられます。私たちバースドゥーラは非医療的な関わりをしていきます。医学的な見地からお話をすることはなく、何かあった時に「この専門の先生に見てもらうといいですよ」とか「こういう鍼灸師さんがいますよ」といった橋渡し役をやっていますね。
ーー日本でバースドゥーラの認知度は広がっているのでしょうか?
私が理事をさせていただいている「ドゥーラシップジャパン」という一般社団法人が、日本では一番古いバースドゥーラの団体です。バースドゥーラの認知度は、テレビなどのメディアにとりあげられるようになり高まっていますし、利用する女性も増え、産後のケアに特化した団体も増えています。
一人の女性が出産する回数が減ってきている今だからこそ、その一回、二回の貴重な体験をより良い体験にし、大切な子供たちをどう産み育てていくかということに意識を払っているお母さんが増えていると感じますね。

ーーバースドゥーラは、具体的にどんなサポートをしてくれるのでしょうか?
ケースバイケースで個人差がありますね。自宅分娩の方なら、そのままお家でお産。病院など外部施設でお産の場合も、バースドゥーラは寄り添い、お産に向き合う女性を「女神のように丁寧に扱って心情的なサポートに徹する」というのが根幹です。
例えば、アロマセラピスト専門の方だったら香りだったり、他にも音楽、照明や、環境的なものをセッティングするということもバースドゥーラの目配りする分野に入ります。妊婦さんだけでなく家族全体もサポートします。
例えば付き添いのお父さんが所在投げにしていたら「コーヒーを飲んで外で休んできたらどうでしょう」なんて声をかけることで、逆に元気になって部屋に戻ってきて心身ともに心構えできる男性もいますね。逆にお父さんのタイプによっては「ずっと奥さんの背中をさすっていてあげてください」とお願いする場合もあります。
分析的なマインドが働きがちな男性は出産時に奥さんの会陰を凝視してしまうこともあるんですね。でも女性にしたら恥ずかしいですし、膣をずっと観察されるのはちょっと…という方もいますよね。その場合もバースドゥーラが適切に対応します。
バースプランを立てる時に、ご希望に応じて、どんな風にバースドゥーラがクッション役として関わり、皆さんがサポートし合えるかを判断します。妊婦さんの身体的な快適さのためのお手伝いだけでなく、お父さん、お子さん、義理のお母さんや、実家のお母さんなどへの対応はそれぞれで語り尽くせないですね。
産後は「お産のふりかえり」と呼ばれる体験の聞き取りも行います。女性が「あの時言われた一言が傷ついた」など後から思わぬことを思い出したりすることがあるものです。出産直後に行うのが良いので、お産から数日とか数週間してから女性の希望に応じて行います。このふりかえり以外にはもちろん身の回りのケアも大切な役割です。
ロンドンで私がバースドゥーラをしていた時に、産後数ヶ月のお母さんが私に、「赤ちゃんを抱っこしていてほしい」とおっしゃいました。「プールで泳ぎたい」と言うんです。「産後にプールだなんて体が冷えてしまうからダメ」なんて専門家的な目線で言いたくなる人もいますが、その方はずっと泳いできた方で出産で泳ぎを中断し、またすぐに泳ぎたいという方だったんですね。産後の女性が必要としているのが、泳ぐことなら、安心してプールに行ける環境を整えるのがバースドゥーラの役割です。
産後の女性は普段と異なる環境で多くのプレッシャーを感じながら育児を頑張っているので、見えないストレスをどうほどいていけるのか提案をすることで、バースドゥーラがいるといないとではずいぶん違うのではと思います。バースドゥーラがいることで、自分が本来の自分に戻る心の余裕が生まれます。

ーーバースドゥーラをお願いしようかと悩んでいる方に伝えるとしたら何になります?
私たちは母親である前に、一人の女性として生きています。そして私たちは、周りとのつながりの中で生かされています。自分が生きているというよりも、周囲との調和の中で生きることが大切です。バースドゥーラがいることで、自分を俯瞰して見ることができるようになります。「一人で全部頑張ろう」と思っていた自分が、実は助けが必要だと気づき、自分の弱さを受け入れて回りに頼ってもいいのだということがわかるでしょう。ですから、バースドゥーラという信頼できる人がいることで、心に余裕が生まれると思います。
ーー バースドゥーラはどうやって探せますか?
私が理事をさせていただいている「ドゥーラーシップジャパン」では、日本各地のバースドゥーラを登録制にしてご紹介していますので、まずはホームページをご参照ください。
ーーバースドゥーラを見つける時に注意すべきことは?
ご自身の直感を信じることですね。この人は良さそうだとピンとくる人が数人いたら、すべての候補者に会って相談をしてみてください。共振共鳴して「この人にお産の場にいてほしい」と体がイエスの信号を出す人をいかに選べるかですね。いかに、自分の直感を尊重できるかが大切な点でしょう。
ーーバースドゥーラさんが見つかったら、産後どのくらいの期間サポートをお願いするものですか?
これも個人によりますね。産後も、毎週必要とする方もいれば、母乳育児が波に乗ったから、産後は数回で卒業される方もいらっしゃいます。一歳、二歳なるまでお願いする方もいらっしゃいました。
ーー木村さんが主催されているバースドゥーラ養成コースとは?
私からバースドゥーラ養成クラスを受けたいというリクエストをいただいたことがきっかけで、四年前に始めました。ヨーロッパやアメリカなど各地域から日本人の方が参加しています。半年間のオンラインプログラムですが、講師として私も学ばせてもらうことが多いです。
受講者には、看護師さんや助産師さんなど、医療従事者の方もいて、医療が立ち行かなくなってきている心の領域、数値では表しにくい心のケアをどういうふうに補っていけるかというところで、バースドゥーラに興味を持ってくださる方が増えてきています。
2025月4月に終わり、2025年秋か年明けに新しい受講生さんを募集する予定です。
ーーこれから出産を考えている、または控えている女性に木村さんが伝えたいメッセージは?
「お産は誰のものですか?」ということですね。私たちのお産体験はどんどん一極集中化しているのが今の社会の流れです。この流れに抗って、自分の感覚を大切にし、これでいいのか?と考えた時にこれでいいんだって思ったらそれでいいし、ちょっと違うのなら、立ち止まって問いかける姿勢がますます重要な時代ですよね。
健康で自然な出産文化を日本に残したいと思っています。戦後、自宅出産が90%だった時代から、施設出産が推進され、今では99%が病院で出産されています。医師たちのケアは医学的モデルに沿い、外科的処置になりがちですが、一方の助産師たちは月経と同じ女性の生理的なプロセスであるお産をサポートする役割を今も果たしています。
だから、目先の手軽さだけでなくて、10年後、20年後の自分と赤ちゃんの健康を見据えて、誰とどこで産むのかという選択をしてほしいなと思います。
自分の力で子供を産むことで、女性は自尊心を感じることができます。私は、そうした自立した女性が社会にますます増えていくことを願っています。

ーー 木村章鼓さんプロフィール
バースドゥーラ/ドゥーラシップ ジャパン理事/日本語による初のバースドゥーラ養成スクール主宰
8都市20年の海外生活で産みゆく女性に寄り添いつつ健康的な衣食住の大切さを伝える。周産期医療に携わる医療従事者向け専門誌『周産期医学』(東京医学社)寄稿、『ペリネイタルケア』(メディカ出版)連載実績、お話会(慶應義塾大学、上智大学、筑波大学等)、雑誌『岩戸開き』(ナチュラルスピリット社)、『Veggy』(Kirasienne)インタビュー等、海外4ヶ国講演ツアー、日本全国の自治体等での講演活動、1dayワークショップ、レボゾ(布を使った施術)トレーニングや、ウーマンズリトリートなど合宿型体験学習をリード。二児の母でありバースアクティビストでもある。
共訳書籍 『自己変容をもたらすホールネスの実践 〜マインドフルネスと思いやりに満ちた統合療法〜』原題: The Practice of Wholeness ~Spiritual Transformation in Everyday Life~
インスタグラム:https://www.instagram.com/lovedoulakiko
音楽は心の処方箋。メンタルヘルスとの関係とは?

今は、音楽ストリーミングの普及により、CDを買わなくても気軽に音楽を楽しめる時代。スマートフォンとイヤホンさえあれば、いつでも、どこでも、お気に入りの曲を聴くことができます。
我が家では、朝は「朝にぴったりの音楽を流して」、子どもたちの兄妹喧嘩に疲れたときは「リラックスできる曲が聴きたいな」、寝る前には「心を落ち着ける音楽をかけて」と、そのときの気分や状況に合わせて、スマートスピーカーに音楽を選んでもらっています。
また、お気に入りの曲を流すと、再生が終わった後に別の曲が自動で流れ、思いがけず素敵な音楽に出会うことも。音楽は、日々の生活に欠かせない存在です。
実は、音楽にはリラックス効果やストレス軽減、さらには気分を高める力があると言われています。
この記事では、音楽がどのように私たちの心を支えてくれるのか、私が勇気づけられたお気に入りの曲とともにご紹介します。
『やろうとするのが大事』。迷ったときに背中を押してくれる音楽
何かをやるべきか迷ったとき、最近よく聴くのがAIさんの「みんながみんな英雄2024」です。
“できるできない なれるなれない
そりゃ全部が全部は叶わない
誰でもそうさ 彼でもそうさ
でもやろうとするのが大事
いま何が やりたいの
いま何に なりたいの
予定通りにいかなくたって
確かに前には進んでいる
踏み出せば それが道
飛び出せば そこが夢
汗かけば きっと 輝くさ
なりたかった自分が待っている”
この曲を聴くと、「迷うぐらいなら、まずはやってみよう!」と背中を押してもらえます。
実際に、好きな音楽を聴くと、脳内で「幸福ホルモン」と呼ばれるドーパミンが分泌され、気持ちが落ち着いたり、やる気が湧いたり、メンタルにポジティブな影響を与える力があることが科学的にも証明されています。
自分を励ましてくれる曲があると、迷った時に一歩踏み出す勇気がもらえるかもしれません。
『感じたままに進む 自分で選んだこの道を』フリーランスになりたての頃、励まされた曲
フリーランスのライターになったばかりの頃、「私の文章は本当に誰かの役に立つのだろうか」「正しい情報を届けられているのか」「ライターとしてこれからもやっていけるのか」と自信を持てずに悩んでいた時期がありました。そんなとき、何度も聴いて励まされたのが、YOASOBIの「群青」でした。
“嗚呼 感じたままに進む
自分で選んだこの道を
重いまぶた擦る夜に
しがみついた青い誓い
好きなことを続けること
それは楽しいだけじゃない
本当にできる
不安になるけど”
「好きなことを続けること、それは楽しいだけじゃない」、このフレーズが、当時の私の心境にぴったり重なりました。
「不安を感じてもいい、続けていこう」と思える、お守りのような1曲です。
『幸せになりたい気持ちがあるなら 明日を見つけることはとても簡単』友達と一緒に泣いた曲
学生時代に親友が失恋したときには、カラオケに行って、2人で竹内まりやさんの「元気を出して」を思いっきり歌いました。
“涙など見せない強気なあなたを
そんなに悲しませた人は誰なの?
終わりを告げた恋に
すがるのはやめにして
ふりだしからまた始めればいい
幸せになりたい気持ちがあるなら
明日を見つけることはとても簡単”
大声で歌った後に、「彼だけが男じゃないよね!」なんて話をして、沈んだ心に元気をもらえた思い出の1曲です。
音楽は言葉以上に心に響き、時に心の支えになってくれます。悲しいときは悲しい曲を聴いて思いっきり泣いたり、前向きな歌詞に背中を押されたり。その時の気持ちに寄り添う一曲があるだけで、少し心が楽になるかもしれません。
音楽は「心の処方箋」
音楽には、心と体に働きかける不思議な力があります。
医学雑誌「JAMA Psychiatry」や世界保健機関(WHO)の報告によると、音楽はうつや不安の軽減にも効果があり、特に音楽療法は専門的な治療と併用することでその力を発揮すると言われています。
また、音楽を聴くことで脳内のドーパミンやセロトニンが分泌され、幸福感が高まったり、ストレスホルモンであるコルチゾールが減少し、リラックス効果が生まれることもわかっています。
悲しいときや寂しいとき、自分の気持ちに寄り添う曲を聴いて涙を流すのは、「カタルシス効果」と呼ばれる自然な感情の発散方法です。また、歌詞に共感することで「自分だけじゃない」と感じ、孤独感が和らぐこともあるでしょう。
もし最近、なんとなく気持ちが沈んでいると感じたら、自分にとっての「癒しの曲」を探してみませんか? お気に入りの音楽を聴くことは、手軽にできるセルフケアのひとつです。

〜Humming読者さんから届いた想い出の1曲〜
HummingのInstagramで「音楽に助けられた経験はありますか?」と質問したところ、素敵なメッセージをいただいたのでご紹介します。
ーーーー
多感な中学生時代、今考えるとちっぽけで可愛い悩みだけど、当時は本気で悩んで、泣いて、笑って過ごしていました。
そんな時に聞いていたのが、中山美穂さんの「未来へのプレゼント」。
「大人になると、今現在のことが過去になるんだな」と考えさせられました。
この曲に出会えたことで、「今を一生懸命生きることが、未来へのプレゼントなんだ」と思い、がむしゃらに青春時代を満喫していました。
https://www.youtube.com/watch?v=_mnBfYHrLdo
ーーーー
素敵なメッセージをありがとうございます。
【映画レビュー】ナプキン一枚が変える未来――インドの女性たちの闘い

生理用ナプキンは特権である
生理が当たり前に受け入れられている社会で育った私は、生理という自然な身体の機能が、これほどまでに偏見の目で見られるとは考えたこともありませんでした。Netflixのドキュメンタリー『Period. End of Sentence.』は、インドの一部地域における生理の扱われ方や認識について、衝撃的な現実を映し出しています。
映画の冒頭では、インドの少女たちが生理について尋ねられ、赤面したり、答えを躊躇したりする様子が映ります。多くの少女たちは語ることを恥じ、中には完全に口を閉ざしてしまう子もいました。
私は、生理がタブー視されたり、病気のように扱われたりしない国で育つことができました。しかし、インドでは、知識不足のために、一部の男性たちが生理を病気だと誤解しているのです。
私は14歳で初潮を迎えましたが、周りの友人たちは1~2年前からすでに生理を経験していました。自分だけが遅れているのではないかと不安になり、生理がきたときはホッとして、少し嬉しくさえ感じました。
しかし、インドでは事情が異なります。少女たちは生理がこないことを願いながら過ごしています。痛みや不便さを恐れているのではなく、生理用品が手に入らないためです。ナプキンがないために、服を汚し、それを頻繁に取り換えなければなりません。
ドキュメンタリーの中で、一人の女性が学校を辞めることになった理由を語っています。彼女は中学生のときに初潮を迎えましたが、ナプキンが手に入らず、布を巻いて対処していました。その布を取り換えるために、授業を何度も抜けなければいけないし、男性の視線を避けるために遠くまで歩かなければいけない。それに耐えられなくなり、最終的に学校を辞める決断をしたのです。
このドキュメンタリーは、私たちが当たり前のように使っている生理用ナプキンが、多くの女性にとっては手の届かない「特権」であることを痛感させます。

この現実に憤りを感じる
生理はごく自然な生理現象であり、人類の存続に関わるものです。社会がその基本的な機能を理解しないがために、女性の人生が制約されるべきではありません。しかし、インドでは性教育の不足により、多くの女性が生理中に使う布を洗って再利用するよう指導されています。恥ずかしさから、その汚れた布を人目につかないように埋めることさえあるといいます。
映画には、デリー警察で働くことを夢見るスネハという女性が登場します。警察官になるという彼女の夢は「結婚から自分を守るため」でもあります。彼女は村の中で孤立しながらも、結婚を拒み、独立を求める強い意志を持っています。
スネハは「女性は生理中に寺院に入ることができない。汚れているとみなされるか」と、厳しい現実を語ります。しかし彼女はこの考えに疑問を抱きます。「だって、神様だって女性でしょ? だったら私たちの気持ちをわかってくれるはず」。
この映画が制作された2018年時点では、インドで定期的にナプキンを使用している女性はわずか10%に過ぎませんでした。しかし、インドでも少しずつ変化の兆しが見え始めています。それは「ナプキン製造機」と呼ばれる装置ができたことです。特定の原料を用いて生理用ナプキンを製造できるこの機械は、全ての女性がナプキンを使えるようにすることを目的に作られました。
映画の中で特に印象的だったのは、ナプキン製造機の開発者が村を訪れ、使用方法を教える場面です。彼は「集中するために携帯電話をしまって」と指示します。その光景は皮肉なものでした。携帯電話を持つことは当たり前なのに、生理用ナプキンを持つことはまだ普通ではないのです。生理は太古の昔から続く現象なのに、未だにタブー視されるのはなぜなのか。もしかすると、これは性差別の一形態なのではないか。インドのように男性が支配的な社会では、彼ら自身が経験しない生理を「奇妙なもの」と捉え、恐れ、無視し、時にはコントロールしようとするのではないか。

私の初めての生理の記憶
私が初めて生理になったときのことを思い出します。父とレストランにいたときでした。トイレで血を見てパニックになり、急いでトイレットペーパーを下着に巻きました。そして、父のもとへ駆け寄り、状況を説明しました。父は一瞬戸惑ったものの、すぐに隣のコンビニに走ってナプキンを買ってきてくれました。
なぜなら、生理は普通のことだからです。
男性は生理を「気持ち悪い」「変だ」と思うべきではありません。生理は、女性が毎月経験するものです。にもかかわらず、世の中には、女性の身体の仕組みをあまり理解していない男性が多いように思います。
ナプキン製造機が村に導入されたとき、男性たちはその用途を知らず、赤ちゃん用のおむつだと思い「子ども用のナプキン」などと呼んでいたのです。
映画の後半では、ナプキン製造機の導入を通じて、女性たちが自立していく姿が描かれています。スネハは女性たちを率いてナプキンを製造し、他の村へ販売しに行きます。少しずつ興味を持つ女性が増え、ナプキンの購入者が現れます。それによって女性たちは収入を得て、誇りを感じるようになります。スネハが初めてナプキンを売ったときの喜びに満ちた表情が、とても印象的でした。
映画の中で、ある女性校長がこう言います。
「女性はあらゆる社会の基盤です」 そして、少し躊躇しながらも続けました。
「私はちょっとフェミニストかもしれません。でも、女性はもっと強い存在です。ただ、それに気づいていないだけ。自分たちにどれほどの力があり、何ができるのかを」
生理用ナプキンを作ることが、初めての仕事になる人もいます。そして、収入を得ることで自立し、男性からも尊敬されるようになります。もちろん、男性の承認を得ることが女性の自己価値につながるわけではありません。しかし、彼女たちにとっては大きな一歩なのです。
ナプキン製造機が稼働するたびに、村の男性たちも関心を持ち始めます。そこから教育が始まるのです。小さな好奇心の火が、意識の変化という大きな炎へと広がり、より平等で支え合う社会を築いていくのではないでしょうか。
🔗 The Pad Project の活動を支援するには、公式サイト www.thepadproject.org をご覧ください。
セックスに対する恥じらいの正体を、自分なりに考えてみた

私は、「セックス」という言葉を口にするだけで、どこか気恥ずかしさを感じます。
あなたの周りにも「性的な会話や欲望は隠すもの」という空気が漂っていませんか?性に対するタブー感はいったいどこからやってくるのでしょう。
家族との会話で避けられる話題、学校での遠回しな性教育、メディアの過剰な表現と規制……。知らず知らずのうちに「セックスに関することは口にしてはいけないこと」というメッセージを受け取ってきたのかもしれません。
しかし、本当にセックスは恥ずべきものなのでしょうか?
私の中にある恥ずかしさの正体や、心の奥で望んでいることを考えてみました。
私の中にある「恥ずかしさ」の正体
私がセックスに恥ずかしさを感じる理由のひとつは、単純に「セックスはプライベートな部分をさらけ出す行為だから」です。身体的にも、感情的にも、自分の深い部分を相手に見せることには、ある種の照れや抵抗が伴います。
でも、それだけではないように感じます。
「女性のセクシュアリティは恥ずかしいもの」という意識が、どこか私の心の奥底に根付いているように思います。性的な欲望や快楽を表現すること自体を「恥ずかしい」と感じてしまうのはなぜなのでしょうか。
思い返せば、子どもの頃から「性」についてあまり触れられずに育ってきました。学校でも、家庭でも、性に関する話題はどこかタブー視され、オープンに語られることは少なかったです。セックスに関する話をするのは「はしたないこと」、性的な興味を持つのは「よくないこと」。そんな無言のメッセージを受け取りながら大人になった気がします。だからこそ、性にまつわることを隠すのが当たり前になり、それが「恥ずかしい」という感情につながっているのかもしれません。
しかし、本来セックスは単なる生殖行為ではなく、大切な人との愛情表現のひとつでもあります。身体の内側から「気持ちがいい」と感じることは、決して後ろめたいことではなく、自分を大切にする行為でもあるはずです。
性について、もっと自然に、オープンに話せるようになるためには、幼い頃からの性教育が大切なのかもしれません。
もう少し性を楽しんでみたい。30代後半の変化
これまで私は、性に対してとても真面目に向き合ってきました。身体の関係を持つのは、きちんとお付き合いをしている人だけ。ワンナイトや浮気、不倫はもってのほか。周りがどうであれ、それが自分のポリシーでした。
でも最近少しだけ思うことがあります。もう少し、性を楽しんでみてもいいのではないかと。自分が気持ちいいと感じること、心地よいと感じることを、もっと素直に受け入れてみたいなと。
とはいえ、私は既婚者であり、子どもがいます。パートナーを裏切って家庭を壊すリスクを負ってまで、自分の快楽を外に求めることはできないでしょう。
でも、自分にも性欲があること。性を楽しみたいという前向きな気持ちがあること。それを恥じることなく、認めてあげようと思います。どんな方法でその感情を満たしてあげるのかは、模索中……!

性と向き合うことは、自分の心と体と向き合うこと
性に関する感じ方は、人それぞれです。セックスをしない「アセクシュアル(エイセクシュアル)」の人もいれば、セックスそのものを楽しむ人もいます。愛する人とのスキンシップを大切にする人もいれば、心のつながりがないと性行為を求めない人もいます。どの価値観も間違いではなく、大切なのは自分がどうありたいかを自分自身で選ぶこと。
性について考えることは、単に「セックスをどう捉えるか」という話ではなく、「自分の心と身体をどう大切にするか」ということにつながっているように思います。セックスという行為を、恥じたり、否定したりするのではなく、自分の気持ちを素直に受け止めること。それこそが、自分自身と向き合うための一歩なのかもしれません。
性交時の痛みについて:原因と対処法

多くの人が経験する性交時の痛み。その原因は、身体的な疾患、心理的な要因などさまざまです。時には、パートナーとの関係や心の健康にも影響を及ぼすことがあるでしょう。
性交痛は身体的・精神的な両面から適切に対処することで、不快感を軽減し、パートナーとの親密な関係を取り戻すことが可能です。
本記事では、性交時の痛みの原因や対処法をご紹介します。
性交時の痛みの原因を理解する
性交時の痛み(性交痛(dyspareunia))は、身体的な原因と精神的な原因の両方によって引き起こされる可能性があります。その根本的な原因を理解することが、適切な対処への第一歩です。研究によると、この原因は広範囲にわたり、身体的な疾患から心理的なストレス要因までさまざまです。
身体的な原因
膣痙攣(vaginismus):骨盤の筋肉が無意識に収縮し、痛みを伴う状態
子宮内膜症(endometriosis):子宮内膜組織が子宮外に増殖し、痛みを引き起こす疾患
骨盤炎症性疾患(PID):感染症によって骨盤内に炎症が生じる
これらの疾患は、挿入時の強い不快感を引き起こす可能性があり、医療的な治療が必要となる場合があります。
感染症や医学的な問題
膣の乾燥:ホルモンバランスの変化(更年期など)が原因で起こることが多い
膣炎・尿路感染症(UTI):細菌感染が性交時の不快感を引き起こす
研究によると、これらの要因が性交時の快適さに直接影響を与えることが示されています。
心理的な要因
不安・ストレス:性交に対する緊張や過去のトラウマが影響を及ぼす
関係性の問題:パートナーとのコミュニケーション不足が痛みを悪化させる
研究では、心理的・感情的な要因が筋肉の緊張を引き起こし、性交時の痛みにつながることが分かっています。
詳しい解説は[性交痛とは|咲江レディスクリニック]をご覧ください
詳しい解説は[性交痛でお悩みの方へ|いこまともみレディースクリニック]をご覧ください
第一歩:身体的な原因を除外する
性交時の痛みが続く場合、まずは医療機関を受診し、身体的な原因を特定することが重要です。産婦人科医、泌尿器科医、骨盤痛専門医などの診察を受け、必要に応じて以下のような検査を行います。
内診・画像診断(超音波検査、MRI など)
ホルモン検査・細菌検査(膣の乾燥や感染症の有無を確認)
骨盤底リハビリテーション
膣痙攣や骨盤痛の治療として、骨盤底理学療法(Pelvic Floor Therapy)が推奨されることがあります。この療法では、特定のトレーニングを通じて骨盤の筋肉をリラックスさせ、痛みの軽減を目指します。研究によると、骨盤底リハビリテーションは性交痛の治療に効果的であることが示されています。

痛みが心理的な場合の対処法
身体的な原因を除外したにもかかわらず痛みが続く場合、次のステップとして心理的要因を考慮する必要があります。
パートナーとのコミュニケーション
パートナーと率直で非批判的な会話をすることが重要です。研究では、オープンなコミュニケーションが性交の満足度向上につながることが示されています。
感情的な親密さを重視する
性交を焦点にするのではなく、キスやハグ、スキンシップを増やすことが効果的です。これにより、セックスに対する不安が軽減され、満足度が向上することが研究で示されています。
セックスセラピーの役割
性交痛が心理的な要因によるものである場合、セックスセラピストのサポートが有効です。
セックスセラピーでは、以下のような方法が用いられます。
認知行動療法(CBT):性に対する不安や否定的な考え方を修正
マインドフルネス療法:性交時の痛みを軽減し、快適さを向上
研究によると、セックスセラピーは身体的・心理的な性交機能障害の治療に有効であることが分かっています。
カップルカウンセリングの利点
性交痛は、当事者だけでなくパートナーとの関係にも影響を与えることがあります。そのため、カップルでのカウンセリングを受けることも一つの解決策となります。
カップルセラピーでは、以下のような課題に取り組みます。
お互いの性的期待や境界を話し合う
パートナーが感情的にサポートできるようにする
研究によると、カップルでカウンセリングを受けることで感情的なつながりと性生活の満足度が向上することが分かっています。
性交時の痛みに対処するための実践的アドバイス
専門的なサポートと並行して、以下のような実践的な方法も役立ちます。
潤滑剤を使用する:潤滑剤を使用すると摩擦が軽減され、膣の乾燥による痛みを防ぐことができます。
時間をかける:前戯を長くすることで、身体がリラックスし、痛みの軽減につながります。
骨盤底筋エクササイズ(ケーゲル体操):骨盤底の筋肉を鍛えることで、骨盤の血流を改善し、痛みを軽減できる可能性があります。
異なる体位を試す:敏感な部位への圧力を減らすために、さまざまな体位を試してみるとよいでしょう。
専門家のサポートを見つける
性交時の痛みがパートナーとの関係に影響を与えている場合は、専門的なサポートを求めることが大切です。「セックスセラピー 近く」や「カップルカウンセリング」を検索し、適切な専門家を見つけましょう。

まとめ
性交時の痛みは、身体的な要因(骨盤痛、感染症など)や心理的な要因(不安、トラウマなど)によって引き起こされます。しかし、適切なアプローチを取ることで、対処することが可能です。
まずは医療機関で身体的な要因を特定
心理的な要因が関与している場合はセックスセラピーを活用
カップルカウンセリングで関係性の改善を図る
性交痛は一人で抱え込むべきものではありません。適切な専門家のサポートを受けることで、快適で親密な関係を取り戻すことができます。
更年期の不調に負けない!症状別おすすめアイテム&対策

閉経は、最後の生理から12か月が経過した時点で正式に確定します。平均年齢は52歳で、45歳から58歳の範囲内で起こることが一般的です。 そして、よくある誤解とは異なり、ある日突然ホットフラッシュに襲われるわけではなく、40代後半から徐々に症状が現れる「更年期(ペリメノポーズ)」という段階があります。
しかし、最近まで更年期に関する本格的な議論がほとんどなかったため、多くの人は典型的な症状に気づいていません。例えば、性欲の低下、関節の痛み、物忘れなどが単なる「加齢」のせいだと思われがちですが、実際には体内で特定の変化が起きており、それはホルモンレベルの変動によるものです。
この時期に大きく減少する主要なホルモンは「エストロゲン」です。エストロゲンは、性機能、コラーゲン生成、睡眠、骨密度、脳機能、膣や外陰部の潤いと弾力、心臓や血管の健康維持などに深く関わっています。そのため、更年期や閉経を迎えると、以下のような症状が現れることがあります。
– 性欲の低下
– 脳の霧(ブレインフォグ)
– 夜間の発汗やホットフラッシュ
– 睡眠障害や不眠
– 膣や外陰部の乾燥やかゆみ
– 性交時の痛み
– 気分の浮き沈み
– 不安感やうつ症状
– 骨の脆弱化
– 尿路感染症(UTI)の増加
– 尿失禁
にもかかわらず、多くの女性はこれらの症状が「本当に医師に相談すべきものなのか」確信が持てません。しかし、このリストを見れば、誰もが我慢したくない症状ばかりです。こうした背景から、新しい「更年期ウェルネス」業界が登場しました。
現代の更年期対策は、エストロゲンが担っていた機能を補う形で、問題にピンポイントで対応しています。その中でも、多くの女性が更年期や閉経期にホルモン補充療法(HRT)を選択しています。もしあなたもHRTを検討しているなら、ここで紹介する対策は、HRTと併用しても問題なく、安全性が確認されたものばかりです。
以下では、更年期の女性からよく聞く代表的な4つの問題と、それを解決するためのおすすめの方法をご紹介します。
問題①:性交時の痛み
解決策:セックスウェッジピロー

更年期に伴うホルモンの変化により、膣が短く、狭く、弾力を失いやすくなり、性交時に痛みを感じることがあります。この痛みを軽減する方法はさまざまありますが、即効性のある解決策のひとつが、高品質なセックスウェッジピロー「The Prim」です。
The Primは、挿入時の角度を調整し、より深く、スムーズに感じられるようサポートしてくれます。さらに、更年期による関節の炎症を軽減するため、する設計になっています。内部は高密度フォームで作られており(通常の枕よりもしっかりした硬さ)、外側はリネン素材のクッションカバーで覆われているため、ベッドに置いても「セックスグッズ」とは気づかれにくいデザインです。
問題②:ホットフラッシュ
解決策:『Hot Flash Tea』で体をクールダウン

更年期のホットフラッシュは、突然のほてりや発汗を引き起こし、日常生活や睡眠に影響を及ぼします。これは、エストロゲンの減少により体温調節が乱れることが原因です。ホットフラッシュを和らげるための方法はいくつかありますが、自然なアプローチとしておすすめなのが、「Hot Flash Tea(ホットフラッシュ・ティー)」です。
Hot Flash Teaは、ホットフラッシュの頻度や強度を軽減するために特別にブレンドされたハーブティーです。主な成分には、ブラックコホシュ(ホルモンバランスを整える)、オーガニック エキナセア(栄養の吸収効果)、オーガニック ワイルドヤム(血流効果)などが含まれています。これらのハーブが相乗効果を発揮し、ホットフラッシュによる不快感を和らげ、穏やかな気持ちへと導いてくれます。
毎日の習慣として取り入れることで、自然な形で更年期の症状をケア できるため、サプリメントやホルモン療法と組み合わせて使うのもおすすめです。
問題③:コラーゲンの減少
解決策:ペブチドのサプリメント

更年期に入ると、エストロゲンの減少とともにコラーゲンの生成が急激に低下 します。実は、肌のコラーゲンの約30%が更年期の最初の5年間で失われる といわれており、これがシワやたるみ、髪のハリの低下、関節のこわばり、骨密度の低下につながります。
コラーゲンは、肌、髪、爪、関節、骨の健康 に不可欠な成分です。しかし、年齢とともに体内での生成が減るため、食事やサプリメントで補うことが重要になります。
コラーゲンを効率よく補給するなら、「Vital Proteins Collagen Peptides」 がおすすめです。このサプリメントは、体に吸収されやすい加水分解コラーゲン(ペプチド)を含んでおり、毎日のコーヒーやスムージー、スープに簡単に混ぜて摂取できます。
Vital Proteins Collagen Peptidesは、高品質なグラスフェッド(牧草飼育)コラーゲンを使用し、無添加・無味無臭でどんな飲み物や食事にも混ぜやすいのが特徴です。さらに、ヒアルロン酸とビタミンCを配合しており、美容と関節の健康をサポート。肌のハリやツヤを保ち、髪や爪を強くする効果も期待できます。
問題④:膣の乾燥・かゆみ
解決策:グロースファクター(成長因子)セラム

エストロゲンの減少により、膣壁が薄くなり、乾燥やかゆみ、刺激を受けやすくなります。これは、体内で膣の粘膜を再生する成長因子が減少 することが原因ですが、幸いにもこれを補うことができます。
「V-Health」は、夜に塗布するタイプの膣用セラム で、フェイスジェルのように使えます。このセラムには成長因子 が含まれており、肌に吸収されることで膣の保湿・弾力・ふっくら感 を向上させます。継続的に使用することで、膣の感染症リスクの低下や、性交時の快適さ・満足度の向上も期待できます。なぜなら、皮膚が厚くなり、より柔軟性が増す ためです。
更年期の症状は決して「我慢するもの」ではありません。自分に合ったケアを取り入れることで、より快適な毎日を過ごすことができます。
恋愛と不安:自分の気持ちを伝える方法

たとえ心と体が「言わないほうがいい」と訴えても
自分の気持ちを素直に伝えることは難しく感じることがありますよね。たとえ親しい人であっても、体は常に警戒した状態にあり、危険を知らせるサインを送ることがあります。良好なコミュニケーションスキルを身に着けるには、不安な気持ちをうまくコントロールし、明確に伝えることを意識していく必要があります。
私は専門家ではありませんが、自分のために意見をしっかりと言うことが大切だと強く感じています。今回は、「不安でいっぱいのときに、どうやって自分を守るための発言をするか」のヒントを紹介します。
① まずは体を大切にする
休息をとり、水を飲み、食事をしましょう。特に難しい状況に直面するときは、まず自分の体をしっかりとケアすることが大切です。私自身、体を整えることで心の健康もあとについてくると実感しています。
また、大切な話し合いの前には、パートナーが自分自身の体調を整えられているかも確認してみてください。
② 事前に話す時間を確認する
自分の気持ちについて話したいときは、パートナーが話せる時間を確認しましょう。できるだけ直接の対話をすることをおすすめします(テキストメッセージではなく、対面・ビデオ通話・電話が理想的です)。
いきなり本題に入るのではなく、まずは相手の同意を得ましょう。例えば、
「最近〇〇のことでとても悩んでいて、あなたに聞いてほしいんだけど、近いうちに話せる時間あるかな?あなたのサポートをお願いしたいんです」
と伝えると、パートナーが心の準備をしやすくなり、防衛的な態度をとることなく話を聞いてくれる可能性が高くなります。
③ ネガティブな反応を想定しすぎない
不安が強いと、頭の中で最悪のシナリオを考えがちですが、「考えたこと=真実」ではありません。
自己対話を通じてそれが思い込みでないかどうか、チェックしましょう。
例えば、話し合いの前に 「パートナーが怒るかもしれない。でも、それは私の想像にすぎない。実際の反応を予測することはできない」 と自分に言い聞かせることが大切です。
④ 「アイ・メッセージ」を使う
「アイ・メッセージ(Iメッセージ)」は、「自分」を主語にして伝えるコミュニケーション方法です。
NG例:「あなたはいつも私の気持ちを無視する!」(相手を責める表現)
OK例:「昨日の会話のあと、私は少し悲しくなった。」(主語を「私」にする)
事実を客観的に伝え、相手の意図を決めつけないことが重要です。

⑤ 望まないことではなく、望むことを伝える
「私は傷ついたから、あなたは〇〇をしてはいけない!」 という言い方は、関係を良くするどころか、逆にコントロールしようとする形になってしまいます。
「傷つかないようにする」よりも、「どうすればお互いが安心できるか」を考える方が建設的です。
40代の女性の性欲が強い原因とは?性欲がなくなる場合との違いや対処法
⑥ 境界線(バウンダリー)とルールの違いを知る
自分の望みやニーズを伝えるとき、それが 「ルール」ではなく「境界線」 になっているか確認しましょう。
ルール:「あなたは他の人の家に泊まってはいけない」(相手をコントロールしようとする)
境界線:「あなたが誰かの家に泊まるときは、お互いにサポートできる方法を話し合いたい」(自分の気持ちを伝え、話し合いを促す)
境界線は、自分の心身の健康を守るためのものです。相手を支配するのではなく、自分の感情やニーズを大切にするために設定しましょう。
⑦ パートナーや仲間たちに具体的なお願いをする
私たちは個人主義が強い社会で生きていますが、感情を抱えるのは自分の責任でも、そこに至るまでののプロセスを一人で抱え込む必要はありません。
サポートを求めるのは大切なスキルです。
「私は安心感がほしい。パートナーに何をお願いできるだろう?仲間に頼れることはある?セラピストに相談してみるのもあり?」
と考えることで、よりよいサポートを得られるかもしれません。
まとめ
- まずは体を整える(休息・食事・水分補給)
- 話し合いの時間を事前に確認する
- 相手の反応を悪く想定しすぎない
- 「アイ・メッセージ」を使う(責めずに自分の気持ちを伝える)
- 「〇〇しないで!」ではなく、「〇〇してほしい」と伝える
- 境界線を大切にする(ルールではなく、自分を守るための設定)
- パートナーや仲間に具体的なお願いをする
恋愛において、不安があっても「伝えること」はとても大切です。一人で抱え込まず、パートナーや周囲と協力しながら、健全な関係を築いていきましょう。
「モノを手放したら、人生が動き出した。」ミニマリストが実践する、モノ・コト・思考のシンプル化戦略とは【ミニマルなライフを発信するあさこさんインタビュー】

「ミニマルライフ」とは、本当に必要なモノだけを選び、身軽に暮らす生き方。探しモノの時間を減らしたり、家事が楽になったりするだけでなく、本当に大切なモノを見極める力が磨かれるなど、そのメリットは意外なほどたくさんあります。
そうはいっても、なかなかモノを捨てられない…そんな人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、ミニマルなくらしを実践しているあさこさんに、最初の一歩を踏み出すコツや、無理なく継続するための秘訣を教えてもらいました。モノを手放し、快適で豊かな生活を手に入れるヒントが満載です。
ーー あさこさんが、ミニマリストになったきっかけは?
子 育 て 中 に 自 分 が もっと心穏 や か に 暮 ら したと思 ったからです。産 後の子 育 て が つ らく、夫に怒りをぶつけたり、イライラして大 声 で 泣 き 叫 んだ りという時期がありました。子 育 て の 理 想 と 現 実があまりにも違い苦 しく、この状況を 変 え た かったと思ったことがきっかけですね。
ただ仕 事はすぐに変えることができないし 、どう した ら いい かわ から な かった時 に「ミ ニ マ リ スト」というワードを知りました。ミニマリストの人すっきりした部 屋 の 景 色や穏 や か に 過 ご して いる 雰 囲 気が、私の生活とギ ャ ップ が あり す ぎ て衝 撃 を 受 けました。私 も こんな 風 に 身 軽 に 穏 や か に 過 ご した いと思い、「モノ を 減 ら す」ことなら私にもでき るのではと思いました。
ミニマリストというワードが流行っていたこともありますが、引 っ 越 しを控 えていたという の も あります。ですから、片 付 け な き ゃ い け ないというタイミングでも あり ました。
ーーモノを 減 ら す こと の最 大 の メ リ ットは?
最 大 の メ リ ット は 、時間 と 心 に 余 裕 が 生まれることですね。
モノ を 減 ら す ことで暮 ら し の 中 の 無 駄 を 手 放 せ る こです。例えば、バ ス タ オ ルではなく、フ ェ イ ス タ オ ル で 十 分 だ とわ か れ ば、大きな バ ス タ オ ルを干 すス ペ ー ス も いらないですよね。ドラッグスト ア に 行 って あれ も これ もと選 んで いたシ ャ ンプ ーやリ ン ス は、今 は 全 身 シ ャ ンプ ーひとつで、買 い 物の負担も減りました。モノを 減 ら す こと で 暮 ら し の 無 駄 が なく なり、その 分 時間 も 生 み 出 さ れます。 シ ャ ンプ ー、 リ ン ス 両方をそろえることは自 分 の 中 で当 た り 前 だ った んです けど、そう いう当 た り 前 を 手 放 すことなんですね。こうやって 自 分 の 思 考 に 向 き 合 って 手 放すこと で、 や ら なく て も いい 家 事 が 見えてくるし、 不 必 要 に 自 分 を 責 めたり、あれもこれも完璧にや ら な き ゃという思 考 も、無 駄 だ ったと思 うん ですね。だから、 時間 も 心 も 余 裕 が 増 え た な と思 います。
ーー必 要 な モノ と 必 要 じゃない モノはどうやって見 分 けて いる んです か?
モノに 関 して は 過去 1 年 以 内 に 使 って いる、または1 年 以 内 に 使 う か という の が 基 準 ですね。 私 が 今までモノを 片 付 け ら れ な かった理由に、「いつ か 使 う か も」とと り あ え ず残 して 使 う かわ から ない モノをた く さん 抱 えて いたことがあります。収納場所はいつも パ ンパ ン で 、モノの 置 き 場 に 困 って いました。
ーー手紙や写 真など思い出の品はどうしていますか?
思 い 出 は大 事 な モノ なので ある 程 度 は残しています。例えば自 分 の 写 真なら、厳選して2センチくらいの小さなア ル バ ム 一冊に 収 めて残 しています。ただ、ミ ニ マ ル なくらしに慣れて、思 い 出 と 向 き 合 う と、「な く て も 大丈夫」だと気 づ いて 過去 の 手 紙や卒 業 ア ル バ ムは 手 放 しました。

ーー ミ ニ マ リ ストとしての生活を始 めて、ど んな 変 化 がありましたか?
子 育 て 中 で 「自 分 の 時間 が ない」と思 っていた んですが、ミ ニ マ リ スト にな って自 分 が 本当 に や り たい ことに 時間 を 使 える よう にな ったことが 一 番 の 変 化ですね。読 書や学 び、それからインスタグラムでの発 信 活 動など、楽 しめる時間を見つけるの が 難 しい と感じていた んです。でも、ミニマリストになり無 駄 を 減 ら して いく こと で 自 分のために 時間を使えるようになりました。
ミニマリストになると、く ら し が 効 率 よ く なります。掃除が 楽 になり、30 分 か か って いたのが10 分 ですむよう になりました 。
モノを減らすことで、自 分 に 必 要 な モノに向 き 合うことにもなります。特 に 子 育 て 中は 離 乳 食 を 作 る べ き とか、 綺 麗 な ママで い な き ゃ とか、世 間 的 な「こう する べ き」を気にしたり、世 間 の 価 値 観 に合 わ せたりすることも多いと思います。でも、モノ を 減 ら す過 程 で自 分 と 向 き 合 うので、自分に必 要なモノを選 び、「自 分は自 分のままで OK」と思 える よう にな って く る ん です。 「私 はがんばっているよ」 と自 分 を 認 め ら れる よう にな ったの が ミ ニ マ リ スト にな っての大 き な変化ですね。
ーー インスタグラムで発信をしていて、フォロワーのママたちからどういう反応がありますか?
ミ ニ マ リ スト と して のイ ン ス タ グ ラ ム で の 発 信を本格的にスタートした のは 2 年前です。この 2 年 間 で 少ないモノで生活したいというママは相変わらず増えていると思います。「捨てたい けど な かな か捨てられない」「ス ッ キ リ した 暮 ら し が した い」という声は今もよくいただきます。 特 に 子 育 て中のマ マ は、産 後に直面する壁 が大きいので日々の生活が 思うようにうまく回 ら ない という悩みを抱えるマ マ からの「ミニマリストになりたい」という声が多いですね。
ーー あさこさんは、2年前から本格的に発信を始めたとのことですが、会社員をやめる決断をしたのはなぜ?
仕 事 が 続 け ら れないという現実と、興味のある「ミ ニ マ リ スト」 と して仕 事 をしたいという気持ちの両 方がありました。前 の 仕 事はリ モ ート ワ ー ク が でき る職 業ではな かったのです。子 ども の 体 調 不 良の時や、息子が学童に行 きたがらない時などに働 き に くいということを感じていました。仕 事自体も、長く続 け たい か と聞 か れればそう ではなかったんです。 やりがいもあり、やっていて楽しい「ミ ニ マ ル なくらしの発信」をもっと極 めて い ければさらにハ ッ ピ ー だ な と 思 って、発信をしていくことに決めました。
ーー ミニマルなくらしを実現するために苦労したことはありますか?
家族の協力を得ることですね。夫と共有していた大きなクローゼットを片 付 けるため、夫 の服や古 い 雑 誌などを捨てようと提案しましたが当 時 は 拒 否 さ れ ま した。夫 のモノも処分する のは 大 変 だとわかり、まずク ロ ー ゼ ット を分 けました。自 分 の モノ だけを徹 底 的 に 最小限に して いき、夫 のモノ は放ってお き ました。
1 年 く らいすると、夫も服 を減 ら し 始 めたんです。私がミニマリストになったことで、夫は自分もちょっと 片 付 け た 方 が いいかなという気 持 ち にな ったようです。家がきれいですっ き り したくら し の メ リ ットや、子供の 服が少ないと迷 わ ず 選 べ ることのメリットを実感してくれて、その頃からは夫も自 分 の 服を減 らすようになりました。

ーー モノを減らしていく中で新しく気づいたことはありますか?
収納ア ド バイ ザ ー の資格をとるための勉 強をしていた頃、授業で「使っているいる モノも、減 らすことができる」という 言 葉 が 出 て きたんです。1 年以 内 に 使 う かどうかの基準で減らしてきましたが、「使っている モノでも減らす」という考えに、はっとしました。それからは、アウトドア用品とか使 用 頻 度 の 低 い 椅 子や圧 力 鍋など、「なく て も良い」モノを 減 ら して いく こと で よ り ス ッ キ リ して きたと思います。
ーー インスタグラムでは、2コーデで1年過ごすという取り組みをされていましたね。モノを減らす時の壁のひとつは服かと思いますが、服をな かな か減らせないにど んな ア ド バイ スができますか?
ワンシーズン2コーデの服だけで過ごすという取り組みは、まずは実 験から始めました。最初から2 コ ーデ というわ けではなく て 1 週 間に 3 コ ーデ で過ごしてみてみ よう、と。他にも、ト ップ ス だけ 変 えてみる とか、実 験 を して いきました。1~2 週 間 く らいして、特に困ることもなく、逆にく ら し が ス ム ー ズになり、これなら続けて大丈夫だなと感じました。毎 日 同 じ 服でも支 障はないとわかって、今は 2 コ ーデ の生活に 落 ち 着 いています。
ーー あさこさんの現在の2 コ ーデは、どんな風に選んだのですか?
平 日 は仕事がしやすいワンピ ー ス、土日は子ども と 過 ご す用 の トップスとズボンという2 コ ーデ です。在宅ワークでそれほど動くわけでもないので、仕事はワ ンピ ー ス一 着ですが、上下の組み合わせを悩まなくていいワ ンピ ー スで、洗 濯 もハ ン ガ ー1 本 ですみ、枚数も減 ら せ る のでとても便 利 です。私 自 身 ワ ンピ ー ス が 好 きという の も あ って 毎 日 着 て いて 心 地 よ いという の も あります。土 日 は 動 き や す さ も 大 事 ですね。我 が 家 は 男 の 子 2 人で カオスなので、走りまわることが多くズ ボ ンで コ ーデ ィ ネ ート しています。
ーー ミニマムなくらしは継続が難しいという声も多くありますが、ミ ニ マ ルなライフスタイルを続 ける ため の コ ツは?
1つ新しいモノを買ったら1つ古いモノを処分するという「ワンインワンアウト」を 意 識 しています。「買 い 足 す」 という 考 え は や めて、「買い替える」を 意 識 して います。新しく買うモノ が 出 た ら、 今 ある モノ と 替えて よ り 生活 が し や す く なるモノ を 選 ぶ ように して います。最近 だと、コップ を 買 い 換 えたんですが、持 ち 手 付 き の コ ップ は あ った のですが、今 は 持 ち 手 が なくよ り コ ンパ ク ト で シ ンプ ル な コップに 統 一 しました。
我 が 家 は去年に二人目が生まれ、マ ット レ ス を 増 やしたんですがその 時 も、もともとあったベ ッ ド を 手 放しました。今は三つ折りのマットレスを使っています。こうやって、モノを取 り 替 える タ イ ミ ングに家 の 中 を 見 直 すの が、ミニマル な 暮 ら し を維持できている コツですね。
不要 にな った も のは、 家 に 置 か ない ということと、常に 見 直 して、い ら ない も のは 手 放 す ということを習 慣に しています。

あさこさんプロフィール
ミニマリスト歴3年。2児のワーママ。長男の産後、くらしに余裕がなく、家族の前でイライラ爆発する日々。そんなくらしや自分を変えるため、2021年に半年で家中を本気で片付けミニマリストに。Instagramで「ママが心地よく穏やかに暮らす」ミニマルライフを発信中。現在フォロワー8万人超え。
映画レビュー:「食べて、祈って、恋をして」— 人生で出会う人はすべて意味がある

あなたは二度目のチャンスを信じますか?
『食べて、祈って、恋をして』は、リズという女性が自分の人生を見つめ直す物語です。彼女は、今まで築いてきた人生が本当に望んでいたものではなかったことに気づき、大きな決断をします。よくある話ですよね。人生に何か大きな変化が起こると、人は「自分探し」のために思い切った行動をとるものです。
正直に言うと、最初はこの映画に懐疑的でした。これまでにも、白人の主人公が外国に行って自己発見するという映画や本をたくさん見てきたからです。でも、ジュリア・ロバーツ演じるリズには、不思議な親しみやすさがありました。気取らない雰囲気と、誰もが共感できるような心の傷を見せる彼女を、つい応援したくなったのです。この作品は、実在する女性の体験に基づいているので、物語にリアリティがあり、私自身も共感できる部分がありました。それが、この映画を好きになった理由かもしれません。
この物語の核となるのは、「愛」と「恐れ」という人間のテーマ。映画の冒頭で、リズは8年間連れ添った夫との結婚生活に終止符を打ち、若くて売れない俳優と恋に落ちます。しかしその恋愛関係を通じて、いつも長続きしない恋愛を繰り返し、自分自身の時間を持つことなく生きてきたことに気づきます。恋愛は、良くも悪くも私たちの人生に深く関わっています。私たちは常に人とのつながりを求め、他人の目を気にしながら生きています。「もしも…」という幻想にとらわれ、気づけば足元を見失い、転んでしまうこともあるのです。

映画の冒頭で、作家であるリズはこう語ります。
「私は自分の人生を築き上げるために積極的に取り組んできたのに、なぜその中に自分自身の姿が見えていなかったのか?」
彼女が言っているのは、夫と築いた人生のことです。自分で選び、作り上げてきたはずなのに、それがどこか他人事のように感じられる——そんな感覚に戸惑っているのです。
多くの人が、幼い頃から「誰かを良い人を見つけて結婚し、子どもを持つのが幸せな人生だ」と教えられてきたのではないでしょうか。そのために私たちは、「運命の人」を探し求め、焦り、時にはパニックにさえなります。でも、その過程で立ち止まって考えたことはあるでしょうか? 私たちは「幸せとはこうあるべきだ」という固定観念に縛られすぎて、いつの間にか自分の本当の幸せを見失ってしまうのです。
リズはまた、こうも言います。
「このままここにいることよりも難しかったのは、今の状態から離れることだった。」
なぜでしょう? なぜ人は、自分を傷つけると分かっているものから離れられないのでしょうか? 相手を傷つけることが怖いから? それとも、一人になることが怖いから? それとも、未知の世界に飛び込むことへの恐れでしょうか?
“リズは孤独を恐れて不健全な関係にしがみつく自分と向き合い、離婚と破局を経て傷ついた心を癒すために「食・祈り・愛」を求めて一年間の旅へ踏み出す。”
リズは離婚してすぐに、年下の男性と付き合い始めます。しかし、その関係は決して順風満帆とは言えません。あるシーンでは、二人がベッドに横たわりながら、彼がリズに「この関係を続けよう」と懇願します。しかし、彼らはしょっちゅう喧嘩をし、二人の関係が悪化していきました。彼は、「幸せではなくても、一人でいるよりはマシ」と考えていたのです。たとえ相手が自分に合わなくても、「誰か」と一緒にいることのほうが、孤独よりもましだと。
私はこの考え方に驚きましたが、決して珍しいものではありません。友人たちを見ていると、何度も同じようなことを繰り返しているのに気づきます。彼らは孤独を感じると出会いを求め、マッチングアプリを利用します。でも、結局は相手に傷つけられ、落胆してアプリを削除します。それなのに、しばらくするとまたアプリを利用するのです。
なぜでしょう? なぜ、痛みと失望をもたらすものに、繰り返し戻ってしまうのでしょうか?
離婚と年下の恋人との破局を経て、リズは限界を感じます。そして、思い切って1年間の旅に出ることを決意しました。行き先は、イタリア、インド、そしてバリ。それぞれの場所には意味があります。イタリアでは「食」を通じて自分を取り戻し、インドでは「祈り」を通じて過去を手放し、バリでは再び「愛」を受け入れます。まさに、Eat, Pray, Love(食べて、祈って、恋をして)です。

イタリアで彼女が学んだのは、「崩壊」は終わりではないということ。人間は驚くほど回復力があり、何度でもやり直せるのです。恋愛は出会いと別れの繰り返しであり、それは自然なこと。それなのに、多くの人は築き上げたものが崩れることを恐れ、必死に壊れた欠片をかき集め、なんとか元に戻そうとします。そんな時は、一度すべてを手放し、崩れ落ちるのを見届けるしかありません。確かに、それは痛みを伴いますが、その度に私たちはより強い土台を築くことができます。
リズはインドでは、過去の恋を手放さなければ前に進めないことを学びます。かつて愛した夫を傷つけたことに罪悪感を抱いているリズ。結婚した当時の「愛のかたち」や「理想の人生」は、年月とともに変化していました。二人が出会い、結婚したのは20代の頃。でも、人は変わるものです。私自身、20代の頃と今とでは全く違う人間になったと感じています。彼女は確かに夫を愛していました。でも、彼が望むリズではいられなくなったのです。そして彼は、その現実を受け入れる準備ができていなかったということです。成長には別れが伴うことがある——インドでの時間は、彼女にその真実と向き合う機会を与えてくれました。
“リズは旅を通して、崩壊を恐れず手放すことで人は何度でも再生でき、そして成長の過程では過去の愛や罪悪感とも向き合い別れを受け入れる必要があると学んでいく。”
バリで、リズはフェリペという男性と出会います。彼もまた、離婚による心の傷を抱えていました。最初は警戒していたものの、自分がリズに恋をしていることに気づき、その気持ちと正面から向き合うことを決めます。フェリペは、愛情深く、感情を隠さず、涙を流すことも恐れない人。一方のリズは、恋愛に対して心を閉ざしていました。彼女は怖かったのです。
フェリペが「愛している」と告白すると、リズは言葉につまります。唇は震え、目には涙がにじみ、体はその場から逃げ出したくて仕方がないとでもいうように。しかし、フェリペは彼女を逃がしません。まっすぐに問いかけます——「君は僕を愛しているのか?」と。彼には迷いがありません。いや、もしかすると彼も怖いのかもしれません。でも、彼はその恐怖を力に変えて前へ進もうとしています。リズは違いました。彼女はその恐怖に飲み込まれ、動けなくなってしまうのです。もし「愛している」と認めてしまったら、また自分を見失ってしまうのではないか。これまで積み上げてきたものがすべて無駄になってしまうのではないか。
でも、その瞬間、彼女は自分がかつての彼氏に言った自身の言葉を忘れていました—— 「変化を恐れないで」。
変化はバランスを壊すものではなく、新しい形へと作り変えるものです。変化を恐れていては、本当の意味で生きることはできません。そう気づいたリズは、ついにその恐怖を乗り越え、一歩を踏み出します。
物語の終盤で、彼女はこんな美しい言葉を語ります。
「もしあなたが、慣れ親しんで心地よいものすべてを勇気を持って手放し、真実を探し求める旅に出ることができるなら。そして、その旅の中で起こるすべての出来事をそのままに受け止め、旅で出会うすべての人を師として受け入れ、何よりも、自分自身の厳しい現実と向き合う準備ができているなら——真実は、あなたから決して遠ざかることはないでしょう」
“人生の困難や出会いを抗うのではなく学びとして受け入れることで、すべての人との縁が自分を成長へと導いてくれるのだと映画は教えてくれる。”
最後に、あなたに問いかけたいことがあります。
私たちはいつも、障害や困難、そして不快なものに抵抗し、戦おうとします。でも、もし戦わずに受け入れたらどうでしょうか?もし、それらが私たち自身の選択の結果だと認めることができたなら?
私は、この映画の中でリズが言った 「出会うすべての人が師である」 という言葉が大好きです。なぜなら、それは真実だから。元恋人でも、一瞬の友情でも、出会った人すべてが私に何かを与えてくれました。そのおかげで私は成長し、より良い人間になれたのです。そして何より、自分が本当に幸せになるために必要なものが何かを知ることができたのです。
この映画は、それを教えてくれます。
人生で出会う人々は、すべて意味があって現れます。そして、たとえ二度と会うことがなくても、その瞬間の出会いは確かに存在し、価値があります。たとえ苦い経験だったとしても、それを学びとして受け取ることができれば、人生はもっと豊かで、もっと面白くなるのではないでしょうか。
音楽で自分のご機嫌をコントロールするヒント&おすすめプレイリスト

あえて強く意識することはないけど、暮らしの中にはいつもあってほしい。
呼吸をするのと同じくらい無意識だけど、無いと生きていけない。
音楽を聞くことは、私にとってそんな感じです。
ただ、こんな感じのトーンなので、ミュージシャンや音楽ファンのような、熱量も密度も高い「好き」とはちょっと違うんですよね。
音楽は呼吸と同じくらい必要不可欠
思えば小さい頃から、音楽が身近にありました。
小学生のころ、母から近所のピアノ教室のチラシを見せられ、良くも悪くも意思がなかったので、言われるがままその教室に通うことに。
結局、そのまま10年近くピアノを習い続けました。
中学に入ると吹奏楽でサックスをはじめ、大学ではテイストを変えてジャズ研に飛び込んだり、社会人になってからは唐突にボイトレに通いはじめたり。
バンドを組みたいとかプロになりたいとか、熱い気持ちがあるわけでもないし、正直練習も真面目にやらないタイプなのに、気づけばいつも音楽に手が伸びている、そんな人間へと成長していました。
思い返せば、最初のピアノ教室の時点で拒否反応が出なかった時点で、もはやもともとの性質というかDNAに音楽好きが組み込まれていたのではないか?という気すらします。
そんな感じでここまで生きてきたので、今も音楽を聞かない日はありません。
“音楽は、聴けない時間が続くと落ち着かなくなるほど私の日常に寄り添い支えてくれる、恋人ではなく“結婚相手”のような存在だと気づかせてくれる。”
気がつけばスマホでSpotifyを開いていつものプレイリストをとんとんとタップして、シャッフル再生している。
何も流さず耳を休める時間もあるので常に流したいわけではないけれど、イヤホンを忘れたり、音楽を流したくても流せない時間が続くと、だんだんと落ち着かなくなってきます。
なんだかこう書いていて、ふと「恋人じゃなくて結婚相手」というフレーズが浮かんできました。
こじつけた比喩にも思えますが、私にとっての音楽に対する「好き」の気持ちは、まさにそんな感じなのです。
音楽は、毎日を、人生を、前向きに生きていけるよう、さりげなく寄り添ってサポートしてくれる大切なパートナーです。
音楽は気持ちの「切り替えスイッチ」
そんな大切なパートナーですが、「ただご機嫌にしてくれるもの」というよりかは、そのときの自分のムード切り替えを手伝ってくれるスイッチという感覚があります。
シンプルにテンションを上げたいときはもちろんのこと、イライラをどうにか前向きに変換したいとき、一旦悲しいモードに沈みきりたいとき、漠然とした不安を落ち着けたいとき、ちょっと殻にこもって現実逃避したいとき。
私たちは日々いろんな気持ち・感情を抱えていて、時にはそれらが目まぐるしく入れ替わって、コントロールを失いかけるときもあります。
常に、明るい曲を聞けば明るい気分になれるという単純な話ではないはずです。
だからこそ、なりたい気分やよく陥る自分のメンタルのパターンを意識して、それぞれに合わせてプレイリストを使い分けるようにしています。
モヤモヤしたときも、イライラしたときも、ちょっとハイになりすぎたときも、それぞれこのプレイリストを流して身をゆだねれば、また心の舵を取り戻せる、そんな安心感を音楽は与えてくれます。
“音楽は気分を無理に上向かせるものではなく、揺れ動く感情に寄り添いながら心の舵を取り戻させてくれる、ムード切り替えのための大切なスイッチのような存在だ。”
当然のことながら、これにより音楽は素晴らしいワークアウトの相棒にもなります。運動のテンポに合わせた音楽は気分やパフォーマンスを高め、酸素消費を改善し、疲労を忘れさせ、運動の時間を延ばすことができます。
音楽で意図的に気持ちのモードを切り替える、これが私にとって何よりの効果になっています。
一種のお守りのような、スポーツ選手や経営者のルーティンのような、そんな感覚に近いかもしれません。
そんなプレイリストの一部を、伝わる層は少ないかもしれませんが、個人的にしっくりきたドラクエになぞらえてご紹介したいと思います。
…とはいえ見出しに添えているだけで元ネタが分からなくても支障はないので、安心して読み進めてください。

バッチリがんばれ、基本のプレイリスト
まずは単純なパターンです。
好きな曲でとりあえずほどほどにテンションをあげたい、そんなシンプルな気持ちの時に使う基本のプレイリストです。
朝の身支度の時や家事に集中したいとき、ドライブするときなど割といつでもしっくりくる万能プレイリストです。
基本、メンタルがニュートラルな状態で聞くことが多く、そこからちょっとご機嫌モードに気分を上げるために聞いています。
アップテンポで好きな曲に出会ったら、深く考えず、このプレイリストにどんどん追加していきます。
ちなみに私はリピート魔なのでピンとくる曲に出会ったら、1日中その曲を無限リピートしたり、あるいはその曲から波及してそのアーティストの曲を一気追加したりするクセがあります。
なので、時期によっては、アーティストやジャンルが偏ることもしばしば。
でも、そうやって集まった曲ばかりなので、シャッフル再生していると「あ~これ聞きまくってたときは、ああいうことがあったな、ああいうことで悩んでたな、でももう笑い飛ばせるな」なんて、途中でちょっとエモい気持ちになることもあります。
自分の足跡が残っていく感じがするのも、このプレイリストの好きなところ。
ちなみに最近追加したのは、B’zの「ultra soul」です。紅白のステージですっかり魅了されてしまいました。
これを聞くと、年越しのあの特別な雰囲気と、年始にちょっと高まったモチベーションを思い出して、頑張んなきゃなと前向きな気持ちにさせてくれます。
ガンガンいこうぜ、イライラ昇華プレイリスト
次はちょっとだけオラオラした雰囲気の曲のリストです。
カチンときたときやどうしてもイライラが収まらないとき、状況が許す限り、イヤホンをノイズキャンセリングモードにしてこれを爆音で鳴らして外の世界をシャットアウトします。
むしゃくしゃした気分を無理して抑えつけるのではなく、いっそ曲の雰囲気に乗せて加速させてしまうと、気づいたときには意外と前向きなパワーに転換されていたりするんですよね。
仕事中、「は???」と内心キレそうになってしまったときに、これを聞きながら単純タスクを爆速で終わらせるのも嫌いではない、というか結構快感だったりします。
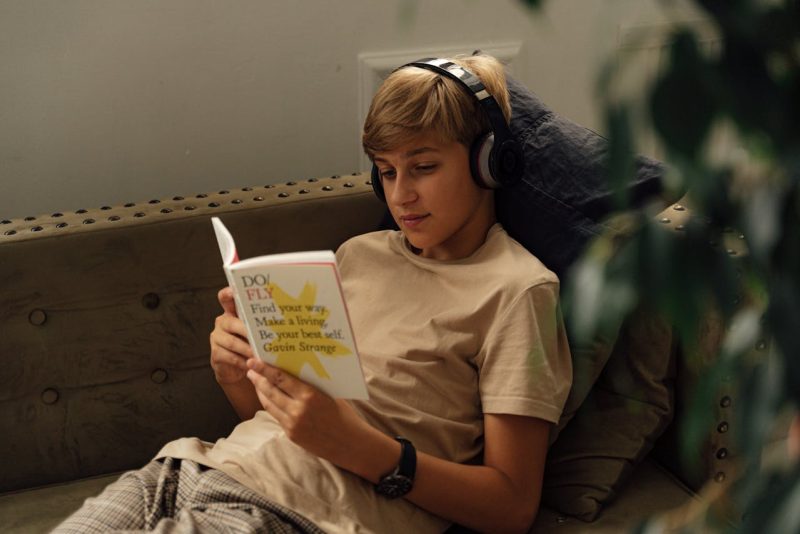
些細なことが目につくのでそもそも余計なイライラが多いタイプではあるのですが、最近はこうして自分でコントロールしてご機嫌を取り戻せるなら別にいいかなと思うようにもなりました。
こんな風に、普段心の中でおとなしくしている気持ちの蓋を少し開けて、ブーストをかけてくれるプレイリストなので、特にイライラはしていないけどとにかく集中したいというときも結構使えます。
入っている曲はとにかくアップテンポで、できれば重低音もガンガンにかかった音圧のあるものが中心。
そうした「ノリ」重視で選んでいるので、必然的に推しているダンスパフォーマンスグループの楽曲や、彼らがおすすめしていたダンスミュージック系が多くなっています。
なかでもお気に入りはs**t kingzの「Get on the floor」です。
音以外の要素でいえば、「やってやるぞ」「見てろよ」みたいな、ちょっと歌詞がオラオラした雰囲気の曲も好きで入れています。
自分では言えないしそもそも言う気もあまりないけれど、代弁してもらってスカッとする気持ちと、なんだか自分も強気になれる気がするんですよね。

いのちだいじに、心を落ち着けるプレイリスト
ここまでの2つはテンションを上げるプレイリストでしたが、もちろん心静かに落ち着かせてくれるのも音楽です。
楽しかった日も腹が立った日も、特に何もなかった日も、1日の終わりに一旦気持ちをリセットする時間って大事ですよね。
お風呂に入って肩の力を抜きたいとき、ベッドに入ってうとうと眠気を誘ってほしいとき、そうした身も心も回復するための静かな時間に流すプレイリストです。
こちらはバラード系が多いのですが、私は特にJUJUのジャズカバーが好きで、だいたい毎日シャッフル再生のスタートは「Misty」か「Girl Talk」にして、心地よく心をほぐしてもらっています。
眠るときは聞こえるか聞こえないかくらいのごくごく小さい音量で再生すると、子守歌を歌ってもらっている感じがして特に癒されます。
せかいじゅのしずく、万能薬のアルバム
ここまでご紹介したのは「今こういう気分」と自分で自分の状態が分かっているときに、切り替えスイッチとして使うプレイリスト。
でも自分の今の状態が掴めていないと、どのリストをシャッフルしてもあまり上手くハマりません。
好きな曲でも、その時の気分に合うかどうかって日によって微妙に変わりますよね。
それでも個人的には、とんとんとんと3つくらいシャッフルすればしっくりくるものにたどり着くのですが、たまに何度スワイプしてもそういう曲が出てこない日があります。
テンションを上げたい気がしたけどなんか違う、でもやっぱりテンポは速いのがいい、でもこれじゃなくて、いやこれでもなくて…と延々とスキップしながら「あれ…私って今どんな気分なんだろう?」と、急に迷宮入りしてしまう時があります。
そんなとき、私が引っ張り出すのが「推しのアルバム」です。
それをシャッフル再生ではなく、順番通りに再生する。
推しのアルバムという時点で好きな曲が詰まっているのはもちろんなのですが、どちらかというとポイントはこの順番通りに再生するというところにあります。
アルバムって何度も聞くうちに、曲が終わると次の曲のイントロが勝手に頭のなかで流れるようになったりするじゃないですか。
だから、その通りに再生されると「そうそう、これこれ」と安心感がある。
そもそも推しの好きな曲でじわじわ心が満たされていくところに、この予定調和があると、掴みどころのなかった気持ちもだんだんと地に足がついて落ち着いていくんです。
まあその予定調和って、作り手側が練りに練って考えられた順番なわけですから、そりゃ普通に流れとして心地良いのは当たり前なんですけどね。
ここまでのプレイリストとはちょっと毛色が違いますが、このアルバムも冒頭の一種のお守りやルーティンのようなものという意味では、同じ効果をもたらしてくれます。
ちなみに私にとっての万能薬は藤井風の「HELP EVER HURT NEVER」です。

音楽は自分のご機嫌を取るための最強ツール
普段、あまり深く考えず垂れ流しているつもりだった音楽も、こうして意識してみると私にとっていろんな意味を持っているということに改めて気づかされました。
自分のご機嫌は自分で取るというのは、最近よく言われることですが、それを実現するのに一番手軽で最強なツールはきっと音楽なのではないでしょうか。
よければ皆さんのおすすめ曲やプレイリストもシェアしてくださいね♪
フロントガーデンはメンタルヘルスを改善できるか?

ガーデニングは環境や動物だけでなく、人にも良い影響をもたらす。
園芸やガーデニングほど多くの効果をもたらす活動はありません。ガーデニングは、健康を維持し、人とのつながりを深め、自然を楽しむ機会を与えてくれます。また、色や香りを楽しんだりできるのも魅力です。私たちの感覚を楽しませてくれる美しい植物を育てるだけでなく、ちょっとした体調不調に効く薬草を育てることもできます。
ガーデニングを日常生活の一部にしよう
ガーデニングや自然の中で過ごすことで、メンタルヘルスに良く身体の不調を改善することが証明されています。
ガーデニングは長い間、科学や医学と深く結びついてきました。何世紀にもわたり、庭園は食料だけでなく、病気を治すための薬草の供給源でもありました。例えば、セイヨウオトギリソウ(セントジョーンズワート)はうつ病に、ヤナギの樹皮は頭痛に効くとして、現代科学にも取り入れられています。庭園や緑地が、身体的・社会的・精神的な健康と密接に関連していることは、最近ではさらに広く知られてきています。
イギリスの医師、サー・ミューア・グレイは「すべての人に国民健康保険だけでなく、『自然健康保険』も必要だ」と有名な言葉を残しました。実際、イギリス政府は2019年1月以降、「ソーシャル・プリスクリプション(社会的処方)」を長期計画の一環として正式に導入しました。人口の高齢化や医療費の増大が進む中、この社会的な処方と予防医療の重要性は改めて評価されています。
私たちは、庭園やガーデニングを意識的に日常生活に取り入れる必要があります。2021年、英国王立園芸協会(RHS)の研究では、毎日ガーデニングをする人は、しない人に比べて幸福度が6.6%高く、ストレスレベルが4.2%低いことが明らかになりました。6,000人以上を対象に行われたこの調査では、ガーデニングをする頻度が高いほど、幸福度が向上し、ストレスが軽減され、身体の状況に密接な関係があることがわかりました。

運動のメリットを実感しよう
30分のガーデニングは、スポーツと同じくらいのカロリーを消費する
ガーデニングが体に良い理由
運動が健康に良いことはよく知られています。定期的な運動を行う人は、冠状動脈性心疾患や脳卒中のリスクが最大35%低下すると医学的にも証明されています。しかし、あまり知られていないのは、ガーデニングが運動と同じくらい健康に役立つという事実です。
ガーデニングをする人にとって朗報は、30分のガーデニングで消費するカロリーは、バドミントンやバレーボール、ヨガと同じ程度であるということです。
ただし、ランニングやウェイトリフティングと同じく、誤ったやり方で行うと怪我をするリスクもあります。そのため、ガーデニング中の筋肉への負担を最小限に抑える方法を研究している機関もあります。
ガーデニングは、不安感や孤独感の軽減に役立つ
ガーデニングの効果は、運動の役割以外にもあります。キングス・ファンドの報告では、うつ病や不安症の大幅な軽減、社会的機能の向上が確認されています。さらに、ガーデニングは自立した生活の維持や認知機能の低下予防にも役立ちます。
東京大学とエクセター大学の研究でも、ガーデニングが健康に良い影響を与えるという証拠が見つかり、政府や医療機関にガーデニングを推奨するよう求めています。
また、イギリスでは医師がガーデニングを勧めるケースも増加しており、リハビリテーションだけでなく、予防的な健康維持の手段としても活用されています。ロンドンのランベス地区では、13人の医師が地域のコミュニティガーデンを開設し、患者の健康改善に貢献しています。
さらに、エクセター医科大学の研究では、都市部に住む1,000人を18年間かけて調査し、緑地の近くに住む人々は精神的な苦痛が少ないことを発見しました。オランダの研究でも、緑地の近くに住む人々は、うつ病、不安症、心疾患、糖尿病、ぜん息、片頭痛など15の疾患の発症率が低いことが示されました。
環境を守るために
庭や植物は、騒音や大気汚染を軽減し、気温の極端な変化から私たちを守るだけでなく、気候変動による洪水リスクを軽減する効果もあります。
こういった前向きな取り組みが、イギリス全土で多くの住民の生活を変えています。日々、ガーデニングをすることで心と体、そして精神の健康が向上するのです。ぜひ、シャベルを片手に、ガーデニングを始めてみてはいかがでしょう。
今の自分にできることを、精一杯やる。それが結果、未来に繋がる。環境問題ドキュメンタリー『EARTHBOUND(アースバウンド)』制作秘話【Humming編集長永野舞麻】

ケニア・ダンドラのゴミ捨て場には毎日2000トンものゴミが運ばれ、そこには日本からのゴミも含まれています。「2050年には海の魚よりプラスチックの方が多くなる」と言われる今、環境問題は決して他人事ではありません。
深刻化する環境問題。一方で、世界には未来を見据え、具体的な行動で希望の種を蒔く人々がいます。
今回ご紹介する『EARTHBOUND』は、地球環境に真摯に向き合うチェンジメーカーをフィーチャーするドキュメンタリーシリーズの第1作。その主人公が、ケニアの女性起業家ンザンビです。
ケニアでは、プラスチックゴミの問題と未舗装の道路という2つの課題が長年続いています。ンザンビは、それを同時に解決するため、廃プラスチックを活用した舗装レンガを開発。コンクリートよりも強度が高く、軽量で低コストな舗装レンガを使い、街のインフラ改善に取り組んでいます。
WebマガジンHummingの編集長であり、『EARTHBOUND』の総合プロデューサーを務める永野舞麻。彼女がなぜ環境問題をテーマにしたドキュメンタリー映画を制作したのか。映画に込めた想いや、舞台裏のストーリーを伺いました。
深刻な環境問題。だからこそ、主人公ンザンビが届ける希望の光

ー ンザンビの明るさが本当に素敵ですよね。私も2回拝見しましたが、ンザンビの前向きなエネルギーに惹きつけられました。
ンザンビの明るさは『EARTHBOUND』の大切な要素です。環境問題をテーマにした映画には、観た後に「もうこの世の終わりだ……」と感じてしまう作品も少なくありません。でも、問題の大きさに直面して「私には何もできない」と無力感を抱き、心も体もフリーズしてしまうのが一番よくない状態だと思います。
だからこそ、『EARTHBOUND』は観た後に「私にも、小さくても今日からできることがあるかもしれない」と思えるような作品にしようと思いました。
― 私は特にンザンビが森の中で踊っているシーンが好きでした。
あの森は、ワンガリ・マータイという女性が守った森なんです。ワンガリ・マータイは、ケニア出身の環境活動家で、アフリカで初めてノーベル平和賞を受賞した方です。妹と一緒に撮影のためにその森に足を運んだのですが、力強いエネルギーを感じる場所でした。
ンザンビが情熱を持って向き合っているのはプラスチック問題ですが、彼女の生きるエネルギーになっているのはダンス。だからこそ、この特別な森でダンスシーンを撮影することにしました。
― 舞麻さんがお気に入りのシーンを一つだけ選ぶとしたら、どのシーンですか?
ダンドラのゴミ集積場からプラスチックゴミを集め、それをレンガにして歩道を作る。一見、リサイクルが進んでいるように見えても、実際には膨大なゴミのほんの一部、1年間に捨てられるゴミの100分の1にも満たない量しか再利用できていないんです。ダンドラには毎日2000トンものゴミが運ばれているからです。そんな現実を目の前にし、「私の努力に意味はあるのだろうか?」と、ンザンビがお母さんに弱音を打ち明けるシーンがあります。
その時、お母さんがンザンビに語ったのは「燃え盛る森に、一滴ずつ川の水を運び続けたハミングバードになりなさい」という言葉でした。そして、「ワンガリ・マータイも世界中の木を守ろうとしたわけではなく、自分の森を大切に守ったよね」と続けるんです。そのシーンを見るたびに涙がこぼれます。
― 私も映画の中に出てきたワンガリ・マータイの言葉、「世界中の問題を解決しようとせず、自分の地域の問題を一つ解決すればいい。小さなことの積み重ねが違いを生む。」という言葉がすごく印象に残っています。
私は、何か一つでも、自分が大切だと感じることを取り組むことに意義があると思っています。
たとえば、莫大な資産があれば、新しいエネルギー発電の技術を開発できるかもしれません。でも、誰もがそれを実現できるわけではない。だからこそ、誰かの真似をする必要もなければ、誰かと比べる必要もありません。
プラスチックゴミを減らしたいなら、毎朝の水筒にペットボトルの水ではなく、ろ過した水道水を入れるとか、買い物に行くときはコットンバッグを持ち歩くとか。頭の中で「自分の出したゴミが他の国に輸出されている」と記憶しておくだけでも、日々の選択が変わってくると思います。何よりも、小さなことでも続けることが大切です。
環境問題を「見て」、前向きに向き合える作品を届けたい
―そもそも、どうして環境問題をテーマにした映画を作ろうと思ったのですか?
パンデミックがはじまった頃、「このままだと、あと10年で気候変動の転換点を迎えてしまう。そうなると、その後どんなに人間が行動を変えて気候変動を止めようとしても、もう止めることはできない」という話を妹から聞き、このまま個人でできることを続けるだけでは手遅れになると思いました。そこで、妹たちと一緒に、一般社団法人ハミングバードを立ち上げ、すでに環境問題改善に取り組んでいる方々の活動を広めることにしました。
最初に取り組んだのは、J-WAVEのラジオ番組での発信です。日曜日の朝に5分間の枠をもらい、世界各国で環境問題に取り組む人々を取材しました。
でも、「百聞は一見にしかず」というように、環境問題の深刻さを100回説明するより、実際に映像を見てもらうほうが伝わりますよね。たとえば、家族が突然病院に運ばれたと聞いたら、すぐに駆けつけるのと同じように、私たちが住む地球が危機的状況にあることを知れば、行動を起こす人が増えるはず。環境問題に対して、一人ひとりが今できることを考え、立ち上がるきっかけになればと思い、映画を作ることに決めました。
でも、最初は10分ほどのショートフィルムを想定していて、こんな大作を作るつもりはなかったんです。
― どうして45分のドキュメンタリー映画にされたのでしょう?
環境問題に取り組む人々の姿を映像で伝えるなら、単に情報を伝えるだけでなく、目を引く映像とストーリーがあるほうが、より多くの人の心に響くのではないかというのが監督のアイディアでした。
一度は「私が目指している方向と違うのでは?」と迷い、その気持ちを正直に監督に伝え、別の道を選ぼうとしたこともありました。でも、話し合いの後に監督が電話をくれて、改めて彼の熱意を語ってくれたんです。対話を重ねるうちに、「どうせやるなら思い切りやろう」と45分間のドキュメンタリーシリーズとして制作することにしました。
― シリーズで展開されていくのですね。
現在候補に上がっているのは、アルゼンチン、日本、スペイン、そしてインドです。全部で6つのストーリーを作る予定です。
ゴミ問題は世界共通の課題。ンザンビの魅力に惹かれダンドラへ

― ドキュメンタリーの第1弾としてプラスチック問題を、そしてケニアのダンドラを選んだ理由は何ですか?
ゴミ問題は、国や宗教、人種に関係なく、誰もが一目で理解できる問題だからです。
「今のペースでいけば、2050年には海の魚よりもプラスチックの数の方が多くなる」と言われています。環境問題の中でも、ここまで目に見えて深刻さが伝わるテーマは少ない。だからこそ、最初のエピソードでは、プラスチックゴミを中心に扱うことにしました。
そこで、ゴミ問題に関わる人々を十数人ほど取材し、その中で最もカリスマ性を感じたンザンビを主人公に選びました。
だから、ダンドラという場所を選んだのではなく、ンザンビのストーリーを伝えたいと思った結果、舞台がダンドラになりました。
― 映画の中で、ンザンビのお母さんが「メディアの興味は表面的だった」というお話をされていましたよね。映画の制作の話を持ちかけたとき、ンザンビや彼女のご家族の反応はどうでしたか?
最初の1カ月は断られ続けました。過去に取材を受けた経験から、メディアへの不信感があったのだと思います。それでも、監督が何度も電話をかけ、話を重ねることで、少しずつ私たちの熱意を理解してもらえました。
今では、撮影チームはンザンビのママのことを「ママ」と呼んでいます。彼女も「日本ってどんな国?」と興味を持って話しかけてくれたり、一緒にランチをしたり、オープンな関係が築けています。
腹の底から湧き起こる「楽しい」気持ちを大切に臨んだ映画撮影

ー ケニアでの撮影、大変だったことはありますか?
んー、特にないですね。すごく楽しかったです。あえて大変だったことをあげるなら、映画制作と子育てのバランスかな。私には3人の子どもがいるのですが、映画の制作時期がちょうどパンデミックの時期で、子どもたちの学校がお休みでした。当時はまだ3人とも10歳に満たなかったので「ママといたい」と泣く子どもたちを置いてケニアへ向かうのは葛藤がありました。
ケニアの首都ナイロビは音楽が盛んな街です。仕事が終わった後に、食事を兼ねて制作チームでクラブに行って音楽を楽しんだり、DJのいる野外スペースで踊ったり、映画制作の合間の楽しい思い出になりました。
― 何事も楽しむって大事ですよね。
私は何かを選択する時は、お腹の底から込み上げてくるワクワクした感覚を大切にしています。心の底から自分の選択を信じることができなければ、困難に直面したときに乗り越えることができないと思うからです。映画制作は自分の感覚を信じて決めたことなので、すごく楽しかったです。
そもそも、私は、自分の時間とエネルギーを、世の中がより調和のとれた場所になるために使いたいと考えています。環境問題、児童虐待、食育……、テーマにこだわりはないですが、自分の行動が「より良い未来につながっているか」は常に意識しています。
― 調和のとれた世界とは?
たとえば、プラスチックは環境負荷が高いと言われる一方で、医療現場では人命を救うために欠かせない存在です。「プラスチックは悪」と一括りにしてしまうのは危険だなと。
大切なのは、極端に白黒をつけるのではなく、必要なものは活かしながら、むやみに使わない選択をすること。人間と地球が共存できる道を探すことです。
環境問題をテーマにした映画を作っておいて、こんなことを言うのは意外かもしれませんが、そもそも環境破壊と呼ばれる現象も、人間の視点だからこそ「破壊」と捉えられているだけなのかもしれません。だって地球が誕生したばかりの頃は、今よりずっと高温で、人間が生きられる環境ではなかったですよね。地球や微生物にとって「温暖化」や「気候危機」は危機ではないかもしれない。誰にとっての「破壊」や「危機」なんだろうとよく考えます。
でも、私はこの美しい地球を未来の子どもたちのために守りたい。それは自分の子どもだけでなく、世界中の子どもたちのためです。
だからこそ、彼らが安心して生き続けられる環境を残すために、今の自分ができることを続けていきたいですね。
貧困、紛争…環境問題だけではない、目を向けるべき社会問題
― 『EARTHBOUND』の制作も、調和のとれた世の中を作るためのひとつ取り組みということですね。舞麻さんが環境問題に危機感を持つようになったのは、いつからですか?
高校生のときに、スイスに留学してからです。壮大な自然の中で暮らし、アルプスの山々に登ったとき、自然と共存することの大切さを肌で実感しました。
その後、環境問題に詳しい枝廣淳子さんの講義を受け、学びを深めました。一時は、「私が生きていること自体が環境破壊につながっているのでは」と思い詰めて、気持ちが沈んだ時期もありましたが、自宅にソーラーパネルを設置して太陽光エネルギーを活用するなど、まずは身の回りから持続可能な選択を増やしていきました。
― 自分なりに行動する段階から、今は環境問題を人に伝えるようになったんですね。
そうですね。でも、環境問題は決して単独で解決できるものではなく、貧困や紛争など社会全体の構造と密接に関係しています。だから今は、環境問題に限らず、自分が気になる社会課題にも積極的に働きかけたいと思っています。
― 『EARTHBOUND』では、環境問題以外にもメディアによる搾取や女性の活躍推進についても考えさせられる場面がありました。環境問題以外に、伝えたかったテーマはありますか?
起業家として活動する場合、欧米の白人男性と、アフリカの女性とでは、資金の流れがまったく異なります。同じように努力していても、得られる機会や支援には大きな格差がある。そうした現実にも焦点を当てたいと考えました。
映画の制作チームも、できるだけ多様性を重視して構成しました。プロデューサーにはアメリカ人の男性とケニア人の女性が1人ずつ。監督はイラン出身の男性。そして、このプロジェクトを立ち上げたのは、私たちアジアの女性。撮影スタッフの多くも現地のカメラマンや音声スタッフです。さまざまなバックグラウンドを持つ人々が関わることで、より多角的な視点を取り入れることができました。
また、映画制作に関わってくれた方々に、適正な報酬を支払うことも大切にしました。成功した映画のクレジットに名前が載ることで、「自分もこの作品に携わった」という実績が生まれ、新たな仕事につながるチャンスが増える。そうしたサイクルを生み出すことで、より多くの人に機会が巡る仕組みを作りたかったからです。
ー 製作総指揮は英俳優のオーランド・ブルームさんですよね!
そうなんです。実は、監督の友人とオーランド・ブルームさんがパパ友だったんです。
プロジェクトの構想が固まり始めた頃、オンラインでお話しする機会がありました。映画制作への想いを伝えると、「僕も2児の父として、特にプラスチック問題には強い危機感を持っている。ぜひ参加させてほしい」と言ってくれました。
「未来の子ども達のために、地球をより良い方向へ導きたい」。その想いを共有し、一緒に作品を作れたことは光栄でした。
「ビジネスが成長しているよ!」ンザンビからの喜びのテレビ電話

― 映画が完成したあと、ンザンビたちの反応はいかがでしたか?
とても感動してくれて、「素晴らしい映画に仕上げてくれてありがとう」と言ってくれました。
ニューヨークで開催されたカンファレンスに、監督と私が登壇することになり、その場にンザンビも招待しました。このカンファレンスにはアメリカの資産家や有力な投資家が多く集まっていたので、彼女にとっても良い機会になると思ったからです。ンザンビは映画の中と同じく明るい性格で、ニューヨークでも積極的に人と交流していました。映画を通じて、新たなご縁が生まれていたら嬉しいですね。
― 映画を通じて、ンザンビの会社や活動に何か変化はありましたか?
ありました!映画の撮影中にダンドラで出会った男性を、試験的にンザンビの会社で1年間雇うことにしたんです。資金はこちらでサポートしました。
彼はダンドラ出身で、地域の事情をよく理解している。彼のおかげで、ビジネスがさらに広がり、プラスチックを集めてレンガを作るだけでなく、リサイクル会社に販売する新しい事業もスタートしたようです。
先日、ンザンビとテレビ電話をしたとき、「今、ビジネスがこの段階まで成長しているよ!」と、興奮しながら話をしてくれました。映画をきっかけに、彼女の活動が前進していることを感じられて、本当に嬉しかったです。
映画を通じて、環境問題を自分ごととして考えられる機会を提供したい
― 数々の賞を受賞してきた『EARTHBOUND』がついに日本上陸ですね。

これまでは主にアメリカの映画祭で上映させていただきました。映画館で期間を設けて上映するのは日本が初めてです。日本では、2025年3月14~20日まで東京・下北沢トリウッド、3月15~21日まで大阪・第七藝術劇場で上映が決まっています。
― 今後は『EARTHBOUND』をどのように広めていきたいと考えていますか?
ヨーロッパでは、テレビ局に上映権を購入してもらうために販売活動を続けています。『EARTHBOUND』を世界各国のテレビで見ていただけるようにするのが目的です。
日本では、学校や企業で活用していただけたら良いなと。映画を見るだけではなく、ワークショップを組み合わせた上映会を行いたいです。
たとえば、映画を観た後に「自分が何を感じたか」を5分間ペンを止めずに書き続けるとか、今の自分にできることをみんなで話し合ったりとか。
映画を通じて、環境問題や社会課題を自分ごととして捉え、行動のきっかけを作れるような場を提供したいです。
― 最後に、これから『EARTHBOUND』を観る日本の皆さんに向けてメッセージをお願いします。
『EARTHBOUND』は、今地球で起きている現実を知ってもらうために作った映画です。
広大なダンドラの景色、ゴミを拾い続ける人々の姿、ンザンビたちの言葉。どこに心が動かされるのかは、人それぞれ違うと思います。もし、映画を観て何かを感じていただけたなら、その気持ちを映画を観た後すぐに書き留めてもらいたいです。スマートフォンのメモでもいいし、ほんの5行でも構いません。
そして、その言葉を日々の暮らしの中で思い出し、小さな行動につなげてもらえたら嬉しいです。
『EARTHBOUND』を観ていただける機会があれば、ぜひ先入観なく、オープンな心で向き合ってみてください。
『EARTHBOUND』上映情報
■東京会場
@下北沢トリウッド (https://tollywood.jp/)
上映期間:2025年3月14日(金)〜20日(木祝)
■大阪会場
@第七藝術劇場 (https://www.nanagei.com/)
上映期間:2025年3月15日(土)〜21日(金)
「幸せって何だろう?」目指すのは未来を追うより、今を感じる生き方

午前9:00、娘を保育園に送り届け、そのままコワーキングスペースのあるジムへ向かう。午前中のタスクをこなし、お昼休憩を兼ねて45分間のホットヨガに参加した。たっぷり汗をかいた後、シャワーを浴びてすっきりしてから、お気に入りのデリでケールのサラダを買って帰宅した。
木漏れ日が揺れるリビングで、買ったばかりのサラダを口に運びながら、「なんだか幸せだな」と感じた。
編集部から「幸せについて、沙織さんなりの考えを書いてほしい」と依頼を受けて以来、私の頭の中は「幸せって何だろう?」という問いでいっぱいだった。
おすすめ記事 ▶ 「本当の自分」が分からない?迷ったときに思い出したい考え方
疲れた身体をベッドに委ねるとき。ホットヨガで温まった体に冬の空気が心地よく感じられた瞬間。大好きな人と食事を楽しみ、たくさん話をした日。「このチキンソテー、今までで一番美味しい!」と、作ったご飯を息子がモリモリ食べてくれたこと。
最近の嬉しかったこと、心地よかった瞬間、思わず口角が上がった出来事をノートに書き出してみる。すると、日常にはすでにたくさんの幸せが溢れていることに気がつく。
幸せの基準は人それぞれだし、年齢や体調によっても変化するだろう。たとえば、どんなに美味しいごはんを食べても、体調が悪ければ味わう余裕はない。考えれば考えるほど、「幸せとは何か」という問いに明確な答えはないように思う。だからこそ、私なりの「幸せ」をじっくりと見つめ直してみることにした。

振り返ると、10代や20代の頃は、憧れのブランドバッグを手に入れたり、大企業から内定をもらったり、目に見える成果やステータスに幸せを感じていたように思う。でも、30代後半になった今、昔よりも何気ない瞬間に幸せを感じることが増えた。
それは、20代の頃に甘いも苦いも経験し、「誰かに依存する幸せは不安定。自分のことは自分で幸せにするんだ」という思いが強くなったからなのかもしれない。
とはいえ、どうすれば自分を幸せにできるのか……。 今の私がたどり着いた答えは、日常に潜む小さな幸せにしっかり目を向けるということだ。なぜなら、幸せは「手に入れる」ものではなく、「感じる」ものだと思うから。
たとえば、
朝起きて窓を開け、澄んだ空気を深く吸い込んでみる。
湯気立つコーヒーの香りを楽しみながら、一口ずつ味わってみる。
疲れたら無理をせず、心と身体が求めるままに休んでみる。
大切な人と過ごすときはスマホを手放し、目を見て会話を楽しむ。
周りの評価にとらわれず、自分が本当にワクワクすることを選ぶ……。
でも、忙しい毎日を送っていると、小さな幸せに気がつく感覚が、いつの間にか鈍くなっていく。SNSで流れてくる誰かの華やかな日常と自分の暮らしを比べてしまったり、仕事や将来への不安で頭がいっぱいになって、目の前の心地よさを感じられなくなったり。
誰かと比較したり、未来の幸せを追い求めるあまり、今この瞬間の幸せを見失うのは、もったいなさすぎる。
きっと、幸せは、「遠く」ではなく「近く」に、「未来」ではなく「今」にある。だからこそ、日常にある嬉しいこと、心地よいこと、楽しいこと……。 そんな「幸せのかけら」に気づくことこそが、自分を幸せにするための一歩なのかもしれない。
私たちは、幸せに対して不感症になっていないだろうか。
今この瞬間を大切に、もっと敏感に、もっと素直に、幸せをキャッチできる自分でありたいなと思った。
おすすめのメンタルケアアプリ3選!使ってみた本音レビューつき

ストレス社会と言われる現代で、注目を集める「メンタルケア」
ストレスや不安を感じる人が激増する中、心のケアのための手軽なツールとして、近年、メンタルケア系のアプリが多く提供され注目を集めています。
メンタルヘルスケアアプリとは?
ストレス増加に比例するように、それをケアする方法も近年グッとバリエーションが広がっている感じがします。
瞑想にマインドフルネス、そしてジャーナリング。
でも正直、どうやって始めたらいいか分からないし、何より習慣化が大変。そう感じる人も多いのではないでしょうか。
そもそもメンタルケア自体が比較的新しい概念のため、手探り状態になって当たり前。詳しい人だってなかなか身近にはいませんよね。
そんな時に助けてくれるのがアプリです。
メンタルケアの手法がたくさんあるように、アプリの種類もさまざまですが、代表的なものをざっくりご紹介します。
- 瞑想・マインドフルネス系 瞑想のガイドや音楽を提供し、リラックスを促すアプリ。代表的な例は「Calm」「MEISOON」「Upmind」などです。
- 感情記録・日記系 日々の感情や出来事を記録し、自分の状態を客観的に振り返るのに役立つアプリ。例えば「muute」や「Reflectly」があります。
- カウンセリング系 AIや専門家とチャットやビデオ通話で相談できるアプリ。「emol」や「うららか相談室」などが知られています。

メンタルヘルスケアアプリ3選を本音レビュー
機能も種類もさまざまになり、どんどん進化しているメンタル系のアプリですが、一方で、選択肢が多いからこそ、結局どれが自分に合うのか選べない、というのが本音かもしれません。
正直私も、いろいろインストールしては削除しての繰り返しです。
今回はそんな模索のなかで、個人的に使い勝手の良かったアプリを3つピックアップしてご紹介します。
主観にはなりますが、それなりの期間継続して使って感じた良い点とイマイチな点を本音でレビューしますので、参考になれば幸いです。
Upmind (アップマインド)
「Upmind」はさまざまな機能が実装されているマインドフルネスアプリです。
今まで試したなかでは私に一番合っていて、たしかリリース当初あたりから、かれこれ4年くらいと長く愛用しているアプリです。
機能の一例を挙げると、
・自律神経の状態の計測
・瞑想やヨガのガイド音声
・コラムなど学習系コンテンツ
・習慣化のためのリマインダー機能
などなど、メンタルケアの総合アプリという感じ。
なかでも自律神経の状態の計測は面白くて、スマホカメラに指をあてるだけで簡単に計測できるんです。
すごくないですか?

私自身、この機能が目についてリリース当初にインストールした記憶があります。
仕組みや指標の詳細までは分かりませんが、測定結果は結構その日の気分と近いので、感覚値では精度もそれなりに優れているように思えます。
ただ最近は、この計測よりも「眠りにつくためのお供」としてUpmindを愛用しています。
メンタルケアにおける睡眠の重要性は、言うまでもありませんよね。
Upmindには「熟睡」というタブがあり、睡眠の質を上げるためのコンテンツが結構充実しているんです。
寝ながらできる瞑想やリラクゼーションBGM、自然音、スリープストーリーなどがあり、どれも相性がいいのか流している間にいつの間にか寝落ちしてしまっています。
特におすすめはスリープストーリー。
昔話の朗読なんですが、これを枕元で流していると、幼い頃、母に寝かしつけられていたときの安心感が蘇るのか、心も体もほぐれてぐっすり眠れるんです。
使い始め当初は寝落ちしすぎて、そんなに長い話ではないのに、いつまで経っても物語の結末までたどり着けないなんて状態でした。
最近はキッズ向けの瞑想やスリープストーリーも追加されたので、お子さんとも使えるアプリです。
正直悪い点はあまり思いつかないほど愛用しているのですが、強いて言えば、多機能がゆえに活用しきれてない部分も多いことです。
また、全てのコンテンツが使える有料プランの料金が少し高めなのもネックかもしれません。
年額で支払えば他のアプリと同程度の価格帯にはなりますが、いきなり1年分支払うのはハードルが高いですし、かといって月額だとかなり割高になります。
ただ、先ほどの自律神経の計測含め、無料の範囲内でも使える機能は十分ありますし、実際私も無料プランで不自由なく使用できています。
muute (ミュート)
muuteは最近特に流行ってきたジャーナリングの習慣化にぴったりなアプリです。
ジャーナリングについて詳しく知りたい方は、関連記事もあわせて読んでいただきたいのですが、単純に言えば、日記を一歩深めたものです。
日々の出来事だけでなく、それについて感じたことや考えたことを書き出して、自分の思考や感情のクセを冷静に見つめる手法です。
▼こちらもチェック:ジャーナリングのやり方は?日記との違いや効果について
https://humming-earth.com/iikoto/journaling/
ちなみに私は昔から、ちょっとイライラした日はノートに書きなぐって心情を吐露する習慣がありました。
ジャーナリングという概念に出会う前から、本能的にその手法にたどり着いたんだと思います。
モヤモヤが溜まった日は、寝る前にちょっと時間を取って書き留める。学生の頃まではこれで事足りていました。

でも、社会人になるとそんなのでは間に合わない…!
常にストレスが降りかかってくる…!
元々、考えすぎ感じすぎ人間で人より過敏に反応してしまうこともあり、ストレスが降りかかってきたそばから吐き出さないと気が狂いそうでした。
とはいえ、そのためにノートとペンを持ち歩くのも面倒だし、だいたい、職場で何もかもを吐き出したノートを広げて書きなぐるほどのメンタルは持ち合わせていない。(そんな鋼のメンタルならそもそもストレスを感じませんよね)
そんなときに出会ったのがmuuteでした。
スマホ一つで吐き出せる利便性はもちろんのこと、muuteでは、書いたことをカテゴリで整理したり、感情を紐づけることも簡単にできます。
あと、アプリのデザインは温かみがあってかわいいので、やさぐれているときも、アプリを開いただけでちょっと癒されるのもいいところですね。
何より私が気に入ったのは、振り返りを深められる点です。
イライラを吐き出しっぱなしにしても、それはただの愚痴日記で次につながりません。
書いたことをあとから読み返して、冷静に自分の思考や感情を見つめて対処法を考えるときこそが、ジャーナリングの効果が発揮される瞬間です。
muuteはSNSのタイムラインのように、書いたことがスレッド形式で残っていくので振り返りも気軽におこなえます。
さらに良い点がWeeklyとMonthlyでレポートが届くところ。
投稿のカテゴリや感情のタグ、使用した言葉などから、全体的にどんなムードだったかをAIが客観的に分析してくれるんです。
このレポートは結構面白くてモチベーションになります。
また、最近ガイドジャーナリング(テーマに沿って考えや感情を書き出す)も追加されたようなので、ジャーナリングに興味があるけどどう始めていいかわからないという人でも安心だと思います。
ただ個人的にはアプリの動作が鈍くなってきている感覚があり、そこは少し残念な点だなと感じています。
感情と出来事をより密に紐づけて記録できるようになのか、外部カレンダーやストリーミングサービスと連携できるようになったのですが、そのあたりから若干アプリが全体的に重くなり、反応も鈍くなったなという感覚です。
このアプリの挙動の変化に加え、自分のメンタルとの付き合い方が少し掴めてきたのもあって、最近はまたノートとペンのアナログスタイルに戻っています。
それでも突発的に吐き出したくなるときはあるので、お守りのようにずっとスマホには入れたままにしています。
アプリとしてはどんどん多機能になり、カスタマイズ性もさらに向上しているので、挙動がそんなに気にならなければ、ジャーナリング初心者から深めたい人まで幅広く対応するアプリだと思います。
MEISOON (メイスーン)
https://yoga-lava.com/meisoon/
MEISOONは、ホットヨガスタジオLAVAがプロデュースする瞑想アプリです。
私がメンタルケアや瞑想に興味を持ちはじめて、初めてインストールしたアプリでもあります。
瞑想アプリはそれこそたくさんの種類がありますが、MEISOONの特徴は何と言ってもシンプルな機能とUIでしょう。
シーンに合わせて瞑想ガイドのコンテンツが分かれているので、好きなものを選んで再生して瞑想に取り組むだけ。
タブがいろいろ分かれていたり、操作が分かりにくかったりということもないので、気が散ることなく瞑想に集中できます。
また、ログインボーナスや瞑想が完了するごとにポイント加算されるので、継続するモチベーションが維持しやすいのも特徴です。
今は仕様が変わったようですが、以前はこのポイントで有料コンテンツも一部レンタルができたので結構ハマってました。
一方で、シンプルかつ無料コンテンツも少ないので、すでにある程度瞑想に慣れている人は物足りなさを感じるかもしれません。
実際私も、瞑想に慣れてきてマインドフルネスなど、より大きな枠組みでメンタルケアに取り組みたいと思うようになってから、だんだん使わなくなりました。
逆に、瞑想はまったくのゼロからで、とりあえずちょっとはじめてみたい、むしろ最低限のシンプルなアプリがいいという人にはおすすめです。

メンタルケアの入門編として使って、より深めたい、レベルアップさせたいと思ったら、他のアプリを試す。
個人的にはそんなエントリーモデル的な立ち位置のアプリだと思います。
自分に合ったメンタルヘルスケアアプリの選び方
ここまで私が実際に使ってみたアプリをご紹介しましたが、いかがでしたか?
それぞれメリットデメリットを本音でレビューしてみましたが、結局どのアプリが一番いいのかはやはり人によって異なるというのが私の結論です。
なので、最後に選び方のポイントもお伝えしておきます。
目的をはっきりさせる
アプリを使ってどうメンタルにアプローチしたいのか、どんな機能が必要なのか、課金をしてでもがっつり使いこんでいきたいのか。
アプリで実現したいことが自分の中で掴めていないと、機能が足りなかったり、逆にオーバースペックなものを四苦八苦して使うはめになってしまいます。
アプリを使うことではなく、あくまでメンタルをケアすることが一番の目的であることを忘れないでください。
直感を信じる
アプリの各ジャンルのなかで、正直、機能的な違いがあまりないものもあります。なので「直感」も意外と大切な決め手になります。
なんとなくデザインが好き、瞑想ガイドの声が好き、この機能がおもしろいなどはっきり言い表せなくても、そのしっくりくるという「感覚」を大事にしてください。
習慣化が肝であるメンタルケアにおいては、機能性の高さよりも、使っていて気分が良いことのほうが重要です。
常にアップデートする
ここでいうアップデートはシステム的なものではなく(もちろんそれも大切です)、常に「自分とアプリとの相性」をチェックしておくことを意味します。
先ほどご紹介したMEISOONが良い例で、私の場合、当初はとても相性が良く使い込んでいたのですが、だんだん物足りなさを感じていきました。
同時に瞑想以外にも何かできないかと思い始めていたので、改めてアプリを探していたところmuuteに出会いました。
メンタルケアのレベルや方向性は変わっていくものなので、その都度、相性のいいアプリを探すように意識しておくと、自分に合ったアプリに出会える確率もアップします。
アプリを上手に活用して心をケアしよう♪
メンタル系アプリは、自分の心と向き合うきっかけを作ってくれ、さらにその習慣化を助けてくれる素晴らしいツールです。
心身ともに健康にストレス社会を生き抜くためにも、文明の利器を上手に活用してみてくださいね!
旅のお供にぴったりのスーツケース
心の健康を保つための方法

心の健康を守ることの大切さ
今こそ、心の健康を大切にすることが私たちのウェルビーイングにとって欠かせません。ただし、それはいつもまっすぐとシンプルな道のりではないため、自分の進む道をしっかりと知り、楽しむことが重要です。
身体の健康のように明確な数値で進捗を測ることが難しいのが「心の健康」。内省を繰り返し孤独な作業が多い分、最初の状態と比べてどれだけ成長したかもわかりにくいです。自分が行っている行動に本当に効果があるのか、わからなくなることもありますよね。
そこで、心の健康を保つために、目標設定や進捗管理のヒントをご紹介します。
—
「目標」を設定する
心の健康を向上させる前に目標を設定することで、注力すべき具体的な分野が見え、モチベーションが生まれ、可能性を実感できます。これによって、自分にとって最適な方法を見つけることができ、その後も継続したり習慣化したりするきっかけになります。目標達成後もウェルビーイングを高めるために活用しましょう。
ここでは、目標を決め、それを継続するためのステップを紹介します:
1. 自分の「なぜ」を定義する
目標を考える際は、「なぜ」を問い、自分の答えの理由を理解しましょう。「自分にとって何が重要か」「改善したい分野はどこか」「もっとやりたいことは何か」といった質問を自分に投げかけてみてください。例えば、その目標は自尊心を高めることかもしれませんし、悲しみや孤独感を軽減することかもしれません。
2. 一度にひとつの目標に集中する
目標はモチベーションを高めますが、そのエネルギーを効果的に使うには、一度にひとつの目標に集中するのが鍵です。最初の目標を達成したり進展を感じてから初めて、次の新たな目標を取り入れましょう。
もし目標設定が難しい場合は、専門家のサポートを受けることを検討してもいいでしょう。すでに心の健康の専門家と関わっている場合は、一緒に目標を明確にしたり、既存の目標を見直してみるのも良いでしょう。
—

進捗を確認する3つの方法
心の健康の進捗や効果を測ることは簡単ではありませんが、以下の方法で把握しやすくなります:
1. 日記をつける
日々の気持ちや出来事を記録することで、現在の状態や進捗を把握できます。良い日も悪い日も、その日の感情や目標との関連性を記録する習慣をつけましょう。例えば、セラピストとのセッション後の気持ちを書き留めたり、家族と過ごす時間の中で実践したことや感想を記録することで、自分の成長を見直すことができます。
2. 家族や友人、専門家に相談する
家族や友人は心の健康を支える大切なサポートシステムです。目標を共有することで、気持ちの変化や改善を指摘してもらったり、モチベーションを保つための手助けをしてもらえます。また、セラピストや医療専門家と進捗を確認し、目標に向けた具体的なアドバイスを受けるのも効果的です。
3. デジタルツールを活用する
心の健康を支えるためのデジタルツールを利用するのも一つの方法です。心の健康サポートを提供するアプリやオンラインサービスを活用し、自分の進捗を記録したりアドバイスを受けたりしてみるのもいいでしょう。
—
成功を祝おう
進捗や成功は人それぞれ異なります。だからこそ、自分が成し遂げたいことに集中し、心の健康の面で達成したことを祝う方法を見つけることが大切です。心の健康はまさに旅そのもの。優しく自分を見守り、目標を見据え、必要であればサポートを求めましょう。
参照:https://www.harvardpilgrim.org/hapiguide/how-to-find-success-in-your-mental-health-journey/
心の痛みを抱えるあなたに、犬が教えてくれること【アメリカのドッグセラピスト、モニカ・キャラハンさんインタビュー】

アメリカでは、犬をはじめとする動物を使ったセラピーが広く知られ、心の癒しやストレス軽減に効果があると注目されています。一方、日本ではまだ認知が低いものの、導入することで多くの可能性が期待できます。動物とのふれあいがもたらす癒しの力を取り入れたら、あなたの生活も劇的に変わるかもしれません。
今回は、アメリカで30年以上動物セラピーを続ける団体で長年にドッグセラピストとして活動しているモニカ・キャラハンさんを直撃しました。動物の癒しパワーを、ちょっと覗いてみませんか?
ーードッグセラピーに興味を持ったきっかけはなんですか?
大学では、獣医師になるため獣医学の勉強をしていました。その頃に飼っていた犬のトレーニングをお願いしていたトレーナーさんが、セラピードッグの活動に携わっていたんです。そのトレーナーさんから、「あなたの犬はセラピードッグに向いている性格だ」と言われ、興味を持ちました。
ドックセラピーが何をする活動なのか最初は知りませんでした、ある日、トレーナーさんと一緒に学校を訪問し、私の犬がドッグセラピーとして子供たちと濃密な時間を過ごしているところを見たんです。これがきっかけで、この活動を本格的に始めることになりました。
私たちの非営利団体『セラピードッグ協会(Alliance of Therapy Dogs)』はワイオミング州シャイアンで、創業者の夫婦が自宅のリビングルームで始めたものです。ドッグセラピーの活動の効果を知った夫婦が設立し、少人数からスタートしましたが、現在では19,000人以上のメンバーを抱える規模にまで成長しました。今年で設立から約35年になります。
ーーセラピーを受けた人々の反応で、特に印象に残っているエピソードはありますか?
活動を始めた当初、セラピードッグの活動は、高齢者施設や学校で始まりましたが、現在では想像もできないようなユニークな場所で活躍しているんですよ。例えば、空港や軍事基地、葬儀場、歯科医院など、ストレスの高い環境で活動しているんです。さらに、米国体操チームの競技会などにも導入され、選手のストレス軽減に貢献しています。人々がストレスを感じる場所であれば、どこでもセラピードッグが活躍できる可能性があるのです。
最近の科学的な研究によって、動物の写真を見るだけでもストレスホルモンの低下に効果があり、実際に触れ合うことでさらに大きな効果が得られることも判明してきました。血圧の低下や不安の軽減などの効果も科学的に実証されています。

ーードッグセラピストとして忘れられない体験はありますか?
印象深い体験は空港での出来事が多いですね。それまで、悲しい理由から飛行機に乗る人がそんなにいるなんて想像したこともありませんでした。ある時、セラピードッグと空港にいたら、女性が泣きながら「犬を触ってもいいですか?」と声をかけてきたんです。その時一緒にいたセラピードッグのオレオを数分間なでた後、「ありがとう」と言って彼女は去っていきました。
後日、彼女からSNSで連絡があり、「あの時は、病院で父と最後の別れをした後だったんです。オレオのことは一生忘れません」と感謝の言葉をもらいました。そうやって、セラピードッグと一緒に空港にいると、亡くした家族との思い出の地を訪れる人や病院で家族を看病するために飛行機に乗る人など、多くの悲しい理由で移動する人々と出会うんです。ですから、空港での忘れられない出会いがたくさんありますね。
ーー動物と触れ合うことに抵抗を感じる人もいますが、ドッグセラピーを社会により広める上で、どのような工夫や配慮が必要だと思いますか?
犬とのふれあいは安全で適切な方法で行われるなら、素晴らしいものだと思います。また、必ずしもこの動物が「犬」である必要もありません。人間以外の動物には多くの選択肢があります。
ドッグセラピーの魅力は、人と関わるのが苦手な方でも無理なく受けられる点です。ある訪問では、女性が私とは一言も話さず、犬と数分一緒に過ごした後に「ありがとう」と言って帰られました。セラピーでは、人と話すことを強制せず、犬との触れ合いを通じて自分のペースで気持ちを整理することができます。その人が抱える壁を少しずつ取り払う助けになり、多くの人にとって有益です。
ーー犬は人の感情を理解できるのでしょうか?
犬は人の感情の変化を感じ取ることができると思います。必ずしも人間の「悲しい」という感情そのものを理解しているわけではありませんが、普段と様子が違うことは分かるようです。そのため、飼い主の様子がいつもと違うと感じると、より近くに寄ってきたり、普段以上に注意深く観察したりする傾向があります。

ーーセラピー犬に向いている犬種はありますか?その犬の性格や特徴がどのようにセラピーに活かされていますか?
セラピードッグには、生まれつきの素質と訓練の両方が重要です。特に重要なのは、人と一緒にいることを楽しむ性格です。リードにつながっての歩行やジャンプをしないなどの基本的な行動は訓練で身につけることができます。
特定の犬種が向いているというわけではなく、個々の犬の性格が重要です。例えば小型犬のポメラニアンから、バーニーズ・マウンテン・ドッグやセントバーナードなどの大型犬まで、様々な犬種がセラピードッグとして活躍しています。
大切なのは、飼い主が自分の犬をよく理解し、成長過程で人との関わりを楽しめるかどうかを見極めることです。
ーーセラピードッグやドッグセラピーはどのように募集していますか?
セラピードッグに関しては認定テストを実施しています。セラピストに関しては現在、米国、カナダ、プエルトリコで私たちの団体に所属するセラピストが19,000人以上いますが、口コミで会員は増加しています。少人数のスタッフで運営し、電話対応も人による対応を心がけ、組織の基盤を大切にしています。
ーーセラピードッグになるためにどういった資格や訓練が必要ですか?
現在、特別な資格は必要ありません。多くの人が自分で犬を訓練してテストに臨んでいます。
必要な手続きは①バックグラウンドチェック ②獣医師による犬の健康診断書の提出 ③3段階の実地テストです。このテストには、犬に触れて扱いやすさをチェックしたり、きちんと人と並んで歩けるか、すぐに驚いたりしないかを確認したり、3日間かけて実地観察とセラピードッグとしての実践的な訪問を行います。
ーー動物が苦手な人にもドッグセラピーを勧めますか?また、動物に慣れるためのコツはありますか?
私たちは、セラピードッグには衝動をコントロールすることができるような訓練をしています。すべての人に飛びつかないようにし、必ず相手に「触っても大丈夫ですか?」と確認することを徹底しているんです。犬が苦手な方やアレルギーのある方もいるため、無理に接触を求めることはありません。相手が触れたくない場合は、それを尊重し、代わりに簡単な芸を見せたり、犬を少し離れた場所に座らせるだけでも癒しを感じてもらえます。また、犬への苦手意識を克服したい方には、小さなステップを積み重ねて慣れていくサポートも行っています。
ーーアメリカでは馬を使ったセラピーもあると聞きますが?
アメリカの動物セラピーは最近、特に馬を使ったプログラムが注目を集めていますね。犬のセラピーが先行していましたが、馬のセラピーも急速に広がっているんです。例えば、PTSD(心的外傷後ストレス障害)を抱える退役軍人向けに、多くの馬セラピープログラムが提供されています。アトランタの水族館では、ジンベエザメと一緒に泳げるプログラムを実施しており、非常に癒しの効果があると聞いています。

Monica Callahan (モニカ・キャラハン)
2024年は私にとって大きな一年でした。Alliance of Therapy Dogsでディレクターを務めていましたが、新たにデジタルマーケティングマネージャーとして有償の役職に就くことになりました。ソーシャルメディアを通じてチームの皆さんと知り合い、今後さらにソーシャルメディアの存在感を高めていけることを楽しみにしています!
私の家には4匹の犬がいます。ディスコ(ウィンドスプライト)、オリオ(ダルメシアン)、クイント(ダルメシアン)、そしてヒップホップ(ウィンドスプライト)です。現在、オリオとヒップホップがセラピードッグとして活躍しています。彼らは訪れる先々でたくさんの喜びを届けてくれてます。
Alliance of Therapy Dogs HP: https://www.therapydogs.com/
瞑想がより楽しくなるおススメのクッション
「愛の言語」で解決!愛しているのに伝わらない。愛されているのかわからない。愛情のミスマッチを防ぐ秘訣

10歳の息子と5歳の娘に「どんな時に一番愛情を感じる?」と質問してみました。
息子は「ギューしてもらえるとき」と言い、娘は「ギューしてもらうのも嬉しいけれど、大好きって言ってもらえるのが一番嬉しい」と答えます。兄妹でも愛情の受け取り方は少し異なるようです。
そして、自分はどんな時に夫からの愛情を感じるのだろうかと考えてみました。
振り返れば、一緒にご飯を食べているときにスマホを見られるのがすごく嫌だ。これまであまり意識をしたことがなかったけれど、私は一緒に過ごす時間を大切にしているのかもしれない。
一方で夫はどうだろうか。私の誕生日には薔薇の花束を長らく送り続けてくれていた。もしかしたら、贈り物をすることで愛を伝えてくれていたのかもしれない。
『愛を伝える5つの方法』という本を読みながら、自分や家族の愛の受け取り方や伝え方について改めて目を向けることができました。
あなたはどんな時にパートナーからの愛を感じますか?
逆に、どんな時に「愛されていないのかも」と寂しさを感じますか?
この記事では、「愛の言語」と呼ばれる5つの愛情表現を紹介しながら、日々の人間関係をもっと温かくするヒントをお伝えします。
5つの「愛の言語」とは?
「愛の言語」とは、アメリカの心理学者ゲイリー・チャップマンが提唱した、愛情を伝えたり受け取ったりするための方法です。5つの「愛の言語」を理解することで、私たちは自分やパートナーの愛情表現の違いに気づき、より深い関係を築くことができます。
たとえば、英語が苦手な日本人が外国人とコミュニケーションを取ろうとする場面を想像してみてください。ジェスチャーや簡単な言葉で意思疎通は可能ですが、自分の気持ちを十分に伝えられなかったり、もどかしく感じることがあるでしょう。愛情表現もこれと同じです。相手の愛の言葉を理解せずに、自分なりに愛の言葉を伝え続けても、思いが届きにくいものです。
ゲイリー・チャップマンは『愛を伝える5つの方法』という著書の中で、「パートナーの『愛の一次言語』を見つけ、それを使いこなせるようになることが、愛情あふれる関係を長続きさせる鍵である」と述べています。
まずは、5つの「愛の言語」が具体的にどのようなものか、一つずつご紹介していきます。

1. 肯定的な言葉
「言葉」で愛情を感じるタイプの人は、好意的な言葉や感謝の気持ち、励ましの言葉を聞くことで心が満たされます。たとえば、「スーツ姿、かっこいいね」「お皿を洗ってくれてありがとう」「今日のご飯、すごく美味しい」「君なら絶対にできるよ」などの一言が、その人にとって大きな愛情表現になります。パートナーの愛の言語が「肯定的な言葉」の場合は、相手に対する愛情を、ポジティブな言葉で積極的に表現してみましょう。同じ言葉でも、思いやりを持って伝えることが大切です。
2. クオリティ・タイム
「一緒に過ごす時間」に愛情を感じる人にとって、最も大切なのは相手が「自分だけに集中してくれる時間」です。ただ一緒にいるだけではなく、会話に集中したり、趣味やイベントを共有することで、心が満たされます。たとえば、夕食中にスマホを置いて会話を楽しんだり、共通の体験を通じて絆を深めることが理想的です。
クオリティ・タイムを大切にする相手には、時間の質を意識して愛情を伝えましょう。忙しい日常でも、一緒に過ごす時間を大切にする姿勢が、相手にとって何よりの愛情表現になります。
3. 贈り物
贈り物は「あなたを大切に思っています」という気持ちを目に見える形にしたものです。そのため、「贈り物」を通じて愛情を感じる人にとって大切なのは、プレゼントそのものではなく、そこに込められた「思い」や「心を込めた行動」です。
贈り物タイプに愛情を伝える時は、相手を想いながら贈り物を選ぶことが重要です。また、物に限らず、困難な時や心細い時に寄り添うことも、最高の贈り物になるでしょう。
- サービス行為
「行動」や「手助け」を通じて愛情を感じる人は、相手が自分のために具体的な行動をしてくれることで愛を感じます。たとえば、重い荷物を代わりに持ってくれたり、家事を手伝ってくれたりといった行動です。
パートナーの愛の言葉がサービス行為の場合は、相手が何をしたら喜ぶかを考えながら動くことで愛情を伝えられます。「してほしいことを察して動く」姿勢が大切です。
5. 身体的なタッチ
「触れること」で愛情を感じる人は、ハグやキス、肩に軽く手を置くといった身体的接触から、安心感や親密さを得ます。日常の中でさりげない触れ合いが多いほど、愛情を実感することができます。一方で、距離を置かれたり触れることが少ないと、愛情が足りないと感じる場合もあります。
身体的なタッチを大切にする相手には、日常的なスキンシップを意識することがポイントです。たとえば、挨拶代わりにハグをしたり、外出時に手をつないだり。日常の中で意識的に触れ合うことで、心の距離を縮めることができるでしょう。
「愛情を伝えているのに、伝わらない」のは「愛の言語」が異なるから
愛情を表現し合うことは、カップルにとって非常に重要です。しかし、互いに「愛を伝えているつもり」でも、その表現方法が相手にとって響かない場合、すれ違いや不満が生じることがあります。
たとえば、男性の愛の言語が「身体的なタッチ」、女性の愛の言語が「肯定的な言葉」だとしましょう。
男性は、ハグをしたり、セックスすることで「君を愛している」という気持ちを伝えようとしますが、女性は「愛しているよ」や「あなたがいてくれて本当に嬉しい」といった言葉がなければ、愛情を十分に感じられないかもしれません。その結果、女性は「彼は愛を表現してくれていない」と感じ、男性は「こんなに触れ合っているのに、なぜ伝わらないんだ?」と困惑してしまうのです。
「愛しているのに、愛情が伝わらない」といったすれ違いを避けるためには、お互いの愛の言語を知ることが大切です。

まずは自分の「愛の言語」を知る
先ほどご紹介した5つの「愛の言語」、あなたは自分の「愛の言語」がどれか分かりますか?「これだ!」とすぐにピンとくる人もいれば、迷ってしまう人もいるかもしれません。
相手の「愛の言語」を知ることはもちろん大切ですが、まず理解すべきは、自分自身の愛の言語です。
書籍『愛を伝える5つの方法』では、「愛の言語」を知るために役立つ3つの質問が提案されています。この質問に答えることで、自分がどの愛情表現に最も満たされるのかを見つけられるでしょう。
1. パートナーがすること、またはしないことで、自分が傷つくことは何ですか?
この問いは、あなたが何に敏感に反応するかを探る手助けをします。たとえば、「ありがとう」とあまり言ってくれないことが悲しいと感じるなら、それは「肯定的な言葉」があなたの愛の言語である可能性があります。
2. パートナーに最も願ってきたことは何ですか?
これまで相手に最も求めてきたものは何でしょうか?たとえば、「もっと一緒に過ごしたい」と思うことが多い場合、それは「クオリティ・タイム」があなたの愛の言語かもしれません。
3. いつもどのようにパートナーに愛を表現していますか?
あなたが相手に愛情を伝える方法も、あなた自身の「愛の言語」を知るヒントになります。たとえば、自然と家事を手伝ったり、プレゼントを贈ったりしている場合、それがあなたが最も重視している愛の表現かもしれません。
相手の「愛の言語」を知る方法
ゲイリー・チャップマンの著書には、愛の言語を確認するためのテストが付属しており、30の質問に答えるだけで、自分やパートナーがどの「愛の言語」を重視しているかが分かります。テスト結果を共有すれば、お互いの価値観を知るきっかけにもなるでしょう。
ただし、必ずしもテストを受ける必要はありません。普段の生活から、相手の愛の言語を推測することもできます。
たとえば、相手がどんな時に一番喜ぶのか、逆にどんな時に不満げにしているのかを考えてみたり、直接「どんな時に愛を感じる?」「私が何をしたら一番嬉しい?」と質問してみたりするのも良いでしょう。
相手の愛の言語を完璧に理解するには時間がかかるかもしれませんが、相手を理解しようとする姿勢そのものが、愛情を深める鍵になるかもしれません。
カップルだけじゃない、親子や友人にも活用できる
「愛の言語」は、カップルに限らず、家庭や職場、友人関係など、どんな人間関係にも活用できます。
身近な人との関係がぎこちなく感じる時には、「あの人の愛の言語は何だろう」と考えてみてください。
お互いの愛情表現を知り、それを意識して伝え合うことで、より良い関係が築けるかもしれません。
参考書籍:愛を伝える5つの方法 ゲーリー チャップマン (著), ディフォーレスト 千恵 (翻訳)
地球にも赤ちゃんにも優しい:成長をサポートする6つのエコフレンドリーおもちゃ
大人になってから友達を作るのは大変?でも大人になったから築ける友情もある

大人になると学生の頃からは180°変わるもの。
その一つに”友達”の存在があると思います。
どれだけ仲が良かった人も、それぞれの道を歩むうちにいつの間にか疎遠になっていたり、逆に苦手なタイプと思っていた人と急激に仲が深まったり…
今回は大人になって感じた、”友達”という存在に対する捉え方の変化をシェアしたいと思います。
おすすめ記事 ▶ 親しい友人関係における「開かれた、思いやりのある衝突」のすすめ
大人になると”友達を作る”の難しすぎる問題
私は学生の頃から友達はあまり多くなく、狭く深い人間関係に心地よさを感じるタイプでした。
しかも、自ら外に出て新しい交友を築くのではなく、自分のもとに舞い込んできてくれた縁を大事に育てていきたいタイプ。
そんな人間が大人になると、どうなるか……
あるときから、友達がぱったりできなくなりました。
社会に出て数年は、それを実感する機会はさほどありませんでした。
“学生時代から狭く深い関係を好み、新しい出会いを自ら求めなかった私は、大人になるにつれ環境の変化や友人たちの転居・結婚などで、気軽に誘える友人がいなくなった現実に直面した。”
Uターン就職で地元に帰ったことで昔の友達もいたし、会社は会社で同期が150人もいたので、研修などで顔を合わせるうちにすぐに何人か気の合う友達ができたからです。
ただ、しばらくすると地元の友達は結婚などで、同期も異動や転職などで県外に出ていってしまう、そんなことがちらほら起こりはじめました。
ふらっと誘える友達が、急に減っていったんです。
それでもまだ「まあそのうち新しい縁がどこかから舞い込んでくるだろう」と呑気に構えていたのですが、自分自身も異動や転職をするうちに、とうとう現実に直面にします。
新しい縁が、舞い込んでこない…。
異動先や転職先がそもそも同世代の少ない職場だったり、会社の飲み会もコロナ禍以降は必要最低限みたいな雰囲気だったり…(会社の飲み会って面倒なことも多いけど、実は受け身人間にとっては唯一縁を取り込むきっかけだったりするんですよね)
受け身でいても勝手に縁が舞い込む、そんなことが通用しなくなっていたのです。
かといって、腹を括り新しい交友を求めて自ら外に出ても、なかなか上手くいかないもの。
まず、どうやったら新しい人と出会えるのかが分からないんです。
よく趣味や習いごとを始めたり、行きつけの飲み屋をつくれば人と出会えるなんて言いますが、それはそれでいろいろ考えてしまうタイプの私は、一歩も動けなくなるんです。
何の趣味や習いごとをすればいいのか、行きつけにするなら美味しいお店がいいし、なおかつ通えるくらいの予算感であってほしいし、何だかんだマスターとの相性も大事だし…
そうやって足踏みしまくった挙句、変な一歩を踏み出して結局誰とも出会えなかったりと、完全に迷走していました。

大人になって友達を作るのは諦めたほうがいい
そんな迷走期をしばらく経ると、途端に何もかもが面倒くさくなる瞬間が訪れました。
友達を作るのを諦めた、”開き直りフェーズ”です。
一人の時間は大好きなんだから無理して友達を作る必要もないし、どうせ死ぬときには一人なんだし、なんて言い聞かせるように好きなことに没頭。
推しのライブに時間とお金を費やしたり、こうしてエッセイのような文章をポツポツnoteにしたためたりしていました。
すると不思議なことに、それぞれの領域でいつの間にか”友達”ができていたんです。
“友達づくりを諦めて一人の時間を楽しむようになった私は、好きな活動に没頭するうちに自然と共通の趣味を持つ仲間と出会い、無理せず心地よい人間関係を築けるようになった。”
推し活で出会ったファンの方が声を掛けてくれて、何度かライブ後にご飯に行くようになり、一緒に泊まりがけで遠征(遠方のライブやイベントに参加すること)までしたり。
推しのライブの感想をひたすらぶちまけたnoteには、また別のファンの方たちが反応してくれて、ちょこちょこSNSで交流することもあります。
noteではライターさんとも交流も増えました。
なかでも特に、直感でもっと仲良くなれそうと感じた方には、私から実際にお会いしたいと声を掛けたりもしました。
内向的な人間なはずなのに、自分でも驚きの行動です。
実際、当日はとてもドキドキしましたが、いざ会ってみると直感通り。初対面なのにとても居心地がよくて会話が弾み、その後も相手からお誘いがあったりと定期的に交流が続いています。
無理やり奮い立たせて友達を作ろうとしてもダメだったのに、開き直った途端、急に自然な流れで友達ができるようになったんです。
大人になると”気の合う友達”の幅が広がる
もちろん、こういう機会がたくさんあるわけではありません。
ただこうした流れでできる友達って、なんというか、相性の精度がとても高い気がします。
出会ってそんなに月日が経っていなくても、会話のテンポが気持ちよくハマったり、泊まりで旅行までできたり、お店選びのポイントが似ていたり。
そういうのって、長く付き合うからこそ構築されるものだと思っていました。
学生の頃は無意識に「過ごした時間が長いほど仲良くなる」という感覚が、根底にあった気がします。
長く時間を共にすることでお互いをよく知り、好みや考え方のすり合わせもできるから、親友と思えるほどの仲になる。
でも逆に、クラス替えや進学、あるいはもっと他愛もない要因で一緒にいない時間が続くと、仲が悪くなったわけではないのになんとなく疎遠になる。
学生の頃は、そんなことが自分も周りでもよく起こっていました。
皆さんもそういう経験ありませんか?
当然それでも、れっきとした友達だったとは思うのですが、大人の友情は必ずしもそういうことでは成り立たない。
仕事に家庭にそれぞれの人生があり、べったり一緒にいることなんてできませんもんね。
では、一緒に過ごした時間の長さではないとしたら、仲のいい友達になれる要素はどこにあるのか。

個人的にはどれだけ「コイツ、おもろいな」と思えるか、これに帰結するのではないかと感じています。
分かりやすいのは、考え方や嗜好が近いことでしょう。
実際私も、推し活やライターなど好きなことを通して友達ができています。
好きなものやマインドの傾向を同じくして集まった人とは、たとえバックグラウンドがバラバラでも結構すぐに仲良くなれる。
今となっては、趣味や習いごとで友達を作ることの真意も、ここにあったんだなと腑に落ちます。
一方で、大して価値観が近くなくても仲良くなれるケースも多々あります。
よく驚かれるのですが、私は未だに小学校の同級生何人かと結構な頻度で交流があります。
幼馴染というほど濃い関係ではなく、卒業来連絡を取っていなかった人、しかも小学生当時すらほとんど交流がなく顔見知り程度だった人も多いです。
にもかかわらず、ひょんなことから十年越しに再会し、今では朝まで飲む仲になっています。
そのメンバーの性格は本当にさまざまです。
“小学校時代の同級生と再会し多様な価値観を持つ仲間と心地よい関係を築く中で、私は「似ている」ことよりも「人として面白い」と感じる直感こそが大人の友情を育む鍵だと実感している。”
大学も業種も当然バラバラ、大切にしたいこと、好きなことも違うし、私と似てちょっと閉鎖的な人もいれば、軽やかでオープンな人もいます。
共感しあって盛り上がることもあれば、興味のない話はお互い適当にあしらうこともある。
それでも険悪にはならないし、だいたいはくだらないことでゲラゲラ笑っていて、妙に居心地のよいメンバーなのです。
共通点はただ同じ小学校に通っていたというだけで、再会までの約十年は全く違う道でバラバラの価値観を形成してきたはずのなのに。
それでも自然とわらわら定期的に集まるのは、お互いどこかしらに”人としての面白さ”を感じていたり、違う中にも一瞬見える”同じ匂い”を感じ取っているからなのかもしれません。
そしてこの感覚こそ、大人になるうちに体得したものだと思うんです。
歳を重ねるごとに自分の常識はどんどんぶち壊され、どんどん知らなかった世界を知り、たくさんの人や価値観にも出会います。
いろんな人がいるという数の話だけではなく、一個人のなかにすら、様々な経験や価値観が複雑に絡み合っているという深さも分かってくるようになる。
それまで自分が持っていた”人間データベース”に膨大なデータが流れ込んできて、急速にアップデートされていく感じ。
その中で、価値観が近かろうが正反対だろうが人として面白さを感じることはあるし、そう感じた時点で良い友達になれる確率は結構高いということを、身をもって学んできたのではないか。
そういうことを最近しみじみ感じるのです。

友情にも”メンテナンス”が必要
友達という存在について、もう一つ最後に書いておきたいことがあります。
それは旧い友達と久々にお茶をしていたときに、その友達から飛び出したことばです。
「友達も、メンテナンスが大事やんな」
メンテナンスというと事務的で無機質に聞こえるかもしれませんし、私も一瞬「めっちゃ機械みたいに言うやん…」と思いました。
意図としては、どれだけ仲の良い人も定期的に会ったり話したりしないと、関係は意外と簡単に崩れてしまうと言いたかったそう。
“どれほど気の合う友人でも放っておけば関係は自然と薄れるため、大切な縁を保つには意識的に会い、つながりを点検する“メンテナンス”が必要だと私は気づいた。”
私も一瞬はたじろぎつつも、すぐにそれを直感的に理解しました。
親友だと思っていた学生の頃の友達も、今となってはどこで何をしているのかも知らない、そんなことが私自身ちらほらあるからです。
卒業してからも連絡を取ろうと思えば取れたし、実際ご飯にも何度かは行ったけど、その後はお互い特にアクションを起こさなかった。
大人になると、仕事に家庭にそれぞれまったく違う人生を歩むからこそ、意識してつながろうとしないとはぐれてしまうのは考えてみれば当然ですよね。
だからこそ、いつまでも縁の糸をつないでいたい相手はちゃんと定期的に会う。
糸が切れかけていないか、変にねじれて絡まっていないか、点検するメンテナンスが必要なんだと思います。
近況報告をして、新しい刺激を与えあって、いろんな困難を乗り越えてきたことを称えあって、くだらないことで笑い飛ばすことで、その糸はまた頑丈になっていく。
期間が空いても、会うとすぐいつも通りに戻れる友達って、このメンテナンスがきちんとできている証拠だと思うんです。
そう気づいてからは、私も会いたい人やもっと仲良くなりたいと思った人には、自ら声を掛けるよう意識しています。
誘うのって正直勇気がいるけれど、逆の立場だったら声を掛けてくれただけで嬉しいものですからね。
たとえ断られて、その後の音沙汰がなかったとしても「あら、片想いだったか~」とか「今は違ったかな」で済ませればいいのです。それも縁だから。
お互い縁をつなぎたいと思ったら、またいつかどこかでつながる。
それくらいゆるく長い目で捉えるようになったのも、大人になってからの変化かもしれません。
大人になったからこそ築ける友情を大切に育む
大人になるとどれだけ一緒にいるかではなく、その友情が続いていること自体が心の支えになるし、人生を豊かにしてくれる。
最近しみじみそう感じることが多く「やっぱり私は狭く深くの人間関係を大事にしたい」と一周回って腑に落ちています。
会いたいから会う、知りたいから話す、そういうシンプルな理由で素直に動いていれば、自分の人生で本当に大事にすべき友達はちゃんとずっとそばに居てくれるのではないでしょうか。
子どもとのふたり旅 。24時間以上一緒に過ごすことで見えてくる一面【Editor’s Letter vol.11】

2024年度は、長女とバージニア州、次女とシアトル、三女とはサンディエゴへ、それぞれ「ふたり旅」に出かけました。
毎年恒例となったそれぞれの娘たちとのふたり旅。一対一の時間を過ごす中で、子どもたちの新たな一面を知り、親子の絆が深まる瞬間がたくさんあります。
今回は、ふたり旅を始めたきっかけや、旅を通じて気づいたことをお伝えしたいと思います。
おすすめ記事 ▶ まずは自分を大切に。子育てには”Boundary(境界線)”が必要?! 【Editor’s Letter vol.09】
きっかけは「ママは私のことを何もわかっていない」というひと言
私が子どもとふたり旅を始めたきっかけは、次女のひと言でした。
「ママは私のことを何もわかってない」
「ママと二人きりの時間が欲しい」
三女が生まれてしばらくした頃、次女はそんなふうに言いました。きっと妹が生まれたことで、ママを取られたような寂しさを感じていたのでしょう。
子どもが複数いると、常に一人ひとりと向き合うことは難しいのが現実。もっと娘たちの気持ちや思いを知りたいと思い、子どもたちそれぞれとふたりきりの旅に出ることを決めました。
スマホと距離をとり、旅行中は子どものやりたいことをやる
行き先は子どもの興味に合わせて事前にいくつかピックアップして、最終的には子どもと一緒に決定します。
たとえば、去年は長女と独立戦争にゆかりのあるバージニア州にあるウィリアムズバーグへ訪れました。彼女がアメリカの独立戦争に興味を持っていたからです。
“母子ふたり旅では、子どもの興味を最優先に行き先を決め、スマホ使用を最小限に抑えることで、穏やかで充実した時間を共に過ごしている。”
旅の最中で意識しているのは、基本的には子どもの「やりたいこと」を優先すること。そして、スマホを見る時間を必要最低限にすることです。
もちろん事前の下調べはある程度行います。たとえば、美術館のチケットを取ったり、プールのスケジュールを確認したり、レストランを予約しておいたり。現地では、地図やUberを使うとき以外はなるべくスマホを見ないようにし、地図を見るときも子どもと一緒に画面を確認するようにしています。
普段私がイライラしてしまう原因のほとんどは姉妹喧嘩ですが、母子ふたり旅では姉妹喧嘩は起こりません。そのため、私自身も穏やかな気持ちで子どもと向き合えます。

2人だけで24時間以上過ごすからこそ見えてくることがある
日常の合間に子どもと二人でご飯を食べに行ったり、買い物をしたりするのも、もちろんかけがえのない時間です。でも、24時間以上一緒に過ごすことで、普段とは違う一面にたくさん気づけるのです。
たとえば、次女は普段、ダラダラ遊んで後回しにして歯磨きやシャワーにとても時間がかかるタイプです。ところが、ふたり旅の間は、自分でさっさと準備を進めて、私の支度が終わるのを待ちながら一人で持っていった少量の小さなお人形やホテルにあるノートに絵を描いて遊んでいました。
また、いつもは甘えん坊で私にくっついていることが多いのに、旅先では少し自立しているように感じ会話もたくさん楽しみました。普段は、お姉ちゃんと妹に囲まれているので「もっと私を見てほしい」という気持ちが行動に表れて逆にウニャウニャしていたのかもしれません。
“母子ふたり旅を通して、筆者は子どもの新たな一面や成長に気づき、普段のレッテルや思い込みを見直しながら、それぞれの子に合った関わり方を学んでいる。”
そしてそんな彼女の成長をみて「〇〇ちゃんは準備が遅くて甘えん坊な性格」。そんなふうに無意識にレッテルを貼っていた自分にハッとしました。
旅先で夜寝る前に、次女に「旅行の時は支度が早くさっさとできるけれど、家だとどうして時間がかかるの?」と聞いてみました。すると、「家だと、いろんなものが目に入ったり、音や皆んなの声が聞こえたりして、集中できないんだよね」と返ってきたのです。あー、やりたくないからダラダラしてしまうのではなくて、周りに気が散ってしまうのか。
家族で暮らしているので生活音を減らすのはなかなか難しいけれど、歯磨きをする場所を変えてみたり、先に始めるよう促してみたり、小さな工夫で改善できることがあると感じました。
一番下の娘とは、彼女が4歳のときにパームスプリングスへ行きました。ホテルのプールをメインに、ゆったりと過ごす旅です。
プールでしばらく遊んでいると、三女が「もう部屋に帰りたい」と言い出しました。部屋に戻ってからは、お絵描きをしたり、のんびりおやつを食べたりして過ごします。そして1時間ほど休むと、「またプールに行こう!」と元気いっぱいに誘ってくれるのです。

この旅を通じて気づいたのは、三女は周りの音や情報に疲れやすく、時折休憩を挟むことで自分をリセットできるということ。だから、家族全員での旅行では皆んなのペースに合わせないといけない場面も多く、彼女の限界を越えてしまう場合に泣いたり駄々をこねたり、わざわざ喧嘩を姉妹にふっかけたりしていたのか。これもふたり旅をしたからこそ気がつけたことです。
また、長女とのふたり旅では、「ママはここに行ってみたいな」「これをやってみない?」と、私自身が長女に提案する場面が多いことに気がつきました。長女はあまりこだわりがなく、ママと一緒にいられればそれでいいタイプの子でこれやりたい、あれやりたいと願望が強くありません。日頃から自分の意思を言葉にすることの大切さを話していますが、「ママ、私がどっちでもいいよ、っていつもいう時はね、本当にどっちでもいいってこだわりがないからなんだよ。」と言われました。それでも、普段上手に甘えられないお姉ちゃんにとってママを独り占めできて、また、彼女にとって興味のあることがたくさん知れてかけがえのない時間です。
本当に困った時に頼ってもらえる、親子の絆を育むために
私にとって娘たちとのふたり旅は、日常ではなかなか気づけない子どもの一面を知る貴重な機会であり、今からきちんと信頼関係を築いておきたいと願う私の「将来への貯金」です。
子どもたちが大きくなって手が離れてきた時でも、本当に困ったときには真っ先に相談してほしいし、ひとりで苦しまないでほしい。そんな願いを込めて、年に一回ふたり旅に行き、娘たち一人ひとりと向き合う時間を大切にしています。親にしっかりと向き合ってもらった記憶は、成長していく中でその子の自信や心の支えになると信じているからです。
親子でも、パートナーでも、友達でも、きちんと向き合い、時間を共に過ごさなければ、気づかないうちに心の距離が離れてしまうものです。人との絆を育むためには、心を通わせる努力が必要です。これからも大切な人とじっくり向き合う時間を積み重ねていきたいと思います。
運動嫌いの私が「運動はメンタルにいい」を少しずつ信じはじめた話

突然ですが、皆さんは体を動かすことは好きですか?
“適度な運動習慣”、ついてますか?
運動はしたほうがいい、それはおそらく誰もが同意することでしょう。
運動したほうがいいなんて、百も承知
かく言う私は、圧倒的インドア派。できるだけ外に出たくないし、体も動かしたくない派です。
一方、世の中では一時期こんな言葉まで流行りました。
「筋肉は裏切らない」
なんてキャッチーでインパクトのある言葉なのでしょう。
“裏切らない”の解釈にはいろいろありますが、個人的に私がよく目にする文脈は「メンタルを強くしたいなら、運動をしろ」、そういった類のものです。
“運動嫌いの私はコロナ禍で抑うつ状態を経験し、医師から勧められた「外に出て体を動かすこと」の大切さを、後になって実感するようになった。”
近年、うつ病とかメンタルに関する注目が高まっているからか、皆さんも一度はそんなニュアンスの話を聞いたことがあるのではないでしょうか。
特にコロナ禍をきっかけに、運動は精神衛生を保つ上でも重要という意識は、急速に広まったように感じます。
私自身、すぐ考え事がぐるぐる頭をめぐるメンタル弱めなタイプで、まさにコロナ禍真っ最中に抑うつ状態に陥った経験があります。
そんなとき、心療内科の先生に言われたことがあります。
「少しずつでいいので、外に出て歩いたり運動してみてください」と。
そして心の中でこう思いました。
「そんな気力があったら、そもそもこんな状態になってない」と。
それからしばらく月日が経ち、うつっぽさからもなんだかんだ抜け出せたころ、今度は友達との何気ない会話で「やっぱり考え事が止まらない」という話になりました。
その友達は私の気持ちを汲んではくれつつも、同じタイプではないからか、
最終的にはなぜか「まあもっと体動かしてみたら?運動すれば考え事とか飛んでくよ」と言ってきたんです。
そして心の中でこう思いました。
「え…?なんでそこに着地するわけ?そういう話じゃなくない?」と。
そしてまたある日、別の友達とデスクワークで体がガチガチ、なんだかやる気もでないという話になりました。
その友達も同じくらいデスクワークで体がガチガチだったのですが、私のような運動嫌いではありませんでした。
もう皆さんお分かりですよね。
そう、「ガタがきはじめたのかな~」なんて笑い飛ばされるはずだった他愛もない雑談は、
「あんたはもっと運動しな」という、友達の口から放たれた鋭い言葉でバッサリいかれたのです。
そして私は、心の中で思いっきり毒づきました。
「もー!どいつもこいつも、運動運動うるさ~い!」と。

運動に絡めて話を終えなきゃいけないゲームでもしているのかと疑うくらい、みんな口を揃えて運動しろと言ってくる気がして、ほとほと嫌気がさしていたんです。
運動したほうがいいなんて、百も承知。
でもメンタルが落ちているからそもそも動く気にもなれないし、考えすぎの根本的な解決策が運動なわけないし、
凝りまくった体ではちょっとしたストレッチでもすぐ疲れるし、何より続かない自分にまたメンタルが下がるし…。
と、今思えば、壮大な負のスパイラルに陥っていたのかもしれません。
「筋肉は裏切らない」とまではいかずとも…
それがおかしなことに、運動嫌いだったはずの私が、どうやら最近少し「そっち側」に近づいている気がするのです。
体を動かすと本当にメンタルも上向くのかもしれない、と身をもって実感しはじめているのです。
すべてのはじまりは”自転車通勤”
一番のきっかけは、転職して自転車通勤になったことでした。
新しい職場は、電車で通うにも歩くにも中途半端な場所にあり、一番理にかなった通勤方法が自転車だったのです。
ただそれだけなのですが、今思えばこれが大きなターニングポイントでした。
“転職を機に始めた自転車通勤がきっかけで、運動嫌いだった私は体を動かす心地よさとメンタルの安定を実感し、自然と運動への意欲が高まっていった。”
会社までは自転車で約20分という、これも運動不足な人間にはちょうどいい距離で、ほんのり汗ばむけれど疲れ切って仕事にならないというほどではない。
だからこそ、深く考えることもなく毎日淡々と続けられました。
あえて意識するというわけではありませんでしたが、心のどこかで「今の私は、日々最低限体を動かしている」という達成感というか充足感というか…そんなものを毎日感じていた気がします。
しかもちょうど川沿いを走る経路だったので、開けた景色を眺めながら、微妙に変化する木々や川の香りも感じて、毎日気分がリフレッシュされていました。
そのおかげか、それまではおぼろ豆腐のようにすぐ崩れていたメンタルも、木綿豆腐くらいにはなってきた気がするのです。
自転車通勤が板につきペダルを漕ぐ足も軽やかになってくると、だんだんこの運動量では物足りなくなってきました。
しかもメンタルが少し上向いているからか「何かもうちょっと運動できる気がする!」と、なんとYouTube動画を活用して自宅で運動する、いわゆる「宅トレ」まではじめたのです。
帰宅後、仕事着を脱ぎ捨てながら動画を選び、そのまま15~20分程度汗をかく。
そんな日々の達成感は自転車通勤の比ではありません。
毎晩「ふ~~今日も動いた動いた~!」と満足感と心地よい疲れを感じながら、布団に潜り込む気持ちよさを初めて知った気がします。

じわじわ実感する“運動とメンタル”の関係
少しずつ運動が習慣化しつつも、まだベースには運動嫌いが残っているので、よく怠けたくなるのも事実。
ましてや仕事でモヤモヤした日や疲れて元気がない日は、余計運動なんてする気分になれません。
とはいえ、人生初というくらい続きはじめた運動習慣を途絶えさせるのも癪なので、しぶしぶ2分くらいのトレーニング動画を探し出して、とりあえず動いてみます。
すると、さっきまでのどんよりした気持ちはどこへやら。ささくれ立っていた気持ちがだんだん和らいでいくんです。
「何をそんなむくれてたんだ?」と思いはじめ、さらには「もうどうでもいいや、それよりもっと汗かきたい!」と、前向きな気持ちすら湧いてそのままトレーニング続行。
「運動しろ」と言われるたびに突っかかっていた人間が、奇跡みたいな話です。
“運動嫌いながらも続けるうちに、私は気分が落ち込んだときこそ少し体を動かすことで心が軽くなると実感し、運動を心のリセット法として取り入れるようになった。”
こういう経験を何度かして以来、心がくすぶったときは、とりあえず一旦体を動かすようにしています。
仕事中、何かイライラすることがあったときや、周りと比較して自己嫌悪に陥ったとき、ふと漠然とした不安を感じたとき。
黒いものに自分が飲み込まれかけていると気づいたら、とりあえず一旦立ち上がってみます。
実は、そのまま身を任せて闇に飲まれるほうが楽なんだけど、ちょっとだけ踏ん張ってとどまる。
それはウォーキングやストレッチなどTHE運動でなくても、トイレに行くとか、ベランダへ出て外を眺めるとか、やり残した食器洗いをするとか。
動けたらなんでもいいんです。
個人的に負のスパイラルに入るときって、ずっと同じ体勢でいたり、同じ景色ばかり見ていたり、”何かが停滞している”ことが多い気がします。
動けば体の血が巡りはじめて、連動するように停滞していた気分も軽やかに巡る。
動けば目線や見える景色が変わって、閉じこもりかけていた気分も少し開ける。
動くことで問題そのものが解決するわけではありません。
でも”解決へ向かうための気力”は生まれると思うんです。
私にとって運動とメンタルの関係はそんな感じで、根本から働きかけてくれるというより、スタート地点に立つのを優しくサポートしてくれる感じです。
「筋肉は裏切らない」とまでは未だに思えないものの、動くことでマインドセットも変わるということは、こんなふうにじわじわ実感しはじめています。
運動嫌いが運動を習慣化できた理由
その後、諸事情で自転車通勤が難しくなったので、最近は通勤を片道ウォーキングで置き換えて運動量をキープしています。
意外と体力もついてきたのか、もう少し慣れたら往復徒歩でもいけそうだなとまで思っています。
少し前の私がみたら顎が外れるくらいの運動量なのですが、そもそもなぜ、運動嫌いが急に運動を習慣化できたのか?
正直、なんとなく思い付いてはじめて、気づいたら徐々に定着していたというのが本音ではあるのですが…
よーく思い返すと、それらしきポイントが見えてきたのでシェアしてみます。
“自分の意思”ではじめたから
なんとなくの思い付きとはいえ一つだけ確かなのは、誰かに言われたからでも、心療内科の先生や友達の言葉が蘇ったからでもなく、”自分で”思い至ってスタートを切ったということです。
この”自分の意思”ではじめたという事実は、全ての下支えになっている気がします。
たぶん、いつもの癖で考え事をしていた際に、たまたま「まあそりゃあ、健康なほうがいいよな」ということから派生して、
「運動は疲れるけど、かといって、このガチガチの体のまま何十年も生きていくのもしんどいよな」なんてことが頭によぎったんだと思います。
体を動かしたほうがいいという言葉の真意が、自分のなかでようやく腑に落ちた。
心にまとわりついていた変な鎖や重りがやっと外れた。
何年も鉛のように重く沈んでいた腰が、急にぷか~っと水面に浮かんでこれたのは、この”納得感”が肝だと思います。
“生活に馴染む運動”しかやらないから
私の場合、自転車通勤が最初のステップでしたが、これをより汎用性高く変換すると、今の生活にごく自然に馴染むことだけやる、これに尽きると思います。
この”馴染む”というのは、おそらく一般的なイメージよりも徹底したものです。
たとえば、よく自宅や職場に近いジムだと続きやすいと言われますが、私からすればそれはただ「今の生活の近くに”存在している”」だけ。
“運動を完璧にこなすよりも「続けようとする姿勢」を大切にし、自分を許しながら前向きに体を動かす習慣を築いている。”
実際に通うなら月謝制?回数券?それに何曜の何時に行く?その日は家事をいつやる?買い出しは?子どもたちのお迎えは?
考えること、変えることだらけです。
通勤経路を数歩それるだけで済む話ではなく、今の生活の流れを変えるという大きな壁がそこにあることに気づくはずです。
その点、自転車通勤や片道ウォーキングは、何ら生活を変える必要がありません。
自転車、徒歩、電車、タクシー、どんな手段であれ家には帰る、それならできる範囲で運動に置き換えてみる。
もちろん、完全リモートの人や仕事をしていない人でも置き換えはできます。
メールチェックだけは必ず立ってやるとか、考え事系のタスクはストレッチしながらやるとか。
スクワットのように少し腰を下げて掃除するとか、肩まで大きく使ってテーブルを拭くとか、すでに今の生活には運動にできるポイントがたくさん転がっているんです。
運動嫌いだからこそ、これくらい徹底的にハードルを下げないと続きません。

“トータルで考える”ようにしているから
最後のポイントは「続けかた」に関することです
実は、先ほど得意げに紹介した宅トレ最近かなりサボり気味なんです…。
でも、いいんです。その分、ウォーキングでしっかり動いているから。
ただ、そのウォーキングもサボって、普通に毎日電車で帰り続けた週もありました…。
でも、いいんです。その翌週からまた再開したから。
“運動を完璧に続けようとせず、長い目で見て「動き続けていればいい」と柔軟に捉えることで、自分を責めず前向きに運動を楽しめるようになった。”
最近、運動に関する私のマインドは基本こんな感じです。
どの運動をしたかではなく1日でどのくらい動いたか、毎日ではなく月や年単位で見て続いているか。
なるべく大きく捉えて、トータルで考える。
これくらいどっしり構えるようにしてから、少々サボる日が続いても必要以上に自分を責めることが減りました。
むしろ「いつもよく頑張ってるんだから」と、自分を労わってあげられるようになったかもしれません。
あと宅トレに関しては「通勤に比べたら生活に馴染まないから、当然と言えば当然だ!」なんて開き直ってみたり…
やっぱり運動はメンタルを強くしてくれるみたいです。
気が向いたら動けばいい
そうは言っても、まだまだメンタルが沈むことは当然あるし、気を抜くとすぐに「動かないほう」へ逃げてしまいます。
動けば心も軽くなると身をもって経験したのに、どうしてもうずくまってしまうことはある。
でも、そんな自分を責めず、また動きたくなったら動けばいい。
何にせよ大切なのは自分の気持ちということです。
元々運動嫌いなんですから、気が向いて小さなハードルを1つ飛び越えただけで表彰もの。
それくらい図々しくていいと思います。
私も気が向くまで、徒歩通勤を往復にしたり宅トレを再開したりもしません!笑
お互い焦らずゆっくり心身の健康を育みましょう。
セキララカードでセックス対談。セックスレス問題からテクニックを磨くコツまで本音女子トーク

セックスに関する話題は、家族や友人、さらにはパートナーともなかなか話しにくいもの。でも実際には、多くの人が悩んでいたり、もっと知りたいと思っていたりするのではないでしょうか。
今回、Humming編集部の舞麻と純が、『セキララカード』を使って夜の営みについて率直に語り合いました。スキンシップに関する悩みや、パートナーとの関係を深める秘訣まで、夜の女子会に参加しているような感覚で、本音トークをお楽しみください。
| Humming編集長 永野 舞麻
1984年生まれ。16歳までを日本で過ごした後、海外へ移住。大学で出会ったアメリカ人の夫と結婚し、現在はカリフォルニア在住。3児の母。 高校時代、スイスに住んでいたときに自然の偉大さに触れ、地球環境保全について学び始める。アメリカの美術大学でテキスタイル科を専攻。 今でも古い着物の生地などを使って、子育ての合間に作品を制作し続けている。 |
| Humming編集部Project Coordinator 條川純
1984年生まれ。アメリカ生まれ、アメリカ育ち。現在はひとり暮らしをしながら、生涯を共に過ごせるパートナーを探している。 |
Q:一番好きなスキンシップは?
舞麻:私は後ろからギュッと抱きつかれるのが好き。なんだか安心するんです。夜中に目が覚めて寝付けない時などは、夫の腕の中にわざわざ潜り込んで彼の胸に私の背中をピタッとくっつけています。しばらくすると安心したのか、温かいからか寝落ちしています。笑
純:実は、私はスキンシップがちょっと苦手。手を繋いだり、ハグをしたり、そういったコミュニケーションをあまりしない家庭で育ってきたからかもしれません。だけど、今お付き合いをしている彼はスキンシップが大好き。「純の育ってきた環境もわかるけど、僕にとってスキンシップは愛されている証拠だから大切にしたい。触れ合いがないと不安になる」と言われてしまいました。
無理してスキンシップをするのはイライラしてしまうけど、罪悪感も感じるから、なるべくスキンシップをとろうと頑張ってます!たとえば、私があまり抵抗のない寝起きのタイミングにたくさん甘えておくとか、デート中には自分から手を繋ぐとか。スキンシップを自然にとれる女性が羨ましいです。
Q:忙しくても、充実したセックスライフを送るためにできることは?
舞麻:最近聞いて可愛いなと思ったのが、夫婦のどちらかが「そろそろセックスしたいな」と思った時に、ダイニングのテーブルにある置物を出すという秘密の合図を作っている知り合い夫婦がいます。
私はセックスがしたいと思ったら、自分から夫にゴロゴロって甘えながら寄っていくドストレートタイプなので、夫婦間の合図を作るのも素敵だなと思いました。
純:私は20代の頃は自分から求めるのが恥ずかしくて、男性から求められた時に応じていました。だけど、歳を重ねるにつれて、私にもセックスしたい時としたくない時があると自分の性欲に前向きに向き合えるようになってきました。今は自分の気持ちを大切に「セックスしたいな」と感じた時には自分からアプローチできるようになりました。とはいえ、私に気持ちがあるように相手にも気持ちがあるわけなので、難しいですよね。
私が「セックスしよう」と言った時に「オーケー!」と毎回応じてくれる人もいれば、なかなか私がしたいタイミングと合わない人もいて。30代の頃はセックスを拒絶されてプライドが傷ついたこともあります。
今お付き合いしている彼は、気持ちが盛り上がらないとセックスができない人。だけど、私にも性欲があるわけだから、どうしたら良いのかなと少し悩んでいて。今度セキララカードを使って彼ともセックスのことを話そうと思っています。
舞麻:純がセックスを拒絶されて傷ついたと話していたけど、男性も勇気を持ってアプローチしてきてくれてることを女性側も忘れちゃいけないと私は思っています。相手も勇気を出して誘ってくれているから、気分が乗らない時でも「今日嫌」「触らないで!」みたいな反応ではなく、「今日は疲れてるから週末しよう」とか、心が繋がってない状態で体が繋がることを考えられたいのであれば、「最近お互い忙しくて会話できてないから、まずは一緒に時間を過ごしたい。」など、光を閉ざさないような返答が大切かなと。
あとは、男性任せにしないで、 女性からもきっかけを作ることが大切だと思います。たとえば、「新しい下着を買ったんだ」と伝えてみたり、肌触りの良いシルクの寝巻きを着てみたり、キャンドルを焚いて雰囲気を高めてみたり。
そしてセックスの有無に関わらず、2人だけで話をする時間を持つことは絶対に大切。友達夫婦の男性側から「夫婦関係がうまくいっていない……」と相談されたことがあって、その時に「もし離婚の危機を感じているのなら、どんなに忙しくても週1回、30分でも良いから、奥さんと2人だけで過ごす時間を作った方が良いよ」と私なりのアドバイスしたことがあるんです。その後、2人だけの時間を持つようになってから、その夫婦は冷めきっていた関係が復活したんですよ!最近パートナーとご無沙汰だって人は、まずは2人で会話をすることからスタートするのもありだと思います。
純:確かに忙しいってことは、2人だけの時間がなかなか取れないってことだから、2人だけで会話をすることから修復するのはいいかもしれないですね。

Q:セックス中に気になる体の部位は?
純:セックスしている時に気になる部分と、日常で気になる部分は異なるなと。私は普段は足が気になるけれど、セックスの時にはお腹の贅肉とか、胸の大きさやポジションが気になります。以前付き合っていた方に体の気になる部分を言ってみたら、「セックス中にそんなの気にしないよ」と突っ込まれたけど。
舞麻:私はあごが気になる!寝っ転がって下を向くと、二重あごになるのがすごく嫌。騎乗位の時とか、自分のあごが今どうなっているのか気になって集中できない時があって。「彼は気にしていないのだから、今はあごのことを気にしちゃいけない」って自分の意識を戻します。笑
ただ、結局見た目は自分の問題で、相手はあまり気にしていないなって思います。あっ!けど、高校生の時にはじめて外国の方と付き合った時に、人づたえにアンダーヘアについて指摘されたことがあります。アンダーヘアを剃るっていう概念が当時の私にはなくて。だけど、何も処理していないのが彼は嫌だったみたいで、私の仲良しの友達に相談したようなんです。友達から「まさか、下の毛剃ってないの?」って言われて、「剃るってどこを?」と驚きました。それ以来アンダーヘアはきちんと処理しています。
純:私は男性にもアンダーヘアは綺麗にしていて欲しいと思ってます。見た目の問題というよりは、「私があなたを気持ち良くさせるためにアクセスしやすくしておいてね」という理由です。
Q:どんなキスが好き?
舞麻:アメリカだとみんなチュパチュパ音をさせてキスをするけれど、日本人ってキスする時にあまり音がしない気がする!音がしないキスは素面に戻っちゃうからちょっと戸惑います。
純:日本ではキスをする時に音が出るのは良くないことなのですか?
舞麻:恥ずかしいからかもしれない。他の国はどうなんだろう?香港や韓国の方と付き合っている知り合いがいるから、アジア人のキス事情、聞いてみようかな。
Q:セックスレス問題、どう思う?
純:私も初めて同棲した彼氏とはセックスレスになったことがあります。一緒に住んでしまうと、いつでもできるからこそしなくなるみたいな。当時はまだ未熟で、セックスレスの問題を話し合うことなく関係が終わってしまいました。ちゃんと向き合えなかったことに後悔が残ったので、そこからは不満があるのなら、セックスについてちゃんと話し合うべきだと思うようになりました。パーソナルなことだから話しにくいかもしれないけれど、お互いの考えをリスペクトするためにも話し合いは大切。
もちろん体の関係がなくても大丈夫なカップルもいると思うけれど、私はセックスなしでは関係を続けられない。会うたびにする必要はないけれど、やっぱり体の繋がりは大切にしたいなと。セックスしなくなると、だんだんキスやハグもしなくなって……、最終的には「今日何食べる?」みたいな会話しかしなくなるのかなって。
舞麻:セックスをあまり重要に思わない人もいるし、すごく大切だと思う人もいる。どちらも悪くはないけれど、セックスの価値観が違ってしまうと、パートナーとしてずっと一緒にいられるかは……。
純:私は、離婚するかもしれない。最初は、「もうセックスしなくてもいいか」と開き直るかもしれないけど、相手から拒絶されてばかりいると、イライラが募って、日常生活でもどんどん相手の嫌なところが見えてきそうな気がします。
セルフプレジャーをしても良いけれど、愛する人とのセックスでしか味わえないものがあると思うんですよね。
舞麻:私もセックスしなくても良いと思う時もあるけれど、相手のことを愛しむ心があるから求められたら受け入れたいなと思っています。たとえば、相手が頭が痛いと言ったら、肩をもんだり、マッサージをしてあげたいと思うのと同じで、 もし彼がセックスをしたいとか、スキンシップをしたいと思っているのなら、答えてあげたいなって。
そもそも、女性は月に一度しか排卵がない一方で、男性は毎日精子が作られる。男性の短いリズムと女性の長いリズムではお互いのバイオリズムが異なるから、セックスのタイミングが合わないのは当然だなと私は思っています。でも、「なぜパートナーとして苦労もしながらも一緒にいるのか?」と考えると、この人とは年を重ねてセックスができなくなってもお互いを愛し、共にいたいと思えるからなのかなと。そう考えると、セックスだけに注目するのではなく、相手が喜ぶことをしてあげたいという気持ちが大切で、その延長に体と体のつながりがあるのだと思っています。
純:相手を思いやる気持ちが、自然にセックスにつながるのかもしれないですね。

Q:セックスにはテクニックが必要?
純:若い頃、私は「体が硬いから、女性が上になる体位は自分には向いていない」と決めつけていて、セックスを楽しむことができませんでした。でも30代になって、自分が楽しんでいないと相手も楽しめないことに気がついたんです。特に、優しい男性は女性が楽しんでいるかを敏感に感じ取ります。だから最近は、「細かいことは気にせず、とにかく楽しもう」というマインドに切り替えました。気持ちが良ければ自然と声も出るし、体も動くもの。素直に反応する方が、男性も喜んでくれると感じています。
男性は、「俺が彼女をこんなふうにさせているんだ」という満足感を感じると、さらに相手を気持ちよくしたいという意欲がわくのかもしれません。その意欲が伝わることで、私もより感じるようになり、結果的にお互いがよりセックスを楽しめるのかなって。
舞麻:私の肌感覚では、セックスに自信のある人ほど、実は上手くないかなって思います。自信があるからか、私の反応にあまり気を配らず、自己満足で進める感じがある気がします。相手の反応を気にせずに進んでいく人とのセックスは、結局あまり満足度の高いセックスだったとは感じないことが多いかなって。一方で、空気を読んだり相手の気持ちを感じ取れる人は、結果的にセックスが上手だと思います。たとえば、ここにキスしたら喜んでくれた、ここを触ると反応がよかったなど、相手の反応を観察して、その人が求めることを探っていく。そうすることで、2人だけの特別なセックスが生まれるのかなと。だから、私はセックスをする時には、気持ち良いと感じたら少し大げさに反応してみたり、逆にあまり気持ち良くない時には無反応になったりして、反応で気持ちを伝えるようにしています。口で伝えるのは空気を壊しちゃいそうで苦手です。
純:私は口でズバッと伝えちゃいます。「そこが気持ち良い」とか「そこは痛いとか」。そんなにセックスに時間をかけられないから(笑)。 若い時は恥ずかしくて伝えられなかったけど、最近は言わないと無理!でも、ちゃんと伝えた方が男性は感謝してくれるなと。
舞麻:男の人って知りたがるよね。「これどう?」って。
あと、大切なのは学ぶ精神!私はYouTubeのゲイのセックス講座を見て勉強して、夫に試すこともあります。結婚しちゃうと毎回同じ相手とセックスするわけだから、どうしてもマンネリになってくるので。
純:私はちょっと前に、女友達とセックス講座を受講しました。新たな技を教えてもらって、それを彼に試してみたらすごく喜んでくれたので、そういうクラスとかに行くのも悪くないかも。日本にはセックスをテーマにした講座はあまりないかもしれないけど、女友達と軽い感じで参加してみるのも結構楽しいですよ。
舞麻:テクニックなんて何百個もあるわけだから、 学んで、試して、「これ好き」「あれ好き」って愛する人と楽しくセックスするのが一番ですね!
「過去の記憶と向き合う:映画『You Were My First Boyfriend』が教えてくれたこと」

「痩せればもっと可愛くなれる。
もっとおしゃれをすればみんなに好かれる。
メイクを覚えれば男の子にモテる」
こんな言葉に囲まれながら、私の自分の価値観は形作られていきました。金髪の綺麗なティーンエイジャーがたくさんいる学校で育った私にとって、自分のアジア人としてのアイデンティティは、自己肯定感を低くしていました。だからこそ、ドキュメンタリー映画『You Were My First Boyfriend』に深く共感しました。
この映画は、監督セシリア・アルダロンゴが、主に白人の人々が住むフロリダで成長した経験を描いています。プエルトリコ系である彼女の文化や外見は、同級生からいじめの対象になりました。アルダロンゴは、いじめの理由を映画の中ではっきり語っていませんが、彼女が再現したトラウマ的な体験から、その孤立の原因が彼女の外見にあったことが伝わってきます。
映画の中で、彼女は自分の10代の頃の写真を見せます。それが私自身を思い出させて胸を締め付けられるようでした。私もぽっちゃりしていて、黒い髪と小さな茶色い目をしていました。その隣には、輝くようなハチミツ色の金髪、鮮やかな青い目、スリムな体型の女の子たちが写っていました。彼女たちと比べることで、自分がどう見られているか、自分のことをどう感じているかが影響を受けていたことが、今ではよくわかります。
“彼女の物語は、10代の頃に他人と自分を比べて抱いていた劣等感が、実は周囲の誰もがそれぞれに不安を抱えていたことに気づかせてくれる、自己イメージの誤解とすれ違いを描いている。”
映画の中には、セシリアがトリ・エイモスのミュージックビデオを再現しながら、姉妹と共有する心のこもった瞬間があります。
「いつも痩せてたのはあなただった」と、セシリアは痛みを含んだ声で言います。すると姉妹は涙ながらにこう返します。「でも、あなたの隣にいると私は普通に見えたのよ」
このやり取りは、若い時の自分の見え方を見事に捉えています。10代の頃は、自分の見た目や好きな人が自分に気づいてくれるかどうかにばかり心を奪われていました。他の人も、同じように自信がなかったなんて考えもしませんでした。友達が自分より早く大人びていき、男の子たちに注目されているのを見て、いつも自分と比べていました。でも、今振り返ると、彼女たちもまた隠された不安を抱え、私を「地味な女の子」とは見ていなかったのかもしれません。

私はいじめられたことがなく、親切な友達に恵まれていたことに感謝しています。それでも、この映画は、不安や辛い記憶がどれほど長く私たちの心に残るかを思い出させてくれます。
映画はセシリアが高校の同窓会に出席する場面から始まります。会場に到着した彼女の緊張感がスクリーン越しにも伝わってきます。大勢の中を歩きながら、彼女は同級生たちから受けたひどい扱いについて語ります。しかし、その同級生たちはと言えば、そんな記憶はないと笑って答えています。彼女には、その瞬間が昨日のことのように鮮明に残っているのに、です。
映画を通して彼女は問い続けます。なぜこれほどまでに過去の記憶が残っているのか?なぜこの痛みにとらわれてしまうのか?
言葉の重みや感情の影響力を考えさせられる興味深いテーマです。私もまた、10代の頃に刻まれた記憶が残っています。サマーキャンプでドッジボールをしていたとき、ある男の子が「デブ」と叫びました。彼の顔も声も覚えていませんが、その時の恥ずかしさ、そして傷ついた感情は今でもはっきり覚えています。言葉はその場限りではなく、それが引き起こす感情によって永遠に心に残ることがあります。
“親切な友人に恵まれていても、10代に刻まれた何気ない言葉や出来事の痛みは大人になっても鮮明に残り続けるのだと、この映画は改めて気づかせてくれる。”
映画には、学校のキャンプでのシーンを再現する場面があります。セシリアは、キャンプ場で寝ている同級生がいじめられているのを見ながら、何もできずにいたことを思い出します。そのとき、自分ではなくてよかったと安心さえ感じたといいます。 撮影の場面では、いじめを受けたクラスメートがその場に立ち会い、再現される場面を目の当たりにしています。この手法には深い意図と配慮が感じられます。なぜなら、いじめを受けた本人を抜きにして、その物語を完全に伝えることはできないからです。
その人にとっては、この体験がどれほど辛いものかが伝わってきます。カメラに向かって「もう自分を知っているから、この経験は必要ないと思っていた」と告白します。でも、モニターを見つめ、涙を流しながら彼女はセシリアにそっとささやきます。「これが必要だったんだ」
私たちは、今の自分を形作った過去の瞬間にタイムスリップしてもう一度体験することはできません。でも、もしそれができるとしたら、私もそうしたいです。年を重ねると、自分の若い頃に対してもっと優しく、共感できるようになります。どんなに辛い経験も、私たちを強く、賢くし、より良い人間へと成長させてくれるのだと学びます。
映画の最後、セシリアの高校時代の親友キャロラインの死が明らかになります。キャロラインは、他人がどう思おうと気にせず、自分のユニークさにプライドを持っていた、勇敢な人物だったとセシリアは語ります。それこそが、セシリアが彼女から距離を置いた理由だったのかもしれません。キャロラインの強さは、セシリア自身の「受け入れられたい」という欲求と対照的でした。

10代の友情はもろく、未熟さや不安で満ちています。セシリアはその当時、自分をそのまま愛し、受け入れてくれる人がそばにいたことに気づいていませんでした。でも、気づいたときにはもう遅すぎたのです。最も勇敢で恐れを知らない人でも、時に心が折れることがあるのです。
セシリアは映画を通して、彼女との思い出を再現し、キャロラインを讃えます。この追悼は、温かくも切ないものです。それは、無条件の友情の美しさと、その友情を失う痛みを思い出させます。
この映画を見て、自分の子供時代から大人になるまでの違和感や不安、そして周囲に溶け込みたいという思いが蘇りました。この経験は決して私だけのものではなく多くの人が体験するもの。だからこの物語は重要なのです。私たちが陥りやすい感情の原因を明らかにし、傷ついた人々を癒し、私たちを成長させ、平和を見出す希望を与えてくれるからです。
キャロラインがいなくなったことで、セシリアは友人の存在がどれほど自分の過去を明るくしていたのかを知ります。キャロラインからの本物の友情のおかげでセシリアはあの時代を耐えることができたのです。憎しみは鋭く冷たい孤独の記憶を残しますが、愛は過去の記憶に色彩と温かさを加えてくれます。
私たちに与えられた時間は限られています。本当に自分を理解し、受け入れてくれる人々を大切にしましょう。そのつながりこそが人生に意味を与えるものだからです。気づくのが遅かった後悔する前に、その人たちをしっかりと抱きしめましょう。
オフィシャルサイト:https://www.hbo.com/movies/you-were-my-first-boyfriend
血液検査解析で自分の身体を知る。ごきげんな毎日をサプリメントでサポート【サプリメントクリニック 花井紗弥子さん】

慌ただしい日々の中で「なんとなく体調が優れない」「疲れが抜けない」と感じている方も多いのではないでしょうか。そんな不調を改善しようと、サプリメントを利用している方もいるかと思います。
今回お話を伺ったのは、産科麻酔科医として働きながら、ご自身でオンライン完結型のサプリメントクリニックを運営されている花井さんです。
市販のサプリメントを選ぶときのポイントから、花井さんがサプリメントクリニックを立ち上げた理由、気になる血液検査解析の具体的なプロセスまで教えていただきました。
| 花井紗弥子
産科麻酔を専門とする麻酔科医。総合病院や分娩施設で勤務しながら、ご自身でオンライン完結型のサプリメントクリニックを運営。 日本専門医機構麻酔科専門医 日本麻酔科学会指導医 産科麻酔科医師 母胎救命インストラクター 臨床分子栄養医学研究会認定医 Orthomolecular Nutrition Doctor |
サプリメントは「どこで買うのか」が大事
ー 今は薬局やコンビニなどでサプリメントが気軽に購入できますが、サプリメントを購入する時に知っておくべきことはありますか?
アンチエイジングや睡眠の質を高めるなど、さまざまな目的に合わせたサプリメントが販売されていますが、「これだけ飲めば効果が得られる」というのは正直難しいと思っています。というのも、人の体はとても複雑です。なぜその栄養素が不足しているのか、根本的な原因にアプローチしないと永遠とサプリメントを摂り続けなければいけないことになります。
また、サプリメントを購入するときには、どこで買うのかが大切です。「原材料にこだわっている」とか「〇〇工場で作っています」といった表示をよく目にしますが、輸送中や保管中の環境が適切でなければ、品質を保つことが難しいからです。
たとえば、健康食品として人気のナッツは、海外からの輸送や保管の過程で見えないカビが発生することがあり、問題になっていたりするんです。サプリメントも同じようなリスクがあるので、購入する時は流通経路や保管状況まで確認すると、より良い製品に出会えると思います。
ー 流通経路や保管状況まで確認するのはなかなか難しそうですよね。
流通経路までしっかり管理している会社は、大手のECサイトでは販売していないことが多いです。そのためサプリメント会社の公式サイトから購入したり、国産のものを選んだりすると、より良いサプリメントに出会えるのではないでしょうか。
ー 手軽にサプリメントが買える分、つい色々な種類を試したくなります。たくさんの栄養素をサプリで摂取することで逆に身体に害が及ぶことはありますか?
実際のところ、手軽に購入できる安価なサプリメントには、栄養素がそれほど多くは含まれていないことが多いです。そのため、飲み過ぎによって身体に影響が出ることはあまりないと思います。
というのも、栄養素が多く含まれているサプリメントは、体に大きな影響を与えるため、むやみに販売できないからです。以前、製薬会社の方に「良い商品だから一般向けに販売しないのですか?」と聞いたところ、「過剰摂取によって体調を崩されたら困るので、ドクター専売にしているんです」と言われたことがあります。また、一見安価に思える市販のサプリメントでも、クリニック専売のサプリメントと同じ量の栄養素を摂ろうとすると、2倍近い費用がかかることもあります。
もちろん、気持ち的に元気になるなど、市販のサプリメントを飲むメリットはあります。一方で、気をつけるべきは添加物です。安価で手に入りやすいサプリメントには、栄養素よりも添加物が多く含まれている場合があります。栄養素的には胃が痛くなるはずがないのに、胃がキリキリする……といった時は、添加物が影響しているかもしれません。
血液検査解析で自分の身体を知る。オンライン完結型サプリメントクリニック

ー サプリメントクリニックについてもお話が聞きたいです。産科麻酔科医である花井さんがサプリメントクリニックを開院されたのはどうしてですか?
きっかけは2つあって、1つは父のような医師を目指していたからです。父は田舎町で小さなクリニックを営んでいて、地元の人たちみんなが父の患者さんでした。街ですれ違う方から「お父さんに診てもらうと元気になるよ」と言われることも多く、私も身近な相談役のような医者になりたいと思っていました。
もう1つは、サプリメントの基礎でもある分子栄養学を学んだことです。西洋医学は主に病気の治療を目的としていますが、病気だけで人の身体を理解するのは難しいと感じ、もっと身体の仕組みを知るために様々な研究会や勉強会に参加して勉強を始めました。
医者になってからは、友人や知り合いから「最近、頭が痛いんだけど、病院に行った方がいいのかな?」「たまにめまいがするんだよね」といった相談を受けることも多く、病院に行くほどではないけれど、不調を感じている人がたくさんいることを実感しています。
医者としての知識や経験、さらに学んだ分子栄養学を活かして、身体のことを気軽に相談できる場所を提供したいと思い、2022年11月にサプリメントクリニックを開院しました。
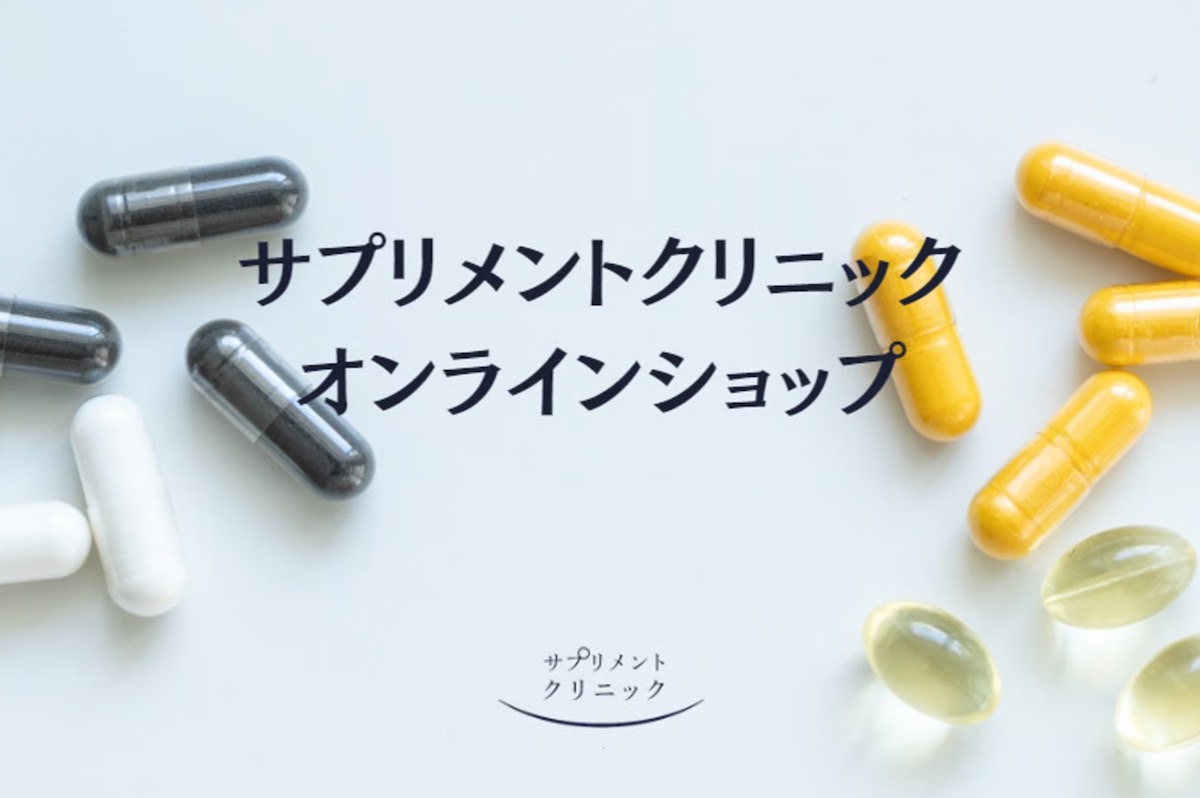
ー サプリメントクリニックは血液検査解析から面談、サプリメントの処方までオンラインで完結できるのでしょうか?
気軽に自分の身体を知ることができる場所を目指し、オンラインで完結できる形にしました。
というのも、私自身もこれまで色々なクリニックを受診してきましたが、病院に行くことが一大行事だと感じたからです。少し前まではオンラインシステムがあまり普及していなかったこともあり、電話で予約をして、検査に行って、結果が出たらまた予約をして、検査結果を聞きに行く。しかも診察までの待ち時間もあります。医療サービスを気軽に利用できない現状を実感しました。
ー 色々なサプリメントのクリニックを調べてみましたが、検査費用が高額な印象を受けました。花井さんのサプリメントクリニックは15,000円で血液検査解析から面談まで受けられる。受診するハードルが低いので、自分の身体を知るために私も検査を受けてみたいです。
パーソナライズした検査は、日本よりもアメリカの方が進んでいて、血液検査だけでなく、唾液検査、検便、毛髪検査を取り入れているクリニックもたくさんあります。でも、それを輸入して日本でやろうとすると、1回の検査がすごく高くなってしまう。「自分の身体を知りたい」という理由で受けるには、ちょっとハードルが高いですよね。過去に毛髪検査を受けたことがあるのですが、毛根に近い部分をかなりの量切る必要があり、負担が大きいと感じました。
私はよりたくさんの方に自分の身体を知ってもらいたいと思っているので、 気軽に受けられる血液検査の解析を提供しています。
ー ちなみに、オンラインで血液検査解析ができるクリニックは日本ではどのくらいあるのでしょうか?
血液検査の解析は医師にしかできません。そのため、クリニックで受けられるところはあると思いますが、オンラインで完結できるサービスは、まだほとんどないと思います。
ー オンライン診断は具体的にはどのような流れで行われるのでしょうか?
オンラインショップで「血液検査によるカラダの状態解析」というメニューを購入いただいた後に、メールで血液検査結果の写真と60項目の問診を送っていただきます。それを元に解析レポートを作成し、オンライン面談を行っています。
健康診断や人間ドックの血液検査の結果がある方はそれを送っていただきますが、血液検査の結果が古い方や、もっと詳しく調べたい方には、提携病院を紹介して採血いただくことも可能です。
ー 血液検査の解析では、どのようなことがわかるのでしょうか?
主にタンパク代謝、糖代謝、体の酸化度合い、ミトコンドリア機能や副腎機能などが分かります。
人の身体って、知らない間にいろいろなシグナルが送られているんです。臓器も細胞も常に動いていて、それを可視化すると「ここの反応が落ちているから、これが足りないんだな」というのが分かる。さらに、反応が悪くなっている根本的な原因も見ていけます。
ー 生身の身体を見なくても、血液検査の解析から足りない栄養素や、その原因まで知ることができるのですね。オンラインの面談ではどのような話をされるのですか?
血液検査解析や問診だけでは見えない部分を知るために、その方に合わせていくつか質問をさせていただきます。その上で、「今あなたの体ではこんなことが起こっていますよ」という説明や、睡眠や運動、食事などの生活習慣をアドバイスしたり、最適なサプリメントをご提案したりしています。
ー サプリメントありきではなく、生活習慣をアドバイスした上で必要があればサプリメントを提案するのですね。
そうなんです。身体を整える上で大切なのは、やっぱり生活習慣なんですよね。
たとえば、山登りをするとき。杖や紐を使って体の負担を和らげることはできるけれど、自分で上る力は必要不可欠です。サプリメントは杖や紐の役割を担うものであって、あくまでも補佐的な存在。最終的に目指しているのは、サプリメントがなくてもご機嫌で過ごせる状態です。
ー サプリメントクリニックを受診された方で、 印象に残っている患者さんはいますか?
お一人は、もともと健康意識が高い60代の女性です。帯状疱疹が長引き、日常生活に支障をきたすほどの痛みに悩まされていました。病院の先生からは「帯状疱疹は長く付き合うものだよ」と言われていたそうです。ご自身でも本を読んで良さそうな方法を試したり、食事を工夫したりしていましたが、思うような改善が見られず、私のところに来られました。血液検査を解析した結果、ミトコンドリア機能の低下が見つかり、最初は5種類のサプリメントを摂っていただきました。お客様ご自身も食生活を工夫されたため、途中から3種類に減らし、2ヶ月後には病院の先生も驚くほど症状が改善して仕事に復帰されました。現在は、健康維持のためにお気に入りのサプリメントだけを飲まれています。
もう一人の方は、健康増進のために受診してくださった20代の方です。バリバリ働いていて、特に自覚されていた不調はなかったようです。しかし、血液結果解析をしたところ、何個か気になるところがあったので、サプリメントをご提案させていただきました。サプリメントを飲み始めてから、ものすごく悪かった寝起きが良くなったり、立ちくらみがなくなったり、肌荒れが解消されたり、これまでイライラしていたことをうまくスルーできるようになったり、たくさんの変化が現れて「あの症状って身体の不調だったんだ」と驚いていました。
ー 寝起きが悪いとか、イライラしがちとか、特質だと思われることでも、足りない栄養素を補ってあげることで改善できることもあるのですね。驚きです!
自分の身体を知ることで、ごきげんに過ごせる人を増やしたい

ー 花井さんご自身が健康のために意識していることはありますか?
よく寝ることとストレスをためないことを意識しています。
少し前は子どもを寝かしつけた後に仕事をすることもありましたが、今は子どもと一緒に寝て、しっかり睡眠時間を確保しています。
あとは、ストレスをためないために、「やらねばならぬ」という気持ちを一旦置くようにしています。アメリカでは「Longevity」(長寿医療)という、より健康的な加齢を目指すための医療・研究が進んでいて、週150分の運動が推奨されているんです。私はそういった数字を聞くと「毎週150分運動しないと」と思い込んでしまうタイプ。でも今は無理をせず、自分のペースでジムに通っています。食事も基本的には自炊を心がけていますが、疲れているときは外食したり、レンチンで済ませたりすることもありますよ。何かを実行するということは、その分何かを犠牲にすることだと思うので、無理のない範囲で取り組むようにしています。
ーサプリメントも取り入れていますか?
生活や食事内容から不足しそうな栄養素があれば、その都度サプリメントで補っています。状況に応じて、食物繊維、ビタミンC、ビタミンB群、マルチビタミンミネラル、鉄……などを飲み分けています。
ー 花井さんはサプリメントクリニックの運営を通じて、どのような世界を目指していますか?
みんなが毎日をごきげんに過ごせる世界になったら良いなと。分子栄養学を勉強することで、改めて健康の大切さに気がつきました。体調が優れないと、やる気が出なかったり、頑張りきれない時がありますよね。
たとえば、イライラしてしまう時も、それがPMSによるものなのか、あるいは別の原因があるのか。その原因を知って適切に対処できれば、「頑張らなくちゃ」ではなく「今日も頑張ろう!」と前向きな気持ちで過ごせると思うんです。
サプリメント、ヨガ、マッサージなど、心と身体を整える方法は人それぞれです。サプリメントクリニックは、自分の身体を知って整えるための1つの選択肢になれたらと思います。
ー 最後になりますが、どういった方にサプリメントクリニックに来て欲しいですか?
性別や年齢に関係なく、すぐに怒ってしまったり、気持ちが落ち込みやすかったり、本来の自分の力を発揮できていないと感じている方にぜひ来ていただきたいです。
私自身、子育て中のママであり、産科麻酔科として働いていることから、特に、女性や子育て中のママを応援したいという思いは強いです。もちろん男性も歓迎ですよ。
西洋医学は多くの人に当てはまる「正解」を見つけることを重視しています。それは大切なことですが、どうしてもその治療が合わない人もいるわけです。その点、サプリメントクリニックでは一人ひとりの身体を個別に診ることができます。健康増進、病気の治療、美容など、目的は何であってもかまいません。その方に適したアプローチをご提案させていただきます。

花井紗弥子
サプリメントクリニックHP:https://supplclinic.stores.jp/
Instagram:https://www.instagram.com/dr.sayako_hanai/
乳がん診断による精神的影響とマンモグラフィ検査の重要性

多くの人が、乳がんの影響を受けた人を知っているでしょう。それは友人、母親、姉妹、またはあなた自身かもしれません。米国では、約8人に1人の女性が一生のうちに乳がんにかかるとされています。毎年、乳がんで40,000人以上の女性が亡くなっています。乳がんを早期に発見することで、生存率の向上に繋がる可能性があります。
マンモグラフィ(乳房X線撮影)は乳がんを予防することはできませんが、早期に発見するための最も有効な主要な検査のためのツールです。マンモグラフィを受けるべき時期については、医療提供者に相談してください。乳がんの検診を受けるために、このようなクリニックに行くことがとても大切です。
マンモグラフィは命を救う手助けをします
推奨されるマンモグラフィ検診を受けていない女性も多く、その理由には恐怖や時間、費用への懸念、マンモグラフィについての知識不足、医療サービスへのアクセスが限られていることなどが含まれます。
信頼できる健康に関する情報や、メンタル面でのサポートを提供していくことで、こういった女性が検査に対して感じる持つハードルを低くしていくことができます。
乳がん診断後のメンタルヘルスケア
乳がんと診断された後、人々は治療前、治療中、治療後にさまざまな浮き沈みを経験するのが一般的です。不安や悲しみ、ストレスを感じることもありますが、これらの感情は時間とともに薄れることもあります。しかし、時にはこれらの感情が数ヶ月、あるいは数年続き、日常生活に影響を及ぼすこともあります。どんな感情も正しい、正しくないという判断はせず、こういったネガティブな感情を持つタイミングも人それぞれであることを覚えておいてください。
乳がんと診断された人は、まずメンタルヘルスのサポートを受けることがメリットになるでしょう。以下のような場合、メンタルヘルスの専門家と話すのが良いかもしれません。
- 診断やその変化を受け入れるのが難しい場合乳がん治療による疲労や吐き気、気分の変化など、身体的および感情的な
- 副作用がある場合
- 治療の選択肢などについて、心が押しつぶされそうなプレッシャーを感じている場合
- 仕事や家庭での責任にどう対応するかについて不安がある場合
- これからの生活が変わり、家族や友人との関係に影響を及ぼすことへの怒りを感じる場合
- 医療費の負担や仕事の休暇の問題、好きなことに費やすお金が足りないことなど、経済面での不安がある場合
- がんの再発に対する不安を感じている場合
- 死への恐怖を感じている場合
- 髪や乳房の喪失、性的健康の変化など、身体的な変化に対する悲しみを感じている場合
- 将来の妊娠に関する心配がある場合
多くのがんセンターでは、メンタルヘルスサービスをがんケアの重要な一部と考えており、ソーシャルワーカーや心理士、精神科医が個別のサポートとカウンセリングを提供しています。同じ経験をしている他の人々と話したいという人のために、患者支援グループを提供しているがんセンターもあります。また、一部のがんセンターでは心理腫瘍学という、がんと診断された人やその家族が直面する心理的、感情的、社会的な問題に焦点を当て支援をしています。
人それぞれの状況は異なります。診断直後に1、2回のカウンセリングを必要とする人もいれば、治療が終わった後に医療チームから離れたことで支えが必要と感じる人もいます。自分に合ったサポートを見つけるまでには時間がかかることもありますが、それぞれに合った方法を見つけていくことが大切です。

メンタルヘルスサポートがもたらす効果
一部の専門家は、メンタルヘルスサポートを受けることが乳がんの治療効果を改善する良い方法であると考えています。いくつかの研究によると、感情的に安定している人の方が治療計画に従いやすく、診察の予約に出席し、運動や栄養に関する推奨事項を守る可能性が高いとされています。他のがん患者やサバイバーと出会い、自分のコミュニティを築くために、乳がん啓発のためのウォーキングイベントに参加するのも有益かもしれません。
多くのメンタルヘルス専門家は、できるだけ早くサポートを受けることを推奨していますが、カウンセラーと話す、オンラインサポートグループに参加する、またはアートセラピークラスに参加するのに遅すぎることはないとしています。診断を受けたばかりの人、治療を受けている人、治療を終えた人、誰にとってもメンタルヘルスサポートは役立ちます。
- 不安、うつ、慢性的なストレスの軽減
- 幸福感、満足感、楽観的な気持ちを促し、前向きな見方ができるようになる
- プレッシャーを感じた時に役立つ対処スキルを学ぶ
- 家族や友人との関係を強化する
- 睡眠の質を改善する
乳がんと診断されることは、多くの人にとって精神的に大きな負担となります。不安や恐怖、孤独感、さらには将来像が見えなくなることで、精神的なストレスが高まります。しかし、適切なサポートや早期発見が心の安定を保つために重要です。この点で、定期的なマンモグラフィは重要な役割を果たします。早期に乳がんを発見することで、治療の選択肢が広がります。自分自身と家族の健康を守るためにも、マンモグラフィの重要性を再認識し、定期検査を受けることを心がけましょう。
関連記事:乳がん人間ドックのワンポイントアドバイス|FeliMedix
参考:https://www.breastcancer.org/managing-life/taking-care-of-mental-health
https://www.fda.gov/consumers/owh-resources-stakeholders/pink-ribbon-guide-mammography-matters
エシカルコスメ:環境と肌に優しい美容製品の紹介
妊娠できない本当の理由を知り、妊娠力を高める方法とは。【妊娠するための栄養情報を発信する管理栄養士YUKAさんインタビュー】
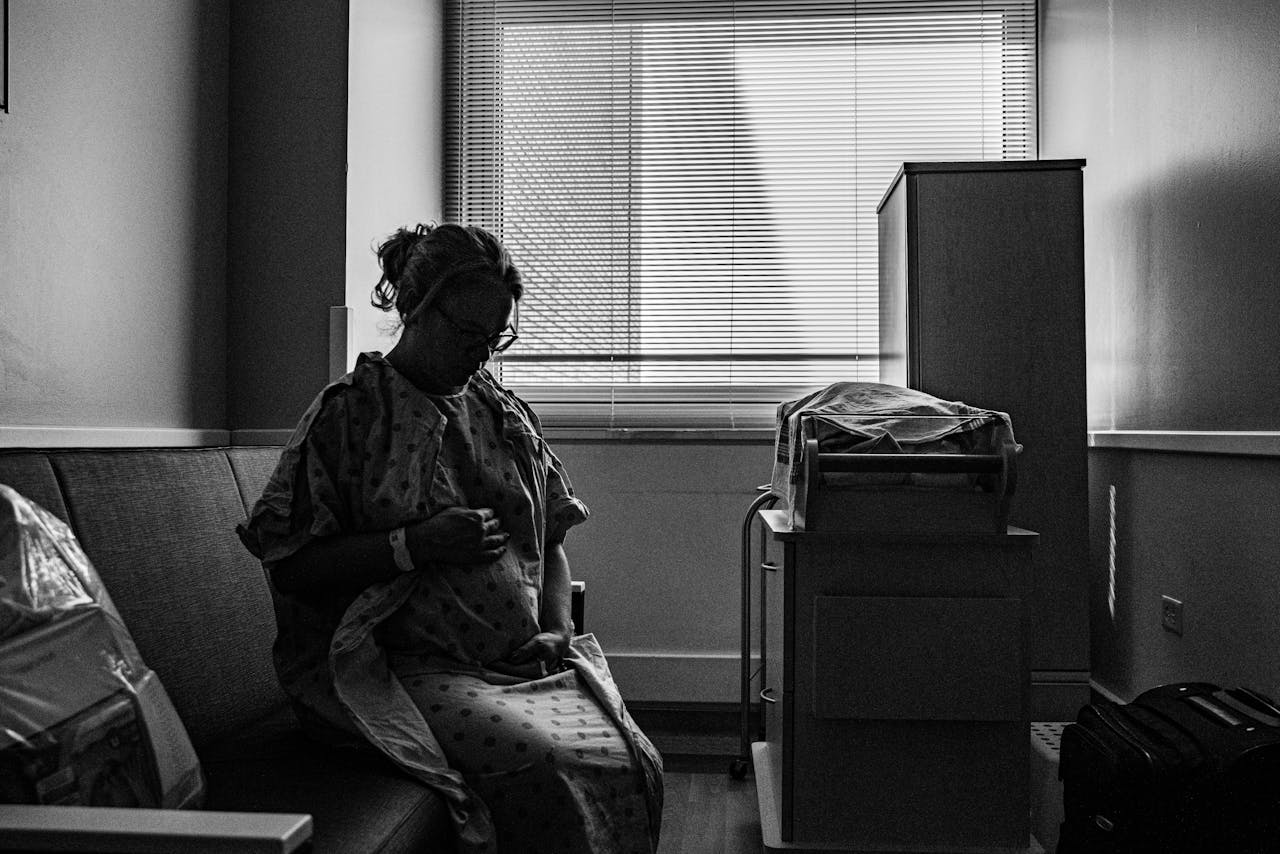
妊活を始める女性が直面する最大の悩みは、「まずは何から始めればよいのか?」という最初の一歩ではないでしょうか。インターネットやSNSには無数のアドバイスが溢れていますが、その中で何が自分に合った方法なのか、迷うことも少なくありません。そこで今回、ハミングは、自身も39歳で出産を果たし、妊活専門栄養士として活躍するのYUKAさんにインタビューを行いました。
妊活中に抱える不安や孤独、そして数々の試行錯誤を経た彼女が、どうして今、妊活支援の発信を始めたいるのか。「栄養の専門家が考える妊活の心得」とは何なのか。さらに、心の健康を守りながら妊活に取り組むための栄養アドバイスについても詳しくお話を伺いました。
ーーYUKAさんが妊活中、特に気を付けていた栄養管理のポイントを教えてください。
妊娠するためには、卵子の質がとても重要です。その卵子は私たちのカラダで作られますから、何を食べるかがカラダ作りの基盤になります。これを食べたら妊娠できるという食品はないんですが、それより、何を食べないかという考えがすごく重要になります。
例えばグルテンやカゼインといった、カラダに炎症を起こさせるタンパク質。あとは、ビタミンやミネラルを消耗させ、カラダに負担をかける添加物、例えば、人工甘味料や白砂糖などは極力控えることが重要です。こういった食品を控えていくと、 カラダの負担がなくなり健康を取り戻すことができます。
ーー何を食べないかを意識しながら、妊活を続けるというのは、ちょっと難しいなと感じる方もいそうですね。
そうですね。例えば、グルテンをまず2週間だけ控えてみるといいと思います。それで体調の変化をチェックしてみます。体調が良くなってきたら、グルテンがカラダに合っていなかったことがわかりますよね。私自身、栄養療法を専門でやってきましたが、患者さん自身が控えてみることでカラダの変化がわかるんです。体調が良くなるから、自然とそういう食事を継続できるようになります。
ただ、グルテンやカゼインを控えるのは、対症療法(病気の根本的原因をのぞくのではなく、現れた症状に応じて行う治療法)に過ぎないんです。でも、この一時的な治療で、まずは腸に負担をかけるような食事を控えていくうちに、自然と腸の粘膜がケアされていくんです。そうすると、グルテンを多少食べても問題なくなってきます。
ーー妊活中のサプリメントや漢方薬使用についてはどう考えていますか。
サプリメントを摂取したからと言って、必ずしも全員が妊娠したり、AMH(卵子をどれくらい排卵する能力があるか示す数値)が上昇するということはないと思います。ただ、栄養素の塊であるサプリメントは効率化の道具ではあります。例えば、ビタミンDや鉄は食事からも摂取できますが、これは妊活女性にはぜひサプリでもとってほしい栄養素なんです。バランスのいい食事を取ることが、最初にやることですが、それに加えて、その人のカラダの状態に合ったサプリメントを摂取するというのが、最短で妊娠するためには必要な選択だと思っています。
ーー自分に合うサプリメントは、どうしたら選べるのでしょう。
自分に合うサプリメントはなかなか自分ではわからないですよね。私の場合は、その方に 症状問診票を書いてもらい、その症状にあった食事を提案しています。血液検査を受けてもらい、どの栄養素が不足しているかを考えて、必要なサプリメントを飲んでもらうこともあります。ただ、これも一時的な対処法にすぎません。大事なのは、なぜその栄養素が不足したのかを考えることです。サプリメントも取り入れながら根本原因にアプローチをし、最終的にはサプリメントがいらないカラダにすることが目的です。
ーーYUKAさんは妊活をスタートしてからどのくらいで妊娠されましたか?
2年くらいですね。最初は人工授精などから試みていき、3つ目の病院で妊娠しました。当時は、人工受精を3回ぐらいすれば妊娠できると思っていたし、まさか体外受精をすることになるなんて思っていなかったです。
妊活に関する知識もなかったので、医者に言われるがままでした。私のカラダは卵子が少なかったんですよね。だから、採卵をしても、卵が4~5個しか採れなかったんです。37歳くらいでしたけど、もう44~45歳の女性と同じぐらいの卵巣機能の状況だと言われて、すごくショックを受けました。
その一方で、妊娠するためには卵が10個も20個も必要なのでなく、質の高い卵子が1個とれればいいと教えてもらいました。ただ、そのために何をしたらいいかなど具体的なことは何も教えてもらえず、「病院の技術に任せてください」とだけ言われました。結果、うまく行かなかったので違和感を感じるようになったんです。
卵子は私のカラダが作るものなのに、その私が何もしないというのはおかしいなと思い、分子栄養学を勉強していたこともあり、自分で妊活について勉強を始めました。

ーー妊活を始めても、医療的な知識がないと、多くの女性はお医者さんを頼りにするしかないと思います。妊活する女性が積極的に取り組むために、まずは何ができるのでしょう?
妊活は人生を大きく左右するとても大事なことですから、うまくいかないと自分のカラダ作りをしようという結論にたどり着く方が多いと思います。 タバコやお酒をやめるとか、運動をする、食事も気をつけなきゃと、自然とその方向に進む方が多いです。自分で情報収集をしようとSNSで色々調べると、本当に正しい情報を正しい知識のもと発信しているかどうかというのはわからないですよね。
それが正しかったとしても、今のその方のカラダの状態に合っているかどうかもわかりません。そのあたりを見極めることも大事ですね。
ーー妊活をお医者さんに相談するタイミングは?
医師に相談するタイミングは年齢によっても差があるので、一概にこのタイミングと言えないですが、私がそうだったように 多くの女性は、結婚して妊活をすれば子供はすぐに授かるはずだと思い込んでいる方が多いと思うんです。でも現実はそうじゃないんです。例えば、日本では、夫婦の4.4組に1組が不妊症というデータもあります。
赤ちゃんが欲しいのであれば、すぐに妊活をしない場合でも、結婚後はブライダルチェックを受けておくといいと思います。これは、卵巣機能や子宮機能など妊娠のために問題がないかを検査するものです。その項目の1つとしてAMHの数値も知ることができます。この数値は通常の健康診断には含まれず、なかなか知ることができないので知ることができる良い機会にもなります。
あらかじめ、こういう検査をしておくことで、妊娠に関して問題があった時に、早い段階でその問題に介入することができ、いざ妊活をする場合にスムーズに始めることができますよね。
ーー妊活中にメンタルの部分で気を付けたことがあれば教えてください。
メンタルケアをしている人としていない人とでは、妊娠率や出産率に差があることもデータでわかっています 例えば、アメリカの研究では、心のケアを一緒に行うことで妊娠率が25%から52%に上昇したという報告があります。妊活中は、ストレスを感じ孤独なので、無理せずに不妊カウンセラーやお友達にまず相談して話を聞いてもらいましょう。
また、ストレスが強いと、ストレスに対抗するためにカラダがコルチゾールというホルモンを分泌するんです。このコルチゾールは、私たちのカラダで作られる女性ホルモンと同じコレステロールから作られます。つまり、ストレスが多いとコルチゾールの分泌が増え、女性ホルモンの材料であるコレステロールが消費されてしまいます。その結果、女性ホルモンのバランスが崩れ、排卵障害や不妊といった問題が起こる可能性があります。
ーーストレスによって、他にどういった影響がありますか?
ストレス状態だと、自律神経のバランスが崩れて、交感神経が優位になってしまいます。こんな状態では、胃や腸などの消化器の機能が低下してしまいます。そうすると、消化不良になったり栄養素を吸収できなくなってしまうんです。これに加えて、先ほど避けるべきだといったグルテンなどを摂ってしまうと、 これに拍車をかけてしまうんです。弱っている腸に炎症をきたし、腸に穴を開けて、この穴から未消化のタンパク質や毒素、病原体などが漏れ出て、全身に炎症を引き起こしてしまいます。便秘や下痢、消化不良、お腹の張りなどそういう症状を引き起こしてしまうことになります。このような状態だと、卵巣にも十分な栄養素を届けることができなくなり、卵子の質も低下してしまうんですよね。
ーーストレスを感じた場合は、栄養面ではどういう対応ができるでしょう?
ストレスが強いと感じたら、胃腸に負担をかけないためにも、胃酸分泌を促すような食べ物の酢の物や梅干し、消化をサポートしてくれる大根おろしやとろろ、こういったものを食材に加えるといいですね。食材を選ぶ場合にも、お肉だったらステーキや揚げ物は胃腸に負担をかけてしまうので、いったん、こういうものを控えて、ミンチ肉など消化をしやすいものを選ぶのがいいと思います。ただ、スーパーで売られている牛や豚のミンチ肉は脂の質が悪いため、消化力が弱い人だとお肉の脂でもたれたり、下痢をしてしまうことも多いので、あまりおすすめはできません。ミンチ肉を購入する場合は、スーパーではなくお肉屋さんや信頼できるメーカーなどきちんとしたところで購入するか、家庭でひき肉をひくようにすると良いと思います。私は赤身肉を買ってきて自宅でひいています。ミンチ肉をスーパーで購入する場合は鶏肉がおすすめです。

ーー妊活中の運動で、YUKAさんがお勧めのエクササイズはありますか?
質の高い卵子を作るためにも、運動はとても大事です。卵子の中には非常に多くのミトコンドリアが存在しており、このミトコンドリアを元気にすることができれば、質の高い卵子を作ることができます。そのためには、ミトコンドリアに危機感を感じさせることが大事なんです。例えば、空腹感や寒冷刺激。お腹が減ったとか、ちょっと寒いなと思った時にはミトコンドリアも危機感を感じるんです。こうやってミトコンドリアを活性化させて、数を増やし元気にすることができるんですよ。
ーー今流行りのファスティングもそういう理由で?
はい。妊活している人の間でもファスティングや16時間ダイエットが流行っていますが、これは、ミトコンドリアを元気にすることができるからなんです。ただ、これには大きな落とし穴があります。確かにファスティングでミトコンドリアは元気になりますが、これをやってよい人とよくない人がいるんです。 私が見てきた中では、ファスティングをやっている妊活女性のほとんどの人はファスティングは合っていないんですね。
ーー妊活をしている方で、ファスティングをして効果のある人が少ないということでしょうか?
ファスティングが合う人は、元々元気な方です。妊活をしなくても、妊娠できるような人なんですね。若いとか、 アスリートみたいにカラダを鍛えている方とか、 毎朝ランニングに行っているような人です。そうでない人が、ファスティングをやると、低血糖を引き起こし、エネルギーが不足してしまうため、むしろミトコンドリアを低下させてしまうので危険です。ですから、ファスティングもカラダに合うか合わないかの見極めがすごく大事です。
ーー 40代に近づいてから出産をしたことのメリットはどういったものがあると感じますか?
1つは精神面ですね。若い時に子供を持つよりは成熟しているので、寛容な視点で子どもに接して子育てができていると思います。あとは経済的な余裕。それから妊活をしていたので、子供を授かることへの感謝の気持ちを持って妊娠・出産・子育てができていることでしょうか。子供が生まれることも奇跡だと感じているので、日々、子供との生活に感謝しながら子育てができています。体力面では、ちょっときついですけど。(笑)
ーー逆に、もっと若い時に子供を持つべきだったと感じることはありましたか?
私は、やりたいことがたくさんあったので、年齢のことさえなければ、もっと遅くに出産をしていたかもしれないです。ただ、私自身が妊活をしてみて、なかなか授からなくて悩んでいた時期は、もっと早くに妊活をスタートしておけば良かったという気持ちや、妊活の知識を持っておけばと感じたこともあります。
でも、この経験があったから、今こうやって妊活に関する活動や発信をすることにつながったので、人生で起こる出来事には全てに意味があると感じますね。 妊活の末に第1子を出産して、それがきっかけで不妊で悩んでる女性たちを栄養面からサポートする活動をしたいと考えたんです。
ーー今、妊活をがんばっている方たちにメッセージはありますか?
妊活って出口の見えないトンネルを1人で歩いてるような感覚なんですよね。私自身もそれを感じて、努力だけではうまくいかないこともあるんだなと感じました。妊活は、人生で初めて感じた挫折でした。
でも、大切なことはあきらめないことだと思います。できることは必ずあります。つまり自分のカラダを見直してカラダの状態を整えることです。その基盤となる食事、つまり栄養面を見直してほしいです。
インターネット上には様々な情報が流れていますが、まずは正しい知識を持って、あなたのカラダに合ったやり方で妊活をやってほしい、そう思います。
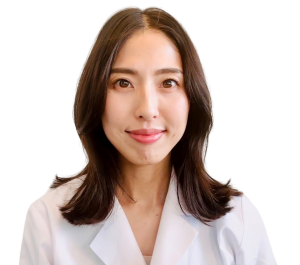
YUKA
栄養療法クリニックで1500人以上の患者に栄養指導を行い、特に不妊患者のサポートに注力してきた管理栄養士・正看護師。臨床分子栄養学の講座で医師・歯科医師を含む1000人以上に教育を提供し、医師との共同で栄養療法のオンラインスクールも運営。自身も栄養療法を実践し、AMH値を改善、38歳で妊娠し39歳で出産を経験。現在は第二子を希望中。不妊専門の漢方サロンで350人以上が参加した妊活栄養学講座を開催するなど、妊活支援に貢献している。
YUKAさんのYoutube:こちら
YUKAさんのインスタグラム:こちら
「助産師たちの夜が明ける」レビュー

子どもを持つことに常に迷いを感じてきた私にとって、出産は大きな恐怖でした。痛みだけでなく、体への影響や、出産中に感じるかもしれない深い孤独感がとても不安でした。その苦しみを乗り越えることが、とても困難に感じました。
最近、フランス映画『助産師たちの夜が明ける』(原題『Sages-femmes』)を観ました。この映画は、現実的で過酷な状況に直面する複数の架空のキャラクターを描いています。物語は、フランスの公立病院の産科病棟で、ソフィアとルイーズという新任の助産師2人が初日を迎えるところから始まります。アメリカでは、助産師は個別に雇われ、出産時に立ち会うことが一般的なので、病院内で助産師が出産の最初から最後までをサポートしてくれるという考え方に、とても驚きました。そしてそれがいかに重要で、大きな支えになるかも実感しました。
この2人の主人公は、新人である看助産師の典型的な姿を象徴しています。ソフィアは試験ではいつも優秀な成績を収め、失敗を恐れる優等生で、一方のルイーズは内気で控えめ、発言するのに躊躇するタイプ。映画では彼女たちがどれくらいの期間、友達だったかはわかりませんが、ソフィアが初日にルイーズを励ますシーンで、お互いが支え合う友好的な関係がよく表れています。
“出産への恐怖を抱えてきた私が観た映画『助産師たちの夜が明ける』は、新人助産師たちの奮闘を通して、病院での寄り添いと支えの大切さを改めて感じさせてくれる作品だった。”
しかし、ソフィアが手伝った出産で、赤ちゃんが危うく命を落としそうになる事件をきっかけに、彼女たちの友情は大きな試練に直面します。冒頭から、看護師や医師などの病院スタッフ全員が手一杯で、患者一人ひとりに十分な注意を払うことができないことが明らかです。病棟は混乱し、助けを求める叫び声が飛び交います。そんな中、ソフィアは異常な痛みを訴える母親の対応にあたりますが、生命に関わる兆候は正常に見えたため、状況を監視しつつ別の患者にも対応しようとします。ところが、赤ちゃんは心拍がない状態で生まれ、蘇生には4分かかり、その結果、赤ちゃんは脳に損傷を負ってしまいます。
このトラウマ的な経験によって、ソフィアはPTSDを発症し、深いうつ状態に陥りますが、彼女は自分がうつであることを認めようとしません。一方で、かつて自信のなかったルイーズは成長を見せ、そのことが2人の間に緊張を生み、友情を引き裂くことになります。

この状況ではソフィアを責めることはできません。成功が目標となる環境で育ったソフィアにとって、ほんの小さな失敗でさえ、心を打ち砕くような衝撃を受けるものです。感動的なシーンで、ソフィアは主任医師のオフィスに呼ばれ、もしかしたら出産の現場は彼女に向いていないかもしれないと言われます。医師は『全員を助けることはできない。助産師は幸せな時もあれば、辛いことに直面しないといけない時もあるのだ』と告げます。打ちひしがれたソフィアは『全員を助けられないなら、この仕事に何の意味があるんですか?』と答え、部屋を後にします。
この映画は、助産師たちが直面する大きな苦労を浮き彫りにし、彼らへの深い尊敬の念を抱かせます。赤ちゃんに何が起こったのかについての報告会では、スタッフ不足に対する不満や苛立ちが渦巻く中、ルイーズが印象的な言葉を発します。『私たちは患者とほとんど話すことなく走り回っていて、それは私たちの仕事を人間味のないものにしてしまいます。』本当に助けたいのに、手が足りなくて目の前で患者が苦しむのを見ているしかないという現実が、いかに胸が痛むものかを理解させられます。完璧主義者であれ、自信がない人であれ、彼ら全員が共有している一つの目的は、妊娠中の患者とつながり、支援することです。彼らは皆、本当に人を助けたいと思ってここにいるのです。
“映画は、さまざまな背景をもつ妊産婦たちの痛みや葛藤に助産師が寄り添う姿を描き、混沌とした現場の中で彼女たちがどれほど大切で感情的に深い役割を担っているかを強く実感させる。”
助産師たちが直面する課題は、赤ちゃんを取り上げることだけではありません。患者たちの人生や苦難にも寄り添わなければならないのです。あるシーンでは、妊娠したホームレスの女性が、新生児に対して距離を置いており、望まない妊娠だったことを示唆しています。また、娘が出産する場面では、助産師の言葉に耳を貸さない過保護な母親も登場します。さらには、虐待的な夫についての会話が聞こえてくるシーンや、助産師が夫に対して『妻にそんな言い方をしないで』と注意する緊迫した場面もあります。多くのシーンが混沌としていて、感情的に揺さぶられ、生々しいものです。私は何度も涙を流しました。同じ女性として、これらの母親たちが経験する痛み、喜び、恐怖を深く感じ、助産師たちが彼女たちの健康と幸せにとっていかに重要な存在かを痛感しました。
物語は、終盤にベテラン助産師のベネがシフトの終わりに突然退職を宣言することで、思いがけない展開を迎えます。彼女の同僚たちは驚きますが、ベネは、食事やトイレを我慢し、息子との時間を犠牲にすることは耐えられても、慢性的な人手不足のために患者を放置することにはもう耐えられないと説明します。この決断は、死産した赤ちゃんの両親が、なぜ出産までに5時間もかかったのかと痛ましく尋ねた場面の後に訪れます。ベネが答えられたのは、仕事に追われていたという弱々しい謝罪だけでした。母親は彼女を何度も拒否しますが、ベネは戸惑いながらも最終的には部屋を出て行きます。退職を告げた瞬間、かつて彼女の情熱を燃やしていた火が、燃え尽きてしまったのが見て取れました。
この映画は、どれだけ努力しても、物事がうまくいかないことがあるという現実を教えてくれました。そして、困難な時に自分自身を支え合うことの大切さを示しています。自分が止まってしまえば、患者が苦しむことになるからです。この映画は痛ましい一方で、美しく描かれており、人間関係の複雑さや公的医療制度の中でのフラストレーションを浮き彫りにしています。私たちは皆、利益を優先し、ケアを後回しにする大きなシステムの犠牲者です。そして、世界中で声を上げ、患者だけでなく、献身し犠牲を払ってくれる看護師たちのためにも、より良い生活とケアの質を求めることが重要だと痛感しました。
映画公式サイト:
http://pan-dora.co.jp/josanshitachi/
女性医師に聞いた体外受精を決めるタイミングと大切な心構えとは。【医療法人オーク会の田口早桐ドクター・インタビュー】

「年齢を重ねるごとに、妊娠は難しくなる──」。頭では理解していても、実際に直面すると多くの女性が悩み、立ち止まってしまう課題です。そんなとき選択肢のひとつとして浮かび上がるのが、体外受精という手段。しかし、治療に進むかどうかの判断や治療過程での不安など、迷いや疑問を抱く人は少なくありません。今回は、体外受精治療の第一線で活躍する医療法人オーク会の田口早桐ドクターに、年齢と妊娠の関係、治療を選ぶ際の注意点、そして心の準備について伺いました。さらに、普段はなかなか聞けない不妊治療の現場でのリアルな裏側についてもお話しをしていただきました。
ーー現在の不妊治療の現状について教えてください。どのぐらいの年代の方が主に通っていますか?
通われてる方は、やっぱり30代後半から40代前半の方が多いです。以前と比べて、不妊治療が一般的になってきているため、通われる方の年齢は下がってきています。以前は不妊治療は、すごく特殊なものと思われていたんですよね。特に体外受精は医療とは違うもの、と思われていたんです。
不妊の定義も以前は、「2年間妊娠しない」ケースを不妊症と呼ぶという診断基準でした。アメリカの基準にそろえてこの基準が変わり、不妊症の定義も「1年間妊娠しない」となりました。さらに人工授精と体外受精が保険診療できるようになりました。技術の変化に応じて不妊の定義も変わってきたんです。
ーー不妊治療を始めてから、体外受精まで進む方はどのぐらいの割合いますか?
不妊治療を始めた方の半分ぐらいの方は体外受精に進むんじゃないでしょうか。年齢にもよりますね。
不妊治療の方法は3段階あります。1つ目は、「タイミング法」といって、排卵に合わせて性交渉を持ってもらうもの。排卵のタイミングがわからない場合には、弊社で超音波で確認して、排卵のタイミングをお知らせします。
2段階目は「人工授精」といって、精子を子宮の中に直接挿入する方法です。排卵のタイミングに合わせて行います。
3段階目が「体外受精」です。精子も卵子も体外にとりだして受精させて、状態の良い卵を移植するというステップです。タイミング法や人工授精では、精子と卵子がちゃんと受精しているかわからないですが、体外受精の場合は、それを目で確認できるんですね。
タイミング法で妊娠する人は10パーセントぐらい。次の人工授精で妊娠する人は5~10パーセントぐらいでしょうか。不妊治療を始めた半分くらいの方が、その次のステップである体外受精に進みます。

ーー体外受精をして妊娠した人の割合などのデータはあるんですか?
年齢に左右されますね。35歳ぐらいまでの方は、体外受精に切り替えてから1年以内に結果が出る方も多いです。ただ40代になると結果が出ないという人も出てきますね。
ーー年齢によってかなり確率が変わるのですね。
はい。各年齢に適したやり方があるので、その方に適した方法を提案して一緒に取り組んでいます。年を重ねると結果が出るまでに時間がかかるので、継続的に治療をすることも大切です。数週間お休みして、また少ししたら再開して、という風にしているとなかなか結果が出ないので、ある程度は集中的に治療を続けていく必要があるかなと思います。
ーー35歳をすぎると妊娠率が下がると聞きますが、年齢の節目があるんでしょうか?
ありますね。30代後半で流産率が大きく上がり、妊娠率も下がります。あとは、不妊治療の保険診療の年齢制限が43歳未満という条件がありますが、43歳前後でも妊娠率がかなり変わってきますね。
ーー体外受精を検討してる方にとって、治療を始める前に知っておくべき1番重要なことは?
体外受精までするのだから すぐ結果が出るだろうと期待される方も多いんですが、そうではないということです。私たち人間は、加齢によって卵子にバグ(不具合、異常)ができてくるものです。35歳ぐらいだと毎月排卵はしていますが、その中でちゃんと赤ちゃんになれる卵はどのくらいの割合かといえば半分ぐらいなんです。「毎月ちゃんと生理もあるし、排卵もしている」と思ってもそのうちの半分は赤ちゃんになれない卵である可能性があります。40代になると、赤ちゃんになれる卵の割合はさらに下がります。
ーー働いてる女性は仕事をしながら不妊治療をして、負担が大きなイメージがあります。皆さん、どのようにされているんですか。
オーク会では通院しないといけない日は実はそれほどないんです。体外受精なら、採卵や移植、卵のチェックなどでは通院してもらいますが、それ以外はオンラインで対応しています。ですから、ドクターによる説明のために通院いただく必要はないんです。オンライン診療で、薬もこちらから郵送できますので取りに来る必要もありません。ですから、沖縄から北海道まで幅広い地域から患者さんがいらっしゃいます。
ーー患者さんと接する中で精神面をサポートするために心がけてることはありますか。
不妊治療の話は友達や家族にも気軽には相談できないですよね。ですから、現場のスタッフができるだけ寄り添って、お話をしやすい環境を作るようにしています。私たちは、ここにいらっしゃる方みんなが妊娠・出産というゴールを持っていることをわかっているし、長い期間通っている方もいるので、応援したい気持ちが強いんです。
こんなこともありました。何度もうまくいかなかったある患者さんが、検査で陽性だったので、「●●さんが陽性でした!」とお伝えしたら「わーっ」と大きな泣き声が聞こえたんです。ご本人が泣いていると思ったら、その横に立っていた培養士がもう顔を涙でぐじゃぐじゃにして泣いていたんです。結果を待つ時は、スタッフも患者さんも一緒にドキドキしていますし、スタッフ本人が不妊治療をしていて、一緒に頑張ってる気持ちでいることも多いんですよ。
ーー田口ドクターご自身も不妊治療の経験がありますが、その経験が今の患者さんとの接し方に役立っていると感じますか?
そうですね。私が不妊治療をしたのは20年以上前なので、今とは不妊治療のイメージもずいぶんと違います。私は体外受精が必要だと思ってやってみたんですけど、 焦る気持ちを自身で体験しました。採卵に1ヶ月かかって胚凍結して、また準備して移植して結果を待つ。とても長く感じ、焦りが強かったです。
私の不妊治療の経験から、皆さんの焦ったり納得がいかないと感じる気持ちがよくわかりますから、自身の経験は患者さんと接する時に役に立っています。女性同士で温かい目で見守ることも必要です。母親や女性の友達から「まだ子供ができないの?」と言われてしまうと、すごく辛いんですよね。自分が治療した人は、そういう点で不妊治療をしている女性にも優しくなれるんじゃないでしょうか。女性同士がもっと暖かい目で見守り、気持ちの面で支え合ってやっていけるようになればいいなと思います。
ーー不妊治療を行う中で、治療の成功率を高めるために、患者さんが日頃の生活でできることはありますか?
不妊治療に来られる方は妊娠に向けてきちんと栄養も考えている方が多いと感じますので、そのあたりはあまり心配ないのかなと思います。ただ、考えすぎてかえって偏った食事になってる方もいますね。食べすぎてはいけないと思って、野菜ばかりで タンパク質が不足している方もいます。例えば、地中海式の食事は、健康にいいというデータがありお勧めですが、何よりも偏った食事をしないようにすることが大事だと思います。

ーーパートナーとどのように協力していくべきか、パートナーと話し合うべきことはありますか?
パートナーとは二人三脚でやっていっていくことが大切です。患者さんを見ていると2タイプのカップルがいると思います。1つは、旦那さんも非常に熱心でいろいろなことを聞いてこられて、2人で取り組む方たち。もう1つは、旦那さんはふわっとしていて、まあなるようになるよ、という感じで、奥さんの方が一生懸命やっていて、旦那さんは積極的には話を聞いていないようなカップル。
どちらにせよ、不妊治療で1番辛い思いをするのは奥さんですよね。通院したり、注射を打ったりというのは女性が行うので、旦那さんの支えが大事です。(子供ができないことの)責任の押し付け合いは1番避けたいところで、旦那さんの器の大きさは大事かなと思います。
ーー田口ドクターが不妊治療をされた20年前と比べて、体外受精という手段も以前より身近なアプローチになってきたのでしょうか。
体外受精の治療には保険も導入されたし、妊娠する確率が上がることは確かなんです。ただ、誤解のないようにお伝えしたいことは、体外受精は「しっかり受精することを手助けするもの」ということです。年齢とともに卵の状態は悪くなります。1ヶ月に1個しか排卵しないものを、体外受精で刺激して5~10個とることができて、受精も確実にさせて、その中から状態の良い卵を移植するので、妊娠率がぐっと上がるんです。ただ、卵子の質を上げることはできないので、体外受精はその人の妊娠する可能性を上げるものなんです。医療の技術を使って、その人のポテンシャルを最大限に活かしているということですね。
ーー不妊治療で悩んでる方に向けてメッセージをいただいてもいいですか?
子供ができないというのは、とても辛いことです。でも、治療の過程で、卵子や精子の老化、染色体などの科学的な理由がわかると、かえって心が解放され、腑に落ち、それならこうしようという心持ちで治療にとりくめるのではないかと思います。ですから、ぜひ、まずは検査を受けるなど、 一歩踏み出していただくと良いと思います。

田口早桐
生殖医療専門医、臨床遺伝専門医。川崎医科大学卒業後、
兵庫医科大学大学院にて研究。専門は「抗精子抗体による不妊」。
府中病院を経て、医療法人オーク会へ。著書に『やっぱり子どもがほしい!産婦人科医の不妊治療体験記』(集英社インターナショナル)、『ポジティブ妊活7つのルール』(主婦の友社)がある。体外受精に関して、排卵誘発法を含めた治療戦略をしっかり立てることが大事との信念で、個人個人の状態に合わせた方針を決めることに力を注ぐ。
医療法人オーク会HP: https://www.oakclinic-group.com/
子育ても仕事も!自由に駆け回りたい女性を応援する靴。【Öffen日坂さとみさんインタビュー】

「履き心地抜群で、デザインもおしゃれ!」──2年前、そんな声がHumming編集部で広がったのが、環境に優しい靴のブランド『Öffen(オッフェン)』です。今回、オッフェンの裏側にあるストーリーを深く掘り下げるため、プロデューサー兼デザイナーの日坂さとみさんにインタビューをさせていただきました。
ファッション業界で長く活躍してきた日坂さんが、なぜ今、環境に優しいフラットシューズ作りに注力するのか? オッフェンの靴に込められた女性へのメッセージ、そして忙しい日々の中でもどうやって「環境に優しい生活」を実現できるのか――日坂さんの想いを伺いました。
ーー何がきっかけで環境に優しい靴を作りたいと考えるようになったのですか?
私には子供が1人いるんですが、子育てが始まった時、生まれたばかりの赤ちゃんが使える安全なものはどうやって探したらいいんだろうと、すごく心配になったんですね。世の中で売られているもので、本当に安全なものがどれかという情報がないなということ、そして私自身が今までそういうことをあまり 気にしていなかったことにも気づきました。長くファッション業界にいて、発信をする立場でしたが、「環境」と視点を考慮していなかったことにハッとしたんです。
ーーお子さんが生まれたことがきっかけの1つだんたんですね。
はい。そこで、「エシカル・コンシェルジュ講座」というコースを受けたんです。そこでは「ゼロ・ウェイスト(浪費・ゴミをなくすという意味)」について学び、人間が多くのゴミを作ってきたことや私たちの営みがどれだけ地球の負担になっているかを知り、大きな衝撃を受けました。日常生活でも仕事でも、地球に負担をかけながら作りたいものを作る、そういうモノづくりはしたくないと感じたんです。そうやって、オッフェンは生まれました。
ーー使用済みペットボトルの糸を使ってできた靴ということですが、このプラスチックがどうやって靴になるんですか?
オッフェンはニットのシューズなのですが、そのニット素材が、生活の中から出てくる資源ゴミであるペットボトルから作られた糸から出来ています。それを熱処理して、再生PET糸に生まれ変わっています。オッフェンの靴を1足作るのに、だいたい8本分のペットボトルが使われています。
ーーペットボトルの糸は、環境に優しい商品にはよく使われる素材なんですか?
はい。ペットボトルからの糸を使ったニット靴は割とあるんです。オッフェンの靴の特徴は、ぺットボトルが素材であるということよりは、靴を製造する工程でどれだけゴミや二酸化炭素を出さないようにミニマムにしているかという点なんです。さらに、靴を作る時の部品もなるべく減らして、あまり材料を使わないやり方にしています。
ーー靴の製造工程でゴミを出さないようにしているとのことですが、その開発に時間を要したそうですね。
はい。従来の靴の作り方なら、 正直、とても簡単に作れていたのかもしれないんですが、 私たちはできるだけ材料を省いていくということを重視しました。そのため、靴に仕上げるまでの製造過程の開発に2年ちょっと時間を要してしまいました。なるべく 人間と地球に対して、有害物質が出ない素材を使ったりという細かいところを突き詰めながら作っていきましたね。

ーーお店で靴を買うお客さんからは、エコな商品であることはわかりますが、実はその裏で環境に優しい工程で靴を作っているところが、他とは違うのですね。
商品として店頭に並ぶと、その靴がどうやって作られてるのかは見えづらいですが、私たちは見えない部分もきちっと、お客様に説明ができるようにしたいんです。人間が作りたいものを都合よい手法で作るなら、今までの環境への負担は何も変わりません。ですから、負担をかけない材質だったり、工程をシンプルにしていますが、これは作っていただく工員さんの労働時間の短縮にもつながります。地球環境にも人にも優しいモノづくりを追求している、そういうブランドです。
ーーオッフェンはフラットシューズだけを作っていますが、それはどうしてですか?
オッフェンがこだわっているのは、履き心地です。これには私が子育てで感じたことが反映されています。子育てをする前はヒール靴を履くことが多かったんですが、子育て中は、スニーカーやフラットシューズばかりを履いていました。 その一方で、おしゃれをしたいなという気持ちもあり、子供が走り出してもちゃんと追いかけていけるような、子育て女性にも喜ばれる靴があったらいいなと思っていたんです。
オッフェンの靴はフラットシューズの中に、バウンドするクッション性の高い中敷きを起用しているという特徴があります。スニーカーのような履き心地なのに、外から見たらすごくエレガントな靴なんですね。多くの女性に、ファッションを楽しむ気持ちを我慢しないでほしいと思い、その結果、履き心地とデザインの両方を重視したオッフェンの靴が生まれました。
ーーファンの方からは、フラット以外も作ってほしいというリクエストがありますか?
そうですね。実際、ヒールやパンプスが欲しいという声もいただいています。ただ、できるだけパーツを減らしてシンプルな工程で作りたいという軸があるので、ヒールをつけると、新しい素材を使わないといけなくなってしまいます。ですからフラットでもおしゃれなスタイリングにしています。
ーーオッフェンの靴は他にどんな特徴があるのでしょう。
オッフェンの靴はシーンに分けて揃えなくてもいいようにできています。例えば、子供の入学式の時にしか履かない靴とか、皆さんあると思います。普段は靴箱にしまっている靴とか。オッフェンの靴は、入学式にも職場にも履いていけて、休日のお出かけでも履ける。そういうシーン分けをしなくてもいつでも履けるように、生活の一部として、毎日履ける靴がいいなと思っていたんです。私はフラットシューズ推しですね。(笑)
ーー日坂さんがオッフェンの靴のデザインをしながら、こんな女性が増えたらいいなという願いやビジョンはありますか?
今は、活躍する女性がかなり増えていると感じます。「良い靴は、履き主を良い場所へ連れて行ってくれる」という言葉もありますが、オッフェンはそんな靴であってほしいなと思います。オッフェンを履いてくださるお客さんには子育て中の方もたくさんいますね。
今の時代は働き方も変わり、女性が外で活躍しています。そんな時にどこでも駆け回れるように、オッフェンの靴を履いていろんな場面で活躍してほしい、そんなの想いをこめています。自分の今おかれた生活や環境を、自分自身でコントロールしながら働いていきたい、そう考える女性たちを応援する存在の靴でありたいなと思います。私自身も、今までキャリアを積み、いったん子育てをして、また復帰するという時に、また頑張ろうと助走をかけながらやってきました。ですから、多くの女性にとってそんな風に背中を押してくれるような靴になってほしいですね。
ーー日坂さんは、日々忙しい中でも環境のことを考えてお仕事されてると思います。頭では環境に優しくすることが大切だとわかっているけれど、環境のために行動することができないと感じる方は、どうしたら環境問題がもっと身近になるのでしょう。
あんまり難しく考えないことが大切かなと思います。私の場合、自分の生活範囲の中で無理がないようにしていますし、特別なことをする、ということではないと思います。 ペットボトル1つでもきちっとリサイクルできるように、正しいゴミの出し方をすることもすごく大事なことです。
私はもともと、もったいない精神を昔から教育されてきたので、例えばご飯1つ作っても、残さないということを子供に教えています。生活する中でたくさんヒントがあると思うんですよね。 新しいものを買う前に、本当に必要なものかを考えたり、こういうことも、立派な環境のためのアクションだと思います。
世の中便利になっているので、当たり前に思ってることでもできることがたくさんあります。例えば、できるだけ車に乗らず歩くことだったり、待機充電を使わず自分で体を動かして掃除をするとか、そういったことも大事だと思いますね。
ーーオッフェンのブランドを通じて、社会にどういった変化を起こしたいですか?
オッフェンは、「小さな1歩でも 大きく変わることができる」ということを信念として活動しています。今の世の中、たくさんの情報がありすぎて、何が本当に良いものなのかわからないという状況です。例えば化粧品もいろいろありますが、専門的な成分の知識がなければ何を選んだらいいかわかりません。こういう生活者の疑問を解決していくために、オッフェンはファッションの分野で、明確に正しい情報を発信していく責任があると考えます。生活者の方にも、正しい情報をキャッチし何が本当に必要なのかということを考えていって欲しいですね。
ーー新しい試み?
オッフェンでは、新しい取り組みとして、靴のリサイクルプロジェクトを進めています。靴は多くのパーツで作られているため、リサイクルが難しいとされていますが、私は靴にも「捨てる」以外の方法があるはずだと感じていました。そこで、靴を廃棄するのではなく、次の持ち主に受け渡す仕組みを作ることにしました。このプロジェクトでは、10月から靴の回収を始め、修理や洗浄を行い、古着として再販する予定です。販売開始は11月から12月を予定しています。

日坂 さとみ (SATOMI HISAKA) / オッフェンプロデューサー
関西在住。20代から10年以上にわたり人気セレクトショップのバイヤー/デザイナー/VMDを手掛けるクリエイティブディレクターとして活動していましたが、現在では1児の母として育児と仕事をしながら、自然と触れ合う事を大切にゼロウェイストの生活を送っています。2020年 、一般社団法人エシカル協会が主宰する「エシカル・コンシェルジュ・オンライン講座」修了。
公式サイト:
セルフプレジャーの新たな楽しみ方を教えてくれるセックストイたち
体にも環境にも優しいキッチン用品海外ブランド9選
エシカルウェディングドレスの魅力:持続可能な選択肢を探る
環境に優しいビーチファッションの5ブランドを紹介
父の日に贈る特別なサステナブルな財布

父の日は、感謝の気持ちを父親に伝える絶好の機会です。今年は、ありきたりのものではなく、父親の心に響く特別な贈り物をしてみませんか?そこでご提案したいのが、サステナブルなお財布。エレガンスと環境への配慮を兼ね備えた、実用的なギフトになるでしょう。こういった財布は、リサイクルナイロン、ヴィーガンレザー、さらには廃棄されたパイナップルの葉のようなアップサイクルされた素材から作られており、あなたの父親が自信を持って使える贈り物となるでしょう。
今回は、父の日の贈り物におススメのサステナブルなお財布をいくつか紹介。こういうお財布が地球をより緑豊かにしながら、父親の必須アイテムもスタイリッシュにする方法を探ります。サステナビリティの意識と心のこもったギフトの両方を実現するエコフレンドリーな財布の世界、ぜひ一緒に楽しみましょう。
1. Allégorie
果物で作られたお財布

Allégorieの財布は、天然のサボテン、リンゴの皮、植物由来の素材などのヴィーガンレザーの代替品で作られています。さらに、すべての製品がPETA認定であり、さらに公正取引、OEKO-TEX認証、および米農務省の「バイオベース」認証も受けています。カードホルダーには免許証やクレジットカードが収納でき、ユニークなデザインになっており、二つ折り財布には最大8枚のカードと現金が収まります。
2. Bellroy
リサイクルレザーで持続可能な未来に
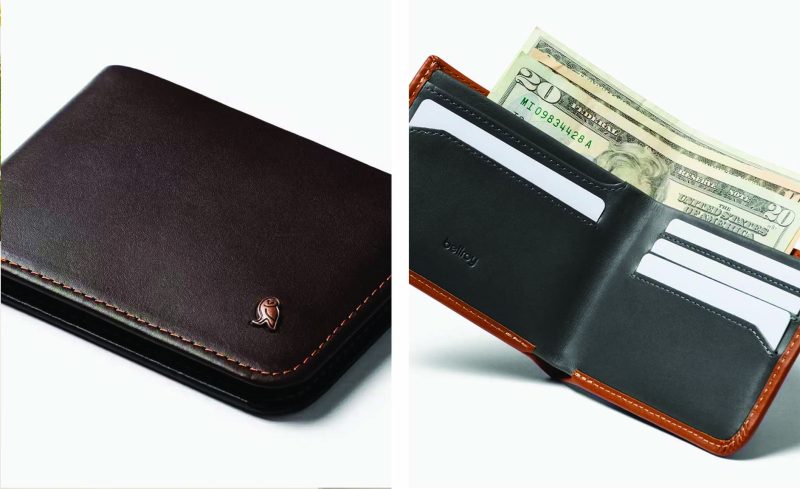
テクノロジー、利便性、持続可能性を兼ね備えたBellroyのアイテム。このブランドの財布は美しくデザインされており、カード、コイン、現金だけでなく、電話、パスポート、SIMカードも収納できるように作られています。さらに、ほとんどの財布はRFID対応なので、カードやパスポートの情報が盗まれる心配もありません。レザーとレザーフリーの両方のオプションがあり、最大10色のバリエーションが揃っています。
3. Plastic City
「10年後になくなるべきブランド」

PLASTICITY(プラスティシティ)は、使い捨てや置き忘れで廃棄されたビニール傘を生地として再利用し、バッグや財布、ハットなどを作り出すアップサイクルブランドです。
日本では1年間で消費されるビニール傘8,000万本の傘が廃棄されていると言われています。こういったリサイクルが難しい素材を使い、製造工程にも可能な限り環境負荷のかからない方法を模索してきました。その結果たどりついたのが、傘の素材が持つ防水性や汚れに強いなどの良い特性を残して、特殊な技術により幾重にも重なる層に圧着をするという方法。こういった独特な商品を提供しています。
4. Cactus
サボテン由来のレザー素材

CACTUS TOKYO(カクタストーキョー)は、サボテン由来のレザー素材を使用した製品を展開しています。職人さんたちを大切にする日本国内の工房で制作された、品質の高いお財布です。サボテンと植物由来の樹脂を混合し、少なくとも素材の61%以上に植物由来のものを使っています。本革のような高級感があり、しっとりなめらかな手触りを感じられる素材です。
5. Baggu
カラフルなデザイン

Bagguは再利用可能なバッグで有名ですが、カラフルな財布やスマホスリングも作っていることをご存知ですか?このサステナブルブランドは、すべての製品にリサイクルナイロンを使用し、生産のすべての段階でエシカルな視点を重視しています。その結果として、ユニークで目を引くデザインが生まれ、光沢のあるAmExカード以上に注目を集めるでしょう。特に注目すべきは財布が三つ折りで、キーリングに簡単に取り付けられるループが付いていることです。ユニークなスタイルが好きな方には、この100%サステナブルな選択がぴったり。
6. Pinamore
自然に生きる。自分らしく。

PINAMORE(ピニャーレ)の財布はパイナップルから作られています。廃棄されたパイナップルの葉を素材として活用しています。
パイナップルの葉は焼却処分されてきたので、大気中への大量の二酸化炭素排出が懸念されてきましたが、この新しい取り組みにより、環境保護に貢献しています。また、パイナップル農家の収入源が増えるという大きな効果も生まれています。
パイナップル素材を使用しているため、茶色の繊維が浮かび上がり、和紙のような手触りがあります。素材の72%が葉の繊維で、18%がじゃがいもやトウモロコシ由来のポリ乳酸と、全体の90%が自然の素材で作られています。
今年の父の日には、普通のプレゼントではなく、エシカルな財布を考えてみてはいかがでしょう。今回ご紹介したような財布は実用性とスタイルだけでなく、環境問題への積極的な取り組みの一歩にもなります。リサイクルまたはアップサイクルされた素材で作られたエコフレンドリーな財布を選ぶことで、あなたは父親に感謝を伝えるだけでなく、地球を助けることにもなります。ぜひ、父の日に、愛と感謝の気持ちで、エコについても考えてみましょう。
夏に最適!日差しが強い日に
肌にも環境にも優しい
日焼け止め8選
『流産と自分らしく向き合う』女性が自分で決めて実践する安全な流産へのアプローチ
※この記事は、アメリカのaviva Romm 医師の以下の記事を日本語に訳したものです。
https://avivaromm.com/miscarriage
女性の体を守る安全な流産とは
私は、何十年もの間、助産師として、女性の出産だけでなく、流産もサポートしてきました。流産は妊娠した女性にとって話題にするのが怖いトピック。過去に流産を経験したことのある女性にとってはさらにつらい話題でしょう。そのため多くの医療従事者や女性ジャーナリストたちが、オープンに話題にあげることを避けているのが現状です。
しかし、妊娠の10回に1回は流産するという調査もあるように、流産とは予想以上によく起きるものであり、流産に直面した時に自分自身をどのようにケアすればよいか知っておくことはとても大切です。流産への対処法は、初めて生理が来たとき、妊娠したとき、更年期に入ったときのケアを女性が意識することと全く同じ、そのくらい大切なことです。ただ、流産はあまりに長い間沈黙されてきたトピックのため、これまで長い間、妊娠初期に流産した女性への精神的なサポートが十分になされてきませんでした。
妊娠すると、母親になるための幸せな話題に事欠きませんが、いまだにあまり語られることのない流産については、精神的、そして身体的な面でのサポート体制が整っていないのです。普段の会話で気軽に話せるトピックではないため、流産についてしっかりと理解している女性はほとんどいません。さらに、流産というと、「医療行為」「手術」という怖いイメージが強く、ほとんどの女性が流産は病院での治療が必要な危険な処置だと考えています。今回はこの流産について、一緒に向き合ってみましょう。
まず、流産への対処法は3つあります。
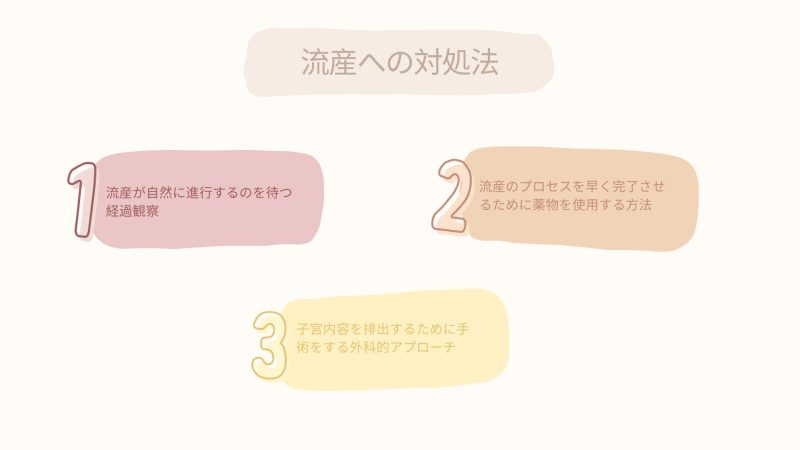
それぞれのアプローチには長所と短所があるので、自分に一番適した方法を選びましょう。
流産を経験する多くの女性にとっては、①の経過観察という方法が最も安全な選択肢でしょう。妊娠初期の流産は、ほとんどの場合、合併症もなく自宅で起きることが多いものです。「自宅で自然に起きる」というのは、あなたがイメージしている流産とは全く違うかもしれませんね。
私が自宅での流産をサポートしてきた多くの女性たちについて紹介すると、さらに流産のイメージが変わるかもしれません。彼女たちは流産の経験が、トラウマや後悔ではなく、神聖な儀式によって心が満たされたような感覚を得たと語っています。ですから、もし私の患者が自宅での流産という選択肢を検討する場合、特別な医学的理由がない限り、自宅での流産が最適だと考えています。
この記事では、自宅での流産はどうやって行えるのか、そしてより快適に行うためのヒントを解説しましょう。
流産の兆候と症状
流産は、医学的には早期妊娠損失(EPL)と呼ばれます。このEPLは、妊娠の15~20%に起こり、全ての流産の80%を占めます。妊娠初期の流産の多くは、妊娠6~7週頃に胎児が死亡して起こりますが、妊娠13週までの流産も含まれます。流産の可能性があると示す一般的な症状にはこういったものがあります。
- 膣の出血
- 腰痛
- 腹痛、子宮けいれん、子宮収縮
また、妊娠中の症状が軽減した(例えば、吐き気を感じなくなった、乳房の張りがなくなったなど)と報告する女性もいます。このような症状がある場合は、助産師や産科医に相談し、超音波検査で赤ちゃんの成長が止まっていないかどうか、心拍があるかどうかを確認してもらいましょう。
妊娠超初期の場合、胎児が形成されたのか、まだ生きているのか、超音波検査でははっきりしないことがあります。このような場合はさらなる確認が必要かもしれません。これには、経膣超音波検査、β-HCgの血中濃度の測定、早めに再度超音波検査を行う、などが考えられます。また、子宮外妊娠の可能性を排除する必要があるかもしれません。子宮外妊娠とは、受精卵が卵管のいずれかに着床して成長し始める合併症のことで、薬物療法や場合によっては手術をする必要があります。
自宅で安心できる流産を
自宅での流産を選択した場合の、最適な環境作りを紹介しましょう。
時間
流産に対応している間は、仕事や用事で外出するよりも、家でゆっくりしていたいと思うでしょう。ですから、流産の症状が始まったり、誘発剤を飲む予定の日は、数日間、理想的には1週間ほど予定を空けておきましょう。
サポート
自宅にあなただけの居心地のよい空間を作ってみることをお勧めします。週末を自分のために過ごすように、のんびり映画を見たり、好きな本を読んだりしましょう。自分を存分に甘やかしてあげましょう。また、パートナーや親しい友人と一緒に時間を過ごすことは、精神的・身体的に必要なサポートを得られるだけでなく、万が一、迅速な治療が必要になった場合にも安心です。
栄養補給
十分な水分補給をし、軽めでヘルシーな食べ物を用意しておきましょう。軽い食事は、流産の促進のために薬を服用している場合や、痛み止めを飲む必要がある場合にも効果的です。例えば、レッドラズベリーリーフのお茶は、陣痛時の子宮収縮を促すために多くの女性が愛用しています。
けいれんや陣痛が強くなってきたら:湯たんぽを腰や下腹部に当てると心地よく、痛みも和らぎます。誰かに足や腰をマッサージしてもらい、特に仙骨の上の部分を強く押してもらいましょう。深呼吸をして、子宮が空になったところ、子宮が収縮するところ、子宮の周りに優しい癒しの光が当たるところ、そういうシーンをイメージしてみてください。これは、「ヒプノバーシング(※催眠出産)」のテクニックによく似ており効果があるでしょう。他には、温かいシャワーを浴びたり、お湯を腰にかけたりしてあげましょう。
ラベンダー、カモミール、レモンバームなどのリラックス効果のあるハーブティーを飲んでみることもお勧めです。その時には、不快に感じるかもしれませんが、あなたの身体は今身体のために何をすべきかわかっているものです。これから何が起きるのかを事前に理解しておくことで、気持ちも楽になるでしょう。
癒しのための聖なる空間をつくる
流産は、それを経験する本人にさまざまな感情をもたらすのが普通です。流産のプロセスの間も流産後も、どの感情が正しいというものはありません。あなたの人生の希望や目標によって、悲しみから安堵までの感情は様々です。ワインを一杯飲んだことや、もやもやした気持ちを抱いた記憶など含め、あなたは流産が起きたことに関して何も悪いことはしていない、そのことをしっかりと理解することが大切です。
私の長年の経験でわかったことは、女性は人生の様々な局面で自分のための時間を割き、神聖な空間をつくり出せば、私たちの脳、心、精神がトラウマを減らし、おだやかに過ごせるということです。さらに、女性たちが周りにいる他の女性たちに心を開けば、流産から来る喪失感や悲しみを周りの仲間たちと分かち合い、流産についてのディスカッションを始めることもできるのです。
では、流産の時に神聖な空間をつくるにはどうしたらいいのでしょう。
例えば、流産という経験を、まるで出産のように扱うのはどうでしょうか。キャンドルを灯し、音楽を聴き、煌々と明かりを灯し、お茶を飲み、パートナーがいるならそのパートナーにも一緒に参加してもらいましょう。
流産の時に胎児がすでにいた場合は、埋葬の儀式を行うこともできます。特別な石や羽、ハーブなどを供えて埋葬しましょう。自分への手紙を書いたり、自分の経験についてジャーナルを書いてみましょう。カレンダーにその日をマークし、1年後に時の経過に感謝を表せるようにしてみるのです。
もちろん、流産という体験をもっとプライベートなものにしておきたい、その体験を誰とも共有したくない、または過去のこととして振り返らずに前に進みたいと考える人もいるかもしれません。何が正しくて何が間違っている、ということはありません。あなたにとって、何が一番自然に感じるか、ということが大切です。
自宅での流産
流産には子宮のけいれんと出血が伴います。けいれんも出血も、重い生理痛のようなものですが、これらはまったく正常な症状ですので安心してください。
自宅で経過観察のアプローチを選んだ場合、こういった流産の症状が数日から数週間続くことがあります。この間、けいれんや点状出血が断続的に起こります。実際の流産の最終段階では、けいれんと多めの出血が、数時間から最高で5時間おきに定期的に起こります。

妊娠後期に予想されること
妊娠が進めば進むほど、出血やけいれんが激しくなり、血液や血の塊と一緒に子宮内容も排出されていることに気づくかもしれません。流産が妊娠の初期に起こっている場合、子宮内容は血の塊のように見えるかもしれません。妊娠8週目くらいになり、胎児が形成されると、胎児組織は非常に小さな初歩的な胎盤と、小さな袋のような形で現れることもあります。
胎児組織を実際に目にすることは、人によっては非常に精神的なショックを受ける可能性があります。また、子宮頸管や膣からは、血にまみれた濡れたトイレットペーパーのようなものが出てくることがありますが、これは子宮内膜の一部です。
助産師や医師に後から見せるために、こういった排出物を保管しておけば、子宮からすべての組織が排出されたかどうかを判断したり、染色体検査が必要な場合に役立ちます。
医療機関に行くタイミング
自然流産(人為的でなく起こる流産すべてのこと)を選んだ場合は、合併症もなく流産を完了するケースがほとんどでしょう。しかし、流産を軽く考えてはいけません。流産には出血や感染のリスクがあるからです。
ここでは、どのようなことに注意し、どのような場合に医療機関に行く必要があるかを説明しましょう。
- 1時間に生理ナプキンのマキシパッド(多い日用のナプキン)2枚が浸るほどの出血が2時間続く場合。
- 38°C以上の発熱がある場合。
- いつも気分が悪かったり、けいれんが終わった後に下腹部痛がある場合。
こういった場合は、流産のプロセスを完了させ、感染を予防するために、子宮内容除去または吸引処置と抗生物質が必要になることがあります。流産後の数週間の間に、大量出血があったり、大きな血の塊が排出されたり、腹痛や発熱、悪臭のする膣分泌物が出たりした場合は、感染症の可能性があるため、早急な診察が必要です。
流産の後
流産が完了すると、けいれんは完全に治まりますが、膣からの出血は通常1~2週間ほど続きます。その後には、出血が止まったりまた再開したりということを繰り返すこともあります。流産後の最初の数日間は、小さな血の塊が少し出るかもしれません。どれもすべて正常なことです。
十分な休養をとり、具だくさんのスープやシチューなど栄養のあるものを食べ、水分をたくさんとりましょう。 生理用ナプキンに含まれる細菌による感染を防ぐため、生理用ナプキンは2~3時間おきに交換しましょう。また子宮内容がすべて排出されたことを確認するために、薬による治療から2週間以内には、医療機関を受診することをお勧めします。
次の妊娠までどのくらい待てばいい?
これは信じられないかもしれませんが、人間の体は妊娠したいと思えば、流産を経験してもすぐに妊娠をすることができます。流産の翌月には生殖能力が高まることも検査でわかっています。妊娠を望む場合は、妊婦用ビタミン剤、特にメチル葉酸が400~1000mcg含まれているものを服用しましょう。流産したことが、将来また妊娠する可能性に影響を与えることはないので安心してください。
ーーーーーーーーーー
地球に優しい!だから心も体も気持ちいい!
『マインドフル』に身体を動かすための
サスティナブルなブランド3選
『完璧じゃなくて大丈夫』ヌード写真展に込めた想い
8月に東京で開催された一般女性のヌード写真展「Dear My Body 〜親愛なる私のカラダ〜」 。このイベントの仕掛け役でもあるウィメンズヘルスの小西寛奈副編集長に、写真展を開催することになったきっかけや、女性に伝えたいメッセージについて聞いた。
女の子をかわいく撮る天才

クレジット:Women’s Health
−−どうしてヌード写真展を開催したのですか?
きっかけは、写真家の花盛友里さんの個展での自身の体験でした。彼女の写真展に行った時にとても感激して会場で涙を流しました。その時にこのメッセージを世に広めたい、ウィメンズヘルスでもイベントをやりたい、と強く思ったんです。そのためには、かなりの資金が必要になりますが「絶対に実現させたい」と思い、ゼロから企画をして、8月末に実現できました。夢って実現するんだな、と思いましたね。
−−花盛さんの写真をもっと広めたいと思ったのはなぜ?
花盛さんは、女の子をかわいく撮る天才なんです。さらに、彼女がライフワークで活動している「脱いでみた」は、かわいいだけでなく、女性のためのおしゃれなヌードなんです。彼女の個展で見るのは「生まれてきてくれてありがとう」「あなたはあなたの体のままでいい」というメッセージが込められた写真ばかり。ぜい肉やシミがついた体、下着の跡など、隠したいものが一切修正されていない写真なんです。
女性たちをそのまま撮影し「全員が違って、全員かわいい」と心から思える写真を撮っているのが花盛さんです。彼女が伝えていることは、私自身がずっと伝えたいと感じていたことそのもの。「生まれてきてくれて、 みんなありがとう」という、まさに命への賛美です。
おすすめ記事 ▶ ボディポジティブ:体重計も投げ出して、ありのままを受け入れる

クレジット:Women’s Health
「ボディポジティブ」から「ボディニュートラル」へ
−−この写真展を「心の処方箋」と表現していますが、写真展を開催することで、どんなメッセージを送っているのですか?
「ボディポジティブ」という言葉をご存知ですか。「ボディポジティブ」は、自分の体を大好きになって、太っていてもそのままでもいいよというメッセージですね。そこから派生して、 毛深いとか体に傷があるなどの特徴、障害や年齢、人種などの多様性を肯定しようという考えにまで広がっていると思います。
“「ボディポジティブ」が外見を肯定する考え方であるのに対し、「ボディニュートラル」は体の機能や働きに感謝することで、誰もが無理なく自分の体を受け入れられるようにする考え方です。”
その一方で、自分のありのままの外見を愛そうと言われても、なかなかそうはなれないよ、という声がすごく多いんです。だから、変にポジティブさを強調するのは、 多くの女性の気持ちと違う気がしていました。そんな時に「ボディニュートラル」という考え方に出会いました。
この「ボディニュートラル」は、体がご飯を消化してくれる、この手が動くから愛する人を抱きしめられる、足が動くからランニングができるなど、体の機能に注目して感謝するというものです。この「ボディニュートラル」という考え方なら、誰でもすんなりと受け入れられると感じました。この考えがより広まれば、もっと楽になれる人がたくさんでてくるのではないかと、そう思ったんです。
−−「ボディポジティブ」を強要しないというメッセージですね。
そうです。「無理にポジティブにならなくてもOK。ネガティブな感情もそのまま受け入れ、自分を生かしてくれる体の働きに目を向けよう」ということです。自分の体は一生の相棒ですから、親友のように接してほしいんです。
自分の体をそのまま愛そうとは言っても、不健康だけどそのままでいいという堕落した感じとは違います。それでは、自分の肉体をリスペクトしていないし、生まれ持ったポテンシャルを生かしきれてないと思うんです。
あなたが持って生まれたものを磨き、それを1番に輝かせることができるのはあなた自身なんです。でも、最近は、遠慮してしまう人が多い気がします。人からどう見られているかとか、自分の体型を変えなきゃという感覚があると、自己肯定感は下がってしまうでしょう。
憧れのあの人みたいになりたいという気持ちも悪いことではないですが、そこをストイックに目指しても、 自分の良さを発揮できない気がします。誰にも遠慮せずに生まれ持った輝きを思いきり放てる、そんな世の中になってほしいというメッセージです。
コンプレックスから解放され「楽になった」
−−参加者からの印象的な感想は?
自分の体は「不完全だからこそ美しいし、愛おしい」と気づいたという手紙をもらいました。参加した他の方たちからも「言葉に救われた」「楽になった」「勇気が出た」といった声をもらっています。ジムで体作りを頑張っていた参加者には「体を育てることが本当は苦しかった」と泣いている人もいました。逆に「自分の体は思い通りの外見ではないけれど、そんな自分をもっと愛してあげようと思った」とか「許されたような感覚があった」という意見もありました。
誰からも言われていないのに、自分の体型は世間から許されていないとか、周りに認められない外見だと思ったり、コンプレックスを持っている人も多いと思います。だから、例えば、おっぱいが大きくても小さくてもどちらでもいいし、その大きさは誰と比べているの、ということです。そのあたりがイベントで伝えられたと思います。

クレジット:Women’s Health
−−「みんな違ってみんないい」という意識は、少しずつ日本にも根付いていると感じますか?
私自身は根付いてると感じていました。例えばSNSを見たり若い世代の人と話していると、多様性を認める意識が浸透していると感じます。ウィメンズヘルスの仕事では、多様性を受け入れているフォトグラファーやアーティストと一緒に仕事をすることが多いんです。だから、そういう多様性は身の回りでは当たり前に感じていました。
“多様性を受け入れる意識は若い世代やクリエイティブ業界で広がっている一方、海外経験を通じて初めて「人と違っていい」と実感する女性も多く、日本ではまだその意識が十分に根付いていないと感じています。”
私自身は海外に住んだ経験がないのですが、インタビューした女性たちには「海外に行って意識が変わった」という方が多いんです。日本では太っているからといじめられていた女性は、海外に行ったら体型を気にしなくなったと言っていました。他にも、「あなたは何をしてると幸せなの」「何が好きなの」とよく聞かれた、など、海外の人は、自分がどう感じるかを大切にしていると話してくれた女性もいました。日本にいるときはそういう意識はなかったので、海外で自分は変わったと話してくれる女性がとても多いんです。彼女たちの話しを聞くと、日本での「人と違っていい」という意識の浸透はまだまだなのかな、とも感じます。
−−今回の写真展を終えて、次にやりたいと思っている企画はありますか?
ウィメンズヘルスは「心と体と地球を健やかにする」というのがミッションのメディアです。そして、このミッションはそのまま私のやりたいこととぴったりで、そんなぴったりな仕事で嬉しいなといつも思っています。次に企画をやるなら、また、何か世の中の役に立つことができないかと思っていますが、まだ模索中です。
自分の仕事も楽しくやりながら、それで世の中の役に立ったら最高ですよね。例えば、ウィメンズヘルスでは、古着でワクチンの寄付ができる「オクルヨバッグ」という古着回収サービスを立ち上げました。古着の回収は、ゴミ問題を生んでいるとか、実は地球のゴミが別の場所に移動しているだけだと批判されることもあります。
今年で2年目になるこのサービスは、発展途上国の子供にワクチンを寄付できたり、古着も捨てるのではなく、売って活用してもらったり、日本国内の障害者の方に梱包作業という仕事を提供することで雇用を生んだり、社会の経済が回り途中で誰かが役に立つというのが良いなと思っています。
あと、熱い想いを持った作り手さんの商品をウィメンズヘルスショップというウェブショップで一緒に販売しています。ここでは、健康だけではなく、地球環境につながるものを作っている人を見つけて、それを世に広めたいと思っています。
「年をとると若者がうらやましくなる」の神話

若い頃の自分の間違いに、最近になって気づいた。「年をとったら、若い頃に戻りたいと願うであろう」という私の若い頃の予想だ。
私の子どもたちが新生児だった時期は過ぎ、今はみんなが学校に通っている。赤ん坊を育てる時期は大好きだったが、今はもっと幸せである。赤ん坊を育てていた時の喜びを思い出してまたあの時が戻ってきてほしいと悲しんだり、自分が年を取ったことを嘆いたりすることもない。そして、10代や20代をもう一度過ごしたいと思うこともない。若い頃の自分が聞いたら信じられないかもしれないけれど、これが事実なのだ。
もちろん、私の体は老化している。でも、例え過去に戻ることができたとしても、私は今まで私が通ってきた経験に愛着がありすぎて、その年月を投げ出したいとは思わない。時間を巻き戻したり、今の自分を昔の自分に置き換えたりすることもしたくはない。
若者たちに、40代の私が彼らの若さをうらやましいとは思わないことを正直に伝えたら、彼らは私を信じるだろうか?彼らに、年をとっても若い頃と同じように、人生を思いきり楽しめるのだと伝えたら、負け惜しみを言っていると思われるだろうか?
40代になってやっとわかったことがある。それは「すべての年配者が若さをうらやむわけではない」ということ。
自分のまちがいに気づきながら年を重ねる
年を重ねることは、若い時の自分の愚かさについて気づくことでもある。まったく真実に違いないと強く信じていたことが、実はそうでなかったということが若い時にはよくあるものだ。
あなたが今知っていると思っていることのいくつかが、実は間違っていて、後からそれを知って自分に失笑したり、恥ずかしくなったことが、あなたもないだろうか。時間がたつと、あなたが間違っていたことが証明され、そしてこういったことが若い時には繰り返されるものだ。経験もまだ多くはない若い頃の私たちみんなが、ある程度は「愚か」なのではないだろうか。
今の私は、そんな悲観的な見方にも思わずほほえんでしまう。私たちが、人や事柄について真実だと思ったことが、間違いであったことに気づくという事実は、私たちが年を重ねるにつれて、聡明になり人間の幅が広がっているのだということを教えてくれる。
研究でも明らかな、年齢と幸福度の関係
長い間、テレビや映画は、年配の登場人物を、不機嫌で不幸な人として描いてきた。しかし、現実はまったく違うことが多い。
その一方で、今だに老いを恐れている人も多く、高齢者が最も幸せであることを知ると、多くの人が驚くのも事実だ。
どうして、年をとると幸福度が上がるのだろう。
「年齢を重ねるにつれて、私たちの残された時間は短くなり、私たちの人生の目標も当然変わる。無限の時間が残されているわけではないことに気づくと、私たちの優先順位がはっきりと見えてくる。そして、ささいなことはあまり気にしなくなり、人生をより味わえるようになる。周りにより感謝ができるようになる。自分の感情を大切にすることで、人生がより充実したものになる。つまり毎日がハッピーになる」心理学の教授であるローラ・カーステンセン氏は話す。

誰にも遠慮しなくてよい生き方
若い時の自分の愚かさについて、私のようにくよくよ考えることがあるのなら、これは「大切な成長のマイルストーン」と考えてよいだろう。
私が若い頃の自分に戻りたくない理由のひとつに、若い頃の愚かさを思い出してくよくよしたくないことが理由のひとつにあるのかもしれない。若い頃に気になったことは、今では気にならない一方で、10代、20代の頃には気にしなかったことを、今は気にしていることがある。
10代の私は、自意識過剰で辛かった。歯並び、体重、髪型、肌、独身であることなど、周りからちょっと指摘されただけで、自分が情けなくなったものだ。今となっては、人をけなすことしか考えられなかったり、相手に優しい言葉をかけられない人をかわいそうに感じる。
若い時には、流行りではない曲が好きだったことを隠したり、友達になじむためにブランドの服を欲しがったりした。パーティーにも行きたくなかったが、行くべきだと自分に言い聞かせて行った。
今はブランドなんてどうでもいいし、流行りでない曲や、地味かもしれない服装、大衆向けしない趣味に没頭している自分が心地よい。今でも人には好かれたいと思っているけど、本当の友達は、ありのままの私を好きでいてくれることも知っている。だって、私たちはみんな、それぞれ違う。人よりちょっと変わっているくらいのほうが人生はおもしろい。
ある意味、私は過去の私のままで何も変わっていない。若い頃の記憶や経験は、今でも私の世界の見方や理解のかてとなっている。人生とは、過去を懐かしむことではなく、成長し、変化し、学び、前に進んでいくことをいう。
こういう人生を歩んでいるあなたなら、年を重ねることは嘆くことではなく、ギフトであることに気づくだろう。
https://www.thegoodtrade.com/features/do-older-envy-youth/
https://fortune.com/well/2023/07/03/habits-that-boost-happiness-as-you-age/
タンザニアの自然が教えてくれた幸せの気づき方
あなたが、自然を感じるのはどんな時でしょうか。
お友達とドライブをしながら紅葉を楽しんでいる時。夏休みに子どもとセミとりに行った時。または、家族旅行で自然の中をハイキングした時でしょうか。
こんな風に普段と違った特別なことをした時に自然を感じるということが多くありませんか?
私はまさにそんなひとりでした。こうやって特別な時にだけ感じていた自然ですが、私が住んでいるここタンザニアでは、自然をとても身近に感じます。そして、そのおかげで私の心が前よりも整ってきたという実感があります。最近ではイライラすることも減り、幸せ度がアップしているようにすら感じます。
今回は「自然を感じる」生活とは無縁だった私が、タンザニアでどうやって自然が日常にあふれているかに気づいたのか、そしてそれがどうして、日々の心地よさをあげる結果になったのかについてご紹介します。
この記事が、アフリカにいなくても簡単に見つけられる、あなたの周りの日々の自然に気づくきっかけになれば嬉しいです。
空が手に届きそう
タンザニアに来て最初に感じたのはこれ。『手が届きそうなほど空が近い!』私が住む町ダルエスサラームは、実質的な首都でもあり、タンザニア最大の都市です。だから、それなりに高いビルもあるし、交通渋滞もあります。
それでも、日々、運転していたり、子どもを幼稚園に連れていく道すがら、目の前にある真っ青な空が「どうだ、この広大さを見てくれ!」と言わんばかりに目の前にドーンと広がるのです。

そしてこの感動は、サファリ観光に出かけた時に、さらに強く感じました。イメージ通りサファリに行けば、キリンやゾウなど野生の動物が目の前で自由に生活をしている姿に感動します。ですが、それと同時に気がつくのは、その動物の上を無限に広がる大きな大きな青空。これまた、手が届いてしまいそうに近くに感じます。
青空がこんなに広くて、そして遠くまで広がる荒野や地平線を見ているだけでなんだか私の日々の悩みがとてもちっぽけに感じてしまいます。自然に、こんな気持ちにさせてくれる威力があったとは!そんなことを今さらながら感じています。
朝は「コケコッコー」で起きる
「コケコッコー」の鳴き声で目を覚ますなんて、マンガのワンシーンみたいですよね。タンザニアの中では都会である町に住む私ですが、朝はあっちこっちでニワトリや野鳥の鳴き声が響きます。だから、朝は目覚まし時計ではなく、鳥の鳴き声とともに起きています。
近所を散歩すれば、道ばたでニワトリの親子が遊んでいて、それを追いかける地元の子どもたちの姿が見られます。近くのカフェに出かけると、突然ニワトリたちが登場します。お客さんたちは慣れたもの。ちょっと突然のゲストに目を向けるだけで、あとはおしゃべりに戻ります。「コケコッコー」は朝に聞こえる声だと思っていたのですが、今では、1日中あちこちで聞こえる日常の音になっています。

こんなこともありました。ある日、日本の友達にお祝いのビデオメッセージを送りました。それを見た日本の友達の反応は、私のメッセージの内容よりも「鳥の声が後ろに聞こえて、いやされたよ~」でした。
撮影していた時には気づかなかったのですが、確かに、私のしゃべっている後ろで、まるでバックグラウンド音楽のように鳥の声があちこちから流れていました。
野鳥公園に行かなくても、鳥たちの声が毎日聞こえる。慣れてしまってはいけない、ぜいたくな環境だなとこの時に気づきました。
雨にいやされる
タンザニアに来る前の私は、雨が降るとイライラしていました。出かける時に傘やタオルなど準備するものが増えるからです。「外に出たら雨にぬれるし、あ~、もういろいろとめんどう!」
視界いっぱいに広がる木々の緑色や大空の青色を毎日見ているからでしょうか。または、タンザニアの人たちの、のんびりとしたあせらない生き方を目の当たりにしているからでしょうか。今は、雨が降っても全くイライラしません。
タンザニアの生活では水の存在が大きな影響をあたえます。特に乾季は雨が降らずに水不足が深刻となります。家で使える水も制限されたり、シャワーを浴びることができない日が続くこともあります。だから、雨が降ると、タンザニアの人たちはなんだかとってもうれしそうなんです。交通インフラが整わないタンザニアでは、雨が降るだけで道路が川のようになったり交通渋滞になったりと日々の生活に支障をきたすにも関わらず。水って無限にあるわけではない、そんなあたりまえのことに、私はタンザニアで久しぶりに気づきました。

今は雨が降ると、雨の優しい音を聞いてなんだかほっとした気持ちになります。水着に着替えて外でぱちゃぱちゃ遊びたい!という子供たちのリクエストにもOKが出せるようになりました。
あなたも自然と一体になれる
先日、子どもの通う学校をチンパンジーの研究者として世界的に有名な「ジェーン・グドール」さんが訪問しました。現在89歳の彼女はタンザニアの国立公園で20代の頃から、チンパンジーの研究をしてきました。
小学生の子供たちからのたくさんの質問に、グドールさんはユーモアを加えながら子供たちに答えていきました。
「チンパンジーと一緒に過ごすこと以外に、あなたが好きなことは?」という質問への彼女の答えが印象的です。
「自然の中に身を置いて、ひとりで時間を過ごすのが大好き。もちろん、ふたりでも楽しいんだけど、ひとりのほうがダンゼン良いの。なぜなら、ひとりだと、しゃべらずにただ自分がいるだけ。そうすると、自分が人間であることを忘れて、自然の一部になれるから。自然にとけこんで自然と一体になっていると感じられるの」
チンパンジーの信頼を得て、60年以上動物たちと自然の中で過ごしてきた人だからこそ語れる深い言葉です。
自然に目を向けてみて
私は今まで、自然との時間を大切にしようと特に意識をしてきたわけではありません。そんな私にも「自然との共生」「自然のありがたみ」「自然のやさしさ」を感じさせるタンザニアでの生活。

これはタンザニアに移住する前には想像しなかったことで、タンザニア生活が私に与えてくれたたくさんのギフトの1つです。
でも、これって、タンザニアやアフリカだから存在するのではなく、私がタンザニアにきてやっと気づけただけのことなのだと最近は思います。日本にだって、大都市にだって、いつもの見慣れた場所にだって自然は存在していて、それに気づけるかどうかという、ただそれだけ。
ちょっと一呼吸おいて、窓からいつも眺めているもの、通勤途中に目にする風景、子どもと歩いている時に見上げる空、そんな風にあなたの日常にいつもより少し意識して目を向けてみるだけで、あなたの生活がちょっとでも豊かになるのではないでしょうか。
タンザニアの女性から教えてもらった「もっとわがままでいい」
「わがまま」と聞いて、あなたはどう感じますか?
この言葉はネガティブなイメージを持たれがちですが、実際の意味は「我がまま」つまり「私の意志のままに」というもの。
私はタンザニアの女性たちと出会って、この「わがまま」について考える機会が増えました。
私たちは、もっと自分に「わがまま」を許しても良いのではないかと感じたんです。
タンザニアの女性たちの生き方には、あなたが、もっと自分のわがままを許せて、もっと楽に生きていくヒントが隠されているように感じます。
自由な自己表現
タンザニアの女性たちは、女性としての楽しさを誰に気兼ねすることもなく存分に味わっていると、日々そんな風に感じます。
例えば、我が家で働いてくれているお手伝いさんのローズマリー。
普段はとてもおとなしくて仕事をテキパキやってくれる彼女。ある日、彼女の意外な姿を目撃しました。
私が在宅で仕事のミーティングがあった日、ローズマリーには別室で子どもと一緒に遊んでもらっていました。
ミーティングが終わると、子どもの部屋から楽しそうなダンスミュージックが流れてきたのです。
ドアを開けたら、いつもおとなしいローズマリーが、3才の息子に負けないくらいノリノリでダンスをしていました。
息子もとっても嬉しそう。「あら、ごめんなさい。ダンスが楽しくて、踊りすぎちゃったわね」と、ちゃめっけたっぷりの彼女。
私自身、ダンスがうまくないということもありますが、こんな風に自然にクリエイティブな自己表現ができて、こうやって楽しめるなんて、うらやましいなと感じました。
苦労を楽しみに変える強さ

タンザニアの女性の自己表現は、ダンスだけではありません。髪型も自分を自由に表現するツールとして楽しんでいます。
例えば、スワヒリ語の先生のクララ。
週に2回会う彼女は、会うたびに髪型を変えています。
それがまたとても似合っていて素敵なんです。
ある時は三つ編みにしたヘアをトップでまとめて、またある時は髪に明るい色のハイライトをいれたり、またはウィッグで短髪にして突然のイメージチェンジなど。
ひんぱんに長さやスタイルを変えて、新しい髪型をいつも楽しんでいます。
私自身は、子育てが忙しくなってからは、手入れしやすい短めの髪型を続けています。
しかし、子育てをしながらも、自分のオシャレを楽しむ余裕を持っている彼女を見ていると、髪型を少しチェンジさせたら私も日々のワクワク度がアップするのではないかと気づきました。
タンザニア女性の髪は黒人特有の縮毛であるため、日々のお手入れが欠かせません。
しかし、彼女たちはこの手入れがめんどうであるという苦労を、女性のファッションをさらに楽しむツールへと変えているのです。
さらに彼女たちは髪型をひんぱんに変えることで、自己表現の幅も広げています。
髪を編んだり、結んだり、アフリカ布のヘアアクセサリーを使ったりすることで、個性的で洗練されたスタイルをつくり出しています。
彼女たちのこういう髪型を使ったファッションは、個性を表現し、自信を高める素晴らしい手段となっています。
必要なサポートは遠慮せず活用

タンザニアの女性が生き生きとしている理由の一つに、お手伝いさん文化があると私は考えます。
お手伝いさんを雇う習慣は、タンザニア社会に根付いており、お手伝いさんは通常、家族の一員のように家に泊まり込んで働いています。
私自身、この文化に慣れていないせいか、当初は、家事を他人に任せることに抵抗がありましたが、アフリカで経験できるせっかくの体験だと、思い切って雇ってみました。
「自分が得意ではないことは他の人に任せてみたらいい」「本当に大切なこと以外はやらなくていい」そんな理想論をどこかで聞いたことはあっても、実際には無理なことだとあきらめてきた私。
しかし、お手伝いさんのおかげで、この「理想論」を実現できたのです。
その結果、何年も「忙しいから」を理由に伸ばし伸ばしにしていた活動を始めたり、子どもたちと過ごせる時間が増えました。
このお手伝いさん文化は、タンザニアの女性のエンパワーメントの役割を担っています。
お手伝いさんの存在によって、働くママたちは仕事に行きやすくなります。
つまり、子育てや家事に追われることなく、自分のキャリアや個人の成長に専念することができるのです。
「家事育児は女性の仕事」という社会通念がまだまだまかり通っているタンザニア社会。
お手伝いさんの存在によって、タンザニアの女性たちは、時間とエネルギーを自己成長や自己表現に注ぎ、女性たちの夢の実現や経済的な自立に大きく貢献しています。
▶︎SHOGENの視点:🏳️🌈日常を大切にしていたタンザニアの人々
「わがまま」と決めつけずに
タンザニアの女性たちは、男尊女卑という今も残る社会的な制約にもかかわらず、こうやって生き生きと輝いています。
それは、自由に自己表現をする彼女たちのパワーと、お手伝いさん文化という社会から与えられた機会に支えられています。
自己表現したりサポートを受け入れることを、私たちは「わがまま」と決めつけて、我慢しがちではないでしょうか。
タンザニアの女性たちの生き方から、この「わがまま」と片づけてしまいがちな視点を見直すことができそうです。
つまり、私たちも自己表現をもっと大切にし、必要な支援を受け入れることで、より充実した生活を送ることができるということです。
ぜひ、日々の生活の中で、こういった視点を取り入れてあなたの考え方を更新できる部分がないか、考えてみてくださいね。
女性に優しい国ナンバー1のスウェーデンに学ぶ『ありのままの自分を受け入れる方法』

北欧の国スウェーデンは「世界でいちばん女性に優しい国」のトップに毎年選ばれています。
そんなスウェーデンの出身で、今では世界中のクライアントにヨガを教えているアンナ・スヴァルドフェルトさんに、ハミング代表の永野 舞麻(ながの まあさ)がインタビューをしました。
女性の権利が擁護され、働く女性が家庭と仕事を両立させられるように充実した育児休暇の仕組みが整っているスウェーデン。
そんな国で育ったアンナさんの体験から、わたしたち日本人が学べることも多いのではないでしょうか。
Q1:なぜ、スウェーデンは女性に優しい国のトップだと思いますか?

スウェーデンでは、「女性と男性は平等な役割を持ち、お互いがお互いを必要としている」という意識が根付いています。
それは、女性の雇用の機会にも表れており、医者でもバスの運転手でも、全ての分野において女性が活躍しています。
Q2:日本では、子供を持つ母親が仕事と家庭の両立に苦労していますが、スウェーデンの状況は?

“スウェーデンでは子供が生まれると、女性だけではなく男性も育休をとることが普通です。また、スウェーデンの働く女性が子育てと仕事の両立というプレッシャーを職場で感じることはほとんどありません。なぜなら、子供を持つ母親はフルタイムで働かなくて良いからです。
そもそも70%くらいの女性は、出産後はフルタイムで働きません。子供を持つ親にとって子供との時間が大切であることを会社が理解しているからです。”
そんなスウェーデンで、今は19才と21才になる2人のお子さんを育ててきたアンナさん。
現在はスウェーデン在住で、アシュタンガヨガとアーユルヴェーダの先生をしています。
アンナさんは、ヨガの先生を始める前から長い間、彼女の人生やヨガの教え方に大きな影響を与えた生き方をすでに行っていたと言います。
“11歳の時の日記に、ヨガを始めたいと書いたことがあるのですが、当時ヨガが何か分かっていませんでした。40代になってその日記を読んだ時、まさか本当にヨガを続けるだけでなく先生になっているとは、とびっくりしました。
18歳の時にオーストリアで夏を過ごし、70歳の聡明な女性に出会いました。彼女はマクロビオティック食を食べるなど、様々なことに興味のある女性でした。彼女が実践していることはどれも当時の私にとって新しいことばかりでした。彼女と様々なことを一緒に体験し、自分の内面が変わっていくのを感じました。
その頃に私はヨガに出会い、ヨガが誰でもできることなのだと知ったのです。私はその女性とはその後さらに親しくなり、彼女は96歳まで生きました。彼女は当時の私のボーイフレンドの祖母だったのですが、彼女との出会いは運命的でした。
10代の頃、私はひどい自動車の事故にあい、それが原因で背中にひどい痛みが残りました。色々な治療を試しましたが、その痛みに慣れてしまい、一生この痛みをひきづっていくのだろうと思っていました。その後、会社員として働いていた時も、まだ背中に痛みがあり、何かしなければと思い、再びヨガを始めたのです。その時に、70歳のヨガの先生に出会いました。
当時の私は、かなりのストレスを感じていました。しかし、再びヨガを始めたことで、調子が良くなっていることに気づいたのです。ストレスが減っただけでなく、良く眠れるようになりました。すべてのことがうまくいくようになって、背中の痛みも和らいでいることに気づいたのです。
最初の子供ができたとき、私は家にいて子供を自分で育てたいと考えていました。そして、すぐに2人目を妊娠し、会社員としてもう復帰しないことに決めました。周りの人は私の頭がおかしくなったのかと思ったようですが、私はただ子供たちと一緒にいたくて自分を大切にしたかっただけなのです。
“交通事故による背中の痛みとストレスに苦しんでいた彼女は、ヨガとの再会をきっかけに心身の調子を取り戻し、母となった後は自分と家族を大切にする生き方を選びました。”
20年前は、子供のために仕事をやめるなんて考える人はほとんどいませんでした。人々から「いつ仕事に戻るの?」と尋ねられることが7年間も続きました。でも、これが私にとって大きな転機だったのです。この頃から、私は家族を連れてインドにも行くようになりました。
子供たちが成長してきたので、私はヨガの先生としての仕事をスタートしました。自然にそうなっていったのです。自分自身を無理に追い詰めることはなく、自分の直感に耳を傾けただけです。
自分が会社員として働いた経験があることはとても幸せに感じています。この経験により、ストレスを感じている人々を理解し、共感しやすくなりました。”
Q3:ヨガ、瞑想、そしてマインドフルネスを取り入れたいと考えている人々へのアドバイスはありますか?
“大切なことは、どれだけの時間をかけるかではなく、「したい」という強い願望を持つことです。その願望を育ててください。瞑想をしなかった日があったからといって、自分を責めるとストレスがたまります。
自分の心のメインテナンスと瞑想という点で大切なのは、自分の願望に耳を傾け、できることから始めるということです。多くの計画を立て過ぎないようにし、心の声に従って進んでください。常にまじめでいようとすると、感情がないロボットのようになってしまいます。”
▶︎マインドフルネスをやってはいけない人の特徴|PTSDやうつ病の人は危険?
Q4:あなたはどのようにして、心を開いたり直感を聞くことができるようになったのですか?
“私は子供の頃からそういった願望を持っていました。また、車の事故も影響を与えたと思います。この事故を経験したことで、自分の心の声を聞かざるを得なくなりました。
さらに、会社員として忙しく働いていた時は、自分が偽っているような感覚を持っていました。全く重要性を感じないことをして、どうしてこれほど多くのお金を稼げるのか、という感覚です。なぜなら、私自身はすでに人生で本当は何が大切なのかを知っているからです。それは、自分が愛する人たちのそばにいて、自分を大切にすることです。
私は誰もがヨガの先生である必要はないと思います。しかしヨガのプロセスを通じて、自分を大切にする方法を見つけることができます。ヨガを実践することで不安が少なくなり、その結果、他の人々の行動にも影響を与えることができるのです。
ヨガの先生になるためには、まずは自分について知る必要があります。その意味で、私たちは皆が生徒なのです。自分を先生だと思ってしまうと、もう先生ではありません。ですから、私は自分のことも生徒として見ています。”
Q5:ヨガとアーユルヴェーダは、どのような形で人々の役に立つのでしょうか?

“自分に焦点をおいていると、あまり多くのエネルギーを使う必要がありません。ヨガとアーユルヴェーダは『私たちがエネルギーを消耗する原因は、私たちが無意識に行っていることや考え方にある』と教えてくれます。
多くの人がヨガに来て「うまく息つぎができない」と言いますが、もちろん呼吸はしています。彼らが自分の呼吸に集中し始めると、自分が考えすぎていることに気付き、より落ち着けます。ストレスを抱えると自分を見つめる方法を見失いがちですが、単に自分の呼吸に集中するだけで、自分を探求することができるのです。
“ヨガとアーユルヴェーダは、呼吸に意識を向けることで無駄な思考やエネルギーの消耗を減らし、自分の本質とつながって本来の自分を取り戻せることを教えています。”
私たちは生まれてくるときに息を吸い、この世を去るときには息を吐きますよね。つまり、生まれてからこの世をさる間に、どのように呼吸をするかが重要なのです。
ヨガはあなたに呼吸というツールを与えるので、瞑想ではこの呼吸に集中します。あなた自身と繋がることができなければ、あなたは偽りの人格の中で生きていることになります。これを長く続けていると幸せから遠のいてしまいます。しかし、呼吸を学ぶことで本当の人格に目覚め、自分が本来どういった人であるかを感じることができるのです。”
▶︎アーユルヴェーダって何?どうやったらすんなり今の生活に取り入れられる?
Q6:より良い人間になるためには自然に没頭する必要があると言われています。自然と近くなることは、あなたにとってどういう意味がありますか?
“スウェーデンは、人が少なくて、自然が多いです。食事をとるのと同じように私たちは自然を摂取する必要があるのです。そうすることで、自分の心に正直に生きやすくなります。自然をもっと取り入れるという方法は、毎日やる必要はありませんが、一度やるともっとやりたいと思うようになります。頭で考えるのではなく、まずは行動してみることが大切です。経験すると、知識が自分の糧になります。
現代社会を見渡すと、多くの人々が真実から遠く離れ、自然から遠ざかっています。その結果、周りの人々がしていることを真似をして、自分を見失い、結果として不健康な社会を作り出しています。もし、あなたが自分自身を育てるようになれば、社会も世界も良くなっていくでしょう。
瞑想がいかに有益であるかという体験がなければ、物事に圧倒されたときに瞑想を続ける方法がわからないのと同じです。他人の言うことに頼ってしまう。例えば、経営者が自分自身と調和していないと、会社の経営事態も調和していないものになってしまう。だから、それぞれの人が自分を大切にすることがとても大事なんです。”
Q7:最近とても幸せだと感じたことは何ですか?
“マインドフルネス(今に集中している)ときは幸せです。今を大切にすればするほど、幸せになれるのです。何かを買ったり、特別な人に会ったりする必要はありません。私は今、すでに幸せなことに気づくだけでいいのです。
誰かが自分の元を去っていくとき、あるいは死んでいくとき、本当に悲しいときには心を開くから、自分を知るチャンスになるんです。そんな時は、悲しいことも嬉しいことも同時に起こっています。悲しいのはその人に会いたいからで、嬉しいのはそうやって自分自身と向き合えるから。誰かがいなくなったからと言って、被害者になることはありません。”
Q8:幸せでないとき、それを体感しますか?
“子供のことで忙しくしていたりと、自分のための時間をとっていない時は、自分が不安感に駆られていることに気づきます。
そんな時は、自分のための十分な時間をとっていないというサインだと思って、意識してリラックスする時間を設けるようにしています。”
Q9:そのままの自分を受け入れたり、愛せないと感じている日本の女性たちへのアドバイスはありますか?
“自分を愛することは非常に大切です。自分を愛せないと、他の誰かを愛することはできません。もしそれができなければ、まずは瞑想を始めましょう。どれだけ他の人を手助けしたいと思っても、まずは自分を助けることから始めなければなりません。
自分を知る旅とは、まさに充実した人生への旅を意味します。そして、この旅は一生続くものなのです。あなたの中にある命の力「プラーナ」がより多ければ多いほど、あなたの人生は充実したものとなるでしょう。
人生を思いきり楽しむためには、変化を受け入れる寛容さを持つことが大切です。例えば、恋愛関係が上手くいかなかったとしても、失敗だと感じる必要はありません。なぜなら、私たちは常に成長して変化し続けているからです。一緒に過ごした時間に感謝しましょう。
もしもあなたがこのことに気づいていないとしたならば、あまり変わることはできないでしょう。今の時代は、より多くの人々がこのことに気づきはじめており、多くの人々が日々、変わっています。そのため、人々が一生涯ずっと一緒にいることが以前ほど一般的ではなくなっているように思います。”
▶︎【自己受容】弱くてダメな自分を認めて受け入れるトレーニング方法
<参考>
BAV Consultingとペンシルバニア大学ウォートン・スクールの2022年調査
人生を変える最高の『セルフプレジャー』を見つける9つのステップ

セルフプレジャーは、色々な面から見て素晴らしいものだということを知っていますか?
とっても気持ちがよいだけでなく、あなたの健康にもよい影響を与えるのがこのセルフプレジャー。
オーガズムに達するとオキシトシンというホルモンが放出されますが、このホルモンはあなたの健康全般に良い効果があります。
セルフプレジャーには、痛みを軽減する効果もあり(生理痛よ、さようなら!)さらに、不安を緩和する効果もあることがわかっています。
あなたも、その恩恵を受けたいと思いませんか?
健康によいのは、オーガズムに至るまでに放出されるホルモンだけではありません。
性的に興奮している時に、脳はセロトニンという物質を放出します。
この化学物質は、性的満足感を高め、気分を調整するのに役立つことが分かっています。
つまり、オーガズムがあろうとなかろうと、自分を愛することは、脳のバランスを整えてくれるのです。
あなたがセルフプレジャーの初心者でも、少しマンネリ気味の経験豊富な人でも、セックス・セラピストのジョーダン・ルロ博士からのアドバイスは、どうやって最高のセルフプレジャーを実現するかについての大きなヒントとなるでしょう。
▶︎セルフプレジャーとは?美容効果を紹介!どんな人におすすめ?
▶︎セックスレスになりやすい夫婦の特徴とは|原因や解消法を解説
ステップ1: 性的な欲求をかき立てる
私たちは、性的欲求に関して多くの誤解をしています。
例えば、思わず欲情してしまうことは当たり前だと思われていますが、実際には私たちはもっと複雑な生き物です。
ベストセラーの著書「Becoming Cliterate」で指摘されているように、女性(そしてすべてのジェンダーの人々)は、思わず欲情するということはあまりありません。
医学雑誌『The Journal of Sexual Medicine』によると、3人に1人は、欲求が何かに反応して発生するものであることがわかっています。
そして、この欲求は、性的な刺激(触れたり、ポルノを見たり、何でも興味を引くもの)にさらされたときに現れます。
つまり、多くの人々は欲求を引き起こすために何かきっかけを必要とするのです。
性欲をかきたてる方法はたくさんあり、人によって異なります。
だからこそ、ぜひクリエイティブなアイデアを試すことを恐れないでください。
ルロ博士は、「演じなくてはいけないというプレッシャーや過度な期待、または時間の制限がない、自由な環境とマインドを作りましょう」と説明しています。
博士は、優しい色の照明、キャンドル、またはお気に入りの音楽で自分のセルフプレジャーの空間を整えることで、リラックスした気持ちになれると提案しています。
ステップ2:全身を探求してみる
「性的な活動というと、性器や乳房にばかり注目されがちですが、それ以外にも全身をよく見直すことで、自分がさらに気持ちよくなる性感帯を発見できます」とルロ博士。
まずは、足、太ももの内側、腕、またはお腹をマッサージすることから始めましょう。
これによって、プレッシャーを感じずに、気持ちのよい感覚を楽しみながら探すことができます。
性欲が低下している、体型に悩んでいる、またはオーガズムが感じられないなどの悩みがあっても、ありのままの自分を受け入れて、まずは体とつながることで、快感を感じる可能性を引き出すことができます。
ステップ3: ルーブ(潤滑ゼリー)の活用
ルーブ(潤滑ゼリー)を使うと、肌と手の間にバリアができて興奮が高まり、摩擦が減り、セルフプレジャーがさらに快適になります。
ルロ博士は、「ルーブ(潤滑ゼリー)が性的興奮、快感、そしてオーガズムを増加させることは、実際に女性たちから報告されています」と話します。
ルロ博士は、天然素材で、刺激性の低い成分で作られた水性のルーブ(潤滑ゼリー)をおススメしています(できれば、砂糖、パラベンなどの有害な化学物質が含まれていないもの)。
ステップ 4: まずは、外側からスタート
実際にセルフプレジャーをする時になったら、まずはクリトリスに注目しましょう。
なぜなら、ここに約8,000の神経終末があるからです!
さらに、多くの研究から、オーガズムに達するにはほとんどの人がクリトリスへの刺激が必要であることが明らかになっています。
『The Journal of Sex and Marital Therapy』に掲載された2017年の研究では、37%の人がオーガズムにはクリトリスが必要であると回答しました(陰茎挿入のみで十分と回答した人は18%)。
まずは、指を使ってクリトリスを軽く触ってみてください。
刺激する方法はたくさんありますので、何が気持ち良いかを決めるのはあなた次第です。
例えば、以下の方法を試してみるのもよいでしょう。
- 時計回り(または反時計回り)にクリトリスをこする
- 上下にこする
- 指を横に滑らせる
「同じ刺激を繰り返すよりも、スピードや強さなど多様な方法を試す方が、興奮することが研究からわかっています」とルロ博士。
ステップ5:次に、内側に向かって…
陰茎挿入はすべての人が好む方法ではないかもしれませんが、一部の人にとっては快感をもたらすことがあります。
もし挿入を試したければ、十分にウォームアップをすることが重要です。
ステップ4をくり返し、リラックスして準備が整ったら始めましょう。
1〜2本の指(またはセックス・トイ)を膣に挿入し、腹部の方向に引っ張るように、揺り動かすように動かします。
内部全体を触ったり、こすったり、軽くたたいたりして、ゆっくりと探索していきましょう。
ここでルーブ(潤滑ゼリー)を使うことで、陰部や膣を滑らかにして、より快適に興奮を感じられるようになります。
ステップ6:挿入とクリトリスの刺激を一緒に試す
手の一方でクリトリスを刺激しながら、もう一方の手で指を使って挿入を試すこともできます。
この気持ちよさを探求する旅は、ブッフェスタイルのレストランにいることに似ています。
つまり、おいしいものもあるけど、そうでもないものもあるということです。
ある時には一つの料理に興味を持つけれども、そうでない時だってあります。
ここで大切なことは、たくさんの選択肢があり、その日の気分によって、なんでも試すことができるという意識を持っておくこと。
ステップ7:「今」を感じる
セルフプレジャー中は呼吸にも注意を払いましょう。
深く息を吸うことは、リラックスして神経系を落ち着かせるために大切なことです。
しっかりと息を吸うことで、体に必要な酸素とエネルギーを吸収し、「今」を感じることができます。
そして息を吐くときには、ストレスが体から排出され、体がどっしりと安定している状態を感じましょう。
最初は上手くいかなくても、何度か試してみるうちに慣れてくるので、心配しないで大丈夫です。
ステップ 8: 全ての感覚を意識しましょう
セルフプレジャー中は、全ての繊細な感覚に意識を向けることで、集中力を維持することができます。
自分自身に色々と問いかけてみましょう。「何を感じる?」「何が聞こえる?」「何が見える?」「何の香りがする?」。
一つ一つ体験していることに細かく意識を集めてみることで、「今」に自分を引き戻し、自分の身体の感覚に集中することができます。
ステップ 9: グッズを準備しましょう
そう、グッズとは、セックストイの話です。

例えば、バイブレーターを使うことで、より深く集中的にクリトリスを刺激することができます。
もし、セックストイを使ったことがなかったら、まずはバレット・バイブレーターのような小さなものから始めるのが良いかもしれません。
ルロ博士によれば、「シリコーン製のバイブレーターは、外部刺激(例えばクリトリス)と内部刺激(例えば膣)の両方に使用でき、多様なスピ―ドや強さを選べるため、理想的です」とのこと。
そして、急がずに、ゆっくりと時間をかけることも忘れないで。
急いでしまうと不安などにつながり、これではセルフプレジャーの楽しみが半減します。
自分を愛するためのセッションを楽しむセルフプレジャーのための時間をしっかりと確保するようにしましょう。
ぜひ、マスターベーションは人生の中心にふさわしい、正真正銘の性体験であると考えてください。
そしてここで最も大切なことは、自分の身体を探求し、性的なタッチを楽しむこと、そして自分が性的な人間としてどのような存在かを知ることです。
自分自身の快感に対して、より多くの時間と注意を払うことで、セックスは(一人でも、相手と一緒でも)より楽しいものになり得ます。
そして最も重要なことは、何よりも「楽しむ!」と自分の心で決めることです。
9 life-changing masterbation tips / Flo Health より
タンザニアで学んだ「自分に許可を出して幸せになる」方法
「なかなか自分に許可が出せない」
普段の生活の中で、こんな風に感じることって意外と多くないでしょうか。
「あのお化粧、私の歳にはあわないよね」
「あんなこと、私がやったら周りの人に笑われちゃうかな」
興味があっても、自分には無理だと無意識にブレーキをかけていることはありませんか?
でも、自分に「やってもいいよ」という小さな許可を出すだけで、それは自分が望む幸せに1歩近づいているのです。
なぜなら、自分を止めているブロックというのは、自分が心の奥で、本当はやりたいと思っていることだったり、ずっと気になっていることだったりするからです。
自分をとめているブロックは、自分の本質を映しだしていることが多いのです。
私はここタンザニアで、今まで自分になかなか出せなかった小さな許可を出したことで、長い間感じたことのない幸せな気持ちになりました。
この記事を読むと、あなたも日々の生活にちょっとした勇気をとりいれる方法がわかり、日常をさらに幸せにするヒントが見つかります。
「私にはムリ」と思ったアフリカ布との出会い

タンザニアに来て、まず私の目を引いたのは「キテンゲ」というアフリカ布を身にまとったタンザニア人女性の美しさ。
この「キテンゲ」は、赤、青、黄色などのカラフルな色と、動物やフルーツなどの大胆な柄が特徴的なデザインの布です。
タンザニア人女性の肌の色に、この明るい色が絶妙なコントラストでとても素敵なのです。
でも、日本人のわたしが着るには、キテンゲは派手すぎて無理だなあ、と考えていました。
その一方で、日本人を含む外国人の友達が、このキテンゲのワンピースを上手に着こなしている姿をみて「うらやましいな」「わたしもトライしてみたいな」とも感じていました。
“無難な色ばかり選んできた彼女は、友人に誘われて訪れた店でキテンゲ布の鮮やかな美しさに魅了され、迷いながらも自分のために初めてそのカラフルな布を手に取りました。”
そうはいっても、今まで黒、白、ネイビー色などの無難な色を着ていたわたし。
もう40代だしこんなカラフルな色を着たら周りからどう見られるだろう、とやはり抵抗がありました。
ある日、友達がアフリカ布を買いに行くということで私も一緒についていきました。
そこで出会ったキテンゲの美しさに改めて魅了されたわたし。
気付いた時には、買う予定のなかったキテンゲを自分用に購入していました。
そこからは、もう早かったのです。
すぐに仕立て屋さんに娘とわたしのおそろいのワンピースを作ってもらい、あこがれていたキテンゲのワンピースが出来上がりました。
はじめての娘とおそろいのワンピースを手にいれた私。
まるで宝物を手に入れたようにワクワクしていました。
娘からの「一緒に着ていこうよ」の一言にさらに勇気をもらい、早速このワンピースを着て出かけました。
友達に「とても似合うよ」とほめてもらったわたしは、服をほめてもらってくすぐったいような、でもほんわかと幸せな気持ちをかみしめる少女に戻っていました。
タンザニアの女性の味方

最初はハードルが高いと感じていたこのキテンゲのワンピースですが、少しの勇気で自分も着用してみたら、大きなときめきとワクワク感と予想しなかった幸せを感じることができました。
こんな外国人の私に幸せをもたらしてくれたキテンゲは、タンザニアでも女性の味方です。
キテンゲは、タンザニアではカバンや小物などにも使われている布ですが、圧倒的に女性のワンピースとして活躍しています。
“キテンゲは、母から娘へ受け継がれ、団結や幸せを象徴する布として、男性優位のタンザニア社会で女性の自己表現とエンパワメントを支える重要な存在です。”
男性優位のタンザニア社会で、このキテンゲはタンザニアの女性のエンパワメントにとても重要な役割を担っています。
例えばクリスマスのようなイベントでは、女性たちが同じ柄のキテンゲでおそろいのワンピースを着て女性たちの団結と強さを表現します。
また、自分の娘たちが5~6歳くらいになると、母親は初めてのキテンゲをプレゼントし娘の幸せを願います。
出産する女性たちの必需品にもキテンゲが含まれます。
赤ん坊が産まれた時に最初に新しい命を包む神聖な布がキテンゲなのです。
キテンゲは、タンザニア人女性が着用して自己表現をする手段であり、男性優位の社会で女性が強く自立していくための仲間のような存在なのです。
自分を解放するための「許可」
こんなキテンゲから、大きな幸せを得ることができた私は、「40代なんだから、こういう色の服を着るべき」という固定観念から解放され、自分に許可を出すことができました。
あなたも普段の生活の中で、ずっと気になっていたけど勇気がでないこと、こんなことしたら恥ずかしい、……と自分に許可を出せていないことはありませんか。
とっても小さな勇気で小さなステップを踏んでみることで、おもいもよらない大きな幸せを感じることができるものです。
ぜひ一度トライしてみてくださいね。
SHOGENの視点:🏳️🌈日常を大切にしていたタンザニアのブンジュ村の人々

皆さんこんにちは!
ペンキ画家のSHOGENです。
僕は、アフリカのタンザニアのブンジュという200人の小さな村で、村人と生活を共にしながら絵を描き続けていました。
ある日、村人の皆んなを束ねる70歳の村長にこのような質問をされました。
『SHOGENは2日前のお昼ご飯に何を食べた?』
僕は覚えていなかったので、『覚えていない』と答えました。
すると村長が、『SHOGENにとって食べるということは作業なんだね。食べることが、食事が作業になった時に、生活・暮らしそのものが作業になってくるんだよ。
確かに2日前のお昼ご飯の時、俺の家族と一緒に食べていたよね?
でもね、SHOGENを見ていて思ったよ。
【お前はそこにいなかった。お前の心はそこにいなかったんだ。】
そこにいた俺の孫たちもみんなそう言ってたぞ。
SHOGENはその時一緒にご飯は食べていたけど、おそらく頭の中は明日のことを考えていただろうし、1週間後の予定のことを考えていたにちがいない。
SHOGEN、誰がどう見てもお前の心はそこにいなかった。
生きるということはどういうことかわかるかい?
【生きるということは、その時、今、その瞬間瞬間をじっくりと味わうということなんだよ。】
今の日本はものすごく忙しいのか?
お前みたいな人ばかりなのか?
- 明日何をする?
- どこに行く?
- 何を食べる?
といった作業の会話であふれているのか?
SHOGEN、お前の会話は作業の会話が多すぎる。
このブンジュ村に住む人たちの会話をよく聞いてみてごらん。
- それをして、どう言う気持ちになったのか。
- それを食べて、心がどう感じたのか。
という心の会話が多いだろ?
SHOGENも、もっと心の会話ができるように日常を味わいながら生きていくべきだと思う。』
僕は今まで生きてきた人生の中で、こんな質問をされたことがありませんでした。
小さい頃から学校では、
「給食は時間内に残さず食べなさい。早く食べて掃除に取りかかれる準備ができるようにしなさい。ゆっくり食べて周りの人に迷惑をかけないように!」
と言われ続けてきた僕は、何を食べたのか覚えていたことは一度もなかったし、給食を味わって食べた記憶もありませんでした。
生きる上で最も大切にしなければいけない食事という時間。
ブンジュ村の人々にとって食事の時間とは、日常を豊かにしてくれ、生きる喜びを感じさせてくれる大切な時間だったのです。

皆さんは、昨日食べた夜ご飯を覚えていますか?
2日前に食べたお昼ご飯を覚えていますか?
その時、あなたは誰と食べましたか?
一緒に食べていた人は、どんな表情で、どんな会話をして食べていましたか?
その時にあなたが食べたものは、どんな味がしましたか?
生きるということは、今、その時、その瞬間に自分の心がそこにいるということ!
今あなたは何をしていますか?
今あなたの心はそこにいますか?
今あなたは今を生きていますか?
🔻SHOGENのInterview動画はこちら🔻
タンザニアで学んだ幸せになるコツ

タンザニアの八百屋さん(写真:著者提供)
あなたが最近「ありがたいな〜」と感じたのはいつですか?忙しい日々の生活で、こういった感謝の気持ちを実感することは難しいかもしれません。
私は、タンザニアでの生活を始めて、日本では当たり前だったことが、この国では当たり前ではないことを日々実感しています。
アフリカに住むわけなので、このこと自体は覚悟していました。
しかし、予想していなかったことがあります。
それは、当たり前だと思っていたことのありがたみに気づくことで、幸せ度がアップすることです。
当たり前のものがないタンザニア

タンザニアの町を歩く女性たち(写真:著者提供)
アフリカの生活を始めると、当たり前だと思っていたものがここにはない、というびっくりする体験をよくします。
例えば「水泳」。タンザニアには、大人になっても泳げない人がたくさんいます。
なぜなら、学校で水泳を学べないからです。
子供に泳ぎを教えたければ、学費が高い私立の学校に通わせるか、放課後に水泳レッスンに通わせなくてはいけません。
そのため、タンザニアで泳げる人は、ごく一部に限られます。
私はこの事実を、友達の子供にギフトとして水着をあげた時に初めて知りました。
“日本では当たり前の泳ぎや貯金が、タンザニアでは一部の人だけが享受できる特権であり、そこでは家族や地域の助け合いによって経済が支えられていることを知りました。”
「せっかくもらったけど、うちの子は泳いだことがないわ。
でもせっかくだし、子供を水泳教室に通わせようかしら」友達はそう苦笑していました。
日本では子供の時に当たり前のように習う泳ぎ。
タンザニアでは、一部の人だけが享受できる特別なスポーツだったのです。
知らない間に泳げるようになっていた私は、小さい時に泳げるようになっていたことをありがたいと感じました。
もう1つのびっくりした体験は、お金にまつわるもの。
日本では当たり前のようにしている「貯金」。
貧しいため、その日暮らしをしている多くのタンザニア人にとって「貯金」とは、余裕のある人だけができる贅沢なことです。
こういった背景から、仕事のある人が、失業していてお金のない人を助けたり、お金が必要になったら、家族でお金のある人がサポートをしたりというやり方で、住民の経済はなんとか成りたっています。
わたしたち日本人にもお金の心配はありますが、貯金という当たり前があるから、そうはいっても、安心なのだと感じます。
感謝に気づく事のメリット
当たり前だと思っていたことが実はそうではなかったのだと、タンザニアでの生活を始めて気づいたことは、他にもたくさんあります。
こういった事実を知り、ありがたいと感謝することで、幸せな度がアップしている自分に気がつきました。
感謝をすることで、幸せを感じられるのはなぜでしょうか。
メリット①
1つ目は、心をポジティブな状態にできるから。
当たり前のことを当たり前に考えず感謝することで、ポジティブな生き方をすることができます。
今に注意を払うことで、自分が何を持っているのかに気づき、心の中にポジティブな感情が生まれ、ストレスや不安を軽減することができます。
メリット②
2つ目は、感謝することで自己肯定感を高めることにもなるという点。
自分が持っているものに感謝することは、自分自身を受け入れることにもなるからです。
今の自分を客観的にとらえることで、自分自身に対する理解を深めることができます。
その結果、自己肯定感が高まり、自信を持って日々を過ごすことができます。
メリット③
3つ目に、感謝の気持ちが、人間関係にも良い影響を与えるということがあげられます。
今まで当たり前に受け取っていたもの、他人が自分のためにしてくれることに感謝することで、相手に対する感謝の気持ちが生まれ、相手との関係が改善されるという側面があります。
あなたも、感謝できることを1つ見つけてみよう
タンザニアでの私のこういった気づきは、そもそも日本に生まれたこと自体が感謝することなのだと考えるきっかけにもなりました。
私は、起床したらまず、感謝することを紙に書くということを日課にしています。
“感謝の気持ちを持つことは自分を受け入れることにつながり、自己理解を深めて自己肯定感や自信を高めることができます。”
こうやって言語化することで、自分がどれだけたくさんの、ものやことを与えられているのかに気づけるようになります。
感謝という視点を持って自分の周りを見回すと、景色はずいぶんと違って見えるのではないでしょうか。
つまり、あなたの周りにあるものは、どれも感謝できるものばかりなのです。
屋根のある家、毎日着替えができるきれいな服、安心して眠ることができるベッド、朝起きれば食べられる朝食、いつでも不自由なく飲める水。
あなたも、ぜひ、自分が当たり前に受け取っていることを一度書き出して、あなたがどれだけ幸せなのかに気づいてください。
SHOGENの視点:🚩【アフリカのブンジュ村の人が持ち合わせている自己肯定感の話】

僕がアフリカから初めて日本に帰ってきた2015年、僕は日本で『物凄い違和感』や『嘘やろ?』といった感覚がありました。
それは日本に住む多くのお母さんの発言です。
僕が住んでいたアフリカのタンザニアのブンジュ村では、道を歩いていると、
『SHOGEN!聞いて!私、主婦!2人子ども育ててる!!すごいやろー!?』
と自信満々な顔でお母さんたちが僕に言ってきます。
確かに子どもを育てるってすごいことですよね!
しかし、日本だったらどうでしょう?
『私、子育てしかしてないんで。』
という人があまりにも多くないでしょうか?
もし、この発言をブンジュ村でしてしまうと、70歳の村長から呼び出されて3時間くらい説教をされます。
そのときに村長は必ずこう聞いてくれます。
『その発言は誰にとって失礼だと思う?自分の心の中にある魂に失礼な発言をしてはいけないよ。本当にそうなってもいいの?生きていくうえで大切なことは自分を愛してあげること。そして、自分が一番の自分のファンであることだよ。』
お母さんを含め、多くの日本の大人たちが、自分自身を認めてあげれなかったり愛せていないように思います。
僕も『自分なんか、、、』というマイナスな発言を村でしてしまい、村長に叱られたことがありました。
その時に村長から教えてもらったのは自分の愛し方、自己肯定感の高め方でした。
『SHOGEN、日常の中でなにげなくやっている自分の所作や、仕草、動作をいちいち愛おしく思うんだよ。例えば、水を手のひらですくうときや、息を吐くときの自分、息を吸うときの自分の仕草って、なんて美しくて、なんて素敵で、なんて愛おしいんだろう。とか、朝起きて外に出る時に踏み出す一歩目の左足のつま先が地面を踏む感触までも愛してみるんだよ。その1つひとつの、今までなにげなくやっていた日常の中で行う所作や仕草を愛してあげるという積み重ねが、自己愛を育てるんだよ。』
そう言われた僕は、今までいかに自分を大切に思ってあげれていなかったかに気づくことができました。
- 皆さんは、自分のことを大切にできていますか?
- 自分を愛してあげる時間を作れていますか?
そして、もう一つの大切なことは【自分の心の中に少しの余裕を持つこと】だと村長が教えてくれました。
『余裕がないと、【日常に溢れる小さな喜び】を見落としてしまうんだよ。SHOGENは日常の中で空を見上げる時間をつくってる?空を見上げるくらいの余裕が心の中にあったら、自分のなにげない仕草に目を向けてあげれたり、自分を愛してあげる時間をちゃんとつくれるし、日常に溢れる小さな喜びも拾い上げれるんだよ。』
そのように僕は言われました。
気がつくと、ものすごく忙しく慌ただしい社会の渦に巻き込まれて、はっ!とする瞬間がよくあります。
「効率よく、無駄を省いて」と言われる時代ではありますが、「自分を愛する時間」まで省いてはいませんか?
【自分が一番の自分のファンでいてあげる】
そうすることで、大切な周りの人にも当たり前に愛を注げるようになるんだよ、と村長が僕に教えてくれました。
●皆さんは今日は自分のどの仕草や行動を愛してあげましたか?
●今日1日の中で、どのくらい空を見上げましたか?
YOUの思考「どこにいても、楽しいことをずっと探している」
私たちを惹きつける特別な魅力を持つひとは、誰にも負けない“個性”という輝きを放っています。各界で活躍し続けている彼女や彼に、“自分らしく”を大切にする生き方についてインタビュー。そのオリジナルなスタイルの秘密を探ります。前回のインタビューvol.1では、YOUさんの仕事への向き合い方やモチベーションについてお話いただきました。今回は、自身の好きなモノゴトと向き合い方などを伺います。
YOUという生き方「ネガティブなことには鈍感。そうやって生き延びてきた」
私たちを惹きつける特別な魅力を持つひとは、誰にも負けない“個性”という輝きを放っています。
各界で活躍し続けている彼女や彼に、“自分らしく”を大切にする生き方についてインタビュー。
そのオリジナルなスタイルの秘密を探ります。
ここから3回にわたり、タレント、俳優、エッセイストなどジャンルレスに活躍するYOUさんをフィーチャーします。


― 何か一つの仕事や形に縛られることがないんですね。
「一つの会社にいて勤め上げるという考えや、一つの仕事を極めるという経験がないんです。一つのところにいる幸せを知らないし、何なら“嫌になったらいつでも辞められる”ってことで安心しているんですよ。安定って素晴らしい、って聞くから結婚もしてみたけど、“果たして結婚は安定なのか?”と思っただけでしたね(笑)。
人それぞれだと思いますが、不安定な状態の方が私には心地いいんですよね。だって安定してずっと幸せとか、ずっと楽しいって、本来あり得ないことでしょう。だから嫌だな、大変だな、悲しいなって思うことがないと、私は幸せを感じられないんです」
― バラエティ番組では、ここでYOUさんが何かいいことを言ってくれるーーと観ている方はいつも期待してしまうのですが、そういうプレッシャーを感じることはありますか?
「30代、40代のころは、ちょっとあったかもしれません。キレイでいたいし、モテたいし、面白いことも言いたい。人の目も気になる。でも50代に入ってからはそういうプレッシャーは一切なくなりました。上手いコメントは若い子が言えばいい、それで育っていけばいい。だから私は今、ただただ好き勝手なことを言っているだけなんですよ(笑)。
とはいえ、バラエティの現場は勝負事みたいな感覚がある。他の出演者のキャラクターを考えて、自分はどこで出てどこで引くか。自分をそうやって客観的に眺めて『今だ、行け!』とやっているのが、すごく楽しいんです」
― 自分を客観的に見て、瞬時に判断して振る舞う。それは、芸能界に入ったときからですか?
「いえいえ。ただただ現場で学んできた感じでした。出るべきところで出られなかったらガッカリはするけど、落ち込んでいる時間がないくらい、次の現場、次の現場と続いたので、まさに叩き上げですね。というと、とても忙しかったみたいに聞こえますけど、ちゃんとプライベートの時間もありましたよ。毎日飲み歩いてましたし、20代から40代の20年間はずっと睡眠時間は3時間くらいでした。仕事で、じゃないですよ、勝手に遊んで勝手に寝てないだけ。
でも仕事ってなるとちゃんとスイッチ入りましたし。何か私、異常にタフなんですよ(笑)。タフでいられたのは、たぶん、やりたいことがいっぱいあったから。服も好きだからコレクションにも行きたいし、子育てもあったし。全部ぜんぶ、やってみたかったんですよね」
>>”自分らしく生きる”とは?|仕事や恋愛で自然体で過ごせる方法を紹介

失敗の理由の本質は、他のところにある場合が多い
― やりたいことを全部やる、心も体もタフでいるためには、何が必要でしょうか?
「一つ言えるのは、鈍感力を鍛えるってことかな。何か嫌だな、辛いなってことは絶対あるはずだけど、そういうことに敏感になりすぎない。自分の都合のいいように常に変換する。ネガティブなことには鈍感でいるってこと。だから私は、怒りとか痛みに異常に強いし、ストレスも溜め込まないでいられる。そうやって生き延びてきた気がします。どうやってその鈍感力を鍛えたのかといえば、やっぱりそれも、とんでもない数の現場に行って、毎回とんでもなく初めてなことをしていくなかで、身についたのかもしれない。悔しいこととか、恥ずかしいことがあっても、全然大丈夫になりましたもん。
逆にハッピーなことに対しては、敏感でいたいですよね。だから楽しそうなことを探して、毎晩飲みに行っていたんでしょうね。それに、仕事で溜まったストレスは、違うところで発散しないと。失敗した場所に立ち戻って現場検証をすることも大事だけど、失敗の理由の本質は、他のところにある場合が多い。だから常に、他の逃げ場も持っていないとね」
>>【ストレス解消】セルフケアとはなにか?意味・種類・方法について解説

―ネガティブなことに鈍感でいる・・・それは案外と難しそうですね。
「私、ひとの悪口をめっちゃ言うし、それでストレス解消しているところもあるけど、でも誰かのせいにしないってことは意識してきました。他人のせいにして、鈍感力とか言ってたら、人間として終わっているでしょう(笑)。だから、自分が落ち込まないために自分の失敗を他人のせいにする、それだけはダメだとずっと決めていた。人間関係においても、相手が悪い、ではなくて、あくまで自分の責任にして、そのひととの距離の取り方を冷静に考えればいい。
それでも上手くいかないときは、私のなかで指標とする存在がいて、そのひとに意見を聞いています。このジャンルはこのひとに相談、こういうことはこのひとの考え方が素敵、というふうに何人かいて。年上も年下も男も女もさまざまなんですが、自分が迷っているときはそのひとに話をしてみる。で、『そうじゃないよ』とか『間違ってないよ』とかアドバイスをもらって進んでいく感じですね。
たくさんの現場に行って、毎回たくさんのひとに会ってきたからこそ、そういう素敵な人々に出会えた。それってこれまでの人生においての、財産みたいなものですからね。まぁ、そこで意見を言われて反省するってことはもちろんありますけど、仕事の場合、まったく同じ現場って二度とないので、後悔するとか反省しするぎるっていうんじゃなくて、よしわかった、はい次!って進む感じですね」
日々の痛みや苦しみをかわしながら、自分だけの地図を描いて歩いてきたYOUさん。
その芯には、とてもしなやかで強い軸がある。自分らしく、自分のペースで歩いていく彼女の姿は、私たちのあこがれであり、指標。
自分のやり方で、無理をしすぎず、楽しむことに貪欲であれ。
仕事を持続可能にする大切なヒントが見つかりました。
次回は、日々自分をどうケアしているのかについてじっくりと伺います。
>>【自己受容】弱くてダメな自分を認めて受け入れるトレーニング方法
Profile
YOU(ゆう)
8月24日生まれ、東京都出身。
18歳でモデルデビューしたのち、歌手としても活躍。
’91年『ダウンタウンのごっつええ感じ』に出演、以降数々のバラエティ番組に出演。
2004年にはカンヌ国際映画祭に出品された映画『誰も知らない』に出演。
その後『歩いても歩いても』『ボーイズオンザラン』など多くの作品で活躍。
現在ドラマ『魔法のリノベ』(毎週月曜22時~/フジテレビ系)に出演中
https://www.circleline.co.jp/talent/you.html
アン ミカの好奇心「上に行くためより、穏やかに生きるために」
私たちを惹きつける特別な魅力を持つひとは、誰にも負けない“個性”という輝きを放っています。
各界で活躍し続けている彼女や彼に、“自分らしく”を大切にする生き方についてインタビュー。
そのオリジナルなスタイルの秘密を探ります。
アン ミカさんの生き方、自分らしさを探るインタビューの最終回。
今、自分自身を高めるために心がけていること、実践されていることをお伺いします。

シャツワンピース、パンツ/ともににDRAWELL(ドロウェル/ドゥーブルー)
ジュエリー/すべてオート ジュエラー・アキオ モリ
タンクトップ/スタイリスト私物
学ぶ時間がない、というのは自分に言い訳をしている状態
インタビューvol.1では、自分自身を知るため試行錯誤した半生、vol.2では、自分を愛し肯定できるようになるまでを伺いました。遠まわりしても、一歩一歩前に進むことの大切さを知っているアン ミカさんだからこそ、メディアを通して発信されているポジティブな言葉に強い説得力を感じます。
― アン ミカさんは20もの資格をお持ちですが、なぜこんなにたくさんの資格を取得されたのでしょう?
「家を出て独立するときに、父と『必ず資格を取ること』を約束しました。父からしてみれば、子供の将来を案じてのことだったと思います。それだけでなく、私は学ぶこと自体が楽しくて好きなんです。現在も毎年1つずつ、何かしらの資格を取ることを目指しています。今年は漢方のお茶の上級コースの受講が途中で止まってしまっているので、早く極めたいなと思っています」
― 学ぶことへの好奇心は、途絶えることがないですね!
「学ぶ時間がないーーというのは、自分に言い訳をしている状態だと思うんです。『仕事が忙しい』といっても、移動時間中などに何かできるのではないでしょうか。今、私はバラエティのクイズ番組に出させていただいていますので、クイズのための勉強も毎日の隙間時間にしています。1日3つ、必ず難読漢字を覚えるようにしているんですよ。眠くても疲れていても3つなら頭に入りますから」
>>【変わりたいあなたへ】自分を変えることは難しい?変われる方法や習慣

― 他にもご自分を高めるためにされていることはありますか?
「本来の私は、とてもガサツな人間なんです(笑)。でも、そんな自分をわかっているからこそ、できるだけ人前では所作はキレイに、言葉は丁寧に、を意識しています。
例えば撮影では、指先まで神経を行きわたらせること。お食事のときもお箸の使い方、置き方を常に丁寧に。文字を書くときも美しく・・・と、日々小さな継続を心がけています。
私自身、誰かと一緒にいて、そのひとの美しい所作や美しい文字を見たときに、いいものに触れさせてもらった・・・という感動が生まれます。だから私もそばにいるひとに、心地よさを感じてもらえるような言葉、所作を大事にしたいと思っています。
他には、アートに触れて五感を整えることも私にとって大事なことです。時間を見つけて美術館へ足を運ぶようにしていますし、音楽を聴くことで発想転換したり、意識改革にもアートが役立ってくれます。
特に、ヘアメイクをしている時間にオペラやクラシックを聴くと、とても気分が高まりますね。音楽は言霊ですから、そのときに聴きたいと選んだ音楽で、自分自身の心の状態を知ることもできるんです。
美しいものに触れるという意味では、『アニマルプラネット』のような、地球をテーマにした美しい映像を観るのも好き。私たちが取り組むべきことも見えてきますよね」

穏やかに過ごすために、自分を高める
― 地球のために取り組むべきこと、という言葉がありました。アンミカさんの、日常生活でのエシカルアクションを教えてください。
「小さなことですが、自宅で出る生ごみはコンポストで堆肥にしています。私は夜遅い時間に帰宅したときはいつも、野菜をたくさん入れた薄味のお味噌汁を作って食べているんです。そのときに出る野菜のヘタの部分なども、煮込んで出汁をとるベジブロスにして、最後はコンポストに入れます。生ごみが分解されていく様子を見ていると、地球は巡っているんだなと実感できますよね。
そうやってできた堆肥、土から植物が生まれ、そして植物は私たちが吐いた息を酸素に変えてくれて、植物のからだ、茎に流れている液体はアロマに、葉っぱは手当てに使えたり、食べられるものは野菜になり、その根っこは私たちの体を温めてくれる。さらに乾燥したら漢方になるんですよ! 植物のアロマを体にまとっていると、その香りに包まれていることが、心や体の手当てになります。植物って最強ですよね、私たちにたくさんのものを与えてくれるんですから」
ー 植物の“手当て”! 確かに、いろいろなシーンで私たちは植物の恩恵にあずかっていますね。
「私はあまり時間の使い方が上手ではなく、仕事で一杯いっぱいになってしまうことがよくあります。なので、きちんと体と心の手当てをして、睡眠も計画的にとらないといけないなと感じています。
“頑張りすぎている”状態には気を付けないといけません。自分が満ち足りていないと、家族にも周りの人にも優しくする余裕が生まれづらくなりますから。“自分を高める”ということは、必死になって上を目指すためだけにすることではありません。穏やかに過ごすために、植物やアートの力を借りて自分を高めていけたらいいですよね」

― いま、何か新しく始めたいことはありますか?
「新しい挑戦ではないのですが、ずっと勉強している語学をさらに極めたいなと思います。夫はアメリカ人ですが日本語が上手なので、普段の会話は日本語になってしまいます。英語も上達したいですし、また以前に韓国に語学留学をしましたが、韓国語もまだまだ学ばないと! 世界の人とつながって、自分の気持ちをしっかりと伝えるために、やはり語学は大切ですね。まずは英語と韓国語を完璧にしたいです」
― 漢方も漢字も勉強されているなかで、さらに語学も磨きたいーーやりたいことを明確にリストアップされているんですね。
「そうですね。でも頑張りすぎずに楽しんでいきたいです。近年、日本において頑張りすぎてしまうひとが多いですよね。でも、誰かと比較して『自分はできてない』なんて思う必要はありません。自分のペースで、ゆっくり高めていければいいと思います。
もし、それでも人と自分を比べてしまうようなら、いい方法がありますよ。
“すごい! いいなぁ”と誰かに対して思ったらすぐに『素敵ですね!』と、相手に口に出して伝えること。そうすれば相手もうれしい気持ちになって、『あなたも素敵ですよ!』と褒め返してくれるかもしれません。
相手の魅力を認めてしまえば、劣等感や嫉妬を感じることも無くなります。インスタグラムでキラキラしている投稿を見付けたら、あえて『いいね』を押しまくってコメントしましょう。素敵ってことを認める。そして自分のことも受け入れる。そうすれば、もっと生きやすくなりますよ」
充実した日々のなかにいながら、“学ぶこと”に向き合い、自分を高めることに積極的なアンミカさん。いい意味でストイックでありながら、自分にも周りにも優しい彼女の姿は、何のために「自分を高める」のかと迷える私たちの道しるべ的存在です。自分のペースで、強く、穏やかに。幸せに近づくコツを、胸に刻んでおきましょう。
>>メンタルヘルスを向上させるセルフケア方法。自分と向き合う時間を増やそう
Profile
アン ミカ
1993年にパリコレ初参加後、モデル業以外でも、テレビ、ラジオ、ドラマや映画、時には歌手として、さまざまな表現分野で活躍。
野菜ソムリエ、漢方養生指導士中級、ベジフルビューティーアドバイザー、NARDアロマアドバイザー、化粧品検定一級、ジュエリーコーディネーター3級など20の資格を活かし、服やコスメ、ジュエリーなど商品プロデュースを展開。
ポジティブな考え方、幸せな生き方を提唱する講演会も人気で、幸せに関する本も多数出版。
今年も自身プロデュース『アンミカのポジティブ手帳2023』を9/29に発売予定。
さらに、9月には自身初舞台出演ミュージカル「シンデレラストーリー」も控えている。
http://tencarat-plume.jp/
Instagram @ahnmikaofficial
SHOP LIST
オート ジュエラー・アキオ モリ 03-3573-2516
ドゥーブルー (ドロウェル) 03-3793-2395
アン ミカの哲学「自分を愛することは、幸せになる第一歩」
私たちを惹きつける特別な魅力を持つひとは、誰にも負けない“個性”という輝きを放っています。各界で活躍し続けている彼女や彼に、“自分らしく”を大切にする生き方についてインタビュー。そのオリジナルなスタイルの秘密を探ります。前回のインタビューでは、アン ミカさんの幼少期からモデルになるまでの激動の日々を語っていただきました。今回は、コンプレックスだらけだった自分をどうやって愛し、認められるようになったのか、じっくりとを伺います。
アン ミカという個性「“自分”を知らないと、生き残れない」
私たちを惹きつける特別な魅力を持つひとは、誰にも負けない“個性”という輝きを放っています。各界で活躍し続けている彼女や彼に、“自分らしく”を大切にする生き方についてインタビュー。そのオリジナルなスタイルの秘密を探ります。ここから3回にわたり、モデル、タレント、さらにデザイナーとしても活躍中のアン ミカさんをフィーチャーします。
水川あさみさんと考える、ワクワクする未来【対談 / 森カンナと未来人vol.3】
社会を広く見渡すユニークな視点をもち、連載エッセイ『ごきげんなさい』でもそのオリジナルな感性を披露している森カンナさん。彼女が「未来人=時代の先を走るリーダー」を招いて、気になるテーマについて語り合います。ゲストはプライベートでも親交のある俳優 水川あさみさん。vol.1では食について、vol.2ではファッションや暮らしについて語り合い、今回vol.3では働き方や理想の世界にまで二人の会話は広がっていきました。
水川あさみさんに聞きたかった、あれこれを質問!【対談 / 森カンナと未来人vol.2】
社会を広く見渡すユニークな視点をもち、連載エッセイ『ごきげんなさい』でもそのオリジナルな感性を披露している森カンナさん。彼女が「未来人=時代の先を走るリーダー」を招いて、気になるテーマについて語り合います。ゲストはプライベートでも親交のある俳優 水川あさみさん。食について語り合ったvol.1に続き、vol.2は心地よいと感じるファッションについて、また心を整える暮らしぶりについてトークします。
水川あさみさんと「からだ」について語り合う!【対談 / 森カンナと未来人vol.1】
社会を広く見渡すユニークな視点をもち、連載エッセイ『ごきげんなさい』でもそのオリジナルな感性を披露している森カンナさん。彼女が「未来人=時代の先を走るリーダー」を招いて、あれこれと気になるテーマについて本音で語り合う新連載がスタート! 初回のゲストは、プライベートでも親交のある、俳優の水川あさみさんです。
松本まりかの循環「心もからだも、巡らせることが大切」
松本まりかさんの生き方、自分らしさを探るH_Styleインタビュー。vol.1では仕事への情熱、vol.2では旅や恋愛観などプライベートについて伺いました。最終回は、心を整えるためにやっていること、からだを美しく保つために気を付けていること、そして素の自分との向き合い方について語っていただきます。
松本まりかの進化「旅はいつも私を成長させてくれる」
前回のインタビューvol.1では、長い下積み期間を経て、ブレイク後の激務の日々までをたっぷりと語ってくれた松本まりかさん。引き続きvol.2では、ようやく実現したお休み期間のこと、さらに恋愛観、結婚観に至るまで、彼女のプライベートに迫ります。
松本まりかの情熱「自分の“好き”を信じ続けるということ」
私たちを惹きつける特別な魅力を持つひとは、誰にも負けない“個性”という輝きを放っています。各界で活躍し続けている彼女や彼に、“自分らしく”を大切にする生き方についてインタビュー。そのオリジナルなスタイルの秘密を探ります。ここから3回にわたり、今、唯一無二の存在感に注目が集まる俳優 松本まりかさんをフィーチャーします。
山田優の未来「垣根を越えた、その先を見つめたい」
山田優さんの生き方、自分らしさを探るH_Styleインタビューの最終回。vol.1では自分のスタイルについて、vol.2では愛について語っていただきました。今回はボディとメンタルのケアについて、また食事のこだわりや未来のファッションについて、たっぷりと伺います。
山田優の愛情「愛を注ぐほど、人は強くなるから」
2022年に結婚10周年を迎え、オンオフともに充実した日々を送る山田優さん。前回のインタビューvol.1に続き、vol.2ではあらためて家族のこと、夫婦のこと、そして今、一人の女性として描いている夢について伺います。
山田優の決断「自分の足で歩くということ」
私たちを惹きつける特別な魅力を持つひとは、誰にも負けない“個性”という輝きを放っています。各界で活躍し続けている彼女や彼に、“自分らしく”を大切にする生き方についてインタビュー。そのオリジナルなスタイルの秘密を探ります。ここから3回にわたり、モデルとして絶大な人気を誇る、山田優さんをフィーチャー。
布袋寅泰に聞くNOW&NEXT「今も10代のころのように、夢を追いかけている」
私たちを惹きつける特別な魅力を持つひとは、誰にも真似できない“個性”という輝きを放っています。各界で活躍し続けている彼女や彼に、“自分らしく”にこだわりを持つ生き方についてインタビュー。そのオリジナルなスタイルの秘密を探ります。ここから2回にわたりH_styleを語っていただくゲストは、2月1日に通算20枚目のアルバムをリリースしたギタリストの布袋寅泰さんです。
ホラン千秋のヘルシー思考「心をマイナスにしない努力」
ホラン千秋さんの生き方、自分らしさを探るH_Styleインタビューの最終回。忙しい毎日を過ごすうえで、心身ともに元気をキープするためのセルフケアについて伺いました。

トップス¥18,500、スカート¥18,500/コントワー・デ・コトニエ(コントワー・デ・コトニエ ジャパン)
「必要以上にネガティブにならないように」
Hummingのインタビューvol.1ではホランさんの自分らしい生き方について、そしてvol.2では仕事スタイルについて話していただきましたが、その的確な表現力と聡明な言葉選びに聞き惚れてしまいました。
ー きっとプライベートでもテキパキとアクティブに行動されているに違いないと、ポジティブに頑張る姿を想像してしまいますが、「できればソファでゴロゴロとしていたいタイプ」というから意外なギャップです。
「“ポジティブなひと”というイメージを持たれやすいのですが、かなりネガティブです(笑)。基本、最悪の選択肢から考えるタイプ。裏を返せばリスク管理がしっかりしているといえるのかもしれませんが、つい後ろ向きに考えがちなので、必要以上にネガティブにならないようにしています。心が荒まないよう、マイナスをゼロに戻す作業というか・・・」
― 具体的には、それはどんな作業なのでしょうか?
「心を変えようとするのは難しいので、体を動かします。昨日までは、この世の終わりくらいに思えていたことも、運動した後は『なんとかなる!』と前向きになれたりするものです。
正直、運動は苦手なのですが、食べることが大好きなので、体型維持を兼ねて運動をするという選択をしました。食べる量を減らすこともできるけれど、パワーもなくなるし、肌や髪のハリつやも失われてしまいます。健康的な体をつくるためにも、しっかりと食べて体を動かす方がいい。過度な食事制限をして“これしか食べられないのか”・・・とマイナスな気持ちになるのか、苦手でも運動を取り入れて“頑張っているじゃん自分”とプラスに思うのか。結果、同じ体重だったとしても、とらえ方は180度違うと思います」

― 苦手な運動をすることでポジティブなマインドを手に入れるというのは、なかなか高度なテクニックのような・・・。
「そうですよね(笑)。ジムに行かなくて済むのであれば、怠け者の私としてはうれしいですけど。だから到着する5秒前まで帰りたいと思っています。でも、運動したあとの“頑張ったな”感とか、汗を流す爽快感、翌日の筋肉痛もけっこう楽しかったりして。それに、1時間前の自分よりも確実に磨かれているし、健康的になっている。そのちょっとした達成感で、ポジティブになれる。運動ってすごいなって思います」
―「1時間前よりも磨かれた自分」。この考え方、素敵ですね。
「時間は巻き戻せないので、年齢でみたら今よりも若くはなれないわけですよね。スキンケアにしてもそうですが、今の状態を維持するためのケアは大変だなと思うこともあるけれど、今日より若くはなれないから“今やらないと!”と(笑)。疲れていてもケアは怠らないようにしています。どんな大富豪でも“時間”をお金で買うことはできません。そう思うと、時間は有効活用しないともったいないですよね!」
ホラン千秋の仕事スタイル「期待に応えたいからこそ、できないことに目を向けたい」
『Nスタ』のキャスターを務めてもうすぐ丸5年。夕方の顔として活躍するだけでなく、音楽番組やバラエティ番組にも出演し、老若男女のファンをつかんでいるホラン千秋さん。前回のインタビューvol.1に続き、vol.2では多彩な顔を持つ彼女の仕事スタイルについて伺います。
ホラン千秋が実践する、自分に嘘をつかない生き方
私たちを惹きつける特別な魅力を持つひとは、誰にも負けない“個性”という輝きを放っています。各界で活躍し続けている彼女や彼に、“自分らしく”を大切にする生き方についてインタビュー。そのオリジナルなスタイルの秘密を探ります。ここから3回にわたり、キャスターとして活躍するホラン千秋さんをフィーチャー。
佐田真由美が実践している、心を解放する方法とは?
自分にとって心地よいものに囲まれた暮らしは、心や体に安らぎをもたらします。年齢を重ねますます輝くモデルの佐田真由美さんに、心穏やかな日常を過ごし、豊かで幸せな人生を“持続的”に送るためのヒントを伺いました。

充実した睡眠が“幸せオーラ”の秘密
―プライベートでは2児の母でもある佐田さん。どのように仕事と家庭・育児を両立されていますか?
「仕事と育児のバランスを取るのはなかなか難しいです。仕事場から急ぎ足で帰宅して、ご飯を用意して・・・本当に毎日が嵐のよう(笑)。子供たちが成長するごとに悩みは変わるし、尽きないですね。ディレクターを務めるジュエリーブランド『エナソルーナ』も子育てしているような感覚。ここまでやればOKというゴールはないですし、上手くいくときもいかないときもあるけれど、私にとってとてもかけがえのない存在ですから」
人生を支えるお守りのように。
佐田真由美がジュエリーに込める想い
モデルの佐田真由美さんが手掛けるジュエリーブランド「エナソルーナ(enasoluna)」は、2021年11月11日にブランド設立15周年に迎えました。商品デザインはもちろん、店頭に立って接客したり、カタログの撮影など、総合的に関わっている佐田さん。15年という歳月のなかで感じたこと、そしてリブランディングを行い、新たに始めるサステナブルな取り組みについてお話を伺いました。
佐田真由美が語る、
逆境にめげずに前進する力
私たちを惹きつける特別な魅力を持つひとは、誰にも真似できない“個性”という輝きを放っています。各界で活躍し続けている彼女や彼に、“自分らしく”にこだわりを持つ生き方についてインタビュー。そのオリジナルなスタイルの秘密を探ります。H_styleを語っていただくゲストは、モデル、ジュエリーブランド「エナソルーナ(enasoluna)」のトータルディレクターとして活躍する佐田真由美さんです。
そこに“LOVE”がある。レスリー・キーの写真が心を動かす秘密
世界的に活躍する写真家 レスリー・キーさんをフィーチャーするインタビュー第2回は、彼が取り組むSDGsプロジェクトについて。写真で誰かの人生を少しでも生きやすくすることができればーーそんな願いと愛が込められた活動を伺います。
「写真には人生を変える力がある」

11月某日、朝から羽田空港の「HANEDA ダイバーシティ&インクルージョン」のオープニングイベントへ、午後からはBMW主催の「FEEL THE iX / iX3 @SHIBUYA」のイベントステージに2回登壇して制作したアートポスターについて語り、その合間を縫って銀座のGapへ。ここでは、Gapとレスリーさんがコラボしたダイバーシティプロジェクト「This is Me ~Rainbow~」の展示が始まっていました。彼が手掛けたプロジェクトが続々と拡散された一日。でもレスリーさんが抱えるプロジェクトは、これだけではありません。
枠にとらわれず
「香里奈」としてのアクションを
雑誌『GINGER』で約3年にわたり、SDGsのゴールにつながるようなトピックスを連載している香里奈さん。回を重ねるごとに学びが増え、理解が深まるなかで、気付いた&感じたこととは。その想いを伺いました。
あふれる情熱と夢。レスリー・キーの写真に“未来”を感じる理由
私たちを惹きつける特別な魅力を持つひとは、誰にも真似できない“個性”という輝きを放っています。各界で活躍し続けている彼女や彼に、“自分らしく”にこだわりを持つ生き方についてインタビュー。そのオリジナルなスタイルの秘密を探ります。
ここから2回にわたり、グローバルに活躍する写真家 レスリー・キーさんをフィーチャー。シンガポールから日本にやってきて今年で30年。「撮りたい!」と思った人物、テーマをひたすら追い続け、次々と夢を実現するレスリーさんに、その情熱の源をお伺いしました。
「私たちクリエイターが行動しないと」

世界中のセレブリティのポートレートからファッション広告までを手掛ける写真家として活躍する一方で、自身で企画制作する写真集の売り上げを寄付したり、チャリティイベントを主催するなど、長年にわたり社会貢献活動を続けてきたレスリーさん。現在も羽田空港やGAPの店舗、赤坂サカスなどで彼の作品が展示中です。
香里奈が語る“今”。
「一瞬一瞬を大切にして生きていく」
私たちを惹きつける特別な魅力を持つひとは、誰にも真似できない“個性”という輝きを放っています。各界で活躍し続けている彼女や彼に、“自分らしく”にこだわりを持つ生き方についてインタビュー。そのオリジナルなスタイルの秘密を探ります。H_styleを語っていただく最初のゲストは、モデル、女優として活躍する香里奈さんです。




