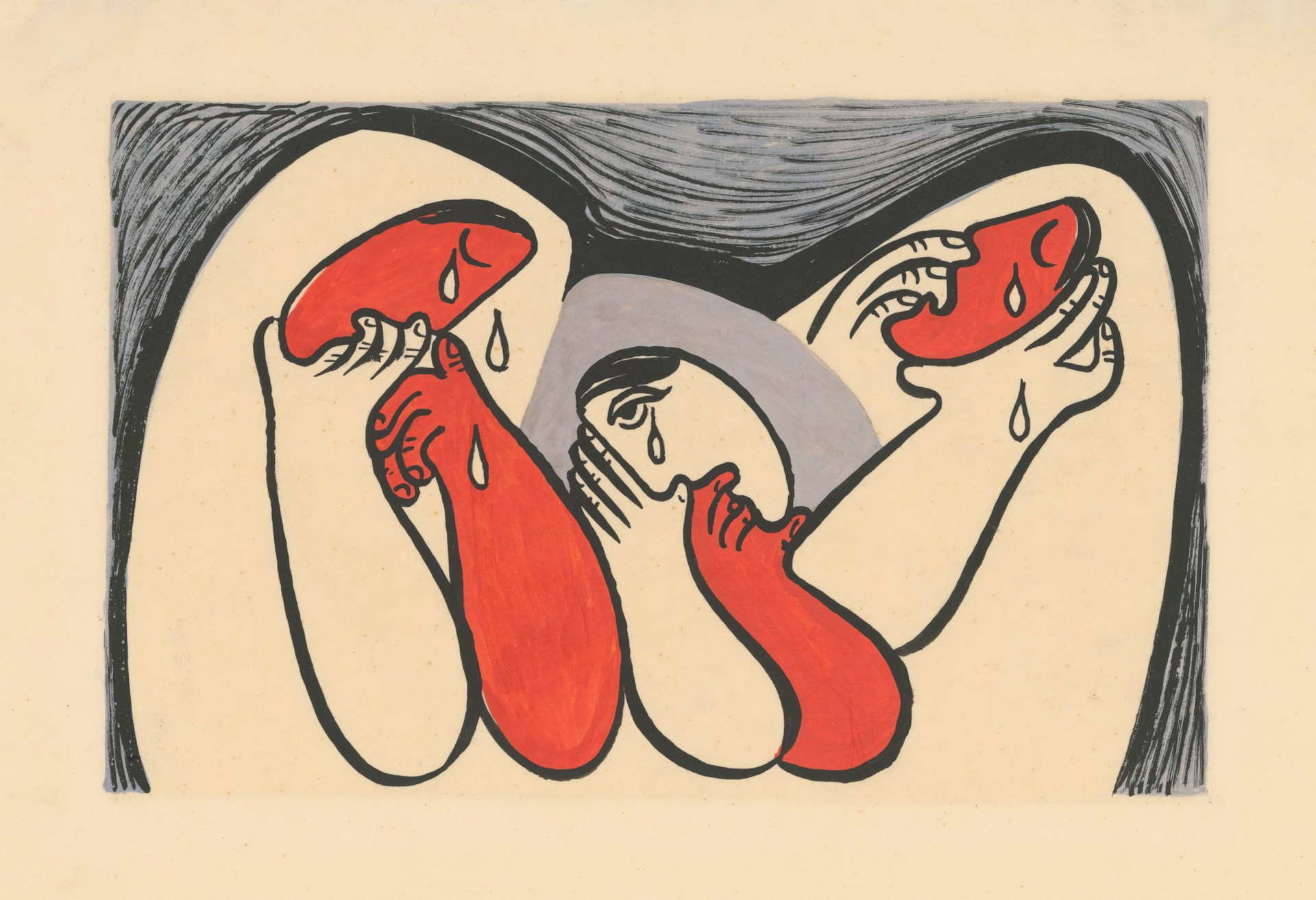私たちにとって、子ども時代の思い出は泥まみれの公園や、友だちとの顔を合わせたおしゃべりではないでしょうか。でも、今やスマートフォンは子どもたちの生活に欠かせない存在となり、その光と影に心を痛めている親も多いはず。
「うちの子はまだだけど、いつまで持たせないでいられるかしら…」
そんなふうに感じていたイギリスの二人の母親のささやかな会話から始まったのが、「スマホのない子ども時代(Smartphone Free Childhood)(以下SFC)」という草の根ムーブメントです。
この活動は、たった一年で数万世帯の家族が参加する全国的なキャンペーンへと爆発的に広がり、学校のルールを変えました。
彼らのメッセージはシンプルで力強いもの。
「子ども時代というのは、スマートフォンに時間を費やすにはあまりにも短い」。
そして提案するのは、「14歳までスマホは持たせない、ソーシャルメディアは16歳まで」という指針です。これは、子どもをアルゴリズムの支配から解放し、子どもの時間を子どもたちの手に取り戻そうという、ポジティブな抵抗の物語。
この驚くべきムーブメントが、どうやって多くの親の心をつかみ、社会を変え始めているのか、今回はその全容をお伝えします。
Contents
親の不安が導火線となった、ムーブメントの誕生
SFCの共同創設者であるデイジーさんは、ジャーナリストとしての経験を持つ一人の母親です。彼女が抱いていたスマホに対する不安は、もう一人の母親との何気ない会話で一気に火が付きます。
「うちの子がスマホを欲しがったら、そろそろ買うわ」という友人の言葉に、デイジーさんは強い危機感を覚えました。「このままでは、友達に取り残されると恐れて、多くの子どもたちがスマホを持ち始めるという避けられない現実がある」と。
実際、イギリスでは12歳の子どもの89%が、そして驚くべきことに5歳から7歳の子どもの4分の1がすでにスマホを持っており、初めてスマホを持つ平均年齢はわずか9歳。これは、なんの管理も行き届かない状態で世界が子どもに向けて完全にオープンとなってしまうことを意味します。彼女は「今行動しなければ、手遅れになる」と強く感じ、それが彼女を突き動かす原動力となりました。
スマホがもたらす心の健康への影響
なぜ、これほどまでに親たちは不安を感じているのでしょうか?
デイジーさんたちが指摘するのは、スマホが子どもたちの心にもたらす深刻な影響です。
例えば、暴力的なものや性的なものなど有害なコンテンツに簡単にアクセスできてしまうこと。また、絶え間ない通知によって集中力が妨げられます。平均的なティーンエイジャーは一日に200件以上の通知を受け取り、勉強や趣味、現実の友人関係に集中することが難しくなっています。他にも、テクノロジー企業は、ユーザーを画面に釘付けにすることで利益を得るために設計されたアルゴリズムの罠や、オンラインでのいじめや、見知らぬ大人によるグルーミング(誘い込み)などの報告も後を絶ちません。
その結果、スマホが普及した2010年頃から、ティーンエイジャーの不安やうつ病の発生率が急増していることが、様々な研究者によって指摘されています。

瞬く間に全国へ広がるムーブメント
デイジーさんは、まず友人のクレアさんとともに、同じ不安を抱える親たちが団結するためのワッツアップ(通話アプリ)でグループを作りました。最初はたった3人から始まったこのグループですが、ある晩、彼女がインスタグラムに短い投稿をしたことをきっかけに、まさかの展開を迎えます。
翌朝、彼女がスマホを見た時には、グループは多くの人達のコメントであふれていました。「まるで魔法のように恐ろしい竜巻が、私たちのキッチンにやってきたような気分だった」と当時を振り返るデイジーさん。
彼女たちは、政府の指針もない中で、「地球上で最も強力で説得力のある企業」に向き合い、「私たちは一人じゃない」と感じたい親たちの切実なニーズにまさに火をつけたのです。
親たちの「行動」が社会を変える
この爆発的なエネルギーを目の当たりにし、デイジーさんたちはブランディング会社での仕事やジャーナリストの職を辞め、SFCを現実の組織として立ち上げることを決めました。
ムーブメントの中心にあるのは、「親の約束」と呼ばれる誓約です。これは、「14歳までスマホなし、16歳までソーシャルメディアなし」という姿勢を守り、学校にも同じ方針を奨励してもらうために、親たちが署名するものです。発足からわずか一年ほどで、南極大陸を除くすべての大陸の14万世帯以上の家族がこれに署名しています。
学校にも広がる変化
SFCは、イギリスの地元の学校とも連携して、具体的な変化を生み出しています。
ある学校の校長は、スマホがもたらす問題を目の当たりにし、低学年の生徒を対象に、登校時にスマホを預ける自主的な預け入れ制度を導入しました。その結果、食堂はスマホをいじる生徒でなく、友だちとおしゃべりや笑いを楽しむ、素敵な雰囲気に変わったといいます。
この成功に手応えを感じた学校は、この預け入れ制度を学年ごとに義務化し、最終的には全校に広げる予定です。さらに、この校長はSFCの支援を受けながら、地域の80校中68校を巻き込み、同様の取り組みを推し進めています。

目的は「禁止」ではなく「バランス」
SFCの関係者は皆、自分たちが「アンチ・テクノロジー」や「スマホ反対派」ではないことを強調しています。
「私たちは『スマホを禁止したい親たち』という報道をされることが多いのですが、そんなことは一度も言っていません。テクノロジーは敵ではなく、私たちがそれをどう使うかが問題なのです」。
彼らの目的は、子どもたちがテクノロジーに依存するのではなく、自信を持って使いこなせるように育つことです。彼らは、デジタルスキルを段階的に構築し、子どもたちが常にデジタルとつながっている状態になる前に、「子どもでいられる時間」を多く与えることを信条としています。
実際、SFCはスマホメーカーとも協力し、SNSへのアクセスは遮断しつつ、必須の情報にはアクセスできる「子どもに優しいデバイス」の開発も進めています。
この草の根の力強いムーブメントは、私たち親が抱える静かな不安が、どれだけ大きくポジティブな社会変革のエネルギーになり得るかを示しています。大切なのは、「私たちは一人ではない」と知り、「子ども時代を子どもたちの手に取り戻す」という明確な意志を持つことではないでしょうか。
このムーブメントを見て、ご自身の子育てにおけるスマホとの付き合い方について、改めて問いかけてみませんか?

ライター:プロフィール

著者:堀江知子(ほりえともこ)|香港在住ライター
民放キー局にて、15年以上にわたりアメリカ文化や社会問題についての取材を行ってきた。
2025年からは香港に移住しフリーランスとして活動している。noteやTwitterのSNSや日本メディアを通じて、アフリカの情報や見解を独自の視点から発信中。
出版書籍:『40代からの人生が楽しくなる タンザニアのすごい思考法 Kindle版』。
Xアカウントはこちら