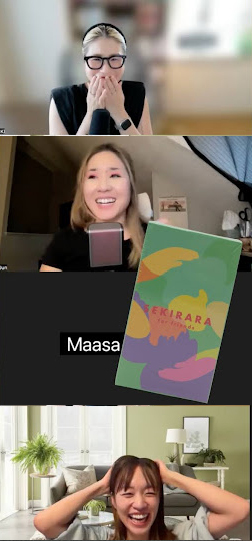仕事から帰宅した夜。
「疲れたからちょっと休憩」と、なんとなくスマホを手に取ってSNSを開く。
気がつくと3時間、4時間があっという間に過ぎている。そんな経験、ありませんか?
私はよく、このパターンをやってしまいます。
寝る前の時間や、予定のない休日の昼間にも、平気で数時間溶かしてしまう。
しかも、たいていその後に待っているのは、強烈な自己嫌悪です。やらなければいけない家事も、翌日の仕事への準備も、全く手につかなくなってしまいます。
ところが、同じように「ゆっくり過ごす」時間でも、全く違う結果をもたらすこともあります。
“同じ「ゆっくり過ごす」でも、SNSで時間を溶かすのは自己嫌悪を招く一方、気ままな散歩や寄り道は心を満たし翌日への活力につながることに気づいた体験でした。”
ある時、やるべきことがいろいろ山積みだったにもかかわらず、なんだかどうしようもなく外に出たい気持ちが湧いてきた日がありました。
もういいや!と、すべてを翌日に後回しにして、身支度もそこそこに適当な服を着て、あてもなく散歩に出かけてみたんです。
買う予定もないけど家具屋さんを目指して、その道中もまっすぐ行くわけではなく好きなように寄り道しながら歩き、帰りはたまたま見つけたコーヒーショップに入ったりして、とにかく好きにのんびり過ごす。
しかもそのコーヒーショップで初めて見るケーキに出会って、それがまぁとても美味しくて。それ以降もちょこちょこ買いに行くほど、すっかりお気に入りになりました。
でも何より大きかったのは、その日の帰宅後の気持ちの変化です。
なんて良い一日だったんだろうと心はとても満たされ、後回しにしたことも明日しっかり頑張ろうと前向きな気持ちが自然に湧いてきたんです。
でも別に、SNSをスクロールする時間だって、同じように「ゆっくり過ごした」はずなのに、むしろそっちのほうが体力も使わないし、なぜこんなにも「その後の気持ち」が違ったのでしょうか。
おすすめ記事 ▶ 些細なことにイライラ…HSP気質な私のストレス攻略法
「ただの甘やかし」と「本当のご自愛」の境界線

本当の意味で自分を労われたとき、気分はすぐに前向きになって、なんだか温かい気持ちがしてエネルギーも湧いてくる。
一方、自分を「ただ甘やかしてしまった」ときは、何時間経っても心のモヤモヤは晴れず、むしろ自己嫌悪で状況が悪化することもある。
振り返ってみると、先ほどの例に限らず、どちらのパターンも何度も経験したことがある話です。
でも自分としては、いずれの場合も「何も考えず好きに過ごすことで自分を労わっている」つもりなのに、かたや前向きな気持ちをもたらし、かたや自己嫌悪を誘発する。
なんとも不思議な話です。
で、私なりに考えてみて少し気づいたことがあります。
それは、よくあるSNSはエネルギーを削ぐといったような話ではなく、それ以前に、自分の状態を正確に見極められているかどうかによるのではないかと。
例えば、漠然と気分が落ちていると感じただけで、「なんかもうキャパオーバーなんだろうな」と判断してしまうことがあります。
でも実は、たまたまやるべきことや予定が一気に押し寄せて圧倒されているだけで、本当はまだ余力があるのかもしれない。
そうした考察もしないまま、すぐに「もう無理だ…」と結論づけてしまうから、本当に気分も体もどんどん重くなって、ご自愛タイムが必要なんだと思い込んでしまう。
ちゃんと自分の状態や本当の欲求を見極めないまま、なんとなく「疲れたから休もう」と判断してしまうと、SNSのような手軽な逃げ道に頼ってしまいがちです。
SNSなら、受動的でいても、特に何も考えなくても、時間を消費できるから。
で、こうなるパターンは「甘え」であり、「逃げ」なのではないかと思います。
例としてSNSを挙げましたが、無思考でとりあえず「ご自愛っぽい」ことをするなら、他のことでも同じ結果だと思います。
なんとなく溜まっていたドラマを見ても、積読のままになっていた本を読むことで自分時間を取った気になっても、それが本当にその時自分に必要なご自愛でなければ、さほど満足感は得られないと思います。
“本当のご自愛は自分の状態や欲求を正しく見極めたときに前向きなエネルギーを生む一方、思考停止で選んだ「ご自愛っぽい」行動は甘えや逃げとなり、自己嫌悪を招いてしまうのだと気づいた話です。”
一方、一呼吸置いて自分の状況を冷静に見つめられたら。
「最近、あの仕事結構重かったもんな」
「プライベートもバタバタしてて、ずっと張り詰めてたんだよな」
「私のキャパからしたら結構限界まできてるよな」
そう自分の中で納得できたら、次は自然と「じゃあ今どんな癒しが自分に必要なんだろうか」という思考が浮かんできます。
そうやって、自分の状態を正確に把握するからこそ、適切な対処法が分かって、結果として本当のセルフ・コンパッションになるのではないかと、最近思うのです。
実際、冒頭の散歩に出かけた日は、いろいろ頑張りすぎていたことを自覚していたし、だからこそ、ここでもうひと踏ん張りするより「外に出たい」という自分の欲求に、素直に従うほうが大事だと気づけたんだと思います。
私なりのご自愛タイムには他にも、映画やドラマを見たり、本やゲームに没頭したり、旅行を計画したり、いろんな選択肢がありますが、それぞれやっぱり適切なタイミングがある気がします。
「外に出たい」と思った日に、「もう遅い時間だから」などと理由をつけて、ドラマの一気見でお茶を濁そうとしても、そんなに満たされない。
本当の意味で自分に優しくするということは、今の自分がどういう状態で、何を欲しているのか、ちゃんと理解することなんだと思います。
つまり、良いご自愛と、そうでないご自愛、両者の違いの根本にあるのは「過程」。
どちらも同じ「好きに過ごす時間」だけど、そこに至るまでの経緯、ちゃんと考えてそこに至ったかが、ご自愛の「結果」を大きく左右するのではないかと、最近ヒシヒシと感じるのです。
自分の状態を正しく見極める難しさ

とはいえ、自分の状態を正しく見極めるということ、自分の疲れや頑張りに気づいてあげるのは、思っている以上に難しくもあります。
他人には優しくできても、自分にはなかなか優しくできない理由も、一つはここにある気がします。
だって、実は他人に優しくすることって、意外と簡単じゃないですか?
傍から見ていると、みんなすごく頑張っているように見えるから、「ギアを落としてもいいんじゃない?」と自然に思えます。
でも自分に対しては厳しくて「あの人に比べたらまだまだ」とか、「こないだ自分を甘やかしてしまったから、もっともっと頑張らないと」となる。
これって、完璧主義とか自分に厳しいという言葉で片づけられるものではなく、自分を適切に評価できていないからだと思うんです。
他人の状況は客観的に見ることができるのに、自分の状況となると主観が入りすぎて、「まだ頑張れるはず」という思い込みに囚われて、本当に必要な休息を取れなくなってしまう。
歩みを緩めることを許してあげられない。というか、怖い。
でも心の底では、もう休みたいという本音もある。
…はぁ、正しいセルフ・コンパッションって、ほんとーーーに難しい!!
ただ、逆にいえば、この評価さえきちんとできれば、意外とセルフ・コンパッションは簡単に実践できるものなのかもしれません。
だからこそ、最近は「自分のやったこと」を正しく把握することに重きを置いています。
私が実践していて効果を感じているのは、定期的に自分の状況を書き出して、客観的に見つめることです。
“気持ちが淀んだときは書き出して自分の状態を正しく見極め、その状況に合った対応を取ることで安心感が生まれ、自然と前向きな気持ちに切り替わるのだと気づいた話です。”
漠然と気持ちが淀んでいるように感じたときこそ、一旦立ち止まって自分の状況や気持ちを一つひとつ紐解いてみる。
最近どのくらい忙しかったか、何で忙しかったのか、それは客観的に見ても膨大な仕事量だったのか、もしくは気疲れしていただけなのか、単に予定が重なってキャパオーバーだったのか。
頭の中で考えてもいいのですが、文字にした方が冷静になれるので、とにかく書き殴るのがおすすめです。
ぶわーっと現状を書き出していくと「いや、たしかに最近めっちゃ頑張ってたわ」とか「あれは結構ハードワークだったのでは?」と思えたり、
逆に「いや、そうでもないな。何をすべきか分かってなくて不安なだけだ」とか「整理したらもう少し頑張れるかも」と、冷静に見えてくることもあります。
前者の場合なら、今の自分に必要な癒しは何か自問自答し、それを実現する。
後者なら、どうやったらもうちょっと頑張れそうかを考え、それを実行する。
ただそれだけに、全集中する。
いずれの状況にせよ、それぞれ正しい対処法が取れたら、不思議と(後者の場合でも!)すぐに気持ちは復活するんですよね。
自分の状態を正しく把握して、それに応じた適切な対応を取れたという安心感が、前向きな気持ちを生み出してくれるのかもしれません。
セルフ・コンパッションは技術

Photo by Tijana Drndarski on Unsplash
自分に優しくするというのは、思っているほど簡単ではありません。
ただ自分を甘やかせばいいというわけでも、厳しくすればいいというわけでもない。自分の状態を正しく見極めて、そのときの自分に本当に必要なものは何かを判断する「一つの技術」なのだと思います。
頑張るときは頑張る、休むときは思いっきり自分を甘やかす。
そんなメリハリのある理想的な生活を実現する第一歩は、今の自分がどんな状態にあるのかを、できるだけ客観的に、そして優しい目で見つめることから始まるのかもしれません。

ライター:プロフィール

とにかく「言語化」することを軸に、
心や頭に浮かぶ漠然とした不安やモヤモヤも「言語化」