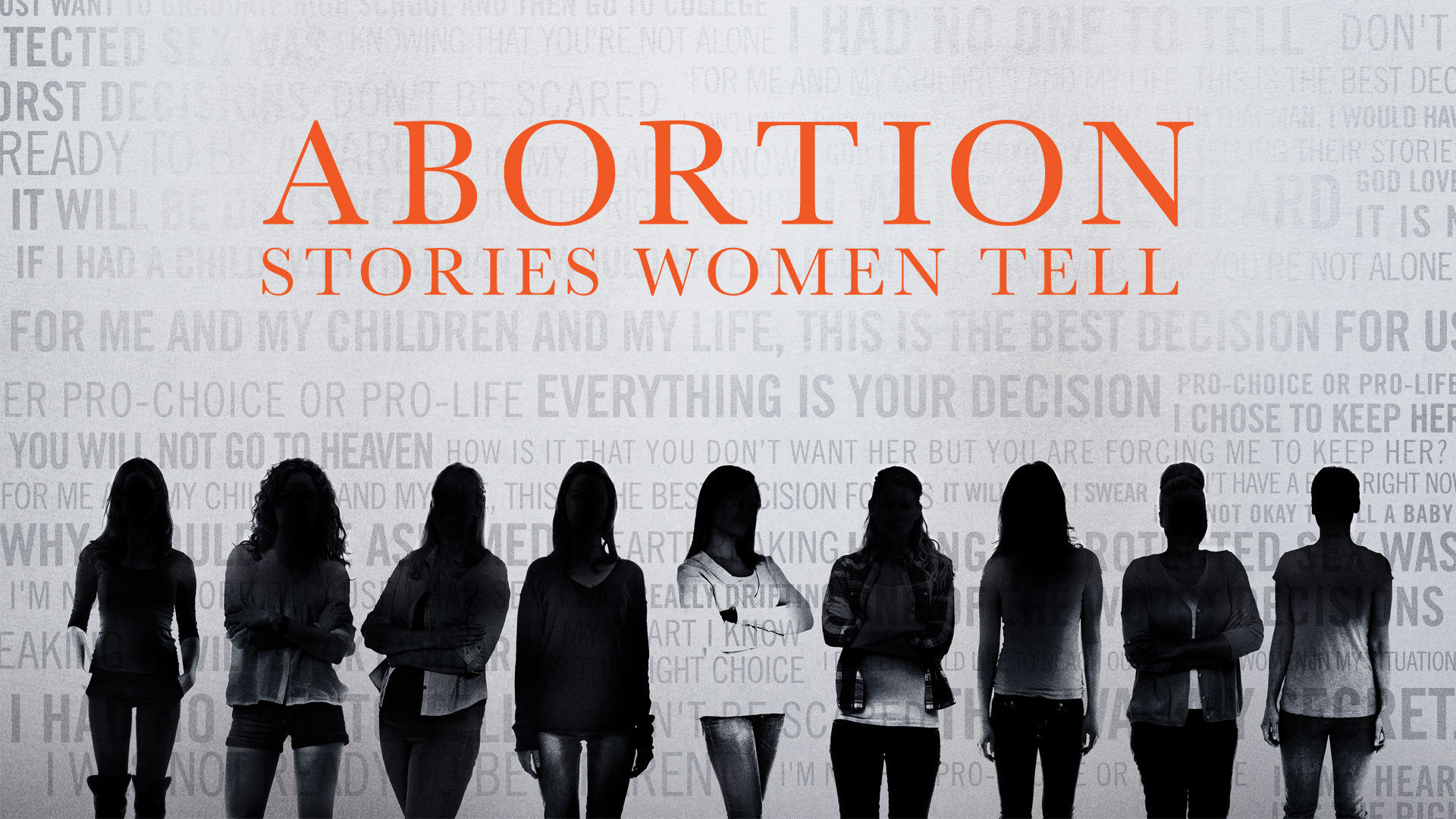Copyright: © 2012 The Weinstein Company. All Rights Reserved.
悲しみって、本当に不思議な感情ですよね。
最初は静かに寄り添っているのに、気づけば糸みたいにじわじわ広がって、体が動かなくなるくらい重くのしかかってくる。
『世界にひとつのプレイブック(Silver Linings Playbook)』は、そんな“喪失の悲しみ”をどう乗りこえていくかを描いた映画です。2012年に公開されて、話題にもなった作品だから、きっと観たことがある人も多いと思います。私もそのひとり。でも今回久しぶりに観て、前とはまったく違う視点で物語に入り込んでいました。
“『世界にひとつのプレイブック』を久しぶりに観て、登場人物たちの不安定さは“扱いづらさ”ではなく深い悲しみと孤独から来ていたのだと気づいた”
初めて観たときは、正直ほとんどのキャラクターが苦手でした。
みんな怒鳴ってるし、情緒不安定だし、責任逃れするし、ずっと不機嫌。ジェニファー・ローレンスとブラッドリー・クーパーの魅力がなかったら観るのをやめていたかもしれません。
でも今回は、少し立ち止まってみたんです。
声のトーンや仕草、表情のちょっとした揺れまで、ちゃんと観察してみた。
そして苛立つ代わりに、「なんでみんなこんなふうに振る舞うんだろう?」って、考えてみました。
すると気づいたんです。
彼らが“扱いづらい人たち”に見えるのは、ただ、深く傷ついているからなんですよね。
悲しみって、あまりにも痛みが鋭すぎて、世界から切り離されたみたいな孤独に陥ることがある。
そんな状態で“いつもの自分”なんて保てるわけがないんです。
結婚を取り戻したいのは、愛のためか、それとも心を守るためか
パットは、妻の浮気相手を殴りつけてしまい、精神科施設に送られます。しかもそのとき妻は、よりにもよって二人の“結婚式の曲”を流していたという…。暴力は絶対ダメだけど、正直パットに同情してしまう気持ちもわかります。
でも、パットは裏切られたのに「まだ結婚生活はとり戻せる」と思い込んでしまう。ニッキはまだ自分を愛している、自分が変われば何とかなる、と。
パットは双極性障害とアンガーマネージメントの問題を抱えていて、それはずっと胸の奥で静かにくすぶっていたものでした。

Copyright: © 2012 The Weinstein Company. All Rights Reserved.
彼の育った家も安定とは程遠くて、こだわりが強い父親と、なにかと張り合ってくる兄。感情的なケアなんて与えられず、心はずっと雑に扱われ続けてきたんです。だから心は少しずつひびが入り、最後には壊れてしまった。
だからパットが必死に結婚生活を取り戻そうとするのは、“愛”というよりも、トラウマから自分を守るため。
本当は結婚生活が終わっていると認めたくない。認めた瞬間、自分が失ったものの大きさに耐えられないから。
悲しみが深いと、現実を見るより“否定してしまうほうが楽”に感じるときがありますよね。
私たちは痛みに耐えるために、時々“別の現実”を心の中に作り上げてしまうんです。
“パットは裏切りの痛みと長年のトラウマから現実を直視できず、壊れた心を守るために「まだ結婚は修復できる」と思い込んで執着してしまっている”
そしてパットは、夫を亡くして自分なりの悲しみを抱えているティファニーと出会います。二人が最初に話した瞬間から、「あ、この二人は似た者同士だな」とわかるくらい相性がいい。パットがズバズバ物を言えば、ティファニーもすぐに言い返す。彼が彼女の夫について踏み込んだ質問をすれば、彼女は彼のフットボールのジャージをバカにする。
周りから見ればめちゃくちゃ気まずい会話。でも、二人にとってはすごく刺激的なんです。
ようやく“自分の強さに合わせて返してくれる相手”に出会えた感じ。
恥と偏見に覆われた“性”と“怒り”の裏側で、二人が見つけたほんとうのつながり
ティファニーは、孤独と悲しみをごまかすために、人の体温にしがみついてしまった。でも突然パートナーを失ったら、誰かの温もりを求めてしまうのは自然なことだと思う。
でも周りの人たちは、その奥にある痛みを見ようとしない。
パットの怒りは“怖いもの”として避けられ、ティファニーの性にオープンな態度は“都合よく扱えるもの”として見られる。
二人は“変な人”扱いされ、まるで人間じゃなく問題そのものみたいに扱われている。
パットとティファニーはお互いの弱さを理解し始めるけれど、パットはまだ“自分とティファニーの間に線を引きたい”と思ってしまう。
“ティファニーとパットは周囲から“問題のある人”と誤解され続ける中で、お互いの痛みと弱さを理解し合い、ダンスをきっかけに少しずつ心を取り戻していく”
ニッキを理由に距離を置こうとしたり、“ティファニーみたいな人とは…”と傷つくようなことを言ったり。
本当は彼が一番理解できるはずの彼女の痛みに。
人って、あんなにセックスが好きなのに、話題になると途端に恥ずかしがるんですよね。
ティファニーはそこを恥ずかしがらず、自分の セクシュアリティ をちゃんと受け止めていて、パットにもそれを突きつける。

Copyright: © 2012 The Weinstein Company. All Rights Reserved.
「あなたは生きるのが怖いのよ!」と叫ぶシーンがありますけど、まさにその通り。
パットは“ニッキへの悲しみ”に自分を包み込んで、自分の一部を消してしまっていたんです。
そこでティファニーはこう提案します。
「ダンスコンテストのパートナーになってくれたら、ニッキに手紙を届けてあげる」と。
最初は抵抗するけど、やがてダンスという“リズムとルール”がパットの心を落ち着かせていく。
動きに集中することで心が静まり、ようやく“自分の気持ちを感じる余裕”が生まれてくるんです。
悲しみの奥にある小さな希望
多くの人は、この映画を「壊れた二人が互いを癒やしていくラブストーリー」と言います。それも間違いではないし、二人がキスしたシーンで私も思わず笑顔になりました。
でも実はこの映画、もっと深いところを描いている気がします。
地下でひっそり泣いている夫。年金を失って息子に執着してしまう父親。依存症から抜け出そうとしている友人。
みんなそれぞれ傷を抱えて、つまずきながらも前へ進もうとしている。
この映画は“人生のやり直し”や“悲しみの先に続く道”についての物語なんだと思います。
悲しみの渦に飲み込まれたとき、人は簡単に希望を見失う。でも、この映画は「それでも一歩ずつ進んでみよう」と静かに背中を押してくれる。
そして、人の“混乱”を外側からジャッジするのではなく、その奥にある痛みに目を向けようと教えてくれる映画でもあります。
もし初めて観たときの自分に声をかけられるなら、こう言いたいです。
「そのカオスの裏には痛みがあって、その痛みの奥には、確かに癒しの芽があるよ」と。

ライター:プロフィール

インタビュー:條川純 (じょうかわじゅん)
日米両国で育った條川純は、インタビューでも独特の視点を披露する。彼女のモットーは、ハミングを通して、自分自身と他者への優しさと共感を広めること。