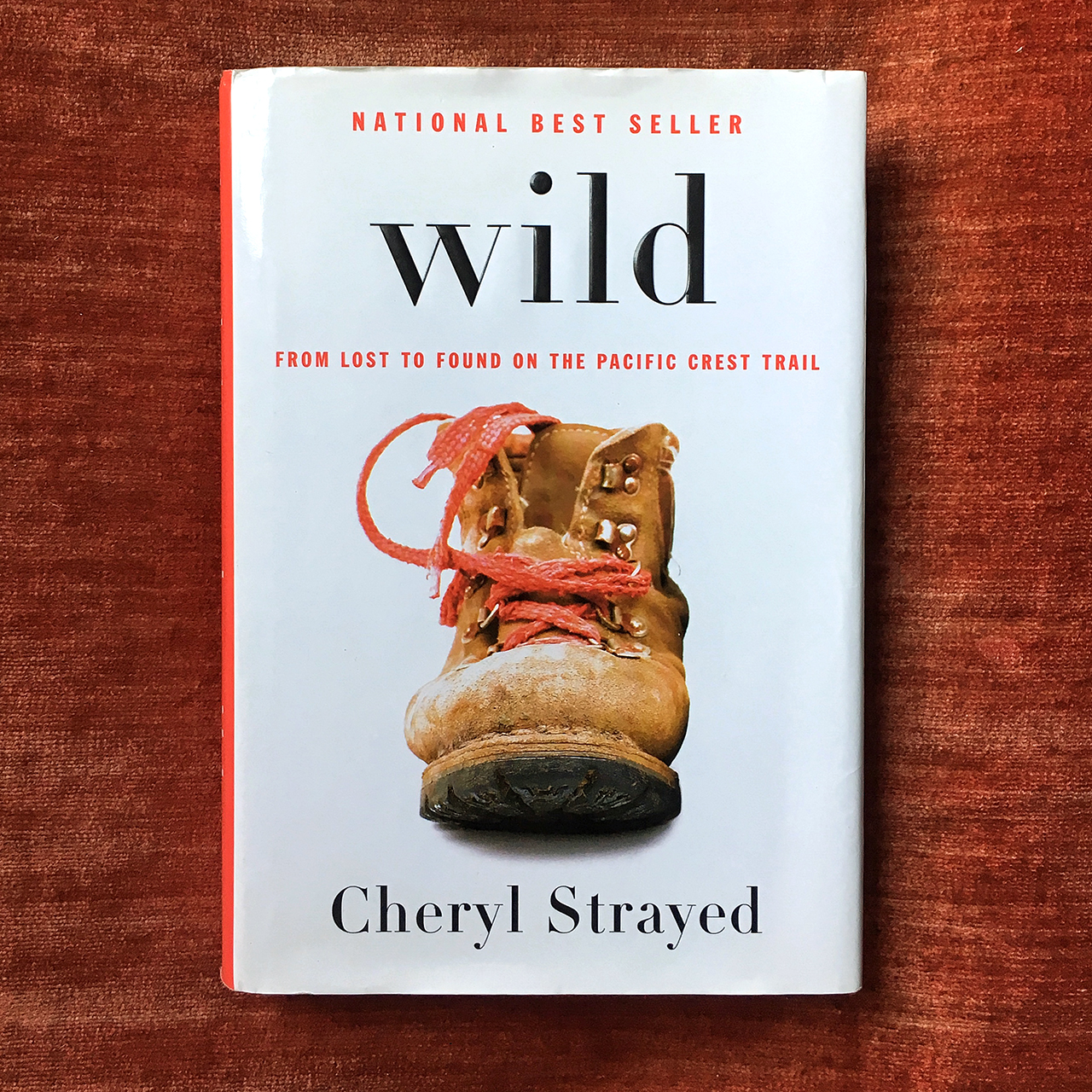突然の別れや予期せぬ喪失。心にぽっかり空いた穴は、深い悲しみに、どう向き合えばいいか分からず、自分を責めることもあるかもしれません。でも、あなたの心に湧き上がるどんな感情も「おかしくない」んです。そして、その悲しみは決して一人で抱え込む必要はありません。今回は、大切な人を亡くした後の心の変化や、悲しみとどう「共に生きていくか」について、グリーフケアを行うリヴオン代表の尾角光美さんに伺いました。
おすすめ記事 ▶ 瞑想をするのにベストな時間は?自分に合ったタイミングで、心と体を整えるヒント
ーー 大切な人を亡くしたとき、落ち込みがちな感情とどう向き合えばいいでしょうか?
まず知っていただきたいのは、「喪失の反応は悲しみや落ち込みだけではない」ということです。例えば、お子さんを亡くした後に仕事を頑張るお父さんや、親を亡くした後に受験勉強に集中する子ども
大切なのは、亡くした直後に様々な感情や反応、影響があるということを知ることです。そして、その反応の多くは「ノーマル」で、自然なものなんです。「グリーフはノーマル」という考え方を広めることを「グリーフのノーマライゼーション」と言いますが、悲しみが深くても、逆に涙が全く出ないとしても、その反応は正常なもので、、自分は「おかしくないんだ」と思うところから始めるのが、グリーフと向き合う上での一本の軸になりますね。
ーー 「知る」ことが大切とのことで、最初はまず何をしたらいいでしょう?
そうですね。ご本人が必要なサポートを探して手を伸ばすのは、亡くした直後はなかなかハードなことなので、周りの人たちが情報などを届けるのがとても大切です。
例えば、私たちのウェブサイトにある「大切な人を亡くした人のための権利条約」はPDFでダウンロードして印刷できるので、「ちょっと参考になれば」とで、さりげなく手渡してみるのもいいでしょう。別に私たちの団体に限らず、「こういうものを見つけたから読んでみたら?いらなかったら別にいいからね」と、相手に選択肢と主導権を渡した上で、手がかりを届けていくのが大切です。
“「私はあなたのお母さんのことを知りたいんだ」ということを示してもらえると、亡くされた方は嬉しいと感じることも多いんです。”
あとは、「積極的関心」を持つこと。亡くなった人のことを知ろうとしたり、亡くした経験をしているその人の「今」を知ろうとすることです。日本人は距離を置くのが礼儀だと思いがちですが、アメリカやイギリスに行くと、初対面でも「お母さん亡くされたって?どうして?」と積極的に聞いてきます。もちろん、聞かれたくない人もいるのですが、それも聞いてみないと相手がどう思っているのかは分かりません。
でも、「私はあなたのお母さんのことを知りたいんだ」ということを示してもらえると、亡くされた方は嬉しいと感じることも多いんです。例えば、「お母さんは名前は何ていうの?」と亡くなった人の名前を聞いてくれること、それは人間だけでなくペットでも同じです。そういった積極的な関心を持ってもらえると、「亡くなって終わりじゃないんだな」と思えるのではないでしょうか。
ーー 尾角さんご自身は、お母様を亡くされたご経験から、現在のグリーフケアの活動へとつながっていったとのこと。当時はどんな心の変化がありましたか?
私は19歳の時に母を亡くしました。当時は、感情の変化はなかったんです。むしろ、うつ病でずっと「死にたい」と言っていた母が亡くなり、それしか選択肢がなかったんだという思いや、自分が「「一緒に死を選んだ」という感覚でした。母親が亡くなる時に止められなかったことを責めるというよりも、共に生きるのが苦しかったので、それしかできなかったんだという思いでしたね。
私にとって、グリーフは感情だけではないということを知れたのも大きかったです。死別後、身体の変化として腰の椎間板ヘルニアになったりした「身体的影響」以外にも、経済的な影響も大きく、大学を何度も中退しそうになり、9年かかって大学の学部を卒業しました。死んだ方がマシだと思った時期もありました。また、親の話をする友達と距離を取ったり、学校に行くのが苦しいと感じたりと「社会的影響」も大きかったんです。

でも幸い、アメリカの「ダギーセンター」という世界最大の遺児支援団体からグリーフのことを学ぶ機会があり、そこで「親が亡くなってホッとした気持ちがあったのはおかしくなかったんだ」とか「身近な人を失って何も感じないこともある」「人間関係に変化が起きるのも自然なことだったんだ」と知ることができたのは、すごく大きな支えになりましたね。
グリーフケアの活動を始めようと明確に思っていたわけではないんです。大学時代に、親を亡くした子どもを支援する団体からのご縁で、自殺で家族を亡くした遺族として行政で講演する機会がありました。そこからたくさんの遺族の方との出会いがあり、活動がスタートしました。
転機は2007年。たまたまGoogleで検索していたら「母の日」の原点が出てきたことでした。ウィキペディアに、亡くなったお母さんの好きだった白いカーネーションを配ったアメリカ人女性が母の日を始めたという話が書いてあって、「なんだ、母親を亡くしている私にとっても母の日は大事な日なんだ」と気づいたんです。それを広めたいという思いから、「母の日プロジェクト」を立ち上げました。
翌年の2008年の母の日100周年にあたり、亡くなったお母さんへ手紙をを募集し、文集を作成したのですが、これに大きな反響がありました。新聞やNHKでも特集していただき、受付の電話がずっと鳴り止まないほどでした。その電話の向こうには、母を亡くして以来、母の日が辛かった人、大嫌いだった人や、虐待を受けていたけれど母と向き合うきっかけをもらった人など、様々な方がいらっしゃいました。この活動は一回きりでは「やめられないな」と感じ、リヴオンという団体を立ち上げることになったんです。
ーー 尾角さんにとって、「死」とはどのような意味がありますか?
とても大きな質問ですね。これまでたくさんインタビューを受けてきましたが、初めて聞かれた質問です。
ありきたりな答えかもしれませんが、私にとって死は「いのちの一部」だと思っています。子どもたちにいのちの授業で「死もいのちなんだ」と伝えると、みんなびっくりするんですよね。やっぱり、「生きる」とか「生まれてくる」ということに意識が向きがちですが、死まであって初めて「いのち」なんです。そして、死してなおそこにはいのちがあり、その亡きいのちとつながることができると私は思っています。
それは、霊能力とか、見えるとかそういう話ではありません。例えば、亡くなった人のことを思って遺品を身につけたり、私にとってはネックレスだったんですけど、ちょっとした日常の中に亡き人のいのち、いのちの一部を感じながら生きている。死がそこにあるからこそ、亡くなった人が残したものになっているんです。
「いのち」の中にも「死」があるし、「死」の中にも「いのち」があると思っています。矛盾しているように聞こえるかもしれませんが、死んでもなお生きているいのちがそこにある。いのちの中にも必ず死を含めていのちが存在する、死なないいのちはない、という両面性があるなと、今自分で説明しながら気づきました。
ーー グリーフケアにおいて大切にしていることは何ですか?
当事者も、支えたいと思う人も、「悲しみをどうしたら楽にできるか」という問いを持つことがあります。でも、多分悲しみの奥にある気持ちって、その人のことを強く思っているからこそ、生まれてくるものだったりするんです。
私には母親を死なせたという罪悪感が今もあるのですが、罪悪感も「母のいのちを助けたかった」という思いがあるから生まれてきているんですよね。だから、私は感情にプラスもマイナスも本当はないと思っていて、人間が勝手にラベルをつけているだけだと考えています。
なので、私たちがグリーフケアで大切にしているのは、どんな感情もジャッジをしないということ、そして、感情の奥にあるものを大事にするということです。感情そのものも、もちろん大事にしますが、表面的なところで判断しないということがとても重要だと思っています。
“私には母親を死なせたという罪悪感が今もあるのですが、罪悪感も「母のいのちを助けたかった」という思いがあるから生まれてきているんですよね”
例えば、東日本大震災の津波で奥様を亡くされた方が、「私が殺したんだ」と自分を責めていたことがありました。でも、それをジャッジせずにそのままに聞いていくと、「自分がそばにいたら助けてあげられたかもしれないのに、私が一緒にいなかったからだ」という話が出てきたんです。その「死なせた」とか「殺した」という言葉の奥には、「助けたい」という計り知れない思いがあったのだと解釈させてもらいました。単純に「あなたが悪いんじゃないですよ、津波が連れ去ったんですよ」と言ったって、何も解決しないし、その人の罪悪感を取り除こうとすると同時に、そこにある大事なものまで聞こえなくなってしまうんです。
私たちはジャッジをしてしまうのが人間なので、大切なのは「ジャッジしている自分に気がついている」ということ。そして、「あ、私ジャッジしてるな」と思ったら、ちょっと「そのままに」この感情を見てみるのはどんな感じなんだろう、とそこを訪ねていくことを大事にしています。
感情を無理になくそうとすると、かえって大きくなるような感覚があります。まるで、お化けを「なくなれ、消えろ、あっち行け」と言えば言うほど、こちらに近づいて大きくなってくるような。ですから「あなたはなんでここにやってきたの?」という感じで、その感情と付き合っていくことをおすすめしています。

ーー 亡くなった大切な人の思い出を風化させずに、感じながら生きていくために、他にできることはありますか?
山のように選択肢や方法があります。亡くしたことを表現する営みを「グリーフワーク」といったりします。ググリーフを大切に、その人自身がグリーフを表現するものすべてをさします。
例えば、誰かに亡くした人の思い出話をすることや、亡き人が好きだった納豆を今日買って食べようとか、日々の日常の食事を通して思い出したり。音楽が好きだった人なら、命日の前に、その人の好きだった曲のプレイリストを作って聴いてみたりするのもいいですね。
最近はAIで故人と話ができるサービスなども出てきていますが、それぞれ表現方法や、亡くした人との関係をを大切にする仕方が違うものです。亡くなった人を想った時に、何をするのが自分にとってしっくりくるのか、それを選んでいくということなんです。
また、日本の文化や宗教的な生活の中にも、グリーフワークはたくさん組み込まれています。お墓参りもそうですし、お彼岸やお盆には亡くなった人が帰ってくると考え、茄子で馬などで乗り物に見立てて作ったりもしますよね。そういった日常の中に、亡くなった人を想う営みはたくさんあるんです。
ーー 私自身、最近、義理の父を亡くしました。小さな子供が二人いるんですが、私は「おじいちゃんはいなくなっちゃったんじゃなくて、天国で見守ってくれているんだよ」と伝えることくらいしかできず…。子どもたちにどう声をかけたらいいか分かりません。
まず知ってほしいのは、子どもであれ大人であれ、亡き人の存在の感じ方は一人ひとり違うということです。大人はつい「お空に行っちゃったよ」「お星さまになって見守っているよ」などと抽象的に説明しがちですが、子どもには子どもなりの実感があります。
例えば「おじいちゃんは今どこにいると思う?」と聞いてみてください。子どもはもっと自由に発想するかもしれないので、もしかしたら「天国の階段の途中で転んでるかも」とか、「土いじりが好きだったから土の中に感じる」なんて答えるかもしれません。
“亡き人の存在の感じ方は多様であることを受け止めてあげてくださいね。”
大人が先に答えを出そうとするのではなく、子どもの話をまず聞くことが大切です。もし話したくなければ「言わなくていいよ」という選択肢も持たせつつ、例えば「おじいちゃんとの思い出で一番嬉しかったことは何?」などと問いかけてみましょう。もしとんかつ屋さんに連れて行ってもらったことが思い出なら、おじいちゃんの誕生日にとんかつ屋さんに行ってみるなど、子どもの感覚を尊重した過ごし方を見つけるのがおすすめです。
亡き人の存在を感じるタイミングや場所は人それぞれです。もしかしたら、蝶々が飛んできたのを見て「あれ、おじいちゃんだったかも」と言うかもしれません。亡き人の存在の感じ方は多様であることを受け止めてあげてくださいね。
ーー 実は私もまだ、義父がこの世からいなくなってしまった現実を受け容れられていない部分があります。来月に、義父のいない家に行き悲しくなってしまうのではないかと、今から心の準備をしているところです。
「受け容れる」というのは、白か黒かではありません。グラデーションのように、心が揺らぎながらで全然いいんですよ。無理に現実を受け容れようとせず、今は距離を取ろうとしている自分をそのまま認めるのもよいのではないでしょうか。
ーー 大切な人を亡くしたことにこれから向き合おうとしている人に、どんな言葉を届けたいですか?
言葉を届けるというよりは、一つの問いを置いておきたいですね。
「あなたにとって、その失ったものを大切にするために、何かちょっと一歩踏み出してみるとしたら、どんなことができそうですか?」
グリーフは「指紋ほどに違う」と言われています。一人ひとり、感じ方も、求めている言葉も違います。だから、私がここで紡ぐ言葉が、ある人にとっては傷つくかもしれないし、ある人にとっては今、心に届くかもしれない、またある人にとっては2年後に届くかもしれない。
ーー リヴオンさんの活動に興味を持った方に、どのようなサポートがあるか教えてください。
具体的な場としては、定期的に、10代から30歳までの死別を経験した若者の集いを、オンラインと京都の現地でそれぞれ行っています。お母さん、お父さん、恋人や婚約者、親友、など、大切な身近な人を亡くした若者たちが、当事者同士で分かち合う場になります。
より幅広い方を対象に行っているのは、「グリーフケア基礎講座」というオンデマンドで受けられる学びの場です。この講座は、自分で自分と向き合うことを目的としていますが、オンラインのオンデマンド動画の向こう側には、一緒にワークをやってくれる人がいたり、私自身も講義をしているので、一人だけど一人じゃない講座を作りました。自分のグリーフに向き合いたいけれど、一人で外に出るのはちょっと…という方には、とてもおすすめです。また、喪失を経験した人を支えたいという方にもぜひご受講いただければと願ってます。
リヴオン: https://www.live-on.me/
Podcast「ゆるやか死生学」 (Spotify)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWfT7GWq-Ow1riGRR1TVnbi0i30HXLpgC (Youtube)

尾角光美 おかく てるみ 一般社団法人 リヴオン代表理事
1983年大阪生まれ。19歳で母を亡くす。あしなが育英会で病気、災害、自殺、テロ等による遺児たちのケアに携わる。2006年自殺対策基本法制定以後、全国の自治体、学校などから講演、研修の講師として呼ばれ、グリーフケア、自殺予防に関して伝え広める。2009年「グリーフケア・サポートが当たり前にある社会」の実現を目指してリヴオンを立ち上げる。石川県小松市勝光寺における「グリーフサポート連続講座」が認められ、寺院とNPOの協働を表彰する浄土宗第5回「共生・地域文化大賞」にて「共生優秀賞」受賞。日本財団国際フェローシップのフェロー5期生に選ばれ、英国に留学、2018年ヨーク大学大学院国際比較社会政策修士号取得。現在英国バース大学の死と社会センターの博士候補生として「成人形成期の親との死別経験による経済的影響」について研究中。現在は主に日本で活動。2023年よりポッドキャスト番組「ゆるやか死生学」を配信中、「死は乗り超えるもの?」「自殺・自死」というテーマで国内外の研究の紹介や、母を亡くした人や僧侶との語り合いなどを行っている。

ライター:プロフィール

著者:堀江知子(ほりえともこ)|香港在住ライター
民放キー局にて、15年以上にわたりアメリカ文化や社会問題についての取材を行ってきた。
2025年からは香港に移住しフリーランスとして活動している。noteやTwitterのSNSや日本メディアを通じて、アフリカの情報や見解を独自の視点から発信中。
出版書籍:『40代からの人生が楽しくなる タンザニアのすごい思考法 Kindle版』。
Xアカウントはこちら