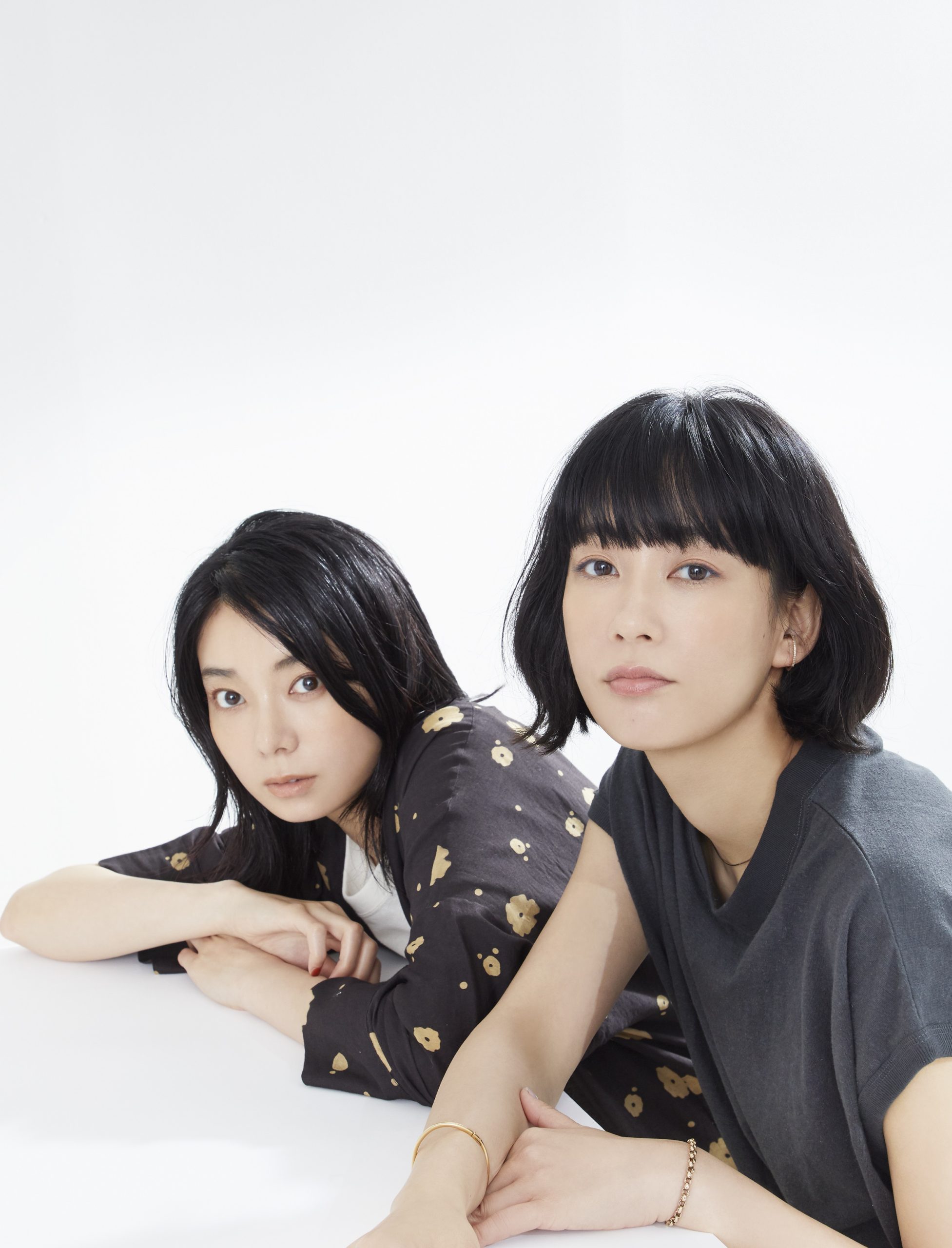【エッセイ】長い髪に少し飽きてきた——でも切ることは、もっと深い何かを手放すようで

あの夏のことを思い出す。
2024年、世の中はボブの熱に包まれていた。ヘイリー・ビーバーやゼンデイヤ、リリー・コリンズ——誰もが軽やかなあごラインのボブにしていて、私もその波に乗るつもりだった。
美容室の椅子に座るまでは。
「パリの女の子みたいな、あの潔いボブがきっと似合うはず」
そう思い込んでいたのに、鏡の前に座った途端、自信はふっと溶けてしまった。
“パリ風ボブに憧れて髪を切ったものの、結局中途半端なロブに落ち着き、帰り道にはすでに後悔と「自分らしくない」という違和感を抱えていた。”
勇気を出すはずだったその日は、結局、どっちつかずの“肩につくロブ”で終わってしまった。
サロンを出るときには、すでに小さな後悔が芽生えていて、それでも美容師さんに笑顔で頷きながら「気に入っています」と言った。帰りの車の中、ミラーに映る自分を執拗に覗き込みながら、「これはこれで悪くない」と自分を説得しようとした。でも、その日一日、どうしても“自分じゃない”という違和感が消えなかった。
サロンを出るときには、すでに小さな後悔が芽生えていて、それでも美容師さんに笑顔で頷きながら「気に入っています」と言った。帰りの車の中、ミラーに映る自分を執拗に覗き込みながら、「これはこれで悪くない」と自分を説得しようとした。でも、その日一日、どうしても“自分じゃない”という違和感が消えなかった。
振り返れば、すべてが衝動的だったと思う。
仕事が始まって数ヶ月、自分なりの“大人のスタイル”を見つけなきゃと焦っていた。
大胆に髪型を変えることが、あせりから救ってくれる気がした。
だけど、床に落ちていく自分の髪を見つめながら、気づいてしまった。私にとって髪は、ただの“外見の一部”ではない。もっと深いところで、自分という存在とつながっているものなのだと。
おすすめ記事:がん治療中の脱毛に向き合う方法〜心と体をケアするために〜
Contents
ロングヘアは、ずっと私の“居場所”だった
自分の髪を自分で決められるようになってから、私はずっとロングヘアだ。
そのきっかけは、まわりの女の子たちの影響かもしれないし、子どもの頃に大好きだった『リロ&スティッチ』のナニに憧れたせいかもしれない。ハワイに住むいとこの Kuʻuipo の、腰まで届く髪にも心を奪われていた。
“長い髪=美しさ”
知らないうちに、こんな価値観が当たり前になっていたのだと思う。
でも、私のロングヘアには、いつの間にか別の意味が宿り始めていた。
母と過ごした小さな習慣。
卵を混ぜたものを頭皮に塗ってくれた日曜日、キッチンバサミで毛先を1センチだけ整えてくれた夜、写真撮影の前日にきつく編み込んでくれた三つ編み。
思春期に自分の身体に自信を持てなくなった頃、ロングヘアは私を守ってくれる“安心の毛布”になっていた。

髪はアイデンティティと深く結びついている
「髪はアイデンティティとつながる複雑な“言語”のようなもの」
心理学者・アフィヤ・ムビリシャカ博士 の言葉は、私自身の感覚を優しく代弁してくれた。
髪は、文化やルーツ、信念を語る。だからこそ、“自分らしくない髪”は心に小さなずれを生むのだ。
“髪は文化やルーツを映す存在であり、自分らしくない髪型は心のずれを生む——そして20代で、フィリピンのルーツとのつながりを自分の髪の中に見いだした。”
20代になって自分のルーツを探す時間が増えた。母の故郷であるフィリピンとのつながりを、言語でもなく肌の色でもなく、“自分の髪”に見いだした瞬間があった。
いとこの ティファニー が言った、 「私たちのフィリピンの髪、本当にきれいだよ」という言葉が胸の奥に残っている。
フィリピンでは、髪は美しさだけでなく、強さや誇りの象徴だ。
植民地時代、男性の長髪が“抵抗のサイン”だったことも知った。
髪は、ただのファッション以上のもの——物語を宿している。
母の髪の歴史にも、私と同じ“揺らぎ”があった
母はフィリピンのダバオで生まれ育ち、若い頃のハワイ時代も姉妹みんながロングヘアだった。 1990年、アメリカンドリームを追ってNYへ移住したとき、初めて髪をバッサリと切ったという。
「新しい人生をスタートするために、何か変えたかった」
そう言う母の目は、少し誇らしげだった。
髪の長さは、その人の人生の変化を映す鏡なのだと気づく。
それは母にも、私にも当てはまっていた。

もう一度、自分の髪と向き合うために
2020年、パンデミックの不安の中で、私は髪をプラチナブロンドに染めた。
あの時は、変化が必要だった。でも、ブリーチで傷んだ髪を見つめながら、「私はここで何を求めていたんだろう」と思ったこともある。
2022年、ようやく地毛に戻し、健康な髪を育てながら、鏡に映る自分がゆっくりと落ち着きを取り戻していった。
それでも最近、また変化を求める気持ちが揺れ始めた。仕事柄、毎日のようにヘアチェンジするセレブを見ているせいかもしれない。
だけど、スタイリストマーク・タウンゼント の言葉が頭に残る。
「自分のスタイルを知っていることには、誇りがある」
それが、私の迷いにそっとストップをかけてくれた。
そして私は、18ヶ月ぶりに美容院へ行った
今回は、インスピレーション写真をしっかり持って。
美容師さんは、傷んだ毛先を少し整え、頬に沿うレイヤーで表情を明るく見せてくれた。
動きのある軽やかなラインをつくりながらも、私の象徴である“長さ”はきちんと残してくれた。
カットの間ずっと「自分らしさ」を失わせないように寄り添ってくれて、切ってもらうたびに安心が積み重なっていくようだった。
美容院を出たとき、髪が腰に触れる感覚にホッと胸がほどけた。
鏡に映る自分を見つめながら、静かに思った。
ああ、やっと自分に戻れた。
この記事は、以下の記事をもとに翻訳・再編集したものです:
https://www.instyle.com/emotional-attachment-long-hair-embrace-identity-haircut-11881224