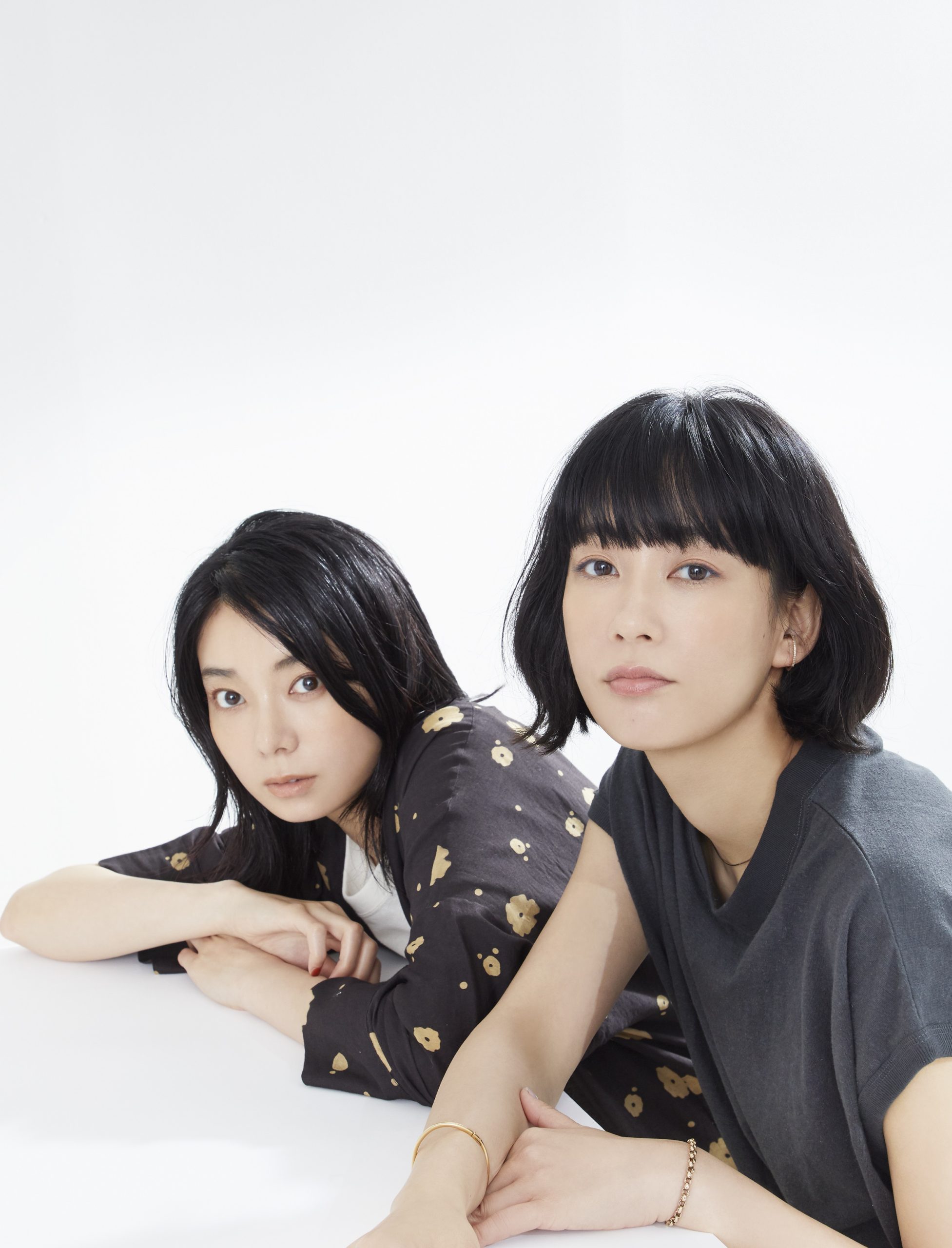幼いころ、母に連れられて行く買い物で、私がひそかに心を躍らせていたのは、雑誌コーナーへと抜け出すひとときでした。流行に敏感だったわけでもなく、化粧に興味があったわけでもないのに、あの光沢を放つ表紙たちは、いつも私を惹き寄せました。そこに佇む女性たちは優雅で、静かに私を見つめ返し、私はただ密やかに「いつか自分も」と願っていたのです。
『About Face』は、そんな時代を彩ったスーパーモデルたちを再び呼び戻し、雑誌の表紙を飾り、ランウェイを駆け抜けた彼女たちが、いまどこに立っているのかを描き出すドキュメンタリーです。彼女たちが歩み出したのは、そもそも「キャリア」という言葉が女性には与えられていなかった時代。その姿は、モデルとインフルエンサーの境目が曖昧に溶けていく現代と、鮮やかな対照を成しています。
おすすめ記事 ▶ 多様性の時代に考える「美の基準」との向き合い方
言葉が人生を左右するとき
当時のモデルは、個人として讃えられる存在ではなく、布をまとった「動くハンガー」に過ぎませんでした。けれども時が経つにつれ、人々の視線は衣服から彼女たちの存在へと移っていきます。強いまなざし、彫り深い頬、強い存在感――それを無視することなど、誰にもできなかったのです。
150センチそこそこの背丈で、丸みを帯びた身体を持つ私は、背が高く細身の彼女たちを羨望のまなざしで見つめていました。モデルになることを夢見たわけではない。ただ、もう少しだけ背が高くなりたいと願っていたのです。艶やかに巻かれた髪も、頬にのせられたチークも、すべてが巧みに演出された幻影だとは知りませんでした。あの表紙の裏には、少女たちに向けられたひとつの声が隠されていたのです――「美しい女の子とは、こういうものだ」と。
“たったひとことの言葉が一生心に残り、人を縛ることも解き放つこともある”
映画は、1945年からモデルとして歩み続けるカルメン・デロリフィチェの姿から幕を開けます。
彼女は古い写真を見つめながら、ふと「自分の足を好きじゃない」とこぼします。かつて母に「棺のようだ」と言われたその言葉は、81歳となった今なお、彼女の心に影を落としているのです。ひとつの言葉が、一生を通して響き続ける――その重さに、ただ驚かされます。
言葉はなぜ、これほどまでに深く心の奥底に根を張るのでしょう。どれほど自信を重ねても、決して消えない言葉があります。
私自身も、母から「少しぽっちゃりしているから痩せた方がいいのでは」と何気なく言われた日のことを忘れられません。13歳の頃でした。その瞬間から、私と自分の身体との関係は複雑なものになり、健康でありたい願いと、罪悪感なく食を楽しみたい思いのあいだで、心は揺れ動き続けています。けれど同じ母が「あなたの笑顔はとても素敵ね」と告げてくれた言葉もあり、それ以来、私はためらわず笑うようになりました。その言葉が、笑顔でいることを許してくれたように。
別のモデル、マリサ・ベレンソンは、母から「あなたの顔はモディリアーニの絵のようだ」と言われたことを語ります。彼女は笑ってそう言いましたが、その笑いの奥には痛みが潜んでいました。たとえ悪意のない言葉であっても、深く心を傷つけてしまうのです。
それこそが、モデルという職業の逆説なのかもしれません。称賛よりも欠点を指摘され、身体を細部まで値踏みされる世界。毒のように思える場所でありながら、それでも無数の少女たちが憧れを抱き続けます。なぜなら、ほんのひと握りの選ばれし者は、繰り返し「美しい」と讃えられるから。――美しさは、世界が何度も教えてきたように、扉を開く鍵であるからです。

権力と偏見にかたどられた「美」
「美しい」とは、本当にどういうことなのだろう。
それは幸せをもたらすのだろうか。――着る人の心よりも、世界にどう映るかだけを求められるこの業界で。与えられるのは、ブランドが選んだ化粧。望まれるのは、彼らが描いた完璧な髪型。強いられるのは、作りものの美しい笑顔。
元モデルのキャロル・オルトは言う。
「それは、本当の私ではなかった」と。
モデルとは自分を売るのではなく、服を売る仕事だ――そう言う人もいるだろう。けれど彼女は続ける。
「服を着て生き生きと存在すること。その姿ごとに価値を見いだされること」。
そこにこそ、人間らしい真実が宿るのだと。
“映画は、美と栄光の裏に潜む搾取や人種差別の現実を映し出し、「美しさ」が権力や偏見に左右され続けてきたことを突きつけている”
映画はまた、目を背けたくなる闇をも映し出す。
ドラッグ、セックス、搾取――それらは例外ではなく、日常の風景だった。繰り返されるうちに、人はそれを「普通」と思い込んでしまう。だが、15歳や16歳の少女たちが酒や薬の漂う場へと投げ込まれ、大人の欲望の視線を浴びるその光景は、あまりに見ていて辛い。少女の身体に「女」の姿を映し出し、思春期そのものを奪う――その異様さは、忘れがたい不快さを伴う。
そして、人種の壁もまた、この業界を覆っていた。
有色人種の女性を表紙に載せることをためらう出版社。
ベサン・ハーディソンやパット・クリーブランドは、白人を優遇する世界で、自らの居場所と声を切り拓いてきた。いまなお続くその戦いの中で、ブランドが放つ言い訳は「非白人モデルをどこに置けばいいのかわからない」というもの。しかし、アメリカの街角を一歩歩けば、多様性に満ちた顔があふれている。その言葉がいかに空虚かは明らかだ。
おすすめ記事 ▶ 映画レビュー:「食べて、祈って、恋をして」— 人生で出会う人はすべて意味がある
アジア人としてアメリカで育った私にとって、雑誌に自分と似た顔を見つけることは大きな意味を持っていた。それは単なる「姿」ではなく、「未来」の可能性だったから。
だからこそ、この映画が不都合な真実から目をそらさなかったことを、私は深く評価したい。
美しさとは、決して無垢でも中立でもなかった。常に権力や偏見にかたどられ、「誰が見るに値するのか」という問いにさらされ続けてきたのだ。

時間がくれる、自信という美しさ
『About Face』は、モデル業界の暗い影を映し出しながらも、最後には「美しさ」と「老い」に新しい光を投げかける。
時間とは戦うべき敵ではなく、強さや自信を宿す源である――この映画はそう語りかけてきます。
彼女たちがキャリアを歩み出したのは、まだスマートフォンもSNSも存在しない時代。アルゴリズムが美を決めるのではなく、環境そのものが扉を開く時代でした。イザベラ・ロッセリーニやキャロル・オルトにとって、モデルは夢ではなく、生き延びるための手段であり、あるいは家族や共同体に背を押されて選んだ道でもありました。だからこそ彼女たちの「老い」に対する眼差しには、他者との比較に曇らされない透明さがあり、その語りはどこか清められた祈りのように響きます。
長年にわたる視線と批評にさらされたからこそ、彼女たちは解き放たれる強さを得たのでしょう。仲間の中には若さを追い、かつての個性を消してしまった者もいた。それでも彼女たちは、成熟こそが美であると信じる世代に生きてきた。成熟はつまり「生きてきた証」であり、そのしるしこそが顔に刻まれるのです。
“『About Face』は、若さを追うのではなく人生を抱きしめることで芽生える自信と、老いを祝福すべき美しさとして描き出している”
あるモデルは言いました。
「誰かとあなたを分ける一番大切なもの――それは“表情”なの」
ボトックスや整形があたり前になったこの時代にあっても、その言葉は胸の奥深くに沈みます。映画も、私自身も、美容の選択を否定はしません。人を本当に幸せにするものなら、それが正解だから。けれど、彼女たちを見ているとわかるのです。揺るぎない自信は、若さを留めることからではなく、人生の物語をそのまま抱きしめることから生まれるのだと。
イザベラが語った一言は、特に心に残ります。
「50代になって初めて、自分は美しいと呼ばれるにふさわしいと思えた」と。
その言葉は、私たちへの優しいささやきでもあります。――焦らなくていい、自分の肌の中に安らぎを見つけるには時間がかかるのだと。美しさとは、消え去るものでも忘れ去られるものでもない。むしろ、時間とともに豊かに花開くもの。
結局のところ、『About Face』はファッションの物語ではありません。
それは耐えること、しなやかに生きることの物語。
女性は美しいだけでなく、強い存在である。老いの旅は隠すべきものではなく、祝福すべきものなのだ――この映画は、静かな声でそう教えてくれます。

ライター:プロフィール

インタビュー:條川純 (じょうかわじゅん)
日米両国で育った條川純は、インタビューでも独特の視点を披露する。彼女のモットーは、ハミングを通して、自分自身と他者への優しさと共感を広めること。